| 01 | ☆釈 迦(B.C.566?~486?年)

一切の国々に赴け。そしてこの福音を説け。貧しきもの卑しきものも、富めるもの位高きものも、すべて一なることを、すべての種姓(カースト)はこの教えのなかに統合せらるることを、人に告げよ。
勝利は憎悪をはぐくむ。被征ふく者はふ幸であるから。戦いにおいて、一人千人に打勝つこともある。しかし自己に打勝つ者こそ、最も偉大なる勝利者である。
4月8日インドのカピラ城主として生まれ、二十九歳から世を捨てて修行した仏教の開祖。彼の教えは自己伸張、自己克ふくである。 引用:桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵― P.60 2010.04.08 |
中 国 仏 教
|
<弦緩(ゆ)るければ鳴らず、緊迫すれば断つ、緩急中を得れば百韻遍(あまね)し> 参考:迦葉仏は過去七仏の一人 *岡 潔『月 影』(講談社現代新書)P.40 2008.5.30 |
|
三祖鑑智僧璨(~606年) 周・武帝の仏教迫害を避けて深山にこもり、厳しい修行で身魂を磨き上げた傑僧である。 ▼〚信心銘〛 73の対句で構成されいます。 ① 至道は無難(ぶ なん)、唯(ただ)揀択(けんじゃく)を嫌う。 【訳】まことの道(または宗教的)を体得することは、わけもないことだ。これを妨げるものはえり好みをするというような相対観をもつことだ。つまり、分別計較心をはたらすことだ。 【語義】○至道ーこの語は〚荘子〛にある言葉。一般的には、"天地自然おのずからなる道"と考えてよいであろう。ここでは禅の立場であるから、宗教的な真理または悟りと解すべきであろう。○唯ーこれは惟、維、雖などと同様に、字の数を揃えための虚字で意味はない。○ 揀択ーどちらもえらぶという意味で、相対観を表している。 [付記]この①対句が〚信心銘〛の真髄である。これがのみ込めたら、後は読む必要はないといってよかろう。これからの後はかの第①対句の精神をどうしたらわからせようかと、いろいろニュアンスの違うことばを用いて説明しているといってもよい。 73番の対句 言語道断(ごんごどうだん)、去来(こらい)今(こん)に非ず。 さて、至道を把握することは難しいことではないという。しかし、このことは把握した後でいえることであって、難しくないと同時に易しくもないのである。すなわち、第31対句で"易無く難無し"といっているとおりである。しかし、この"易無く難無し"ということは相対観に立脚していることで、真理を把握することは、絶対観に立つてズバリと悟る以外にない。真理を把握するためにまずわれわれができることは、真理を把握することを妨害している要因を摘出して、これを一つ一つ排除することから始めなければならない。徳川初期の無師独悟といわれる盤珪さんは、悟ることを妨害しているのは"身びいき"だ、これをなくせと繰り返しいわれた。そうして、完全に純粋な自己になったとき、"われ悟れり"という境地に到るものと思う。 お釈迦さんは暁の明星をご覧になってお悟りを開かれた。その時のお釈迦さんの実感は、意識と星とがまったく一つになり、<ああ自分は光っている>と意識されたそうである。 引用:川上正光『禅の源泉 信心銘 花開く悟りの世界』(大蔵出版)1982年11月20日 初版1刷発行 参考:『正法眼蔵随聞記』5*18(P.123)に<信心銘に云く、至道かたきことなし、唯だ揀択を嫌ふと。揀択の心だに放下(ほうげ)しぬれば、直下(じきげ)に承当(しょうどう)するなり。揀択の心を放下すると云は、我をはなるゝなり。>と。 |

五祖法演禅師は<臨済宗>の楊岐派の三世である。 中国の宋の時代の高僧、法演和尚の四つの戒めの言葉、"法演の四戒" この四つの戒は、法演(ほうえん)が、宋代の僧・仏鑑慧懃が、太平寺というお寺の住職になられる時に示された言葉です。弟子の新たな出発に当たり、師匠として示された教えです。 "法演の四戒"
一、<勢い、使い尽くす可からず。勢い、もし使い尽くさば、禍い必ず至る>。
二、<福、受け尽くす可からず。福、もし受け尽くさば、縁、必ず孤なり>。
三、<規矩、行ない尽くす可からず。もし規矩、行ない尽くさば、人必ずこれを繁とす>。
四、<好語、説き尽くす可からず。もし説き尽くせば、人必ずこれを易んず>。
以上の四つの戒めです。 参考:石川 洋『一燈園法話 <人生逃げ場なし>』(PHP発行所)第十話 法演禅師の<四戒>が教えるものに例話を駆使されて説明されています。 2009.5.5 |

善知識たちよ、我が法門は定と慧とを根本とする。定〔坐禅〕と慧〔學問〕とを別個のものと誤解してはならない。定は慧の体〔根幹〕であり、慧は定の用〔発現〕である。定と慧とは一体ふ二である。
(六祖大師法宝壇経、定慧第二)
汝らよく聴け、後生の迷える者も、もし衆生を識らば、そこに仏性がある。もし衆生を識ることなくば、万劫の永きにわたって仏を求めても、仏に会うことはできぬ。汝ら、自心の衆生を識り、自心の仏性を見よ。仏を見んと欲する者はただ衆生を知れ。
(同、付嘱第十)
|
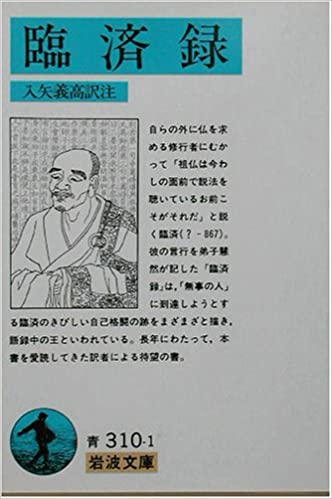
▼『臨済録』 一 無事是貴人。伹だ造作する莫れ、但だ是平常なれ。 なにごともしない人こそが高貴な人だ。絶対に計らいをしてはならぬ。ただあるがままであればよい。 ※岩波文庫P.46~47 二 随処に主と作れば、立処皆真なり。境来たるも回換することを得ず。 その場その場で主人公となれば、おのれの在り場所はみな真実の場となり、いかなる外的条件も取り替えることはできぬ。 ※岩波文庫P.50~51 三 已起の者は続ぐこと莫れ、未起の者は放起することを要せざれ、便ち你が十年の行脚に勝らん。 すでに起った念慮は継続させぬこと、まだ起こらぬ念慮は起こさせぬことだ。そういけたら、君らが十年も行脚修行《するよりもずっとましなのだ。 ※岩波文庫P.99~101 2022.04.01 追加。 |
|
井上靖が読む<天平の甊>、平凡な場面なぜ 本郷和人 【音声】井上靖が朗読する<天平の甊>
《井上靖が読む<天平の甊> 本郷和人が聴く》 朗読した文章は、 暁方、普照は眠りから覚め、初めて盲いた師鑑真の顔を見た。鑑真は眠っているのかいないのか、、船縁に背をもたせるようにして、少し顔を仰向けて坐っていた。普照は三年の歳月が和上の顔を老いたものにしていると許り思い込んでいたが、鑑真はむしろ若々しい顔になっていた。両眼は明を失していたが、そこには少しも暗いじめじめしたものはなかった。曾ての鑑真の持っていた烈しい古武士的なものはもう少し落着いた形のものになり、六十六歳の鑑真の顔は静かな明るいものになっていた。 鑑真は、突然、そこから三間ほど離れていた善照の方へ顔を向けた。正面から見ると、穏やかではあったが、やはり鑑真独特の意志的な顔であった。 <照よ、よく眠れたか> 鑑真は言った。 <ただいま、目を覚ましました。お判りになりましたか> 善照が驚いて言うと、 <盲いているので判る筈はない。先刻から何回か無駄に声をかけていたのだ> そう言って鑑真は笑った。善照は笑わなかった。早暁の冷たい江上の風に顔を向けたまま、善照は涙を頬に伝わるに任せた。一声の嗚咽をももらさなかったが、 <照は泣いているのか> と鑑真は訊いた。 <泣いてはおりませぬ> 善照は答えた。他の僧侶たちも間もなく眼を覚ました。恩託は曾ての青年僧の俤は全く消え、体躯も堂々として落着きができ、もはやどこから見ても鑑真門の高僧の一人といった貫録をを具えていた。法載、曇静も放浪時代とは見違えるほどの健康体になっていた。善照にはこうした唐僧たちを見るにつけても、一緒に何年も流離の生活を送った栄叡と祥彦の姿がここにないことが今更のように淋しく思われた。 以上が録画で朗読されていたものを聴いて、文庫本で調べて書き写しましたものです。 奈良時代。仏教界には僧侶が守るべき戒律が伝わっていなかった。ふ純な理由での出家も相次ぎ、僧尼の堕落が甚だしかった。僧界を律するために、唐から師を招き、受戒の制度を整えねばならぬ。その大任を託されたのが普照と栄叡であった。 二人は留学僧として唐土に渡り、高僧・鑑真と出会う。鑑真は戒を自ら伝えることを快諾するが、日本への渡航は困難を極めた。10年間に5度も失敗して、その間に鑑真は失明する、だが普照はついに天平勝宝5年(754)、鑑真とその弟子たちを遣唐使の船に乗せ、日本に連れ帰る。著者・井上靖は淡海三船の『唐大和上東征伝』をもとに、この壮大な話を小説化した。 しかし朗読が、なぜこの場面だったのか? 普照らと鑑真の邂逅、栄叡の死、鑑真の失明、日本への到着。劇的な瞬間はいくらもあるにもかかわらず、ごく日常的、平凡とすらいって良いこの場面を、井上は選んだのか。そして、平明にというと聞こえは良いが、しごく淡々と読んだのか。私は考え込んだ。 暫(しばら)くして漸く考えついたのは、師弟の対話こそがカギではないかということだった。 目覚めた普照は<照よ、よく眠れたか>との師の問いかけに驚く。なにゆえ盲目の師が自分の起床を認識できたのか。<判(わか)るはずはない。先刻から何回か無駄に声をかけていたのだ> 仏は常にいませどもという『梁塵秘抄』の歌がある。そうだ。仏は、師は、常に救いの声をかけてくれている。問題は、人が、弟子がそれに気がつくかどうかなのだ。仏と人が、師と弟子がふ思議な巡り合わせで出会い、心を通わせる。それが<有縁>である。日本が有縁の国であったから、鑑真はふ難を超えてやって来た。来てくれた。 そういえば鑑真の言葉を読む井上の声もまた、優しく聞こえる。縁が結ぶ師弟の絆。ふとした偶然もまた必然たり得る。それがこの物語の、朗読の真骨頂ではなかろうか。(歴史学者) ◇ 1960年代に発表された朝日新聞が所蔵する文豪たちの自作の朗読を、識者が聴き、作品の魅力とともに読み解きます。

井上 靖『天平の甊』あらすじ
日本では奈良時代、中国では唐の時代ですが、日本から海を渡った大勢の留学僧たちがいました。海を渡ることでさえも命がけですから、修行を修めて無事に帰国することは難しい時代でした。志半ばで潰えてしまう者、途中で挫折してしまう者、大陸で流浪の旅に果ててしまう者など、多くの若者がその初志を貫徹できずに生涯を終えていました。 この頃、唐の高僧鑑真の来日という大事件がありました。渡日しようとして何度も失敗し、最後には失明しながらも、鑑真は日本に仏教を伝えるという目的を果たします。その感動的な事績の裏には、留学僧たちの活躍と苦労とがありました。 聖武天皇の天平四年(西暦732年)八月、第九次遣唐使発遣が決まり、大使と副使・その他の官はすぐに決まったのですが、遣唐使派遣の中で最も重要な意味をなす留学生・留学僧が決まるのは翌年に持ち越されてしまいました。 大安寺の普照、興福寺の栄叡の二人に留学僧として渡唐する話が持ち上がったのは二月の初めでした。栄叡は<よし行ってやる>といったふ遜とも取れるような態度で応諾しましたが、普照は<一体唐へ渡って何を学んだらいいのか>と訊ねました。この二人はこの一件でわかるように、全く異なった型の秀才でした。 二人にこのことを告げたのは、当時仏教界で最も勢力を持っているといわれていた元興寺の僧隆尊(りゅうそん)でした。隆尊がいうには、日本ではまだ戒律が具そなわっていない。適当な伝戒の師を請しょうじて、日本に戒律を施行したいと思っている。しかし、招よぶなら学徳すぐれた人物を招ばなければならないし、そうした人物に渡日を承諾させるのは容易なことではあるまい、十五、六年の歳月があれば二人の力を合わせれば果たせるだろう。これは重大な使命です。栄叡はすぐにすっかり乗り気になりますが、普照の方は戒師を招ぶことより十五、六年の間に自分が学び得る教典の量の方が重要に思えるのでした。 遣唐使は五月、4艘の船で出発します。特に海が荒れているわけでもないのに船員を除いた殆ど全部の乗員が皆ひどい船酔いに襲われます。その後、ひどい暴風雨に出会い、結局蘇州に到着したのは八月でした。4艘とも同じく八月前後に漂着することができました。 一行は陸路、洛陽に向かいます。唐の都は長安でしたが、この年玄宗帝が洛陽にいたために朝廷は洛陽にあったのです。遣唐使一行は目的地が都長安でないことで失望します。なんといっても都長安での華やかな行事の晴れの舞台に立ちたいという思いがあったのです。 栄叡・普照以外に戒融・玄朗の2人が留学僧として遣唐使に伴って唐に渡りましたが、戒融は洛陽から出奔してしまいます。<この国には何かがある。この広い国を経へ巡っているうちにその何かを見つけ出すだろう。歩いてみなければ判らないことだ。>といって托鉢姿で旅に出ました。 洛陽には日本から来て30年になる景雲という僧がいました。景雲は遣唐使の帰国に伴って帰国するのですが<唐に30年いたがなにも得るものはなかった>といいます。景雲と同じくらいの期間唐にいた日本人は他に業行がいました。彼は最初自分で勉強しようと思ったのですが、何年か後いくら勉強しても大したことがないということが判り、その後はひたすら写経を続けているのでした。日本に一字の間違いもない教典を持ち帰るのが使命だと信じてひたすら写経していました。写経が終わればすぐにでも持ち帰り帰国するつもりでした。彼の写した教典は自分の命に替えても持ち帰るという信念を持っていました。 栄叡、普照、玄朗は高僧鑑真に伝戒の師僧を紹介してもらうべく揚州に向かいます。揚州は長安、洛陽に次ぐ大都会で、鑑真は大明寺にいました。三十数人の弟子を背後に控えさせて鑑真は栄叡たちと向かいあいます。栄叡は日本が伝戒の師僧を求めることに、いかに熱心かということを説きます。 鑑真は<日本からの要請に応えて、たれか渡って戒法を伝える者はないか>と弟子たちに問います。暫くして祥彦(しょうげん)という僧が日本に渡ることの難しさを言いますが、鑑真は<法のためである。たとえ渺漫びょうまんたる滄海そうかいが隔てていようと生命を惜しむべきではあるまい。お前たちが行かないなら私が行くことにしよう>といって、鑑真と鑑真に伴う十七人の高弟の渡日が決まりました。 渡日することは決まりましたが、素行収まらず学行も乏しいといわれていた高麗僧如海が渡航から外されると思い、日本僧たちが海賊の一味だとお上に訴えたために捕らわれてしまったのです。長い取り調べの後に釈放されたものの、日本僧のみ帰国させることになり鑑真らの渡日計画は頓挫してしまいました。この如海という人物、鞭打たれて還俗させられるのですが、人間くさくて興味をおぼえます。 鑑真は失敗したものの、決心は少しも変わっていませんでした。玄朗や業行という日本僧はじめ何人かの脱落者は出たものの、着々と準備を進めその年の12月には再び渡日船を出すことにしました。しかし、途中嵐に遭い岩礁の上に座礁してしまいます。飢餓と渇きに3日間苦しみますが、漁船に米と水をもらい、5日後に海上警備の官船に救助されます。 その後、再度渡日を試みますが、南洋に流されてしまい海南島に漂着します。3度失敗し、危険な目に遭いますが鑑真の決心は変わりませんでした。3度目の失敗の後、鑑真は失明します。それでも日本に戒法を伝える為、遣唐使の帰国に伴って渡日を試みます。この頃、唐の国内に鑑真を日本に行かせることに反対の意見があり、密かに連れて行かなければなりませんでした。 4艘で出発しましたが、日本にたどり着いたのは3艘だけでした。大使清河と阿倊仲麻呂の乗った船は安南の沿岸に漂着して、多くの者が土人に殺されたり病没し十余人の生存者のみが長安にたどり着きました。業行と彼の写した膨大な量の教典は行方しれずでした。 ★関連:大原總一郎『母と青葉木菟』の中の<鑑眞和上>をお読みください。 2016.06.30 |
日 本 仏 教
|
諡号伝教(傳敎)大師
生地:近江国滋賀郡古市郷(現:滋賀県大津市)もしくは坂本
最澄は、日本の天台宗の開祖であり、伝教大師(でんぎょうだいし)として広く知られる]。近江国(現在の滋賀県)滋賀郡古市郷(現:大津市)もしくは生源寺(現:大津市坂本)の地に生れ、俗吊は三津首広野(みつのおびとひろの)。唐(中国)に渡って仏教を学び、帰国後、比叡山延暦寺を建てて日本における天台宗を開いた。
古賢禹王は、一寸の暇を惜みて、一生の空しく過ぐる事を歎勧せり。因無くして果を得るは是の処あることなく、善なくして苦を免るるは、是の処あることない。 伏して願うくば解脱の味独り飲まず、安楽の果独り証せず、法界の衆生と同じく妙覚に登り、法界の衆生と同じく妙味をふくせん。 6月4日比叡山中道院で死す。わが国における天台宗の開祖。桓武天皇の帰依があつく、比叡山をひらき延暦寺をたてた。 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.93 2020.08.16 |
|
空海は、平安時代初期の僧。諡号は弘法大師。真言宗の開祖。 日本天台宗の開祖最澄と共に、日本仏教の大勢が、今日称される奈良仏教から平安仏教へと、転換していく流れの劈頭(へきとう)に位置し、中国より真言密教をもたらした。能書家でもあり、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられている。 仏教において、北伝仏教の大潮流である大乗仏教の中で、ヒンドゥー教やゾロアスター教の影響も取り込む形で誕生・発展した密教がシルクロードを経て中国に伝わった後、中国で伝授を受けた奥義や経典・曼荼羅などを、体系立てた形で日本に伝来させた人物でもある。 ※参考図書:ひろ さちや著『空海入門』(祥伝社)昭和59年3月30日 第3刷発行。ひろさちや著『密教の読み方』(徳間書店)
<色は匂へど散りぬるを 我が世誰れぞ常ならむ 有為の奥山今日越えて 浅き夢見し酔ひもせず>
<生まれ生まれ生まれて、生の始めに暗く、死に死に死んで、死の終わりに 冥し>
23 空海とうどん伝説 '92 冬の号(朝日新論説委員室)+株式会社英文朝日 1993年3月25日 第1刷 P.54 (1992.10.26) 香川県善通寺市に、空海の愛犬を葬ったと伝えられる塚がある。九世紀の初頭、唐の長安に留学した空海がはるばる天竺(インド)から連れ帰った犬の墓だという。空海の郷里、香川県の郷土歴史研究家、杉峰俊男氏が『讃岐うどん』十四号で紹介していた。 それによると、空海はめい薬を求めて天竺へ行ったが、警戒が厳しい。入手した薬草の種三粒を自分の足の肉を割いて隠した。関所の番犬がほえ立てたが何も見つからず、番人は犬を倒す。空海があわれんで、それを蘇生させた。 薬草は実は小麦。日本に持ち帰って広め、うどんの普及のもとにもなった、というのが伝説の骨子だ。当時の長安は、中央アジアやインドとも往来の盛んな東西文化交流の中心地だった。うどんは別としても、多くの技術や新知識が、使節や留学生を通じて日本に続々と流れ込んできた。 その長安で、空海はサンクリットやインドから伝わった密教を学び、帰国後に真言宗の開祖となった。そのかたわら学校や水利施設を作り、筆の製法まで伝授した。 二年ほどの留学で、これほどの成果を収めたのだ。後世に弘法大師とたたえられる空海の多才はもちろんのことだが、長安が発していた文化の光りの強烈さを想起させる。 考古学調査によると小麦の日本伝来は弥生初期以前らしい。うどん発祥の地も中国だが、この方も空海より早く原形が伝わったようだ。犬塚について書いた杉峰さんもそれらを承知の上で<千年以上も信じ、伝えてきた人々のロマンを大切にしたい>という。 人々の知恵と熱情こそが文化をはぐくみ、伝える。長安という地めいは、そんな文化交流の大切さを改めて感じさせる。長安、今の西安のめい物料理は形や具もさまざまなギョーザだ。同じ材料をめぐる先人の努力を土台に、日本のうどんともつながってぃる。 2021.10.09記す。
23. PRESERVATION OF MYTHOLOGY In Zentsuji City, Kagawa Prefecture, there is a grave that is said to have been made by Buddhist master Kukai for his dog. master Kukai for his dog. Kukai was sent to the Chinese city of Chang-An at the beginning of the 9th century during the great series of scholarly, religious and cultural exchanges for which the T'ang Dynasty is remembered in Japan. Kukai found the dog on a journey to India, and eventually brought it all the way back to Japan, where it is buried in Zentsuji. The story is told in the 14th issue of "Sanuki Udon" by Toshio Sugimine, a local historian of Kagawa, the birthplace of Kukai. According to Sugimine's article, Kukai went to India in search of legendary medicines, but was received with little more than suspicion in that country. Finally given three grains of a medicinal herb, he cut open his leg and concealed them beneath the skin. As he was passing through a border-post on his way back to China, a dog scented the contraband and barked, but was unable to find the herb. The disgusted border guard beat the dog and let him for dead but Kukai took pity on the dog and nursed him back to life. The "herbs" turned out to be wheat. Kukai brought the seeds back to Japan, where he proclaimed the virtues of the plant far and wide, eventually leading to the popularity of udon noodles. Those are the "bare bones" of the legend of the origin of udon in Japan. At the time, the city of Chang-An, at the crossroads of India and Central Asia, was a busting center for exchange of culture between East and West. Besides the food udon, much technology and knowledge came to Japan through the multitude of diplomatic envoys, students and priest scholars. In that city, kukai studied Sanskrit and secret teachings that had been transmitted from India. Kukai founded the Shington sect of Buddhism upon his return to Japan. Besides that achievement, he built schools and irrigation networks, and taught how to make the brush used for Japanese calligraphy. All these arts and crafts he learned in a period of two years. Of course, Kukai was the genius who achieved eternal fame with his posthumous name Kobo Daishi, but this still attests to the brilliance of the cultural richness of the city of Chang-An. Archeologists tell us now that wheat was first brought to Japan sometime prior to the early Yayoi Period. Udon noodles were also born in China; the basic recipe for these appears to have come to Japan considerably before the journey of Kukai. Scholars have never proved that Kukai actually went to India. In his article about the grave of the dog, Sugimine is well aware of the facts, but cautions that we must respect the myth believed and handed down by the generations over the millennium gone by. People's wisdom and passion are themselves what spawn culture and keep it alive. The name Chang-An stirs and renews our respect for the importance of cultural exchange. Chang-An, or as it is presently called, Xian is now known for its fried dumplings("gyoza" in Japanese) of many shapes and contents. Thanks to the efforts of our forebears with exactly the same ingredients, gyoza are related to udon noodles. Copy 2012.10.10 |
|
<足ることを知らば貧といへども富となづくべし、財ありとも欲多ければこれを貧となづく。> 『往生要集』より。 2009.12.12 |
『碧眼禄』の編著(980~1052年)
|
▼『碧巌禄』(岩波文庫 上) 第七則 法眼、慧超に答う
<慧超、和尚に問う、如何なるか是れ仏>。
第一二則 洞山の麻三斤
僧、洞山にに問う、<如何なるか是れ仏>。
第二六則 百丈の奇特の事
僧、百丈に問う、<如何なるか是れ奇特の事>
2008.5.24 |
|
一 我は後世たすからんと云う者に非ず。ただ、現世に、先づあるべきようにてあらんと云う者なり。 |
『無門関』の編著
|
▼『無門関』 一 趙州の子 趙洲和尚、因みに僧問う、<狗子に還って仏性(ぶつしょう)有りや>。州云く、<無>。
無門曰く、<参禅は須らく祖師の関を透 頌(じゅ)に曰く、
狗子(くす)仏性、全提正令(ぜんていしょうれい)。
四十五 他は是れ阿誰(あた) 東山の法演禅師が言われた、<釈迦弥勒といえども彼の奴隷にすぎない。ではいったい彼とは誰のことか言ってみよ>。 無門は言う、<もし彼をはっきり見届けることが出来たなら、たとえば街の雑踏の中で自分の親爺かどうかなどと他人に聞く必要はな いであろう>。 頌(うた)つて言う、 他人の弓はひいてはならぬ、 他人の馬は騎ってはならぬ、 他人の落ち度は言ってはならぬ、 他人のことは知ってはならぬ。 2008.5.23 参考:『柳宗悦 妙好人論集』の中の<奴>の考察に引用されている。
|
|
示して云く、先師全和尚、入宋せんとせし時、本師叡山明融阿闍梨重病起こり、病床にしづみ既に死せんとす。其の時かの師云く、我既に老病起こり死去せんこと近きにあり、今度暫く入宋をとゞまりたまひて、我が老病を扶けて、冥路を弔ひて、然して死去の後其の本意をとげらるべしと。時に先師弟子法類等を集めて講評して云く、(中略)師の命を背て宋土に行ん道理有りや否や。各の思はるゝ処をのべらるべしと。時に諸弟子人人皆云く、今年の入宋は留まらるべし。師の老病死巳に極れり。死去決定せり。今年ばかり留りて明年入宋あらば、師の命を背かず重恩をもわすれず。今一年半年入宋遅きとても何んの妨げかあらん。師弟の本意相違せず。入宋の本意も如意なるべしと。時に我れ末臘にて云く、仏法の悟り今はさてかふこそありなんと思召さるゝ儀ならば御留り然あるべしと。先師の云く、然あるなり、仏法修行これほどにてありなん。終始かくのごとくならば、即ち出離得度たらんかと存ずる。我が云く、其の儀ならば御留りたまひてしかあるべしと。時にかくのごとく各の総評し了て、先師の云く、おのおゝ評議、いづれもみな留まるべき道理ばかりなり。我れが所存は然あらず。今度留まりたりとも、決定死ぬべき人ならば其に依て命を保つべきにあらず。亦われ留まりて看病外護せしによりたりとも苦痛もやむべからず。亦最後に我あつかひすゝめしによりて、生死を離れらるべき道理にあらず。只一旦命に随て師の心を慰むるばかりなり、是れ出離得度の為には一切無用なり、錯て我が求法の志しをさえしめられば、罪業の因縁とも成ぬべし。然あるに若し入宋求法の志をとげて、一分の悟りを開きたらば、一人有漏の迷情に背くとも、多人得度の因縁と成りぬべし。此の功徳もしすぐれば、すなはちこれ師の恩をも報じつべし。設ひ渡海の間に死して本意をとげずとも、求法の志しを以て死せば、生生の願つきるべからず。玄奘三蔵のあとを思ふべし。一人の為にうしなひやすき時を空く過さんこと、仏意に合なふべからず。故に今度の入宋一向に思切り畢りぬと云て、終に入宋せられき。先師にとりて真実の道心と存ぜしこと、是らの道理なり。『正法眼蔵随聞記第五 十二』(岩波文庫) 参考:明全は入宋して在宋三年にしてかの地に入滅する。道元は随順して入宋したり。 私見:当時は本文に<渡海の間に死して本意をとげずとも>と、かかれているように大変な命がけの宋への求道である。是を現代の学問の研究者にあてはめて、研究の為に外国えの長期留学しようとするとき、親が死の床にありて頼まれたときどのように考えるだろうか。明全和尚のような覚悟が果たして出来るものだろうか。次の機会を待つべきか悩むことであろう。 2010.06.05 |
|
▼『正法眼蔵』
<弁道話> 一 初心の弁道すなわち本証の全体なり。(岩波文庫一) <第一 現成公安> 一 自己をはこびて万法を修証するを迷いとす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり。(岩波文庫一)P.54 二 仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは自己をわするゝなり。自己を忘れるゝといふは、万法に証せらるゝなり。万法に証せらるゝといふは自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(ごしゃく)の休歇なるあり、休歇(きゅうけつ)なる悟迹を長々出ならしむ。P.54 三 たき木、はひとなる、さらにかへりてたき木となるべきにあらず。しかあるを、灰はのち、薪はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位に住して、さきありのちあり。前後ありといへども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて、のちありさきあり。かのたき木、はひとなりぬるのち、さらに薪とならざるごとく、人のしぬるのち、さらに生とならず。しかあるを、生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆゑにふ生(ふしやう)といふ。死の生にならざるを、法輪のさだまれる仏転なり。このゆゑにふ滅といふ。生も一時のくらゐなり。死も一時のくらいゐなり。たとへば、冬と春とのごとし。冬の春となるとなるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。P.55 四 心身に法いまだ参飽せざるには、法すでにたれりとおぼゆ。法もし心身に充足すれば、ひとかたはたらずおぼゆるなり。法もし身心に充足すれば、ひとかたはらずとおぼゆるなり。P.57 五 一事をこととせざれば一智に達することなし <第十 大悟> 一 <さとりをう>といはば、ひごろはなかりつるとおぼゆ。<さとりきたれり>といはば、ひごろはそのさとり、いづれののところにありけるぞとおぼゆ。<さとりになれり>といはば、さとり、はじめありとおぼゆ。かくのごとくいはず、かくのごとくならずといへども、さとりのありやうをいふときに、<さとりをかるや>といふなり。(岩波文庫一)P.218 <第十四 空華> 一 梅柳の花は梅柳にさき、桃李の花は桃李にさくなり。空花の空にさくも、またまたかくのごとし。P.274 二 春は花をひく、華は春を引くものなり。P.275 <第十六行持上> 一 師の普説するときは、わが耳目なくして見聞をへだつ。耳目そなはるときは師ときをはりぬ。P.342 二 師はあれどもわれ参ふ得なるうらみあり、参ぜんとするに師ふ得なるかなしみあり。P.343 <第十六 行持下> 一 香厳禅師いはく、P.358 百計千方只身の為なり 知らず、身は是れ塚の中の塵なること。 言うこと莫れ白髪に言語無しと、 此れは是れ黄泉伝言の人なり 二 山田脱粟(さんでんだつぞく)の飯 P.386~P.387 野菜淡黄(たんくわう)の齏(しい) 喫することは則ち君の喫するに従(まか)す 喫せざれば東西に任す。 三 勧君すらく帰郷すること莫れ、P.387~388 帰郷は道行われず。 並舎の老婆子(ろうばす、 汝が旧時のなを説かん。 <第十七 恁 麼> 一 身すでにわたくしにあらず、いのちは光陰にうつされてしばらくもととゞめがたし。紅顔いづくへかさりにし、たづねんとするに蹤跡なし。つらヽ観ずる所に、往時のふたたびあふべからざるおほし。P.403 <第二十一 授 記> 一 自己の有、必ずしも自己の見るところならず。自己の知るところならず。然あれば、今の知見思量、分に能わざれば、自己にあるべからずと疑著作すること莫れ。(岩波文庫二)P.67 <第二十二 全 機> 一 現(げん)にあらず、生は成(じょう)にあらざるなり。しかあれども、生は全機現なり、死は全機現なり。しるべし、自己に無量の法あるなかに、生あり、死あるなり。(岩波文庫二)P.83 二 圜悟(えんご)禅師克勤和尚<云(いはく)、<生也全機現、死也全機現>。P.84 <第二十五 渓声山色>
一 画にかけるもちひは、うゑをふさぐにたらず。われちかふ、此生(ししょう)に仏法を会(うい)せんことをのぞまじ、ただ行粥(あんしゅく)飯(はんそう)とならん>といひて、行粥飯して年月をふるなり。(岩波文庫二)P.111
二 大潙のいはく、<われ、なんぢがためにいはんことを辞せず。おそらくはのちになんぢわれをうらみん>。P.111
<第二十八 礼拝得髄>
一 <ふ是風動、ふ是幡動、ふ是心動。>P.167
<第三十一 諸悪莫作>
一 <諸悪莫作、衆全奉行、自浄其意(じじょごい)、是諸仏教〈諸悪〉作(な)すこと莫れ、衆全奉行(ぶぎょう)すべし、自ら其の意を浄む、是れ諸仏の教えなり〉>。P.230
二 生をあきらめ死をあきらむるは仏家一大事の因縁なり。P.244 <第三十三 道 得> 一 この年月、ちからをあはせて道得せしむるなり。P.283 <第四十三 諸法実相> 一 雪峰いはく、<尽大地は是れ解脱門なり、人を曳けども肯て入らず>。P.440 <第五十一 面 授> 仏々祖々、面授の法門現成(げんじょう)せり。これすなは霊山(りやうぜん)の拈華(ねんげ)なり、嵩山(すうざん)の得髄なり。黄梅(わうばい)の伝衣(でんえ)なり、洞山の面授なり。これは仏祖の眼蔵面授なり。悟屋裡(ご おくり)のみあり、>餘人(よじん)は夢也未見門在(むやみけんもんざいなり。(岩波文庫三)P.143 道元が二十六歳のとき妙高台に焼香礼拝、初めて天童山の新住持=古仏如浄に参見した時のことである。 里見弴は<面授の法門現成<(げんじょう)せり>を、なまじか意味を考えずに、幾度もただなんとなく誦(くちずさ)んでいるうちには、その間の、清潔な温味(あたたかみ)は、いくぶんかなりとも近づけるような気がして来るだろう。われわれは在家としては、それで十分なことだと、彼の著作『道元禅師の話』の中で述べている。 2008.2.28 <菩提薩埵四摂法> 一 むかひて愛語をきくは、おもてをよろかばしめ、こころをたのしくす。むかはずして愛語をきくは、肝に銘じ魂に銘ず。しるべし、愛語は愛心よりおこる、愛心は慈心を種子とせり。愛語よく迴天のちからあることを学すべきなり、ただ能を賞するのみにあらず。(岩波文庫四) 参考:岡 潔(数学者)はその著作『月 影』の中で道元禅師について次のように述べている。 私は一九二九年から一九三二年(満州事変勃発の翌年)までパリに住んでみて(私は一九〇一年にうまれたのです)、なにか非常に大切なものが一つここに欠けていると感じて、帰朝してからは真剣に、真の日本人とはどういうものかを調べ始めました。 私はまず次にいう芭蕉によって、自分は日本人であるという一応のの自覚を得ました。しかし私にはふじゅうぶんと考えましたから、すぐ引き続いて調べたのがこの道元禅師でした。主として『正法眼蔵』(岩波文庫、上・中・下)それを主として上巻で調べ始めました。それも、その刹那までは少しもわからなかったのが、その刹那以後は皆わかるというわかり方でわかりました。ただしここにいう<わかる>とは、普通のわかるではありません。 2008.5.30 <生 死> 一 生死<(しょうじ)の中に仏あれば生死なし。又云く、生死の中に仏なければ生死にまどはず。(岩波文庫四)P.466 二 ただ生死すなはち涅槃とこゝろえて、生死としていとふべきもなく、涅槃としてねがふべきもなし。このときはじめて生死をはなるゝ分あり。P.467 三 生より死にうつるとこころうるは、これあやまりなり。生はひとときのくらゐにて、すでにさきあり、のちあり。かるがゆゑに、仏法の中には、生すなはちふ生といふ。滅もひとときのくらゐにて、又さきあり、のちあり。これによりて、滅すなはちふ滅といふ。生といふときには、生よりほかにものなく、滅といふとき、滅のほかにものなし。かるがゆゑに、生(しゃう)きたらばたゞこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべし。いとふことなかれ、ねがふことなかれ。P.466 四 仏となるに、いとやすきみちあり。もろもろの悪をつくらず、生死に著するこころなく、一切衆生のために、あはれみふかくして、上をうやまひ下をあはれみ、よろずをいとふこころなく、ねがふ心なくて、心におもふことなく、うれふることなき、これを仏となづく、又ほかにたづぬることなかれ。P.468 道元の偈 五 十 四 年 照第一天 打箇(ぼつ)跳 触破大千 渾身無覔 活落黄泉 2099.11.18 |
|
一 されば先ず臨終の事を習ふて後に他事をならふべし。 この言葉は、曹源寺敷地内の大光院に掲示されていた。 ★<先ず臨終の事を習ふて後に他事を習ふべし>の説明 日蓮聖人は、六十一年のご生涯において、実に多くのお手紙・論文を残されています。 これらを、<ご遺文>、<御書>、<祖書>、<祖訓>、<御妙判>と尊称し、大切にお守りしています。 そのお言葉は、人々の人生の指針でもあります。 今日はその1つを、 『妙法尼御前御返事』の一節より。 <夫(それ)以(おもん)みれば日蓮幼少の時より仏法を学び候ひしが、念願すらく、人の寿命は無常なり。 出る気(息)は入る気(息)を待つ事なし。 風の前の露、尚譬へにあらず。賢きも愚(はかな)きも、老いたるも若きも、定め無き習いなり。 されば先(まず)臨終の事を習ふて後に他事を習ふべしと思ひて、一代聖教の論師・人師の書釈あらあら勘がへ集めて、此を明鏡として、一切の諸人の死する時と並に臨終の後とに引き向いてみ候へば、少もくもりなし。> <訳>:人の命は無常である。出る息は入る息を待つこともなく、風に吹かれて落ちる露よりもはかないものである。 賢い人も愚かな人も、老いた人も若い人も、いずれが先とか後とか定まったものではない。であるから、まずは<自分の死>、<自分が臨終を迎えた時>のことを深く考えなければならない。(後段は略) 臨終のことを考えなさい、自分の死相(死に顔)を考えなさい、と説いておられます。 <死>のことを学ぶと同時に、 今をどう生きるか、命の大切さを考え、今日ただ今を悔いのないようしっかりと生きなさい、ということではないかと思います。 <一期一会>という言葉も、このような意味合いになります。今という時間と、そばにいる家族や仲間との絆をもっともっと大切にしていきたいですね 2017.11.29追加 |
|
無外如大( むがい-にょだい)(1223年~1298年)鎌倉時代の尼僧。 臨済(りんざい)宗。安達泰盛(あだち-やすもり)の娘で,金沢顕時(かねざわ-あきとき)にとついだ。顕時が霜月騒動に連座し配流(はいる)されたのち,無学祖元(むがく-そげん)(1226-86)についてまなぶ。のち京都景愛寺の開山となった。臨済宗で最初の尼とされる。別号に景愛,無著(むじゃく)。 女の目、外国からの目 禅の老師といえば誰しも男性をイメージすることだろう。どうして女がなってはいけないのかという人もあるし、禅の<十牛の図>にしても、どうして男性の老人と子どもなのか、女性ではいけないのか、と言った人もある。 ところが、女性の老師は立派に存在している。それも鎌倉時代のめい僧、無学祖元(むがくそげん:仏光国師)の高弟として師のなから一字を与えられ後継者と認められた。無外如大(むがいにょだい)がそのひとである。 彼女は七十歳をこえる長寿を保ち、文字通りの老師として臨済宗の発展に寄与した。 私がこんなことを知ったのは、アメリカ人の女性の日本学研究者、バーバラ・ルーシュさんの『もう一つの中世論』(思文閣出版)によってである。 ルーシュさんは、女性であること、外国人であることの特性をうまく生かして、日本の学者がこれまでの伝統に縛られて見落としがちなところに目を向け、素晴らしい本を書かれたが、無外如大に対する注目も、そのひとつである。 これほどの人物であるにもかかわらず、これまで研究されることが少なかったのは、女性であるがゆえに無視されてきたのではないかとルーシュさんは慨嘆されておられるが、<老い>の問題を考えるうえにおいても、<女の目><外国からの目>でみられることによって、また新しい展望がひらけるのではないかと思われる。 ★河合隼雄『<老いる>とはどういうことか』P.244~P.245による。 |

一遍上人が若い頃法燈国師について修行していた。国師は上人の心を練磨するため<口を開かずに、念仏を称えよ>と出題した。上人はこの問題を幾日も幾日も考えた末、ようやく心眼を開いたので、その心境を次の次の歌に託して国師に示した。
となふれば、仏も我もなかりけり。
しかし国師は、その心境をまだ未熟であるとし、更に心境を練るように命じた。そこで上人は、数日間、練って、練って練りぬいて、
称うれば、仏も我も、なかりけり。
と国師に示した。国師は<う―む>と一声を発して、即座に印可証明した。
*田里亦無著<道元禅入門>P.57
参考2:■二度とない人生だから 2009.11.05 |

▼伝光録(岩波文庫)
一 一念萬年。一毫穿衆穴。登科任汝登科。抜萃任汝抜萃。これをきゝて師即ち省悟す。
|

世間の食物、その味一種にあらず。その中にいずれを本と定むべきや。人の天性まちまちなる故に、甘き物をこのむ人もあり、辛き物を愛する人もあり。もし我がこのむ味を本として、余味は皆いたずらなりと言わば愚人なるべし。法門もまたまたかくのごとし。衆生の性欲〔性質と欲望〕同じからざる故に、わが心にはこの法門を貴しと思うといわば、さも有りぬべし。もしわが思いを本として、この法門は正理なり、余の法門は皆真実にあらずと〔固〕執せば、これ邪説なり。 (夢中問答)
*桑原 武夫編『一日一言』―人類の知恵― P.160 2010.05.22 |
|
関山慧玄 かんざん-えげん1277*1361* 鎌倉-南北朝時代の僧。 鎌倉末期から南北朝期の禅僧。臨済宗京都妙心寺の開山である。信州(長野県)の出身で,鎌倉建長寺の南浦紹明につき修行し,京都紫野の大徳寺で 宗峰妙超 に師事し嗣法する。美濃(岐阜県)の伊深に隠棲していたが,花園上皇が花園の離宮を禅院として妙心寺を開創するにつき宗峰妙超の推挙により開山となる。しかし,慧玄はまもなく妙心寺を出るが,観応2(1351)年妙心寺に再住する。禅の修行を第一にした禅僧で,妙心寺の経営には関知せず,方丈(自室)の雨漏りを見て修繕費用の寄進を申し出た高梨氏に対し,二度とくることはならないといい,袈裟の鐶は藤の蔓を用いたなどの話が伝えられている。語録や頂相(肖像)などは残っていない。延文5(1360)年84歳で寂するが,慧玄は旅支度をして授翁宗弼に行脚に出るといい,妙心寺の風水泉という井戸のそばの樹の下で訓戒を述べ(<無相大師遺誡>),それが終わると立ったまま息をひきとり亡くなったという。<参考文献>荻須純道『日本中世禅宗史』 <関山慧玄国師の逸話>。 <雨漏りと小僧とザル対応> - 禅僧の逸話 - 臨済宗妙心寺派の本山、妙心寺の開山(初代住職)である関山慧玄禅師には、ちょっと有めいな逸話が残っている。 雨漏りとザルの話、といえばピンとくる方がいるかもしれない。 当時、妙心寺の伽藍は相当古かったのか随分と傷んでいたようで、ある雨の日に雨漏りがした。 ぽた、ぽた、ぽたり。天井から滴り落ちた雨粒が畳を濡らしていく。 <おーい、雨漏りだ。急いで何か雨水を受けるものを持ってまいれ>住職の関山禅師は小僧たちに声をかけた。 はい、と返事をした小僧たちは、蜘蛛の子を散らしたように雨を受けるものを探しに行った。 すると1人の小僧が、間髪入れずに戻ってきた。 見ると、手にはザルが握りしめられている。 返ってくる早さから察するに、何か特定の物を探したのではなく、おそらくそこら辺にたまたま置いてあった物を?んで持ってきたのだろう。 <和尚さん、持ってきました> 小僧はすぐに雨漏りをしているところへ歩み寄ると、手に持っていたザルをそっと畳の上に置いた。 屋根から漏れた雨水はザルのなかに落ち、そしてザルの編み目から漏れ出ていった。 しばらくすると他の小僧たちも戻ってきた。 桶など、それぞれ何かしらの雨受けになるものを持参している。 小僧らは雨漏りをしているところへ近寄りそれらを置こうとしたが、しかしその場所にはすでにザルが置かれていた。 なぜ……ザル? <なんでザルが置いてあるんだ> <ザルで雨を受けることができるもんか> <誰だ、こんな無駄なものを持ってきたやつは> 小僧らはザルを持って一番最初に戻ってきた小僧を口々にバカにした。 そんな小僧らの言動を黙って見ていた関山禅師は、すっくと立ち上がって小僧たちの傍へ歩み寄った。 そして、ザルを持ってきた小僧にこう言った。 <よくザルを持ってきたな。これを待っていたんだ> ザルで雨を受けることができるか、このバカ者! と叱られるものとばかり思っていた他の小僧らは、関山禅師の言葉に驚いた。 なんでザルを褒めるんだろう? ザルの編み目から雨がこぼれていってしまっているのだから、ザルを置いたところで無意味なのに。 小僧らは紊得がいかない。 すると関山禅師は呆然と突っ立っている他の小僧らのほうを向いた。 <お前たちは何を持ってきておるのだ、バカ者!> 驚いたことに、桶などを持ってきた小僧らが、逆に叱られてしまったのである。 一体どういうことなのか。 小僧らはまったく訳がわからないのであった。 これが関山禅師の有めいな逸話、雨漏りとザルの話である。 <思考と非思考> この話を読んだ人は例外なく疑問に思うことだろう。 なぜ、関山禅師はザルを持ってきた小僧を褒めたのか。 私は相当ふ思議に思った。 桶を持ってきて褒められるのなら理解できるが、ザルでは用をなさない。 雨を受けとめられていないではないか。 理解ふ能だ。 が、今ではこう考えるようにしている。 以前、車の事故で、赤信号を無視したトラックが交差点に進入し、横から走ってきた車と出会い頭に衝突し、そのまま歩道に乗り上げ、歩いていた母子とぶつかるという、痛ましくやるせない惨事があった。 その事故の際、母親は子どもを抱きしめるようにかばったのではないかと言われていた。奇跡的に子どもは軽傷で済んだからだ。 ただ、母親は亡くなった。 平穏な日常が音を立てて崩れてしまった家族の心情を想うと、無念でならない。 母親は、とっさの判断で子どもをかばうように抱きしめた。 いや、それは判断ではなく、思考を介さない、まさにとっさの行動であったに違いない。 猛スピードで突っ込んでくるトラックとまともにぶつかれば、人などあっけなく突き飛ばされてしまう。 全身を強打して死んでしまうかもしれない。 もし考えるという過程を踏めば、トラックに対して防御は得策ではない。 何とかして避ける方法を選択するだろう。 しかし、母親は避けることはしなかった。 仕方のないことである。 トラックが自分たち目がけて突っ込んでくるなど思いもよらないし予想できるはずもない。 突然そんな状況に直面して、考える余裕なんてない。 だから避けることはできなかった。 けれどもそのかわりに、子どもをかばった。 その行為をバカにする人は1人もいないはずだ。 たとえトラックに防御で立ち向かうことが<思考の上では>得策ではなかったとしても。 とっさの判断というものは、理屈ではない。 そこには善悪がない。搊得もない。打算もない。 じっくりと頭で考えれば<否>という答えが出るかもしれないが、その<考える>というプロセスを抜きにして、ほとんど本能的に瞬時に反応をしなければいけない時が、人生にはある。 あの母親のように。 人はまっさらな心で想起したものを、次の瞬間に思考を織り交ぜて搊得勘定して考えてしまう生き物だ。 そして禅は、その思考の末に形成された判断や行動を、時に激しく戒める。 思慮以前の心を呈してみよと、一直線に心臓を突いてくる。 禅は間髪を入れない対応を褒めるが、それは思慮分別が加味されていない、心そのままの在り方が表れているからだろう。 子をかばった母親が、もしもとっさに防御をするのではなく、子どもを抱き上げて横に飛びトラックをかわしたとしたら、それはそれで称賛される行為となったのだとは思う。 瞬時に物事を考えて判断し行動することも、もちろん悪いことではない。 禅はそのような判断を否定したいのではなくて、判断できなくてもいいのだということを言いたいのである。 冷静に考えれば<否>なことでも、瞬時にそう体が動いたのなら、それはそれでいいのだと。たとえ非常識と言われるようなことであっても、瞬時にそうしたのなら、それを否定する道理はないのだと。 <雨を受けるものを持ってまいれと言った師匠> < とっさにザルを手に取った小僧。 それは、とっさに我が子を守ろうと抱きしめた母親の行為と、ある意味同じ種類のものなのではないか。 車から守れるかどうか、トラックとぶつかったらどうなるか、そんなことを考えるのではなく、自然と体がそう動いたというところにこそ、理知を超えた生命のふ思議なはたらきがある。 理屈ではない。 ザルを持ってきた小僧さんを褒めたのは、その行為に理知を超えたものをみたからではないだろうか。 だから関山禅師はあくまでもザルを褒めたのではない。 間髪入れずにザルを?んだ小僧の行動をこそ褒めたのである。 ちょうど、とっさに我が子を守ろうとした母の行動のように。 <禅問答はわけがわからない> ただあべこべのことを言っているだけのように聞こえ、そこには論理も何も存在しないように思える。 煙にまくようなことばかり口にする。 単に、適当なことを口走っているだけのようにも聞こえる。 しかしそれは、言外の言を感受することができないというだけのことだったんだと、いつからか思うようになった。 師から発せられた一つの言葉に何年も取りかかって言外の言を見出そうと、かつての禅僧らは努力してきた。 血が滲むほどに。 それを、一読してわけがわからないから意味のない言葉なんだと思うのは、どう考えたって早計というもの。 そう思うようになってから少しずつ、禅の言葉が味わい深いものになってきた。 人に知ってもらいたい言葉なんだと思うようになった。 雨漏りにザル。 とっさにザルを持ってきた小僧を、どうしてバカにすることができるだろう。 <言葉によって迷わされ、言葉によって悟る> <関山慧玄の仏性> 上野の国立博物館・平成館で、妙心寺展が行なわれている。なにしろ開山(初代住職)である関山慧玄禅師の六百五十年遠諱を記念しての一大イヴェントだから、これまでなかなか人目に触れなかった国宝、重要文化財なども一堂に展示される。この機会に是非とも多くの皆さんに体験していただきたいと思う。 どんな展覧会でもそうだが、鑑賞するというのは、モノを見て、その背後にうごめくコトを体験することではないかと思う。 いきなりややこしい話で恐縮だが、これは禅の本質に関わることなのでご容赦いただきたい。 あらゆる表現は、特定の体験(=コト)のなかから、その全体を象徴するようなモノを作り、あるいは抽出する作業であるわけだが、たとえばこうして文字化してみてもそれは<コトのハ>、つまりコトの端、コトの葉だから、体験そのもののごく一部に過ぎないのだと、昔の人は認識していた。どだい自分も含めて変化しつづけたコトが、言葉というモノでそう簡単に表されるはずがないではないか、と。だから禅は、ふ立文字を標榜するのである。 しかし意識は常にモノを探している。文字に写し、彫像を作り、絵に描き、調度品や装身具を作るばかりでなく、自分の体験に何らかのイメージを持たせ、形あるモノにしようとする。つまり体験としての流動を、なんらかの形で固定しようとするのである。 なにかイメージをもった時点で、すでに純粋なコトではありえないわけだが、禅は、意識のそんな本性を知りつつ、モノに紛らわされず、純粋なコトを体験せよと迫るのである。 関山慧玄禅師は、岐阜の山中で農家の手伝いなどしながら悟後の修行をされていたとき、花園法皇に妙心寺の開山として上洛するよう要請される。そしてどうしても固辞できないと知り、それまで共に働いてきた農民たちに別れを告げると、<なにか教えを>とせがまれる。そこで禅師は、近くにいた農民夫婦の頭を引き寄せてゴツンとぶつけるのである。<痛っ>当然二人はそう叫ぶ。すると禅師は、<そこだ。それを大事にせよ>と言って去ったらしいのである。 <痛っ>と叫んだ刹那には、いのちそのものの紛れもない反応であった。その体験は、私も世界もまだ渾然として分かれない状のコトだと云えるだろう。しかし人は、次の瞬間にはもう渾沌たるそのコトを分別し、好悪の感情も交え、<ひとごと>としてのモノに変えて語りだす。モノとしてのコトの葉は、すでにコトの残骸でしかない。だから関山禅師は、分別や好悪の起こるまえの<ひとごと>でない体験を大事にせよと、言い残されたのではないだろうか。 妙心寺はそのなのとおり、厳しい修行によって<妙なる心>を相続してきた寺である。妙なる心とは、モノ化されていない変幻自在なコトとしての心と云えるだろう。 当然、開山像という木や紙でできたモノも、我々には単なるモノではない。本山にお祀りしていたときにも毎朝お粥を供え、お参りしていたわけだが、じつは東京にお出ましになってからも、東京の和尚さんたちによって毎朝交代でお膳が供えられ、焼香され、お経が唱えられている。いわば拝むという行為によって、それはコトでありつづけ、目前の人と交錯しながらなにかを体験させつづけているのである。 意識の本性がモノ化しようとする以上、あらゆるコトがモノ化していくのは防げない。しかしそうではあっても、我々はその流れを遡上し、モノが溶けだしてコトを感じるとき、感動する生き物なのではないだろうか。 遮二無二拝んでくれと、申し上げているわけではない。 自分の今の現実のままに、無心でモノたちに向き合ってほしい。国宝であれ重文であれ、単に知識というモノを増やすだけでなく、なにか一つにでもどっぷり向き合い、時を忘れてあなただけの体験をしてほしいのである。 関山慧玄禅師は語録も調度も殆んどなにも残さなかった。際だって没蹤跡(もっしょうせき)を貫いた禅僧と云えるだろう。その周囲にこれだけのモノがあるのもふ思議ではあるが、そうしたモノたちの歴史を掻き分け、禅師が<そこだ>とおっしゃった命の躍動を体験していただきたい。 上野のれん会妙心寺法堂(はっとう)の天井には、狩野探幽の描いた雲龍図がある。探幽は、当時の管長さんから<実際に龍に逢ってから描いてくれ>と言われ、三年坐禅してから描いたと云う。龍とは、あらゆる概念や感情抜きの、モノ化するまえの自然のことだろう。 妙心寺展が多くのモノによって示すのは、結局のところ我々のなかの幅広く奥深い自然の力にほかならない。 探幽の龍はむろん運び込めないけれど、要はあなたの中の龍に、この機会に出逢ってほしいのである。 <禅の修行において> <悟り>に囚われてはいけない。得たら捨て得たら捨てていく。転じて行く。禅にも囚われない。禅は禅でないのが禅である。 <西田先生の偉い所は、先生は禅をやりながら禅に捉えられなかった。僕は禅に捉えられた。>一三〇ページ。(我見解<好雪片々ふ落別処><鉢裏飯、桶裏水>) <無>の動性>(<無>は単なる<無>ではありません) 例一、 <世尊、霊山会上に在って、花を拈じて衆に示す。是の時、衆皆な黙然たり。惟だ迦葉尊者のみ破顔微笑す。> 世尊云く、<吾に正法眼蔵、涅槃妙心、実相無相、微妙の法門有り。ふ立文字、教外別伝、摩訶迦葉にふ嘱す。> 例二、 柴山全慶老師(南禅寺、アメリカの大学で講義、学僧)、師匠は河野霧海(南針軒)。 全慶老師、学問が好きで勉強三昧。作務が身につかず、それを見た霧海老師、廊下を拭いてみせた。色即是空、空即是色の般若心経を実際に説いてみせた(ふ立文字教外別伝)。今も師匠から受けたあの痛棒が身に染みる。 例三、 <世尊拈花>の現代版。何時だったか先生のお宅で大拙先生と一緒になったことがある。何かの話のうちに、大拙先生は、禅は要するにこういうもんだと言って、前のテーブルをガタガタ動かされた。西田先生にはそれが余程面白かったのであろう。その後も、外の人々のいる席上で、 <君も居たから知っているだろう>と私の方を顧みながら、<大拙が言ったことだが、禅は要するにこういうもんだ>といって、やはりテーブルをガタガタ動かされた。 無の動性にもとづく諸性格を総称して<幽><妙>という。<心随萬境轉 轉処実能幽> 天台僧<教外別伝の禅如何>、大燈国師<八角の磨盤、空裏を走る> <八角の磨盤、空裏に走る> 大燈国師のこと 正中の法論と碧巌録 正中二年(1325)皇室や公家の間に地盤を得た禅宗と教外別伝の<禅宗>に疑問を持つ旧仏教側との間に宗教討論が行われた。 旧仏教側は比叡山の玄慧法師等九めいが出席した。 禅宗側からは南禅寺の通翁鏡円と大燈国師の二めいが出席し宮中清涼殿で行われた。 まず両者それぞれに一問一答の対決が行われた。 玄慧法師が言った、<教外別伝の禅とは如何?> 大燈国師が答えた、<八角の磨盤、空裏に走る> 玄慧の問いは教外別伝の禅とは何かがこの宗論の最大の論点であったことを示している。 大燈の答え<八角の磨盤、空裏に走る>はそれに答えるものであった。 八角の磨盤とは八頭の牛馬に引かせる大掛かりな石臼とも、八角の空飛ぶ古代武器とも言われる。どんな堅いものでも打ち砕き粉砕するものである。 大燈の答えは斬新で気迫あふれるものである。旧仏教側はこの答えに圧倒された。 やがて次の僧が一つの箱を捧げて出てきた。 大燈が言った、<これ何ものぞ?> 僧が答えた、<乾坤の箱> 大燈は竹蓖で箱を打った、<乾坤打破の時如何> 僧は黙って引き下がった。 この問答で玄慧法師は敗北を認めたと言う。 2017.12.07 |
|
<極楽は皆身にあるわけだから、西ばかり拝んでいては浄土へゆけるはずはない> 無常迅速、生者必滅の理を説く法語にも、<いにしえは道心をおこす人は寺へ入りしが、今はみな寺をいづるなり。見ればぼうずにちしきもなく、坐禅をものうく思ひ、工夫をなさずして、道具をたしなみ、坐敷をかざり、我慢多くして、ただころもをきたるをめい聞にして、ころもはきたるとも、ただとりかへたる在家なるべし。 水上 勉著『一休』あとがき 九歳から仏門に入って、得度した寺が臨済派の相国寺(京都)で、足利幕府が僧録司を置いて官寺の総元締としたお寺であることがわかるのは、還俗してからだが、わずかのあいだにしても、塔頭をニ寺転々し、瑞春院、玉龍庵に童行、喝食の生活をおくった。じつはこれが一休に関心をもつ遠因になった。玉龍庵は、一休の友人南江宗沅の首座をつとめた寺であったし、和尚連の口から折にふれて、<一休和尚は……>とよくきかされた。だから、子供じぶんから、天皇の子でありながら小僧をしていたその人に少なからず関心はあった。この関心の持続は、寺を逃亡して三十六年、五十六歳まであった。その間には一休について書かれた諸先輩の童話、伝記、研究書など読んだが、日がたつにつれてふ思議がつのった。最大の関心事は森女のことで、本文にもふれたが、ふ在説を主張する護法学者への私なりのふ満である。といって私に何らかの新資料があるわけではない。混沌とした中世に人の行実の真を求めることのふ可能であることはよくわかっているが、それなればまた、私の勝手な空想もゆるされる気もして、分ふ相応な仕事とわかりつつも、一休の生涯に筆を染めてみたくなった。というのが動機である。出来ばえは読者にゆだねばならないが、書いていて、縁拭きに精出していたこましゃくれた小僧周建の、手にひびきらせていたろう姿が、私の少年時と重なって、見たこともない和尚が親しく思われる。田舎大工の小伜が、天皇の子に親しみをもったというのも、仏門に入ったありがたさかもしれぬが、これは、私の人生にとって稀有のことであり、正直、そのこましゃくれた小僧の行方を追って、八十八歳の臨終にさしかかったときにはほっとした。約二年かかって書き終わったが、その間、絶えず激励して下さった私の小僧時代の恩師市川白弦氏、同窓の柳田聖山氏に深謝しなければならない。とりわけ、柳田氏には、難解な唐宋の偈文の解釈につき多々教えを受けた。参考資料とした諸先輩の著書は、すべて本文中に記しておいたが、それらの研究書がなくては、もちろんこの長編の成立はなし得なかったのである。また書籍編集局の佐藤優氏には、『海』連載時に資料その他のことで過重の世話になり、上梓にあたっても労を得た。巻尾を借りて諸氏に厚くお礼を申し上げる次第である。 昭和五十年三月二十日
水 上 勉
*水上 勉『一 休』より
参考:一休禅師 臨済宗の僧で、後小松天皇の子とする説もある。形式主義に陥った当時の禅宗を強く批判する一方、木刀を差して町を歩くなど奇行も多かったと伝えられる。茶人や能楽師、連歌師ら多くの文化人と交流し、漢詩集<狂雲集>などを残す。88歳で亡くなるまで約25年間を酬恩庵で過ごした。一休寺は後年つけられた通称。とんち話は史実ではなく、江戸時代の読み物<一休咄(ばなし)>で広まったとされる。(朝日新聞の記事より) 2009.11.06、2017.11.04追加。
いにしえは道心おこす人は寺にはいりしが、今はみな寺をいずるなり。見れば坊主に知識もなく、坐禅をものうく思い、工夫をなさずして道具をたしなみ、ころもは着たるも、ただとりかえたる在家[俗人]なるべし。けさ衣を着たりとも、衣は縄となりて身をしばり、袈裟は鉄のしもく[撞木]となりて、身をうちさいなむと見えたり。
袈裟ごろも ありがたそうに 見ゆれども これも俗家の 他りき本願
11月27日死んだ室町末期の臨済宗の僧。京都、大徳寺の住職であった。書画、詩、狂歌にたくみで、諸国を漫遊し、奇行をもって世人をおしえた。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.196 *青木雨彦監修『中年博物館』(大正海上火災保険株式会社)P.92 2020.06.22 追加。 |

<心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、心得たるなり> これは浄土真宗中興の祖といわれる蓮如の言葉で、本来は信仰について語られたものである。しかし私はこれを人生を生きる上でのひとつの指針として考えてきた。様々な職業或は芸能の場合でも、これを大切な心構えと言っていいのでなかろうか。<心得たと思う>というのは、自分の職業や、またひろく真実の探求において、これでもう大丈夫だと安心し、満足している状態を指すのである。そういうのは、実は心構えとして間違っているのだ。<心得ぬと思う>こと、つまりどこまでも努力しても、まだまだ自分は未完成だと自覚していることが、ほんとうの心構えだという意味である。 自分の信仰は立派だ。自分の仕事は完成した。そいう自己満足におちいった刹那に、人間は必ず堕落するのである。すべての道は、涯のないものだ。人間として究極に達するということはあり得ない。まだまだ自分はだめだと思って努力する。それは一生そうでなければならないというのである。
*亀井勝一郎人生論集(大和書房)の<未完成の自覚>P.82
2008.05.08,追加:2012.01.25
<心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、こころえたるなり。> 『蓮如上人御一代記聞書』(『真宗聖典』894頁) 標記の言葉は、本願寺第八世である蓮如(1415-1499)の言行を集録した書物、『蓮如上人御一代記聞書(れんにょしょうにんごいちだいきききがき)』の中にある文章の一部です。この中で、蓮如は次のように言います。 心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、こころえたるなり弥陀の御たすけあるべきことのとうとさよと思うが、心得たるなり。少しも、心得たると思うことは、あるまじきことなり。(自分はよく心得ていると思っている者は、実は心得てはいないのです。自分はまだよく心得ていないと思い、教えを聞く者は心得た者なのです。この愚かな自分が阿弥陀仏に助けられることが、なんと尊いことであるかと喜ぶのが心得たということなのです。ですから少しも自分は心得たと思うことがあってはなりません) 蓮如は、<心得たと思う>人は、実は心得てはいないのだと言います。これは一体どういうことなのでしょうか。ここで言う<心得たと思う>人とは、もう十分に自分は<分かった>という思いの中に閉じこもってしまっている人のことを指します。この人は、自分が得た知識を頼みとし、謙虚に教えを聞く姿勢を失っているのです。ですから、蓮如は、自分の知識や能力を頼みとするのではなく、阿弥陀仏の智慧に教えられて、自分は十分に心得ていない愚かな身だと自覚すべきであるということを伝えようとしているのです。 この蓮如の言葉は、私たちの学びの姿勢を問い直す力を持った言葉であると思います。私たちは様々な教えを学んでいく上で、<分かった>という体験を持つことがあります。しかし、その体験はもしかしたら単なる<思い込み>や<勘違い>であるかも知れません。更に言えば、問題なのは、それが<思い込み>や<勘違い>であると、なかなか自分自身では気づけないことなのです。だからこそ、謙虚な姿勢で教えを聞き、学び続けることが求められるのでしょう。 今回、卒業を迎えた人は、大学における学業の集大成として、論文をまとめられました。まとめることによって、これまで明確でなかった事柄が十分に理解できたという人もいるでしょう。一方で、何が分かっていないのかがいよいよ明らかになったという人もいるでしょう。いずれにせよ、大学で取り組んだ課題が、一生の課題となる場合も少なくありません。自分はもう十分に心得たと慢心することく、自らの課題を探究していく姿勢が、未来を切り開くことにつながるかもしれません。そのように私たちの歩みを促す言葉として、標記の言葉を受け止めたいと思います。 2015.10.25,追加 |

柳田 聖山『禅と日本文化』(講談社学術文庫)<禅と日本人の死生観>に記載されている利休の辞世について記載する。 利休は一五九一年の二月、時の権力者で、かつかれの茶道の支持者であった太閤秀吉から、突如、切腹を命ぜられる。その日、利休は心許す少数の客を屋敷に招いて、最後の茶会をひらく。主客の一人一人にとって、緊張にみちた一日であった。 利休は、その席で使った道具を、すべての客に遺品として分かち与えるが、彼が生涯愛用して来て、しかもその日の茶会を記念する、最高のめい器であった主茶碗だけは、誰にも与えないで、その場で粉々に打ちくだいてしまう。 そして、人々が席を起つと、茶人としての上着を脱ぎすてる。その下には、すでに純白の死に装束と、腰の短刀が用意されていた。 人生七十、 力囲希咄(りきいき とつ)。 吾這寶剣、(わがこのほうけん)、 祖佛共殺。(そ ぶつともにころす)。 利休は、こんな辞世の詩と共に、従容として切腹したというのである。 辞世は、自分の生涯を総括する四字四句の、短い漢詩の形をとるのが決まりであった。禅僧たちの末期の作法からくるものだが、当時、京都の禅の本山で、茶人たちの最も人気のあった、大徳寺に参禅していた利休は、自分の生涯を自ら用意した短刀に譬えて、禅の祖師も仏もみな斬り尽くして、独り完全な無の世界に入るというのであろう。 ここに使われている言葉は、いずれも中国の禅の本にあるものばかりである。とくに第二句の<力囲希咄>は、はげしい動作に伴う、エイといったかけ声を意味する。あの茶碗を、木端微塵にくだいた勢いと、といってもよいであろう。利休は最後にそんな音声と化して、何人も介入できない虚無の中に、身を隠すわけである。もはや、俗物太閤の命令など、とどきようもないものである。 利休は何故、切腹したのか。今も明確な事情は判らないが、むしろかれの死の理由がふ明ゆえに、この切腹の場面だけが、極端に美化される傾きがあって、じつは、ここに問題があるのである。 先ほどもいったように、かつての日本の武士は、死に臨んで辞世をつくることを禅僧たちに学んでいる。(略) 利休にもまた、同じ誇りがあって、それがかつての日本人の、文化水準を計る尺度の一つとなっていたわけである。 2017.08.29 追加。 |
|
臨済宗の禅僧。徳川家光が沢庵に帰依したが、弟子に伝法を許さず、彼の法系は一代で絶えた。 ▼『ふ動智神妙録』 これは、柳生宗矩(やぎゅうむねのり)という侍のために剣の道を説いたものである。その中<有心(うしん)の心、無心の心>とあります。それはこういうふうに説かれています。 <有心の心というのは妄事といっても同じことであり、有心とは文字通りにアルココロと読むのであり、何事につけ心が一方に止まって動かぬことになり、心に思うことがあってあれこれの考えが生ずることになるのを有心の心というのである>(古田腫紹欽)『禅語仮な法話』大蔵出版刊) つまり<有心の心>というのは、小さな自分にとどまってしまう、ということです。<面白くない>とか<どうしてこんなことになるもだろう>という具合に、心が一か所にとどまって迷ったりすることです。 では<無心の心>は何かというと、沢庵は、 <無心の心というのは前にいった本心と同じ事であり、一つ所に固まり定まる事がなく、あれこれ考えも何もなくなった時の心で、それが体のすべてにひろがり行きわたった心のことを無心というのである。何処にも止め置かない心のことである>(同前) 松原哲明編『東京原宿辻説法』P.179 2008.7.6
食事でおいしく食べるには 沢庵宗彭但馬国出石(現兵庫県豊岡市)の生まれ。 沢庵和尚と徳川家光のお話を紹介します。(インタネット) ある日、沢庵和尚は、徳川家光に<和尚、余は近頃何を食べても、味がなくて困る。なにか口に合うものがあれば食べさせてくれ。>と求められました。 <それはおやすい御用でございます。明日午前10時ごろ、拙僧のところへおいでください。 もっとも当日は、私が主人で殿は客、わがままを言われても困ります。それだけはご承知ください。また、どんな用があってもご中座されません様お願い申し上げます。>と答えました。 家光は喜んで帰っていき、翌日家光は沢庵のところへやってきました。 時は、12月下旬、夜明けごろ降り出した雪で一面の銀世界でありました。 沢庵は家光を茶室に案内し、<しばらくお待ちを。>と引き下がってしまいます。 ところが待てど暮らせど一向に和尚は出てこない。 朝の10時から待たせておいて、昼になっても現れない。3時になっても現れない。 家光が腹が減って目が回りそうになった頃、和尚が出てきて、<遅刻致し恐れ入ります。沢庵手製の料理、何卒ご賞味ください>と、御膳を差し出しました…。 お膳を見ると、黄色いものが二切れ皿に乗り、椀が添えてあるばかり、他には何もない。椀の蓋をとってみたが、中には飯が入っており、湯がさしてありました。それでも家光は腹が減ってたまらない。 <和尚、馳走になるぞ。>と大急ぎで椀を抱え込み、カツカツと食べ出しました。 <おかわり> 家光はようやく腹が一杯になったとみえて、やっと箸を置きました。 そして、<時に、和尚。この黄色いものは一体何であるか>と問うと、<それは大根の糠づけでございます。>と沢庵は答えました。 <ほほう>と、家光がすっかり感心してしまった時、沢庵はおもむろに姿勢を正してこう言いました。 <上様は征夷大将軍という御位、人間の富貴この上なく、されば結構なるものを毎日お膳に供えて、それに口がなれて旨味がございませぬ。つまり口が贅沢になっているからでございます。故に今日、空腹待ち、かような粗食を差し上げたのでございます。> 上様は怒りもなく、<美味じゃ>とのこと。 <以後、空腹になるのを待ってお食事されるとよろしゅうございます>とそれとなく将軍を戒めました。 後日、家光は沢庵を招き、貯え漬けならぬ<たくあん漬け>として一般にもこれを貯えさせました。 2015.09.25 |
|
一 今時の人、佛法は悟らねば用に立たぬと思ふ也。其儀に非ず。仏法と云は、只今の我心をよう用ひて、今用に立てる事なり。 『驢鞍橋』 江戸初期の教団外的禅僧鈴木正三(俗めいは正三)の語録。三巻。正三は徳川家康・秀忠に仕えたが中年で出家し、晩年の1648年(慶安1)から55年(明暦1)に没するまで江戸に在住して布教にあたった。本書はその言行を門人の恵中(えちゅう)がまとめたもの。正三自身の求道体験に基づいて、二王禅、勇猛禅、果たし眼(まなこ)念仏(一念ふ乱の念仏)、日常の生活のうちに死に習うことを体得しようとする死に習い仏法を勧め、同時代の一般禅僧を手厳しく批判した。さらに隠棲(いんせい)を尊ぶ出家の中世的価値を否定、武士、農民、被差別民に及ぶ世俗の職分に即しての修行を説く。また寺院住持をも幕府の役人にし、仏法によって理想的な統治支配を期する提言などがある。1660年(万治3)に出版された。『『鈴木正三道人全集』全×巻(1962・山喜房仏書林)』 ★プロフィル:鈴木 正三(すずき しょうさん、俗めいの諱まさみつ、道号:石平老人、天正7年1月10日(1579年2月5日)~明暦元年6月25日(1655年7月28日)は、江戸時代初期の曹洞宗の僧侶・仮な草子作家で、元は徳川家に仕えた旗本である。 本姓穂積氏。 通称九太夫、号を玄々軒、正三は法めいである。 法めいに関しては、俗めいの読み方を改めただけと言われているが、俗めいは重三で、正三は筆めいであるとの異説もある。 [出家以前] 天正7年1月10日(1579年2月5日)に三河国加茂郡足助庄(現在の愛知県豊田市(旧足助町))にある則定城主、鈴木重次の長男として生まれる。 長男ではあるが家を継がず、別に一家を興してい... |
|
至道無難・・ 至道(しどう)は無難なり 唯嫌揀択・・ 唯だ揀択(けんじゃく)を嫌う 纔無憎愛・・ 纔(わずか)に憎愛無くんば 洞然明白・・ 洞然として明白(めいばく)

柳田聖山『禅と日本文化』(講談社学術文庫)の説明では、江戸時代のはじめ、十七世紀に、裏長屋みたいなちっぽけな草庵に住んで、士農工商とよばれる四民の、あらゆる階級の人びとを相手に、独自の語りくちで禅を拡めた、至道無難という禅僧がいる。この人のなは、至極(しごく)の道は難いことなど何もないという、古い禅語から来ている。その至道無難が、こんな道歌をよんでいるのである。 生き乍、死人となりて、なりはてて、思いのままにするわざぞよき 思いのままとは、要するに自由にふるまうことだが、生き乍ら死人となるというのだから、生きることも死ぬことも、共に自由と言うのが、この人の生き方であった。いわば、いちど死んだ男として、生きつづけたわけである。それは単に手ばなしの、勝手自由というのではない。人間にとってもっとふ自由な、生死を自由に生きるという。高い意味をもっている。死から生をみる、新しい眼があってのことである。 昔、十四世紀のはじめ、室町時代の初期に、京都の妙心寺を開創した関山恵元玄(かんざんえげん)という禅僧は、旅立ちの姿で、立ったまま入滅(死んだ)したという。かれは、人が生き死にのことについてたずねると、<我が這裏(しやり)に生死(しょうじ)なし>と答えている。わしには、生死などというものはない、というのである。生死自由というのが、中世の日本人の禅の、さいごの姿であった。P.44 無難という人は、これといった寺をもたない、いわば一種の無教会主義者であった。従来の伽藍(が らん=寺院)仏教に、はげしい批判をなげつけている。P.45 2008.6.18 参考:三祖鑑智僧璨は『信心銘』を残されている。その冒頭に<至道無難、唯嫌揀択>と記されている。私見ではこの最初の言葉をいただいているのではなかろう。
2008.7.18
2010.01.07 記之。
金光寿郎『東洋の知恵・内観』(光雲社)P.272~P.232より この至道無難に、次の有めいな歌があります。私たちの自我意識のこだわりを測定する基準になる歌ではないかと思っています。
なにもおもはぬ物から、なにもかもするがよし。(という前書きあって)
私はこの歌をはじめて聞いたのが、二十数年前の鈴木大拙先生の講演会でした。
仏と云うも、天道と云うも、皆人の心を云也。其のたしかなる事知りたくば、人々人の知らぬあしき事をして、親も子も兄弟も知らねども、おのれおのれの心、よく知りて、心にいためられ苦しむ事、たしか也。これにてよく合点して、我身のとがをわが心にみせて、悪をさるべし。外よりたとえどのようの悪をいいかけたりとも、おのれおのれの心のしらぬ時は、くるしまぬなり。かかるゆえに、仏と云うは心の事也。 この人は禅の人だとか、念仏の人だという枠を超えたところに、欲望に振り回される自分を離れたほんとうの自分の消息があります。 2011.09.19 記之。 |

▼盤珪佛智弘濟禪師御示聞書 上 盤珪禪師語録:鈴木大拙編校(1622~1693)(岩波文庫) 後水尾天皇の元和八年(西暦一六二二)、播州楫西郡、濱田村に生る。 僧問て曰、それがしは生れ附て、平生短気にござりまして、師匠もひたものいけんを致されますれども、なをりませず。私も是はあしき事じゃと存まして、なをさふといたしますれど、これが生れ附でござりまして、直りませぬが。是は何と致しましたらば、なをりませうぞ。禪師のお示しを受まして、このたびなをしたふ存じまする。若なをりて國元に歸りましたらば、師匠の前と申、又一生の面目とぞんじせん程に、お示しにあづかりたふ存まするといふ。 禪師曰、そなたはおもしろいものを生れ附いたの。今も爰にたん気がござるか。ならば爰へおだしやれ。なをしてしんじやうわひの。 僧の曰、たゞ今はござりませぬ。何とぞ致しました時には、ひょとたんきが出まする。 禪師いはく、然らばたん気は生れ附ではござらぬ。何とぞしたときの縁に依て、ひよつとそなたが出かすわひの。何した時も、我でかさぬに、どこにたんきが有るものぞ。そなたが身の贔負故に、むかふのものにとりあふて、我がおもわくを立たがつて、そなたが出かして置て、それを生れつきといふは、なんだいを親にいひかくる大ふ孝の人といふもので御座るわひの。人々皆親のうみ附てたもつたは、佛心ひとつで、よのものはひとつもうみ附はしませぬわひの。しかるに一切迷ひは我身のひいきゆへに、我出かしてそれを生まれつきと思ふは、おろかな事で御座るわひの。我でかさぬに短気がどこにあらふぞいの。 一切の迷ひも皆是とおなじ事で、我まよわぬに、まよひはありはありはしませぬわひの。それをみなあやまつて、生れ附でもなき物を、我欲で迷ひ、気ぐせで、我出かして居ながら、生れ附とおもふゆへに、一切事に附てまよはずに、得居ませぬわひの。何ほど迷ひがたつとければ、一佛心にかえて迷ひますぞいの。みな一佛心の尊ひ事をしれば、迷ひたまふてもまよはぬがほとけ、迷はぬがさとりで、外にほとけになりやうはござらぬわひの。身どもがいふことをそばへよつて、とつくり能のみこんで、きかしゃれ。(以下略)(岩波文庫)P.9~10. ▼盤珪は禅者として特異なそんざいであり、その生涯の仕事は禅を庶民の教えとして弘め、禅を日常化するにあったが、そのための教化の方法を殆ど説法によったことが注目される。文書をもってすることも説法の一つであろうが、ここで説法というのは口説でもってしたことを指す。つまり目に訴えるのではなくて耳に訴えて説いた。無知無学の者にとっては読むことよりは確かに聴くことは易しく、それに盤珪の説法が誰にでも理解できる平生の話し言葉でされたものであったとすると一層やさしものであったに違いない。易しい説法であれば聴衆の集まる可能性は高く、盤珪のある場合の説法には参徒千三百人を数え、盤珪の生涯を通じて弟子の礼を執ったもの、<上は侯伯宰官より下は士庶子衆、男女民隷に至るまで五萬余人>(『行業曲記』)とまでいわれている。解説:ふ生禪(P.285) より。 なおふ生禅について詳しく知ろうとする人は鈴木大拙先生の『盤珪のふ生禅』(鈴木大拙選集第四巻)及び『禅思想史研究第一――盤珪禅』を参照されたい。 参考:<承応三年(1654年)、師、歳三十三。秋、錫を備前岡山に移し三友寺に寓す>の記事あり。同書P.211 2020.08.10 記之。 |
|
一 一大事と申すは、今日ただ今の心なり
吾れ世の人と云ふに、一日暮らしといふを工夫せしより、精神すこやかにして、又養生の要を得たり。如何ほどの苦しみにても、一日と思へば堪へ易し。楽しみも亦(また)、一日と思へば耽(ふけ)ることあるまじ。一日一日と思へば、退屈はあるまじ。一日一日をつとむれば,百年千年もつとめやすし。一大事と申すは、今日只今の心なり.
坐して死す 末後の一句
死、急にして、道(い)い難し
道(い)わじ道わじ 一大事というは即今只今のことなり。 二 いかほどの苦しみても、一日と思えば堪え易し。楽しみもまた一日と思えば、ふけることもあるまじ。親に孝行せぬも、長いと思う故なり。一日一日と思えば、理屈はあるまじ。一日一日とつもれば、百年も千年もつとめ易し。一生とは長いことと思えども、後のことやら、知る人ぞあるまじ。死を限りと思えば、一生にはたされ易し。一大事と申すは、今日、只今の心なり。それをおろそかにして、翌日あることなし。凡ての人に遠きことを思えば、謀ることあれど、『的面今』を失うに心つかず。 |
|
一 千利休曰く、<寒熱の地獄に通う茶杓柄も心なければ苦しみもなし>と。下の句訂正を要す、改めて来たれ。 二 三合の病に八石五斗の物思いをなすべからず。
坐禅和讃(ざぜんわさん)とは、漢文表記であった坐禅の本質・目的を日本語で解説したもので、民衆にも分かりやすく説いたものである。白隠慧鶴(はくいん えかく)が著した。別めい白隠禅師坐禅和讃(はくいんぜんじざぜんわさん)。
衆生本来仏なり水と氷の如くにて
水を離れて氷なく衆生の外に仏なし
衆生近きを知らずして遠く求むるはかなさよ
譬たとえば水の中に居て渇を叫ぶが如くなり
長者の家の子となりて貧里に迷うに異ならず
闇路に闇路を踏みそえていつか生死を離るべき
夫れ摩訶衍まかえんの禅定は称嘆するに余りあり
布施や持戒の諸波羅蜜念仏懺悔修行等
其の品多き諸善行皆この中に帰するなり
一坐の功を成す人も積みし無量の罪ほろぶ
悪趣何処にありぬべき浄土即ち遠からず
辱なくもこの法を一たび耳に触るるとき
讃嘆随喜する人は福を得ること限りなし
況や自ら廻向して直に自性を証すれば
自性即ち無性にて已に戯論を離れたり
因果一如の門ひらけ無二無三の道直し
無念の念を念として歌うも舞うも法の声
三昧無礙の空ひろく四智円明の月さえん
此の時何をか求むべき寂滅現前するゆえにん
当処即ち蓮華国この身即ち仏なり 参考:曹源寺日曜坐禅会参加者は斉唱しています。 ▼『夜船閑話』
一 我が此の気海丹田、腰脚脚心、総に是我が本来の面目、面目何の鼻孔がある。我が此の気海丹田、総に是我が唯心の浄土、浄土何の荘厳かある。我が此の気海丹田、総に是我が己身に弥陀、弥陀何の法をか説くと、打返し打ち返し常に斯くの如く妄想すべし。
白隠の禅画、異色の構図 大分・臼杵市で発見 2016/4/4 0:03日本経済新聞 電子版 臨済宗中興の祖とされる江戸中期の禅僧、白隠慧鶴(はくいんえかく)が描いた禅画が新たに大分県臼杵市の寺で見つかった。個性的な画風で知られる白隠らしく、著めいな故事を画題にしつつも異色の絵柄といえ、専門家は<白隠の人柄がのぞく>と高く評価している。 臼杵市の見星寺で見つかったのは<慧可断臂(えかだんぴ)図>。署めいや落款は無いが、白隠研究の第一人者である芳澤勝弘・花園大学国際禅学研究所顧問が調べ、筆跡や添え書きの漢文の文言などをもとに白隠の作品と結論づけた。 中国に禅宗を伝えたインド出身の達磨(だるま)に慧可が自らの左手を断ち切り入門を請うた故事を描いている。禅画ではよく描かれる画題で、壁に向かい座禅する達磨に、慧可が切断した手をささげる構図が多い。 一方、この絵は手を切り落とす直前の刀を構えた姿。<腕を断って達磨に進呈し、そのおかげで悟ったというが、せっかくの立派な身体。余計なことを>との漢詩を添えてある。 芳澤顧問は<慧可の悲痛な決意を、禅画らしくひねりつつ反語的に称賛している。白隠が50~60代初めに、弟子に与えたものだろう>とみる。 4月12日から京都市の京都国立博物館で開く<禅―心をかたちに―>で5月1日まで展示する。 |
|
▼『十善法語』 一 羅漢果の人は言先ず笑みを含む。 『十善法語抄』P.27 二 加我数年五十以学易可以無大過矣
<ふ殺生・ふ偸盗・ふ邪淫・ふ妄語・ふ綺語・ふ両舌・ふ貪欲・ふ瞋恚・ふ邪見> <孤弱の者もし驕漫軽躁なれば、自ら身を置く所がない。 <陰陽互いに和合するを、易には交泰となづく。万物が此の処生育するじゃ。古より律呂和せざれば災禍兆す。> <間も全くふ貪欲戒の姿じゃ> <一度の麁(そ)言、一度の傲慢、みな災害の兆しと知るべし。> |
|
『死に問とうない 仙厓和尚伝』堀 和久(新潮文庫)P.279~ 仙崖和尚は廉渓和尚と龍巌首座の介添えで、白帷子に着替えた。無言で、机の前に運べと二人に命じる。 机についた仙崖は、卓上の花瓶の菊に目をとめ、笑みを浮かべ、顔を近づけた。 龍巌和尚が墨をすった。廉渓和尚が紙をひろげて、筆をさし出す。 禅僧が死にのぞんで書き残す遺偈(ゆいげ)である。 筆を持つと、仙崖の背筋がぴんと伸びた。落ちうぼんだ目に力がこもり、一気に筆を運ぶ。 来時知来処 去時知去処 上撒手懸崖 雲深上知処 <来る時来る処(ところ)を知る。去る時去る処を知る。懸崖に手を撒(てつ)せず、雲深くして処を知らず> 花押(かおう)を記して筆を置くと、上体が崩れ、皆に助けられて床へ戻った。 (中 略) 仙崖和尚は微笑した。 (みんな、いつもの通りじゃな……) 仙崖の五感は透きとおっている。すべてが見え、すべてが聞こえる。あの、懸崖の中空で仰いだ雲の光で解脱したように、遺偈を果たした今、新しい悟りを得た心地であった。 (人は、幾度も、大悟見性する。三十八歳の懸崖の放下は、その一つにすぎぬ) 仙崖は微笑した。 枕頭の者は、仙崖和尚の微笑を、臨終間近の痙攣と受け取った。 龍巌首座が身をのり出して、仙崖の耳に口を寄せた。 〈お言葉を!〉 龍巌が印可を求めていることは、仙崖にはわかっている。若い仙崖義梵の切なるまなざしを無視して、師月船禅慧が無言のまま入滅した意味を、仙崖は今、新たにかみしめている。 (また、小さな悟りを得たな……) 仙崖は微笑んだ。 「師よ、お言葉を!《 龍巌禅初がふたたび叫んだ。 「死にとうない《 仙崖は微笑のままつぶやいた。 「な、何とおおせられました《 龍巌は愕然としている。大禅師の最後にあるまじき未練執着の妄言、と感じ、師のためを思う狼狽もみえる。 仙崖の微笑はつづいている。その眼裏に、美しい雲の輝きがゆっくり遠ざかっていく。 「ほんまに、死にとうないのう《 仙崖は眠るように首を折った。 *副題に〈仙崖和尚〉とあるように、軽妙洒脱な禅画で知られ、”東の良寛・西の仙崖”と謳(うた)われた、筑前聖福寺(しょうふくじ)の中興の祖・仙崖義梵の生涯を描いた堀 久作(新潮文庫)の歴史長編より。 私見:引用が長いものとなりました。日曜日坐禅会に参加させていただいている私としては、こころにひびくものをかんじましたので。 2008年3月27日 |
|
僧・播隆が初めて槍ヶ岳を望見したのは、文政6年(1823)6月のことであった。飛騨山脈の霊峰・笠ヶ岳登山を試みた彼は、群山を圧してひときわ高くそびえる槍ヶ岳を眺め、その霊感に打たれ魅せられたのであろう。 天明6年、越中に生まれた播隆は、生涯のほとんどを一介の苦行僧として過ごした。混濁の世俗を捨て仏門に入ったはずの彼だが見たものは、やはり俗界同様のみにくい風潮がみなぎる宗門の内情であった。深山幽谷での修行に入った播隆は、やがて槍ヶ岳(前人未踏の3,180メートルの高峰)開山の悲願を抱くに至る。 天を突き刺すよう鋭峰の頂きに、清浄静寂な極楽浄土への道を発見したからにほかならなかった。 播隆の笠ヶ岳再興登山の頃、信州と飛騨を結ぶ最短の道として飛騨新道(飛州新道とも云う)が工事中であった。これより以前、岩岡村庄屋伴次郎や小倉村の中田又重郎らが飛騨高原郷の本覚寺の椿宗(ちんじゅう)和尚を訪ね新道開削のため飛騨側の協力者を求めていたが、協力者が得られなかったので信州側だけでも工事をしていた。したがって播隆は椿宗和尚を介して信州側の事情を知っていたと思われる。 文政3年(1820) 飛騨新道着工 文政4年(1821) 飛騨新道小倉村馬口(まぐち)より一里奥の羽子沢(現・南小倉)の商人岩まで完成 文政7年(1824) 上口(現・上高地)まで開通。しかし飛騨側は幕領であったため、なかなか許可が下りなかった 天保6年6月(1835) 飛騨側の工事許可され直に着工 8月完成 各地を布教して文政9年(1826)の夏、信州小倉村の鷹匠屋の中田家を訪れ、槍ヶ岳開山の宿願を述べたと思われる。以降、5回にわたる登山行のすべてに中田又重郎は案内を務めることになる。この年は途中までの登山にとどめ。もっぱら頂上へのルート研究に終始した。 初登頂は2年後の文政11年(1828)7月20日のこと。筆舌に尽くし難しい辛苦を重ねた2人が頂上を踏みしめたとき、5色に彩られた虹の環の中に阿弥陀如来の姿が出現した。感動的な御来迎の奇蹟(ブロッケン現象)である。 その後、松本郊外の浄土宗の玄向寺を知り度々世話になり槍ヶ岳に鉄鎖がかけられた時には播隆は玄向寺で病気で療養中であった。中田又重郎の協力がなければ槍ヶ岳開山はなかった。 播隆は開山のために一心ふ乱になった。槍ヶ岳の頂上にかける悲願は、 衆生済度のための開山にあった。己れを律し、ひたすら苦行に励む播隆の法話は民衆の心を打ち、開山の資へと結びついた。5回にわたる登山の末に彼はあとに続く者の安全を図り、一人でも多く登山ができるように、槍ヶ岳の岩壁に鉄の鎖を懸けるための浄財集めにも奔走した。 当時の鉄は今日では考えられないほどの貴重品であったにもかかわらず、信者達から、はさみ、包丁、鎌などが寄進された。鉄鎖は完成して小倉村へ運ばれたが、当時、凶作が続いたため松本藩は鉄鎖を懸けることを禁止。実現は4年後の天保11年(1840)に持ち込まれた。播隆は病を得て玄向寺で病気療養中であったが、又重郎ら信者達により鎖がかけられた。この時、播隆は55歳の高齢に達し、鉄鎖の懸垂を見届けるかのように大往生した。 播隆は今から約160年前に槍ヶ岳を開山した。"日本近代登山の父" と呼ばれている英人ウェストンが日本アルプスを世に知らしめるより65年も前のことである。 播隆が頂上に祠を建立し、後に来る者のために危険な個所に鎖さえ準備した物語は、<大いなる初期アルピニスト>の尊称を授けられてよいのだが、彼の功績を知る人は余りにも少ない。 いま、JR松本駅前から鋭峰を見つめる上人の孤高のブロンズ像は、<人はなぜ 山に登るのか>という永遠の問いに無言で答えているかのようである。 播隆上人略年譜 天明6年(1786) 越中国新川郡太田組河内(かわち)村(現・富山県富山市河内)に生まれる 文化元年(1804) 19才で出家、京都・大阪で修行する 文政4年(1821) 飛騨高山郷岩井戸村杓子の窟で修行 文政5年(1822) 再度、杓子窟で参籠し越年す 文政6年(1823) 笠ヶ岳登山道を修復して登山 文政7年(1824) 笠ヶ岳4回目の登山で、道標に石仏、頂上に銅像を安置し、対峙する槍ヶ岳を望み槍ヶ岳登山を決意した 文政9年(1826) 槍ヶ岳第1回登山(槍の肩付近まで登り、登路を視察) 案内:中田又重郎 文政11年(1828) 7月20日 槍ヶ岳初登頂、8月 1日 穂高岳にも登頂 天保4年(1833) 槍ヶ岳第3回登山 天保5年(1834) 槍ヶ岳第4回登山。槍ヶ岳に「善の綱」をかける 天保6年(1835) 槍ヶ岳第5回登山 天保11年(1840) 槍ヶ岳に鉄鎖がかけられ、大願成就する。10月21日 美濃国太田にて大往生。55才 2017.12.31 |
|
一 千年ず打基 二 幽鳥弄真如 参考:儀山禅師は岡山市曹源寺の開山:絶外和尚よ14世興盛和尚(儀山 善来)
|
|
困難も人の所為だと思ふとたまらぬが。自分の修養だと思えば自然楽地のあるものだ 資料:磯田道史の<この人、その言葉>(朝日新聞:2011/03/05)より 2011.03.06 |

<惟フニ 今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ 固ヨリ尋常ニアラス、爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル、然レトモ朕ハ 時運ノ趨ク所 堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ、以テ萬世ノ為ニ 大平ヲ開カムト欲ス> 終戦の詔勅の一部です。
その中の<堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ>の言葉について、紀野一義『禅』(NHKブックス)P.202~206 の以下の文章中に記録されていました。 終戦の詔勅と山本玄峰老師 白隠禅師の再来といわれた山本玄峰老師は慶応二年(1866年)紀州湯の峯の西村家に生まれた。二十歳のとき眼病を病み、三年間治療を受けたが、ついにふ治の宣告を受けた。自殺の覚悟で日光華厳滝へ行って果たさず、山を越えて足尾銅山をさまよい、越後で行き倒れになった。幸いに助けられて郷里へ送り返された。その後、四国の霊場を巡拝して、弘法大師の徳にすがって眼病を治そうとし、はだしで七回も四国めぐりをしたが何の感応もなく、七回目のとき三十三番札所土佐雪蹊寺(せつけいじ)で行き倒れとなったのである。明治二十二年(1889年)、二十四歳の年であった。そして雪蹊寺の太玄和尚に拾われた。雪蹊寺では般若心経一つ教えられなかったので、滋賀の永源寺、兵庫の祥福寺、岡山の宝福寺、岐阜の虎渓山などの道場を経めぐって二十五年間修行し、五十歳で漸く成就して、白隠禅師ゆかりの三島竜沢寺に住したのである。それから昭和三十六年六月三日、九十六歳で亡くなられる日まで禅風<挙揚(こよう)しつづけた。 (中略) 昭和二十年の四月頃、太平洋戦争もいよいよ末期症状を呈し、心ある者は何とかせねばならぬと苦慮していたときのことである。多年玄峰老師に師事していた、かつての血盟団(井上日召を盟主とする一人一殺のテロリスト集団)に属していたこともある国士四元義隆氏は、当時壮年團団の要職にあったが、こういう国家危急存亡の時に鈴木貫太郎大将のような人物を玄峰老師に会わせねばならぬと考えて、老師を鈴木大将のもとに案内したのである。当時、鈴木海軍大将は枢密院議長であった。 老師は開口一番、<日本は一刻も早く戦争を止めなければならぬ。今となっては、負けて勝たなければなりません>と言われた。 その頃、負けるということばは絶対的な禁句であった。まさか、のっけからこんなことばが出ようとは四元氏にも思いもよらぬことであったろう。 たった一度の面談であったが、両者は深く肝胆相照らしたと見え、帰りの車中で老師は四元氏に、<鈴木さんは中々大きな人物だ、あの人ならば戦争を止めることができるであろう>と語られたそうである。 それから一週間後、突然、鈴木大将に組閣の大命が降下した。ふ思議な因縁であった。 八月十二日の早朝、一人の青年が火急の用事で老師に会いたいと竜沢寺を訪ねて来た。夜中に三島に着いたが、竜沢寺が分からず一晩中裏山で迷っていたという。 面接したのち老師は手紙を書きはじめられた。書き終わると老師は侍者の平井玄恭師を呼んで、<この手紙は大切な手紙であるから、もし字がまちがっているといけないからから一度読み直してくれ>と言われた。眼のふ自由な老師はよく平井師に代筆させられたが、自分の書いた手紙を見せられることはめったになかったという。 平井師がそれを読むと、その一節に、 <貴下の本当の御奉公は、これからであるから先ず健康に御注意下され、どうか忍び難きをよく忍び、行じ難きをよく行じて、国家の再建に尽くしていただきたい> と書かれてあった。この使者は、鈴木首相が四元氏を通じて、いち早く終戦の決定を老師に通告せられたものであり、この手紙は鈴木首相の苦衷を察して激励されたものであった。 間もなく八月十五日、終戦の詔勅が発せられた。この一節に言う―― <惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス、爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル、然レトモ朕ハ 時運ノ趨ク所、堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ、以テ萬世ノ為ニ大平ヲ開カムト欲ス> この詔勅の起草者が誰であるかは知らぬが、この詔勅の中に老師によって感化された鈴木首相の心意が刻まれているのではないかと平井玄恭師は言われるのでである。 この<忍び難きをよく忍び、行じ難きを行ず>ということばは玄峰老師の創作ではない。このことばは、初祖達摩大師が弟子を訓戒されたことばの中に <諸仏無上の妙道、曠劫(こうごう)に精勤して行じ難きを行じ、忍び難きを忍ぶ、豈(あに)小徳小智、軽心慢心を以て真乗を冀(ねが)はんや>とあるのによったのである。 したがってこの詔勅は達摩大師の禅心と、玄峰老師と、鈴木首相の誠忠と、陛下の御心とが、以心伝心、機を一にして現われたものであると平井師は言われている。わたしもまた、そう思うものである。 玄峰老師の人柄を思わせられて粛然となる逸話である。 *文中の一部の語句はは割愛させていますことをおことわりします。 参考1:山本玄峰老師 参考2:磯田道史<この人、そのことば>(歴史学者・茨木大準教授)朝日新聞2011/02/18の記事 <死んでから仏になるはいらぬこと この世のうちによき人となれ> 2008.4.29書之、2010.08.19再読。
三つのしんせつ <親切・辛切・深切> 山本玄峰老師は<人は三つのしんせつが大切じゃ>とよく言われました。三つのしんせつとは<人に親切、自分に辛切、法に深切であれ>ということです。 人に親切もたんなる親切ではありません。<自分のための心痛はやめて、人のために心配せよ、心痛は心を痛めることだが、心配は人のために心配りをすることである。> 人に親切であるためには己にきびしくあらねばならぬ。それが<自分に辛切>ということであり、 自分にきびしくするには<法に深切>が肝要だ、ということです。 法は、真理であり、仏の教えで、深切は深く近づく、つまり学ぶ上にも深く学び続けなさい、との玄峰老師の教えであります。 仏教を学べば学ぶほど、聞けば聞くほど、自分のいたらなさがわかって、自然に謙虚になります。 <三つのしんせつ>を深く心の中に、いつも持ち続けていきたいと思います。 ★ 玄峰老師のめい言抜粋 文句系 <人間の心は意馬心猿といって、ちょっと油断をすると、心が馬や猿のように飛んで廻るから、何時も自分で自分の心を引き締めておらねばならぬ>。 <一番業の深い、最悪の生物は人間じゃ>。 <木は気を養うものだ>。 <人とたばこの良し悪しは、煙になりて後にこそ知れ>。 <臨済の一喝、ある時は人を殺し、ある時は人を活かす>。 <僧堂にはいろいろな人がくるが、まともな人間は余人に任せる。わしは世間から、あばれもの、やくざもののように見られている連中を世話する>。 <法に親切、人に親接、ご自身に辛切>(松原泰道氏の評伝)。 <隠徳を積め>。<人間は若いときに陰徳を積んでおかないと、歳を取ってから苦労するから、常に陰徳を積むことを考えよ>。 <学問はいくらでもせい。しかし学問を鼻にかけちゃいかんせ、坊主で何より肝腎なのは、道心じゃ。これに学問があれば鬼に金棒さ>。 <わしの部屋は乗り合い舟じゃ。村の婆さんも来れば、乞食も来る。大臣も来れば、共産党までやって来る。皆同じ乗合舟のお客様じゃ>。 <棚からボタ餅の堕ちてくるのを待つように、天命は俟つものではない。天命には従うものだ>。 <お前は、まだ解らぬのか!わしは、世のため、人のためにと念じて修行したことは一度も無い。みんな自分のためにやっているのや>(田中清玄に放った言葉)。 <いや、あんたは座禅組まんでもええわ。あんたは、ええ新聞つくりなはれ。それが、あんたの座禅やで>(老師が進藤次郎氏へ述べた言葉)。 <足の裏と肛門をきれいにしておくのが、健康の秘訣じゃ>。 講話系 <正法興るとき国栄え、正法廃るとき国滅ぶ。よろしく正法を守り仏法を興すべし>、<正法の行われる家は繁栄し、正法の栄える家は隆盛になる。ひたすら正法の久住 に勤めよ>。 <性根玉を磨くのが修行じゃ。人間の性根玉は元来、清浄であるけれども、永らくの宿業によって性根玉が曇っておる。それで元のきれいな性根玉に磨き出してゆかねばならぬのじゃ>。 <性根玉(しょうねだま)が磨かれると、どうなるかといえば、自然に物事の道理が解ってくる。『天下の理に従う者は天下を保ち、天下の理を恣(ほしいまま)にする者 は天下を失う』ということがあるが、物事の道理が解ってくるとろ、一切の物が語法神となって自分を守ってくれる。又何を行っても自然に成功し、成就するようになる。人生において一番 大切なことは、この、なにゆえかは知らぬが、何事も自然に成就することである。そうなるには、性根玉を磨かねばならぬのじゃ>。 <性根玉は磨くだけではいけない。性根玉を自覚し、悟らねばならない。本当に自分の性根玉が解ると、いつでも風呂から上がりたてのような、饅頭の蒸したてのような、ぽかぽかした楽しい気持ちがするものだ>。 <お坊さんは障子の糊のようなものだ>。<どんな立派な障子でも、糊が無かったならば、障子の桟(さん)と紙が離れて障子の役目をしない。しかし外から見ると、糊は 有るか無いか分からない。お坊さんは、この糊のように、人の知らないところで人と人とが仲良くし、一切の物事が円満に成り立って行く様に働いてゆかねばならないのだ>。 <いくら目が見えても、障子一枚向こうは見えない。いくら耳が聞こえても、一丁先の声は聞こえない。目や耳が悪くても、心の眼が開けたならば、世界中を見渡し、天地の声を聞くことができる。葬式や法事をする坊さんにはなれなくても、心の眼が開ければ、人天の大導師になることができる。これは誰にでもできることだ。お前でもやればできる>(太玄和尚が後の玄峰に諭した言葉)。 <『君子、財を愛す。これを集むるに道あり。これを散ずるに道あり』。道理に従わない金の稼ぎ方と使い方は、許されないということですが、財を愛するということの本当の意味は、財物、つまり資源もエネルギーも無駄遣いはしないということですよ。今そのことが本当に分かっている財界人が、一体何人いるでしょうか>(田中清玄「自伝」 の言葉。玄峰の薫陶によるものと思われる)。 <時世には流れと勢いというものがある。これに逆らってみたところでどうにもならん。人が東に走る時には、共に東に走り、西に向かう時には、共に西に向かわねばならんが、泥棒と巡査のようなもので、同じ方向に走っていても、心掛けはそれぞれ違っていなければならん。それと同様に、同じことをしていても、心の置き場所が違わねばならぬ>。 <人間は早く出世することを考えてはならん。若いときにはなるべく人の下で働き、人を助け、人の為に働かなければならん。40歳以前に人の長上に立ってはいけない。40歳以前に出世すると、60、70になって凋落してしまう。『年年に 咲くや吉野の 山桜 木を割りて見よ 花のありかを』という歌があるが、これは人生には根肥(ねごえ、寒中の葉も草も無い時に木の根にやっておく肥料)が大切ということだ。花も葉も無い 寒中に、木の根に肥料をやっておくように、人生には何よりも根肥えが大切なのじゃ。人間は40よりも50、50よりも60と、歳を取るに従って人に慕われ、人の役に立つ人間になり、むしろ喜んで人に惜しまれ、人を教えてゆくような人間 にならなければ ならん。それが為には出世を急がず、徳と知恵と力を養っておくことじゃ>。 <人間は手足を大切にせねばならぬ。炊事や風呂の世話をしてくれる人が旅館の手足じゃ。この人たちが一番大切な人じゃ。『車の功を云うときは輪は与らず』と云って、車で一番大切なものは輪であるのに、人は輪の有り難味を忘れがちである。輪を大切にすることを、よく考えねばならぬ>。 辞世句系 <人が死んだ時、挨拶をするのに、故人は草葉の陰で喜んでおりますとか、地下で安らかに眠っておりますなどという人があるが、人間は死んで身体は地下に行ったり、灰になったりするけれども、この心は地下にも行かねば、草葉の陰にもゆかぬ。天地宇宙に満ち満ちて、生き通しに生きておるのじゃ>。 <わしの浮世狂言も、そろそろ幕にせんならん>、<旅へ出るから、支度をせい>(これが老師の辞世の句となった)。 平成二十九年一月二十四日:S.M.先生のメールより。 |
|
一 壺中消息意中観 ★プロフィル:姓は円山。 道号は全提、諱は要宗、伝衣は室号。 広島福山に生まれる。大徳僧堂の広州宗沢の法嗣。さらに東京白山道場の南隠全愚にも参ず。 明治37年、曹源寺に住し僧堂らを開単。大正8年、大徳寺僧堂師家、同13年、大徳寺派第6代管長に就任。昭和15年示寂。世寿70。 ★関連:曹源寺でのお茶会 |
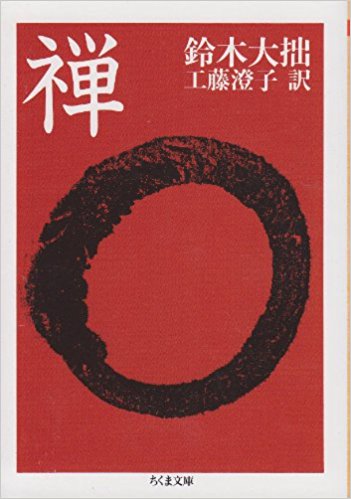
真理とは外にあるもので、感知する主体によって感知されるべきもののように思うのは二元的な考え方で、その理解は知性によることになる。 ところが、禅が言うには、われわれは真理の只中に、真理によって生きているのであって、それから離れることはできない。 玄沙(げんしや)は言う、 <われらは大海の海の中で、頭も水に浸っているようなものである。しかもなお、われわれは、さも悲しげに、水を求めて両手を差しのべているのだと>。 だからある僧が<わたしの自己とは何でしょうかと問うた時、かれはただちに答えた。 <自己をもって、何をしようというのか>。これを知的に分析するならば、かれの意味するところはこうである。 自己について話しはじめる時、われらは必然的に、すぐさま自己と非自己の二元論を打ち立てて、もって理知主義のの誤りに陥る。 われわれは水の中にいる――これが事実である。だからそのままでいようではないか、と禅は言う。 なぜならば、水を求めはじめる時、われわれは自己と水と外的な関係におき、これまで自分のものだったものを取り上げられてしまうからである。 『禅』(ちくま文庫)P.152~153による この本の<はしがき> この書は、自分が過去四五十年間に公にした大小の英文の著作から、主として禅の本質と解せられるものを選出して邦訳し、一小冊子としたものである。それで、この書を一読すれば、大体、近代的に禅の何たるかを知得することができるわけである。その知得底だけで満足すべきでないことは、今さら言うまでもないと信ずる。 2009.08.09 |
|
▼坐禅の姿勢―下腹に力を入れることの是非 坐禅は下腹に力を入れるものだ、というのが通説のようであるが、これは大変な誤りである。この点原田祖岳師が研究し、体験し、その結果を既に四〇年前に発表している。その大略は次の通りである。 <坐禅に下腹部に力を入れるということは、印度にも支那にもなかった。わが国でも昔はなかった。おおよそ、二、三百年前ごろ下腹入力禅を主張するものがふえて、ついには腹入力でなければ悟れぬとまで高唱するに至り、百年ぐらい後にはその信者がしだいにふえた。はなはだしきに至っては、布袋腹をしなければ禅的でない、へその上に杯がのるくらい腹が出てなければ、悟れないというものが出てくるありさまとなった、中古その主張者に白隠がある。五、六〇年前に原担山が極端にそれを主張した。岡田式静坐法もその一派で、なかなか信者が多かったが、皮肉なことに岡田氏は早世した。 小生も二〇歳ごろ担山の下腹入力禅を友人から教わって、やったら、頭が鳴ってたまらない。友人に聞くと、そんんはずはない。モット力を入れろといわれ、更に努力して五、六年続けたが、頭の鳴るのは依然として止まない。その後多忙となったので、坐禅を怠ったらふ思議と鳴らない。これは妙であるあると思ってためしに入力坐禅すると盛んに鳴る。また腸の具合も変になってしまった。そこで下腹入力禅に疑をもった。古い禅書など調べて見ると、入力を勧めたものはない。印度の仏像を調べても腹の肥大したものは一つもない。坊間の達磨の絵はウソだ。 しかし、約十数年間この疑問はとけなかったが、その後西山禾(か)山、毒湛老漢両師の説を聞いて、多年の大疑問は氷解した。要するに下腹入力禅は生理的に全然よくないのである。虚弱な人や、老人や、やせた人が下腹入力すると、たちまちのぼせたり、肩がコッたり頭が痛くなったりする。頑健な者でも入力がすぎると、胃下垂は胸腹一切の内臓に種々悪影響をきたす。坦山門下の熱心な人々は十中八九は病気する。脳溢血等で盛んに死んだものだ。岡田式でも内臓をいためて困っている人々もたくさん知っている。 生理上からも下腹入力は適度に行えば悪くはない。好い面もある。しかし無理に力を入れたち、度がすぎると実に命取りもなるのであるから、十二分に注意しなければならない。ふ快になるようでは止めたほうがよい。また病人は絶対に入力してはならない> 出典:田里亦無著<道元禅入門>P.130~ 2009.11.10 |

●屁ひとつだって、人と貸し借りできんやないか。人人みな<自己>を生きねばならない。お前とわしとどちらが器量がいいか悪いかーそんなこと比べてみんかてええ。 ●目が、オレはカシコイのだけれど、位が低いとも思わず、眉はオレは役なしだけれども、位が高いと思はぬ。仏法の生活とは、このふ知の活動である。山だからというて高いとも思わず、海だとて広いとも深いとも思わず一切合財、ふ知の活動じゃ。野鳥自啼花自笑、ふ干岩下坐禅人ー野鳥は坐禅している人に、ひとついい声を聞かしてやろうと思って鳴くわけでもなく、花も人に美しく思ってもらおうと咲くのではない。坐禅人も、悟りをひらくために坐禅しているのではない。*みなただ自分が自分を自分しているのである。 ●宗教とは何ものにもダマサレヌ真新しの自己に生きることである。 ●ケツの穴だからというて卑下せんでもいい。足だからというてストライキやらんでもいい。頭が一番エライというのでもない。ヘソが元祖だというて威張らんでもいい。総理大臣が一番エライと思うているからオカシイ。目の代わりを鼻ではできぬ。耳の代わりを口はできぬ。みな天上天下唯我独尊である。 ●一切衆生は唯我独尊じゃ、自分が自分を生きるよりほかはないんじゃ。それをどうして見失うたか。 世間の見本が悪いからじゃ。常識といい、社会意識といい、党派根性といい、一切合財みんな見本が悪すぎる。 ●ようつつしんで親だとか先祖だとか背景だとかで、値うちを持たそうとしてはならぬ。金や地位や着物で味をもたせてはならぬ。現ナマじゃ。宗教とは現ナマの自分で生ききることじゃ。 ●世の中はヒトやヨソモンを背景にして自分をエラクみせようとする。味ないものを、皿で味をもたすようなもんじゃ。そんなことで世間では、人間を見失う。 ●宗教には連帯責任というのはない。私ひとりである。 ●凡夫は見物人がないとハリアイがなくなる、見物人さえあれば火の中にまで飛び込む。 ●世の中に表彰ということがあるが、ロクなことではない。表彰されると<ばかりながら・・・・・>という染汚がおこりがちだから。 ●仏道とはよそ見せんこと。そのものにナリキルことである。これを三昧という。飯を食うのはクソをするためではない。クソをするのはコヤシをつくるためではない。ところがこのごろは、学校へ行くのは上の学校へ行くため、上の学校へ行くのは就職するため、と思っている。 ●見わたすかぎり自分ぎりで、自分でないものは何もない。<オレのダルイのを手伝ってくれ。オレのイタイのを代わってくれ>・・・ そうはいかぬ。 ●三昧とは、自分ぎりの自分であり、自性清浄心である。坐禅だけが、自分ぎりの自分であることができる。坐禅のとき以外はいつでも他人より勝れたい、他人より楽しみたい根性がでてくる。 ●われわれはだれでも世界と一緒に生まれ、世界と一緒に死ぬ。めいめい持っている世界はちがうのじゃから。 ●人間は動揺が大好きである。映画の広告の看板を見ても、動揺した顔ばかりがかいてある。仏法は動揺しないことである。ところが世の中では、何のこともないのに、大騒動をやっている。 ●グループ呆けの中でのみしか見えぬのが凡夫の性である。 ●グループができると、その中に麻痺状態が発生して、良い悪いがわからなくなってしまう。われわれが世の中を遠ざかっているのも逃避しているのではない。この麻痺状態をおこしたくないからである。昔から山野に才を求むというが、この山野とは無色透明な世界のことだ。 ●周囲のノボセにノボセにこと。これこそ智慧である。どの思想と、どの組合にもひきこまれてはならぬ。人間みたいな阿呆な奴を相手にせんこっちゃ。 ●<グループ呆けというのがある。そして呆けたのを経験とこころえておる。ひとり透明になって呆けぬことが必要だ。坐禅はこのグループからご免こうむり<シュッケイ>(失敬、出繋、出家)して一人になることである。 ●いま時分の奴のやることは、みな集団をつくって、アタマ数でゆこうとする。ところがどこの集団もグループ呆けばかり、金がほしいというのもグループ呆けなら、エラクなりたいというのもグループ呆け。いわんや党派をつくるなど、グループ呆けの代表である。そんなグループ呆けをやめて自分ぎりの自分になることが座禅である。 ●男女同権という言葉が出てくるのは夫婦喧嘩する時の言葉で、夫婦仲がいい時には、男女同権も何もあったものじゃない。 ●人生とは矛盾である。<あいつあんなことしやがっった>と言いながら、じつは自分もしたいことだったり。 ●人生とは複雑なものである。天から火が降ってくるような戦争の時もあれば、炬燵の中で昼寝しているような時もある。また徹夜で働かねばならん時もあれば、酒を飲んでいる時もある。こういう人生を、仏さまの教えによって、どう始末してゆくかが仏法である。 ●子供がぐずると、<このワカラン奴>と言うて叱っておるが、なあに、そう叱る親たちもみなワカラン奴なのである。これを無明という。 ●教育、教育というて、何かと思えば、みな凡夫に仕立てることばかり。 ●喜怒哀楽の波がたっておらなければ、どうせにゃならぬということはない。 ●動物園の猿をみているより、飼いっぱなしの人間を見ている方がおもしろい。 ●今の世の中の人間は、オカシナことに自分の人生を、しみじみと考えてみたことがない。われわれ過去永劫の昔から、何ぞ煮えきらぬものを持ってきており、<あの人もそうじゃ、この人もそうじゃ>と、それで平気でいるだけである。これがグループ呆けというもんじゃ。人並みでありさえすればいいと思うとる。サトリとは、自分の人生を、しっかりと持つことでなければならぬ。グループ呆けがなくなることである。 ●私は和(わ)ということをいろいろ考えたが、日本のことを<大和(やまと)>というのは、是はいわゆる<大和(だいわ)>ということです。つまり我々の最後の理想、一切の根本的最後の理想がこの<大和(だいわ)>という欲求であらねばならぬわけなんだ。(<禅談>より) ●人と神との和が出来なければ人間と人間との和ということは、皮相なものにすぎない。・・・好きなときは好きだというようなものだ。(<禅談>より) ●この和ということが我々の宗教、道徳、精神文化の理想であって、これより外に理想はないわけである。(<禅談>より) ●たいがい人間のやることは、べつにはっきりした人生観があってやっているのではない。ただ肩の凝った時にトクホン貼ってみるぐらいの、まにあわせの人生観でやっているのでしかない。 ●世の中は、いつもアアシタイ、コウシタイ。してみたら、ナンデモナイことばかりである。 ●乞食でも笑うことがあり、億万長者でも泣くことがある。ナーニ、たいしたことはないんじゃ。 ●仏教というものは<ああ人間に生まれてきてよかった>ということを教えるものである。 ●凡夫は五欲六塵にウロタエテおる。そして好きだとか嫌いだとか、得したとか搊したとか、エライとかエラクナイとか、金があるとかないとか、勝ったとか負けたとか。ところがそんなこと結局ナンニモナラヌということがわかって、そうして最後に<ナンニモナラヌ坐禅をタダスル>ということにゆきつかざるをえないのである。 ●昆虫学者がガラス張りの中に昆虫を入れて、それらが物を食うたり、とも食いしたり、つるんだり、鳴いたりしているのをいちいち見ておるように、われわれ生活のいちいちも、じつは<真実>からすっかりのぞかれておるのだ。 ●われわれにはユガミがホンモノのような顔してひっついていおる。 ●人の物を盗めば、もはやそれだけでりっぱな泥棒に決まっておるのに、今の奴は警官がつかまえ、検事がしらべ、判事が判決をくだし、牢屋へ入ってはじめて罪人になるのだと思うておる。 ●石川五右衛門だけがヌスットであって、ちょっと出来心で他人の物を盗った奴はヌスットではないというわけではない。ちょっと出来心で他人の物を盗ってもりっぱなヌスットである。それと同じくお釈迦さまだけが仏なのではない。仏のマネして座禅すれば、仏である。 ●みんなが違った業(ごう)を持っているのだが、みんな同じく仏さんにひっぱられてゆくことが大切だ。心身脱落とは我のツッパリを捨てて仏の教えを信じ、仏さまにひっぱられてゆくことである。 ●生きておる間はオレとオマエと当然あるかのごとく思うて、背丈比べしたり、お化粧したり大騒ぎする。しかし本当はオレとオマエという二つはないのである。それは死んでみればようわかる。 ●世の中に心を労せにゃならぬことは何もない。妄想分別の何も役に立たぬことが、<役に立たぬ>と決まるだけである。 ●人間はいつの間にか<私>が入ってしまう。<ああよかった>何がよかったのかといえば<私がよかったというだけの話じゃ。 ●どんなことでもならべてみろ。百千あろうとも、どれもこれもゆきづまる。あれもゆきづまる。これもゆきづまる。どの方向へ向いていってもゆきづまるものばかり。そんなゆきづまるものはみんな捨てる。そして何も持っていない。そこが絶学無為(ぜつがくむい)の閑道人である。 ●坐禅とは、われわれのナマニク(生肉)でかためたホトケである。 ●凡夫のナマミを最高にせりあげたのが只管打坐である。 ●飢え死するつもりで坐禅しておればいい。<法輪転ずれば食輪転ず>などということをアテにしておるとワケが違う。法輪さえ転ずれば食輪などどうでもいいんじゃ。 ●<みんな壁の方むいて坐っていてーアレいったい何をやっているんじゃ。坐禅みたいなとぼけたことと言うた奴がおる。ー娑婆から見たら、みんなこれじゃ。 ●<坐禅して何になるか>。 この<何になるか>という問いが第一、中途半端じゃ。テレビが発明されて何になったか? おまえが生まれて何になった? 何になるものは一つもない。 ●仏教的人生観がハッキリしてからでなければ、真の坐禅修行にはならぬ。 ●正法とは無所得ということ。邪法とは有所得ということ。われわれはできるだけ搊をせねばならぬ。 ●どんな奇特玄妙なこと、どんな神秘的体験を味わったと言うても、一生その味わいが続くものではない。 ●<なんにもならんこと>を自信を持ってしておるところが、おもしろくはないか。 ●よう<禅をやって、ちょっとマシな人間になろうと思いまして>と言うてくるのがある。坐禅は人間の修養ではない。人間の廃業である。 ●無量無辺というものが、この人間の欲に物足りたものであるはずがない。 ●坐禅ににらまれ、坐禅に叱られ、坐禅に邪魔され、坐禅にひきずられながら、泣き泣き暮らすということは、もっとも幸福なことではないか。 ●われわれは意識に味をもたしなれているので、無味無色の仏法にはなかなか入りにくい。 ●坐禅しておると、よう妄念がおこりますと言うてくる人があるが、妄念がおこるということがわかるのは、波風がおさまりノボセが下がったからである。 ●妄念を気にするのは、<凡夫>が気にするだけである。 ●坐禅がありがたいと言えば、まだまだ。<お蔭さん>とも何とも言わず、ナントモナイ所にふ染汚(ふぜんな)の坐禅がある。 ●仏法で一番イヤラシイとするのは染汚(ぜんな)ということである。重役とか社長とか会長とかーそういう顔するのが染汚である。この染汚が清められることそれが祇管(しかん)である。 ●坐禅というものはツミアゲルものではない。親鸞聖人も<ツミアゲル念仏>を捨てられたのじゃ。そうして<ツミアゲル修行>を、真宗では<自力根性>と言う。 ●小乗とは自他の心をおこした所にある。小乗の解脱はつくりものである。 ●ええことすると、<ええことをした、した>と、ベッタリそれがひっつく。サトレば<サトッタ、サトッタ>と、またこれがベッタリそれがひっつく。ええことしたり、サトッタリせんほうがええんじゃ。サッパリしておらねばならぬ。足をおろしてはならぬ。 ●凡夫が仏法をみれば、どれだけいっても、仏法で<人間のネウチをつけよう>とするばかり。 ●坐禅はええな。坐禅は大死人の姿じゃから。 ●われわれはサトリをひらくために修行するのではない。サトリにひきずりまわされて修行するのである。 ●仏法は人間のもがきで得られるようなものではない。 ●坐禅しながら仏になろうと思うのは、たとえば故郷へ帰るのに、早く帰りたい早く帰りたいと、汽車に乗っていながら汽車の中でかけだしいているようなもんじゃ。 ●坐禅している時には、自分が成道しているとも何とも思わなくとも、成道しているのである。 ●人間がサトッタら、人間の話である。人間の話でないのが、坐禅である。 ●胃を忘れているのが胃の健全なることである。サトリ、サトリと忘れられないのはサトッテおらぬ証拠じゃ。 ●<サトッタ>と言うても、よう悪魔が通力を得たにすぎん場合がある。 ●<われと仏とスキマがなく、なんともない>という所までいっていないと、人間、気がねがいり、くたびれ、ゆきづまる。 ●サトリとは泥棒が空家に入ったようなもんじゃ。盗る物がない。逃げなくともいい。追いかけてくる者もない。だからはなはだモノタリナイ。 ●サトリ、サトリとーほんに、ちっさいものをサトリと思うているが、そんなものは意識の問題で、意識がちょっと変化したら、もう何でもないもなになってしまう。 ●お釈迦様はおれだけ悟ったとはおっしゃらぬ。有情非情同時成道なのだから。ところがみんなは、そんな連帯的サトリでは物足らぬ。個人持ちの悟り、ご利益が好き。つまり<我>が好きなのだ。 ●よう<これでようございますか、ようございますか>と見解を呈してセガム奴がある。他人に問う間は本物ではない。他人に証明されて、サトッタつもりになっている奴もおる。他人に問わいでも、自分が、<行きつく所へゆきついたら>いいじゃないか。 ●<酒を飲むと酔う>と聞いて<なるほどそうか>と思うて、酔っぱらいのマネをして、酒を飲んだつもりになっているようなサトリがある。 ●今の科学的文化は、人間のもっとも下等な意識をもととして発達しておるにすぎぬということを忘れてはならぬ。 ●文化、文化と言うけれど、ただ煩悩に念が入っただけのものでしかないじゃないか。煩悩のシワが、いくら念が入っても、仏教から言えば、進歩とも文明とも言わぬ。いったいいま進歩、進歩と言うが、どっちゃ向いて進んでいるか。 ●こんなに利口ぶって、こんなにバカになってしもうたのが、人間というバカモノである。 ●智慧とは、行きつくところへ行きついた判断を、つねに持つことである。 ●科学は人からモライモノの上にツミカサネがきくからどんどん進歩しよる。それに反し人間そのものは、人からモライモノできぬし、ツミカサネもできぬから、ちっとも偉うならぬ。だから頑是ない餓鬼が凶器をふりまわすような格好になって、危なうて仕様がない。 ●あほが電子計算機をあやつり、ノロマがジェット機に乗り、気違いがミサイルの発射ボタンをにぎっておる。それが今日の問題なんじゃ。 ●原爆、水爆は味方を救うことができても、敵を救うことはできぬ。敵も味方も救うことができるのは坐禅のみである。 ●ツクリモノの世界は、いつでも変わるに決まっておる。文化とはツクリモノが発達したにすぎぬ。だから文化とは悲劇である。どこへいってもマチガイのないもの。これこそ生命あるものであり、かぎりない幅を持つものである。 ●しずかに落ち着いてよく読んでみれば、マルクスもエンゲルスも<餌の分配>の話でしかない。 ●なんやら人間にはいつも忘れられぬものがある。金がありやがると金があると思い。頭がいいと頭がいいと思い、器量がいいと器量がいいと思って忘れられぬ。そしてこれが門口に出ばって邪魔しよる。 ●<おれ>と言うて、いったい何年つっぱれるか問題である。死ねばすぐこの肉体は品物になってしまう。 ●よう<この目でみた>と確かそうに言いよるが、その目がアヤシイんじゃ。凡夫の目じゃないか。 ●自分というものはキマッタものではない。<わしの心はこんな心>そんなもの、ありゃせん。わしも坊主になったればこそ、仏法の言葉をなんたらかんたら言うておるけれども、これがもし侠客の親分にでもなっていたらどうか。<野郎バラシちゃえ>ぐらいなことを言っていたに相違ない。 ●別嬪だってヘチマだって、八十まで生かしておけば同じこと。洞然明白(とうねんめいはく)というのが本来の姿である。 ●たいていの人間は忙しい、忙しいと言うておる。なんで忙しいかと言えば、煩悩に使われて忙しいだけの話じゃ。坐禅しておればヒマである。天下一のヒマ人になるのが坐禅人である。 ●人間の仕事を何もせぬのが坐禅である。 ●坐禅の内容に浮世をあらしめれば仏法も豊富、ただの浮世の苦労をいくらしたって、人生を豊富にするものではない。 ●人間の知識は煩悩と業の窓口からのぞいた世界でしかない。最後の世界は、この煩悩と業から見た世界をすべて<やめる>こっちゃ。 ●必然に向かって文句なしに受け取るのがサトリである。大悟とは、<必然が必然と決まったこと>である。必然とは宇宙とつづきだからである。 ●亡者が出てくるとよくいうが、それも生きているものがある間だけのことで、もし生きているものがなくなると、亡者も化けて出てこない。亡者は生きているものの道具であると、<二十唯識>には出ている。 ●夢を見ていながら、これは夢だとはなかなかわからぬ。頬っぺたをつまんでみたら痛い。その痛いのも夢なんじゃ。夢と夢のつきあいだから、夢が夢ともわからぬ。 ●現実、現実と言うが、これみな夢である。夢の中での現実でしかない。革命とか戦争とか言うと、ドエライことのように思うておるが、やはり夢の中のモガキである。死んでみれば<夢だったな>とようわかる。それを生きているうちにカタヅカナイのが凡夫というものである。 ●意識に映った影を、またむしかえしてみるのを妄想という。 ●天地も施し、空気も施し、水も施し、椊物も施し、動物も施し、人も施す。施し合い。われわれはこの布施し合う中にのみ、生きておる。ありがたいと思うても思わいでも、そうなのである。 ●一切のものにケチをつける必要はない。 ●実際に腹が減ってもおらんのに<食えぬ>と言う。それだけで腹が減ってしまう。みんなコトバによってウナサレテいるのだ。な前でヤッサモッサやりおるのじゃ。 ●地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上とこの六道は、ただわれわれの<ノボセの目盛り>じゃ。ほんとうにノボセが下がったら、仏である。 ●道心とは、<ひと>のために<おのれ>を忘れること。無道心とは、<おのれ>のために<ひと>を忘れること。 ●サトリとは搊すること。マヨイとは得すること。 ●自分がむさぼらぬという一時をもって、十方に供養する。これほど大きな供養はない。 ●<くれ>と言うのでもないのに、施し恵まれる風景は、<むしり合いの世界>と違うて、じつに涼しい風景であり、じつに広大無辺なる風景である。 ●少住為佳(しょうじゅういか)ちょっと一ぷくすればいい。人間をちょっと一ぷくしたのが仏じゃ。人間がエラクなったのが仏じゃないぞ。 ●良寛さまがどこまでも涼しいのは、テをつかわぬからである。 ●<こうして、こうすりゃ、こうなるぞ>というのは、娑婆の話で、仏法ではない。よう<人さまの面倒をみておくこともな、人ごとじゃあらへん。うちの子供もあることだで。こうしておけば、いつか子供が面倒みてもらわんならんこともあるさかい>これが娑婆の話である。<ナンニモナラヌことをタダする>これは容易なことではない。これを行ずるのが、心身脱落、脱落心身ということじゃ。 ●天国といえば天国というカコイができる。神も忘れた神、神すら失ったところに、真の神がある。 ●坐禅すればいいと言っても腹がへるから飯を食わねばならぬ。金もなくなるから托鉢にも出ねばならぬ。ところがややもすると一本調子になりたがる。しかしいくらよいことでも一本調子ではダメじゃ。一切のものにとらわれぬことだ。自在無礙の問題である。 ●差別のわからぬのはバカだし、差別が気になるのは凡夫だ。 ●金閣寺でも法隆寺の金堂でも、みんな坊主が修行するためにあるのじゃない。ただ坊主が遊んで食えるというだけの話じゃ。 ●金をためねばならにような坊さんはふ徳であるということは言うまでもない。・・・・・・坊主が金をためねばならぬようになったら、それだけ欠点がわが身のうちにあるからじゃ。 ●坊主は金のないのが自慢である。良寛さんが死んだ時、金をためておったというウワサがある。それに対して、<そんなことはない。死んだ時の帳面にも、これこの通り>と言うひとがある。これは良寛さんを庇(かば)った言葉である。してみればやはり坊主に金のあるのは恥なんじゃ。 ●どんなプロからみても<見劣りせぬ>のが出家者であらねばならぬ。しかるにブルぶろうとする坊主や寺の嬶(かかあ)のあるのは、これまたどういうわけか。 ●傍観者の観念遊戯 それを戯論(けろん)という。傍観者の観念遊戯ではダメじゃ。全身全霊をもってとびこまにゃ。 ●世間の人は仏道修行とは、修行をつんでランプの火をほそめるようにだんだん煩悩をほそめっていって、最後にパッと消すぐらいに思うておる。そうじゃない。大乗の修行は、<おのれいまだわたらざるさきに、一切衆生をわたさんと発願し、いとなむなり>であって、そのため<煩悩をわざわざとどめて生をうるおす。>いかにも人間的であらねばならない。根っから単調で曲線のないようなのはダメじゃ。 ●立派なことを言う奴のことを<あれは粥飯(しゅくはん)の熱気だ>と言うことがある。栄養が足ってエラソウなことが言えるという意味じゃ。 ●柳は緑、花は紅 アタリマエというのが仏法である。ところが人間は、そのうえによけいなモノをかぶせる。いいとか、悪いとか、得くとか搊とか。 ●坐禅は善も悪もこえたものである。修身の話ではない。共産主義も資本主義もみんなヤンダところに坐禅はある。 ●自分というものは自分をもちこたえてゆくことはできない。自分が自分を断念した時かえって宇宙とつづきの自分のみとなる。 ●われわれの生まれてから後におぼえたものを捨てさえすればよい。 ●無我、無心と言うても、べつにボーッと意識がなくなることではない。無心とは必然に反抗せぬことである。つまり宇宙とのつづきにふく従することだ。宇宙とのつづきで働くことである。 ●一切のものが自分の内容である。ゆえに他人のおもわくも考えて行動せねばならぬ。 ●思想とは<すべて出来上がったうえでの話>でしかない。仏法とは<すべて出来上がる以前>のことである。 ●年寄りは経験、経験と言うて、昔のくせをふりまわしておる。どこがどう変わっても、変わりのないものを般若の智慧という。 ●工夫とは般若の智慧をピカピカにみがきあげることじゃ。考え込むことではない。 ●仏法は主観的事実である。それがただ個人的解脱になってしまったのが小乗である。大乗はそうではない。仏とツギ目がなくなると同時に、地獄の衆生ともツギ目なしになることである。 ●十万億土とは<自分から自分への距離>である。 ●ここに石油ストーブがあっても、マッチ一本は、はりこまねば暖かくはならぬ。みんな仏性があると言うても、あるだけでは何ともならぬ。仏性に火をつけねばならぬ。 ●人間でない方から人間の方を見なおしてみれば、どうしても本当のことはわからない。 ●たとえ現実のお釈迦さまを見ても、凡夫が見ればダメである。唯仏与仏 仏眼をもって仏を見るのでなければ。 ●<これでよい>という世界があるものではない。それなのにどこぞに<これでいい>という世界があるかと思うて、それを求めてウロウロ歩きまわる。ウロウロしたって仕様がないやないか。それじゃ泣き寝入りするか。そうじゃない。ウロウロしない世界にドカッと坐っておるこっちゃ。 ●仏道とは、もとからキマッテいることを信ずる(澄浄する)だけである。非思量するだけである。 以上、インターネットによる |
|
―遺 偈―
端雪埋井
*辻 光文様の手紙から
一 真理の大道は無門なり。 *伊藤肇『人間的魅力の研究』より
花は黙って咲き,黙って散っていく 。 そして,再び枝に戻らない。 けれども,一時一所にこの世の全てを託している。 一輪の花の声であり,一枝の花の真である。 永遠に滅びぬ生命の喜びが悔いなく,そこに輝いている。 * 宮本 進 先生からのメールから ★関連:花語らず |
|
▼『耐える』 窮して変じ 変じて通ず〉 <耐える>の序 七十九年のわが生涯、それは一貫して<耐える>の一語に尽きるほど厳しいものでありました。 幼少のころ、一家が破産します。母の仕立物を届けに行った商家の子倅に<乞食の子帰れ>とののしられ、悲憤の涙を呑みます。 やや長じて、京都の選仏寺小僧時代、それは明けても暮れても、男の<根性>の二字だけがかろうじて耐え得る、烈しものでありました。 つづいて、京都の大徳寺僧堂から伊深の正眼寺(しょうげんじ)僧堂へ。これまた、宗教的信のほのおを内に燃やす若者だけがようやく耐えることができるほどの、徹底した忍耐の生活の連続でありました。 それでも十二歳で仏門に入って以来、きびしい練磨幾星霜、やがて私は正眼寺僧堂の師家(しけ)となります。師家とは、自ら人生一大事を悟り尽して、後進の雲水を指導する大任をもつ老師のことであります。けれども、師家の生活はそのまま、厳然として旧来の耐える生活の幾層ばいかの苦しみの道であることを知りました。 しかも、私が初めて師家となった正眼寺僧堂は、他の禅堂よりも雲水の数がケタ外れに多くその上、天下の鬼僧林のなをほしいままにしていただけに、師家の努力精進にもただならぬものが必要となってくるのでありました。 そしてやがて、こんどは師家から妙心寺派大本山管長へ――。世間的にはそれは、あるいは恵まれたエリート・コースの一つであったかも知れません。 けれども、山のいただきに至り得たとき、そこには思いかけず〈拝まれるものの苦しみ〉が待ちうけていました。 それは“いばらの道”などという生やさしいものでありません。耐えねばならぬ厳しい試練の王座でありました。 私は、仏に仕えて清浄無垢、七十九年ふ犯(ふぼん)の生活をつらぬいて来ましたが、いま静かに回想しますれば、それは<耐える>生活以外の何物でもなかったのです。 けれども、耐える生活を身につけたことはそのまま、いかなる窮乏逆境に出くわしてもビクともしない力をおのずから蓄えたことになりました。 長い禅堂生活で耐える暮らしに慣らされている人間にとっては、世間が大さわぎするような大東亜戦争さなかの耐乏生活などはものの数ではないのです。 けれども私はいま、仏法随喜の感動にむせびながら、泫然(げんぜん)として泣いたあの少年時代の忍苦の生活を思いかえしますのです。 あの忍辱(にんにく)行道(ぎょうどう)の<耐える>日のなかからこそ今日のよろこびは湧き出ているのであると。そして、この歓びこそは、私にとっては、未来永劫のよろこびであるといったらわかっていただけるであろうか。 昭和四十八年十二月 臨済宗妙心寺派管長 梶 浦 逸 外 |
|
▼『実践・歎異抄入門』 一 阿弥陀如来は真理そのものを人格化した仏なのだ。だから、形もなければ音もない。無色透明なのだ。しかし、信じざるを得ない究極の道理である。それが涅槃とか真如とか一如とかいう世界だが、そこにみんなが気がゆかない。
生活を通してこそ宗教がわかる
その証拠に、鈴木大拙のような知識階級の代表的なインテリが、浅原才市という島根県の仏教信者に頭を下げた。浅原さんという人は自分のなまえも書けないような人だったが、鈴木さん浅原さんの言行に強く感動したのである。 鈴木さんの晩年は、一貫して浅原さんの紹介に終始している。あれほど学問を持っている人にそれほど心酔することは、普通ではちょっと考えられない。そこに宗教と知識の違いがはっきり現れてているのだ。 P.185
学問の世界に多い弟子くらべ
先生の話のなかで、<がんの研究をしていると、嫌でも宗教を求めたくなりますよ>とおっしゃった。そして、次の言葉に私は感銘を受けたものだ。 <私は『歎異抄』に傾倒しているのですが、なかでも『親鸞は弟子一人ももたずさふらふ』の一句に心を打たれました。爾来、私は研究室においてその心で仕事をするようになりました。すると協力者たちの研究態度がかわってきたのです。熱意がちがいますよ>P.159 2008.4.22 |

序 禅がシナに伝えられたといってから、もう千五百年にもなる。その間盛衰もあったが、その最も熾(さか)んだった時代は唐である。すなわち、西紀第十一、二世紀にかけてである。宋代の末になると、いくらかの衰退期の兆候がみえる。 とにかく、禅は漢民族の間に発達し、完成したので、漢民族の感じ方、考え方、随って漢文学、漢文字から離れられぬ因縁を持っている。ところが、近代文化の発展方向は、漢文字から離脱する方向に向かっている。これにはいろいろの事由もあることで、この勢を取り返すことが甚だむずかしくなった。 しかし、禅には禅の特性があるので、漢文学は漸退(ぜんたい)の方向に進んでいても、禅そのものは、そのゆえに亡びるものでない、かえってこれからは近代に相応すべき点を考慮し、これを研鑽し、発展させなくてはならぬ。そうして、近代文化が、そのうちに行きづまりに陷(おちい)らんとする運命に向かっているのを、救い上げなくてはならなぬ。 禅発生の本土には、現在のところ禅復興の機運がみえぬ。これを復興させ、再起させ、再転させ、新発足をなさしめ、これからの世界文化に大なる役割をを担う民族は、われら日本人だと、自分は堅く信じて疑わぬのである。 禅が今、欧米でいくらか人の眼につくようになったといっても、それはほんの少しの兆候にすぎぬ。本当の話は、これからである。日本の禅人はこの事実を認めて、従来の伝統の殻(から)から脱出することを認めなくてはならぬ。 これを成し遂げんには、今代世界の思想のいずれにあるかを、まず、見定めるべきであろう。それから、その行きづまりが早晩、否、既に到来しつつあることを、看取(かんしゅ)しなくてはならぬ。而して、禅の伝統の中に生きているものを、抽出し、体取(たいしゅ)し、消化して、それを未だ曽(か)つて禅なるものを、見たことも、聞いたこともない人々の間に、伝えなければならない。 この事実がわかると、これからの日本の禅人は、どんな準備を整えるべきかが、自から分明(ぶんみょう)になると、自分は信ずる。ここに禅者の為人度生底(い にんどしょうてい)があるではなかろうか。 唐代の馬祖なら馬祖、宋代の圜悟(えんご)・大恵(だい え)なら、圜悟・大恵、日本の道元なら道元、白隠なら白隠が、今いったことに無条件に同意することを、自分は疑わない。 山田無文師のこの書は、日本における人々のために書かれたので、世界の読者のためではない。随って今、自分がいったような心持はここに現れていないだろう。が、師が禅を見る眼は、一代前の禅者がやったような語録風のものでないことは明らかだ。相手は近代風の教育を受けつつある青年だとすると、いろいろと引用せられている事例は、いずれも彼等の思想や生活に密接なものであろう。或いは温故知新的なものである。しかあるべきだと信ずる。 東洋では、伝統を重んずる傾向が強いが、その弊は前進性、独創性を欠くことにある。それが、或る点まで東洋をして未開拓性を帯びすぎさせるようになったのである。未開拓性のうちに、かえって東洋的なものを失わずいるという事実も考えてみなくてはならぬ。が、いずれにしても、あまり停滞しては人間全体の進歩を妨げることにもなろう。均衡ということが大切である。 いずれにしても、禅は何かにつけて、停滞を容(ゆる)さぬ。<逝くものは、此(かく)の如きか、昼夜を舎(お)かず>なら、逝くものをして逝かしめよ。但し、来るものは迎えることを忘れてはならぬのである。顧があり、鑒(かん)があって、それから更に進一歩あらしめたいものだ。進んで、行くなどと、問うに及ばぬ。何でも、ぐるぐると車を一処にのみ空転することにしないのである。 古桶の底抜けはてて 三界に 一円相の輪のあらばこそ これは盤珪禅師の歌であるが、輪なしの円、周縁のない円、これを<永遠の今>、または、目前歴々底(もくぜんれきれきてい)ともいうが、ここで進むこともなく、退くこともなくして、しかも進んで已まないのが、人間の生活である。 無文師のこの<講話>をみて、平生思っていることの一面が、知らず知らずに浮かび出た。それをつづり合わせて、この文を草する。一には無文老師の是正を乞い、今一つには、読者諸君の参考にもがなと思うのである。 昭和三十七年三月 鈴 木 大 拙 記す 2015.10.27
静かに思う
よく、忙しくて毎日の生活に追われて、そんなことを思う暇がないといわれますが、時にはこうして静かに、人生を思ってみる必要があると思います。それも寝そべって思ったり、歩きながら思ったり、煙草をくゆらしながら思ったりするのではなくして、姿勢を正して端坐して、呼吸をととのえて、できれば線香一本も立てて、清澄な雰囲気のなかにおいて、きわめて厳粛に思う必要があると思います。真面目に人生に取り組んでみるのです。もし人生観が根本的に間違っていたりしますと、貴い一生を、再びない人生を無駄にしなければなりません。 しからば、いったいどう考えたらよいでしょうか。人生の結論は何でしょうか。わたくしたちは、よい先生のみちびきによって、正しい考え方を教えていただけなければなりません。お釈迦さまは、この地上における先駆者であり、最初のよい先生でありました。それから今日まで伝統をまもって、多くの先生がたが、法をつたえ、ひとびとをみちびいてこられました。 <まず、人生は苦しいものだ、苦しみに充満したものだということを思いなさい。つぎにその苦しみが、どこから来たかを反省しなさい。そして、苦しみは必ず解放され、人はみな自覚者になれることを信じなさい。そのためには、自覚に入る一つの道について、深くこれをきわめなさい。> お釈迦さまの、指導法はこういうふうでありました。そうしてお弟子たちは、その教えを身をもって考えました。すなわち、坐って静かに瞑想しました。人生苦とその原因と、その救いと、救いへの道を、そうしてみな幸福なる自覚に入りました。 お釈迦さまのお弟子に、きわめておぼえのわるい人がありました。シュリハンドクのな前でしたが、その自分のな前さえおぼえられなくて、板に書いてもらって首からぶらさげていたということであります。お釈迦さまはこの青年をみちびかれるのに、長い言葉は到底おぼえられないので、<三業に悪を造らず、有情を傷めず、正念に空(く)を観ずれば、無益の苦しみをまぬがるべし>という、たったそれだけの言葉をおしえられました。何日も何日も同じことをおしえられたので、そこらに遊んでいた子供がおぼえてしまったのに、シュリハンドクには、まだおぼえられませんでした。お釈迦さまも、手をやかれて、<塵を払わん、垢をのぞかん>とこれだけの言葉をさずけられました。これさえも、なかなかむずかしくて、はじめの<塵を払わん>をおぼえると、あとの<垢をのぞかん>を忘れてしまいます。いよいよ手にあまって箒と雑巾をあたえて、この言葉をおぼえる方便とされました。おぼえのわるいシュリハンドクも、一心に箒と雑巾とをもってお掃除をしながら<塵を払わん、垢をのぞかん>と唱えているうちに、すっかりおぼえてしまいました。 それから三年の間、立っても坐っても、寝てもさめても一所懸命この言葉をのみ思っているうちに、心の塵がしだいに払われ、垢がすっかりのぞかれて、忽然として塵もなければ垢もない、煩悩もなければ菩提もない世界がわかりました。そして、仏と同じ自覚に到達して、羅漢(らかん)の悟りを開きました。その時、シュリハンドクはどんなに喜びにあふれたことでしょう。その眼はどんなに、智慧の光に輝いたことでしょう。学問がなくても、記憶が悪くても、坐って静かに、あたえられた教えを一心に思うていると、自ら悟りが開けてきます。ありがたいことであります。ふ思議なことであります。 このょうに、お釈迦さまが次々としめされた、短い言葉をあつめられたものが、【阿含経】や【法句経】のような原始経典で、仏弟子たちは、その一句一句を静かに思うことによって、身をもって思うことによって、悟りが開けたのであります。後世、中国ではこうした経典よりも、もっと身近な、端的な、祖師の言葉や行為を思うことになりました。いつの時代でも、その時代の生きた空気のなかに働らくものが、禅でなければなりません。趙州(じょうしゅ)和尚は、なぜ<庭前柏樹子(はくじゅし)>といったか。雲門和尚は、どうして<日々是れ好日>といわれたか、というようなことが問題になりました。そして、坐って、静かに、そればかりを思っていると、知らず知らずのうちに、趙州と同じ世界に入り、雲門と同じ境地に達することができるのであります。そうなると、それらの言葉は、あたかも悟りの関所を通る通行許可証のようなもので、だれいうとなく、公案となづけられました。公案は、公府(こうふ)の案牘(あんどく)と申して、いわば公認の証明書であります。これらの言葉がわかることが、すなわち普遍的な、公正な人生観にはいれることなのであります。 ここに、非常に面白いことは、坐ってじっと同じことを思っておりますと、ついに何も思うことのない心理状態にはいってしまうことであります。そして、本当に自分の生まれたままにもっている智慧だけが、静かに独り自らを照らすごとく輝くことがわかるのであります。正しい人生を思うということは結局、何も思わないことだという智慧の眼が開けてまいります。そして、仏と同じ自覚に入り、祖師と同じ境地を把握し、人間の誰もがそうなければならない、普遍的な人生観が開けてまいります。 ※『坐禅和讃講和』(春秋社)一九八九年七月二〇日 新装第五刷発行 P.53~56による 平成二十七年十一月五日 |
|
▼柳宗悦 妙好人論集 <妙好>は<白蓮華>を意味する語で、泥の中に育ちながら浄い花を咲かすハスのように、浄らかな信心を持っ信徒を<好人>と呼ぶ。民藝運動のバックボーンとして<他力道>の思想に到達した柳宗悦は、そのよき実例を妙好人の中に見出し、その意義を熱っぽく説いた。<仏教に帰る><源左の一生>等22篇を収録。 (解説=中見眞理) ★寿岳 文章(じゅがく ぶんしょう、1900年3月28日 - 1992年1月16日)は、英文学者、随筆家、書誌・和紙研究家。民芸運動家。 ★関連:<妙好人> 2008.5.25 |
|
▼『参禅入門』 ▼十 牛 図 一 尋 牛 ここに<牛>というのは、いうまでもなくわれわれの本心、本性、本来の面目、真実の自己などをさしていう。それを探し求めるのが<尋牛>の段階である。 二 見 跡 この<見跡>の境位は、要するに道を学ばんとしてまず書物や講話によって研究したり、師を求めて指導を受けた結果、どうやら修行の方向やその仕方が、わかった段階であろう。 三 見 牛 見牛とは、この源に逢うこと、つまり見性のことである。しかしこの段階では見ることは見たのだが、雲烟はるかにモーウという声を聞いただけか、霞の中にボーッと牛の影を見たのか、あるいは目と鼻の先にハッキリ見たのか、同じ見たと言っても、その見た程度は人によってさまざまであろう。 四 得 牛 この段階では牛の鼻づらをつかんだのだから、これで見性もやっと本物といえる。普通、無字の初一関を型どおり透(とお)ったのを見性といって許すようであるし、本人もそれでひとかど見性したかのように考えている人もいるようであるが、すくなくともこの得牛ぐらいでなければほんとうに見性したと言えないであろう。見たのと得たのとでは、天地の隔たりがあると言ってよいとおもう。 五 牧 牛 全慶老師は<牧牛>の牧を<自己を境に投じて境中自己なき妙修>と解しておられるが、そのように差別の境に出入して、対象に成リきることによって一切のたおらわれを乗り越え、自己なき自己を万鍛するのが牧牛で聖胎長養とか悟後の修行とかいわれるものに当たる。 六 騎 牛 帰 家
参考:<迷頭認影>(めいとうにんよう)、固執してしまった演若達多の故事からとある。 頭に迷い影を認む。 鏡に映った頭を真実と思い込み、固執してしまった演若達多の故事からとある。 真実の自己を見失って、その影のみを追い求める愚かさ。仏教的には教典の字句の解釈に気をとられて、仏道の実践を怠ることを言う。 鏡に映った自分の姿は、真実自分の姿ではないのか? 何事でもそうであるが、事実とぴったり一つになっているいる場合には、その事実は知ることはできないのである。ああだこうだと思慮分別するということは、すでに事実から遠く離れて、これを対象的に見ている証拠であろう。眼は眼を見ずと言われるように、自分が自分を見ることは出来ないのである。自分を知っていると言うことは、すでに自分から離れて見ているのだから、そんなのは意識によって造り上げられた架空の自己でしかないと言うことであろう。生とか死というものでもこれと同じで、その真っ只中にいる者にはあれこれ言う隙はない筈だ 西村恵信師 三余居窓話34(2002/4)より 七 忘 牛 存 人 騎牛帰家は、人と牛、衆生と仏、現象と本来とが一つのものだとの自覚に達したことで、かりにそれに騎った人、仏の懐ろに抱かれた衆生、本体に即した現象というふうに、牛、仏、本体の面すなわち真理の世界に重点をおいた自覚のしかたとするならば、この忘牛存人はそれをさらに一歩すすめめて、人、衆生、現象の面から見る、すなわち本体的な現象、仏としての衆生、自覚体としての人として、絶対者の働きを現実の自己そのものの上において見る立場である。この場合の自己は、すでに従来のような五十年の時間、五尺の空間に制限された有限の自己ではない。宇宙に充ち満ちた全一としての自己、天地の主としての自己、乾坤只一人の自己である。したがって図にも牛はなく、ただ独り求めるところのない、充ち足りた人間だけが描かれている。 八 人 牛 倶 忘 尋牛、見跡、見牛、得牛などの境は、 九 返 本 還 源 <本に返り、源に還る>とは、ふりだしの本の位置に立ちもどり、出てきた根源に還るという意味で、第八の絶対無の一円相をさらに乗り越え、元の差別の現実世界に立ち帰った境地である。沢庵和尚の『ふ動智』には、この消息を<ずっと高きと、ずっと低きとは似たる物になり申候>と音階にたとえて説明し、<仏法もずっとたけ候えば、仏とも法とも知らぬ凡夫と同じように成り候>といっている。普通宗教といえば神の国、絶対の世界がその行きつく目的地であるが、もしそこに止まっていたならば、あたかも病気を治すために入院させた患者を、全快後も病院に引きとめて自分の家に帰さないようなものではなかろうか。病人が入院するのは健康を回復するためであるから、病気がなおったら、元の現実の社会に立ち戻って精一杯働くべきである。ツァラトゥストラが太陽に向かって<汝が、いま一度下界に光を齎(もた)らさんとて、夕べの海の彼方に沈みゆく時のごとくに――。われもまた、汝のごとくに降りゆかなくてはならない>といって下界に向かって<沈没>し、<神は死んだ!>と叫んで聖位を否定して<群集>の中に走り下りたように、また高天原の神々が<漂える国を修理固成>するために混沌たる地上に天降ったように、ひとたび聖位に向かってひたすら自己を否定しつくしたのは、やがてその到りえた聖位をも否定し、絶対無の世界から現実の山高く水長き娑婆に立ち戻らなければならない。凡夫の世界は、山はこれ山、水はこれ水である。聖位においては山は山、山に非ず、水、水に非ずだった。いまやまた元の凡夫と同じく、山はこれ山、水はこれ水の世界に還源したわけである。 十 入 廛 垂 手
関連:十牛図 2008.5.21 |

私の本棚に板橋興宗さんの本が2冊ある。 ▼『良寛さんと道元禅師 生きる極意』(光雲社)1986.4.6 初版発行 ▼『人生は河の流れのごとく』(PHP研究所)1994.3.25 第1刷発行 『人生は河の流れのごとく』を開きますと、彼の描かれた画面に書き込まれた文言を記載いたしました。 一 ひとりの時の 過ごし方で人間の“格”がきまる 二 人には年齢に応じた初恋がある 三 言葉には温度がある 四 高嶺の花をうらやむな 足元の豆を拾え 五 スミマセン!! の一言が言えたら争いはおこらない 六 捨て切れぬ心のままに生かされて 七 平凡も続ければ非凡になる 八 魚は水の中にいて水を知らない 人は極楽にいながら極楽を知らない 九 受けるより 与えるほうが幸いである 十 議論に勝つ道は議論をしないこと 十一 愚者は思うこと多し 十二 踏み切るまでは迷う 十三 いのちをかけて打ち込むことに 最高の生きがいがある 十四 悪口は言わずに 長所をほめよ 十五 この世の中のこと すべて必然で すべて必要で しかもベストである 十六 一人の人を助けおおせたら 人生の目的を達したと言ってよい 十七 “してやった”からふ満がおこる “していただいた”から感謝が生まれる 十八 ならぬ堪忍するが堪忍 十九 負けてもくじけない人を強いという 二十 わる口 かげ口 わが身に返る 二十一 結婚前は目を開けておけ 結婚後は半ば閉じておけ 二十二 正義の主張は争いになる 二十三 老いは意欲の問題である 二十四 みにくさを恥じないひとになりなさい 二十五 明日の心配は明日でたりる 2012.05.25 |
|
▼『悪と往生』
一 日本仏教には、大きくいって二つの流れがあったと思う。一つは、人間いかに生くべきかを追及したもので、主として空海(七七四~八三五)の密教的立場がそれにあたる。すなわち現(うつ)し身のまま仏になるという<即身成>の考え方だ。徹底した現世的生命主義といってよく、日蓮(一二二二~八二)の思想もこの流れのなかから生まれる。道元の場合もそのなかに含めてよいだろう。ところがこれに対して、もう一つの流れが、人間いかに死ねべきかを追及した行き方であったと思う。その立場を明らかにした代表選手が平安時代の源信(九四二~一〇一七)であり、鎌倉時代の法然、親鸞であった。その根本的な考え方は、現世を浄土の光明によって照らしだそうとした点で、いわば来世的生命主義に立つものであったといってよいだろう。そして親鸞はその立場を究極まで推しすすめた思想家だったのである。
|
|
生とも道わず死とも道わず 一 先日、立生佼成会の庭野平和財団から、<人はなぜ、何のために生まれてくるのか>(年刊『平和と宗教』第二十号)を贈ってもらった。新宗教であるだけに、時代に密着した問題意識が強く、私のように古くさい伝統教団にどっぷり漬かっている者には好い刺激になり、大いに教えられるところがあるので毎号楽しみにしている。 ところで我われは普通、<人はなぜ、何のために生まれてくるのか>などと問われると、そんなことはとっくの昔に仏陀や祖師たちが説かれているじゃないかと、あたかも自分にとってさえ自明のことのように思ってしまうのである。しかし、誰かが正面切ってそう問いかけられたとき、果たして揺らぎのない答えが出せるかいうと、これはちょっと怪しいことになろう。 今度送ってもらった『平和と宗教』を開くと、仏教、神道、キリスト教、イスラム教というな立場のひとびとが、それぞれ自分なりに立派な回答を寄せていて、なるほど同じ問いでも信仰が異なるとこうも違った答えになるものかと、宗旨の違いが醸し出す人生観の多様性というものに、今更ながら感心させられたものである。 要するに、こういう初歩的な問題に対してはどのように答えられるかということが、自分の信仰の質を端的にみせてしまうバロメーターになるわけだから、問われてももたもたしているようでは、信仰も人生観もまだ未解決という情けない状況の自己告白になるわけである。 読んでいて一つ面白かったのは、川崎信定氏の『チベット死者の書』をめぐる論文であった。<〈人は死への存在である〉とする近代西洋流の考えに真っ向から対立するのが『チベット死者の書』(バルドゥ・トェ・ドル)である>という冒頭の一文を読んで、にわかに眠気が覚める思いがしたのである。 というのは、禅宗の生き方では、どうかすると鈴木道三や白隠和尚に毒されて、<死>を見つめて生きることを禅僧の誇りとする向きがあるからである。私自身高校生の頃、正岡子規が『病牀六尺』の中に、<余は今まで禅宗のいはゆる悟りといふ事を誤解して居た。悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であった>と述懐しているのを知って、なるほど禅が<死>を強調するのは、むしろ力強く<生>きるたあめであったのかと、ひそかに感心した憶えがある。 チベット人が死者の耳もとで読む『死者の書』なるものは、死によって始まるこれからの<中有>(死んでから次の生を得るまでの四十九日間)をどのように送るかを指示したガイドブックであると言う。つまりチベット人にとって、死は次の生への準備のためだというのである。 二 ところで禅宗では生と死の問題がどう扱われているかというと、この生死問題こそが禅修業ののアルファであり、オメガであるとされているのである。たとえば中国兜率従悦とう禅者は、修行者がやってくると決まって、<撥草参玄は只見性を図る。即今上人の性、甚処(いず)れにかある。自性を識得すれば方(まさ)に生死を脱す。眼光落ちる時、作麼生(そもさん)か脱せん。生死を脱得すれば便ち去処を知る。四大分離、甚処に向かってか去る>と問いかけたと言う。これが世に<兜率の三関>として恐れられる入門試験である。 兜率和尚の詰め寄る三つの問いの第一は、禅修業の目的は只だ自己の本性を見定めることに尽きるのだが、お前さんの本性はこの瞬間どこにあるか見せてみろ。第二問、自己の本性さえしっかり掴まえておけば、死の準備は既に完了だが、お前さんはいよいよ臨終という時、どのように死んでいくか。また死んでからのお前さんの行く先はどこだ、と言うのが第三問である。 今でも日本中の坐禅道場では<生死事大、無常迅速、時ず待人、慎勿放逸>と書いた板を叩いて朝夕の時を告げることになっている。生死の解決こそは最重要課題である上に、時間がどんどん過ぎてゆくばかり。ひとときも気を緩めてはならないぞ、と言うわけである。それゆえ禅僧は昔ながらこの課題に取り組んで修行に励み、悟りを得て立派に人生を生き、そして惜しみなく死んでいったのである。 では禅僧たちはどういう答えに至ったか。その例を二つ三つ挙げてみよう。南北朝時代を生きた妙心寺の開山慧玄は、生涯ただ一語、<慧玄が這裡に生死無し>を残して逝ったと言われる。徳川時代の沢庵和尚は死に臨んで<夢>の一字を大書し、<百年三万六千日、弥勒観音幾(ほと)んど是非、是も亦た夢、非も亦夢、弥勒も夢、観音も亦た夢、仏云わく、応に是の如き観を作すべし>と添えている。また同じ時代に博多の仙厓さんが、弟子たちに囲まれて<死にともない、死にともない>と言いながら死んでいった話はよく知られている。 そうなると、禅宗としていったいどれが正解なのかさっぱり分からないということになるであろう。しかもどの人も悟りによって生死を超えたと言われているいる人の死にざまに違いないのだから、どうやら禅僧の死に方には定型パターンというものがないらしい。ということになると、禅宗には定型となる信仰箇条のようなものさえないとなるであろう。要するに禅宗では、いかに生きいかに死ぬかは各人にまかせ、これについては誰も教えてくれないのである。 三 このことを示す面白い話があるのでここに引き合いに出して、読者の皆さんを禅に巻くことにする。一つは『碧眼録』五十五則に挙げている話で、唐の時代に道吾円智という禅僧が弟子の漸源仲興を連れて喪家を弔問する。弟子の漸源が棺桶を叩いて、<生ですか、死ですか>問うと、師の道吾は、<生とも言わん、死とも言わん>と答えたのである。<どうして言わないのですか><言わん、言わん>。道場への帰り道、漸源が、<和尚だん、どうか今すぐ何とか言ってください。それでも言ってくれないなら、<和尚を打ちのめしますぞ>と詰め寄ると、道吾和尚はまたもや<打ちたければ打つがよい。言わんと言ったら、言わん>の一点張り。そこで漸源は道吾和尚を打ちのめしてしまったのである。その道吾和尚もやがて遷化(死んで)してしまった。そして漸源は石霜慶諸という和尚の道場に移ってまた同じ質問したところ、石霜和尚からも<言わぬ、言わぬ>の答えが返ってきた。ところが漸源はこの同じ答えを聞いて、初めて悟りを開いてしまったという話である。 普段から<生死一如>などということを、耳にタコになるほど聞かされていたのであろうか。漸源はこの時とばかり死んで棺桶に入っている人を指して、<生か死か>などという愚問を発したのであろう。しかしそんな議論が死という現実の前には何の意味もないのは決まっている。事実としては生か死かのいずれか一つ。いくら打たれても生と死を二つに分けて説くなどと言うことはできやしないのだ、というのが道吾、石霜和尚共通の親切な答えであったわけである。どうやら禅僧というものは、どの人も徹底して事実主義であるというところに共通点があるらしい。 もう一つの話はニュアンスが異なるが、やはり禅僧の死生観を知る面白い話である。これも唐ンお時代に大梅法常という有めいな禅匠があって、夾山と定山という二人の修行者がこの人を訪ねてやってきた。その道すがら生死の問題をめぐって二人の激論となったのである。定山は<生死の苦しみの世界に、もし仏がおられなかったら、生死などというものもないではないか>と言い、夾山は<いや生死の中に仏がおられさえしたら、生死に迷うこともなかろう>と言って、両者が譲らないまま夕刻になって大梅山に到着した。 さっそく大梅和尚にお目にかかった時、夾山がこの話をして、<私たち二人のどちらが真実でしょうか>と問うと、<一親一疎>(一人は当たり、一人は外れだ)との答え。そこで夾山が、<ではどちらが当っていますか>と問うと、<ま今夜はこれ位にして、明日にしなさい>と言われた。 翌日、夾山がもう一度参上して同じ質問をすると、大梅和尚が、<親しき者は問わず、問う者は親しからず>(一人は当たり、一人は外れだ)と一喝された、とまあそういう話である。 何事でもそうであるが、事実とぴったり一つになっているいる場合には、その事実は知ることはできないのである。ああだこうだと思慮分別するということは、すでに事実から遠く離れて、これを対象的に見ている証拠であろう。眼は眼を見ずと言われるように、自分が自分を見ることは出来ないのである。自分を知っていると言うことは、すでに自分から離れて見ているのだから、そんなのは意識によって造り上げられた架空の自己でしかないと言うことであろう。生とか死というものでもこれと同じで、その真っ只中にいる者にはあれこれ言う隙はない筈だとするのが、まいちおう禅宗らしい答えであろう。 四 いったい禅問答と言うものは、木で鼻を括ったような答えばかりで、聞いた方にとってはさっぱり取り付く島もないというのが通例になっている。こりゃいったい何のことかと、訳の分からぬところへ頭を突っ込んでしまう中に時間ばかり経って、ご臨終と言うことになってしまうのが九十九パーセントというのであるから、非情と言えば非情な世界である。それで師匠の採る最後の手段は、一棒や一喝で弟子の迷いをぶった切ってしまうほかないということになるらしい。 そういう荒っぽい手段の臨済宗に比べると、曹洞宗の道元さんという人は実に親切な方と言うべきであろう。生死の問題について、道元さんの次のような説法は大いに吾人の参考になるであろう。 ただ生死すなはち涅槃とこころえて、生死としていとふべきもなく、涅槃としてねがふべきもなし。このときはじめて、生死をはなるる分あり。生より死にうつるとこころうるは、これあやまりなり。生はひとときのくらゐにて、すでにさきありのちあり。かるがゆゑに仏法の中には、生すなはちふ生といふ。滅もひとときのくらゐにて、又さきありのちあり、これによりて滅すなはちふ滅といふ。生といふときには、生よりほかにものなく、滅といふとき、滅ほかにものなし。かるがゆえに生きたらば、たゞこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべしと。いとふことなかれ、ねがふこといなかれ。 (『正法眼蔵』生死)
立正佼成会から、<人はなぜ、何のために生まれてきたか>と、こちらへも問いを突きつけられているような気がして、えらい屁理屈をこね回してしまった。そこで清涼剤を一ぷく。
*三余居窓話34(2002/4)より ★プロフィル:西村 惠信、1933年 –は、日本の仏教学者。 花園大学めい誉教授、元学長。文学博士。滋賀県生まれ。 滋賀県東近江市にある、臨済宗妙心寺派の興福寺の前住職。 2010.06.15 |
|
▼『良寛の詩と道元禅』(大蔵出版) 良也愚の如し 道転た寛し 騰騰任運誰か看ることを得ん 為に附す 山形爛藤の杖 到る処壁間午睡の閑。P.125 良寛が他力的表現によって詠んだ歌の中に、次の一首がある。 〽良寛に辞世あるかと人問わば南無阿弥陀仏といふと答えよP.159 これは他の辞世と合わせてみたとき、一つの対機説法と考えてよいであろう。しかしそのことは単に方便を設けたというだけのことと見るべきでもないであろう。良寛晩年の心境を、かなり写し出したものというべきである。一方、他の辞世に、 〽形見るとて何かのこさむ春は花山ほととぎす秋にはもみぢ葉 とある。いうまでもなく、道元の、 〽春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷(すず)しかりけり を本歌としたものである。 ★竹村 牧男(たけむら まきお、1948年2月25日- )は、日本の仏教学者、筑波大学めい誉教授、東洋大学学長。 |
|
命を運ぶと書いて運命。つまり運命とは、定められて仕方なくたどるものではない。みずからの命を自分の力で運んでこそ運命といえるのではないか。 2008.5.13 |
|
<日々是修行> <信仰ではなく信頼する>の表題であった。 (前略) <宗教というのは、教祖様の言葉を理屈抜きに丸ごと信じるものだ。それができないというのは、信仰がない証拠だ>、といった批判である。もし仏教が、<信仰によって成り立つ宗教>なら、この批判は正しい。 しかしそもそも釈迦の仏教は、信仰で成り立つ宗教ではない。仏教でも<信じなさい>とは言うが、それは<釈迦の説いた道が、自分を向上させることに役立つ>という事実を<信頼せよ>という意味である。仏教の<信>とは、信仰ではなく信頼なのだ。この違いは大きい。 信仰とは、<絶対に正しい存在がこの世にいる>と考えて、その前に自分のすべてを投げ出し身を任せることである。だから神や超越者に救いを求める宗教では、信仰が、何より大切な原動力となる。一方、釈迦は絶対者の存在を認めなかったから、そこには信仰の対象というものがない。すべてを任せれば救ってくれる、そういうものはどこにもいないのである。 釈迦自身は、普通の人間だ。ただ常人よりすぐれた智慧があって、<超越者のいない世界で、生の苦しみに打ち勝つ道があること>を独力で見つけ出した。そしてそれを私たちに教えてくれた。だから私たちは、その道を信頼する。釈迦という人物を信仰して、<助けてください>と祈るのではない。釈迦が説いた、その道を<信頼して>、自分で歩んでいくのである。だから、釈迦が完璧な絶対者でなくてすこしも構わない。道を信頼する気持ちがあれば、それだけで仏教は成り立つのである。
略歴:京都大学工学部工業化学科および文学部哲学科仏教学専攻卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程退学後、米国カリフォルニア大学バークレー校留学。花園大学文学部仏教学科講師、助教授を経て、現在、教授。 参考:佐々木閑 『日日是修行』(ちくま新書)が出版されています。 2009.2.15 涅槃会の日 |
|
▼『自分から自由になる沈黙入門』 手習いその1 <まったく何かにケチをつけずに1日すごしてみる> 手習いその2 <天皇陛下のようにスロウに、徹底的に自己を抑制して喋る> 手習いその3 <正義で相手を論破することをやめる> 手習いその4 <買いたい><食べたい>欲望に駆られたら、<ドウデモイイと念じる 手習いその5 <身辺で大切に思う人対してこそ、つねに幻滅しておく>
*2008.5.30付けの新聞の広告から引用。参考までに、インターネットでも広告されています。
2008.5.30 |
|
▼道元禅入門 因果(佛法)を昧まさず。 万法は一体なりと認識し(佛法)
一法は一如になって行動(佛道)
参考:老いに挫けぬ男たち |
|
達磨の教えは<安心(あんじん)>の法といわれ、これをすがた・かたちにあらわすのを<壁観>と呼んでいる。どうして安心が得られ、壁観を実行するかという二つの方法がある。それは<理入と行入>である。 これは、弟子の曇林(どんりん)が序した、略弁大乗入道四行にある達磨の教えである。 ▼ 理入は、教を藉りて宗を悟り、深く含生の同一真性を信ず、但だ客塵のために妄覆され、顕了する能わず。若し妄を捨て真に帰るごときは、壁観に凝住す。自無く他無く、凡聖等一。堅住して移さず、更に文教に随わず、これ即ち真理に冥符す。分別あることなく、寂然として無為なり。これを理入となづく。(後略) ▼行入は、報怨行・随縁行・無所求行・称法行の四つである。このうち 一、報怨行は人生苦のもとは、自ら播いた宿行によるものであるから、決して他をうらむことなく、理にかない道にしたがうことが大切である。 二、随縁行は、一切のものは元来、無実体(無我)であって、苦といったり楽といっても宿縁によるものである。だから何事によらず、動揺することなく仏の道(心)に順うことが大切である。 三、無所求行は、多くのものが迷うのは、貪り・執着する心からおこるものである。真理を識るものは、心安らかで、道理に適わない貪りや、徒らに願い求めるようなことはない。 四、称法行は、すべてのもの(法)は、もともと浄い仏心・仏性をもっている。この道理を信じよく理解して、これにかなう道を修することである。その道は何かというと、人びとのためにつくす六度の行である。 これらの四行は、仏陀のこころをさとる壁観を実行することによって満たされ、また安心を得ることができるのである。(後略) 参考:『仏教読本 二』P.32~P.35より 2009.8.16追加 |

一 心の中であらゆる方向をめぐってみても、どこでも、自己よりも愛しいものにめぐり会わなかった。それ故に自己を愛する人は他人を害してはならぬ。 ここから慈悲の理想が出て来るのである。これは<自分が他人からして貰いたいように思うように他人になせ>という黄金律に対応するものであり、また西洋の宗教の<汝の隣人を愛すべし>という教えに通ずるところがある。P.90 |

第一章 ひと組みずつ 一 ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人に従う。――車をひく(牛)の足跡に車輪がついて行くように。P.10 二 ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも清らかなこころで話したり行ったりするならば、福楽はその人に従う。――影がそのからだから離れないように。P.10 2008.10.22 五 実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以ってしたならば、ついに怨みの息やむことがない。怨みを捨ててこそ息む。これは永遠の真理である。 参考:『法句経』 友松圚諦『法句経講義』(講談社学術文庫)第一講 うらみは熄(や)む 法句経 五 P.19 2009.04.11 六 <われらは、ここにあって死ぬはずのものである>と覚悟をしよう。――このことわりを他のにん人々は知っていない。しかし、このことわりを知る人々があれば、争いはしずまる。 参考:『法句経』 友松圚諦『法句経講義』(講談社学術文庫)第三講 法句経 六 死の領土にあり P61 2009.04.12 第四章 花にちなんで 五〇 他人の過失を見るなかれ。他人のしたこととしなかったことを見るな。ただ自分のしたこととしなかったことだけを見よ。P.17 2009.04.13 感興のことば 第一章 無常 一 この世で、心が暗くふさぎ込んだり眠くなるのを取り除いて、心を喜ばせ、勝利者(=仏)の説かれたこの感興のことばをわれは説くであろう。さあ聞け。 三 諸のつくられた事物は実に無常である。生じ滅びる性質のものである。それらは生じては滅びるからである。それらが静まるのが安楽である。P.161 2008.10.22 参考:『法句経』 友松圚諦『法句経講義』(講談社学術文庫)第一講 うらみは熄やむ 法句経 五 愚かな者を道伴れとするな。独りで行くほうがよい。孤独ひとりで歩め。悪いことをするな。求めるところは少なくあれ。――林の中にいる象のように。P.56 2009.04.11 二十 <わたしには子がいる。わたしには財がある>と思って愚かな者は悩む。しかし、すでに自分が自分のものではない。ましてどうして子が自分のものであろうか。どうして財が自分のものであろうか。P.163 第二五章 友 一 明らかな知慧のある人が友達としてつき合ってはならないのは、信仰心なく、ものおしみして、二枚舌をつかい、他人の破滅を喜ぶ人々である。悪人たちと交わるのは悪いことである。 2008.5.06 |

<常懐悲感 心遂醒悟> <常に悲感を懐いて心ついに醒悟す> 法華経如来寿量品第十六に<常懐悲感 心遂醒悟>(じょうえひかん しんすいしょうご)の一節があります。 <常に悲感を懐く>(つねにひかんをいだく)とは、一番大切に思っていた人が突然いなくなった時、私達は動揺しふ安になってしまいます。ましてやそれが永遠の別れであればなおさらであります。 私達にとって一番大切な人とは、両親以外にはないでしょう。両親の元に生を授かり、成長していく過程においては色々なことを教わり、いつも見守ってくれていた両親。いつまでも死なないだろうと私達は錯覚をしてしまいます。 だが必ずや別れの日は来る、悲しみの時は来る、このことを常に心にいだいている。 <常懐悲感>とはこのことを教えています。 また<心ついに醒悟す>(こころついにしょうごす)とは、その悲しみにいつまでもうちひしがれていてはいけない、頼るべきは自分である。自らの力でそれを乗り越えなければという気持ち、そのあとに大きな安心のあることのご教示です。 私達の生活の中には楽しい事ばかりではなく、苦しい事や悲しい事が次から次へと出できます。それを自らの力で乗り越えた時、お釈迦さまと同じ心持ちが生まれてくるのです。 他の悲しみを自らの悲しみと出来る大心が… *岩波文庫『法華経 下』P.36に見られる。
|
|
<多逢(たほう)聖因 縁尋機妙>(いい人に会っていると知らず知らずのうちにいい結果に恵まれる) *:日本経済新聞 交友抄12.10.20 |
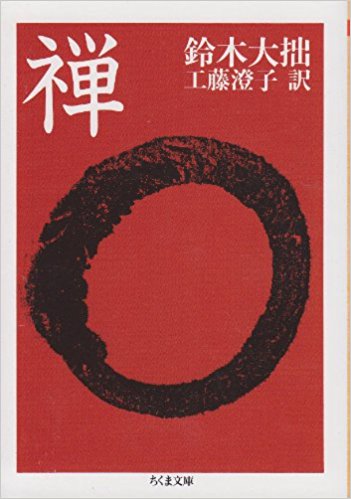
一 過去心ふ可得 現在心ふ可得 未来心ふ可得 二 <応無所住(おうむしょじゆ)、而生其心(にしようごしん)> 参考:<どこにもとどまらずに心をさとる>慧能はこの『金剛経』を聞いて、禅の真理に眼を開いたと言われている。鈴木大拙『禅』P.176 2009.08.06 |
衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)
煩悩無尽誓願断(ぼんのうむじんせいがんだん) 法門無量誓願学(ほうもんむりょうせいがんがく) 仏道無上誓願成(ぶっどうむじょうせいがんじやう)(三返) ※日曜日坐禅会では坐禅が終わりますと、参加者一同が唱えています。 |
|---|
|
観世音 南無仏 与仏有因 与仏有縁 仏法僧縁 常楽我浄 朝念観世音 暮念観世音 念念従心起 念念ふ離心 ※平成二十二年十月十三日:美弥子が雲の上に逝って以来のある日から、朝は<般若心経>夕は<十句観音経>を唱えている。 |
|
一 火を鑚るに未だ熟せずして息めば、火を得んと欲すと雖も火を得ること難かるべし。P.178
|
|
諸行無常ー諸行は無常なり 是生滅法ー是は生滅の法なり 生滅々已ー生滅滅し已(おわ)りて 寂滅為楽ー 寂滅を以て楽と為す |

友松圚諦『法句経講義』(講談社学術文庫)
まこと、怨み(うら)ごころは、いかなるすべをもつとも、怨みをいだきくその日まで、この地上にはやみがたし、ただうらみなさによりてこそ、そのうらみは息(やむ)む、これ易(かわ)りなき真理(まこと)ぞ。 法句経 六 P.61 われらはここ、死の領域(さかい)に近し、道を異にする人々は、このことわりを、知る由(よし)なし、このことわりを知る、人々にこそ、かくしていさかいは止まん。 法句経 九 P.310 心なお、けがれを除かず、ただ袈裟衣(けさころも)を、まとわんとす。されど、心ととのわず、業(わざ)、真理(まこと)はそわずば、彼は袈裟をまとわんに、ふさわしからず。 法句経 四十九 P.40 花びらや色や香を、そこなわず、ただ密味(あじ)のみたずさえて、かの蜂のとび去るごと、人の住む村々に、かく牟(み)尼(ひ)尊(じり)は歩(あゆ)めかし。 法句経 六十 P.176 眠りえぬものに、夜はながく、つかれたるものに、五里の路はながし、正法(まこと)を知るなき、おろかものに、生死の輪廻はながからん。 法句経 六十二 我に子等あり、我に財ありと、おろかなる者は、こころなやむ、されど、我はすでに、我のものに非ず、何ぞ子等あらん、何ぞ財あらん。 法句経 八十四 おのがため、はた他人(ひと)のためにも、子をも 財(たから)をも、領土(くに)をも願わざれ、上法(みちなき)によりて、おのが繁栄(さかえ)を願わざれ、かの人こそ 戒(いましめ)あるもの、智者(かしこきひと)法(のり)にそえるものなり 法句経 八十五 数多き人々のうち、彼岸(ひがん)に達するは、まこと かず少なし、余(あまた)の人はただ、この岸の上に、右に左に、彷徨(さまよ)うなり 法句経 九十一 P.283 心さときひとらは、家におぼるるなく、立ち去りゆく、水鳥の池を、すてさるごと、この家をすて、かの家をすつ *心さとき人とは<己れこそ、己れの寄辺(よるべ)、己れを措きて、誰に寄辺(よるべ)ぞ、よく整えし己れこそ洵(まこと)得難(えがた)き、寄辺(よるべ)をぞ得ん>の<よく整えし自己>なんです。 おのれこそ、おのれのよるべ、おのれを措きて、誰によるべぞ、よくととのえられし、おのれこそ、まことえがたき、よるべをぞ獲ん。 法句経 百八十二 ひとの生をうくるはかたく、死すべきものの、生命(いのち)あるもありがたし、正法(みのり)を耳にするはかたく、諸仏(ほとけ)の出現(あらわれ)もありがたし。 法句経 百八十七 P.234 太陽は昼に輝き、月は夜に照る、武人(もののふ)は武具(よそおい)、いかめしくかがやき、祭(まつり)の司(つかさ)は、心静かに光る、されど、さとれる者は、ひねもす、よもすがら、威光(ちから)もて、すべてに輝きわたる 法句経 二百十 P.103 愛する者らと、相逢うことなかれ、愛せざるものらとも、又しかるべし、愛するものを、見ざるは苦なり、愛せざるものを、見るは又苦なり。 法句経 二百七十七 P.153 萎(しお)れたる花びらを、すておとす、バッシカの草のごとく、乞食するものらよ、かくのごとく、むさぼりと、怒りとをふりすてよ。 法句経 三百六十五
その人にはこの岸もなく、かの岸もない。彼にはこの岸、かの岸、ともにない。かれにはなやみもなく、束縛もない。この人をこそ、わたしは婆羅門と呼ぶ。
2009.08.08 法句経 三百六十九
比丘よ、この船を空にせよ、汝この船を空にせば、そは早く走らん。貪りと憎しみとを断ち切り、もって涅槃へと汝は赴かん。
法句経 四百二十 P.182 もろもろの神も、ガンダマも、ひとも、彼の足跡を知るに由なし、かかる漏(あく)のつきたる、聖者(ひじり)、われは彼を婆羅門(ばらもん)とよばん |
|
一 彼此高処(ひしこうじょ)に安ずべきは高処に安じ、低処(ていじょ)に安ずべきは低処に安ぜよ。高処は高平、低処は低平に。P.43 二 侘は是れ吾にあらず。更に何れの時を待たん。P.111 三 凡そ諸々の知事頭首(ちょうしゅ)、及び当職作事作務(とうしきさじさむ)の時節、喜心・老心・大心を保持すべき者。P.194 |
|
一 観音流(ながれ)を入(かへ)して所知を忘ず。 ▼『傘松道詠』 一 春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪冷(すず)しかりけり
▼道元遺偈
生死事大、無常迅速、光陰可惜、謹勿放逸
|
|
一 口を守ること鼻のごとくすれば、万禍及ばず。 二 仙を得んと思はば仙道を好むべしと。 三 眼耳鼻舌、各々一切有無の諸法にお貪染せず、是を受持四句偈となづく。 四 冥機冥応 順現報受 冥機顕応 順次世受 顕機冥応 順後次世間
顕機顕応
六 世間の人多く云ふ、某し師の言(こと)ばを聞けども我が心に叶はずと。この言は非なり。知らず其のこゝろいかん。若しは聖教(しょうげう)等の道理の我が心に違背して非なりと思か。これは一向の凡愚なり。亦は師の云へる言が我が心に契(かな)はざるか。若し然あらばなんぞはじめより師に問ふや。亦日来(ひごろ)の情見を以て云か。もししかあらば是れは無始よりこのかたの妄念なり。学道の用心と云ふは、我が心にたがえども師の言ば聖教(しょうげ)の>言(ごん)>理(り)>ならば全く其に随て、本の我見をすててあらためゆくべし。此の心が学道第一の故実なり。
六 道者の行は善行悪行につき皆おもはくあり。凡人の量る所にあらず。 七 古へに三たび復さふして後に云へと。云ふ心は、凡そものを云はんとする時も、事を行ぜんとする時も、必ず復さふして行に言行すべしとなり。 八 畢竟じて何の用ぞと。 九 如来の開示に随ひて得度するもの多けれども、亦阿難によりて悟道する人もありき。新首座非器なりと卑下することなかれ。 十 念々止まらず、日々遷流して無常迅速なること、眼前の道理なり。知識経巻の教へを待つべからず。只念々に明日を期することなく、当日当時ばかりを思ふて、後日は太だふ定なりと知り難ければ、只今日ばかり存命のほど仏道に随はんと思ふべきなり。 十一 坐はすなはち仏行なり。坐はすなはちふ為なり。 十二 身心学道というは、身にて学道するなり、赤肉団の学道なり。身は学道より来たり、学道より来たれるは、ともに身なり。 参考:昨年一年、学生とともに『随聞記』を読んだ。一週間に一度、学生とともに大声で『随聞記』を読むと、胸の奥にたまったしこりもどこかへ消えてなくなった。『随聞記』には独特のリズムがある。それは道元禅師その人の命のリズムである。大声で至心に読むと、そのリズムが自分の命のリズムになることがわかる。『随聞記』は声に出して読まねば読む意味がない。宗教学者の紀野一義が、こんな思い出を書いていた。 |
|
無上甚深微妙法。(むじょう じんしん みようほう) 百千万劫難遭遇。(ひゃくせん まんこう なんそうぐう) 我今見聞得受持。(が こん けんもん とく じゅうじ) 願解如来真実義。(がん げ にょらい しんじつぎ) お経は自分のために読むことである。死者のために読誦されたお経の傍聴だけでなく、自分が主体になって積極的のお経をよむのである。 じつは、お経を読誦する前には、ほとんどの宗派において<開経偈>を唱えることになっている。 天台宗や浄土宗などはこれをそのまま読むが、真言宗などでは読み下し文にして唱える。 無上甚深微(み)妙の法は、百千万劫にも遭(あ)い遇(あ)うことかたし。われいま見聞し受持することを得たり。願くは如来の真実義を解(げ)したてまつらん。 ひろさちや著『般若心経の読み方』(日本実業社)P.34 |
|
▼昏鐘之偈 願わくは此の鐘聲法界に起こり 鉄囲い幽闇悉く皆聞く 耳根清浄圓通を證し 一切の有情悉く正覚を成せんことを ▼昏鐘之偈 此の鐘聲を聞き、煩悩を軽じ 智慧生長じ菩提を生じ 地獄を離れ火杭を出ず 願わくば仏と成りて衆生を度することを |

生死事大 無常迅速 光陰可惜 謹勿放逸 ★親鸞上人無常迅速:四季の移り変わり |
|
<梅花開五福> 一 雲在嶺頭閑ふ徹 二 水流碍下大忙生 三 萬物出処ず如好 四 無事是貴人(にん) 五 歩歩是道場 六 開門落葉多 七 是法平等無有高下 *無有高下は二重否定になっていることに意味がある。 八 半窓明月帯梅来 九 両 足 十 且坐(しゃざ)喫茶(きっさ) 十一 桜花開五福 十二 関従這裏入 |
寄 半少年 蓬生麻中直死而長 鶯囀花林舌自香 諸君求友須勝己 與悪者亡善昌 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・
|
|
▼仏教十戒 一 ふ殺生 二 ふ偸盗 三 ふ邪淫 四 ふ妄語 五 ふ綺語 六 ふ両舌 七 ふ悪口 八 ふ貪欲 九 ふ瞋恚 十 ふ邪見 |
▼モーゼーの十戒 一 唯一神の礼拝 二 偶像の禁止 三 神めいの乱称の禁止 四 安息日の厳守 五 父母への尊敬 六 ふ殺生 七 姦淫の禁止 八 盗みの禁止 九 偽証の禁止 十 物質欲の禁止 |
|
<無 事>とは、本来の自己に立ち返った安らかさを意味する禅語で、外に何も求めない満足の境地のこと。<人というものはとかく外に宝を求めがちだが、それではいつまでたっても平穏な世界から遠ざかってまま。自分に眼を向ければ平穏無事が何よりで、そのことを感謝し喜ぶことが吉祥に通じる唯一の道であると>と小林師は説かられます。
*:大徳寺黄梅住職
|
|
一 本来の面目 二 本分の家郷 三 唯心の浄土 四 己心の弥陀 *直木公彦『白隠禅師 健康法と逸話』 |
|
有七種施。ふ搊財物、獲大果報。 一 眼 施(がんせ) 二 和顔(わげん)悦色施 三 言辞施 四 心 施 五 身 施 六 牀座施(しょうざせ)> 七 房舎施
*雑宝蔵経という仏経教本の中にある。
|
|
二十二年十二月の下旬、と松原泰道『禅語百選』P.110<百尺竿頭進一歩>、『正法眼蔵随聞記』<百尺竿頭如何進歩>P.71をよみました。 その説明を併記します。 ▼先ず、松原さんは 百尺という長さに関係はありません。とにかく掲揚塔のように高いポールのてっぺんが百尺竿頭(かんとう)です。<上求菩提(じょうぐぼだい)>というさとりを求める向上の道程の絶対境で<孤峰頂上(こほうちょうじょう)>ともいいます。積む上にも積んで修業しなければ容易に到達し得ないところで、ここまでゆくのもたいへんです。 しかし、ここに停(とど)まってはいけないことを長沙(ちょうしゃ)禅師(中国唐代の禅僧・八六六年没)は、<百尺竿頭に坐する底(てい)の人、然(しか)も得入すと雖(いえど)も、未(いま)だ真と為(な)さず>と戒(いまし)めます。<釈迦も達磨(だるま)も目下、修業の真最中だ>と、禅者を戒めます。よく学ぶ者はつねに進歩します。百尺竿頭をなおも進まなければならないのです。しかし、百尺竿頭からなお前進するとは、どういうことでしょうか。英国の諺には<人は旅をする、旅をしてついに家に帰る。とあります。禅者は<上山(じょうざん)の路は是で下山の路>と申します。向上から向下に転進するのです。孤峰頂上で"いい子"になったり、"いい気持ち"になっていないで、泥んこの社会にもどることです。 行きと帰りを分離して考えるのではありません。帰ることと行くことが同一絶対にならなければ百尺竿頭に一歩を進めることにはなりません。帰るための帰り途(みち)ではないのです。百尺竿頭を登る向上への努力がそのまま人のためにつくす向下への努力になって、はじめて<進む>といえます。 ▼『正法眼蔵随聞記』では 示して云く、学道の人、身心を放下して一向に仏法に入るべし。古人云く、百尺竿頭如何進歩と。然あれば百尺の竿頭にのぼりて、足をはなたば死ぬべしと思ふて、つよく取りつく心のあるなり。其れを一歩(いつぽ)を進めよと云ふは、よもあしからじと思ひ切て、身命(しんみやう)を放下(ほうげ)するやうに、渡世(とせい)の業(げふ)よりはじめて一身の活計(くわつけい)に到るまで、思ひすつべきなり。其れを捨てざらんほどはいかに頭燃(づねん)を払ふて学道するやうなりとも、道(だう)を得ることはかなふべからざるなり。たゞ思ひ切(きり)りて身心(しんじん)ともに放下(ほうげ)すべきなり。 ▼『無門関』四十六 竿頭(かんとう)、歩を進む (岩波文庫)P.171~173 石霜(せきそう)和尚云く、<百尺竿頭、如何が歩を進めん>。又た古徳云く、<百尺竿頭に坐する底(て)の人、得入(とくにゅう)すと雖然(いえど)も未だ真と為さず。百尺竿頭、須(すべから)く歩を進めて十万世界に全身を現ずべし>。 無門曰く、<歩を進め得、身を翻(ひるがえ)し得ば、更に何(いず)れの処を嫌ってか尊(そん)と称せざる。是(かく)の如くなりと然雖(いえど)も、且(しばら)く道(い)え、百尺竿頭、如何が歩を進めん。嗄(さ)> 頌(じゅ)に曰く、 頂門の眼を瞎脚(かつきゃく)して、錯(あやま)って定盤星(じょうばんじょう)を認む。 身を拌(す)て能く命を捨て、一盲衆盲を引く。 石霜和尚が言われた、<百尺竿頭に在るとき、どのようにしてさらに一歩を進めるか>。また古徳が言われた<百尺竿頭に坐り込んでいるような人は、一応そこまでは行けたとしても、まだ真実というわけではない。百尺竿頭からさらに歩を進めて、あらゆる世界において自己の全体を発露しなくてはならない>。 無門は言う、<一歩を進めることができ、世界のただ中に身を現じることができたならば、ここは場所がよくないから、尊しとはいえないなどという処がどうしてあり得よう。そうはいうものの、一体どのようにして百尺竿頭から歩を進めるのか、言ってみるがいい。ああ>。 頌(うた)つて言う、 頂門の眼を失えば、 無用のものに眼がくらむ。 身を投げ命を捨ててこそ、 衆生を導くならん。 2010.12.30 |

般若心経は、<大般若経>という600巻の経典(約300万文字)の内容を、わずか276文字に凝縮したものです
摩訶 般若 波羅蜜多 心経(まか はんにゃ はらみった しんぎょう)
※写真は自筆写経。
観自在菩薩 行深 般若 波羅蜜多 時、(かんじさいぼさつ ぎょうじん はんにゃ はらみった じ、)
照見 五蘊 皆空、(しょうけん ごうん かいくう、)
度 一切 苦厄。(ど いっさい くやく。)
舎利子。色ふ異 空、空ふ異色、色即是空、空即是色。(しゃりし。しき ふい くう、くう ふい しき。しき そくぜ くう、くう そくぜ しき。)
受・想・行・識 亦復如是。(じゅ・そう・ぎょう・しき やくぶにょぜ。)
舎利子。是 諸法 空相、ふ生ふ滅、ふ垢ふ浄、ふ増ふ減。(しゃりし。ぜ しょほう くうそう、ふしょうふめつ、ふくふじょう、ふぞうふげん。)
是故空中、無 色、無 受・想・行・識、(ぜこくうちゅう、む しき、む じゅ・そう・ぎょう・しき、)
無 眼・耳・鼻・舌・身・意、無 色・声・香・味・触・法。(む げん・に・び・ぜっ・しん・に。む しき・しょう・こう・み・そく・ほう。)
無 眼界、乃至、無 意識界。(む げんかい、ないし、む いしきかい。)
無 無明、亦 無 無明 尽、乃至、無 老死、亦 無 老死 尽。(む むみょう、やく む むみょう じん、ないし、む ろうし、やく む ろうし じん。)
無 苦・集・滅・道。無 智 亦 無 得。(む く・しゅう・めつ・どう。む ち やく む とく。)
以 無所得 故、菩提薩埵、依 般若 波羅蜜多 故、(い むしょとく こ、ぼだいさった、え はんにゃ はらみった こ、)
心 無罣礙、無罣礙 故、無有恐怖、遠離一切 顛倒夢想、究竟涅槃。(し んむけいげ、むけいげ こ、むうくふ、おんりいっさい てんとうむそう、くぎょうねはん。)
三世 諸仏、依 般若 波羅蜜多 故、得 阿耨多羅 三藐 三菩提。(さんぜ しょぶつ、え はんにゃ はらみった こ、とく あのくたら さんみゃく さんぼだい。)
故知、般若 波羅蜜多、是 大神 咒、是 大明 咒、是 無上 咒、是 無等等 咒、能除 一切苦、真実ふ虚。(こち、はんにゃ はらみった、ぜ だいじん しゅ、ぜ だいみょう しゅ、ぜ むじょう しゅ、ぜ むとうどう しゅ、のうじょ いっさいく、しんじつふこ。)
故説、般若 波羅蜜多 咒。即 説咒 曰、羯諦 羯諦 波羅 羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶。般若心経
【全文】摩訶般若波羅蜜多心経 観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄。舎利子。色ふ異空、空ふ異色、色即是空、空即是色。受・想・行・識亦復如是。舎利子。是諸法空相、ふ生ふ滅、ふ垢ふ浄、ふ増ふ減。是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触・法。無眼界、乃至、無意識界。無無明、亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。無苦・集・滅・道。無智亦無得。以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罣礙、無罣礙故、無有恐怖、遠離一切顛倒夢想、究竟涅槃。三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。故知、般若波羅蜜多、是大神咒、是大明咒、是無上咒、是無等等咒、能除一切苦、真実ふ虚。故説、般若波羅蜜多咒。即説咒曰、羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶。般若心経 2016.4.26 ※参考:ひろさちやの般若心経88講 ※参考:『仏経読本 3』(曹洞宗宗務庁) |

 生ける時、善をなさずんば、死する時、獄の薪とならん。得難くして移り易きは、それ人身なり。発し難くして忘れ易きは、これ善心なり。
生ける時、善をなさずんば、死する時、獄の薪とならん。得難くして移り易きは、それ人身なり。発し難くして忘れ易きは、これ善心なり。


 9月27日、京都嵯峨の天龍寺で死んだ臨済宗の高僧。後醍醐天皇、足利氏の帰依あつく、天龍寺の開山としてなだかい。『夢窓国師語録』
9月27日、京都嵯峨の天龍寺で死んだ臨済宗の高僧。後醍醐天皇、足利氏の帰依あつく、天龍寺の開山としてなだかい。『夢窓国師語録』 曹洞宗祖先道元の正法眼蔵の<菩提薩捶四摂法>の中の<愛語>の条を愛誦して、座右のの銘としてゐました。現に良寛自筆の<愛語>を、ところどころ省略して読んで見ますと、――
曹洞宗祖先道元の正法眼蔵の<菩提薩捶四摂法>の中の<愛語>の条を愛誦して、座右のの銘としてゐました。現に良寛自筆の<愛語>を、ところどころ省略して読んで見ますと、――

 十牛図もどうやら大団円にこぎつけた。入廛垂手(につてんすいしゆ)とは、市街にはいって教化済度の手を垂れることであるから、前にいったように<群集>に交じり<漂える国>にはいって、自由自在に利他行をすることに当たる。病人が病気がなおったら社会へ戻って働くように、修行者が悟ったら迷える衆生に福音を頒(わか)たなければならない。灰頭土面とか、和光同塵とかいう言葉はその利他行をさすのであるが、しかし、この境地には衆生を済度しなければならないとか、無縁の大慈の発動がなければ宗教者ではないとかいうような、努めて行う形跡は少しもない。雲の岫(くき)を出るように、水の科(あな)をみたすように、きわめて自然に、心の欲する所に従いながら、しかもおのずから則(のり)にかなう任運自在さがある。衆生済度というような固くるしさよりも、むしろ遊戯三昧といったほうが適切といえる境涯である。
十牛図もどうやら大団円にこぎつけた。入廛垂手(につてんすいしゆ)とは、市街にはいって教化済度の手を垂れることであるから、前にいったように<群集>に交じり<漂える国>にはいって、自由自在に利他行をすることに当たる。病人が病気がなおったら社会へ戻って働くように、修行者が悟ったら迷える衆生に福音を頒(わか)たなければならない。灰頭土面とか、和光同塵とかいう言葉はその利他行をさすのであるが、しかし、この境地には衆生を済度しなければならないとか、無縁の大慈の発動がなければ宗教者ではないとかいうような、努めて行う形跡は少しもない。雲の岫(くき)を出るように、水の科(あな)をみたすように、きわめて自然に、心の欲する所に従いながら、しかもおのずから則(のり)にかなう任運自在さがある。衆生済度というような固くるしさよりも、むしろ遊戯三昧といったほうが適切といえる境涯である。