ー私の古典散歩ー』1974年11月発行 新潮社――
|
田辺聖子「文車(ふぐるま)日記ー私の古典散歩ー」1974年11月発行 新潮社 田辺聖子は「更科日記」の少女がそうであったように、古典を夢中になって読みつつ育った少女だった。その彼女が「今までの人生で私は、一つ、また一つと、大好きな古典作品を心の底にためていった」ものを、この本にしている。本の中に67もの章があるにもかかわらず、古典案内の解説書にはしていないのは、彼女が自分の好きな古典ばかりを語っているからだろう。これだけの数の多様な古典を縦横に語ってしまう実力には恐れ入る。 あとがきにある。 「わが愛熱や執着もまた、あるいは古典ぎらいな方、古典に不案内な方への、おのずからなる道しるべになるかもしれぬと思うようになりました。」 私はいま、「萬葉集」や「古事記」などに、今まで縁もゆかりもなかった方々に、好きな指環やブローチのように身近に手馴れ、いつくしんで頂きたいと思ったりしています。」P.277 「民族遺産としてこんなすぐれた古典を多く持つという日本という国は、何というすばらしい国でしょう。私は母国・日本をとても誇りに思い、また好きです。」P.278 平成29(2017)年5月14日 |
|
むかしはものを(小倉百人一首) P.17~19 〽あひみてののちの心にくらぶればむかしはものを思はざりけり 権中納言敦忠(九〇六~九四三:黒崎記) 百人一首の歌の中では、私の好きなものの一つです。(百人一首43番目の歌:黒崎記) 平明なことば、なだらかなしらべ、一読して意味がすらすらりとわかります。「あう」というのは、昔の語意では男女のあいだの直接的な恋愛行為を指します。 恋の夜を体験したあとは、いろんな物思いのたねがふえた、これにくらべると、昔は何んとわけ知らずの、単純なこころだったことよ、というほどの意味でしょう。従来もそう解釈されてきました。 しかし、私はこの歌の「あひみての」という語句に、複雑な皮肉のひびきを感じます。そしてその作者が男であるという点でも、大いに興味をもたないではいられません。従来行われてきた素直な解釈は、あまりにも女性的にすぎる気もされます。 この男は、かねて恋い焦がれていた女と、とうとう、恋の一夜を持つことに成功した。 朝まだき、彼は馬に騎ってか、あるいは牛車の奥ふかく身を隠してか、女のもとから帰ってゆく、そのとき男の胸にあるのは、あんがい、白けた思いかもしれない。恋の手だれであるこの男は、一つの恋がいま、はかなくうつろい、色あおざめ、しぼんだことに気付いたかもしれません。 あの女を望んで得られず、あんなに烈しく目もくらむ思い出、渇(かわ)くがごとく欲していたとき、その気持ちは、今思えば、じつに浅はかで単純なものだった。あの女を得たいというだけでいっぱいだった。しかしいま、その欲望は燃えつき、充(み)たされ、鎮められてしまった。たちまちの心がわり、とまではいわぬけれど、冷たい、水のような醒めた思いが、男の胸をみたしはじめています。男は恋が生まれ恋が死ぬときの大きな動揺をかんじています。 この男にとって、女は思いのほか物足りぬ人だったのかもしれませんし、また、いったん躰(からだ)を交わしたあとは、心ざまが急速に浅くなってゆく、男の性(さが)のせいかもしれません。 女のほうは昔より恋心が募り、男の方は反対の意味で「昔は単純だった」と思う。一つの歌が、女性的解釈と男性的解釈と両方にとれるところが私には面白いのです。そして今の私には、男性的解釈のほうが、より現代的な感じで、現代の男も中世の男もかわらぬ男ごころ、という点で面白く思われます。 作者の敦忠は、左大臣藤原時平の三男で、世にときめく貴族でした。「世にめでたき和歌の上手、管弦の道にもすぐれたまへり」といわれた芸術家でもありました。 敦忠の美しい北の方(妻)は、もと、時の東宮のお妃だった人でした。東宮と妃の恋の文使いをつとめたのが、若い日の敦忠だったのです。文使いの青年貴公子と妃のあいだに通いあう心があったのかどうか、東宮薨じたもうたのち、妃は敦忠の北の方になりました。 *北の方:公卿など身分の高い人の正妻の敬称。 敦忠は北の方を愛していましたが、あるときこんなことをいいました。「私の一族はみな短命だから、私も必ず短命でしょう。あなたは、私が死んだら今度はきっと、あの文範の思いものになるでしょうね」文範というのは、敦忠の家に出入りする家令の青年でした。無論、北の方はびっくりして否定しました。「思いもよらぬこと、そんなことは決してありますまい」と誓いました。「まあ、見ていてごらんなさいよ」敦忠は笑いながら申しました。 まもなく彼は三十八歳の短い生涯を終えました。その後、果して予言通り、北の方は文範を夫とする運命になりました。 敦忠はきっと、男女の愛の微妙なながれのゆくすえを、早逝者の直観で洞察していたにちがいありません。彼は醒めた人の眼で、世を見、恋を見ました。「むかしはものを思はざりけり」は、彼の皮肉なつぶやきだったかもしれません。 平成29(2017)年5月17日 |
|
あつもり(平家物語) P.20~22 「平家物語」は美しいほろびを謳う物語です。それぞれの人の最後を語るとき、最も美しく最も力強く、感動的な昂揚(こうよう)をしめします。 幼帝のご入水、能登守の最後、忠度の最後、そして木曽義仲の最後。 なかでも、やはりいちばん感動的で美しく悲しく、ドラマチックなのは、敦盛の最後ではありますまいか。 一の谷の合戦で、破れた平家は浮足立って浜辺へ落ちてゆきます。 坂東武者たちはそれを追って汀へ追いつめる。源氏方の中に熊谷次郎直実(なおざね)は、よき大将軍に組まばやと物色するうち、平家の武者一騎、馬を海へうち入れ、沖の舟めがけて泳がせるのを発見します。萌黄の匂の鎧に、鍬形打ちたる甲、こがね造りの太刀という美しい武者ぶり、「まさなうも敵にうしろを見せさせ給ふものかな、かへさせ給へ」と扇をあげて招くと武者はいさぎよく取ってかへし、立向かってきました。 汀でむずと組んだ屈強の侍の熊谷、なんなく取りおさえて、首をかこうとかぶとをはねのけみれば、これはいかに、 「年十六七ばかりなるが、うす化粧してかねぐろなり……容顔まことに美麗なりければいづくに刀を立つべしともおぼえず」 わが子の小次郎ぐらいの年で、薄化粧して歯を染めている美少年です。熊谷はなさけを知る武将でした。この一人を助けたとて源氏が負けるものではあるまいと助けようとしますが、しかし「ただとくとく首をとれ」と若武者はけなげに言い放ちます。 武門の意気地、熊谷は泣く泣く首を打ち、のちにこのいたたましい思い出が、彼の出家遁世の契機となったことは、ひろく世に知られる通りです。若武者は錦の袋に入れた笛を腰にさしていました。それで、この公達は経盛の一子、無官大夫敦盛とわかったのでした。 このエピソードが、文楽に歌舞伎に謡曲に、とひろく愛されてきたのは、熊谷の人間味ある心と敦盛の散りぎわの美しさを、人は、いとおしまずにはいられないからでしょう。 敦盛は一騎打ちになって組みしかれてから、「あはれたすけたてまつらばや」という熊谷の好意を武士らしく拒みます。さらには、その前に熊谷に招き返されて、すでに海へ乗り入れている馬の首をたてなおし、取ってかえします。 人は、その心ざまに打たれないではいられない。なぜ少年は敢て引っ返したか。 江戸の笑い話に、敦盛のことが出ています。「なぜ敦盛はとって返したか」ということをみんなで論じている。おいらなら委細かまわず逃げてゆくがなあ、ということになって、結局「敦盛も熊谷とは思わなんだのさ、何かうしろからおいおいと呼ぶから手拭いでも落としたのかと思ったんだ」という笑い話です。 敦盛が熊谷に「かえさせ給へ」と声をかけられたとき、彼は恐怖よりも、男の、武士のプライドでその心をいっぱいにしたことでしょう。 浜や汀には、雑兵が見ていたかもしれない。あるいは、誰も、熊谷とこの若武者に気付かぬ乱戦の最中だったかもしれない。 しかし敦盛はどちらにしても引っ返すプライドをえらんだのです。「それは男のええかっこや、僕は、逃げるのがプライドや」と現代の若い男性がいいました。 *こんな想像をするのも古典散策の楽しみか。 たしかに、引返して討たれる方がたやすく、満場注視の中で逃げ出す方がむつかしいということもあります。そして、後者の方が、より強い男の誇りなくては、かなわぬ場合もあります。人間の強さ、男の誇りは、一見、格好の悪い卑怯みれんな振舞いの場合にこそ要るのでしょう。しかし敦盛は格好よさの絶頂で花と散る誇りをえらびました。それは人々が夢みる一つの男の死の典型なのです。それゆえにこそ、敦盛の最期は、人々の心にいつまでも熱く燃えるのです。 *参考:角川文庫『平家物語』下、P.103~105 「敦盛最期の事」。この本を引きだして読むと、この記事の中の「熊谷が発心の心は、出で来にけり。」に赤色の傍線を引いていた。(黒崎記) *敦盛の態度は、先の大戦中、海軍兵学校の卒業生たちのそれを思わずにいられなかった。(黒崎記) *書写していると、琵琶法師を思い出した。それをインターネットの平家物語 祇園精舎/岩佐丈を聞いた。 平成29(2017)年5月18日 |

北浜の米市(日本永代蔵) P.23~25 井原西鶴(1642-1693年)という人は、どんな顔をしていたのでしょうか。残された画像でみると、傲岸な表情を浮かべています。 私は、西鶴が誰かから話を聞いている。つまり、取材している表情などが一番、想像しやすいのです。 いったい、西鶴という人は、元禄という社会の上から下まで、裏から表まで、見透し知りつくしていたかに思えます。武家社会も町人世界も、男も女も、彼にとっては飽くなき好奇心と、貪欲な知識欲の対象でした。殻は人間社会のことなら、どんなことにでも、猛烈な興味と関心を示しました。 彼の小説には、だから、社会のありとあらゆる階層・職業の男女が登場します。 大名も乞食も、坊主も商人も、やくざ、遊女、でっち、奥方、浅葱うら――つまり地方武士――たいこもち、豪商、陰間役者、百姓、漁師、いろんなさまざまの人間が、泣いたり笑ったり、怨んだり、恋したり、さまざまの人生模様をくりひろげます。 オレの知らぬ人生、人間などあるものか、といった西鶴の傲岸、尊大な自負心が、いたるところに躍動しています。 さぞかし現実の西鶴は、屈折の多い、ひとすじ縄でゆかぬ、いやな中年男だったでしょう。 意地わるく、そして自ら恃むところ厚いゆえに、他の作家や文学者を声高くおとしめて憚らぬ、不遜な自信家でもあったでしょう。その彼が好奇心の塊になって、 「それからどうした! え!」などと、つめよらんばかりに迫ったりすのですから、取材される側はたじたじとなる。 「いやですね、旦那」 などとへきえきしながら、つい彼の強引さにひきずられて、浮世の苦労、人の身の上の流転などをしゃべってしまう。。西鶴は乞食のムシロ小屋の中であろうと遊女の床であろうと、商家の店先であろうと、どこへでも出かけていって、人の世のこぼれ話をたのしんだことでしょう。彼は面白さに有頂天になり、フムフムと夢中で聞いて、かくして彼の小説的財嚢はますますふくらんでゆく、といったふうだったかもしれません。それが彼の傲岸不遜な作風と人がらを支えたかもしれない。しかし、傲慢な自信だけでは作家の資質として完全とはいえますまい。彼の文章は、決してそれだけではないことを示したいます。 西鶴の文章はリズミカルで、しかも言葉が豊富多彩、その上、内容がぴっしりつまっていて、要するに中身が濃いのです。それが惜しげもなく、ツルべ打ちに出てくるのですから、その面白さに、読むものはあっけにとられます。――私の大好きな一節をとり出しますと、「日本永代蔵」の巻一「波風静かに神通丸」の章、大阪は北浜の米市、中の島の米問屋がたちならぶあたりの風景描写です。さかんな商いのありさまを、彼は口いそがしく、こう活写します。
※参考角川文庫『日本永代蔵』P.302。記述は少し異なる(黒崎記) なんという、的確でしかも、北浜・米市の活況は元禄の浪花商人の誇りであり、感激であったでしょう。それはそのまま西鶴自身の誇りと感激でもありました。彼は商いの活気を愛し、人のいとなみの盛んなのを愛しました。彼の小説の底にあるのはそれです。西鶴はどんな小説にも「生きている喜び」を謳わずにはいられない作家なのでした。 2025.11.29 記す。
|
|
男の友情(木曾義仲と巴午前) P.29~34 男と女のあいだに真の友情はあるのでしょうか。私にとってはいつも尽きせぬ、興味ある小説のテーマです。 『平家物語』や『源平盛衰記』にもみられる木曽義仲と巴御前の物語は、私には男と女の友情のように思えてならないのです。 巴は義仲の実質的な妻であり、義高という子供まで持ちました。また義仲にとっては最愛の恋人であり、妹のような幼なじみでもありました。 義仲は二歳のときに戦火に追われて母のふところに抱かれたまま、木曽谷にのがれました。木曽谷には乳母の夫中原兼遠がいたのです。 兼遠はゆくすえ、源氏の棟梁とも仰がれるべきこの幼な児をたのもしく引き受け、心をこめて養育しました。そして息子の樋口兼光、今井兼平、娘の巴たちも、あげて義仲の無二の友となり、最初の、そして最も忠実な家来になりましら。 治承四年(一一八〇年)、いよいよ時が来て、義仲が平家打倒の旗をあげたときも、それから連戦連勝、平家を打ち破って京へ入ったときも、つねに彼ら乳兄弟は、義仲のそばを離れなかったのです。 けれども朝日将軍とよばれた義仲の得意絶頂の時代は短く、たちまちに今度は、範頼、義経の鎌倉勢に追われる身となります。 六条河原で木曾勢はめざましく戦ってほとんど玉砕、山科、四の宮河原をすぎるころには、ついに主従七騎になってしんまいました。しかもその七騎の内にも巴は討たれずに残っているのです。 「平家物語」によれば、彼女は、 「いろしろく髪ながく容顔まことにすぐれたり」 *『平家物語』(角川文庫下巻)P.64 木曽谷の美しい女鹿のような彼女は、また打ち物とっては鬼もひしぐといわれた強力(ごうりき:つよゆみ)の女丈夫でした。剛弓を引き、荒馬をのりこなし、「度々の高名、肩をならぶるものなし」という、りりしい女武者であったのです。 巴その日のいでたちは萌黄おどしの腹巻に五枚甲の緒をしめ、連銭葦毛の愛馬「春風」に金覆輪の鞍を置き、黒髪をうしろに長し、額には天冠をあてるという、美しくもいさましい武者すがた、彼女は、夫であり恋人である義仲を守って、敵をけちらしながら、ここまで逃れてきたのでした。 *ジャンヌ・ダルクを想う。 義仲は、乳兄弟・今井四郎兼平の行方を案じていました。 「幼少竹馬の昔より、死なば一所で死なんとこそ契りましに、ところどころでうたれん事こそかなしけれ、今井がゆくゑをきかばや」 四郎は勢田をかためていましたが、これも義仲を心配して都へ引き返す途中、大津の打出の浜でゆきあいます。 「互に、なか一町ばかりよりそれと見知って、主従、駒を早めて寄りあふたり」 どんなに主従手をとりあって喜んだことでしょう。「契はいまだくちせざりけり」 」最後の一戦をと、敗残の兵を集めて思うさま戦います。 義仲このとき三十一歳、色白き美青年です。その日の装束は赤地錦の直垂に唐綾おどしの鎧をきて、鍬形打った甲の緒をしめ、いか物づくりの大太刀をはき、石打ちの矢を負い重籐の弓もって「きこゆる木曽の鬼葦毛という馬の、きはめて太うたくましゐに、金覆輪の鞍をいてぞのッたりける」 今日が最期と観念した木曽義仲の戦いぶりはすずやかで壮快でした。「あぶみをふンばり立ちあがり、大音声をあげて」名のりかけます。 「昔はききけんものを、木曽の冠者、今は見るらん、佐馬頭兼伊予守、朝日の将軍、源義仲ぞや。甲斐の一条次郎とこそきけ。たがいによい敵ぞ。義仲うッて兵衛佐に見せよや」 一条の次郎の勢は、すわこそ、「只今名乗るは大将軍ぞ。あますな者共、もらすな若党、うてや」とどっとうちかかり、乱戦になりました。こちらは名代の屈強の木曾勢三百余騎、攻め手の六千余騎の中を、たてさま・よこさま・蜘蛛手・十文字にかけわってけちらし、け破って出たころには、味方は五十騎ばかりになっています。なおも迎える敵勢のかこみをかけわりかけわりゆくほどに、ついに主従五騎になってしまいました。 その五騎の内にも、巴はまだ討たれずに残っているのでした。 義仲は巴にいいました。 「おのれは疾う疾う、女なれば、いづちへもゆけ。我は討死せんと思ふなり。もし人手にかからば自害をせんずれば、木曽殿の最後のいくさに、女を具せられたりけりなンどいはれん事も、しかるべからず」 義仲はもう死の覚悟をきめています。武士の最後の時まで女を連れていたといわれたくない、と巴を去らせるのです。彼は、巴だけは生き残らせてやりたいと思ったのでしょう。 巴は「なほ落ちもゆかざりけるが、あまりに言われ奉りて」最後の働きをお見せしてからと、敵勢の中へかけ入り、首を一つ切って、別れがたき義仲と別れます。
義仲にとっては巴を去らせることが、最大の愛情だったのでしょう。けれども、巴は、義仲と共に死にたかったのです。 童女の日から、兄とも恋人とも夫とも頼んだ義仲という男への愛は、強い友情に支えられいたのです。 共に生き共に戦い、男と同じ条件で、ここまで生きのびたものを、しかし最後には、男と女として、へだてられたのです。 やがて義仲は、四郎と主従二騎になってしまいます。 「日頃は何ともおぼえぬ鎧が、今日は重うなッたるぞや」と義仲が述懐します。四郎は声を荒げて励ますのです。 「御身もいまだ疲れさせ給わず、御馬も弱り候はず。何によッてか、一両の御着背長(おんきせなが:鎧)を重うはおぼしめし候べき。それは味方に御勢が候はねば、臆病でこそ、さはおぼしめし候へ。兼平一人候とも、余の武者、千騎とおぼしめせ。矢七つ八つ候へば、しばらく防ぎ矢つかまつらん。あれに見え候、粟津の松原と申す。あの松の中で御ン自害候へ」 しかし義仲は四郎のそばを離れようとせず、いい切ります。 「義仲、都にていかにもなるべかりつるが、これまで逃れくるは、汝と一所で死なんと思ふためなり。所々で討たれんよりも、ひとところでこそ討死をもせん」 そして馬の鼻を四郎の馬とならべ、敵中にかけ入ろうとしますので、四郎は馬からとびおり、主の馬の口にとりついてとどめます。 「弓矢とりは年ごろ日ごろ、いかなる高名候へども、最後のとき不覚しつれば長き疵にて候なり。御身は疲れさせ給ひて候……」 四郎は、さきに義仲をはげますときは、まだ御身も御馬も疲れてはいられぬものを、と叱咤しました。でもいまは最後です。「よくここまで戦って来たものです。おたがいに……。花を咲かせた一生だったではありませんか。やることはやったのです。あなたは疲れたのだ……」男のやさしいいたわりと、あつい友情が感じられる四郎の言葉です。四郎はなおもとききかせます。名もなき雑兵にうたれたりなされては、口惜しいではありませんか。 義仲はやむなく栗津の松原さしてただ一騎かけこみます。四郎は五十騎ばかりの敵勢の中へかけ入り、名乗りをあげて、射残した矢を射かけ、打ちものとって馳せ、さんざんにうちやぶって時をかせいでいました。けれども義仲は深田の中へ馬をのりいれ、足をとられた所を射切られ、ついに首をとられました。その勝ちなのりを聞いた四郎は、 「今は誰をかばはんとてか、いくさをばすべき。是を見給へ、東国の殿原(とのばら)、日本一の剛の者の自害する手本」 と太刀の先を口に含み、馬より逆さまにとびおち、貫いて自害しました。今井四郎兼平行年三十三歳、義仲より二つ上の乳兄弟は、かねての契りのとおり、もろともにほろんだのです。 男たちの友情は、共に美しく死にほろぶときのためのもの、ーーそして、男と女に、もし友情があるとすれば、それは共に生きるときのためのものではないかと……私は、義仲と巴、義仲と四郎を並べたとき、思うのです。 参考:巴が義仲と別れてから:落ち延びた後に源頼朝から鎌倉へ召され、和田義盛の妻となって朝比奈義秀を生んだ。和田合戦の後に、越中国礪波郡福光の石黒氏の元に身を寄せ、出家して主・親・子の菩提を弔う日々を送り、91歳で生涯を終えたという後日談が語られる。(黒崎記) 平成29(2017)年5月20日6:12 |
|
心あひの風(催馬楽) P.35~37 あるとき、私が越前・福井駅におりましたら、元気のいい高校生の少年が数人、剣道の道具をかついで、やってきました。ぞの道具には「武生高校」とありました。そういえば、武生はここから遠からぬ町、私はとてもなつかしかったのです。 現実の武生市は知りませんが、古い昔の唄に、こんなものがあるのを思い出したからです。 道の口 武生の国府にこれは催馬楽のうたの一つです。 催馬楽は、おもに平安期ごろ、貴族たちに愛された歌曲なのですが、もとは、庶民のひなびた里うただったのです。それを管弦にのせて調子やメロディーをつけ、貴族たちは宴会でうたいました。だからこの文句も、流れ流れてゆく浮かれ女の哀愁がこもっています。 道の口というのは、地方へくだる道の、ほんのよりくち、という意味。越前は京にちかいところです。武生には国府の役所があり、人々の交通もさかんで、遊び女も集まったことでしょう。 「あたしは武生の国府にいると親に伝えておくれ……仲好しの風よ」 というわけです。「さきむだちや」というのは、はやし言葉です。 柳田国男さんは「アイの風」または「ァユの風」とは、海岸に向って吹く、航海によい風、船を港入りさせ、くさぐさの珍かなるものを、なぎさに向って吹きよせてくれる。人間にとって、なつかしい、仲よしの風という意味のことを「海上の道」で、いっておられます。(※参考:柳田国男著『海上の道』がある。岩波文庫などで入手できる。黒崎記) この唄を口ずさんだのは、武生の国府の町まで売られ売られてきた遊女でしょうか、少年でしょうか。私のような年ごろの女はふと、映画の「阿片戦争」で唄われた淋しい唄を、思い出さずにいられないのです。 風は海から吹いてくるアイの風はやさしく港へ吹きつけ、また船を送り出してくれる。 風のたよりというけれど、わが思う人に伝えてくれないものかしら、あたしがここに生きてるって……。古い、古い唄でありながら、いまのはやりうたとすこしもかわらない、ほんとうに人間の発想というのは、千年前も、いまも、さして違わないものです。 こんな唄を唄わずにいられない人たちの身の上を、あれこれと考えると、私はやっぱり「山椒大夫」の物語を思い浮べたりします。 おどろおどろしい中世の闇。 鬼か夜叉のような人買いの横行。武者ばらのいくさ、人もなげにはびこる物盗り、引きはぎ。中世はくらい、蒙昧な、闇の世代でした。もしそれ、力ない女や子供たちがひとたび恐ろしい運命に捲きこまれたら、「山椒大夫」の邸に売られた安寿と厨子王のような、からい目にもあったことでしょう。五百年ほどあとの室町時代のうたにも、こんなのがあります。 人買い船は沖を漕ぐ とても売らるる身を現代でも人買い船は、西に東に走っています。 東南アジアの少女たちだけでなく、心ならずも、あるいはわが心からふるさとを離れて流浪する運命に、身をゆだねている人はたくさん、います。みちのくち、武生の国府に、 われはありと 親に申したべふと、面を打つ風に、心あらばたよりをことづけたいと思う人は多いでしょう。 2022.09.09 重陽の節句の日、記す。
|
|
舟 唄(土佐日記) P.77~79 「土佐日記」にある別の一面、ふしぎな明るさ、ユーモアは、作者の、舟旅への感興からきています。 ことに、作者が今まで知らぬ、かこ(船人)、かじ取りのたたずまい。荒々しい船頭らのありさま、いうことすること、うたう唄。 上流階級であった国司の一行としては、彼らのうたう歌声に、耳を傾けずにはいられませんでした。 彼らは舟仕事をしながら、哀愁こめてうたいます。
なほこそ国のかたはやみあれ わが父母 ありとし思へば
情けを知らぬげな、むくつけき海の男たちが無心にうたう歌は、はるばると海の上にひびきわたり、人々の旅愁をかきたてたことでしょう。 土佐の国府を出て、海岸づたいに北上し、鳴門海峡から紀淡海峡をわたり、和泉の灘から淀川をさかのぼって桂川に入り、京へつくというのが土佐海路のコースですが、千年の昔ゆえ、二カ月ちかくかかる大航海です。 「山も海もみな暮れ、夜ふけて、西ひんがしも見えずして天気のこと、かじ取りの心に任せつ、男もならはぬは、いとも心細し。まして女は舟底にかしらを突きあてて、音をのみぞ泣く」 ならわぬ舟旅に、みんなは悲しみ苦しんでいるのに、船頭、水夫たちは平気で、 「舟唄うたひて、何ともおもへらず」 その歌がまた、のんびりした、野趣満溢のたのしいフォークソングなのです。おそらく、そのころの民衆のはやり唄だったのでしょう。
補注春の野にてぞ、音をば泣く。春の野で声をあげて泣くよ、ススキの葉で手を切りながら摘んだ若菜を、今ごろは、親がむしゃむしゃむさぼり食っていることだろう、それとも姑が食っているのか。ゆうべの可愛い子ちゃんがまた来ないかな、あの金をもらわなきゃ。うそをついて掛買いをして、金も持ってこず、自分も顔をみせもしない。――かへらや、というのは、ハヤシことばだといわれています。 「これらを人の笑ふをききて、海は荒れるれども、心はすこしなぎぬ」 ほんとうにこの歌には間抜けたユーモアがあって、これにメロディーや拍手がついて唄われれば、ついふき出すおかしさがあったでしょう。 荒くれ男たちは何の教養もない無心な人々ながら、それだけに、いう言葉ふと、おもしろいのです。 「黒鳥のもとに、白き波をよす」 などとつぶやく言葉さえ、何か身にしむ風趣として都びとの耳にはとまります。 ことにおかしいことがありました。ある日、<舟を早く出せ、天気がよいのに>といいますと、かじ取りはかしこまって叫びました。 「み船より 仰せたぶなり 朝きたの いでこぬ先に 綱手はや引け」 一行はそれを聞いて、「あやしく歌めきても言ひつるかな」と興じ入ります。「この言葉の歌のやうなるは、かぢ取りのおのづからの言葉なり」 船頭がいつも使っている言葉で指図すると自然にみそひと文字の歌になっていたのです。「朝きた」は、朝、はげしく吹く北風のことです。私はこのくだりを読むといつも、以前ラジオで聞いた愉快な天気予報を思い出します。 「明日は北東の風うす曇り 天気しだいによくなる見込み」 とまれ、「土佐日記」にあるこんなユーモアに、私は作者、紀貫之の男らしい大らかさを発見して、貫之が好きなのです。 補注:「土佐日記」(角川文庫)P.20「舟歌うたひて」(原文)。P.50(現代語訳) 2025.12.02 記す。 |
|
ロマンのページ(今昔物語) P.80~82 これ一冊あれば、決して退屈しない本、というのがあります。私には「今昔物語」です。 この本はあまりにも厖大、浩瀚なもので、たいていの人は、むつかしい名前の羅列された、仏教説話集、天竺、震旦の部を、とばしています。実は、私も、そうです。そうして、「本朝」の「世俗」なんてタイトルのところを読むのです。このお話集を、「日本のアラビアンナイト」といわれたのは、小島政二郎氏ですが、一つ一つのお話は短いけれど、奥ゆきがあって、アラビアンナイトよりも多彩で変化にみちています。 この本をよむと、平安末期というのは、乱世蒙昧なりに、決して無気力・頽廃の時代ではなかったようです。この中に出てくる主人公たち、天皇・皇后、大臣・武士・僧侶から、乞食・遊女、ひさぎめ(行商人のおばさん)、猟師にぬすびとに至るまで、みんなィキイキと、正直に、闊達に生きています。ぬすみ、人ごろし、放火、思い立つと矢もたてもたまらず、欲望のままに悪業(あくごう)を犯すかと思うと、酷烈な乱世に生きながら、仏の教えを守って慈悲の心を失わない男や女、それらが笑ったり、泣いたりしながら、縦横無尽に活躍します。全篇、「今ハ昔」からはじまり、「トナム語リ伝へタルトヤ」で終ります。 ところが、中に、ごくまれに、「未完」のおはなしがあります。人の手から手へ写すあいだに、紙がちぎれ、やがて散佚したのでしょう。 また、そういう、「以下欠」となっているお話に限って、あとがとても知りたいのいです。 今は昔、ある身分の高い貴族がありました。妻のほかに、ひそかに愛人を持っていましたが、折も折りとて双方がいちどきに懐妊し、どちらも女の子ができました。夫はよん所なく妻に打ちあけました。妻はやさしい心の女でした。<じゃここへ引きとって一緒に育てましょう>といい、「此ノ継子ヲニクシトモ思ハデ、我ガ子ニモ劣ラズ思ヒテスグシケルニ」姫君につけられた乳母の方は、その子が同じように大事にされたのが憎くてならないのです。乳母はひそかに腹心の下女をよび、
と、愛人の生んだ方の赤ちゃんを渡します。下女がとっとと、赤ん坊を抱いて道をゆく途中、美々しく勢ぞろいした、あるお金持ちの一行にゆきあいました。そのお金持ちの夫婦は、子供のないのを悲しんで観音さまに子を授けて頂くよう、お詣りに来たのですが、卑しげな下女が美しい赤ちゃんを抱いているのを見咎め、いろいろ聞きただします。どうせ捨てろと命じられた子供なので、下女は喜んで、夫婦に与えました。 「ヒトへニ観音ノ御助ケ」 と、夫婦はとび立つばかり喜び、抱いて帰って大切に育てました。――さて、親の家では大さわぎして失われた赤ちゃんの行方をたずねましたが、消息はしれぬまま、残された姫君を一層、大切に育てました。姫君は美しく成長し、これまた似合いの、美しい公達と結婚しました。しかし楽しい新婚生活も束の間、姫君はふとした病がもとではかなく世を去ります。青年の悲嘆はは見る目もいたわしいほど、彼は、もっぱら神ほとけにおまいりして亡きひとをしのんでいました。ある日、ふと、路上で会った、あえかな姫君、なんとその面かげは、恋しい亡き姫に生きうつしの美女ではありませんか。彼は「目モクレ、ムネモサワギテ」必死にあとをつけますが、はぐれてしまいます。夢中でさがし求めること幾日か、ついにある大きな邸の門から出てくる少女が、かの日、姫君のお供についていた子供だったことを発見します。…… 残念! ここでページはちぎれ、そのあとは永久に未完です。印刷された本にはみな、非情に「以下欠」となっています。ああ、でも、このページからは、かぐわしいロマンの風が吹いてきます。私はあれこれ結末を作りつつ、これこそ「物語のいできはじめのおや」ではないかと、うつとりするのです。 2025.11.30 記す。 |
|
さくらの歌(新古今集他) P.100~102 さくらが咲きました。 さくらの歌は、やはり私には「万葉集」よりも、「古今集」「新古今集」のものが好きです。たとえば、 〽見渡せば春日の野辺にかすみ立ち咲き匂へるは桜花かも (万葉集) というのよりは、 〽みよしのの高ねの桜ちりにけり嵐もしろき春のあけぼの (新古今集)(新古今和歌集』:岩波文庫P.44 三三:黒崎記) の方が好きです。桜は、素朴に歌われるよりは、一種の様式美をもって表現された方がにつかわしいのです。 みよしのの歌の方は、「最勝四天王院のしやうじに、吉野山かきたる所」とい詞書(ことばがき)が、歌の前についていて、障子に描かれた吉野山の絵にそえられた歌、ということがわかります。 まるで、イラストレーションの一部のように美しい歌ではありませんか。私は、春、花便りがきかれはじめると、ふっと、くちびるにこのなだらかなしらべの美しい歌がのぼるのです。このあいだ、神戸の護国神社の桜を見にゆきましたら、風に吹かれてふぶく花びらで、あたりは白くつつまれ、夢幻のような美しさ、「嵐もしろき春のあけぼの」というのは、字でかいた絵のようです。 この作者は、後鳥羽上皇なのです。あの多芸多趣味、ありあまる才気の君、一世にかくれもなきすぐれた歌人、そして、承久の変で政治的に失脚して、隠岐の島へ流された悲劇の帝王でもあるのです。上皇の歌は、どれも珠玉のように美しく、「〽ほのぼのと春こそ空に来にけらし天のかぐ山かすみたなびく」(新古今集春歌)というのも、私は好きです。私は、ちいさなガラス細工の動物や、花や蝶の指輪や、陶器の人形といった、こまごました美しい、あるいはかわいらしいものを集めるのが好きなのですが、それらのコレクションと同じように、こんな美しい歌を、心の中に一つ、二つ、とためてゆくのが、大好きなのです。 むかしの歌集には、ことば書き、というのがあります。「和泉式部日記」や「建礼門院右京大夫集」は、ことば書きがそのまま、小説風になったりしていますが、「どんな場合によんだ」あるいは、「こういう歌でお返しをした」などと作歌成立の事情ともいうべき、「前説」がことば書きです。この、ことば書きと、歌とがいかににもぴったりしていると思うのは、「古今集」にある、紀貫之の歌です。 〽歌たてまつれと仰せられし時能に、よめたてまつれる 貫之 〽桜花さきにけらしもあしびきの山のかひよりみゆる白雲 山峡に白くかすむは、雲かさくらか。このことば書きのおうようさ、上品さ、何の作為もないままに、つくろわぬ気高さが、すらりと出、またそれに呼応して、歌の姿も品(しな)たかいものがあります。曲雅、というのは、こんなことば書きと歌のことをいうのでしょうか。両々釣り合い、補い合っているような美しさで、私はこの歌は、ことば書きと共に味わうものだと思ったり、します。 西行も美しい桜の歌をのこしました。「吉野山やがて出でじと思う身を花散りなばと人やまつらむ」(訳:吉野山に分け入ってそのまま山から出まいと思うこの身を、花が散ってしまったら戻って来るだろうと、親しい人は待っているだろうか。)などは私の好きなコレクションの中へ加えていますが、でも、西行は武士の出なので、その勁(つよ)さが私には近づきにくいときがあります。それで恥ずかしいな、と思いながら、告白しますが、ほんとうに好きなのは、絵本のような歌です。 〽山里の春の夕暮れきてみれば入相の鐘に花ぞ散りける 能因法師 絵のような桜は、絵のように歌われるのがふさわしいのかもしれません。 平成29(2017)年6月06日 |
|
魅惑の男(蜻蛉日記) P.103~107
補注「蜻蛉日記」はいかにも女のすなる書きもの、という気がします。なぜなら、女は、男と女との愛憎関係に氏か、本質的な関心をもたないのではないかと思えるからです。 これは、千年の昔に生きた一人の人妻が、その夫との長年の夫婦生活の相剋を、綿々とつづった、日記風物語ですが、ほんとうに男女関係のエッセンスのような、おもしろい本です。 文章は、「源氏物語」より古雅で難解ですが、文学的質度のたかさからいうと、源氏より上かもしれません。 作者の名は右大将・藤原道綱の母、とあるだけで、呼び名はいまでも分かりません。かりにかげろうと名づけましょう。 夫の名は分かっています。藤原兼家、のちに関白にまでなった人ですが、辣腕の政治家で、おのが野望をとげるためには兄弟、一門をも仮借なく葬り去るほどのすさまじい男です。 「蜻蛉日記」をよむたのしみは、また、この男を知るたのしみでもあるのです。じつをいいますと、私は、「蜻蛉日記」にあらわれた兼家という男に、すっかり魅惑されているのです。 強引でずうずうしく、大胆奔放で、色ごのみで、しかもやさしく、たのもしい所もあるといった――端倪すべからざる、したたかなものなのです。 この当時、男は重婚を許されています。妻たちはそれぞれの親の家で、夫の訪れをまつだけです。子供が生まれば、妻の手もとで育てます。夫は自分の家にはどの妻もおかず、気の向くままに、何人もの妻の家へ出かけます。妻の地位に格差はありませんが、そこは人間、おのずから愛情の深浅によって親疎ができます。 かげろうは美女で、有名な歌人でもある、つまり才媛でしたが、結局は、この時代の女のつねの、嫉妬に身をやく運命からのがれませんでした。 兼家は他の女のもとへいくときも、平気で彼女の邸の前を前駈に警蹕させ、供をしたがえ、牛車で悠々とすぎてゆきます。邸の下男たちが「中門おしひらきてひざまづきて居るに、むべもなくひきすぎぬ」という仕打ちなど、平気でする男です。 だから、たまに夫がくるとかげろうはありったけの怨み言をいいます。果ては「岩木のごとして明かしつれば」夫も怒って帰ってしまう。そうかと思ふと時には侍女の目も恥かしいほど、戯れたり、あるいはまた怨みごとをいうあいだ、眠ったふりをしたりする、ずるい男です。また時には雨の日にふと来たりして、さすがに堅い妻の心もとけるのですが、明日も来るからね、という夫の言葉を信じてまつうちに、半月、ひと月、たよりもないという、……そうです、律儀な誠実な女にとっては、地獄の苦しみともいうべき夫婦生活なのでした。 でも、兼家はまた、彼女の出産、彼女の母の死、などのときにはさすがにまめまめしく、世話をし、采配してくれます。たよりがいある男なのです。 兼家が急病で倒れ、ほかの女の邸へかつぎこまれた時がありました。彼は使者を出して、夜半こっそり、かげろふをよびよせます。 かげろうふは本邸の夫人に遠慮がありましたが、兼家がかさねて、車で迎えによこして促しますので、出かけました。 暗い縁にかげろうはたたずんでさがしておりますと、<ここにいるのが見えないか>と夫が手をとってみちびき入れてくれました。
なんという可愛い男のセリフでしょう。積年の閨怨も雪のように溶け、かげろふは男にひしと心がよりそうのでした。 と、思ふと、病いが癒えるが早いか、色ごろみの兼家はもう新しい愛人を作ったりするのです。 かげろうは嫉妬の苦しみに負け、寺へ入って尼になろうと決心しました。それを力ずくでつれもどしたのは、やっぱり、夫の兼家なのでした。西山の寺にこもり、どんな人のいさめや忠告にも耳をかさず、出家をかたくなに念じていたかげろふのもとに、兼家はまっすぐ、やってきます。散ったものを取りかたづけ、袋に入れ、車に積ませ、仕切りをとりはらい、<さあ、仏においとまごいをしろ>と冗談をいって、かげろふの手をとり、笑いながらむりやり車に押しこむのでした。彼は彼のやりかたで、かげろふを愛していたのです。 かげろふは中年になり、ようやくに、嫉妬や妄執の業苦から、いささかときはなれて、夫やわが身を見るようになりました。思いがけなく兼家がたずねてくれた夜のあけ方……。 「雨いとのどこかにふるなり、格子などあげつれど、れいのやうに心あわただしからぬは、雨のするなり」 いつもは朝になるとあわただしく帰る兼家が、けさはゆっくりしている。それは私への情愛からではない、きっと雨のせいだろう――かげろふはそんな風に考える女になっていますが、しかし、その彼女の眼からみても、中年に達した夫の男ぶりは水際立つものでした。 供の男たちは来たか、などといいつつ夫は起き出して、なよらかかな直衣、よきほどに柔らかな練絹の袿を下に着こみ、帯をなかば垂れつつゆるやかにしめて歩いてきます。侍女たちが、朝餉はいかが遊ばしますか、とお伺いをたてますと、いつも食わないのだから、べつにいい、と、きげんのいいようすも、おのずから威と気品がそなわり、美しい男なのです。 「太刀を」 といいますと、息子がとって膝まずいて捧げるのでした。のどかに縁を歩いて庭を見やり、――庭を雑然とさせてしまったなあ、――などといいます。やがて車がさしよせられ、夫はゆっくり乗りこみます。中門から出た車の、前駆をおう声も、かげろふをなつかしく、たのもしく、慕わしい心地にさそうのでした。 このとき兼家四十四歳、大納言という高官に加えて大将に進み、自信と威厳にあふれた男の魅力をあますなくそなえています。でも、そんな魅力的な夫の訪れもごく、たまのことでした。 「そののち、夢の通ひ路たえて、年くれはてぬ」 夫のおとずれはいよいよ、間遠になり、たよりも通り一ぺんのものになりました。ただ息子の道綱のみ、父と母の邸をゆき来してわずかに消息をもたらし、縁をつないでいます。 いまは道綱も青年となり、公達の一人として世に出る年頃でした。かげろふは、息子の将来にのぞみをつないで生きます。 でも来しかたをふりかえったとき、はたして私の一生は何だったのかとかげろふは自問せずにいられませんでした。秋冬、物思いにくれてはかなくすぎました。そしていつも、かつえていました。兼家への恋がみたされないことが、彼女の心を飢えさせていたのです。かげろふは長い苦しみの半生をかえりみつつ、筆をとってかきつづけまっす。 「……ふりける雪、三四寸ばかりたまりていまもふる。簾をまきあげてながむれば、『あな寒』というこゑ、ここかしこにきこゆ。風さえはやし。世の中、いとあはれなり……」 夫を憎みながら愛し、愛しつつ憎み、そのくせ、かげろふは夫に恋していたのです。 妻に恋されるほど、兼家は魅力のある男なのでした。 補注:「世界名作辞典」(平凡社)P.122 2025.12.06 記す。 |
|
うまずめ(清少納言) P.108~110 「枕草子」の作者、清少納言という女は、こんにちの研究では、結婚して、一子をあげたのではないかと推定されています。 しかし私は、彼女は石女ではなかったか、あるいは子供を産んでも、手許から放してしまって、子供縁のうすい女ではなかったとか思っています。 なぜなら、彼女のエッセイ集「枕草子」の中にある、子供の描写は素晴らしいからです。光りかがやいているからです! イギリスの女流作家、キャサリン・マンスフィールドも病身で子供を持たなかった女(ひと)でした。彼女の子供の描写もまた、じつに生彩を帯びています。 私は、現実に子供をもてば、こうまでその愛らしさを端的に描出できないのではないかといつも思います。 「枕草子」の名高いくだり、「うつくしきもの(愛らしいもの」の幼い子供の可愛らしさはどうでしょう。 「二つ三つばかりなるちごの、急ぎて這ひくる道にいと小さき塵のありけるを、目ざとにみつけて、いとおかしげなる指にとらへて、大人などにみせたる、いとうつくし」 またおかっぱあたまの童女が、目の上までかかった髪を、あたまをかしげてふり払って物を見ている愛くるしさ。美しい赤ちゃんをちょっと抱いて遊ばせてあやしているうちに、とりついて寝入ってしまうその愛らしさ。
「こころときめきするもの。ちご遊ばする所の前、わたる」 「つれづれなぐさむもの。三つ四つのちごの、ものをかしういふ」 その片ことも、そのしぐさも、彼女にとってつきぬ愛執と、新鮮な好奇心をかきたてるものでした。 その愛情や執着、好奇心は、「ちご」たちが自分のものでないから、なのです。 自分で子供をもつ人は、決して、こういう第三者的な好奇心をもちますまい。清少納言の、愛情にあふれた観察は、いきいきしていればいるほど、ヒトの子供をみる女の目なのです。 「いみじう白く肥えたるちごの二つばかりなるが、二藍(ふたゐ=染の色)のうすものなど、衣長(きぬなが)にてたすき結(ゆ)ひたるがはひ出でたるも、また、短きが袖がちなる着てありくも、みなうつくし」 「八つ、九つ、十ばかりなどの男児の、声は幼なげにて書読みたる、いとうつくし」 棒切れや弓みたいなものを持って遊んでいる小さい男の子も、たいそう可愛い。 「車などとどめて、いだき入れて見まほしくこそあれ」 その愛情には、自分が自由にできない、この愛らしいせつない生きものへの憧憬・羨望の影が、煙のように立ちこめています。 だから清納言は、子供のいやらしさ、にくらしさも鋭く指摘します。 「にくきもの。物聞かむと思ふほどに、泣くちご」 「見苦しきもの、例ならぬ人の前に、子負ひて出で来たる」 調子づくもの、母親に連れられて遊びに来、他人の部屋の大事なものをさがし出してとりちらかす子供、それを母親もまた制しもしないで、だめよ、などとにこにこしているだけ、こんなのは親まで憎らしい。 憎さげなちごを、親からみると可愛いのか、片ことをまねしているのなど笑止だ。 これということもない人が、子供をたくさん作っているのも、わずらわしい。 その直截な辛辣さ。この口ぶりはもう、まるで男性のものです。 あの、母になった女たちがもつ、子供に対してとめどなくのめりこんでゆくようなあいまいさ、「これこそ我が骨の骨、肉の肉なれ」というからみつくような一体感のもつ妖気は、彼女の文章にはありません。「枕草子」は颯爽たる、石女の文学だったのです。 |
|
ころもがへ(与謝蕪村) P.120~122 御手討ちの夫婦なりしを更衣 蕪村 江戸時代には(旧暦)四月一日、十月一日をもって春夏の衣を更えました。いまは四季、かわらぬ風俗ですが、町中いっせいに、衣がぬぎかえられる季節は、ほんとうに、季あらたまるという感じだったでしょう。殊には初夏、風もかおる日、町にはかろやかな春着、夏着のあふれるうれしさ。 「人は春服をととのへて高き丘にのぼり、春風春水一時に来るとうた」うのです。 ほととぎす。花たちばな。一年で一ばん美しいとき。 蕪村は、この美しい季節に、「御手討ちの夫婦」を配したのでした。私は、この句をことさら秀句とも思いませんが、でも、たいへん好きなのです。 蕪村の句には、たのしいフィクションが多いのです。彼は歴史絵巻風な、物語の一シーンのような句をたくさん作りました。 鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな (※参考:蕪村俳句集 岩波文庫P.81、鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分哉:黒崎記) 指貫を足でぬぐ夜やおぼろ月 (※参考:蕪村俳句集 岩波文庫P.21、さしぬきを足でぬぐ夜や朧月:黒崎記) 私は、これらの句から、物語をあれこれ作りつつ、一句また一句とよむたびに、本を一冊よんだような豊潤な酩酊を与えられます。蕪村の句は、さながら一篇の小説と同じ重みに感じられたりするのです。 御手討ちの夫婦も、たぶん蕪村の想像でしよう。現実のことではありますまい。 武家方では恋愛は、きついご法度です。もし露見すれば不義者として成敗されてしまいます。でも、若侍と、可憐なお腰元は、(勘平とお軽のような)いつとなく、恋し合ってしまいました。お家を乱す不義者と、あたまの固い三太夫は声もあららかに詰ろうとしますが、やさしい奥方は、かげになり、日向になってかばわれたかもしれません。「殿に申上げます」と白髪あたまをふりたてて青筋立てている三太夫を、奥方はまあまあ、と抑えて、「わたしに任しておきや」などといわれる。殿さまのごきげんのおよろしき時など見はからって、そっと心くばりして、よしなにとりなされたことでしょう。怒りっぽい殿様のことですから、持ってゆき方によっては、どんな大事になったかもしれません。でも怒りっぽいだけに根は単純で善人なので、奥方のとりなしで、「よきにはからえ」とおうようにいわれたでしょう。 奥方はそっとお腰元と若侍を、しるべのもとへ落してやったり、身の立つようにはからい、新生活のはなむけを下さったかもしれません。 とび立つ思いのお腰元と、若侍。本来なら二人重ねてお手討ちになっても文句のないところなのに。希望にみちてお邸を出ます。 晴れて二人の人生がはじまります。町は初夏、さわやかな衣更えの季節と同じく、二人もまた、生れかわったような人生の第一歩なのです。 「更衣」には、たくさんの句があります。でも有名な「越後屋に絹裂く音や更衣」(其角)などよりもやっぱり、私は「御手討ちの夫婦」と更衣のさわやかな季節のとり合せを、ことに面白く蕪村らしいと思います。 そういえば、「野分」の句も、べつに何が上についてもよいわけです。しかし「鳥羽殿」ときたとき、ここはやはり「野分」という語と、「鳥羽殿へ五六騎いそぐ」という状景とはぬきさしならぬものと感じられます。「おぼろ月」も指貫でなければならない的確さがあります。蕪村は不義者、いたずらものたちにあたたかい共感をよせ、祝福しています。更衣という、さわやかで美しい季節に配するには、絶対、御手討ちになるべかりし恋人たちでなければならないのでした。 2022年9月04日記す。 |
|
ありがひもなき世間(沙石集) P.123~125 無住というお坊さんが十三世紀の終りごろいました。彼は名僧とうたわれた人ですが、生来、話好き、酒好き、垢ぬけたお坊さんでした。六十ちかくなって、それまで見聞きしたさまざまのことを書きとめたくなって、「沙石集」という本を書きました。書き出したのは、弘安二年(一二七九年)ごろ、つまり蒙古来襲の二年前で、しだいに物情騒然としてきたころです。 「沙石集」は「今昔物語」と同じように、庶民生活のさまざまのエピソードをあつめています。私は、「沙石集」から、よく小説の材料を仰ぐことがあります。ただ、無住はそのつもりで書いたのでしょうが、終りには必ず、仏道談義、信仰のすすめ、で結ばれていることが特徴です。そして、無住の見識はすべて、すぐれて味わい深く、彼がなみなみならぬ「人生の達人」だったことを思わせます。それに、一つ一つの話の面白さは無類で、読んでいて楽しいのです。文書も、男らしく硬質で、簡潔です。 私の好きなお話は、巻九「君ニ忠アリテ栄タル事」というのです。 ある年、世間でふしぎなことがはやりました。くじで相手をきめて互いに贈りものをすると、不慮の災難(無住は横災、ということばを使っています)をまぬかれるという迷信です。身分高きもいやしきも、このくじに夢中になりました・あるお公卿さまのお邸でも、くじ引きがあったのですが、当主の殿のお相手を引きあてたのは、なんと、一ばん貧しい、殿にお目通りもかなわぬ身分の侍だったのです。「不運ノ到リ」と彼は思い、周囲もそう、うわさしました。
「長いことお世話になった。死なばともに、と誓いあった夫婦の仲だけれど、もうおしまいだと。私は出家して世を捨てるつもりだ」 妻はおどろいて問い返します。なぜ、そのような」ことを……。この妻も、ささやかな商いをして世をわたる「貧シキ女人」なのです。 男はわけを話します。互いのくじの相手には、それ相当の贈りものをすべきなのです。これが同輩なら適当にごまかせるのですが、殿が相手では、どうしようもありません。見苦しいものでは恥をかき、人に笑われるだけ、りっぱなものを用意しようとすれば資力がない。この上は、あとをくらまし、夜逃げをするのみだ、というのです。 妻はすぐ、答えました。 <何をいうの、あんた、このあばらやと土地を売ったら何とか金はできますよ、同じ出奔するのなら、ちゃんと殿さまへ失礼のないようにりっぱな引出物をさしあげて出ればいいじゃないの> 夫は妻のやさしいことばをきいて心苦しさがまさります。 「今まで貧乏で、お前にいい思いの一つもさせることができなかった。それなのにこの上、おれのためにお前まで流浪させるなんて心苦しいよ」 妻はさえぎって、原文によれば、「先世ノ契リアレバコソ、妻夫ㇳモナリテ、今日マデ志カハラズシテ、スゴシツラメ。栄ヘバ同ジク栄ヘ、惑ハバ共ニコソ惑ハメ」 妻は、当然のような顔つきで、更に言いつぐのでした。 「あんたが出家するというなら、あたしも共に尼さんに」なりますよ> そして彼女は、強く、こう言い放つのです。 「コレホドノアリガヒモナキ世間ハ、惑フㇳモ歎クニモタラズ」――こんな、生きてる甲斐もない世の中は、行き場に困ったり歎いたりするほどのこともありませんよ。 夫は妻に励まされ、家土地を売ってその金で金銀の細工物をつくり、当日、殿に献上しました。貧しい彼が何を持ってくるかと、目引き袖引きしていた人々は、あっと驚いたのです。殿も感嘆され、その返しの引出物に土地を賜わり、その男は以後、あべこべに大いに富み栄えた、という話です。無住は「妻ノ志コソマメヤカニ哀ニ覚ユレ」といっています。 私はこの妻の、したたかな人生観を示す言葉を、愛するものです。彼女のうちには、人生で一番大切なものと、そうでないものとの違いがハッキリしています。彼女が即座に夫との愛を選んだとき、「コレホドノアリガヒモナキ世間」と吐きすてるようにいえたのは、無学な貧しい彼女が、その違いだけはしっていたからなのです。 2022.09.08 記す。 |
|
おちくぼ(落窪物語) P.141~143
「源氏物語」が書かれる前後、世間にはたくさんの物語が流布していました。「枕の草子」や「更級日記」を見ると、見られぬタイトルがいっぱい並んでいます。 「住吉物語。埋もれ木。月待つ女、梅壺の大将。松が枝。こま野。ものうらやみの中将。交野の少将。とほ君。せりかは。しらら。あさうづ。みづからくゆる。かばねたずぬる宮」……なんという、心をそそる題でしょう。 でもかなしいことに、これら、さまざまの物語は、当時の人に愛読されつつも、いつとなし散り散りになり、やがてわすれられ、消えてゆきました。 あるいは「源氏」という強い輝きをもった美しい星の前に、光を失ったというのでしょうか。また、「源氏」という巨大な本流にそれぞれの小川は、まきこまれ、合流したというべきかもしれません。 「その中で「源氏」に吸収消化されぬ、異質の個性をもった物語だけが、千年の風雪に堪えて生きのこりました。「伊勢」「竹取」「宇津保」「落窪」などです。 私はこの「落窪物語」がとても好きなのです。 これはいかにも男性の筆になると思われる、(作者も書かれた時期もわかりません)大まかで粗っぽいタッチ、しかも構成がきちんとしていて、いきいきとマンガ風な人物、たいへんよくできた美しい通俗小説なのです。
ある中納言の亡くなった妻の忘れがたみの姫はまま母の北の方に冷遇されて、離れの、一段低くなった間におしこめられ落窪の君とよばれて、憂くつらい日を送っていました。北の方の産んだ姫たちは花やかにかしずかれ幸福な結婚もしているというのに、落窪の君はたべものもなく、着物もなく、ひもじい寒い思いをし、異腹の姫の婿のため、お針女の仕事に追い威まくられという暮しでした。 でもこのシンデラレに、王子さまが現われました。右近の少将というすばらしい貴公子です。少将は姫の逆境に同情し、また、その美しさ聡明さに魅せら、ひそかな恋人として通います。少々の従者、帯刀と姫の侍女、あこぎの二人が、それぞれのあるじのため、心をくだいて恋をとりもつおもしろだ。 北の方は姫に恋人がいると知って、夫の中納言にあしざまに告げ口をし、姫はとうとう一室に錠をおろしてとじこめられてしまいます。その上、北の方は好色な老人の典薬助をやって姫を襲わせます。あやうし、落窪の君! もう猶予はなりません。 少将は帯刀とあこぎの手引きで、北の方らのるすを幸い、姫を救いにのりこむ。錠があかないので男二人の力で戸をうちこわし、姫を抱いて車に乗せ、首尾よく自分の邸へつれ帰りました。北の方らが帰宅して大さわぎ、北の方は誰の仕わざとも分からないので怒り狂います。読んでいて思わずハラハラして手に汗にぎり、北の方がしてやられたところでは快哉を叫んだりする、ほんとうにページをくるのももどかしい面白い部分です。 さて、このあと少将は、存分に北の方に復讐します。そして姫は、少将の出世につれ、いよいよ幸福なくらしを送ります。 作者は庶民の願望に充分にこたえて、その栄華の物質的幸福を力こめて詳述するのですが、それよりも女性読者をひきつけるのは少将の純愛です。少将は大臣の姫の婿にと懇望されたのをふり切って、財産も親の後だてもない、みなしごの姫をただ一人の妻として貞潔を誓うのでした。これはいかにも通俗小説の典型でしょう。善玉悪玉入り乱れ、美しく聡明なやさしいヒロインが運命にほんろうされる、まさに少将と姫の純愛にあったのです。永遠に古く、永遠に新しいテーマだったから、千年の風雪に堪えたのです。 2025.12.04 記す。 |
|
あやゐがさ(梁塵秘抄) P.150~154 君が愛せし綾藺笠古い古い、民謡です。 〔梁塵秘抄〕という、八百年ほど昔の歌の本にのっています。歌といっても、萬葉・古今といったみやびやかな敷島の道ではなくて、当時の民衆が愛誦した、今様という流行歌の、歌詞をあつめたものなのです。 だからこの歌もきっと、ふしをつけて歌ったり、舞ったりしたものでしょう。 綾藺笠は、藺をあんでつくった笠で、武者たちが狩りや旅のときに用いた、スポーツ用ともいうべき笠。戦いの兜や、女用のなまめかしい市女笠とちがって、綾藺笠は瀟洒な風趣をもたらします。 私は〔梁塵秘抄〕の中でこの歌がいちばん好きです。何という軽やかでリズミカルな、美しい歌でしよう。 清らかな若殿ばらの、愛用の笠が風に吹かれて、はらりと賀茂川に。やあれ、かしこぞ、流るるは、と連れの人々はわらわらと水辺に下り、笑いさざめく。賀茂の川水はその頃、空よりも清澄に冷たかったでしょう。さらさらさけよ、ということばのすがすがしさ。川の水も秋の夜も。 この歌に似たものに、芥川龍之介の「相聞」と題する詩があります。これもさわやかにかろく美しく、私の好きな作品です。 風にまひたるすげ笠のこんな歌をひろめたのは、諸国を流浪する傀儡子たち(人形使いのジプシー的芸能集団)や、巫女、琵琶法師、遊女、白拍子たちでした。賀茂川の水辺をゆく若殿ばらの一行の中にはきっと、裾をからげて白い素足を川水にひたす、陽気な遊女もいたでしょう。 我を頼めて来ぬ男あんなにかたくちぎりをこめ、あてにさせておきながら通ってこなくなった憎らしい男。 あんな奴、角が三つ生えた鬼になって人にきらわれるがいいわ。霜や雪あられの降る冷たい水田の鳥となって立ちつくし、足が冷えればいいんだわ。それとも池の浮草か、あっちへゆれ、こっちへゆれ、さまよい歩けばいいのよ――。 天真爛漫に毒づいています。名もない民衆の心々の喜び悲しみは誰からともなくわき上がる歌声になり、人々に愛せられ、歌いひろめられてゆきました。 舞へ舞へ 蝸牛美少女巫女たちが声をそろえて歌い舞う、この世ながらの浄土のような華やかさ、そしてその低音部に、呻吟する如きべつの歌声が、たえずひびきわたります。―― 遊びをせんとや生れけん 仏は常に在せどもあかつきの仏、というところが、はかないあこがれを象徴するようで、私の好きな歌です。 百日百夜は独り寝と 人の夜夫は何せうに 欲しからず 我が子は十余になりぬらん 田子の浦に汐踏むと いかに海人集ふらん 我が子は二十になりぬらん 博打して歩くなれ このごろ都に流行るもの 柳黛 髪々 似而非鬘 しはゆき近江女 女の盛りなるは 一四五六歳廿三四とか 三十四五にし成りぬればこれらの歌を編集して、〔梁塵秘抄〕と名づけられたのは、ほかならぬ後白河院でした。 源平が血みどろの死闘をくり返しているあいだ、たえず権謀術策の中に生きた人。――清盛。義仲、義経。頼朝。あまたの人間の盛衰を見つつ、みずからの時代の暗黒の巨魁であった王者。院が民謡の歌を憑かれたように好まれたのは、六十年の波乱にみちたご生涯を通して、生きること、歌うことの何たるか、そのはかなさ、と同時に、その永遠のいのちを非凡なお眼に見ぬかれたからでしょうか。 2022.09.06記す。 |
|
あーら わが君(落語) P.167~170 ふるい落語に、大阪でいう「延陽伯」、東京で「たらちね」というものがあります。 私は、この中に出てくるお嫁さんの延陽伯こと、お鶴さんが好きなのです。 やもめの「喜ィさん」の家に、美人がおこし入れ(もおかしい、ボロ長屋ですが)してきます。 お嫁さんを迎える喜ィさんの支度が、また、たいへんすてきで、私は、こんな婚礼(結婚ではなく)にとてもあきがれをおぼえます。 かんてき(七輪)に火ィいこして茶ァわかして酸い酒の一ぱいも買うて、何でもええから、あたまとしっぽついた魚買うて」 この時分のふつうの町人たちの結婚支度は、式亭三馬の「浮世床」にもありますが、まずざっとこんな具合でした。 「仲人が葛籠を背負って、左の手に鉄獎壺を提げて、右の手に酒を一升提げて来たは、イヤまた恥をいはねえぢャァ理が聞えねえ。ソコデ、おれは商ひから帰って、今に大方、花嫁が来るだらうと思ふから、豆腐を小半丁買って来て、鰹節をかいている所へお輿入れよ。それから仲人が指図して、すぐに花嫁が茶釜の下へたきつける、仲人が味噌を摺る。ソコデ、仲人の懐から出した三枚の鯣を焼いて、三々九度よ。ナントどうだ……」、 待ちながら喜ィさんは、あれこれと、花嫁が来てからの生活を想像します。 そこのところが、この上なく聞いていて、楽しくおかしい。喜ィさんの大ぶりな茶碗と花嫁の、「薄手の可愛らしい」茶碗がならぶさま、お茶漬を二人してかきこむ、チンチロリンのガーサガサ、ポーリポリの、バーリバリ……という、おなじみのところなど、聞いていて、喜ィさんの弾みと期待がこちらにもつたわってくるような、たのしい場面です。 喜ィさんは、結婚生活、男と女の二人していとなむ新しい人生に、とても夢と期待をもっています。やもめの喜ィさんにとっては、女房、嬶というのは、永遠の女性、ペアトリーチでもあるのです。 だから、夫婦ゲンカの想像すら、喜ィさんにとっては、手の舞い、足のふむ所を知らず、という、わくわくするような夢なのです。 ところが、やってきたお嫁さんは、高貴な家に奉公していた人で、言葉がちんぷんかんぷんで、無学な喜ィさんにはちっともわからない。そこが、この落語のおかしみで、ねらいどころなのですけれど、このお嫁さんも、わざとそういう言葉を使って、無学な新郎を煙にまいているのではないところが、よけい、おかしみをそそります。 このお嫁さんは、精一ぱい敬語を使って、みずからも、手鍋ひとつ下げてやってきた新生活への希望を表現しているわけです。 喜ィさんの方は、お公卿さんの言葉は使えません。双方、外国人同士のようなあんばい、名を聞かれて有名なセリフを、嫁さんは答えます。
どこからどこまでが名なのか、喜ィさんは困りはてます。翌朝はそれでも、延陽伯のお鶴さんは亭主より早く起き、 「あーら、わが君」 と呼びかけて、朝食をつくってすすめますが、葱を一わ、買うのにも、「こりゃ、門前に市をなす賤のおのこ。おのこやおのこ」と呼びかけて、八百屋まで、あっけにとられてしまう。 でも、お鶴さんとしては、一生けんめいなのです。 お鶴さんは、「酸い酒と小魚」で、偕老同穴をちぎった亭主に、生涯をかけて、ついていくつもりでいます。むつかしい言いまわしや、いささかのよみ書き、学問は、亭主の喜ィさんよりは堪能かもしれませんが、お鶴さんは、そんなことは気にもとめていません。彼女の考えることは、祝言の翌朝、喜ィさんより早くとびおきて、「白米のありかはいずくなりや」と聞き、ねぎ一わ買うにも「わが君の御意に召すや召さぬや、伺うあいだ、しばらく門前に控えておじゃ」と喜ィさんをたいせつにするだけです。お鶴さんと喜ィさんの結婚こそ、最もやさしく美しく。プリミティブな強いむすびつきのような気がします。 2025.12.01 記す。 |
|
浅茅が宿(雨月物語) P.171~173 わが国の古典文学の中で、いちばん美しく、いちばん悲しい”愛の物語”は、と問われれば、私はためらわず、上田秋成の「浅茅が宿」を推すでしょう。 この短篇小説を読んだあとのふかい感動は、すぐれた長篇の大河小説「源氏物語」五十四帖にも匹敵する。 上田秋成は、享保十九年(一七三四年)に大阪で生まれ、七十六歳で、京都で死んだ文学者です。その出自は定かでないのですが、早くに富裕な商家に養われ、自由に学問・文芸に遊ぶことのできる少・青年時代を過ごしたことは、秋成にとって、たいへん、幸せでした。その才能を大いにのばせたからです。 彼は気むずかしく、偏屈な人のように伝えられていますが、それは、心があまりにもデリケートで、生一本だったからではないでしょうか。彼の小説を読むと、至純な心の主人公たちが美しくえがかれていて、作者そのひとと重なります。あまりにも頭がよく、俊敏明察の人であった秋成は、世間の大方の人の多欲、通俗、蒙昧に堪えられなかったのでしょう。 「浅茅が宿」は、「雨月物語」という短篇集の中に収められている一篇です。彼の三十代なかば、脂ののり切ったころの作品です。 もとの話は「剪灯新話」にあるお話ですが、秋成は、日本の室町時代の話に作りかえ、美しい雅文調の小説に仕立てました。 下総の国に、勝四郎という男がありました。京へいって商いをして家を興し、身を立てようと志し、妻の宮木に、しばしの別れを告げます。 宮木は美しく「人の目とむるばかりのかたちに、心ばへも愚かなら」ぬ女でしたが、夫が他国へゆくのを心ぼそがり、「あしたに夕べに忘れ給はで、はやく帰りたまへ。命だにとは思ふものの、あすを頼まれぬ世のことわりは、たけきみ心にもあはれみ給へ」と、涙ながらに夫を送り出します。もちろん勝四郎も秋風立つまでには帰るつもりでした。 しかし、世は戦国時代の幕開け、諸国動乱のころでした。関東はたちまち、戦にまきこまれました。里の女わらべはちりぢりに逃げまどい、宮木もとほうにくれます。 夫は秋をまて、といった。だからそのころまでは、と頼みにして心ぼそく暮らしていましたが、そのうち卑女も去り、たくわえもつき、年もくれました。それでもなお、愛する夫からは、何のたよりもありません。 そのころ、夫の勝四郎も、京の戦乱にまきこまれていたのです。戦火は、相愛の夫と妻をへだててしまいました。勝四郎は、旅の途中、病に伏し、あるいは放浪し、「七とせがほどは夢のごとくに」すごしてしまいました。 「古さとに捨てし人の消息をだに知らで、忘れ草おもひぬる野辺に長々しき年月をすごしけるは、まことなきおのが心なりける物を」勝四郎はどんなことをしても故郷に妻をさがそうと決心し、やっとのことで帰りつきます。日は早や西に沈み、「雨雲はおちかかるばかりに暗」かったのですが、ようようたずねあてたわが家に、幽鬼のようにやせおとろえた妻はいました。勝四郎は別れてからの辛苦を涙ながらに語れば、妻もまた、七年の長いあいだ、みさおをたててまちつづけた心を語り、「今は長き恨みもはればれとなりぬることのうれしく侍り」と泣きつつ、ともに再会のよろこびに夜のふけるのも忘れました。 勝四郎はふと目をさましました。これはいかに、荒れはてたむぐらの庭に、朽ちたあばらや、かたわらに臥(ふ)した妻の姿はなく、塚だけがのこっています。卒塔婆の文字も消えがちに「さりともと思ふ心にはかられて、世にもけふまでいける命か」ゆうべの妻は、妻の霊だったのです。相逢うたましいが、冥界から風にのってやってきたのでした。勝四郎は塚の土をつかんで泣き伏します。 参考:それでも、きっと帰ってくると期待するわが心に乗せられひきずられて、よくもまあ、今日まで生きてきてしまったことよ。これが私の命というものなのか。(黒崎記) 秋成は、至純の愛は、たえず、死とうら表に貼り合わせになっていることを、いいたかったのだと、私には思えます。人間至高の愛は、死と調合しなければ、完成しないのだと、思想家の秋成は夢みていたのでしょう。 平成29(2017)年5月25日 ※参考:浅茅が宿 ★日本古典全書『上田秋成集』(朝日新聞社刊)P.88~~99・現代語訳対照『雨月物語』大輪靖宏訳注(旺文社文庫)P.70~99 ★現代語対照『雨月物語』(旺文社文庫)P.70~99:雨月物語 巻之ニ 浅茅が宿 |
|
おさん(心中天網島) P.177~179
「うたひの本は近衛流、野郎帽子はわかむらさき」ときまっていますが、そのように、「悪所ぐるひの身のはては、かくなりゆくと定まりし……」 天満に店を張る紙屋治兵衛は、妻子もある身でありながら、曽根崎の遊女、小春におぼれ、はてはお定まりの、店もかたむき、親類に意見され、妻子も離別されるという運命におち入りました。 それでも治兵衛は、小春を思い切れません。小春もまた、そういう悪所の女でありながら、純情でやさしく、美しく、心から治兵衛を愛しています。 それゆえ、彼女は治兵衛の妻のおさんから、どうぞ夫と手を切ってほしい、このままでは二人は心中するばかり、「女は相身たがひごと、切られぬところを思ひ切り、夫の命をたのむたのむ」と書きくどいた手紙をもらい、衝撃を受けます。そうして心ならずも、恋しい治兵衛にあいそづかしをするのでした。 治兵衛はうつうつとこたつに蒲団をかぶつています。「まだ曽根崎を忘れずかと」おさんは呆れながら引きのけると、治兵衛は泣いているのでした。おさんは思わず、かきくどきます。 「あんまりぢゃ治兵衛殿。それほど名残惜しくば誓紙書かぬがよいわいの。をととしの十月中のゐの子に、こたつあけた」祝儀とて、まあこれここで枕ならべてこのかた、女房のふところには鬼がすむか蛇がすむか、二年というもの巣守にして」ようやく、夫婦らしく家へもどってきてくれたかと思えば、もう小春を思うて泣いている。 「ほんとうにむごいつれない、さほど心残らば泣かしゃんせ、泣かしゃんせ、その涙がしじみ川へ流れて、小春の汲んで飲みゃろうぞ、エゝ曲もないうらめしや」と膝にだきついてかきくどきます。 近松門左衛門の書いた「心中天の網島」というお芝居に出る女房のおさんは、貞女、と昔からいわれてきたタイプですが、門左衛門は、おさんに熱い血と心を与えました。おさんは、身も世もなく、夫と愛人の小春を嫉妬しているのです。身を投げてとりみだし、物狂おしいまで、夫を責めるのでした。型通りの貞女ではないのです。 治兵衛は弁解します。ちがう、これはくやし涙なのだ。あの心変りした売女など、もう何の恋しいことがあろうか。あの小春を、憎らしいべつの男がうけ出すらしい、さぞおれのことを金につまったあげくの果てと、大坂中に笑うていいふれるであろう、問屋中のつきあいにも男がすたる、それが口惜しい、と無念の涙をこぼすのでした。 おさんははっとします。 「いとしや小春は死にゃるぞや」 治兵衛はあざ笑い、「ハテサテなんぼ利発でもさすが町の女房ぢゃの。あの不心中者なんの死なう。灸をゑ薬のんで命の養生するわいの」 「いやさうでない、わしが一生言ふまいとは思へども、かくしつつんでむざむざ殺すその罪もおそろしく大事のことを打明ける」 とおさんは手紙で小春をくどいたことを治兵衛に打ちあけ、 「アゝ悲しやこの人を殺しては、女同士の義理立たぬ。まづこなさん早ういて、どうぞ殺して下さるな」 と夫にすがりつき、泣き沈みます。 おさんは商用にとりのけてあった金を出し、さらに箪笥から衣類をすべてとり出して、 「わたしや子供は何着いても男は世間が大事」 小春を受け出して男の意地を見せて下さんせ、と治兵衛にすすめます。 おさんは、自分の立場など考えられないのでした。あんなに夫を愛している小春が、夫を思い切り、ほかの男と添うというのは、小春が死ぬ決心でいるからにちがいない。小春の命をとりとめなくては……。 また、夫が、社会の場で、問屋仲間のつきあいで、金に困って、惚れた女を人にとられたと恥かかされてはならぬ、と、夫の立場でばかり考えます。もし小春が夫に受け出されたら自分は「子供のうばか、ままたきか、隠居なりともしませう」と泣くばかり、治兵衛は妻のやさしい心根に返す言葉もありません。 「あまりに冥加おそろしい、この治兵衛には、親の罰天の罰、仏神の罰はあたらずとも女房の罰」があたると心でおがみつつ、それでも、治兵衛は、小春と心中しなければならぬ成りゆきでした。おさんのような美しい心の女房をもちながら、やはり死なねばならなかった治兵衛に、作者は人間のふかい業をかいまみせてくれます。それにしても、おさんは貞女ではなく、「日本のマリア」、観音さまのような女です。 2025.12.03 記す。 |
|
さめやらぬ夢(建礼門院右京大夫集) P.188~194
寿平四年(一一八五年)春、平家一門が西海の藻くずと消えたとき、都にのこされたゆかりの人々の心もまた、生涯消えぬ悲しみを味わいました。 もと建礼門院に仕えて、右京大夫と呼ばれて彼女もそのひとりでした。彼女の恋人、平資盛も、海に沈んだのです。 補注1右京大夫は、教養ゆたかな父母の才能をうけついで、歌にも音楽の道にもたけた、わかい美しい女でした。 はじめて高倉帝の中宮・建礼門院徳子の宮廷に出仕したのは十六七のころ、わかい帝と中宮を中に、世は平家のおごりの春、全盛時代でした。ときめく平家の公達や殿上人があまたある中で、科の情は、一つ二つ年下の資盛と恋におちました。――華やかな、宮廷ぐらしをしていても、浮ついたことはするまいと、かたく思いきめていたのに……。 「おもひのほかに物思はしきことそひて、さまざま思ひみだれしころ」と、彼女はのちに、自分の補注4歌日記「建礼門院右京大夫集」に書いています。 資盛は重盛の次男、入道相国清盛の孫になります。正妻もいる身で人目をはばからねばならぬ、物思わしい恋でしたが、彼女にも資盛にも、いちずな、真剣な恋でした。 しかし世はただならぬさわぎにまきこまれていました。高倉帝の崩御、清盛の死去をさかいに、栄華を誇った平家は、音立てて没落していきます。 ついに永寿二年七月、平家は、幼帝・安徳天皇を奉じて都を落ちます。 「寿永元暦などのころ世のさわぎは、夢ともまぼろしても、あはれとも、なにとも、すべてすべていふべ際にもなかりしかば、よろづいかなりしとだにおもひわかれず、中々おもひも出でじとのみぞ今までもおぼゆる」 宮仕えもやめ、家に引きこもっている彼女を置いて、親しかった人々は都を落ちてゆきました。その惑乱とかなしみは、今思い出すのも辛いほどだ、と彼女は書いています。 あんなに華やかに時めいた平家一門の人々が一転してこんな運命になろうとは……。 世の人みな、夢うつつかと、惑いました。 今日も明日も、都をすててゆく人々……。あの人も、この人も。 恋人の資盛も例外ではありませんでした。彼はこのとき、二十四歳、蔵人頭という要職にあって公務が忙しい上に、世のさわがしさもあり、つねよりも人目をしのんで、あわただしく彼女と別れを惜しみました。資盛は沈痛に申しました。 <もう生きては都へもどれないだろう。これから先は、便りもしない。だが、決してあなたをおろそかに思ってのこととは考えないでくれ、自分でそう気強く思い切らないと、未練が残って辛いのだ。死んだと聞かれたら、せめて菩提を弔ってくいださい> 彼はさすが、嫡々の平家の大将、男らしくそう言いすてて、別れてゆきました。 それが今生の別れになりました。 平家があそこで討たれた、ここへ落ちた、と聞くたびに右京大夫の胸は不安とかなしみに張り裂けます。 「夜のあけ、日の暮れ、なに事を見きくにも、かたとき思ひたゆむ事は、いかにしてか、あらむ」 どうかしてせめてもう一日、と思うこころが通じたのか、ある夜彼女は、恋人がいつもと同じ姿で、何か物思わしげに沈んだようすでいる夢をみました……あたりは、風がひどく吹いていました。目がさめ、彼女はしばらく、胸さわぎがしずまりませんでした。もしや、あおのひとの身変事でも……。それとも、ただ今の今、あの人は、夢の通りの姿で、どこかの室で物思いに沈んでいるのかしら。
なみ風のあらき騒ぎにただよひてさこそはやすく空なかるらめ
「おそろしき武士ども、いくらもくだる」 平家を討つ源氏の武者たちが、たくさん西へくだります。平家敗戦の悲報は次々にもたらされました。あるいは生けどりになった人、あるいは討たれて首を都へはこばれた人、入水したと聞く人、……ついに怖れていた時がきおました。寿永四年春、平家一門、壇の浦に沈んだというのです。 補注2資盛は、弟の有盛、いとこの行盛らと共に手をとって海へ入ったとききました。二十六歳の花のいのち――覚悟はしていたけれど、右京大夫は茫然として、涙さえ出ないほどでした。長いこと泣き暮し、どうかして忘れたいと思いつつ、「あやにくにおもかげは身にそひ、言の葉ごとにきく心地して」かなしみはいいようもありませんでした。 資盛は、死んだと聞いたら菩提をとむらってほしいといい遺してゆきました。けれど世は平家ゆかりということさえ、はばからねばならぬありさまでした。右京大夫はかなしみにくれる心をはげまして、ひそかに志ばかりのとむらいをします。彼からの古い恋文を料紙に漉き直させて経を写し、また仏のおすがたを手ずからかきとどめて、尊いひじりにお供養をたのんだりしました。その紙に、なお恋人の手蹟が残るのも、目もくれ魂も消えるかなしさでした。長い年月に、たまり、たまったおびただしい恋文。そのとき、かのおり、あのひとはこう誓い、ああも契った。そのうれしい思いの名残りの文がらを、いま漉きかえして、尊勝陀羅尼、かなしいお経の文字を書こうとは。
かなしさのいとどもよほす水ぐきのあとはなかなか消えねとぞ思ふ かばかりの思ひにたへてつれもなくなほながらふる玉の緒も憂し 平家の人々の哀れな最期も、いくつも聞きました。ことにおいたわしいのは女院――海に沈まれたのを引き上げられ、心ならずも生き長らえてご落飾、大原の里にお住いになっていられるのを彼女はたずねます。昔の雲居の奥ふかく華やいでおわしたお姿を知る身には、山道のけしき、御いおりの粗末なたたずまい、「夢うつつともいふかたなし」 そのかみは六十人あまりの上臈女房にかしずかれておわしたのに、いまはお仕えする尼三四人ばかり、その人々も、いずれが誰であったか見分けられぬほど、やつれはてているのでした。 「花のにほひ、月の光」にたぐえられた美貌の女院も、いとし子を西海に失いたまい、はらからや親に後れられた悲痛な運命に、別人のごとく面がわりしていられます。右京大夫の真心こめたなぐさめに女院も共に新しい涙をもよおされたことでしょう。
今や夢昔やゆめとまよはれていかに思へどうつつとぞなき 補注3生き甲斐ない命と思いつついきながらえてしまいました。来る年も来る年も、思い出はいよいよあざやかに、悲しみは深くなるばかりでした。そのうち、思いもかけぬことでしたが、たって人にすすめられて、再び宮仕えすることになりました。世は後鳥羽天皇の御代になっていました。昔は身分の低かった殿上人のだれかれが、今では押しも押されもせぬ上臈部になっているのを見るにつけても、資盛が生きていたら、ああもあったろう、こうもあったと思われるのでした。新帝・後鳥羽天皇が、昔お仕えした、おん父みかど高倉帝によく似ておわすのも感慨ふかいものがありました。 公の古い書類に、かの「さめやらぬ夢とおもふ人」、資盛の署名が、蔵人頭としてとどめられてあるのも、彼女を悲しませるのでした。そして彼女は老いました。
水の泡と消えにし人の名ばかりをさすがにとめてきくも悲しき
老いてのち、藤原定家が、新勅撰集のうたをえらびあつめるために、彼女のもとへ、「書きおいたものがありますか」とたずねてくれました。そしてその折、「どちらの名にしょうか思われますか」ときかれたのも、うれしい思いやりでした。晴れの勅撰集に入れられるときの、彼女のよび名を、その昔、建礼門院にお仕えしていたときの名が、のちに後鳥羽院にお仕えしてからの名か、どちらを取りましょうかというのです。 「名をただ、隔てはてにし昔のことの、わすられがたければ『その世のままに』などと申すとて、 言の葉のもし世にちらば忍ばしき昔の名こそとめはほしけれ」
この右京大夫の悲しみは、先頃の戦争で愛する者を失った何十万の女たちにしおのままかよいます。いま、彼女たちはその思い出を抱いてつつましく老いてゆきつつあります。 第二次大戦に出征した若者たちも、さながら資盛のように、故郷の恋人や妻にあてて、ひそかな便りを託し、万感の思いをこめて死地におもむいたのです。
「昨夜、月光をあびて静かに眠りにはいらんとする東京を離れた。――今日の君の胸中を思うて、心中ひそかに哭し、君健在なれと熱き祈りをおくる。今は君の手でしるされる日記の文まで想像できるような気がする。 |
|
幾山河(若山牧水) P.195~197 〽吾幾山河越えさり行かば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆく この、若山牧水の歌に、心をしびれさせなかった昔の女子学生がいたでしょうか。この歌は、秋の匂いをさながらもたらすような歌でした。少女の私には、秋は、この歌と共に訪れました。 若者の心に、ぽとりとしずくをおとして、その水滴がやわらかい紙ににじむように、心をぬらしてゆく歌でした。 牧水は、昭和三年に亡くなった歌人ですが、もう古典の中に入れてもよいように思われます。そのしらべの美しさ、純粋さ、そのくせ、しんに強い線が男っぽく通っていて、いかにもゆったりと、おおらかな味わいのする歌です。 今よんでみても、その新鮮さはちっとも失せていません。そして、牧水の歌を一つまた一つと夢中でおぼえていたころの思い出も、もろともに、レモンのように匂い立ちます。 〽いざ行かむ行きてまだ見ぬ山を見むこのさびしさに君は耐ふるや 少女の私には、ほんとの人生のさびしさはわかりませんでした。戦争中の日本には「旅ゆく」という、おおらかな情感は想像もできませんでした。それだけになお私は、見知らぬ国への旅、さびしさの果ての幾山河をあごがれたのです。 〽吾木香すすきかるかや秋くさのさびしききはみ君におくらん この歌をおぼえたのは林芙美子さんの小説だった思います。軍隊へ入った夫から、女主人公の妻へあてた手紙に、この歌が書きつけてあったのです。私は、われもこうという草をみたいと思って、熱心に調べたことをおぼえています。 〽白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ 〽多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふひとのあれかし こういう歌を少女時代によむと、一つの歌だけで、一時間も、ぼんやり、いろいろ考えごとができるのでした。「白鳥は‥‥‥」の歌など、すぐれたふかい交響楽を聞いたあとのように、いつまでも余韻がのこって、体のうちの小さな鐘はひびき交わし、鳴りどよもし、やわらかな心の中に消えることなく、この歌が彫りつけられてゆくのでした。 牧水の恋歌には、抽象された格調高さがあります。あたらしい古典美、というような。 〽山を見よ山に日は照る海を見よ海に日は照るいざ唇を君 〽ともすれば君口無しになりたまふ海な眺めそ海にとられむ 〽君かりにかのわだつみに思はれて言ひよらればいかにしたまふ これらの恋歌は、どれだけたくさんの若者の、日記や恋文の端にかきつけられてきたことでしょう。 牧水の歌は、そこに特徴がありました。若者たちは、牧水の歌を、自分の歌のように思いなして使うのでした。どんな若者の、どんな恋にも、牧水の歌はぴったり、はまってくれました。引用する、というものでなく、若者たちが自分で作るべかりし歌、そのものが、牧水の歌でした。 〽かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな 古い村、古いまちを通るとき、また、人生の中歳に達した人が来し方をふとふりかえりみるとき、私たちは自分の作りたかった歌を、牧水の歌の中からみいだします。もう牧水が歌ってくれた以上、私たちはそれを口ずさむだけでよいのです。私が彼の歌を古典という所以です。牧水は、酒を愛した人でしたから、ちゃんと、こういう歌も、作ってくれました。 〽白玉の歯にしみとほる秋の世の酒はしずかに飲むべかりけり 平成29(2017)年8月21日 |
|
浮世風呂(式亭三馬) P.201~204 私が何となくゆうつなときなど、ふと、とり出してみたくなる本は、式亭三馬の「浮世風呂」「浮世床」という、こっけい本である。 たいへん面白くて、読んでいるうちに、笑えてきます。 三馬は、江戸末期、一八〇〇年代のはじめに活躍した、大衆小説作家で、「浮世風呂」「浮世床」は彼の代表作です。これらは、ずいぶん、その当時の人々に愛されたものでした。 三馬は戯作の筆もとりましたが、一面、手がたい実業家でもありました。薬商をいとなんで化粧水などを製造し、それを自作の小説の中にも宣伝するといった、ジャーナリスティクな才能にもめぐまれ、お金もうけも、決して下手ではありませんでした。 そんな三馬が書いた小説は、だから卑俗ですが、説説力があります。写実的で現実の重みがあります。 「浮世風呂」は銭湯に集まる江戸庶民の会話、「浮世床」は、床屋に集まる人々のそれを書きとめて、さながら、江戸時代のテ-プレコーダーをまわして聞くようです。 その会話の面白いこと、さながら息遣いから口吻まで想像できるおかしさは、十返舎一九らのこっけい本の、作為的なおかしみと、全然、別のものです。 筋はなくても、さまざまな身分、生活環境、性格の人々を、会話でかきわけてあるだけですが、おのずから、そこに三馬の見識というか、社会をみる目の皮肉さというか、そんなものが浮き上がってくるのも、たのしいところです。 「浮世風呂」三篇、「春は曙、やうやう白くなりゆく洗粉に、旧年の顔を洗う初湯の烟、細くたなびきたる女湯の有様、いかで見ん物とて、松の内早仕舞ちふ札かけたる格子の下に佇み、障子のひまよりかいま見るに、その様おかしくもあり、又、おのが身のぶざめいたるは、あさましくもありけり」女湯の中の会話を、そーっとぬすみ聞きしてみましょう。 ト書に「髪の毛のうすき女房、二人にて流し合ってゐる」とあります。 ※参考:【ト書き】:脚本で、せりふの間に、俳優の動き・出入り、照明・音楽・効果などの演出を説明したり指定したりした文章。(黒崎記) お川「コウコウ お山さん、お前の隣ぢゃァ、夕も夫婦喧嘩があったの、久しいものさ。なぜああだろう」このお川さんのとなりには、新婚の夫婦が住んでいるとみえ、岡焼き半分で、こきおろします。 お川「屋敷から下りたてのおかみさんに、もちたての女房だって、間がなすぎな、お縁さんのそばによって、のろけた顔を見なァ」三馬の会話の面白さは、ほんとうは落語の口述のような部分がよくわかるのですが、ここへ引用したのは、ある意味で感慨があったからです。 お川さんのいう夫婦論・男女論は、いまの世の婦人雑誌、女性週刊誌の説く夫婦論・男女論と、本質的にはかわっていません。 百七十年昔の夫婦論から、まだ変化していないというのは、これは、男と女の本質論なのではないでしょうか。 そういうことをいえる三馬というひとは、卑俗に平明に書きながら、本当は、すごく世の中のことを知りぬいていたのではないかと思われます。ふかく物を見ていたのでしょう。 世間のこと、人の心、人の性格などに、どん欲な好奇心と愛情をもち、それを、しかし粉飾しないで、素材そのままのように投げ出しました。三馬は人間の肉声が好きでした。ナマの生活が好きでした。それを面白がる自分の心のままに、筆が宙をはしって、出来上ったのが、「浮世風呂」「浮世床」なのでした。 平成29(2017)年5月14日 |
|
知盛最後 (平家物語) P.208~212 元禄二年(一一八五年)三月二十四日。 卯の刻(午前六時)に戦いははじまりました。 名にしおう激流の瀬戸。「門司・赤間・壇の浦はたぎッておつる潮なれば」源氏の船は潮に向っておしおとされ、平家の船は潮に乗ってすすみ、源平死力をつくしての戦いは、はじめ、平家の有利とみえました。 しかし午後になって潮の流れはかわり、その上、平家を見限って源氏につく船が出て来て、にわかに平家の旗色はわるくなりました。 平家の総大将は新中納言、知盛。平家随一の猛将です。私はこの男が好きなのです。 三十四歳の男ざかり、この人を措いて、平家の侍大将はないというような、勇ましいもののふでした。「平家物語」は、知盛の最後を美しく描き切っています。 知盛は決死の覚悟をきめていました。彼は今まであらん限りの力で平家の頽勢を支えてきたのです。今日が最期の決戦と知っています。彼は船の屋形に立って大音声で武士たちに下知します。「戦は今日ぞ限り。者ども、少しも退く心あるべからず。天竺・震旦にも日本我朝にも並びなき名将勇士といえども、運命つきぬれば力及ばず、されども名こそ惜しけれ、東国のもの共に弱気見ゆな。いつのために命をば惜しむべき、是のみぞ思ふこと」 補注 彼はすでに一の谷の合戦で、息子の知章を死なせています。まだほんの少年の息子は、彼をかばおうとして敵に討たれたのでした。その傷(いた)みぞ知盛は癒すすべもありません。最後の決戦に死力をつくして戦うこと、それしかないのです。 しかし源氏の船は、勢いするどく攻めたて矢をいかけ、平家方はしだいに浮き足立ました。「源平の国あらそひ、今日を限りとぞ見えたりける」源氏の兵たちは、平家の船にどんどんのりうつってきます。源氏もまた東国そだちの荒えびす。命おしまぬ猛々しい侍たちです。平家方の水手かじとり、「射殺され、斬り殺されて、船を直すに及ばず、船底に伏しにけり」 知盛は、形勢を見て、安徳幼帝のおわす御座船に小舟をこぎよせていきました。 「世のなか、今はかうと見えて候。見ぐるしからん物どもみな海へ入れさせ給へ」 今はこれまでです。見苦しいものはみな海へ捨てなさい、と女たちにさしずして、みずからそのあたりをきよめるのでした。女房たちは口々に、中納言さま、いくさはどんな様子でございますか、と聞きますと、「めずらしきあづま男をこそ、御らんぜられ候はんずらめ」 珍しい東国男をごらんになれるでしょう、と知盛はからからと笑うのでした。なんでこんな時にご冗談を……と彼女たちは鳴き声を立てて叫びます。 知盛は、こんな時にこそ、冗談がいえるのでした。精神は死力をつくして戦ったあとのさわやかさに澄んでいます。 清盛の妻、二位の尼君も、かねての覚悟通り、女なりとも敵の手にかかるまじと、安徳帝を抱き奉って、ふなばたへ歩みよります。 主上ことしは八歳、「おんかたちうつくしく、あたりもてり輝くばかりなり。御髪黒うゆらゆらとして、御背中すぎさせ給へリ」ふしぎそうに、私をどこへつれていくの、と仰せられます。尼君は涙を抑え、幼帝の小さく美しいおん手をお合せ申して、 「浪のしたにも都のさぶらうぞ」 となぐさめ奉って、千尋の海へ身を投じられました。つづく建礼門院、あまたの女房たち、波の上には花を散らしたような、阿鼻叫喚の様だったことだったことでしょう。 平家の公達も、次々といさぎよく船から身を沈めました。平中納言教盛、修理大夫経盛、鎧の上に錨を負い、手を組んで海へ入ります。資盛、行盛、有盛らも共に「手に手をとりくんで一所に沈み給ひけり」 この中にも、総大将宗盛・清宗父子は、入水する勇気もなく、みかねて人々が海へつきおとしましたが、泳ぎができる上に、鎧も身にまとわず、死ぬに死ねないでいるところを源氏軍に、生け捕りせられました。 それをよそめに、華々しい武者ぶりは、知盛につづく勇将と謳われた能登守教経でした。 今日を最後と、矢だねのあるほど射つくして、白柄の大長刀で薙ぎまわります。その奮戦ぶりを、知盛は余裕をもってながめつつ、使者をたてて「能登どの、いたう罪なつくり給ひそ。さりとてよき敵か」といわせます。とるに足らぬ雑兵などを討って、そう罪つくりをしなさるな、と声をかける知盛に、闊達な男らしさがうかがわれます。教盛は聞こえる暴れん坊若様です。「さては大将軍に組めということか」と刀の柄を短く持って、源氏の船にとびうつり、のりうつり、白兵戦を挑みます。めざすは九朗判官、源氏の総大将の首、しかし判官は身軽く舟をとんで危ういところを脱し、いまはこれまでと教盛は、舟につったって大音声で、われと思わん者はこの教盛を生けどりにして鎌倉へ曳け、頼朝に会うて、ひとことものいうぞ、と「おそろしなッどもをろかなり」というすさまじさ。 大力自慢の源氏方の侍が三人、どうと教盛にうちかかります。教盛、一人を海に蹴り入れ、二人を両脇にかいばさんで「いざうれ、さらばおれら死途の山のともせよ」と、海へざんぶと入りました。 知盛は静かに、つぶやきます。「見るべきほどのことは見つ」 ああ見た。ほろび栄える人の世のありさま、運命の転変のおもしろさ、おもしろうてやがてあはれなきさまざまを見とどけた。
知盛は、めのと子の家永をよんで、約束だぞ、共に死のう、といいます。家永、「子細にや及び候」(申すまでもございません)たがいに鎧二領を着、手をとりあって海に入りました。名を惜しむもののふたち二十余人、おくれじと手に手をとって、一所に沈みました。「平家物語」の、このあとの文章は、わけてぬきんでた名文です。 「海上には赤旗・赤じるし投げすて、かなぐりすてたりければ、竜田川の紅葉ばを嵐の吹きちらしたるがごとし。汀(みぎは)によする白波もうす紅にぞなりにける。主もなきむなしき船は、汐にひかれ風にしたがッて、いづくをさすともなくゆらゆらゆくこそ悲しけれ」 参考:〚平家物語〛(角川文庫下)P.206 敗けいくさの海上にただようかなしみを簡潔に叙しています。 「見るべきほどのことは見つ」――知盛は死にのぞんで、ゆくりなく、宇宙の大きな意志をかいまみたのでしょうか、死も生も一如、知盛はほほえんで死んだにちがいありません。 いま、関門海峡には大きな橋がかかりました。八百年の昔、この下の海で、「見るべきはどのことは見つ」とつぶやいた人の思いを秘めて、潮はとどろと渦巻いています。 補注:「平家物語(下巻)(角川文庫)P.200~201。 平成29(2017)年5月27日 |
|
雪ちるや(小林一茶) P.213~216 雪ちるやおどけも言へぬ信濃空(『一茶俳句集』岩波文庫P.306:黒崎記) 冬は、小林一茶の句の思い出されるときです。 私のように暖国の関西に生まれた人間には想像もつかぬ、雪の下の人々の感情が、一茶の句には暗く烈しく渦巻いています。 一茶は、雪を風流なものと、賞で興じるのは、雲の上人のことだとあざわらうのでした。 一茶のいう、「下々の下国の信濃」では、 「木の葉はらはらと峰のあらしの音ばかりして淋しく、人目も草も枯れはてて、霜降月のはじめより白いものがちらちらすれば、悪いものが降る、寒いものが降ると口々にののしりて、――初雪をいまいましいというべき哉」 荒くきびしい自然の猛威に加え、少年時代の一茶は、まま母にいじめられて育ったと、「生ひ立ちの記」にかいています。異母弟が生れてからは子守をしていて泣くと、一茶がいじめたのではないかと責められ、 「杖のうき目あてられること日に百度、月に八千度、一とせ三百五十九日、目のはれざる日もなかりし」 若い日の私は、一茶の不遇な少年時代に同情し、一茶がそのため、長じてやさしいおじさんとなり、「やれ打つな蠅が手をする足をする」(『一茶俳句集』岩波文庫P.243:黒崎記)「痩せ蛙負けるな一茶これにあり(『一茶俳句集』岩波文庫P.320:黒崎記)」 などという、よわいものに哀れみの涙をそそぐ、童心詩人になったのだと、思いこんでいました。 しかし、一茶の句や伝記をよむと、中々、そんな単純なのものではないのです。 一茶は少年のころ、江戸へ奉公に出されました。一七〇〇年代の終りごろでした。辛い放浪時代のうち、いつか一茶、俳諧師としての人生を歩んでいました。故郷を追われ、うしろだてもなく、深い学問もない彼には、この道もまた、いばらの道だったことでしょう。 夕燕我にはあすのあてはなき『一茶俳句集』岩波文庫P.102:黒崎記) 梅咲くやあはれ今年も貰ひ餠『一茶俳句集』岩波文庫P.107:黒崎記) 年の市何しに出たと人のいふ『一茶俳句集』岩波文庫P.78:黒崎記) 春立つや四十三年人の飯『一茶俳句集』岩波文庫P.77:黒崎記) 貧窮と屈辱と孤独に身をすりへらした一茶は、いつしかそんな年となっています。富裕な俳人仲間をたよっては流浪し、食いつなぐ日々の辛いくらしは、彼を、気むずかしく傲慢で、時に卑屈な屈折した人柄に染め上げたようでした。 故郷の父を見舞ったときに、たまたま父は病いおもく、一茶はそのまま、居ついて看病しました。それが『父の終焉日記』です。
その文章の、まあなんと強引で、自分本位なことでしょう。ここではまま母も異母弟も冷酷無残な悪人にされ、真に父のことを思う孝行者は一茶ひとり、と書かれています。とすれば「生ひ立ちの記」にある「杖を日に百度」というのも、かなり一茶流の誇張があるのかもしれません。「我ときてあそべや親のない雀」『一茶俳句集』岩波文庫P.208:黒崎記)も、彼らしいポーズだったかもしれません。独断的な文章や発想は、私をして一茶の人格を疑わせるに充分でした。それに、彼は父の死後十二年間も、異母弟と遺産相続で争い、ついにはむしりとるようにして、故郷の一角の地を、自分のものにしています。五十の坂をこえて若い妻を迎え、死なせたㇼ別れたりして三度妻をとりかえ、浮世の欲望に執着するさまも、むき出しにしました。 ほんとうに一茶という男は、ひとすじなわではゆかぬ野性的な、あらあらしい、ねじけまがった性格にみえました……ところがそのむくつけき野人が、どうしてあんなに、美しい、やさしい句を、ひょいひょいと、口にのぼせるのでしょう、澄んだ詩人の目と童心がなくてどうしてこんな句がよめるでしょう。 雪とけて村いっぱいの子どもかな『一茶俳句集』岩波文庫P.202:黒崎記) うつくしや障子の穴の天の川『一茶俳句集』岩波文庫P.189:黒崎記) 湯けぶりも月夜の春となりにけり『一茶俳句集』岩波文庫P.174:黒崎記) これもまた疑いない一茶の一面だったのです。 私にとって、人間というものの面白さ、ふしぎさを教えてくれるのは、いつも一茶です。 20222年09月05日。 |
|
黄葉夕陽村塾(漢詩) P.217~219 私は漢詩のもつ、あのきりっとした硬質のリズム感と、そこにくりひろげられる、清澄なイメージの世界が好きです。 日本人が漢詩をつくるというのは、ちょうど、英語の詩を書くのと同じで、所詮、本家の国の詩人たちに及ぶはずがはありません。けれども、本来、すぐれた資質をもち、万事につけて熱心な日本民族は、渡来した漢字文化にたちまち夢中になりました。漢文・漢詩の素養は、知識階級男子の不可欠な条件でした。そうして日本人の漢詩もたいそうすぐれたものが作られるようになり、時には本家の中国の文人に、おほめを頂戴するほどの詩人さえ出ました。 江戸末期は、漢詩のたいそうさかんだったときで、有名な漢詩人がたくさん出ました。頼山陽はもっとも人に知られた詩人でしょう。山陽の詩句は派手で鋭く強く個性的ですが、私としては、あまり好きではありません。 ――といっても、私は漢詩についてはお恥ずかしいことながら深く知らないのです。起承転結の展開とか平仄(ひょうそく)・韻脚などのきまり、絶句や律など種類が多く、むつかしい約束ごとがあり、それらに通じていればより一そう味わい方も面白くなるのでしょうが、私が読むのは国語まじりの読み下し、いわゆる詩吟などで唱い上げられるよみかたです。 菅山茶という、江戸末期の儒学者がいます。中国風名前ですが、これはペンネームで、備後・福山の人です。わかい頃、京都にゆき、儒学を修め、のち郷里にかえって若者たちを教えました。その塾の名を「黄葉夕陽村塾」といいます。私は「松下村塾」という名も好きですが、この名前もすばらしいと思います。そして、若者たちに勉強させる機関としては、こんな風に一人のすぐれた先生が私塾を開いて、真剣に学びたい意欲をもっている若者だけを教えるというのが本当ではないかと思います。ーー菅山茶は一代の碩学でしたし、また人格の温和で謙虚ななことでも知られ、彼を敬慕する生徒が多く、しまいに塾は収容しきれなくなって、とうとう藩の塾にしてもらい「廉塾」と名づけました。 彼の詩は、語句がよくこなれて、やさしい人柄と、しずかな詩人の目がかんじられます。「冬日雑詩」という詩があります。
寒鳥相追入乱松 隔渓孤寺静鳴鐘 寒鳥 相追ウテ乱松二入レバ 寒い澄んだ冬の暮れの状況です。鳥たちは追ったり追われたりしつつ、ばらばらに生えている松林に入ってゆく、谷の向こう側の、ぽつんと建っている寺では静かに鐘を鳴らす。山風がにわかにわきおこり夕べの雲をあつめて吹き払うと、西南の峰の三つ四つに雲がみえる……風の寒さが身に感じられるような詩です。「路上」というやさしい詩もあります。
反照入楊林 沙湾晩未冥
反照ハ楊林ニ入レバ 夕日はかわやなぎの林にあかあかとさしこみ、そのため水際もまだあかるく照り返っている。母牛と仔牛は、川をへだてて、のどかに鳴き合っている。…… 漢字と漢字のつらなりは固そうにみえますが、かえり点を打ってゆっくりと味わってみますと、一語一語が珠玉のように光ってそれがふれあうたび、たまゆらのさわやかな音をたてます。悲壮なもの、烈しいものが漢詩の本分のように思われますが、しずけさとやさしさのあふれる漢詩もまた、人々に愛されてきたのです。 平成29(2017)年5月25日 |
|
峯のあらし (小督局) P.220~222
高倉天皇と言うみかどは、「平家物語」によれば「むげに幼主のときより性を柔和にうけさせ給へり」、やさしいお気立ての方でした。 まだ八歳のいとけない年頃に即位させられ、ほんの少年のころに、結婚させられ……帝は、物心つく前から、平家一門の、政治的配慮でその人生を人々に操られ、動かされ、強いられてきたような運命の方でした。 おん父は後白河法皇、平清盛は、義理の叔父に当り、二大実力者の間にあって、天皇とは名ばかりの地位、そして結婚相手は、清盛の娘、徳子……。 帝は仕組まれた運命のレールを、そのまま動かされて、青年となられました。 補注 ところが、帝が、ご自分で、運命をえらばれる日がきました。それは、当時、宮中第一の美女で、ならびなき琴の名手といわれた小督局と、恋におちられたからです。 この恋は清盛の怒りを買いました。わが娘の中宮徳子に、一日も早い皇子ご誕生を、と願っている清盛は、帝が、ほかの女に心をうつしていられるのに堪えられないで、小督をなきものにせよ、といいつけます。 小督は心を痛めました。わが身はどうなっても帝にご迷惑がかかっては、と「ある夜内裏をいでて、ゆくゑも知らずうせ給ひぬ」 突如、恋をひき裂かれた帝は、悲しみにくれて、小督のゆくえをたずねられましたが、清盛をおそれて、お味方する者もないありさま。八月の十日あまり、月の美しい宵です。帝は「人やある」と呼ばれます。遠くにひかえていた仲国が、お答えしますと、小郷ののゆくえを知らぬかととのお尋ねです。噂では嵯峨の奥にかくれすむそうな。探し出すことはできぬものだろうか。涙を押さえてのお尋ねです。 仲国の心は、若い薄幸な二人の恋人たちへの同情で一ぱいになりました。よろしゅうございます。私がおさがしいたしましょう。この美しい月夜、琴の名手の小郷どのは、みかどのおんことを思い出しまいらせて琴をひいていられるかもしれませぬ。琴の音をたよりにあちらこちらをさがしてみましょう。彼はすぐさま「名月にむちをあげ、そこともしらずあこがれゆく」のでした。このあたり、まるで、大和絵をみるような「平家物語」の名文です。 「亀山のあたりちかく、松の一むらある方に、かすかに琴ぞきこえける。峰のあらしか松風か、たずぬる人の琴の音か、おぼつかなくはおもへども、駒を早めてゆく程に、片折戸したる内に、琴をぞひきすまされたる。ひかへて是をききければ、すこしもまがふべうもなき小郷殿の爪音なり。楽は何ぞとききければ、夫を思うて恋ふとよぽむ想夫恋という楽なり、さればこそ、君のおんことおもひ出まいらせて、楽こそおほけれ、此の楽をひきたまひけるやさしさよ」 みつけ出された小督は、ひそかに内裏へ迎え入れられました。禁じられ堰かれた恋であってみれば、よりいっそうそれは二人を暗く烈しく包んだことでしょう。しかしたちまちその恋はおそろしい清盛の耳に入ってしまいました。小督は捕えられ、尼にして放たれました。帝は憂憤やるかたなく、苦しみにやつれ、恋にやせ、ついに、おん年二十一、というみじかい生涯を終えられました。小督は濃い墨染の衣をまとわされたとき、花のような二十二だったと伝えられまっす。 いま小督の墓といわれるのは大堰川の渡月橋のそばと、東山清閑寺の高倉天皇の御陵の内と、二つありますが、私としては、高倉帝のそばによりそうように埋められたと思いたい気がします――もとより御陵の内は、さしのぞくことは許されませんが、ひともとの杉の根元に、ひっそりと、宝篋印塔が据えられているそうです――私が訪れた日は寒い冬の一日でした。ひえびえする空気、折々こぼれる霧雨のしずく、と思ふとふと雲が切れて、もみじの梢に日が当り、全山さやかに青くなりました。しいんとした高倉帝のご陵内の、すがすがしい玉垣のうちにその杉の木は立っていました。小督の塚のしるしがあるのは、あの杉の木なのでしょうか。すでに肉体は大地に還り、いまは二人の恋と、月夜の琴の音だけが八百年ののちにも、れいろうと澄んでひびき交しています。恋人たちのやさしいねむりを思い、私はふり返りふり返り、石段を去ったことでした。 補注:「平家物語(上巻)」P.281 三 小督の事 2025.12.03 記す。 |

世間胸算用 (井原西鶴) P.223~226 西鶴は大晦日をテーマにした『世間胸算用』という小説集を書いています。 商人・町人の金のやりくり算段、大みそかほどたいへんなものはありまん。昔は年に数回の節季払いでしたが、大みそかは一年の総決算、この二十四時間の峠を越さねば、あらたまの春とはならず、人々は足をそらに金の算段に走り狂います。 「けふの一日、鉄のわらじを破り、世間を韋駄天(足の早い神さま)のかけ廻るごとく、商人は勢ひひとつのものぞかし」 必ず掛け金をとって帰らねばと意気ごむ掛取り、わびごとを言いつくして果ては狂言自殺をもくろむ人々、ありそうでないものは金、裕福そうな町家も一歩内へはいれば火の車、西鶴は大みそかを舞台に、虚々実々のかけひき、やりくりを面白おかしく描きます。面白うてやがてかなしき大みそか、金、金、金の浮き世のさまざまを、例の口早な、凄いテンポでやつぎばやに、西鶴はたたみかけて語るのです。 「世間胸算用」は、彼の作品中では一ばん面白いものではないかと、私は思います。 金に操られる人生を、西鶴はながめながら、そのむごさと共におかしみ、面白さも見のがしていません。ことに、貧乏長屋の大みそかの、とぼけたおかしみは無類です。 金のやりくり算段は、むしろりっぱな冨家のこと、「いっそ貧しい下層町人は気楽なものです。貧乏長屋六七軒、「何として年をとる事ぞと思ひしに、皆、質種の心あてあれば、少しも世を歎く風情なし」 米みそ・たきぎ・醤油・塩・あぶら、貧乏人には貸し売りするものもないので現金払いゆえ、大みそかがきてもふだん通り、「帳(掛取り帳のこと)さげて案内なしにうちへ入るものひとりもなく、誰におそれて詫言するかたもなく、楽みは貧賤にありて、古人の詞、反故にならず」 正月のことは何として埒あけることぞ思ってみていると、みんなそれぞれ質をおく覚悟があって手廻しよくしているのが、哀れにもおかしいのです。 一軒からは、古い傘一本に綿繰一つ、茶釜一つ、かれこれ三色で、銀一匁借りて「事すましける」 銀一匁は米が二升五合買える程度の金でした。 その隣家では、女房のふだん帯、男のもめん頭巾、蓋なしの小重箱一組、機織りの筬、五合桝と一合桝二つ、石皿五枚、仏の道具いろいろとりあつめ、二十三色で、「一匁六分借りて年を取ける」 その東どなりには舞舞が住んでいました。門付芸人ですが、元日からは大黒舞に商売替えするので、面と小槌一つあれば、正月中の口過ぎはできます。それまでの商売道具の烏帽子、ひたたれ、袴は「いらぬ物とて、弐匁七分の七に置きて、ゆるりと年を越ける」 そのまたとなには、小うるさい貧乏浪人が住んでいました。年久しい売食い生活、おもちゃの手内職もいまはすたれ、 「今という今、小尻さしつまりて、一夜を越すべき才覚なく、似せ梨地の長刀の鞘をひとつ」女房が質屋へ持って来ました。こんなものが何の役に立つものか、と質屋の亭主が投げ戻すと、浪人の女房、顔色をかえて、「人の大事の道具を、何とてなげてそこなひけるぞ」といきりたちます。 「質にいやならば、いやですむ事なり。その上何の役に立たぬとは、爰が聞所じゃ。それはわらが親、石田治部少之輔乱に、ならびなき手がら遊ばしたる長刀なれども、男子なき故にわたくしに譲り給はり、世に有時の嫁入に、対の挟箱の先へ持たせたるに、役にたたぬものとは先祖の恥。女にこそ生れたれ、命はをしまぬ。相手は亭主」 ととりついてなきわめくので亭主も閉口頓首、さまざま詫びても聞き入れず、そのうち近所の者があつまって、あの女の連れ合いの浪人は、がらがわるい。ゆすりがお得意のうっとうしい男、ききつけて来ぬうちに、ほどよいところで手を打ちなされと仲に入り、とど、銭三百と黒米三升で、「やうやうにすましける」女はまだ、こんな米では明日の用に立たぬというので、碓まで貸して、米を踏ませて帰しました。質屋はふんだりけったりです。西鶴はさらりとあとへ、 「扨ても時世かな、この女もむかしは千二百石取たる人の息女、萬を花車にてくらせし身なれ共、今の貧につれて、むりなる事に人をねだるとは、身に覚えて口をし。是を見るにも貧にては死なれぬものぞかし」 浪人のとなりに、一人ずみの三十七八ばかりの女、身のたしなみ目だたぬようにして、色香もすこし残っているのがいますが、正月の用意は、 「はや極月(十二月)のはじめに、万事を手廻しよく仕舞ひて、割木(たきぎ)も二三月までのたくはへ、肴かけには二番の鰤一本、小鯛五枚、鱈二本、かん箸、ぬり箸、紀伊国御器(うるしぬりの食器)鍋ぶたまでさらりと新しく仕替え」というソツのなさ。また、そればかりではありません。世間づきあいもぬからず、「家主殿へ目ぐろ(塩づけの魚)一本、娘御に絹緒の小雪駄、お内儀さまへはうね足袋一足、七軒の相貸屋へ、餠に牛蒡一抱づゝ添て、礼儀正しくとしを取ける」 西鶴は、あとへするどくつけ加えます。 「人のしらぬ渡世、何をかして、内証のことはしらず」 商いをする様子でもなし、何をして生活をたてているのかしら、内輪のことはわからない。お囲いものか、ただしはもっと人にいえない商売か――けれども、この女の、手のぬかりない正月仕度が、手まわしがよいだけに澄ましている顔が目にみえるようで、おかしみをさそわれます。 「まことに世の中の哀れを見る事、貧家のほとりの小質屋、心弱くてはならぬ事なり、脇から見るさへ悲しき事の数々なる、年のくれにぞ有ける」 と結びながらの西鶴は、貧乏人は貧乏人なりの才覚や工面を、大商人のやりくりと同じに扱い、おかしがっています。富貴も貧賤も人間のいとなみはみな同じ、西鶴はつれなく鋭い筆致のうちに、あたたかい共感を人間のくらしに寄せています。 2022.09.08記す。 |
|
失われた夢(滝沢馬琴) P.236~240
種彦の「偽紫田舎源氏」が、江戸末期の女性たちに大いにうけたとすると、男性たちに熱狂的に愛読されたのは、滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」ではありますまいか。これはまさに男のよみものです。 仁義礼智忠信孝て悌の八字を彫った水晶の珠(たま)は八方に飛んで、やがて八犬士が生まれ、数奇な運命を辿って里見家を再興します。八犬士がたがいに織りなす波乱万丈の物語、義士の奮戦あり、悪人の奸計あり、妖怪の幻術あり、美女の貞節あり、毒婦の淫乱あり、忠臣の苦節あり、一巻は一巻と、目もあやな興趣ぶかい場面がくりひろげられ、巻をおくあたわず、手に汗をにぎるシーンの連続です。 量からいっても、九十八巻、百六冊の大長編です。稿を起したのは文化十年(一八一三年)馬琴が読本(よみほん)作者として脂ののりきった四十六の男ざかりでしたが、完結したときは七十四歳になっていました。前後二十八年かかって書き上げた超大作でした。 しかもその間、たよりにする息子は病没し、あまつさえ馬琴自身、失明するという不幸にまで見舞われました。彼はそれにもめげず、嫁に口述筆記をさせ、血のにじむ努力を払ってかきあげました。この一作に、彼は生涯の夢と情熱と才能のありたけをこめて書きました。永遠にのこる大作品、と信じて心魂こめて、書いたのでした。 しかし、いま、悲しいことに、馬琴の原作をよもうとする人は、ありません。 そのむつかしい漢字の羅列(馬琴は和漢の教養がふかく、つい作品の中に、その知識をつぎこむのです)それにもまして、登場人物は善玉悪玉にわかれ、善玉は修身の教科書のようなことをしゃべり、悪玉はまた全くの悪人です。そうです。馬琴は、善を勧め、悪をこらすという、人の道のお手本としての骨格を、小説に打ち出し、それが彼の、自分は他の凡百の戯作者とちがう、というプライドでした。 それゆえ、西洋の小説の概念が、明治になってわが国に入ってきたとき、まっ先に槍玉に上り、おとしめられたのは馬琴の小説でした。あんなに彼が心こめて書いたのに……。 「八犬伝」はそんな、つまらない物語でしょうか。この長々しい物語をルビにたよりつつよむ内に、私は登場人物の運命の推移から、この世は因と果で対立しているといった人生の一大パノラマが展開されているいるのに気付きました。とくに楽しいのは紙芝居みたいに華やかな、極彩色の場面です。 「八犬伝」巻の三、第六十六回、庚申(こうしん)山の怪猫退治、年へた山猫は、赤岩一角を食い殺し、みずから一角に化けて人々をたぶらかせています。八犬士の一人、犬飼現八と、角太郎は怪猫を打ちとろうとします。 「死せしと見えたる仮一角は、忽地呻く声振動して、障子紙戸も裂るが如く、雙テを張て身を起せば、はじめに異なる奇怪のの相貌、既にと死老る山猫の、形態を露す面部の斑毛、眼の光は百煉の、鏡を並掛たる如く、(以下略) 息もつかせぬ名文です。七五調を緩急自在に駆使して、切迫感に美しさを与えています。馬琴は自分で字を作ったりしましたので、ふしぎな字がいっぱい出てきます。語句のえらび方に、馬琴なりの強い嗜好があり、それらから立ちのぼる妖しい香気が、阿片のように読者を酔わせてしまいます。そうして次々とくつがえる運命の転変に、人々はためいきついて読み痴れてゆくのでした。 近代文化は勧善懲悪や義理人情を否定することからはじまりました。しかし、それと同時に、私たちは馬琴の作品のもつ、たぐいまれなエネルギー、行間にみなぎる樹熱、すじはこびの奇想天外な面白さ、巧緻な趣向、小説をよんで知湧き肉おどるといった夢やロマンをも、失ってしまったような気がしてなりません。 2025.11.30 記す。 |
|
きつね妻(日本霊異記) P.245~249
「日本のアラビアンナイト」といわれる「今昔物語」の、タネ本になったのは、それより三百年も前の、奈良朝の末に書かれた「日本霊異記」です。 これも、「今昔」に劣らず、面白いお話がいっぱい盛られています。 ただこの本は、仏教説話集であるところに特徴があります。奈良時代は仏教のさかんな時代でしたが、末になるにつれて世はみだれ人心はすさみ、仏の教えを守る人が少なくなりました。世を救い、人を教化すべき僧侶の中でさえ、むざんな堕落瘦、破戒尼が出るしまつでした。 奈良の薬師寺に景戒というお坊さんがいました。 彼はそんな世の中に心をいため、仏の道を少しでも弘めるためにと、筆をとって物語をかきあつめました。景戒は想像力のゆたかな、好奇心のつよい、弾力ある心の人でした。古い中国の本や、民衆の間に伝わる伝説を拾い、縦横に脚色し、翻案して、その時代の人々に共感できるような話につくりかえました。 そして、物語を通じて、仏の功徳、因果応報のことわり、仏教徒として生きる道などを説きました――そういうと、いかにも抹香くさく、形式的な説教集のように思われがちですが、一つ一つのお話が、とてもいきいきして面白いのです! 正史には出てこない奈良時代の民衆の日常生活や考え方が、目前にみるように、ありありと浮ぶ、たのしい本なのです! 文章は漢文ですが、正式の漢文ではなく、和風の漢文というべきか、ゴツ゚ゴツ゚して、そして率直な文体が、古拙でいいかんじです。 私の大好きなお話は、閻魔大王のお使いできた、ユーモラスな鬼の話。 中巻、巻二十四、「閻魔王の使の鬼、召さるる人の賂を得て免す縁」というくだりです。 聖武天皇の御代楢磐嶋という人がいました。 彼は商用で越前まで旅し、ひとり家へ帰る途中、志賀の唐崎でふとふりかえると三人の男が一町ほどうしろを歩いていました。宇治まで来たとき、男たちが追いつき、一緒になりました。磐嶋は何気なく、どちらまでいかれますか、とききますと、おどろくべき答がかえってきました。 「閻魔王の闕の楢磐嶋を召しに往く使いなり」 磐嶋は仰天しました。 <それは私でございます、何のためにお召しになるのですか> 使いの鬼はいいました。 <知れたこと、寿命が尽きたせいだ。われらは先に、お前の家へいってたずねたら、商用で出ているという。やっと出先でつかまえたのだ。家へかえるまでしばらく猶予してやる。お前をさがしてあちこち奔走して飢え疲れた。何か食い物はないか> <ここに干し飯がございます> 磐嶋は大いそぎでさし出しました。きっと楢磐嶋はさまざまの感慨が胸にあふれて、顔色もかわっていたかもしれません。使いの鬼は親切な鬼だとみえて、 <あんまりわれわれに近づくと毒気にあてられて病気になるから、近よらぬ方がよい。それに、こわがらなくてもよい>
磐嶋は家につくなり、大宴会をして鬼たちにご馳走しました。鬼はだんだんあつかましくなり、 <おれは牛肉が好きだ。牛肉を食わせろ> などといいます。磐嶋は、こうなると何の肉でもさし出したい気持です。 <わが家に斑牛が二頭ございます。これをさし上げますから、閻魔庁へ引き立てられるのだけはお許し願いたいのですが> 鬼たちは考えました。 <そうだな、我々はいまお前のご馳走をたらふく食った。そのお返しに許したいのだが、そうすると、我々は重い罪になって、鉄の杖で百回打たれてしまう。もし、お前と同じ年の人があれば、それを身代わりにするのだが> 鬼たちはひたいをあつめてはかり、結局、同じ年の生れの身代わり男をさがし出し、連れていくことになりました。 <その代りに、金剛般若経を百回読め、お前の牛を収賄したために我々が罪におとされるかもしれないからな> と鬼はいい置いて消えました。磐嶋は、早速、尊い法師のもとへゆき、心をこめて鬼のために供養し、おかげで九十までの齢を保ちました。 この鬼は人間くさく、とぼけたおかしみがあって、当時の人々の心がいきいきと反映しています。 狐を妻にする話はわが国に多いのですが、それも「日本霊異記」からでしょうか。上巻第二のお話―― 欽明天皇の御代、美濃の国大野郡の男が、広野の中で美少女に出あいました。男はたちまち彼女に恋して、妻にするために連れ帰りました。 ところがその家の犬の子が、いつもこの妻に歯をむき、唸るのです。妻は怖がって、あの犬を殺して下さいと夫にいうのですが、夫は犬を可愛がっていたので、殺しませんでした。あるとき、犬がひどく妻にほえかかり、かみつこうとして追いかけました。妻はおびえて惑い、たちまち狐のすがたをあらわして垣の上に登って逃げました。 男のおどろきは、いかばかりだったでしょう。 狐は、かなしげに去りもやらず、家のまわりをめぐって鳴きます。男は叫びました。 <お前とおれとは、子まで生した仲ではないか。おれはお前を忘れないぞ、ここをすみかとして、つねに来て寝よ> 狐はその言葉にしたがい、来て寝ました。それで<きつね>という名になりました。昔は、野干といっていたのです。 でも男にとって、いつまでも、まなかいに残るのは、狐ではなく、赤い裳をひく、なよやかな、細腰の美しい妻でした。男は妻恋しさに堪えかねて歌います。
恋は皆我が上に落ちぬたまかざるはろかに見えて去にし子ゆゑに
人外の生をうけたもの間にも、真の愛は育つと、古い世の人々夢想したのでしょうか。恋はみな、仏の上になだれおちた、という表現のある仏教説話集なんて、ほんとうにすばらしいと思います。 2025.12.02 記す。 |
|
ゆく河の流れ(方丈記) P.250~252
このごろの少年少女に、すぐれた古典の名文の一節を暗記させないのはなぜでしょうか。私には受験勉強などより、ずっと大事なことにおもえるのですが。 昔の学生たちは『方丈記』や『平家物語』の冒頭の一章など、まる暗記させられたものでした。リズム感のある名文なので、若者はすぐおぼえてしまいます。みずみずしい若いあたまに刻みつけられた記憶は、一生消えません。 そのうち二十代、三十代、四十代と生きるにつれて、その文章の意味を、年ごとに深く汲みとるようになります。わけも分からず暗記していたものがたえず新しい意味をもって生き返り、その生涯の血肉となります。古典というものはそういうものです。 「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みにうかぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例しなし。世の中にある人と栖と、また、かくのごとし」…… 旧制高等女学校のひるさがりの教室、少女の澄んだ声で朗読されていた『方丈記』……。きのうのことのように、私の耳もとにありありとよみ返ります。なんという流麗で、しかも、ものさびしい味をたたえた名文でしょう。 「朝に死に、夕に生るならひ、ただ水の泡にぞ似たりける。知らず、生れ死ぬる人、いづかたより来たりて、いづかたへか去る。また知らず、仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。その、あるじと栖と、無常を争ふさま、いはばあさがほの露に異ならず」 『方丈記』の作者、鴨長明が生きた時代は、日本歴史の中でも最も激しい動乱の時代でした。源平の争乱、平家の没落、鎌倉幕府の出現。 花の京都は荒れに荒れ、公卿たちは零落してゆきました。それに加えて、ひまなくおこる天変地異。大火、大地震、飢饉、悪疫の流行、つむじ風……おそろしい時代でした。 若い長明の、澄んだ眼と心に、この世の地獄ともいうべき酸鼻のかずかずが焼きつけられていきました。 大火に吹きたてられて逃げまどう人々。燃え落ちる大邸宅。 安元三年四月廿八日(一一七七年)風の激しく吹く夜、都は大火に焼かれ、はては朱雀門・大極殿・民部省などに移って一夜に焦土となりました。 「吹き迷ふ風に、とかく移りゆくほどに、扇をひろげたるが如く末広になりぬ。遠き家は煙に咽び、近きあたりはひたすら焔を地に吹きつけたり、空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じて、あまねく紅なる中に、風に堪へず、吹きさられたる焔、飛ぶが如くして一二町を越えつつ移りゆく。その中の人、現し心あらむや。或は煙に咽びて倒れ伏し、或は焔にまぐれてたちまちに死ぬ……七珍万宝さながら灰燼となりにき」 家も垣根も虚空にまきあげてしまう治承四年(一一八〇年)のつむじ風も地獄の業風かと思われましたが、元暦二年(一一八五年)の大地震はことにもすごく、「山はくづれて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり。土裂けて水湧き出で、巌割れて谷にまろび入る」 飢饉が襲うと、力ない庶民はばたばた倒れました。これも悲惨なことでした。 「築地のつら、道のほとりに、飢ゑ死ぬるもののたぐひ、数も知らず。取り捨つるわざも知らねば、くさき香、世界にみちみちて、変りゆくかたちありさま、目も当てられぬこと多かり」 長明は世におごり、富を誇ることの空しさを見てしまいました。無常と、世の転変と、人の存在のはかなさは、彼に、「どうやって人間は生きるべきか」を探求させました。 五十になって彼は出家して、京の郊外の日野山に一丈(三メートルあまり)四方の小さな庵を作ってこもりました。「方丈記」というタイトルは、ここから出ています。 彼は、このわびしい山奥のひとりぐらしを愛しました。蕨の穂をしきつめて寝床とし、仏に仕え、念仏し、木の実を拾って飢えをしのぎ、月の明るい夜は琵琶を弾いてみずからをなぐさめました。 しかし『方丈記』の真骨頂は、さきの冒頭の名文と、そして沈うつな最後の一章だと、私には思われます。 この、中世最高の知識人の一人である長明、死を目前に控えた、老長明の知性は、みずからの、隠遁者ポーズの虚飾をするどく見破らずにはいられませんでした。 「仏の教へ給ふおもむきは、事にふれて執心なかれとなり。今、草庵を愛するも、とがとす。閑寂に著するもさはりなるべし」 方丈の小庵を愛するのも「要なきたのしみ」だったと彼は言い捨てます。そのとき、長明の目には、美しい西空夕映えが浄土のように映っていたことでしょう。
私はこの文章を読み、旧制中学校での暗記させられたことをおもいだしました。田辺さん(同世代の人)の古典(国語)の名文の暗記と異なりますが…… ▼中学2年生でした。漢文の時間に吉田松陰の「士気七則」を暗記させられました。 披繙冊子。嘉言如林。躍躍迫人。顧人不讀。即讀不行。苟讀而行之。則雖千萬世不可得盡。 噫復何言。雖然有所知矣。不能不言。人之至情也。古人言諸古。今我言諸。今亦詎傷焉。 作士規七則。 先生が下記の書き下し文のように読み、私たち一同が口をそろえて読みますと、教室にその声がこめられました。先生のお名前は太刀川先生でした。 冊子を披繙すれば、嘉言(かげん)林の如く、躍躍(やくやく)として人に迫る。顧(おもふ)に人読まず、即(もし)読むとも行はず、苟くも読みて之を行はば、則ち千万世(ばんせ)と雖も得て尽す可からず。噫(ああ)、復た何をか言はん。然りと雖も知る所有りて、言はざること能はざるは、人の至情なり。古人は諸(これ)を古(いにしへ)に言ひ、今我は諸れを今に言ふ、今亦た詎(なんぞ)傷(いた)まん。士規七則を作す。 現在でも、「冊子を披繙(ひはん)すれば、嘉言(かげん)林の如く……」と口ずさむことがあります。 ▼次に、「中国史」を村上先生から教えられました。この先生からの考査を思い出しました。考査の前に自分なりに勉強した解答を書きますと、意外にも点数が低いので不思議に思ったことがありました。その後、偶然にも先生の問題には教科書の記事を丸暗記して書かないと評価されないことをしりまして、教科書を繰り返し読み、覚えて解答するとかなりの高得点になりました。 先生が何を意図されての理由はわかりませんが、柔らかい頭の少年に中国史を記憶させようとされたのでしょうか。英語にしても短文を暗記させられた記憶があります。その影響か、私は漢文も英語も好きな科目になっていました……。 平成二十六年五月三十日 |
|
これ小判(川柳) P.256~259 日本人て、ちょっといいな、と私が思うのは、私たち日本人は、あげて詩人の要素があるように思えるからです。 参考:俳句菌とカメラ菌 日本人には、俳句・短歌という、手みじかな表現形式があって、たいそう便利なせいもあります。 見わたしてみると、俳句・短歌の素質のあるひと、そこまでいかなくても親近感をもっているひと、なだらかな五七調の波に身をゆだねて快いひと(五七調に抵抗を感ずるというひとは、また、そのひとなりの詩の波長をもっています)がなんと多いことでしょう。こんなに文学的な民族があるでしょうか。ちまたに住む、名もなき人が、それぞれの感情を託して、みじかい詩形にまとめようとどりょくします。まとめるべき芸術的衝動を多くの人がもっているというのは、民族文化のレベルが高いのではないでしょうか。 私がことにおもしろく思うのは、芸術的衝動という志の高いものとべつに、日本人には独特のユーモア感覚があることです。 世態人情のおかしみ、機微をとらえて、うまくうがった短詩が発達しました。それを「川柳」といいます。そして、これこそ庶民のたのしみになって、どんな人々でも手がるにつくれる、身近でしたしい庶民文学となりました。 江戸時代、一七〇〇年代の後半からさかんになりました。宝暦、明和、安永といったころ、将軍家重や家治の時代です。 もとは前句付けといいました。たとえば、「飽かぬことかなかな」という前句を出して一般から付句を募集します。選者がいて、入選した句をすりものにして発表するのでした。その選者(点者)というか、先生の一人が、江戸は浅草の名主だった、柄井川柳(からいせんりゅう)でした。この前句付けばかりをあつめたものがのちに「誹風柳多留(はいふうやなぎだる)」として出版されました。前句付けはやがて川柳というなでよばれ独立した一つの詩形になりました。 さきの「飽かぬことかなかな」につけられたのは、 〽これ小判たった一晩いてくれろ 庶民の家には、小判一両など、めったに長く滞在しない。右から左へ御通過あそばすのです。庶民は小判をひたいに当て、一晩でもとどまってほしいとねがう心理、一両は当時米一石買えたといいます。金ピカの小判をじっくりとっくりながめて飽きぬ心地のおかしみがよく出ています。 川柳は人のなさけのあたたかさを恰好のテーマにします。川柳の根本にあるのは、人情の共感だからです。 〽母親はもったいないがだましよい ころりと子供にだまされる昔のお袋は、さぞやさしいお袋だったのでしょう。無学だけれどもやさしくて、子供のいうことは尤も尤も、とうなずいてくれる、親爺にだまって小遣いをくれるお袋なのでしょう。そして、どら息子も、ちょっぴり良心の呵責を感じています。親をだましてはバチが当たるのだが、と重々わきまえながら、うるさい親爺よりはだましよいとお袋にうまいことをいって泣き付くのでしょう。 〽貫之は猫をおひおひ荷をほどき 川柳作家にかかっては史上の有名な文学者も現実の日常卑近な生活者にひきずりおとされてしまいます。紀貫之は、かつて「土佐日記」のくだりでのべたように、土佐守として赴任していました。任はてて都へかえってきたときの土産は、さぞかし、土佐名物のかつおぶしだったのではあるまいか、とすれば、荷をほどくとき猫が寄ってきただろう、というおかしみです。彼らはそうやって武蔵坊や清盛や義経ら、英雄豪傑までみんな、親愛にみちた揶揄の対象にします。 〽なまつばきはき吐き巴打って出る 巴御前は男まさりの武勇もの、それでもさすが女ゆえ、打ちものとって勇ましく打って出ながらなま唾を吐くのは、おめでたのしるしでもあるのでしょうか。 〽さがしました仲国馬を下り これもいうまでもなく小督の局を勅命でさがしてきた仲国の奉答です。 参考:能の四番目に「小督(こごう)」という出し物があります。 高倉亭の寵愛を受けていた小督だったが、清盛の娘徳子が帝の中宮となったため、宮中を離れる。帝の嘆きは深く、嵯峨野に彼女がいるという噂に、源仲国が探しに行くが見つからない。十五夜の因る、きっと彼女は琴を弾くに違いないと報告すると、高倉帝は馬を下さり、仲国はその因るこれで出かける。(仲入)嵯峨野では思った通り、悲しみをまぎらわすために琴を弾く。探しあぐねた仲国が、法輪寺まで来ると聞こえてくる琴の音、「想夫恋」の局。ついに隠れ家を見つけるが、小督は中に入れようとしない。帝からの手紙を渡して返事を請うと、小督は感涙にむせぶ。仲国は名残を惜しむ舞(木枯らしに……)を披露して都へ帰って行く。 (ウェブによる) 〽やわやわと重みのかかる芥川 業平をやわらかく暖かく、からかっています。 参考:やわやわと 重みのかかる 芥川。《芥川とは平安時代の色男、在原業平が二条后を盗み出し、背負って渡ったという川の名前です。絶世の美女の柔らかさを堪能したことでしょう。》 日本の庶民の中には、大きなユーモア感覚のながれがあります。現実の生活が苦しいときにも、人々は一方でたえず、ふしぎな距離感をもって、われとわが身を笑うおかしみを忘れませんでした。現代も一見、そういうものがありげですが、実際は、単なる道化や、冷たい嘲笑や、才走った裁きの笑いにすぎないような気がします。 古川柳のもつ、おとなの距離感をもった暖かい笑いから遠いような気がします。 平成29(2017)年6月6日 |
|
黄表紙の色男(山東京伝) P.263~265 「江戸生艶気樺焼」という、江戸時代のユーモア小説があります。 作者は山東京伝。江戸中期、一七〇〇年代の終りごろ活躍した人気作家です。
写真説明:水野 稔著『黄表紙・洒落本の世界』(岩波新書)P.111に挿入されている図。 これらの本は、町人たち、熊さん八っつぁんや女たちがよろこんでよむ通俗小説、ということになっていましたから、プライド高いインテリたちや武家は手にとるのもいさぎよしとしない風でした。でもそれはうわべのことで、ほんとうは、みんな、内々で読んで腹を抱えて笑ったり、思わずふき出して、まわりを見廻したり、していたにちがいないのです。私は謹厳なさむらいが、非番の日の長屋で、こっそり、「江戸生艶気樺」などをよんで、つい頬の筋肉をゆるめたりしているのを想像するのが好きです。 劇画ですから、絵と文章と一致していなければ、その効果が上がらないのは当然です。 この点からも、自分で絵を描けた京伝の本は面白いのです。 この小説は、京伝二十五歳の、まさに才気とエネルギーの充溢していたころの作品です。
「とんでもなく浮名のたつ仕打ちがありそふなものだ」 なんとか、世間にもてはやされる浮名の主人公になりたい、と考えるのはそのことばかり。腕におりもせぬ女の名を彫って、さも言い交した恋人がいるごとく見せかけ、更にそれを嫉妬して灸で消す女がいたようにみせかけ、痛いやら熱いやら、 「色男になるも、とんだつらいものだ」 芸者をやとって、家へかけこませ、どうぞして若旦那といっしよになりたいと泣かせる、家の下女たちも、あの若旦那にほれるとば物ずきな女もあるもんだねえ、とあきれ顔ですが、艶二郎はいい気分。 「もふ十両やらふから、もちっと大きな声で、隣あたり、聞こへるやうに、たのむたのむ」 ところが、町内では何も知らず、かわら版にたのんで「評判評判、仇気屋のむすこ艶二郎という色男に、うつくしい芸者がほれて駈けこみました……ただじゃ、ただじゃ」とひろめてもらっても、ただでもそのすりものを買うものもないありさま。 この上は遊里で浮名をあげんものと、吉原へかよいつめ、金をやって新造・禿に袖をひっぱらせ、色男きどりで、「これさ、まァ、はなしてくれろ」などと悦に入っております。 さらに色男というものは、そねまれて、なぐられるものだと、地廻りの若い衆を金でやとって「人高い所にてぶたれるつもり」が、若い衆の勢いがつよくて、ぶち所わるく、片息になって「気付けよハリよ」とさわぐありさま。ようよう「よっぽど馬鹿ものだという浮名すこしばかり立ちけり」 さらにこの上はと、親にねがって勘当され、親が勘当せぬというものをむりに七十五日「と期限つきで勘当してもらい、遊女と狂言心中……読者は、ありうるはずもないこっけいの連続に、「うそつけ」と思いながら、つい読み通し、腹を抱えて笑ってしまいます。切れ味のいいおかしみは、主人公が徹頭徹尾、「よほど馬鹿もの」まるでダメ男、という設定からきています。
※参考:黄表紙について、水野 稔著『黄表紙・洒落本の世界』(岩波新書)P.115~118に『江戸生艶気樺焼』の話が書かれている。(黒崎記) 2022.08.09記す。
|
|
ただ狂え(閑吟集) P.266~269 「淀の川瀬の水ぐるま だれをまつやらくるくると」とい歌のひとふしは、浪花、それも淀川べりに生き育った私などには、耳になれた子守うたのようなかんじでした。曾祖母や老いた乳母、女中衆たちは自分なりのふしをつけて、台所にすみや隠居部屋や縁先で、ちいさくうたうのでした。あるときそれは、ためいきのようにも聞えました、またあるときは心はずむ日の鼻歌のようにいそいそとしていました。 私は、そんな歌詞は、彼女たちの即興かと思っておりました。 ずっとのちになって、「閑吟集」という室町時代の小歌をあつめた本を読んでいましたら、 「宇治の川瀬の水ぐるま なにと浮世をめぐるらう」 というのがありまして、古い歌なんだな、とびっくりしました。四百五十年も昔から私たちの遠い祖たちは、うれしいにつけ悲しいにつけつけ口ずさんできた小歌らしいのでした。 ※参考:(岩波文庫)六四 P.14 宇治の川瀬の水車、何と浮世を廻るらう。(黒崎記) 「閑吟集」は室町ごろにはやって歌われていた小歌・庶民の愛唱歌謡をとりあつめて、書きのこしたものです。編者の名はわかりませんがお坊さんのようです。昔、春秋のおりふしに遊宴の席でともに歌いあそび、「声をもろともにせし老若、なかば古人となりぬる懐旧のもよほしに」「忘れがたみにもと思い出づるにしたがひて、閑居の座右にしるしをく」と序に書かれています。永正十五年(一五一八年)に、出来たこともわかります。 これらのみじかい歌は扇で拍子をとり、また一節切の尺八の伴奏で歌われたのです。のちにこれに踊りがつき、やがて海の彼方から渡米して三味線が入り、歌も長くなって、舞台や色町の芸能に流れてゆくようになります。 私の好きな歌がここにはたくさんあって、「閑吟集」はたのしい歌の本なのです。 憂きもひととき うれしきも 思ひさませば ゆめ候よ ※参考:(岩波文庫)一九三 P.29 憂きも一時、嬉しきも思ひ覚(さ)ませば夢候よ。(黒崎記) どんな男や女が、半びらきにした扇のかげで口ずさんだのしょうか。 世のなかは霰よの ささの葉の 上のさらさらさっと降るよの 参考:(岩波文庫)二三一 P.33 世間は霰よの、笹の葉の上のさらさらさっと降るよ。(黒崎記) あまり言葉のかけたさに あれ見さいのう 空ゆく雲のはやさよ 参考:(岩波文庫)三三五 P.34 餘り言葉のかけたさに、あれ見さのう、空行く雲の早さよ。(黒崎記) 応仁の乱後五十年、京も地方も動乱につぐ動乱、その中で庶民はしぶとく生きぬいています。どんな焼跡にても根をおろし、食べ、飲み、歌い、恋をし、笑うのです。 あまり見たさに そと隠れて走ってきた まづ放さいの 放して物を言はさいの そぞろいとしゅうて 何とせうぞの 参考:(岩波文庫)二八二 P.39 餘り言葉のかけたさに、そと隠れて走って来た、先ず放さいのう、放して物を云はさいのう、そぞろいとしうて何とせうぞのう。(黒崎記)
いま結た髪がはらりととけた
参考:(岩波文庫)二七四 P.39 今結た髪がはらりと解けた、如何様心も誰そに解けた。(黒崎記) 身は破れ笠よの 着もせで 掛けてをかるる 参考:(岩波文庫)一四九 P.23 身は破れ笠よのう。きもせで掛けて置かるる。(黒崎記) ただ人には馴れまじものじゃ 馴れてのちに はなるゝるるるるろるが大事ぢゃるもの 身はさび太刀、さりとも一度、とげぞしょうずらふ 参考:(岩波文庫)一五五 P.24 身は錆太刀、さりとも一度とげぞしょうずらう。(黒崎記) ただ置いて霜に打たせよ 夜ふけて来たが にくいほどに 参考:(岩波文庫)二〇三 P.30 ただ置いて霜に打たせよ、夜柳更けて来たが憎い程に。(黒崎記)
ここにはほんの一行半句の、いい歌がたくさんあります。
梅花は雨に、柳絮は風に、世はただ嘘にもまるる 参考:(岩波文庫)一〇 P.8 梅花は雨に、柳絮は風に、世はただ嘘に揉まるる。(黒崎記)
ただ人は情あれ 槿の花の上なる露の世に うらやましやわが心 夜昼 君に離れぬ
なにせうぞ くすんで
参考:(岩波文庫)五五 P.13 何せうぞくすんで、一期は夢よ、ただ狂へ。(黒崎記) 2021.10.20記す。 |
|
野ざらしの人(松尾芭蕉) P.270~274 若いころ、私は芭蕉の名句といわれるものに親しみがもてませんでした。わび、さび、しをりなどというムードに反撥を感じていました。「古池や蛙とびこむ水の音」も、芭蕉開眼悟達の名句と教えられたせいか、よけいきらいになりました。「野ざらしを心に風にしむ身かな」も、わざと悲壮がっている気がしましたし、そう思ってみると、「芭蕉野分して盥に雨を聞く夜かな」もポーズができすぎている感じがしました。それに、ときどき、何でこれが俳句だろう?とあたまをひねるようなものもありました。「あら何ともなや昨日はすぎてふぐと汁」「夏の月御油よりいでて赤坂や」「枯枝に鳥のとまりたるや秋の夢」――若い私にとって芭蕉はへんにもったいぶった趣味人のじいさん、という感じでした。それに一種の芭蕉信仰というか、神様扱いで、おびただしい研究書や注釈書があるのも、却って若者を鼻白ませるものでした。芭蕉は長いこと、私にとって縁なき人でした。 私は蕪村から俳句の面白みを学びました。そうして読みすすむうちに、やっぱり芭蕉へたどりついてしまいました! 芭蕉はもともと、おかしみ、あそび、言葉のたわむれであった俳諧を、高雅な文芸にまでたかめた人、というのが、私どもに与えられた知識(それは多分に受験勉強用のもの)ですが、その知識を一応とり落した中年になってから読むと、まさに、彼の句は、「おとなの句」でした。 芭蕉の経歴を知るにつれて、「あら何ともなや……」「夏の月……」の句は、彼が自分の真骨頂を発揮するまでの、談林風時代の過渡期の作品だということもわかりました。 中年の彼は俳諧宗匠として充分、らくに食べていける名声や経済的基盤ができていました。しかし彼は俗世的栄誉や富に心を傾けられないたちの人でした。 ひとつところに安住せず、さらに高い境地をもとめて、芭蕉はたえずとびたちます。旅をすみかとし、風狂漂泊に身を置く心のたかぶりが、そのまま「野ざらしを心に風のしむ身かな」の決意になってゆく過程も、わかる気がしました。 芭蕉は「寸々の腸をさく」ばかり一句に思いをこらし、推敲に推敲をかさねます。その熱い緊張と気負いが、寸分スキのない、格調たかい句になって「奥の細道」できわまります。
荒海や佐渡によこたふ天河(『おくのほそ道』岩波文庫P.44:黒崎記)
芭蕉の句の中で、私の好きなものの一つです。私は、この句は実景そのままでなくて、芭蕉のイメージで組みたてられた句だと思います。この地へ旅したことは事実なのですが、芭蕉の眼に映るのはイメージの中の荒海や島かげでした。それが上すべりにならず、現実以上の真実として美しく結晶しています。この銀漢のもとの荒海の佐渡は波しぶきに打たれながら、実在の島よりも現実的に私たちの心に影をおとします。
四方より花咲入って鳰の海 鳰の海は琵琶湖の別名です。鳰はかいつぶりのことですが、琵琶湖には多く見られるので、こんな愛称がつけれたのでした。 春。まんまんたる琵琶湖の水に、四方から花吹雪が舞い散るありさまです。芭蕉は故郷の伊賀上野へ往還のみちすがら、京や大津に杖を曳いて、たびたび、琵琶湖のそばに足をとどめています。「ゆく春を近江の人と惜しみける」という句も、湖の駘蕩たる春色と湖国にすむ人のあたたかい人情に、かくべつの感懐をもよおしたからでしょう。 やがて芭蕉は、風雅の道を究めつくして、「軽み」という境地にたどりつきます。肩をおとし、肘のかまえをすて、高く悟りながら俗にかえる体の句の心を、しきりにさぐり求めます。ひとときも現状に狎れたり安閑と満足したりしない芭蕉の潔癖な芸術家魂なのでした。 此の秋は何で年よる雲に鳥 私の最も好きな芭蕉の句です。多年の漂泊にさすが老いを感じはじめた五十一歳の芭蕉は、浮雲や鳥に生涯の夢を賭けた自分を思い返しています。 芭蕉は生涯に五度も旅に出ました。その最後の旅は東北から裏日本を訪ねる行程六百里、六ヵ月にわたる長い長い旅でした。 芭蕉はその折の紀行文と発句をまとめて〔奥の細道〕となづけました。彼はこの作品を愛し、誇りに思い、幾度も幾度も、くり返しくり返し推敲しました。世に発表して名声を博そうとか、お金をもうけようなどという気の全くない彼は、手もとにおいたまま、心ゆくまで書き改めるのでした。(〔奥の細道〕が出版されたのは、彼の死後です) 詩人がそんなに心魂をかたむけて書き上げた〔奥の細道〕は、だから、たるみもくもりなく、ぴんと張りつめて鳴りひびくような硬い美しさをもっています。漢文まじりで簡潔に力強く、そのくせ和んだあたたかみをたたえ、ふしぎな魅力のある文章です。ふんだんにちりばめられた、冴えた一句一句が、また文章とにおいうつり、ひびき交し、照りはえあって、魅力をたかめています。源氏、枕といった女流の文学とは全く異質の男性の文章の流れを、芭蕉はつくり出したのでした。 この旅には弟子の曽良が従いました。彼も自分で随行日記を書きのこしていますが、それと照合すると、〔奥の細道〕はかならずしも現実通りの旅日記ではないそうです。現実は雨降りなのに、芭蕉のそれでは、日光さんさんといった句が残ったり、数日逗留したのに、すぐ出発したように書かれてあります。 それはむろん、そうあるであろうことで、芭蕉の書きとどめる現実は、「詩人の感じた現実」だったのです。現実と虚構のあいだを、詩人のイメージは自在にかけめぐり、あらたな別の真実をつくり上げるのでした。 〔奥の細道〕は、この調子高い名文からはじまります。 「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也。船の上に生涯をうかべ馬の口とらへて老をむかふる者は、日ゝ旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず……」 元禄二年(一六八九年)も初夏のころおい、「奥羽長途の行脚ただかりそめに思ひたちて」「もし生きて帰らばやと定めなき頼みの末をかけ」紙子ひとつ、雨具、墨筆のたぐいのみを肩に、出発した芭蕉は、ときに四十六歳でした。 折々は辺土のむさくるしい貧家に一夜の宿を乞い、「灯もなければゐろりの火かげに寝所をまうけて臥す。夜に入りて雷鳴、雨しきりに降りて臥せる上よりもり、蚤蚊にせせられて眠らず。持病さへおこりて消入るばかりなん」という苦労を重ねつつ、「はるかなる行末をかかへて、かかる病おぼつかなしといへど、羇旅辺土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん、是れ天の命なりと、気力いささかとり直し、路、縦横にふんで伊達の大木戸をこす」 あるいは平泉で、藤原三代の栄華のあと、義経討死のあとを見、 「さても義臣はすぐって此城にこもり、功名一時の叢となる。『国破れて山河あり、城春にして草青みたり』と笠うち敷きて、時のうつるまで涙を落し侍りぬ。(『おくのほそ道』岩波文庫P.34:黒崎記) 夏草や兵どもが夢の跡」(『おくのほそ道』岩波文庫P.83:黒崎記) 芭蕉はぞんぶんに、声あげてうたっています。朗々と心ゆくまでうたい上げています。その純一な陶酔は、文学的節度と、芭蕉の美意識によって、美しくととのえられ、かえって文章に強さを与えています。そればかりか、読むものにも酩酊がのりうつって、いつしか、芭蕉の自己陶酔に同化してゆくのです。私が芭蕉をちかしいものと考え、その句や文章を味わうことに楽しみをおぼえたのは、この自己陶酔の余波を共にかぶって心をたかぶらせる快さをみつけたからに、ほかなりません。芭蕉はふしぎな世界へ私たちをつれていってくれる案内者なのです。 2022.09.03記す。
田辺 聖子 (たなべ せいこ)プロヒール 1928年3月27日生まれ。日本の小説家。大阪府大阪市生まれ。淀之水高等女学校を経て樟蔭女子専門学校(現大阪樟蔭女子大学)国文科卒。恋愛小説などを中心に活動し、第50回芥川龍之介賞など数多くの文学賞を授与されている。文化勲章受章者 |
 「難波橋より西、見渡しの百景。数千軒の問丸、甍を並べ、白土、雪のあけぼのを奪ふ。杉ばへの俵物、山もさながら動きて、人馬に付けておくれば、大道とどろき地雷のごとし。上荷・茶船、かぎりもなく川浪に浮かびしは、秋の柳にことならず。米さしの先をあらそひ、天秤、二六時中の金にひびきまさって、この家の風、暖簾吹きかへしぬ」、
「難波橋より西、見渡しの百景。数千軒の問丸、甍を並べ、白土、雪のあけぼのを奪ふ。杉ばへの俵物、山もさながら動きて、人馬に付けておくれば、大道とどろき地雷のごとし。上荷・茶船、かぎりもなく川浪に浮かびしは、秋の柳にことならず。米さしの先をあらそひ、天秤、二六時中の金にひびきまさって、この家の風、暖簾吹きかへしぬ」、
 駒敏郎氏は「泣く泣く戦場をあとにする巴を見送ったとき、義仲は(木曽が去った……)と感じただろう」(保育社「木曽路」)とのべていられます。駒敏郎氏の「木曽路」には、木曽義仲の一生が簡潔に紹介されてありますが、たいへん美しい名文です。
駒敏郎氏は「泣く泣く戦場をあとにする巴を見送ったとき、義仲は(木曽が去った……)と感じただろう」(保育社「木曽路」)とのべていられます。駒敏郎氏の「木曽路」には、木曽義仲の一生が簡潔に紹介されてありますが、たいへん美しい名文です。
 「ィカナラム所ニモ落システテ、犬ニ食ハセテヨ」
「ィカナラム所ニモ落システテ、犬ニ食ハセテヨ」
 そうして、いろいろのことを夫婦らしく語り合い、兼家はやはり、一ばん愛しているのはお前だったと病の床で告白するのです。まだ魚など食べていないのだが、お前が今夜来るので一緒に食べようと思って待っていた、と、病後はじめての食事の箸を、かげろうふと共にとります。
そうして、いろいろのことを夫婦らしく語り合い、兼家はやはり、一ばん愛しているのはお前だったと病の床で告白するのです。まだ魚など食べていないのだが、お前が今夜来るので一緒に食べようと思って待っていた、と、病後はじめての食事の箸を、かげろうふと共にとります。
 男は悄然と家に帰り、妻にいいました。
男は悄然と家に帰り、妻にいいました。
 「落窪」は昔から、まま子いじめの物語、で通っていて、まま母、まま子への大衆の同情関心が、この小説を生きのこらせたとのだと人もありますが、それだけではないでしょう。
「落窪」は昔から、まま子いじめの物語、で通っていて、まま母、まま子への大衆の同情関心が、この小説を生きのこらせたとのだと人もありますが、それだけではないでしょう。
 「わらわ、父はもと京都の産にして、姓は安藤、名は啓蔵、字は五光と申せしが、わが母三十三歳の折、ある夜、丹頂を夢み、わらわをはらみしがゆえに、たらちねの胎内を出でし頃は、鶴女鶴女と申せしが、これは幼名、成長ののちこれを改め、延陽伯と申すなり」
「わらわ、父はもと京都の産にして、姓は安藤、名は啓蔵、字は五光と申せしが、わが母三十三歳の折、ある夜、丹頂を夢み、わらわをはらみしがゆえに、たらちねの胎内を出でし頃は、鶴女鶴女と申せしが、これは幼名、成長ののちこれを改め、延陽伯と申すなり」
 そのとき、右京大夫は七十六歳でした。のちになって二十年も仕えた後鳥羽院時代の呼び名より、若かりし日に、ほんの五六年呼ばれた、建礼門院右京大夫という名のほうを彼女は臨んだのです。――そして、その名は歌集に、いまもとどめられることになりました。
そのとき、右京大夫は七十六歳でした。のちになって二十年も仕えた後鳥羽院時代の呼び名より、若かりし日に、ほんの五六年呼ばれた、建礼門院右京大夫という名のほうを彼女は臨んだのです。――そして、その名は歌集に、いまもとどめられることになりました。
 平家の柱石だった清盛の死につづく一門の凋落、壇の浦の決戦、幼帝の最期、親しい友や肉親の死にざまも、すでに目にした。おお、女院が御髪を熊手にかけて引きあげられ給うそうな。あわれ長らうべくもあらぬ命をとどめられ給うた。あれ、あそこの船へ、宗盛父子が生けどられて救い上げられる。それもこれも、人の力の及ばぬ運命かもしれない。宗盛らしい運命かもしれぬ。それもよし。
平家の柱石だった清盛の死につづく一門の凋落、壇の浦の決戦、幼帝の最期、親しい友や肉親の死にざまも、すでに目にした。おお、女院が御髪を熊手にかけて引きあげられ給うそうな。あわれ長らうべくもあらぬ命をとどめられ給うた。あれ、あそこの船へ、宗盛父子が生けどられて救い上げられる。それもこれも、人の力の及ばぬ運命かもしれない。宗盛らしい運命かもしれぬ。それもよし。
 私はそれを読んで、一茶という人間の性格がますます底しれぬもののように思えました。
私はそれを読んで、一茶という人間の性格がますます底しれぬもののように思えました。
 などと注意してくれます。こわがらなくともよい、といわれたって、閻魔の庁からお迎えがきtr、もうすぐ命運がつきようとしているのに、こわがらずにいられるでしょうか。
などと注意してくれます。こわがらなくともよい、といわれたって、閻魔の庁からお迎えがきtr、もうすぐ命運がつきようとしているのに、こわがらずにいられるでしょうか。
 彼は浮世絵師でもありましたので、このさしえも自分でかいています。さしえというより、このころの大衆小説である。「黄表紙」とよばれた本は、こんにちの劇画のように、絵が中心で、他の文や会話は、つけたりのように、余白にびっしり書きこんでありました。
彼は浮世絵師でもありましたので、このさしえも自分でかいています。さしえというより、このころの大衆小説である。「黄表紙」とよばれた本は、こんにちの劇画のように、絵が中心で、他の文や会話は、つけたりのように、余白にびっしり書きこんでありました。
 百万長者のひとりむすこ、仇気屋、艶二郎というのが主人公の青年。自分でいっぱしの色男きどり。ところがさし絵の艶二郎は、色男なんて顔ではなく、梅の花型を二つに割ったような団子鼻に「へ」の字眉、それがまず、ふき出させます。艶二郎は日頃、
百万長者のひとりむすこ、仇気屋、艶二郎というのが主人公の青年。自分でいっぱしの色男きどり。ところがさし絵の艶二郎は、色男なんて顔ではなく、梅の花型を二つに割ったような団子鼻に「へ」の字眉、それがまず、ふき出させます。艶二郎は日頃、
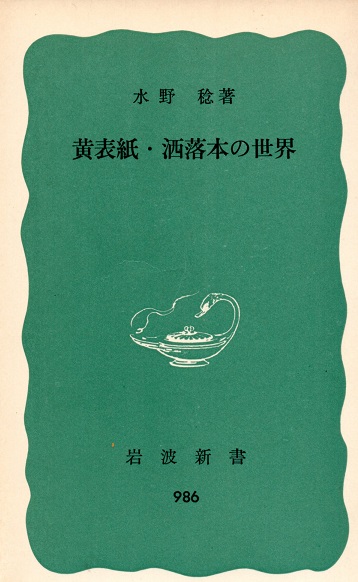 京伝はすっきりした江戸前のしゃれっけと風を捲いて舞いあがるような才気で、さっと書き上げるのでした。――おかしけりゃ笑いな。おれは教訓はきついきらいさ――京伝はそういっているようにみえます。京伝は現実を一度ほぐして、また笑いにくみてたてる作家でした。
京伝はすっきりした江戸前のしゃれっけと風を捲いて舞いあがるような才気で、さっと書き上げるのでした。――おかしけりゃ笑いな。おれは教訓はきついきらいさ――京伝はそういっているようにみえます。京伝は現実を一度ほぐして、また笑いにくみてたてる作家でした。
 酒の酔いが虹のように立ちこめ、あでやかな小袖がひるがえり、若衆の緑の黒髪が灯に映えます。女の流し目、ふみしだかれる衣のすそや帯のはし、宴のたのしみはきわまりをすぎようとして、一座が声合せて歌っのは、こんな歌だったでしょか。
酒の酔いが虹のように立ちこめ、あでやかな小袖がひるがえり、若衆の緑の黒髪が灯に映えます。女の流し目、ふみしだかれる衣のすそや帯のはし、宴のたのしみはきわまりをすぎようとして、一座が声合せて歌っのは、こんな歌だったでしょか。