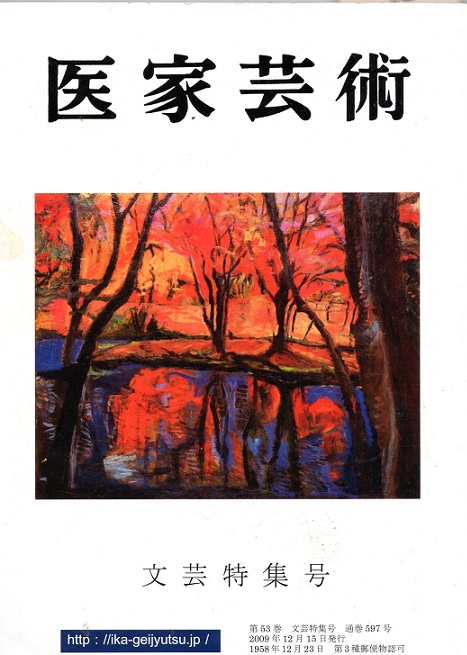| 村山正則さん『随筆集』「縁側の語らい」 | 村山正則さん『閑話つれづれ』 |
|
☆珈琲( コーヒー)と水
喫茶店に入って席に着くと、まずコップ一杯の水が出される。この何気なく出される水。店側はそれにどんな意味を込めているのか。つまらぬ疑問をカネガネ感じていた。この国ではどこの家庭を訪ねても、コーヒーは出てもコップの水の出る所はないのに。…… いつだったか、改装前の日本橋丸善の喫茶室で、顔なじみの断髪の女性にきいてみた。 ――「当然の習慣で特別な意味はないですよ。これも食文化の一つでしょう。口をすすいで味覚を新鮮にすればおいしく味わえるのでは……。コーヒーを出すまでの間のつなぎかしら。」 ――銀座のカフェ・ド・ランブルに行ったとき、カウンターで粋なマスターにきいてみた。 ――「注文をきいて豆をひくので時間がかかるんですよ。おもてなしの意味もあろうし、……水があれば注文を頂いた証しにもなりますしネ。」――なるほど、ナルホド。 かってフランスに旅した時、パリでもマルセイユでも、どこのカフェに入ってもコップの水は出なかった。フランスはそんなヤボなことをしないのか。日本だけの習慣か……と思っていたら、ドイツ、アメリカを訪れた友人の話では、日本と同じように出されるそうな。―― 「喫茶店は憩いの場所。ゆっくりと時間を過ごして頂き、語り合いの場として寛いで頂くのはコーヒー一杯では間がもたないでしょう。コップ一杯の水があれば、それなりに……」 倉敷の珈琲館の主人が笑いながら應えてくれた。 今日も、岡山の丸善の喫茶室でコップの水を手にして思った。コーヒーのあとで飲む一杯の水は、やっぱり喫茶店にはなくてはならぬ名脇役なのであろうか。P.24~25 2018.06.21.追加。
☆顔――雑感
私たちの周辺には夫々に自己を主張した様々な顔がある。医師という職業は、人の顔をみることも大切な仕事の一つであろう。毎日の外来で面接する老若男女一人一人の顔には、その人の心理、感情、性格……と共に、表情の裏にある生活環境までを見せているのだ。 人間は日常、無意識のうちに自分の顔の長所、短所を個性としながら、それを表情として表に出している。"Gesiht" というドイツ語は「顔」だがあ、「人にみせるもの」という意味のあることを、昔、教わった記憶がある。 今日、都会の街を歩けば四十五ケ国の人間とすれ違うと言われる国際交流の時代にあっては、夫々の顔にその特質がみえて面白い。日常生活の中にあっては、やはり心に残る顔は新鮮な子供の表情と、長年の試練が刻まれた老人の顔にその美学をみる思いがする。 外来で小学生の女の子が無心な表情で坐っている。愛らしいその美を自分で意識しないところに本当の愛らしさ、美があるように思う。総じて子供の顔は当然のことながら、皮膚、筋肉、殊に口もとがひきしまっていていかにも新鮮であるが、人間の顔は年齢と共にその口もとにゆるみが見えるようである。歳と共に最初にくずれてくるのは、どうも口もとのように思える。 毎日、ヒゲを剃りながら己の顔を眺めるが、そこに与えられた素材の質と配列をみているうちに、最近トミに口のしまりの衰えに気づく。この現象は六十五を過ぎた「高齢者」という称号を頂いた頃からであったろうか。 どんな悪人の顔でも、寝た顔は天使になるといわれるが、なるほど緊張のとれた寝顔は調和が生まれ、自ずとやさしさがもどるのか。死顔にも汚れをなくした安らぎをみることがある。かつて人体解剖実習でみた遺体に、生前の活力を停止した手の表情と共に、安らかな仏にも似た顔が思い出され る。 ――ところで、アメリカの企業界のリーダー条件として、一、胃が強いこと(健康であること)、二、臨機応変のスピーチが出来ること、三番目にフォトフェイスがよいこと――の三点があげられているが、この写真写りがよいこと――とは何か。思うに、自分の顔に責任の持てる人――ということであろうか。表玄関である顔と奥の間の生活が一致していることを云うのであろうか。 「モナリザの微笑」のナゾを、ある解剖学者が分析した結論として、顔の七つの筋肉が二ミリ収縮した表情である、と森繁久彌氏が随筆に書かれていたが、医療行政改革の進む今日、医師の表情は顔の筋肉が五ミリほど硬直しているのではなかろうか。せめて地盤のゆるみかけた顔面の筋肉を三ミリほど収縮させて、ゆとりある表情で患者に接したいものである。 P.129~135 2018.06.17.追加。
☆残 心
先日、デパートの入り口で大きなガラスドアを押して入った女性が、後ろを振り向きもしないで手離したドアの反動に、危うくぶつかりそうになって驚いた。 買い物で店に入る、用事で建物に入る、デパート、病院、郵便局……どこでもドアというものから出入りしなければならない。自動ドアなら問題はない。大きなガラスドアを押すか引くかして出入りする時、公共の場であれば当然あとから続く人がいる。その時、ちょっと振り返ってドアを押さえておく位の配慮があって而るべきであろう。幼児は言うまでもないが、高齢者でも(――ボクだって言いたくはないが、この部類に入るんだが……)大ケガをしかねない。後に続く人の為にドアを持って待ってくれる人には、この頃滅多に出会わなくなった。こんな世相を見るにつけ、古い話だが、旧制中学時代のT校長先生の講和を、フト思ひ起こすのである。 「――きみたちが先生に呼ばれて職員室に入る。ドアを閉める。キチッと閉まったか、振り返ってそれを確かめる。帽子を脱いで帽子掛けに掛ける。帽子が揺れて落ちないか。目でしっかり確かめる。そして先生の前に進む。これを「残心」という。 「残心」! 心を後(アト)に残す。一つの行動のあとに必ず心をのこして、落ち度がないかを確認する。――」 静かな声で訓されたT校長の声が、今も耳に残っている。P.155 先生の「随筆集」の中のこの部分を読み私も思い出しました。アメリカのニューヨークでの体験です。市内のバスに乗り込もうとすると、先の人が後の人の為にドアを必ずおさえてくれている。また、雨の日にのりこむと、傘は自分の両膝の間に挟みこみ、他の乗客をぬれさせないようにしている。更に気のついたことは、乗り降りに自分の持ち物が人様にあたらないようにしている。それでもあたると、「ソーリ」と謝る。 追加1:このホームページの写真は村山正則先生(外科医師)の描かれたものです。この随筆集は先生の四冊目です。非売品であるのが残念です。 追加2:■随筆 2009.3.6追加 2008.6.15
☆ウ ソ
最近はテレビや新聞で、エリート層の人間がどんな悪事をしたのか、謝罪する姿をよく見せられる。官僚、企業、警察、病院……その組織としての不祥事に対して、その責任者、幹部が横一列に並んで、起立、礼、謝罪文の朗読、礼、着席――と例によって例の如き光景をみせる。カワウソみたいな首筋を見せて頭を下げる光景は、かつての日本には見られなかった風景である。 殊に医療関係の場合、責任地位にある方々が居並ぶ姿は、さすがに見るに耐えないものだが、奇異にかんずることは、居並ぶ医師が申し合わせたように白衣を着用していることである。白衣は医師のシンボルであろうが、それはあくまで仕事着、予防衣ではないのか。私達が教室に入局した頃は、Shurez' あるいは Kittel と称して、上着、上っ張り、即ち不潔なものとして、すくなくとも食事の席では脱衣すべきものとやかましく言われたものであった。テレビと言う公器の前で謝罪する席に、仕事着で臨むとはいかがなものか。マスコミが、医療ミス謝罪の映像として白衣姿の方が「絵」になると考えてそれを要求するのか。御本人が医師らしく白衣姿で臨むのが当然――と考えるのなら何をか言わんやであろう。たとえ、診療の場から着替える時間もなく駆けつけたのだ……としても。…… ――ところで、今の世の中、人間倫理から物品、食品に至るまで、ごまかし、ウソが余りにも多すぎる。まァ、ウソも方便……と言われて人生の一つの「薬味」であった頃は、世も平穏であった。フランスのラヴレーと言う文学者は、「三つの真実にまさる一つのきれいなウソを……」という言葉を残しているが、ウソと言うものはこうありたいものである。この国のエリートたちの知的犯罪をみていると、「三つのうそにまさる一つの汚れた真実……」という気がしてならぬ。P.163~164
▼爽涼随想二題 『医家芸術』<文芸特集号>平成二十一年十二月
◎生活の中の音
かってこの国の生活には「静けさ」というものがあった。朝、目を覚ます。窓をあける。小鳥が無心に囀っている。新聞配達の人が来たのか、自転車のブレーキの音。しばらくして「おはよう、ごくろうさま」と隣のオバサンの声。……こうした静かな音の中で一日が始まった。一昔前の生活には貧しい中にも豊かなゆとりがあった。
今はどうか、瀬戸大橋という不粋なものが絶景の中に建設されて以来、現代の文明社会、車社会は、余りにも自己本位で、人間の作り出す騒音の中に習慣づけられながら活かされているのが私達の共通の悩みでははないか。物売りや廃品回収車にとりつけたスピーカーは殊更に音量をあげ、文字通り騒音を撒き散らす。加えて、事もあろうに空からの威圧的な宣伝飛行。――世界広しといえども、こんな騒音を許しているのはこの国だけじゃないか。
今日の生活の中のいらだたしさと、どうしようもない文明のわがままを思う時、二十一世紀の近代文明の進歩を否定するものじゃないが、せめて十九世紀の昔に思いを馳せて、人間中心の生態系をとり戻すことを考えたら、――と思うことの切なるものがある。 ◎子供の眼
子供はときに真実を教えてくれることがある。園医をしている幼稚園に検診に出かけたある日、園長先生が園児たちの絵を見せてくれた。幼児の絵は度々見る機会もあったが、こうしてじっくりと見つめていると、色んな事を教えられる。
みる人の心をとらえる絵画というのは、邪心のない幼児の表現のように「真実」を捉えているところにあるように思える。子供の絵は、ときに真実を教えてくれる。「見えども見えず」――といわれるが、これは考えてみれば、「絵画」ばかりではなさそうだ。 読後感:「静けさ」は、ほんの一部にしかのこっていません。しかし、曹源寺境内には「超静けさ」が保たれています。そこでは人が修行している心との融合した「静けさ」をかんじます。 中川一政画伯のみる姿は対象と本人が一体となっているのではないかと教えられました。また子供の描く絵のお話では、岡本太郎画伯が「カンバスからはみ出す絵を描け」といわれていたお話を思い出しました。この言葉には「全宇宙の真理」を内臓したものを描けといわれていたのではないかと。 村山正則先生、ありがとうございました。味わいながら読ませていただきます。 2010.01.06 |
|
この題名の本は、村山正則先生(外科医)より平成28年2月にいただいたほんです。 この著作には、最下部の参考の画像、その他自作の絵が随所に挿絵に使われています。 はじめのひと言 赤枝郁郎先生の遺志を継いで 「こくほ岡山」コラム欄で四十年近くご執筆を続けられてこられました赤枝郁郎先生から、ご逝去の十日ほど前に、お電話をいただきました。私にこのコラムを引き継いでほしいとのご要望でした。あまりにも突然のことでしたが、先生の体調を思い、その任の重さを考慮する暇もなく、お引き受けの旨返事をしました。 「そうか、やってくださるか。これで安心した」…という、やすらかなお声が今も心に残ります。それは、先生との最後の対話になってしまいました。 先生と私との交流は、旧制中学時代より三年後輩として、今日まで七十年余りの長きにわたり、医師として、また人師として、多方面に人生哲学を教わって参りました。仏道に帰依され「寂照」という名にふさわしい生き仏のような自然の風格の中に、このコラムでご承知の先生独自のユーモア、ウイットとともに、人間の生き方への教訓をお会いするたびに会得させられた喜び、感銘は、永劫に忘れることができません。 不肖ながら先生のご遺志を継がせていただき、私の医師として生きた六十年の体験をもとに、高齢社会への生き方を考えてみたいと思いペンをとりました。 日常の、中高年患者さんとの対話の中で、人生の最大の節目は社会的役割や肩書きから解放されて、自分自身の生活がこれから始まる、人生はこれからが本番ーという感慨をいつも感じておりました。ちまたでよく耳にする、「もう六十、もう七十…」という悲観論よりも、まだ六十まだ七十…と考える赤枝先生流の楽観論的生き方ともいうべき、今まで自分の出会えなかった隠れた才能、遺伝子を見出す発想の転換ともいうべき、この中高年期の生き方を、共に語り合おうと、始まったのが「こくほ岡山」誌への四年三ヶ月間のコラム欄への投稿エッセー。 それをまとめたのがこの小誌です。 日常生活の中の千思万考つれづれの閑話。私にとっては七冊目の随筆集発刊となりました。
どこからでもおよみ頂ければ幸いです。
※四十九のエッセイを書かれています。今回はその中から独断偏見で選んだものをを掲載します。
「健康」は「医師」よりも「意志」で!
体の内臓の存在を意識することから老化が始まる…とも言えるのじゃないか。めまいや頭痛から脳の存在を、胃障害から胃や腸の存在を、腰痛、肩こり、膝の痛みから脊椎や四肢関節の存在を意識し始める。 ━そこで医師を訪れる。早期発見、早期治療も大切なことだが、医学の発展とともに高齢期の検診では、どこかに異常は見つかるものだ。しかし、検査数値に悩まされることなく、それはあくまで一つの目安として、日常生活の中で自らに快い健康感があれば、検査数値に少々の異常を指摘されても自分は健康━と前向きに考えるのが一つの生き方でありましょう。
貝原益軒の養生訓にも、「人間の命は我にあり。天にあらず」という老子の説を教えています。自分の健康は自らの「意志」で、日常の生活習慣の健全な保持に心掛けることが大切であることを知るべきではないでしょうか。
「しわ」の美学
こんな難しいことを言う人が時にいる。しかし、人間の体からシワを駆逐することは、情緒の感性を否定することにもつながるんじゃないか。 シワとは、生きてきた人間の年輪の象徴として刻まれた、尊いものではないのか。 額、顔、眼尻、頬、口もと…のシワが、しゃべったり笑ったりするたびに、その表情の中で演技をしている。年を重ねるだけ生きてきたのだ。体力の衰退のほころびとしてシワになった。━いいではないか。 そのシワを誇りにしたらどうだ。 シワの相談を受けるたびにそう言って、その人の顔のシワの演技をたたえてあげることにしている。 "ソマリアの子をそっと抱くヘップバーンの星霜深きしわやさしけり" オードリー・ヘップバーンが63歳で亡くなる前に、ユニセフ親善大使として飢餓地帯を訪問したとき、難民の子を抱いた彼女のしぐさ、表情の中に刻まれたシワのやさしさが、人の心を打ったあの報道写真。そこに添えられた、ヘップバーンの顔のシワの美しさをたたえた一句が思い浮かぶ。 「年をとるのは仕方がない。それだけ生きてきたんだから当たり前じゃないの」━と、女優である杉村春子が言っている。「シワはその証明じゃないの」━と。 改めて自分の顔を見る。シワだらけだ。この手もシワシワ。そして、シワの中に散在するシミ。━そう、それだけ生きてきたのだ。
シワを誇りに生きたいものだ。
痛みについて━人間の存在の根底に痛みがある━ 医学誌の成人健康調査で、日頃自覚する症状のトップに挙げられているのが肩や腰の痛み(三十六%)とある。三人に一人が訴えるこの痛みは、日常の診療で医師を悩ます症状でもある。痛みのとらえ方が主観的で個人差の幅が大きいことも一つの原因ではあろうか。 痛みの部位と症状は診断上、重要な手がかりなるものだが、頭痛、腹痛を訴えても、どう痛いのかとなると表現はまちまちだ。 「キリキリ痛む」、「針を刺すような痛み」、ヅキズキ、ヒリヒリ、チクチク……表現法にも個性がある。 視、聴、嗅、味、触の五感の中で、お互いに分かち合えない、共有できないのが触覚であり痛みである。痛みは、本人の感覚を他人に理解してもらうことができないことが多い。「人の痛みを知る」、「わが身をつねって人の痛さを知る」と言われるが、いかに科学が進展しても血圧や血糖値のように数値化したり、画像化することも出来ない、この痛み。苦痛とは、最も人間的なものであろう。 文学の世界で、肉体の痛みを文字に表現しているのが、正岡子規の「病牀六尺」に見られる。痛みが言葉にならないことを知りながら、子規は絶叫、号泣…という文句をくり返し書いているが、痛みこそ「生の証し」と思えばこそ、その苦痛を言葉の表現に求めてゆく…。 英語にも痛みの表現はいろいろあるようだ。頭痛、腰痛など鈍痛には ache’擦過創挫創など瞬間的な痛みは hurt’歯痛は pain’のどが痛いのは sore’と、表現を使い分けている。その点、日本語ではヒリヒリ、チクチク、キリキリ……といった擬態語と呼ばれる表現を思うと、英語は具体的、論理的な表現というなら、日本語は、感覚的、情緒的表現というべきか。 日常、自覚する痛み、苦痛は、私も持っている。腰痛、下肢神経痛疼痛。老齢期特有の脊椎管狭窄症というヤツ。自分だけしか分からぬ、この痛み、苦痛。 "人間の存在の根底に痛みがある"とドイツの哲学者M・ハイデッガーが言っている。
もし、人生に痛みがなかったらーと考えると、なるほど、さもありなんと思わせられる文句ではある。
━らしさに想う
「男は男らしく、女は、しとやかに女らしく」━私たちの若い頃はよく聞かされたものだ。 戦後、多くの日本的な美風、美意識、日本人にふさわしい文化が捨て去られたことは惜しまれてならないが、その中の一つに、この「らしさ」も含まれていたように思う。 「らしさ」とは、その場にふさわしい態度、誇り、矜持(きんじ)のことであろうに。 教師は教師らしく、学生は学生らしく… 今きけば旧弊の文句なのだろうが、現今の男女平等時代であっても、「らしさ」があれば人間関係も落ちつき、やさしさ、ゆとりが見えるのではなかろうか。 「なでしこジャパン」の女子サッカー選手だって、出るところに出る時は、女性独自の和服、表情が女らしさを決めていたではないか。「らしさ」を感じさせる人は、安心出来る。 政治家らしい政治家、企業家らしい経営者、職人らしい職人、医者らしい医者、父親らしい父親、母親らしいお母さん…
「らしさ」を漂わせる人が少なくなった━こんなことを思うのは、お年寄りらしい高齢者だけであろうか。
書斎の話
毎年、年の暮れには机上だけは整理して、来るべき一年間は浄机で・・・・というさゝやかな決意は、いつしか雑机乱机へと変転をくり返して何十年。所詮、夢でしかない。 読書には明窓は快いが、書きものには明る過ぎると気が散る。書斎のことを「北堂」といって北向きでうす暗い部屋をよしとする・・・・と言われるが、わが書斎は南向き。「南堂」で満足している。
書斎の机には引き出しがある。三つある。中央と両脇。分類して色々の物を入れる。大事なものばかりだが、一年、二年経つと、その一部は不用品になる。上に重ね下に差し込み、目的の異なる物があふれる。どこに何があるか判らなくなる。引き出しはとかく古い物の在り場所を忘れてしまうから、矢張り必要と思う物は机上に置いて整理するのも、書斎の主のたしなみであろう。
なぜ捨てられぬ
毎月届けられる書籍、雑誌、医学誌の類の山を眺めながら、思い切って処分すればサッパリするだろうなど思いながら決断しかねている。書籍に限らず、日常の身の回りの品々にしても、置いていても何の役に立たないのは自分が一番よく知っているのに…。 どうしようもない物もある。使い道は皆無。捨てようにも捨てる値打ちもない━と言うのもおかしいが、そんな物にも「無用の用」ということもある。「無用の極まる所、稀有(けう)の用を生ず。」━というではないか。何年かに一度ぐらい、「おお、とっておいて良かった。」という稀有の用を生ずることがあるから困るのである。 「無用の用」…といえば、こんなこともある。山水画や広告紙など、紙面一杯を埋めるよりも空白部分を残すことによって表現の効果がある━と言われるが、無用部分部分の効果というべきか。かつて赤枝郁郎先生がよく言っておられたが、話し方でも途切れることなくペラペラやられるとかえって耳に入らないものだが、話上手は間のとり方にあると。これも無用の用━というべきか。 そんなことを思いながら、捨て方が分からない、困ったものだと思いながら困っている。当世風ではないのである。少年の頃、廃物利用を教え込まれ、もったいない思想を教えられて育った名残か。
こんな人間がこの世を終えた時点で、戦時体験を知らぬ世代が、「何でまた、こんな物まで。」…と呆れながら捨ててくれるのであろうか。
後姿の美学
その点、後姿はその人の本来像が見えて、味わい深い表情が見えるものである。 道を歩く老人、若者、無邪気な幼児の仕草・・・・そんな光景の背中に、飾らぬ個性が見えて、その美学の描写を独り楽しんでいる。 老人の背中は過去を語り、青年の後姿は未来を語っている。老齢者でも未来に目をむけて行動能力のある人は背中に若さを見せている。「生きる」ということは未来をもつこと、ということを教えられるのである。 かつて女優の田中絹代も、その自伝に「映画の演技の中で最も味のあるのは、カメラに背をむけての芝居です。それが出来れば俳優も一人前と言えましょう」と書き残している。 大統領、総裁、学長、社長…というのはプレジデント(President)という語で表現されるが、語源は「人の前に坐っている人」である。後姿が頼りになる人、人をリードするには背中をもってする━という意味であろうか。中国の孟子も言っている「人間は面(おもて)よりも背中の方が大事である。徳や力というのは、先ず面に現れるがそれが背中に(後姿)に見えてこそ本物である」と。 後姿の美学がそこにあるように思う。
人間の後姿の美学と教訓を日常生活の中に観察しながら、絵の勉強もしてゆきたいと思っている。
あとがき 想えば、今は亡き赤枝郁郎先生からこのコラム欄を引き継いだのは、平成二十三年新年号からでした。この四年三ケ月。五十一編のコラムを書かせて頂き、先生の御意志を継がせて頂けたことに感謝申し上げます。 随筆、文章とは何か、…赤枝先生とたびたび語り合つたことを思い起こします。 随筆(コラムを含めて)とは普段着の寛(くつ)ろぎの中に、気ままな「ペンのオシャベリ」といった軽やかな気持ちで書かせていただいた四年間でありました。 文章というものは料理みたいなものだ。料理はおいしい上に栄養もなくてはならない。文章もそうだ。読む人の関心をひきながらおもしろく読んで頂く。加えてその中に内容がなくてはならぬ。あの料理をもう一度食べたい…と希(こいね)う如く、あの文章をもう一度読んでみたいという魅力は、文書も料理と同じようなもの。━━こういった赤枝先生らしい発想、理論をなつかしく想い起します。 この欄を担当された赤枝先生は四十年近く続けられと聞いている。この度の思いがけない廃刊に先生もあの世でさぞ惜しまれておられることだろう。
末筆ながら、この小誌発刊にあたり、サンコー印刷株式会社の竹入氏からいろいろと援助を頂きました。深く感謝いたします。
平成二十七年師走
参考:村山先生の絵画
|