(朝日選書)1989年1月20日 第5刷発行
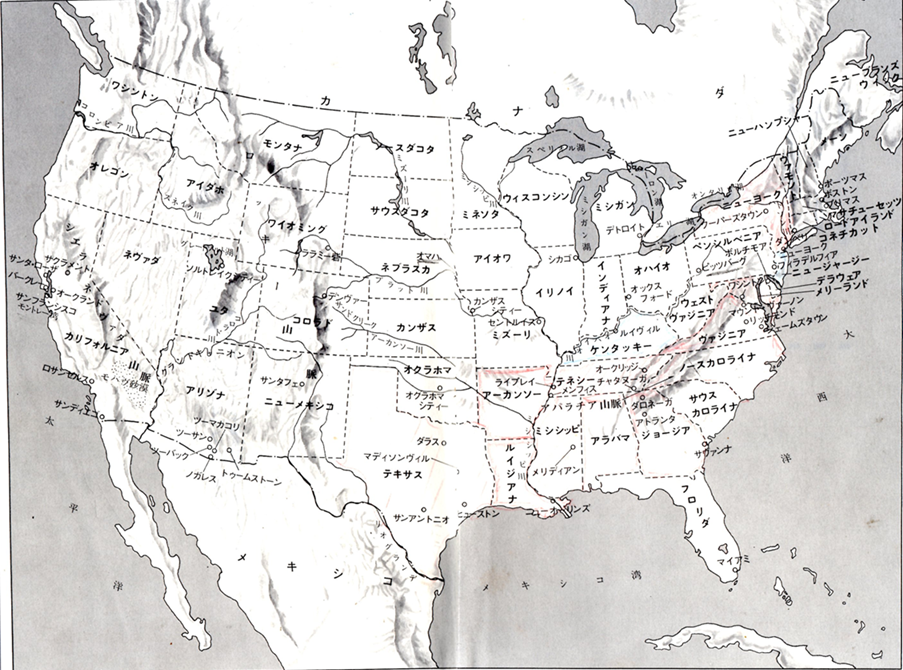 ★猿谷 要著 アメリカ歴史の旅 イエスタデイ&トウデイ 1989年1月20日 第5刷発行 朝日選書 1989年7月3日 購入 歴史の真実と虚偽 黄金を夢みた征服者たち P.5
一体何が、これほど荒涼とした未知の半砂漠地帯に足を向けさせるような情熱を、人びとの心のなかにかき立てたのだろうか。 いくら進んでも、前途には果てしない山なみと、荒野と砂漠が広がっているばかりだった。私がいま自動車でその跡を追ってさえ、その空間の無限さに気も遠くなるほどなのに、四世紀半も昔に馬と羊を連れたスペイン人の探検隊は何に憑かれてこの広漠とした土地を、それを二年も三年もの歳月をかけて歩きまわったのだろうか。 絵のなかで見たことがあるロードランナーという奇妙な名前の鳥が、道の端をかすめるようにして走った。場所はアリゾナの南端、メキシコとの国境で、私が辿った砂利だけの山道は、十六世紀のなかばにスペインのコンキスタドール(征服者)たちが、飢えに苦しみながら歩きまわった場所なのである。その指揮官の名は、ッフランシスコ・バスケス・デ・コロナド――。 一五一九年から三年がかりでメキシコのアステカ帝国を滅ぼし、さらに一五三二年にはペルーのインカ帝国を征服したスペイン人たちは、その後、メキシコの北に横たわる未知の土地に対しても、探検隊を送りはじめた。碧眼にダーク・ブロンドの頭髪、濃い頬鬚を生やしたまだ三十歳の青年指揮官コロナドもその一人で、彼は一五四〇年、大部隊を編成してメキシコを出発し、彼らがニュースペインと総称していた新しい征服地の北辺を探る長途の旅についたのである。
コロナドにはもう一つ、具体的な夢があった。それは七つの不思議な魔法の都シボラを発見しようということである。イベリア半島がかつて回教徒に攻められたとき、七人のポルトガル司教が遁れて大西洋を渡り、七つの都を建設したという中世の伝説を、他の人びとと同じように彼も信じこんでいた。その時から二十年あまり前、スペインの他の探検隊ポンス・デ・レオンの一行もまた、不老不死の泉がそこにあると信じて、フロリダ半島を二度も探検したほどである。 ヨーロッパ人たちは、中世一千年の間にたくさんの伝説を、自分たちをとりまく外の世界に対して作っていて、それを新大陸にあてはめようとしたのだ。当時の絵のなかには、犬の頭をした人間の住む島や、えたいの知れない怪物のいる海が描かれていた。巨人やこびと、頭がなくて胸に眼がついている人間、翼のある鷲の頭の獅子などが、ヨーロッパの人の頭にでき上がっていた。コロンブスも西インド諸島に到着したとき、部下に命じて怪物を探させたほどである。 だから赤銅色の皮膚をした先住民族をこの大陸で見たとき、スペイン人たちの困惑はひどいものだった。彼らは一体何者で、どのように取り扱っかつていいか、スペイン人には判らなかったのだ。 結局、征服者はインディアンに強制労働をおしつけるようになり、インディアンのなかにはアクを抜いていないタビオカの汁を飲んで自殺する者が出たほどだという。一方では、インディアンを対等の人間として考えようとする修道士もいたし、インディアンの女と生活を始めるスペイン人たちも多かった。後に北米に上陸するイギリス人がインディアンを追い払いながら生活するのとは違って、中南米のニュースペインでは、よくても悪くても一つの世界の人々が混じり合って生活するようになった。コロナドも自分の探検隊のなかに、なんと千人近いインディアンを道案内や荷役のために加えていたのだ。 さて、そのコロナドは、話に伝えられた七つの都シボラを発見しただろうか。 物好きにも私が何時間も荒野を走り続けてやっと到達したメキシコ国境は、コロナド・ナショナル・メモリアルという名がつけられていて、このあたりで彼の一行は飢えに悩まされ、毒草を食べて何人もの人が死んでいる。しかし彼はなおも北へ向って進み、アメリカ西部独特のあの頂を水平にカットした山やまの上に、かなりの数の建物が群れているのを発見した。アドべという日焼きレンガの上に粘土をぬった建物で、太陽が直射するとそれは山肌と一緒に濃いピンクの色に輝いた。長旅のあと、やっと辿りついたコロナドの一行の眼には、ほんの一瞬、すばらしい宮殿のように見えたのである。 今の地名でいうと、それはニューメキシコとアリゾナの州境に近いズ二―のインディアン集落だった。トルコ石の繊細な細工を作る有名な部族である。コロナドは自分も負傷するほどの激戦を行なって、やっとこの集落を占領する。しかし彼があれほど夢に描いていたあのシボラの七つの都は、七つの小さなインディアン村にすぎなかった。 コロナドはひどく落胆したが、ここに駐屯しながら部下のロべス・デ・カルデナスの一行に西方を探検させる。そのカルデナスはホピ・プエプロのインディアンたちが住む地域を通りぬけたあと、そこから先は人も馬も進めないような大地の大亀裂に遭遇した。悪魔の爪痕だとしてもそれはあまりに大きすぎたし、神の造形だしても、それはあまりに恐ろしい姿だった。それがコロダド川が大地に刻んだグランド・キャニオンだったのである。 カルデナスたちがこの凄まじい光景を眼の前にして、どんなに驚いたか想像に難くない。その頃までヨーロッパ人がもっていた、もっとも精巧な新大陸地図でも、北米はほとんど輪郭さえ掴めていない霧のなかの大陸だったのだ。 コロナドは失望して一五四二年にメキシコに戻ったが、この未知の土地への限りない夢と冒険――先住民にとっては、まったくの災難となったが……これこそ、新大陸の世界へ旧大陸の人びとを急速に招きよせた最初の原因であったろう。私は炎熱のメキシコ国境を車で走りながら、その同じ道を通ったといわれるコロナド探検隊の巨大なエネルギーを、一つ一つの砂利の上に感じた。
メイフラワー号の神話 P.11
ボストンから南に車で一時間ばかり走った海岸に、プリマスという小さな町がある。一六二〇年に、あの有名なメイフラワー号がイギリスからここに到着し、アメリカ北東部最初の植民が行われた場所として、歴史の浅いこの国では最大の国民的史跡となっている。
官製のアメリカ史に従えば、自ら「聖徒」と称したピルグリムたちは、上陸に先立って誓約書にサイインし、自分たちが自由に市民の政治団体を組織し、公正で平等な法律を作ってこれを守ることを誓いあった。のちに多くの植民地もこれにならったので、自由民の自由な選挙というアメリカ・デモクラシーの伝統がここに築かれた、ということになっている。 現在このプリマスを訪ねてみると、メイフラワー号を模したメイフラワー二世号が小さな埠頭につながれていて、バスで到着する観光客がひきもきらない。二世号は一八一トン、長さ約三五メートル、幅八メートルあまり、一九五七年にイギリスで復元され、五十三日かかって大西洋を実際に渡ってきたのである。 この船はともかくとして、彼らが最初に上陸したというという記念の大きな石の方はどうだろう。まるでギリシャのパルテノン神殿を思わせる巨大な円柱でかこまれ、手すりの外からただありがたく拝観するばかりだ。この石は「国家の基石」とまでよばれているそうだから、さしずめ戦前の日本でよく話に聞かされた、あの高千穂峰の跡といったところだろうか。 一行はイギリスから当時六十六日かかって、一六二〇年十一月九日、ケープ・コッド沖に到着したが、しばらくここを踏査して定住には不適と判断し、再び乗船して西に進み、十二月十六日にプリマスに到着したとき、この大きな石に足をかけて上陸したというのである。史跡というよりは、聖者の聖跡といった感じだ。 それにしてもイギリス人たちは、一足早く新大陸にやってきて中南米はほとんど手にいれたスペイン人たちを、冷酷無残な征服者とよんでいる。スペイン人たちが先住インディアンに対してその表現通りの態度をとったこともたしかだが、同じヨーロッパ人でありながら、一方が冷酷無残な征服者であり、他方が神聖な植民者であるというのは、身びいきにも程があるといえるだろう。 大体ピルグリムというのは、イギリス国教会の浄化をめざしたピューリタンのなかの一分派であり、こと小さなメイフラワー号にすし詰めにされた百ニ人の乗員のうち、なんらかの意味でピルグリムという人たちは、わずか四十一人にすぎなかったのだ。彼らが「よそ者」とよんだ過半数の人びとは、たいていが仲の悪いイギリス国教会のメンバーだったから、二カ月あまりの航海が平穏無事であったはずがない。 つまりこのメイフラワー号は、自分たちの信仰を貫こうという人びとよりも、単に少しでもいい暮らしをしようとして、ヨーロッパを脱出してきた人びとを多く乗せていたのである。ちょうど十七世紀を迎えたヨーロッパは、ペストの流行、くり返される戦争、周期的にめぐってきた寒冷期などのため、かつてないほど悲惨な時代となり、飢えに苦しむ人びとは大変な数に上った。暗く住みにくいヨーロッパから逃げ出すことができれば、少しくらいの苦難は問題にならなかったのだ。 そういう異質の人びとを乗せて、大西洋上のメイフラワー号は難航した。本国でジェームス一世の迫害をさんざん受けてきたピルグリムたちは、ある歴史家の意見によると、船のなかで「ずうずうしく意地悪で、そのうえ不平ばかりいっている連中だった」という。 よそ者との対立は日増しに激しくなった。過半数を占めるよそ者たちは、毎日のようにピルグリムを罵り、船長たちが仲裁にはいって、やっと殴り合いをとめたようなことが一度や二度ではなかった。 反乱とか暴動とかいう表現を使ってもいいようなことが起こっている。一度は、自ら聖徒と称するこのこのピルグリムたちが、いつのまにか船中の支配権を握ってしまったことを他の者たちが知ったきであり、もう一度は、ピルグリムたちが他の人びとの意見を無視して、自分たちの信仰を押しつけようとしたときである。 上陸してからのピルグリムたちは、平気でインディアンの食糧を盗み出した。もっとも最初のひと冬の間に、飢えや寒さ、壊血病などのために人々は次つぎに倒れ、次の春に生き残っていたのは半分以下の五十人にすぎなかったというから、見栄も外聞もなかったというのが実際の姿だっただろう。 この頃、聖者のなかの指導者だったウィリアム・プラッドフォードの妻ドロシーが自殺した。その原因はまったく不明のままだが、いずれにしても輝かしいアメリカの歴史のスタートを飾るにふさわしくない悲惨な事件である。、 聖者たちは、その後イギリスから到着して付近に植民地を作ろうとした人びとがピューリタンでないことを知って、ことごとに彼らの生活を妨害した。聖者にとって、こういう不道徳な連中とインディアンとは、ともに排除しなければならない敵とみえたのだ。 そこで聖者の一人スタンディッシュは、友好的な態度をよそおって、インディアンの首長を謀殺しようと計画した。名誉を重んじる首長は、食事の招待を受けてやってきた。十八歳の弟と二人の部下を連れて――。四人が部屋に入ると同時に、鍵がかけられ、スタインディシュとその部下たちは、いっせいに剣を振って襲いかかった。客を丁重にもてなす習慣のインディアンたちにとって、まったく予想もしない出来事だったに違いない。首長と二人の部下はずたずたに切り裂かれ、十八歳の青年は人びとの前に出されて、縛り首になった。 プリマスの聖者たちは大喜びでスタンディッシュの帰還を迎え、首長の首を防塞の杭の先端に釘で打ちつけた。長年の間この首は、プリマス名物の一つになったといわれている。そればかりか聖者たちは、この事件を自分の意思に従わない者へのみせしめとして、隣の植民地を脅迫しはじめたので、恐れをなした住民たちは、船に乗ってメインの方へ逃げ出してしまった。 いつの世でも、どこの国でも、歴史の初めの部分は美化され、神秘化される。アメリカの場合も、決してその例外ではない。 そして今日もまた、善男善女の観光客は全米からこの生地プリマスを訪れる。拝観料を払ってメイフラワー号二世に乗りこみ、ガイドの説明に耳を傾け、聖者上陸の石を拝んで記念写真をとる。それがアメリカ人であることを自分に納得させる楽しい確証となるのである。 2025.03.21 記す 四〇ドルの酒で買ったニューヨーク P.17
ニューヨークの中心、マンハッタン島には、土一升金一升といってもいいような場所に、巨大なセントラル・パークが、ながながと南北にひろがっていて、都市計画の周到さをはっきりと物語っている。 その公園の西を走る八番街の、公園に面したほぼ中央の七七丁目に、ニューヨーク歴史協会の建物が、あまり人目を惹かずに建っている。 今でこそ多くの矛盾を露呈しているが、依然として現代文明を象徴する偉大なニューヨークというこの都市が、百年前、二百年前にはどんな姿だったのかを、写真や絵や実物で見せてくれる楽しい博物館だといっていい。 この公園の反対側、東の方に走る五番街をずっと北の方に行くと、もうイースト・ハレムへはいる境界ともいえる一〇三丁目に、これまたひっそりとニューヨーク市立博物館が建っている。 この博物館の方は、百年前、二百年前などという程度ではなく、このマンハッタン島に植民が行われた最初の物語、三百五十年前にまでいきなり私達を連れ戻してしまうのである。 ヴァジニアに初めてイギリスの植民地ジェームズタウンがほそぼそスタートしてから二年目の一六〇九年、北部ではプリマスにメイフラワー号が到着する十一年も前に、オランダ政府の命を受けたヘンリー・ハドソンは、自分の名をつけることになる川をはじめてさかのぼった。 その後も何度かオランダ船がこの川を探検して、沿岸に住むインディアンたちに酒をふるまい、毛皮の取引などをして友好関係を結んだが、一六二六年にはオランダ西インド会社が、物々交換でインディアンからマンハッタン島を購入した。 これは後に、「史上最大のバーゲン」といわれる取引となった。なんとこのとき会社側がインディアンに支払った品物は、アルコール類や日用品など六〇ギルダー程度の金額のものにすぎず、現在の価格に直すと、せいぜい四、五〇ドルだったのである。 この場所にやがて世界でもっとも高い摩天楼が建ち並び、世界金融界の中心ができるようになろうとは、この取引に従事した両方とも、当時どうして予想することができただろうか。 ともかく、マンハッタン島の南端に、オランダ人たちは小さな植民地をつくり、母国にちなんでニューアムステルダムとよんだ。この町が、川沿いに点在するオランダ領植民地の中心となったのだ。 いまニューヨーク市立博物館のなかに入ると、いきなり一六六一年九月上旬の土曜日という古い時代のなかに、まるでタイム・トンネルをくぐり抜けたような形で、投げこまれてしまうのだ。 当時築かれた砦の一部が再現されていて、そこに登るとニューアムステルダム全体の情景が、パノラマとなって周囲に展開する。建物約三百、住民約千三百人、すべてが指呼の距離である。 ずっと後にハドソン川のほとりの美しい田園地帯に住み、名作『スケッチ・ブック』を残したワシントン・アーヴィングは『ニューヨークのオランダ移民史』という本のなかで、オランダの歴代総督を酷評し、とくに二代目トウィラー総督は、 「まるまる太った、怠惰で貪欲な人間で、肉体の快楽のためにはすべてをギセイにした」これに対して四代目の総督、義足のピーター・スタイヴサントはかなり厳しい統治者で、たしかにどの前任者よりも公正ではあったが、大局を見定めるような融通性に欠けていたので、かえってこの町の空気を沈滞してしまったという。 一六四七年に総督としてこの町に赴任してきたスタイヴサントは、酔っぱらいや口論が絶えないのを見て、早速次のような布告を掲示した。 「前総督とわが参議会との忠告にかんがみ、神のお怒りがわれわれの上に落ちないように、かわりに神の祝福を受けることができるように、すべての醸造者、酒場の所有者、宿屋の主人公に次のように命令する。こんなに厳しくては、かえって人びとの尊敬を集められないだろう。 一六六四年の夏、イギリス国王の弟ヨーク公の命を受けて現れた四隻のフリゲート船体を前にして、この総督は徹底抗戦を叫んだが、町の人びとはその命令に従わず降伏し、このときオランダのニューアムステルダムはイギリス領となり、ニューヨークとその名を変えたのである。 生き生きと目の前に蘇える歴史の一齣を目にしっかり焼きつけて、博物館から出た私は、そのまますぐにマンハッタンの南端に出かけてみた。オランダの砦があった場所はバタリー公園になっていて、ここから南に自由の女神がすぐ近くに見え、北を振りかえると、目をふさぐばかりの摩天楼の連なりである。
物々交換の市場のあとは、巨大なこの都市の胃袋をまかなう魚河岸になっていて、近くの埠頭では抱き合った男女が、いつまでも対岸のブルックリンを眺めたまま動かなかった。
※写真は魚河岸のある所 アメリカでもっとも魅力のある三つの港町、ニューヨーク、ニューオーリンズ、サンフランシスコがイギリス人に開拓されたのではなく、それぞれオランダ人、フランス人、スペイン人によってまず開かれたことは、なんという皮肉なことだろうか。いまマンハッタンの南端に佇んでいると、この国の幅広いバイタリティーが、歴史の大きな流れを通して浮かび上ってくるのである。 2025.03.22 記す ついに上がった革命の烽火 P.25
一七七〇年三月五日、その日ボストンの路上で、どんな事件が起こったのか。 この年は、メイフラワー号がボストンの少し南の海岸プリマスに到着してから、奇しくもちょうど百五十年目にあたっていた。 一世紀半もたてば、はじめは赤ん坊だった植民地人が、すっかり一人前の若者に成長したとしても、それはむしろ当然のことだろう。一七七〇年頃には大西洋岸のイギリス領十三州だけで、推定二百万人をこえていた。これはすでに、北米全体のインディアンよりも多い数である。 三〇〇〇マイルもの大西洋が間にあったので、子供が肉体的な成長をとげたばかりでなく、精神的にもすっかり親から離れてしまったことを、イギリス本国が十分に理解できなかったのも無理はない。 一七六〇年代にイギリス本国の窮乏した財政を救おうとして植民地に課したいくつもの条例は、たちまち激しい反対に出あった。イギリス本国の議会に代表を送ることを許されていないわれわれは、そこできめられた課税を支払う必要はない、というのである。 百五十年の間、植民地には経済的成功への道が、すべての人びとに平等に開かれていた。そのため植民地の人びとは、国王を頂点にいただく本国人が対人関係を垂直に考えがちなのに対して、すっかり水平に考える態度が身についていたのだった。 だから一七六五年の印税条例には各地で大きな反対運動がおこり、「自由の息子」や「自由の娘」などという抗議団体が生れた。ヴァジニジア議会ではパトリック・ヘンリーが、 「われわれに自由を与えよ、さもなくば死を与えよ」 と呼びかけるありさまだった。 このすさまじい抵抗は、イギリスのグレンヴィル内閣の交替を促し、翌年、印税条例は撤回されたが、その後さらに新しい課税の条例が次つぎに出されてきた。 ボストンにイギリス軍が常駐するようになったのは、一七六九年のことである。それらの条例を実施するためにやってきた駐屯軍の費用が、自分たちのおさめる税金でまかなわれていると考えると、ボストン市民の不満は高まる一方だった。日曜日の安息日に、歩哨交替のため笛を吹いたり太鼓を叩いたりするイギリス兵たちに対して、信仰の深いボストン市民はすっかり腹を立てていた。 三月五日、北国のボストンの街角にはまだ雪が残っていた。憎悪の的になっていたイギリス兵二人が、ちょっとしたきっかけでボストン市民に襲われ、袋だたきにあった。騒ぎが大きくなり、市民たちは外にとび出してきて、税関の建物の前の歩哨めがけて、雪を投げはじめた。 雪景色のなかで赤い軍服のイギリス兵は、絶好の目標となったことだろう、歩哨は驚いて救援を求め、プレストンという大尉が二十人ばかりの兵士をつれて駆けつけた。 群衆のなかに、クリスパス・アタックスという黒人がいた。かつて奴隷だった彼は、ひそかに逃亡して水夫となり、この群衆を指導してたのだ。一九七五年発行の『建国二百年ボストン・ガイドブック』にも、群衆を励ましてイギリス兵に襲いかからせたのが、他ならぬ彼であったと書かれている。 イギリス兵たちは、かねて通達されていた命令をよく守り、石や雪を投げつけられたり、罵声を浴びせたりしながらも、銃剣をかまえたまま、かなり長い間じっと我慢していたらしい。そのうち一人の兵士が棍棒で殴り倒された。たまりかねたその兵士は、立ち上がりながらとうとう発砲し、これをきっかけに、他の兵士たちもいっせいに発砲した。立ち込めた煙が消えると、アタックスを含めて三人の死骸が路上に横たわり、他に二人の男が致命傷を負って倒れていた。 ボストンの急進派たちは、この事件を早速「ボストン虐殺事件」と名づけ、全植民地に報道して、イギリスへの敵意をかき立てた。事件のすぐ後でプロパガンダのために描かれた絵を見ると、背後にはっきりと「ステイト・ハウス」のレンガ造りの建物が描かれている。 もう一昔前、はじめて私たち夫婦がこの場所を訪ねたとき、何のしるしも見当たらないので、妻はなかなか信じようとしなかった。親切そうな中年の男に、ボストン虐殺の場所を尋ねると、ここがそうだ、と彼は答えた。 そのとき妻は、ふと日本語でこうつぶやいた。「まさか」 するとその男は、わが意を得たという顔でこういった。 「そうです。奥さまのいう通り、マサカーはここで行なわれたのです」 事件を見下ろしていたはずのその建物は、去年久しぶりに訪ねてみると、巨大なビルの谷底にひっそりと沈んでいた。 虐殺が行われた側のバルコニーでは、それから六年後の七六年年七月十八日、やっと届けられた独立宣言文が、集まった人びとの前で朗読されたのである。 「すべての人は平等につくられ、創造主によって一定の奪うことのできない権利を与えられ、そのなかには、生命、自由、および幸福の追求が含まれていることを、われわれは自明の真理であると信ずる」長文の独立宣言書のなかでも、エッセンスはこの部分にある。これは、当時はもちろん現在でも、思わず目をみはるような内容だといってよい。だからこそこの文章は、長くその後世界の人民を鼓舞したのだ。当のアメリア人は意識しなかったが、アメリカの革命は世界の革命の口火となり、ベトナム社会主義共和国も独立のときこの文章を引用している。 ところが、今のアメリカではどうだろうか。世界に誇るべき自国の独立宣言文の一部を見せられて、これは共産党の宣伝文ではないか、と疑うような人が少なくないのである。2025.03.23 記す 独立戦争の陰に消えた夢 P.31
一七七〇年代のことといえば、歴史家の筆はすべて大西洋岸に進行中だったアメリカの革命、新しい共和国を生み出そうとする動乱にだけ集中して、他をほとんど顧みようとしない。しかし、ちょうどそれと同じ頃、この大陸の反対側の太平洋沿岸でも、実は大きな変化がはじまろうとしていたのだ。 ボストンで虐殺事件がおこる前年の一七六九年春、南国の溢れるような陽光をいっぱいその帆に受けて、一隻の疲れきったフリゲート船が、当時人影まばらだったサンディエゴ湾のなかに入ってきた。近くに住んでいたインディアンたちは、その光景をみて仰天したという。「翼のある家」などまだ見たこともなかったからである。乗っていたのは、カリフォルニアへ植民をしようとするスペインの探検隊であった。十六世紀にもスペインはカルフォニアの海岸を船で探検したが、なにしろ中南米のほとんどを独占していたスペインには、カルフォニアへ植民する余裕がなかったのだ。 二百年あまり空白の歳月が流れて、一七六九年の夏、サンディエゴのプレシディオ(要塞)・ヒルの上に、セラ神父がカルフォニア最初のミッション(伝道寺院)を建てた。 それからあと、スペイン人がみせた情熱はすさまじいものがある。翌七〇年にはずっと北上して、風光明媚なモントレーに上陸した一隊は、ここにも新しいミッションを建設した。なんとそれから三十年の間に、広大なカルフォニア海岸の南半分にわたって、十九カ所ものミッションを建ててしまうのである。これらの寺院は、白というよりもいくらかピンクがかった壁で仕上げられていて、いかにも南国の自然のなかに融けこんだような建物である。ここがインディアンたちとの交易所や伝道所となり、さらには植民地化の拠点ともなったのだ。 ところで、海路と並行して、陸路でメキシコ北辺からカルフォニア中央部に到達するコースを、どうしても作りあげる必要がおこってきた。「英雄的な資質をもち、カシの大木のように強健で、砂漠のように寡黙であった」といわれるフアン・パウティスタ・デ・アンサにその命が下ったのが、一七七四年のことである。 私は、アンサが探検隊を組織してその壮大な旅に出た出発点を訪ねてみたいと思った。彼がそれまで指揮官としていたツーバック根拠地を出発しようとしている絵を、一度見たことがあるからである。 ツーバックは、アリゾナの南端にあった。あと二十分も車で南に走れば、メキシコとの国境の町ノガレスがある。今でも半砂漠といっていい荒涼たる土地で、少し傍道に入ると電柱と同じくらいの高さのサボテンがずらりと並んでいた。近くのツーマカコリという所には、スペイン人が建てたミッションの廃墟があって、雲一つない青空のもとに、森閑として立つていた。なかに入ると、聖壇のマリア像が無残に剥奪され、むなしく外形だけをとどめている。この近くのピーマ・インディアンたちに破壊されたのだという。 やがてツーバックに近づくと、私はまぎれもなくあの絵のなかに描かれたのとまったく同じ形の山が眼の前にひらけて来たのを見て、少年のように胸を躍らせた。キャル・ピーターズという画家が描いたアンサ遠征隊出発の絵には、約三一五〇メートルのライトソンを主峰とした連山が背後に聳え、いかにもスペインの根拠地らしく、アドべという日焼きレンガの建物がちらちらと見えている。 アンサは命を受けた年に、一度予備調査を行なった。ツーバックから七十四日かかってモハヴ砂漠を横切り、今のロサンゼルスに近いサンガブリエル・ミッションに到達している。だから二度目は、まず初めのうちに同じルートをたどればいいのだ。最大の目標は、人に伝え聞くサンフランシスコまで一挙に足をのばし、そこに植民の拠点を築くことであった。彼がツーバックを出発したのは一七七五年十月二十三日のことで、そのとき二百四十人もの部下を従え、約一千頭もの家畜を連れていたという。 同じこの年の四月十九日早朝、大陸の反対側のボストン郊外では、豊かな森の連なるレキシントンの原野で、のちにミニットマンとよばれるようになる植民地側の民兵たちと、イギリス駐屯軍との間に最初の銃火がかわされて、独立への熱い火蓋を切っていた。 一方では、大西洋岸でワシントンが独立軍の指揮をとりはじめていたとき、他方では太平洋岸を目指したアンサ探検隊が、アリゾナのなかをヒラ・リヴァーに沿って西へ進んだ。ここは第二次大戦の最中に、日本人(二世や三セ世)が強制収容された場所の一つである。
※参考:ヒラリバー戦争移住センター(Gila River War Relocation Center)は、第二次世界大戦時にアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスの南50キロメートルのヒラリバー・インディアン保留地(Gila River Indian Reservation)にあった、日系アメリカ人収容所。日系人の間では「比良」の表記が当てられる事もあった。
何カ月もかかって砂漠や山脈を越え、とうとうアンサがなだらかな丘の上から美しいサンフランシスコ湾を見下ろしたのは、一七七六年三月のことで、それから四月にかけて、平和でのどかな湾の周囲を調査し、砦でミッションを建てる場所を決定した。アメリカの独立宣言省が出される三カ月ほど前のことである。結局、その年の九月には砦が、十月にはミッションが建てられ、スペイン領サンフランシスコは、アメリカ独立宣言の年に誕生することになったのだ。 当時、このカルフォニアから南米の南端までを領有した強大なスペインから見れば、独立したばかりの合衆国はまだ小さな赤ん坊にすぎなかった。しかしその後、スペインの新大陸における政治的野望は跡かたもなく消えうせ、アンサの壮途もいまとなっては一場の夢にすぎない。 巨大な植民帝国を作ろうとしたものと、デモクラシ―の国家をともかく築こうとしたものとの、これは必然の結果であったろう。歴史とは、まさしくこの浮沈の別名なのである。2025.03.25 記す
ミシシッピに挑んだ蒸気船 P.37
東は樹木に蔽われたアパラチア山脈の落葉の間から、北はミネソタの美しい静かな湖から、西はカナダ国境に近いロッキー山脈の岩肌から……あらゆる場所の水脈を集め、茫洋六五〇〇キロを流れる世界第一の長流ミシシッピ、インディアンが「父なる大河」とよんだこのミシシッピを初めて下った白人は、ラ・サールというフランスの探検家である。 彼は植民地時代もなかばの一六八一年暮れ、ミシガン湖の南端からイリノイ川を下り、やがて大河ミシシッピに合流して、翌年四月ついに河口に到達し、果てしないメキシコ湾の大きなうねりを見た。ここで父なる大河はその偉大な役割を終わり、母なる大洋に戻るのである。 ラ・サールは国王ルイ十四世の名に因んでこの地をルイジアナとよんだ。彼はその後部下に暗殺されて四十三歳の生涯を閉じたが、一七一八年になってフランスは彼の遺志を継ぎ、河口の近くにヌーヴェル・オルレアンを建設する。今のニューオーリンズは、フランス人の手によって誕生したのである。 両岸をまだ鬱蒼とした原始林に包まれ、土色の泥流が渦巻いて流れる大河とその無数の支流は、アメリカが独立してから、西へ向かう者のもっとも重要な交通路となったが、一八一一年、この大河の運命に重大な転機が訪れることになった。若い共和国アメリカにとって、まだ創世期にあったといえるこの年に、初めて蒸気船がミシシッピにその姿を現わしたのだ。しかもその壮挙に挑んだのは、二十四世紀最初の大統領となったセオドア・ローズヴェルトの、三代前の叔父にあたるニコラス・ローズヴェルトである。 大体この年は、ミシシッピ流域に天変地異が続いて起った。春の増水は例年になく激しく、あちらこちらで水があふれ、まだまばらに住みついていた程度の開拓者たちの間では、恐ろしい疫病が流行した。やがて無数のリスが、群れをなして南に移動しはじめた。支流のオハイオ川では、数えきれないほどのリスが溺れて死んだという。 夏になると、巨大な彗星が夜ごとに現れて、その光芒は目もあざやかに夜の大空を彩り、大きな災害の前兆のように見えた。 やがて秋が訪れると、果たして恐ろしい異変が襲いかかった。ミシシッピ中流の広大な地域に、かつてなかったほどの大地震が発生したのだ。大地は波のように揺れ、あちこちらに亀裂が稲妻のように走った。川の両岸の土手が崩れたり、泥だらけの川底が逆にもり上ってきたりした。春の洪水と秋の地震は、川筋の一部を変えてしまったほどである。 そこへ今度は、火と煙を吐く船の出現である。これを初めて見たチカソー・インディアンは火を噴くカヌーだと考え、煙突から火花や煙が噴きあがるのは、夏がもう一度戻ってきたのかと思ったという。ロバート・フルトンがはじめて蒸気船をニューヨークのハドソン川に浮かべ、松の木を燃料にして火の粉を黒煙と一緒にまき散らしながら、水の流れにさからって川をのぼり、人びとを驚倒させたのは一八〇七年のことだった。 ニコラス・ローズヴェルトは早速フルトンに申し出て、西部の川に蒸気船を走らせ、開拓の進度を一挙におしすすめようとしたのだ。しかし深くてゆったり流れているハドソン川と比べて、ミシシッピやその支流オハイオ川は、激流あり、浅瀬あり、しかも船の水路になる水脈がまだ十分にわかっていない。そこでニコラスは、オハイオ川のかなり上流に位置している町ピッツバーグでみずから設計して平底船を作り、一八〇九年ニュオーリンズへ下る船旅に出発した。 これは彼のハネムーンでもあったのだ。花嫁のリディアは愛くるしい勇敢な女性で、友人たちがとめるのもきかず、進んでこの危険な船旅にのり出したのである。ニューオーリンズまでの平底船の旅を無事に終わった。この新婚夫婦は、再びピッツバーグに戻り、西部の川に向いている平底の蒸気船を建造し、「ニューオーリンズ号」と名づけた。残念ながら、今この船がどんなものであったか知ることはできない。万一蒸気が駄目になったときのことを考えて、日本のマストを作り、ニコラスが特許権をもっていた水をかく水車の車輪を、船の片側につけていたらしい。 しかし今度こそ、友人たちはリディアの同行に強く反対した。彼女はもう間もなく母となる体だったからである。しかし好奇心の旺盛なリディアは友人たちの忠告もきかず、大きなお腹を抱えて、夫と一緒にニューオーリンズ号の乗りこんだ。 ルイヴィルの近くに、濁流の渦巻く危険な浅瀬の続いた場所があって、川の増水をまたなければその場所を越えることはできない。船がその時期を待っている間に、リディアはルイヴィルの町で子供を産んだ。 いよいよ急流乗り切りを決行しようというとき、せめてその部分だけでも馬車で陸路を行くようにとすすめる人びとの言葉を断って、彼女は赤子を抱いたまま、夫と運命をともにしたのだ。 ミシシッピの本流に入るまでに、船は何度も同じような危険をやっとの思いで乗りこえたが、そのあとで航行中にあの大地震に出あったのである。土手は崩れ落ち水中に没した。それまであった島も、たちまちのうちに姿を消した。川底が盛り上がって、水の上に姿を現わした。なんとも恐ろしい異変だった。アメリカ中部を襲った地震のうち、記録に残っている最悪のものである。 水路の急変、機関の故障などに悩まされながらも、ピッツバーグを出発してから約三か月半もかかって、勇敢なこの夫婦は一八一二年一月にニューオーリンズに到着した。これがこの大河に蒸気船を導入した最初の画期的な旅であった。 それから二十年ばかりたったとき、若きリンカーンも中西部の農産物を平底船に載せてこの川を下ったし、さらに二十数年後には、この川のほとりに住んでいた青年マーク・トウェーンは、蒸気船の水先案内人となって何度もこの大河を上下した。 しかしこの舞台の主人公はラ・サールやローズヴェルト、それにリンカーンや『トム・ソーヤ』の作者などではなく、無名で歴史に刻み続けるミシシッピそのものなのである。
ロシア帝国南進の夢の跡 P.43
サンフランシスコを訪ねたとき、友人からその話を聞いて、私は一瞬耳を疑った。 「ここからあまり遠くない場所に、昔ロシア人が砦を作ってね、今でもその跡がちゃんと残っていますよ」 カリフォルニア一帯はかつてスペイン領土だったから、南国の豊かな陽光を浴びたカトリックの寺院はあちらこちらで見受けるが、ロシアという国からすぐ連想されるような、雪と氷でとざされた風景は、あまりにもカリフォルニアのイメージに合わない。第一そんな話を、私はその時まで聞いたこともなかった。 私たち夫婦は思い立って、よく晴れわたった秋の日の朝、ゴールデンゲート・ブリッジを渡って、まっすぐ一路北に向かった。田舎道をだいぶ走ってから海岸に出ると、静まり返った小さな港町があった。物音ひとつしないほどの、まるで絵にかいたように美しい港で、目の前には大きなペリカンがゆったり空中に舞い、電線にはカラスが十羽ばかり並んでとまっている。 聞けば、ヒッチコックの「鳥」という映画は、ここでロケをしたのだそうだ。とたんに、なんとなく背筋が寒くなる。もう一昔前、妻がヒッチコックにねだって描いてもらった彼の横顔のスケッチを思い出した。私の頭のなかでその横顔が、いたずらっぽく、ニコリと笑ったような気がしたからである。 それからしばらく海岸の曲がりくねった道を走ると、川が静かに海に注いでいる平和な景色が見えてきた。その川がロシアン川というのだと聞いて、私は驚いた。この川を、今から一世紀あまり昔に、ロシア人が何人も船を浮かべて上り下りしたのだろうか。 この川から先は、大変な難路だった。絶壁が海岸に迫っているため、道は右に左に曲がりながら、その急斜面の山のへりを登っていくのだ。ハンドルを握りながら左手を見ると、遠く足もとに太平洋の白波が砕けていた。このぞっとするような難所を終わって、やっと目的の砦が見えてきた。人家のあまり見当たらない海岸に、一軒の建物がひっそり並んでいる。 車を止めてから砦にたどりつくまでに、私たちは海沿いの道を長く歩かなければならなかった。近づくと、ひろびろとした太平洋に向きあって、四メートルもある高い木の塀をめぐらした砦の出入り口が見えてきた。砦の外周をなすこの木の壁はほぼ正方形で、一辺が一〇〇メートルあまり、中央に井戸の跡があって、当時を偲ぶ建物が一部だけ復元されて建っている。 一八一二年にロシア人九十五人と、アラスカ人四十人がここにやってきて、この砦を作りあげたのだという。その後の最盛期には、砦の内外にできた建物は八十五棟、おそらくカリフォルニアの一角に、ロシア帝国の威風を誇るほどになっていたことだろう。 どうしてこんな場所までロシア人が南下してきたかというと、もともとはアラスカ経営を円滑に行なうためである。ロシアはその頃ロシア領アメリカ植民会社を作ってアラスカを経営させていたが、この会社を牛耳っていたのが、日本にも来たことがある敏腕なニコライ・レザノフだった。しかしアラスカはあまりにも寒くて食糧の自給ができないため、ずんぐりした総督のアレクサンドル・パラノフは、海岸を南下して砦を作り、食糧や毛皮の交易所を作るよう部下に命じたのだ。 残された木造の建物をのぞいてみると、窓の少ない暗い部屋の中で、男たちがウオツカでも飲みながら、トランプで退屈をまぎらわしているような光景が、ふと頭のなかに浮かんできた。 女性はほとんどいなかったので、彼らはセックスでずいぶん不便をしたに違いない。しかしそのうち、男たちは遠慮なく、近くに住むインディアンの女たちと一緒に生活するようになった。ロシア人とインディアンの混血児が、何人もカリフォルニアに生れて育った。また他の白人たちが誰も入ってこないような早い時期に……。 ここに根を下ろしたロシア人たちは、船を何隻も建造し、ロシアン川を遡って内陸に入ったり、サンフランシスコ湾のあたりまで南下したり、食糧を積んでロシア領アラスカを往復したり、結構この砦を繁盛させていたのだ。 一八三〇年代に入ると、砦の生活にも余裕ができて、アレクサンドル・ロチェフという指揮者を訪ねたフランス人は、砦のなかの彼の部屋の立派なのに驚いて、モントレーにあるメキシコ総督の家よりすばらしい、とほめている。そのフランス人は、美人のほまれ高いロチェフ夫人がピアノでモーツァルトを弾くのを聞いたり、フランスのワインをすすめられたりして、歓待されたのだった。 つまりその頃のアメリカは、西南部をメキシコに、西北部をロシアとイギリスに押さえられ、太平洋への出口はなかったのである。だから後になってアメリカは、アラモの戦いでメキシコ領への侵入をはじめ、イギリスとは条約を結んでその進出を防がなければならなかった。 ロシアは……アメリカにとって幸いなことに、アラスカの経営に失敗し、この砦、フォート・ロスを撤退することになった。 一八四二年、ロシア人からこの砦を買いとったのは、なんとその後七年目に自分の農園のなかから金鉱が発見される、あのジョン・サッターなのである(五六ページ参照)。サッターはロシア人たちの残した武器、弾薬、牛、羊などを、船でサクラメントにある自分の砦にまで運んだという。 ロシア人たちが抱いたカリフォルニア南進の計画は、こうしてわずか三十年の白昼夢に終ったが、砦を出て再び目にしみいるような太平洋の波の輝きを見て、私自身もまたその白昼夢から覚めたように思った。
アラモ砦を忘れるな! P.49
毎日のように、荘厳な落日が西空に浮かぶ雲を真っ赤に染めながら、さえぎるもののない地平線のかなたに沈んでいく広大なテキサスの原野に、「フロンティアのヒーロー」と謳われたデヴィ・クロケットが、十二人のテネシー出身者を引き連れてその姿を現わしたのは、一八三六年二月上旬のことである。 彼は勇敢な開拓農民としての生活や、度重なるインディアンとの戦闘を通じてばかりでなく、テネシーの州会議員を二期四年間、ついでテネシー選出の連邦下院議員も二期四年間を務め、野性的で風変りな議員として、広くその名を知られていた。政治生活をやめて野に下り、翌年テキサスに姿を見せたとき、彼はちょうど五十歳。戦機の迫っていることを知りながら、アモアの砦に入ったのは、すでにそれなりの覚悟をきめていたのだろう。 フランス一国よりも広いこのテキサスは、その頃スペインから独立してまもないメキシコの領土だった。しかしメキシコにとっても中央からあまりにも遠い辺境のテキサスには、アメリカ人たちがメキシコ政府の許可をとって入植し、当時その数は二万人に近く、原住メキシコ人よりはるかに多くなっていた。ところが一八三四年メキシコに政変がおこり、サンタ・アナ独裁政権をつくりあげたので、アメリカ人たちはひそかに自国の政府から援助の約束をとりつけ、テキサスの独立をめざして反乱をおこしたのである。メキシコ側ではこの反乱を鎮圧するため、サンタ・アナ自ら大軍を率いてリオ・グランデを越えた。こうしてその数五千とも六千ともいわれるメキシコ軍は、アメリカ人がとじこもったアラモの砦に迫っていたのだ。 この事態を知って、反乱をおこしたアメリカ人の指揮者ヒューストンは、サン・アントニオを守っているトラヴィス大佐に命じ、町を放棄して後退させようとしたが、大佐は逆に古くからある荒れ果てたカトリックの寺院にたてこもり、サンタ・アナの大軍を迎え撃つ準備をととのえた。 デヴィ・クロケットが到着したのは、そういう避けられない戦いの始まる直前のことだった。寺院を砦にして戦うことは、ほとんどそのまま死を意味していた。守る者の数は僅か八十七人にすぎなかったのである。
やがて――最後の日がやってきた。それは、戦闘が始まってから十一日目とも、あるいは十三日目ともいわれている。 早朝から、メキシコ軍の攻撃が二回も繰り返された。辛うじてその度に撃退はしたが、すでに砲撃であちらこちらの壁面が崩れていた。三回目の総攻撃では、とうとう砦のなかにメキシコ兵がなだれこみ、敵味方も分らないような肉弾戦になった。 昼近くに、すべては終っていた。トラヴィス大佐も、デヴィ・クロケットも、両刃のナイフを発明したジム・ボーウィンも、その他この砦を守っていたすべての人びとは、砦の各所に死体となって横たわっていた。 ある歴史家は、こう書いている。
メキシコ軍はこのアラモで、合計千五百人の死傷者を出したという。一方反乱軍の方は、アラモ全滅の知らせにふるい立ち、今のヒューストン市の近くでメキシコ軍を迎撃した。彼らは口ぐちに「アラモを忘れるな!」と叫んで襲いかかり、とうとうメキシコ軍を追い散らして、サンタ・アナまで捕虜にしてしまった。こうしてアラモの犠牲の上に、テキサスはローン・スター(孤独なる星)共和国として独立することになったのである。
ところでこの共和国は、それから九年たった一八四五年のはじめに、合衆国に併合された。かねての筋書き通りに、奴隷制度を認める州として……。
いまアラモの砦があるサン・アントニオを訪れると、やたらにアラモという字が眼につく。アラモ・ホテル、アラモ・ナショナル・バンク、レストラン・アラモ、その上、アラモ・トヨタといった具合である。
私がアラモの砦を訪ねたのは、土曜日のことだった。朝から制服の軍人たちが、群をなして参詣にやってくる。週末の休暇にここを訪ねるのは、軍人としてまず理想的なコースなのだろう。彼らは廃墟の入り口でちょっと立ちどまるようにして、帽子をとってからなかに入る。まさしくここは、メイフラワー号に乗って新大陸にやってきた人たちが上陸したというあの記念の岩と同じように、国家的記念碑なのだ。軍人たちの顔には、緊張した敬虔な気持がはっきりとにじみ出ている。
しかしテキサスが合併された翌年に、メキシコとテキサスの国境問題がこじれて、戦争が発生した。アメリカ軍は待ちかまえていたようにメキシコに侵入し、一八四八年の終戦の条約では、カリフォルニア、アリゾナ、ニューメキシコなど広大な土地をメキシコから奪いとる。
彼はこういう反戦運動をしたため、すっかり人気を失って、その後しばらく故郷で弁護士業に専念することになるが、ずっと後に、共和党の大統領候補になったとき、当時をふり返ってこう書いている。
西部開拓の天国と地獄 P.55
大工のジェームス・マーシャルは自分が作った製材所の水車があまりよく回っていないのに気がついた。なにしろその水車は、直径が四メートルもある大きなもんだった。よほど水の流れが強くないと、十分に回るはずがないのだ。
すぐ横には、西の方にいかめしい姿を見せて聳えているシエラネヴァダ山脈から流れ出したアメリカン川が、自然の静けさを破りながら、さわやかな音を立てて流れている。マーシャルはこの川から細い溝を掘って、水車迄水を流したのだ。
彼はすぐに、水車がうまく回らないのは、その溝を流れる水の量が少ないからだと気がついた。もっと溝を深く掘らなければならない。スコップを持って、彼は早速、溝の底の土をさらい始めた。こうしておけば、ここを流れる水の勢いがずっと強くなって、重い水車もうまく回転するようになるだろう……。そのときマーシャルの目に、なにやらキラリと光るものがとびこんできた。溝の底の土のなかに、キラキラと光るものがあった。その光る砂粒を掌にのせてみると、初めて彼の顔色が変わった。どうもこれは、金らしい。いや、金に違いない……。
マーシャルはそれをポケットにしまいこむと、一気に馬を飛ばしてサクラメントへ向った。サクラメントには、自分を使っている主人であり、この辺一帯の大農園をもっているジョン・サッターが住んでいた。それは、このカリフォルニアがメキシコ領からアメリカ領になるわずか十日ばかり前の、一八四八年一月二十四日のことである。
当時、極西部のこの土地に住む人びとはごく僅かで、サッターはメキシコ政府から広大な土地を借りうけ、人びとを使って農園を作りはじめていた。マーシャルは、その使用人の一人であった。
彼はサッター砦にたどりつくと、急いで主人の部屋に走りこみ、そのままドアに鍵をかけてしまったという。息をはずませながら、彼は金の砂粒をポケットから取りだし、それをテーブルの上に置いた。サッターが調べてみると、それはまぎれもなく本物の黄金だった。
二人は翌朝、こっそりと、黄金が発見された場所コロマに向かった。水車にひく水をせきとめ、ふるいのなかに溝の底の砂をのせ、ほんの少しばかり動かしてみるだけで十分だった。素人にもすぐにそれと分かるほど、鉱脈は豊かで、地面にむき出しになっていた。
一体この秘密が、どの位の間、人に洩れないでいたのか、今となっては正確に知ることができない。しかしマーシャルの下で働いていたヘンリー・ベグラーというモルモン教徒は、次のような日記を残している。
そればかりでなく、噂をきいた人たちは、みんな浮き足立ってしまった。兵士は武器を捨て、官吏は仕事を放り出し、水夫は船を置き去りにし、大工はハンマーを、左官はコテを、みんな投げうって、砂金採取のシチュー鍋を片手に、この川めがけて殺到した。
噂はやがて、東部にも伝わった。ゴールド・ラシュはこうして始まった。オレゴン街道を伝わったり、パナマ海峡をこえたり、あるいは遠く船でマゼラン海峡を迂回してまで、夢につかれた人びとがカリフォルニアを目指した。フォーティ・ナイテーズ(一八四九年にやってきた山師たち)は、みな一攫千金を狙ったのだ。
ところが――マーシャルの金鉱発見からわずか一年前、場所も同じシエラネヴァダ山脈の分水嶺近くで、西部開拓史上もっとも悲惨な事件が起こっていた。
はるか遠くイリノイを出発した農夫ジョ―ジ・ドナーとその一行は、カリフォルニアに向かう最後の難関のこの山脈で、十月下旬に早くも大雪に出合ってしまった。そのとき一行は、男二十七人、女十七人、それに子供が四十三人で、やむをえず山深い湖のほとりに三棟の丸太小屋を急造し、ここで越冬しながら救援を待つことになった。二度ばかり救援を求めるために数人を出発させたが、なにしろ正確な地図などまったくない当時のことで、みな遥かに連なる壮絶な雪山を眺めて戻ってきた。
食糧はもう底をついていた。十二月十六日、ついに男十人と女五人が決死の脱出を試みる。六日目男一人が脱落し、さらに激しい吹雪にあって、ついに男四人が寒さと飢えて倒れた。ここで初めて、そのときまで辛うじて生き残っていた人たちが、友の人肉を口にする勇気をふるい起こすのである。数日後にはさらに三人の男が死んで、そのときも死体はさらに生きのびる人たちの生けにえとなった。女五人は一人も餓死しないですんだが、男は十人中、助かったのは僅か二人にすぎない。
救援隊が作られて、やっと雪のなかの小屋を発見したのは、もう二月十八日のことだった。
小屋のなかの惨状は、とても文字にするに耐えられない。生き残っていた女性の一人は、救援隊をうつろな目で見て、こういったという。
「あなたたち、カリフォルニアから来たのですか。それとも天国から舞い降りてきたのですか」
小屋へ入ってみると……鍋のなかの肉片になっていた隊長のドナー、父親の肝臓を焼いて食べていた子供たち……こうして一行八十七人中、四十人は、残りの人の生命をつなぐ糧となったのだ。いま西部のいくつかの場所では、年に一度、ドナーに似た人を選んでその日だけ朝から晩まで腹いっぱいに自由に飲み食いさせるという習慣が残っている。
こうしていかめしい山容のシエラネヴァダは、その東側と西側で、同時に天国と地獄を分けて作ったのである。
2025.03.28 記す
西部終着駅へ走るオレゴン街道 P.61
一八五二年、オレゴンへの長い旅の途中、現在のオマハの近くで、ジョン・クラークという人は次のような日記を書いている。
その他にも死にかかっている人たちが何人かいて、みなコレラか、ハシカか、それとも天然痘だった。埋葬する穴を掘っている人もいれば、病人を看病している人もいた。
女子供は悲しげに泣き叫び、薬を探しにとびまわっている者も、ほとんど手に入れることができない様子だった。われわれはテントをたたんで一マイルほど先に進み、悲しみの声の聞こえないところで、やっとテントを張った」
西部で育ったリンカーンの伝記をみても、祖父は森で開拓作業中にインディアンに襲われて死に、母は彼がまだ八歳のときに、ミルク病という流行病で死んだ。たった一人の姉も、結婚後まもなく病気でその短い生涯を終わっている。ましてや太平洋岸のオレゴンまで行こうという者にとって、疫病、厳しい天候、乏しい食糧、インディアンの妨害などはじめから覚悟しなければならなかった。
現在のネブラスカ州を東から西に流れているプラット川は、割合渡河しやすいので、現在のオマハのあたりから、この川に沿って人々は遡った。あたりは一面の高原である。
プラット川のほとりで、一八四九年にチャールズ・ゴールドという人が書いた日記。
「ヤングが撃って、スコットを死なせた。一行はそこで裁判を開き、ヤングの有罪を決定した。絞首刑か銃殺刑を選ばせると、彼は後者を選んだ。処刑はすぐに実行された」
こんな苦労までして、なぜ人々は東部から西部へ進んだのだろうか。
一八四〇年代に入ってから、アメリカ中の人たちは、まるで熱に浮かされたように、西方への進出を夢みていた。テキサスを併合した一八四五年、ニューヨークのジャナリスト、ジョン・オサリヴァンが書いた次の文章は、国民の気持をよく代弁したものだった。
西へ向って膨張するという、この「明白な天命」は、オレゴンへの道に集約して現われていた。多くの人が、あらゆる困難をこえて、ひたすらオレゴンへ向った。このコースが、当時太平洋岸にいたる一番安全な道だったのである。
プラット川の上流にララミー砦がある。ここで休憩したりして、さらに海抜二千数百メートルもあるワイオミングの大高原を西へ進み、アメリカ大陸の分水嶺にさしかかる。そこにスウィートウォーター川が流れている。
一八四三年、ジェシー・アプルゲイトという人が残した日記。
さて分水嶺を越えると、川は南に流れてコロラド川の上流となる。ブリッジャー砦をすぎて西南に山脈を越えると、一八四七年二モルモン教徒の一団がやって来たソルトレーク・シティに出るが、西北に進路をとると、険しい山を越えたあと、今のアイダホ州でスネイク川のほとりにたどり着く。
一九七六年に上流でダムが決壊し、大被害を出したこの川は、名前の通りに不気味である。激流あり、早瀬あり、深い淵ありで、おそらく多くの人がこの川で生命をうしなったことだろう。十数年前、私の友人の夫は、この川で釣をしている最中、舟がひっくり返って溺死した。
一八六二年、E・S・マッコマズという人の日記。
今のオレゴン州へ入るあたりから、スネイク川と別れ、あくまで西北へ向って原野を進むと、アラワラ砦のところでコロンビア川にぶっかる。悠々たる大河だが、それでいてなかなか気が許せない川だ。
一八四一年、ジョセフ・ウイリアムズ牧師の残した日記。
あと、川は真西に流れて、太平洋にそそぐ。オレゴン街道の終点である。幾日もかかって、太平洋岸から逆にオレゴン街道をドライブした私は、あちらこちらで無人の境を行くような気がした。
この西方への膨張熱は、一八五三年、日本に開国を迫るという形で現れる。さらに一八九八年にはハワイを併合して、ついにフィリピンを領有する。二十世紀後半の朝鮮戦争やベトナム戦争さえ、ある程度までその延長線上に考えることができるだろう。
2025.03.29 記す
南軍の挽歌・アトランタ攻防戦 P.67
まったく今までどれほど多くの日本人が、この小説を読み、この映画をみたことだろうか。
アメリアの北部と南部が、それぞれ違った生活信条を抱いて激突し、戦争はもう四年目に入っていた。深南部ジョージアの州都アトランタに迫る北軍のシャーマン将軍。敗残の負傷兵が一杯になったアトランタの路上で、アシュレーを探そうと必死に走り回るスカーレット。北軍殺到の知らせにすっかり恐怖に陥った町の片隅で、にわかに産気づくメラニー。そのうち北軍の砲火を浴びて、町々に火の手が上がる。その焔のなかを、スカーレットやメラニーを乗せて、馬車で脱出をはかるレット・バートラ。
これは、おなじみ『風と共に去りぬ』の一場面で、日本では舞台でも再現されたほどである。
いまアトランタのダウンタウンにある市立図書館や、郊外の美しい杜にかこまれたエモリ―大学の図書館を訪ねると、この小説の世界各国版が並んでいて、御本尊のアメリカ版を除けば、なんと日本画一番多くの種類の版を出しているのが分かるのだ。
南北戦争――アメリカの歴史をまさしく前半と後半に二分する分水嶺にあって、世界最大といわれるこの内戦も、一八六四年にはようやく大勢が決しようとしていた。両軍の首都ワシントンとリッチモンドを結ぶ線上とその周辺では、なお繰り返し死闘が続いていたが、一部の北軍は遠く西から迂回して、南部の奥深く侵入しようとしてたのだ。テネシー州の東南端にあるチャタヌーガは、切り立った絶壁のルックアウト山や、なだらかな馬の背がつづくミッショナリー・リッジなどにかこまれ、当時暴れ川といわれたテネシー川が、ざわざわと音立てながら流れている町である。
一八六三年末に北軍は激しい南軍の抵抗をようやく打ち破って、この町を占領する。このあと北軍のグラント将軍は、それまで一緒に戦っていた部下のシャーマンに十万の大軍を与え、ジョージア侵攻を命令した。
勢いに乗ったシャーマンは、途中のケネソー山を守備する南軍を蹴散らし、一八六四年の夏の終り、アトランタの北端に迫った。
いまアトランタのグランド公園にあるサイクロラマは、この町の凄まじかった攻防戦を、みごとに再現している。
ここの円形劇場では観客の方が中央に集まって、自分たちを取り巻く絵や模型の大パノラマを、時間の経過につれて眺めることができるのだ。場内は一度真っ暗な闇となり、懐中電灯の一条の光が、物語の発端を描いた部分を照らしだす。柔らかな南部なまりの女性が、北軍の進入や南軍反撃の模様を、時には大きな海原のようにゆったりと、時には波立つ激流のように力をこめて、話しはじめるのである。
それにつれて、小銃のはじけるような音、腹にひびく大砲の重おもしい炸裂音、けたたましい軍馬のいななき、突撃を合図するラッパの響き、それに加えて兵士たちのあげる喚声などが、遠く、近く、聞こえてくるのだ。私は思わず、雨もよいの闇夜のなかで、鬼火のちらちら見え隠れする平家歴代の墓の前に坐り、一心不乱に琵琶をかきならしながら、壇ノ浦の平家滅亡のさまを語り続ける耳なし芳一の姿を思い浮かべたほどである。
こうしたアトランタは、九月二日に降伏する。しかしシャーマン将軍の目的は、もう一つ別のところにあった。彼はジョージア全体を蹂躙し、あらゆる経済資源を略奪し、南部人に物心両面の打撃を与えようと計画していたのだ。
二カ月あまりアトランタを占領したのち、シャーマンはこの町に火を放ち、十一月十五日に有名な「海への行進」を開始する。ちょうど収穫を終わったばかりのジョージアの沃野は、数十キロのもの幅にひろがって南下する数万の大軍のために、ほとんど無抵抗のまま荒され尽くした。
シャーマンの命令は広く解釈され、南部人をこらしめるため、部下は遠慮なく復讐のためのうっぷんを晴らしたのだ。彼らは家や工場を焼き払い、女性を犯し、食糧を奪い去り、鉄道の線路を根こそぎ引き抜いた。シャーマンは十二月二十一日に大西洋岸の古い町サヴァンナに入り、クリスマスのプレゼントとして、サヴァンナ占領をリンカーン大統領に打電したという。
私はちょうど一日がかりで、アトランタからサブァンナまで車で走ったことがあるが、行く先の町々には、今なおシャーマン略奪のあとを物語る標識が立っていた。
このとき北軍は、南部への復讐を思う存分晴らしたと思ったかもしれない。しかしこれは逆に、南部人の心のなかに、北部への深い怨恨をその後長く刻みこむことになるのだ。
南北戦争は正味四年間、一国の内戦とは思えないほどの凄まじさで行なわれた。生命を失ったもの、両軍あわせて六十万をこえ、大規模な戦闘だけでも数十回に及んでいる。いいかえれば、北部も南部も、それほど固く自分たちの信条を守り、互いに譲らず、ぶつかり合ったのである。
当時北部にはもう奴隷はいなかったのに、南部経済は奴隷労働によって支えられていた。資本主義化された北部は、保護貿易を望んでいたが、綿花の輸出に賭けていた南部は、自由貿易の方が都合よかった。北部は連邦政府の強化を願がっていたが、南部では各州の自治を希望していたのだ。
南部の敗北は、その後のアメリカが北部の望んでいた方向に進むことを意味していた。そればかりか、南部が北部にどのように取り扱われたという点を除くと、その後のアメリカの歴史のなかから、敗者南部はしばらく姿を消してしまうのである。つまり歴史とは、やはり強者のもの、勝者のものであろう。
いま戦争後の敗者南部の姿は、そのごく一部が、アトランタの地下街などで復元されているにすぎない。そこにはレンガを敷きつめた歩道の上に、ガス灯がほのかにゆらめき、ビクトリア王朝時代のムードを残した建物の窓のステンドグラスから、一世紀前の光が今も妖しげに洩れている。
2025.03.30記す
地球の裏側まで伸ばした触手 P.73
テキサス州サンアントニオにあるアラモ砦のすぐ隣に、一八五九年にできたというメンガ―・ホテルが建っている。アラモで壮烈な戦いがあったとき(四九ページ参照)から半世紀以上たった一八九八年五月、がっしりとした身体つきの男が、このホテルに入ってきた。見るからにエネルギッシュなその男は、つい先日まで海軍次官の要職にあったセオドア・ローズヴェルトである。彼はレオナード・ウッドが司令官となって組織をはじめた第一騎兵義勇軍に、副司令官として参加するため、ここにやってきたのだ。
その時アメリカは、スペインとの戦争に沸き立っていた。戦争になった直接の原因は、あのキューバにある。フロリダ半島のすぐ南に横たわっているこの島は、かつて広大な領土を誇っていたスペインの、最後に残された植民地だった。
もう何年も前から多くのアメリカ人は、スペインの圧政下に苦しむキューバの独立を願っていた。それはちょうど一世紀あまり前に、自分たちが通ってきたのと同じ道のように見えたのだ。一九九六年の大統領選挙では、アメリカの二大政党がともにキューバ解放を叫んだほどである。
以前からスペインとその植民地の間に戦争が絶えなかったので、アメリカの新しい軍艦メイン号が、キューバ在住のアメリカ人の生命や財産を保護する目的で出かけたところ、九八年二月、キューバのハバナ港内で突然爆沈し、二百六十人の将兵が死亡するという事件が発生した。
その直後、アメリカ中に巻きおこった世論は、「メイン号を忘れるな!」の一語に尽きる。このときスペイン側は戦争の回避に努力をしたのだが、マッキンレー大統領は開戦に踏み切った。
ウッド大佐が騎兵隊を募集しはじめたとき、その事務所をアラモ砦のすぐ隣のホテルに設けたのは賢明な措置だったといえるだろう。なにしろアメリカ人は、「アラモを忘れるな!」という愛国的なスローガンを、その時もまだ決して忘れてはいなかったからである。
ローズヴェルトは当時まだ三十九歳、このホテルで部隊の編成に当たった。年の若さに似ず、有名な存在だったので、彼を慕って続々と義勇兵が集ってきた。有名な「荒馬乗り連隊」である。
彼らはミンストレル・ショーによく使われた「今夜は一騒ぎしよう古い街角で」という歌を、進軍の時の歌にきめた。この歌と、もう一つスーザの新曲「星条旗よ永遠なれ」は、この米西戦争の最中、全米を風靡したのだ。
さてこの連隊は、ろくに訓練もしないままキューバに進撃した。サン・ホアン高地占領に参加した。ローズ・ヴェルトはただがむしゃらに前進を命じたが、実は小高い丘からスペイン軍に狙い撃ちされ、ひどく危険な状況だったのである。
結局、この高地を陥落させたため、ローズヴェルトはたちまち戦争のヒーローとなり、戦後は凱旋将軍として盛大な紙吹雪で歓迎されている。この人気がまもなく彼を大統領の椅子につかせることになるのだ。
この他にも大勢のヒーローが生れたが、スペイン領フィリピンへ出撃したデューイ提督もその一人だ。彼は暁のマニラ湾に侵入し、ほとんど損害を受けずに、スペイン艦隊を降伏させたのだった。
戦争は、わずか十週間で終わってしまった。これほど労少なく、しかも効果の大きかった戦争は珍しい。
大体、開戦を避ける道はいくらでもあったろう。スペインはアメリカとの戦争を望んでいなかったし、アメリカでも開戦に躊躇する意見が少なくなかった。
メイン号爆沈事件がなんといっても直接のきっかけだったが、実はメイン号を沈没させた魚雷が、果たしてスペイン人によって発射されたものか、それとスペイン人の仕業のうに見せかけてアメリカ人を怒らせるために、キューバ人が発射したもか、誰にも分らなかった。
それどころか、当時キューバに投資されてりたアメリカの資本は五〇〇〇万ドルにもなっていたので、アメリカを開戦に踏み切らせてキューバを属国にするため、あるいはアメリカ人自身がメイン号を――という可能性さえ考えられるのだ。
そういう不明朗さは、戦後処理にもあらわれている。キューバを解放するはずの戦いだったのに、地球の反対側のフィリピンを二〇〇〇万ドルでスペインから手にいれる。その頃のアメリカ人たちは、フィリピンが島の名前なのか罐詰の名前なのか、分からないほどだったのである。
ローズヴェルトは強引にも、「フィリピン人の多くは自治に適するようになる何の兆候もない」と述べる有様で、結局フィリピンにはアメリカ軍政が実施されたが、ダグラス・マッカーサーの父アーサー・マッカーサー将軍は、その時の司令官の一人である。
フィリピン人から見たとき、「これはアメリカの大きな背信行為だった。フィリピンにはホセ・リサールとかエミリオ・アギナルドなど、以前からスぺイン人の支配に抵抗を示す指導者がいた。アギナルドはアメリカ軍を解放のための協力者として大歓迎したのに、気がついてみるとアメリカ人は、スペインに代る圧制者として乗りこんできたのである。
そのときからフィリピン人のゲリラ隊と、それを鎮圧しようとするアメリカ軍隊との間には、血なまぐさい死闘が展開される。戦争そのものの何倍かの損害を、アメリカは蒙ることにでなるのだ。同時にまた、アメリカ兵士がフィリピンでみせたアジア人への傲慢さは、一層多くの反感を買う原因となった。
この時の教訓を、半世紀以上たったあとのベトナムで生かせなかったことは、アメリカ人がまだ十分に歴史的感覚を身につけていないからであろう。
ともかその頃、ローズヴェルトはこう叫んでいたのだ。
「私は自分の臆病を隠すために、人道主義という口実を持ち出す人に我慢ができない。……しなければならなぬ第一の、そしてもっとも重要な仕事は、わが国旗の優越性を確立することである」
大地震・サンフランシスコ潰滅 P.79
一九〇六年、四月十八日早朝、サンフランシスコの東の空は白んでいたが、町はまだ目覚めていなかった。
ジェシー・クック警部は新米のアル・レビイにばったり出会い、街角で二言、三言、冗談を交わした。その瞬間、大地がぐらぐらっと揺れはじめた。後にこの町の警察部長になったクックは、遠くで大地が雷のように轟くのを聞いた。
と後に彼は回想している。
レンガがあちこちで崩れ落ち、土埃りが舞い上がるなかで、下敷きになった人びとの悲鳴が聞こえた。
最初の衝撃は、翌日の新聞によると、五時十三分から四十八秒続いたと書かれているが、実際には六十五秒から七十五秒の間くらいだったという。
有名なセントフランシス・ホテルに泊まっていた鉱山技師のジョン・フアリッシュは、そのときの記憶を次のように書いている。
「私は何かが鳴り響くような大きな音で眼が覚めたが、それはちょうど杜を走り抜ける強い風の音と、絶壁に波が砕ける音が一緒になったようなものだった。
次の瞬間、近くで大爆発が起ったような激動がきて、建物を土台まで揺り動かした。きしんだり、すり砕いたりするような音が聞こえ、建物と煙突のつなぎめが崩れ、ゆらゆらと地面に倒れかかるような、凄まじい物音が起った」
四階建てのパレンシア・ホテルは、なんと下がつぶれて平屋になってしまった。クックがかけつけた警察署は、もう廃墟も同然であった。崩れ落ちたレンガンの下敷きになり、一瞬にして生命を失った人の数は、すぐにわからないほどであった。
この大地震に襲われたのはひとりサンフランシスコだけではない。この町を中心に、幅は二〇マイルから四〇マイルほど、長さは海岸線に沿って南北二〇〇マイルにわたった。サンノゼに近い州立精神病院は完全に倒壊して、患者や付き添い百人あまりが死亡した。サンフランシスコの北五〇マイルにあるサンタ・ローザでは、町のすべてのレンガ造りの家が倒れてしまった。
湾を隔てた対岸のオークランド、バークレーをはじめ、スタンフォード大学や、南では当時四歳の少年だったスタインベックの住んでいるサリナスの町までが、大きな被害を受けた。
サンフランシスコでは、激しい余震が何度もやってくる前に、もっと恐ろしい事態がすでに発生していた。それは、他ならぬ火事だった。後にドーアティ消防署長代理は、市のあらゆる場所で約五〇カ所から火事が発生した、と報告しているが、正確な数字はだれにも分からない。
その日の朝、とうとう火事の警報は鳴らなかった。チャイナタウンにあった警報を鳴らす建物が倒れかかっていたのである。結局火は四日間燃え続け、市の中心となっていたビジネス街の全部と、住宅街の五分の三が灰燼に帰した。
まだ幼い少女時代にこの大地震に出あったキャスリン・ヒュームは、当時のことを生ま生ましく語っている。
「丘の上で町が燃えるのを見つめていると、一人の男が『ああサンフランシスコ、ゴールデンゲートの女王』と叫んで、木の切れはしを投げました。大人たちはみな、お葬式に出ているときのようでした。
お母さんの頬には涙が流れていて、子供たちのように燃えている建物を眺めていることができませんでした。私たちのまわりの男たちも、お母さんと同じように泣いていました。それは、町のなかに仕事をもっていたり、焼けて融けてしまった銀行の屋根の下にお金を預けておいたからではなく、自分たちが生まれ育った懐かしい場所が燃えているからでした」
それほど、みなこの町を愛していたのだ。だからこそ、その後の復興作業にとりくむ熱意も違っていたのだろう。負傷者の救出はすぐ始められた。
とはいっても、公園はどこも避難者で一杯になり、最小限の家財道具を持った人たちが、煙のたちこめる街角で右往左往しなけれならなかった。
結局、この大地震の被害は、サンフランシスコだけで死者四百五十人、被害を受けた建物二万八千戸、被害総額は当時の金で五億ドルに達したという。
しかし銀行の対応はみごとだった。火事が終った日から、どの銀行も焼け残った他の建物を借りて臨時の営業を開始したし、六週間以内にどの銀行も、地震前と同じくらいの仕事ができるように、態勢を立て直した。
前市長ジェームズ・フェランは当時のシュミッツ市長の政敵だったが、この重大な緊急事態に、自分のオフィスも潰滅するという打撃を受けながら、復興への協力を申し出て、シュミッツ市長よりも大きな貢献をしたほどである。
まだ余燼がくすぶっているうちに、市ではサンフランシスコ復興四十人委員会を組織した。この委員会を中心に、損害査定、下水道、病院、道路拡充、公園、貯水槽、財源、古いビルの没収その他の問題について、多くの小委員会を設けて討議を重ねた。
そのうち、市の区画の基本をきめるパーナム委員会は、大火後わずか一ヶ月目には計画表を提出し、しかもすぐに採択された。これが現在のサンフランシスコの区画を決定したのである。
まだ新しい建物がたっていない廃墟のなかで、この計画に従い、まず整然と道路が区切られ、舗装ができていった。
市当局の迅速な対応と市民の協力は、こうしてほとんどパニックもおこさず、アジアへの門としてのサンフランシスコを復興させたのだ。
十九世紀なかばの金鉱発見いらい、この町は多くの魅力をひめて発展してきたし、地震当時はアメリカの勢力が世界的に伸びたときだけに、これほどの天災が町の歴史に致命傷にならなかった。難をいえば、このときから排日感情が高まったという点であろうか。
当時の日米感情は、全米的レベルでは良好で、日露戦争
政治の栄光と悲惨
一対七でも賛成とした大統領 P.87
ここに興味深い一枚の絵がある。初代大統領に選ばれたジョージ・ワシントンが、一七八九年四月に彼が愛したヴァジニアのマウント・ヴァーノンを出発して、船でニューヨークに到着したときの絵である。
はじめ大統領の就任式は三月四日に予定されていたが、あらゆる準備が前例のないものだったために、手はずはしだいに遅れて、大統領に選ばれたという公式の知らせが彼のもとに届いたのは、やっと四月にはいってからのことであった。
新しい共和国の首府はとりあえずニューヨークと定められたので、マウント・ヴァーノンの邸を出発したワシントンは、たけなわの春を楽しみながら、途中まで馬車で進み、ニュージャージからは船に乗ってニューヨークに到着した。このとき沿道はどこも、人びとの熱狂的な歓呼で埋まった。彼の到着にそなえて月桂樹の凱旋門を作った町もあり、白衣の少女たちが道に花をまき、歌を歌って彼を迎えた町もあった。
植民地のときはイギリス軍の副将となってフランス軍やインディアンと戦い、独立戦争では四散しがちな訓練もない軍隊を率いて善戦し、憲法制定の会議でも百出する意見をなんとかまとめ上げたワシントンは、もうだれがみても文句のない初代大統領だったのである。
この一枚の絵は、ワシントンがどれほど熱っぽい歓迎を受けたかをよく示している。彼をみつめる群衆の感動的なまなざし、興奮して帽子を振る人たちの群れ――。
じっとこの絵を見ていると、人物の配置や全体の構図など、ふとキリストを描いた宗教画を想像しないだろうか。
事実、憲法制定会議でも、大統領の問題について人びとは苦慮した。なかには人気を終身にすべきとか、陛下とよぶべきだと考える人もいたのだ。つまりイギリスの君主に対応するものをつくろうとした人も、そのなかに何人もいたのである。
「あなたは皆に尊敬されているのですから、いっそ君主の位についたらどうでしょう」
とのべた友人もいたという。
「長い間軍隊を指揮してきたのですから、その軍隊を率いてこの国を治めたらどうですか」
と進言した友人もいたという。
しかし一方で、アメリカ人はすっかり疑い深くなっていた。まだ独立する前のころ、イギリス本国から派遣されてくる総督たちの横暴に、すっかり手を焼いていた各植民地の人びとは、総督の再任を禁止する法律をつくったところが多い。今なおかなりたくさんの州で知事の再選を禁じているのは、そのころの名残なのである。
議会、大統領、最高裁という三権分立のバランスも、そういう心配から生まれたものだが、このままでは議会に多くの権限が集中しそうなので、それを防ぐために大頭領制を考えたといってもいいだろう。
しかし実際にはその後主客が転倒して、大統領が議会を見下ろしてしまうほどの高い丘に向かって登りだすのだ。
ワシントンはフランス革命が始まってヨーロッパが動乱に巻き噛まれると、議会に相談もしないで中立を宣言しているし、大統領の権限は小さいほどいいと考えていたトマス・ジェファソンも、大統領になってから独断でルイジアナの広大な土地をフランスから買収した。
デモクラシーの具現者と賞賛されているアンドリュー・ジャクソン大統領は、かねてからインディアンを西方に追い払いたいと思っていたので、そのインディアンの協力者を保護する判決を最高裁長官ジョン・マーシャルが下したとき、彼は憤怒してこう叫んだ。
「マーシャルが下した判決なんだ。奴に法の施行をやってもらおう」
リンカーンは自分で断固として信じていることを行なうとき、閣僚の意見を黙殺することもあった。奴隷解放宣言をつくりあげる経過について、次のように友人に語っている。
「私は閣僚と協議せず、また知らせもしないで、奴隷解放宣言の草案を書きあげ、いろいろと深く考えたあとで、この問題について閣議を招集しました。私は閣僚に対し、私がこの手段をとる決心をしたこと、皆さんを呼んだのは、その是非について意見をきくためではなく、宣言の趣旨を知ってもらうためであること、などを話しました」
ジャクソンの例を除けば、ワシントンの中立宣言、ジェファソンのルイジア購入、リンカーンの奴隷解放宣言などは、みなアメリカの発展を促した史上有名な業績で、だれもその価値を否定するものはないが、その政策がとられた経過は、かなり独断的なものだったといえそうだ。
リンカーンについては、また次のような話も伝わっている。あるときリンカーンは、一つの案をもって七人の閣僚を招集した。閣僚はみなその案に反対した。するとリンカーンは、閣僚の顔を見渡しながら、こういった。
「では皆さん、一対七で賛成と決定しました」
私たちはこの話を、もしこれを同じ共和党のニクソンにおきかえたら、一体どんな印象をうけるだろうか。
歴史の経過とともにアメリカの大統領がもつ権力は強大になる一方だが、その大統領にだれでもなれる可能性があるのだということが、いまなおアメリカの弾力の一つとして残されている。
ほとんど教育も受けず、十五歳で衣服商の徒弟に出されたフィルモア、みじめな丸太小屋に生れたリンカーン、同じように質素な丸太の家に生れたアンドリュー・ジョンソン、貧しい牧師の子で大学に進めなかったクリーヴランド、高校に通いながら田舎のドラックストアで働いたトルーマン……。こうした人びとが大統領にまでなった経過は、そのまま「アメリカの夢」の実現だった。そういえば元大統領ニクソンも、また、南カリフォルニアのあまり豊かでない家に生れたのだ。2025.04.09 記す
魚河岸と映った米議会 P.93
これは、日本人が集団で蒸気機関車に乗った最初の記録といえるだろう。
それ以前にも、ジョン万次郎やジョゼフ彦のように、個人的には乗るチャンスに恵まれた者もあったが、これは一八五八年(安政五年)に結ばれた日米修好通商条約の批准書を交換するため、アメリカから回された船ポーハタン号に乗って、一八六〇年(万延元年)二月に日本を離れた使節団の一行が、パナマで生れた初めて蒸気機関車に乗ったときの記録である。
乗ったのは、使節団七十七人のうち、サンフランシスコで病気になった一人を除く七十六人で、筆者は使節団の副使村垣淡路守、当時四十八歳で、日付は四月二十七日(以下陽暦)となっている。
先行した咸臨丸は、艦長に勝麟太郎、軍艦奉行の従者に福沢諭吉、通訳に中浜万次郎という面白い組み合わせだったが、こちらの方は太平洋岸に到着しただけで帰国しているので、集団でアメリカ文明の衝撃を受けたのは、村垣ら一行の七十六人の方であった。
とても好意的な紹介である。同時にあまりにも違う外の世界を見て、チョンマゲ姿の日本使節団一行が、借りてきた猫のようになっている光景が眼に浮かぶようだ。
ワシントン最大のウィラード・ホテルに泊まったので、生活ぶりも混乱をきわめる。
村垣淡路守の日記によると、
※参考図書:世界ノンフィクション全集/14 (筑摩書房):遣米史日記 村垣淡路守範正 川村善二郎訳 P.291
また従者の一人、加藤素毛の『二夜語』には次のような部分がある。
「浴槽は長持ちのような箱で、白銅が張ってある。ねじが二つあって、一つをひねれば熱湯が出、他の一つからは水が出る。両方一時に開いて湯と水の加減をしてから浴槽に入って座ると、浅いのでヘソのあたりまでしか湯がない。後で聞くと、寝て前を洗い、うつぶせになって背中を洗うのだそうだ。天井に蓮の実のようなものがあり、ねじをひねると清水が滝のように落ちてくる。
さて、五月十七日、いよいよホワイトハウスを訪ねて、批准書を交換することになった。アジアから来た珍しい一行を眺めようと、ホテルとホワイトハウスの間は人波で埋まり、よい場所にはプレミアムがついたほどだという。ホワイトハウスでは、狩衣や烏帽子、鞘巻きの太刀などに威儀を正した日本の代表たちが、民主党の大統領ジェームス・プキャナンに国書を捧呈する。こういう席上にも大勢の女性が列席しているので、日本代表はびっくりした。
その日の村垣日記。
……合衆国は世界一、ニの大国であるが、大統領は総督で、四年ごとに国中の入札で定めるよしであるから、国君ではないが、御国書も与えられたことがあるので国王の礼を用いたが、上下の別もなく、礼儀も少しもないので、狩衣を着たのも無益であったと思う」
ズボンを見て股引と思ったのだが、当時の日本の常識から考えると、この日記のようなことになったのであろう。
さて一行は、大統領招待の晩餐会や舞踏会に出たり、各地の見学に出向いたりして手厚い歓迎を受けているが、国会議事堂を見学したときの村垣日記には、次のような面白い部分がある。
何か云い終って、また一人立ち、前のごとし。何事なるやと聞くと、国事は衆議し、各意見を残らず建白するのを、副大統領が聞いて決するよし。……
二階に上って、またこの桟敷で一見せよというので、椅子に腰かけて見る。衆議の最中なり。国政の重要な評議であるが、例の股引をつけ、筒袖を着た姿で、大音にののしるさま、副大統領の高い所にいるありさまなどは、わが日本橋の魚河岸の様子によく似ている、とひそかに語り合った。
村垣淡路守はこうして遠慮なく自分の尺度で相手を酷評したが、各地におけるアメリカ人の歓迎ぶりはなかなか熱狂的で、ニューヨークに一行が着いたときには、それが最高潮に達した。使節団の泊まったホテルの前では歓迎大パレードが展開し、参加した軍人の数だけでも千五百人に及んだという。
次の詩は、ブロードウェーを通る使節団を賛えて、国民詩人ホイットマンが書いたものである。
西の海を越えて日本から来た
礼儀正しく 日焼けした
二本の刀を腰にさす使節たち
悠々と四輪馬車にゆられ
帽子をかぶらず
今日 マンハッタンを通っていく
二月 咸臨丸、浦賀を出航。
政府高官が食べた大陸横断鉄道 P.99
リンカ―ンが大統領に就任した一八六一年、ワシントンにある連邦議会には、一旗あげようという企業家たちが、廊下や控室にひしめいていた。
コリス・ハンティントンもそのなかの一人である。当時四十歳、働き盛りの彼は、この広大なアメリカ大陸を横断する最初の鉄道建設の許可状を手に入れようとして、ひそかに二〇万ドルの大金を持ってやってきたのだ。
彼は東部の農家の子として生まれ、少年時代には父の農場で働いていたが、その後、商人としてでもかなり成功している。二十七歳のときカリフォルニアで金鉱が発見されたことを知り、人びとが殺到することを見込んで商品を送り込み、自分もカリフォルニアに移住して、金物商を始めた。
やがて彼は鉄道建設に詳しいなぞの男セオドア・シューダと組んで、大陸横断鉄道の建設権を一挙に政府から獲得しようとしたのだ。それには一八六一年という年が、ちょうど都合がいい年だった。それまでも企業家たちは、何度もこの途方なく大きな計画の夢について論じあっていたが、北部と南部の意見が合わなかったのである。
北部ではシカゴかセントルイスから出発し、オレゴンかカリフォルニアに通じるコースを主張したのに、南部ではメンフィスかニューオリンズを起点とし、テキサスを通って南カリフォルニアに出るコースを主張して譲らなかった。
ところが一八六一年はじめには南部諸州がほとんど合衆国から脱退し、とうとう南北戦争が始まることになったので、今では南部の主張をまったく無視することができるようになったのだ。あと問題は、だれがその権利を政府から貰うことができるか、である。
ハンティントンが持っていった二〇万ドルの大金が、どのような形で政府高官の間にばらまかれたのか、それは分らない。ただはっきりしているのは、翌年、彼が無一文でカリフォルニアに戻ったこと、彼の手には大陸横断建設の許可状が握られていたこと、などである。
当時の西部は、まだまったく無人の境といってもよかった。というより、急激に人口が減っていたインディアンたちの土地であった。そういう場所に、日本流でいえば私鉄を敷こうというのだから、政府から援助がなければ、とてもできるものではない。
一方、政府の方も、もちろん初めての経験だから、どのくらい援助すればいいのか見当もつかなかった。それでハンティントンの許可状には四〇〇万ドルの交付金と、沿線九〇〇万エーカーの無償の土地がついていたのである。
こうして彼が、スタンフォード、クロッカー、ポプキンズらと一緒に組織したセントラル・パシフィック鉄道は、サクラメントから東に向かって鉄道の敷設を開始した。
同時に許可権を貰ったもう一つの会社、ユニオン・パシフィック鉄道は、オマハまで伸びていた鉄道をさらに西へ延長しはじめた。あとは両鉄道の競争で、両者の接合点は初めからきめてはいなかったのである。オマハから西へ向かったユニオン・パシフィックの方は、ほとんどが高原で自然の障害は少なかったが、労働力の不足と、インディアンの攻撃に悩まなければならなかった。、
工夫には主としてアイルランド人を使い、時には直接アイルランドで工夫募集の広告を出したりした。ワイオミングの大高原では、スーやシャイアンの戦士たちに何度も攻撃され、騎兵隊が鉄道の敷設を守ったり、時には工夫たちが銃をもってインディアンと戦わなければならなかった。
サクラメントから東に向かったハンティントンたちのセントラル・パシフィックは、まず峻険なシエラネヴァダ山脈にぶつかった。レールの一本一本が、南米の南端を迂回するか、まだ運河ができていないころのパナマを越えて運ばなければならなかった。
労働力は一層不足していた。そこで会社ではそのころから入植していた中国人たちを工夫に使い、遠く中国まで人集めが出かける有り様だった。この時使われた中国人の工夫は、一万人にのぼったという。
私は物好きにも、この二つの鉄道に沿って幾日も車で走ったことがあるが、ネヴァダなどでは今でもまったく人家が見当たらない砂漠のなかを、単線の鉄路だけがどこまでも延々と続き、まるで建設当時に時代がもどったような錯覚を抱いたほどだった。
鉄道会社は行く先々の准州や町からも寄付金を集めたりした。そして着工してから七年目の一八六九年、塩分が多くて身体が浮かんでしまうグレート・ソルト・レーク(ユタ州)の北側で、両者は完全にドッキングを完了した。レールを枕木に固定するための最後の釘には黄金製のものを使い、一同はシャンパンを抜いて祝いあった。日本では新橋から汽笛一声、最初の汽車が動き出す三年前のことである。
この両鉄道にならって、ノーザン・パシフィック鉄道、サザン・パシフィック鉄道、サンタフェ鉄道などにも許可が下り、政府が七二年までにこれら鉄道会社に下付した国有地の合計は、なんとフランス、ベルギー、オランダの本国の合計面積に等しかった。
その他一マイル建設するごとに、状況に応じて一万六〇〇〇ドルから四万八〇〇〇ドルまで、政府のローンを貰うことができたのだ。おまけにハンティントンたちは、鉄道会社に莫大な債務を背負わせ、債権者の政府が要求しても、会社は支払いができないようにしてしまったのである。彼やその仲間はたちまち大金持ちになり、カリフォルニア政府を買収することができたほどだったという。彼の財産は、当時の金額で約四〇〇〇万ドルと推定された。
彼はかつて二〇万ドルの大金をワシントンの高官たちの間にばらまいたが、そのワシントンはあまりにも大きな実を結んだのである。
ダイナマイトと銃で闘った労働争議 P.105
一八九二年、ピッツバーグ郊外のホームステッドにあるカーネギ―鉄鋼会社の工場で、すさまじい事件が発生した。、
会社の支配人ヘンリー・フリックが、組合を一気に粉砕しようとして、新しい提案を示したことが発端になった。当時その会社の労働者のうち、組合に加入している者は僅か四分の一に過ぎなかったので、場合によっては組合を押し潰してxしまうことが、不可能ではないように見えたのである。
それにしても、フリックの提案は苛酷なものだった。かなりの数の労働者を解雇し、残りの者も二二%賃金をカットするというのである。組合側はもちろんこの提案を一蹴した。するとフリックは工場を閉鎖し、ウインチェスター銃で武装したスト破りを三百人も雇い入れて、組合に加入していない労働者を動員し、工場の再開を計ろうとした。
三百人のスト破りを請け負ったのはピンカートンという有名な探偵団で、FBIがなかった当時、この組織は各州にまたがる多くの事件を引き受けていた。約三十年前、大統領就任式に臨むリンカーンを、イリノイ州からワシントンまで護衛したのも、このピンカートンであった。
この措置に起った労働者たちは、組合に入っていない者までいっせいに立ち上がり、ロックアウトに対してはストライキで対抗した。彼らは工場のわきを流れているモノンガヒーラ川を警戒するためランチを雇い、一日二十四時間川面を上下して、ピケットラインの態勢を作りあげた。
一方会社側に雇われたピンカートンの一団三百人は、特別列車と馬車を乗り継いで、ホームステッドの工場から五マイル下流の地点に到着する。ここからいくつかのモーター船に分乗した彼らは、一挙に川をさかのぼり、工場のわきへ上陸しようというのである。
あらかじめ知らせを受けていた労働者たちは、あちこちから銃をかき集め、川辺に防塁を築いて迎え撃った。どちら側が最初の一発を撃ったかは、今なお不明のままである。いずれにしても、労働争議史上まれにみる血まみれの戦いが、川岸をはさんで激しく展開した。それはもう、労働争議という常識をはるかに越え、一つの戦闘といってよいものであった。死者は両方で十六人、負傷者の数は数十人に上った。戦いはピンカートンの船がみな退却するまで続いたのだ。
戦闘では組合側が勝ったが、その後の法廷闘争でフリックは組合幹部を、陰謀、反乱、殺人の罪で訴え、百八十五人もが告発されることになった。刑務所入りをまぬかれようとすれば、組合は五〇万ドル以上の保釈金を積まなければならず、賃金も入ってこなかったので、この経済的破綻のためにストは四カ月半で崩壊してしまった。
流血事件を伴った大争議は、単にこの事件ばかりではなかった。アメリカの労働争議は使用者側の暴力と労働者側のストで彩られているといった方がよい。
少し時代がさかのぼった一八八六年に組織された「労働騎士団」が、シカゴのマコーミック刈取機械会社のストを支援して、八時間労働制を要求したことがある。
ヘイマーケット広場に集まった約千人のスト参加者に向かって、ある無政府主義者がアジ演説を始めた。そこへ警官たちが乗りこんできて解散を命じたとき、突然ダイナマイトが警官のなかに投げこまれたのである。
これは不幸な偶発事であったかもしれないし、周到に計画された事件だったかもしれない。爆発に続いて双方がピストルで撃ち合い、結局、警官八人が死亡し、両方で数十人の負傷者が出ている。しかもこの後、八人の無政府主義者が殺人容疑で逮捕され、ダイナマイトを仕掛けた真犯人が不明のまま、四人が絞首刑に処せられるというあと味の悪い事件になっているのだ。
さらにさかのぼって一八七七年には主要鉄道会社四社が一〇%の賃金カットを発表したのを契機にストライキが各地に広まり、大勢の植えた失業者たちがストを応援した。このためシカゴ、ピッツパーグその他の都市では、州兵と群衆が衝突して、連邦軍を呼ばなければならなかった。ボルチモアでは在郷軍人が出動し、スト中の労働者や見物人にまで発砲して、死者十人、負傷者十人という被害となった。
これは西部の場合でも同様で、西部鉱山経営者協会と西部鉱山労働総同盟などは、両方とも公然と暴力で対決した。経営者側が機関銃をもったスト破りを雇うと、労働者側は事務所をダイナマイトで爆破するという有り様だった。
こういう歴史を振り返ると、なぜ十九世紀末のアメリカでこれほど労働争議が暴力化したのだろうか、という疑問が湧いてくる。おそらくその最大の原因は、政府が組合の権利を守るために介入しようとはまったくしなかったので、組合としては、団結権、スト権などの基本的な条件からはじめてあらゆる権力を自分でかちとらなければならなかったからであろう。その上この時代になると、西部には安くて良い土地がもうなくなっていた。今までのように、不満な労働者はどんどん西部へ移住するという安全弁の役割を、西部が果たさなくなってしまったのである。
さらにこの当時は、東欧や南欧から物凄い数の移民が流れ込み、毎年数十万人の新しい労働者が現れ、労働条件を押し下げていたのだ。だからジェイ・ゴールドのような鉄道企業家に、「私は労働者階級の半分を殺すために、残り半分を雇ってやることだってできるんだ」と豪語させるようなことになったのであろう。、
また当時の労働組合に対して、大衆が理解を示さなかったことも原因の一つである。ニューヨークのセツルメントを指導した女性リリアン・ウォルドは、社会主義者が恐れられ、いま共産主義者が恐れられているのと同じように、当時労働組合が恐れられていたとのべている。
会社全体の利潤が使用者側や株主ばかりでなく、労働者にもかなり回されるようになったのは第一次大戦以後のことであり、第二次大戦後この傾向はなお強くなった。そのため今の労働組合は、戦うときは断固として戦う姿勢を保ちながらも全般的に穏健化し、むしろ保守化の傾向さえ見せはじめている。第二次大戦後、アメリカ全体が徐々に保守化の傾向を強めているのは、ここに大きな原因の一つがあるのだ。
り続けるために、労働者の賃金カットを通告したのであ
汚職にまみれて死んだ大統領 P.111
一九二三年の春、ハーディング大統領がアラスカへの旅を計画している矢先、妙なことが続いて起こった。
大統領がもっとも好きだったフォール内務長官が辞任したかと思うと、復員局法律顧問のクレーマーが、深夜ピストル自殺をとげたのである。しかもその場所は、大統領の信頼厚い復員局長官フォーブスが、大統領から買い取った家のなかだった。
その後まもなく、休暇を終えてヨーロッパから帰ってきたフォーブスも、大統領に辞任を申し出た。後になって考えてみれば、この三人は自分たちが行った悪質の汚職が、上院調査委員会の手によって暴かれだしたことに気がついたからだったが、肝心の大統領は事の重大性をあまり理解していなかったらしい。
クレーマ―の自殺現場にあった遺書が、その夜のうちにハーディングの手許に届けられても、「そんなものはいらないよ、持ち帰ってくれ」
といって、目を通そうともしなかったという。
しかし内務省や復員局をめぐる汚職は、その頃ワシントンの消息筋の間でささやかれいた噂ごく一部にすぎず、それがようやく大統領の耳にも入りはじめたのだった。さすがに大統領は、かつて腹心の部下だったジェンー・スミスを呼んで問いただすと、スミスはたちまち口を割り、大統領のとりまき連中がホワイトハウスへ流れこまないようにしていた噂話を、すっかり白状してしまった。
「よろしい。もう帰りたまえ。しかしきみは、明日逮捕だぞ」
ジェンシーはその晩、かつて自分のボスだった司法長官ドーハティと一緒に住んだことのある豪華な邸で、ピストル自殺をとげた。ドーハティは共和党のボスで、凡庸な男ハーディングを大統領にまで仕立てあげた裏の実力者である。
不吉な翳りが、大統領のまわりにしだいにその色を増していた。ハーディングはそれをふり払うようにして、六月になると六十五人の一行をひきつれ、アラスカへの演説旅行に出発する。途中カンザスシティーで、辞任したばかりの前内務長官フォール夫人がひそかに訪れ、約一時間大統領と密談をして帰った。なんの話だったのか、今もって明らかにされてはいない。旅行中、大統領はしだいに神経質になり、何かにおびやかされているような不安を隠しきれなかったという。二年半前の大統領選挙では、いつも微笑を絶やさず、ハンサムで気のいい男だったハーディングにしては、大変な変わりかただといえよう。
旅行の途中から、彼はブリッジやポーカーなどのゲームに溺れ、それから、信頼しているドーハティ司法長官を旅先に呼びつけ、二人だけで長時間会談したが、終わったとき大統領の顔は、怒りと怖れで土色になっていた。ドーハティはこそこそ姿を消し、二度と大統領に会うことはなかった。ハーディングがアラスカの帰途、サンフランシスコで心臓発作のため急死したからである。
ハーディングはそのとき五十八歳の働き盛りだったので、毒を仰いで自殺をしたのではないか、夫人が毒殺したのではないかという説もあるが、ともかくある種の強迫観念が彼の死を早めたことは事実であろう。
そして彼の死後、政府高官のおびただしい汚職は、上院調査委員会の手によってしだいに明らかとなった。
一朝有事の際に備えて海軍省が保有していた石油埋蔵地のうち、ワイオミングのティーポット・ドーム、カリフォルニアのエルク・ヒルズなどを、内務省の管轄に移す行政命令を大統領は出したが、大統領のお気に入りのフォール内務長官は、これを民間に入札もせずに払い下げて、当時の金額で二三万ドルと十万ドルのリベートを受け取っていたのである。
事件の決着がついたのはハーディングの死後実に八年目で、前内務長官フォールは収賄の罪で刑務所に送られた。無能だった海軍長官デンビイも、次の大統領クーリッジに解任されている。
復員局長官だったフォーブスも、悪どい金儲けをやっていた。病院の敷地を決定するたびに、高騰する地価へのりべートを受け取り、また膨大な量の医療品に「疵物」という印を押して、何分の一かの値段で特定の会社に払い下げた。このため、政府の損害はニ億ドルに上ったという。フォーブスは大統領の死後三年目に、詐欺罪で刑務所入りとなった。
ハーディングを操った陰の実力者ドーハティ司法長官は、どうやら罪はまぬかれたものの、政治生命はすっかり絶たれてしまった。つまり、大統領が好きで任命したような者、同郷オハイオ州出身者などの多くが、驚くほど平気で汚職をおかしていたのだ。
ヘイズ郵政長官は共和党全国委員会を代表して収賄していたし、ミーンズは禁酒法の時代に密売業者と手を組んで大儲けをし、のちに刑務所送りとなっている。
外国資産管理局長ミラーも刑務所に入り、その他有罪判決を受けた者、自殺した者、精神病院に送られた者など、さまざまである。
結局ハーディング大統領に人を見る目がまったくなかったことは間違いなく、ただ大統領自身がいくつかの汚職に自ら関係していたのかどうかという点になると、多分そうではなかろうとかいうことができない。
ハーディング夫人は遺体を解剖することを断固として拒否し、夫のあらゆる手紙や書類は、その大部分を故郷オハイオで焼却してしまった。
ド・アレンはハーディングを「ただ平凡な田舎者で、平均的な好色家」と書いているが、大統領は情婦のナン・プリトンを、ホワイトハウスの裏口からこっそりと呼び入れたりしていたのだ。彼女はずっと後に、二人のあいだに生れた娘をテーマにして、『大統領の娘』というスキャンダラスな本を書いている。
気に入った連中ばかりをホワイトハウスへ呼び、グラスを傾けながらいつもポーカー遊びをしていた大統領――といって非難するのは容易だが、実はそれが当時、全米を風靡していた保守的な傾向であった。結局国民は、自分たちと似たような政治家しかもつことができないのである。
コッペパン一個に行列した大恐慌 P.117
こんなことを、一体誰があらかじめ想像できただろうか。つい何ヶ月か前、就任したばかりのフーヴァー大統領が、アメリカから永久に貧困がなくなる日は近いと大見栄を切ったのに、国民全体が何年も灰色の日々を過ごさなければならなくなろうとは。
一九二〇年代、アメリカの物質的繁栄は頂点に達していたかのように見えた。自動車は普及して街に溢れるし、ラジオはどの家でも買うことができたし、映画という新しい映像のジャンルは人びとを惹きつけていた。大都市では摩天楼が次つぎに競争で建てられ、土地ブームがおこり、株式は高騰した。労働者の生活も眼にみえてよくなった。フーヴァーでなくても、この繁栄は永遠に続くと信じこんでいたのだ。
一九二九年十月二十四日、「暗黒の木曜日」とよばれるようになるこの日からの株式の大暴落を見ても、なお人びとは夢を捨てきれなかった。人びとが本当に心から恐れおののいたのは、翌年に入ってからである。
どの町にも、失業者が溢れた。恐慌のシンボルとなったリンゴ売りが街角に立つようになったのは、一九三〇年秋の頃からである。たとえ職がなくても、街角に立ってリンゴさえ売れば、一家が食べていける最小限度の収入があったのだ。リンゴ売りのなかには、つい先日まで工場の技師だった人や、株のブローカーをやっていた人、時にはなんと会社の社長までやった人がいたのだった。
後に「将軍ベッドに死す」を書いて、一躍有名な小説家になったチャールズ・イエール・ハリソンもまた、その頃のリンゴ売りをやっていた。彼の記録によれば、朝まだ暗いうちから起きて、リンゴ生産者連盟のビルの前に並び、一箱のリンゴを二ドル二五セントで買い求める。その箱をかついで地下鉄の入り口の方に歩いてゆき、一個五セントでそのリンゴを売るのだ。午後四時頃になると全部売り切れるが、一箱七十二個のうち四個ぐらいは悪くなっているのだ。その分は彼の夕食となり、売り上げは六十八個分の三ドル四〇セントである。そのうちから箱代の一〇セント、地下鉄の一〇セントを差し引くと、十二時間もの勤労の所得は九五セントだったという。
一九三〇年暮れには家のない失業者が激増したので、ニューヨーク市ではイースト川近くに仮宿泊所を急いで建てたが、「ゴールド・ドック」と皆によばれたこの建物で、暗澹とした日々を過ごしたある人は、二十年後に当時を回想して次のように書いている。
朝五時に鐘が鳴りました。まだ暗かったのですが、私たちは一列になっていやな臭いのするトウモロコシがゆの皿とコーヒーらしいものを貰い、そのあとリンゴ箱を買いにウェスト街に行って並んだものです」
ローズヴェルトが大統領に就任した一九三三年には、失業者が千五百万人にも増加して、職のある者も賃金カットをまぬがれることはできなかった。ニューヨーク市だけでも街頭の靴みがきで暮らしている者が七千人にも上ったという。ちょうどその頃、ソ連から熟練労働者六千人の求人申し込みあって、これに応募したアメリカ人はなんと十万人にもなった。ヨーロッパから希望を抱いてアメリカに渡った人びとが、争ってソ連へ職を求めて出かけようとは、一体誰が予想できたろうか。
ニューディ―ル政策によって景気は少しずつ上向いていくが、それでもなお、一九三〇年代のアメリカは、世界の多くの国がそうであったように、灰色のムードのなかにあったといっていい。とくに三〇年代前半の不況の深刻さは、革命がおこったとしても不思議ではないほど、人びとの心と生活を荒廃させた。事実三〇年代を通じて、アメリカ共産党の勢力は伸び続けた。三〇年代末には党員数六万をこえるほどになり、CIO(産業別労働組合会議)では組合員の約四分の一が、なんらかの形で共産主義者の影響を受けていたといわれている。それにもかかわらずアメリカでは、革命といわれるようなものはとうとう起こらなかったし、起こりそうな気配もなかった。一体それはなぜだろうか。
おそらくアメリカには、共産主義を異質のものとする強固な同質性があって、その同質性のなかで二大政党が交互に政権をとっているからであろう。共産主義自体がアメリカ化してこの同質性のなかに融けこまない限り、いつも異質性の存在としてはじき出されてしまうのである。
それではどうしてこの強い同質性が生れたのだろうか。
おそらくそれはアメリカが雑多な移民の国であるために、かえってアメリカの国旗と国歌に対する中心傾向が強いためであろう。移民が少しでもアメリカ人になりきろうとして払う努力は、そのままアメリカ社会の同質性を作る求心力となったのだ。封建制がアメリカになかったことも、社会主義や共産主義が育たない理由といえるだろう。
ともかくアメリカ人たちは、革命を起こさずにこの灰色の日々を耐え通した。しかしその心の底には、永久に消えない傷が深く残った。日本では第二次大戦を境に価値観が大きく変動し、戦前派、戦後派という言葉を生んだが、アメリカではこの大恐慌を経験した者とそうでない者の間に、越えられないほどのギャップを生んだのだ。
アメリカ史のなかで一つの分水嶺を探すと、それはこの大恐慌だと答える学者が少なくないのである。
東部の都市に住む労働者と、南部や西部の農民とを比較
2025.03.31 記す
狂気の赤狩り旋風 P.123
「皆さん、私の意見では、もっとも重要な政府の機関である国務省に、共産主義者が広くはびこっています。
私は今この手のなかに、いつも共産党の党員証を身につけているか、共産党に間違いなく忠誠を誓っている人びと、二百五人もの名前を持っています。しかもそういう人たちが、今でもなおわが国の外交政策を作成する手助けをしているのであります。
われわれの政府のなかにいる共産党員について議論するときに、記憶しておかなければならないことが一つあります。それはわれわれが、新しい兵器の青写真を盗んで銀三十片を手に入れるだけのスパイに直面しているのではない、ということなのです。
われわれは、それより遥かに危険な活動に直面させられています。なぜなら、敵がわが政策を動かし、作成するのを許すことになっているからです」
一九五〇年二月に共和党の上院議員ジョゼフ・マッカ―シーは、ウェストヴァジニアでこういうショッキングな演説を行った。辺鄙な場所だったせいもあって、初めはそれほど注意を引かなかったが、二度三度と彼が他の場所で同じ演説をくり返すと、それはたちまち爆発的な反響を全米にまき起こした・
国務省といえば、日本の外務省プラス・アルファであり、副大統領よりもむしろ国務長官の方が、大統領に次ぐ第二の実力者なのである。その国務省のなかに共産党員が大勢いて、その名前はいま私の手のなかにある、といって紙片をひらひらさせながら、上院議員が叫んだのだから、世論がそのため沸騰したのも無理はない。
マッカーシーがこういう形で歴史の表面に姿を現し、たとえ数年間でもいまわしいマッカーシズムの時代を作り上げるようになつたのは、まさしく舞台が彼の登場を待つのにふさわしい状態になっていたからである。
アメリカは一九四五年に第二次大戦を終わったとき、全体主義打ち負かしたと思ったとたんに、今度は共産主義という新たな敵に直面した。まだ戦勝気分に酔っていた四六年に、イギリスのチャーチルはもうアメリカで「鉄のカーテン」の演説を行っている。
四七年には一方でヨーロッパの経済復興を援助しながら、トルーマン大統領は政府職員に忠誠審査を実施した。映画の都ハリウッドでは赤狩りが始まり、ロバート・テイラーその他の俳優は喜んで下院の非米活動調査委員会に出席、多くの証言を行なったため、十人の映画人が検挙されている
四八年には、もと国務省の政治局長で、当時カーネギー国際平和団の会長だったアルジャー・ヒスが、かつて共産党員だったことがあり、今はソ連に情報を流しているスパイだとして告発された。このとききびしくヒスを追究し、反共の闘士として名をあげたのが、当時まだ三十五歳の下院議員だったリチャード・ニクソンである。
四九年には、アメリカが戦争中支援し続けた中国に、共産主義を奉じる中華人民共和国が成立してアメリカ人を愕然とさせ、さらにソ連の原爆所有が明らかとなって、科学上の秘密を渡したという容疑でローゼンバーグ夫妻の裁判が始まり、のちに夫妻とも死刑となった。
共産主義に対する危機感がこうしてまさに爆発しそうになっていたときに、それに点火したのが他ならぬマッカーシー上院議員だったのである。マッカーシーの議論は、しだいに膨張した。
ローズヴェルトとトルーマンの二十年にわたる民主党の期間は、アメリカ国家に対する反逆の時代であり、だからこそローズヴェルトは第二次大戦でソ連を助け、トルーマンはマッカーサー将軍が共産中国を攻撃するのをやめさせてしまった、というのだった。
共産主義者のスパイが政府部内や大学、会社などにひそんでいて、モスクワでスターリンがボタン一つ押せば、彼らはいっせいに立ち上がってアメリカを倒すだろうというような妄想が、マッカーシーの巧みな扇動によって全米を風靡した。
一九五一年までにトルーマンは、国家に忠誠を尽くさないと思われる分子千二百人あまりを政府から追放したが、こういう風潮にいや気がさして辞任した者は二千にも上った。共産主義に対するこの国をあげてのヒステリー症状は、アメリカにとってこれが最初ではなかった。第一次大戦直後にも、まったく同じような症状が起っている。
ロシアでボルシェビキ革命が成功したり、一九一九に年アメリカでストが三千回以上も起こったりして、国民の間に「赤」への恐怖が高まると、パーマー司法長官は一九二〇年の初めから赤狩りを開始し、逮捕者は数千人に及んだ。その年四月に病後初めて開いた閣議の席上でウィルソン大統領は、
「パーマー、アメリカのなかの赤を一掃せよ」
と叫んだという。
このとき逮捕された者の多くは無実だったが、おかげでパーマーは一時国民的英雄となった。メーデーには政府転覆の計画があるといって州兵や警察を動員したものの、実際にはその日一発の銃声も響かず、パーマーの作った赤の恐怖はすぐ底がわれてしまった。
しかしマッカーシーの場合には、それが数年間続いたのだ。学者も、ジャーナリストも、批判をまったく封じられてしまった。国外追放になった人もすくなくない。
だが、さしものマッカーシーも、五四年にはその勢力を失った。いま人びとは歴史の一ページに彼の名を残し、彼一人だけを悪質な扇動者としてすましているが、言論の自由さえ封じる恐怖の赤狩りの時代を作ったのは、ひとり彼だけだったのだろうか。彼はただ、時代の風潮を悪用しただけの人間ではなかっただろうか。二回も同じような現象が起こっているのをみると、共産主義に対する常軌を逸したヒステリー症は、アメリカ国民の一つの性格となったのではないだろうか。
だからこそマッカーシー自身は没落しても、その系譜は同じ共和党のゴールドウォーターに受け継がれ、アメリカの底流となって、国際緊張の一方の土台を作っているのである。
マッカーシーによる赤狩りの旋風が吹き荒れていた一
2025.04.04 記す
大統領暗殺は歴史を変えたか P.129
一九六三年、日米衛星中継の最初のニュースが、「ケネディ大統領凶弾に倒れる」だったのは、一体なんということだろうか。ケネディ大統領は十一月二十二日金曜日の朝、ダラスでこういった。
「アメリカの大統領を暗殺したいと思う者がいたら、それはたいして難しいことではない。望遠レンズのある銃をもって、高いビルの上で待っていればいいのだ」
これは、大衆の面前に無防備なまま姿を現さなければならないアメリカ大統領の、避けることのできない運命なのであろうか。
思えばリンカーンが暗殺されたのも、イースターの聖金曜日である。このことから、二人の暗殺にはあまりにも歴史的な符合が多すぎるといって、今なお人びとの間でつきることのない話題になっている。まず二人とも、夫人同伴の上、公衆の面前で殺された。リンカーンはフォード劇場の観衆のなかで、ケネディはダラス市民の見ている前で――。二人を殺した犯人らしい人物は、いずれも裁判にかけられずに殺された。リンカーンを暗殺した南部人の俳優ジョン・プ―スは、十ニ日後タバコ小屋に隠れているところを、騎兵隊に包囲され、ケネディを暗殺したオズワルドは、二日後警官にかこまれて護送される途中、ごく近くまできたルビーという男にピストルで殺された。
リンカーンは一八六〇年の大統領選挙に当選し、ケネディはちょうど一世紀後の一九六〇年に当選している。リンカーンのあとを継いだのはアンドルー・ジョンソン副大統領で、ケネディの場合はリンドン・ジョンソン副大統――。リンカーンにはケネディという名の秘書がいて、大統領がフォード劇場へ行くのをとめたという。一方ケネディにはリンカーンという秘書がいて、大統領がダグラスへ行くことに大きな不安を抱いていた。
これらの不可思議な符合は、一層この二つの暗殺事件の上に神秘な翳を落としている。たとえばリンカーンを暗殺し、国務長官シュワードに重傷を負わせた暗殺団の一味四人は処刑されたが、その背後で糸を引いていたのは、当時の陸軍長官スタントンではなかったかというような推測が、今なお思い出したように議論されているのだ。
ケネディの事件については、今さらいうまでもない。六四年に発表されたウォーレン調査委員会の膨大な報告書を政府は公式の結論とし、それ以後調査を行なっていないが、オズワルドの単独犯罪とするこの結論に挑戦して、どれだけ多くの本や論文が今まで書かれたことだろうか。
映画「ダラスの熱い日」も、その疑惑を具体化して、テキサスの資本家や右翼などのグループが、慎重におしすすめた謀殺だという結論を出している。
それにしても、アメリカの歴史の前半に暗殺された大統領が一人もいないことは、暗示的である。独立してまもない頃のアメリカでは、大統領の安全についてはほとんど注意が払われなかったし、それで事実何もおこらなかったのである。三代目の大統領ジェファソンなどは、一八〇一年の就任式当日、自分の宿舎から国会議事堂まで、一人の護衛もつれずに歩いていったという。
一九七五年大統領フォードが二度も凶弾に見舞われかかったことは記憶に新しい。アメリカ史上、現職で暗殺されたのは四人になるが、すべてリンカーン以後の時代である。つまり時代が下がるにつれて、暗殺およびその未遂事件が増大している。それだけアメリカ社会の歪が大きくなったともいえるだろうが、果たしてこれらの暗殺は、多少なりともアメリカのコースを変えたであろうか。多くの歴史家はそれを認めたがらない。民主主義を土台とした国家の構造さえ揺るぎないものならば、暗殺は歴史を変えることはできないのだ、と。
しかし、果たしてそうだっただろうか。たしかにいくつかの暗殺が民主主義という政体そのものを変えることはできなかったが、実際には歴史のムードを大きく変える働きをしたのではなかろうか。
リンカーンが暗殺されたとき、彼は再選されて二度目の就任式を行ったばかりで、任期はまだ三年十一ヵ月も残っていた。平凡な南部人ジョンソンがそのあとを継がず、リンカーンが引き続き政権を担当していたならば、戦後の南部はあれほど混乱せず、南北の和解ももっと早い時期に行われいただろう。人種問題もおそらくゆるやかなテンポながら、別の解決方法を見いだしていたに違いない。リンカーンの暗殺は、単に彼の残された任期の間だけにとどまらず、少なくともその後十年間の国家の進路を変えてしまつたかもしれないのである。
マッキンレーが暗殺されず、内政外交に精力的なエネルギ-を発散したセオドア・ローズヴェルトが大統領に昇格していなかったら、二十世紀初めの歴史はもっと平坦な別のものとなり、あるいはウィルソンの登場を促すような舞台も作らなかったであろう。
フランクリン・ローズヴェルトは、大統領に当選してまだ就任しない期間に、マイアミで凶漢に襲われた。五発も発射された弾丸のうち、一発でも彼にあたってその生命を絶っていたら、あの壮大なニューディール政策を、一体誰が代って遂行できただろうか。おそらく彼の暗殺は、アメリカ全体に、巨大な灰色の翳を落としたに違いない。
また一九六〇年の大統領選挙では、一般投票わずか〇.ニ%の差でケネディがニクソンに辛勝した。ほとんど、同点といってもよかった。にもかかわらず、いったんケネディが大統領に就任すると、時代の流れは鮮やかに変わり、ケネディの時代とよばれる、活気に満ちた独特の時代が現出する。
結局、大統領は国家全体の顔であり、その時代をリードする一種のムードを創り出すのだ。そのことを考えると、ケネディが突然この世から姿を消してしまったことが、その後の歴史を変えなかったと、果たして断言することができるだろうか。
一九六〇年代には、ジョン・F.・ケネディ大統領のほか、弟のロバート・ケネディ上院議員、黒人指導者のマーチン・L・キング牧師とマルコムXなどが暗殺されている。リベラルからラディカルに属するこれら四人が今なお健在だったら、アメリカ全体の雰囲気はもっと明るいものだったろうと考えると、改めて暗殺のもつ意味の重大さに、誰しも愕然とするのではないだろうか。
七代目の大統領ジャクソンは政敵が多かったせいか、
原爆投下を肯定する国民世論 P.135
第二次大戦の終結まぎわ、ハワイには南太平洋方面の日本人捕虜が集っていた。日本に生れた同志社大学教授のオーディス・ケーリ氏は、当時その収容所長となり、戦時下としては考えられないほど友好的に、その収容所を運営していた。
ケーリ氏は原子爆弾が広島に落とされたことを知ったときの日本人捕虜たちの様子を、次のように書いている。
彼(捕虜の一人)は体をふるわせて、それだけを叫び続けた。誰しも気持ちは同じだった。もう参
りかけている日本に、これほどの異常武器が必要だろうか。しかも、落とされた所は、どんなに武装
していようと、一般市民が密集して住んでいる都市である。降伏を早めるにしても、余りに犠牲が
大きすぎるのではないかというのである」
おそらくこれは、当時の日本人の平均的な気持ちであったろう。
ところがアメリカには、かなり広く原爆投下を認める国民感情がある。と同時にケーリ氏は、良心
的なディーンという中尉がこれを聞いて、「頭をかかえたまま、タイプライターの陰に顔を埋めてし
まった」とも書いている。ケーリ氏自身もそうだったに違いない。
「戦争の真最中にねえ。よくもこれだけのことがいえるよ。新聞もよく載せたよ。日本では考えら
れないことだ」
〔捕虜の一人の}幡さんがしきりと感心した」
つまりアメリカには、たとえ戦争中でもこのような爆弾を投下することに反対する世論も少なくないのだ。それでは一体、この前者と後者の数の比率は、どの位になっているのだろうか。それは世論調査という形で、およその傾向を知ることができる。
朝日新聞社が一九七一年に、アメリカのルイス・ハリス世論調査所に依頼して行った調査のなかは、次のような項目が入っている。
「アメリカが第二次大戦中に日本に原子爆弾を投下したのは、やむをえないことだと思いますか。間違いだと思いますか」
これに対する回答は、
やむをえなかった 64%
間違いだった 21%
わからない 15%
つまりアメリカ国民の三分のニは、原爆投下を肯定しているのである。
この世論調査の一年前に、私はアメリカ南部のある大学で、「私のみる歴代大統領の評価」という話をしたところ、早速次のような質問を受けた。
「あなたはAクラスおよびBクラスのどちらにも、トルーマンをいれなかった。それはなぜですか」
私はトルーマンが大統領の平均よりは上であることを認めたあとで、あえて取り上げなかったいくつかの理由をあげて、さらにつけ加えて、
「それに彼は、原爆投下を命じた世界でたった一人の人間ですからね」
というと、この発言には不満な様子をした学生が少なからずいたのである。
今でも広島と長崎への原爆投下を肯定しているアメリカ人たちの平均的な考え方は、一つには真珠湾奇襲への当然の報復。二つには戦争終結が長引いた場合に、増加したと思われるアメリカ兵の損害を未然に防いだ効果、などである。
それにまた、プラス・アルファが加わることもある。私の友人で、黒人の文学者として著名なジョン・O・キリンズ氏は、くり返し私にいったものだ。
「なぜ原爆をドイツに落とさないで、日本に落としたのか、それも一回で威力は十分示せたのに、わざわざ二回落としたのか」
第一の疑問に対しては、ドイツの降伏までに原爆が間に合わなかったのだ、と答えることもできるだろう。しかし第二の疑問に対して、私は答えるすべを知らない。アメリカ国内でさんざん人種差別の苦しみをなめてきたキリンズ氏は、日本人に対するアメリカ人の差別感情をいいたいのである。
ベトナム戦争のとき、現地にあってアメリカ軍全体を指揮したウェストモーランド将軍は、はっきりとこうのべている。
「東洋人は、西洋人のようには命を重くみないのだよ。東洋では、命はあり余っていて安いのだ」
こういう考えをとりやすいのは、年齢の高い層、軍人、右寄りタカ派の政治家などである。力をもって相手をねじ伏せなければならないと考えるようなタイプの政治家が、結構有力な大統領候補にまでなるのだ。六四年共和党のゴールドウォーター、六八年民主党から飛び出して第三党を作ったウォレス、それに七六年の共和党のレーガンなど……。
一九七二年、私はコロラド大学に滞在中、「ナガサキの日」に行われたベトナム反戦のキャンドル・マーチに参加した。ところkがそれから四日後、『ボウルダー・デイリー・カメラ』紙の論説欄に、ヒロシマ、ナガサキ、二十世紀のソドムとゴモラか』というタイトルを発見して、思わずぎょつとなった。
ソドムの綴りが間違っているのは御愛嬌だが、長い論説を書いたその女性はかなりの日本通だった。ヒロシマもナガサキも、ちょうど旧約聖書創世期に出てくる悪徳の都市、ソドムとゴモラのように、神の怒りにふれて、住民もろとも焼き払われたのではないか、というのである。
ロシマへの原爆投下をアウシュヴィッツの業と同じだと考え
て、勝手に心のなかで、日本人を自分のアンネ・フランク神
話だとしてしまっているのではないだろうか。……
もしヒロシマのことを思い出せといわれたら、私たちは真
珠湾のことを思い出そうではないか。ナガサキの日を記念し
ようといわれたら、あの拷問のようなパターン死の行進のな
かで、鞭うたれ、血を流し、渇きに苦しみながら死んでいっ
たアメリカ兵士たちのことを、思い出そうではないか。……」
人びとの心のなかで、まだ戦後は十分に終わっていない。今や日米間に重大な問題はない、などという安易な考え方はつつしもう、と私はその時考えた。
女の「美徳」が揺れつづけた半世紀 P.141
一九七五年の秋ワシントン郊外で、ある父親から面白い話を聞いた。
「驚きましたね。娘が大学へ入学したら、大学ではなんと、ピルの使用法を書いたパンフレットを学生に渡し、ピルが必要ならいつでも取りにきなさい、というんですよ」
中年のその父親は、本当に心の底から驚いている様子だった。わずか、ニ、三十年の間に、父親がついていけないほど、女性の方が先に進んでしまったのである。
考えてみれば、過去数千年間、人間は妊娠しないですむ性交の可能性を追究してきたといえる。だからピルの発見によって人間は、とくに女性は、どれほど解放されたか分からないのである。参政権を獲得したことよりも、ピルを自由に使えるようになったことの方が、女性解放の上でははるかに重要な意味をもっていた、と説く学者も少なくない。
こんなわけだから、アメリカでも女性が昔から自由だったわけではない。それどころか、少し時代を遡ると、アメリカの女性も比較的最近まで、意外に古風だったことが分るのである。性の問題を追究したⅤ・パッカードは、過去百年間におこった女性の役割の変化が、それ以前の五十年の変化よりも大きなものだったと、指摘している。
たとえばアメリカでも、女性が参政権を得たのは、やっと第一次大戦後の一九二〇年にすぎない。しかも南北戦争の時まで奴隷だった黒人が、解放された直後の一八七〇年に参政権(ただし男性だけ)を与えられているのに、奴隷解放のために戦ってきた女性が、その後半世紀も参政権を与えられずにいたことは、男性の女性に対する偏見が無意識的にいかに大きいものだったかを物語っている。
いまから百年前の女性は、黒いドレスで全身をくまなく被っていた。男性は女性の顔と手が、わずかにドレスの外に出ているのを見ることができただけである。女性は家のなかにあって夫に尽くすのが美徳とされ、職業をもっている者の数はまだ極めて少なかった。キリスト教がこういう女性の美徳を説く役割を果たしたことはいうまでもない。
その女性が急速に変わったのは、一九二〇年代である。女性は参政権を獲得してから、急に大勢が政治家になったりはしなかったが、まず若い女性たちから、古い生活様式や価値観を放棄したのだ。おそらく、参政権の獲得は、長い間参政権が拒否されていたためにタブーとされていた多くのものの、崩壊の象徴にすぎなかったのである。そして女性たちは、取り払われたタブーのなかから、政治などの問題よりも、身近な日常生活の解放にまずとびついたのである。
たとえば、それまで地面をひきずるように長かったスカートが、一挙に膝のあたりまで短くなり、黒い木綿の靴下が、肌色の絹やレーヨンの靴下に変わった。長い髪を切って断髪とし、パーマネント・ウエーヴが流行した。
それまで不道徳の象徴のように思われていた頬紅や口紅が、あっというまに全米にひろまった。タバコをのむ女性が増えたし、禁酒法の時代だったが、女性は男性と一緒に酒を飲むようになり、セックスについても自由に話しあうようになった。
しかし三〇年代に入ると、女性たちはそんな余裕がなくなってきた。かつてなかった大恐慌に見舞われ、夫の就職の心配の方がもっと切実なのものとなったからだ。女性も毎日の生活に追われ、ニ〇年代のように時代の先端をきるフラッパーな娘はいなくなった。
四〇年代には、女性がいっせいに男性の職場に進出した。女性の自我意識や平等への要求が高まったというよりは、第二次大戦のため働き手が軍隊にとられて、労働力が不足してきたからだった。
そのため、五〇年代のマッカーシズムが荒れ狂った保守的な時代には、また女性が家庭に戻って家事に精出すことが美徳とされたのである。それは変測的だった四〇年代への、一種の反動のようなものであり、多くの女性もまた、マイホームを守ることだけに満足を見いだしていた。
再び大きな変動が襲ってきたのは、ケネディの登場に始まる六〇年代だった。このとき女性たちは、黒人たちの公民権運動やベトナム反戦運動、大学の反乱、公害反対運動などに積極的に参加しながら、社会の矛盾を見抜く力を養い、改めて男女間の格差の大きさに気がついたのだ。
同一の労働に対しては、男性と同一の賃金を、というきわめて理論的な要求がまず高まった。新しい女性解放の先駆者となったペティ・フリーダンは、一九六三年に『新しい女性の創造』を出版し、六六年には女性解放組織の中心となった「全米女性連盟」(NOW)を創立する。
女性の権利の平等は、こうして今少しずつ実現されている。「……となった最初の女性」という表現が新聞などで盛んに使われるようになった。「アメリカ史上で国務省の局長となった最初の女性」とか、「海軍が受けいれた最初の女性パイロット」といった具合であり、これは今まで女性がいかに広範な職場から閉め出されていたかを物語っている。
一般社会の空気も、女性の平等を理性的に迎えいれようとしている。「もし支持する政党が女性を大統領候補に選んだら、あなたは彼女に投票しますか」というギャラップ世論調査に、一九三七年にはイエスと答えた者が三一%しかいなかった。しかし五五年には五一%になり、七一年には六六%にまで増えている。
今まで男性だけのものだった職場にも、女性がどっと入りこんでいる。土木建築、自動車修理、バス・トラックの運転手、警官、消防士……数えていけば、きりがないほどだ。しかし、それに伴って、それまで女性に与えられていた特別の保護もまたなくなっている。たとえば、働く女性には重い物を持たせてはいけないという重量制限、深夜勤務など……。
一九七五年ニューヨークのホテルで、エレベーターに男が平気で先に入っていくのを何度も見た。バスのなかでも、女性が立っていて、男性が平気で座っている。レディーファストの国では、初めて見る珍しい光景であった。
聞いてみると、これは女性が平等の権利を主張すると同時に、女性であるがために持っていた甘えを、自ら放棄した結果であるという。ウーマンリヴも、ここまで進んできたのである。
ミシシッピに散った三人の若者 P.147
南部の公民権運動がしだいに高まって、三十万人もの人びとがワシントン大行進に集まった時から九カ月、ケネディ大統領が南部のテキサス州ダグラスで凶弾に倒れてから六カ月がたって、一九六四年五月、北部のオハイオ州オックスフォードにあるウェスタン女子大学に、続々と大勢の若者たちが集まり始めた。
その多くは北部や西部の大学生で、ちょうど長い夏の休みに入るところだった。安楽に暮らせるはずのその休みを、彼らは学生運動非暴力連帯委員会(SNCC)と人種平等会議(CORE)という二つの公民権団体の呼びかけに応じ、場合によっては生命を賭けるほど危険なひと夏の運動に、自らとびこんできたのである。
このとき計画された「ミシシッピ夏期自由計画」は、参加者がミシシッピ州の黒人の家に分宿し、黒人たちに選挙の登録を促進させ、南部の政治を根本から一変させようと狙ったものである。
アメリカでは日本と違って、成年に達した者が自動的に選挙権を与えられるという仕組みになっていない。選挙ごとに登録してパスしなければ、投票することはできないのだ。しかもこの登録は各州ごとに違っていて、南部ではどこでも黒人に対してとくに厳しく、実質的には投票を制限しているのに等しかった。
人種問題で最悪といわれるミシシッピでは、当時人口の四二%が黒人だったのに、実際に登録をすませた黒人はその七%にしかすぎず、黒人の意志は政治にまったく反映されていなかったといってよい。
ウエスタン女子大学に集まった約千人の若者たちは、過半数が白人で、女性も大勢含まれていた。学生ボランティアたちはここで二週間の特訓を受け、やがてミシシッピ各地に散っていった。当然、保守的な白人層からの抵抗が予想されたが、果たして被害は日常茶飯事のように発生した。黒人の教会が次々と焼き打ちされたり、すれ違いざまに殴打されたり、なかには発砲されて、負傷する者も出てくる有り様だった。
そのうち六月二十一日になって、シュワ―ナ――とグッドマンという二人の白人と、チャーニーという黒人が行方不明になった。この知らせは、参加者たちの間に恐ろしい衝撃となって伝わった。その三人は、数日前焼き打ちにあったネショバ郡にある黒人教会を調べるため、ステーションワゴンにのって出発したのだという。
現場で彼らは一人の黒人信者が火事の晩、大勢の白人暴徒に気の遠くなるほど殴打されたという話を聞いている。帰途、三人は、セシル・プライスという保安官捕にスピード違反で逮捕され、罰金二〇ドルを払って釈放されたときは、もう午後十時を過ぎていた。それから帰途を急いだはずなのだが、三人とも二度と友人の前にその姿を現さなかった。
ほかの参加者たちは、すぐに事態の重大性を悟った。このミシシッピという州は、その時から十年前に連邦最高裁が公立学校での白黒共学判決を下したとき、州選出の有力な上院議員イースト・モーランドが、その判決に反対の声明を堂々と出したようなところである。上は州知事から下は警官まで、ほとんどが人種の純血を叫ぶ白人至上主義者ばかりだったといってもよい。警官は黒人に対する暴力には目をつぶり、黒人のデモを押えることにばかり注意を向けていた。
ここでは法律さえも黒人にとって保護の役割を果たさず、反対に迫害の手段として使われている有り様だったのである。
この恐怖に満ちた特殊な環境を、そこへ身をおかずに理解することは難しい。しかしそれが、南北戦争後一世紀も後進地帯といわれてきた深い南部の実態であった。映画「イージー・ライダー」を観た人は、なぜ主人公たちが最後で突然無残に殺されるのか、理解に苦しんだに違いない。
三人の若者のうち、シュワ―ナ―はニューヨークに住むCOREの会員で、夫人も黒人のためのコミュニティ・センターを作るため、一緒にこのミシシッピで働いていた。グッドマンも、ニューヨークの大学の二年生で、この二人とも、ミシシッピのメリディアンに住むチャーニーという黒人の若者と一緒になって、仕事を進めていた最中のことであった。
三人の捜索について、現地の警察があまりにも非協力的なので、激怒したロバート・ケネディ司法長官は、FBIに緊急捜査を命令する。三人の死体が発見されたのは、それから六週間も後のことで、ある農場の土手の土のなかに、深く埋められていたのである。容疑者がいもづる式に十数人もあがったが、そのなかにはなんとプライス保安官捕もはいっていたのだ。しかし後になって、全員証拠不十分のために釈放されてしまった。
三カ月以上にわたって行われた「自由への夏」の犠牲は、この死者のほか、負傷者三人、発砲を受けた回数三十五回、殴打された者八十人、逮捕された者は延べ一千人、教会の焼き打ち三十五件、家屋爆破三十件という凄まじさだった――。
これに反して、投票権拡大という効果の方は、すぐ目に見えて現れなかった。しかしこの一夏の衝撃的な体験は、予期しなかった方向に向って、大きな波紋の輪を広げはじめるのである。
この運動に参加したマリオ・サピオたちは、夏が終わってカリフォルニア大学バークレー校舎に戻り、公民権運動を体験して得た思想や戦術を、フリー・スピーチ・ムーブメントに結実させ、全米に先がけて学生反乱の火の手を上げたのだ。
翌六十五年、ジョンソン大統領がベトナム戦争への本格的介入を始めると、早速、大規模な反戦運動を展開した若者たちの多くも、それ以前に公民権運動へ参加し、そこから社会の矛盾や不公正に対する目を開かれていったのである。
ウーマンリブ運動でさえも、この例外ではなかった。六十年代前半の公民権運動に加わった女性たちは、そこから学びとったものを、リブ運動のなかに展開させたのだった。
南部も、徐々に変わり始めていた。六四年に二百十六万にすぎなかった南部の黒人投票数が、『ニューヨーク・タイムズ』紙の推定では、七六年の大統領選挙で約四百万に倍増している。こうなると、もはや南部のどの地域でも、黒人の存在を無視することはできない。黒人はこの十数年間に、「見えない人」から「見える人」へ大きく変貌したのだ。
そして、この一九六四年には、同じ深南部のジミー・カーターという政治家が、州上院議員再選のために、全力をあげて戦っていた。
ニューサウスはアメリカを救えるか P.153
「私は皆さんにはっきり申し上げたい。人種差別の時代はもう終わったのだ、と」
一九七一年一月、深南部ジョージア州都アトランタで、新しい知事ジミー・カーターは、就任式の演壇に立ってこう語りかけた。
これは彼の就任演説のなかで、もっとも人々を驚かせた部分である。というのは、前年に行われた予備選挙のとき、カーターは同じ民主党の有力な対抗馬、元知事のカール・サンダーズがリベラル派寄りの印象の強かったのに対して、かなり保守的なイメージを与えていたからである。
事実、その選挙で、カーターは労働者やホワイトカラーの保守的な票を獲得し、黒人票は僅か五%にすぎなかったのだ。
その二年前、六八年の大統領選挙で、隣のアラバマ州から第三政党候補として名乗りをあげた人種差別主義者ジョージ・ウォレスは、ジョージアで悠々と勝利をおさめたが、今度はその票をごっそりと、州知事候補のカーターが手に入れたのである。
それはちょうど、一世紀前にリンカーンがとった戦術に似ていた。リンカーンは、奴隷解放をスローガンに掲げると大統領選挙に勝てないことを知っていたので、まず勝つためには妥協を重ね、奴隷解放などを公約にしないで当選した。しかし就任してから、自分が長年考えていたその理想を実現させたのである。
カーターのこの就任演説を聞いて、ちょっと怒ったのは、おそらく横に控えていた副知事レスター・マドックスだろう。マドックスはその前日まで知事だった人で、州憲法が再選を認めないため、今度は副知事に打って出て当選した。カーター知事のもとで一期副知事をつとめ、四年後にはまた知事に帰り咲こうという魂胆である。
マドックスが一躍米にその名を知られるようになったのは、一九六四年七月、ジョンソン大統領が公民権法にサインした直後のことだった。アトランタンのダウンタウンで、黒人を絶対に受けいれなかった「ピグリック」レストランの経営者マドックスも、この公民権法が成立した以上、黒人を客として迎えなければならないことになった。早速三人の黒人学生が、テストケースの一つとして「ピックリック」に乗りつけた。何事かが起こることを期待していたテレビ、ラジオ、新聞などの記者の前へ、この時マドックスはピストルを片手にして現れたのだ。息子のジュニアが、斧を持ってついてきた。
マドックスは、黒人たちにピストルをつきつけて叫んだ。
「すぐに帰れ、もう二度と来るな」
彼の姿は、その夜のうちに電波にのって全米に広まった。そして驚いたことに、彼はこの事件でたちまち数多くの支持者を獲得し、「ピックリック」は今まで以上に繁昌した。
もちろん、黒人たちも負けてはいない。彼を公民権法違反で訴えたのだ。マドックスは対抗して記者会見を行い、そのテープをレコードにして売り出すという意気ごみだった。
しかし、いうまでもないことだが、法廷で彼は敗れた。罰金その他で一〇万ドルという損害であった。彼には支払う能力がなく、ととうレストランを閉じて売り払わなければならなかった。
ところが、運命は意外な方向に展開する。それまで何度かアトランタン市長選に出て勝てなかったマドックスに、この事件いらい同情が高まり、二年後の六六年に、彼は知事選で難航のすえ再選するのだ。カーターはこの時、民主党の予備選第三位で惜敗している。
その時から、マドクスの名は全米に知られ、舞台でさえ上演された。右寄りのタカ派で、人種差別主義者というレッテルを貼られて……。北部のインテリから見たマドックスは、まさに時代遅れの道化者であった。同じ右寄りのタカ派でも、アリゾナの有名な共和党上院議員ゴールドウォーターは、当時テレビでこういったものだ。
「ジョ―ジアは南部で一番進歩的な州だったが、まったく突然、石器時代の人間が現れたんだね」
しかしそれでもなお、今から十年前の一九六六年にはジョージア州民が彼を選んだのである。彼や彼を尊敬する隣の州のアラバマのヴォレスは、やはり保守的な南部人の偶像であった。
私がアトランタンで暮らしている時、マドックス知事は、全米的な反戦の日にあたり、反戦運動に反対の声明を出して、自分と同意見の者は日中ライトをつけたまま車を走らせてくれ、とよびかけたほどである。
しかし……その間にも、時代は確実に変わりはじめていたのだ。ここに興味深い数字がある。ギャラップの世論調査によれば、南部の人の間でも、かなり急速な意識変化が行われていた。
「黒人が少しいる学校へ子供を通わせますか」という質問に対して、一九六三年には、六一%が反対していたのに、七〇年には反対が僅か一六%に減少している。北部の白人の反対は、六三年の一〇%から七〇年の六%に減少している程度で、南部白人の意識がかなり急速に北部のそれに接近してきたといえる。
事実七〇年に当選した南部の新しい知事のなかには、ウォレスやマドックスのような、扇動的タイプの政治家ではなくて、対話を基調にする穏健派が、フロリダのアスキュー、ヴァジニアのホルトンなどをはじめ、かなり登場している。
カーターを含めてこういう政治家たちは、みなニューサウスの先駆者として評価された。こういう人びとと比較すると、たしかにマドックスやウォレンスは急に古めかしい陰影を帯びてくるのだ。
「人種差別の時代はもう終わった」と叫んだカーター知事は、四年間亡霊のようにつきまとうマドックス副知事に悩まれたはしたが、州政府の黒人職員を一・五倍にしたり、州庁舎に初めて黒人の肖像画を掲げたりした。それはアトランタンを基盤に公民権運動を続けた故キング博士のものであった。
「オレがまた知事になったら、あんな肖像はすぐに引き下ろしてやる」
マドックスは部屋の隅でそうつぶやいただけで、七四年の知事選で大敗した。一九七六年の大統領選挙でもウォレスの後を継いで立候補したが、もうまったくの泡沫候補にすぎず、いま彼は急速に過去の人となり始めた。カーターがアメリカ全体の次代をになう人としてその後脚光を浴びたのと較べると、なんというあざやかなコンストラストであろう。
さてカーター大統領が、南北戦争で敗れて以来、貧しい後進地帯で、屈折した劣等感をもつ深南部の出身であったことは、その時のアメリカにとって大きな意味をもっていた。
アメリカは六〇年代にベトナム戦争という建国いらいの最大の過失をおかし、七〇年代にはウォーターゲート事件という醜悪な体験をもった。その他にもインフレや失業の増加、犯罪の増加など、いまアメリカ人の心のなかに、挫折感は深淵のように横たわっている。
この深く病んだアメリカの傷跡を癒すために深南部の大統領が登場したのは、実にふさわしい選択だったといえるだろう。
たとえば、選挙戦を通じて、彼はたびたびコンパッションという言葉を使っている。いたわりとか、同情とかいった意味であり、これはアメリカのなかで唯一の敗戦経験地域に生れ育った南部人だからこそ、出てくる発想ではないか。「ベトナム戦争の忌避者には、すべて恩赦を与えます」ともカーターはいった。これもまた、彼のいうコンパションの政治の現われであろう。
私は二十年後、三十年後のアメリカが、今のように軍事や経済の大国であるばかりでなく、二十一世紀の人間の新しい価値観を追究して、文化的な指導国家になるだろうと信じている。たとえばアメリカはベトナム戦争のとき、自国の戦争に堂々と世論が反対した世界史上最初の国となったのだ。
人間も国家も、挫折を経験することによって成熟する。カーター大統領が果たした役割は、アメリカが成熟して大人になった時代の第一ページとして記録されることになるだろう。
2025.05.01 記す
人間の平等と差別
インディアン娘の烈しい恋 P.161
何度かの植民に失敗したあと、イギリス人がやっと新大陸の一角ヴァジニアに永続的な植民の根拠地ジェームズタウンを作りはじめたとき、彼らにとって色恋の沙汰など問題ではなかった。生きていくだけの食糧を手にいれられるかどうかということだけが、当面するすべての問題だった。最初の入植者ジョージ・パーシーの残した次の記録は、そのさし迫った事情をよく説明している。
食べ物はごくわずかで、それも水にふやけてしまい、一日五人の人間を養える程度だった。飲みものは川から汲んだ水で、水位の高いときは塩からく、水位の低いときはよごれが多くて、仲間のうち大勢がそれでられた。こうしてわれわれは、一六〇七年八月から一六〇八年一月まで、五カ月間を悲惨な状態で暮らしたのだ」
こういう窮状を救ってくれたのは、付近に住む友好的なインディアンたちであった。白人はインディアンから食物を貰ったり、生活の仕方を教えられて生命をつないだのである。
実際、ヨーロッパ人が新大陸の各地でインディアンから教えられて知った農作物は、おどろくほど多様な種類にわたっている。トウモロコシをはじめ、ピーナツ、ココア、やまいも、じゃがいも、いんげん豆、タビオカ、かぼちゃ、メロン、それに後でのべるタバコなど……。いま世界最大の農産物輸出国となっている合衆国の農産物のうち、実に七分の四はインディアンに教えられたものである。
当時のイギリスの入植者とその近くに住んでいたインディアンとの間には、いろいろな形の接触が始まった。もちろん、友好的な関係ばかりだったのではない。むしろ、お互いに警戒しあい、そして小競り合いがくり返されることが多かったのである。
ところが、首長ポーハタンの娘ポカホンタスだけは違っていた。彼女は白人を見たときから、それまで聞いたこともなかった人間が現れたことに、大きな好奇心を燃やしていた。相手の人数はわずかだったし、それも飢えと寒さで苦しんでいた。それを見て彼女が気の毒に思い、なんとか助けてあげたいち考えるようになったとしても不思議なことではないだろう。事実、彼女は父の目を盗み、植民者に道を教えたり、食べものを与えたりしたようである。しかしその程度のことならば、植民の初期の歴史の間には、同じようなことをしたインディアンの女性が何人もいたに違いない。ただ彼女には、その名を不滅にするような出来事が起ったのだ。
植民者のなかのもっとも有能な指導者ジョン・スミスが、ポーハタンの部下に捕らえられた。彼らが到着して半年ほどたった一六〇七年十二月のことで、パーシーの記録にある通り、植民者がもっとも悲惨な生活を送っていた頃のことである。ポーハタンは将来に禍を残すことをおそれ、部下に命じてその頸を刎ねさせようとした。そのとき突然ポカホンタスが現れて走りより、自分の体でスミスをかばい、父に向ってこう叫んだ。
「お父さん、この人を助けてあげて下さい。もしどうしても駄目ならば、私も一緒に殺して下さい」
首長ポーハタンは、びっくりして目をみはった。しかし娘を殺してまでスミスの生命を奪わなければならない理由はない。こうしてこの可憐なインディアンの娘は、有能な青年指導者の生命を救うことができたのだ……。
これは、アメリカの少年少女たちが一度は聞かされる美しい恋の物語である。
ジョン・スミスはこのとき二十七歳、すでにフランス、オランダ、イタリア、オーストリアなどの軍隊で豊富な経験をもつイギリス人で、軍人としても、外交官としても、また探検家としても、非常にすぐれた才能をもつ人物だったようだ。しかも行くさきざきで女性たちの間に人気が高かったというから、颯爽とした風貌の青年だったに違いない。
ところが、このとき彼女は、多分まだ十二歳の少女に過ぎなかった。多分、というのは、不幸にして彼女の生涯はあまりにも短いものであったし、時代もまた古いことなので、残念なことに資料が十分に残されていないからである。
豊かな陽光と恵まれた自然のなかに育ったヴァジニアのインディアン娘、ポカホンタスの心を動かした青年スミスは、それから一年半ばかり後にイギリスに戻り、とうとうヴァジニアには二度とやって来なかった。彼女の恋は実らなかったのだ。
一六一三年、彼女が十八歳のとき、今度は逆にイギリス人が彼女を捕えて人質にした。しかし、どの植民者もジェームズタウンのなかで彼女を丁寧に取り扱ったという。彼女が教会でキリスト教に改宗し、レベッカという洗礼名を受けたのもこの頃のことである。
ジョン・ロルフという当時二十九歳の入植者が彼女に求愛したのは、その翌年のことだった。ロルフはスミスがイギリスに去った翌年ヴァジニアに到着したあと、すぐ妻に死なれ、その後、「西インド変種」とよばれていたタバコの一種を移植して大成功した有力者である。
二人はやがて愛しあうようになり、総督や父も出席して、教会で正式に結婚式をあげた。タバコの栽培にも打ちこんだ彼女は、夫に連れられて一六一六年イギリスに渡る。インディアンの王女レベッカはたちまちロンドン社交界の人気を集めるが、翌年三月、テムズ河口の、町で帰国の準備中、天然痘にかかって急逝した。わずか二十二歳の若さであった。
不思議な縁というのだろうか、彼女の父のポーハタンという名前は、それから二世紀半ばばかりたって、突然日本人の前に現れる。幕末の騒然とした情勢のなかで、初代駐日アメリカ総領事タウセンド・ハリスは、自分が結んだ日米修好通商条約の批准を急ぎ、日本から新見豊前守正興正使とする一行を送り出すが、このとき七十七人の日本人を乗せ、咸臨丸より三日おくれて太平洋に乗りだしたアメリカ船の名は、この首長の名に因んだポータハタン号だったのである。
彼女の結婚は、インディアンとユーロッパ人の初期の友好関係の象徴として、歴史にその一ページを刻んだ。しかし、彼女が生きてヴァジニアに帰ったら、まもなく父が死んだあとで、その父の部下たちと夫の仲間たちが、互いに殺しあう流血の惨事をみなければならなかったであろう。
ポカホンタスがイギリスで死んだ翌年、父のポーハタンもまた死んで、後継者にはオぺチャ、ンカノーが選ばれた。彼は急増するイギリス人を今のうちに滅ぼそうと決心し、一六二二年二月二十二日早朝、植民地を急襲して三百四十七人を殺戮した。この時いらい、両者の間に平和はとうとう戻らなかった。2225年04月10 記す
「涙の道」をゆくチェロキー P.167
今からもう一昔も前のことである。
深南部のジョージアに住んでいた私は、森や湖の多い北ジョージアの、松に蔽われている山やまのなかをドライヴしていて、突然植民地時代のような長いスカートをはいた女性たちが歩いている不思議な町に出合った。
ダロネーガというその町は、標高約六〇〇メートル、人口約二千五百、ちょうどその日はお祭りで、着飾った人びとが広場に集まり、飲んだり食べたり、見世物に顔を出したり、まるで日本の村祭りのようなムードだった。
ところが役場に陳列してあるのを眺めて、私は思わず驚いて声をあげた。みな金鉱発見のものばかりだったからだ。アメリカで金鉱発見といえば、一八四八年にカリフォルニアで始まったものと考えていた私は、一八二八年にここで金鉱が掘り当てられたことを、その時までまったく知らなかった。だが――一八二八年といえば、ここはまだ白人の土地ではなかったはずだ。チェロキーというインディアンの立派な国があった場所である。
私はそこで、やっと思いあたった。一八三〇年に時の大統領ジャクソンが、アメリカの東南部一帯に住む文化的に高いレベルのインディアン諸国家に対して、ミシシッピ川の西側に移住するように、強制移住法を成立させたのは、この金鉱発見とも大きな関係があったというわけだ。そういえば、ダラネーガというこの町の名前も、「黄色いお金」という意味のインディアン語に由来している。アトランタにある州庁舎の黄金のドームも、その後ここで掘られた金で造ったものだという。
お祭りの喧噪のなかで、私の頭のなかは、まだ十分に書かれていない歴史の一ページに遡っていた……。
チェロキー、その名前が美しいように、彼らの住んでいた土地もまた美しかった。アパラチア山脈の南端がゆるやかな裾野をひろげているあたりに、彼らは幸福に住んでいた。山があり森があり、湖があった。山の稜線はみななだらかで、頂上まで樹木に包まれていた。
冬の適度な寒さ、夏のしのぎよい暑さ……この恵まれた自然のなかで、チェロキーは立派な一国としての体裁を作りあげていたのだ。議会をもち、裁判所の組織もできていた。領内で金鉱が発見された一八一八年には、セコイアという混血の指導者が作りあげたチェロキー語のアルファベットをもとにして、英語とチェロキー語を一緒に並べた週刊の新聞『チェロキー・フェニックス』が発刊された。
同じ年、これも白人との混血で、チェロキーの間に信望の高かったジョン・ロスが、アメリカの憲法にならった新しいチェロキー憲法のもとで、初代の大統領に選ばれた。つまり新しいスタートの年に、金鉱発見という"災害のもと"がふりかかってきたのである。
ジョージア州政府が前からチェロキー国家の土地の浸蝕を続けていたので、ロスは早速ワシントンへ出向き、モンロー大統領に会見して調停を依頼している。それにしても、一八二八年という年は、チェロキーたちにとってよほど運命の年であったに違いない。その年の秋に、インディアンを対等の人間とみていなかったアンドリュー・ジャクソンがアメリカの大統領に当選し、たちまち西方への強制移住を求めてきたからである。ロスはその後何度もワシントン政府と交渉して嘆願したが、その効果はまったくなく、そればかりかロスの不在中にワシントン政府はチェロキーの反ロス派と新しい条約を結んで、三八年五月を移住の最終期限として決定してしまった。
その年がくると、スコット将軍が七千人もの部下を率いてチェロキーに到着した。兵士たちや一般の白人がチェロキーの美しい土地に群がり集まった。家のなかを略奪したり、女を犯したりという暴虐な行為があちこちで起こった。ロスはもう、西へ向って旅立つ以外に方法はなかったのだ。
当時派遣されてきた兵士の一人が、後になって次のように書いている。
大河ミシシッピをこえ、オクラホマの地まで全行程は約一三〇〇キロ、支給された一枚の毛布とわずかばかりの荷物をもって、きびしい寒さに向かうこの季節に、彼らは「涙の道」についたのだ。
政府は一人の全経費六六ドルとして移住を白人業者に請け負わせたので、業者は食費を最低にきりつめた。そのためチェロキーたちは身体の抵抗力を失い、寒さや病気のため、次つぎに倒れたり、脱落したりしていった。
橋のない川の渡河、冷たい雨や雪、泥のようになった通路、伝染病の流行――そのなかで脱走をはかれば、監視の兵士たちに容赦なく射殺された。悲惨な旅のなかで、ロスの夫人のクォーティーも死んだ。彼女はもともと病弱だったが、同じ馬車のなかで寒さにふるえている子供に自分の毛布を与え、急性肺炎で死んだのだ。
前に引用した兵士は、このことについて次のように回想している。
一八三九年三月オクラホマへ着くまでに、移住者総計一万数千人のうち、その四分の一が死んだ。文字通りそれは「涙の道」だった。しかも、そのオクラホマさえ、半世紀あとで白人は、前言をひるがえして侵入してくるのである――。
ダロネーガのお祭りは、いつまでも続いている。私の頭のなかをよぎった歴史の一齣は、いつになったら陽の目を浴びることができるのだろう。陽気に踊り浮かれている人たちを後に、私は重い心をひきずるようにしてハンドルを握った。2025.04.22 記す
虐殺だった「栄光」の戦闘 P.173
日本では大政奉還が三年後に迫っていた一八六四年、アメリカ西部のコロラド准州東南部で、十一月二十九日の早朝、一体どんなことが起こったのだろうか。
東部ではまだ南北戦争の最中で、大勢は北軍の勝利がほぼ明らかとなり、南部に侵入した北軍のシャーマン将軍が、アトランタを焼き払い(六七ページ参照)、大西洋岸のサヴァンナめざして行進していたころのことである。
北軍、つまり合衆国陸軍は、一方で南部の反乱軍と戦いながら、他方では、人口稀薄でまだ州に昇格していなかったコロダド大高原の一角で、開拓者の前進を妨害するインディアン部族を一挙に殲滅し、輝かしい勝利の一ページをその歴史に加えたというのである。
現に事件発生後九日目の十二月八日付『ロッキー・マウンテン・ニューズ』紙は、大々的な見出しを掲げてその勝利を祝っている。
野蛮人の群れ消滅す
インディアン五百を倒す
わが方死者九、負傷者三十八
新聞はなお栄光に満ちた戦闘の模様を伝えていたが、そのなかで、コロラド民兵軍の隊長シヴィングトン大佐の言葉を載せている。
の村で、そこには約九百人から千人ぐらいの戦士がいた。
わが軍は首長ブラック・ケテルはじめ、ホワイト・アンテロープやリトル・ロウブなどの指導者、
および四五百人のインディアンを殺した」
この軍隊がデンヴァーに帰還したとき、彼らのパレードはまるでフロンティアの救世主のように大歓迎をされ、なかには剥ぎとってきたインディアンの頭皮を、自慢げに振りかざす者もあったという。
ところが――。
この戦闘に参加した将校や兵士たちのなかに、ワシントンの上官に宛てた手紙を書くものが出てきた。その手紙やインディアンと交易していた白人の業者たちの手紙から、戦闘の模様がそれまで伝えられていたものと少しずつ変わってきたのである。
そのうち、目撃者さえ二人も現れた。ジョン・スミスとエドマンド・グェリアーという交易業者で、陸軍の攻撃が行われたとき、たまたま加わっていたのだ――。この二人の証言では、インディアンンの居住地にはせいぜい八十か百くらいのテントがあっただけで、住民も五百人以内、しかもその三分のニは女や子供たちだったという。他の証言によっても、殺されたインディアンの大部分は、非戦闘員だということが分ってきた。
これでは、シヴィングトン大佐の報告が、かなり虚偽に満ちたものだったことになる。第一、そのとき白人側とインディアン側との間には、一時的にせよ休戦協定が結ばれていたはずなのである。
もともとこの地方は、シャイアントとアラパホという二つのインディアン国家のものだったが、一八五〇年代の末に、パイクス・ピークと名づけられた山の周辺で金鉱が発見された。一攫千金を狙う山師たちがここへ入りこむためには、途中の高原地帯でインディアンの接触が多くなったのは当然だった。若い怒れるインディアンたちは、鉱山のキャンプや駅馬車などを襲撃するようになった。
しかしインディアンたちは、普通冬の期間戦いをしない習慣だったので、シャイアン国家の首長ブラック・ケテルは、デンヴァーにいるコロラド准州知事やライアン砦の司令官に休戦の申しいれを行なった。この申しいれはいつたん拒否されたが、交代してきた新しい司令官は休戦の提案を了承し、インディアンに保護することを約束したが、それをシヴィングトン大佐にはそれを伝えなかった。
こうして、問題の十一月二十九日がやってきた。ブラック・ケテルは数百人のシャイアンをひきつれ、サンド・クリークという小川のほとりにテントを張って休んでいた。彼は陸軍の接近を知ってはいたが、休戦の協定が守られることを固く信じていたのだ。
標高一〇〇〇メートルをこえる高原の、寒い初冬の朝が明けた。東の空に一条の光が昇ったとき、シヴィングトン大佐は約千人のコロラド民兵軍に攻撃の命令を下した。丘の上の砲門がいっせいにとどろいた。
テントのなかではね起きたブラック・ケテルは、事の重大さをさとり、まずアメリカの国旗を掲げて、戦う意志のないことを示した。しかし、軍隊の攻撃は少しもやまない。彼はすぐに白旗を打ち振るったが、それもまったく無視されてしまった。
このときシヴィングトン大佐が、この戦闘によって個人の業績に名誉ある一ページを加えようと望んでいたことは確かだし、白人兵士たちが相手のインディアンを対等の人間と考えていなかったことも事実である。そうでなければ、次に起ったことは理解することはできない。
もう一人のシャイアンの指導者ホワイト・アンテロープは両手をあげ、英語で「やめろ! やめろ!」と叫んだが、その叫びは沸き立つような喧噪と混乱のなかで消え、何発かの弾丸がたちまちその体を貫いた。
シャイアンの戦士たちは、いったん小川の土手の所に退いて防戦したが、人数の点でも、武器の点でも、ほとんど本格的な戦闘とはいえなかった。それでも、争いが昼ごろまで続いたのは、それがもう残虐なインディアン狩りというような状態になったからである。白人兵士たちの行動はまったく常軌を逸していた。
殺したインディアン戦士の頭皮を剥ぐ者もいたし、逃げまどう女たちを大勢で追いかけて犯し、ナイフでその身体を切り開く者もいた。泣き叫ぶ子供を平気で撃ったり、ナイフで刺したりする者もあった。
日本のテレビでも放映したアメリカ映画「ソルジャ・プル―」は、この事件をとり扱ったものだが、虐殺や暴行の部分がひどくカットされていた。現実には、それが延々と何時間も続いたのである。
それから約一世紀の歳月がたって、一九六八年のアメリカ独立記念日に、ロンドンで初演されたアーサー・コピットの劇「インディアン」は、アメリカ陸軍が西部でインディアンに対してとった行為と、ベトナム人に対してとった行為を、みごとにダブらせたものであった。
証言者、ジョン・スミス。一八六五年
三月十四日。上下両院合同調査委員会。「インディアン
大地の霊は白人を憎んでいる P.179
かつてわが祖先たちが、この偉大な島(北米大陸)を所有していたときがありました。祖先たちの土地は、太陽が昇るところから、沈むところまでに広がっていました。
偉大な精霊は、その土地をすべてインディアンたちが使うようにしてくれたのです。偉大な精霊は、われわれの食糧としてバッファローや鹿やその他の動物を創りました。熊や鹿の皮は、われわれに衣服として使わせてくれました。……
また精霊は、大地に命じてパンのためのトウモロコシを作らせました。
しかし、邪悪な日がわれわれの上にやってきました。あなた方の祖先が大きな海を渡り、この島に上陸したのです。その数は、ごく僅かなものでした。
そして彼らは、敵ではなくて味方を見いだしたのです。彼らが告げたところによると、彼らは自分の国の意地の悪い人びとから逃れ、信じる宗教を守ろうとして、ここにきたということです。
彼らは僅かな土地を求めました。われわれは気の毒に思ってその要求をきき、彼らはわれわれの間に住むことになったのです。
われわれはトウモロコシや肉を与えました。ところが彼らはそのお返しに、われわれに毒(心を迷わせるアルコール飲料)を与えたのです」
このときレッド・じゃカットは、インディアンにキリスト教を伝えたいと申し出てきた白人側に向かって、多くのインディアンたちが感じていることを、彼独特の雄弁をふるって語った。彼は一七九二年に初代大統領ワシントンに招かれて、首都ワシントンへ出かけている。大統領は彼と食事をともにしながら、白人の力の優越性を誇り、白人に敵対することの無益さを印象づけようとした。
しかし彼は一向にひるまず、そのあと上院で演説をして、インディアンと友好関係を結びたいのなら、白人が善意と寛容を示さなければならないことを逆に力説している。たしかに彼のいう通り、この新大陸に白人が植民を始めたとき、その白人はひとにぎりの少数派にすぎなかった。
現在のアメリカは世界一の工業国であると同時に、世界最大の農産物輸出国でもある。そのアメリカの全農産物の七分の四が、インディアンに教えられたものということは前にのべた。
農産物ばかりではない。少しアメリカ人の生活を注意して観察すれば、文学の上ではいうまでもないが、音楽、演劇、法律、医薬品、神話、民間伝承、民芸、料理、衣服、それからヘアスタイルなどにいたるまで、どれほどインディアンの影響が滲みこんでいるか分からないほどである。
言葉にしても、同様だ。母音の多い美しい響きが、今もいろいろな形で残っている(メモ参照)。
けれど、その後インディアンの土地はしだいに奪われ、白人の殺戮にあって人口も激減した。白人が植民をはじめたころ、今の合衆国にある土地は、百万人あまりのインディアンが数百の国家をつくって住んでいたが、十九世紀の後半には一時十万人以下となり、いまやっと八十万人に回復した。
ところが現在になって、白人に破壊され尽くしたかと思われたインディアンの生活様式が、皮肉にもまた甦ってきたのだ。高度に管理化され、人間性を失いはじめたアメリカ文明に対して、貴重な示唆を与えはじめているのだ。インディアンたちは、自分を養っている動物や魚を絶やしてしまわないように、十分注意して生活した。白人があとから絶滅させてしまったバッファローも、必要最小限しか獲らなかったし、捕えた魚がまだ小さいときは、また川のなかへ戻してやった。それがインディアンの生活様式だった。
一九六〇年代の若者たちの心を捉えた対抗文化について書いたシオドア・ローザックは、そのなかで、あるインディアン女性の言葉を次のように引用している。
しかし白人は、地面を鍬で掘り起こし、木を引っこ抜き、なんでも殺してしまう。木はいう、”やめてくれ、痛いよ。痛めつけないでくれ”と。でも彼らは、木を切り倒して割ってしまう。大地の霊は、白人を憎んでいる。……
インディアンは何物も決して傷つけない。しかし白人は、なんでも破壊する。彼らは、岩を爆破して地面に散乱させる。
岩はいう、やめて"やめてくれ。お前は私を痛めつけている"と。しかし白人は気にかけない。……大地の霊は、どうして白人を好きになれるだろうか……」
インディアンは自然と一緒になり、自然のなかに融けこむようにして生活していたのだ。自然を征服し、自然を破壊することによって文明を築いてきたアメリカは、いま明らかに行き詰まりをみせている。若者たちがインディアンの生活様式に新しい道への示唆を見いだすとすれば、アメリカ人たちはかつて野蛮人として軽蔑していたインディアンたちから、いま文明の名のもとに、大きな審判の座に立たされているのではないか。
英語のなかに、美しい母音の響きをもつインディアン
アフリカ西海岸からの黒い積荷 P.185
アメリカすべて移民の国である、といったら、それは大きな間違いになるだろう。
先住アメリカ人であるインディアンのことは別としても、いま総人口の一一パーセントにもなっている黒人たちは、自分の意思でこの大陸にやってきた移民などというものではなく、アフリカ大陸から無理に略奪されてきた人びとだからである。
もちろん奴隷は古くからどの世界のもあったが、約四世紀もの間、アフリカ西海岸から黒人たちをアメリカ大陸の各地に送り続けた大西洋上の奴隷貿易と、その規模の大きさや残酷さの点で肩を並べられるのは、他にまったくないといっていい。
一体どの位の数の黒人が大陸に奴隷として連れ出されたか、今となっては正確に知ることができない。
もちろん、それがすべて北米へ送りこまれたわけではなく、むしろ過半数は中米、南米、とくにブラジルに送りこまれたのだが、それでも一八六一年に南北戦争が始まったとき、合衆国には南部に奴隷約四百万、主として北部に自由な身分の黒人五十万、合計四百五十万人もの黒人がいたのである。
一八八~九ページの奴隷船の絵は、最大限の利益をあげるために、奴隷という積荷がどれほど無駄(?)なくつめこまれたかを示している。どんな生活がこの船のなかで待っていたのか、この絵を見ればある程度の想像はつくだろう。
奴隷狩りや奴隷取引が行われたのはアフリカ西海岸一帯にわたっていたが、とくにその中心になったのは、現在のナイジェリアにあるぺニン湾で、ここからたとえば中米の西インド諸島まで二カ月あまりの航海は、途中が赤道に近い関係もあって、まるで地獄への旅であった。
大西洋上には神はいなかった。
ぎらぎらと焼けつくような太陽だけが、まぎれもなく人間が人間を売買して運ぶ所業を見ていた。何十年も何百年も、その人間が神の心に気がつく日がやってくるまで……。
鎖につながれた黒人たちは、身動きできないほど狭いスペースのなかで、一日二回だけの食事を与えられる。アフリカ系の粗末なものか、あるいは普通馬の飼料にされる皮の硬いたらなた豆である。この豆はヨーロッパではもっとも安く手に入る飼料で、まずどろどろになるまで煮つめ、それにしゅろ油、メリケン粉、水、とうがらしなどを混ぜて作った食べものだった。
それは、とてもまともに食べられるようなものではない。監視が十分でないようなときは、奴隷たちもお互いにこのどろどろした食べものを、相手の顔に塗りあったりしていたという。
ジョン・ニュートンという牧師は、ある奴隷船を見て、次のような記事を書き残している。
もちろん反抗する奴隷や、海にとびこむ奴隷もいたが、ただ死の運命だけであった。こうして反抗や逃亡や病死などで、輸送中の奴隷の死亡率はとても高く、疫病は遠慮なく白人船員の間にもひろまった。
四百四十人の奴隷と十七人の白人船員を乗せたゾング号は、航海中赤痢に見舞われ、六十人の奴隷と七人の船員が死亡した。残りの者もすっかり衰弱しているのを見た船長は、船員を集めてこういった。
また、ある十一歳の黒人の少年は、次のように書き残した。
この奴隷貿易はあまりにも儲かったので、西ヨーロッパのたいていの国や、やがて合衆国になるイギリス領の北米植民地人が、争ってこれにとびついた。
ラム酒、マスケット銃、火薬、弾丸、リンネル、キャラコ、錫製器具、ガラス玉などをアフリカで奴隷と交換し、新大陸各地の港に運んだのである。
北米へ輸入されてからの奴隷たちは、各地の奴隷市場で売りさばかれ、ヴァジニアのタバコ、カロライナの米、ルイジアナのトウキビ、そしてやがては南部一帯の綿花を生みだして、アメリカの富と文化を作りあげる土台となったのだ。
たしかに、奴隷が運ばれたのは北米だけではない。しかしその奴隷に自由を与えるために、四年間もの大きな戦争を行い、六十万人もの人がそのために死ななければならなかったのは、全世界でただアメリカ合衆国だけなのである。
十年ほど前、毎年のように夏になると、全米各都市に黒人の暴動が発生したが、私にはそれが、かつて長いあいだ犯され続けた母なる大陸アフリカへの、黒人たちが奏でる鎮魂歌のように聞こえてきた。
そればかりか、アメリカ人たちは、たとえばバス通学などの紛争にみられるように、祖先たちの犯した所業のツケを、これから先どれほど長い間払い続けなければならないのだろうか。
十九世紀後半のアメリカの国際法学者
十六世紀 八八万人
大統領も奴隷を所有していた P.191
ジョージ・ワシントン(1732~1799年)はよく人に、「私も早く官職を退いて、金儲けに精を出したい」と漏らしていたという。政府の重要な官職についていたのでは、自分個人のための儲けができないからである。アメリカでも、今ではワシントンのような政治家ばかりではないが、それにしても、政府の高官になることによって私腹を肥やしている日本の政治家とは、やはりどこか根本的な違いがあるようだ。
ところで、そのワシントンには父や兄から譲りうけた農園や牧場のほかに、結婚してから富裕な妻から受けとった大農園があって、この経営に当たることが、彼個人の仕事だったのである。当時こういう農園は、たいていタバコを栽培していた。また農園の労働力はほとんど黒人奴隷に頼っていたので、ワシントンの財産は広大な農園や牧場の不動産と、黒人奴隷という動産からなっていたわけだ。
※写真の説明:平成2年7月24日、私が訪問した。
もう一方の写真は、一九七五年秋天皇がここを訪問される前の日に撮ったもので、まさしく奴隷たちが干し草を積み上げていた同じ場所である。
ワシントンは独立戦争の最中でも、部下の黒人とよく一緒に戦った。有名なデラウエア渡河のときも、プリンス・フィップルとオリヴァー・クロムウェルという二人の黒人が、オールを漕いで彼を対岸へ渡したのだ。
またフィリス・ホィトリ―という黒人の女性詩人が彼の勇気をたたえた詩を送ると、彼は早速陣中から丁寧な返事を書き、
とのべている。
独立宣言書の起草者で、三代目の大統領となったトーマス・ジェファソンもまた、ヴァジニアの農園に大勢の奴隷をもっていた。ずっと後の一八五三年に、自由な身分のウィリアム・ブラウンという黒人が「クローテル、大統領の娘」という小説を発表したが、これはジェファソンが黒人に生ませた娘を主人公にしたものである。
実際には、ジェファソンは三十九歳のとき妻に死なれ、そのまま生涯独身を通した。彼がその後身のまわりの世話をさせた美しい混血の女性と結ばれ、一女をもうけたらしいことを、小説としてではなく、最近では事実として証明しようとする歴史家も現れているほどである。
こういう建国の祖父といわれる人たち――ワシントンのように誠実な人や、ジェファソンのように進歩的な人などが、日常生活で普通に奴隷を使っていたということは、たしかに歴史のパラドックスといえるだろう。しかし、この二人に限っていえば、二人とも良心の呵責を感じる瞬間をもっていた。
ワシントンは公式の声明に奴隷制度を非難したことは一度もないが、甥にあてた手紙のなかで、こう書いた。
ジェファソンも死ぬ六年前の一八二〇年に、暗い気分でこう書いている。
「奴隷制度というこの重要な問題は、夜なかの火事の警鐘のように私をめざめさせ、恐怖で私をいっぱいにした。すぐにそれを、私は国家の弔鐘と考えた。
しかし、奴隷をもっていた大統領のすべてが、こんな具合だったわけではない。
典型的な奴隷州ヴァジニア生まれ、ヴァジニアに死んだジョン・タイラーは、第十代大統領として一八四一年から四年間、ホワイトハウスに住んでいる間、ずっと何人もの奴隷たちを家事労働に使っていた。ヴァジニアで奴隷を使って生活していた彼が、同じように奴隷制度を認めていた首都ワシントンへ引き越すのに、奴隷を連れていくことは当然と思えたのだ。おそらくホワイトハウスで家事労働をした奴隷たちは、奴隷という身分のなかではもっともよい取り扱いを受けたことだろう。
ところが、それでもなお、ジェームズ・クリスチアンという奴隷は、ホワイトハウスから逃亡した。奴隷制度を認めていない北部のペンシルベニア州に逃げこんで、やっと安全な場所に辿りついたところで、彼は多くの人々の質問を浴びた。ホワイトハウスから逃げ出した奴隷ということで、珍しがられからである。「あなたはタイラー大統領が好きでしたか」という質問に対して、その奴隷はこう答えている。
※奴隷人口の変化
北部各州は州ごとにだんだん奴隷制度を廃止し、リンカーンが大統領に当選した一八六〇年には、北部に奴隷制度を認める州はなくなっていた。
2025.03.20 記す
奴隷の「女モーゼ」タブマン P.197
「神様、私はこれから、あなたのみもとに参ります。どうか私を守って下さい」
ハリエットがごく僅かな食べものをハンカチに包み、両刃のボウィーナイフ一本だけを持ってそうつぶやいたとき、彼女は死を覚悟したといっていい。それほど南部の奴隷が北部に逃げこむのは難しかったし、捕えられたときの仕置きの凄まじさを、彼女はよく知っていたからである。
奴隷が逃げ出さないように、主な道路や橋などには見回りが歩いていた。その上、十分に訓練を受けた猟犬が、逃げた奴隷を追いかけるために、たいていの農園に飼われていたのだ。
しかしハリエットは、もちろん成功を夢みていた。彼女がいたメリーランド州のドーチェスター郡というのは、奴隷制度を実施している南部全体からみれば、ずっと北部寄りの場所で、奴隷制度を認めていない北部のペンシルべニア州境まで約二〇〇キロほどの距離だった。そのとき彼女は二十八歳。南北戦争が始まる十二年前の一八四九年のことで、カリフォルニアの黄金めざして人びとが西部へ向った年だった。
ハリエットは父と一緒に畑仕事をするとき、奇妙なことを父から教えられていた。一体どうすれば誰にも知られないで林のなかを走り抜けられるかとか、どうすれば林や野原で木の根や野イチゴなど、食べられるものをみつけられるか、ということである。父はいつの日か娘だけにでも、この奴隷という悲惨な境遇から逃げ出してもらいたいと考えていたのだろう。
ハリエットはそういう父の教えをいま生かしながら、やっとある白人女性の家にたどりついた。いつだったか、彼女が畑仕事をしているところへ馬車で近づいてきて、「助けがいるときは、私に知らせるのよ」と、ひそかに知らせてくれた女性の家である。
当時、奴隷たちを助け出そうという秘密の組織が北部を中心にいくつかできていて、人びとは「地下鉄組織」およんでいた。その白人は、南部に住んでいながら、こっそりこの地下鉄の役割を果たしていたのだ。
彼女はハリエットが逃げこんできたことを喜んだ。すぐ食事を出し、夜が明けないうちに、次の駅まで行かなければいけませんと注意した。
彼女にいわれた通りのコースをたどって、明けがたまでに指示された家に着いてみると、そこには白人の男が待っていて、食べものを出したり、細かな注意をしたり、すべては第一の家と同じだった。
昼間ハリエットは、その家の庭仕事を手伝った。夜になると、今度はその男が彼女を馬車に乗せて、ある場所まで連れていってくれた。
「さあお前、この土手に沿って北へ行くんだよ。そうすると、お前を待っている次の駅にぶっかるからね」
男は別れるときに、そういった。
ハリエットはこうして、しだいに北部への州境に近づいた。時には干し草のなかに隠れたり、ポテト貯蔵の穴にもぐりこんだり、屋根裏にひそんだりして、必死に追っ手の眼をのがれなければならなかったが……。
それでもとうとう二週間目に、その州境を越えることができた。さあ、ペンシルベニアだ。これでもう、自由なのだ。私は自由の身になったのだ! 彼女はそのときの感動を、次のように記した。
彼女は自分が逃亡に成功したことだけに満足しなかった。自分は自由になっても、両親や兄弟がまだ奴隷として苦しい生活を続けていると思うと、どうにも我慢ができなかったのだ。その上、メリーランドには、まだ自分の夫が残っていた。ハリエットは二十四歳のとき、ジョン・タブマンという若い自由黒人と愛しあって結婚し、同じ小屋に住んでいた。
南部にも僅かながら自由の黒人がいて、そういう自由黒人と奴隷の結婚も、多くの場合認められていたのだ。その奴隷の所有者が、奴隷の仕事に支障をきたさないこと、生れた子供は奴隷となること、などを条件に、そういう結婚を認めていたからである。
ハリエットは、危険を冒してまたメリーランドに潜入した。そしてまず、ちょうど逃亡中だった姉一家四人を救い出すことに成功した。二度目は、兄弟のほかに二人の男を救出した。
そして三度目は――夫のジョンが、他の奴隷女と一緒に暮らしているのを発見したのだった。彼女は絶望に打ちのめされたが、すぐに気をとり直した。夫を連れ出すのをきっぱりとあきらめた彼女には、ぐずぐずしている暇はなかった。いつ自分が発見され、捕えられか分からないのだから……。来る年も、くる年も、彼女は危険な南部への潜入をくり返し、そのたびに、十人、二十人と奴隷たちを北部に連れ出した。
暴動を起こして捕えられ、処刑されたデンマーク・ヴェセイ(「メモ」参照)の歌を、彼女はいつも口ずさんでいた。
はるかにエジプトの国まで
そして 老いたる王に告げよ
わが民を解き放てと
この一人の大胆な女性の噂は、しだいに奴隷たちの間にひろがり、ひそかに彼女は「モーゼ」と尊敬されるようになった。
普通、逃亡奴隷を捕えたときの賞金は一〇〇ドルどまりだったのに、この女モーゼへの賞金はだんだんと高くなり、奴隷所有者たちの間で、とうとう四万ドルという値がついた。
幸い彼女は最後まで捕えられることもなく、のちには両親も助け出し、約十年間に十九回の潜入で、合計約三百人もの奴隷を北部に連れ出している。
一八五九年、南北戦争が始まる二年前に奴隷解放のために兵をあげて処刑されたジョン・ブラウンは、彼女に出会ったとき、こう叫んで、その勇気を賞賛した。
「やあ、タブマン将軍!」
奴隷制度が続いていた南部では、暴動がたえずどこか
移民を待ち受けていた運命 P.203
鉄道王ヴァンダービルド一族のぜいたくな邸宅が並んでいた五番街のあたりは、南北に細長いマンハッタン島の、ほぼ中央にあたっている(一八~一九ページ参照)。ところが、この五番街をもっと南に下がっていくと、その東側には、見るも無残なスラム街が軒を並べていたのだ。
ニューヨークの同じこの小さなマンハッタン島のなかで、しかもまったく同じ時代に、一方では世界でも有数の大富豪たちが、互いに華やかな社交界で豪華さを競いあい、他方ではヨーロッパから到着してまもない文なしの移民たちが、職もなく不潔な貧民街のなかでうごめいていた。
十九世紀末から二十世紀はじめにかけて、ニーユ―ヨークのマンハッタン東南部、つまりイーストサイドの下町が、一体どんなに貧しかったか、当時の写真でも見なければ、とてもその実態を理解できないだろう。幸い、当時のすさまじい貧困ぶりを伝える写真が少なからず残っている。たとえば、ジャーナリストのジェイカプ・A・リースの『他の半分はどう暮らしているか』という本は、当時の人びとを驚かせたばかりでなく、今の私たちにもショックを与える力をもっている。
その中に載せられた写真をみると、密集した小さなアパート、塵芥にまみれた通路、日のあたらない不潔な部屋、家具らしいものは見当たらず、狭くて貧弱な台所、毛布にくるまっただけで寝ている人びと、栄養失調でうつろな目をしている子供たち……。
リース自身、一八七〇年に二十一歳でデンマークから移民してきていらい、初代移民の苦しさをほとんどみな経験してきた。失業、飢餓、絶望、そのあげくは、何度か自殺してしまいたい衝動にかられたという。一八七七年にやっと『ニューヨーク・トリビューン』紙に雇われて、警察署係りの記者となった。当時のニューヨーク警察は、イーストサイドのスラム街の真っ只中にあったので、彼は仕事を通じてもまた、スラム街の実態を熟知することになったのである。リースは次のように書いている。
どうしてこんなことになったかというと、そのころすでに高度に発達していた資本主義体制のなかで、後から後から絶え間なく殺到する移民があまりにも多く、そのため失業者は増え、だれにでもできるような労働の仕事にありついたとしても、賃金が驚くほど安かったからである。
そのころ、アメリカに希望を抱いてヨーロッパからやってくる移民たちの数は、たとえば二十世紀の最初の十年間に、何と八百万をこえていた。一九〇〇年当時の総人口が約七千六百万だから十年間に一割以上の移民がどっとやってきたのだ。
一八八六年に完成したニューヨーク港の自由の女神は、アイルランド人、ドイツ人、ユダヤ人、イタリア人などの大群を迎えいれた。そして彼らはまず、暗くてじめじめした各地の貧民街に落ち着いたのである。
移民のこういうひどい生活は、あまりヨーロッパに知られていなかった。先に新大陸へ移民した親戚や友人からは、概して成功を誇張した手紙がくるし、移民を奨励する船会社の広告は、必ず成功を約束する華やいだ言葉で埋められていたからである。
そのうえ、ヨーロッパの生活は、だれにも楽しいものとはいえなかった。十九世紀のなかば、アイルランドでジャガイモの大不作が続いたとき、新大陸への移民が急増したのもこのためで、ケネディ大統領の四代前の祖先が移民したのも、この時だった。彼らはみな、新大陸に夢を抱いて到着した。新大陸がもう新大陸ではなくなるころになって……。
リースは警察署周辺の取材活動を通じて、こういう貧民街につきものの人たち――コソ泥、酔っぱらい、乞食、家なしの放浪者、ヨタ者、売春婦やそのヒモたち――と知りあった。しかし、そういう時、いつも彼の心のなかを占めていたのは、自分もかつては経験してきた同じような貧しい人びとへの、ヒューマンな愛情だった。彼はこう書いている。
フランスの作家ポール・プールジェが、マンハッタンの貧民窟パワリー街を訪ね、
一方では、鉄鋼王カーネギーが、年間二千数百万ドルの収入を得ていたときに、労働者たちは一週六十時間働いて、平均年収が四〇〇ドルから五〇〇ドルにすぎず、一九〇二年、ボストンの女の売り子たちは、週給五ドルか六ドルにすぎなかったという。
当時の社会学者ロバート・ハンターによれば、いくら働いても生活必需品を思うように買えない貧困層の数は,全人口の数人に一人の割合になっていた。ニューヨークのイーストサイドばかりでなく、ボストン、フィデルフィア、シカゴのような大都市や、ニューイングランド、ペンシルベニア、オハイオなど、東北部の工業地帯のすべてに、貧困層が大きくひろがっていたのだ。
彼らの多くは二世の時代になって、親がいたスラム街から脱出し、中産階級の下の方に仲間入りするのだが、裸一貫の移民たちがその間にもつぎつぎにやってきたので、貧困層はいつまでも消えなかった。太平洋岸に、まったく異質のアジア系移民がどんどん入りはじめたのも、大体同じころだったのである。
南北戦争に破れ、北部資本の植民地のような存在にな
嫌われたカトリック教徒 P.209
大統領選もたけなわの一九二八年八月二十日、オクラホマシティーの公会堂に乗りこんだ民主党の候補アルフレッド・スミスは、まるで別の国にやって来たような違和感を覚えた。これはスミスの長い政治生活を通しても、珍しい経験だった。彼はすでに革新的な知事として、ニューヨークで四期八年間をすごし、都市生活者や労働者たちからは熱狂的な支持を受けていたのである。
ところが、このオクラホマシティーではどうだろう。大体汽車がこの駅に着いたとき、彼を迎えた人びとの表情は、妙に硬くて、冷ややかだった。そればかりか、頭からすっぽりと頭巾をかぶったあの不気味なクー(またはキュー)・クラックス・クランの一団が、敵意に満ちた行動を見せて並んでいたのだ。
公会堂の演説会は、予想もしないような大混乱となった。約三万人の聴衆は、初めからスミスの演説を聞こうなどとは思っていなかったのである。
「やめろ、この不道徳漢め」
「カソリック教徒など、尻尾を巻いて引き上げろ」
「アイルランド人はひっこめ」
「禁酒法に反対の奴のいうことなんか、聞いてやるものか」
罵声が演壇の彼のまわりに集中した。
ずっと後のことだが、一九六三年十月、テキサス州ダラスで演説した国連代表アドレイ・スティヴンソンはスミスが経験した弥次と怒号に見舞われた。演説が終わったスティーヴンソンは、一人の女にプラカードを頭にぶつけられ、一人の男につばをはきかけれた。彼は一か月後に予定されているケネディ大統領のダラス訪問に危険を感じて、警告を発したほどである。
そういう例を考えてみると、オクラホマシティーでスミスの演説会が大失敗に終ったのはまだいい方で、彼の身の安全が守られたことを満足しなければならない、と考えているのも当然のことであろう。
一体なぜ、一つの国のなかでこんなことが起きるのだろうか。一方では熱狂的な支持者に囲まれたスミスが、他方では、なぜこれほど敵意に溢れた人びとに非難されなければならないのだろうか。
スミスの地盤となったニューヨーク州は、東部を代表する知的な存在であり、とくに彼はニューヨーク市やその周辺など、土地に住む人たちから、その進歩的な政策のため、ほとんど絶対的支持を得ている。
しかし、同じニューヨーク州のなかでも、北西部の田園地帯はいつもスミスの敵にまわっていたのだ。だから南部と西部の接点にあたる農村地帯の中心地オクラホマシティーで、選挙運動中のスミスが敵意で迎えられたのも、ある程度当然だったといえるだろう。
それにしても、そのむき出しの敵意はあまりにも露骨であった。一体どうしてクラウン(kkk)などまで出てきたのだろうか。
十九世紀末から二十世紀のはじめ、東部の各都市、とくにニューヨークに殺到する外国からの移民の数は、まさに頂点に達していた。しかもそれは、ほとんどアメリカを形成していたアングロ・サクソン系移民ではなく、アイルランド人、ユダヤ人、イタリア人、ポーランド人など、従来の標準でいえば非アメリカ的とみなされていた移民ばかりだった。
その上、アイルランド人やイタリア人はほとんどがカトリック教徒だったから、その点でもプロテスタント中心の立場から見れば、非アメリカ的だったのである。
アルフレッド・スミスは、父方の祖先がイタリア系、母方はアイルランド系、スミス自身は幼児洗礼を受けて、聖ジェームズ教会に所属していた熱心なカトリック信者だから、二重に非アメリカ的な条件を背負っていたのだ。だからアングロ・サクソン系以外の住民や、カトリック教徒の多いニューヨークで州知事を毎回有利にすすめることができたスミスも、民主党の大頭領候補となって西部や南部の農村地帯を前にしたとき、異質な妨害にぶつかったことになるのである。
その異質な障害のように見えたものこそ、実は伝統的なアメリカの価値観に支えられた人たちだった。それがいわゆるWASP(アングロサクソン系白人でプロテスタント)という基盤である。
一九一五年に南国ジョージア州で再選された第二次クラン(KKK)が、たちまち中西部や西南部に拡大し、十年後には全米五百万の会員をもつほどに大発展をとげたのは、WASPの価値観を脅かす危機に立ちむ向かおうとしたからに他ならない。
このクラウンを復活させたウィリアム・シモンズは、プロテスタント中でも大きな派の南部メソディスト教会に所属する巡回牧師であったし、このクラウンが新しい土地に勢力を伸ばすとき、まず白人プロテスタントの牧師に接近する方法をとったのも、当然のことであったろう。
このKKKから見れば、アイルランド系、カトリック教徒、しかも白人たちがようやく成立させた禁酒法に反対という、これだけの条件が揃えば、スミスはまさに不倶戴天の敵である。
一九二〇年代にKKKの援助で知事に当選した人は全米で十人、上院議員十三人という勢力を見れば、それを敵にまわした時の恐ろしさが分るだろう。一九六〇年の大統領選でも、カトリック教徒だったケネディに反対するパンフレットや印刷物が、全米で二百万部以上もばらまかれ、プロテスタントの牧師代表数百人はワシントンに集まって、カトリックの候補者に投票すべきでない、という声明を出したほどである。
スミスは、果たして大敗した。もしその上で黒人であったりしたら、選挙戦の最中に暗殺されていたかもしれない。
スミスの場合は、カトリック教徒だが大統領候補に選ばれた、というだけで、歴史的大事件だったのである。もちろんケネディは、大統領に当選した最初のカトリック教徒だった。アメリカでも、なかなか「すべての人間は平等」というわけにはいかないのである。2025.04.02 記す
各界を牛耳るユダヤ人 P.215
一九六八年秋のはじめ、ニューヨーク市マンハッタンでアパート探しをしているうち、私は何度か奇妙な経験をくり返した。眺めのいい高級アパートメントに「空室あり」という札が下がっているのを見て、なかに入ると見事に断れるのだ。じろりと私の姿を眺め、「残念だが空室はありません」といわれる。「外には空室ありと出ていますよ」と尋ねると、
とすまして相手は答えるのである。
ところが翌日その前を通ってみると、相変わらず「空室あり」と書いてあるのだった。
二、三度続けて同じように断られれば、どんなに鈍感な人間でも何かに気がつくはずである。友人にそのことを尋ねてみると、彼は肩をすぼめてこういった。
「私だって同じですよ。ユダヤ人ですからね」
その年、アメリカ・ユダヤ人協会から発表された調査結果によれば、マンハッタンのイーストサイドにある百以上の高級アパートから、ユダヤ人が微妙な形でしめ出されていることが明らかとなった。
「あなたがここに入っても、あまり楽しくありませんよ」
そいう婉曲的な断わり方をされるのである。
それにしても、ユダヤ系に対するこの眼に見えないような偏見や差別と、実際には各界でユダヤ系が勢力を振るっている実態との矛盾を、一体どう考えたらいいのだろうか。もともとユダヤ人はヨーロッパ各地ですでに厳しい迫害を受けていたし、アメリカへ逃れてきてからも、キリスト教に対するユダヤ教という著しい対照をもっている。
一八七〇年代に中欧で迫害されたユダヤ人が大量に移住しはじめ、八〇年代以降は東欧からの移住が主流となった。こうしてアメリカのなかのユダヤ人が、問題にならない少数派から、かなりの勢力をもつ少数派に成長したとき、アメリカのなかでも急速にユダヤ系に対する偏見や差別が表面化してきたのである。他の少数派集団と同じように、当然彼らも真のアメリカ人に同化しきろうとして、WASP風に名前を変えてみたり、WASP風に振る舞おうとして努力した。
ユダヤ系のインテリ雑誌『コメンタリー』の編集長ボドーレッツは、コロンビア大学に在学中、一方では忠実なユダヤ人であろうとしながら、他方では一生懸命WASPのコピーになろうと努めたことを、著書のなかで自嘲をまじえながら回想している。だからユダヤ系の人びとは一人残らず心に深い傷跡をもっていて、疎外感や被害意識がそこから生まれてくる。その傷の深さは、ほぼ同一民族で構成されている日本人には理解できないほどである。
一九七六年にノーベル賞を受けたソール・ベロ―の作品のなかには、ある日突然、浮浪者風の男が現われて主人公を脅迫しはじめる話があるが、ユダヤ系の人びとは、すべての異教徒が自分たちに強い反対の感情をもっているのではないかと、深い疑惑を抱いているのだ。
この被害意識は、一方では逆に選民思想を育てている。それが一種の逆差別といわれるほど大きくなっている場合もある。たとえば、ユダヤ系とそうでない者との結婚を認める者は全米で五九%にまで増加したが、ユダヤ系の親の方は九〇%以上が、自分の子供が異教徒と結婚させたくないと考えているのである。ユダヤ系の人びとの優越感は屈折していて難解だが、その一つの特色に偏見や差別に反抗する好戦性がある。彼らは異教徒に対して優越感をもつだけでは十分でなく、それを異教徒に知らせたいという気持ちが強い。
スポーツ界は体力での優越性を示す絶好の例となるので、サンディ・コーファックスのような野球選手は、一躍ユダヤ系社会のヒーローとなってしまう。頭脳での優越性を示している例は数限りなくあるが、全米的なレベルでもっとも著名な例は、前国務長官キッシンジャーであろう。
ちょうど多数派からの疎外感に悩まされている黒人とユダヤ系が、戦後アメリカ文学の主流をになったように、キッシンジャーの活躍ぶりは、ここで改めて書く必要もないほど華々しいものだった。なにしろ国務長官というポストは、実質的には大統領に次ぐ要職であり、アメリカ生まれではない彼は大統領になる資格が与えられていないので、国務長官は昇りうる最高のポストだといっていい。貧しい移民の子が、そのポストについたのだ。しかも、ギャラップ世論調査によると、過去三年間、もっとも尊敬する人物の第一位を占め続けているのは、実にこのユダヤ系のキッシンジャーなのである。たまたま魅力のある大統領がいなかったというせいもあろうが、彼がこのように高い評価を与えられているのは、彼がいわれのない偏見や差別をはね返そうと努力した結果ともいえるだろう。
こうしたユダヤ系の人びとの活躍のため、一昔前から見るとこれでも一般の人びとのアレルギーはずいぶん減少した。ギャラップ世論調査では、「もし支持する政党がユダヤ系を大統領候補に選んだら、彼に投票するか」という質問に対し、一九三七年にはイエスと答えた者が四六%だったのに、五六年には六二%と上昇している。
最近になって、ユダヤ系をしめ出していたカントリークラブやビジネスマンクラブも、入会をだんだん認めるようになってきた。早く同化したいという努力とこの自尊の精神が、差別のなかの成功をかちとる原因だったのであろう。しかし差別が緩和するにつれて、ユダヤ系はやがて「人種の坩堝」のなかに融合され、その特色を失ってしまうのだろうか。それともその特異な性格をいつまでも持ち続けるのであろうか。
ユダヤ系アメリカ人は推定約六百万、全人口の三%に
ある日本人妻のその後 P.221
雄大なロッキー山脈の東麓にあるコロラド州のデンヴァーに、一九七五年の夏、八軒目の日本レストランが開店した。デンヴァーは人口約五十万、周辺部分を加えると百二十万という大都市で、日系人や日本人が数千人住んでいるとはいうものの、日本料理のレストラン八軒目というのは、多少乱立気味の感じである。八軒目にできたその店の名前は「カブキ」。盛り場を少しばかり外れている。
以前には付近にメキシコ系市民の住む貧しい区域であり、この辺もごみごみした失業者のたまり場所だったという。いま都市開発で、だんだんそういう区域が取り払われている。
酒類販売許可をもっているレストランなので、入ると右側はカウンターの並んだバーになっている。食事のテーブルが十卓くらい。奥には畳敷きの部屋が二つあって、そこに掘りごたつ式のテーブルがおいてある。いかにもムードはアメリカのレストランらしく、窓がないから昼間から暗く、照明だけである。その照明に壁に写楽の絵が浮かんで見える。提灯が下っていたり、日本人形が飾ってあったり、バーのカウンターにはまねき猫まで、ちょこんとこちらを向いて座っていた。
そのカウンターの向こう側に、日本女性が二人、とまり木に並んだお客を相手にして、こまめに、キビキビと動きまわっている。実はこの二人が、このレストランの共同経営者なのである。カズコ・ジョンソンさんは熊本出身、ノブコ・シュワブさんは佐賀出身。近隣の県だが、知り合ったのはごく最近だそうだ。
カズコさんは横浜でアメリカ兵士と結婚したが、夫があまりひどいアルコール中毒だったので、カリフォルニアのサンジエゴに住んでいるときに離婚した。その後、今から十年あまり前に建設業をしていたジョンソン氏と知り合って再婚、今では十三歳の子供が一人いるという。
ノブコさんは二十年近く前に、横浜で軍人のシュワブさんと結婚した。いま御主人はやはり建設関係の仕事だが、子供がいないので、デンヴァーに移転してからは奥さんが美容院を開業、そこでお客の一人カズコさんと知り合った。知り合ってから、この店を共同で開業するまで、わずか半年足らずである。この二人の日本女性に、共同でこの店を始めさせたのは一体何だろうか。
二人とも横浜でアメリカ人と結婚したのは、もう二昔も前の朝鮮戦争のころだ。今よりも日本人全体の心のなかでアメリカの評価が高かった時代だから、アメリカ人との結婚はバラ色の人生を約束していると思えたであろう。しかしその二人とも、両親には結婚を猛烈に反対されたという。その反対を押しきって二人は結婚し、アメリカへ渡ったのだ。かなり多くの日本女性が、理想と現実の大きな隔たりに幻滅を感じて失望してしまったように、ここでも二人のうち一人が離婚している。
現在は生活に何の不満もないのだが、カズコさんは子供にもう手がかからくなり、ノブコさんは子供がいない。そこで何か新しい仕事でもしてみようかと思い出した二人がぱったり出会って、たちまち意気投合し、どうやら「カブキ」の開店にこきぎつけたというのである。
「私たち二人とも、それぞれの主人に反対されましたわ。酒類販売許可のついているお店なのでね」
つまり二人は、かつて両親の反対を押しきってアメリカ人と結婚し、今また夫の反対を説得してこのお店を開店したのだ。
「だから、意地でも成功させなければね」と二人は話し合っている。モンタナからやってきた若くて腕のいい板前さんを加え、今では七人もこのお店で働いているのだ。
日本女性の心意気というべきなのだろうかいずれにしても、お客は大部分が白人だというから、このお店の繁昌は、そのまま日米交流の小さな縮図である。
それから一週間ばかり後で、テキサス州サンアントニオの美しい運河のほとりで休んでいると、突然きれいな日本語で話しかけられた。
「日本の方ではないでしょうか。あそこにいる御夫婦はどうも日本の方のようだ。懐かしいだろう、お前、行って話しておいで、と主人がいうものですから」
と中年の女性がいった。見ると、運河のほとりに並んだ出店の一角に、陶器を並べて売っている優しそうな男の顔が見えた。彼女の夫は長年軍隊に勤めていたが、最近定年退職をして気候のいいこの地に移り、妻の制作した陶器を並べて、のんびりと旅行客相手に商売をしているのだという。
話をしているうちに、運よく二人の娘さんまでやってきて、一家四人でカメラに収まってくれた。二人とも大学の学生で、少しは話せるように日本語の勉強をしているのだそうだ。
考えてみると、終戦後まもなく日本の女性と結婚をしたアメリカ兵たちは、その後どんな職業についても、そろそろ定年退職の時期を迎えているのだ。
さらにそれから数日後、アリゾナ州の砂漠に囲まれた町ツーサンで、アメリカ人の友人に連れられて、最近開店したというたった一軒の日本レストランに案内された。入口に小さな鳥居があり、なかはかなり広かった。開店まもないせいか、日曜の夜でも客の数はまばらだったが、畳の上の琴をみて、妻は思わずその前に坐り、二、三曲弾き始めた。
この店の奥さんも、御主人はこの町の大学の先生だそうで、家のなかでブラブラしていてもしようがないというので、この仕事を始めたという話だった。
どうやら、政府や経済界のいう政治とか貿易とかだけが、日米関係の中心である時代は終わっている。民間のこういう細やかな交流こそが、民衆レベルでのもっとも大切な相互理解の要素であり、結局これからの日米関係の中心になっていくのではないだろうか。
アメリカ人と結婚するという形ではなくて、第二次大
社会の表層と深層
「近代強奪貴族の」の誕生 P.229
ニューヨーク市マンハッタンの中央を南北に走っている五番街は、流行の最先端をゆく華やかな街路で、ここに住むことができる人びとは、その住所だけでも、限られたごく一部の金持ち階級であることを物語っている。もう一昔前になるが、いまは亡きギリシャの富豪オナシスと結婚したジャクリーヌ・ケネディが、その時まで住んでいたのもこの五番街だった。
その五番街の、しかも六〇丁目前後のもっともすばらしい地域に、ヴァンダービルト一族の大邸宅が七つも建てられたのは一八八〇年代のことである。
当時の代表的な建築家リチャード・ハントが、ウィリアム・ヴァンダービルトのために建てた十五世紀フランス風の大邸宅や、ジョージ・ポストというこれも著名な建築家が、コーネリアス・ヴァンダービルトのために建てたレンガと石の大邸宅は、なかでも有名である。これらの建物は、みな当時の金額で三〇〇万ドルをこえるものであり、しかも内部は、ヨーロッパやアジアの各国から集めた絵画、彫刻、壺、敷物などで、けばけばしく埋まっていた。
この一族は、みな鉄道経営でのし上ったにわか成り金で、ニューヨークの他にも百をこえる部屋のある大邸宅をロングアイランドに持っていたり、寝室だけでも四十もあるフランスの城のような建物をアッシュヴィルの建物などは、二三〇平方マイルもの私有地のなかにあったので、農務長官が自分の省に割りあてられる予算よりも、ヴァンダービルトが個人の山林のために使っている金額の方が多い、と嘆いたのは有名な話である。
しかしなんといっても、ロードアイランドのニューポートに建てた二つの大邸宅は、たいていのアメリカ人の腰を抜かせるのに十分だった。二つとも絢爛としたヴィクトリア朝風の城のようなもので、あるいは宮殿といったいいかもかもしれない。
私もアメリカ人のk見物人にまじって、その内部を見てまわったが、十九世紀の終わりに新しい貴族階級が誕生したのをまざまざ見る思いがした。そのうちの一つは、夫人が誕生日のお祝いに夫から贈られたもので、内部の装飾を加えると、当時の金額で一一〇〇万ドルもしたというのだ。
ところがヴァンダービルトのような金持ちは、他の産業分野にまだまだ何人もいたのである。鉄鋼王といわれたアンドルー・カーネギーは、一九〇〇年の一年間に、個人収入が二千数百万ドル、しかも所得税はなかったのだ。だから、ニューヨーク最高のホテルといわれるウォルドフ・アストリアに四十人の客を招待し、二十種類もの料理を揃え、贅を尽したディナーで一晩一万ドルを支払った人間の話を聞いてもさほど驚かなくてもいいのかもしれない。
しかし今から八十年も昔の一万ドルが、一体今ではどのくらいの金額に相当するものか、私には見当もつかないが……。
当時石油王ジョン・ロックフェラーの広大な敷地のなかには、八十近い建物があり、自動車が金持ちだけのものだった時代に、五十台分のガレージがあったという。もっと驚くことは、いつでも自由にゲームが楽しめるように、全部で一〇〇キロをこえるゴルフ・コースが準備されていて、ときには千人以上の使用人が、その敷地のなかに住んでいたというのである。こういう百万長者がどのくらいいたのか、正確にはわからない。しかし、建国百年祭を迎えた一八七六年頃、その数はすでに全米で一千人にも達し、十九世紀の終わりには、その数が五倍にもふくれ上がったことは確かだった。
金融資本家の頂点に立ったジョン・モーガンは、五番街の隣りのマジソン街に、世界の名作を集めた大理石の邸を構え、ロンドン郊外にある邸にもヨーロッパ絵画のコレクションを作って、多くの芸術愛好家をうならせた。
彼ほどでないにしても、鉱山を掘りあてて一夜で成り金になった者もいれば、それぞれの業界を独占するくらいの大企業に発展する者もあった。
ウォール街を中心にした社交界へ入ることが、新しい成り金たちの社会的地位を認めるシンボルになったのだ。一万ドルもかけて中世の鎧を黄金で作り、それを身につけて舞踏会に出かけた者もあったという。つまり当時のアメリカでは、政府が企業に何らの干渉もしなかったので、資本主義がまるで実験室のなかで培養されるように、純粋に発展したのである。
この頃の実業界の百万長者たちは、人びとは中世の封建領主になぞらえて、「近代強奪貴族」とよんだ。中世に農奴たちが貢物を領主に献上したように、今では農夫や労働者や小さな小売商の店主などが、独占形態を完成した新しい「強奪貴族」たちに、低賃金とか、利子とかいう形をとって、貢物を払わなければならない、というわけである。こういう強奪貴族のなかには、自分がそのまま政治家なってしまう者もいたが、たいていは政治家を陰から金であやつるようになった。彼らは、いつでも自分のいうことをきく議員たちを、十人くらいはポケットのなかに収めていたといわれている。
リンカーンは南北戦争がまだたけなわの頃、ゲティスバーグの戦場を訪れて、「人民の、人民による、人民のための政治」というあの不朽の演説をしたが、それから二十年後には、「人民を治めるための、ボスによる、実業家のための政治」となってしまったのである。
「荒馬乗り連隊」を指揮したセオドア・ローズヴェルトは、たしかに対外的には棍棒を振りかざした帝国主義者であったが、こういう傾向には激しい敵意を抱いていた。
この時代のことを書いた彼の自伝のなかに、次の部分がある。
「個人主義的な物質主義が荒れ狂った時代で、個人の完全な自由は……実際問題として、強者が弱者を食いものにする完全な自由を意味していた」 2025.04.11 記す
世界を支配するウォール街 P.235
ここに驚くべき数字がある。
本社はニューヨークにありながら、利益のなんと七〇%を海外であげている会社があるのだ。百カ国あまりの国に約二百五十もの支店をもっているという。ファスト・ナショナル・シティ・バンク改めてシティバンクが、その会社である。各国通貨の取り扱い、各国事業への融資、そのうえ石油の代金で豊かになったアラブ諸国からはオイルダラーの流入など、まさに金融による世界戦略の最先端に立っている。
この超巨大銀行も、もとを調べれば、一八一二年にアメリカがイギリスと戦争を始めた年、ニューヨークに誕生した小さな企業にすぎなかった。それがイギリスとの戦争に触発された産業革命の波に乗り、南北戦争後はおもに鉄道、鉄鋼、石油など急激に膨張した諸産業に融資し、自分もまるで雪だるまのように大きくなったのである。
海外にも投資の対象を探すようになったのは主として米西戦争以後のことで、二十世紀へ入ってから少しずつ中米諸国へその触手を伸ばしはじめた。一九三四年から三六年まで活動を続けた上院のナイ調査委員会の発表によると、アメリカが第一次大戦に参加したのは、世界の民主主義を救うためではなく、むしろ金融業者や武器製造者などが利益を守るために策謀したからだ、ということである。つまり第一次大戦当時、すでにアメリカの金融業界や製造業界は、自国のなかだけの限られた範囲から大きくはみ出して、利潤を求める対象を全世界に広げはじめていたのだ。
海外で高収益をあげている例は、他にいくらでもある。たとえば今や世界最大の石油会社となったエクソン、海外収益率は六二%、やはり本社はニューヨークで、事業を進めている国は百カ国以上にのぼり、三十四カ国に六十七の製油所があり、世界最大のタンカー船隊を持っているという。この会社は、創立されてからまだ百年もたっていない。一八八二年にロックフェラー一世がオイル・トラストの中心的な存在としてつくりあげて以来、二十世紀に入ってトラスト規制法のために解体させられながらも、本体は依然として世界最大の石油会社の実質を崩さなかった。
ゼネラル・モータズ(GМ)などは、もっと若い会社だ。それなのに年間収入は十あまりの国を除けば、世界のどの国の収入にもひけをとらないという。なにしろ売上高は、アメリカでもっとも豊かな北東部十一州の一般収入の合計よりも多いというのだから、ちょっと信じられないほどである。創立は第一次大戦中の一九一六年で、それから十一年後にはもう先発のフォードを追い越して、世界最大の自動車製造会社に躍り出た。
その頃すでにアメリカ国内での需要は頂点に近づいており、ヨーロッパ諸国への輸出を狙ったが、関税引き上げで抵抗されたため、部品を現地で組み立てるというノックダウン方式を採用して対応し、今では全生産台数の三〇%を海外で組み立てているという。
こういうアメリカ企業の海外進出は、第二次大戦以後とくに際立っている。一九六〇年代には十年足らずのうちに、アメリカ企業の直接海外への投資している金額は、三三〇億ドルから六五〇億ドルに飛躍した。しかもこれは、いまなお一日一〇〇〇万ドルの割合で増え続けているのだ。
国内では業界が寡占の状態にあり、国外にも無数の国に支店を設けているような超巨大企業は、一つの会社というよりも、一つの国家というに等しい。取り扱っている金額の大きさ、政治的、社会的な影響力の広さなどからいって、これらに匹敵できるのは、世界のなかでもおそらく少数の大国だけであろう。しかもこれらの巨大企業は、合衆国という世界最強の国家の権威によって、しっかりと守られている。その象徴的な光景を、私たちはマンハッタンの南端、ウォール街に見ることができるのだ。
アメリカの、さらに全世界の金融界に対して決定的な影響力をもつこのウォール街も、三百年あまり前にこの島の南端にオランダ人の植民地となったとき、インディアンの襲撃を防ぐために木の柵をめぐらせたウォール(妨害)の跡である。
※挿絵の写真説明:ウォール街:正面がハミルトンの墓のあるトリニティ教会
アメリカ最大の金融資本として歴史にその名を刻んだモーガン銀行もここにあるし、シティバンクのライバル、チェース・マンハッタン銀行の本拠もまたここにある。
今このウォール街を歩くと、アメリカ人の一人ひとりが株に気を奪われて大騒ぎをした一九二〇年代の熱気が、ふと甦ってくるような気がする。月給日にはサラリーマンが必ずおめあての株を百株くらい買って帰った時代、病院へ行っても患者が株の話しか医者にしなかった時代、犯罪や国際問題よりも、株の相場が重大ニュースになった時代……。
またウォール街の一角には、一六九六年に建てられたというトリニティ教会の古い建物がある。高層ビルに囲まれて、谷間のようにひっそりとしたその墓地には、ワシントンに信頼されて初代財務長官となったアレクサンダー・ハミルトンの墓が静かに横たわっている。彼は独立宣言書を書いたジェファソンとことごとく対立し、アメリカに初めて二大政党をつくった一方の旗頭であるが、同時にアメリカ資本主義育ての親といわれる人でもあった。
そのハミルトンはいま、自分の墓を取り巻く摩天楼のおびただしい群れを眺め、アメリカ資本主義の世界的発展に喜んで拍手を送っているいるのであろうか。それとも、自国のなかだけではあきたらず、世界各国に利潤を求めて手足を伸ばしている貪欲さに、むしろ顔をしかめているのだろうか。
同じニューヨークを基盤にする連邦党のハミルトンと
自動車文明の光と影 P.241
日本もいつの間にか、同一面積あたりアメリカの八倍もの自動車をもつ、名実ともに自動車文明の国になってしまった。その他の点でも、日常生活がアメリカ化されて、日本の生活様式はひどく類似してきたように見える。それでは生活感覚も似てきたかというと、これがとんでもない間違いなのである。
最近、日米両国で同時に行われた世論調査によれば、テレビ、冷蔵庫、自動車、新聞、電話など、現代生活に欠くことのできない五種類の品物の生活必要度を順番に並べさせたところ、アメリカでは自動車が第一位で、日本では逆に自動車が最下位になったという。実際にはこれほど違うのだ。アメリカでは自動車を持たないほど日常生活で決定的に不便なことはない。バスや地下鉄が発達しているニューヨークのマンハッタンなどを除いて、アメリカでは自動車を持っていないことは、ほぼ人間ではないことに等しい。
一体どうして、これほど自動車に依存する社会ができ上がったのだろうか。私の推定によれば、おそらくその原形は、馬車という形で、自動車が発明される以前から、すでに出来上がっていたのではないだろうか。
今から百年前のピクニックの写真を見ると、一頭立ての小さな馬車がたくさん並んで写っている。馬車があれば人びとは、玄関の前から歩かずに友人の家を訪ねることができたし、買物に行くこともできた。そればかりか、気の遠くなるようなこの大陸を横断して、人びとは東部から西部へ、馬車に乗って移動することもできたのである。日本では参勤交代で地方から江戸へ人びとが歩いて移動していた時代に、アメリカではもう馬車がどの家庭でも、生活必需品になっていたのだ。
おそらくそれは、アメリカという国の途方もない広さに原因があるだろう。ニューヨークからサングランシスコまでの距離は、パリから東に向かって、東欧諸国はもちろん、モスクワも越え、なんとウラル山脈に達するほどなのである。こういう国では、地方自治が発達するのも当然の話だし、便利な交通機関の必要度もそれだけ高いといえるだろう。その上、この国では、どんな発明品もすべての人が使えるようにという一種の平等性が、建国いらい人びとの心を捉えていた。今から六十余年前ヘンリー・フォードはT型大衆車を発表するに先立って、次のような声明を出している。
このフォードの考え方の平等性は、イギリスの機械工学が量より質の問題に取り組んだのに対し、初めて大量生産という形で現れた。コンベヤー・システムを導入し、大胆に規格の標準化をはかったのがそれである。アメリカ社会はヨーロッパ諸国に比べて人手不足に悩んできたので、技術の発達によってそれを補う必要が、一層切実な問題でもあったのだ。
こうしてアメリカの自動車産業が先鞭をつけた大量生産システムは、その後の世界を一変してしまったといっていいかもしれない。つまり科学や技術についての考え方を、根本から変えてしまったからである。
フォードがT型車を発表してから十五年にあたる一九二三年には、典型的なアメリカの町である「ミドルタウン」で、もう三世帯のうち二世帯が車を持ち、なかには風呂もない貧しい家でさえ車を持っていた例がたくさんあって、調査にあたったリンド夫妻を驚かせたという。
いま世界中には、三億五千万台に上るあらゆる種類の自動車が走っているが、そのうち八〇%に当たる二億七千万台は、アメリカの自動車工業が生産したものであり、いかにアメリカが全世界的な自動車王国になっているかが分かるだろう。
振り返ってみるとアメリカの歴史は、人びとの移動の歴史であったといえるかもしれない。開拓者たちの東部から西部への移動、南部黒人の北部都市への移動、そして今でもアメリカ人は、世界中のどの国民よりもよく移動する、いつも、よりよい生活を求めて……。
しかし同時にアメリカ人は、この便利な自動車の普及に対する代償を確実に払わされている。
たとえば、一七七五年独立のために戦争の火蓋を切っていらい、戦争に参加して実際の戦闘のために死んだアメリカ人の総計は約六十四万人なのに、二十世紀へ入ってから自動車事故で死んだ人の数は、実に百七十万人にも上っているのだ。
またアメリカのように広大な土地をもつ国でさえも、排気ガスが問題になり始めてからすでに久しい。飛行機から眺めると、どの都市も上空を厚いスモッグに蔽われていて、時には晴れているのか曇っているのか分からないようなこともある。かつてニューヨークのマンハッタンに住んでいたころ、五月下旬の金曜日に突然猛暑がやってきて、オフィスのひける午後五時ごろ、立体化された駐車場から一時にはき出される車の洪水で、あらゆる道という道が埋まってしまった。
私はその時の恐怖感を、今も忘れることができない。ニューヨークの市街路は直線なので、前後を車に挟まれて動かなくなったバスの窓から私が見たのは、ビルとビルの間の空間を蔽いつくした車の大波であった。どの車も、三十分ばかりはピクリとも動かなかった。皆がいっせいにマンハッタンを脱出しようとすれば、こういうことになるのだ。つまり道路の面積よりも、車の占めようとする面積の総計の方が、そのときずっと多くなったのである。あれは、車中心の社会が行き詰まった果ての、車地獄の風景であったのかもしれない。
結局自動車というものも、ちょうど原子力が平和の目的のためにも、また人を殺すためにも使えるのと同じように、いつまでも両刃の剣として存在し続けるのであろうか。
私は、一九七二年に太平洋岸から大西洋岸まで往復横
諸悪の根源、飲酒を禁じよ! P.247
本条が承認されてから一年後からは、アメリカ国内およびその領土内で、飲むためにアルコール飲料を製造、販売または運搬することを禁止し、さらにアルコール飲料の輸出入を禁止する。
この大変な内容をもった憲法修正案が議会で成立したのは、一九一七年十二月のことで、その後必要な数の州の承認を得、一九一九年一月に公布された。条文の示す通り、それから一年たった一九二〇年一月から、いよいよアメリカは禁酒の時代に入ったのである。
専制主義の国で独裁者がこういう憲法を作るのならばともかくとして、アメリカのような民衆主義の国で、一体どうしてこのような禁酒法が施行されるようになったのだろうか。「ローマは一日にして成らず」という古い諺の通り、この驚くべき憲法修正案が成立するまでには、長い禁酒運動の歴史がアメリカにはあったのである。すでに独立する以前の植民地時代から、各地域ごとに教会が中心となって、禁酒の法律を成立させようと運動を展開していた。牧師たちは、飲酒をもっともひどい社会悪の根源と考えていたのだ。
一八三〇年代には運動が高揚し、アメリカ禁酒促進協会やアメリカ禁酒連盟などが作られたほどで、一八四五年までに北西部の准州ではアルコール飲料の販売を禁止し、中西部の一部でも、部分的に禁酒法を実施するところがでてきた。しかしこういう運動は、女権拡張運動のなかに融けこんだり、奴隷解放運動のなかに吸収されたりして、再び禁酒運動が高まったのは南北戦争以後である。
一八七四年には女性クリスチャン禁酒連盟が、一八九三年には酒場反対連盟ができ上がった。こういう人たちは、南部や中西部の農家を一軒一軒歩き回るほど熱心だった。
「皆さん、酒を飲むのをやめましょう。酒さえやめれば、今より一層よく働くようになり、こういう貧乏からも抜け出られるでしょう。このままでは体によくないし、第一家庭も破壊されてしまいますよ」
と彼らは説いて回った。
一八七二年からは毎回の大統領選挙に、禁酒党という政党が候補者をあげて戦うようになる。この政党にいわせると、犯罪も、暴力も、怠惰も、すべて飲酒が原因であり、飲酒は社会のあらゆる悪の根源をなすものだった。そのため、第一次大戦へアメリカが参戦する以前に、実に二十一州が各州ごとに禁酒法を実施しはじめいたのである。
その上、大戦への参加は、一層全米的な禁酒運動をもり上げた。禁酒による食糧の節約、作業効率の向上、戦意の高揚などが直接の目的で、この運動は連邦議会へ猛烈な圧力をかけ、とうとう全米的な禁酒法を成立させてしまったのだ。
一九二〇年、いよいよ禁酒法が実施されることになったとき、この運動で活躍してきた人たちは、これで清潔な生活が保障されたと信じ、
「やれやれ、どうやら終わったぞ」
と考えたものだが、実は終ったのではなく、むしろ何かが始まったのである。
H・アスベリ―はこの時のことを次のように書いている。
禁酒法が発効したその日から、実際にはもぐり酒場があちこちにできたのだが、それでもなお、もぐり酒場第一号の栄誉をになったのは、ニューヨークの中心、マンハッタンのグリニッジ・ヴィレッジで、安ホテルを経営していたバーニイ・ギャラントという男だということになっている。彼は入り口のドアに小さな四角い窓をつくり、内から外を覗いて、客を十分確認してからなかに入れた。その酒場の会員証をもっているか、あるいは常連の客の紹介でもなければ、なかなか通そうとはしなかったのだ。
もぐり酒場は、たちまち全米にひろまった。禁酒法の時代を通じて、ニューヨークだけでも三万軒あまり、アメリカ全体では二十万軒をこえたと推定されている。
もぐり酒場にもピンからキリまであって、ブロードウェーの夜の女王といわれたテキサス・ギナンがマダムをしているような店では、平気で一晩何百ドルもとったが、安酒場では体をこわしそうな酒を出し、バーテンは賭博や売春の客引きもやるとう有り様だった。
もちろん、それだけのもぐり酒場を支える密造所があちこちにあったのだ。密造のウイスキーをムーンシャインというのは、夜の月明かりでこっそりと醸造したり運搬したからである。
人びとはそうして造られた小型のウイスキー瓶を、脚に巻きつけたり、腰のまわりに下げて上衣で隠したり、あるいは空洞のステッキに流しこんだりして、こっそりとパーティを開くのだった。
これを取り締まる警官たちのなかには、買収されて密造や密売を見逃している者も多かったが、専門の禁酒取締官のイジーとモーの二人のコンビのように、数年間で押収した密造酒が五百万本、逮捕者千人あまりというめざましい成果をあげた者もあった。
最近ではさすがにそういう地域も減っているが、私自身もジョージア州では酒類の製造および販売を禁止している郡(ドライ・カウンティ)に住んでまごまごしたたことがあるし、旅行中オクラホマ州のある町では、どのレストランも「ノービアー」でびっくりしたことがある。日曜は安息日なので、酒類の販売は認めない、という禁酒法の名残のような規則は、今でも各地で守られているのだ。
今になって振りかえってみると、南部や中西部の農村地帯で高まったこの禁酒法実現への願望は、新興の都市や産業主義、急激な社会変動などに対する、古い禁欲的なアメリカの挑戦だったように思われるのである。2025.04.14 記す
※写真は「禁酒法」に関連した図書:常盤新平『酒場の時代』ー1920年代のアメリカ風俗ー(サントリー博物館文庫) 一九八一年五月二〇日 第二刷
暗黒街のマフィア P.253
「ピーター・ヘネシーというニューオーリンズの警察署長は、州最高裁での証言を数日後にひかえ、自宅の玄関前で猟銃の乱射を浴びて倒れた。この事件の起訴状のなかに、次のような部分がある。
マフィアの構成員は、主にイタリア人とシチリア島人だ。彼らは多くの場合、自分が犯した罪に対する刑罰を逃れようとして、偽名を用いて故国を離れた者たちである」
この事件は一八九〇年のことだから、十九世紀末には早くも組織犯罪が大規模にひろまっていたということになる。それにしてもこの事件には、大きな後日談がついているのだ。
殺された署長はイタリア人のマフィアという秘密結社を追っているところだったので、十九人ものイタリア人が容疑者としてあげられた。ところがかなりはっきりした有罪の証拠があったのに、彼らが雇っていた有能な弁護士のため、全員無罪釈放ということになってしまったのだ。、
激昂した市民たちは、すぐに大規模な抗議集会を開いた。この時六千人もの市民が集まったという。
「法律が無力なとき、人民が委任している権利は、人民の手に取り戻さなければならない。裁判所がやりそこなったことを、人民が直接に行うのだ」
こう叫んだ群衆は刑務所に殺到し、十一人のイタリア人を殺した。刑務所のなかで射殺された者もいたし、外へ引き出されて、群衆にリンチされた者もいた。これが険悪な国際問題にまで発展する。イタリア政府は公式に抗議文を出し、大使の召還を命じた。結局アメリカ政府は十二万五千リラの賠償金を支払って、ようやく解決をみたのである。いいかえれば、それほどマフィアとイタリア系移民の関係は深く、またイタリア系移民は他の人びとから敬遠されていたのだ。一体どうしてそんなことになったのだろうか。
マフィアというのは、二百年も前にシチリア島にできた秘密結社で、初めは暗殺や暴力を手段とする一種のレジスタンス運動だったのだという。しかし、その後性格を変えて犯罪的な要素だけが多くなり、シチリア島人の移民と一緒に、アメリカ各地の大都市に入り始めたのである。
不思議なことに、このイアリア系移民と日系移民は、似ていることが少なくない。両方とも集団で大量に移民が入ってきたのは、一八七〇年以降である。量はもちろんイタリア系の方が一ケタ多く、一九三〇年までの移民数は四百五十万を越えている。一世、二世、三世などの比率は、両者ほぼ同じである。ところが十九世紀末から、北部や中部イタリアよりも、後進地帯といわれるシチリア島を含んだ南部イタリからの移民が激増した。たとえば移民の頂点に達した一八九九年から一九一〇年までの十二年間に、イタリア系移民二百三十万人のうち、実に百九十万人までが南部イタリアの出身だったという。
南イタリア人は貧しい農夫が大部分で、方言も強く、一般に視野が狭くて、自分の村以外の者をストレインジャーとして取り扱ったが、その反面、ファミリー単位の結びつきがとても密接だった。母が子供を可愛がるあまり、息子がなかなか家を離れられない。こういう特色は犯罪組織のなかにも現れていて、マリオ・プーズオの『ゴッドファザー』では、血のつながりがかなり美化されていたといっていいだろう。
ともかくシチリア島を含む南部イタリアの移民たちは、アメリカへやってきてもすぐに有利な仕事は残されていなかったから、初めは未熟練労働者として、貧しい生活を送らなければならなかった。
私自身ニューヨークで道を尋ねた相手の若者が、イタリア語しか話せない移民だと知って、びっくりしたことがある。彼らは第一カトリック教徒だったし、言葉をはじめ風俗習慣が違うし、その上みな貧しく教育も低かったから、先着のアメリカ市民からはかなり毛嫌いされるようになった。一九二〇年代に無政府主義者のサッコとパンゼッティの二人が、身に覚えのない殺人事件で起訴、処刑された「サッコ・パンゼッティ事件」も、イタリア系移民に対する差別がその根底にあったといえるだろう。
N・グレイザとD・モイニハンの『人種の坩堝を越えて』によれば、一八九〇年にニューヨークでは、イタリア系移民が五%に過ぎなかったのに、一九二〇年には一四%となり、一九三〇年以降は市民の六人に一人はイタリア系になったという。シチリア系の犯罪組織が、ニューオリンズ、ニューヨーク、シカゴなどの大都市に侵入してくるのを、誰も防ぐことはできなかったのだ。
※写真は「マフィア」に関連した図書:ゲイ・タリーズ 常盤新平訳『汝の父を敬え』1973.11.25 2刷 新潮社
たとえば、一九三〇年、『シカゴ・トリビューン』紙の警察担当記者、アルフレッド・リングルが路上で背後から撃たれて死んだ事件があった。生前の勇敢な報道ぶりを知っていた市民たちは、彼の死を悼んで二万五千人も葬儀に参列した。しかし、死後判明したところでは、実はリングルは組織暴力から信頼されていた仲間で、死んだときもカポネから贈られた高価なダイヤモンドのバックルを身につけていた。かつて政府の下で仕事をしていた法律家が、今ではマフィア経営の企業を守るために活躍している例も少なくないのだ。
オルメタとよばれるマフィアの掟はきわめて固く、殺されても口を割らないので、その内情は分かりにくい。そればかりか、マフィアの存在を信じようとしない人びとも多く、時には取り締まりの総元締めともいうべき司法長官さえ、その例外ではないのである。
初めてこの犯罪組織と真剣に取り組んだ司法長官は、一九六一年に就任したロバート・ケネディで、彼がフーヴァーBI長官さえその存在を信じていないことを知り、デスクを叩いて激怒したのは有名な話である。
二十年代なかばにその職を退いたニューヨーク警察署長レイモンド・マーティンは、マフィアの存在を信じないような司法長官が現われないことを望む、といっているが、組織暴力が存在していることは、国民のなかに幾分かはそれを黙認する堕落した要素がひそんでいて、ある程度は国民全体の責任ともいえるであろう。
一九二〇年代から三〇年代にかけて、中西部一帯を荒しま
リンチ横行の文明国 P.259
「リンチ団が結成され、三人の黒人をこれから広場でリンチする予定」
こんな広告が新聞に出たとしたら、今では大変な騒ぎとなるだろう。
ところが十九世紀末(明治中頃)のアメリカ南部では、新聞に予告も出さない場合でも、事前に人びとに知らされ、公衆の面前で堂々と無残なリンチが行われるというようなことが、それほど珍しくはなかったのである。
広告ではなく、新聞の記事としてはもちろん無数にあらわれている。
『ニューヨーク州・トルース・シーカー』紙、一八八〇年四月十七日付、
『シカゴ・トリビューン』紙、一八九五年十一月二十二日付。
『ニューオリンズ・タイムズ・デモクラット』紙、一九〇〇年三月二十四日付。
「テネシー州ライプレィ発。今朝、町の中央部で、ルイス・ライスという黒人の死体が木の枝から下っているのが発見された。ローダデイル郡の巡回裁判所の裁判で、白人を殺したという容疑の黒人に対して有利な証言をしたため、暴徒が怒り狂って彼を殺したものである」
リンチの統計などあまりあてにはならないが、それでも一八九〇年代の十年間は、毎年少なくても百人、多い年は二百人を超える人びとがリンチで殺されたという。多分、実際にはもっと多いだろう。被害者の中には白人もいるが、もちろん黒人が大部分である。
白人は完全に黒人たちを自分より低い存在とみなしていたから、黒人がその低い生活に甘んじている限り、とくに危害を加えないが、ひとたび自分たちが引いたカラー・ラインを突破してくる黒人が出ると、たちまち見せしめのような形でリンチを行なうのだ。だからウェストポイントに初めて黒人が入学すると、名誉ある陸軍士官学校の歴史を汚した黒人というわけで、たちまち暴徒に襲われることになる。
それにしても、時には白昼堂々とリンチを行ったりするのは、その地方の世論がそれを黙認しているからだといわなければならない。
『ニューヨーク・ワールド』紙、一九〇〇年十二月三十日付。
だから、官憲(白人)がリンチを見ても見ぬふりをするのも、当然ということになる。数年前に亡くなったコロンビア大学のホーフスタッター教授は、その著書『アメリカの暴力』の中で、リンチの実際をなまなましく、次のように描写している。
また『リンチの百年』という本によると、南北戦争が始ま前の一八五九年からの一世紀の間に、リンチで殺された黒人の数は、わかっているだけでも最低約五千人に及んでおり、氏名、日付、場所が全部記されている。
十九世紀末といえば、アメリカの独占企業は繁栄の頂点に達し、工業力では世界の先頭を切っていたイギリスに追いつき、そして追い越しはじめていた。夢のある国として、東欧や南欧から移民が殺到していたところである。しかし、皮膚の色が違うというだけの理由で、毎年二百人もの人が殺され、おそらくその約十倍の人々が傷を負わされているような社会が、一体本当に夢のある文明社会といえるだろうか。二十世紀に入ると、黒人がどっと北部にも移住するようになるので、リンチや人種暴動は南部だけでなく、全米にひろまることになるのだ。
思うにアメリカには、何か犠牲者を探し出して、多数派が狂信的に荒れ狂うような反理性的伝統がある。自分たちだけの力で無から創りあげた国だけに、他の国ほど国家の中心になるものが具体的な形で存在していないから、そのためにかえって求心力を探し求める偏狭な愛国心が、理性を無視した異常な現れ方をするのではないだろうか。それまでにも、一八二〇年代にはフリー・メーソンとう結社の人びとが、一八四〇年代には新しく流入したカトリック教徒のアイルランド系移民たちが、そのつど一般大衆のヒステリックな行動の犠牲になってきた。今度はそれに人種差別の要素が加わって、一層残酷でサディスチックな暴発となったのである。
しかし、第一次大戦が終わった頃から、リンチへの抑止力が少しずつ効果をあげてきた。一九三一年にはアラバマ州スコッボローで二人の白人女性が九人の黒人青少年に暴行されたといわれる事件が起こったが、黒人たちはリンチの危険を何度もまぬかれ、とうとう全員が無罪判決をかちとっている。つまり、でっちあげだったのである。
その後、しだいにリンチの数は減少して、一九五二年、初めてリンチなしの”輝かしい記録”を残した。
だが、それからも公民権闘争が高まるにつれリンチは再び増加する。まだ多くの人びとは一九六八年にキング博士がある白人に暗殺されたのを記憶しているだろう。映画「イージー・ライダー」で、主人公たちが無残な殺され方をされるのを見ても、イエスタデイはまたどこかで、ひそかに息づいているのである。
一八九二年三月、ミシシッピ川に面したテネシー州の
ブルースからジャズへ P.265
十九世紀の末、南部を中心に黒人に対するリンチが荒れ狂っていた頃、黒人には黒人としての、新しい力が湧きはじめていた。南北戦争のあとで各地にできた黒人大学からは、卒業生がどんどん世に送り出されていて、そのなかには両人種から尊敬を集めたブッカー・ワシントンのような新しいタイプの指導者もうまれてきていた。建築、農業経営、印刷、精肉、製靴、看護などという分野で、技術を身につけた黒人たちが、初めのうちは少数ながら、中産階級を形成しはじめていたのである。
その上、黒人たちはちょうど同じ頃、非常に豊かな才能をある分野で発揮するようになった。それは限定されたプロだけのもつ才能というよりも、黒人大衆全体にしみこんだ習慣、または生活様式といってもいいものから生まれた特有の音楽であった。たとえば、一八八〇年代の終わり頃までに、黒人霊歌はほとんど全米にくまなく広まっていた。
奴隷時代を通じて黒人は、キリスト教への信仰を求められたので、南北戦争以前から自由な黒人の間には、リチャード・アレンのように自ら牧師となったり、教会を建てたりする者が現れていた。
リロイ・ジョーンズによれば、キリスト教は奴隷のしつけとして使われたのに、奴隷たちにとってキリスト教は、耐えがたい日常生活のなかで耐える力を与えてくれる精神の糧となったという。
旧約聖書時代の迫害されたユダヤ人の悩みは、そのまま奴隷制度のもとで苦しむ黒人の悩みと重なりがあった。イスラエルの民を引き連れてエジプトを脱出したモーゼにあやかって、奴隷たちをくり返し北部に逃がしたハリエット・タブマンが、黒人たちの間で「女モーゼ」とよばれたのはそのためである(一九七ページ参照。)
そして、アフリカから強制的に連れてこられた黒人と、キリスト教と、奴隷制度の過酷な生活とが重なって、黒人霊歌という音楽が創りだされた。実に霊歌は、奴隷が割りだした最初の純粋なアメリカ音楽といっていいだろう。その黒人霊歌は、一八八〇年代に土着的な実用の段階から、洗練された一つの芸術的な形式へ移りはじめていた。と同時に、黒人民謡や労働歌、叫喚歌、霊歌などすべての黒人の歌は、その頃からはっきりとブルースの形を帯びてきたのである。
ブルースの生れた背景も、奴隷生活や、自由になってからも一向に楽にならない農村生活などで、黒人がそれまでに作りあげてたすべての音楽を母胎にしていた。文字があまり重要ではない生活だったので、喋ることと歌うことはあまり区別がなく、トーキング・ブルースでは一日の仕事を終わった黒人たちが、ギターやバンジョ―を小屋の前にもち出し、歌と語りをおりまぜ、一つの分野を作ったのだ。
ブルースの父といわれるようになるメンフィス生まれのウィリアム・ハンディは、自分のあらゆる経験から、ブルースとよばれる音楽を完成の域に高めていく。ある時は道路に寝ながら、貧しいギタリストたちが、「イースト・セントルイス」という曲を弾いているのを聞いたり、鉄道の駅で関節のゆるんだような黒人が、ポッンポッンとギターを鳴らしているのに耳を傾けたりして、感動に身を震わせた。こういう体験はみな、彼がその後、「セントルイス・ブルース」を作曲するときの血ともなり、肉ともなったのだ。
ブルースはソロで演奏され、個人的色彩が強い。抑圧された生活からにじみ出る哀歓が、感じるままに演奏され、歌われる。一九二〇年にマミー・スミスが「クレイジー・ブルース」というレコードを作ってから、ブルースは南部の農村地帯から他の地域へ、大きくひろがった。
しかしその頃には、ニューオ―リンズを中心に発展してきたジャズが、新しい生命力をもった黒人音楽として、一躍全世界の注目を浴びた。第一次大戦中、前線を慰問して回った黒人ミュージシャンたちは、ドイツが毒ガスを使っても占領できなかったフランスを、たちまちジャズで征服してしまったからである。
ジャズのふるさとニューオ―リンズでは、今でもラテン系の官能の色濃い中心街の古めかしいプリザヴェション・ホールのなかで、夜ごと黒人ミュージシャンたちが熱っぽいデキシーランド・ジャズを演奏して、多くの白人聴衆を魅了している、一体どうしてここにジャズが生れたのだろうか。おそらく、かつてスペイン領だったり、フランス領だったりした経験とか、アフリカや西インド諸島から輸入されてくる黒人たちの奴隷市場があったりしたことが、多様な異文化間の混血を深め、ジャズ発生の母胎をつくったのではないだろうか。その上この都市には、スぺイン人やフランス人と血の混じったクリオールという黒人層が古くからあって、かなり高い文化を受け継いでいた。南北戦争以後、彼らは歿落して一般の黒人なみになってしまったが、黒人たちの間には社交的にも文化的にも、相互扶助の組織がたくさんできていて、歌や音楽がその媒体になっていた。葬式のときのバンド演奏もこうして生まれたものであり、「賢者の行進」はその典型的な申し子である。
その後、ジャズは中心がシカゴに移り、さらにニューヨークにも波及していくが、十九世紀末から二十世紀はじめにかけて、黒人特有の文化が、一面では悲哀に満ちて、他面では陽気に生命力をほとばしらせながら、全世界に向かって溢れ出たのだった。
それにもかかわらず、今でもなお黒人文化が、公式にはたびたび黙殺されている。一九六八年に暗殺されたキング博士は、最後の著書『黒人の進む道』のなかで、興味あるエピソードを紹介している。
アトランタのある学校で「アメリカを偉大にした音楽」というプログラムに招待されたところ、さまざまな移民のフォークソングが演奏されながら、最後まで黒人霊歌やブルース、ジャズなどの黒人音楽は無視されたままだった、というのである。黙殺する白人がいても、ブルースやジャズは生き続け、発展し続け、世界に影響を与え続けている。だが、ジャズに熱狂する日本の若者たちも、果たしてどのくらい理解しているのだろうか、ジャズの発生にまつわる黒人たちの悲惨な生活の環境を……。
一九二〇年代、ニューヨークの中心マンハッタンの一角
南北戦争の名将が創案した野球 P.271
今から百十年あまり昔の南北戦争が、実は野球の普及に大切な役割を果たしたのだといっても、信じない人がいるかもしれない。戦争というものは、最前線で敵と向かいあっている時以外、そんなにいつも緊張していなければならないわけではない。むしろ後方部隊は、いざという時の出動に備えて、少しはリラックスしていた方がいいのだ。そんな時、北軍の将兵は、北部にひろがり始めていた野球というゲームを楽しんだのである。
第一、野球を初めて創り上げたといわれるアプナー・ダブルディは、ウェストポイントの士官学校を卒業して将校となり、南北戦争中もあの有名なゲティスバークの戦闘に大活躍をして、南軍の名将ロバート・リーを撃退し、後年戦場に銅像を建てられたほどの人なのだから、野球と南北戦争の関係は、予想以上に密接なのである。
ダブルディはわずか二十歳のとき、ニューヨーク州のほぼ中央部にあるクーパーズタウンという小さな町で、野球を考案したのだといわれている。考案したといっても、もちろん原型となったものがあったはずで、それはイギリスの古いスポーツとして知られているクリケットだといっても、野球を純粋の国家的スポーツだと信じているアメリカ人の自尊心を、それほど傷つけるにはならないだろう。ダブルディが創始者だということは、一九〇七年に組織された調査委員会の結果によったもので、現在クーパズタウンには、野球の歴史の栄誉をたたえる殿堂が建てられている。
ダブルディはその後ウェストポイントを卒業してから、メキシコ戦争では後に大統領となるザカリ・テイラー将軍のもとで戦った。南北戦争が始まると、北軍の数ある将軍の一人として勇名を馳せたのである。ダブルディ将軍が、後方部隊の余暇に野球を奨励したのは想像に難くない。しかしその頃の野球は、もう彼が考案した頃のものとはかなり違っていた。
一八四五年というと、ダブルディが初めて野球を創ってからわずか六年後のことだが、アレクサンダー・カートライトというニューヨークの技師が、それまでの不備な規則に大幅な修正を加えていたのだ。たとえばそれまで菱形だったダイアモンドを正方形にして、一辺をそれぞれ九〇フィトーと定めたのも、この時である。
カートライトはまた野球専門のニッカポッカー・クラブを結成した。南北戦争が始まる三年前の一八五八年には、全米野球選手協会もでき、その年ニューヨーク市の郊外ジャマイカで行なわれたニューヨークス・クラブと、ブルクリン・クラブの試合では、史上はじめて二五セントの入場料をとったという。
しかし、実情はまだニューヨークを中心にごく一部で行なわれていたにすぎず、ましてやプロ野球選手がいたわけでもない。だから、北部各州の将兵が一団となって戦った南北戦争は、野球をひろめる絶好の機会ともなったのである。ダブルディ将軍がそんなに努力しなくても、北軍の後方部隊では、ルールを知っている者が他の将兵たちに教えたから、夢中になってこの新しいゲームに打ち興じたのである。だから、戦争が終わって北軍の将兵が各州に戻ったとき、野球はたちまち北部全体にひろまった。
戦争が終わった翌年の一八六六年、フィラデルフィア・アスレティックスとブルックリン・アトラティックの試合では、チームの人数が現在の通り九人となった。この時は31対12でフィラデルフィアが勝っている。大学間の試合は南北戦争が始まる二年前の一八五九年が最初で、この時はチームが十三人ずつ、どちらかが65点に達すれば勝ちというルールで、アーモスト大学が73対32でウィリアムス大学に勝った。65点に達しても、その時のイニングは終わりまで戦ったので、こういう点数になったのである。ボールは今より小さくて軽かったので、それだけ点が入りやすかったのだろう。
戦争終了後四年目には、全米最初のプロ野球クラブが誕生した。それがシンシナティ・レッド・ストッキングズである。このクラブは翌年にかけて各地を巡回試合し、八十連勝を記録した。ホームランの数は、百五十試合中で百六十九本という記録だった。
日本に伝えられたのは、南北戦争後わずか八年目の一八七三年、明治六年のことで、今の東大の前身である開成学校に赴任したアメリカ人教師ホレイス・ウィルソンが、学生に初めて教えたことになっている。日本での歴史も、意外に長いのである。
ウィルソンは七三年から四年間、開成学校で数学を教えたが、今では本業の数学よりも、野球を伝えた人として名をとどめている。もちろんウィルソンが伝えなくても、アメリカから野球が日本に輸入されるのは、ほとんど時間の問題であったろう。当時は他にも大勢のアメリカ人教師が日本に赴任していたし、またフィラデルフィアのハイスクール在学中に野球を覚えた牧野伸顕のような人が、明治七年には帰国して開成学校に入学し、そこで友人に野球を教えたりしていたからである。
ともかく日本には、西南戦争以前にもう野球の種子がまかれていることになるのだ。
開成学校では、雨の日にもみのや笠をつけて練習したという話なので、輸入した当初からよほど日本人に向いていたのだろう。オリンピック・ゲームには採用されていないほどあまり国際的ではないこの野球が、どうして太平洋をはさんだこの二つの国で、とくに熱っぽく燃え上がったのだろうか。
かつてテレビがアメリカで急速にひろまった一九五〇年代に、それまでラジオを通して尊敬していた大リーグの選手が、実は黒人だったことを画面を通して知るようになっても、白人の少年たちの熱狂ぶりが少しも減りはしなかったという。
アメリカではいま、フットボールやバスケットボールのように、テンポの早いスポーツが野球の人気に追いついている。しかし野球をテーマにしたフィリップ・ロスの『素晴らしいアメリカ野球』のように、破天荒で面白い小説が書かれるのをみると、アメリカの方が日本より、野球が一般生活のなかに滲み透っているといえそうだ。
一八四五年にカートライトがつくったといわれるルー
明治初期の日本の野球用語
OKコラル決闘の真相 P.277
私がはじめて保安官(シェリフまたはマーシャル)という名をしっかりと心のなかに刻んだのは、ジョン・フォードの映画「荒野の決闘」を見たときだった。今でもこの映画が、数多い西部劇のなかでも、最高の名作の一つだと信じている。
荒涼とした半砂漠地帯のなかに、ぽっんとできや小さな町、ひと山あてこむ山師が入ってきたり、牛を追うカウボーイが通っていくだけ。うらぶれた酒場の入り口に立って、外を見まわすワイアット・アープ。静かに流れてくる「いとしのクレメンタイン」の哀愁をおびたメロディ……。
それから私は、しばらくこのワイアット・アープに熱をあげた。第一、実在の人物だし、なんといっても西部開拓史のなかの代表的ヒーローだという印象が、私の心にすっかり焼きついてしまったのだ。その信念が少しばかりぐらついたのは、彼の実際の写真を見てからだった。ヘンリー・フォンダの演じた、あの渋味のある、男らしい、それでいて人間味あふれる情感が、ヒゲの垂れ下った実物の彼の写真をいくら見ていても、なかなか浮かんでこなかったのだ。彼のイメージが一層動揺したのは、八十一歳まで長生きして、一九二九年にベッドの上で平穏に死んだのを知ってからである。
疑いが次々湧いてきた。アメリカでもすでに伝説化しているあの有名なOKコラルの決闘も、実際には果してどんなものだったのだろうか。
事件は、一八八一年(明治十四年)十月二十六日に起った。私がそこへ訪ねていったのは、ちょうど同じころの季節で、雲一つない大空から、南の国の太陽が無遠慮に照りつけていた。トウームストーン(墓石)という奇妙なこの町は、標高一五〇〇メートル、アリゾナの東南部にあり、ニューメキシコにもメキシコにも近い荒野の真っ只中で、今でもここに出かけるのは、容易なことではない。現在の人口は約千二百人、古くからの町の中央には、三、四本のストリートが直角に交わっているだけだった。
こんな退屈そうな場所に人が集ってきたのは、一八七七年に銀の鉱脈が発見されたからで、噂はたちまち尾ヒレをつけて広まった。眼の色を変えた男たちが殺到し、テント、掘立小屋、酒場、ダンスホールが建ちはじめ、いわゆるブーム・タウンがここにもできたのである。
そんなときだから、何をしているかのか分からないようなワイルド・ウェストのならず者たちが集ってきたのは当然のことで、アープ一家とクラウント一家の対立も、決して珍しい出来事ではなかった。ただ、どうしてこの対立が起ったのか。どんな形で決闘が行われたかについては、まさに諸説紛々といったところである。
町の保安官の一人だったヴァージル・アープが、酒場を経営している兄のワイアットやモーガン、それに賭博者でかつては歯医者でもあったドラ・ホリディと連れ立って、クラウント親子とマクローリィ兄弟の合計四人のいる所へ出かけ、相手の武器を取り上げようとしたところが、発砲されたので応戦したという説。
アープ兄弟の方がこっそり駅馬車襲撃の計画を立てているのを、親の方のアイク・クラウントに見られてしまったので、彼を消してしまおうとして出かけたのだという説。
アープ兄弟と闘った四人は、カウボーイのギャングたちから送りこまれ、その暗殺を依頼されていたのだという説。
これではまるで真相が分からない。
決闘場所は実に狭い場所で、コラルというのは、人家のすぐ横にある小さな家畜置き場のことである。このコラルの裏側近く、フレモント・ストリートに面した狭い場所で、四対四の撃ちあいがあったのは、その日の午後二時半ごろだったという。映画ではかなり長く派手なアクションで撃ちあっているが、各自の距離はせいぜい十数メートル、どちらが勝つにしても、時間のかかるはずがない。十秒ですべては終わった、といわれているが、なんの隠れる場所もない近距離での決闘だから、おそらく五秒くらいで大勢は決まっていただろう。
クラント側では親のアイクが逃げてしまい、息子のビリーとマクロりー兄弟の三人が死んだ。
アープ側では、ヴァージルとモーガン兄弟が重傷、ホリディも手傷を受けたが、ワイアットだけはまったく無傷だった。
事件後に行われた裁判で、ワイアットはもちろん自分に都合のよい証言を行なって無罪になっているが、ヴァ―ジルは保安官をクビになり、結局アップ兄弟はこの町を去った。
決闘には加わらなかったが、マクロ―リにはもう一人の兄弟がいて、彼の書いた手紙によると、クラント側の正当性が主張されている。第三者の証言もまちまちなので、まるで西部版「藪の中」のような感じである。いずれにしても、アープ側が善玉で、クラウント側が悪玉だったという証拠はどこにもない。
数年前に亡くなった著名な歴史家ホーフスタッターは、はっきりこう書いている。
つまり彼はたしかに一保安官だったこともあるが、その前後にはプロの賭博者だったこともあり、酒場を経営したり、駅馬車を襲ったり、人殺しをしたりしたこともあるらしいのだ。
とすれば、ジョン・フォード監督は、映画史上の名作を残すと同時に、一般観客を喜ばれそうなヒーローを創造するために、あえて忠実を歪曲する一役を果たしたことになるのではないだろうか。
私は今までに、こんなにすさまじい光景を見たことがない.
アメリカ庶民のアイドル P.285
リンカーンが暗殺されたあと、実にたくさんの伝説が彼について生れた。それはまったく雨後の筍のように自然発生的なもので、真っ当なものもあれば、荒唐無稽なものもあった。そのなかに、次のような話がある。
「南北戦争中の南部で――ある日とてつもなくみっともない一人の行商人が、ファニーお嬢さまの家に立ち寄ったもんだよ。とても背が高くて、痩せていて、なんでもきょろきょろ見回していたようだ。
ひどく暑い日だったもんで、ファニーお嬢さまは気の毒に思って、冷たい牛乳を飲ませてやりなさったんだよ。その男は品物をひろげて売りながら、南部の兵隊はどのくらいいるのかとか、リンカーンが奴隷を解放したらどうするのとか、いろいろ尋ねたもんだ。
そこへヴァジニア奥さまが出てきて、リンカ―ンの名前なんかこの家でいってはいけない、あいつは余計なことをする悪魔なんだといって、大騒ぎになったのさ。その男は笑い出して、”リンカーンって、そんなに悪い男でもないだろうに”そういって帰ってしまった。
ところが、ニ、三週間もしてからなあ、ファニーお嬢さまのところへリンカーンから手紙が来たもんだ。この間はとてもやさしくしてもらってありがとう、と書いてあったそうだ」
それにしても、戦争中にリンカーンがこっそり敵情視察に出歩いたというようなあり得ない話が、一体どうして人びとに好まれて語り伝えられたのだろうか。おそらくその最大の理由は、ここに語られているリンカーンのイメージが、ヒーローというよりもむしろアイドルというに近いからであろう。
いうまでもなくリンカーンには、数多い政争のなかで心に茨を植えながらも妥協を重ね、大統領になってからは奴隷の解放と連邦の維持という二大目標を達成しながら、ついにその栄光の頂点で凶弾に倒れたという神話的なイメージが一方にある。それはうっかりすると、人びとの罪を背負って十字架にかけられたイエスの生涯にも比較されそうな、荘厳なイメージである。
ところが、ここにのべられているリンカーンは、あくまで丸太小屋で育った野人としてのイメージであり、冗談をいいながら一緒に食事ができるような、血の通った身近な人間なのである。大衆から眺めたこの身近さは、十九世紀末にもう一人のアイドルを作りあげた。貧しい移民の子としてこの新大陸に上陸し、苦しい少年時代を過ごしながら、のちにアメリカ鉄鋼業の過半を掌中におさめたアンドルー・カーネギーである。
カーネギーの自伝によると、両親がスコットランドからアメリカへ渡ろうとして家財道具を売り払ったとき、一家の渡航費にはまだ二〇ポンド足りなかったという。アメリカへ来てからも朝の暗いうちから起き、一週二ドルを手に入れるために、石炭にまみれ、真っ黒になって働かなければならなかった。これがたいていの移民のたどった運命だったからこそ、彼の生き方は大衆の共感を得ることができたのであろう。
しかし、両方ともに血の通った身近なアイドルでも、その中身は大統領から大実業家に変わっている。同じように一文なしからスタートしても、若者たちが苦学して法律を学び、大統領への道を目指したような時代から、機敏に立ち働いて大儲けをし、金の力で政治家をアゴで使いたいと思う時代へ、もう移り変わっていたのである。
二十世紀へ入ってその移民が制限され、多くの人びとが一定の生活水準を楽しめるようになってくると、かえってもやもやとした贅沢なフラストレーションが、国民の間にゆっくりと拡がり始める。そのとき軽い単座の飛行機を駆って、二十五歳の青年がニューヨークからふわりと舞い上がった。
丸一日大西洋上を飛び続けたリンドバーグが、パリの灯を見て無事に着陸したとき、そのフラストレーションは一気に解消する。当時ニューヨークのマンハッタンでは、後から後から天にも届く超高層ビルが競って建てられていたが、この自前の一青年はそんな競争を小さなものに思わせるほどの偉業をなしとげたのである。
ニューヨークを世界最高の都市にしたあらゆるビルは、まるで彼を迎えるときにまく紙吹雪のためものかと思われた。それまでシカゴとセントルイスの間を飛ぶ複葉機の平凡な郵便飛行士にすぎなかった彼もまた、どの大衆からも手の届く存在であった。だれもがヒーローになれることを示したアイドルだったのである。それにしてもリンドバーグは、幸いなことに、個人的偉業が人びとに衝撃を与えることができる最後の時代を生きていた。第二次大戦後は、個人の業績に代って集団の機能が、人びとや国家の運命を左右するようになったからである。
もうそうなると、人間は大量生産の機械の一部に融けこんでしまって、個性などが生かされる道はあまり残らなくなった。物質的にはますます満ち足りるようになりながら、それでいて個性がすっかり喪失した時代に、思いがけない形でハリウッドから一人のアイドルが誕生する。三十数年の短い生涯を、人びとの眼の前からさらと流れ去るように駆け抜けたマリリン・モンローである。
彼女にもまた、だれでもが言い寄れるような錯覚を起こしやすい、不思議な身近さがあった。取りつきにくい美人ではなく、どこのレストランでも出会いそうな親しみが、身体の隅々に溢れていた。
彼女が戦後世代の象徴的アイドルになり得たのはなぜだろうか。セックス・アピールの衣装を着て現れたニンフだっただろうか、おそらく、そうではなかろう。身近な親しさの他に、彼女には何かしら、没個性の時代をわびしく生きる人びとに、安らぎを与える不思議な天性があったのだ。
一九五〇年代、パックス・アメリカーナ(アメリカの全盛)の時代にも、人びとは、高度に管理化が進みはじめた社会のなかで、それぞれに心に傷を負いながら生きていたが、その傷口を近よってなめ、癒してくれるような、そのモンローだったのであろう。
映画の「帰らざる河」のなかに見せた、彼女のあの荒々しい野性とやさしい女らしさの奇妙な融合は、現代に生きる人びとの心の砂漠のなかに、忘れていた魂の古里に対し、深い望郷の気持をもたせたに違いない。
戦後、彼女に代わるアイドルはまたどこからもうまれてはいない。これこそ、現代のアメリカがまさしく現代の過渡期にある証拠ではないだろうか。
フランクリン・Ⅾ・ローズヴェルト大統領(民主党)は、
初めて大西洋を飛んだ女性パイロット P.291
カナダの東部に、ニューファンドランドという大きな島がある。その東南部、大西洋に面した小さな港町ハーバー・グレイスで、アメリア・エアハートはひそかに発進のチャンスを狙っていた。一九二七年五月、リンドバーグが単独で大西洋を越えてパリまで飛び、一躍アメリカを代表するヒーローになってから、その時までちょうど五年の歳月がたっていた。その五年間を、アメリアは決して無為にすごしたわけでない。リンドバーグの飛んだ翌年、彼女は他の二人の男性パイロットに同乗して、同じニューファンドランからイングランドの西のウェールズまで、二十時間四十分で飛行した。
リンドバーグはパリまで飛んで三十三時間もかかっているから、この三人の同乗飛行も快挙には違いないし、それだけでも、「大西洋を飛んだ最初の女性パイロット」といえるものだった。しかしその時、彼女は同乗しただけで、実際には一度も操縦桿を握っていなかったのである。だから彼女自身は、自分が大西洋を飛んだ、とは少しも考えていなかった。
そこで飛行機も新しく用意し、いろいろな機械についての知識も身につけ、大西洋の航空気象も十分に研究して準備をととのえたアメリアは、ついに好機を捉えた。リンドバーグが初めて飛んだ時から満五年後のなんと同月同日、すなわち一九三二年五月二十日の午後おそく、彼女の愛機「ロッキード・バガ」は、女主人公一人を乗せ、ひっそりとハーバ・グレイスを後に飛び立ったのである。
もしこれが成功すれば、女性による世界最初の単独大西洋横断飛行だった。アメリアはこの時三十四歳。女性らしい化粧をすることもなく、飛行機にだけ熱を上げていたので、その一年前に結婚したばかりだった。夫のパトナムは、いうまでもなく、妻のこの飛行を全面的に支援していた。
はじめ彼女は一気に高度をとって、四〇〇〇メートル近くで水平飛行に移った。当時の飛行機としては、相当な高度である。その方が安全ではあったのだが、やがて目の前の高度計が突然激しく揺れだした。高度計が故障したのだ。それからあと、海面からの高度を肉眼で測定しなければならなくなった。これが陸上であれば、山や川、それに村や家などの大きさを基準にして、いま自分がどの位の高さを飛んでいるのか、およその見当はつくのだが、海面だけが相手では、それもまったく不可能だった。
夜の十一時、それまで出ていた月が見えなくなった。天候の悪化だ。嵐が近づいていた。低気圧の下にもぐりこむよりは、その上に出た方がどれだけ安全か分からない。そこで彼女は、ますます機首をもち上げて高度をとった。すると、みるみる気温が低下した。両翼に氷がはりついて、白くなっていくのが見えた。愛機がそれだけ重く、鈍くなったのが分かるような気がした。
このままでは、危険だ。アメリアは雲のあい間を縫うようにして、機首を下げた。しばらくそうしていると気温は上がったが、やがて波の砕けるのが脚下に見えてきた。そうなると、今度は機首を上げなければ危ないのだ。
後に彼女は、その時のことをこう書いている。
「今から考えてみても、大西洋上のその夜の思い出は、気の滅入るようなものばかりだった。たとえば排気管からチラチラ見える焔を見ても、なんとも憂欝な気持で、溺れて死ぬのと、焼かれて死ぬのは、どっちがいいなのだろうと、そんなことばかり考えていたものだ。真っ暗な深夜、五時間もの暴風雨のなかで、ただ機械をたよりに安全を守ろうとして、私は根限りの奮闘を続けた」
こういう故障に加えて、高度、速度、方角、ガソリンンの残量など、たえず考えなければならなかった。しかし悪条件がこれほど重なっても、運命の神は彼女を見放さなかった。
夜が明けてきて、ガソリンも残り僅かになったころ、前方にアイルランドの先端が見えてきたのである。彼女は出発してから約十五時間で、酪農場に働く人びとや群れ遊んでいた牛たちを驚かせながら、ロンドンデリーのある牧場に着陸した。愛機は傷つき、疲れ果てていたが、これは大変な偉業だった。リンドバーグいらいの五年間に、単独で大西洋の横断飛行に成功した人は、他にまだいなかったからである。彼女はリンドバーグに次いで実に二人目で、しかもその二人目が女性だったことは、世界のひとびとを驚倒させた。
アメリアを迎えたヨーロッパの反響はすさまじく、イギリス、フランス、ベルギーなどで多くの勲章を受け、王室にも招待されて歓迎された。アメリカは当時かつてない経済恐慌のなかで喘いでいたので、暗いムードを吹きとばすような彼女の壮挙に沸き返った。フーヴァー大統領は、ホワイトハウスに彼女をよんで晩餐をともにした。
大空に対するアメリアの挑戦は、これで終わったわけではない、その後もアメリカ大陸横断ノンストップ飛行、ハワイ・サンフランシスコ間太平洋単独飛行、メキシコシティー・ニューヨーク間ノンストップ飛行など、いずれも当時の航空界に衝撃を与えるような記録を残し続けた。
一回目の大西洋同乗飛行のあと、アメリアは『二十四時間四十分』という著書を発表し、女性がパイロットとして不適当だという通説に反論した。第二作『楽しいからこそ』のなかでは、女性の権利や能力が正しく評価されるように説いている。すぐれた才能と勇気をもつ女性が、最後にゆきつく点は、必ず男女同権という目標をかかげることだったのである。
多くのすぐれた飛行家がそうであるように、一九三七年六月一日、双発の愛機「イレクトラ」を駆って、彼女は世界一周飛行の壮途についた。同乗者は航路調整のフレッド・ヌーナンスただ一人。マイアミから南下して南米の東岸を進み、アフリカを経て、インド、東南アジア、オーストラリアまで、実に二万五〇〇〇マイルを彼女は飛んだ。
途中各地から書き送った記事によって、彼女の飛んだ航跡ははっきりしている。七月一日、ニューギニアの東端ラエから、南太平洋のハウランド島をめざして飛ぶ途中、彼女の愛機は姿を消した。彼女の消息について、ラエから『ヘラルド・トリビューン』紙へ入った最後の無電は、次の通りである。
「アメリア・エアハートは本日十時、ハラウンド島に向けて出発せり。太平上、同島まで二五〇〇マイルあまり、かつて他の飛行機によって征服されしことなき航路なり」
その後、飛行機や艦艇の大捜索隊が派遣されたが、ついにその片鱗さえ発見することができなかった。
私が一九七五年秋、アリゾナのある退役将校を訪ねた時、彼は日米開戦の初期、サイパン島で捕虜になっていた一人のアメリカ人が処刑された記録があり、それが彼女に違いない、と断言した。そんなことがあっていいものだろうか。彼女は人知れぬ南海の果ての、美しい海の底に沈んでいるのだ、と私は今も固く信じている。
2025.05.02 記す
「報道の自由」は一日にしてならず P.297
今から4もう五年前のことになるが、当時まだ三十四歳のニール・シーハン記者は、六月十三日付の『ニューヨーク・タイムズ』紙上から、国防総省がひそかに研究をすすめてきたベトナム秘密文書の分析を載せはじめた。
これが時のニクソン政権を震撼させ、国家の利益か、報道の自由かをめぐって、最高裁にまでもちこまれた事件の発端であった。やがて『ワシントン・ポスト』紙も戦列に加わり、その後全米の主要新聞のいくつかが、続々と秘密文書のコピーを入手して、公表に踏みきった。
この時、最高裁は六対三で新聞の勝訴を決定したが、その時『ニューヨーク・タイムズ』は社説のなかで、「情報に通じることもなく、自由な報道機関もなくては、国民が目を開いて物事を考えることができない」とのべている。
同紙の副社長ジェームズ・レストンはかねがね、国家的決断が迫られる問題については、いつも国民の目の前にはっきりさせておくべきだ、とのべていたが、この信念が、ベトナム秘密文書の公表に社運をかけた同社の態度を支えていたのだ。
ソンミン虐殺事件をあえて公表したシーモア・ハーシュ記者。「ベスト・アンド・ブライテスト」を書いて、すぐれた指導者たちがベトナム戦争にのめりこんでいく経過を分析したデービッド・ハルバースタム記者。ウォーターゲート事件で次つぎに驚くべき事実を国民の前に明らかにした『ワシントン・ポスト』のボブ・ウッドワードとカール・バーンスタイン記者。その他、毎年ピュリッツア―賞を受賞するような、多くのすぐれたジャーナリストたち、「ハーツ・アンド・マインド」で戦争にまつわる腐敗や偏見をみごとに描いたテレビ関係者たち――。
こういうジャーナリズムの伝統は、一朝一夕にでき上がるのものではないが、その系譜をさぐると、なんと植民地時代にまで遡ることができるのだ。その頃イギリス本国では、一六九五年まで新聞の発行に国王の許可証が必要で、それ以後も検閲制が続き、実質的に報道の自由はなかったといってよい。このため一六九〇年にボストンで発行された植民地最初の月刊新聞は、真実であると信ずるものを報道するという基本理念を明らかにしたので、国王から派遣された総督の命により、僅か第一号で発売禁止となってしまった。
当時ニューヨーク州は不幸にもコネチカットやローズアイランドほど自治を認められていなかった上、一七三二に着任した総督ウィリアム・コスビイは、イギリスで浪費した財産を植民地人への課税で埋めあわせようと考えた人物であった。ニューヨークに到着したその日、コスピイは狭い道路を思うように馬車を走らせる邪魔をしたといって、一人の農夫を鞭うたせた記録が残っている。その上彼は、前任者が死んだ日から着任の日までの給料の半額を支払うように要求した。その給料はすでに臨時の代行者リップ・バン・ダムに支払われていて、ダムが当然返済を拒否すると、彼は裁判にもちこんで、執拗にその支払いを求めたのである。
この裁判を扱うことになった州最高裁の三人の判事のうち、二人は総督の側についたが、首席判事ルイス・モリスはあくまでも反対したため、とうとう新総督にその職を追われてしまった。
その時ニューヨークにあった唯一の新聞は、ウィリアム・ブラッドフォードの出している『ニューヨーク・ガゼット』で、この新聞は総督のいうままになっていた。
ブラッドフォードの徒弟だったことのあるジョン・ピーター・ゼンガーは、自分で新聞を発行したいと思っていた矢先でもあったので、ルイス・モリスを協力者とし、一七三三年十一月五日、週刊新聞『ニューヨーク・ウイークリ・ジャーナル』を創刊した。
ゼンガ―はこの新聞で、遠慮することなく総督の政治を批判し、「自由な新聞というのは、少数の編集者や記者ばかりでなく、すべての市民にとって必要欠くことのできないものである。批判する自由がなければ、市民としての他の自由もやがて失われるだろう」と書いている。
たちまち総督はニューヨーク市議会や裁判所に圧力をかけてきたが、それらがみな拒絶されてしまうと、今度は直属の参議会に命じて特定の号を焼却させてしまった。さらに数日後、ゼンガ―は逮捕されて、シティー・ホールの三階に監禁される。彼は最後まで執筆者たちの名を明かさなかったので、他には誰も逮捕されずにすんだ。九カ月間にもわたる監禁中、他の人びとの協力で新聞は発行され続け、毎日のように彼は妻や後援者と連絡をとって、獄中から原稿を渡し校正したりしたという。
一方かねてから総督反対運動に参加していた二人の著名な弁護士アレクサンダーとスミスは、この間ゼンガ―の弁護に立ち上がったが、遂に弁護士の資格を剥奪されるという報復を受けた。
こうして、フィラデルフィアのすぐれた弁護士アンドルー・ハミルトンが最後に登場する。そのときすでに七十歳をすぎていたハミルトンは、一七三五年にゼンガ―が治安を乱したとされる裁判に出席し、落ち着いた大胆な態度と熱のこもった雄弁で、十二人の陪審団に語りかけた。
「いまあなた方の高潔な行動によって、奴隷の生活よりも自由を愛するすべての人びとが、あなた方を専制の企てを失敗させた人びととして誇りに思うようになることは明らかです。……われわれの国の自然も法律も、われわれに一つの権利を与えているのです。それは、真実を語り、そして書くことによって、専制権力をあばいたり、それに反対したりするという自由なのです」
別室に退いた陪審員たちは、十分足らずの協議の末法廷にもどり、評決を下した。「無罪」と……。わっと歓声が法廷をゆるがした。翌日フィラデルフィアに帰るため船に乗ったハミルトンを、ニューヨーク市民は祝砲で見送ったという。
もちろんこの事件で、報道の自由がいつも守られるという保障ができたわけではない。権力は多くの場合専制を好み、腐敗を生みやすいから、報道の自由を守るたたかいは、永久に続かなければならないのである。
いくらジャーナリストだからといっても、これほど黒
あとがき P.317
本書は一九七六年のアメリカ建国二百年にあたって、一年間『週刊朝日』に連載したものである。
もつとも、ちょうど連載のなかほどにさしかかったとき、長年の十二指腸潰瘍が悪化して幽門狭窄をひきおこし、緊急に入院して手術を受けなければならない事態になったので、やむをえず病院に入っていた五週間分だけ休載し、読者や編集部の方々に予期せぬ御迷惑をおかけしてしまった。従ってここに収録したのは、四十八週分となっている。
このような形で一冊の本にまとめるにあたって、読みやすいように全体を四つの章に分類した。週刊誌ではふんだんに使った写真や絵を、ここでは多少割愛しなければならなかったが、本文でとり扱っている内容を中心とした年表と、日本語で読める参考文献一覧をあげることにした。
さて、いま全世界に影響力をもつアメリカを理解するために、こうして改めてその過去を現在との関連で振り返ろうとすると、一九六〇年代にアメリカのなかから湧きおこった各種の変革が、過去を眺める眼をかなり大きく変えてしまったことを、痛切に感じないわけにはいかない。
たとえば、五〇年代から始まっていた黒人革命は、六〇年代に入って最大の国内問題となって火山のように爆発し、またこれに参加した白人リベラルたちは、広く社会の矛盾に開眼してベトナム反戦運動、大学紛争、ウーマン・リヴ運動などを展開した。さらに、黒人革命に刺激を受けた他のマイノリテイ集団の現存の体制に対する挑戦、公害反対闘争、ヒッピーによって代表されるカウンター・カルチャーなど……。
こうした一連の、いわば疾風怒濤のような六〇年代を経てみると、その大きな置き土産となったのが、自国をみる眼を変えたということではないだろうか。
私はそういうことを頭に置きながら、この連載では毎回自由にテーマ―を選び、自由な書き方をしてみようとした。それぞれ毎回読みものとしての面白さを出しながら、それでいてアメリカの歴史や社会の本質について考えるということは、取り組んでみると最初私が考えていたほど生ま易しいものではなかった。多くの人びとの協力がなかったら、この連載を続けることはできなかっただろう。
そういう意味で、連載の仕事を支えて下さった『週刊朝日』の涌井昭治さんと岡井輝雄さん、毎回原稿と写真のことで一緒に頭を悩ませて下さった平泉悦郎さんや他のスタッフの方々、それにこの本をまとめて下さった図書編集室の角田秀雄さんたちに、ここで暑くお礼を申しあげたい。
1977年春 猿 谷 要
選書版あとがき P.319
この本は、一九七六年のアメリカ建国二百年祭にあわせて、その年ちょうど一年間、『週刊朝日』に「イエスタデイ&トウデイ」というサブタイトルをつけ、朝日新聞社から出版した。いまこうして装いを新たにし、三たび多くの読者に読んで頂けることになったのは、著者としてこんなにうれしいことはない。
実際私は旅が大好きで、趣味は何かと聞かれると、躊躇なく旅と読書と答えることにしている。これに散歩を加えたいのだが、いまは都心に近い喧噪のなかに住んでいるので、散歩を楽しむことなどとてもできない。その分だけ、余計旅に惹かれることになるのだろう。
国内もあちらこちら、ずいぶん旅をしたが、海外の場合はなんといってもアメリカが多い。一九六六年に「九九日九九ドル」という長距離バスの切符を買って、夫婦でアメリカ中を回ってから、どうやら病みつきになったような気がする。六八にはニューヨークに住んでカナダへのバス旅行を楽しみ、六九年にはニューヨークからハンドルを握って南部のアトランタに引越し、それからは暇にまかせて南部各地をドタイヴした回った。
一九七二年にはカリフォルニアで中古車を買い、三カ月間夫婦でドライヴ旅行を続けた。この時のことは、『現代の幌馬車』(朝日新聞社)という本になって残った。七四年はカリフォルニアの友人から車を借り、昔のオレゴン・トレイルに沿って走ったり、ロッキー山脈を越えたり、約一ヵ月西部数州を走っている。七五年は全米を飛行機でとび回ったが、七七年は再び西部各州をこれも約一カ月、砂漠や荒野や山岳の間を走り回り、そのあとの三週間、カナダ政府の招きで東はケベックから西はヴィクトリアまで、カナダ各地の旅を続けた。こういう体験は、『アメリカ大西部』(新潮社)として実を結んでいる。
七八年はアトランタに一夏腰をすえて、レンタカーで気の向く場所を訪ねて回った。『アメリカ南部の旅』(岩波書店)はその時の体験を描いたものである。その後も、七九年はラテン・アメリカ、八〇年はサンフランシスコで、一夏……といった具合で、毎年のように夫婦での珍道中をくりひろげている。
しかしどこを旅していても、本能的に歴史家としての眼で対象を見ているのに気が付く。訪ねる土地の歴史的な背景を調べておいたり、入念に地図を眺めて地形を頭のなかにいれておいたりする。史跡を探した場合は、なるべくそのなかに自分の身体と心を融け込ませようとする。南部の町の奴隷市場の跡に長い間佇んでいるうち、それまでに読んだたくさんの奴隷の手記などが頭のなかに甦ってきて、もし自分が奴隷であったという恐ろしい思いが、実感として私を包んでしまったことがある。歴史家として私はこういうことを「追体験の旅」とよびたいと思っている。実はこの本は私にとっての「追体験の旅」が生みだした成果だといえるかもしれない。
それにしても――『週刊朝日』に連載した時から、もうまる十年の歳月が過ぎた。変化の激しい現代に生きていると、十年間というのはもう遠い昔のような感じがする。旧稿を書いている時は、フォード大統領時代のアメリカだった。書いている最中に、南部人ジミー・カーターが彗星のように登場して、大統領に当選した。それが今は、レーガン大統領の二期目も終わりに近づいている。八六年十月にはアトランタにカーター前大統領の業績をたたえる立派な記念館がオープンした。開館三日目に私たち夫婦はそこを訪ねて、歳月がまるで音を立てて流れているのを見るような思いがした。
十年たてば、アメリカを見る眼も違ってくるのではないだろうか。そう自問すると、まったく同じだとはもちろんいえない。微調整しなければならないこともあるだろうし、疑問符もいくつか浮かんできたりする。しかし私はいまこの本を読み返してみて、原則としては修正を加えないことにした。というのは、歳月の流れによる多少の気持の変化よりも、私が当時この本を書くために傾けたエネルギーの方が、はるかに重要なものだと感じたからである。その時の熱気のようなものを大切にして、この本のなかでまたそっくり再現したいと念願している。
そんなわけで、やむをえない修正以外は、すべてもとの文章のままである。ただこの十年間に、アメリカについての参考文献はかなり増えているので、巻末に新しい形で書き加えた。
日米関係は戦後四〇年あまり、摩擦は絶えることなく起っているが、全体としてはしだいに成熟の方向に向っているといっていいだろう。それでもなお、相互理解の不十分なためのトラブルが少なくない。米英間、米仏間では起こらないですむトラブルが、なお日米間には発生しやすのである。この本が、そういうギャップを埋めるためにささやかなお役に立てれば、著者としてこれ以上の幸せはない。
一九八七年早春 著 者
※参考:『週刊朝日』(しゅうかんあさひ)は、朝日新聞出版(2008年3月までは朝日新聞社)が発行していた週刊誌。1922年に創刊され、『サンデー毎日』(毎日新聞出版)と並び、日本で最も歴史の長い総合週刊誌だったが、創刊101年後の2023年をもって休刊した。数十年にわたり毎週火曜日発売だった(首都圏など)。最盛期には153万9500部の発行部数を記録した。休刊直前の発行部数約7万4千部は『週刊アサヒ芸能』(徳間書店)に次いで業界第8位だった。(黒崎 記)
2025.07.01 記す
主な著書(手持ち)
『アメリカ南部の旅』(岩波新書)
『西部開拓史』(岩波新書)
|
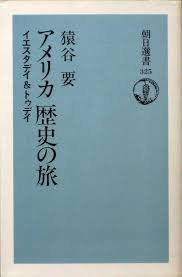 黄金を求めてであろうか。もちろん、それはいうまでもない。このときにまでに征服されたアステカ帝国やインカ帝国などから、金銀の財宝は海を渡ってスペイン本国に流れはじめていた。土地も財産もないスペイン大衆が、新大陸に黄金の夢を抱いたとしても、それはむしろ当然のことだっただろう。そして彼らは、イギリス人やオランダ人が後にするような商業活動で富をつくるよりも、その富を一気に探し求める冒険の方に憧れていた。その上、地上の栄光は天上の栄光と一致するものと考えていたので、コロナドも異教徒に対する布教のための修道士を何人もつれて、探検の旅を続けたのである。日本に来たフランシスコ・ザヴィエルの布教が同じ頃だったことを考えると、それはある程度理解することができるだう。
黄金を求めてであろうか。もちろん、それはいうまでもない。このときにまでに征服されたアステカ帝国やインカ帝国などから、金銀の財宝は海を渡ってスペイン本国に流れはじめていた。土地も財産もないスペイン大衆が、新大陸に黄金の夢を抱いたとしても、それはむしろ当然のことだっただろう。そして彼らは、イギリス人やオランダ人が後にするような商業活動で富をつくるよりも、その富を一気に探し求める冒険の方に憧れていた。その上、地上の栄光は天上の栄光と一致するものと考えていたので、コロナドも異教徒に対する布教のための修道士を何人もつれて、探検の旅を続けたのである。日本に来たフランシスコ・ザヴィエルの布教が同じ頃だったことを考えると、それはある程度理解することができるだう。


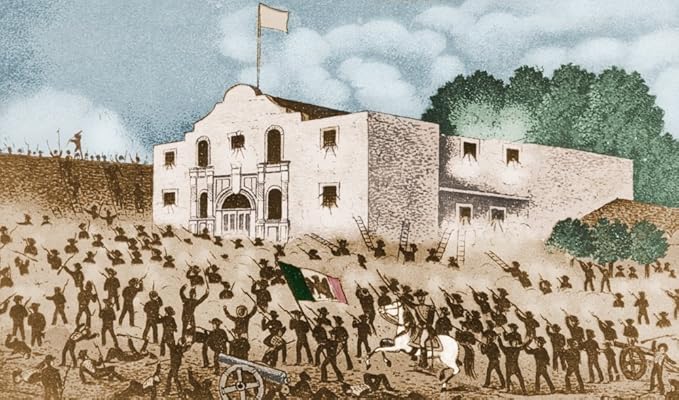 二月下旬から三月上旬にかけて、死闘が毎日繰り返された。小さな寺院を包囲したメキシコ軍は、大きな津波が海岸に激しく打ちよせるように、ときの声をあげて周囲から殺到した。梯子をかけて壁面をよじ上ろうとするメキシコ兵もあった。これだけの大軍を、二百人たらずのアメリカ人たちが幾日も死守したのは、ほとんど奇跡ともいっていいだろう。
二月下旬から三月上旬にかけて、死闘が毎日繰り返された。小さな寺院を包囲したメキシコ軍は、大きな津波が海岸に激しく打ちよせるように、ときの声をあげて周囲から殺到した。梯子をかけて壁面をよじ上ろうとするメキシコ兵もあった。これだけの大軍を、二百人たらずのアメリカ人たちが幾日も死守したのは、ほとんど奇跡ともいっていいだろう。
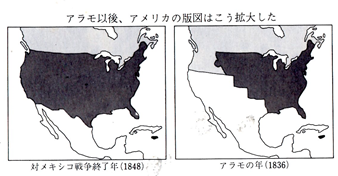 この経過を見ていて、アメリカ側のやり方に不信の念をもった人が、ごく僅かだがいたのだ。この戦いが防衛のための戦いではなく、侵略のための戦いであったことを堂々と議会でのべたのは、まだ新米の下院議員だったエイブラハム・リンカーンである。
この経過を見ていて、アメリカ側のやり方に不信の念をもった人が、ごく僅かだがいたのだ。この戦いが防衛のための戦いではなく、侵略のための戦いであったことを堂々と議会でのべたのは、まだ新米の下院議員だったエイブラハム・リンカーンである。

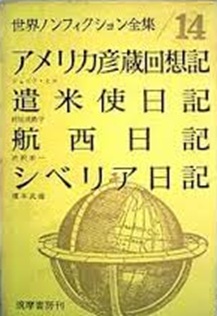
 そのウォール街に沿って、初代大統領ジョージ・ワシントンがバルコニーに立ち、人びとの歓声を浴びて就任式を行ったフェデラル・ホールが建っている。そして正面の階段にはワシントンの大きな像が、まるでニューヨーク証券取引所を守るような姿勢で立っているのだ。
そのウォール街に沿って、初代大統領ジョージ・ワシントンがバルコニーに立ち、人びとの歓声を浴びて就任式を行ったフェデラル・ホールが建っている。そして正面の階段にはワシントンの大きな像が、まるでニューヨーク証券取引所を守るような姿勢で立っているのだ。
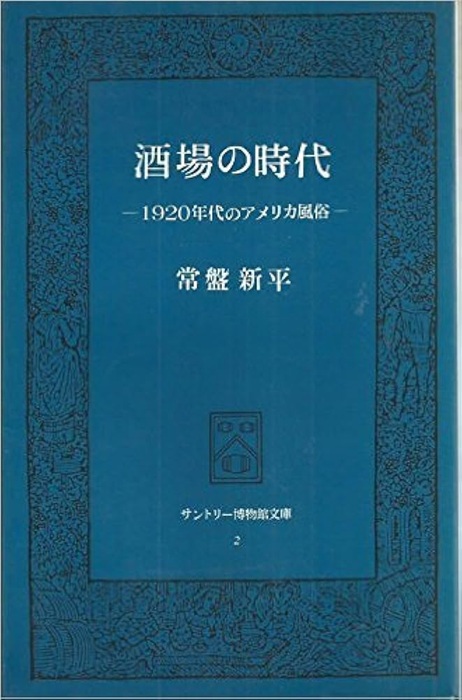 結局、「動機の点では崇高だった」この禁酒法も、かえって社会を混乱に陥れ、国民の遵法精神を破壊するというので一九三三年に廃止されたが、その後もなお、各州または各部単位で、禁酒法を守っている場所が少なくなかった。
結局、「動機の点では崇高だった」この禁酒法も、かえって社会を混乱に陥れ、国民の遵法精神を破壊するというので一九三三年に廃止されたが、その後もなお、各州または各部単位で、禁酒法を守っている場所が少なくなかった。
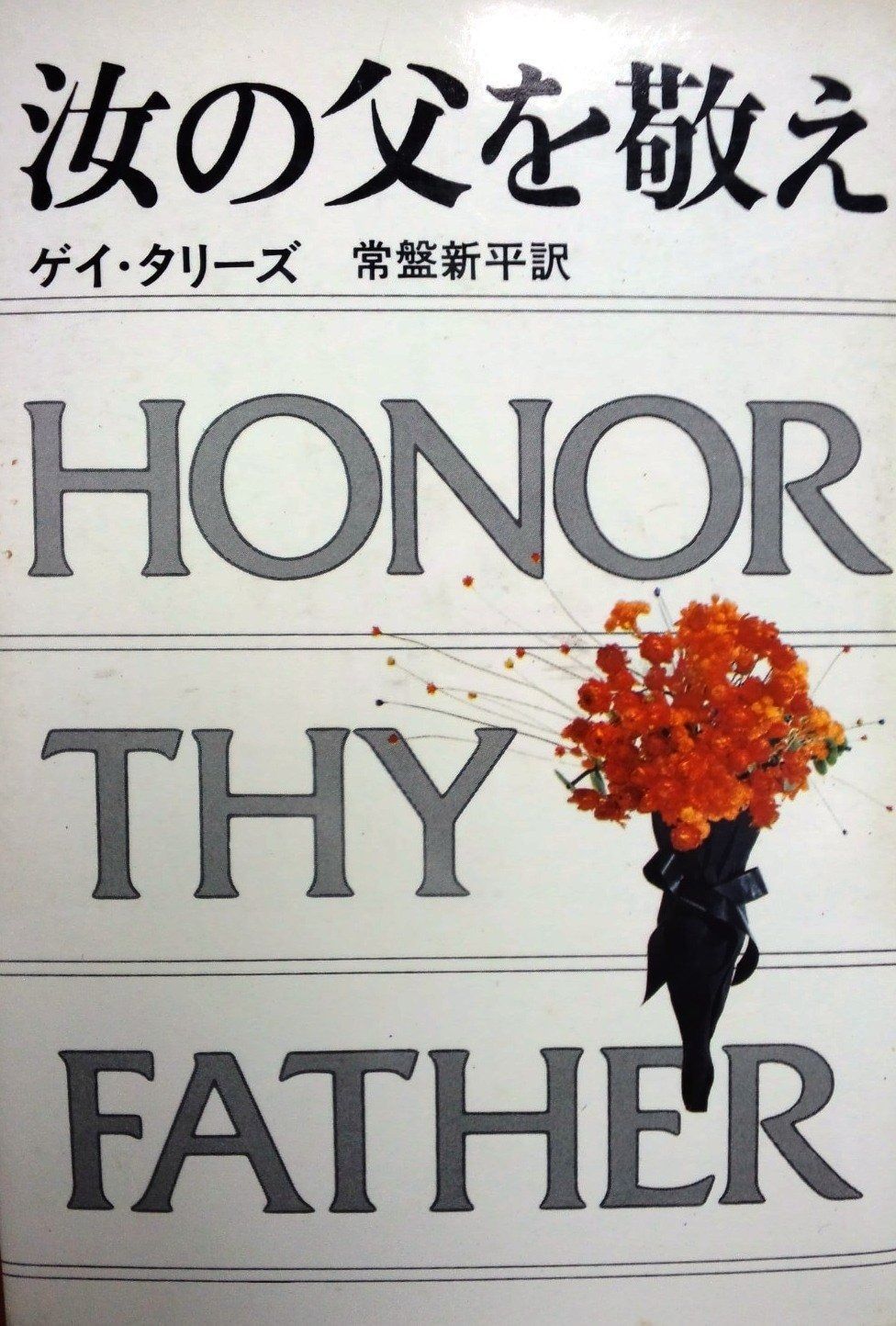 マフィアは一九二〇年代の禁酒法を利用し、酒の密輸、密造、密売などたちまちその勢力を拡大した。ナポリ生まれのアル・カポネがシカゴで全盛を誇れたのも、そのためだった。その他、麻薬、売春、賭博などのルートで莫大な資金網を作りあげ、その資金は腐敗した政治家、警察、司法関係者などの懐に入って、マフィアの行動に暗黙の了解を与えるところまで進んでいた。
マフィアは一九二〇年代の禁酒法を利用し、酒の密輸、密造、密売などたちまちその勢力を拡大した。ナポリ生まれのアル・カポネがシカゴで全盛を誇れたのも、そのためだった。その他、麻薬、売春、賭博などのルートで莫大な資金網を作りあげ、その資金は腐敗した政治家、警察、司法関係者などの懐に入って、マフィアの行動に暗黙の了解を与えるところまで進んでいた。