昭和三十四年十月十日 初版発行
| 行名 | 名 前 | P | 名 前 | P | 名 前 | P | 名 前 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | あげは | 97 | あめんぼ | 101 | あぶらぜみ | 110 | あめりかざりがに | 123 |
| あかざ | 213 | 赤翡翠 | 216 | アラビアの星 | 218 | あさぎまだら | 230 | |
| 赤とんぼ | 246 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| い | いぬさふらん | 133 | 伊勢海老 | 156 | 一輪草 | 184 | いわぎぼうし | 185 |
| 無花果(いちじく) | 241 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| う | うすばかげろう | 21 | 鶯 | 52 | うすばふゆしゃく | 53 | うそ | 76 |
| 鶉 | 103 | 薄雪草 | 135 | うめばちそう | 137 | 烏骨鶏 | 170 | |
| うすきつばめえだしゃく | 215 | うらぎんひょうもん | 220 | 海猫 | 228 | ***** | ***** | |
| え | えんじゅ | 96 | エーデルワイス | 113 | えんまこおろぎ | 136 | えぞすみれ | 200 |
| お | おおわた | 37 | おやまぼくち | 59 | おたまじゃくし | 67 | おとしぶみ | 78 |
| おなもみ | 146 | おおひめぐも | 164 | おおいぬふぐり | 174 | おおとびさしがめ | 179 | |
| おおよしきり | 207 | 追河 | 208 | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| か | 蟷螂 | 11 | かたつむり | 17 | ががいも | 22 | 羚羊 | 28 |
| 蚊柱 | 30 | ガロワ虫 | 36 | かまどうま | 41 | かいつぶり | 50 | |
| カンガルウ | 72 | 蛙 | 73 | 黴 | 74 | かけす | 80 | |
| かめのこてんとう | 86 | かやつりぐさ | 140 | 貝殻虫 | 167 | 鹿子蛾 | 238 | |
| き | きつりふね | 29 | キャベツ | 33 | きばねはさみむし | 57 | 雉鳩 | 65 |
| 雉 | 98 | 金魚 | 141 | 夾竹桃 | 205 | きまだらせせり | 222 | |
| きばねしりあげ | 237 | 銀竜草 | 242 | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| く | 草雲雀 | 25 | 葛 | 34 | クリスマス・ローズ | 45 | くものすかび | 49 |
| くさぎかめむし | 60 | くつわむし | 129 | くろぐわい | 142 | くろほうじゃく | 145 | |
| 栗の虫 | 149 | くちなし | 161 | クロッカス | 189 | 孔雀蝶 | 192 | |
| 黒種草 | 221 | 黒百合 | 227 | クレマティス | 239 | ***** | ***** | |
| け | けんみじんこ | 51 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| こ | こがねぐも | 24 | こあじさし | 27 | こがら | 58 | ごきぶり | 106 |
| こなぎ | 131 | 小綬鶏 | 134 | ごぜんたちばな | 156 | こげら | 183 | |
| 蒟蒻 | 206 | 駒鳥 | 209 | 駒草 | 225 | こばいけいそう | 236 | |
| さ | 鷺 | 71 | 鮭 | 75 | 笹魚 | 128 | 鰆 | 198 |
| 蠍 | 234 | 菜亀 | 240 | さるとりいばら | 244 | ***** | ***** | |
| し | 白蟻 | 19 | 七面鳥 | 43 | しもばしら | 54 | 虱(しらみ) | 70 |
| 猩々袴 | 85 | 紫苑(しおん) | 111 | 四十雀 | 121 | しめじ | 148 | |
| 猩々木 | 154 | じょうびたき | 160 | 十二指腸虫 | 190 | しゃが | 211 | |
| しろつめくさ | 217 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| す | すもも | 12 | 忍 冬 | 87 | すずめばち | 88 | すけばはごろも | 122 |
| 鈴 懸(すずかけ) | 169 | すずめのかたびら | 180 | 鈴蘭 | 224 | すすき | 250 | |
| せ | 銭苔 | 39 | せぐろせきれい | 40 | 雪渓虫 | 233 | ***** | ***** |
| た | たまあじさい | 15 | 太刀魚 | 23 | たばこ | 105 | 旅人のよろこび | 153 |
| たちばなもどき | 166 | 狸 | 177 | 玉菜 | 195 | たから貝 | 245 | |
| ち | ちょろぎ | 48 | チューリップ | 62 | 沈丁花 | 201 | ***** | ***** |
| つ | 釣舟草 | 26 | つめたがい | 112 | つわぶき | 144 | つるこけもも | 147 |
| 燕 | 203 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| て | 鉄道草 | 83 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| と | 時計草 | 13 | 毒蛾 | 14 | どうがねぶいぶい | 114 | とうもろこし | 120 |
| とりかぶと | 130 | とわだかわげら | 159 | どろばち | 212 | とっくりばち | 223 | |
| な | なんじゃモんじゃ | 38 | 夏水仙 | 69 | ならえだたまふし | 84 | 夏蜜柑 | 102 |
| なぎいかだ | 146 | なずな | 190 | 菜亀 | 240 | ***** | ***** | |
| に | にむらさき | 31 | 庭石菖 | 89 | においすみれ | 187 | 二輪草 | 194 |
| ね | 猫 | 32 | 猫柳 | 176 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| の | のぼろぎく | 68 | 蚤 | 138 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| は | 薔薇 | 46 | 花菱草 | 79 | 春紫苑 | 82 | ぱせり | 90 |
| 蜂 | 99 | 蓮 | 126 | はこべ | 171 | 蠅 | 178 | |
| はるぜみ | 204 | はしぶとがらす | 243 | 葉鶏頭 | 247 | ***** | ***** | |
| ひ | ひぐらし | 16 | ひよこ | 63 | ひとりしずか | 66 | びろうどもうずいか | 92 |
| ひらたくわがた | 104 | 羊 | 115 | ひがん花 | 139 | 桧葉やどりぎ | 151 | |
| ひげがら | 157 | ひよどり | 165 | 標本虫 | 173 | 雲雀 | 188 | |
| ひらいそがに | 191 | ひとで | 235 | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ふ | 富士桜 | 77 | 蕗 | 94 | 風船虫 | 108 | ぶゆ | 125 |
| フランクリニヤ | 155 | ふたもんあしながばち | 181 | ブーゲンビレア | 182 | ***** | ***** | |
| へ | ベツレヘムの星 | 44 | 蛇 | 81 | べにひかげ | 127 | べっこうばえ | 152 |
| 平家蛍 | 219 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ほ | 酸 奨 | 18 | ほくろ | 61 | ほねがい | 116 | 蛍蛾 | 132 |
| 鯔 | 143 | ほととぎす | 150 | ほんしろすいせん | 193 | 頬白 | 197 | |
| ほんだわら | 231 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ま | まがも | 47 | まいまい蛾 | 91 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| み | 木菟(みみずく) | 35 | みやませせり | 95 | 水引(みずひき) | 109 | 茗荷(みょうが) | 117 |
| 蓑虫 | 162 | みどりかみきり | 214 | みんみん蝉 | 229 | みずくらげ | 232 | も | もくれん | 55 | 樅 | 168 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| や | やすで | 93 | やまとびけら | 118 | やつで | 163 | やにさしがめ | 175 |
| やぐらざくら | 186 | 夜光虫 | 210 | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ゆ | 雪虫 | 56 | ゆうがおびょうたん | 100 | 雪柳 | 172 | 百合の木 | 196 |
| ら | 薤(らっきょう) | 20 | らっこ | 42 | 雷鳥 | 226 | ***** | ***** |
| り | リボングラス | 107 | 輪鋒菊 | 119 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| る | るりひらたむし | 202 | 縷紅草 | 249 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| れ | レモン | 64 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2024年10月より写し始めた。2025年01月13日、全部写し終わった。
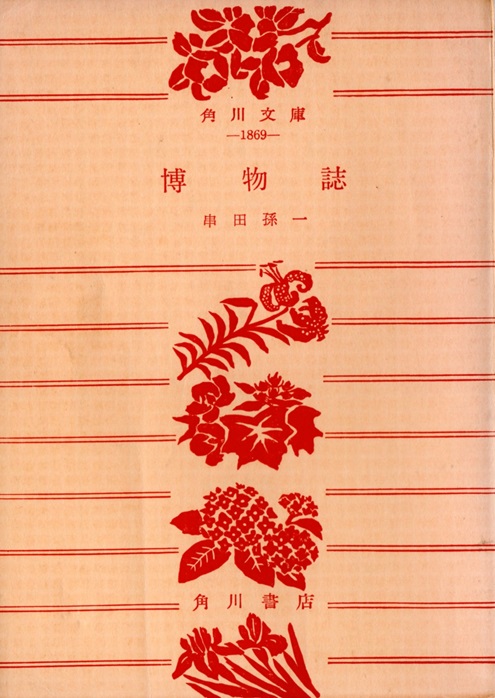
★串田孫一『博物誌』(角川文庫)昭和34年10月10日 初版発行 ★蟷螂(かまきり) P.11 蟷螂については書くことがいっぱいあって困る。ファーブルに負けないつもりだというほどの元気はないが、ひと夏、つまり蟷螂にとっての一生を、じっくりつき合って来たので、少少感情揉んだもからんで来ることになって、書くことが沢山あっても具合が悪くて書きづらい。 ところが今日、いつも葉書ばかりをくれる友だちが、珍しく、十一円の簡易書簡をくれた。封緘葉書がいつの間にかそんな名前に変っていたのだ。上下のミシンをぴりぴりと破いてみると、用件の終りに、カマキリが脱皮したと書いてあって、ぬけがらが二つはいっていた。簡易書簡の中には何も入れてはいけないんだよ、そりゃ違反だよ、という人もいた。しかしそれはもう届いてしまったし、はいっていたものは、ともかくもぬけがらなのだ。 僕はそれよりも研究の不足を痛感した。ぬけがらによってその蟷螂の雌雄を区別する方法を知らない。この二つの、脱ぎすてた薄い衣装には何のしるしもない。ズボンだろうか、スカートだろうか。余計なことだがこんなに薄くすけていいんだろうか。
※参考:「蟷螂」は漢名から。 車が近づいても逃げないことから當郞(当郎・当たり屋)の意。 「螳螂・鎌切」とも書く。 「トウロウ」とも読む。 2024.11.01 記す。
★すもも P.12 ぼたんきょう、ハタンきょう、いいかえればプラム……プラムは梅じゃないの。何だかよく分からないから果物屋の前で知ったかぶりをすると、鉢巻をしたおやじと喧嘩になる。こいつを三つ、と言って買わなければならない。 こいつは甘いかい?
それじゃだめだ、甘ずっぱくなくっちゃあ。 果物屋のおやじをからかってから買うと、すももは味が悪くなる。こういう香りと味とが微妙に交ざり合った食べ物を買う時には微妙なのだ。 僕はこいつを二つ買う。少々かたいのを選んで買う。すもものはじらいが、禿げちょろけの白い粉になってうっすら残っている。こんどはそいつをズボンでふいて、果物屋の店先でかぶりつく。山と積まれたすももが、自分たちの運命を見せつけられてぎょっとする。気の毒なことをしたと思う。 僕はそんな時、喉が渇いているばかりでなく、ちょっと悲しんでみたいのだ。すももの甘すっぱさは、街を歩きながら食べると、泥だらけになった少女の悲しみを覚えさせる。 笑うがいい、泥だらけになっては、やっぱり可哀そうだ。
★時計草(とけいそう) P.13 この花は時の記念日に咲くのではない。また、昆虫たちの媾曳きの時間に役立つ花でもない。見たところ時計の文字盤のようだという。至極単純な名前のつけ方をしたものである。しかし外国では、もう少し念の入った名前をつけている。 Passiflora つまり受難の時に使われた道具をこの花の中に見つけたのである。 僕はこの植物の鉢植えを貰ってから、実に注意深くそだてていたのだが、一度は茎がぽっきり折れて、沢山の花を黄色くしてしまった。もう駄目かも知れないと思ったが、それを花壇に下してやると、また根本から新しい芽を出した。それがまた枯れかけて、今度は三度目の復活だ。いくら自分のうちに恐ろしい道具を持っているからとは言え、これは全く受難の花である。これでは一体いつになったら時計のような花を見ることが出来るのだろう。 その後僕は、「受難の花」という文集を出した。その時に、この花の研究書かと思って買った人から手紙が来た。その人は時計草の実から汁をとって、パッション・ジュースというものを創ろうと思っているということである。
※参考:「パッション」 1 熱情。激情。 2 キリストの受難。また、キリスト受難劇。受難曲。 ※参考:中南米の各国で薬用とされる.ブラジルでは果実を鎮静,抗不安薬として用いる.西インド諸島,メキシコ,オランダ,南米では根を鎮静,駆虫薬として用いる.モーリシャスでは全草のチンキ剤,エキスを精神的要因からなる不眠症に,根は利尿薬,葉の煎液は催吐剤として用いる.アルゼンチンでは葉を鼻かぜ,肺炎などの抗菌薬とされる.その他,中南米では様々な疾患に利用される. 観賞用として栽培される.和名は,分裂した雄しべが時計の長針,短針,秒針に見えることに由来する. 熊本大学医学部
★毒蛾 P.14
毒蛾のことでこのころ、誰もがむず痒いような、板痒いような恐怖にとらわれている。そして新聞を念入りに読むので、エウプロクチス・フラヴァなどという堂々とした」名前までも大分覚えられてしまった。もっとも、なんとかフラヴァ程度に覚えている人が多いのだが。
どうです。この辺にはまだやって来ませんかな。何となく本場のように思えますが。 訪ねて来る人は庭の藪の方をちらっと見てそう言う。僕は同じようなことを何度もきかれる。その度に、昆虫図鑑をニ三冊、書棚から取り出して、「これですよ」と言って見せる。イギリスの蛾の本も見せる。そして図鑑の、毒蛾の仲間の並んでいるとこへ栞なんかを挟んだりしておくのは野暮だと思う。今のところ、僕の昆虫標本箱に、まだこいつがいないのが残念でたまらない。それで近くの櫟木林(くぬぎばやし)を散歩しながら、血眼になって探しているのだが一向に見つからない。 黄色の粉がいっぱいついているやつをピンセットの先でつまんで、涼しそうな顔をしているお嬢さんに見せながら、こんなことをもそもそと言ってもみたい。 自然というものは実にうまく出来ていますね。毒蛾が沢山発生したのは一体何のためだか知っている? あなた方がいよいよ裸に近い身なりになって来たでしょう? 自然は羞恥心を取り戻させることが出来ないもんで、毒蛾なんかを多量に飛ばせるんですからねえ。全く感心しまいますよ。 ※参考:ドクガ科まとめ 毒蛾図鑑 著者村松佳優 ドクガ科とは? チョウ目に含まれるグループで、ガの仲間になります。名前だけ聞くと怖いイメージですが、毒を持っている種類が多いわけでもありません。しかし、ドクガの仲間で幼虫の時期に毒針毛(どくしんもう)を持っているものが身近に見られ、有名なので名前の由来になったようです。蛾の仲間では珍しく「チャドクガ」などは成虫でも毒毛を持っているのも影響があると思います。英名だと「Tussock moth」で草むらにいる蛾のことで、毒に対してのイメージが強いわけでもありません。 一部種類は成虫でオスとメスの形態が大きく異なっているものがいるのも面白い点です。 チャドクガの幼虫はサザンカやツバキなどの身近な植物につき、集団で群がっていることがあります。細かな毒針毛を持っているので被害も多い種類なので注意が必要です。命に関わることはありませんが、腫れやかぶれが起こります。 2024.12.21 記す。
★たまあじさい P.15 ぬかるんだ雨の日の道を、近くの丘へたまあじさいの蕾のふくらみを見に行く詩を作ったのはもう三年前になる。その時小さな一本を抜いて来て、窓辺へ移植したのが今年はぐんとふえて、次々と花を咲かせている。いかにも大切なものがはいっているように、しっかりと握りしめたまんまるい蕾がほぐれると、そこからざっと三百ほどの花が咲く。 決して実を結ぶことのない装飾花の方が、ずっと花らしく目立っているけれど、ほんとうの花は、薄紫の霞だ。涼しく甘い夢だ。しかし僕はその夢の構造を一応は知って置かなければならない。窓から思い切り身を乗り出し、拡大鏡をあてる。
長く、しなやかに曲ってのびている雄蕊(おしべ)は、こうして見ると海底の藻(も)のようにも見えるし、それがまた迷宮のようにも思われる。その一本一本の、何というみずみずしいしなやかさだろう。僕は自分の体があまり無様(ぶざま)に大のが悲しい。そこにとろんと光る蜜を吸うための口を持っていないことがいかにも口惜(くや)しい。
僕はついに、スリッパのまま窓から外へ出てしまう。せめて花の中へ自分を入れることで満足しようと思って。するとその時、拡大鏡の中のその迷宮に、一匹のひめひらあぶの雌が飛び込んで来た。翼を持つ彼女の勇敢な飛び込み振りはなかなか見事だったが、彼女はどうもそこで蜜を吸うよりも、ただ紫の夢の中でころげ回るのを嬉しがっているようだ。 ※参考:タマアジサイは、日本固有種の落葉低木で、東北南部から関東・中部地方の太平洋側山地の日陰がちな場所に生育します。樹高はほぼ普通のアジサイと同じで1、5メートル程度です。他のアジサイ類よりも開花期が遅く、盛夏〜秋に見頃となります。 タマアジサイの花序は、白い装飾花と、明紫色の普通花(中心部に集まる、果実を結ぶ花)の対比が涼やかです。 タマアジサイは、他のアジサイが終わりを迎えようとする7月から一つ一つ咲き続け、秋までその花を楽しむ事... 2024.11.19 記す。
★ひぐらし P.16 ひぐらしは一体なぜ夜明けと夕ぐれとになくのだろうと考え出してからもう三年目になる。専門の昆虫学者に訊ねてしまえば、あっさり解決することかも知れないが、一つぐらい、誰にも教えを仰がずに、発見の悦びを味わってみたいのだ。
ところでひぐらしが鳴くのは明るさの変化なのだろうか。それとも気温のせいなのだろうか。夕立が来る前にも鳴く。そうかと思うと、夏の高原の森では、そんなことに全く関係ないように鳴いている。僕は毎朝毎夕、ひぐらしの声とともに、寒暖計の水銀を、正確によみ取るために拡大鏡で見ては記録し、その時間をも記入した。 幼稚で、愚かで、ひとには離せないような実験の方法だったのだろうか。嘲(あざわら)うものがいたら僕は言ってやるつもりだ。根気を少しばかり身につけようと思いまして。 それなら同じことでも今年は少し気の利いた方法を考えよう。ひぐらしをいっぱい虫籠に入れ、冷房装置の完全な建物に出たりはいったり、地下鉄の階段を昇ったり降りたりしてやろう。 ※参考:ヒグラシについて調べてみると、6月下旬から9月中旬頃まで活動し、日の入り前後の薄明時によく鳴くことが名前の由来になったとある。 俳句で秋の季語にされるなど、ヒグラシは晩夏に鳴くイメージがあるが、夏の初めから意外と長い期間、鳴き声を聞くことができるようである。 2024.12.27 記す。
★かたつむり P.17 かたつむりに僕が熱をあげた一つの理由は。その名前がなかなかいいからだ。キムスメマイマイとか、オトメマイマイとか、クチべニマイマイとか。それに、オオペソマイマイ、コペソマイマイ。ただこれらはその生殖器を丹念にしらべなければならないので、それがつらい。別段悪い心はなんにもないのだが。 かたつむりの雄と雌、どこで区別するか知っている? と訊ねると、なかなか面白い返答が出る。貝の左まきが雌に決まっているじゃないか、そんなことを言う人もいる。 僕は息子の手を引っぱって藪の中をがさごそとよく歩いてものだ。雨あがりの日に、ゴム長をはいて。そしてこういものを見つけるのは、幼い眼の方がいいのだ。
「これはひだりまきみすじいまいというのです。おとこでもおんなでもありません」 ※参考:カタツムリにはオスとメスの区別がなく、雌雄同体です。同じ種類の大人になった個体が生殖器をお互いに受け入れ、両方が卵を産みます。 カタツムリが雌雄同体である理由は、あまり移動しないため別個体に会う機会が少なく、たまたま出会った個体が同性であると交尾をすることができないためと考えられています。 雌雄同体のカタツムリの一部は、ラブダートと呼ばれるカルシウムでできた針を相手の体に突き刺して受精させます。ダート表面に塗布された特殊な分泌液が卵子を受精させるのを手助けします。 ※参考:カタツムリの「カタ」は、「笠に似た貝」「笠を着た虫」の意味で「笠」が語源。 かつての笠は、縫い糸を螺旋状に縫ったため、「貝」の形容ともされている。 「ツムリ」は、「つぶら」「つぶり」「つぶろ」と同系で貝の呼称。:
★酸 奨(ほおずき) P.18
僕は久し振りに丹波酸奨を鳴らしたくなった。あの赤い頬っぺたを、誰に遠慮することもなく、くにゃくにゃと可愛がって、そのうちに種子(たね)が走馬灯のように回り始める。僕は丹波酸奨が八百屋の店にもあることを忘れていたので、縁日をさがして、とうとう買って来た。 それを揉みながら、昔のように胸がわくわくした。というのか、昔の胸のわくわくを思い出した。そしてさっきのフランスの酸奨のことをちょっとしらべたことから、一体フランス人に酸奨が鳴らせるものかどうかを考えた。ジャン・ジャバンだの、ジャン・ポール・サルトルだの、フランソワーズ・ロゼエの口許がいやに官能的に浮かんで来た。
★白蟻 P.19 僕は蟻についてはニ三本の本を読んだことがあるだけで、特別実験をしたこともない。それともう一つは、フォルミカ選書というのが出る時に、蟻のマークを描いたことがある。なかなかうまく描けなかったし、蟻に立ってもらったので、後脚ががに股になって気の毒な姿になった。
白蟻の研究をしている昆虫学者の来訪をうけ、実に面白くお話を伺った。その巣の王室の中に、巨大な体をながなが横たえて、絶えずお産をし続けている女王。その女王はときどき機嫌を悪くすることもあるらしい。部屋にはいり込んだまま、産卵しどおしなのだから、機嫌を悪くするのも無理はないと思う。するとその周囲に、ひたすら彼女につかえる」ことを光栄に思っているにちがいない働き蟻は、彼女の意志を遠くの蟻たちに伝達するために、顎をかつかつと鳴らすのだそうだ。昆虫学者は、挿絵が沢山はいっている厚いフランス語の本を取り出して、時々蟻のような顔になって説明してくれる。
そのうちに、いかにも無格好に、頭ばかりがふくれ上り、その先が尖っている変な蟻の絵が出て来た。この頭を武器として勇敢に戦う兵蟻である。しかし、その説明によると、こうした武器を持っているために、こいつらは自分では何も食べることが出来ない。それで働き蟻に食べさせて貰っているということだ。武器を持てるもの。なるほど。自分では食えない。僕がそのことを頻りに感心し始めると、軽率な人間社会のことにあてはめるのは危険ですとたしなめた昆虫学者の笑いが妙に印象深かった。 ※参考:シロアリは黒アリと姿が似ていて、黒アリ同様に集団で生活することから、 「白アリ(白いアリ)」と名づけられたと考えられています。 ともに集団の中に「働きアリ」「兵隊アリ」などの階層がある「社会性昆虫」ですが、 実はシロアリはゴキブリの仲間(ゴキブリ目)、黒アリはハチの仲間(ハチ目)に分類されます。 2024.12.22 記す。
★薤(らっきょう) P.20 昔僕らが子供のころ、ある漬物屋の主人にラッキョというあだ名をつけた。あまりきれいでないつるつる頭が実にラッキョの形だった。いつも前掛けをして店先に坐っていた。
皮をむく。そう、正確に言えば鱗片葉(りんぺんよう)を剥いでいるのである。猿のしゃがんでいるあの容子。あの内股の足つき。そして、黒い爪の指先は、人間そっくりだと思ってみていると、リウマチにかかっているようにも見えて来る。 これが最後だぞ。あれ。今度はどうだ。猿も「畜生」といって舌を打つ。今度こそはうめえものが出て来るぞ。はてな??? ついに放り出された。小さくなった羅は、中(ちゅう)っぱらの、時々歯をむき出している猿に言うのだった。 仕合せだぜ、君は。腹を立てながらも、あたしの着物を一枚一枚脱がせながら、勝手な夢を見続けているじゃないか。 そうだ、包丁を持ってざっくりとやることを知らない猿は、それだけ人間よりも幸福である。 ※らっきょうの植え付け時期は8~10月ごろで、収穫時期は翌年の6~7月ごろです。収穫の目安は、球が肥大し葉が黄化したころです。
★うすばかげろう P.21 毎晩、夜の冷たい風を入れようと思って開け放っておく窓から、風とともにスタンドの灯に集って来る大虫小虫の死骸が、翌朝はうんざりするほど机の上にある。ふっと吹けばみんな床へ落ちてしまうが、多くは仰向けになって死んでいるその死骸のうちから、姿の面白いのや珍しいのを一つ選んで、二十四色の色鉛筆でノートに描くことが、僕のこの頃の日課の一つである。そしてニ三十分のあいだ、僕は小学校の優等生になった気分だ。極く正確に描きたい時もあるし、多少戯画化したくなる時もある。こっちの気分なのか。それとも死骸の恰好かも知れない。
今朝、四枚のうすい翅(はね)を結んだリボンのようにひろげたうすばかげろうを描いた。朝の風が、短命な彼女を、いまは少し風変わりなちりほこりとしてもてあそんでいる。死んでいる彼女が、生きているように転ぶ。七色の、いや、もっと複雑な光が、彼女の翅の上で名残を惜しんでいるが、それは僕の色鉛筆がいくら二十四色あっても出せない。
彼女は幼いころ、なかなか残忍な真似をしていたものだ。蟻地獄を作って、そこへ落ち込んで来る蟻を砂の中で噛みついた。そんな生活をしたことも、忘れてはいないようだ。なぜなら、最後には実に静かに、およそ翅を授けられたものの、最上の慎ましさをもって空中を舞った。騒々しい音を立てることの決してないヘリコプター。こうして見ると、うな垂れた触覚が、死んでもなお懺悔を続けているようだ。 ※参考:迷路とも見える繊細なベッコウ細工の骨組みの間にシースルーのうすぎぬが張られている。 光のあて方によって羽の色は千変万化し、虹色に輝く。 その天女のうすぎぬのような羽で陽炎のようにユラユラと飛ぶ。 その様が薄羽陽炎の名の由来なのである。 2024.12.22 記す。
★ががいも P.22
さんざん調べてやっぱり分からないというのも案外いやな気持のしないものである。アスクレピアスという花を花屋で見てからのことだ。この花の名は、多分ギリシャの医学の神アスクレピオスから来たものと思われる。格別の薬用植物でもないのに、なぜ医者の神とこの植物とが結びついたのかという疑問である。
ところが植物分類の上で、アスクレピアダセアエはががいも科のことである。そのががいもの実にのって(恐らく二つに割って舟にして)大国主神(おおくにぬしのみこと)のところへやって来るのは少名毘古那神(すこなひこなのかみ)というちっぽけな神で、このことは古事記に書いてある。ところがこの神も医学の神であり、獣医の先祖であるが、どうしてががいも実に乗って来たのか。ががいもも薬草ではない。日本と西洋とで、薬にもならない植物が同じように医学の神と関係を持っているのは、なにかいわれがありそうなのだが……。 実は以上のようなことを新聞に書いた時に、沢山の手紙を頂いた。ががいもは立派な薬草である。種子の綿毛が止血剤になり、乾葉をいぶせば防臭剤となる。またその綿を枕に入れると、頭のほてりがなおり、安眠を得、長寿を全うする。それには家伝の秘法もある。また別の文献によれば発汗、袪痰剤にもなるらしい。 そうなると僕の疑問は解決したことになるなのだろうか。 2024.12.05 記す。
★太刀魚 P.23 玄界灘だ。なんにも波がない。船は気の毒なほど揺れない。僕は舳先(へさき)の、一番突先きに腰かけていたって平気だ。スリッパをつっかけたまま、足をぶらぶらさせていたって、おつこちない。それに海の中もまる見えで、青い大陸の秘密も、わざわざもぐらなくともよく見える。長い航海のうちにはこんなこともある。
太刀魚が四匹ならんでいる。これはちょっとした見つけものだと思って僕はいよいよ体を乗り出す。船より遅い。体をくねらせて、水中で立ち泳ぎをしている。これはすっかり軟化した青龍刀だ。この辺は昔から戦いの名所で、沢山、刀が沈んだろうからな。沈んだ刀は、魚たちを盛んにおどかしたものだが、今ではもうすっかりとなまくらの味を覚えてしまった。
君たちは知っているだろうか。恐らく知るまいが、殺されて、うまくするとお嬢さんの首玉にまきつくことが出来るんだ。君たちの体の銀白のそれがね、真珠になる。あの頸飾(くびかざ)りの。まあ、そんな夢でもみながら、くねくね泳いでいたまえ。ただ贋真珠だからね、心得ちがいをしないように。 四方の太刀魚はお互いに横の仲間を見ながら、どこかへ行ってしまう。心得ちがいって、何のことだろう。贋物だと、その頸はどうだっていうんだろうね。 ※参考:この魚は、世界の温帯から熱帯にかけての沿岸に広く分布しています。 その平らで細長い体形に加え、まばゆいばかりのメタリックな銀白色の体色から、多くは刀にちなんだ名前で呼ばれます。 また、水中で見ると、あたかも溺れかけているような印象を与える立ち泳ぎの姿に由来するとする説もあります。 2024.12.22 記す。
★こがねぐも P.24
僕のこの実験はまだ正確な結果が出てこない。しかしいつかは立派な成果をおさめる日が来るだろう。ハモニカ、竹笛、オカリナ、トライアングル、僕も相当立派な楽器を沢山持っている。それをひとかかえ、全部庭の隅に持ち出して鳴らす。梅と山椒の植え込みには蜘蛛がよく巣をかける。例えばこがねぐもなどが特大の巣をぴんと張ってくれると、それで実験準備は整う。
彼女は八本も脚を持っていることに劣等感を覚えて、無理して二本ずつ揃え、X型に気取っている。なかなかスマートですね。あなたのお國では。今年は。Xラインですか。僕はそれから彼女を踊らせるちゃめの実験にとりかかるので、そんなことでも言ってご機嫌をとっておかなければならない。 バッハだってかハイドンだって、チャイコフスキーだって、またお望みならば秋田おばこだって、何だって吹けるのだが、実験は即興曲ですることにしている。ドオードドン、シエレレミイ、ミイミミファ。こうして笛やハモニカで彼女を騒状態へ誘う音色をさがす。科学的に説明すれば、吹きながら、巣の糸のある部分に共鳴する音をさがしている訳である。 どこかで糸がふるえると、蜘蛛は虫がひっかかったのかと思ってそっちの方へ駆け出し、またこっちでふるえるとこっちへ駆け出し、乱舞をはじめるであろうというのが僕の夢だ。「こがねぐものためのラブソディ」「女郎蜘蛛に寄す」というような曲が使うられる日はまだ遠いのだろうか。 ※参考:コガネグモ科コガネグモ属に属する日本で最も身近な蜘蛛の一つで、丸い腹と脚に見られる黄色と黒の太い横縞模様が特徴。 名前の由来は腹の形が小判を思わせる事から。 2024.12.28 記す。
★草雲雀 P.25 ある花や虫の名前を誰から教えられたのか、想い出そうとしてもさっぱり覚えていないのが普通だが、またそれが妙にはっきり記憶に残っているものもある。 草雲雀(くさひばり)の名前は、僕が九つの年の、関東大震災の時、その当時ハイカラな耳かくしのどこからの令嬢から教わった。大地震で僕の家は全部つぶれ、近くの家に居候をしていたが、その耳かくしも家がなかなってそこに厄介になっていたらしい。今でも、フイリリリリという声をきくと、借りていた四畳半の丸窓から見えた草むらを想い出す。 それからニ三年後、東京に自分の棲む家も出来、少年時代にはいった僕は、皇居の濠の土手へ行くと、盛んに草雲雀が鳴いているので、つかまえようと思い毎晩薄暗くなると、虫籠と大きな懐中電灯」をさげて出かけたが、僕にはつかまえられなかった。
それは自分でつかまえられなかった口惜しさからだろうか。あんまりけちな姿だったからだろうか。 ※参考:コオロギ科の昆虫。 体は茶褐色で、長い触角をもっている。 草の間にフィリリリリと澄んだ音色で鳴く。 雲雀のように美しい声で鳴くので、草雲雀の名がある。 2024.12.16 記す。
★釣舟草(つりぶねそう) P.26 三年前の秋に、日帰りの山歩きの途中で道にまよった。まよっても大して心配のないところだったので、秋草の中をおよぎまわるのも楽しかった。そうしして道のない沢を登っている時も、釣舟草があんまりいっぱいに咲いているので、小さい一株を抜いて来て庭の隅に植えた。次の年は赤紫の花を咲かせ、僕は大層満足だった。去年は僕の額に八の字が寄った。というのは、少少いい気になって筋骨たくましい赤い腕を四方に、傍若無人にのばしはじめたからだ。
その前進のしかたは、きつりふねや鳳仙花の戦法と同じで、種子を猛烈な勢いですっ飛ばすのである。つやつやした緑の莢(さや)は、内緒で力瘤を入れていて、ちっとでもさわると、無茶苦茶に破裂して、その種子は三メートルも四メートルも飛ぶ。僕は充分に身構えているつもりでも吃驚(びつくり)する。そのためにこいつらは気短か者という学名を貰っている。 僕は手を下さなければならない時が来たと思った。弾き出される黒い種子は、頬にぶつかって来る。そんなちっぽげなものをぶつけてみたって、痛くなんかあるもんか。不遜な彼らの、これが最後のもがきかと思った。そうすると僕の耳には、君も相当気短か者 だねという声が聞こえたり、来年は花壇でお目にかかりましょうというつぶやきが聞こえる。 2024.10.25 記す。
★こあじさし P.27 東京日比谷の、濠の角にはいつも魚が集まっている。この濠に鯉の幼児を沢山放したところは、いつも人だかりがしていたが、今ではもう濠の水をのぞき込んでいる人もいない。魚がそこに集まるのは、人が何か投げてくれるだろうという意地のきたない根性からではなく、彼らをねらう鳥を恐れ、人間をたよりに集っているのだ。 雲の流れの早い風の日に、みかげ石に腰かけて、東京湾からここまで翼をのばしてやって来たこあじさいの群を見ていた。ひらひらの蝶のような飛び方をしているかと思うと、その長い翼を畳んで、急降下して魚をねらう。風が強くて、濠の水には小皺(こじわ)がいっぱい寄っているせいか、こあじさしはなかなか魚とりに成功しない。 熱心に見ているうちに、僕の後には、はるばるアメリカからやって来た軍人さんの、少しばかり偉そうなのがいて、この鳥の名をたずねる。オデュポンの『アメリカの鳥』を持っている僕は、これを知らなくては大変だ。 コレハアナタノ国ニモイル Little Tern デスヨ。ワタシガアナタノ国へ行クコトガアッテ、コレニ会エタラ、ドンナニウレシイデショウ。
※参考:コアジサシは漢字で書くと「小鯵刺」。 「鯵刺」は魚のアジを突き刺すという意味があります。 これは、アジサシが小魚を見つけると矢のような急降下で、魚を捕える特徴に由来しています。 海岸、干潟、河口など開けた水辺に飛来。 2024.12.09 記す。
★羚羊 P.28
動物園で羚羊が死んでしまった。これは鹿の仲間ではなくて、牛の仲間である。しかし牛も喪には服さなかった。細い脚を縄で結えられて、羚羊は剥製株式会社に回されたが、まだ復活してこない。こいつは、角が短いだろう? だから名前だけで鹿にはなれないんだ、覚醒会社の小使が知ったか振りをして言う。
羚羊は天然記念物であることを自分では知らない。それを知っていれば、山であんなにおどおどしないだろうに。 動物園では檻を空けておく訳には行かないので、かわりの一頭を生け捕ることになったが、天然記念物という名前のために、役所では幾枚もの紙に大勢の人たちが、丸や四角いハンコをいっぱい捺(お)した。そうして選ばれた役人は、動物園の人たちをつれて山へ向った。山では猟師たちが通達書を受取って二十数人、村役場の前に鉄砲を小脇にかかえて集って来たが、彼ら猟師たちは、一人残らずこの天然記念物の毛皮を着ていた。 僕はこの話を、ある山からのかえり汽車の中で聞いたのだが、その人のリュックサックの中にも、もちろん羚羊の尻皮がはいっていたにちがいないと思う。 ※参考:「褥」は毛の敷物の「しとね」のことで、意味的にはカモシカの語源と同じである。 漢字では「羚羊」とも書くが、「羚羊」は「レイヨウ」という別種である。 人間の美脚をたとえて「カモシカのような足」と言う際の「カモシカ」も「レイヨウ」のことを指しており、実際のカモシカの脚は太いため、とても美しいとは言い難い。 2024.12.28 記す。
★きつりふね P.29 これはヒマラヤの山中にも咲く鳳仙花の仲間だが、植物学者リンネは Impatiens noli-tangere という学名をつけ、我ながらうまい名前をつけてやったと思って、さぞかしにっこりしたことだろう。わたしは気短かでさわちゃいやよ。といういみである。黄色の小舟のような花をいっぱいぶらさげてから、細長い莢(さや)が出来るが、そいつにちょっとさわると、突然はじけて種を勢いよく飛ばす連中なのだが、こんな学名がついているのを知ってしまうと、きつりふねの多い藪を歩くのはむずかしい。 四日間も雨に降られていた八ヵ岳の谷で、僕はもう小屋にぼんやりしているのもほとほとたまらなくなくなると、濡れるのも承知の上でそこらの藪を歩いた。藪のきつりふねとは大分親しくなったようである。 最初のうちは、黙っていた。ただ自然から与えられた仕方で、自分たちの種族を保存するために、忠実に、いじらしくなるほど忠実に種を少しでも遠くへ飛ばしていた。しかし馴れて来ると文句を言うのもいた。
ごめんごめん。だけどいいじゃないか。種子をまき散らすことは祝福すべきことなんだから……。 でもあたしの、あんまり勢いよくって……。すっ飛ぶんですもの。恥ずかしいの。 24.11.08記す。
★蚊柱 P.30
右にいも畑、左には大根、畑のへりには枯れた韮(にら)がそのまま並んでいる。僕はそんなところへ陣取って、ラスクをぽりぽり食べながら、夕陽に色づく欅を描いたり、枯草の土手を描いたり、遠くの方に見える傾いたような家を描いてみた。 うすい紫の靄の中で秋をもやす太陽が真赤だ。風景の燃焼も最後に近づいている。 その時に気がついて、目の焦点を切り換えててみると、目の前に五六匹の蚊がもやもや始めた。それが見ているうちに、どこから集って来るのか、その数は二十匹にふえ、もうよくは数えられないが三十匹にもなったろう。揃いも揃って病人みたいに、青白く弱々しいものばかりだ。人の血を吸おうなどという元気のあるものは全然いない。 これは多分あかいえかの雄ばかりだが、蚊柱というものは変に懐しく昔のことを想い出させるものだ。遠い遠い、あの廊下の角の軒の下。僕は蚊柱を見ながら泣くのを我慢したことがあったように思えて仕方がない。 ところでこの蚊柱の成因については完全な説明が出ていない。交尾の前奏だろうということだけである。彼らの群音は聞こえない。秋の日暮に雌を知らない雄たちが集って、青春のもやもやをこうして慰め合っているようだ。僕は出来そこないの自分の絵に××を沢山かいて蚊柱と題した。 ※参考:そもそも「蚊柱(かばしら)」ができるのは、なぜ? 蚊柱は数十~数百匹ものユスリカで構成されていますが、そのほとんどは雄(オス)のみであることをご存知ですか。雌(メス)はいたとしても1匹から多くても数匹しかいません。 1匹では些細な羽音も、数百集まれば結構な音のボリュームに。雄は集まってそれぞれ羽音を鳴らし、基本的に単独行動する傾向にある雌を呼び寄せるべく、自分たちの存在をアピールしています。そう、ユスリカにとって蚊柱は大切な“出逢いの場”なのです。 繁殖期になると雌はたった1匹で蚊柱の中に飛び込み、相手を見つけて交尾し、産卵します。蚊柱を見つけさえすれば、ユスリカの雌は圧倒的に有利な状況で、運命の相手と結ばれるというワケです。 ユスリカは通常、卵塊(らんかい)と呼ばれるかたまりの状態で水中に産み落とします。その形は、球状だったり紐状だったり様々。また、種類によって卵数も異なります。例えば、セスジユスリカが一度に産むのは500個程度、オオユスリカは約2,000個にも及ぶようです。他のハエ目と同様に卵から幼虫となり、蛹(サナギ)を経て成虫になります。ちなみに蛹の期間は、数時間から数日程度。その後、成虫になってもわずか数日しか生きられません。 うっとうしく感じる蚊柱ですが、儚い命を繋ぐために奮闘するユスリカの雄の集合体と捉えると、少し不快感が和らぐ方もいるのではないでしょうか。しかし、残念ながら、無害と言い切れない一面もユスリカは持っています。 2024.12.28 記す。
★にむらさき P.31 これは蝶の名前として、現在でも堂々と通用しているが、この蝶を撲滅しようとつとめている人は、僕の周囲にも何人かはいる。しかしまだぞくぞく発生する虞れはある。
それからヘルマンヘッセの本の中でも、幅を利かせて、飛び回っている。ところがこんな名前の蝶は、どこにも存在していない。それならこの怪蝶発生の原因はどこにあるか。 Schillerrafalter は学名 Apatura ilia とうので、それはこむらさきにあたる。少なくもそれに近い。ただそれが、独和辞典のうちで最も信用されているものに、「にむらさき」と誤って載っているだけのことである。
辞書というものは、信用せざるを得ない。しかし、動植物のようなものには、かなりの神経を使った方がいいし、池の中に鯛が泳いでいたりしたこともある。
こむらさきはきれいな蝶である。これが、ドイツの優れた文学の邦訳書の中で、夢の世界へ誘うような紫の光を見せてくれるのはいつのことになるだろう。 ※参考:こむらさきの名前の由来・・・ハネが紫色に光り、オオムラサキに比べて小型であることからコムラサキ。 2024.12.23 記す。
★猫 P.32 子猫が、少しも猫らしい疑いの顔付をしないで、澄して僕の部屋へはいって来てから、そして猫嫌いだった僕に追払う暇も与えずに肩へ飛び乗ってから、もう一年になる。
手ごろの所に並んでいた美術全集は、爪切鋏で切ってやるのもなかなかむずかしい子猫の爪でぼろぼろになったが、考えて見れば僕も猫のことでは、随分書かせてもらったので文句は言えない。 この二代目のうちの一匹だけが何とも言えない手つきで部屋の戸をあけることを覚えた。少なくもそこの戸だけは立付が大変いいことを証明してくれた訳だが、その度に僕は立って戸を閉めに行かなければならない。人間という奴は、立ちあがる時に舌打ちをするという奇妙な癖があると、猫は首をかしげる。それよりも僕にとってもっと残念なことは、この歳になってついうっかり猫撫声を出してしまうことだ。 お前、つでに、もう少しお利口にならない? 自分で戸をあけてここへはいってきたんだろう? そうしたら忘れずに閉めるんだよ。猫はそれが分ったような顔をするからいやになる。 ※参考:寝るのが好きという意味の『寝』と『好む』を組み合わせた『ねこむ』から『ねこま』になり、『ねこ』になったと考えられているのです。 また、『鼠』と『神(こま)』を組み合わせて『鼠神(ねこま)』としたという説もあります。 猫がネズミを捕まえる習性があるのは、よく知られています。 2024.12.28 記す。
★キャべツ P.33 いつもトンカツの仲間であるこのキャベツが、八百屋の店先に並んでいると、一種の風格をもっている。青白い達磨、青白い文学的達磨、あんまりからかうと腐る。 フランス語ではシュウ。複数になると、SをつけずにXをつけること。シュウ・シュウと重ねると、「お気に入りのひと」。しかし生憎と八百屋の店にはキャベツの山だ・ そこへ衰えた紋白蝶がやって来てまごまごしている。今度はキャベツたちがこの蝶をつかまえてからかい始める。 知っているよ、君の生れた畑へ行ってみたら、白ペンキの家が建っちゃったというもんだろう? ウ? 絶亡的な奥さん。大分お腹が重たそうだね。便々たるもんだね。
彼女は自分の危険を考えなかった。恥ずかしさも何も思わなかった。またそこから生まれる幾つかの生命のことを心に懸けるゆとりもなく、八百屋の店の、どっちりと構えたキャベツに卵を産んだ。ただそのつとめを果たすために。 ※参考:キャベツという名はラテン語のcaput(頭)に由来。 江戸時代に、オランダ人が長崎へ持ち込んだためにオランダ菜と呼ばれ、観賞用に栽培したものは葉ボタンと呼ばれました。 キャベツの原形といわれるケールのような野生種をケルト人がヨーロッパに広め、その過程でいまのような丸い形になりました。 ※参考:モンシロチョウの名前の由来は、「紋のある白いチョウ」で、「ちょうちょ、ちょうちょ、なのはにとまれ・・・」の歌のモデルです。 長い間日本人に親しまれてきたチョウで、日本の春の風景には欠かせないもので、さなぎ越冬するため見つければ、春が来たと思ってもよいでしょう。 2024.12.29 記す。
★葛(くず) P.34 秋風が山を撫でる。山が白っぽくなる。葛の葉がその裏を見せるからだ。これが山の木々にからみつくと、秋が奇妙に荒れ、もうこれですべてが終るという感じだ。年寄りは寂しがる。
土手をのぼった。薄を分け、滑り落ちそうになりながら、木々にからまっている葛を見つけると、根もとの方を鉈(なた)でぶっ切り、腕にからませておいて力一杯に引張った。頑強な葛は、茎を断ち切られても一向に平気だった。時には、その蔓をもって、僕は松の枝から飛び降りた。風の強い秋の一日、老人を寂しさから救うために、僕は汗を多量に流し、みみずばれを足にも手にも、頬っぺたにも作った。その老人は僕の父なのだが、そうして一日の努力で、目の前の土手の葛はあらかた退治は出来ても、寂しさはきえなかったようだ。 僕はその時以来、山道を歩いていても、葛を見つけると、つい目のかたきにする癖がついてしまった。葛の葉のうらみというのはこれである。 ※葛餅(くずもち、くず餅)は、日本で作られる葛粉を使用した和菓子。また、小麦粉からグルテンを分離させた後の浮き粉を発酵させた「久寿餅」という同音の和菓子。同名だが主に関西と関東で原料と製法の異なる二種の和菓子がある[1]。いずれも黒蜜やきな粉をかけることが多い。
★木菟(みみずく) P.35 東京雑司ヶ谷の鬼子母神で、飯塚エイというおばあさんが薄の穂をうまくまるめて、腰のあたりを糸できりりと結んで、木菟を作っている。親子木菟というのは、翼の下から、もう一匹小さい木菟が顔を出している。この薄木菟のほとんど亜種と言ってもよいものが、武蔵野の深大寺にもいる。筆筒を立てておくと、こんなものでも睨むことがある。やはり木菟だから夜中になると一層目が光る。僕は、これや、赤ペコや、鯛車(たいぐるま)など、こういう種類のものばかりを集めた動物図鑑を作ることを想い立って、無罫の大型の帳面を一冊下ろす。そして先ずこの木菟を出来るだけ丹念に描いて、次のような記録を作ってみた。 シンダイジズク(薄梟鸱科)学名 Otus hoyahoides Mag. var. Miminashi 羽色は銀褐色、やや紫を帯びたところがある。アオバズクに似て頭丸く、耳がない。胸のふくらみは極端で、ここにさまざまの想いが貯えてある。深夜鋭く光る眼も、しばしば胸のふくらみにかくれることがある。横から見ると猿に似ている。鳴声はウフウフウフ。嘲笑を含んでいるように思える。
※参考:漢名木菟・木兎(ぼくと)は、樹上性のウサギの意味(菟は兎に同じ)で、羽角をウサギの長い耳になぞらえたもの。 鵩(ふく)・鶹(りゅう)・鵂(きゅう)は1文字でミミズクを表す。 角鴟(かくし)・鴟鵂(しきゅう)の鴟はトビ・フクロウ類の総称。 参考:大原總一郎著『母と青葉木菟』(春樹社) 2024.12.04 記す。
★ガロワ虫 P.36
横浜の総領事をしていたガロワさんを訪ねたのは昭和十六年だった。仏印へ向って横浜を引き上げる時に、蔵書を処分したいというので出かけた。
山手の、領事館の地下室でも、古典の叢書類をさがしたが、二階の割合に狭い部屋の、机の上に、画集だの、装本のきれいなものなどが、僕のために準備され、並べてあった。 愛想のいい奥さんは、紅茶がいいかキャフエにしょうかなどと訊ね、しばらくして、ちょっと出かけて来るからと言って僕を二階のその部屋に残して行った。やがて、鬚の黄ばんだガロワさんがパイプをくわえてはいって来た。僕は二言三言、お世辞のつもりのフランス語を喋ったが、むっつりした彼は、昆虫標本箱の引出しに手をかけた。そして振り向きながら、アナタは虫家デスカ。好キデスカ、と訊ねた。 コレ、ワタシノ日本ノ最上ノ想イ出。ゴランナサイ。そう言って見せてくれたのがガロワムシだ。彼が、蟻の鬼のようなこのけちな虫けらを日光で発見したのは、僕が生れた大正四年のことである。 伝え聞くとこではガロワさんは、現在、半年をパリで、夏を中心とした半年を郊外で、虫家としての晩年を送っているらしいが、僕の歳とともに古びて行くガロワムシが、彼の傍で日本の最上の想い出になっているだろうか。 ※参考:ガロアムシGalloisiana nipponensisが代表種。 和名および属名などにつけられているガロアは、フランス人の外交官の名で、日本で初めてこの昆虫を日光の中禅寺(ちゅうぜんじ)で発見したのを記念し、名づけられたものである。 2024.12.29 記す。
★おおわた P.37 大わた来いまま食わしょ まァまがいやならもち食わしょ この間からおおわたがよく飛ぶ、晩秋から冬にかけて、風のない日暮れにこの虫は真白な衣装をつけて、まるで小さな夢遊病者だ。どこかで落葉を焚いているのかしら。灰が飛んで来たかと思うこともある。熱心に翅を動かして飛んではいるのだけれど、どこへ行こうとしているのか、その意志は見極められない。僕は母が教えてくれた歌を想い出す。母は老いてもうその歌を忘れてしまった。 今日は、潰してしまわないように、そっとその二匹をつかまえ、昆虫の本を数冊開きながら、顕微鏡で羽の脈や触覚」をしらべ、ノートにかいた。
これは恐らく綿虫亜科のりんごめんちゅうらしい。何しろ潰れ」易いので、針先でいじっていても息苦しくなり、自分の指先の大きすぎるのがにくらしくなる。そして脂蠟腺(しろうせん)から分泌されたその綿は、ちっともきれいなものではなかった。僕は、この小夢遊病者の、その異常な夢の結晶が見られるように思っていたのだが、僕の勝手な夢想の方を訂正しなければならない。
しかしこの分泌物は雨露や外敵からの保護に役立っているということである。また最近放射能を含んだ雨が降り出したようだが、おおわたは、そんなことが起っても、自分には関係がないように変に悠然と」飛んでいる。 ※参考:この虫の呼び名としては、他に綿虫(わたむし)、雪蛍、東京地域のオオワタやシーラッコ、シロコババ、京都地域のゆきんこ、おこまさん、伊勢地域のオナツコジョロ、水戸地域のオユキコジョロがある他、しろばんばといった俗称もある。小説『しろばんば』のタイトルは、この虫に由来する。 2024.12.29 記す。
★なんじゃもんじゃ P.38
未知の読者からのお手紙により、明治神宮外苑のなんじゃもんじゃが枯れそうだというのでお見舞いに行った。植物医でない僕には何とも診断が下せないが、野球場の外の素人野球の鞠が飛び交う芝生に、全く邪魔もののように、痩せほそって立っている姿は気の毒である。この木の本名はひいらぎ科のひとつばたで、大正十五年の明治神宮奉賛会が立てた傍らの石碑にもその名は大きく書かれている。
「此の樹は古くより青山六道の辻にありて俗に六道木又ナンジャモンジャとも呼べり吾邦に稀なるものを植物学者の注目する所となり旧時の位置をそのままに維持し来り大正十三年天然記念物として指定せられたるものなり」 またそのそばには、「右原樹は昭和八年枯死したるにより、嘗て其樹より根分けして育てたるを昭和九年十一月植え継ぐ」と書いてある。僕はいかにも栄養不足で、もう神経も衰弱し切っているような幹を撫で、写真を撮った。そんなことをしたところで、どうなるものでもないのに。 ところで、なんじゃもんじゃという名は、水戸黄門がそう名づけたと言われる千葉県神崎神社の楠(くすのき)を本物または元祖として、筑波山のあぶらちゃん、山梨県の鶯宿峠(うぐいしやどとうげ)のりょうめんひのきなど、方々でいろいろの木につけられている。奇妙な現象のような気もするが、風変わりな得体の知れない男が、昔はみんな哲学者と呼ばれていたようなものだろうか。便利な名前である。 ※参考:「なんじゃもんじゃ」は、ヒトツバタゴの別名で、その由来は、他では見られない珍しい木を珍しがって呼んだことにあります。 ヒトツバタゴは、本州中部の木曽川流域と対馬に自生する落葉高木で、初夏に雪を被ったように真っ白な花を咲かせます。日本では東濃地域と愛知県、長崎県対馬市の一部でしか自生しておらず、自生地では国の天然記念物に指定されています。 「なんじゃもんじゃ」の由来には、次のような諸説があります。 水戸黄門が下総の神崎神社の御神木を「この木はなんじゃ」と尋ねられたとき、土地の人が「なんじゃもんじゃ」と問い返したという説。 神社・仏閣にある御神木と見慣れぬ種類の大木を「なんじゃもんじゃ」と呼ぶ説。 木草学者の水谷豊文が、タゴノキ(トネリコの方言名)と見誤って単葉のタゴ、つまりヒトツバタゴと名づけましたという説。 ヒトツバタゴの英名は”Chinese fringe tree”で、「fringe」とは「ふさ飾り(状のもの)」を指します。 2024.11.20 記す。
★銭苔 P.39 ぶらっと訪問した家の、小さな坊ちゃんが僕の手をひいて、ジャングル見せてあげようと言う。僕はその家の裏木戸をくぐり、台所のかげの寒い日かげへ連れて行かれながら、はてジャングルとは、と考える。どぶのへりの湿ったところに一面にはびこっているぜにごけだ。 幼い頭のその空想は、今そこに小さくひょろひょろと伸びた雌性器を椰子の木と見たてものである。僕の頭はどこまでその空想について行くために切り換えが出来るだろうか。椰子の密林へはいって行こう。小さい坊ちゃんは僕の手を離さない。というより話すのを忘れている。僕たちは何かしらないがそこを急いで歩いて行く。しかし私の頭にはせいぜい、毒槍(どくやり)を持った主人と、五六匹の元気のない鰐の幻影ぐらいしか浮かんで来なかった。何しろその日かげは寒い。
葉とも茎とも言えないようなものを同節体というのだが、かりにニセンチ半ぐらいの雌性器が椰子の木ほどのものだったら、僕たちは、その下に何がかくれているかわからない同節体の上を歩きながら、どんなにかヒロイックになってしまったことだろう。
僕はその日、一片のぜにごけを貰い、手帳のあいだに挿んで来た。大学で講義をしている時に、手帳からそれが机の上に落ちた。僕は今度はほんとうにジャングルの幻想が湧いた。 ※参考:苔類の葉のようなものは葉状体と呼ばれますが、葉状体の表面には六角形の白っぽい穴があり、全体の形が昔の穴あき銭に似ていることから『銭苔(ゼニゴケ)』と名づけられたようです。 2024.12.30 記す。
★せぐろせきれい P.40 普段から見なれているこの鳥について、今別段、珍しい観察をした訳ではない。天を斜めに突いて行くような波状の飛び方も、電線工夫たちが、針金を長くのばして叩く時のような黄鶺鴒(きいせきれい)よりは少々風邪気味の声も、全く変りはない。 ただここに、最上川の庄内平野へと流れ込む手前の、両側から川をつまんだような清川付近の渓谷である。驟雨性の雨がさっきから盛んに秋をまき散らし、川を濁らせている。僕はもちろん濡れている。
淋しい秋だ。その秋の流れる中で、暖地へ渡って行かない背黒鶺鴒の声には、遠くの山の端に見えている青空のような明るさが感じられる。 ※参考:セキレイという名は中国の呼び名「鶺鴒」を音読みしたもので、「背筋を伸ばした美. しい姿勢の鳥」という意味をもっています。 セキレイは日本の文献に最初に現れる記念す ... 2024.11.05 記す。
★かまどうま P.41 友人からの手紙に、気がついてみると今夜はさっぱり虫の声が聞こえないけれど、一体いつ頃から鳴き止んでいたのだろうかと書いてあった。僕はその手紙を受取る三日前に、蟋蟀(こおろぎ)が夜おそく、ほそぼそと独唱していたのを聞いて、そのことを日記にも書いておいたところだ。十一月初めである。 こうして虫の声が絶えてから、妙にその生存振りを見せているのはかまどうまである。流石にもう大分弱っているなあと思ってつかまえようとすると、びっくりするほど跳ねあがる。彼らは夏のうちから、ただ黙って暗いところにいるが、あたりの賑やかに歌うことを誇っていた連中が姿を消すと、急に目立って来る。
風呂を焚きつけながら、大分きたならしくなった釜のうしろを掃除していると、ニ三匹はまだ出て来る。その中には柄の大きいまだらかまどうまもいる。こんな奴はあまり狼狽もしないで、ちょくちょく風呂をたてて貰いましょうかね、こう寒くなっちゃ、温まらないとやり切れませんからな、そんなことを言いそうな顔をしてこっちを見る。
はっきり言うことを許して貰えるなら僕も言うけれどね。どうも僕は君を好きになれないんだ。ほんとうに悪いと思うんだけど。まだ小さい時に、君になめられると頭が禿げるって、誰かが教えたような気がして仕方ない。それが未だに残っているんだな。 それにしても何という見事な脚の筋肉だろう。これだけは僕も認めざるを得ない。 ※参考:かまどのような薄暗いところにいて、馬のように飛び跳ねる虫なので、「カマドウマ」と名づけられたようです。 夜になると台所やトイレなどに出てきて驚かせますが、衛生的な害はありません。 2024.12.17 記す。
★らっこ P.42
らっこという海獣は太りすぎている。海水に棲むのだから、痩せていてはならないと思うが丸々と太り、またそれを苦にはしていないし、メーグルなどという薬も知らない。みんな一緒に太りすぎているからだ。
僕はらっこと聞くと、その海獣を想い出すまえに、悪いことだが、らっこという異名をつけられていた物理の先生を想い出す。おじいさんで、ころんころんで、可愛くて、いつもその姿に見とれていた。そうして、そこにどんな法則があるのか、どんな現象が起 こるのかさっぱり聴いていなかった。 出版される前にその図版だけを見て推薦文を書いた立派な動物図鑑が出來あがり、送られて来た。そしてぱっと開いたそこにらっこがいた。冷たそうな北の海に仰向けに浮んで、両手であわびを、大事そうに持っている。そしてなぜだかぼんやりしている。もうじきに眠ってしまうんだなと思う。ゆりかごにひとり置き去りにされて、もう泣きさけぶことにも疲れた子供が、玩具(おもちや)を持ってうつらうつらしているのと、一体どこがちがうのだろうか。 ただ僕は、このらっこが眠るのを待って、大切なあわびをねらっているものがいそうで気が揉める。記載の文章をよんでみると、この動物は、夜になると浮藻(うきも)を体にまいて、こんな風にぷかりぷかりと浮び「ながら眠るのだそうだ。浮藻を体にまくのは、風邪を引かないための可憐な用心なのかしら。 ※参考:アイヌ語ではアトゥイエサマン(海のカワウソ)とも呼ばれるが、夜にこの言葉を使うとカワウソが化けて出るため夜間はラッコと呼ぶようになったという伝承がある。 2024.12.30 記す。
★七面鳥 P.43 クリスマスのこの犠牲者を、慈悲深いはずの信徒たちが一向に救おうとしないのに、僕がそれを考えるのはあんまり馬鹿げている。七面鳥を御馳走になたらくとも、僕には僕らしく毎年の降誕祭がやって来る。それに彼女たちの顔のあたりにある皮膚病はひどすぎる。ルナール風に言えば癇癪の皺だ。
まだ幼いころ、たった一度、僕の家に七面鳥が贈られて来たことがある。籠の中で縄でがんじがらめになっていた。しかしこの鶏の怪物は、決して諦めてはいなかった。恨みだの怒りだの、世界に存在するすべてを憎んでもまだ足りないような顔をしていた。これを贈ってくれた人は、クリスマスにかこつけて、僕の家に対する長年の恨みを晴らそうとしているにちがいないと思った。
僕に今、一羽の七面鳥をくれるものはいないだろう。けれども、中学生時代のファーブルがおもしろがってやったように、翼の下に首をつっ込み、手で抑えて二分間ゆすぶるのだ。彼女は目を回し昏睡する。死んだ真似をするのではない。彼女は死について哲学したことがない。ただ僕は、この尊大な容子がどうも気に入らないので、一度でいいから、愛する七面鳥よ、と言えるようになるために、少しいじめてやりたいのだ。 ※参考:和名のシチメンチョウは漢字で七面鳥と書きます。 これは、首のところに露出している皮膚が、興奮すると赤、青、紫などに変化し七つの顔(面)を持つ様に見えたことが由来とされています。 シチメンチョウが家禽として食用になったのは、ネイティブアメリカンの食料とされていた西暦1000年頃が始まりというのが有力です。 2024.12.17 記す。
★べツレへムの星 P.44 キリストが生れた時に見なれない星が現われた。このべツレへムの星が何だったのかということで、大勢の天文学者たちは真剣になって沢山の計算をした。聖書にはほんとうらしく書いてあるからだ。
この、六方に張って、緑色を帯びた白い花を見ていると、清浄な星の光を想わないでもない。すがすがしく、少しは神秘的な匂いを嗅いでいる気持ちにならないこともない。 旧約の列王記略下に、サマリヤに糧食が乏しくなった時、驢馬の頭だの、鳩の糞までが大層値が上がったと書いてある。驢馬の頭の方は、ぐつぐつ煮込めば何とかなりそうだが、鳩の糞とはどういうことなのか。 これは本物の鳩の糞で、塩の代用にしたのだとか、また聖書の方々に出ているいなご豆のことだという解釈など、いろいろの説があるが、それはこのオルニソガルムだという人もいる。目立つものにはさまざまな名前がつくものだが、星から鳥の糞まではずいぶん隔たりがある。 またこの花をフランスでは、十一時の夫人と言う。十一時にならないと目を醒さない、寝坊な貴夫人である。 2024.11.09 記す。
★クリスマス・ローズ P.45 僕は数年魔に、この花のことで五六日、根気よく文献をあさり、またギルシャ語の大家を訪ねたりしてものである。その詳しいことは「アリポロン自伝」という小説にしてしまったが、ギリシャの哲人たちは、これをへレポロンと言って大切にしていた。というのは、彼らが大論文を書いたり、厄介な論敵とわたり合ったりする時、自分の胃の腑に溜まっている腐った気が、霊魂の邪魔をしないように、この草の助けを借りたということである。ヒロポンのようなもので、それをどういうふうにするのか多分、煎じても飲むと、頭がすっきり。狂人にも効力を示すので、今、辞書には、治癲草(ちてんそう)という訳語もついている。
つまり賢者は常に愚者たる可能性を持っているようである。僕は自分の精神活動ががらりと変わるような草花を、庭にずらりと植えておいて、思う存分に賢くなったり、また必要に応じて愚かになったりすることが出来たら……とそんな夢を見ている。 2024.11.09 記す。
★薔薇(ばら) P.46 僕は立ちどまって薔薇の花を造っている白衣の男の手先を見た。彼はガラス張りの檻の中で、片手に混沌としたクリームのはいった三角帽をさかさに握っていた。
ところがこの薔薇も、本物のようにするためには、花びらのへりをややそらせなければならない。白衣の造物主は、そのこつを心得ている。彼は一枚の花びらを造ると同時に、口をとがらせて息を吹きかける。どろどろのクリームはその男の息をうけていよいよ薔薇のようになる。 この見学によって、お菓子の薔薇をねらわなくなるのは僕だけではないだろう。造物主は奥座敷で仕事をしてくれた方がよさそうである。 2024.10.27 記す。
★まがも P.47 すでに手紙では知り合っていた東村山の貯水池の番人T氏を訪ねた。彼は鳥類の学者ではないが、観察の時間は幾らでもあるので、いろいろとこの貯水池に集って来る鳥の生態に詳しい。鳥ばかりでなく、植物の咲き始める時期にも、またそこを散歩する人間についても。僕はT氏からまがもの生態について、なかなか雄弁な話を聞きながら、その数え切れない群を双眼鏡で見ていた。気持の集中のせいだろうが、眼鏡で見ていると、声までも近くに聞こえるようだ。何を話しているのかは分からないが……。 今年は例年よりも大分早く彼らは渡って来たという。歳の暮れなのに、今日は、気温二十度を越した暖かさだ。氷はどこにもない冬の水に浮かびながら、春のようなs錯覚を起しているのもいるだろう。
※参考:江戸時代前期になって 「まがも」 と呼ばれるようになり、定着した。 名前の由来は、それこそ "カモの見本のようなカモ" ということであろう。 2024.12.06 記す。
★ちょろぎ P.48 甘党である僕は、正月の御馳走は何でもきれいに食べる。しかし黒豆の、てらてらの光の中に真紅のちょろぎがはいっているあの赤と黒は、目と口とを同時に楽しませてくれるのが好きだ。
ちょろぎがどんな植物の根であるかを知っている人は案外少ないようだ。僕は、ジャン・ジャック・ルッソオの、植物に関する幾つかの手紙を読んでいる時に、 epiaire という植物にぶっかった。「わたくわっこう」と手元の辞書には出ているが、どうにもならないので、あっこっちと植物の本を歩き回ると、最後にちょろぎにぶつかり、これを覚えることが出来た。 地下茎の先に、どうしてこんな塊茎が出来るのか、まるでガラガラ蛇の尻尾みたいだ。その後、西洋料理ではこれをゆで、バターいためにし、グレピーソースをかけて食べるということを聞いた。うまいかどうか、食べたことはない。原産地の中でその存在を主張させておいた方がよさそうである。 現在、庭でちょろぎを栽培するという念願がかなった。うんと殖やし、梅酢につけたり、バターいためにしたり、また新しい料理を考えてやろう。 ※参考:ちょろぎの由来には、次のような諸説があります。 中国語の「朝露葱」が日本語読みされたもの 韓国語でミミズを意味する「チョロンイ」が転じたとされるもの ちょろぎはシソ科の植物で、中国が原産とされており、江戸時代に日本に伝わったと言われています。おせち料理の定番として梅酢漬けの赤いちょろぎがよく使われ、縁起をかついだ漢字表記が当てられています。 ちょろぎは、次のような意味が込められています。長寿を願う、健康でまめに長く働くことができるように、子孫繁栄。 ちょろぎは、1つの種から多くの塊茎(かいけい)が収穫できることから、「子孫繁栄」の願いも込められた縁起物です。 2024.11.21 記す。
★くものすかび P.49 ほとんど毎年、正月の餅がなくなるころになると、その上にせっせと繁殖するさまざまの黴(かび)にさそわれて、これらの菌類についての知識をふやそうとするのだが、僕の知識の方は、餅の上の黴のようにはふえてくれない。 信州から届いたからと言って持って来てくれた餅の最初にあらわれたかびが、どんな具合に繁殖して行くかを見ていたが、これは別に、僕の知っている限りの信州人の性格や、その発展振りとは関係なそうであった。 黴の胞子嚢にはいろいろの形がある。わたかびのように、腕をのばし、自分の頭をかかえ込んで悲観しているものもある。これはほんとうに可哀そうな、いじらしい恰好である。また、おおかびのように、誰かが握手をしてくれるのを待っているようなものもある。
僕は自分のごつごつの頬を、知らないうちに撫でて溜息をついていた。 ※参考:クモノスカビ(Rhizopus)は、菌界・接合菌門・接合菌綱・ケカビ目・クモノスカビ科(あるいはケカビ科)に属するカビの和名である。 基質表面をはう菌糸の様子がクモの巣を思わせることから、その名がある。 2024.12.30 記す。
★かいつぶり P.50
しばらくこの池にも御無沙汰していたのだが、今日夕方来てみると、三十羽ほそのコガモが水面に浮かんだり、岸辺の石の上に押し合って並んでいた。水に浮いているのは、のび上って羽ばたきをしたと思うと、意味ありげなお辞儀をし、何やら啼き合っている。
その群がっているコガモに対して、一年中この池を棲いとしているカイツブリは、物珍しげに近寄ってみる。相変わらずカイツブリはアベックで、コガモの仲間入りをしたくもあるし、またどやどややって来た連中に対して、ちょっとした矜持もすてにくいらしい。 あんまりばかな顔して見とれてるもんじゃないよ。こっちへ来いよ、いい加減に。 でもちょっとばかしね。あの眼もとのきれいな色。いいわよ。 勝手にしろ。カイツブリの彼氏は、その容子に似合わないが、いささか憤然として飛び立って行く。笛を吹きながら、お前にはもう用はないというふうなそぶりさえして。彼女の方は今日は彼のあとを追わなかった。そのようなちっぽげな頭をどうも悩ましているらしかった。ファッション・ショウを見た田舎の娘のように、出来ない相談の憧れと羨望をいっぱいにしているらしかった。 ※参考:「カイツブリ」の語源は、水を掻いたり潜ったりする様「掻きつ潜り(カキツムグリ)」から転じたという説などがあり、その名が示すとおり泳ぎを得意とする鳥である。 主に淡水の湖沼で暮らす。 主食は魚である。 クビナガカイツブリの羽根は非常に高密度で撥水性が高い。 2024.12.15 記す。
★けんみじんこ P.51 寒い夕ぐれに、近くの池で久し振りにプランクトン・ネットをひいた。濡れる手がどんどんかじかんで来て悲しかった。かいつぶりの笛も夕靄の中だった。 とっぷり暗くなってから戻り、集めて来た水を幾滴もしらべたが、どうも相変わらずミジンコの類ばかりが目立って、新しいものは見つからない。小さな変なものを少し根気よく見ようとすると、ミジンコは一滴の水の中で大きくあばれ回るのだ。
このケンミジンコ(多分、メンキクロップス・ロイカルチ)の奥さん連中は、卵の袋をでかでかと両脇にぶらさげて実に何とも元気なものだ。こんなに乱暴をして、流産する心配はないのかしらと思う。そんな心配はともかくとして、一滴の水に大きな世界があ
るので、僕はそこに物語をそそぎ込んで、何時間でも、その水が渇くまで見ていることがしばしばある。しかし時にはもっと冷ややかに観察しなければならない。
卵以外のところで、雌雄を区別するには、触覚の曲り具合とその太さを比較しなければならない。それで苦労してスポイトで吸いあげて一滴の水にふたりを一緒にした。一ミリ強の体のふたりは、近よればお互いにはじき飛ばし、息使いを早めることもなく、まことに恬淡としている。僕は中学校の教師をしていたころに、いたずら者の生徒たちに、英語の女の先生と二人、せまい教員室にしめ込まれ、少々狼狽したことを想い出した。 ※参考:カイアシ類の別名「ケンミジンコ(剣微塵子)」はオイトナ亜目の一部とエルガシルス亜目を除く、キクロプス目に分類される種のことを指すことが多い。 胴体を剣の刃、第1触角を鍔に見立てた名称である。 2024.12.30 記す。
★鶯 P.52
鶯は三つ音と言って、調子を高めながら三段に鳴く。そんなうまい囀りを早春の山の中などで聞けば、それは大変にいいものだが、うまく鳴けないのが庭へ来ていると、こっちはつい、どっこいどっこいとこっちが力を入れてしまって息がつまる。自分ではうまく鳴いているつもりらしい。そんな顔をしている。全く臆面もなく……。この頃は、人間も少々それに似た歌をきかせてくれる。こっちの首を長くのばさずにいられないような、唇の裏をこっそり噛んでいないとお腹が揺れ出してしまうような、そんな歌を聞かせてくれる。いいことである。
今は、まだ囀るすべを知らない鶯が、垣根の小虫を盛んにあさっているが、こいつも、実にせっかちに舌打ちをするので、僕は気がもめて仕方がない。虫にうまく逃げられたからと言って、いちいちいかにも残念そうに舌打をしなくたっていいじゃあないか。 別に残念だからチェッと言うんではありません。あまりおせっかいなことは考ええないでもらいましょう。 どうもよく考えてみると僕の方がこの頃はよく舌打をする。夜中に食べようと思ってかくしておいた鴬餅を食べられてしまった時なんか、立てつづけに十回ぐらいチェッと言ったような気もする。 ※参考:ウグイスの名前の由来は、里山や林の奥のほうで「ホーホキェキョッ」と、求愛のさえずりを、オスがしています。 「ウグ」は、「奥」という意味で、「イス」は「出ず」奥から出てくる。 という意味だそうです。 2024.12.06 記す。kusida.usubahuyusyaku.png
★うすばふゆしゃく P.53 冬の真最中というのに、ガラス窓の桟に蛾が一匹とまっている。冬毎に一二度は必ず見かけるうすばふゆしゃくが、今年もこうして冬景色を眺めている。 近くの子供たちが、日あたりのいい、うちの縁側に陣取って、あぐらをかき、しかめ面なんかして、いかにも」もっともらしく将棋をさしている。よし、ひとつ意地の悪い試験をしてやれ、そう思って、僕は、あ、毒蛾が出たぞ、ほら見て4ごらん、大変だ、そう言って少々大袈裟に騒ぎ立てた。去年の夏には毒蛾で子供たちもずいぶん専門家らしい口をきいていたし、実物も見ているので、彼らの頭にその映像がどれほど鮮かに残っているかをためしたわけである。僕の芝居がうまかったせいかも知れないが、彼らはすっかりほんとうに毒蛾が発生したのかと思い込んだ。
将棋をさしていたのも、それをあれこれ口出ししながら見物していたのも、窓ガラスのところに集る。並べてみれば大分ちがうのだが、黒点があることだけで覚えていると、おや、そうかしらと思う。僕も何年か前にの冬に、この蛾を見て驚いた記録を、日記帳か何かに残してあるはずである。
寒い冬の日をわざわざ発生するうすばひゅしゃくは、どうも大分風変りなもので、その思想もあんまりすなおではないようだ。人間にも変な人種がいるが、ひねくれものの蛾もいる。もっともこの雅の雌には翅がない。まだ生えないのではなく退化したらしい。彼女たちに翅があれば、いい気節をえらんで飛び回りたくなるのではないか。 2024.12.30 記す。
★しもばしら P.54
これは土を押しあげる氷柱(つらら)の群ではない。しそ科の、ニ尺ほどにのびる多年性植物の名前である。この植物自体はそんなに珍しいものではない。秋に白い総状花を咲かせるから、そんな時に見つけて置いて、鉢植えにでもしておけば、しもばしらという名のいわれを見ることはむずかしくない。もっとも寒い土地でないと駄目だ。それはこの枯れた茎から氷の花が咲く。中に含んだ水分が凍り、方形の硬い茎を裂いて外へ美しく現れる。
そんなに高い山でなくともよい。むしろ雪のない低い山の方がいいのであるが、真冬に月あかりをたよりに一晩中ほっつき歩いた末に、朝日を受けて、自分の体を裂いて美しい思念の花を咲かせているのを見てやれば、ともどもにその感動も大きい。 野宿など平気で、ランタンをさげて独りで夜の山を歩いていた時分、まだ小鳥たちも眠り続けている山の峠でこれを見つけた時に、僕の胸がきゅんと痛んだことを忘れない。 僕の胸は、いたってけちなもので、氷の花を咲かせることなどは出来ないけれど、一度は見ていい光景である。いつかこれは自分」一人でみているのは惜しい気がして、かじかむ手をこすりながら、しもばしらの根を掘りかけたことがあるが、忍苦はかくも美しいものではあっても、そんなに見せびらかすものではないと思いかえして、そのまま山を下りて来た。 ※参考:日本固有の植物で秋に白い清楚な花をつける多年草です。 シモバシラ(霜柱)の名前の由来は、冬の時期に、枯れた茎に、地中から吸い上げた水分がにじみ出て、氷の結晶のような白い柱ができることからとされています。 2024.12.31 記す。
★もくれん P.55 よく観察するためには、離れて見詰めているだけでは足りないし、時にはある方法をもって、可能なものにも手を下さなければならない。大切そうに、少しずつあたりの容子をうかがいながらののびて来た木の芽をちぎり取って、剃刀の刃でずばりとやらなければならない。こうして僕はこれまで何匹かの蝶を殺し、花を摘んで花弁(はなびら)をむしった。美しく咲くべき花の芽にとっては、たとえ僕がそこからどんな貴い知識を得ても、何かしら残念な行為には違いない。 しかし僕はもくれんの芽を切ってその容子を見た時に安心した。それは一種卑怯な安心である。この花芽と葉芽とをあたたかく守っているビロード製の苞(ほう)。北風からも、あの雪からも、時には小鳥の痛い嘴からも守っていた苞は、どこを見ても無理がなく、自分の使命を実に満足げに味わっているのだった。
2024.10.26 記す。
★雪虫 P.56
長い吹雪のあとで、二月の山が珍しく晴れ渡り、僕は小鳥の声などもする谷川岳のマチガ沢を、ちょっとした哀感も感じながら、強情にスキーで登っていた。ほとんど連日の、大小の雪崩に、このかなり広い谷もかまぼこ型にもりあがり、そうして登っているうちにも、東尾根からくずれて来る雪塊が足下を頻りにとおりすぎた。
その谷の、またずっと下では、春先の芽ぶきの夢を抱いたまま、木々は雪崩に倒され、大きな枝まで、なまなましく折れていた。そんな谷の中で、今生命の欣(よろこ)びを味っているものは何か。それは雪崩のあいだを悠然と這い回っている雪虫である。 雪虫と呼ばれているものには、いろいろなことが文献として出ているが、僕がその時に拾いあげて、手のひらを這わせたのは、ふたとげくろかわげらで、歩きながら、飛ぼうとするのでもなしに時々翅をひろげた。春や夏の谷にこびりついている残雪に見かけるせっけいかわげらよりはいくらか小さいものである。今日はほとんど快晴と言ってもいい天気で、この虫たちも気分が余程いいらしく、僕の手を這いながら、のんびりとしていて逃げようとする容子もない。 僕はこの虫に語りかける言葉もなかったので、マッチ箱に入れ、これから先の、いよいよ雪崩に気を配らなければならない登りに、一つの守護神として持ち歩くことにした。 ※参考:成虫になると蝋状の白い綿毛をまとってフワフワと飛ぶことから、「雪のような虫」として「雪虫」と呼ばれるようになりました。 2024.12.31 記す。
★きばねはさみむし P.57 今年の一月から、庭や往来や、そのほかおみがけないところで出会った昆虫類の名前を、手帳から書き抜いて整理していた。もう夜も更け、眠らなければならない時間だと思いながらそんなことをしていると、僕の、いつも焦げ茶のコールテンの上衣(うわぎ)の、袖口に、まるで私もどうか仲間に入れてくれないかというように、一匹のはさみむしがよぼくたと歩いて来た。僕は何のもてなしも出来ないが歓迎をする気持ちは充分ある。たとえ三十分一時間と寝る時間がおくれようとも。 このはさみむしは、すぐに気がつくのであるが、金色のちっぽけな翅をまことに得意げにつけていて、これをよく見てくれなくては困るという容子だ。この翅は金色と言ってもはでに輝くものではなく、何か骨董品のどこからか取って来たようなものである。
※参考:体は細長く、尾端にハサミを有し、種ごとに特 徴的な形態をしており、オスにおいては顕著である。 ハサミを有すことが本目の名前の由来と なっている。 2024.12.31 記す。
★こがら P.58
三月と言っても雪の山はまだ厳冬期とかわらない。吹雪で息がつまりそうになることもある。どんなに遅くなっても灯をつけて越えるつもりの南アルプス北沢峠の、近くまで来ていながら、どうしても方角が分からなくなり、倒木の下の雪に穴を掘って一夜を明かすことにした。雪がさらさらで思うように穴も掘れない。それにしてもこんなことをするのは僕にとっては久し振りで、体全体に力を入れ、零下十四度の寒気から生命を守っていた。木々の梢が互いに触れあって音を立てる。
その雪の森に、今はっきりと生きているのは、自分以外に何がいるだろう。星も、夜半になって昇った月も、ぼんやり目ざめている僕を慰めてはくれたが、実に冷たい光だった。 やがて朝がやって来る。この薔薇色の夜明けを待っていたものは僕だけではなかった。左手の一本の大きなしらべの梢で、囀りはじめた一羽のこがらの声は、僕に身ぶるいをさせたほど美しかった。小さな喉から、こんなにも鋭く強く、森に点々と眠る仲間の、今日の目ざめを催すように、可憐な勇気をつたえて来る。それを聞いたのは僕の耳ではなく、確かに僕の生命だったように思う。 窮屈に、並べたスキーの上に腰を下したままかれこれ七八時間、凍らないようにだき抱えていた靴をはいて、雪の穴から飛び出す元気を目ざめさせてくれたのは、冬をこの高い山にとどまって、去った年の秋の、残りの木の実をさがしながら送っていたこのこがらの声だった。 ※参考:白檜 シラベ シラベはマツ科モミ属の常緑針葉樹で、日本の固有種です。モミの仲間は、琉球諸島を除く日本全国に分布しており、樹形が綺麗な円錐形となることから、天と地を結ぶ神聖な樹とされてきました。その中でもシラベは、富士山の山麓など海抜1,500mから2,500mほどの高地で育ちます。 ヨーロッパでは、モミの仲間は不滅の生命・再生・豊穣の象徴とされ、クリスマスツリーとして親しまれています。また民間療法としては、呼吸器系の不調の改善やリラックスのために活用され、療養のためのサナトリウムは、モミの仲間の森につくられてきたという歴史があります。最近では成分の一つフェランドレンの消臭効果が期待され、消臭剤の原料にもなっています。枝葉の香りは、鎮静作用の大きいエステル類の酢酸ボルニルが豊富で、爽やかさの中に優しく深い甘みが感じられます。 ※参考:雀(カラ)は「鳥」を意味する漢字で、カラ(雀)類はシジュウカラ科の総称です。 四十雀(シジュウカラ)よりも一回り小さいから小雀(コガラ)と呼ばれるようになりました。 小さくて丸っこくてモフモフしているようにも見えるのでとても可愛らいく感じます。 2024.12.10 記す。
★おやまぼくち P.59 まだ雪のちらついている深い谷や、雪がほとんど氷となっている風あたりの強い高原には春の訪れがない。しかしもし誰かが、その雪や氷を掘ってみれば、その下には春の営みをきちんと準備している草の芽を発見するだろう。 南アルプスのかなり長かった山脈から、どうにもすぐ帰るのがいやだった僕は、信州の霧ケ峰に知人の山小屋を訪ねた。そしてその翌朝、気温は零下十一度に下り、強い風の中を晴れた車山の方へ登って行った。 縞(しま)になった、かりかりの大斜面だが、その一面のまばゆい白の中に、去年の秋、一きわ丈高くのびて咲いたおやまぼくちの、枯れたまんまの花が、雪面から顔を出して、いかにも嬉しい頑固もののように立っていた。
それには、僕たちが海老(えび)の尻尾と言っている氷片がこびりつき、枯れた花ながらしまめ面をしているように見えた。ポケットから小型の写真機を出し、その影などを考慮に入れて三枚撮っておいた。
雪の下の、この春先は萌え出す新しいおやまぼくちは、今にここに立っている亡霊のような頑固者の姿を知らない。亡霊のようなといったけれど、帰ってから五本のフィルムを現像すると、おやまぼくちを撮ったはずの三枚だけが何も出ていなかった。 ※参考:オヤマボクチ(雄山火口)とは キク科の多年草です。 オヤマボクチの名の由来は火を着火させる際に火口として利用されたからその名がついたそうです。 ※参考:北海道西南部、本州の近畿地方以東、中国及び中国中部に生える多年草。日当たりの良い山野、草原で見かける。高さ50~100㎝位。根生葉は大型の三角状卵形、先は尖り基部は心臓形。花は秋、暗い紫色で大型の頭花を数個つける。山国ではソバのつなぎとして若葉を使う。 東邦大学薬学部 2024.11.21 記す。
★くさぎかめむし P.60
上州の奥の山の宿へ、今年は二月と三月の末に続けて出かけ、同じ部屋へニ三日ずつ滞在した。宿と言ってよいか、山小屋といってよいのか、ともかく昔から山の根拠地として厄介になっている家で、いつも気持のいいもてなしを受けている。
そこの、この二度の滞在中、僕の安眠を頻りに妨げたのは小さなかめむしの群だった。寝ているうちにうっかりと潰しでもしてしまったら、その臭気は翌日の山までついて来る。それで見つけるたびにそっと紙でつまんで外にすてていたが、彼らはほんとうに根気よく、あとからあとから襲って来た。 成虫で冬を越す連中はこの他にもいるが、普通はもっと遠慮深く、半分死んだようにしているものだが、こいつは肩に生意気にもパットなんか入れて威張っていた。それで余計癪にさわった。 越後から手伝いに来ていた十八の娘は、いつも仲間からからかわれていた。なんて言う名前? とたずねても、おらの名前はチョンとうんだと言っている。靴に油を塗りに、土間へ行くと、彼女はそこの鉄板ストーブのそばにしゃがんでいる。 おめえはみんなから嫌われて。可哀そうにな。おらと仲よくしろよ。そんなことを言いながら、頬っぺたの真赤なチョンは、このくさぎかめむしを火箸ではさんではさかんに火にくべていた。 ※参考:「クサギカメムシ」という名前は、この虫がクサギ(臭木)に付くことに由来します。クサギはクマツヅラ科で、実を染料に使ったり若葉を食用にしたりする低木で、葉に悪臭があることで知られています。なお、カメムシは体が六角形で、カメの甲羅に似た形をしていることから「亀虫」とよばれるようになりました。 2024.12.31 記す。
★ほくろ:春蘭(しゅんらん) P.61 三年前の春先の山で、一株掘って植えたほくろが、忘れていたが今年はじめて花を咲かせた。もうずいぶん長く咲き続けているけれど、まだ一向にしぼむ様子がない。少しも目立とする気持ちもなく、それでいて立派だ。ほくろは春蘭(しゅんらん)とも言う。蘭の中には、ずいぶんあからさまな感じのものもある。それで秘かに愛されるというよりも、特別な寵愛をうけて品評会に持ち出される。 僕も、時々、百貨店を歩いている時に、蘭ばかりでなく、薔薇やグラジオラスの展覧会があって、のぞくことがある。その品種の名前だけでなく、そこまで育てた人の名前もついていることが多い。そしていつも素人コンテストの会場を想い出して具合が悪くなる。 花にせよ、人間の女性にせよ、きれいなものはやっぱりきれいでいいけれど、ある場所に並べられ、その美を競い始めると、美を愛する心をどこかへはじき飛ばしてしまった奇妙な個性だけがそこに並んでいるようで、どうにも淋しいものである。
2024.10.27 記す。
★チューリップ P.62 文献による僕の知識では、この球根たった一個で、寝台、衣服一揃い、小麦二駄、ライ麦四駄、牛四頭、豚八頭、葡萄酒大樽二、ビール四樽、バター一樽、チーズ1000ポンドに値したという時代があった。そのころの話で、持参金としてチューリップの球根を一つ持って来たお嫁さんを貰って狂喜した男もいる。これは一六三四年から三七年にかけての、オランダのチューリップ狂時代のことである。
2024.10.28 記す。
★ひよこ P.63 家の前の道に立って、今朝から盛んに鳴いているひよどりの容子を見ていた。ひよどりは、いつでも、その意味が僕にも分かりそうな鳴き方をするものだから、つい外へ出て木々の梢の方を見あげてしまう。ひどく悲痛な声を出しているけれど、あれは嘘だと思う。深刻ぶって甘えているんだ。まるで人間とそっくりだ。 頭の奥の方がシンシンシンとして来る気持だ。小川のせせらぎのとうな、遠くの方を風鈴屋が通っているような、」きれいな音が聞こえる。それが少し近づくと、縁日の日なんかに、風に吹かれて経木の尾羽をキュルキュルキュルと回す赤い黄いろの燕、あの音になって来る。 やがて坂道の下の方から三台の自転車が現われ、不思議な音はその荷かけから出ていることが分る。ボール箱を四つずつ重ね、小さな穴をぶつぶつあけ、養鶏場のマークをつけてひよこを運んで行くのである。 ヒヨヒヨ ひよひよひよ ヒヨヒヨ ひよひよひよ ヒヨヒヨ ひよひよ
※参考:ヒヨコの由来①:鳴き声がそもそもヒヨコ。 ヒヨコは、そんなトロけるような可愛い声で鳴きますよね。 「ヒヨヒヨ」と鳴く「子」だから「ヒヨコ」。 2024.12.31 記す。
★レモン P.64 高村幸太郎さんの死が伝えられたその日、僕は遠くから訪ねて来た友人に高村さんの詩を読んでいた。若い友人は、まだニキビがぽつポつ見える襟首をたれて、聞いた。
…… 智恵アさん斯(こ)ういうところが好きでせう という「案内」を読み、その岩手県の小屋から届いた葉書のことなども想い出しながら、詩集をめくっていると、「レモン哀歌」が出て来た。僕はその時に全く別のことを想い出した。もうかれこれ半年も前に、ある人から、「レモンの花どんな花ですか」と訪ねられ、しらべて書き送る約束をしておきながら、そのままにになっていたのである。 僕はそれから幾つものレモンをしぼった。この冬は、寒い夜にレモンをしぼり、熱い湯をさして飲む習慣がついていた。サンクスとの色のいいのも、和製の青いのも、しぼってしまえばそんなに味は違わなかった。 そんなことをするたびにレモンの花のことを考えた。年中断続して咲くというその花は大体白くて、花弁の外側がいくらか紫を帯びているということである。それを見ていないことを告白するのは恥かしい、その花をどこかの海に近い丘の上で見る日に、僕はだれのことを想い出すだろうか。トパアズ色の香気の中からだれの顔が浮かんで来るだろうか。 ※断続的に開花し、結実することがある。しかし、一年中結実させていると木が弱るので、晩春に咲く花だけを結実させ、それ以外の時期に咲いた花は全て摘み取る。 ※トパーズは黄玉とも呼ばれる宝石です。確かに色はレモンと同じ(※無色 ... もっとそのまま感じればよいのかもしれません。 「トパアズいろの香気」
★雉鳩 P.65 このところ雉鳩(きじばと)の声をよく聞く。そろそろ繁殖期にはいったのであるが、デデッ、ボーボーというあの低い声は、いかにも不精者の、お尻の重い、だるそうな姿を想わせる。実際雉鳩はものぐさな様子をしている。 雪国に住んでいたころにもこの声をききながら、自分の頭がどこまで鋭くなって行くのか心もとなく思ったことがある。またいつか一週間ほど伊勢に泊まっている時、その家の庭の、松の梢にいい加減粗雑な巣を造っているのを見た。大きな音を立てて、芝生におり、そこらの枯草をくわえ、しばらくぼんやりしていてから、どっこいしょうに梢へ戻る。何度も何度も、まだ日は長いというふうに、繰りかえし、時々何のためだか鳴く。それは何度も仕切りなおしている重たい力士を思わせた。
※参考:日本では全国で広く繁殖する留鳥「キジバト(雉鳩)」。 体色がキジに似ていることに由来し、別名「ヤマバト」ともいいます。 山地の森林に生息し、かつて狩猟が盛んな頃は滅多に姿を見せませんでしたが、年々銃の扱いが厳しくなるにつれて人を恐れなくなり、近年は市街地でもよく見られます。 2024.12.10 記す。
★ひとりしずか P.66
数年前の春に、すみれの種類をいろいろさがしながら、小金井から国分寺の方へと歩いて行ったことがあるが、その時、何の気なしに日かげの土手を登ってみると、そこの林の下は、一面のひとりしずかの花で、呆れかえってしまった。 この花にとって、こんな名前をつけられていることがそもそも至極迷惑千万なことなのかも知れない。どんな花でも一つ一つを見ればそうなのかも知れないが、それも一本一本を見れば孤独な顔つきをしていないこともない。 花弁を持たないこの裸の花も、じっと見つめて首をひねっていると、向こうから言われそうである。あなたもやっぱり孤独が好きな人間のお一人でいらっしゃいますか。孤独がお好きな方々がお集りになって、大層賑やかにしていらっしゃることはありますまいか。それではこの花も、人間の真似をしているのか幾組も草むらに集まっていることが多い。
★おたまじゃくし P.67 体外受精の行われたあとの、ひきがえるのぬるぬるの、紐状の卵を田んぼからうんと取って来た。三月の下旬だった。 それを注意してみていると、ゼラチン質の層をかぶったまま細胞分裂をするのもあるし、どういう加減か、卵のうちにそのゼラチンから外へ出てしまうものもあった。そうしてやっと五ミリほどのおたまじゃくしが、ガラスの大瓶の中で次々とちらちら泳ぎはじめた。それはいかにも子供っぽい動作で可愛らしかったが、やがて聞かざるを得ないひきがえるの大合唱を想像して慄然としてしまった。そうでなくとも、神経の加減が少しどうかしている夜は、遠くの蛙の声が気になって眠られなかった。
※参考:元正天皇が無事快復されたことで、杓子は縁起物となり、「お多賀杓子(おたがしゃくし)」と呼ばれるようになりました。 そこから、「お玉杓子」「お玉」と転じ、形が似ているカエルの幼生まで、オタマジャクシと呼ばれるようになりました。 現在ではご飯用を杓文字(しゃもじ)、汁物用を杓子と言いますが、昔は区別なく使われていました。 2024.12.10 記す。
★のぼろぎく P.68 周囲何粁という広さで、かちっと舗装してある、そこは東京の」まんまん中。地震の国のことだから四十階、五十階というばかばかしい建物はないが、それでも大小のビルディングが続いている街の、その歩道のほんの片隅に、僕はのぼろぎくを見つけた。二月のからっ風にさらされて、その花は何とも貧相だったろう。
だがまことにけなげな花ではないか。日にそこを、何千何万という人が、みんな用ありげに忙しく通るのに、ほんのわずかな、実に危険な安全地帯を見つけて、きっぱりとその存在を主張している。植物界の代表というような誇りをもって。 僕はそこを通るたびに声をかけたものだ。相変わらず元気だね。結構なことだ。つらいだろうが、僕は尊敬している。しゃがんでゆっくり話し込みたいのだが……。 ところで丁度その角のビルディングが改築され、新しい玄関がそこに出来た翌日、のぼろぎくは早速踏み倒され、四日後には全く姿を消してしまった。僕は長いあいだの知り合いとして、また芽をふくかも知れないその根をどこかに移してやろうかとおもったが 、建物の改築によって新しく出来たはずの安全地帯をどうしても見つけることはできなかった。 参考:ノボロギク(野襤褸菊)という名前は、花の後の果実が熟して白い毛で覆われた状態がボロ切れ(使い古した布切れ)のように見えることに由来しています。また、同じキオン属のボロギク(サワギク)に似ていて野原に生えることから名付けられました。 ※参考:ノボロギクにはピロリジジンアルカロイド類(PAs)が含まれ、誤食すると肝障害を引き起こし、重篤な場合は死亡する。 市民は「ノボロギク」を「ベニバナボロギク」と間違えて喫食していた。 両種は同じキク科に属し、葉の形が似ている。 2024.11.12 記す。
★夏水仙(なつすいせん) P.69 夏水仙は一名、「葉見ず花見ず」と言われている。線形の葉が、わっさわっさと繁っている時には花は咲かず、夏になって花径が勢いよくのびる頃には、もう葉は枯れていない。花は自分の葉を知らなず、葉はその花を知らない。庭にその鈍頭の葉が、大きな爪のような恰好で出て来るのは、まだ地面が凍っているころであるが、今年はその出方が早すぎるようである。どういうことなのだろうか。 暖冬異変による現象ではなく、しばらく前から僕の家に飼われることになった犬が、好んでそこに寝るからである。好んでというよりは、そこが、こんもり高くなっていて、繋いである鎖の限界のうちで一番気持ちがいいらしい。
その葉はのびはじめるとかなりの勢いで成長するので、ある朝雨戸をあけるとうちの、吠えることも知らない詩人肌の犬が、一夜にして伸びた葉に持ちあげられて、そのまますいこすいこと眠り続けている姿を見るのではなかと思う。 2024.10.28 記す。
★虱(しらみ) P.70 虱(しらみ)に会えなくなってからもう何年になるだろう。僕はそれをさびしく思うこともあるし、あの姿を見て、時々ぞくぞくとしたくなる。それでは、どうすればいいのか。河べりの日なたで、シャツを裏がえしてみているコスモポリタンの前に立ちどまってみるが、一匹十円でもいいから譲ってくれませんかとは、どうも言いにくい。コスモポリタンとの会話は、神様との会話以上にむずかしい。
それから別の一隊は、髪の毛を密林と心得ているターザンたちである。猛烈に繁殖することの早いターザンたちである。時たま襟首のあたりまでやって来るのもいる。ここから先は砂漠というやつなのかと思う。そして思案しているうちにぽたりと落ちる。こういううっかりものは、僕らの両手の親指の、爪のあいだで死刑に処せられるのも止むを得ない。彼らのつぶれる時の、かすかな音。蚤よりずっと陰性なその動作。それにしても、こんなにも僕たちに近く生きようとしている。 英国人は、この虱を、最も人間の身近かにいる家畜と呼んでいる。彼らとその親しみを失いたくないなら、決して拡大鏡や顕微鏡でのぞいてはいけない。 ▲私は子供のころ(戦前)の夕方、妹の髪に寄生していた虱を母親が櫛で虱をとっていた。その翌日もまた翌日も同じことをしていた。なんでかとおもっていた。「猛烈に繁殖する」ときさいされているので納得した。 さらに調べると「成虫は交尾後、ヒトジラミで1日8~10個、一生で約100~200個程度の卵を産む。ケジラミはやや少なく1日1~4個、一生で約40個程度産卵する。寿命はヒトジラミの成虫が約1ヵ月、ケジラミの成虫が約3週間程度である」と。 数量的はともかくも、毎日散乱して成虫になっていたのである。と。 戦後、進駐軍が進駐して、DDTを人にも散布して殆ど駆除されたようである。 ※参考:『目で見る昭和全史』(読売新聞社 1989)p131「シラミ駆除にDDT散布」(昭和21年) 2024.11.10 記す。
★鷺 P.71 東海道線をいい加減のところまで下って、また上って来たひとが、僕に話すのだった。あれはどの辺だったかしら……。ちっちゃな白い鷺がいたんだけれど……。 僕はその人がどんな旅行をしたのか、汽車の中で何を食べたか、そんなことは考えない。むしろ、昔僕が見た鷺は、薄ぐもりの日の河原にひとりぼんやりしていて、鉄橋をとおる汽車の窓から見ると、今にも自殺をしそうな気がきでなかったことを想い出す。 それで、ちっちゃいというけれど、どのくらいだった? 実はね、白鷺には、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、つまり大中小あるんで困るんだけれど。
するとその人は急に残念そうな顔付になって、それならコサギにちがいないという。どうしてそんなに残念だったのか。
そんな大中小があることなんか知らなかったもんで、鷺の赤ちゃんだと思ったの。赤ちゃんのくせに、片脚で立つなんて、ずいぶん生意気なまねが出来ると思っていたのに。ダイサギの赤ん坊なら、やっぱり這っていたはずですね。 さて僕は返事に困る。 ※参考:「白兎(しろうさぎ)」のことを古来から通称「さぎ」といい、一羽二羽と鳥のように数えます。 そこから「(さぎ)する」とは、この「因幡の白兎(しろうさぎ)のマネをして相手を騙(だま)す」という意味 で古来から使われてきたのです。 2024.12.10 記す。
★カンガルウ P.72
奥さま。お嬢さま。皆さん。大層やさしい顔をなさって……。 ほんとうに、どんなお澄しの奥さまも、この」カンガルウの前ではちがった顔になる。異様な切なさに、足をとめて、その鼻の」頭を見ている。ただ動物園の、ほとんど尻尾ではねていつ」カンガルウを想い出すものはない。もっとも近よって見ているうちに、急にいじりたくなって、子供のカンガルウをお腹から引っぱり出してしまった者もいたということだ。 さてそれでは、僕もまた、個性をすてて、同じように薄よごれて教室へはいって行くことを考える。けれども学生さんたちは、僕の切ない容子を見ているうちに眠ってしまうだろう。 ※参考:「カンガルー」という名前は、クイーンズランド州北部に住むグーグ・イミディル(Guugu Yimithirr)族(グーグ・イミディル族)の人々が、オオカンガルーのことを「gangurru(ガングルー)」と呼んでいたことに由来しています。 2025.01.01 記す。
★蛙 P.73
僕は先頃、まことに立派な、百舌(もず)のつくった蛙の速贄(はやにえ)を見つけ、それを山椒の枝からとって来た。ひからび切った蛙は、どこを見ても苦悶の姿はない。山椒の、今なお鋭い棘(とげ)が左腹からささって右腹につき抜けている。蛙は百舌の、けたたましい哮(たけ)りに、耳を蔽いながらしばらくはもがいていたにちがいない。しかし、この最後の、幕切れのみえが、あまりに立派なので、僕は詩人K氏に贈ることをやめてポンポン入れの中に大切にしてある。そしてその姿を時々見るたびに、どんなふうにして殺されるか知れない自分が、こうしたみえを切ることが出来るように、踊りでも習っておきたくなる。 2024.12.05 記す。
★黴 P.74
毎年、梅雨期になると、僕は黴についての知識を豊富に持ちたいと思う。それはなぜか。
どうも英国製の本に余計、黴が生えるように思うんですが……と僕は、スコットランドの田舎にでも置いておきたいような老学者にいうと、彼はすでに、アメリカ製の本の黴との、比較研究をやったことがあるような話をする。 僕はその晩、顕微鏡を取り出し、プレパラートの上に、ハドスンの『ダウンランド』に生えた黴をそっと移す。あのダウンランドに生えた黴。錯覚を起しては大変である。そして、一応、検鏡の結果をノートに記し、次には、日本の本の、僕の昔の本の黴をのぞく。うっかりすると、その菌糸の描く抽象に感服してしまいそうである。ハドスンの本に生えても、僕の本に生えても、聖書に生えても、黴は黴である……。 しかし僕は、気がついてみると、黴などに特別の興味を持っている訳ではない。それはどうも書庫の掃除を怠っている言訳の用意をしているのである。友だちが遊びに来て、僕の書棚から本を取り出した時、ほこりだらけで済みません、とあやまるよりも、その黴はね、何というんだか知っている? 多分、不完全菌門のデマチウムという奴らしいんだがね、どうだろう? ち言った方が堂々としているからだ。 ※参考:中国の最も古い辞書によれば、「黴」は“モノが長雨にあたって次第に湿度が高くなるにつれて青黒く変化する。 これすなわち黴であり”とあります。 黴という漢字は「黒」という漢字と「微」という漢字の省略形が組み合わさってできた文字であるといわれています。 2025.01.02 記す。
★鮭 P.75 北海道の冷たい紺色の海でつかまった鮭が、台所の天井からぶらさがっている。どこもかしこも塩だらけだ。彼は完全に死んでいる。あまり完全に死んでいるので、せめてもの心づかいに結んでやった黄色いリボンが実に不似合いなのだ。 この鮭は仲間と一緒につかまった時に、何か祈りの文句を述べただろうか。十字架のキリストのように、鮭らしく「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」をつぶやいただろうか。どうもそんな想像をするのは明らかに間違いのようである。 この表情全体を、鼻面のへこみ、うらめしげな眼つきもすべて人工によるものである。つまり人間は、一尾の鮭をなるべく長く、腐らせずに、何度でも楽しんで食べてやろうと思って、塩でぎゅうぎゅうの目にあわせたのである。
※参考:(ギリシャ)ēli ēli lemā sabachthani(エリエリレマサバクタニ) と ... 「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と訳される。十字架にかけられたイエス=キリストが叫んだとされる言葉。 ※参考:鮭という漢字は,もともとはフグを指す字であったということなので,日本語のスケという音 を表現するために,鮭という字が当てられるようになったのかもしれない. 広辞苑は,サケの項で 「アイヌ語サクイベ (夏の食物) からとも、サットカム (乾魚) か らともいう」 と説明し,サケの語源がアイヌ語であるとしている. 2024.1.11 記す。
★うそ P.76
富士山に登った。四月の富士は前にもスキーを背負って上ったことがあるが、息が苦しい。五合目の小屋で強い雨を伴った暴風の鎮まるのを待っていたので、出発も遅かった。夕方になってやっと辿りついた頂上は、氷片が無気味な音を立てて飛ぶ強風で、立つていることは出来なかった。それにあの突風は相変わらず、ひっぱたくような吹き方をする。
吉田口五合目から馬返までの樹林帯の道には、夏の登山者のために、木々の名前がたんねんにつけられていて、僕も勉強しながら、翌日どんよりした天気の中をゆっくり降りて来た。手帳に書きつけた種類だけrで五十七。小鳥の群が森の中をにぎやかに流れて行ったあと、頭はぼやんとしびれているようだったが、立ちどまっている僕をないしょで呼んでいるようなかすかな口笛の音がする。おや、と思っても、すぐに振りむくことをためらうような、恥ずかしそうな音である。もし誰かがほんとうにいてこっそり呼んでいるのだったら「どうしよう。 それは白檜(しらべ)の枝を多分虫を求めて渡っていた二羽のうそだった。小鳥屋の籠の中にみるうその頬は、少し紅をさしすぎるんじゃないかと言ってやりたい赤さだが、こんな森の中で、その声といっしょにちらっと見ると、もう人間の仲間には滅諦に見られない美しい恥らいの色だった。ギリシャの哲学者アリストテレスのお嬢さんが一番好きだと言ったその色だった。 ※参考:名前の由来は「嘘」ではない うその名前の由来は「嘘・本当」のうそではなく、口笛を意味する古語「うそ」とされています。 うその鳴き声は普段聞く機会の多いヒヨドリの「ヒーヨ」と比べると、少し低め、弱めでやわらかい感じがして、まさに人の口笛にそっくりです。 2024.12.11 記す。
★富士桜(ふじざくら) P.77 小型のさくらなのでまめざくらという名もあるが、富士山の麓ではいま満開である。ぼけと一緒に自分の季節をたのしもうとしている。 高等学校のころ、友人と絵具箱をかついで箱根の方をスケッチ旅行をした。その時、峠をクウクウと言って越すバスの、若い女の車掌さんに教えてもらったことを忘れずにいたかれんなさくらである。富士の広い裾野には、五六ミリにのびたからまつの芽が、うす緑の、ねむたい色を果しなく煙らせていたが、その中で、若い少女のあどけなくきょととした眼のように、ふじざくらは咲いていた。
2024.10.28 記す。
★おとしぶみ P.78
植物の方にはいろいろとロマンチックな名前やら、ひねった名前のものが多い。それに比べて昆虫の方にはどうも気の毒な名が沢山あって、これは少々不公平だ。けれど、大して姿もよくないくせに、おとしぶみなどというこんないい名前をもらった虫も少なくないどう。それはこの虫がなかなか器用なまねをするからだ。
僕のところでは、毎年、ごみためをかくすように作ったちょっとした竹の垣にからみついたはとやばらの葉を好んでまくが、くぬぎ、なら、はんの木の葉で落文(おとしぶみ)を作っているのを見たこともある。言いがたき事を書いて、わざと人目につくところにおく。あの落文だが、彼らにはどんな言いがたき事があるのか。 ありますとも、ばかになさらないでくださいよ。姿でもって、いろいろと軽率な判断をなさるのはいけませんな。 この葉の中には橙色の小さな卵が一つ二つはいっている。それが秘密なのだ。僕はこの卵入りの落文をとり、シャレーに移して孵化させようと試みたがうまくゆかない。かさかさに乾いてしまう。むれた脱脂綿の上に置いてもいけない。それは葉脈を切らず、卵を包んだ葉が枯れないように、適度のしめりを保っているように、この小さな虫も、酒壜の栓みたいな無格好な頭をひねったのだ。 ※参考:町 内でもたくさん見つけることが できる、このくるんと巻かれた 小さな葉っぱ・・・その作者の名は 「オトシブミ」。 江戸時代に、直接 手渡すことができない手紙を巻 き物にして道端に落としたとい う「落とし文」が、その名の由来 です。 葉っぱの巻き物? ふしぎな昆虫を発見! 2025.01.02 記す。
★花菱草(はなひしくさ) P.79
北米カリフォルニアあたりが原産で、明治のはじめに渡来したものだという。それでカリフォルニア・ポピーというわけだ。鉢植えのものを買って来ると、黄色というよりも赤に近いぱっとしたオレンジ色の花が見られる。ホントニ、キレイデス。一面デス。とアメリカの人が言った。それはそうだろうと思う。ところが、種から育てると案外ひねっこびた花が咲いたりする。僕の庭は寒いからいけないのかも知れないが、どうもかなしい花しか咲かない。それでもいいのだが、僕はこの花のことをずっと前に書いてからある種の痛々しい親しみを感じて、よく育ってくれないと、なにかしら自分のせいのような気もする。そしてついに畸形が生れた。
このあいだから、どうも葉の一部がちぢれていると思って、毎日それとなく気にしていたのが、その一部から黄色の葯(やく)のようなものが生じ、その数は十五本ほどで中央は緑色だった。そうかと思うと鳥の翼に似たものもあり、気味の悪いほど痩せた指をすり合わせているようなところもある。畸形の説明は詳しくしても要領を得ないものだが、ともかく花が変化したものである。それを写生しながら思ったのであるが、僕は精神的な畸形をを知らずしらず面白がっていることが多い。第一僕自身の精神だって正常だという証拠は何もない。けれども、自分の育てたものがこんなふうになると、珍しがるよりもやはりいやだった。 ※参考:花の名前の由来:花の形が花菱紋に似ていることに由来しています。4枚の花弁が菱型に並ぶ様子が特徴です。 2024.11.11 記す。
★かけす P.80
五月なかばになっても今年は雪が多く、谷川岳の芝倉沢を、湯樋曾川(ゆひそがわ)の近くまでスキーで下って来た。ところどころ、落ちればおしまいの口があいていたが、大体はべっとり雪で、雪崩のための岩や土が雪の上にたまっていた。深い霧が昼頃から雨になり、ずぶぬれだったが、その日に朝から鳥がよく鳴き、耳の楽しい山だった。
木の下に雨をよけて休んでいると、ジュウイチイ、ジュウイチイを繰りかえし、それが段々高い音になって行くので、誰かが鋸の目立てをしているのかと思う。けれどもこの声はとぎれとぎれに、鈍く、またくるしそうに聞こえる。可哀そうに病気だな。胸が痛いのだな。僕は、天幕に戻るのが少しおくれても、繁みの中で何が起っているのかを見届けたいと思い、あまり足音を立てないように近よって行くと、そこから飛び立ったのは、淡いぶどう色に藍色の翼をちらっと見せたかけすだった。 かけすは他の鳥の声をまねしてこれまでも時々だまされた。口笛だの人の言葉をまねる。 だまそうと思ったわけでもないんです。私の声はあんまりきれいではないので、発声の練習をしていたというわけです。このごろは山男の中に、あの奇妙な発声をするヨーデルを悲愴な声で歌うものがふえて来た。かけすよ、すでにこれはまねごとなのだから、木々のこずえでこのヨーデルのまねだけはしない方がよい。 ※参考:動物の声や他の鳥の声を真似ることもある。 樫の実を好んで食べるので、平安時代から「樫鳥(かしどり)」と呼ばれていたが、江戸時代からは「懸巣(カケス)」とも呼ばれるようになった。 カケスの名前の由来は、巣を懸けるようにして作るからとも言われる。 2024.12.11 記す。
★蛇 P.81 水辺の鳥のうちで、いや全鳥類のうちで、こあじさしほどの美人は少ない。僕は方々の河岸で、また海辺に近い湖を渡る小舟の中から、純白の翼を、ペーパーナイフのように張ってみたり、くりっとした頭を、少々てれたように下に向けている姿を見ていると、息をするのを忘れる。僕が息をこんな具合にとめるというのはそのほかにはあまりない。 天竜川を渡った。それも汽車で通ったのではなく、わざわざ長い橋を歩いて渡った。豪雨のあとで、川は濁流が方々で渦を巻いていた。その時に僕は、こあじさしと、頑固な蛇との対話を聞いたことがある。蛇は川を渡るつもりで泳ぎ出して流されてしまったのだ。 少し方向を左にとって。そうするとあそこに洲があるから…… おれは向う岸へ行くんだ。 そんなに意地を張ったら、死にますよ。 おれは向う岸へ渡るんだ。 あたしが教える洲に一度上がって、しばらく休んで。 おれは今、向うの岸へ行くんだ。
※参考:蛇は、古くから豊穣神・天候神として信仰の対象とされてきました。 脱皮をするヘビは「復活と再生」を連想し、不老長寿や強い生命力につながる縁起のいい動物と考えられています。 また、蛇は餌を食べなくても生きながらえるため、「神の使い」として崇められてきました。 2024.12.11 記す。
★春紫苑(はるしおん) P.82
今、どこの庭にも、路傍にも、電車の走る土手にも、ほとんどいたるところにといってよいほどに春紫苑が咲いている。
無論僕の家にも抜いてすてたいほど咲いている。白いのが普通だが、時々ごくうすく紅をさしたようなのもある。エリゲロン・フィラデルフィクスという学名であるが、フィラデルフィアの春の翁ということになろうが。北米原産の多年草である。 昭和五年に初版の出た園芸の本を見ると、最近四五月ごろに花戸(かこ)で見かけるようになったが、繁殖力が非常に強いので、今にほうぼうに雑草化するのではないかと書いてある。この筆者の予言はそのとおりになったて、今では春紫苑はもう売りものにならない。 花にとっては、この繁栄ぶりはよろこぶべきであるが、そうなれば名前も忘れられ花びんにさされることもなくこんなものが昔はねえ、と言って見る人もあるが、春紫苑は昔も今も全く変りなく、人間の評価とは無関係に澄してきれいな花を咲かせている。 僕は雑草という言葉を使うときに、その花の気持がぴんと響いて来てためらわざるを得ない。動物の中でも、数が少なければ大事にされ、天然記念物となって保護をうける。人間はいまのところ、とうてい記念物となる望みは持てない。雑として扱われる。そして僕の書くものもすべて雑誌の中へたたき込まれる。 ※参考:春紫苑(ハルジオン)という名前は、キク科の植物「シオン(紫苑)」に似ていることから、植物学者である牧野富太郎氏によって名付けられました。シオンは秋に咲く紫色の花で、ハルジオンは春に咲くシオンという意味です。 ※参考:毒性 ハルジオンは接触皮膚炎を引き起こします。 それに触れる人の感受性により異なります。 猫と犬に対しては軽度の毒性があり、葉、茎、花、根のいずれかの部分を大量に摂取すると、消化不良や皮膚の刺激などの症状が現れる可能性があります。 2024.11.13 記す。
★鉄道草(てつどうぐさ) P.83 ひめむかしよもぎという菊科の植物は誰でも知っている。名前を知らなくとも実物を見れば、これかという。この草は明治草、御維新草という別名を持っている。ならべついでに学名まで書けば、エリゲロン・カナデンシス。北米、カナダあたりが原産地で、日本にやって来たのが明治初年である。 わざわざ持って来て植えたのではなく、何かの荷物にその種子がついて来てこぼれて生えたのだろうが、それから鉄道線路を順に種子がはこばれて、今では高山は別として、日本の到るところに生えている。僕は数年前に九州の小さい離れ島でも見た。こんな具合に繁殖力の強いものは他にもあるだろうが、ともかくこれはそんなことから鉄道草という名がついている。
以前、僕の友人は線路の石を気にして、ついに日暮里の近くで蛇紋石を拾った。勇敢にホームから飛び降りて、田端の方へ歩いて行って見付けた「のだが、彼自身もまた見付けられてひどくどやされたそうだ。この勇気と覚悟こそ、僕には必要である。 2024.11.13 記す。
★ならえだたまふし P.84
いろいろの植物に、奇妙ないがや疣(いぼ)が出来ていたり、また葉がちぢれているのを見かける。これは単純な、植物の皮膚病ではない。これは多くの場合、昆虫が寄生をしていて、そのために植物のその部分が異常に発育をする。これを虫癭(ちゅうえい)という。
僕はこれを集めていたことがある。集めるという気持には全部集めるという願いがいつもついて回る。それで、これならそんなに種類はあるまいと思ったのであるが、飛んでもないことだった。それに瓶や空缶に枝をさして置くと、ある時期になって、そこから小さな虫たいがうようよ生まれて来るので、とてもたまらない。実際皮膚病のように気味の悪いものばかりだが、その名は外国の貴族のように長たらしい。 楢(なら)の小枝の堅い粒々はいつの間にかぽつぽつ穴があいて空っぽになって行く。いつ穴をあけ、どんな顔をして出て来るのか、それはついに見届けられなかったけれど、中には実にかわいいたま蜂の一種がいる。まだ使えない羽を背中につけて、ころがって夢を見ている。立つことも出来ないで脚をちぢめているが、虫癭を割って取り出そうとするとその脚をひっかけて、しきりに自分のバンガローの中へ戻ろうとする。蜘蛛の糸のようなものを引いている。「マダボクタチハ世ノ中ノ風ニアタルノは早スギルノデス」という変に心得た様子をして。 2024.12.06 記す。
★猩々袴(しょうじょうばかま) P.85 方々の山からの便りに、今年はどうしてか、猩々袴ガ実にきれいだと書いてよこすものが多い。気のせいか、僕も山を歩いていて、妙にこの花が例年よりたくさん咲いていると思う。しして花の色が鮮やかでもあるような気がする。
登るのには長い尾根をたどる。もう少し早く登れるかと思って、のんきに休みながら行ったら、残雪が出て来て道がかくれ、かれこれ一日たっぷりかかってしまった。もっとも、いろいろの花が咲いていたので、早く歩くのがもったないかった。そしてこの猩々袴の花はかなり上の方の残雪の付近で見かけたが、五六百メートルの辺では、花の終わったものが五十センチにものびてまるで別の植物のような姿をしていた。僕も、実をいうと、別のものかと思ってスケッチブックにていねいに描いて来たが、老いてその花蓋(かがい)が黄ばんだ猩々袴にちがいないことがしらべて分かった。人間でも盛りを過ぎてから急に人相の変るものがいるらしい。このごろよく外で会う人で、どこかの学校でいっしょだったらしいことしか思い出せないで困っている人物がいる。 2024.11.26 記す。
★かめのこてんとう P.86
こんな文章を書きはじめてから、ほとんど毎日、マッチ箱に虫がはいって来たり、薬の瓶に蛾がはいって来たり、植物がはさまって来たり、僕にとっては嬉しい贈物だ。けれどもニ三ミリの小動物のひからびたものを、つぶれないように扱いながら名前をしらべたり確かめするのは、楽しいけれどもひと仕事である。それも、一度に十数匹も届いてしまうと、手のつけようがない。学校の講義のことなんかが、妙に頭にひろがる。しかし何が出てくるか、僕にとってはびっくり箱である。そして、今日、元亀のいい三匹のかめのこうてんとうがはい出して来た時には、黒と朱の鮮かな色が土人の盾のように見えて、偽りなく驚いた。前からなじみ深いものが出て来てもどくっとすることがある。このてんとう虫は分泌物を出すのがこれの習性の一つだが、マッチ箱の中には橙色のしみが沢山あった。
かめのこうてんとうは羽虫の幼虫を食べるが、てんとう虫は多く益虫で、なかにはイタリアまで害虫を食べにやとわれたものもある。学名はミラピリス(驚くべき)。僕がびっくりしたのも彼に対する正しい態度だった。植物ではおしろいばながミラぴりす。夕方に濃厚なお化粧をされては驚く。人間では博学な哲人ロージャ―・ベーコンが、ドクトル・ミラピリス(驚異すべき博士)である。 ※参考:大きさは約1センチで日本最大級のテントウムシです。 全長は一般的に見られるナナホシテントウの2倍ほどあるそうです。 背中の模様がカメの甲羅に見えるので「カメノコ」と名がついています。 2025.01.03 記す。 ★忍 冬(すいかずら) P.87 自然界の姿、色、匂いなどが、僕たちの気持をうまく代弁してくれることもずいぶんある。何だか、あの人のことを考えると、すみれの花を思い出す……と言ってみたり、真紅の薔薇があってくれるので、ずいぶんたすかっている人もいる。……だって、美しい花はいつまでも路傍に残ってはおりません、などと言われると、何となくあきらめられる人もいる。しかし自然界のそれらを逆に僕たちが形容しようとなるとむつかしい。色だけでなく、そこに瑞々(みずみず)しさが加わっているのをどんなふうに説明したらいいのか。
※参考:日本全国、朝鮮半島、中国に分布する暖地では常緑蔓性木本です。蔓は右巻きに伸びて、葉はこれに対生しまれに輪生することもあります。葉は冬も枯れず寒さにも耐え忍ぶということから別名を「忍冬」と呼ばれます。花期は初夏で、花は2個並んでつき、初めは白ですが、時が経つと黄色に変色し、盛りを過ぎる頃は白色や黄色の花が入り乱れてます。その様子から生薬名を「金銀花」といわれます。 近縁種にはヨーロッパ産のハニーサックルL.sppがあり、こちらも昔は喘息、泌尿器疾患、出産時に用いられてきましたが、現在では薬用としては主に東洋産のスイカズラが用いられています。 東邦大学薬学部 2024.10.29 記す。
★すずめばち P.88
M氏は玄関でそれを渡して帰ったので早速僕は懐中電灯を片手に持ち、長い針金の先で洞窟の探検をする。懐中電灯を持つ手も使いたくなると、灯は口にくわえる。どんな知恵によって、こんなにも巧みに木の皮をかみくだき、自分の唾液をまぜて薄くのばしたものか、こけげたパイの皮のようなものがはがれる。僕の好きなお菓子のバウム・クーヘンみたいなところもあるが、食べてみる気はない。 所々に柱を作り、六角形の独房は奥深くつづいている。そしてそこには、彼らの死骸は一つもなく、亡霊も「いない。ただ一匹、僕の部屋に移されてからも執念深く獲物をねらっている蜘蛛の目が時々光っている。たなぐもらしい。 ※参考:「スズメバチ」の名は、その大きさが「雀ほどもある」または「巣の模様が雀の模様に似ている」ことに由来する。 また、地方によりスズメバチを指して「くまんばち」と呼ばれるため、同じく地方によって「くまんばち」と呼ばれるクマバチ(Carpenter bees) が、しばしばスズメバチと混同されることがある。 2025.01.02 記す。
★庭石菖(にわせきしょう) P.89 あなたの好きな花の名を教えて下さい、という葉書が来る。往復葉書なので返事を書かない訳には行かない。こういう時に僕はいつでも、むらむらと博愛主義者になる。 花に限ったことではありません。僕はすべて平等に愛します。少なくとも平等に愛することを念願としております。人間でも……。 これが返事だが、折りかえしまた葉書が届く。無理をなされなくてもよろしかったのです。失礼しました。僕はどんな人か知らないがひどく気に入った。博愛主義もこんなところで崩れる。
庭石菖はダイヤモンド草。丸い種。丸く生まれて丸く実るそれがまた愛らしい頭だ。 ※参考:毒性 ニワゼキショウは人間、猫、犬にとって有毒です。 摂取すると、症状として消化器系の不調や刺激が現れることがあります。 植物全体が有毒であるため、誤って摂取しないよう注意が必要であり、症状が現れた場合は迅速な治療が求められます。 2024.10.29 記す。
★ぱせり P.90
外国の品物や様式が無闇にはいり込んでいる国では、お互いに、田舎者にされて、常に誰かに嘲笑されている。止むを得ない。そんなことがあったからと言って、緑のかおりのパセリを食べないことにするのは愚かである。 僕もだいたい、きれいに洗ってあるかどうかを見定めて食べることにしている。それだけでなく、緑をお食べなさい、太陽を食べないから背中が凝るんですと医者に言われてから、時々多量に食べる。それで花壇の一部にパセリを栽培し、今は花盛りである。 典型的な複繖形の花で、およそ十三に分れた先に二十内外の細かい花の数である。花は食べても葉よりは香りがない。まことに目立たない花だが、昆虫には極めて人気があって、蟻、蠅の類から大小さまざまのものがいつも集まっている。すぐそばでは真赤なけしも咲いているのに、こっちにばかり寄って来る。彼らにとってのパセリの花がどういう魅力を持っているのか、ほんとうのところ分からない。小さな昆虫たちがごたごたしている中で蟷螂の子供たちは、彼らをつかまえる練習をさかんにしている。ところが、もっともらしく鎌をかまえて飛びつくが、蟻につきとばされて、危く落ちそうになる。 ※参考:薬草としては、強い利尿作用が知られており、泌尿器の感染症や結石の治療や痛風にも良いとされている。 また、通経作用が伝承されており女性薬としても用いられてきた。 さらに、リウマチ、貧血、皮膚の老化防止、捻挫の腫れの痛みの緩和にも効果があると言われている。
★まいまい蛾 P.91 雌にくらべてやっと半分ぐらいしかないこの蛾の雄は、雌を求めるのにみっともないようにくるくる飛びまわり、それでこんな名前をもらっている。もう少し落ちついてくれないものかと雌はいつもそれを苦にしている。 あたし、目がまわって、何が何だかさっぱりわからなくなっちゃう。もう少し静かに飛んでくれたらどう?
その蛾の幼虫、つまりぶらんこ毛虫が、薔薇の葉のかげにかくれていたが、この毛虫は殺さなくともやがて死ぬ。まだ卵のころに、一匹の蜂が来て、あっという間に卵を産みつけられた。毛虫は空に飛び立つ日を奪われながらも、生きていなければならない。そして薔薇の葉陰でだるい毎日を送っているうちに、体の中で生れた蜂の子どもが体をやぶり、ぞろぞろ出て来て、もうほとんど動けなくなった毛虫のそばに白い小さな繭を五十ほど作っている。僕は以前、そこからぶらんこやどり蜂が、それまで世話になって、いま瀕死の姿でいる毛虫には何の挨拶もなく飛び立って行くのを見た。彼らのあいだには、恩も義理も何もない。そのさっぱりしている関係は、こうして生命にかかわるような大事件でありながら、自然であって、また極めて静かなものである。僕たちにはとうてい真似は出来ない。自然はしばしば多くの生命のために一つの生命が失われることを許している。
※参考:マイマイガの名前の由来は,その飛び方にあるといわれています。 初夏の昼間,オスがひらひらと飛び回る姿からきているというのです。 学名の種小名disparは,成虫のオスとメスの色や大きさが非常に異なっていることから来ていて,「ペアでない」という意味を持っています。 2025.01.02 記す。
★びろうどもうずいか P.92 こんな変な名前の植物が、ドイツ、イギリス、フランスの小説の中などに時々出て来る。もちろん日本の植物ではないが、だれが日本名をつけたのか、このもやもやした長い名前がいかにもうまくその植物を言いあらわしている。というのは、三年ほど前、ある薬草園でこぼれていた種子を拾い、庭へまいたら、高さ二メートル以上にも及ぶ毛深い化け物ンおようなものが出て来たが、これがびろうどもうずいかで、今年も黄色の花を咲かせている。
新聞にこの植物のことを書いたら、米沢、秋田の方から、近くに生えているという葉書を頂いた。駐留軍が来てからのことか、その辺のところはよく分からない。 外国では、書物によって調べてみると、この花には、悪魔はらいの力があるとか、これを採取すると雷に打たれるとか、花の位置で冬の寒さを占うとか、さまざまの言いつたえがある。またこお植物を蔽う毛は細かに枝分かれしていて、蝋燭の芯にする。薬草としては、肺炎、気管支炎、痙攣、痛風、歯痛、神経質に効くということであるが、そんな威力を持っていることが分ると、種子をひろったばちでも当りそうな気がして来る。 ※参考:ビロードも毛蕊花も毛の多いことからの名前で、花や茎、葉の全てに細かい毛がある。 ※参考:花,葉は鎮静,収斂,鎮咳作用があり,気管支疾患,喘息,不眠症,下痢に用いる.気管支疾患,喘息には花25gを沸騰した水か牛乳1 Lに入れ,使用前に漉して1日カップ3杯を食間に飲む.伝染性の皮膚病や炎症には葉を潰して湿布する.打撲傷,関節痛,痔疾には花や葉に2倍量のオリーブ油に入れ,2週間放置後,ろ過したものを患部に塗布する. 熊本大学薬学部 2024.11.17 記す。
★やすで P.93 花壇の草取りが忙しくなって来た。そのむしられた草の中にも、残される草のかげにもさまざまの陰性の小動物が見つかる。 これは一種のたのしみであるが、折角かくれて平和にしているのに、悪いような気がすることもある。一晩降り続いていた雨のあがった朝、やすでは花壇の草むらにはびこっていた。これは大変な数だった。あるものはその長い体を巻いて寝ころんでいたし、あるものは、細かい脚を、粗密の波状に細かく動かして歩いていた。彼らはほとんど、速くもおそくも歩けない。逃げるのでも、またかくれようとするのでもない。そして湿気を全身に集めているような、いやなにおいがする。
やすでの種類は六千三百種もあるということだが、この長いのは、おびやすでの一種で、僕は目がちらちらしてその群を一分間も見ていられない。
ただ変なことを想い出したのであるが、関東大震災のあった年の夏、友だちのいなかった私は、毎日毎日この害虫を割箸でいっぱいつかまえ、片脳油につけては殺していた。鎌倉の山の中でのことであるが、半ズボンに草履をはいて、蝉のなく家のまわりを取って歩くと、ほとんど際限がなかった。またこんなにやすでが出て来たのはおそらく大地震でもある知らせなのだろうか。 ※参考:ヤスデという名前(なまえ)は脚(あし)が多(おお)いという意味(いみ)の「八十手(やそで)」という言葉(ことば)が由来(ゆらい)しています。 2025.01.02 記す。
★蕗(ふき) P.94 春の山の、麓の谷を歩いていると、、時々、ぼこっと穴があく。そのときはもう足はそこに落ちている。重い荷を背負っている時には、その足を抜き出すのに一苦労するし、力を入れるためみ、また次の足が新しい穴をあける。山歩きをしている人はそんなことはよく知っている。しかし、春の雪はよごれていても、やがてしばらくのあいだにこんな雪とも別れなければならないと思うと、穴に落ちてもあまり口惜しくはない。
雪の下の、暗い中で、蕗だまって育ちながら、まだ日光を知らないのに、ほのぼのとしていた。そして僕の、足を踏み込んだみっともない姿を嘲笑することも知らないように、こうつぶやいていた。 天井を破って下さって、ほんとうに嬉しゅうございます。お陰さまで、わたしも、薹が立たたないうちに春風にあたることが出来ました。 蕗の根もとの、ぐじゅぐじゅの土をひたす水も、雪解けの春の水だ。ツルゲネフがどこかにいるのではないかと思って、しゅんとした木立のあたりを僕は振りかえる。 ※参考:花茎や葉は鎮咳去痰,苦味健胃作用があり,咳,胃もたれ,胃痛,喉の痛みなどに用いる.生の葉は切り傷,虫刺されに外用する.生の根は打ち身,外傷,喉の痛みに服用,またはつき潰して患部に塗布する. 葉柄や花茎は食用である. 熊本大学薬学部
★みやませせり P.95 どんより曇った空の下、僕はねむたい空気が流れる尾根にねころんで、谷をへだてた山々を眺めていた。ひとつ絵でも描いてやれ。ごつごつの山を描くことは案外たやすいが、ただ緑の起伏が続いているようなのんびりした風景をそれらしく描くのは相当厄介である。 まだ幾分早いらしく、あんまりいろいろの種類の蝶は飛んでいない。近くに赤松の大きな死骸があるが、それは別段蝶の発生とは関係がない。 ただ今日、山麓を歩いているころから、またここでも盛んに飛んでいるのは、みやませせりである。翅をたたまず、黄ばんだ紋をちらちらみせるが、あまり見栄えもしない。けれどもそれだからと言って、決して軽蔑するいわれはない。 それにみやませせりは、多産であるために、かえってこうして路傍を低く飛んでいることが出来る。どんなに欲張りでも、これを二匹もつかまえれば、もうあとは何の意欲も起らない。多い糸いうことは幸せなことでもある。
※参考:名前の由来・・・深山で見られるセセリチョウの仲間であることから。 生息環境・・・平地~山地の落葉広葉樹林。 手入れされた日当たりの良い雑木林でよく見られる。 2025.01.03 記す。
★えんじゅ P.96 僕が小学生のころ、と言えば大正の末期であるが、東京三宅坂付近に住んでいた。そこから半蔵門へ続く濠端に並木が植えられ「いぬえんじゅ」という札が下がったのでその名を覚えた。記憶がいいわわけではない。毎日そこを通って学校へかよっていたからだ。
※参考:花は伝統的には止血薬として鼻血,痔,血便,血尿,性器出血などに用いる.高血圧,動脈硬化,脳卒中の予防にもよい.民間では歯肉炎の出血に炒った花を塗布する.痔の出血やかゆみには花や葉を粉末にして塗布するか煎液で洗う. 古くから街路樹,庭園樹などとして植栽されるほか,蜜源植物として重要である.若葉はゆでて食用となる 熊本大学薬学部 2024.10.29 記す。
★あげは P.97 夏型のあげはが今、僕の目の前で羽化しかけている。昨夜から今朝にかけて色が変る。刻々にと言っていいほどに変って来る。長いあいだの、あの鮮やか緑がもうなく、薄いセロファンをかぶった黒と黄色の、最後の瞑想が終る。この蝶の蛹にとって未解決の問題も沢山残っているだろうが、もうそれも切りあげなければならない。痙攣(けいれん)に似た運動を始める。山椒の葉を食べていた頃の思い出や悪夢をここに残して、晴れた大空へ、今日は飛び立つことが出来る。 僕は独り言でこの蛹に景気をつけてやっているが、なかなか出て来ない。産科の本をさがしてももう間に合わない。ときどき頸のあたりを縮める。そんなまね、しなくたっていいんだよ。それとも痒いの? 掻いてあげようか。蛹の中の蝶の背中を掻いてやるのは、やさしい仕事ではない。 玄関があく。今大切なところなのだ。大概のことは邪魔になる。背中が割れて来る瞬間を見落してはならない。蝶の羽化を初めて見るわけではないが、僕はきっと新しい発見をするだろう。僕自身の脱皮の方法を教えて貰えるだろう。講義に出かけなければならない時間が近づく。それよりもこの原稿を渡す約束の時間も迫って来る。あげははまた同じような運動をする。
その時突如、全く突如、背中を割って出て来た鮮かすぎるほどの色の蝶は、虫干し前の羽織を背中につけて、この原稿紙の上を走り回る。これで御満足でしょう? と言った様子で。
※参考:アゲハチョウの語源は、「羽を揚げて」休む様子から来ているそうです。「揚羽蝶」をモデルにしたデザインが平家の家紋に多く使われているのは有名です。古くから私たちの生活に溶け込んだチョウであったことがわかります。 2024.12.18 記す。
★雉 P.98 五日市から少し山の方へはいったところに、野鳥実験所がある。この付近の人に訊ねると、ああ雉屋敷ですかと言って教えてくれる。ルポルタージュをたのまれ、新聞社の人と画家のT氏と三人でそこへはいって驚いた。ずらっと並んでいるのは鶏小屋ばかりである。そして現に鶏がコケッコーと鳴いているので、これは商売がえしたに違いないと思ってがっかりした。
国家がお金を出して、こんないいことをしているとは、何という嬉しいことだろう。画家のTさん。ここでは焼鳥の話はやめておいた方がいいですよ。あとにしましょう。 けれども僕がそこで段々と話をきいていると、狩猟家のために雉を殖やしているような口ぶりにもなって来た。何しろ狩猟家からは税金をとっている。やっぱりそれでは国家はお金を出すはずである。 僕はきれいな色どりの雉の横顔を見てそこを出る。自分たちの大切な子供たちがいつか人間の腰にぶらさがる運命を、彼らは薄々でも知っているだろうか。 ※参考:字源 - 「雉」という文字は、発音を表す「矢」に意味を示す「隹」を組みわせた形声文字である。 「矢のように飛ぶ鳥を意味する」と解釈されることがあるが、民間俗説に過ぎない。 ネコのキジトラは毛色がメスのキジと似ている事からの由来である。 2024.12.06 記す。
★蜂 P.99 僕はこの頃よく肩が凝る。仕事をいやいやするからだろうか。一つ一つ、文字を枡目に埋めて行く商売なんで……と思ったら、すぐにその想いが肩に集って僕をいじめる。注射をしても貰うといい、連れて行ってあげようと言ってくれる友だちもいるが、僕はそんな時、庭に立てた鉄棒に飛びつく。機械体操らしいものは出来ないが、だんだん軽々と回れるようになった。肩の凝りには多少いいような気がする程度だが、手のひらにはいつも立派な肉刺(まめ)が出来ている。 天気がいいな。山にでも行っていれば、どんなに荷物が重くったって、肩なんか凝ることは絶対にないんだがな。そんなひとり言を言いながら、太陽の熱でもう大分熱くなっている鉄棒に飛びついた。そして僕は意気地なくも悲鳴をあげざるを得なかった。のんびりと鉄棒で日なたぼっこをしていた蜂をにぎってしまったのである。 蜂は思い切り僕の手のひらに注射をして飛んで行った。
おれたちの仲間を食い物にしやがって。貴様は少したちが悪いぞ。おれたちと堂々と勝負をしたらどうだ。命のとりっこを男らしくしたらどうだ。
僕は庭のまん中で手を振り回しながら、そんな声を聞いた。僕はそれでも、その蜂の正体を見届けることが出来なかったのをすぐに残念に思った。そして次の瞬間に、そのすばやく姿を消した蜂に感謝することも忘れなかった。なぜなら、彼の注射は肩の凝りに実によく効いたからだ。 2024.12.07 記す。 ★ゆうがびょうたん P.100
やままゆが科のおおみずあおを一名夕顔瓢箪(ゆうがおびょうたん)とい。五月から八月にかけて、青磁色の大きなでっぷりした体をときどき見せる。燈を見つけて来る種類ではあるが、体が大きいだけあって、せっかちにははいって来ない。僕の家の近くでも、毎年ずいぶん発生するが、部屋の中までやって来るのはほんの一匹か二匹で、あとは街灯のまわりを回っている。
つい最近、夜、急に出かけなければならない用が出来た。その夜、ゆうがびょうたんは沢山生れた。うすく遠方から灯がさして来る林の中で、彼らは紋付を着て、古風な夜会をひらいているようだった。僕は立ちどまって、そんなに急がなくてもいいような気持になって来た。中年の奥さんたちが、白粉をぬった襟を見せて、こんな色の夏姿で夜会に出かけた頃のことを、僕も覚えていないことはない。そこでどんなことを喋り合っていたのか、それは知らない。大した話もしないで、ただじろじろ他人の様子をうかがっていたのだろう。 しかし折角立派な紋付も、みんなお揃いでは困る。申し合わせたのでもなく、偶然同じ着物を着て生れてしまったのである。人間の奥さんたちと同じように、この蛾たちも一切自分の衣装については触れずに、ひらひらと小暗い葉かげに集っていた。まるで、明るみに出ることをためらっているように。 2025.01.03 記す。
★あめんぼ P.101 もうそろそろ梅雨があけるのか、今日は強い雨が降っていたかと思うと急にかっと日が照った。木々の影が呼吸をしているようだ。夕方そんな天気もだいたい落ちついたので、井之頭の池へ行くと、おびただしいあめんぼが池の水面を走っていた。池の水の流れ出すあたりでは、流されて来てはまた飛びはねて戻り、すべり台で遊んでいる子供たちと似ていた。 僕は用心のために持って歩いた傘な先をつかって、一匹でいいから掬(すく)いあげようとしたが、それはどうしても成功しなかった。おもたかの繁みの中にもいっぱいいるので、まちがえて傘の先に飛びついて来るのもいそうな気がしたが駄目だった。
※参考:アメンボの名前の由来は、飴のようなにおいがし、体つきも棒のようであることから「飴棒(アメンボ)」と名づけられました。 アメンボは、稲を枯らす害虫ウンカを退治してくれる益虫です。 ウンカの幼虫が水面に落ちてくれば、その波紋を足で感じ取って近寄り、針のような口を差し込んで体液を吸ってしまいます。 2024.12.07 記す。
★夏蜜柑(なつみかん) P.102 気の毒なことに、種痘(しゅとう)を怠ったためか、今ごろ珍しい天然痘のあばた面である。それに重ねて黄疸(おうだん)である。そう言えば、手製のフルーツ・ポンチを食べるたびに、想い出してかなわない。
君ノ組ノネ。アノ。顔が白クテサ。ホラ。帽子ヲイツモコンナ風ニカブッテサ。 アア原君カイ? 名前ヲ知ラナインダヨ。ホラ、コノ間学校ノ門ノトコロデ。コンナ恰好シテタ人サ。 アア山本君カ? 名前知ラナインダッテバ。 アア分ッタ分ッタ。アノ、夏蜜柑食べナガラ笑ッテルミタイナ顔シテルンダロ? ウン。ソウ。 アレハ石井君ダヨ。石井君がドウシタノ? 石井君ガドウシタンダッケ。 夏蜜柑を食べながら笑っているような顔なら僕だってよく知っている。石井君でなくても、 2024.11.26 記す。
★鶉 P.103 鶉(うずら)というと、僕はアドリア海を渡って来るその大群を想い出す。それはあまり太っていない。モンテーニュがイタリア旅行をし、ローマの長い滞在から再び歩き出して、アンコナへ来た時に、うんざりするほど鶉を食べさせられた。 「事情を確かめところによると、鶉はここへ、スラヴォニアから大群をなして来る。そして毎晩、こちらの海岸に網を張り、鶉の声色をいつかって、それの通る上空から招き下ろすのである」 僕はそのありさまが、今では自分で見たように、記憶に残っている。可哀そうなこの鳥は、みんな焼かれてイタリア人の口にはいってしまう。しかし、鶉の声色とはいったいどんな声を出すのだろうか。
実をいうと、その正体を知るまで僕は大層悩んだものだ。垣根のあいだからのぞき込んでみるのは、その音の性質上、つつしまなければいけないことのように思っていた。 今はどうか知らないが、ルネサンスの頃のイタリア人は、アドリア海に向って、毎晩、ジュルジュルジュルと言ってこの鳥を呼び寄せていたのだろうか。 ※参考:低地にある草原・農耕地などに生息し、種子、昆虫などを食べる。 秋季から冬季にかけて5 - 50羽の小規模から中規模の群れを形成することもある。 和名は「蹲る(うずくまる)」「埋る(うずる)」のウズに接尾語「ら」を付け加えたものとする説がある。 繁殖様式は卵生。 2024.12.12 記す。
★ひらたくわがた P.104
近所の幼い昆虫採取家たちは、池のほとりや林の中にそれぞれ秘密の樹を持ち、その樹皮のさけ目やほら穴を宝庫としている。
僕はある時、そんな小さいさい虫家をつれて夜の公園を歩いたが、実に詳しいので呆れた。彼は灯をつけない。木に登り、手さぐりで、まだその穴にいるかどうかを確かめる。大切なものをとられてあらそいが起ることもある。 一週間ほど前に、三人の小学生が来て、縁先でがやがやいっている。僕のうちへわざわざやって来ては口喧嘩を始める時には、大概虫のことが争いのもとになっている。「おじさん、これひらたくわがただね」と一人がいう。それは確かにそのとおりだった。 こうして彼らのために、僕の図鑑も大分よごれて来たが、喧嘩までしてその名をしっかりと覚えてくれるなら、図鑑がよごれてもそれを気にかけない。 その子が得意になっておしゃべりをしながら忘れて行ったくわがたが、空罐の中でまだ死なずに、さびしい音を立てている。もう一週間も立つというのに昼も夜もがりがり音を立て、つるつるの壁をのぼりかけては仰向けにころがる。閻魔大王のような顔をしているが、生への執着は強く、空しい努力を続けている。 ※参考:ヒラタとは平べったい体型をしていることから名付けられたものだが、非常に幅広いことにより平たく見えるだけで、実際の体の厚みは全クワガタムシ中でも最も厚い部類に入る。 種小名のtitanusはギリシア神話の巨人族であるティターンに由来している。 2025.01.04 記す。
★たばこ P.105 たばこをのんでいる人のうちで、たばこの花を知っている人はどのくらいいるだろうか。なす科のこの花は、ぐんとのびた先に、四方に向って咲くのので、サイレンを想い出す。 こんな記録も何年か後には貴重になるかも知れないが、戦争をするとたばこがのめなくなる。僕もたばこの代用として、どのくらいの種類の植物を煙にしてすってみたか、正確には覚えていない。緑茶、紅茶、いたどり、柏(かしわ)。それからとうもろこしの鬚やら、その辺のごみまですった。 紅茶の葉はもちろん一度のんだあとのをほして、それをパイプにつめる。煙とともに火をのむこともあるし、パイプがこげて、お尻に穴があく。
そして、とうとうもろこしの鬚をパイプにつめ、ただ気やすめにくさい煙を出しながら、たばこの花を観察し、ノートにスケッチをしていた。誰もいないので、偉いとは思ってくれなかった。 ※子供のころ、たばこ畑があり、乾燥場もあった。専売局が管理していた。 ※戦時中、タバコが配給制になり、タバコだけが配給されていたので、インド紙の英語の辞書を破ってつかって、たぼこを包み吸っていた。 ※戦時中、「金鵄」という名のタバコがあった。「金鵄(きんし)上がって十五銭 ~昭和18年~」から、戦中に歌われていた。 タバコ「金鵄」の元の名前は「ゴールデンバット」昭和15年に敵性語を用いてはいけないと改名され。「金鵄」は当時もっとも大衆に親しまれていたタバコ。 ※戦後、進駐軍のオーストラリヤの兵隊から煙草を貰っている人もいた。 ※戦後、昭和27年頃は「ピース」という名のタバコがあった。
★ごきぶり P.106
それはやまとごきぶりでしょうと教えてくれた人がいるが、ともかくてらてらの油っこい奴の雄が郵便受けの中にいた。彼女は台所や喫茶店を走り回っている雄とはちがって羽が短いのですぐ分かるが、郵便受けを何と心得たのか、産卵しかけている。こんなところでのんびり構えようとすると、どさっと郵便がはいって来て胆(きも)をつぶす。胆だけでなくて自分がそっくり潰れるかも知れない。それとも僕のところへ来ると郵便物の検閲をしようとで思っているのか。臓腑が全部出てしまうのかと思うほど赤味をおびた卵は大きい。それを産みかけて走り回る。
僕はやはり郵便物につぶされることを心配して、彼女をガラスの壜に移した。すべて生物は、自分に危機が迫ると、せめて種族を残そうとして、あわてて卵を産む。そのごきぶりも確かに例外ではなかった。しかし卵を産み落すと、その卵を食べはじめた。五分もかからないうちに薄いセルロイドのような殻のほんの一部分だけを残して食べつくしてしまった。何という呆れたことをするのだろう。僕にはそんなところを見せて、それが何のあてつけになるのだろう。ひょっとすると、わが子殺してから自害するのかと思った。ところがそれから四日目の今日、再び前と同じ大きさの健全な卵塊を産もうとしている。落ちついて産むことの出来なかった卵を食べてしまうと、それがお腹の中で再び整頓され、産卵管から顔を出す……。どうも僕には彼女が手品師としか思われない。 ※参考:ゴキブリは江戸時代から「あぶら虫」とか「ごきかぶり」とか呼ばれていました。 前者は今でも呼び名に使われ、植物にむらがる「アブラムシ」の仲間とよく混同されます。 また後者は「御器噛り」の意味で、 ゴキブリが食器をなめることに由来する分かりやすい名です。 2024.12.07 記す。
★リボングラス P.107 花壇のへりによく植えられているリボングラスは、他の花が次々咲いている夏の間に、「ちょっと失礼して」葉を失うが、秋になればまた盛んに葉を出して、真冬でも忠実に庭を飾ろうとしている。 僕のところでは薔薇の根もととあと二三箇所に植えてあるが、冬枯れの庭にあまりその薄緑の葉がいきいきしているので、冬の庭を写生するとそこだけが嘘のようになる。
そのリボングラスがこの春先から「転身」をはじめた。僕はまさかと思っていたが、リボンと見られていたその葉は容貌をかえ、野性味をおびてどんどんのび、ついに花を咲かせた。根を掘ってみれば、ちょろぎと全く球がついている。一名ちょろぎがやといわれているのはこれだ。そして変わり果てた姿は、もう花壇のへりを飾るには不都合な「おおかにつり」である。先祖に戻ったといおうか、自然にかえったといおうか、僕にはその原因がまだつかめない。肥料のかかり具合か、それとも気まぐれを起こしたのか。ともかくリボングラスは今どんどんと「おおかりつり」に変っていって、手のほどこしようもない。
リボングラスばかりではない。園芸植物は時々昔のことを想い出すものである。楽屋へかえって、衣装を脱ぎ、さばさばする役者ンおようなものだが、楽屋がないのだから仕方がない。 ※参考:リボングラスという名前は、リボンの形をしていることに由来しています。リボングラスはヨーロッパ原産の園芸品種で、イネ科オオカニツリ属の多年草です。葉は細長く、白色の縦縞が入っています。根元がこぶ状に大きくなるのが特徴です。 2024.11.22 記す。
★風船虫 P.108
毎年、夏の夜になんということもなく待っているのはこの風船虫である。ひと降りあればいくらか涼しくなるのにとういう期待はずれのしたしむ暑い晩に、羽蟻の群にまじって、この小さい虫はやってくる。灯火にやって来るうちでも、蛾のような粉っぽさも、羽蟻のようなむずむずした感じもなく、飲みのこしの水がはいったコップにでも飛び込めば、得意の潜水を見せる。
今年は風船虫の大群はまだやって来ないが、ニ三日前の夜、たった一匹飛んで来たので、僕は、絵筆をふいたために赤くよごれた布のはしを、小さく切ってコップの水の中に沈ませると、彼は僕の幼い日に見たと同じように、潜って行ってそれにつかまって水面まで浮いて来る。 こんなことを教えてくれたのは誰だったのかしら。海水浴に行くので腕が赤黒くなっていた。その腕で頬杖を突いていつまでもいつまでも、コップの中の赤い小切れを持ち上げている姿を見ていた。そして朝になるとこの小さな友だちは一匹残らずいなくなって、水がまずそうに机の上においてある。 今の僕にとっては風船虫は、こみずむしという名であることも知っておかなければならないが、なぜ小切れを持ちあげたりするのかそれは分らない。というより、彼は小切れといっしょに浮き上るとは思っていないのだろう。信念というものにつかまっているつもりの僕らが知らないうちにどこかへ漂ってしまうようなものだ。 ※参考:水中をクルクルと泳ぎ回るこの生き物の名は、ずばり「ミズムシ」。 もちろん白癬菌の「水虫」とはなんの関係もなく、カメムシ科の水生昆虫。 初めて見たときは、刺されると痛いマツモムシかと思ったのですが、背泳ぎで泳ぎまわるマツモムシとは違いお腹を下にして泳いでいます。 そして、体長1cmほどのこの虫こそが、「フウセンムシ」。 なんでフウセンムシなんて名前がついているのかと調べてみたところ、どうやら浮力が大きく、水底の土や水草などにつかまっていないと、浮いてきてしまうようです。 その性質を利用して、小さくちぎった色紙を水に沈めてフウセンムシが浮か沈みするのを楽しむ遊びがあるんだそうです。 江戸時代から昭和初期にかけては 「風船虫」の名前で夜店などで売られるほどの人気ぶりだったみたいです。 言語学者の金田一春彦氏も「我が青春の記(東京新聞出版局1994)」の中で、「コップの中に入れると、水の底から紙切れなどを水面に運んでくる虫もたくさんいて、感激した。本郷ではフウセンムシといって夜店で売っていた虫である」と記しているとか。 2024.01.04 記す。
★水引(みずひき) P.109 水引はだれもが知っている珍しい花ではないまた人によって好ききらいもなさそうな、目立たないものである。梅雨があけるころから、秋までほとんど変わらない様子なので、そのあいだに一二度、ああそうそう今年も水引が赤い砂粒みたいな花をつけたと思う。そしてそんなことを想った旧い夏の日の窓辺を考える。僕は確か、ある文章で、夏のはじめのころの出来事を書き、その時に水引を、ある効果を考えながら文章の背景につかった。そして秋になっても、水引は衰えず赤くぼつぼつ咲いているのを見て、これはべつのものに変えた方がいいかも知れないと思いながらそのままになっている。そんなことを思い出す。
花には、遠くからながめた時の名前や、のぞき込んでつけた名前や、色によるもの、形によるものなどがあって、これを分類してみたり、名前の花の名のつけ方を比較したら面白いと思う。水引はある程度、遠くから見た名だが、夏中、蝉の声で蜂の羽音をじっと聞いているアンテナのようだ。 ※参考:水引は、和紙をこより状にして、水のりを引いて乾かして作ります。 また、手作業の時代は着色水にひたして引きながら染めていたので、水引の名前になったと言われています。 水引には魔除けの意味があり、神聖な場所との区切りに水を引いて清めることから水引の名前になったと言われています。 2024.11.09 記す。
★あぶらぜみ P.110
ある蝉の研究家が、あぶらぜみを飼育した時の表が、その著書に出ている。一九四〇年の八月二日に産卵をし、翌四一年六月二日に孵化し、四六年の八月二日になって羽化している。蝉の飼育は、土の中のことでもある。根気のいる仕事だと思う。そして個体によっては、羽化が一年おくれるものもあるし、場所によってもちがってくる。
僕はその飼育表を見ている時、地中で実験されているこの蝉の幼虫が、木の根を静かにしゃぶっているあいだに、地上で自分は何をしていたろうかということを考えた。昭和十五年から二十一年の夏までのこと、つまり長い戦争の歴史が作られて行った時代だった。それらの日のこと、特に、学校の講義も休みになった夏に、何をしたかを覚えていないことをほんとうに恥かしく思う。 それらの夏の日に、僕は蝉の声を聞いたような気もする。街の中とはいえ、かなり木の多いところに住んでいたので、確かにあぶらぜみは鳴いていたに違いないが、それもよく覚えていない。ただこのあぶらぜみの羽化したころには山村にいたので、よく森に出かけたが、そこでも蝉が鳴いていたというはっきりした記憶がない。 ※参考:アブラゼミの名前の由来は羽が油に濡れたような色であるから、というものと、油で何かを揚げているような音を出すからという2説があるようです。 夏の夜、長い幼虫時代を終えて樹上で羽化する様子は、白く輝きとても神秘的です。 2025.01.05 記す。
★紫苑(しおん) P.111 庭の紫苑がぐんぐんのびたのは何年前の夏だっただろうか。その夏は雨が多かった。そして夏の日ぐれに、細かい雨が降りかかる紫苑は、そのあたりに、夢の雰囲気ともいうべきものが作られる。紫にけむるそこには、僕の過去がすぐに漂い始める。 ……落葉松(からまつ)の林を歩いたな、下にはいっぱい、苔が青々としていたな。水も流れていたな。……それは紫苑とは何の関係もないように僕には思えるのであるが、何かつながりを持っているのかもしれない。 そうかと思うと、そんなことがあったかどうかはわからないが。僕は急に少年に戻って、かすりの着物を着て、新しい下駄をはいて、どこかの電車道を歩いている。そして手に鳥籠をさげている。何の鳥だかよくわからないが、つい最近までいい声で鳴いていたのに、急に黙ってしまったので、心配になって小鳥の医者にみてもらいに連れて行くのである。
※参考:「紫苑(しえん)」という名前には、次のような由来があります。 花の色から名付けられたと考えられる。花は薄紫色で、広い場所や土地を表す「苑」と組み合わせて名付けられた可能性があります。 中国名の「紫菀(ジワン)」の音読みである。 平安時代に秋の名月をこの花の間から眺めたことから、「十五夜草」という別名がある。 また、シオンの花言葉には「君を忘れない」「遠くにある人を思う」「追憶」などがあり、平安時代の説話集『今昔物語集』に収録されている物語に由来しています。 ※参考:鎮咳去痰作用があり,痰の多い咳,慢性の咳,血痰の混じる咳などに用いる.漢方処方は杏蘇散などに配合される. 観賞用として栽培される.朝鮮では若芽を煮て乾燥し,野菜として利用される. 熊本大学薬学部 2024.11.24 記す。
★つめたがい P.112
僕は貝の蒐集をした経験はないが、遠く九州の海から送ってもらった貝を、多少整理して箱に持っている。それはめったに出したことがない。やはり自分で、どこかの海辺から拾って来たものでなければ、そういう意味での愛情はない。 それならなぜ、僕はつめたがいのようなものを好むのか。正直に言えば理由なんぞないのであるが、これは、必要があれば耳の役目をしてくれそうな気がする。それで、こんな貝をいつもポケットに入れておいて、人にも聞かせてもしかたのない文句を、この貝に聞いてもらうというわけである。時には、懺悔聴聞僧の耳にもなってもらったり、時には、昔の歌の聞き手になってもらうようなこともあるだろう。それで、つめたがいの、きれいに磨き込んだのを一つ持っていたいのである。 ※参考:由来・語源 東京湾周辺での呼び名で『渚ノ丹敷』より。 語源は不明だが、馬や牛の爪に似ている貝なので「爪貝」、もしくは「つべ」はお尻のことなので丸くお尻に似た貝かも。 2025.01.05 記す。
★エーデルワイス P.113 僕がもし欧州のアルプスへ行くことがあって、そこに咲いているエーデルワイスを見ることがあったら、毛ぶかい顔を見ながら言うだろう。 やっとお目にかかることが出来まして、まことに嬉しゅうございます。私の国には、山へ登る人が大勢おります。それはそれは大変な数で、この大多数の人はあなたのことをよく存じております。そして中には、あなたの、ひからびた姿を箱に入れて、大切にしている人もおりますが、実際にこうしてお目にかかった者は極めて少ないので、まことに光栄に存じます。 そんな讃辞をのべながら、この花を見せてやりたい人のことを思い出すだろう。そして自分だけが今エーデルワイスの前にいることを、あまり幸福なことだと思わなくなるだろう。それから日本へもう一度帰ることがあって、スイスへお出になったそうですが、エーデルワイスをごらんになりましたか、と訊ねられた時、ええ見ましたけど、そんなに大騒ぎするほどの花でもありませんよという自分の言葉も考えてしまうだろう。
今は、最近、日本の女流登山家の集りであるエーデルワイス・クラブから頂いたものを持っている。みんな黙って見ているが、欲しいと思う人も多いに違いない。 かかわることなので うっかり間違えて ※参考:エーデルワイスエキスはコラーゲンやヒアルロン酸を分解する酵素を抑制したり、チロシナーゼ活性を抑える作用、消炎作用、殺菌作用などが相乗的にはたらき、アンチエイジング・ホワイトニング効果に優れた成分として用いられます。 また、クロロゲン酸、タンニン、ビサボラン誘導体などを含み、高い高酸化作用によりシワやたるみを防止します。
★どうがねぶいぶい P.114
どうがねぶいぶいがニ三匹夜の仕事机の周囲を飛び始めたら、もう葡萄の葉の運命は決まったようなものだ。朝早く葡萄畑をゆらしてみると、夜葉を食べるために襲ったやつらがばたばた落ちる。幾らかは飛んで逃げるが、多くは踏みつぶされるがままになる。翅を持ちながら何という度胸のいい奴だろう。いやそうではない。なまじっか鞘翅(しようし)なんか持っていて武装しているつもりになっているからつぶされるんだ。愚かものさ。思いあがり方がにくらしいじゃないか。それならやっぱり踏みつぶしてやることにしようか。 僕は、これは葡萄の葉を食う害虫だと信じていたが、徹底的に葉を食べてしまうために、まだ青い葡萄の房がむき出しになり、真夏の太陽をじかに受けるようになって、それで葡萄が甘ずっぱく熟するのかと考えたので、害虫という名を取りのぞこうかと思っていたところだ。 いつまでも葉かげにかくれて恥かしがっては熟するはずもない。 ※参考:ダイコン(大根):属(和名属)ラファヌス(ダイコン)、学名Raphanus sativus、ラテン語読みラファヌス・サティウスラファヌス・サティヴスやダウクス・カロクが ※参考:ダウクス・カロタ:野生人参 ※参考:さや‐ばね【鞘翅】 〘 名詞 〙 甲虫類の背面をおおう前ばね。 キチン化して硬く、飛ぶためよりも体を保護する役割をもつ。 2025.01.05 記す。
★羊 P.115 いい加減のことを言っていても多数の人がそれをほんとうらしく思って感心するのが演説のうまさであろう。その要旨をを一口で言えば、合成樹脂の工業をもってしなければ日本危うしということである。その理由はここでくりかえすまい。国歌の興亡にかかわることなので、うっかり間違えて伝えては大変である。さまざまの表現が、流れるようにあった中で、荒々しいしぶきとなって僕に降りかかって来た言葉がある。 「……そうすれば、わたしは今大蔵大臣をしている。いいですかね。僕が大蔵大臣になればですよ。この化学工業を盛んにしているから、豪州だろうがどこだろうが、羊なんか一頭もいなくなっている……」 僕はもうその先を聞いていられなくなった。この地上から羊が死に絶えてしまう。あの沢山の丸いお尻も、ハイヒールも見られなくなってしまう。何という淋しいことをこの人はすらすらと言えるのだろう。そしてミレエやセガンティーニの絵の中にだけ、かつて地上に住んでいた動物としてその姿を残すようになってしまうとは。
僕は今後羊に会うたびにそのことを思いだすだろう。そしてそのことを話してやる勇気なんかとても持てないだろう。 ※参考:「羊」の語源・由来 「羊」の語源・由来には諸説ある。 茨城県家畜協会の機関誌「家畜茨城」によると、日本では古い時代には羊が飼育されていなかったため古名がない。 古書「和訓栞」には、「羊」の語源は「干支の未(ひつじ)」だと記載されている。 2025.01.05 記す。
★ほねがい P.116
貝類図鑑を見ていると、僕はひどく羨しくなる。何しろ完全に自分を隠してしまうことが出来るし、それがどんなに便利なことだろうと思う。誰が引っぱり出そうとしたって、絶対に顔を見せてやるものか。そう思いながら殻軸にからみつく筋肉に全身の力を集めている時、どんなに気持ちがいいだろう。
僕は気にいらないことがあると、もう誰にも会いたくなくなる。そんな時に玄関で声がするとほんとうに困る。会えば必ずにこにこして、どうです、お元気ですかなど言うに決まっているから、困るというより口惜しいのだ。 そんなに羨しいなら、押入れにでもはいって、中からおさえていたらどうです。 そこで僕の、貝に対する好みがはっきりして来る。どんな殻の中に隠れたいか。何と言ってもこの時こそはほねがいがいいと思う。蛤のような二枚貝の中に閉じこもって、頃を見はからって外の様子を覗くのもいいかも知れないが、そして内緒で舌を出してやりたいこともあるけれど、隠れる以上は憤然として、その中で怒っているのが分らなくてはつまらない。それには角がいっぱいに出ているのを選ぶべきである。 これはどうも大分おかしい。貝を羨む僕の心は矛盾だらけである。一体何のために隠れようとするのか。 ※参考:ホネガイ とは、アッキガイ科の巻貝の一種である。他の貝を捕食する肉食の貝で、前水管溝が棘状に長く発達して、魚の骨格を連想するところから、この和名で呼ばれる。棘は外套膜縁に一列に形成され、成長に伴い回転して背面の棘となる。120度毎に棘が形成されて、二つ前に形成した成長の妨げとなる棘を、自分で切断する。 2025.01.06 記す。
★茗荷(みょうが) P.117 茗荷の花が咲いた。僕の部屋のわきへ茗荷を移し植えたのはもう大分前になるが、うす暗く茂った根もとから、青白く、近よってみればうすく黄ばんで、幽霊のような花を咲かせる。一日でその花は終る。 僕は茗荷を特別に好んで食べない。食べれば食べられるもの、普段忘れていても一向に平気なものの中に入れてある植物である。釈迦の弟子の般特(はんどく)がよく物を忘れ、自分の名まで忘れるので、名前を書いた札を首にかけてやった。その般特が死に、彼の墓からはえたのがこの草、それで「茗荷」と呼ぶ。そんな話だの落語で「みょうが屋」の話などを聞いた僕は、少年のころ物忘れするのを怖がった。
茗荷の花はしみじみと見ているとなかなかきれいだ。ひらひらとして、またくるりとまるまって、あまりきれいなので、何か音楽でもやりたくなる。そして、これを七八輪、真赤な菓子盆にでもころがしてみると、オペラの舞台を見ているような気持になれそうで ※参考:熱帯アジアが原産地ですが、古い時代に渡来して帰化植物として本州、四国、九州、沖縄の山地林野の樹木の下影に自生しています。広く民家で栽培されている多年草です。「正倉院文書」や「延喜式」には、宮中料理に用いられていた記載があることか よく“茗荷を食べると物忘れがひどくなる”と言われますが迷信です。(それは落語の「茗荷宿」から広まった話です) 東邦大学薬学部
★やまとびけら P.118
新潟県の巻機山(まきはたやま:新潟県南魚沼市と群馬県利根郡みなかみ町の境、三国山脈(越後山脈・上越山地)にある標高1,967メートルの山。日本百名山、甲信越百名山、新潟100名山、越後百山、ぐんま百名山のひとつ)を本沢からの登ろうと思って失敗した。大きな雪塊が崩れ落ち、滝と一枚岩とでどうにも進めなくなり、口惜しい気持ちを重たく抱いて引きかえした。登川の岸に張っておいた天幕に戻ったのは夜十一時をすぎ、蛍がさかんに飛んでいた。この沢は無雪期に登ったものはまだないと言われている。
その翌日は、ザイルをほしたり、岩にへばりついて午睡をしたり、やかましい急流の岩の上ですごしたが、急流にすむ小動物をいろいろ見つけた。 やまとびけらの幼虫は、流れによってつるつるにみがかれた花崗岩の、ほんのわずかのくぼみに、砂粒を集めた実に美しい巣を作っていた。ちょっぴり砂がたまっているようだった。小さい自分の、まだやわらかな体を保護するために、これ以上の工夫は誰にも出来ないだろう。僕はその一つを、可哀そうだと思いながらこわして、中から出てもらった。自然がくだいた色とりどりの砂をこんなに巧みに積みあげ、はり合わせて、ブロック建築を川の中に造っているこの建築師は、きまり悪そうに、頭をかかえた様子をしていた。 こんな格好をされると、なぐらないでくれと小さくなっているように見えて、つい、充分な観察も出来ずに流れの中へかえしてやってしまう。 ※参考:体より思い石で作った巣を移動するときは引きずって歩きます。写真は正に巣ごと引越しをしている姿ですが人間ではこんな苦労は考えられません。 2025.01.06 記す。
★輪鋒菊(りんぽうぎく) P.119 これは貴婦人の帽子だ。今はこんなきれいな帽子を、うまく頭にのせるだけの自信のある人はいないだろう。この花のことを、今日はわざわざ、まつむし草と言わずにいるのは、この山麓の日だまりが、特別に高貴で、古風なかおりさえしているからだ。 もう丸い種子になっているものもあるが、それがまた帽子屋の坊主頭だ。 どこまで行っても、一向にこの花は減らない。僕はこれから、どこまで登れるか、一人で山へ登る。 するとどうだ。やっぱり秘かな期待が実現して、妖精たちが近よって来る。息をころし、動いてはいけない。妖精たちの襟飾りは、それぞれに翻っているが、風に乗って飛んで来た冠毛を、巧みにつないだ銀色の呼吸だ。
やがてこの草原へおりると、どうだ、みんなそれぞれに、輪鋒菊(りんぽうぎく)を頭にのせて、ファランドールをはじめる。この帽子は、瑠璃色のレースとなって、ななめにかぶるものにも、まぶかにかぶるものにも、甘く涼しい影で顔をかくしている。
僕は確かに眠っていた。秋の太陽があそこにある。妖精たちは、うすい靄(もや)のようになって、時々は透明に光ながら、僕を誘うように山へ消える。輪鋒菊はみんなここにあって、かすかに揺れている。 ※参考:マツムシソウ科の多年草で、日本各地の高原や低山に生育する。 丈は六十センチから七十センチくらいで、初秋うす青紫色の花を柄の先端につける。四センチくらいの花は中心が菊のように筒状花となり、周縁を花びらが取り巻く。一説にはマツムシの鳴く頃咲くのでこの名があるといわれる。西洋松虫草のように園芸化さ れたものもある。 2024.11.22 記す。
★とうもろこし P.120 天竜川に沿って走る飯田線に乗って甲斐駒や仙丈岳を眺めていた。
山形県の小屋住まいの時にも、畑にはとうもろこしを植えて大事にしていたし、東京へ戻ってからも、しばらくは重要な食糧だった。 僕はそれらのとうもろこしの中に、お化けを見つけた。黒穂病にやられ、無様にふくれ上がっているのを、三度ほどちらっと見た。その僕の家の菜園にもこの化けものが出現し、ざら紙のノートにその絵を描いておいたものが今も残っている。黒穂病菌は土にまじってそのまま冬を越し、いい季節になると菌糸をのばすという頑強なものらしいが、このとうもろこしの奇怪な姿は、同情のしようもない。 もし僕の指先がこんなふうになったら……もし僕の鼻が……と思うと、土をいじるのも怖くなる。もっとも僕たちだって、小さなことが頭のどこかに引っかかって、それがふくれ上ってどうにもならないこともあるのだが。 ※参考:黒穂病(英名:Common smut)はほとんどのトウモロコシ栽培地で発生する病害です。黒穂病は Ustilago maydis という菌により発生しますが、この菌は土壌および作物残渣上で生存します。この菌は植物についた傷から侵入して、あらゆる組 織に感染することができ、特徴的な炭状の瘤を作ります(図1)。 ※参考:とうもろこしには、食物繊維、ビタミンB群やビタミンCなどのビタミン、カリウムやマグネシウムなどのミネラルといった、さまざまな栄養素が含まれ、便秘解消や美肌への働きなどが期待できます。 2024.11.27 記す。
★四十雀 P.121 郵便局の局長さんが僕に色紙を渡して一つ……という。絵でも字でも……。そこで僕は四十雀の絵を描き、JINSEI WA SHIJUKARA SAIFU MO SHIJYUKARA といたずらをした。それが郵便局の窓口にかかったが、財布が空なのは貯金をしたからだという注釈がついていた。 このごろ、ちょっと久しぶりに、また四十雀の陽気なおしゃべりが聞こえて来る。朝六時半をすぎると、六羽七羽の仲間が、どこをどう飛んで来るのか、僕の窓辺の柿の木や、合歓の木へやって来る。合歓の木には確かに毛虫がいる。実際、彼らがその一匹を、大胆に食いちぎっているのを見た。腹の中がかゆくんならないかと思う。だれも知っているはずの、普通の四十雀なのだが、頬が白いので、頬白が来ていますねという人もいる。
やや性急な、甲高い、うれしいことをさらにさがし求めてはよろこんでいるようななき声が、僕の気持にも一種のはずみを残して、彼らは九時十時になると姿を消す。そんな日には仕事もうまく進むし、大学へ出かけて行っても講義が名調子で出来る。
ところが三日まえから彼らは来ない。家の垣根のそとから空気銃で一羽をうち落した者がいたのだ。今日その死骸を草むらに見つけたが、蟻がいっぱいたかっていた。得意の胸の黒筋も、さびしくよごれていた。 ※参考:名前の由来はさまざまですが、スズメ40羽分の価値があるからというもの、多く(40羽ぐらい)群れるからというもの、「シジュウ」と聞こえる鳴き声からというものの3つの主な説があります。 ちなみにゴジュウカラ(五十雀)という小鳥もいます。 2024.12.08 記す
★すけばはごろも P.122
こうして荒れて行く花壇の、ひとつひとつの草の枯れ方も僕には大変勉強になる。僕自身どんな具合に枯れて行ったらいいかと思うと、いい加減には見ていられない。 そんな庭に、そろそろすけばはごろもがじっと羽を日にほしはじめる。必ずしも今多くなるのではなく、草の若い茎から液を吸っているようだが、葉が落ち、庭の乱れのうちにすき間ができると、この小さな蝉のような姿が目立って来る。羽衣などという、虫としてはいい名をもらっていることを知らないものだから、どれどれ立派な衣装を見せてごらんと近づいと、バネの仕かけがかくしてあるようにぴんと飛んで行って、またどこかの茎へぺたっとはりついている。 蝶は甲虫の仲間とちがって、これはあまり夏休みの宿題用の標本箱には入れられない。網でとるのは大げさだし、指先でつまんでやろうとするとうまく逃げられる。ともかく逃げることのうまいものはこんな五六ミリの虫でも頭がいいように思えるのはどういうことなのだろうか。 ※参考:スケバハゴロモ(透羽羽衣)は、カメムシ目(半翅目)ハゴロモ科の昆虫で、カメムシの仲間です。 本州、四国、九州に分布します。 名の由来は、透明な翅を持つハゴロモの仲間である事から。 2025.01.06 記す。
★あめりかざりがに P.123 これがアメリカから渡って来たのは一九二一年だということである。したがって僕は幼年時代にこれを取って遊んだこともないし、はさまれて驚いたこともない。 こういうことは年代をはっきり覚えておかないと、何となく幼いころのあのつめをおさえつけて、ぴんとはねられたような気になる。
誰がとって来るということもなく、庭の水甕の中にいつもこの赤黒い武装者が一ニ匹はとらわれている。そして夜中、時々曲った腰を勢いよくのばすので、びしっという音を立てる。それは案外寂しい音である。そしてこういう動物は、顔付から言っても、持っている鋏から言っても、いかにも頑丈そうなので、放っておかれ、そのために苦しい想いをしなければならない。可哀そうなものである。僕は夜半に、あんまり彼らのはねる音が聞こえると、懐中電灯をつけてのぞいてみる。むき出しの目玉は八方を睨んでいるようだが、やっぱり僕のほうだけを見てもいるようだ。その、何かをねがい、秘かに祈っている様子も、長いあいだみていると分かって来る。
ホントニ淋シイノデス。ヤガテ死ヌコトモヨク分ッテイルシ、ホントニ……。 それも僕には分る。ただ、むき出しの目だまからは涙をこぼすことが出来ないんだね。そうなんだね、と僕は言ってやる。 ※参考:アメリカザリガニは名前のとおり北米原産ですが、なぜ日本で身近になったのでしょうか? 実は人間が持ち込んだのです。 1927年(昭和2年)に、食用ガエル(ウシガエル)養殖の餌として、神奈川県鎌倉郡岩瀬にあった鎌倉食用蛙養殖場に20匹持ち込まれたのが最初とされています。 2025.01.06 記す。
★なぎいかだ P.124 うちの庭にもときどき奇妙なものが出現する。よく考えてみて、原因のおもいいたることもあるが、このなぎいかだはどうしてこんなところにやって来たのか分からない。分からない時にはすべて子供のいたずらということになる。生えたのではなく、さしであったのが、そのままついてしまったのだ。しかし、それ以来近くの家の庭の垣根を気をつけてみているが、なぎいかだは見当たらない。
この先のとがった葉のよなものは枝である。そんなばかなことがあるものかと思うし、百合の仲間だというのも、変な感じがする。幾ら変であっても学問は尊ぶばなければならない。 暖地に生えるなぎの葉に似ているのでこの名をもらったのだろう。なぎの葉を、鏡の裏に入れておくと合いたい人の姿が鏡に現れる。これはその代用にはならないだろうが、なぎいかだが出現して三年目になり、来年あたり、僕はこの花に会いたいものである。
★ぶゆ P.126 昆虫図鑑の双翅目直裂亜目蚋(ぶゆ)科には、ウチダツノマユブユとか、コウノホソスネブユとか、オオキツメトゲブユなど十二匹のぶゆが並んでいるけれど、僕の瞼や目にまで飛びついて来たやつは、一体どれなのかさっぱり見当がつかない。腮鬚(えらひげ)の各節の長さの比をはかって、それで決定することは、はれあがった瞼をぱちくりやりながら出来る仕事ではない。 何しろここは滅多に人間の踏み込んだことのない河べりの藪の中で、そこへ天幕を止むを得ず張った僕は、覚悟はしていたけれどぶゆの攻撃には気が狂いそうになった。頬の片方をやられて、爪でいいいいとおしているうちに、頸の方を三箇所はやられる。それをえいと思ってつねっているうちに手くびをやられる。火を焚き、その煙の中へ顔をつっ込んででもいなければどこもかしこも凸凹になってしまう。人間の尊厳について、むりやりに考えてみようと思ってもだめだ。彼らは死を恐れない。死の恐怖よりも、血を吸うことの方が比べものにならない悦びなのだから始末にいけない。
襲うのか、したって来るのか、ともかく近寄って来る者を最初から除けようといおうのは男らしくない。
※参考:ブユは、ハイキングやアウトドアなどの季節に、山間部に多く発生し、刺されると激しいかゆみや腫れ症状を引き起こす厄介な虫です。
2025.01.06 記す。
★蓮(はす) P.126
昔は僕もいろいろのことを信じたものだ。両手の爪をちゃりちゃりこすり合わせると、親が死んで家が貧乏になることだの、人のまわりをぐるぐるまわると蛇になることなど、どんぐりを食べるとどもりになるだの……。そしてそのとおりになったら、かなり忙しい。
ある年の夏の夜明けに、僕は幾日も幾日も蓮池へ、花の咲く時の音を聞きに行ったものである。花火のように大きな音がするのかと思って、明け切らぬ池畔(ちはん)に出かけては耳を澄ましていた。 どんなに静かにしていても音は聞こえなかったけれど、花火でも、しめっているとブスッというだけのこともあるのを知っていたから、なかなか期待を捨てなかった。そしてひょっとするとそこから何かが飛び出すかも知れないとさえ思っていた。 今度はポンと言った。けれども鯉がだましたのだ。 今僕が、格別の遺言を書き残さないで死ぬと、金紙と銀紙で作った蓮の花を、棺の前に置かれるだろう。白木の道具とこの金銀の蓮が、僕の死んだことをはっきりさせるのだが、そこで、棺の中から僕はポンと言ってみたいものだ。その時に、蕾だったその造花が、うまい具合にひらく仕掛けまで作っておきたいものだ。 2024.11.23 記す。
★べにひかげ P.127 九月の山にはべにひかげが多かった。清水峠を中心に、千八九百の高さでひろがる上越国境の山々には、尾根のところどころに小さい池があり、その付近には、いわしょうぶの白い花がいちめんだった。その花穂の一つ一つに、べにひかげがとまって、体をいろいろに曲げながら蜜を吸っていた。翅の色の紅が、朱に近いほど鮮やかなものもいたし、黄土色に古びているのもいた。しかし、それだけ群れていても、鳴かない蝶は実に静かだ。そして手を振って歩くと、ニ三匹一度につかまえてしまうこともあったし、記録をつけるためにひろげた手帳にまで来てとまって行くのもいた。 どれどれ、見せて。あたしのことなんて書いたの?
「あきあかねの大群が風向とは無関係に清水峠の方へ進んで行く。べにひかげは花の上から動かない。オンナジ花ニオンナジ蝶々」ほら見てもいいけど何のことか分からないだろう? ね?
天幕がばたばたとさわがしい風の朝、蝶たちは、いくぶんか羽を持つ身の不幸をかみしめながら、黄ばんだ草の中へかくれて、風に対してさからうこともなく、従順に閉じた翅をたおしていた。これも高嶺に棲む蝶の、風をよける習性の一つであろうが、多くの蝶におくれて秋の山に静かに住むものの謙虚な生き方が感じられた。 2025.01.07 記す。
★笹魚 P.128
植物に寄生してその一部を片輪にする昆虫はたくさんいるけれど、川に落ちて鰭をふり出し岩魚(いわな)になるということまでを人間に考えさせるのだから、大した芸術作品である。僕はていねいに写生してから鱗の一つをはがしてみたら、ニミリほどの紅色の幼虫が出て来た。 その後、訪ねて来たお嬢さんが、ほんとうにこれが岩魚になるのかと思いましたから、実物を見せて、これですよ、安心して下さいと僕は話した。そして、もう一つの鱗をはがして、ね、これ、この赤いの見えるでしょう? そう言ってささたまばえの点のような幼虫を見せると、彼女は言うのだった。なるほどねえ。これが岩魚になるんですか。そんなふうに感心されると僕はもう何も言えなくなってしまう。 ※参考:笹魚が本当の魚になるはずがありません。その正体は、ササウオフシ(笹魚附子)という「虫こぶ」の一種なのです。虫こぶというのは、虫嬰(ちゅうえい)、あるいは英名でゴールとも呼ばれます。昆虫が卵を産み付ける刺激あるいは幼虫の分泌物によって、植物の細胞の一部がコブ状に異常変化してできる、腫瘍(しゅよう)のようなものです。稈からタケノコが生えているように見える笹魚ことササウオフシは、その名もササウオタマバエ(笹魚玉蝿)という、タマバエ科の昆虫(でも成虫はカのように見える)が、笹の新芽に卵を産卵することで発生したものなのです。ひとつの笹魚には、一頭の母親が産んだ卵から産まれた、たくさんの幼虫が暮らしています。保育器もしくは「ゆりかご」のようなものです。春から初夏にかけて羽化し、笹魚の中から外界へと飛び立っていきます。けれども中の幼虫がすべていちどに羽化するわけではありません。ここが、このタマバエの面白い生態です。 2025.01.07 記す。
★くつわむし P.129 夜汽車に乗って居る時に、虫の声は、奇妙にはっきり聞こえる。何か訳があるのだろうが、走っている汽車の窓へ、チンチロリンと声だけが投げ込まれて来りすると、僕は一段と旅らしくなる。遠くの家の灯が見え、その家の軒に吊るしてあるらしい虫籠で、くつわむしが景気よく鳴いているのが、すぐそこのように聞こえることもある。
昨夜も十二時近かったと思うが、秋風の中であまり虫がよく鳴いているので、懐中電灯を持って、露にぬれながら近くの草原を小一時間歩いて見た。ころぎ、くさひばり、まつむし、うまおいなどが多かったが、遠くの畑の方から、くつわむしのやかましい声がするので、そこまで行ってみた。
遠くだと思ったが、こんなに遠くだとは思わなかった。途中で戻ろうかと思ったが、僕をこんなに歩かせた正体をどうしても見てやりたくなった。それは畑のへりの茶の木の中だった。電灯をつけると鳴きやむかと思って、繁みに顔をつっこんでから灯りをつけたが、くつわむしはただ夢中になって音を出していた。くびのあたりの発音鏡が、せわしなくハート形になってふるえているが、どこでどうして音を出しているのか本から得た知識をここで確かめてみることはむつかしい。この褐色の、でっぷりしたくつわむしは、狂ったように音を出し続けている。彼はもう自分の音を出す目的などはとうの昔に忘れたように、自分のジャズに熱狂していた。 ※参考:名の由来 ●鳴き声がくつわの音(たづなを引くために馬にくわえさせる金具がくつわで,これが馬の動きに合わせてガチャガチャと音をたてる。) に似ているから。 2024.12.12 記す。
★とりかぶと P.130
カロッサが死んだ。彼が小さいころもこの花が毒だと教えられたらしいが、彼は花には別に毒がないことを知っていて、この帽子をとるとどんなものが出て来るかその秘密を知っていた。かぶとをぬがせると「指の間にかわいらしいすみれ色の車が現われ、ちっぽげな鳩が銀の梶棒でそれをひっぱっている」というのである。フランス人たちはその車を「ヴィナスの車」」と言っている。幼いころのカロッサのような子供が僕の近くにいたらどんないいだろと思う。 ※参考:ハンス・カロッサ(Hans Carossa,1878年12月15日 - 1956年9月12日)は、ドイツの開業医・小説家・詩人。謙虚でカトリック的な作風であった。 ※参考:トリカブトという名前の植物は存在せず、一般的にはキンポウゲ科トリカブト属の植物のことを指します。本属の植物の多くに見られる特徴として、地下部のいわゆる親芋に相当する塊根(母根)から新たな塊根(子根)ができ、それが次の年の母根になるというサイクルの擬似一年草であることがあげられます。 一方、トリカブトといえば毒草という印象があるかもしれませんが、事実、非常に毒性が高いアコニチンなどのアコニチン系アルカロイドを植物全体に含有しています。その塊根(子根)は附子(ブシ)とよばれる生薬にされますが、そのままでは作用が強すぎるため、一般には、安全に用いるために加工を施します。古くは木灰や石灰をまぶしたり塩漬けにしたりしていましたが、現在は高圧釜で加圧加熱をするのが普通です。この加熱によりアコニチンなどは毒性の低い化合物に変換されます。附子にはこれら有毒成分の含量の上限が規定されているため、過度の心配は無用です。 附子は鎮痛・強心・新陳代謝機能亢進・利尿などの薬効で知られる生薬で、八味地黄丸・真武湯などの漢方薬に配合されます。また、体を温める作用が強く、冷えを伴う症状を対象にした漢方薬に用いられます。 ただし、減毒されているといえ作用の強い生薬ですから、附子を含む漢方薬は専門家の指導の下で安全に利用するのが良いでしょう。また、附子にはドーピング規制物質のヒゲナミンという化合物が含まれていますので、アスリートの方は附子を含有する漢方薬にご注意ください。 東京薬科大学。 2024.11.07 記す。
★こなぎ P.131
家の前の道が、簡単に舗装され、それはありがたがったが、重たい地ならしの車が門の段をこわした。これを放っておくわけにも行かないので、コンクリートで修繕し、そのついでに池をつくったというのがほんとうの話である。
それよりも、こなぎの花の色は実にきれいだ。決して葉よりも高くのびて目立とうとするところがなく、競って虫を呼びとめようとする気勢もない。ひたすら魚たちのために咲いているように、下を向いているものもある。 ※参考:最近,コナ ギを栄養分析した結果,ビタミンやミネラルが多く含まれ,野菜として栄養価が高いことが報告された。 そのため,改めて食材と しての価値が注目されている。 また,中国では民間薬にも利用され,解毒,鎮咳作用から,高熱,喘息などに用いられる。 2024.11.10 記す。
★蛍蛾 P.132
生来元気がなく、羽を持っているものでこれほど確実につかまえられるものもまれである。ところが、蛍蛾ほどに、逃げる気持ちさえなくのんびり構えられると、つかまえる意欲もわいて来ない。それに、これはいやなにおいがする。 僕は自分のどこから出て来るのか分らない勇気を出して、どこからにおって来るのか分らない臭さをかいで見る。湿気臭い、かび臭い、青くあさい。そしてそれらを総合すると胸が悪くなって喉がおっとなる。結城を出してもやはり警戒している僕の鼻は思い切ってにおいを受け取っていない。 中学二年の子供に、怒るかも知れないがかいでもらうと、こいつはね、ええと平家のころのにおいだな、ともかくちっとやそっとの昔のにおいではないな、という。白線の入った黒衣に赤い帽子はなかなか気取ったもので、スタンダール的衣装であるし、また流行の色どりであるようだが、蛍蛾はなるほど古風な臭さである。 ※参考:ホタルガの成虫は、5〜6月と9〜10月の2回出現します。 頭が赤く、 腹が黒いことがホタルに似ているとして命名されました。 2025.01.07 記す。
★いぬさふらん P.133 この春先に、いぬさふらん(コルシカム)の球根を一つ頂いた。 これを下さった方は植物に詳しい若い方だったが、僕のことを研究して下さっていて、どうしても実物を見たいのでやって来たという種類の方だった。実物の観察報告は受け取っていないが、がっかりなさったのであろう。けれども、この球根は、正しく僕を悦ばせる贈物だった。卵形ではあるが、親指の先ぐらいおしりがとび出していて、園芸種にはこれがないということだった。そしてこれは、何もしないで机の上に出もころがして置けば、秋に花が咲くということだった。 その秋がやって来た。それとなく注意しているよ、ほとんど突然まるで蛹(さなぎ)から蝶が出る時のように芽を出し、毎日寸法をはかっていると、それからの伸び方は実に早く、十三日に二十五センチになって、薄く淡い紫をおびた花を二ホンの花茎から六つも咲かせた。一回も太陽の光にあてないのに、秋を知ることの何という的確さだろう。僕には、秋が来てくれては困る。夏の仕事がたくさん残っている。
※参考:いぬさふらんの名前の由来:AI による概要 イヌサフランという名前は、アヤメ科の薬草であるサフランの花に似ているが、食用にならないことに由来しています。 「イヌ」には「似て非なるもの」という意味があり、サフランの花に似ていますが、実は全く違うものという意味です。 ※参考:イヌサフランの有毒物質は、球根や種子に含まれるコルヒチン(colchicine)です。 鎮痛薬として使用されますが、嘔吐・下痢などの副作用を示し、重症の場合は死亡することもあります。 2024.11.12 記す。
★小綬鶏 P.134 この鳥、なんていうの? そう言って芳ちゃんが持って来た時には、小綬鶏(こじゅけい)はもうボール紙の棺の中にはいっていた。またこのあたりを、空気銃を持った男が徘徊しはじめた。確かに打たれたあとがあって、血が羽毛にこびりついている。
まるまるとした小綬鶏は、突然甲高く鳴きはじめて、僕の夢をさましてくれた。夢を破られたなどとは決して思っていない。見続けていたかったような夢は僕にはない。君の仲間には複雑な感謝をささげている。僕はそれにはっきりとは気がついていなくとも、小綬鶏の鳴声に導かれていたことさえ 死骸を前において、どうしたのかと思っている芳ちゃんを傍に立たせて、僕はくらくらする。僕がまよい込む草むらは、まだこれからもいっぱいありそうだ。 ※参考:漢字では「小綬鶏」と表記され、名前の由来は古代の中国の役人が服につけていた「綬」という組み紐に、模様が似ているからだとか。 全長は鳩と同じくらいの27㎝程で、全体にずんぐりとした形です。 顔は赤茶色で頭部と胸は青味のある灰色です。 2024.12.13 記す。
★薄雪草(うすゆきそう) P.135 夏の山旅の記念として、未知の方々から高山植物の押花を送っていただく時、うれしいと思いながらふと暗い気持ちになる。これらの植物を採取するには、かなり面倒な手続きをして許可を得なければならないのを知っていたのだろうか。 しかし、今日は、この花はだれかに摘みとられ、道に棄てられていた、と言って、薄雪草を送って頂いた。 白というよりはほとんど銀色に光る細かい毛が僕に山の太陽と霧とを想い出させた。そればかりではなく、辿れば」一ニ時間は容易にたってしまうほどの多くの想い出を次々と湧きあがらせてくれた。大した魔力である。そしてその葉には、小さな虫がつつましく口をつけながら這った跡さえ残っていた。
こいつもたまらない。薄雪草の葉に紋様を描くのは何だろう。蝶の食草にちて戸籍しらべをはじめる。それでまた一時間。
この花には僕自身の想い出は何もつながらない。けれども、もう一度ていねいに押しなおし、台紙にとめて額に入れていこう。この日本のエーデルワイスの一つを。そういえば最近、ヒマラヤのエーデルワイスも贈られ、僕のまわりには、自分では摘むまなかった高嶺の花がだんだんにぎやかに飾られて来た。 ※参考:薄雪草(ウスユキソウ)という名前は、茎や葉に白い綿毛が密生して薄雪をかぶったように見える様子に由来しています 2024.11.12 記す。
★えんまこおろぎ P.136
ついにやって来たな。ばかに元気がいいじゃないか。えんまこおろぎが、つやつやとした体を、今年は机の上にあらわした。油でも浴びて、彼らの流儀に従って化粧をして来たにちがいない。暗い、しめっぽい処を好むのに、この頃では虫の世界でも、ドライということがはやるのか、電灯の下できょろきょろしている。
相変わらず人相はあまり「よくない。えんまこおろぎなぞと名をつけられていることも知らずにいるらしいが、全くよく似ている。 部屋の、床と壁の間が、本やがらくたの重みで段々大きく口をあけて来たので、床下から探検にやって来る。それなら僕の方にも訊ねたいことがある。 君たちの彼女は、用を済ませると彼をあっさり食べてしまうけれど、あれは僕から見ると、ひどく残忍なことで、出来ることなら考えなおしたらいいんじゃないか。そうすると、こおろぎは、きりりとなって僕に言う。あなた方の言葉はよく知りませんけれど、可愛いひとに向って、食べてしまいたいと仰言ってるんでしょ? そして食べてもらいたいと思うことだってあるんでしょ?なぜそれなのにためらうのです。不完全な愛し方しか出来ない癖に、「恋愛論」なんか、少少滑稽ですよ。可愛い人を食べてみてから愛のモラルでも論じてもらいましょ。 ぼんやりしている僕を残して、秋の夜もさらに更けて行く。 カマキリの雄は、なぜ雌に食べられるのか? カマキリといえば、交尾時に雄が雌に食べられるという、痛ましいエピソードが有名です。雄は頭を食べられると、脳にある交尾抑制作用が解除されるのだという説まであるようです。しかし、この性的共食いが本当ならば、雄とはなんと情けない存在なのでしょう。 ※参考:カマキリ博士の安藤喜一※ さんによると、雌雄をペアにして観察すると、次の4通りの結果が得られるそうです。 (1)正常に交尾して、共食いなしでわかれる。 (2)雌が雄の頭を食べて、その頭のない雄と交尾する。 (3)交尾した後に、雌が雄を食べる。 (4)交尾せずに、雌が雄を食べる。 85頭のオオカマキリの雌で観察した結果によると、雄が雌に食べられる割合は10%以下に過ぎないそうです。カマキリの雌成虫は、性成熟してから交尾の準備ができるまでに2週間ほどかかります。それより前に雄を近づけると、交尾相手としてではなく、餌として認識して食べてしまうのです。 雄が食べられるもうひとつの原因は、カマキリの捕獲本能にあるようです。目の前で動くものを、自慢の鎌(前脚)で即座に捕らえる習性があり、交尾後に雌の近くで不用意に動き回れば、雄は獲物として捕獲されてしまうのです。性的共食いはほかのカマキリでも見られ、雌と比べて雄の体が小さく捕獲しやすい種ほど、その頻度は高くなるようです。 『カマキリに学ぶ』安藤喜一著 北隆館(2021) 2024.12.08 記す。
★梅鉢草(うめばちそう) P.137 梅鉢草は、昔作りかけた僕の植物地誌(フ ロ ラ)の第一頁に描いた花である。そこでこのフロラは真秋の最中にはじめられたことが分る。 それは長く続かなかったが、時間を幾らかけてもよかった時代だったので、一つ一つ色をぬり、丹念なものだった。しかもちょっと版画風な趣きも加えたりした。 あの萱(かや)の原の、その萱の刈りとられたあとに、白くつやつやと、変にはっきりと咲いた花だ。茎のなかごろに、大きく目立つ葉っぱが一枚ずつついている。それが逆さにはいたスカートのようだ。 最近雨に降られながら、長い長い峠への径を辿っていた。重い荷物が肩へめり込み、一歩一歩はもう苦しみの向う側へ突きぬけてしまって、頭もしびれていた。霧の流れる山の斜面が明るくなって、もうそろそろ峠が近いと感じた時、足もとに幾つもの梅鉢草が、澄し込んで空模様をみていた。僕はもちろん久し振りで懐かしかった。こっちを向いて笑ってくれないのが不思議なくらいだった。
花々は黙って歓迎する。むしろそれだから僕は困ってしまう。寂しいような、恥ずかしいような、誰かに来てくれるといいと思うような、具合の悪いその感じ。
こういう時に手帳を出し、詩でも作ればいいのだ。「梅鉢草の寄す」という題にして、求愛の気持をこの花に向って実験してみればいい。 ※参考:梅鉢草の花の由来:紋所(家紋)のひとつで、変形に、中心部がおしべの形ではなく、ただの丸になっている「星梅鉢」がある。菅原道真や前田利家の家紋として有名で、湯島天神など天神社でよく見かける。家紋に由来する植物名には、ほかにハナビシソウ(花菱草)などがある。 2024.11.11 記す。
★蚤(のみ) P.138
猫の蚤をとっていたら、今日は時間の大切な日なのに一時間を蚤と一緒につぶしてしまった。つぶした蚤をしらべたが、「ねこのみ」であるか「ひとのみ」であるか、その種類が容易には分からない。残念なので顕微鏡を出す。ねこのみが猫にのみ寄生するとは限らず、いぬのみが猫へ来ていることもあるので困るのだ。
「頭楯溜を欠く。頬剛棘櫛は鋭く黒色で七八本の棘より成る」。第一棘は第二棘と等長……」という具合なのだが、段々に、小さい無限に近づいて行く恐ろしさ感じないこともない。そして時々、どっちみち痒いんだもの、蚤は蚤でいいじゃあないかと誘惑が蚤のようにちくりにちくりとさす。 大変なことをはじめてしまった。死んだ蚤のしんとした世界だが、僕は生きているので遠くのラジオシャンソンも聞こえる。蚤の種類は世界中六百種も見つかっている。何という根気だろう。 五百何種類も分かっていて、そのほかにもいるかも知れない変な希望をもって蚤の身体検査をして行った人のその根気には頭をさげなければならない。 僕はまだねこのみだかどうかがよく分からない。猫は、そんなことをしている僕の膝の上でやすらかに眠っている。蚤をとってやったという愛情などは、こんな時にはお話にならないほど単純なものに思える。 2024.11.10 記す。
★ひがん花(ひがんばな) P.139 今日、雨の中で子供が、母親に断って庭の花を友だいに持たせてやっていた。雨の中を栗拾いに誘い、大分ぬれたのでそのままかえすと家で叱られると思ったのか、それとも僕の家へ遊びに行くことをその家の人が知って、帰りに花を買っておいでと言われていたのかも知れない。 植木鋏で、みずひきを切ったりしていたがひがん花を持たせてやろうとすると、母親がそれを切るのはいいけれど、その花をいやがるおうちがあるからおやめなさいと言った。 僕も誰からとなく、この花は縁起が悪いとということを聞かされていた。しばらく忘れていたそのことを想い出した。 関東大震災の時に、家が潰れ、近くの大きな家に一家世話になっていた。余震がいつまでも続いていたので長い間松林の中で生活していた。僕はまだ十にならない頃で、地震の恐ろしさをすぐ忘れて、遊びに出かけた。そしてひがn花がきれいに咲いていたので、子供心にも、それを摘んでみんなに悦んでもらいたいと思った。何しろ大人がみんなですぐ青い顔をしてうろたえるのでは仕方がないよな気持ちもあった。
★かやつりぐさ P.140
このあいだ、裏の畑から、まだ残って草原を夕方歩いている時もそんなことを思い、一本のかやつりぐさをぬいて、土手に腰かけた。どこからか懐しいにおいがした。それは無論この草の、昔から変らずに持っていたものだろうが、僕は幼稚園の物置小屋の裏手の、黒く防腐剤の塗ってある板塀に沿った空地を想い出した。 その物置小屋は暗くて、冬になると持ち出される達磨ストーブが積みかさねてあって、いたずらっ子たちは時々そこまではやって来ることがあったが、その空地には誰も来ることがなかった。 ある時先生に見つかった。こんなところにいないで、みんなと遊びましょうねと先生は、僕の腕を引っぱるのでもなく連れて行ったが、そう言いながら一本のかやつりぐさをとって蚊帳(かや)をつくるのを教えてくれた。 土手に腰かけてそれを想い出したので、蚊帳を作ってみたら、その先生の白い手が浮かんだ。 ※参考:腊葉標本(さくようひょうほん)腊葉維管束植物の標本の形式でもっとも一般的に用いられているもので, 押し葉標本 ともよばれる. ※参考:カヤツリグサ科は茎が三稜なのが特徴であり、これを両端から裂くと二裂せず、四辺形をつくり、その形が蚊帳を連想させることから一般名としてカヤツリグサの名前が古くからあった。 ※参考:原野や道端に良く見られる多年草で、茎や葉は煎じて健胃・整腸に効能があり、 心臓病等の薬用植 物。 若い茎や葉は洗って生のままサラダに、 また生で一夜漬けにして食用。 日本各地の林内のやや乾いた壁面や 岩の間、 人家付近の石垣などに生育 する半夏緑性のシダ植物。 2024.11.23 記す。
★金魚 P.141 金魚は人間が鮒から作りだしたものだということである。長い鰭をゆらゆら動かしている姿を、僕は悪いけれどあまり美しいとは思わない。それに珍しいからと言って、「蘭鋳(らんちゅう)」とよぶあの金魚の顔から頭にかけてのひどい皮膚病はいかにも悲惨で見ていられない。 新宿でK氏に会った。あの詩人の。うん、丁度いいところで会った。あのね、うちの金魚が皮膚病なんだけれど、いい薬しらない? 僕も金魚はよく皮膚病にやられるということは聞いていたが、治療法は知らなかった。K氏は誰にきいたのか、赤チンをぬってやってるのだそうだ。ぴちんぴちんとはねるのを掌にのせて、筆で赤チンをぬる。てり焼きの魚に醤油をぬる時みたいにぬる。そして水に入れると、その辺の水を赤くしながら泳いで行くんだ、きれいなんだ。
※参考:実は金魚の先祖は、およそ1700年前に中国は長江で発見された突然変異の赤いフナ。 西暦3世紀頃のことで、その後10世紀には宮廷で飼育されるようになりました。 金運をもたらす魚として「金魚」と名付けられます。 そう、金魚は偶然生まれた姿を人間が世に留めた、自然界には存在しない魚。 2024.12.08 記す。
★くろぐわい P.142 八九年ほど前に、高校時代からお世話になっている渡辺一夫先生をお訪ねした時、これを持って行きませんかと言われ、くろぐわいを頂いて来た。その名のとおり、黒いくわいであるが、すぐには芽が出そうもない。確か、先生の郷里の新潟から届いたものらしかった。僕は戦争の真最中に、弥彦線の燕というところにおられた先生をお訪ねし、三日ほど御厄介になったことがあるので、そんなことも思い出しながら、くろぐあいを頂いて来た。
今の家へ越して来て間もないころだったが前に住んでいた人が置いて行った大きな甕(かめ)が庭にころがっていたので、それに泥と水を入れ、僕は十個のくろぐわいが少なくも三十個ぐらいになる夢をちらっと見ながら埋めた。筒型の葉が甕いっぱいに茂ったのはそれからどのくらいしてからだっただろうか。 僕は渡辺先生にそのことを報告したが時期を見はからって根茎の先にあるはずの塊茎を掘り出すことしかしなかったため、いつの間にカこの植物も絶えてしまった。しかしともかく栽培をしたことがあるので、くろぐわいについては知っているような口をきくけれど、実際にはその味を僕は知らない。 ※参考:クログワイは秋になると、地下茎の先に直径 1cm ほどの小さな塊茎(いものようなもの)をつくりま す。 この塊茎は食用になり、かつては飢きんで食糧難に陥ったときの貴重なでんぷん源でした茹で て三杯酢で和えると美味しいと言い、生食も OK です。
★鯔(ぼら) P.143 僕は釣をしたことがない。したがって鯔を釣りあげて悦んだこともない。けれど秋の海岸で、漁師が夕方もどって来るのを待って、その晩のおかずを買おうと思っていると、舟いっぱいに鯔ばかり積んで来たことがある。それならこっちも鯔ばかり食べてやろうと腹をきめたが、大きなやつを五尾食べたらといったらそれは法螺(ほら)の方かも知れないが、赤い夕陽の中でうんと食べたことだけは確かだ。 鯔のお臍を食べたことあるかい? こいつを食わなくっちゃあ話にならない。こりこりしていてね。そんなことを言って、腹をさきながらお臍と称する算盤玉みたいなものを食べていた人がいたが、あれは胃である。それがかたいのは胃痙攣を起しているのである。
※参考:子供のころの故郷では、長浜という釣り場では海岸の沖百メートル辺りに鯔の監視櫓を設けて、鯔漁をしていた。 ※参考:鯔の由来 つくりに使われている甾という漢字は「あぶら」を意味しており、鯔の幼魚のお腹には黄色い脂肪が詰まっていることから魚へんに甾で「鯔」と書くようになったのだとか(諸説あり)。 鯔のほかにも、鰡や鮱と書くこともあります。 2024.12.18 記す。
★つわぶき P.144
つわぶきという名を覚えたのは中学二年の時である。植物の発生から教えられたのではない。
僕はそのころサッカーをしていた。それも試合の最中だったが、球を蹴りそこね、体は宙へ飛びあがり、背中から落ちた。すぐ立ちあがろうとすると左側の膝に全然力が入らない。びっこを引いてやっと家に帰り、自動車で病院に行った。「オスグッド・シュラッテル氏病、左膝関節外傷性水腫」という病名を与えられた。一年も足を思うように使えなかったので、それで何十年たってもそのややこしい病名をわすれない。 絆創膏や包帯で足をぎりぎり結(ま)かれ、少しでも曲げると逆戻りしてしまうと言われていた。それでもいつか休みの日に、友だちの家まで遊びに行った。そこには、もう八十近いおばあさんがいて黄八丈のもっこり着ていたから寒いころだったと思う。 そのおばあさんに、足のそういう怪我にはこれが一番効くと言って帰る時につわぶきを一株持たされて来た。僕はそれをすぐ庭に植え、どういうふうにしていいのか分からなかったので、つやつやしたその葉をとって膝にあてておいた。誰かにきいて、あぶってからあてたように思う。効果がありそうににも思えなかったが、友だちに効目があったようにおばあさんに伝えてもらった。 そしてすっかり忘れた頃、秋の虫の声の中に黄色いつわぶきの花が咲いていた。 ※参考:日本薬理学界の記事:「ツワブキ」主な使い方として、打撲、おできなどの腫れもの、切り傷、ものもらいに対し、生の葉を炙り軟らかくなったらちぎって患部に貼ります。 ※参考:ツワブキ(石蕗)という名前の由来は、葉に艶(つや)があることから「つやぶき」と呼ばれ、転じて「つわぶき」になったと言われています。 また、漢字で石蕗と書かれるのは、葉や茎が蕗(フキ)に似ていることと、海岸の岩や石などの間に多く自生していることに由来しています。 ※参考:解毒,健胃作用があり,フグやカツオによる食中毒に根茎の煎液や葉の汁を服用する。打撲や出来物,湿疹などに生の葉を火にあぶって柔らかくしたものや,青汁を患部に貼る。また,痔には葉の煎液で患部を洗ったり,煎液を服用したりする。観賞用として植栽され,若い葉柄は食用になる. 2024.11.11 記す。
★くろほうじゃく P.145 赤い煉瓦を買って、花壇のへりをちゃんとした。これまで焼夷弾のに一部分らしいものを使っていたが、煉瓦にかえると花壇もひき立って来る。額縁のようなものである。いまは少し赤すぎるけれど、一二年たってほんのり苔が生えるころには一層わが庭も寓話風に整うだろう。 その花壇には、今、段々と花は少なくなり、天国の青を若干にじませた朝顔と、はなうりくさがまだまだと言った顔をして咲いている。そのはなうりくさの、少し受け口の花へ、くろほうじゃくは毎日出勤しては蜜を吸っている。体が太くて、海老の尻尾みたいなものまでついている割に翅小さいので、のんびり動かしているわけには行かない。音を立てている。同じ仲間のすきばほうじゃくは、大層手回しがよくて、蛹から出るとすぐに鱗粉をふるい落してしまう。こうしておけば、粉をふりおとす心配はないし、いやがられることも少ない。
はなうりくさは紫の顔をくろほうじゃくの方へ向けて待っている。彼は綿棒のような口を花の喉に突込んで、ルゴールをぬってやっているようだ。
君のは少しひどいよ。扁桃腺が大分はれているからな。お次は。もっと大きくあけて。 この蛾は日に何人の風邪ひ引きを往診する名医なんだろう。 ※参考:ハナウリクサ(花瓜草)1年草 インドネシア原産。草丈20~30cm、茎は4稜で細毛が生え、葉は対生し長さ4~7cmの卵形で先が尖り、葉脈が良く目立ち縁に鋸歯がある。花は淡青色の筒状で5深裂し、花冠の直径約3cmで葉腋に1個ずつつけ、側弁と唇弁の先は濃紫色、唇弁の中央に黄色の班が入る。白、ピンク、黄など色々ある。別名トレニア。花期は8〜10月。学名は、Torenia fournieri ※参考:スキバホウジャク:島根県レッドデータブック情報不足に指定されており、希少な種。 長い口を伸ばしホバリング吸蜜をするクロスキバホウジャク。 ハネは中央部分が透明だ。 スカシバやホウジャクのなかまは太い体でたくみに空を飛び、さながら「空飛ぶエビフライ」である。 ヒメクロホウジャクやホシホウジャクと違い、スキバホウジャクは花を前足でおさえながら吸蜜をしており、お行儀がよいようだ。 別種クロスキバホウジャクとよく似ているが、後翅の付け根がオレンジ色であることからスキバホウジャクと思われる。 ※参考:クロホウジャク(黒蜂雀):鱗翅目の昆虫 スズメガ科 北海道~屋久島、沖縄、台湾、中国、韓国、他に分布 方言名:ハベル スズメガ科なのでジャク(雀)、ホバリング(空中停止)もできる蜂のような飛び方をするのでホウ(蜂)、全体が黒っぽいのでクロとなってクロホウジャクという名前になったと思われる。 2024.12.21 記す。
★おなもみ P.146 おなもみの実が秋になると目立って、何ということもないのにとって来る。ちくちくする針がのび、その先がちょっと曲っているところがまた妙に面白い。何にすることもないのに、ほとんど毎年必ずとって来て机の上にころがしておく。
去年はこれを写真によった。古道具屋で、極く小さい写真機を買った。それで、おなもみの実を撮ったらよくとれた。一フィートのところから撮った。魚の骨を主にし、そこへこのp実をばらまいて、芸術的な構成を考えたわけである。写真屋がひどく感服していた。しかし写真屋は大概感服する。けなしたら次にはもう現像も何もたのまない。 それで今年もおなみの実にあったのであるが、それが何と、アクセサリーを売る店のガラス戸棚の中に並んでいた。売物かとたずねたら、一つ四十五円だと言った。こんなものをつけている婦人にうっからさわって、離れなくなったら大変である。 ※参考:オナモミという名前は、「雄なもみ」で、「なもみ」はひっかかるという意味の「なずむ」に由来すると言われています。 オナモミはキク科の植物で、果実は指先ほどの大きさの卵形で、トゲが全体に生えています。トゲの先端がカギ状に曲がっていて繊維にからみつく性質があり、ひっつきむしとも呼ばれます。 オナモミはアジア大陸が原産で、日本には古くに侵入した帰化植物と考えられています。しかし、近縁種のオオオナモミやイガオナモミの繁殖の増大や、自生地の宅地化などにより減少が著しく、環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧II類に指定されています。東京都区部および北多摩では絶滅状態と推定されています ※参考:オナモミの有毒成分はカルボキシアトラクティロシドと同定されており、細胞内での酸化的リン酸化とミトコンドリア膜におけるATPの転移を阻害することが報告されています。この中毒の特徴の一つである低血糖は、この酸化的リン酸化の脱共役と関連しているものと考えられています。オナモミによる家畜中毒のほとんどは、成長した植物ではなく地面に落ちて発芽した実を食べて起こることから、中毒は多くの場合早春に起きています。オナモミは食するよりも秋から冬にかけて採取した果実を耳飾りにした方が良いかもしれませんね。 2024.11.20 記す。
★つるこけもも P.147
信州霧ケ峰にアイヌ伝説の小人コロボックルという名をつけた小屋が建ち、招かれて行って来た。この高原も秋になってから雨が降り続いて、からまつも金色に光ってはいなかった。草刈りのすんだあとだったせいもあるが花はほとんどなく、もうその草原は雪を待っているような色つやだった。
想えばこの草原には、初夏のきはげはが頻りに羽化する日の記憶や、つきはんみょうが飛び立ってはとまり、筒鳥がねむく鳴いていた日のこともある。そして冬の、零下十一度の朝のこともある。
小屋の主人はまだ若いが、もてなしの一つとして、つるこけももの実を下の湿地からとって来て漬けておいてくれた。その一つは灰皿のへりに飾りとしてのせてあった。まだ漬けてから日が立っていないので、すっぱくてだめだといったが、つぶつぶの赤の、赤黒く熟れて甘いのや、片面が白く、はじらいの色を残しているのや、僕は一つ一つを口に入れながら古い山旅でこの実を食べた思い出をたどった。そしてなお手のひらに幾つぶかをもって小屋の外に出た。霧がいっこうに動かない。褐色の斜面を見ながら、まだ知らないスコットランドにいるような気持になった。日本のつるこけももの実を思い出しながら、クランペリーの実を食べているような……。
※参考:ツルコケモモ(クランベリー)という名前の由来は、鶴(crane)のベリー(berry)です。これは、ツルコケモモの小さな実が鶴の好物だったことや、花の形が鶴のくちばしに似ていることに由来しています。 また、北米の湿地帯に自生していることから、「漂う果実」を意味する"cranberry"とも呼ばれています。 ツルコケモモは、つるうめ科の常緑のほふく性低木で、地際を這うように生長します。果実は小さくて丸く、甘酸っぱい味が特徴で、ビタミンCやフラボノイドといった抗酸化物質を豊富に含んでいます。 ツルコケモモとは - スイーツモール クランベリー(ツルコケモモ)とは? クランベリー(Vaccinium macrocarpon)は、つるうめ科の低木性植物... 高さ約10〜20cmの蔓性の植物で、小さな実は熟すると鮮やかな赤色になります。 この小さな実が鶴の好物だったことや、花の... ※参考:クランベリー(ツルコケモモ)の栄養 クランベリーはポリフェノールやキナ酸、ビタミンCなどを含有していると言われています。 ポリフェノールやビタミンCは美肌効果が期待できると言われている栄養素です。 2024.11.19 記す。
★しめじ P.148
そりゃ大変だ。そう言って専門家でない僕の苦労を慰めて下さる方もいる。しかし、はっきりしないと気持ちが悪い。たとえそのために十人の友だちを怒らせることがあっても、気になることをそのままにしておくわけには行かない。 つい四五日まえに中学生が新聞紙に包んだものを持って来て、これ食べられますかと言う。帆足計さんの息子さんだ。あけて見るとしめじだ。においをかいでみてもしめじだ。けれども大丈夫ですね、毒ではありませんね、と念を押されると僕は自信がなくなる。持っている限りの本でしらべてみると似たようなものが沢山あるし、結局、食べられると思うけれど気味が悪いと思ったら絶対に食べないで、と言うより仕方がなかった。 その坊ちゃんが帰ってからも気になるのでしらべていると、大正十年十月八日、猛毒のタマゴテングダケをしめじと誤って食べて一家四人全部死亡した例などが出ていたし、翌日の新聞にもきのこの中毒の記事が出ていた。青味がかって毒々しいそのかさの色が目にちらつく。それはほんとうのしめじだったらしく、そこの一家の元気なことを知らされたが、きのこの鑑定だけは恐ろしくてもうお断りだ。 ※参考:しめじに含まれる食物繊維は、整腸作用があり便秘予防に役立ちます。 また、血糖値の対策にも有効です。 食物繊維は便の材料となり便通を促す作用や、善玉菌が増えるのを助ける作用があり腸内環境を整えます。 また食物繊維には糖の吸収を穏やかにし、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあります。 2024.11.23 記す。
★栗の虫 P.149 風が吹き栗の実が落ちる。僕の家の木ではないがこっちへ向って落ちて来る。ゆでて食べようとすると蛆のような虫がいる。せっかく硬い皮をむいたのに残念な気がするが、そのこと自体が栗を食べることにつきもののようである。むしろ、虫食いでない、完全なものにあたる方が少なさそうで、半分腐っているとか、かちかちになっているか、さもなければ虫がいる。それは拾った栗ではもう当たり前である。 栗の害虫にはいろいろの種類があるが、実の中におさまりかえっているのはクリミガと、いま僕の食べようとしていたものから出て来たクリシキゾウムシの子供である。大人になると鳥のしぎのくちばしのように長い口を持つ。これで若い実に穴を深くあけ、卵を産みつけ、幼虫は人に見つけらなければ栗の実とともに地中に埋って冬を越し、翌年成虫となって現われるという仕組みである。
※参考:クリの名の由来は、実が黒褐色になるので「黒い実」→「黒実(クロミ)」→「クロ」と呼ばれるようになり、これが転じて「クリ」となったという説が有力なようです。 2025.01.07 記す。
★ほととぎす P.150
ところでこの花の方のほとぎすの特徴として、三つの外花被の下の方に、丸いふくらみがあるが、その中にたまっているはずの蜜をなめてみようとする時、薄紫のぼちぼちが、何か伝染病にかかった皮膚のように見えて来て、蜜の味をためすこともためらってしまう。ちょっと離れて、ちらっと眺めるのには大変きれいな紋様も、なめて見るほどに近づけると、ぞっとするようなものがある。五六メートル以上近づくとがっかりする着物の紋様だってあるし、そういう種類の人間もいる。 英名は Toad-Lily という。つまり、そのまま訳せばヒキガエル・ユリである。せいぜいびっき百合ぐらいにしか訳せない。外国でも、そんな名前をもちいながら園芸植物として栽培されているが、名前のつけられ方によって、花の顔つきも変って来るはずである。
★桧葉やどりぎ(ひばやどりぎ) P.151 三宅島の阿古小学校の先生が、この春先から四年の生徒といっしょに島の植物を採取し、謄写版で百種の植物を図鑑にされたものを送って下さった。 この先生も植物を特別に勉強された方ではないらしく、苦心して調べ、それがていねいに整理されている。今後も続けて行くということだが、ほとんど実物を丹念に写生し、またその記載が子供たちのために面白く書いてある。「ふじなでしこ……さびがはまにたくさんあったな」というふうに。 こういうふうに書いてあると、子供たちもああそうか、あれかと思う。そして名前を知りたいと言ってはさんであったのが、この桧葉(ひば)やどりぎだった。
島の人は椿の葉が化けたと言っているそうだが、さかき、いぬつげその他にも寄生するもので、僕もはじめて見ることが出来た。紀州の高野山や名古屋の長禅寺などでは、霊木として、いろいろの伝説を結びつけているらしい。
島の人は、椿の葉がいったい何に化けたと思っているのだろうか。かにさぼてんと見る人もいるだろうし、その名のように檜の葉とも見える。島の方言には「つばきひじき」というのもある。寄生されている以上、もとの木は害をこうむる。これは動物でも、僕たち人間でも、また国のようなものでも同じことである。 ※参考:ヒノキバヤドリギはツバキ科(ヒサカキなど)、モチノキ科、モクセイ科などの常緑樹に半寄生(自ら葉緑素を持ち光合成を行うことができる)して、水や養分を ...含まれない: 2024.11.16 記す。
★べっこうばえ P.152
今すぐ出してやるから、ちょっとのあいだこのガラスのびんの中へはいってくれたまえ。君のことはよく知っているつもりなのだが、それが危険なのだ。翅の点々のそいの位置をまちがえてはいけないし……。
秋が深くなって、今日はほんとうにいい天気だ、何だかこんなことをしているのももったいないような午前、僕はべっこうばえをガラス窓の内側に見つけることが多い。去年も一昨年も、その前も、内側にいる以上、いつか、どこからかはいって来たはずである。 日があたっていると、そのべっこう色がいよいよ明るく暖かにとろんと光り、胸を滑られせては時たま立てる羽音が、ミルクをかける前に軽く押しつぶすコーン・フレークの音である。 小春日和のこの日あたりに、べっこうばえはガラスの外へ出ようとしているのだろうか。どうもそれが毎年のことなので、彼がわざわざ好んでこんなところに暖まっているように思われる。 ここから、ほら、見てごらん、垣根にそって、蜂やあぶの行列だ。こんな日は今年はほんとうに珍しい。それで、あんなにせつせと働いている。 そんなことを言ってやっても、べっこばえは仲間に加わろうとはしない。窓を開けても飛んで行かない。 ※参考:由来 べっこうは、「ゆべす」とか「えびす」とも呼ばれています。 「べっこう」とは、色や形がべっ甲の「かんざし」に似ていることから、そう名前がついたと言われています。 お正月やお祭りの時に、よく昔から食べられている富山県の郷土料理です。 2025.01.09 記す。
★旅人のよろこび(たびびとのよろこび) P.153 伊豆の天城山を歩いた。
日が暮れてからしばらく懐中電灯で道をたどっていたが、気持ちのいい山頂の草原を見つけてぐっすり眠った。夜半の雨に冷たくぬれたが、翌日は薄陽の秋の中を海へ向ってくだる道だった。木々の落葉がしっとりしていた。花のないさびしい小径(こみち)だったが、僕は突然うれしいものを見つけた。それは初秋の白い花をすっかり落して、銀色の羽毛をいっぱいにつけている仙人草だった。 少しひからびた西瓜の種子に、品よく赤と金とをさらりと塗ったような実から、強い風の日に飛び立って行く最後の夢を託した羽毛が、いじらしい巻毛だった。 宮沢賢治の「おきなぐさ」のように、自分を舞いあげ運んで行く風が吹いて来るのを、首をのばして待っている姿だった。
2024.11.24 記す。
★猩々木(しょうじょぎ) P.154 クリスマスにちなんだ花は沢山あるが、その中の一つに猩々木がある。ポインセチアと言った方が通りがいいかも知れない。
そんなにして僕のためにとっておいて下さった花なら頂にあがらなければならない。熱があって赤い顔をしていても、要らないなどとは言えない。電線が風に唸っていた。それから犬が何匹も吠えていた。 その晩かかえて来たのが鉢植えの猩々木だった。赤い花ではなく、枝の先の赤い葉を、くるんでくれた紙の包みの上からちらちらのぞかせながら、僕はがたがた寒さにふるえて帰って来た。多分僕の顔は猩々(しょうじょう)のようだったにちがいない。それから二週間床についていながらこの花をしみじみと眺めた。小さな青蛙が、何匹も集って会談しているように見えた。何を語り合っているのだろう。青蛙たちは信心深いかどうか知らないが、それは、キリストがべタニアのマリアから猩々木を貰ったかどうかを議論している姿にも見えた。 ※参考:ポインセチアという名前は、アメリカの初代駐メキシコ大使であるポインセット氏の名前に由来しています。ポインセット氏は、メキシコで自生していたポインセチアを見つけ、 ... ※参考:東南アジア原産の一年生草本で、草丈は50〜70cm。江戸時代から明治時代中期まで盛んだった藍染は、このアイの生葉を刻み、発酵させて加工した藍玉を用いた。これは葉に含まれるindicanが加水分解および酸化をうけて青色染料のindigoとなる。また、薬用としては、果実を藍実(ランジツ)と呼び、解熱薬や解毒薬とする。 2024.11.14 記す。
★フランクリニヤ P.155 どうもこの頃、気にかかることが、たまる一方だが、このフランクリニヤという木が、現在もなお健かに、秋になると花を咲かせているかどうか、一体、だれにどういう手続きで訊ねたらよいのだろうか。 つばき科のこの木を、ジョージアの森で発見したのは、一六九九年アメリカに生れたジョン・パートラムという人である。彼は農業のかたわら独学で植物の研究をし、毎年秋になると方々の野や森へ採取に出かけていた。そこで一本の見なれない木を発見したというのである。 この人はベンジャミン・フランクリンと親しかったので、自分の発見した木をフランクリニヤと名づけた。豪華な花を咲かせるこの木は、それ以来、何年たっても、どこからも発見されないということなので、世界中で一本しかない木である。原木から二三本は分けて移植したようだが、それもどうなっているか分からない。
2024.11.14 記す。
★伊勢海老 P.156 伊勢へ行ったのは、冬のことで、途中でも雪が降り、滞在中にも大雪が降って寒かった。
僕はこの大海老が、海底の岩かげで威張っているところなどを想像することは出来なかった。何とかして小さくなることをねがい、鬱々として不幸な夢を見続けている様子しか浮かんで来なかった。 それで、この海老がつかまったことを、そしてこうして僕にその一部分を食べられていることを、それほど気の毒とは思わなかった。 海老の脳みそがどんなところにあるのか今は分からない。けれども、ぴりっとした何かを食べた時、僕の口の中へ、この海老の理想像がはいって来た。 それは彼の幼年時代の姿だった。 ※参考:「いせ」の名が付いた由来には威勢(いせい)がいい海老 が 「いせ海老」と呼ばれるようになったという説や、伊勢湾・志摩半島で多く獲れたことからその名が由来しているといわれています。 伊勢えびは角や足がとれないように丁寧に網から外されます。 ※:平成元年8月17日(木)United State America Main State Bar Harbor へ旅行:N.Y. City→ Boston→ Bangor→ Bar Harborへ LaGuardia Air から旅行。 ▼無事目的地に到着して、The Holiday Inn に止宿。(Bar Harbor Regency)リゾートホテルに類する。部屋からの海の眺望は素晴らしい。2:00過ぎても Swimming Pool で泳いでいた。テニスコートも2面ある。 平成元年8月18日(金) 夜中3時に目が覚めた。家内が蕁麻疹(ロブスターがあたったのだろう)、持参のパンシロンを飲む。 ロブスターの食感は弾力がつよくプリップリ、一方伊勢海老はロブスターと比べると食感は柔らかめです 2024.12.19 記す。
★ひげがら P.157 僕はこの鳥をまだ目撃したころがない。本で見ると、迷鳥として一九二〇年十月二十二日に、山形県で、ひがららの雄を一羽とったという記録があるだけなので、その後にどこかへ現われたことがあるにしても、この実物を見ていないのはそう恥かしいことではない。
最近会った人が、安達太郎山の表側と裏側とでは山雀(やまがら)の顔付がちがって、裏の方ではひげが生えているそうだが……という話をしていた。僕は、そのことを知らなかったし、案外有名なことかも知れないと思って、鳥の本をかなり詳しくしらべたが、そんなことは出ていなかった。ひょうっとしたら、ひげがらのことかと思ったので、その方をしらべると、迷鳥として一羽つかまえただけだと書いてあったわけだ。
ひげがらのひげは、正当なひげというのではなく、「黒色鬚状の羽毛」である。僕は一人の、鬚をたくわえている友人を思い出した。僕よりはずっと若い、しかも独身者である。そして、彼自身の気持は僕にも分からないが、彼の気持を分かろうとして煩悶している周囲の人たちの気持が変に分かって来た。 安達太郎山の裏にすむ山雀よ。君がほんとうにひげがらでないのなら、僕はやはり煩悶しなければならない。 ※参考迷鳥:きわめてまれにしか渡ってこない鳥をいう。(野外観察ハンドブックー① 山野の鳥 <財>日本野鳥の会:P.7) 2024.11.13 記す。
★ごぜんたちばな P.158
夏の山の、涼しい樹林に白い花を咲かせるこのごぜんたちばなのことを、なぜ今ごろ書くのか。
十一月初旬、冬を出迎える気持で、尾白川をさかのぼって甲斐駒に登った。尾白渓谷の紅葉は楽しかったが、幾つもの大きな滝を一つ一つ高巻きして登るので時間がかかり、谷を離れる間に日が暮れて野宿をした。その翌日、二千二百メートルをさかいに降った雪は、頂上付近の幾つもの岩峰をすっかり冬気色にしていたが、その冬と秋とのさかいに、ごぜんたちばなの真赤な実が一本の茎に一つ二つずつ残っていた。丸く集って、にぎやかに残っているものはどこにも見当ラなかった。 おそらくその多くは、自分の使命を感じて、落葉や苔の下にもぐり込み、さも勿れbあ小鳥たちに運ばれて行ったのだろう。だが今なお葉の先に、色あせることもなく、すべてx果実の持つ魅力を失わずにいるものは、みんなつまさき立って首をのばし、舞い落ちる雪片を頭上にうけることさえ期待して、あどけなく白い季節の到来をながめていた。 僕は雪の舞い落ちている中へ入った時、この新しい雪をただ眺めていることは出来ず、飛びついて受けとめるようなことをした。 ※参考:ゴゼンタチバナ(御前橘)という名前は、石川県の白山の最高峰である「御前峰」で発見されたことに由来しています。また、カラタチバナのような赤い実をつけることからこの名前が付けられました。、 2024.11.13 記す。
★とわだかわげら P.159 新雪の甲斐駒に登ったその日、夕方五合目の小屋で荷物をととのえ、出発をしたのがもう夕方だったので、一時間も歩かないうちに真暗になって、ランプのあかりで降りて来た。その尾根はところどころ痩せていたし、梯子がかかっているところもあり、のんきな夜の山径(やまみち)ではなかった。
そしてはじめて水音をきいたのは、よほどたってからだったが、まだ千メートルのところまでは来ていなかった。喉はかわいていたが、荷をおろしてコップを出すのが面倒だったので、おそらく夏の登山者がすてて行ったつぶれた空罐でその水を飲み、ちょっと気になるので、罐の底にのこった水を灯りに照らしてみると、二センチ足らずの、気味の悪い虫がはいっているのを友だちが見つけた。これは羽を持たない十和田かわげらである。夏の山でその幼虫を見たが、成虫を見つけるまで、僕のノートに余白をあけておいたものだった。
陣羽織のような背板が、のびた爪みたいにとび出していて、何かにひっかかるとはがれてしまいそうだ。冷たい水にひたって、これからは厳しい冬だのに、この虫は隠者を気取ってゆう然と歩いている。静かな山にひっそりとしていいかも知れないが、いったいこの生命」は何によって守られているのだろうか。、 ※参考:1931年に新種として記載された際の完模式標本の採集地が十和田湖和井内であったことからトワダカワゲラと命名された。 カワゲラ目の中でも最も原始的な形態を持つ種といわれ、成虫になっても翅を持たない、幼虫期には腹部末端に冠状の鰓を持つ、などの大きな特徴を持つ。 2025.01.08 記す。
★じょうびたき P.160
専門家でもないのに、花や小鳥のことをたずねられことが多くなると、妙に勘が働くようになり、「このごろ庭へよく来る鳥で……」とそこまで聞くと、じょびたきだなと分かってしまう。「それで喉のあたりがちょっと黒くて……頭はグレーで……」とこちらから言うのは失礼だから、はてなと鳥のように首をかしげながら、その人がどこまで細かに観察をしたかを聞くことにする。井之頭にある僕の家を訪ねてくれる小鳥も、毎年減って行くばかりだが、じょびたきは今年もやって来た。
ああこの枝だったな。この山椒の実だったな。彼は懐かしそうに尾をうごかしている。そしてあの小さな体の中のどこかに、火打石がしまってあるように、カツカツという音を立てる。翼の白い紋が目立つので、紋付鳥と呼んでいるところもある。なかなか義理 がたい鳥で、こうして紋付を着てあいさつにやって来る。 ところが、どういうものか彼は奥さんを同伴してやって来ることはない。家内はどうも着物がよくないもんで、御挨拶に出たがらないのでございます……と言ってべこべこ頭をさげる。 じょうびたきのお土産は毎年、からっと晴れた冬の、あの胸毛のようなやわらかいオレンジ色の日ざしである。 ※参考:名前の由来である「尉(ジョウ)」は銀髪を意味し、「鶲(ヒタキ)」は「火焚」とも書き、鳴き声が火打石を叩く音に似ているところから名付けられました。 雄は頭が銀髪のような銀白色、顏が黒色で腹部が赤茶色、翼の一部に紋のような斑点があるのが特徴です。 20224.12.09 記す。
★くちなし P.161 戦争の末頃から、しばらく北国に移り住んでいた僕は、再び東京近郊へ戻って来た時に、なんとなく久し振りに見る懐かしい草木にめぐりあうのがうれしかった。
夏のはじめに甘い香りを夕やみの靄に漂わせていたくちなしは、今、かたい果実を結んでいる。緑の線をオレンジ色のふくらみ外側に残して、白い花からどうしてこんなきれいな色が出るのかと思うように目立っている。それは、どこか遠い国の、ずっと昔の町に、ぽつんぽつんと立っている街灯のようにも見える。
この実を見て思い出すのは、戦争がやっと終わってから、行列をして受け取って来た配給の白い布を、この、実で黄いろく染めた時の、なんとなく少しばかりゆとりが出来たと思ったそのよろこびである。飛鳥時代からの染料をつかって、同じ方法で染めてみたその布は実に鮮明な明るい黄色だった。何を作るにもぽっちりばかりその布は、いくらきれいな色に染められても壁に画鋲でとめておくより仕方がなかったが、しばらくして、それはまた幼い子供のエプロンになり、ぼろぼろの着物をかくしてくれた。 ※参考:精神安定,消炎,解熱作用があり,精神不安,不眠,目の充血,鼻血,黄疸,各種の炎症,耳鳴り,声がれなどに用いる.粉末は打撲や捻挫に小麦粉や卵白と混ぜて外用する.漢方処方では,茵蔯蒿湯,黄連解毒湯,加味解毒湯などに配合される。 花は美しく芳香があり,観賞用として植栽される.新鮮な花弁は酢と醤油で煮て食べる.乾燥して茶に混ぜて香り付けにもする.果実は黄色着色料として沢庵漬,栗きんとん,菓子類の着色になる. 熊本大学薬学部
★蓑虫 P.162
十二月に入ると、毎年、その年の仕事を出来るかぎり早く整理して、来年の計画を立てるのがたのしみである。その時ばかりは命が三つ四つ欲しくなる。今年の仕事もすまないうちに考えている来年の仕事の一つとして、蓑虫の生活をしらべることがある。
秋に、うちの柿です、案外おいしい柿ですと言って枝ごともらったきざ柿を、僕はもう大分前に食べてしまったが、その枝に三匹のみのむしが住んでいるのを見つけて、そのまま花びんにさしてある。自分のはく糸にぶらさがって奇妙な運動をする。やっぱり時には退屈することもあるのだろうか。それとも、背中が痒いのだろうか。そうかと思うと、枝から出た棘のようにはりついていたりする。柿の枝に棘なんぞはえていないのに、もし棘の真似をしているのら、蓑虫は、小鳥がそういうことに無頓着なのを知っているのかも知れない。ひめみのが幼虫だろうが、僕は我慢してひっぱり出さずに、成虫となる来年の初夏を待とうと思う。と同時に、庭の木にいる十数匹のみのむしにも印をつけ、翅をつけて飛び立つ雄や、一生を蓑の中ですごす雌や、みのむしの姿になって、はい出す子供たちまで、必ず見届け、ノートの数ページを「父よ父よ」と鳴く虫のことで埋めてみようと思う。 ※参考:ミノムシ(蓑虫)は、チョウ目ミノガ科(学名:Psychidae)のガの幼虫。 一般には、その中でもオオミノガ、チャミノガの幼虫を指す。 幼虫が作る巣が、藁で作った雨具「蓑」に形が似ているため、日本では「ミノムシ」と呼ばれるようになった。 2024.12.13 記す。
★やつで P.163 やつでは、あんなに大きな葉をひろげているのに、自分の家にあったかどうか思い出せないほどに、なんとなく庭にある木だ。僕は家の植物分布を一度紙にかいたことがあるので、やつでのある場所も知っているが、多分あったはずだという程度の人が多いいのではないかと思う。今、どこの家でもその雄花、雌花の立派な繖形(さんけい)の花が咲いているが、それも気づかずにいることがある。 花火のような、レースの玉のようなその個性の花が、どんな割合でついているかを気にしているが、僕の見たところでは、はっきりしたつき方はないようである。しかし、全然無秩序というわけでもあるまい。 雌花のほうは、幼いころちぎりとって、投げて遊んだ触覚がなつかしい。これは、そんなふうに乱暴に投げたりするものじゃあなくってよ。こうしてお手玉にするのよ。そんなことを言われながら、僕は自分がちぎり取ったこの玉をどこかの女の手に取りあげられてしまったことがあるような気がする。あるいは昔の夢かも知れない。
※参考:よく見ると、花の形が2種類あります。雄花と雌花が分かれているわけではありません。一つの花が日が経つにつれてその役割を変えるのです。 まずおしべが成熟して花粉を出します。花粉を運んでもらう虫を呼ぶために蜜も出します。この時期を雄性期(ゆうせいき)というそうです。 やがておしべと花びらが散り、蜜も止まります。そして、今まで小さかっためしべが伸び始めます。 めしべが成熟するとふたたび蜜を出して虫を呼びます。花粉を着けてもらうためです。この時期は雌性期(しせいき)と呼ばれます。 このようにおしべとめしべの成熟する時期がずれているのは、同じ花の花粉がめしべに着くことを避けるための工夫です。近親交配をすると性質の劣る子孫ができる可能性が高いからです。他の植物でもよく見られる仕組みですが、ヤツデの場合は形が分かりやすいですね。 ※参考:ヤツデは右上の構造式の化合物を含みます.これはサポニンの一種です.サポニンはシャボン(石鹸)の元の言葉で,薬効として,せき止め(鎮咳),痰を除く(去痰)の作用があり,咳,痰が出る風邪の症状の時に,乾燥したヤツデの葉 5-10gを水約500 ccで約半量まで弱火で煎じ(約30分),滓をこし去り,煎液を3回に分けて服用します.また,煎じた液でウガイをするのも効果があります.外用薬で,乾燥した葉,約50-100gを布袋に入れ煮出し,その煮出した液を風呂に入れ入浴剤として用いると,リュウマチ,腰痛等に効果があるといわれています. サポニンを含むものを沢山摂取すると毒性が出ますので御注意下さい. 熊本大学薬学部 2024.11.19 記す。
★おおひめぐも P.164
廊下や天井や軒先の蜘蛛の巣は根くらべのようなもので、払っても払ってもすぐに張られる。相手はこれが商売なんだからとてもかなう訳はない。不精者らしく思われないためには、そこに棲んでいる蜘蛛について若干の知識をもっていれば言いわけは立つ。僕が軒先を貸しているのは、おおひめぐもの五六世帯であるが、母屋をとられる心配だけはない。
それに、気をつけていると、これらの夫婦が結婚をする前には、つつましい順序をふみ、雄が少し離れたところから糸を引いて、はっきりした返事が来るまでは雌に近づかない。何という慎ましい、遠慮深いプロポーズだろう。そして成立した結婚後、生れた沢山の卵を糸でていねいに包んで巣にかけてある。さくらんぼうの種みたいだが、いったい今その中で、卵から子ぐもがかえっているかどうかが気になるので、今朝はついに切開手術を行った。 けしつぶよりも小さい子どもたちが、ぎっしりつまって動いている。この中には雄も雌もごたまぜになっているにちがいないが、育ってからのあの慎まさを、どこで教えられるのだろうか。「結婚の倫理」という本を持っていない癖に。 僕はそれをつぶし殺すことは出来なかったので母親とともに、だらしなく張った網の中へかえしてやったが、多分その袋の穴を、専門家らしくつくろうだろう。
※参考:節足動物門クモ形綱真正クモ目ヒメグモ科に属するクモ。 ヒメグモとはもともと小さいクモの意味であるが、そのなかでは大きいのでこの名がある。 2025.01.08 記す。
★ひよどり P.165 晴れわたった日にも、どんよりした寒い日にも、ひよどりの群はよくやって来る。家の前の道路のわきと、その東西百メートルほどのところに欅があって、その間をみごとな波状を描いて、ピッ、ピッ、ピピッと鳴きながら飛んで行く、一度羽を体にぴったりとつけて、紡錘形の、標本にされた時のような姿で、こんなことちょっと出来ないだろうとというように天を突いて行く。
いつも来る群のうち、三羽だけが、どうも僕の家の庭先が気になるらしい。さざんかが咲いているのだ。その蜜をちょっと吸いたいのだ。
灰色の、どこにも派手な色をもっていない鳥だが、木の枝にとまって、何かこそこそ言い合っていたり、くわえて来た木の実をそこでせかせか食べたり、特に、事もなげにすらりと飛び立って行くようすが実におもしろい。なにもしないのにいつも逃げ腰でいる鳥は、こっそり見ていてもさびしくなるが、この三羽は、さざんかの花びらを思う存分つつき散らして遊んで行く。どうせいつかは散る花なんだ。沢山遊んで行くがいい。けれども、ひょっとすると、うまく仕込んだら、自分たちの散らした花びらをひと所に片づけて行くようになりそうに思える。 ※参考:鳴き声は「ヒーヨ! ヒーヨ!」などと甲高く聞こえ、和名はこの鳴き声に由来するという説がある。また、朝方には「ピッピッピピピ」とリズムよく鳴くこともある。 2024.12.13 記す。
★たちばなもどき P.166
黙っている僕の方を四十人ばかりの学生さんがふしぎそうに見ている。いつもそこでは、連続の話ではなく、一回ごとの読切講義というのをやっているので、今日はデカルトかな、まさかカントではあるまいなと学生さんは待っている。僕は哲学の話はどうしてもする気がしない。 そこでこの灌木について五分ほどしゃべって帰って来たことがある。原産地は中国の雲南だが、明治の中ごろ福羽逸人博士がフランスから持って来て新宿御苑に植えたということである。初夏に咲く白い花よりも、橙色(だいだいいろ)のつやつやした冬の実の方が僕には講義準備の戒めを与えてくれるばかりでなく、かわいらしく見える。雪でも降りかかると一段とあたたかそうに見える。雪の山小屋にともる灯のように見える。 ※参考:タチバナモドキという名前は、果実の色や形がミカン科のタチバナに似ていることに由来しています。タチバナモドキの果実は橙色でやや扁平な球形で、ナシ状果と呼ばれる偽果です。 タチバナモドキはバラ科トキワサンザシ属の植物で、フランスから明治時代に日本へ導入されました。トキワサンザシ、カザンデマリとともにバラ科トキワサンザシ属の植物の総称であるピラカンサに含まれます。 ※参考:陳皮(ウンシュウミカン等の成熟果皮)と橘皮は,これまでの経緯や現状の流通状況から考えて本来同じ物であり,効能も同じと考えられる.そのため薬効についてはウンシュウミカンのラベルを参照. その他,果肉をホワイトリカーに付けたタチバナ酒を食膳に飲むと,食欲を増進させる. 京都御所の紫宸殿(ししんでん)には「右近橘」とよばれるタチバナが植えられており,神聖な樹木として神社仏閣の境内に古くから植えられてきた.観賞用として切り枝や鉢植えの樹を利用するほか,台湾では調味料としても使われている. 熊本大学薬学部
★貝殻虫 P.167 蜜柑の皮に、黒い胡麻のようなものがこびりついていることがあるが、あれも貝殻虫で、ていねいにはがすと中に一ミリほどの虫がいる。今日僕が見たのはそれよりも小さい葉蘭の葉についている「はらんながかいがらむし」である。殻を葉からはがし取るとき、剃刀の刃を使ってずいぶん慎重にやっても、なかの虫をつぶして、赤っぽい一滴の汁にしてしまう。やっと取り出して顕微鏡でのぞいたが、肩が凝ってしまって途中二三度体操をする必要があった。
雄雌の別は、殻の色と形で分るが、虫自体は、方々から光をあててみても、その部分はわかりにくい。こんな時にいつも思うのは、すなおに三百年ほど昔に引き戻されて驚かなければならないということである。パスカルがシロンを見ながら無限に小さいものに近づき、そこにもまた一つの宇宙があると言ったあの驚きを知ることである。この小さい虫の足を見よ。そこを血管がとおっている。その中の一滴の血液。そこにまた一つの宇宙がある。……
僕は正常な位置に戻るために、今夜は星空をしばらくながめよう。パスカルも、二つの宇宙のあいだに宙ぶらりんになっている人間へそこから戻るのに、恐らくそんなことをしただろう。 ※参考:カイガラムシの生態を抑えて的確な防除をしたいものです。 アブラムシと近縁の昆虫で、実はセミやウンカと同じ仲間で、国内では約400種類確認されています。 名前の由来は体がロウやワックスで作られた「カイガラ」で覆われ、植物の表面に固着しているからです。 2025.01.08 記す。
★樅(もみ) P.168
僕の家のは、まだ子供の乳母車があってそれにのせて買ってきたのだから、もうずいぶん古くなるが、今は下枝がなく、まことに貧弱な樅である。植木鉢が小さくなって」しまって、苦しくてたまらないのである。 しかしこの木については、毎年毎月ごろに一番成長するかをはかったり、こずえに出る新しい芽の出かたを記録したりした。ある年、新しい葉が巻いて、その中に小さい幼虫を見つけた。これは明らかに害虫であるが、正体をつかみたいので、樅の木は擬制になった。まだ確信をもっては言えないが、恐らく「もみひらたはばち」という蜂の幼虫だろうと思う。六月ごろに羽化するところを見とどけたいと思いのがしてしまう。 こんな樅にはもう何も飾れない。そのやせほそり方からいって、これはキリストの木と呼ぶことにした方がよさそうである。受難のキリストの生れかわりである。 ※参考:モミ(樅)という名前の由来には、次のような説があります。 風に揉み合う様子から「揉む」を語源とする説 美しい萌黄(もえぎ)が語源という説 神聖な木で信仰の対象となっていたことから「臣の木(オミノキ)」が転じて「モミの木」となったという説 モミはマツ科モミ属の常緑針葉樹で、モミソ、トウモミ、モムノキ、サナギ、オミノキとも呼ばれます。厳しい冬でも葉が枯れずに色鮮やかな緑を楽しめるため、昔から強い生命力の象徴とされ、神聖な木として扱われていました。クリスマスツリーとして飾られるのも、このためです。 モミの学名は、シーボルトとツッカリーネによって命名されており、「硬いモミ」という意味です。 ※参考:モミから抽出したオイルは殺菌作用や鎮痛作用があり、咳や喉の痛み、気管支炎、鼻水などの呼吸器系の症状を緩和させてくれます。 また、抗ウィルス作用があるため、風邪やインフルエンザなどの病原菌の増殖を抑制し、予防にもつながります。 2024.11.14 記す。
★鈴 懸(すずかけ) P.169 花が咲いて目立つ植物もあれば、青々としげった時に人目につくものもある。今、街を歩いていると、鈴懸の実が目立ちますね、ときのう来た友だちが言った。一昨年、日比谷公園の脇の街路樹の枝を下している時に、鈴懸の実を沢山広いあつめ、それをぶらさげて音楽会へ行ったことを思い出した。街路樹の手入れをしているような人の中には、大層怖い人もいるので、慇懃に挨拶をしたら幾らでも持って行けと言われたので、いっぱいぶら下げて見たが、スメタナを聴きながら、この実が気になって困った。その実が今も三つ壁にぶらさがっている。
ヘブライ語でこの木のことをアルモン(Armon)という。種という意味だそうだが、その皮のはがれることから出た名前らしい。旧約聖書にもこの木のことが出て来るが日本語訳では「欅(けやき)」とか、「桑の青枝」になっている。 2024.10.31 記す。
★烏骨鶏 P.170
たくさんの年賀状を頂きさまざまな鶏の絵が集ってうれしい。生物学者の水野為武さんからは七種の鶏のそれぞれ名前と大きさの記入された葉書をいただいたし、黄色の色鉛筆でたった一つの卵がころんとしているのや、ちょっとしゃれたものには鶏の足あとだけ描いてあるものもあった。僕も一つ今年は気のきいた年賀状を作ろうと思って公園の鶏舎にニ三度通ったが、うまく行かなかった。
僕は鶏を飼ったことはない。しかしその表情を見ているのは好きだ。なかでも烏骨鶏(うこつけい)の、はでな赤の全くない白黒の色どりが好きだが、これはなかなか見られない。 家からあるいて親戚の家まで二十分、その途中の烏骨鶏を飼っている人がいて、いつもそこであのスパッツをつけた、妙におだやかな歩きぶりを見るのがたのしみである。そこの人は何をしている人か分らない。また、どういうつもりでこんな鳥を飼っているのかも考えられない。しかし、いいものを持っている人である。速水御舟もこれを描いていたと思うが、母鶏として卵を抱くのがうまく、雉の人工繁殖などには彼女も一役かって、雉がせっせと産む卵をていねいにあたためているのを見たこともある。 ひたすら人間に奉仕している多産な仲間のことをどう思っているか、一度感想をききたいものである。 ※参考:真っ白でフワフワな羽で覆われていますが、実は、その羽の下にある肉と骨は真っ黒。 烏骨鶏という名前の由来は「烏」(カラス)のような黒い「骨」を持つ「鶏」だからなんです。 中国では古くから滋養強壮に良いとされ、親しまれてきました。 今回はその烏骨鶏の肉、骨、卵、すべての美味しさに迫ります。 2025.01.09 記す。
★はこべ P.171 冷たい風はさかんに吹いているが、日だまりにはもう春がぽつぽつ見られるようになって来た。今日ははこべの花を見たが、ただ開花の記録としてその名を手帳に記すだけでなく、持ち帰ってしらべた。小鳥のためにも兔のためにも、何度も何度も摘んだことのあるこの草の花について、いったいどれだけのことを知っているか。
はこべの花はしぼむと一度下へたれ下り、実が熟すると再び立ちあがるが、これも僕の発見ではない。なぜそんな特性があるのか、これも答えられない。だんだんあやしくなる視力を補うためには、見るための努力をいっそう重ねなければならないだろう。
しかし図鑑をたよらずに、はこべの花の花弁が十ではなくて五つであることを自信をもって数えられるようになるには、どうも努力や年期のほかに、他のいっさいのことをあっさり忘れられる特性を身につけなければならないだろう。この五つの花弁は底の方まで深くさけているのである。 こういう細かいものを念入りに見ているうちに、息詰まって来るような苦しさに襲われることがよくあるが、それではだめである。無理のない呼吸を続けながら自分の、これらの微小なものに比べて大きすぎることを忘れなければならない。 ※参考:利尿,浄血,催乳作用などがあり,虫垂炎,胃腸炎,浮腫,産後の肥立ちの遅れ,産後の腹痛,母乳不足などに用いる.虫垂炎には奇効のあった例が多く,青汁をたくさん飲む.また,歯痛,打撲傷,腫れ物には生汁を外用する.歯茎の出血,歯槽膿漏の予防には茎や葉の乾燥物,もしくは炒った青汁に塩を加えた「はこべ塩」で歯を磨く.ヨーロッパでもハップ剤や軟膏として皮膚の化膿症や潰瘍に利用される. 春の七草の一つとしてしられる. 熊本大学薬学部
★雪柳(ゆきやなぎ) P.172 雪柳は僕の庭にも一本あるが、近くの公園の池のへりに並んで植えられてあるので、花の咲き具合を見るのには便利である。この小灌木の名は、花が咲くと雪をかぶったようになり、そしてその枝が柳に似ているのでこう呼ばれているのであるが、ほんとうの花の時期は四五月ごろである。花の一つ一つは小さいうえに、それほど特徴のある形もしていない。けれども離れて見た時の、その集団の美しさは、花ということを忘れてたのしい。
園芸の本を見ると、「促成栽培が容易」だと書いてある。花の少ない冬に人の気持を慰めてくれるし、せっかちな人の心をくんでくれるわけだ。しかし、勝手に狂った咲き方をし、気まぐれた人を驚かせることはいいとして、促されて簡単に花を見せるというのは、僕のモラルでは少々戒めてやらねばならない態度である。 2024.11.19 記す。
★標本虫 P.173 ひところ昆虫標本を作ってみたが、手間がかかるし保存がやっかいなのでやめにした。それに、所有したという安心から、何も調べなくなるという傾向さえ生まれて来た。その乱雑にしたままの箱をなにかに使ってやろうと思って整理していた。二箱ぐらい残すことにして、そこへ形も色も完全になっているものを集めた。その時、腕の上を小走りに逃げて行く小さい虫を見つけた。つきつめてみると、それは僕のかつての標本の中にはいなかった標本虫の一種であることが分った。 長い触角を懸命にふって、ややスマートな足でどこかへ逃げて行くつもりなのだろう。その虫は乾燥した動物質を食べて生きている。それは確かにこの虫にとって正しい生き方をしているわけだが、虫の仲間が、残忍な人間の手にかかって針にささって並んでいるのを見ているうちに、そのふくしゅの手段としてもうこれ以外には考えられないというように標本を食い荒しているように思える。
2025.01.09 記す。
★おおいぬふぐり P.174 ことし庭のすみにはびこったおおいぬふぐりは例年よりもきれいな瑠璃色を見せてくれるような気がする。朝日があたりはじめて三十分ほどたつと小さな花が開きそろうが、一つ一つが自分から光っているようだ。この花冠は微風にも落ちやすく、午後になると花の数は減る。小虫が蜜をのんで去る時に落とすものもあるらしい。
またおおいぬふぐりの学名には聖女ヴェロニカの名がついているけれども、これはまたどういうつながりがあるのか分からない。 ※参考:オオイヌノフグリという名前は、その実が犬の陰嚢(いんのう)に似ていることに由来しています。植物学者の牧野富太郎博士は、日本に古くからある在来種「イヌノフグリ」に似た植物に「イヌのふぐり」という意味のラテン語の学名をつけました。オオイヌノフグリはイヌノフグリよりも花が大きく、この名前が付いたと言われています。 また、オオイヌノフグリは、あたり一面に青い花を咲かせる姿が夜空に星が瞬くように見えることから、「星の瞳」とも呼ばれています。英名ではキャッツアイとも呼ばれます。 2024.11.17 記す。
★やにさしがめ P.175 週に一度出講している学校へは、二十五分ほどで玉川上水のへりを歩いて行ける。このあたりもどんどん丘の畑が宅地に変って家が建つが、まだひろびろとしている。そして何度も通る道だから、春から夏にかけて咲く花も、秋にみのる木の実もだいたい覚えている。学校への往きかえりに道草を食う習慣はもう一生なおりそうにもない。 その道の途中に大きな黒松があるが、その樹皮をこっそりはがしてみるのは冬の散歩のたのしみで、僕は今日、予想どおりに一匹見つけた。幼虫であはあるがもう何齢かに育っていて群をなしていない。
これはおおとびさしがめとちがって刺すようなことはしないが、コールタールをかぶったようにてらてらした体は黒すぎて恐ろしい。その上全体ぶつぶつが沢山ある。瞼のない小さな目はぱっちりしているが、その動作は、どうにもねむくてかなわないといったようすである。
松の木に限らず、いま木々の幹は冬を越す虫たちの、午前三時ごろの寝床だろうか。 ※参考:黒くて体の表面に松ヤニを塗ってべとべとしている。 ヤニサシガメの ... 和名の由来もこれであると思われる。 2025.01.10 記す。
★猫柳(ねこやなぎ) P.176
東京郊外の、川とも言えない小川のへりを、僕はまだ霜7どけのひどい土を踏んで歩いた。靴の裏にこってりつく泥を、枯草になすりつけたりするが、踏み込むと靴をとらられそうになる。向こう岸飛び移ったり、またこっちに戻ったり、そうして足をすくわれそうになってしがみついたのが猫柳の枝だ。
たのむぞ、しっかりしていてくれよ。僕はその小川を大きくまたいだ姿になってしまう。そしてまだ手をはなすわけには行かない猫柳の枝には、三角帽をかぶった、白いほわほわの小人の猫の顔が幾つも幾つもこっちを向いている。時々その顔を見合わせて首を縮めているように思える。 両方でお互いにからかいながら、僕は流れに跨ったまま春を感じはじめる。川は澄んでいて、時々、ちょぽん、ちょぽんと何か言う。そして大きく息を吸い込むと、土の中でのびあがってする虫たちのあくびの匂いが入って来た。 ※参考:猫柳という名前は、花穂が猫の尾に似ていることに由来しています。江戸時代まではカワヤナギと呼ばれていましたが、明治以降に銀色の花穂を猫の尻尾になぞらえて猫柳と呼ばれるようになりました。 猫柳はヤナギ科の落葉低木で、中国、朝鮮半島、日本に自生しています。3~4月に銀白色の花穂をつけ、花穂が美しく切り花などに利用されます。 ※参考:①解熱やむくみを取る目的で、乾燥品五~十五㌘を水三百㍉㍑で半量になるまで煎じ、一日三回に分けて飲む。 ②打ち身、腫れ物には、煎じた液をつけるとよい。 ③リウマチなどの痛みを取る目的でお風呂に入れると良い。 2024.11.18 記す。
★狸 P.177 雪の深い山間の駅をすぐ目の前に見おろしている宿に三晩ほど泊まっていた。今年は雪が特別に深いためか、山のけものたちも食べ物をうまくさがせないと見えて、夜雪の中を狸が駅まで食べものをさがしにやって来るそうだ。穴に眠っていても腹が減って無精をしていられないのだろう。 ゆうべもね、十一時ごろに寝ようと思ってちょっと外を見るとね、あのホームの灯の下をちょこちょこかけ足で向うへ行ったり、またこっちの方へ来たりしているのがよく見えましたよ。宿の奥さんは僕に話す。駅員たちも何とかしていけどりにしようと思っているが、なかなかつかまらないらしい。
僕はその姿を見てやろうと思って、夜中に目をさますと、勇気を出して起きてみるが、ホームに並んだ灯のところに、丸く雪の降っているのが見えたばかりだった。
ゆうべも来たようですが。ゆうべはどうだったかね。そういって奥さんはまた、ちょこちょこ狸の話を同じようにする。僕はそれを結局何度きいたことになるのだろう。どうもしまいには、実際に狸の姿を見ることはどうでもよくて、奥さんから同じ銚子で話をきいて、狸のかけているところを想像してみるのが楽しみになっていたらしい。 ※参考:タヌキの語源には、田の怪しい動物の意味で「タノケ(田之怪)」や、田の猫で「タネコ(田猫)」に由来する説。 タヌキの皮は、手や腕を保護する「手貫(たぬき)」に利用することからという説。 死んだふりをして人を騙すところから、「ダシヌキ(出し抜き)」に由来する説。 2025.01.10 記す。
★蠅 P.178
伝染病の研究をしておられる専門の方に、蠅の駆除は今が一番いいのですかとうかがうと、行政的にはそういうことになるのでしょうというお返事だった。行政的に。なるほど、僕なんかついぞ使ったことのない言葉だが、これから使わせて頂こう。蠅と言ってもさまざまな種類がいるので、それぞれの生活史を知っていないと、いつが実際にいい時だと」いえないわけである。
便所の汲取口の周囲の、土の中には蠅の蛹がいっぱいいるということは、たいがいの人が知っているが、実際に掘ってみると、その数のおびただしさには呆れてしまう。もちろんぬけがらもずいぶんあるが、土をふるいにかけると、ちょうど鼠の糞のような蛹がいくらでも見つかる。そして割ってみると、またうじに近いのや、羽の形がぼんやり見えるようなものやいろいろあったが、僕はこれだけは、火に焼いてもあわれとhさ思わなかった。 冬の休みに何か手伝うことはないかとうろうろしている方々に、はえの蛹焼きをおすすめしたい。行政的によいことだと思う。 ※参考:ハエとは漢字で書くと蠅。 虫にカエルを意味する黽という文字を合わせた漢字です。 名前の由来には諸説あり「羽が這う」から変化してハエ。 2024.12.21 記す。
★おおとびさしがめ P.179 『この虫は秋の終りごろから私の家の二階に出入りして、住みついてしまいました。そして私を刺しました。痛みは半日ばかり消えず、赤くはれて、三日ぐらいたってからもお湯に入るとむずがゆく……』 こんな手紙が届いた。ラジオ・ドクターになったような気持になる。それと一緒に、雪の秋田からとどいたのはおおとびさしがめの雌だった。かめむしの類は、よく成虫で冬を越すものがいて、冬の山間の宿に泊まったりすると、のそのそ近よって来ることがある。
家を持ち、その家をあたためることを知っている人間は利口のようだが、その人の住いを澄して越冬の場所にしているこの虫は、もうちょっと余計に利口である。炭が高くとも自分たちには全く関係がないという顔をしている。 ※参考:大きな体で人が近づいても逃げようとする様子もありません。横からみると長い注射針のような口が見えます。オオトビサシガメ Isyndus obscurus これがサシガメの名の由来なんですね。これで刺されたら痛いんだろうなぁ。 2024.12.24 記す
★すずめのかたびら P.180
温室に入れて花を早く咲かせたものは別として、一月、二月に花を見せる野草はもちろん少ない。けれどもいくつかは数えあげられる。青い花が日だまりにいっぱい笑っているようないぬふぐりや、黄色いきじむしろは寒いうちから賑やかである。そのなかでうっかり忘れているのはこのすずめのかたびらである。穂が出ているのはもう秋のことであるが、このごろその小穂から、やっと目に見えるほどの雄蕊がのぞきはじめている。道ばたの、乾ききった土に、この草はうす緑に、早春らしい日なたをもう作り出している。
この緑が春を土の中から誘い出す。しかも静かに、決して大袈裟な創世の動揺もなく、誘われたものは、やがて到ところから滲み出すだろう。 植物で、雀の名をその頭にもつものはかなり多いいが、「雀の帷子」とはどういうところから出た名前だろうか。これは虫眼鏡を片手にさがそうとしても見当たらない。ただ紫を帯びたその穂が、見ているうちに薄い着物のように思われて来ないこともない。寒の雀がこんなものをまとったところで少しも暖かくなりそうもないのに、すずめのかたびらという名は何か善意のおののきが感じられて、五月に咲く同じようなからすのかたびらよりは僕は好きだ。 ※参考:スズメノカタビラという名前の由来は、花穂(小穂)の形がスズメが着るような小さな帷子(カタビラ)に似ていることに由来しています。帷子とは、裏地のない一重の着物です。 スズメノカタビラはイネ科の小型の雑草で、人家のまわりや公園、畑地などに多く見られます。秋に発芽し、冬を越し、早春2月ころから秋までほとんど年中開花します。寒い地方では一年草となります。 2024.11.18 記す。
★ふたもんあしながばち P.181
ふたもんあしながばちは、秋に、それもちょっと日の光が欲しくなるほどの長雨の続いたあと、生垣や物干のあたりから舞いあがる。それが冬のあいだは姿を消し、再び庭へやって来るのは、毎年二月の末近く、それも春らしい空気が、上衣(うわぎ)でもぬごうかという気持を起こさせるころだが、今年は天気続きで、季節に忠実な彼らも、少々頭をひねってやって来たらしい。前ばねをいかめしく合わせるのがこの蜂の一種の気取りらしいが、そんな姿で、日なたの柱をのぼったり、横にはい回ったりしていた。こうしてやって来た蜂のあとをつけてその巣のありかを見つけるのはむつかしいが、僕の家の軒下などにはなく、どこかそう遠くない植え込みの下枝あたりに住んでいるのだろう。
p>
※参考:フタモンアシナガバチは、本州以南では人家周辺で最もよく目にするアシナガバチである。 腹に一対ある丸い紋が和名の由来。 2024.12.25 記す。
★ブーゲンビレア P.182
さむざむとした気持ちで、戦争のニュースを聞いていた頃に、よくこんなような島の名を耳ににした記憶があるはずである。それも確かにフランスの航海家ブーガンヴィーユに関係はあったのだが、この花も彼を想い出さずには眺められない。
熱帯植物園へ写真撮影に行って来た人が、こんなきれいなものがあったんですと言って手帳のあいだから出したのがこれだった。いたかずらという和名がついているが、もともと南米ンおものである。この苞ンお色の薄い赤紫を何と言ったらいいのだろう。数世紀前の洋書のあいだから出て来そうな色である。 彼が帰ってからスライド映写機を開いて、これをスクーリンにうつしてみる。三枚の苞にはさまっている花梗(かこう)のひからびたのも見えるが、この桃色の苞は、天国から追放された天使たちが、自分の心臓の鼓動をかくすためにつかったものにちがいない。それでこんなふうに薄赤く染まったのだろうし、血管もここに見えているこの天使たちは、だんだん図々しく地上の人たちと交わって、しまいには心臓のトクトク言う音をたのしむようになって、このプラカップをすててしまったのだろう。 ※参考:ブーゲンビレアという名前は、フランスの植物学者フィリベルト・コマーソンが発見した植物の友人である船員のルイス・デ・ブーゲンビルに由来しています。 ブーゲンビレアは南米原産のオシロイバナ科の低木やツル性植物で、1760年代にブラジルのリオデジャネイロで初めて発見されました。 また、ブーゲンビレアの和名は「筏葛(イカダカズラ)」で、花の姿が筏のように見えることが由来です。花のように見える苞を筏(いかだ)に、中心の白い花を人に見立てたことからきています。 ※参考:ブーゲンビル‐とう〔‐タウ〕【ブーゲンビル島】 の解説 《Bougainville Island》パプアニューギニア東部の島。地理的にはソロモン諸島に属す。中心地は南東部のアラワ。ココア・ココヤシや銅を産出。第二次大戦中、日本軍が占領。連合軍との激戦地になった。名称は、フランスの航海者L=A=ブーゲンビル(1729〜1811)にちなむ。 2024.11.15 記す。
★こげら P.183 ちょうど一年前の二月にも、ここ谷川岳東側の湯檜曽我川(ゆひそがわ)をさかのぼって行ったが、今度も比較的気温が高く、三種類の雪虫が、さかんに雪の上を歩いていた。四泊の小屋生活をするため、荷物は少し重かったが、ほとんど流れの雪にかくれた川を、小鳥たちが飛び回っているのを見ながら、せっせと歩いた。吹雪のあいだに、こんな暖い日が縞のようにはさまっているので、山の鳥たちも虫や木の実をさがして楽しめる。僕も時々汗をふき、煙草に火をつけるが、一人で歩いているとかえってゆっくり休んで行く気が起らない。
遠雷のような雪崩の音がしていた。 ※参考:名前の由来は、もともとキツツキの名前の由来が、キツツキの古名「けらつつき」からキツツキと変化しており、コゲラは小さなキツツキから「こけらつつき」、日本人特有の短く表すゆえに「こけら」から濁音が入りコゲラと呼ばれる様になったというのが主流です。 2024.12.14 記す。
★一輪草(いちりんそう) P.184 春先の山の麓の暖かそうな草むらに、すっきりと白い花を見せている一輪草を見つけると、誰かが白秋の詩を想い出すだろう。「真実寂しき花ゆえに、一輪草とは申すなり」「……一輪さくのが一輪草、二輪さくのが二輪草、まことの花を知る人もなし」
死んだ魂が花になったという話はこのほかにも沢山ある。 ※参考:全草にアルカロイドのプロトアネモニンやアネモニンなどの有毒成分を含み、たくさん食べると胃や腸が炎症を起こし、吐き気や下痢などの症状が現れる。 葉や茎の汁が皮膚に付着すると肌の弱い人では水泡ができる場合もある。
★いわぎぼうし P.185 四月はじめの後立山の唐松岳では、氷片や小石が真横に飛ばされているような風で、気温もかなり低かったが、八方尾根を下るにつれて、雪の表面に春の表情があらわれて来た。遠くから見れば山々は目も痛いほどに光っているが、次第に雪がよごれ、よごれが浮き出して来る。そのぐすっともぐる水っぽい雪の上を雪虫がさかんに歩いていた。そして解けはじめる雪の上には、すぎ去った年の虫の死骸や、落葉などが諄々とあらわれて来るが、どういうものか、いわぎぼうしの枯れ葉がたくさん出て来る。
山の秋風に、淡い赤紫の花がゆれ、やがて初雪が舞いとぶころにこの葉は枯れながら方々へ飛んだのだろう。一昨年もほぼ同じころに、八方尾根を登りながらこの葉を雪の上で拾いあげたことを思い出した。
もともと強い葉であるが、葉脈も、裏面の細かい横の脈も、長い柄にある斑点もはっきり残っている。なお雪深い山で、春の訪れを告げるものはいろいろあるが、いわぎぼうしの枯れ葉は、この尾根ではいつも印象的である。 ※参考:ギボウシという名前は、つぼみの形が日本の社寺仏閣や橋の欄干に付けられる伝統的な装飾品である「擬宝珠(ぎぼし)」に似ていることに由来しています。また、葱坊主に似ていることから名付けられたという説もあります。 ギボウシは、キジカクシ科リュウゼツラン亜科ギボウシ属(学名: Hosta)の総称で、東アジアに分布する多年草です。日陰でもよく育ち、観賞価値の高い植物です。学名の「Hosta(ホスタ)」は、植物学者であるニコラス・トーマス・ホストの名前に由来しています。 夏の朝に咲く儚い一日花「ギボウシ」 2024.11.17 記す。
★やぐらざくら P.186
花屋の店先に、いま桜草がずいぶん並んでいてきれいだ。花にも葉にもきつい色がなく、春らしいやわらかな生命を見せている。僕は桜草がすきなので、街を歩いていてもうれしいが、毎年、この花にも流行があり、今年はキューエンシスという鮮かな黄色の花が目立つ。明治の末に渡来したもので、牧野富太郎博士が、「やぐらざくら」と名をつけた。花のかたまりの下に、葉が一段つくので、やぐらのように見える。
英国のキュー植物園で、一八九七年に出来た自然交配種である。もとの二つの種類の性質が、街の花屋でも見られる。というのは、並んでいる鉢を見ると、薬でもふりかけられたように、白い粉が茎と葉にかなり目立ってついているものがあるが、これがアラビア原産のいっぽうの親に似ているところである。 片方は茎に赤味があって、白い粉のないもの、これはヒマラヤが原産なので、寒さにはさすがに強い。僕のところにはもう数年前に信州の山で、そこに住んでいた詩人から頂き、持ちかえって植え移した野生の桜草があって毎年桃色の花を見せていたが、今年はどうも消えてしまったらしい。淋しいものである。
※参考:ロンドン南西部のリッチモンド地区にあるイギリス王立の植物園が「キューガーデン(キュー王立植物園) Royal Botanic Gardens, Kew」です。1759年に宮殿に併設された、熱帯植物を集めた庭園として始まり、現在では120ヘクタールの敷地に4万種以上の植物が育ち、700万点以上の植物標本を持つ、世界最大の植物園となりました。
1840年に植物園として開放され、2003年には世界遺産に登録されています。世界各国のガーデンスタイルを見ることができ、年間100万人以上が訪れる人気の観光スポットです。 2024.11.26 記す。
★においすみれ P.187 庭の日溜りに、幾種類かのすみれを集めてみようと思って、毎日胴乱をかついで草原や土手に沿って道を歩いたことがある。そして新しい種類を見つけると、ていねいに掘ってその発見の場所を手帳に記録した。
僕の書く文章は少々甘ったるいところがあるかも知れないが、批評をして下さろうとする方は星菫派(せいきんは)を想い出して下さるらしい。まことに光栄である。批評家は案外語彙が少ないと見えて、同じようなことを何度も言われているうちに、わが庭少々すみれを植えておかないと申しわけないような気持になって来た。星はどうもわが庭に並べて光らせておくことが出来ないので。
ずいぶんすみれがふえてるね。少し貰っていい? そう言って持って行くすみれは大がいにおいすみれである。色が濃くていい匂いがして、何となくつやつやしているのを選ぶ。彼らはそれを庭へ植えるのかどうか知らない。誰かの胸にでもさしてやろうという魂胆かも分らない。それならば、彼らこそ、そのすみれに感謝すべき星菫派でなければならない。 ※参考:V.odorataの地上部⇒シロップにして咳に。浸剤にしてマウスウォッシュに。 V.tricolorの地上部⇒浸剤にして慢性の皮膚症状やおむつかぶれに。チンキ剤を泌尿器の症状に。 生の花と葉⇒サラダの彩りに。 花⇒卵白を十分に説いて塗り、グラニュー糖をまぶして砂糖菓子に。砂糖漬けにしてリキュールの香り付けに。 効能 抗炎症、去痰 成分 サポニン、サリチル酸、アルカロイド、フラボノイド 東邦大学薬学部 2024.11.03 記す。
★雲雀 P.188
雲雀のさえずりは、自分の住む縄張りを他の仲間に知らせるためだといわれているが、僕はこれから市役所へ道路計画をききに行くところだ。近くに杭が打ち込まれ、いろんな噂が立つので気になったわけだが、雲雀のように楽しげに領域を主張できないことが、うっすらとさびしい。 ※参考:漢字では「雲雀」と文字をあてます。 これは体の色がスズメとよく似ていて、空高く舞うことにちなみます。 雲まで届きそうな高い空を飛びながら鳴く習性をじつによく表している名前です。 2024.12.14 記す。
★クロッカス P.189 十日近く山にいて、吹雪のひどい日に下りて来た。ふもとの春めいたぬかるみの道を歩くことをたのしみにしていたが、汽車に乗っても雪は降り続いていた。それでよけいに、帰宅後のわが庭の変化が目立ったが、出かける前に一二輪咲きはじめていたクロッカスの、すっかり咲き そろっているのが、僕に、山ばかりへはいり込んでいないで、少しは庭を見る季節になったことに気がついてくれと訴えているようだった。
二列横隊に並べて埋めておいたものが、幾分横へその葉をのばしているのや、頸をかしげているのやさまざまあって、花は花らしくくつろいでいるのは、見ていて楽しい。台所のガラスもこれで当分黄色に光っているだろう。
僕は古いノートを開き、クロッカス属(さふらん属)とコルシカム属(いぬさふらん属)との相違についておさらいをする。細かいところを実によく忘れている。そんなことをしながら、二十数年前にもらったスイスのカレンダーに、春のざらめ雪の消えて行くへりから順に紫や白のクロッカスの咲き出している写真のあったことを思い出す。「春来りなば……」というドイツ語をその時覚えた。かっきりとした季節の変り目に向って、僕の感動はあまり変化していない。 ※参考:効 用:■ 婦人病予防⇒更年期障害、月経困難、月経過多、生理痛などに。 ■ めまい、頭痛、ヒステリー、不眠症などに。 ■ 記憶障害の改善⇒成分の色素配糖体クロシンは脳の神経細胞に作用し、伝達効率を高める効果を期待できます。 ■料理の色づけ、香り付けに。 ■染色に。 東邦大学医学部 2024.11.03 記す。
★なずな P.190 ここ数日、変に冷たい風が吹きつづけて、丘の畑みちを歩いても、日かげには驚くほどの大きな霜柱が立っている。近よって来る春の足なみが、だいぶ狂っていることは確かだ。それでもいつもなら日だまりには菫が幾種類か見当るころだと思って出かけたが、それは全然なくて、かえってなずなの小さな白い花が目につくのだった。そしてもう花の下のほうには、果実が出来ている。三味線の撥(ばち)のようには、僕には見えないが、優曇華(うどんげ)といわれているくさかげろうの卵のように見えてかわいらしい。
※根生葉(こんせいよう)とは、植物の根元に密集して生える葉のことを指します。タンポポやホウレンソウなどが代表的な例です
★ひらいそがに P.191 たくさん足があるくせに全くかすかな足音を立ててこの蟹は僕の側へやって来た。別段僕に用があるわけでもない。また、物珍しく、変な哺乳動物を見物に来たというわけでもないようである。湘南の海岸へ遠足に出かけた子供がとって来たひらいそがにが、洗面器から逃げ出すことはできたが、海へかえる道も分からず、額にしわを寄せて思案していたのだ。
どうもぱっとしない蟹であるが、一二時間はつき合ってやってもいいと思う。しらべてみるといわゆる爪の板のようなひだと、目を引込めるくぼみの近くの稜線のつぶつぶとすり合わせて音を出すと書いてある。その器官のことを stridulating organ ということも覚える。さてその音が果してどんな音か、またなぜそんな音を立てたくなるのか、僕の額にも蟹の甲殻のような八の字がよる。
やがて蟹は泡を吹きはじめる。その泡がぴちぴちとはじける音が、なにか僕に文句をいっているように聞える。翻訳をすると相当高級な言い回しらしいが、不平を並べていることに間違いはない。摩擦による音楽はどうも聴かせてもらえないらしい。蟹は不機嫌である。 2024.12.23 記す。
★孔雀蝶 P.192 まだ雪の多い山旅を終えて、帰りの汽車の窓から春がすみにうすれてゆく山々をながめていると、急にもう一度雪を踏みたくなった。そう思った時にはもう汽車を降りていたのであるが、重い荷を駅にあずけて、スキーだけを持って消えて行く雪を求めながら、一晩小屋にとまった。高原の雪は今、北の斜面にまだ多かったが、雪どけの水が、そここで、ぼこぼこ音を立てて流れていた。 僕たち三人は、恐らくここを滑るのは自分たちが最後だろうといいながら、執念深くスキーをつけたまま草の上を歩き、泥水の中を歩き、また道のへりにほそ長く残っているこちこちの雪の上を滑った。
山での生活がこんなに長くなり、それにすなおに帰らなかったためか、僕の感情もこの蝶に近づいているように、平静である。 ※参考:開張5.5cm成虫の前翅長は26-32mm。4枚の翅の表側前縁にそれぞれ大きな目玉模様がある。目玉模様は水色の小さな斑点を含んだ黒い大きな斑紋で、その周囲を黄白色の環、さらに外側を黒の環が囲む。この目玉模様は鳥類などの天敵から身を守る効果があると考えられている。また、目玉模様がクジャクの飾り羽を思わせるのでクジャクチョウの和名があり、英名でもクジャクと同じく "Peacock" と呼ばれる。目玉模様以外にも、翅の表側は鮮やかな赤褐色で、褐色の縁取りがある。 一方、翅の裏側は褐色で、翅のつけ根を中心とした同心円状の細かいしま模様がたくさん走っており、表側のような鮮やかさはない。枯れ葉や樹皮に止まって翅を閉じると擬態となり、周囲との見分けがつきにくい。 2024.12.23 記す。
★ほんしろすいせん P.193 山からおそく帰宅して、なにか残っているかと思いながら台所へはいると、 山から夜おそく帰宅して、なにか残っているかなと思いながら台所へはいると、もう大分前に死んだ猫のことを思い出した。台所の床にいつも夜、かつお節のかかったご飯が置いてあったので、それで思い出したのかと考えてみると、そうではなくて、どこからか猫の匂いがして来る。猫の毛の中に、あたたかくほんのりとしているむれ臭い匂いとも違い、もっと露骨な臭さである。 棚の上の花瓶に小型の白い水仙が、そろそろしおれかけたまま差してある。猫のにおいのもとはどうもこの花らしかった。
水仙属(ナルキッスス)の種類もなかなか多くて、このほんしろすいせん(パビラケウス)をさがし出すのにもかなり手間がかかったが、園芸事典をよんでいると、この花は、香りが猫の尿のにおいに似ているので「大ねこ」とか「ねこしょん」という俗名を持っているということだった。
もちろんいいにおいではない。しかし、僕は猫のいない夜ふけの家のさびしさを感じた。ああそうそう、お前がいたんだなと思うような存在こそ、いないとなると淋しい。天井の鼠も、図々しく騒いでいた。 2024.11.27 記す。
★二輪草(にりんそう) P.194
二輪草が咲いた。確かに花は二つあるが、そろって開かず、片方はまだ蕾がかたい。ほとんど無数の花を一度に咲かせるものもあれば、下の方から順に咲き上って行くものもある。二輪草は、どういう気持ちかよくわからないが、」せめてにこやかな顔を揃って見せればいいものを、こうして遠慮している。
北原白秋の「……一輪咲いたが一輪草、二輪咲くのが二輪草のとおりであるが、この花の数が二輪とは限っていないし、同じアネモネ属には三輪草もあるので、断定を下すまえに、十分の用心が必要である。 中国の伝説に、かわいがっていた子供が死に、悲しむ親の夢にあらわれて、この花を私と思って育ててくれという話があるが、その花が、一輪草であったり二輪草であったりしている。 この白い花弁のようなものは萼で、普通は五つとなっているけれど、僕の眼の前に、いくぶんうつむいていて、困ったような顔つきをしているのは七つである。花弁はないことになっているが、二輪草も花びらを開いてみせているつもりではないかと思う。余計なことだが、雄蕊がだいぶ多すぎて、うるさそうである。
★玉菜(たまな) P.195 町の中で生活していると、玉菜(たまな)、つまりキャベツの花をみたことがないという人が案外多い。これから初夏にかけて、あのたくさん葉の中央から花茎がのびて、うすい黄色の十字型の花を咲かせる。四枚ある花弁の一つは二センチほどの大形の花である。 前の晩に、きざんだキャベツにマヨネーズのかかったものを食べたが、翌日のあさ台所へ行くと、上部の横つらをそがれた玉菜の切口が盛り上り、総状の花を咲かせるべきたくさんの花の胎児が、幾重にもおおいかぶさっていた葉が突然切り落されたことに驚いたように、おそるおそる頭をもたげているのを見た。僕は思わず、薄気味の悪いことを考えた。人の頭が、ばさっと切られた時、その人の隠していた生きている観念が、なおしばらく生き残って、姿を持ったものに変っていたら……。
※参考:キャベツという名はラテン語のcaput(頭)に由来。 江戸時代に、オランダ人が長崎へ持ち込んだためにオランダ菜と呼ばれ、観賞用に栽培したものは葉ボタンと呼ばれました。 キャベツの原形といわれるケールのような野生種をケルト人がヨーロッパに広め、その過程でいまのような丸い形になりました。 2024.11.27 記す。
★百合の木(ゆりのき) P.196
葉をぶらさげて見ると形が半纏(はんてん)に似ている。戦争中幸いにして華々しく戦場に立つことの出来なかった僕は、町会の仕事を手伝っていたが、取りこわしになった家の材木をかついだり、屋根瓦を数枚ずつ重ねてしばったりする時、僕は家の物置にかけっぱなしになっていた半纏を見つけ、それを着ていると、大そうよく似合うと言われたことを、この木の葉を見るたびに想い出す。 昨年の秋に植物の好きな若い友だちからもらった苗木が今、庭でさかんに芽を出している。毬(まり)があたって、先が折れたために、少し姿が悪いが、やがてそれも目立たないようになるだろう。その姿は、小さな手をかざしているようで、まことに滑稽である。ニ三日して、その手をひらくと、これまた小さい半纏である。まれに六十メートルにもおよぶという大きな喬木を、ややこごみながら観察できることもうれしい、これから先毎年のびて行くようすを見られるのもたのしみである。 2024.11.27 記す。
★頬白 P.197 頬白(ほほじろ)の啼声は「一筆啓上仕候」ということになっているが、「仕候」がどうもそんな具合に聞こえない。「源平つつじ」「丁稚鬢づけいいつけた」「金粒五粒生んどった」などと聞いた人もいるということである。鳥の声を人間の言葉になおしたものを、日本ばかりでなく外国のものまで集めてみるとおもしろいだろう。 これから頬白よりも頬がはっきりと白く見える鳥もいるので、姿を見てあれは頬白じゃないよという人もいる。そういうふうに自信たっぷりにものを言う人は、四十雀(しじゅうから)の頬の白いのを見てあれが頬白というだろう。人間が自然を見る目はだんだん変わって来ているし、名前ばかりが変らずに残っているので、どうしてそんな名をつけたのか考えられないものも多い。
※参考:成鳥は全長17 cmほどでスズメとほぼ同じ大きさだが、尾羽が長い分だけ大きくみえる。 翼開長が約24 cm。 成鳥の顔は喉・頬・眉斑が白く目立ち、「頬白」の和名はここに由来する。 2024.12.14 記す。
★鰆 P.198
魚扁に冬は? このしろさ。よく知っているね。それじゃあ、魚扁に秋は? どじょうだよ。そんなら魚扁に夏は? 誰かの頭に、夏の土用うなぎがちらっと見える。 ※魚扁に秋は「かじか」「いなだ」「どじょうう」魚扁に夏という漢字だけは存在しませんと。 鰆は北海道から南の方までの、沿岸近くの濁った水に棲んでいる。瀬戸内海に多いが、この魚の色だの味だのが、あのあたりの景色を想い出させるような気がする。冬のうちは比較的海の深いところへ下がっているが、四月になると卵を産むために入江など、浅いところへ群れてやって来る。そこをつかまえる。習性を訂正しない限り、鰆は春になるたびに捕縛されなければならない。 けれども実際に味のいいのは冬のころで、寒鰆と言っているが、この魚の顔をしげしげと見た人は少ないだろう。特別に悧口そうな顔付をしてはいない。 ※参考:名前の由来 細長いという意味の「さ(狭)」に「はら(腹)」、つまり腹が狭くほっそりとした体形というのが語源である。 一般的に鰆の漢字を使うが、これは春に産卵のため外界から瀬戸内海に入り込み、春に漁期を迎えることから「春を告げる魚」が字源となった。 ※まつりずしは、「岡山ばらずし」「備前ばら寿司」とも呼ばれ、備前岡山地方ではお祭りや祝い事、来客の接待などに作られる。野菜や魚介、瀬戸内海の豊かな食材を詰め込んだ、華やかなちらしずしである。江戸時代、岡山藩主であった池田光正公が、ぜいたくをしないように「庶民は一汁一菜にせよ」との節約令を出した。そこで庶民は、魚や野菜をすしの具に使えば飯を食べる時のお菜ではなくなる、という理屈で、たらい状の半切り桶の中に詰めたすし飯に、味をつけた野菜や魚介類を十種余りも入れて、かき混ぜて食べた。入れられる具材の魚や野菜は、家庭や地域によってさまざまで、サワラやアナゴのほかにもモガイ、エビなどの魚介類や、タケノコやゴボウを入れることもある。また、まつりずしを蒸して温めた「ぬくずし」という食べ方もある。「ぬくい」は岡山の方言で「温かい」を意味する。 2024.12.19 記す。
★十二指腸虫 P.199 アンキロストーマ・デュオデナーレ。あのイタリアで、デュビニが見つけた線虫類の名を僕は覚えてかえろう。幼いころ、入院していた母を見舞に行った時に、目のはれっぽたいお医者さんが僕にくれた。
僕は伝染病研究所の研究室を訪ね、試験管の底で、うようよしている十二指腸虫の仔虫を、顕微鏡でのぞかせてもらいながら、こいつはちょっと防ぎようがないぞと思った。どんなふうにして人間の肉体を宿主として這入りこんで来るかということは研究され、用心の方法も教えられているけれど、これをほろぼすことはもちろん、よせつけずに置くことも無理だと思った。大体、呼んでみても、あやしてみても、全然知らん顔をして平然と体操をしているような奴は防御のしようがない。 2025.01.10 記す。
★えぞすみれ P.200
けれども春から夏にかけて野山や路傍でめぐり合う数々のすみれを、記憶の箱の中へ採取して、それを思い出す時には語り合うことも出来るだろう。 薄く濃く、また赤味を持ったさまざまな紫。白いすみれ、夏の山に咲くたかねすみれやきばなのこまのつめ。えぞすみれはえいざんすみれ、かくれみのなどという別名も持っている。そして一つの大きな特徴は葉が裂けていることである。普通三つに裂け、それがまた二つに裂けているので、花を着けないうちはすみれの葉とは思えない。僕が春の山道を歩いている時ににこっそりさがしている花である。 2024.11.04 記す。
★沈丁花(じんちょうげ) P.201 庭の沈丁花は一尺たらずのものであるが花を開きはじめた。いつもどこからかこの花の香が漂って来て、ああことしも咲き出したかと思うのに、花の方をことしは先に見つけた。 小説家の円地文子さんが、御歳よりから教えられてこの花を丁子(ちょうじ)とよんでいたと書いておられたが、僕も確かにそう教えられていた。母は今も丁子と言っている。丁子は日本では見られないモルッカ島原産の熱帯植物であるが、沈香や丁子に香も姿も似ているので沈丁花というのである。
『本草綱目啓蒙』を見ると「花後実ヲ結ブ南天燭子ニ似タリ」と出ている。日本の沈丁花は普通雄であるために実を結ぶことがなく、僕も見たことはないが、まれに熟して南天のような赤い実がなる。この実は辛いので「こしょうの木」ともいわれているが、さきの本には「実ニ毒アリ食スレバ半日バカリ煩悶ス」と書いてある。僕は沈丁花の実を食べて煩悶している人のようすがどうもこっけいでたまらない。
円地さんも辞書を引いて沈丁花と丁子とが別のものであることを発見されたようだが、僕も確かに長いあいだ、この花を堂々丁子と呼んでいた。ある。
★るりひらたむし P.202
この一週間、白馬岳を中心にあちこち歩いた。五月というのに吹雪の日もあった。連山は再び純白に光った。山のふもとの小屋へ戻って来た晩、煙草をのんでぼんやりしていると、僕の足をはいあがって来る小型のかみきり虫のような、暗い瑠璃色の虫がいた。しかしこの色は実にいい。人間はずいぶんさまざまの色を作り出しているが、こんな深みのある色の服を着ている人を見たことがない。この虫ははじめて見かけるものだったが、山地に成虫で越冬するるりひらたむしであることや、わが国の産のひらたむし科の仲間では一番大きいものであることが分った。
この小屋は去年の秋に建てられ今度はじめて開いたのである。ところでどうだろう。虫は人間よりも先にこうして冬ごもりにいい場所を見つけ、僕がやって来たことにどうも少々不満の色さえ見せている。あらかじめつぶされることを予期しているようにその体はぺしゃんこであるが、かみつく用意も十分あって大顎は実にいかめしい。新しい床板の上を、思案にくれて歩いて行くようすが気の毒だった。 ※参考:著しく扁平な体つきをした美麗肉食甲虫。山地の原生林に生息し、立枯れや倒木などの樹皮下に見られるほか、土場などの伐採木に来ることもある。成虫・幼虫共に樹皮下で他の昆虫を捕らえて食べる。成虫は冬期、樹皮下などで越冬する。日本産ヒラタムシ科の中では最大種で、ベニヒラタムシの大きさに見慣れていると、本種のデカさにびっくりする。狙って見つけるのは難しいが、カミキリムシ等を探して倒木や立枯れを見ていると、たまに見かける事がある。 2024.12.24 記す。
★燕(つばめ) P.203 僕が去年、山へ登るまえに泊まった新潟県のある村の宿屋は、その部屋をスケッチ・ブックに描いておいたほど、黑光りがしていて大きな柱がそこここに見え、感じがよかった。 山へ登る朝、少し寝坊をしてしまったので急いで靴をはいている時、そこの土間の天井に燕の巣があって、親燕はその子供にせっせと餌を運んでいた。燕の渡って来るのは、その辺だと四月なかばごろだろうか。まだそれでも雪深いところなので、村の人たちはもう燕が来たなどと言って空を見あげることだろう。 燕が子供に餌を運んでいる様子は、都会にいてもよく見られるが、子供たちが三角に大きくひらいて、喉のどの辺で鳴くのか、せっくように騒ぎ立てている。親は順に餌を口に入れてやっているだろうのに、その度に、一応全部の雛鳥が大きく口を開いて騒ぐ。ひょっとしたらまちがえて、続けて自分の口に虫を入れはしないかとおもうのだろうか。
その燕の子たちが飛び立って行く、やわらかな初夏がまたやって来る。 2024.10.07 記す。
★はるぜみ P.204
以前、湘南の方に家があったころ、裏が山になっていた。そんなに高い山ではなくて、まあ丘といった方がいいかもしれないが、そこには松が多く、夏なんぞは蝉の声で頭ががんとなった。蝉地獄という感じさえした。
ところが春先、そろそろ五月になろうちうころ、いつから鳴きはじめたとも分らないが、蝉らしい声がする。僕は、誰から聞いたことだったのか、あれは松の虫と言って蝉ではないと思い込んでいた。そのおそわり方が余程断定的だったせいか、疑ってみようとも思わなかったし、正体をつかまえてみようともしなかった。 はるぜみのことを、マツムシ、マツゼミ、またクダマキなどとよんでいる地方も実際にはあるが、蝉であることは確かである。この蝉の姿を見たのは、もう余程あとになるが、ひぐらしに似てもっと小さい。姿ばかり見ていると、もっと細い、鋭い声を出しそうなのに、にぶいねむそうな声である。 この声は、今でも毎年聞いているが、春のけだるさが一層まして来るようだし、日ざしが強くなって来て、草のいきれた匂いもする。散歩をしていても、もうそろそろハンカチの季節である。 ※参考:春蝉(ハルゼミ)とは 日本と中国各地のマツ林に生息する小型のセミで、和名通り春に成虫が発生する。 ある程度の規模があるマツ林に生息し、マツ林の外に出ることは少なく、市街地にはまず出現しないが、周囲の山林で見られる場合がある。 日本では、セミの多くは夏に成虫が現れるが、ハルゼミは和名のとおり4月末から6月にかけて発生します。 鳴き声はわりと大きいが生息地に入らないと聞くことができない。黒い小型のセミで高木の梢に多いため、発見も難しい。(↑ウィキペディアフリー百科事典引用) 2025.01.11 記す。
★夾竹桃(きょうちくとう) P.205 地の神の娘に、白妙姫という色のまことに白い美女がいた。若い神々はこの白妙姫を得ようと思って夢中になっていたが、彼女の心にかなう者がいなかった。若い神々の中に、植物の神がいたが、これこそ白妙姫にも父の神にも気に入ったので、婿君になることを告げると、意外にも、彼は、こんなにまっ白い姫君は、まるで死んでいるようで好きになれないと言って断った。
花の伝説というのはこんな調子のものが多い。その話をきいた中学校の運動場の隅に夾竹桃が一本あって、夏の休みがはじまる頃になると紅色の花が見られたが、中学生たちも、この伝説をきかせた国語の先生も、夾竹桃が校庭に植わっているのを知らなかったらしい。
★蒟蒻(こんにゃく) P.206 群馬県の方から重たい植木鉢が届いた。それを預かった方は、うちの近くのお菓子屋まで持ってきたので、僕のところへはそのお菓子屋の娘さんが抱えて来たので驚いた。紙包みをほどいてみて僕は更にびっくりした。さてこれはなんだろう。
これは蒟蒻(こんにゃく)の花の芽であって、今ほうぼうの山地に咲いている水芭蕉と似た構造であるが、長くつき出しているものには付飾棒という名がついている。この中にまだ咲き出すには早い雄花雌花が包まれている。 おでんやで、僕はすまして蒟蒻を食べているが、なにをかくそう、この花は知らなかった。そして同時にいま知ったことは英語でもフランス語でもコンニ」ャク(Konjak)である。だれかをさそっておでんを食べに行き、蒟蒻の花知っている? ときいてみたくなって来た。
★おおよしきり P.207 近くの井之頭公園から流れ出る川には、今もなおかろうじて葦が残っていて、おおよしきりが盛んに鳴いている。この鳥が暖国から渡って来て鳴きはじめるのは五月に入ってからで、初夏には毎日狂ったように鳴き続けている。
僕は毎年三四回は、その流れへ双眼鏡を持って出かけ、葦の茎のあいだにうまく作る巣のあり場所を遠くからのぞく。首を振り立てて、あのギョツ・ギョツ・ケケシケケシというようすがおもしろくて、巣をさがす眼鏡はいつも親鳥の方に向けられてしまう。自分の領域を守ると同時に、巣をねらうものの気をそらせる声である。
去年の夏近所の子供がその巣をとって来てしまった。うす緑色の地色に斑点のある卵が五つはいっていた。こんなことをするものではないと言ってやったが、それを幾らかで買いとって葦の中へ吊しに行くことも出来なかったので、僕はもうこれで、おおよしきりの声もその流れでは聞くことができなくなると思っていた。それだけに、今年にぎやかな声を聞いた時には僕のよろこびは大きかった。 ※参考:オオヨシキリはウグイスの仲間で、東南アジアから渡来する夏鳥です。 ヨシ原(葦原)を好み、ヨシを切り裂いてその中にいる昆虫等を捕食する性質が、その名の由来と言われています。 2024.12.14 記す。
★追河 P.208
魚のおいかわは追河と書くようである。川の上流から川を追いかけて行くという感じを、単純であるが実にうまくな前にしている。東京ではハヤ、またはヤマベという。ウグイのこともハヤという。東北地方ではヤマメをヤマベといい、魚の名前は余程気をつけないと間違いやすい。
末の子供が毎日雨の中を根気よく魚をとりに行く。うちの池はいっぱいになるし、またよごれた雨のせいかよく死ぬ。どうせ死ぬなら、食べてやったほうが魚もよろこぶという結論がでて追河を天ぷらにした。はらを出さなかったのでにがかったが、それほど評判は悪くはなかった。次の日にはから揚げにして南蛮づけにした。このほうが、味というものに無頓着な僕らにはよかった。 なにしろ、いま産卵期の追河の雄は、薄赤く光ってまことに美しい。真珠のようである。子供は得意で今夜も明日の魚とりの用意をしている。これだよといって魚の本を見せたが、「不味であるが取り易いので……」という説明をそのまま読んでやってはがっかりすると思い4,「おいしいけれどもなかなかつかまえにくい」とかえて読んだ。しかし実際はどうなのだろう。一度一緒に捕って見なければならない。それはともかくとして、都会近くに住む僕も、子供のとった魚の夕食を食べられることをうれしがった。 2024.12.19 記す。
★駒鳥 P.209 駒鳥の声を知っている人も多いが、山で実際にその声を聴きながら姿をうまく見付け出した経験を持っている人は案外少ないかも知れない。僕はもう三年前になるが、五月に鳥海山(山形県と秋田県に跨がる標高2,236mの活火山)に登った。千メートルから上は残雪で、スキーを使ったが、その雪と草の堺に、ちょっとしたしゃれた小屋があり、気持ちがいいので四日ほどそこに滞在していた。 日中は、日が照っていると裸になって滑りたいような日もあった。その時、もう夜の明けるのも早かったし、ずっと早起きしていたが、朝毎に聴いた駒鳥の声が忘れられない。霧がだけかんばんにからまるようにして流れている中で、ヒンカラカラカラという、こっちの気分もきりっとなるような声をさんざん聴いた。早朝の、雪の中から頭を出した岩の上で、僕は遠くの、聖書に書かれたどこかの暁を想った。その時も、雪のある谷間を、駒鳥の姿を求めて大分歩いてみたが、どうも見届けることが出来なかった。
※参考:和名の由来は、「ヒンカラカラカラ」と馬のいななきのようなさえずりをすることから、「駒鳥」と名付けられた。 日本列島の特産種で、夏鳥として北海道から屋久島までの山地に飛来し繁殖する。 北日本では、標高の低い山地にもみられる。 2024.12.15 記す。
★夜光虫 P.210
僕が、どういう加減か、五月の海を急に見たくなって、太平洋に向って突き出したある岬の突端で一夜をあかした時、夜半近くから波がよせて来るたびにそこがちらちらと縞になって光るのを見て、これが夜光虫だと思ったことがある。風の強い夜だったし、その光が段々気味悪く見えて来たので、自分で求めてやって来たものの、夜明けが待ち遠しかったことをよく覚えている。しかし相当昔のことで、夜光虫の正体をはっきり見届けたわけでもないので、恐らくそうだろうと言うより仕方がない。
夜光虫は薄い桃色の、一ミリほどの小さな原生動物であるが、沢山集って光りはじめると、人間の気持に異常に作用を及ぼすのは事実である。暗闇の中で光を発するものは、蛍の光に至るまで、人の魂を誘い出すような力を持っている。僕もたしかに、五月の海にこの光を見てから、しばらくのあいだは、やや精神的に変化があったことを認めざるを得ない。翌晩、海岸の宿に泊って、幻想的な物語を作ったりしたのも、夜光虫のためらしい。人の精神は、パスカルも感心したことだが、一ミリくらいのものによっても、実に簡単に左右され、いつまでも影響をうけていることがある。 ※参考:夜光虫とはノクチルカ シンチランスというプランクトンで,一般的に夜光虫と呼ばれており,分類上は植物プランクトンの渦鞭毛藻類に分類されています。夜光虫と呼ばれる名前のとおり,夜に刺激を与えると青白く発光します。(発光する様子は,夜に船で夜光虫が多くいる海域を航行している時や波打ち際などで観察できます。) 2024.12.26 記す。
★しゃが P.211 僕がまだ小さいころには、小さい僕にも巻紙で手紙をくれる人が幾人かいたし、そういう人には僕の方からも巻紙をもって返事を書いたものだった。その一人に、特別親しい知り合いでもなかったが、よく手紙の中に絵を描いてくれた人がいる。もちろん、巻紙に描く絵だから日本画だったが、誰が見てもこれは上手だと感心するようなものだった。もっともその人は建築家で、ヨーロッパを回って来たこともあり、ローマの話などをしてくれたものだった。 気節の花がおもだったが、ある時、しゃがが描いてあった。僕はまだ名前を知らなかったので、多分母から教えられたのだと思うが、次に実物を見た時に、それはしゃがだと確信をもって言えるほど正確にそれらしく描けていた。
★どろばち P.212 どろばちはよく薄のような細い葉の裏に巣を作る。並べて四つ五つ、もっと沢山続けて作ることもある。散歩しながら、草むらの繁みに入り、葉を裏がえしてみると、どろばちの巣ばかりではなく、いろいろの見つけものをする。
蜘蛛は網を張ってずいぶん大がかりに翅のある昆虫をとらえるが、蜂にちくりとやられ、しびれた体を巣に運ばれて、卵からかえった蜂の子の食物になる。人間が蜘蛛を食べるという話はきいていないが、蜂の子を好んで食べる人は多い。 これは別のことだが、土蔵作りの名人としては、人間とどろばちとでは、どっちがいい腕を持っているだろうか。 ※参考:体長13mm前後のドロバチで、腹部に黄色い2本線が入っているところが特徴です。 家の外壁や枯草の茎などに、泥をこねてトックリ型の巣を作ることが名前の由来です。 巣を作ったら卵を1つだけ産み、そこに幼虫の餌となる青虫を大量に詰め込んでフタをします。 2024.12.24 記す。
★あかざ P.213 川沿いの道を雨あがりに歩いた。僕が全部うつって、まだ雲が三つもうつるくらいの水たまりが道をさえぎっている。そのあたりが全体赤っぽいのはあかざがいっぱいあって、わかい葉の赤紫色のせいだった。それが白ければしろさだ。この赤紫は前から気になっていたが一種の粉状のものである。僕はどうもある種の色に酔う性質があるらしいが、それが必ずしも快い気分に発展してくれるとは限らない。
※参考:原産地はインドから中国です。平安時代に編纂された百科事典の要素をもつ「和名類聚抄」にその名が載っているので、かなり古い時代に渡来し畑で栽培されていたようです。シーボルトに東洋のリンネと言わしめた江戸時代の本草学者小野蘭山の著した『本草綱目啓蒙』に「野生なし、春月 種を下す、また去年の子(種)地にありて自ら生ず・・・」と書かれています。このことから江戸時代には野生はなく、毎年春に播種栽培していたと思われます。なおも、よく似たシロザと区別するため「苗葉花実皆灰藋(しろざ)に同じ」とあるので、シロザはよく見られる野生であったようです。 学名のChenopodium album はシロザを示しvar.centrorubrum は中心が赤い変種であることを意味するので、シロザはどこにでもあったと思われます。 草丈は1.5m、稜のある茎は直径3~5cmになり、木本状になります。葉は有柄で互生しています。若葉は鮮やかな赤紫色で名前の由来になっています。若葉は食用になり、古い茎は水戸黄門や芭蕉が使ったといわれている杖になります。まっすぐで軽いため杖に加工され、中風の予防や治療によいといわれますが、科学的根拠はないそうです。 東邦大学薬学部 2024.11.05 記す。
★みどりかみきり P.214
夜おそく帰宅して、急ぎの仕事をすませてから眠ろうと思うと、風呂が立っているのに気がついて、少したいてはいった。蛙の声がずいぶん盛んになって来たと思いながらぼやんと湯ぶねにつかっていると、最近新調した洗い桶のへりを、みどりかみきりが根気よく、長い触覚を振りながら歩いていた。
湯気をとおして深夜の灯りのせいか、鞘羽の緑色の光沢も、また細い脚の鋼(はがね)のような艶も実にきれいだった。かすかな音だが、かみきりむしらしいギイギイという音も出していた。 僕はどのくらいそれを見ていたか分からないが、もういい加減にしておこうと思っている時に、鞘羽をちょっと開いて、紫色の、薄い翅の一部をちらっと見出た。二度とは見せてもらえなかったが、緑のさやの下に、夢の翼をていねいに畳んで持っているこの虫をうらやましいと思った。僕も、こういう具合に翼ある夢を持たなくてはいけないと思う。それを考えると頭がくらっとする。そしてこの虫は、夢の翼のたたみ方について、僕にいい課題を与えてくれた。 ※参考:カミキリの意味を「紙切り」や「噛み切り」と思っている方も多いと思いますが、漢字で書くと「髪切虫」。 噛む力が強く、髪を切ってしまうほどだったことからその名がついたとされます。 また、長い触覚を牛の角になぞらえ「天牛」と呼ばれるほか、触覚が長いことから「Longhorn beetle(英名)」とも呼ばれます。 2024.12.24 記す。
★うすきつばめえだしゃく P.215 こういう長い名前は覚えにくいようであるが、「淡黄燕枝尺蠖」という漢字を見ると、その色や姿をそのままな前にしたようなものだから、案外忘れにくい。 雨の日が続いたあとの日ざしをうけて、今は蝶や蛾がさかんに羽化する時である。きのうはほとんど家の中で仕事をしながら、五六種類の蛾を記録したが、いずれも雨のあがるのを待っていて飛び出したものらしい。このうすきつばめえだしゃくも毎年必ず見かけるものだが、もう縁側の戸をかなりおそくまで開けておくようになったので、部屋の灯を求めてはいって来たものだ。後翅のとがったところの大小の赤い点以外にはsほとんど白である。
2024.12.24 記す。
★赤翡翠 P.216
あかしょうびんはみやましょうびんと言われたり、猩々しょうびんと言われたりしているが、昔、群馬県のある温泉に十日近く泊っている時に、大弓場の娘さんが、この鳥の、キョーロロロという啼声をきいて、あ、ケロロが啼いたと言ったことを思い出す。そしてその辺では、親不孝鳥と呼んでいるが、そのいわれを話してくれた。いつもこの鳥は親の頼むことをしないで、反対のことばかりして困らせていた。その親鳥は、死んだ時に川へでも流されては大変だと思って、「わしが死んだら川に流しておくれ」とたのんだ。すると子供はせめて親の遺言だけはすなおに聞いてやろうと思い、そのとおり川へ流したという物語である。
「多分それが後になって分ったらしいの。雨が降って川の水がふえるとよく啼くんです」 僕は大弓を遊ぶ。たまにすぽんと的(まと)にあたる。今しがた新緑に太陽の照りかえしがまぶしかったと思っていると、また薄暗くなって雨が降りはじめる。宿の番傘をさして、すべる径(みち)を少し谷の方へ降りて行くと、この鳥の赤い姿が、荒々しく一線に飛んで行くのが見える。親不孝かどうかは知らないが、いたずらっ子の容子ははっきり見える。 ※参考:「赤色のショウビン」の意。カワセミの古名“ソビ”が“ショビ”を経て“ショウビン”と転じた。 ○平安時代から「ミヅコヒドリ」と呼ばれ、江戸時代前期から「アマゴヒドリ」とも呼ばれ、江戸時代後期に「アカショウビン」の名が生まれた。異名;「アカヒスイ」「ミヤマソビ」「ミヤマショウビ」「キョロロ」「ヤマセミ」 2024.12.15 記す。
★しろつめくさ P.217 徳川時代に、ガラスの器が輸入された時に、われぬように詰めものいなってやって来たのがこのつめくさである。思えばかなしい渡来ぶりだが、帰化の仕方は堂々たるもので、ポランの広場などは実に見事なはびこり方をしている。 「つめくさの花の咲く晩に、ポランの広場の夏まつり。つめくさの花のかおる夜は、ポランの広場の夏まつり」宮沢賢治の、あの酒くせの悪い山猫が、黄色のシャツで出かけて来る。そうするとポランの広場に飴が降る。
※参考:「ポランの広場」:宮澤賢治全集 第十二巻(筑摩書房) 2024.11.05 記す。
★アラビアの星 P.218
雌蕊の、厳密に言えば子房の黒は幾分みどりがかったものであるが、六枚の純白の花弁と黒い星とのあいだに、淡い黄色で雄蕊がまるく寄り合っている。その調和は、花の世界のすぐれたバレエの一場面である。これだけは人がどんなことをしても真似られない沈黙の澄み切った表情である。細長い黄色の葯を見るとそれもやはりそれぞれの顔付であるし、花全体を改めて見ても立派な綜合の表情である。 僕は庭でこの花の一輪を出来る限り正確に描いていたが、何も言えなくなった。細かい雨が降り続いている。 ※参考:クロホシオオアマナ(黒星大甘菜)は、地中海沿岸が原産の春咲きの球根植物です。花の中心にあるめしべが黒くてよく目立ち、オオアマナの仲間であることから、和名では「クロホシオオアマナ」とも呼ばれます。環境が合うと他の植物を駆逐するほどによく繁殖するため、プランターや境界のある場所に植えた方がよいでしょう。 2024.11.27 記す。
★平家蛍(へいけほたる) P.219 ほたるは「火眠る」ということらしいが、あたたかみのある名前である。だが蛍の光には熱がない。昨年までは僕の住んでいる近くでも、この青白い光を見かけたが、今年はどうだろうか。何しろ家が多くなって、蛍も別段あかりを必要としないだろう。しかし、その発光器をすててしまうようなことはしない。一体蛍は何のために光るのか。 幼虫のうちから彼らは光る。不器用な光り方ではあるが、ともかく光る。幼虫の時代だけ光るのもあるが、大きくなると光り方も起用にばり、雄と雌とで信号をやる。種類によって色の区別もあるし、第一、点滅の回数がいろいろある。コッチへコナイ? イッテモイインダケド。それは僕に考えられる限りの人間の言葉である。それらしい人間語訳である。恐らく大きな誤訳だろう。 しかし光の信号は、そんな醜悪な人の言葉とはおよそちがった、僕たちの想像からはあるかに距った情緒をかくし持っていることだろう。 籠に入れた蛍は青臭い。それを、あんまり「いやだと思わずに、口に水を含んで吹きかける。ただ彼らが腹にあかりを持っていて何も隠せないのは辛いだろう。 ※海軍兵学校兵学校の卒業式が済むと、真新しい軍服姿になった候補生たちは、在校生徒や教官たちの見送る中を、機動艇に分乗して表桟橋から離れて行く。そのとき軍楽隊が「オールド・ラング・サイン」(「蛍の光」の原曲)を演奏するのが慣例になっていた。ところが戦時下ますます激しくなった適性語追放の空気から、卒業式行事でこの曲を演奏するのは取り止めてはどうか、という意見が出てきた。スコットランド民謡だから、というのがその理由である。しかし井上校長は「名曲は名曲である。敵味方を絶している」として廃止の意見を斥けた。「蛍の光」は戦時中、国内どこの学校でも聞かれなくなったが、兵学校では終戦の年まで使用された。
★うらぎんひょうもん P.220 このたては蝶科の飄々とした姿を見ると、六月のしめっぽい暑さがはっきり理解されはじめる。湿度計もその針をだるそうに動かしている。湿度計八十パーセント。ほんとうにそうなのかしらと思う。そういう空気を好んで生まれるうらぎんひょうもんは、真夏になるとさすがに疲れを感じるのか夏眠をする。
菫の葉を食べて育ったこの蝶が、成人してからなぜとげとげの薊(あざみ)などを好むのかをふしぎがっているものもいるが、僕にはそれがよく分る。説明をしては野暮だ。 それから六月七日に蛹になる光景を徹夜して見ていたことを忘れられない。その三日前に菫を食べることをやめ、箱の中でさかんにぶらさがりたがっていたが、夜明け、ちぢまった足が青い光を帯びてどこが顔とも分らないとぼけた顔がかたまる。 ※参考:ウラギンヒョウモンは大型ヒョウモン類の一種でギンボシヒョウモンに似ていますが、後翅裏面外縁の星の数が5つが本種、4つがギンボシで区別できますので、写真を撮るときにはこの部分ははずせません。 2024.12.25 記す。
★黒種草(くろたねそう) P.221 kusida.uraginhyoumon.png 今度の家には庭がありません。それで今年は木箱へ土を入れて黒種草を作っています。こんな葉書が遠方から来たのは大分前だったが、木箱に育てた黒種草がもう咲いているだろうか。僕がこのうちでも白いものより淡碧色の花が好きだが、どちの花が咲いているだろうか。 1 南欧原産のこの花には、恋する人に会えなくなった女が苦しみにながら死んでこの花に化したという伝説がある。よくありそうな花の伝説であるが、、それにつけ加えて、そんなことから、この花を寝床の下に入れて眠ると、夢の中で恋人に会えるということである。それで英国では Love-in-a Mist などという名前をつけているのだろうか。せめて夢の中だけでも恋人に会えたらと思うのは、古めかしいことのようであるが、そんなことを考える人が今はいないとも言い切れないような気がする。
ある年の夏、僕の庭ではこの草に奇妙な姿の幼虫がいっぱい高xtうていた。それは結局つのとんぼであることが分ったが、毎日気にしていたために、、黒種草の種子の出来具合も同時に記録出来た。 2024.11.27 記す。
★きまだらせせり P.222 せせりちょう科の蝶は、どっちかというと体がずんぐりしている。それにニ三のものをのぞいては、翅の色などもぱっとしないので、捕虫網をふり回して歩く連中にはどうもあまり評判がよくない。
せせり蝶は、なかなか見分けにくいところもあるが、このきまだらせせりはまず間違えることはないだろう。僕はこの蝶を見るたびに、人間は彼らの翅の色や文様にあまり気をとられすぎて、その動作に気を配ってやることが小ないと思う。そしてもし、蝶の物語をつくるようなことがあれば、この蝶については、派手な孔雀蝶などとは全く別な書き方をしてやらなければならないだろう。 ※参考:ひっかいてほじくるという意味の「セセリ」から命名されたセセリチョウの一種、小型で黄色地に黒っぽい斑模様が見られるところから名付けられました。 2024.12.25 記す。
★とっくりばち P.223 あけたてのはげしい僕の家の廊下のガラス戸のうちで、たてつけが悪くて動かしにくいのが一枚ある。それをこの蜂は知っていた。 僕は実をいうと、今年もこの自信たっぷりの、相当腕のいい左官屋が、このどんぐるばちのはかまのような巣を作るのを見そこなった。もしも今ここに、泥の徳利が二つあったら、こっそりと小窓をあけて、ファーブルがさんざん苦心をして観察した有さまをのぞいて見ただろう。天井からぶらさがっている一本のほそいザイルは何のためにあるのかを、僕も確かめたかった。
がらす戸の桟で新しく生れて、この土製のバンガローで育った一匹の蜂が、今日そこから飛び去ったあと、僕はピンセットと拡大鏡で、空家となった巣の中をしらべた。蜂の食べのこした、ひからびた蛾の幼虫の死骸と、十九個の健康な糞があり、雲母(きらら)のように光るその内壁は実に静かだった。蜂にとっては揺籃(ゆりかご)だったが、餌食となったいも虫にとっては、これは墳墓である。
僕は大好物のお菓子のバウム・クーヘンを想い出しながら、少しずつ土壁を崩していると、考古学者になったような気がして来る。 ※参考:腹部の基部が強くくびれ、その形が徳利(とっくり)を思わせるのが和名の由来。 泥の練り土で器用に壺(つぼ)状の巣をつくり、草木の枝や家屋の壁などにかける。 2024.12.25 記す。
★鈴蘭(すずらん) P.224 街を歩きながら、花屋の店頭や、そのほかのところで鈴蘭を見ると、僕は必ず想い出すことがある。それはある高原の療養所から送られて来た一通の手紙である。
僕はその手紙をよんで淋しくなったし、もう長いあいだその療養所にいるらしい、花を愛するその患者をどういう言葉で慰めたらよいか困った。もうあれから三年たつが、どういうことになっただろうか。 鈴蘭の一種に「ドイツすずらん」がある。これは英語で Lily of the Valley, フランス語でも Lis des Vallies といい、共に「谷間の百合」であるが、そのまま直訳されると、少なくとも鈴蘭とはちがった花を考えるだろう。 ※参考:スズランの名前の由来は、白い鈴のような花をつけ、ランの葉に似ていることに由来しています。学名の「Convallaria majalis」は、ラテン語の「谷(Convallaria)」と「5月に花が咲く(majalis)」という意味です。 スズランには、次のような別名や花言葉があります。 「聖母の涙」という別名があり、キリスト教の伝説に由来しています。イエス・キリストが十字架にかけられ母マリアが涙した時、その涙が流れ落ちた地面からスズランが咲いたという伝説です。 花言葉には「再び幸せが訪れる」「純粋」「謙遜」などがあります。春の訪れを知らせてくれる花であることに由来して「再び幸せが訪れる」という花言葉がつけられています。 和名には「君影草」という名前もあります。 スズランは全草に強い毒があり、赤い実を食べたり、若葉をギョウジャニンニクと間違えたりするなどの注意が必要です。切り花で使う場合は特に飾る場所には注意しましょう。 2024.11.17 記す。
★駒草(こまぐさ) P.225 夏の賑やかな山は避けているので、このところしばらく駒草には会わない。最近ずっと会っていないけれど、どうしているかしら、と旧い友だちのことを、何かの時にふと思い出して考えるように、駒草の本の扉などに描いてあるのを見ると、想い出す。 ずっと以前でも、夏の高山には女学生たちが先生に連れられて登って来た。汗で顔を赤くして、すれちがいに見ると、どうして山なんかに来てしまったのかしらとというような顔付を見うける。それは今も別に変りことだろう。その数はふえ、人の服装は変ったろうけれど。 けれども花は顔も姿も変えない。
女学生の一団で、引率している先生が、「先生オコマグサはどれですか、早く見せて下さい」とせめられていたのを見かけたこともある。 ※参考:学名命名者:牧野富太郎 2024.11.05 記す。
★雷鳥 P.226 雷鳥は生存の争いについて、一つの心境を持っているようである。彼らが、人間が必ずしも善良ではないことを知りながら、近寄って来ても逃げずにいてみようと申し合せてあるようである。
雷鳥は鳴かない方がいい。あまり聲がよくないから。人の頭の中で、この鳥についての愛情がこんがらがってしまう。あんないやな声の鳥をどうして可愛らしいなんて思うのだろう? などと言われそうに思って。それは人間界ではよくあることだから。 けれども、恐らく君たちの知らないことを教えてあげようか。君たちの声はまるで蛙みたいだ。低いところのことは知らないだろうが、蛙という奴がいるんだ。それから昔の人は、君たちが雷という虫を食べていると思っていた。その虫がこんな声を出すのだと思っていた。それで、実はその辺がどうもあやしんだが、君の絵を描いて持っていて、雷が鳴り出した時に掲げると落雷をまぬがれると思い込んでいた。さっぱり分らないだろう。幸いにして僕にもよく分らない。 ※参考:ライチョウの語源には、天敵を避けるためカミナリが鳴るような時に活発に活動することから、「雷の鳥」になったとする説。 2024.12.15 記す。
★黒百合(くろゆり) P.227 少年時代に立山へ登り、ザラ峠をとおった。この峠は佐々成政が通った峠である。その近くで黒百合を見た。 これはあのあたりへ行った人ならば珍しい経験ではないが、そこで黒百合の伝説をきいて、ふしぎな気持になった。花の伝説というものは、時たまなまなましい感じを与える。 佐々成政は、妾の小百合と小姓の竹沢龍四郎の中を疑って、二人を殺した。それでも足りずに小百合の一族を十八人も殺した。小百合が殺される時に、恐ろしい顔になって、「立山に黒い百合が咲いた時は、佐々の家はほろびる」と叫んだ。それから後、黒い百合が咲いたのを成政は淀君に献じた。そのことから北政所の怨みを買って、最後にはザラ峠を越えて関東へ落ちなければならなくなり、死にのぞんで言った早百合の言葉のとおりになった。
※石川県の「郷土の花」である(「県花」ではない。
★海猫 P.228
その入江には海猫がひどく多くて、大きな赤ペンキを塗ったブイに何羽も群れて、さかんに鳴いていた。錨をおろしただけだと、船が流される虞があるので、ワイヤーと船とブイを繋ぐのである。その作業は軽業に近くて、甲板からのぞき込んでいた僕は、水夫たちの大胆な動作に呆れていた。 その作業のあいだ、自分たちの休み場所を奪われた海猫たちが、いかにも不服そうな声で鳴きながら、すぐ近くの海面でわざと大げさに羽ばたいたり、不器用にあわてたりしていた。船の人たちは、誰一人そんなことには目もくれずに、力仕事に就いていた。 双眼鏡でみると、嘴の先の赤と、瞼の赤がよく分る。口先と目許のその赤さは、それを眼鏡でで見た瞬間にエロティツクな感じをあたえた。泣きはらした目を想い出すだろう。冬の間行っていた台湾あたりの海岸で、何かあったのかもしれないと想像しながら。 ※参考:ウミネコはカモメの仲間で、全長約45センチメートル、翼を広げると115センチメートルくらいになります。 背と翼の上面は黒色で、下面は白色。 白い尾に黒い帯があります。 「ミャーオ ミャーオ」と聞こえる声が猫の声に似ていることが和名の由来といわれています。 2024.12.15 記す。
★みんみん蝉 P.229 蝉は、みんみんに限らずうるさいと思うことがあるが、初夏のころ、いつ梅雨があけるか分らないように雨ばかり続いて、一向に蝉の声がきこえて来ないと、これも淋しくて、からっと晴れた夏の炎天がほしくなる。 蝉の生活史は案外はっきり分っていないらしく、アメリカの十七年蝉とみんみん蝉と、あぶらぜみだけだということである。去年の七月下旬に、銀座につとめている友人が来て、みんみん蝉が銀座で鳴いていたと知らせてくれた。何時から何分聞きけていたと言って、それを手帳に書きつけてあった。彼の手帳にはそのほかにどんなことが書いてあるか知らないが、そのことは貴重な記録になるだろう。
※参考:夏を代表するセミの一つ。 「ミーン、ミンミンミンミーン」と鳴く鳴き声から名前がついた。 2025.01.11 記す。
★あさぎまだら P.230 これは、そんなに高い山へ登らなくても会える。僕もひところ蝶をつかまえることに熱中していたことがあるが、あさぎまだらをつかまえたのは、ある谷の、涼しい風の遊んでいるような日かげだった。枯枝にぶらさがっていると、落ちそこねた枯葉のようで、この擬態(ぎたい)には相当自信を持っているらしい。
葉っぱだろう? あんな蝶いないよ。 蝶であることを否定しているのは、小さい昆虫採取家のお伴をしている父親のようである。そのうち、たまたま、あさぎまだらは、ゆるやかに飛んで、二人のすぐ目の前の枝に、今度は翅をひろげてとまる。谷の風も涼しいが、この蝶の前翅の淡青色も涼しそうである。 父親は、子供から捕虫網をうけとる。子供の方が上手なのだが、残念ながら手が少しばかり届かない。よし、おれが捕えてやる、と意気込んだが、捕虫網の一ふりは空しかった。あさぎまだらは、まだらに射し込む夏の日をきらりきらりとうけながら、谷へ下って行く。けれども、まるで人を誘い込むように、もう一度戻って来て、さっきよりニ三メートル下の枝にとまる。 親子はこうして段々山径(やまみち)を離れて、谷の方へ下って行った。二人の額には汗が光る。 ※参考:観察ポイント「翅の色が名前の由来!」 淡い青緑色に見えませんか? 「浅葱色」(あさぎいろ)と呼ばれるこの色が、名前の由来なのです。 2024.12.20 記す
★ほんだわら P.231 僕は海がきらいではないが、船に乗るという面倒があるので、ほんとうに親しむ機会は少ない。海岸を歩くこともこの頃は少ない。けれども、たまに歩くと、波の崩れ方が変ったわけではないし、磯の匂いには懐しいものがある。かえって訪れることが極く少ないために、あの匂いあの潮風には特別な感慨が集まる。 そういう海岸を歩いて、もしほんだわらが打ちあげられていたら、僕はやはりまっさきに、あの気胞を見つけて潰すだろう。ぬるぬるの、割ってしまえばはかない気胞の、ぷつんと割れる時のその音を聞くために。そしてまた指先から逃げて行きそうになる球をうまくつかまえている触感を想い出すために。
海が荒れたあとには、砂浜にいろいろの、かなり深海の海藻までがごっそりあげられている。海がにごっていて泳ぐ気も起らない時、このほんだわらの、おおばもくなどを腰にぶらさげて騒ぎ回ったこともあるあが、もうそんな土人ごっこをすることはないだろう。ほんだわらの球を潰して、昔を懐しむことさえも、どうやら気恥かしいことだと思いながら、海の遠くに、無理に新しいものを見ようとするだろう。
※参考:おおばもく:多年生の海藻で一年中みられる。体は円錐形の付着器で岩に固着しており,その頂部から太い円柱状の茎を出す。茎は上部では押しつぶされたように平たくなり,ゆるくねじれる。葉は和名のとおり大きく長いへら状で20cm以上になる。葉の先端は丸く,へりに鋸歯はみられないことが多い。上部の葉は細く小さい。気胞の多くは楕円形で大きく,細長い冠葉をつける。手ざわりは硬くすべすべしている。生体は明褐色~茶色。 長さ:1~2m 付着器の直径:3~5cm ※参考:由来・語源 神馬藻、陣馬藻は「神功皇后(じんぐうこうごう 記紀にある)が三韓征伐のために九州から渡航するとき馬秣(馬のエサ)が不足して困った。 そのとき海人族の勧めでホンダワラをとり、馬を飼った」、というのが由来とされる。 すなわち神功皇后の率いる神の馬の食べる藻=神馬藻と書くようになった。 2024.12.20 記す。
★みずくらげ P.232 たこの口はどこにある? あのまるいのは頭でしょう?
泳いで来たのか漂って来たのか、そこに入江には、手のひらにすくいあげてもなおはみ出すくらいのみずくらげが沢山浮いていた。これはあんどんくらげのように刺さないことを知っていたので、掬いあげては放りなげた。寒天質がぷりぷりしていて、どっしりとした重みがある。 僕は友だちと二人で、入江を出て、沖の岩まで泳いで行こうとした。もちろん、旧い夏のことである。岩は潮がひいている時でもやっと五六寸出ているくらいだったので、潮がみちて来たり、波のある時には近よれなかった。けれどもこのやっと二人がのれる孤島にいると、魚の群のとおるのもよく見えた。 みずくらげはその中で顔などというものは水に流したsというふうに魚の方は見ない。 ※参考:和名ミズクラゲは、体が透けており水と見分けがつきにくいこと、また水分を多く含み水っぽいことなどからの命名と見られる。 傘に4つの目玉状の模様が現れることから、ヨツメクラゲ(四ツ目クラゲ)と呼ぶ地方がある。 これは目ではなく胃腔と生殖腺である。 英名は他の近縁種も含めてmoon jelly(月のクラゲ)と呼ばれる。 2024.12.18 記す。
★雪渓虫 P.233 雪に棲む虫は、このかわらげの類でも幾つかいて、冬の雪深い山で、いかにもその場所を間違えたというように無器用に歩いているのを見かける。 この雪渓虫(せっけいむし)は、冬も出るのかも知れないが、夏の残雪の上を歩いているので、歩き方は同じようによたよたしているが、涼しさを求めている一種の虫の智恵を思わせる。 ある山小屋の主人が訊ねる。この虫はどういうふうにして生きているのかまだ分っていないっていうんだけれど、ほんとかね。確かに、「生活史は明らかでない」と本に書いてある。誰かしらべているかも知れない。そんな研究はしていないかも分からないが、それを僕がしてはいけないのかしら。
雪渓から蒸気がのぼり始める夏の朝、その夜をどこでどんなふうにすごしているのか、やっと一センチほどの、翅のない細い黒い体で、彼らはどこへ行こうとしているのだろうか。 散歩ですよ、と彼は言うだろう。 2024.12.25 記す。
★蠍 P.234
さそりを僕は漢字で、蠍と書くことがあるが、活字になるとときどき蝎(読み:てらむし)になって来る。僕はさされたこともないし、よく言われるように長靴の中にかくれているのを見付けたこともないが、満州へ行った父が、お土産にさそりのアルコール漬を持って来てくれた。それが何年も机の上にあった。極東蠍だったのだろう。
この毒のはいったふくらみのある針は、僕にいつも緊張した状態を呼び起こしたが、うっかりしている時というのはたくみに用心のすき間をねらっているから、さそりのいる国へ行ったら必ずやられるだろうと思った。踏んだと思ったら、思い切って踏みつぶしてしまえばいいということであるが、これは並大抵の勇気では出来ない。普段からそれだけの度胸を身につけているためには、何を踏みつけて練習したらいいのだろうか。 幸いにして、僕はサソリに対して警戒を必要とする国には4いない。天井に長々とのびている巨大な星のサソリを見て、古い夏のことでも想い出していればいいのである。毒針のところには、Gとかλとか、かわいい星が集まっている。 ※参考:ギリシャ神話では、乱暴者の狩人オリオンを殺したサソリとされており、この一件以来オリオンはサソリを恐れるようになったといわれている。 夏の星座である「さそり座」が地平線から上ってくると「オリオン座」が沈み、反対にサソリが沈むとオリオンが上ってくるという、星座の位置関係を上手く表わした神話だ。 2024.12.26 記す。
★ひとで P.235 ほでは」海星と書く。そのほかに書きようががない。人間の描く星である。油壷の臨海実験所へひと夏に何度も出かけたことがある。僕は水槽の中に生きているものや、アルコール漬になっているものをそれほど丹念に見てはいなかったが、だんだんに海の動物に知り合いが多くなって来た。 ある時、ひとでの前で、その生態を大きな声で説明していた人がいた。彼は蛤をつかまえて、根気よく二枚の貝をひらいて、自分の胃を外へ出して食べるというようなことを説明していた。本当かしらと思いながら聞いていた。それは今になって調べてみると嘘ではないらしい。貝を開けるのには、蛤と三十分ぐらい引っぱり合いをしていると、蛤の方が力尽きて貝を開いてしまうということである。
僕はぽかんとしてしまった。海の底や磯には大変な世界があるものだと思った。少年の僕をつかまえてしまったその驚異の世界からつれ出してくれたのは何か。
一人の少女が、ひとで、ひとでと言いながら、ひとでと自分の手とを見くらべているのを見たのである。 これは僕と自然との関係を自分自身に説明する一つの秘密である。 ※参考:東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所(通称:三崎臨海実験所)は神奈川県三浦半島の西南端に位置し、半島の東側は東京湾、西側は相模湾に面しています。 世界的にも稀な豊かな生物相を有するこの地を動物学研究の拠点とするため、東京大学三崎臨海実験所は1886年(明治19年)に現在の三崎の町にわが国最初の、世界でも最も歴史の古い臨海実験所の一つとして設立されました。1897年(明治30年)に、より生物相の豊かな油壺に移転して現在に至っており、2016年には創立130周年を迎えました。設立以来、多数の国内外の研究者・学生に利用され、その数は年間延べ2万5千人にもなります。 わが国における生物学の発展に大いに貢献をしており、世界的にも、ウッズホール(米)・ナポリ(伊)・プリマス(英)の各実験所と共に海産動物研究の歴史に大きな足跡を残しています。 ※参考:ヒトデの名前は形が人の手に似ていることに由来します。 英語ではスターフィッシュ(星の形をした魚)と呼ばれています。 タッチングプールなどでは常連の生物で、子供たちにも人気のある癒やし系生物の一つです。 2024.12.26 記す。
★こばいけいそう P.236 ばいけいそうよりは小さいとはいえ、高山帯の植物としては大柄で目立つから、これは案外名前を知っている人が多い。そして写真機を持っていると撮りたくなる花である。
Sさんとこの時一緒だったんじゃありませんか。僕はかなり前にSさんから、こばいけいそうの写真を貰ったことがあるが、写された花が、どうもそれと同じものと思ったので、こんな失礼なことを言ってしまった。しかしそれはそのとおりだった。 これは別段、何の事件の原因ともならない。実をいうと僕は、写真に書く文句を考える時間をかせいだが、何と書いたかは全く想い出せない。 2024.11.05 記す。
★きばねしりあげ P.237 二十数年前に何度か登った谷川岳のカタズミ岩へ、もう一度登ることは去年から僕のひそかな念願だったが、息子とザイルを結んで、霧と雨との中を登り、KⅢの頂上に立った。ぐっしょりぬれたシャツの僕たちは、なにも見えない濃霧の渦の中で寒かったが、それぞれにうれしかった。
2025.01.12 記す。
★鹿子蛾 P.238
毎年、梅雨があけるころになると鹿子蛾(かのこが)が姿を見せる。彼女は日中出歩くのが好きなので、あらかじめ夏の烈しい日光と、それが草かげにもれて来る時のまだらの文様を考えて、こんな翅をひろげている。黄色の帯を、一つは胸の上高く、一つは腰の下低く、二本しめている。
僕は彼女に壜にはいってもらい、例によってまず写生をしていると、このガラスの内側を尻の先でさぐるようなことを始めた。お産が始まる。時計の秒針と、くり出されてくる象牙色の小さな卵を見くらべ、うみつけられる卵の順を記録しはじめた。約四十秒に一個、八個ほどうむと三分休憩をする。僕はついに負けた。二百数十個の卵を三時間以上かかってうむ彼女を最後まで見ている根気はなかった。 ところで小さいながら二百数十の生命を僕は預ってしまったのだろうか。鹿子蛾の幼虫の食卓も分かっている以上、飛び立って行くまでは世話をしなければなるまい。 派手な着物を着たご婦人に僕はつかまってしまった気さえする。もちろんつかまえたのは僕なのだ。一つの生命を預るつもりで、こんなことになろうとは思わなかった。心すべきである。 ※参考:カノコガは「鹿子蛾」と書き、蛾の一種で、成虫の翅が黒く、半透明の斑紋がある。 それが鹿の子供の背中の模様に見えることに由来するという。 2024.12.26 記す。
★クレマティス P.239 デュアメルの『わが庭の寓話』は僕の愛読書というより、もっと大切な本だが、その中の「完全のための弁護という章でプレーズが次にように言う。尾崎喜八さんの訳を拝借する。「森や垣根のテッセンの花は綺麗ではないけれど、なんとも言えない佳い匂いをただよわせている。園芸家はそのテッセンに手を加えて、不自然なものして、すっかり形を変えてしまった。君たちの青や赤のテッセンは目ざましい花は咲かせるが匂い」というものを全く持っていない。してみると、僕等は成る力を獲得することはできるが、そのためには別の力を失わなければならないという事になる。なんという苛烈な哲学だろう!」
そのテッセンはフランス語で La elematite であるが、「森や垣根のテッセン」のは、日本の仙人草やぼたんづるによく似たヨーロッパ産の白い花の咲く野草の C. Vitalilba に、東洋種のものを交配させた園芸種のことだろう。したがってプレーズは、このために暗い気持ちになる必要はなかったのである。
僕の記録の中に採取されているクレマティス属の花には、信州高遠の、蓮華寺の裏手にある輪島の墓に咲いていた「かざぐるま」がある。初夏になると、「テッセン」と言って花屋に並ぶものである。 ※テッセン ... テッセン (鉄線、学名: Clematis florida)は、キンポウゲ科センニンソウ属のつる性植物。 ... また、クレマチスを指して「テッセン」と呼ぶこともある。
★菜亀 P.240
近くの畑に昼顔が咲いていた。もうこの畑は今年は耕作しないで、家が建ってしまうらしい。ひとたび農夫が棄てると、畑は大急ぎで原野に戻ろうとする。その昼顔にしばらく目をとめていると、ながめがいっぱいいる。臭いかめむしの仲間で、あぶら菜や大根にたかって害をするため「菜亀」という名がついている。
ところが数十匹かたまっているうちの大部分はまだ幼虫で、背中の文様がちがうし、成虫のように肩がいかっていない。しかし幼虫も手でつかむことをおそれるほど臭い。なぜこの虫はこんなに臭い必要があるのだろうか。 彼らの体の一部には臭腺があって、そこから特に刺激をうけて出す分泌物が臭い。このにおいをいやがるのは人間ばかりではないので、やはり自分の体を守るためということになるなのだろうか。これに関しては他説もあるようだが、この臭気のために人も手を出さず、いやがるものばかりなので、それでこんなに黒とオレンジの派手な色をしていても、ちょっと葉かげに身をかくす程度でどぎまぎしないのだろう。 数匹持ちかえろうとして、毒壜を近よせると、ぽろりと落ちる。それを拾いあげるのには僕にもかなりの勇気が必要だった。 ※参考:ナガメ(菜亀、学名:Eurydema rugosa Motschulsky, 1861)は、カメムシ目カメムシ科の昆虫。和名は「菜の花につく亀虫」の意味で、アブラナ科の植物に集まることから名づけられた。 2025.01.13 記す。
★無花果(いちじく) P.241 僕がいまいる家に越して来た時には、裏庭の方に無花果(いちじく)がいっぱいあって、ちょうど夏の終りころだったので沢山なっていた。割ると中に蟻がはいっているようなのが甘くておいしかった。そしてこんなに沢山のこの果実を食べたことはこれまでになかった。それがニ三年後に、かみきりむしにやられて、一本ずつ倒れ、今では一本も残っていない。果物屋で買って食べるほど好きではない。その木が倒れる前に、かみきりむしは、ドリルで穴をあけるように、地面にいっぱい木の粉を落すのが痛々しい。
花嚢の中に白い小さい花が出来るが、それを割ってしらべるよりも、そっとしておいて熟してから食べたいと思うので、この花はなかなか見る機会がない。
「誓書」の中には変な話がよくあるが、イエスが腹を4へらし、遠方に無花果を見てそばへ行くと葉ばかりである。実のなる時節ではなかった。そこで「今後爾の果を食う人あらざれ」と言うと一晩でその木が枯れてしまったというのである。ずいぶんひどいことをしたものだと思う。あるいはかみきりむしが喰っているのを見て枯れるのが分っていたのかも知れない。 2024.11.27 記す。
★銀竜草(ぎんりょうぐさ) P.242
姿が全部白いというのはどうしてこんな薄気味の悪さを感じさせるのだろうか。昔、高野山の墓場で雪ゆかたを着た尼さんにばったり出会ってふるえ上がったことがある。 僕は南アルプスの赤薙川(あかなぎかわ)を最後のところで尾根にとりつき、二千メートルほどのところを雨にぬれながら登っている時に、たくさんの銀竜草を見たので、それになれて来たが、軽井沢にいる姉からうけ取った葉書にまだ返事を出してないことを想い出した。 「庭のすみにふしぎなものを見つけました。茎の高さ五センチ、花一センチ、茎も花も葉もロウソクのように真白で半透明」 銀竜草の説明はこれで十分であるが、大分おくれて出すことになるこの返事に、何かうまい文句はないものかと考えながら広河原峠へ着いた。 2024.11.27 記す。
★はしぶとがらす P.243 富士川の河岸で、流れを一時間半ほど眺めていた。もう山から下りて来てしまった僕はつまなそうな顔付だったかも知れない。渡って行くほど浅くはない流れの向うに大きな中州があって、そこにカラスが二羽歩いていた。歩いていたり、雀のように足をそろえてはねていたりした(黒崎記:ホッピングと言う)。
カラスは夏の終りころまでは集団生活をせずに、家を持って子供をそだてる。この二羽のハシブトカラスはどういう関係かよく分らない。夫婦というより親子のように思えた。
川岸の家から、娘さんがバケツを持ってごみをすてに来る。ニ三分後に一羽はそこへやって来て餌をあさり、何か大きなものをくわえて行った。待っていたもう一羽がそばによると、それを仲よく食べていた。雲のあいだから時々、まだ暑い陽のもれて来る河原で、彼らはやがて加わる集団への心構えをつくっていたのかも知れないが、お互いに黒々と胸を張り、面倒なことは何も考えずに、川を渡る風に向って、静かな呼吸をしているように見えた。 ※参考:ハシブトガラスは太いくちばしを持つ都会派のカラス ハシブトガラスの名前の由来は、「ハシブト=くちばしが太い」こと。 名前の通り、立派な太くて湾曲したくちばしを持っています。 2024.12.16 記す。
★さるとりいばら P.244 動物の中でも賢いことになっている猿でもこの刺にはひっかかる。ことりとまらずとか、へびのぼらずとか、動物の動作を、その植物を見て何とはなしに想像させるのはおもしろい。
田舎住いをしていた時分、幼い子供がどうしても昼寝をしないような時、無理に寝かそうとしてもつまらなくなり、河原へ遊びに行く。石ころのあるところばかりを歩いていればいいが、川の水の曲り具合でそうばりも歩いていられず、藪にはいると、子供は急に声を出すことがある。 そんな時に見ると、さるとりいばらにかかって、小さい草履をはいている足があわれに見える。仕方ながなく背負って、手をうしろへ回して歩いていると、今度は僕がこれにやられる。早く赤い実が出来てくれれば、それを危険信号にしてよけて行くが、緑っぽい花の時にはだめだ。どうしてこんな意地の悪い草がはえるのだろうと思う。 2024.11.05 記す。
★たから貝 P.245 昔はたから貝とだけ覚えていて、それで海岸でこれを見つけたりすると、お金を拾ったように思い、少しはうれしい気がした。それともたから貝という名を知っていたからだろうか。 この貝には、今少し思い出してみると、黄色たから、ほしだから、子安貝などがある。特に八丈だからとも言っている子安貝は、その模様がある種の猫に似ているので、僕の幻想はひろがった。そのころ猫を飼ったことがなかったために、却って、眠ってしまった猫がこういうものではないのかと思って、その冷たさが不思議だった。 それで今でも、昔呼びならわしていたように、これはネコッカイと、訊ねられると口許まで出て来る。
僕はこれを湘南のある海岸で幾つか見つけてから、大切に艶を出して持っていたが、ひょっとした加減で、ぶちの文様が無闇と薄気味悪くなり、こんな皮膚病にかかったようなものをいじっていると、自分にもそれがうつって、背中にぶちぶちのあざが出て来るように思った。
さてそれからしばらくのあいだ磨きをかけて大事にしていたこの貝はどうなったのだろうか。誰にやってしまったのだろうか。 ※参考:タカラガイの名前は、昔この貝がお金として使われていたのが由来。 この日はたくさんおちてました。 貝の中に模様があったり、タカラガイ探しは面白いですよ! ちょっと形が変わっていますが、ヘビガイは様々な形があり、とぐろを巻いていないようなものもあります。 2025.01.13 記す。
★赤とんぼ P.246 上越国境の尾根を、天幕を背負って歩いていた。もう山では秋風が、夜なんぞは天幕をぱたぱた言わせていた。
僕は忘れることもないはずのこの蜻蛉(とんぼ)のことをやはり手帳へ書く。やや正確のつもりで、あきあかねの群と。しかし果してあきあかねで誤りないだろうか。なつあかねかも知れない。その区別は胸側斑や生殖鈎(せいしょくこう)を、むしろ異常な辛抱強さをもって比較する必要があって、いまはもう秋だから、あれはあきあかねだと呼ぶことは非常に危険なのである。そのために、赤とんぼという名も残しておいてもいいだろう。 2024.12.09 記す。
★葉鶏頭(はげいとう) P.247 鶏の頭というものを、特にその鶏冠(とさか)を美しいと思う人はあまりない。それはどう見ても、もう手当の仕様のない、ひどい皮膚病である。けいとうの花にはずいぶん異品があって、それぞれ名前がついているが、その赤い部分の気味の悪さはさほど変わらない。けれど葉鶏頭の葉の赤さはちがった趣があって、これをいっぱい植えてある庭の秋は真赤にもえる。 いつか訪ねた家の庭は葉鶏頭だらけで、これは恐ろしくきれいなものだと思った。 外国へ行ったまま帰って来ないそこのご主人が、葉鶏頭が好きで、それで早く帰って貰いたい気持ちから庭をこんなふうに飾っているのだと説明された。
小学二年になるお嬢さんが、この赤い葉の中に分け入って、姿が見えなくなって歌をうたっていたのが大層印象的で、御主人は遠い国でどんなことをしているのか知らないけれど、早く帰って来ればいいににと思っ
★椋鳥 P.248 ニ三年前まで秋に「なると椋鳥(むくどり)がよく庭へやって来たが、昨年は庭に来ているのを見かけなかった。体が大きいので、ほかの小鳥たちをいじめるのではないかと思うが、そんなことはしない。あまりきれいな鳥とは言えないが、嘴と足との黄色なののが得意でないこともないらしい。 鳥を見るとすぐうぐいすだろうかと考える者がいるが、内田清之助氏の試食したところによると、うまくはないそうである。それと、この鳥は千羽に一羽、毒を持っているから食べてはいけないという言い伝えがある。それは嘘なのであるが、こうして非常に巧みな言い方をして、この益鳥を保護してやろうとしたものらしい。
また椋鳥のむれと出会うために、半日ほど林を歩いてみよう。椋鳥は一羽一羽の顔付などは分からないので全部椋鳥である。それで何年たってもあの鳥だと思って懐しむ。
2024.12.16 記す。
★縷紅草(るこうそう) P.249 kusida.mukudori.png
普段は通らない道であるが、僕の家から駅へ出るのにそれほど回り道にもならない。その道の曲り角の家の垣根に毎年縷紅草(るこうそう)が咲く。紅色の花のうちでは小さくて好きだが、僕の家にはない。一度作ってみたのは、まるばるこうの方で、その心臓型の葉は花に対して少々大きすぎる。縷紅草の方は葉が猫の骨のようで、花に似合っている。
この縷紅草の花が咲く家は、今はどういうことか空家になって、ここしばらく雨戸が開かない。別にそれほど気をつけている訳ではないが、実によく持ち主が変わる。十年のあいだに七八回は表札が変っただろうか。いつかはどこかの会社の寮になった。二階の廊下にそれぞれの人の着物がいつもほしてあるような時代もあった。
2024.11.24 記す。
★すすき P.250
どうせわたしはかれすすき……
僕はそうでもないと思う。しかしまたそうかも知れないと思う。「枯れすすき」の歌は亡国の調べだそうである。
けれども今は、虫めがねをもって、その披針形の小穂を見る。秋の七草の一つとしてではなく、また尾花の姿にひかれることもなく、はっきりと知らないものを念入りに見るために。
すすきの葉はつかまると手を切る。つかまえるならば、ぎゅっとにぎらなければならない。臆病な握り方をしていると手が切れる。それは確かに一つの風刺である。つかまえようとさえしなければ何の心配もない。
参考図書:野外観察ハンドブックー① 山野の鳥 <財>日本野鳥の会
野外観察ハンドブックー② 水辺の鳥 <財>日本野鳥の会
|
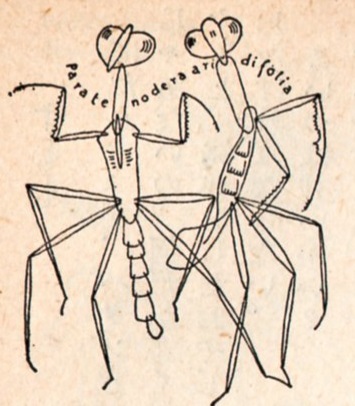 うっかりしていると、なかなか凝ったことをする友だちのことだから、このぬけがらを僕に送ってくれたことによって、彼の思想的脱皮を伝えているのかも知れない。あるいは、彼にとっていま重要な間柄にある彼女が脱皮したことを知らせてくれたのかも知れない。僕はさっきからルーペをもって、その衣装の検査を続けているのだが……
うっかりしていると、なかなか凝ったことをする友だちのことだから、このぬけがらを僕に送ってくれたことによって、彼の思想的脱皮を伝えているのかも知れない。あるいは、彼にとっていま重要な間柄にある彼女が脱皮したことを知らせてくれたのかも知れない。僕はさっきからルーペをもって、その衣装の検査を続けているのだが……
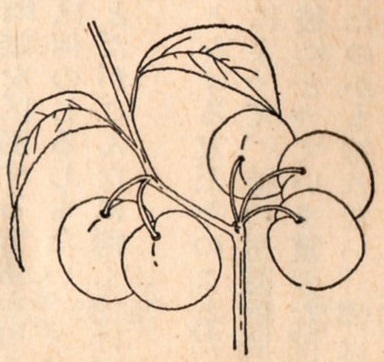 甘いですとも。
甘いですとも。
 恐らくその時のパッションは受難の意味ではなく情熱の方だろう。熱くして飲んでもよし、冷たくして飲んでもよい。
恐らくその時のパッションは受難の意味ではなく情熱の方だろう。熱くして飲んでもよし、冷たくして飲んでもよい。
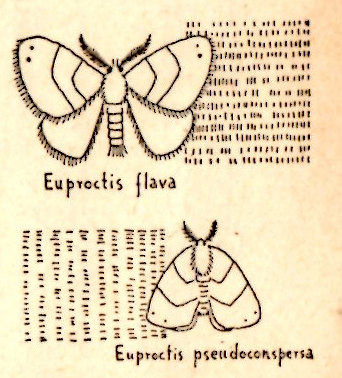
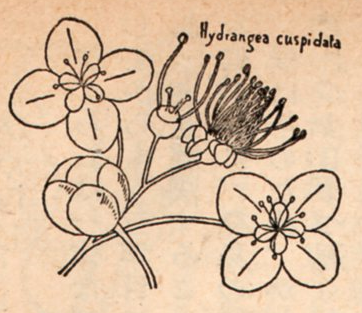
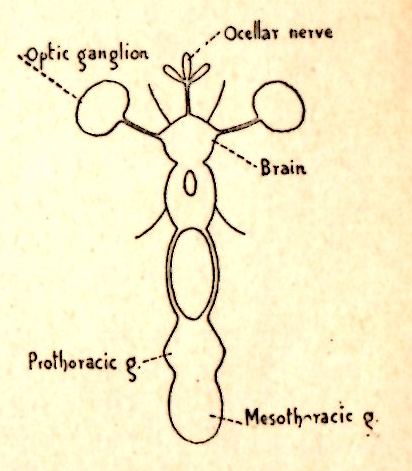 僕はそのため、かれこれひと夏、早起きを続けた。四時十五分、それが少しずつ遅くなってから鳴くようになる。そころになると床の中で僕の耳はぴんと立って来るようだ。遠くの方で一匹鳴き始めると、それにつられて方々でカナカナがはじまる。旧い夏の想い出をカナカナはつれて来る。
僕はそのため、かれこれひと夏、早起きを続けた。四時十五分、それが少しずつ遅くなってから鳴くようになる。そころになると床の中で僕の耳はぴんと立って来るようだ。遠くの方で一匹鳴き始めると、それにつられて方々でカナカナがはじまる。旧い夏の想い出をカナカナはつれて来る。
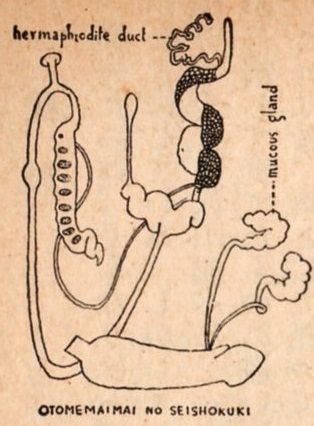 その息子が小学校へあがってしばらくしてからだ。先生は一匹のデンデンムシを板の上に這わせた。これは何というものか知っていますね。このことで、作文を書いてみることにしましょう。そう言ったのだそうだ。後で教室を参観に行くと、作文が貼り出してある。「おうちをかついでいるから、にげたくないのです」「ぼく、せんせいがさっきこれをひろっているのをみました。ちゃんとみちゃった」僕はわが子がどんなことを書いたか、それを読むのがつらいような気持になったが、ついにそれを見っけた。
その息子が小学校へあがってしばらくしてからだ。先生は一匹のデンデンムシを板の上に這わせた。これは何というものか知っていますね。このことで、作文を書いてみることにしましょう。そう言ったのだそうだ。後で教室を参観に行くと、作文が貼り出してある。「おうちをかついでいるから、にげたくないのです」「ぼく、せんせいがさっきこれをひろっているのをみました。ちゃんとみちゃった」僕はわが子がどんなことを書いたか、それを読むのがつらいような気持になったが、ついにそれを見っけた。
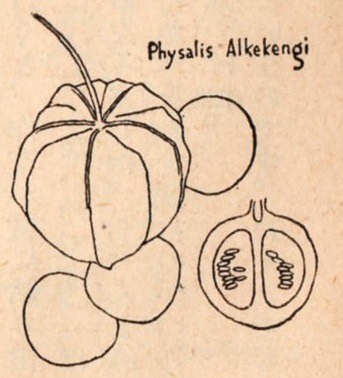 農夫たちは、せんなりほずきを、畑にはびこるということで目のかたきにしている。しかしまた、どこから運んで来るのか、観音様の四万六千日に沢山並べるせんなりほずきは、やっぱり彼ら農民たちが丹精して育てたものに違いない。
これは昔、薬として売っていたものらしい。解熱剤である。酸奨は何となく東洋的なので、文献を見ると、フランスでは、葡萄畑の、あの棚の下に沢山生えているようだ。百科事典では、果物の仲間にはいっている。僕は単純に一つの連想を作ってしまう。フランスのsる地方では葡萄酒のコップの底にこれを沈めておいて、いい加減の時にぶちゅっと噛むのかと思う。それでフランスでは酸奨のことを冬の桜ん坊といっているのかと思った。だが、この国でも何かの薬にしているだけだしい。
農夫たちは、せんなりほずきを、畑にはびこるということで目のかたきにしている。しかしまた、どこから運んで来るのか、観音様の四万六千日に沢山並べるせんなりほずきは、やっぱり彼ら農民たちが丹精して育てたものに違いない。
これは昔、薬として売っていたものらしい。解熱剤である。酸奨は何となく東洋的なので、文献を見ると、フランスでは、葡萄畑の、あの棚の下に沢山生えているようだ。百科事典では、果物の仲間にはいっている。僕は単純に一つの連想を作ってしまう。フランスのsる地方では葡萄酒のコップの底にこれを沈めておいて、いい加減の時にぶちゅっと噛むのかと思う。それでフランスでは酸奨のことを冬の桜ん坊といっているのかと思った。だが、この国でも何かの薬にしているだけだしい。
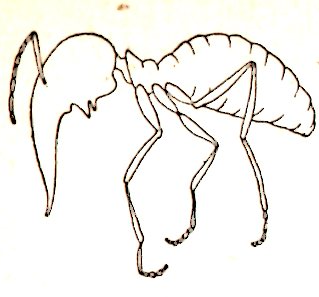
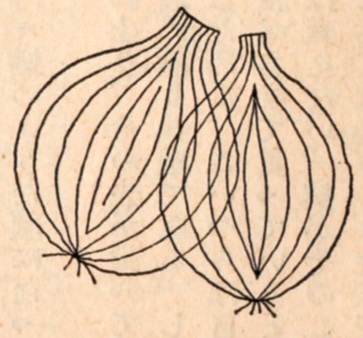 羅は、漬物屋の店先まで来ると、すっかり甘ずっぱくなって「楽京」と書かれる。猿が熱心に羅の皮をむいているのは昔からよくある光景だ。ただ、訊ねてみると、そんなところを実際に目撃した者はほとんどいない。みんな見たことがあるような気がしているだけだ。
羅は、漬物屋の店先まで来ると、すっかり甘ずっぱくなって「楽京」と書かれる。猿が熱心に羅の皮をむいているのは昔からよくある光景だ。ただ、訊ねてみると、そんなところを実際に目撃した者はほとんどいない。みんな見たことがあるような気がしているだけだ。
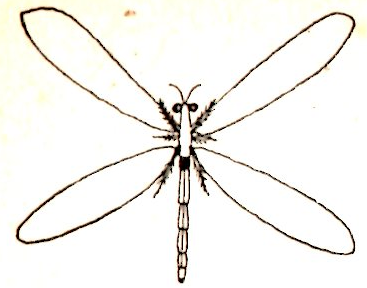
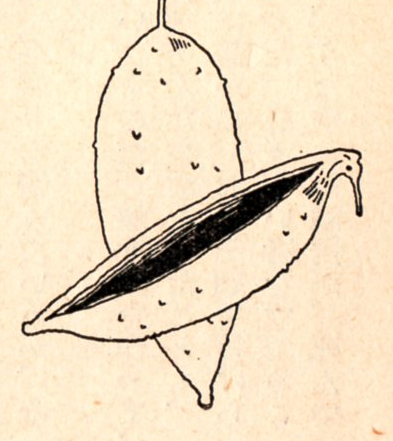
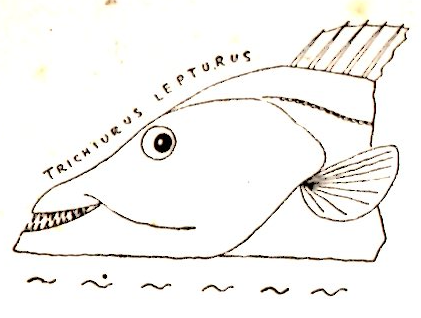

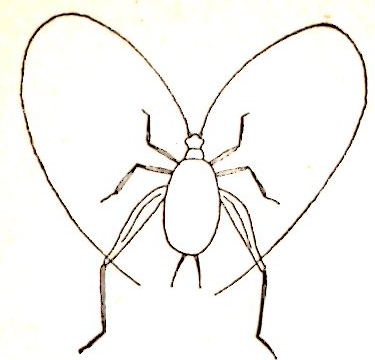 ところがある晩、机の上に置いたまんまの虫籠を見ると、西瓜の種みたいなけちなやつがいて、そこにあるふた切れの胡瓜(きゅうり)の上を這い回っていた。草の中にいる時とは大分ちがった、貧弱な鳴き声を聞いた時、これが草雲雀だと分かったが、僕は誰がつかまえてくれたのかも訊ねずに、その日の夕暮れに濠端へ逃がしに行った。
ところがある晩、机の上に置いたまんまの虫籠を見ると、西瓜の種みたいなけちなやつがいて、そこにあるふた切れの胡瓜(きゅうり)の上を這い回っていた。草の中にいる時とは大分ちがった、貧弱な鳴き声を聞いた時、これが草雲雀だと分かったが、僕は誰がつかまえてくれたのかも訊ねずに、その日の夕暮れに濠端へ逃がしに行った。
 ところが今年は僕もついに我慢出来なくなった。土手を下り、花壇の中にまで彼らは前進した。しかも何の宣言もなしに、庭の平和のためにこらしめなければならない。
ところが今年は僕もついに我慢出来なくなった。土手を下り、花壇の中にまで彼らは前進した。しかも何の宣言もなしに、庭の平和のためにこらしめなければならない。
 軍人さんはふふんという。そしてくぼんだ眼がぱちぱちと動いたようだ。そのうちこあじさしは五羽六羽と連れ立って銀座を越えて海へ帰って行った。僕はアナタモオ帰リニナリタイデショウとは言わなかった。
軍人さんはふふんという。そしてくぼんだ眼がぱちぱちと動いたようだ。そのうちこあじさしは五羽六羽と連れ立って銀座を越えて海へ帰って行った。僕はアナタモオ帰リニナリタイデショウとは言わなかった。
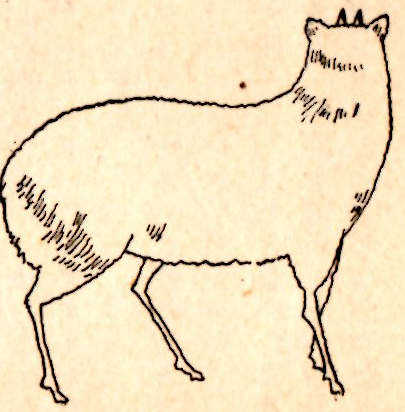
 さわっちゃいやって言ってるでしょう?
さわっちゃいやって言ってるでしょう?
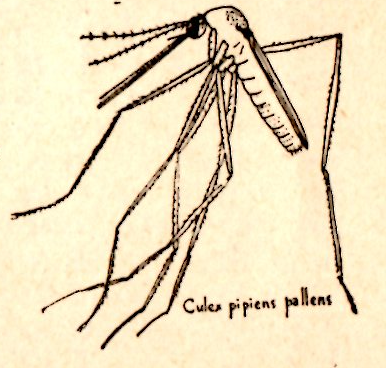 天気がいいので、夕方近く久し振りに写生をするつもりの散歩に出かけた。
天気がいいので、夕方近く久し振りに写生をするつもりの散歩に出かけた。
 例えばかつて、『蝶の生活』という、ドイツの愛蝶家フリードリヒ・シュナックの本の翻訳が出た。そこでは、にむらさきが群れて水を飲み、宝石のように連なっていた。そして「翅の表面に天鵞絨(ビロード)からは眼の覚めるような光が反射してくる」
例えばかつて、『蝶の生活』という、ドイツの愛蝶家フリードリヒ・シュナックの本の翻訳が出た。そこでは、にむらさきが群れて水を飲み、宝石のように連なっていた。そして「翅の表面に天鵞絨(ビロード)からは眼の覚めるような光が反射してくる」
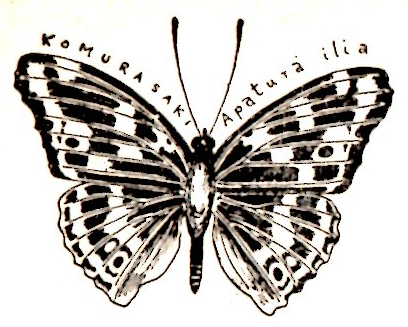
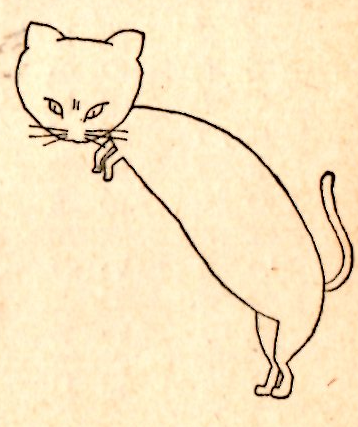 それが、数えれば腹の立つほどの多量の魚を食べ、また驚くほどの魚の頭を喰い残しながら成長し、十九匹のボーイフレンドを作り、うっかり、見てしまった僕もぞっとするような享楽に耽った末に、チビを三匹産んだ。あまり美貌とも思われなかったものを選んだことが、子猫の毛色から判って、僕は一応溜息をついたが、どうにもならない。
それが、数えれば腹の立つほどの多量の魚を食べ、また驚くほどの魚の頭を喰い残しながら成長し、十九匹のボーイフレンドを作り、うっかり、見てしまった僕もぞっとするような享楽に耽った末に、チビを三匹産んだ。あまり美貌とも思われなかったものを選んだことが、子猫の毛色から判って、僕は一応溜息をついたが、どうにもならない。
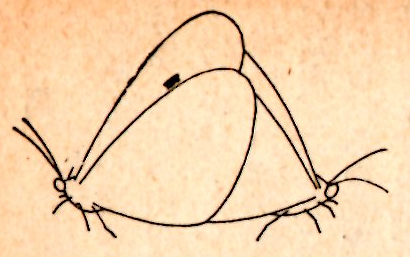 キャベツたちはこの雌の蝶が、お尻をまるで猫の尻尾(しつぽ)のようにぴんと立てて雄を待っていた姿を知っていた。その翅のひろげ方。羞恥を脱ぎすて蹴飛ばしてしまった容子を想い出す。紋白蝶は、よごれて裂けた翅で自分を浮かせているのがやっとだ。産みたまえ、どこへでも構わない。そう言われて紋白蝶は決意の産卵を始める。お尻を今度はつの字に曲げて。
キャベツたちはこの雌の蝶が、お尻をまるで猫の尻尾(しつぽ)のようにぴんと立てて雄を待っていた姿を知っていた。その翅のひろげ方。羞恥を脱ぎすて蹴飛ばしてしまった容子を想い出す。紋白蝶は、よごれて裂けた翅で自分を浮かせているのがやっとだ。産みたまえ、どこへでも構わない。そう言われて紋白蝶は決意の産卵を始める。お尻を今度はつの字に曲げて。
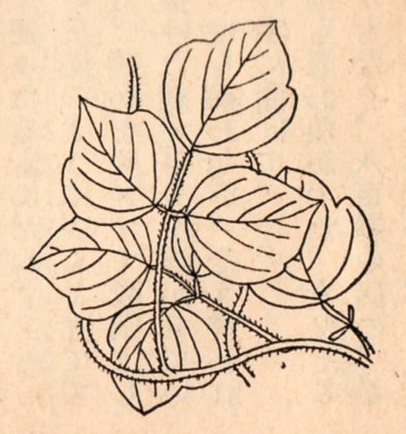 僕はそれまで老人の寂しさというものをどうでもいいと思っていたが、こんなことがあった。お前何かすることあるのか。おれもやるから、あの葛を退治してくれないか。老人の顔と、風にあおられは白々とする葛を見較べているうちに、老人の寂しさが分って来た。
僕はそれまで老人の寂しさというものをどうでもいいと思っていたが、こんなことがあった。お前何かすることあるのか。おれもやるから、あの葛を退治してくれないか。老人の顔と、風にあおられは白々とする葛を見較べているうちに、老人の寂しさが分って来た。
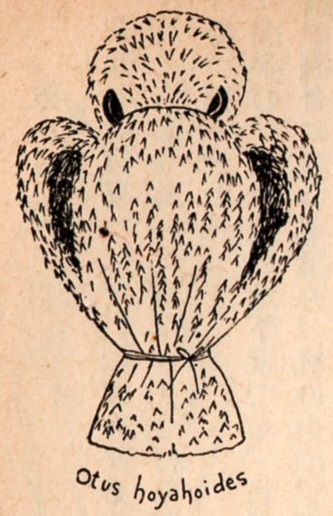 しかし、幾らウフウフと鳴いても、眼光は炯々(けいけい)としていても、何となく悲しい姿である。大正生れの僕は「枯れ芒(すすき)」の歌を知っている。漢文の先生が、こんな悲哀荒涼の調子の歌が流行してと言って涙を流してなげいた。その枯れ薄で作られた木菟は、言い忘れたけれど純国産である。
しかし、幾らウフウフと鳴いても、眼光は炯々(けいけい)としていても、何となく悲しい姿である。大正生れの僕は「枯れ芒(すすき)」の歌を知っている。漢文の先生が、こんな悲哀荒涼の調子の歌が流行してと言って涙を流してなげいた。その枯れ薄で作られた木菟は、言い忘れたけれど純国産である。
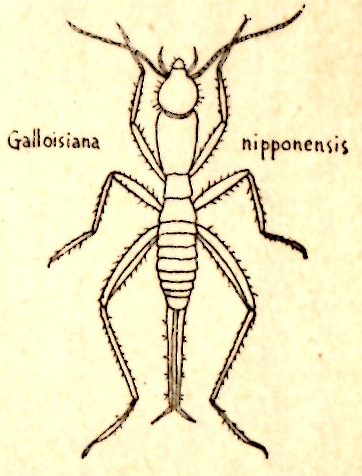
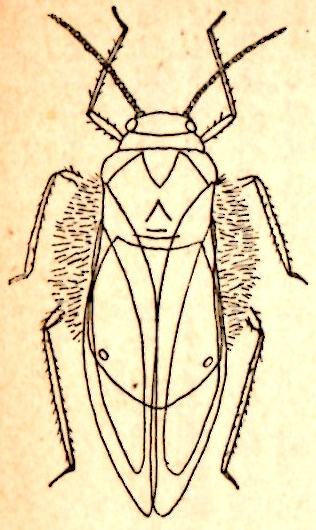


 ごろごろの石も濡れている。そんな渓谷を、しきりに背黒鶺鴒は、二羽三羽、それ以上多くは群れずに、上流へ向ってあとからあとから、幾らでも飛んで行く。時々、雨の降りかかる河原の石を尾羽で叩きながら休んで行くのもある。鰊(にしん)を吊した綱を川に張り、それに蟹を喰いつかせて採っている男が一人いる。笹舟の一番先に体を乗り出し、綱を手繰りながら川の中央ぐらいまで進んで行ったが、また岸へ戻って来た。一体どんな蟹がとれるのかと思ってその男に訊ねたが、もうこのところ、山の沢に散り込んだ紅葉がこの川にもいっぱい流れ込んで来て、そのために餌にしてある鰊がかくれ、今日は一匹も採れないという。もうこの蟹採りも終りらしい。
ごろごろの石も濡れている。そんな渓谷を、しきりに背黒鶺鴒は、二羽三羽、それ以上多くは群れずに、上流へ向ってあとからあとから、幾らでも飛んで行く。時々、雨の降りかかる河原の石を尾羽で叩きながら休んで行くのもある。鰊(にしん)を吊した綱を川に張り、それに蟹を喰いつかせて採っている男が一人いる。笹舟の一番先に体を乗り出し、綱を手繰りながら川の中央ぐらいまで進んで行ったが、また岸へ戻って来た。一体どんな蟹がとれるのかと思ってその男に訊ねたが、もうこのところ、山の沢に散り込んだ紅葉がこの川にもいっぱい流れ込んで来て、そのために餌にしてある鰊がかくれ、今日は一匹も採れないという。もうこの蟹採りも終りらしい。
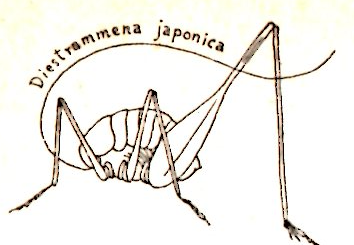
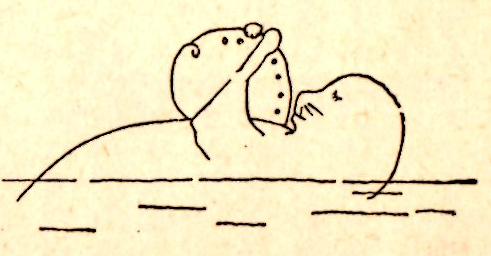
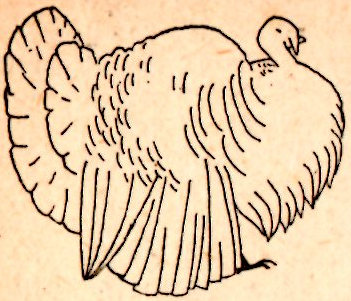
 まだ、べツレへムの星という名をつけられた花がある。ほそばのおおあまなと言われているオルニソガルム Ornithogalum umbellatum である。
まだ、べツレへムの星という名をつけられた花がある。ほそばのおおあまなと言われているオルニソガルム Ornithogalum umbellatum である。
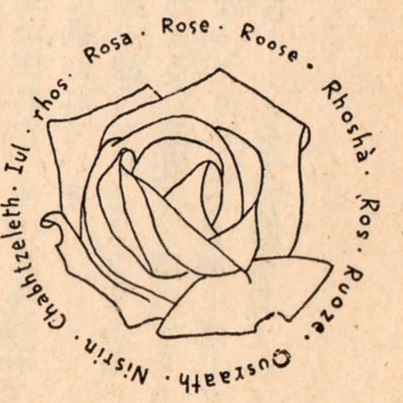 人間はこうして、食べることのできる薔薇の花を造っている。なぜ薔薇を食べようとするのだろうか。デコレーションケーキというものは、とかく争いのもとになることは承知の上で、人間は甘い薔薇を造りつづけている。子供たちも大人も、その花を堂々と、またひそかにねらう。それはこの花が愛のシンボルであるからでも、美しいからでもない。ただ甘いクリームのカタマリであるがために、むきになってジャンケンをする。
人間はこうして、食べることのできる薔薇の花を造っている。なぜ薔薇を食べようとするのだろうか。デコレーションケーキというものは、とかく争いのもとになることは承知の上で、人間は甘い薔薇を造りつづけている。子供たちも大人も、その花を堂々と、またひそかにねらう。それはこの花が愛のシンボルであるからでも、美しいからでもない。ただ甘いクリームのカタマリであるがために、むきになってジャンケンをする。
 小学校のころ、僕は濠端づたいに学校へかよっていた。三宅坂から半蔵門をとおって九段まで、朝は走り、電車にも乗り、帰りはぶらんぶらんと、傘なんか蹴っ飛ばしながら歩いた。その時、濠の水ぎわに、椎の実を並べたような日なたぼっこをしている彼らを羨ましがった。僕の学校では厳格なフランス人の先生がいて、休み時間に、校舎の日だまり並んでいる僕たちを、怖い顔して追っ払い、無理に遊ばせたからだ。貯水池の上を低空で、ばからしい速さで何とかいう飛行機が飛ぶと、まがもは青い首をのばして一応飛び立つ。それが小学生だった僕たちの容子に似ていた。
小学校のころ、僕は濠端づたいに学校へかよっていた。三宅坂から半蔵門をとおって九段まで、朝は走り、電車にも乗り、帰りはぶらんぶらんと、傘なんか蹴っ飛ばしながら歩いた。その時、濠の水ぎわに、椎の実を並べたような日なたぼっこをしている彼らを羨ましがった。僕の学校では厳格なフランス人の先生がいて、休み時間に、校舎の日だまり並んでいる僕たちを、怖い顔して追っ払い、無理に遊ばせたからだ。貯水池の上を低空で、ばからしい速さで何とかいう飛行機が飛ぶと、まがもは青い首をのばして一応飛び立つ。それが小学生だった僕たちの容子に似ていた。
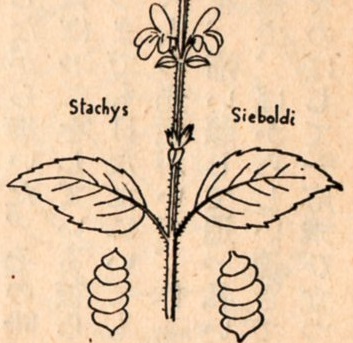 梅酢につけられたちょろぎを、普段食べようと思うとなかなか買えない。毎年正月になると、庭に栽培しようかと思う。そして山歩きの時に梅干しの代りに持って行ったらと思う。
梅酢につけられたちょろぎを、普段食べようと思うとなかなか買えない。毎年正月になると、庭に栽培しようかと思う。そして山歩きの時に梅干しの代りに持って行ったらと思う。
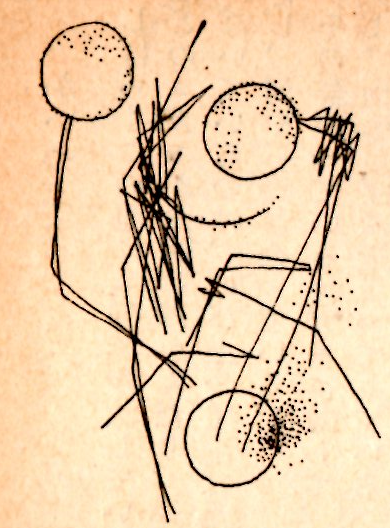 くものすかびの胞子嚢はまんまるである。僕の好きなダイヤモンド草の種みたいに可愛らしい。そして叩いてみればやはり正直に粉を出すし、その胞子のくっつき具合で、悪い癖だとは思うが、表情を見てしまう。それにしても、こんなにまんまるいものには、決して怖い顔を想像したり、意地悪の顔を考えることがない。どうしてなのだろうか。
くものすかびの胞子嚢はまんまるである。僕の好きなダイヤモンド草の種みたいに可愛らしい。そして叩いてみればやはり正直に粉を出すし、その胞子のくっつき具合で、悪い癖だとは思うが、表情を見てしまう。それにしても、こんなにまんまるいものには、決して怖い顔を想像したり、意地悪の顔を考えることがない。どうしてなのだろうか。

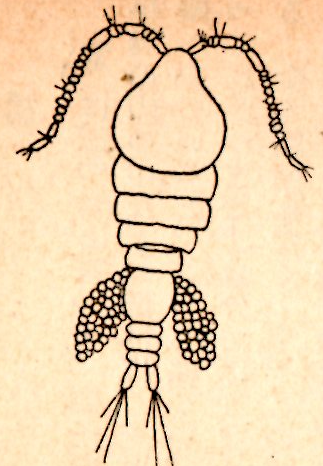
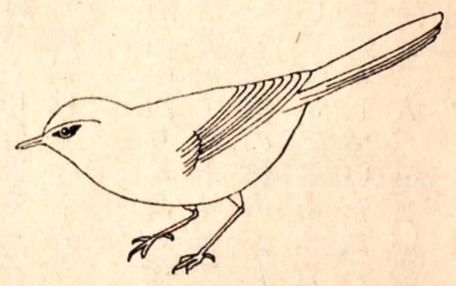
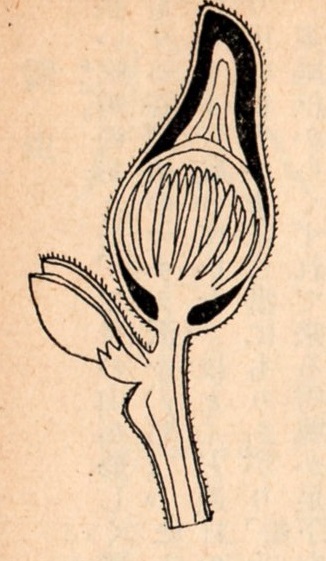
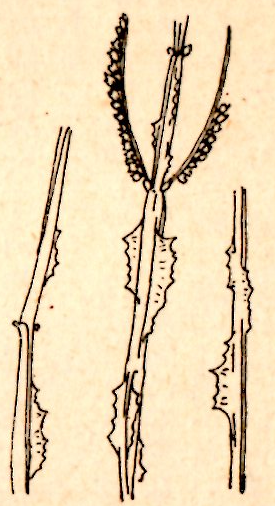
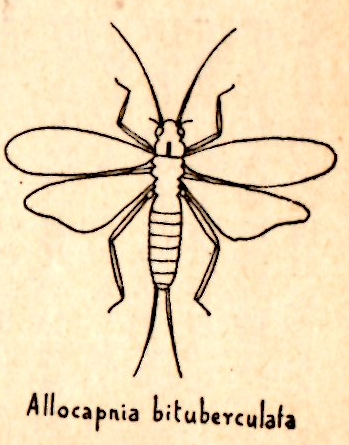
 そこで僕も念入りに図鑑を見たわけであるが、一体これはどこからやって来たのだろうか。「北海道に普通」と書いてある。北海道から何の知らせを持ってはるばるやってきたのだろうか。もうほとんど力尽きたように、机の上に仰向けになって、脚を行儀よく胸の上において死を用意している。夜更けの部屋はぐんぐん気温がさがる。こんな虫がひょうっこりとやって来たりすると、昔からの癖で、どうも何かの知らせのような気がしてならない。忘れていたことはないか。忘れていた人はいないか。
そこで僕も念入りに図鑑を見たわけであるが、一体これはどこからやって来たのだろうか。「北海道に普通」と書いてある。北海道から何の知らせを持ってはるばるやってきたのだろうか。もうほとんど力尽きたように、机の上に仰向けになって、脚を行儀よく胸の上において死を用意している。夜更けの部屋はぐんぐん気温がさがる。こんな虫がひょうっこりとやって来たりすると、昔からの癖で、どうも何かの知らせのような気がしてならない。忘れていたことはないか。忘れていた人はいないか。
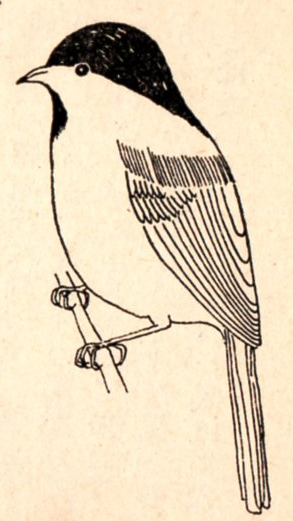
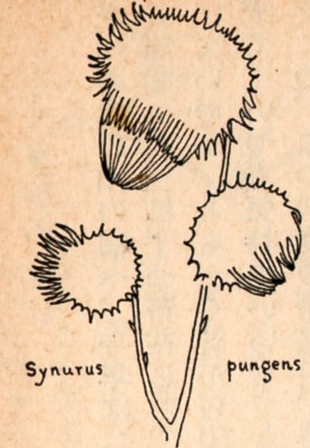
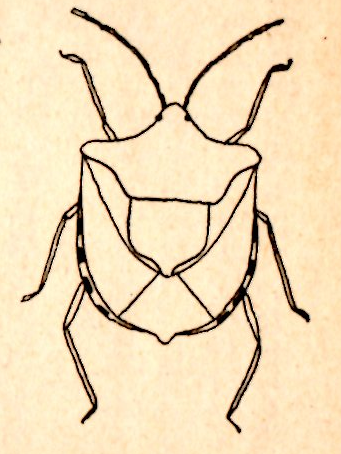
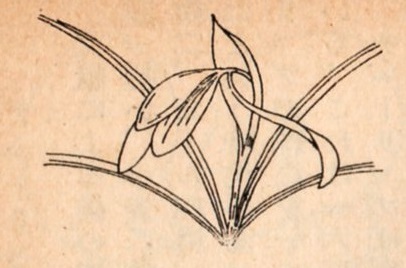 家の草むらも、そろそろ賑かになっえ来た。同じ場所に去年も全く同じようにお咲くものや、移動して澄ましているものもある。ほくろはその草むらのかげで大きく手をひろげて大地を抱えてみたいという姿だ。なぜかその顔をのぞいてみることも僕はためらう。さっきまで花の好きな友だちが来ていた。僕は話をしながら時々ほくろのことを想い出したけれど、とうとう見せなかった。
家の草むらも、そろそろ賑かになっえ来た。同じ場所に去年も全く同じようにお咲くものや、移動して澄ましているものもある。ほくろはその草むらのかげで大きく手をひろげて大地を抱えてみたいという姿だ。なぜかその顔をのぞいてみることも僕はためらう。さっきまで花の好きな友だちが来ていた。僕は話をしながら時々ほくろのことを想い出したけれど、とうとう見せなかった。
 チューリップは南欧には野生もあったが、栽培種が近東から入ったのは十六世紀後半で、たちまち大流行となった。この栽培種は突然変異で、さまざまの雑色の花が現れるのが特徴であるが、オランダの栽培家たちがこれに注目し、競って新種を作り出すようになった。そのため、貴族も農民も、また煙突掃除人までが商売道具を売り払って種子をまき、球根を育てて成金の夢を見、その投機に士農工商入り乱れて熱中し、花の美しさなどはどうでもいいことになった。一六三七年春、突如破局が来て取引は停止され狂瀾は終ったが、後この熱は英仏へ移り、アディスンやラ・ブリュイエールの文中に出て来る。デュマの『黒チューリップ』にオランダの狂乱時代を描いたものがある。彼はこの小説の中で、四月中旬に植えた球根を翌月初めに咲かせているが、これは少々無茶な話である。
チューリップは南欧には野生もあったが、栽培種が近東から入ったのは十六世紀後半で、たちまち大流行となった。この栽培種は突然変異で、さまざまの雑色の花が現れるのが特徴であるが、オランダの栽培家たちがこれに注目し、競って新種を作り出すようになった。そのため、貴族も農民も、また煙突掃除人までが商売道具を売り払って種子をまき、球根を育てて成金の夢を見、その投機に士農工商入り乱れて熱中し、花の美しさなどはどうでもいいことになった。一六三七年春、突如破局が来て取引は停止され狂瀾は終ったが、後この熱は英仏へ移り、アディスンやラ・ブリュイエールの文中に出て来る。デュマの『黒チューリップ』にオランダの狂乱時代を描いたものがある。彼はこの小説の中で、四月中旬に植えた球根を翌月初めに咲かせているが、これは少々無茶な話である。
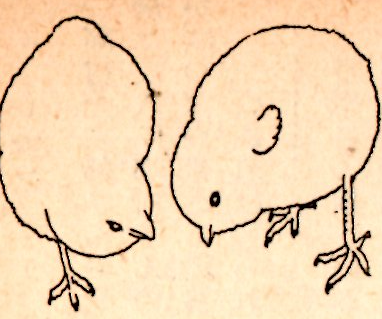 欅の梢のひよどりは黙ってしまう。そして枝から落ちそうに首をかしげている。仲間だぞ、おれたちの。確かに。あんなに厳重に箱にいれられんじゃあ、救ってやるわけにも行かないな。僕も考える。僕だって救ってやるわけにも行かない。自転車の振動で、すっかりとおびえ切っているひよこたちを、慰めてやることも出来ない。
欅の梢のひよどりは黙ってしまう。そして枝から落ちそうに首をかしげている。仲間だぞ、おれたちの。確かに。あんなに厳重に箱にいれられんじゃあ、救ってやるわけにも行かないな。僕も考える。僕だって救ってやるわけにも行かない。自転車の振動で、すっかりとおびえ切っているひよこたちを、慰めてやることも出来ない。
 三畳あれば寝られますね
三畳あれば寝られますね
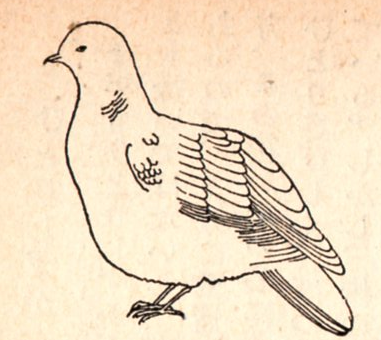 今朝は七時少し前に鳴き始めた。七時に目覚まし時計をかけ、昨夜どうしても終らせることの出来なかった仕事の続きにかかろうと思っていた。しかしあの声を聞くと急に体がだるくなり、目覚ましを鳴らないようにしてまた眠ってしまった。二十分ほどして目をさますと,まだ鳴いていたので、僕は雉鳩の顔を見てやろうと思って外へ出た。高い松の繁みにいるのが、芽を吹きだした欅をすかして見える。じっとしている。仲間を呼んでいるのでもないようだ。ただ鳴き止むのを忘れている。僕は冷たい水で顔をざぶんざぶん洗いたくなった。
今朝は七時少し前に鳴き始めた。七時に目覚まし時計をかけ、昨夜どうしても終らせることの出来なかった仕事の続きにかかろうと思っていた。しかしあの声を聞くと急に体がだるくなり、目覚ましを鳴らないようにしてまた眠ってしまった。二十分ほどして目をさますと,まだ鳴いていたので、僕は雉鳩の顔を見てやろうと思って外へ出た。高い松の繁みにいるのが、芽を吹きだした欅をすかして見える。じっとしている。仲間を呼んでいるのでもないようだ。ただ鳴き止むのを忘れている。僕は冷たい水で顔をざぶんざぶん洗いたくなった。
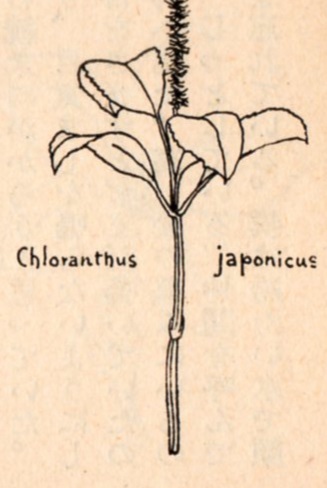 今年もひとりしずかが実に賑やかに咲いた。僕はこの花がちっとも嫌いではないし、前に拡大鏡でその裸花を写生したこともあるので、充分に愛着を持っているつもりだ。しかしまた一方、この花がその名にふさわしいように、藪の小暗いところに、ひとりさびしく、ぽつんと咲いているのを見たいものだと思っている。しかし、僕の庭に限らず、どこで見かける時にも沢山かたまって咲いている。
今年もひとりしずかが実に賑やかに咲いた。僕はこの花がちっとも嫌いではないし、前に拡大鏡でその裸花を写生したこともあるので、充分に愛着を持っているつもりだ。しかしまた一方、この花がその名にふさわしいように、藪の小暗いところに、ひとりさびしく、ぽつんと咲いているのを見たいものだと思っている。しかし、僕の庭に限らず、どこで見かける時にも沢山かたまって咲いている。
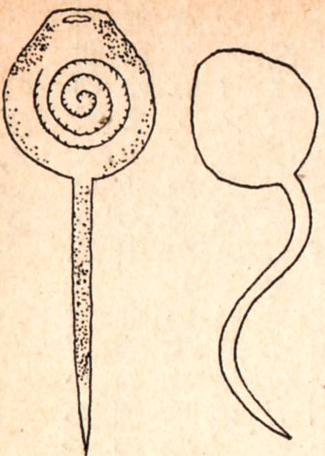 ところがある日、その何百というおたまじゃくしが突然全滅し、とろけてなくなってしまった。これには僕は唖然としたが、それは、同じ田んぼの水の中にいて、卵と一緒にすくいあげられ、ぴんぴんはねて、これらのおたまじゃくしのお守りをしていた一匹のぬまえびが瓶の中で死んだためらしかった。ぬまえびは、ガラスにうまく脚がひっかからず、脱皮しそこねて死んだらしい。その死とおたまじゃくしの死とのあいだには、プトマイン中毒か何かの作用があることは分かったが。僕の目には見えない大事件だった。「一瞬にして死の水と化する」事件が、蛙の世界にもおこったのである。
ところがある日、その何百というおたまじゃくしが突然全滅し、とろけてなくなってしまった。これには僕は唖然としたが、それは、同じ田んぼの水の中にいて、卵と一緒にすくいあげられ、ぴんぴんはねて、これらのおたまじゃくしのお守りをしていた一匹のぬまえびが瓶の中で死んだためらしかった。ぬまえびは、ガラスにうまく脚がひっかからず、脱皮しそこねて死んだらしい。その死とおたまじゃくしの死とのあいだには、プトマイン中毒か何かの作用があることは分かったが。僕の目には見えない大事件だった。「一瞬にして死の水と化する」事件が、蛙の世界にもおこったのである。
 犬という動物も、飼ってみると変なものである。欣然とすれば、それを隠したくも隠せないような、始末の悪い尻尾を持っているし、呼ばれても、面倒臭い時には、地面にすりつけたまま首をあげず、上目使いでこっちを見る。それで、わざわざトタンを買って来て、小屋を造り、乾いた藁を敷いてやったが、そこにいないで、土の上に寝そべっている。それで犬の方は知らないのに、地下の夏水仙は春の錯覚を起こして、早目に葉を出した。
犬という動物も、飼ってみると変なものである。欣然とすれば、それを隠したくも隠せないような、始末の悪い尻尾を持っているし、呼ばれても、面倒臭い時には、地面にすりつけたまま首をあげず、上目使いでこっちを見る。それで、わざわざトタンを買って来て、小屋を造り、乾いた藁を敷いてやったが、そこにいないで、土の上に寝そべっている。それで犬の方は知らないのに、地下の夏水仙は春の錯覚を起こして、早目に葉を出した。
 あの戦争は、虱と僕とを思い切り親しませた。想えば貴重な、実に嬉しい経験だった。彼らはシャッの緑地を遠慮深く一列にならんで歩いた。そして見つかると恐縮して動かない。半透明な体の中で、心臓がふるえているのも分かるようだ。
あの戦争は、虱と僕とを思い切り親しませた。想えば貴重な、実に嬉しい経験だった。彼らはシャッの緑地を遠慮深く一列にならんで歩いた。そして見つかると恐縮して動かない。半透明な体の中で、心臓がふるえているのも分かるようだ。

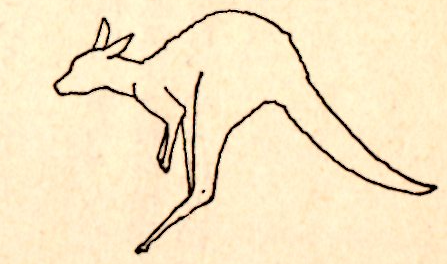 僕が大学へ講義に行く途中、近道をするために、ある百貨店の中をとおる。そこを利用する者は僕以外にもかなりあるので、いつもごったがえしている。そしてそのとおり路に化粧品売場があって、各種の芳香の総合」された匂いが胸をむかつかせるし、お化粧の実演をしているのも、ちらりとは見なければならない。僕は女性でなかったことを改めて感謝し、また男性であるために。……ここまで考えては頭がくらくらする。その売場のすみで、今日もカンガルウの親子が、音楽に合わせて歯を磨いている。薄くよごれて、全く個性をすてて、電気の流れている限り、一日葉を磨いている。
僕が大学へ講義に行く途中、近道をするために、ある百貨店の中をとおる。そこを利用する者は僕以外にもかなりあるので、いつもごったがえしている。そしてそのとおり路に化粧品売場があって、各種の芳香の総合」された匂いが胸をむかつかせるし、お化粧の実演をしているのも、ちらりとは見なければならない。僕は女性でなかったことを改めて感謝し、また男性であるために。……ここまで考えては頭がくらくらする。その売場のすみで、今日もカンガルウの親子が、音楽に合わせて歯を磨いている。薄くよごれて、全く個性をすてて、電気の流れている限り、一日葉を磨いている。
 詩人K氏が蛙の詩で文学賞をもらってから、なんだか蛙のことが書きづらくなった。それでも晩春の夜の田んぼ道を歩いていると、僕には僕で感動が起る。そうして「蛙」という題をつけた詩を作ったこともある。憎み合う声でもなく、と言って特別に愛し合う声でもないが、どうどうとして羨ましかった。しかし、ここ四五十年のあいだは、誰も「蛙」という名の詩集を出版しようとは思わないだろう。
詩人K氏が蛙の詩で文学賞をもらってから、なんだか蛙のことが書きづらくなった。それでも晩春の夜の田んぼ道を歩いていると、僕には僕で感動が起る。そうして「蛙」という題をつけた詩を作ったこともある。憎み合う声でもなく、と言って特別に愛し合う声でもないが、どうどうとして羨ましかった。しかし、ここ四五十年のあいだは、誰も「蛙」という名の詩集を出版しようとは思わないだろう。

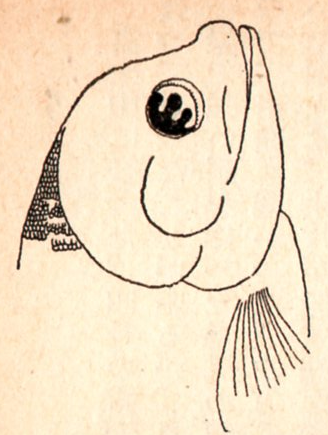 実際、暮れから正月を迎え、こうしてわが家の台所の天井にさらしものにされてから半月になる。そして、まさしくサーモン・ピンクそのものの肉を見せているが、徐々に下半身から切り落とされ、無に近づいて行く。隣りには、五島列島の緑色の海から似たような運命を背負って来たするめが吊るされている。彼らは死んだものらしい対話もできないほどに、完全に死んでいる。
実際、暮れから正月を迎え、こうしてわが家の台所の天井にさらしものにされてから半月になる。そして、まさしくサーモン・ピンクそのものの肉を見せているが、徐々に下半身から切り落とされ、無に近づいて行く。隣りには、五島列島の緑色の海から似たような運命を背負って来たするめが吊るされている。彼らは死んだものらしい対話もできないほどに、完全に死んでいる。
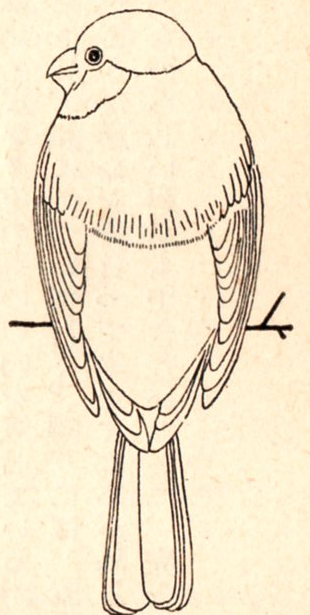
 しかし、このさくらの花は、ほとんどすべてが下を向いている。のぞき込んでもじっと下を向いて、首をちぢめてる。雨も降り出していたが、そんなことでこんなに臆病者らしくしているはずはない。それともこれがこのさくらの特徴なのかと思っていると、頭上を大砲の弾が飛び、また近くで、機関銃の音がしはじめた。何という腹立たしい音だろう。なんという殺伐な響きだろう。しばらく行くと、白ペンキの立札に、大きく黒々と、「弾は路の三〇〇〇フィート上空を通過するから危険はない」と書いてある。そんなことを言ったって僕は安心しない。すべてがぶちこわしである。溜息をつくばかりである。まして小心のふじさくらには、この音がたまらなく怖いのだろう。
しかし、このさくらの花は、ほとんどすべてが下を向いている。のぞき込んでもじっと下を向いて、首をちぢめてる。雨も降り出していたが、そんなことでこんなに臆病者らしくしているはずはない。それともこれがこのさくらの特徴なのかと思っていると、頭上を大砲の弾が飛び、また近くで、機関銃の音がしはじめた。何という腹立たしい音だろう。なんという殺伐な響きだろう。しばらく行くと、白ペンキの立札に、大きく黒々と、「弾は路の三〇〇〇フィート上空を通過するから危険はない」と書いてある。そんなことを言ったって僕は安心しない。すべてがぶちこわしである。溜息をつくばかりである。まして小心のふじさくらには、この音がたまらなく怖いのだろう。
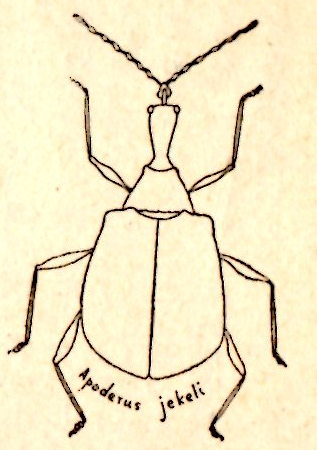

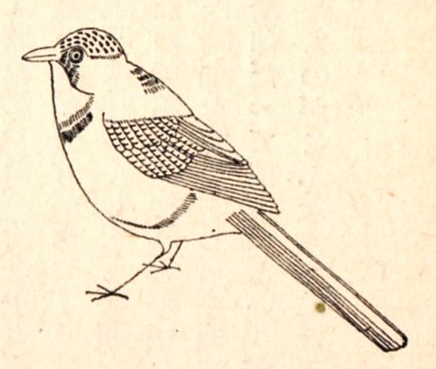
 鎌首をあげて頑張っていたが、長い体がくたくたになっていた。もう河口もすぐそこだ。蛇はたすからなかったろう。美しいあじさしは、その後も頑迷な蛇のことを想い出したに違いない。
鎌首をあげて頑張っていたが、長い体がくたくたになっていた。もう河口もすぐそこだ。蛇はたすからなかったろう。美しいあじさしは、その後も頑迷な蛇のことを想い出したに違いない。

 僕は自分のいる井之頭から都心に出る時は吉祥寺から電車に乗ることが多いが、大分前から、鉄道線路に生えている植物をしらべることを考えている。この考えは至極単純であるが、鉄道草的原理によって、新宿付近には信州の方に見られる植物があり、上野の構内付近には、東北、上越、ともかく北の方のものが運ばれて来ているかも知れないと思っている。
僕は自分のいる井之頭から都心に出る時は吉祥寺から電車に乗ることが多いが、大分前から、鉄道線路に生えている植物をしらべることを考えている。この考えは至極単純であるが、鉄道草的原理によって、新宿付近には信州の方に見られる植物があり、上野の構内付近には、東北、上越、ともかく北の方のものが運ばれて来ているかも知れないと思っている。
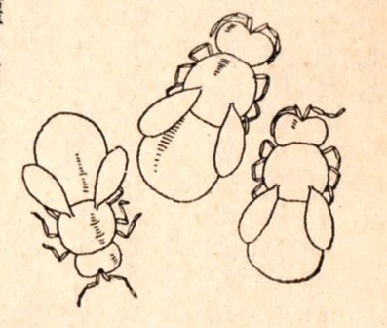
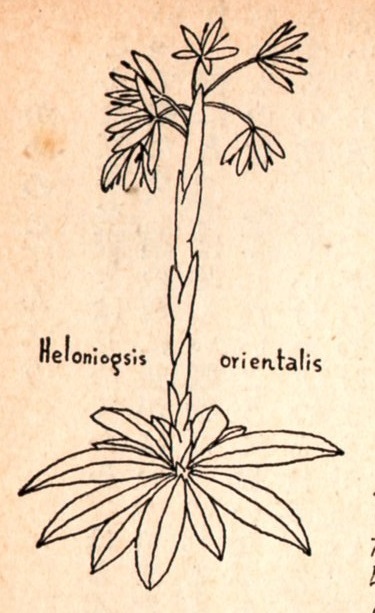 新潟県の八海山は二千メートルにも足らない山だが上はギザギザの岩石である。去年の春から、登りたいと思って機会を待っていた。
新潟県の八海山は二千メートルにも足らない山だが上はギザギザの岩石である。去年の春から、登りたいと思って機会を待っていた。

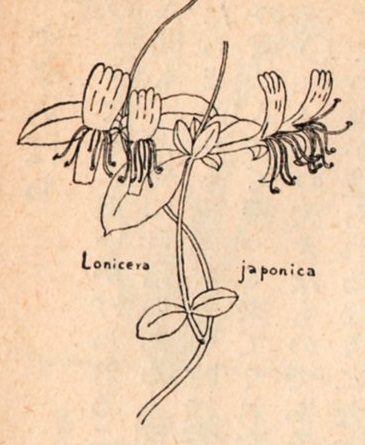 忍冬(すいかずら)はいろんな木にからまりついて、白と黄色の花を咲かせている。黄色のは枯れかけているのだが、そのために金銀花という名をもらっている。つまり金と銀ではないがただの黄色と白でもない。にぶい赤味と、品のいい光がある。僕の嗅覚は優れてはいないが、こぶしやくちなしの匂いに足を止めてしまうように、忍冬も今しきりに、方々の家の垣根のかげから僕をなやます。うっかりなやますと書いたが、この甘ったるさは、人間がどんな技巧や演技を使っても表せない。エルマンのバイオリンも、どんな名優の色眼も及ばない。もしもほんとうにこんな匂いを持っている人がいたら、……それを想像すると怖い。いn忍冬に集っているあぶたちを見るといい。いっこうに蜜を吸わず、具合悪そうに葉の上をつっ突いていた。
忍冬(すいかずら)はいろんな木にからまりついて、白と黄色の花を咲かせている。黄色のは枯れかけているのだが、そのために金銀花という名をもらっている。つまり金と銀ではないがただの黄色と白でもない。にぶい赤味と、品のいい光がある。僕の嗅覚は優れてはいないが、こぶしやくちなしの匂いに足を止めてしまうように、忍冬も今しきりに、方々の家の垣根のかげから僕をなやます。うっかりなやますと書いたが、この甘ったるさは、人間がどんな技巧や演技を使っても表せない。エルマンのバイオリンも、どんな名優の色眼も及ばない。もしもほんとうにこんな匂いを持っている人がいたら、……それを想像すると怖い。いn忍冬に集っているあぶたちを見るといい。いっこうに蜜を吸わず、具合悪そうに葉の上をつっ突いていた。
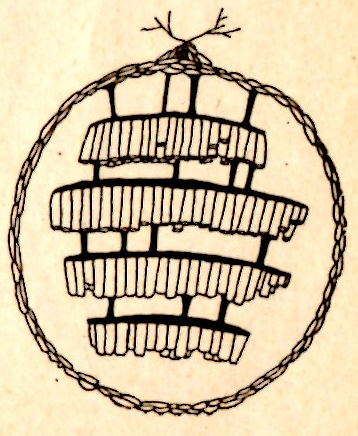 この大きな蜂に追いかけられることがあったら、腕力に自信のある人間も、舌先に自信のある人間も、頭をかかえて逃げるだろう。たちわまりも説得もその時は役立たない。画家M氏が、ビニールの網に入れて持って来てくれたのは、もんすずめばちの巣で、直径三〇センチの大きなものであるが、今はすでに廃墟となっている。この巣が造られるようになってから時々その話をきいていたが、僕はいそがしかったし恐ろしかったので、まだ蜂の棲んでいるあいだは見に行かなかった。丸い廃墟を壊さないと、独房の数は分からないが、四段合計すると八百は充分に越える。
この大きな蜂に追いかけられることがあったら、腕力に自信のある人間も、舌先に自信のある人間も、頭をかかえて逃げるだろう。たちわまりも説得もその時は役立たない。画家M氏が、ビニールの網に入れて持って来てくれたのは、もんすずめばちの巣で、直径三〇センチの大きなものであるが、今はすでに廃墟となっている。この巣が造られるようになってから時々その話をきいていたが、僕はいそがしかったし恐ろしかったので、まだ蜂の棲んでいるあいだは見に行かなかった。丸い廃墟を壊さないと、独房の数は分からないが、四段合計すると八百は充分に越える。
 その時、庭石菖が好きだと書いたことを想い出した。鎌倉の野柴の中にころがって、好き勝手に本を読んでいられた頃、その芝の中から庭石菖がいっぱい咲いていた。紫のと、紫の線がはいった白いのと、それを、地面に顔を押しつけて横から見ると、この花の気持に急に近づくのが嬉しくて、それですっかり好きになっていた。しかしそれだけではない。暇だった僕は、恐らくのんびりと、花の姿から、少女の映像でも創りあげていたにちがいない。僕は今だってそのくらいのことは出来る。けれども、悪い癖は、いい加減のところでとどめ置くことが出来なくて、その映像をつい超現実的なものにしまうことだ。
その時、庭石菖が好きだと書いたことを想い出した。鎌倉の野柴の中にころがって、好き勝手に本を読んでいられた頃、その芝の中から庭石菖がいっぱい咲いていた。紫のと、紫の線がはいった白いのと、それを、地面に顔を押しつけて横から見ると、この花の気持に急に近づくのが嬉しくて、それですっかり好きになっていた。しかしそれだけではない。暇だった僕は、恐らくのんびりと、花の姿から、少女の映像でも創りあげていたにちがいない。僕は今だってそのくらいのことは出来る。けれども、悪い癖は、いい加減のところでとどめ置くことが出来なくて、その映像をつい超現実的なものにしまうことだ。
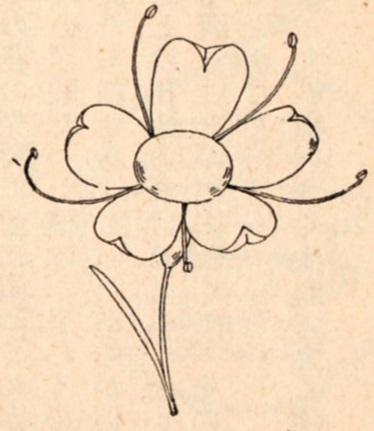 ある奥さんが、少し上等なレストランでサンドイッチをとり、お皿についていたパセリを食べたら、くすくす笑われたと僕に報告した。程よくふくれた顔つきで。
ある奥さんが、少し上等なレストランでサンドイッチをとり、お皿についていたパセリを食べたら、くすくす笑われたと僕に報告した。程よくふくれた顔つきで。
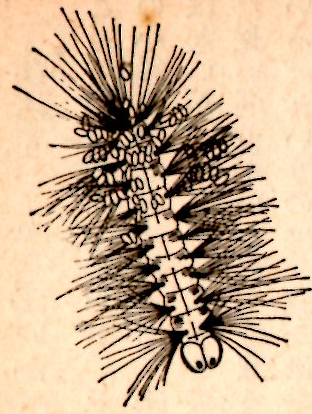
 種子が沢山とれるので、よかったらあげようかと言っても、庭に咲いているその姿を見てしまったものは、まあいいやと言って持ってゆかない。
種子が沢山とれるので、よかったらあげようかと言っても、庭に咲いているその姿を見てしまったものは、まあいいやと言って持ってゆかない。
 僕もそうして谷をのぼりながら、踏み込んだ足を、抜き出した穴をのぞいてみると、そこにうす緑の蕗が一本笑っている。
僕もそうして谷をのぼりながら、踏み込んだ足を、抜き出した穴をのぞいてみると、そこにうす緑の蕗が一本笑っている。
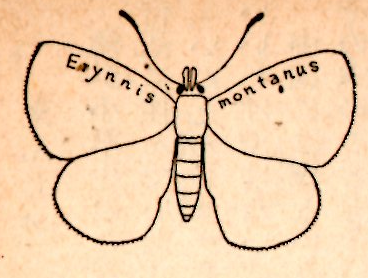 ところが気がついてみると、何という多産な人間なのだろうか。今ここから目立つのは、遠くの尾根みちを歩いている捕虫網を手にした昆虫愛好家たちである。幟を立てて行列して進んで行く。大群という名に値するほどである。山の昆虫たちも観察しているにちがいない。ニンゲンは特に週に一回、日曜日を好んで異常な出現をみる。
ところが気がついてみると、何という多産な人間なのだろうか。今ここから目立つのは、遠くの尾根みちを歩いている捕虫網を手にした昆虫愛好家たちである。幟を立てて行列して進んで行く。大群という名に値するほどである。山の昆虫たちも観察しているにちがいない。ニンゲンは特に週に一回、日曜日を好んで異常な出現をみる。
 中国には槐(えんじゅ)という木がある。戦争で長いあいだ向うにいた人にその木のことをきいてみたら、一里塚などに植えられて「槐碑」といわれているということまで教えて貰えた。日本に昔からあった「えんじゅ」は、古名を「えにす」というが、それ
を「槐」と同じものだと思っていた時代がある。ところがしばらくして実物に接してみると「槐」と「えんじゅ」とは決して同じものではない。そこで外国のものを本物だと思う考えから、日本の「えんじゅ」を「いぬえんじゅ」と呼びかえるようにした。 これが一般の説明であるが、考えてみればずいぶん滑稽な話である。つまり、別のものはどこまでも別のものであって、えんじゅの本物を「槐」とする理由は何もない。牧野富太郎博士は「槐」を「しなえんじゅ」と名付け、日本の在来種を「えんじゃ」というふうに整理された。 外国崇拝のために、古来日本にあるものを、実にあっさりと、当然のように否定し、にせものとしてしまった例は、えんじゅばかりではなく、今でもいろいろと思いあたる。
中国には槐(えんじゅ)という木がある。戦争で長いあいだ向うにいた人にその木のことをきいてみたら、一里塚などに植えられて「槐碑」といわれているということまで教えて貰えた。日本に昔からあった「えんじゅ」は、古名を「えにす」というが、それ
を「槐」と同じものだと思っていた時代がある。ところがしばらくして実物に接してみると「槐」と「えんじゅ」とは決して同じものではない。そこで外国のものを本物だと思う考えから、日本の「えんじゅ」を「いぬえんじゅ」と呼びかえるようにした。 これが一般の説明であるが、考えてみればずいぶん滑稽な話である。つまり、別のものはどこまでも別のものであって、えんじゅの本物を「槐」とする理由は何もない。牧野富太郎博士は「槐」を「しなえんじゅ」と名付け、日本の在来種を「えんじゃ」というふうに整理された。 外国崇拝のために、古来日本にあるものを、実にあっさりと、当然のように否定し、にせものとしてしまった例は、えんじゅばかりではなく、今でもいろいろと思いあたる。
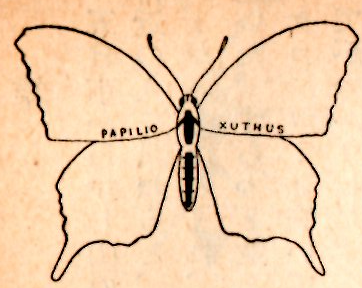
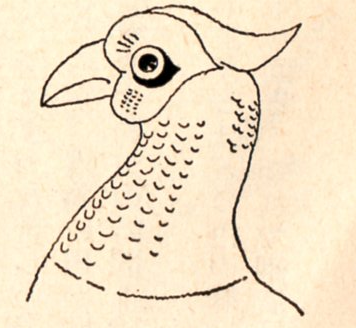 ところが、ここは、日本の山野に野鳥がどんどんいなくなるので、人工的に殖やして、放鳥するのが仕事なのだ。その主なものは雉で、一夫三婦の雉にせっせと卵を産ませ、その卵をあたためるのが鶏の役目だった。どうりで彼女たちはちっとも肩身のせまいような様子をしていないばかりか、職員然としていると思った。
ところが、ここは、日本の山野に野鳥がどんどんいなくなるので、人工的に殖やして、放鳥するのが仕事なのだ。その主なものは雉で、一夫三婦の雉にせっせと卵を産ませ、その卵をあたためるのが鶏の役目だった。どうりで彼女たちはちっとも肩身のせまいような様子をしていないばかりか、職員然としていると思った。

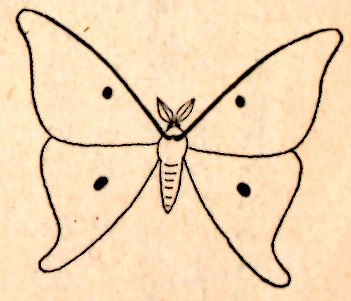
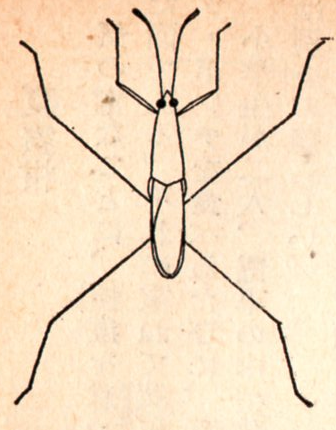 そんなことをしながら、ここにはあめんぼと大あめんぼと二種類いると思っていたが、よく見ると大きいのは雌の背中に雄がおぶさっているのだった。水草の葉の上で生れたのが、成虫となり、早速こんな楽しみを覚えたのか。少し早すすぎのではないかと思う。それは種族保存のための営みというよりは、遊びに近い動作で背中に雄をのせた雌が、他の一組を追いかけてみたり、一人のものが寄って来ると、いかにも冗談らしく横面を張りとばすようなこともしていた。あたしたちのところへ来たって駄目でしょう? よくごらんなさいよ背中を。背中に誰がいるかをさ。そんなふうにはじき飛ばすのだ。僕はおせっかいに相手を見つけてやるが、何が気に入らないのか、一緒にならない。静かな池の、とろんとした日ぐれだった。
そんなことをしながら、ここにはあめんぼと大あめんぼと二種類いると思っていたが、よく見ると大きいのは雌の背中に雄がおぶさっているのだった。水草の葉の上で生れたのが、成虫となり、早速こんな楽しみを覚えたのか。少し早すすぎのではないかと思う。それは種族保存のための営みというよりは、遊びに近い動作で背中に雄をのせた雌が、他の一組を追いかけてみたり、一人のものが寄って来ると、いかにも冗談らしく横面を張りとばすようなこともしていた。あたしたちのところへ来たって駄目でしょう? よくごらんなさいよ背中を。背中に誰がいるかをさ。そんなふうにはじき飛ばすのだ。僕はおせっかいに相手を見つけてやるが、何が気に入らないのか、一緒にならない。静かな池の、とろんとした日ぐれだった。
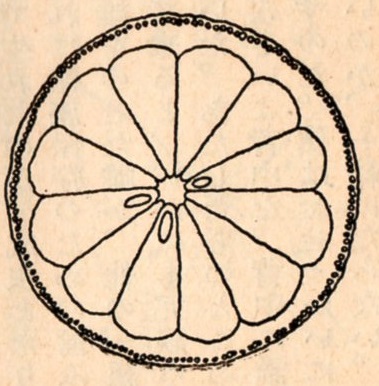 小学生が二人、電車の中で僕の立っている前に腰かけている。二人は別々の組らしい。
小学生が二人、電車の中で僕の立っている前に腰かけている。二人は別々の組らしい。
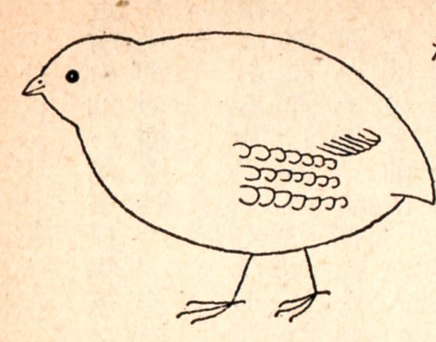 僕の家の隣りで、鶉を飼っていたことがある。花壇の垣根のかげに何羽かいて、僕が花の診察に回っていると、突然、おやと思うような音を出す。ジュルジュルジュル、グジュグジュグジュと言って。
僕の家の隣りで、鶉を飼っていたことがある。花壇の垣根のかげに何羽かいて、僕が花の診察に回っていると、突然、おやと思うような音を出す。ジュルジュルジュル、グジュグジュグジュと言って。
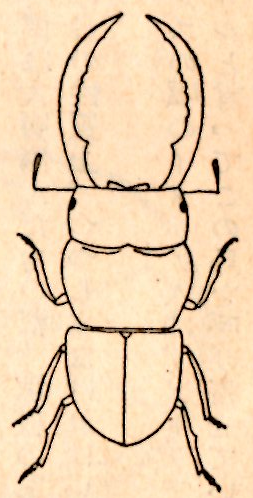
 僕がそのころ逃げかくれていたところは、東北の田舎で、前がずらっとたばこ畑だった。黄色になって、明らかに枯れて、誰が見てもこれは役に立たないと思われるような葉が落ちているいることもあったが、それをひろってパイプにつめるようなことも決してしなかった。
僕がそのころ逃げかくれていたところは、東北の田舎で、前がずらっとたばこ畑だった。黄色になって、明らかに枯れて、誰が見てもこれは役に立たないと思われるような葉が落ちているいることもあったが、それをひろってパイプにつめるようなことも決してしなかった。
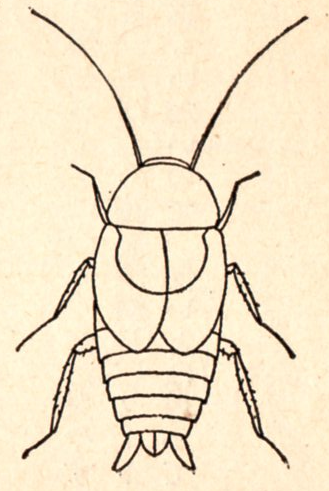

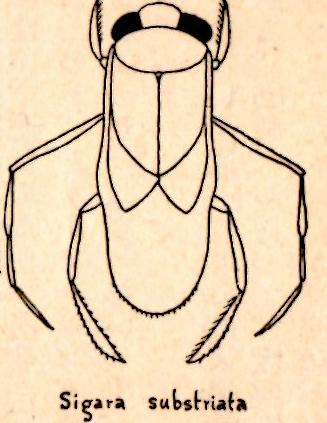
 細長い花軸を下から見れば猫の顎みたいで、うすきいろく、上から見れば深みのある実にいい赤だ。僕の心臓はこんな色かしらと思う。そして次にレンズをとおして見れば、花弁はなく、四つに裂けた萼(がく)の中にはやはりきちんと道具がそろっている。
細長い花軸を下から見れば猫の顎みたいで、うすきいろく、上から見れば深みのある実にいい赤だ。僕の心臓はこんな色かしらと思う。そして次にレンズをとおして見れば、花弁はなく、四つに裂けた萼(がく)の中にはやはりきちんと道具がそろっている。
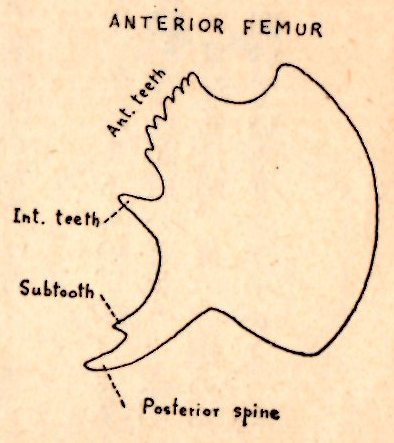
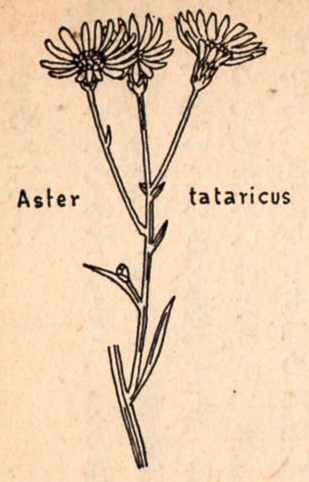 そんなふうに紫苑を見ると、僕には幾らでも夢が誘い出されてくる。それでいつか、ふとうまいことを思いついたらば、この花の名前のいわれなども取り入れて、伝説めいた物語を作ってみようかしらと思っている。だがそれ以来、誰が決めたのでもないが、庭に紫苑は咲かない。そんなことも物語のうちでは何か役だつことになるかもしれない。
そんなふうに紫苑を見ると、僕には幾らでも夢が誘い出されてくる。それでいつか、ふとうまいことを思いついたらば、この花の名前のいわれなども取り入れて、伝説めいた物語を作ってみようかしらと思っている。だがそれ以来、誰が決めたのでもないが、庭に紫苑は咲かない。そんなことも物語のうちでは何か役だつことになるかもしれない。
 貝を拾いあつめてみると、僕の好みもまた変ってくるだろうけれど、今のところでは、どっちかと言えば、巻いている貝の方が好きである。そして、巻いていると言っても、ほねがいのように、とげ張ったものより、このつめたがいのように、丸っこいすべすべのものの方が好きである。だから、どうしてもつめたがいと言うのではなく、こはくだまとか、ひろとらだまか、その口が大きく、そして全体が球のように、手ににぎってもなんとなく気持ちのいいもの、形よりは触覚を少しばかり満足させてくれるものがうれしい。
貝を拾いあつめてみると、僕の好みもまた変ってくるだろうけれど、今のところでは、どっちかと言えば、巻いている貝の方が好きである。そして、巻いていると言っても、ほねがいのように、とげ張ったものより、このつめたがいのように、丸っこいすべすべのものの方が好きである。だから、どうしてもつめたがいと言うのではなく、こはくだまとか、ひろとらだまか、その口が大きく、そして全体が球のように、手ににぎってもなんとなく気持ちのいいもの、形よりは触覚を少しばかり満足させてくれるものがうれしい。
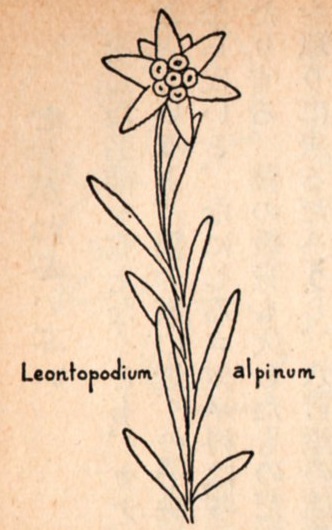 けれども私はエーデルワイスはいい花だと思っている。昔貰ったものはアルプスの恐らくお土産もので、それも大事にしていたが、山好きの少年に事もなげにやってしまった。
けれども私はエーデルワイスはいい花だと思っている。昔貰ったものはアルプスの恐らくお土産もので、それも大事にしていたが、山好きの少年に事もなげにやってしまった。
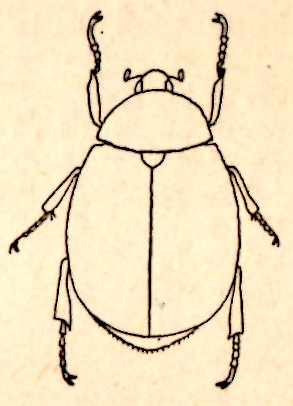 そんな名前を覚えなくとも、カナブンブンじゃないか、などというと、僕の家の近くの子供たちは承知しない。僕がすぐに分らないと、なにしろコガネ科は多いからねと言って、慰めてくれたりする。僕の教育も大したものだと思う。今に魚屋は学名で注文を取りに来るだろうし、八百屋の店先にはラファヌス・サティヴスやダウクス・カロタが並ぶだろう。
そんな名前を覚えなくとも、カナブンブンじゃないか、などというと、僕の家の近くの子供たちは承知しない。僕がすぐに分らないと、なにしろコガネ科は多いからねと言って、慰めてくれたりする。僕の教育も大したものだと思う。今に魚屋は学名で注文を取りに来るだろうし、八百屋の店先にはラファヌス・サティヴスやダウクス・カロタが並ぶだろう。
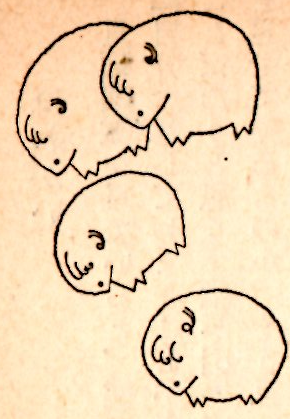
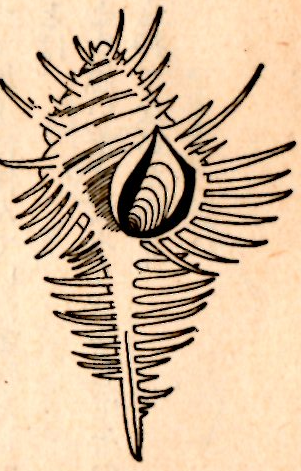
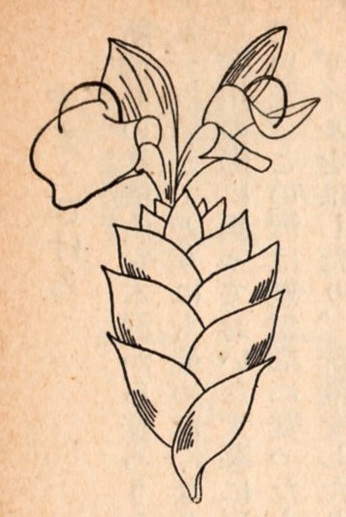 フランス語の単語一つ忘れると、そのためにひどい目にあうような教育を受けたため、うっかり茗荷が口にはいることまで極度に警戒した。このごろになれば、いろいろ忘れたいことが出来てくる。般特がうらやましくことさえある。しかしこれが単なる伝説である以上、好んで食べてみても仕方がない。
フランス語の単語一つ忘れると、そのためにひどい目にあうような教育を受けたため、うっかり茗荷が口にはいることまで極度に警戒した。このごろになれば、いろいろ忘れたいことが出来てくる。般特がうらやましくことさえある。しかしこれが単なる伝説である以上、好んで食べてみても仕方がない。
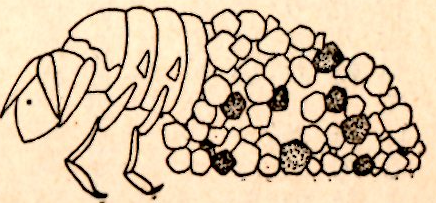
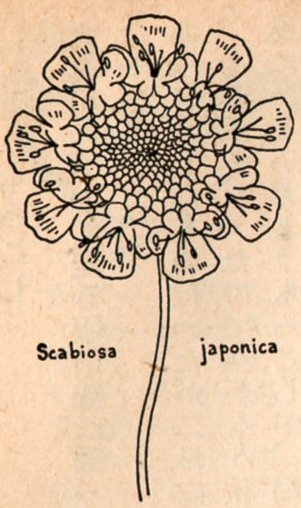
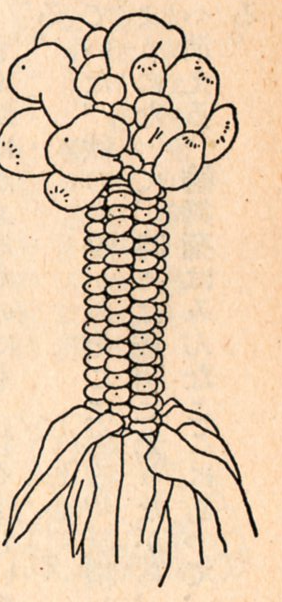 あっさりしたものだったが二日ほど前に颱風がとおり、そのあとだったので空がもう秋だった。そして強い風にかしだとうもろこしが、畑のわきでよく実っていた。ぎいぎいぽきりとそれをもぐもぐ感じを久し振りに想い出していた。あの腕をもぐような気分を。
あっさりしたものだったが二日ほど前に颱風がとおり、そのあとだったので空がもう秋だった。そして強い風にかしだとうもろこしが、畑のわきでよく実っていた。ぎいぎいぽきりとそれをもぐもぐ感じを久し振りに想い出していた。あの腕をもぐような気分を。
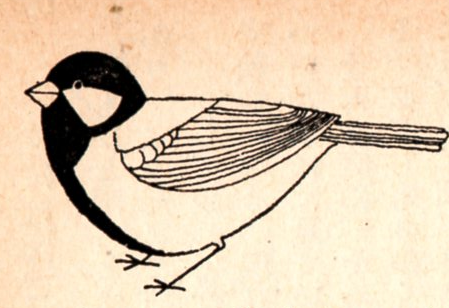
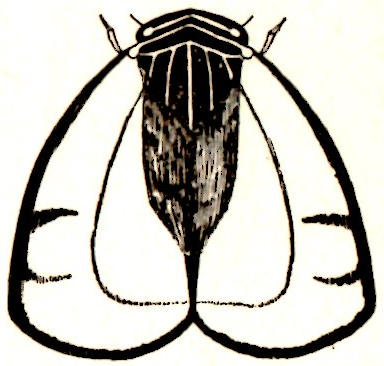 庭もひと雨ごとに黄ばみはじめる。ちょっとした風に倒れるものもあり。立ったまま枯れて、小さいつる草にからまれているものもある。
庭もひと雨ごとに黄ばみはじめる。ちょっとした風に倒れるものもあり。立ったまま枯れて、小さいつる草にからまれているものもある。
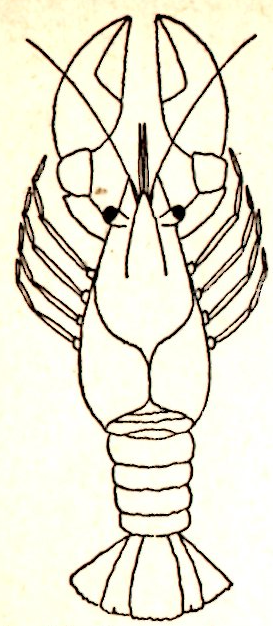
 聖書の中のエゼキエル書に、「人の子よたとえアザミとイバラなんじらの周囲にあるとも……」と書いてあるが、そのイバラを、なぎいかだだといっている学者もいる。パレスチナには、さわると痛い植物が多いようだ。
聖書の中のエゼキエル書に、「人の子よたとえアザミとイバラなんじらの周囲にあるとも……」と書いてあるが、そのイバラを、なぎいかだだといっている学者もいる。パレスチナには、さわると痛い植物が多いようだ。
 方法が「ないわけではない。例えば……。しかし、僕は血をあたえてもその種類を見極めるまで、ファーブル的精神によって、間抜けにさされていることにしよう。
方法が「ないわけではない。例えば……。しかし、僕は血をあたえてもその種類を見極めるまで、ファーブル的精神によって、間抜けにさされていることにしよう。
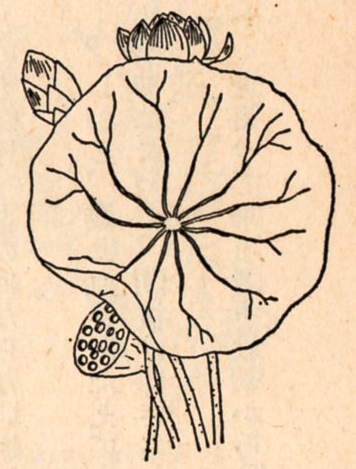

 霧の流れている上越の山を、ぐっしょりぬれて熊笹を分けながら歩いている時、その節の一つから奇妙な魚のようなものが生えているのを見つけた。もちろんこれは虫癭(ちゆうえい)だと思ったが自信がないので帰ってからしらべてみると、『蒹葭堂雑録(けんかどうざつろく)』にささうお(篠魚)のことがあって、「谷水に落ヒタリテ、ヤガテ鰭フリ出デ、ツイニイハナトイフ物ニハナレリトイフ」と書いてある。僕は実に痛快な空想なので、ひどくよろこんだ。そして、これはこのままにいておきた気さえしたが、虫癭の本を見ると、ささたまばえの寄生するもので、「ささうおふし」という名がついていた。
霧の流れている上越の山を、ぐっしょりぬれて熊笹を分けながら歩いている時、その節の一つから奇妙な魚のようなものが生えているのを見つけた。もちろんこれは虫癭(ちゆうえい)だと思ったが自信がないので帰ってからしらべてみると、『蒹葭堂雑録(けんかどうざつろく)』にささうお(篠魚)のことがあって、「谷水に落ヒタリテ、ヤガテ鰭フリ出デ、ツイニイハナトイフ物ニハナレリトイフ」と書いてある。僕は実に痛快な空想なので、ひどくよろこんだ。そして、これはこのままにいておきた気さえしたが、虫癭の本を見ると、ささたまばえの寄生するもので、「ささうおふし」という名がついていた。

 庭への出入り口の前に池をこしらえた。子供が魚をとって来ては、たらいやバケツを占領してしまうもんで、と人にはいうが、僕はこの小さな池に水草を入れたり、微生物を飼ったり出来るようになったのがうれしくてたまらない。
庭への出入り口の前に池をこしらえた。子供が魚をとって来ては、たらいやバケツを占領してしまうもんで、と人にはいうが、僕はこの小さな池に水草を入れたり、微生物を飼ったり出来るようになったのがうれしくてたまらない。
 欅や柿の葉が水面いっぱいに散り込む日も近いが、そしてやがてはかたく氷のはる冬も来るだろうが、今はともかく田んぼですからすぐって来たこなぎがつやつやと浮いている。ぶっくりと腹をふくらませている布袋葵(ほていあおい)よりはほっそりとした小柄だが、その葉のハート型は、水から手を出していかにも太陽の光を受けとめている感じである。
欅や柿の葉が水面いっぱいに散り込む日も近いが、そしてやがてはかたく氷のはる冬も来るだろうが、今はともかく田んぼですからすぐって来たこなぎがつやつやと浮いている。ぶっくりと腹をふくらませている布袋葵(ほていあおい)よりはほっそりとした小柄だが、その葉のハート型は、水から手を出していかにも太陽の光を受けとめている感じである。
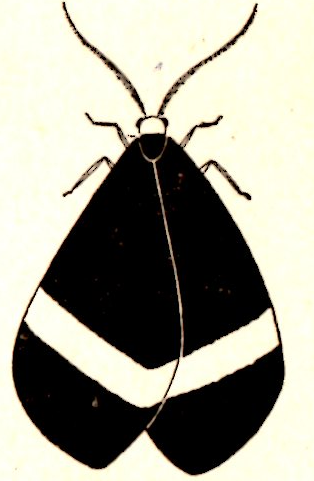 梅雨がそろそろ上るころに一度あらわれ、また九月ごろになってから姿を見せる蛍蛾は、日のあたらない藪の中をちらちらしている。赤い頭に黒い体。これは誰が見ても、蛍蛾としか呼べないようなもので、その証拠には、その名を忘れる者は絶対にないと言っていい。
梅雨がそろそろ上るころに一度あらわれ、また九月ごろになってから姿を見せる蛍蛾は、日のあたらない藪の中をちらちらしている。赤い頭に黒い体。これは誰が見ても、蛍蛾としか呼べないようなもので、その証拠には、その名を忘れる者は絶対にないと言っていい。
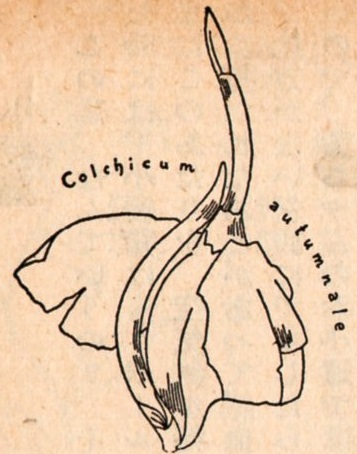 黙って準備をし、言訳をしながらおどおどしている僕のことなどは眼中にない。そして窓から何げなく見ると、庭の草むらに埋めておいたいぬさふらんも、同じ日に花を見せていた。
黙って準備をし、言訳をしながらおどおどしている僕のことなどは眼中にない。そして窓から何げなく見ると、庭の草むらに埋めておいたいぬさふらんも、同じ日に花を見せていた。
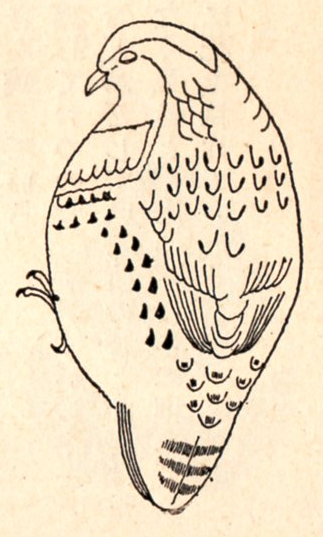 仕方がない剥製にでもしたらとすすめたが、少し値段が高いので、芳ちゃんのお小遣いでは無理だった。それじゃあ仕方がない、こみ合っているけれど、また共同墓地に埋葬することにしよう。小綬鶏よ。人間を恨んでくれ。僕を恨んでも構わない。気がすむまで憎み切って、そして死んでくれ。僕らの仲間が一人のこらず銃をすてるようになるまでには、まだまだ大変だ。
仕方がない剥製にでもしたらとすすめたが、少し値段が高いので、芳ちゃんのお小遣いでは無理だった。それじゃあ仕方がない、こみ合っているけれど、また共同墓地に埋葬することにしよう。小綬鶏よ。人間を恨んでくれ。僕を恨んでも構わない。気がすむまで憎み切って、そして死んでくれ。僕らの仲間が一人のこらず銃をすてるようになるまでには、まだまだ大変だ。

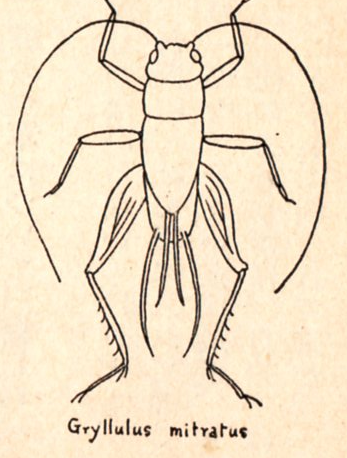

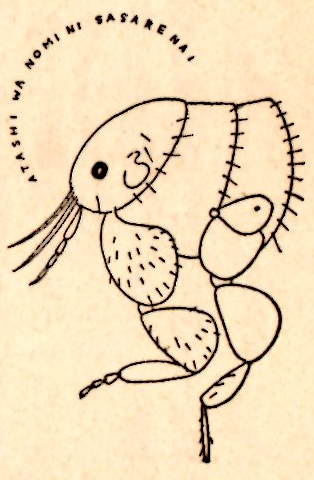
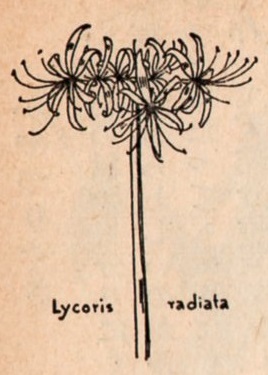 ところが、その花を五六本持って戻ると、そんな花をとってはいけないと言われ、何か悪いものをかかえていたようにそこへすてた。詳しく理由なんぞは訊ねなかったけれど、地震と関係があるような気がした。そして後に、地に埋められた人の霊がこうして咲くように思った。よく見ればきれいな花だ。
ところが、その花を五六本持って戻ると、そんな花をとってはいけないと言われ、何か悪いものをかかえていたようにそこへすてた。詳しく理由なんぞは訊ねなかったけれど、地震と関係があるような気がした。そして後に、地に埋められた人の霊がこうして咲くように思った。よく見ればきれいな花だ。
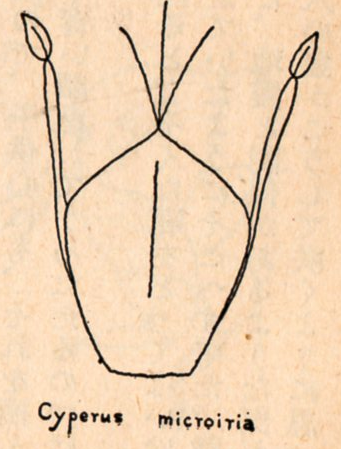 いね科の植物も分かりにくくて閉口だが、かやつりぐさ科のものも実にまぎらわしいのが多くて困る。いい加減に覚えていると、いつまでたっても曖昧なものが沢山残っているので、一度腊葉(さくよう)でも作って、充分時間を潰しながら覚えてしまわければいけないと思う。そうしないと、これは、何とかかやつりということでいつまでもごまかしてしまうことになる。
いね科の植物も分かりにくくて閉口だが、かやつりぐさ科のものも実にまぎらわしいのが多くて困る。いい加減に覚えていると、いつまでたっても曖昧なものが沢山残っているので、一度腊葉(さくよう)でも作って、充分時間を潰しながら覚えてしまわければいけないと思う。そうしないと、これは、何とかかやつりということでいつまでもごまかしてしまうことになる。
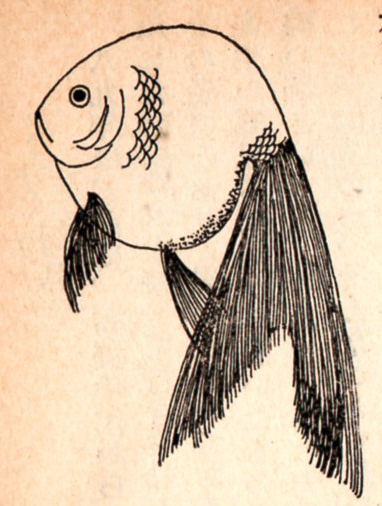 僕はもちろん家に戻ってから、金魚の皮膚について調べた。いろいろな病気がある。中でも鱗に寄生するうおじらみ。これは少々興味がわいて来た。金魚を飼おうかしら。そのうおじらみをピンセットでつまみとるたのしみのために。そして原形の鮒にまで戻してやることは出来なくとも、蘭鋳の顔と出目金の眼だけは何とかして昔のようになおしてやりたいと思う。
僕はもちろん家に戻ってから、金魚の皮膚について調べた。いろいろな病気がある。中でも鱗に寄生するうおじらみ。これは少々興味がわいて来た。金魚を飼おうかしら。そのうおじらみをピンセットでつまみとるたのしみのために。そして原形の鮒にまで戻してやることは出来なくとも、蘭鋳の顔と出目金の眼だけは何とかして昔のようになおしてやりたいと思う。
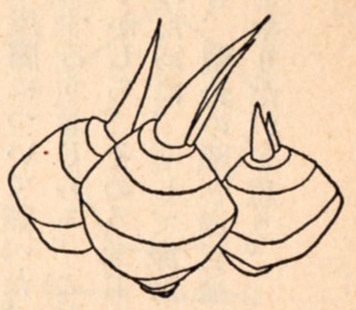 まだ食糧に困っていた頃だったので口にはいるものを持ちかえれば悦ばれた。けれどもこれはすぐ食べてしまうにも珍しすぎるので図鑑を看たり、日記のわきにスケッチをしたりしていた。そして食べるのを我慢して、どんなことになるか分からないけれど泥に埋めることにした。
まだ食糧に困っていた頃だったので口にはいるものを持ちかえれば悦ばれた。けれどもこれはすぐ食べてしまうにも珍しすぎるので図鑑を看たり、日記のわきにスケッチをしたりしていた。そして食べるのを我慢して、どんなことになるか分からないけれど泥に埋めることにした。
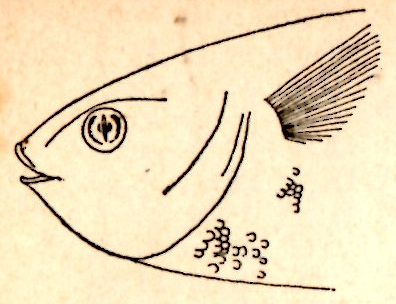 事典という者はいろんなことが書いてあるので嬉しい。この魚は幼年時だをハクと言い、少年時代をオボコと言い、青年時代をハネカエリという。そして成人してボラになるが、その中でも特別の大鯔をトドという。それから先はもうないので、それで「トドの詰り」というにおだそうだ。何をどう信用していいのか分らなくなってしまう。
事典という者はいろんなことが書いてあるので嬉しい。この魚は幼年時だをハクと言い、少年時代をオボコと言い、青年時代をハネカエリという。そして成人してボラになるが、その中でも特別の大鯔をトドという。それから先はもうないので、それで「トドの詰り」というにおだそうだ。何をどう信用していいのか分らなくなってしまう。
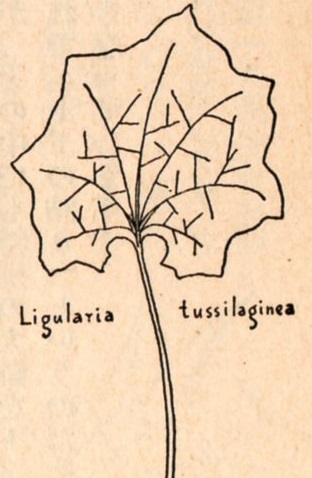
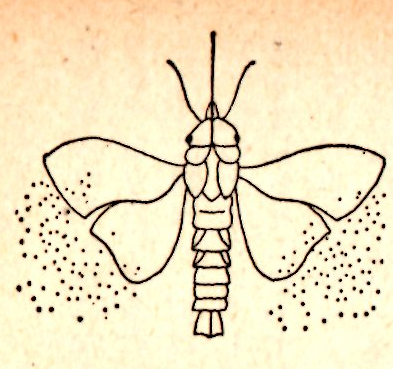
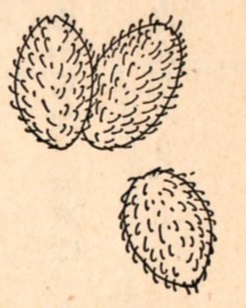 猫のおもちゃにやってしまった時もあった。猫が前脚で、少し気味悪そうにさわっているのを見ていると、それがやまあらしの一寸法師のようにも見える。結局猫も、変な気持になって、最後には横目でみながら行ってしまう。
猫のおもちゃにやってしまった時もあった。猫が前脚で、少し気味悪そうにさわっているのを見ていると、それがやまあらしの一寸法師のようにも見える。結局猫も、変な気持になって、最後には横目でみながら行ってしまう。

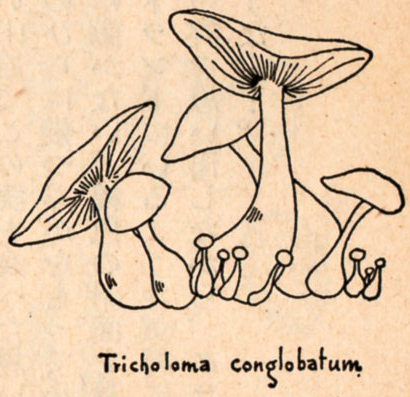 相変わらず動植物の鑑定では頭を悩ましている。しかし面白くないこともないので、送られて来た小虫のために数時間を有意義につぶすことはよくある。
相変わらず動植物の鑑定では頭を悩ましている。しかし面白くないこともないので、送られて来た小虫のために数時間を有意義につぶすことはよくある。
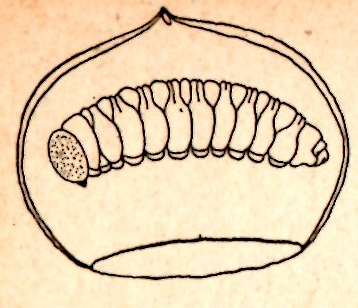 栗といっしょにほかほかとゆでられてしまったこの虫はどうにも救いようがない。何ともお気の毒だがその名にふさわしいしぎのような姿にはもうなれない。僕はそれからもう一つの栗を食べた。今度は虫もいない。それにうまい。虫がいなくてしかもうまいものがあるということは、卵を産みつける時にこの実は特別にうまそうだという判断はしないで、矢鱈にに穴をあけるのだろう。しかし、栗の木自身が害虫目録を作ったら、人間かその筆頭にあらゆるものの大害敵として書き込まれるにちがいない。
栗といっしょにほかほかとゆでられてしまったこの虫はどうにも救いようがない。何ともお気の毒だがその名にふさわしいしぎのような姿にはもうなれない。僕はそれからもう一つの栗を食べた。今度は虫もいない。それにうまい。虫がいなくてしかもうまいものがあるということは、卵を産みつける時にこの実は特別にうまそうだという判断はしないで、矢鱈にに穴をあけるのだろう。しかし、栗の木自身が害虫目録を作ったら、人間かその筆頭にあらゆるものの大害敵として書き込まれるにちがいない。
 これは鳥のほととぎすではない。鳥のほとぎすの胸毛の、そのまだらによく似た斑点が、花の内側にあるので、こんな名をつけられたにちがいない。僕も秋ごととにこの花が咲くと鳥の方のほととぎすを想い出す。そしてすぐそのなき声を考えるけれども、もともと、まだら模様というものは、だんだんと見ているうちに気味が悪くなる。こんなふうに、植物と鳥ばかりでなく、自然界では、同じ名を貰っている蝶と貝がいたりして、滑稽な間違いが起る可能性がないこともない。
これは鳥のほととぎすではない。鳥のほとぎすの胸毛の、そのまだらによく似た斑点が、花の内側にあるので、こんな名をつけられたにちがいない。僕も秋ごととにこの花が咲くと鳥の方のほととぎすを想い出す。そしてすぐそのなき声を考えるけれども、もともと、まだら模様というものは、だんだんと見ているうちに気味が悪くなる。こんなふうに、植物と鳥ばかりでなく、自然界では、同じ名を貰っている蝶と貝がいたりして、滑稽な間違いが起る可能性がないこともない。

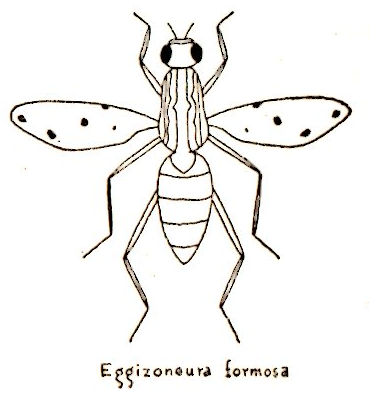
 天城山から八丁池、万三郎、万ニ郎と長い道をやって来た。曇ってもいたが森林が多く、ひめしゃらのあの幹の色が人間の肌のようだった。
天城山から八丁池、万三郎、万ニ郎と長い道をやって来た。曇ってもいたが森林が多く、ひめしゃらのあの幹の色が人間の肌のようだった。
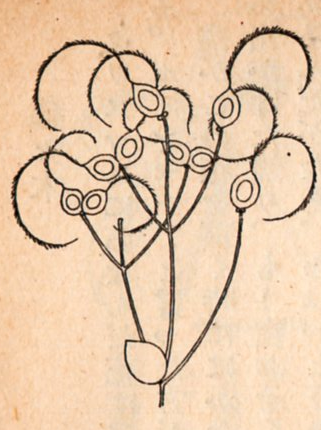 僕はかつて、この仙人草に極く近い植物を、英国人たちが、 Traveller's joy つまり、「旅人のよろこび」と名づけている意味をうまく理解しかねていたが、今はその心がそっくり自分のうちにあったことを発見した。地図をひらき、僕にとって記念すべきその場所に、小さく印をつけた。
僕はかつて、この仙人草に極く近い植物を、英国人たちが、 Traveller's joy つまり、「旅人のよろこび」と名づけている意味をうまく理解しかねていたが、今はその心がそっくり自分のうちにあったことを発見した。地図をひらき、僕にとって記念すべきその場所に、小さく印をつけた。
 僕がこの花を頂く時にはかなり悲愴だった。熱があるのを承知で外へ出かけた帰り、もう夜おそく、寒い風が吹いていた。あげたい花があるんだがなあ、ちょっとうちへ寄って下さらないかしら……。それとも……ここで待って下さるかしら……。
僕がこの花を頂く時にはかなり悲愴だった。熱があるのを承知で外へ出かけた帰り、もう夜おそく、寒い風が吹いていた。あげたい花があるんだがなあ、ちょっとうちへ寄って下さらないかしら……。それとも……ここで待って下さるかしら……。
 このパートラムというアメリカのお百姓さんは、なかなかいい人だったらしく、みんなからオネスト・ジョンと呼ばれ尊敬されていた。僕はこの名前を大砲より先に、世界で一本しかない木の発見者として知っていたが、大砲にそんな名前をつけるようになった国を少々軽蔑してもよさそうである。
このパートラムというアメリカのお百姓さんは、なかなかいい人だったらしく、みんなからオネスト・ジョンと呼ばれ尊敬されていた。僕はこの名前を大砲より先に、世界で一本しかない木の発見者として知っていたが、大砲にそんな名前をつけるようになった国を少々軽蔑してもよさそうである。
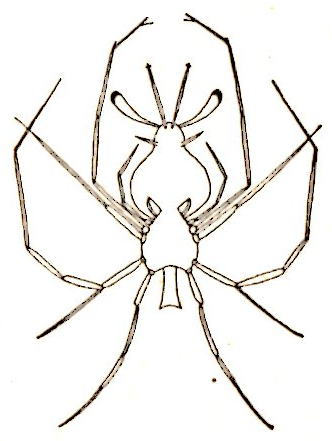 その時のスケッチの中に、伊勢海老(いせえび)のでかいのが描いてある。これはほんとうに大きかった。単に海の底で死にそこなっただけではなく、肉体的な成長をとめるべきバネがはずれたままになったようなものだった。
その時のスケッチの中に、伊勢海老(いせえび)のでかいのが描いてある。これはほんとうに大きかった。単に海の底で死にそこなっただけではなく、肉体的な成長をとめるべきバネがはずれたままになったようなものだった。
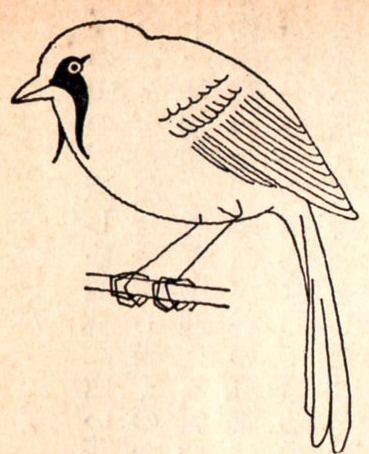
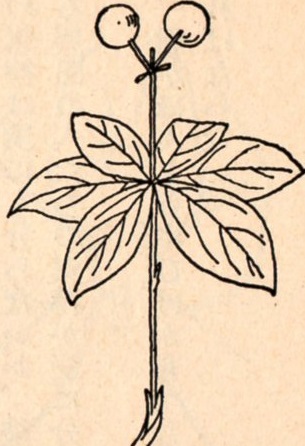
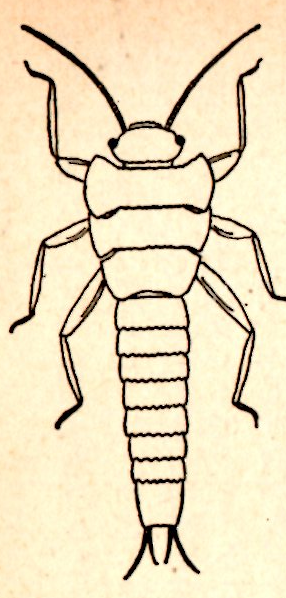



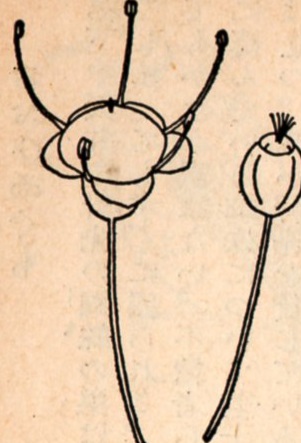 雄花にレンズをあてて見ると、中央の蜜のてらてらしているところが罐詰の桃のようで、なめると甘い。今日は冷たい雨降りで虫はやって来ない。すぐ隣り合っているのに、花粉ががうまく運ばれるかどうか、気が気でない。
雄花にレンズをあてて見ると、中央の蜜のてらてらしているところが罐詰の桃のようで、なめると甘い。今日は冷たい雨降りで虫はやって来ない。すぐ隣り合っているのに、花粉ががうまく運ばれるかどうか、気が気でない。


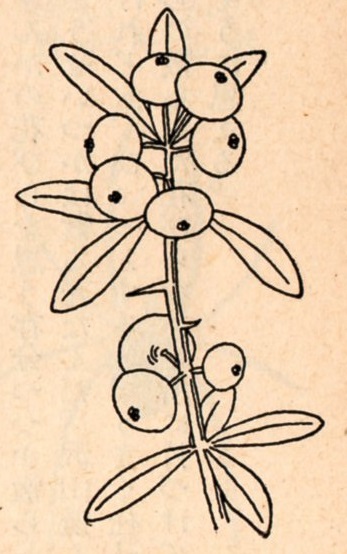 だれでも教壇に立っている人は同じだと思うから言うのだが、講義の準備が出来ていないのに学校へ出かけて行くのは実につらいものである。四五年前のちょうど今ごろ、もうそろそろ冬休みにしようかと思いながら、重たい気持ちで学校へ行く途中、よその家の生垣に、このたちばなもどきの、ちっぽげな蜜柑のような実がいっぱいなっているのを見て、こっそり小さい枝を折り、それを哲学の教室まで持って行った。
だれでも教壇に立っている人は同じだと思うから言うのだが、講義の準備が出来ていないのに学校へ出かけて行くのは実につらいものである。四五年前のちょうど今ごろ、もうそろそろ冬休みにしようかと思いながら、重たい気持ちで学校へ行く途中、よその家の生垣に、このたちばなもどきの、ちっぽげな蜜柑のような実がいっぱいなっているのを見て、こっそり小さい枝を折り、それを哲学の教室まで持って行った。
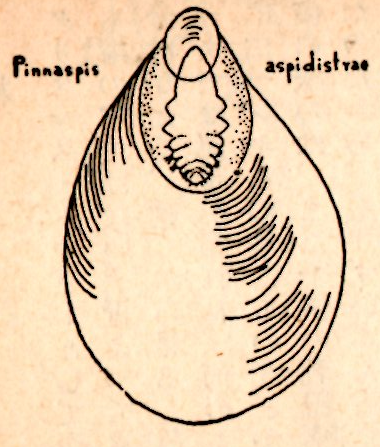
 クリスマス・トゥリーとして売り出されているものは、必ずしも樅の木ではない。近よって見るこのと種のものはかえって見分けがたく、遠くから見ると色がちがう。実際、日本のクリスマスでは部屋が飾れれば何の木でもいいのだし、無花果の枯れ木に白ペンキをぬったものなどかえってきれいなものだった。
クリスマス・トゥリーとして売り出されているものは、必ずしも樅の木ではない。近よって見るこのと種のものはかえって見分けがたく、遠くから見ると色がちがう。実際、日本のクリスマスでは部屋が飾れれば何の木でもいいのだし、無花果の枯れ木に白ペンキをぬったものなどかえってきれいなものだった。
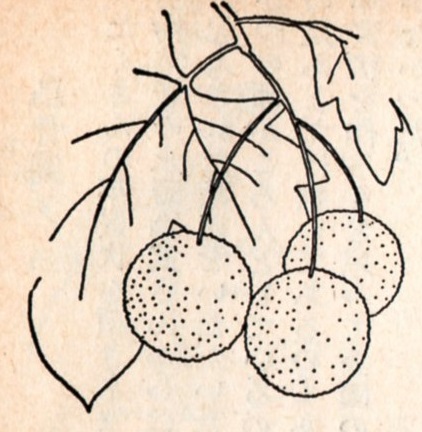 小アジア原産のこの木は、明治のころにはいって来たものだが、同じころに北米原産の「あめりかすずかけのき」も移入して、そのどちらも街路樹になっている。はっきり区別できるのは、すずかけの実は一本の花軸に数個なる点であるあるが、樹皮がはがれるということもある。
小アジア原産のこの木は、明治のころにはいって来たものだが、同じころに北米原産の「あめりかすずかけのき」も移入して、そのどちらも街路樹になっている。はっきり区別できるのは、すずかけの実は一本の花軸に数個なる点であるあるが、樹皮がはがれるということもある。
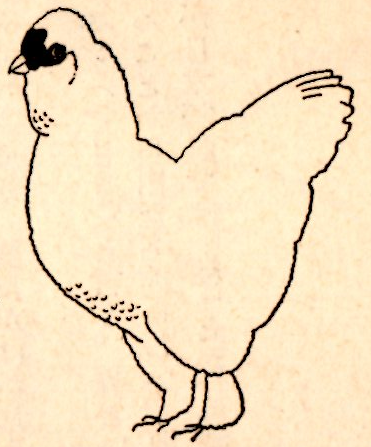

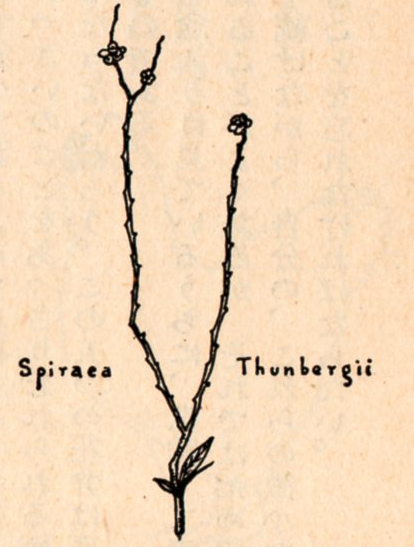 ところが、なにも手を加えないのに、この花はよく狂い咲きをする。去年の秋、かなりおそくなってから、池のへりでずいぶん花を見たし、今は年を越える時分に開いたものが黄ばんでくっつているほかに、また一ニ輪ずつ新しく咲いている。
ところが、なにも手を加えないのに、この花はよく狂い咲きをする。去年の秋、かなりおそくなってから、池のへりでずいぶん花を見たし、今は年を越える時分に開いたものが黄ばんでくっつているほかに、また一ニ輪ずつ新しく咲いている。
 僕は「ナガヒョウホンムシ、採集の場所は標本箱」というラベルをつけてこの虫をたった一匹、がら空きになった標本箱のまん中にピンでとめた。ふくしゅうをしたこの虫は、他の標本がなくなった後の箱にぽっんととめられているのにふさわしい。
僕は「ナガヒョウホンムシ、採集の場所は標本箱」というラベルをつけてこの虫をたった一匹、がら空きになった標本箱のまん中にピンでとめた。ふくしゅうをしたこの虫は、他の標本がなくなった後の箱にぽっんととめられているのにふさわしい。
 もう果実も大分垂れ下がっている。この果実のようすが、不名誉な名前の原因なのであるが、わざわざ別名のるりばなひょうたんぐさと呼ぶ必要も感じられない。
シェークスピアの「ハムレット」の中に、王妃が、紫蘭のことを「あの花を口汚い羊飼いたちはみだらな名で呼んでおりますが……」という箇所がある。どんな名前で呼んでいるのかシェークスピア学者の誰かがきっとしらべたことがあるだろうが僕は知らない。けれども外国にも気の毒な名をつけられてしまった花もある。
もう果実も大分垂れ下がっている。この果実のようすが、不名誉な名前の原因なのであるが、わざわざ別名のるりばなひょうたんぐさと呼ぶ必要も感じられない。
シェークスピアの「ハムレット」の中に、王妃が、紫蘭のことを「あの花を口汚い羊飼いたちはみだらな名で呼んでおりますが……」という箇所がある。どんな名前で呼んでいるのかシェークスピア学者の誰かがきっとしらべたことがあるだろうが僕は知らない。けれども外国にも気の毒な名をつけられてしまった花もある。



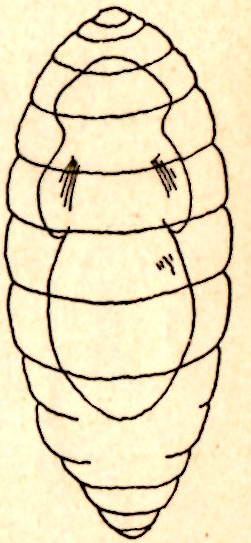
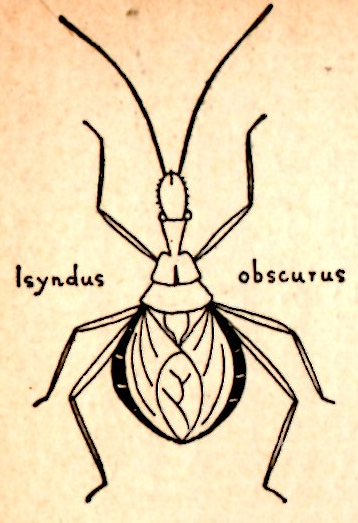 これは日本産のさしがめのうちでは一番大きいもので、口さきは、、めったには刺しませんよというようにつつましく折りまげてある。君は秋田のお嬢さんをいじめたんだろう。どのくらい痛いものか、ちょっと刺してごらん。刺してもいいよと言って腕の上にのせて、もさっぱり元気がない。長い旅で疲れたのか、寒さにだるいのか……。
これは日本産のさしがめのうちでは一番大きいもので、口さきは、、めったには刺しませんよというようにつつましく折りまげてある。君は秋田のお嬢さんをいじめたんだろう。どのくらい痛いものか、ちょっと刺してごらん。刺してもいいよと言って腕の上にのせて、もさっぱり元気がない。長い旅で疲れたのか、寒さにだるいのか……。

 僕が特別にこの蜂に注意するのは、いたって単純な理由である。その腰の、なかな優美にふくらみ始めるそのあたりにつけている二つの黄色い紋が、いかにも得意だからだ。蜂は柱から逃げない。触覚は真剣にうごかしているが、腰つきには、このあざやかな二つの紋を見てくれなくては……というような自信が見える。
僕が特別にこの蜂に注意するのは、いたって単純な理由である。その腰の、なかな優美にふくらみ始めるそのあたりにつけている二つの黄色い紋が、いかにも得意だからだ。蜂は柱から逃げない。触覚は真剣にうごかしているが、腰つきには、このあざやかな二つの紋を見てくれなくては……というような自信が見える。

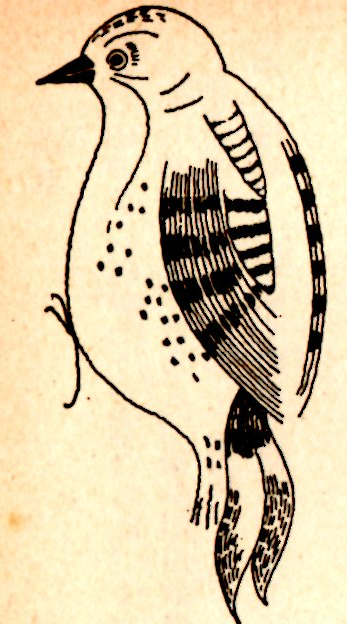 そのうちに、二羽のこげらが木々を幹から枝へ、また枝から幹へと、ぺったりはりついたまんま登り下りしている姿が僕の足をとめた。すぐ近くの枯木に彼らの巣かとも思われるかなり深い穴があったので、スキーをはずしていちおうのぞきに登ってみたが、木登りのうまいこげらの目に、ひとりでそんなことをしている僕の姿がどんなにぶざまに映っているかを思って恥かしくなった。枯木は春がはっきりやって来る前に倒れるだろう。それを知っているのか、こげらはそこには巣を作っていなかった。
そのうちに、二羽のこげらが木々を幹から枝へ、また枝から幹へと、ぺったりはりついたまんま登り下りしている姿が僕の足をとめた。すぐ近くの枯木に彼らの巣かとも思われるかなり深い穴があったので、スキーをはずしていちおうのぞきに登ってみたが、木登りのうまいこげらの目に、ひとりでそんなことをしている僕の姿がどんなにぶざまに映っているかを思って恥かしくなった。枯木は春がはっきりやって来る前に倒れるだろう。それを知っているのか、こげらはそこには巣を作っていなかった。
 寂しい花ではあるけれど、一輪草は明るい。二輪草のようにふたりで明るく咲いているよりも、ひとりで明るい顔をしているのはけなげな様子にも見えてうれしくなる。
この花には、支那に伝説がある。ある家にかわいらしい子供がいて、両親から大切にされていた。その子供が、まだ五つにもならないうちに死んでしまった。両親は大そう悲しんで、毎日その墓のまわりをうろうろ歩いては泣いていた。ところがある晩、その子供が夢にあらわれ、一本の花を持っていた。そして、「私はいま浄土にいて幸せにしていますけれど、御両親があまり悲しんでいらっしゃるの御仏が気の毒に思われ、私にこの花を持たせたのです。私と思って育てて下さい」と言った。悲しみの心のまよいかと思ったが、夜の明ける待って墓へ行くと、そこに、夢にみた花が咲いていた。両親は自分の愛児の魂として大切に育て、それが一輪草だという話である。
寂しい花ではあるけれど、一輪草は明るい。二輪草のようにふたりで明るく咲いているよりも、ひとりで明るい顔をしているのはけなげな様子にも見えてうれしくなる。
この花には、支那に伝説がある。ある家にかわいらしい子供がいて、両親から大切にされていた。その子供が、まだ五つにもならないうちに死んでしまった。両親は大そう悲しんで、毎日その墓のまわりをうろうろ歩いては泣いていた。ところがある晩、その子供が夢にあらわれ、一本の花を持っていた。そして、「私はいま浄土にいて幸せにしていますけれど、御両親があまり悲しんでいらっしゃるの御仏が気の毒に思われ、私にこの花を持たせたのです。私と思って育てて下さい」と言った。悲しみの心のまよいかと思ったが、夜の明ける待って墓へ行くと、そこに、夢にみた花が咲いていた。両親は自分の愛児の魂として大切に育て、それが一輪草だという話である。
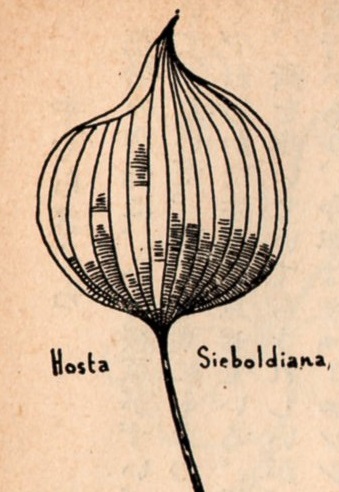


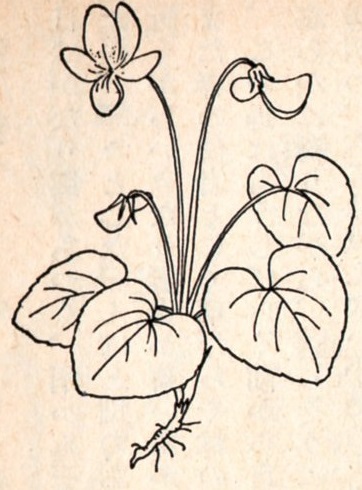
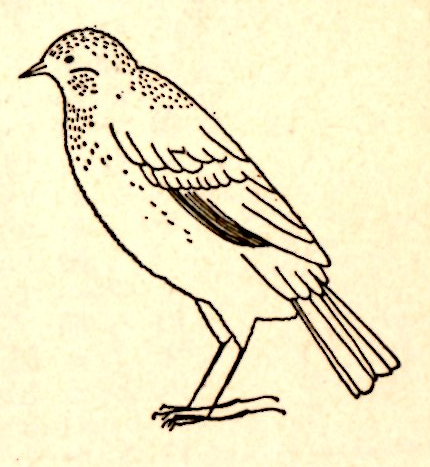 今日はかなり雲があつく、雨かみぞれでも降り出しそうな空模様だが、寒々とした田んぼと畑のあいだの道を歩いて行くと、近くからいきなり雲雀が舞いあがった。同じようにして、蝶もまた春の使者として草むらや林の中から飛び立つこともあるが、この鳥はもうしばらく前から自分の声を整えていたように、高らかに囀りながら、嬉しそうに羽ばたく。空中に建てられた透明の、人には見えない小鳥の大建築を、六階七階八階と、エレベーターに乗って昇って行く。僕は腕時計の針をほとんど反射的に見て、雲雀の空中にいる時間をはかる。去年、こうして彼らの滞空時間を手帳に記録していたが、その癖が、今年最初に出会った時に、ひょっと出て来たのである。数日前に関東平野を走る汽車の窓から、遠くの空に雲雀らしい姿を見たが、これは確かめられなかった。
今日はかなり雲があつく、雨かみぞれでも降り出しそうな空模様だが、寒々とした田んぼと畑のあいだの道を歩いて行くと、近くからいきなり雲雀が舞いあがった。同じようにして、蝶もまた春の使者として草むらや林の中から飛び立つこともあるが、この鳥はもうしばらく前から自分の声を整えていたように、高らかに囀りながら、嬉しそうに羽ばたく。空中に建てられた透明の、人には見えない小鳥の大建築を、六階七階八階と、エレベーターに乗って昇って行く。僕は腕時計の針をほとんど反射的に見て、雲雀の空中にいる時間をはかる。去年、こうして彼らの滞空時間を手帳に記録していたが、その癖が、今年最初に出会った時に、ひょっと出て来たのである。数日前に関東平野を走る汽車の窓から、遠くの空に雲雀らしい姿を見たが、これは確かめられなかった。

 しかし僕はなずなについては、ここしばらく根生葉を注意してみることになるだろう。根生葉は羽状にさけるとは本に書いてあるが、それが魚の骨のように、葉とは思えない姿に変わっているものが多い。ちょうどいい機会でもあるので、植物奇型の勉強にかかろう。奇型とは……という定義から本によってひとまず学ばなければならない。そして最も興味あることは、なぜ奇型にならなければならないのか、その原因をさぐることであろう。諦めるより仕方のないことをもう一度考えなおすことが勉強の一つである。しかし、人間の精神の奇型などということはいっさい考えないようにしよう。
しかし僕はなずなについては、ここしばらく根生葉を注意してみることになるだろう。根生葉は羽状にさけるとは本に書いてあるが、それが魚の骨のように、葉とは思えない姿に変わっているものが多い。ちょうどいい機会でもあるので、植物奇型の勉強にかかろう。奇型とは……という定義から本によってひとまず学ばなければならない。そして最も興味あることは、なぜ奇型にならなければならないのか、その原因をさぐることであろう。諦めるより仕方のないことをもう一度考えなおすことが勉強の一つである。しかし、人間の精神の奇型などということはいっさい考えないようにしよう。
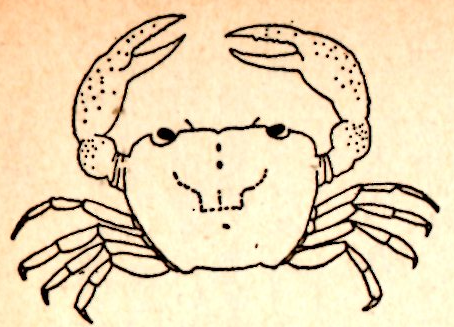
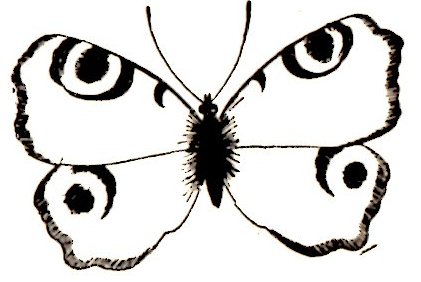 その時、林にかかるところで、一匹の孔雀蝶が、僕たちをさそうように飛び立った。 geisha (芸者)という学名をつけられているこの蝶は、成虫で越冬する種類であるが、どこにうまく隠れていたのか、翅に少しの傷もなく、はでな紋付で明るい光を浴びていた。スキーをつけて孔雀蝶を追いかけるのははじめての経験だった。
その時、林にかかるところで、一匹の孔雀蝶が、僕たちをさそうように飛び立った。 geisha (芸者)という学名をつけられているこの蝶は、成虫で越冬する種類であるが、どこにうまく隠れていたのか、翅に少しの傷もなく、はでな紋付で明るい光を浴びていた。スキーをつけて孔雀蝶を追いかけるのははじめての経験だった。
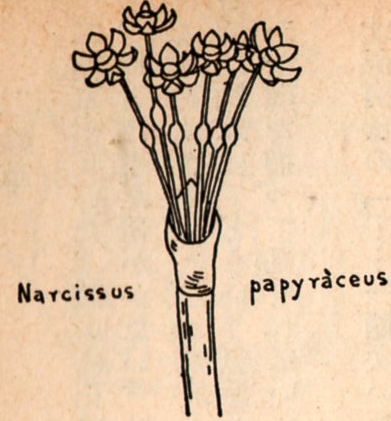

 このままにしておいても、これらの小さな蕾が花となるまでに育つことは考えられない。けれども、おし葉として保存した花が、新聞紙のあいだで種子(たね)に変っていたこともあるし、死んだはずの植物は、僕たち動物には想像も出来ない死後の生活を営みつづけていることがある。
このままにしておいても、これらの小さな蕾が花となるまでに育つことは考えられない。けれども、おし葉として保存した花が、新聞紙のあいだで種子(たね)に変っていたこともあるし、死んだはずの植物は、僕たち動物には想像も出来ない死後の生活を営みつづけていることがある。
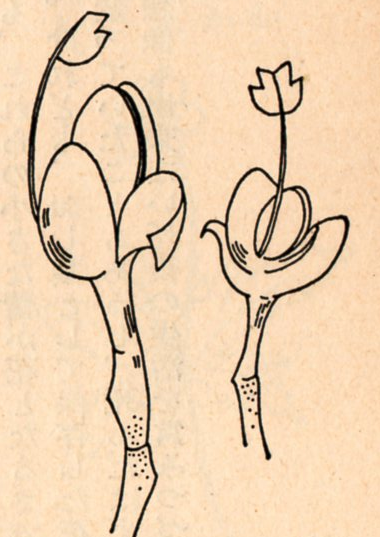 英国でこの木をチューリップ・トゥリーというのも、日本でゆりのきと呼ぶのも、もうそろそろ咲きはじめる花が、チューリップや百合に似ているからであるが、僕ははんてんぼくという別名もおもしろいと思っている。
英国でこの木をチューリップ・トゥリーというのも、日本でゆりのきと呼ぶのも、もうそろそろ咲きはじめる花が、チューリップや百合に似ているからであるが、僕ははんてんぼくという別名もおもしろいと思っている。
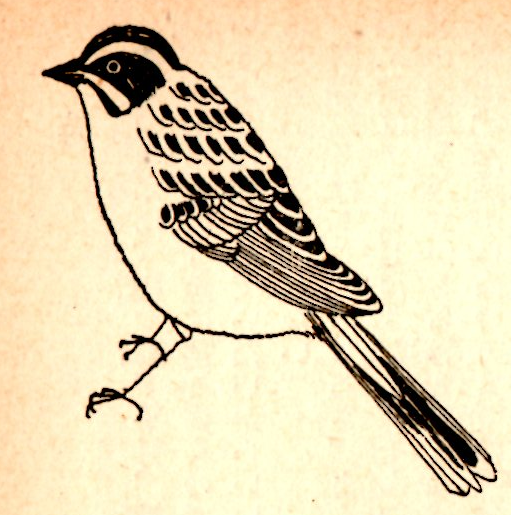 双眼鏡をさげて、茅原のすみにかくれ、彼らの求愛の容子だの、領域を守ための仕種を見ていると、おかしくなったり、楽しくなったり、急に淋しくもなる。そういう自分の気持に注意がよせられるようになったら、もう監察は切りあげ来なければならない。る
双眼鏡をさげて、茅原のすみにかくれ、彼らの求愛の容子だの、領域を守ための仕種を見ていると、おかしくなったり、楽しくなったり、急に淋しくもなる。そういう自分の気持に注意がよせられるようになったら、もう監察は切りあげ来なければならない。る
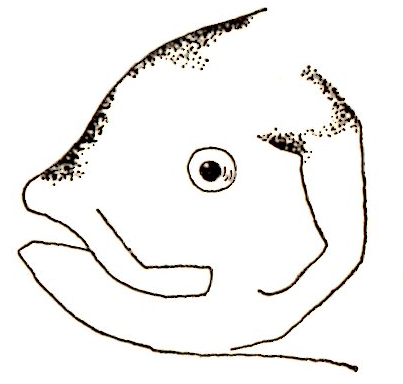 四月の魚には、鯛や鰤(ぶり)、平目、鰊(にしん)、かれいなどがあげられてあるが、さわらという魚は鰆と書くので季節感が強い。春の魚は俺さというような顔をしていないからいいようなものの、不満に思って魚もいるかも知れない。
四月の魚には、鯛や鰤(ぶり)、平目、鰊(にしん)、かれいなどがあげられてあるが、さわらという魚は鰆と書くので季節感が強い。春の魚は俺さというような顔をしていないからいいようなものの、不満に思って魚もいるかも知れない。
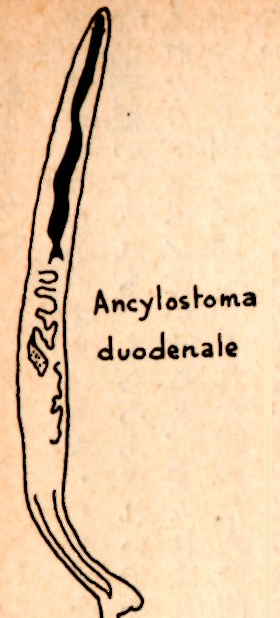 これはね、もう死んでいるからこわくない。おかあさんのお腹の中でね、これがあばれていた。小さい壜に、虫とも糸屑ともつかないものが数匹アルコール漬になっていた。そこに、中を見るのに邪魔っけな紙が貼ってあったから、多分この名が書いてあったに違いない。
これはね、もう死んでいるからこわくない。おかあさんのお腹の中でね、これがあばれていた。小さい壜に、虫とも糸屑ともつかないものが数匹アルコール漬になっていた。そこに、中を見るのに邪魔っけな紙が貼ってあったから、多分この名が書いてあったに違いない。
 ラ・フランスとか、プリンセス・オヴ・ウェールズとか、立派な園芸種のすみれも、もちろんきれいでそれにふさわしい箱に入れたり、リボンをかけると、すみれは私たちの複雑な気持ちをそっくり引き受けて、これを贈った人の前へ出た時には、言いたいことをうまく喋ってくれるかも知れない。重宝なものであるけれど、やっぱり、こっ恥かしいことには変りない。
ラ・フランスとか、プリンセス・オヴ・ウェールズとか、立派な園芸種のすみれも、もちろんきれいでそれにふさわしい箱に入れたり、リボンをかけると、すみれは私たちの複雑な気持ちをそっくり引き受けて、これを贈った人の前へ出た時には、言いたいことをうまく喋ってくれるかも知れない。重宝なものであるけれど、やっぱり、こっ恥かしいことには変りない。

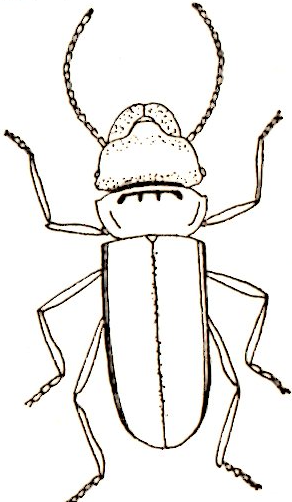
 そういえば人間の子供でも、兄弟で、何か貰う時にはいざこざが起りやすい。不公平を監視する幼い目は光るし、自分だけに多く分配されるのを期待する目はするどく、またあどけなく光る。
そういえば人間の子供でも、兄弟で、何か貰う時にはいざこざが起りやすい。不公平を監視する幼い目は光るし、自分だけに多く分配されるのを期待する目はするどく、またあどけなく光る。

 色の白きを嘆きはじめた白妙姫は段々やっれて来た。父の地の神はそれを天の神に告げると、天の神は自分の夾竹桃をとって与える。それを持ちかえると、娘はその紅い花をもんで紅色の雫を顔に熱心に塗った。すると、白い顔は美しい赤味がさして、植物の神は悦んでお婿さんになることを承知した。
色の白きを嘆きはじめた白妙姫は段々やっれて来た。父の地の神はそれを天の神に告げると、天の神は自分の夾竹桃をとって与える。それを持ちかえると、娘はその紅い花をもんで紅色の雫を顔に熱心に塗った。すると、白い顔は美しい赤味がさして、植物の神は悦んでお婿さんになることを承知した。
 さといも科の商物であることは見当がついたが、暗紫色の気味の悪い姿が、これはひょつとするとなにかの化けたものかも知れないと思わせる。知らない者をすぐに異常なものと考える悪い癖が僕にはまだ残っている。
さといも科の商物であることは見当がついたが、暗紫色の気味の悪い姿が、これはひょつとするとなにかの化けたものかも知れないと思わせる。知らない者をすぐに異常なものと考える悪い癖が僕にはまだ残っている。

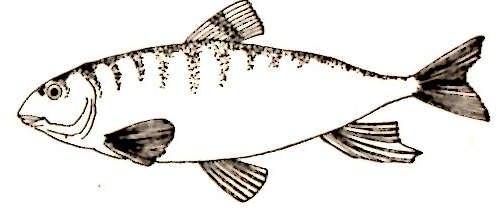
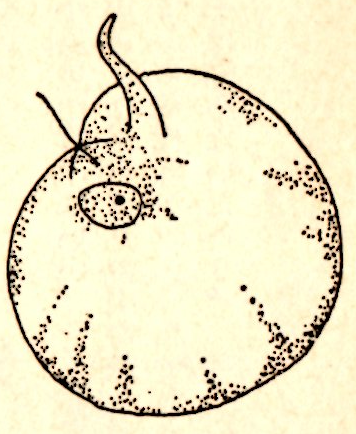
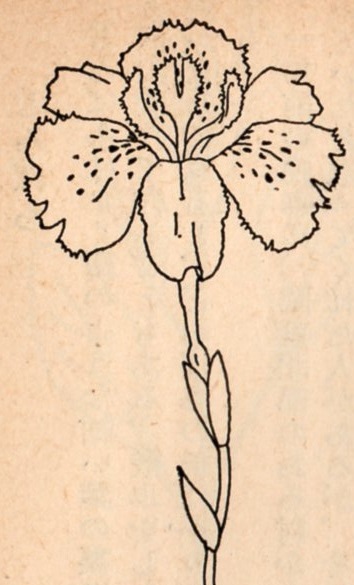 それで、この花の名を覚えるについては、大変に贅沢なことをしたようにも思っているが、しゃがという名は射干と書く漢名から来たのではないかという説しか聞いていない。けれども射干は、ひおうぎのことであろう。それからこの花のことを胡蝶孔(こちょうか)とも書いているが、しゃがに一番よく似ている蝶というと何だろうか。色はともかく、姿は「シーたては」ということだろう。
それで、この花の名を覚えるについては、大変に贅沢なことをしたようにも思っているが、しゃがという名は射干と書く漢名から来たのではないかという説しか聞いていない。けれども射干は、ひおうぎのことであろう。それからこの花のことを胡蝶孔(こちょうか)とも書いているが、しゃがに一番よく似ている蝶というと何だろうか。色はともかく、姿は「シーたては」ということだろう。
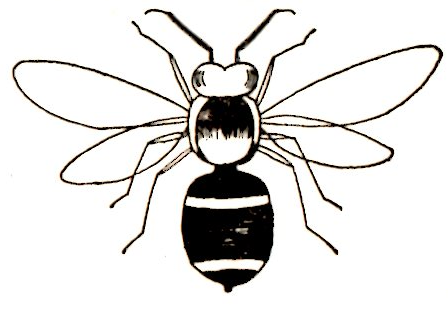 一年前の晩春に、関東北部のある村からうちの土蔵の壁にこんなものがついていたと送ってくれた人があるが、それもどろばちの巣で、もう卵からかえり、蜂はどこかへ飛び立ってしまった後だったが、幼虫の時代にさんざん食べた蜘蛛のひからびた脚や胴の一部分がのこっていた。ビニールの袋に入れ、それを多量の屑糸で包んで、完全のまま届き、今も残っている。
一年前の晩春に、関東北部のある村からうちの土蔵の壁にこんなものがついていたと送ってくれた人があるが、それもどろばちの巣で、もう卵からかえり、蜂はどこかへ飛び立ってしまった後だったが、幼虫の時代にさんざん食べた蜘蛛のひからびた脚や胴の一部分がのこっていた。ビニールの袋に入れ、それを多量の屑糸で包んで、完全のまま届き、今も残っている。
 なぜこんな粉をふかなければならないのか、それがなぜ赤かったり白かったりするのか。僕は葡萄の実の表面につく粉やその他のものを考えながら、家に持ちかえって拡大鏡でみると、細かいぶつぶつが、一つ一つ光っている南京玉だ。これをつないで、幾人の少女のくびを飾ることが出来るだろう。植物生理の本を読みなおす前にそんなことを考えて遊んでしまう。そして悲しい気持ちでこの草をうでて食べた戦争のころを思い出したが、その当時あかざを食べすぎてひどい火傷(やけど)のような「アカザ皮膚炎」にかかった人もいる。まさかこのきれいな南京玉がいけなかったのではあるまいか。
なぜこんな粉をふかなければならないのか、それがなぜ赤かったり白かったりするのか。僕は葡萄の実の表面につく粉やその他のものを考えながら、家に持ちかえって拡大鏡でみると、細かいぶつぶつが、一つ一つ光っている南京玉だ。これをつないで、幾人の少女のくびを飾ることが出来るだろう。植物生理の本を読みなおす前にそんなことを考えて遊んでしまう。そして悲しい気持ちでこの草をうでて食べた戦争のころを思い出したが、その当時あかざを食べすぎてひどい火傷(やけど)のような「アカザ皮膚炎」にかかった人もいる。まさかこのきれいな南京玉がいけなかったのではあるまいか。
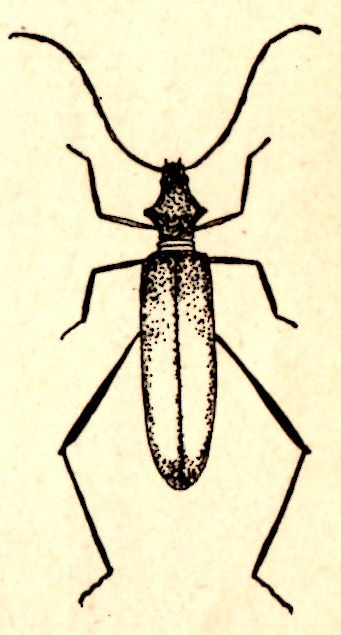
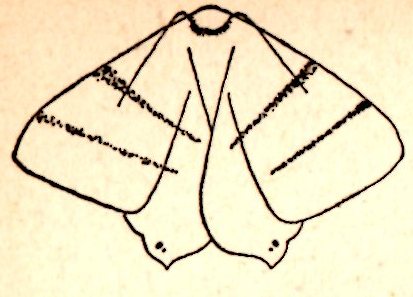 この雅は今朝机のわきの板へとまっていた。何という静かな姿だろう。短い生涯を、決してあせる様子もなく、ただこうして憩いつつすごしている姿は、予感におびえることもなく、あわただしく悦び狂うのでもなく、確信にみちたその姿は。前翅と後翅の線が正確に一直線になるように翅をたたむ。僕はそれを見ていると非常に洗練されたポーズのようで、これにはかなわないと思った。
この雅は今朝机のわきの板へとまっていた。何という静かな姿だろう。短い生涯を、決してあせる様子もなく、ただこうして憩いつつすごしている姿は、予感におびえることもなく、あわただしく悦び狂うのでもなく、確信にみちたその姿は。前翅と後翅の線が正確に一直線になるように翅をたたむ。僕はそれを見ていると非常に洗練されたポーズのようで、これにはかなわないと思った。
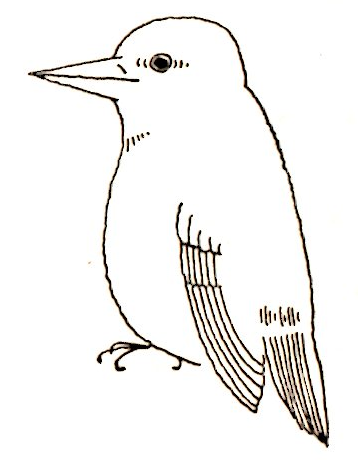
 しろつめくさは童話の野草にだけ咲いているのではない。Trifolium repens という学名は匍匐(ほふく)する三つの葉という意味があるが、三つの葉と言われると四つ葉のクロバーをさがして、人は幸福を夢見る。その四つ葉はさがそそうとすると容易には見つけにくいけれど、ひょっとした時に、ひとかたまりの四つ葉を摘みとることが出来る。誰か幸福になりたがっているものはいないだろうか。戦場」に傷ついた兵士が、傷を癒してくれた乙女にささげたこのシンボルを、愛と幸福と感謝のシンボルをほしいものはいないだろうか。
しろつめくさは童話の野草にだけ咲いているのではない。Trifolium repens という学名は匍匐(ほふく)する三つの葉という意味があるが、三つの葉と言われると四つ葉のクロバーをさがして、人は幸福を夢見る。その四つ葉はさがそそうとすると容易には見つけにくいけれど、ひょっとした時に、ひとかたまりの四つ葉を摘みとることが出来る。誰か幸福になりたがっているものはいないだろうか。戦場」に傷ついた兵士が、傷を癒してくれた乙女にささげたこのシンボルを、愛と幸福と感謝のシンボルをほしいものはいないだろうか。
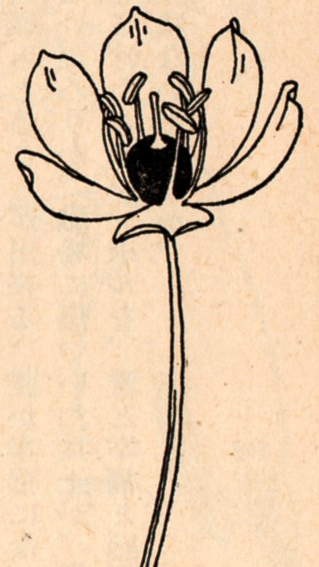 前に、ベツレヘムの星という名の花のことを書いたが、同じオルニソガルム属のもので、いま、アラビアの、星が咲いている。秋に球根で植えたものであるが、雌蕊(めしべ)の黒いのが特徴で、和名は「黒星おおまな」である。命名者には悪いが、黒星という日本語が特別な意味を持っているので、僕はアラビアの星の方がはるかに名前としては好きだ。アラビアの星といっ理由は分からないが、黒い光を想像できるのはおもしろい。
前に、ベツレヘムの星という名の花のことを書いたが、同じオルニソガルム属のもので、いま、アラビアの、星が咲いている。秋に球根で植えたものであるが、雌蕊(めしべ)の黒いのが特徴で、和名は「黒星おおまな」である。命名者には悪いが、黒星という日本語が特別な意味を持っているので、僕はアラビアの星の方がはるかに名前としては好きだ。アラビアの星といっ理由は分からないが、黒い光を想像できるのはおもしろい。
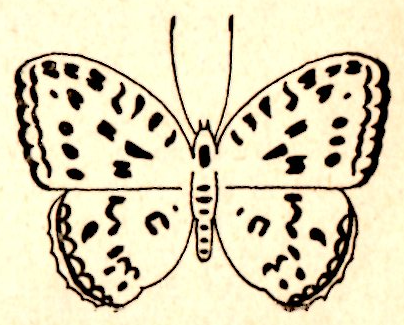 僕のこの蝶についての記録は、五月二十四日に幼虫を見つけ飼育し出す。菫が好きなことを知っているので沢山食べさせる。この幼虫は前年の秋に卵の中でかえってから、そのまま冬を越して来た強い奴なのだ。六月七日に蛹となり、六月二十四日に羽化した十七日間蛹でいたことを見届けたわけである。
僕のこの蝶についての記録は、五月二十四日に幼虫を見つけ飼育し出す。菫が好きなことを知っているので沢山食べさせる。この幼虫は前年の秋に卵の中でかえってから、そのまま冬を越して来た強い奴なのだ。六月七日に蛹となり、六月二十四日に羽化した十七日間蛹でいたことを見届けたわけである。
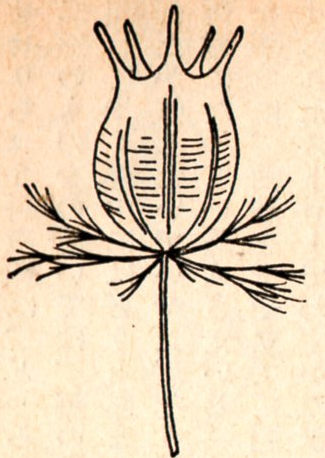 黒種草はもちろんその黒い種子からつけられた名前であるし、学名もニゲラである。
黒種草はもちろんその黒い種子からつけられた名前であるし、学名もニゲラである。
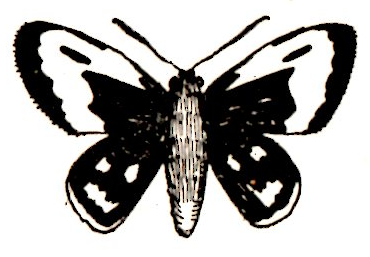 何だか蛾みたいでいやだ、そう言ってちらっと見ただけで、その無関心を得意になっている人さえいる。けれども、決してそんなことはない。後翅を平らに、前翅をやや立てて薊のはななどにとまって、めいめい口にとりつけられたストローでわずかの蜜をせっかちに吸っているのを、まあゆっくりと見てみるがいい。
何だか蛾みたいでいやだ、そう言ってちらっと見ただけで、その無関心を得意になっている人さえいる。けれども、決してそんなことはない。後翅を平らに、前翅をやや立てて薊のはななどにとまって、めいめい口にとりつけられたストローでわずかの蜜をせっかちに吸っているのを、まあゆっくりと見てみるがいい。
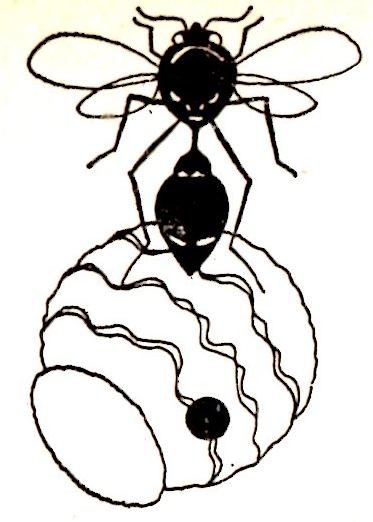
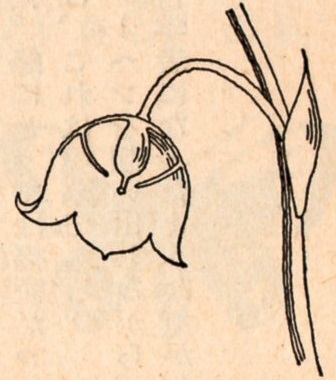 その療養所の一患者からの手紙だったが、自分のいる病棟のわきには、鈴蘭がきれいだった。鈴蘭ばかりでなく、いちやくそう、べにばないちやくそうなどの花も眺められたのに、この二三年、患者たちが根ごと掘り、中には大量に掘って都へ送り、お小遣いかせぎをしている人もある。それで、今年などはもう余程遠くまで歩いて行かないとそんな花を見ることが出来なくなってしまった……、ということが書いてあった。
その療養所の一患者からの手紙だったが、自分のいる病棟のわきには、鈴蘭がきれいだった。鈴蘭ばかりでなく、いちやくそう、べにばないちやくそうなどの花も眺められたのに、この二三年、患者たちが根ごと掘り、中には大量に掘って都へ送り、お小遣いかせぎをしている人もある。それで、今年などはもう余程遠くまで歩いて行かないとそんな花を見ることが出来なくなってしまった……、ということが書いてあった。
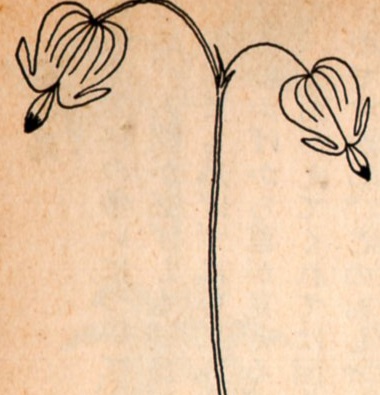 ある人がこれも昔、案内をたのんで歩いたら、この岩のかげに駒草が咲いているはずだがと言って近づいたら、ちゃんと咲いていたので、さうがに山に詳しいものだと言って感心していた。しかし、山の径を歩いていると、ちょっとした岩などを妙によく覚えてているもので、その案内人が一週間ほど前にそこをとおったことがあるなら、駒草のありかお知っているのはさほど感心することでもないだろう。
ある人がこれも昔、案内をたのんで歩いたら、この岩のかげに駒草が咲いているはずだがと言って近づいたら、ちゃんと咲いていたので、さうがに山に詳しいものだと言って感心していた。しかし、山の径を歩いていると、ちょっとした岩などを妙によく覚えてているもので、その案内人が一週間ほど前にそこをとおったことがあるなら、駒草のありかお知っているのはさほど感心することでもないだろう。
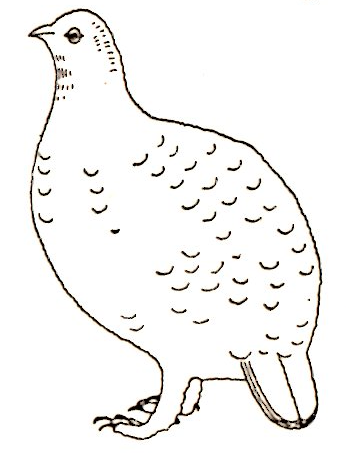 偃松(はいまつ)のかげから首が見える。冬も夏もその目もとをちょっと赤くして、まちがえてくれては困りますよ。めそめそ泣いていたのではないですから。このおしゃれには、何か秘密がありそうである。
偃松(はいまつ)のかげから首が見える。冬も夏もその目もとをちょっと赤くして、まちがえてくれては困りますよ。めそめそ泣いていたのではないですから。このおしゃれには、何か秘密がありそうである。
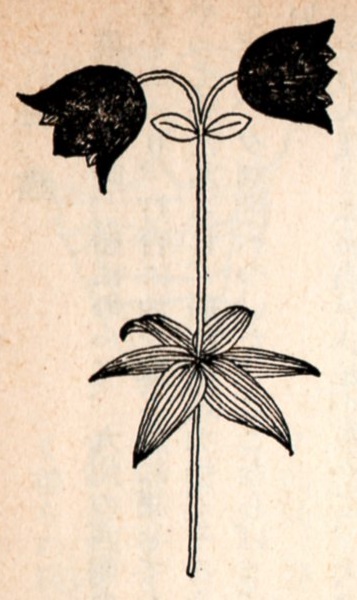 黒百合という花に、僕自身は何も関係ない。というより、僕は僕らしくこの花との関係を結び、想い出を持てばいいわけであるが、伝説の力が強くききすぎることもあって、暗い紫色がどうも気になる。そして花の伝説を知ることは恐ろしいと思う。
黒百合という花に、僕自身は何も関係ない。というより、僕は僕らしくこの花との関係を結び、想い出を持てばいいわけであるが、伝説の力が強くききすぎることもあって、暗い紫色がどうも気になる。そして花の伝説を知ることは恐ろしいと思う。
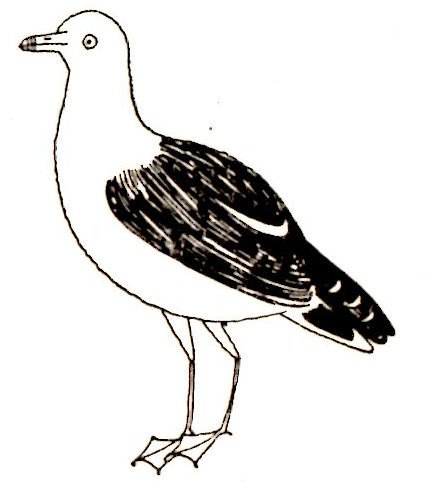 僕はその時、船にのって、九州の西側の島をめぐっていた。島をめぐり、灯台に油を運ぶ船に乗せてもらっていた。颱風がやって来たある日、船は全速力で、そろそろ荒れ模様の海を走り続け、夕刻港へついた。ここならばまず安全だという港へはいった。
僕はその時、船にのって、九州の西側の島をめぐっていた。島をめぐり、灯台に油を運ぶ船に乗せてもらっていた。颱風がやって来たある日、船は全速力で、そろそろ荒れ模様の海を走り続け、夕刻港へついた。ここならばまず安全だという港へはいった。
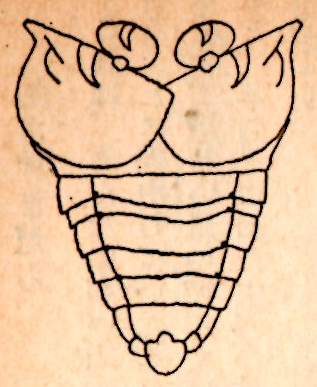 みんみん蝉は、あぶら蝉と同じで、七年間を土の中で生活してやっと親になるはずだが、その蝉はどんなところで地下の生活を送っていたのだろか。仮に銀座あたりの地下にもぐっていたとすれば、這い出そうとして、何遍かアスファルトの舗装道路に下からぶつかって、気の毒な思案をしたのではないかと思ったりした。蝉は大体夜、土の中から這い出す。そして足がかりのいい場所を選んで、夜脱皮をする。けれども青白い羽の、まだまっ白いのがおろおろしているのを、今年も一度や二度は見るだろう。そして蟻に惹かれて行く彼らの屍(しかばね)をみなければならないだろう。
みんみん蝉は、あぶら蝉と同じで、七年間を土の中で生活してやっと親になるはずだが、その蝉はどんなところで地下の生活を送っていたのだろか。仮に銀座あたりの地下にもぐっていたとすれば、這い出そうとして、何遍かアスファルトの舗装道路に下からぶつかって、気の毒な思案をしたのではないかと思ったりした。蝉は大体夜、土の中から這い出す。そして足がかりのいい場所を選んで、夜脱皮をする。けれども青白い羽の、まだまっ白いのがおろおろしているのを、今年も一度や二度は見るだろう。そして蟻に惹かれて行く彼らの屍(しかばね)をみなければならないだろう。
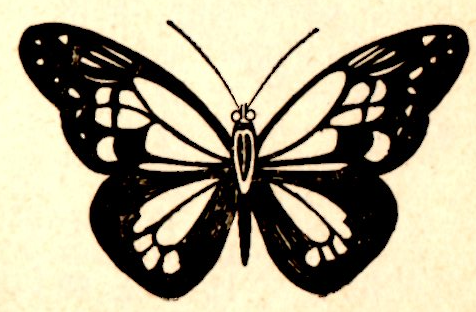 あれは蝶だよ、確かに蝶だよ。
あれは蝶だよ、確かに蝶だよ。

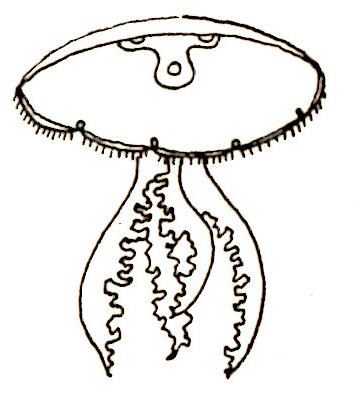 と言った質問と同じように、くらげの口は4どこにあるか、あのひらひらしているのは何かということは学校で習ったことがあっても、僕たちとあまり姿がちがいすぎるので忘れてしまう。彼らは波のまにまに漂っているばかりでなく、少しは泳ぐ。
と言った質問と同じように、くらげの口は4どこにあるか、あのひらひらしているのは何かということは学校で習ったことがあっても、僕たちとあまり姿がちがいすぎるので忘れてしまう。彼らは波のまにまに漂っているばかりでなく、少しは泳ぐ。
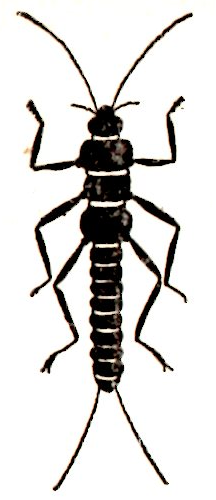 山でこの虫に会うたびに、僕は誘惑を感じる。中途半端な今の学問から、昆虫の方へ転向しさえすれば、それを堂々たる口実に山へはいっていられるからだ。
山でこの虫に会うたびに、僕は誘惑を感じる。中途半端な今の学問から、昆虫の方へ転向しさえすれば、それを堂々たる口実に山へはいっていられるからだ。
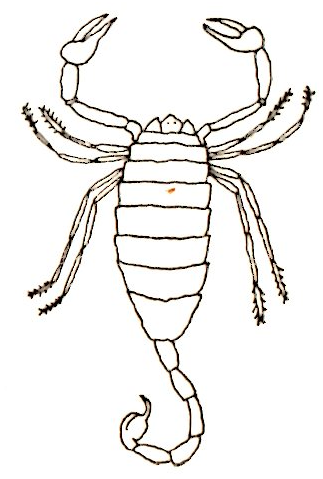
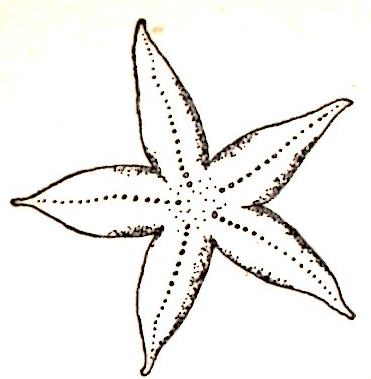
 ある時山小屋で紹介されたお嬢さんが、こばいけそうの写真を出して、これ、私がとった写真なんですけれど、何か書いて下さいませんかと言って僕に渡した。俗にいう気のきいた文句を、あまり待たせずに書かねばならない。ところがそのこばいけいそうはどうも見覚えがある、と思った途端に、これは知っていますと言ってしまったほど、確信があった。お嬢さんはきょとんしていた。
ある時山小屋で紹介されたお嬢さんが、こばいけそうの写真を出して、これ、私がとった写真なんですけれど、何か書いて下さいませんかと言って僕に渡した。俗にいう気のきいた文句を、あまり待たせずに書かねばならない。ところがそのこばいけいそうはどうも見覚えがある、と思った途端に、これは知っていますと言ってしまったほど、確信があった。お嬢さんはきょとんしていた。
 その岩峰の頂上にはさまざまの翼ある虫たちがやって来た。しりあげむしがさかんに飛んで来ては、僕たちの腕や膝にとまった。前翅と後翅とをきちんと重ねるので翅が二枚のようにしか見えない。多く山地にいるしりあげむしも翅の文様によって、また、蠍のようにもちあげている腹部の末端の形によって区別されるが、めったにはやって来られない岩の上で、虫の特徴をノートに書いたりしていると、このきばねしあげは翅をふるはせ、僕の膝を飛行場の滑走路のようにして、向きをかえて霧の中へ飛んで行った。僕たちはそこでパンをかじった。いつまで立っても去りがたい頂上が、だんだんのんびりした庭のように思えて来た。昔もそこで仲間と昼寝をしている時、しりあげむしなどがやって来たかしら。
その岩峰の頂上にはさまざまの翼ある虫たちがやって来た。しりあげむしがさかんに飛んで来ては、僕たちの腕や膝にとまった。前翅と後翅とをきちんと重ねるので翅が二枚のようにしか見えない。多く山地にいるしりあげむしも翅の文様によって、また、蠍のようにもちあげている腹部の末端の形によって区別されるが、めったにはやって来られない岩の上で、虫の特徴をノートに書いたりしていると、このきばねしあげは翅をふるはせ、僕の膝を飛行場の滑走路のようにして、向きをかえて霧の中へ飛んで行った。僕たちはそこでパンをかじった。いつまで立っても去りがたい頂上が、だんだんのんびりした庭のように思えて来た。昔もそこで仲間と昼寝をしている時、しりあげむしなどがやって来たかしら。
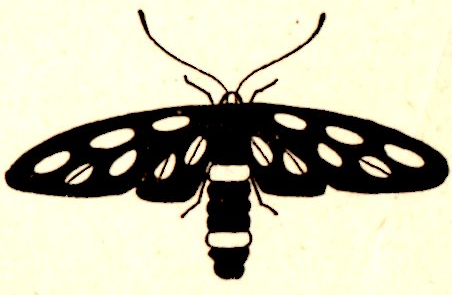


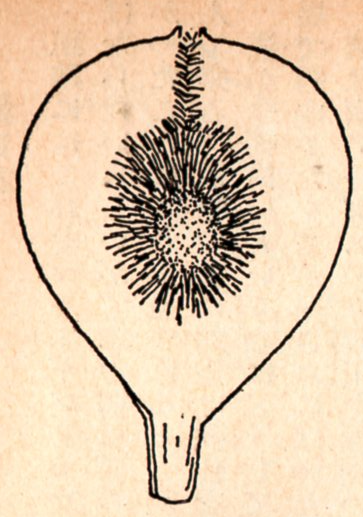
 正確にはこれはマルミギンリョウソウといわなければならないらしいが、山の樹林帯の中で、少し暮れかかったころにこれを見つけると、幽霊草という名が浮かんで来る。植物のこの幽霊は孤独を好まないようで、集まって咲いている。
正確にはこれはマルミギンリョウソウといわなければならないらしいが、山の樹林帯の中で、少し暮れかかったころにこれを見つけると、幽霊草という名が浮かんで来る。植物のこの幽霊は孤独を好まないようで、集まって咲いている。
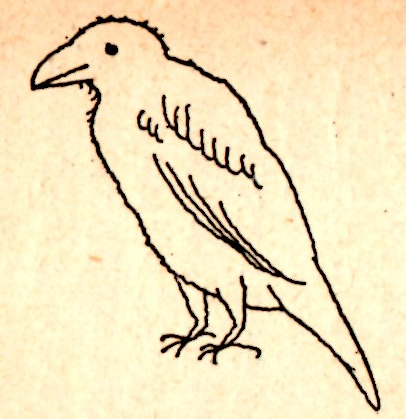
 僕もこのさるといりいばらに引っかかることがある。そのてららてらと艶の葉を見ると一応は警戒しているが、河原のへりの草むらの道の道もないようなところを歩いていると、ぱりぱっと気持ち悪くからまることがある。
僕もこのさるといりいばらに引っかかることがある。そのてららてらと艶の葉を見ると一応は警戒しているが、河原のへりの草むらの道の道もないようなところを歩いていると、ぱりぱっと気持ち悪くからまることがある。
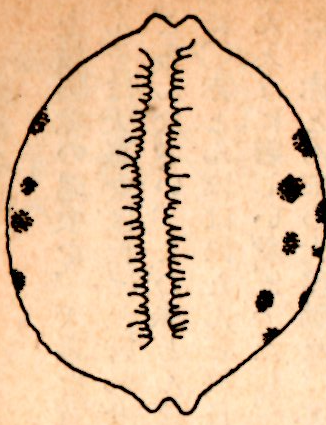
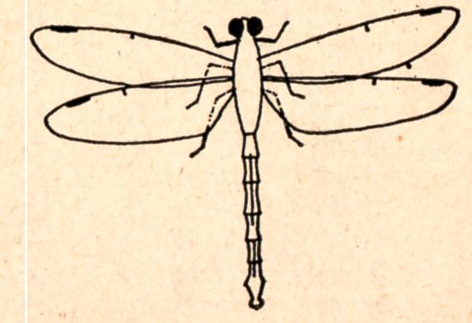 ごらんなさい、この赤とんぼの群れを。風の方向や、気流とは一応無関係に、赤とんぼはほとんど終日、同じ方向に向って飛んで行った。それはほんとうに夥しい数だったし、その中で一匹も逆へ飛んで行くのがいなかった。赤とんぼの大移動だ。実にその集団生活は立派だった。かさかさに光る翼を持つ無言の赤い点の流れを見て、誰かただ習性なのだと思っていられるだろう。
ごらんなさい、この赤とんぼの群れを。風の方向や、気流とは一応無関係に、赤とんぼはほとんど終日、同じ方向に向って飛んで行った。それはほんとうに夥しい数だったし、その中で一匹も逆へ飛んで行くのがいなかった。赤とんぼの大移動だ。実にその集団生活は立派だった。かさかさに光る翼を持つ無言の赤い点の流れを見て、誰かただ習性なのだと思っていられるだろう。
 ヨーロッパにもこれはあるだろうかと訊ねられ、僕もこの植物が出て来る小説を二つ三つ思い出しながら、あるようですけれど、こんなにきれいな庭はないでしょうといい加減のことを言った。
ヨーロッパにもこれはあるだろうかと訊ねられ、僕もこの植物が出て来る小説を二つ三つ思い出しながら、あるようですけれど、こんなにきれいな庭はないでしょうといい加減のことを言った。
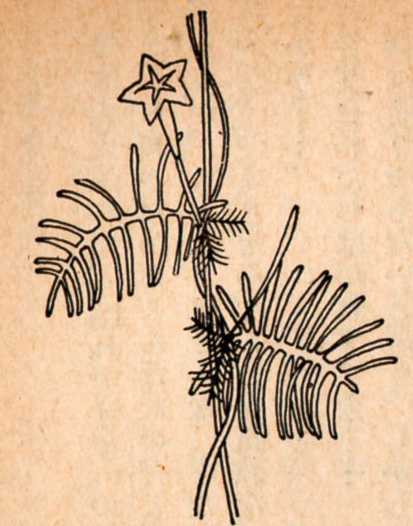 それは縷紅草の花とは関係はない。關係のあるはずはない。しかしこの花は、植え込みの外側の垣にからまっているので、その家に住んだ人のうち、どれだけ気がついていたか分からない。けれど僕の家では、あの曲り角の縷紅草の家の角と言っている。表札が始終変わるので、今の大臣と同じように誰もその名の記憶がない。
それは縷紅草の花とは関係はない。關係のあるはずはない。しかしこの花は、植え込みの外側の垣にからまっているので、その家に住んだ人のうち、どれだけ気がついていたか分からない。けれど僕の家では、あの曲り角の縷紅草の家の角と言っている。表札が始終変わるので、今の大臣と同じように誰もその名の記憶がない。
 僕は大正生まれで、「枯れすすき」の歌なんぞを聴きながら育ったからこんなのだと言われたことがあるが、こんなとはどんなかは訊ねなかった。つまりそんなことを訊ねないのが枯れすすき的なのかも知れないと僕は賢く思ってしまったから……。
僕は大正生まれで、「枯れすすき」の歌なんぞを聴きながら育ったからこんなのだと言われたことがあるが、こんなとはどんなかは訊ねなかった。つまりそんなことを訊ねないのが枯れすすき的なのかも知れないと僕は賢く思ってしまったから……。