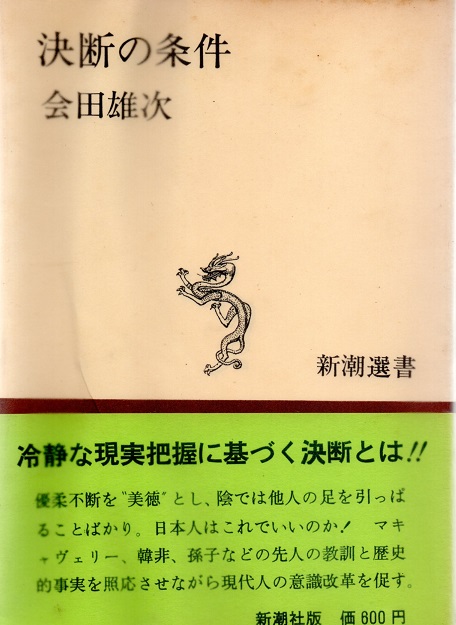
★会田雄次『決断の条件』(新潮選書)昭和50年7月20日 ニ刷
21 民はもとより勢いに屈す。よく義につくもの寡(すく)なし。 韓非子 P.145~160
今日ではもっとも問題の多いはずの発言である。大衆の要求は必ず正しいという不可解な感情は現在の日本で当り前の前提になっているからだ。しばらく韓非の説明を聞こう。孔子は天下にかくれもない聖人であった。行ないを治め、よるべき道を明らかにし、天下を遊説してまわった。だが、孔子の説く仁義をよろこび、その義を美として感服して弟子になったものは、何千万人の中でたったの七十人であった。仁を貴ぶものはこれほどすくなく、義をよくするものはそれほど容易に発見し難いものなのだ。しかも七十人といっても本当に仁義を身につけたものは孔子一人だった。そのことはかれが生涯嘆息しつつ、この弟子たちを説き続けなければならなかったことでも明らかである。
ところが一方、明君とはいえないものではない魯の哀公(春秋時代)でさえ、一度王位につくやその領域の民の一人としてそむくものはなくすべて臣従した。このように民は力につくものだ。そこで孔子も国に帰り、哀公が君、孔子が臣下となった。孔子は哀公の義についたのではない。その威風に服したのである。孔子でさえ力につくのだ。
このような意見に反対することは容易である。ところで、私がこんな主張を"決断の条件"に入れたことにはわけがある。つまり、日本人一般の、このような見解に対するお定まりの反応に対して文句がいいたいからだ。殆どの人は、「それは単純すぎる見方だ。世の中のことはそう簡単にいくものではない。恩威ならびに施すということが大切だ」という風に反論する。
ところで中国のこの時代の韓非と正反対の性善説、つまり仁義主義者は、そうはいっていないのである。恩威ならびではなく、恩つまり仁義「だけ」が人を悦服させるのだという。やはり一方の単純論を唱えているのだ。日本人は相手を論破せんがため、極端な論旨の刃をますます鋭くといでいくというやり方を苦手とする。それは議論のための議論であり、若者の空論であるにすぎぬ、現実はそう簡単ではないといって両者を止揚・総合したような顔をしたがる。しかしそれは止揚でも総合でもない。論理の否定であるにすぎぬ。現実主義というのでもない。現実は複雑だというのなら、その複雑な論理を構築しないかぎり、現実主義の主義という名に値しない。現実は複雑なのだからというだけでは思考でも論理でもない。要するに思考停止なのだ。
といって韓非のこの説は「力は正義」なりといった飛躍をやっているわけではない。論理一貫性をぎりぎり押し進めていっているにすぎぬ。
この論理一貫性の押し進め方である。そういう思考が可能な人間となれる訓練法である。私たち日本人の間では、その訓練は東大式のただ試験のための勉強とか、このごろ流行のクイズを解くような形式思考のための形式思考の訓練とか、今度はいやに飛躍した何事も経験だといった経験論になってしまうようである。
本当に論理性に強くなり意志決定が可能な人間になるためにはどうしたらよいのか、屁理屈だけが上手、というより駄々子的な自己主張をこねるだけの現代の若い人々を作って来たような戦後の教育法ではどうにもならないことは、はっきりしている。
 ニクソン時代アメリカで、大統領を動かしていた男、裏の大統領、米大統領についで世界で二番目に強大な権力を持つ男といわれていたのはキッシンジャーである。かれは亡命ユダヤ人の息子として、頭はよかったが教育もなく、気も弱い人間だった。それを「強い男」に仕立てたのは、国防総省で陸軍参謀総長顧問のフリック・クレーマーだといわれる。かれこそキッシンジャ―に炎のように燃焼する生をえらばせたその人なのだが、その決邸的な言葉はこうだった。「男というものは飢え、マルセイユの波止場に全くの一人でほうり出される。そんな時でも身につけているたった一着の背広を狙って男があとからつけてくる。そういった、ギリギリの状態に追いこまれてこそ人間は、はじめてこの世というものを理解することができるのだ。こういうとき『理性』とか『善』は無力である。かれはひとり起ち上がって戦うか、さもなければ死ぬだけなのだ」(クラフト、世界第ニの男『諸君』七一年六月所載)。
ニクソン時代アメリカで、大統領を動かしていた男、裏の大統領、米大統領についで世界で二番目に強大な権力を持つ男といわれていたのはキッシンジャーである。かれは亡命ユダヤ人の息子として、頭はよかったが教育もなく、気も弱い人間だった。それを「強い男」に仕立てたのは、国防総省で陸軍参謀総長顧問のフリック・クレーマーだといわれる。かれこそキッシンジャ―に炎のように燃焼する生をえらばせたその人なのだが、その決邸的な言葉はこうだった。「男というものは飢え、マルセイユの波止場に全くの一人でほうり出される。そんな時でも身につけているたった一着の背広を狙って男があとからつけてくる。そういった、ギリギリの状態に追いこまれてこそ人間は、はじめてこの世というものを理解することができるのだ。こういうとき『理性』とか『善』は無力である。かれはひとり起ち上がって戦うか、さもなければ死ぬだけなのだ」(クラフト、世界第ニの男『諸君』七一年六月所載)。
韓非の言葉もこのようにしてとらえるべきだろう。イザヤ・ペンダサンがのべているように、私たち日本人はよくせっぱつまるというが、ユダヤ人、広くは欧米人からみればそれはちょっともせっぱつまっていないのである。むしろチャンスに挑戦されているに過ぎない。ペンダサンは、日本人は環境がよすぎるので、それに甘えすぎてているのだという。学生にいい分、労組のいい分、経営者のいい分などたしかにそうだが、それは最近のことだ。戦前はずい分つらい環境に置かれていた人も多かった。そんな条件を考慮に入れてもいきづまったとはいえないのにのびてしまった場合が多いといえる。個人の挫折、経営の行きづまり、運動の敗退みんなそうであろう。つまり決断を回避したままずるずると破局の中にのめっていくだけだったという判定が下されるのである。この「ずるずる」は、私たちのどうすることもできないような民族的性格だ。うまくいっているときは調子づいてとんでもなく強そうに見え、勢力も出し、よく働くが、周辺の状況がおかしくなると、とたんにがっくりと来て参ってしまう。
それはつまり、日常の思考や行動においてこのクレーマーの忠告のように、私たちは自分の心を極限状況に置いて考え、行動する訓練を絶対といってよいほどやる習慣がなかったからである。キッシンジャ―だってこのような忠告がなかったら、ぬるま湯のような知識を売りものにするだけの大学教授の生活に――それでもアメリカの教授は日本の私たちなどより遥かにきびしい条件にあるが――ひたって生涯をすごしたかも知れない。
自分をまず極限状況的な心境に置け。そういう説を聞くと、すぐ私たちは、「愛が必要だ」「誠意をもって話し合ったら理解されるはず」「もっと努力を」とかいった反応する。しかしそういうことを実際にやることは殆んどない。要するに意志決定を一寸のばしに逃げる口実として立派なことをつぶやいたり、意志決定ができない弱さをかくすために善や愛などとわめいているにすぎないのである。
2024.01.07 記す。
22 すぐれた将軍は部下の将兵を戦闘が避けられない状態に追いこむ。 マキャヴェリ P.151~156
窮鼠はかえって猫を咬むという諺が示すように、死地に陥りそうになったものの生きる力は途方もなく強いものだ。それゆえ、相手を死地に陥れることは、どのような戦争指導者も決してやらない。包囲しても完全包囲して全滅させようとすると、それは不可能ではないにせよ、それこそ死物狂いの反撃をうけて攻撃軍の方が大損害を蒙ることはたしかである。だから必ずどこかへ精神的あるいは物質的な脱出口をあけておかねばならない。そうすると敵は死闘する意欲を失い、そこへ殺到する。そこを攻撃する。あるいは上手に降伏させてしまう。そうすればこちらは軽微な損害で相手に大打撃を与えることができる。どうしても全滅させねばならないときは、大変ゆっくりとした包囲攻撃で行かねばならぬ。たとえば秀吉の高松城水ぜめ、または後の小田原城攻囲作戦などがそれだ。だがこの場合は圧倒的な力量差がないと成功しない。
こんなことは戦術上の常識だが、この逆が自軍の使い方である。自軍を決死隊にさせるには、例えば背水の陣のように自らを死地に陥れることが必要になる。
だが、それは賭けだ。自軍が全滅する可能性がある。それを承知の上でならよいけれど、マキャヴェリの時代ではそんなことはできない。当時の戦いは傭兵戦であった。自分で軍隊を養っておき、金であちこちの君主や都市に雇われて戦争をする。そういう戦争請負人(傭兵隊長)どうしの戦いが常道だった。部下の一人を殺すことも、武器一つを失うことも、大切な商売道具を失うことだ。全滅させたりしたら無一文になってしまう。そんな無茶はできない。君主など傭い主の方とは勝ったらいくら、城をとったらいくらという風に戦果に応じて割増し金を貰うように契約をしているけれど、負けたらその報酬はうけられない。勝たねばならぬ。その工夫が傭兵隊長の能力である。
だからこそ、現在の経営作戦で、マキャヴェリの見解が役に立つのだ。日本の「作戦要務令」なども有効に相違ないが、そこにある根本思考は、国防戦である。一部隊の全滅などを必要とあらば一向差支えない。たとえば今度の大戦での大作戦の計画票を見れば、ある日まで名前がのっているが、急に消えて二度と現れない部隊がある。その日の戦いで全滅が予定されているのだ。これでは犠牲に供し得る子会社をたくさん持っている大会社の経営作戦になら適合するだろうが、自軍の存廃に全てをかける傭兵隊長の戦陣訓としてはちょっと困るのである。
マキャヴェリはいう、うっかり背水の陣はしけない。相手に背水の陣もしかせられない。といって戦いは遂行し、自軍をして勝たさなければならぬ。そこでそのような戦いの必要性、運命(フォルトゥーナ)が戦うことを必要(ネチェスタ)にした。つまり戦いの必然性というものを心から将兵にのみこませねばならぬ。それには、一所懸命に説教するだけでは駄目である。その必要性というものが、全機能をあげて自軍の将士に働きかけ、敵軍には働きかけぬようにしなければならないと。
よく考えて見るとマキャヴェリの、残虐、狡猾に見えるいろいろの教えは、この運命の与えた必然性を、どのように国民にのみこませるというところにあるようだ。人は何とか口実を作って自分で戦いの意志決定をすることを逃げるものだし、その口実に論理性や道徳性を与え人気を得ようとする学者や宗教家や評論家を使おうとする。そういう「えらい人」は掃いて捨てるほどいる。そして国家、企業といった組織体はずるずると崩壊や衰退へと落ちて行くと思われるからである。
ではどのようにして、戦いの必然性を教えるか、第一には敵が途方もなくひどい連中であり、普遍的な社会道義の上からも、その存在を許し難いものだということを教える。それには相手陣内の反乱者の言葉を引用するのがもっとも効果的だ。――仲間の悪口をいうのが好きな日本人はその点、これほど「敵」に乗ぜられやすい集団はないと思われるほどである。――こうしてこういう敵には条約締結も妥協も無駄だと考えさせるのである。
第二には自分たちは立派だと思いこませる。
第三には、その逆のことだが、相手に対し全員がひどい裏切り者になるようにしむけるか、あるいは相手を全面的にののしって、もうこうなったら到底こちらと平和裡に話をつけようとは考えまいとこちらの全員が思うようにさせる。もっとも大変ずるくなるけれど、実は相手をそうおこらせないように、相手をののしることばは味方の将兵に対してだけ、いかにも相手にそういっているような姿で吐いておくのである。
このように全将士に戦いの必要性がその全機能をあげて働きかけ、将士の意識のすみずみにまで貫徹して、はじめて将軍は戦いの意志決定を行うのだ。
松永弾正久秀は織田信長に降伏しては謀反すること三度、終に自分の居城である信貴山城を信長の長子信忠軍に攻略され、城に火を放って自決した。ところで不思議なのは一度負けたら部下は散り散りになってしまう、大変不人情なこの戦国時代に、進んでかれと運命を共にしようとした将士が、人の噂だが五千人もいたということである。
人徳は全くない久秀であった。勝目もすくない。だのにそんなに多くの人間がついたということは、久秀の弁舌がうまかったためではないだろう。かれは絶えず陰謀を企て、叛乱することで、将士とともに叛乱共同体とでもいうものを作り上げていたといってよい。
久秀と同じく、彼の部下だって、もう信長に内通するわけには行かない。一時は命をゆるし、つかってくれるだろうが、いずれは成敗されるにきまっている。信長だけのことではない。あの松永弾正の部下という「汚名」を着てしまった以上、もはや日本中の誰一人だって信用してくれるものはないだろう。そういう気持ちがこの五千人を、すくなくとも、その主だった家来たちを死の籠城へとおもむかせたのだと考えられる。
マキャヴェリのこの方策は、例えば現在の中国の指導者が、七憶の国民を戦う一つの火の玉に化し去ったその見事なやり方と完全に一致しているといってよい。経営戦略の場合も、戦うという意志決定を可能にする最大の条件は、自分の部下や協力者が、戦いの必然性を、はたして本当に感じてくれるかどうかということにあるはずである。
※傭兵については、岩波文庫『君主論』P.89 第十三章 「援兵と混成軍と国民軍」の中に傭兵について書かれている。
2024.01.08記す。
23 人主は心を己が死を利とするものに加えざるべからず。日月は外に暈囲(うんい)するも、その賊は内にあり。その憎む所に備うるも、禍は愛する所にあり。 韓非子 P.156~161
これは恐ろしい言葉である。いくら外敵に備えて見ても、敵は実は内部にいる。その内部の敵だって憎むものだけを用心して見ても駄目だ、災禍は実は愛する者から発する。そういうことである。
この辺りの韓非のいい分は至言に近い。あまり余計な私見を加えないで、そのいうことを聞いてみよう。
名御者の王良いは馬を愛し、越王句践は人を愛した。だといって、それは動物愛護の精神とかヒューマニズムによる行為なのでは全くない。馬は走るからであり、人は戦うからだ。医師が患者の傷を吸い血を口にふくむけれど、それは肉親の愛情からそうするのではない。赤の他人に対してもそうするのは利益からである。
車作りの職人は、みんなが金持ちになればよいと思っている。棺桶作りの職人は人の死ぬことを願っている。けれど、だからといって前者が道徳家で後者が悪人ということにはなるまい。人は金持ちにならねば車を買わないし、人が死ななければ棺桶は売れないからだ。死ぬのを願うのは人が憎いからではなく、かれらの利益が人の死ぬところにあるからだ。
 こんな意見を聞いて、ステファン・ツヴァイクの名著『マリー・アントワネット』を思い出される方も居られるだろう、フランス王ルイ十五世が死ぬ。寵妃をはじめ重臣たちは悲しみに沈んでいる。だがその王宮の一角からかすかなどよめきが、悲しみの静まりをおびやかすように伝わり、やがて大きな波動となって来る。皇太子つまり今やルイ十六世となった新王の近臣たちがおもわず洩らす万歳の叫びだ。奇妙な対照、最大の悲しみの中に最高の歓喜がおさえ切れずにほとばしる。だが、この両者は別に対決していたすわけではない。ルイ十五世は陰謀によって倒されたわけではない。利の動きに人の動き、人の気の動きが流れているだけのことである。ツヴァイクは、その天才の筆で淡々と、しかも冷酷無残、この上もなく鋭利に、この間の情勢をえがき出して見せてくれたのである。
こんな意見を聞いて、ステファン・ツヴァイクの名著『マリー・アントワネット』を思い出される方も居られるだろう、フランス王ルイ十五世が死ぬ。寵妃をはじめ重臣たちは悲しみに沈んでいる。だがその王宮の一角からかすかなどよめきが、悲しみの静まりをおびやかすように伝わり、やがて大きな波動となって来る。皇太子つまり今やルイ十六世となった新王の近臣たちがおもわず洩らす万歳の叫びだ。奇妙な対照、最大の悲しみの中に最高の歓喜がおさえ切れずにほとばしる。だが、この両者は別に対決していたすわけではない。ルイ十五世は陰謀によって倒されたわけではない。利の動きに人の動き、人の気の動きが流れているだけのことである。ツヴァイクは、その天才の筆で淡々と、しかも冷酷無残、この上もなく鋭利に、この間の情勢をえがき出して見せてくれたのである。
ここがむつかしいところだ。利害関係だけで結びつけられているものは、計量できる。したがって操作も可能だし、造反も防止できよう。だが、その利の上に愛がからむ、という状況が当然生まれよう。主従、友人、男女という関係などは当然そうなる。道学者はそこに利害関係は作用しないとか、作用する二にしても、愛の力の方がはるかに優越すると主張するのだが、韓非はそんなときでも利害が基本だと説くのだ。私は利害関係が絶対優越するとはいわない。韓非はもちろん潜在意識、深層心理というものを知らなかった。だが、そういったものの根強い拘束力を見抜き、このような動物的な利害感覚のおそろしさを強調したのだ。その点は偽善的で事態の本質を直視せず、女子供の感傷に訴えるだけの道学者流よりはるかにまともだといえよう。
私たちの陥る陥穽(かんせい)は、利害ととりわけ複雑にからみ合う愛情関係の中に置かれた人間は、愛しか見ようとしないものだという点である。人は本能的に自分の心の中にある動物的、唯物的な要求を否認したがる。他人に自分をカッコよくみせようとするためでもあるが、自分一人で反省するときだってそうだ。ふつうそれを良心の働きと称するのだけれど、問題はこの心のうごきは自分の心の中の動物的利己心の存在を認めないでおこうとしてそれに目をつぶるだけで、それを克服しようとする努力は決してやっていないことにある。すこしでもそれをやれる人は稀に見る超人的人物であることをこそ韓非は手きびしく指摘しているのだ。殆どの場合、この否認の根源力は良心といったものではなく、並みはずれの恐怖心でしかない。
そこで私たちは自分の心、人の心にある愛と利との混同を見抜けなくなる。自分自身さえ見まちがうのだから他人の意識構造の動きなど把握できりはずがない。そこから悲劇と破局が開始される。韓非のこの言葉は、この間の事情を喝破したものに外ならない。
ふたたび、戦国時代に例をとると、明智光秀が信長を倒したとき、致命的な計算ちがいをした。細川幽斎父子の同調を期待したのだ(※「決断の条件2」12章参照)。幽斎と光秀は将軍義昭を世に出すため長い労苦を共にした心友である。信長に仕えて日も浅い。幽斎の子忠興は光秀の娘――のちガラシャ――を妻とし、狂気したように溺愛している。この父子が光秀の行為を是認してくれるだろう。そうすれば細川も宮津の一城主の地位から自分と天下を二分するほどの太守になれるだろうし。
この光秀の予測ははずれた。京都の貴族で権謀術策の極の世界を生きぬいた幽斎の計算はそんなに甘くはない。はるかに緻密であった。光秀は敗れると踏んだ。かれは全くの中立を宣告したのだ。
驚いた光秀はもう一度手紙をかいた。それは、今日も細川家のもとに残されている。司馬遼太郎もいうように、事の意外に顔面蒼白となった光秀の顔が見えるような悲痛な内容の手紙である。細川の拒絶を知った瞬間、光秀は滅亡をはっきり直感した。うらむ気力もなくなった。支離滅裂、とり乱し切った何とも憐れな手紙だ。
意志決定のときは、何よりも、愛の根底にある利を直視せよ。直視できぬ人間はみじめな失敗をする。極めて自明なこの論理は、しかし、現在でも、私たちが常に心に持ちつづけねばならないいましめとして存在する。それを否認したい本能を持つのが人間というものだからであろう。
2023.10.09 記す。
24 君主の利は相ともに異なるものなり。主の利は能ありて官に任ずるにあり。臣の利は能なくして事を得るにあり。主の利は労ありて爵禄するにあり。臣の利は功なくして富貴なるにあり。主の利は豪傑の能を使うにあり。臣の利は朋党の私を持ちうるにあり。 韓非子 P.163~168
この「主」とは支配者のことだが、それを君主とも、経営者とも、主権在民というなら一般大衆と置きかえてもよい。その場合、「臣」とは順に、官僚、社員、政治家ということになる。すこし注釈をつけると、「相ともに異なるものなり」というのは絶対に相反するという強い表現で、単に一致しないということではない。「豪傑」というのも能力者というぐらいだとお考えいただきた。
この君主の利害関係の矛盾は、もちろん労働者と資本家という階級間の矛盾ではない。常識では利害が一致すると考えられる者同士の矛盾関係を鋭く指摘したものである。
現代の臣従関係に読みかえ、いろいろ想像すると誰でも思い当ることが多いはずだ。第一の「能」の問題は、いわゆる差別反対、つまり能力による待遇制反対の声となって現われていよう。「功なくして富貴」とは一律賃金引上げという要求が代表しよう。「朋党の私を用うる」とは、一見まことに公正で誰も反対できぬ組織を作り、抽象的大義名分をかかげながら実はそれをつかって私利の増大をはかるという傾向に現れている。総じて現在はすべてがマスコミ的に表現され行動される世界だから、何でも大衆運動のように見える。逆にいうと大衆運動として報道される事象は、実は私たち周辺の比較的小さいスケールの人間関係の圏内の中で常におこっていることを、そのままに反映していると考えてよろしい。公害摘発が、実は無能な研究者の一番手軽で確実な研究業績作りの手段で、自分の地位保全にに役立ったというようなことも案外多いのである。
管理者の覚悟として重要なのは、このような臣主の矛盾を直視し、安易なヒューマニズムだとか、連帯だとかに逃げないという決心である。これは良心を持つなとか、不真面目であれという意味ではない。かくす、ごまかす、居直るなどのすすめでないことはいうまでもない。良心を持つとは自分の心の中にも、そういうものがあることを直視し、いいかげんな迎合者や道徳屋や偽善者にならないとうことでなければならぬ。一般的な、テレビの団地ママ向け番組の立脚点からすれば、冷酷無残か、あるいはふらち極まる人間であってこそ、はじめて意志決定が可能になるのだ。愛情に満ちた意志決定などありはしない。それは結局流されただけである。もちろん流されて結果的には成功することもある。大英帝国の絶頂期を築いたヴィクトリア女王はそういう点での成功者だったといわれる。宣戦をはじめ何も決断できない。その間に事態が変って決定しなかった方がよかったということになる。そんなことの連続だったというわけだ。だがこれなら長であって長でないことになる。
そこでこの意志決定者の心得だが、第一に、いかなる人間も信じてはいけない。能力、長所を評価することは必要だが、全幅の信頼、つまり盲信してはいけないのだ。息子をも信じてはならない。息子が危険だというより、臣下がその信頼を利用するからである。韓非は他の場所で趙の恵文王(戦国時代)の例を挙げている。李兌(りだ)という男は恵文王の父、武霊王が息子を盲信していることを知り、たくみに恵文王にとり入り武霊王を餓死させた。妻や妾を盲信してはならないことはもちろんである。
第二に仁を説くものを容れてはならない。仁それ自体は悪いことではない。しかし競争者がないという稀な例外の場合をのぞき、そういう人間が内部に存するときは、自分をごまかすとともに、正に競争者に褌(みつ)を与えるようなものである。自壊の準備を自分でやる必要はない。仁者の意見が外に対する宣伝用でわり、内部の意志決定に影響することはないという見事な組織であれば別ではあるが。
第三に決定権は完全に自分に集中せよ。これは人の意見を容れないということとはちがう。自分の意志決定を他人にまかすぐらいなら長の立場に立つべきではない。
要するに臣主の利害が反するとは、君主とか長とうものは、完全に孤独だということを意味する。孤独に平気でいられる人間か、さらには孤独を生甲斐とする人間でないかぎり、長を欲してはならない。そんな人間でも飾りものの長ならこなせる。現在は張という地位がやたらとふえている。組織は長でない人間でも長であることを保証できるようになっているからだ。その結果、大部分の長は値しない人で占められている。そういう人は孤独でなくともすむ代り、みんなから内心で、さげすまれ馬鹿にされることに甘んじなければならぬ。その地位にあるかぎり、本気で接触してくれる人間が存在することはあり得ない。そんな人々は本当の孤独とは違った孤独の中に住むことになる。いつも着物だけは絶対にほめてもらえる醜女の孤独みたいなものだ。それも嫌だというのなら、およそ長を望むのは絶対矛盾の要求を持つことになろう。犬ならどんな人でも主人と思ってくれる。そういう人とだけ接触するか、あるいはバーでこのごろの若い者はと泣言をいうか、上の奴は目がないといばって見せるかしか、どうにも仕方ない人間だといえよう。
近代社会における人間の教育とは、個人に独立能力を与えること、つまり孤独に耐える人間を作ることに存する。知識や技術を付与するのはそのためである。しかし、私たち日本人に完全に欠如しているのは、教育とは子供を、家庭をはじめ被保護者を収容する共同体圏から追放する準備を加えていくことだという認識である。つまり日本人のいう孤独に耐える人間とすべく、しだいにそういうものからつき放して行くという訓練だという認識である。
だから私たちは孤独になれない。幼児性がいつまでも強く残り、「母」の乳房を求めつづけ、いい齢になってもそれが与えられないと、国、政治、会社、学校に対し、だだをこねる。淋しがって泣く。
しかし、この幼児が長になりたがるのだ。觚独人であるからこそ、人間関係が生まれる。幼児には人間関係は存在しない。あるのは人情関係だけである。幼児には意志決定ができない。私たちはどうも意志決定を論ずる前に、まず自分が幼児であるかどうか、何人をも信じないですみ得る孤独人であるかどうかを反省する方を先決問題とする人間のようである。
2024.01.10 記す。
25 人間はきわめて単純なもので、目先の必要性に、はなはだ動かされやすい。だからだまそう思う者にとって、だまされるような人間は自由自在に見つかるものである。 マキャヴェリ P.169~174
これは、あの有名な、「君主たるものは、ライオンの威厳と力と狐の狡智を身につけねばならない」という主張をした文章中の一句である。だから、この「だまそうと思う者」というのは、君主だとか商人だとか、ともかく狐の狡智を持った人間のことである。そういう人間にとっては、だまされがっている人間が無数に存在する。だまされたくて仕様がない人間をだまして、一体どこが悪いのか、詐欺師だとか女蕩しが検挙されたとき、かれらがそういう言葉を出して「居直る」という例がよくある。新聞というのは、いわゆる高級紙にしたところで小学生程度の道徳観で武装した、いわゆる団地ママ、投書夫人的心情を以て販売政策としている。そういう目から見たら、そういういい方は居直りとしか思えないにちがいない。けれど、案外それはまっとうな感覚ではないのだろうか。
私たちの周辺に押しよせて来る情報、とくに戦後のそれは新聞、週刊誌からテレビ、ラジオまで殆んどみな、だまされる人間は即ち善で、だます人間は悪という前提の上に成立つている。相当な知識人までがこんな前提をつけて疑わないのは日本人だけだ。だます方が途方もない悪人だったときは別として、被害者が間抜けだったり、当然の防衛処置を怠っていたときは、どこの国だってその責任を問われるのがふつうである。自動車の鍵をかけ忘れ、駐車中に社内のものを盗まれたといって届け出ても相手にしてくれる警察は有難くも日本だけである。しかも、その金額が大きければ大きほど同情もしてくれ騒いでもくれるが、ヨーロッパだったらそんな大金なのにどうしてと逆に呆れ顔になって行く。そんなことをするのはふつうの人間を泥棒にしてしまう仕業だ。忙しいのに自分の不始末で警察はもちろん、一般人にまで「迷惑」をかける奴があるかと叱られるのがおちである。
こうなったことは、日本人の判官びいきという特性の上に、戦後はアメリカのピューリタニズムが加わったからであろう。女性、とりわけ主婦という社会に直接責任を持たぬ女たちの感傷主義がそれに拍車をかけたことはすでに触れた通りだ。
だが注意しなければならぬ。判官びいきというのは正義感が強いということでは決してない。劣等意識、あるいは正義漢なるが故に俺は損をしている。だから損をしている奴に同情せざるを得ないのだといった、いじましい自己正当化の感覚が強くまじっているのである。それに善人主義をとる今日のアメリカのピューリタニズムは全くの偽善と化している。だからそんなものは、利用する必要はあるが、道義的に心を悩ますべきことでも何でもない。
日本のこのような判官びいきは全く表面的、言葉の問題だけにすぎない。いざとなればすべての連中が強い方に雪崩をうってかたむくことはこれまでの歴史が証明するところだ。意地をつらぬき通した人間が、恥ずかしいぐらいにすくない民族なのである。
だまされる人間、だまされたがって人間が充満していることは、日本だってどこだって全く同じだ。ただ日本社会はそれをあまりはっきり指摘すると、いろいろ文句をつけれれるということを特徴とするだけのことである。それだけ女々しい社会なのだといえよう。しかし、本当に意志決定を下すとき、だまされる奴でこの社会が充満していることをはっきりとした前提にしなければならない。実例をあげればこうだ。
ミラノの城主フランチェスコ・スフォツァー(一四〇一~六六)は名君として有名である。だが、その出身は傭兵隊長にすぎない。あらゆる権謀術策をもって、うまうまと傭主であるミラノのヴィスコンティ家をのっとった男だ。およそ信心気なかったのだが、ミラノの大聖堂を大金を投じて完成整備させたり、宗教者からは偉大なる信仰者として尊敬された。しかし、かれの立場は極めて簡単である。「わしは信仰心など持たぬ。しかし民衆はわしが篤信の人であることを望んでいる。信者になろう」。そして奇妙にも、かれはこんな自分自身を本当の信者で偽信者だとは思っていなかったらしいのである。
だまそうと思っている人間の周辺には、つまり権力者や管理者のまわりには、それに便乗してだまされる人間をだまそうと思う人々が集まって来る。ルネサンスでは人文主義者、つまりヒューマニストといわれる学者文人がそれである。かれらの大部分は信仰なんか持っていなかった。死ぬ前だけ、地獄がこわくなって信仰に入る連中は多少いたにせよである。かれらは坊主どもの堕落ぶりを知りぬいていてそれらを軽蔑し、憎んでいた。にも拘わらずこの人文主義者たちは、君主に信仰深くふるまうことを求めたのである。そうすれば民衆はついて来る。自分の地位も安全だ。それに君主がお寺とかいろいろの土木建築をやり祝祭をやってくれると、それに応じ自分たちもいろいろの収入を得るかとができるからだ。芸術家も同じことだった。だからルネサンス時代というのは、信仰心がもっともうすれ、ギリシャやローマの神々が復活した大変現世主義の時代だけれど、不思議なことには各種の教会や聖書を主題にした絵画や彫刻があふれるほど作られた宗教芸術の最後の極盛期でもある。
政治とか、経営とか、管理というものはだまされる存在を前提としてはじめて成立するものであろう。意志決定はだから、だます立場に立って行うべきで、だまされる立場からやれるはずがない。、
ただその際、だますということを口にしては駄目である。ルネサンスの君主もそんなことはいっていない。スフィルツァーがいったということは当時の伝説である。日本の君主は正直すぎる。戦国の名君だった朝倉敏景は、その家法に、「神社や寺に寄進するのは無駄のこと。ただその前を通るとき馬でもとめて、その荒廃をなげき悲しむ言葉を坊主や神主たちにかけてやるだけで充分だ」とぶちまけてしまった。これでは坊主がついて来ない。朝倉家は、だから永保ちしなかった。ルネサンス人はもっと狡智で、人文主義者もそんなことは一言ももらさなかった。ただその行動によって信心気など毛頭なかったことが明らかにされるだけである。
あくまで、正論を旨とするような顔をつらぬく。地獄のえんま様でもそれを押し通す。実は完全にだます側に立っているというのが、マキャヴェリのえがく理想の君主像なのだ。もっともマキャヴェリには、おれはそれを見抜ける世界唯一の人間だという自負はあったらしいけれど。
2024.01.21 記す。
26 謙譲の美徳によって尊大をうちくだけると考えることは大抵失敗に終る。 マキャヴェリ P.175~180
マキャヴェリの言葉はまだつづく、ひかえ目な態度というのは何の益もないばかりでなく、むしろ有害だというのが多くの場合である。とりわけ嫉妬やその他の理由でこちらに憎悪感をいだいている横柄な人物に対して、こちらから下手に出た場合などはなおさらである。
私たち日本人は世界の民族の中でも、ちょっと例がない特殊な精神構造を持っている。その一つに、こちらがへりくだり誠心誠意で行けばかならず相手もそれに応じるはずだという信仰があることが挙げられよう。それはそれでよいとする。ただ大変具合の悪いのは次の二点である。第一には本当に誠心誠意とか、一片の私心もない真心など人間が持てるものだろうかとういう反省は一向持たないということだ。昔の人々にはあった。戦後の進歩主義者にはそれがなくなった。女性には、そもそもそういう反省がない。そんな反省あったら子供を育てて行けないからである。
第二点は、こちらが誠心誠意で行くとき相手がそれに応じてくれないと、やたらに腹をたて相手を悪ときめつけることだ。これははなはだ女性的な感情であろう。どんな場合でも、どのようにこちらに応えるかは相手側の勝手である。それに相手は誠心誠意など欲していないのかも知れない。例えばこちらが女性のとき相手の男性は肉体だけを望んでいるのかも知れない。親戚関係だけが問題なのかも知れぬ。国家間交渉のとき相手が望んでいるのは、金銭的、物質的な賠償か援助だけかも知れない。それだのにこちらが真心だとか反省だけを与えようとしたら迷惑至極で、おこってしまうのにきまっている。日本人は甘えを基本とした精神構造を持つといわれる。それはその通りだ。つまり、相手は自分に対して好意を持つはずと頭からきめてかかって、交渉したり何かを恃んだりするのである。好意を持っていないと判ると相手を人非人呼ばわりする。進歩派の言い分はすべてそれだ。つまり自分の容姿や才能に劣等意識を持っていたり、その人とつき合う人間がどうも好感を持ちにくい、そういう人々が日本ではいわゆる進歩派になる傾向が強い。それは決して当人の責任でもなく、好意を持たない方が悪いのだけれど、人間というものはそういうものだ。いかに精神が立派でも醜悪で身体もさっぱり魅力がない女性を、喜んで女房にする男は残念ながらめったに存在するものではない。
そういう客観的理由を否定し、社会悪のせいにする。ついでに、自分に責任がある自分の短所、怠ける、妬く、怨む、ひがむといった条件までをどこかへ責任転嫁してしまう手段がいわゆる進歩的言論というものなのだ。そういう言論の理論自体はともかく、そういう理論を奉じる人々の心理というものはそのように解明されねばならない。もちろん万人に愛される人で生活能力もある進歩主義者という例外はある。だが、そういう例外的な人はその生涯の中で、必ず転向とか変節とかちょっと奇妙な分派活動に走るものだ。肉体的な劣等意識か、それとも肉体化したような性格的ひがみか、そういうものがない限り日本では「正統な」進歩主義者として持続して行くことは大変困難だからである。
こういうことで、日本人の誠心誠意主義とか、謙譲主義とかざんげ主義とかいった対外態度は劣等意識のごま化しだけの全くインチキなものだが、問題は、マキャヴェリが指摘するように、それがインチキでなくても大抵失敗に終るという点なのだ。、
日本は今GNP自由世界第二位の生産力を誇り、まだ躍進をつづけている。ということは世界中の嫉妬感や反感憎悪につつまれているということになる。マキャヴェリが「とくに」と強調した場合にあてはまるわけだ。今後の日本外交が途方もない困難の中を歩むといいう見通しが立てられねばならぬ理由である。
ところで、いま考えようとしているのは外交ではなく個人の意志決定の場合の話である。日本人はみな自己卑下病にかかっている。やたらと横柄なものもいるが、それは逆に虚勢が表面に出て来たのにすぎない。両方とも、本質的に自信がないということから結果するのである。
そこで、この場合、卑下をしつづけていると実力がないと見られ軽蔑される。早く卑下を打ち切った方が上位に立ち対決に勝つ。いつ、どういう風にそれをやるかだ。それが意志決定のチャンスになると考えられよう。
しかし、私は、もうすこしちがう立場をとっている。私たちは卑下病(その裏返しの虚勢尊大病)にかかっている。最初からそれを持たぬ方がいつもどうも勝っているようだ。そのように観察しているのである。
悠然と、礼儀正しくは構える。だが、マキャヴェリのいうように、絶対に譲歩してはならない。妥協してはならない。鷹揚に相手のなすままになっていては絶対駄目である。そして相手のたくらみを見抜いぬいたら、こちらの力は乏しくとも断乎として戦う決心をし、その準備にかからねばならない。相手はそのときはじめてこちらを尊敬するのである。
戦う決心もなしに相手と重大な交渉をし、成功をおさめようと思ってはならない。無条件降伏を覚悟して、相手から何一つでも与えられたらこの上ない幸福だというな話は別だ。こちらの利益をある程度主張しなければならない。したがって相手にある程度損をさせねばならぬ、我慢もさせねばならぬといったとき、戦う準備なしに交渉するほど馬鹿な行動はない。
国家間の交渉の場合、戦いは武力の行使から経済断交、外交決戦、いろいろある。戦後日本の政府側のアメリカ追随、野党側の対中国土下座外交は、ともに見られたものではなかった。ニクソン訪中発表後の経済界の右往左往ぶりは正に、「眼中に利しかない商人どもは、利のためには肛門をもなめることも意に介せぬ」(水野広徳『この一戦』)と軍人に批判されたことを思い出させる。別に軍人にかぎらず外国人は、正にこのような状況に「エコノミック・アニマル」という最大の蔑称を与えたのである。石油危機直後の対アラブ叩頭もそうだろう。私たちは外交も、いや民族のプライドも信義も何もない。そんなものよりトイレットペーパーの方が遥かに大切な国民のようである。
それはよいとして私たちの相互の対人交渉も、実はみんなこうなのではなかろうか。そして無意識のうちに、会社側は労組を、労組は会社側をという風に経営者、政治家、官僚、学者、マスコミ人は、相手側を、さらに仲間どうしで、お互いに傷つけ合い軽蔑し合っていることになっているのではなかろうか。
※参考:水野広徳『この一戦』については、〔桜井忠温と水野広徳(一)(P.304)〕。また「利のためには肛門をもなめることも意に介せぬ」については会田雄次『日本人材論⦆P.119 に記載されている。
2024.01.12 記す。
27 勝を見ること素人の知るところに過ぎざるは、善の善なるものにあらず。戦い勝ちて天下善というも善の善たるものにあらず。よく戦うものは、勝ち易きに勝つものなり。 孫子 P.181~186
イタリア人を描いた戦後の名著として有名な、ルイジ・パルツィーニの『イタリア人』の中に面白い話がある。イタリア人にとってもっとも理解しにくいのは、北の方の国々の道徳的格言である。例えばイギリスの古い教訓に、「抵抗力のない人間を蹴ってはならぬ」というのがある。弱い者いじめはいけないということだ。さあ、これがイタリア人には解せない。強い奴を蹴ったりしたら仕返しされたり、大変ではないか。こちらに何の損害を受けることもなく蹴れる相手が出て来たのにどうして蹴ってはいけないのだ。面白いし、利益があるかも知れない得ばかりではないか。そういうのである。別にイタリア人に限らない。「弱きをたすけ、強きをくじく」ではなく、「強きをたすけ、弱きをくじく」のが人間の本音としては当たり前の心情であり、世の中はみなそのようにして動いている。ただイギリス人や日本人やドイツ人は、理屈ぽく、道学者的趣味があるので、ともかく、その反対のことを主張したがる。イタリア人にとって、そんな道徳趣味は無縁の世界だ。それだけのことで、だからイタリア人は人が悪く、イタリアの社会はひどい社会だという風に誤解されるのだけれど、それは間違いであろう。ただ人間の本性をすこしばかり率直に表現する連中の住んでいる国にすぎない。
イタリアがこうなったのは、ローマ以来の古い国だったことと、その地理的特質のため、絶えず外国から侵入され、十九世紀末まで統一国家にならず、日本の戦国時代みたいな混乱が千年ちかく続いたということにあるのだろう。ここで生き抜くためには、ただ真面目に働いていたら何とかなるというような単純なことでは到底駄目である。強盗に備え、喧嘩に勝つためには腕ぶしも強く、武器の取扱いにも習熟していなければならぬ。法律に強く弁も立たねばならない。自分一人で、検察官、弁護士、警官、泥棒、職人、ともかくすべて一切を兼ね備えねばならぬ。そのようなきびしさが、今日の日本のように政治や社会に対する途方もなく甘い要求と正反対な生活態度を生んだもとといえよう。そして今日の世界の現実は急速にそうなりつつあるのである。偉い立派な人々のいう希望的な観測とは正反対に、先進国でも、開発途上国でもい、日本国内でも。
 孫子のこの言葉も、やはり、はるかに峻厳な競争社会における臨戦の心構えをのべたものだ。もう少し詳しく、かれの説明を聞くことにしよう。
孫子のこの言葉も、やはり、はるかに峻厳な競争社会における臨戦の心構えをのべたものだ。もう少し詳しく、かれの説明を聞くことにしよう。
多くの者にはっきりそれとわかるような勝ち方は、本当にすぐれた勝ち方ではない。勝った勝ったと世論が騒いでもち上げるような勝ち方も同じことだ。例えば毛を一本もち上げたといって誰も力持ちだとは思うまい。太陽や月が見えるからって良い目だと思う人はあるまい。雷鳴が聞えたって耳がよいと思うものはいまい。
しかしながら、本当にすぐれた勝ち方というのは、そのように誰でもが当然だと思う勝ち方をすることなのである。この”決断の条件”でも一度ふれたが、信長は桶狭間で勝ち、一挙に名声を博した。だがその後二度と奇襲戦法を使わなかった。あんな勝ち方は真の勝利ではないと自覚したからだ。それが本当の名将というものである。
本当の勝ち方は、勝ち得る条件を作っておき、極めて自然に勝つという勝ち方である。人はそんなとき誰もその智謀をほめず、その勇敢さをほめることはない。それがよいのだ。自分の方を不敗の地に置き、相手の寸毫の隙を見のがさない。負けるはずがないのである。
これが孫子の意見で、まことに大人の目といえよう。日本人のように小児体質、せいぜいのところいさみ肌のお兄さん程度の人間成長度にしか達しない国民には、このような大人の勝ち方は歓迎されないかも知れぬ。だが、大衆に喝采され、マスコミでもてはやされた経営の神様は、その後どうも途中で見事に失敗してしまうようだ。そこには、以上のような理由があるといえよう。
ところで意志決定だが、戦う、勝負に出るという意志決定はいつ行われるのだろうか。おそらく常識的には二度である。戦うときめて最初の準備を行ないはじめたときと、いざ決戦を開始するというときとの。第二の段階で万全の道ではないと判って戦いをやめるときもふくめて。
常識では戦いをするという決意はむつかしくないが、やめるというのは難しいということになっている。なるほど、例えばこちらがかなりのへまをやっても負けるはずがないというほどの見込はつかないけれど、多分勝てるだろうということでしかないときだって、その多分にひかれて決戦に出るのをやめるという決断は中々やりにくい。
しかし、真剣な準備は戦おうという決定がなされてはじめて可能なのだ。準備だけはしておいてといういい加減なことでは本当の準備ができるはずがないのである。
すくなくとも戦うのをやめようという決断は副次的決断である。なるほど日本のような下剋上的民主主義の世界では、それで押されてたった自分の裁可を変えることはむつかしいだろう。しかし会社などで下剋上があったとすれば、それは下意上達がうまくいつてるのではなく、統率ができていない会社、つまり、もう敗れている会社なのである。第二段の意志決定は、決戦でも、陣地撤収でも、そうむつかしいことではない。やめるときは自分が不安にかられてのことだし、決戦には騎虎のいきおいということが多いからだ。
やはり本当の意志決定、決断は断じて戦おうという決意を定めるときである。そしてその決断には、万全の準備を果し、必勝不敗の地位をきずくという決断が同時にふくまれていなければならない。そのことをこそ孫子が語っているいるのである。
ただ一つここに私の意見を入れておこう。自分をふくめて、その準備に精神力は勘定してはいけないことである。精神の鼓舞には努力しなければならぬ。そういう計量的に比較できないものを勘定に入れることは、今度の戦いで日本が大敗したと同じ結果を招くことになるにちがいない。準備にはならないのである。
※参考:孫子の言葉は金谷 治訳注『孫 子』(岩波文庫)P.45 形篇(第四)では、
勝を見ること素人の知るところに過ぎざるは、善の善なるものに非ざるなり。戦い勝ちて天下善なりと曰うは、善の善たる者に非ざるなり。故に秋毫を挙ぐるは多力と為さず。日月を見るも明目(めいもく)と為さず。雷霆(らいてい)を聞くは聡耳(そいうじ)と為さず。古えの所謂善く戦う者は、勝ち易きに勝つ者なり。故に善く戦う者の勝つや、智名も無く、勇功も無し。故に其の戦い勝ちて忒(たが)わず。忒わざる者は、其の勝を措く所、已に敗るる者に勝てばなり。故に善く戦う者は不敗の地に立ち、而して敵の敗を失わざるなり。是の故に勝兵はまず勝ちて而る後に戦いを求め、敗兵は先ず戦いて而る後に勝を求む。
2023.12.06 記す。
28 信頼できるよき市民(議会)ならば、たとえ激昂して常軌を逸した民衆が事態を憂慮すべき方向へもって行こうとするのを目のあたりに見ても、決して、そのために審議を遅滞させるようなまねはしない。 マキャヴェリ P.187~192
あるとき京大教養部の過激派学生がまた校舎を占領封鎖し、授業が全面ストップした。占領の目的は前期試験を阻止するためだそうである。その理由は前期期末試験の施行は我々を学校へしばりつけることによって、成田闘争をつぶそうとする一連の陰謀によるものだ。その陰謀を阻止するためだというのであった。
笑ってはいけない。学生の要求というのは、みんなこういうたぐいで、大学解体をいうかと思うとその口からおれたちみんなに全部優をよこせと絶叫したりする。この伝で次年の大学入試も沖縄返還反対運動を破壊する陰謀だということになった。前期試験も入試も別に謀られた臨時の企画ではなく、毎年同じ日に行われる定期試験である。大学生に限らず今日の政治的騒ぎというものは、このような論理でない論理でうごくことが多い。裏には学生の試験恐怖症がある。それに火がついて、こういう論理で大騒ぎがおこるのだ。正常な論理では誰も騒ぐ気になれないのである。
ところで、かっての各大学の騒ぎだが、理屈はどのようにつくにしろ大体みんなこれに似たりよったりの論理だった。だが恐ろしいのは教授会の方の対応というのが、またマキャヴェリのこの論証を借りれば、この騒ぎに呼応して会議を混乱させ対応策から大学改革まで一切の審議を遅滞させるのが常例であった。つまり信頼するに足りぬあしき教授の会ということになる。
ところで、なぜマキャヴェリのこのような指摘が決断の心得になるのであろうか。
たしかに意志決定を行うとき、自分だけが熟慮断行するということでは、今日のような情報化社会のもとでは無理無益である。最後に自分が断を下すのはもちろんとして、ブレーンの意見を聞く、一般の提案をつのる。広く一万人集会という大衆会議を開くといったある市長さんの場合から、先生や先輩や友人と相談する。本を読んで考えるという若者の場合から、すべて「審議」にかけることが必要だ。読書だって、こちらがアンケートを出して、それに応じてくれるという読み方をする訳だから、やはり一つの「対話」か「会談」になる。私はそのときの決断の方法をいっているのだ。
こんな世論に迷って会議を遅滞させるような議員の意見は一切とりあげるな。結論を出し得ないような会議なら開くな。そんな議会は解消してしまえ。それが大切な条件なのである。
なるほど自分が考えるため、いろいろな情報を提供してくれる人や組織は必要かも知れぬ。それはしかし、次元の低い相談役である。現在は情報化社会だというけれど、それは無駄、情報過剰時代ということでもある。どんな情報でも、そこには必ず伝達者の主観、取捨選択が入っている。そのようなフィルターなしに入ってくる情報は存在しない。世論調査というものだってその通りで、ときには調査企画者ないしは組織の恣意をこういう客観性の装いをこらすことで押しつけようとする場合もある。かなりの正確度を得られるが、タバコとならば未成年者と女子がいるだけでもあってはならない。
う つまり私たちは単に情報をうけるだけではない。直接体験以外の――自分の野次馬的監察はあてにならない――すこしでも間接的な情報は、みんな一つの判断をもった情報である。私たちは主観を通過した情報の洪水の中で、絶えずそれを判断し、選択しつつ生きて行くことを強いられているわけだ。
人間の価値は、情報判断能力にある。すこしでも指導的立場にある人は、その判断を公にし、それを主張し、実行して行く責任を持つ。情報はいろいろ持っているが、判断はできないというような人間は、指導的立場にある資格はない。決定できぬ会議は無意味でである。そんなものの意見にしたがうことは、自ら自分の資格を放棄することである。
逆にいえばこうだ。このような情報過剰時代には、その情報が正しいかどうかは、その情報をもたらしたものが、はっきりしたその情報に対する態度、判断を持っているか否かにかかわるということである。
この判断とは、しかし、予見、先入観によるえり好みであってはならない。イデオロギーと信仰が先立つ人の意見は決してとり入れてはならい。流れから宙に浮いた老人の判断、利益目的の御注進といった種類の情報も駄目、判断とは、判断者が責任を持つ判断のことである。この点をとりちがえてはならない。
今日fでもまだ忍者ブームとかで、子供漫画や小説にはしきりに忍者が出て来る。その忍者のすばらしい技能を持ちつつ、「偉い人」の恣意のままに使われ、その権力のため犠牲になる崇高な人物だ。「進歩的」な漫画ほどそうだ。
何とも奇妙な話である。本当の能力者というものがそれほど卑屈になれるものか。かれらが「いぬ」であるのは当然だろう。判断の提供者ではないからだ。忍者のもたらすものは噂だとか、情報の一断片にすぎぬ。総合判断者がそこに必要となる。だからこそ重んじられるれなかったのである。信長だろうが、秀吉だろうが、軍事会議は武将の判断を聞いているので、その判断の基礎情報の一部だけがしのび連中からもたらせたものなのである。しかも、かれらの情報は主人公一人だけが知っているのでなく、会議の席上で公開されているのがふつうである。その程度のものだったのだ。
マキャヴェリは、さらにいっている。大切なことは、どう実行するかを腹に据え決定することで、言葉のつじつまを合すことではない。実行が決定し、行われたら、言葉などいくらでも作られると。その言葉を作るものとして官僚があったのだ。飾りが欲しければ、取りまきの詩人、美術家、学者を作ればよろしいということになる。
今日の混乱は、言葉であるが実行と責任のない世界が生み出したものであろう。このような世界は大変すみにくいように見えて実は案外楽な世渡りができる社会なのである。事由は簡単だ。腹をくくり、本当に責任を負う決心さえすればよいのである。そういう道を行く人は僅かしかいないのだから、誰も知らないバイパスのようなもので、言葉とかアイディアとか何とかで混み合った本道のイライラをよそにスイスイ通って行ける。
意志決定についてなによりも大切なのは、情報にふりまわされ判断と決断のない会議から学ぶなということである。ついでに申し上げると、日本の学問は意志決定ができなくなるように人間を育てるということにある。上級学校ほどそうだで、自分の好き嫌いもわからなくなるようになってしまった先生が大学教授には多いのである。自己解体とか何とか悲痛そうな声をあげているか解体すべき自己などなくなっている人も多い。そのような小田原評定を地で行ったような判断保留だけの本をいくら読んでもマイナス効果しか生まないであろう。
2024.01.14 記す。
29 (指導者たるものは、いつも)必要にせまられてやむを得ずとる行動でも、自分の意志で行なっているふりをしなければならない。 マキャヴェリ P.193~198
この提言の例証としてマキャヴェリが挙げているのは共和制期のローマの元老院(セナトゥス:羅: senatus)の決定である。元老院は軍務に服する人には国から給料を支払うという決定を下した。それまでは自費を投じ、つまり武器も自前で調達ということをやって来ていたのである。こんなしきたりのままでは長期戦に耐え得るはずがない。包囲戦に従事したり、遠征したりは到底無理となる。拡大しつつあるローマとしては、しかし国費負担制をやらざるを得なかったのだけれど、そんなことはおくびにも出さず、自らの創意によってこの政策をうち出したという態度を見せたのである。
平民側は大喜び、ローマ中が歓声につつまれた。野党派の中では、そんなことをすると平民の税金が重くなる、平民はこの提案を拒否すべきだとアジった。しかし、民衆はこの提案に賛成した。元老院側はどんな憤懣を国民に与えるかを知って居り、たくみに貴族側が負担をうけるような新税法を提出した。野党派はまるで元老院の立派さを証明するために反対したようなものだ。こうしてかららは全く窮地に立ってしまったというのである。
この教訓はすこしむつかしい。論理的にではなく、「必要にせまられている現実」の解釈に関してである。まず、必要に迫られていうことだが、元老院のこの場合そう緊迫性があったとは思えない。攻撃されてあわてて反撃するというのは選択の余地のない必要上の行動だが、マキャヴェリのいっているのはもっと大局的な緊迫性である。大抵の人間は、そのような緊迫性に気がつかないか、気がついても優柔不断のため何もできない。やれる人間は相当なものである。だからこそ、それほどの人間でも自然と自分の創意工夫でやったように思いこむのだともいえよう。そこでマキャヴェリが警告してくれなくても、必要にせまれるなら誰でも当然そういうことをするという反論もできるかも知れない。
しかし、ここが大切なところである。それは私がマキャヴェリや中国古典に託して、ずっと説いて来た基本線の問題にかかわって来る。つまり、無自覚的にそう思い、そういう態度をとり、そういう行動に出るのか、自覚してやるかどうかということだ。必然性をいち早く見てとる能力、決断によってその必然性に対処する能力があるということ。この能力も大したものではあるがそれだけでは充分とはいえない。いや画竜点睛を欠くものだといえよう。自分自身の能力をはっきり計量的に自覚し、そういう醒めた心で、醒めていることを他人に悟られぬようにやってのける必要がある。その能力こそが大切だという点である。
マキャヴェリは実にここまで見通していなかったのかも知れぬ。かれはむしろ単純な露悪家、義悪家ぶった人間だという人もある。そんな底の浅い人間ではないことは確かだが、イタリアという国の本質を知らない人にはそう思われても仕方のない面もある。それにやや人間性の洞察に甘いところが時に出て来るという欠点もあるようだ。とりわけ古代ローマ崇拝がルネサンス人の常として大いに作用している。そこでの実例が過大評価され、それが人間省察の不足となってはねかえっている。現代ほど歴史事実が豊かに伝えていたらもっと鋭い見方になったろう。だからマキャヴェリや、それに中国古典でも、それから学んで現代を考えるためには、そのまま直線的に学びとるのではなく、もう一段と突っこんで反省して見る必要があるのである。
「建武の中興」は北條氏の、とくに高時の相つぐ失政から生まれた。天皇に政権が帰ったことは後醍醐天皇などの能力にもよるが、北条氏の滅亡ということはまあ必然だったといってよい。ところがそのはじめ天皇の挙兵を聞いていち早く呼応して備後を平げ、京へ出ようとした桜山四郎入道などは当初大した勢だったのが、正成の赤坂城が陥落するなど形勢非となって窮地に陥って一族ともに自決してしまう。これなど必然は必然だったが対応の仕方が早すぎたといえよう。正しい対応でも、そこに醒めた精神が働いていないと大失敗するという例証である。その点足利尊氏などは見事なものだった。こんな例証は無数に存在するのである。
もう一ついわねばならないことは、必然だろうが、相当な決断だろうが、ともかく意志表現と行動に出たときは、その時点において相当度のアフター・サーヴィスをやる覚悟が必要だという点だ。実をいうと、その覚悟があるからこそ、全くの必然に押し出された行為でも、自分の意志で行なったような顔つきができるのである。元老院が、貴族の方が平民よりもうんと重い税を――といっても収入が大だから自分側の本当の負担は大したことでなく、総体的には数の多い平民の方がたくさん税金を払うことになるのだが――ひきうけるという覚悟をして軍人の給与支給の決断をしたというのはそうである。
物質的にであれ、精神的重荷であれ、労働であれ、かなり先の時点まで自分が負担を負いつづけるという覚悟なしに一切の決断をしてはならない。そうでない決断など決断にならない。「万一の場合は俺が責任を負う」などということでいかにも自分の決断のようにいう人があるが、万一のときなどというでは決断ではない。自分で自分のその決定を決断だと思っては必ず失敗する。必然にうごかされたことを決断だと思いこむのと同じように、必ずこれこれの負担はかかって来るが、それは俺がひきうける、それも長期にわたってという条件を担ってではないと本当の決断にならない。それに、その覚悟なしに自分の意志で決断したように見せかけようたって、それは不可能である。やがてみんなが見破ってしまうからだ。桜山入道の失敗は正にそういうところから来たといえよう。楠木正成はその点赤坂城が陥落しても見事にのがれ、今度は千早城で大成功をおさめるのである。元老院の決定でも同じことだ。自分の能力を知る醒めた目がり、相当なアフター・サーヴィスをやる見通しと決意が充分あったため成功したのだといえる。
決断したふりをする。これは絶対に必要なことだが、ふりを押し通すには実質がいる。その実質とは、誠実だとか、意志力とかいった道徳ではない。醒めた目で自分を計量する能力だ。そういうことを知るのが子供でも青年でもない大人の智慧というものなのである。
2024.01.16 記す。
30 将に五危あり。必死は殺さるべきなり。必生は虜にさるべきなり。忿速(ふんそく)は侮らるべきなり。廉潔は辱かしめらるべきなり。愛民は煩わさるべきなり。軍をくつがえし将を殺すはかならず五危をもってす。 孫子 P.199~204
「孫子」は経営者たらんと夢を持つ人だったらもうとっくに読んで居られよう。だからここへ出すのはすこし変なものだが、意志決定の際の条件として中々参考になる。あえて挙げて見た。
第一には必死になりすぎるなということ。これはいたるところで私たちが接する教えである。弓のつるは平生ははずしておかぬと駄目だとか、有名なのは宮本武蔵が一乗寺下り松の決闘の直前、吉野太夫に会ったとき、かの女が最も大切にしていた琵琶の胴を破って中身が空なのを見せ、「心を」はりつめているばかりではだめ、琵琶は鳴りませぬ」と啓示した云々という話だとか。
第二の生命だけは助かろうとばかり考えていると生命は助かるが捕虜になってしまう。第三は短気ですぐおこる人間は軽侮され、人に利用されるだけだ。戦国では福島正則がその代表として有名である。
ここまでは誰でも反対しない。いわば中学校の生徒程度の社会観、道徳観、人間観で充分理解できる意見である。しかし、それだけのことだったら人間洞察にはならない。大人の智慧が必要なのだが、この小中学生の頭脳のまま停滞してしまう「正義の大衆」が王様となったのが近代社会というものである。この近代社会では、科学や論理など技術的な知識は大いに発達したが、本当の人間省察ということでは哲学でも何でもさっぱり駄目。結局はヨーロッパ近代以前、ヨーロッパ近代以外の智慧に頼らねばならぬ。この第四と第五が、その智慧の例である。孫子が、はじめは誰でも容易に理解でき、賛同する条件を挙げ、フンフンとうなずいているうちに、今度はさっと大人の意見を出す手際は何とも鮮やかなもので私などは、かれの智慧そのものより、その智慧の出し方のうまさに嘆賞することが多いのである。
廉潔がどうしていけないのか。団地夫人などは、それが売り物の政治家にはすぐ参ってしまう。部下だってそういう将を慕うはずだし敵も買収を諦めるではないか。しかし、こういう疑問は戦う相手を安物だとしての話である。参議院全国区の有権者相手ならそれで成功するでしょう。だが相手が上手だったらどうする。潔癖症の人間は名誉に弱い。これを傷つけられると逆上し、思慮分別、冷静な利害得失を忘れ、みすみす敵の術中に陥ってしまう。相手が海千山千の曲者だったら勝負にならないのだ。女子供(さらにそのような男)相手の選挙やマスコミ戦術やPR作戦にしても、競争相手とのPR戦争となれば話は複雑になる。意思決定は容易ならぬ大物を相手とする覚悟が常に必要となろう。そのときこの教訓は生きて来るはずだ。廉潔の人間は常に非命に倒れる。キリストから孔子から、ソクラテスから、下っては加藤清正、西郷隆盛に至る有名な人を考えられたい。もちろん、こういう人は運よく名を残せた。名を残すのは個人としては結構かも知れないが、管理職、経営者が会社をつぶし、仕事をつぶし、名だけ残しても何にもなるまい。いわんや名も残せぬ廉潔失敗者に至ってはそれこそ無限に存在するのだから。もっとも、この廉潔とは真の意味における廉潔者ではない。学生や先生やママさんと同じく、自分だけでそう思っている人間のことである。本物の廉潔者だったら、などにはならない。つきつめていえば、この地上の人間世界の中では生きて行けないはずである。
第五の愛民もむつかしい問題である。それを自分自身の絶対の掟とした西郷南洲は正にそのために乱をおこし、数千人を殺して自刃しなければならなかった、なぜか。
将にとって民は可愛いものであろう。しかし、それは度し難いほど愚劣な存在でもある。愚劣だけではない、その欲望にはきりがない。気位もつけ上ってきりがない。そのことに思いをいたすなら、愛民とは民のつけ上りへの迎合ということの代名詞でもあり、将を亡ぼす要因となることが理解できよう。
ところで、私が、この孫子の言葉を管理職、経営者の意思決定の条件に持って来たのには、多少の感慨を以てである。官庁にとっては見事な組織を作り、それを運営して行くことが至上命令だろう。企業にとっては売上高、入場者、来客、視聴率、そういうものが第一義であり、唯一絶対な存在であることは判る。ところで、その企業内の感情はどうだろう。若いうちはそういう利潤絶対主義に反抗的になることもあろう。しかし、管理職ともなれば、いつか、その批判の心はなくなって、仕事、会社第一主義になるものである。私は、決してそれを堕落だとは思わない。そういう立場にたつのが当然だと考える。愛民は駄目だと知った立場だと思う。
しかし、企業の利潤増大、会社の発展、それのみを目指して意思決定をするとき、私はこの愛民、つまり大衆のつけ上りや無知をあおったり、それに迎合したりする、つらさだけを意識してほしいと思うのだ。つまり最大利潤を求めること、それが公害の排除など当然のことをした上で何とも不条理な、反社会的行動だと知りながら、あえてこれを選ぶ決意をしてほしいということなのである。さらに言えば、人間を組織化することは人を地獄に陥れるものであり、教育は人間を不幸にすることであるのだ。そういう意志決定を行うことによって、若者の無責任な自分だけが正義感でそれでよいとする幼児性、女性性を脱却することができるのだ。さらに、未来の経営者として、ちょっと嫌な言葉だが、真の国士の立場に立てる可能性を作り出して行けることになるのである。現在の経営者には、残念ながら、企業利益をこえた立場に立てる人があまりにも少なすぎる。今まではそれでよかった。しかし、今後は世界一、ニを争う大国の責任者としてその責任は、それだけでは果し得ない。未来の日本の運命は、人類と運命を共にするはずだ。そういう運命を担うべき、今日の中間管理職、中間的指導者の責任は、あるべき最高責任者の卵として、常に意志決定の際に、この苦い米を食べていただきたいのである。
※参考:冒頭の「孫子」の言葉は、(岩波文庫)『孫 子』P.90 九変篇第八にあり。
2023.12.18 記す。
おわりに
日本人は甘えの世界に住んでいるといわれる。たしかにその通りで、序論でのべたように、日本人にとって意志決定とか決断という言葉ほど、その民族的性格に無縁な言葉はない。私たちは浮世の潮流にただ流され、その中でせわしげに、これもあれもと右往左往しつつ求め歩いている世界に生きているようである。
しかし、そのような「なれ合い」で事が済んで行くのは日本のような同質社会内部だけに限られよう。ここまで発達した日本はあらゆる側面で、異質な海外社会と密接な関係を持って生きて行かねばならない。そこで生残って行くためには、私たちにもっとも不得意なこれかあれかの選択も、イエスかノーかのはっきりした意志表示も必要になってくる。泣声を大きく、そして念入りに駄々をこねてさえ居れば世論とやらがわき、政府が腰をあげないしせよ、誰かが何とか」してくれる日本とはちがうのである。
それに、日本の内部でも、指導者が御輿にかつがれて何とはなしに進んで行ける時代ではなくなった。上や下方への責任転嫁で事が済んで行ける時代ではなくなった。社会や組織が大きくなり整備されるに至ったからである。企業でも官庁でも、長になる人間には、はっきりした責任が要求される。もはや模倣するには先蹤者がいなくなった先進国になった以上、隣百姓主義は成立しない。自ら思考し、決断することを必要とする人々がふえて来た。
しかし、今日の日本は、まだこの意志決定の世界とは全く無縁な精神状況にある。いや、日本は意志決定即ち悪とされるような特殊な社会なのである。しかも国民の大部分はそのことに殆んど気がついていないのである。多少とも西洋史をやった私は、切にそのことを痛感する。それを思い、あえてヨーロッパでさえ一部の人々から悪魔の書とされるマキャヴェリを中心に、意志決定の条件を書いて見た理由である。本書を読んで意志決定を要求されるであろう人々がすこしでも何か得るところがあったと感じていただければ、私の意志は通じたわけである。
終りになるが、本書発行にいろいろお世話いただいた新潮社の方々、とくに担当になって下さった鍋谷契子さんに厚くお礼申し上げたい。
昭和五十年四月
会 田 雄 次
※すべて記載終わった。2024.01.15。