(角川文庫)昭和六十二年六月十日 第五刷発行
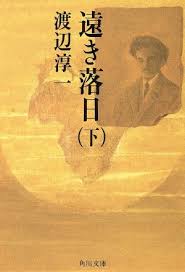
目次
第一章 デンマーク
あとがき 解 説 郷 原 宏 主要参考資料・取材等協力
第一章 デンマーク P.5
1 コペンハーゲンは小さいが美しい街である。 英世が訪れた明治三十六年(一九〇三)は、この国の世界的童話作家アンデルセンの死の三十年あとで、街には彼の存命当時そのままに、尖塔をいただいた教会やレンガ造りの建物が緑のなかに静まりかえっていた。丘に立てば澄みきった空の下、海図をみるようにいくつもの岬が突き出て、まわりを白い波がとり囲んでいる。家は赤、青、白と、童話の国そのままに色とりどりの屋根が並び、家と家は花壇で結ばれている。 「夢のようで、仕事が手につきません」 コペンハーゲン到着後、守之助への第一報に英世はこのように書いている。
この年十月、満二十六歳の野口英世はニューヨークを発って、デンマーク留学の途についた。 大西洋を横断し、途中まずパリに着く、ここで英世は欧州スタイルのアフタヌーン・コートとシルクハットを新調して、写真館で記念撮影をした、小柄な英世が、黒のコートとシルクハットをかぶった姿は、少し滑稽で不似合いであったが、英世は大真面目でカメラの前に立った。 そこで休息のあとデンマークへ向かった。 コペンハーゲンの国立血清研究所長のマドセン博士は、まだ三十二歳の少壮学者であった。彼は「ノグチ」という男が、フレキスナー教授の下からくることを知っていたが、それがこんな若く、しかも日本人だとは知らなかった。このあたりがアメリカ人の人物紹介の面白さで、日本なら当然、国籍を先に書くところを、フレキスナーは英世の研究実績だけを詳しく書いてよこしたのである。学問の世界に重要なのは、その男がやってきた業績で人種や年齢は関係ないとはいえ、徹底している。 マドセン博士は英世を快く迎えたあと、「自分をいくつだと思うか」と尋ねた。英世は少し考えて、「わたしは年齢を当てるのは苦手ですが、六十五歳くらいでしょうか」と答えた。 マドセン博士は、この日本人は本気か冗談か、と呆れ顔で、実は三十二歳だと答えた。アメリカにいて大分、外人の顔は見馴れていたが、英世はさすがに驚いた。外人は年齢より老けて見えるが、倍近い年齢をいってしまった。 「日本では年上の人に敬意を表す場合、できるだけ年齢を多くいうのが礼儀です。本当は百歳ぐらいとでもいおうかと思ったのですが、六十五歳ぐらいがよろしいかとおもったものですから」 ウイットをまぜながら英世はいいつくろう。アメリカへ来て、右も左もわからなかった当時ならうろたえたが、いまは軽いジョ―クをいう程度の余裕と自信ができていた。 血清研究所は意外に小さかった。マドセン博士らの数多い論文を読んでいただけに、かなり大きな研究所かと思って来てみたが、所長以下所員は四人しかいなかった。 このマドセン博士の仕事のやり方は、少し変っていて、朝、出勤してくると、所員が前回やった結果を、暢んびりききながら一時間か二時間を過ごす。それから自分の部屋へ行き、またしばらくお茶を飲んだり雑談をしているようにみえる。 北里研究所からフレキスナー研究所のように走り続けてきた英世には信じられない悠長さだが、ここでは科学の経済的応用などということは一切考えなくてよかった。各自が思いどおり好きなことをやり、好きなときに休む。お金や生活のことなどを心配する必要はない。死にもの狂いだったフィラデルフィア時代からみたら、まさに、別世界の暢気さである。 だがこうした暢んびりした環境から次の仕事へのアイデアを探っていくというのが、マドセン博士のやり方だった。充分頭を休め休養し、そのあいだに次の研究へのエネルギーが燃えあがってくるのを待つ。 かって仁科博士が研究所をつくったときも、これに似た状態だったといわれている。所員を高給でかかえながら、とくになにをしろと指示はしない。所員の自由に任せておく。初めのうちこそ、所員達はなんの負担もないので、勝手気儘に遊んでいるが、そのうち遊ぶのにも飽いてなにか仕事をしたくなってくる。そのエネルギーが充満してくる機会をとらえて、一気に仕事をさせる。いいかえると無理に仕事に追い込まず、やる気が醗酵してくるのを待つ。 「いまほど、自由で幸せな時間を過したことはありません」 英世は手紙にそんなことを書いているが、まさしくこの研究所は天国であった。とくに贅沢をしなければ、研究所からの給料で生活は充分やっていける。しかも博士以下、研究所員、さらにコペンハーゲンの人達はみな親切であった。 アメリカ人も気さくで陽気だが、デンマーク人は、それに加えておっとりしている。人を軽蔑したり、疑うということがない。小柄な英世が街を行くと、名も知らぬ人が帽子をとって、「おはよう」と、微笑みながら声をかけてくれるし、道をきけば目的の場所までわざわざ従いてきてくれる。こんな平和で静かな街が、この世にあるとは夢のようである。 「学者というものは、こういうところで、じつくり腰を落ち着けて研究すべきものかもしれません」マドセン博士につぶやきながら、英世はようやく一生を研究者として過ごす決心がついた。 この研究所で、英世はファミュルナーという学生と研究室をともにした。研究室は二十坪はあり、床は石で壁はタイル張り、水道管留具はいずれも真鍮でよく磨かれている。研究所には掃除夫が何人もいて、いつもきれいに整頓されていた。マドセン博士も綺麗好きで、テーブルやソファなどに北欧風の凝ったものを置くのが趣味だった。 英世は極力気をつけるようにしたが生来のだらしなさがつい出る。研究所にきて三か月目に、論文を一つ紛失したが、マドセン博士はとくに非難することもなかった。「場所が変ったせいか、わたしはまだ浮ついているようです」自省をこめて、英世は守之助への手紙に書く。 この研究所で、英世はマドセン博士とともに、蛇毒の免疫についての研究をはじめた。アメリカからくるとき、英世はガラガラ蛇の毒液を乾燥させた粉末を百グラムほど持ってきていた。これを山羊に注射し、山羊の血液中にこの毒に対する抗毒素を発生させる。そのうえで血清をとり、蛇に噛まれた動物に注射してやると、血清中の抗毒素が働き大事に至らず助かる。 実験がうまくいったとき英世は異様にはしゃぎ、誰彼となく口をきき、冗談をいう。だが失敗すると途端に頭を抱えこみ、無口になる。 「まるで世界が終ったかのような気のふさぎようだ」ファミュルナーは、その感情の起伏の激しさに呆れるが、英世にはこういうエキセントリックなところがあった。仕事に熱中しだすと、食事も忘れて打ち込むが、逆に気がのらないと、研究室も論文も乱雑に放りなげたまま遊び出す。英世の毀誉褒貶は、この性格のいずれの面を見たか、そしてそれを許せるか否かによって、ずいぶん異なってくる。 この国立研究所に、デンマーク王家のインゲボルグ内親王と英国のアレキサンドラ皇后が連れ立って見学に訪れた。小さな、しかし民主的な国だけに、皇族の訪問といっても格式ぶらない。四、五人のお付の人だけ連れて、マドセン博士の案内で廻られた。 内親王は特異な風態の英世に目をとめられて、どこからきたのか、ときかれたあと、「デンマークに一人できて、淋しくありませんか」と声をかけられた。 英世は硬くなって辛うじて、「いいえ」とだけ答えた。 このあと内親王は国王に、日本人が国立研究所にきて勉強していることを告げたらしい。その後マドセンが国王陛下に会ったとき、「研究所にいる日本人は元気か」と尋ねられた。それをアメリカへ帰ってから、マドセンの手紙で知った英世は感激し、「もったいない」と手紙に頭を下げた。 「国王陛下がわたしのようなことまで御存知とか、これほどの感激はございません。いまはひたすらコペンハーゲン時代の、楽しく幸せだった日々を、思いおこすばかりです。インゲボルグ内親王には、幸運にもお会いすることができ、お姿はいまも胸にやきついています。あのような高貴な方の思し召しに、いかにしてこたえるべきか、方法とてわかりません。わたしは先生を通して、陛下の御健勝と輝かしき御統治、さらに多くの芸術家および科学者の輩出することを、ひたすらお祈りするばかりです」 帰国後マドセン博士に宛てた手紙だが、明治時代に、日本の貧農に育った英世にとって、王室というのはまさに神に近い存在であった。 研究所に来て二か月ほど経って一九〇四年一月、英世はマドセン博士とともに英国へ行った。オックスフォードでの血清学会に出席のためである。このとき、英世は英国と英国人について遠慮のない批判をした。一部は好意的であったが、ほとんどは批判的なものであった。アメリカのように開かれた国しか知らなかった英世にとって、イギリスの古色蒼然とした権威主義と東洋人を見下すイギリス人の態度に我慢がならなかったのである。 これをきいたマドセンは、「君はイギリスに来たら、たちまちいろいろ感想をのべるが、デンマークではいくらきいてもなにもいわなかった。それはどういうわけかね」 「デンマークでは、わたしは先生に教えを受けてている一介の学生です。こんな若造が、御国のことに、いろいろ批判がましいことをいっては罰が当たります。とくに先生のお父様は陸軍大臣という要職にある方ですから、失礼のないように控えていたのです」 「そんなことは遠慮せず、感じるところがあれば、どんどんいってくれたまえ」 「いえ、デンマークに関しては、わたしが批判する余地など、まったくない平和で明るいこの世の天国です」 デンマーク人の鷹揚な優しさにくらべ、英国人はみな無愛想で貧相な東洋人などに目をくれる者もいない。 2 この年、二月四日、日本はロシヤに対して宣戦を布告した。 北欧圏にあって、ロシヤと密接な関係にあったデンマークでも、このニュースはいち早く知らされ、人々は戦いの進展について論じ合った。外国生活が長くなるにつれナショナリストになっていた英世は当然無関心でいられない。このとき、英世が血脇守之助に送った手紙には、当時のヨーロッパの様子がよくでている。 「(前略)今回の日露戦争は、先の日清戦争の復讐をかね、わが国の積年の怒りをはらす戦争であれば、全国民一致団結して対処していることと思います。 二月八日からの度々の旅順海戦はすべてわが軍の勝利に帰し、欧州各地は電撃にでも触れたように驚き、疑い、嫉妬と、さまざまな感情が混り、重なっています。ロシヤは欧州で最強国と思われ、全ヨーロッパはロシヤの動きに口出しするのを避けているほどですから、今回の日本軍の勝利をきいて、みな予想外の感を抱いています。 小生は英・独・仏はじめ当所の新聞など、あらゆる新聞を買いこみ、戦争の情報を求めています。戦地の報道は、どの新聞も大同小異ですが、各新聞の社説はまちまちで、その都度、各国の考え方が推測されます。 フランスの新聞は大半がロシヤ贔屓で、政府与党などは公然と、ロシヤに加担すべきであると唱え、日本を半未開の野蛮国呼ばわりしています。ドイツはもう少し狡猾で、表面は中立と見せていながら、陰でロシヤに情報を通じ、最終的勝利をおさめるように画策しているかのようです。ドイツの新聞の日本に関した記事は、フランスに劣らず悪口罵言をきわめています。これに反しイギリスの新聞は、陰に陽に、日本を援け、国民の同情を向けるようにしているようです。最近、チベット問題でロシヤと危機一髪の状態であり、フランスとの国交も切迫していることなどききますが、それらが日本に好意的な理由なのかもしれません。 またロシヤの黒海艦隊大小合わせて十五隻東洋に向けて進航中、スエズ海峡で引戻しの命令にあったとの説もありますが真偽はよくわかりません。もっともこの艦隊は実戦にはあまり役に立たないとの評判もあり、若し東洋に廻航すれば、日本艦隊の餌食になるだけだろうといわれています。バルチック艦隊も、しきりに東航をくわだてているようですが、ジブラルタ海峡を通過し難いとか。陸上の戦闘はまだないようです。 あるフランスの新聞は、日本軍二個連隊が、コサック兵のため旅順付近で全滅させられたと伝えていますが、嘘ではないかと思っています。 概してヨーロッパは人種的親近感から、ロシヤの勝利を祈っているようですが、多数の新聞は、陸上の戦闘がどうなるかということに、関心を抱いているようです。彼等は日本軍にくらべて、ロシヤ軍の優勢を信じ、ロシヤの必勝を予言しています。これは海軍はともかく、日本力郡がいかに勇敢かを知らぬからで、あい。すでに30の強力なのを知ったら、なんというか、彼等は野蛮な日本人は戦いに適している、というかもしれません。 彼等はしばしば我国を蔑視し、道義的文明が遅れていることをあざ笑っています。たしかに表面的にはそうかもしれませんが、日本国民はどんな場合にも、道義に背いたようなことはするわけがありません。日本軍人は戦時平時において、まだ彼等のような泥棒、殺人、強姦などをせず、日本人はまだ白人のように隠密に悪事を働いたりはしません。また彼等はしばしば日本男女間の乱れを公言しますが、では彼等ははたしてどんな生活をしているのか。妾、間男、私通、売春、いたるところで目撃します。 彼等は日本人はまだ自分達の内容を知っていないと思いこんでいるようです。しかし余程愚鈍でもないかぎり、彼等の内情を探ることぐらいたやすく、白人の特長は外面はよく装い、綿密な観察力(これは猜疑心と併行します)を有する点にあります。しかしいつか、世界の物質文明が同程度に達したときには、彼等の特長は黄色人種にもゆき渡り、白人だけの特長でなくなることは間違いありません。小生、近頃、日本より新聞を受け取らず心細い次第です。この手紙と同時に時事新報社へ送金したので、遅くとも四月末には新しい新聞を見ることかと期待しています。 斎藤氏からは、九月以来文通がなく、わたしも手紙を出していません。一体、どんなことになっているのか不明です。わたしの留学中は約束の娘を教育すべきだと思うのですが、……少し情けない話しです。猪苗代からは毎度、破談を希望してきますが、三か年間、待ちに待っている娘の気持を思うと、心も痛み、大いに返答に困っています。愚母よりは三、四度同じような手紙をよこしており、このさいどうしたものか、判断しかねています。 ついては大変恐縮ですが、恩師の御意見、および斎藤氏の方の始末などにつき、御教え下されば幸いです。 この手紙がそちらに着くころには、陸戦の様子もわかるころかと思います。ひたすら我軍の全勝を祈り、あわせて皆々様の健康をお祈りいたしています。当地はかなり厳しい寒さですが、雪はほとんど積もりません 御奥様はじめ、皆々様によろしくお伝え下さい。まずは御無沙汰をお詫びし、近況報告まで」
日露戦争と許婚者のことと、英世の頭はそれらのあいだを目まぐるしく動く。しかし戦争がはじまって、英世は落ち着いて仕事をしていられなくなった。 学問的には、人材主義の定着していない母国に愛想をつかしながら、いざ戦争となると話は別である。東洋の未開国の黄色人種として、欧米人のなかにいた英世が、ナショナリストになるのは無理もなかった。日本へ大金十四円を送って新聞を求めたのも、戦争の様子を知りたい一心であったが、四月になっても送ってこない。英世は苛々しながら、横文字の新聞と、人々の噂で戦争の様子を探っては、守之助への手紙に次のように書く。
「日露戦争開始以来、日夜戦争のことばかり心にかかり、研究も手につかぬ状態です。二月四日の仁川および旅順の海戦は、全世界を驚かし、東郷提督の名は小さな子供でさえ知っています。その他、その折々の海戦の結果は、即刻、欧州に響き渡ってきます。 ロシヤ提督アレクセーエフの名は、不名誉な軍人の代名詞となり、東軍の司令クロパトキンの動向が注目されています。(中略)昨夜の来電では、ロシヤ艦ぺテロポールスキ号沈没、マカロフ提督戦死のことでしたが、今朝はそのことについてはなにも触れていません。陸戦のほうも第一戦は日本の勝利を報じていましたが、昨日は我軍の斥侯五十名が鴨緑江でロシヤ兵のために全滅させられたとか、牛荘でも新たな戦闘準備の気配があるとかきいています。 新聞のニュースソースは、主として、モスクワ、ロンドン、ベルリン、パリなどのもので、英米派は日本軍の勝利を知らせ(ときどき誤報もありますが)、独仏系の新聞はロシヤの勇気を称え、敗報に反論し、時には日本軍の名誉棄損を企てています。 社説は英米は日本の味方(アメリカのヘラルドトリビューンだけはロシヤ贔屓)、独仏はロシヤ派です。したがって独仏の新聞社説には、黄人禍という言葉がしばしば現われます。ことに癪にさわるのはドイツ人です。彼等は狡猾で面憎く、フランス人は丁度スペタ女郎の肌合いで、無闇にロシヤ人に入れ込んでいます。まったくフランスのやり方は見下げはてたものです。癪なのはこの二国です。 デンマークは掌大の小国ですから、世界に対する政治的勢力はほとんどゼロにちかいのですが、ここも人間の集まりですから黙ってはいません。いろいろな意見の人はいますが、大体は日本に同情的です。しかし、ロシヤの目を恐れて、比較的こそこそと論じるだけ。御存知のとおり、王室は親類仲です。しかし国民は王室とは別で(ヨーロッパにおいては、これが当たり前のことになっています)、先日、当時の皇太子(すなわち英・露二国の皇后の兄)が研究所に御訪問され、その翌日は、所員一同と小生は皇居に招かれ、夕食の御馳走になりました。まったく平民的な感覚で、皇室一同われわれ臣民と同席で、面白く対談され、二時間ほどで退出されました。 この手紙を書いている最中に号外あり、"ロシヤ旗艦ペテロポールスキ号、水雷に触れて沈没。六百余名溺死。二十二名救助。新任アドミラル・マカロフ以下参謀部全滅。大公ウラジミロヴィッチ親王重傷、目下プリンス・ウチトムスキー替って指令中"との情報あり、旅順の陥落も目前ときいています。かさねがさね、日本軍の活躍は目覚ましいかぎりです。本便にて欧文の日露戦争記を差上げます故、なにとぞご覧下さい。かわりに戦争雑誌をぜひお送り下さいますようお願いします」
この手紙、英世のナショナリストの真髄がよく現れているが、同時に、当時のヨーロッパの趨勢を知るには、きわめて貴重な資料ともいえる。 この手紙の日付は明治三十七年四月十四日、そしてこの八か月後に、難攻不落を誇った旅順の要塞は陥落する。勝利とともに日本の力が認められ、それを背景にマドセン所長の好意も手伝って、英世はコペンハーゲンで急に人気者になる。 学界はじめ財界などの会合に招かれ、感想などきかれ、饗応を受ける。 英世は日本の皇室と臣民の礼儀正しさ、一致団結などを話し、自国のPRにこれ努める。まさに民間大使ともいえる活躍であった。 一方この間に、ニューヨークのロックフェラー医学研究所は着々と準備を重ね、十月より開設の運びとなった。 「十月一日までに、ニューヨークに到着するよう、帰国されたし」 フレキスナー所長からの手紙を受けとり、九月の半ば、英世は心を残しながらデンマークをあとにする。 この間、ほぼ一年、初めは戸惑い、やがてロシヤとの戦争に一喜一憂しながら、十篇の論文をまとめ、マドセン、ファミュルナーという貴重な医学徒を友達として得ることができた。
第ニ章 ニューヨーク(Ⅰ) P.19
1 一九〇五年十月、英世はニューヨークへ戻ると、ただちに新設のロックフェラー研究所の首席助手に任命された。五年前、日本から一人でフレキスナー教授のもとにおしかけてきたときは、月八ドルの小遣銭を与えられただけだったが、いまは月給百八十ドルである。 新設のロックフェラー研究所は、ニューヨーク東部のイースト川に近い五十番街にあった。研究所はまだ建築中で、フレキスナー所長以下六名のスタッフは出来上がったばかりの煉瓦建てのビルの一画に陣どった。六名のスタッフのうち、二名は三十代の教授で英世より上席だったが専門は違う。あとの三人は英世より下だから、実質的には彼の思うままに研究ができる。しかも年齢は英世が一番若い。 デンマークからフィラデルフィアに戻ったのが九月二十二日、十月にはすぐニューヨークへ引越し、十一月一日からは早くも実験に着手するという張切りようであった。 研究テーマは依然として蛇毒であった。血清反応というのは入り込んだら果てしない、見方によっては泥沼のような部門であるが、英世は蛇毒に関する著書を一冊書きあげるまでは続けるつもりであった。 「俺のうしろにはロックフェラーがついている」このころ、英世はニューヨークで会った日本人に誰彼となくいった。 たしかにロックフェラーが、この研究所のために投じようとしていた金は膨大で、すでにつくられた財団の資金だけで百万ドル、さらにそれの数倍の資金が投下される予定になっていた。かつてモルモット一匹さえもらえなかった英世が、いまは実験動物も施設もつかい放題、仕事のためなら誰も文句をいわないし、邪魔する者もいない。 ニューヨークへ移るとともに、英世は下宿を研究所に近いレキシントン街に見つけた。ワンルームで、他に簡単な炊事ができる流しがついているだけである。フィラデルフィアのときもそうだったが、英世は住居にあまり関心がなかった。一日の大半を研究室で過すわけだから、部屋はベッドがあって眠れればよかった。それでも今度の部屋は現代風にいうとマンションの一室で、フィラデルフィア時代よりは広い。もっとも研究所のサラリーからみると、まだまだ粗末なものではあった。 幼時からボロ家に育った英世には、住居に金をかけるという発想がなかった。部屋の調度といえば、ベッドと書棚、あとは中央に大きなテーブルが一つあるだけだった。このテーブルは簡単な読み書きと食事兼用であったが、中央にはいつも一枚の写真立てが置かれ、そのなかで一人の女性が笑っていた。デンマーク留学中、コペンハーゲンで知り合った女性で丸顔の笑顔が優しい。英世はこの女性に好意を抱いていて、帰りがけにようやく写真を一枚だけもらったのである。 「あなたの恋人か?」 来客が尋ねると、英世少し照れたように首を振って、「そうではないが、日本人はこういう、優しい丸顔の女性を好むのです」と答えた。 顔の輪郭だけは山内ヨネ子に似ているともいえるが、このころ、英世の脳裏からはすでにヨネ子のことは遠ざかってた。かわって異国で三年半、ひたすら生きるためにのみ頑張ってきた男が、このごろになってようやく、女性への恋情を覚える心のゆとりがでてきたことはたしかであった。 このアメリカ第一の都市ニューヨークで、英世は新しく何人かの日本人と知り合いになったが、そのなかの一人に有機化学研究の第一人者高峰譲吉がいた。高峰は英世より二十二歳年上で過燐酸カリの研究のためアメリカに渡り、一九〇二年にはニューヨークに自分の研究所を創設していた。彼の名をとった消化酵素タカジァスターゼは、一九〇九年の発見であるが、英世と会った一九〇五年には、高峰の名は既にアメリカでも広く知られていた。だが英世はこの科学界の先達と日本人会などで数度会っただけで、それ以上の親交はなかった。それは英世にその気がなかったというより、高峰のほうで英世を避けていたといったほうが当っていた。 身なりにかまわず礼儀知らずで、一度自分のことを喋りだすと止まるところを知らない、そんな独善的で破調感のある英世が、日本のエリートである高峰にはうさんくさい存在に思えたのである。だが運命の悪戯とでもいうべきか、この二人はニューヨークのウッドローン墓地の比較的近い位置に葬られている。高峰の墓は大きな石室に囲まれ、なかに日本の旗や桜を映したガラス絵などが置かれているのに、英世のはただ、土盛りの上に石碑が立っているにすぎないが、死後二人はきわめて近いところにいるともいえる。 ともかく英世はニューヨークでは、あまり人付き合いのいい方ではなく、親しくなった日本人もあまりいなかった。フィラデルフィアでは淋しさと貧しさが、いやでも英世の足を日本人に向かわせたが、渡米後四年を経て、もはや無理に日本人を求めなくても自活していける。なまじっか、嫉妬と中傷の日本人と付き合うより、陽気なアメリカ人と付き合ったほうが気が楽だった。 こんな状況のなかで、二人の日本人客が訪れた。一人は奥村鶴吉という歯科医で、英世が守之助の家に世話になったとき同居していた男である。 英世は奥村がフィラデルフィアに着いたと連絡を受けると、すぐニューヨークから駆けつけ、元の下宿に一緒に泊り、一日中奥村を案内して歩いた。ずぼらなようで、こういうところ英世はよく尽す。奥村はのちに英世の伝記としては最も秀れた『野口英世』を著したが、このときの出会いが一つのきっかけともなっている。 もう一人、英世を訪れてきたのに宮原林太郎という男がいた。宮原は星一の紹介できたのだが、背が高く眼が異様に大きい男だった。本来医師で医学の勉強にきたのだが、とくにレントゲン撮影に関心をもっていた。彼はのち帰国して、日本で初めてレンゲン写真を撮る。 どういうわけか、英世はこの宮原と気が合った。どちらも少し偏屈で一人よがりのところがあったが、なにごともやり出すと止まらない一途なところもよく似ていた。二人は連れ立って食べたり、飲んで歩いた。 だがロックフェラー研究所の首席助手で、百八十ドルのサラリーをもらいながら、英世の生活は一向に楽にならなかった。ニューヨークにきてすでに一年経った一九〇五年のクリスマスにさえ、冬服がなく、外套は薄いレインコートで間に合わせる始末である。百八十ドルもの金をどこへ費っていたのか、英世はその理由を友人に、「先年の世界漫遊のため借金を生じ、未だに返済に追われているため」と答えていた。 しかしデンマーク国立研究所への往復旅費は、ロックフェラー研究所で負担したものだし、血清研究所でも一応生活に不足しない程度の給料は出ていた。普通の生活をしていれば借金する必要などない。この留学で英世個人が負担したのは、帰途ドイツやフランスに立ち寄ったときの費用くらいのものだが、アメリカへ戻った時点で英世には事実かなりの借金があった。その内訳は、まずデンマーク留学中に、所長のマドセンやファミュルナー等から借りた金である。それとロンドン、パリなどで遊んで日本人からも借りたものだが、こちらの方は主に女につかった。 アメリカに渡って以来、多少おさえていたとはいえ、英世は相変らず精力旺盛であった。それが学問に向けられてているときは、偉大な研究のエネルギー源になるが、女に向けられたとき無分別な浪費につながる。二十代後半の独身としては無理のないところもあったが、英世の遊び方はあまりにも計画性がなさすぎた。女が欲しいとなると見境がつかなくなる。まっすぐ娼婦の館に駆けつけて、初めに出てきたのを抱く。値切ったり、馴染みになって安くあげてもらうといったこともしない。そういうことはすべきでないと思いこんでいる。学問にはうるさいのに、こと女にかけては相手のいいなりだった。 みかねた知人が、「女に余計な金を使うのは止せ」と忠告しても、笑ってうなずくだけで、また同じことをくり返す。「あんな勉強家が、女のことになるとどうして馬鹿になるのか」知人は溜息をつく。 だが英世の立場にたってみると、女への浪費もある程度無理のないところもあった。 なによりも英世の最大の不幸は、フィラデルフィアでもコペンハーゲンでも、これと決まった恋人がいなかったことだった。恋人がいれば、その女性と欲望を処理することもできるが、英世にはいくら努力をしてもそんな相手はできない。黒い髪がやや縮れ、子供ほどの背丈しかない指の不具な東洋人に近づいてくる白人女性などまずいなかった。あるいは熱心に誘えば一人くらいできたかもしれないが、それをつくるだけの余裕も勇気もなかった。それでも欲望は人一倍ある。そうなると金で抱ける娼婦のところへ行くより仕方がない。すべての欲望を娼婦で癒すとしたら、莫大な出費になることは当然であった。 女性だけでなく一般の買物にも、英世には計画性がなく衝動買いするところがあった。デンマークに行くときもパリに立寄り写真を撮ったが、その折りわざわざシャンゼリゼの高級洋服店へ行って、黒のコートとシルクハットを買い込んだ。ロックフェラー研究所府に移っても、高給をいいことに、一本五十セントもする高級煙草を一度に何ケースも買いこんで吸ってみる。しかも金の足りない分は、つけにする。生活の必需品でもない煙草を、借金までして買い入れる必要もないと思うが、そういうところの歯止めがきかない。また友達がきて嬉しくなると、レストランへ行って一度に十人分も頼んで結局食べきれず、半分以上残してしまう。 英世にはほどほどということがなかった。極端に多いか少なすぎる。いってみれば平衡感覚がない、生活人としては一種の失格者であった。 この借金にくわえて、デンマークからの帰途、船でカードをしてかなりの額を奪られてしまった。大体、英世は賭けごとの上手なほうではなかった。相手の心理を読んだり、自分の気持を隠したりすることができない。いい手がくると気色満面になるし、悪くなると急に沈み込み、相手に手のうちがすべて読まれてしまう。それなのに誘われると、いやといわない。船中で負けて、カードで知った船客からまた借りる。 日本人ならいざ知らず、外人に借りた金は払わないわけにはいかない。とくにマドセンやファミュルナーは学問の師であり、友でもある。「漫遊の借金」というのは内容はともかく、事実ではあった。 だが借金に慣れていた英世も、さすがにこの年の冬には、自分の金銭への計画性のなさに自分であきれ、これでは駄目だと改めようとした。 そのきっかけになったのは、この年の秋から冬にかけて悩まされた痔疾である。もともと英世には痔の気があったが、長年の椅子への坐りづめと、この冬の寒さによって一気に悪化してきた。下宿から研究所へ十分とかからぬ道を歩くのさえ辛く、そろそろと歩幅を縮めながら行くので倍以上の時間がかかる。 医師に診てもらうと即座に入院して手術を受けなければならないという。迷った末、痛みに耐えかねて決心したとき、初めて金がないのに気がついた。保険制度のまだ完備していなかった当時のアメリかでは、手術を受けるとなるとかなりの出費になる。 「どこを向いても知らぬ人ばかりのアメリカにいて、一旦病気になったときの薬料を貯えておかないとは、その日暮しの労働者がやむなくやること、独立した人間のなすべきことではりません」英世は自らの反省を、こんなふうに守之助に述べたあと、 「今年からはじめて独立して、自分一人で会計をやりくりすることになりましたが、万事に経験なく、失敗など多く、いまだに一文の余裕もありません。この不愉快さは渡米以来のどの不愉快さにも、優ることもありません。節約はしようと努めてはいるのですけれども、長年の依頼的生活の習慣が天性となり、まことに苦しい実状です。しかし小生も今年は三十歳、一人前の紳士の待遇を受けていては、しかるべき体面も保たなければなりません。もはや無思慮な少壮時代ではないことゆえ、おおいに心を改めて血路を開く決心です」と神妙である。 フィラデルフィア時代には、フレキスナー教授が、英世の性格を見こして、生活費だけを渡しあとは貯金をさせて必要なときだけ衣類を買って渡すというやり方だった。いわばお仕着せに従っていたようなものである。だがニューヨークに来てからは、さすがにそうもできない。すでに三十に近く、研究所の首席助手である。自分でやりくりせよ、と給料全額を与えられる。大抵の者は喜ぶのを、英世はそれで行き詰まってしまった。もらっただけ費う浪費癖は一向に改まっていない。 結局、英世にはいつも誰か人がついて、生活面を管理してもらう必要があった。春になったからこの背広、冬になったからこのコート、下宿はここで、食事はこれ、というようにしかるべき人がついて決めてやる。その分では贅沢をいわないし、黙々と食べている。なまじっかな金をもらうより、生活面では管理された方が余程楽である。その方が頭をすべて学問に向けられる。 「多年の依頼的生活が天性となり」と、知ってはいても改められない。その馬鹿さ加減を非難することは容易だが、だからこそ異様なまでの学問への集中力が生まれてきたといえなくもない。 2 新設のロックフェラー研究所で、英世が取組んだ蛇毒の研究はフィラデルフィア以来の継続研究であった。この領域では、英世の仕事はすでに一応の評価を受け、オスラー博士編集の『医学大系』の「蛇毒」の項を執筆することになっていた。またこれとともに、フレキスナー博士と梅毒の第一期、第二期患者の病巣から、スピロヘ-ターパリダの存在をたしかめる仕事をはじめ、さらに四月からトラコーマの研究にとりかかった。 このトラコーマの研究は英世が手をつけたなかでも難問中の難問で、最後まで解決できなかったものの一つである。この年の暮のマドセン博士への手紙には、「トラコーマ患者の結膜の炎症部には、多数の細菌が存在しているため、まずこれらの細菌から片付けていかなければなりません」と述べている。 たしかにトラコーマ患者の結膜には種々の細菌が認められる。だがこれらはトラコーマになったあとの二次感染で、トラコーマの原因そのものではない。それはのちにウィールスの仕業とわかるが、当時はまだウィールスを確認する顕微鏡はなかった。いわば永遠に見付からぬものを追っていたわけでのちに英世はこの研究を放棄する結果になるが、この失敗が、そのあとの黄熱病の研究にも尾を引くことになる。 このころ、東京では斎藤家との縁談の話が、いよいよ大詰めを迎えていた。 斎藤家では結婚の約束をしてから、すでに五年近く待たされ、独身の娘を、これ以上家においていくわけにはいかなくなっていた。一体、どういうつもりなのか、いままでじっと待っていた斎藤家も我慢ならず、英世の真意をききたいと血脇守之助に迫ってきた。 守之助は何度か、英世に問い質したが、さっぱり要領をえない。最後には「自分はまだ当分帰る気はないから、どこか嫁にでも行くなら、それでもかまわない」と、無責任な返事である。いっそ女性のほうからアメリカへ押しかけたらとも考えたが、英世の真意もよくわからないのに、太平洋をこえて外国へ行くなど、当時の子女として出来ることではない。 追いつめられた守之助は、ついに独断で縁談を破壊することに決心した。 「ようやく、世界的に業績を認められようとしている学者を、いま引き戻すのは忍びないことですから」守之助はそういったあと、婚約の条件として、英世が受け取った渡航費二百円を返す条件で解消を納得してくれるよう頼んだ。 結局、娘は青春を五年間、無為に過ごしたことになる。守之助が極力、怒りをおさえて、解決したことを英世に告げると、折返し次のような簡単な返事がきただけだった。 「ありがとうございました。わたしもこれでようやく自由の身になり、研究に没頭できます。返済にお立替えいただいたお金は、早急にお返しするつもりです」 だがこの借金はそのままとなり、十年後、英世が帝国学士院恩賜賞を受けたその賞金の一部から返済されるまで放置されるままだった。 この婚約解消を見こしたように、英世はアメリカへ持ち帰ってテーブルの上に飾っておいた写真の主との縁談を強力にすすめていた。マドセン博士にも依頼し、その縁者がアメリカへ来た機会をとらえてわざわざ会いに行ったが、結局この女性は、コペンハーゲンの名流の出だということで、英世が思っていたほど、相手は積極的でなかった。ただ家族が親日的ということで、英世に好意的だったにすぎなかった。この話が破談になると、英世はただちにテーブルから写真をはずして抽斗の奥にしまい込んでしまった。 こういうところの、気分の転換は早い。 「そうか、それならいい」振られて英世は再び学問に熱中する。 このころ、奥村がよく英世を訪れたが、英世はほとんど研究室に泊りこみで、週に一度くらいしか下宿に帰ってこなかった。研究室の同僚が、「帰らないのか」と誘っても、「ここは俺の家だ」といって頑張っている。 もっとも研究室に寝泊まりするとはいえ、朝から晩まで研究していたわけではない。大酒は飲むし、煙草もヘビイスモーカーである。そのうえ、徹夜、夜更かしなど平気でやる。滅茶苦茶というか、自由気ままな生活である。 ニューヨークに来て一年も経つと、英世は一風変った男として、研究所のなかでも有名になっていた。 たとえば英世は実験室ではほとんど白衣で通すが、その白衣がいつも汚れていて、裾のほうに頭大ほどの穴があいている。それを一向に気にする気配もなく着て、おまけに一旦、仕事のことを話し出すと止まるところを知らない、相手が疲れて逃げ出そうとしても追ってくる。しかもその話が絶えずつまずき、言葉を探しながら、ときに意味不明のところもある。他の者が、英世の意見に納得し相槌を打つまで離してくれない。 しかし話題が食物や街の流行などの話になると、たちまち黙りこんでしまう。そちらのほうは、まったくといいほど知識がない。それでも、仲間が、「あそこの洋服はいい」などというと、給料日の翌日はすぐ三十ドルも四十ドルも出して買ってくる。しかも帽子から靴まで一緒に揃える、買った翌日には、それを着込んで得意然としてやってくる。 だが、そんな服装は三日ももたない四日目には、もう前のよれよれのワイシャツと、型のくずれた背広に戻って、ネクタイを少し緩めてくる。「あの服は高くてもったいないから、もっと着たほうがいい」と、同僚がすすめると、面白くなさそうに眉をひそめる。 今度は少しでも計画的にと大きな金銭出納簿を買ってきて、一セントの出し入れでもうけると宣言するが、それは三日坊主で、一週間すると帳簿は本棚の奥にしまい込んでしまう。 四月二十三日付、守之助への手紙に、英世は次のように書いている。「わたしはまだ、他人を扶助する力はありませんが、自分一人だけ生きて行くには、なんとか心配なくなってきました。不意の出来ごとのため、二十年満期で六千円手に入る保険に加入することに決めました」 一見、殊勝そうにみえるが、これも決意だけで実行に移されなかった。これでは駄目だと自分では思いながら、抑止のきかぬ衝動的な性格がつい計画を打ちこわしてしまう。 3 このころ、三城潟の英世の実家は相変らず貧窮のどん底にあった。 リュウマチで長いあいだ寝たきりだった祖母のみさは、この前年二月に亡くなり葬儀でもの費りが重なったうえ、父の佐代助の酒びたりは深まるばかりであった。あちこちの店に行っては借り倒し、家からは金をくすねていく。さらに他家に忍びこんで盗み酒さえする。 佐代助はすでに完全なアル中だった。酒が入らないと頭がぼうとして手足が震えてくる。舌ももつれてきて、話すこともわからなくなる。酒のためになら善悪の見さかいがつかなくなる。酒が入って機嫌のいいときは柔和でおとなしく素直で、働こうという気力もある。だが切れてくると別人のように変り、暴れ出す。どこか住み込みで働こうとしても、「佐代助のほうで月々十円もってきてくれるなら」といわれる始末である。 この義父を見ならったのか、イヌの夫の善五も酒好きで、他の店に借金こそしないが、働いた分はすべて酒に消えていた。イヌは二人の子供があるうえ、最後の子の産後の無理がたたって、いまだに畑の荒仕事はできない。すべてが五十すぎたシカ一人の肩にかかっていた。 さらに東北地方は前年から冷害で凶作が続いていた。おかげで最低の税金も納めれず、税務署から田畑の強制転売の指示を受ける羽目になった。幸い、転売は野口家の遠縁に当る渡辺忠作の援助で免れたが、農家のくせに米を食べられず、稗と粟ばかりだった。 見かねた小林栄がときどき米を送ったが、それもいっとき息をつくだけで、すぐなくなる。一日生きていくのがようやくのところへ、長年、応急手当てで支えてきた家が朽ち、雨漏りがひどく土壁もくずれて外から家のなかが丸見えになっていた。 シカは家を建て直したかったが、そこまで手がまわるわけもない。せめて夫の佐代助でもいなければ少しは楽になる。シカもまわりの人もそう思うが、アル中では誰も雇ってくれる人はいない。行きつくところ、小林栄に相談することになる。小林もいろいろ考えたが、うまい方法はない。だが、このまま佐代助を野口の家においたのでは、ますます世間の顰蹙をかい本人も自堕落になるばかりである。それに英世の名声にも傷がつく。 「それじゃ、わたしが預かろう。毎日一升酒というわけにはいかないが、二合程度で我慢させて、家の仕事を少し手伝ってもらおう」 「先生から厳しくいうて下さったら、あの人も少しは心をいれかえると思いますが」 シカには願ってもないことである。佐代助は酒は飲むが、普段はおとなしい男だった。いわれたとおり使い走りや、草とり、雑巾がけなども真面目にやる。小手先も結構器用だった。ただ酒が欲しくなると我慢ができなくなる。中毒だから体内の血のほうが騒ぎだす。小林は佐代助に二合までは飲ませる。そのかわり真面目に仕事をすること、という条件で身柄を引取ることにした。 一方、英世の弟の清三は、小学校を出たあと、小林栄の世話で若松の新城という酒造店に勤めていた。清三は英世からみると気が弱く、奉公が辛いと逃げ帰ってきたことがあるが、シカは「男は首でも刎ねられるとき以外、泣くものではない」と叱りつけ、その夜のうちに若松へ追い返した。戻った清三は真面目に勤め、二十歳の徴兵検査では甲種合格にとなってこの年の十二月に仙台の歩兵連隊に入隊した。 この清三は、二年後除隊して新城家に戻り、同家の主人に認められ娘との結婚の話がすすめられた。だが同じ若松市内の餅屋の娘を好きになり、妊娠させていたことが知れて小林栄の怒りをかった。 仕方なく清三は会津を離れ、屯田兵として北海道北見に近い野付牛に入植し、数年後同じ町の郵便局員の娘と結婚し、養子婿入りした。その後一時鉄道に入ったが、事故に遭って肢を傷め、のち妻と二人で「ニコ二コ屋」という料理店を開いた。 大正四年、英世が帰国したとき、親戚縁者が集まり盛大な会が催されたが、そのときも清三は北海道に残ったまま生涯英世と会うことはなかった。女のことで故郷を追われた者として、いまをときめく兄に会う気になれなかったのであろうか。、 英世、父佐代助、清三、そしてシカと、ことあるごとに、野口家では小林栄の世話になり、それだけに小林の発言力は大きかった。 これら次々と続く実家の苦境を、英世は知らなかったわけではない。シカは仮名まじりの文を辛うじて書けるだけで、自分から英世に手紙を出すことはできなかったが、かわって小林が逐一報告していた。家がぼろぼろで、外から丸見えであることも、父が飲み歩き、不義理を重ねていることも知っていた。月々十円も送れば、ずいぶん楽になることも承知である。 だが英世がアメリカにいたあいだ、家に送ったのは百円にも満たない。送るとは書きながら、現実にはほとんど送らなかった。 月給百八十ドルもとっている身分で、月々ニ、三十円の金を送るくらい簡単なはずだが、例の浪費癖が英世を苦しめていた。それに金を送っても、どうせ父の酒代になるといういいわけもあった。 そのかわり英世はアメリカからシカに高価な産科用器具を送った。器具は難産のとき嬰児をとり出すための最新のもので、いったん血脇守之助に送り、そこから小林栄に転送され、シカに届けられた。父や姉弟には冷淡でも母のシカにだけは尽す。その英世の気持だけは終生変わることはなかった。 だが折角の器械も医師用で産婆の使用は許されず、家に飾っておくだけであった。しかしのちに、会津の産科医が懇望して譲り渡したので、見かえりに金をえて、多少の助けにはなった。 4 ロックフェラー医学研究所が正式に完成したのは一九〇六年三月である。英世が一九〇四年十月に着任してから一年半あとである。建物は茶褐色で煉瓦状に積み上げたもので、イースト川に面した高台に、ひときわ目立っていた。英世はこの二階の東南の一室を与えられたが、そこの正面からはブラックウェル島から大西洋まで望まれた。 フレキスナー所長の室も、英世と同じ階にあった。 この完成と前後して、英世はアパートをレキシントン・アベニューから東六十五番街に変えた。今度の家賃は、一週五ドルと安いうえに、研究所にも近い。いまでいう5DKで、そのなかの一室を研究専用につかえる部屋にした。ここには奥村がきて、さらに宮崎も出入りした。 一度、奥村は英世に連れられてニューヨークの下町を飲み歩いたが、一晩に十八軒もの店を連れていかれて驚いた。しかも新しい店に行くたびに、英世はビールを飲み、ニドルくらいずつチップを払っていく、奥村があきれて勘定してみると、一晩で三十八ドルも使っていた。 新しいアパートに移ったのは、自炊をして倹約しようという目的でもあったが、これでは意味がない。 「少し、気をつけたら」奥村が忠告すると、英世は「心配するな」と逆に奥村の肩を叩く。 「人間は飲むときには、愉快に楽しく飲まなければいかん」 たしかに英世の飲み方は豪快だし、行く先々の店でも、みな英世をよく知っていた。酔うと陽気になり、多額のチップをおくせいか好かれてもいた。だが翌日となると、前夜の浪費に気がつき、しょんぼりしている。 「東京にいるときと少しも変っていない」奥村は溜息をつくが、この浪費癖は佐代助のアル中と同様もはや治しようもなかった。 この年の暮、奥村が日本へ帰ると入れ替りに、宮原が同居しはじめた。もっとも英世は帰ってこない日が多かったので、実質的には宮原のアパートのようになってしまった。 たまに英世が帰ってきても奥の部屋に入りこんで原稿ばかりを書いている。炊事をする気など初めからなく、いつも宮原がつくる破目になる。 だが食事のときや、仕事に疲れたときなど、英世は宮原のところにきて例の自分だけいいたいことを一方的に喋った。気が合っただけに宮原には研究所で面白くなかったことや、女のことまで隠さず話した。 珍しく、英世は宮原とだけ金銭の貸借関係がなかった。英世が借りたいと思っても、もともと宮原は金を持っていないし、彼も英世と同じく持っているとすぐ費ってしまう性格である。うっかりすると、逆に英世のほうが借りられる怖れさえある。 金の貸し借りがないことが、二人の気持をかえってすっきりさせていたともいえる。 二人はよく女を買いにもいった。宮原もそちらのほうは旺盛だったが、一度英世は女性と泊ったホテルで手帳を落した。服を脱ぐときにポケットから落ちたのか、なかには手帳とともに、自分の名刺も入っている。 「俺の名前がばれたりしなかな」 女を買いにいくときの元気さからは想像もできない悄気ようである。 「そんなもの、女か掃除婦が見つけたって捨てるだけですよ」 宮原がいっても、「いかんいかん」と頭を抱え込む。 英世はとてつもなく無頓着なようで、自分の噂話とか醜聞に対して極端に神経質なところがあった。絶えず他人がどう見ているかということを気にする。やることは大胆なのに、一旦、気にしだすと信じられないほど小心になる。 かつて北里研究所や検疫所時代に人の噂にさんざん苦労させられた、その苦渋があとを引いているともいえるが、同時に独特のナルシスティックな性格が他人の眼を必要以上に意識させていたともいえる。 反面、小心ということは細心ということにもつながり、この資質は科学者としては必ずしもマイナスではなかった。なにごとにも注意深く対処する性格は、実験に関しては有効な武器でもあったが、手帳を失ったことより、名刺をなくしたことを気にするところが、英世の英世らしいところでもあった。この手帳入れは結局出てこなかったし、もちろんそれでとくに不祥事もおきなかった。 この年が明けた三月、宮原はニューヨークでの留学を終えて帰国することになったが、発つとき英世は羨ましそうにいった。 「お前は運のいい男だ。いつまでも外国に留まらず、日本に帰ることができる。帰ったら開業という目的もある。だが俺は帰るわけにいかん。この指の曲った手では日本に帰っても開業するわけにいかないし、飛び出してきた以上、順天堂へも北里研究所へも戻れない。細菌学をやる以上、俺は一生ここにいなければならない。日本へはもう帰れないのかもしれない」 「そんなことはないさ、日本だっていつか受け入れてくれるよ」 「そのことは俺はもうあきらめている。とにかく、ここで頑張って努力する、もし成功しなければ自殺するだけだ」 外国でいかに栄光を得ても、帝大万能の日本では、開業試験あがりの英世が受け入れられる余地はない。どう日本を恋しても日本に戻りきれない自分を、英世ははっきり自覚していた。 「自殺なんて、怖ろしいことをいうなよ」 「でも、俺は白人達に東洋人の力を見せてやるんだ。頑張れば俺達だってこれだけできる。お前らに負けはしない。それをはっきり教えてやる」 「頼むよ、お前ならきっとそれができる」 最後の夜、二人は徹夜して語り合った。
宮原が去ったあと、英世は戻らず、空家同然になっていたアパートに、一人の日本人がころがりこんできた。歯科技工師で技工学習のため留学していた荒木紀男である。荒木は歯科医学院へ通学中、守之助の家に寝泊まりしたことから、英世の噂をきいていただけに、初対面ではあっても、他人のように思えない。だが英世のほうは荒木を見て戸惑った。荒木はまだ二十そこそこの眉目秀麗な男だった。 大体、英世はハンサムな男は好きではない。自分の不具で小柄というコンプレックスが増幅されるからだが、荒木は初めから英世を崇拝していた。高山歯科医学院では、英世の評価は天才と狂人と、両極端にわかれていたが、荒木は天才と思いこんでいるほうの男である。当然のように、英世を「先生」と丁重に呼ぶ、英世はたちまちこのハンサムだが自分を尊敬しているらしい男が気に入った。 「君さえよければ、ここに住みたまえ」 どうせ部屋はあまっているのだし、炊事もやってくれそうだ。荒木のほうは、尊敬する英世の側にいられるのだから、異存はない。 だがこの同居は金銭的には荒木の一方的な損になった。というのも、英世は例によって荒木から金を借り続け、荒木は家庭が比較的裕福ですぐ送ってもらえたからである。 「君、十ドルもっていないかね」英世にいわれると、つい出してしまう。「ちょっと借りる」とはいうが、それきり返してくれない。それが積もり積もって半年も経つと五百ドルをこした。 「先生の金銭への感覚は変っています。困っているときは一銭の金にさえ神経質になるのに、あるときはあきれるほど大雑把につかいます。結局、先生は手許に持っているのが不安のようです」 荒木は英世の性格を的確に見抜いて、東京の友人への手紙に、そんなふうに書いている。 だが、荒木は英世に貸した金をふみ倒されるのを怖れていたわけではなかった。むしろ尊敬する先生の役に立つのなら、それでいいと割り切っていた。実際、荒木は金で買う以上の助言と教育を、英世から受けていた。彼から得たものはとても買えないと思う。たとえば新しい研究をはじめるとき、英世はその研究について発表されている人の文献を読み返し、それからその実験を一つずつやってから、研究方針の第一案、第二案、第三案と定め、それから仕事にとりかかる。英世のテーマのとり上げ方の巧みさは、この基本研究のたしかさに原因があった。 一度、荒木がロックフェラー研究所へ遊びに行ってみると、英世が試験管を洗っていた。 「そんなことは小使いにやらせたらいいじゃありませんか」荒木がいうと、英世は怒った顔で、 「たしかに小使いにいえばやってくれる。だがもし彼にやらせて滅菌が不完全で失敗でもしたらどうする。試験管に雑菌が入って折角の仕事が無駄になる。自分で滅菌してやれば自分の仕事に自信がもてる。俺は自分で試験管を洗わないような男の仕事は信じない。手間がかかって時間の浪費のようだが、自分でやるほうが正確で間違いがないんだ」こうした骨身惜しまぬ態度は生涯変らなかった。 またスピロヘ-ターの研究に入ったころ、英世は研究所だけでは足りず、アパートに帰ってきても、ほとんど眠らず仕事を続けていた。ある夜、荒木が深夜起きてみると、研究室のほうで、臼でもひくような音がする。不審に思って覗いてみると、英世がワイシャツをたくし上げ、煙草をくわえたまま乳鉢を摩っている。 「なにをしているのですか」荒木が起き出して尋ねると、英世は振り返りもせず、 「猿に梅毒スピロヘ-ターを植え、その脳をとり、菌の分布を調べるために磨りつぶしているのだ」 「それなら僕がします。乳鉢磨るくらいなら日本でも何度かやってますから」 「折角だが断わる。君を疑うわけではないが、俺は自分のやった仕事しか信用できないんだ」 自分の手でやり、自分の目でたしかめたものしか信じない。その依怙地なまでの完全主義は、英世の仕事の評価を高くし、ノグチがやったことなら間違いない、という神話さえ生むに至った。だが、そのあまりの自己中心的な仕事のすすめ方が、英世から共同研究者を奪い、孤独で唯我独尊的な仕事に走らせる結果ともなった。 それはともかく、当時、ロックフェラー研究所の首席助手でありながら、これほど自らの体を酷使して仕事をする研究者はいなかった。 「ノグチは一体いつ眠るのか」誰もが驚嘆し、感心するとおり、これほど徹底して、自分一人ですべてをやっていたら、眠る間がなくなるのは当然であった。 「先生はよく体が続きますね」呆れる荒木に、英世は怒ったように、 「人間というのは、四十までになんとかしなければ駄目だ。創造力も体力も若いうちのほうが秀れている。一応の仕事をする人は、みな四十までにある程度のところまではやっている。俺はいま三十一だが、四十まであと九年しかない。時間なぞはすぐ経ってしまう。俺達が話しているいまの時間も、世界のどこかで誰かが新しい研究をして発表しているかもしれない。休んでいるとすぐ追い抜かれてしまう。それを思ったら眠ってなどいられない。ぼんやりなにも考えず、手足を動かさず寝ているなんてもったいないことだ」 荒木が英世と一緒に暮らした三年間、英世は寝巻というものをつかわなかった。本を読み、実験をして疲れたら、靴を履いたままベッドに横になる。横になった途端もう眠っている。そしてニ、三時間で眼が覚めると、そのまま顔も洗わず研究室の机に向かう。下着などに文句をいいながら替える。そして新しいものを着るとまた三日も四日も替えない。 すべて研究優先の生活ではあったが、といって英世がまわりの者に不親切だったわけではない。気の合う相手にはよく尽し、よく教えた、ただし多少押しつけがましいところもあったが、そこには英世、一流の哲学でもあった。たとえばニューヨークにきて一年ほど経ったころ、荒木は英世に論文を書くようにすすめられた。 「折角アメリカまで来て、人のやっていることばかり見て感心していても仕方がない。君も歯科をやりだして十年以上経ったのだから、そろそろ君独自の考え方もあるだろう。それを論文にして発表してみてはどうだ。この国では大学を出て知識がある、といっても誰も認めてくれない。自分からこれだけあると、はっきり文章に表して見せなければ駄目だ。黙っているのは無いと同じで、仲間からおいていかれるのだ」 はっぱをかけられて、荒木はおそるおそる考えていたことをいってみた。英世はうなずくと、 「初めは大きなテーマでなく、小さくて手っとり早いのでいいから、まず手をつけることだ。デンタルコスモス社の編集責任者のエドワード・シー・カークは俺の友人だから紹介してやる。 カークは当時、ペンシルバニア大学の歯科部長であった。 「ご紹介していただくのは有難いですが、ご承知のとおり、僕はまで英語力が弱くて、うまく書き表すことができません」荒木が辞退すると、英世は即座に立上り、 「そんな引っ込み思案でどうする、書けないのなら、俺が書いてやるからいってみろ」と、ペンと紙をとってきた。 やるとなると一刻も猶予をおかないのが、英世のやり方である。仕方なく荒木も自分のノートを持ってきて、論文の内容を喋り出した。細菌学とはぜんぜん違う分野の話を、英世は葉巻をくわえながらメモしていく。三十分ほどで、荒木が話し終えると、英世はすぐセクションペーパを持ってきて机に向かった。 「よし、いま書いてやるから待っていろ」 そういうとメモを見ながら一気に書き出す。一時間ほどで、たちまち八ページほどの論文を書き上げると、一旦読みなおして荒木に渡した。 「これでよい、出してこい」 「いまからですか?」時計を見ると、午前二時を過ぎている。 「もう遅いから、明日の朝起きたらすぐ行ってきます」 「駄目だ、いま行くのだ。中央郵便局なら夜中でも開いている。今夜のうちに送っておけば、明日ゆっくり眠れるだろう。それに今夜出すのと、明日出すのと、半日の違いで、同じ論文が先に届いたほうが、落とされないかもしれない。実験や論文は早い者が勝つのだ」 英世にいわれて、荒木は夜の街に出た。そのときのカーク宛の紹介状には、次のように書かれていた。 「この論文は特別秀れたものではないと思います。しかしこれを書いた者は日本から来た前途のある若者で、わたしのところで面倒を見ています。もし本文を掲載していただければ、本人は向上の心に燃え、さらに秀れた論文を書くものと信じます。よろしく御一読の上、ご検討下さい」 その夜、荒木は郵便局へ行って戻ってくると、英世は再び乳鉢で猿の脳を磨りつぶしていた。 5 ロックフェラー研究所に移って二年半経った一九〇七年(明治四十年)六月、英世はペンシルバニア大学から「マスター・オブ・サイエンス」の称号を受けた。もっとも学位といっても、名誉学位で、正式の論文審査があったわけではない。ペンシルバニア大学での英世の献身的な努力に報いるため、フレキスナーの推薦によって具体化したものである。この授与式のときの推薦状で、当時の日本と、英世の評価をある程度しることができる。 「本日、われわれはヒデヨ・ノグチ氏に出席を願っております。 周知のように現在、日本は強国に成長し、東洋から外に向かって揺るぎなき歩みを続けております。額に王をいただき、かぎりない勇気あふれる精神力が、まぶしいほどの光彩を放っております。鎖国をとおして長かった沈黙の時期を経て、日本はいま将来を見通し、確固たる地歩を築きあげているのです。 日本の覚醒は世界の歴史における驚異の一つであります。半世紀というきわめて短期間のあいだに、イギリスがヨーロッパ大陸にそって伸展したように、隣接する海岸線にそって伸びる、海に囲まれた島々から成る日本は、平和の技術においても、戦争の技術においても、アジア大陸において絶対の優位を保っていることは明らかです。かくの如き覚醒と進歩は、英雄的な過去をもち、常に自らの内部に偉業を成しうる可能性を秘めてきた民族によって、はじめて成しえたものといえましょう。 日本は一方ではその固有の文明のなかに存する最大のものを維持しつつ、他方では西洋文明から国民が是しと判断し、吸収しうると考えられるものは、すべて精力的にとり入れています。日本国民は固有の英知とともに、アングロ・サクソン民族のもつ勇気と野心も兼ね備えています。これら二つの男性的民族は、さまざまな領域において人類の運命に大いなる影響をもつにいたる社会的、政治的な力を代表するものであります。、 もちろん二つの民族が完璧な協調関係に入るには、まだ多くの時間が必要とされましょう。しかし二つの民族が知的接触をしたことによって、本日われわれは若き秀れたゲストを招待することができたわけで、まことに喜ばしいかぎりであります。 ヒデヨ・ノグチ氏は、一八九七年、東京の医学校を卒業され、一九〇一年ペンシルバニア大学に来られるや、ただちに一般病理学の研究にとり組まれました。その後同大学医学部の教授連にくわわれましたが、一九〇四年、さらに幅広い研究活動のため同大学を退職されました。 氏は氏の生国の人々のもつ熱烈な進取高揚の精神を代表する一人であります。氏は一国から他国へと伝達される科学的知識は、すべて両国の富の一部になるものであることを充分認識され、愛国的精神と人類愛的精神をもって科学の分野でライフワークをおしすすめられています。 われわれは氏によって寛大な性格と、洗練された礼儀作法、明敏な知性、倦むことを知らぬ精神力、揺るぎなき目的意識をもって研究にとり組む重大さを教えられました。 ここに氏の発表された『ヘビの毒性の生物的成分に関する論文』および医学に対するいくつかの寄与に対して、当大学理学修士号が授与されることを、われわれ評議員一同切に望むものであります」
公式の推薦状だけに、かなり儀礼的な表現が多いが、それでも当時の日本および英世のアメリカにおける評価を知ることはできる。このなかで、英世の経歴として、東京の医学校を出たことになっているが、これは誤りで、いうまでもなく、正式な医学校を出ていない。だが英世がペンシルバニア大学、ロックフェラー研究所に出した履歴書にはすべて、「一八九七年東京医学校卒」となっている。 してみると英世は、どこの医学校を出たことにしているのか、自ら記した年賦の一八九七年というのは、済生学舎に入学した年で、この年の十月に医術開業試験に合格している。済生学舎は医術開業試験を受験する者達への、いまでいう予備校みたいなもので、正規の学校ではないし、入学はあっても卒業がなかった塾である。学生達は、医術開業試験に合格すれば自然にやめてしまうのだが、英世は卒業と見なし、済生学舎というのではわかりにくいとして、東京医学校としたのでもあろうか。この種の経歴の改竄はまだ他にもあり、一八九七年より九八年まで、東京総合病院助手となっているが、この期間は順天堂医院にいた時期に相当する。ここにも順天堂というのでは外国人にわかりにくいとして、東京総合病院としたのであろう。 一八九九年、横浜検疫所検疫官となっているが、それも正確には検疫官補である。一八九八年より一八九九年、東京歯科大学で病理解剖学講師とあるが、当時は東京歯科医学院で、大学ではなかった。これらの事実を、当の英世が知らないわけはない。知っていていてあえてこのような学歴を書いたことは明らかである。いかにアメリカが実力だけの世界とはいえ、この程度の学歴は書かざるをえなかったのであろうが、ここに、英世の学歴コンプレックスをみることができる。 この学位授与とともに、英世はロックフェラー研究所の「アソシエート」になり、一年後にはさらに「アソシエート・メンバー」に昇格した。このあと研究所の最高スタッフである「インステチュート・メンバー」まで一階級を残すだけである。フレキスナー所長の推薦があったとはいえ、白人社会のなかで、東洋人としてはまさに異例の昇進である。 名誉学位をえたとき、英世は血脇守之助に喜びをつたえたあと、次のように書いている。 「科学の世界は、なにかを得ようと夢みているときが花で、実際手にしてみると、その喜びは意外に薄いものです。それどころか、一つの目的が達せられると、さらにもう一つと新たな希望が生まれ、さらに自分を苦しめる結果になります。しかし私はくじけません。これから先は日本の学位をとりたいと思っています」 このあと、日本の博士号をとった数人の医学者の名前を列記したあと、 「私が日本の科学にどのような功績を残したか、それはわかりませんが、欧米においては、このなかの北里、志賀を除いて、私より有名な者はおりません。日本で学位をとった者は無数にいても、それらの名を知っている人は、ほとんどいません。欧米で通用しない学位など笑止のいたりです」 まさに英世がいうとおり、日本の博士は欧米では通用しなかった。とくにアメリカでは、こうした肩書より、どんな仕事をしてきたか、それだけが問題であった。だがそのお笑いにすぎない学位を、英世は欲しいと思う。その理由として、「日本のことしか知らない母を喜ばすために」というのが、その言葉の裏に、英世自身の学位への憧れがあった。 欧米でいかに評価されようと、日本で評価されるのでなければ意味がない。そうでなければかつて自分を冷遇した連中を見返したことにならない。アメリカと同時に、日本の学界にも君臨するのが英世の望みであった。 一九〇三年、ドイツのメチニコフとルーははじめて猿に梅毒をうつし、その二年後、シャウデインは梅毒病原菌としてのスピロへーターを発見し、翌一九〇六年、ワッセルマンが梅毒診断に有効なワッセルマン試験を開発した。それらは医学界のみでなく、当時の新聞、雑誌に発表され、大きな社会的反響を呼んだ。 十九世紀後半から二十世紀にかけて梅毒は世界中に拡がり、「亡国病」と呼ばれていた。コロンブスのアメリカ大陸発見以来、梅毒はまたたく間に全世界に拡がり、上は一国の宰相から下は一労働者まで、梅毒に冒され、悩む者が多かった。スラム街には梅毒で鼻が欠け、皮膚に発疹ができ、脊髄から脳に拡がって麻痺をおこし、痴呆になった男女がたむろしていた。梅毒の治療は全世界の人々が、ひとしく望んでいた夢であった。その第一のとっかかりができたのである。このころから英世はこの研究にとりくむ。 もっとも、英世は以前から梅毒の研究には食指が動いていた。これまでやってきた蛇毒の研究は、それなりに価値のあるものではあったが、なんといっても社会的影響が少ない。南米や東南アジアでは、いまだにかなりの人が蛇毒で命を落としてはいるが、被害は熱帯の地域にかぎられている。しかもその多くは後進国で白人社会とはあまり関係がない。それからみると、梅毒は先進国、後進国の別なく、全世界に拡がっている。梅毒研究発表の一つ一つが、先進国の注目を浴びる。研究に華やかなものと地味なものがあるとすると、梅毒はまさに前者の筆頭で、現代の癌に匹敵する大物であった。いや見方によってはいまの癌以上に一般の人々の関心があったともいえる。 自己顕示欲が強く、常にセンセーショナルなテーマへ目を向けていた英世が、この研究に興味をもたないわけはなかった。しかも好都合なことに、ワッセルマン試験は、梅毒患者の血液をもちいる血清反応で、英世がこれまでやっtきた蛇毒の血清反応と同じである。 だが英世はワッセルマン試験には改善の余地があると見ていた。 たしかに当時のワッセルマン試験は、梅毒患者に陽性にはでるが、その他の患者にもかなりの頻度で陽性に出る。しかも方法が煩雑で時間もかかる。より正確に、より鋭敏に、より簡単に、それがワッセルマン試験を追試した学者達の共通の願いであった。このなかで血清学を研究してきた英世は至近距離にいる学者の一人であるといえた。 いまがチャンスとみた英世は、全力を挙げてこの研究に取り組む。 「ようやく、人間を相手とする仕事にとりかかりました」守之助への手紙で、梅毒研究に着手した喜びをこう述べている。 いままでの蛇毒の研究は、押しかけ助手という弱い立場でフレキスナーから一方的に与えられたテーマであった。全力を尽して頑張りはしたが、やはり蛇ではなく、人間から血をとり、標本をつくりたかった。いつまでも続く蛇相手の仕事から抜け出したいと願っていた。そのチャンスがきたのである。このときから、英世の研究への熱意は、異様をとおりこして狂人に近くなる。 このころアパートに同居していた荒木は、英世を「二十四時間人」と呼んでいた。一日二十四時間中、ほとんど起きて研究している。たまに眠ると、机の上にうっ伏したままか、椅子に凭れて仰向けになるだけで、一時間もすると、もう起きて仕事をはじめている。 「そんなに無理をしては、体に毒です」見かねて荒木が注意すると英世は笑って、 「人間は大丈夫だと思えば大丈夫なものだ。人は心意気で生きるものだ。なにくそ、という気持があればなんでもできる」 「でも、先生のやり方はあまりに無茶です」 「心配するな。俺は本当は少しも眠くなんかないんだ。何日徹夜しても平気だ。でも明日の仕事のためには、いま寝たほうが得だ、そう思ったときだけ寝ている。これでもちゃんと考えているんだ」 考えているかどうか、若い荒木にも到底真似はできない。 「失礼ですが、そんなに急いで仕事をなされなくても、一つの発見というのは、毎日着実にやっていれば、やがてはもたらせるものではないでしょうか」 「君のようなことをいっていては、いつまでも皆と同じところにとどまることになる。少しでも他人から抜け出そうと思ったら、他の人の倍以上の努力をしなければ駄目だ。二歩も三歩も出ようとしたら、その何倍も努力しなければならない。いまこうして君と話しているあいだも、世界のどこかで誰かが顕微鏡を覗いて狙っている。ほら、きこえるだろう、彼等の迫ってくる跫音が」 突然、英世は首をつき出し、壁のあたりを嗅ぎつけるような仕草をする。まるで幻聴でもきいているようで、荒木は薄気味悪くなって黙りこんでしまう。 一九〇七年から八年、そして九年と、英世は矢継早に論文を発表する。 「梅毒の血清診断についての批判的考察」「いわゆる梅毒性抗生物の運命」「ワッセルマン試験とプロテイン・リポイズ及び塩類の関係」「梅毒血清診断の自然かつ簡単な方式について」などが代表的なものである。 「これは金になる研究だ」英世は荒木に得意気にいったが、たしかに梅毒の研究はスポンサーがつきやすかった。梅毒を治すための研究というと財団、企業、個人、などで援助を出すところが多い。金持も貧乏人も、ひとしく悩んでいる病気だから当然といえば当然ともいえた。 「金なんか、もらう気になればふんだんにある」英世は豪語したがそれは満更嘘ではなかった。こと研究費に関しては不自由することはない。 しかも英世が新しい論文を発表する度に、新聞が書きたてる。そろそろタネがないとなると、記者達は英世のところにきて、新しい発見はないかときく。英世は待っていたように論文を見せる。そこで研究内容を素人にわかりやすく、世間受けするように多少脚色していい、それを新聞はまた書きたてる。 煽られて次々と地方の研究者が英世のところに見学に訪れる。学者だけでなく医学には素人の人もやってくる。眠る暇も惜しんでいながら、英世はこういう来訪者には時間をさき、懇切に説明した。ときには、相手が素人であることを忘れて、理解が悪いと怒りだしたりする。 梅毒の研究者として、「ドクター・ノグチ」の名は学者間だけでなく、一般の人達にも有名になってきた。 この一連の仕事のなかで、英世の研究業績として特に評価の高いものが二つあった。 一つは、それまでワッセルマン試験に用いていた羊の血球を、人間の血球に変え、それによる試験法を考案したことである。この方法のほうが従来のより合理的で、鋭敏であるといわれていた。 もう一つはワッセルマン試験を調べるうちに思いついたものだが、梅毒は皮膚や四肢とともに脳や脊髄も冒す、この冒された梅毒患者の脳脊髄液を調べると蛋白成分が異常に増加している。この事実を見出し、その増加を見分ける方法をつくり出した。これは「野口酪酸反応」と名づけられて発表された。 例によって、英世はたたちに守之助へ手紙でしらせる。 「昨年は脊骸癆(当時は梅毒患者の一部がなるところから、梅毒との関連が疑われただけで同じ梅毒の一亜型という確証はなかった)を診断する方法を発見しましたが、昨年の冬から今年の初めにかけ、第二の診断法を発見し、アメリカ、ドイツ、イタリア、南アフリカなどから賞賛の声しきりです。とくにパスツール研究所長は小生の論文を翻訳し、早速フランス医学界へ紹介してくれました。現在、小生の方法を勉強のため、各大学、病院などから派遣されてくる学者は毎日三から四名を数え、問い合わせの手紙は十通をこします。なお先週は州立精神病院に招かれ、一時間ほど講演してまいりました。これら関連論文四通お送りします。何卒御笑覧下されたく、御覧済みの上は文部省へ御転送願います」 これらの四つの論文は、のちに英世の日本での学位申請のさい、主論文になったもので、「蛇毒の血球に及ぼす保護作用についての研究(英文)「化学的作用により補体が非動性となり又は再生することについて(仏文)」「蛇のヘモーリゼ・パクテテリオリーゼ及び毒性との関係について(英文、フレキスナーと共著)」「蛇毒及び蛇血清の構造(英文、フレキスナーと共著)」の四つである。 論文を守之助に送りながら、英世の本当の目的は、文部省に転送してもらうことであった。 あくまで、自分から好んで文部省に論文を提出するののなく、他人が偶然まわしたという形で、学位審査の対象にしてもらう。ここに英世の日本の学会に対する屈折した心理が読みとれる。 この論文のなかにフレキスナーと共著のものが二つ入っている。このことについて、英世は荒木に、「ボスに引き立ててもらい、可愛がってもらおうと思えば、いろいろ我慢しなければならないこともある。俺の論文など、すべて自分一人でやったものだけど、フレキスナー博士から、自分の名前もいれろ、といわれたら断わるわけにいかなかった。しかし一度いれたら、彼のほうが上席だから、彼の論文のような感じになってしまう。俺の論文にはそういうものだけで三篇もある。まったく口惜しい話だが、こういうことはやはり我慢しなければならない。そういうことの積み重ねで、フレキスナー博士の信頼をかち得たというわけだよ」 このあたりは、日本の学界の内情にも似ている。英世の論文は百篇に及ぶ論文の、わずか三篇であり、蛇毒に関する仕事がフレキスナー博士の継続研究であったことを思えば、被害は少ないともいえる。 このころ、英世は狂ったように論文を書きまくった。玉石混淆で、あるものは単なる実験データーの羅列にすぎないものや、顕微鏡所見の紹介にすぎないものがあったが、英世は初めて見て、知ったことはすべてペーパーにした。 「なにごとも発表しなければ、相手にわかってもられない。自分だけが知っていて黙っていることは、なにも知らないのと同じことだ」 英世はいつも荒木にいっていたが、この考え方はヨーロッパ以上にアメリカでは徹底していた。建国後日の浅いアメリカは、人間の評価のすべてがいかに自己表現をしたかにかにかかっていた。その男がどこの生れで、どこの育ちであろうと、そんなことは関係ない。生れや血筋よりいまなにをして、どれだけの知識をもっているか、それを表現しないことにわからない。研究の内容を発表し、一般の人にまで理解してもらうことで、新しい研究費をもらい、ポストが保証される。雄弁が金で、沈黙は石ほどの価値もない。こういう開かれた風土に、英世の自己顕示欲が加わって倍加された。 一九〇九年と一〇年と、たて続けに、英世は蛇毒に関する本を出版した。とくに初めの「蛇毒及び蛇毒論」に対しては、カーネギー研究所から出版費五千八百ドルの援助があり、刊行に当っては慰労金として、さらに五百ドルが贈られた。二冊目のほうは、梅毒の血清診断法について述べたもので、前者が血清学の基礎事項を主に扱っているものからみると、応用篇にあたる。 この本の第一稿を、英世は二週間で書きあげた。「一晩に一章のペースで書きあげる」と豪語したとおりのペースであった。この本では細菌や器具の図解まで、すべて英世自身で描いたが、それがまたなかなか上手であった。 原稿は一旦書き上げたあと、同僚のルイス博士に廻され、そこで書きなおされてからカリスキー博士へ廻され、それで町医者の英語になおしてから英世に返された。アメリカで出版するとなると、英世の日本的英語では、いささか不安があったのである。だが英世は直されてきた原稿の一部を再び改め、自分一人で書いた論文であることを強調するため、日本流の英語の部分を意識的に残したりした。 「私の意図をよりよく伝えるため、ニ、三か所書き改めました。そのため、文章は円滑流暢でなくなったかもしれませんが、よろしく校正のほど、お願いいたします」校正者にこんな手紙」を出しているが、ここにも英世の自己表現の逞しさが現われている。 これだけ研究に熱中していても、英世の生活の窮乏は相変らずだった。生来の、金銭への計画性のなさが一向に改まらない。 このころ、同居していた荒木が恐れていたことが二つあったが、その一つは英世に研究のための血を採られることだった。梅毒の研究のため、患者の血と対照するために健康な人の血が必要になる。これに荒木の血を提供せよと迫るのである。 「おい、また一〇〇cc頼むよ」 英世はごく気軽なので血が欲しいとなると、見境がつかなくなる。ときには、荒木は三日続けて一〇〇ccずつ採られ、炊事の準備もできないほどふらふらになったこともある。「荒木君」と呼ばれただけで、吸血鬼に声をかけられたような気持になる。 恐怖のもう一つは、いうまでもなく借金強要である。 相変わらず、英世は金づかいが荒く、なくなるとテーブルの上に紙片を置いていく。 「本日五弗入用」「十弗必要」と、墨字の達筆で書いていく。 その字を見ると荒木は寿命が縮まる。このころ荒木は日本からの仕送りもあるし、歯科の陶材で、ある程度の金儲けもできるが毎度ではやりきれない。すでにはっきり記帳しているだけでも七百ドルに達している。黙っておくと、これから先、どれだけとられるか知れない。荒木は決心して、夜、英世が仕事の手を休めた機会をみていってみた。 「わたしはこれまで、先生のご要望にそって、できるだけのお金を工面して参りました。しかしこれ以上続けては、わたしは破産します。先生のお体にもよくありません。精神的にも気まずいことになろうかと思いますので、この次からははっきりお断わりしますからご了承下さい」 英世は一瞬怪訝そうな顔をしたが、すぐうなずいて、 「いや、わかった。君のいうことはよくわかったから今日だけ頼む」 それでは、今回だけということにいたしますが、もう一つ、申しにくのですが、いままでにお貸したお金を、月々いくらずつでも結構ですから、お返し願いたいのですが」 「なるほど……」 「返して欲しいというのなら返さないわけではない。しかし君も知っているとおり、金が一旦、僕の懐に入ってしまうと、もう駄目だ。金のほうが勝手に出て行ってしまう。君がそれほど返して欲しいなら、僕の給料日に研究所にとりにきて、先に必要なだけとってゆきたまえ」 「それでは申し訳ありませんが、そのようにやらせていただきます」 荒木はいわれたとおり、翌月から給料日ごとに借金の先取りをした。だが英世はいくらとられたか調べもせず、残った金を無造作にポケットにおし込むだけだった。 6 このころ、梅毒の病原菌は半ば発見され、半ば未確認という状態であった。一九〇五年、ドイツのシャウデインとㇹフマンにより、梅毒スピロヘ-ターが発見され、この微生物は梅毒患者の病巣に存在することが、他の学者にも確認されていた。だが、病原菌としての最終的な決定には、それを他の動物なり人間に移して、同じ病気が発病するという確認が必要であった。ただ病巣のまわりに同じような微生物が発見されるというだけでは、病気に付随するなかにはなにかの都合でまぎれこんだものかもしれない。 ところで、この同定(細菌を確定すること)には、まず病原菌と思われるものだけをとり出し、増殖させ、これを動物なり人体へ植えつけていく手順が必要になる。いわゆる細菌の純粋培養である。 これまで発見された肺炎菌とか赤痢菌といったものは、いずれも寒天に肉汁や血清などを含めた培地に移植するだけで、増殖していった。この方法で純粋に培養することが可能であった。だが、梅毒スピロヘ-ターについては、そういう単純な方では成功しない。いろいろな学者が挑んだが、この微生物だけは純粋培養がうまくいかない。 スピロヘ-ターというのは「螺旋状球菌」という意味で、そのなかにさまざまな種類がある。シャウデイン等が発見したのは、そのなかのトリポネーマに属するもので、長さ六ないし一五ミクロン、十から十二の屈局部を持ち、正しくはトリポネーマ・パリドウムというものである。これまで各学者が培養を試み、実際、成功したという報告もあったが、顕微鏡で詳しく調べるとスピロヘ-ターではあるが、別種のもので、正確にはトリポネーマ・パリドウムではない。なかには、動物に移植して梅毒を発病させえたという報告もあったが、さまざまな不純物がまじったものであったりした。こんなことから、一部では、シャウデインのいう梅毒スピロヘ-ターが、はたして梅毒の病原菌であるのか、疑うものさえでてきた。 英世が挑んだのは、このスピロヘ-ターの純粋培養に対してである。もちろん、これに成功したら、一躍、世界の花形学者になり、社会的にも名声を博することは間違いない。 しかし実験はそう簡単にはいかない。まず、いかに梅毒スピロヘ-ターを手に入れ、これを純化させていくいかということが問題になる。 当時、梅毒が猖獗をきわめていたところだから、脳病院か慈善病院へ行けば、梅毒患者の血清は簡単に採ることはできた。ここで英世は考えた末、梅毒にかかっている兔を利用することにした。この兔の睾丸にスピロヘ-ターを接種すると、三、四週間で大量の同じスピロヘ-ターが発生する。これをとり、さらに次の兔へと、移し変えていく。 これには理由があって、睾丸には一種の浄化作用があり、何代も移植をくり返していくと、他のスピロヘ-ターや雑菌が消滅して、最終的には純粋の梅毒スピロヘ-ターだけが残されていくい。本来、細菌学者が試験管でやる仕事を、兔の睾丸に課したわけでらる。 第二の、そして最も重大な問題は、こうして最終的にとり出されたスピロヘ-ターを育てていく培養基を、いかにしてつくるかということであった。ここにはもちろん他の雑菌は入ってはならない。純粋に、梅毒スピロヘ-ターだけが生きていける培地が必要になる。もちろん微生物といえども、生きていくためには栄養が必要である。当然、培地にはこの養分を入れなければならない。 英世はさまざまな培地をつくってみた。初めは兔の血漿(血液中から有機成分を取り除いた液状の部分)から、馬の血漿、さらに血清だけを加えたものなどをつくってみる。いっときは成功したように見えて、突然死滅したり、急に他のスピロヘ-ターが増殖したりする。不安定で、なかなか一定しない難しさがあった。あるときは血清に水をくわえて稀釈する。もちろん滅菌水をつかう、だがやはり成功しない。 悩んだ末、英世がドクター・スミスに話すと、彼が、「その血清水に、新鮮な動物組織をくわえてみたらどうか」と提案した。英世はこの案にとびついた。この辺りは研究に没頭してきた者の勘というべきものかもしれない。たしかに新鮮な動物組織は生体から引き離されあとも、しばらく生きていて呼吸する。このときまわりから酸素を吸収する。 培養基をつくるときに起きてくる一つの問題は、そのなかに小量ながら空気が入ることであった。滅菌はともかく、完全真空にはしにくい。ところが、この空気が、とくに酸素があると生きていけないスピロヘ-ターがある。もし新鮮な組織をくわえれば、それが邪魔な酸素を吸いとってくれるのではないか。その生きた組織はスピロヘ-ターの養分にもなるだろう。以上の考えから英世はさまざまな実験を試みた。 まず各筋肉組織から、肝臓まで加えて調べてみる。だが、予想されたとおり、生体の組織には余計な細菌が付着していて、折角の培地を汚染してしまう。ときにはもちこまれた細菌で、培養基のなかが溢れてしまう。さらに肝臓には糖分があり、これが培地内で酸化して、逆にスピロヘ-ターを殺してしまうという結果も生じる。何回もの実験がくり返され、最後に英世は比較的安定した組織として腎臓と睾丸を発見した。これなら汚染も少ないし、スピロヘ-ターに影響も与えない。 こうして英世は培養基の最終的な詰めに入った。彼が用いたのは、細菌学者が通常つかうのよりはるかに長い試験管であった。この五分の四までを血清水で満たし、そこに新鮮な組織を加える。ここで無菌であることをたしかめるために、三日間、恒温器に保存し、細菌の発生しないことを確認してから、兔の睾丸からとった梅毒材料を接種する。 この試験管をパラフィン油紙でおおい、空気が入らないように英世が特別に考案した坩堝に入れ、孵卵器におさめる。この坩堝に入れるところが、いわゆる「ノグチ式」の特殊なところで、他は特に変りはないといわれている。この方法で、数百本の試験管に植えつけ、これを毎日とり出しては、一本ずつ調べる。毎日、新しいものをつくっては、古いものを調べていくのだから、試験管は増えていく一方である。個々の組織片の切り方、血清と水の微妙な比率、密閉の仕方、それらの些細なことで、梅毒スピロヘ-ターが増殖するか、しないかが決定される。これから先は肉眼では推測できないミクロの世界である。何千本試みても、すべてが失敗するかもしれないし、そのうち一本だけ成功するかもしれない。だが、その一本も見逃すわけにはいかない。 一九二〇年の春以降、英世はこの仕事に没頭した。研究室は試験管の山であった。しかも、その一つ一つを、英世は自分の手で洗浄し、培地をつくっては接種する。一人で観察から試験管洗いまでやるのだから、いくら時間があっても足りない。研究室で仮眠し、ふと魘されたように目覚めると、そのまま孵卵器を開いて、試験管を見る。ある一瞬、どこから試験管に、スピロヘ-ターの繁殖がみられないともかぎららない。一瞬のチャンスを逃しては終りである。 「どんなアメリカ人でも、彼のスタミナと精神力には敵わない」フレキスナーが呆れてつぶやいた。 「いかなる西洋人も、ノグチの真似はできない。二十四時間、彼は働きどおしだ。おそらくあの仕事への打ち込みようのなかには、われわれに理解できない、日本独特の哲学があるのだろう」 いま流にいえば「神風研究」というところかもしれない。 全然家に戻ってこない英世を案じて、荒木が研究室に行ってみると、英世はぼさぼさ髪に血走った眼で、葉巻を口から離さない。 「少しは休まなければ、体に毒ですよ」荒木が忠告すると、英世は憤然と、例の甲高い声で、 「人間は体のことを考えるようになったら終りだ。自分をいたわるようになったら、もうエネルギーはなくなったということだ。若いくせに、おまえは老人みたいなことをいう」と、逆に説教をくらう。 まさに、このころの英世は、本人が梅毒で狂ったのではないか、と思われるほどの、研究の狂人であった。だが、ようやくその努力が酬われるときがきて。 「こうして、六種類の培養物を得るために一種類ごとに数えきれないほど失敗を重ね、最後に突如、その発生を見るにいたったわけであります」 のちに発表して論文に英世自身が述べているように、純粋培養の成功は、ある日、突然訪れた。 その日も、期待と不安をもって孵卵器を開くと、そこに螺旋状をした梅毒スピロヘ-ターだけが繁殖しているのが見えた。 「おや……」半信半疑で顕微鏡下でたしかめると、まさしく目的のスピロヘ-ターが動いている。 「やった……」 英世は思わず両手を挙げてとび上がった。そのとき研究室の端にいた助手達は、その日本語がどういう意味かわからなかったが、重大な発見がなされたらしいことだけは理解できた。ただちにフレキスナーに伝え、所員全員に触れて歩いた。顕微鏡を見せる全員が「お目出とう」と握手を求めてくる。 その夜、英世は家に戻ると、荒木を前に、部屋中を踊りくるい、それから荒木を連れて十数軒ほどバーを飲み歩いた。 「大丈夫ですか」荒木は本当に、英世が梅毒で脳を侵されたのではないかと疑った。
"ドクター・ノグチ、梅毒スピロヘ-ターの純粋培養に成功" そのニュースは、たちまちニューヨークからアメリカ各地、そして全世界へ拡がった。 「一九〇五年、ドイツのシャウデインが発見したスピロヘ-ターを、ノグチが完成させた」 ニュースは学界だけでなく、一般新聞の社会面にも、大きく書き立てられた。 豊かな資金量を誇るとはいえ、研究所としてはまだ駆け出しのロックフェラー研究所が、この発見で世界の注目を浴び、もちろん英世自身も、世界の細菌学者のトップグループにのし上った。 「六十五番街に住む細菌学者は、ニューヨークだけでなく、世界に名を知られた科学者だ」人々はそういって、街を行く英世を、「あれがノグチだ」といって振返った。 おかしなもので、この発見で英世の歩き方まで変り、いままでの前屈みでせかせかと歩くのが、少しゆったりと大股になった。ときにはシルクハットをかぶり、杖を持つことも多くなった。 だがこの発見で、梅毒が征服されたわけではなかった。シャイデインにより、梅毒の原因として、梅毒スピロヘ-ターが指摘され、それがノグチによって純粋に培養されるようになった。梅毒をひき起す大凡のメカニズムはわかってきたが、治療はこれからである。 この病気を治すには、まず、純粋培養で得られたスピロヘ-ターを体内で相殺するワクチンをつくり出すことである。英世の発見は、その完成の一過程にすぎない。 余談めくが、梅毒の治療そのものに関しては、この前年、秦佐八郎がドイツのエールリッヒと共同で開発したサルバルサンのほうが、はるかに効果的であった。秦は英世と同時に、北里研究所に入った同期生だが、有力者の口添えがあり、地方とはいえ岡山の医学校の出身であった。英世が早々に北里研究所を出たのに秦はエリート研究生の道を歩き、北里の推挙を受けてエールリッヒ研究所へ留学していた。 サルバルサンは、スピロヘ-ターそのものへの追跡をあきらめ、梅毒という臨床症状の軽快を狙って見出された薬であり、基礎実験より臨床効果を求めた研究であった。効果のありそうな弾をいくつか打って、その一つの当たるのを求める、極端にいうと無手勝流の研究に近い。 だがここにも大変な努力と忍耐が必要であった。「忍耐強い日本人の秦だから出来た」と、エールリッヒも、秦佐八郎の思い出のなかに書いている。 もちろん、英世はサルバルサン発見のことも知っていた。秦そのものに個人的な恨みはなかったが、北里時代から恵まれた研究者として羨望は抱いていた。その男が、エールリッヒと共同で、梅毒の治療薬を開発して脚光を浴びた。英世がそれを意識しないわけはなかった。 ともかく、ヨーロッパで秦が梅毒の治療薬の発見を、翌年、アメリカで英世が梅毒の純粋培養法をと、この数年で医学界における日本人の評価はおおいに高まった。 純粋培養に成功した英世が、このあとすすむ道は、梅毒ワクチンの完成である。 結核菌が発見されたあと、免疫ワクチンとしてツベルクリンが開発されたとように、英世は梅毒にもワクチンを創ることは可能だと考えていた。どの病気に対しても、英世は治療薬よりワクチンのほうを考える。これは臨床医でない、細菌学者の宿命といえる。 「薬などは、いくら発見しても知れている。病気になってから薬をのんでも仕方がないだろう。それよりワクチンで病気にならないように防ぐのが第一だ」英世はこんなこともいっているが、その底に、秦への対抗心がなかったとはいいきれない。 いずれにせよ、一つの病気の病原菌が発見され、その純粋培養ができるようになると、それを基に、その菌を退治するワクチンなり治療法の発見が、次の課題になる。 過去、コレラやペストやチフスなどが、そういう過程を踏んで征服されてきた。いまや、世界で、純粋のスピロヘ-ター・パリドウムをもっているのは純粋培養に成功した英世だけである。英世だけが、好きな分だけ欲しいまま、純粋のスピロヘ-ターを利用することができる。このことはワクチン製造に当って、他の学者より圧倒的に優位を占めたことになる。 英世はこの、自分で培養したスピロヘ-ターから、一つの安定した試作品をつくり、これを「リスチン」と名付けた。これは結核発見に用いられる「ツベルクリン」にならって名付けたもんだが、その働きはほぼ同様である。すなわちツベルクリンは、一種の結核菌の純粋培養されたもので、これを少量、被験者の腕に接種する。健康な人なら、ほとんど反応を示さないが、潜在的に結核にかかっている人では、体内の結核菌と反応し合って、まわりが赤く腫れあがる。これがツベルクリン反応で、ごく最近まで結核患者の早期発見につかわれていた。リスチンもこれとおなじように梅毒患者の早期発見につかえると英世は考えたのである。 早速、健康な兔と梅毒にかかった兔と、両方にリスチンを注射してみると、予想どおり、梅毒の兔のほうに反応が強くでた。それで自信を得た英世は、健康な人と梅毒にかかった人に、それぞれ試みた。この場合、万一リスチンの量が多すぎ、健康な人まで梅毒にかかっては問題である。梅毒にかからない、しかし体内にスピロヘ-ターがある場合は、確実に反応する、必要にして最小量の注射が望ましい。これを試みた結果では、初期と第二期の患者では、はっきり反応がでないが、第三期および遺伝性の梅毒では、明瞭に反応がおきる。まさしく、リスチン中のスピロヘ-ターが、患者の体内のスピロヘ-ターと感作し合ったのである。 英世は得意であった。ついにリスチンのワクチン化の第一歩に成功したのである。この仕事をおしすすめていけば、いまのワクチン反応より、さらに鋭敏な方法が確立するかもしれない。ひいてはそこからワクチンが完成され、人類の長年の夢である梅毒征服も達成されるかもしれない。英世はさらに脚光を浴びる自分の姿を想像して、上機嫌である。 「いまに、世界中すべての人間が、俺を人類の救世主として崇めるかもしれない」 そんなことも荒木に口走った。 だが、いまのリスチンの段階では、まだまだ威張れるものではない。たしかにスピロヘ-ターの純粋培養に成功し、それからつくり出したリスチンで、梅毒患者の反応を引き出すことはできる。しかし現実に、それが反応を示すのは、第三期から先天性梅毒で、初期や第二期のものには効果がない。早期発見という以上は、初期以前の、なにもわからない時点で発見できるものでなければ意味がない。 「他の連中も必死に迫ってくる。さらに急がねばならない」英世は口ぐせのようにつぶやきながら、さらに研究にうち込む。 当時、英世と同じように、スピロヘ-ターの純粋培養を試みた学者はかなりいた。ほとんどが失敗だったが、そのなかでドイツのポアス博士が成功したと報じられことがある。これをきいた英世は早速疑問を提出した。 コペンハーゲンのマドセン所長への手紙のなかで、「ポアス博士はシェレスキーの膠化血清でパドリウムを培養することに成功したと述べているようですが、私もその方法を試みて一度も成功しませんでした。彼だけ首尾よくいった理由がわかりません」と述べたあと、さらに「ポアス博士の培養基には、ある臭いがあるとのことですが、私の培養基には決してそんな悪臭は生じませんでした。私は梅毒スピロヘ-ターとそっくりで、悪臭を発つスピロヘ-ター株数種を手許にもっていますが、ポアス博士が培養したのは、おそらくその種のスピロヘ-ターではないでしょうか」と、疑っている。 たしかにある方法で純粋培養が可能となった以上は、その方法でやるかぎり、誰がやっても成功しなければならない。ポアス博士だけが成功して、他の者ではうまくいかないというのでは困る。英世はポアス博士の方法では、決して純粋培養はできないと信じている。事実、博士の方法は、雑種のスピロヘ-ターが混じっている可能性が強くなり、博士自身もこの方法を撤回せざるをえなくなった。 だが、そういう英世自身の方法も、のちに何人かの学者が試みたが成功せず、果して本当であったのかと疑われるはめになる。皮肉なことに、英世がポアス博士に向けたと同じ批判を、やがて英世が受けることになった。 だが、それはのちのことで、現時点では英世だけが、梅毒スピロヘ-ターの純粋培養に成功したと思われていた。英世はこのリスチンをマドセン所長へ送るとともに手紙で、 「ご返事遅れましたが、遅れた理由は、リスチンをお送りしたいと思い、そのためいろいろ試験をくり返したためであります。いまようやくテストを終えましたが、これだけで五、六百回の試験は可能かと思います」 マドセンがこのリスチンを受けとって、梅毒患者につかってみたか否かはわからない。それにたとえつかって梅毒患者に反応がでたとしても、それが梅毒スピロヘ-ターのみの純粋なものであったか否かも、いまとなっては不明である。 それはともかく、いまや英世は、世界で梅毒スピロヘ-ターを純粋培養しうるテクニックを持った、ただ一人の男になっていた。彼が必要と思えば、その培養法で自由自在にスピロヘ-ターを増やすことができる。 ドクター・ノグチの名は世界に拡まり、欧米各国から問い合わせや、教えを乞う手紙が殺到した。ロックフェラー研究所では、ノグチをいまの首席助手から主任研究員にしようという話が持ち上っていた。 このころから、英世の態度にわずかながら変化が生じ、部屋で研究していたかと思うと、突然いなくなったりする。以前から、ふらりと出かけることはあったが、そういときは大抵、研究室か日本人クラブにいて将棋をさしていた。それがどこを探してもいない。飲みにでも行ったかと思っていると、ニ、三時間して素面で帰ってきて、にやりと笑ったりする。またときに家具店などに行って、衝動的に椅子やテーブルを買いつけ、あとで届けられて置き場所に苦心している。 このころ、先生は少しおかしいのではないか、荒木がそんなふうに思っていると、英世のほうから突然、話し出してきた。 「君には悪いが、もしかすると、この部屋を出ていってもらうことになるかもしれない」 「なにか、僕が不都合なことをしたでしょうか」驚いてききなおす荒木に、英世は笑いながら、 「そんなことではない。実は、今度結婚しようかとおもっているのだ」 「先生が、誰とですか?」 「メリー・ダアジスという白人の女性だ」 いままで、英世に女の影といえば、コペンハーゲンから持ち帰った写真の女性くらいなものだった。その相手は英世のほうがかなり気にいっていたようであるが、いつのまにか写真は片付けられ、それ以来、彼女の話はきいていない。 もちろん、ときどきイースト・サイドのほうにいって、女は買っているし、荒木もニ、三度連れていってもらったことはあるが、それは遊びで結婚にはほど遠い。いずれ妻が必要なことはわかるが、まだまだ先のことだと思っていた。 「本気ですか」 「もちろんだ、おかしいか」 「いいえ、そんなことはありませんが……」 「僕もそろそろ三十六だからな。写真を見るか」 英世は背広の内ポケットから、名刺ほどの大きさの写真をとり出した。白いワンピースに鳥の羽根のついた帽子をかぶり、軽く斜めを向いている。目が大きく白人にしてはふっくらとして、体格もいい。 「綺麗な人ですね」 「本当にそう思うかね」 ききなおされて、荒木は戸惑った。正直いってさほど美人ではない。十人並みの顔だが、そういうのが礼儀だと思っていったまでのことだった。 「いろいろ不満をいいだすときりがないが、このあたりで妥協しておくのが無難かと思ってね」 「日本のお母さんの許しはえたのですか」 「いま話すとこわれてしまうから、そのうち話すことにするさ」 英世はそういうと、自分からブランディをグラスに注いで飲み干した。 7 英世の妻、メリー・ダアジスについてはあまり知られていない。数多くある野口の伝記のほとんどが「明治四十五年四月、英世はメリー・ダアジス嬢と結婚した」という一行で片付けられている。 これはどういうわけなのか。野口英世伝の多くが日米間の険悪な時期に書かれ、そのため、アメリカ人と結婚した部分を意識的に素通りしたとも考えられるが、それだけとも思えない。なにか偉人伝中の人として、その部分だけは感心しないところでもあったのか、実際、メリー自身が、かなり問題のある女性であったことはたしからしい。 だがそれにしても、彼女の資料はあまりにも少なすぎる。伝記作家が、メリーのことを極力省こうとしたせいもあろうが、日本に帰った英世自身も、彼女のことについては、ほとんど語っていない。書く方も書かれるほうも、両方とも隠そうとした。それが死後五十年を経て、さらに謎に包まれたというべきかもしれない。ここでは数少ない資料と、聞き書きから、彼女の姿を想像するよりない。 メリー・ダアジスは英世と結婚したとき、二十八歳であった。アイルランド系のアメリカ人で、父はペンシルバニア州のスクランド市で鉱山業を営んでいたといわれるが、結婚した当時は家業は大分傾いていたらしい。 二人の出会いがどこであったか、そしてなにがきっかけであったか、それもまったくわからない。当時、英世と親しかった日本人何人かが馴れ初めを尋ねたが、英世はただ笑って答えなかった。 しかし研究所や仕事の関係で正式に知り合った関係でないことだけはたしかである。 英世はときどき、研究の合い間に一人で飲みに出かけたが、そのニューヨークの下町のパブあたりで、偶然知り合ったのでもあろうか。それというのも、メリーはかなりの酒好きであった。英世が飲み出すと一緒に飲む。しかもアイリス系女性独特の、興奮しやすい、ややはすっぱな感じの女であった。 二人は結婚するとき、互いに禁酒を誓い合ったが、そうしなければならぬほど、酒好きあったともいえる。そして、この誓いは、結婚後一か月もしないうちに破られた。 ともかく、英世は、この自分より背も高く、大柄な白人女と、明治四十五年の四月に、ニューヨークの対岸のジャージーシチーで結婚した。このとき、英世は、かねて知り合いの音楽家のグリーンバーグ夫妻と一緒に式を挙げた。教会で、牧師の前で誓うだけの簡単なもので、日本人で立ち合った者は一人もいなかった。二人だけのごく内密な式であった。 結婚後、二人は東六十五番地から、マンハッタン・アベニュー一番街のアパートに移った。ここには洋画家の掘市郎がいたが、その五階の隣の部屋があいたのを機に移ってきたのである。 英世はこの堀に、自分がここに住んでいることは内密にしてくれ、と頼んだ。各学者との応接や手紙のやりとりは、研究所で出来るので、家を知らせなくてもたいして不都合はない。 英世が二人の棲家を隠そうとしたのは、一つには結婚したことがロックフェラー研究所に知れると、妻の扶養手当や年金などが必要になり、研究所側がそれを嫌って、来年度の契約を破棄するのではないかと恐れたからである。当時、英世は首席助手でありながら、まだその地位の保持に、確たる自信をもっていなかった。なにかの理由で人員が削減されるとすると、黄色人種である自分が、まず真先に槍玉にあがると思っていた。とにかく英世は、メリーを、日本人に合わせるのを極力避けていた。実際、英世の結婚生活の実態を見たのは、隣にいた堀だけで、結婚後、ここへ日本人を招待することはほとんどなかった。 「メリーは野口の研究に対して、理解とか協力というようなことのできる女ではなかっ」た堀はメリーについて、そんなふうに述べている(野口英世記念会報昭34・10・10号)がメリーはいわゆる日本的な良妻ではなかったことだけはたしかである。 英世が日本人ながら、ロックフェラー研究所の主要な研究スタッフで、優秀な細菌学者であることは、メリーも知っていた。実際、それだからこそ、小柄で貧相で、性格も好みもよくわからない東洋人と結婚したともいえる。 メリーにしても、いっときは、この風采はあがらぬがエネルギーに満ちた男と、甘い新婚生活を築くことを夢みたかもしれない。だが、結婚すると、その日から、英世は研究室にこもりきりだった。しかも遅く帰ってきては、標本などを一杯かかえこんで、また顕微鏡を覗き込む。茶の間のテーブルから、キッチンにまで、プレパラートや試験管を並べて、家庭が研究室かわからなくなる。 夫の仕事のために耐える、などという訓練を受けていないアメリカ女性である。しかもアイルランド系で、ただでさえ勝気で喧嘩っ早い。英世の帰りが遅い、顕微鏡ばかり覗いている、本ばかり読む、と文句をいっては怒る。英世も負けてはいない。遅く帰ってきて、メリーがビールでも飲んでいるよ、露骨にいやな顔をし、女はあまり酒を飲むものではないと説教もした。 「日本に、そんな女はいない」英世がいうと「それなら、日本の女と結婚したらいいでしょう」といい返す。 二人ともエキセントリックなところがあるから、喧嘩になり出したら大変である。大声で罵り合い、やがて取っ組み合いの大喧嘩になる。メリーのほうが体格がよく、英世はよく押し倒されて、テーブルや棚の食器類をこわした。見かねて堀が仲裁に入っても二人は止めず、取っ組み合いの果て、最後に両方が疲れ果てて、ようやく終る。 一度、英世が講演でハワードに発つという晩に、大喧嘩をして、メリーは旅行の準備してくれなかった。英世は世話をやいてくれる者がいないと、下着や金のあり場もわからない男である。 やむなく、英世は空の鞄だけを持って、堀の部屋にとびこみ、そこでワイシャツと金を借り、ようやく船に間に合うということもあった。 しかし、といって、いつも喧嘩ばかりしていたばかりでもない。二人が機嫌のいいときは、英世が妻をメディと呼び、メリーは英世をヒディと呼んでいた。英世の社会的地位や収入は魅力的だったが、といってメリーはそれだけに惹かれたわけでもない。日曜日にも休もうとしない英世の体を気遣って、メリーは堀に頼んで、魚釣りに連れ出してもらったり、将棋の相手になってくれるように頼んだりもした。 「しかし、野口にはあの細君でよかったのだ。普通のアメリカ人気質の婦人であったら、それこそ有名人となった野口と同道して、パーティのなんのと着飾って出たがるところだが、メリーは赤貧に耐えることができたのだから」これはのちの堀の述懐である。 実際、ロックフェラー研究員で、年俸三千ドルとっていても、その生活は必ずしも楽ではなかった。結婚しても、英世の金銭感覚のなさは相変らずだったし、メリーも計画的な女ではなかった。一度、夫婦で写真を写すことになったが、メリーに着飾るほどの服がなく、カーテンにするはずの生地をつまんでスカートに見せかけて、写したこともあった。 英世と結婚する前、メリーは一時、いまでいうヒッピーのような生活をしていた時代もあったらしい。そのせいか、いささかすれっからしではあったが、反面気取らずおしゃれには無頓着なところがあった。我儘な女ではあったが、根は必ずしも悪人ではなかった。 堀に、「子供はどうして生まないのか」ときかれたとき、メリーは「わたしは腹が立つと、かあっとなって自分がわからなくなる性質だし、ノグチもあのとおり、気違いじみているところがあるから、こんな夫婦では、どんな性質の子供ができるかわからないでしょう。子供はいないほうがいいんです」と答えている。英世にもし子供がいても、いっとき無性に可愛がるかと思うと、次の瞬間忘れたように研究に没頭する。気が向くと、外国のどこへでもとび出していき、家を忘れる男が相手では、落ち着いて子を生む気持ちになれなかったメリーの気持もわからぬわけでもない。その意味ではメリーもまた、狂気の人野口の、一人の犠牲者といえなくもない。 いずれにしても、この夫婦は、日本人の常識から見ると、一風変わった夫婦で、外から見ただけではなかなか理解できない。一般の日本人から見たら、まさしく悪妻に違いなかった。英世もそのことを怖れて、日本人を家に招くことを避けたが、メリーのほうも、客がきても無愛想だし、英世や日本の国について、理解しようという努力はほとんどしなかった。 互いに、自分の個性をむき出しにして、一応、夫婦という形態だけは採っている。英世にとって、家庭はあっても、ないに等しかった。後年、英世はこのことを淋しいと思ったようだが、その侘しさがまた学問に向かわせるバネになったともいえる。
このころ、英世には、いくつかの綽名がつけられていた。その一つは、「二十四時間不眠主義者」であり、さらに「細菌と同居者」などというものもある。だが最も英世をよく表しているのは「人間発電機」という綽名である。はたから見ると、まさに英世は永遠に動き続ける発電機そのものに見えたのである。 だがそんななかでも、英世が研究から頭をそらす時間があった。唯一の楽しみの将棋をさすときである。英世の将棋はさほど強くはなかった。初段には達しない、せいぜい五、六級というところであった。だが好きなことは好きだった。しかも指すのが早い。一局十分から二十分くらいで終る。初めのころは日本人クラブで指していたが、そのうち隣の堀とよく指すようになった。英世は性急だが、堀はどちらかというと悠然としている。そんなとき、「こんなものに、長考するのは馬鹿だよ」という。だが力は堀のほうがニ、三級は上だった。まともにやると勝てない。しかし英世は負けても負けても挑戦する。ものごとに熱中したら見境がなくなる性質だが、将棋も同じだった。一日に十番でも二十番でも指す。 堀が、「もういい加減やめよう」といってもきかない。とくに堀が勝っているあいだは、絶対に止めようとしない。そのうち、堀が根負けして負け出すと、手を叩いて喜び、「どうだ、参ったか」という。そして「最後に勝のが、本当に強いんだ」とうそぶく。 英世のアパートでやっているときには、メリーは十一時ころまでは起きているが、あとはさっさとベッドに入る。それでも二人はやっている。そのうち、寝室のほうからメリーが叫ぶ。 「ヒディ! いい加減にやめたら」 英世は答えない。盤を睨んだまま、縮れ毛をかき上げ、うなっている。 「もう一時よ」 また怒鳴っているが答えず、「もう一番」と、指しはじめる。そのうち、あきれはてたのか、メリーの声はきこえなくなる。 「これで安心して指せる」 堀は疲れて早く眠りたいので、ときには、故意に負けてやる。そうすることしか、解放される手段はない。こうして最も多いときには一晩で四十一番指したことがあった。最後には英世が二十一勝二十敗となり、一番勝ち越したところで、ようやく解放された。しかもそのあと、英世は再び研究にとりかかる。 「大変なロスをした。大失敗である」 そんなことをつぶやきながら、慌てて顕微鏡を覗きだす。そのくせ、少しでも暇ができると、すぐ堀に将棋を指そうと誘いにくる。 「こんなに指して、疲れてからまた研究では大変でしょう」 堀がいうと、英世は「俺は将棋のときは、頭を休めているのだから、少しも疲れないよ」 と笑う。実際、英世のように早指しでは、あまり頭を使っているとは思えず、すべて勘でさしているようなものである。だが、とにかく最後にはスタミナで押し切る。 「怖い男だ」 将棋を指したあと、研究室へ向かう英世を見て、堀は、人間とは別の怪物を見るような無気味さを覚えるのが常だった。 8 このころ英世の研究は梅毒、トラコーマ、オロヤ熱へと、次第に間口を広げられていったが、中心はやはり梅毒スピロヘ-ターであった。 ところで、これまで梅毒の病原体のことを、単にスピロヘ-ターと呼んでいたが、その用語について、整理しておく必要がある。 まず、これまで単細胞の小さな生きものを、一般的に細菌と呼んできたが、このころから、さらにリケッチャ、ウィールスの存在が推測され、微生物は新たに、細菌、リケッチャ、ウィルースなどに分類されるようになった。このうち細菌は、その形態から丸い形のもの、棍棒状のもの、ぐるぐる螺旋状になるものの三種類に大別され、それぞれ球菌、杆菌、螺旋菌と呼ばれている。スピロヘ-ターは、この螺旋菌のなかの一種である。しかし、このスピロヘ-ターという言葉は、微生物を細分化していく、目、科、属の各々につかわれていて、きわめてわずらわしい。いまこの関係を表に示すと、次のようになる。
このうち、梅毒スピロヘ-ターは、正しくは、「スピロヘ-ター目、トリポネーマ科のトリポネーマ属に属している、トリポネーマ・パリドウム」ということになる。正確には、そう呼ぶべきであるが、実際はスピロヘ-ター目のトリポネーマ科に属していることから、単にスピロヘ-ターとかトリポネーマで、トリポネーマ・パリドウムを表している場合がある。これから、さらに細分化していく点からもトリポネーマ・パリドウムと正確に呼ぶのが誤解がないと思われる。
このころ英世が関わった微生物は、細菌をこえて、リケッチャからクラジミア、ウイ―ルスにまで拡がっている。これを病原体と病名の関連で記すと、次のようになる。 一、細菌――「ペスト」、「破傷風」、「結核」。コレラ、ジフテリア、百日咳、赤痢、腸チフス、パラチフス、猩紅熱 ニ、リケッチャ――「ロッキ山斑熱病」、「オロヤ熱病」、発疹チフス、ツツガムシ病 三、クラジミア――「トラコーマ」、オウム病、そけいリンパ肉芽腫(第四性病) 四、ウィールス――「天然痘」、「狂犬病」、「小児麻痺」、「黄熱病」、インフルエンザ、はしか、日本脳炎(鈎括弧内は、英世が直接、研究にたずさわったもの) このうち、細菌、リケッチャ、クラジミア、ウイ―ルスなどの違いは、前三者は光学顕微鏡で見えるが、ウイ―ルスだけは見えない。また核酸の構成上、DNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)の両方が、前三者にはあるが、ウイ―ルスにはないとか、人工培地での発育も前三者では可能だが、ウイ―ルスでは生えないなど、種々の違いがある。 しかしいずれにせよ、英世が研究した時代には、これほど正確な形で分類はすすんでいなかった。それどころか、黄熱病や小児マヒの原因が、ウィールスであることさえ、わかっていなかった。英世をはじめ、二十世紀初頭の細菌学者は、未解決のこれら病原体に挑み、その大体を究め、分類作業をすすめていく段階であった。 ところでこのころ、英世が没頭していたのは、麻痺性痴呆患者の脳組織のなかに、トリポネーマ・パリドウムを証明することであった。 前にも触れたが、麻痺性痴呆は、梅毒の末期によく現われ、梅毒との関連が疑われて、別名脳梅毒ともいわれていた。脊髄癆などとともに、一種の変性梅毒と考えられたのである。しかし、患者の脳組織にトリポネーマ・パリドウムが発見されないかぎり、そう断定するわけにはいかない。もし永遠に見付からない場合は、梅毒にきわめて類似する別の病気も、考えなければならなくなる。英世はこの確認のため、脳病院へ行き、麻痺性痴呆で死亡した患者の脳をもらってきて、そこから膨大な組織標本をつくった。 このとき、英世の脳の標本を提供するのに便宜をはかったのが、現在ロスアンゼルスに住む、アメリカ人で唯一人、英世の研究をしているプレセット女史の父のプレセット教授であった。 麻痺性痴呆で脳が侵されているとはいえ、実際の脳は白く、正常人のそれと変わりはない。はたしてどこにトリポネーマが潜んでいるのか、皆目見当がつかない。これを英世は細密に、脳から丹念に刻んでいく、数ミクロンの切片だから、脳のあらゆる箇所を調べるとなると、膨大な数になる。しかも、各々について、さまざまな染色法をこころみてみる。わずかな染まり方の違いで、見逃すかもしれないからである。 英世はスピロヘ-ターに関しては自信があった。すでに純粋培養のときに、見飽きるほど見ている。しかも英世の強みは、そのすべてを自分の手で染め、眼で見てきたという経験がある。 彼は毎日、二百枚の標本を一まとめにし、それを一枚一枚検べていった。眼が疲れたら、いっとき休み、また検べる。研究室では足りず、自宅に持ち帰って、さらに続ける。将棋に熱中した日も、二百枚を消化することを忘れない。大海のなかに小舟を探すに等しいが、たしかにトリポネーマはいる。見つからなくてもいるに決まっている、いや、いなければならないのだと、英世は自分にいいきかせながら仕事をした。 「おい、まだか、まだ出てこないのか」「トリポネーマ君、トリポネーマ君……」 英世はよく一人でそんなことをつぶやきながら顕微鏡を覗いていた。深夜、その声に起きたメリーは、この人は本当に頭が狂ってしまったかと思ったりした。 人間ダイナモは、朝、昼、晩と、トリポネーマを求めて働き続けた。 やがて、一九一三年(大正二年)の夏の深夜、英世は一枚の組織標本の片隅に、トリポネーマ・パリドウムが染め出されているのを発見した。 その瞬間、英世は顕微鏡を覗くのに、高さが手頃で愛用していたピアノ用の丸椅子から立ち上がり、「ダアジス、ダアジス」と叫んだ。 英世はそのまま、寝室で眠っているメリーに、「見付かったぞ、見付かったぞ。起きろ」と揺すり、掛布をはねとばしてベッドから引きずり出した。 その夜、ニュ―ョ―クは暑く、英世はシャツだけを着て下はパンツ一枚であった。 いきなり起こされたメリーは、下着のまま踊り狂う夫を見て、夫がなにか、重大な発見をしたらしいことはわかったが、その姿のあまりの奇矯さに、一緒に喜ぶ気にもなれず、呆んやり見ていた。 だが 英世は、メリーの手を握り、無茶苦茶な接吻を額から耳、そして首にふりまくと、そのまま隣の堀の部屋に駆けつけて行った。この時、午前二時を過ぎているが、なにごとかと堀が起きてドアを開けると、シャツにパンツ一枚の英世がいきなり抱きついてきた。 「見付けたぞ、見付けたぞスピロヘ-ターがいたのだ。見てくれ」 堀に、細菌の知識はなにもなかったが、強引に部屋に連れていかれて、顕微鏡を覗かせられた。 「そこの右上に、細い紐が捻じれたようになっているのが見えるだろう。それがスピロヘ-ターだ」 いわれると、たしかにそれに似たものが見えるが、堀にはそれがどれくらい重大なものか見当もつかない。そのまま、英世は興奮で眠られず、門外漢の堀は、一晩この発見がいかに重要なものであるかということを、きかされるはめになった。 やがて戸外が白み出し、陽がハドソン川の上流に昇るころ、英世はトリポネーマ・パリドウムが染め出されて標本を持って、フレキスナー教授の家へ急いだ。早朝の突然の来訪に、ナイトガウンのまま起きてきたフレキスナーは、トリポネーマを発見したときいて「本当かね」といった。 「とにかく、入りたまえ」 フレキスナーは、すぐ英世を応接間に案内し、標本を見た。 「たしかに、そうでしょう」 そのころ病原体の鏡検に関しては、すでにフレキスナーより野口のほうが優れていた。英世がこれだけ自信をもっている以上は間違いはないのだろうフレキスナーはうなずいた。 「よくやった、これは君だけではなく、研究所にとっても、大変な名誉だ」 フレキスナーは、英世の肩を叩き、しつかりと握手した。 「いますぐ朝食の準備をするから、それを食べながらゆっくり話そう」 そういわれて、英世にはじめて徹夜のあとの空腹が襲ってきた。
第三章 ヨーロッパ P.88
1 麻痺性痴呆症の患者の脳に、トリネーマ・パリドウムが存在するだろうということは、当時、多くの学者が考えていたことであった。すでに一部の学者は、脳の切片から標本をつくり、トリポネーマを検索していた。染色法は、トリポネーマを探すのに一般的な「鍍銀染色法」であった。狙いも目的も同じである。なのに、何故、英世だけが先んじて発見することができたのか。 これには、まず第一に、英世の、あくなき努力とねばりをあげねばならない。毎日、二百枚以上もの標本を半年以上も見続ける、その忍耐力が発見の第一の要因であった。しかも英世の場合は、脳組織の切除から染色まですべて一人でやる。実験の第一段階から自分の眼と指でたしかめ、助手がつくった標本を覗くだけの他の学者とはスタートから違っていた。さらに、英世にとって幸運だったことはトリポネーマが脳組織内で実質的に深く入り込んでいたことである。多くの学者は、過去の経験からトリポネーマがよく存在する血管まわりばかりを探していたが、これでは容易に発見できない。英世の、しらみつびしとでもいうべき、執拗な検索が功を奏したといえる。 ともかく、英世はこれで、トリポネーマ・パリドウムの純粋培養に次いで、いままた麻痺性痴呆患者の脳組織内にトリポネーマを発見するという、二つの偉業を成しとげたわけである。さらにトラコーマ小体を培養し、狂犬病に迫り、はては小児麻痺の原因さえを発見しかねない勢いである。全世界の学者が、英世の業績に感嘆し、注目するのも当然であった。 だが英世、脳組織内にトリポネーマを発見したという報告だけでは満足しなかった。 たしかに、それは大きな発見に違いなかったが、ヨーロッパにはまだ、英世の仕事を評価していない学者もいた。「このごろ矢継早に成果を発表するが、アメリカの研究所にいる日本人学者など信用できない」、そんな風潮が医学的に先進国であるヨーロッパにはあった。これはある程度無理もないことで、トリポネーマの純粋培養や脳内組織内発見などが、そう一朝一夕でできるとは思われていなかったし、トリポネーマ・パリドウム自体にもさまざまな似通った形があり、誤認され易い菌でもあった。 英世はこの疑いを晴らすため、トリポネーマの染色された標本を、トリポネーマの発見者へじきに送って確認してもらおうと思った。だがこの発見者であるシャウジンは、近代細菌学の天才といわれた人だが、この七年前に敗血症の研究中、その犠牲となり、二十五の若さで命を絶って、すでにいなかった。仕方なく、標本をシャウジンの弟子である、エーリッヒ・ホフマンの許へ送ってたしかめてもらった。 英世は自信満々であったが、そのとおりホフマンはこの標本を見て、トリポネーマ・パリドウムであると答えてくれた。さらにホフマンはこの年の二月、ボンで開かれた病理学会にこの標本を展示し、最大の讃辞をもって英世の業績をたたえた。 さすがにドイツ医学の巨頭であるホフマンの賛辞の効果は著しく、これで「ノグチ」の名は、全世界の科学者のあいだに拡まり、細菌学の第一人者としての地位を保証されることになった。 この年の九月、英世はウィーンで開かれた、第八十五回のドイツ医学会に、正式に主賓として招待されたのである。 このときの喜びを、英世は小林栄への手紙に次のように述べている。 前略、昨年暮以来、成功した研究は、一、小児麻痺の原因発見、ニ、精神病ことに麻痺症患者の脳中に、梅毒菌の現存を証明したこと、三、狂犬病の原因などです。いずれも世界の学者を困らせていたもので、そのうちの一つでさえ、大発見というべきものですが、私はその三つもの難問を、わずか、七、八か月の間に完成したわけです。
一読、いかにこのころの英世が意気旺んであったかが想像できる。ノーベル賞など、すでに目前に迫っているかの感さえあるが、事実英世の周辺にはそういう噂もあったし、英世自身もかなりその気になっていた。 だが、ノーベル賞は、英世の前を素通りしていく。 後年、東大の青山胤道博士は、「野口にノーベル賞が与えられなかったのは、賞の権威を守る意味からして幸いであった」と喝破した。この発言は、単に日本人学者の妬みからだけとはいいきれない。この手紙にあげた三つの業績のうち、第一の小児麻痺と第三の狂犬病の二つの病原体の発見は、のちにいずれも誤りであったことが証明される。
第二の麻痺症患者の脳中に梅毒菌を証明したことには、皮膚性病学の権威、土肥慶蔵博士が、「梅毒の最も怖ろしいことは、末期の痴呆と脊髄癆になり四肢の自由と頭の思考力を奪われることである。もしこれがスピロヘ-ター・パリドウムの直接作用であることは、野口氏の病理組織的研究において、初めて決定的に立証されたのである。現在、梅毒治療法の第一の要諦は、早期に『ネオサルバルサン』兼蒼鉛 これを見てもわかるように、英世の仕事には玉石混淆、いくつかの落ちこぼれがあった。要するに、出来がいいのと悪いのとの差があった。だが、それは英世一人の責任に負わせることもできない。自然科学の発展段階で、学者が誤る迷路にまぎれこんだ結果ともいえる。みなが「ドクター・ノグチ」の華々しい登場に感嘆し、英世自身も自分の仕事に自信をもっていた。 2 九月二日、ニューヨークを出発した英世は十日後パリに到着、そこのコンチネンタル。ホテルに宿泊した。ここで、英世はかつて北里柴三郎などが訪れたパスツール研究所や、サン・ルイ病院などを訪れた。また彼は、デフフォッセ教授、プルトン博士などと、パリ在住の著名な学者と会食し、歓談した。 大体、欧米は科学者の遇し方が厚い。とくに梅毒に悩まされていたヨーロッパ各地は、英世の渡欧を、救世主の再来のように熱狂的に歓迎した。新聞には、ノグチ来訪の記事を大きくかかげ、行く先々の駅には、科学者はもとより、駐在の大・公使までが出迎えた。 このときの駐仏大使、石井菊次郎は、当時の模様を、 「私はある朝、ふと新聞を見ると、"有名な日本の大学者、野口博士パリ訪問"という大きな表題の下に、写真をのせて、業績が記載されていた。それが各新聞にのり、見出しの大きかったことに驚いたが、このことをもって、フランスの大衆が、いかに博士の研究に尊敬を払っていたかがわかった。私は大変感動し、急に肩身が広くなった思いをした。それは丁度、明治二十五年に北里博士が来仏された時と似ていた。しかし野口博士は、とんと大使館などには寄りつかぬ人であった。早速、博士を探すことにして、パリのホテルをくまなく探したが、われわれのペースとは違って、一生懸命探していたころは、すでにベルリンかブラッセルかに行っていて、ついに合うことができなかった」と述べている。 この一文からも、いかに英世が歓迎されたかがわかる。それにしても、日本大使館の間抜け振りも相当なものであった。おそらく石井大使などその新聞を見るまでは、野口の存在など知らなかったであろう。しかも、日本人の学者であれば、当然、向こうから訪ねてくるはずだとのんびり構えている。 明治以来の官僚や大使館員達の横着さがうかがえるが、これでは、英世が日本の大使館はなにをやっているのか、と立腹するのも無理はない。大使館を無視したのは、そういう怠惰への一つの批判でもあった。 パリからウィーンに着いた英世は同市最高の「インペリアル・ホテル」に泊った。 この学会は、正しくは、「ドイツ自然科学者と医師とのつどい」という名で、医学者ばかりでなく、化学、生物、物理など、各界からの学者が五千名近く集っていた。当時は医学もまだ分科せず、自然科学の各分野と関係をもつていたので、こういう名前で呼ばれていたのである。 この学会は本来、ドイツ国内の都市でやるのが建前となっていたが、ときたまドイツ語圏の別の土地で開かれることもあった。今回はウィーンで開かれた四回目の会で、ウィーン全市をあげて熱烈な歓迎ぶりであった。とくに英世について、新聞は「日本の凱旋」という見出しをつけ、最大級の賛辞をのせた。 英世の業績もさることながら、この背景には、オーストリアがバルカン半島をめぐって、ロシヤと開戦直前であったのが、日露戦争でことなきをえたことによる、オーストリア人の日本贔屓があったことも見逃せない。 ところでヨーロッパの医学事情に敏感な日本の医学雑誌は、ドイツでの医学会のことは必ずとりあげていたが、どういうわけか、この会にかぎって無視してしまった。会がドイツ国内でなかったので見逃してしまったのかもしれないが、あとで英世は口惜しがり、もしドイツで開かれていたら、自分の講演のことは、もっと大きく日本でも報道されたに違いないと語っている。 ともかく、この学会の二日目に英世の特別講演がおこなわれた。 会場は、内科、精神科、神経科、梅毒科の医師でうずまり、一部は場外まであふれた。 講演はワンガー博士が英語で代読し、それをウィーン大学のワグネル博士がドイツ語に翻訳した。彼は麻痺性痴呆の患者にマラリア原虫を注射し、高熱を誘って治すという方法考えた医師で、のちにノーベル医学賞を受けた人である。 この年、一か月半前のワシントンにおける第十七回国際医学会では、同じ北里研究所にいた秦佐八郎が梅毒治療薬サルバルサンについての共同講演者となり、期せずして、大きな学会に、日本の医学者が連続登場という結果になった。 「秦の仕事はエールリッヒとの共同研究であり彼の指導でおこなわれたものだ。しかし私のは私自身でやりとげたもので、内容もはるかにこちらが上である」英世は、秦を意識しながら、こう断言した。 内容の優劣はともかく、英世の講演は大きな反響を呼び、改めて「ノグチ」の名前がクローズアップされた。 講演中、英世は演壇の片隅に坐っていたが、うしろのほうは、講演より、ノグチを一目見たいという人で、おし合いへし合いしていた。講演が終り、英世が降壇すると、会員が一斉に、「ノグチ、ノグチ」といって押し寄せ、握手を求める。まるで有名なタレント並みの扱いであった。 だが、この大会で英世が最も嬉しかったのは、講演のあとフリードリッヒ・フォン・ミュラーから、すぐ会いたい旨の連絡を受けたことだった。 ミュラーといえば、ドイツ医学会というより、世界の医学界の大御所である。当時の医学界のすべての人事は、ミュラーの一言で決まるといわれたくらいのボスである。ドイツ医学を信奉する日本の医学者にとっては、まさに神様のような存在であった。その人から、直接会って話をききたい、と申し込まれたのである。 ウィーンにきていた東大の真鍋教授がこのことを英世に告げると、英世は一瞬立上り「なにっ」と叫んだ。 「ミュラーがわざわざ俺のところにくる。そんなわけはない。なにかの間違いだろう。もう一度たしかめてみろ」 「いえ、たしかにミュラー博士です、もうじき、この学会場のお見えになります」 「本当か、本当にミュラーが、この俺を訪ねてくるのか」 英世はそういうと、会場の控室でワイシャツ姿のまま躍り出した。嬉しくなるといつもそうだが、英世は阿波踊りりのように両手をあげ、ぴょんぴょんとはね上がりながらくるくる踊り廻る。呆気にとられている係員の前で、「これが踊らずにいられるか、躍れ、躍れ」と、日本語で叫んだ。 「先生、静かにして下さい。間もなくこちらに博士が見えますから、背広を着てください」真鍋の要請で、英世はようやく服を着た。 このとき、ミュラーは他に所用があり、英世の講演はきかれなかったが、論文の内容はすでに知っていた。このミュラーくらいになると、会場に到着すると、係員が、「ただ今、自然科学会会長、フリードリッヒ・フォン・ミュラー閣下、ご到着」と叫ぶ。すると会員は一斉に立ち上がり、拍手で迎える。まさに皇帝並みの扱いであった。 英世はミュラーを控室を出て会場の中程で迎えた。 「ロックフェラー研究所の、ヒデヨ・ノグチです」 英世はドイツ語でそういうと、ミュラーの前に深々と頭を下げた。 「ミュラーです。あなたがドクター・ノグチですか、遠路よく来てくれました」 そのまま、二人はしっかり握手する。伝記記者のすべてが強調する、英世、一世一代のクライマックスである。 「閣下に会えて、こんな光栄なことはありません」 「私も、あなたのような優秀な学者に会えて、幸せです」 長身のミュラーを、日本人でも小柄なほうの英世が見上げる。一見、父と子が対面しているように見えたが、英世は臆せず、胸を張っていた。 ミュラーの言葉はミュヘンなまりの強いドイツ語で英世のドイツ語の力では理解しがたいところがあった。だが、大勢の前で、わからない表情をするのは癪だから、わかったようなうなうなずき方をする。するとミュラーはますます真剣に話しはじめる。英世は次第に怪訝な顔をして、首を傾げる。「どうか?」と尋ねられても答えないでいると見かねた真鍋が、ミュラーにいった。 「英語で話してみてくれませんか、英語のほうがよく通じるはずですから」 ミュラーは率直にうなずいて、今度はドイツなまりの強い英語で話す。 「この会が済んだら、ぜひミュンヘンにも来て、あなたの講演と、標本の供覧をお願いしたい。そしてドイツの科学界が、いかにあなたに好意を抱いているかを、わかってもらいたい」 英世はおおいに喜ぶ。ドイツ科学界の巨匠ミュラーから直接招待を受けたのだから大変な光栄である。 「ダンケ・シェーン」英世は自由の利く右手で、しっかりミュラーのグローブのような大きな手を握り返した。 二人のうしろには、なお次々と、ドクター・ノグチと話したがっている学者が犇めいていた。なかなかノグチに近づけないで、真鍋に紹介を頼みにくる者もいる。演壇にはいまデモストレイションを終えたばかりの顕微鏡がおかれたままで、そこには小児麻痺の病原体が展示されていた。学者達は、それを覗いては、英世の手に、名刺だけでも、といっておいていく。英世が少しでもあいたとみると、すぐ近づいて話しかけてくる。前後左右から声をかけられ英世は応対に休む暇もない。 まさにひっぱりだこのもてようで、しかもいずれも、「立派な研究だ」「いまの講演に感動した」「自分達の研究所にも一度寄ってくれないか」といった讃辞である。英世はそれらにいちいち答えながら、「行くのは待ってくれ」と答えざるをえない、ミュラーの申し出は受けても、他の学者のところまでいちいち出かけるわけにもいかない。とにかく、英世は「ありがとう」をくり返して、次々と握手をする。 だがそのなかで一人、英世に疑問を述べる者がいた。まだ三十前後の青年だが、「自分はコッホ研究所から来たものだが」といってから、「あなたの研究には疑問がある」といった。 初め、英世は他の学者と握手をして聞こえないふりをしていた。いまここで議論をはじめても仕方がないし、次々と名刺を渡し自己紹介してくる学者達と挨拶を交わすことで精一杯である。英世としてはこの機会に、いままで知らなかったヨーロッパの学者達と一人でも多く面識を深めたかったが、その青年はしつこく横で喋りはじめた。 「あなたのやった純粋培養法でトリポネーマ・パリドウムが培養されるとは、とても考えられない。密封したり、組織片を入れるだけで培地が変るというのは少し簡単すぎはしないか」 大声でこういわれては、さすがに黙っているわけにいかない。英世は青年を振り返り、いいかえそうとしたが、思うような言葉が出てこない。すると青年はさらに続けた。 「小児麻痺の病原体にしても、それがたしかだという確証がない。そういうのが見えたというだけで病原体と断じるのは早計ではないか」 英世の顔は次第に赤らんできた。怒るとき静電気がおきるのか、英世の縮れ毛はさか立つように見える。いまもそうらしい。真鍋も、まわりの者もはらはらしているが青年はかまわず続ける。 「わたしのみでなくわがコッホ研究所のスタッフの大半も今日の発表だけで病原体と断じることはできないと思っている」 「待て」 ついに英世が怒鳴った。ようやく言葉の整理がついたらしい。 「たしかに、コッホ研究所はヨーロッパでも第一流の研究所かもしれぬ、だが、一流が最良でないことは、レストランを見てもわかる」 「レストランと研究所は違います」 「要するに、君のところには、わたしの仕事の価値を評価するだけの人間がいないということだ。私は無能なわからない男に話す時間はない」 「あの病原体は単なる雑菌ではないのですか、わたしはあの種のものなら他にも見ています」 「君は一体、何年間、細菌学を研究しているのだ」 背の小さな英世が、長身のすらりとしたドイツ男を睨みつけ、一瞬まわりは静まり返った。 「私と話したいなら、もっと勉強してから出てこい」 英世はそういうと、手に持っていたその男の名刺を、みなの前で引き裂いた。 まわりはドイツ人と日本人だけである。一瞬、「おつ」というどよめきがわき、しらけた空気が流れた。相手の青年は、さすがにいいすぎたと思ったのか黙った。 「質問があるなら、また別の機会にしたらいい」 真鍋がそういって二人のあいだに入り、他の学者たちも両者を押しとどめた。 「若造のなにもわからぬくせに、失敬だ」 英世はなお日本語で叫んだが、真鍋は「相手にしないほうがいい」とおし止めた。 めでたい場で、どうしてこんなことになったのか、真鍋は早くなかに入るべきだったと後悔したが、しかし、なんとも痛快ではあった。世界の一流学者の面前で、「日本人がドイツ人の学者を叱りつけたのである。しかも世界でトップといわれるコッㇹ研究所が後ろ楯についている学者を、「無学者」ときめつけたのである。それに、青年は反撥できなかったし、まわりの者も、青年は常識知らずと見たようである。 「あなただから、あれだけいえたのです。正直なところ、きいていて胸のつかえがおりる気がしました」真鍋がいうと、英世はまだ興奮さめやらぬ顔で、 「帰ったら、あの男の論文を徹底的に調べ、つぶしてやる」と叫んだ。 事実はともかく、英世の勢いは、コッㇹ研究所も少壮学者も問題にしていなかった。 その夜、学会主催の夕食会があり、ドイツ皇帝は名代として、皇族を差し遣わした。ここでも、英世はメインテーブルの中程にミュラーと並んで坐った。 「私の生涯にとって、こんなに嬉しく、素晴らしい夜はありません」 英世は言葉少なく謝意を述べた。 翌朝の新聞には、「日本の勝利」という見出しとともに、英世の顔写真が大きくのり、演説の内容が紹介された。まさに、学会、市民、あげての歓迎であった。 この背景にはロシヤと戦争に入る直前、日露戦争によって救われたという、オーストラリアの特殊事情も考えられるが、それにしても、一日本人で、これだけの歓迎を受けたのは、あとにも先にも英世以外にはいなかった。 3 ウィーンでの学会を終えたあと、英世はフォン・ミュラーの待つミュンへンへ向かった。 すでに先に帰っていたミュラーの停車場まで自ら出迎えにきていた。そこから英世はミュラーと同じ馬車にのり、彼の私邸に招かれた。そして夜はミュンヘン周辺にいる科学者、医学者主催の盛大な晩餐会が開かれ、翌日、市の公会堂で英世の講演会が開かれた。 当時、ミュンヘン在住の日本人で、ノグチの名前を知っている者はほとんどいなかった。きいたことのない名前だがドイツ医学会の大御所である、ミュラーが駅まで迎えに行ったというのだから、よほど偉い男に違いない。そうした好奇心も手伝って、会場には無縁の日本人まで詰めかけた。 ここでも英世は梅毒トリポネーマの発見について話した。ここに二日滞在したあと英世はミュンヘンからフランスに向かった。ここには赤痢菌を発見した志賀潔が学び、また、秦佐八郎とともに梅毒治療薬のサルバルサンを創り出したばかりのエールリッヒ博士が、やはり停車場まで迎えに出ていた。ここでも英世は盛大な歓迎を受けたあと、市の医学会で講演をおこなった。 英世の講演に感銘したエールリッヒは、英世の成功を祝し、市の医学会名で、英世を送り出したロックフェラー研究所に宛てた祝電を打った。 フランクフルトでの講演を終えると、英世はその足でデンマークに向かった。ここにはかつての恩師マドセン博士がいて、招待してくれたのである。英世がコペンハーゲンにある国立血清研究所に留学してから十年の歳月が経っていたが、この間に、英世は世界でも最も有名な医学者の一人になっていた。 英世はマドセン博士と久々に握手を交し、翌日、市内のパラット・ホテルでの、デンマーク医学会及び生物学会席上で講演をおこなった。 かつて英世がこの地に留学したこともあって、デンマークでの歓迎はひときわ盛大であった。とくに国王クリスチャン十世は英世に「ナイト」の称号を授けるとともに、ダンネプログ勲章を与えた。 このあと英世はノルウェーに行き、クリスチャリ市、及びぺルゲン市の各医学会で講演したあと、隣国のスウェーデンに入り、ストックホルムで講演し、デンマーク留学時代に一度会ったことのあるインゲポルグ内親王に招かれた。 北欧三国を巡った英世はさらに海をこえてイギリスへ渡る。十月五日から二十五日までロンドンに滞在し、王立医学会その他の会で講演した。その功に対し、王立医学会は英世とロックフェラー氏に感謝状を贈呈した。 イギリスのあと、英世は再び海を渡ってドイツに戻り、ベルリンに向かう。ここでも盛大な歓迎を受け講演した。 かくして、ヨーロッパに上陸して五十一日間、十か所の都市を訪問し、正式の講演だけでも十一回を数えた。交通不便だった当時のことを思うと、まさに驚異的な強行軍である。だが、この旅行によって「ノグチ」の名は全ヨーロッパに広まった。いまや世界の医学者で、ノグチを知らない者はいない。 英世はそのときの満足を血脇守之助に、次のように書き送っている。 「各地で受けた歓迎はまことに素晴らしく、ときには有難迷惑の感さえありました。実に、私が主賓として出席した、正式の晩餐会、昼食会の数は三十八回におよび、皇族に招待されたのは二回、その忙しさは大変なものでした。各宴会ではヨーロッパの高名な学者と同席し、彼等の話をきき、情報を交換し、友情を分かち合いました。 (中略)コペンハーゲンでは、クリスチャン十世よりとくに小生にダンネブログ勲章が授けられました。これは日本でいえば、旭日三等勲章に匹敵するものですが、この夏スペイン皇帝より贈られたイザベラ勲章と合わせて、二つの外国勲章を持つことになりました。さらに噂によればスウェーデン国王からも、小生へ叙勲する旨、内々の意向があるときいています。勲章ばかり欲しがるわけではありませんが、小生のように異国にいる者にとっては、各国の勲章が、処世上の有効な武器となりえます。とくに最近のアメリカのように、排日思想の強いところでは、外人と対抗して仕事をやっていく上に、無言の力となりえます」
やがてベルリンを最後に、英世は帰米の途につく。九月二日にニューヨークを発って再び英世が戻ったとき、ニューヨークはすでに晩秋の十一月九日であった。 ヨーロッパで名を挙げた英世に対するアメリカ医学界の英世への評価は当然上っていた。今までは、ロックフェラー研究所にノグチという優秀な研究者がいる、という程度の認識にすぎなかったが、ヨーロッパ各地で講演をし、ミュラー、エールリッヒにまで招かれたとあっては、もはやそれではすまない。帰国して一か月も経たないうちに、マウント・サイナイ病院から、同病院に新設する研究所の所長になってくれないか、という誘いがきた。条件は年俸六千ドルである。当時、家族で一週四、五十ドルあれば一応の生活ができるといわれていたのだから大変な高給である。もちろんいまのロックフェラー研究所の給料より倍近く高い。しかも独立した研究所の所長である。 英世は食指が動いた。給料も高いし、所長になって思いきり自分の好きなことをやってみるのも悪くはない。それに自分が、アメリカの研究所の所長になったときいたら、日本人の学者達は驚くだろう。あの東大や北里研究所の、日本だけで威張っている教授連も、今度こそ一目おくだろう。 英世は一応引き受けることに腹をきめて、フレキスナー所長にいってみた。 「マウント。サイナイ病院から、所長としてきて欲しいと、いってきているのですが、いかがなものでしょうか」英世が少し迷惑そうな表情でいうと、フレキスナー所長は青い眼で探るように英世を見て、 「それで、君の気持はどうなのだ」 「給料も六千ドルということですので、行ってもいいと思っているのですが」 「なるほど、いまのままでは、君の力からして少し安すぎるかもしれない」 「いえ、わたしは特に不満があっていっているわけではありません」 君の気持はわかった。だが、その話を決めるのは、あと三日ほど待ってくれ給え」 約束どおり三日後に、フレキスナーは昼食会のあと、英世を自分の部屋に呼んで条件を示した。 「この前の件だが、できることなら断念してもらいたい。そのかわり、研究所では君を正研究員に昇格させて永久契約を結びたい。さらに年俸は五千ドルを支給することにする」 「私を正研究員にしてくれるのですか」 英世はききおかえした。これまで英世は準所員であった。正所員というのは各セクションの部長と同じ待遇である。広いロックフェラー研究所にも、正所員は、所長のフレキスナー、病院長のコール、生物学部長のレープ、生理薬物部長のメルザー、化学部長のレヴィン、実験外科部長のカレル(1)の六人しかいない。いずれもアメリカはじめ、世界各国から引き抜かれてきたトップクラスの学者ばかりである。そのなかに英世を入れるというのだ。しかも給料もアップするという。 「年俸五千ドルは、マウント・サイナイよりたしかに一千ドル低い。そのかわり当研究所の研究費は、サイナイよりはるかに豊富なはずだ。ここなら自由に金を費えるし、研究所としての名もある。どうだ。この条件で残ってくれないか」 英世は、一日考えさして欲しいといって部屋を出た。正直いって、フレキスナーがそこまで考えてくれているとは思わなかった。せいぜいいまの給料を五、六割上げるくらいかと思っていた。条件を示されたとき、英世は即座に「残ります」といってもよかった。だが、いままでは出るつもりだったので、心の整理に一日かかった。 翌日、英世は昨日の条件で残ることを伝えた。 「給料は来年からアップするから、いま少し我慢してくれ」 フレキスナーはようやくほっとした表情で英世の手を握る。 アメリカの学者はドライというが、金についてもはっきりしていた。能力のない者は古くからの弟子でも、どんどん馘にするかわり、優秀であればどこまでも条件をよくしてとどめようとする。働いている側も条件が合わなければ、さっさと他所へ出ていくい。互いに条件を出し合うことに躊躇しない。「この取引は公正だったと思います」と守之助への手紙へ書いたように、英世は満足だった。 ロックフェラー研究所の正所員は一応、形式的に、年に一度、研究所の理事会で互選によって選ばれることになっていた。一九一四年(大正三年)七月、英世はついにロックフェラー研究所の正所員に昇進した。さらに翌一五年には、「アソシエーション・オブ・アメリカンフィジシャン」の会員に推薦され、スウェーデン国王から北極星勲三等を下賜された。まさにアメリカ医学界の最高峰にたどりついたといえる。 一九〇〇年、二十五歳で、無一物のままフレキスナーのもとにころがりこんでから十四年目、このとき、英世はまだ三十九歳の若さであった。
※(1):アレキシス・カレル 渡部昇一訳『人間この未知なるもの』MAN,THE UNKNOWN(三笠書房)P.20
アレキシス・カレル(Alexis Carrel, 1873-1944)はフランス(Sainte-Foy-les-Lyon)に一八七三年(明治六年)六月二十八日に生まれた。ディジョン(Dijon)及びリヨン(Lyon)の大学に学び、一九〇〇年(明治三十三年)にリヨン大学で医学の学位を取得、そこで二年間、講義用の死体解剖助手をしながら自分の研究をはじめた。しかし、当時の唯物論的医学の風潮が強かったフランスの大学においては神秘家的の素質のあるカレルの学者としても前途は明るいものではなかった。それに幻滅を感じたカレルは三十二歳の時(一九〇五年、明治三十八年)にカナダに渡り、牧畜業をやろうとする。幸いにシカゴ大学のハル生理学研究所(the Hull Laboratory of the University of Chicago)に勤務することになり、牛の牧場を作ることを断念した。更に幸いなことには、彼の才能がフレキスナー(Simon Flexner, 1863-1946)の目にとまり、ニューヨークにあるロックフェラー医学研究所(the Rockfeller Institute for Medical Research) スタッフとして招かれることになった。フレキスナーは赤痢菌を分離したり、脳脊髄膜炎の治療血清を発展させたすぐれた細菌学者・病理学者であると共に、他人の才能を見出してその業績を伸ばしてやるという研究組織のリーダーとして稀なる素質をもっていた。ロックフェラー医学研究所の設立に彼が参加し、そこで指導者の地位にあったことは、カレルのためにも、また日本の野口英世にとっても、いな医学の進歩そのものにとっても極めて幸いなことであった。フレキスナーなかりせば、カレルも野口もなかったことは、ほとんど確かなのであるから。 フレキスナーの下でロックフェラー医学研究所で研究するようになってからのカレルは、魚が水を得たように生き生きとし、次から次へと大きな業績をあげた。そして六年後の一九一二年には同研究所の正会員になった。この年に彼は、血管縫合と内臓移植の新法の開発によってノーベル生理学・医学賞を授けられた。彼は更に肉体から切り離された組織を生体外で培養し、無限に生かしておくという可能性の研究を行なっている。そして、この当時としては突飛ともいえる仮設を実証したのである。すなわち、彼はまだ卵の中にいる鶏の雛から心臓の組織が昭和二十一年まで、つまり彼の死後二年経つまでガラスの器の中で生き続けていたわけである。この実験は培養液さえ適当であれば、組織の細胞は普通考えられるよりも何倍の長さに生きることを証明したわけで、生体を考える上で特別に意味深いものであることは言うまでもない。 4 この年の四月、英世に、東大から理学博士の学位が授与された。日本の学位は、三年前の一九一一年に、すでに医学博士号が授与されていた。このとき提出された論文は、主論文が「蛇毒の血球に及ぼす保護作用についての研究」「化学的作用により補体が非動性となり又は再生することについて」「蛇毒及び蛇血清の構造」の三篇、他に副論文が九十三篇であった。これだけ多数の論文を提出した者は、英世をおいて他にいなかった。だが、英世はこの論文を東大でなく京大の医学部に提出した。しかも本人から直接でなく、血脇守之助が推薦した形で提出した。本来、英世が東京で医術開業試験を受け、一時的にせよ北里研究所にいたことを考えれば、東大に送るのが自然で、京大に提出するのはいかにも不自然である。 だが英世は、意識的に東大を避けた。北里柴三郎は東大出あり、研究所にも東大出の医師が何人かいたが、英世は彼等にあまり好感を抱いていなかった。いじめられた記憶さえあれ、楽しかった思い出は一つもない。単身アメリカに渡ったのも、東大出ばかりが優遇される日本にいては駄目だと見切りをつけたからである。アメリカにきて、日本の学者が井の中の蛙で、外国から教えを乞うだけの存在であることもわかった。欧米に一、二年留学しただけで、帰国すると、すぐ教授になって大きな顔をしている。そんな連中に俺の論文を審査されてたまるか、というのが、英世の本音であった。 「小生の博士論文は、多分一、二年後には許可となることと思います。日本の大学や政府がなにをいったところで、世界に認められつつある小生の学業は、博士以上の価値あることと確信しています。日本の博士の肩書の二つ三つくらいあったところで、海外に出てくると見向きもされないようでは、なんの効果もないと思います」 例によって守之助への手紙のなかで憂さを晴らしたあと、 「二、三年、ドイツに留学し、ろくにドイツ語も話せぬ連中が、帰国早々博士の学位を受けるのは、まことに奇妙な話です。彼等は世界の医学界では、まったく無名の存在です。自国でのみ、洋行を金看板としてごまかしているのは、日本医学の恥辱です。小生は幸い、日本博士の称号の必要もなく、たとえ持って人に示したところで、欧米人の目には鼻紙同然、彼等は日本学位を重んじません。したがって小生は日本の学位はどうでもよろしいのです」 こうはいっても、英世の本心はやはり日本の学位が欲しかった。それが世界で通用しないことは充分承知していながら、自分より劣る者が、学位をとっているという事実が口惜しかった。それにくわえて、英世には大学を出ないが故の学歴コンプレックスがあったし、日本にいる恩師や友人に対して誇るには、外国での馴染みのない栄養より、日本の学位をとることが手っとり早かったからである。 その結果、明治四十四年、京大から医学博士の学位が授与された。 だが、今回の論文は東大に提出された。内容は一九一〇年以降からはじめられたスピロヘ-ターに関する一連の仕事である。世界の一流の学者を前に絶賛を浴びた業績を、日本の大学で認めないわけにはいかない。どうだ、今度こそ参ったろう、目前に東大の教授がいれば胸を張ってみせたいところだが、 「俺をいじめた奴等に、世界的論文を見せたところで仕方がない」正直、英世はそういいたい気持だった。 ここでも論文はすんなり通った。もっとも、前回の蛇毒にせよ、今度の梅毒スピロヘ-ターの論文にせよ、日本にそれを審査するだけの専門家がおらず、実際は質疑のしようもないフリーパスであった。 これでともかく、英世は医学博士と理学博士の二つの学位をえたことになる。しかも一方は京大、一方は東大である。大学も出ず、私塾から医術開業試験に合格しただけの者としては、初めてのケースであった。 ロックフェラーの正所員になり、各学会の正式メンバーに推され、各国の栄誉勲章を受け、二つの学位をえて、一九一四年から一五年にかけ、英世はまさに学者としての最高の階段を登りつめた。もはやロックフェラー研究所において、「ドクター・ノグチ」の名は、外すことのできない重要な看板であった。 当時、ロックフェラー研究所に入り、いまなお健在なドクター・ストークスは、そのころのノグチの思い出として、 「研究所に入って、初めての昼食会のとき、ドクター・ノグチも出られるというので、私達は緊張して待っていた。やがて各所員が着席して昼食会がはじまろうとした直前に、ドクター・ノグチが現われた。小柄でせかせかした歩き方で自分の席に近づいていく。私達は、"あれがドクター・ノグチだ"と囁き合った。彼はみなのうしろからテーブルを覗きこみ、"なんだ、今日の昼食はまずそうだな"といった。みなの前で、そんなことをいえるドクター・ノグチに私達は改めて感嘆した」と話してくれた。 研究所をわがもの顔で動いている、英世の自信が窺える。 かくして正式所員になるとともに、英世には特別の研究個室が与えられ、白人の女性秘書の他に専属の助手が三名ついた。研究費も、彼が要求するものはほとんど特別のことがないかぎり全額認められた。 当時ロックフェラー研究所は資金が豊富で、設備も一流であったが、研究所としての格は、ヨーロッパのそれにくらべると、まだ二流であった。ロックフェラー研究所としても、財団としても、早くいい研究成果を発表して世界の一流研究所の仲間入りをしたい。そのためにぜひスター学者が欲しい、その要求に、「ドクター・ノグチ」の存在はまさにかなっていたともいえる。 この年(一九一四年)から、第一次世界大戦がはじまり、ヨーロッパ各地が戦場と化した。ヨーロッパ在住の学者は、落ち着いて研究するどころではなく、一部の者は野戦病院にまで狩り出される。科学者にとっては受難のときが訪れた。だが、このことは相対的にアメリカの医学界のレベルを引き上げることになった。皮肉なことに戦火に巻きこまれて研究が手につかぬあいだに、アメリカの学者は悠々と仕事ができた。間もなく戦火は止むが、ヨーロッパ医学の退潮、とくにドイツ医学の地盤沈下は、このころからはじまったといえる。 それにしても、英世はいいときにヨーロッパへ行ったものでさる。もしあれが一年でも遅れていたら、各国の反目が激しく、あれほど成果のある旅はできなかったかもしれない。とにかく、いまや英世は学者としても恵まれた立場にいた。世界でも最も優秀と折紙をつかられた医学者が、最良の条件の下にいる。だが、ヨーロッパからの帰国後、英世の仕事は必ずしも順調ではなかった。 このころ,ロックフェラー研究所の主な研究テーマの一つに、小児麻痺に対する血清学的研究があった。小児麻痺の病原体については、ヨーロッパ旅行前、英世がすでに見出し、各地の講演会で示していた。また旅行中、研究所の二人の助手がさらに分離することに成功し、また一人は、英世と同じ染色法で、組織中からその微生物を見付け出していた。このことから、フレキスナー所長は、さらに一歩すすめて、病原体に対する血清ワクチン製造のため、まず病原体を大量に培養することを英世に依頼した。 しかし、この仕事に対して、英世は必ずしも協力的ではなかった。その理由の一つは、病原体分離から大量培養の仕事が、英世個人の仕事でなく、研究所全体の共同研究になっていたからである。 フレキスナーにしてみれば、研究所の有力スタッフを投入して、この仕事をすすめるつもりであったが、英世は以前から共同研究を好まなかった。他人の仕事を信用できない英世にとって、共同研究は最も苦手である。共同研究では相手に気をつかったり、議論するだけ余計な手間に思われる。それに英世自身、小児麻痺の問題はすでに片がついたと思っていた。ヨーロッパで、自ら標本を持参して、顕微鏡で病原体を示し、さまざまな賞賛をえた。その病原体の分離を、いま初めからやり直したところで、たいして価値はない。 さらに英世がこの研究にのり気になれなかったことは、共同研究者のなかに、先に発表した病原体を疑っている者がいることだった。この点については、先のウィーンの学会で、コッㇹ研究所の青年が疑問を提出し、英世は怒りのあまり、その男の名刺を引き裂くという一幕があった。さすがにロックフェラー研究所には、それほどはっきり疑問をうち出している者はいなかったが、多少疑っている気配はある。そして現にアメリカでも、一地方の学者が、英世とはまったく別の病原体を、小児麻痺のそれだと発表している。 英世はそれらの疑問を、即座に否定した。 「なにおいまさら寝惚けたことをいっているのか。私の病原体はすでにヨーロッパでも認められている。この私が、この目で確認したものに、誤りがあるわけがないではないか」 ヨーロッパでの栄光に輝いた英世は初めから相手にしなかった。だが言葉の鋭さにくらべて、その内容は、「この俺がやったのだから……」というだけで、論理的な裏付けに乏しかった。ヨーロッパから帰って以来、英世はかなりの自信過剰になっていた。 「彼等がやったところで、そう新しいものが出てくるわけはない」 この仕事に英世は初めから非協力的だった。共同研究者として名を連ねても、実際にはほとんど仕事をしなかった。それより英世は新しい狂犬病の仕事に精力を向けていた。目的はその病原体の生活史と、その免疫機構の解明である。この仕事は当然のことながら、英世一人でやる。 だがこの研究にとりかかって間もなく、英世自身、あまり期待がもてそうもないことを知った。狂犬病小体については、すでにパスツール等によって見出され、もしそれが病原体であるなら、彼等が免疫物をつくっているはずであった。 英世はさらに豚コレラの研究に手を出す。 「私はこの病原体の発見に最善をつくすつもりです。もし、この病気についてなにかの発見があれば、何人の名前が出ようと、それは私が成しとげたことと思って下さい」 守之助に書き送る英世はあくまで個人プレイの好きな、一匹狼であった。だが、狂犬病も豚コレラについても、一向に好ましい結果はでてこない。 苛立った英世はさらに以前手をつけたことのあるトラコーマに向かう。さらには天然痘のワクチンの純化の仕事もはじめる。また、新たにアメリカに流行しはじめた口諦疫にも首をつっ込む。しかしこのいずれにも、満足すべき結果は出てこない。なににでもとびつき、いっときがむしゃらに突きすすむが、少し行き詰まると急に息切れした犬のように、へたへたと蹲み込む。かつて英世一流のねばりと慎重さが、少しずつ欠けてきていた。 この仕事の不調を裏書きするように、偶然受けた健康診断で、「心臓肥大」が指摘された。 「激しい運動は避け、無理をしないように少し休息をとることです」医師がいうのに、英世は疑わしげにうなずいた。 すぐ日本の友人やマドセン博士に「少し緊張して仕事をやりすぎ、ごく軽い心臓病をおこしたようです。でも私はちっとも気にしていません。正常の人でも心臓が肥大することは、よくあることのようですし、二、三か月もすれば、じき治る病気のようですから」と書き送った。 だが英世の仕事は体が資本であった。才能もさることながら、人一倍の努力、こまめに体を動かし、寝食を忘れて仕事をする。それが英世の今日をつくりあげてきた。それを考えると、休息を命じられたことは、やはりショックではあった。「人間ダイナモも、少し油が切れてきたのか」冗談半分にいいながら、その実、かなり不安ではあった。医師にすすめられて、英世はエレベーターつきのアパートへ移った。 「なにものも、自分をおさえつけることはできない」 そう豪語していた英世の前に、ようやく暗雲がたちこめてきた。仕事の面でも、青ばかりの快適な高速から、黄色の信号が近づきつつあった。 だが、その優さを吹き飛ばすように、日本から吉報が届いた。当時、日本で学者に与えられる最高の賞であるといわれた、学士院恩賜賞の報せである。
第四章 貴 国 P.117
1 帝国学士院恩賜賞は、いうまでもなく、わが国学者の与えられる最も優れた権威ある賞ということになっている。いまでこそ、学者に対してはこの他にいくつかの賞が創られているが、当時としては数少ない賞のうちの、最高の栄誉であった。この受賞者は、名のとおり帝国学士院の会員によって選ばれるのが原則であったが、あらゆる賞がそうであるように、選考委員とコネのある者が有利であることはいうまでもない。 過去の恩賜賞の内容からみて、英世の業績が低かったというわけではない。それどころか、欧米で見聞したことを紹介しただけの当時の学者の仕事とくらべて、英世の仕事は一段抜きんでていた。恩賜賞を与えられても当然の業績ではあった。 このとき、英世を積極的に推したのは、血脇守之助の知人で宮中の侍医をしていた三浦謹之助博士で、彼は守之助から英世の仕事をきき、欧米での評価の高さを知っていた。英世へ博士論文を提出するようにすすめたのも三浦であった。この三浦の熱心な推薦と、学士院院長菊池大麓に、かつて英世が石黒忠悳を介して会っていたことが幸いした。なかに東大系の一部の学者に反対があったが、それを押しきって英世の受賞が決まった。 一九一五年(大正四年)四月、この賞の報せを知ったとき、英世は、妻がバス・ルームでシャワーを浴びているのもかまわず、駆け込んでいった。 「メディ、俺はついに帝国学士院賞をもらったぞ」 そんなことをいっても、アメリカ人の妻にわかるわけはない。 「日本で最も偉い学者に、天皇陛下がじきじきに下さる賞だ、最高の名誉と他に金を千円貰える」 それにメリーはようやく、賞の意味を理解した。 「おめでとう、でもとにかくここから出ていって」 二人はバス・ルームで向かい合っていた。英世はうなずくと、「俺はみんなに報せてこなければならない」といって背広を着た。 受賞の報せとともに、七月五日に、日本で授賞式があるから出席されるようにという連絡があった。まさにお故郷に錦をかざる絶好のチャンスであった。血脇守之助はじめ、日本にいる知人達はみな、英世は喜び勇んで帰国するものと思っていた。 だが英世は帰らなかった。理由は、単に忙しくて時間をとれない、というだけのことである。英世はそれを守之助に報らせ、お祝いにきた日本クラブの面々にも伝えた。 早速、画家の堀が、英世の家にきてきいた。 「こんな名誉な機会に、なぜ帰らないのですか。日本を発ってもう十五年になるんでしょう、みんな待ってます。それに恩賜賞の授賞式に欠席するなんて、陛下に対しも失礼でしょう」 「それは俺も気になる」英世は好物の葉巻を口髭の下でくゆらせながらいった。 「しかし、いま帰っては恩賜賞のために返ったように思われる。陛下には申し訳ないが、日本の賞などは日本の学位と同じで、つまらぬ学者達でさえ貰っている。世界のレベルから見たらまだまだ低い賞だ。俺のこれまで貰った賞のどれよりも低い」 「それは、あなたからみればそうかもしれません。しかしあなたは日本人でしょう。日本の学者や学会を一方的にけなすのはいけませんよ」 「君がなんといおうと俺は日本の学者は嫌いだ。とくに東大の連中は顔を見るのもいやだ。東大出でいい男といえば真鍋くらいなものだ。あとは日本だけで権威をつけ、世界では通用しない田舎者ばかりだ。そんな奴の前で、嬉しそうに恩賜賞を貰えるか」 さすがの堀も、英世の頑固さに溜息をついた。 「あなたの気持はよくわかりますが、そう我を張るものではありませんよ。それに母さんも待っているでしょう」 「母には会いたい。でも日本は遠いからね」 「旅費のことが心配なのですか」 「それもあるけど、とにかく、俺はいまは帰らない」 結局、恩賜賞は血脇守之助が代って受け取ることになり、その賞状と賞牌は小林栄を通して、母に見せてくれるように頼むことになった。 「私は帰りたい気持はやまやまです。この数年は老いた母のことが気になり、夜もろくろく眠られぬ日もあります。だが私の研究はいま最終の時にさしかかっています。これを抜ければ、ノーベル賞も夢ではありません。ノーベル賞金は、毎年世界の優れた学者十名(理、化、医、文、政、慈善、哲、其他一名ずつ)を選抜し、各人に四万円ずつ贈られものです。医者でこの名誉をえたものはすでに十名になりますが、アメリカではまだ一人もいません。前大統領ルーズベルト氏に日露戦争の平和の功に対し与えられたのみです。ヨーロッパの医学者ではエールリッヒ、ベーリング、メチニコフ、パブローフ、コッホ、其の他です。もちろん日本ではまだ誰もいません。人の運は予測できないもの故、私がこの賞を受けないと断言することもできません」 守之助への依頼の手紙に、英世はこのように書いた。病気などでなく、仕事が忙しいというだけの理由で、恩賜賞の授賞式に出席しなかったのは、あとにも先にも英世ただ一人であった。
この恩賜賞受賞が決まった翌月、石塚三郎は猪苗代の撮影会のあと、三城潟に寄って、英世の母の写真を撮った。 石塚はかつて高山歯科医学院で、英世と一緒に玄関番をしているが、学院を卒えたあと越後長岡で歯科医院を開業し、その地方の有力者となり、代議士になっていた。 石塚はこの写真を、近況報告かねて英世に送った。 「是非一度帰ってきたらいい、お母さんもこんなに年齢をとられた」 写真の母はつぎはぎだらけの袷に、モンペをはき、背を丸めて写っていた。英世が別れた当時より痩せて小さくなり、髪の半ば以上が白くなっている。このときシカは六十二歳になっていた。 「お母さんは相変らず苦労している。この写真を見て、誰が医学博士・理学博士野口英世氏の母と思うだろうか。このお母さんのためにも、ぜひ帰ったらどうです。人々のあいだに恩賜賞受賞の記憶が新しいいまこそ、故郷に錦をかざる絶好の機会です」 この写真とともに母シカが自ら書いた手紙が同封されていた。 おそらくチビた鉛筆で、一字一字たしかめながら書いたのであろう。平仮名と片仮名まじりの稚拙な文章である。だがそのなかに母の子を思う真実があふれている。母から子に宛てた手紙として、まさに名文中の名文といえる。 猪苗代の野口記念館には、この原文が保管されているが、文句の形は修正して、文章だけを記しておく。
『おまィの。しせ(出世)にわ。みなたまげました。わたしもよろこんでをりまする。なかた(中田)のかんのんさまに。さまにに。ねん(毎年)よこもり(夜籠り)をいたしました。べん(勉)京なぼでもきりがない。いボしほ(烏帽子)わこまりをりますか。おまいか。きたならば。もしわけ(申訳)かてきましよ。はるになるト。みなほかいド(北海道)に、いてしまいます。わたしも、こころぼそくありまする。ドかはやく。きてくだされ。かねを。もろたこトたれにも、きかせません。それをきかせるト。みなのれて(皆飲まれて)。しまいます。はやくきてくたされ。はやくきてくたされ。はやくきてくたされ。はやくきてきたされ。いしょ(一生)のたのみて、ありまする。にしむいてわ。おか(拝)み、。ひがしさむいてわおかみ。しております。またきたさむいてわおかみおります。みなみむいてわおがんでおりまする。ついたち(朔日)にわ。しおたち(塩断)をしております。ゐ少さま(栄昌様)に。ついたちにわ。おかんでもろておりまする。なにおわすれても。これわすれません。さしん(写真)おみるト。いただいておりまする。はやくきてくたされ。いつくるト。おせ(教て)てくたされ。これのへんち(返事)ちまちまちてをりまする。ねてもねむられません』(烏帽子ー近隣の部落名。栄昌様ー隣家の鵜浦栄昌、天台宗の修験者)
英世は迷った。正直いって、母の写真にはショックを受けた。まだまだ元気だろうと思っていたのが、老いて子供のように小さくなっている。青年期から壮年期に向けて、英世が逞しくなったのに対して、母はその分だけ確実に老いたようである。 「帰ったほうがいいだろうか」英世はメリーに相談してみる。 「会いたいのなら帰ったほうがいいわ。でもお金はどうするの」 このとき年収五千ドルも貰いながら、ノグチ家は相変らず余裕がなかった。ときにメリーがヒステリーをおこしてビールを飲んだり、手当り次第に買物をすることもあるが、そんなことは知れていた。問題なのは、やはり英世の浪費癖だった。五千ドルももらい、差し当たり債鬼に悩まされることもないだけに、英世はますます気が大きくなっていた。友人とレストランなどに行っても、メニューもろくに見ずに、のっている料理すべてをもってこいなどと注文する。 後年、英世がブラジルで研究をして帰るとき、現地の人達が残った高価な薬品の処置について尋ねた。英世は即座に、「君達が自由につかい給え」と答えた。だがそのあと、ロックフェラー財団でそれをめぐって一悶着がおきた。 気前がいいというか金銭に無頓着というか、公私の区別さえつかない。あれほど細密な仕事をする男が、こと金に関しては、先天的と思われる欠陥があった。メリーも、英世の金遣いの荒さにあきれて、いまは半ばあきらめていた。 「星さんに頼めば、なんとかなるかもしれない」 星一は福島県の同郷でフイラデルフィア時代から知っている。いまは日本に戻って製薬会社を創立して順調にいっているようである。英世はこの星に頼まれて、細菌の医学界情報などを送っていた。 「しかし、日本に行くとなると、相当の日数がかかるし、仕事も中断しなければならない」 「どうせこのところスランプなのでしょう。いっそ日本へ行ってきたら、調子が戻るんじゃないの」 このごろ夫は深夜、仕事をしているかと思うと、一人で考えこんでいたり、夜中に「駄目だ、駄目だ」と叫びだしたりするのを、メリーは知っていた。 「やはり、少し休んだほうがいいだろうか?」 「仕事のことはわたしにはわからないわ。でも迷っているくらいなら、日本へ行って気分を転換してきたほうがいいでしょう」 アメリカ人だけに、メリーのいうことははっきりしていた。 「よし、行ってこようか」 英世はようやく決心し、翌日、フレキスナーの承諾をうると、ただちに日本の星に宛てて電報を打った。 「ハハミタシ、ニㇹンニカエル、カネオクレ」 まるで、英世のほうから命令しているような電文である。 電報を受け取った星は、すぐ五千円を送ってよこした。星は前から英世の浪費癖を知っていた。帰るにしても、ろくな洋服を持っていないだろう。英世とメリー夫人との旅費、それに郷里に錦をかざるにふさわしい服装など買い改めたとしても、なお充分すぎる金額であった。 だが、メリーは結局日本へ来なかった。 「一緒に行こう」 英世は誘ったが、彼女は即座に「わたしは行かないほうがいいでしょう」といった。 「日本は遠すぎるし、食物も住むところも違うのでしょう。それに日本の男性は奥さんを連れて歩くのが嫌なのでしょう」 皮肉まじりだが、メリー自身東洋の果てまであまり行きたくもなかった。英世にしても、白人の妻を日本に連れていって、はたからいろいろいわれる煩雑さや、貧しい生家などを見せる憂鬱さを思うと、強いて誘う気もおきなかった。 2 大正四年九月五日午後四時、英世の乗った横浜丸は横浜港の第一埠頭に接岸した。 この三時間前から血脇守之助と小林栄は、ともに日本郵船横浜支店楼上で待機していた。 二人は船が接岸する前、本牧沖に現われた時点で先に船に乗り込み、英世に会うつもりであった。 岸壁には英世の帰国を待ちわびて、北里研究所は検疫所時代の仲間、それに新聞記者などが詰めかけていた。その人達の前に、英世は例の薄汚れた背広姿で現れるのではないか。長い外国生活で、日本の事情にうとく、つまらぬことを喋りだすのではないか。それで、また評判を落してはたまらない。世界の第一級の学者として恥かしくない姿であって欲しい。大学者といっても、二人にとっては、さんざん迷惑をかけられた子供か書生としてか思えない。とにかく先に会って、服装を点検し、注意を与え、岸壁の歓迎陣の様子などを伝えておくほうが間違いない。そんな思いやりから待っていた。 だが、どういう手違いがあったのか、郵船の社員が駆けつけてきたときはすでに「ただいま、桟橋に到着いたします」という連絡が入ったところだった。 「冗談じゃないぜ、われわれは本牧沖で乗り込む手筈だったんだ」 守之助は怒ったが、もはやどうしようもない。慌てて二人は歓迎陣のいる桟橋のほうに駆け出した。 かつての清作は、はたしてどんな姿で現れるのか、二人が不安と期待で見上げていると「野口博士だ」とい声とともに、一斉に拍手が湧き、カメラマンのフラッシュがたかれた。 守之助は一瞬目を閉じ、それから恐る恐る人々が手を振る方向を見た。一等船室の上甲板に、英世の小さな体が胸を張って立っていた。きちんとモーニングを着て、例の縮れた髪をきれいに撫でつけ、右手に持ったシルクハットを激しく振っている。珍しく白い歯を見せ、穏かに笑っている。どこから見ても洋行帰りの堂々とした学者の姿である。 「よかった」守之助がほっとして横を見ると、小林栄も目を瞬かせながら、しきりにうなずいている。 やがて英世は甲板からタラップを降り歓迎陣のなかに入った。 「先生」 群がる人々のあいだを英世は真先に守之助の前にかけより、それから横にいる小林榮の手をとって「父上」といった。 明治三十三年、単身渡米してから、十五年ぶりの再会であった。 「ただいま帰りました」 英世はそれだけいって頭を下げた。二人はなにもいえず、英世に手をとられたまま目を伏せていた。英世より二人のほうが泣いていた。 他の出迎えの人々と握手を交したあと、英世は貴賓室で簡単な記者会見をした。 「この十五年間、一日たりとも日本のことを忘れたことはありません」 英世はそう述べたあと、最近の自分の仕事について簡単に触れ、「自分がこれだけのことをやれたのも、すべて日本にいる皆様のお陰だと思っています」と答えた。 欧米で数多くの記者会見を経験してきただけに答えの勘どころもよくわきまえ、守之助と小林栄の心配はすべて杞憂であった。 記者会見のあと、英世は同郷の先輩六角謙吉が用意した二頭立ての馬車に乗って横浜停車場に行き、そこから汽車で東京へ向かった。同乗するのは血脇守之助、小林栄はじめ、横浜検疫所、北里研究所の同僚、それに数名の新聞記者などであった。 やがて汽車は夜八時、東京駅に着いた。そこにも、英世のかつての高山歯科医学院、北里研究所時代の同僚、知人をはじめ、東京歯科医学専門学校の生徒など、多数が出迎えていた。 英世はその一人一人と握手をし、「ありがとう」「ご苦労さん」をくり返した。 そこから血脇守之助、小林栄とともに自動車で宿泊先の帝国ホテルに入ったが、ここでも数十人の歓迎者と挨拶を交し、歓談した。 午後十時、ようやく来客が去って、守之助、小林等、身近な人ばかりとなった。そこで初めて会津のことなど話し、十一時過ぎて、小林は親戚の家に帰ることになった。英世はハイヤーを頼み、恐縮する小林を、自ら送り届けてきた。
翌六日、日本にきて初めての朝である。 英世は、まず、文部大臣を訪ねて恩賜賞の謝礼を述べたあと、東京市長、日本医師会長、東京医師会長らを訪れ、帰朝の挨拶をした。さらに白金の北里研究所へ行き、北里所長に挨拶をした。 「よく帰ってきた、ご苦労さん」かつて研究所に君臨し、所員を震えあがらせていた北里も、いまは老いてずいぶん穏やかになっていた。 「おかげさなで」英世はそれだけいって頭を下げた。 守之助のたてたスケジュールでは、この挨拶廻りのなかに、東大学長への挨拶も入っていた。だが英世は、即座に「行く必要はない」と断った。 「学位をもらっているし、青山学長は日本の医学界の第一人者だから」 守之助がすすめても、英世は、東大の学位は理学部から貰ったものだし、青山はなんの世話にもなっていない」といってつっぱねた。 恩賜賞の受賞に対して、青山が反対したこともきいて、英世はいままで以上に、東大閥に神経質になっていた。 英世が横浜に着いたとき、桟橋には東大の真鍋教授が迎えにきていたが、真鍋はかつて、英世がウィーンの医学会に招かれたとき案内役をかってでていらい親交があった。この真鍋のところへ、英世は社中でわざわざ近づいてきて、「君は東大を代表して迎えにきてくれたのか」ときいた。 一瞬、真鍋は戸惑ったが、すぐ「そうです」と答えた。 実のところ、真鍋は個人的に迎えにきただけで、東大の代表ではなかった。それどころか東大は英世の帰国できわめて冷淡であった。真鍋が横浜へ迎えに出るときも、世界的な学者が帰ってくるのに、せめて東大を代表する者が一人くらい迎えに出るべきではないか、と教授会で訴えたが、他の教授達は黙ったままなにもいわなかった。 正直なところ、教授達は世界でのノグチの名声を、それ程知ってはいなかった。現実にウィーンにいて、ミュラーの歓迎を目のあたりに見た真鍋とは、そのあたりの認識が違っていたし、それといま一つ、学長の青山胤通が英世をあまりかっていなかった。 「もともと医術開業試験あがりの北里にいた者が、アメリカでちょっと名をあげたからといって、わざわざ迎えに行くまでもあるまい」 学長がそんな考えだったから、教授達も知らぬふりを装った。だが真鍋はみんなに訴えた。 「あの人は、いまや日本を代表する世界的な学者です。アメリカの研究室にいても、ヨーロッパでも彼の名を知らぬ人はいません。恩賜賞を受け、ノーベル賞候補にもあげられている人を無視するのはまずいのではないでしょうか。きくところによると、石黒忠悳男爵もホテルに挨拶にうかがうとのことです」 当時の医学界の元老格であった石黒忠悳は、英世が東京に着いた翌々日、宿泊先の帝国ホテルに訪ね、歓迎の言葉を述べた。石黒公まで行くとなっては、青山も知らぬ顔をしているわけにはいかない。その日、午後、青山は急遽予定を変え、帝国ホテルに出かけることにした。 青山が挨拶にくる旨を、真鍋が告げると、英世は「本当か」と二度たしかめた。それから。「ついに東大学長が俺のところに挨拶にくるか、青山もついに俺に頭を下げるか」といって大声で笑いだした。 結局、その日は石黒忠悳、青山胤通など、医学界からジャーナリズム、政界まで、多くの名士が挨拶に現われ、英世はその応対に忙殺された。そしてその夜、初めて歓迎晩餐会が北里博士の主催で開かれた。会の出席者は北里研究所の出身者、門下生が中心であったが、英世はとくに頼んで、血脇守之助、小林栄の列席を認めてもらった。 かつて研究所でモルモット一匹もえられず、動物小屋の掃除ばかりさせられていた研究生のために、北里は静かに歓迎の言葉を述べた。それに返して英世は「私の今日あるのは、北里博士をはじめ、所員のみなさんの、親切な指導とご援助のたまもものです」と答えた。 謙虚な、控え目ないい方であったが、ききようによっては痛烈な皮肉ともとれる挨拶であった。 3 九月五日、日本に帰国してから三日後の八日、英世は郷里の会津に向かった。懐かしい母に会うためである。 だが、このときの英世の気持はいささか複雑だった。故郷を離れて十五年ぶりの帰郷である。母はもちろん、生れ育った山も湖も見たい。ニューヨークのどまんなかにいても、磐梯山や猪苗代湖の姿は忘れたことはない。だが、故郷はいうまでもなく山河だけが残っているわけではない。そこには、家族とかつての知人や旧友達もいる。英世を「手ん棒」とあざ笑った男達もいた。もちろん、凱旋将軍さながらに帰ってくる英世に、いまさらそんなことをいう者などいるわけはない。昔の悪童達にしたところで、そんなことをいったことを後悔し、忘れたいと思っている。 英世も、いまさらそんなことにこだわっていない。それより、英世が気がかりなのはこれまで故郷の友達から借りた金のことである。初めはじきに返すといって借りたのだが、医者になれば返すになり、さらにアメリカへ行けば高い給料がもらえるから返すと変ってきた。この間借りた金は莫大な額になる。まともに計算のしようがない。そのほか、うまいことをいってせしめてきた背広や本、その他の物品など数えあげたらきりがない。 「出世払い」という言葉があるが、英世はいま、まさしく出世していた。これ以上望めないほどの栄光の座についているが、いまさら払う意志もないし、その余裕もない。 「故郷の者達はどう思っているのか、なかには自分を恨んでいる者もいようし、大噓つきだと触れまわったり、金を返せと、押しかけてくる者もいるかもしれない。それを思うと、故郷へ帰る気持も重くなる。 だが、この英世の心配は杞憂に終わった。 英世の乗った汽車が郷里の翁島停車場に着いたとき、駅頭では一斉に花火が打ち上げられ、ホームには、郡会議員、村会議員はじめ各区長、役場吏員など四百余名が整列して待ち受けていた。さらに駅頭には、「歓迎、野口英世博士」と書かれた大きな緑のアーチが建てられ、その前には翁島はじめ、近村の小学生が並び、一斉に「万歳」を叫んだ。沿道には英世を一目見ようと集まった人々が小籏を振って出迎え、家々は国旗を出して祝意を表すといったありさまだった。 一行は村長が決めたスケジュールによって、駅頭から村の八幡宮に向かい、英世が礼拝して帰国報告をおこない、社頭で参集した人々に挨拶した。次いで村長と旧友の八子弥寿平が代表して歓迎の辞を述べ、お神酒で祝杯をあげ、さらに英世が謝辞を述べて歓迎会は一旦解散した。 このあと、英世は三城潟村内三十軒の一軒一軒を訪れ、留守中家族が世話になった礼をいい、菩提寺長照寺の墓に詣で、そのあとようやく家に向かった。 この間、母のシカは人々の前に現われず、家から一歩も出ずひたすら英世が戻ってくるのを待った。 英世が横浜に着いたときも、一刻も早く会うようにと、小林栄が同行をすすめたが、「めくせぇ母が、いっぺぇの人前さ出だら、かえって邪魔になるだけだ」といって辞退した。そのかわり、家に戻る前に、お世話になった家々に帰郷挨拶をすること、菩提寺に先に詣でることなどは、すべて小林栄を通じてシカが指示したものだった。世界的な大学者も、母の命令には一言も逆らわなかった。 そのいいつけを果したあと、英世はようやく家に戻ってきた。 シカは英世の到着前から、生家の前の小道の前に出て待っていた。セルの袷を着て、背は曲っていたが、顔だけはしっかり前方を見詰めている。 やがて初秋の白く乾いた道の彼方から人力車の列が見えてきた。田舎の道では、見たこともない長い列である。その先の車が五十メートルまで近づいたとき、突然、先の車が止った。どうしたのか、とみなが見ていると、いきなり黒いモーニングを着た小柄な男が飛び降り、まっしぐらにシカを目がけて駆け出してきた。 「おっ母……」 母の姿を見て、英世は車に乗っていられなかったのである。 「おれ、帰ってきた……」 少年のときの言葉そのまま、英世は母に抱きついた。明るい午後の光の下で」、世界的な学者がしっかりと母に抱きついている。人力車に乗ってきた人達も、家のまわりで待っていた人達も、活動のシーンでも見るように身動きもせずに二人を見ていた。 「えがったなあ、えがったなあ……」 シカはただうわ言のようにいってうなずき、英世の肩を叩いた。苦難をわかち合った母と子の十五年ぶりの再会、といえば、それまでだが、見方によってはこの情景は異様であった。 このとき家の前で待っていたのは、母のシカだけではなかった。父の佐代助も、姉も、その夫も、甥達もいた。その他、近くの家の人達が大勢集まっていた。だが、英世はそれらの人達には目もくれなかった。ただ一人母だけを求め、駆けつけて抱きしめた。その姿は、「俺が会いたかったのは母だけだ」と訴えているようでもあった。 実際、母との長い抱擁を終えたあと、待っていた父や姉と目を合わせたが、英世は、父には軽く頭を下げただけで、姉のイヌには「元気だったが」と声をかけ、姉の夫にの善吾には「ただいま帰りました」といい、横に並んでいた甥の栄には「大ぎぐなったな」とそれぞれ一言ずついっただけだった。 子供のときから、父は貧しい家計をかえりみず酒を飲み、母を困らせるだけだった。母が苦しみ、一家がどん底の生活をしたのも父のせいである。その嫌悪感が自ずと表に出てしまった。 いま戻った家は、かつて英世が生まれ育った家ではなかった。帰国の前年、生家の右隣りの家が北海道へ移住することになり、五畝ばかりの田とともに手放すことになったのを、買ったものである。三百円と、当時の田舎でも考えられぬ安値であったが、「いまの家では英世が帰ったときに、あまりにもみすぼらしい」という小林栄の意見で買いとった。しかし初めのうちは床もなく、間仕切りにも蓆をつかっていたが、英世が帰国するとなって、慌てて畳や古い襖をいれて形だけは整えた。もっとも家具までは手がまわらず、近くの親戚から借りあつめて、座布団や茶道具などもようやく揃えるというありさまだった。 この家で、英世とシカは膝が触れ合うほど近づいて話を続けたが、父の佐代助は控えめに二、三メートル退ってただ黙ってきいていた。 だが、ここでも英世は落ち着く暇もなかった。 その夜は村の奥野商店で帰朝歓迎会が開かれ、翌九日には、村の青年達に講演をおこない、夜は長浜の港屋旅館で全村の歓迎会が開かれた。十日は朝早く、猪苗代古城町の小林宅を訪れ、小林夫人とも会って、留守中の数々の尽力に、改めて礼を述べた。 このとき、学士院恩賜賞金の千円のことが話題になった。この金は血脇守之助を通して小林栄が受け取り、シカと相談して一部急場の借金に当てていたが、大部分はまだ残っていた。 小林栄は、その金で田畑を買っておくことをすすめ、英世もこれに同意して一任した。この話はのち、隣村千里村の豪農・小檜山氏の耳に入り、時価の三分の一近くの金額で分けることが決まり、小林栄はこれに「恩賜田」という名をつけた。 このあと、英世は母校の猪苗代小学校、猪苗代同窓会などで記念講演をし、さらに旧友だけの集りに出席し、自ら「竹馬会」と名付け、色紙や葉書などを書いた。 さらに十四日からは、喜多方町で耶麻郡医師会、若松市で会津医師会、会津中学校、工業学校、福島市で福島県医師会など、それぞれ講演をおこない、各地の歓迎会に出席し、第一回帰郷の日程を終える。 まさに、歓迎に次ぐ歓迎の十日であった。英世は改めて、郷土の人達の好意に感謝し、帰ってきた喜びを噛みしめた。 だが、すべてが英世に心地よいことばかりではなかった。帰ってきて三日目に、英世は小林宅に挨拶に向かったあと、八子弥寿平の家を訪れた。 八子は小学校からの同級生で、家は相変らず薬屋をやっていた。昔から気前のいい男で、貧しいが成績のいい英世を尊敬していた。英世はこの八子の心理を応用して、子供のときからずいぶん金や品物をしぼりとってきた。英世が上京するときは、金や衣類を渡し、東京へ行ってからも、父に内緒で金庫から大金を持ち出して英世に渡している。 「借金魔」とも「男芸者」ともいわれた、例の巧妙な手口で、金をせびられると、人のいい八子はひとたまりもなく、若松時代から東京時代まで、八子が吸いとられた金は見当もつかない。若き英世を支えた血脇守之助と並ぶ、大スポンサーであった。 さすがの英世も、八子にはいささか気がひけていたせいか、今度の帰郷に当って、英世は最大のお土産として、金の鎖のついた懐中時計を三個だけ買ってきていた。最も世話になった小林栄、血脇守之助、八子弥寿平の三人に渡すためだった。そのかぎりでは、英世は八子の好意を忘れてはいなかった。帰郷したときの歓迎会で、八子が友人代表になったのも、かつて世話になった八子を、いくらかでも立ててやろうという英世の発案からである。 この時計と、籠につめた蜜柑を持って、英世は八子の家を訪れた。弥寿平は、いまや世界的になった大学者が、わざわざ自宅へ訪れてくるというので、朝から家人や手伝いをつかって大掃除させていた。掃除も終え、打水もした玄関に英世が現われた。 家のまわりには、有名な野口英世が現われるというので、近所の人達が人垣をつくって見守っていた。 八子は得意満面で、英世を奥の座敷に招き入れた。そこで挨拶を交したあと、英世が果物籠とともに、金の鎖の時計をとり出した。 「これは帰朝に当って、ニューヨークで買い求めてきたものですが、いままでの世話になったお礼と思いまして……」 英世には奪われることはあっても、もらったことなど一度もない。その男が見たこともない舶来の時計を持ってきてくれたのである。八子は信じられぬ顔で時計を見ている。 「これ、本当に俺にくれんのがぁ?」 「もちろん、あなたの御恩はどんなときにも忘れたごどはありません」 「ありがとう、清さんは、ほんなに俺のごどを思ってでくれだがぁ」 弥寿平が時計を手にとってさすっていると、横に坐っていた弥寿平の母が冷えた声でいった。 「弥寿平、ほんなもの、もらったらだめだ」 いきなりいわれて、弥寿平は母のほうを見た。七十に近い弥寿平の母は、上体をきりっと伸ばし、英世を睨みつけると、息子の手から時計を奪いとり英世の前へ投げ捨てた。 「お返しすっがら」 英世も、弥寿平も妻も呆気にとられている。と、弥寿平の母が一気に喋った。 「ほんなもので、いままでおらんぢがら持ってった銭の帳消しがでぎっと思ったら大間違ぇだ。あんだは弥寿平の人のいいどごさつけごんで、どんだけ家から奪りあげだが、わだし夫は、おめごど恨んで死んでった。あんだのおかげで、家もおれだぢもなぁんぼ難儀したが……」 そこまでいうと、彼女は両手で顔をおおうと、 「帰れ、出でげ、泥棒……」 「おっ母」 慌てて弥寿平が泣きじゃくる母をおさえたが、すでに座は白けきっていた。 「清さん、気ィ悪くしんなな、おっ母は興奮して、あだまがおがしくなってるだけだから」 おれはおがしくなんかなってねぇ、こんな泥棒、早ぐ追い返せ……」 狂ったように叫ぶ母をみなが部屋の外へ連れ出す。そのなかで、英世は一言もいわず、ただうつ向いていた。 4 十日間の会津、福島への旅を終えて、再び東京へ戻ってきた英世には、連日休む間もない講演と歓迎のスケジュールが組まれていた。その一部を抜き出すと次のようななる。 九月十八日、午後五時帰京、七時より在京当時の知人達による歓迎晩餐会(築地田中屋) 十九日、三共製薬株式会社塩原又策氏主催による晩餐会(浜町常盤屋) 二十日、血脇守之助氏主催晩餐会(有楽町生命保険協会・北里柴三郎博士、菊池大麓男爵、渡部鼎等出席) 二十一日、北里研究所訪問、見学 二十二日、緒方、北里、三浦博士、鈴木陸軍、本多海軍医務局長、石黒、高木両男爵等、有志発起人による歓迎大晩餐会(浜町日本橋倶楽部) 二十三日、東京医科歯科学校における講演会、午後六時より金杉英五郎博士主催歓迎晩餐会 二十四日、北里研究所宮島幹之助博士と、千葉県下におけるワイル氏病調査に出向 二十五日、帰京、午後一時より南葵文庫にて講演、夜、徳川頼倫侯邸晩餐会に出席 二十六日、正午麻布奥田邸にて猪苗代在京同窓会に出席、午後二時より医学雑誌社合同主催講演会、午後六時より済生学舎同窓会歓迎会(上野精養軒) 二十八日、午後六時、順天堂医学院歓迎会(柳橋深川亭) 三十日、旧尾張藩主徳川義親侯招宴に出席 ホテルでゆっくり静養をとったのは、この翌日の十月一日のみで、このあと二日には、東大の皮膚科学会で講演、その夜は山上御殿の東大同窓主催の招宴に出席した。 その夜、会津より母親シカと小林夫人が上京、翌日は小林栄が再び上京してきた。これは英世が招いたものであり、折角、帰国してゆっくり一緒にいられない母を慰めるためと、七日からはじまる関西力に連れていくためであった。 このとき、父の佐代助は上京してこなかった。英世の招待の電文に、父の名はなかったし、佐代助自身も同行する気はなかった。母と父への、英世の尽し方は対照的だった。 猪苗代に戻ったとき、それを見かねて友人の六角譲が、英世に聞いたことがあった。 「あれではちんと、お父が可哀そでねぇが」 だが英世は無表情に、 「父は単純な人で、酒だけ飲んでれば満足する人だから、父を喜ばすには、金をやって酒だけ与えておけばいいんだげんども、ほんでは深酒して、体を悪ぐしてしまう。いま程度の不自由さのなかで、自分で働いだ分だけ飲んでんのが、結局、長生ぎさせる道だべ」と答えた。一応もっともな理屈ではあるが、英世の心のなかでは、アル中の人間失格者として、すでに父を見放していた。 二日から五日間、英世が日中、講演や挨拶に出歩いているあいだ、母シカ」と小林夫妻は東京市内を見物して歩いた。シカにとって初めての東京見物である。英世はホテルの車をつかうことをすすめたが、三人は「もつてぇねぇ」といって固辞した。だが英世は強引におしづけ、三人が車に乗るのを見届けて外出した。しかし折角の東京での再開も、午前のいっときで、夜は英世が帝国ホテルに泊っているのに、母と小林夫妻がベッドに休めないところから日本旅館と別れ別れになる。親子はなかなか二人だけで寛ろぐ機会がない。 やがて十月七日、早朝、英世と母シカ、血脇、小林夫妻の同伴の関西旅行がはじまった。ここでも英世は自由な時間はほとんどなかった。午後五時名古屋に着くや、五時から市会議事堂の講演会に出て、そのあと銀行集会所の歓迎晩餐会に出席した。 翌八日、宇治山田に向かい、伊勢神宮を参拝したあと、親子一緒に二見ケ浦の二見館に宿泊した。 この夜、当地の医師会、歯科医師会主催の歓迎会に出席しようとした矢先、東京から「勲四等賞旭日小授賞」叙勲1の電報を受けた。 そして翌九日、一行は大阪に入った。まず大阪高等医学校(現大阪大学医学部)校長佐多愛彦博士の案内で市内を見物したあと、十日は大阪西部の景勝の地箕面に向かった。 この箕面行きは、翌十一日から、またぎっしりつまったスケジュールに追い廻される英世に、母や親しい者だけで水いらずに、のんびり過ごしてもらおうという佐多博士らの配慮から計画されたものである。 当日、佐多博士は一行の宿舎の大阪ホテルに二台の車を廻し、案内役に細菌学の福原義梅教授が同行した。一行はまず大阪城を見たあと、箕面に向かった。いまでこそ箕面は阪急沿線のひらけた住宅地になっているが、当時は訪れる人はほとんどない。初夏の新緑と秋の紅葉のとき、大阪、神戸から遠出してくる人があるくらいのものだった。とくに宴席のもたれた「琴の家」は滝へ通じる川沿いの滝道をさかのぼった先にあり、途中からは車も通らなかった。 一行はその坂道の手前で車を降り、草履にはきかえ、谷川沿いの家へ向かった。このとき英世の一行は、別棟の茶室で茶を飲んで一服したが、シカは足が遅いし、茶の作法も知らないところから、先に「琴の家」に着いて休んでいるといって出かけていった。 「琴の家」では、間もなく英世一行が到着するというので緊張して待ちかまえていると、日焼けした小柄な老婆が先に現われた。 「ここが琴の家だべか」 「そうですが、滝はもっと先ですよ」 女中はこの田舎者らしい老婆を、滝見物か山菜採りにでもきたのだろうと勘違いした。 「おれは、佐多博士のお招きできたんだげんども」 たしかに今日の宴席はは佐多博士からの申し込みだが、それに出席するにしては、いかにもふつり合いである。女中はすぐ女将を招んだが、やはり納得がいかないので、一行がくるまで、一旦、玄関の左手の控室に休ませておいた。 その直後に、英世が到着し、二階の大広間へ行ったが、母が着いていないことを知った。 「六十すぎの老婆が先にこながったでしょうか」 それで、女将ははじめて、控室にいる老婆が英世の母親だとわかった。 「そうとは知らず、とんだ失礼なことをいたしました」 女将と女中が平謝りに誤って、シカを慌てて宴席に案内した。 このときの出席者は、佐多博士以下、福原義梅博士に、木下東作博士、有馬頼吉博士ら、大阪高等医学校の教授達を中心に、英世母子、血脇、小林夫妻、石塚三郎ら十人ほどのごく内輪のものだった。 宴席は「琴の家」の二階の、八畳と六畳の二間を襖を外して広間にし、八畳の床の間を背に英世母子が坐り、まわりを血脇、小林夫妻らがとり囲んだ。 この八畳間の眼下には紅葉のあい間に渓流が見え、谷川のせせらぎがたえずきこえてくる。奥箕面随一の景勝の地であった。 ここで、英世は出された珍味を、一つ一つ説明をしながら、自ら箸でとって母の口へ運んでやった。 これを見た大阪「富田屋」の名妓八千代が、「あれほど偉いお方が、まわりに居並ぶ先生など眼中になく、ひたすら老いた母に孝養を尽されている。私も母一人子一人の身だが、ああまではできない」といって、途中で席をはずして、廊下の端で泣いた。 実際、女将もその場を見て感動し、改めて英世の孝行の深さを知った。 これが、いわゆる「琴の家における野口博士の孝養」として、広く伝えられることになる。 翌月の新聞には「博士の孝心に感じて八千代泣く」という題で、このときの情景がこまかく報道された。大阪毎日新聞の記事は次のようになっている。
……同家の別座敷で、すぐさま昼餐会が開かれると、膳の上の刺身をとりあげて、「おつかさん、これは鰹の刺身ですよ、美味しいですか? 小林の奥さん、あなたは焼魚がお好きでしたね……」と野口博士は隣の母堂や小林老夫人の手をとらんばかりにして機嫌をとって、自分も夢中で嬉しがる。 「山家で生れ、刺身など覚えないうちに外国へ参りましたね、やっとこの十日ばかり前から食べられるようになりましたが、母などはただ御馳走に魂消るばかりですよハ……」 お相伴の記者に母を紹介される。やがて招ぜられた土地名代の舞妓の踊りとなってからは、母堂や小林老夫人達は箸も取落しそうな顔で気抜のようになっていられる。母堂の横顔を、野口博士が覗き込んで、「どうです、面白いものでしょう、さあ召し上がれ、松茸のお汁ですよ、その蓋がお椀になるのだそうですよ」と手ずから給仕に余念もない。 そのありさまを眺めながら血脇氏は涙ぐんで「諸君、この野口君のねんごろな心情の一部が、他の当世紳士にあったら、社会の風儀は淳厚になるだろうに、いまさらいうのもおかしいが、わずかばかりの世話をした自分に対して、十二年間に二百余通の長い手紙を呉れた。野口君の情誼には常に泣かされていたものですが、こんな田舎の婆さんと連れ歩いて、人前も道路も頓着なく、思いのままに孝心を発露する今回の事実には、涙がたまらなくこぼれるのです」と語り出したとき、佐多博士も福原博士も眼に一ぱいの涙を浮かべた。昼餐は二時に済んで一同は箕面の滝に遊んだが、母堂と小林夫妻とは奈良見物に行った。
当時、この料亭の主人公の妹であった南川光枝さんも、英世の母への孝養の姿を目のあたりに見て感動した一人で、彼女はその感激を忘られず、これも若かりしころ英世の講演を聞いて感動した歯科医の戸祭正男氏などと話すうちに、野口英世の銅像を建立することを思い立った。 かくして資金の大半は光枝氏が負担し、さらに足りないところを、有志の浄財に求め、これに大阪府、箕面町なども協力して、昭和三十年十一月十二日に銅像が完成し、除幕式がおこなわれた。
いまこの地に立てば、緑の樹間をとおして「琴の家」の一角と、その下を流れる清流をのぞむことができ、六十余年前、英世がこの地で母のため自ら箸をとって食べさせ、それを見て涙した人々の感動が、静寂のなかに改めて思い返される。 5 帰国中の英世の記事は各紙によく出た。 横浜到着のことはもとより、会津や関西遊説の様子なども、行く先々の新聞でとりあげられた。とくに箕面の「琴の家」の場面は、貧しかった子の母への孝養という日本人好みの話題で、全国紙にも広く紹介された。 だが、これら新聞記事のなかで、英世の妻メリー・ダアジスのことについて触れたものはまったくない。英世の経歴の紹介でも、学問的な面ばかりで家族についてはなにも触れていない。 これはもちろん、英世が妻を連れず、単身で帰国したことに最大の原因がある。記者のなかには妻のことで質問する人もいたが、これに対する英世の答えはいつも素気なかった。アメリカの女性で、メリーという名であることしかいわない。それ以上尋ねようとすると、それは仕事のこととは関係ない、といってつっぱねた。 大体、英世は自分の家庭について話すのをあまり好まなかった。アメリカについても、自分の家に招いたのは堀のようにごく一部の者だけで、外国の家庭でよくやる家族ぐるみのパーティもやらなかった。仕事一筋で、家庭的という点では落第だった。 妻のことについては、英世が気のりしないようなので、記者のほうもあまりしつこくきかなかった。それに外国の女性と結婚しているという記事は、英世のいまの立場に似つかわしくないところもあった。当時は、国粋主義華やかな時代で、日本を代表する学者は、女性への好みも純粋に日本人的であって欲しいとい願いもあった。 しかし、今回の帰国に当って、英世は妻のメリーダアジスの写真を一枚だけ持ってきていた。胸開きのワンピースを着て、正面を向き、やや笑いかけている。英世はこれを母に見せた。メリーとの結婚に当っては、母になんの相談もせず、事後承認の形で納得させた。その詫びのつもりであった。シカはその青い目の嫁を見て「アメリカ人つったって可愛らしぐで、ずいぶん大っきそうなおなごのひとだなぁ。こんだったらお前 とうまぐ合うべぇ」といった。 うまく合うというのは性格的なことか、あるいは小柄な英世に好ましいということなのか、ともかく英世はそれにもかすかに笑うだけだった。 「そのうじ、お前が日本に帰ってくるごどになっだら、このひとは従いてくるべぇが」 「もちろん従いでぐる、あいつは俺の妻だから、日本さ来たら、おっ母さだって孝行しっから」 「んだって、おれは言葉わがんねぇがら、なんて挨拶したらいいかわがんねぇ。ずっとお前の側さついででくれだら、ほんでいい」 「とにがく、おっ母の娘だと思って、この写真を手許さおいでおいでくれ」 「ありがど、大事にとっておくがらなぁ」 シカは写真に一礼して懐におさめた。結婚はしたが、母に合わせることもできない。その穴埋めのつもりでもあったが、シカは生涯この女性に会うことはなかった。そのとき予感したかどうかはともかく、彼女にとっては終生、写真だけの嫁であった。 箕面で清遊した英世は、翌日から再び、講演と招待宴に追い廻された。まず十一日は大阪高等医学校で講演し、夜は大阪医師会の歓迎晩餐会、さらに会津出身者の歓迎会に出席し、十二日は大阪、堺、神戸三市で続けて講演会をおこなった。 英世の講演は、医師や科学者が聴衆のときは、自分の研究を中心に学問的なものだったが、学生や一般の人に対するときは、自分の生い立ちからアメリカでの苦闘時代を語る人生教訓的なものだった。もっとも教訓といっても、おしつけがましいことでなく、幼時貧しくていかに苦しかったか、ということを切々と語る。 英世は、普段は口数が少なかったが、講演で興がのってくると顔は紅潮し、早口になる。そこに会津訛りがまじり、一種異様な熱気がただよってくる。 当時、英世の講演をきいて貧しさから発奮したり、海外へ挑戦した青年も何人かいる。現在夙川で歯科医院を開業されている長浜昭義氏も、その中の一人で、すでに七十七歳になられるが、いまもはっきり英世の熱っぽい語り口を、脳裏にとどめているという。 技巧的とはいえないが、一途な熱気が聴衆を魅了し、一度話し出すと、おざなりな形では済まされない。一応、講演時間の予定は決まっているが、必ずといっていいほど長くなり、疲れていても、話しだすと時間を忘れる。その一つの例が京都での講演会だった。この日、英世は朝、大阪を発って京都に入り、京大総長の出迎えを受けたのち、京大の昼餐会に出席し、午後から法科大講堂での講演会での講演会にのぞんだ。ところが、はじまって十分ほど経ったとき、突然腹痛を覚えた。連日の疲れのせいか、始める前から顔色が悪く、鈍い痛みがあったが、それをおして登壇したのである。胃部をおさえて耐えようとしたが、耐えきれず、そのまま横の椅子に坐り込んだ。 聴衆は心配して見守り、主催者側の数人が壇上にかけつけた。胃痙攣でもおこしたのか、脇腹を抱えて呻く英世を見て、大学では一旦、中止しようとした。だが、英世は「待て」といって、首を左右に振った。そのまま、六分椅子にかけていたが、やがて腹に手を当てたままそろそろと立ち上がった。それから一つ深呼吸をすると「失礼しました、これから続けます」といった。 京大総長や教授連が慌てて引き止めたが、英世はかまわず喋り出し、予定どおり一時間半の講演を終えた。 こうして十月十七日、関西での日程のすべてを終えて、東京へ戻ったが、ここでも種々の講演や招待宴が待っていた。 この二度目の東京滞在中、英世がとくに喜んだのは、十九日に文部省に出向き、かねてから報せのあった1勲四等旭日小授賞を受けたときだった。 「おっ母、これが天子様がわだしに下さった勲章だよ」英世は背広の前にぶら下げて、子供のように胸を張ってみせた。
英世の帰米の予定は十一月四日であった。船も横浜出発の「佐渡丸」と決まっていた。それで帰ると、十一月の末までにはニューヨークに戻れる。アメリカでの仕事のスケジュールを考えると、それがぎりぎりの期限だった。日本にいられる期間も、あと十日余りとなって、英世の身辺はさらに忙しさをくわえた。講演会や歓迎会は受けているときりがない。それよりいま一度、会津へ戻り、買う予定の田の名義書き換えや、家のことで相談しなければならない。 十月二十二日、まずシカが小林栄と東京を発ち、二十三日に英世も東京を発って会津へ向かった。 この二度目の帰郷で、恩賜賞の賞金で田畑の契約をすませると、さらに父のことについて母や姉達と相談した。 父の佐代助は、一時小林栄の許に引き取られていたが長続きせず、また村内を遊び廻っていた。相変わらず働きもせず、酒ばかり飲んでいる。すでに完全なアル中で、酒がきれると手足が震え、舌もよくまわらくなる。この父の処遇について、英世は北海道の弟の清三の許へ送るよう主張した。清三はかつて若松に奉公にいっているとき、市内の餅屋の娘を妊娠させ、夜逃げ同然に北海道へ渡った。一時、小樽で鉄道員をやっていたが、その後北見へ移り、小さな飲食店をやっていた。 「清三のとごだったら、酒も飲めるし、店の留守番ぐらいにはなるべぇ」 英世はそんなふうにいったが、その実、厄介払いであった。さすがにシカは決めかねているふうだったが、英世はさらに、 「あの人は、ここにおいでおぐど駄目になるばっかりだ。みんな昔から知っている人ばっかりで、掌を合わせて頼まれっと、つい飲ませてしまう。困るとお母の財布を盗む。万事他人に甘えて、自堕落になっていくだけだ」 「んだって、北海道は遠ぐで、寒いべなぁ」 「お母は、一体、どれほど、あの人にいじめられればいいんだ、これまで、どれぐらい苦しめられできたか、わかってっぺ」 英世は父のことを、「お父」とは呼ばなかった。小さいときからの、生活をみていると、そんなふうに呼ぶ気にならず、第三者の醒めた目で「あの人」としかいえない。 「もし、お母が、まだここに、あの人をおいておぐというんだったら、俺は恩賜金で田畑を買うのを止めるよ」 そうまでいわれては、シカも英世の意見にうなずかざるをえなかった。一緒にいる姉のイヌも、その夫の善吾も、父を北海道へ行かせることには異論はなかった。清三のほうも、父がくることには、とくに歓迎でもないが、よいって反対でもなった。大体、清三は兄弟のはずれ者で、その点で、心情的に佐代助と通いあうものがあった。 「んだって、あんな遠いどごまで、行くっていうべぇが」 「こごにいられないどなれば行かざるをえねぇでしょう。もしお母がいいづれぇんなら、わだしがいうよ」 シカは驚いて顔を挙げたが、英世は平然と、 「大丈夫だ、あの人だって、こごでいわれるより、誰も知らねぇどごへ行ったほうが幸せなんだがら。もぢろん、北海道にいく以上は、当座、酒を飲むに困んねぇ程度の小遣銭は持たせてやっがら」 それで佐代助の北海道行は決まった。結局、そのことは英世がいわず、義兄の善吾から話すことになった。佐代助はそれをきいてなにもいわず、一言、 「みんなのいうどおりにする」とつぶやいた。 6 三城潟に三日間いたあと、英世は旧友の石塚に誘われて新潟に行った。石塚はシカの写真を撮り、それを英世に送って帰国を促した張本人だった。わざわざ三城潟まで迎えにきて新潟へ向かう途中、汽車が会津若松を通ったとき、石塚が思い出したように山内ヨネ子の話をした。 「彼女はいまこの町さいる。あのあと結婚したけど、連れ合いが死んでしまって、いまは一人らしいど」 英世の脳裏にゆっくり十五年前のことが甦った。そのころ、英世は一途にヨネ子を追っていた。何度も手紙を出し、検疫官の金モールのついた制服を着て訪問したのも、ヨネ子によく思われたい一心からだった。だが、ヨネ子はまったく相手にしてくれなかった。ときに勉強を教わることはあっても、英世からの一方的な押しつけで、むしろ迷惑そうな顔をされただけだった。 それから十五年の歳月が経っている。すでにヨネ子のことは忘れたつもりであった。アメリカへ渡って間もなく、ヨネ子が結婚したという知らせを受けたときの衝撃も、すでに昔のことであった。 だが、心のなかにはずっとヨネ子の影が尾を引いていた。守之助の紹介で会った女性との婚約を破棄したのも、放埓さが原因とはいえ、その裏にはヨネ子の面影を追っているところがあった。それどころか、いまの妻のメリーとも、いま一つしっくりいかないのは、ヨネ子のイメージが残っているせいでもあった。 「どうだ、逢ってみねぇか、彼女はもちろんお前が帰ってきてんのを知っているから。お前が逢うっつったら逢うと思うけどともなぁ」 石塚がうかがうようにいったが、英世は車窓のふちに腕を乗せて外を見たまま答えない。 会津はヨネ子と初めて逢った町で、その格子戸のあいだからラブ・レターを入れて、叱られたこともある。その町が迫ってきている。やがて窓から目を戻すと、英世はいった。 「折角だけんとも、いいよ」 「んだけども、ここまで来たんだから、逢うだけだったらいいだろう」 「いや、やめるよ」 今度は英世ははっきりと首を左右に振った。いまなら、ヨネ子は喜んで逢いにくるかもしれない。昔の非礼を詫び、丁重に迎えてくれるかもしれない。だが、いまさら逢ったところで、二人のあいだがどうなるわけでもない。たとえ詫びられたところで、昔の苦々しさが甦えるばかりである。それに、いま、のこのこ逢いにいったのでは、まだ未練があるように思われる。逢いたくても逢わない、そうすることでしか、昔の口惜しさを晴らす手段はない。 「もう済んだごどだよ」英世は自分にいいききかせるようにいった。 そのまま新潟に行った英世は、新潟医専で講演をおこない、そのあと市内の鍋茶屋での歓迎会に出席した。そこで一泊した翌二十七日、磐越西線で再び郡山に戻った。その途中三城潟で再びシカと姉や義兄達に会って、最後の別れをした。 「気ィつけでな、毎日、中田の観音様さお祈りしっから、無理しでぇで、体、大事につかえな」 シカが皺だらけの手で、英世の手を何度もさする。 「大丈夫だ、俺はまで四十だがら、それよりおっ母こそ、体に気ィつけて、まだまだ二十年も、三十年も長生きしてな」 「冗談いうんじゃねぇ、人間ちゅうのは寿命があんだから、おれはもう今度、いろんなどごさ連れでってもらって、いままでの六十年分、いっぺんに生ぎだような気がしる。もうこれで、いつ死んだっていい、本当におめのおがげで、ありがど……」 あとはただ、手を握って泣きじゃくる。英世も涙が出そうになるのをこらえて、シカの手を握り返す。 「心細いごどいわねぇで、長生きしてくれ、俺もおっ母がいだから、これまでやってこれだんだから、おっ母に死なれたら、なんにもできなぐなる」 「おめどもあろう者が、なに気ぃ弱えごどいうんだ」 母に叱られても、それは英世の一面の真実でもあった。 「今度アメリカさ帰ったら、毎月三十円送っから、少ねぇかもしれねぇけんども、これがらはそれでのんびりして、少し遊び歩いでな」 「もってぇねぇ、人間は働けるうちに働がねがったら罰当る。ほれより、今度くっとぎは嫁連れで、早く帰ってこ」 「三年後には、まだ帰ってくっから」 「三年後だな、みなが欠けねぇうぢに、必ずな……」 母と子は、もう一度しっかりと抱き合う。小柄な世界の大学者と、六十をこした老婆が目を赤くしてうなずき合う。はたから見ると、羨しいとも異常とも思える情景であった。 やがて駅へ着き、発車の時間がくる。ベルが鳴り汽車が動き出した。三城潟の小さなプラットホームはすぐ途切れる。 シカが曲った腰を伸ばして必死に手を振る。同郷の人達も、みな一斉に手を振り、万歳を叫んだ。その人の群に向かって英世は窓から上体をのり出し、「おっ母ぁ……」と叫んだ。
東京に戻った十月二十八日から十一月四日の出発まで一週間あったが、その間も英世は繁忙をきわめた。帰京した翌日の二十九日には、午前中東京女子医専で講演をおこない、夜は東大教授入沢達吉博士の招待宴にのぞんだ。三十日は横浜の茂木氏別邸に招かれ、そのあと神奈川県医師会で講演し、夜は医師会の歓迎晩餐会に出席した。 翌三十一日は午後から、千葉医専で講演会がおこなわれた。 この日、佐代助は、英世を見送るため上京する小林栄と一緒に郡山駅まで同行し、そこから北海道へ行くべく、一人で東北本線に乗り換えた。別れぎわ、小林栄は改めて、野口英世の名を恥ずかしめないよう、北海道へ行っても酒を慎み、真面目に働くよう訓した。佐代助は頭を垂れ、ただ黙ってきていた。 「ほんじゃ、わがだな」最後に念を押し、このまんま乗ってれば、明日の朝には青森さ着くがら」と教えた。 佐代助は小林に一礼し、右手の風呂敷包みを持つと背を丸めて列車に乗った。数日前、盛大な見送りのなかで帰っていった息子と較べて、淋しすぎる北への旅立ちであった。 一方、東京にいる英世は、二日には早稲田の邸宅に大隈侯を尋ね、歓談したあと、護国寺の川上元次郎の墓へ参り、最後に血脇守之助邸を訪れ、改めて帰国の挨拶をした。 その後、木挽町で守之助夫妻、小林栄等、親しい者だけで、日本最後の離別の宴がおこなわれた。 十一月四日付、東京日日新聞には、「野口英世博士再び米国へ」というタイトルで、以下の記事が掲載されている。
「野口英世博士は今四日午後、横浜出帆の佐渡丸にて再び米国へおもむく筈。昨朝、博士は朝食前に友人とともに撮影に行き、旧師血脇守之助氏はじめ、訪客の、帝国ホテル喫煙室に博士を待つ者多く、そのうち博士は帰り来る。名刺を通ずれば、博士は曰く、 この講和中に出てくる学者中に、東大のいわゆる大物教授が一名もなく、各地方の少壮教授たちだけに触れているところは、いかにも東大嫌いの英世らしい。なかでもとくに、ワイル氏病や、恙虫に関心をしめしているのは、当時の英世の研究がこの方向に向けられていたからである。 新聞に掲載されることを考えて、はっきりいっていないが、二か月間におよぶ日本滞在で、英世は改めて、日本の学界の問題点に気がつき、それとなく友人達に語っていた。 たとえば、日本はこれから、もっともっと学術の振興に金をかけなければならない。とくに文科優位を改めて、理科系に多くの金を出すべきである。また学者達は、少し偉くなるとすぐ、政治的な動きをし、学問をないがしろにする傾向がある。自分は一生学問のみに専心し、他へ脇見をしないつもりである、といったことである。 今度の帰国に対する朝野あげての歓迎で、英世はおおいに気をよくし、かつてのように、単に東大とか、洋行帰りときいただけで嫌うといった、短絡的な反応はなくなるとともに、日本の学問や学者全体をより広い視野から見詰めるだけの余裕もできていた。 かくして十一月四日、英世帰米の日がきた。この日、午後零時三十分、英世はまず東京駅から横浜に向かう。 出発の一時間前から東京停車場は見送りの人で溢れ、ホームの中央は、一時麻痺状態になるという騒ぎだった。英世はこの混雑を避け、一旦、貴賓室に入り、そこで見送りにきた徳川頼倫侯爵、徳川義親侯爵、石黒忠悳男爵、佐藤進男爵らと握手を交し、そこからまっすぐプラットホームに出た。そこも狭く、数名の車掌が出て、見送り人を整理するという始末だった。 やがて汽車が動き出すとともに、ホームでは一斉に手を振り、「万歳」の歓呼がおきた。 そこから横浜に着いて、船は午後三時の出発であった。 すでに、埠頭は見送りの人であふれていた。大学関係者や親しい友人、新聞記者などが、次々と握手にくる。英世を一目見ようと集まった一般市民も加わり、英世のまわりは花束や花籠でうずまった。 やがて午後三時、ドラの音とともに、見送り人は甲板から下船し、埠頭と船を結んでいたブリッジが外された。 三時十分、船は長い汽笛をならすと、ゆっくりと埠頭を離れた。上甲板の最後尾に、英世が立っている。右手には十数本のテープを握り、左手に帽子を持って振っている。 期せずして「野口英世博士、万歳」の声が、秋の埠頭に湧き上った。 かつて、血脇守之助と学友一人の見送りを受け、三等船室のデッキから心細そうに手を振っていた英世の、十五年経ったとはいえ、いまの華やかさを想像した者は誰もいなかった。
第五章 ニューヨーク(Ⅱ) P.160
1
二十日余におよぶ船と汽車の旅を終えて、英世がニューヨークに着いたのは十一月二十六日であった。 このとき、英世のトランクには、寝巻、錦織、ふくさ類、手編みものなどがお土産に入っていた。いずれも母のシカや親戚の米治、おはまなどがつくってくれたものである。さらに別便の小箱には鎧、竹編もの、陶器など、各地でもらったものが詰め込まれていた。 待っていたメリーはそれが珍しく、すぐ身につけたり友達に見せながら毎日眺めていた。 だが、英世は一日の静養のあと、二日目からは早くも研究所に出勤した。一日としてじっとしていられない、英世らしい性急さである。 しかしこのとき、英世はこれからの自分の研究をどうするか迷っていた。 三か月前、日本に帰国したとき、英世の研究は八方ふさがりの状態だった。迷路に入ったように先が見えない。その不調から脱し、気分転換をはかるための日本行きでもあった。十五年ぶりで母や知人に会い、各地で盛大な歓迎を受けて、たしかにいっときの欝状態は治った。長い間仕事から離れていて改めてやる気もおきた。だが、それは気持のうえだけで、現実になにをやるか方針が決まったわけではない。気持こそ充実したが、行きづまっている状態に変わりはなかった。 それでも英世は二つの研究を頭にえがいていた。一つはロッキー山脈紅斑熱であり、一つはワイル氏病である。 ロッキー山紅斑熱は名のとおり、ロッキー山周辺の原住民に多発する病気で、全身に紅い斑点がでて、山麓に多いダニによって媒介されると考えられていた。英世がこの病気に興味を抱いたのは、これに日本の恙虫病が似ていて、とくに新潟地方に多い。日本に帰って、英世は日本に関係がある病気の研究に手を染めたいと思うようになっていた。専門はともかく、一般の人々は英世がどういう仕事をしたのかわからない。蛇毒やスピロヘ-ターの研究といってもピンとこない。やはり破傷風免疫血清を発見した北里とか、赤痢菌を発見した志賀といったほうが素人にはわかりやすい。ロッキー山紅斑熱の病原体を探れば恙虫病の原因も解明できるのではないか、そしてそれは自分の名前を日本の、とくに新潟地方の人々にはっきりうえつけることにもなる。 帰米語十日めにはハーバード大学まで出向き、ロッキー山紅斑熱の実状について調べ、十二月にはこの病気の第一人者であるウォルべッハ博士に会い、二月にはワシントン当局にダニの入手法について依頼した。さらにボストンの研究所へも行って病気を調べた。かくして当然のことながら、英世とウォぺッハ博士とのあいだに、新たにロッキー山紅斑病原体発見をめぐって、激しい先陣争いがくり拡げられることになった。 もう一つのワイル氏病は日本でも多く、かなりの死亡率であったが、この病原体はすでに一年前、九州大学の稲田・井戸両教授によって発見されていた。すでに先覚者がいて、その点ではいまさら手をつけても、さして張のある仕事ではないが、この病原体がスピロヘ-ターであるところが興味をそそった。 英世はこの二つに向かって研究を開始した。例の、ひたすら体力を注ぎこんですすむやり方である。 だが今度の英世には、かつて梅毒スピロヘ-ターの純粋培養法や、脊髄癆の患者の脳切片にスピロヘ-ターを求めたときのような熱気はなかった。新しい仕事とはいえ、往時の研究にくらべたら今度のはスケールが小さい。それにいままで働き過ぎたせいか根気が続かない。気持だけは焦るがいま一つ体のなかから燃え上がるような熱気はなかった。 しかし、相変わらず意気だけは高かった。日本で大歓迎を受けてから、英世は改めて、自分は日本を代表している学者だという自信と自負を抱くようになった。文部省から、東北大学教授の山川章太郎と九州大学助教授大平得三の二人が留学生として英世の許に派遣されたことも、さらに責任を痛感させることになった。もはや英世は日本を追われた学者でなく、日本が誇りとする学者である。 このころ、英世がニューヨーク市街を歩いていたとき、たまたま若いアメリカ人がすれ違いざま「ジャップ」とつぶやいた。英世すぐ引き返し、その男の前に行き、「いまいった言葉をもう一度、いってみろ」といった。 男は二十前後の青年だったが、戸惑っているのに、 「私はロックフェラー研究所のノグチというものだ」と名乗った。 青年は初めておどろいたように英世を見詰め、それから「失礼しました。なにも知らなかったものですから」と謝った。 「ロックフェラーのノグチだから、そういってはならぬということではない。どの日本人に対しても、そのような言葉をつかうのは失敬なのだ。わかったかね」 「済みません」 青年はそういってたち去る。本を小脇に抱えているところをみると、学生だったのかもしれない。だが、学生にかぎらず、一般市民のあいだでも「ロックフェラー研究所のノグチ」の名は、かなり知られてはいた。 2 このころ英世はよく牡蠣を食べていた。帰国の前あたりから疲れやすいうえに心臓が弱り、根をつめて遅くまで仕事をすると、次の朝起きられないことがある。弱った体には牡蠣がよくきくと研究所の友人にきいたからである。 たしかに牡蠣は一種の強壮剤で疲れに多少効果はあろうが、それだけですべてが治るわけでもない。とやかくいっても英世は年齢であった。四十を越してはもはや二十代のような無理はきかない。だが英世はそうは思わない。かつてあれほど頑張れたのに、どうして弱くなったのか、牡蠣でも食べれば元に戻るのではないか。一度思いこむとまっしぐらに進むのが英世の性格である。以来一日に四ケースもの牡蠣を食べたりしたが、これではいくら効き目があるといっても無茶すぎた。 その牡蠣が思いがけない事件を引きおこした。 一九一七年五月の末、英世は突然高熱に襲われ、体温計ではかると三十八度もあり、顔全体が赤くなっている。メリーは病院へ行くことをすすめたが英世は断わり、「ただの風邪だろう」といっているうちに四十度近くになり、目もかすんでくる。アメリカにきて、こんな高熱に冒されたのは初めてである。二日目に研究所のリプマン博士が見舞にきて、すぐ入院するようにすすめられた。 だが、英世はなお頑張った。「もう二、三日たてば落ち着くでしょう」 他にはいわないが、英世は内心で熱が出た原因の見当がついていた。一週間前に、ワイル氏病の研究をしているとき、誤ってピペットの血清を吸いこんでしまったが、それはワイル氏病にかかったネズミの血清でスピロヘ-ターが含まれいる。今回の熱はそれが原因でワイル氏病がうつったに違いない。 だが研究者がピペットを吸いすぎて感染した、などといっては恥である。心配だが、初めの一週間さえのり切ればワイル氏病はおさまる。できることならこのまま自宅で療養して治したい。 しかし熱は一向に下がる気配はない。それどころか二日目には意識さえ薄れかけてきた。リプマン博士らは危険を感じて、救急車で英世をマウント・サイナイ病院へ運んだ。そこで改めて調べてみると病気はワイル氏病でなく腸チフスで、このところしきりに食べていた牡蠣が原因だろうとわかった。 病院に運ばれたとき、英世はすでに脱水状態におちいっていた。 チフス菌は腸に潰瘍をつくり放置しておくと穴があく。こうなると腹膜炎をおこして生命が危険になる。英世はすでにこの末期だった。サイナイ病院の医師達が集まって相談し、ある医師はただちに手術をし、腹膜の穿孔している部分をふさいで、膿を排出する必要があると主張した。だがリプマン博士は手術に反対だった。いま開腹したのでは衰弱しきっている体に負担をかけてかえって危険である。いましばらく様子を見るべきである。 英世自身も手術を拒否した。いまお腹を開かれては、それで駄目になるような気がする。意見が分かれながらも医師団は治療に専念した。点滴をし、解熱剤をうちながら恢復を待つ。だが容態は一向によくならない。相変わらず高熱が続き、体はどんどん痩せていく。ときに痙攣が襲い、目だけがとび出たように見える。舌は腸チフス独特の濃い 苔がおおい、脹れている。 医師達の多くは、駄目だろうと見ていた。危険を冒してでも、早いうちに手術に踏みきるべきだったかもしれないが、いまはもう時期を失している。だがそう思いながら、一方ではあれほどのタフな男が簡単には死なないだろうとも思っていた。 英世危篤の報は、ニューヨークの日本人会はもとより、日本へも直ちに電報でしらされた。 「野口博士倒れる」と、新聞は毎日のように英世の容態を伝え、母のシカは願かけに、連日、片道二十キロもある中田観音を往復した。 「おれのような役立たずな体が、あの子の代りになんだったら、どうぞ召し上げくだされ」 シカは必死に祈り、猪苗代は小林栄を中心に、旧友達が集まって、新聞社の情報に一喜一憂し、東京では血脇守之助らが経過を見守っていた。 彼等はみな、英世が今年四十二の厄年であることを思い出し、もしかして、と不吉な思いにとらわれていたが、反面英世ならきっときり抜けると思う。いつのまにか、野口英世は不死身である、というような印象を人々は抱いている。 高熱に苦しみながら、英世の頭は意外に明晰であった。診察にきた医師達がどんな表情をし、脈をとりにきた看護婦の手がどんな感触か、すべて覚えている。 妻のメリーは毎日、アパートから病院へ通ってきて、英世の顔を見ては「どうなの」と尋ねた。 「大丈夫だ」英世の答えはいつもそれだけだった。それ以上いいたくても、舌が脹れて思うようにいえない。メリーは一、二時間でまた帰っていく。重態だからといって泊ることはない。 「私がいても仕方ないでしょうから」そのあたりはアメリカ的な割りきり方だった。 昼のあいだ、英世はうつらうつらしているが、ときに思い出したように、「このまま死んでもいい」といったり、「いま死ねるならずいぶん楽だ、早く楽になったほうがいい」というかと思うと、「ちかごろは自分で幸せだと思うことはなかった」」などと口走る。しっかりしているようで、いくらか熱で混乱しているようである。 多くの医師の予想では五月三十日が一つのやまと思われていた。それをのり切ればなんとか助かるかもしれない。 そして期待どおり英世はこのやまをのりきった。発病して一週間なにも食べず、点滴と唇をかすかに濡らすだけでいっとき肥りかけていた体が、いまは四十キロそこそこになっていたが、英世はへこたれなかった。 六月に入り三日が過ぎた。毎日四十度近く続いた熱が、四日の日は三十九度台でおさまった。わずかに恢復の兆しが見えてきて、医師団は初めて、お茶を一杯だけ飲むことを許した。腸が破れているだけに飲みものは慎重にしなければならない。 腸チフスの熱の特徴は振幅が激しいことである。午前中、四十度をこえたかと思うと、午後には三十七度台に下る。五日、六日と熱は相変らず続いていたが、最高が三十九度ぎりぎりのところで止まり、どうやら峠は越えたようである。 少し熱が下がりだすと、英世はいろいろ文句をいい出した。「眠りたいけれど眠らない」「部屋が暑すぎる」「脚がだるい」医者か看護婦の顔を見ると必ずなにか訴える。メリーが病院にくる時間が、約束から一時間遅れたといってぶつぶついう。だが文句をいうのは、少しずつ恢復してきた証拠でもあった。医者も看護婦はそれを知っていたから、適当に受け流していた。 六月十日ころから、ようやく流動食を食べられるようになった。初めは刺激しないようになま温かいスープを少量与え、異常ないことをたしかめてからコンソメスープに変る。 「久しぶりに飲みものが入って、胃袋が驚いている」英世は冗談をいって笑うようになった。 腸の穴の空いた箇所は腹膜炎をおこしていたが、慢性化して新しい組織でおおわれ、その形でおさまっていくのがチフスの恢復期の特徴だった。 十日を過ぎてようやく東京にも「危機は脱した」という電報が打たれた。 「いますぐ研究室に抜け出したりしない以上、まず大丈夫でしょう」 リプマン博士が皮肉まじりにいうと英世は笑顔でうなずいた。初めのとき、手術をすべきであったどうかはわからないが、博士も英世も手術は頑固に拒んだ。手術を拒否した二人の勝利とまではいえないが、一応、その選択は間違っていなかったようである。 少しずつ元気の出てきた英世は日本人クラブから講読本と探偵小説をとり寄せてもらって読みはじめた。前からそれ以外には関心はなかったし、ときに論文を手にしたみるが、ニ、三ページも読むと疲れてしまう。 さらに十日も経つと、フランス語やスペイン語の文法書を読みはじめた。体が恢復するにつれ再び前向きの意欲が湧いてきたのである。 当然のように研究のことも気になり出してきた。できたら研究室に行ってみたいが、この体では難しい。英世は助手のスティープや秘書のチルデンを病室へ呼び、ロッキー山紅斑熱とスピロヘ-ターの培養状態をきいた。リプマン博士らの医師に見付かると叱られるので、午後の比較的医師のこないときを見計らって部屋に入れる。スティープは進行状態をいろいろ説明するが、それだけでは納得できず、途中からは白衣の下のポケットに試験管をつっこんで持ってこさせて見る。誰かがドアをノックすると慌ててしまいこみ、いなくなるとまた覗きこむ。 再び英世の狂人的な研究がはじまりそうだが、一日の大半はベッドに横になったまま、うつらうつらと過した。窓にあふれる初夏の明るい陽を見ていると、猪苗代での少年時代、若松から東京へ出たときのことなどが次々と思い出される。 この十数年間で、こんなにのんびり自分のことをふり返ったのは初めてだった。とにかくアメリカへきた十年間はいっときも休まず走り続けてきた。実験をし、論文を書き、また実験をする。それ以外なにも考えず、そのおかげでいまの地位を得て名声を得たともいえる。 だがこんな生き方がはたして賢明であったのか。走り続けて、それなりのものは得たように思うが、それが幸せであったか否かはわからない。このまま走り続けてどうなるのか、ふとつまらぬことで死ぬような気がする。今度のチフスで辛うじて死から免れたがもしあそこで死んでいたら、自分は走っただけということになるかもしれない。珍しく英世は立ち止まり、人間の幸せとか、生き方についてまで考えてみる。 七月に入って、医師達はおうやく、「もう大丈夫だ」と宣言した。あとは体力の恢復を待つだけである。排泄中にもチフス菌は発見されなくなったし、食欲もでてきた。だが退隠するには、なお、一か月間、便中のチフス菌がないことを確認する必要がある。 このころから英世は床にうつ伏せになってよく手紙を書いた。まず小林夫妻に、そして血脇守之助へ、危機を脱して、また新しい出発をする決意を書き送った。さらに自分の容態が日本の新聞で刻々と報道され、多くの人々が恢復を祈ってくれたことに対し、広告欄をかりて謝意を表した。 一か月後の八月初め、ようやく退院許可がでたが、このとき英世の体重は四十四キロ、病気になったとき五十九キロであったから、実に十五キロ近い減少であった。 退院許可がでて、英世はその日のうちにも帰るつもりでだったが、考えてみると、治療費や入院料が滞っている。二か月余のあいだの看護婦つきの個室の料金と治療費は馬鹿にならないが、年俸五千ドルももらう学者として払えない額でもない。しかし例によって家にはほとんど貯えがなかった。 「どうするのですか」 メリーはまるで他人ごとのようにいう。 「参った……」 正直いって、これまではチフスから助かることばかり考えていて、金のことは頭になかったが、それにしても暢気な夫妻である。だがとにかく金を払わないことには退院できないし、高給をもらっているくせに、ない、ともいえない。困った挙句、英世は再び星一に電報を打った。かつて帰国のとき、英世は星に頼んで五千円の金を送ってもらっている。いままた治療費を頼むのは、虫がよすぎると思ったが、といって他に、大金を送ってくれそうな人はいない。 期待どおり、星からはただちに五千円の金が送られてきた。星は同郷人として、英世を見捨てておけなかったが、それだけで一年のうちに一万円もの金を送れるわけでもない。その裏には、英世の浪費癖に呆れながら、明治維新以来、ことごとに冷飯をくらわせられてきた会津の口惜しさを、英世によって晴らそうという県人意識がなかったとはいいきれない。 大金を受け取った英世は早速、治療費を払い、ついでにそれまでの借金を払って無事退院した。さらに残った金で世話になった医師から看護婦一人一人にまで贈りものをし、主治医にはプラチナの時計をプレゼントした。それでもあまっているので車を買い、おまけに新聞広告で見た別荘地を買い取った。五千円は一瞬にして消えてしまったが、それが英世の使い方であった。
退院して半月後の八月中旬、英世はメリーと新しい車に乗って新しい山荘のあるシャンデーケンへ向かった。もっともこのときは別荘はまだ出来ていず、村のホテル住いであった。 シャデーケンはニューヨークから四時間ほどの山地で、当時からニューヨークの避暑地であった。ここで英世は二町ほどの土地を買い、応接間、食堂、書斎、二つの寝室などを別荘を建てる。もちろん、広告でたまたま、建物も業者のいうまま値切ったりはしない。 メリーは周囲が荒れているので、あまり気がすすまなかったが、英世は山の姿が故郷の会津に似ているので気にいって、一目見て決めてしまった。まだ電気もなく自家発電機を据え、水も電動式で汲みあげる、静かというより淋しすぎる場所であった。 だが山荘の裏手にはエプソン川が流れていて、ヤマベやアユが面白いほど釣れる。さらにあたり一帯は山が屹立し、その先には湖水もある。 ここで英世は本を読んだり、釣をし、また堀にすすめられて絵を描いたりした。 もともと英世は、字は達筆であったが、絵もなかなか上手だった。エプソン川で釣った魚や、自画像など、ここで描いた絵がいまも残っているが、学者の余技としては一級品である。ここで夜は論文を読み、ときに顕微鏡をのぞく、どうやら英世の生活も人並みの余裕と平静さをもちはじめたようである。 だがそれも一か月と続かず、九月初めにまた原因不明の高熱が出て、再びニューヨークへ戻ることになった。 シャンデーケンからニューヨークまで汽車で仰向けに寝たまま、かたわらにメリーがつききりであった。ニューヨークではただちにロックフェラー研究所の附属病院に入り、調べると腸チフスの再発であった。もっとも再発といっても、前回慢性化で落ち着いた腹膜炎が、ぶり返したもので安静にしていれば落ち着くことだった。そのまま一か月半入院して、十月の末にようやく退院した。 だが、今度は一週間も経たず、妻のメリーが腹痛を訴え、医師に診てもらうと虫垂炎ということだった。そのままメリーはルーズベルト病院に入院し手術をする。経過は順調で三週間で退院したときは、すでに十一月も末だった。 ところが、妻から感染したかのように、今度は英世が虫垂炎にかかった。虫垂炎は本来、伝染するものではないが、稀にこういう家族間に発生することもある。英世は再びマウント・サイナイ病院に運びこまれたが例によって手術されるのは反対だった。しかし前の腹膜炎のあとに、いままた虫垂でも破けて腹膜炎を重ねたら、命とりになるだけに、今度だけはリプマン博士も手術をすすめた。 仕方なく英世は承諾して手術がおこなわれたが、初夏から続く入院生活で体力がなく、一時は肺水腫をおこして危険な状態にまでなった。 英世、再入院の報せは再び日本にもたらせた。シカは再び中田の観音さまに通った。その効あってか、肺水腫は落ち着き、年が明けた正月の四日にようやく退院した。 この年は腸チフスにかかってから、再発、妻の虫垂炎、そして英世の虫垂炎と、まさに野口家にとって疫病神にとりつかれたような年だったが、英世は数えの四十二歳、まさに男の厄年であった。
第六章 黄 熱 P.174
1
一九一八年の年が明けた。大正七年である。この年、日本では米騒動がおき、世界では前年にロシヤ革命が起り、この年シベリア出兵という事件がおきた。 英世の研究者としての歩みをふり返ると、一九〇〇年アメリカへ渡り、数々の業績をあげたあと日本へ帰り、再度渡米後チフスにかかって静養する。これまでの十七年間と、病癒えた一九一八年からアクラで倒れるまでの十年間の二つに、大きく分けることができる。いまこれを前期、後期とすると、前期はひたすら栄光の地位を目指してがむしゃらにすすんだ、いわゆる「光の部分」であり、後期は、その研究に暗い影がさした、いわば「影の部分」ともいえる。 もっとも、それは後世、彼の業績を通していえることで、そのときは英世自身、陰に向かっているとは思っていなかった。 この影の部分がどのようにして英世に訪れたか、それを書く前に、英世が最後の研究者としての十年間、ひたすら追い求め、ついにそれで倒れる黄熱病について触れねばならない。 黄熱病は幸い日本ではいまだ発生したことはないが、世界的には亜熱帯から熱帯に広くみられ、とくにカリブ海沿岸から南米、さらにアフリカ諸国に多かった。歴史的にはペスト、コレラと並ぶ恐怖の伝染病の一つで過去、数えきれぬ人々がこの病気の犠牲になった。 この病気は英語名で Yellow Fever といわれるとおり、高熱とともに全身黄色味を帯びてくる。これは肝臓が冒されて黄疸が現われてくるためだが、同時に激しい頭痛と悪寒があり、顔面は充血し、末期は暗黒色の吐物を吐き続けて死亡する。これまで、この病気については、港町で流行する、という定説があり、中南米でもアフリカでも大流行をみるところは、きまって船の出入りする港町であった。 アメリカ政府がこの病気の対策に積極的にのり出したのは、米西戦争、それに続くパナマ運河開削工事に当って、多くの兵士や労働者がこの病気で倒れたのが原因であった。 アメリカでも一七六八年にニューヨークとフィラデルフィアで大量発生を見、その後はニューハンプシャー州から南はフロリダへ、西はテキサスからミシシッピー河を経てセントルイスまで拡がった。この年から一八二一年の約半世紀のあいだに、フィラデルフィアで二十回、ニューヨークで十九回、ボストンで七回の流行を見ている。 二十世紀に入ると、北米での流行はようやく鎮静化したが、ニューオリンズから南部諸州ではなお猛威を揮い、土地の人々は田舎に避難したり、街に出ても握手を拒んだりした。それでも死者は減らず、一部都市では機能が停止し、死体埋葬業者のみ昼夜休む暇もないという状態が続いたりした。とくに南米、西インド諸島は、常にこの病気に襲われ、黄熱病は一名、「西半球の恐怖」ともいわれた。 以前からアメリカ政府はこの病気の撲滅に関心を抱いてきたがきめ手がつかめず、そのうち米西戦争がはじまったが、この戦争で死ぬ兵士より、黄熱病で死ぬ兵士のほうが多い状態であった。さらにアメリカは一九〇三年パナマ運河建設権をえて、運河開削に当ったが、その工事をすすめるのにも、ぜひ黄熱病を征服しておく必要があった。 ここで政府は軍医ウォルター・リードを委員長とする「黄熱病研究委員会」を発足させ、この病気の究明に当らせることにした。 一つの重大な病気を征服するには、まずその病原体を解明することが先決問題である。病原体がわかれば、それを培養して対抗策を講ずることもできる。だがその研究過程で黄熱病は多くの犠牲者をのみ込んだ。 ところで、黄熱病に対して医学的なアプローチがなされたのは、一八八四年、ノットの仕事が初めてであった。彼は黄熱の発祥地と患者の話から、この病気が蚊によって伝えられると考えた。続いてカーロス・フィンレーも同じような考えを発俵したが、推測的なものではっきりした証拠は掴めなかった。だがセオポルド・スミスは、牛のテキサス熱がすでにこの病気にかかっている牛の血を吸ったダニにより、新たな牛に伝染されるという事実を知り、病原体がある種の昆虫によって移されることを実証した。 一方、ニューヨークはじめ主要な港町では、黄熱の流行地からくる船をいかに扱うべきか、いろいろ論議されていた。ある保健官は人の衣服から貨物まで、徹底的に蒸気消毒すべきだといい、ある者はそれほどまでする必要はないという。ニューヨーク市民の不安の声に、クリーブランド大統領は、特別保健官を発生地であるエジプトに派遣し、黄熱の蔓延状態を調査させたりした。またリードは別の発生地キューバへ行き、いままで疑われた病原体が、黄熱と無関係であることなどを実証しようとした。 このころ研究者のあいだでは、黄熱病の流行が一般の病気と異なり、港町を中心に発生することが注目されていたが、この点について研究者達は次のように考えた。まず黄熱は一度かかって治ると二度とかからない、いわゆる免疫ができ、「人ー蚊ー人」の鎖が断ち切れると、その地方での新たな発生はおこらなくなる。だが港町のようなところでは、絶えず人々が出入りし、新しくその地に来た人達は免疫をもっていないため幾度となく流行がくり返される。結果として港町は黄熱発生の巣窟となる。 リード委員会が初めに手がけたことは、まず、蚊が本当に黄熱を媒介するのか否か、それをたしかめることであった。委員会はフィンレーが繁殖させていた蚊について研究をはじめ、委員会のメンバーであるカロルとラジアが、自ら実験台になり、自分の腕を蚊に噛ませた。さらに委員会は数人の篤志実験メンバーを募り、同様の実験を試みた。 もし本当に黄熱にかかったら死ぬかもしれない、その意味でこれは決死隊と同じである。リードが陸軍軍医であったからできた実験でもあった。 この結果、志願したウイリアム・デーンという兵卒は黄熱にかかったが、カロルはかからなかった。だがラジアは一度目に刺されたときは罹病しなかったが、二度目に刺されたときに罹病し数日で死んだ。これが黄熱研究のにおける初めての犠牲者であった。しかしこれによって、蚊のうちの「ネッタイシマ蚊」が黄熱を媒介する事実が確認され、研究の方向が確立された。 とにかく蚊にさえ刺されなければ黄熱にならないのだ、とすると蚊を絶滅させればいいのだ。 ここにゴルガスという精力的な軍医が現われた。パナマ運河地帯の衛生官に任命されて現地に行くや、早速蚊の絶滅運動に取り組んだ。彼はパナマ周辺はもとより、黄熱の発生しそうな地域の、湖や沼や水溜り、汚水槽など、すべてに石油をかぶせることを考え、この遠大な計画の実行にとりかかった。だが当然のことながら、運河のまわりは人の出入りが頻繁で湖沼も多い。交通量も激しく、人や動物が他所から蚊を運んでくることもある。とくに一番問題なのはエクアドルである。ここが黄熱の最大の発生源だが、ここから近いパナマは、そのとき一度だけ蚊を駆除しても危険は去らない。 「まずエクアドルの黄熱を叩くことだ」 たまたま第一次大戦が勃発し、ゴルガスは軍医総監に任命されるや、親友の医師、アーサー・ケンダルを呼び、エクアドルの港町グアヤキルへのり込むように依頼した。やや考え方が単純だが、そこで黄熱をくい止めれば、メキシコ、ペルー、ブラジルの黄熱もおさめることができると考えた。 ゴルガスはさらに「黄熱の病原体を解明できるような、優秀でファイトのある医師はいないだろうか」とケンダルに尋ねた。ケンダルは即座に「ロックフェラーのノグチ」の名をあげた。「彼ならファイトがあるし優秀だ。それにグアヤキルまで行ってくれると思う」 かくして英世は後半生の最大の研究テーマである黄熱と取り組むことになる。 ケンダルからエクアドル行きの話をきいたとき、英世は一週間ほど余裕をおいてから、「行く」と答えた。 そのころ英世は研究に行き詰まっていた。ロッキー山紅斑熱やワイル氏病に取り組んでいたが、思わしい進歩はなかった。それになによりもこれらの病気では相手が小物すぎた。それにくらべて黄熱は大きい。いまや黄熱の征服はアメリカ全体の社会問題にもなっていた。相手にするのに不足はない。それにこれまで調べてきたワイル氏病とも関係がありそうでもある。行き詰まっている状態を打破するには絶好のチャンスかもしれない。 ただこの仕事はかなり危険であった。免疫のない者が現地に乗り込むことは死につながるかもしれない。それに病が癒えてまだ半年と経っていない。赤道直下のエクドアルの生活は病後の体には厳しいかもしれない。このままニューヨークにいれば恵まれた環境で研究していける。 だが英世は行くことにした。このままでは駄目だ。研究の行き詰まりが、英世をまだ見ぬ異国へ駆りたてた。 これまでの経過でわかるように、黄熱に関した研究のほとんどはアメリカ人によってなされてきた。リードやゴルガスはもとより、ノットもフィンレーも、ラジアも、実験台になった兵卒まですべてアメリカ人だった。英世も国籍こそ違え、アメリカの学者である。しかも英世が出かける二年前の一九一六年に、ロックフェラー財団の国際保健部のなかに黄熱委員会がつくられ、財団としても積極的にこの研究に援助をはじめていた。いわばアメリカが全力をあげて取り組んだ病気の一つである。 ロックフェラー研究所にいた英世が、この病気に関わり合いをもつのは、むしろ当然の成り行きともいえた。 2 一九一八年六月二十七日、英世は病後のふらつく体でエクアドル行きの汽船に乗った。 「わたしはいま、アメリカ政府の陸軍部と、ロックフェラー財団国際保健部からの依頼により、黄熱病の研究のためエクアドルに出張するところです。流行病の蔓延する熱帯へ行くのは危険だと、とどまるようすすめてくれる人もいます。研究所から主任研究員として行くのはわたし一人です。でもわたしは行きます。いや、行かねばならないのです。体のほうはもう大丈夫です。一行は二十人で、わたしの他にアメリカ人の医師や化学者、看護婦なども含まれています。わたしの荷物だけでも十六個で、そのほかにはモルモットもいれました……」 出発に当って、小林栄に宛てた手紙だが、そのなかに研究の行き詰まりを打破しようとする英世の決意が滲んでいる。 七月十六日、一行はエクアドルのグテアヤネル港に到着した。 黄熱の研究のため、ということで、町の受入れ態勢は好意的で、エクアドルには日本人の入国を禁止する法律があったが、英世は制限を受けなかった。地方にしてはホテルもまずまずだし、現地の医師も協力的である。 だが多少の行き違いもあった。たとえば到着と同時に着くはずの荷物が着いていない。一部がパナマのポルポア港で積み替えのとき遅れて残されたらしい。すぐ交渉したが、やはり二個は未着である。英世は巻脚絆をつけていたが、現地人達はそれがおかしいといって笑った。そういうものをつけても、蚊は腕や頭にも襲ってくるから無意味だというが、英世は、これで脚に注意を払う分を他の箇所に向けられるはずだから無効なわけはない、といい返した。 現地の人々は遠来の人達が必要以上に黄熱を怖れ、グアヤキルが伝染病の巣であるようないい方をされるのを嫌っていた。とくに英世達と同じ船できた歌手のマリア・バリエントスが、黄熱を怖れて下船を拒否したと報道されてから感情を害していた。彼等自身は黄熱に免疫性をもっている者が多いだけに、外国から来た人々が何故そんなに怖れるかわからなかった。 英世は着いた翌日から、黄熱病院の一室を借りて仕事を始めた。だが実験器具に未着のものがあり、研究室自体ただの部屋で、無菌培養器、冷蔵庫、消毒器、石油ランプなど、基礎的なものからまず揃えなければならない。しかもそれを発注してもこの土地徳湯のスローモーなやり方で苛立ってくる。 さらに現地の医師や助手は手伝おうとしてくれるが、自分でやらないと気が済まない英世のとってはかえって邪魔である。 「わたしは一人でできるから結構です。手を引いて下さい」 英世が断わると、エクアドルの医師もアメリカの医師も不思議そうな顔をする。彼等には、偉い学者なのにすべて自分でやろうとする英世の態度が理解できず、そのうえ言葉の関係で断わり方がきつくきこえる。ドクター・ノグチは、なにか知られたくないことがあって隠しているのではないか」 そんなあらぬ疑いまでかけられてしまう。 みなが馴れぬ土地で、むし暑さもくわわってつまらぬことでいさかいをおこしたりする。英世は不快になると一言も喋らず、機嫌がよくなると、やたらに話し続けるが、その違いが大きすぎて、また余計な詮索をされたりする。 だが、馴れてくるに従って、その種の行き違いは次第になくなった。エクアドルの医師も助手も英世が人嫌いで、かなり神経質なことを知った。絶えずせかせかと落ち着きがないのも本来の性格だとわかったらしい。 グアヤキルにきて一か月後に、英世は早くも黄熱の病原体と思われる微細な生物を発見した。 「それは患者の血清中にいつも見付けられるものではありませんが、かなり有望なものです」 英世はただちに、フレキスナー所長宛の手紙に書き送った。 ケンダルは現地で、英世の仕事ぶりを見て、感嘆し、「こんなに仕事に熱中し、すべてを自分一人でやって、大丈夫なのか」と心配したが、英世は笑って「いつもこうだよ」と答えた。 「まったくドクター・ノグチは実験の軍師のようだ。まず黄熱病退治の戦略を立て、それをすすめると、あらかじめわかっていたように、予想どおりのものを発見したものをいかに処理するかまで見通している」そういって感嘆する。 エクアドルの医師達も、とっつきの悪さはともかく、英世が真剣に研究に取り組んでいることだけはわかった。少なくとも、今度アメリカからきた一団の医師のなかでは最も誠実で意欲的である。現地の人達は、英世のまわりを邪魔しないように取り巻きながら、なにか自分でできる仕事はないかと待っていた。もし頼まれたら、モルモットをおさえる仕事でも、試験管洗いでもすすんでやる気である。 九月に入ると一行は早くも帰米の準備にとりかかった。医師達はエクアドルにおける黄熱流行の様子を調べ、防疫体制を検討することで満足し、黄熱病そのもの研究をやる気は初めからなかった。それだけの仕事なら二か月の滞在で充分だし、それで来た名目も 立つ。この熱帯の衛生環境の悪いところに長くいるのは感心しない。 九月初め、一行はグアヤキルから引き揚げたが、英世一人はとどまることにした。ようやく真正の黄熱病患者の血液と組織から病原体と思われる微生物を発見し、それを培養して増やしているところである。それらは予定されたとおりスピロヘ-ターで、ワイル氏病の病原体に似ているが少し違う。それをモルモットに植えて感染させたら、黄熱病の病原体と断言できるかもしれない。 一人だけ残るノグチに、エクアドル人は好感を抱き、さらに便宜をはかろうと申し出てきた。英世は現地ではできるだけ英語をつかわず、片言ながら覚えたてのスペイン語をつかった。この態度も現地人に好ましくうつったらしい。 一行が帰った一か月後に、英世はついに黄熱の病原体を発見したと確信した。梅毒の研究以来、飽きるほど見てきたスピロヘ-ターの一種である。まだ正式に発俵する段階ではないが、もはや、黄熱の征服は時間の問題とも思えた。 この報告をいち早くきいたエクアドル政府は英世に、近く国立の研究所を建てる予定なので、そこの所長として高給で遇するから来てもらえないかと申し出た。だが英世はこれを丁重に断った。まだニューヨークへ戻ってやらなければならないことが沢山あるし、ここではなにかと不便である。エクアドル政府は引きとめるのをあきらめ、代わりに送別会を開いて感謝の気持を表すことにした。 十月二十九日夜、英世の盛大な送別会がグアヤキル市内の支庁ホールでおこなわれた。知事はわざわざ首府のキトーから山を越えてやってきたし、軍司令官、グアヤキル市長、最高裁判所長官、大学総長、警察長官など各界の代表者が集まった。 冒頭、知事は立ち上がって次のように謝辞を述べた。 「あなたの偉大な発見で、わが国はまた将来を与えられました。過去、何世紀にわたって恐怖と悲劇のなかにいたわが国民は、あなたの研究のおかげで、再び平和と安心をえるでしょう。病気が一掃されたとき、この国には外来者があらわれ、産業は発達し、南米で最良の楽園となるでしょう。私達は決してあなたの名前を忘れません。尊敬する貴兄、野口英世の名は、わがエクドアルの栄光とともに、永遠にこの地に残るでしょう」 これは決してオーバーな表現ではなく、このあと、英世はエクアドル名誉大佐を与えられ、剣を贈呈された。 これに応えて英世が立って挨拶をする。 「わたしが今日、満足すべき研究結果をえたのは、お国の政府はもとより、関係病院、医師諸兄の甚大なお力添えがあったお陰です。この実験結果はいずれニューヨークへ戻ってから発表することになっていますので、いまここで詳しく述べられませんが、黄熱の災禍を僕滅するに、かなり有力な手段の手はじめになるということだけはたしかであります。わたしはこの愛する国で、みなさまと一緒に黄熱病に立ち向かう共通の喜びをわかち合えたことを嬉しく思っています。エクアドルの勇敢な陸軍は、わたしに大佐の称号を与えられ、司令官に任じて下さいました。もしお国がわたしを必要とするとき、わたしは誰よりも先に招集に応じてはせ参じるでしょう」 こういう演説をやらせると、英世は実にうまい。他人の感動する勘どころを本能的に知っているというか、いつも人々を感涙にむすばせる。演説が終るとともに、一斉に拍手が湧き、「ノグチ・ノグチ」の声が会場に響き渡った。日本人と同じ、熱しやすいスペイン人の大合唱だった。 かくして十月の末、英世は病原体発見とエクアドルとの友好という二つの大きな成果をえて、グアヤキルからニューヨークへの帰途についた。 だがこのとき、英世は確実に、学者としての失敗の第一歩を踏み出していた。 「ノグチの行くところ、可ならざるはなし」と血脇守之助が恐縮したとおり、これまでの英世の足跡は成功に満ち満ちていた。ロックフェラー研究所でも、ノグチが行けばなんとかなるだろう、という期待があった。そして今度も、また成功をおさめたかに見えた。いままでアメリカの多くの学者が、あらゆる努力をして解明されなかった病原体が、研究開始後わずか三か月で発見されたのである。しかも、これまで黄熱に関しては素人同然の学者が達成したのである。まさに電光切火の早業としかいいようがない。 「ノグチだから出来た」恩師のフレキスナーも溜息をついた。 だが、いかに英世といえども三か月で発見というのはあまりに早すぎた。これほど全世界に猛威を揮った黄熱は、一人の男の三か月の研究で解明されるほど簡単なものではなかった。 しかしこのとき、英世も、他の多くの学者も、まだ彼の研究の誤りに気がついてはいなかった。何人か疑問を抱いている者もいたが、それをはっきりいい出すほどの確信もなかった。 だが英世は当然のことながら、自分の研究にまったく疑問を抱かず、ニューヨークの戻ると、ただちに実験結果を論文にまとめはじめた。 わかったことは少しでも早く発表しなければなばならない。研究はなにをやったか、ということも大切だが、誰が一番早かったか、ということがより大切である、というのが英世の信条である。 膨大な資料を整理し、顕微鏡所見の図をまとめ本文を書く。一篇の論文を書きあげるのに十日はかかるが、今回のエクアドルの出張だけで、十篇近い論文ができそうである。 英世のなかに再び梅毒スピロヘ-ターに挑んだときのファイトが甦ってきた。 だがこのとき、故郷の翁島村で母のシカが病床に倒れて危篤状態にあった。 英世がグアヤキルを発った数日あと、シカは風邪をひいた。丁度、村にインフルエンザが流行ってそれに冒されたのである。初めは軽くみていたところもあるが、一週間経っても快くならず、それどころか十日目から呼吸が苦しくなり、熱も上がってきた。姉のイネは慌てて、小林栄と相談し、新潟から石塚、東京から宮原などを呼んで診てもらった。 だが診察の結果は肺炎ですでに重態でであった。六十五歳の高齢では、うち克つのは難しそうである。 その重態の枕元に、英世から小林栄に宛てた電文が届けられた。内容は短く、エクアドルで陸軍大佐の称号を受け、黄熱の征服へ第一歩を踏み出したこと、だけが書かれていた。 小林が教えてやると、シカは満足そうにうなずき、「ありがてぇごどだべ」と床のなかで掌を合わせた。宮原はただちに英世に、母の重態を報らせようとしたが、ニューヨークに問い合わせると、英世は途中パナマに寄りニュ―ョ―クに戻るのは月末になるという。船のなかでは連絡はつかないし、たとえついたところで日数がかかりすぎる。とにかくいまはなんとか、治すことである。 だがシカの病状は快くならなかった。十一月の十五日、一つのやまがあり、それはなんとかのりきったが、衰弱は激しく、あと数日しかもちそうにもない。 宮原は以前、シカに絹の布団を贈ったことがあるが、シカはもったいないといってつかっていなかった。それを敷くことをすすめると、シカはようやく納得して、「折角のいただきものだから、その上さ寝かせてもらうべぇが」と頭を下げた。 シカはすでに死を覚悟しているようである。熱でうるんだ顔で、短い呼吸をくり返し、あとはうつらうつらと眠っている。ときどき、なにか祈っているような言葉をつぶやくと、「セイサク、セイサク」と叫ぶ。 「頑張るんですよ、もう一度息子さんに会うんですよ」宮原が声をかけると、微かに笑い、「あの子が偉ぐなれだのは、中田の観音さまのお助けがあったがんだ、おれはもう死んでもいいよ」とつぶやく。 静かな眠るような往生であった。 十一月十五日、英世の乗った船がニューヨークに着いた。珍しくメリーが出迎えに船にまで乗り込んできたので英世が驚くと、伝えられてたのはシカの訃報であった。 一瞬、英世はメリーを見、それから日本からの電文を読んだ。数分間見詰め、それから自分にいいきかすようにうなずいた。 「日本へゆきますか」 「いや、いい」 英世はゆっくり頭を左右に振った。 「いつか、こういうことはあると思っていた」英世は自分にいいきかせるようにつぶやくと、「母の死んだ日は、ちょうどパナマの病院で医師達に実験を見せていたときだった」とつぶやいた。 メリーは、ことさらに英世の母の死を避け、留守中にアパートを四階から二階へ替ったことなどを話した。 「それはいい、帰ったらシャンペンでも飲みながら愉快にやろう」 英世はそういうと、自分を励ますように先になって歩き出した。 3 ニューヨークに戻った翌日、英世は早くも研究室に出勤した。 「大丈夫ですか」研究所の仲間が心配しても、英世は「こんなに元気だ」と両手を広げて陽気に答える。仲間はさらにそっと尋ねる。 「お母さんが亡くなって、落胆なさったでしょう」 「母が死んだからといって、どうして私が悲しまなければならないのですか。母はあの世に行ってしまったのではないんです。体は消えても、母は私の体に残っているから淋しくはありません」 日本を発つとき、もしかして母とはもう会えないかもしれないと、ある程度覚悟はしていた。その危惧が現実になっただけである。船で半月もかかる外国にいる以上、母の死にめに会えぬ事態が起きることは避けられない。 前回、日本に帰って母に会ったことで、英世の心の区切りはついていた。欲をいってはきりがない。自分にそういいきおかせた以上めそめそしたくない。 母の死を振り切るように、英世は仕事に熱中した。まずやることは、エクアドルで採取してきた標本から、黄熱病の病原体を確定し、それを論文にまとめて発俵することである。 グアヤキルにいるときから、英世はこの病原体について、大凡の見当をつけていた。これまで調べた黄熱病のなかに、特殊なスピロヘ-ターが発見されたが、それが問題の病原体らしい。このことはすでにグアヤキルにいた医師達に報告し、あとはニューヨークに戻って再確認し、論文を書くだけになっていた。 だが、それを正式に発表することにまったく不安がないわけでもなかった。なによりも困ったことは黄熱病とワイル氏病とが非常に似ていることだった。 ワイル氏病は、十九世紀の後半にドイツのアドルフ・ワイルによって確認された病気で、悪寒戦慄とともに高熱を発し、吐気、下痢に続いて黄疸が現われてくる。臨床症状では黄熱とよく似ている。だが死亡率は黄熱ほど高くはなく、爆発的な流行を見ることもない。合併症を起した場合は怖いが、そうでないときはさほどでもない。当時としても、黄熱よりは一段軽い病気と見られていた。 この二つの病気は臨床症状もさることながら、血清中に認められるスピロヘ-ターは同一のものか、あるいは違うのか、持ち帰った標本を細分化し、一枚一枚比較検討する。さらに黄熱病にかかった患者から採取して血で感染したモルモットを剖検し、その血液や臓器の変化を調べる。また純粋培養したスピロヘ-ターを接種したモルモットの状態を観察する。 これらの調査の結果、最後に両者は別のものと断定した。 かくして一九一九年(大正八年)、英世はついに黄熱の論文の発表に踏みきった。 まず初めの論文では黄熱の発病から一般的な症状、経過を詳細に述べた。黄熱は発病してから五日ないし六日目が最も危険で死亡率も高く、七日を過ぎるころから峠をこし、十日をすぎると死の危険はあまりない。だが十一日目ころから激しい黄疸が全身に拡がり、これは簡単には消えない、論文はそうした症状、経過についての特徴から、グアヤキルと他の地方の黄熱を比較し、両者が同じものであることを記載した。 さらに黄熱に罹患したモルモットの症状、解剖結果を詳細に報告したうえ、五番目の論文では、黄熱にかかって治った患者から採取した血清が、英世が見つけた黄熱スピロヘ-ターを死滅させ、あるいは運動を停止させる効果があることを述べた。これはこのとき発表された一連の論文のなかで最も重要な部分で、この事実によって、英世は黄熱の病原体をスピロヘ-ターの一種と断じ、これを免疫学的におさえうる可能性を暗示したことになる。実際、英世はエクアドルですでに黄熱のワクチンをつくり、それを一部の人達に試験的につかっていた。おかげで黄熱に罹患しなかったという結果がでて、英世の意気はおおいにあがった。
ここで英世は確信をもって黄熱の病原体が、ワイル氏病などで見られたものとは違う。新種のスピロヘ-ターであると断定し、それを「レプトスピラ・イクテロイデス(1)」と命名することにした。そしてそれからつくり出されたワクチンがきわめて有効であることを発表した。
この論文の完成とともに、英世は記者会見をしたが、それには学術担当者だけでなく、社会・経済関係の記者まで集まり、政治家の記者会見以上の賑やかさであった。
大体、英世は華やかさが好きな人で、この記者会見を見た学者のなかには、演出臭が強すぎると非難する者があった。アメリカ自体が自らを売り込む社会でもあった。徒手空拳でアメリカにのり込んだ一介の東洋人としては、そうして地位を築いていくより他に手段がなかったともいえる。
かくして一九〇〇年以来、二十年間にわたってさまざまの学者によって追究されてきた黄熱病は、英世のわずか三か月の研究によってその全貌があきらかになったかに見えた。
実際、エクアドルの政府は英世の成功を祝い、彼がグアヤキルに滞在中、実験を行った研究室を記念館として保存し、そこに一九一八年七月二十四日、ロックフェラー研究所員、日本細菌学の権威野口英世博士、黄熱病を発見す」と記した青銅板入りの石碑を建てた。
「野口英世博士、黄熱の病原体を発見」「ワクチンを完成」「世界の恐怖の結末」「黄熱ついに征服される」中南米からアメリカ、さらにヨーロッパの新聞にさえ、それらの記事が華やかに紙面をかざった。
だがこの華々しい英世の発表を見ながら、ひそかに疑問を抱いているグループがいた。それはまだ少数で、確実な反論の決め手はもっていなかったが、彼等は彼等なりに着々と準備を整えていた。
第七章 中南米 P.194
1
一九一九年夏、黄熱の恐怖が今度はメキシコを襲った。この夏、メキシコは異常に大量の蚊を発生し、それにつれて黄熱が流行した。とくに低地の都市に狙われ、ユタカン半島のメリダがその中心地となった。
十二月、英世はこのメリダへ乗り込む。目的は再び黄熱の症状を調べ、患者から自分の発見した病原体を見出し、前回エクアドルで見出した病原体を確認することだった。英世の発見したものがまさしく黄熱の病原体であるならば、今度のメリダの患者のなかにも当然それは見出されるはずである。
ニューヨークを船で発った英世は、途中ハバナに立寄ったあと、メキシコのプログレッソへ着き、そこから汽車でメリダへ向かった。
このときメリダは黄熱の発生後三か月を経て、大流行はかなり下火になっていた。
だが英世は到着早々、ホテルにメリダの医師、衛生関係者などを集め、自分が黄熱の研究のためにここまで来たこと、黄熱病患者がいたら血液、標本などの採取に協力してくれるようよう要請した。
この演説と一種の質疑応答を、英世はすべてここへ来る途中で習得したスペイン語でやった。
遠いニューヨークから黄熱の蔓延するユカタン半島まできて、現地の言葉で話す英世に、土地の人達は素直に感動した。ただちに医師達から患者の血液や、死者の標本などが提供された。
レプトスピラ
英世は国立病院正門左手の一室を研究室とし、そこで研究に没頭した。黄熱はすでに峠をこし、現在罹病しているのは三人しかしかいなかった。うち一人は恢復期であり、一人は死を目前にし、発病直後の最も病原体が活溌に動いている時期と思われる患者は一人だけだった。
英世はこれら患者から、毎日血液をとり、それを培養基に貯え、さらに動物に接種して経過を見た。
初めはなかなか目的とする(1)「レプトスピラ・イクテロイデス」は発見されなかった。
次第に英世は不機嫌になり、顕微鏡を覗く目が血走ってくる。末期はともかく、最盛期の患者の血液には必ず病原体が存在するはずである。もしなければ、ここの病気が黄熱でないか、英世の発見した病原体が黄熱のそれでなかったかのいずれかである。連日、新しい動物に接種しては、すでに罹患している動物を解剖して調べる。有名なドクター・ノグチが来ているというので、研究所のまわりにはいつも現地の医師や医学生達が一目でも見ようと集まっていた。
だが英世は彼等に一瞥もくれなかった。たまに仕事に疲れて中庭に出ても一言もいわない。あきらかに不機嫌な徴候である。現地の人達もこの高名な学者を刺激しないようにただ遠巻きに見ていた。
やがて一か月後、英世は黄熱病患者の血清を接種された豚のなかに、問題のレプトスピラを見つけた。朝から解剖をはじめ、標本をつくって発見したのは夜十一時を過ぎていた。
「よし、これだ」英世は嬉しいとき、日本式の万歳の恰好をして躍り出す。その姿は阿波踊りそっくりだった。「いたぞ、いたぞ」今度は英世は両手を上げて叫び、死体となった豚の頭を、「よくやった、よくやった」と撫ぜつづけた。
「この晴れきった夜空に輝く月のなんと美しいことよ。月に照らされたこの庭ほどロマンチックで美しいものはない。なんというこの充実した南国の夜よ……」
それまで、「畜生」とか「この豚め」といった言葉で溢れていた日記帳に突然、詩的な言葉が現われてくる。いつものことだが、研究の成否によって感情の振幅が激しい。
病原体を発見した翌日は、研究室の前に集まった医学生達に自分かのほうから話しかけ、「よかったら研究室を見ないか」と誘った。急な態度の変り方で戸惑っている学生達に顕微鏡を覗かせ、自ら黄熱の病原体の説明をする。学生達はその機嫌のよさに、半ば驚き半ば呆れながらきき入っている。
「やはりメキシコの黄熱も、エクアドル、パナマで発生したものと同じです。私の発見したレプトスピラはここでも証明されました。さらに私のワクチンは、この地のかなりの人を黄熱にかかることから救ったようです」
ロックフェラー研究所の恩師フレキスナー所長に、英世は自信をもって報告する。
メリダにおける黄熱撲滅に対する功績に対して、メキシコ学士院は英世に名誉会員の称号を与えた。
年が明けた二月、英世はニューヨークへ戻り、ここで再び記者会見し、「ドクター・ノグチ、黄熱の病原体をメキシコでも発見」の報告は再び全世界に拡がった。
だが落ち着く間もなく、英世は二か月後の四月にペルーへ出張する。今度は南米ペルーで黄熱病が発生したのである。再び黄熱を追って南米へ。
この旅行は英世にとって、いままでになく快適な旅であった。それまで、英世は各地へ旅行していたが、途中一度や二度はきまって不快な目にあった。主に英世を東洋人と見ての、下級船員や税官吏などによるいやがらせであった。ときには警官が銃で脅したり、船長自らあからさまにチップを要求することもあった。だが今回はその種のいざこざはまったくなかった。船員はもちろん、同じ旅行者の態度も、高名な学者と知って、丁重であった。
「今度の旅行で、私はアメリカ人旅行者の日本人に対する態度について、従来の印象をあらためねばなりません。もちろん彼等の多くは私の使命を承知しており、またおそらく私が何を代表しているかを知っているのでしょう。"黄熱病征服"のすこしばかりの宣伝がおおいに役立ち、すくなくとも一般の人の興味をよびおこしまして、私がこれにくわわっていたために、自然、私をより多く尊敬するようになったもののようです。私が謙遜するにおよばない理由をおわかりでしょう。機会さえあれば有利な新聞宣伝をおこなうことは(私のように迫害を受ける民族の者pにとっては)人間の義務だと信ずることになりました……(後略)」
クリスとパルから研究所の友人に出した英世の手紙の一節である。(エクスタイン著『野口英世』)
十日の船旅のあと英世はペルーの最北端の港パイタへ着いた。早速研究をするつもりだっが、現地には肝腎の研究室としてつかえるところがない、やむなく海ぞいの場所に木造の小屋を建て、実験動物や培養基、実験器具などを揃えたが、とても満足できる実験はできそうもない。基礎医学の伝統などまったくないペルーで、ニューヨークのような研究をしようという自体が無理だった。
おまけに黄熱病患者は思ったほど多くなく、いまかかっている者も大半は末期の恢復期であった。
それでも英世は実験を開始した。だが血清を保存する冷蔵庫はすぐ壊れるし、培養基はいつのまにか汚染されている。患者は汚い藁の上で寝ていて、血液の採取ひとつにしても怖れて容易にさせない。
しかし」ここでも、英世は患者の血清中から前に発見したと同じスピロヘ-ターを見出し、この地の黄熱がエクアドル、メキシコと同じものであることを証明した。さらに現地人の多くが英世のワクチンのおかげで黄熱にかからず、無事に過ごした事実をたしかめた。
やがて英世はペルーの首都リマに招待され、学界から政界、財界あげての歓迎会に出席した。その会には大統領も出席し、歓迎の辞を述べた。その返礼に、英世はスペイン語で、黄熱の病原体発見とワクチンについて演説し、最大の拍手を浴びた。
先のエクアドルでの成功により、中南米一帯にはすでに英世の名前が響き渡っていた。
席上、大統領は、リマに設立予定の国立衛生研究所長としてきてくれないか、と頼んだ。「年俸二万ドルで五か年契約、その年限に達したらさらに契約を結び直し、途中死亡のときには遺族に五万ドルを支払う」という好条件であった。
だが英世は即答を避け、ニューヨークに戻り、フレキスナー博士と相談のうえ返事をすると答えた。金には食指が動いたが、初めからここに移る気はなかった。黄熱を除いては、この地で研究に好都合なことはほとんどない。ただ大統領の申出をすぐ断わるのは少し失礼すぎたからである。
五日間リマに滞在中、英世はリマ大学名誉教授の称号を受け、大臣や各国大公使の訪問を受けた。さらに帰国のときには国をあげての晩餐会を開いてくれた。
2
二か月間のペルー滞在を終えて、英世がニューヨークに戻ったのは六月の末だった。英世は一応、ペルーから招請の話があったことをフレキスナー所長に告げたが、フレキスナーはもちろん反対であった。
「もし君が望むなら、米国内でも二万五千ドルの年俸で招請するところはあるだろう。それを南米に行くがごときは引退する老人のすることである。たしかに研究所は給料は劣るだろうが、これほど充分の研究費と、自由の地位を保証されたところはないはずだ」
英世はそれに異論はなかった。フレキスナーはさらに、老後も財団から年俸の四分の三の年金が与えられ、死亡の際は遺族ならびに血族に終身扶助が与えられることを説明した。
初めから企んだわけではないが、今回の外国からの招待要請が、結果として英世の報酬をあげることになった。
このあと七月には、英国から口蹄病(牛疫)の研究を始めるに当って、その細菌学主任としてきて欲しいという申出があった。これは先にフレキスナー所長が万国赤十字会出席の途中、イギリスに立寄ったとき、英国政府から希望されたもので、フレキスナーが承知してきただけに断わるわけにいかなかった。もっとも身柄はロックフェラー財団においたまま一時的にイギリスに行く、いわば交換教授に近いもので、日時ははっきりしないが十一月ごろから半年くらいという予定になっていた。
このころ、「ドクター・ノグチ」の名は米国社会ではかなり有名で、所長のフレキスナーの名を知らない人はいても、ノグチの名前を知らない人は少なかった。ニューヨークの街を歩いていても、英世を見ると道を除け挨拶する白人がいる。それは老人といわず少年といわずかなりの数になる。小柄で特徴ある外見がいっそう彼等の注目を惹いたともいえる。
これもすべて、英世がことあるごとに記者会見をし、自分の研究成果としてだけでなく、社会的事業として発展していったところにあった。学者の一部には、それに眉を顰める者もいたが、しかしそのおかげで、英世は東洋人としてのハンディキャップを積極的に除いていったともいえる。
黄熱に取り組んだ一九〇二年から二一年にかけ、英世はさらに数々の栄誉に輝く。まず二〇年の十一月に、先のメリダでの功績により、ユカタン医科大学名誉医学博士の称号を受け、十二月にはフィラデルフィア市から世の中に有益な発見発明をした人に贈られる「ジャン・スカッと・メダル」を贈られた。さらに翌年にはブラウン、エール両大学から「ドクトル・オブ・サイエンス」の称号を受けたが、このとき同時にフランスのキューリー夫人も同じ学位を受けている。
かつて梅毒に関わる一連の研究で名声をえた英世は、いままた黄熱への業績によって、その名はきわまったかのように見えた。
英世の恩人であり、最大のスポンサーであった血脇守之助がアメリカにきたのは、この翌年の五月であった。
英世は喜び、全力を尽して守之助の歓迎につとめた。
まずホテルはニューヨークで最良の一室をとったが、あまりに豪華なので、守之助は途中で逃げ出した。こういところ、相変わらず金はないのに浪費する癖は抜けきっていなかった。
だが英世が誠心誠意、守之助を歓迎したことはたしかで、守之助がいるあいだ、毎朝、六時に研究所に行って一日の仕事の手はずを整え、八時には早くも守之助の泊まっているホテルに現われ、その日の見物、見学の予定を説明し、同行して案内をした。
仕事の邪魔になるのではないかと、守之助は断わったがどこまでも従いてくる。しかも英世一流のスタミナで、見物、視察、招待、夜の宴会まで、ぎっしりと予定が組まれている。初めの宴会には、フレキスナー所長はじめ、研究所の各部長まで列席させ歓迎につとめる。守之助はその強引さに驚き、恐縮しきった。
さすがのフレキスナーも、「ミスター・チワキを、歓迎で責め殺してはいけない」と冗談まじりに忠告するほどだった。
だが英世の歓待はとどまるところを知らなかった。守之助一行がワシントンに行ったときは自分も同行し、現地では陸海軍軍医団が総出で出迎え、ニコルズ軍医がつききりで案内するというありさまだった。さらに守之助に陸軍軍医学校で講演させ、自ら通訳をかって出て、日本の最も偉大な歯科医であり、自分の恩人であると紹介した。守之助を最も驚かせたのは、国務長官ヒュースに会わせてくれて、さらに大統領ハーディングに面会できたことであった。とくにヒュース長官は執務中ながら、わざわざ守之助の手を握り、「ドクター・ノグチがいることは、わがアメリカの誇りである」と褒め讃えた。
これらはいずれも英世の名声があってこそ実現したことだが、はっきりいって、日本の大使より、英世のほうが米国社会では力があったといって過言ではない。当時英世の紹介があればアメリカのほとんどの高官に会うことができた。
一か月半のアメリカ東部での滞在を終えた守之助一行は、やがてニューヨークを去るが、この間三十八日間、英世と守之助は顔を合さぬ日は一日もなかった。あるときは朝から深夜まで行動をともにし、ワシントンからペンシルバニア、さらにはシカゴまでも従いていって世話をやいた。そのあいだも研究を中断しないように、秘書のチルデンはじめ、助手に毎日電話連絡をし、仕事の様子をきき、段取りを指示した。
別れるとき、守之助は駅頭で英世の手を握っていった。
「若いときから、私は君の世話をかなりみてきた。ときにはこんなに面倒をみなければならないのかと悲しくなることもあった。だが、今度の旅行で、私が君に尽くしたことは完全に帳消しにしたい。今回の旅行でそれにあり余る充分の好意をいただいた。本当に君の尽力には心から感謝している。ありがとう」
英世はそれをきいて首を左右に振りながら、
「冗談じゃありません。私は日本で受けた恩義を帳消しにしようなどと思ってお世話をしたわけでありません。私はアメリカに長くいるとはいえ、日本の恩人に、ヤンキー気質まる出しの打算的な男ではありません。アメリカ人にはともかく、日本人の恩人に、そんな心を抱くわけはありません。私はただあなたのお世話をしたくて、ついて歩いただけのことです」
「ありがとう、私のいい方が悪かった。とにかく嬉しかった」
二人はもう一度、しっかり手を握り合った。発車のベルが鳴り汽車が動き出した。
「じゃあ、お元気で」
「君も元気で、なにごとも急いではいけない。自重するのだよ」
「わかりました」
英世はうなずき、偉大なスポンサーと金喰い虫といわれた男は初めて満足の笑いを浮かべた。このとき、英世が守之助に贈った土産は、エクアドルで買ってきたパナマ帽と、守之助の妻に金の飾り時計一個であった。
だがその六年後、急ぎすぎた結果の孤独な死が英世に襲うとは、守之助も英世自身もまだ気がついてはいなかった。
3
やがて大正十二年(一九二三)の年が明ける。英世は数えて四十八歳になっていた。
この年の七月、英世の父佐代助が死亡した。死因は肝硬変になっていた。
八年前、佐代助は、北海道の英世の弟清三のところへ引きとられて行ったが折合いが悪く、二年で三城潟へ戻ってきていた。そのころから肝臓を病み、ときどき医者にかかっていたが、生来の酒好きは治らず、家人の隙を見ては飲んでいた。彼の場合は、まさしく長年のアルコール中毒で肝臓を損ねたものである。それでもシカの生きていたころまでは、元気だったが、シカが死ぬと心細くなったのか、急に床に臥しがちになった。シカの死後、野口の実家は、長女のイヌとその夫の善吾の代になっていたが、相変わらず生活は苦しく、満足に医者にかかる余裕もなかった。
だが貧しいといって、世界的な学者の父を放置しておくわけにもいかない。ここでも小林栄が面戸を見、若松から渡部鼎博士を呼んで診てもらった。渡部鼎は地本の医師六角譲と相談のうえ、佐代助の容態をニューヨークの英世へ連絡した。だが英世からはこれに対し、なんの返事もなかった。
父のために、いろいろ面倒を見てくれる郷里の人には感謝しながら、といって「よろしく頼む」というほどの感情が、英世にはおきなかった。正直いって、英世にとって父の病は自業自得としかうつらなかった。
英世にとって父の死はむしろ歓迎すべきものだった。これまで父が生きているおかげで、どれだけ苦労をし、まわりの人達の恩義を受け、肩身の狭い思いをしたかしれない。その負担から、父が死ぬことでようやく解放された。悲しみよりむしろほっとしたというのが本心であった。
大正十二年七月三日夜、佐代助は数人の家族に看とられただけで息を引きとった。世界に誇る学者の父でありながら一生華やかな脚光をうることも、子供達から愛情をかけられることもなかった。自業自得とはいえ、シカとくらべると酬われることのない一生ではあった。
佐代助の遺体は小林栄らによって葬送されたのち、野口家の菩提寺である長照寺のシカの墓の側に埋葬された。
この二カ月後、東京で関東大震災がおきた。この悲報はたちまちニューヨークにも知れ、英世はただちに安否をきづかう手紙を小林栄に出した。
「ただいま空前の一大天災を新聞で知り、まことに寝耳に水、驚き、悲しみのどん底にいます。父上、母上様(小林栄夫妻のこと)には異常はありませんでしたか。おうかがいいたします。新聞では概略だけでくわしく知る由もなく、私も実父の悲報その他のお手紙をいただき、お礼を申し上げようと思いながら、学事、俗事に追われ機会がなく、今度の凶事まで放置していた不孝につきましては、お詫びの仕様もありません。深くお詫びします。小生はこの秋からブラジル国に三ないし四か月の予定で出張します。
今度の天災で、東京の星、宮原、奥田、赤星鉄馬、古河虎之助、葛原猪平らの友人、および血脇恩師一家はいかがいたしたでしょうか。早速承り度く思います。人生の栄枯実にはかなきものと感じ入る次第です。ご両親様のご無難の細かな様子一刻も早く知りたく思います」
父の訃報がきても、返事の一本も出さなかった英世が、大震災の報せには早速問い合わせの手紙を出している。
大震災の被害は大きかったが、英世が心配して血脇守之助ら、東京在住の知人達の生命に別条はなかった。
安堵した英世のところに、さらに吉報が届く。この年十一月、英世が帝国学士院会員に推薦されたという連絡である。
この学士院会員は、日本の学者の最高の名誉とされているが、老齢の学士院会員の慣れ合い的選挙で決まることは、いまも昔も変わりない。この会員への推挙は老学者を対象にしたいわゆる長生きへのご褒美といったおもむきが強く、それだけにとくに、どの業績へというはっきりした目途はない。長年の斯界に尽くした努力へといった漠然とした理由が多い。
英世がこの時期に学士院会員になったのも、単に欠員ができ、それを石黒忠悳らが強く推したからである。八年前、恩賜賞をまらったときには、それなりの理由はあったが、今回はとくに理由はなかったが、それでも、なにもわからぬジャーナリストは
賑々しく、「野口英世博士、学士院会員に推される」と書き、さらに「長年の細菌学に関する功績により」という、わかったようなわからないような理由を書き添えた。
英世は受賞の報せにも、とくに喜びは現わさなかった。恩賜賞をもらったときのように、「日本の学者はついに俺を認めたか」と叫びもしなかった。連絡がきたとき、「そうか」と一言うなずいただけだった。いまさら、日本の学士院会員になったところで、それが対外的になんの価値もないことを英世は知りすぎるほど知っていた。それに、そんな些細なことで満足していられない重大なところに、英世自身がさしかかってもいた。
これより前七月に、ジャマイカのキングストン1で、世界の熱帯病会議が開かれ、英世はこれに参加し、黄熱に関する論文を発表したが、これに対し賛否両論がでた。
まず反対に立つたのはアメリカのアグラモンテであった。彼はかって、キューバに派遣された陸軍のリード黄熱委員会のメンバーであり、キャプテン格のリードらと黄熱に関して長い研究歴を誇っていた。
彼の野口論文への反論の要点は、野口博士が発表した病原体はワイル氏病原体ときわめて類似している。こお二者のあいだには実質的な差はなく、同一の菌株のなかに見られる相違以上の違いをこえてはいない。このようなものを、いかに野口博士の主張とはいえ、黄熱体の病原体と認めるわけにはいかない」という理由だった。
アグラモンテは血清学的にいくつかの類似点をあげながら、これを論証した。
この反論は英世の成果を根底から揺るがす重大なものだった。
「二つは同じ菌株であり、きわめて類似している」ということは、いいかえると「あなたはウイル氏病の病原体を、黄熱病の病原体と誤認している」という指摘に他ならない。もしこのような否定的な発言を真向からされたら、かつての英世なら、その場で相手を怒鳴り散らしたかもしれない。事実、十年前、ウイーンでコッホ研究所の若者に研究の不備をつかれたとき、英世は大勢の面前で「無礼者」と叱った。
だが、いまの英世には怒鳴るほどの気力はなかった。というより、怒鳴るだけの根拠がなかったといったほうが当っている。
司会者に反論を求められて英世は登壇したが、このとき英世は、「あなたの意見の基礎としている実験的証拠は、レプレドとホフマンにより提供されたもので、両者はあきらかに二次的感染をとりあつかったものであり、今回の反論としては具体的な意見をなさない」といっただけだった。
この反論は英世の発言にしては珍しく迫力がなかった。二次的感染であろうがなかろうが、問題は二つの病原体が似ているという事実で、そのことに対する直接的な回答にはなっていない。
さらにアグラモンテは発言を求めて、「黄熱の伝達には、病菌をもっている蚊が、人体を一度噛んだだけでうつすことができる。それにくらべて野口は博士のやり方はモルモットにしても、あまりに大量の患者の血清を注射しすぎて、正常な感染形態とはいいがたいのではないか」と批判した。
これに対して英世は「実験というのは、すべてこのようなやり方を踏襲しているものであり、私のやり方が、動物に病気をうつすやり方としては最も一般的である。現実の実験者は誰もあなたのような批判を本気で受けつけないだろう」と答えた。
英世のいうことはたしかにそのとおりだが、これもアグラモンテへの誠実な反論とはいいがたかった。動物実験が人体感染と違いすぎることについては、いろいろな学者によって問題とされていたことなので、英世には前向きの反省がなく、さらに重大な疑義にはただ一般的なやり方だから、ということで誤魔化したともいえた。
座がしらけたとき、ヘンリー・カーターが発言した。
「私はもし、自分の娘が熱帯地方へ行くとしたら、野口博士が創薬したワクチンを娘にうってやるでしょう。以前、アンデスの高原地帯から五百名のヴィンセ・ドールス大隊が入営したとき、三百名にワクチンが接種されました。それからあとの一群には、前回より少量のワクチンが接種されました。この初めの一群とあとの一群をくらべると、初めのほうが、黄熱病にかかる者は少なく、第二群のほうがいささか多いという結果がでました。私は以上のことから、野口博士のワクチンが有効だと思います。しかしそれは決して、有効と信じているとは違います。有効らしいが絶対とは断言できない、その微妙なところに、このワクチンの問題があるようです」
カーターの発言は、英世の病原体とワクチンを大筋では認めるという好意的なものであったが、全面的に信用するものではない、彼のいうとおりの微妙な発言であった。
だが次に立ったニコルズははっきり、「私は野口博士のいうレプトスピラ・イクテロイデスが黄熱の病原体であると信じます。他の人はともかく、わが米国軍医学校では野口博士の意見に賛成です」と断言した。
このニコルズの発言は英世にとって、力強い味方となった。彼がいいきったとき、英世は泣き出しそうな顔になった。
だがアグラモンテの意見は、集まった者達を動揺させるに充分ではあった。少なくとも野口博士のいう病原体だけでは解決できそうもない、なにかその奥にもう一つの問題があることを暗示させた。これに対し、野口やニコルズの意見は、他人がなんといおうと、「自分は信じている」といった類の主観論で客観性がなかった。英世は最後に発言を求めていった。
「私が強調したいのは、特殊な技術と細心を要するこの種の実験的研究には、各人が最高の技術と、それを駆使できる能力をもっていることが前提であるということです。これなくして論じたところで、それは机上の空理空論にすぎないものになってしまうということです」
英世は実験の技術に関してだけは、誰にも負けないという自負があった。事実、すべての人が、英世の実験での才能は認めていた。だが反面、そこに自信過剰からくる危険性もあった。
「みなが俺と同じだけの苦労をし、技術をつみ上げて論じているのか、問題を論じるなら、それだけの技術を積んだうえでこい。そうでないかぎり、話したところで意味はない」英世はいまこそ、そう叫びたかった。
4
この年十一月、英世は南米ブラジルへ向かった。ブラジルで黄熱病が発生したという連絡を受けたからだが、同時に、ブラジル学界に生じた野口黄熱病原体に関する批判に答えるためでもあった。
この批判の火の手は、エクアドルでワクチンの効用について論じられたことから燃え上がり、それがキューバで大袈裟に取りたてられ、ブラジルで一層大きくなった、というのが真相であった。とにかく疑われているとあっては行かざるをえない。
これで、エクアドル、メキシコ、ペルーにくわえて、五度目の海外遠征である。
その都度、黄熱の病原体を確認し、いずれの地の黄熱も同じであることを証明してきたが、それでも、「野口怪し」の異論がおきる。それも年々おさまるどころか、反論の声はいっそう強くなってくる。
キングストンで、アグラモンテにあからさまに反論されたあとだけに、今回の南米行きは英世にとっては反論の絶好のチャンスであった。
「あれだけ俺がいってもなお信用しないのか」その憤りとともに、もしかして、自分の発表は間違っているのかもしれない」そうした一抹の不安がないわけでもない。
十日、ニューヨークを出発した船は、二十五日にリオデジャネイロに寄港し、ここから北に向かい、三日後パイヤに着く。ここには先発のホワイト・スキャンネル等が準備して待っていた。
英世はここの「オスワルド・クルーズ」研究所を借りて研究にとりかかる予定であったが、着いてみると、ここも建物は立派だが、水道やガスがなく、消毒器を持参してきても、これを電流と直結するコンセントもない、おまけに最も大切な暗視野顕微鏡が入った荷物が未着であった。
さらに来てみてわかったことだが、肝腎の黄熱患者がいない。九月に三人発生したが、その後は一人も出ていないし、探すのならかなり奥地まで行かなければ駄目だろうといわれた。
「この国の人は約束するが守れない。医者は来るといって容易に来ない。大体この国は熱帯で、複雑なものごとを考えたり、書いたりするのに適しません。人々は日がな、だらだらとし活力がありません。この国にはこの国のテンポがあるらしく、それは到底われわれの受け入れられるものではありません」
英世は例によって不満のたけをニューヨークのフレキスナーへ書き送る。
だが患者がいないといって遊んでいるわけにもいかない。英世は現地の学者から、この地の暗視野顕微鏡が三つあるのをきき出し、それらを持ってこさせた。長年使っていなかったらしく部品が欠けているものもあったが、三台合わせてようやく満足な一台をつくりあげた。
「暗視野顕微鏡一つさえ満足に見ることのできないものが、どうして自分の」発見に反対など唱えることができるのか」英世は痛烈な皮肉を、現地の医師達にあびせる。
それはたしかに英世のいうとおりで、現地の医師達は、英世と対抗できる充分な技術を経験も持っていなかった。実力がないのに、ただアグラモンテや一部の学者の尻馬にのって、「そうだそうだ」と騒ぎたてる。では「お前は一体どういう研究をしたのか」と問い詰められるとなにも答えられない。
もつとも、ブラジルで「野口に批判続出」というのは、一部の学者お大袈裟な情報で、来てみると、批判らしい批判はほとんどなかった。それどころか、遠路はるばるきて日本学者に、ブラジル人達はむしろ好意的であった。それを知って英世の機嫌もなおっていく。
だが、黄熱患者がいないのでははるばる来た甲斐がない。
一瞬もじっとしていられない英世は、この地独特の鞭毛中の感染症があるのを知って、こちらの研究に手をつけはじめた。さらに麻疹が出たときいてはすぐ駆けつけている。
その間、英世は現地の医師を集め、覚えたてのポルトガル語で、自分は黄熱患者の血液を採って調べたいこと、そのためには黄熱から恢復した人でもいいからできるだけ早く、そういう人を探してもらいたい、と頼んだ。
現地の医師達はようやく英世の熱心さを理解した。一度気心を知ると、彼等は誠実である。
この日本の医者が、研究一筋の真面目な男であることを知ると、助手となって働き出した。風采は上がらぬが研究の鬼のような英世に、女医学生の一部やエレミタという原住民の女中まで好意を寄せてきた。だが英世はそれにも気がつかず、毎日、鞭毛虫や麻疹の標本をつくり顕微鏡を覗いている。
やがて十二月半ば、待望の黄熱患者の血液が手に入った。それも現地の医師をとおして数人分が届いた。英世はこれをもとに動物に接種しながら、さらに医科学生達に実験のデモストレイションをおこなった。それらの一部始終を見て、現地の医師達はようやく実験操作の難しさと、大変な努力を要することを知る。そして彼等は一様に、英世の信奉者となった。
二か月後ここでも、英世は同じ方法で病原体を見付け、ブラジルの黄熱病も、エクアドル、ペルー、メキシコのそれとまったく同じであることを証明した。
「遠征は成功した」
ただちに英世はニューヨークへ打電した。キングストンで一旦打ち萎れたかと思った英世は、ブラジルで新たに自信をえ、もはやアグラモンテなどには負けないと思う。
翌年の二月二十四日、英世は四か月のブラジル滞在を終えてニューヨークへ戻ることになった。
出発のときには知事以下の多数の学者、名士らが見送りにきて、名残を惜しんだ。きたときは敵地に乗り込むような緊張感があったが、四か月のあいだで、ほとんどの医者が英世のファンになっていた。
英世がオストワルド研究所に新たに整えた設備は、消毒器から冷蔵庫、特殊培養器など高価なものばかりだったが、これらはいうまでもなく、すべてロックフェラー財団の金でまかなわれたものである。
だが出発に先立って、器具の処置についてブラジルの医師がきいたとき、英世はいとも簡単に「もちろんいらない、君達にあげるよ」と答えて、あとで財団とのあいだに物議をかもすことになった。
第八章 ニューヨーク(Ⅲ) P.216
1
ブラジルから帰ってからの英世は、しばらくニューヨークにいて仕事をした。一九一八(大正七年)黄熱の研究にとり組んでから二年間が最も腰を落ち着けていた時期であった。
しかしその研究内容はめまぐるしく変った。
このとき黄熱は英世にとって、すでに終った仕事であった。病原体を発見し、それによってつくられたワクチンがある程度効果があるとすれば、それで充分であった。あとはどこかで別種の黄熱が発生すれば別だが、そうでないかぎり、研究としては完成したものとなる。他人はいざ知らず、英世はそう信じていたし、実際、信じられなければ、これまでの研究が間違っていたことになる。
この時期、英世が主に手をつけたのは鞭毛虫の感染症であった。これはブラジルにいるときに興味を抱き、その後ホンジュラスに鞭毛虫のいる植物があると聞き、そこまで訪ねていったりした。またシャンデ―ケンの別荘でも、この仕事を継続した。
次いで一九二五年ころからは、再びロッキー山紅斑熱にとりかかった。大量のモルモットをこの病気に罹病させ、病原体を探る作業をすすめていた。
さらにペルーのリマから一本の血液の入った試験管が届けられたことから、オロヤ熱の研究を手がける。この病気は、インカ帝国の時代からペルー人を悩ませた病気で、全身にいぼが出てくる奇病であった。ときとして発熱し、全身が蒼白になって重症の場合は死ぬ。十九世紀の終りころ、リマからオロマへ向かうアンデス横断鉄道敷設中に、数千人の労働者がこの病気で死亡したといわれる。
ペルーの医師の大部分は、この病気の急性期のものはいわゆるオロヤ熱で、慢性期のものがヴェルーガ病で、両者は同じものだと考えていた。
一九一三年、ハーバード大学の熱帯医学研究グループは、この病気を調べ、患者の赤血球中にバクテリアに似た原生動物を見付け、これが病原体であるとして、パルトネラ・パシリフォルミスと名づけた。さらにこれはオロヤ熱の原因であるが、ヴェル―ガ病とは異なると発表した。この五年後にペルーに在住の昆虫学者が、この病気は昆虫によって広められると主張し、三月にダニが、七月にはサンチョウバエが主役をなすとした。
ここに英世が登場し、一本の試験管から、さまざまな動物に接種させ、病原体を培養するのに成功した。そしてアカゲザル、ミドリザル、イヌ、ウサギ、ハツカネズミ、モルモットなど、あらゆる動物に感染させ、くわしく調べた結果、英世は次の結論を出した。
「ヴェルーガ病も、オロヤ熱も、ともに同じものである。発症の違いは、罹病者の抵抗力と体質によるものであり、毒性の強弱によって、ヴェルーガ、オロヤ両方の反応を見ることができる」
英世はさらにハーバード学派が、先の実験で、別の病気と謝った理由を克明に説明した。
相手の誤りを指摘しながら、自説を主張するのは気持がいいものである。英世は快適な気持でこの論文を仕上げた。自らヴェルーガ病患者の血液を注射して死亡したキャリオンら、多くの犠牲者を出して、なお不明だった原因が、英世のわずか一年有余の研究で解決してしまった。英世はここでも、また最後の勝利者になったようである。
この余勢をかって、英世はさらにトラコーマにも手をつける。当時、トラコーマはインディアンのなかで広く蔓延していたが、英世はインディアンの多い、アリゾナ州のレーンボー・ブリッジへ向かった。
ここですでに盲目になった患者らから組織切片をとり、これをアカゲザルの目に接種する。目的は病原体を確認し、その撲滅策を考えることであるが、たしかに猿にトラコーマを発病させることはできたが、病原体ははっきりしない。だが、この病気は日本にも多い。
「もし、トラコーマの病原体が発見できれば、多分、ニ、三年のうちに東洋へも調査におもむくことになるかもしれません。そうすれば日本にも立寄り、久しぶりにみなさまとお会いすることができます。その実現の日がくることを、小生は心から望んでいます」
血脇守之助に書き送ったが、その願いもむなしく、この翌年、英世はまるで方向の違うアフリカへ向かうことになる。
英世が解決済みと思った黄熱が、再びアフリカで発生し、野口が見出した黄熱病原体への疑惑が、再び囁かれるようになったからである。
2
一九二三(大正十二年)十一月、ブラジル遠征から戻ってから、一九二七年(昭和二年)十月アフリカへ遠征するまでの三年間、英世は鞭毛虫感染症、ロッキー山紅斑熱、オロヤ熱、トラコーマと、当時、問題になっていた流行病に次々と営んだ。
だが、この成果は必ずしも満足すべきものではなかった。一応、学界で認められ、自分でも納得できたのはオロヤ熱に関する研究だけで、他はいずれも未解決であった。なかでもトラコーマはいま一歩のところまできたが、決め手は見出せなかった。それらは曇りガラスから外界を見ているように、なにかしら見当はつくが、はっきりとは見えない苛立たしさにも似ている。
「時間が欲しい、時間が欲しい」英世は口癖のようにいい続けた。
「少しは暢んびり休むものよ。人間は頭を休めなければ、いいアイデアも浮かばないでしょう」
メリーが溜息まじりにいう。結婚してこのかた、夫が多少とも暢んびり休んでいるのを見たのは、一九一七年の夏、腸チフスになったあと、シャンデーケンの山荘で休養したときくらいのものである。あとはひたすら働きづめで、折角買った山荘も標本や顕微鏡が積まれた研究室になっていた。
「あなたはもう五十をこえたのよ、いつまでも若いと思っていたら大間違いだわ」
「人間は一か月以上休んではいけない。それ以上休むと、頭が一旦からになり、また元のペースに戻るまで一か月以上はかかる。結局二か月以上まるまる休んだことになり、その損害は大きすぎるのだ」
英世独特の理屈だが、それは満更根拠のないものではなかった。チフスで休んだあと半年近く、英世の仕事はまったくといっていいほどすすまなかった。その足踏みを、英世は病気のせいでなく、頭を休ませて怠けたせいだと思いこんでいた。
「あなたは自分がわかっていないのよ」
いままで数えきれないほど夫婦でいい争いをしてきた。ときには取っ組み合いになり、大柄なメリーが英世を壁ぎわに押しつけたこともあった。そんなときは大抵、英世のほうから黙ってしまう。少し淋しそうに目を伏せ、やがて書斎に引っ込むか、研究室に出かけてしまう。
表面はメリーが勝ったようにみえるが、無言のまま最後は英世が自分の意見をとおしてしまう。日常のことはともかく、こと仕事に関しては考えをまげない。いくら「休め」といっても、無意味なことはわかっていた。
日本人が、こんなに働きづめで動きまわるとは知らなかったわ」
メリーが皮肉まじりにいう。
「人間は太陽に従って動くのだ。太陽が動いているのに、人間が休むというのはいけないことだ」
英世の理屈に、メリーは両手を拡げて肩をすくめるだけである。
正直いって、メリーは夫を尊敬していいのか、軽蔑していいのかわからなかった。
現実にはたしかにロックフェラーの主任研究員で、年俸だけで五千ドルももらっている。みなが「先生」と呼び、街を行くと白人でさえ頭を下げる。さまざまな大学の有名教授や所長から手紙がくるし、電話もかかってくる。近所の人は、みな「偉い人だ」という。
だが家にいてやっていることといえば、本を読むか顕微鏡を見るだけである。あとは将棋をさしている。面白い話題も、機智に富んだユーモアもない。冗談をいって笑い合うということもない。二十四時間中、ほとんどが仕事一筋に向けられている。ときに将棋をさしたり、魚釣りをするのも仕事の合い間の休息で、結局仕事のためであることに変りはない。
もちろんパーティなどには行きたがらないし、連れてもいけない。軽妙な会話を楽しむという余裕などまるでない人だから、すぐ不機嫌になるし、相手の機嫌も損ねてしまう。たまに熱心に話していると思うと学問のことで、あとはせいぜい外国の話とか、日本の国がいかに素晴らしいか、ということを自慢するくらいのものである。会がつまらないとなると、これから踊りがはじまる直前にでも平気で帰ってしまう。
もっとも英世がダンスを嫌うのは、小柄でほとんどの女性よりも背が低いせいもあって、「ダンスなど、人間の考えた最低の遊びだ」とけなす。
だが背のことが気になるならメリーと踊ればよかったし、現に大きな女と小さな男という組み合わせはいくらでもあった。ビア樽のように肥った女に、しがみついて踊っている小男も、巨木のような大男に蝉のように貼りついて踊っている女もいる。陽気なアメリカ人は、外見でとやかくいわない。愉快で楽しければそれでいいのだ。そんなことで、いちいち考え込み、怒り出す夫の気持がメリーにはわからない。
若いとき貧しくて苦労したというのが、それにしても深刻癖が強すぎるし、なにごとにも大真面目すぎる。アメリカ人は貧乏のなかで育っても、もう少し暢気である。いまはロックフェラーの主任で、「ドクター」なのだから、もう少し雄弁になっていいと思う。英世が歌ったり、躍ったりしたら、みんな手を拍いて喜ぶはずだが、それを一人だけ苦虫を噛みつぶしたように不機嫌でいる。
実際、英世は不機嫌を隠せない男であった。不快でも素知らぬ顔でいたり、ジョークで晴らすということもない。万事、嬉しいか悲しいか、楽しいか不快か、正しいか間違っているか、二つに一つである。その中間を受け入れる弾力的なところがない。
メリーが安心して夫と一緒に行けるところといえば、教会くらいしかなかった。そこなら敬虔に頭を下げているだけで済む。英世も教会は嫌いではない。週に一度、教会へ行って礼拝していると、頭が洗われる気持ちがする。
メリーが夫と連れ立って歩いた記憶といえば、その教会えの行き帰りと、シャンデーケンの山荘近くの山道を散歩したくらいのものである。それでも英世は歩きながら植物を採ったり、「この花のなかにいる問題かも知れない」などとつぶやきながら標本箱におさめたりする。あるときは、道の途中の古井戸の汚水が漂白剤で浄化されているのを見て、スピロヘ-ターが死滅してしまうと怒ったりする。
散歩しながら、頭のなかは仕事のことが渦巻いている。
それ以外、二人で旅行したといういう思い出はまったくない。せいぜいニューヨークとシャンデーケンの往復を一緒に車に乗ったくらいで、世間一般のアメリカ人の夫婦とは大分違う。そのつもりで接すると無性に腹が立ってくる。
だが、といって英世は冷たいかというとそうでもなかった。いつも仕事のことばかり考えているだけに、家庭のことに関してはメリーに任せきりだった。なによりもいいことは、アメリカの夫のように金にうるさくないことだった。研究所から給料がおくられてくるが、それがいつ、どれくらい入ってどれくらい出たかも知らない。その金をメリーがどう使おうと一切無頓着だった。
本人は仕事ばかりしているので、小遣いはほとんどつかわない。たまに日本人クラブに将棋をさしていくとき小銭をもっていくくらいのものである。
もっとも金に無頓着なだけに一旦つかいだすと手がつけられない。金があってもなくても注文してしまう。一度、クラブにいた日本人全員を連れて中華料理店へ行き、払えなくなって呼び出されたこともある。たとえ現金がなくても、一流の店なら「ドクター・ノグチ」といえば顔がきくのでつけは増えるばかりである。
いつ、どこから請求書がくるかわからない不安はあるが、金にうるさくないだけはたしかである。もっとも、これだけ計画性なくなっていれば、他人にとやかくいう権利がないのも当然である。
それと仕事に追われてほとんど家にいないので、メリーは割合暢気である。たまに家にいてもほとんど書斎に入りきりである。ときに空腹になると不機嫌になることもあるが、口に入るものさえ与えておけばあまり文句をいわない。
社交嫌いだから、もちろん家でパーティを開いて客を呼ぶということもない。そのため料理をつくり、ホステス役をするといった煩雑さもない。淋しいといえば淋しいが、その分だけ暢気なこともたしかである。それでも退屈なメリーは人恋しくなる。たまに研究所の同僚や日本人を連れてくると、英世にかわってメリーが相手をする。どういうわけか、英世は自分で客を連れてきていながら、肝腎の話が終ると黙り込んでしまう。それから四方山話をしたり、相手の好みそうな話題を探すということもない。
このころ、英世の住んでいたアパートに太田好昭という日本人がいた。彼はまで二十二歳だったが、美術品を扱う山中商会の社員でニューヨークに来ていた。
何度かエレベータで会うちに英世を知って、部屋にも遊びに行ったが、彼がいっても英世はぼんやりソファに坐っているだけで、とくに話もしない。太田青年のほうで話しかけると、簡単に答えるだけである。
大体、英世は日本人クラブに行っても、ほとんど話をしなかった。クラブに行くのは日本の新聞を読むのと、将棋をさすためだから、それ以外のことは不必要といった態度である。多くの日本人は、あの奥で将棋をさしているのが野口英世だと、遠くから見ているだけで、たまに前までいって、名刺をさし出し自己紹介する者がいても、英世はうなずくだけで、すぐ将棋盤に向かう。考えている最中は話しかけても、返事をしない。
英世の家のリビングルームは二十畳もある大きなものだったが、備付けの家具以外余計なものは一切ない、だだっ広い感じの部屋だった。
無口の英世に代って、メリーがホステス役を引き受け、紅茶とクラッカーを出すと、メリーは太田青年に仕事のことやら友達のことなど、いろいろときく。アメリカの女らしく、メリーは陽気で屈託がなかった。太田青年が画を売るこつなどを話すと、いろいろきき、楽しそうに笑う。横で英世もきいているが、とくに笑いもせず腕組みしている。メリーは英世がいることなど忘れたように話しかける。
太田青年が、英世の邪魔かと思って帰ろうとすると、「この人は、仕事をしたいときは、放っていても研究室に行きますからかまいません」と引き留める。
夫婦なかが悪いのかと思うと、そうでもなく、休日など楽しそうに腕を組んでエレベータにのり込んでくる。太田青年が挨拶して、「どこへ行くのですか」ときくと、「教会よ、これだけがお仕事」といって、メリーはにっこりと片目をつぶる。それに合わせて英世もかすかに笑っている。
「仲がいいのか悪いのかわからない」それが太田青年の野口夫妻を見た実感であった。そしてそれはまた、英世やメリー自身同じだった。
正直いって、「お前は妻を最高に愛しているか」ときかれると、英世は少し考えざるをえない。そんなに嫌いではいないが、しかし絶対的に愛している、ともいいきれない。アメリカの女性と結婚した以上、こんなところで納得するより仕方ないのではないか、そんな気持ちに近い。
同じ質問をメリーにぶっけても、やはり首を傾げげてしまう。「そりゃ不満はあるけど、仕方がないところもあるわ」そんな答え方しかできそうもない。お互い不満はあるが、まあまあという感じに近い。
幸か不幸か野口夫妻には子供ができなかった。三十七歳の晩婚だったから、子供をつくるならば急がなければならなかったが、そのころ子供どころではなかった。フレキスナーの好意でロックフェラー研究所に招かれたとはいえ、そのまま残れるか否かの正念場であった。そこで頑張り、梅毒スピロヘ-ターの研究を成して欧州旅行に出発した。帰ってきたかと思うと日本へ戻り、その後腸チフスにかかった。そのあとは黄熱という大物の研究にとりかかり子供を欲しいと思う暇もなかった。それに万一できたとしても、アメリカ人との混血では、という不安もあった。
アメリカに長くいながら、英世は意外にナショナリストであった。どうせ子供をもつなら日本人同士の子供を欲しい。その意味ではメリーと結婚しているかぎり、子供をつくっても仕方がない。それに心の底では、子供ができるのを怖れる気持ちもあった。自分は背が低く、そのためこれまでずいぶん口惜しい思いをしてきた。その自分に似ては困る。子供にまで同じ苦労を味わせたくない。さらに酒癖の悪い父親の血を継いでも困る。父は単なるアルコール中毒で、遺伝形質に関係ないとは知りながらやはり気になる。それにたとえいい子が生まれたとしても、無事に育てられるかどうかわからない。自分のように幼いときに怪我をしないともかぎらないし、その辛さはもう骨身にしみるほど体験してきただけに、この過ちを子供にまで味わせたくない。
そんなことを考えると、素直に子供をつくる気になれない。
メリーもとくに子供を欲しがっている様子はなかった。大体が暢気に毎日を過ごせればいいほうで、将来の計画など深く考えないほうである。それに子供など産んで、育児にしばられるのなどあまり気がすすまない。初めに数年間は、お互いに子供ができないように注意した。それは英世がいい出し、メリーも同意したものだった。
だが途中からはとくに避妊に気を配ったわけでもない。妊娠しないのに慣れて、互いに注意を払わなくなったが、やはり子供は生まれなかった。それが男のほうに欠陥があったのか、女のほうに欠陥があったのか、あるいは偶然なのか、わからないが、いまさら調べるまでもない。英世は五十になり、すでに子供をもつ気などはなくなっていたし、メリーもそれでとくに淋しがることもなかった。
すごく愛しているわけではないが、といってとくに嫌っているわけでもない。充分に満足しているわけではないが、といって不満をぶつけあうわけでもない。結婚した以上、このあたりで妥協していくより仕方がないのではないか。結婚後十数年を経て、二人は日本風にいう、枯れた心境になっていた。
3
この三年間のあいだに、英世はさらにいくつかの栄誉を受けた。
まず一九二四年(大正十三年)に、フランス政府から、レジオン・ド・ヌール勲章を贈られた。
この章は、第一は名誉賞状、第二は青銅牌、第三は銀牌、第四は鍍銀牌、第五は金牌と五つの段階があった。英世に贈られたのは、このうちの最上位の金牌であった。
理由として「野口博士を植民病理学に貢献せる学者にして、また黄熱に対する戦闘に従事すべく、悪疫の猛火中に突進せる勇士なりと認める」とあった。
さらに翌一九二五年には、パリ大学より名誉学位が贈られ、コーペル賞牌を受けた。
一方、日本からは「正五位」に叙するむねの伝達があった。
相変わらず脚光を浴びているように見えたが、英世のアフリカ行きの日は確実に迫っていた。もっともこのころ、英世はまだ自分がアフリカに行くことになるとは思っていなかった。
英世がアフリカに発ったのは昭和二年十月だが、その半年前の三月に、小林栄に宛てた手紙は次のようになっている。
城母の小伝御手写のもの二通、まことにかたじけなく拝掌いたしました。いまさらながら涙が流れる次第です。(中略)小生なお幾多の欠点はあるも、今日迄多少の仕事を成せたのは、慈母、慈父御両方のお助けによるもので、愚母もそのために小生を導くことができたような次第です。小生いずれ恩父の御一生を書き度いと念じております。恩父のような慈悲深き方はこの世の中に珍しく、小生の家の第三代の御世話までもしていただき、もったいないかぎりです。
願わくばこの世で今一度、御目にかかり度いと念じております。なにとぞ御達者に御いで下さいますよう、神かけて祈っております。(中略)なお生家のこと、御厚意はありがたいながら、情をかけすぎるのは若年の独立心を消失せしむることと信じます故、手足のきく身体の丈夫なる青年者がたより扶助を望む如きはもっての他にて、血縁その他に関せず、補助せぬほうが宜敷いかと存じます。もし姉が食うに困る場合には、小生より月々少々なりとも送るつもりです故、なにとぞ御知らせ下さるよう御願いいたします。
次に小生の最近の研究を申し上げます。一昨年の五月に申し上げたかもしれませんが、小生再びトラコーマの原因の研究をはじめ、昨年五月八日にはメキシコ国のアルパケルケ市に出張し、当地の米国印度人(日本人に似たる人種)中のトラコーマ患者より材料を採取して帰国、詳細に分析し、数ヵ月で諸種の細菌を分離し、その一つがトラコーマ様の眼病をおこす性質のあることを発見しました。その後ますます研究を重ねていますが、多分、本当の病原体であろうと思います。実験動物には主に猿を用い、一匹で八百ドルもかかるありさまで、いかに富裕な研究所といえども、なかなか困難な仕事です。ともかくこの研究が適中すれば、全世界三千万人のトラコーマ患者のためとなることですが、いずれ確定次第また御連絡いたます。
その他では南米ペルー国のオロヤ熱の研究、ますます進行し、ほとんど完成も間近の状態ゆえ、御安心下さい。
小生の健康はきわめて良好にて、朝から晩まで働いても疲労をほとんど覚えません。この地も、三月に入って寒気もいくらか穏やかになり、凌ぎよくみな喜んでおります。故郷の雪はまだ尺余もあるかと思います。冬籠りの窮屈さ御察しいたします。なにとぞ御自愛遊ばされ、風邪をひかぬ様祈りあげます。
なお申しあげたいこともありますが、後便に譲ります。
昭和二年三月一日
慈父様、膝下
小生の家の第三代というのは、姉の息子が跡を引き継いだことをいっている。ここで、あまり補助しないほうがいい、といっているのは興味深いが、英世にとって、シカのいない実家は、もはや無縁の存在でしかなかったとみえる。姉が生活に困るなら、その分だけは送る、というのも、一時期苦労をともにした姉への共感だっただった。
トラコーマに関してはこの手紙の直後、病原体を発見したが、のちに正確な病原体でないことが、他の学者によって証明された。
なお、この手紙の冒頭には珍しく短歌が添えられている。
積む歳の重みなるにやきのふ今日、忘れざらねと時は経にけり
英世は手紙や手帳に、いくつかの短歌を書き残した。それらは概して常識的というか、わかりやすいものが多い。
この他に、一年前に詠んだのに、次のようなのがある。
(母君の御健康を祈りて)
浮雲の行来暇なき冬の空、遠からざめ立つ春の日も
(母君の病まるるを想ふ)
よしたとひ此世
定型や用語には比較的よく気を配られているが、歌の仕上がり自体は、やや平凡といわざるをえない。
第九章 アフリカ P.233
1
昭和元年はわずか六日を経て、昭和二年に移る。西暦一九二七年、英世は数えの五十二歳に達していた。若かったころの華々しい活躍からみて、いよいよ世界的細菌学者として学界に重きをなし、円熟期に入るべきときだった。だが、英世の身辺は騒然として、落ち着く暇はなかった。
その最大の理由は、後半生を賭けた黄熱、トラコ―マ、オロヤ熱などの研究が、いま一つはっきりしないことだった。とくに黄熱はエクアドルにまで乗り込み、いち早く病原体を発見し、治療用血清まで創りあげ、人類の救世主として大きな反響を呼んだ業績であった。
だがその反響は一部の国にかぎられ、社会的な面での評判だけが先走っていた。人々の熱狂的な支持にかかわらず、学界の一部には依然として野口の発表を疑問視する声があり、その批判は年とともに大きくなってきていた。
すでにペルー遠征のときに立寄ったキングストン1で、英世の論文は厳しい批判を受けたが、「ノグチ疑わし」の声は年とともに高くなってくる。さらにその前年、西アフリカで黄熱が発生し、その病原体が英世のいうような単純なものでないらしいこと、ノグチの血清はまったくといっていいほど無効であることが確かめられた。
この年の二月、同じ黄熱研究にたずさわっていたホワイト博士が、ロックフェラー研究所を訪れて英世に忠告した。
「あなたの名誉のために、西アフリカへ行くべきではないでしょうか」
「もちろん、行くべきときがきたら、わたしはすすんで行くつもりです」
「しかし失礼な質問かもしれませんが、もしアフリカまで行って、万一、あなたの研究が間違っていたとしたら、どうするのですか」
「ご心配して下さるのはありがたいが、わたしもそれなりに覚悟はできています」
ホワイトはそのいい方の厳しさに、かえって不安を覚えた。
しかし、より不安なのは英世自身であった。
もしかして間違ったのではないか……。
その疑問は、ときとして英世自身の脳裏をかすめる。そんな時、きまって思い出されるのは、日本からきた稲田教授と一緒に病原体を顕微鏡で見たときのことである。
英世に会う一年前、稲田教授はワイル氏病の病原体を発見し世界に報告していた。英世は自分の発見した黄熱の病原体を見せながら、「君の見付けたワイル氏病のとは違うだろう」ときいた。稲田は黙って答えず、さらに「ちがうだろう」と何度も念をおす英世におしきられたようにうなずいた。だがそのときの稲田教授の顔にはあきらかに困惑があった。
稲田は納得していなかったのではないか……。
いま細菌学者のあいだで囁かれている疑問は、「ノグチは黄熱とワイル氏病の病原体を混同したのではないか」ということであった。その批判に、英世は敢然と立ち向かった。
「ワイル氏病と黄熱病は、臨床像も病原体もきわめて似ている。実際、種も属も同じだ。だがその先はたしかに違う」
自ら試験管迄洗ってやった仕事を間違うわけがない。もし間違っていたら、これまで生涯の大半を費してやってきたスピロヘ-ターと血清反応の見方で根本的な誤りをおかしたことになる。
そんなことがありうるわけがない。だが次の瞬間、あるいは……とも思う。
どんな偉大な学者でも間違うことはある。人間である以上、絶対に間違いはない、といいきることはできない。
一部の学者は、ノグチの仕事の誤りを指摘したうえで、「しかし、それはドクター・ノグチの責任ではないし、黄熱の患者から直接血を採取したわけではない。彼はただ現地の医者が黄熱の患者の血だというのを受け取って調べただけである。その第一段階で間違っていれば、ノグチの仕事も間違うことになる」ともいった。
これは批判者のなかでも比較的英世に好意的な意見であった。実際、英世はすべて黄熱が発生したという連絡を受けてから現地にのりこんでいった。発生地はいずれも熱帯の未開の地で、連絡が入るまでに時間がかかり、それから準備をして船で出かけるのだから、ずいぶん間があくことになる。英世が現地に着いたころには大抵、流行は下火になり、新鮮な材料が手に入るのが難しくなる。この悪条件下で、しかも現地の未熟な医師の診断では、黄熱とワイル氏病を間違うことは当然考えられる。
だが、といって英世の責任が解消されるわけではない。
試料の受けとりにどのような問題があったにせよ、「これが病原体だ」と発表し、断言したのは英世自身であった。しかも、その発表には当初から「ワイル氏病ではないか」という¥疑問が出されていた。さらに黄熱の病原体は素焼きを透す超微細な、いわゆる濾過性病原体ではないか、という意見もあった。それらを無視して英世は独走した。
「ベテランの俺が見付けたのだから間違いない」という自信過剰がマイナスに出たのかもしれない。一部の学者が専門的な反論の枠をこえて反撥したのも、その強引すぎた態度にあったともいえる。
アフリカでの黄熱病原発生とともに、再びブラジルで英世への批判が再燃した。この地は以前から英世の研究に取り組むすさまじさに鳴りを潜めていただけで、学問的に納得したわけではなかった。英世はこの地で、エクアドルやメキシコで発見したと同じ病原体を見出したが、その後、現地の学者のいずれも確認できないでいた。英世はそれをテクニックのまずさだと一蹴したが、はたしてそれだけなのか。さらに、そのあとに発生した黄熱には、英世の血清は効果がないことがたしかめられ、新たにニューヨークからのり込んだ学者も、やはりドクター・ノグチの発見した病原体は見出せなかったと報告してきた。
世界各地からくる情報はいずれも英世に不利だった。そのなかで英世はさまざまな思いを巡らす。
もしかすると臨床的に黄熱病と見えるなかに、二つの病気が含まれているのではないか。一つは自分が発見した病原体が原因になっている黄熱病、もう一つはその病原体が関係しないタイプの黄熱病。そして第一のはエクアドルやメキシコの黄熱であり、第二のはアフリカやブラジルのそれではないか。とくにブラジルで黄熱が流行したリオはアフリカと交流がある。そのために同じタイプの黄熱病が発生したのではないか。
だがこの推定もよく考えてみると、いくつかの疑問点があった。たとえば南米型、アフリカ型というが、臨床の病像はあまりにもよく似ているしそれにアフリカと交流があるといえば、エクアドルのグアヤキルやパナマもないわけではない。リオまできていたら、これらの港町にも拡がっていいはずである。
憂鬱な報せはさらに続く。
アフリカで黄熱患者の血清を猿に注射して罹病させることに成功したという連絡が入ってきた。
これは学問的に重大な意味を含んでいた。いままで英世が調べてきた黄熱病は猿にうつすことができなかった。エクアドル、メキシコはもちろん、ブラジル、ペルーでもうつせず、人類だけが特有に罹患するものだと思われていたが、アフリカと南米では黄熱病がまったく違うものであることを示している。そしてこれまでの南米の黄熱病にワイル氏病が混じっていたとすると、過去、黄熱と考えられていたものには次の三つがあることになる。
すなわち、アフリカ黄熱病と南米黄熱病、そしてワイル氏病。
これではアフリカへ行かぬかぎり、世界の黄熱病を征服したことにはならない。それにアフリカの黄熱をおさえてこそ、ワイル氏病と間違ったのではないか、という疑問に答えることができる。
だがはたしてうまくいくだろうか……。
もしアフリカへ行って、アフリカと南米と二つの黄熱病が同じものであったらどうするのか。両者が同じなら、いままでの研究は黄熱を見逃し、ワイル氏病の病原体だけを追っていたことになる。いままでの仕事のすべてが根底からくつがえる。
不安のなかで、春から初夏に移る。
ロックフェラーから、アフリカへ行ったドクター・ストークがさらに猿をつかって黄熱の研究をはじめたという報せがとどく、彼等は西海岸の港町のラゴスで、新鮮な黄熱患者の血清をつかって研究しているという。彼等からノグチの指摘した病原体を見出した、という報せはない。
やっぱり間違いであったのか……。
不安と焦燥のうちに、再びニューヨークに夏が訪れてくる。
七月、英世は例によってシャンデーケンの山荘にこもった。前からシカゴ大学のジョルダン博士に依頼されて、スピロヘ-ターの項目を分担執筆することになっていたが、延び延びになっていた。正直なところ、黄熱の問題が片付かないかぎり、スピロヘ-ターについて書く気になれないが、もうこれ以上延ばすことはできない。
覚悟をして書き出したがや筆はすすまない、少し仕事をしてはすぐ止め、魚を釣ったり絵を描くが気はのらない。魚が糸を引いているのも忘れていたり、突然、描きかけていた絵を塗りつぶしたりする、そうかというと煙草を銜えたまま何分も火をつけず呆んやりしている。
休んでいるようにみえて、頭のなかは行き詰まった仕事のことだけ考えている。
「もしかして、ノグチは笑い者になるかもしれない」そんなことをいったかと思うと、「いまに、きっとわかるだろう」とつぶやく。また「ノグチの名は必ず後世に残る」といってうなずく。
「どうかしたのですか」メリーがきくと、「なんでもない、心配しなくていい」という。そして「人間は五十までにいい仕事をすればいいのだ」とつぶやき、「俺は六十になったら死んでもいい」といったりする。
「このごろ、先生は急にお老けになりましたね」
山荘の近くの老婆がメリーにそんなことをいう。たしかに毎日会っているメリーにも、英世の白髪が増えたのがわかる。
この夏、英世が描いた油絵に、一方に月が、一方に星があり、あいだに黒い山が浮き出ている暗い色調の絵がある。夜眠れぬままに描いたものだが、当時の英世の苦悩が滲み出ているともいえる。
九月の初め、シャン―デケンからニューヨークの戻ると、英世はメリーにアフリカ行きを宣言した。
「アフリカですって」
メリーは大声をあげた。
「そんなところに、なんのために行くの?」
「もちろん、黄熱のためさ」
「あなたは気でも狂ったの、アフリカってどんなところだか知っているの?」
「もちろん行ったことはないが……」
「冗談じゃないわ、いくら仕事だって、そんなところへ行ったら終りよ、今度こそ死んじまうわよ」
「でもラゴスやアクラは英領だし、白人もいる。研究所だってできているんだ」
「イギリス領の病気ならイギリス人が行って治せばいいでしょう。なにもアメリカにいるあなたが、そんなところまで出かけて行く必要はないわ」
「メディ、大丈夫さ、とにかく俺は行かねばならないんだ」
妻にというより、英世は自分にいいきかすようにいった。
「知らないわ、あなたが行きたいなら勝手に行くといいわ。そして地の果てで死ぬといいわ」
まさしくメリーにとって、当時のアフリカは大西洋を渡り、さらにヨーロッパから南下して、何日で着くのか見当もつかない地の果てであった。アフリカときいてまっ先に思い出すのは黒い奴隷達である。いまでこそ奴隷制度はなくなったが貧しく不潔な黒人達は街にあふれている。その人間達の故郷であり、文明の光りなど届かぬところへ夫が行くというのである。
「わたしは反対よ」
メリーは肩をそびやかすようにはっきりといった。
「これほど反対する妻を英世が見たのは初めてだった。いままでペルーやブラジルに行ったときは、そんな遠いところ……」というだけで、それ以上の反対はしなかった。仕事なら仕方がないという態度だったのが、絶対反対を唱える。
アフリカは血の果てという感覚もあるし、夫が満五十一歳になって、赤道直下の土地では無理だという心配もある。だがそれ以上に、メリーはもうそろそろ落ち着きたかった。夫を特に愛しているわけでもないが、といって嫌っているわけでもない。何年も一緒にいればこの程度のもので、世間一般の夫婦並みかと思う。夫は夫で、仕事一筋に自分勝手にやってきた。いまではそれで割り切れたし、納得することもできた。
だがこれからまた一年も放っておかれることを考えると我慢がならない。たしかに一人でいるのは楽だが、そう長くてはやりきれない。それに夫に万一のことがあっては困る。そこから先は多少打算も入るが、まだまだ生きてくれなくては困る。もうそんな危険なことをしないで、ニューヨークかシャンデーケンで暢んびり過ごしたい。これまで一生懸命やってきたのだから、もういいではないかと思う。とにかくアフリカへ行かせたくない。
メリーの反対が予想以上に強かったことで、英世はそれ以来、アフリカ行きについて妻に話すことはなくなった。これ以上、妻を興奮させないほうがいい。だが行く決心は変らない。
妻がなんといおうと、行かねばならないのだ。このままでは自分の地位が危うくなる。アフリカ行きは黄熱に取り組んだ学者の宿命というべきものである。
しかし、メリーにかぎらず周囲はすべて反対した。日本人会では、みなが遠征を中止するように訴えたが、彼等が心配するのはアフリカはあまりに遠く気候的に合わないうえに、英世が五十をこえていることだった。
「もう、かつての若いときとは違いますよ」
代表して日本人会長が忠告する。みな、日本の名誉である野口博士に、万一のことがおきるのを怖れていた。
だが英世は答えなかった。たしかに、心配してくれるのはありがたい。「日本人の名誉である博士」といってくれるのは嬉しい。だが黙ってここにいたのでは、その名誉さえ失われるかもしれない。彼等は、自分が追い込まれている立場の苦しさを知らないのだ。
九月十日、英世はロックフェラー財団のオコンナー博士に会った。博士は財団の役員で、前回のブラジル遠征から、今回のアフリカ行きについても、資金の面倒をみてくれる予定になっている。
そこで最終的な打ち合わせを終えたところで、改めて、オコンナーがきいた。
「本当に行かれるのですね」
「もちろんです」
予算請求書にサインしながら、博士はまだ半信半疑だった。
「あんな暑いところへ行っても大丈夫ですか。少し顔色が悪いし、辛そうに見えますが」
「昨夜、徹夜したからで、別に心配はいりません」
「でも心臓が悪いようですし、きくところによると糖尿病もあるとか」
「心臓のほうはもう落ち着いています。それに糖尿は、日本人は米飯を食べすぎるからなるので体質的なものです。日本人は、馬鹿の三杯飯、というくらい米を食べるのですが、わたしはとてもそんなに食べられません。たまたま、二杯も食べたあとで糖尿の検査をしたとき陽性に出ただけで、アフリカで米を食べなければ治るはずです」
英世はつとめて冗談めかしていった。
だが、軽い糖尿があり、心臓がよくないことはたしかであった。徹夜で仕事をした朝などは息切れがし、呼吸が苦しくなり、僅かの階段を昇るのも口を開け、肩で呼吸をする。英世の心臓病というのは、正確には心肥大に過ぎなかったし、糖尿病は軽くあったが、その原因は単なる食べすぎであった。小柄な身体に似ず、食べるときはよく食べたが、いずれにせよ、たいした病気ではなかった。
それより問題なのは、オーバーワークであった。いかにスタミナがあり、精神力があったとしても、五十をこえて徹夜をし、翌日もほとんど眠らないという状態が続いては顔色が悪かったり、息切れするのは当然である。
だが英世は「年齢のせい」とは思いたくなかった。「病気が邪魔をしている」と思い込もうとする。
英世の友人達もアフリカ行きには反対だった。研究所の親友のカレスキー博士は、英世の立場を理解したうえで、やっぱり行かないほうがいいという。
「ロックフェラーの主任研究員であるあなたが、なにも地の果てのアフリカまで行く必要はありませんよ」
カリスキーにとっても、アフリカはあまりにも遠すぎた。
「それでは、あなたはわたしがこのまま研究所にいて、誰か知らぬ医者が、一か月以上も前にアフリカで採った血を受け取って、それで研究しろというのですか、これまでわたしがもし間違ったとしたら、患者の血を採るのを、現地の医者に任せたせいですよ。いままた、ここに暢んびりいて、同じ誤りを犯させようとするのですか」
「わたしはそんなつもりでいっているのではありません。ただあなたの健康を思っているだけです」
「それはりがたいが、わたしは行かねばならないのです。行って自分で患者に会い、その腕から血を採り、その新鮮な血で研究をしたい。あなたも学者なら、この気持ちはわかるでしょう」
そういわれると、カリスキーも返す言葉はない。たしかに、いまのノグチは学者として瀬戸際に追い込まれている。
「失礼だが、あなたは無茶をやる人だ。自分の体をいたわり、コントロールするという能力が欠けている。そお無謀を熱帯のアフリカでやられては大変だと思っているのです」
「それはよくわかっています。でも、わたしは一日も早く、この黄熱という奴を片付けたいのです。アフリカへ行って、きっぱりとけりをつけて、すっきりした形で帰ってきたいのです。この世に生まれてきたのは、なにかこの世のためになることをするためでしょう。その最大の仕事が目の前にぶら下っているのです。これを完成できたら、わたしは死んでもかまわないと思っています」
「わかった、幸運を祈るよ」
カリスキーはそういうより仕方がない。
だが、それから数日後に、アフリカから悲報が届いた。
先にアフリカへ行っていたスートクスが死んだという報せであった。ストークスは研究所の若いスタッフで半年前から、英世の代理のような形でアフリカへ行っていた。彼は九月の初めに帰る予定だったが、半月ほど出発を延ばした。そのあいだに黄熱にかかったらしい。
「なぜ早く帰らなかったのか……」英世はテーブルを叩いて残念がる。
「やっぱり、アフリカ行きはやめたほうがいいのじゃありませんか」
研究所のスタッフや友人がいうと、英世は苦笑して答える。
「君わたしは何年、黄熱病を研究してきたと思うのかね。わたしは誰よりも病気を知っている。黄熱だってわたしが行けば敬遠するさ」
英世の準備は着実にすすんでいた。すでに十月の二十二日と決定した。まわりの者も、みな知っているが、メリーだけにはいっていない。教えると、なんといいだすか、さすがの英世も妻には弱かった。だがいつまでも隠しておくわけにもいかなかった。
出発の半月前、英世は突然決まったようにして、アフリカへ行くことを告げた。
「二十二日にアフリカへ出発する」
「やっぱり……」
メリーは英世を見たままなにもいわなかった。怒るより、なんとこの人は馬鹿なんだろう、ただ呆れていた。
「ほんのしばらく行っているだけさ、仕事はじきに終るよ」
「…………」
「学者の妻というのはこういうものなんだ。君が笑って、"行ってらっしゃい"といってくれないと、わたしは気持ちよく行けないじゃないか」
「…………」
「頑張って、君が強くなければ困る」
逆に英世が励ますが、メリーはやはり黙っていた。学者の妻はこういうものだ、といっても、それは日本人の感覚で、アメリカ人のメリーには通じなかった。
出発の日が近づいても、友人達の中止を求める声はやまなかった。
「いまなら、まだやめるといっても間にあいますよ。やっぱりやめたほうがいい、いやな予感がするのです」
「君達は、俺が死ぬとでも思っているのか?」
「そうは思いませんが、だがやはり心配なのです」
「たしかに、わたしは死ぬかもしれない。もう帰ってこないかもしれない」
「まさか、悪い冗談は止めて下さい」
反対に友人のほうで慌てる始末である。
出発前にまとめておかなければならない論文があるし、留守中、やっておいてもらわねばならない仕事もある。いままですべて自分一人でやってきただけに、あとを託すのが大変でる。
再び徹夜の日が続く。
この隙を縫って、英世はコネンコフという彫刻家の彫像をつくらせた。それは英世から望んだことでなく、研究所のリーという同僚が、アフリカへ行く前に是非つくっていくべきといい出したからだった。
「わたしは忙しくて、そんな暇はない、それに外国へ行く前に彫像をつくるなんて、まるでわたしが死ぬことを予言しているみたいではないか」
英世はのり気でなかったが、リーは熱心にすすめた。
「コネシコフは間もなくイタリアへ帰るし、いい彫刻家ですよ、あなたほど学問をした人は、いずれ彫像が必要になってきます。そのためにもいまつくっておいても悪くはない。自分の絵とか彫像というものは、あまり年齢をとらないうちにつくっておくものです」
リーの弁舌につられて、英世はつくってもいいような気持になってきた。
「じゃあ、短い時間でいいのだね」
「半日もあれば、下書きだけはできますよ」
「写すのは顔だけだね」
「胸元から上というのが多いようですが」
「それで結構」
英世は、怪我をした手や低い背丈まで描かれることを怖れていた。
「少しきりっとした顔にしてくれるように頼んでくれ。わたしのなかには、そういう頑固なところがあるからね」
やがて二十一日のアメリカ最後の夜がきた。
十九、二十日と二晩続けて徹夜をして、坐っているのさえようやくなのに、研究室で仕事をしている。十一時にようやく家へ帰るが、そのまま書斎に入って書類の片付けをしている。午前一時に、メリーにブドウ酒をもってきてもらい、、「今夜はこのまま仕事を続ける」といった。
「駄目よ、明日は出発だし、少しは寝なくては」
「そうかな」
英世は珍しく素直にうなずくと二十分ほどしてベッドに入った。
翌朝は久しぶりに眠って顔はさっぱりしていた。服を着かえ、最後の食事を終えてから、引き出しにしまってあった亡母の墓碑銘の拓本をとり出し、手に持っていたバッグに詰めた。
「どうして、そんなものを持っていくのですか」
メリーはいやな予感がしてきいた。
「別にどういうことはないよ」英世はかすかに笑い、「出発だからね、陽気な顔をしておくれ」とメリーの肩に手をかけた。
やがて呼んであったタクシーが来て、英世は軽く背伸びしてメリ―と接吻を交すと出かけた。
そのままニューヨークの桟橋へ。
準備万端整っていたはずが、そのとき、どういうわけか、メキシコ、ペルー、ブラジルと、遠征の度に肌身離さず持っていたお守り札を研究所へ忘れていった。それは日本へ帰ったとき、母からもらった故郷の中田観音のお札であった。
2
英世の乗った汽船サイジア号は大西洋を横断し、イギリス西岸のリヴァプールへ向かった。
ヨーロッパ、メキシコ、南米と、英世は長い船旅を何度も経験したが、その間、語学を勉強するのが常だった。各国人が乗り合わせている船中は、語学の勉強に、うってつけである。航海の度にドイツ語、スペイン語、フランス語をマスターし、今回はロシヤ語に取り組んだ。
「船中で退屈することなどはない。むしろ言葉の練習でニューヨークにいるときより忙しいのだ」
英世は冗談半分にそんなことをいった。
ニューヨークを発って二日目に、英世は一通の無線電信を受け取った。発信人はロックフェラー財団理事長のヴィンセント博士で、「航路の平静と研究の成功を祈る」という内容のものだった。
過去、黄熱病の研究のために、英世がロックフェラー研究所から持ち出した金は莫大な額にのぼる。だがいまだに、その研究は成功に達していない。英世はヴィンセント博士に合せる顔がないと思い込んでいただけに博士から直接、電文が届いたのは嬉しかった。英世は博士の好意に感謝し、新たに決意を燃やした。
やがて船はリヴァプールに到着した。一旦、下船した英世は、早速各地へ電報を送った。妻のメリー、研究所のスタッフ、日本の友人達へ、さらにドイツのカール・ハーゲンペックへ宛てて、できるだけ大量の猿をアフリカへ送ってくれるよう注文した。
一週間の休息のあと、いよいよアフリカへ向かう。今度の船はイギリスのアッパム号であった。
リヴァプール出発前、英世はまだ西アフリカのどこで研究するか、決めていなかった。
黄熱が発生したのは、黄金海岸からナイジェリアにかけての一帯である。ナイジェリアのラゴスには、すでにロックフェラーの研究所があり、スタッフの一部が行っていた。英世がここで仕事をするなら問題はなかったが、例によって、英世は彼等と一緒にやることに気がすすまなかった。彼等のなかには、英世の仕事を疑問視している者がいたし、一人でやるほうが気が楽だった。いままで共同研究でうまくいったのものは一つもない。
迷っているところに、アフリカで最近黄熱病患者が発生したという情報が入ってきた。英世はそれを理由に、ラゴスを避けてアクラへ行くことにした。
リヴァプールを出港した船はリスボン、カサブランカを経て、アフリカ西岸を南下していて、カナリア群島を過ぎたところから次第に暑くなり、乗客は冬服から夏服に着替えた。
途中、船上でいくつかの無線電信が入った。まずハーゲンベックからは「猿の注文は承知した。すぐ送る」という連絡が入った。アクラからは、ドクター・ノグチを歓迎すること、研究室にはコレブ病院の一部を提供すること、動物室の猿の収容能力は五十頭であること、などが報告されてきた。
だが九日目に、最近、西アフリカでは黄熱の新患者はいない、という情報が入って、英世はたちまち憂鬱になった。新しい患者がいないのでは、はるばるアフリカまできた甲斐がない。
広い西アフリカだから探せば、一例ぐらいは見付けることはできるだろう。万一見付けからなくても、ラゴスの研究所に行けば、患者の血清は保存してあるに違いない。そう自分にいいきかせながらダカール駐在の医務総監へ、もし黄熱の患者が発生したら患者血清はすぐ送ってもらえるふうに依頼する。
そんなことをしているうちに船はセコンディ―に着いた。ラゴスのロックフェラー財団出張所に勤務している二名の医師が出迎え、彼等はそのまま英世に従いてアクラへ行くことになっていた。彼等から、他にマハッフィー博士が、ラゴスからアクラへ派遣される予定になっているときかされて、英世は喜んだ。マハッフィー博士ならニューヨークで知っていて気が合うし、仕事も信頼できる。
十二月十八日、船はようやくアクラに着いた。十月二十二日ニューヨークを発ってからからほぼ一か月に及ぶ船旅であった。
当時のアクラは黄金海岸の中心都市で、人工七万とも八万ともいわれたが、黒人の街では正確な数はわからない。西海岸ではラゴスと並ぶ主要な都市であったが、大型汽船が接岸できる岸壁はなく、船は沖合に泊って艀に移り、岸辺に来ると黒人の担ぐ床板にのって上陸した。
植民地はどこでもそうだが、どこにも貧しい黒人があふれていた。港に近い下町のジェームス・タウンには、土と石で囲いをしただけの家が密集し、黒人のほとんどは裸足であった。女たちは頭の上に籠をのせ、片手に子供を抱えているが、その子達はみな一様に痩せ、下腹だけがふくらみ、一目で栄養失調とわかる外形をしていた。男達は部族の出身を現すさまざまな刀傷を頬につけ、路傍に坐り所在なげである。
人々が集まるのは水汲み場だが、それも一区画に一か所しかかなく、そこで顔を洗えば食器も洗い洗濯もする。ところどころに鳥や犬の死骸があり、そのまわりには蠅と蛆がたかっている。水が足りないので、人々は雨が降るのを待って外にとび出して体を洗う。それでも、街の黒人は簡単なズボンやシャツを着ていたが、郊外へ出ると、下半身だけ布をまとった現地人がニッパヤンの家に住んでいた。
メキシコやブラジルペルーにも、それぞれに文明から遅れた現地人がいたが、それ以上にこの土地の人々は遅れていた。わずかに街の中心部に白人が住んでいたが、それらの地域は黒人居住区住民とは区別されていた。
英世のために用意された家は、都心部から少し離れたコレプにあった。このあたりの白人の家がみなそうであるように、湿気と毒蛇を防ぐため、床を高くあげ、まわりに白いテラスがある。部屋は三つである。さほど大きくはないが、ここでマハッフィー夫妻と同居することになり、英世は左端の、入口が別についている部屋を借りることにした。
研究所は家から歩いて十分とかからない。そこと隣の黒人専用病院は、イギリス政府が建てたものだが、所長のヤング博士は英世のために、その半ば以上を提供した。英世はその一番奥の五坪ほどの部屋を自分専用の研究室にし、手前の十坪の部屋をバッチェルダーなど助手達の仕事場にした。動物小屋はその研究室と向かい合っていた。
上陸の翌日、英世は早速このあたり一帯の医師を集めていった。
「私はニューヨークから黄熱の研究のために来ました。メキシコ、エクアドル、ブラジル、ペルーとまわって、ここで最後の決着をつけるつもりです。それには是非ともみなさんの協力が欲しいのです。私はベストを尽くします。最善を尽しさえすれば、その結果についてはなにもいうことはないと思うのです」
上陸直後、土地の医師達を集めて決意を述べ、協力を求めるのは、英世の常套的な手段であったが、今度の演説のニュアンスが違っていた。「ベストを尽くせば、結果についてはなにもいうことはない」といういい方no
なかに、今度の研究に対する英世の不安が垣間見えていた。
研究所長のヤングはイギリス人だが、英世に好意的だった。彼は英世より十歳ほど若かったが、ノグチの名声はよく知っていた。
「なにかお手伝いすることがあれば仰言って下さい。私でできることなら、なんでも致します。それに黒人の助手なら何人もいますから」
「ありがとう。でも当分は一人でできる仕事ばかりだから結構です。もしできたら部屋を掃除する者と、動物を世話する者が欲しいと思います」
英世は一人で仕事をしたかったが、それはヤングにもすぐわかった。
「ドクター・ノグチは少し疲れて苛立っておられるようだ」
初めのころの日記にヤングはこう書いているが、事実、晩秋のニューヨークから、赤道に近いアフリカへきて、英世の体調はあまりよくなかった。夜は寝苦しいし、寝汗をかく。気温は三十度前後で、ニューヨークの真夏とさして変らず、それに海岸に近くて風があるので、さほど不快な気候ではない。
それより英世を苛立たせるのは、期待したほど黄熱病の患者がいないことだった。よくきいてみると、アクラの黄熱病はこの夏で峠をこえ、十一月以降、黄熱病の新しい発生はないという。それにリヴァプールで頼んだ動物の到着も遅れている。はるばるアフリカまできて、すぐ仕事に手をつけられない状態が、性急な英世を苛立たせる。
そのくせ、ときどき機嫌のいいふりを見せて、黒人達にまでおどけて見せたりする。
「なにか不自由なものはありませんか?」ヤングがきくと、「なにもない」という。そして「今度、新しい動物が入ったら実験に着手するから手伝って欲しい。わたしはあなたを信頼しています」などと調子のいいことをいう。
だが数日後には、今度は急に不機嫌になり、ヤングの言葉尻をたれてからんでくる。
「あなたは、アメリカお学者として関心があるだけで、完全には信頼していないのでしょう」
先日、英世が遅くまで黄熱病の病原体について、自分の考えていることを喋ったことに対し、素直に賛成しなかったことが原因らしい。ヤングはすぐいいわけをした。
「野口先生、私は先生がお話しになり、どう思われるかときかれたから素直に意見を申上げただけです。私は自分の意見が絶対だと思っていません。もちろん先生に反感があって、申し上げたわけでもありません。私は先生を尊敬していますし、先生のお役に立つことならなんでもしたいと思っているのです」
「悪かった、君の好意はよくわかった」
今度は急に英世はヤングの手を握り、泣き出す。
英世はもともと感情の起伏が激しい躁鬱症的傾向が強かったが、アフリカへ来て、それがさらに強まったようである。年齢をとって疲れやすくなったうえに、仕事の不調がくわわり、さらに遠い未開の国へきた苛立ちが、いっそう精神を不安にさせていた。これではいけないと思いながら改められない。英世自身も、ときにそんな自分をもてあます。
黄熱の新しい発生はないが、といっていつまでも黙って待っているだけにはいかない。やむなく英世はラゴスの研究所から患者の血清をとり寄せて仕事をはじめることにした。ラゴスにいる学者達と一緒に仕事をするのを拒んだだけに、彼等から血清をもらうのは、気がすすまなかったがいまは仕方がなかった。
ラゴスから血清をえて仕事を始めると、英世は突然もっと大きい家に移りたい、といい出した。
「なんとか探してみましょう」ヤングは答えて家探しをはじめた。
いままでの家でとくに不都合はないはずだったが、英世は自分のロックフェラー研究所での地位からして、いまの家では貧弱すぎると考えた。そのきっかけは、現地人が殺して毒蛇を見に出かけたとき、たまたま見た白人の医師の家が、大きく豪華だったことが原因であった。名もない白人の医師より自分が小さい家に住むのはおかしい。それにいまの家はマハッフィー博士と同居である。入口は違うといってもやはり気兼ねする。もっと大きい家を要求するのは当然である。
英世はもともと住居などに頓着する性質ではなかったが、反面地位や外見には必要以上にこだわった。
「世界一の学者である俺が、こんな家に住むのはおかしい……」
成りあがり者によくある力の誇示だが、実際、貧農の息子からここまできたのだから、そういう不満が出るのも無理もなかった。しかも英世はそう訴え、要求しながら、たえず白人社会における自分の地位を測っていた。要求してどれくらいの我儘が通るか、それで自分の評価を探ろうとする。それは白人社会で抜き出ようとした男の自分に対する英世の目の判定法であり、仕事をすすめていくうえでの原動力でもあった。
ヤングはすぐ英世の希望どおりの家を見付けてきた。いままで住んでところより少し遠くなるが、やはり床が高く、白塗りの平屋で部屋が五つもある。英世は早速その家へ移り、イギリスの警官に交渉して金網を張らせた。さらに英国皇太子がこの地方を旅したとき奉仕した現地人の料理人を雇い、他に二人の召使と運転手を置いた。それで世界のトップクラスの学者の地位と力を誇る。事実、大邸宅に移って、あたりの白人達の英世を見る目が変ったこともたしかであった。
現地の黒人達は日本人を見るのは初めてだった。
「旦那は黒人なのか」召使の一人が不思議そうにきく。
「いや、黒人ではない」
「では白人か」
「白人でもない」
「じゃあなんだろう」
「日本人だ」
そういっても誰もわからない。英世は昼食や夜食のあとの休息時に召使や研究所の助手などを集めて日本の話をした。東洋の端にある豊かで美しい国で国民の背丈はあまり大きくはないが、みな頭がよくて礼儀正しい。昔はサムライというのがいて強かったが、いまも強くて、つい少し前にはロシヤを破ったのだ。こんなとき英世は最高のナショナリストになる。日本へは誰も行ったことがないのだから誇張が入るが、黒人達は、なにも知らず見果てぬジャパンという国に敬意を抱く。
「君達はもっと迅速に、正確に仕事をするようにしなければいかん。日本人はみな早く確実だ。朝だって夜だって、いつも働き、勉強している」
黒人達は英世の毎日を見ているから素直に納得するが、自分達の暢気さを改めようとはしない。
「まったく、この国の土人達ときたら、太陽と椰子の実さえあれば生きていけるという考えのようです」
メリーに苦情を訴えたように、黒人の仕事ののろさには腹が立った。皇太子に奉仕した料理人といっても、要領は悪いし調味もよく間違え、教えてもすぐ忘れる。
「やはり、マハッフィー夫妻と一緒に住んで食事をしたほうがよかった」
改めて英世はマハッフィー博士夫妻と一緒のときの快適さに気がつく始末だった。
十二月になったが相変らず三十度前後の暑さが続いた。熱帯だから四季はなく、雨季と乾季だけである。十二月は乾季で、北のサハラ砂漠から巻き上げられた砂塵が風にのってくる。現地の人達はタマフ―ンと呼び、おかげで上空はいつも薄曇りで、海の色も冴えない。このころは花の数も一年で最も少ないが、それでも火焔樹やブーゲンビリアが色どりを添えている。ときどき現地人が頭の籠にオレンジやパインナップルをのせて売りにくるが、それも黙って行き過ぎるか、樹蔭に休んで客を待っているだけである。
十二月の初め、英世はダカールへ血清を採りに行く白人の技術者のところへ行った。そこで採決の方法を説明すると、男は「あなたに教えてもらわなくても、その程度のことは知っている」と答えた。
「君が知っていても、私には私の方法がある。その方法でやってきてもらいたいのだ」
「これまで私は何回もやってすべて成功しています。私は六頭の猿を持っていって植えつけてくるつもりですから御心配なく」
このところ英世は必要以上に神経質になっていた。それは仕事に対する苛立ちと不安から増幅されたものだが、少しでも自分に反抗的であったり、礼儀を失する者がいると厳しくやりとめた。
「若造のくせに余計なことはいうな。君は私に命令されたやり方でダカールへ行って採ってくればいいのだ」
「私はたしかに若造で、あなたほど有名でないかもしれません。だがあなたのスピロヘ-ターの研究はやがて失敗に終るはずですよ」
瞬間、英世は男を見据え、「君には頼まん」と叫んで部屋を出ていった。
白人とはいえ、たかが病院の技師にすぎない、そんな男に生意気な口をきかれたことが我慢ならなかったが、同時に、そんな男にまで、ノグチの研究は失敗するかもしれないと教えた者がいることがさらに不快である。
英世に失礼なことをいった白人が、ラゴスの研究所で入れ智恵されたことは間違いなかった。英世のスピロヘ-ターの研究が行き詰まることを予測できるのは西アフリカでは彼等しかいない。
英世は黄熱とは別の悪意がある目が、自分に向けられているのを知った。しかもその敵は同じロックフェラー研究所出身の仲間である。
英世は改めて孤独を感じた。この広いアフリカに日本人は自分一人で、他は白人と黒人だけである。いまの口惜しさや苦しみを訴える相手は誰もいない。
夜は暑いが結構風はある。ここから南十字星は高度二十度くらいの低い位置に見える。英世は家に戻って、フレキスナーやメリーに手紙を書き、電文を送る。
「仕事は順調です。間もなく本格的な研究に入ります」「この地では、私の研究がすすむのを見て、妬んでいる人がいるようです。でも、そんな連中には負けません」「この遠征で、私の研究は完成し、もう二度とニューヨークを離れることはないでしょう」
淋しいときにかぎって、英世は威勢のいい内容を書く。
再び英世の猛勉が始まった。ラゴスの奴等を叩きのめすには、ひたすら努力するしかない。いまに病原体を発見して奴等の鼻をあかしてやる。ヤングはもとより黒人達も驚いた。
「ドクター・ノグチはいつ起きて、いつ眠るのか」
アメリカできかれたと同じ質問が、ここでもくり返される。
当時、英世の下で働いていた黒人助手のウイリアム氏が、いまもアクラに住んでいる。年齢はそのころ二十五、六だったというから七十半ばにもなろうか。この人のドクター・ノグチへの思い出は、「偉い人」の一言につきる。
「よく勉強をし、仕事をしていました。あんなに働く人を、私は生涯で一人も見たことがありません。もちろん他の白人の医師達など問題になりませんでした」
そこはコレブの旧黒人病院、いまのガーナ大学医学部の一角で、研究室の入口の壁に銅板がはめこまれ、そこに「野口英世博士、日本の偉大な細菌学者であり、ロックフェラーの主任研究員である野口英世博士が、ここで黄熱病の研究をし、人類の幸福のために尽した」と記されている。石造りだけあって、建物は五十年余を経ても微動だにしない。
英世が自室に使っていた部屋は、いまは病院の臨床検査室になり、さまざまな器具やタイプが置かれている。左右に窓があり天井にへりコプターの翼のような扇風機が廻っている。それは英世がいた当時のままだし、壁の蚊除けの金網も、同じように張り巡らされていたらしい。
「私達は夕方、実験のあと片づけをして帰りました。でも朝きてみると、研究室は夕方以上につかい捨てた試験管やシャーレで溢れていました。先生は私達が帰ったあと、また部屋に来られて研究していたのです。何時までしたのかわかりません。たまに朝来てみると、部屋の隅で、机に肘をついて眠っている先生をよく見かけました。
五十歳をこえて、熱帯の国で頑張った姿が偲ばれる。ウイリアム氏はさらに続ける。
「白人の医師は威張り、私達をよく叱りましたが、ドクター・ノグチはそんなことをはとんどなく優しい人でした。ただ仕事が遅いときだけ少し不満をいいました。私達は彼の満足のいくように一生懸命やり、彼はそれに応えるように、よくチップをくれました。あんなに沢山チップを呉れた医師を私は知りません」
英世はいつもポケットにイギリス硬貨を持っていて、黒人達に与えた。ときには無造作に一ポンド紙幣を渡すこともあった。誰よりも勉強し、誰よりもチップを呉れたとしたら、下に働く者が従いていくのは当然である。
英世はもともと現地人や自分の下で働く者には好意的だった。威張ったり叱ることはあまりなかった。強く反撥し、闘ったのはすべて白人に対してであった。それは無能な現地人への諦めもあったが、同時に、下層階級出身としての思いやりでもあった。「強きをくじき
弱きを助ける」そうした思想が、英世の頭にこびりついていた。
だがそれとチップを多く与えたのは必ずしも同じ理由とはいえない。
ウイリアム氏をはじめ、下で働いていた現地人達は、研究所の正規の職員であった。研究所の長である英世が命令し、仕事をさせる度にチップをやる必要はなかった。事実、アメリカ人やイギリス人の医師達は、仕事の上でチップをやることはなかった。
西欧人は必要以外にチップをやらない。やるにしても必要最小限にとどめる。とくに黒人や現地人に与えることは滅多にない。むしろ彼等が尽すのが当然といった態度で毅然としている。これに較べて、日本人はチップをやり過ぎるのかもしれない。そして英世はケタ外れて彼等にチップを与えた。これは英世の生来の金づかいの荒さもあろうがはたしてそれだけであろうか。もしかして小柄な東洋人として馬鹿にされたくない、負けたくない、そんな意識が、必要以上にチップをやらせたのではないか。いわば成りあがり者としてのコンプレックスが、その底に潜んでいたといえなくもない。
しかし、たとえそうだとしても、ウイリアム氏の思い出は、かぎりなくノグチに対して優しく温かい。それはウイリアム氏だけでなく、ガーナの医療関係者、知識人らすべてに及ぶ。
同じ日、私達が英世の死んだ国立病院を訪れたおり、副院長のE・ドッグパーツ氏が、外来の患者診察を中止して、わざわざ院内を案内してくれた。彼は各病棟に行く度に、そこの看護婦や患者達に、「この人達は日本からドクター・ノグチの取材にきた人達だ」と説明して歩いた。古い看護婦や事務員達は「ノグチ」の名をきくと、にっこり笑い、私達に握手を求めてきた。若い看護婦で、ノグチの名を知らない者がいると、副院長は「駄目だな、それではお前は看護婦の資格がない」といって笑わせた。
学問的な業績はともかく、死後五十年余を経て、「ノグチ」の名は燦然と西アフリカの地に語り継がれている。
3
季節は十二月に入ったがアフリカの気候は変らない。毎日三十度近い暑さが続き、朝夕だけわずかに涼しくなる。耳をすますと単調な波の音だけが、幾世紀ものあいだ眠り続けてきたアフリカを象徴するように響いてくる。
英世」は東北の会津に育ったせいもあって暑さは苦手であった。とくに病気をしてからはこらえ性がなくなった。ニューヨークでは夏のあいだはほとんどシャンデーケンの山荘で過してきたが、アフリカでは避暑に逃げ出す場所もない。北の高原のほうには多少涼しいところもあるときいたが、アクラより未開のところではとても行く気になれない。
だが暑さより英世を悩ませたのは、この地の人々の能率の悪さであった。
着いて一か月近くになるが、まだ本格的な実験ができない。船で必要な器具は運ばれてきたが、陸揚げされ研究所に運ばれてくるまでかなりかかる。ときには途中で失くなることもある。器具が着いていざ仕事をはじめようとすると電源がなかったりコンセントが不良であったりする。すぐ直すように指示しても、修理工は一向に現われず、口やかましくいってようやく直ったと思うと、アンペアを間違っていたりする。
黒人達のスローモーな仕事ぶりに、性急な英世は苛立つばかりである。
「この地で、私を苦しめるのは待つ長さです」やり場のない怒りを、英世は手紙でメリーとロックフェラー研究所秘書のチルデン嬢にぶちまける。
それに研究に最も大切な黄熱病患者の血清を、ラゴスの研究所からもらわねばならないことが、最も不快である。折角アフリカまで来た以上は自分で患者を診て、その患者から血をとり、そこから病原体を探り出したい。ラゴスからの血清では、いつのものかわからないし、果して本当に黄熱患者のものか、疑い出したらきりがない。事実、ラゴスから送られてきた血清を、さし当り手許にあった十頭に注射して経過を見るが、なんの変化もおこらない。
黄熱病の病原体は、チフス菌や肺炎菌のように、試験管内の培養基では増殖しないし、じきに死滅してしまう。保存しておくには、しかるべき動物に注射して生体内で増やしていくより方法がない。いいかえると動物自体が培養基の替りになる。
ラゴスから取り寄せたのはこの保管が悪かったのか、輸送に問題があったのか、いずれにせよ、実験用の猿に黄熱病が発生しないことには、本格的な研究をはじめられない。
焦っているうちに、東部の仏領トーゴランドで黄熱病が発生したという連絡が入った。そこは距離にするとさほど遠くはないが、道が悪く、途中自動車が通れない場所もあるらしい。馬で片道一日の行程である。英世はただちに人をやって、患者の血液をとりに行かせた。
トーゴに続いて今度はセネガルのダカールで発生したという連絡を受けた。これも仏領である。英世はただちにフランス総監の了解をとり、そこへも採りにやらせる。
患者がいると思ったアクラでは発生せず、離れたところで発生するのは皮肉だが、ともかくそれらの患者の血清を集めて実験はすすめられた。
黄熱病に感染した猿は、急に元気がなくなり、目が充血し、黒い吐物を吐き出し、やがて死ぬ。熱はあるものもないものもある。黒い吐物は胃や腸壁の血管が破れて出た血の塊りである。発病するとただちに血をとり、他の猿に植える。死亡するとすぐ解剖して肝臓、腎臓をはじめ、各臓器の変化を調べ、その標本をつくる。一頭の屍体から百枚をこす病理標本ができあがり、それを一枚一枚につき、特別の変化や病原体らしい異常なものがないかどうか調べていく、さらに新しい血液を注射された猿にカルテをつくり、毎日、体温や体重の変化などが記載される。同じ血液を注入されたものでも、感染する猿もいるし、感染しないものもおる。また感染したなかにも、比較的早く発病するものと遅いものとがある。猿の強さにもよるのだろうが、感受性の個体差もあるのかもしれない。
この種の実験で望ましいことは、血液を注入された猿が、同じ形で発病し、同じ病状を現わすことである。もしあまり違うとすると個体差をこえて、病原体のなかに多少性格の違うものがあるのかもしれないということになる。いいかえると、同じ黄熱病でも、出血傾向中心に襲ってくるものと、肝臓を中心に冒すもの、腎臓を先に冒すタイプといった具合である。猿の現わす病状の違いに応じて、さらに病原体の種類が分けられていく。その各々をまた別の猿に注入していき、さらにその各々について解剖し、標本をつくり、顕微鏡で調べていく。
実験の規模はどんどん拡がり、それに応じて猿がますます必要になってくる。
英世がアクラに着いて間もなく、三十頭の猿がドイツから送られてきたがそのうちの五頭は、船の長旅のせいか、間もなく死亡した。どういうわけか、ナンヨウアカザルは、アフリカの山野には沢山いるのに、一旦、ヨーロッパに送られ、そこからまた実験用として送り返されてくる。動物商がドイツ人やイギリス人のせいかもしれないが、おかげで日数がかかり値段も高くなる。十一月いっぱいはこの猿三十頭にチンパンジー一頭、他に血をとるための猿が一頭いたがこれではすぐ足りなくなった。
英世はさらにラゴスの研究所をとおして、ハーゲンペックやローマンなどの動物商に百頭の猿を発注した。彼等からはただちに送ると返電がきたが待っても一向にこない。苛立つうちにようやく四十頭がきて、続いて二十頭がくる。だがそのあとはばったりとこなくなる。
どういうわけなのか、問い合わせの電報を打つと、もう当分、猿はないという。一旦は送るといって、途中からないというのは約束違反である。直ちに電報を打つと、猿は注文通り送っているという返事である。不思議に思って調べてみると、動物はラゴスの研究所へ行く分と合わせて送ってよこすため、アクラへ行く分が途中でラゴスにとられていることがわかった。注文もラゴスで一括して依頼した場合には、アクラの分はけずられている。
「ラゴスの連中が、私の仕事の邪魔をしているのです」
英世はマハッフィー博士に不満をぶちまける。
「彼等は、あとから来た私に、追い抜かれるのをおそれているのだ」
腹が立つと、英世はすぐフレキスナーやニューヨークの友人に電文を打つ。もっともマハッフィ―にいうようにあからさまにいえないので、「血液でも猿でも、ラゴスに頼んだのではさっぱり埒があきません」という表現になる。
ラゴスではドクター・ビュイックやハドソンなど、ロックフェラー研究所のメンバーが来て仕事をやっていた。アフリカでは彼等のほうが先輩であり、アフリカ黄熱病に関しては自信を持っている。英世が黄熱病を研究するのなら当然、彼等のところへ挨拶に行くべきであった。それを拒否して一人アクラに居坐り、イギリスの研究所で仕事をして、しかも患者血清がない、猿が足りないといっては、分けてよこせという。
ロックフェラーでの地位からいうと、英世はたしかに上であり、所長のフレキスナーの信任も厚い。いわばロックフェラーのスターであり、実力者でもあったが、ここはアフリカである。ビュイックらはたとえ相手がノグチでも、ことアフリカ黄熱病に関しては英世に負けないという自負があった。ノグチは南米の黄熱病でミスを犯し、いままたアフリカにきてミスを犯そうとしている。しかも相手は小柄な東洋人だという蔑視もあった。もちろんそんなことはあからさまにいわないが、あとからアフリカにきて、大きい顔をして動物を買いつけていく身勝手なノグチに、厭がらせをしたくなるのも無理がないともいえた。
英世はラゴスを通さず、個人的に動物商と交渉することにした。とくにラゴスとのつながりの深いハーゲンペックは捨てて、ローマンだけに頼むことにして、ようやく順調に入るようになった。
アクラの動物小屋は、狭い中庭をはさんで研究所と並んで建っていた。研究室の窓から覗くと、動物小屋の内側まで見えるが、ここは五十頭の猿を収容すると一ぱいだった。
英世はただに小屋を増築したかったが、ここはイギリスの研究所である。英世が遠慮がちに所長のヤングにいうと、彼は即座に承諾した。このあたり、ヤングは英世にきわめて協力的だった。
この動物小屋は現在も研究室とともに残っている。木造の平屋で緑のペンキははげ落ち、物置小屋になっているが、全長七、八十メートルはある細長い建物である。最盛期、ここには約四百頭の猿と、数十頭のマントルヒヒ、チンパンジーなどがいた。これを世話する現地人だけで四十人、一日三トンの飼料を要した。
「世界一の動物小屋だ」
英世は仕事の合い間に、何度も動物小屋を覗いては自慢そうにつぶやいた。
かくして実験らしい実験ができるようになったのは、着いて一か月も経った十二月の半ばからである。
それから十日も経ずしてクリスマスが訪れた。その前夜、英世はヤング所長、マハッフィー博士、二人の白人医師らとともにクリスマスイブの夕食をともにした。
英世は上機嫌でシャンペンを傾け、アメリカの友人達へ、いくつものお祝いの電報を打った。相変らず、この地の仕事のやりにくさや、気候の悪さなどを遠慮なく批判したあと十時近くに自室に退った。
翌日は土曜日だったが、英世は研究室に現われなかった。これまで英世は日曜といっても仕事を休んだことはなかった。休日でも必ず一度は研究室に姿を見せる。アメリカにきて休んだのはこの日が初めてだった。
その日はスタッフもみな休み、研究室にきたのは、動物係のウイリアムだけだった。人気のない英世の研究室を見て、さすがにドクター・ノグチもクリスマスだけは休むのだと思った。
だが翌日曜日も英世はこなかった。他のスタッフならともかく、ノグチが二日続けて休むのはおかしかった。夕方、二人の研究所員が彼の家へ行ってみると、英世はベッドのなかで寝ていた。
「どうしたのですか」尋ねる所員に、英世は少しお腹をこわしただけだと答えた。
「いけません、すぐ入院したほうがいいですよ」
病院嫌いの英世が珍しく素直にコレプにある白人専用のヨーロッパ病院2に入院した。
初め熱はほとんどなく軽い嘔吐だけだった。単なる胃腸障害かと思ったが、黄熱病の疑いがないわけでもなかった。英世はそれを気にしたが、主治医のオプライエンに自信ありきにいった。
「大丈夫、私はニューヨークを出てくるとき、ワクチンを注射しているから黄熱にはかかりません」
このワクチンは英世自身が黄熱病患者の血清から創ったもので、メキシコやエクアドルで効果があったものである。いまもし、アフリカの黄熱病も南米型と同じだとすると、効き目は現れてくるはずだし、たとえ違うにしても、同じ系統の病気であるなら、かなりの効果は期待できるはずである。
だが、そういいながらも、英世は不安であった。もし二つの病気が違うものなら、ワクチンの効果はない。それは死の不安とともに、いままでの黄熱病の研究が、アフリカでは無駄なことを証明することになる。
「こんなアフリカまできて、黄熱病にかかるなんて、私は余程馬鹿な男だ」
英世はしきりに、病室専属のイギリス人看護婦に愚痴をこぼす。
ニューヨークから一か月余もかけてアフリカまできて、まだ充分の成果を上げないうちに病気に倒れてしまった。その腹立たしさと口惜しさが英世の気持を暗くする。一日中、ほとんど口もきかず、ただベッドのなかにうずくまっている。看護婦が食事を運んでいっても見向きもしない。
「少しでも、食べないといけませんよ」
看護婦がいうと、強制されて食べたところで意味がない、という。
「強制であれ、なんであれ、お腹のなかにはいってしまえば栄養となるのです」
「それでは、あなたが食べさせてくれますか」
「もちろん、博士がお望みならそのようにいたします」
看護婦はパンを千切り、英世の口のなかに一つずつ入れてやる。パンをいくつも刻み、大きい切片から大将、大佐、兵長というように軍人の位をつけておく。「さあ大佐まで平らげました。あとは将軍クラスだけですよ」看護婦はそんなことをいいながら、英世の口におし込んでやる。機嫌をなおした英世は、「よし、将軍などはすぐやっつけてしまう」と燥ぐ。
もともと英世には、子供じみたところがあり、それだけに、母親に叱られ、宥められるようなやり方をされると反撥できない。それはいっときの気紛れともいえるが、その底に、母シカ一人に育てられてきたマザーコンプレックスが潜んでいた。
しかしいつもこんな調子でうまくいくとはかぎらない。いくら呼びかけても返事をせず、「起きているなら、返事をしなければいけません」というと、突然、「こんな中途半端な状況では死んでも死にきれない。早く仕事をしなければならない、いつまでもこんなところで暢んびり休んではいられない」と、起き出そうとする。
「いま起きたら自殺するようなものです。自分の仕事が大切だと思うなら、まず体を大事にしなければなりません」看護婦がいうとさらに不機嫌になって、「あなたは私が弱いと思っているのだろう」とひがむ。そして、「私はドクター・ノグチだ。世界のノグチだ。こんなところで、あなたと暢んびり話している暇はないのだ」と叫ぶ。
だが数分もせず、急に人が変ったように声が弱くなり、「なにか失礼なことをいったろうか」と、自分がいったことを気にしだす。
「別に気になど留めていません」看護婦が軽く受け流しても、英世は「自分は貧しい農家で育ったのでしつけがきちんとできていない。すぐ自分勝手なことをいい他人を傷つける。粗野で身勝手で一方的なのは、生れつきなので、つい他人を傷つけるものです」と謝り、貧しかった子供のときのことを延々と話し出す。
看護婦たちは、病気への不安と仕事の停滞で、英世の気持が波打っているのだと思う。急に気難しくなったり、大人しくなったり、扱いにくい患者だが、根は悪い人ではないと見ていた。
発病して五日目には食欲はないが、うまく宥めてやると一人前を平らげるようになった。
「あなたのおかげで、今日はとてもよく食べられた」そういって笑ったかと思うとすぐ、私は死ぬかもしれない」と、いい出す。
「博士のような無茶をやる人は、そうそう簡単に死ぬものではありません」
「しかし、ここはアフリカだからね」
「アフリカだろうと、助かる人は助かります。第一、博士の病気は博士が考えているほど、重大なものではありませんよ」
看護婦のいうことはある程度当っていた。入院して五日目を過ぎて、医師達は英世の病気は黄熱病ではないと思いはじめていた。
たしかに英世は黄熱病に感染する可能性はあったが、その後に訪れるはずの出血症状はなかったし、臨床検査でも黄熱に特徴的な蛋白尿や血球の減少が少なかった。発病する前の様子を調べると、夜間研究室で空腹になって、空けて数日経ったカニの缶詰を食べたらしい。しかもそれは実験で死んだ猿と一緒の冷蔵庫に入れておいたらしい。几帳面なようで、英世にはこういう無頓着なところがあった。
古いカニ缶でもあたった、単なる下痢ではないか……医師達はそんなふうに考えた。
だが英世はその考えに不満だった。今回のはやはり黄熱病である。ただ、それが典型的な症状を現さなかったのは、ノグチ・ワクチンが効いたからである。
英世がくる前、アフリカで死んだストークスも、初めは英世と似た症状だった。それが途中から例の黒い吐物を吐いて死亡したのは、ワクチンをうっていなかったからである。彼がもし事前にノグチ・ワクチンをうっていれば助かったはずである。
一週間も経つと英世は完全に恢復した。まだ退院の許可はおりていなかったが、こっそり病院を抜け出し、マハッフィ―博士の家にいって食事を馳走になった。
「もう大丈夫なのですか?」心配そうにきく夫人に、英世は「ワクチンをうっているから、死ぬわけはありません」と、自信あり気に答える。そして、「やっぱりドクター・ノグチは馬鹿ではないのかもしれない」といって一人で笑い出す。
このころ英世は道化て自分をよく三人称で呼んだ。それで客観視したつもりだが、主観的であるのに変りはない。
入院してから十日で英世は退院した。
今回のが黄熱病であったか否かは、医師団にもわからなかった。黄熱病の病原体が発見されていないのだから、最終的にそうだと断定する根拠もなかった。だが、もし本当に黄熱病だったとしたら、英世自身の血清を猿に注射しても黄熱病と同じ症状を起すはずである。新鮮な患者の血清がないと嘆いていたが、その新鮮な材料が最も手近にでてきたのである。
実際、英世は自分の血を看護婦にとってもらい、それを猿に注射してみた。だが猿にはとくに異常はおきなかった。してみると、英世の病気はやはり黄熱病ではなかったかもしれない。あるいはそうであったかもしれないが、ワクチンの作用で毒性が消されたか、さもなくばアフリカと南米の黄熱病はまったく違うものかもしれない。
病気は治ったが、黄熱病への疑問はかえって深まってくる。
退院した日から、英世は再び研究室に直行して仕事をはじめた。
「あなたは体を酷使しsぎる。もう少し暢んびりしたらどうでしょう。少し気晴らしに遊んだほうがいい仕事ができるし、あなた自身のためにもなるとおもうのですが」
ヤングが忠告すると、英世は一旦うなずいてから、
「たしかにあなたのいうとおりかもしれないが、残念ながら私は育ちが貧しいので、小さいときから暢んびり遊ぶことに慣れていないのです。せいぜい余暇を楽しむといったらチェスくらいのものです」
「それでは私がその相手になってさしあげましょう」
ヤングはチェスがかなり強かった。英世は初めたて続けに三度負けた。が、あきらめない。それから逆襲に転じて一勝する。その後は一勝一敗のような成績が続く。三時間近くやっても、英世は止めようとはいわない。例によって、最終的に勝ちこすまで続ける。
「もう一局」「もう一局」といって都合十一局やる。それで一つ勝ちこしたところでようやくやめる。
「久しぶりにチェスができて楽しかった」
そういって部屋へ戻って休むかと思うと、これから研究室に出かけるのだという。
「それでは遊ぶどころか、かえって無理をすることになりますよ」
ヤングがいうと、英世は、「チェスに使う脳と研究につかう脳は違うから、これで結構休んだことになるのです」と答える。
家にばかりいてはまずい。たまに戸外でスポーツもしたほうがいいと、今度はヤングはテニスやゴルフに誘うが、英世は一向にやる気はない。小柄だから負けるのを気にしているのかもしれないが、とにかく負けず嫌いな人らしい。
海水浴なら勝ち負けはないだろうと思って、海に誘う。西アフリカでは満月の夜に誘いあって海に行くか習慣になっていた。英世は行かないというが、病院の看護婦達もみな行くからといって強引に誘った。英世は渋々ついてきたが海には入らず、海岸でみなと話をしている。こういうときはいつも輪の中心になり、道化たことをいって笑わせ役になる。そして海水浴が終ると、女性達を自分の車に乗せて、次々と送って廻り、最後に一人となったところで研究室へ戻って、再び仕事を始める。
「これではかえって、あなたの仕事を邪魔したようなものだ」
ヤングが謝ると、英世は笑って、「こういうのが、私の性に合っているのだから気にしないで下さい」という。
ドクター・ノグチは我儘勝手だが、どこか淋しい影がある。人一倍燥いでいても孤独である。おかしな、わからない男だと思いながら、ヤングはそこに惹かれてのいた。
4
やがて一九二八年の年が明けた。昭和三年である。アフリカでのこの正月が、英世の生涯で最後の正月ともなることはもちろん英世自身も知るわけもなかった。
新しい年を迎えて、英世の仕事は順調にすすんでいた。動物商に直接頼むようになってから、猿は順調に入るし、組織の標本も増えていた。いままでは黄熱病の病原体を含むものとして、六つの系統的な菌株を培養していた。これら各々を猿で増殖させ、純粋化していきながら、注入して動物の変化を調べていく。
新しい年がはじまるとともに、ヤングはますます、英世の実験にはまり込んでいた。初めのうち、英世はヤングに実験の詳しいことはなにも話していなかった。ただ各種の血液を得て、動物に植えて結果を見る、その程度のことしか説明していなかったし、ヤングもそれ以上きこうとしなかった。ノグチは一人でやりたがっていて、口出しされるのを好まないようである。ヤングはノグチの好きなようにすればいいのだと思っていた。
だが前年の暮あたりから、英世は実験の立ち入った内容まで、自分から話すようになってきた。
ヤングはもともと病理学者で、さまざまな病気で死んだ動物の標本を調べるのが専門である。黄熱病で死んだ猿の調べるうえで、ヤングの知識は貴重だった。英世はこのヤングの知識を信頼し、いろいろ相談し、意見をききたくなった。だがそれ以上に、初めから親切だったヤングに好意を抱いていたのもたしかだった。
一方ヤングは世界的な高名な細菌学者と一緒に研究できることは、プラスにこそなれマイナスになることはない。
英世は動物が死亡する度に解剖し、各組織の標本をつくると、それをヤングに見てもらった。自分も見るが、それではどの菌株を植え、どのような症状をとった猿か分かるので先入観が入る。ヤングにはその過程を知らせず、標本だけで客観的に判定してもらう。
それまで、ヤングはは黄熱病にかぎらず、この地方全体の風土病を調べていたが、いまは黄熱病の研究にかかりきりになっていた。
私的なことではマハッフィ―が、仕事のうえではヤングが、英世のよき理解者であった。英世はこの二人に、おおいに助けてもらったが、ただ一つ、死んだ動物の解剖だけは彼等にやらせなかった。死体解剖は黄熱病に感染する可能性のある最も危険な作業だった。それに二人を巻き込みたくはない。どんなときでも英世は自ら解剖し、助手に現地人をつかう。黒人達はみな黄熱病の免疫をもっていて、たとえ菌に触れても感染することはない。英世は自分自身、免疫を持っているか否かはわからなかったが解剖は慣れていたし、どの組織に最も菌が多く危険かを知っていた。ときにヤングが手伝おうかと申し出ても許さず、見学させているだけだった。、
英世の下には三十数人の現地人がいたが、その元締めはウォルコットであった。彼は黒人のなかでは賢く、前にラゴスの研究所で働いていたというので重用したが、仕事は意外にずぼらだった。
猿の発情期を無視して実験に出したり、死んでも放置していたりする。一度そのために、折角培養してあった菌が全滅する危険にさらされたこともあった。しかも彼は途中で、英世の実験データーを盗み見してラゴスに送っていることがわかった。
英世は自分のデーターを他人に見られたからといって困ることはなかった。向こうが知りたければいつでも教えてやる用意はある。だがなにもいわず、秘かに見られていたことは、気持のいいものではない。
それにしてもラゴスのスタッフは大人気なさすぎる。前の動物のことといい、今度のことといい、彼等は明らかに対抗的である。そのことを考えると英世は腹がたってくる。この広いアフリカで信用できる者は誰もいない。マハッフィーとヤングだけは好意的だが、彼等にばかり愚痴をこぼすわけにいかない。
こんなとき、英世は痛切に妻のメリーに逢いたいと思う。
メリーは英世の仕事には、関心がなく、いろろいろ話してやっても覚えようとせず、それどころかまともにきいていたこともない。大体メリーは学問に興味を持つような女性ではなかった。だがメリーに不満や愚痴を訴えると気持ちがおさまるし、メリーになら「あのラゴスの奴等……」と罵っても構わない。学問について以外なら、彼女はやはり英世の唯一人の理解者だった。
「気候はそちらで考えているほど悪いわけではありません。もう慣れました。病気をして以来、再びマハッフィー夫妻と一緒に食事をするようになって、体はずいぶんよくなりました。仕事のほうは順調にすすんでいます。二月中には一応の目途がつき、四月ごろには帰れるようになると思います。一人で淋しいでしょうが、もう少しですから待って下さい。暇なときには芝居か買物でもして気を紛らして下さい。それから必ず手紙を下さい。手紙は時間がかかるから電文にして下さい。あなたの電文だけが私の心の支えです。もう五時を過ぎ鶏の声がきこえてきました。夜通し仕事をして疲れたので今日はこれでやめます。手紙を待っています。愛するメディへ。あなたのヒディ」
英世は半月に一度は、このような手紙をメリーに送り、どの手紙にも返事を欲しいと訴えた。
だがメリーがアフリカの英世へ手紙を書いたのは、わずか三回だった。それも「元気でいます……」というだけの素気ないものだった。
それはエクアドルやペルーに遠征したときも同じで、手紙で見るかぎり、メリーにくらべて英世のほうが愛しているようにみえる。事実、どちらが深く思っていたかといえば、英世のほうといって間違いはない。
だがメリーも英世を愛していなかったわけではなかった。メリーは英世を愛し、尊敬もしていたが、男にかしずくタイプの女性ではなかったし、手紙を書くといった面倒なことは嫌いな、陽気で屈託のない、いわゆるヤンキータイプの女に過ぎなかった。
ともかく、ここはなにをいっても地の果てのアフリカである。どんな文句をいい、苦衷を訴えても、相手に届くには時間がかりすぎる。その淋しさから逃れるように、英世は仕事に没頭する。
二月の初めころから、英世の頭に、病原体と推定できるあるものがまとまりかけていた。だがまだそれはヤングにもいわない。いうと逃げていきそうな気がする。光が見えそうではっきりしない。いまが最もきつい八合目である。
英世の実験はますます広がっていた。一人では到底処理できそうもない猿を買い込み、実験が始まって以来、すでに六百頭余の猿が死亡し、解剖を受けているが、猿は実験動物のなかで最も高い。
「ドクター・ノグチは金を費いすぎる」という噂が囁かれはじめ、それはラゴスの研究所まで拡が©つていく。
さすがにヤングも気にして、「もうこれ以上増やさないほうがいいのではないですか」という、既設の動物小屋では足りず、増築した小屋もすでに余裕はなくなっていた。
「研究に当って、金のことを考えているのでは、ろくな仕事はできません」
英世は平然としていう。たしかにそのとおりだが、これではロックフェラーも大変だとヤングは財団も大変だとヤング財団のほうに同情する。
だが口では威勢のいいことをいっていながら、英世も金のことが気がかりであった。
「ラゴスの奴等は、私の研究がすすみすぎるものを妨害しているのだ」「金のこという前に、彼等とわれわれと、どちらが仕事をしいているか、それをみてくれなければ困る」
文句をいいながら不快が高じてくると、いきなり頼信紙をとりあげて、不満を書きなぐる。そして夜でも朝でもかまわず現地人に、すぐ電信局に行ってこいという。
そのくせ時が経って冷静になると、「さっきの電文は出したろうか」ときき、助手が出していないというと安心して、「あんなくだらないものは、いちいち出さなくていい」といって破り捨てる。
とにかく英世の性急さは年齢とともにますます強まるようである。猿の到着が、約束より一日でも遅いと、もう苛立ち電報を打てという。だが船の一日、二日の遅れはやむをえない。すでに沖まできていると答えると、自分で港まで行って、こちらから船を出して運んでこられないかという。いまは早朝だから昼まで待って欲しいといっても、急がせるように連絡しろと叫ぶ。
ヤングはともかく、助手達はノグチという男が、どういう男なのかわからなかった。仕事に熱心なのはわかるが、少し抜けているところもある。性急で怒りっぽいと思うと、ときに小心で、やたらにサーヴィスがいいときもある。
「ドクター・ノグチは自分の名誉にとらわれすぎている」という人がいると思うと、「彼は研究者だが、統率者ではない」という者もいる。さらには「あの人は権力を持っている子供だ」と見る人もいた。
それらはどれも当っていて、その実、英世の一面にすぎなかった。
いまやヤングは、そんな批判をおさえる側に立っていた。ヤングも助手達の不満はよくわかる。だが英世が全力を尽して仕事に没頭していることだけは事実である。「彼は一生懸命なのだ」そういうと、みなすぐ納得する。小さな不満はあっても、みなノグチを愛し、尊敬していることに変りはなかった。
三月に入って、ヤングはますます英世の仕事に巻き込まれて、自分の研究のすべてを捨てて、英世のスケジュールどおり動いていた。
毎日、飼育動物の症状を調べ、その何頭かを解剖して標本をつくる。出来上がった一枚一枚を丹念に調べる。英世もヤングだけには気を許して何でも喋る。それを思うといっそう他人ごととは思えない。
英世の仕事のペースは、朝十時か十一時ころに研究室に出てきて、昼食のあとしばらく休憩して夕方までぴっしり仕事をする。夜に一旦家へ帰って食事をとるが、そのあと再び出て来て、朝の四時か五時まで仕事を続ける。
やがて明方、静まり返った海岸線を一人でドライブして家へ戻る。ときに海辺で車を停め、煙草を吸いながら一服する。陽はまだ昇ってこないが、東の海岸線はすでに明るい。白々と静まり返った海を見ていると、ふと日本の海辺にいるような錯覚にとらわれる。
だが振り返ると、海岸線はどこまでも椰子の樹が続き、ときたまみえるのはニッパヤシの小屋か洋館だけである。陽はないが、すでに風のなかに熱帯のなま温かさが滲んでいる。
煙草を喫い終ると、英世はゆっくり歩き出す。歩きながら椰子の実を拾い、思いきり海へ向って投げる。一人で砂浜に坐り、突然、「おい」と叫んで走ってみる。
「おっ母ぁ」と叫び、「あさりの味噌汁飲みでぇ」といってみたりする。久しぶりに日本語がすらすらでてきたことで安心して車に戻る。
家に着くのは大抵六時を過ぎてからで、本当に眠るのはニ、三時間である。ときには家に戻らず、研究室の椅子に凭れて眠ることもある。あるときは机にうつ伏せになり、目覚めると額に机のあとが生ま生ましくついていることもある。
初めのあいだ、夜中に仕事をしているのは英世一人だったが、途中からは夜間専用の助手と運転手を配置することにした。そうしなければ、夜に死んだ猿の解剖が追いつかない。
「ドクター・ノグチは眠るのが嫌いなのだ」
現地人がそんな噂をしていた。三月の末、英世はついにある重大な発見をした。
解剖した猿の組織のなかに特徴的な微生物が見えたのである。それは南米で発見したスピロヘ-ターによく似ている。英世は直ちに、この微生物体を他の動物に注射すると、黒い吐物を出して死亡した。解剖すると、胃のなかに同じ吐物がたまって肝臓と腎臓が冒されている。
これこそ、アフリカ黄熱病の有力な病原体かもしれない。……英世はすぐニューヨークのフレキスナーへ発見の電報を打ち論文を書こうとした。
だがヤングは慎重論だった。
もしこの未知の微生物が病原体であるなら、それを培養し、最低五、六世代を経て純粋化し、それを注射したすべての動物が罹病することが証明されたうえで発表すべきである。いま速断するのは早計ではないか。
ヤングの意見は正論であった。ある動物の組織中に、特異な微生物が発見されたからといって、それが即病原体かどうかはわからない。特徴といっても、それは病原体でなく、病気になった結果の一つの所見にすぎないかもしれなかった。
「この猿達は、ダカールからもらった血液で罹病したグループです。とするとこれはラゴスにもいっています。彼等も当然感染させて同じような所見を見ているかもしれません。それを発表しないところをみると、病原体と速断できない、なにかがあったのかもしれません」
「そんなことはない。彼等と私では仕事の質が違う。同じことをやっていて私に見えて、彼等には見えないのだ」
これが英世の台詞だった。梅毒の研究のときも、トラコーマの研究でも、英世が発見した病原体は、他の学者が調べていて見逃したものから見つけ出してきたのである。
たしかに英世は自分で標本づくりをして、人が見ないところまで丹念に調べた。そんなところに病原体はあるはずはない、と思われるところまで探索して発見した。同じ標本でも、自分が調べれば新しい発見ができる。彼等とは実験への気構えが違う。
「どうせ、彼等の眼はふし穴だからね」標本読みに関しては、英世は絶対の自信をもっていた。
だが、ヤングと同じことをフレキスナーも怖れていた。僕の許には毎日のように英世から電文が届き、ニューヨークにいながら、フレキスナーは研究のすすみ具合の逐一を知っていた。
二十数年間、英世の仕事を見続けてきて、フレキスナーはノグチが少し性急に論文を書きすぎる癖があることも知っていた。
「新しい進歩を喜ぶ。だが慎重に、発表は早まるな」
フレキスナーからの返電がきては、さすがの英世も、一旦発表をおさえざるをえない。さらに念入りに標本を調べ、菌株の培養をはじめる。だがメリーにははっきりと宣言した。
「ようやく新しい病原体と思われるものを発見しました。これはあまりに平凡なことであり、いままで調べた誰も気がつかず見逃していたものです。今度の発見はあまりにも革命的なので、すぐには誰も認めようとはしないでしょう。でももはや解決は時間の問題です。この仕事をまとめて五月末までにはニューヨークへ帰りたいと思っています。体の状態は最良です……」
嬉しくて英世は黙っていられなかった。フレキスナーやヤングの慎重論におされて、発表は控えたが、実験が終りに近づいたことはたしかだった。
「よし、あと一息だ」
英世はただちに猿百頭を注文し、半月後には二百六十頭を注文する。
最近、動物小屋を管理しているのは黒人のウイりアムである。彼はウォルコットと違って真面目に確実に仕事をするが、一人では、すべての動物には目が届きかねる。彼は一頭ずつ首にラベルを下げ、そこに何月何日になんの処置をしたか記されているが、それがときどき引っ搔いてなくなったり消えていることがある。そんなとき、現地人のなかにはいい加減に番号札をとりつけたり、報告を怠る者もいた。
英世はそれでデーターが大幅に狂うことを怖れて、飼育係には何度も厳しくいってあるが、それでも手を抜く者がいる。仕事の能率も悪いが、確実性でも劣る。
苛立ってくると、英世は黒人を呼びつけ紙切れに「チップとして、英貨一ポンドを与える」という走り書きをした。金を持っていると、落とすので、紙に書き込み、給料日に、黒人達が持って来た紙の数に応じて、支払いをしてやる。
このやり方は現地人に好評だったが、それだけ金がかかる。それにチップをもらいたいばかりに必要以上に動き廻る者もいた。だが一生懸命働けばお金をもらえるということで、彼等はいくらか働くようになるし、少なくとも英世の前では従順で、能率的だった。
三月から四月にかけて、英世は病原体と思われる微生物を追った。
たしかに、これまでの研究のなかで、最も有力な所見で、病原体の可能性は強い。だがいま一つ決め手はない。
四月の半ば、ラゴスからドクター・ハドソンが研究所へやってきた。彼は最近の情報交換と、できたら英世が分離した菌株をもらうのが目的であったが、英世は戸惑った。ラゴスのスタッフはあまり好きではないが、初めに血清をもらって世話になっているし、なんといってもロックフェラーで仲間である。気はすすまないが無下に断わるわけにはいかない。
どうしたものか、英世はフレキスナーに連絡して返答を求めた。
だがフレキスナーは、君の自由な裁量で決めてよろしい、といってきただけであった。フレキスナーにしても、そこまで介入する気ははなかったのである。
英世はハドソンの申し入れを受け入れることにし、同時にハドソンに新しく発見した微生物を見せることにした。公式には発表していないが先に見せておけば、彼等が先駆けすることはないだろうとい読みからだった。
種々のデーターを交換し、議論したあと、英世は確信をもって肝臓の微生物標本を見せた。
「どうだ」
勢いこんで英世がきいた。が、ハドソンの答えは素気なかった。
「これは、ただの枯草菌じゃありませんか」
「なるほど、あなたにはそうとしか見えないわけですな」
英世は平然を装ったが、顔はたちまち蒼ざめていた。いわれてみるとたしかに病原体と思ったものは枯草菌に似ていた。そうとは断定できないが、改めて見るときわめて類似しているし、実際、黄熱病患者の組織に枯草菌があってもおかしくはない。英世も枯草菌を知らないわけではなかったが、黄熱病を追うあまり忘れていたのである。
間違ったかもしれない……。
一度疑問が湧くと、急速にいままでの自信が揺らいでいく。たしかにこの病原体は培養が不完全だし、注入された動物のすべてが、同じ症状を見せたわけではない。同じ菌株からとったにしては波がありすぎた。
発見の喜びが大きかっただけに、違うかもしれないと思ったときの失望も大きい。なによりも絶対に自信があると思っていたスピロヘ-ターの顕微鏡所見でミスを犯したことがこたえた。
ハドソンが帰ってからの英世の落胆ぶりは甚だしかった。ときには食事もせず、話しかけても返事もしない。顔からは生気が失われ、三つも四つも老けたように見えた。
このころ撮った英世の写真に唯一つ、火傷をした左手が写っているのがある。いつもカメラを向けると素早く手を隠したのが、このときにかぎって平然と出している。手を隠す余裕もないほど、ショックを受けていたのである。
「もし、あの微生物が病原体でないとすると、黄熱病の病原体はスピロヘ-ターではないのだろうか」
暗い予感が英世の頭に浮かんでくる。あれがスピロヘ-ターでないとすると、南米で発見した病原体はどうなるのか。あれはたしかにスピロヘ-ターである。とするとやはり南米の黄熱病とアフリカのとは違うのか。いや二つとも本当は同じもので、ともにスピロヘ-ターではなく、一部の学者がいっているように、素焼きも通す超微細なウィ―ルスに近いものかもしれない。
はっきりいって、この時点での英世は南米で発見した病原体は黄熱病のものではなく、ワイル氏病のものであったと訂正すべきだったかもしれない。どうやら早まって、ワイル氏病のスピロヘ-ターを、黄熱病の病原体と誤認したらしい。だが、まだそうとはいいたくなかった。それでは南米での研究のすべてを否定することになり、ひいてはこれまでの自分に向けられた批判を、そのまま受け入れることになる。
深夜ベッドに入ってすぐ眠られぬままに、「野口英世は馬鹿かもしれない。大馬鹿野郎かもしれない」とつぶやくかと思うと、「いや、野口はまだ負けない。なかなか負けるものではない」などと、独り言をいう。
昼休み一人で考えこんでいる姿は老人のようである。生れつきの縮れ毛にも白髪が目立ち額のところは少し禿げ上がっている。顔が小さくなり、その分だけ皺が増えたようである。歩き方も以前は小さな体を大きく見せるように、胸を張って歩いていたのが、いまは軽い猫背で、背中が淋しそうである。
「仕事のやりすぎではありませんか」「五十歳を過ぎて、熱帯でこんなに無茶をしてはいけません」マハッフィーやヤングが心配するのに、英世はただ笑ってうなずくが、その忠告は決して守らない。
猿は次々と感染して死んでいくが、解剖は少し遅れがちになっていた。いままでのようにすぐやらず、一、ニ日に一度やることもある。
英世はいま、黄熱病がわからなくなっている。
一体、この正体はなにのか……。
なにか深い泥沼に足をとられ、目に見えぬ糸でがんじがらめに縛られているような気もする。
アフリカの雨季が近づいていた。風が湿気を帯び、ときどき雷鳴が走る。ときにスコールがきて、ガラスが割れるかと思うほどの激しい雨滴が窓を叩く。と、たちまち雨があがり、再び痛いほどの陽が射し、草花が生き返ったような鮮やかさを増す。
激しい雨も、眩しいほどの光も、原色の草花もいまの英世には厳しすぎた。
英世はアメリカへ戻ることを考えていた。このままいても研究の急速な進歩は望めそうにもない。黄熱病に関する資料だけは充分すぎるほど出来たからこれを持ち帰ってニューヨークで再検討しよう。
調べて検討するだけなら、設備が整い、妻もそばにいるニューヨークのほうがいい。
初めの予定どおり、アフリカで解決することはできなかったが、まだ負けたわけではない。自分の研究室へ戻ってじっくり調べれば、新しい発見ができるかもしれない。
五月四日、英世は妻とフレキスナーに、五月十九日アクラを発ってリヴァプール経由で帰国する旨の電報を打った。
ニューヨークには六月半ばごろに着く。
一度決めると、もう一刻も早くアフリカを去りたかった。
英世はただちに帰国の準備をはじめた。
出発に先立って、ラゴスに行ってハドソンらに別れをつげておこう。
五月十日、英世はアクラへ立寄ったラゴスの研究所のドクター・ビュイックと、ラゴスへ向かった。アクラからラゴスへ、船で一昼夜の旅程である。
十一日、ラゴスに着き、研究所見学、ハドソン、ビュイックらと夕食をともにして、ホテルで一泊。
翌十二日、朝、軽い腹痛を覚えた。だが見送り来たハドソン、ビュイックらと歓談し船に戻った。
午前十一時、船はアクラに向けて出発した。このあとアクラで五日間過して帰国する予定で、ニューヨークは目前であった。
英世が激しい悪寒と嘔吐に見舞われたのは、その夜からであった。
終章 アクラに死す P.294
英世の乗ったアッパム船は、一昼夜の航海ののち、翌十二日の昼近くアクラに着いた。
この間、英世はずっと寝たきりであった。桟橋に迎えに出たマハッフィーは、英世の容態が悪いのを知り、早く上陸できるように頼んだが、なかなかスムーズに運ばない。当時のアフリカの港は、大型汽船が横づけできる桟橋はなく、船は一旦沖合に停泊し、そこから艀で桟橋まで運ばれてくる。
いまもそうだが、ガーナはあまり能率のいい国ではない。「病人がいるから、よろしく頼む」といって、現地人がうなずいたが、それだけでは駄目だった。あるいはチップでも出せばよかったのかもしれないが、とにかく現地人のあいだで手違いが生じたことはたしかだった。
乗客が下船しはじめて一時間後に、ようやく英世は艀に移された。しかもそれまで小降りであったのが、急に激しい雨になり、小さな龍巻きが通りすぎた。その間、艀は母船に横づけになったまま、小一時間ほど嵐が過ぎるのを待った。英世は艀に横たわったまま雨除けをかぶっていたが、全身ずぶ濡れになった。
ようやく上陸したのは午後三時であったが、英世はぐったりして、口もきけぬありさまである。マハッフィーはただちに自分の車に乗せて自宅へ運び、ベッドに休ませた。
「寒い……」英世はそれだけいうと、沈み込むように眠りこんだ。
マハッフィーはずっと横について英世の様子を見ていたが、顔は熱く、ときどき苦しげに首を振る。ただの風邪とは思えない。
夕方五時に、マハッフィーはオプライエンの往診を依頼し、診察の結果ただちに入院がきまった。
かくして午後六時、英世はヨーロッパ病院2へ入院し、オブライエンの監督の下、ドクター・フランクリンが受持医になった。ヨーロッパ病院は、かつてカニ缶詰を食べて腹痛をおこしたとき入院した病院であり、オブライエンはそのときの主治医であったから、英世のことをよく知っている。
入院時の英世は、顔は熱で赤く、頭痛と体の節々の痛みを訴え、体温は華氏一〇三・六度であった。さらに緊急検査の結果、尿中に蛋白が認められた。
熱帯地方にいて熱が出たとき、まず最初に考えられるのはマラリアだが、血液の検査の結果は陰性であった。
一晩、解熱剤とリンゲル氏液を与えて様子を見たが、よくなる気配はない、それどころか、翌朝はさらに熱が上がり、一目で目は窪み、鬚が浮きあがり、別人のように衰弱した。しかも午後に一度、午後に二度と合計四度にわたって黒い吐物を吐き、排尿は午後に一度あったきりだった。
これらの症状から、医師団は黄熱病を疑った。
黄熱病の一般的な経過は、三日から六日の潜伏期のあと、突然、高熱とともに悪寒戦慄をともない、頭痛、腰痛、嘔吐などがおこる。この状態が四、五日続いたあと、一旦熱が下がり、症状が軽快する。いわゆる寛緩期で、ここで治れば問題はないが、そのあと再び発熱し、強い黄疸症状と腎臓障害をおこしてくると致命的で、一週間前後で死亡する。致死率は場所によって違うが、四〇パーセントとも七〇パーセントともいわれていた。
黒い吐物は、胃の血管が切れた結果であり、出血傾向を示し、尿が少ないのは腎臓障害の結果である。しかも全身の痛みと高熱、さらに英世自身が、きわめて感染しやすい危険な状態にあったことなどを考えると、黄熱病であることはほぼ疑いがなかった。
十四日の午後、嘔吐のあい間を見て、主治医のフランクリンが英世にいった。
「黄熱病については、博士のほうが詳しいと思いますが、われわれ医師団としては、博士のいまの病気を黄熱病と断定していいと考えています。治療もその線にそっておこないたいと思いますが、博士のお考えはいかがでしょうか
英世は黙ってフランクリンのいうことをきいていたが、やがてかすかにうなずくと、
「どうして、わかったのか……」とつぶやいた。
実際、そう思うのは無理もないことであった。
これ以前に、英世は自ら黄熱病の病原体を発見し、ワクチンをつくっている。それをうてば黄熱病にはかからないし、万一かかっても軽く済むはずだと公言していた。さらに自分は絶対に黄熱にはかからない、なぜなら実験動物の、どこに病原体が最も多く、なにが最も危険かをよく知っているからだともいっていた。
その当人が黄熱病にかかったのである。「わからない」というのが本音であった。だがこの時点で英世はまだ楽観していた。いまは苦しいが、じき寛緩期が訪れて楽になる。その裏には、ワクチンをうっているから大丈夫だという確信があった。
診断が確定したところで、マハッフィーはただちにニューヨークにいるフレキスナーと、メリーに宛てて打電した。
フレキスナーからは翌日、すぐ返電があった。
「ドクター・ノグチの病気を知って憂慮。あらゆる便宜をはかって援助を願います。ノグチへ愛を、あなたへ感謝を」
このあと、フレキスナーからは連日のように、容態の問い合わせと、連絡に対する返電が続く。
だが、妻のメリーからはなにもいってこなかった。
五月十五日、発病してから四日目に、英世の体温は急に下がり、嘔吐も落ち着いてきた。いわゆる寛緩期に入ったのである。
もはや黄熱病であることは疑いがなかった。
この日は、英世は少し元気になり、マハッフィーやヤングらと、それぞれ三十分ほど話をした。意識は正常だったが、全身の痛みと、倦怠感はなおかなり強かった。
翌十六日も落ち着いていた。体温と脈搏は正常だったし、嘔吐は朝方一度あっただけだった。肝機能の検査結果は、比較的良好だったし、排尿の回数も増え、尿中蛋白は減っていたが、腰痛と怠さは相変らず続いている。
午後ビュイックとウォルコットがラゴスから見舞にきた。彼等は英世がラゴスに来て発病したことに気をつかっているようだった。
だが英世は機嫌がよかった。
「このまま恢復するでしょう」というビュイックに、「もちろん、恢復しなければ死ぬよりないからね」といって笑った。
だが彼等の見舞以上に英世を喜ばせたのは、フレキスナーからの電文であった。
「ドクター・ノグチの症状軽快の電文を受け想像できぬほど安堵、あなたを含めた現地の人達の好意と献身を感謝します。ノグチへ愛を、フレキスナー」
英世はそれをマハッフィーから渡されて、いつまでも見詰めていた。
二十八年前、単身、フィラデルフィアのフレキスナーの許へおしかけて以来、フレキスナーとノグチは一心同体であった。英世は、フレキスナーにだけ研究から個人的な悩みのすべてを打ち明け、相談し、フレキスナーは誰よりも英世を信頼し、自分の最愛の弟子として遇してきた。いま発病というなかで、その子弟の愛情は見事に開花していた。
しかし、メリーからはやはりなんの連絡もなかった。
五月十七日、発病して六日目である。朝のうちは異常はなかったが、午後から肝臓部の痛みを訴え、終日うとうとと眠り続けた。
一般に、黄熱病は発病して一週間をのり切ると、助かる可能性が高いといわれている。医師団も息をころして、英世の病状を見守っていた。
五月十八日、この日を無事に越せば、一週間をのりきったことになる。もしかして、このまま再発せずに助かるかもしれない。医師団は前途に希望を抱いた。だが、はっきりした再発症状こそなかったが、尿は少なく全身の倦怠感は強かった。一度トイレに行こうとして起き上がりかけたが、力がなくそのままベッドに崩れ落ちた。
マハッフィーが、英世のさらに小さくなった体にタオルをかけてやる。
「ありがとう」
英世はうなずき上を向く。淡いグリーンに塗られた天井に白いプロペラ型の扇風機が低い音をたてて廻っていた。
天井を見ながら英世はつぶやいた。
「蚊に刺されたわけはないんですね」
マハッフィーがきくのに、英世はゆっくりと首を左右に振った。
「猿の解剖のときに、感染したんじゃありませんか」
「しかし、いままでは大丈夫だった」
感染経路についてはマハッフィーもヤングも、他の医師達もわからなかった。英世がくる前に倒れたストークスがその一人である。
「なにが、原因だったのか……」英世にそうきかれても、門外漢のマハッフィーに答えられるわけがない。黙っていると英世がつぶやくようにいった。
「結局、われわれは黄熱病については、なにもわかっていないんだね」
それはまさしく英世の敗北宣言であった。かつて黄熱病の病原体を発表し、華々しくワクチンの効果を説いたその男が、いま同じ病気にかかって首を傾げている。
電線経路も、病原体も、治療法もわからない、その不可思議の海のなかに、英世は小舟のように揺れていた。
やがて五月十九日の朝が明ける。この朝八時、英世は突然軽い癲癇ようの発作に襲われた。発作は三分間くらいずつ二度おこり、そのために舌を噛んだ。発作中、失神状態におちいり、意識を失い、その後一時的に精神錯乱状態におちいった。
マハッフィー夫妻は、ほとんどつきっきりで看護し、医師団は懸命に治療した。
だが治療といっても、ウィールスが原因の黄熱病には、これといった決め手はない。現在では、患者血清を注射して症状をやわらげる方法もあるが,当時は対症療法だけだった。強心剤と精神安定剤を注射し、アルカリを補給し点滴を続ける以外に方法はなかった。
五月二十日、前日のような発作はおきなかったが、衰弱は甚だしく意識は朦朧としていた。ときどき、「早く、早く……」といったり、「おっ母……」と叫ぶ。夢うつつの境をさまよいながら、英世の頭は仕事のこと、故郷の会津を行き来しているらしい。もっとも前者は英語だが、あとの言葉は日本語だったので、誰も意味はわからなかった。
マハッフィーからニューヨークのフレキスナーへ、さらに電文が打たれる。
「ドクター・ノグチの容態、きわめて重大、望み少ない。われわれはひたすら神に祈る」
フレキスナーからはすぐ折返し電文がきた。
「全力を尽されたし、わたしもひたすら神に祈る。ドクター・ノグチへなお一層の愛を」
夕方から心臓が弱まり、ときどき脈も結滞する。黄疸はさほど強くはなかったが、腎臓障害が著しく、血中尿素の増加による腎性昏睡におちいっていた。
そのまま二十日の夜が過ぎる。
明けて五月二十一日、英世はなお眠り続けていた。それでもときに目を開き、虚ろな目でゆっくりとあたりを見廻す。
だが、話しかけてもほとんど答えない、一、二分、目を開いているかと思うと、疲れたようにまた閉じる。あとはただ短い呼吸を続ける。かつてあれほど逞しく、働き続けたノグチが、いまは呼吸するのさえ苦しげである。走り続けてきた五十二年間の疲れが一気に襲ってきているようだった。
午前十一時、英世は再び目を醒ました。ベッドのかたわらにいたマハッフィー、ヤング、そして主治医のフランクリンを、順にたしかめるように見た。が、はっきり見えているのかどうかはわからなかった。
「気分は?」
フランクリンがきくと、英世は軽く首を左右に振ろうとしたが、その力もいまはなかった。
「しっかりするんですよ」
マハッフィーがいったが、英世は答えず目を閉じた。それからかすかに口が動き、辛うじてききとれる低い声でいった。
「なにが、なんだか、わからない……」
それが英世がこの世でいった最後の言葉だった。
そのあと再び昏睡におちいり、あとは呼びかけても目を醒ますことはなかった。
やがて午前十一時五十分、英世は突然、眉を顰め、首を二、三度振った。それから子供が啜り泣くような低い声をあげたかと思うと、次の瞬間、急に力尽きたように薄く鬚の生えかけていた顎を落した。
枕元にはただ一人、アメリカ人のマハッフィーが付いていただけだった。
直ちにフランクリンが駆けつけてきたが、すでに脈はなく、心臓は、英世の研究への心残りをうつすように、なお数度打ち続け、それから短い間をおき、もう一度打ち返したのを最後に、永遠に聴診器から消え去った。
このとき、一九二八年(昭和三年)五月二十一日、アフリカの太陽は中空にとどまり、赤い土と白い石が続くアクラの街は、光のなかで午後の休息に入ったまま静まり返っていた。
英世の死については、多少の異説がある。その一つは自殺説であり、一つは他殺説である。
自殺説の根拠は、英世のアフリカ行きが、学術的に四面楚歌の状態のなかで、英世自信、自分の業績に疑問を抱いていたという特徴をもとにしている。遠くアフリカまで行って、英世はさらに自信を失う。口では強いことをいったが、いずれ自説を訂正せねばならないことは目に見えていた。たとえ南米黄熱病とアフリカ黄熱病とは違うといってみたところで、いい逃れにすぎないことは、英世自身が知っていた。新しい学者達は、すでに単なる細菌を追う時代から、超微細病原体であるウィールスを追う時代に入っていた。それに乗り遅れた英世が遠からず、厳しい批判を浴びることは明白であった。
「ドクター・ノグチは、アフリカへ行き、黄熱病になることによって、学問上の批判を逃れた」という説もある。
これにくわえて、最も危険な七病日をのりきったのに、八病日に至って急に悪化したのは不自然だ、と疑問を提出する人もいた。
だが、これらはいずれも説得力に欠ける。それはアフリカから英世がフレキスナーや妻のメリーへ送った、おびただしい手紙と電文の内容を見ればすぐわかる。
英世は心底からニューヨークへ帰りたいと思っていた。研究の成果はともかく、まだまだ巻き返しを狙い、ファイトを燃やしていたことは紛れもない事実である。
さらに七病日を過ぎたといっても、その日を過ぎれば絶対に助かるというものではなく、現に黄熱病で八病日や十病日以後に死んだ人は沢山いる。まして一日くらいの違いで、自殺と断定するのは行き過ぎというものである。
他殺説の根拠はいっそう薄い。これは英世がラゴスに行った直後から発病したことから、ラゴスで故意に黄熱病をうつされたのではないか、という疑惑から生じている。
この背景には、英世とラゴス研究所との不仲があげられる。
だが、いかに不仲であったとしても、ラゴスのスタッフが、英世を殺さねばならない理由は見付からない。彼等は、初めから英世の業績を疑っていたのであり、英世が膨大な実験データーをニューヨークへ持ち返ったところで、新味ある発表が打ち出されるとは思っていなかった。
他殺などという陰謀な方法をつかわずとも、自然科学の世界では、誤った学説は自然に消し去れられていく。すでに落日のノグチ(書名『遠き落日』と関連:黒崎記)をラゴスのスタッフが改めて消さねばならない理由はない。
さらに黄熱病の潜伏期が三日ないし六日であることを考えれば、この説がいかにナンセンスであるかが知れる。ラゴス滞在一日で、その帰りの船で発病した英世は、当然、ラゴスにいく数日前に、アクラで感染していたと考えなければならない。
他殺説は、おそらく当時、医学に無知なアクラの現地人のなかで囁かれたことなのであろう。
彼等は自分達のボスとしてノグチを慕っていた。同じアメリカの研究所がラゴスにあるところから、なにかと張り合う傾向があった。アクラとラゴスでは、現地人同士でも、あまり仲がよくなかった。そんな状態で、自分のボスがラゴスに行って病気になってきた、というので拡まった噂なのであろう。
英世の死後、遺体は英世に最も協力的だったヤングの手によって解剖され、肝臓の一部が摘出された。これは標本としてロンドンの博物館に保存されているが、あきらかに黄熱病による黄疸の症状が残っている。
※参考:イギリス植民局医学研究所の所長で、野口英世の協力者だったウィリアム・A・ヤング博士は、5/21に死亡した野口英世の解剖後、5/29に死亡しています。
死後に、遺品等は本国(イギリス、当時のガーナはイギリスの植民地)に持ち帰られたので、「当然、ロンドンにあるだろう」→「ロンドンの博物館にあるだろう」→「ロンドンの博物館に今も保存」となったのでは?と推測します。ウエブサイトによる。
さらに英世が臥床中、ヤングは英世の許可を得て、英世自信の腕から血をとり、それを猿に注射して、同じ黄熱病を発病させることに成功した。
英世の遺体は解剖後、この地で最良のオータムウッズの棺におさめられ、その内側は鉛で裏打ちされていた。棺は一旦、溶接密閉され、さらに木屑でパッキングされた。
英世の現地での葬儀は、死んだ翌々日の二十三日午後五時四十五分から、イギリス系のプレスプレタリアンミッション教会で、フレイズ神父および現地の牧師達により執りおこなわれた。
葬儀ではマハッフィー夫妻、ヤング所長の他、ヨーロッパ、アフリカ人など多数参列し、ラゴスのスタッフもかけつけて哀悼の意を表した。最も親しかったマハッフィーは棺に花を添えると蹲って泣き、身近で働いた黒人達も英世の寝棺にとりすがって別れを惜しんだ。
英世の計画によれば、ラゴスから十三日に帰り、約一週間のあいだで残りの仕事のあと片付けをしたあと、五月十九日にアクラを出る船で出発する予定で、すでに切符の手配もしてあった。
もしその船に乗れば六月の初めにはニューヨークへ着くはずであった。
英世の死後、マハッフィーとヤングは、さまざまな実験データーや培養チューブ、資料、研究書などを、シアン化合物で滅菌したあと、トランク、資料箱に密閉し、フレキスナーのところへ送り届けた。
英世個人の私物のなかには、フレキスナーへのお土産として、アフリカ産の革のクッションと蔦でつくった布があり、さらに同僚のラッセル、秘書のチルデン嬢への土産、そして妻のメリーにはアフリカ模様の布地と小さなプレスレットが買ってあった。これらも英世が愛用した顕微鏡とともに、すべてニューヨークへ送り返された。
かくして、アクラでの悲劇は終ったかに見えたが、英世のあとを追うようにヤングがまた黄熱病に襲われた。彼は英世の死後五日目の五月二十六日、突然発熱し、仕事の疲れだといっていたが、翌二十七日には黒い嘔吐をくり返し、二十九日、寛緩期もないまま急死した。
彼の場合も蚊にさされてはいない。とすると、英世の死後、解剖したり、その後放置されたままになっていた猿の解剖を英世に代ってやったときに、感染したとみるのが妥当であろう。
ヤングは本来、黄熱病の研究者ではなかった。それが英世がのりこんできたため、英世を助け、手伝ううちに黄熱病の研究にとりつかれた。その意味では英世の巻き添えになった犠牲者ともいえる。
だが生前、英世はヤングには、危険だからといって、黄熱に感染した動物の解剖をさせなかった。それが英世の死後、自らかって出たのが新たな悲劇を生み出す原因となった。
かくしてストークス、ノグチ、ヤングと、黄熱病は無数の現地人にくわえて、有能な学究を死へひきずりこんだ。このあと黄熱病の病原体は、ウォルター・リードらが予測したとおりウィールスであることが確認され、英世の発見した病原体が誤りで、ワクチンも実効がないことも明確になった。現在、ノグチ・ワクチンが一時的にでも、効いたような印象を与えたのは、ワイル氏病患者が、黄熱にしても寛緩期に与えられた例を誤認したのであろうと推測されている。いずれにしても二〇マイクロミクロン(マイクロミクロン=ミリメートルの千分の一の大きさ)程度の微細なウィールスを当時の顕微鏡では見ることは不可能であり、ウィルースそのものについても、そのころはまだはっきりわかっていなかった。その意味において、黄熱病やトラコーマなどウィールス疾患に挑んだ野口の敗北は、個人の失敗というより、学問の発展途上における必要やむを得ざる誤りであったともいえる。
「野口英世死す」の悲報は、ただちに全世界に伝えられた。
日本では各紙が「世界的学者、人間の偉大な恩人、野口英世博士がアフリカで逝く」と大きく報じ、その日の読売新聞では第一面で英世の死を報じたあと、社会面で「世界的大医学者・逝ける野口博士」と見出しをつけ、さらに「世界を驚かした数多の発明」「フレキスナー博士の恩顧で病菌王となるまで」と題して、その一生を振り返っている。また二十六日の同紙「婦人欄」では。「悲しみに沈む、尊き学問の犠牲、野口博士の未亡人」として、メリー夫人の写真とともに、「夫人へ哀悼の意を」と記されている。そして最後に、「夫人には子供はなく、夫君の故国日本の土はまだ一度も踏んだことはないが、今後あるいは博士の遺髪を持って日本を訪れるかもしれない。しかしそれについては、まだどこにもなんの知らせもないそうである」と書かれているが、結局、夫人の来日は実現しなかった。
英世の死の報を受けて政府は勲二等旭日重光章を追贈し、東京及び郷里会津で盛大な追悼会がおこなわれた。
だが英世の死を最も悲しんだのは、アメリカにいたフレキスナー博士かもしれなかった。彼はノグチの死を知ると、ただちに教会へ行って祈りを捧げ、それから一か月、毎日、愛弟子のための礼拝を欠かさなかった。英世の遺体がニューヨークへ戻ってきたのは六月十ニ日で、翌十三日には、ロックフェラー研究所主催の盛大な追悼葬儀が開かれ、日本人、アメリカ人など多数が参列した。
英世の遺体はロックフェラー研究所が寄贈したニューヨーク市北郊のウッドローン墓地に埋葬され、英世の名と業績を刻んだ墓碑が建立された。また英世の妻メリーには、死後研究所から月々六百ドルの年金が贈られさらに一九二八年には恩給として三千七百五十ドルが贈与された。
二十八年前、わずかな金だけ持ってフィラデルフィアへ単身とびこんで来た一人の小さな日本人が、ひたすら学び、走り続け、数々の栄光をえて、いまようやく走ることを終えた。
「お前はいつ眠るのか」とみなに驚かれた英世が、誰にも妨げられずゆっくり眠ったのは、太平洋を越えた異国の墓地のなかであった。
現在ロックフェラー財団医学部図書館の正面玄関の左右には、ロックフェラー一世の胸像と向かい合って野口英世の胸像が並び、明治の半ば単身アメリカに渡ってきた一日本人の業績をたたえている。
日本の英世の墓は、故郷翁島村長照寺に、かつて孝養を尽した母と、憎みきった父の墓石の間に墓標が立てられたが、戦後、同じ境内に英世・メリー夫妻の墓が、新たに建立された。またその遺髪は、生家の中庭の石碑の下に埋葬されている。戒名は「大仁院殿済民英世居士」である。
「野性時代」一九七五年一月~七八年七月号(四三回連載)・加筆
|

 この宴会の開かれた「琴の家」はいまも、箕面公園の一隅にあり、英世達が寛いだ二階の広間もそのまま残されている。
この宴会の開かれた「琴の家」はいまも、箕面公園の一隅にあり、英世達が寛いだ二階の広間もそのまま残されている。
 像の建てられた場所は、「琴の家」の上を走る滝道から二十メートルほど上った台地で、像は上野の科学博物館前にある、白衣で試験管を握った姿をうつしたものである。
像の建てられた場所は、「琴の家」の上を走る滝道から二十メートルほど上った台地で、像は上野の科学博物館前にある、白衣で試験管を握った姿をうつしたものである。
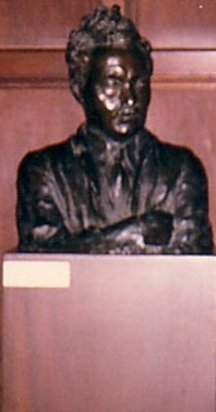 出発前の寸暇をさいて、英世はモデルになった。その肖像は出発までには間に合わなかったが、のちに完成し、いまはロックフェラー大学図書館入口に、ロックフェラー一世の肖像とともに残されている。
出発前の寸暇をさいて、英世はモデルになった。その肖像は出発までには間に合わなかったが、のちに完成し、いまはロックフェラー大学図書館入口に、ロックフェラー一世の肖像とともに残されている。