(角川文庫)昭和六十二年六月十日 第七刷発行
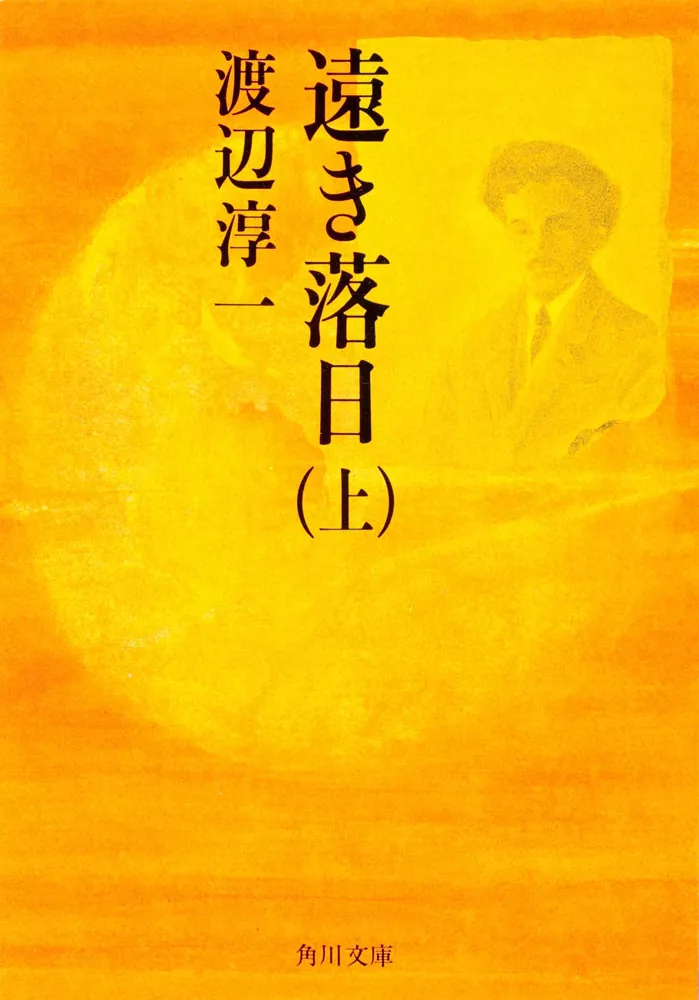
目次
序章 メリダにて
序 章 メリダにて P.5
一九七四年八月二日、私はメキシコの首都メキシコシイティから、カリブ海に飛び出したユカタン半島の突端にある街、メリダへ向けて飛び立った。飛行機は翼に黒い鷲印のついたメキシコ航空のボーイング727である。 この航路はメキシコシイティとユカタン半島を結ぶローカル線で、いつもは比較的空いているらしいが、このときは夏のバカンスのせいもあって満席であった。黒い大きな瞳、整った鼻、濃い口髭、メキシコ人特有の人懐っこい笑いと、騒々しさをのせて、飛行機は一路ユカタン半島へ向かう。 飛行場を飛び立ち、急上昇して夏の雲を抜けると、進行方向の右手に、一つだけ、雲の上に頭を出した山が見えた。標高五四五二メートル、ポポカテぺトル山だと同行の日系二世の山田氏が説明してくれる。 メキシコは全体に山地が多く、メキシコシイティそのものも二二四〇メートルの高地にある。私はそれを見ながら、五四五二メートルから二二四〇を引けば、三二〇〇余になるから、丁度日本人が富士山を見上げる感じになるのかと考えた。実際、その山は富士山に似ていた。裾野のほうはともかく、雲から出た部分は、見事な二等辺三角形で、その山頂に純白の雪を戴いている。富士山を思い出したせいか、私はこの山が、メキシコで最も高いのだと思っていたが、さらに西へすすみ、ポポカテぺトルが視界のうしろに退るころ、それと入れ替わりに同じくらいか、あるいはそれより高いと思われる山が、続々と雲の上に現れてきた。これらの山はポポカテぺトルのように整った容姿ではないが、やはり山頂は雪を戴き、そのなかで最も高いのが、標高五六七五メートルのオリサバ山である。 このの街に野口英世が訪れたのは、いまから五十五年前の一九一九年の暮れである。このとき、野口はニューヨーク、ロックフェラー研究所の主任研究員で、その春黄熱病原体を発見した功績により、米国医学会から銀牌を贈られたばかりであった。 この年に、野口がこの街を訪れた理由は、もとより黄熱病の研究のためであった。 当時、この白い街はまだ黄熱病の恐怖に沈んでいた。 黄熱病(イエローフィバー)といっても、いまのわれわれにはぴんとこないが、かつてペスト、天然痘、コレラなどとともに、世界を震撼させた悪性伝染病の一つである。 この病気は字のごとく全身が黄色くなり、高熱が出て死に至る。全身が黄色くなるのは、末期に肝臓が侵され、急性肝炎を起して黄疸をきたすからである。感染すると同時に、真夏でも、歯が合わぬほどの震えがきて、たちまち腎臓と肝臓が侵され、最後は呼吸困難で息絶える。発病から死までは、三、四日か、長くても五、六日といわれ、一応一週間、もちこたえた者だけが辛うじて生き残る。その致命率は、土地によって四〇パーセントとも、七〇パーセントともいわれていた。 白いメリダの街は、野口が来たときも、いまのように太陽の下で静まりかえり、ときに黄熱病患者の断末魔を告げる喚きと、家族の泣き声だけが、石壁の家から洩れていたのかもしれない。
私はここに来る前、ニューヨークにいて、そこからイースタン航空でメキシコシイティに入り、メリダに着いた。その間、実際の飛行時間は七時間余りであった。その行程を野口は五十五年前、汽車で走りづめで二週間かかってきた。だがこの間、野口は列車の寝台つきのコンパートメントに入ったまま外へ出なかった。 車掌は、野口がメキシコのメリダまで行く切符を持っていることは知っていたが、コンパートメントのドアが閉められたままなので、心配になり、ドアをノックしてみた。 「なんだ」 数度ドアをノックしたところで、ようやく返事が戻ってくる。 「あのう、なにかご用はないかと思いまして」 「ない」 それで野口が生きていることだけはたしかめられたが、なかでなにをしているかは、まったくわからない。ただこの小柄な乗客がたまに停車する駅で、売店から大量の食糧を買いこむのが見られたが、その姿は鼻の下にちょび鬚を生やし、髪はぼさぼさにして、ズボンを吊りバンドで支え、いかにも風采のあがらない東洋人だった。 ともかく、こうして野口がメリダに着いたのは十二月の六日であった。
五十五年前、野口はこのホテル(ホテル・レㇹルマ)に着くと、その夜、町の公会堂にメリダの医師、医療関係者の全員を集めて次のような講演をした。 「私は昨年、黄熱が猛威を揮うエクアルドに出張し、調べて、その血清のなかから、黄熱の病原体であるレプトスピラ・イクテロイデスを発見しました。一九〇〇年、アメリカ医学界がこの黄熱に挑戦して以来、二十年間、多くの年月と莫大な研究費を投じて、なお不明であった病原菌を、私は幸運にも二か月の短時間で発見することができたのです。これで黄熱撲滅への第一歩は開かれ、あとはこの菌をたたく治療法を、考えればいいだけです。いままでの、やみくもの戦闘と違い、これからは目標がきまった、正攻法の攻撃がはじめられるのです。野口は演説の上手い人であった。少し甲高い年齢よりも若い声で、抑揚をつけ、壇上で卓を叩き、のってくると全身を躍動させる。小柄だがエネルギッシュで、喋りはじめるとその小柄な体がひとまわり大きく見えた。 この五十五年前の演説をきいた人が、いまなおメリダの街に住んでいる。メリダのカレー街四十五番地に住む、ドクター・オトリイオ・ヴィラヌエヴァ氏である。
ロスアンゼルスではニ泊して野口英世の研究家として有名なプレセット女史に会ってきている。彼女の父親がロックフェラ―研究所の精神科教授をしていて、野口と親交があった関係から、野口に興味をもち、研究を始めた人である。 野口の研究業績の一つに、梅毒患者の脳から、梅毒の病原菌であるスピロヘ-ターパリダを発見し、その菌の純粋培養に成功したというのがあるが、その研究にプレセット女史のお父さんが積極的に協力した。当時野口は、梅毒頭がおかしくなって死んだ患者の脳の切片をつくり、その標本調べていたのだが、彼女の父親は、その梅毒患者の脳を提供する便宜をはかったのである。 この時、プレセット女史のお父さんは「日本のドクター・ノグチは偉い男だ」と、当時まだ子供だったプレセット女史に話したという。彼女が野口に興味をもちだしたきっかけは、以上のようなわけだが、それとは別に、彼女は幼いころ野口に抱かれたことがあるらしい。ここで、あるらしい、というのは、プレセット女史は、そのことをはっきり記憶していないからである。彼女の父がニューヨークにいたころだから、彼女がまだ三、四歳のころらしいが、女子は、母親から「ドクター・ノグチが家にきて、あなたを抱いたのよ」と、きかされていた。 白人の名家の娘が、小柄な風采のあがらぬ東洋人に抱かれる図は、なにやら奇妙な感じもするが、野口はそれほど彼女の一家から信用をえていたということにもなる。 いまプレセット女史は六十歳をこえ、カルフォニア工科大学につとめる夫君と、ロスアンゼルス郊外の高級住宅であるアルパデナに住んでいる。暇があるせいもあるが、大変な勉強家で、アメリカで発行されたエクスタイナーの野口の伝記をはじめ、フィラデルフィア、ニューヨークまで足を延ばし、野口に関するさまざまな資料を集められている。 おそらくアメリカにおける、野口研究家の第一人者であろうが、私の野口についてのいくつかの質問に、女史はある面では熱心に答え、ある面ではきわめて素気なかった。 「お国は違うが、あなたも私も野口の研究家です。その意味であなたは私の友人でありライバルでもあるからです」プレセット女史は、沈黙の理由を、こんなふうにいって悪戯っぽい笑いを洩らした。
このプレセット女史との話で、最も感心したことは、彼女はいわゆる日本の伝記作家のように、野口を一方的に偉くて立派な学者とばかり見ていないことである。野口の偉かった部分は偉いとしながらも、、しかしまずかったところはまずいと、冷静な眼で見ている。 「彼は非常に熱心な、いい学者でしたが、最後のころは、やや焦りすぎ、学者として大きなミステイクを犯してしまいました」 こういう野口観については、私も同感であった。 間違いなく、野口は偉大な学者でありながら、最後に大きな過ちを犯している。彼の学者としての業績は、かつて最高の評価を受けたにもかかわらずいまはあとかたもなく消えている。正直いって、野口の学者としての評価は、死後、急速に失われてしまった。おそらく日本の学者でこれほど毀誉褒貶の激しい人はいないだろう。これまで日本の伝記学者はそれを知りながら、あえて野口を偉大な学者として書き続けた。 伝記というのは、往々にして作中人物を過大評価し、その人物の都合のいいように書かれるものだが、野口の伝記ほど、その傾向のいちじるしいものはない。かつて日本の歴史が、歴史家によってゆがめられたように、野口の一生も、伝記作家によって大きくゆがめられ、実際の野口とはまったく別の野口がつくられたのである。
このあたり、プレセット女史のいうことは的を射ていて、数ある野口英世の伝記のなかで、この本だけは、いささか趣を異にする。だが、それでいいかというと、やはり疑問は残る。野口の出生から克明に追ったその伝記は、たしかに野口が日本にいた部分はよく書かれているが、渡米してから死に至るまでの部分はいささか駆け足で不満足の部分が多い。この点ではこれまでの野口英世の域を出ないし、それに日本にいた部分も、当時すでに世界の偉人としてつくりあげられた野口の像を壊すまいという配慮が、いたるところに見られる。 これは必ずしも著者の責任というわけでなく、いかに奥村氏が正確に書きたいと思っても、時代の流れが、すでにそのようなものを書かさないところまでおし迫っていた、というべきかもしれない。 それはともかく、日本の野口英世伝の共通の弱点は、第一に、最初から野口を、偉大な医学上の発見をした学者として見ようとすることであり、第二は、渡米してからの野口の実像が、よく書かれていないことである。アメリカに行ってからの野口は、表立った年賦から、有名になっていく過程を単純に書きつらねるばかりで、その裏の苦悩や、不安は少しも書かれていない。 だが、といって、この部分をいい加減に済ましていい、というわけではない。野口のあの異様にかたくなでエキセントリックな性格は、維新で遅れをよった会津という独特の土壌に育まれたとはいえ、二十五歳から死に至る五十三歳までの、人生の最盛期を野口は外国で暮らしているのである。野口を書く以上、この時代を駆け足でとおりすぎるわけにはいかない。この時代を克明に追うことが、野口の一生を浮き彫りにする上で重要な作業だが、この点でプレセット女史は、日本の伝記作家よりはるかに有利な条件にあるといわなければならない。 彼女はアメリカに住んでいるうえ、恵まれた経済力と、あり余る暇を駆使して、世界各国に野口の足跡を追っている。日本にも、過去二度きて、野口の生家のある猪苗代湖畔にも足を運び、日本における野口英世研究の大凡も、その欠点も、承知している。
第一章 猪苗代 P.35
1 私が野口英世の生家を訪れたのは、一九七二年の八月の末であった。すでに夏休みも終りに近く、観光客は少ないかと思ったが、生家や、それに続く記念館には、かなりの人が詰めかけていた。 会津若松から猪苗代町まで車で三十分。いまは町村合併により、長田、堅田などとともに、猪苗代町に包含されているが、かつて野口が生まれたころは、翁島村と呼ばれていた。正しくは福島県耶麻郡翁島村大字三和字三城潟と呼ばれていた。 野口という姓そのものは、三城潟では名門に違いないが、英世の生れた野口家そのものは分家で、しかも英世が生まれたころは零落し、母親シカ一人が働いていた日銭で辛うじて飢えを凌ぐという状態であった。 英世の父の佐代助など、家にいないほうがましで、帰ってくると朝から酒に浸り、シカが夜も寝ずに働いてえた金をくすねては博打に使うというありさまで、家族を苦しめるためにだけ存在したといったほうが当っている。後年、英世が外国へ渡り、郷里の母や知人へ送った手紙の、どの一片にも、父について書かれていないことでも、そのあたりのことは想像がつく。 これにくらべて、母のシカという人はよく出来た人であった。この人については、野口に関する伝記のすべてが絶讃して止まないが、たしかにその努力と忍耐は並みのものではない。(P.38) 2 英世の母のシカは嘉永六年、野口岩吉の娘みさと隣村からの婿善之助のあいだに長女として生れた。二人のあいだに初めての子として祝福されるべきが、シカが生まれて間もなく、この野口家はにわかに零落の速度を早める。 一人おき去りにされたシカはまだ八歳になったばかりで、しかも家には足腰の立たない祖母がいる。 大抵の子供なら、泣きじゃかるだけなのに、このころから、シカは並みはずれた聡明さと勝気さを備えていた。 シカの聡明さと勝気さは、普通の子のように、ただ泣き叫んだり、傍観していることを許さない。どんな苦境に追い込まれても、全力を尽し突破していこうとする。この頑張りは、まさしく、のちの英世が受け継いだ素質そのものである。 八歳でニ瓶家の子守をしながら、シカはそれだけに甘んじていない。同じ年頃の娘達が字を習っているのをみると、無性に習いたくなり、隣の千手院法師鵜浦寿康という人に頼み込み、いろはの仮名文字を、書いてもらって、子守の合間に読むようにした。さらに字を憶えるため、主家の人達が寝静まるのを待って、盆の上に灰を置き、月の光を頼りにその上に指で字型を書いたともいう。 後年、シカが野口英世に送った手紙が、現在野口記念館に保存されているが、平仮名、片仮名、ときに漢字まじりの、乱れた字体ではあるが、ちびた鉛筆をなめながらも必死に書いた親の心情がよく現われている。 官軍に抗らったということで、以来、会津はさまざまな迫害を受ける。たとえばこの後東北本線の施設に当り、若松はかつて二十三万石の城下町を誇った東北有数の都市であるのに鉄道から見放され、町の発展は大きく阻害された。さらに会津出身者というだけで中央政府にいれられず、明治の末まで、そこから中央官界にめぼしい人物はほとんど出なかった。白虎隊、磐梯山と歴史的・観光的には有名になったが、人々自体は恵まれない。その口惜しさが同県人の団結を強め、いろいろな問題はありながら、野口英世を盛り立てていった原動力ともなった。P.45 明治五年、二十歳になったとき、シカは三城潟から一里余りへだてた小平潟に住む小檜山惣平の長男佐代助を婿に迎えた。 3 だが佐代助は、代々野口家の男達が、ふしだらで怠けものであったと同じような欠点をもっていた。初代の清太郎はともかく、岩吉、善之助、佐代助と、どういうわけか、野口家は男運が悪い。いずれも気が弱く、農耕を嫌い、屋敷奉公に流れ歩く。一か所に腰を落ち着けているところがなかった。 佐代助の実家の小檜山家は、学者組とも呼ばれる家柄で、一族から多くの優秀な人材が輩出している。学問に熱心であるとともに、頭もよかった家系である。佐代助ももちろん、その一族の一人として、頭はよかったに違いない。事実、そうでなければ、英世のような優秀な人材が生まれるわけはない。英世の性格からみて、母の血のほうを強く受けてはいるが、母と父、両方の聡明さが相まって、英世が生まれたと考えたほうが適切であろう。 いずれにせよ、佐代助は学問の程度はともかく、資質的には、かなり優秀な男だったと思われるが、その頭のよさが、逆に彼の一生を狂わせたともいえる。 はつきりいって、佐代助は百姓に向いている男ではなかった。少しでも頭が切れ、小才が利く者であれば、当時の百姓が、労多いわりに恵まれることの少ない、割りの悪い職業であることは見抜けたはずである。 佐代助の悲劇は、百姓をするには頭が利きすぎるが、といって他の職業をするほどの勇気もない、中途半端なところであった。 当時、三城潟では、佐代助が百姓仕事をしているのを見たことがないといわれたほど、佐代助は働かず、朝起きるとすぐ居酒屋へ駆け込み、コップ酒を二杯飲むのが習慣であった。 三城潟には、港屋と古川屋という二軒の居酒屋があり、佐代助は毎日このどちらかに出入りし、のちに港屋に、野口家の田、二反ほどが、酒代のかたとして取られている。さらに、この数年あとには、佐代助の縁続きである猪苗代の小檜山家にも田を売り、英世が生まれたころには、西久保と三城潟の田だけが残っていたが、ここはよく湖の水をかぶり、実際にはほとんど収穫の望めないところだった。 シカは結婚してすぐ、佐代助が頼りにならない男であることを知った。一日中、酒浸りで、仕事といえば、三城潟の郵便配達夫として一日十銭前後の駄賃をもらうだけで、それも思い出したようにやるだけで、もらった金はすぐ酒に費ってしまう。 シカは再び、夏は農家の日雇いを、冬は雪の峠をこえて若松まで橇で荷を運ぶという、男でさえきついといわれた重労働に追われた。 こんな貧弱のなかで、明治七年四月、まず長女イヌが生まれる。次いで二年後の明治九年十一月、野口英世が産声をあげる。母のシカは二十五歳、父佐代助は三十六歳であった。 4 野口英世の姉は明治七年の戌年に生まれたところから、その干支にちなんでイヌと名付けられた。当時はこうした名前のつけ方が多かったが、その二年後に生れた英世は、初めの戸籍では清作となっている。これはシカの曽祖父清太郎からとったものだが、この清作が、のちに英世となったのは、次のようないきさつがある。 明治三十一年八月、清作は自分を高等小学校まですすめてくれた恩師の小林栄夫人が重態だときいて会津へ戻った。このとき、清作は二十三歳、その前年、医師開業試験に合格し、北里研究所に勤めたばかりであった。 夫人の病気は腎臓病で、ほどなくもちなおしたが、たまたま清作が付添っているとき、隣のベッドにいる人から坪内逍遥作の『当世書生気質』を借りて読んだ。この本は当時の流行小説としてなかなか人気のあったものだが、これを読んでいるうち、偶然、小説なかに、「野々口精作」という人物が出て来るのにぶつかった。野々口精作は医学書生で秀才の誉れ高く、故郷の期待を一身に受けて上京するが、ふとしたことから酒と女に身をもち崩し、遊郭三昧の生活に溺れる。 野口と野々口と、一字違いだが、名前も、医学生であるところもよく似ている。しかも酒と女に溺れるところまでそっくりである。当時清作は研究所の差別待遇にいや気がさし、人々から借金を重ねては、吉原から横浜の遊郭まで遊び歩いていた。 一読、清作は自分のことかと驚いた。誰かが自分のことを密告し、それをもとに坪内先生が書いているのではないか。気になった清作は、悩んだ末、小林栄に改名したい旨を申し出る。 「有名な小説に、同じ名前のあんな破廉恥な男がでてくんのではやりきれません」 もちろん清作は、東京での自分の行状が主人公にそっくりだから、とはいわなかった。真面目な少年時代しか知らず、期待をかけてくれている恩師に、そんなことをいえた義理ではない。なにも知らない小林栄は清作の申し出を単純に、名前が似ているから嫌なものだとうけとった。 「ほんなに気にくわねぇんだったら、変えたほうがいいべ」 「しかしすぐにいい名前は浮かびません。どうせ変えんだったら立派な名前にしてぇんです。ほんで新しい名前の名付け親になってもらえねぇでしょうか」 「私でよがったら、考えっべ」 自分が見出した片田舎の少年が、いまや東京で医師になり、妻の病気に駆けつけて、名付け親にまでなってくれ、というのである。小林栄としては悪い気はしない。数日後、小林は「英世」という名を書いてみせた。 「英という字は、小林家で代々用いられてきた名で、人にすぐれるという意味だ。世はこの広い世のなかをさす。英世とはすなわち、世にすぐれた人物、第一級の人物という意味だ」 この名をきいた途端、清作は大きくうなずいた。いかにも賢そうでしかも品がある。清作という百姓然とした名とは大変な違いである。 「ありがとうございます。この名前ならもう誰にも負けません。いただいた名前をはずかしめねぇように頑張ります」 このときから、清作はさっそく英世と名のり、役場へ改名した旨を届け出た。 明治二十二年十月二十一日、ようやく役場の戸籍簿の清作は抹消され、新たに英世と記載された。 だが小林栄はのちに『当世書生気質』に野々口精作という人物が登場することを知り、後年、英世が西アフリカで死んでから坪内逍遥に直接手紙を出し、小説中の野々口精作が、野口清作をモデルにしたのか否かを尋ねている。 復、故野口博士に関する御追憶談は洵に耳新しく、深き感興を以て拝読致し候。彼の拙作は明治十七年起稿、十八年出版のいたづらかき甚しき架空談、人物の姓名なども大方出たらめに候。あの頃故博士は九歳か十歳にておはし候ひけむ。姓名の類似は申す迄もなく偶然に候。何故医学生にあの如き放蕩者を作りいだし候ひしかと申すと、当時東京大学医学部と称し候ひし本郷の医学校は、其専門の然らしめし所か、学生中に洒落者多く銭つかひもあらきとし風耳盛んなりし故、さてこそあの如き諷刺を試み候ひしに過ぎず、もっとも借金書附の如きは多少のよりどころありしものに候。 坪内雄蔵というのは、もちろん逍遥の本名である。 この文面を見れば、小林栄がこのころ、かつて清作が遊蕩三昧にふけっていたことを承知していたことがわかる。 また坪内逍遥が、野口英世の話をきき、早速雑誌「キング」などに書きたい、と申し出ているところは、いかにも作家らしい好奇心のあり方として面白い。このあと逍遥は英世のことを、随筆くらいに書いたかもしれないが、はっきりした記録はない。小林栄としては、さすがに英世の遊蕩時代のことは語る気にはなれなかったのかもしれない。 5 清作が生まれたとき、野口家は相変わらず貧乏のどん底にあった。父の佐代助はときに翁島郵便局の下働きとして、郵便物を配達していたが、それは正式の逓送人が休んだときだけの臨時雇いで、それ以外は朝から酒と博打にあけくれていた。 一旦、奉公先から帰ってきた祖父の善之助は、つれあいのみさと折合いが悪く、また家を出て行き、残ったみさは五十前だというのに、体のあちこちが痛むといって一日中、家にぶらぶらしているだけだった。 イヌと清作、二人の乳呑児をかかえ、怠け者の母と、金を持ち出すだけの夫を持ち、シカの苦労は深まるばかりであった。 それでもシカは一人で頑張った。春から夏は他の田に働きに出て、終ると湖畔に行って小蝦をとり、それを朝早くから売り歩く。冬は近くの家の柿や芋を仕入れては、戸の口、蟹沢あたりまで売りに出て、わずかな暇があれば近くの小間使いをし、夜は更けるまで草履や縄を編む。 近所の人達はその強靭さに驚嘆し、人わざでないと噂し合った。 このころ、シカの心のよりどころは新鶴村にある中田観音であった。 シカはここへ祖母のみつに連れられてきたのが初めてだったが、それ以来、信心を深め、終生、祈ることを忘れなかった。 やがて明治十二年の年があけ、清作は数え四歳の春を迎える。 このころ、父の佐代助は月輪村に働きにでたきりで家には二人の子供と祖母のみさしかいなかった。 シカは相変わらず日中は田を耕し、夜は湖畔に出て蝦をすくい、明け方近く売りに出るという生活を続けていた。当時の野口家は、田の仕事だけでは日銭が入らず、生活していけ」なかったのである。 その日は四月の末で、春の遅猪苗代のあたりも眠くなるような陽気に包まれていた。終日、田を打ち、疲れはてたシカは日暮とともに一旦家へ戻ると、大鍋に水をいれて囲が裏の鈎にかけてから、汁に入れる菜を採るため外へ出た。 シカが家の方角から、異様な泣き声をきいたのは、それから十数分ほど経ってからだった。その声は生暖かく暮れかけた春の宵を引き裂いた。 手に持った籠を捨て、駆け戻ったシカが見たのは囲が裏のなかに手を差し込んだまま泣いている清作であった。その上には直径三十センチもある土鍋が傾き、そこから洩れた熱湯で、あたり一面、灰と煙でおおわれていた。 シカは草鞋のまま掛け上り清作の体を囲が裏から引き戻し、抱きしめた。清作の小さな左手は、灰と湯をかぶったまま、しっかりと握られている。 どうすればいのか、シカは動顛してわからなかった。火傷には酢味噌や、ジャガイモのすり身をつければいいという程度の知識はあったが、狂ったように泣く清作には、手のほどこしようがない。さすが強気なシカも皮膚の焼けた臭いのする拳を開く勇気はない。そのまま、シカは清作を抱き、頬を寄せながら、ひたすら観音経を唱えながら祈り続けた。ようやく痛みもおさまり、疲れとともに清作が泣き止んだのは、それから一時間も経ってからだった。 シカは怖る怖る、清作の左掌を覗いてみた。 瞬間、また火がついたように泣き出す。垣間見た左掌は赤く爛れ、水泡になりかけたまわりから、膿のような液が滲んでいる。シカは改めてボロ布にジャガイモのすり身をつけ、痛がる清作の手に巻きつける。 出かけるとき、運悪く母のみさは不在で、長女のイヌは外で遊んでいた。いつもそうするように、シカは藁で編んだ籠に清作いれて出かけたが、すべてに好奇心を抱きはじめた清作は、自分で籠からとび出し、火の燃えている囲が裏に近づいたのである。 シカはひたすら自分を責め、このあと二十一日間、仕事以外のときはすべて清作を抱き続けたまま不眠不休の願をかけた。一睡もせずひたすら祈り続けたため十日後からは瞼が腫れあがり、一時はものさえ見えなくなった。 丁度、軽く拳を握った形で、先が擂粉木に似ている。子供達のつける綽名は、いつもいいえて妙だが、「手ん棒」という綽名は哀しいが見事に、その感じを現わしている。 シカはあやしながら、それ以後どこへ行くときも清作を背負っていった。田で働くときは畔の籠や樹から吊るした袋に置き、雨の日は八つ足とういう竹を地面に立て、その上を筵でおおって雨風から守った。子を不具にした償いは、自らその苦しみをともにするしかないとシカは信じていた。 6 野口家の貧しさは、清作の手の不具の状態も変わらぬまま、清作は数えて八歳になった。 明治十六年四月、清作は翁島の三つ和小学校に入学した。清作が入ったころは、まだ座敷に坐り机を並べる寺小屋式のものであったが、初等科、中等科、高等科の三科に分れ、初等、中等が各々三か年、高等が四か年になっていた。 入学した年、清作は郡役場から二等乃至三等の成績優秀賞を受けているが、初等科三年、いまでいう小学校三年のときには一等賞となり、以後ずっと首席を続けている。入学したとき、本や墨を買う金もなく、シカが以前奉公したことのあるニ瓶家に、代吉という同級生がいることから、その好意で買い整えてもらったが、成績は誰にも負けなかった。 だが腕白盛りの子供達は、清作に「手ん棒」という綽名をつけ、ことあるごとにからかった。初めのうちこそ逆らったが勝目はなく、そのうちそれをいわれるのが嫌さに、清作は学校に行かず、野や山で一人で時間を過して帰ってくることもあった。こんなとき、シカは生来の強気で清作を励ました。 「おめは手が不自由だから百姓はできねげんとも、頭がいいんだから、勉強で見返してやれなぁ」 何度かいわれているうちに、清作も母の気持がわかってくる。不具のハンディキャップを補うには学問しかない。清作はさらに勉強する。かくして小学校四年のときには級長になり、さらに全学年つうじて最優秀の子に与えられる「生長」になり、代用教員に指名された。これは成績優秀の子を一時的に教員代りにする制度で、教師の少い地方ではよく行なわれている。 シカは悦び、借金までして当時まだ数名の生徒しか来ていなかった洋服を買ってやり、清作はそれを着て颯爽と教室に登場した。 だがまだ小学校四年生で、人一倍小柄だった清作が大きめの洋服を着て、教壇に上がる姿はいかにも滑稽であった。教わる生徒達にしても、いままで一緒に机を並べ、手ん棒を馬鹿にしていた貧農の子が先生では気乗りがしない。彼等は背の低い清作を困らせるために教壇をはずしたり、故意に袋でおおっていた左手に当ったりして、その悪戯を防ぐために、シカが教室まで出かけて見張りしたこともあった。 ともかく、身分は生徒で、実際は先生という奇妙な状態のまま、清作は六年になり、卒業試験を受けることになった。 当時、小学校を卒業するには、その上の高等小学校の教師や視学官がきてテストをし、それに合格しなければ卒業できなかった。このとき、郡視学とともに、三つ和小学校に来たのが、猪苗代高等小学校の首席訓導であった小林栄であった。 このテストは、生徒を一人ずつ呼び出し、試験官が口頭試問をするという形式だったが、そこで、成績は優秀ながら左手を袋におさめ、常にうしろに隠している少年に会った。 これが小林と清作との初めての出会いである。 小林はこの少年に興味をもち、いろいろ家庭の事情まで尋ね、今後のことについて困ったことがあれば相談にくるようにさとした。シカは清作からこのことをきくとすぐ息子をともなって小林家を訪ねることにした。こういうところ、少年期の引っ込み思案の清作にくらべ、シカは積極的でものおじしない。この性格は後年、清作の行動にも大きな影響を与えた。 小林のところへ行ったシカは、家庭の貧しさから、火傷のこと、高等小学校へ行かせたいがお金がないことまでありのまま話した。まさに当って砕けろといった感じである。親子の情熱に感動した小林栄は猪苗代の高等小学校に進学することをすすめた。 「手が悪んだったら働がしてもてぇした収入になんねぇべ。高等小学校に通うぐれぇのぜにはてぇしたごとねぇ。是非進学させたほうがいいべぇ」 小林に励まされてシカはやる気になった。いままで優秀だとはいえ三城潟の小さな小学校でのことである。それが猪苗代の高等小学校の教師までにみとめられたのである。 「この子の勉強のためなら、おれはどんなことだってします。どうがよろしくお願えします」 シカは畳に額をすりつけ、何度もくり返した。 考えようによっては、このとき清作の手が不自由であったことが、ある意味で幸いであったともいえる。もし五体健全であったら、シカは清作を上級学校にやることは考えなかったかもしれない。 「この子は不具で、一生おれが面倒みてやんねばならんねぇ」そんな使命感がさらにシカをかりたて、清作を上級学校すすませたともいえる。へ 「不具の息子を高等小学校にやって、おシカは気が狂ったんでねぇが」土地の人達は、そういって呆れはてた。 しかし勝気なことではシカも清作も人後におちない。さらに陰口には二人とも慣れている。 明治二十二年の四月から、清作は三城潟から往復三里の道を猪苗代の高等小学校へ通いはじめた。 ここでも清作はたちまち頭角を現わし、級の首席におどり出る。 自分の勉学のため、母と姉が血みどろになって働いてくれている。自分から学問をとれば手ん棒という綽名しか残らない、そんな切羽詰った気持が、清作をさらに勉強にかりたてたともいえる。 こんなとき手が不自由とはいえ、十四、五歳にもなる若者を高等小学校に通わせていることは、世間からみるとずいぶん贅沢に見えた。その齢になれば、みな野良で働いているのに、借金に追われている家の息子が高等小学校に行っているとは、なんと身の程わきまえぬ傲慢なことか。シカはそんな世間の眼が痛いほどわかった。だが、といって、ここまできた清作を百姓に戻してはいままでの努力が無意味になる。 迷ったイネは、長女のイヌに婿養子を迎え、その男に野口家を相続してもらうことを考えた。 だがイヌは、この話を受けつけず、さらにすすめられると家を出て、近くの庄屋に女中奉公に入ってしまった。 イヌに断わられたシカは、そのうち清作に嫁をもらうことを考えた。 だが清作もこの話は受けることができなかった。 「だめがなぁ」 シカは万策尽きてつぶやいた。こうなっては世間の眼をやわらげるため、学校を止めさせなければならないかもしれない。 「おっ母、おれ」、できるだけ働くから、このまま学校さ行がしてくれ」 清作が坊主頭をそっと下げた。 「いいがら、おっ母はまだ頑張れっから」 シカはさらに自分をふるい起す。この子のため、という心の支えさえあれば、どこまでも強くなれる。シカはある意味でかつての自己犠牲に殉じた典型的な日本の母であった。 7 母親シカの強引な説得にもかかわらず、結局、清作はおとめの結婚を承諾しなかった。それは自分の学業を続けるため、母が考え出した苦肉の策だとは知りながら、どうしても受ける気にはなれない。だが実際には、その一か月あとから、おとめは清作の家にきて同居をはじめた。 清作の甥にあたる野口栄の『叔父野口英世』の回想記では、清作が十七歳、おとめが十九歳のとき、二人は結婚したと、はっきり書かれている。清作の結婚は、渡米したのち、メリー・ダアジス嬢との結婚がはじめてであり、日本の国籍にも、他に結婚したという記録は残っていない。 このやり方に清作はもちろん不満であった。「やんだってゆったんでねぇが」と母に詰問した。 だがすべて、自分の学業を続けるための非常手段だときかされては、それ以上非難するわけにもいかなかった。 おとめは甲斐甲斐しい女だった。朝早くから起きて清作の弁当をつくり、日中は田に出てシカと遅くまで働いたが、清作はほとんど言葉もかけなかったし、同衾することもなかった。一年ほどいたが、おとめは清作が自分に気のないのを知って、再び実家に戻った。正式に入籍こそしていなかったが、婚家を追われたに等しい。 いずれにせよ、おとめのことは清作にとっては、青春の苦い思い出の一齣にすぎなかったが、おとめにとっては後世、偉人となった男と接した忘れられない思い出となった。 8 結婚騒動迄起しながら、清作は一日も休まず猪苗代の高等小学校に通った。家から学校まで一里半の距離は雪がくると難儀で、冬の間、近郷から通う生徒の大半は猪苗代町に下宿したが、清作は黙々と雪道を歩き続けた。 小学校から高等小学校にかけて、清作は多くの級友やその親達から、さまざまな施しを受けている。なかでも八子弥寿平、秋山義次、六角譲、小林才治らには大変な世話になっている。とくに八子弥寿平は、父が猪苗代町の富豪であり、人の好いぼんぼんであったところから、幾度となく清作に無心をされた。 弥寿平としては、清作の頭のよさに敬服していたし、勉強を教えてもらったり、写生画などを代筆してもらっている弱みもあって、頼まれると無下に断われない。ずるずるということをきいているうちに、ノート、教科書から外套まで、みなとられてしまう。 なかでも高等小学校卒業間近のころに無心された漢文の教科書は大物であった。 「みんなが持ってんのに一人持ってねぇんだ。本さえあれば首席になれんだげんとも、なんとか工面してもらえねぇがなぁ」 この台詞を清作はいまにも涙を出さんばかりの哀れっぽい口調でいう。清作の欲しかった教科書は標註漢文教科書全四巻で、合わせて三円という高価なものであった。当時の白米一升が十二、三銭であったから、大変な額である。 弥寿平は良家育ちだけあっておっとりしたところがあり、頼まれると嫌とはいえない。その気弱な性格を見込んで頼みこむ。恵み、与えられる者の差はあっても、実際は蛇に見込まれた蛙同然であった。 このころから、清作はすでに人間はどういう点に弱く、どういう頼み方をするときてくれるかといった、処世術を身につけていた。 小さいときから他人の恩恵を受け、それで生きてこなければならなかった男の身につけた習性といえばそれまでだが、清作の面白いところは、そうした哀願をすることに恥じないところだった。恥じるどころか、むしろ、「俺は優秀なのだからもらうのが当然だ」と開きなおっている。表面こそ哀れっぽい仕草や声を出すが、内心はむしろ相手を軽蔑している。実際それだけの自信があったからこそ、臆面もなく無心をくり返せたともいえる。 「わがった。なんとか工面してみっから、待っててくれ」 気の弱い弥寿平はそう答えてみたものの、三円という金はいかにも大きすぎる。自分で働いていない身分としては、到底揃えられる額ではない。 迷った末、弥寿平は金箱から盗もうとして父に見付かり、問い詰められて清作に頼まれたことを白状した。 弥寿平の父の留四郎という人は、商人であったが、なかなか学問にも熱心な人だった。日頃から弥寿平や人の噂から、清作の優秀さをきいていただけに、清作に三円与えることを承認した。 翌日の午後、学校の帰りに、清作は弥寿平に連れられて留四郎に挨拶に行った。丁重に今回の好意への礼をいい、頭を下げる。そのあと次のような借用証を父親の前ですらすらと書いた。
一金参円也 漢文教科書四冊代 無心だけならともかく、こういう大袈裟なことをするところが清作の清作らしいところだが、この裏には借用証とはいえ漢字ですらすら書いて留四郎の歓心をかっておこうという魂胆もあった。これがまだ十七歳の少年がするのだから、誰でも驚く。 留四郎は、改めて清作の優秀さに感心し、「おめほどの優れた少年は会津一帯を探してもいねぇ」と賞めちぎった。そのとばちりを受けて、弥寿平はかえって小言をくらうという有様だった。 「これで救われました、この御恩は一生忘れません」 清作は両手を畳につき、深々と頭を下げる。留四郎には左手の汚れた布につつまれた手先が一層いたいたしくうつる。 だが清作はこの金を返さなかった。借用証にははっきり、六月廿五日まで、と期限を書いたが、期日がきても平然としていた。清作ははじめから、留四郎も弥寿平も借金の返済を迫るような人でないことを見抜いていた。彼等は自分に施しを与えただけで満足するタイプの人である。清作はそれを知っていたからこそ、借用証まで書いたともいえる。 それにしてもこの父子から、清作が無心した金品は厖大な額にのぼる。 このあと金から日用品、衣類まで、さらには清作が東京に出たあと、五円、十円と無心を重ね、総額はいくらになるか、千円は軽くこすともいわれている。いまの金でいえば、三千万円にでも相当しようか。 清作のまわりの者は、大なり小なり、金の面で彼の被害を受けているが、八子父子ほど大きな被害を受けた人はいない。まさに、みしり獲られた、という表現が当っている。 「この人からとれる」と思うと清作は徹底的に引き出した。すこには済まなさより、頭の優秀な者に金が与えられるのは当然だ、という自信に満ちた論理があった。富める者からは奪うべきだ、という階級論理ではなく、より優れた者が金をもらうのは当然、という論理であるところが変ったところである。 9 こうした土地の人々の援助は、清作が十七歳で手術を受けたとき、さらに大がかりになった。 清作は以前から、棒のようになつた手を、なんとか物を掴んだり、持てるようにだけでもなりたいと願っていた。 はたして手術をして治るものか、四歳とのときに火傷をして、すでに十三年の歳月が経っている。指が曲って掌面についたまま、放置されていたので、人差し指も薬指も、幼児のままほとんど成長していない。わずかに癒着の軽かった拇指だけが、いくらか大きくなっているだけだった。 さすがに高等小学校にきてからは、「手ん棒」と、罵る者はいなかったが、みなが同情の眼で見ていることはあきらかだった。これまで、清作はその同情の眼を逆用して、金や品物を無心していた。 「頭は優秀だけど貧しく不具」といういいわけが、施す者達に一種の快感と満足感を与えるらしい。清作が人々に媚び、施しを堂々と受けたのには、自分は優れているという自負とともに、施すことで彼等も楽しんでいるはずだという醒めた目もあった。「不具もつかいようだ」と、清作は秘かに思っていた。だがどういういいわけをつけたところで、不具は不具でしかない。それでどのように人々の同情をかい、金品を得たところで、不具という事実は変らない。 誰かいい医師にみてもらえば、治るのではないか。そう思うがもちろん知っている医師などいないし、これまで受けてきた屈辱と苦悩のすべてを吐き出し、みなの同情を引きつける。それで援助してくれる人を待つ。 すでに清作の不具は誰もが知っていた。みなが知って憐れんでいるのだからこれ以上、隠すのは無意味である。むしろそれを堂々と公表して、さらに圧倒的な同情をかちとる。いままでの対個人でなく、公の場で、清作は開きなおることにした。心を決めて書いただけに、この作文は見事な出来ばえであった。大体、清作は名文家で、手紙に書かれた文章などは、いまからみるとやや大袈裟で、美文調にすぎるが、緩急ところをえて、リズム感に溢れている。文字も達筆で澱むところがない。 担当の小林栄は、一読してこの文章に感動した。引きしまった文章で、しかも正直に心の奥底までさらけ出している。少年の単なる悲しみでだけでなく、人間が心に抱いている卑劣さや、弱さまで臆面なく書かれている。小林栄はこれを、自分だけの胸に秘めるのは惜しいと思い、職員たちに廻し、さらに教室で生徒全員に読んできかせた。 いままで、不具ではあるが優秀で自分達とは少し違う人間だと思いこんでいた生徒達はこの作文をきかされて感動した。日頃は少し生意気な清作が、こんな悲しみをもっていたかと思うと、なにか急に親しみを覚える。 小林栄はこの生徒達の反応をみて、清作の手を治すために、みんなでお金を集めることを提案した。 これにまっ先に応じたのが、例の八子弥寿平以下、秋田義次、松江源次等である。彼等が率先して金を出し、これにつられて級友全員が各自十銭宛募金することになった。さらに足りないところは教職員が出し、ようやく十円の金が集まった。一人の生徒のために、これだけの金が集まったのは、猪苗代の学校はじまって以来のことだった。清作は教壇に上り、お礼をいいながら、悪びれるところはなかった。清作としては、まさに思いどおりの結果になっただけだった。 一応、十円という金が集まったところで、小林は医者探しをはじめた。 何人かの人の意見をきいた結果、最近アメリカから帰国し、若松市に開業したばかりの渡部鼎氏に白羽の矢を立てた。手術してもらう医師もきまって、清作はシカに付き添われて若松に行った。 渡部医師は清作の手を診察して、「完全にもとのままとはいえないが、簡単なものを掴める程度までには治るだろう」と答えた。 もちろん清作は喜んだが、それ以上に、シカの喜びようは大変だった。早速日頃信仰する中田観音の方向を向いて手を合わせた。 十月半ば、念願かなって清作は渡部医師の手術を受けた。まず手全体に麻酔剤を注射し、痛みを消したところで、折れ曲がった指を一本一本剥がしていく。癒着の比較的軽い拇指は容易に剥げるが、人差し指と中指、薬指はなかなか離れない。十三年間放置されていたあいだに、指と掌のあいだに新しい血管ができ、少しメスをすすめてだけで、血が溢れ出た。 約一時間ほどで、指のほとんどは剝がれたが、掌面は皮下組織が露出し、皮膚はなかった。医師はその部分に軟膏を塗ってガーゼを当て、さらに指を伸ばした位置で副木で固定した。 渡部医師は植皮術をしなかった。当時の医学テベルとしてはある程度止むをえないことでもあるが、このとき植皮をしておけば、清作の手はかなりよくなっていたに違いない。少なくとも、指の関節や腱は健在だったのだから、牛乳ビン程度のものまで持ったり、握れるようになったはずである。 しかし植皮をしなかったため、折角の手術もあまり意味のないものにしてしまった。 のちに清作は東京に出てから、もう一度、この手術のやり直しを受けているが、その結果もあんまりかんばしいものではなかった。 ともかく、手術は終り、清作はそのまま入院することになった。 当時は健康保険はなく、すべて実費である。渡部医院の一日の入院料は一円二十銭だった。当時若松における一流旅館の宿泊代が二十五銭だったというのだからかなり高額である。 十円のうちから手術料や薬品代を払い、一円二十銭の入院料を払うと、何日もいられない。結局、弥寿平や秋山等、裕福な若者からさらに募金をつのって入院を続けた。こうして十日間入院して、清作は三城潟へ戻ってきた。 この手術を受けた翌年、清作が高等小学校最後の年に、猪苗代高等小学校の石川栄司校長が退職し、それにともなって、首席訓導だった小林栄が近くの千里小学校に転任することになった。それをきいた清作は、学校の弁論会の連中に働きかけ、激しい留任運動をはじめた。 明治二十六年四月、数え年十四歳のときから十八歳の春まで、四年間続いた小林栄と清作のつながりはここで絶たれ、以後清作は主に手紙の上で、小林と交信を続けることになる。
第二章 会津若松 P.81
1 猪苗代の高等小学校を卒業したもののそのあとの身のふり方について、清作にはっきりした目途はなかった。その点については母のシカも同様であった。 いままでは、まわりの人達に馬鹿にされたくないという一心で勉学に励んできたが、いかに成績優秀とはいえ、高等小学校を卒えただけでは、せいぜい村の小学校の代用教員になるか、手紙など代筆して小銭を稼ぐ程度である。それも学校に欠員がなければ、実家の農業に戻るより仕方がない。いまさら農業に戻るなら、なんのために四年間、世間の冷笑をかいながら高等小学校に通ったかわからない。 迷った清作とシカは、再び千里小学校の校長になった小林栄を訪れて相談した。 「たしかにこのまんまで勉学を止めるんは惜しいし、中途半端だ」 小林も同感であったが、といってどうしたものか、即座に妙案は浮かばない。野口家にお金さえあれば、若松や東京へ進学させることは簡単だが、一文なしで上級にすすもうというのだから難しい。 「おめえの優れた頭をいかすっと、教師か役人が、まあ他に医師っちゅうもんがあっけども」 小林がいうと、突然、清作は体をのり出した。 「俺、医者になります」 「なに」 小林とシカは呆気にとられて清作を見た。当時の貧乏百姓の息子としては、教師か役人にでもなれたら大変な出世で、それだけで、いずれは村の有力者になることが保証されていた。それがさらに難しい医者になろうというのである。 「おめ、本気か?」 「俺は絶対医者になりてょ。俺のような体の悪い人を治してやりてぇんです」 それはもっともな理屈だが、一介の百姓がはたして医師などになれるものか。 ご維新までは、医師になりたい者は、まずしかるべき医者の門下生になり、そこで修練を積んで認められればよかった。あとは独立して、名声さえ博せば、いくらでも患者がきた。だが明治政府によって新しい学制が敷かれてからは、すべての官立の医学校を卒えた者か、医師国家試験の難関を突破した者にしか医師免許証は与えられなくなっていた。 野口家の貧しさでは、もちろん医科大学には行けない。それでもあえて医者になるとすると、私学塾ででも勉強して開業医試験を受けるより途はない。 だがこの開業医試験が大変な難関であった。 「なかなか普通のことでは、開業医試験には合格しねぇど、若松がらだって、まだ合格した者はいねぇ」 「ほんでも、俺やってみます」 どうせここまできた以上清作はなまじっかなものになる気はなかった。みんなが「あつ」と驚く、凄いことをしたい。その裏には清作の強い虚栄心もあったし、不具でおさえつけられたきた日頃の鬱憤もあった。 「きっと頑張ってみっから、やらせてください」 そうはいわれても、いざ具体的な方法となると小林もわからなかった。これまで何人もの生徒が進学について相談にはきたが、医者になりたいというのは清作が初めてだった。 「どうか、清作の望みをかなえさせてやってくだせぇ」 驚きから醒めてシカも真剣に頼み込む。考えた末、小林はひとまず、清作の手術をしてくれた若松の渡部医師のところへ行くことをすすめた。 「試験を受けるっていっても、まず医学の基礎知識を身につけねばなんねぇ。その第一歩として渡部先生のところに行くのがいいべぇ。あの先生なら洋行帰りで新知識は豊富だし、幸いおめえのごども手術をしてご存じだべぇ。一度若松まで行ったうえで直接お会いして、門弟にくわえていただくように頼んでみたらどうだ。もし門弟が駄目なら、掃除夫でも給仕でもいい、とにかくお願いすんのだ」 たしかに小林のいうとおり、いまの清作が医師になる道といえば、渡部医師にすがるよりなさそうであった。 「俺、やってみます」
翌日、清作はシカがつくってくれた握り飯を背に、若松へ向かった。二城潟から若松まで五里半(二十三キロ)、朝の早いうちに発って、若松へ着いたのは正午を少し過ぎていた。清作はそのまま魚町の渡部医師が経営している会陽医院」を訪れた。 応対に出た玄関子は、清作を見ると途端に胡散臭そうな顔をした。みすぼらしい少年とも青年ともつかぬ男が、手ぶらで立っていたからである。 「私は一年前、渡部先生にこの左手を手術していただいて十日間入院していた野口清作どいうものです。院長先生にお願えしてぇごとがあって、二城潟から参ったものですが、なんとかお取次ぎを願えないでしょうが」 「お願ぇしてぇ用件というのは?」 「先生にお会いしたうえで、直接申し上げてぇのです」 「少し待ってろ」 清作は玄関の先の待合室で苛立ちながら待っていると、ようやく先程の男が現われて視察室に案内した。部屋に入ると、渡部院長は正面の肘掛椅子に坐って、カルテらしいものを読んでいた。 「なんの用件かね」 渡部院長の声はいかめしい外見に似ずやさしかった。 清作は一年前に手術を受けて非常に感謝していること、それ以来、自分も医者になり、不幸な人々を助けることを夢みてきたこと、それには掃除夫でも給仕でもかまわない、先生お側について教わりたい、といったことを一気に喋った。渡部院長は、この熱心に喋り続ける男を、黙って見ていた。そして清作がいい終ると待っていたようにうなずくと、 「おめえのいうことはわかったが、いま家では書生はあまってるげんとも特別に置いてやろう」 「ありがとうございます」 「委細はいま案内してきた根本にいっておぐから、あいつからいろいろきいでくれ」 それだけいうと、渡部院長はまたカルテを読みはじめた。 2 明治二十六年五月、清作はこうして会陽医院に住みこむことになった。ニ城潟を出たとき、シカは清作のために木綿縞の袷と兵児帯をつくり、親友の秋山義次は木綿の袴をプレゼントした。 このころ会陽医院には長谷沼票策という筆頭書生の他、五人ほどの書生が住み込んで渡部医師の代理や、医院の雑用をやっていた。そこに清作が一人くわわることになった。 だがこの半年後に、もう一人の少年が会陽医院に飛び込んでくる。名は吉田喜一郎といい、若松に近い喜多方町の出身である。 この吉田少年は清作のような貧農の息子と違い、中級の農家で、父親ともども入門を依頼にきた。しかも衣類、小遣いの他、一年に米四俵の食費持ちという条件であった。 渡部院長は、清作とこの吉田少年が、書生達のなかでもきわ立って優秀であることをすぐ見抜いた。 二人は互いに意識しながら、深夜の二時、三時まで勉強を続けた。 二人とも俊才とはいえ、吉田少年がやや天才肌なのに対し、清作はむしろ努力型だった。才気もさることながら、清作の特徴はむしろねばりで、そのねばりは、母のシカから受けついだ天性の忍耐力と、手ん棒と呼ばれた屈辱から成っていたともいえる。
この若松時代に、清作は同じ医師の和崎義路と新横町の和田遷吉氏から英語を学び、一年でカーライル伝からクライブ伝までマスターした。またドイツ語を、同じ若松在住の文学士、佐竹元二氏につき、のちにフランス語を三之町の天主協会のフアヴィ、マリオン、デフラタの三氏に学んだ。さらには会陽医院の倉庫に、大量の漢書が眠っているのを見付け、これを片っぱしから読破した。 このころ、たまたま会津地方に回帰熱が流行し、渡部医院長はドイツから千二百倍まで見える顕微鏡を購入した。当時の値段で、百二十円というのだから、相当の高額である。渡部院長はこれで、回帰熱患者から採取した血清を調べ、その病原菌を浮かび上らせた。 「いいが、よく見ておくんだぞ、これがかのドイツのオーペルマイヤ―が発見した、回帰熱の病原菌であるスピロへーターだ」 医学書生達は先を争ってこれを見る。そのとき、清作は待っている書生達を尻目に、悠々と人の倍以上も見続けた。たまりかねた長谷沼票策が、「おい、ノグ、おめ不具のくせに、いい加減にあげねぇが」と怒鳴った。 このときから長谷沼との関係は、ますます険悪なものになった。
明治二十七年、日清戦争が始まると共に、衆院議員に当選していた渡部鼎は、三等軍医として招集されることになった。 渡部は留守中の世帯を縮小するため、清作や長谷沼など一部を残し、多くの書生に暇を出し、この機会に、吉田喜一郎も若松の名医斎藤幸源の門に移ることになった。この整理が片付き、いよいよ出発となったとき、渡部は残った書生や職員全員を集め、今後、医院の用務から会計まで、一切を清作に任せることを告げた。 大体、会陽医院には本宅側と病院側という二つの勢力があって、ことあるごとに、いがみあっていた。本宅側というのは本妻を中心とする一派であり、病院側は、院長の愛妾を中心とする側である。これに長谷沼等古手書生達の反目が加わる。学問はともかく人間の機微にうとかった清作は、単純に正夫人に報いるのが筋と、自然に本宅側に肩入れした。だがこのやり方は、たちまち病院側や長谷沼達の反撥を招き、医院は統一のとれぬまま誤解と中傷が渦巻いた。 たまりかねた清作は、恩師の小林栄に手紙を出し、留守責任の地位を辞職することを訴えたが、小林はこれに強く反対した。ととえ困難とはいえ、渡部先生が抜擢くださった恩誼を思い、出来るかぎりの努力をせよ、という理由からである。 この励ましで、清作は再びやる気を起して、勢力争いはともかく、自分でできるだけのことをやってみよう。世間のつまらさとはいえ、この一年は、学問しか知らなかった清作が、人間の厳しさを知った、貴重な一年であったともいえよう。 3 このころ、清作はよく、会陽医院の前の、福西という醤油問屋に行って、東京からくる読売新聞を読んでいた。当時、新聞をとっている家は少なく、会陽医院には東京国民新聞しかきていなかった。 たまたま、その日、表の床几で新聞を見ていると往来を行く女学生が目に止まった。おさげの髪に紫の袴で、右手にそのころ流行りだした皮の鞄を持っている。まだ十五、六か、ほっそりした横顔は、いかにも良家の子女といった品格があった。 まことに一目惚れであったが、もちろんその女学生の名前も住所もわからない。 そのまま二か月が過ぎた秋に、清作が本宅で夫人と話をしていると、たまたま、院長の妹に見送られて帰る女性がその女学生であった。 院長の妹に、その女学生の名をたずねた。 「あの方は会津女学校に通っていて、いまは三之町で、お母さまと二人で暮らしているけど、もとは会津藩の山内家の直系の娘さんです。戦争でこんなことになったけど、ご自分で家を再興することを考えているわ」 どうやら清作とは段違いの名門らしい。だが、清作はそんなことではあきらめない。 その日部屋へ戻ると、清作は早速、ヨネ子に宛てた手紙を書いた。封書の表には、「三ノ町、山内ヨネ子様」とし、差出人は「ヨネ子の親友マチより」と偽名をつかった。 この手紙の冒頭は、<勿驚、乞ふ一片の親書発して茲に至るを、誰か怪しまむ、一縷の情……>と、いかにも漢文に熟達していた清作らしい美文調だが、これに仮名もふらず、彼一流の達筆で書かれてはヨネならずとも戸惑うに違いない。 とにかく、女学生のヨネ子には難しすぎた。しかも最後に、「S・N生」としか書かれていないので、差出人はマチ子ではない。完全な悪戯だと考えた。ヨネ子はこれを母に渡し、母の千代はこれを会津女学校のヨネの担任に渡した。 学校側でも放っておけず、S・Nというイニシァルや筆蹟から本格的に差出人を探した。その結果、半月もせず、犯人は会陽医院の野口清作であることがわかった。 清作なら貧しい農家の出とはいえ、学識もあり、会陽医院をあずかる人物である。女学校の教師といえども簡単に叱るわけにもいかない。担任の教師は、その手紙を一括して天主教会の牧師に渡し、その牧師から清作に訓戒してもらうように頼んだ。 「おめは一人前の立派な男なんだから、こんな悪戯はしねぇように」 牧師が清作を呼んで訓したが、手紙の内容は悪戯というより、交際をしたい、という真面目なものであった。いまなら、学校から教会まで、大騒ぎするほどのことではないが、当時は男が女に付け文すること自体が事件であった。 「わだしは悪いごとなどしたとは思いません」 「んでもこのやり方は異様です。とにがく向うでは交際する気はないようです」 こんなわけで、清作の真情は理解されなかった。ただ清作が好意を抱いていることだけは、牧師からヨネ子母子に伝えられたが、結局、なんの返事ももらえられなかった。 明治二十八年の末、日清戦争は終結し、翌年の春、渡部院長は無事会津に戻ってきた。出かけてから約二年ぶりの帰郷である。 清作は早速、この間の病院行事から家事の一切を報告し、さらに出費の一銭にいたるまでを記録した「戦役中会計明細表」なるものを提出した。しかもそのすべてを英文で書きあげた。 渡部院長はは改めて清作の几帳面さと綿密さに驚き、感謝した。 この渡部院長が帰郷した三か月後の夏、彼の友人の歯科医である血脇守之助が若松にやってきた。 この血脇守之助は当時、東京の芝伊皿子坂にある高山歯科医学院の幹事をしていたが、渡部院長に招かれて、会津地方の歯科夏期出張診療にきたのである。このころ会津地方に正式の歯科医はなく、連日患者が殺到した。血脇守之助は日中はこれらの患者の治療に専念し、夜になると、渡部院長の許を訪れ雑談していた。外科と歯科の違いはあったが、二人とも旧制の医療体系を批判し、新しい医療体系の確立を求めるという点で意気投合していた。 たまたまこの血脇守之助が、会陽医院の薬局で深夜まで勉強している清作に目をとめた。 いつも勉強している感心な男だと思って、なに気なく覗くと、原書で病理学の本を読んでいる。こんな田舎に、難解な原書を読む書生がいるものかと、守之助は好奇心を起して清作に話しかけた。そこでよくきくと、町の牧師や中学の教師について英語とフランス語とドイツ語を学んで、いまではほとんど辞書もなしに読めるという。しかも基礎医学に関する知識も深い。 「もし、君が東京に出て勉強するようなことがあれば、自分も多少力になれるかもしれない、来たら寄ってくれ」 そういって清作に名刺を渡した。清作は本能的に、誰が自分の利益になるかを見抜く才能に優れていた。いまも守之助の顔をみて、この人は自分にとって大切な、近付いて損はない人だと感じた。 清作は、自分の手が不自由であること、家が貧しく、書生になって勉強しているが、いずれ東京に出て開業医試験を受けたいことを告げた。守之助は、清作のちぢんだ手を見て、一層同情をそそられた。 不具は間違いなく、ハンディキャップではあったが、一面、人々に強い印象を与えるという点では好都合でもあった。実際、清作に会ったほとんどの人が、なにかこの男にしてやらねばならないような気持に誘われたがそれは天性の話し上手や、媚びの的確さにもよるが、それも左手の不具ということがなかったら、成立しなかったかもしれない。 ともかく、この夏の血脇守之助との邂逅が、小林栄、渡部鼎に次ぐ、第三の重要な人物を知る発端となった。
第三章 芝伊皿子 P.96
1 清作が故郷の会津を捨てて、東京進学の途についたのは、二十一歳の春である。 この上京にあたって、清作はまず手紙で小林栄の意見を求めた。 自分は若松の渡部院生の門に入ってすでに四年になる。この間、自分なりに精一杯、勉学に努めてきたが、おかげで医術開業前期試験にだけは合格できそうな気がする。渡部先生にはいろいろお世話になったが、医師になるには、東京に出て、さらに研鑽を積むよりはない。先生に充分のご恩返しもできず、ここで東京に行くのは心苦しいが、医師試験に合格することが、渡部先生へのご恩返しにもなると思うので上京したいが、どうだろうか。手紙の趣旨は以上のようなものである。 小林からは間もなく、賛成だが、あくまで渡部院長と円満に話し合って出立するべきである、といってきた。そこで清作は直接、渡部院長に口頭で申し出た。このころ渡部は議員稼業に熱中し、病院の業務をほとんど清作にまかせていたので難色を示すかと思ったが、意外に簡単に納得した。 「たしかに、おめのいうどおりこれ以上ここにいても仕方がね。あとのごどはどうにかなるから、思い切って東京に出たらいいだろう」若くして自らも開業試験に合格しているだけに、こういうところはものわかりがよかった。さらに渡部は「東京は人だけ沢山いるが、広くて心もどねぇ。少ないがこれを持ってげ」といって即座に十円を出し、さらに血脇守之助宛ての紹介状まで書いてくれた。もっとも紹介状のほうは、清作が頼んだのだが、渡部はいやな顔をせずその場で書いてくれた。渡部は清作のエゴイスティックな性格を充分知りながら、そこにむしろ、若い逞しさを感じてもいたのである。 小林栄、渡部鼎と、二人の有力なスポンサーの了解をえた清作は早速上京の準備にかかった。 まず三城潟の母に知らせ、それから病院の職員、近くの知人、はては通ってくる患者にまで、いちいち報告して別れをつげた。そして若松を発つときには、わざわざ山内家にまで行き、ヨネ子の母に「今度、渡部医院を辞め、東京で本格的な医師の修業をするごどにしました」と挨拶をした。 このころ、山内ヨネ子も女学校を卒え、女医になるべく上京する予定だときいたので、清作は東京での住所でもきこうという魂胆もあったが、ヨネ子は不在で逢えず、母親はただ「頑張って下さい」といっただけだった。 若松を引き払い、一旦三城潟に戻った清作は、ここでも向かいの村長の仁瓶家から、小林栄宅、さらに近隣の各家から昔友達、果ては通りかかる村人にまで挨拶をし、上京すること告げた。 これまで近所の者には目もくれない清作が、今度は自分のほうから話しかける。人々は、東京に行くともなるとあれほど嬉しいものかとあきれたが、清作の愛想のよさは上京の喜びからだけではない。みなに知らせ、挨拶をしながら、あわよくば餞別をせしめようという打算もあった。 実際、清作はこの挨拶まわりでかなりの金を集めた。とくにこれまで、助言はするが経済の援助はほとんどしなかった小林栄までが、今回は思いきりよく大枚十円を餞別に呉れた。 「ご恩になった先生から、こんな大金をもらえねぇです」 「お金はあるにこしたことごどねぇ。とっておげ」 そういわれるのを待って、清作は申し訳なそうに頂戴する。これで辛抱すれば一か月は食べていける。上京後は一応、渡部院長が毎月十円ずつ送金してくれることになってはいたが、いつまで続くものか当てにならない。清作はさらに旧友や、隣近所の人々から二円、三円を集め、約四十円近い金を持って、勇躍故郷を旅立った。 このとき、清作が書いた「志を得ざれば、再びこの地を踏まず」という文字は現在も猪苗代湖畔の生家の茶の間の柱に残っている。まさに悲愴な決意だが、当時の青年はこの種の大層な言葉を好んだ。その意味では格別、新鮮というわけではないが、この言葉は偽らざる清作の本心でもあった。 だが、清作が医者になるために上京するのだときくと、村人達の多くは、裏で、「野口の息子がお医者になったら、お天道さまァ東の川桁山に沈んで、西の愛宕山から出っぺ」といって笑った。笑わぬ者も、その意欲には感心しながら、誰一人として本当に医者になれるとは思っていなかった。 もちろん清作は村人達が笑っているのは知っていた。たとえ餞別は呉れても、不具の身で無理するな、といった憐みの目で見ている。わずかに成功を信じているのは、母のシカと渡部院長だけで、小林栄すら、はたしてなれるものかかなり危ぶんでいた。だが清作にはそれなりの成算があった。少なくとも前期の筆記試験だけは、問題集などを見ても、まず合格できそうな気がする。 いよいよ出立の日、母のシカは戸口に立ち、一旦は見送ったが、そのままあとを追って清作と一緒に歩き出した。このころ磐越西線はまだ開通せず、東北本線に出るには本宮駅まで、九里の山道を歩かねばならなかった。 「おっ母、もういいてば」 清作は何度もそういっては母を帰そうとするが、荷物運びで鍛えた健脚のシカは止まろうとしない。南烏帽子を越え、長瀬川の川岸までにきたところで、シカはようやくあきらめた。 「んじゃ気いつけで、体だけは大切にしろな」 「おっ母もな」 貧しくはあったが、清作は母の愛だけは充分すぎるほど受けていた。
2 明治二十九年九月、清作が上京してまっ先に落ち着いたのは、本郷四丁目の大成館という下宿である。 清作はひとまずこの下宿の一室を借り、直ちに受験勉強にとりかかった。 当時の医術関係試験は前期と後期に分かれ、前期は物理学、化学、解剖学、生理学など基礎科目の筆記試験で、後期は外科学、内科学、薬物学、眼科学、産科学、臨床実験など、いわゆる臨床科目が中心になっていた。普通、かなり頭のよい男が真面目に勉強したとして、前期に三年、後期に七年はかかるといわれていた。 上京して一か月経った十月の初め、清作はまずこの前期試験に挑戦した。 清作はあらかじめ、この筆記試験には自信があったが、思っていたとおり一発で合格した。 まず、最初の関門を突破したわけだが、難関は後期試験であった。前期はあらかじめ応募者をふるいにかける、いわば荒選びの作業であった。こうなったら是が非でも後期試験に合格しなければならない。前期だけでは医者の資格はもらえず、結局無意味になる。 だが後期試験に合格するためには、どこか医学校に通って臨床を覚えなければならなかった。 当時、これら試験だけで開業医の資格をとろうとした青年のため、門戸を開いていたのは済生学舎という私学塾であった。この塾は明治の医師であり、論客でもあった長谷川泰が創立した私立医学塾で、いまの湯島四丁目、丁度湯島會舘のある場所にあった。 後期試験を目指すとなると、清作もやはりこの済生学舎に行くのが手っとり早い。風評よからぬとはいえ、後期試験に必要な臨床を、ある程度マスターできるのは、ここしかなかった。 前期試験が終ると、清作はすぐにもこの学校に入学したかったが、九月に上京してきて、十月を終えた時点で、清作はすでに無一文になっていた。 渡部院長や郷里の誰それに無心の手紙を書こうと思うが、こう上京間もなくでは、さすがにいい出しにくい。 考えた末、清作は血脇守之助のところへ行くことにした。 このころ血脇守之助は水道橋の近くの三崎町の自宅から、芝伊皿子坂上の高山歯科医学院に通っていた。清作が訪れたのは、この高山歯科医学院のほうである。 取次にでてきた玄関子は、風采のあがらぬ清作に怪訝な顔をしたが、渡部医師の紹介状もあるので、守之助に取り継いだ。この歯科医学院で守之助は教鞭をとりながら、学校を統括する事務長のような仕事もやっていたのである。 享年の夏、渡部医院で会ってから、ほぼ一年ぶりの再会であったが、守之助は清作を覚えていた。大体、清作は人を訪ねていって、忘れられたことはないが、それは清作の非凡さもさることながら、左手の不良という身体的な特徴がおおいに役だってもいた。 「それで、いまはなにをしているんだね」 守之助の問いに、清作は前期試験に受かったこと、これから後期試験に向けて、済生学舎で勉学したいことなどを告げた。 「なるほど、それはいい。もう少しだから頑張り給え」 守之助は自分の経験から後期試験が正念場であることはよくわかる。このとき、守之助は二十七歳で清作とわずか六歳しか違わなかったが、貫禄は圧倒的に上だった。 清作は例の哀れっぽい口調で、金の無心にきたことを告げた。 「もし学校で使っていただければ、人力俥夫でもいたしますが、なんとかお取り計らい願えないでしょうが」 清作のようなルーズな男は、生活費をもらうより、どこかに住み込んで、食事を保証してもらったほうが安全であった。 「弱ったな」 守之助はなんとかしてやりたいが、ここは高山院長の家で、守之助の自由にはならない。彼自身も食費の他月給四円で雇われている身であった。 「では一応、院長先生におききしてくるから、待っていてくれ」 守之助が清作のことを告げると、高山院長は、「いま、学院ではその男が必要なのかね」と一言だけきいた。 「いえ、そういうわけでもありませんが」 「じゃあ断わりなさい」 守之助は困ってしまった。院長に内緒で住まわせるわけにはいかないが、といって会津からわざわざ出てきた男を追い返すわけにもいかない。迷った末、守之助は学院の隣りの寄宿舎に住ませることにした。 こうして清作は、隣の寄宿舎の一室にころがりこむことになる。 だがじっとしていることのできない清作は、廊下から次第に賄にまで顔をだすようになり、一か月もしないうちに、堂々と学院へも出入りするようになった。しかも学院の小使いが年老いて、休みがちなのをいいことに、始業時間の鐘を鳴らしたり、洋灯や便所の掃除までやりだした。 もちろんこれらは無償ではない。そうしたアルバイトをすることによって、いくらかの金をもらう。寄宿舎で朝夕の二食は保証されていたが、昼食と、深夜の空腹を満たすには余分の金も必要だった。 清作の優れていたところは、こんな小使いとも居候ともつかぬ状態にありながら勉強を忘れないことであった。 芝にきて二か月経った十一月の末、清作は人伝に、伊皿子町でエリザ・ケッペンというドイツ人がドイツ語を教えていることをきいた。清作はすぐその人についてドイツ語を習いたくなった。すでに若松で英、仏語をマスターしていた。主要国後で残っているのは、同時に学んだもののまだ十分ではないドイツ語だけだった。だがこの授業を受けるには、毎月一円の月謝がいる。 清作はまたまた、守之助にこの金の無心する。 さすがに守之助は図々しい奴だと思ったが、無下に断わるのも気がかりである。後年、清作には「男芸者」という綽名さえついたが、清作の頼み方には、一種、人をひきつける哀切さがあった。無心されたものが放っておけない気持に追いこまれる。妙な切迫感があった。だが守之助の四円の薄給からでは、一円といえども大金である。しかも月謝となると毎月である。 「とても無理だ」 万策つきて守之助が溜息をつくと、清作がこともなげにいった。 「先生の月給をあげでもらってはいかがでしょう」 守之助は驚いて野口を見た。たしかに給料が少なくて出せないとうのであれば、元の給料を上げれば済むことである。守之助は少ない中でのやりくりばかりを考えていた。いわれてみるとそのとおりである。 「なるほど」 守之助は改めてうなずいた。いかに食事つきとはいえ、一人前の医者が月給四円とは安すぎる。前々から、そのことに不満は抱いていたが、これも修業と思って我慢してきた。高山医院の学識を体得するためには、これくらいの不満は耐えなければならないと思いこんできた。だが労働に見合ったお金を要求するのは当然の権利でもある。守之助は勇気を出して高山院長にいってみた。 「まことに申し上げにくいことですが、医師としての体面もありますゆえ、いま少し給料を上げていただけないでしょうか」 まわりくどいいい方だったが、高山院長はすぐうなずいた。 「よし、七円にしよう」 これは予想外の収穫であった。初めは一喝の下に退けられるか、せいぜい一、二円の値上げだと思ったが、それが一挙に三円の値上げである。 「うまくいったぞ、三円上げてくれたぞ」 守之助は笑みをたたえて、清作のところへかけつけてくると、 「これも君のおかげだ。当分のあいだ二円ずつ小遣いをやろう」 というところが、守之助の人のいいところである。三円上がった以上、二円出さないと悪いと思う。 ともかくこうして清作のドイツ語勉学がはじまった。 勉強がはじまると、いままで几帳面にやっていた鐘つきも、便所掃除もほとんどやらない。 なにごとによらず一つに集中したら、他をかえりみないのが、清作の性格でもあった。 3 芝伊皿子にあった高山歯科医学院の建物は、現在はもちろん残っていない。 歯科医学院は伊皿子坂を登りきる直前に、西向に建っていたが、江戸時代、この坂は「潮見坂」と呼ばれていた。当時はこの坂上から東側を望めば、眼下に芝浦から東京湾を一望の下におさめられていたのである。 ここで英気を養う、といえばきこえはいいが、現実に清作の地位は下級小使いにすぎなかった。それも正式採用ではない。おしかけ子使いである。清作の仕事は、廊下や部屋の掃除、ランプのホヤ拭き、始業終業時間の鐘慣らし、それに使い走りといったものである。 それにエリザ・ケッペン夫人にドイツ語を習うようになってからは、勉強に熱中して、掃除から、鐘を鳴らすこまですっぽかすようになった。この皺寄せをくらった菊池という受付係は憤慨して、清作に文句をいったが、一向に改めようとしない。 清作にしてみれば、「才能もない奴が、俺の代りの下働きをするのぐらい、当たり前」という気持だったが、先輩の受付係としては我慢がならない。たまりかねて、菊池は血脇守之助に幾度となく文句をいったが、守之助はきいたふりをしてとりあわせなかった。自分の小遣いで勉強している男ではあるが、その一種異様な勉学への打ち込みに方におされて、さすがの守之助もいい出しかねたのである。 やがて明治三十年の年が明ける。この年の二月に、清作は四か月に及んだドイツ語の勉強を終えた。 「もうこれで大丈夫だ」 自ら自慢するとおり、このころになると、ドイツ語の日常会話はもちろん原書まで、ほとんど辞書なしに読めるようになっていた。大体清作は、語学について、先天的な才能があった。外国語の学習は論理ではない。いわゆる実感的なものだが、清作はこの勘をとらえるのが早かった。まず一旦は素直に復唱して覚え、言語に馴染む。それは彼の生来、身についた環境順応力の強さといわゆる会津のずーずー弁に対するコンプレックスがかえって外国語へ対する意欲になって現われたともいえる。 こうして、英独仏と、三か国語をマスターした清作は学院にあった医学書を片っ端から読みはじめた。しかし、これだけで後期開業試験に合格できるわけではない。後期にもパスするためには、やはり済生学舎に入って、臨床医学を学ばなければならない。次の後期試験は十月であったが、それまであと半年余りしかない。 清作は焦っていた。だが当然のことながら、済生学舎に入るには金がかかる。今度はいままでのように、一円とか二円の月謝では済まない。 会津を出るとき、渡部鼎は毎月十円宛送るといったが、実際には上京して、一か月で送金は途絶えていた。このころ渡部は女性関係のもつれから妹が会計を握り、彼の自由にならなくなっていたのである。 やむなく高山歯科医院でも、清作は借金の天才として名をはせることになるこの時期守之助から、学院の職員、さらには学生から小使いに至るまで、彼の被害を受けない者はいなかった。 清作は、再び守之助に借金を申し込んだ。 「十五円か……」 一言いったきり守之助はうなった。そのころ守之助の給料は七円にあがっていたが、その倍以上の金を出せというのだから難しい。そんなことができるわけはない。断わることははっきりしていたが、それではこれまで目をかけてきた好意が無駄になる。守之助が考えこんでいると、清作がにやりと笑った。 「一つ、案があるんですが、高山先生は、いつも病院は儲からない、と仰ってるわけですね」 当時」、高山医院は歯科医志望の学生を教授しながら、一方で歯科医院を経営していた。いまの医科大学と附属病院の両方を一人でやりくりしていたようなものである。高山は、この両方の長で、血脇守之助は主に、学生のほうの講義を担当していた。もともと学者肌だった高山は、学生への教授と、臨床の歯科医と、両方を兼ねる忙しさにくわえ、経営のわずらわしさに悲鳴をあげ、病院は儲からないと、頭から決め込んでいるところがあった。 「いっそのこと、先生が高山病院から病院を受けついで、自分で経営なさってはいかがでしょう」 「わたしがか?」 守之助が呆れるのに清作はけろりとして、 「高山院長は、お忙しい方だし、病院経営のような下世話なことは、性に会わねぇんだと思います。だから先生が任せて欲しいと申し出れば、許してくださると思うのです。あの病院が儲けがらねぇわけはありません。先生が専心して経営に当られたら、いまよりずっと楽になります」 「それで、どうするのだ」 「ほうしたら、先生の給料はずっと上がるでしょうし、わたしへの十五円も……」 守之助は唸った。なんという突飛なことを考えるのか。前回、小遣いを二円アップしたときも、院長に給料増額を要求せよとけしかけたが、今度は病院経営権までとってしまうというのである。それでお前も楽になるし、自分も安心して金をもらえるという理屈である。 「そんなことはいえない」 一応は首を左右に振ったが、考えてみると、これはたしかに魅力のある計画であった。守之助は高山院長の見識に敬服してはいたが、いつまでも薄給に甘んじて学生に講義するだけでは不満であった。もう少し患者に接して診療もしたい。それには清作のいうことが、一番手っとり早いかもしれない。 「そんなことはいってみても、高山先生がお許しになるわけがないからね」 「そうあきらめず、とにかく当ってみるごどです。私は大丈夫だと思います」 清作はいかにも自信あり気である。またまた年下の男にけしかけられた形で、二日夜、守之助は恐る恐る高山院長に申し出た。病院全体の経営権を譲れというのだから、いまから考えると、とてつもない話だが、当時は万事がのんびりしていた。大体、学者が病院を経営するなど邪道だと思われていた時代だから、厚かましいことは厚かましいが、ひどく失礼に当たるというわけでもなかった。 それでも、この申し出をきいた瞬間、高山院長は、 「君は気でも狂ったのか」といった。 「そんなわけでもありません。先生が学校と病院に頭を悩まされているのを見るのは辛いので、微力ではありますが、私が専心、病院の経営に尽くせば、先生もお楽になり病院もいまより少し楽な状態にもっていけるかと思うのですが」 病院収支を検討した結果、積極的に宣伝し、技工科などを値上げすれば、充分採算に合うことは、すでに清作が調べあげたデーターで分かっていた。 「君が本当に黒字にするというのか」 高山院長は腕を組んで考えこむ。たしかに病院経営は、彼にとってはかなりわずらはしいことであった。経営権を任せよ、といっても、院長が代表者であることに変りはない。とにかく守之助には、経営の苦しいときも、薄給で頑張ってもらったという恩もある。信頼のおける男であることはたしかである。 「急なことなので、しばらく考えさせてくれ」 高山もさすがに、その場でイエスとはいいかねた。 守之助は多少の脈ありとみて、清作の調べたデーターをもって、さらに院長を口説いた。こうして一か月のあと、高山院長はついに守之助の申し込みを受け入れ、経営のすべてを任せることに納得した。、 「成功」 当時の青年はよくこの言葉をつかった。いかにも明治の気概に溢れた台詞だが、いまの人はこの言葉どおりの気持だった。 「やってみればなんとかなるものだなあ」意外な進展に、守之助は述懐すると、 「人間、その気になれば、出来ねぇごどはありません」このあたり、若輩の清作のほうが、一枚上だった。それでは、来月からわだしに十五円いただけますね」 成功の喜びより、まず約束だけははっきりしておこうというわけである」 「もちろん、君のおかげで経営を任されたのだから、十五円は毎月渡すよ」 「きっと、お願ぇ」します」 この半月のあとに、清作は本郷四丁目の下宿に移る。一年前、東京に出たときに泊った下宿に近かったが、今度は二階で広い窓もあり、八畳間でかなりのゆとりがある。ここから済生会学舎は、ゆっくり歩いても十分の距離だった。
第四章 本郷時代 P.118
1 当時の済生学舎の講堂は木造で横に長い机と椅子が並び、大きいところは、五百人からの学生を収容することができた。ときに壮士風あり、ハイカラ風あり、硬派軟派とり混ぜ、袴をつけ、草履や朴歯の下駄を鳴らして教室へ入ってくる。 清作にとって、医学の正式の講義をきくのはこれがはじめてであった。嬉しさのあまり、早朝から夜まで十四時間も講義をききっ放しという日もあった。 清作がこの学舎で山内ヨネ子に逢ったのは梅雨のあけた、夏のはじめのことだった。ヨネ子は清作が上京するころ、やはり医学を志して東京へ進学するといっていたが、そのまま消息は途切れていた。会津若松を発ったとき、わざわざ家まで尋ねて、母に門前払いをくらわされたのが最後である。 清作が女を抱いたのは、伊皿子にいるとき、学院の男に連れられて、洲崎に行ったのがはじめてであった。二城潟では仮祝言まであげて同居したおとめとさえ、手一つ握らなかった清作が、東京にきてはじめて女を知った。 当時、吉原の女は、小店で四十銭といわれたが、一度遊びを知った清作は金さえあれば、通うようになる。それでも伊皿子のときは、金がなくて行くのはかぎられていたが、本郷にきてからは、深川や吉原に河岸をかえて、頻繁に行くようになった。 これでは十五円もらってもたちまち消えてしまう。伊皿子から本郷へきて、相変わらず借金を続けたのは、この女遊びのためである。この清作の遊びには、守之助もうすうす気付いていた。 「あんな自堕落な男に、金の援助をするなどお止めなさい」 何人かの友人が忠告したが、守之助はここでも見て見ぬふりをした。 たしかに遊ぶが、勉強もする。いわゆる遊里に好きな女ができて、いれあげている、というのではない。ただもてない苛立ちと、精力のはけ口として遊んでいるだけだと守之助は睨んでいた。 とにかく貯えということの苦手な男だから、一度にお金をもらうと、たちまち消えてしまう。なくなると、またいまにも自殺しかねないような顔で無心にくる。清作のいうとおり、守之助が専心して以来、病院の経営状態は好転していた。五円や十円の金くらいなら自由にならないこともない。守之助ははじめのうちは二円、三円と渡したが、こう頻繁ではやりきれない。渡すとそれだけすぐつかうのを知って守之助は、月のうちの十五円を三度に分けて渡すことにしたがそれでも清作の金欠病はなおらない。 2 本郷の新しい下宿に移り、済生学舎に通って、後期開業試験へ準備を重ねていた清作にとって、一つだけ気がかりなことがあった。それは後期臨床試験のなかに「打診法」という一項があることだった。 打診はいうまでもなく、患部に当てた手背を、もう一方の人差し指と中指の先で軽く叩く。空箱の上を叩いた場合と、なにかものが詰っている場合とで、音が変るように、打診による微妙な音程の差で、胸郭内の空洞や滲出液の有無を判定する。現在のように、精密なエックス線撮影や心電図が開発されてからは、あまり意味がなくなったが、当時としては聴診と同時に、きわめて有力な診察法であった。 五年前に、清作の指は渡部医院で手術を受けて、いくらか伸びはしたが、拳を握った形であることに変りはない。拳から指を一直線に、平らに伸ばすことは難しい。清作はこの不具のため、正確な打診ができなくて試験に落とされることを恐れた。 なんとかうまい方法はないものか、迷った末、清作は血脇守之助に相談してみた。困ったとき、近くにいて頼りになるのは守之助をおいて他にない。 清作が打診の不能を訴えると、守之助はおおいに同情した。今度は、いままでのような小遣いのせびりでなく、肉体の欠陥に根ざした無理からぬ願いである。世話好きというより、清作にとりつかれた形の守之助は、早速東京大学外科学教授の近藤次繁博士に頼んでみた。 すでに夏に入り、後期試験の十月まで、もうあまり余裕はない。近藤教授は診察した結果、完全にもとどおりにはならないが、いまよりは少しよくなるという見解であった。そしてたとえ指は完全に伸びなくても、それなりの打診法はあるから医者になっても心配はない、といってくれた。 守之助も清作も、手術をしてもらいたかったが金がない。 「正直などご、いま手術の全額は払えねぇかもしれませんが、不足な分は月賦ででも払わせていただけねぇでしょうが」 清作がいうのに、教授はしばらく考えていたが、やがて事務長を呼んで相談した。 「まともにかかると、大変なお金になりますから、学用患者ということにしてあげましょう」 学用患者というのは大学にだけある制度で、学問的に興味ある珍しい病気の患者や、貧しい患者を無料で入院させ、そのかわり、学生の勉学のために自由に診察させるという条件がつく。 清作の場合、火傷のあとの癒着が、とくに珍しいわけでもないから、あきらかに後者である。もっとも、学生の教材用といっても、内科の患者のように、やたらに打診や聴診されるわけでなく、ただ不具の手を診られる程度だから、さして苦痛ではない。それより誰の世話にならず、ただで治してもらえるという喜びのほうが大きい。 だが、清作はこのとき、はじめて天下の帝大医学部の学生達を身近に知ることになった。 当時、帝大の医学部を出たものは無試験で医者になれた。大学を卒業することが即医師免許証の交付を意味した。これに反して、清作のように大学に行けなかった者は、前期・後期の難しい医術開業試験をパスしなければならない。 帝大生は優秀とはいえ、ごくかぎられた一部の人しか大学に行けなかった当時としては、エリート中のエリートであった。なかに稀に苦学生はいても、大半はやはり良家の子息である。清作はこれらの医学生が、学用患者である自分の手を眺め、手指をあれこれ動かすのに黙って耐えなければならなかった。同じ医学を志す者でありながら、一方は診る側であり、一方は診られる側である。後年、清作が帝大出の医学者へ、激しい闘志を湧かせたのは、このときの屈辱が、そもそもの発端であった。 それはともかく、近藤教授は清作にきわめて好意的であった。五年前に手術して瘢痕で固くなったところを再び開き、念入りに指を伸ばす。すでに発育不良の中指以下は、剥がしてちびて機能的には期待できなかったが、中指と拇指だけはいくらか動くようになった。とくに拇指は良好で上下左右に、かなり自由に動かせるようになった。今度は切開のあと、植皮も一部くわえられて、前回からみると、指はちぢんではいるものの、かなり開く。 ほぼ二十日間で創は癒えて、包帯をとったあと、教授は正常に伸びきらぬながらもその手で不完全ながら打診する方法まで親切に教えてくれた。 一か月で退院して、清作はようやく後期試験への自信をえた。入院中、いろいろ手をいじった帝大生への対抗心からも、是非、合格しなければならない。 十月の初め、ついに医術開業後期試験の日が訪れた。清作は前日、半年ぶりに床屋へ行き、東京風のさっぱりした刈込みをしてもらうと、高山歯科医学院時代の友達から借りた袴をつけて試験場に臨んだ。 この後期試験には、学説と実技試験の二つがあった。第一日の外科の実技試験のとき、清作は聴診器を持たずにいった。大体、清作は自分の聴診器がなくて、いつも他人のを借りていたのだが、この日は外科だから必要ないと思ったのである。 だが試験に臨んでみると、患者は股の淋巴腺に潰瘍をもち、お腹の不快感を訴えていた。 「お腹の聴診をしてみたまえ」試験委員にいわれて、清作は困った。 医者になろうとしているものが、聴診器をもっていないともいえない。 「実は今日、内科の試験を受ける者に聴診器を貸してもっておりません。申し訳ありませんが先生のをお貸しいただけないでしょうが」 受験生にしては少々図々しい男である。試験委員はあきれながら自分のを渡した。 清作は借りた聴診器を患者の腹に当て、腸がほとんど動いておらず、かなり膨張していることから、潰瘍にくわえて、腸閉塞の症状もあることを告げた。この診断はなかなか当をえていて、試験委員達は一斉にうなずいた。 実技と学説と、二日におよぶ試験が終って、十日後にその結果が発表された。 清作は見事に合格した。このとき受験者は八十名中、合格したのは次の四名だけだった。 立花為太郎(富山県士族)、小川保次郎(鳥取県士族)、松田正直(長野県士族)、野口清作(福島県平民)。 いずれも士族の出身のなかで平民は清作一人である。 このとき、合格者四名は直ちに、近くの写真館に集まって記念撮影をした。 現存する清作の写真で、最も古いのは、この一年前に、神田淡路町の江木本という写真館で撮ったもので、一人でまっすぐ前を向いている、上半身だけのものである。 合格記念に撮った写真は、前の椅子に二人が座り、うしろに、二人が立っている。清作は向かって右手後ろに立ち、左手は前の人の肩ごしに隠している。 いつも蓬のような長髪だったのが、この時の頭は見事に刈りこまれ、一見、坊主頭のように見える。十月も末で、みな羽織を着ているのに、清作一人、着物に袴だけで、羽織はない。 合格を知った清作は、まっ先血脇守之助のところへ駆けつけた。 「受かりました」 清作が息せききっていうと、守之助は一言、「そうか」とうなずいただけだった。それ以上いう言葉もなく、守之助はただしっかりと清助の手を握った。 3 清作が医師開業試験に合格したことは、たちまち、二城潟に知らされた。 母のシカは、この合格の電文をもって近所にふれてまわった。 清作は「医者になったげんとも、やっぱり天道様は東から出っぺ」シカはそういって、狂ったように笑った。 このころ、シカは農業のかたわら、近村一の助産婦といわれた親戚の野口クマという産婆について、助産術を習い、クマに次ぐ産婆として名を成していた。清作が医術に励んでいると思うと、自分も少しでもそれに近づこうとする、どこまでも勝気で意志の強い女であった。 シカが喜んだ以上に、清作は嬉しかった。早速、下宿の主人から仲間、高山歯科医学院の職員などに告げ歩いたうえ、前期試験で落ちた山内ヨネ子おところまでいって、合格を報告した。 無邪気といえば無邪気だが、そのあたりが、清作のあけっぴろすぎて、反感をかうこところである。 だが、この喜びのあとにすぐ次の問題がおきてきた。 小林栄はもちろん、田舎の人達はみな、清作が開業試験に合格したからには、当然、故郷にでも帰って医院を開き、いままで苦労してきた母や家族を援けるのだと思っていた。当時は学者として大学に残ったり、研究に従事するのは帝大出の医者で、開業試験をパスした医者は、ほとんどが合格と同時に開業するのが常だった。実際、母のシカも、清作は帰ってくるものと考えていた。
しかし、清作には故郷へ帰る気はまったくなかった。いまこそ、「手ん棒」と馬鹿にした連中を見返してやる。故郷に錦を飾る絶好のチャンスであったが、清作の頭からは、そんな小さな望みはとうに消えていた。
彼はそのことを、また血脇守之助に訴えた。
「わだしは御承知のとおり、左手が不自由です。ほれに自分でいうのも残念ですが、背もあまり高くなく、風采が上等ともいえません。このような状態では、いくら学問があったどしても、患者が集まってくるなどは思えません」
これは清作の偽らぬ実感でもあった。水呑百姓の手ん棒であったころを知っている故郷の者達は、たとえ医師免許をえたからといって、すぐ集まってくるとは思えない。そんなことより、東京でさらに学問を積み、一流の学者になりたい。とにかく、この手では臨床医は不利だ。
守之助も清作のいうことに同情した。毎日不具の手をさらすのは辛いだろうし、これほどの頭をもった男を、田舎に帰すのは惜しい。
守之助は高山院長に頼んで、とりあえず清作には高山歯科医学院の病理学と薬物の教師として、働いてもらうことにした。この案に、清作はもちろん異存はなく、母のシカにも手紙で報告したが、反対すると思ったシカは、「おめのいいようにやっだらいいっぺ」とあつさり承諾した。どんな苦境でにあっても、すすむことを忘れなかったシカは、まわりの知識人より、さらに進歩的だったともいえる。
こうして清作は高山歯科医学院の教壇に登ることになった。
「昨日までの小使が今日は先生」とは、このとき高山歯科医学院で言われた言葉だった。たしかに昨日まで鐘を鳴らし、教室のランプを磨き、「清作」とよばれていた男が、突然、袴をはいて教壇に上ってきたのである。一瞬、みなぽかんとし、それから渋々頭を下げた。
後年、清作はこのときのことを、「自分の一生のなかで、あれほど痛快で愉快だったことはない」と述べている。まさに三階級特進以上の抜擢である。
清作は得意満面、講義をはじめた。以前からそうだったが、清作はあまり照れるということのない男である。照れるのが、一つの知性の表現とするならば、清作にはその種の知性はなかったかもしれない。なにごとにも照れることなく、抜け抜けとつきすすむ。そこが江戸っ子と違う田舎者の清作の強さでもあった。
いままで「清作」と呼び捨てにしていた連中を見返して、いっときは満足した清作であったが、半年もしないうちに、高山歯科医学院で教鞭をとることに飽いてきた。
いつまでもこんなところで、歯科の学生に教えていたところで仕方がない。教えることはたしかに気持のいいことだが、反面、自分でうるところははあまりない。もう少し立派な医師の許へいって、本格的な医学を教わりたい。いっとき、いい気分になってもそこで安住しない。常に現状に不満を抱いて前向きにすすもうとする、それが清作をこれまで支えてきた。
「できたら、臨床の勝れた先生がいらっしゃる、順天堂医院に入って、腕を磨きてぇんですげんとも」清作の申し出をきいた守之助は、素直にうなずいた。
たしかに高山歯科医学院などで、うずもれてしまうのでは、東京に踏みとどまった意味がない。守之助は、自分も学院で教鞭をとるだけに飽きたらず、病院経営にのりだした事情もあるので、清作の気持はよくわかった。
「順天堂に、菅野徹三という医師を知っているから、頼んでみよう」
守之助はそういって菅野に頼んでくれた。
順天堂医院は当時湯島にあり、千葉県佐倉出身の外科医、佐藤尚中が創設しただけに、外科学の大家が轡を並べていた。もっとも、そうはいっても、病院の格やスタッフは、問題なく東京大学が上である。
清作もできることなら、帝大のほうで学びたかったが、当時の帝大は、開業医試験上りの医者はほとんど採用しなかった。また、採用しても、かなりの差別をつけられる。そんな事情もあって、私学の中心である順天堂医院を選んだのだが、入ってみると、ここも臨床はなかなかやらせてもらえそうもない。
ここで清作が初めに与えられた仕事は、菅野徹三が編集主任をやっていた「順天堂医事研究会雑誌」の手伝いをすることであった。しかも給料は賄付きの月二円である。
済生学舎にいたころは、下宿代や食費は自分もちとはいえ、守之助から毎月十五円をもらっていた。それからみると大変な収入減である。しかも希望していた臨床の勉強は、容易にかなえられそうもない。
だが、雑誌編集の手伝いは、清作にとって、結構楽しい仕事であった。
一般の臨床こそやらせてもらえなかったが、絶えず病室に出入りして、医学的に興味ある患者を診て、検討することは自由であった。菅野氏は、少しでも興味がある患者がいたら図書館にある文献で調べ、その結果を文章として報告するよう命じていた。のちの清作の、なにごとでも論文にまとめる技術や、その早さは、このとき習練したものである。
そこで清作は持前のファイトで、病気を調べ、論文を書きはじめた。元来が、書くことは好きな男だったが、直接患者を診察しても治療まで手を出せない口惜しさが、いっそう、論文を書くことに熱中させた。
この順天堂時代の、清作の論文はかなりの量にのぼる。とくにこの方面と、しぼられているわけではないが、月に平均二本をこすハイスピードである。とにかく、清作にとっては小さな論文とはいえ、そこに自分の名前がのって、活字になるのが嬉しかった。
菅野は清作の仕事熱心に感心しながら、徐々に編集の仕事を任せるようになってきた。仕事の点では不満はなかったのだが、月給二円というのは、いかにも安すぎる、例によって、月給をもらうと身につけておかない性質だから、二円くらいでは、もらった数日で消えてしまう。あとは例によって、まわりの人から金をせびり、借金を重ねるばかりである。
このころ、医師の免許証交付に当っては、六円、支払うことが必要だったが、その金策がなかなかつかない。たまりかねた清作は、また守之助のところに頼みに行く。
このままでは、病室に行くどきの袴どころか、スリッパさえ買えません。なんとかもう少し増額してもらえるよう、菅野先生に頼んでもらえねぇでしょうか」
守之助もたしかに二円では安いと思う。菅野医師にいってみる旨、約束すると、清作はさらに、
「当座のお金として、ほんの少しでいいのですが、貸していただけねぇでしょうか」と切りこむ。
順天堂からわざわざきて、ただで帰るわけはない。守之助は戸惑った表情を見せたが、やがて懐から財布をとり出すと、清作の前に投げ出した。
「これで早く免許証を受けとって、散髪にでも行き給え。そんな薄汚い恰好では、患者はもちろん、仲間からも敬遠される」
「申し訳ありません。このご恩は一生忘れません」例によって、清作は平身低頭してお金を受け取る。
あとで財布を開いてみると二十円という大金で、早速、友人の石塚というのに託して、次のような手紙を守之助に届けさせている。
十一月二十三日
野口清作
血脇守之助閣下
守之助は、清作の大袈裟には慣れていたが、こんな手紙をもらって不快なわけもない。また調子のいいことを書きやがって、と思いながら、読んでいるうちに、なんとなくいい気持になってしまう。
ともかく、守之助の口ききで、月給は二円から三円にアップされた。実際、それくらいでは焼石に水だったが、それでも当座は少し息をつける。だが免許証を受けとり、借金を返すと、守之助からもらった二十円もたちまち消えていた。
当時、順天堂では、院長と科長回診に従くときは、必ず袴をはくこと、という内規があった。医師である以上、身形を整えるのが基本である。
だが清作は着物はともかく、袴までは手がまわらない。やむなく外科の回診だけは、着物の上に手術着を着て誤魔化していたが、手術着のない内科の科長回診には従いていけない。あまりの汚さに、菅野にも度々注意される。
困った清作は同僚の田原氏に苦境を話して、洋服一揃えをプレゼントしてもらう約束をした。ところが、これが田原から守之助の耳に入り、おおいに叱られる破目になる。
当然、清作のところへ守之助から怒りの手紙が届いた。内容は、医師ともなったものが、わずかな縁を頼って、洋服をせびるような、そんないじましいことはやるな、ということだった。
「それほど洋服が欲しいのなら、なぜ私にいわないのか」
守之助としては、清作のいじましさに腹が立ったが、それ以上に、自分以外の男に頼っていったことが不快だった。
4
方々への借金と、田原医師に洋服の無心までしたことで、血脇守之助から怒りの手紙を受けとった清作は狼狽した。
大体、清作はそれまで、守之助を軽くみていたところがあった。守之助は学力識見ともに優れ、東京での第一のスポンサーではあったが、日頃は寛大で滅多に怒るということがなかった。清作がきめられた仕事を怠け、酒と女に金を浪費しても、見て見ぬふりをしてきた。
守之助としては、清作が遊ぶのは、不具と貧しさからくる心の屈折と、ありあまるエネルギーを吐きだすためで、将来への発展の一つのステップに過ぎないと見ていたが、清作はそれをいいことに図にのっていた。守之助が高山歯科医学校を経営するようになり、経済的に楽になったのも、すべて自分が入知恵をしてやったおかげである。スポンサーではあっても、あまり威張れるわけではないと、たかをくくっていた。
それが突然、怒りの手紙をよこしたのである。
文章は落ち着いて、短いが、それだけにかえって怒りがひしひしと伝わって来る。
正直いって、知人に洋服を無心したくらいで、何故そんなに怒られるのか、清作には理解しにくいところもあったが、ここは守之助に謝るにこしたことはない。とやかくいっても守之助はまだまだ有力なスポンサーである。
だがそれにしても、この手紙はなかなかよく出来ている。
まず平身低頭、謝ったあと、袴がなくて内科回診に行けない憐れさを強調し、同郷の知人が病院にきて、何故洋服にしないのかときかれ、その人から母に伝わり、送金するという手紙がきたこと。このお金がきたら、すぐ時計を買い、残りで早急にこれまでの借りを返すつもりである、と殊勝なことをいっている。さらに洋服の件は、田原医師から、シャツ類は古物をやるから、ズボンだけ買えばいいといわれ、国から金がくればそうするつもりで、服をもらう約束をしただけだと、いいわけをしている。
さすがに守之助はこの手紙に誤魔化されることはなかった。手紙は、一見、丁重に謝っているようにみえて新たな借金の申し出であった。守之助はその裏の意味を知りながら黙っていた。これ以上、簡単に金を渡しては、清作のためにかえってよくない、しばらく困らせておいたほうがいいと考えた。
たまりかねた清作は、今度は三城潟の同級生、八子弥寿平に無心の手紙を出すことにした。
しかも金を要求しながら、自分を宣伝することも忘れない。直接の受持ちの患者もいなかったのに、順天堂の入院患者全員が、自分の患者であるようないい方をし、雑誌編集の下請けにすぎないのを、あたかも編集長であるように書いている。
さらに小学校を出ただけで、なにもわからない子に、医学雑誌を送りつけて驚かす。おまけに、二十円を五十円にアップする。
人が善く、ひたすら東京を尊敬し憧れる、田舎者をたぶらかす、それは態のいいかたりであった。
このとき、八子は実家の薬種業がいささか左前で、金策に苦労しているときであった。五十円の大金など、到底工面できる状態ではなかったが、父と妻に内緒で、売上金を誤魔化して、いわれたとおり五十円を為替で送金した。
こうして小心な八子には信じられぬ大胆な方法で、ようやく工面した五十円を手にした清作はヨネ子の従兄の菊池良馨を誘い出し、吉原へくり出した。
野口英世の伝記で、このころの清作の放蕩について触れたものはない。たまに触れても、「勉学のかたわら、気晴らしに、ときどき遊ぶことがあった」といった程度の書き方である。
現在、野口英世について最も誠実な伝記だといわれている奥村鶴吉氏の英世伝にさえ、「一度やりかけると徹底的にやる。それが彼の特長でもあり、短所でもあった。彼は学術研究にかかっても、二晩、三晩、部屋から出て来ない程、熱心でもあった。その徹底的な心持ちが、いま他の方面にも現れているのである」と書かれているだけである。
とにかく高山歯科学院から順天堂、そして下宿の仲間と、清作を知っている男で、金の無心をされなかったものは、一人もいない。さらに近くの食堂、小店、吉原など含めたらどれくらいの額になったものか、おそらく数百円は優に超えていたと思われる。
清作を知っている者は、すなわち被害者、いいかえると清作はいつも債鬼のなかで暮らしていたともいえる。
大体が、子供のときから、人から施しを受けるのには、慣れてきた男である。いまさら医師になったからといって、施しを受けることに、精神的負担など感じるわけもない。それどころか、才能が優れている者が劣る者から金をとるのは当然だ、という考えの持主である。
渡部鼎や守之助が忠告したところで、きくわけがない。大体が、彼等とは生れから、育ってきた環境が違いすぎた。羞恥心の原点がはじめから狂っていた。
この金を十日で費いきった清作は、一週間後の三月二十日八子弥寿平に手紙を書く。
また二十円の無心である。
八子は再び家騒動まで起して、金策に走りまわる。八子はまさに、蛇に睨まれた蛙同然であった。
第五章 北里研究所 P.151
1
金の借り方に、壮絶という形容はおかしいかもしれないが、清作の借り方は、まさに壮絶とかいいようがない。だがこの清作も、ときには自分で金を工面することを考えたこともあった。
郷里の八子弥寿平から、五十円、二十円と、連続せびりとって、さすがに気がひけたのか、清作は独文の医学書を翻訳して金を儲けることを考えた。このとき手をつけたのが、カールデンの『病理学細菌学検究術式要綱』である。この本は、病理学や細菌学で必要な標本のつくり方や、その顕微鏡所見などを記載したものだが、清作は会陽医院にいたときから、この本の翻訳ににとりかかっていた。清作にとっては馴染みのある本だった。
だが、この翻訳は一部、順天堂医院の医学雑誌に発表しただけで、結局は完成しなかった。
大体、この儲け話は初めから無理だった。当時は翻訳本の読者は少なくて、まだ出版など出来る状態ではなかったし、無名の清作が訳者では、売れるわけもなかった。それをおだてられるままに、本気にとり組んだのは、清作の自信過剰の為せるところであった。
だがこの本を熟読し、翻訳するうちに、清作は細菌学を専攻する決心ができあがってきた。
この選択は後年、彼の一生の進む道を決めた点できわめて重要である。もし彼が、細菌学以外の道を進んだら、おそらくその後の彼の名声はなかったことは想像にかたくない。
清作が細菌学を選んだ直接の理由は、やはりこの『病理学細菌学検究術式要綱』を熟読したことによる。これで清作の細菌学への目は開かれた。
だが、これはあくまできっかけで、清作が細菌学をやろうと決心した最大の理由は、その学問の華々しさと、それゆえに名声をうるのに最も手っ取り早いと考えたからだった。
当時、順天堂の仲間に、「医者で一番早く有名になれるのは、細菌学を専攻することだ」と、明言してはばからなかった。
たしかに、当時の細菌学は、医学の花形であった。ロベルト・コッホが結核菌を発見し、レフレルがジフテリア菌を、フレンケルが肺炎菌を発見する。一方、日本では志賀潔が赤痢菌を、北里柴三郎が破傷風菌の純粋培養に成功し、さらにペスト菌を発見する、といった具合に、細菌学者は全世界の脚光を浴びていた。血の病、気の病などと称して、病気を体液の流れの異常と理解していた当時の漢方にとって、細菌の発見は大きな驚きでありショックであった。何万人もの人を死へ誘う疫病の大半が、この細菌というものを介して罹り、その細菌を撲滅する方法が発見されれば、その病気は地上から消えるのだという。これは当時の庶民の医学常識を根底からくつがえす、医学の進歩そのものを、まざまざ印象づける事実だった。
しかもこの学問を専攻する細菌学者というのは、驚くほど高価で複雑な顕微鏡という機器をつかって、目に見えぬ細菌を見付けるのだという。一種の救世主的存在ですらあった。
明治三十年代の細菌学は、まさにその花形中の花形であった。その華々しさはおそらく現在の癌研究の比ではない。続々と発見される菌と、その発見者が医学雑誌の巻頭を飾り全世界の新聞や雑誌でもてはやされる。学問への興味といより、口惜しさからが学問を選んだ清作が、この細菌学に目をつけぬわけはなかった。一介の医師になることなどに飽き足らかった清作にとって、日本一から世界一を目指すには細菌学こそ絶好の学問であったともいえる。
細菌学を専攻すると決めてはみたものの、実際にそれを学ぶには、いろいろな問題があった。
まず当時は細菌学を研究している場所は東京帝国大学医学部の細菌学教室か、芝愛宕下にあった北里研究所(伝染病研究所)ぐらいであった。しかもこの二つは、いずれも帝大の医科出身者でなければ助手として採用してもらえない。
清作は悩んだ末、順天堂の上司である菅野徹三い相談してみた。
「君は臨床医になるよりは、学者の方が向いている」
菅野は簡単に賛成したが、清作が日本一の名声を得ようなどと考えているとは思ってもいなかった。それより手の不具と、背の低いところから、臨床医よりは学者のほうを希望しているのだろうと単純に考えていただけである。
「細菌学を専門にやるなら、スタッフや設備からいって北里研究所のほうがいいだろうが、しかしねぇ……」
菅野も、清作が帝大出でないことがひっかかった。
「たった一つ考えられるのは、ここの佐藤院長は、北里先生と昵懇のあいだだから、佐藤院長に頼んでみたらなんとかなるかもしれない。あるいは駄目かもしれないが、一応、僕から頼んでみよう」
菅野はそういってくれたが、清作は安心できず、さらに血脇守之助に会って、細菌学をやる決意をのべ、北里研究所入りを取り計らってもらうように頼んだ。
「俺は直接は知らないが、日本医事週報社の川上元次郎氏に頼んでみよう。彼なら北里先生と親しいはずだ」
守之助も菅野医師と同じ理由で、清作が細菌学者になることには賛成だったが、北里研究所入りが簡単にいかないことも知っていた。だがこの時の二人の努力は大変なものmだった。
菅野は早速佐藤院長に会って清作のことを依頼し佐藤院長の紹介状までとってくれたし、守之助は川上氏のところへ数回足を運んでくれた。
この研究所の門戸の堅さは、いまからは想像もつかない。学問を好きなものなら誰でも入れてよさそうなものだが、当時は確固とした序列があった。
単なる下働きならともかく、助手に帝大出でない者を採用したとなると規則が乱れる。給料一つにしても、帝大何年卒の者はいくらと、決まっているが、それ以外の者には初めからとり決めがなかった。それにいままでも何人か入所希望者があったものをすべて断っているだけに、清作だけ例外を認めるわけにいかない。
さらに医師開業試験に合格したとはいえ、それは速成の臨床医をつくる目的で、基礎医学はほとんど身につけていない。とくに細菌学のように技術の難しいものは、基礎から教えるのに手間がかかり、かえって邪魔になる。野に遺賢ありとはいえ、一応、優秀なのは帝大に入っているのだから、そこからくる人材で間に合うという考えでもあった。
北島柴三郎個人は、東京帝国大学のやり方の古きに反撥して、独立の研究所をつくったのだが、それでもこの古さである。このあたりは、当時の社会体制や学閥を無視しては理解しえない。
だがここで、北里柴三郎は営団をもって、清作の研究所入りに同意した。これはもちろん、佐藤院長や川上氏の斡旋のおかげでもあるが、それ以上に北里個人の進歩性と反骨精神が幸いしておいえる。
しかし入所は許可されたものの、清作の身分は正式所員でなく、月俸十三円の見習助手であった。
それにしてもこの待遇は、当時としては破格であった。このとき、やはり帝大出身でない秦佐八郎という男が、同時に採用された。秦は岡山の医学校出だが、のちにドイツで梅毒治療薬のサルバルサン六〇六号を発見して名を成した。野口、秦と、後年世界の医学界に名を成した二人がこの年同時に入ったのだが、そのときは、帝大出という純粋性が汚されるといって、所員のあいだでずいぶんと不満が出た。
ともかくこうして明治三十一年四月、二十三歳の春、清作は晴れて北里研究所入りを許される。
初めの日、清作はまっ先に、北里所長のところへ挨拶に行った。北里博士は長身で、上から見下すように清作を見た。
「君のことは、佐藤先生と川上君を通じて知っている。ここは細菌学に関しては日本の最高の研究所だ。五年も経てば、外国へ行けるチャンスもくる、それまでしっかり頑張るのだ」
やがて自分も外国へ行き、世界の名だたる学者に伍して研究できる。清作は北里所長を見上げながら、未来へ果てしない夢を抱いた。
だが現実はそう甘くなかった。
当時、北里研究所には、所長をはじめ、志賀潔、浅川範彦、柴山五郎作、守屋伍造、村田昇清ら、日本の医学界をリードする俊秀が集まっていた。この下にさらに十数名の助手がいた。清作はこの先輩助手について基礎医学を教わった。、
ずいぶん医書を読んで、学識があるように思っていたが、清作の知識は単なる寄せ集め雑学であった。独学で、系統的に教わったことのない悲しさ、とてつもない難しいことを知っているかと思うと、ごく常識的なことがわからない。知識にでこぼこがありすぎる。
清作は医学の第一歩からやりなおするつもりで彼らに教わる。所員たちは清作に比較的親切で、桑田という助手などは、試験管の持ち方から教えてくれた。
だがこれを単純に、彼等の親切心として理解するわけにはいかない。正直いって彼等は清助を自分達より一段低い者として見ていた。いまの官庁でいうと、上級試験を通ったキャリア組とノンキャリア組との違いのようなもので、基礎的な知識や技術を教えておいて、自分達の仕事の手伝いをさせようという程度の考えしかなかった。それと彼等は清作の語学力に目をつけていた。細菌学はともかく、清作の語学力はかなりのものである。彼等はこの語学力を吸収する見返りとして、細菌学を教えたのである。
清作も、こうした所内の序列に応じ、ノンキャリア組として基礎的な知識や技術を教わり、彼等の仕事を手伝っていれば問題はなかった。そのかぎりでは語学のよく出来る重宝な男として可愛がられたに違いない。
だが技術をマスターするにつれ、清作は一流の負けん気が現われてきた。
初めは、有名な帝大出の研究者のあいだで仕事ができるということだけで感激だったが、そのうち彼等の手伝いだけではあきたらなくなってきた。なにか自分で独自な仕事をしたい。
一介の見習助手が、一人歩きを主張しはじめたのである。
このとき、清作が最初に提出した要求は、モルモットを三匹もらいたいということであった。だがこの要求は一蹴され、おまけに見習助手が実験動物を要求したといってたちまち所内の噂となった。
帝大を出ていない見習助手の分際で、しかも基礎講習さえ終えていない男が、モルモットを要求するとは図々しい。当時、モルモットは貴重な実験動物で、部長クラスでさえ、年に五匹以内と決められていた。これを名もない見習助手が、三匹も要求したというのだから、
「あの男は少し頭がおかしいのではないか」
事務局の職員は清作を「モルモット君」といってからかった。
この事件は清作にとってかなりのショックであった。野心に燃え、意気揚々とのりこんではみたものの、ここにも学閥の壁があった。先輩の研究者達は、みな学問熱心で親切ではあったが、それは従来の序列を崩さないという範囲内で成立していることで、それをとびこそうとする者は、たちまちはじかれる。
これに追討ちをかけるように、顕微鏡事件が起きた。これは事件というには少し大袈裟だが、ある日、ドイツから最新型の顕微鏡写真機が到着した。いままでの顕微鏡はただ覗いてみるだけだが、今度のは眼で見たものをそのまま写真に撮ることができた。この機器は到着はしたものの、解説書はすべてドイツ語のうえに難解で、誰も簡単に手を出せなかった。このとき、清作はドイツ語ができるところから説明書を読み、自分一人で操作したい旨、部長に申し出ようとして、係りの所員に厳しく叱られた。
「こんな高価な機器を、お前などの手に触れさせられるか」
モルモットに懲らず、彼はまた身のほどを弁えず出過ぎたのである。
2
この北里研究所に勤める一か月前に、清作は突然、故郷の会津へ帰っている。明治二十九年九月に上京してから、約二年ぶりの帰郷である。
この帰郷の理由は、一つには、医術開業試験に合格し、科学者の殿堂といわれる北里研究所入りが決定し、故郷に錦を飾ったという意味にもとれる。だがその本当の目的は、旧友八子弥寿平に会い、新たに金品をせびるためであった。
この年、磐越西線の全線開通の一年前であったが、清作は郡山から歩いて三城潟に入った。
久しぶりにみる故郷は、田植えも終り、一面に青い田が波打っているが、清作はその気色に見とれる間もなく、八子家を訪れる。ここで清作は、弥寿平の両親や本人に丁重な挨拶を述べたあと、祝杯を受けながら、法螺を吹きはじめた。
泣きながらものをせびるというのはあるが、これは威張りながらものをせびっているのである。
素朴な八子一家は、清作の名演説に、またまたころりと参ってしまった。もっとも、八子の嫁だけは、清作のいうことに懐疑的だったが、ものを与えないかぎり、この場を去りそうもない。
こうして、清作は二日間、八子の家に泊り続け、法螺のかぎりを尽して、三日目にようやく腰をあげる。このとき、清作が八子からもらったものは、帽子、懐中時計、インパネス、紋付羽織、糸織袴、糸織袷、糸織綿入、そして襦袢にいたるまで、実に十数点を数える。一部、弥寿平のお古もあったが、すべて上等品で、金額になおすと、どれくらいになるものか見当もつかない。
清作はこれら着られるものは着て、着られないものは風呂敷に包み、肩に背負って、八子家を辞した。八子一家は、それに丁重に頭を下げ、道端まで送る。まさに説教強盗以上の図々しさではある。
この帰り途、小林栄と三城潟の母の許に立寄り、帰郷したのが六月七日であった。
このあと、清作は六月十三日付で、八子弥寿平に礼状を送っている。
表現がオーバーで調子がいいわりに実のないところは、いくつかの手紙で見てきた。ただ文字はなかなかの達筆で、これらは現在、猪苗代湖畔の記念館に保存されている手紙でもよく知られる。
3
この年、六月から年の暮まで、清作の周辺には、あわただしいことが重なった。その第一は、清作の北里研究所入りと入れ替りのように、血脇守之助が清国(中国)漫遊の旅に発ったことである。
当時中国大陸は清国の支配下であった。守之助は一応、病院の基礎も確立したので、この隣りの大国へ渡って実情を視察してこようと思い立ったのである。
この出立に先立って、守之助は留守中の高山歯科医学院の診療を石塚三郎に一任したが、同時に学院の講師をしていた清作にも留守を頼んだ。学校の実際的な運営は石塚に委ね、これの補佐として清作を指名したのである。
六月三十日、血脇守之助の歓送会が開かれたが、そのとき石塚と清作は、それぞれ次のような歌を詠んだ。
いましばし別れに袖は濡らすとも何時か相見んもろこしが原
とつ国に名をあらはさん吾友のしばしの別れ嘆かざらまし
送別の儀礼的な歌ということもあって、いずれもとくに優れたものではないが、後のほうが清作の歌の、
「名をあらはさん吾友の……」という箇所がいささか気にかかる。
いうまでもなく、守之助は年齢的の清作の六歳上だし、医術開業試験合格者としても先輩である。それ以上に田舎の一介」の書生を今日まで育ててくれた恩人である。その人を、たとえ謡のうえとはいえ、「吾友」と呼ぶのはどういうことなのか。いままでの経緯からいえば当然「吾師」とでも詠むのが当然である。好意的に解釈すれば、それほど親しかったということにもなるが、やはり少しくだけすぎの感じは否めない。
石塚の歌の「何時か相見んもろこしが原」とあるところを見ると、あとから石塚が清国に駆けつけ、二人で一緒に旅行する予定であったことを暗示している。守之助は清作にいろいろ援助はしたが、現実に自分の後継者としては石塚のほうを認めていた。このころ清作はすでに自分の手には届かぬ、別の世界にすむ男として、後継者としては、あきらめていたともいえる。
順天堂から北里研究所入りにかけての、清作の異様なまでの八子弥寿平への金銭のせびりは、裏を返せば、いっとき熱心だった守之助の援助が、やや冷めかけていたことと無縁とはいえない。
やがて七月、守之助の渡航が数日のあとに迫ったとき、小林夫人重病の報せがとびこんだ。清作は早速見舞状を出したが腎臓病で病状ははかばかしくなく、さらに重態だという連絡が入った。
できることなら、清作は会津に戻って夫人の看病をしたかった。日頃の手紙で、「御城母さま」とか「御慈母さま」と書いてきたのだから、重態のとき、折角医師になった自分が行かないのでは意味がない。
このあたりは鉄面皮に金を無心して歩いた男とは思えぬ殊勝さである。
だが清作にはもう一つ、この際故郷へ帰って自分の医学技術を披露してやりたいという野心もあった。臨床こそほとんどやっていないが、清作も正式の免許をえた医者である。その技術を恩師の夫人に施せたらこれこそ最大の恩返しである。
しかし悪いことには、研究所に入ってまだ日が浅く、守之助に高山歯科医学院のことを頼まれてもいる。だが、といって行かぬわけにもいかない。迷った末、清作は石塚に事情を話し、研究所には欠勤届を出して猪苗代へ行くことにした。このとき清作は、腎臓病治療に関する最近の医学情報を、順天堂や研究所の医師達から充分仕込んでいった。
小林夫人の主治医は六角といって、猪苗代で古くから開業して人望のあった人だが、清作は早速、この医師と対で向かい合って治療法について話し合った。
清作の知識は諸先輩からのききかじりで、経験豊かな六角医師には敵わないが、それでも信望あつい名医とドイツ語を交えながら話している清作を見て、小林夫妻や見舞いの人達は感嘆した。
この清作の熱意が通じたのか、それから間もなく、夫人の病状は小康に向かったが、このとき坪内逍遥の『当世書生気質』を読み、野々口精作という不良学生が登場するのを知ったのである。
清作から英世へ改名になったきっかけは、前に触れたが、この帰郷がなければ、後年の「野口英世」の名は現われなかったかもしれない。
こうして猪苗代滞在半月で、今度は東京から、石塚が病気で倒れたから至急帰って欲しい旨の連絡を受けた。
血脇守之助がいないいま、石塚が倒れては大事である。清作は今度は東京へとつて返す。幸い石塚の病気は風邪でたいしたことはなかったが、東京へ戻ってからの清作は多忙をきわめた。
まず朝起きると、まっすぐ研究所へ行って医事週報の編集の手伝いをする。また高山歯科医学院の雑誌『歯科医学雑誌』の編集も手伝う。それにガーデンの原書の翻訳仕事もある。この短い期間、清作はそれまでの奔放な遊びを控えているが、それは『当世書生気質』を読んだあとのショックが残っていたからでもある。
それにしても、この年はどういうわけか清作のまわりに病人が続いた。九月の半ば、今度は少年時代からの友人であった秋山義次が、わけのわからぬ高熱で悩まされているという噂が伝わってきた。
秋山は猪苗代時代に、袴をくれたり、左手の手術のとき、若松まで送ってくれた男である。それが東京の下宿で一人苦しんでいるときくと、放っておくわけにもいかない。清作は直ちに本郷区役所裏の秋山の下宿を訪ねた。
秋山は痩せ細り、高熱で魘されて床についている。きけば八月に関西へ旅行したあと、急に腹痛にとりつかれ、そのまま熱が出て動けなくなったという。臨床をやっていない清作に、はっきりした診断などつきようもないが、売薬で治る簡単なものとは思えない。なにやら容易ならぬ病気らしいという感じだけはわかる。清作は翌朝、人力車を連れてきて秋山を乗せ、順天堂に運び、内臓の権威である佐藤副院長に診てもらった。
意外なことに、その結果は「腸チフス」ということだった。
チフスなら北里研究所が専門である。清作は研究所の附属病院へ入院手続きをし、三日後に秋山を迎え入れた。
こういことになると清作はよく動いた。金を借り借金を踏み倒す点では、まさに傍若無人んだが、反面尽すところはよく尽す。これほど恩義をわきまえる気持ちがあるなら、借金などしなければよさそうなものの、そうはいかない。この破綻性が清作の欠点でもあり、また魅力でもあった。
やがて明治三十一年が暮れる。このごろから清作の遊びが再び激しくなる。このころ、清作は悶々と楽しまぬ日を送っていた。
春、前途の希望に満ちた北里研究所入りして半年余りで、やる気を失くすとは早すぎるが、それにはそれなりの理由があった。
前に書いたように、研究所に入ってから、清作はモルモットを要求し、顕微鏡操作を申し出て、ともに一蹴された。大学を出ていない見習助手がなにをいうか、というわけである。
医学者の殿堂、北里研究所に通っているとはいえ、清作のやっていることは、試験管洗いとか、動物小屋の掃除といったことである。毎日、先輩の使った試験管を、棒ブラシで洗い、乾滅器に入れる。またモルモットや兔に餌をやり、糞を片づけ藁を取り替える。たまに実験に加わるとしても、兔の耳をおさえたり、犬に轡をかませたり、肢を摑まえる程度である。
その間に、標本のつくり方や顕微鏡をのぞかせてもらうにしても、それは特例で、本業はあくまで下働きである。
研究所に入ったとき、北里所長は、「五年もしたら外国へ留学できるだろう」といつたが、実際には、それが遠い夢物語のようである。
たしかに研究所からは毎年ニ、三名の人が欧米留学に出ているが、清作の前には、なお四、五十名の留学候補者が控えている。しかもあとからは優秀な学士がどんどん入ってきて、清作のようなノンキャリア組を抜いている。これを待っていたら、清作に順番が回ってくるのはいつのことか、ざつと数えただけでも、二十年くらいはかかりそうである。そんなことを待っていては五十歳を過ぎる。そんな年齢になって外国へ行って果して世界に名を成す大学者になれるのか。考えるだけで暗澹となる。
これにくわえて、暮の十一月、石塚が血脇守之助に招かれて清国へ渡ったことも、一つのショックであった。石塚はたしかに真面目で優秀な男ではあったが、清作はこの男には負けないと自負していた。医術開業試験を受けたあと、石塚は歯科医としてすすんだが、清作は初めから歯科をやる気はなかった。同じ医者でも、専門的に一段低い歯科医など、清作には何の魅力もなかった。
だが石塚はいまや、守之助の第一の弟子として高山歯科医学院を担って立ち、今回はさらに清国まで出かけて行く。なにやら先を越されたという思いと、方向を誤ったのではないかという迷いにとりつかれる。
「頑張れば外国へ留学できる」とは、あくまで帝大出の学士のことで、それ以外の者に、そんな道は開かれていない。一日、清作は同時期に入った秦佐八郎にそのことをいってみた。
「俺達はどうせ駄目だべ」
だが佐八郎の反応は少し違っていた。
「留学できるできないより、いまは一生懸命に学び、先輩に追いつくのが先でしょう」
佐八郎は帝大出でないとはいえ、岡山の医学校を出ている。おまけに父祖は代々藩侯の侍医である。
「あんだは士族の出だからな」
最後には、この穏健な男にまで嫌味をいってしまう。
実際、同じ入所で、ともに帝大を出ていないとはいえ、清作と佐八郎では、研究所の待遇はいささか違っていた。見習助手で、二人とも試験管洗いや動物小屋の掃除をさせられても、清作はどちらかというと汚い小屋へさし向けられられ、ときには所員の使い走りも命じられる。
これに反し、佐八郎は新年度から一匹のモルモットが与えられ、自主実験も許されていた。
この差は二人のうしろだての違いにも原因があつた。
清作は佐藤順天堂医院長の紹介状があったとはいえ、入所するときだけで、それ以後、なんの後押しもない。実際、佐藤院長にしても、清作とはほとんど面識がないのだから、それ以上運動する理由もなかった。
これにくらべれば、士族出で藩医の養子というバックははるかに強大であった。地方とはいえ医学校を出て基礎教育も受けている。
清作は口惜しがるのも無理はないが、当時の社会事情としては、止むをえないところもあった。
こんなところで、ただ下働きをしているだけでは駄目だ。
清作は心中深く思う。
このままでは虚しく青春を浪費するだけである。急がなければならない。深夜秘かに自分を鞭打つ。しかし具体的にどうすればいいか、ということになると、清作もはっきりした方策を見出せなかった。
4
北里柴三郎は嘉永五年(一八五二)の生れだから、明治元年には、数え年十七歳ということになる。生れは熊本県阿蘇郡北里村で、家は村の名と同じように、代々総庄屋をつとめていた名門であった。
十五歳のとき、まず熊本に出て細川藩の儒者栃原助之進に学び、次いで藩校の時習館に学んだが、これはご維新とともに廃校になり、明治四年、同じ熊本の古城医学所にすすんだ。この学校は翌年、官立熊本医学校となり、現在の熊本大学医学部に引き継がれている。
初め柴三郎は医学を学ぶ気はなく、洋学を学ぶ手段として医学を選んだのだが、オランダ医師セー・ゲ―・ファン・マンスフェルトに顕微鏡を見せられたのが、細菌学を志す発端となった。
この医学所で三年間、オランダ医学を教わった柴三郎は、明治七年に上京して、東京医学校(東京大学医学部)に入り、八年後の十五年七月、三十歳で卒業した。このとき二期上に森鴎外がいたが、鴎外は卒業が二十歳だから、年齢では柴三郎のほうが、はるかに年上ということになる。
卒業後、柴三郎は各地方の病院長や医学校校長の職をふりきって、はるかに薄給の内務省衛生局に入った。この選択は後年の北里柴三郎の大成におおいに役立った。当時の衛生局長は長与専斎であったが、彼は大阪の緒方洪庵塾で学んだことから、同門の福沢諭吉とも親しかった。このことが、のちの柴三郎の生き方に大きな影響力を与えることになる。
柴三郎の衛生局での仕事は、ヨーロッパ先進国の医事衛生制度や各種統計を調査し、それに意見をそえて提出するということであった。ここで彼が初めて手がけたのが、それまで野放しになっていた医師免許を規制する、医術開業試験規則の整備であつた。
入局二年後の明治十八年,柴三郎は内務省よりドイツ留学を許され、ゴッホ研究所に行くことになる。この研究所長ロベルト・コッホは、この二年前、コレラ菌をを発見したことで有名で、当時この門下には、腸チフス菌発見者のガフキー、肺炎菌のレフレル、ジフテリア菌のベーリング、細菌化学のエールリッヒなど、後年世界の医学界に名を成した逸材が集まり、パリーのパスツール研究所と双璧を成していた。
ここで三年間、柴三郎は寝食を忘れて研究に没頭する。そして四年目、破傷風菌の純粋培養に成功して、一躍、世界の学界に認められ、翌年、破傷風免疫体を発見し、この業績によってプロイセン大学から外国人で初めての、プロフェッソルの称号を受けた。
このあと、柴三郎は、結核菌の研究にとりかかっていたが、留学期限が迫ってきた。
長与専斎は、わが国の結核の現状からも、その研究をさらに続けられるようにと、明治天皇から御手許金一千円下賜という恩恵を受けられるように申請いてやり、これによってさらに一年間留学が延期された。このあたり、柴三郎が長与専斎らに、いかに期待されていたかがわかる。
しかし留学五年ともなると、さすがにそれ以上許すわけにもいかない。当時、柴三郎には、ケンブリッジ大学に新設された細菌研究所の所長をはじめ、米国ペンシルバニア大学、ブルックリン、ボルチモア市などから招請があったが、それらを振り切って帰国した。
彼は外国より、まず日本で伝染病研究所をつくることが重要だと考えていたが、帰ってみると祖国は意外に冷たかった。というより、日本では伝染病が猖獗をきわめているのに、衛生思想はまだそんなにすすんでおらず、彼を受け入れる場所がなかったのである。
長与専斎は柴三郎のような有為な学者が、内務省などで書類をいじっているのを惜しみ、このことを福沢諭吉に話した。熱血漢の諭吉はおおいに憤慨し、ただちに研究所創立のため、私財を投げだし尽力してくれた。
こうして明治二十五年五月、芝公園の一隅に、建坪十余坪、上下六室、二階建ての家屋が建てられが、これが我が国最初の、しかも民間による伝染病研究所のはじまりで、もちろん所長は北里柴三郎が任命された。
ところでこのころ、大日本私立衛生会にも伝染病研究設立の計画があり、長与専斎はは福沢諭吉に、その芝の建物を、そのまま衛生会の所管に移してはどうかと話してみた。
諭吉は、北里柴三郎に運営のすべてを任せる、という条件で、その案をのみ、土地建物のすべては、そのまま衛生会に引き継がれることになった。
翌二十六年、私立衛生会は研究所の移転増築を計画し、芝区愛宕山の内務省用地の払下げを要求し、さらに医政家の長谷川泰らを動かして、研究所への国庫補助をえようと運動した。
だがこれに対し、文部省は独自に東京帝国大学内に国立の伝染病研究所を創る案を議会に提出する動きを示し、北里研究所を無視する態度に出た。しかも北里柴三郎に、新設の国立研究所のほうへ来ないかという誘いまでかけてきた。しかし北里はいまさら自分が育ててきた研究所を捨てて行く気はない。はっきり断わり、ここに衛生会と文部省との反目が起きた。
衛生会や北里としては、こちらで設立せよと働きかけたときは無視し続け、さらばと民間の手でようやく創り上げ、これから軌道にのろうという矢先、今度は国立のをつくるというのはあまりに勝手すぎると思ったのである。
北里が思ったのは無理もないが、文部省としても、ようやく衛生思想が強まり、研究所の必要に気がついたが、民間のに頼るのでは面子がたたないという理由もあった。
双方、対立が続いたが、結局、衆議院議員の長谷川泰が画策し、私立衛生会伝染研究所への国庫補助案を提出、これを満場一致で可決させ、ついでに文部省案を廃案に追い込むことに成功した。
この長谷川泰という人は長与専斎、石黒忠悳などと並ぶ、明治医政界の大物で、野口英世が学んだ済生学舎の創立者でもある。
かくして明治二十六年、研究所は新たに建設され、国庫補助もうけて、ようやく伝染病研究所らしい形態をととのえることになった。このときの正式の呼称は、大日本衛生会伝染病研究所であったが、一般的には北里研究所の名で呼ばれていた。
英世が入所したのは、この衛生会所感時代の研究所でるが、入所した翌年、明治三十二年、衛生会と円満話し合いのうえ国営に移されることになり、新たに国立伝染病研究所となり、名実ともに、日本の伝染病研究所の中核となる。
この国立研究所が現在地の芝白金台に移されたのは、これから六年後の明治三十八年で、このとき、痘苗製造所、血清薬院を併合し、ドイツのコッホ研究所、フランスのパスツール研究所とともに、世界の三大研究所として、名をはせることになる。
5
明治三十二年四月、北里研究所の国立移管とともに、英世は正式の助手として判任官待遇となり、月俸十五円を支給された。いわゆる正式の国家公務員となったわけだが、上級職員の手伝いであることに変りはない。
ところがこの春、英世に意外なチャンスが訪れた。もっとも、それは結果論で、英世自身それが自分の将来を左右する運命の転機になるとは思ってもいなかった。
四月の半ば、アメリカ、ジョンス・ホプキンス大学病理学教室の、シモン・フレキスナー教授が、フィリッピンにおける米国軍隊の保険衛生状況の視察のあと、日本に立寄った。一行は帝国ホテルに泊り、観光を楽しむとともに、世界的名声の北里博士を訪問し、同時に研究所の見学を希望した。北里博士はもちろん喜んで承諾したが、このときホテルへの出迎えとして、英語のできる英世を差し向けることにした。
当時の日本の医学界はドイツ学派が主流を占め、ドイツ語を話せる者は多かったが、英語が出来る者は少なかったのである。英世は勇躍、一張羅の背広を着込んで帝国ホテルに出迎えに行き、そこから車に同乗して研究所に着き、なかを案内して歩いた。
日頃は容易に近づくこともできない上級職員のあいだにまじり、彼等のいうことを通訳し、フレキスナー教授の質問をとり次ぐ。英世がいなくては会話は一歩もすすまない。なにか急に自分が偉くなったような気がして得意になっていた。
だが、その夜、教授歓迎晩餐会が研究所で開かれたとき、英世も教授について会場に入ろうとすると、職員に制せられ別室で待機させられた。
この待遇は英世にはこたえた。どう英語をつかったところで、彼等は英語を単なる英語使いの案内人としてしか見ていなかったのである。必要なときは利用するが、それ以外のときは退っていろ、という。それでは運転手や車夫に対するものと変らない。晩餐会での拍手を遠くドアごしにききながら、英世は改めて、自分が一介の助手に過ぎないことを知らされた。通訳という仕事が済めば、また動物小屋の掃除夫に戻される。
大正四年、学士院賞をえて帰郷したとき、英世はこのことを思い出して、歓迎会の席上、次のように述べている。
「あのとき、いやしくとも自分は医師の一員であり、通訳という重要な任にあるにかかわらず晩餐会からはずされ、別室で一人夕食を食べさせられた。これは異国で言葉が不自由な賓客に対して、まことに失礼なやり方である。口にこそ出さなかったが、さぞやフレキスナー教授は不快に感じれれたに違いない」
フレキスナー教授の心情に託していってはいるが、この一言に英世の口惜しさがよく現れていた。
だがこの屈辱が、英世にさらにやる気を起させた。かつて手ん棒と笑われ、水吞み百姓の子と蔑まれたのが、頑張りのもとになったように、この口惜しさが、英世の次の飛躍の原動力となる。
この夜、北里博士は夕食会のあと、翌日の大阪の衛生講演会に出席するため夜行で大阪へ向かった。
出発間際に、北里博士は英世を呼んで「フレキスナー教授一行は、さらに二日間、東京に残ってろいろ見たいといっているから、粗相のないよう、ご案内するように」と命じたあと、西洋式の儀礼などについて注意をしていった。
北里博士がいなくなっては、もはや英世の天下である。しかも研究所からは案内のため、正式の休暇が与えられている。翌日から、英世は教授一行を東京各地に案内する。東京どころか、東洋ははじめての人達ばかりだから、どこに案内されても一向にわからない。
血脇守之助は清国に行って不在だったが、英世はまず一行を高山歯科医学校に案内した。フレキスナーにとってあまり関係のないところであったが、英世はここで自分が院長であるかのように振舞い、歯科衛生について滔々と論じた。さらに順天堂に連れていったり、菊池や旧友の秋山にまで会わせてフレキスナーと親しいところを見せびらかした。
だがこの案内中、最大のヒットは、フレキスナー教授に、自分のことを売り込んだことだった。
東京を案内しながら、英世は機会を見ては、自分が順天堂と北里研究所で勉強してきた優秀な研究員であることを力説した。細菌学に魅せられ熱中していることを話す。
だが外国の学者の常で、彼等は名声や言葉より実質を尊ぶ。「貴方の論文はなにがあるか、あったらむせて欲しい」といわれたとき、英世は詰った。研究所に入ってからの細菌学に関する論文は一つもない。仕方なく、順天堂の医学雑誌に発表した『小児の壊疽について』というのと、翻訳していた『病理学細菌学検究術要綱』の二つを示した。
フレキスナー教授教授はうなずいたが、もとより日本文の論文は読めるわけがない。
だが英世はひるまない。
「自分はまだ若いが、いつか機会を見て、アメリカに渡り、そちらの優秀な施設で研究してみたいと願っているが、どういものでしょうか」
みちろんフレキスナーはその意見に賛成した。
「日本の学者は、ドイツ医学に傾倒しているものが多いが、私はそうは思いません。アメリカがこれから伸びる国であるように、アメリカ医学もこれから大きな花を咲かせると信じています」
こういわれて悪い気がするわけがない。しかも、三日間、熱心に案内してくれた青年である。
「あなたがわが国にいらっしゃるなら、お力添えを致しましょう」
フレキスナー教授はそう答えたが、これはあくまで儀礼的なものだった。
だが、英世はこれを真に受けた。いや、儀礼的な意味がこめられているとは知りながら、この言葉をでも頼りにしていくより方法がなかったともいえる。
後年、英世が単身、ペンシルバニアのフレキスナー教授のもとを訪れたとき、教授はその無謀さに呆れ、一旦は追い返そうとした。そしてのちに、
「私は彼が渡米することをすすめはしなかった。ただ近く、ジョンソン・ホプキンス大学からペンシルバニア大学へ移ることを、いっただけである」と述懐している。
とにかく、この三日間の案内行で、英世は自分の印象を、強く教授へ焼きつけることにのみ全力を尽した。その他の衛生施設の案内や観光などは二の次であった。
一日だが、教授一行に同行した研究所の所員は、英世の強引さに辟易して、「あいつは隙間さえあればどこにでも入りこんでくる。風のような男だ」とあきれたが、言い得て妙である。
教授一行は三日間の滞在を終えて、無事横浜からマニラへ向かっていった。
このフレキスナー教授一行の案内は、英世へもう一つの幸運をもたらした。そのころ医学界の元老として重きをなしていた、男爵石黒忠悳老が、教授が日本視察の結果、どのような感想をもらしているか、知りたいといって、夜英世に説明にくるように呼び出しがかかってきた。
石黒邸へ参上するなら、当然、もう少し上席の者を、という意見もでたが、三日間付ききりだったのは英世一人で、しかも通訳をしていたのだから彼に行かせるよりないだろうということになった。
英世は喜び、かつ緊張した。なにせ華族の家へ行くのなぞ初めてである。すでに初夏に近い陽気だったが、一張羅の冬服を着て石黒邸に出向いた。
石黒忠悳は越後の出で、長州・土佐といった明治政府閥と無縁ながら、華族になっただけあって、ものにこだわらない炯眼の主であった。風采のあがらぬ、貧相な英世を応接間にとおし、夕食を接体した。
初めは、英世は緊張してあがりつぱなしであったが、
「教授達は、日本をどのように見、どこが欠点だといっておられたか」ときかれ、答えるうちに次第に調子が出てきた。
英語で、多少わからなかったところは、自分の意見をくわえながら巧みに話す。こういうところ、ツボをとらえ、的を射た話し方は彼の独壇場である。もっとも、そうはいっても、英世の話し方は、いわゆる立板に水という感じとは違う。かなりきんきんした声で、早口であるが、東北弁特有の訛りがあった。
石黒男爵はいちいちうなずいたあとで、「ところで、君の出身はどこかね」と尋ねた。
「会津です」
「そうか、それで訛りがあるのか」
会津と越後は、かつて東北同盟を結成し、官軍に抵抗したことからも、ある種の共感があった。石黒男爵は懐かしがったあと、
「会津若松に、渡部鼎という名医がおるが、ご存じかな」ときいた。
「あの人は、わだしの恩人であり、恩師です」
「そうか。それは奇遇じゃ」
以前、渡部鼎は、東京遊学中、石黒男爵の恩顧を受けたことがあったことから、石黒は渡部を知っていた。思いがけぬことから、さらに話がはずんで、英世はおおいに愉快な一夜を過ごした。
もちろん、このとき、英世は自分を売り込むことも忘れていない。後年、石黒老は野口英世追悼会の席上で、「一目見たときから、尋常一様でないと思った」と、讃辞を呈している。
こうして、フレキスナー教授教授一行の案内役として、英世は所内に存在価値を示したが、それもつかの間、この直後に不快な出來ごとがおきた。
順天堂に続いて、北里研究所でも、英世は図書の整理係を命じられていたが、たまたま図書の在庫調べがおこなわれることになった。このとき、英世は自分の立場を利用して、重松という友達に、五冊の本を貸していたが、このうち三冊は原書で、うち二冊は研究所員も持ち出し禁止の医学全書であった。
英世は慌てて、重松に返還するようにと要求したが、すでに売却したり、他人にまた貸しして、彼の家には一冊もなかった。無い以上、当然、英世が弁償すべきだが金はない。万一持っていたとしても、そう簡単に手に入る洋書ではない。ここで英世は図書係としての責任を追及されることになった。
英世はうっかり貸した友人が悪かったと、しきりに弁明したが、素直にききいれられなかった。それどころか、自分が持ち出して売却したのを、なにやらわからぬ人に貸したとしていい逃れをしているのだろうと、疑われた。
「百姓の倅で、大学を出ていないごどから、こんな差別を受けるんだ」
英世は憤慨したが、疑われるにはそれなりの理由もあった。
日頃から、英世は勉強するが、公私の区別なく、勝手に図書を持ち出し、ときには同僚のものも平気で持っていて、何日も返さず、紛失したものもあった。所員への金の無心も相変らずである。
そんなだらしなさを知っている所員が疑うのは無理もなかった。この問題はついに北里所長の耳にまで入り、呼び出された。
「貸した相手のことはともかく、官有物を貸し出し禁止という取り決めがあるのに、所員以外の者に貸し出したこと自体が、すでに無責任ではないか」
北里所長は英世を叱り、図書係を解任し、しばらくはこの問題は預かりおく、と告げた。
いままでも、あまり楽しくなかった研究所が、このときから、英世にとってはさらに住みにくいところとなった。
日頃から、自分のとくになることだけ求め、先んずることばかり考えていた英世のエゴスティックな態度に、こんなとき周囲の反感がふき出してきた。所員達は、やはり医術開業試験あがりは駄目だとか、育ちの悪さは争えないものだ、と陰口をきく。いまや同期の秦佐八郎さえ相手にしてくれず、英世はますます楽しまぬ日を送らざるをえなくなった。この一か月後、北里所長は英世を呼んで、横浜に新設される海港検査所に勤めてみてはどうか、とすすめた。
当時、海港検疫の重要性がようやく認識され、横浜、神戸、長崎、門司に設立されることになり、伝染病の専門家が必要とされていた。
「検疫所に行けば、給料は月三十五円、いまより二十円も上るし、検疫官として充分の待遇もしてくれる」
北里所長のこの誘いは英世の才能をかってか、あるいは図書紛失事件の責任を問うてか、判然としない。細菌学の研究者の本道からいえば、検疫所行きは左遷ではあるが、しかしそのほうが、英世がやりやすいだろうという、一種の温情とも受けとれた。
いずれにしても、このまま研究所にいたところで、他人に仕え、妥協いていくことの不得手な英世が伸びていく余地はほとんどなかった。
「仰言るとおり、横浜へ参ります」
英世が検疫所行きを納得したのは、その二日あとだった。
第六章 横浜検疫所 P.190
1
「検疫」とは名のとおり、疫病、すなわち伝染病のひろがるのを予防するため、外国から入ってくる人や品物について検べることである。もちろん疑わしいものがあれば、診断のうえ菌の検出をおこない、伝染病と判明すれば、ただちに消毒し隔離しなければならない。これら一連の業務は海港検疫法で定められ、それによって厳密におこなわれる。
鎖国を解いた日本において、まず第一に整備しなければならなかったのは、この海港検疫業務であった。
明治政府は明治三十二年四月、新しい法令にもとづいて、まず横浜海港検疫所を設けた。場所は一応、神奈川県庁内に仮設されたが、実際の検診、消毒、隔離といった作業は、県庁から南へ十キロ離れた長浜海岸の長浜消毒所でおこなわれた。ここは現在は、横浜検疫所長浜措置所と名将は変っているが、横浜の金沢八景に近い、富岡を背にした美しい海岸沿いにある。
敷地だけで約二万坪といい、そこに事務所から上級船員宿泊室、下級船員宿泊室、浴場、さらに南の山かげには隔離病棟、検査室、研究室の大半が、ほぼ明治時代そのまま残っている。
海港検疫所とはいえ、当時は日本の表玄関であり、建物にもずいぶん気が配られている。とくに上級船員宿泊室は、海側に広いロビーをともなった一室三ベッドのゆったりした部屋で、応接室、談話室もあり、風呂も室一つ宛て備えられ、近代的ホテルと較べてもさして遜色ない。藤棚のある庭からは、多行松の並ぶ芝生の先に、長浜の海が展がり、その彼方に房総半島の先端が望まれる。
宿泊者のないときは、ここでよく洋式の宴会が開かれ、与謝野鉄幹、晶子夫妻なども度々来ていたというが、たしかに海と松の庭に面して立つ白塗りの洋館は、当時としては、ずいぶん瀟洒な建物であった。
外国人を慰めるといいながら、実際は日本の高官が、別荘のように利用していた。
これに対して、南の下等浴場や隔離病院のある側は、山ぎわのせいもあってか、さすがに暗く、ひっそりしている。それで隔離病院は、一室三人のゆったりしたスペースで、いまの病院の大部屋よりは、はるかに豪華である。この病院の手前にコンクリート建ての検査室があるが、ここで野口英世は終日顕微鏡を覗いて頑張った。
かつては、この病院の西百メートル先から、高級船員宿泊所まで、海岸線が迫り、船着場が二つあった。ここには、検疫所専用の小舟があり、外国船が入ってくると、一旦、この沖合に停泊させ、検疫官がそれに乗って、停泊船にのりこんだ。そこで伝染病の予防接種をしていない者は、宿泊所に滞在させ、病気の疑いのある者は隔離病院に収容した。
宿泊所に収容された船員は、各種の伝染病の潜伏期間の十日から二週間、留められたうえ、異常なし、と認められて、初めて正式に上陸が許される。したがって、ここは異国からきた外人達が、日本の土に触れる最初の場所であった。日本にはきたが、半月間、とくに用事もなく一か所に留めおかれる。その無聊を慰める意味からも、この建物や庭が吟味されて造られたのは当然である。
だが、現在、この宿泊所も病院も、実際には使われていない。鍵をかけられたまま、措置所入口にいる守衛さんが、管理しているだけである。現在では、入国カードが完備し、伝染病の予防接種をしていないで入国してくる者は、まずありえない。余程の後進国でも、伝染病に対する措置はかなり行き届いていて、コレラやペストなどの患者が入ってくることは、まずありえない。
それでも、万一、これらの患者が発生したら収容する、外国専用の隔離病院が現在日本にはない。横浜の隔離病院が、昭和三十八年に一度使われただけで空家同然のままなお残されているのは、そうした新しい隔離病棟の設備が欠けていることと無縁ではない。
しかし、途中、何度か手をくわえられているとはいえ、明治時代から七十数年を経て、宿泊所も病院も老朽化ははなはだしい。すぐ近くに迫っていた海も、埋立工事で、ほぼ一キロ先に押しやられ、往時の華やかさは偲ぶべくもない。
最近、横浜市では、この一帯を長浜公園として甦らせようという考えらしいが世界の環境衛生の発達とともに、すでに無用の長物と化したいまとなっては無理もない。ただその際、野口英世にゆかりのある検査室だけでも残し、野口記念館として再生させたい、という案が、現横浜検疫所の岩田所長などを中心にすすめられている。
それが実現すれば、野口英世のゆかりの地が、いま一つ世に出ることになる。
明治三十二年、野口英世がこの横浜検疫所に来たとき、所長は飯尾次郎、検疫医官星野乙郎、海港検疫官として元神川県警部だった横山信徴らの名前が見える。
英世は検疫医官捕だから、実質的には、星野医官の下にいたことになる。ここに着任したとき、英世の月給は三十五円であった。
いままでの北里研究所の給料のほぼ倍額である。当時、月六円あれば、食事つきの一応きちんとした下宿にとまれたいうのだから、結構な丘陵ではある。
英世がここに移ったには、図書の紛失事件で、北里研究所にいづらくなったのが最大の理由だが、この高い給料にひかれたこともたしかだった。それに外国船員に接する検疫所にいれば、なにかの折、外国へ行くチャンスが訪れるかもしれない、という期待もあった。
ここにきて四か月経った九月の初め、英世は検疫のために長浜桟橋から消毒所の舟に乗って、沖合に停泊中の「亜米利加丸」に乗りこんだ。この船で、英世は船艙で高熱に魘されている二人の病人を見つけた。一人は中国人で一人は日本人である。まだ残暑が厳しい、三十度をこえる暑さだというのに、二人とも毛布にくるまったまま、絶えまなく襲ってくる悪寒に震えていた。きくと、三日前から、こんな状態が続いているという。
尋常な病気ではない、英世は震える患者を助手に押さえさせて診察した。胸から背、そして下腹まで探ると、両の股の淋巴腺が腫れてる。
「ペストじゃないか」一瞬、英世は患者の顔を見た。
ペストは一名、黒死病ともいわれ、当時最も恐れられていた病気の一つである。かつての伝染病がほとんど征服されたなかで、ペストはなお存在し無気味な怖さを秘めている。
この病原菌は鼠によって媒介され、発病すると、四十度をこす高熱と激しい震えが続き、やがて眩暈から吐気、そして意識が朦朧とし、ついには心臓まで冒されて一週間以内に死亡する。現在、東南アジア、アメリカ大陸の一部になお存在し、入港したとき、検疫官が船に行って、必ず鼠の糞や穴の有無を調べるが、これはすべて、ペストを恐れての処置である。
この病気で、特に多いのが腺ペストで、この場合は小さな傷口から侵入した菌により、各部の淋巴腺が腫れてくる。英世がペストを疑ったのは、二人の乗船員に、この症状があったからだった。
英世はただちに二人を、長浜の隔離病院に移し、血液と排泄物を検べ、同時に上級医官に、ペストの疑いがあることを報告した。
まだ衛生思想の発達してない明治時代とはいえ、ペスト発生は大事件である。西欧の文献に、ペストにより一町村や一地域が全滅したという報告は、いくらでもある。もし、この二人が真正ペストだとすると、日本初の上陸となる。横浜消毒所は極度に緊張し、病院の周辺は厳戒態勢がとられた。
はたして、本当のペストか。……
検疫所には単なる敗血症だと主張する医師もいたが、英世は断固としてペスト説を固守した。
これより五年前(一八九四年)北里柴三郎は、A・J・イェルサンとともに、ぺスト菌を発見していた。いわばペスト菌に関する世界一の権威が、すぐ身近にいたわけである。
ただちに北里研究所から、志賀潔等が隔離病院に現われ、患者の血液、排泄物を顕微鏡で追った。そして最後に、北里柴三郎自ら数十枚の標本を丹念に検べた結果、この二人をペストと断定した。
英世の見通しが正しかったのである。
ここのところを、従来の伝記では「野口英世あすすんで船に乗り込み、疑問視する他の医者を振り切って、日本で最初のペスト患者を発見しました」ということになっている。
だが、これは少し褒めすぎで、たしかに、英世は船にのりこんで患者を発見したが、夏に高熱で魘され、悪寒戦慄があれば、伝染病を疑って隔離病院に収容するのは、当たり前の処置である。そのとき、淋巴腺が腫れているのをみて、ペストを疑うのも、検疫官ならば当然のことである。
反対した医師も、その程度の知識はもっている。ただ怪しいと疑ったうえで、断定はできないとためらっていただけのことである。
病気の最終決定は、患者からその病気の菌が検出されたところで決まる。チフスらしい患者から、チフス菌が発見されたらチフスと断定していい。
菌を発見し、その種類を定めるのを「同定」という。このとき、最終的にペスト菌発見し、同定したのは北里柴三郎その人で、英世はなんの関係もない。事実、この日本疫学史上に残るペスト騒動の記録に、野口英世の名前は一字も出てこない。
検疫所医師の最下級の医師補では、名前が出るわけもないし、北里以外は見たこともないペスト菌をそう簡単に同定できるわけもない。したがって、このペスト事件については、「英世が日本最初のペスト患者を発見した」というのではなく、「英世がペストらしい患者に初めて接した」と改められなければならない。
一般に学識豊富な学者ほど、みだりに断言はしない。豊かな知識が、ドグマを避けさせる。この論からいえば、高熱と淋巴腺の腫れだけで、ペストと断定するのは、いかにも大胆すぎた。一度でも診たことのある病気ならともかく、全然診たこともないものを、臨床所見だけでそう簡単に断じられるものではない。結果として、当ったからいいようなものの、当らなかったら恥をかくところであった。
発見は、早いにこしたことはないが、早まってはいけない。この、ドグマを恐れぬ功名心が、後年、英世の学者としての生命を縮めることにもなった。
ところで、このペスト騒動には、もう一つ余話がある。
ペスト患者は運よく、この横浜で発見されたが、「亜米利加丸」はその三日前、神戸港に入港していた。神戸にも、横浜と同様、海港検疫所があったが、こちらでは肝腎のペスト患者が見逃されていたことになる。この問題は大きな反響を巻き起し、ただちに国会でも取りあげられ、国の検疫体制の不備が追及された。このとき、答弁にたったのが、衛生局長をやっていた長谷川泰であった。長谷川は質問した議員を壇上から睨みつけて、
「検疫医官の給料を三、四十円にしておいて、港に入ってくる船、すべての検疫をやれってのは気違い沙汰だ。伝染病が入ってくるのが恐ければ、まず医官の給料三倍にすることだ」と、逆に反撃した。
いま、こんなことをいったら、たちまち失言騒ぎだが、当時は万事鷹揚だった。質問した議員もこの意見に納得し、翌年から検疫医官の給料は、ほぼ倍増になった。英世には願ってもないことだが、残念ながら、英世はこの恩恵に浴さぬうちに、横浜検疫所を辞めてしまう。
2
このペスト騒動があった翌月の十月の初め、英世は突然、北里所長から、すぐ来るように、との電報を受けた。
英世がすぐ横浜から芝の研究所へ駆けつけると、北里所長はいきなり、君は、清国へ行く気はないか?」ときいた。
「といいますと……」
「いま清国の牛荘でペストが流行しておるが、最近、その地の各国領事館員が集まって、国際予防委員会というものを組織した。そこで向うの衛生局から、是非、そのメンバーとして日本人医師を招きたいといってきておる」
”日本でペスト患者発見”という報道は清国にも知れわたったらしい。
「もし行くなら、向うでは、月給二百両を払うといっている」
英世は少し考えて、「行きます」といった。考えたのは、行くべきか否かでなく、二百両あれば、何ヵ月でアメリカへ行く旅費が貯まるかということだった。当時の清国の二百両が、日本円でいくらくらいに価するものか、一両一円と単純に計算しても、検疫所の給料の六倍近くになる。
「是非、行かせてください」
話はそれで簡単に決まった。
この清国行きは、もちろん北里所長個人の推薦である。日本からの医師は、同じ伝染病研究所の村田昇清博士を団長格に十五名で、いずれも伝研、東大の俊秀ばかりであった。このなかへ、英世をくわえたところをみると、大学を出ていないとはいえ、英世のエネルギッシュな行動力、そして語学力を、北里所長が高くかっていたことがわかる。
清国行きが決まって、英世がまつ先に考えたのは、同郷の山内ヨネ子に逢うことだった。以下略。
第七章 清国・牛荘 P.203
1
九月の末、英世は正式に、横浜海港検疫医官補を辞職した。五月に北里研究所より移って、わずか四か月に満たぬ勤務であった。
辞職と同時に、彼は清国牛荘行きの旅費および支度金として、九十六円をもらった。
旅費は、清国行きの舟が神戸から出る予定になっていたので、全員は一旦、神戸へ集結する。当時、東京から神戸までの汽車賃は三円少々であった。したがって、あと九十余円が支度金として与えられたことになる。
そのころ、安い背広が上下一着の値段が、三円くらいであったから、かなり高額の支度金である。これと九月分給料や退職手当をいれると、いっとき、英世は百五十円近い大金を持ったことになる。
だが、この大金が、十月の半ば、神戸出港の折には一銭もなくなっていた。
これについて、英世は、いままでの借金が多すぎて、債鬼にたちまち奪われてしまった、といい訳している。
事実、英世に金が入ったらしいときくと、高利貸から高山歯科医学院、順天堂、北里研究所などの同僚達が一斉におしかけてきた。
こんなわけで、退職して半月経った十月半ばに、旅費も支度金もふくめて、百円余の金は、きれいになくなっていた。
「困った……」
いまや集合地の神戸まで行く汽車賃さえなかった。もちろん、衣類やバッグなど、旅行に必要なものもない。すべてを費いきって、英世は初めて悩む。これは大変なことになったと気が付く。
金策がつかぬうちに、やがて十月十六日、村田昇清を団長とする一行は英世一人をおいて東京から神戸へ向けて出発した。一行は神戸で関西からの学者と合流し、結団式を終えたあと、十九日、神戸発の船で出帆する予定になっていた。これに遅れたら、清国行きは駄目になる。それどころか、支度金だけとって逃げたことになり、学界からは完全に抹殺される。
思いあまった英世が、結局、泣きこんだ先はまた血脇守之助のところだった。
「ご恩は決して忘れません。本当にこれが最後です」
そんなことをいいながら、「最後」がもう十回を軽くオーバーしている。
このとき、守之助は結婚して世帯を持ったばかりで生活はかなり苦しかった。独身のときならともかく、妻がいては、そう金は自由にならない。
英世がそれこそ借りてきた猫のように小さくなって、苦衷を訴えるのを守之助は黙ってきいていた。
やがて英世の話が途切れたとき、「じゃあ、少し待ちたまえ」といって、立上った。それから小一時間後に、十五円の金を英世の前においた。
「いまはこれしかない。これだけあれば、一応、背広やコートを買って、神戸まで行けるだろう」
「これ、どうしたのですか」
そのとき。守之助の妻が新しい茶を淹れてもってきた。まだ初々しい二十一、ニの新妻だったが、一時間前とはまるで違う。いかにも不快そうな眼差しで英世を睨み、茶のおき方も邪険である。
そういえば、ニ、三十分前、奥の部屋で、守之助と妻がいい合っているのを、ちらときいた。そのあと、妻が出て行き、それから帰ってきて、すぐ十五円が差し出された。
「まさか、奥さまの晴着を質屋にいれて得たお金ではないでしょうね」
「そうだったら、どうするのかね」
「いえ……」
口籠ったが、いまは質屋から借りてきた金であろうと、貰わないわけにはいかない。
「わたしは、これから神戸に行くだけですから、こんなにはいりません。五円あれば充分です」
英世はそういうと、一旦、懐にいれかけた十五円から十円を戻した。
「まあいい、折角十五円つくったのだから、もっていくといい」
血脇守之助の偉いところは、英世に倹約せよとか、貯蓄しなければいかん、とお説教をしないところだった。相手の要求額はともかく、一応、自分で出せるだけの金は出す。もちろん、英世の場当り的ないいわけもきいていなかった。
気持ちが大きいといえば大きいが、英世の浪費癖は、もはや説教くらいでは治らないとあきらめていたのである。
「本当に五円あれば大丈夫です。船さえ乗ってしまえば、住むところも食べるもんも、すべて無料ですから。
さすがの英世は、今度だけは全額もらいかねた。
「それでは、出発祝いにこれをやろう」
守之助は自分の書斎から、かつての盟友友田原博士からもらった米国製のスーツケースをPyレゼントした。
「ご恩は一生忘れません」
同じ台詞をくり返して五円を手にした英世は、その足で日蔭町の古着屋へ行き、そこでプランコの背広上下を二円で買った。上下揃いといえばきこえはいいが、霜降りの夏服である。これに二十銭にまけさせたハンチングをかぶり、翌十八日、東京を発った。
これで発たなければ、十九日の神戸出港に間に合わない。ぎりぎりの出発である。しかも、このときもなお、英世が外国へ行ってしまうというので、借金とりが新橋スティションに待ちかまえているのを避けるため、わざわざ品川まで歩き、そこからようやく汽車に乗った。
もちろん見送る人は誰もいない。うつかり、出発時間を友達に告げると、借金をとりにくるから、教えられなかったが、ただ山内ヨネ子にだけは伝えておいた。
出発ぎりぎりまで、窓から顔を出していたが、ヨネ子はついに現れなかった。
2
英世が神戸に着いた日の夕方、船は早くも神戸港を発った。
みな、家族や知人とテープを交し、別れを惜しんでいるのに、英世一人、見送る人はいない。しかし、英世はそれを特に淋しいとも思わなかった。それより、これで債鬼の群がる日本から離れたと思い安堵した。
神戸を発った船は瀬戸内海を抜け、ほぼ一昼夜で門司に着いた。ずいぶん遅い航海だが、それでも当時としては外洋専属の豪華船だった。下関が日本最後の夜ということで、その夜一行は上陸し、下関一の料亭「春帆楼」にあがった。
ここで芸者を呼び、歓楽のかぎりを尽す。日本女性との逢瀬も、これが最後で当分望めそうもない。
一行はおおいに遊んだが、初めから割り勘という約束になっていた。宴たけて、やがて会費徴収という段になって、英世がいない。やむなく英世の分はみんなで出しあって船へ戻ると、英世はすでに先に帰って眠っていた。
このとき、もし金があれば、まだまだ遊んで帰船に遅れたかもしれない。あるいは一人なら借財が払えず、ひきとめられたかもしれない。金がなく、みなと一緒であったということが、かえって幸いだったといえなくもない。
やがて五日間の船旅のあと、一行は清国牛荘に着いた。
この間、みなはそれぞれ、日支辞典や日支会話の本を見ながら、中国語を勉強した。いずれも帝大出の、俊秀気鋭の学者だったが、中国語には弱かった。これら、本を片手に勉強する連中を尻目に、英世は一人船倉に下りて、下級船員の中国人と身ぶり手ぶりで話した。寝るとき以外はほとんど中国人と接していたが、苦力のような下級船員のあいだに、日本の偉い学者がとびこんできた、というので、おおいに歓迎された。
もっとも、おかげで相当不潔な部屋でまずいものまで馳走になったが、効果はてきめんであった。もともと、語学には天才的な能力の持主である。一週間後、牛荘に着いたときは、日常会話には、ほとんど支障のないまでになっていた。
牛荘は正しくは New Chuang と読む。中国東北区遼寧省遼河の下流に沿う都市で、清の成豊十一年(一八六一)に開港され、以来、満州と中国本部を結ぶ港として主要な役割をはたしていた。
別に営口ともいい、いわば中国の北の玄関口でもある。
ここに降り立った一行のなかで、野口英世は断然目立った。全員が冬の背広にコートを着こみ、山高帽などかぶっているのに、英世一人、霜降りの夏服に、ハンチングをかぶっていた。
受け入れた中国衛生局では、初め、英世を通訳と錯覚する、という笑えぬ一幕もあった。実際、彼は一行のなかでは、とび抜けて中国語ができた。迎えに出た中国人と、早速中国語で打合せをし、道行く人にも平気で話しかける。それが昨日今日、覚えたと思えぬなめらかである。
おまけに、英、独、仏語にも通じているから、自然重要な話はすべて、英世をとおして相談されることになる。
一行は牛荘から、この地区周辺の衛生局管理地に分散配置されることになったが、英世は、語学力をかわれて団長の村田昇清とともに、牛荘衛生局本部詰めになった。ここは、各分局医員への、指示伝達、監督するところだから、いわば衛生局の中枢である。
ここに腰を落ち着けながら英世は生来の積極さで、警官から知事らとまで親交を結び、邸に招かれた時に漢詩を贈ったりした。
これら医師団の一行は、牛荘におけるペスト撲滅を第一義として派遣されたものだが、彼等が着いたとき、ペストはすでに下火になりかけていた。
ペストは拡がり出すと一気に流行するが、終末もまた早い。それは季節が冬に移りかけて、寒気が幸いしたともいえる。英世達が行ってからは、新たなペスト患者の発生はほとんどなく、結果的に、医師団は牛荘一帯の一般医療、衛生行政にたずさわるということになった。
派遣された医師団は、日本人だけでなく、英、米、露など、白系医師も一緒だったが、なかで日本人医師は皮膚の色も近いところから、中国人に人気があり、一般患者もかなり押しけかてきた。特に英世の診療室の前には早朝から患者が長い列をつくった。
いうまでもなく英世は臨床医ではない。順天堂でも北里研究所でも、患者を直接診ることはほとんどなく、雑誌編集の手伝いや、細菌の培養、検出などを主にやっている。海港検疫所にいたから、伝染病に関しては多少の知識はあったが、一般の病気に対しては、ほとんど経験はない。その英世が人気があったのは、技術よりも、英世の診療態度が熱心で好意をもたれたからだった。よく相手の話をきき、何度も何度も脈をとり、聴診器を当てる。それらを、自分らと肌の色が同じ東洋人が中国語で話しながら診てくれる。
大抵の医師は中国語が話せず、助手か看護婦がなかに入って通訳する。それに白人の医師達は、初めから一般の支那人を真面目に診る気などはなかった。せいぜい高官や金持ちだけを、かなりの謝礼をとって診るくらいで、あとは医療行政にときどき口出しをするだけだった。それからみると、英世の誠実な診療態度は、群を抜いていた。この英世のエネルギッシュな、偏見のない態度を評価して、帰国直前、牛荘衛生局、国際衛生局は次のような感謝状を英世に贈った。
一九〇〇年六月廿八日
牛荘衛生局長 シセール・ハウラ
局員代表者 ドクトル・フィリッポ・ヤッセンスキイ、
ドクトル・デ・パルフ・デーリー
英世は派遣医師団のあいだでは、断然光ったが、臨床の患者を診ることが、楽しかったことも事実であった。
日本では医術開業試験あがりとして、ろくろく患者を診せてもらう機会もなかったが、清国では自由に患者を診ることができた。日本では厳存する差別も、外人医師団のあいだに入ってしまえば消えてしまう。生身の患者を、自らの手で診断し治療し、その経験を追う。面白いといえば語弊があるが、こんなやり甲斐のある仕事はない。本当は臨床医になりたかったのが、手の不具から、あきらめた無念さを、英世はいま異国で晴らしていた。
だが臨床だけでなく、英世は基礎研究も怠らなかった。牛荘滞在中、英世は「ペスト菌の寒冷に対する抵抗力の研究」なる論文を英文で書き、これを同僚医師と連名でアメリカのフレキスナー博士へ送った。こうして気力充実、臨床と研究に励んだ、といえばきこえはいいが、同時に、かなり遊んだことも事実である。
大体が、当時の中国は遊興にはこと欠かず、おまけに月給は二百両という高級とりである。じっと宿舎にいろ、というほうが無理である。
牛荘の歓楽街は、いわゆる城外にあり、そこへ行くには、門を出て行かなければならないが、深夜はすべて門が堅く閉ざされる。研究に没頭していて気がつくと、すでに門が閉じた時間になる。遅いから明日にでも思っても、一度行きたいとなったら抑えがきかない。明日ということは信じられない性質だし、なによりもエネルギーがあり余っている。
ついに英世は石壁をよじ登って出かけることを覚えたが、二度目に運悪く警邏中の衛兵に掴まって留置された。結局、翌朝、派遣日本医師であることが証明されて釈放されたが、その後も何度も塀をのりこえた。
こうして二百両の高級は、消えてしまう。
初めの、清国に行けば渡米旅費がつくれるという夢も、たちまち怪しくなった。
「これではいかん」一時は、人並みに自分を責めるが、遊び出すと止まらな。
「金など、明日になれば、またどうにかなる」と思いこんでしまう。
英世が本気に、金を貯めなければいけない、と思い出したのは、清国に渡って半年余がすぎたころだった。それも、来月一杯で契約期間が切れるという、ぎりぎりのときである。
「このまま無一物で帰るのでは、はるばる来た甲斐あない」
英世が暗澹とした気持ちになっていると、折よくロシア衛生局から、われわれのところで働いてくれないか、という誘いがあった。
滞在半年で、英世はロシア後をマスターしていたが、条件をきくと、いままでに優る三百両である。
英世はこの話にとびつき、日本人助手一名とともに派遣団と別れて残ることにした。こうして三か月、さらに滞在を延長したが、金は残るどころか、むしろ借金が増えていく。
結局、牛荘の治安状況が悪化し、ロシア隊も引き上げ、英世は帰国することになったが、その間、英世が残したのは、料亭への借金証書ばかりであった。
第八章 神田三崎町 P.215
1
野口英世が中国牛荘から日本へ帰ってきたのは、明治三十三年七月である。ここで英世はどこにも勤めない自由の身になった。
本来、清国派遣の医師団は、それぞれの勤め先を一時休職の形で出向き、帰国すると再び前の勤務先に戻る、いわゆる「出向」の形ででるのが普通であった。事実、団長の村田昇清氏も、帰国後、再び伝染病研究所に戻っている。
だが、英世だけは、横浜検疫所を退職して行ったので、帰国後すぐ勤めるところはなかった。
それには事情があり、英世も希望すれば、検疫所は一時休職にし、帰国後、すぐ復帰できる形で行くこともできた。英世は帰国後再び検疫所に勤める気はなかった。諸外国の一流医師と清国に招かれた以上、また検疫所の医官補に戻るのでは淋しすぎる。
清国から帰ってきたら、大学や研究所から引く手あまたに違いない。それに月二百両の高給で一年もいれば、かなりの金が貯まるはずだった。それでアメリカに渡るのが、第一の目標だった。さらにいえば、一旦、まとまった金をみて、借金を返しておきたかった。だが、いま戻ってきてみるとそれらすべては、画に描いた餅に帰していた。
例の浪費癖で、アメリカに渡るほどの大金はできなかったが、それでもニ、三か月、遊んでいられるくらいの余裕はあった。金があれば、堅苦しい研究所勤めなどに戻る気はしない。
英世がこのとき、まっ先に考えたことは、山内トヨ子に逢って、正式に結婚のプロポーズをすることだった。(P.216)
清国から帰って、まっ先に駆けつけたのに、居留守を使われたのでは立つ瀬がない。
それほど俺を嫌いなのか……。
それ以来、英世は二度とヨネ子を訪れることはなかった。
2
ヨネ子との恋に破れた英世は、この直後、三城潟に帰省した。失恋の痛みを癒すという意味もあったが、しばらく外国へ行っていて、急に故郷が懐かしくなったのである。それに、外国で第一級の待遇を受けたことを吹聴したい気持もあった。失恋したらその感情だけに止まっていない。そこからすぐ脱却し、新しく動くことを考える。その気分転換の早いところが、英世のよさでもあり、逞しさでもあった。
この帰郷のとき、英世は背広上下に鳥打帽をかぶり、手に皮のバッグを持っていた。突然の帰郷で迎える者もいない。磐越西線の鈴島停車場から一里半の道を歩き、湖畔の三城潟に着く。
生家の隣りの松島屋の前まで来ると、幼友達の代吉が、馬鈴薯を選んで笊に入れていた。
「久し振りだな」
英世が肩を叩いたが、代吉はぽかんと見上げたがなにもいわない。
「俺だよ、清作だよ」
「ああっ、野口の清作さんが……」
代吉は、はじめてうなずくと、改めて英世を上から下まで見渡した。
「なんだ、洋服来て立派になって、とってもわかんねぇべ」
外国から帰ってきたんだよ。もう少し立派な洋服もあるんだが、人力車がないと汚れんてなぁ、無理に悪いのを着てきたど」
例によぅて、英世の法螺がはじまる。だが代吉は素直に信じる。
「清作さんが、偉くなって洋服着てけえってきたど」
叫びながら、村中に告げて歩いた。
その夜、三城潟の小料理屋に、旧友や村の顔役など、十数名が集まって、盛大な英世の歓迎会が開かれた。山内ヨネ子に拒否され、卑劣な借金魔と罵られた男も、故郷に帰れば、「外国にまで招かれた伝染病の大家」として、村一番の出世頭であった。主賓の席に坐らされた英世は、次々に注ぎにくる村人の盃を受けながら、上機嫌になり、日本はじめ、米英露など、各国の高名な学者と研究したこと、支那の高官に招かれて歓談したこと、料亭での豪華な遊びなどを話した。
みなは、うなずきながら、憧れと尊敬の眼差しで昔の清作をみつめる。
ますます愉快になった英世は、現地で覚えた清の唄を歌い出し、さらには、躍りまで披露した。
座は賑やかになり、ついに全員が英世に従いて踊り出す。失恋の痛手など、思い出す間もない、乱痴気騒ぎになった。
翌日、二日酔いで寝ていると、代吉が、「清さん、疲れでっとこ済まねげんとも、村の病人を診てやってくんねぇが」と頼みに来た。外国に招かれるほどの伝染病の大家なら、治らない病気も治してくれるのではないか、と村人達がいっているという。
正直いって、英世には臨床には自信がなかった。牛荘でやったとはいえ、一時的なもので、本当の実力がないのは、英世自身が一番よく知っている。
「僕は、おっかと、おめらの顔を見だくて帰ってきただけのだ」英世がいうが、代吉はあきらめず、
「んでも、清さんが医者になったら、お天道様が、西の愛宕山から昇るって、みんな笑ってだんだ。俺は口惜しくて、ほいづらに、しっぺげぇししてやりだくて」、
代吉の言葉をきいて英世の負けず嫌いな性格が頭をもたげた。
「よし、ほんなら診てやっぺ」
「ありがでぇ、俺あすぐ、みんなに報せでくつから」代吉は手を叩いて駆け出した。
翌日、松島屋の奥の一室で、英世の診察がはじまった。小さい村だから、口コミだけで充分拡がる。しかも、外国まで行ってきた名医の無料奉仕だというので、五十人近い患者が押し寄せた。
薬も注射も持っていない英世は、診察したあと若松の森川薬局に宛て、処方箋だけを書いて渡す。無料の上に、丁寧だということで、この診察は、大評判であった。
野口英世の一部の伝記には、これで佐藤某の性病や、山崎某の心臓病など長年の難病が一度に治り、いずれも長生きしたと書かれているが、これは眉唾である。英世の書いた処方箋の薬を、薬局からもらったぐらいで、それらの病気が治るわけはない。もし治ったとしたら、梅雨時の季節の移りとともに、いっとき落ち着いただけで、完治とはいいがたい。
それはともかく、この治療で、太陽が愛宕山の方から昇るという連中も黙り、代吉や母のシカが面目をほどこしたことはたしかである。
この診察の翌日、英世は八子弥寿平の家に、自分から訪ねていった。
今回の帰郷は、故郷への懐かしさが第一であったが、みなに歓迎されているうちに、英世は別の考えが浮かんできた。
もしかして、弥寿平に頼むめば、渡米の旅費を調達してもらえるのではないか。
それは東京を出るときから、考えていたわけではなかった。いかな英世も、さんざん迷惑をかけた挙句、いままた、渡米費用までねだるほどの厚顔さはなかった。
だが、帰郷して、人々の歓待を受けるうちに、英世の考えが変ってきた。これだけ、村人達が熱狂しているところをみれば、弥寿平なら、金を工面してくれるのではないか、英世は次第に生来の図々しさを取り戻した。
久し振りに遇った弥寿平は、例によって甲斐甲斐しく英世をもてなした。いままでは口先だけで、実態をしらなかったが、実際に診療してみせたのである。しかも、外国まで行ってきた名医だという肩書もある。いまはすっかり偉くなった英世を、弥寿平は神様のように思い込んでいる。しばらく昔話を語り合ったあと、英世はおもむろに切り出した。
「実は、アメリカの伝染病学の第一人者であるフレキスナー教授から、是非来てくんねぇか、と呼ばれてるんだ」
「それ、本当がぁ」
弥寿平は目を丸くしている。中国に行ってきたのさえ、大変なことだと思っているのに、今度はアメリカの大学者に招かれている、というのである。
「俺の論文に感心して、一緒に研究をしようど、いってきたんだが、なんせ、アメリアに行ぐにはお金がかがっからなあ」
「それ、どのぐれぇかがんだ」
人のよい弥寿平は、たちまちのってきた。英世はなお、アメリカ医学や、フレキスナー教授の偉いことを吹聴してから、
「五百円あればアメリカに行って、世界一流学者になれんだげどなあ」
「五百円かぁ……」
「アメリカに行けば、いくらでも銭は入る、いま貸してくれる人がいだら、俺は一生、その人のご恩は忘れないつもりだ」
作戦は図星だった。しばらく考えたあと弥寿平は自分からいい出した。
「その銭、なんとか工面してみっか」
「おめ、貸してくれるのか?」
「ああ……」
「済まねぇ、一生恩にきるぞ」
英世はいきなり弥寿平の手をとると、ぽろぽろ泣き出した。こういうところ、特に演技というわけではない。このとき以外でも、嬉しくなったり感動すると、英世はすぐ涙を流した。そう思い込むと、すぐその気になれる、かなりナルスティックな性格でもあった。
喜んだ英世はたちまち陽気になり、あとは酒を飲み、唄」を歌い、その夜はそのまま弥寿平の家に泊った。
だが、この渡米費用は、意外なところからケチがついた。
翌日、恩師の小林栄の家に行ったとき、たまたま、渡米の話になり、弥寿平から五百円借りることを告げると、小林は急に腕を組んだまま黙り込んだ。
「本当に、八子君が工面するって」いったのか」
「近いうちに、なんとかしてやるっていってくれました」
「それは、止めたほうがいいど、人の援助でアメリカに行ってどうすんだ、いつも他人を頼りにする、ほんな生活ばっかり続けていだら、やがて自分が駄目になる。いま五百円の金を借りて、アメリカに行って、誰が一体、八子に返すんだ。自分で自分の道を切り拓くんだったら、初めから最後まで、ぜんぶ自分の力で切り拓いたらどうなんだ」
これまで、ほとんど小言をいわなかった老校長の眼に、怒りが溢れていた。
「人のごどばかり頼りにしてっと、人間がいやしくなる。人間の品性がいやしくなる。人間の品性がなぐなくなる。おめが将来、世界の大学者になんだったら、まずそごから鍛え直さねばなんね」
さすがに、小林は、英世の実態を見抜いていた。口先や手紙では、うまいことをいうが、肝腎の性格がふしだられで、人に迷惑をかけて平気でいる。これではいくら偉くなったとしても、人間として尊敬されない。いつかいってやろうと思っていたのが、機会を得て、ほとばしり出た。
「おめがいくら学問があっても、人がらもの借りるかぎり、おれはおめを尊敬でぎねぇ」
小林の言葉は、さすがに英世にこたえた。いくら不義理を重ねても、偉くなりさえすれば人々は感心して見逃してくれる、そう、たかをくくっていたのが、そうでない男がいた。しかもそれが、「父上様」などと、大袈裟な表現をしてきた小林校長である。
「申し訳ありません」
「自分自身がいだんねのに、他人の力を頼りにするのは間違いでした。渡米旅費のごどは、もう一度初めから貯えで出直しまう」
「おめはまだ若げぇ、これからチャンスはなんぼでもある」
小林の励ましに英世はうなずいたが、それで英世の性格が根本から治るかどうかは、また別の問題である。
3
会津から東京へ帰ってから、英世は小林栄に約束したごとく、自力で渡米旅費を調達することを考えた。当時、横浜からホノルル経由でサンフランシスコまで十六日間の船賃は、三等に載ったとして六十円であった。これにアメリカ大陸横断の汽車賃、さらに着いた当座の生活費などを考えると、二百円の金が必要になる。
この金をどうして得るか、考えたところで、英世は具体策はない。
大体、英世は小さいときから、自分で働いて金を得ることのない男であった。
ある伝記によれば、「磐梯山の麓の貧しい農家に生まれ、小さいときから猪苗代湖で、しじみ貝を採り、それを売り歩いて……」といった貧乏物語が延々と述べられているが、英世がしじみ貝を売った、という事実はないし、もちろん土のかけらもいじったことはない。手は不具だが頭は賢い、ということで、母のシカは、英世を勉強一筋に向かわせた。たしかに生活環境は貧しかったが、勉学だけしていればよかった。その意味では、英才教育を受けたともいえる。
物心つき、小学校から高等小学校、さらに上京しても、常に他人からの援助で学問を続けてきた。勉強する代償として金を与えられる、という屈辱さえ、乗り切ってしまえば、こんな恵まれた環境で、勉強してきた男も珍しい。
この甘やかされた環境が、海港検疫所に勤め、牛荘で高級をとろうとも、金を残せなかった原因の一つであった。
小林栄に誓ってはみたものの、結局、誰からか金を出してもらうことを考えるより手段がない。
誰がいいか、思いめぐらすうちに、また小林栄の言葉が甦える。
「人に頼ってはなんね」
そうか、と思い反省するが、またすぐ、スポンサーを見付けることを考える。
どう改めようと思っても、自分から汗水垂らして働く方策が浮かばない。まこと、英世が「男芸者」と、陰口を叩かれたのは的を射ていた。
そうこうするうちに一か月が経ち、気がつくと、手許には一銭もなくなっていた。牛荘から帰ってきたとき、百円近くあった現金が、一か月であとかたもなく消えていた。
それでも、故郷へ帰ったり、東京に一か月余いて、百円だから、英世にしては、長もちしたほうである。金が失くなって、さてと考えて、行くところは結局、血脇守之助の家しかなかった。
当時、守之助は神田三崎町にいた。ここで治療所と住宅を一緒にして住んでいたが、この跡は現在の三崎稲荷神社の現在地と一致する。
「また来たか」
守之助にとっては「窮鳥再び舞い戻る」といった感じである。
「なにか、勤め口はないでしょうか」
半年前、清国行きに先立って、神戸までの旅費もなく、守之助が工面した五円を借りていたことなど、もう忘れた顔である。
「変りばえしないが、東京歯科医学院の講師でよければ、なんとかしてやるが……」
このとき、かつての高山歯科医学院は、神田に移り、東京歯科医学院の名前が変っていた。
「それで結構ですから、明日がらでも勤めさせて下さい」
「しかし、清国の衛生予防会に招待されたほどの君が、なにも僕のところにお勤めなくてもいいと思うが」
守之助の疑問は無理もない。清国派遣の医師団は、いずれも優秀な伝染病医学の権威者であった。帰ってきても、大学や研究所へ戻る気になれば、簡単に戻れるはずだった。
だが、この世界のボスである北里柴三郎は、英世が、一旦、退職しているのをいいことに、一言も声をかけなかった。英世がもはや日本で勤める気はなく、アメリカへ行く、と豪語していたことにも原因がある。一人で行くといっている者を、こちらから援けてやる必要はない。それに牛荘での英世の悪評が、かなりあくどく北里の耳に入っていた。
英世はたしかに中国語をあやつり、中央病院で一生懸命働いた。最後には、予防委員会から感謝状までもらったが、同行した日本人医師団では顰蹙をかっていた。
仕事には熱心ではあるが、抜け駆けが多すぎる。同行団では大学を卒ない、医術開業試験上りの最下位であるのに、語学ができるのをいいことに、中心人物のように振る舞った。さらに牛荘の警察、知事といった高官と付き合って、自分を売り込むことに専念する。はては連夜遊び歩き、借金を踏み倒す。要するに、身の程を弁えず出すぎたのである。
以前から、仕事熱心だがくせがある、と睨んでいた北里は、帰国後の英世を徹底的に無視した。向こうからくるなら、食べていく程度の仕事を与えてやるが、それ以上は構わず、といった態度である。
英世はもちろん、そのあたりの空気を知っていた。
退職し、帰ったらすぐアメリカへ行く、などといったのは、いい過ぎであった。金を貯められない己の性格を知っていれば、もう少し控え目にしておくべきだった。
ともかく、伝染病学界の大ボスである北里柴三郎に睨まれたのでは、どうしようもない。一旦、糊口をしのぐとしたら、東京歯科医学院しかない、清国で一時は三百両の高級を食でいた英世は、いま再び、東京歯科医学院の二十円そこそこの給料に甘んじることになった。
4
神田三崎町の東京歯科医学院に舞い戻った英世は、再び歯科医学生を相手に講義をはじめた。
英世は東北会津の出身だけに、生涯、その言葉には色濃く会津訛りが残っていた。東京の学生達は、英世のこの訛りをきいて、ずいぶん笑った。
なかでも、「此処……」というのを「ここんとり……」というのが勇名で、生徒達はよく真似、なかには「ここんとり先生」と呼ぶ者もいた。英世が外国語に堪能いなった一つの理由は、この方言へのコンプレックスもあった。
ともかく、東京歯科医学院で働きながら、英世が狙っていたのは、あくまで渡米である。
だが、現実に、金策の目途はまったく立たない。
牛荘から帰った当初、もっていた小銭はとうに費い果たし、学校からの給料では、その日その日、暮していくだけで精一杯である。
焦りながら日ばかり過ぎていく。
たまりかねた英世は、またまた血脇守之助の前に出て渡米費用の調達を依頼した。どう考えても、結局、頼るところはここしかなかった。だが守之助に、そんな大金があるわけがない。当時の守之助は、東京歯科医学院を引き継いだばかりで日も浅く、少な生徒数に対する経費のやりくりで追われていた。
「困ったな」
ありありと困惑の表情を浮かべながら守之助は真剣に考える。このあたりが、血脇守之助の偉いところで、借金魔がまた借金を申し込んできたからといつて、一概に退けない。英世にとって、それが必要な金か否かをみきわめる。
たしかにこのまま東京歯科医学院で埋もれていたのでは、英世の学者としての生命は、中途半端に終ってしまう。これまでの努力が水泡に帰す。帝大を出ず、しかも奇行の多い英世では、もはや日本では受け入れられそうにもない。このあと大成するとしたら、外国へ行くより方法はない。守之助はそこまで見通していたから、英世の願いが、突飛なものとは思わなかった。
日常の遊ぶ金はともかく、今度の金だけはなんとか工面してやらなければならない。実際、そうでもしなければ、いままで英世に注ぎ込んできた守之助自身の金も、無駄金になってしまう。考えた末、守之助は諸外国の事情にくわしい日本医事週報社社長の川上元次郎に相談した。
川上は野口の癖のある性格も、金のないことも知っていた。由緒正しい医学者連中から爪はじきされていることで、当時の英世はかなり有名だった。
「あいつは、どうせドイツ、フランスといった、まともなところにはむかん。大体そういうところへ行く金もないし、組織のがっちりしたところでは無理だ。いっそのことロシアにやったらどうだ」
「ロシアですか」
「そりゃ独仏にはかなわないが、結構偉い学者がおる」
「でも……」
いくら金のない異端児といえども、シベリアのイメージの強いロシアにやるのでは、いかにも可哀相である。
「本人はアメリカに行きたいと、いっているのですが」
「アメリカなど、ヨーロッパからみたら医学の植民地だ。行ったところでなんの役にも立たん」
当時の日本医学会の観方は、なにごともドイツが一番、次いでフランス、イギリスなどヨーロッパ、アメリカは数段下というのが一般的な観方だった。
「たしかに、そのとおりかもしれませんが、これから伸びていくという意味で、アメリカも面白いんじゃありませんか」
「伸びたとしても知れているが、ロシアがいかんとなると、アメリカしかないな」
川上は消極的にアメリカ行きに賛成した。それで行先は決まったが、肝腎の金は川上も持っていない。
「それでは金杉英五郎に会ってみてはどうか。彼なら出してくれるかもしれぬ。私から手紙を書いてやろう」
この金杉英五郎という人は、のちの慈恵医大の初代学長で、日本の耳鼻咽喉科の草分け的存在になった。当時は東京慈恵医院医学校の教授などやっていたが、剛直で世話好きな人だった。
川上は早速、金杉宛に野口英世の渡米費用工面方の依頼書を書いてくれた。守之助はそれを持って金杉宅に行く。金杉は手紙を見ると、
「昵懇にしている川上君からの頼みだから、断われないが、野口君が北里門下なら、北里に相談するのが先だろう。そこで彼が半額出そうというなら、自分もあと半額を出してもよい」と答えた。
川上元次郎は英世にニ、三度会ったことがあるだけで、個人的にはなにも知らない。金杉に至ってはなんの面識もない。そんな男の渡米旅費だが、知人を介して頼まれた以上断われない。恩師の北里が半分もつならば半分はもとうという、明治という時代は、さまざまな貧しさがあったが、一面、こうした鷹揚な、人生意気に感じる人も多かった。
だが、この計画は結局失敗に終った。このあと、守之助は北里博士を訪ねて、金杉の意向を伝え、資金援助を頼んだが、北里はにべもなく断った。
「金杉君個人が出すのは勝手だが、私は出しかねる」
北里が難色を示すことは、ある程度想像できた。牛荘から帰国以来、北里は英世を無視きっていた。同行の医師達から、現地での英世の独走ぶりをきかされて、不快に思っていたのである。英世としてもすぐ、謝りに行けばよかったものを、放っておいた。
そんな無作法な男に、北里が簡単に金を出すわけはなかった。
断わられた守之助は、再び金杉英五郎を訪れ、全額醵出方を依頼した。
だが、金杉は、「恩師の北里が信用していないような男に、私が出すわけにはいかない」といって、断わった。
この一連の経過をきかされたとき、英世は堅く唇を噛んだまま、天井を睨んでいた。
己の不徳のいたすところとはいえ、これが医学界を背景とした醵金に頼ることは、まず不可能に近くなった。
「ちくしょう」歯噛みしたところで仕方がない。
「日頃にすべきところに尽し、信用をえておかないからだ」
守之助が初めて小言らしい小言をいった。
絶望から次に英世が考えたことは、船医になって外国へ行くことだった。
このところ、英世が小林栄宛に書いた手紙に、この間の事情がよくうかがわれる。
偖而御老母様の摂生法中の要領に就き御下問被下候処、(略)
六角氏の御好意は奉深謝候、此事に就きては小生が帰郷(故郷より)之時、横浜に参り態々六角氏を訪問し(土産持参で)記帳の旨を話し且つ漸次小生の希望を吐露せんとて早々氏の門を叩き候も折悪しく不在に而面会せず名札と土産のみ置き帰京せしが、其後未だ機を得ず其儘と致置候。勿論外国船の医師として而傭ふ会社(外国の)は大抵六角氏の手によるとの事なれば、小生の親友にて六角氏と旧交ある人が小生の意を通じ周旋を依頼し呉るゝとの都合の相成居候、此かる折柄なれば六角謙吉氏の手紙は非常に好都合に御座候、何れニ三日中に罷出可申候
国の六角氏は本日御礼状可差上候、猶御会合の折はよろしく御願申上候其他に小生は血脇氏の協力にて日本郵船会社の重役連に口をかけ置申候、是は第一初めに欧州航路に移ることに御座候、尤も最終手段なりしが、今日は其必要を認めず候(下略)
この手紙にある、日本郵船の重役というのは、当時東京歯科医学院の講師であった藤島太麻夫氏の叔父のことである。英世は藤島の叔父が、日本郵船の船医採用嘱託試験医であるのをきいて、直接交渉に出向いた。
だが船医は彼地に着いたら降りるというわけにわけにはいかず、帰りも乗ってこなければならない。いわゆる片道船医は許されないと報らされてあきらめた。
しかし、この交渉のためにいままで資格だけとって実際に手にしなかった医術開業免許をはじめて受けとった。いま考えると暢気な話だが、当時は免許交付に当って必要なわずかの手数料を惜しんで、そのままにしている人がかなりいた。
英世もその一人だったが、船医の交渉に必要ということで、金を工面して交付してもらったのである。したがって、英世の医術開業免許状の正式下付日は、明治三十三年九月十三日となっている。
こうして折角とった免状も、外国へ行けないとあって、無意味なものになってしまった。
5
この年の秋、守之助は英世を連れて、数日、箱根塔の沢温泉に遊んだ。表向きは紅葉見物であったが、実際は、外国行きの望みが絶たれて失望している英世を慰めてやろうという親心から出た旅だった。
ここで血脇らは、同じ宿に泊まっていた、東京麻布に住む斎藤弓彦氏一家と知り合った。
この斎藤夫人は四十間近の気品のある人だったが、たまたま英世の部屋が深夜遅くまで灯がついているので不思議に思い守之助に尋ねた。
「あの男は、わたしの学院で、講師をしている野口英世という男ですが、アメリカ留学のため、ああやって毎晩勉強しているのです」
「こんな温泉宿にまで来て、学問しているのですか」
「あいつは、勉強し出すと狂ったようにする性質で、真夜中まで咳払したり、鼻をかんだり、うるさいことです」
守之助が苦笑すると、夫人はうなずいた。
それから十日後、東京へ帰った守之助宅へ、突然、斎藤夫人が現われた。夫人は丁重に一別以来の挨拶をしたあと、突然、自分の姪を英世にもらってもらえないかといい出した。
「お見かけしたところ、真面目で学問一筋の方のように思いましたが」
「それはありがたいのですが……」
英世の遊ぶのを知っている守之助は、ひたすら恐縮する。
「姪は、決して美貌とは申せませんが、二十歳で、婦人としての躾も充分いたしているつもりです」
「ご好意は、ありがたいのですが、こうしたことは所詮本人同士の問題、はたからとやかくいってもはじまりません。あの男にも話した上で、いずれ御返事申し上げます」
丁重にその場は逃れたものの、放っておくわけにもいかない。翌日、守之助は学院へ行くと、英世を呼び出して、結婚する気の有無をきいてみた。
英世は解せぬといった顔をして守之助を見ていたが、やがて用心深そうに、
「あなだは、わだしを結婚させて、アメリカ行きを断念させようというのですか、そんな手には、わだしはのりません」
「いや違う。実は塔の沢で会った斎藤夫人が、是非君に姪御さんを世話したい、といってきたので……」
「なんであれ、わだしのいまの望みは、外国へ行くごどだけです」
守之助も英世の気持は、よくわかる。
英世にいわれたとおり守之助は再度訪れてきた斎藤夫人に断わったが、夫人は一向にあきらめる気配はない。さらに訪ねてきて、守之助では埒があかぬと知ったのか、今度は、東京歯科医学校に現われて、直接英世を口説きにかった。
このころ、夫人は人伝てに英世が大変な遊び人で、かなり借金があることも知っていた。だが夫人は、温泉にまで来て、深夜狂ったように勉強する英世の姿が忘れられなかった。風采があがらず、手が不具とはいえ、将来なにか成しとげる男だと思う。その見方はたしかではあったが、それにしても大変な気の入れようである。
だが、英世には結婚する気なぞ毛頭ない。自分一人さえアメリカに行けないでいるのに、この上、結婚などしたら永遠にチャンスは失われる。英世が辞退すると、夫人が思いがけないことをいった。
「それでは、結婚の条件として、わたしのほうで、あなたがアメリカへ行く旅費を工面いたしましょう」一瞬、英世は、信じられぬように夫人を見た。
「早くいえば、持参金ということですが、それでお約束いただけますか」
「本当に、旅費を出してくれるのですか」
「わたしの口から申し上げる以上、偽りなど申しません。あなた様のほうでも、結婚のお約束は、たしかに守っていただけなければ困ります」
「…………」
「よろしいですか」
「少し考えさせて下さい」
さすがに一人で判断しかねる。英世は夫人と別れるとすぐ、このことを守之助に相談した。
「婚約だけして、行こうかと思うのですが」
英世はすでにのり気だったが、守之助は腕を組んで考えこんだ。
「そんなうまいことにいくかな。ともかく金を受け取ったら、もう逃げられないぞ」
「でも、結婚は帰ってきてからでもいいわけですから」
「そうなれば、あまり長く向うに行っているわけにいかなくなる」
「長くなったら、向こうに呼べばいいでしょう」
「そんなことは、親御さんが許すわけがない」
当時の距離感からいうと、娘がアメリカへ行くなど、一生ほとんど会えぬと同じことだった。
「いま目先の餌につれられて結婚するのは、間違いじゃないかな」
「間違いであろうとなかろうが、そうしなければアメリカへ行けません」
そういわれると、守之助としても一言もない。
「とにかく、わだしはこの話を受けるつもりです」
「本人の君がそういうなら、仕方がないだろう」
守之助も渋々納得した。
このときの、結婚相手の女性は、元は東京都麻布に住む斎藤弓彦氏の姪であったのを、のち養女として斎藤家に引き取った娘であった。したがって姪というのは誤りで、正しくは養女というべきだった。
斎藤家は紀州の出で、元士族ではあったが、さして高禄を食んでいたわけではない。後年、英世が恩賜賞を得て帰国したとき、紀州公に会う仲介をしたのが、この弓彦氏であった。一応士族出身とはいえ、当時は一介の公務員で、二百円の金は、かなり無理をしてつくった金だった。
ともかく、これで話は成立し、改めて守之助が斎藤家に結婚を申し込むことになった。そのとき、約束として、英世は渡米旅費二百円を受けて渡米したあと、できるだけ早く帰京して結婚する、という条件であった。英世は納得し、斎藤家では異存はなく、婚約はすぐその場でまとまった。
この一週間後、英世は再度、会津へとって返す。渡米決定の報告と、両親、恩師らへ別れを告げるためだった。
「野口んどごの清作が、この暮にアメリカ行がれんだってよお」
この噂はたちまち、狭い三城潟に拡がった。
「ついに外国さ行かれっか」「偉えごどだなあ」「外国語を三つも四つもべらべらだど」村人の驚異と尊敬の眼差しのなかを、英世は実家から小林栄宅、八子弥寿平などを訪れた。外国への出立と挨拶だが、もちろんそれだけではない。
このとき、小林栄から百二十円、八子弥寿平から百円の餞別を受けとった。
弥寿平はかねてから、外国行きのスポンサーになる、といっていたのだから、よしとして、可哀相なのは小林栄であった。地方小学校の校長とはいえ、少ない給料と、夫人が養蚕で貯えた金を、喜んで差し出した。
百円といえば、当時では土地つきの結構な家を一軒買えた。それを栄のみならず夫人まで出すことに賛成した。小林夫婦にしてみれば、外国へ行くといっても、英世のことだから金はないのであろう。長い別れの餞別として、これくらい仕方がないという気持であった。
だがそれ以上に、いまこの男に尽くしておかなければ悔いを残すといった追われるような気持もあった。それは弥寿平も、少額ながら、十円・二十円と出した旧友や親戚も同じだった。調子のいいことばかりいう借金魔だと知りながら憑かれたように、みなが吸いとられていく。いま出しておかなければバスに乗り遅れる。英世にはそんな、人々を駆り立てるような不敵さと無気味さがあった。各戸をまわり、ほぼ三百円近い金を懐にした英世は、勇躍、故郷を発った。
「おっか、元気でな」
翁島の停車場まで送りにきたシカの手をしっかり握った。
「アメリカ行って、しばらく金を送らねぇけど我慢してくれなぁ」
「なあに、家のごどは心配ねえがら、思い切り勉強して、もっどもっど偉くなって帰ってこう」
シカは皺だらけの堅くなった掌で、息子の掌を握り返した。
だがこのとき、野口の実家は相変らず貧窮のどん底にあった。父の佐代助の酒びたりは一向になおらず、足腰の衰えとともに、荷物運びなどで得ていた収入もなくなっていた。さらに祖母のみさは長年のリウマチで廃人同様である。こんなとき、長男が、家を放って異国になぞ行けるものではない。
しかし英世は、身て見ぬ振りをした。
一般の常識からいえば、英世は単純に偉いとはいい難い。孝養を尽し、母を大切にしたといっても、それは後年のいっときで、大半は不幸のし放しだった。単に親孝行という点では、素直に家に残った長女のイヌや、のちに出奔はしたが弟の清三のほうが上である。
英世は口でこそ、「済まね」「おっかに悪い」というが、具体的にはなにもしなかった。一本の草を採ることも、一片の土を耕すこともしない。家の惨状を知りながら、また自分だけの世界へ帰っていく。エゴイストといえば、これほどのエゴイストはいなかった。
第九章 旅立ち P.242
1
会津から帰京した英世は、アメリカ行きの準備に追われた。
そのころアメリカといえば、太平洋のはるか彼方の国というだけで、実際に行ったことがある者はほとんどいなかった。旅行記もないし、どこからどこへ鉄道が走り、どれくらいの旅費がかかるものか、それさえよくわからず、ましてや一か月、いくらくらいの生活費がかかるのか見当もつかない。英世は外務省やアメリカ大使館に行って、そのあたりの知識をつめこみ、さらにパスポートの交付申請、持っていく衣服や下着、旅行鞄などを整えなければならない。大抵の男なら、一人で行くのが心細くて尻込みするところだが、英世は意気旺んに準備に走りまわった。
十二月の半ば、英世渡米の話をきいた奥田、秋山、六角等、東京在住の同郷人、十余人が集まって、英世の送別会を開いてくれた。場所は九段坂上の「玉川堂」という筆屋の二階であった。いずれも三城潟や会津若松以来の友人達ばかりである。みな金がなく、とぼしい金を出しあって質素な宴であっただけに、英世も他の友達もほとんど酔わず、おかげでこの日は馬鹿騒ぎすることもなく済んだ。
この三日あと、麻布の斎藤家から結婚を条件とした支度金二百円が、血脇守之助をとおして、英世にとどけられた。
「向こうが誠意をこめて整えてくれたお金だ。この好意を無にしないように頑張ってきてくれ」
守之助の励ましに、英世は改まって両手をつき、
「先生には本当にお世話になりました。このご恩は一生忘れません」と、深々と頭を下げた。
だが事件は、このすぐあとにおきた。不運なことに、斎藤家から二百円を渡された日から、日本出発の日まで、五日の期間があった。
斎藤家から金をもらった翌日、英世は横浜に出かけた。もとの検疫所の仲間に別れを告げ、ついでに、渡航について便宜を計ってもらうためである。検疫所の連中は英世を迎えて、それぞれに励まし、前途を祝してくれた。そこまでには問題はなかったが、ここで調子にのった英世が、
「どうだ、もうこれでしばらくみなとも会えない、これから一つ別れの宴でもやろうじゃないか」と自分からいい出した。
「よし、それは結構だ。送別の宴をやる以上、われわれが金を出し合って開こう。たいしたこともできないが、どこか近くの料理屋でいいだろう」
「いや、みなにはこれまで世話にばかりなってきたから、今日は俺がもつ。任してくれ」
英世は大きく出た。もっとも、この横浜検疫所時代の仲間には、英世に金を貸したまま、踏み倒されたものがかなりいた。牛荘から帰ってきたときの金や、会津から集めてきた金でほとんど返してはいるが、すべて返済というまでには至っていない。
「一生に一度の洋行の送別宴だ。もっと派手なところでやろう」
例の、金をもつと気が大きくなる癖がでて話はさらに大きくなり、長浜消毒所から検疫所の職員にまで案内書がまわされ、その三日後、総勢二十数人が神風楼にくりこんだ。
この神風楼は、当時、神奈川随一といわれた料亭で、いまの伊勢佐木町のあたりにあった。三層の楼閣を成し、周辺の三業地を圧する外観を誇っていたが、ここで芸者を揚げ、無礼講の大騒ぎが始まった。
一度、酔い出すと見境いのなくなる英世である。それにアメリカ行きで、気勢があがっている。
「これは相当の額になるが大丈夫ですか」
途中で消毒所の事務官が心配してききにきたが、英世は相手にしない。
「かまわぬかまわぬ、金のことなら心配すんな、ここにたっぷりある」
だが宴も果て、女との一夜も明けて、翌朝請求書を見せられたとき、英世は仰天した。初めの会費での予定以外に百五十円もオーバーしている。自分が誘って派手にやろうといい出した以上、払わないわけにもいかない。
幸い、斎藤家からの金など三百円を越す額を持ってはいたが、払うと、三十数円しか残らなかった。
子守の、一か月の給金が五、六円といわれた時代である。まさに凄絶な浪費である。
払い終って、英世は初めてことの重大さに気がついた。実のところ、衣類も鞄も、まだ買っていなかった。それどころか、これでは到底、アメリカなど行けない。
だがアメリカ行きの船の出帆は、三日後に迫っている。驚き慌てて、行きつくところは、またも守之助のところしかない。それでも一日考えあぐねた末、おずおずと守之助の前に出ると、英世はべたりと額を畳につけた。
「大変なこどをしてしまいました」
「なんだ」
守之助が身をのり出すのを上目づかいに見て、
「昨夜、横浜で友人と送別の宴を張りまして、その際、斎藤家からいただいた金を、すっかりつかってしまいました」
守之助はなにもいわない。実際、いう気力もなかった。
正直、守之助は怒るより情けなくなった。これで一人前の医者だといえるのか。守之助は断固、英世の渡米をあきらめさせようと思った。これではいつまでも、他人に迷惑をかけるばかりである。渡米をあきらめて、この際とことん苦しめばいい。
だがそう思いながら、守之助のほうにも弱味があった。斎藤家との婚約を仲だちしたのは、守之助自身である。なにも知らない斎藤家では、支度した二百円の金で、英世は数日後に出帆するのだと信じこんでいる。
こんな時、芸者を揚げて一夜で費ってしまったとは、とてもいえない。三日後の出発はともかくとして、一か月以内ぐらいには、どれかの船便で行かせないことには恰好がつかないが、といって二百円もの大金を、おいそれと都合できるわけもない。
「弱った……」懐手した守之助は途方に暮れる。
「みんなが送別の宴をしてくれるというんで、ほんの少しのつもりだったんですが、こんな大金を費う気など毛頭なかったんです」
英世がいくらいいわけしたところで、消えた金は戻るわけもない。
「とにかくこのままではいかん」
金を受けとって、アメリカへ行かないとなると、詐欺師と同じである。このことが斎藤家にわかれば、向こうでは返済を求めてくるか、即、結婚を強要してくるに違いない。守之助がいま方々に頭を下げて歩けば、二百円の金は、なんとか集まるかもしれなかった。守之助には、その程度の信用はある。だがその理由が、英世の渡米費用の穴埋めだと知れたら、英世の悪名は拡がるばかりである。
「どうしたものか」
放蕩息子同然の英世を前に、守之助は溜息をついた。
とにかく名案はない。そのままたちまち日が過ぎて出帆予定の日がきた。
結局、金はできず、切符も買えない。斎藤家からは早速、出発をどうして延期したのかと問い合わせがきた。
「本人が少し風邪気味で、半月後に出る船にしました」守之助はそういって、当面をつくろう。
その夜、英世が再び守之助の家にきて、両手をついた。
「先生、なんとか私を行かせてください。お願いです」
いいなが、ぼろぼろと涙を流す。それほど行きたいものなら、遊ばなければよかったものを。だがこの理屈は英世には通用しない。そのときはそのときで、いまはいまなのだ。
「一生のお願いです」
なんとも、一生のお願いの多い男だが、そうはいわれても、守之助にも金はない。
「助けてください」恥も外聞もなく、英世は守之助の前に這いつくばる。
「止めなさい」見かねて守之助が叱った。
「お金はなんとかしよう」
「本当ですか」
「本当も嘘も、そうしなければ、君はもう日本では生きていけなくなるだろう」
守之助は吐き捨てるようにいうと立上った。
そのまま守之助は高利貸しのところへ駆けつけた。馬鹿げているが、どう考えたところで、その手段しかなかった。このとき、守之助は衣類から家具一切を抵当に入れた。家もといわれたが、それだけは信用で許してもらった。
こうして大枚三百円の金が出来上がったが、さすがにこりた守之助は、すぐ金を英世に渡さず、まず先に船賃を払って切符を買った。さらに必要な衣類を、その都度買って渡し、英世に現金は持たせなかった。
かくして、ようやく十二月五日、横浜出帆の亜米利加丸で行けそうになって、英世は北里博士のところへ挨拶に行った。以前、渡米旅費の調達をことわられたはいえ、恩師は恩師である。
「そうか、いよいよ行くのか」
北里はうなずくと、新調のスーツに身を包んだ英世を珍しそうに眺めた。
「それで、向こうではまず、どこに行くのだ」
「フィラデルフィアの、フレキスナー教授の許へ参ります」
「教授とは連絡はついているのだね」
「はい、是非来るようにと、お招きいただいています」
「お招きをね……」
北里はかすかに笑った。
東洋の島国の一医学徒に、高名な教授が、是非こい、などと、声をかけるものか。日本滞在中通訳をしてもらって世話になったくらいで、面倒を見ようなどというだろうか。すでにドイツからヨーロッパ留学をして、外国の医学界では、口先やお世辞だけでは通用しないのを北里は知っていた。いくら偉そうなことをいっても、要はその人物の業績である。いい仕事をし、いい論文を書いたものしか認めない。
その点、野口にはまだ、世界の医学会で通用するような、論文は一つもない。順天堂の医学雑誌に発表したものも、諸外国の文献の紹介とか、病状の臨床報告にすぎない。オリジナリティのある仕事など一つもしていない。そんな男を、遠い太平洋の彼方から、わざわざ呼び寄せるだろうか。
この北里の危惧は当然だった。実際、その点では英世も不安があった。アメリカに行くと吹聴して歩いても、肝腎の受け入れ側から、なにかきているわけではない。
「小生、資金を貯め、必ずや貴国へ行って、医学の勉強をしたい所存であります。その折はよろしく、御指導御鞭撻下さいますよう、伏してお願い申し上げます」そんな内容の手紙をフレキスナー教授に送っても、なんの返事もこない。
このあたり、北里研究所や東大から派遣されていく医師の場合と、まったく違う。官費で留学する連中は、あらかじめ行き先がきまり、滞在期間も、指導教授もきまっている。そこで、なにを教わり、なにを学ぶかということまで約束ができている。
日本政府と大学から、公式のルートを通じて、正式に依頼され、向こうからも受け入れる旨の返事がきてから出発する。もちろん彼地での滞在費も、帰りの船賃も保証されている。
だが、英世の場合は、これらの保証がまったくなかった。要するに行き当りばったり、あとは当って砕けろ、というやりかたである。
だが、北里は不安を感じながらもなにもいわなかった、実際勝手に行くという者へ、とやかくケチをつける必要もない。しかしさすがに不憫とおもったのか、フレキスナー教授他、滞欧中に知りあった北米にいる二人の学者宛に添書だけ書いてくれた。
「一人では大変だろうが、行く以上は、しっかりやってきたまえ」
最後に北里は自分から手を差し出して握手をしてくれた。
2
明治三十三年十二月五日、英世がようやく日本を発つ日がきた。
その日、彼は新調の紺の上下の背広を着て、新しく買ったバッグを右手に提げた。他に衣類や書物の入った二つの行李は友人達が担いだ。
新橋駅頭には、血脇守之助夫妻をはじめ、秋山、六角等、旧友、それに検疫所、北里研究所時代の知人など十数人が見送った。そのなかには許婚者の斎藤ます子もいた。叔母である養母と並んで、黒紋付の正装で、控え目にホームのうしろに立っていた。もちろん母娘とも、今度の切符が、守之助の借金で買われたなどとは思っていない。照れてか、英世は許婚者のほうにはほとんど振り向きもしなかった。婚約は守之助と養母のあいだですすめられただけで、英世としては許婚者に愛情を覚えるほどの親しみはなかったし、さらに金をもらっていることが、負い目にもなっていた。
新橋駅を発つとき、英世ははじめて、斎藤母娘の前にきて、「それじゃあ、行ってきます」と、一言だけいった。
この日、横浜港から亜米利加丸で出発する人のなかに、守之助の知人の小松緑という外交官がいた。彼は米国公使館書記官として、赴任する途中であった。守之助は、この人に、英世のことを呉々も頼んだ。いままで、苦労をかけられどおしであっただけに、いざ手放すとなると心配でたまらない。
「いいか、小松氏はワシントンまで行く。途中、船のなかから、彼地に上陸しても、彼の横を離れるな。かたときも離れず、いろいろ教えてもらって、万事、間違いのないようにやるのだぞ」
苦労をかけられた子ほど可愛いというが、いまの守之助の気持は、まさにそれと同じだった。小松氏は二等船室だったが、英世は下の三等船室だった。ドラが鳴り、見送り人の下船が告げられたとき、守之助は三等船室の甲板で、いままでおさえにおさえてきた不満を一気に吐き出すように、英世の欠点を指摘し、強く訓戒した。そして最後に、
「いいか、向こうへ着いたら、どんなに辛くとも頑張るのだぞ。きっといい仕事をして、帰るときには、立派な学者になって帰ってこい。そうすることしか、これまで君にまつわりついた汚名をそそぐ手段はない。間違っても中途半端で投げ出したりするな。今度こそ、君が本当に秀才であったか、一部の者達がいう背徳漢であったか、それが試される時だ。わかったな」
そのまま守之助はしっかりと英世の手を握った」。
「きっど、頑張ります」
二人は手を握りしめながら、英世より守之助が涙で濡れていた。
やがて出発のドラが鳴り、デッキに出た船客から一斉に紙テープが投げられた。赤、青、黄、さまざまなテープが交叉するなかで、英世一人、デッキの端に立って手を振っている。
その中で横浜まできて見送るのは、守之助と東京歯科医学院の学友が一人、見送り人わずか二人という淋しい船出であった。
このとき英世は二十五歳、いまの数え方でいうと満二十四歳と一と月の若さであった。
第十章 フィラデルフィア P.253
1
横浜を出港した「亜米利加丸」の第一停泊予定地は、ハワイのホノルルだった。当時、横浜からホノルルまで、十二日間の行程である。
英世は三等切符であったが、同行の小松外交官の口添えで、二等船室に切り換えてもらった。三等は船底の畳敷きの大部屋だが、二等は一段上で、十人前後のコンパートメントにわかれていた。
船は外海に出るとじきに、強い嵐に見舞われ、はじめの三日間は激しく揺れ続けた。三日目はとくにひどく、船室の小窓の一部が割れ、甲板に繋留されていたボートの一隻が波に流された。乗客達は船酔いに悩まされ、あちこちで吐き、蒼い顔で横になる者が続出した。
だが英世はほとんど船酔いにかからなかった。
「タフな人ですね」小松は英世の強さにあきれたが、同時に、鈍重な男だとも思った。
この嵐のあいだも、英世は思い出したように、鞄から英文のシェクスピアを取り出して読んでいた。
「そんな古いものを読んでも仕方がないでしょう。アメリカへ行くのだから、もっと現代的なものを読んだほうがいいですよ」見かねて小松がいうと、英世は首を振って、
「古くても、シェクスピアは英語の古典です。なにごとも、まず古いものから読んでいくというのが順序です」といって受けつけない。
アメリカへ初めて行くというのに、先輩の意見をききいれようとしない。英世にはこういう頑固なところがあった。
やがて十二日目に、船は予定どおりハワイへ着いた。ここで一日碇泊するが、三等船客は上陸を許されない。それを英世は、小松の従者という名目で上陸し、一日、ホノルルの街を見た。
英世にとって、初めて目にするアメリカである。異国の風景に臆するかと思ったが、例の好奇心と大胆さで、早速、店員や通行く人に話しかける。「天気がいいな」「これは面白い、いくらだ」その程度の会話だが、よく通じるので、英世はご機嫌だった。
ここで英世はアメリカ案内のカードを一組買った。懐中乏しい英世が、ハワイで求めた、ただ一つの買い物である。
翌日、ホノルルからサンランシスコへ、再び船旅がはじまる。この間六日。十二月五日横浜を発って、到着が十八日後の十二月二十二日であった。ただちに入国管理手続と検疫を受けたあと、英世は夜遅く、港に近いパレスホテルに泊った。小松も一緒である。ホテルに入って、英世は血脇守之助に宛てた礼状を書いた。
サンフランシスコで一日、休息をとった英世達は、翌日、フィラデルフィアへ向けて大陸横断鉄道に乗る。サンフランシスコから四日半の行程である。小松と英世は、別々の車室だったが、食事の度に、小松は英世を誘いに行った。
「いえ、わだしはまだ腹が一杯です」朝と昼、英世はきまって断わる。素直に従うのは夜だけである。
「君は腹が空かないかね」不思議に思って小松がきくと、英世は「わだしは、陽の明るいうちは、食欲がおきない性質なのです」と平然としている。
英世が懐中乏しいために、一日一食にしていたのを、小松が知ったのは、ようやく三日目であった。
「食事代くらい、わたしがもつ。一緒に行こう」三日目の朝、小松が誘うと、英世はにっこり笑ってついてきた。
食堂車に行くと、ハムエッグ、トーストから、さらにスパゲッティまで二人分を軽く平らげ、それ以来、ワシントンに着くまで、小松はずっとおごり続けた。
この横断鉄道に乗っているあいだ、英世は暇さえあれば、ホノルルで買った絵入りのカードを見ていて、沿線の景色や風物にはほとんど目を向けなかった。
「少しのんびり、まわりの景色でも見たらどうかね」見かねて小松がいうと、
「このカードには、有名な場所の景色と案内が一緒に書かれていますから、こちらを見ているほうが便利です。風景は見ても、説明がなければ、見たことにならないでしょう」
なんとも変った男だと、小松は黙ってしまった。
「なにか困ったことがおきたら連絡したまえ」小松はワシントンの住所と電話番号を書いた名刺を渡すと、英世ははじめて心細そうに小松を見て礼をいった。
2
ワシントンからフィラデルフィアまでは汽車で半日の行程である。
かくして十二月二十九日の朝、英世は目的地のフィラデルフィアに着いた。十二月のフィラデルフィアは、かなり寒い。雪は降っていないが朝靄のなかに霜が降りていた。英世は行李と鞄を両手に持つと、六本の円柱で支えられられた中央ステイションのホールを抜けて表に出た。
駅から出た人の列が広い路を渡り橋のほうへ行く。街の中心部は、その橋の先のほうらしい。途中、カードで勉強してきたとはいえ、はじめての街である。地図を見たところで、大学がどの方向か見当がつかない。
フィラデルフィアは、大西洋岸のデラウエア湾に注ぐデラウエア川の西岸にもあり、河口から一二〇キロ上流に位置している。背後にペンシルバニア炭田と油田をひかえ、交通の便もいいところから工業都市として栄えたところで、現在は人口二百五十万をこえ、ニューヨーク、シカゴ、ロスアンゼルスに次ぐ、アメリカ第四の都市である。
だが、この街の歴史はさらに古く、一六三六年、スウェーデン人の植民地集落として開かれ、一六八二年、ウイリアム・ペンにより、クエーカー宗徒のペンシルバニア植民地の首都となって、街の体裁が整った。街はデラウエア川と、その支流であるスクール・キル川にはさまれた地域が、最も賑やかなところで、ウイリアム・ペンの発案で、ブロード街とマーケット街という、二つの直角に交叉する路を中心に、碁盤の目状に区切られている。
一七七八年七月四日、アメリカ合衆国の独立宣言が、この街のインディぺンデンス・ホールでおこなわれ、自由の鐘が鳴ったのは周知のとおりである。当時から一八〇〇年までは、連邦政府の首都となり、合衆国最大の都市であった、
フレキスナー教授のいたペンシルバニア大学の創立も古く、一七四〇年、ベンジャミン・フランクリンによって創設され、市の北西部五〇万平方メートルの敷地にあり、医科・薬科・工科・理科などの各部があった。英世が行った一九〇〇年には、中心地のマーケット街に電車が通っていただけで、他は荷馬車が走っていた。
※参考1、ベンジャミン・フランクリン
参考2、広島大学・東広島キャンパス250万平方メートル。
駅頭に降りた英世はしばらくあたりを見廻し、それから駅前に止まっていた荷馬車を呼んで、ペンシルバニア大学へ行ってくれるように頼んだ。
車夫はいっとき、不思議そうに英世を見た。小柄でさえない東洋人が、行李と大きな鞄をぶら下げている。喋ることは一応わかるが、なにやらあくの強い英語である。しかも左手はズボンのポケットにつっこんだままである。
「大学のどこですか」
「医学部の、フレキスナー教授のところへ行きたいのだ」
そういわれても、車夫に教授のことなどわからない。とにかく荷物をのせて医学部へ向かった。
当時、フレキスナー教授の研究室は医学部のローガンホールという建物にあった。これは別名メディカルホールとも呼ばれ、四階建ての独立ホールで、病理や解剖など、基礎医学の研究室が集まっていた。この建物は現在ものこっていて、がっしりした左右対称の、コンクリート造りで、中央の階段と、三角形のトンガリ屋根が特徴的である。荷馬車をこの正面で降りた英世は、十五段の階段を、行李と鞄をもって昇り、正面受付でフレキスナー教授の在否をたずねた。
まだ朝の九時を少し過ぎたばかりだったが教授はすでに出てきていた。
まことに運がいいとしか、いいようがない。もしフレキスナー教授が外国か、旅行にでも出ていたら、英世の運命は大きく変ったかもしれない。
英世の突然の来訪に、フレキスナー教授は仰天した。
正直いって、フレキスナーは目の前に立っている男が、誰なのかわからなかった。日本から来た、ドクター・ノグチときいて、はじめて、東京へ行ったとき通訳してくれた小男だと思い出した。
「お約束どおり、先生の下で勉強するため、日本からやってまいりました」
そういわれても、フレキスナーに約束した覚えはない。たしかにアメリカへ来い、といったかもしれないが、それは外交辞令で、本気でくるとは思っていなかった。もしくるとしても事前に連絡をよこすか、一応の了解をとるのが礼儀である。それが大きな荷物をもって、一方的に押しかけてきたのである。
「一生懸命働きますから、助手に採用してください」
いかに教授といえども、大学本部に相談せず、助手を雇うわけにいかない。
「あなたが突然、こんな形でくるとは、わたしは思ってもいませんでした。どうして手紙の一通ぐらいくれなかったのですか」
「お手紙でお許しを得てから、とも思ったのですが、直接会ってお願いしたほうが早いと思ったのです」
「ここの大学の研究生は、みな自費で勉強しているのですが、あなたはその費用はあるのですか」
「残念ながら、それはありません」
「じゃあ、どうするのですか」
「ここで働かせてもらいながら勉強したいと思います」
「突然そんなことをいわれても無理です。すぐ採用するわけにはいきません」
「わたしはなんでもしますから、なんとか頼みます」
フレキスナーは露骨に困惑の表情を見せたが、英世も必死である。ここで追い返されたのでは、なんのためにアメリカに来たのか、わからない。このときの困惑を、後年、フレキスナー教授は、英世の思い出として、
「まったく、あのときは驚いて、日本から本当にきたのか信じられなかった」といっている。しかし日本からはるばる来たものを、すぐ追い返すわけにもいかない。
「ここでこうしていても仕方がない。宿はとりましたか」
「どこがいいか、わたしはよくわかりませんので、安いところを探していただけませんか」
フレキスナーは、英世の図々しさにあきれながら、ともかく心当たりのところに電話をかけてくれた。何箇所かに電話をかけてようやく見つかったのが、大学の近くにある二階建ての下宿の、古ぼけた屋根裏の一室であった。もちろんフィラデルフィアで最低の下宿である。ともかくこれで宿はきまったが、職のほうは、そう簡単にはいかない。
その日からフレキスナー教授は、学長や病院長へ話してみたが、やはり恰好な仕事はなかった。実際に日本からぼっとでてきて、英語も不自由な若い男を、雇用するもの好きな者はいない。
「いろいろ探してみたのですが、医学に専心できるような働き口はないようです」
「そではわたしは困ります。命じられたとおりなんでもいたしますから、ぜひ働かせてください」
このあたり、日本なら泣きの一手でなんとかなったかもしれないが、合理主義のアメリカでは、そうはいかない。三日後、フレキスナー教授は最後の断を下すようにいった。
「やっぱり、いまのところ外国人を雇う目途はありません。残念ながらあきらめて下さい」
いささか冷たい宣告だが、偏屈のフレキスナーにしては、これでもよく面倒をみたほうである。フレキスナーを知る人達は、英世の下宿を探したことさえ、よく世話をやいたと感心したほどだった。それはともかく、英世はまったく進退きわまった。あるいは、と思っていた予感が現実となっていた。
英世はあてもなく、ぼんやり異国の屋根裏から外を見下す。枯木の先に十二月の冷たい空が広がっている。懐中には二十三ドルしか残っていない。これでは幾日かの生活を支えるだけで、どこにも行けない。得意の借金作戦も、外人相手ではうまくいかない。
誰かいないか……考えて真先に頭に浮かぶのは、いまワシントンにいる小松緑であった。この広い異国で、一度でも面識があるのはフレキスナー教授をのぞけば彼しかいなかった。英世は早速、ワシントン領事館の小松氏へ宛てて手紙を書いた。だがこの手紙が少しおかしかった。
「無事フィラデルフィアに到着。早速ペンシルバニア大学に近いホテルに居を定め、勉学にとりかかりましたが、いささか通じにくい欠点があります。これ以上この地にとどまっていても、あまり有効とは思えませんので、一旦ワシントンかニューヨークへ出たいと思っています。御地の公使館あたりで働き口でもないものか、探していただけないでしょうか。それについて、まずニューヨークへ出たいと思いますので、誠に申し訳ありませんが、その旅費をお送り下さいませんか」
まことに奇妙というか、不思議な手紙だが、これには英世なりの考えがあった。
まず、アメリカへくる途中、フレキスナー教授に招かれて行く、といった手前、大学を追われたとはいいにくい。そんなことをいっては小松から日本の血脇守之助にまで嘘がばれてしまう。大学に籍はおいたが、一時ニューヨークへ行くという形にしたい。しかし早急に働かなければ干上がってしまう。そんな配慮が、この奇妙な手紙を書かせる結果となった。
ところが、これを受け取った小松は、また変に解釈してしまった。彼は、英世がきまぐれで、ニューヨークへ遊びに出たい、といっているのだと思った。
「前略、お便り拝見しました。お元気な様子はなによりですが、お申しこしの件は、少し異論がございます。フィラデルフィアの英語は訛りが強いとのことですが、わたしは特にそうとは思えません。フィラデルフィアで通じないなら、おそらくニューヨークでも駄目ではないかと思います。いずれ学業成って、ニューヨークに出られると仰言るなら、旅費など工面いたしますが、いまのところは、しばらく馴れるまで、御地で勉学されるほうが得策ではありませんか」
英世の強がりが裏目に出てしまった。
フレキスナー教授と小松緑と、二人に振られて、英世は途方に暮れた。このままでは餓死するか、不良外国人として日本に強制送還されるかのいずれかである。もはや出歩く気力もなく仰向けに倒れたまま、天井だけを見詰めている。
このとき、英世が描いたという絵が残っている。輝く星の下に波が逆巻き、そこに骸骨が横たわっている。波濤をのりこえて、飢え死ににきた、という意味ででもあろうか。
進退きわまったとはいえ、英世は完全にあきらめることをしない。
駄目とは知りながら、なお、連日フレキスナー教授のところへ行って頼みこむ。このあたり、東北人特有のねばり強さを発揮した。
もつとも、他にといって英世にやることはなかった。一日中、家にいて天井を睨んでいるだけでは気が狂いそうになる。それにしても、あれほどはっきり断わられたのを、さらにのこのこ出かけていく心臓も大変なものである。普通の人間なら、このあたりでホームシックにかかり、ノイローゼになるかもしれない。
日参している小柄な東洋人をみて、さすがにフレキスナー教授も気の毒に思った。大晦日の午後、フレキスナーは研究を終えたあと、英世を部屋に呼んだ。
「君は毒蛇についての知識がありますか」
きかれた瞬間、英世は目を瞬かせた。毒蛇など日本にいない、沖縄に行けばいるらしいが、本土から離れているせいもあって、本格的に研究している者は少ない。
「いま、われわれの仕事の一部として、毒蛇の研究をしているのです」
英世はふと、伝染病研究所で、先輩の守屋という医師が、ハブについて研究しているときいたことを思い出した。もちろん英世はそのハブをみたこともないし、研究の内容も知らない。だが、ここで知らないといっては、終ってしまう。どうやら教授はそのことについて仕事をくれようとしているらしい。
「こちらの毒蛇については、あまりよく知りませんが、ハブについてなら、よく知っています」
「そうか、それは好都合だ」教授はうなずくと、
「その毒蛇の研究のほうで、ちょっと人手が足りない。もしよかったら、そちらのほうを手伝ってくれないか」
「喜んで、お引受けします」
「しかし大学の助手ではなく、私の個人的な助手ということだから、正式のサラリーは払えない。私のポケットマネーから、月八ドルしか払えないが、それでもいいか」
「もちろん結構です」
「八ドルではやっと食べていくだけで、下宿料や衣類の費用は足りないから、不足分は国のほうから送ってもらわなければならないだろうが」
「大丈夫です。とにかくお願いします」
毒蛇の仕事だろうが、八ドルだろうが、かまっていられない。とにかく、いまはここにしがみつくより方法はない。
「それでは、来週から、私の個人的な助手ということで、通ってきてください」
「ありがとうございました」
「明日からは、ニュ-イヤーの休みなので、仕事は四日から始めてもらいます」
「わかりました」
英世は深々と頭を下げた。
とにかく、これでいましばらく、アメリカにいられそうだ。教授の部屋を出て、英世は「やった」とつぶやき、東の日本の方角をみて、「ついに研究所に残ることになったぞ」と叫んだ。
だが、仕事はなま易しいものではなかった。
当時フレキスナー教授は、毒蛇から蛇毒を抜き、それの血清学的研究をすすめていたが、蛇を摑え、介助する助手が少なかった。これの係は、すべて黒人だったが、気味悪さと危険のため、なかなかなり手がいない。これに英世を当てようというのである。
何も知らない、しかも手の悪い東洋人にいきなりそんな役をやらせて可哀相といえば可哀相だが、勝手にとび込んできた英世のほうが悪いことはたしかだった。それも、なんとかいまのメンバーで間に合うのを、フレキスナー自らのポケットマネーで雇おうというのだから、教授の好意であることは変りない。
毒蛇は怖いが、とにかく教授の許にいられそうだ。不安と期待の交錯するなかで、英世は一人、布団にくるまって、一九〇一年の元旦を迎える。このとき明治三十四年の正月である。
3
明治三十四年一月三日付の、英世の血脇守之助宛の手紙のあらましは、次のようになっている。
粘りに粘った末、フレキスナー教授から、蛇毒の研究助手として雇うことにしようといわれた、その直後の手紙である。
「先頃は非常に苦悶の手紙差上げ……」というのは、教授から採用できないといわれ、途方に暮れたときのことである。「教授の親切なるには驚入申候」とあるが、フレキスナー教授にとっては、親切というより、強引で哀れな日本人からの押しかけ助手の処置に窮しての結果ともいえる。
「本日公使銀行の事申上置候処、無効の由……」は、小松緑氏の許へ転がり込もうとして、断わられたことだが、「無効の由」とは、手のこんだ表現である。「華府行は見合わせ有らましを教授に話候処……」も、断られて行くに行けず、進退きわまっていたのだが、これではまるで、自分から見合わせたようにきこえる。
「教授は意を決して金子の国元より来るまで、一切引受勉強せしめ呉るる旨申出だし……」とは、なんと図々しいことか。たしかに教授から、、雇ってもよい、といったとはいえ、喜んでいい出したわけではない。申出とは、言葉のニュアンスが大分違う。おまけに、「金子の国元より来るまで」とは、いかにも功名である。フレキスナーの言葉を借りて、このあと借金の督促をしている。
これに対する守之助の返書は、一応、教授の好意で研究室に勤めることになったことを喜び、だが東京歯科医学院経営当初で、経済的余裕が少ないことを述べたあと、これが最後の送金で、これ以後は君自身の力でやり給え、成功か失敗かは、ひとえに君自身のあり方にかかっている、と訓戒を垂れている。
しかし文句をいいながら、今回もまた百円の為替を送った。
血脇守之助は、後年子息の日出男氏に、「男にだけ惚れるな」と述懐したという。(野口英世記念会・関山秀夫氏)
惚れて女に注ぎこむ金はしれている。しかし男は怖い。一度吸われたら、どこまで吸いとられるかわからない底無し沼である。女は適当なとき、愛想づかしや別れもあるが、男はそうはいかない。一生、金をくいつぶす。年頃になったばかりの息子への言葉としては意外だが、英世に吸いとられ尽した守之助の言葉として考えるとき、いかにも実感がある。
守之助が英世に与えた金はどのくらいの額にのぼるか、当時の金で、一万円とも、数万円ともいわれる。それも、惚れた弱味である。
いかんいかん、と思いながら、奪られていく。
ところが、この送金された百円には後日談がある。異国でようやく得た百円の、あまりの嬉しさに英世は興奮して、これを紛失してしまう。大切に、何度もたしかめるうちに落としたのである。さすがにこのときは紛失したからまた百円送れとは、いいかねた。
「去る二十日御恩送の金子五十弗到着、無事に拝受仕候間 何卒御放神是祈上候。知らぬ他郷に在りては殊更に有りがたく轍鮒之水にも癒やまして辱く拝し奉り候」
礼状の文面はともかく、心は泣いていた。もっとも、この金はのちに、郵便局と交渉して受けることができたが、しばらくは、フレキスナー教授のポケットマネーから渡してくれる月八ドルで生活するより仕方がなかった。
いかに物価が安かったアメリカとはいえ、当時、独身の男性一人が生活するには、最低月二十ドルは要るといわれていた。生活のレベルの低かった黒人労働者にしても、十五ドルは必要だった。このときの英世の下宿は、文字通り物置用につくった三階の屋根裏で暖房もなかった。犬が残飯をあさるように、母屋の人々の食べ残しを喜んでもらう。そうするより生きていく道はなかった。
このとき、英世はローガンホールの研究室の一隅に籠りきりで、夜遅くまで帰らなかった。のちには寝袋を持ちこみ、それにくるまって、夜を過すこともあった。
「お前は一体、いつどこで眠るのか」と研究所員があきれていたが、英世はただ笑っていた。英世にしてみれば寒い下宿より、研究室のほうがはるかに寝心地がよかったのである。
それにしても、英世に与えられた仕事はかなりひどいものだった。「研究室に出勤の事に御座候」と、守之助の手紙には書いたが、現実に研究室でやることは、毒蛇の飼育と、蛇毒をとり出すことが主だった。
普通の人間なら、檻のなかにいる毒蛇の群を見ただけで逃げ出してしまう。とぐろを巻く無気味さに胆をつぶす。もちろん英世も怯えた。出来ることなら逃げだしたい。だが、英世に逃げる道はなかった。
先輩の黒人助手サムから見よう見真似に教わり、ゴム手袋をはめ、そろそろと檻のなかに手をつっこんだ。しかし英世の左手は火傷で自由がきかない。太目の試験管を、辛うじて持ちこたえるだけである。毒蛇をおさえるには心もとないが、毒蛇を扱ったことがさると、フレキスナー教授にいった手前もやらないわけにはいかない。
この研究室の動物飼育室には、アメリカ、中南米諸国などから捕獲してきた毒蛇が十数種類いた。これら毒蛇は一般的に、頭部が三角形で体が太く、尾部は短いのが特徴である。毒腺は脊椎動物の唾液腺に相当するもので、そこから輸毒管によって上唇部から毒牙の基根部に開口している。
蛇毒は、大きく分けて血管毒と神経毒の二種類があり、血管毒の場合は、咬まれるとすぐ、局部に斑状の出血がおき、まわりはたちまち暗紫色になって膨張し、痛みが激しく、淋巴管炎をおこして淋巴腺が腫れてくる。同時に熱が出て痙攣が現われ、出血が続き、やがてしきりに眠たがり、一週間ぐらいで死ぬことが多い。神経毒のほうはさらに症状が激烈で、咬みつかれてなんの手当てをしなかった場合、ほとんど痛みはないが、一時間前後で死亡する。
前者の血管毒に属する蛇毒をもっているものの代表は、まむし、はぶなどで、後者の神経毒の代表格はコブラ、雨傘蛇などである。
この毒蛇に咬まれた場合の手当法としては、直ちに、その上部を紐かゴムできつく縛り、血行を止めて、咬まれた部分を切開し、毒が入った血を流し出す。さらに蛇毒を消すには、三パーセントの過マンガン酸カリの溶液で拭くのがよいとされている。しかしこれらはあくまで応急的なもので、根本的には蛇毒を中和させる抗毒血清の注射が最も有効である。
当時すでにこの抗毒血清はつくられていたが、蛇に咬まれるのは山奥の、しかも深夜が多く、この血清が間に合わないことが多かった。アメリカの一部や、中南米では、この予防が、重大な問題であった。
フレキスナー教授のところでやっている研究は、この蛇毒の治療対策はもちろんだが、同時に、この各種の蛇毒による抗原抗体反応を調べることから、免疫学のメカニズムを解明しようという目的も含んでいた。
それにしてもこれは危険な研究で、大体コブラ一匹からとり出される毒で、モルモット一万数千匹、鳥なら三十三万羽を殺すことができるといわれている。
この蛇毒に、英世は立ち向かった。
檻のなかに手をつっこんだ途端、血に飢えた毒蛇は鎌首をもたげる。これを別の手に持った針金で巧みに誘導しながら、うしろから素早く首根っこをとらえる。そのまま檻から引出し、両頬の唾液腺の部部をおさえ込み、たまっている蛇毒を吐き出させる。
ジャングルを跋渉し、蛇には馴れている黒人たちもこの作業には辟易する。まして毒蛇などいない日本内地に育った英世にとってこれほど恐ろしい仕事はなかった。
だが、英世は逃げなかった。実際逃げようにも逃げる道はなかった。初めは捉えそこなって噛まれそうになったり、悲鳴をあげることもあったが、数日も経つとどうやらうつかまえられるようになった。それでもときどき失敗する。研究熱心で小器用な英世は捕えるこつを覚え、巧みに蛇毒を吐き出させた。
毒液は淡黄色透明でかなり粘っこく無味無臭の液体である。そのまま乾燥すると水分が消え、淡い黄色の粉末になるが毒性は失われない。研究には、この粉末が保存されて使われる。
4
英世が怯えながらも、毒蛇に立ち向かうことになって一か月後に、フレキスナー教授は、サンフランシスコに発生したペスト患者対策のため、出張することになった。
ようやく落ち着きかけていた英世にとっては、フレキスナー教授の不在は心細い。だが、教授は出立に先立ち、蛇毒研究の第一人者である、ミッチェル博士に宛てて、野口をよろしく指導願いたい旨の紹介状を書いてくれた。
このサイラス・ワイア・ミッチェル博士はペンシルバニア大学神経病理学の教授として長年勤めたあと退職して、大学評議員とともにフィラデルフィア医学会会頭の要職を占めていた。いわば、フレキスナーの先任教授であり、父がやはり病理学で蛇毒の研究をしていたところから、そのあとを引継いでいた。
「ミッチェル博士は嘗て大学教授の席にあること四十余年、今は老退して当大学評議員の上席、当処医学会会頭の要位を占め居申候、同博士は神経病学の泰斗にて幾多の発見有之世界に知れ渡りたる人に御座候、昨春世界漫遊中日本に立寄られ候節は、大学教授連中、北里博士一門、陸海軍の偉傑、立野博士等一決して同氏の歓迎会を催したりし同席上にて、北里博士も歓迎演説を致され申候こと有之申候」
後年、英世は会津の小林栄へ手紙で、ミッチェル博士のことを、こんなふうに伝えている。
北里博士が歓迎演説したほどの人物に、自分は直接指導を受けていることを自慢したかったのであるが、それにしてもこれほどの大物に、フレキスナー教授が、サンフランシシスコ出発に先立ち、自ら紹介状を書いた、というのは、いささか眉唾である。
いかに親切なフレキスナーでも、日本から押しかけてきた、蛇係りの私設助手のために、わざわざ紹介状を書くとは思えない。たしかに書くには書いたが、英世に強引に頼まれて仕方なく、と解釈するのが自然であろう。
英世はこのときすでに、日本来訪によってミッチェル博士の名を知っており、機会を見て、いつか近づきたいと思っていたのである。
その間のいきさつはともかく、フレキスナーが出発すると、英世は早速、紹介状を持ってミッチェル博士の許を訪れた。
突然の小柄な東洋人の来訪に、ミッチェル博士は驚いた。普通なら会わぬところだが、フレキスナーの紹介状を持っているのでは、追い返すわけにもいかない。
「私は北里先生の下で細菌学を研究し、推されてフレキスナー教授の下に勉強に参ったノグチというものです」英世は有効に北里の名前を使った。
「今度、教授の下で蛇毒の研究をはじめましたが、神経病学の権威でいらせる博士の御意見を伺っておきたいと思いまして」
日本ではかなり上手だと思っていたが、現実にアメリカへ来ると、英世の英語は、まだまだこころもとなく、少しこみいった話になると通じなかった。だが、この下手な英語が、この場合はかえって好都合であった。一歩つっこんだ学術的な話になると、蛇毒についてなにも知識がないのがばれてしまう。
英世がミッチェル博士に会おう思ったのは、なにも直接指導を受けるためではない。実際、六十を過ぎた老博士が、一介の私設助手に手をとって教えるわけもない。この訪問は、日本式の顔つなぎ、いわゆる表敬訪問ともいうべきものであった。
ミッチェル博士は、この得体の知れない異国人に驚きながら、ともかく、「毒蛇をとおして免疫学をいま一度、基本から洗いなおしてみるように」と述べた。
北里博士も一目おいた医学者と、膝をつき合わせて話ができたことに英世は感激した。
「きっと、免疫学に新しい分野をきり拓いてみせます」
例によって、英世一流の大言壮語を抜け抜けと吐く。
だが、英世は、大きなことを言うことで、自らを縛っていたともいえる。北里に、フレキスナーに、そしていままたミッチェルに、法螺を吹くことで自らのなかに新しいファイトを燃え上がらせる。法螺を単なる法螺に終らせず、改めてその目的へ向かって努力するところが、英世の偉大さであり、才能でもあった。
かくして英世の猛烈な蛇毒への勉強がはじまる。
蛇毒採集以外の時間、英世は大学医学部の図書館にこもって、蛇毒に関する英・独・仏各国の文献資料を漁り、片っ端から読破した。さらに重要な部分は、念入りに書き写しメモをとる。表向きは蛇の飼育係でも、気持ちは一流の研究者である。仲間のサムは、仕事を終れば酒を飲み、陽気に遊び歩いているのに英世は図書館に通う。朝から晩まで、さらに閉館日も頼みこんで勉強を続けた。
「あの小さな日本人は、よく勉強する。凄い野郎だ」研究所のスタッフは驚きあきれた。
勉強はするが貧しい英世を見かねて、サムはときどきパンを持ってきて分けてくれたし、守之助の紹介で知った同じ大学のカータ教授は、ときどき自宅に呼んで夕食をご馳走してくれ、さらに徹夜で勉強したいときには、家をつかえともいってくれた。もし日本の大学で、素性もわからぬ一介の動物係が、こんなことをしたら、かなりの顰蹙をかうか、下っ端のくせに、出すぎた真似をするなとしかられるのがおちかもしれない。
だが、アメリカ人はその点、明るく寛大であった。出る釘を打つ前に、力は正当に認めていく。
それにしても、このころの英世の生活は苦しかった。月八ドルでは、着るものなど一切買えない。研究所の職員からもらった白衣の裾を切って背丈に合わせ、袖をまくりあげ、食事といえばパンと水だけである。カータ教授宅の食事が唯一の栄養源だが、それも毎日というわけにはいかなかった。
以下は二月二日付、血脇守之助に宛てた手紙である。
次に小生儀過般申上候通、教授の厚意にて当分は無事に日々勉強罷在候間乍憚御放慮被成下度是祈候。
小生の研究は蛇毒に就てに候、朝より夕まで忙はしく暇も無御座候、殊に多数の参考書(英・仏・独共に)を要し候事とて、随分骨が折れ申候(呵々)、夜に入れば其日の実験記事(極めて詳細を要し候)に暇をつぶし居申候。
得意の英語は半分も不通実に閉口此事に御座候、毎夜小時間宛下宿屋の神さんや娘さんに稽古を頼み居申候。本国の風習は実際上拝金主義に候。併し小生は「ペンニ―レス」に候得共、別に軽視せられる事なく、却って好遇を受け居申候。
小生の大学に於ける席は特別実験室にて、小生のために須要の材品悉く供給し呉れ申候。普通北里博士の研究室にて共有物なる高価のものなどは皆専有に候、一週間前に教授フレキスナー氏は政府の命にて桑港に出張せられ候(ペスト患者の疑い歟)、其際大学の仕事(責任ある)の一部を小生に与へられ申候。恐くは或位置(有給の)を与ふる前触れかと存申候も、何れ浮沈は世の慣ひ、決して当てには不致候も、一寸御申上置候。
噫思出せば亜米利加丸甲板にて頂きし御餞言は、小生をして如何に大胆ならしむることよ、実に人生を咀嚼せし金言に御座候。(下略)
来る三月には元当大学生理学教授ドクトル・ミッチェル氏渡日せらるるょし、此間面会の際申居られ候。同氏は蛇毒研究者として世界にて有数の人に候。其他神経病学者に候。且つ晩年に至りては文学を嗜まれ、著述頗る多く、名声当市(否米国医界)に嘖々たる人に候。時として同氏より紹介を求められ候節は、恩師へも御紹介可申上候間、宜敷願上申候。時節柄御自愛専一奉存上候
匆々頓首
二月二日夜
血脇恩師
同御奥様
My address: 3328 Walnut St., Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. or c/o Prof Flexner.
Medical Hall, University of Phila., U.S.A.
ここにはもはや、渡米当初のような、差し迫った焦燥感はない。苦痛は苦痛なりに、一応落ち着いてはいる。それにしても、英語にはさすがに参って、「呵々」と、溜息をついやのは、あとにも先にもこの手紙だけである。
「ペンニーレス(penniless)」だが、軽視されない、というのも、いかにも勝気な英世らしく、実験について、北里研究所では共有であったものが、ここでは自分専有だと威張りながら、北里研究所への皮肉を書くことも忘れなかった。
ともかく、こうして最初の三か月が過ぎる。
やがて四月の半ばすぎ、フレキスナー教授がサンフランシスコから帰ってきた。このとき、英世は教授不在のあいだに、蛇毒に関するあらゆる文献をまとめた二五〇ページにおよぶ文献を提出した。
これには、フレキスナー教授も一驚した。
「これをすべて、君一人でやったのか」
「もちろんです」
教授は英文で書かれたページをめくり、改めて信じられぬ顔で英世を見詰めた。アメリカ人でさえ、三か月の短時日では到底できない。
翌日、フレキスナー教授は英世を部屋に呼んで、月額手当、二十八ドルを与える旨を告げた。
このあと英世が死に至るまで、アメリカでも稀な一心同体の子弟といわれるフレキスナーと英世の強固な子弟関係は、このときまさにその第一歩を踏み出したといえる。
5
野口英世が生涯取り組むことになった「免疫」の語源イミュニティは、元来、租税その他の公的な負担から特別免除されることを意味したインムニタスからきている。中世以後では行政、司法、財政上など、国家権力の強制から自由である特権、一種の治外法権(イムニテート)をさすようになり、近世になって「厄のがれ」といった意味をもつようになった。この意味が医学の分野に入ってきて、感染病から免除される、あるいは受け付けない状態をさすようになった。
ところがこの免疫には自然免疫と獲得免疫とがある。このうち自然免疫とは、人間が生まれながらに備えている免疫で、たとえば牛痘に人は絶対にかからない、といった類のものである。これは種族による特性でもあるが、年齢や世、種族なども特性が認められている。
これに対して獲得免疫というのは、人間が生来、環境への抵抗の結果、持ちえた免疫で、たとえば、「はしか」や「おたふく風邪」にかかった児が、二度とそれにかからないといった類のものである。
この獲得免疫は、病気にかかることによって得られるが、予防接種によっても可能である。このことはジェンナーの種痘で一躍有名になったが、パスツールの炭疽病に対する予防接種などで、さらに研究がすすめられた。
ところで、ジェンナーやパスツール等が試みたのは、いわゆる「弱毒生菌免疫法」という方法で、人間に病気をうつさない程度に弱めた病原菌を植えるやり方である。しかしこれではときに、本格的に発病する危険があるところから、菌から出される毒素を熱処理で弱くしたり、殺したり、あるいは無毒化したものを注射する方法もある。またジフテリアや破傷風のように、その菌の毒性をなくしたトキソイドを注射し、血清のなかに一度に大量の抗毒素を発生させ、その血清を人間に注射して間接的に免疫を獲得させるというやり方もあった。
いずれにせよ、生体は自分に不利なある毒性が入ってきたとき、一時的に抵抗し混乱するが、それに打ち克つと、やがて体内にそれに対抗する抗体をつくり出す。こうなると二度目に菌が侵入してきても、混乱せず外敵を打消すころができるようになる。これは生体の基本的な防衛機構である。
英世がアメリカへ渡った一九〇〇年初頭は、一八八〇年代のパスーツルの狂犬病、炭疽ワクチンの完成により免疫学の基礎が開かれ、一八九〇年にはべーリング(※黒崎記:第1回 ノーベル生理学・医学賞を受賞)や北里柴三郎によりジフテリア抗毒素が発見され、治療血清に道が開かれるとともに、免疫現象が試験管内で認められるという画期的な進歩があった。これにより、さまざまな細菌や毒素に対する抗体が血清中に確認され、これを精製分離して、その化学的な本態を追究するところまですすみかけていた。
だが、より基本的なところ、すなわち馬がどうして抗菌素をつくるのか、そして抗菌素がいかにして毒物を中和するか、というメカニズムになると皆目見当がつかない。エーリッヒ以下、多数の学者がこれに諸説を立ててはいたが、いまだ決定的なものではなかった。
ところでこのころ、ベルギーのポルデー教授が細菌のかわりに、ある動物の赤血球をほかの動物に注射すると、受け入れた動物はその赤血球を溶解するという事実を確認して話題となった。この溶解作用は生体に入ってきた毒を溶かすのであるから、一種の免疫である。当然、この機構の解明が問題になったが、当時、この溶解現象に取り組んだのはヨーロッパの学者が主で、アメリカでこれを研究テーマにしている者はまだいなかった。
しかし毒蛇の毒も血球を溶解するという事実はミッチェル博士によって、すでに知られていた。すなわち、人が毒蛇に咬まれると、その人の血液はかたまらず血球が変化する。この変化と、ポルデーのいう溶解現象のあいだに、なんらかのつながりがあるのではないだろうか、当然ながら、ミッチェル博士はこのことに着眼した。
ミッチェルからフレキスナー、そして野口にいたる一連の蛇毒の研究は、こうした推論の延長において成されたわけである。
ミッチェルは医学者であるとともに小説を書いたという人だけに、その記録したものにはなかなか面白いものがある。たとえば蛇毒が血球を溶解するメカニズムを解明するヒントとして、「ノース博士とその友人」の章で、博士は、ある夜帰宅したらドアの前に敷いてあるマットが、一瞬、蛇がとぐろを巻いているように見えた。それは黒糸と黄色糸が交差して織られていたが、そこから、蛇毒は一つでなく二つの要素の比率によって毒性が違うのではないか、と思いついたと述べている。
との発想はたしかに当っていた。
ある動物の血球が他の動物の血球によって溶解されるに当って、二つの要素があり、一つは双摂体といい、もう一つは補体といわれる。この一方の双摂体だけでは血球を溶解せず、補体をくわえてはじめて溶解する。この点から、蛇毒が血球を溶解する場合、それは双摂体として働くのか、補体であるのか、あるいは両方なのか、さもなくば全然関係はないのか、という疑問がでてくる。
英世が関係した研究は、具体的にいうとこの実態を解明するという作業であった。
このころの英世の研究生活はいまでいう猛烈社員そのままのエネルギッシュなものであったが、また同時に彼らしい強引さと、向こうみずなところもあった。たとえば血清をつくるため、動物から大量の血をとる作業のとき、大きな犬なら殺さずに、肋骨のあいだに注射針を射し込んで心臓から直接とり出すことができる。
だが英世はこの比較的簡単な作業でも、よく失敗した。針が心臓をそれて肺に刺さったり、深く刺しすぎて心タンポナーデを起して殺してしまったこともあった。
初めは英世が日本人で、手が不自由なこともあったので、研究所のスタッフも大目に見ていた。
だが黙っていると何度でも失敗する。失敗するのはいいとして、何故失敗したかを考えずに、ただがむしゃらにつきすすむ。同僚のゲ―はさすがに見かねて、「少し考えながらやってはどうか」と注意したが、英世は「一瞬うなずくだけでまた失敗を繰り返した。
採取した血液は遠心沈殿器にかけ、上層の血清と底に残る血球部分に分離する。これから上澄みを捨て、血球部分を食塩水でそそぎ、最後に洗って稀釈していく。各倍数毎に稀釈した液に、これもいろいろの程度に薄めた毒液を注ぎ、この反応を肉眼と顕微鏡で調べていく。長く根気のいる仕事であったが、英世はこの仕事をしながら、遠心器から試験管の並ぶ実験台のあたりで、煙草の吸殻でいっぱいにした。
日本にいるころから、英世はかなりヘビースモーカーであった。ゲーの机は窓際にあり、英世のは室のほぼ中央にあったが、英世のほうは雑然と本が積みあげられ、ところかまわず吸殻や紙片などが捨てられ、汚なく、きちんと整頓されたゲーのそれと対照的だった。
実験をしながら、英世はもちろん手の不具を気にしていた。なるべく見られないようにしてはいたが、試験管を持つ仕事は手を隠すわけにはいかない。拇指と人差指がチビた形で寄り添っていたが、この間に試験管を一本だけはさむことができた。だが忙しくなると一本持つくらいでは間に合わない。慣れてくると各指のあいだに四、五本はさむ人もいる。英世もあとでは右手にピペットを持ち、左手に四本の試験管を持って稀釈していけるようになった。が、そうすればするほどチビの左の指が目につく。だが同僚達は極力見て見ないふりをしていた。ゲーはのちに、「ノグチの手は少し変ではあったが、どこがどうなのか、具体的には見たことがない」といっている。
それにしても英世が最も苦労したのは、蛇の扱いであった。
蛇をおさえつけるには、まず輪のついた針金の先端に特別の布切れをつけ、そちらに蛇の関心を惹きつけ、そこにとびかかろうと首を擡げた一瞬、素早くうしろから後頭部をとらえる。そこを持って左右から毒腺を締めつけ、時計皿の上に蛇毒を吐き出させる。
緊張の一瞬である。
こんなとき英世の眼は異様な輝きを見せた。同僚のゲーは、「ノグチはああいう怖いことをするのが好きなのではないか」といったが、たしかに英世には、ややサディクスティックな性向があった。がむしゃらな仕事のやり方や、理非はともかく相手を論破する執拗さなど、その一種の現われともいえた。
この蛇毒の採取とともに、蛇に餌を与えるのも憂鬱なことの一つであった。蛇毒は食後のほうが採取しやすい。生きたものを与えるために、毒蛇の檻に兔を入れてやる。そのまま、英世は部屋の隅でじっと待っていると、「キイッ」と、兔の悲鳴のような声がきこえてくる。
英世はこの、兔が食べられている間、待っているのが一番辛かった。
やがて食べ終ったと思うころ、そっと檻を覗く。兔が一羽減っていれば、一羽食べられたわけである。兔を食べた蛇は腹のふくれ具合ですぐわかる。
満腹の蛇は決して余計に食べないが、蛇の間にはさまれた兔は、恐怖ですでに失神状態になっている。
四月初め、英世ははじめて学内の病理学会の集会で、蛇毒に関する研究報告をする機会を与えられた。
英世は勇躍教壇に立ち、図を示しながら喋った。
四月二十一日付、血脇守之助宛の手紙には、「(前略)且つ小生は蛇毒研究に関する論文も公表することなれば、米国に航せし目的の一部は実行せしもの、将来の辛酸は固より本望の御座候、(後略)」と書いた。
嬉しさのあまり早速報告したのだが、その実、出席した病理学者は、「あの東洋人は、なにをいっているのかさっぱりわからない」と、首を傾けた。
英世の英語は日常的なことならともかく、学会で喋るには、まだ未熟であった。
それにしても、渡米わずか四か月で、学内の集会とはいえ、一介の私設秘書に発表させるとは、やはりアメリカは開放された国だった。これが日本の学会でならまずありえない。英世がそのまま北里研究所に残っていたとしても、そんな機会に恵まれたとは思えない。英世はさらに「大学教授連及書記等は小生の為、頗る親切にして到底学資を以て入学せる普通学生の得がたき幸福を稟け居申候……」と書きくわえている。
このころ、英世は渡米直後フレキスナー教授に紹介された下宿を出た。原因は金がときどき失くなることであった。もちろん英世はたいした金をもっていないから、盗まれるのは少額である。この家には母親と娘が一人いて、英世は彼女等に英語を習っていた。家族にも家にも慣れて出る気はなかったが、盗難が二度、三度となると、さすがにいい気はしない。
迷った末、出ようと思っていることを告げると、親娘二人で「このままいてくれるように」と懇願した。それで英世は一旦は残るつもりになったが、それが英世への好意からでなく、大学側の心証を悪くすることを恐れているためと知って、英世は直ちに出ることに決めた。
次に移ったところは、大学には前より遠いが、歩いて十数分の南三十三番街であった。
6
当時のフィラデルフィアの大学教授の家は、チェスナッツ街一帯の高級住宅地にあって、いずれも広い庭をとった三階建ての鉄筋であった。内部もマントルピースに豪華な家具を備え、絨毯を敷きつめ、天井にはシャンデリアが輝いている。
こうした家を見る度に英世はその豪華さに驚き、感歎した。
「金持ちはもちろん、貧しい者も応接間をもち、できるだけ飾り立て、人々の目をたのしませます」「応接間は多くの通行人の目にとまる場所に設け、カーテンで半ば隠し、きわめて魅力的な外観を備えています」守之助の手紙に、英世は洋館のなかを詳しく説明し、さらに当地の新聞や雑誌も送った。
ペンシルバニア大学の研究室は部屋がニ、三十坪はあり、そのなかにずらりと実験台が並び、試験管が林立していた。日本ではまだ珍しく、英世など容易に触らせてもらえなかった顕微鏡が、学生一人に一台ずつ与えられるという状態である。しかも兔やモルモットなど、実験動物に使う金が、毎日五十ドル近くになる。かつて北里研究所でモルモットを請求して、若輩のくせになにをいうかと笑われたことと較べれば、雲泥の違いであった。
この年八月二十四日の守之助への書翰では、来年四月に、守之助が歯科講義叢書を出す予定だと伝えてきたことに対して、「題目はなるたけ買う人の目を惹くもののほうがいいが、その点"叢書"というのは少し面白くありません。私の考えでは、将来版を改めるにつれ、漸次に訂正して立派な教科書にする予定で、題名は拡大して"歯科医学講本"としたほうが、よいと思います」と述べたあと、「できることなら日本の医学週報をときどき送っていただきたい。またよい詩集とか、思想と胆力を養う教養書なども送っていただきたい」と希望している。
さらに、
又、小生の当地に来つて学びしものは、学術の外に世の中は如何なるものなるやの一端を大いに学び申候。栄枯とは如何なるもの、貧富とは如何なるもの、人間は如何なるもの、生活は如何なる方法を以て満足すべきもの、社会及び個人は如何なる関係あるもの、自己の所信と天職等に就き、面白く感居申候。
殊に人種間の軋轢及び和合など、中々面白く御座候。此等の渦中にあって常に保つべきものは「望み」と「徳義」に御座候。即ち人間には此の二者を実行するより以上の快楽は無之候。
小生は今日既に渡米の目的の一半を実行致申候。唯他の一半は一部運命にして一部は躬行に御座候。偖而小生渡米の当時の理想は(今更白状すれば)頗る狭小に候ひし、即ち一部否殆んど栄誉を得んとの考へが第一番に有之申候。
然るに今日は此の考へは全然消失して、単に斯道の為に一生を犠すること、若し其位置を日本にて得る能はざれば糊口し得る独立の方針を執り、傲慢なる官制の下に束縛せらるることを避け、藪医者でも何でもよろしい円満に此の世を過ごし、自ら成し得る丈に力を以て他人を助け、其成功を見て満足可致候。
畢竟、無為無能視せられ、而かも自から恃む処あらば充分に御座候。如何なる位置にあるも自己の意志を実行するは左程難きものに無之候。
追伸
小生の二か年任期とは二か学期にして、毎年十月より翌年五月末までに候。然るに小生は本年一月より持続して本年の九月まで、一日も休まず研究したる故、二学期以上の時日は既に経過致申候。就而は本年十月より来年五月末までに第二の学期を消費する次第に御座候。即ち翌年六月に満期に御座候。其後多分大学と関係を絶つことに相成可申候。危機は愈々御前に迫りつつあり申候。ニ、三回の通信をやればすぐに其日に相成可申候。
時下残暑の候は御自愛専一に奉祈上候 頓首拝白
九月十六日夜半
英世
血脇守之助侍史
この手紙を見ると、英世の気持がずいぶん変ってきていることがわかる。
外国での苦労、ここでみたさまざまな社会の動きから、ただがむしゃらに名誉だけを得ようとすることが、いかに無意味なものであることか、そして自分のやりたい仕事に専一でき、他人を助けることができれば、それで満足である、といいきっている。英世のこのあとの足跡を追えば、いうとおり実行したとは思えないが、気持の上だけでも、そう思うようになったということは画期的なことだった。
さらに春ころまでは、生活とお金のことばかり書いてあったのが、このころから視野を広げ、アメリカ社会のあり様に対しても観察批判している。だが、そのころはまだ、来年六月の研究期間後について、はっきりした目途をもっていなかった。
なおこの手紙のあとに、
「マッキンレー氏一昨年午前二時十五分死亡、副大統領ルーズヴェルト氏大統領の後を襲ふ。 Roosvelt と申候。氏は一農家の子にして幼時は牧童に候。全市半旗を掲げ国内服喪。来る十七日は華府にて国葬の筈」と記している。
ここにあるとおり、第二十六代大統領、マッキンレーは無政府主義者の凶弾に射たれて死亡した。
この事件の背景について英世は「大統領を倒したのは無政府主義者の仕業で、米国のようにさまざまな移住民から成立している国では、マッキンレー氏の提唱するような帝国主義は、一部の下層民に不満を与えるばかりです」と、守之助の手紙で述べ、さらに「弱肉強食的な米国社会では、はずれ者が多く生まれ、これがみな人間は平等という意識があるおかげで、かえって上流階級への妬心が生じ問題をおこすようです」と分析し、「これらは欧米における専制政治の名残りともいえます」と見ている。そして「アナーキストは社会に害悪を流すが、彼等のよってきた心情を考えれば、また当然です」と、かなり同情的である。
だが英世は無政府主義に賛成していたわけではない。「彼等は追いつめられた亡民だ」といいながら、「わが国には数千年におよぶ確固とした国体があり、天皇と臣下の区別ははっきりして、親子の関係も秩序正しく保たれています。外国のようにニ、三代で主権者が変り専制を敷かないところが最も優れていて、このような国体の下で生活を営んでいる日本人は幸せです」と断じている。
アメリカ流にいうと、英世一家はまさしく日本の流民であり、弱肉強食の弱肉のほうであった。日本の底辺の国民として育ちながら、日本は万世一系の国体があるから日本人は幸せで、アナーキストは排出しないだろうと考える。このあたりに英世の社会認識の甘さが見られるが、そこには明治三十年代という時代背景も考えなければならない。
この日本は明治維新を経て、ようやく近代国家への第一歩を踏み出したときであった。いまから考えれば明治憲法は天皇を主権者とみなした反動的なものであったが、江戸という過酷な封建時代からみれば、はるかに開かれた自由な時代であった。このあとに続く富国強兵政策による社会的な歪みもまださほどでなく、国民すべてが前向きにすすんでいたときであった。
このような時代に育った英世が、日本の国体に疑問を抱かなかったのは、無理ないともいえる。文化的にも経済的にも、はるかにすすんでいるアメリカにきて、この国に負けないものとして国体の無比をあげるところなど、良きにつけ悪しきにつけ、英世は明治の日本人であった。
しかし英世に日本の社会体制への批判がなかったわけではない。
同じ守之助への手紙のなかで、「米国での一般の交際は金の有無によって左右され、専門的交際はその人の実力と、学問への取り組み方によってきまります。人間に階級はなく、人権平等というのは実に現実的なものです」と半ば感心し、半ば呆れたあと、「日本のような小さな島国で、幾つもの華族があることなど、こちらではとても理解できないことです」と述べている。
このころ、英世はフレキスナー教授の努力により、大学から直接給料をもらえる状態になっていた。もっとも給料といっても大学の研究費の一部をさいたもので、月額三十ドルで、これで食費から衣服、下宿代の一切を払わなければならない。
この見返りの業務として一定の研究問題が与えられ、その研究に従事するという仕組みであった。
英世が守之助への手紙のなかで、何度もこの研究が終ればアメリカにいられなくなるかもしれないと憂えていたのは、いまだ大学の正式の助手でなく、その研究が終れば要員としての給料をストップされる不安があったあらであった。
このような状態の研究生をなんと呼ぶのか、日本ではさしずめ臨時助手とでもいうのかもしれないが、英世は自らを「名誉助手」と称して、「この名誉助手は信用と技術とを兼ね合わせてでなければ容易になれるものでなく、わたしのこれまでの実績と、中国で発表した黒死病に関する研究実績、日本で出版した医書、実験録等を検討した結果、推薦されたものです」と述べている。
たしかにある日ぶらりとやってきた東洋人が、研究費から給料まで出してもらう待遇を受けるのは、尋常なことではない。考えようによっては、これはいつまでもポケットマネーをけずるわけにはいかなかったフレキスナー教授の苦肉の策といえなくもない。いずれにせよ名誉というのは、普通は市長とか学長につけるもので、助手の上に名誉を冠したのは、おそらく英世がはじめてであろう。
大言壮語するだけに英世はよく頑張った。相変わらず不眠不休の勉強が続く。
7
やがて十一月十三、十四の両日、フィラデルフィアで、「ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス」の総会が開かれた。このとき英世は「蛇毒の溶血性細菌と毒性に関する予備的研究」と題して、ミッチェル博士と連名で発表するチャンスを与えられた。
もっとも連名といっても、正式の演壇で発表するのはミッチェル博士で、英世はその横で、博士の話に合わせて試験管や希釈液を見せながら実験のあらましを動作で説明する、いわば発表助手で、英世自身は一言もものをいわなくてもよかった。
だが英世は興奮した。説示役とはいえ、こんな権威ある会に出られるチャンスなど滅多にあるものではない。たしかにこの会は、当時のアメリカの自然科学界の集会では最も権威あるもので、会員は全国で百名に限定され、当日はそのうちの三十名が出席した。
このなかにはワシントン大学のコムストック教授、ジョンス・ホプキンス大学総長のレムゼン教授、エール大学のプラッシュ及びブリューワー教授、生理学のチッテンデン教授など、アメリカ自然科学界の重鎮が出席していた。ここで英世はミッチェル博士の紹介により実験手技を披露し、英世自身の言葉によると「出席者の誰からも異議は出ず大成功であった」と、興奮気味に述べている。
しかしそれは無理もないことで、ここに出席したした人達は、一流の学者ばかりではあるが、いずれも専門が違う。異議が出なかったというより、正直いって専門外でわからなかったといったほうが当っていた。ただ彼等は科学者の勘として、その実験が興味ある面白い点をついていることだけは理解できた。
このあと、夕方からべルヴュ・ホテルで夕食懇親会がおこなわれ、英世も招待されたがこのときの喜びを、
「会員以外の出席者は四名で、一は当大学医科部長マーシャル氏、他は教授フレキスナー氏、衛生学教授アポット氏であった。自分の席は幸い右側に電気学者のブリューワー教授、左にはジョンス・ホプキンス大学病理学教授ウェルチ氏(この人はフレキスナー教授の先生で、小生を孫のように可愛がってくれました)、次に医学部長、その先に測量家のヘーグ氏、小生の向かいには、かねてから尊敬していた化学者チッテンデ氏(今日の消化化学は同氏およびドイツのクェーネ氏に負うところが多大です)、其の隣りには教授フレキスナー氏。それより正座に移って主人役のワイア・ミッチェル氏(いうまでもなく蛇毒研究に当っては三十年以来有名です)で、その右横に総監コムストックおよびレムゼンの諸氏でした。小生はこのような席で幸運にもミッチェル博士の紹介で、出席者のほとんどと知る機会をえ、これから冬季の休みを利用して、彼等を順に訪問するつもりです。ジョン・ホプキンスはじめエール、コロンビア、ハーヴァード各大学の人々から熱心に来遊をすすめられました」
と守之助に報告し、さらに、
「なお、一寸申しそえておきますが、当夜席上、日本人で名前が出たのは北里博士と箕作佳吉博士の二人だけでした」
このあたりは、なにやら英世がこれら二人の日本人と同列のような錯覚を起しかねない書き方である。
このとき発表した論文には、共同研究者として、ワイア・ミッチェルと野口英世の二名が連なり、フレキスナー教授の名ははずれていた。
英世はこのことが気になって、フレキスナー教授に、「一緒に名前を連ねてはいかがですか」といってみたが、フレキスナーは首を横に振って「一つの論文に三名の名前を連ねるのは多すぎる。わしは一向に構わぬからそのままでよろしい」と答えた。
ミッチェルは何故、フレキスナーに声をかけなかったのか、そのあたりの真意はわからないが、ミッチェルが、すでに教授となり、自主的な研究を始めていたフレキスナーより、自分の命じるとおり素直にやる英世のほうを可愛がっていたことはたしかだった。
「今回はともかく、この次の報告では私と君の連名にしよう」フレキスナーにいわれて英世は、「よろしくお願いします」とだけ答えた。
蛇毒研究の専任助手として、ミッチェルとフレキスナーと、二人のボスにはさまれて英世の立場は微妙であった。
アカデミーで発表したことにより、英世はパッシュ基金の「スミソニアン・インスティチュート」のスカラーシップを受けることになり、「ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス」および「カーネギー科学研究所」から二千ドルの研究費を受けることになった。推薦者はミッチェル博士であった。
この金はもちろん研究のためで、私用に流用することは許されないが、ともかくこれで当分彼の立場は安定した。英世は早速ミッチェル博士に礼をいいに行き、さらに研究に専心することを誓った。このあたりの率直な態度が、ヤンキーそのままのミッチェルに好かれた原因でもあった。
この研究でスタッフに入って、「ヒデヨ・ノグチ」の名は、フィラデルフィアの新聞に初めてのり、論文は日本の医学雑誌にも転載された。
かつてフレキスナー教授来日の様子をきくため、英世を自宅に呼んで説明を求めた石黒忠悳男爵は、この記事を知って、みずから英世にお祝いの手紙を送ってよこした。感激した英世は、このあと論文が発表される度に毎回別刷りを石黒男爵に送り続け、謝意をつくした。
ともかく英字新聞にのったことで、英世の名は在米邦人のあいだでも知られるようになった。
ワシントン在住の高平公使も英世に関心を抱いた一人で、フィラデルフィア名誉領事のオストファイア氏がワシントンに赴いた折、彼に英世のことをいろいろ尋ねた。オストファイア氏はフレキスナー教授などからきいたことを、懇切に話してきかせたので、高平氏はおおいに感激して、ワシントン在住の日本人達にさらに話してきかせた。
英世はこのことをきいて喜び、一日、領事館を訪れてオストファイア領事に礼をいった。領事は英世を歓待し、彼からフレキスナー教授に、さらに給料でもあげてもらえるように頼んでみようとまでいってくれた。
このあたり、急な野口株の上昇に、英世自身もいささか面喰ってもいた。
このころから英世はフィラデルフィア在住の日本人とも付き合いができ、同市の日本人会にも出席するようになった。この会は毎月持ち廻りで各家庭に招き、日本食を食べながら、日本語で話し合う、日本人だけの気さくな会であった。
英世はいつも招かれているほうだったが、英字新聞にものり、いささか有名にもなったので、ワルト通りにある自宅に彼等を招待することになった。もっとも、招待といってもキッチンとリビングルームだけの小さなアパートで、料理も英世が自分でつくらねばならない。
このとき、英世は会津で食べたことにある鶏の丸焼きをつくろうと思った。
ところが台所で鍋に湯を沸かし、鶏を買ってきて羽根をむしっているうちに、毎日のように実験動物を扱っていたせいか、条件反射的に蛇毒の溶血現象のことが思い出された。
どうしてそうなるのか、考えてうちに書斎から参考書をとりだし読みはじめた。ニ、三ページのつもりが、読むうちに熱中して、友達を招待していることを忘れてしまった。それから三十分ほどして晩餐会の時間になり、友人達がおしかけてきた。そこで英世は初めて鍋に鶏をいれたままに気がついて、鍋を開けてみると、鶏はなおぐつぐつと煮えている。英世は早速、、中央の大皿に差し出したが、みな妙な顔をしたまま箸をつけようともしない。
「野口さん、なにか、変な匂いがしますよ」
「どうしてかな」
「これは臭くって、とても食べられやしないぜ、まさか腐った肉をいれたんじゃないでしょうね」
「そんなことはない、肉屋から今朝殺したばかりのを買ってきたんだが」
「うっかりして、鶏の内臓を出すのを忘れて、腸も糞もそのままに煮てしまった」
「冗談じゃありませんよ。そんなものを食わせられちゃかなわないね」
「つい、本を読みながらやったものだから」
悪びれず頭を下げる英世に、空腹の苛立っていた日本人達も怒るわけにもいかず、ただあきれて溜息をつく。
英世には、気違いのように勉強する反面、こうした抜けたところがいくつかあった。研究仲間のパンチングは、英世によく「少し休んでサーカスでも見てこいよ、それは素晴らしいぜ」とけしかけるが、英世はいつも、「今日はちょっと忙しいので」といって断わる。
「なんなら俺が招待しようか」といっても、「いや……」と笑うだけで行こうとしない。研究室にいるあいだは、食事時間以外は、実験に没頭しているか、仲間と研究について議論するだけである。
「一体、日本人はいつ寝るのだ」と、同僚のゲーがあきれていたのも、このころである。
これほど仕事に熱中していながら、時々とてつもない失敗をやらかす。
このころ実験室に一頭のマングースが届いた。ゲーが大変な骨折りの結果、税関の許可書をえてジャマイカから取り寄せたものである。
マング―スは毒蛇を殺すという点で興味ある動物で、その血球は他の動物のように、毒蛇の液によって溶解するか否か関心がもたれていた。毒蛇を殺して平気なところをみると、この動物の血球だけが、溶解しない特殊なものなのかもしれない。貴重な動物だが噛みつく危険もあるので、実験の前にあらかじめクロロフォルムで麻酔しておくよう、英世が命じられた。ところが英世はこれを、麻酔をかけず殺してしまった。折角ジャマイカから運びこんだものを、なんの実験もしないうちに無駄にしてしまったのでさる。さすがにこのときだけはフレキスナー教授に厳しく叱られた。
「どうして、もう少し要領よく出来ないんだ。お前はわれわれの研究を邪魔するためにここにいるのか」
へまをすると、英世はきまって無口になり、ときには休むことさえある。このときも二日休んだ。
ゲーなどは、上司に無理なことをいわれたら、いい返すべきだ」というのだが、英世は、「日本では目上の人にそんなことはしない」といってうなだれるだけである。
「叱れたとき、ノグチはまるで小動物のように、部屋の片隅で小さくなっている」と、ゲーはあとで述懐している。英世としては、いいかえしたいにも言葉がスムーズに出てこないうえ、いたずらに反撥して、大学を追われてはまずいという思慮もあった。
失敗したとき、英世はよく下宿で一人で泣いた。強そうにみえても英世もただの男であった。自分の至らなさへの腹立たしさと、異郷での一人の寂しさが身に沁みた。だがそれも大体一日休めば、気持ちがふっ切れる。大体、英世には、調子のいいときはやたら騒ぎ、一旦落ちこむとほとんど口をきかない、躁鬱的なところがあったが、それがアメリカに来てからは特に強くなっていた。
それにしても、今度の失敗だけはさすがにこたえた。これで実験は一頓挫をきたす。例によって仕事も手につかず、隅のほうで小さくなっている英世のところへ、パンチングがきて、
「どうしたイエロベリル君。まあ元気を出して飲みに行こう」と誘う。
このころ英世は一部の仲間にイエロベリル(黄禍君)と呼ばれていた。この言葉は、本来、アジア人種のヨーロッパの侵害を恐怖した想像説をさすが、必ずしも悪い意味で使っていたわけではない。英世の勉強ぶりが同僚に一種の驚きを与え、それをもじったまでのことだった。
このパンチングと英世はよく飲みに出かけた。場所は下町の豚肉料理をさかなにウイスキーを飲む安酒場である。ここでウイスキーをお替りし、ぼそぼそ話すうちに英世の気持は次第に晴れてくる。
「たしかに失敗したお前は悪いが、失敗するお前に麻酔をかけさせたボスも悪い。今度気をつければそれでいいのだ」アメリカ的ドライさにうなずきながら、英世はやはりそうスムーズには割り切れない。
だがこのころになると、英世も研究室の仲間と大分親しく口をきけるようになっていた。
たとえばこの秋、ローマ法王レオ十三世が逝去し、研究室の若者は集まって、後任法王に誰がなるかということで賭けをした。こういうとき、英世は月給三十ドル余りしかもらっていないのに、きまって最高額の五ドルを出した。しかも彼は、法王選出の細かい手続きなどよく知らぬのに、みなと対等かそれ以上の大きな賭けをする。上の制限がなければ、もっと出したかったが、とにかく掛け金一つにも、英世の負けん気が露骨にでた。
またなにか会があって、座が陽気なってくると、英世はきまって同僚に流行歌を歌うようにすすめた。
「君はアメリカの歌が好きなのか」友達が尋ねると、英世は平然と「好きだが、それ以上に、歌をきいていると、こちらの俗語を覚えるからな」と答えた。
アメリカにきて二年近くたっても、英世の英語はまだよく通じるとはいえなかった。単語はかなり知っていても発音がまずい。ときには簡単な会話にさえてこずることがあった。
仲間は彼の英語をさして「牡牛の英語」といっていた。興奮するとアメリカ人には、牡牛がものをいっているように、きこえたからである。
「俺の欠点は手の不具とそして英語がまずいことだ」
英世は自分でそう思っていた。しかし持ち前の図々しさで、誰彼となく摑まえて英語を喋る。さらに研究室に、<英語のほか喋るべからず>という貼紙をして、日本語を一切喋らないようにした。
また英世は白衣のポケットに、いつも年老いた白鼠を一匹しのばせていた。
「俺はこの鼠の言葉が全部きける」英世は自慢そうにいっていたが、たしかにその鼠は英世によくなついていた。彼からパンをもらうと美味そうに食べ、またポケットにもぐり込む。
初め、研究室にはメスの鼠が十二匹いたが、このオスの白鼠が彼女等と関係して歩いた。しかしいまはもうこの白鼠はオスとしては役立たずになっていた。
「要するに名誉親父さ」
英世はそんな綽名をつけて、一人で白鼠となにやら話し込んでいる。人々は動物好きな男だと怪訝な表情をしていたが、そんなときの英世は孤独だった。
万事に好奇心が強く、積極的な性格とはいえ、英世はやはり日本人だった。大学の構内などで、向こうから先輩や仲間がくると、英世は早めに立ち止って相手が近づくのを待って挨拶する。帽子をかぶっているときは、それをきちんととって頭を下げ、それから思い出したように握手をする。研究所の廊下などで会っても、つい廊下の端に寄るようにして軽く会釈する。
英世には日本の流儀が忘れられないだけだが、それがアメリカ人から見ると、控え目で礼儀正しく見えた。ある同僚は彼の態度を評して、「ラフカディオ・ハーンの小説に描写されているのとそっくりだ」と感心した。
だが慇懃かと思うと、マングス死亡事件にみるように、要領が悪く、とてつもない失態をやらかす。さらにみなの顰蹙をかったのは、彼のだらしなさだった。これは英世の性格で、整理整頓ということを一切しない。
ローガンホールの彼の研究室を覗いた他の教授が、そのあまりの汚さにあきれ、「あんなだらしのない男は駄目だ、絶対に大成しない」と、口をきわめて罵ったが、この教授にかぎらず、他の同僚も英世のだらしなさには、ほとんどあきれていた。蔭では「汚ない日本人」という綽名さえ与えられていたが、英世のだらしなさは、猪苗代の貧しい家で育った乱雑さが身にしみついた、としかいいようのない生来のものであった。
8
このころ、英世は日本人会で一人の日本人に会った。のちに星製薬を創立した星一である。当時、星は英世の三つ上の三十歳、コロンビア大学に留学したあと、ニューヨークで「日米週報」という新聞を出し、ワシントンに行った帰りに立寄ったのだった。
二人は話しあううちに、英世は三城潟で星は石城と、ともに福島県人であることがわかった。早速、二人はお国言葉で話し合い、会のあと、英世は星を自分の下宿へ誘った。
例によって英世の部屋は家具らしい家具は何もない、若い二人は部屋の片隅にあるダブルベッドに腰を下ろしたまま語り合った。
このときも、英世が真先にいい出したのは金を貸してくれ、ということだった。英世が日本人会に行くのは、在留邦人との親睦もさることながら、他人のおごりで食事をし、金を持っていそうなスポンサーを探すのが目的であった。星の実父は村長で郡会議長も兼ね、ニューヨークで新聞社まで経営しているときいて、英世がとびつかないわけがない。だがその申し出を星は諭しながら断わった。
「なんとか食べていければそれでいいんだ。俺なんか、来た当初は食うや食わずの日が何日もあった。以前ならともかく、いまは雑誌の発行で金がかかり、君に援助する余裕などはない」
実際、星はそのころ、「日米週報」にくわえて、「ジャパン・アンド・アメリカ」という英文雑誌の発行をはじめたばかりで、これに「日米週報」でえた金の大半をつぎこんでいた。
この星という人は、やることが一風変わっていて万事スケールが大きかった。当時、アメリカに留学していた日本人のほとんどは、卒業論文に日本に関係あることをテーマにしていたが、星は敢えて、「アメリカにおけるトラスト」という、アメリカ独自のテーマを選んで学位を得た。「ジャパン・アンド・アメリカ」も、日本人がアメリカで、アメリカ人向けの雑誌を発行するという、当時では信じられないような野心的な企画であった。
困難を知ると、一層そこに向かって突きすすみたくなるのが、星の性格であったが、英世は、この星のスケールの大きさにいささか呑まれて、借金のほうはあきらめた。
「ところで、君がこちらで頑張っていることを、『日米週報』の記事にしたいから、一度研究室を見せてくれないか」彼は早くも新聞記者根性を出した。
英世は一緒に下宿に泊った翌日、星をローガンホールへ案内し、自分の研究室から動物小屋、さらにフレキスナー教授の部屋まで見せて廻った。研究室では、「これが顕微鏡だ、覗いてみろ」と、得意だった。いわれるとおり、星は覗いたが、両岸を開けたまま覗き込んでいる。
「これは驚いた、あんたは新聞記者なんかより、医者になったほうがいいよ」
「どうして?」
「大抵の人は顕微鏡を覗くとき、鏡に向けた眼だけをあけて、もう一方の眼は閉じている。だが医者は顕微鏡を見ながら、もう一方の眼でスケッチできるように両岸を開ける訓練が大切だ。これができたら学者として一人前だ」
「なるほど、褒めてもらったのは、ありがたいが、残念ながら俺は子供のときに右眼に矢が当って、あいているように見えるが、左の眼しか見えないんだ」
英世は改めて星の眼を見てから、
「失礼なことをいったようだが、実は私も左手がこんな状態だ」
英世は初めて自分から、ちびた左手の指をさし出した。星はそれを見ていたがやがて英世の肩を叩いて
「学問の世界で、片眼や片手ぐらいいうことをきかなくても、たいしたことはないよ」
これ以来、二人は急に親しくなり星はワシントンへ行くたびフィラデルフィアで降り、英世の下宿に泊っていくようになった。
二人は合う度に夜を撤していろいろなことを話した。アメリカ滞在期間は星のほうがはるかに長いので、彼が教える場合の方が多い。
「この国では、とにかく頑張ることだ。一生懸命やっていたら、きっと応援する人が現われる。この国は日本と違って人間はみな自由で生き生きしている」
星の意見に、英世は大きくうなずく。この星が泊っているときに、英世あときどき深夜に起き出して、服を着ることがあった。
「どうしたんだ、寝呆けたのか」
「いや、これからちょっと研究室へ行ってくる。君はそのまま休んでいてくれ」英世はそういうと、そそくさと部屋を出ていく。
英世は時間毎に、病原菌の変化を測定する仕事をしていたが、夜中に一旦出かけると帰らず、星が研究室に行ってみると、兔の横につききりで観察していることもあった。
だらしなく、自分勝手なところがあるが、やり出すと熱中する。そんな英世を、星は将来性があると見込み、英世もスケールの大きい星に惹かれた。こうして二人の友情は深まっていったがこのとき星はまだ、英世が将来大学者になることも、自分がこの男にかなり金をせびられる身になることも、思ってはいなかった。
9
英世がフィラデルフィアに来て一年半が過ぎた。この間、英世一流の頑張りで、ようやく生活も安定してきていた。豊かではないが贅沢をしなければ一応、人並みの生活はできるようになった。
大体、フィラデルフィアという街は敬虔なクエーカー教徒が多く、道徳的色彩の濃い街であった。遊ぶといえば、パブみたいなところで軽く飲んだり食べるだけで、低俗な遊び場はほとんどない。月、三十ドル前後の金で、英世がなんとかやっていけたのは、この遊び場がなかったお蔭ともいえる。
遊ばないとその分勉強できるとはいえ、さすがに下宿で一人でいると、日本のことが思い出される。猪苗代のこと、母のこと、小林栄、血脇守之助、そして友達など。
このころ、英世に会った日本人は、彼から母のシカのことはよくきかされたが父の佐代助のことは誰もきいていない。なかには、英世は母一人で、父は死んでいるのだと思っている者さえいた。英世にとって、父のことは思い出したくない、忘れたい存在であり、アメリカから日本に送られた数十通の手紙のなかにも、父のことについて書かれた文章は一つもない。子供心に抱いた父への侮蔑と嫌悪感は長じても変ることはなかった。
しかし、表面は強そうに見えても、英世もときにホームシックにかられ、ニューヨークにいた友達の児玉にあて、「あなたがホームシックになった時には、いつでもお便りを下さい。あなたがそのようなときには、僕も矢張り同じようなものですから」と書き送っている。守之助や小林栄へ、しきりに手紙を書いたのも、生来の筆まめにくわえ、異国での淋しさが、それをさらにかりたてたともいえる。
だがこの勘、一通の手紙も出さず、しかもなお心で思いつめていた人が一人だけいた。山内ヨネ子である。
清国に行くとき態よくあしらわれ、アメリカにくるときにも会えなかったヨネ子のことが、いまだに忘れられない。斎藤ます子と婚約しても、心はヨネ子のほうを思い続けている。
その後どうしたか、気になってもアメリカまで、消息が伝わってくるわけでもない。思いあぐねた英世は、会津若松に開業したヨネ子の従兄の菊池良馨宛に手紙を書いた。自分がいまペンシルバニアにきて研究していること、もう落ち着いて大分馴れたことなどを書き送った。本当はヨネ子のことをききたいのはやまやまながら、すぐ書かないところが、英世の純情なところであった。
菊池からは折返し、渡米していることをきいて驚いたこと、ついては眼科か耳鼻科、咽喉科のいい医学書があれば送ってほしいといってきた。金のない英世が、ここで大枚を投じて、当時評判だったデ・シュワイニツ博士の本と診断学の本を送り、同時に送った手紙の端に、「ヨネ子さんはお元気でしょうか」と一行だけつけくわえた。
菊池からは、本を受け取った礼状とともに、ヨネ子はその後医師免許状をとって開業し、同じ医師の香川俊雄と結婚して新婚家庭を送っている、と書いてよこした。菊池は、英世がヨネ子を好いていたことを知っていたが、いまさら隠したところで仕方がないし、英世も昔ほどヨネ子に執着しているわけではないと思ったからである。
だが、それを読んだ途端、英世はそのまま手紙を握りつぶして捨てた。それから机に向かって、一気に手紙を書いた。
<夏夜に飛去る流星、誰がこれを追ふものぞ、君よ、快闊に世を送り給へ……>
そのときの手紙の一節である。英世の数ある手紙のなかでも、際立った一節だが、そこに、去っていった友への未練と口惜しさ滲み出ている。
さらに日記に「自分は彼女を将来ただ一人の女性として、大切にしたいと願っていたが、すでに夢は砕かれこの悲しみは一生忘れない。かくなる上は、ひたすら勉学に励み、その夫、森川某に抜きんでることで見返してやる」と書きこんだ。
この後、英世は菊池への手紙のなかで、一切ヨネ子のことについて尋ねることはなかった。菊池へ送ってよこすのは英語の論文と、自分がいかにアメリカで期待されている研究者かというだけだった。
だがヨネ子が去った今となっては」、菊池の存在は、英世にとってなんの価値もない。その菊池への手紙は次第に間遠くなっていったのは仕方がない。
これほどヨネ子のことを好いていたのだから、婚約者の斎藤ます子のことがおろそかになるのも無理はない。アメリカに来きてから、斎藤家英世は無事に着いたという手紙を一通送っただけだった。
齋藤家ではさすがに心配して、守之助の許へ、英世がいつ帰国するのか、何度も問い合わせがあった。全然、帰る気のない男を、しきりに待っている夫人と英世の板ばさみにあって、守之助は困りはてた。
「いま少し研究の目途がつくまで、待ってみて下さい」そういって、その場をつくろう。
このころ、英世の母親のシカは、親戚の野口クマをしのぐほどの産婆になっていた。法律が変り、産婆にも資格が必要になって勉強を始めたのである。
実技ではすでに、高齢のクマに負けぬほど上手で、師匠のクマより上だともいわれていたが、年齢をとってからの勉強は大変である。だがシカは生来の負けん気を発揮し、十日間、坂下町の三宅女史のところに住みこみ講習を受けた。幼いとき、村の僧侶に仮名文字をおそわっただけのシカが、生理学や解剖学を教わる。ごく初歩的なものとはいえ、普通の人では到底続かない勉強であった。
シカは頑張って、ついに村で一人だけ資格をえた。ところが、資格をとっても、産婆を開業するだけの資力がない。仕方なく村長は村民から金を募め、それでシカに時計や聴診器などを買って与え、ようやく有資格の産婆を獲得するというありさまだった。
母子はよく似るというが、この頑張りはまさしく英世そっくりであった。
だが、シカの家は少しも楽にならなかった。村でただ一人の産婆として、ほうぼうから口をかけられたが、「家は昔から貧乏で、みなさまのお世話でこれまで生きてこられました。産婆の礼金など大層なものはいりません。ほんの思召しだけで結構です」といって、貧しい者からは金をとらない。
英世の弟の清三は若松に年期奉公に出ていたが、家には、姉のイヌと養子がいて、そのあいだに、栄、寅吉、英策と小さな子が三人続き、さらに七十を越えて、ほとんど動けぬ祖母のみなさんもいた。それに佐代助は相変らずシカの働いてきた金をくすねては飲み歩いた。村の人びとは、シカには絶大な信頼を寄せてはいたが、これだけ扶養者がいては、楽になるわけもなかった。
この年の初夏、一九〇二年の六月、英世はフィラデルフィアを離れて、北米のボストンに近いマサチューセッツ州ウッズホールの臨海生物研究所に三か月の予定で出張することになった。目的は各魚類から血を採り、これらの蛇毒による溶血作用を調べるためであった。
七、八月といえば、欧米の学者はほとんどが長い夏休みをとるときだが、英世は単身、海浜へ行って研究を続けようというのである。着いた翌日、ニューヨークにいる友人の児玉に宛てて次のように書いている。
「前略、ウッズホールの風景は丁度横浜の西方の長浜に似ていて綺麗です。ここには二人の女子研究生が居ります。両方とも若くはなく、むしろオールドミスというべきでしょう(後略)」
英世がここに来ているあいだに、会津若松の小林栄の実母が死去し、次いで小林夫人が再度病床に伏した。その都度、英世は丁重な見舞いの手紙を出し、すぐ駆けつけていけないことを嘆いている。
この八月に小林栄に出した手紙のなかに、「今日猪苗代小学校を東京大学の上に置き、恩師を大学教授の上に奉ずる事、敢而難からず相成申候……」という一節がある。自分にとって、猪苗代小学校は東京大学より偉大であり、小林恩師は大学教授以上の人である、と訴えているのである。例のオーバーな表現といえばそれまでだが、このなかに小林栄への敬意と東大へのあくなき反抗精神が読みとれる。
やがて九月になり、三か月の研修を終えて英世はウッズホールからフィラデルフィアへ帰った。
帰来すると、フレキスナー教授は、英世をペンシルバニア大学の正式の病理学助手に任命し、近くドイツへ留学させる予定であることを告げた。
これを聞いた瞬間、英世は「本当ですか?」と何度もたしかめ、フレキスナーがうなずくと、「ありがとうございます」といって、自分から教授に抱きついた。
これで身分の不安定な研究助手から大学の正式の助手になれる。しかもヨーロッパに行ける。アメリカがいいとはいえ、医学を専攻する以上やはり一度はヨーロッパに行ってきたい。それほどヨーロッパがすすんでいるというわけではないが、ドイツ医学一辺倒の日本では、ドイツで学んできたこと自体が、経験に花をそえることになる。
大学の正式助手からヨーロッパ留学と、突然、英世の前途が開けたが、これには英世の努力以外に、もう一つ別の背景もあった。当時アメリカの富豪ロックフェラー氏から、医学の進歩のためにと、総額百万ドルに及ぶ寄付の申出があり、これによってニューヨークに最新の医学研究所が設立されることになっていた。この初代所長に、ミッチェル等の推挙によりフレキスナー教授教授が内定したのである。
この研究所は病理だけでなく、微生物、衛生から臨床まで、医学全般にわたり優秀なスタッフを集めた総合研究所を造る予定だったがフレキスナー教授はここに、ペンシルバニア大学の数十人のスタッフのなかから英世一人を連れていこうと考えていたのである。このあたりはまさしく、アメリカの学者のフランクというか現実的なところで、人種や年功などに関わらずファイトがあって仕事のできる男を抜擢する決して情実にとらわれない。
フレキスナーは英世をニューヨークへ連れていく準備といて、まず正式の助手にし、それから一度ヨーロッパに留学させておこうと考えた。正式の行先は、コペンハーゲンのメルワル・マオセン管下にある国立血清研究所であったが、その実態はドイツ系の研究所と変らなかった。
この喜びを、英世はいち早く小林栄に報告した。
「幸い今年度より先は正式の任命を受け、大学にても万事好都合に御座候。且つ前便申上候通り、いよいよ明年はヨーロッパに研究のため留学を許される予定(これは小生より頼みしにあらず、大学にてその資格ありと信じ、充分学資を給し、留学をせしむるなり。今日まで外国大学より留学を命ぜられた日本人はなし)(中略)実に自ら嬉しく御座候。ドイツ留学は多分満一か年かと存じ候。しかし研究の都合により二か年になるやもしれず(後略)」
しかし、ドイツを通りこして北欧に行くことが、英世は少し気がかりではあった。それで軽く見られては困る。年が明けた次の手紙では、
「(前略)何故にドイツを後にしてコペンハーゲン府に行くかというと、同地にはあらかじめ有名な学者がおり、世界の視線は漸々彼地に向かいおると、早くも師フレキスナー博士と米国病理学の指導者たるウェルチ博士両人が看破し、流行のドイツを後にして機先を制し、小子をコペンハーゲン大学に送る訳で、留学費の都合などで小国にゆくのではありません。世界第一の学者につかんが為ゆくのであります(後略)」とわざわざいいわけをしている。
ともかくヨーロッパ留学がきまり、英世はドイツ語の勉強に取りかかる。
まず、それまで住んでいたワルト通りの下宿を引払うと、サンソム街の、以前ライイン地方に住んでいたことのあるドイツ系アメリカ人の家に下宿を変える。ここの家の両親は四十代で、四人の娘と一人の男の子がいた。この子供達は、英世にあまり馴染まなかったが、英世は臆せず自分のほうから話しかけて、日常会話のなかでドイツ語を勉強した。
ようやく英世は世界の檜舞台に向かって第一歩を踏み始めたようである。だがこのとき一つの難問が待ち受けていた。
血脇守之助へ、再びヨーロッパへ行くと書き送ったら、ただちに斎藤家との婚約はどうするつもりなのかと、問い詰めてきたのである。
正直いって、英世はもう、斎藤ます子のことなど頭になかった。できることなら早急に解消して、なかったことにしたかった。
だが日本を発つ前、婚約の証しとして二百円もらってきている。もし婚約を破棄するなら、これを返すなり、事情を説明しなければならない。幸い、斎藤家からはこのところ手紙もこないし、英世も出していないが、守之助のところへは、ときどき苦情が寄せられていた。それに音を上げて、守之助も英世に確答を求めてきたのである。
「斎藤の方は近頃少しく疎音のまま過ぎております。ことに許嫁の娘よりは年始状すら参らず、小子も意外な気持でおります。小子は今年秋には渡欧の資金を手にする予定ですので、そのときニ百円は立派に返済するつもりです。これから先方の態度が変ってくることもたしかでしょうし、結局、破談に終るかと思います。そうなれば実に先方に対して気の毒なことです。もし小子からドイツに行く準備も出来、万事好都合であると、細かいことまで連絡しておけば、喜んで待ってくれるかもしれませんは、このところずっと都合の悪い手紙ばかり送ってきたので、多分こちらを疑っていようかと思います。とにかく成行きは予測できず、幸になるか不幸になるかは、ただ天だけが知ることです」
この手紙だけ読むと、斎藤家のほうが不誠実にきこえるが、それは英世のいいがかりにすぎなかった。実際、金を借りた自分のほうで賀状を出さず、外国へ手紙など書いたこともない娘から賀状がこないというのはいいがかりに近い。無責任ななんとも要領を得ない内容で、旅費が出たら、そこから二百円を工面して払うといっても、その実、それだけの余裕ができる自信などはなかった。
そのまま一か月過ぎたあと、英世はついに最後通牒に似た手紙を斎藤家へ出した。
内容は、今後学費として四、五千円、無利子無抵当で貸してはもらえまいか。もしそれが駄目ならこちらへの留学は七、八年延長するつもりである、というものだった。
身勝手というか、図々しすぎる要求だが、英世のほうは破談覚悟だから怖いものはない。
これに対し、一か月以上経って斎藤家から返事がきた。
もちろん、四、五千円もの大金を工面できるわけがない。それは断わったうえで、許嫁はあなたの将来の妻です。したがっていまは大切に当家に預っておくが、いつまでも年齢をとるのにこのままにはしておけません。一刻も早く期日通り帰ってきて下さい、とひたすら嘆願する。
だが英世はこれを読んで、再び小林栄に次のような不満を洩らす。
「(前略)斎藤家でも大変当惑しているようです。しかしながら一言の助言もくれず、ただ帰れ、だけの要領のえぬ返事は、どこまでも、無頓着かと思います。その後、小子よりは一回も連絡せずに放棄したままにしています。どうなることやら、手をこまねいて、向こうから破談の申込みあるのを待つ次第です。いずれにせよ、この秋、渡欧に当って、問題の二百円は返すつもりです。金を戻せば、斎藤家より破談の話あるかと思います」
無頓着で身勝手なのはどちらなのか、とにかく、英世の頭のなかは、許嫁者のことなどかけらもなく、ひたすら栄光のヨーロッパ行きでいっぱいであった。
2025年(令和7年)8月24日、抜き書き終った。
|
 この点で、プレセット女史の見方はかなり厳しく、日本では比較的よいとされている、エクスタイナー著の『ドクター・ノグチ』でさえ、「教訓的すぎて、一方的な伝記である」といって、おおいに不満を洩らす。そして、日本の野口に関する伝記は、昭和八年に岩波書店から出た、奥村鶴吉著の『野口英世』が、比較的正直で正しい本だという。
この点で、プレセット女史の見方はかなり厳しく、日本では比較的よいとされている、エクスタイナー著の『ドクター・ノグチ』でさえ、「教訓的すぎて、一方的な伝記である」といって、おおいに不満を洩らす。そして、日本の野口に関する伝記は、昭和八年に岩波書店から出た、奥村鶴吉著の『野口英世』が、比較的正直で正しい本だという。