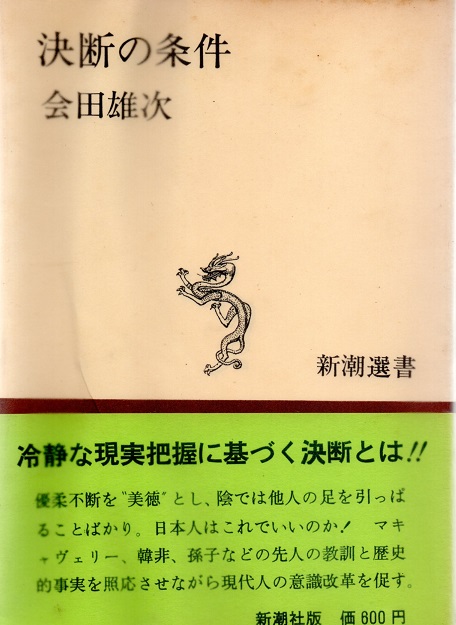
★会田雄次『決断の条件』(新潮選書)昭和50年7月20日 ニ刷
11 現実をあしざまに罵り、過去をたたえたり、未来に憧れたりするのは、あぶない欲求不満の人々である。 マキャヴェリ P.85~90
人間の欲望は無限だが、それを実現し得る可能性の範囲は極めて乏しい。だから当然のこととして誰でもが現状不満である。自分に関しても、周辺に関しても、それが、しかし、すこし度の過ぎた人間は何事も決して成就できない。何かを破壊することはできるけれど、建設的な事業は一切無理である。そのような人間を多数参加させた組織はただ消滅するだけで、何の成果ももたらすことはできないであろう。
とはいうものの、人が現状不満でつねに現状打破を目指していることから、あらゆる進歩が生まれて来るのである。もし、真宗のいう「妙好人(みょうこうにん)」のように食うや食わずの貧困状態に置かれながら完全に現状肯定的で、ありのままの現実をすべて仏の意志として肯定し、ただ受取るだけの人で世の中が充満したなら、そこには平和だが永遠に何の変化もない社会が出来上ってしまうだけだろう。それだったら極楽浄土に相違ないけれど、そこの住民には生きる張りが全くないことになる。
だから現状不満そのものがいけないというのではない。自分の、そして人々の現状不満が本当の進歩と建設をもたらすものなのか、単なる妨害者、破壊者で終るものかを区別することが重要だということなのである。その区別をするためには一つのはかりがある。
昔の諺に、「棒ほど願って針ほど叶う」というのがある。この諺の真の意味を、ただ理性的にではなく、身体全体で知っているもの、つまり体得している人間なら建設へ参加できるのだ。
では、そういう体得ができた人間か、できていない人間かをどうして見わけるのか。自分自身の反省をふくめてである。
その診断は被害妄想狂ないしはヒポコンデリ:「(ドイツ)Hypochondrie」病気不安症)か否かという精神病の判断に準じたらよい。当人に不満の具体的内容をいわせて見る。それが、例えばベトナム戦争がけしからん、すぐ平和をといった風の全く自分の直接環境と関係のないものに限られたとする。この場合、アメリカ軍に水爆を千発も落させ無人の境にしての平和なのか、北ベトナムに勝たせサイゴン政権を倒しての平和なのか、そういう具体的意見が全くない「純情」な女子高校生のようであっても構わない。ただのセンチメンタリズムで教えられた通りに感じ、何者かに命じられた通り思考し、行動している、そんな人々は幼稚で全然頼りにはならず、扇動によって動く条件によっては危険な愚かしい存在だが、それ自体は別に破壊者的ヒポコンデリーではない。だが、もしそのような自分にとって実体のないものを、自分の周辺現象と短絡させる傾向があったら、それは危険である。というと難しそうだが、例えばこうだ。「バター・イエローによる食料品の着色は日本人を根絶しようとするアメリカ帝国主義の陰謀だ」などといわれれば何だかおかしいと誰も気がつく。そんなのは煽動屋だということは子供でも判る。しかし、「国民の一斉健康診断は体制による国民の健康管理で、徴兵制の準備をはじめたことを意味する」という先生の意見は総合雑誌などに堂々と論文として通っている。これがヒポコンデリー現象なのである。そういう人を観察していただきたい。どこかにひどい病的な劣等意識を内在しているから。
誰でもすぐおかしいと判る「風吹けば桶屋が儲かる」論を一所懸命に説く人間もおかしいと考えてよい。「GNPは自由世界第二位なのに国民個人所得は二十位というのは日本社会のひずみを示す」という人は、劣等意識が被害妄想すれすれの危いところにいる。GDPと個人所得の算出法に全く無知なことから来る結論だが、問題はそういう短絡の仕方だ。単に知識の不足のせいとはいえない。性格である。だからこうい人は、それが間違えである理由を説明しても納得せず、必ず、「そりゃそうかも知れないが、でも日本が歪んでいることは確かだ」と反論を試みるからである。
マキャヴェリのこの指摘は、すこし意外に思われるかも知れないが、チーム作りに当ってまず排除すべき人の認定の仕方を教えるものである。自分も反省してみて、自分がもしそういう人間であったら事の成就はまあ諦めた方がよい。何度も断っておくが、これは建設的な仕事の場合である。ぶちこわしのときはこういうのを利用する方が有利かも知れない。狂人に刃物というのは殺傷の危険があるからだが、人をやっつけるなら狂人を使い刃物を持たせるのはたしかに名案であろう。
懐古趣味に淫している人が駄目なのはわかる。SF的世界に逃げこむことを目的としている人間に、実行力がないことも判る。しかし、たとえば明治維新の志士の復古主義、ルネサンス時代の古典主義者はどうなのかとも反論されるかも知れない。
――職業人、たとえば歴史家などは別である。こんなのは毒にも薬にもならない――。夢中の行動的復古主義者はみんな古い制度をぶっこわすことに役立つにすぎぬ。藤村の『夜明け前』が示しているように、平田神学の狂信者の本陣の主は明治政府が自分の希望とは全くちがった方向に進んで行くのを見て気が狂ってしまう。しかし誰からも相手にされない。そういうものだ。明治政府のとった道が唯一の正しい道だったかどうかは議論の分かれるところだが、かりにどんな方向へ明治政府が進んだにせよ、それが民族国家の成立発展という当時の世界史の発展に応じる建設的なものであったなら、復古主義の信者たちはやっぱり全部排除されたことであろう。「狡兔死して走狗烹(に)らる」という言葉は、こういう場合もふくんでいるのである。
建設には当然破壊工作もふくまれる。そのためには、こういう未来・過去への狂信者を利用するのはいい。ただ、その場合、破壊目的が達成された段階で、どのように、こういう人を排除するかを、あらかじめ計画しておく必要がある。前にもふれたが、そういう連中に行き過ぎ行為をさせ、処断ということで、バッサリやってしまうのもえげつないが一策ではある。のたれ死にさせるという方法も考えられる。そのときになって「狂気」というレッテルをはる工夫もある。――走狗は烹られる危険がある――。
一方国の中で、会社の中で、要するに組織の中で何かをしようとするとき、仲間づくりが必要だが、その仲間に入れられない連中からいろいろ「妨害」行為が出ることを覚悟もしておかねばならぬ。そしてある段階でそういう妨害を排除する行動が必要になるが、そのとき、断乎として倒さねばならないのが、この過去・未来の狂信者なのだ。かりにその妨害が老婆心や好意からのものであxtyてでもである。信長は過去の亡霊の根拠地比叡山の延暦寺を焼いたが、その際、一山の僧侶は善悪を問わず、「玉石ともに」くだいた。学僧・善僧がいるからこそ、この邪悪の巣が生きのびたという訳だ。たしかに全部殺しつくさねば新時代の基盤は作れなかったろう。戦国時代ではあるまいし、現在別に殺すことはないけれど、亡霊を覆滅しつくさねば、建設は不可能だということをは悟らねばならない。
現状不満は発展へのエネルギー源だが、被害妄想的な現状敵視は破壊にしか役立たぬ。どちらに属する人間かという区別は学生などでは一見してわかるが、すこし年齢がいった人に対する判定はむつかしい。過去・未来への熱中者がそれだという図式は意外に思われるかも知れないが、それが実はこの被害妄想ないしはヒポコンデリー的人間の年の功によるメッキであることが多いからである。自他ともに戒心が必要なところだろう。
2023.12.31 記す。
12 自分に触れ自分の真実を知っている人は少数しかいないが、そういう人々でさえ、外見だけしか判断しようとしない大衆の意見にあえて反対派しないものである。 マキャヴェリ P.91~96
知己に期待することなかれ、これは君主に対する忠言であるけれど、別に君主だけではなく、すこしでも人の長の立場にある人、ないしは指導的人間になろうと欲する人が胆に銘じておくべき言葉である。
明智光秀の謀反は悲惨な結果に終わった。徳川政権は秀吉に関する事象をすべて悪く解釈することに全力を挙げた。秀吉方の人間はみんな、歴史評価の上で大変損をしている。ところが信長に関するかぎりそうではない。だから光秀は信長を倒して悪名を得、秀吉と戦って同情されているのだからプラス・マイナス・ゼロ、評価はバランスを得ているはず。それに光秀の謀臣、斎藤利光(としみつ)の娘が家光の乳母として権勢を振った春日局である。主殺しは忌避されていたとはいえ、戦国時代は、主殺しから親殺し兄殺しなど当り前のことだった。だから徳川時代には光秀に同情的で光秀が叛いたのは、よほどの事情があったとして、信長の虐待ぶりを、これでもかこれでもかという風に語り伝えている。つまり作り上げている。
にもかかわらず、光秀の挙兵謀反後の暗さとぴうものは、さすがの徳川時代の史家たちもどう隠しようもないほどひどいものだった。
信長を討ったとき、光秀が自分を理解してくれるであろう信じて疑わなかった二人の友人がいる。細川藤高と筒井順慶である。藤高は幕府の旧臣であり、光秀は浪々の最中、藤高と知己になり、奈良の寺で僧侶になっていた義昭を脱出、還俗させ、あらゆる苦心を払って遂に信長の助力のもとに義昭を将軍につけることに成功した。その義昭が信長にそむいたときなど、この二人がなめた心労は筆舌につくし難いものだっただろう。しかも藤高の嫡子忠興(ただおき)は光秀の娘のガラシャを正室に迎え、それを溺愛している。光秀が何者といえどもさくことができないであろう友情を信じたのは当然だといえよう。
だが、宮津の城にあった藤高は再三の願いにもかかわらず、光秀に味方しなかった。秀吉についたというのでというのではないが、ちゃんと連絡している。
筒井順慶も姻戚関係にあり、光秀の庇護の大きかった男である。信長とはうまくいってはいなかった。味方に馳せ参じるのが当たり前の立場である。
このような人でさえ光秀を裏切った。なぜか。光秀が無能だったからではない。数多い信長の武将の中でも教養、軍学の知識、戦争能力、治世の手腕、その他全般的に光秀はもっとも傑出していた。かれに匹敵し得たのは秀吉ぐらいのものだろう。素性も名家の出身である。欠点といえば人間がやや暗く、信長の武将中では新参者にすぎぬ。後者の点から見れば新参の足軽出身で風貌の上がらぬ秀吉などとくらべものにならぬ。暗さでいえば家康などひどいものだった。そのことは藤高も順慶も充分知っていた。しかも味方しなかったのだ。
光秀は大気者であることを証明しようとしてしきりに金銭をばらまき、租税を免じ、賑かな行事を催そうとした。だが誰もついて来なかった。「公卿たちはまるで唖になったようだ」と当時の伝聞は記している。みんな息をのんで次の事態を待ちうけていたのである。そのことを順慶も藤高も察し、そして大衆の側、つまり大勢の側についてのだ。
秀吉が勝ったとき、柴田勝家、家康、滝川一益(かずます)ら容易ならぬ敵が残り、政権の前途は容易に決しがたかったにもかかわらず、こんなことにはならなかった。かれの周辺は沸き立つような賑かさになった。なぜか。公卿や大名たちに先見の明があったとはいえない。そんな連中は稀だった。民衆が湧きたってしまい、それにひずられたからだ。
くどい追究になるが、別に民衆の叡智といったものではない。大義名分があったということよりはるか以上にどう伝わったか、ともかくも秀吉という人間の陽性さによって沸いてしまったのである。とたんにみんなついて来たのだ。
指導者だとか、文化人だとか、いわゆるエリートたちは、自分自身を自分自身の判断で決定して行く人間のように思われている。だが事実はその逆だ。たしかに、かれらは大衆よりはるかに多くの情報を持っている。より正確な決断とより断乎とした行動をとる結果を生むことになるだろうか。
正反対である。人間ははそんな上等な頭脳を持っていない。アメリカ人やその反対の社会主義理論に共通した根本的な誤りは人間を高く評価しすぎるところにある。そういう誤認というより願望の上に、どんな精密な理論や正義や道徳をうち立てたって、その誤りを増大させていくだけのことだ。中国やソ連やアメリカの社会が 前二者があらゆる密告とスパイ組織と秘密裁判の上に、後者が偽善と迷いの上に成立っていることは充分認識する必要があろう。信頼を余り多く持つことは不決断と迷いに直結するのである。
それに管理や支配指導の立場にある人は、もし行動を誤れば失うものも多く持っている。失うものを持たず、ただどちらの道が獲物が多いかを判断するだけの大衆の方がずっと決断しやすい。大衆はたやすく判断し行動する。もちろん、その判断が、判断の時点で正当だったかどうかははなはだ疑問だ。だが、指導的立場の人々がそちらの方へなだれて行くことによって、大衆の判断と行動を正当化してしまうのである。すこし歴史を正しく見ればその通りになっている。マルキストが常に大衆が正しいといっているのは大間違いだが、みんなが、よってたかって正しいとしまうということなら、間違いとはいえないだろう。公害問題でも、外交でも、新聞の反応とさらにそれにつづく識者の反応を注意して見られたい。三島由紀夫事件に対し、最初罵ったマスコミや政治家や識者がどういう風に反応していったかを観察されたい。左派も右派も識者というものは自分たちの派、つまり群の先頭にたって導こうとはしない。群の動向をうかがい、それについて後方から煽っているだけのことである。
知己は信ずべく信じ難い。だが、信じ難いといって、俺は孤独とか、人生は……などと泣き声をだすことはない。知己を頼り得、信じ得るものとするのは、相手でなくして自分の意志と能力にかかっているからである。
決断を下すとき、変転し激動する周辺をしかと見定め、流れの本質を直感し、それに身を投じなければならぬ。本当の流れにそわぬかぎり、いかなることも成功しない。知人をあてにして無謀な行動をおこし、誰もついて来ないといってすこしの間ならうそぶくことも可能だが、それはうそぶいているのではなく、ひかれ者の小唄をうたっているにすぎぬ。とにもかくにも意志決定に際し、知己の援助や協力を希望的に観測し、それに期待するのは失敗の最大原因、もっともつつしむべき事柄なのである。
2024.01.03 記す
13 無理強いされた約束は守る必要はない。 マキャヴェリ P.97~102
ローマの執政官スプリニウス・ポスツミウスはサムニウムとの戦いにやぶれ、武器は全部とりあげられ、ローマの代表者として屈辱極まる約束をしてローマに帰って来た。
このままでいけばスプリニウスの政治的生命は終るところである。いや、政治生命どころの騒ぎではない、本当の命さえ危なかったかも知れない。
ところが実際はそうでなかった。スプリニウスは自ら元老院に出廷して訴えた。「こんな和平条約は守る必要はない。それは無理強いされた結果だ。自分はローマの全権代理でも何でもない。単なる一軍の将たるにすぎぬ。そう自分は主張したにもかかわらず、敵は無理やり、全面的和平条約を強いたのだ。そんな約束にローマが拘束される必要は毛頭ない。その責任はそういう条約を結んだ自分と自分の幕僚だけが負うべきだ。ローマは私たちを捕え、サムニウム人にひきわたしたらよい」と主張したのである。それは自分が屈服したのは命が惜しいからではない。部下将兵を救うためだったという主張にもなる。見事ないい分といえよう。
元老院は結局その意見に同意した。スプリニウスとその側近とを捕え、サムニウムに送り、同時に、かれの結んだ協約は全部御破算にすると通告した。
ここでマキャヴェリによれば運命の女神はスプリニウスにほほえみかけたのだ。その勇気に感じたサムニウム人はスプリニウスを捕えておかず、礼を以てローマに送りかえしたのである。かれはローマ人から凱旋将軍以上の栄誉を以てむくいられた。
私たちは明治以来、ヨーロッパの近代文明を受容し、政治と社会を近代化することに全力を挙げて来た。第二次大戦前にその路線に対する反撥がおこり、超国家主義へと暴走して大戦へと突入するに至ったのだが、ここで惨憺たる敗北を喫し、アメリカの占領下に入ることによって、前より遥かに徹底した近代化路線を歩むことになった。要するにいわばこの百年、私たちは懸命に欧米化、つまり近代化して来たといえる。
しかし、私たちが真似て来たヨーロッパはフランス革命後のヨーロッパである。私たちはその近代を生み出した地下の根とは無関係だった。日本の近代化は、だから、きた着物、せいぜい肌着ぐらいのところで肉体化するまでには至っていない。
近代社会における人間の結合の基本である契約についても同様である。私たちは結んだ契約を守ることが、近代社会成立のための絶対的な前提と教えられ、その通りに信じ、実行している。
たしかに会社経営、販売その他の契約は実行されている。たとえば納期がおくれたりすることとなると、日本に今尚強く残っている非合理な封建制の遺風のためであり一刻も早く脱却すべきことと主張されているのである。
ところで政治的側面はどうだろう。議員の公約は、約という文字が示す通り、書面こそかわさないが、公衆の面前、ヨーロッパでいえば神の御前で、もし私が当選したら必ず実行するということで議員候補者が選挙民との間に結んだ契約である。だが、それが実行されたことが一体どれだけあることだろう。国際条約だって同様である。今度の戦争で日本は原爆とソ連の侵入でとどめを刺されたことになったが、このソ連の満州侵略はいうまでもなく日ソ不可侵条約違反である。かつてのロシア帝国は自分が結んだ国家条約や協定を一方的に破棄することで札つきの国だった。破るために結ぶのではないかといわれたほど、守り続けた条約は稀である。ソ連もその点見事な後継者だ。ポーランド、フィンランドへの侵入、ルーマニア、日本などの領土奪取、すべて契約違反だ。
政治は経済より遥かに非合理な性格を持っている。組合など政治闘争をやる場合、ないしは政治がからんで来た場合、その行動が突如として非合理的で、狂気をはらむものとなり、指導者に「おかしな人間」が選ばれるのも、そのことを物語っている。
私が、日本人は近代社会の根を知らない、枝葉だけを知っているというのはここである。たしかに契約は守らねばならない。それは当然のことだが、それだけしか知らないのをイミテーション近代主義者という。契約は、正にマキャヴェリが教える通り、破られる場合も、破ってよい場合もあるのだ。ただ、そこに条件がある。
 日本の明治の法律には決闘の条項がない。ヨーロッパでは最近まであった。明治憲法も当時政治顧問だったフランス人ポアソナードの草案には入れてあったのを、山県だとか伊藤だとかが、決闘という習慣は日本には存在しなかったといって省いてしまったのである。なるほど武士は存在し、武士道はあったけれど、騎士とは不可分な決闘というものはなかったようだ。
日本の明治の法律には決闘の条項がない。ヨーロッパでは最近まであった。明治憲法も当時政治顧問だったフランス人ポアソナードの草案には入れてあったのを、山県だとか伊藤だとかが、決闘という習慣は日本には存在しなかったといって省いてしまったのである。なるほど武士は存在し、武士道はあったけれど、騎士とは不可分な決闘というものはなかったようだ。
交渉にはあくまで合理的手段をつくす。争いも法律にもとづいてやる。契約も断じて守る。だが、そこは人間のこと、そう完全にはいかない。法律がすべてを網羅しているとは限らない。妻を寝取られた場合などそうである。そんなとき最後の決を決めるものとして決闘があったのだ。法律的にも、手続き、立会人などの条項が定められていたのである。
破棄の条件とはこの闘にかかはる。破棄してもよろしいが、その代り、見事に居直らなければならないのである。「法律は破りました。でも、法律さんよ、私は守ってくれ。法治の民主国として人権の保護を」といった現在学生のような甘ったれは許されないのだ。
無茶な環境のもとに、脅迫や詐欺などによって結んだ契約は破っても毫も差支えない。むしろ破るべきだ。これがヨーロッパの近代の根である。その根を知らないところに日本人の誤謬も、甘えも、責任転嫁も、偽善も、あらゆる近代的悪徳が存在するのである。今度の戦争で、日本がソ連に、英米との間をとり持ってもらおうと申し入れ、弱点を見すかされて満州への侵略を以て酬いられたことなど、悲劇でも何でもない。単なる喜劇であるに過ぎぬ。大学騒動で、教授が学生から、「お前は約束したじゃないか、確認書に署名したじゃないか。今更なんだ。それでも学者か」などとたたみこまれて、オタオタしているのも同種の喜劇である。あらゆる脅迫にもかかわらず、断じて署名しないか、あるいはじゃんじゃん署名し、約束して、本質的な居直りによって見事にそれを破棄するか、どちらかだ。あちらへフラフラ、こちらへフラフラするから窮地に陥り、双方から軽蔑されるだけのこととなる。契約を破る必要がある場合もある。破る能力なしには契約を結ぶ資格がないのだ。契約の意志決定には、それを敢てやれる意志力がまず必要なのである。
2023.12.16 記す。
14 亡命中の人間の言葉を信じるほど危険なことはない。 マキャヴェリ P.103~108
アレキサンドロス大王の叔父のエイロス王に対し、亡命中のルカニア人が自分たちが手助けしてイタリア全土を手に入れられるようにしてあげよう、それは可能だとふきこんだ。王これを信じイタリアに軍を進めたのだが、この亡命者の手にかかって死んでしまったのである。どういうことなのか、実はルカニアの支配者が自国の亡命者にエぺイロス王を殺せ、そうすれば帰国を許してやると約束した。それを狙った亡命者たちに王はまんまとだまされてしまったのである。
マキャヴェリはこの例を挙げ、亡命者に初めから、だます意志があろうがなかろうが、ともかく彼らの言葉を信じてはならない、亡命者のふりまわす信義とか約束などは反故に等しいものであることを知らなければならない、このことは国家統治の任に当たる支配者が毎日のように当面しなければならぬ課題なのだと助言しているのだ。
日本では亡命者どころか、ベトナムの脱走兵など――私の経験によれば亡命者とちがい、戦闘からの脱走というのは人非人的性格を持たぬかぎり容易にできるものではない。全滅戦は別だが――を有難がって三拝九拝している。その語っていることを真実としてアメリカを攻撃している。国際オンチというべきだろう。
日本につぐ国際オンチ国アメリカでは、ケネディ大統領がマキャヴェリがもっともいましめている失敗の模範ともいうべき愚挙をやらかした。キューバからの亡命者の言葉をそのまま受けとったのだ。キューバにはカストロの新政権に反対のものが極めて多く、政情は不安定だ。ごく僅かの兵力を送ればみんな一斉に立ち上るだろう。新政権覆滅は簡単だ云々。ケネディはまともにそれを信じこみ、そのぐらいのことで大成果が得られるならと「解放戦」にのり出した。大失敗だった。成果どころか世界中の笑いものになった。笑いものだけではすまない。カストロを助けようとするソ連と正に一触即発の危機、人類の全部を滅亡させかねない全面戦争のほんの一歩手前まで行った(一九六二年のキューバ危機)。しかし、かれがマキャヴェリの通切な、真情をこめたこの文字に接し、それを理解していたら、あんなへまはやらなかったに相違ない。
結果は逆だった。政府の情報が正しかったというわけではない。陸軍の得た情報というのはたしかに裏面の、いわゆる真相物だったが、かれらが酒席の間に接した相手は、多くは新政権からドロップ・アウトした連中だった。そういう不平居士のいいかげんな話に乗せられていたのである。
だからこのいましめは別に亡命者に限らない。今日では亡命者にもいろいろある。むしろ広くいって脱落分子・落伍者に関するものと考えればよい。脱落といっても脱退者ではない。おちこぼれた人間のことだ。何か事をなすとき、こういう連中のいうことを信じては駄目なのである。
もちろん脱落者が無能力者というわけではない。逆に、羽ぶりを利かせている連中が有能ときまっているわけのものでもない。酒場での批判や悪口がみんな根も葉もない嘘ばかりというはずのものでもない。だが脱落者の意見というものは、悲憤慷慨、いかにも正義漢らしく見える。策謀にたけた人間のものとも見える。能力があるがゆえに悲運に泣いているように見える。
だが、それは正にそう見えるだけなのだ。それに私たちは判官びいきである。結局、脱落者を無闇と高く評価してしまうことになる。ベトナムの脱走兵が、苦労して送りこんだスェーデンで何をしているか、考えて見るがよい。怠惰と無能と臆病が脱走させた殆んどの原因なのを、すべて社会正義感と反戦の志のためにと考えるところに間違いがあるのだ。考えるだけなら、いくらそう思っても差支えないけれど、かれらと一緒に何かしようとしたら、脱落者のもたらす情報を基盤に行動しようとするとき、この評価の間違いは命とりとなる。自己の精神の堕落をも招きよせる。
信長も秀吉も家康も、「亡命者」、謀反人、内通者の意見はよく徴した。だが、かれらが成功者として残ったのは、その意見の裏づけを取ったからである。細作(さいさく:間諜)を使い、そういう連中の相手陣営における信頼度を充分以上にたしかめた。かれらの情報と、こちらで得た情報を照合し、一致しないかぎり動かなかった。
弱きを助け、強きをくじくのはただ任侠道の看板だけでなく、現実世界ではすべて「残念ながら」絵空事である。強きを助け、弱きをくじかぬかぎり、事はうまくいかない。ただ「強き」と「弱き」を現在値において考えると、単なる迎合者になってしまうというだけのことである。弱きとは知能、意志力、忍耐力、決断力、信頼性のどこかが致命的に欠けた人間のことである。逃亡者、脱落者の九十パーセントまではそういう人なのだ。レッテルで人間を判断してはいけないけれど、しかし、このドロップ・アウト人というレッテルは、一流大学卒とかイデオロギーのメッカとか、酒場でかれの洩らす真相とかよりはるかに信頼度が高い。ともあれ、それはかなり人物眼ある人々の総合的判断の結果だからである。現在の日本で、能あり立派な人間がドロップ・アウトしたままということはあり得ない。もちろん多少の損得はあるが、殆んどはどこかまでいっている。ダメなのはダメだからである。ゆめそのダメなのと一蓮托生という気にならないように。
2024.01.04 記す。
15 真の見方は武器をとって立ち上がれと要求し、敵は中立をすすめるものだ。だが、おろかな君主はたいてい中立を守り、身を亡ぼしてしまう。 マキャヴェリ P.109~114
この主張はマキャヴェリは比較的単純に説明している。はじめに断っておくが、この主張は弱者に向っているのである。ライオンがうさぎと狸の争いに組する必要はない。私がこの意見をとり上げたのは、日本人は国においても弱者だし、個人としても自分自身で戦うのでなく、どちら側につくかという決断と意志決定をすることが切実な運命の分岐点になるような人間が多いからである。
戦いはどちらかの勝利に終る。マキャヴェリはいう。そのとき、「中立者たるあなたはかならず勝利者の餌食になる。それどころか敗北者の鬱憤ばらしや、溜飲をさげる種にもなってしまう。そしてその場合、自分を守ろうに名文は成り立たず、かくまい、庇護してくれる人もなくなってしまう。というのは、勝利者は逆境のときに助けにならないようなあやしげな者を味方にもちたがらないからであり、他方敗者の側も、進んで武器をとり自分の運命を賭けようしなかったものを、受け入れようとはしないからである」。
こんなことを今いうのは、現在の世界の国際情勢と日本の国内の世論の動向との両方を併せ考えるとき、かなり勇気がいる。マキャヴェリの活躍中のフィレンツェでも同様だった。この国は列強の争いの渦中にあってイタリアの統一の道をめざさず、国内の敵たちを競争者と見てその攻撃に努力し、列強に対しては中立主義をとり、列強の鉾先を国内の自分の敵に向けようという策謀に全力をあげていた。だからマキャヴェリは罵られ、こんな提案は一顧だにされなかった。おかげでその後のフィレンツェはもちろん、イタリア全土が戦場となり荒廃の一途をたどることになるのだ。内紛というものは本来、そのような道をたどるという公算が極めて大だろう。
といって、私はここで国家論をやろうとするのではな。現実の日本内部についての意志決定の場合の参考にするため、この言葉を挙げたのだ。もうすこし考えてみよう。
中立を守れというのは、争っている両陣営からではなく、時には第三者の身上相談的な意見として出て来る。そこで自分がそういう立場に立たされたときの心構えである。自分が休まず、おくれず、働かずで、ともかく家庭の幸福や趣味への沈殿を志しているなら、中立者から俺と同じようにせよというこの忠告を守っておいた方がよいだろう。ただ、そういう中立者は上司だろうが、先輩だろうが、無気力者か、社外活動者であることが多い。まずその人の生活をよく観察し、その人が人生を楽しんでいるかいないかをよく考える必要がある。バーなどで荒れるような無気力人間だったら、そのすすめにしたがうことは、自分もその道を辿ることになろう。関ケ原の戦いのあと黒田孝高(よしたか:「黒田官兵衛」別名:黒田如水:黒崎記)は九州から京へのぼった。旅宿へは人が訪ねて来て門前市をなした。孝高豊前の中津にあって大いにあばれまわり、家康を裏から援助した。子供の長政は関ケ原で大功をたて大大名になろうとしている。それにあやかろうとしてだろう。だが孝高は子供の長政を馬鹿よばりした。家康を助けたから早く片づきすぎた。もうすこし戦乱を長びかせ浪人に職を与えるものだというのである。
そこへ山名禅高が現われ、忠告した。「家康はうたぐり深い人だ。あなたが大名たちと夜おそくまで密談したり、とりわけ家康の次男で秀吉の養子だった秀康と話されるのは面白くありませんよ」と。孝高は、「おれは秀吉が死んだとき天下を狙ったのだ。家康を亡ぼすのは難事とは思えない。だが歳をとったので諦めて国をすて、単身京へのぼって来た。それなのに臆病者がいろいろ噂をたてる。あなたもそれを信じるか、人間はあちこち気をまわさず平気でいることが必要なのだ。あんたはそんな調子だから国を失ったんだ」とまくしたてた。禅高は声もなく赤面する一方だった。
これは孝高の気概を示す言葉だ。その反面、家康にはもう対抗する気なしということを示し、同時に家康にあんたが天下をとろうとするのは当たり前のことという側面援助の言葉でもある。容易ならぬ見事な発言だが、ここで私のいおうとするところは別にある。
山名禅高は鳥取城の城主で秀吉の中国攻めのとき投降したのだが、かつては「七分の一殿」――日本の七分の一を領する――といわれた大家だった。それが無気力のせいで秀吉の御伽衆となり、名家好きの家康から七千余石を与えられて満足するまでに落ちぶれた。孝高はそんな情けない一生しか送れぬ人間がこのおれに、とおこったのであろう。現在だったら中立しかとれないこの禅高など一石ももらえぬはずである。美貌の娘を秀吉に売って生きていた男とさえいわれるからだ。中立主義で気楽に生きられることもなくはないが、すべての人の軽侮の目に平然と耐える能力だけは持っていなければならない。
さて、「味方をする」にしても、決断するにはいろいろ考えなければならないことがある。
倫理観で行動するなら、どうなっても愚痴をいわない決意が必要である。日本人ほど愚痴をいい合い、お互いにそれで慰め合っている民族は珍しい。愚痴は反逆でも抵抗でもない。そういう発言を許している社会を「女のくさったような」社会という。現在、私たちはすこしぐらいその不潔さを反省してよいときである。
負けても、負けた方が立派な人間ないしは集団であるかぎり、そう心配はいらない。「負けた方だって力のかぎり、あなたを声援してくれる。あなたと運命をともに分ちあえる同行者となってくれる。運がふたたびめぐってくることもあろう」からである。
ただ味方する場合考えなければならないことがある。その相手と自分の力の差だ。圧倒的に自分より強いものの味方をしても何もならない。相手は別に恩にも何も感じないだろう。そして勝つことでより力を得た相手は、こんどは協力者に対し臣従を求めるだけだ。それはわざわざ相手に捕虜になりに行くようなものである。負け方にしたら、今度はその復讐の鉾先を弱い方、つまり自分の方に向けてくるにきまっている。味方をしてよい場合は、相手が自分を必要とし、しかも自分が味方に加わることに「よって勝てる場合である。もっともそれぐらいの力量が自分にないときは、中立をとれの、味方をしてくれnと誰もいって来ないだろう。ついでにいっておこう。誰もそういう争いに自分をまきこみに来ない、人徳があるせいだ、正義漢のせいだなとうぬぼれれてはいけない。要するにあなたは無視されているに過ぎないのである。
※参考:岩波文庫『君主論』第二十一 君主は尊敬を受けるためにいかに振舞うべきか P.138~144
※参考:神坂次郎著『男 この言葉』(新潮文庫)P.251 黒田如水
2024.01.05 記す。
16 忠臣の使いを稽留し、その事を聴くなく、すみやかに代をおくをなさしめ、おくるに誠事をもってし、親しみてこれを信ずれば、その君まさにまたこれに会わんとす。まことによくこれを嚴にせば、国すなわち謀るべいし。 六韜文伐篇その五 P.115~120
これまではマキャヴェリ先生の言葉をひいて来た。一人のものだけを使っていると、すこし一本調子になるおそれがある。これからはときどき中国の戦略戦術の古典である『韓非子』や『孫子』や『呉子』や『尉繚子』や、それに著者ははっきりしないが、『六韜』や『三略』の言葉をひいて見よう。
それらの解釈は、大体日本の権威ある説にしたがうけれど、私流の意見もはっきり打ち出すことにする。というのは、日本人は漢字に対する一種の先入観を持っている。漢文文化はいさましく、すがすがしく、直截で剛毅であり、ひらがな文化は女性的と考えているようだ。古典などとりわけそう見られている。確かにそういう点はあるけれど、しかし中国にも文弱人は無数にいたわけだ。そして人々の執着深さや粘着力や陰険さなども超大国だけに日本人とは比較を絶している。私は漢文を読むときは、まずこのような先入観を排することが必要だと思っているのである。
さてこの文章はなかなか難しい。この文章は文伐篇から引いたものだが、文伐というのは戦わないで、つまり外交や謀略などで敵国をやっつける方法で、この十二法の中のこれは第五の方法である。
敵国から忠臣・賢臣が外交使節としてやって来たときは、相手の意見をきかず、のんべんだらりと交渉を長びかせ、敵国をイライラさせて交代の使者を来させるようにする。この交代の使者に対しては、友好的態度をとって交渉を成立させる。敵国の君主は、前の使者より、この使者を信頼するようになるだろう。これを厳密にやっていると敵国を見事に謀略にかけ、やっつけることができる。そいう内容だ。
ところで、この文章の意味を理解するためには、もうすこしつっこんで考えねばならないとこがある。あとで来た交代の使者というのは、何の形容もついていないが、あせって送りこむような使者は忠臣の意見に反対する不忠臣か、あまり賢くないか、功名にあせったり、権力欲にとりつかれた小人か、ともかく上等のものではないということは自明の前提になっている。その点を読みこまねばならない。君主がこんな安物を信頼し、賢臣忠臣をしりぞけるようになったら、占めたものだということである。
ついでながらいっておくと、中国の指導者たちにとっては、そのイデオロギーにかかわらず、古今を通じ、この『六韜三略』というのは『孫子』などとならんで常に手を離さぬ座右の銘であり書である。したがって、その内容など一言一句暗記できるほど知りつくし、研究し抜いているのである。現在の中国の日本に対する取り扱いも、こういう角度からも考えねばならない。ところで、有難い民主国である日本の「君主」は、タレントなどという空っぽ人間に数百万票を投じて国会へ送りこむ「民衆」である。そういう外交折衝、外交官の評価などをどのような基準によって下すつもりであろうか。
こうなって来ると、スターリンと不可侵条約を結んで意気揚々と帰国した松岡外相がはたしてどうだったかという疑問が出て来る。松岡外相は日本の外相としては出色の人間だったけれど格のちがいというか、その役割は日本に致命傷をもたらすことしかならなかったのだ。何しろソ連は、これで見事に日独伊の鉾先を英米に向けさせうまく死闘させた。もっtもすこしやりすぎてドイツ軍の主力を自分の敵としてよびこむという失敗をやったものの、対日本に関しては最高に有利に、日本には最高に不利に事をはこぶ結果になったからだ。アメリカに叩きのめされた日本が完全に無力になったのを見こし、松岡との条約を一方的に破棄して満州を侵略、自軍は無傷のまま濡手に粟のごとく南カラフトから千島の全部を手に入れてしまった。あの不可侵条約は日本には損害だけをもたらしたのである。スターリンはモスクワの駅まで松岡外相を見送りに来るという異例の待遇をやり、外相を有頂天にさせたけれど、そのとき胸中で何を考えていたことだろうか。外相にくらべ、冷静そのものであったことはたしかなのだが。
 ※「スターリンはモスクワの駅まで松岡外相を見送りに来る」に関連記事。豊田 穣『松岡洋右』悲劇の外交官 下巻(新潮文庫)P.457 松岡の一行がカザン駅へ着くと、スターリンが来た。
※「スターリンはモスクワの駅まで松岡外相を見送りに来る」に関連記事。豊田 穣『松岡洋右』悲劇の外交官 下巻(新潮文庫)P.457 松岡の一行がカザン駅へ着くと、スターリンが来た。
新聞の「命令」により中国へのりこんだ田中首相が、松岡のような轍をふまぬことになれば幸いである。
この『六韜』の教えは、もう一つ、相手国の賢臣・忠臣と腹を割って事を談じてはならないという教訓にもなる。そんな人間が自国に不利で、こちらに有利なことをしてくれるはずがないからだ。そんな人と腹を割って何もかも話し合い、事を処理したと思っている場合は、大抵相手の術中に陥ったので、自分が自国に対する「裏切り者」となっているのである。相手は自分を「悪臣」とは思わないまでも、「賢臣」ではないと断じていることは確かであろう。
日露戦争のとき、海軍の戦略を担当した秋山真之参謀のやり方は、いつも一枚上手で行くというやり方だった。相手が桂馬を出して来たら銀で、金なら飛車を向けるという風に、初期の仁川沖の海戦から、ウラジオ艦隊をやっつけた蔚山沖の海戦から、すべて、この伝で勝つべくして勝った。人間関係の戦略でも同じことをやるべきなのだ。ただ、軍艦とちがう、戦争ともちがう。えらい奴が出て来たとて、おいそれとうまく対応できない。ここでは、えらい奴が出て来ないよう、出て来ても機能しないようにさせるべきなのだ。それが外交交渉に入る前の外交計略なのだ。この百年間日本は、そんなことを考える能力が全くなかった。日米繊維交渉だって日中交渉だって、策略は一切されなかった。こちらは向うの望む人を出し、しかもあちら側はこちらの意向を無視して代表を出して来る。日本に外交なしといわれる所以である。
二国間の交渉とか、取引とか、そんな大問題は一応さしおくとする。対他企業、対官庁、対圧力団体、ともかく相手を「やっつけ」ねばならぬ場合、私たちは当然この問題を考えねばならぬ。私たち日本人の一番の欠陥は、相手の人間性にほれこんだり、参ってしまう所にある。エライ人が胸襟を開いてくれたり、真情を吐露したり、へりくだって応対してくれたりすると、いっぺんに感激してしまう。そして無意識のうちに裏切り者の役割を果たしてしまうことになるのだ。相手が心からの誠意で来ているのか、途方もない大物でそんな芝居をやっているかは、別問題として。
もっともこういう感激性は日本人の欠点であり、同時に良さでもある。強いて矯正する必要はない。ただ、その欠点をさらけ出さぬため、大物、偉材とは決して腹をわってつき合わないこと、小物だけを相手にすること、そのことだけは、肝に銘じていてほしい。自分は決して大物ではないのだから、その反省を欠き自分でそう思ったときは万事が終っているのだ。それも自分だけなら失敗してもよいが、自分の属する組織、民族、国家に大きな損害をもたらすことになろう。小物政治家たちが大物気分で出かけて行って手玉にとられ、日本にずい分損を与えている状況に私たちはもういい加減に癇を立ててもよさそうなものである。
202312.13 記す。
17 亡びんとして存するあたわず、危くして安んずるあたわずんば、智を貴しとするなし。 韓非子 P.121~126
マキャヴェリよりもその構想が壮大で、思考ははるかに徹底的だといわれるのが、前三世紀のはじめ、韓の王、安を父として生れた韓非である。その文章五十五篇を集めたのが、今日『韓非子』とよばれるものだ。これから、ときどきこの『韓非子』を引用して考えてみることにしたい。
趙国の晋陽の城に、晋の猛将知伯が晋と韓と魏の三国の軍勢をひきいて攻めてきた。趙の王、襄子は賢臣張孟談(ちょうもうだん)を用いて、城を三年にわたって守備し抜く。だが、食糧も兵力も財力も乏しくなり、将士は疲労して、ついにどうにも守り切れなくなった。襄子は張孟談をよんで、「もう降伏するより仕方がない。三国のうち、どの国に降伏したらよいだろうか」と相談した。そのとき張が答えた言葉がこれである。その意味は、「亡びかかってももちこたえ、危地に陥っても活路を発見できないようでは智慧とはいえません」である。張はこう答えて、ひそかに敵陣に侵入し、魏王と韓王に会い、知伯を裏切るように説得し、見事に知伯を「やっつけてしまうのだ。
ここに語られる張孟談の自分の知能とと知識に対する絶対的な自信と、快刀乱麻を絶つような実行力は、もし、こんな人間が現在存在したら溜息が出るほどのすばらしさである。たしかに知識とは本来そういうものであるはずなのだ。だが今日の日本ではどうか。
大学騒動の際、大学の先生たちは、みごと「智を貴しとするなし」ということを証明した。大学の権威が崩壊したのは当然だろう。もっとも、これは、学生側の行動が日本共産党の下部組織である民青と、それと絶対に対立した新左翼の各派があって統一がとれていない。したがって対応の仕方がない。教師側にもあらゆる立場の人がいて、お互いに足をひっぱり会った。そういう一面もある。けれど根本的には、日本の学者は自分自身で思考し――そのためには決断し、選択しなければならない――一つの思想を生み、育て、発表することはやらない。ペンダサンが『日本人とユダヤ人』(※P.174参考:黒崎記)の中でいっているように、主として西欧で流行している思想なり学問なりをうまく自分のもののように見せかけるだけである。もっとも、それは至芸に類するとペンダサンはほめているのだが、これはほめているいるのでは勿論なくて、相当な皮肉である。ともかく、それでは自分というものがないわけだから至芸かどうかは知らないが決断も選択もできないことは確かである。いわんや創意工夫して危地を脱する芸当に至ってはだ。学んで、つまり文字通り真似だけで、考える訓練はすこしもやっていないからである。
だが、もう一つ考えねばならぬことがある。学問と実用とは無関係だとか、すくなくとも非実用な、学問であればあるほど、上等な学問だという思想はどこで生まれたのだろう。美それ自体の追及が芸術であり、芸術家と職人は、その点では区別されるという考え方も、同じ時に成立したといってよい。
私たち日本人は、それを近代思想に本質的な考え方だと思いこんでいる。だが、どうもそうではない。イギリスやアメリカには、功利主義やプラグマティズムの名のもとに、実用主義が大勢を支配している。学問のための学問というのは、実は近代思想の中の少数意見にすぎないのだが、なぜか日本では支配的意見、根本理念と考えられているようだ。
ではなぜそういう意見がドイツに強く、そして日本に極めて素直に受け入れられたのだろうか。私はそれは両国ともに辺境の国で、劣等意識が強かったせいだろうと推定している。イソップ物語にすっぱいぶどうという話があることは誰でも知っていよう。ぶどうにとびついたが、どうしても採ることができなかった狐が、「ふん、あんなすっぱいぶどうなんかいらないや」と負けおしみをいう話である。ドイツは、近代初頭ではイタリア、あとではイギリスやフランスという自分たちより繁栄している国をとなりにもち、しかも自分たちはいろいろ努力しているのだが、どうしてもそれに追いつけない。自分たちは優秀で勤勉な国民だという自負は大変強い。そうなったら追いつけ追いこせが果たせない理由を何とか発見しないと虫がおさまらぬ。イギリスやフランスは近代学問や芸術で繁栄を誇っている。となると、自分たちは学問や芸術で劣っているのではない。それを実用目的に奉仕さすべきでないという正しい信念を持っているだけだ。だから生活水準が低いのはやむを得ない。そういう考え方に落ち着くわけである。このことは国家相互の間にもいえる。個人相互の間にもいえる。日本もドイツと同じことだった。明治以来富国強兵策をとりロシアに勝って軍事大国にはなり得たものの、国の繁栄、国民の生活水準は及びもつかぬ。そこに学問と実用は無縁だというひかれ者の小唄的な意見が出て来たのであろう。
それは、それでよいとする。だが、日本人がこうして知識、学問を実用より遠ざけた結果何がおこったか。学問が迫力も何もない、青白き学者のお遊びになりはててしまっただけである。
議論ばかりしてきたが、結論はこうだ。あいつは人物だとか、あいつは誠実だとか、そういう評価だけで人と組すべきでない。そのどんな「立派な人物」でも知的能力に欠ける人と組んでは必ず失敗する。自分たちより賢い人間を敵にしては決して勝てないのである。
もう一つの結論。意志決定は智によって行わねばならぬ。意志力だとか実行力だとかいって、知的判断なしに行動するものをドン・キホーテというのだ。馬鹿が勝つ世界はこの地上にはあり得ない。あったらそれは地獄だ。『イワンの馬鹿』はユートピア思想に過ぎない。反語の連続として一応筋が通っているが、ちょっと考えるとふき出したくなるような矛盾が、至るところに露呈している。馬鹿で途方もない働き者イワンという、そもそも矛盾する性質を両立させているその前提から無茶なのだが、ここではユートピア論としてそういう点は問わない。問題は、例えば外国から兵隊が攻めて来て略奪する。イワンの国の人々は、イワンと同じような人間なのだが、そんなことをして何になるといって説教する。侵略者たちはその説得を容れて帰ってしまう。そいう点だ。侵略者がその馬鹿さかげんに呆れて、何もしないで帰るということでないリアリティが生まれないないのだが、そういう筋はどうして作ることができないはずである。だから、ここでは阿呆たちが突如として大群の敵兵を説得できる智者になってしまうのだ。矛盾もいいかげんにしろというのが子供心の私の感想だった。だが、それは大学のえらい先生に質問したって正しい説明できぬ問のはずである。
智を軽蔑したり、実用との結合をいやしめるのは、敗者のまけ惜しみでしかない。自分に智がなければ、決断に智者を利用すればよいのだ。そのことも『韓非子』は教えてくれているのである。
2023.12.11 記す。
18 小忠を行なうは、すなわち大忠の賊なり。 韓非子 P.127~132
この言葉の意味はやさしい。小さな忠義は大きな忠義の敵であるということである。ただしこれを大義親(しん)を滅すという、大義のためには親子や友人との私親を滅せよという道徳訓にとってもらっては困る。大体道徳訓などは、人生の不可解さに対する洞察力も、共感も、社会の複雑さに対する正しい認識も、何もなしにいくらでも作ることができる種類のものだ。そういうものなら私はここでわざわざとりあげることはしない。まず韓非がとりあげた例を見ていただこう。
の共(きょう)王が晋の厲(れい)公 と戦った。楚軍の旗色悪く、共王自身も眼に傷を負うほどだった。その戦いの最中、共王の部下の将軍子反(しはん)は疲れて水を求めた。従者の穀陽という男が酒を満した盃を差し出した。「戦いの最中だ。いかん、酒は」と子反はこばんだ。穀陽は、しかし、「酒ではございません。御安心を」と嘘をつく。嘘だと知りながら、その言葉に迷い、子反はとうとうその盃を口にした。つかれている。戦況は悪い。根から酒は好きだ。一口ではやめられず遂に酔っぱらってしまった。
その日の戦いすんで、日が暮れて、共王は、明日こそはと思い将軍をよびにやったが、身体の具合が悪いといって来ない。自ら子反の陣へ出かけ、将軍のとばりの中へ入ろうとした。ぷーんと酒のにおいが鼻をつく。共王はそのまま首(こうべ)をめぐらした。共王は思う。「今日の戦いで私自身傷ついた。こうなれば頼りとするのは将軍だけだ。だのに将軍はあの有様、わが国、わが軍がどうなろうと平気なのだ。もう戦争はやめた」と。共王は軍をひいて帰国すると、大罪を犯したとして子反を斬った。穀陽は何も子反を陥れようとして酒をすすめたのではない。主人の身体と精神を案じ、忠義のつもりで酒をすすめたのだ。ただいえるのは、その小忠が主人を殺した。小忠は大忠の敵だということである、云々。
韓非のいうことはよく判る。ただ、ここで私が問題にしたいのは、忠ということでなく、眼前の利益と、背後の大利との関係をどう見るかである。穀陽の立場でなく、子反の決断である。
大利と小利は相反することが多い。しかし、大利と小利は相反することが多い。しかし、大利と小利、眼前の利と遠く大きい利が、いつも相反するものなら、決断は比較的簡単だ。現実は、そうでなく、一致したり、相反したりするのである。だからこそ、賢い人でも決断に迷い、失敗したりするのだ。そうでなければ小人、愚者が失敗し、大人、賢者は成功するという簡単なことになってしまう。
私たちは決断に迷いがちである。そのとき決断するには重大な注意事項がある。ひろく遠くおもんばかれというむつかしいことではない。子反は、酒を出されたとき、直観的に、いけないと退けた。だのに、こざかしい従者のうまいうそに迷って酒を呑んだから失敗したのだ。
将棋や碁で、「下手な考え休むに似たり」という。そういう勝負ごとにかぎらない。私たちは思考しているつもりでいて、実は迷っているにすぎないことが極めて多いのである。あるいは、自分の欲求を満たそうとのみ思い、そのいいわけを探しているにすぎないのである。まあ、「私の主張」とか、新聞の投書とか、学者の評論などを注意していただきたい。正義、大義を堂々と論じているいるものほどそうなのだが、何とまあ、自分のいいわけにカッコよい言葉や論理を使っているだけのものが、多いことか。
最初の直感こそ大切にすべきなのだ。何か嫌な予感がする。しかし、やりたい。予感を抑え、そのやりたい気を理屈づけようとするのが私たちの常なのだが、逆にその予感を大切にし、それを分析することが重要なのである。予感を分析して見て、それが単なる気おくれにすぎないとか、全くの杞憂であるということなどがはっきりすれば、それでよい。はっきりしないなら、慎重にやること、手控えが必要なのだという証明なのだと考えねばならない、子反の失敗はこの直感を否定したところにある。
ところで、この直感力である。私たちは、それを養わなければならない。決断はとっさにやらねばならぬことも多いから尚さらのことだ。直感力とは瞬時の間に、その本質を把握する能力のことだが、残念ながらどうもそれは、天性に近い能力らしい。すくなくとも大人になってから、その能力をつけようとするのはかなり困難である。といって、何とかはしなければならぬ。オカルト・ブームというのは、あまり直感力がない人が、それを神秘的に考えて子供のお告げなどに頼ったりすることの流行をいうのだが、こういのは例のスプーン曲げと同じくインチキが殆んどである。当るのはまぐれにすぎない。もっと考えねばならないのだ。どうするか。
本当の直感力は、広い知識がないと働かない。それかあれかという簡単な命題ではなく複雑な条件に対応しなければならないときはとくにそうである。何よりも、自分の専門を越え、広い知識を身につけねばならぬ。その知識とは、法律、経済、それも技術的なこまかい知識のことではない。そういうものは、それほど必要ではない。人間学が何よりなのだ。それを養うためには、我伝引水になるが歴史に学ぶことが一番だろう。といっても、社会史など、社会構成史とか、近頃の何とか研究は駄目。昔の、具体的にいえば十九世紀風の物語的な歴史叙述、それも詳しい古典がよろしい。それが面倒なら多少フィクションをふくむが歴史小説が一番だ。例を挙げれば司馬遼太郎氏の『坂の上の雲』など。もっともあまりフィクションにすぎるものは駄目。小説家の思考より、歴史事実の方がはるかに人生の本質を語るものだからである。
もう一つ注意。直感を発動させる訓練が必要だが、ある経営者は新聞の社会記事を見て、俺ならこうすると、いつも事件の当事者の行動とちがう方法を考えることにしていると教えてくれた。変な例だが、犯人がつかまったと記事がある。その犯人のいいぐさ、しぐさが報道される。それを読んで、こういういい方、こういう言動が記者にこういう影響を与えた。ではこうしたらという風に考える。考え名が詠むというのだ犯人の言動は、必ず、それを書いた記者に、好悪それぞれの影響を与えている。記事はそういう記者の主観の入ったものになっている。そういうことをふくめて考えながら読むのだという。これは、すばらしい直感力の養成法だと私は思う。
最後に、この一挿話からの相当えげつない結論を一つ。私は実は韓非の狙いはそこにあったと考えるのだが。
殺陽は子反を陥れようとしたのではない、と韓非はいう。だが、そう思っていたのだとすれば、これは見事な成功の例になりはしないか。つまり、やっつけようとする相手に対し、その相手の個人的な身近な利益だけを計ってやるという手だ。それは相手にうらまれず――自分でくやむ以外、口に出して文句のいえる筋合いではないから――他人から害をうけることなく、目指す相手をやっつけることができるからである。
2023.12.10 記す。
19 功なきを賞すれば、民、偸幸(とうこう)して上を望む。過を註せざれば、民、懲りずして非をなし易し。これ乱の本なり 韓非子 P.133~138
功績ないものに賞を与えると人民はつけ上がって、それからそれへと高きをのぞんでとどまることがない。過ちを罰しないと平気で悪事を働くという意味だ。しかし私がこの文章を出したのはこの言葉の面白さからではない。もともと賞与であったものを年末手当などとやってしまったことが戦後日本の「大失敗」だった。官吏の年末手当の半分は勤勉手当である。だがそれはみんなに一様に与えられている。休んでも、ストをやって働かなくてもこの賞与はもらえるし、働いてもふえるわけではない。年功というわけのわからない功以外、官吏には功による昇給は絶無に近い。これではみんながつけ上がるだけで、働く気がなくなるのは当然だ。それでも日本の官吏はイギリスやイタリアの官僚よりまだよく働くといういうのが、私には判らないのだけれど。この句は、今更ながら、この当たり前の指摘を忘れた日本のおろかしさを思い出させてくれる。
しかし、私は、そんなことより、この結論のもとになった韓非の挙げる挿話を紹介したいのである。
斉の桓公(春秋時代)が酒に酔って冠をなくし、それを恥じて三日間も朝廷に姿を見せない。総理の管仲がいった。「そんなこと国を持つものの恥とはいえません。どうして政治でもってそれを雪(すす)ごうとはされないですか」と、桓公はなるほどと思い、官の倉をあけて貧民にほどこし、囚人を調査して¥軽い罪のものを出してやった。ところで人々はそれをどう受けとったか。
三日たつと人民の間にこんな歌が流行した。「王さま、王さま、もう一度冠をなくして下されや」。馬鹿にされただけなのだ。
日ごろ善政をしかないでいて、自分の失敗をつぐなわんために善根をほどこす。そんな君主は自分の利だけあって、天下のこと、人民のことは念頭にない男だ。桓公は「善政」をしくことで、自分がそんな人間だということをわざわざ全国民の前にPRしたのである。
民衆はそのことを知っている。だから桓公に対して感謝するよりも、もう一度失敗してくれと歌にして要求しただけだった。公の権威は地に陥ちた。韓非はこれを桓公は一つの過ちをつぐなったけれど、同時にもう一つの大きい公的な過ちを作ったのだと批判している。そして、故なき「善政」はこのように国民をつけ上がらせるだけだとのべているのである。
私はこの点を更にもうすこし突っこんで考えた。故なき善政をしくことは、とりわけ賞を与えたり、減刑をしたりすることは、ただ人々をつけ上がらせるだけではない、「さては、王様、何か悪いことをしたな。それで御機嫌をとっているのだ」という風な誤解を与えてしまうということである。桓公は冠をなくしたという風に、理由がはっきりしていたから、軽蔑を招くだけで済んだ。ふつうの場合だといらざる誤解を招くという結果を生むだけに終わるものである。
何か弱みがあるらしいという誤解を受けないにしても、困った結果を生むことも多い。古代ローマ帝政時代末期は、やたらと祝祭日がふえ、休みが多くなった。人心がだらけて来たこともあったが、歴代の皇帝が人気とりのため、やたらに祭日を作ったということもある。その結果、「安物で治績が上がらぬ政治家ほど祝祭日を作る」という諺が生れたのだ。こうなると休日を作れば治績が上がらないということの証明にされてしまう万博にもそんな効果があった。現在の会社では休日作りは一種の操短だという声も出て来ている。まだそんな声はとても一般化しない働きすぎの情況だけれど、これからは安易な休み作りは足許を見られたりなど思いもかけぬ結果を生む公算が大きくなって行くだろう。
大学の騒ぎで、学生が教授と団交した。団交とはつるし上げの代名詞である。恐怖にかられた教師側は、その要求を次から次へと容れて行った。ところで、大勢の中から声があり、「おーい。何も俺たちのいうことをそうみんな聞かなくてもよいんだぞ……」。そして全員どっと笑いくずれたというのである。
ここが意思決定のむつかしいところ。おだてるとつけ上がる。叱ると反撥する。全面賛同するととりくむ姿勢が安易に流れる。これは別に管理者の部下に対する嘆声だけではなく、平等なチームの討論でも、意見具申の場合でも、個人の決断の場合でも自己反省としていえることである。
ここでは三十歳から四十歳前後までの現代の中間管理職など、日本チームの指導者一般のこととして考えて見よう。例外はあるが、この世代の人々の特徴はやはりこの斉の桓公だということである。自分の能力に対する確乎たる自信ががなく、それを補おうとして人気とりをいつも考えている。だが、やることが信賞必罰でないので部下の心の中には、ひそやかにではあるがいつも桓公の歌がうわれている。一方上司もそういう自分を軽く見る。そこでイライラして、愚痴不満をもらし、妙なところへつつかり、何もかもを体制や組織のせいにして反体制的言葉を吐くことでそのイライラを解消させようとする。この世代にはそういう人々が圧倒的に多いのである。
このような人々は、まず、孤独に耐える訓練をすることである。つき合いも必要だし、部下の気持も聞いてやらねばならない。しかし、それで孤独から解放されるわけでもない。死ぬときはどうせ一人で死ぬのである。情死ではあるまいし、女房子供だって一緒に死んでくれるわけではない。年齢は確実に加えられて行く。老いるとは絶対の孤独を目指して生きて行くことなのだ。家庭の中でも会社でも、疎外を生甲斐にせよ。三十、四十の男が小娘のように、家庭でも俺は孤独だと淋しがるなど醜態以外の何物でもない。
心からなる共感だとか、連帯とか、心のふれ合いとかそういうものをやたらと求めたがるのは女性か子供かである。そういうものの空虚さを知ることが三十歳として「立ち」得た人間の価値なのだ。
独断はいけない。ボスの専断性の害は身にしみて知っている。チーム全員が心を合せなければ何事もうまく行かない。そういう反論が出ることだろう。現に、そういう教訓は雑誌ででも何でもいやというほどなされている。それはその通りだが、私の考え方はちがう。ボスの独善的支配はいけないとは、今日では六十歳以上の老人に対していうべき言葉である。今日三十歳台から四十歳台の人々にそんな人はいない。そういう人にはむしろ逆をいわねばならぬ。他人、とりわけ若い人々のことを気にしすぎ、それに迎合したり、へつらいすぎだと。桓公の愚をくりかえすような意志決定ばかりしているではないかと。
2023.11.27 記す。
20 民衆の希望する自由など叶えてやれるものはないのだから、君主は、その一つの希望、つまり復讐心を満足させてやればよい。 マキャヴェリ P.139~144
これは前に一度出した教訓、「大衆の憎まれ役は他人に請け負わせよ」というのとダブル話である。しかし、ここでいいたいことはちょっとちがう。
マキャヴェリは鋭く見抜いていた。民衆の大多数は自分の生活の安定と平穏無事を願って自由を求めている。しかし、ごく一部の連中は、「実は自分が命令する立場になりたいからこそ自由を求めているのである」と。
マキャヴェリは、「ごく一部の連中」といっているが、現在のように自分はミドルクラスだと信じている人間が圧倒的になった日本では、「その指導者の多くは」という形容をつけた方がぴったりするかも知れない。それと革命をおこしたプロレタリア独裁を夢見ている人を加えるとその数はうんとふえる。私の知っているかぎりでも、いわゆる進歩的文化人とか学者とかいうものの大半は、支配者になりたいが、このままではなれそうもない、そこで指導者・支配者・管理者を加害者という言葉に置き換え、自分は被害者になりすまし、被害者から脱出し、自分も指導者にと叫んでいるのだ。本心はそこにある。
これは要するに社会一般の自我が高まって来たからだと考えられよう。各人が個性にめざめ、個性の発揮を強く望むようになったからでは決してない。
ところで、先年話題になったイザヤ・ペンダサンは、その著『日本人とユダヤ人』の中で「全員一致の決議は決議でないはずだ。ユダヤ人は、したがって多数決しか認めない。だが日本人は全員一致を大変尊重する。奇妙だ」ということをのべている。たしかにその通りだ。けれどもこの全員一致主義は日本人の思考が妥協的だという理由によるものではない。大勢がそうなりそうだと議論の段階で自説を撤回する、長いものにはまかれろという姿勢のせいである。要するに個人主義が確立していないからにすぎぬ、現在においても、この傾向はそう変わっていない。匿名投票のようなときだけ、反対意見が出現するのである。
だからこそ私たちは心にとめなければならない。自分の決断が満場一致で通ったとしても、それは決して全員が心から賛同してくれたのではないということを。論議をつくさなかった、あるいは大勢に順応しただけで、内にひそむ不平と反対は大きいのである。
そこで、私たちがやらなければならないことは、この不平と反対を実践段階でどう克服して行くかである。面従腹背をどうして発見し、それをどう処理して行くかである。大変大きくいうと、日本では意見具申であれ、責任者の決断であれ、意思決定はそう困難ではない。あとの実行の方が問題なのだ。私はこの”決断の条件”で、意志決定そのものよりも、それにまつわるいろいろの処理を説いて来た理由もそこにある。欧米の場合は議論をつくすし、それによって集団の意志が決定されたら、実践の方は大した問題ではない。旧帝政ロシアやドイツのような後進的な諸国には面従腹背的な要素が残っていたが、先進国ではそういうことはなったからである。
日本は先進後進といった単純な尺度では計り得ない社会だが、何しろ人間関係にこだわりすぎ、内部関係では表立った対立論はうち出しにくい。反抗感や反抗姿勢は裏面での陰惨なものになる。新しいことをやるには抵抗が多い。けれど、経営戦略などみんなが賛成したころやるというのではすでに手おくれである。反抗運動粉砕に全力をそそがなければならぬ理由がそこにある。
しかし、その粉砕も正面切ってやっても効果はない。反対者の手にのるだけだ。水面下の敵に対しては、こちらも潜水して対抗しなければならないのである。
まず、煽てるという手がある。信長姉川の戦ののとき、秀吉の賢策で明朝総攻撃という軍議が決定した。柴田勝家、丹羽長秀などは新参の猿めが、と快くない。談合して明日はさぼることにした。秀吉はこれを悟って信長に意見具申する。信長はそれを容れた。こっそり一人ずつこの二人を呼んで、「さすが勇将、汝のとこころはちがうのう。他の者の陣はおびえ切って、全く気勢が上がらぬのに汝のところだけは燃えているようじゃ。頼みとするのは汝だけだ」といって刀を与えたのである。二人とも大感激、のんびり寝こんでいる部下を叩きおこし、両方とも負けてはならじと突進した。これを見て、みんな、あの談合はだし抜く気だったのかと結束たちまち乱れ、戦いは大勝利に終わったというのである。
この話はもちろん作り話だろうが、日本人の陽気好みには、こういう話は大変うまく適合するものと見え、同種の挿話がよく出て来る。実際は、「馬鹿はおだてるにかぎる」というかなり残酷な考え方に通じるのだが。
陰惨な反抗は、こううまくそらすことはできない。そこで用いられる手は、前もって犠牲者を用意しておき、それへすべてを集中させるということだ。マキャヴェリの挙げている実例はもっとひどいもので、実は自分が側したとつねづね考えていた競争者に、あらかじめ辞を低うして、節を屈して款(かん)を通じておき、その人の意見に同調したかに見せかけるという手である。
ここまで、えげつなくすることは、しかし日本人の本質に会わない。うまい人は彼の犠牲者を作りあとで酬いるとか、反抗者相互を対決させ、そのエネルギーを消耗させてしまうということをする。その手は柴田の使い方に似ている。反対者の中の一番の旗がしらを重用するのである、正面切って重要しなくてもよい。表や裏で、さすが人物だとか、あの反対論には充分以上の論理はあるとか、自分も、あのやり方でやってもよい、いや、実際、あの方がよいとも思ったのだが、ただこの点だけがひっかかるのでとか、何とか大変敬意を払い、その反対者に近づくふりをする。他の者は、「何だか変だ、奴は」と疑心を持つ。そうなったらもうしめたものである。
道徳的説教は、マキャヴェリや韓非の偽善としてもっとも排撃するところで、
2023.11.29 記す。