|
神坂次郎著『男 この言葉』(新潮社) はじめに――家訓社訓はヒト臭い P.11~15 家訓や処世訓などというと、堅苦しいもの、カビのはえた古くさいもの、時代遅れなものとして冷笑される風潮がある。ことに知識人と称する人種には、その傾向が濃い。 処世訓といえば、十八世紀のイギリスで有名な政治家チェスターフィールド伯爵(一七七三年歿)が子息におくった、おびただしい数の手紙もそれであろう。親が息子に宛てた書簡だから、どうしても教訓臭がつよい。このチェスターフィールの書簡集を、 「あろうことか父親が、売春婦のマナーや、ダンス教師の立居振舞いを子に教える気か」 と嘲笑したのは当時の大学者ジョンソン博士であった。 石頭のジョンソンには<学問も教養もある息子が、高級娼婦たちがもっている魅力的で人をそらさぬあの社交術と、ダンス教師の優雅な作法を身につければ鬼に金棒。どれだけ魅力的な紳士になることか>と、考えるチェスターフィールド伯の《挙措やわらかく、事においては剛毅》という、わが子へのアドヴァイスや、血の通った処世訓など分ろう筈もなかったのであろう。 ともあれ、人の世を生きていくため、わが国でも天皇、公卿、将軍、武将、大名、武家、豪商から庶民にいたるまで、さまざまな時代さまざまな人びとのために家訓、庭訓(父の教え)、家法、掟書、遺訓、書置、壁書、藩訓、社是社訓といった訓(おしえ)が説き語られている。 これらの訓の濫觴(起源)は、なかば伝説的なひびきをもって伝えられている聖徳太子の、《一にいわく、和をもって貴しとなし、忤うことなきを宗とす。人みな党あり、また達る者少し。これをもって、或は君父に順がわず、また隣里に違う》 第一条、人はやすらぐことを貴ばねばならない。たがいに対立せぬように心するがよい。党派をつくれば主人や父、近隣とも争うことになる……といった蒼古たる『憲法十七条』から、《万のことに淫することなかれ、躬 を責めて節せよ。賞罰を明らかにすべし。愛憎に迷うことなかれ。意を平均に開いて、好悪によることなかれ。よく喜怒を慎みて、色を形すことなかれ》 という宇多天皇の『寛平御遺誡』などと数えきれないほどある。 この種の"訓"のなかで、読んでいて、"にんげん"の表情が泛かびあがってくるのは、乱世の武将たちの家法や、近江や京、伊勢、大坂商人たち実践派の商訓であろう。 昭和から平成にかけての各社の社訓のなかでも(空疎な建前だけのものが多いのだが)いきいきしているのは、小売では売上げ日本一のビッグストア、ダイエーの、 《先制攻撃こそすべてである》 《良い製品を安い価格でどんどん売ろう》 や、はじめて石鹸が売りに出された明治二十三年当初、まちがえてこれを喰った人が口の中を泡だらけにしたというエピソードをもつ花王石鹸の、 《清潔な国民は栄えり》 というのから、健康飲料ヤクルトの切なる願いである 《健康で長生き》 そしてまた、大成建設の草創期の会長の人生哲学を掲げた 《ウソをつくな》 などは企業姿勢を直截に浮かびあがらせていて、感じがいい。 異色なのは熱海美術印刷の 《社員は失敗する自由がる》 そして、出光興産の 《学問の奴隷になるな》 《法律、組織、機構の奴隷になるな》 《権力の奴隷になるな》 《主義の奴隷になるな》 などは創業者出光佐三の哲学であり、経営理念でもある。雪印乳業の、社訓ともいわれる《低 賞 感 微》 《三ム(だらり)》 は、ちょっと謎めいて愉快である。これは昭和三十八年社長に就任した瀬尾俊三の語録から出たもので、 低……社員は、応接する相手よりも低く頭をさげよ。 賞……つねに、相手をほめよ。 感……いつも、感謝の気持ちを忘れるな。 微……表情は春風のように、微笑をたたえて人に接すること。 そして次の《三ム(だらり)》は、ムダ、ムラ、ムリの三のムをしめしていて、これを忘れぬようにムの後ろにつく三文字を、 「祇園の舞妓のダラリの帯じゃ」 と覚えさせているのは、世間によくある硬直した社訓などとは、一味ちがう。 すぐれた"訓"のなかには、先人たちが遺した人生の知恵が凝縮している。そんな、歴史の舞台を足早に通りすぎていった男たちの哀歓と、かれらの"人生を読み"その横顔を垣間見るのも興味深い。 歴史といえば、『太平記』に登場する南朝の忠臣、上野国(群馬県)新田郡の住人、八幡太郎義家十世の孫、新田義貞の《ギャンブル訓》などは、いかにも乱世といった面がまえで、後世の教訓臭をおびおた"訓"の枠を蹴破った荒々しさが、一種、痛快である。 《まず博奕(ばくち)をせんに……》 と、『新田左中将義貞教訓書』に説う。 《一には心、二には物、三には上手、四には性、五には力、六には論、七には盗人、八には害なり。この八の一も負けては勝つことあるべからず》 《まず一に心とは、負くるを大事と思うべからず。二には物とは、持ちぬるを一ツ立て、負けぬれば二ツたて、十負けぬれば廿たて、かくいのごとくするに、一度かきおとさぬこおとさぬことなし。三に上手とは……》 博奕に大事なのは、第一には心、負けてあわてるようではいかぬ。第二には物、つまり賭ける物をたっぷり持つこと、一つ賭けて負ければ次には二つ賭けよ、それでも負ければその倍を賭けよ。負けて負けても相手のばいばいを賭けていけば、ついには勝利をつかむことができる。第三番目には、博奕の技術にすぐれていなければあらぬ。第四は、ギャンブラーとしての性格、気迫に満ちていること。五番目の"力"というのは、腕力だ。賭けても賭けても負けがつづいた場合、相手を殴りつけても財物を奪い返せ。 第六の"論"とは、博奕が過熱してトラブルが起き論争になったとき、相手を言い負かし、不利も有利に言いくるめ論破する弁舌が必要である。第七の"盗み"は、勝つためには相手の目を盗んでイカサマをやれ。勝負の世界は"勝つ"こと以外に用はない。で、最後の第八の"害"というのは、以上述べた条々、いずれも効果が出なかった場合は、相手を斬り殺して財物を奪い盗れ……という凄まじいばかりの"訓"である。 が、これが南北朝という争乱の修羅を生きる心境であったのであろう。生ぬるい根性では、到底、生きていける世界ではなかった。 天下破レバ破レヨ 世間滅ビバ滅ビヨ 人ハㇳモアレ 我身サエ富貴ナラバ と、二人の天皇のもとに日本全土が真二つに分れ、一門一族、骨肉相喰み、親が子を、子が親を殺し、裏切り、変節いとまない"自由狼藉"の時代であった。 2021.07.02記 |
多くの人に会して多く知恵を得よ
|
上杉鷹山 国家は私すべきものにあらず(1,751~1,823年) P.18~22 ずいぶん以前のことなのだが、アメリカ大統領ジョン・F・ケネディに、「大統領閣下、あなたが尊敬する日本人は?」と日本人記者が質問したことがある。そのときケネディは、信長でも秀吉、家康でもなく、徳川中期の地方の一大みようにすぎない、 「ヨーザン・ウエスギ」 のなをあげて記者団をおどろかせた。 ――上杉鷹山(一七五一~一八二二)、日向(宮崎県)高鍋藩三万石秋月種美の次男で幼名を直丸。のち治憲、鷹山は号である。宝暦十年(一七六〇)出羽(山形県)米沢十五万石の藩主、上杉重定の養嗣子となる。 が、十歳の直丸(鷹山)が赴く以前の米沢藩は、財政のどん底に喘いでいた。もっとも上杉家の貧困ぶりは今に始まったものではない。謙信以来の歴々の名家も、関ケ原合戦で西軍、石田三成に加担したため、会津若松百三十万石から米沢三十万石に減封処分されるが、不運は更に続く。嗣子に恵まれなかった三代藩主の急逝によって、家名断絶、米沢藩取潰しの瀬戸際に立たされるが、三代藩主夫人の父、保科正之の斡旋によって救われ、吉良上野介義央の子、三郎を養子にむかえ、半知、つまり半分の十五万石に削減される。 それからが地獄であった。現在の企業なら経営の枠組みが縮小されれば、それに応じて減量し、従業員の人員整理にかかる。ところが、上杉家ではそれをしなかった。当時、幕府が定めた大みょう家の軍役は、平時では一万石につき約二百人。十五万石に半減された上杉家の場合なら三千人でいい筈だが、家臣団は従来のままの六千人。かれらの俸禄だけでも、十三万万五千石が必要である。 こうした放漫経営に拍車をかけたのが、吉良上野介に嫁いだ三代藩主綱勝の妹と、上野介の子、三郎が上杉家四代藩主になるという、吉良家との二重縁故であった。諸事、豪奢が家風ともいう吉良家出身の、派手好みの浪費狂の四代藩主の行状と、その実家である吉良家へ年々送りつづけた莫大な経済援助が、ただでさえ苦しい上杉家の財政を破綻させ涸渇させた。 江戸藩邸へは、売掛金の催促に連日、町人たちが詰めかけ、それらの借金の清算もできず、やがては藩主が登城する行列に必要な経費にも事欠き、やむなく重臣たちが甲冑刀槍、衣服まで質に入れして急場をしのぐという有様であった。そのころ巷では、金に縁のない上杉家を揶揄して、 「鍋釜のなかに"上杉弾正大弼"と書いた札を入れておけば、金気がとれる」 と噂される始末であった。 借金と言えば、江戸の豪商三谷(みたに)家をはじめ出羽酒田の本間家など、借りられるところはすべて借りつくし、藩士たちからは俸禄の借りあげ、領民からは過酷な搾取と、火の車財政のやりくりをしてきた米沢藩が、絶対絶命の窮乏の極に立たされたのは、宝暦三年(一七五三)。幕府から上野、寛永寺中堂普請を命じられての出費、五万七千四百両余と、同年洪水による領内の被害三万七千七百八十余石、そしてその翌年の凶作被害損耗高七万五千八百二十余石の減収であった。だが、それに追打ちをかけるように宝暦五年、六年と奥羽地方一帯に大凶作が襲来する。領内の窮士貧民は小ぬか藁だんご)、松皮だんごや木の根を喰って飢えをしのいだが、その顔色はすでに、《人間の色合にて之無く候》という有様であった。 「もはや、自滅か」 万策尽きた重定は、藩主の地位を放棄し、十五万石の領土を幕府に返上しようと前代未聞の決断をした。 この、重定の封土返上は尾張中な言徳川宗勝に諭されて中止し、明和四年(一七六七)重定隠居。かわって鷹山、九代藩主になる。時に十七歳。家督をついだ鷹山はこのとき、 受次ぎて国のつかさの身となれば 忘るまじきは民の父母 今日からは家臣や領民の父となり母となり、かれらをいつくしむ政治をおこなおう、との決意を和歌に詠んでいる。 しかし、この時期の鷹山の立場は、前社長が投げ出した倒産同然の老朽会社を、若い養子の社長が懸命になって再建しようというのに似ている。 鷹山の施策第一弾は、従来の諸儀式、仏事、祭礼、祝事を取り止め、または延期し、五十人の奥女中を九人に減らし、藩主以下全員、食事は一汁一菜、綿服の着用、贈答の品は一切廃止……と十二ヵ条に及ぶ倹約令の公布であった。そしてその徹底を図るために『志記』と題した一文を書いて、その意とするところを重臣たちに伝えた。だが、「死にかかっている魚は頭から腐っていく」というが、若い藩主に対する重臣たちの反応はつめたい。 「けッ、かよう貧乏くさい倹約令など、武威を天下にふるって隠れもない不識院(謙信公)さま以来の面目を汚す気か」 と、贅沢に狎れた家臣たちは鷹山の倹約令を嘲弄し、なかでも正面から非難蔑視した奉行職の千坂対馬、色部修理、江戸家老の須田満主など七重臣は病気と称して出仕しなかった。 「やむを得まい」 鷹山の処断は峻烈であった。重臣たちに、切腹、隠居閉門と採決を下したあと鷹山は、大倹約令を実施し、竹俣当綱、莅戸善政らを重用し、農村の復興に取り組み、藩士たちにも開墾を奨励し、備籾倉をおこして打ちつづく不作にも備えた。このため天明の飢饉には一人の飢死者も出なかった。そして鷹山は農家の副業を奨励し桑・楮・漆の栽培を指導し、さらに製糸技術の改良、織布技術の輸入をはかり京都や越後の小千谷から職人を招いて、鷹山みずからが産業技術の先頭にたったので、大いに工業が興り、江戸で売りさばかれた米沢の織物はひときわ声価を高めた。 鷹山のすばらしさは、奇蹟にちかい再建をなし遂げたあとも、自分は一汁一菜、綿服という質素な生活を守り続けたことであろう。天明五年(一七八五)米沢藩を黒字財政にのせたあと、鷹山は前藩主の実子、治広に藩主の座を譲り隠居するという、見事な進退をみせている。まだ三十五歳の鷹山が、である。 そのとき鷹山が、藩主の心得として治広に与えたのが『伝国之辞(譲封之詞)』である。 《一、国家ハ先祖より子孫へ伝候国家にして、我私すべき物にㇵ無之候 一、人民ハ国家に属し足る人民にして、我私すべき物にㇵ無之候 一、国家人民の為に立たる君にて、君の為に立たる国家人民には是なく候 右三条、御遺念有間敷候事 天明五巳年二月七日 治広殿 机前 治憲(花押)》 ここでいう国家とは米沢藩、人民とは領民のことだが、「君主は国家、人民のためにたてられたもので、君主のための国家、人民があるのではない」という愛民の思想は、はるか後世の海の彼方のアメリカで《人民による、人民のための、人民の政治》と叫んだリンカーンの言葉を思い出させる。 日本人記者から質問お受けたときケネディは、wざれわrでとは逆に、ヨーザン・ウエスギの言葉を思い泛べたのであろう。 鷹山の『伝国之辞』は、ゲティスバーグのリンカーンのあの有名な演説より、八十年も前に書かれている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.18~22 2021.06.21記 |
|
二宮尊徳 多く稼いで、銭を少なく遣うは富国の達道(1,787~1,856年) P.23~27 二宮金次郎といえば、戦前、小学校の校庭に立っていたあの銅像、薪を背負い歩きながら本を読んでいる苦学少年といったイメージが強い。そのためか、貧しい家に生れたと思われがちだが、その実家は相模国栢山村(神奈川県小田原市栢山)の裕福な農家で、二町三反の地主でもあった。 ところが好人物の父が、またたく間に財産を減らし、それに加えて酒匂川の氾濫で田畑は濁流にのみこまれ、後に残されたのは、ごろ石の散乱する石河原だけであった。二宮家が貧乏のどん底に叩き込まれ、重い薪を背負った少年農夫「二宮金次郎」が登場するのは、この頃のことである。 《幼年時代の困窮艱難実に心魂に徹し、骨髄にしみ、今日なお忘れることあたわず》 十四歳で父を、十六で母を失った金次郎は、母の実家にひきとられた弟二人と別れ、伯父のもとで働くことになった。この時期、金次郎は一つの志を立てている。あるとき、金次郎は、路傍に捨てられていた苗の束を、廃田の水たまりにうえたところ、やがては籾一俵を得た。廃地廃物より物を生じ、生じたものに花が咲き、一粒はやがて数百千倍に増える。《積小為大》(『報徳記』) 小を積んで大となす天地の証明、そう思った金次郎は、毎日、夜明け前に起き入会権がある山に入って薪を切り二里の道を歩いて小田原城下へ売りに行った。そしてその途中、声をあげて『大学』を読みながら歩いた。 「いまの境涯から這いあがるには、学問しかない」 こうして寝る間も惜しんで刻苦勉励した金次郎は、二十四歳のとき二宮家を再興し、一町四反五畝の田畑を持つ身になった。 が、金次郎は小地主としての現状に甘んじてはいない。田畑のすべてを小作に出した金次郎は、小田原藩主の家老で千二百石、はつとり十郎兵衛の邸に若党として勤め、その給金と年に三十~四十俵入る小作米を換金し、利殖をはかっている。 金次郎が奉公したのは、学問への期待があったからだ。服部家の若い三人の子息を藩校へ送迎するのが金次郎の仕事であったが、その講義中戸外で、『四書五経』などを立ち聞きして、独り学んだ。 服部家で三年、栢山村に帰った金次郎は隣村の娘きのと結婚。が、ほどなくはつとり家から家政の建て直しを乞われ再び故郷を出る。これは以前、はつとり家を去るとき経費節減の私案として『御家政取直趣法帳』を十郎兵衛に献上していたのが、きっかけとなったのだ。 服部家での"財政顧問"としての金次郎の第一歩は、倹約と《推譲》の道ととなえた独自の仕法であった。 《推譲の道は百国の身代の者、五十石の暮しを立て、五十石を譲ると云う。此の推譲の法は我が教え第一の法にして則ち家産維持から漸次増殖の方法なり。家産を永遠に維持すべき道は、此外になし》(『二宮翁夜話』四) 借財の山をかかえこんでいる服部家のために金次郎は、倹約を説き実践に移すためさまざまな手段をとっている。例えば燃料を節約させるために鍋釜の底についたススをこそげ落させ、そのススを買い取ってやるなどして、奉公人たちに節約が得になることを覚えさせて、倹約への意欲を掻きたたせている。 《多く稼いで、銭を少なく遣い、多く薪を取って焚く事は少なくする。是を富の大本、富国の達道という。然るに世の人是を吝嗇といい、又強欲という、是心得違いなり》(『二宮翁夜話一』) 金次郎の財政再建の見事さは、金融や計数に明るく、複利計算の妙をも心得ていたことであろう。藩庁の低利子貸付金に目をつけた金次郎は服部に四百六十両借り出させ、このうち負債の三百七十両を清算し、残りの九十両を服部家の家臣たちに貸付け、その利鞘を稼いで藩庁への元利の返済にあてた。こうして数年後、服部家には三百両もの余裕金が残った。 はつとり家再建後の金次郎の身辺は、にわかにあわただしくなる。幕府老中で小田原藩十一万三千石の藩主、大久保忠真から命じられ、分家である下野国(栃木県)桜町四千石の旗本、宇津家の乱脈財政の建て直しにむかう。 が、各地を奔走して帰宅しない金次郎の留守を守りきれれなかった妻きのは、離別をもとめて遂に去っていく。けれど、金次郎はそれを振り返る時間もなかった。 農政官として桜町に着任した金次郎は、寸暇を惜しんで領内を巡回し、農民たちの援助や指導をつづけた。荒地を開墾する農夫などをみると金次郎は、栢山村の田畑を処分して持参した自分の金の中から惜しげもなく賞金を与えた。 やがて服部家の上女中であった波と再婚した金次郎は、桜町に移り住み、雨の日も風の日も領内の巡回をつづけた。こうして、重税のため勤労意欲を失って放棄されていた田畑も甦りをみせはじめたころ、気象の異常さを感じた金次郎は、領内の農民たち各戸に一反ずつ稗、粟などを蒔くことを厳しく命じた。 「皆、よう聞け。この稗、粟に年貢はかけぬ」 金次郎のこの予感は適中した。はたしてその秋、大冷害に襲われ諸国大凶作、餓死者は各地にあふれた。世にいう天保の大飢饉である。が、金次郎の指導によって各戸一人五俵以上の雑穀を貯えていた桜町領からは一人の餓死者も出なかった。 こののち金次郎は、藩主大久保から小田原領内七十二ヵ村の仕法を命じられ困窮農民の救済にむかい、そのほか烏山藩、下館藩などの仕法に奔走。天保十三年(一八四二)老中、水野越前守忠邦から幕府御普請役格に登用され、利根川分水路見分目論見御用に任じられている。 二宮金次郎、実名を尊徳、世間のなは"尊徳"。農政家としての尊徳が救った村は六百五ヵ町村、かれ独自の仕法をもって根本から建て直したもの三百二十二ヵ村、ひとりの困窮民も借財もなく村を再生させたもの二百ヵ村を超える。 行動的な経済家ともいう彼、尊徳がユニークなのは、その卓抜な金銭感覚であろう。 一枚の田から何石の米がとれるか、その米を換金すればいくらになるか。 「米倉に米俵を積みあげ、何年待っておっても米は増えぬ」 が、この米を売った金を巧みに運用すれば、二倍も三倍もの利息が稼げるのだ、と尊徳は説う。 「農民たち個々の零細な金でも、まとまれば大きくなる」 それを貸付け利に利を生ませ、その利益を村に還元し農地を改良し……と尊徳は、農民信用金庫への構想を熱っぽく語りつづけてやまない。いまから百四十年前のことである。 「千両の資金で千両の商売をするのは危ないことだ。千両の資本で八百両の商売をしてこそ堅実な商売といえる。世間では百両の元手で二百両の商売をするのを働きのある商人だとほめているが、とんでもない間違いである」 と、尊徳は説う。 平成の泡沫経済のなかで目の色を変えて奔走している虚業家たちに、聞かせてやりたい言葉である。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.23~27 2021.06.20記 |
|
陶の朱公 気が短い者は取引がすくなくなる(1,787~1,856年) P.28~32 巨億の富に恬淡として悠久の人生をおくった"貨殖"の達人が中国の春秋戦国の頃にいた。 世にありし日のなを范蠡。戦前の小学唱歌にも、『太平記』のなかで隠岐に流されてゆく後醍醐天皇の奪還をはかった忠臣、児島高徳が、桜の木を削って《天莫空勾践、時非無范蠡》天、勾践を空しゅうするなかれ、時に范蠡なきにしもあらず、と書き失意の天皇を喜ばせたというエピソードにも登場し、そのなを謳われていたほどの有めい人で越王勾践を扶けて宿敵、呉王夫差への復讐を遂げさせた男である。 范蠡の凄みは、その進退の見事さであろう。呉の国を平定し、最大の功労者として上将軍に任じられ権勢並ぶ者のない地位に立ったとき范蠡は、 《蜚(飛)鳥尽キテ良弓蔵セラレ、狡兎死シテ走狗烹ラル》 兎狩りには猟犬が必要だが、兎を獲ってしまった犬に用はない。やがては、飼犬に手を咬まれることを案じた飼主から犬は殺されてしまう。必要がなくなった功臣の運命もまたこうである。と名せりふを遺して越の国を去って行く。 范蠡のこの予感は、みごとに適中する。かれが家族や従臣、財宝を積んで海に乗りだした後、かれと同じ功労の臣で宰相の地位にあった文種は、群臣たちに妬まれ中傷され、主君の勾践から"異心あり"として殺される。
かれの賢名はやがて国内にひろがり、望まれて宰相となる。こうしてまた数年、斉の国を建て直し富ませ治績大いにあげた鴟夷子皮は、 ※参考図書:『史記列伝』五(岩波文庫)P.155 <家居すれば千金の富家となり、官仕すれば宰相となる。いま人生の幸福の極限をきわめている。このような栄誉のもとに長居してはならぬ。居れば必ず災厄に見舞われるものだ> そう言うと鴟夷子皮は、稼ぎ貯めたすべての財を惜しみなく貧しい友人や郷党の人びとに分け与え、自分はまた家族や従臣たちを連れ、斉から遙か西南にある陶に赴いて居を定めた。 陶の地で朱公と名を改めた彼は、ここで経済人として<致富の術>を縦横に駆使し、 《鉅(巨)万ノ富ヲ累ネルコト三度》 この間、貧人窮民を救うため財を擲つこと二度。朱公のなは世間にひびき、天下の富人と称せられたと『史記』は語る。 その朱公が、致富の要諦を説いて書き残したと伝えられる十六巻三十二項目にわたる訓戒の書『陶朱公致富栄業良規』がある。 《生意要勤緊(仕事は意欲に満ち、勤勉であること) 懺情則百事廃(怠け心があると、すべて駄目になる) 用度要節倹(必要とする費用でも出来るだけ切りつめ質素にすること) 奢侈則用途渇(支出を放漫にすれば必要なときに金がつきる) 接紊要温和(人に接する場合はおだやかな態度でなければならぬ) 躁暴則交易少(気が短い者は取引がすくなくなる) 買売要随時(売買取引は機をみて敏速にすべし) 挨延則機宜失(のろのろしていると潮時を失ってしまうぞ) 議価要訂明(価格はいつも明確に取り極めること) 含糊則争執多(これを曖昧にしておくと必ず紛争のもとになる) 賖欠要識人(信用取引には前もって相手の人格を調べておくこと) 濫出則血本?(乱売乱買ばかりしていると搊をするぞ) 賬目要稽査(帳簿や勘定はいつもきっちりと整理しておけ) 懶怠則資本滞(怠けておると資本の回転がとまってしまう) 優劣要分清(良い品と粗悪な品は判別しておくこと) 散漫則必要廃残(物ごとを散漫にしていると、かならず廃物がでる) 用人要方正(人を使うには性格のよい人物を用いること) 詭譎則受其累(狡猾な人物を使えば、なにかと悶着がおこる) 出紊要謹慎(金銭物品の収支には注意せよ) 大意則錯漏多(大ざっぱにしていると誤りや手ぬかりが多くなる) 貨物要面検(商品は、常に現物をみて確かめておけ) 濫収則售価低(計画もなく、うっかりと仕入れすると売値が低くなる) 期限要約定(金銭の支払いや物品の受け渡しの期限は必ず守ること) 延遅則信用失(遅延すると信用を失ってしまうぞ) 銭財要清楚(金銭の関係だけは、いつもすっきりしておけ) 糊塗則弊売生(これを曖昧にしておくと必ずふ正や弊害がおこる) 臨事要責任(仕事をする場合かならず責任をもつこと) 放棄則受害大(しまりのない気持ちで仕事をすると、大きな搊をするぞ) 主心則鎮定(企業を束ねていく主人たるもの、いつも心を落ちつけ、ずしりとかまえておること) 妄作則誤事多(軽率妄動すると、判断を誤り失敗することが多くなるぞ)》 陶の朱公が春秋戦国(紀元前七七〇年~紀元前二二一年)のころに著したこの致富の要諦は、今日でもなお充分に味わうべきものをもっている。 その朱公の次男が、あるとき商用で楚の国に行って、酒の上の争いから人を殺し、投獄されるという事件があった。これを知った朱公は、 「人を殺せば、わが身も罪を受け死刑になるは当然であろう。が、昔から"千金ノ子ハ市ニ死セズ"富豪の息子は死刑にならぬと諺にもある」 そう言うと朱公は三男をよんで、黄金千鎰(三百六十キログラム)を牛舎に積ませ、次男の助命に差し向けることにした。が、これを聞いて怒ったのが長男であった。 「弟の命にかかわる危難の時に、私をとりおいて三男がいくというのではこの家の嫡男としての面子が立ちませぬ。面目を失った以上、私は自殺するしかない」 と思い詰めた顔つきでいう。やむなく朱公は長男に、楚王の側近や高官連中を買収するための千金を持たせて出発させた。 が、失敗であった。長男は泣きながら処刑された弟の遺骸と手つかずの黄金千鎰を持ったまま帰ってきた。 しかし、朱公は冷静であった。 「儂には、こうなることが最初から判っておった。幼い頃から儂と共に苦労してきた長男は黄金がいかに得難く貴重なものか知っていたので、潔く使うことが出来なんだ。ひきかえ、朱家の財宝の中に育った三男なら、千万金であろうと必要なれば平気でばら撒くことができた。当然のことが、当然の結果を生んだまでのことよ」そう言ったという。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.28~32 2021.07.04記 |
|
諸戸清六(上) 温かき飯は食うに手間取り時間を空費す(1,846~1,906年) P.33~37 幕末から明治にかけて稼ぎに稼いだ大富豪に、諸戸清六という男がいた。 その先祖というのは伊勢国(三重県)揖斐川沿岸で加路戸新田を開拓し大地主にのしあがったが、祖父の代に家運傾き、父の清五郎は塩問屋、米穀、肥料の仲買商など、さまざまな仕事に手を出したがいずれも失敗、失意のうちに世を去る。 この大借金の加路戸屋を六千百二十円という負債もろとも引きついだのが、清六、十七歳のとき。一円で米が約三斗(四十三キログラム)買えたという時代である。清六は、押しかけてきた債権者と話しあい、十年間無利子で毎月五十一円四十銭ずつ、つまり十年間で借金を返済するという契約をかわした。 「いまに見ちょれ。儂ア、天下一の金満家になつちゃる」 加路戸を去って桑なにでた清六は、ちいさな搗米屋を開業し、大借金返済のため二十ヵ条の自家訓をおのれに課し、猛烈きわまりない働きぶりをみせた。 清六の、その自家訓というのは、 《第一条 今日よりは酒、煙草一切厳禁のこと。 第二条 従来自分の食糧は一日八合なれど、借金皆済までは必ず六合に減ずること。 第三条 温かき飯は手間どり時間を空費す。今日以後、借金皆済まで冷飯たるべきこと。それも茶漬たるべきこと。 第四条 忙しき時は、むしろ食わざること。二度くらいの欠食で空腹をおぼえるようでは、金はたまらぬと心得べし。 第五条 飯を盛り替える時間は惜しきゆえ、二個の椀を用意しておき一杯に盛りおくこと。 第六条 昼飯は必ず帳場で食すべきこと。それも一口にて食し得べき握り飯を二個ずつ用意しておき、用の合間に食すべきこと。 第七条 飯の菜は生ミソの中へ鰹節と生姜を入れて煮詰め、それを少しずつ冷飯の上へのせ、茶漬にして食うこと。 第八条 字は仮な書きがよし、手紙、帳面、すべて人より早く書くべきこと。 第九条 ソロバンは通常がよし。ただ書くこと早く、間違いなきよう稽古すること。 第十条 家裏の空地は一坪にても利用し、茶、大根、すべて野菜をうえ込み、汗の実は必ず他より買うべからず。 第十一条 家の付近に竹木縄類が落ちておれば、それを拾いあつめ宅に持ち帰って何かに利用すること。 第十二条 冬季、火鉢へ炭を入れるを廃し、薪を長さ五寸程に切り、縄を巻いて灰の中へ入れておくこと。 第十三条 下駄、草履三、四足ずつ家の各所の上がり口に並べおき、いつ何処にても上り下り自由になし、時間を省き得ること。 第十四条 道をゆく時は、後足を先へ先へと歩くよう練習すべし。人が一里歩く間に一里半歩くべし。 第十五条 買い出しの場合は、夜行をして相手の家へ早朝に着くこと。早朝なれば先方必ず在宅なり。 第十六条 買い出しは必ず日の暮れまでに片付け、船、車に乗りても、その夜のうちに帰宅し、決して宿屋に泊まらぬこと。 第十七条 旅行具の道具は常に一ところにまとめておき、イザといわば、すぐさま飛び出し得るよう用意のこと。 第十八条 遠出の際は小石多き道のみ草鞋で歩き、通常の道は草鞋をぬぎ、はだしで歩くこと。 第十九条 道に草鞋が落ちておれば拾い来たり、水で洗い、日に干しておき、夜業の合間にこれをつくろいて履くこと。 第二十条 渡し賃は一厘一毛(銭貨の最低の単位)にても払うことは無易なり、寒中の他は衣類をまとめて泳ぎ渡るべきこと。。 ――といった条々である。 諸戸清六が偉大なのは、この二十ヵ条を作ったことではない、すべて実行したことである。 こうして約束の十年目、血のにじむ思いで大借金の返済を成し遂げた清六は、以来、近隣の農村で買付けた米を美濃や尾張方面に船で運んで売りさばき、帰りの船には薪や雑穀などを積んでくるという稼ぎぶりで、明治初年、すでに数万円の財産を掴んでいたという。 その清六のうえに、思いもかけぬ幸運が舞い込んでくる。明治十年(一八七七)の西南戦争であった。 「やるか!」 清六は素迅い。 米価の高騰を予測し、全財産を投じて米を買い占め、巨利を掴んだ清六は、おりから新政府が、西南戦争でがたがたになった赤字財政を補填するため濫発に濫発をかさねていた紙幣に目をつけた。 この時期、巷に氾濫する紙幣と正金(銀貨)のあいだに大きな価値のひらきがでていた。正金を銀貨と書いたのは、当時のわが国保有の正貨のほとんどが銀貨であったからだ。 ともあれ、この新政府の紙幣に視線をむけた清六は、 《(紙幣が)銀貨に対して八十五銭の打歩を生ずるに至りし際、再び全力を尽くして紙幣を買占め、以て莫大の利を博し、後日(経済界)の巨豪の基礎を作った》(『諸戸清六翁』) という。 おそらく清六は、大蔵卿、松方正義が「兌換銀行条例」を公布したその瞬時の潮どきに乗じて、紙幣と正貨との兌換(引き換え)によって荒稼ぎをしたのであろう。 これと同様の例は、安田善次郎の場合にもある。 善次郎は、新政府が強行した「紙幣と正貨の等価通用」の布告を一日前に察知し、三十八円で買い占めに奔走、そのボロ紙幣が翌日には三ばいに化るという濡れ手に粟の大儲けをしている。 諸戸清六が蓄財をかさねていく経緯は銀行王、安田善次郎のそれと酷似しているが、清六の成功の背後から支えたのは粗衣粗食と、鉄のような意志で展開した勤倹力行であった。 ある晩、所用の帰りに清六が、桑なの近くの坂道に通りかかると、ひとりの車曳きが坂道を登り悩んでいた。清六はその車の後押しをして坂を登らせてやった。そして、夜まで働いている車曳きをねぎらうように、財布をとりだして「車力どん、夜遅くまで働いて感心だねぇ」と、一枚の銭を与えた。その一枚の銭に車曳きは妙な顔をした。「仮にも天下の金満家といわれる諸戸の旦那とあろうお人が、文久銭一枚とはねぇ」。鼻先で嗤うと車曳きは清六の掌に文久銭を返した。 「ああ、要らないのかぇ車力どん。文久銭一枚でも儂が汗を流して稼いだ大切なお金だよ。お前さんは一生、車を曳いておわるのだねぇ」 そういうと清六は、背を返して歩きだした。以来、土地の人びとはこの坂を、諸戸の「文久坂」と称んだ。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.33~37 2021.06.16記 |
|
諸戸清六(下) 多くの人に会して多く知識を得よ(1,846~1,906年) P.38~44 西南戦争による米価の高騰と、明治新政府が濫発した紙幣と正貨の打歩、つまり貨幣の実質価値が名目価値より下落した場合の差額、によって莫大な利益を得た諸戸清六は、その巨利を資本に次々に事業を興し、日本財界の奇傑として表街道を驀進していく。 《明治二十年(一八八七)木曽川工事に着工せらるるや其の水利の便を洞察して沿川の荒蕪地を廉価に買入れ、美田を得、また植林事業に着手して巨万の富源を作る等々その画策するところをみな成功せざるはなし》(『大日本人名辞書』) 《(彼の)財産の主なるものは土地にして伊勢、伊賀、紀伊の三国に跨り莫大の面積に渉り地租(土地税)実に二万円以上に達す》 清六は終生、松坂木綿の衣服をまとい粗食に甘んじていたが、吝嗇ではない。諸戸家に勤める丁稚の中で有望と認めた少年には学資を給し学校教育をうけさせ、飲料水に悩む桑なの町民のため十五万円投じて水道を敷設してみたり、また、日本帝国海軍に軍艦建造費を献納するなど、豪快な金の使いぷりをみせている。 奇行の多かった清六のエピソードの一つに、文明開化の岡蒸気こと"汽車"が登場する。当時の鉄道は、料金は高いし、鉄道頭の配下にある鉄道寮の役人たちは「人民どもを乗せてやる」といった、お役所風を吹かせていた時代である。 《何人によらず鉄道の列車にて旅行せんと欲する者は、まず賃金を払い手形(切符)を受取るべし、然らざれば列車に来るべからず》 《乗車せんと欲する者は遅くとも十五分前にステションに来り切手(切符)を買うなり、手都合を為すべし》 そんなある冬の日。 東海道を走る列車の一等車に、素足に草鞋脚絆といったみすぼらしい身なりの老人が乗っていた。検札にきた車掌が、 「おい、ここは一等車だ、お前などの乗るところじゃない」 そう咎めると、老人は袂から一枚の白い一等切符をとりだし、 「これがあっても、駄目かね」 と微笑った。 こうして列車が桑なに近い小駅に停ったとき、数人の地方役人が乗りこんできた。役人たちは社内に腰かけている老人を見ると、あわてて帽子をぬぎ低頭した。一等車の乗客たちが、怪訝な表情でそんな光景を眺めているうちに、列車は桑な駅に着いた。と、役人のひとりが席をたってドアを開けると、老人は悠々と降りていった。 「あの爺さんは?」 乗客の一人がそう訊くと、 「ご存じないのか、天下の千万長者、諸戸清六様を」 「なるほど、桑名の諸戸なら、一等切符どころか、この列車を全部買切ったところでふしぎはない」 乗客たちは、たがいに頷きかわした。 このとき、一等乗客が言った言葉どおり、清六は後日、愛娘のために一列車を買い切り、その特別列車に花嫁道具を満載して嫁入りさせている。 その日、桑なの町民たちは国旗をかかげ、花火を打ちあげ、諸戸家万歳をとなえて見送ったという。 清六と親交のあった東京の実業家、森村市左衛門は、 「彼の汽車旅行は、いつも赤切符(三等)だったといわれているが、そうではない。車中は有益な話を聞く耳学問の勉強の場だと考えていた彼は、一等に乗ってもよい話が聞けそうもないと思えば、すぐに二等車に移り、二等で話しが尽きると、こんどは三等にという場合が多かった。もちろん、彼が喜んで聞いたのは経験談で、車中を見渡して大工でも左官でも、なにか経験のありそうな顔を見かけると、すぐにその人に話しかけるという風だった」 と、述懐する。 清六は、この森村(維新後真っ先に対米貿易の道を開き、森村組を創業。男爵)の家をよく訪ねたが、無益な雑談などはしないで、自分の用事だけをどんどん喋って、それが終ればすぐに帰っていくのだが、時には「もっと活きた話をしてくれ」と子供のように"話"を催促することがあったという。 そんな清六の手紙も変っていて、 「それでいて要領を得ていること、驚くばかりであった」 と森村は語っている。 この森村とともに親しかった大隈重信(政治家、侯爵)は、招かれて二度、桑なの諸戸邸を訪ねている。 《その低はさながら一城郭をなしているが、強盗を防ぐ方法として、見上げるばかりの高土塀の内側に濠を設け、それに河水を湛え、材木を漬けてあり、それが養魚場にも充ててある。その魚で、月に六回ずつ、奉公人に馳走するという趣向だ。(略)諸戸は我輩(大隈)を迎えるために、岐阜提灯を連ねて、火を入れてくれたが、それを吊るす時、下女が誤って蝋燭の火をその提灯に移らせて、一つを燃やしたら、諸戸が思わず声を立てて、「しまった、五十銭」と叫んだのがおかしかった。この一語に、諸戸の真情が流露している》(『大隈伯百話』) 大隈と清六の関係は深い。「紙幣と正貨の等価適用」の法が発令される直前、それを察知し巨利を博したという舞台裏に、こんな大隈の横顔がちらつく。 晩年、諸戸家の家法、家訓をつくることを思い立った清六は、全国の富豪たちの間を巡歴し、諸家の家憲を聞き、それらを下敷にして『諸戸清六遺言』を書き残している。 《(一)時間は金、忘れてはならぬ。 (二)顔をよくするより金を儲けよ、金儲かり家富まば自然と顔もよくなる。 (三)どこまでも銭のない顔をせよ、銭のある顔をせば贅費多し、たとえ銭なき顔をして人に笑われることあるも、後日には誉められる。 (四)派手にすべからず出来るだけ質素にせよ、衣服は垢の付かぬ木綿服にて充分なり。 (五)身代を減らさぬ考をするには平素交際する人を選べ。 (六)一銭の金を骨折って儲けよ、楽して儲けた金は落とし易し。 (七)無益の道具類は買うな、買えば他人に見せたくもなり、自然と自分の職業を怠り、時間を費す可し、慎まざる可からず。 (八)身代を減らす者は大抵、口先はよくて尻結びの無い、先の見込みの付かぬ者なり。 (九)多く人に会して多く知恵を得よ。 (十)馬鹿になれば悧口、悧口になれば又馬鹿、馬鹿になって物事を尋ね、馬鹿になって商売せよ。 (十一)できるだけ人の下風に立ちて、頭を下げる者は必ず勝を占む。 (十二)人と商売の話をなすもおのれの見込とする。所謂「キキメ」(ここ一番の決め手)一つは決して人に洩らす可からず。 (十三)二年先きの見留を付くべし、マグレ当にて儲けし金は、他人の金を預かったと同じことなり。 (十四)商取引をなすには先方の掛引を見分けるが肝腎なり、之ができぬ者は商売をするな。 (十五)身代を大きくしたいならば、丁稚下女の為る事まで?気を付けて差図せよ。小さい事に目を付けぬ者は到底大事はできぬ。》 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.38~44 2021.06.24記 |
|
浪華ノ大隠壮健 牝鶏晨に鳴く時はその家に禍あり((1,700年ころ) P.45~49 江戸期のサラリーマン武士の処世心得といったものに、大道寺友山(一六三九~一七三〇)の『武道初心集』がある。『葉隠』語録が《武士はいかに死すべきか》を書いたものとすれば、この『武道初心集』はサムライの新人たちに、現世を《いかに生くべきか》説いた書である。 ちょっとユニークな武士学入門書は、諸藩の武士たちの家庭に普及し愛読され、藩が消滅した後の明治末年ごろまで読まれていた。おどろいたことにこの本は海を越えて英国に渡り、イオギリス人A・K・サドラーの手によって翻訳され、武士道のテキストとして、 『The Beginner's Book of Bushido』 と題され、一九四一年に国際文化振興会から刊行されている。 この本で友山は、組織のなかに生きる新人のサムライたちのために筆を走らせ武士道を語り、微に入り細をうがって書きつづけていくのだが、家庭でのサムライの心得《妻に対して如何に対処するか》という条になってくると、にわかに語気を弱めて、溜息する。 怒りにまかせて女房を拳骨で殴りとばしたりするなど言語道断、夫たるもの《如何なる事あるも、ただただ堪忍せよ》と友山は説くう。 これを読んでいると、いまも昔も、女房族の手ごわさ、したたかさに手を焼いて途方にくれているサムライたちの表情が泛びあがってくる。 女といえば、わが女房のすさまじさに手を焼いた男たちの例が幾つかある。 戦国きっての暴れ大みょうの福島正則でさえも、浮気が発覚して正室(妻)から大薙刀で斬りつけられ、その形相の物凄さに仰天し、奥から家臣たちのいる表の間に逃げこんできて 「さてもさても、女の悋気したる勢いほど恐ろしきはなし、悪鬼羅刹とはこれなるべし」 と溜息したというが、猛妻たちの壮大な悋気の余韻はこの時期まだ残っている。 松江二十六万石の京極若狭守は、幼い頃から叔母(二代将軍秀忠の妻)の超ヤキモチぶりを見て恐妻ノイローゼになり、正室の目をおそれるあまり妾腹のわが子の出生を公儀に届けずひた匿しにし、国元でひっそりと育てていた。ところがある日、若狭守が急死したため《京極家、嗣子ナキヲ以テ封除、断絶》と、二十六万石を幕府に没収されてしまっている。 小倉藩の家老、長岡佐渡の妻おこまは、細川忠興とその妻ガラシア玉の娘だけに気が強い。が、このおこまの方の侍女に思いをかけた佐渡は、老女(女長官)を掻きくどいてようやく首尾をとげ、以来、なにくわぬ顔で逢う瀬を重ねていた。ふたりの密会がばれたのは、細川家伝来の天下の名香、白菊の伽羅からである。おこまの方は、侍女の衣服からかすかにただよっつてきた白菊の伽羅の移り香を感じて顔色をかえた。「おのれ!」と叫ぶなりおこまの方は、矢庭に侍女の髪毛を掴んでねじ伏せ、 「あな憎や!」 とばかり、手元の焼け火箸をとって侍女の胸を突き刺し、三度突き刺して殺してしまつた。 唐津八万三千石の大みょう、寺沢兵庫頭の場合も、あわれである。 兵庫頭の度重なる浮気に逆上して実家に帰ってしまった正室おせんの方におどろいた兵庫頭は、慌てて呼び戻すための使者を走らせたが、おせんの方は冷やかに、 「もはや、過ぎたる夢でありますゆえ」 と、素気ない言葉を返すばかりである。これを気に病んだ兵庫頭は、思いつめたあまり菩提寺に入って、切腹してしまった。 《正保四年十一月十八日、兵庫頭発狂シ浅草海禅寺ニ入リ自刃シテ封除セラル、三十九歳》 こうした"勇気凛々"の女房族の話ならザルに盛りあげるほどある。江戸時代の爛熟期、文化・文政の庶民の世界を覗いてみて 《今、軽キ裏店ノ者、ソノ日稼ギノ者ドモノ体ヲ見ルニ……》 と『世事見聞録』の筆者はいう。 以下、現代風に読みくだしてみると、 ――近ごろ、裏長屋に住む人びとの様子をみると、親は苦しいやりくりをしてその日その日を送っているのに娘の方は親たちにおかまいなく、べったりと化粧し晴れ着をきて男たちと遊び暮らし、女房のほうもまた娘に負けず、夫が働きに出かけた留守をさいわいに、隣近所の女房寄り集り、みなみな亭主の甲斐性のなさを言いちらし、花札など博打に興じ、あげくの果ては若い男を相手に酒を飲み、芝居見物や料理茶屋に出かけ、夕方疲れて帰ってきた亭主を顎の先でこきつかい、酔ざめの水を持ってこさせるなど、 《女房ハ主人ノ如ク、夫ハ下人ノ如クナリ、懈逅、密夫ナドノナキハ、ソノ貞実ヲ恩ニ着セ、ソレヲ崇ブリ、コレマタ兎角ニモ気随ワガ儘ヲナスナリ》 ――この時期、商家の女房たちの勁さも格別で、安永二年(一七七三)に刊行された商家の教科書ともいう『町家式目 分限玉の礎』の著者、浪華ノ大隠壮健翁は、 《妻は内(家庭)を守り、勝手廻り(台所)を能くするが身の役目なり、商いごときにつき談合せらるることありとも、智慧顔に善悪を分け、勝手不勝手いいなすは却って身代の妨げなり。牝鶏晨に鳴く時はその家に禍ありと深く戒しむなり》 と、世の亭主たちを代弁して"女房訓"に説う。 《家内を見廻り、(無駄な)費なきようにと守るべし》 《物妬み、中言(陰口・中傷)告口を慎しみ、物事意地悪く人に当るべからず》 《下女丁稚を使い者(使用人)と侮ることなかれ。別して心付(チップ)、それぞれに致すべし》 《仮にも男体したる者と囁き小話(などする事を)忌むべし》 《己が器量を鼻にかけ、不埒の所存あるべからず》 《夫の家、始め貧にして後栄えたりとも、高慢無用たるべし》 《夫の家、始宜しく後零落れたりとも悔るまじ》 《身代不相応の衣装、櫛、笄用ゆべからず》 《芝居見物、遊山等々度々出て、世間に顔見らるること慎むべし》 《……右の条々、女房たるもの朝夕忘れず嗜む者は、女夫喧嘩の物言なく家栄え子孫多く、女の鑑たるべし》 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.45~49 2021.06.15記 |
|
北条早雲 万民に対し、一言半句にても虚言申すべからず(1,456~1,519) P.50~54 桶狭間に出陣する信長が、「人間五十年……」と幸若(わか)の『敦盛(あつもり』を三度舞ったというのも五十を一生と考えてのことで、彼自身もまた四十九歳で戦火のなかに消え、越後の上杉謙信も四十九歳、甲斐の武田信玄は五十三歳で病没している。 が、伊勢新九朗長氏、のちに早雲庵宗瑞と名乗った早雲(かれ自身北条を称したことはない)の人生は、五十七歳から始まっている。早雲の人生の前半は謎に包まれた部分が多く、その出自についても諸説あって明白ではないのだが、早雲自筆の書状を信じるとすれば伊勢平氏の後裔、関氏の支族ということになる。 かれの妹が海道随一の守護大みょう、今川義忠の室となり寵愛をうけて北川殿とよばれ、義忠とのあいだに生まれた竜王丸が今川家の嗣子となったのをみると、早雲もまた、没落した名族の末流というのが妥当であろう。 後に早雲、妹の北川殿を頼って駿府(静岡県)に下向し、今川家の食客となる。 この居候早雲が世にでるきっかけとなったのは、今川家の内紛である。文明八年(一四七六)足利将軍義尚の命をうけた義忠は、遠江(静岡県)の斯波党討伐のため出陣するが、その帰途、土一揆に襲われて落命。 これが発端となって今川家は、四歳の嗣子竜王丸(のち氏親)派と、跡目を狙う一族の今川範満派に分れて、一触即発の危機に陥る。このとき早雲は、甥の竜王丸を扶け後見人としての策謀を傾け、 「危ういかな。いま、今川家が真二つに分れて争えば、近隣諸国の思う壺となりお家滅亡は必定」 と調停に乗りだし、範満を討って 紛争解決に奔走し、その功労によって長享二年(一四八八)氏親(竜王丸)から駿河、富士十三部を与えられ興国寺城(沼津市根小屋)の主となる。このとき早雲数えて五十七歳。 新九朗長早雲の人生の見事さは、老人にありがちな性急さを微塵も見せなかったことであろう。軍を起すにあたっても、諸事、無理押しをせず、五年でも十年でもたっぷりと時間をかけ(後述するが、そののち小田原城攻略、相模国平定まで三十年の歳月をかけている)周到な調査や根まわしをし、機が熟したとみるや疾風迅雷、一挙に事を決している。 《齢スデニ半百(五十)ヲ越エ》(『永享記』)た晩年からスタートした早雲には、若年の頃のようなやり直しがきかないのだ。一つの躓きは全生涯の失敗につながる。 興国寺城主になった早雲は、当時の武将たちが五公五民の年貢、ひどいところでは七公三民(税率七〇%)の酷税を課していたのを、 《年貢過分の故、百姓つか(疲)れ苦しみ餓死に及ぶ。以後(わが領分では)年貢四ッ(四〇%)収むべし》 と布告した。ながい放浪のうちに早雲は、百姓たちの最大の願いは、いかに喰えるか、いかに安楽に日々をおくることができるか、に尽きるということを知っていた。早雲の人心収攬の巧みさは、百姓の手に六〇%もの収穫を与えたほか、疫病に苦しむ領民には薬を、貧窮に喘ぐ民には銭を貸し与え、みどころのある者には、後にその貸銭を棒引きに」しtヴぇやったとである。こうした施策ぶりは早雲以前には見られない。 《此人(早雲)慈悲の心ふかくして百姓をあわれみ是によって百姓共「かく慈悲なる地頭殿にあいぬる物哉」とよろこび「此君の情には命の用にもたつべし。あわれ世に久しくさか(栄)えかし」と、心ざしをこばずという者なし》(『北条五代記』) こうした早雲の政治が爆発的な戦力に化るのは三年後、堀越公方を内紛に乗じて攻め滅ぼし、伊豆一国のあるじにのしあがった伊豆進攻の時である。早雲軍進発の報に百姓たちは、《累年の御あわれみを忘れがたし。御扶持人も我等も同意なり。地頭殿(早雲)を一国の主になし申さんこそ願いつれ。縦(たとえ)いのち捨るとも、露塵惜しからじ、はや立ち給え》 と口ぐちに叫んだという。 いっぽう、早雲軍が急襲した敵方の土豪や百姓たちも、かねてから早雲の善政にあこがれ、「われらが国も早雲殿の国にならばや」と、たちまち呼応し、堀越公方足利茶々丸は自刃。 日本史の区分によると、早雲進撃のこの延徳三年(一四九一)から「戦国時代」が始まる。 ともあれ、こののち早雲が小田原城乗っ取り、念願の相模国を平定し後北条五代の覇権の基を築きあげ、永正十六年(一五一九)八十八歳で老衰死するまで、現役として戦国街道を全力疾走する経緯は司馬遼太郎の歴史小説『箱根の坂』などの諸書によって、すでに世間周知のことであろう。 早雲は生命力の勁い男であった。白髪ではあったものの、逝去の日まで歯、目、耳から精神まで《サナガラ壮年ノ時ニカワラズ》(『鎌倉九朗後記』)であったというから、よほどの節制のもとに身を鍛え、いたわりつづけてきたのであろう。そんな早雲を越前の朝倉宗滴は、《伊豆の早雲は、針をも蔵に積むべきほどの蓄えつかまつり候つる。しかりといえども、武者辺(軍事費)に使うことは玉をも砕つびょうに見えたるに候》 早雲という男は、日頃は針のようなささやかな物まで蔵に仕舞い込むほどの倹約家だが、いざ合戦ともなれば貴重な宝石さえ惜しげもなく打ち砕くという思い切った使い方をする――と、早雲の細心さと果断な実行力を激賞している。 早雲は晩年、わが越し方をふり返って彼の人生観とも家訓ともいうべき日常の心得を『早雲寺殿廿一箇条』として側近の者に物語っている。 《朝はいかにもはやく起べし。遅く起れば召使小者まで油断し使われず、公私の用を欠くなり。果しては必ず主君にみかぎられ申すべしと、ふかくつつしむべし》 《少しの隙(暇)あらば、物の文字ある物を懐に入れ、常に人目を忍びて見るべし、寝てもさめても手馴れざれば、文字忘るるなり。書く事も同じ》 明日をも知れぬ乱世のなかで、懐中の書物を読みふける。それは、ひょっとすると若き日の早雲の姿であったのかもしれない。 《御通り(主君の前)にて物語抔する人の辺りに居るべからず。》傍へ寄るべし。況や我身(が乗りだし)雑談、虚笑抔しては上々(重役や上級者)は申すに及ばず、傍輩にも心ある人には、みかぎられ(見捨てられる)べく候也》 《正直を憲法にした上たるをば敬い下たるをばあわれみ、有るをば有るとし、無きを無きとし、有りのままなる心持、仏意冥慮にもかなうと見えたり》 この二十一箇条は、きわめて日常的な訓だが、苦労人の早雲だけに、含蓄のふかい言葉が多い。なかでも、 《上下万民に対し、一言半句にても虚言申すべからず。かりそめにも有のままたるべし。そらごと(虚言)を言いつくればくせになりてせせらるる(暴かれる)也。人に頓てみかぎらるべし》 の条は、可能なかぎり流血を回避し人命を失わず、家も焼かず田畑も荒らさぬ国盗りを念願した政治家早雲。かれの面目躍如たる一箇条である。血みどろで、酸鼻をきわめた信長流の国盗りだけが戦国のすべてではない。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.50~54 2021.05.31記 |
|
安田 善次郎 (1,838~1,921) 勤なると共に倹なれ、倹なると共に勤なれ P.55~59 明治の金融王と称われた勤倹堂主人こと安田善次郎(初代)が越中富山から江戸に出てきたのは安政元年(一八五四)十七歳の時であった。 武士とはなばかりの、軽輩微禄の貧苦をきわめた家に育った善次郎は、幼い頃から商人にあこがれていた 「この世の中で」 と、おさない善次郎は思う。 「サムライより強いものは金じや」 こうして、商人として身を立てようと決心した善次郎は、三つのことを心に誓っている。 一、能力を頼まず独立で商人として身をたてること。 一、虚言をいわぬこと。 一、収入の八割をもって生活し、その他は貯蓄すること。 江戸での善次郎は、両替商に奉公し、銭両替に必要な知識を学んだ。こののち善次郎は、(玩具店に四年、海苔屋に三年奉公した後、日本橋の小舟町に一家を構えて、海苔と鰹節との小売を始めた。それは二十五歳のことだった) と、後年、善次郎と親交のあった陸軍軍医総監、子爵の石黒忠悳は『吾輩の見た安田と大倉』(『実業之世界』明治四十一年)のなかで語っている。 《その時、安田君は考えた。商売を繁盛させるには、近所の評判からよくしてかからねばならぬ。といって贈物をするには金がかかる。それではと毎朝、五時に起きるところを四時に起きて、両隣の店先を掃除して、水を撒いて置くことを続けた。それで(両隣の店では)一体誰が掃除してくれるのか、近頃引っ越してきた海苔屋さんだ、と評判が次第に高くなった。これらの親切な遣り方が、安田式ともいうべきもので、今日までそれを貫いている。その一方では元方(帳簿)の勘定を正確にして、品物を安く仕入れて客に売る。それでお客は芝あたりからも来るようになって、店は次第に繁盛した。これが現今資産数千万円と称せられる富豪安田の初めである》 が、一説では、このとき善次郎は店の方は一切妻の房子にまかせ、自分は大きな袋を肩に、毎朝《風呂屋を廻って風呂屋の穴銭(小銭)を大銭に両替して》歩いていたという。 ともあれ、機を見るに敏な善次郎は幕末、維新の混乱に乗じ明治新政府の極秘情報を掴んで太政官札を買占め、一日で三倍もの利益を得るという濡れ手で粟の大儲けをしている。 その善次郎が次に目をつけたのは、廃藩によって禄高に応じて新政府から与えられた、一種の失業手当、秩禄公債である。公債の償還期限は十五年だが、生活苦に喘ぐ士族たちはそれを安く叩き売り、換金を急いでいた。善次郎はそれを手当りしだいに買い集め、公債を担保にして、借りた金は高利で貸し、利を稼ぎに稼いだ。 やがて二万円という大金をつかんだ善次郎は、これをスプリング・ボードとして明治七年(一八七四)、新政府の官金御用達ともいう司法省為替方にのしあがり、自己資金三万九千余円に加えて、自己の判断で無利子の官金を、三十万円の枠内で使える特権を得た。 余談になるが当時の四等巡査の月給六円、小学校長の古参で十五円。新政府高官のサラリーは、東京府知事が二百円、太政大臣の三条実美、右大臣の岩倉具視で八百円、内務卿の大久保利通は千円といった時代である。 こうして勢いに乗じた善次郎は、明治九年、第三国立銀行、十三年、安田銀行を設立。彼の勢力の下に集まったのは明治商業銀行、金城貯蓄銀行、百三十銀行、日本商業銀行、京都銀行。そのほか二十二銀行、十七銀行、肥後銀行、九十八銀行、高知銀行、根室銀行、信濃銀行、群馬銀行、山形銀行……と、続々と彼の傘下に加わり善次郎は金愉界の最高実力者として"富"への階段を駈けのぼっていく。 立志伝中の人となった後も善次郎は初心を忘れることなく、ある人から、<どうすれば、そんなに成功できるのでしょうか>と訊かれたとき、善次郎は、 「儂はただ、若い時から"勤倹貯蓄"を実行しただけ」 と応え、勤倹貯蓄などといえば、ただ倹約して貯金するだけのように思うであろうが、そうではない。 《勤倹とは勤勉にして節倹を守るの意にして換言すれば「業務を勉強し、冗費を節する」の謂なり、即ち勤は積極的の語にして進取を意味し、倹は消極的にして保守を意味す。故に両者相俟って始めて其効著るし、余は諸子に教えん、勤なると共に倹なれ、倹なると共に勤なれ。 夫れ易きを好み、難きを避くるは人の常情なり、勤倹は美徳なりと雖も、其の実行に至っては頗る至難の業に属す。茲に於てか意志の強固即ち克己心の養成を最も肝要とす。余は日常目撃する処に依り、意志薄弱の徒が常に失敗の悲況に陥るの例証を挙げ、克己心の必要する反証とせん》 そう言って善次郎は、『安田善次郎家訓』のなかで、彼が説く勤倹貯蓄談の実行の困難なことを語り、意志薄弱な者が失敗する例を一つひとつ揚げていく。 《第一、意志の弱き人は……》 なにごとにつけても気が移りやすく、衣服なども流行を追って外見ばかりを飾る。こうした表面だけの欲望にとらわれる人間は出費がかさみ、ついには先祖伝来の財産まで減らしてしまう、貯蓄などとんでもない話である。 《第二、意志の弱き人は》 深い思慮もなく友人知己の保証人などになって、自分から災難を求めることがある。一時の人情にかられて自分の利害を考えない人に、なんで勤倹貯蓄ができようか。 《第三、意志の弱き人は》 商売上の取引などをするにも、いつも人の後になって、いわゆるヒケをとる(負ける・おくれを取る)。こうした人は情実にこだわり、つねに搊失をまねくものだ。 《第四、意志の弱き人は》 困難な事や紛糾した事件などに直面すると、たちまち弱音を吐いたり、これを避けようとして、なにごとも成し遂げることができない。こんな人物は結局、発憤して事に当ろうとする覇気がないので、向上することなど出来る筈はない。 《第五、意志の弱き人は》 その行動がいつも不規律で、精神が活発でない。こんなことで勤倹貯蓄ができる筈はない。《要するに勤倹貯蓄実行の骨髄は自己の情欲を抑制し、己に克つことに在り、斯くも勤倹貯蓄を遂行するは、人生の必要事項として、又成功の一手段なり》 善次郎はこの自家訓を実行するだけでなく、他人にもそれを奨励した。また毎年二季、従業員たちのボーナスを渡す時に、その袋の中に貯蓄を勧める善次郎の文章が入れてあった。その字句がまた懇切で、こうしてトップから勧められると、従業員たちもついボーナスを銀行預金してしまうということになる。で、 「安田銀行は賞与金に百万円支出しても、それはみな預金として入ってくることになるし、従業員のほうも自然に金が積みたてられて、後には皆々、その社長の好意を徳とした」と、市島謙吉の『春城代酔録』にいう。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.55~59 2021.06.16記。 |
10 浜口梧陵
|
浜口梧陵 財は末なり、信は本なり、本末を明らかにすべし(1,820~1,885年) P.60~64 安政元年(一八五四)十一月五日七ツ刻(午後四時ごろ)はげしい地震があった。海上で大音響がしたと思うと地面が波だつように揺れ、瓦が吹っ飛び家屋が倒壊し土塀が崩れ、天に舞いあがる土けむりのなかで地獄絵図が展開した。 世にいう安政の大地震である。 南海道沖を震源地とするこの地震は、後年の史料によるとマグニチュード八・四。関東大震災の七・九よりはるかに強烈なものであった。 その激しい揺り返しに、悲鳴をあげて逃げまどう広村(和歌山県有田郡広川町)の人びとの混乱の中で浜口儀兵衛(七代目)は、海をみた。 と、その眼のなかに、くろぐろと底をみせて沖に退いていく海水がみえ、その海水が、はるか沖合に長い堤のようにぶ気味に盛りあがっていくのが見えた。 「津波だ……津波がくるぞ」 儀兵衛は叫んだ。 が、その声も、ごぼう色の夕闇の中に散乱する瓦礫に気をとられ、逃げ場を失って右往左往する村びとたちの耳には届かないようであった。 しかし、猶予はならない。儀兵衛は声を叫げて番頭の茂兵衛や下男たちを呼ぶと、火をつけたタイマツを持たせ高台につづく田圃への径を駈け走らせた。 そこには、もう獲りいれられるばかりになった、浜口家の財産というべき数百数千の稲束が架けられていた。儀兵衛に命じられた番頭や下男たちは、その稲束の群に火を放け火を放け、稲束を焼きながら高台にむかって走った。浜風にあおられて燃えあがった火は、昏れがたの空を焦がし炎焔と燃えあがった。 「大旦那の稲塚が燃えちょる!」 消火に駆けつけた村じゅうの若者や老人や、女や子供たちは息を喘がせ高台への径を走りのぼった瞬間、地軸をゆるがすばかりの轟音と共に、夜の海に一抱えほどの火柱が立つのを見て戦慄した。 稲束を焼いて村びとを大つなみから救った儀兵衛の行為は、日本に帰化したギリシャ生まれの英人、ラフカディオ・ㇵーン(小泉八雲)を感動させた。ハーンはそれを『生ける神』として著述し、その作品は海外に紹介されて感動の波紋をひろげた。戦前、小学校教科書に掲載されていた『稲むらの火』の話は、ハーンの原作を逆輸入して日本語に訳したものである。 ㇵ―ンの書いたこの『生ける神』について、エピソードがある。英国に留学していた儀兵衛の末子、浜口擔(のち衆議院議員)が一夜、ロンドンの日本協会で講演をした。 そのあと、ステラというイギリス夫人が立って「いま講演したㇵマグチは、ハーンの書いた『仏田の落穂拾い』の中にある"生ける神"のあの偉大なㇵマグチと同じなだが、なにか関係あるのでしょうか」と司会のアーサーに訊ねた。アーサーが、「いかにも、このㇵマグチこそ彼の実子である」というと会場は、一瞬、声にならない感動でどよめき、次の瞬間、割れるような拍手と歓声が湧きあがり、しばらく鳴りやまなかったという。 浜口儀兵衛。文政三年(一八二〇)、紀伊半島の中央部にあたる有田郡広村に生れる。儀兵衛は通称で名を成則、号は梧陵。浜口家は代々湯浅醤油の醸造元で、元禄年間海を越えて下総・外川(銚子市)に進出したほどの豪商であった。 醤油といえば七百四十年前の建長元年(一二四九)、源実朝の菩提をとむらうため宋(中国)に渡った覚心(紀州興国寺開山)が径山興聖万寿寺の典座寮(台所)で味噌の醸造を会得して帰国し、興国寺隣郷の湯浅の地で《径山寺味噌ヲ醸造セルニ其ノ槽底ニ沈殿セル液ノ食物ヲ煮ルニ滴セルヲ発見シ、種々工夫ノ末、終ニ醤油ナル物ヲ醸造スルニ至ル。是ㇾ日本醤油ノ起源ナリ》(『湯浅醤油発祥記』)と伝えられる。 その醤油を天文四年(一五三五)大坂に輸送販売したのを皮切りに、江戸期に入ると販路は更に拡がり、紀州徳川家の御仕入醤油として特別の庇護をうけ、浜口家はじめ湯浅醤油醸造業者たちの関東進出がはじまる。 こうして紀州藩御用船同様の特権を与えられ、気候、原料、水と三拍子そろった銚子に工場(ヤマサ醤油、ヒゲタ醤油の前身)を建て、江戸日本橋に店をかまえた浜口家の醤油は、世界最大の消費都市江戸にむかって陸続と運ばれていく。 が、山に高低があり海に干満があるように、豪商と称われた家にも盛衰がある。六代目のとき事業に失敗し、家運大いに衰えていたのを嘉永六年(一八五三)七代目儀兵衛を襲名した成則(梧陵)は寝食を忘れて家業に精励し奔走し、やがて一族から浜口家中興の祖と仰がれるほどに挽回している。この浜口家に、家職を守るための二十二ヵ条が遺されている。その中から幾つか抜きだしてみると、 《祖先の勤労を常に心に銘ぜよ》 《財は末なり、信は本なり、本末を明らかにすべし》 《綿服咬菜。家富むと雖も綿服粗食、質素を旨とし、主従均食、共労。家族、雇人に至るまで同様の食事を為し、共に働くべし》 《雇人を持つ(扱う)に家族(同様)を以ってし、主人と雖も奉公人同様に心掛くべし》 《奉公人にも商売上の利潤を分ち、その労に酬ゆべし》 《春帰秋行。毎年、春を待って帰り、秋に至り江戸に赴くべし》 当主は、仕事の暇な春を待って帰郷し祖先を祀り、寒仕込みの準備のため忙しくなって秋から江戸に引きあげてくること。 《国許に帰りたる時は(当主としてではなく)客分の待遇を受くべき事》 《妻を娶るには必娶於卑、必ず卑き者よりせよ》 妻の実家は浜口家より財産、地位など、より下位であることを守ること。これは質素勤勉の家風をまもるためである。 《(当主たる者)徒手飽食して家産を受くるを許さざる事》 《自ら忍びて時の至を待ち、かまえて訴訟を起す勿れ》 他と紛争がが起こっても短慮な振舞いをしてはならぬ。よくよく我慢をして相手の理解を待て。訴訟沙汰に勝つても得るところは何ひとない。 《進んで田畑購うとも、退いて(金策に困って)所有の土地を売却する勿れ》 《同族間の縁組(結婚)は厳禁すべし》 《同族相救うに就いては深くその原因を糾明し区別するところあるべし》 同族血縁の情にひかされて家業の運営を誤ってはならぬ。 《家督相続ならびに分家は軽忽にすべからず》 余程の理由のない限り、当主の都合だけで隠居することは許さない。本家、分家を嗣いだ以上、力の限り働きぬくのが歴代当主の務めである。七代儀兵衛の後、家督を嗣いで八代儀兵衛が登場するのは、還暦をむかえた六十一歳のときだ。 ともあれ、七代目儀兵衛、江戸では勤王の志を抱いて洋学者、佐久間象山に師事し、勝海舟、福沢諭吉と親交をかさぬ開国論を主張。明治元年、和歌山藩勘定奉行、学習館知事、明治政府の駅逓頭(通信大臣)となる。 明治十七年(一八八四)、海外巡礼の途中、ニューヨークにて客死。六十七歳。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.60~64 2021.06.05記 |
百戦百勝も一忍にしかず
11 大道寺友山
|
大道寺友山 一服の茶を啜るに付いても、其さま拙からざる様に(1,639~1,730年) P.66~70 元禄という世は、町人の時代であった。諸国で城下町の建設がおわり、都市に人口が集中し、貨幣価値が浸透して商品の流通にたずさわる町人たちの生活は急上昇し、いっぽう、関ケ原からすでに百年、サラリーマン化した武士は、泰平のなかで禄を貰って寝て暮らすだけの遊民になってしまい、役所に出ても、 《我も人も畳の上の奉公斗にて》 《畳の上を這いまわり、互いに手の甲をさすり舌先三寸の勝負をあらそうのみの善悪にて、身命をかけての働きとては之無き事に候》 という時代であった。 そんな、息のつまりそうな役所の中で、ときには古参たちの憂さばらしとして、陰湿な、後輩や新参者いびりがはじまる。わざと事務を複雑にしてみたり、書類の不備を言いたて突き返したり、御番入りの振舞(初出仕の挨拶)と称って高価な御馳走をおごらせてみたりなど、さまざまな嫌がらをしている。 こうした風潮のなかで、泰平の世のサムライの心得、"期待される武士像"として兵学(軍事学)者、大道寺友山によって描かれたユニークな武士学入門書に、『武道初心集』がある。 友山のこのサムライ訓五十六条は、のちに信州松代藩十万石真田家の国家老、恩田公準によって四十四条に削られ、天保五年(一八三四)江戸の書店、和泉屋吉兵衛によって松代版『武道初心集』上中下三巻として刊行されている。 余談になるが、この恩田は松代藩の財政再建と『日暮硯』の著で高名な恩田木工の曾孫である。 仮名まじりの平易な文章でつづられた『武道初心集』は、一世紀ちかい人の生を通りすぎてきた老兵学者が、泰平無事の世にスタートする武家の子弟たちにむけた温かい眼差しが感じられる本である。 この中で友山は、組織の中に生きるための心がまえ、行住坐臥、言語対応など当世の武士としての処世の法を語りおえたあと、その項の末尾を必ず《初心の武士心得のため、よって件のごとし》という言葉で結んでいる。 「にんげんというものは」 友山はそう説う。 「誰もが"死"という存在を忘れて、この世に何日までも逗留するつもりで油断しておるゆえ、赤目を吊りあげて他人と争い、欲心も深くなり、人の物と見れば欲しくなり、わが物を惜しみ、欲しき惜しきの穢き根性が湧いてくるのじゃ」 ゆらい武士というは、正月元旦の朝、雑煮を祝って箸をとる瞬間から、大晦日の除夜の鐘が鳴るまで、日夜常に心に"死" を思い抱き、 《朝夕、手足を洗い、湯風呂にも入って身を潔く持なし、毎朝髪を結い、(略)時節に応じたる衣服を着し、(略)尊卑に随いて相当の礼儀を尽し、無益の言語を慎しみ、たとえ一椀の飯、一ぷくの茶を啜るに付ても、其さま拙からざる様にと油断なく是をたしなむ》 という心がけが大事である。人間のあさましさは、その"死"を忘れるからこそ、 《つねに大酒、淫欲等の不養生を致し脾腎の煩(内臓の病気)をしでかし、思いの外なる若死を致し候》 そして、また友山は「択友」のくだりで、 「奉公する武士にとって最も必要なのは、心をゆるせる友」 だという。多くの同僚の中から、勇気すぐれ道理を重んじ思慮ふかく、言うべき時にわが意見をはっきりと述べる、そのような朋輩とは日頃から親しく深いまじわりを結んでおくことだ。こうした友が一人でもおれば、いざというときに強い味方になる。 「にんげん関係のなかで用心すべきはお互いの"弱さ"で結びつくことである」 酒や博打や遊びの仲間なら、すぐに何人でもできる。小唄や浄瑠璃を唸って、だらだら遊びで夜明かし、それでいて、「儂が、お前が」と心をゆるしあった仲だというが、そんなものは友人でも何でもない。ちょっとした言葉の行き違いで口論し、もはや絶交! などと怒鳴りあうような友人なら、 《貌は武士にても、心は夫人足(労務に駆りだされた人足)に等しい》 武士が生涯の交わりを結ぶ友、生死をともにする友人を得るためには、ながい歳月にわたって互いの心を見届けあうことが必要なのである。 また、勤務についても、この先、いつ迄も勤められると思い、その歳月のながさに退屈し、心もゆるみ、目の前の仕事にしても、「なあに、それは明日にしよう、これは次にまわしておこう」と、投げやりな仕事ぶりで、あげくの果てには、その仕事も同僚間で、 《彼方へはね此方へぬり(あちらにまわし、こちらへ押しつけ)誰一人身に引懸け(責任をもって)世話のやき手もなければ、諸事いやが上にかさなり(仕事が山積し)つかえて、不埒(不都合)なる事に成行候》 というのも、厄介なことはすべて翌日、翌月、翌年と、行く先の歳月を頼みにするからである。 役所への出勤にしてもそうだ。いつもぐずぐず出そびれ、 《(まず)茶を一服、煙草を一服と申て、ふよつき(ぶらつき)女房や子供と一口ずつの雑談に時を移して、宿(業)を遅く出ては俄かに狼狽、大汗を流して番所へ駈付、寒中にも扇をつかいながら、ちと叶わざる(のっぴきならぬ)用事にて遅く罷出候などと、利口(いいわけ)がましく申すなどは、うつけ(まぬけ)たる事と申すべく候》 こうした友山の教訓は、平成に生きる私たちにも立派に通用するのだが、友山の『武道初心集』が刊行された後、さらに世俗的な処世心得で懇切丁寧、噛んでふくめるように詠みぶりの『番衆(勤番者)狂歌』が登場してくる。「わが当節の武士にとっては、仕事よりも何よりまず人間関係が大事である」 《近辺の相番(同僚)または古番(古参者)へはつねに親しく付届(贈物)せよ》 《頭衆へ見舞(挨拶と贈物)は月に一度なり寒暑、非常の見舞は(この)外なり》 《番頭、組頭、または伴頭の子ども(や)親類(にも)近づいていよ》 上役に逆らわず、勤番先では次の言葉だけ使っておれば、わが身は安泰である。そこで、 《世の中は諸事ご尤もありがたい御前ご機嫌さて恐れいる》 《手れん(人あしらいの方法)とは左様でござるご尤も御意(仰せ)の通りおめでたい事》 先ごろ、不肖の息子のため大学へ裏口入学をはかって発覚、マスコミを騒がせたタレントがいたが、今も昔も親馬鹿ぶりは渝らない。 《近年は惣領どもの御番入り、親がかわって願書出すなり》 とはいえ長男はまだいい。二男三男の厄介人が部屋住のまま老いて、なお養子先を求めている姿は悲惨である。 《部屋住も五十(歳)以上に至りては(藩庁へ)養子願の伺いをせよ》 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.66~70 2021.06.04記 |
12 山本五十六
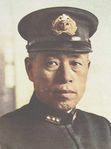
山本五十六 百戦百勝も一忍にしかず(1,884~1,943年) P.71~76 連合艦隊司令長官、山本五十六は、男くさい魅力をもったリーダ~である。渾身、気魄に満ちた五十六は、その強烈な個性のゆえに感情の振幅も大きい。 激情の人であり、ときには情愛の人といわれ、茶目っ気もあった。身長百六十センチメートル足らずで躯幹短小、目の玉も躰もきびきびとよく働いた。その五十六が、海軍省の正面階段を大股で、どんどん駆け上っていく姿はまるで堀部安兵衛が高田の馬場へ走りこんでいくような風情であったという。
五十六の家系は、雪深い越後長岡藩四千石牧野家に仕える槍術指南役、儒者として百二十石を食んでいる。その長岡藩に、藩祖牧野忠成(ただなり)が家臣に示した『参州牛久保の壁書』という十七条の蕃訓がある。侍の恥辱というのは、戦場でおくれをとることでだけではなく、その他にも数々あると、忠成は説(いう)。 《第一 虚言又は人の中を悪(あ)しく言いなす事。 第二 頭をは(殴)られても、はりても恥辱の事。 第三 座敷にても路地にても慮外(ぶしつけな振舞)の事。 第四 親兄弟の敵をねらわざる事。 第五 堪忍すべき儀を堪忍せず、堪忍すまじき儀を堪忍する事。 ……(以下、略)……》 父祖たちの出自の地、三河国牛久保での草創の頃の苦しさを忘れるな、という藩祖の言葉を、三百年近く愚直に守りつづけてきた藩士の骨の硬さは、越後長岡の地に住みながら、遠い故郷の三河言葉を使いつづけてきたことをみてもわかる。 幕末の風雲のなかで長岡藩は、越後長岡独立、武装中立《を叫び、黒つなみのように殺到した北陸道鎮撫軍を迎撃。長岡藩軍事総督、河合継之助の下知をうけた五十六の祖父、高野秀右衛門は火縄銃六挺を交互に使って群がり寄せる敵十数人を射殺し、弾丸がつきると敵中に斬込み闘死。父の高野貞吉も銃士隊小隊長として転戦、会津若松城で負傷している。 が、長岡戦争は敗北し、河合継之助戦死のあとを守って長岡藩の総司令官になった二十三歳の若き家老、山本帯刀は降伏勧告を拒んで斬首、山本家は廃絶。明治新政府の「逆賊」河合、山本家への処断は苛烈である。朝敵の汚名が両家から消えるのは、五十六が生まれた明治十七年(一八八四)であった。そして、罪名消滅した山本家を、旧藩主牧野忠篤から望まれて五十六が相続するのは、そのまた遥か後年の大正五年(一九一六)、五十六が海軍少佐のころであった。 五十六はその相続の日を五月十九日、長岡落城の痛恨の日に決めたのも、無念の思いを罩(こ)めたのであろう、この頃から五十六は、無法な官軍を相手に六砲口に三百六十発元込め式連射機関銃ガトリングガン三門をぶつ放し、死闘を展開した河合継之助に、はげしく心を傾斜させている。継之助が、 《一忍以支百勇(一忍をもって百勇を支うべし)》 と、よく書いたのに倣(なら)って五十六も 《百戦百勝上如一忍(百戦百勝も一忍しかず)》 と書いたという。 海軍兵学校に入ったとき教官から、お前の信念は、と訊かれた五十六は、 「痩我慢であります」 と応(こた)えている。十八歳のこの五十六の横顔から、苦汁に満ちた「長岡魂」が泛(うか)びあがってくる。作家の山本周五郎が、その作品の中で「自分の傷が痛いから、おれは人の傷の痛さがわかるんだ」といっているが、五十六の身辺には、そうした心の翳(かげ)りがみえる。嬉しいにつけ悲しいにつけ、五十六はよく泣いた。にんげんとしての情が、常人よりもはるかに多量であったのであろう。 五十六が部下に接したとき、喜びをわかちあう場合よりも、悲しみを噛みしめた時のほうに彼の真面目が光を放っている。丹精し手塩にかけて育て上げた海鷲のエース、白相(しらそう)が飛行機事故のために死んだという知らせをうけたとき、五十六は海軍省詰めの記者たちと歓談していた。と、その瞬間五十六は、にわかに大粒の涙をこぼし、手放しで涙を流し、あまりの嘆きに怺(こら)えかね、部厚い唇を結んだまま、涙をしたたらせながら無言で部屋を出ていったという。 また、白相らと三羽烏とうたわれていた南郷少佐の戦死を弔うため、南郷の父を訪ねた五十六は、悔みを述べているうちにこみあげてくる悲しみに堪えなくなり、声をあげて泣き、さらに悲しみをつのらせて号泣し、随従の者に助けられて南郷家を辞去するという有様であった。 五十六の部下への愛情を伝えるエピソードに、こういうのがある。"赤城"の艦長時代、波荒い飛行甲板に着艦しようとした一機が、目測を誤った。このままでは海中に転落すると思った瞬間、五十六は駆け寄り、その尾翼にしがみついた。が、それくらいで止まる筈はない。「あっ、艦長が!」。叫びをあげて士官や下士官、兵たちは主翼や尾翼に縋りつき転落寸前の飛行機を引き止めた。「山本長官の部下思いは、単なる人情ではなく命がけの迫力を感じました」と、部下であった山口多聞(たもん)中将は語るが、多くの将兵が五十六を「ウチの長官」と称(よ)んで慕ったのは、こういうことからであろう。 もちろん、連合艦隊司令長官としてのリーダーシップを構成しているのはこうした"情"ばかりではない。強烈な行動力、勝負師としての度胸と決断力。大艦主義の海軍のなかで、誰よりも早く、「航空主力、戦艦無用論」を唱え、飛行機による艦船攻撃の優位性を説いた。それも精鋭主義よりも、 「艦船攻撃は絶対に量だね」 と主張しつづけた五十六の先見性。鬱屈したときなど、ずしりと重い特製の竹刀を掴んで道場に出、越後人特有のせかせかした動きで全身から精気を噴射するよに飛び込み、火をふくような斬撃をくり返している五十六。そんな気魄に将兵たちは魅(ひ)かれていたのであろう。 その五十六の趣味にギャンブルがある。無類の勝負好きの五十六は、暇さえあればルーレット、トランプ、花札、玉突き、麻雀(マージャン)と、あらゆる賭けごとに挑んでいる。これくらいギャンブル好きな男も珍しかった。かつて欧米視察の旅の途中、モナコに立寄った五十六は目の色をかえてカジノで遊び、連戦連勝、勝ちに勝ちまくり、あまりの勝負運の強さに、「カジノへの入場を拒否された"世界で二人目の男"の記録をつくった」 という風評(うわさ)がたった。その噂が五十六の生涯の自慢であった。 「若い士官はブリッジ(トランプ)をやれ、賭けごとに打ち込むと、先が見えるようになる」 そう言って五十六は、つねに「勝負ごとの三徳」を若い士官たちに語っている。 一 賭けごとは勝敗の有無にかかわらず、冷静にモノを判断する修練ができる。 一 機を狙って相手を撃破する修練ができる。 一 大胆にして細心、その習慣を身につけることができる。 「但し、私欲をはさんではいかぬ。熱中してはいかぬ。冷静に局面を観察していれば、かならず勝つ機会がわかる。それを辛抱して待つのだ」 疾風迅雷ともいわれる山本作戦の起爆薬になり、その行動の炸薬(さくやく)になったのは、こうした五十六独特のギャンブル哲学であったのかもしれない。 神坂次郎『男このことば』(新潮文庫)P.71~76より。 参考1:小林虎三郎 参考2:第26、27代連合艦隊司令長官。海軍兵学校32期生。最終階級は元帥海軍大将。栄典は正三位大勲位功一級。1943年に前線視察の際、ブーゲンビル島上空で戦死。旧姓は高野。 戦死された時、私は中学4年生であった。全国民が悲しみに包まれていた記憶が鮮明に残っている。 2020.10.10記す。 |
13 真田幸村
|
真田幸村 われに挑む一人の男もなきか(1,567~1,615年) P.77~81 戦国騒乱の世というのは、生ぬるい根性では生きられる時代ではなかった。慶長五年(一六〇〇)天下分け目の関ケ原合戦に真田家は"家"を保つため真っ二つに分かれ、幸村は父の昌幸と共に西軍、石田三成に加担、兄の信之は東軍、徳川家康に属して、親子兄弟が袂を分かって戦いにのぞんだ。 が、関ケ原で西軍が壊滅し、戦後、昌幸、幸村父子は罪を得て紀州高野山の久度山に配流の身となる。そして、天下に比類のない軍略で秀吉の舌を巻かせ家康に二度までも苦汁をなめさせ、徳川軍を翻弄した謀將、昌村も、十一年後の慶長十六年(一六一一)、失意のうちに久度山で死ぬ。 以来、幸村は妻子やわずかな家臣とともに更に三年の歳月をこの地で過ごすことになる。久度山での幸村の暮しは困窮をきわめたものであった。 現在も真田家の菩提寺、高野山蓮華定院に残る無心状のなかで幸村は、 「その後ごぶさたを致しております。さて、(使いの者に持たせた)この壺に焼酎をお詰めくだされ。一杯詰めてこぼれぬよう壺の口をしっかり目張りしてくだされ。壺二つに焼酎の件よろしく願いまする」 と、酒を愛した貧しい日々を語り、また、老いのしのびよる身の歎きを姉婿の小山田壹岐守に、しみじみと書き連ねている。 《とかくとかく年のより申し候こと、口惜しく候。我らなどもにわかに年より、殊の外、病者になり申し候。歯なども抜け申し候。ひげなどもくろきはあまりこれなく候》 この手紙からは、テレビや映画などでよく見る、百万の兵馬をひきいて天下を切り取りかねまじき風貌をした印象とはうらはらな、歯がぬけ髭も白くなり、病がちな小男といった幸村の表情が泛びあがってくる。これが現実の幸村であった。現実といえば、幸村は柔和で心やさしい人物であったと、兄の信之の追懐の言葉にある。 九度山での不遇の時代の幸村の見事さは、終始柔和で、わが身を腐らせなかったことであろう。逆境にあっても落ちこまず、心を荒ませず、つねに自然体で、世を拗ねていないことだ。 こうして慶長十九年(一六一四)十月、久度山で朽ち果てるのかと半ば諦めていた人生の涯の、四十八歳の幸村の前に、大坂入城を勧める豊臣家からの使者がやってくる。 「行こうぞ、大坂へ」 決断した瞬間から、幸村は豹変する。 大坂に入城し五千の軍兵を預けられた幸村は、将兵の軍装を燃えたつような赤一色に統一した。風になびかせた真田の旗はもとより、のぼり差物から甲冑にいたるまで、ことごとく真っ赤に染めあげた真田隊の、赤備えの派手やかさは敵味方の目をひいた。 《真田左衛門(幸村)赤のぼりを立て一色赤装束にて》(『山口休庵咄』) 《真田が赤備え、躑躅の花の咲きたるが如く……》(『武徳編年集成』) 赤という色は人の心を昂奮させる色であり、戦場にのぞんだ将兵たちを奮いたたせる色でもあった。幸村自身も、緋おどしの鎧に鹿の角の前立うった兜をかぶり、金覆輪の鞍に紅の厚総をかけた馬上にある。幸村は、こうした演出を心得た男である。心にくいばかりに敵味方の戦場心理を読みぬいた男である。真っ赤な火の玉に化って突撃してくる真田隊の凄絶さに恐怖した徳川軍は、もろくも四散し敗走する。 こうした演出ぶりは、現代にも通用する。人びとの心を目的にむかって直進させるために、軍隊での軍服、工場での制服のような工夫も必要なのである。すぐれたリーダーとしての資格は、いかに部下たちをおのれの統率のもとに魅き込むか、集団催眠をかけられるかであろう。戦闘指揮官としての幸村は、こうした器量を完璧なまでに備えたリーダーであった。それなればこそ真田隊は精強であり、はるかに巨大な相手に挑み、撃破するという奇襲戦法も可能であったのだ。 にんげん幸村の魅力を語るエピソードの一つに、大坂入城の供をした高野山の庄官(庄屋)の地侍ら百五十四人の男たちがある。久度山幽居十五年のあいだ、幸村の人となりに接した男たちが吸い寄せられるように集まってきたのである。 そして彼らは、この風采のあがらない小柄の老人に嬉々として奮迅し、全員燃えたつ火の玉となって雲霞のような徳川軍団に突撃すること数度、幸村討死の後も、その場を去らずことごとく死んでいくのである。この中には、高野山の奥から鉄砲を肩にやってきた猟師たち三十余名もいる。主将が討死した場合、将兵たちは戦場から落ちのびていくのが戦国の世の常であって、全員戦史というのは異例のことだ。 《真田日本一の兵、いにしえよりの物語にも(これほどの精兵は)これなき由、惣別(東軍の陣中で)これのみ申す事に候》と島津(家久であろう)が国元へ送った手紙の中にある。 そして戦場での幸村は、こうした部下からの信頼に見事に応えて 翌、元和元年(一六一五)夏ノ陣の河内での激戦で伊達正宗軍を撃破し悩ませていた幸村は、大坂城へ引きあげるとき、群がりたつ東軍にむかって、 《関頭軍勢百万も候え、武士は一人もなく候》 と大声で罵倒し、悠々と引きあげていった(大坂陣『北川覚書』)。 このときの幸村の、あまりに不敵な、惚れ惚れするような勇将ぶりは、味方でもある大坂方の武将たちも妬んだほどであったというから、幸村に従う将兵たちは心ふるへるほどの感動をおぼえたにちがいない。もちろん、これは幸村得意の演出だが、こうしたことは理屈ではない。部下を心服させ、よろこんで死地に赴かせるための指揮官として、よほどの器量、人間的魅力がなくては愜わぬ芸であろう。 戦闘指揮官幸村のすばらしさは、機略縦横の作戦ぶりはもとより、死ぬための戦いでしかなかった夏ノ陣の悪戦苦闘の中にあっても悲愴感さえ泛べていなかったことであろう。肩ひじを張ったり、まなじりを吊りあげたりすることなく自然体で、それどころか最後の突撃に入る前日など、どこで死んだら一番分がよいか、家康殿の様子をちょっと眺めてみましょうわいなどと、茶臼山の丘にのぼり、家康本陣を観察したりして、将兵たちを微笑わせている。リーダーとしての幸村の、こうしたモノに動じない腰のすわりと余裕が、真田隊の志氣を掻き立て結束をより強いものにしたことは慥かである。 世に人使いの名手というのがある。傍にいるだけで、それだけでもう胸が熱くなり、芳醇な酒のように人の心を酩酊させてしまう、そんなにんげん的魅力をもった男である。西郷隆盛や山本五十六がそうであった。彼らから声をかけれただけで、「もう、この人のためなら死んでもいいと思った」と後に部下たちは、述懐している。幸村も、そんな男であったのであろう。 それにしても、河内の野をうずめつくすような徳川軍団の前に進み出た幸村が、「関東軍百万もあれど、われに挑む一人の男(武士)もなきか」と叫んだという光景は、事にのぞんだ際のリーダーのあるべき姿を描きだしている。 戦国の世に残すべき"家"をもたなかった幸村が、歴史のなかで遺した唯一つの"訓"である。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.77~81 2012.05.26記 |
14 柏屋三右衛門
|
柏屋三右衛門 不働き、我儘には相共に意見申すべく候(1,601~1,689年) P.82~86 いつの世の"戦争"でも、どの時代の"商売"にしても、いち早く情報をつかんで素迅く戦略、商戦を展開したほうが勝つ。 いまから三百年ほど前の天和・貞享年間、これに気づいて実行したのが柏屋こと柏原家初代の三右衛門である。 柏原家の系譜によると、初代の三右衛門は肥後熊本の加藤家の臣、柏原郷右衛門の後裔で京都の人(『柏原洋紙店八十年史』)。京の問屋町、五条下ル三丁目で呉服や小間物の仕入販売をおこなっていたが、堅実な商いぶりによって三右衛門は、京都人が理想とする、全国の諸大みょうが集まってくる江戸に店舗をかまえる「江戸店持ち京商人」に成長し、豪商への道を歩きはじめる。 新興商人として登場した柏屋の特徴は、従来の大商人たちがその『家訓』のなかで、《新儀停止(新しい事業に手を出すな)》 《一業専心》 と経営の多角化を戒め、それを忠実に守りつづけたのと逆に、小間物諸色問屋、呉服問屋、木綿問屋、紙問屋、漆器問屋、蝋問屋と思いきった多角経営に取り組んだことであろう。 この柏屋商法の特色は、既成の大商人たちが米を中心にした大みょうや裕福な町人たちのみを得意先にしていたのを尻目に、江戸という世界第一の消費地に住むおびただしい数の庶民大衆を"商売"の相手に、かれらが必要とする品物を売りさばいたことであろう。 柏家のこの多角経営のシステムは、各業種各店の搊失、危険をたがいに支えあい扶けあい、経営の安泰を強化していった。 それまでの商人たちと生き方を異にした柏屋は、こうして京に本店(柏原本家)をすえ、柏屋グループの陣頭に立った柏原家の当主は、諸店の資金運用、商品仕入れに専念し、これらを集中管理するための決算書を作成、経営の合理化をはかっている。 つまり、江戸の諸店は年間の純利益を本店におさめ、次の年度の資金を本店から借り入れるという方法をとり、また、この運営の安全をはかるため、江戸店から番頭が絶えず京都本店と連絡をとり、本店の指示をうける。なかでも、商品相場や市場の情報には金額を惜しまず超特急の「仕立便」を用いるよう本店から厳命されていた。 当時の『江戸飛脚便仲間定制』によると、江戸・大坂間の飛脚便の種類は「並便」「幸便」「仕立便」の三つからなっている。並便は便をまとめて一定の日に発送するのでおよそ二十五日。幸便というのは、定日にまとめて発送するのだが、飛脚は昼夜兼行で走行するため所要日は十日。超特急便の仕立便になると、即刻、飛脚が突っ走って大坂まで三日半から五日というすさまじい速さで書状が届けられていた。この三日半便になると、百匁の重さの書状で七両二分。仮りに一両を現在の十万円とすると七十五万円になる。が、 《(相場の)高下に付き存じ入りこれ有り候節は……》(柏原家『家内定法帳』十八箇条) という家訓をみれば、柏原家がいかに情報を"商人のいのち"として重視していたかかがわかる。そしてその通信文も、金額や日時、商品名なども極秘を守るため秘密の符号を使っていた。数字にしても、 《一(き)二(や)三(う)四(の)五(ね)六(江)七(と)八(て)九(み)十(る)》 と記した。この符号を一から十まで連ねてみると、 《京の値江戸で見る》 と、いかにも京商人らしい符牒になる。 柏屋グループが江戸で扱う商品の大部分は、京、大坂に集結する西国物で、土佐や伊予の紙、河内の木綿、京呉服や扇、小間物、紀州黒江の漆器などであった。これらの商品のなかでも、江戸へ海上輸送された大衆向きの河内木綿は、木綿問屋としての柏屋を一躍、天下第一の太物(木綿)問屋の地位に押しあげてしまった。(『江戸呉服問屋長者番付』寛政期)。 だが、柏屋の後継者たちは細心であった。それでもなお気をゆるめず、いかにすれば柏屋が安泰に存続できるかという心をくだいていた。この勢いに乗じて増資をし、どれだけ店舗を増やすか、などというよりも、いかに手堅く柏屋を守るかというほうが大事であった。 大名なら、よほど重大な失態か不始末さえなければ御家安泰の保障はされるが、商家はどれほど豪商になっても、明日の安泰を保障してくれるものは何もないのだ。安心も油断もできぬ日が、来る日も来る日もやってくるのだ。初代三右衛門……二代孫左衛門……三代助右衛門……四代孫左衛門……五代三右衛門と、柏屋の当主たちは、絶えず危機意識を抱きながら"豪商"としての道を踏みしめていった。 当主といっても、考えてみれば、柏屋の"家"を守り、次代へゆずり渡すための、 「家を預かっている奉公人」 にすぎないのであった。その"家"の運営にしても、当主の独断専制ではない。柏屋に長く勤めた功労多い番頭の中から"別家"にとりたてられた人びとや、その別家のなかの古参の"老分"などが、本家当主を中心にした会議に加わる、一種の合議制なのだ。 老分や別家の人びとは、主人よりも主家の家業を優先させる権限を柏原本家から与えられていた。まんいち、主人に素行不良や独断経営の行動があった場合、その行状を詰問し糾弾し、当主の座から追放することさえもできたという。 こうした柏原家歴代の主従の心の根にあるのは、人よりも家、主人よりも店という強烈な経営思想であり、冷徹なまでの家業意識であった。 《一、店の商売の儀につき、諸事相談の上、古来より致来候格式を以て仕るべく候。尤も毎月五日、月並みの会合堅く相勤め、諸事善悪承合、不埒のなき様に朋輩中勤め方身持ち等申し合せ、我儘働き申すまじく候。何事によらず諸事相談の上仕るべく候》 《一、自分商売仕り候儀、堅く無用に候、並に請合に入るなど、堅くいた申すまじき事》 《一、不働き(怠け者)又は我儘致し候やから之あり候わば、相共に意見申すべく候、再三不得心の上は暇(解雇)遣し申すべき事》 《何事によらず惣じて大事は小事より発り申し候。此旨よく心得有るべく候、尤も面々身の養生常の事に候、若し病人出来候わば、油断なく相共に気を付け申すべき事》 柏原家におけるこのファミリ・コントロール要綱『家内定法帳』は、年ごとに激化する経済競争に対処し、商業経営における安定基礎おつくるため柏屋主従のあいだで強く守りつがれていた。こうして京、江戸の巨商として発展をつづけていく柏原家に、さまざまな豪商の血が流れこんでくる。 京都第一の富商といわれた那波屋から迎えた養子、八代目孫左衛門のもとに三井家、宗睦の娘が嫁し、さらに九代目孫左衛門のところに松坂屋、伊藤次郎左衛門の愛娘が嫁いで、柏原家を富ませた。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.82~86 2021.06.13記 |
15 海保青陵
|
海保青陵門 物を売り物を買うは、世界の理なり(1,755~1,817年) P.87~91 「男一匹、本気で相手にしてよいほど値打ちの確かなものは、この世でひとつしかない、それは金のことさ」 と言ったのは文豪、オノㇾ・ド・バルザックだが、その金についてアメリカの経済雑誌『フォーチュン』(一九九〇年九月十日号)が発表した恒例の"世界の長者番付"によると、世界一の金持ちは四年連続して産油国のブルネイ第二十九代国王サルタン・ハサナル・ボルキァ・ムイザデン・ワダウラで総資産は二百五十億ドル(約三兆六千二百五十億円)、その殆どが石油、天然ガスの輸出と、おびただしい国外投資で稼いだ利益で、一日あたりの収入は約四十八億円だというから、気が遠くなるほどの金額である。 第二位はサウジアラビアのファㇵド国王とその王室で百八十億ドル、第三位が製菓で有&名なアメリカのフォレスㇳ・マーズ氏とその家族の百二十五億ドル。第四位がイギリスのエリザベス女王の不動産など百十七億ドル。日本人では西武鉄道のオーナー、堤義明氏の七十三億ドル(一兆九百五十億円)が第七位に顔をみせている。
《世ニアルㇹドノ願イ、何ニヨラズ銀徳(金の力)ニテ叶ワザルコト天ガ下ニ五ツアㇼ、ソレヨリ外ハナカリキ》 この五ツというのは、地水火風空の五つの原素から成り立っている生命をさしているのだが、そのイノチ以外のものは、すべて金の力で解決のつかないものはこの世にない。にんげん万事金の世の中と、偶然ながら符合しているのがおもしろい。そして西鶴は、そのお金持ちの資格を、 《銀百貫目ヨリシテ是ヲ分限(富者)ㇳ云エリ、千貫目ノ上ヲ長者(富豪)》 だと定義している。以前この西鶴の定義を平成の現在の銀の地金相場に換算して「一千貫ならたったの一億円、それくらいの小金持ちなら掃いて捨てるほどいる」と力説していた人もいるが、歴史の中の金勘定はそんな単純なものではない。元禄のその当時といえば大坂心斎橋ちかくで間口六、七間の家が銀一貫三百七十匁で買えた時代である。 ともあれ、そんな"分限"や"長者"になるために西鶴は、暮しの処方箋として、 《朝起五両、家職二十両、夜話八両、始末十両、達者七両》 この妙薬を朝夕服用すれば、かならずお金持ちになれると説う。ここでいう"両"とは、薬の分量のことで、一両は四匁。つまり、家職(家業)に励むこと第一、次に始末(節倹)、夜話(夜業に精をだして達者(健康)で朝は早起きをする。これが当時の大坂商人たちの経営方針であり、人生哲学であったのであろう。 この商都大坂に住む分限、長者といわれた銀主(諸大名の金貨)の家に、 《貧乏払い》 という奇妙な風習があった。毎月晦日(月末)になると、番頭が、味噌をこんがりと焼いて、その焼味噌の大きな塊りを、 《口ヲワンㇳアクヨウニシテ、口ヲヒロゲテ》 と、茶碗か壺のような形につくり、それを両手に捧げ持って旦那のいる居間から奥座敷、小座敷や店、倉庫、台所の隅まで、どたどたと走りまわる。 貧乏神の大好物は焼味噌だから、いい匂いに誘われ、焼味噌のなかに飛びこんでくる。こうして店じゅうに巣くっている貧乏神を焼味噌の中に入れてしまうと、しっかりと口を封じ、貧乏神のいっぱい詰ったその焼味噌を持ったまま番頭は往来に走り出、川の中へ投げこむ。 「こうした風習を児戯にひとしいと嗤うかもしれないが」 と、近世異色の経営コンサルㇳ海保青陵(一七五五~一八一七)はいう。 青陵は、荻生徂徠(一六六六~一七二八、江戸中期の儒学者)の非合理主義を否定し近代的リアリズムを踏まえ、新しい時代を切りひらこうとした新経済理論の提唱者でもある。その著『稽古談』で青陵は、この"貧乏神払い"の風習は、貧乏神を嫌うといことを手代から丁稚、下男下女にいたるまで知らせるための行事だという。 ああ、こんな子供だましのような真似までして旦那や番頭が"貧乏"を嫌うのかと思わせるのが経営者としての知恵である。 《大坂ノ貧ヲニクミテ富ヲコノムコㇳハ天性ナリ》 《旦那の第一ニコノムモノハ金銀ニテ第一ニイヤガルモノハ貧乏神也ㇳ思バ、是日夜朝暮箸ノアゲオロシニモ此事胸中ニアル也。サㇾバ算用(勘定)搊徳(搊得)ゴㇳ、入金ノ多クナルヨウニスルコト、出金ノスクナクナルヨウニスルコト、心ニヤムナキコㇳユエ、家内一統皆貧ヲ嫌ウㇳ言ウ家ニナル也》 こうした、低成長下の経済を凝視する青陵の現実尊重の視線は強烈である。 《金ㇳ言ウコㇳヲ言葉ニモ言ヌヲ、真ノ武士ㇳ心得ル》 から、武士が貧乏から脱けだせないのだと青陵はいう。 《阿蘭陀ハ国王ガ商イヲスルㇳイッテ、(武士や儒者どもは)ドッㇳ笑ウ也。サㇾド、己レ(たち)モ、ヤㇵリ物ヲ売リ物ヲ買ウナリ、物ヲ売リ又物ヲ買ウㇵ、世界ノ理ナリ》 考えてもみよ、君臣の関係にしても「売り買い」ではないか、青陵の語気は鋭い。 《古エヨリ君臣ハ市道(売買の関係)ナリㇳ言也。臣へ知行(俸禄)ヲヤリテ働カス、臣ハチカラヲ君へウリテ米ヲㇳル。君ㇵ臣ヲカイ、臣ハ君へウリテ、ウリカイ也。ウリカイガヨキ也。ウリカイガアシ(悪)キコㇳニテハナシ。凡ソウリカイノコㇳハ、君子ノスルコトデナイㇳ言ハ、ミナ孔子ノ利ヲイㇳウコㇳヲウノミニシテ、ノミコミソコノウタル也》 《卿大夫士(天皇や諸大みょうの臣)ハ己レガ智力ヲ君へウリテ、ソノ日雇賃銭ニテ喰ウテオル也。雲助(駕籠かき)ガ一里カツギテ一里ダケノ賃ヲㇳリテ、餠ヲ得酒を得ルニ何モチガイハナシ》 天皇と公卿や藩主と家臣の関係にしても、すべて「売り買い」である。この売り買いこそが、天地の理だと青陵は声を重ねる。 百年一日のごとく、農民から米を収奪することだけに明け暮れ、商品経済の大切さに目をむけようとしないのは無能な家臣たちの"俸禄"の食いつぶしであり、能力のある家臣から見れば暗愚な藩主は生涯の不作、折角の知恵も宝の持ち腐れ、骨折り搊である。 《食イツブシハ君ノ損ナリ、骨折リ損ハ臣ノ損ナリ、ㇵナハダ不算用(勘定にあわない)ナリ》 そう言うと青陵は、諸藩の重役たちに藩営の商業を勧め、武士もまた経済の大事を知り、他国に特産品を売りつけ大いに稼ぎ、利に利を積み、藩財政の建て直しをはかるべきだという。 《一体、天理ハ理ヅメ也。ウリカイ利息ハ利ヅメ也。国ヲ富サンㇳナラバ、理ニカエルコト也》 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.87~91 2021.06.22記 |
16 山本勘助
|
山本勘助 食すといえども一升の米、座して三尺、寝るは六尺(1,493もしくは1,500~1,561年) P.92~96 日本のなかの"戦国"というのは、中国の周の威烈王から秦の始皇帝の天下統一までの群雄割拠の時代を"戦国時代"と称ったのにならって、日本の乱世にあてはめ、応仁の乱から豊臣秀吉の天下平定までの動乱期をいったものだ。 この激動の時代、世にこころざしを得ず戦国の野を放浪したサムライたちは多い。 かれらは、しかるべき武将のもとに身を寄せ、知謀あるものは軍略を、腕におぼえのある男は、"陣借り牢人"となって戦場に出、敵の首を掻き斬って金穀(銭と米)を稼いでだ。 戦国武者というのは一種の自由労働者で、 「武士は二君に仕えず」 どころか「七たび牢人せねばオトコ(一人の武士)ではない」といわれ、その人間市場でオトコを売るのが稼業であった。 槍をかざして一番乗りをするのも敵の首を叩き切るのも、出世のため金のため、というのがサムライの本心であった。後年の、"禄"をもらって寝て暮らすだけの遊民、世襲制公務員に変身したサムライとは、生き方、考え方がちがう。 《君ニ仕エテ忠ヲ尽サンニハアラズ、(戦に出るのは)名ヲ立テ家ヲ発セン(興そうとする)バカリ也》 《合戦ノハタラキニ心ヲ尽スハ、子孫ノタメㇳモ申スベシ》 こうして、一介の素牢人から関東の王にのしあがった伊勢新九郎こと北条早雲、油の行商人となって諸国を歩きまわった"戦国の蝮"国盗り大みょうの齋藤道三、織田軍団のノンキャリア組から天下を掴みとった太閤秀吉など、戦国を放浪した男たちの表情は多彩である。 武田騎馬軍団の軍師(参謀)とともいわれる山本勘助もまた、その一人である。 武田晴信の謀臣、山本晴幸(勘助)。三河国牛窪に生まれ、二十歳のころから諸国を遍歴し三十有余年、甲斐国に辿りつき晴信に仕える。このとき勘助、すでに五十二。 放浪中の辛酸について『続武将感状記』は、こう語る。 《山本勘助、室町将軍家に仕官を望みけるが》 事ならず京を立去る。わが身を托するのは、 《安芸の大江(毛利)元就に如くはなし》 そう思い定めて旅立ったものの、人生というのは、おもしろい。 途中、葛井寺(大阪府藤井寺)で逗留しているあいだ、門前の老婆の一人娘の入婿となり、団扇の手内職をして米を稼いでいる(こうして思わぬことで勘助は、藤井寺名物"小山団扇"の元祖となる)。 で、この地にとどまること数年。ようやく安芸に辿りつき、厳島に詣で知人の棚守謀に挙されて元就の前へ罷り出る。が、二日たち三日すぎても元就からは何の返辞もない。棚守がそっと伺いをたてると、 「ああ、あの牢人めなら要らぬわ。用いざれば他国へ走り、安芸の毛利などとよからぬ噂を立てるにちがいない。されば一日も早よう此処から立退かすべし」 と元就はいう。かくして勘助、失意を抱いて、また、旅に出るしかなかった。 勘助が武田家に仕えたのは、一説によると武田の重臣、板垣信方の推挙によったのだというが、 《丈短く色黒く》 ながい放浪と、各地での「陣場稼ぎ」の戦闘で、満身創痍の有様であった。 が、これを見て晴信(信玄)大いによろこび、 《かくの如き醜貌をして、なお盛名あるというは、その能もって知るべし》 と知行二百貫を与え、足軽大将に任じた。そののち勘助、晴信の旗本五人の内に加えられ、晴信の参謀として、抜群の"軍略"で敵城を落とすこと九ヵ城。諸戦での功を賞せられ、禄八百貫。 晩年、勘助は、あるじ晴信が信玄を号するにおよんで自分もまた剃髪し、道鬼斎と号した。 永禄四年(一五六一)上杉謙信との川中島第四度目の会戦で激闘、全身に八十六ヵ所の傷を負い、壮絶な戦死を遂げる。享年六十九.(『甲斐戦国志』『甲陽軍艦』)。 ――というのが山本勘助の来歴だが、"信頼すべき文献に見当らない"として架空の人物視する人もいる。が、最近はその関係書などが発見され、ようやく勘助の実在が認められるようになってきた。 ともあれ、この勘助が語った戦国武者の心得を、信玄が家臣に命じて記録させたと伝えられる聞書き『山本道鬼入道百目録』が遺されている。 《一、嗽、手水して宗廟の御神、次に産土神を拝念し、天恩地恩父の恩母の恩、まず天恩は、昼夜日月の運行明暮を知り、随時の雨風に万物をば長ずる。》 地の恩は、わが住所居し、五行を自由にし、五穀を以て身命を相続する。地の恩莫大なり。父母の恩を思うには、毎朝前へ出て、夜中の安否を伺い、食事の好みを聞き合せ、夫々に孝養すべし。父母の死後には、その霊前に向かいて、生前に物いうごとく、幼少より長ずるまで、海山の恩報ぜずして別れたる残念を申訳し、香花燈明茶具霊膳は、手ずから備うべし。人多く召し仕うとも、他に手掛けさすべからず。かくの如く志を運ぶ時は、冥加に叶う。冥加の二字、闇より加うると書を以て起るべし》 文中にある"五行"というのは、古代中国の学説で、天地の間に循環流行している人間や動植物に大事なもの、万物組成の元素の意味である。 以下、その百二ヵ条のなかから戦国武者の教訓としてユニークなものをアトランダムに四、五ヵ条を抜き書いてみると、 「武士たるもの、驚破! という時のため干飯(携行用保存食)、梅干、鳥目(金銭)を袋に入れておくこと。また枕元には、六尺棒と草鞋を二足置いて寝よ」(第三十六条) 戦国乱世というのは、生きていられるということ自体、異常な幸福であった。 「この世にもう何の未練も、望みもない、などという者を近づけるな。なんとなれば、にんげん、身分の上下にかかわらず、みな、明日という日に望みを託しているからこそ、その勤めに出精し、身を正しておれるのだ。人の世に希望を持たぬ者など、なにをしですかわかったものではない」(第八十条) 《人食すといえども一升の米に過ぎず座して三尺、寝るは六尺を以って足る》(第十条) 飯を喰うといっても、一度に二升も三升もの飯が喰えるわけでなし、金にまかせて贅沢な普請をしてみても、寝るのに必要なのはたった六尺。 「嫁をとるときには、相手の美醜などどうでもよいが、日頃の評判を近所で聞いて、よくよく調べておけ。つましい娘か派手好きな娘か、親に孝行か、家来たちをいたわるか、どうか、それが大事だ。仲人の言葉など信じてはならぬ」(第九十条) と、戦国という修羅をくぐりぬけてきた勘助は、しずかに語りつづけている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.92~96
神坂次郎は、――というのが山本勘助の来歴だが、"信頼すべき文献に見当らない"として架空の人物視する人もいる。が、最近はその関係書などが発見され、ようやく勘助の実在が認められるようになってきた。 新田次郎はその著作『武田信玄 火の巻』あとがき、 信玄と云えば、その影に添うごとく軍師の山本勘助が出て来る。ところが、この山本勘助なる人物は、山県昌景の組下にいた身分の軽い武士で川中島の戦のときには物見をやったていどのことしか分っていない。山本勘助の子が、妙心寺派の僧となったが、この男が学があって、武田信玄の事蹟を集めて、これを物語風にまとめたものに、小幡景憲が加筆し高坂弾正が遺したと称して江戸初期に出版したものが『甲陽軍鑑』だと云われている。原本を山本勘助の子が書いたとすれば、父親を軍師に仕立てるのは当然であろう。軍師山本勘助という人物は、他の信用置ける資料には全く出て来ないから、山本勘助が実在の人であったとしても軍師でなかったことは確実と見てよいだろう。だが、なんと云っても、武田信玄のことになると、この『甲陽軍鑑』の影響力が大きく、軍師山本勘助が出ないとおさまりがつかない。そのために、武田信玄の側近の一人であった、駒井高白齋のような人物が蔭にかくれてしまったのであろう。 2021.05.20記 |
17 三野村利左衛門
|
三野村利左衛門 凡百の事、繁を省き簡をとれ(1,821~1,877年) P.97~102 三井財閥草創期の大番頭、三野村利左衛門の前半生は、伝説の霧の中にある。 一説によると、信濃(長野県)または出羽(山形県)に生まれたとも、いやそうではなくて、出羽の浪人を父に、江戸で生まれたのだ、ともいう。が、いずれも確証があっての事ではない。 《三野村利左衛門は、幕末から明治の初年にかけての大変動に際し、天下の富豪が相ついで倒れてゆくなかに、三井家二百年の家運を一再ならず危機を救い、新時代に即応する三井の基礎を建てた殊勲のひとりたるのみならず、幕府及び明治維新政府の枢機に参画して幾多の放れ業を演じた覆面の功労者である》(『自叙益田孝翁伝』長井実編刊) 父と共に京、大坂そして九州日向へと放浪する利左衛門は、その旅先で父とも死別し、天涯の孤児となり、放浪無頼の生活をつづけたのち、天保十年(一八三九)江戸にくだり、干鰯問屋、丸屋に住み込み奉公をはじめる。利左衛門十九歳。 のち、その才覚を認められ旗本、小栗家(十一代)の中間になり、さらに神田三河町の油、砂糖問屋、紀ノ国屋三野川利八の娘なかと結婚。三野川利八を襲名した利左衛門は、紀ノ国屋の財を足がかりに、小銭両替商を開業。これが江戸における筆頭両替商、三井両替店に出入りするきっかけとなる。 当時、ペリーの黒船来航で日本は大きく揺れ動き、豪商三井家もまた、再三にわたり幕府から、 《元治元年(一八六四)、御用金上納百万両》 《慶應元年(一八六五)、御用金上納一万両》 と、巨額の御用金を申しつけられ、破産の危機に直面していた。 《(またしても)御勘定奉行小栗上野介(十二代・忠順)ヨリ百万両ノ御用金ノ御用金ヲ申付ケラレタルガ、我ガ三井ㇵ百万両ハ愚カ三万両ノ金モ融通デキズ》 という有様であったと、江戸三井両替商番頭の齋藤専蔵は語る。 こうした御用金上のうを拒否すれば、そのシッぺ返しに幕府は三井家に「闕所」(財産没収)を言い渡すことは必定である。 「どうしたものか?」 頭をかかえてしまった三井家では、減額を嘆願することにした。このとき浮びあがったのが、出入りの脇両替屋の利八のなである。小栗家二代にわたって信頼をうけていた利左衛門なら、 「うまく、小栗を説いて……」 こうして三井家から小栗説得を依頼された利左衛門は、勘定奉行所にむかった。結果は大成功であった。 「ええっ」 利左衛門の報告に、三井家重役たちは歓声をあげた。それはそうであろう。減額どころか、利左衛門は、 《御用金一件ハ河流ㇾㇳナリタルナリ》 つまり利左衛門は、三井家への御用金は免除、そのうえ幕府が江戸市中への金融緩和政策として行っている、貸付金の取扱い業務「江戸勘定所貸付金御用」まで貰ってきたのである。 こうして三井家重役の絶大な信頼を得た利左衛門は、三井家当主、三井八郎右衛門高福に対面を許され、三井の三、紀ノ国屋美野川利八の美野川の野、亡父の養子先の木村の村をとり、三野村を名乗り、 《利八コト三野村利左衛門ヲ御用所限、通勤支配格》 と破格の扱いをうけ、三井入りをする。利左衛門、四十六歳。 以来、利左衛門は幕末維新の"金融"争乱の真っ只中を奔走する。 その第一の危機は、王制復古を宣言する新政府からの軍資金の要求である。新政府に加担するか、幕府に与するか。激動する経済の動きのなかで、右するか左するか、迷いに迷っている重役たちを尻目に利左衛門は、 「新政府を……」 と、幕府勘定奉行小栗忠順の恩情に目をつぶる思いで、決断をくだしている。 このとき、三井家同様新政府への軍資金をもとめられた豪商たち、平野屋、加島屋は、徳川三百年の情義にひかれ、新政府の申出を拒否している。 これは一種の大ばくちであったが、利左衛門は、かねてから目をつけていた京都を本拠とする御為替御用達の小野組、小野善五郎や、おなじ御用達の島田八郎左衛門(蛭子屋)の動向をみて、踏みきったのであろう。 利左衛門のこの情報分析は、的中した。 幕府に賭けた平野屋、加島屋は脱落し、明治新政府の"官金為替御用達"を掴んだ三井、小野、島田の豪商三家は、政府金融業務の一切を取扱い、富の上に富を重ねていった。 が、新政府への傾斜を深めていきながら三井大番頭の利左衛門は、すでに次なる"政商"への階段をのぼりはじめている。 その手はじめは、政府高官や大蔵省の高級官僚たち、時の権力との癒着であった。 この間の利左衛門の八面六臂の活躍ぶりについて三井両替店の番頭、斎藤専蔵は、 「(利左衛門は)いつも麻裏草履をはいて、木綿の着物に、皮色木綿の打裂羽織、白の小倉の袴、それに大きな刀をさして、それで東西を稼ぎまくるのです。(略)一時間と坐ったことはない。私どもに用をいいつけるにも、座っていちゃいかぬ、立てという。三野村がくると皆立って、直立で話をしなければならぬ」 と述懐している。 そして、旋風のように奔走をつづけながら、三野村もまた、 《凡百の事、繁を省き、事用は立ちどころに弁じ、重複を煩わすなかれ、長幼を論じ礼節に拘るなかれ。業を捨てて礼するなかれ。時機を失するなかれ。平常よく断の一字を守れ》 と使用人たちに説う。 利左衛門と当時の政府高官との接触ぶりについて、こんな逸話がある。 明治四年(一八七一)十月、新政府の岩倉具視、木戸孝允、大久保利通ら最高首脳の大半が欧米視察にむかうことになった。その送別の宴で、留守政府をあずかる西郷隆盛が、大久保の代理として大蔵卿をつとめる井上馨の前に、ぐいと盃を突きだし、 「れれはこれ、三井の番頭さん、一杯いかがでごはすか」 とからかったという。 ともあれ、こうした三井の布石が、やがて三井を新政府最大の御用商人の座に押しあげていく。 この時期、利左衛門の腹案のなかに、 「政府金融業務の独占」 がある。長州出身の井上にしても、薩摩閥の息のかかった小野組などの政商を叩き潰し、金融関係を三井ひとつにすれば、すべて好都合である。 明治七年十月、新政府は政府金融業務にたずさわる者は、公金相当額の抵当を用意すべし、という命令を通達した。そんな巨額の抵当が、にわかに用意できる筈はない。かくして、小野、島田は失格、脱落。 こうして利左衛門は、政府金融の独占に成功した。 三井家における利左衛門の最後の仕事は、大蔵卿大隈重信の庇護の下、日本最初の民間銀行(現さくら銀行)、三井物産を発足させたことであった。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.97~102 ※関連:三井財閥三百年の繁栄の基礎を築いた三井八郎兵衛高利(一六二二~九四)。 2021.06.11記 |
18 朝倉敏景
|
朝倉敏景 昼夜眼をふたぐことなく、工夫を致せ(1,428~1,481年) P.103~107 戦国乱世の"下剋上"ぶりを絵に描いたような男が、越前(福井県)朝倉五代の祖という朝倉敏景(孝景、一四二八~八一)である。 当時、敏景のために所領を掴み取られた都の公卿たちは、黒けむりをあげんばかりの悪罵酷評を敏景に浴びせかけている。 「このたび、朝倉弾正左衛門尉(敏景)が死んだという噂を耳にしたが、よろこばしい事だ。なにしろ、あ奴こそ天下の悪事はじめの張本人だからな」(『親長卿記』甘露寺親長) 《越前国足羽御厨の、四百貫の荘園を朝倉弾正左衛門めが押領、言語道断の所行》 《年貢六千五百疋(一疋は銭十文)の安保の領も、弾正左衛門押領》 《七千疋の東郷荘も、四千三百疋の清弘みょうも、四千疋の次田名も、すべて弾正左衛門が押領》(『桃花蘂葉一条兼良』) 「呵責ない非道ぶりにて荘園を押領しおった細川勝元と朝倉孝景めに罰があたるように神に呪詛していたが、ようやく今日、その願いがきき届けられ細川めが死んだ。神の思召しのありがたきことよ」 と、兼良の子、奈良興隆寺の尋尊も、口をきわめて罵りつづける。 が、それが乱世なのである。下剋上というが、"上"が傲慢で下民を虐げ搾取するばかりで"徳"のない支配階級に対して《天が命を革める》その革命の声に応えて起つことこそ、天命にかなうことではないかと"下"はうそぶく。 「時こそ、いたれり!」 それにしても、新興勢力の旗手、敏景の蹶起ぶりはすさまじい。 朝倉家は代々、越前の守護大みょう斯波氏の家臣で、敏景の代にいたって斯波家の三家老(甲斐、織田、朝倉)の一人に立身した 敏景が出世のきっかけをつかんだのは、主家である斯波家を二つに割り裂いた、義敏と義廉の二人の養子の相続争いであった。この争いがやがて、"応仁の乱"の引き金になる。 ※関連:"応仁の乱"について、内藤湖南著『日本文化史研究』(講談社学術文庫)昭和58年3月18日 第6刷発行の中に 現代日本を知るには、応仁の乱以後を知れば十分だと喝破している。 このとき敏景は義廉を擁立して西軍(山な宗全)に属した。が、東軍の実力者、細川勝元からの、 「われに加担すれば、越前守護職に任ぜよう」 との一言で、ころりと気が変った。守護大みょうになるというのは、長いあいだの夢であった。 「応!」 とばかり、目をかがやかせた敏景は、昨日までの主人の義廉を投げ捨てて、一族をひきいて東軍に駆けこんだ。 戦国大名の先がけとして、応仁の乱という嵐のなかで《一孤半身より》身を起して、《不思議に国を》持つ身になったと述懐する敏景と同じ思いを、子の教景(朝倉宗滴)も感じている。 生涯、合戦にあけくれた教景は、乱世の生き難きを『宗滴話記』八十ヵ条のなかで、しみじみと語る。 《武者ハ犬ㇳモイエ、畜生ㇳモイエ、勝ツ事ガ本ニテ候》 生涯、合戦にあけくれた教景は、乱世の生き難さを『宗滴話記』八十三ヵ条のなかで、しみじみと語る。 武者たるもの、たとえ犬畜生とののしられようと、勝つことが本分……だという。実力主義の世界の、血と汗と涙のなかで培われたプロの言葉だ。 ともあれ、あるじの斯波義廉をしのいで、足利一門の有力者でなければなり得なかった越前守護職に、将軍義政から任ぜられた敏景は、勇躍、西軍を討伐し、越前の地に勢威をふるった。 晩年、入道した英林宗雄と号した敏景は、子孫のために家訓十七箇条(『朝倉敏景十七箇条』(群書類従本)、『英林壁書』(黒川本)、『朝倉英林入道子孫へ一書』(新井白石本)とも称う)を遺している。 《於朝倉之家宿老を不可定。其身の器用忠節によりて可申付之事》(一) 朝倉の家においては家老を定むべからず。その身の能力、忠勤によりて申しつくべき事。 以下、興味ぶかい箇所を読みくだして列記してみると、 「先祖代々門閥の家格であっても、実力のともなわない者に団(軍配・指揮権)をあずけてはならぬ」(二) 《名作の刀脇指など、好ませられまじく候。そのゆえは、仮令、万疋の太刀を持ちたりといえども、百疋の鑓百丁には勝れ間敷候。然れば万疋をもって百疋の鑓を百丁求め、百人に持たせ候わば、一方は相防ぐべき事》(四) 《京都より猿楽(能楽の旧称)などたびたび呼びまねき、見物を好ませられまじく候。その金額を領内の猿楽上手の者に与え、京にのぼらせ、猿楽を習わせれば、領内の文化も栄え、末々までよろこばしき事》(五) 《朝倉一族はじめ家中の者ども、年の始めの出仕は布子(ふだん着)たるべき事。高禄の者、軽輩の者、いずれも華美を慎しみ布子を用いるべき事》(八) 「家臣のなかで、みにくい顔つきにて風采あがらぬ者であっても真面目に勤める者には情をかけるべし。また、臆病な男であっても容儀や立居振舞の見事な者は行列の供や、他家への使者に使うがよい。この二つにはずれる者は召し抱えておっても無駄である」(九) 「おのれの役職に精勤するものと、怠ける者とを同格に扱ってはならぬ。精勤な者まで怠け心を抱くようになる」(十) 「さほど不自由でなければ、他国から流れてきた牢人などに右筆(書記役)させられまじき事」(十一) 他国者に機密文書を扱わせるということぐらい、危険なものはない。 「年に三度ぐらいは、正直で才覚のある者を選んで国じゅうを歩かせ、四民それぞれの口謁(申し立て)を聞き、それを報告させること。機会をみて当主自身、巡検にまわるべき事」(十四) 「勝とうとする戦、取ろうとする城攻めに際して、殊更に吉日を選び、方角などを考え、いたずらに時日を空費してはならぬ。いかに吉日とて大風の日に船を出したり、大軍に唯一人にて向えば、如何なることか。たとえ悪日悪方角であろうとも、情報をあつめよくよく虚実を考察し、臨機応変に対処すれば必ず勝利を得るものぞ」(十三) 戦国のこの当時、出陣するにも吉日を選び方位を選び、酒を飲むにも馬に騎るにも数々の作法があった。甲冑を着用するにも一定の順序と方式があり、"八幡殿ノ殿"というのがある。下帯一本から出陣の上帯切りまで十八段から二十四段までの故実(古い慣例)があった。縁起をかつぐ武将などになると、二千八百の軍神に酒を手向け、九億九万八千七百七十二の夜叉神に祈りをささげる、というのだ。 だが、合理主義者敏景の冷徹な目は、そのような故実に惑わされてはいない。 「いかにすればこの乱世を生きぬけるか」 そのため敏景は、この十七箇条の奥書に、 《昼夜眼をふたぐ(とじる)ことなく、工夫を致し、ある時は諸々の名人をあつめ、その語るを耳にはさみ、思案を致しおるゆえ、いまにかくの如く(安泰)に候》 《あいかまえて子孫の者ども右之条々よく服膺し、昼夜相勤めて、長く胎闕 |
世渡りの業は、傘
19 本多正信
|
本多正信 堪忍は身を立つるの壁 (1,538~1,616年)
人の世の人それぞれの浮沈は、巨木な"時"の流れのなかにある。関ケ原の合戦は、三河以来の戦場の血と汗のなかの徳川氏を築きあげてきた武功派譜代の輝ける舞台の幕切れでもあった。やがて時代は、徳川氏が戦国大みょうから江戸幕府創設という流動する政治、社会の変化のなかで、家臣団の実権は"武功派"から"吏僚派
こうした時代の潮流の中で、戦場での武勲もない、鷹匠 文治派の謀臣、本多の台頭は、あたらし武士像の出現でもあった。 「百姓は財のあやまらぬよう不足なきよう治めること道なり」(『本左録』)の言葉で有名な本多佐渡守正信。祖父の代から松平(徳川)家に仕えた本多の家系とはいえ、正信の家の本多は、徳川四天王といわれた本多平八郎忠勝家のような名門本多とは別の、低い位置にあった。 《鷹師、会計の小吏より出身して馬上の武功なしといえども、吏務は慎察にして、文筆の志ありければ漸く登康》(『台徳院御実紀』》 など記されているように、戦国のこの当時、貴賤とみられていた下級役人であった。 正信の前半生は紆余曲折をきわめている。幼い頃から家康に仕えた彼が、三河の一向一揆に加わり叛乱軍の参謀役として主君に弓を引き、やがて故郷を出奔して京に走り、松永久秀のもとに身を寄せる。松永は一目で正信の器量才覚を見ぬいて、
《人に語りていわく、久秀、松平家より来る侍を見ること少なからず、多くはこれ武勇の輩
と思ったが、正信はその久秀のもとにも長くはとどまらず、加賀や越後を転々とし流偶 その正信が家康に詫びを入れ、帰り新参の鷹匠として食禄四十万石を与えられたのは永禄十二年(一五六九)、正信三十二歳のとき。後年、正信が幕閣の要職にありながら民政への鋭い感覚をもっていたのは、この民情探索の役目でもあった鷹匠や、彼にとって冬の時代ともいう三河出奔後の諸国放浪の時代の体験からきている。
武田討滅後、甲斐の国の動揺を治めるため行政官として目ざましい活躍をみせた正信は、にんげん通 「れからは、火を発した者に切腹を命じよ」 と言いつけた。翌朝、正信が出仕するのを待ちかねて、 「昨日申しつけたこと、みなに達したか」 と訊く。すると正信は、
「上様のお言葉、昨晩よくよく考えてみましたるところ、もし誤って三河以来の譜代高禄の屋敷から火がでました場合、切腹を仰せつけることは出来ますまい。と、軽い身分の者のみを切腹させ、譜代大身の者なら赦 言われてみると、正信のいうとおりである。 また、映像や小説などでみると家康は温厚、忍耐をわきまえた武将……となっているが、それは外交上の"顔"で、本来は極めて短気、時には近習たちの過失を口汚く罵倒し、怒りに目を吊りあげ今にも手討ちせんばかりの形相をみせる時がしばしばあった、 そんな時に正信は、家康の御前へにじり寄って、 「何ごとに候や」 と家康に訊く。と、いきり立った家康は口に泡を噛んで、 「こ奴(やつ)めが、かような振舞を致しくさって」 それを聞くなり正信は、 「上様のお怒り、ご尤もでござる」 そういうと叱りつけられている近習を睨みつけ、家康も驚くほどの大声で、
「汝 正信は矢継ぎ早に、手討ちにされようとする近習の家代々の忠勤ぶりを(家康に聞かせるように)大声で叫びあげ、
「汝もその心がまえによって、今日よりいよいよ相勤めよ、上様にもさよう思 正信が激しく長々と喋っているあいだに、家康の怒りはとっくに冷めてしまっている。
「これ、何をしておるか、お声をお出しなされたゆえ、上様には咽喉
こうした正信の配慮によって、近習たちもお咎
一介の鷹匠から、江戸幕府の最高頭脳に立身しながら、正信はつねに質素であった。俸禄は相模(神奈川県)玉縄(たまなわ)三万石、それ以上の加増を正信は辞退しつづけている。その正信の壁書
《一、淫酒 二、堪忍は身立つるの壁
三、苦労は栄華の礎 四、倹約は君に仕うるの材木 五、珍膳(ちんぜん)珍味(を好む)は貧の柱
六、多言慮外(無礼)は身を亡 七、人情は家を作るの畳
八、法度 九、花麗(華麗、派手)は借金の板敷
十、我儘は朋友に悪
生涯、清貧に甘んじ無欲に徹し、家康政権を推進してきた正信の最後の仕事は、豊臣討伐の大坂ノ陣であった。「やるか!」かねてから社寺の修造に事よせて豊臣家の財力を蕩尽 おりから家康は病臥していたが、その知らせを耳にした途端、 《大坂討滅コソ本望ナリ》 と叫び、枕頭(ちんとう)の刀を抜き放ち、床の上に飛びあがったと伝えられている。
この後、冬ノ陣では、「総堀 正信の死は、あるじ家康の死の五十日目である。
家康が正信をみること朋友のごとくであったと伝えられる本多佐渡守正信、元和 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.116~116 2021.06.02記 |
20 岩崎弥太郎
|
岩崎弥太郎 会社の利益、搊失は社長の一身に帰すべし(1,835~1,885年) 三井財閥の富は、江戸期を通じて二百数十年の歳月と伝統のうえに築かれたものだが、徒手空拳、一代にしてわが国二大富豪の一つにのしあがった男がいる。三菱財閥の創始者、岩崎弥太郎である。 いま、一代にして……と書いたが、正確にいえば明治初年から彼が死を迎える明治十八年(一八八五)まで、わずか十八年間に、こういうべきであろう。 岩崎弥太郎。 天保五年(一八三四)土佐国安芸郡井ノ口村の地下浪人、つまり郷土株を売り払って半農民になった家に生まれた。幼い頃から勉学への思いは強く、頭も人いちばい切れるのだが、直情径行型で激しやすい性格が災いして、立身への足がかりは容易に掴めなかった。 安政五年(一八五四)藩士、奥宮慥齋(ぞうさい)の従者という名目であこがれの江戸にむかい、念願の安積根齋(あさいこんさい)の塾に入門する。しかし、この勉学生活は一年も続かなかった。父が喧嘩騒ぎを起して、重傷を負ったのである。学問を中断して帰郷した弥太郎は、 「かかる偏頗(へんぱ)(不公平)が許されてよいのか」 と、この喧嘩の裁きをつけた役所の非を鳴らし罵倒し、投獄されること七ヵ月、親戚や縁者たちが八方手をつくして出牢はさせたが、《居村追放、高知城下四ヶ村禁足》の処分をうけた。
この追放が赦された後、弥太郎は親戚であり友人でもある後藤象二郎(明治維新、大政奉還の仕掛人の一人)の紹介で、土佐藩きっての有力者、有田東洋の門下生となり、彼の推挙によって下横目 ところが、長崎に着いた弥太郎は、調査などそっちのけで花街に入りびたり、連夜ドンチヤン騒ぎをくりひろげ、またたく間に公費を使い果たして無断で帰ってきた。かくして弥太郎は、役職を取りあげられ罷免。 が、これくらいのことを気にする弥太郎ではない。また後藤象二郎に泣きつき、慶應三年(一八六七)藩営の土佐商会長崎出張所主任として再び長崎に赴任、外国商館を相手に大いに才腕をふるう。ところが、このときも亦上役と衝突し辞職届を叩きつけて帰国する。しかし、後藤象二郎に説得され、三たび長崎にむかう。 こうした長崎での藩営の商事会社"土佐商会"時代におぼえた資金操作の妙が"商売"というものの醍醐味を弥太郎に教えた。
《我は別段に一商会を経営し、往々 この時期、弥太郎は外国商館を相手に手当りしだい外債を借り集め、十九万両からの資金をつかんでいる。
弥太郎のこの資金操作の見事さを後年、政治家であり文人であり、改進党の中心人物の一人であった矢野龍渓 《三菱会社の社長たる者はなかなかの策士である。あの業(海運業)をはじめた時、先ず入用もないのに金を借り、期限の来る前に利息をつけてチャンと返す。しばしばこれをやって貸し方の信用を増して置いて、今度は大口の借款を諸方に申し込み、大金を掻き集めた、それが回転資金の大部分になったというのである。これは世上の噂にすぎぬが、そういう噂を産むくらい、奇抜に見られていたと見える》 と、『龍渓閑話』で述べている。 ともあれ、商務官僚を志した弥太郎の前に、倒幕の嵐が吹き荒れ、明治新政府が誕生、廃藩置県が行われた。 「時こそ来れり!」 弥太郎は目をかがやかした。それはそうだ。土佐藩の命令をうけ"土佐善兵衛"を名乗り土佐開成社を預けられ、経営していた弥太郎の前から土佐藩が消えてしまったのである。 「いっそ、商人になって天下の金を掴んでみるか」
この千載一遇のチャンスに遭遇した弥太郎は、藩営の土佐開成社(資金と建物、六艘の汽船と二艘の曳舟)を「九十九 《機会というものは、人間一生の内に一度や二度は必ず来る。けれどもそれを捉えそこねたら、その人はもうそれなりになってしまう。河や海に魚が群を成してくることがあるが、機会の来るのもそれと同じだ。それっ、魚が集まったといって網を作ろうとするのでは間にあわぬ。いつ魚が来ても、すぐに捕えられるように、不断に準備していて、その場になって、まごつかぬようにしておかねばならぬ》 弥太郎は晩年、"機会"についてそう語っている(『随想録』高橋是清)。 こうして三菱蒸気汽船会社をひっさげて出発した弥太郎は、明治新政府の要人となった後藤象二郎や、大隈重信、大久保利通らの強力な援助のもとに"政商"として発展をつづけていく。なかでも明治十年(一八七七)の西南戦争では政府軍の兵士や軍需物資の輸送を一手にひきうけ、一年たらずのあいだに百四十万円もの大金を稼ぎ、三菱財閥の基礎を築いた。 海運業を独占して天下の政商にのしあがった弥太郎は、 《およそ事業をするには、まず人に与えることが必要である。それは、必ずより大きな利益をもたらすからである》 と言い、つねに政府高官をまねいて豪華な酒宴をひらいていたという。
弥太郎のワンマン体制のもとに設立されたこの大三菱の「立社大栽 《会社ノ利益ハ全ク社員ノ一身ニ帰シ》 と強調したり、事業不振の際は 《月給ノ幾分ヲ減少シ、且、傭ヲ止ムルコトアルベシ》
などと減給、解雇をぬけぬけと明示しているところなど、まったく異色の「社則」で、微笑 その社則三ヵ条(明治十八年改正)を列記してみると、
《第一条 当会社ハ姑 第二条 故ニ会社ノ利益ハ社長ノ一身ニ帰シ、会社ノ損失モ亦社長一身ニ帰スベシ。 第三条 前条ノ如シㇳ雖モ、会社盛大ニ相成リ利益ヲ得ルコト多分ナル時ㇵ、一体ニ月給ノ幾分ヲ増加スルコトアルベシ。又会社ノ事業興ラズ多分ノ損失アルㇳキハ、一体ニ月給ノ幾分ヲ減少シ、且、傭ヲ止ムルコトアルベシ。》 弥太郎が育てた大三菱の見事さは、錚々たるビジネス・リーダーの中から三人の日銀総裁、二人の首相を生んだことだ。 参考:第3代総裁:川田小一郎、第4代総裁:岩崎彌之助、第5代総裁:山本達雄。 参考:岩崎弥太郎の娘を妻とした第24代首相加藤孝明、第25・28代首相若槻礼次郎、岩崎家の縁戚である第44代首相幣原喜重郎と歴代首相が3人も住んでいる(以上故人)。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.116~120 2021.05.21記 |
21 徳川家康(上)
|
徳川家康(上) 生涯座右の銘とした失意の自画像(1,543~1,616年) 戦国の世とはいえ、松平竹千代(のち徳川家康)ほど過酷な運命にもてあそばれた子は、またとあるまい。幼児として母のふところで甘えられたのは、まだ物ごころもつかないあいだで、三歳の時にはその母とも生別している。理由は、母の実家である水野家の動向が、強大国家、今川家の不興をかうことを父の広忠が恐れたからである。 あわれなのは竹千代であった。三歳で母と生き分れ、六歳の幼さで人質として駿府の今川家に送られていく。が、その途中、広忠が後添いに迎えた妻の父、戸田宗光(康光ともいう)に欺かれ、その身柄を永楽銭百貫文(『三河物語』大久保彦左衛門)で敵方の織田家に売りとばされる。 これが家康七十五年の人生の中で遭遇した最初の"大難"であった。家康の悲運は、そんな想像を絶した"四度の大難"と"六度の大戦"に見舞われていることであろう。 "四度の大難"というのは、 一、織田へ売られたとき(六歳) 二、三河の一向一揆のとき(二十二歳) 三、三方ヶ原の大敗戦のとき(三十一歳) 四、本能寺の変のとき(四十一歳) であり、また"六度の大戦"というのは、 一、姉川の戦い(二十九歳) 二、三方ヶ原の戦(三十一歳) 三、長篠の戦い(三十四歳) 四、小牧長久手の役(四十三歳) 五、関ケ原の合戦(五十九歳) 六、大坂ノ陣(七十三歳) そしてこの大難と大戦の両方に出てくるのが三方ヶ原の一件である。
――元亀 「時こそいたれり」
風林火山の軍旗をはためかせた三万五千の遠征軍は、一路、京を目指して進撃の途についた。信玄の上洛をはばむものはない。尾張の織田信長にしても、所詮、信玄の敵ではない。織田同盟の最前線基地にある家康から援軍を懇願された信長は、三千の兵を差し向けたものの、出発する武将たちに「信玄と戦うてはならぬ」と、強く言いふくめている。信長は、戦国の古豪ともいう信玄と戦う愚を知っている。この巨大な敵に向かうには時機 「三河殿も、いまは息をひそめて時を稼がれよ」 と信長はいう。それはそうである。家康の手元にあるのは徳川八千の軍兵と、義理で出向してきている織田援軍三千である。全兵力を投入して兆戦してみたところで、百に一つの勝算もない。ところが、浜松城での戦評定の場で家康は、思いも寄らぬ下知を下した。 「翌朝、全軍出撃!」 日ごろ、石橋を叩いて叩いて、なお渡ろうとしない慎重な家康が、敗けるとわかった戦に、みずから飛び込んでいったのである。
「いかに信玄が勇猛とはいえ、よもや鬼神ではあるまい。それが、人もなげにわが屋敷うちを踏通ろうとするのじゃぞ、汝
と家康は、土肌色の顔をひきつらせて言いつのったという。この夜の家康は、常になく強引であった。武将たちは口ぐちに無謀さを説いて思いとどろませようとしたが、家康はまるで人変りしたような険しい表情で家臣たちを睨 しかし決断したあとの家康は、心の動揺を抑えるように、しきりに爪を噛んでいたという。
アメリカの軍事医学によると、爪を噛む癖のある兵は、戦闘にのぞむと発狂すると説 西洋史上巨大な権力を握った男のひとりであるアドルフ・ヒトラーにしても、その心理の底流には余人の窺い知れぬ臆病さが秘められていたという。ヒトラー研究の古典というヘデインの『ヒトラー伝』や、バロックの『ヒトラー・独裁政治研究』によると、素顔のかれは《月の光が怖くて》《すこしでも不安をおぼえると小指をしゃぶった》という。とすれば、戦場で不安に襲われた時、いつも爪を噛みつづけたという家康のそれと酷似している。 ともあれ、三方ヶ原の大地をとどかせて黒つなみのように進撃してくる武田騎馬軍団三万五千にむかって、突撃を敢行した徳川軍は、瞬時にして四散、馬の平首にすがりついて遁走した家康は、背中にすがりついてくる武田軍の叫喚を振り払うように浜松城に逃げ込んだ。恐怖のあまり家康が、鞍壺に脱糞したといわれるのも、この時のことだ。
ところが、いまにも発狂するのではないかと思うような形相で逃げ帰った家康が、がらりと音をたてるほどに人変わりするのは、城の搦手 この瞬間から家康の行動は、いままの表情が嘘のように、不敵なくらいの豪胆さを発揮する。家康は、怒涛のように押し寄せてくる武田軍に防戦するため、城門を閉めようとする城兵を制して、
《城門ハ閉ル事アルベカラズ(略)門ノ内外ニ大篝 と命じ、そのまま城内に入って奥女中に湯漬けを持って来させ三杯掻き込み、その場にごろり横になって高いびきをかいて眠りこんでしまった。 いっぽう、浜松城に迫った武田軍は、真一文字に開かれた大手門、あかあかと大かがり火が燃えたつ城外、城内は、打ち水をして掃ききよめられ、深として人かげもない。この、不敵な無防備ぶりに遅疑し、気を呑まれた武田軍は、 「やぁ、徳川めらは、よほどの計略をたて待ちうけておるぞ」 と、為すところなく引きあげていったという。
こうした家康の"負
徳川美術館に現存するその中の家康は、逃げ帰ったばかりで片方の籠手
家康はこの薄気味悪い画像を、生涯(絵で描 2012.06.05記 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.121~126 |
22 徳川家康(下)
|
徳川家康(下) 我一人の天下とは思うべからず(1,543~1,616年) 徳川家康の言行や逸話と伝えられるもののなかに「戦場における指揮官の心得」といった話がある。
《一軍の將たるものは、味方諸人のぼん 戦闘部隊の將たるものは、(兵士の後頭部ばかり見える)後方の安全地帯にいて口さきばかりの下知(指揮)をしていては、とても戦闘に勝てるものではない。將みずからが勇気をふるいたたせ、敵に突進していくのがよいのだ。 勝敗というものは、その時どきの運次第。勝とうと願っても勝てぬときもあるし、また、思わぬときに勝ちを得ることもある。戦場にのぞんで、いたずらに思案するは、かえって不利をまねくものと心得よ……と家康はいう。 戦場での家康が勇敢であったのは、『徳川実紀』などに登場する次のエピソードを見ればよくわかる。晩年、彼は指の中節にできたタコのために指の屈伸も思うようにならなかった。
これは、若いころから数知れぬ戦場にのぞんだ家康が、最初のうちは采配をかざして指揮しているが、戦いが白熱化してきて 切所
と、身をのりだし、右の拳を固めて鞍の前輪を叩きつけ、その激しさのあまり皮肉が破れて血が流れ、そのようなことが数限りなくあったあらだと説 その野戦の名手であった家康に、「武将」から「政治家」への転換を決断させたのが、豊臣秀吉を敵にまわして戦った小牧長久手の役である。
この戦闘で家康は、神速ともいうべき機動作戦を縦横に駆使して、秀吉軍に強烈な打撃を与え後手 しかし、戦争というのは総力戦である。武力闘争のほかに、政治、外交、経済など、さまざまな要素がふくまれている。家康は局地戦としての"戦闘"に勝ったが、大局的な"戦争"には完膚なきまでの痛撃をうけている。
じじつ、小牧の役ほど覇者への道を驀進 秀吉のこの機略には、一種、商人に似た流動感がある。これは、謀略というよりも「取引」にちかい。秀吉の見事さは、陰に陽に相手の目さきに利をちらつかせて、人を多く殺すことなく味方にひきこんでしまったことだ。 おどろいたことに秀吉は、家康がかついでいた小牧の役のめぃ目人の代表ともいうべき織田信雄までを懐柔し、家康の気づかぬあいだに単独講和をむすんでしまったのである。
こうなると家康の立場はあわれだ。いままで唯一のものとして掲げていた"盟友信長の遺児を守る"という大義名分の旗じるしが、あっ、と気づいたときはすでに秀吉が担
「おのれ、府甲斐 この小牧の役での敗北は、家康の視座を武力から政治へと大きく変換させた。家康の動向はこの頃から「政治」にむかって激しい傾斜をみせる。
家康はふたたび、かつて信長との盟約に無類の律儀 《内府(家康)の律儀さよ》 と信頼をよせられるほどの実直さで恭順ぶりをしめし、忠実にその命を奉じた。 《人は、上下、大小に限らず、事の道理を分別し、知ること専要なり》(『故老諸談』)
防御本能がつよい家康は、自分を守るために、自分を空 《万事、用心のなきというはなく》(『岩淵夜話別集』) そうした家康の「律儀」の上に歳月が流れていく。その年月のあいだ家康は、秀吉から権謀術数や政治の仕組みについて多くのことを学びとっている。家康は、この屈辱に満ちた辛酸の日々を無駄にすごしてはいない。一度懲りれば二度と同じ過失を返さない男である。
「いまに見ておれ、豊臣の奴輩 家康の凄味は、かつて自分に苦汁を飲ませたものを、そっくりそのままのかたちで相手に投げ返し、酷烈きわまりない報復をとげていることだ。
三方ヶ原で信玄に惨敗
豊臣を討滅して天下を掴むというのは、家康の執念でもあった。家康はその一事に、ながい生涯の果ての命の一しずくまでを賭
その大坂(豊臣)が家康挑発にのって軍 こうして関ケ原、大坂冬・夏ノ陣と豊臣方を断滅し、すべての事をなしおえた翌年家康は、しずかに死を迎えている。
死にのぞんだ家康は、なん戸 「まことに、水もたまらぬ斬れ味にて」 そう家康に告げると、家康は皺ばんだ頬に微笑をうかべて、その血刀を手にとり二度、三度、声をあげて素振りをくれ、 「われ、この剣をもってながく徳川の天下を鎮護せん」 といったという。戦国武将の最後を物語るにふさわしい、凄絶なエピソードである。
この時期、家康に迫ってくるおのれの死を予期していたのであろう。最後にのぞんで将軍秀忠(家康の三男)をまねき、老臣の誰彼を呼びよせ、いかにも人生の惨苦ことごとく嘗 《天下は天下之人の天下にして、我一人の天下とは思うべからず。国も又、一国之人の国にして、一人の国にはあらず》(『武蔵燭談』) 日本国六十余州は、そこに住む人びとの天下であって、われ(将軍)ひとりの天下などと思ってはならぬ。諸大みょうたちの領国や、家もまた藩主や家長ひとりのものではない、と人の上にたつ者の独断や専横な振舞いをいましめ、
「儂亡 こうして、戦国の長距離ランナー家康は、いかにも実際家の老人らしい訓戒をのこして逝く。安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士。享年七十五.
家康の死後、朴質な三河者たちは、亡主の下知をまもり、その訓 2012.06.06記 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.127~131
人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し。 急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし。
心に望み起こらば、困窮
堪忍 勝つ事ばかり知りて、負くること知らざれば害その身に至る。 己を責めても人を責めるな。及ばざるは過ぎたるより勝れり。 先に行くあとに残るも同じこと 連れて行けぬをわかれぞと思う
「滅びるときには自らの力で滅びよ」
万一徳川家に一大事が起こったときに見るようにと遺した密書が、水戸家に保存されていた。
石川 洋『一燈園法話:人生逃げ場なし』(PHP)P.84
|
23 岩垣光定
|
岩垣光定 世渡りの業は、金のごとくすべし(1,757年ごろ)
旧
《屏風と商人はすぐ(真っ直ぐ)に立たぬという事あり、しかし屏風は、下のゆがみし所へはたゝぬものなり。商人もその通りにて、五歩と一割の利は、極
商人と屏風は曲がらねば立たぬ、などと世間では誤解して莫迦
この記述などを読んでいると、まるでロッキード事件から最近の泡沫
《我が金の有
《いかに銀儲 この商人訓のなかで岩垣は、自力本願の商人の道を説き、日常の生活から商家の運営、金融に関する教えや商業手形の扱いなど、こと細かに極めて具体的に語りつづけている。 残念なことに著者、岩垣光定の来歴は不明だが、巻末の、
《宝暦 丁丑春
をみれば、宝暦七年(一七五七)ごろの京都あたりに住んでいた人物で心学(平易な言葉と通俗な譬喩で説いた庶民学)者か、また跋文(あとがき)などを読むと、心学をまなんだ商家の主人かとも思える。心学といえば、京都の儒者で経済学者でもある岩垣月洲の父、岡田南涯 ※参考:石田梅岩
ともあれ、当時の京の巷で岩垣が見聞し、体験した『商人生業鑑』五巻のなかから興味ぶかい条
《身過
岩垣がこの商人訓を書いた時代は、従来の「貴穀賤金 そうした風潮のなかで岩垣は、 《町人は禄(収入)なき事を常に忘れず》 利を稼ぎ生計を立てるのが本分だと言ってのける。
「商人というものは」百姓のように田畑も持たねば、武士のように定禄 《(わが店に)出入る人の影にて商いをし、妻子を養い渡世するゆえ貧なる人いやしき人にても、売買用にて来る人を主人のごとくおもってつとむべし》
《金銀の儲けは多くてもあてにはならず、始末(倹約)にて溜るは少なくても、積れば多く確かなり、(略)纔
《世には盗人という者、人の財宝を奪取て世をわたるは実に悪業なれど、今日の暮しならぬゆえ、命を捨てものにしてすること是非もなし。人の子として幼少よい親の介抱によりて(一人前の)人となり、芸能、。商い道残る所習得 世間には自分より利口な人がいくらでもいるということ、おぼえておけ。まことに賢い人は、賢ぶった顔をしない。例えて言えば、酒がいっぱいつまった樽は、音をたてたりはしないものだ。 《万事、時節の勢いを知りて進むときは進み、退くべき時は退くを(まことに)かしこき人というンあり》
《世渡りの業 商いというのは傘のようなものだ。(商機というなの)雨が降れば傘(商い)をひろげ、雨がやめば傘をすぼめて(慎重に)商いを堅めてゆけ。 著者の岩垣光定は、いかにも長い歳月、京の町家ぐらしをし、商人たちの生きざまを見聞きしてきた苦労人らしくやわらかな語り口で、「屏風」ではじめたこの商人訓を「傘」商法のくだりで結んでいる。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.132~137 2021.06.30記 |
24 伊藤長次郎
|
伊藤長次郎 若い時は難儀して老いては仕合わせが大いに吉(1,873~1,959年)
家訓というと、どうにも肩肱
「深酒はいかぬぞ、博奕なども所詮は"場(賭場)朽ち"、白粉くさい妓
と口癖のように掻きくどいていたようなのが、ひょっとすると後の世の末裔
《酒
などと鹿爪らしい表現で書き留められ、それがいつか「ご先祖さまご遺訓」となって伝えられたという例もないではない。しかし、そういう家訓というのは、一応の体裁を整えてはいても、ナマの肉声がもっていた説得力やバイタリティが希薄になっている場合が多い。
こうした凡百の家訓群のなかで、ときたま、いきいきした語り口の、ひどく人間臭い家訓などに出逢うと、妙に吻
その一つに幕末から昭和二十年ごろ播磨(兵庫県)十一郡にまたがって田畑をもっていた千町長者こと、今村村の伊藤家の家憲がある。小作人三千を擁して関西一と称
それらをここに紹介してみたいのだが、現代風な解釈など加えると、せつかくの雰囲気が伝わらない。原文のまま味わっていただこう。
《一、朝は随分と早く起るべし、(大切な時間をうかうかと寝ていては)勿体ない事なり。
一、心得違いでビンボーしては先祖代々の汗アブラも水の泡にして子孫も女房も難儀、又我身も難儀して人に嗤われㇳンㇳツマラズ。
一、医者には常に気を付けよ(ふだんから親しくしておけ)生身の事故、火急な病人も有るものなり。
一、寺とは随分仲よくせよ。敬せよ。布施は我身分相応に上げよ、(お)経を値切る(のは)罪なり。
一、禍福は門ならず、ただ人の招く処に在りと云えり、此の招き塩梅
一、仁、義、礼、智、信を喩
一、シマツ(倹約)はその家々によりて致し様があるものなり、兎角
一、不調法(あやまち)致した人を見て慎しみ、手柄致した人を見てまねすべし、さすれば世間に笑う人はなし、不調法する人も我が師匠なり。
一、女の美なるは傾国
一、食事は大食わるし、又先の食事の消えざるにその上に喰うはわるし、とかく腹八合(分)に喰え。食より病を起すなり、病は口より入り、禍は口より出
一、酒は朝より九ツ(真昼の十二時ごろ)迄わるし、又一合位を度々飲むは吉、大酒は至って悪し、唯よく働く人は一合位いつもよし。
一、四十歳迄の無事仕合せ(倖せ)は役に立たず、若い時は難儀して老いては仕合わせが大いに吉、依って衆も武家も難儀した程大徳(大きな得)なり、末を思うてシンボせよ。
一、仕合せは務めとシンボの報いと知れ、外に仕合せも運もなし。
一、朝早く起き、よく勤めたら八百万
一、半麦飯の香の物を食べ、その上は驕奢
一、其の道を勤めずして禄を貪り、故無くして宝を得るのは禍の基なりと云えり、拾いものすな(するな)、無理な儲けをすな、不義の富貴はうかべる雲とも云えり。
一、むそう(汚たく)儲け清う喰えと云えり、たとえ牛馬の糞を手でこねても、家業ならばよく勤めよ、また清う喰えとは、いげ(隠元)豆一勺でも盗みし物を喰うな。
一、家内上下ともに同じ菜(副食)に致すべし、別に菜を拵
一、菜は一日一度なり、一人前に三文より四文のもの、その上はおごりなり。
一、おごりさえせずば安穏にはくらされる。身の上(自分が)奢りて躰をいためるはアホ。
一、喧嘩は致すべからず、家内喧嘩は、一匁(一両の六十分の一)より安き事出来申さず。搊なり。
一、わが身(の)勤め(に)てくしゃくしゃ云うな。
一、我が子には慈愛は深く致して稽古又仕事などはキッㇳ申し付くべし、やだくさ(ぐうたら)に致すべからず。
一、仕事は昼夜きっと致すべし、大家も小家もその家々の仕事あるものなり、ぶしょうもわるし。
一、若い時は雪霜雨露を受けずば老いてよろしからず。若いときは難儀せよ。
一、運は拵えるが大いに吉、運次第運次第と云うべからず、倹約して能く働けば必ず必ず運来るべし。
一、倹約は則ち道なり、倹とは糾
一、人は皆勤め(努力)も働きもせずに此の世も未来も楽にやる積りにする。依って両方とも叶わず。
一、口に喰うと云うは中々無きものなり(自分の稼ぎで喰っていくというのは並たいていの事ではない)二百貫匁の身代でも親より預りたるものをへらしては口に喰うとは云わず(親から貰った財産を)へらさぬ人は稀なり、依って古き人も基を拵える人はあっても、保つ人は稀れなりといえり。
一、今日より驕奢(をしようと)思う人は一人もなし、是丈の事(ぐらい)は大事なし、是れ丈は大事なしとじりじりといつの間にやら驕奢となる、万事分限せよ(身の分際を考えよ)。》
この家訓を読んでいて愉快なのは、突然(近郷の住人らしい)「四六瓦屋の旦那」なる人物が登場するくだりである。
「身をもつというのは、高価な着物を着るということではない四六の瓦屋の旦那をみよ。よき身代というのは調子の低い(倹
神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.138~142
2021.06.28記
|
25 徳川吉宗

渋沢 栄一 一物に接するにも必ず満身の精神を以てすべし(1,841~1,931年)P.148~152
生まれた時期が幕末の天保年間、在所が関東平野の中央に位置する武州、血洗島村
家は代々富農で、農耕や養蚕、藍作りのほか、藍玉(藍の葉を醗酵させて固めた染料)の製造販売や金融業も営んでいた。幼少から家業を手伝った渋沢は、十四歳のころ藍玉の販売、藍葉の大量買占めをひとりでやってのけるるという商才をみせているが、その若き日の藍への思いは、後年彼が雅号を"ruby>青淵
家業に奔走すると同時に学問への情熱も燃やした渋沢は父から漢学を、隣りの手許村 《貴様はつまらぬ男だ、いま此の場で直に承知したと挨拶しろ》 という。 この日の屈辱が、封建制度に対する不満と反抗となって、やがて渋沢は尊王攘夷の道を突っ走ることになる。
《(代官は)当然の(ように)年貢を取りながら返済もせぬ金員を、用金とか何とか名を付けて取り立てて、その上、人を軽蔑嘲弄して、(まるで)貸したものでも取返すように、命示するという道理は、そもそもどこから生じたものであろうか、察するに彼の代官は、言語といい動作といい、決して知識のある人とは思われぬ、かような人物が人を軽蔑するというのは(官職を世襲するという)徳川政治から左様になったので、もはや(幕府は)弊政の極度に陥ったのである(略)。自分もこのような百姓をして居ると、彼らのような、いわばまず虫けら同様の、知恵分別もない者に軽蔑せらねばならぬ、さてさて残念千万なことである。これでは何でも百姓を罷 いらい渋沢は《慷慨憂世》の思いを抱いて、尊王攘夷派の尾高淳忠、渋沢喜作と共に六十九人の同志を集めて武装蜂起して「高崎城乗取り、横浜焼打ち」の一大攘夷計画をくわだてる。幕吏の知るところとなり、計画は頓挫。渋沢は血洗島村を出奔、江戸にむかう。二十四歳の時である。 こののち渋沢は、人生の大転換をむかえる。一橋家の用人、平岡四朗のすすめで攘夷論を捨てた渋沢は、一橋慶喜の御用談下役として出仕するが算勘(さんかん)の才を認められ一橋家の財務を預る御勘定組頭となる。 人生の運というのは、こうしたものであろう。二年後の慶應二年(一八六六)一橋慶喜は徳川家を嗣ぎ、十五代将軍に、家臣である渋沢もまた幕臣となる。翌年、慶喜の命をうけた渋沢は、パリ万国博にむかう慶喜の弟、徳川 昭武に随行してヨーロッパ各国を巡歴することになった。この西欧視察の旅で渋沢は、攘夷思想の無意味さと、ヨーロッパの工業や経済制度の重要さを、いやというほど思い知らされた。これからの日本は、 「一に経済、二にも経済」 だと、経済の仕組みや、金融制度、株式制度の知識の吸収に渋沢は夜も昼もなく没頭する。
こうして、明治元年(一八八八)十一月、徳川昭武一行は帰国。が、この間、日本は大きく変わっている。徳川幕府はすでに瓦解し、将軍慶喜は静岡の地で謹慎の身であった。その静岡藩の勘定組頭として出仕した渋沢は、わが国最初の共力合本法 以来、六十年、合本主義の旗手として実業界に乗り出し「経営の指導者」「会社づくりの名人」として渋沢がはたした役割は大きい。第一国立銀行を設立し頭取となり、つづいて国立銀行条例の改正、銀行集会所の設立、日本銀行の設立……王子製紙会社、日本郵船、大阪紡績、加えてわが国最初の私鉄、日本鉄道から鉄道国立化にいたるまで、彼が手掛けた鉄道は日本全国にひろがり、おびただしい数になった。この他にも「およそ彼が着手した事業で成功しなかったものはない」といわれたくらい、経営の世界における彼の洞察力と指導力は卓絶していた。渋沢がかかわった業種は、以上のほかに、 保険、鉱山、製鋼、陶器、造船、印刷、精油、築港、開墾、機械、教育、セメント、ビール醸造、煉瓦製造、水産、製糖、人造肥料、硝子製造、ホテル経営、輸出入業、倉庫…… など五百余、日本の産業すべてが網羅されているといっても言いすぎでではない。 「実業家というのは(わが頭脳と腕で)金を儲けることによって国に尽くしているのだ」 と強い信念ももつ渋沢は、政府の要人に癒着し、その特権によって暴利をむさぼっている政商たちの醜状に、日頃から苦々しいものを感じていた。
その渋沢栄一が生涯の信条とした家憲三則がある。第一則 処世接物の綱領。第二則 修身斉家 《一 言、忠信を主とし、行、徳(篤)敬を重んじ、事に処し人に接するには必ずその意を誠にすべし。
一 益友を近け、搊友を遠ざけ、苟 一 人に接するには必ず敬意を主とすべし。享楽遊興の時と雖も、敬礼を失うことあるべからず。
一 凡
一 富貴に驕
一 口舌は禍福の因 渋沢の口癖は 「事業は人なり」 ということであったが、晩年その『青渕百話』のなかで、 「事業家として最も警戒せねばならぬことは、協力者の不道徳、不信用だ。これほどおそるべきものはない」 と語っている。 財界の雄、渋沢財閥の大御所として活躍するかたわら彼は、後進の育成のために東京商法講習所(のち東京商科大学・現在の一橋大学)をはじめ多くの実業学校を創設し、援助をした。 昭和六年、子爵、渋沢栄一は九十二歳の波瀾多い人生の幕をとじた。
参考:『論語 巻第八 季氏第十六』
四 孔子の曰く、益者 2008.10.15
公共性を重視して活動した企業家としては、様々な名前が挙げられるだろう。しかし、経済活動と社会公益活動の両分野で大きな働きをした人物として、渋沢栄一を欠かすことはできない。
「東の渋沢栄一、西の五代友厚 欧州見聞とカルチャーショック
「日本資本主義の父」、「近代化の父」と呼ばれた渋沢栄一は、江戸末期の一八四〇年(天保十一年)に現在の埼玉県深谷 この欧州滞在時に渋沢は、武士が支配する日本社会との違いに気づいた。欧州では、商人地位の高さが国富につながっていること、また、役人が自国のものを売りこむことは決して恥ではないことを知り、日本の経済や産業の近代化のためには、人々の意識を大きく変えなければならないことを痛感した。
そして、渋沢は、江戸時代の官学であった朱子学に起因した、「商人は左の物を右へ取り渡すだけのゆがんだ利益を取る」、「義を重視する武士と異なり、商人は利益を貪る」という賤商観 五百の経済事業、六百の社会公益事業に関与 儒教的人道主義者で、国のために尽力するとう意識が強かった渋沢は、求められたさいには厭わず、様々な事業活動に尽力した。「財界の大物」といわれた渋沢が関わった経済事業の数は約五百、社会公益事業の数は約六百といわれている。事業数でいえば、社会福祉、保健・医療、労使協調、国際親善および世界平和促進、教育、災害運動などの社会・公共事業のほうが経済的な事業よりも多いのである。 渋沢も孫三郎同様、金銭を儲けることだけに専心した企業人ではなかった。経済活動と社会公益活動の両方に積極的に関わり、経済と倫理の調和を追及した企業家の先駆者であった。(以下略) 参考:大原孫三郎 2015.12.24 |
仁に過れば弱くなる、義に過れば固くなる
|
水野南北 生涯の吉凶ことごとく食より起る(1,757~1,834年)P.154~158
甘い清涼飲料を与えた実験室の二十日鼠 「にんげん生涯の吉凶ことごとく"食"によって左右される」
と説
水野南北。もとの名を鍵屋の熊太、巷の無頼漢である。五歳の頃、両親を亡くした熊太は。大坂阿波座で鍵職人をしている叔父弥助に引き取られ、鍵や錠前づくりを仕込まれるが、十歳のとき盗み飲みした酒が彼の人生を狂わせる。やがて酒代に窮した熊太は、叔父が稼ぎ貯めた有金をつかんで、出奔し、無頼遊侠の群れに身を投じる。性、凶暴。刃傷沙汰 その日、ネギ畑に囲まれた難波村の土橋ですれちがった老僧は、熊太の顔をまじまじと見て、 「ああ、いかんな。死相が出ておる」 と嘆息した。これを聞いて顔色をかえた熊太は食ってかかったが、
「まぁ聞け、いま三眼六神
腹をたてた熊太は、老僧の頭を殴りつけて帰った。が、老僧の観相はおそろしいほどに適中した。北浜の材木河岸 こうして五ヵ月たったある日、熊太は思いがけなく大坂の町角で、あの"死"を予告した老僧に出逢った。老僧は穴のあくほど熊太の顔をみつめて、 「奇妙じゃ、死相がきえておるわ」
と首をかしげた。そして老僧は「この五ヵ月のあいだ何があったか」と訊いた。熊太が瑞竜寺の和尚との食事のことを告げると、「それじゃ、人には天禄
老僧がこのとき熊太に、節食が寿命を延ばしたといったことばは、現代人の目からみても理に適っている。だいたい、熊太のような極道無頼の生活は放埓で不規則で、女色におぼれ血の気の多い魚や鳥獣の肉を啖
ともあれ、こうして老僧、水野海常の観相学に傾倒した熊太は、海常に弟子入りし、人間の運、不運や生死を予告する"顔"というものの相
「よいかな、観相というのは、ものの貌 師の海常から"水野南北"の名を与えられた熊太は、やがて「千人観相、万人観相」の悲願をたて、南は長崎から北は青森へと数年、巡歴をつづづけた後、ふたたび大坂に帰って、さらに人々の"顔"を観るため床屋の下働きとして三年……次いで"にんげんの躰"を観るため風呂屋の三助として三年……そして更に"相"を失くしたにんげんを観るため、難波千日前の火葬場で死者の顔や躰を観ること三年。
こうして、観相家として大坂の巷に立った南北の(観相術)は、すさまじいばかりに人間の"相 「だまって坐れば、ぴたりと当たる」
そんな南北の風説 「しかし……」 当代随一の観相家として世に躍り出た南北にも、なお心迷うことがある。誰彼の運命を当てたところで、それが何であろう。命を運ぶというその"運命"を予知し、凶運を吉運に導いてこそ真の相法というものではないか。そして"食"に注目した南北は、食うというもっとも素朴な営みを運命学にまで昇華させていく。 《禍を福に転ずるの道は食に在り》 そのことは彼の著『南北相伝』全十巻、『相伝極意、修身録』全四巻にくわしい。 《生涯の吉凶ことごとく食より起る。怒るべきは食なり、慎むべきは食なり。(略)常に大食暴食の者、たとえ(人相学的に)相貌大いによろしくとも、身分しかと治まりがたし》
南北のこの「慎食の教え」、食の相法は、南北自身の世間放浪の経験と見解から発した独創的なものであった。唐
《食の多少を以て富貴貧賤寿夭
《凡そ心身を養うの本は食なり、それを厳重に養わざれば心身厳重ならず、身を治まること能
百発百中と称 それはもはや相学だけのものではなく、すでに一つの思想であった。
南北が実証によって理を極め、集大成した希代 晩年、南北は光格天皇より《天下一》の号を賜わり、従五位出羽之介に叙せられている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.154~158 2021.06.08記 |
|
陸奥宗光 堪忍のできるだけ堪忍すべし(1,844~1,897年)P.159~164
土佐海援隊、坂本竜馬
紀州藩勘定奉行、伊達宗広の六男に生まれた陸奥は、藩の政変によって父は幽閉、陸奥も家族らと共に城外十里四方追放の身となる。当時、牛麿と名乗っていた十歳のころである。この時の藩庁への恨みは深く陸奥の胸に灼 いらい陸奥は、久度山、高野山、奈良などの農家を転々としながら勉学に打ちこんだが、打ちこめば打ちこむほど屈辱の思いがこみあげてくる。遂に思いを決した陸奥は、
朝 飄身(ひようしん」)漂泊難船に似たり 他事争い得ん鵬翼(ほうよく)の生ずるを
一挙に雲を排して九天に翔 の詩をのこして出奔、江戸にむかう。このとき陸奥、十五歳。この、紀州藩憎しの思いが、いつか陸奥を勤王思想に突き進ませていく。 こうして幕末風雪のなかを江戸から京にのぼった陸奥は、ここに居を移していた父、宗広と再会。この父の家で土佐の坂本竜馬を知る。 やがて勝海舟の神戸操練所から坂本竜馬の海援隊に入った陸奥は、長州の伊藤俊輔(博文)、土佐の後藤象二郎らと勤王の革命運動に奔走する。が、陸奥の行動は世の常の志士からみれば異色であった。 《他の連中が討幕とか挙兵とか目を吊りあげて議論している時でも、しずかに本を読み考えているようであった。》 と、大江卓の後日譚にいう。 頭のよさで定評があったが、あまりにも理知的で冷静さを失ったことがない陸奥の評判は、海援隊でもあまりよくない。誰よりも陸奥の見識と才幹を愛し将来を期待していた隊長の竜馬でさえも、 「こいつは他日ひとかどの人物になるにはちがいないが、あまり才幹を弄すと同志に憎まれ、殺されるかもしれん」 と案じたという。
坂本が心配するのもむりはない。当時の志士たちの写真をみても、いずれも眼光けわしく、手にピストルや太刀を摑みすえた殺伐としたものばかりだが、その中で若き日の陸奥は、まるで映画で見る鞍馬天狗そのまま、黒頭巾に黒ちりめんの紋付をぞろりと着流し、腰の大小は落し差し、白たびに舞妓のはくような木履
もっとも、こんなところは世間より一歩進んだ現実と抱負を論じて、土佐勤皇党の首領、武市半平太から「ほらふき竜馬」と冷やかされた坂本の、よれよれの袴に洋靴、ふところ手をして写真におさまっている姿と似ていなくもない。似ているといえば、坂本の「ほらふき竜馬」と同様に陸奥もまた、めまぐるしく変転する現実の先々を読みながら、巧みに身を処していくその変貌ぶりを「うそつき小二郎」と称
陸奥の第二の出発は、この坂本竜馬の死を乗り越えた時からはじまる。王政復古が成って明治新政府が生まれると陸奥は、岩倉具視の推挙を得て徴士 このあと陸奥は、備前藩士による外人殺傷事件(神戸事件)、土佐藩士によるフランス人殺傷事件(堺事件)、イギリス公使の遭難事件などの外交問題を処理して、のち摂津、兵庫など諸県知事を歴任。明治四年、神奈川県知事、同五年、陸奥が主唱する地租改正問題に取り組み地租改正局長となる。同八年、元老院議官。 しかし、陸奥ほどの《衆を超えた見識と才略》の持ち主が薩長閥で占められた新政府に満足できる筈はない。おりからの西南戦争に乗じて土佐立志社と語らい政府転覆をくわだてる。が、事は未然に破れ、投獄されること五年。 明治十五年、特赦出獄した陸奥は、伊藤博文のすすめで欧州諸国を巡歴し憲法を調査。帰国後、不死鳥のごとく新政府に返り咲いた陸奥は、駐米大使、山県内閣の農商務大臣、枢密顧問官となり、第二伊藤内閣の外務大臣として列強諸国、メキシコ、イギリス、清国(中国)、ロシアを相手に、鮮やかな外交手腕をふるう。
明治のジャーナリスト鳥屋部春汀 《奇才、術策に富み、人よんでカミソリ大臣》 と評した陸奥の、そのカミソリが凄まじい斬れ味をみせるのは、明治新政府の大きな課題であった条約改正を見事に成し遂げた瞬間である。 卓抜した政治手腕で強国イギリスと対等で通商条約を結んだ陸奥は、ロシアの干渉を拒絶、日清講和条約、三国干渉などの外交面の難局を切りぬけると、日本の外交史上忘れることのできない足跡を残している。しかもそれが薩摩や長州の藩閥政治のなかで、藩閥のバックもない一匹狼の彼が、それだけの功業を成したのである。並々ならぬ見識と力量といわねばならない。 しかし、その陸奥を評して、
《彼は理想もあり目先も見えたが、権略家だけに人にたいしては現金であった。朝 と『当世策士伝』にいう。 だが、それが政治の本質ではないだろうか。陸奥は感情に走ったり思想的な立場によって左右される男ではなかった。 つねにそれを冷然と凝視している現実家であった。事をなすに当っては細心に考慮し、断行すれば手段を選ばなかった。このため陸奥の"策"には違算がすくない。だが、この陸奥の合理精神は、近代の夜明を迎えたばかりの日本で理解される筈はなかった。この時代、陸奥ほどの近代感覚をそなえた政治家は大久保利通ぐらいのものであろう。
辛酸に満ちた人生をくぐりぬけ、冷徹な眼で現実を瞶 《諸事堪忍すべし 堪忍のできるだけ堪忍すべし 堪忍のできざることに会すれば決して堪忍すべからず》 と、よく言ったという。そしてまた陸奥は、 「日本人にはNOといえる者がすくない。どうしてもYESということができぬ場合は、敢然としてNOと言え」 と、声を重ねている。 が、世間は時として軽率である。 陸奥が誠実の行為と信じた、勇気のある「NO」が、冷淡、不親切などの批判をうけ、そのため陸奥は数多くの政敵をつくった(『陸奥宗光伯』)。 陸奥が広吉に語った「NOという気魄」が、平成日本の、腑抜けたような外交に最も欠けているものであろう。明治三十年八月、伯爵、陸奥宗光死す。五十四歳。欧米列強と骨身を削るような外交の辛苦が、いつか胸を冒していたのである。死の直前、友人の一人に陸奥は、ぼそりと言った。 「皆と離れ、家族と別れて逝くのを淋しいとは思わないが、もう政治ができなくなると思うと、それが滅法かなしいよ」 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.159~164 2021.06.24記 |
|
藤堂高虎 常によき友と咄し、異見をも請け申すべく候(1,556~1,630年)P.165~169
戦国時代というのは「七たび牢人せねば武士
その戦国の世に、それを絵に描
こうして「渡り武者」となった高虎は、槍をかつぎ具足を背にして戦国の野を放浪する。高虎は不運であった。近江の阿閉淡路守
やがて高虎は手づるを得て織田信長の弟、信行の子、織田七郎兵衛信澄に仕える。ところがこの織田信澄も、妻が明智光秀の女
次に高虎は、秀吉の弟、羽柴秀長に仕え、禄三百石を振り出しに、播州別所攻め、九州の島津攻めで奮迅し、やがて二万石、従五位下
さすがの高虎も、六度目のこの不運にはがっくりした。しかし、後年「戦国の寝業師」と称 この高虎の懸命の「賭け」は当った。かれの遁世を知った豊臣秀吉は、その志をあわれみ、「予に仕えよ」 と高虎の翻意をうながした。召喚の命をうけた高虎は伏見城に赴き、秀吉に拝謁し、伊予七万石の封をうける。秀俊の死から、わずか二ヵ月のことである。
こうしてピンチをチャンスに活 「戦国を生きるに必要なのは、戦場働きよりも、処世の巧妙さであろう」 そのため高虎は、大恩のある秀吉にさえも容赦ない目をむけ、観察しつづけている。 「豊臣の世も、所詮は秀吉一代か」 秀吉の老齢、朝鮮出兵の濫費は諸大みょうと領民を疲弊させ、豊臣政権への魅力を失わしめている。 「となると、次の天下は?」 それは云うまでもなく、関八洲に広大な所領をもつ徳川家康である。高虎は、身をすり寄せるように家康への接近をはかった。そしてやがて秀吉が死病の床につく頃になると高虎は、豊臣色の濃い反徳川派の大みょうたちの動向を探って、その情報を細大もらさず家康のもとに運びこんだ。ほどなく秀吉が死に、家康と反徳川の石田三成党とのあいだに不穏な気がただよいはじめた。ある夜、三成らの家康打倒の陰謀を察知した高虎からの急報によって、家康は大坂の高虎邸に難を避け、危機を脱した。 「佐渡守(高虎)殿は奇特の仁じや」 そんな高虎の行為が、徳川家の重臣たちに不愉快な筈はない。後年、高虎は徳川家に"大忠"の者として外様大みょうでは真っ先に"松平"の姓を許され譜代同然の扱いをうけたのも、諸侯に先んじてわが身を売り込んできた高虎の行動を徳川家が賞したからであろう。 家康が石田党討滅の軍をひきいて天下分け目の関ケ原にむかったのも、開戦前から、時々刻々と変化する諸大名たちの動向を細かに報告しつづけた高虎からの諜報によってである。この時期、舞台裏での高虎の活躍は巧妙をきわめている。関ケ原の合戦は小早川秀秋らの裏切りによって形勢は逆転する。が、この裏切り大名たちは、開戦直前、家康の密命をうけた高虎が、ひそかに裏面工作をしていたものだ。 関ケ原の陣ののち、これら一連の"功みょう"によって高虎は、一足跳びに二十万万石の大みょうになり、それがやがて二十二万万石……二十七万石……そして伊賀および伊勢半国に山城、大和の一部を加えて三十二万千九百五十石の身上にのしあがっていく。 こうした高虎の処世法を物語るエピソードがある。あるとき、二条城の改築を命じられた高虎は、設計図を二通りつくった。 「このわけが、わかる」 高虎は近習にいった。二種類というのは、誰の目にも不備な図面と、見事にすぐれたもの二種類である。その二つの図面を家康に差し出せば、よい方を家康が採る。当然であろう。で、不備な図面を選ぶのは、もちろん高虎である。こうしてあるじの選んだすぐれた図面をもとに仕事をすすめていく。
「万事、善 と高虎は言ったという。ゴマすりの権化と化したような、世間功者の高虎らしい言葉である。だが、このゴマすりの、名人芸ともいう保身術が、藤堂藩三十二万三千九百五十石を、徳川三百年のあいだ一粒の減封も国替もなく安泰にすごさせたのである。 その高虎が、嫡男高次に遺した全文二十一ヵ条からなる、藩主としての心得がある。それらの中から幾つか掲げてみると、
《一、常によき友と咄(はな)し、異(意)見をも請
《一、家中の者共奉公の道、忠こそあらば、小忠を大忠になし、加増をも遣
《一、家中の者、武道の上、傍輩 家臣のどんな小さな手柄でも、それを大きく賞して俸禄を増やしてやるがよい。また、藩士の中でずばぬけた忠節の士があれば、これを他国の評判になるほどの褒美を与え家来をつけてやるなど、他藩よりも家臣を重用して召使うがよい。
《一、代官物賄
藩士たちの仕事の中でも、徴税や経理、または食糧、弾薬の運搬補給を役目とする者も、戦闘部隊同様に目をかけてやれ。戦場に出て戦う藩士も、後方にあって作戦のため軍需品の補給、輸送やその事務にたずさわる藩士も、車の両輪である、と高虎はいう。いかにも人生の辛苦を甞めてきた、苦労人らしい訓 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.165~169 2021.06.12記 |
30 大村 彦太郎
|
大村 彦太郎 商いは高利によらず、正直によき物を売れ(1636~1689年)P.170~175 戦前、三越、松坂屋、高島屋などと肩を並べたデパート業界の名門であった東京、白木屋おなが、全国浦々浦々に知れわたったのは、昭和七年(一九三二)歳末の大火によってである。 《白木屋大火のいましめ 外出時には必ずズロースを 同デパートの専務語る》(朝日新聞7.12.23) 《今度の火災で痛感した事は女店員が折角ツナを或いはトイ(樋)を伝わって降りてきても、五階、四階と降りて二、三階のところまでくると下に見物人(野次馬)が沢山雲集して上を見上げて騒いでいる。若い女の事とて(着物の)裾の乱れているのが気になって、片手でロープにすがりつきながら片手で裾をおさえたりするため、手がゆるんで墜落してしまった。(略)今後女店員にはこうした事のないよう全部強制的にズロースを用いさせる積りですが、お客様の方でも万一の場合の用意に外出する時にはこの位の事は心得て頂きたいものです。尊い犠牲者が教えてくれたこの教訓を無駄にせぬよう努力する積りです》 この、十四人の女店員の墜死が、日本人の女性にパンティをはかせるきっかけになるのだが、白木屋百貨店の来歴は、湖国近江(滋賀県)の片ほとりからはじまる。 寛永十三年(一六三六)長浜で生まれた大村彦太郎(初代)は、幼くして父道与と死別し、母親の実家、河崎家に引きとられた。河崎家は、飛騨の材木を京、大坂で売りさばく材木商、白木屋をひらいた。 一説によると、彦太郎が京へ出立する時、日頃から学んでいた長浜、良疇(りょうちゅう)寺の法山和尚から、 「くじけることなく(商売に)励むためには信仰が大事じゃ」 と小さな観音仏を与えられ、 「成功したら、十年後この寺を訪ねてこい」 と励まされたという。 京にでた彦太郎は、材木商のかたわら綿布などの行商に出精すること十年。相当な財を蓄積した彦太郎は、約束通り長浜の法山和尚を訪ねる。 よくやった。が、さらに十年、世に知られる商人になって訪ねてこい? 法山の言葉にふるい立った彦太郎は、これを機会に投機性が強くて不安定な材木商をやめ、小間物、呉服の分野への進出をはかり、江戸に赴いてお江戸随一の繁華街、日本橋通二丁目に小さな店をかまえた。 しかし、彦太郎は慎重であった。開業当初は、多額の資金を寝せねばならない呉服扱いを避け、ひたすら、 商内(あきない)は高利をとらず 正直に 末は繁盛(彦太郎の道歌) と、正直と奉仕に徹する商法を展開した。 彦太郎が念願の呉服に手をだし、羽二重(純白の絹布)を売りだしたのは、開業六年目のことである。白木屋、大村彦太郎の地道で堅実なこの商法は、やがて彼を銀五百二十余貫(純資産)の大商人の座に押しあげていく。 こうして彦太郎は十年後、ふたたび長浜に法山和尚を訪ねる。 「よくやった、あと一息じゃ彦太郎、こんど来る時は日本一の商人になってこい」 法山の激励をうけた彦太郎は以来十年、江戸きっての商人、小間物類から呉服を扱う大呉服店にのしあがって、三たび良疇寺の法山和尚を訪ねるが、その時すでに法山は世を去っていた。彦太郎はその、人生の師ともいうべき法山の墓石にすがりつき、声を放って哭(な)いたという。 彦太郎が大番頭に命じて家法をつくらせたのは、創業八年目の寛永十年(一六七〇)のことである。この、五項にわたる簡潔な家法は、その末尾に番頭以下使用人十四人がそれぞれ署名し、大番頭の中川治兵衛に差出した一種の誓約書ともいうべき異色の『白木屋定法』であった。 《一、御公儀様より仰せ出され候御法度の旨相守り申すべく候事 一、衆中(人びとの中で)誰に寄らず悪事(を働く者)は申すに及ばず非儀申さる者御座候わば、見付け次第少しも隠し立てず早速申出べく候、(略)合点参らざる(なつ得いかぬ振舞のある)者御座候わば、議事(誰彼)に寄らず申し進む(出る)べき事 一、諸事非儀(よからぬ振舞)之なき様に人々我(わがまま)を慎み正直に相勤め偽なる儀申すまじく候。殊に他所に於いて女さばくり(おんな道楽)仕り申すまじく候事 右の趣相守り申すべく候。少しも違背仕るまじく候、仏神は(この)紙面に及び候。 仍 如 件 寛文十年九月晦日 横田太兵衛 高田又兵衛 (以下十四人) 中川治兵衛 殿》 元禄二年(一六八九)大村彦太郎逝く。 彦太郎が、法山和尚と約束して三度目に長浜を来訪した日から十年目、二代目彦太郎は、亡父にかわり良疇寺を訪れ、法山と彦太郎の冥福を祈って銀五十貫を寄進している。 創業者彦太郎の商いに対する《商いは高利によらず、正直によき物を売れ》という堅実と倹約を家訓とした姿勢は、二代目彦太郎以降の彦太郎代々に受け継がれ、三井家の越後屋に迫るほどの大呉服店となり、当時の商人たちの理想である、京都に本店を持った、いわゆる「江戸店(たな)持ち京商人」として繁栄の一途を辿っていった。 大村家の家法は、こののち、白木屋中興の祖といわれる四代彦太郎によって享保八年(一七二三)に改訂、増補されている。 《一、酒は商人衆(取引先の商人を)饗応(接待)の為に候処、手前に過ぎ(自分で酩酊)候えば商人衆へ無挨拶(失礼)、他所(よそ)にて酒用い(宴席を設け)候事無用たるべく候。酒の上にて宜しからざる事も之れ有る物に候間、堅く相守り申さるべく候事。 一、諸式(諸商品)商事の儀、地田舎集衆(地方の得意先に限らず商人衆(取引先)を大切に致すべく候、少しの買物致され候衆中を尚以て懇篤に致し遣し申すべく候。大商人衆中の分は自然大切に成候間、買物多少に限らず、客衆を随分懇意に遊ばされ何とか相調え帰り申候みぎりは、見世端(みせばた)まで成べく腰をかがめ懇に挨拶致(せば)又重て買物に被来候(こられ)。》 お客様が買物をして帰るときは、買物の多少にかかわらず、店の表まで出て腰をかがめ、心をこめてお礼を申しあげれば、また、買物に来てくださるものである。 ――こうして白木屋は、江戸から東京へと三百年にわたる風雪を乗り越え、明治三十六年(一九〇三)わが国最初の洋式建築百貨店として登場。デパート業界に新風を吹き込む。 が、歳月というのは酷薄である。白木屋代々の人々が営々と築きあげてきたこの百貨店も、戦後、横井英樹の乗っ取り騒動に捲きこまれ、東急百貨店に吸収。現在の東急百貨店日本橋店からは、かつてのイ白木屋の面影は偲ぶよしもない。 神坂次郎『男この言葉』P.170~P.175 2021.06.12記 |
31 足利尊氏
|
足利尊氏 文武両道は、車輪の如し(1,305~1,358年)P.176~181
足利尊氏といえば、戦闘を終えて凱旋してしてくる勇壮な武将ぶりを描いた画像が伝えられている。尊氏の子義詮 足利氏の祖は、八幡太郎源義家の第三子、源義国の晩年、足利の別業(別荘)にこもり、その次男の源義康が足利の庄を伝領したことからはじまる。 のちに室町幕府の創設者になる尊氏(別名を高氏)はこの直系、足利貞氏(さだうじ)の嫡男として生まれている。
この足利氏の氏寺である鑁阿寺( 「天下を取れなかった八幡太郎義家が、七代目の子孫に生まれかわって、かならず天下を取る」
といった『鑁阿寺の置文( そしてその義家から数えて五代目の足利義氏のとき、機会がやってきた。鎌倉の三代将軍源実朝が、鶴岡八幡宮で暗殺され、頼朝系の血統が絶えた。源氏の嫡流から後継者を選ぶとすれば、足利義氏こそ最有力の候補者であろう。 しかし、その期待は空しかった。 頼朝の外戚でしかない北条氏が、名目だけの将軍を京都から迎え、その実権を握り、みずから執権(幕府長官)として勢威大いにふるったのである。 こうして足利一族の不満のうちに時が流れ、七代目の足利家時の代になったとき、北条氏に膝を屈しているわが身に堪えられなくなった家時は、 「わが命にかえて、三代目の子孫に天下を取らせしめたまえ」 と置文して、割腹して果てた(『難太平記』今川了俊)。 高氏はその家時から三代目にあたる。 鎌倉幕府の御家人(直属の臣)として歴々の陽のあたる場所にいたとはいえ、高氏というその名も、執権、北条高塒から一字与えられたものだ。 この足利一族の「源氏再興」の悲願を背負った高氏が、動乱の『太平記』の世界に登場してくるのは、二十七歳の時である。 「天皇ご謀反!」 皇居を脱出して笠置山にたてこもった後醍醐天皇討伐のため、高氏は幕府の大将軍として出陣。世にいう元弘の変でる。
以来、高氏の行動は背信、変節いとまない騒乱のなかで転々とする。 昨日の味方が今日の敵となり、一門一族のなかでも我欲おもむくままに裏切り、殺し合い、血で血を洗うような修羅の世界であった 当時のこの武士たちの向背、去就ただならぬ世相を語るものに《降参半分ノ法》というのがある。いったん裏切っても、状況不利とみれば降参すればよいのだ。「降参人は、所領の半分または三分の一を差出して詫びを入れれば、首まで取られることはない」という慣習が立法化されていたから、簡単に裏切り、寝返りをくり返していた。
元弘三年、笠置で捕えられ隠岐(島根県)に流された後醍醐帝はふたたび脱出。後醍醐帝軍を討つことを命じられた高氏は、ひそかに後醍醐帝の綸旨(
けれど、尊氏はほどなく後醍醐帝と対立し、持明院の豊仁(
尊氏の来歴を駆け足で眺めてくると、いかにも乱世の梟雄( 尊氏をよく知る臨済宗の禅僧、夢窓疎石の尊氏評によると、かれのすぐれたところが三つあり、
「第一に、戦場にのぞんで咲( という。 そんな尊氏のやさしさと教養の深さをうかがわせるのが、光明天皇を即位させた二日後、清水寺におさめた見事な筆跡の「願文」である。
《この世は夢のごとくに候。尊氏にだう(道)心たば(賜)せ給( 建武三年八月十日 尊氏 (花押)清水寺》
この修羅の世はまさに悪夢のようだ、と嘆じた尊氏は、せめてあの世に赴いたとき、迷い多い私を救うてくだされ、この世での果報というものがあれば、弟の直義に与え、直義を穏やかにすごさせてくだされ……という尊氏の念(
をく露の はや落ちにきや女郎花((等持院(尊氏)殿百首)
こうした尊氏の魅力は、勝ち戦よりも退却の場合に、より濃くあらわれてくる。当時の、欲望をぎらつかせた将兵たちは、ひとたび退却するとなると雲散霧消、まるで春の大潮が引いていくように、数万あった軍団もたちまち、わずか十数騎などといった惨憺たる有様になるのが常であった。が、戦いに利なく尊氏が九州へ落ちていった時など、その悠々たる態度と、勝利に逆転した場合の「呉れっぷり」のよさが人心を集め、やがて九州から巻き返しにでて東上し、逆寄( 尊氏は最晩年の延文二年(一三五七)二十一箇条からなる『等持院御遺言殿』を書き残している。
《文武両道は、車輪の如し。一輪欠ければ人を度( 国を治めるものは学問を身につけるべきである。とはいえ、戦だけを働きとする武者には学問などは無用である。 《五兵にたずさわる者に、文学は無用なるべし》
刀など五種類の武器をもって戦う男たちに学問は無用。生かじりの学問をもてあそべば、口先ばかり達者で心正しからざる《侫者( 神坂次郎『男この言葉』 P.176~181 2021.05.24記 |
32 豊臣 秀吉
|
豊臣秀吉 主人は無理を云うなるものと知れ(1,537~1,598年)P.182~187 にんげんは、その長い生涯において身を引き裂かれる思いで決断を迫られる場合がある。 歴史は、そんな人生の岐路に立って、決断という名のサイコロを投じた男たちの明暗とさまざまな表情を描きだしている。
一瞬の決断に賭 歴史は、そんな男たちの、人生の転機に賭けた成敗を、淡々とわたしたちに語りかけてくる。 主君、信長の死という悲運を逆手にとって、天下人への"運"を秀吉が掴むのは、わずか一時間余の決断であった。
だが、その一時間余こそ秀吉が一世一代、脳漿
このとき秀吉は、中国遠征軍の司令官として備中(岡山県)高松城攻めの本陣で、毛利・吉川 「しかし……」 本能寺の変を知った瞬間、秀吉は思った。 「それが、どうしたというのだ」 遠征軍をひきいて各地に布陣している織田家の武将たちの誰よりも速く、光秀討滅に駆けのぼれば、ナンバー1になれる。
秀吉の決断は早い。すぐさま毛利家と和睦を結んだ。間一髪であった。この和議の誓紙 この後の行動は機敏をきわめている。
こうして中国撤退の秀吉軍二万余の軍団は、連日の雨と洪水で泥の海と化した山陽道を凄まじい速度で駆けぬけて行った。これが後のちまで秀吉の「中国大返
篠 備中高松を出て姫路まで行程六十キロ。ここまでくれば毛利軍から追撃される懸念もない。 姫路に着いてからの秀吉の行動は、なんとも豪快で底抜けに明るく、天下取りの面目躍如たるものがある。城に入った秀吉はすぐさま風呂に入って汗と泥を落し、湯殿にすわりこんだまま、小姓を呼び、一切の軍令を発している。世にいう「お湯殿の号令」である。 陣立てを下知すると秀吉は、次に金奉行や蔵奉行を呼びよせ、姫路城にあるだけの黄金、銀、銭から八万五千石の米一粒残らず秀吉軍団の武将から足軽、小者にいたるまで知行(石高)に応じて全員に分け与えてしまったのである。
その夜、秀吉はじめ全軍の将兵は泥のごとく眠って、翌、払暁 「者ども、駈けよ!」
戦いには、「機」というものがある。いかに大軍を抱いていてもその機をはずしては玩具 尼崎での秀吉は、全軍の将兵におびただしい魚や獣肉を振舞って精気を充満させ、天下分け目の決戦の地、山崎にむかった。このとき、各地から従軍をもとめて加わる諸大みょう軍のため秀吉軍団は雪だるまのごとくふくれあがった。
後日譚になるが、このとき秀吉の家臣で足腰も立たぬ病のため行軍に加わっていない男がいた。山崎の合戦のあと秀吉は、この家臣を斬罪 秀吉軍の進撃の予想外の速さに、光秀軍は動揺した。秀才型の光秀は、こうした不測の事態への対応が不得手であった。
動揺するといえば、娘婿の細川忠興 こうした秀吉の、天下取りとしての「英雄的資質」のあらわれの一つは、この(姫路城でみる)呉れっぷりのよさであろう。呉れっぷりのよさが人を動かすのは、戦国の世も平成の現在の「政治」の世界もかわりはない。 こうした秀吉の「人たらし」「カネくばり」は、こののちの諸戦場でも、よく見られる。敵の首を掻き切って駆け戻ってくる武者たちに、本陣の秀吉は、 「あつぱれ、ようやった」
と傍 《多くの金銀を土蔵に積んでおくのは、有能な人間を牢に押し込めておくに等しい》 という秀吉の、生涯最大の大盤振舞は、天正十七年(一五八九)聚楽第で徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝ら大みょうたちへのカネくばりであろう。 このとき秀吉が、家康らに与えたのは金五千枚、銀三万枚、これだけ貰えば、誰だって「粉骨砕身」を誓ってしまう。 秀吉が日ごろ、近臣たちによく語っていたという処世訓が幾つか伝えられている。
《一、朝寝すべからず
秀吉が一代の栄をきわめた絢爛豪華な聚楽第が完成したとき、その門の扉に誰かが、 「奢るもの久しからず」 と落書きして貼り付けていた。
それをみた秀吉はにやりと微笑 《奢らずとも久しからず》 と、書きくわえたという。
大気者
神坂次郎『男この言葉』P.182~187
|
33 伊達 政宗
|
伊達 政宗 仁に過れば弱くなる、義に過れば固くなる(1,567~1,636年)P.188~194 戦国の梟雄といわれた伊達政宗は、晩年、波瀾をきわめたみずからの生涯を振り返って一つの詩を詠んでいる。 馬上少年過ぐ 世平らかにし白髪多し
残躯
楽しまざるをこれ如何
少年と書いて、わかき年とよむのであろう。この清々
正宗は、その誕生からして劇的であった。母は出羽山形城主、最上修理大夫義守の娘、義子で、戦国の世のならいで米沢城の伊達輝宗のもとに輿入れしたが、この美貌の新妻は"鬼婆"とよばれたほど勝気で驕慢であった。嫁して五年、子宝にめぐまれず、やがて伊達家の老臣たちから離別ばなしがもちあがり、輝宗に側室をすすめよという話がでてきた。
この噂を耳にして目を吊り上げた義子は、高名な和尚を湯殿山に籠らせ、わが身も白衣をまとい護摩を焚き、死物狂いの祈願をつづける。こうして懐妊した義子は、世子、梵天丸(正宗)を生み落した。梵天丸は勝気な母の意地と執念が生ませた奇蹟の子であった。
だが、こうした稚
美貌でわがままな母は、みにくい正宗を嫌い、正宗の弟竺丸を溺愛し、夫の輝宗に再三、正宗を廃嫡し竺丸を跡継ぎにしようと働きかける。そして輝宗が同意しないとみると、刺客を正宗の寝所におくりこみ、眠りこんでいる正宗を絞殺しようとくわだてるが、事は未然に破れる。
しかし、こんなことで断念する義子ではない、次には毒殺をはかるが、これもまた未遂におわる。危険を感じた父の輝宗は、家督争いの根を絶つため、天正十二年(一五八四)正宗に伊達家十七代の当主の座をゆずり、隠居してしまった。ときに正宗十八歳である。
のち正宗は、父の輝宗が敵方の畠山義継に拉致されたのを知って駈けつけ、畠山を銃撃して殺すが輝宗はそのとき義継から刺殺されるという、正宗生涯最大の悲劇が起こっている。
ともあれ、輝宗の死によって伊達家中に完全な独裁権力を築いた正宗は、以来、二万三千余騎の伊達軍団をひきい奥羽の覇者街道疾駆しつずける。
父の死の翌日、芦名、佐竹、岩城、石川ら連合軍三万を相手に激戦をくりひろげ、剽悍無類の武みょうを天下にひびかせ、やがて、仙道七郎を征服し、さらに出羽国に進撃し所領百万石。二十三歳にして、かつての藤原三代と肩を並べるほどの広大な領土をわが手に掴んだ。
天正十八年(一五九〇)豊臣秀吉が小田原の北条氏討伐の軍をおこし、奥羽の諸大みょうに小田原参陣をもとめたとき正宗は、
「いまは と形勢を観望して、出兵をしぶっていた。
その後、戦況は北条氏に不利とみた正宗は、ようやく重い腰をあげた。このときの正宗の演出ぶりは見事である。秀吉に謁見するにあたって、髪を水引で結び、白衣の死装束で諸大みょうの居並ぶなかを、秀吉の前に膝行 これが効を奏したのか、旧芦名領は没収されたものの七十余万石は安泰であった。 正宗の二度目の危機は、戦国の葛西大崎の一揆を正宗が背後から煽動しているという疑いをかけられた時である。※葛西大崎一揆(かさいおおさきいっき)は、天正18年(1590年)に発生した、豊臣秀吉の奥州仕置により改易された葛西氏・大崎氏らの旧臣による新領主の木村吉清・清久父子に対する反乱である。
この時も正宗は、行列の先頭に金箔を貼りつめたわが身の磔
こうして一歩踏みはずせば奈落に転落しようという修羅を踏みこえてきた正宗に、次のような
《一、仁に過ぐれば弱くなる
義に過ぐれば固くなる
礼に過ぐれば諂
智に過ぎれば嘘をつく
信に過れば搊をする
一、気長く心穏やかにして、万
一、朝夕の食事はうまからずともほめて食ふべし。元来客の身になれば好嫌ひは申されまじ
一、今日行
仁・義・礼・智・信の五常、五倫(りん)を政宗流に解釈し、苦しいことや不自由なることがあっても「この世に客にきた」と思えばよいのだ。たとえ、朝夕の食事がまずくとも、「この世に客にきた身だ」と思って喰ってやれ、と政宗は説
おさない頃から辛酸をなめてきただけに、正宗には人に接する時の気くばりがある。
《かりそめにも人に振舞うとあらば、料理第一と心得よ》
人に馳走するときは、家人だけにまかせず、主人も目くばりしてその人の好むものを品よく出すべきである。
相手の身分にかかわらず、正宗が心くばりをしたという例が、次のエピソードの中に読みとることができる。
――あるとき伊達邸へ、友人の毛利長門守がきた。長門守は違い棚に置かれていた「香匙火箸」
これは模様のよい香匙でござる、いずれ拝借して写したいものよ」
「いつにても、お持ちなされ」
何日か経ったある日、長門守から
「いつぞや約束の香匙を借りてまいれ」
と家臣のひとりが使者を仰せつかった。その家臣は、聞きなれぬ品物の名に、それから先、馬に乗るのにも降りるのにも、口のなかでもごもご、
「香匙火箸、香匙火箸」
と呟き呟き、伊達邸へ着いた。そして取次に出た伊達の家臣に、早速、香匙火箸の借用を申し入れた。
「香匙火箸?」
そういうと伊達の家臣のほうも耳なれない品のなを呪文
ところが、数多い部屋の唐紙を開け閉めし、立つたり坐ったりしているちに、ころりと「借用の品物」の名を忘れてしまった。
「ええい、いま一度訊いてくるか」
と、小走りに使者の前まできて、
「さて、先ほどお伺い申しましたあの品のなは?」
だが、運の悪いことに使者の方も、取次の者に述べた途端、吻
その手紙には「今日の使者ぶり、あつぱれ日本一の者、よき褒美(を与え)なされたし」と書かれていた。正宗は、借用の品のなを失念し苦しまぎれに「わが(毛利)家の作法」と胸を張った使者の、その武辺者らしい負けぬ気を愛したのであろう。使者の家臣は即日、長門守から加増されたという。
神坂次郎『男この言葉』 P.188~194
|
|
徳川頼宣 父母に孝行、法度を守り、奢らずに家職に勤めよ父母に孝行、法度を守り、奢らずに家職に勤めよ ((1671~1602年)P.195~201
徳川家康が才はじけて勝気で、宝子 「紀州は南海に突出して、西のかたは阿波、淡路を制し、北は京都、近畿をひかえ、東方は大和、伊勢につらなり西国第一の要衝である。ゆえに至親の者に守らしめよ」 との家康の遺命をふくんだ頼宣は、駿河、遠江(静岡県)五十万石の地を離れて紀州に入国する。 これが俗にいう"駿河越え"である。このとき頼宣に従ってお国入りをしたのは家臣ばかりではない。おびただしい数の百姓や商工業者も加わり、ちょっとした民族の大移動の観があったという。そのせいか、城下町和歌山の方言は、いまも三河方言の残欠を尾骶骨のようにとどめている。こうして徳川御三家の一、紀州一国と伊勢の一部をくわえて五十五万五千石の紀州徳川家が誕生する。 頼宣の向う気の強さは、十四歳で大坂の陣に初陣したときの話からもうかがえる。先陣をゆるされず、その不満を茶臼山の本陣にいる家康に訴え、涙をこぼして口惜しがった(『藩翰譜』)。 と、傍にいた松平右衛門大夫が慰め顔に、 「若君はこの先、まだ幾度か先陣の機会もござりましよう」 そういうと頼宣は、 「おのれ、この頼宣に十四歳が二度あるか」 と睨みつけたという。
そんな頼宣の覇気を、家康は愛していたようであった。そしてそのような頼宣であればこそ《紀州の地、治世し難し》と、諸国でも治めにくい国の一つとされていた紀州を懐柔し、あるいは恫喝し、よくおのれの掌中のものとし得たのであろう。当時の紀州は寺領七十万石を豪語する根来 頼宣はその不穏の気の充ち満ちた紀州に武を備え、産業の振興に力をそそぎ、新領土の国づくりに非凡な才腕をふるう。そうした治世のなかで、ひときわ目につくのが、万治三年(一六六〇)の正月、みずから筆をとってしたため、領民たちに公布した『父母状』であろう。これにまつわる一つのエピソードがある。 ある年、山ふかい熊野の奥で、父親を殺害した男が捕まった。
捕縛された男は、すぐに調べられたが、目を吊り上げて役人をにらみつけ、「なにを、吐 と、うそぶき、悔いる様子もない。これには、役人も手を焼いた。言葉をつくして、親殺しがどのような大罪であるかを説いても、諭しても、この男には通じないのである。 始末に困った役人は、思いあぐねた末、上役に報告した。 その報告が、やがて頼宣のもとにとどけられた。 おりから夏のことで、扇子をつかいながら聞いていた頼宣は、やがてぱちりと扇子をたたみ、頬づえをついたまま、ながいあいだ考えこんでいた。 「おそろしいことだの」 しばらくして頼宣は、溜息した。 「いかに熊野の山中とはいえ、わが領内でかように禽獣(鳥や獣)にも劣る者を出したのは、すべて予の不徳のいたすところ。かというて、わが罪を知らぬそやつを、そのまま罰することもなるまい」 人いちばい孝行心のつよい頼宣には、親殺しなどとは想像することもできなかった。 頼宣は、その男の身柄を和歌山城下の獄舎に移させると、儒者の李梅渓に命じて牢獄の中で孝経の教えを説かせた。 こうして梅渓の牢獄通いがはじまる。 しかし、それは徒労であった。 大学者、李梅渓の心をこめた孝経の講義も、熊野山中で自儘に生きてきた男の耳には遠いようであった。 そして一年たち、二年たち、三年目に入った。 そんなある日、いつもは挙措おだやかな梅渓が、あわただしい足どりで登城し、頼宣の前に進みでた。 梅渓は、唇をふるわせた。
「か、かの男め……はじめて涙をこぼし"いままで人の道もわきまえず生きてきたわが身が恐ろしい。このうえは一刻も早う、御成敗くだされ"と頭 梅渓の報告に、頼宣はゆっくりうなずいた。 「おのれの非を悔い、にんげんの道理をわきまえたなれば、ふびんながら"法"にしたがわせよ」 で、ほどなく男は処刑されたと『大人雑記』にいう。 この事件があった後、頼宣はふたたびこのような心得ちがいの者が出ぬようにとの思いで書きあげたのが、『父母状』である。
《父母に孝行に 法度 頼宣はこの文字を李梅渓に書かせ、謄本をとらせて広く領内の士庶に配布した。以来、この六十余字が紀州藩の道徳教育の教科書となり、明治のころまでつづいた。
剛毅快闊で、みずからを南海の竜 その頼宣に、寛永寺の長老が 「南竜公と申された頃とは、ずいぶんお変りなされました」
そう言うと頼宣は、自嘲するような口吻 「なんの、睡竜(眠り竜)とてまだ夢をみる」
と嗤 頼宣は晩年、『紀伊亜相頼宣卿訓論』として、「若き大将の心得べき事」「老職(重役)の若き輩の心得べき事」「頭職の心得べき事」など、さまざまな訓
《一、御感 一、物ごとになずみ(馴れしたしみ)うばれる(心奪わる)べからず 一、心の留守之なき様に仕るべし》
そして主人たる者もまた、知恵才覚のある家臣の意見によく耳を傾け、これをわが身の役に立てれば、自分はひとりであっても《家老、大身 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.195~200 2021.06.26記 |
国に法令多きは恥の基なり
|
武田信玄 奉公人の得物を見知りて、諸役を仰せつけよ P.202~207 骨肉相食むというが、武田信玄とその父、信虎との争いほど凄まじいものはない。信虎は、わが身によく似たはげしい長男の信玄を嫌い、かねてから信玄の廃嫡をたくらみ、温和な次男信繁を愛し、後嗣にと考えていた。勇猛をうたわれた荒武将の信虎だけに、その偏愛ぶりは目にあまるものがあった。 ある年の正月などは、信玄を黙殺して、これ見よがしに祝儀の盃を信繁だけに与えたという。 「いまに見ておれ」 信玄が、信虎追放の計画を練りはじめたのはこの日からである。天文十年(一五四一)六月、その機会がついに来た。 おりから信虎は、娘婿の今川義元を訪ねて駿河に出かけていた。その留守を狙って行動を起した信玄は、駿河に通じている甲斐国境を封鎖し、信虎の供をした家臣の家族を人質にとり、信虎を捨て甲斐に帰れと呼びかけた。あわれなのは信虎である。従臣たちはみな、信玄の呼びかけに応じて帰国し、信虎はただ一人、駿河にとり残され、八十一歳で亡くなるまでの二十五年間、今川家の食客となり、やがてその今川からも追われ、欝々と世を過ごすことになる。 父を追放し武田家を掴み取った信玄は、次いで信濃に出兵し、妹婿にあたる諏訪頼重を討滅。信濃になだれこんだ武田軍団は、さらに上田城の村上義清を撃破し、信濃の守護大みょう、小笠原長時を越後に追い落し、甲斐一国をわが物にし、駿河の今川義元、相模の北条氏康と三国攻守同盟を結んだ。 こうして背後を固めた信玄は、越後国境に迫り、上杉謙信と川中島で五度の合戦をかわしたが勝敗決するに到らず。のち剽悍天下に鳴る甲信二万五千の武田騎馬軍団をひきいた信玄は、天下への夢を抱き西上の途につく。 ※参考:頼 山陽(らい さんよう/1781-1832)の漢詩「不識庵機山を撃つの図に題す」に基づく詩吟『川中島』。
題名のとおり、武田信玄と上杉政虎(のちの謙信)の「川中島の戦い」を題材としている。歌い出しは「鞭声粛粛 歌詞・読み方 鞭声粛粛 夜河を過る(べんせい しゅくしゅく よる かわをわたる) 曉に見る千兵の 大牙を擁するを(あかつきにみる せんぺいの たいがを ようするを) 遺恨なり十年 一剣を磨き(いこんなり じゅうねん いっけんを みがき) 流星光底 長蛇を逸す(りゅうせい こうてい ちょうだを いっす)(以上黒崎記)
信玄は勇猛であったが、その軍事行動は細心で緻密であった。軍を進めるにさいしても、さまざまな情報を掻き集め、行く手の山や川、池の一つ一つまで調べあげて絵図をつくらせ、それをもとに計画をたて、突撃にあたっても一騎駈けはゆるさず、隊伊を組ませて組織的な行動をとらせていた。 すぐれた民政家でもあった信玄のすばらしさは、在世中ひとりの叛臣もださなかったというその人間管理、卓絶した家臣統率力であろう。それを語ったものに、
《法度
という五ヵ条の訓
《第一条、大将の人をよく目利 大将たるもの、家老や家臣たち個々の人柄を掌握し、その得手を知って職務を命じなければならぬ。これらの人材を果物にたとえれば、梅や桃などは先に花が咲き、のちに実がなる。また、ザクロや瓜などは、まず実なりてのち花咲くものなり。さてま蓮花という物は、花も実も一度なるものなり。 「この三様は、人間も同じである」 国持大名は、こうした家臣の特性を生かした使い方をせねばならぬのだ。
また家臣たちもよく聞け。わが身に音信
もともと、贈物ばかりして上役の歓心を買おうと、慇懃な面 《第二条、》武士たらん者の手柄、無手柄を上中下によくわけて、鏡にて物の見ゆる様に、大将の私なくなさる事》 大将たる者、家臣の忠節忠勤に応じて与える恩賞は、よくよく心得たうえで私心なく、誰の目にも依怙贔屓なく鏡でも見るように公平に与えなければならぬ。 また、上役が下役の手柄を横取りしたり、大功(大手柄)をたてたのを軽く扱ったりすると、家臣たちはどれがよいのかわからなくなり、忠節忠義をつくす考えがなくなるものだ。
《第三条、兵 兵どもの手柄への恩賞については、かならずその手柄に応じて上位の恩賞、中位の恩賞、下位の恩賞を与えねばならぬ、上位の手柄の者に中位の恩賞が与えられたり、下位の手柄に上位の恩賞に対するようなねぎらいの言葉などかければ、忠節な者ほど落胆し、張合いをなくして忠誠を尽くそうという者がいなくなる。辻斬りや喧嘩、辻相撲、粗暴な振舞いをする者などは本物の勇気ではないから、戦場にでてロクな働きができるわけはない。こうした家臣が多くなれば、誰も法度を守らなくなる。 《第四条、大将、誰も慈悲なさるべき儀肝要なり》 大将は慈悲心をもって家臣に接することが大事である。 慈悲の心がなければ、世の有為無常もわからず、重臣で贔屓の者ばかりを重くもちい、軽い身分の者の勤務ぶりを評価しようとしないから、軽輩微禄の者や不弁者(貧乏人)は、いかにすぐれていても忠節や忠義のつくしようがない、それらが全軍にひろがり、わが身大事とばかり誰も進んで忠節をつくそうとしなくなるものだ。 そうなると口先だけの世間巧者や追従者ばかり横行し、道理も義理もわからなくなってくる。そうした家臣じゃ出世をしても、それを主君のおかげだとも思わず、みなみなおのれの力だけで立身したと思いこみ、主君のことなど考えようとしなくなる。
《第五条、大将のいかり給う事、余りなければ、奉公人油断ある物なり。油断あれば自然に分別ある人も背 大将たる者は温和なだけでは駄目で、必要なときは血相を変えて怒気をみなぎらせて、家臣たちの心をひきしめる事が大事だ。 ただ、その場合の怒りかたに思慮分別をはたらかせねばならぬ。家臣の罪科の軽重を誤ったりすれば、逆効果で、そのような大将の"法度"を誰も守らくなる。法度を守らなければ軍規が乱れ、戦場に出ても勝ことなどない。仮りに、まぐれで勝ったならば、かえって油断を生じ、やがては大敗に通じるものだ。
《一城を構え、人数引き廻す侍大将ども、その工夫専ら有るべき事肝要なり。右五ヶ上の理 こうした信玄の言行を書き伝えた『甲陽軍鑑』は、 《信玄公右(五ヶ条の訓)の趣、善悪の沙汰、黒白のごとくわかり、賞罰明らかなること、天のごとく、地のごとくあそばし、よく法度をたて、よくさいはいを取って、味方をいさめ、敵をおかしかすめ給う》 と述べ、家臣たちを、"適材適所"に差し向け、馬上の戦さにすぐれた関東の敵には、馬と足軽用兵にすぐれた家老の内藤修理を……、こがえし(小返し・軍勢の退却後に一部の兵が引き返して戦うこと)をよくする徳川家康へは、小いくさを能くする山県三郎兵衛を差し向けるなど、
《敵の行 と記している。 神坂次郎著『男この言葉』P.202~207
参考:新田次郎著『武田信玄』全四巻(文藝春秋)昭和四十九年六月十日 第十三刷
新田次郎著『武田信玄 風の巻』あとがきによると、 信玄と云えば、その影に添うごとく軍師の山本勘助が出て来る。ところが、この山本勘助なる人物は、山県昌景の組下にいた身分の軽い武士で川中島の戦のときには物見をやったていどのことしか分っていない。山本勘助の子が、妙心寺派の僧となったが、この男が学があって、武田信玄の事蹟を集めて、これを物語風にまとめたものに、小幡景憲が加筆し高坂弾正が遺したと称して江戸初期に出版したものが『甲陽軍鑑』だと云われている。原本を山本勘助の子が書いたとすれば、父親を軍師に仕立てるのは当然であろう。軍師山本勘助という人物は、他の信用置ける資料には全く出て来ないから、山本勘助が実在の人であったとしても軍師でなかったことは確実と見てよいだろう。だが、なんと云っても、武田信玄のことになると、この『甲陽軍鑑』の影響力が大きく、軍師山本勘助が出ないとおさまりがつかない。そのために、武田信玄の側近の一人であった、駒井高白齋のような人物が蔭にかくれてしまったのであろう。
私は武田信玄を書くに当って、なるべく史料に忠実であることを願った。それが、歴史小説の使命のように思えてならない。人物の設定にもいろいろ気を配った。山本勘助が使い番衆になったり、間者になったり、敵地に入って工作活動をする細作 新田次郎著『武田信玄 火の巻』あとがきによると、 火の巻でもっとも力を入れて書いたものは太郎義信の事件である。太郎義信は父信玄に逆心を抱いたが為に座敷牢に入れられ、ついには自害して果てたということは『甲陽軍鑑』に書いてある。品十二には、永禄十年御自害候。病死とも申也。と書いてあり、品卅三には、其年の春、三十の御歳、太郎義信公御自害也。と書いてある。同じ『甲陽軍鑑』でも、自害説の他に病死説を取り上げているところを見ても。真相は伝えられていなかったに違いない。川中島の大会戦のときから信玄と義信とが中違いをしていたとか、義信が飯富兵部と共に信玄を追放しようとしたなどということはおそらく俗説で、真相は信玄の駿河進攻作戦に対して義信が反対したから自害させられたという歴史家の見方が正しいであろう。ただ自害したか病死したかについては全くわからない。分らないところが小説になるのである。私が自害説を取らずに病死説を取ったのは、私の史観であって、ここで自害説を取れば、私の中の信玄像は根底からひっくりかえってしまうことになる。昭和四十六年五月(以上黒崎記) 2021.05.18記 |
36 上山英一郎
|
上山英一郎 鶏口となるも牛後となる勿れ(1,862~1,943)P.195~201
社是、社訓といえば企業の"旗"だが電通の<鬼十則>のように行動規範をずばりと打ち出したような個性的なものは、意外にすくない。たいていはその文脈も似たりよったりで、誠意、信用、創意工夫などといった常套句を織りまぜたものや、どこまで本気なのか、建前ばかり謳 先ごろも「大口顧客への損失補填」という證券スキャンダルが台風のごとく通りすぎたあと、有名証券数社の"社是"をゆっくり眺めてみると、 《顧客と共に栄える》 《顧客と共に~信頼と発展~》 《顧客と共に繁栄しよう。信用を重んじ、誠実に奉仕する》 《證券業の使命を認識し顧客への奉仕を第一とする。信用を重んじ勤勉誠実を旨とする》
というのだから、その白々しさに破顔
こうした建前ばかりのフレーズにくらべると、上方商人の血をうけつぐ大阪の老舗 《良い暮しを望むなら、一所懸命に働け》(書画材料の『丹青堂』) 《商いは牛のよだれ》(すき焼きの『北むら』)
と、みずから信じるところの商人道を語って直截
飾り気がないといえば、創業一四〇五年の蒼古 その金剛家第三十七代、金剛喜定が残した<遺言書>に『職家心得之事』がある。要約すると、
一、曲尺 一、読み書き、そろばん等の稽古は専ら致す事。 一、世間の人々の交わりいたすとも、物事を頼み過ぎてはいけない。 一、大酒は、いたさない様つつしまなかればならない。 一、身分に過ぎた華美な衣服をまとうな。 一、門人、弟子に至る迄、目下の人には厚い心で接しなければならない。 一、何事も人とあらそってはならない。 一、どんな人にでも、いんぎんに接しなければならない。 一、諸事取引する相手とは無私正直に面談する事。 ――という。 海を越えてきたといえば、中国古典の故事を創業者の経営信条とし、社訓にしている企業がある。 《鶏口となるも牛後となる勿れ》(『史記』蘇秦列伝・『戦国策』韓策) 除虫剤の事業を興した上村英一郎は、商品の品質、信用、経営などの方面からみても、つねに業界のトップメーカーとして立つという自負のもとに、
黄金の鶏
を社のシンボルマークにした。
寧
「大きなものの尻尾
と説
この、黄金の鶏を心意気とした上山は、和歌山県の有田箕島に生まれた。箕島は、有田川の河口にひらけた、両岸の山々をうずめつくす壮大な蜜柑畑に囲まれた町である。
除虫菊発祥の地であるこのあたりは、戦前まで、初夏になると雪のような白い花におおわれた除虫菊の一大栽培地であった。
この除虫菊の、白い可憐な花にふくまれている強力な殺虫成分に着目したのが上村英一郎である。有田地方で一、二といわれる豪農の家に生まれた英一朗は、上京して慶應義塾に学ぶが病を得て、帰郷、家業の蜜柑農に励む。
そんな英一朗の蜜柑国に福沢諭吉の紹介状をもらったアメリカ人、植物輸出入会社のH・E・アーモア社長がやってくる。英一郎がアーモアから貰った一つまみの除虫菊ビューハクの種子を山田原の地に蒔くのは明治十九年(一八六六)のことである。
この除虫菊が、やがて全国にひろがっていくのだが、その背後には除虫菊が国家事業として有力なことを、四国、中国から北海道まで全国を巡回し講演会をひらいて力説し、希望者には無料で種子を配って播種
「除虫菊は、農家の裏作として麦よりも有利で、山畑や荒蕪
と、英一郎は熱っぽく説いてまわった。
後年、この英一郎のひたむきな指導に感謝した岡山、広島、香川、愛媛など除虫菊の生産地の人びとは、尾道の千光寺公園に頌徳碑
ともあれ、自宅付近に工場を建て、兵庫県尼崎に分工場、大阪をはじめ北海道から遠くニューヨークにまで支店を置き、総生産量の六割をアメリカに輸出するまでになった英一郎は、明治二十九年、シベリア鉄道の終点ウラジオストックで三階建てのビルを支店にし、巨大な看板をかかげてロシア人を仰天させるなど、派手な活躍ぶりをみせる。が、明治三十八年、朝鮮の支店に赴いたとき、何物かに狙撃されたり、翌三十九年、戒厳令下のシベリアを旅行中にスパイ容疑で逮捕され、銃殺されかけたり、死に直面したこともしばしばであったという。
除虫菊の栽培に成功した英一郎も、渦巻き式蚊取り線香の型式に定着させるまで幾つかの苦難に直面している。カイロ灰式から仏壇線香にヒントを得た棒状蚊取り線香が開発され、輸送中の破搊が減少したという大正期から昭和十年代までが蚊取り線香の黄金期であった。昭和十年の除虫菊の干花三十九万九千貫、わが国除虫菊生産の最高記録である。殺虫剤開発に生涯を賭けた情熱の人、上山英一朗、昭和十年天寿を全うして逝く。八十歳であった。
英一朗が、白い除虫菊の花に託した夢は、戦後、大輪の花を咲かせる。
アメリカ軍によってもたらされたDDTが過大に宣伝されたため、一時は除虫菊産業は消滅してしまうのではないかと憂慮されたが、防疫用除虫菊乳剤の製造によって立ち直り、日本経済が好転しはじめた昭和二十六年、除虫菊の輸出もまた本格化した。
英一朗が興した除虫菊栽培は、やがて除虫薬品の原料が化学品となって時の流れのなかに姿を消していった。が、新しい家庭用殺虫剤、農薬、除草剤、各種防疫剤などを開発した彼の後継者たちは、《為鶏口、無為牛後》の旗じるしのもとに更なる躍進をつづけておる。もちろん、茶の間におくりこまれている、華やかな"金鳥"のテレビ・コマーシャルなど、彼が知ろう筈もないのだが。
神坂次郎『男この言葉』 P.208~212
2021.06.01記
|
37 三井高利
|
三井高利 単木は折れ易く、林木は折れ難し(1,622~1,694年)P.195~201
伊勢松坂の越後屋、三井高俊の女房(法名を殊法 この四男が、三井財閥三百年の繁栄の基礎を築いた三井八郎兵衛高利(一六二二~九四)である。少年期の高利は、この松坂の店で母から、商家の丁稚として厳しくしつけられていた。
当時の商人の理想は「江戸店 「お前も、江戸の兄の店で商売を習うてくるがいい。その路銀に、これを持ってお行き」 そういうと殊法は、十両分の松坂木綿を馬の鞍につけた。道中、これを売り旅費を稼いで行けというのだ。こうして江戸にむかった高利は、道々それを売りながら旅費を稼ぎだしたばかりでなく、たっぷり小遣銭まで懐中に入れて江戸に着いた。 長兄の俊次は、高利の商才を試すつもりで、ある日、三貫文の銭を高利の前に置き「これを元手に、今日一日いくら稼げるか、やってみるか」という。うなずいた高利はは、その銭で草鞋を買い、江戸で一番人出の多い日本橋のたもとに立ち、通りすがりの百姓や商人、人夫に売りつけ、夕方、五貫文の銭をかついで帰ってきた。 以来十年、長兄から店をまかされた高利は、銀百貫目ほどであった江戸店の資金を千五百貫目(約二万五千両)に増やしている。
高利の商才に舌をまいた俊次は、このように智恵のよくまわる弟が空おそろしくなってきた。将来、高利が独立して商売仇にでもなれば、俊次の店はおろか、わが子たちはみな高利に圧 「で、お前は松坂に帰って、母上に孝養をつくしてくれ」 そういう俊次は、厄介払いをしたような顔つきで銀百貫目を高利に与えて、江戸から追い落した。 以来、高利は老母に仕え店を守り、江戸での独立の夢を抱きながら欝々といて二十余年の歳月を逸している。江戸の俊次が死んだとき、高利はすでに五十二歳であった。が、高利は、「待っていたり!」 と老いた顔に血のいろをみなぎらせて躍りあがった。かねてからこの日のために、高利は三人の息子を江戸におくり、俊次の店で修業させていた。その息子たちを呼び集めると、本町一丁目に呉服、太物(綿織物)の店をひらき、故郷の屋号をとって越後屋となづけた。 後年の三井財閥の基礎となる巨富は、晩年の高利のこの店で稼ぎ出されたものである。 こうして雌伏二十余年、高利が練りに練った、当時としては誰も思いつかなかった卓抜な商法が次から次へと打ち出されるのである。 その頃の"本町通り"の商人は、大みょうや上級武士、金持ちの町人や大百姓を相手に、得意先をまわって品物を見せて売り、盆暮二度に支払いをうけるという掛売り商売をしていた。 ところが、高利が考え実行したのは"本町通り"で売られているのと同様の呉服を、安く大量に一般庶民大衆を相手に売ろうという斬新な商法であった。 それは「現金掛値なし」つまり定価による現金販売の実施である。そして得意先をまわる人件費を節約した「店売り」であり、いままで一反を単位として売っていたものを、庶民も買えるように「切り売り」をしたことであり、さらに各地の同業者相手に薄利多売を実行した「諸国商人売り」であった。 こうした高利の経営の合理化と顧客への奉仕を徹底した"安くて、掛値なしの現金払い"の店頭売り商法は大当りに当った。
が、これをみて面白くないのは"本町通りの老舗"商人たちである。得意先の大みょう家までが越後屋に注文をしはじめるという始末に腹をたてて、越後屋の台所先の敷地へ惣雪隠 「そのかわり……」 後継者である高平(八郎右衛門)のなで江戸八百八町に引札(広告チラシ)をくばり、"現金、安売り、掛値なし"の駿河町の三井越後屋(三越)の名を世間に撒きひろげていった。 高利のこの商法は、江戸の人びとをよろこばせ、元禄元年(一六八八)、井原西鶴の『日本永代蔵』に《毎日金子百五十両ずつならしに(平均して)商売しける》とあるのが享保年間(一七一六~三六)、新井白石の『石書』では《一日千両ずつ平均に商い有るなり》となり、さらに下って文化十三年(一八一六)の『世事見聞録』に《千人余の手代を遣い、一日千両の商いあれば祝いする》と書かれるほどに繁盛をきわめている。 『三井八郎併兵衛高利 遺訓』
《単木は折れ易く、林木は折れ難し、汝等相協戮輯睦 一本の木は折れやすいが、林となった木は容易に折れないものだ。わが家の者は仲むつまじく互いに力をあわせ家運を盛りあげ固めよ。 《各家の営業より生ずる総収入は、必ず一定の積立金を引去りたる後、始めて之を各家に分配すべし》 一族各分家の商いにおいて得た利益金は、一定の積立金を差し引いた後はじめて各分家に分配すること。
《各家の内より一人の年長を挙げ、老分 一族各分家のなかから一人の年長者を選んで、各分家はみな老分の命をきくこと。 三井家には京都六家のような、独特の結社組織があるが、《老分》の制度をもうけ、一族の和合をはかり、各分家の主人たちは、 《凡そ一家の事、上下大小の区別なく、之に通暁する事に心懸くべし》 と、一家の中のことは、どのようなことでも主人たる者知り尽くておき、
《賢者能者 能力のある者の活用に最大の注意を払い、下の者の中から不平や恨みを抱くようなことのないよう、注意せよ。 《堅く奢侈を禁じ、厳に節倹を行うべし》 天和三年(一六八三)、高利は駿河町南側の地を東西に分けて、東側を呉服屋、西側を両替店とした。これが後の三越百貨店、三井銀行となったことはいうまでもない。 神坂次郎『男この言葉』 P.213~217 2021.05.22記 |
|
勝夢酔
一生不動にて朽ちける事、ああ恥ずかしきかな(1,802~1,850年)P.195~201
家訓や人生訓といったものは、かくかくしかじかの辛酸辛苦の果てに我が家をここまで築きあげた、よって子孫たるもの儂
あまりの放埓、無頼の行状が問題になったので三十七歳の春、隠居して夢酔
《息子(勝海舟)がしつまい(まじめな)故に益友をもととし悪友につき合わず、武芸に遊んでいておれに孝心にしてくれて、よく兄弟をも憐 と言い、さらに声を重ねて、
《(男たるもの)身を立て名をあげて、家をおこす事がかんじんだ。たとえばおれを見ろよ。理外にはしりて人外(無法)なことばかりしたから、祖先より代々勤めつづいた家だが、おれひとり勤めないから家にきず(疵)を付た。是がなによりの手本だわ。今となり醒めていくら後悔をしたからとてしかたがない。(略)人間になるにも其通りだ。どんよく(貪欲)迷うとうわべ(表面)は人間で心は犬猫どうよう(同様)になる。真人間になるように心懸るが専一だ。文武諸芸みなみな学ぶに心を用いざれば不残
天保十四年寅 左衛門太郎入道 夢酔老》 と述懐する。 ――この、勝海舟の父、小吉(夢酔)の波瀾に満ちた、自叙伝とも、喧嘩の自慢話ともいうべき家訓の書『夢酔独言』の中の、彼の人生を覗いてみよう。 ※参考図書:『夢酔独言』*勝子吉自伝*(角川文庫)(黒崎記)
越後国小谷郷から江戸へ出て検校
養子縁組をするためには、支配役と組頭に挨拶をして承認を得なければならないので、七歳の亀松が大人髷 「なは小吉、年は当年とって十七歳」
だというと、支配役の石川右近将監
「十七歳か、それにしてはちと老 ということで、無事認めて貰った。 町内きっての暴れ者の小吉は、この年、年長の悪がき二、三十人を相手に大げんかをして手下にしてしまい、八歳のとき、本所亀沢町に屋敷が移ると、飼犬同士の噛みあいが原因で小吉ら侍の子グループと職人のせがれたち四、五十人が大げんかにになり、小吉はなまくら脇差を抜いて奮迅。仕立屋の悪たれの弁次の眉間に一太刀、「ぎゃつ!」と尻餅をついた弁次が溝の中へ転げこみ這いあがるところを二の太刀で顔を切る。ということで小吉ら八人は勝ちどきをあげて帰ってきた。
こうしてチンピラの世界に名をひびかせた小吉は、九歳から柔術、十歳で馬、十一歳で剣術の道場通いをする。苦手だったのは十二歳から林大学頭 文化十二年(一八一五)十四歳の五月、養家の祖母《ばばぁどのにいびられ》腹をたてて、七、八両盗みだして家出を決行。上方をめざして東海道をのぼるが、途中の宿でゴマの灰(旅人などの財物を欺き盗む者)に着物も大小も金も持ち逃げされ、襦袢一枚で乞食になり、伊勢大神宮に詣でようとするが、鞠子の宿では博奕打ちに頼まれ、賭場への銭運びをしたり、病気になって行き倒れているところを旅の僧に助けられたり、惨憺たる放浪をつづけていく。あるときなどは狼の出るという山中で野宿し、寝返りをうった途端に崖から落ち、金玉を打って気絶し、それが原因で金玉が腫れ、おかしな恰好で辿りついた小田原の漁村では人のよい漁師に救けられた。漁の手伝いをしているうちに見込まれ、三十娘を貰って養子に入らぬかという話がもちあがってくる。が、 《おれも武士、こんなところに一生いてもつまらねぇから、江戸へ帰って》 と、帰心矢の如く、漁師の娘の機嫌をとって喜ばせ《浜の仕事に行く》からと弁当をつくらせ、戸棚にあった銭三百文と娘の着物一枚を失敬して夜八ツ(午前二時)遁走。かくして放浪四ヵ月で、ぼろぼろになった小吉は江戸に辿り着く。が、まさに危機一髪。 「今月帰って来なければ、月末には期限切れで家名断絶するところであったが、間にあって帰ったのは、まずまずめでたい」 と支配役の石川から言われて、小吉は冷汗をかいた。
冷汗といえば、十六歳で組頭の屋敷へ《逢対
以後、直心影流 十八のとき世帯を持つが、借金山積し、出奔。甥の新太郎に連れ戻され、座敷牢に閉じ込められること三年余。この牢ぐらしのあいだに、小吉はちゃっかりと、新妻に嫡男の麟太郎(海舟)を生ませている。 小吉の行状は、隠居した後もなお改まる様子はない。 《一生不動にて朽ちける事、子孫に面目なき事いわん方なし、ああ恥ずかしきかな》 神坂次郎著『男この言葉』P.218~222 2021.06.27記 |
|
渡辺崋山
眼前の繰廻しに百年の計を忘る勿れ(1,793~1,841年)P.195~201
幕末憂国の受難者であり、画家として高めいで、国宝『鷹見泉石
幼少から貧困に苦しみ、八歳で若君の伽役 「おのれ、いまに見ておれ」
と発憤した崋山は、大学者への道を志し、家老で儒者の鷹見星皐 「画家たるに如かず」
と転向、平山文鏡、白川芝山 こうして近習役から紊戸役、使い番と累進した崋山は、晩年、家来末席に出世していた父の跡目をついだ。遺禄八十石。 二十六歳のとき正確な写実と独自の風格をもつスケッチ『一掃百態』を描き、二十歳で結婚。このころから崋山は蘭学や西洋画に傾倒し、『四州真景図』、学門の師である『佐藤一斎像』など西洋画特有の遠近法や陰影を駆使した作品を仕上げ、三十四歳の春、江戸にきたオランダ国の使節ビュルゲルを訪ねたりして西洋の文物への関心を深めている。 慊堂
天保三年(一八三二)四十歳で江戸家老に栄進し禄百二十石。崋山は農民救済をはかるため、悪徳商人と結託した幕吏が計画した公儀新田の干拓や、農民の生活をおびやかす領内二十一ヵ村への助郷 また、飢饉に備えての養倉「報民倉」を建築。農学者、大倉永常を登用して甘藷を栽培させて製糖事業を興すなど、藩政への貢献は大きい。 当時、崋山は海外の新知識を得るため、田原藩主の異母弟で若くして隠居していた三宅友信に蘭学を勧め、大量の蘭書を購入。シーボルト門下の俊才で町医者の高野長英や岸和田藩医、小関三英、田原藩医の鈴木春山らに蘭書の翻訳をさせた。 この蘭学研究グループを集めた三宅友信の巣鴨邸は、やがて江戸蘭学者の集会所の観を呈し、崋山はいつかその代表としての立場に押しあげられていった。
当初、崋山や長英、三英の交友からスタートした蘭学研究は、海外事業に強い関心をもつ幕臣、川路聖謨 崋山自身も例外ではなかった。時事を討議し幕臣の腐敗無能ぶりを詰問した。『慎重論』を草して、憂国の情を披歴している。また、伊豆の代官で西洋砲術家、海防策に心をくだいていた幕府きっての開明派である江川英龍のために崋山は、海の彼方から迫ってくるヨーロッパ勢力による危機や、江戸湾周辺の防備計画について述べた『西洋事情御答書』を書き送っている。
これらのことが幕府の目付、幕府の目付、鳥居甲斐守輝蔵 のち崋山、藩地田原へ蟄居。幽閉所での崋山の暮しぶりは窮乏をきわめている。
《かようなお預け人(崋山)は、一日も早く死ぬるを役人は喜ぶことで、その手当は甚だおろそかで(食にも事を欠くような)まことに貧家の様であった。画弟子何がしの女は、家が富んでいたので、これが主となり、古い弟子どもが申しあわせて、月に二分(一両の半分)ずつを送った。崋山はその謝礼として、屏風一双ぶりの絵を作って江戸(の弟子)に送った。これで少しは飢寒を免れた》(『反古 また、門弟の福田半香は、崋山の貧を救うために江戸で書画会(即売会)をひらいた。 ところが、かねてから開明派の崋山の活躍ぶりを苦々しく思っていた守旧派の藩老や藩士たちは、この書画会をみて、 「蟄居中にあるまじき、不謹慎なる振舞」と騒ぎたて、いまに、「近く藩公(第十一代・康直)は、公儀からのお咎めをこうむる」 という噂を撒き散らした。
こうした風説 《不忠不孝渡辺登》 と大書し、納谷のなかで切腹自殺した。
田原藩家老としての崋山が《富めるものはますます富み、貧しきものはいよいよ貧しく、窮民所々に騒擾 その彼が、ある商人から頼まれて書いたという商人訓がある。 《一、まず召使いより早く起きよ 《一、十両の客より百文の客が大事》 一、客人(商品を)気に入らず、返しにきたらば売る時より丁寧にせよ 一、繁盛するに従い、益々倹約せよ 一、小遣いは一文よりしるせ 一、開店の時(初心)を忘れるな 一、奉公人が出店を開いたら、三ヵ年は食扶持を送ってやれ》 藩老であり、すぐれた知識人であり見事な画人であった崋山の、こうした商人訓はめずらしい。
この他、崋山は藩の御用金調達のため大坂に出向いていた真木重郎兵衛のために《八勿
《一、面唔 一、眼前の繰廻し(やりくり)に百年の計を忘る勿れ
一、眼前の功を期して後面の費 一、大功は緩にあり、機会は急にあり、ということを忘る勿れ
一、面
一、挙動を慎み、其恒
一、人を欺かんとする者は事に欺かる。不欺 一、基立って物従う(基本ができてこそはじめて物事は進む。基礎こそ大事)、基は心の実というを忘る勿れ》
崋山の訓戒はいまなお新鮮である。眼前の遣繰 神坂次郎著『男この言葉』P.223~227 2021.06.19記 |
|
河村瑞賢
なすところはみな夢幻にして、実相を悟るべし(1,618~1,699年)P.195~201
名もない車曳きから天下の巨富を掴んでのしあがった元禄の開発事業家 通称を十(重)右衛門。生活の道をもとめて十三歳で江戸にむかう。が、生き馬の目をぬくという江戸での車力(車曳き)暮しに絶望した彼は、やがて都落ちをする。 その失意の道中の小田原で、十右衛門は旅の僧から、 「惜しいのう、おぬしの人相には立身、富貴の相がでておるに、それを江戸に捨ててきたのか」 そう言われて十右衛門は、ふたたび江戸へ引き返していく。そして品川の海岸まできたとき、おりから盂蘭盆すぎて浜辺には仏前に供えた胡瓜や茄子がおびただしく打ちあげられていた。 「これだ、これだ」
それをみた十右衛門は、近くにいた乞食たちに銭をやり、それを拾い集めさせ漬物にして売りだし、大もうけをした。こうして稼いだ金を資金に、大八車を買い求め車曳きたちを集め事業としての車力業の第一歩を踏みだした。おりから江戸は、市街地造成の真最中で、建設現場は活況を呈し、普請場に運ばれていく土石や木材の車や、河岸
大江戸開発ブームの花形である車両運送の親方になった十右衛門は、稼ぎ集めた金を投入して材木商となり、深川霊巌島に住む。当時の材木商というのは普請と作事 こうして車力の親方十右衛門から材木商土木建築業河村瑞賢(瑞賢は号)へと転身した彼の前に、明暦三年(一六五七)江戸城をはじめ江戸市街の大部分を焼きつくすという未曽有の大火、本郷の本妙寺で娘の供養のため振袖を焼いたのが原因となった「振袖火事」がおこる。 「いまだっ!」 瑞賢は機を見るに敏であった。 わが家に迫る火の手を尻目に、手元にあった十両を懐中につっこむとまっしぐらに木曾へ走った。
瑞賢は素迅
江戸大火の風評
子供が貰った小判の玩具におどろいた主人は、瑞賢をよほどの分限者(富豪)と思ったのであろう。あとから金をもってくる番頭を待っているという瑞賢に、持ち山すべての材木を売り渡す証文に印を捺した。そして、瑞賢が傭 が、すでに遅い。かれらはみな瑞賢から彼の言い値で高価な材木を買うしかなかった。材木商たちに売却した代金で山林王への支払いをすませ、残りの大量の材木を江戸に運んだ瑞賢は、他の材木商よりはるかに安い材木を売りだし、すべて売りつくして巨利を博した……という。
当時、江戸の町では、「抜群の知恵者」ということを人びとは「瑞賢ぶり」と言い囃
あるとき、芝、増上寺本坊の大屋根の棟瓦 「なんの、造作もないこと。まあ、御覧じあれ」
そいうと瑞賢は、大凧をつくり、本坊の前で空高くあげた。凧は、長い凧糸をつけたまま本坊の屋根を越えて、本坊の裏手に降りた。瑞賢がその糸を手繰ると、凧糸はやがて紐 江戸の巷で語られたこれらの瑞賢の工夫や出世譚の信憑性はさておき、瑞賢が万人にぬきでた知恵働きと、みごとなばかりの決断(実行)力の持ち主であったことは明白である。 デベロツパーとしての瑞賢の偉大さは「幕府御用」の金看板のもとに海運界の地方分権(諸国大みょう領)を解体し、幕府のお声がかりの事業として奥州(福島、宮城、岩手、青森)からの東廻りの航路、そして近世海運史上画期的ともいう出羽(山形)からの西廻り航路を開発したことであろう。 従来、東廻りの場合、那珂湊(茨木)や銚子で陸揚げし、江戸に向い、西廻りなら敦賀(福井)などで陸揚げして陸路をとらねばならぬという不自由さがあった。
陸上輸送といえば、仮に大坂から江戸へ千石の米を運ぶとすれば馬千二百五十頭、馬子 瑞賢のこの陸路を併用しない本州一周航路の出現によって、経費や日数は激減し、米俵の荷くずれや損耗もなく、その他の物産も安価に輸送され、江戸、大坂はもとより諸国の都市に飛躍的な繁栄をもたらした。 瑞賢はこの新航路開発の功績によって幕府から三千両を与えられ、その後、大坂安治川の開削や、 《銀千貫目を一息(一瞬)に儲けた》(『商売記』三井高治) という京都御所の入札や、採掘銀の入札や、採掘銀半分を与えられるという幕府銀山の経営など、国家規模の開発事業家として巨万の富をたくわえている。 元禄十一年(一六九八)、将軍綱吉に謁見をゆるされ、旗本となった瑞賢は、河村平太夫を称して立身をきわめ、翌年、波瀾に満ちた人生の幕をとじている。享年八十二. 瑞賢は晩年、その著のなかで、
《夢幻の身を以て夢幻の身を育て夢幻の身を厭
と説 神坂次郎著『男この言葉』P.228~232 |
|
徳川宗春
国に法令多きは恥の基なり国に法令多きは恥の基なりP.195~201
世に、これほど痛快な男はない。徳川宗春、さきのなを通春 この宗春の、思いもかけぬ幸運ぶりは、のちに生涯の政敵となる八代将軍吉宗(紀州徳川家二代光貞の第四子で、越前丹生三万石。が、父の光貞はじめ三代、四代とつづく兄たちの突然死のため五代藩主にのぼる)の運命と酷似しているから、歴史というものは皮肉なものだ、 藩主の座についた宗春の胸中には、幕府憎しの思いが黒けむりをあげている。反感の理由は、将軍職候補として最短の距離にあった尾張徳川家が、そのチャンスを二度までも流したことであろう。 それにしても尾張徳川家は不運つづきであった。六代将軍家宣の病状が悪化したとき、病床の家宣は、わが子家継の幼少さと病弱を危ぶみ、 「予の跡目は、尾張吉通に……」 と遺言して死んだ。尾張家は、次期将軍への期待に目をかがやかしたが、幕府閣老たちの反対によって、家宣の世子家継が将軍となる。だが、家継は三年後に病没。 「さて、このたびこそ将軍に……」
と、二度目の好機到来に尾張徳川家は胸はずませたが、次期将軍と家宣から望まれていた四代吉通は二十五歳の若さで急死してしまう。不運はそれだけではなかった。五代藩主をついだ三歳の五郎太も就任二ヵ月で世を去り、さらに六代藩主継友までが《暴 こうした悲運の尾張徳川家にかわって、颯爽と八代将軍に就任したのが紀州藩主徳川吉宗であった。思いもかけぬ紀州徳川家の登場に、尾張徳川家は愕然とした。そしてやがて尾張領内では、 「じつは……」 藩主たちの死は、吉宗がひそかに差しむけた隠密によって毒殺されたのだという噂がささやかれ、誰もがそれを強く信じた。 「お殿様、ご残念!」 兄、継友のあとを嗣いで尾張徳川家のあるじになった宗春は、そんな藩士や領民たちの憎悪を一身に抱いて、吉宗という巨大な独裁者の君臨する幕府に抵抗し、挑みかかっていく。標的は将軍吉宗の「享保の改革」であった。
おりから吉宗は、五代将軍綱吉の頃から疲弊の度を深めてきていた幕府財政の建直しに取組んでいた。元禄以来の華美の風を矯 それは、なんとも異様な光景であった。行列の先頭を、長大な、真紅のキセルがゆるゆると進んでいく。長さ二間(約三・六メートル)。そのキセルの先端から、時折、ぷかりぷかりと白いけむりが立ちのぼっているのである。
行列のあるじは、いうまでもなく徳川宗春だが、それにしては行装 享保十六年(一七三一)江戸を発して名古屋にむかった宗春は、入国と同時に、領民たちにおどろくべき改革を申し渡した。 「遊芸、音曲、芝居興行も自由、遊郭も設けよ」 宗春の政治は、厳しい上にも厳しく締めつけ鬱陶しい緊縮政策をとっている吉宗の「享保の改革」の引っくり返しであった。長い歳月にわたって疲弊し破綻に瀕している財政が、吉宗のいう"倹約"だけで切り抜けられようとは、宗春は思っていない。 「考えてみよ」
宗春は、お国入りするにあたって、藩主としての抱負と施策方針を二十一ヵ条にまとめた自著『温知政要(尾張亜細相宗春卿 家訓)』のなかで説
《省略倹約の義は、家を治むるの根本なれば、尤も相勤むべき事なり、第一、国の用縮まり不足しては、万事さしつかゆる(差支える)のみにて、困窮の至極となる。さながら(とは申せ)めったに省略するばかりにては、慈悲の心うちくもりて、覚えずしらずむごく(酷く)不仁になる仕方出来 いたずらに倹約を叫んで締めつけるだけでは為政者としての慈悲の心薄くなり、庶民を苦しめるばかりではないか、と宗春はいう。 《国に法令多きは恥の基なり(略)諸令多くなれば、破る者また多し、法令多く過ぐれば人のこころいさみ(活発さ)なく、せばく(狭く)いじけ、道を歩くにも後光を見まわし》 という状態になるものだ。 宗春のこの『温知政要』のなかには、平成の現在でもそのまま適用しそうな言葉が多い。
《たとえ千金をのべたる物にても、軽
という条
《万 この、人それぞれ各人の用を知って使えとう条など、わが身の趣味嗜好を最高のものと信じている吉宗への、そしてまた峻烈な法治主義をかかげて幕府にのぞんでいる吉宗の政治姿勢への痛烈な批判である。 ともあれ、宗春の大改革で名古屋の城下は空前の繁盛ぶりをみせる。日本国中が貧寒とした緊縮ムードに喘いでいるなかで、な古屋だけが開放的で活気に満ちた別天地であった。それまで藩法で禁じられていた遊郭が十二の町に拡がり、歌舞伎芝居の常設劇場が十四町に設けられ、それぞれの周辺に見世物小屋、料理屋などの商売店が軒をつらね、この繁華の地を求めて諸国から遊芸人や商売女たちが稼ぎを目当にどっとながれこんできた。宗春が打ち出した「民と共に楽しむ」積極策は見事に当った。 が、この『禁令無視』の行状が吉宗の怒りをかい、幕閣から隠居謹慎を命じられた宗春は、な古屋三ノ丸の角屋敷に幽閉されること二十三年。没後もなお幽閉を解かれず、かれの墓石は金網をかぶせられたままであった。その罪がゆるされ、金網が取り払われるのは死後七十六年目の天保十一年(一八四〇)。政治というものは残酷なものである。 神坂次郎著『男この言葉』P.233~238 2021.06.26記 |
|
勝海舟
なんでも人間は子分のない方がいい (1,823~1,899年)P.195~201 《上った相場もいつか下る時があるし、下った相場もいつかは上がる時があるものさ。その上り下りの時間も、長くて十年はかからないよ。それだから、自分の相場が下落したと見たら、じっとがまんしておれば、しばらくするとまた上がってくるものだ。大奸物、大逆人の勝麟太郎も、いまは伯爵、勝安房様だからのう》 ※参考:勝海舟 勝部真長編『氷川清話』(角川文庫)P.47<人間の相場の上がり下り> "大奸物""大逆人"というのは徳川家を薩・長に売り渡したと旧幕臣たちが、勝を非難した言葉である。
「なにを吐
勝海舟、幕府小普請組の勝左衛門太郎(小吉)の嫡男に生まれ、初めの名を義邦、通称を麟太郎。その風貌は、
《短小赭面 赤ら顔の小男であったが、眼光は鋭く、一種おかすべからざる異彩を放っていたという。
貧困のうちに育った海舟は、七歳のとき、江戸城大奥につとめる親戚の阿茶局 だが、その喜びも束の間であった。一橋家を継いだ慶昌はほどなく死去。幼なくして失脚の苦汁を味わった海舟は、父、小吉のもとに帰っていく。
この海舟の悲運を誰よりも嘆いたのは小吉である。が、不運は重なる。九歳の時海舟は、野犬に金玉を噛み裂かれ生死の間をさまよう。傷口を見てふるえている外科医を殴
「子供が狂犬 と噂をした。 海舟は、こうした無頼だが子煩悩な父の愛情を独り占めにして育った。十九歳で蘭学をまなんだ海舟は、刻苦勉励、安政二年(一八五五)蕃書(オランダの書物)翻訳係を仰せつけられ、以来、たちまち頭角をあらわし、幕府の海軍創設の第一歩という長崎海軍伝習生、講武遺所砲術師範、海軍操練所頭取となり、やがて万延元年(一八六〇)正月、軍艦咸臨丸の艦長として太平洋を横断、アメリカにむかう。
《(二月十一日)日本軍艦咸臨丸(サフランシスコ)港内へ進み来る。大檣
帰国後海舟は、将軍家茂の信任を得て軍艦奉行並従五位下 こうした幕府海軍きっての高官であり、当代随一の海外新知識の持ち主である海舟のもとに、勤皇・佐幕をとわず有為な人材が群がりあつまってきた。
論争を吹っかけにやってきて逆に心服して弟子になってしまった坂本竜馬や、吉村寅太郎(のち天誅組)、桂小五郎(木戸孝允 幕府の軍艦奉行、陸軍総裁、そしてやがては幕府軍すべての実権を掴んだ軍事取扱いに昇進した海舟は、慶應四年(明治元年、一八六八)鳥羽伏見の戦いに幕軍を撃破して攻めのぼってきた西郷隆盛と会見し、江戸総攻撃を未然に防ぎ、無血開城したことは史上有めいである。 この会談が、海舟と隆盛の"腹芸"によって成就したという話が伝えられている。が、政治というバケモノが、そんな腹芸だけで動く筈はない。 政治は、力である。海舟は、隆盛の背後に、薩・長に大きな影響力をもつイギリス公使バークスの存在があるのを察知している。 「江戸が戦火に包まれて焦土と化せば、バークスが期待する横浜貿易への夢が瓦解してしまう」 それを承知で、薩・長が戦さなどは仕掛けてくるものか、と海舟は隆盛の胸のなかを読んでいる。 「が、万一……」 薩・長が血迷って総攻撃の挙に出たとすれば、海舟は即座に幕府海軍の総力をあげて、<薩・長軍を背後から攻撃する>という計画を、隆盛との会談で言葉の端ばしにちらつかせている。 海舟は周到であった。 総攻撃にそなえ、四つ手駕籠に乗ってなだたる侠客の親分衆を訪ねまわり、 「貴様らは、金の力やお上の威光で動く者ではないから、この勝が自分でわざわざやってきたのだ」 と言い、いざという時には江戸に進撃した薩・長の前後左右、四方八方から火をかけ、江戸八百八町を焼き払うための協力を求めて、親分衆から、 「この顔が御入用なら、いつでも御用に立てましょう」 と快諾を得ている。 そんな海舟の魂胆を、明敏な隆盛が読みとれぬ筈はない。
こうして海舟は、内戦を抑え、虎視眈々
《明治維新に勝った方の官軍というのは(略)薩長という各自の殻も背負っているし、とにかく幕府を倒すために歩調を合わせることに政治力の限界があった。ところが負けた方の総大将の勝海舟は、幕府のなくなる方が日本全体の改良に役立つことに成算あって確信をもって負けた。否
と説
野 《なんでも人間は子分のない方がいいのだ。西郷も子分のために骨を秋風にさらしたではないか。おれの目でみると、大隈(重信)も板垣(退助)も始終自分の意見をやり通すことができないで、子分にかつぎ上げられて、ほとんど身動きできないではないか。およそ天下に子分のないのは、おそらくこの勝安房一人だろうよ。それだからおれは、起きようが寝ようが、しゃべろうが、自由自在、気随気ままだよ》(『氷川清話』) ※参考:勝海舟 勝部真長編『氷川清話』(角川文庫)P.235 と皮肉な口ぶりで、そう嘯いている。 明治三十二年一月二十日、海舟歿す。 「どうやら死ぬ時がきたようぜ」 と言って床につき、眠るように逝った。家人がブランデーで死水をとった。 神坂次郎著『男この言葉』P.239~244 2021.07.01記 |
公益の為には財を吝(おし)む勿れ
43 徳川光圀
|
徳川光圀
苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし (1,628~1,701年)P.195~201
天下の副将軍こと水戸黄門(中な言)が家来の助さん、格さんと共に全国各地を旅し、行く先々で悪をこらしめる話は、江戸のころから有名である。その漫遊記のストーリイは、いつに変らぬワン・パターン、同工異曲そのものながら、平成の現代もなお、助さん格さんが一しきり大あばれしたあと、金蒔絵 「一同ひかえい! この葵の御紋が目に入らぬか。ここにおいでのお方様をどなたと心得る。おそれ多くも前(さき)の天下の副将軍、水戸のご老公なるぞ」 と印籠がアップになれば、テレビの視聴率もグ―ンとあがる。 ついでながらこの「水戸黄門」のテレビ第一回目の放映はいまから二十三年前の昭和四十四年(一九六九)だから、テレビ界きっての人気番組である。
こうしたエピソードをもつ水戸光圀は、徳川御三家の一つ、水戸藩頼房の十一男十五女の第七子に生まれた。母の、谷左馬介の娘久子は、大奥に仕える老女の娘でもあり、一目で心を奪われた頼房は、側室として邸 《水(堕胎)ニナシ申ス様ニ》 と命じたのである。 が、気骨のある三木は、闇から闇へ流してしまう前に頼房の母、英勝院に相談したうえ、ひそかに久子を自分の屋敷に引取り、そこで生み落させた。その子が、光圀であった。
《英勝院、御父ㇵ頼房公、第三ノ御子(三男)御母ハ谷佐馬介ノ女
こうして生れた光圀(当時は長丸)は、五歳のとき、英勝院のお声がかりで頼房の子と認知され、水戸城に入り千代丸をな乗る(長男頼重はこの時期まだ披露(正式認可)がなく、次男亀麻呂 少年時代の光圀の行状は、そのいのちの誕生を父から拒絶されたという反抗の揺り返しのように、藩主の世子にあるまじき粗野な振舞が多かったという。
御三家のなかでも水戸家は江戸定府
《ソノ返(度)数多キニ御コマリナサㇾ、御筆ヲ二、三本ヅツ束ネ、御握リ御書キ遊バサㇾ候ニ付キ、御反故 父から云いつけられた宿題を早く片付けようと筆二、三本握って書いたと、晩年、光圀自身も告白しているが、反抗期の光圀少年の肝の太さは、七歳のときの生首一件をみてもわかる。 ある夜ふけ、頼房は光圀の度胸を試すため、斬首した罪人の首をさらしている刑場へ取りに行かせた。うなずいた光圀は、気おくれした様子もなく出かけて行き、死首が重いのでもとどり(髪の毛を束ねたところ)をつかんでずるずる引きずって帰ってきたという。
光圀の身辺には、つねに三人の傅役 悪所通いといえば、、某夜、例の如く屋敷を脱けて娼家に泊まっていたところ、小石川の水戸屋敷の近くで火事が発生、急いで帰ってくると屋敷の門前は、
《挑
門前を家臣たちが固めて入る隙間
おりから、水戸家へ出入りの商人たちが水籠 「海北孫右衛門の(家の)者にて候」 と声をかけ、すまし顔で入っていったという。
こうした放埓 江戸時代の殿様というのは不自由なもので、寝所では毎夜、枕元や廊下、次の間に小姓が不寝番をし、側室と寝るときも同じ部屋のなか老女控えてい、便所に行くにも御供つきであった。隠居の身であっても、自由気ままな旅など出来よう筈はない。 光圀の無頼な行状がおさまるのは、頼房の強い意見があっての事からとも、十八歳のとき、『史記』の『伯夷伝』を読み、兄の頼重をさしおいて自分が相続人になっていることの順逆に悩んだ事だともいう(『桃源遺事』)。 のちに光圀は、兄頼重の子を養子にして、水戸家三代目をその宗淳に継がせている。
六十三歳で隠居して常陸太田の西山荘にこもった光圀は、助さんこと佐々木助三郎、格さんこと渥美格之丞のモデルともいう佐々木宗淳
晩年、光圀は子孫のために九ヵ条の訓戒『徳川光圀壁書』をのこしている。いかにも彼らしい、野人の趣のある訓 《一、苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし 一、主人と親は無理(を言う)なるものと思え、下人は(頭の働きの)たらぬものと知るべし
一、掟に怯 一、欲と色と酒をかたきと知るべし
一、朝寝すべからず。咄 一、(ものごとは)九分(どおりしてのけても)にたらず、十分はこぼるる(やりすぎてもいけない)と知るべし 一、子ほど親を思え、子なきものは身にくらべ(くらべ)て、ちかき手本と知るべし
一、小さき事は分別せよ、大なる事に驚くべからず(小さいと思える事でも、よく考えて処理せよ、大きな事であっても慌 一、(思慮)分別(する)は堪忍にあるべし(堪忍に勝るものはない)と知るべし》 神坂次郎『男この言葉』 P.246~250 2021.06.03記 |
44 黒田如水
|
黒田如水 分別過ぐれば大事の合戦はなし難し国に法令多きは恥の基なり (1,546~1,604年)P.195~201 かつて秀吉が近臣たちに、
「この秀吉が死ねば、儂 と、たわむれて言ったことがある。訊かれて近臣たちは困った。応えようがないのである。で、皆がもじもじしていると、秀吉は声をかさねて、 「これは座興ゆえ、思うままに言うてみせよ」 そう促されて近臣たちは、やむなく重い口をひらいたが、かれらの挙げた大みょうのなは、いずれも五大老の徳川家康、前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元といったものであった。 「なにを言うておるか」 秀吉は薄く嗤って、近臣たちをじろりと見、
「ただ一人、天下を掴む者がある。わからぬか、あの瘡 「は?」 近臣たちはいぶかしげな表情をした
秀吉のいうカサ頭は、黒田官兵衛孝高
「わずか十二万二千石の黒田が、どうして天下を奪 近臣たちは口ぐちのそう言うと、秀吉は、 「なんの、なんの、その方らにはまだカサ頭めの根心が読めぬとみえ」 かの高松を攻めしとき、右府(信長公)の訃報をうけ、夜を昼についで東上し、明智光秀を討滅して以来、交戦大小数度におよんでいるが……と秀吉はいう。
それらの大事にのぞんではこの秀吉も、呼吸 「世に怖ろしきものは徳川と黒田よ。されど徳川は温和なり。黒田のカサ頭こそ、なんとも心をゆるし難きものなり」 そう言うと秀吉は、いまいましげに舌を鳴らしたという。
――その黒田孝高(一五四六~一六〇四)。幼名を万吉といい、播磨国(兵庫県)御著 黒田家の出自は、戦国大名の多くがそうであるように、はっきりしたものではないが、近江国伊香郡黒田だといわれている。その近江から黒田氏が備前国福岡に転じたのは永正の頃で、戦乱を逃れて更にそこから播磨の御著の地で黒田家は、家伝の目薬「地味膏」を商い、財をふとらせ、小地主になった。 それが運の開けるもとで、孝高の父の頃になると近隣に鳴りひびくほどの大地主にのしあがった。当時、黒田家にあつまる郎党、下男は二百人に及んだという。おりから乱世、大みょうになる基盤はできている。やがて孝高は、小寺官兵衛のなで歴史の舞台に登場する。 中国攻めの軍をひきいて下向した秀吉を姫路城に迎えた孝高は、秀吉に三つの策を献じている。いずれも卓越した策であった。この智謀に舌を巻いた秀吉は、孝高と誓書を交換して兄弟の約を結んだという。
以来、孝高は秀吉の参謀の竹中半兵衛と共に、帷幄 史書によると、そのくだりを、
(此時、秀吉変を聞き、未だ何とも詞
という、本能寺の変の飛報をうけて秀吉が呆然としていると、傍にいた孝高が秀吉の膝をほとほとたたき、微笑をうかべて「ご運の開かせ給うべき時が来たのでござりまする。この機を逃さず、巧 のちに孝高は、このことを秀吉が側近の者に洩らしたという噂を耳にするや、 「南無三宝!わが家に禍い迫ったわ」 と髪をおろして隠居し、如水を号し、家督を嫡子の長政にゆずってしまった。 そしてなお孝高は、秀吉の疑心を避けるために側近を離れず、参謀として、小田原征伐、朝鮮の役に従っている。こんなところははいかにも孝高らしい、芸の細やかな行動である。 秀吉の死後、孝高は家康に与したが、心底では「あわよくば天下を」と虎視眈々、野心を燃やしつづけている。
と、運よく関ケ原である。けれど、そんな孝高の心術 「あの阿呆めが」 と、苦りきったという話しがある。 この、関ケ原の騒乱に乗じた孝高のみごとさは、豊前中津を打って出て、豊後、筑前など手当りしだいに攻略しわが手に納めるという怪物ぶりを発揮したことであろう。 孝高の心中は、こうして九州全土を制圧したうえ、家康と三成が戦い疲れた頃を見はからって中央に進出し、天下を取ろうという魂胆であった。 (関ケ原の時、家康と三成と取合、百日も手間取らば(二人が戦いに疲れたところで)我九州より攻登り、勝相撲に入りて(漁夫の利を得て)天下を掌の中に握らんと思いたりき) と孝高は後年、臨終の床で長政にそう述懐している。 (その時は、子なる汝も打ち捨て、捨殺して一博打打たんと思いしぞかし。天下を望む(者)は、親も子も顧みては叶わぬなり)
言うと孝高は、紫の袱紗 《軍(いくさ)は死生の界なれば、分別過ぐれば大事の合戦はなし難し》 戦は生きるか死ぬかの大ばくちゆえ、思慮が過ぎては大事の戦はできぬ。時によっては草履と木履を片々にはいても駈け出す心がまえがなくてはならぬ。食物がなければ何事もできぬものなり。ゆえに金銀をつかわず、兵糧をたくわえ一旦緩急の軍陣の用意を心がけておけ、そういったという。 話が前後したが、戦国の勝負師、黒田如水のしぶとさは、関ケ原の戦後、いままでの謀反気など何處吹く風といった顔つきで、ぬけぬけと家康に祝いを述べ、息子の長政のために筑前福岡五十二万石をちゃっかりせしめていることであろう。 ※参考:黒田如水 神坂次郎著『男この言葉』P.251~255 2021.05.16記 |
|
山片蟠桃 し経済ハ民ヲシテ信ゼシムルニアリ (1,748~1,821年)P.195~201
江戸後期の大阪で、「大名であれ旗本であれ、借金をせねば暮らしていけぬ者は、"貧民"だ」と言い放った男がいる。升屋小右衛門、町人学者としてのなを山片蟠桃 「仙台藩などというても、(こちらは)年貢米をカタに返済できぬほどの金を貸しておるのだから、仙台六十二万石は升屋の物も同然だ」
と小右衛門は辛辣
百姓が年貢に出した残りの米を藩が「米札」(一種の私製紙幣)で買いあげ、江戸に運んで売った現金を両替商にまわしてその利息を稼ぎ、藩財政再建に充 「それなら、手前どもで一万五千両ほど御用だていたしましょう」 これで資金の方は都合がついたが、東海廻し(太平洋)で江戸へ運ぶために仙台、銚子、江戸と三ヵ所に役所を設ける必要がある。
「その費用も升屋がお出ししましょう。が、これらの役所の雑費
と小右衛門はいう。だが、いつの場合にも役所というのは融通のきかない石頭ばかりで、前例のない金は一両も出せない。もともと「算用 「なるほど、それなれば」 小右衛門はうなずいた。その二百両のかわりに、 「一俵一合のサシ米をおゆるしくださらぬか」
サシ米というのは、俵の米の品質をチェックするとき、俵へサシ(刺 「おお、それならやすいことじゃ」 と役人は、快諾した。
「サムライどもの阿保 小右衛門は、心の中で舌をだした。
当初、二百両支給せよと切りだしたのは作戦である。二百両を升屋に支出して、もし小右衛門の施策が失敗した場合、その責任は係役人が背負わされてしまう。だが、一俵につきたった一合のサシ米が減ったところで係役人には痛くも痒
ところがこの一俵一合が莫迦
この六千両が、以後、升屋の金蔵
このサシ米や買米、回米で、傾きかけていた升屋や仙台藩を立て直した大番頭の小右衛門に、当主の重芳(升屋四代目山片平右衛門)は感謝の意を罩 小右衛門が町人学者、山片蟠桃として名をあらわしてくるのはこの頃からである。号の蟠桃は、升屋山片の番頭、をなぞらえたものである。
学問を好んだ蟠桃は、《書生の交りは貴賤貧富を論ぜず》と四民平等をうたった町人の学問所、懐徳堂に学び、朱子学を中井竹山、履軒 《太陽ハ天地ノ主ナリ、地ハ主ニアラズ、太陽動カズシテ(略)》
と、日本最初の地動説とも思える一節もある。天文学に興味をもつ蟠桃は、観測器械をつかって天体観測をしたり、奇児
《紅毛ナドノ国ハ、国王元ヨリ商売ノ大将ナリ。万国ニ奔 そして蟠桃は、外国と交易をするには、天文、地理の知識が必要だと述べる。
《先年(松平定信の寛政改革)諸 《経済ハ民ヲシテ信ゼシムルニアリ。民信ゼズシテ何ヲカナサン。民ヲ信ゼシムルハ唯ソノ身ノ行イアルノミ》 商いとえば、物価は需要と供給が決定するもので、政治権力が介入したところでどうなるものでもない。かえって高騰をあおりたてるばかりである。
蟠桃はまた、神仏や迷信は人間の心がつくったもので、霊魂などというものは存在しないと言い、日本の神々が生まれ、国土草木を生む……という(本居宣長などの)学者たちの愚陋
《今ノ巫祝 もともと神や霊魂など有りはしないのだ。
《死シテ何
《ソノ魂魄 《人ノ生ズルハ草木ノ萌生スルガゴㇳク、ソノ死スルㇵ枯ルルガ如シ、又ソノ子アルㇵ種実ヲ蒔テ生ズルガ如シ、スベテ一種一衰ノ道理生ㇾテ、グングンㇳ陽気盛ンニナリテモ、亦ツヒニオトロエ、命尽キ死シ、消散シテテ土ニ帰ス》
ある時蟠桃の友人が重病になった。が、祈禱師
「儂 そう詰め寄ると、祈禱師は仰天して逃げて行ってしまったという。実学家蟠桃の面目躍如たる逸話である。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.256~260 2021.06.07記
|
|
伊勢貞親 珍物到来せば多少によらず進上いたすべき也 (1,417~1,473年)P.195~201 にんげんには、誰でも口癖がある。 古典落語の名人といわれる桂文楽は機嫌のよいときはいつも、 「あぱらかべっそん」 などと意味不明の言葉を呟いたというし、洋酒の寿屋の創業者鳥井信次郎は、「やってみなはれ、やらなわかりしまへん」 が口癖であった。 サムライの世界では、柳生家の高弟、高田三之丞などはちょっと変っている。道場にでて試合相手に袋竹刀をかまえると、 「おいとしぼう、おいとしぼう」 と叫んで斬撃した。 高田の尾張方言を訳してみると、「おいたわしや、おいたわしや!」だから、対峙した相手にすれば嫌な気分になる。 鎌倉幕府の執権、北条泰時の口癖は、 《道理ほど面白きものはなし》
であり、感激したときや嬉しい時など、しばしばこの言葉を口にしていたという。そして驚いたことに泰時は、この口癖である「道理」を中心にして、日本最初の『貞永式目
これから述べようとするのも、中央政界きっての傍若無人ぶりを発揮し、あくのつよさで室町幕府の政所
高望王
貞親もまた家職をついで六代将軍足利義教
《幕府(義政)貞親を呼びて父と云い其の妾
と信任されたことをよいことに、義政夫人、日野富子らと結んで専横をきわめ、将軍家の後嗣問題に介入、足利義視 この事件が応仁の大乱の点火薬になる。貞宗が父の、あまりの横暴ぶりを見とがめて泣いて諫言し、かえって怒りをかい勘当されるということがあったのは、この時である。 はたして、貞宗が危惧したように貞親は山な宗全に憎まれ、
《貞親(は山名を)懼れて遁走し蹤(蹤跡
という破目になる。貞親失脚のあと貞宗は、おだやかで堅実な人柄と穏健な政治力をかわれ、義政の命をうけて政所執事となり、かねてから養育の任にあたっていた義政の子、九代将軍義尚 だが、器量ゆたかな貞宗でも、父の貞親の眼からみれば、世間知らずで頼りなげに思われたのであろう。前述の"愚息"のための三十八ヵ条にも及ぶ教訓を語り授けている。その中から幾つかを抜き書きしてみると、
《一、いずくよりも珍物到来せば多少によらず進上いたすべき也。殊に初物などは一ツ二ツ(だからこそ)其の興あり。予、若年の比 たくさん手元にあっても初物などは少量進呈するほど珍重されるものだ、というところなど、贈物のコツを語って見事である。
《一、人に酒などすすむる事、第一にちかづく媒
数多い訓 《一、上意のよきもの(将軍の覚えよき人)又は(将軍と)くちなどきくものとは常によんで(招待して)知音(親しく)して物をもとらす(贈り物をする)べき也。かようなればいうべき事をもいわずかたうどになる物なり(だまっていても味方になってくれるものだ)》
《一、いかなる不肖の者尋来ともかろがろ出 とるにたらない身分の者が訪ねてきても、気軽に会ってやれ。わざわざ訪ねてきて、会えずに帰るは残念に思うものだ。このようなことをつづけておれば、大事な人も疎遠になっていくものである。そうした人たちが世間に悪評をふり撒き、またそれを小耳にはさんで悪い噂をひろげていく。たとえ病床にあっても、寝巻のままでも会ってやれば人というものはよろこぶものだ。
《一、いかに気にあわざる者来たり共可対面
《一、人と知音するには、兼好法師がいえるごとく無能なる者と寄合う事何の詮かあらん。雑談にもかようの者は人の上さ(噂)や賤 無能だと言っても、極心(誠実)な者は自分の鏡ともなるし、又、酒宴などで座持ちのよい男も大事ゆえ、目をかけてやるがよい。 こうした貞親の訓戒は三十八ヵ条の中には、平成の時代にも通用するような事例が多い。貞親はすべてを語りおえたあと、次のように結んでいる。 《右条々、子を思う心の闇にくらまされて暁のねぶり(眠り)をすますごとにおもい出る事どもつくすなる心に、猶おろかなる筆にまかせて貞宗に与え侍る。もとよりいましめのためなれば他人の一覧におよぶ事あるべからず。 子をおもう親の心の闇晴ていさむる道にまよわずもがな
于時 神坂次郎著『男この言葉』P.261~265 2021.06.18記 |
|
本間 四郎三郎
公益のために財を吝む勿れ 十成を忌む (1,732~1,801年)P.195~201
江戸時代の豪商、豪農で、かつて日本一の大地主と称 本間さまには およびもないが せめてなりたや 殿様に
《金銀財宝は積んで山の如く、伊呂波 と、巨大な経済力で山形地方に君臨していた。その本間家が筆頭株主の商事会社、本間物産が倒産したと新聞で報じられたのは一九九〇年十月で、まだ記憶に新しい。 本間家は代々、その家憲とするところの、
《十成 を守り、財を成しながら利益の大半を地域の人びとのために還元してきた。
日本海を吹き荒れる強風は、酒田の町に一冬に一メートルもの砂を積もらせる。その砂嵐 時の流れといってしまえばそれまでだが、本間家のこの表舞台からの退場は惜しまれてならない。 本間 四郎三郎(一七三二~一八〇一)――。 本間家中興の祖といわれる四郎三郎は、はじめ久四郎、名を光丘。天下第一の豪農として庄内藩十四万石の領内において、藩主をはるかにしのぐ二十四万石の大地主である。
本間家の祖は、寛永年間(一六二四~四四)すでに商業を営み、酒田三十六人衆の一人として町政に参与し、元禄年間、海の商人として庄内地方や最上平野に産する米、藍、漆、晒蝋 四郎三郎が、父、庄五郎光寿のあと本間家を嗣いだのは宝暦四年(一七五四)。 以来、四郎三郎は、
«父祖の志を体し倹素にして経済の利に通じ神社仏閣を修築し最上川の水利を治し天明の凶歉 という。 宝暦四年、四郎三郎は父の遺志を継いで前述の、酒田、西浜の防砂林のしょく林に取り組んだ。が、これは尋常の事業ではなかった。黒松の苗木はうえてもうえても、烈しい風害をうけ飛来する砂に埋没し、苗木を保護するための竹矢来を組むなど、吹きつける砂あらしと格闘すること十二年、ようやく砂防林の完成にこぎつけている。 かくして藩主、四郎三郎の功を賞し町年寄を命じ、のち士分に取りたて小姓格となる。 明和五年(一七六八)、鶴岡、酒田両城の普請を成し遂げ、備荒備蓄米として藩庁に二万四千俵を献上、この米が、天明三~八年(一七八三~八八)の大飢饉から藩士や領民を救うことになる。 《両者(二件)の功を以て併せて(四郎三郎に)禄五百石俸三十口、物頭格に班す» 庄内藩のパトロンとしての四郎三郎の奔走はなおもつづく。焼失した江戸藩邸の再建をはじめ庄内藩の窮乏を救うため財政すべてをゆだねられ、その上、幕府から安べ川、富士川、大井川の改修工事を命ぜられ、その資金借入れに大坂、兵庫の豪商たちを訪ねて成功――と八面六臂の活躍ぶりを四郎三郎はみせている。
こうして四郎三郎の経済手腕のあざやかさをみて、藩主を通じて財政整理の救援を委嘱する諸藩あとを絶たず、なかでも窮迫貧困ぶりを天下に知られた米沢藩、上杉治憲
《治憲の徳、天下に鳴る、(その背後に)四郎三郎の献貸与 という。この他にも四郎三郎は、酒田港口に私費をもって灯台を建て、氷結する最上川の氷上に板を敷き 《旅人の陥没を防ぐ» など、公共のため激務に従事すること三十六年、寛政九年病を以て辞するも、 《(藩主)これを慰諭して聴せず》 享和元年、没す。七十歳。 《一、公共事業に全力を竭し、公益の為に財を吝む勿れ。 一、神を敬い、仏を崇ぶは誠心誠意を喚起する所以なり。一日も信仰の念を忽せにすべからず。 一、貧を憫み弱を扶け盛んに陰徳を施すべし。 一、勤倹の二字は祖先以来の厳訓たり、宜しく朊膺してその功徳を発揮せよ。 一、深く子弟の教育に注意し、忠孝の心を涵養すべし。 一、富豪の者と縁組すべからず。須らく清素なる家庭の子女と婚を結ぶべし。 一、勧懲の制を設け、農事を奨励し、小作人を優遇すべし。 一、家庭の静粛は長幼の序を厳にするにあり、決して紊ることある可らず。 一、世態(世間の有様)人情を究め、心身を修養するは、一家を治むるに於て必要なることに属す。宗家の嗣子たる者は必ず全国を漫遊すべし。》
――この《宗家の嗣子たる者は必ず全国を漫遊すべし》という条
※:広瀬旭荘
《田舎人、一たびは三都を観ざるべからず(略)京の人は細なり、大坂の人は貪なり、江戸の人は夸(尊大)なり、江戸の人は客気 という。
《一、額に汗して得たるものに非 こうした本間家家訓の中で、特異なのは、 「収入の分配法」 を記した項であろう。
《一、上
二、神仏の加護、祖先の偉効に依りて家隆
三、各戸あって地主賑 四、残余の四分の一を以って其家計に充て、勤倹自ら奉じ、勤めて剰余を生ぜしめ、之を蓄積すべし。》
つまりこれは、本間家の当主たちが代々守りつづけてきた《十成を忌む》冨の充溢 神坂次郎著『男このことば』P.266~272 参考1:日本一の地主・酒田本間家 参考2:社是・家訓
幕末最強「庄内藩」無敗伝説を知っていますか 薩長も恐れた東北の「領民パワー」 東洋経済オンライン
庄内藩の最強伝説を支えた酒田の豪商、本間家の門構え 戊辰戦争といえば、薩摩・長州(薩長)など「官軍」の一方的な勝利というイメージを持たれる方が多いことだろう。会津藩(福島県)以外の奥羽越列藩同盟軍は大した抵抗を見せることなく降伏した……と。 だが実際は、同盟軍は一方的に負けていたわけではない。前回(反薩長の英雄「河井継之助」知っていますか)紹介した長岡藩(新潟県)のほかにも、庄内藩(山形県)は「官軍」寄せつけず、薩摩兵と互角に戦って勇猛さを見せた。にもかかわらず、「薩長史観」(なぜいま、反「薩長史観」がブームなのか)では、故意に無視されてきたと歴史家の武田鏡村氏は語る。 『薩長史観の正体』を上梓した武田氏に、知られざる「庄内藩」の強さについて解説していただいた。
惨憺
酒井忠篤 庄内藩は、江戸市中取締役となったときから、薩摩と反目する関係にあった。
薩摩は西郷隆盛の指令で江戸市中を騒擾
薩摩は庄内藩を逆恨みして、奥羽鎮撫軍(新政府軍)を差し向けた。薩摩藩士の下参謀大山格之助が副総督の沢為量 奥羽(東北)の戊辰戦争で初めて戦火が交わされたのが、庄内兵と薩摩兵・新庄兵が対戦した清川の戦いである。初めは薩摩兵が優勢であったが、支藩の松山藩や鶴岡城から出兵して来た援軍で薩摩兵を撃退した。 庄内兵は天童を襲って新政府軍を追い払い、副総督の沢為量は新庄を脱出して秋田に向かった。さらに庄内兵は、新庄、本荘、亀田を攻めて無敵を誇った。
庄内兵の奮戦を支えたのが、酒田の豪商本間家である。本間家は北前船 庄内兵は、7連発のスペンサー銃などの最新式の銃砲や大量の弾薬を手にした。近代兵備を装備し訓練された強力な軍隊だったのだ。 また、新政府軍との戦いで庄内藩は最終的に4,500人の兵を動員しているが、そのうち2,200人が、領内の農民や町民によって組織された民兵だったという。このような高い比率は他藩では見られないもので、領民と藩との結び付きが強かったことがうかがわれる。国際法を知らなかった新政府軍
新庄藩を攻め落とした庄内兵は、やはり新政府軍に与 内陸と沿岸の両方面から秋田に攻め入り、「鬼玄蕃」と恐れられた中老酒井玄蕃が率いる二番隊を中心に連戦連勝で、新政府軍を圧倒した。 秋田藩は古風な出陣ぶりで、従者に槍や寝具などを持参させていた。このため新政府軍の総督府から、無益の従卒を召し連れて出軍して機動力を欠いていると叱責されている。
また、秋田藩はアメリカ軍船を購入したが、これにロシア国旗を掲げて庄内の鼠ヶ関 新政府軍は外国軍に協力こそ求めなかったが、坂本龍馬が熟読し、幕府の海軍が遵守した国際法「万国公法」通じていなかったのである。 庄内藩は、しだいに同盟諸藩が新政府軍に恭順・降伏していくと、孤立を恐れて秋田戦線から退却する。庄内藩が降伏したのは会津降伏の4日後、明治元(1868)年9月26日のことで、奥羽では最後に新政府軍に屈している。勝ち戦続きで、領内への侵攻を許さなかった末の恭順である。
庄内藩は果敢に新政府軍に挑み続け、ついには降伏したわけだが、新政府軍の報復に慄 だが西郷は、東北方面の戊辰戦争ではほとんど出番がなく、ようやく庄内に着いたときには戦いが終わっていたというのが実情であった。しかも多額の戦後賠償金をせしめることができたのであるから、寛大に振る舞ったのではないだろうか。 なお、この戦後賠償金は、本間家を中心に藩上士、商人、地主などが明治新政府に30万両を献金したものである。
ちなみに、会津藩は23万石から3万石と大幅に減封された。そして、ふ毛の地・斗南 だが、庄内藩は17万石から12万石に減じられただけであった。一時は会津、平と転封を繰り返したが、先述の戦後賠償金や領民の嘆願により明治3年(1870年)に酒井氏は庄内に復帰した。 ここでも庄内藩は、領民たちの尽力により救われたわけである。ちなみに天保11年(1840年)にも、幕府による領地替えの計画が持ち上がったが、領民の嘆願により取りやめになった経緯がある。 こうした領民との結び付きといったソフトパワーの面からも、庄内藩は「最強」だったといえるのではないだろうか。 平成29年10月28日、2012.05.17追加。 |
|
(1,719~1,788年)P.195~201
徳川期における最も偉大で進歩的な政治家とも称
紀州藩の軽輩であった田沼の家が、歴史の表面に浮びあがってくるのはこの意行の代である。紀州徳川家から徳川宗家に入って八代将軍の座に就いた吉宗に随従して江戸にくだった意行は、三百俵御小なん戸役 いっぽう、将軍の世子、家重の小姓としてスタートした意次は、天下の人士を瞠目させた空前絶後ともいう出世ぶりをみせるのだが、それを年表風に列記すると、 元文二年(一七三七)十九歳、主殿頭に叙任。 延享三年(一七四六)二十八歳、小姓頭取となり、御役料百両。 延享四年(一七四七)二十九歳、二千石に加増。 寛延四年(一七五一)三十三歳、九代将軍家重の御側御用取次となる。 宝暦五年(一七五五)三十七歳、五千石に加増。 宝暦八年(一七五八)四十歳、遠州(静岡県)相良一万石を拝領し、大みょうに。 やがて家治に将軍職をゆずって隠居した家重は、その臨終の枕頭に家治を呼んで、 《主殿はまとうど(完全な人物)なり、ゆくゆく心を添えて召使わるべきよし御遺言ありしにより》(『徳川実紀』) 十代将軍家治はその遺言をまもり、意次を一万五千石に加増。以来、意次は家治の側近ナンバー1の官僚政治家として卓越した才腕をふるう。 四十九歳で御用人となり加増二万石、相良城主となる。五十一歳、側用人兼老中格に列し三万石という破格の立身をとげる。 老中職といえば、将軍綱吉の寵臣、柳沢美濃守吉保でさえ、正式の老中にはなれなかったのである。この一事をみても意次の出世は、信じられないほどの幸運に包まれていたといえる。 意次の幸運は、なおもつづく、 五十九歳、三万七千石……六十三歳、加増をうけ四万七千石となる。 信じるべき資料によると意次は、細面の美男で才気渙発で、切れ者の官僚にありながら驕ったところがなく挙措おだやかで謙虚な人柄であったという。下僚に対しても物腰低く、人間関係の達人で、政治家としても当時の猫の目のように移り変る経済社会を広い視野で眺め、鎖国いらい立ち遅れている日本を開国に転じ、沈滞の底にある経済の活性化をはかろうとしていた。 「そのためには……」
海外貿易の道をひろげ、国内でも北海道に百十六万町歩の開拓、七万人移住の計画や、千島、樺太開発の大構想など、現実を凝視
海外貿易といえば、意次の嫡男の山城守意知 ――だが、こうした意次父子の心にくいばかりの仕事ぶりに、諸大みょうや旗本たちは黒けむりをあげるほどの妬 「あの、成り上り者めが」 そんな彼らの目に、軽輩微禄の意次が将軍家重・家治のお声がかりで天下第一等の権力者にのしあがり、古い因習を次から次へと破って政治の世界に新風を吹きこませている姿ほど憎々しいものはない。 だが、心の中ではそう思いながらも彼らは、猟官運動のために田沼邸に日参じ、意次、意知に世辞を振り撒き、阿諛(へつらうこと)し、追従の限りをつくしている。それは意次の前に平身低頭した松平定信や、肥前平戸城主、松浦静山の例をみればわかる。 が、好事魔多し。政治家としての意次の晩年の不運は、明和七、八年(一七七〇、七一)の全国的な大旱魃から、天明三年(一七八三)にいたる数々の天変地異である。うちつづく飢饉、災害、疫病、伊豆大島三原山の大噴火、浅間山の爆発に民衆は戦慄した。この災禍の原因は意次父子の奸悪な政治を天が懲らしめているのだ、という噂がささやかれ、そうした黒い風説に追打ちをかけるように、山城守意知が江戸城内で旗本、佐野左衛門に斬りつけられ横死するという事件が起っている。この刃傷の原因はいまも不明だが、すでに老境にある六十六歳の意次にとって、嫡男である政治改革の唯一の同志でもあった意知の死は致命的であった。
だが、意次は父である前に政治家であった。五体を引き裂かれるような思いを怺 この日から、意次の運命は逆転する。
失脚後の意次に浴びせかけられた、いわれなき中傷の殆どは「成り上り者」意次の卓越した政治手腕に対する保守派門閥大みょう、旗本たちの嫉妬と憎悪である。反田沼派の彼らが振り撒いたデマに踊らされた巷の人びとは奸悪の侫人として意次父子を罵倒し、讒謗(誹謗)の限りをつくしている。従来の諸資料や文献のなかにみる"賄賂伝説"もその一つである。田沼事件は、幕府を舞台にした一種の「お家騒動」であり、欲望芬々 みずからについて語らず、記録も残すことのなかった意次だが、唯ひとつ子孫のための家訓ともいうべき遺書(田沼道雄氏蔵)を残している。意次の処世信条であるこの七ヵ条の訓は、忠義、孝行、武芸、学門といったもののほか、 《交誼に裏表なきよう心掛くべし》 《家人(使用人)をあわれみ、賞罰に依怙の沙汰あるべからず》 《百姓、町人に無慈悲なる扱いなすべからず、(わが)家の害、これに過ぐるものなし》 といった要旨のものの他、財政問題については、 《勝手元不如意にて貯えなきは、一朝事ある時の役に立たず,御軍用に差しつかえ、武道を失い、領地頂戴の身の不面目、これに過ぐるものなし 》 と述べ、捌紙までつけ格別の注意を与えている。武士の収入というのは予定以上に増えることはない。凶作による収入減、不時の出費、それらが重なれば憂うべき結果を招くものだ。借金をした場合、利息は十分の一、千両借りれば知行百両減じたものと同じゆえ、利子の支払いと元金の返済に窮し、更に借金し、遂には大借財となりたる例、世間に極めて多し。ゆえに、 《常に心を用い、いささかの奢りもなく、油断せず要心すべし》 と意次は、その遺訓のなかで声を重ねている。 神坂次郎著『男この言葉』P.273~277 2021.06.10記 |
|
岡左内
金の徳は天下の人をも従えつべし国に法令多きは恥の基なり (1,590年ころ)P.195~201
銭
唸る……といえば、いまから千年ほど昔の中国に袁
「ああ、それはカネが友(金
と破顔 で、そのカネの話だが、戦国のころ、金銀に異常な執着をもつ武士がいた。
《陸奥の国、蒲生氏郷
つねに角栄螺 ところがこの左内、世にもまれな金銀好きで、並はずれた倹約家で家来にも常に口ぐせのように、
「銭を蓄 と倹約、貯蓄を奨励し、自分から率先して、 《常に草履をつくり、売る》(『土稿会談』)
という、なりふりかまわぬ蓄銭癖をみせ、せっせと銭を貯
この左内の唯一の愉
《一月 と、稼ぎためた大判や小判、銀貨などを座敷中に撒き散らし、ふんどし一つの裸になってその上でころげまわることぐらいだ。
「あような呆気
という家中の侍たちの陰口も耳に入ってくる。が、いかに吝嗇野情と称
《あるとき、いつもの如く金銀を並べて居りしに、近きあたり(近所)の士あらそいをし出し、方人 座敷いっぱいに撒き散らした金銭をそのままに、喧嘩を仲裁して左内が帰ってきたのはその翌日であった。その間、左内は、金銀のことをすこしも気にする様子はなかったという。
左内の馬の口取りをしている中間
《金の徳は天下の人をも従えつべし。汝 手文庫のなかから小判十枚を取りだし、中間に与えたとう。
上田秋成の『雨月物語』のなかの「貧福論」によると、その夜、黄金の精が左内の夢枕にあらわれて、夜っぴて左内と金銭論、経済、処世、貧福論をかわし、遠寺の鐘が五更 ※参考図書:『雨月物語巻之五』「貧福論」日本古典全書〚上田秋成〛(朝日新聞社)P.162~ 後年、蒲生家が減封されて宇都宮に移っていったため、会津に土着した左内、新領主の上杉家に召し抱えられて知行千石。
そののち、上杉家が石田三成と呼応し、反徳川の軍を挙げたとき左内は、「軍費の御用意のため、永 当時、新領土会津に移ってから二年という上杉家の財政は"戦争"をするにしても窮迫のどん底にあった。主家でさえそんな状態だから、家臣たちの貧寒ぶりはあわれなものだ。にわかの出陣の支度に狼狽した同僚の一人が、守銭奴と陰口していたにもかかわらず、左内の前に低頭して、泣くような声で借金を申しこんだ。 「ああ、よろしゅうござる」
吝嗇だと思っていた左内が、案に相違して明るい顔つきで、きりだした額そのまま貸してくれたので喜び、踵 「なるほど、かねてから左内殿が金を大事にしろというたのは、この時の備えがためであったのか」 以来、家中の者は誰ひとり左内の悪口を言わなくなった。
そのうえ、このときの伊達政宗軍との合戦、摺上川 その左内に、背後から迫った黒革おどしの鎧、三日月の前立物をした兜をかぶった黒武者が、背中めがけて一太刀斬りつけた。一瞬、振り返りざま左内は、片手なぐりに相手の兜の真っ向から鞍の前壺まで斬りつけ、返す二の太刀で兜のシコロを斬り飛ばし相手の太刀を斬り折り、三太刀目で右の膝口を斬撃し、黒武者を遁走させている。 「おのれ卑怯なり馬を返して勝負せよ!」 と左内は呶号した。その黒武者が、じつは敵将、伊達正宗であった。 左内の奮戦にもかかわらず上杉家は、関ケ原ののち家康から国替えと減封に処せられている。左内はふたたび牢人。その後、左内があの時の荒武者だと知った政宗は、その武勇を愛し三万石をもって招こうとした。だが左内は辞退し、会津若松六十三万石に返り咲いた旧主、蒲生家に一万石で仕えた。 帰り新参として蒲生家に出仕した左内の蓄銭癖は、更に昂じている。
金
後年、みずから死期を覚った左内は、病床から主君、忠郷
この左内の弟、岡備中守の娘と山鹿六右衛門のあいだに生れたのが、山鹿流軍学の祖で赤穂藩家老、大石内蔵助の師、山鹿甚五左衛門、素行 神坂次郎著『男この言葉』P.278~282 2021.06.29記 |
 こうして斉の国に上陸した范蠡は、心機一転、ここでのなを鴟夷子皮と改める。シヒというのは革袋のことで、巻くも伸べるも自由、つまり進退自在の人、という意味なのであろう。『漢書』の<貨殖伝>の范蠡のくだりや、『史記』の<貨殖伝>によると、一族や家族、奴隷らと農事に従い、節倹しながら牧畜し、商業し努力したところ、数年ののち数千万金を積むほどの富豪になったという。
こうして斉の国に上陸した范蠡は、心機一転、ここでのなを鴟夷子皮と改める。シヒというのは革袋のことで、巻くも伸べるも自由、つまり進退自在の人、という意味なのであろう。『漢書』の<貨殖伝>の范蠡のくだりや、『史記』の<貨殖伝>によると、一族や家族、奴隷らと農事に従い、節倹しながら牧畜し、商業し努力したところ、数年ののち数千万金を積むほどの富豪になったという。

 金といえば、《この世で唯ひとつ》の信ずべきものとバルザックが言ったのと同じことを、元禄時代の文豪、井原西鶴もまた『日本永代蔵』のなかで、次のようにいっている。
金といえば、《この世で唯ひとつ》の信ずべきものとバルザックが言ったのと同じことを、元禄時代の文豪、井原西鶴もまた『日本永代蔵』のなかで、次のようにいっている。

 「東の渋沢栄一、西の大原孫三郎」 兼田 麗子著『大原孫三郎━━善意と戦略の経営者』(中公新書)P.193~196より
「東の渋沢栄一、西の大原孫三郎」 兼田 麗子著『大原孫三郎━━善意と戦略の経営者』(中公新書)P.193~196より

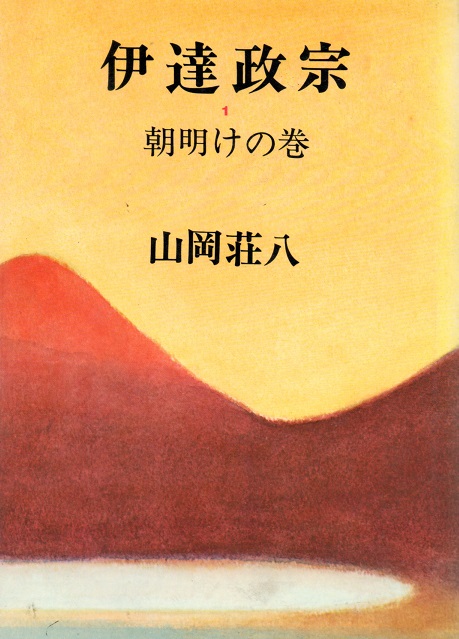 ※参考図書:山岡荘八『伊達政宗全六巻』(毎日新聞社)昭和四十五年九月二十日 第三刷
※参考図書:山岡荘八『伊達政宗全六巻』(毎日新聞社)昭和四十五年九月二十日 第三刷
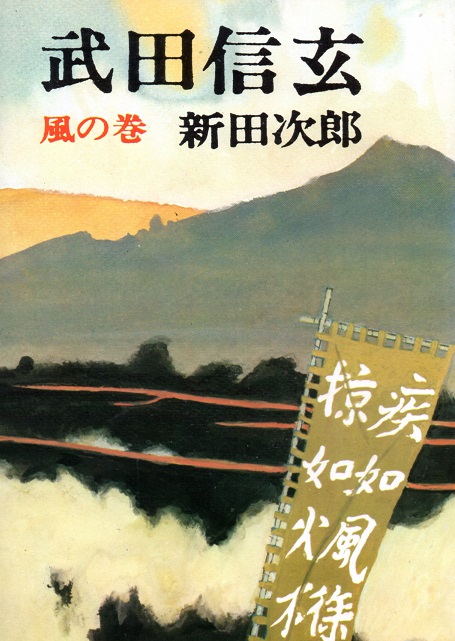
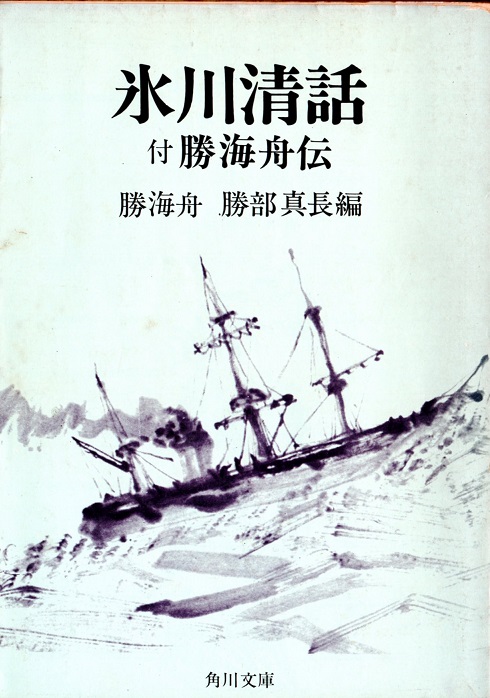 氷川清話
氷川清話
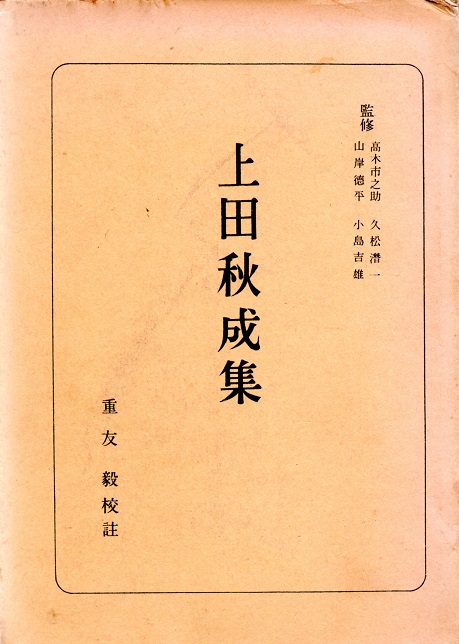 ※参考図書:日本古典全書〚上田秋成〛(朝日新聞社)P.161~
※参考図書:日本古典全書〚上田秋成〛(朝日新聞社)P.161~