〔柴田宵曲著〕・著作集第八巻の一部
|
鍋島閑叟と古賀穀堂 森銑三著『史伝閑歩』(中央公論社)P.23~28 天保七年の九月、佐賀鍋島侯の儒員古賀穀堂は、病の床に臥していた。年は五十九歳になっている。まだまだといってよい歳である。それだのに、医療に抜かりがないのに、病気は重くなる一方で、日に日に衰弱が加わって行くのだった。穀堂のそうした様子を耳にして、もっとも心を痛めている一人に、主君の鍋島直正があった。 直正はこの年まだ二十三歳の若年ではあるが、幼少の頃から穀堂の教育を受けて、穀堂には特別の親しみを持っている。穀堂によって、聖賢の道を学ぶことを得た。そして今は、儒学の精神を身に体して、一藩に治を敷こうとしている。穀堂を政治の顧問として、これからもその意見を聴いて行きたく思っている。直正にとって穀堂は、何人も増した、掛けがえのない人物だったのである。その穀堂が病んで、再起が気づかわれている。直正は気が気でなかった。 何はともあれ、見舞いに行きたい。直正はそう思った。それだのにそのことは、近臣によって阻まれた。「これまで殿様が、家老の病気をお見舞いになった先例などはござりませぬ。ましてこれよりも身分の低い儒者の家へお越しになったりしますのは、あまりにもお軽々しゅうございましょう」 そう言われて、直正の心は納まらなかった。穀堂はただの儒者ではない。予の師匠だ。師匠の病気を弟子が見舞うのに、なんの差支えがあろうか。直正はそう言い張りたかった。けれども、年は行かなくても、直正の人物は練れていた。家臣の止めるものを押し切って、よしそれが正しいにもせよ、自分の所存のままにふるまうべきでないと、常々自制しているのだった。 見舞いに行くのを、直正は一応思い止まりはしたが、心はそのために楽しまなかった。そしてまた穀堂は、その後にも衰弱を加えているであろうと思うと、矢も楯もたまらなかった。 一日、秋晴れの爽やかな日があった。 「珍しく気持ちのよい日だな。遠乗りをして来ると致そう。馬の用意をいたせ」 直正は、何気なくそう命じて、用意もそこそこに、馬に跨って城を出た。その後には、ただ数えるばかりの家来が従った。 この日は、事実よい日和であった。蒼空は高く澄み渡って、浮雲一つない。秋らしい穏かな日射しが、いずこにも行渡っている。 騎馬の直正は屋敷町に差しかかった時、そこに菊を作っている屋敷があって、垣越に黄白の花の咲き乱れているのが、美しく眺められる。直正は、つと馬を止めて、「あの菊の花を、少しばかり所望してまいれ」と言いつけた。 遠乗りにお越しになるのに、花が欲しいなどとおっしゃるのはと、いぶかしく思ったが、それをとやかく口にしたりなどすべきでない。お供の一人が、すぐに庭木戸から這入って行って、お旨を伝えて花の一束を貰って来た。家の者もそこへ出て、「手作りの花を、御所望に預って、面目に存じまする」と、御挨拶申上げた。 直正は、花の得られたのに、満足のていであった。そしてまた馬を進ませる。けれども少し行ったところで、ぴたりと馬を止めた。皆がきつくと、そこは穀堂の屋敷の前なのであった。 「古賀の家の者に、予が見舞いにまいったと申せ。けれども、病人は寝たままでいるがよい。強いて起上らせたりせぬように……。はっきりそう申せ」 ここに至って、お供の者たちも、殿の今日のお外出は、穀堂先生の病気お見舞いなさるのがお目当てだったことに気がついた。 殿様が、前触れもなしに、いきなりお越しになったのに、古賀の家の者はあわてふためいた。しかしお馬の殿様を、いつまでも表に待たせて置くわけには行かない。病室に散らばっているものを、片付けるのもそこそこに、わずかに病人の枕許に褥を敷いて、お迎え申上げた。 直正は、わざと目立たぬように、庭口から入って、庭を過ぎて、病室へ来た。開け放した、明るい一間の中ほどの床に、穀堂は仰臥して居り、起上らぬようにとのいいつけに、ただ顔だけを横にして、殿をお迎え申上げた。薄手の布団の上には、穀堂の晴れの上下(かみしも)が、拡げて置いてある。それは急いでそうしたのだった。 病間に近づいた直正は、やつれ果てた穀堂が、両眼を濡らして、こちらを向いているのを見た。 いつの間に、かようまでも衰えたかと思うと、直正の胸は塞がった。けれども、強いて気持を押し隠して、設けの座に着くなり、顔を穀堂に差しつけるようにして、「藤馬」と、その通称で呼びかけた。「気分はどうか」 穀堂は、何かお答え申上げるようだったけれども、言葉がかすれて聞き取れない。 直正は、わざと何でもないようにいった。「一度見舞いに来たいと思っていながら、何かと障りがあって参りかねた。――それできょう、かように会うことができて嬉しく思うぞ」 そして背後の若侍から受取った花を出して見せて、「どうじゃ、奇麗であろう。途中の家から貰って来たのじゃ。これを見て気を晴らすがよい」 そういって、家人の持って来た器に、無雑作に手ずから差入れた。 病床の穀堂は、殿のお心尽しのありがたさに、制するのも聞かずに、辛うじて半身を起して、型ばかりの御礼を申上げた。 そして家の者を顧みて、その花の一つを摘ませて、それを自分の乱れた髪に差させて、喜ぶ¥ばしさに堪えぬ様子だった。 直正は、「もうよい、もうよい。楽にいよ」と、強いて穀堂を枕に就かせた。 直正には、いいたいことが、幾らでもあるようだった。けれども長居をして、あとで体に障ったりするよではあらない。 「きょうは、これだけで帰るとしよう。遠乗りをして来るといって、城を出たのに、長居はなるまい」と、ありのままを打明けた。 直正は座を立った。敷石に揃えてある草履を穿いてkぁら、また振返って、穀堂を見た。ししtふぇ「くれぐれもたいせつにいたせ」の一言を残して通りに出、ふたたび馬上の人となった。穀堂は、両眼に涙をいっぱい溜めて、殿の後姿を見送っていた。 心にかかっていた見舞いを終えた直正は、遠乗りなどは、もうどうでもよいと思った。けれども、そういって出て来たのだからと思い返して、郊外に出るだけは出て、黄金に色付いた田の面を見た。そしてただそれだけで帰城した 帰っても直正は、穀堂の病床を訪うたことなどは、誰にもいわなかった。そしてその見舞いのことは、それなりにすんでしまった。 数日後に、穀堂の訃報がもたらされた。直正は、それを聞いて暗澹とした。そして先日、遠乗りをかこつけに穀堂に会って来たのを、せめてもの慰めとした。 古賀の家へは、表向きの使者が立って、直正の哀悼の旨が伝えられた。心の籠った供え物もあった。遺族の者たちは、殿のお気持の忝なさに感泣した。
この小編も、また「想古録」に拠った。明治二十六年四月十九日の新聞に載すところを、書き直したのである。その記事を基に、多少の敷衍はしたが、それも許されるであろう範囲において、kいわめて少量にしたのに過ぎないことを断って置きたい。一応『鍋島正直公伝』にも当って見べきであったが、拙事にかからずらっていて、そのことが出来ないでしまった。 直正は、後の閑叟である。幕末から明治へかけての名君として知られている。この閑叟のこと、それから穀堂のことなど、「想古録」にはまだまだ記事があるのであるが、右の一話だけで、余事にはわたらずに置くことにした。その余の材料は、なお他日整理した上で、おいおい紹介して行くことにしたい。 ※参考:小島直記著『回り道を選んだ男たち』P.266「いい話」の中に「森銑三著『史伝閑歩』には「鍋島閑叟と古賀穀堂」もその一つである」と上の記事のあらすじを一頁にまとめて引用している。 2023.07.10 記す。 |
|
海舟・鉄舟・泥舟 森銑三著『史伝閑歩』(中央公論社)P.60~65 俗に三すくみという。智略の縦横をもって任ずる勝海舟も、山岡鉄舟の勇猛心というか、その内に蔵する力には、まいらざるを得なかったらしい。 勝家の台所へは、旧幕臣の不平党が絶えずやってきて、出された酒を飲んで管を捲く。おれたちをだしにして、自分だけが高官になって、大きな顔をしていやがる。なんでもかまわぬから、飲み倒してやれ、というのが、彼等のやけぱっちな気持だった。海舟はその者たちの飲んで放言するのにまかせていたらしいが、時に騒ぎ立てて、手に負えそうもない時は、書生を鉄舟のもとへやって、来てもらいたい、と頼む。よし、とばかり鉄舟が来て、台所へ顔を出して、皆さん、お揃いですか、という。今まで騒いでいた者たちは、ただその何でもない一言に萎縮して、手持ち無沙汰になってしまい、おい、帰ろうと、促し合って、ごそごそ出て行くのだったという。自分で顔を出して、かれこれいったりしないで、わざわざ鉄舟に来て貰う。海舟は、そういう手段を知っていたのである。やはり海舟は智者だったといえるかもしれない。 鉄舟は、明治以後は剣豪をもって知られ、その剣は向こうところがなかった。しかし鉄舟の剣も、はじめは天賦の膂力を恃んで、技は二の次に置いた傾きがあり、ただ敵を倒せばよいのではないかというのが、その考えだった。泥舟は力量よりも、技を重んじて、その技をどこまでも精錬せしめようとした。それで二人の議論する時は、根本的に一致しないものがあったのであるが、後に鉄舟が一刀流の奥義を悟った時、己の考え方の誤っていたことに気がついて、泥舟のもとに到って、これまでは誤解して居りました、と素直にいって、頭を下げた。その態度がどこまでも坦率だった。その時、泥舟はにっこり笑って、それはおめでたい、しかし大分御手間が取れましたな、といったそうである。剣の鉄舟も、槍の泥舟に対しては、一目置かざるをえなかったのである。
参考:鉄舟と泥舟の関係:高橋 泥舟(たかはし でいしゅう、天保6年2月17日(1835年3月15日) - 明治36年(1903年)2月13日)は、日本の武士・幕臣。 江戸において、旗本・山岡正業の次男として生まれる。幼名を謙三郎。後に精一郎。通称:精一。諱は政晃。号を忍歳といい、泥舟は後年の号である。母方を継いで高橋包承の養子となる。 生家の山岡家は槍の自得院流(忍心流)の名家で、精妙を謳われた長兄・山岡静山に就いて槍を修行、海内無双、神業に達したとの評を得るまでになる。 生家の男子がみな他家へ出た後で静山が27歳で早世、山岡家に残る英子の婿養子に迎えた門人の小野鉄太郎が後の山岡鉄舟で、泥舟の義弟にあたる。
鉄舟は終生剣をもって立っていたのであるが、明治以後の泥舟は、天下一品を以って称せられた鎗をも忘れるが如く、 狸にはあらぬわが身は土の舟こぎ出さぬのがかちかちの山 とよんで、官途に就こうともせず世を忘れ、世からも忘れられて、その一生を終えた。社会人として生きた鉄舟は、泥舟のその生き方に、敬意を払わずにはいられなかったらしい。 泥舟には泥舟としての、そうした高風があったのであるが、その泥舟は、また海舟の機略を認め、それをおよび難いものとしたというから面白い。 「海舟は鉄舟を畏れ、鉄舟は泥舟を畏れた」とは『徳川の三舟』の著者佐倉達山氏のいうところで、それをもって三すくみの形だったとするのであるが、佐倉氏は海舟と鉄舟とについて、さらに一話を伝えている。 明治何年であったか、朝廷から海舟と鉄舟とに、維新当時に国事に尽くしたことどもを書いて出せとの御沙汰があったのに、海舟は気安く書いて差し出した。それは相当に詳密なものであったらしい。その後で海舟は鉄舟に逢ったので、「あなたも差出しなさったか」と問うたら、鉄舟は無造作に、「自分で自分のことを書立てたりしては、自画自讃になってしまいます。そういうものは、拙者は出しません」といって、洒然としていた。その一言は、海舟にはよほどこたえたらしく、「おれは山岡にやられた。どてっ腹に洞穴を開けられた」と人に語ったそうである。 佐倉氏はなお、鉄舟と次郎長との一話をも伝えている。 明治初年のことであったが、たまたま訪うた次郎長に、鉄舟は一振りの短刀を与えて、「これは名刀なのだが、お前にやろう。けれども一大事だと思った時でなくては、抜くのではないぞ。それだけを心掛けるようにせい」と戒めた。 次郎長は、ありがたくいただいて、帰途に就いたが、箱根の山中で、雲助から酒手をゆすられた。次郎長は、黙ったまま応じない。雲助は次郎長を、ただの男と見くびって、「酒手を惜しむなら、駕籠から出てうせろ。おれたちを何だと思っていやァがる」と悪口雑言する。 次郎長も思わずかっとなって、刀の柄に手を掛けたが、その時、頭に閃いたのは、山岡先生の一言だった。かような奴等を斬って棄てたところで、それは刀を汚すものだ、と気が付いて、「よしよし酒手は、いいなりにくれてやろう。駕籠を急がせろ」と命じた。 すでに三島へ着いたら、そこにはもう知らせを受けた子分たちが、何十人も迎えに出ていた。駕籠から出る次郎長に、お帰りなさいませ、と頭を下げる。 その様を見て、雲助はびっくりした。さては清水の次郎長親分だったのかと気がついて、にわかに身を縮めて、いうところを知らなかった。次郎長は、その様子を流し目に見て、懐から金を出して、「これが酒手だ、取って置け」という。雲助は尻込みして、手を出すことを得せず、後に、願って次郎長の子分に加えて貰ったという。鉄舟の一言を肝に銘じて、一時の怒りに軽挙妄動しなかった次郎長は、さすがに好漢というべきであった。 この話は私は『徳川の三舟』に拠って始めて知ったのであるが、これを読んで、以前何かで読んでいた一事を思い出した。ある時、次郎長は、鉄舟に向って、「先生からいただく手紙は、文句がむつかしくて、読んでもよくわかりませんや。これからは手紙を下さる時は、どうか仮名で願います」といった。そうかと鉄舟は承知した。それで以後次郎長に与える手紙は、全部を仮名で書いたというのであった。その後の展覧会だったか、鉄舟の次郎長にあてた仮名の短簡を見たことがあるが、それが実に要領のいい口語文で、気持のいいものだったことを覚えている。清水方面に、その仮な文の手紙を所蔵する人があるならば、それは天下の珍品として、どうか大切にして貰いたいものと思う。 『徳川の三舟』には、なお鉄舟と耶蘇教の宣教師との奇話が出ている。これも他書でも見たことがある話であるが、序にここに載せることとしよう。 一日、宣教師の一人が鉄舟を訪うて、キリスト教のありがたさを説いた。鉄舟は黙って聴いているばかりで、一語も発しない。宣教師はなおも得意になって弁じ立てたが、鉄舟はついに何ともいわぬ。宣教師もついに張り合い抜けがして、話を打ち切って、意見を問うたら、鉄舟はいきなり、あははは、と大笑いをした。ただそれだけで、また口を閉じて、何もいおうとしない。宣教師もついに手持ち無沙汰な状態で、立去らねばならなかった。
しかしそれだけでは、すっかり愚弄せられたことになるので、腹の虫が承知しない。それで今度は、同僚の数輩をも語らって、改めて鉄舟を訪うて、こもごも道を説くことが、この前以上だった。
宣教師等はいった。「さような人のあるわけがありません。あなたは、それがあるとおっしゃるのですか」 鉄舟はいった。「あります。耶蘇以上にえらいものがござる。それはこの山岡鉄舟でござる」 鉄舟の声は、雷の落つるがごとくであった。宣教師等は、度胆を抜かれて、さらにいうところを知らず、ほうほうのていで出で去った。
『徳川の三舟』の著者佐倉氏は、鉄舟の門下であった。だから同書の内でも、鉄舟の逸聞を語っている条々に、もっとも精彩がある。 この書は、昭和十年の刊行であるが、世に流布するものは多くはないらしい。よって、かような書物の出来ていることを、海舟の研究を志す人々に知って置いて貰いたくて、この一文を草して見た。 やや海舟を抑えて、鉄舟を上げるような内容になったが、序に、少し前に明治の古い新聞に見えていた一事を記して、結びとしよう。 どこかの理髪床に、海舟と鉄舟との額を掲げている店があったそうで、その紹介がしてあったのであるが、鉄舟の方は道歌風の歌を一首書いているだけで、格別のことがない。海舟の方は、暁の空に鳥がニ、三羽飛んでゆくところを略筆で画いて、その上に、「朝寝すべからず」としてあったそうである。もしこれが床屋の亭主が請うて書いて貰ったものとすると、絵と文句とがいかにも適切で、応病与薬の妙を極めているし、その床屋へ行く客たちにも「朝寝すべからず」の教訓は、そのままにうなずかれるものがあったであろう。床屋には床屋向きのものを揮毫して与える。海舟は頭の自由自在にはたらく人だったことを感ずる。 某日記す。 |
|
土井聱牙逸事 P.70~74 大正六年に津市で版にした『聱牙(ごうが)先生三十七回忌辰追薦録』という、和装の小冊子がある。その量はいうに足りないが、それに附載せられている茅原清の「先師聱牙先生逸話」が大変いいもので、土井聱牙その人が、紙上に躍り出ている感じがする。今その中の若干条を紹介して見よう。
ある者が、妻を娶ったが、器量が悪いからといって、離別しようとしていた。 聱牙はそれを本人から聞いたが、何ともいわなかった。立って行って勝手から、小盃を二つ手にして来て、それをその者の前に並べて置いた。見るとその二つの内の一つは、素焼の粗末な盃で、今一つの方は、どこ焼なのか、美しい色をした物だった。その二つの盃に、聱牙は二つの酒徳利から酒をついで、「飲んで御覧」といった。その者は、いわれた通りにした。二つとも飲んでしまった時に、聱牙がいった。「どうだい、味は」 その者は、粗末な盃の方を指して、「こちらの酒は、いい酒でございました」といい、今度は美しい盃を手にして、「こちらの酒は、よくはございませんでした」とあからさまにいった。 それを聞いた聱牙は、笑っていった。「そうだろう。それなら見かけのよしあしなどは、どうでもよいことがわかったかい。見た目がよくても、酒そのものが悪くててはおしまいだ。見た目は悪い盃でも、中の酒がよければ、それでよいではないか。人は見目よりも心だよ。――わかったか」 その者は、両手をついて、その通りでございました、といって謝した。そして妻を去ることは思い止まって、醜い妻と一生むつまじく暮らしたとのことである。 聱牙は、人を喩すのにも、かようなうまい喩し方をすることの出来る人だった。
聱牙は、世間からは、ただ粗放な磊落な人物として見られていた。それも事実だったに違いないが、実はそれは、聱牙の一面というに過ぎなかった。 ある時門人の一人が、「先生、何々の事実は、何の本に出ているのですか」と問うた。聱牙は、「それは何の本だよ」と何でもなく答えたが、「それじゃ貴公に一つ、拙者の腕前を示そうか」といって、持ち合わせた手拭で目隠しをした。そして座右の本箱から、手さぐりで、一冊の書を取り出し、それをまた目隠ししたままで、ぱらぱらと繰っていって、この辺だろう、といって差し出した。見ると、門人の求める記事は、ちゃんとそこに載っていた。 聱牙は、平素用の済んだ書物をしまう時には、その順序を揃えて、本箱に収めた。だから入用の時には、暗闇でもその書を取り出すことが出来た。「学者の書物というものは、軍隊と同じことだ。いざという時に、自由に出されなくては、役に立たぬ。公等もそれが出来るようにして置き給え」といった。
※参考:出船の精神 長い航海をして、母港に帰れば、船乗りは一刻も早く上陸したいものである。そこで針路そのままで入港して、繋留すれば、作業も簡単で時間も少なくて済むので上陸も早くなり、乗員が喜ぶのはわかりきっている。だから船長もそのようにしたいのだが、決してそうはしない。入ったままの状態ー入舟というーにしておくと、次の出港のとき苦労する。また、なんどきに、緊急避難の事態が発生しないとも限らないから備えておかなければならぬ。 そこで、乗員がいかに疲れて、面倒くさくても、また早く上陸したくても、船を反転、後進させて繋留する。この状態を「出船」という。狭い港の海面で、前進、後進を繰り返して船首を回すのであるから、なかなか難しく時間もかかる。波風があればなおさらである。しかし敢えてこれをするのが出船の精神である。
聱牙は、書生が退屈せぬようにと、折々は『聊斎志異』の講釈をして聴かせた。そんな時には、机の上にある筆や墨や、その他を取上げて、「よいか、これがその男で、これが家だとしよう」などと、人物に擬した物を動かして、目に見えるように噛み砕いて話した。書生たちは、その話に耳を傾けた。 聱牙は、何の講義をするのにも、「筆記などしてはならぬ」と申渡して置くのだった。「書生は、紙に書きつけるのではなくて、心に記すのが肝心だ。筆記にたよったりしては、機に臨み、変に応じて、その知恵を繰出すことが出来ぬ」といった。
聱牙はいった。「史書を読むのには、読んでよくわかるところを、繰り返し読むがよい。そうする内に、わからなかったところが、自然にわかるようになる」――森曰く、原文に史書とあるから、そのままにして置いたが、これは何も史書には限らない。経書子集(中国の古典的書籍の4部の分類。経部(経書)・史部(史書)・子部(諸子)・集部(詩文などの文学書)):黒崎記)でも同じことであり、漢書のみならず、国書にしても、同様のことがいえるだろう。 聱牙は、黙読を否なりとした。「黙読をしていると、人の話しているのが耳にはいって来たりして、精神が乱される。鬼を拉(ひし)ぐような声を出して読むがいい」といった。――森曰く、これも、四書、漢籍の区別なく文章のよいものなどは、殊に音読する。そうしてその暗誦の出来るまでにもなっていたら、文を書く上にも、大いに益になるものがあろう。このことは私は、内田遠湖先生からも教えられている。 聱牙は多読主義者だった。「たくさん読まなくッちゃ駄目だよ」といった。それで、「唐本なら日に三寸、仮名交りの本だったら、五寸読め」といった。――森曰く、今の学校では、一年かかつても、右の三寸といい五寸という量の何分の一くらいしか進まないだろう。それくらいの本を読んだところで、何の足し前になるものではない。
聱牙の学識を知る者が、「先生はなぜ書物を著して、後世に伝えようとなさらぬのですか」と問うたら、答えていった。「拙という者の者のいおうと思うところは、孔子や孟子が、とうに述べている。わざざわざ拙者のいわねばならぬことはない」
聱牙の文章を、拝見願いたい、という者のあった時に、聱牙はいった。「拙者は韓退之を学ぶ者だ。拙者の文章が見たかったら、『韓文』を読めばよい」
聱牙は、自分の文章を人にみせびらかそうとはしなかったのであるが、門人たちの文章は、念を入れて修正し、その上にその門人を呼んで、机の前に坐らせて、その説明をして聴かせた。
聱牙は常にいった。「天下にすたり者などはありはせぬ」と。それで父兄の持てあましている若者があると聞くと、自分の方から申出て、その者を引取って教えて、どうにか世渡りの出来るところまで仕込んだ。それでそうして世に出た者が、数十人にも及んだことだった。
聱牙はいった。「学問をするのは、楽しいことの筈だ。それを苦しいというのは、字句に金しばりせられているからだろう」
以上に記するところは、全体の十分の一程度に過ぎないことを断って置こう。かような調子で書いた、うぶな人物資料を知りたいとことを、常々願っているのであるが、なかなかよいものにぶつからない。それだけに私は、芦原氏の記述を珍重したく思うのである。 2023.07.12 記す。 |
|
明治の人物一千人 P.104~116 明治三十六年の十一月三日、すなわち当時の天長の佳節に、『読売新聞』では創刊三十年を記念し、六十頁という膨大な新聞を発行して、自ら祝賀の意を表したが、その六十頁の大半を割いて、明治の人物一千人の一口評という特別記事を掲載しているのが、今日から見ても、思い切った趣向を成している。何しろ千人の評を一日で出すのであるから、文はあくまでも簡潔を旨として、一行で片づけられている人もまた多く、長いのも、七、八行を出ない。もちろん社内で手分けして書いたのであろうから、出来栄えに多少のムラのあるのは致し方のないことで、その千篇の全部を感心するわけにいかないが、とにかく短刀直入に、その人の核心に触れようとしているのが快く、そのいうところが、少しの媚態をも伴わぬ。そこに当時の新聞記者の心意気の知られるものもあって、時にその評がそのままには受入れかねるにせよ、執筆の態度のよいのに敬意が表せらる。そして当時の読売新聞社には、腕こきの記者が揃っていたことにも感心させられる。 選ばれた一千人は、一方的に偏せずに、上下の各階級に及んで居り、その顔ぶれを見ただけでも、明治のわが国がいかに人物に富んでいたかの一事が知られて、その点にも特別の感銘を受ける。 今その一千人の短評の中から、私の読んで特に興味を感じた条々を、掲載順に摘出して行って見る。それに就いて私自身の感想めいたものをつけ加えたのは、余計なことをしているといわれるかも知れないが、そう思われる人達は、私の付記などは飛ばして、本文だけを読まれて差支えぬ。 川上操六。「時艱思偉人、嗚呼君をして今日に在らしめば……」 千人評の第一に川上将軍が挙げられている。日露の風雲の急を告げている時、上の評は全国民の等しく抱く感慨であった。 木戸孝允。漢文であるのを書下して掲げる。「其の度量南洲に及ばず。其の勇断甲東に及ばず。卓識通方に至りては、則ち遥かに両者を凌ぐ」 文明政治家として、甲東よりも、南洲よりも上にあった孝允は、南洲と同年に、南洲に先んじて病没した。 山岡鉄舟。「剣、書、禅」 鉄舟その人を、ただの三字で評し去っているのが手際である。千人評の中では、これが最も短い。 中村正直。「福沢ほど広くはなかったが、それだけ深い所はありしなるべし。同人社の先生として、『西国立志編』の訳者として、明治の精神的文明は、彼に負ふこと尠しとせざるなり」 「天は自ら助くる者を助く」の『西国立志編』冒頭の一語が、明治前半期の人々に、どれほど大きな刺激を与えたか。 高橋泥舟。「槍術に於て八万騎中の第一の名人、昔の伊勢守」 明治以後のその人は、鳴かず飛ばず、それでいて世人はその人の存在を認識していた。 柳家小さん。「生意気に風邪なんか引きやして、ちょっとばかり咽喉を痛めてをりますが、今晩は小言幸平衛……ハクション」 小さんの落語は、しいて聴衆を笑わせるようなことをしないでおかしくて、いうにいわれぬ味があった。ああした自然の芸の持主に、今誰があるだろう。 鷲津穀堂。「文章も詩も一寸やれた」 穀堂先生も、「ちょっとやれた」で片づけられている。 橋本綱常。「橋本景岳は天下の病を医せんと欲し、二十七歳にして西郷隆盛と並び称せられ、綱常は其弟として纔かに人の病を医するを以て、聖代の恩沢に浴せり」 景岳を掲げるために、綱常の抑えられたのは気の毒であるが、上の評言は、即ち綱常その人もそのままに受取るところであったろう。 竹本大隅太夫。「義太夫を唄ふ者は多し。真に義太夫を語るものは一人大隅か。声低うしして能く聞こえざる処に千斛の妙味あり」 義太夫節はもう滅びたといってよいだろうか。今は二十歳前後の流行歌手が、全国の人気を背負うている。 吉田玉造。人形遣いである。「斯界屈指の名人なり。其顔の円く玉に似たるを以て玉造と名づく」 千人評は政治界や学界の人物ばかりを偏重したりなどしていない。 鱸松塘(すずきしょうとう)。「星巌門下の秀才にして師より受くる所をを守りて失わざるは唯此人あり。但変通の才なし」 変通の才のなかったところに、松塘その人があったといおうか。世には変通の才のあることをもって、われは顔をする連中が多すぎる。 仮名垣魯文。「さるほどに魯文の翁も吾が読売新聞の人物一千人に数へらるることこそ幸多けれ」 まあ入れておこうかくらいにあしらわれている。しかしこの人はこの人で、世の中を賑かにしてくれたことを、認めてもよいだろう。 福岡孝弟。「一気呵成に反故の裏に起草したる五箇条の御誓文が、一字一句を修正せずして、各参議の賞賛を博し、遂に御嘉納となりたるは、氏gは一世一代の功名譚!」 五箇条の御誓文を拝誦する時、私等は今でも明治の大御代が、一つの大きな理想の下に開かれたことを痛感する。 佐藤進。「李鴻章の負傷を療治して、支那の勲章を貰ふ」 支那の勲章を貰ったと、軽く片づけられているが、かえってほほえましい。 尾上多見蔵。「大阪の老優、石川五右衛門などうまし」 多見蔵の芸など、古風の一語に尽きるのではないかと思われるが、その五右衛門に、どんなに古風なよさがあったか、一度見て置きたかった。 梅ケ谷藤太郎。「其の力は即ち常陸山に若かず、其の体格もまた之れに及ばずと雖も、然も之と競ひ立つて覇を争ふものは、彼れが緻密なる性格の然からしむる処。力士は単に力と体とを以て世に立ち得るものにあらざるを見る」 千人評の筆者は一々判定すべくもないが、この一項は上司小剣と見て、恐らく誤らないであろう。 月岡芳年。「浮世絵の衰へたる際に出で、艱難して芳年風を起し、幾多の秀才を門下より出せり」 芳年の絵は、骨ッぽくていただきかねるが、秀才を養成した事実は、大いに認めなくてはなるまい。 黒川真頼。「掏摸に財布を奪はレ、従容呼び返して曰く、オイオイまだ紐が残ってうぃる」 これは昔からいろいろの人に結びついている逸事であるが、真頼博士にもそうした逸聞のあったことを,初めて教えられた。 小金井小次郎。「明治の初年三宅島に流され、居ること十二年、荒蕪を開きて万民に産業を授け、小次郎井戸の余慶流れて尽きず」 小金井小次郎などというと、ただ講釈師の張扇に叩出される博徒の親分かと思ったら、その人に上のような伝うべき事績があった。 高崎正風。「陳腐、平凡」 一言もないといおうか。もし明治天皇がこの条を御覧になったとしたら、呵々大笑遊ばされたことだろう。 山川健二郎。「泰西窮理の学を修むと雖も、其人は則ち古武士の典型」 私等は、明治・大正の代に、健二郎博士に依って、古武人を目のあたりに見た。 山県有朋。「人の悪い隠居なり。槍の名人」 伊藤は性格が明るいので得をした。山県の方は陰気臭いので損をしている。 尾上菊五郎。「技芸に於て人間が修養して達し得る限りに達したりといふべし。また芸道に忠実なること、世間其の比を見ず」 至言。団十郎に較べ少し芸人臭い嫌いはあるが、団十郎には出来ない役が、幾らでも出来た点でも、菊五郎は優に団十郎の向うを張る。 柴四郎。「佳人の奇遇著者」 この人は政治家としてではなく、政治小説家として記憶せられている。 森鴎外。「翻訳に於ては厳正にして誤謬なく、評論に於ては博引傍証、蓋(けだ)し大家なり」 「蓋し」の一語に多少の意味が含ませてある。 富岡百錬。「変な字をかき、変な画をかく」 いうまでもなく鉄斎である。この項は、望月玉泉の「奇麗な画をかく」の項の次に置かれている。しかし今となって見ると鉄斎一人が重んぜられ、誰も奇麗な絵を画いた玉泉のことなどは、口にしない。 大山巌。「維(こ)の石巌々、鬼乎人乎。誰か知らん内助、人あり、才あり色あり。幽蘭、頑石に伴う。艶千羨奈々々」 これも漢文なのを書下した。大山大将という書きにくい人物を、巧みに処置しているのを買いたい。 市川團蔵。 「空しく老いたり」の一語に、万斛の同情がある。 市川団十郎。「日本人にして世界人物辞書に列したるは、独り市川団十郎のみ。河原乞食中の絶品」 団十郎が家康に扮し、清正に扮する時、舞台には家康があり、清正があって、団十郎はいなかった。 西郷隆盛。氏名の下の括弧に、「英雄」としてある。「八千子弟秋風散。百ニ都城夜月寒」 一語褒貶に及ばず。しかも隆盛その人は、この二句の裡に、髣髴として浮び来る。 西郷従道。「馬鹿のやうで利口、シマリのないやうで、何処かシッカリした男」 兄隆盛についで従道侯が出ており、大分軽く取扱われいるが、今になって見ると、人物の大きかった点では、侯の方が一枚上だったとも思われる。隆盛はこだわるところがあった。侯にはそれがない。侯その人には天衣無縫の妙がある。侯は不思議な人物だった。 雲照律師。「五濁の世を厭ひて、生きながら木乃伊(ミイラ)にならんと心懸けて居る人、但し毎晩牛乳五合を飲む」 明治の世に在って、律師は平安朝の戒律に生きた。お釈迦様も牛乳を飲んでいる。律師が牛乳を飲んだって、異とするに足るまい。 荒木竹童。「日本一の尺八吹と聞えたり」 この一言、竹童も莞爾としてうあずいたであろう。ああ一芸の士。 田中正造。「外粗豪びして内極めて精緻、滔々数万言の演説立板に水を流し、冷嘲熱罵、口を衝いて出で、総べて是れ出放題出鱈目の観あれども、実にニ、三日前より苦心惨憺、議論を胸中に構成し、一言一辞苟(いやし)くもせざるの概あるは、世人の未だ知らざる所なり」 記者もこの人に対しては、真正面から物をいっている。 三宅雄次郎。「その文は即ち竪板に水、其の弁は即ち横板に飴」 しかも三宅は好んで演壇に立ち、訥弁の雄弁をもって称せられた。明治・大正・昭和を通じての言論界の巨人は、このひとであった。 江原素六。「麻布中学校長、温厚の君子人」 かねて代議士でもあったのに、政治的な野心など微塵もなくて、政友会の陣笠に安んじた。かねてまたクリスチャンでもあったが、その人は古武士の如くであった。何ということなしに慕わしい人だった。 常陸山谷右衛門。「絶大の怪豪、特に其の体格に於て前古無比と称す。その人物の剛愎にして併も機智に富み、意志の非常に強烈なるは人多く知らず」 テレビもラジオもない時代だったのに、力士常陸山の名は、役者の団十郎と共に、三尺の児童も知っていた。 松井源水。「源水独楽を廻すか、独楽源水を廻すか、源水独楽と同心一体の妙あり」 独楽廻しなどまでと軽蔑してはならぬ。その技は即ち神に入っていた。 乃木希典。「鉄砲玉の恐くない人、部下を愛する人、製錬潔癖の人、古名将の風ある人、日露開戦せば真先に引張り出したき人なり」 一語一語がそのままにうなずかれる。この時、将軍はまだ陸軍中将だった。 清浦奎吾。「月給四円の小学校教員より大臣に出世す。兎に角えらいやね」 清浦はこの時、農商務大臣だった。「えらいやね」と言われる所以。 清元お葉。「鶯の啼くや小さな口あけて(蕪村)」 千人評には、古人の俳句をもって評語に代えているのも幾つかあるが、その中ではこれなどが手際物だ。 大久保一翁。「只何となく捨てがたし」 旧幕臣で、東京府知事として令名があった。それで氏名の下に註して、「名望家」としてある。 大倉喜八郎。「御用商人の隊長」 その隊長が、後に華族様となった。 清水次郎長。「さァ来いと富士を背中にしよつて立つ男の仲の男一疋」 一誦溜飲の下る思いがする。 新門辰五郎。「徳川の流れ濁りて、三つ葵の葉枯れなんとすや、旗下八万騎の武士も多くは腰抜けの役立たず。剣客には近藤勇、侠客には新門の辰五郎たヾ二人、聊か人意を強うするに足るのみ。――鳴りひびく金竜山の鐘の声ハ百八町聞かぬ人なし」 この項も悪くはないが、次郎長のに較べて、長いだけに感銘が薄くなっている。 守田勘弥。「日本市川団十郎の技倆も、勘弥の指揮に頼るあらざれば、彼が如き盛名は得難かりしならん。其の智謀縦横、実に梨園の張子房なり」 惜しいことに、そうした人がついに不遇に終った。 伊藤博文。「誇才而愚、居貴尚鄙、老益好色、懦夫之魁」 日露の開戦の数か月前になる三十六年の十一月頃は、伊藤は恐露病患者として、ほとんど国民の全体から、はがゆがられていた。そうした時に成った伊藤公評として、上の四言四句の言は見ることを要する。 下田歌子。「海老茶式部の横綱!」 この評もまた、歌子その人を尽くさない。東亜の興隆を念頭とした歌子は、ただの女流教育家だったとすべきではない。 依田学海。「島田三郎をなぐらんとしたるは、ツイ此間の事なり。程もなく三郎刺客に襲はれる。 とにかく元気のいいおじさんだった。トルストイを間違えて、トルトースイが何だ、と気焔を挙げた。島田三郎くらいは、もとより眼中になかったであろう。 品川弥二郎。「風紀大臣、国民協会副会頭、念仏庵主、苦談楼主、尊攘堂建立者、而して人に与ふる手間、常にやじの二字を書す。松陰先生の子弟多しと雖も、その師承する所の幾分を服膺して忘れざるは、弥ニを除きて幾人かある。――念仏の声も止みけり時鳥」 精神家の一語、品川子に最も適切なるを覚ゆる。 徳富猪一郎。「或は其の佞姦狡獪を嘲る、然れども一種の才子たるは疑ふべからず。殊に冗漫拉雑なる文体を創(はじ)めて、一時青年子弟の渇仰する所となる」 徳富蘇峰ほど、その評価ンのぐらついた人も少いかも知れない。そしてその評価は、今後どういうところに落ちつくであろうかを知らないが、蘇峰の名声も、今では大分薄らいでいる。読売の記者は、蘇峰の文をもって「冗漫拉雑」と評している。蘇峰の崇拝家だった人達は、これをどう見るか。 頭山満。「豪傑乎、英雄乎、抑々亦た無能にして虚名を博する徒か。我之れを知らずといへども、其の壮士の親方たるは、衆目のひとしく認むる所」 氏名の下の註記には、「バンカラ」としてある。明治には浪人を以て目せられる人々がいた。頭山はその浪人組の大親分であった。頭山のためなら、いつでも命を投出そうという子分が、何百人もいた。薩長藩閥の巨頭達も、頭山の存在を無視することが出来なかった。 川上音二郎。「兎角の評はあるが、ドコかえらい所がある」 團菊の在世中に、新派劇というものを樹立した。川上ならではといwざざるを得ぬ。 徳川慶喜。「徳川末世の将軍にして、政権を奉還し、よく朝廷に恭順せしは人の知る所。乞ふ無評を以て評となさん。 「無評を以て評となさん」の一語の、最も痛切なるを覚ゆる。 柴五郎。註に「陸軍大佐」とある。「北京籠城の際、事実上列国聯合軍の総指揮官として防御計画の宜しきを得たるはh人の知る処、君の名は日本より欧米に高し。 柴五郎大将のことは、雑誌『歴史と人物』に拠って、認識が新たにせられた。千人評はこの人をもって終わっている。
特に数えて見ないが、ちょうど一千人になるらしい。しかも成った記事の原稿は、千を余ったらしく、それらを「奇人」だとか、「ハイカラ」だとかに分類して、本文の中に六号活字で小さく載せている。その「奇人」の中の「大槻如電」に、「奇人の偽物だと言ふ評判」とあるなど、また見るべきものといおうか。 以上抄出するところは、ただその一端に過ぎないが、その評語を受入れるにせよ、受入れまいとするにせよ、千人評が大いに読みごたえのする記事だった一事は、何人も認めざるを得ないであろう。 昭和の初め頃だったであろうか、ある漫画家が嘆息していることを、何かで読んだ記憶がある。それは、近頃は議会へ行っても、平凡な顔をした議員ばかりで、画き栄えのする人がいなくなってしまった、とうのであった。 もしもその漫画家を、明治の三十年代にでも生存せしめて、『読売新聞』で選んだ一千人の人人につぎつぎと会わせて、その人の漫画の肖像でも作って貰うことでもしたとしたら、その漫画家は、どんなに生き甲斐を感じたことであろうか。そんなことが考えられて来る。 『読売新聞』で選んだ一千人にも、まだ洩れた人がある。夏目漱石などもその一人で、漱石は上の一千評の後、ニ、三年して文壇に登場する。そうした人々をも加えたら、一千人を千五百人にも、二千人にも増すことも、さほど困難ではあるまい。とにかく明治は、人材の輩出した時代であった。しかもあらゆる方面に、異彩を放った人物が出ている。それらの人物を通じて、明治という時代を,改めて考察するということがなされてよいのではあるまいか。そんな気持から、あえてその千人評の紹介を試みた。明治という時代を、わざと詰まらない時代だったかのようにいい触らして、得々としている人達もいる世の中であるがそうしたことをいいたい人々は、何とでもいうがよかろう。明治時代に人材の輩出しているということは、巌然たる時日である。いかに控え目に物をいうにしても、明治は賑かな時代であったと思うのである。 附言。以上を書いてしまってから、上の千人評には、もと『読売新聞』にいて手腕を振った某氏などが、社外に在って手伝っているのではあるまいかと、ふッと思って見た。しかし確証も得ないで、軽率な物いいをするのは差控えよう。ただしそのことは今少し考えて見たいと思っている。 2023.07.15 記す。 |
|
明治四十二年十二月六日以後の『読売新聞』に、「忙人勿読」という、やや変った題名の随筆が連載せられている。署名はなくて、ただ▲〇△としてある。▲〇△とだけでは、何人が書いたのか、見当もつけかねるが、その第一回の書出しに、服部長七の名が出ているのを見るなり、私はおやと思った。この随筆は、ひょっとしたら中井錦城なのではあるまいか。 そう思って読んでいくと、服部のことが、第一回から第五回まで続いており、私の全然知らなかった逸事が、その中に記されている。そして中井錦城の著『無用の書』にも出ていて、それに拠って既に知っていた話も一、二、その中にある。「忙人勿読」は、やはり錦城なのではあるまいか。いっそうそう考えたくなって来る。 しかしその一事は、急速に解決しようとしなくてもいい。私は「忙人勿読」に拠って、服部の逸聞を知ることを得たのを喜びとする。服部は実は私の郷土三河国碧海郡の生んだ異色のある人物で、私はこkの人物に特別の親しみを持っている。 よってここに、「忙人勿読」を中心に、服部その人のことを、少しばかり書いて見たいと思う。 各府県における築港工事についtヴぇ知るところのある人なら、服部長七の名を記憶していよう。 服部は天成の築港技師であった。彼の前には、難工事がなかった。いかなる怒涛も狂瀾も、彼を如何ともする能わざること、あたかも虎豹豺狼が、猛獣使いにわけなあく馴らされてしまうのと同様だった。 服部はいった。「今日の技師の皆さんは、水と風と土砂との関係や、それらの一つ一つの性質についての研究が足りません。人間の小智慧でこしらえた数学や、力学や、工学や、そうしたもので、大自然の猛威に抵抗しようとうことからして間違いです」と。 その言葉の裡には、いうべからざる妙味がある。服部は大言壮語したけれども、その大言壮語は、つぎつぎに事実となって現れた。その佐渡の築港のごとき、ときの内務大臣品川弥二郎子爵をして、感歎措く能わざらしめたのである。 服部は、内務省の技師の作った難工事の設計書が、子爵の手許にあるのを見るなり、「これは駄目です」といい放った。 その無遠慮な一言に、子爵はむっとした。「駄目だとは何だ。貴様はじきに、人の仕事にケチをつけたがる。悪い癖だ」子爵はそう叱りつけた。 服部はそれを聞いても、ただ笑っているばかりだった。 「まあどうか実際を御覧下さい」静かにそういって引き退(さが)った。 佐渡の港は、技師の設計によって出来上った。けれども出来たかと思うと、風波のために壊されてしまった。これはいかんと、工事をし直したが、それもまた狸の土舟同様に、ぶくぶく物となってしまった。 品川子爵も、ついに我を折った。改めて服部を呼出して、「佐渡の築港の一件は、不面目の至じゃ」と、率直に自分の非を認め、「新しく設計をして貰いたい」と請うた。築港の経費は、最初の時が十万円かかった。二度目はそれを上廻っている。三度目の今度は、十五万円かかろうか。それとも二十万円かかろうか。いずれにせよ、経費は嵩むであろうが、それhあ止むを得ない。幾らかかろうとも、工事は遂行させなくてはならぬ。――子爵は、そう肚を極めていた。 子爵の腹中は見え透いている。しかしそれにつけ込んで、暴利をむさぼろうという服部ではなかった。 「それでは七万円引受けましょう」 あっさりとした出方に、子爵は一驚した。 「それは安過ぎはせぬか。お前の迷惑になりはすまいか」子爵は念を押した。 「大丈夫です。そんなにかかりはしません。――けれども二万円だけ、前金でお渡し願いましょう」 「前金か。――それは困ったな。会計法のこともある」 子爵が難色を示したら、服部はいった。 「人に物を恃むのに、法律や規則がありますか。お厭ならそれまでです。私はご免を蒙りましょう」 そういって出ていこうとする。服部と手を切っては、事が運ばない。子爵はあわてて、「まあ待ってくれ」と呼止て、「そう早まっては困る。何とか方法を考えよう」と、下手に出た。そこで服部は、前金の入用な理由を説明した。 「材料も前金でととのえますと、安く上がります。それから人夫頭も、現金で約束しておきますと、思うように使えて、都合よくいくというものです」 「そうか」と子爵はうなずいた。それでどう工面せられたか、要求通りに、二万円の金を拵えて渡された。服部はすぐに佐渡に赴いて、現場の検分に及んだ。その上に、土地の古老に何かと問いもして、十分の自信を得て工事にかかり、これまでの工事とは反対の方面の地点に防波堤を築き、ついに堅牢無比の港を築き上げた。 品川子爵は、服部の技𠈓と人物とに、信頼せざるを得なくなった。
しかし服部の奇功を奏したのは、築港工事の一事にとどまらなかった。 やはり品川子爵の内務大臣の時だったが、上野公園において開催せられる勧業博覧会に、大規模な噴水が建設されることとなった。工事の係長には、当時技師として名のあった某氏が当り、服部はその手伝いということになっていた。 けれどもその技師の設計には、大きな誤りがあるのだった。そのままに造ったりしたら、管が壊れてしまう。そうしたことが、服部にはちゃんとわかっていた。 それでそのことを技師に告げて、注意を求めたけれども、技師は高くとまっていて、職人風情に何がわかるかと、機嫌を損じたばかりで、そのいうところに耳を籍(か)そうともしない。 それに対して服部は、口論に及んだりなどはしなかった。すぐに人力車を深川の木場へ飛ばして、自腹を切って、長さ数十間の水管を造ることを命じて来た。 数日して、技師の設計通りh雲水の工事は終ったが、試験として水を送ったら、案のじょう水管が壊れて、水は中途から流れ出てしまう。天に沖する筈の噴水は噴き上らない。 博覧会の開期は、間近に迫っている。品川子爵は気が気でなかった。けれども技師先生は、自分の設計の欠点には気がつかぬ。またしても前通りの工事を進めようとして、職人たちを促し立てた。 そしていよいよ水管を敷設することになった時、服部は技師に向って、「期日がもう迫っています。今夜は徹夜で仕事して、水管を埋めることにしましょう」といった。技師は喜んで、「では、そうしてくれ」と、万事を服部に任せて帰宅した。 「さァ、この時だ」とばかりに、服部は技師の造らせた水管を取りのけ、近所まで運ばせておいた、別誂えの水管をそれに代えて、夜明けまでに、すべての工事を完了して、何食わぬ顔していた。 翌朝現場に来た技師が、通水の試験をしたら、水は威勢よく噴き上る。何も知らぬ技師は大得意だった。旨くいったとばかりに、鼻をうごkまかした。噴水の竣成したことに、品川子爵も満足した。 服部は、その後も沈黙を続けていた。それで噴水は、表面上は技師の力で成ったかのようになっていたのであるが、誰からともなく、事実はそうでなかったことが、子爵の耳に入った。子爵は半信半疑で、服部を呼出して問い訊すと、やはりその通りであった。噴水の水管には、服部の造らせたものの使ってあることが判明した。 「あの技師、怪しからん奴だ」と、子爵は息捲かれる。 そうしたら服部は、取りなしていった。「いや、技師というものは、大方あのくらいのところです。XXさん一人が駄目なのではありません」 子爵は、深くうなずかざるを得なかった――。
以上は「忙人勿読」に記するところであるが、なおそれには、服部の宇品築港のことも述べてある。しかしそれは、前に一言した錦城の『無用の書』にも記されているのであり、その方がずっと精しい。 よってここには『無用の書』に拠って恕することとする。 亡くなった服部長七ほど、海面工事に巧者な人はなかった。明治十年代のことであるが、時の広島県令千田貞暁は、宇品湾築港のことを思い立って、内務省にそのことを願い出た。それで同省の御傭のオランダ技師に設計せしめると、経費が四百万円かかるとのことだった。それはあまりにも巨額である。ために工事は行き悩みを来した。 そうしたら服部がそれを聞いて、「私に任せて下さい。十七万円で仕上げましょう」という。もしそれが出来るなら、そのような結構なことはない。けれども十七万円は四百万円に対して開きがあり過ぎる。千田県令は服部を呼んで、一週間の期限を与えて、工事の再調査を命じた。「承知しました」といって引き退った服部は、小舟を雇って湾内に浮かべて、毎日釣をして日を送った。 そのことを耳にした県令は、服部が出頭するなり、「貴様は不届な奴だ。釣ばかりしていたというではないか」と詰問した。 服部は平然たるもので、「釣は釣ですが、魚を釣るんじゃありません。草鞋を釣っておりました」という。 「何、草鞋を……」県令には、わけが分からない。 その時、服部は説明していった。 「あの湾内で釣をしますと、草鞋がかります。それから考えますと、流れは決して急ではありません。オランダの技師は、最初から急だと一人ぎめにきめているものだから、それでやたらに経費のかかることにしてしまったのです。どうか私に任せて下さい」 服部は自信をもっていう。かくして工事は服部が引受けた。 服部は自分で工夫して造って、服部人造石の名で呼ぶ石を、さらに新しく多量に造り、それを使って予定通りに工事を完成した。そうして宇品港が成ったところから、日清戦役、北清事変、日露戦役は勿論のこと、最近のシベリヤ出兵まで、軍隊の輸送が容易に出来て、陸軍はどれだけの便益を得たか知れなかった。功を以て千田県令は男爵に叙せられた。しかしそれなら服部の方にも、男爵くらい授けられてよいのではなかったか。 右の宇品港の一条は、主として『無用の書』によ拠ったのであるが、『無用の書』と「忙人勿読」と重複する話が今一つあって、その内容がまた奇抜である。 これまた「忙人勿読」の方に拠って記したい。 あるとき服部は、岡山県庁からの依頼で、知事たちと一緒に海岸を視察したところが、服部は堤防やら水門やらの一つ一つを丹念に見て廻っている。知事たちは手持無沙汰で、服部一人を残して、先に県庁へ帰ってしまった。 ニ、三時間後れて、服部も帰って来たが、知事の顔を見るなり、「今度の工事は、ご免を蒙りましょう」 藪から棒の申し出に、「どうしたのか」と問うと、「こちらには、私よりもえらい人がおります。堤防の工合といい、水門の塩梅といい、実によく出来たもので、並大抵の仕事ではありません。――それにしても、一体あれは何という人がしたのですか」と聞く。 知事も即答が出来なくて、旧記の類を調べたら、熊沢蕃山の造るところだったことがわかった。それでその由を服部に告げたら、服部は、「へえ、熊沢さんと申しますか。その熊沢さんにお目にかかりたいが、どちらにお住まいでしょうか」と聞いた。 知事は唖然として、いうところを知らなかった。 「忙人勿読」にはかようにあるが『無用の書』には、それは服部が旭川の落ち口の堤防を調べた時のことだったと、場所がはっきり挙げてある。そして服部は知事に向って、「そのバンザンというは、なかなか遣る男だ。一度会って見たいが、ちょっと紹介状を書いて下さらんか」といったのに、知事は一驚したとしてある。
「忙人勿読」には、服部が履歴書を書いて出すのを辞退した話が出ている。これは私の以前からの知るところの話で、やはり『無用の書』で見たとように思ったところが、それは記憶違いであった。この一事は、福本日南がその著『石臼のへそ』の中に書いているのだった。 やはり品川子爵の内務大臣当時に、服部は多年の功績が認められて、表彰されることになった。それで履歴書の提出を求められたのであるが、服部は履歴書が何か、いっこうに知らない。「これまでして来たことを書いて出すのだ」と聞かされて、「それはご免を蒙りましょう。私は土方同様のもので、若い時分に、人の女房と出来てしまったことなどございます。今さらそんなことまで申上げられません」という。 使に行った役人はあきれて、 「いや、そんなわたし事まで書かなくてもよいのだ。よいことだけを書けばよいのだ」そう聞かされて、服部はまたしても拒んだ。 「悪いことは棚に上げて、よいことばかり書くのですか。そんな虫のよいことは、わたくしには、なおのこと出来ません」と、とうとう書くのを断ってしまった。子爵はこれを聞いた、服部の人物に、今さらのように感歎せられたという。 右の一事は要約して叙したのであるが、日南は四回続きでこの服部のことを書き、その打止めにこの逸事を期して、「彼は今なhお老健で、依然か各地の土功に尽瘁しつゝあると聞く」とし、さらに、「斯くの如き真摯の人、当世に時めく上流社会に其れ果して幾何かありや。道聴途説は君子の取らざる所なれど、快感動いておのずから禁ぜず、聴くがままを書きつけ置く」として筆を止めている。 三河の人士の特質として、律義の一事が昔から挙げられるのであるが、右の逸事よりして、服部もまた律義の人物だったことが明確にせられるのであり、私もまた三河生れの人間として、明治に生きた服部に、最も三河人だったことの認めらるのに、大きな喜びと誇りとを感ずるのである。 日南の『石臼のへそ』は、大正三年に成ったのであるが、日南の書いているように、服部は当時なお健在だったのであり、それより五年を経て、大正六年七月十八日に没した。年を享くること八十歳だった。
「忙人勿読」に服部のことを読んだのを機縁に、それを中心として、この一文を草して見た。『無用の書』にも『石臼のへそ』にも、まだ紹介してもいい話があるし、その外にも服部のことを書いたものは、幾つかあるのであるが、それらには目をつぶっておくこととする。ただし大分前に、何の新聞だったかに、読者からの短い投書の載せられていた一事だけを、附記しておきた。 神戸港の改築のことのあった時だったと思うが、ある請負師の出した設計図の出来のよいのに、役人が感心して、「誰に相談して作ったか」と問うたら、その請負師は、「誰にも相談しません。海へ出かけていって、浪と相談して来ました」と答えたそうである。 その投書には、かようにあった。服部とも、長七ともしてはいないのであるが、「浪と相談して来た」という奇言を吐く者は、服部をおいて、外にありそうに思われぬ。この話は、服部のことと断じてよいのではあるまいか。 「忙人勿読」は錦城の草するところと見てよいかどうか、この一事は、なおしばらく疑問としておこう。 最後に締めくくりとして一語を添えるなら、服部は無学文盲な男で、仮名すらもろくろく書けなかった。それでいて彼は天才だった。 「おれの技術は、水の神と風の神のとからの直伝だ」と豪語した。学問を鼻にかける専門家などは、その眼中になかった。そしてその豪語に値する仕事を、服部はいたる所にしている。服部長七は奇男子だった。 2023.07.09 記す。 |
|
七七七五の四句二十六音から成る唄を、俗謡の名で呼ぶことにする。 その俗謡は、信長時代に起ったという説を読んだことがある。なるほどそうであろうかと思われる。 俗謡は庶民の間に生まれた唄である。庶民が勃興して、漸次社会的な存在となろうとしていた安土桃山時代に、この俗謡が生れ出でたという事実には、偶然ならぬものが感ぜられる。わが国の歌といえば、和歌が代表するわけであるが、その和歌は、時代を経るに従って固定化し、老化もして、生気を失ったものとなってしまっていた。ただ貴族たちだけの弄びものとなり、机上で作られて、目で読まれる⒨おのとkなってしまい、その上なまじいに歌学などというものが起って」、庶民には縁遠いものになってしまっていた。庶民たちの間に、自分たちは自分たちの、もっと溌溂とした謡が欲しいという要望が起ったというのは自然のkおとであり、そうした要求が具体化して、俗謡となったと見ることが出来よう。 俗謡には何の約束もない。自分たちの日常使っている言葉を、そのままに使って謳えばよい。だから俗謡のすべては、誰でも聴けばそのままにわかる。何の解釈が入るのでもない。そしてその謡は、それぞれの節で謡った。樵夫は山で、漁夫は海で、農夫は野良でそれを謡った。馬子も謡えば、駕籠舁も謡った。男だけで反くて、女も謡った。それが口から口へと伝えられて、全国に拡まり、各地で各様ンい節づけられて、郷土色の豊かなものともなった。酒筵の席でも謡われ、謡に舞踊が附けられて、盆踊りになどにも用いられて、そしてわが国の庶民の生活は、大いに豊かなものとなった。 俗謡の発生地はもとより明らかでないが、関東よりも関西の方が、先に流行を来たしたとだけはいえる。田園だけではなくて、都人士もこれを口にするようになり、西鶴の『一代男』や、それにつぐ浮世草子にも取り入れられ、ついでまた近松が、その浄瑠璃に多く取入れて、詞章を賑やかにした。お夏清十郎の事件に触れた。 向ひ通るは清十郎ぢやないか、笠がよう似た菅笠が の謡などは、『五人女』にも、使い、近松も使っている。この謡などは、誰知らぬ者もないほどになっていたらしい。 それだのに江戸では、八百屋お七の放火事件があったのに、それが俗謡にはならずにしまっているのが寂しい。江戸でできたことのはっきりしている謡といえば、 君と寝やろうか五千石取ろか、何の五千石君と寝よ などが浮かんで来るが、それは天明の藤枝外記の心中の一件を謡ったので、時代がだいぶ下る。 沖の暗いのに白帆が見える。あれは紀の国蜜柑舟 なども、江戸でできたのであろうが、また少し時代が下がるのではないかと思われる。かえって江戸では、 潮来(いたこ)出島の真菰の中で、あやめ咲くとはしほらしや などの潮来節を地方から輸入して謡い、それが大はやりにはやったりした。 しかし江戸で生まれて、地方へ行った謡もないではない。 花のお江戸の両国橋へ、坊さん簪買ひに来た など、両国界隈の賑わいを謡ったものだのに、それが土佐へ行って、 土佐の高知の播磨屋橋で と作り替えられ、ついにそれが、よさこい節を代表する謡になってしまった。今では東京でも、「土佐の高知の」と謡っている。 かように甲地の謡が乙地に取られながら、甲地ではぼんやりしている例が少なくない。 伊予へ伊予へと草木も靡く、伊予は居よいか住みよいか などはそれである。これは近松以前の古浄瑠璃に取入れられている謡で、「伊予は居よいか」の句でこの謡は生きるのに、今はこれを佐渡の謡にしてしまい、「佐渡へ佐渡へと」と謡って澄ましている。しかし「佐渡は居よいか」では、何の変哲もない。 箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ の馬子唄も、今では結びを「大井川」として、それでよいことにしているが、原唄は「大晦日」であった。「大晦日」でこの唄は面白くなるのに、「大晦日」と謳う人などはない。しかし明治の十年前後には、まだ「大晦日」だったらしい証拠が、幾つか挙げられる。 ついこの間、ラジオで、 会津磐梯山に振袖着せて、奈良の大仏婿に取ろ と謡っているのを聴いたが、磐梯山を花嫁に見立てるのは無理がある。これも原唄は、「関の地蔵に」で、それならとうなずかれる。 俗謡については、今少し書きたいことどもがあるが、それはまた別の機会に譲ろう。しかし今ひと言を書き添えるるならば、俗謡には作者がない。ありはしたろうが、作者の名は伝えられていない。この一事よりしても、俗謡は庶民の声として見ることができる。そして今日にも生命を有する俗謡には、ニ、三百年も謡いつづけられているものがあるのだから、謡の生命は相当に長い。それらの謡を聴く時、過去の人々の哀歓のその裡に籠っていることを感ずる。この俗謡というものは、われわれ日本民族の無形の文化財の一つとして、大切に守って行くべきものだと思う。そしてまたこの俗謡に拠って、わが民族の民族性というものを考察することなども、せられて然るべきであろうと思うのである。 2023.07.29 記す。 |
|
本郷の動坂町で戦災に罹って、無一物になった私は、家内と共に、板橋の石井鶴三さんの方へ転がり込み、それからずるずると厄介になることが、半年間に及んだ。鶴三さんは、家内の母方の叔父さんになるのである。 鶴三さんの家にいる間に、私は足に腫物をこしらえて、それがいつまでも治らぬにのにh閉口した。けれども気分には障らぬので、多少は奉仕的な意味を籠めて、二階のあちこちにつくねてある、鶴三さんの画稿を整理した。新聞の連載小説の画稿である。 鶴三さんは苟もしない人であった。それで4連載小説の下絵も、そのk一つ一つを、半紙に毛筆で画かれた。鉛筆で構図を作るようなことをせずに、ぶッつけに毛筆で画くのであるが、それを何回というこtヴぉもなしに画き直し画き直して、ただの一枚を完成するのに、夜を徹したりせられることすら珍しくはなかった。それは鶴三さんには、精魂を尽くしての仕事、全力を挙げての仕事なのであった。だから私から見ると、りっぱに完成した絵になっているものが、何枚でも出て来るので、それらを私は、感心して見ながら、別に新聞の切抜きの保存してあるのと、照らし合せて揃えて行った。時には外の小説の挿話が紛れ込んでいたりして、何の挿話なのか分からぬ場合は、二階から降りて行って、鶴三さんに訊す。と何の絵なのかが、すぐに解決した。 いっだったか、そうして分った絵の一つを、鶴三さんは、存外よく出来ているといって、見入っていると思ったら、傍らの筆を取って、画中の人物の手首に、小さな弧線を二筋、画き加えられた。それに拠って、その手首は,円味を帯びることになった。画き捨ての絵で、今後誰にみせようという当てもないのに、わざわざ輔弼する、私はちょっと驚いた。 吉川英治の『宮本武蔵』の挿絵は、鶴三さんの挿絵の内でも、ことに評判のよかったものであるが、作者が武蔵の人物を、はっきりと掴んでいないものだから、挿絵が画きにくくて困る、とこぼされた。それは別の人から聴いたのであるが、いかにも鶴三さんらしい言葉だと思う。鶴三さんが挿絵を画かれる場合など、作者が鶴三さんを引っ張って行くのではなくて、挿絵画家の鶴三さんの方で、反対に作者を引いて行く観があった。 直木三十五の『南国太平記』の挿絵も、評判のよかったものであるが、その中に示現流といったろうか、薩摩に伝わる剣法のことが出て来るのに、直木の書いている原稿では、その流儀の構えというのが、どのような形にするのかがわからない。直接直木に聞いて見ても、要領を得ない。鶴三さんは、その一事を知るために、鹿児島まで出かけて行って、専門家の構えの実際を見て来られた。 同じくその『南国太平記』についての挿話であるが、作中の人物が、牡丹の咲く頃に江戸を立って、西上するところがあった。ところが何回か後に、その人物が箱根を越すところには、箱根の山上には、秋風が吹いているというようなことを、直木は書いていた。鶴三さんはあきれて、わざわざ電話を掛けて、途中であまり日数を費していませんか、と注意した。直木も内心は、しまった、と思ったかもしれないが、それでも平然として、大衆文学というものは、由来そういうものだよ、覚えて置き給え、といったそうである。その後に単行本となった『南国太平記』は、そこが直してあるかどうか。 『南国太平記』の画稿を整理していて知ったのであるが、手傷を負うた一人の侍が、川端にかがんで、その傷を洗っているところを画いた一図があった。それなどは凄惨な気分が漲っている絵であったことを思う。 さらにそれより前の中里介山の『大菩薩峠』の挿絵も見事なもので、鶴三さんはそれに依って、挿絵画家中の第一人者を以て目せられるに至ったのであるが、鶴三さん自身は、あの挿絵には、『田舎源氏』の絵などの影響があります、といって、それほどには認められなかった。けれども私などには、かえって草双紙式の気分の出ているのに、親しみを感ぜられる。よし国貞「などの影響にあるにせよ、りっぱな鶴三さんの絵になっている。 鶴三さんの挿絵の現代物には、久保田万太郎の『春泥』がある。その中の二、三の人物が、雨の夜に料亭で話し続けるところがあるのに、鶴三さんは、そのところの一回に、もう雨戸を閉した料理店の戸外の様子を画いた。久保田氏もそれには感心したそうである。このことは、直接鶴三さんさんから聴いている。その『春泥』が、春陽堂から、菊判の単行本として出た時、鶴三さんはその装幀をして、外題も書いた。鶴三さんの字では、それなどがもっとも出来のよいものではあるまいかと思う。 なお単行本には、鶴三さんの口絵一葉があって、それがまた出来がいい。向島の堤に、新派俳優の二、三人が行くところで、それが木版の色摺になっているのである。あれは鶴三さんの版画としても、珍重すべきものと思う。ただしその『春泥』を、私は久しく手にしていない。 私が揃えて一括ずつにして置いた鶴三さんの画稿は、今でもその家に無事にあるのであろ。それらの下絵の一つ一つには鶴三さんの魂が宿っている。どうかそれらの画稿が、散らばったりしないで、どこか然るべきところに納まって、永久保存の途が講ぜられようにしたいものである。 芸術という仕事は、作家の魂を、対象とする作品に打ち込んで行くことであろうと、私は思っている。そんなことを鶴三さんに向っていったことなどはなかったが、私のこの言は、鶴三さんから、うなずいて貰われようと思う。 鶴三さんの仕事の範囲は広かったが、その画稿の一枚を見ても、私はそこに鶴三さんその人を感ずる。そして鶴三さんは、ほんとうの芸術家であったことを思う。鶴三さんはこの数年、自宅に閉じ籠って病を養い、その間誰にも逢うこtヴぉをしないで、そのまま静かに、あの世に去られた。鶴三さんらしい最後であったと思う。きのうの朝の新聞がその死を奉じており、そのニュースの後に、中川一政氏の追悼の談話が付け添えてあるのを見たら、私は私として、急に何か書いて見たくなった。それでこの一文を草したのであるが、鶴三さんから、静かな口調で、君は相変わらず、ぞんざいな文章をかきますね、といわれそうである。 ※参考:小島直記著『老いに挫けぬ男たち』「うらやまな眼――宮本武蔵④」に、石井鶴三についての記述fがある。 2023.07.10 記す。 |

録雨の次には,露伴を取上げる。露伴もまた、正岡子規、尾崎紅葉、斎藤緑雨の三人と同じく慶応三年の生まれで、その点でも次に引出すにふさわしい文人だからである。しかし露伴は戦後までも世にあって、子、紅、緑三人の二人分以上も生きていた。それだけにまた、その文筆活動の量も多く、質に於てもすぐれている。露伴は、文学者たると同時に、学問の人でもあり、正に一箇の巨人として世にあった。そして随筆家としても、同年の三人の内では書いているものが断然多く、明治以降の一大随筆家となっている。 随筆家としての露伴を書すのには、私は外のものはとにかくとして、『洗心録』の一書を見直したいなどと思ったら、幸いにしてK君から借りることを得た。然もその書は河村清雄のカバーも無事の美本で、旧知に巡り合ったような感を深うした。私には楽しくその書を再閲した。 『洗心録』は大正三年に成った露伴の文集で、四六判で、四百頁を越えて居り、六十篇近い文がそれに収められいるのであるが、附録の三篇を除いては、尽くが文語体のもので、既に円熟の境に入っているその文が、実にめでたい。殊にそのうちの「ひとり言」六十七則と「人の言」六十九4則とは、純然たる随筆で、他の篇々よりも量もある。露伴の随筆のめでたさは、この二篇をとおして、遺憾なく知ることが出来るのを喜びとしたい。 まずその「ひとり言」の数則を抄する。 「香木をたくに、其のまことの芳(かんば)しき気は、烟の未だ微少(いさゝか)も立ちのぼらぬ先に迸り出づるなり。人の心の匂もまた然り。其の人の一念我にむかひてまことに優しく美しき時は、其の人いまだ口を開きて言葉を出さず、身をもて行(おこなひ)をしめさずと雖も、はや其の優しさ美しさの溢れ迸りて、我が胸に浸み通る心地す。此の心の匂のいつもめでたき人をば徳のある人とは云ふなり」 仲のよい同士が、終日何ということもなしに一緒にいる。ただそうしているだけで楽しい。必ずしも言を交えるには及ばない。二人の間には、気持ちの交流するものがあるのである。 「要ありて、明日の朝、何の刻には必ず起き出でゝ、かくかくの事を為さんと深く思ひ入る時は、其の刻に至りて多くは目さむるものなり。睡りたる我をを其の刻に至りて呼び起こして覚めしむるは何ぞや。我ならば我は睡り居れるなり、丑の下刻(げこく)も寅の上刻も知るべきにはあらず。我ならずば我がほかに人は無きなり、右隣も左隣も来れるにはあらず。そもそも睡れる我の如何にして睡れる我を覚ますぞや。又抑々睡れる我の、眼を開かず、燭をも秉(と)らず、時計をも探らずして、如何にして今の何の刻に当るといふ事を知りて、睡れる我をさますぞや。我(が)の中の無我か、無我の中の我か。此の睡れる我(われ)を起しさます我を主と仰ぎて身を終らんか、一度(たび)は覚まされながら、睡むたし睡むたしなどとて復(また)寝入らんとする我がために奴(やつこ)とされて世を終らんか。人の一生の追分(おいわけ)はこゝにありといふべし」 私の母などは農家の阿弥陀様の信者であったから、仏様が起して下さるのだととして疑わなかった。私等の身辺にも、神仏へでも持って行かなくては解決しない問題が、幾らでもあるのである。 「秋にしては過ぎし春を思ひ、老いては若かりし昔をしのぶならひなり。鬢の霜を鏡の中の寒き影に認め、藜(あかざ)の杖雨の後の滑らかなる路に頼むに至つて、人誰かは彼の時かうも為すべかりしを、其の折はさうも言ふべかりしをと思はざるもの無からん。されど其もまた果敢無(はかな)く甲斐無し。温飛卿の誌の句、事は雲に随つて去んぬ身は到り難し、夢は煙を逐うて鎖(さ)えつ水おのづから流る、といへるあり、所謂実参体得の佳き句なるべし。何といふ事は無けれど人を動かすなり」 「ひとり言」から、纔かに三条を紹介したに過ぎないけれども「人の言」に移ることとする。その中からやや長い一章をまず挙げる。 私などは目前の雑事に逐われて時を過ごしている者であるけれども、時にはかような随筆を読んで、古人の詩境の妙に思いを馳せたりするだけの心の余裕を持っているだけでも、仕合せだとしてもよいであろう。 「或男生活(みすぎ)の聊か苦しからぬやうになりしより、古き陶器(やきもの)を集むることを楽(たのしみ)となし、かゝる事に数十年の功を積める老いたる数寄者を師に頼みて、共に古き道具など売る店々をあさりし末、或所にて青磁の花瓶の佳品(よきもの)を見出しければ、数寄者は値も高からねば買ひ玉へと奨勧む。男も佳品(よきしな)とは思ひけれども大なる疵付きてありければ、あわれ疵無きばと云ひて、終に買はず。数寄者はこれを見て冷笑(あざわら)ひながら、おのれ自ら買ひ取りつ。さて帰るさの途ににて男に対ひ、卿(おんみ)は心に味ひ無き人なり、我が如きものの友ならず。疵無き花瓶を求めんとならば、新しき物売る店にて購はんに、いくらも之を得べし。かく南北かけらを彷徨(さまよひ)ひあるさて要も無きものの古びたるに、手を触れ眼を注ぐは、面白き趣きのあるものを得んとすればなり。されば物の形、釉(くすり)の色だに面白くば、疵の一ツ一ツありたりとて何の厭ふべき事かあらん。喜びてこれを購ふべきなり。卿(おんみ)知らずや、蜷川式胤(のりたね)は陶器(やきもの)の欠片(かけら)のみを一ト藏も有ち居しなり。数寄者の優しき心よりは欠片(かけら)をだも猶棄つるに忍びず、まして少しばかりの疵あるものをや。物の疵を厭ふほどの趣き無き人の友となりて歳月(としつき)を経んおも興無し。共に道具屋あさるもこれまでなり、といひて判れんとしければ、男はひたすらに己が心の浅かりしを詫びて、それより古(いにしへ)の明主良将といはるゝほどの人は皆疵物の疵を厭はず召抱へて、功を立て名を成せしものなることを悟り、疵物を厭はず買ひ集めしほどに、やがてあらゆる陶器を蒐め得しとぞ」 露伴としては、これなどはただ無雑作に書流した一章というに過ぎまいが、内容的に見て、好教訓といわなくてはなるまい。陶器のことは解らないが、それを多く、書物の上に持って来ていうならば、新本の真新しいものばかりを買集めて、虫食い本や、欠本、端本にもまれたそれぞれのよき面白さの存することを知らぬようでは、真の書物好きということを得ないであろう。古刊本ともなれば、その零葉(れいよう:黒崎記)もまた尊く、それが研究の資料ともなる。それらはそれらとして、貴重な存在をなしていることを知らねばならぬ。 「ある年老い徳すぐれたる僧に若き女の、如何様に心を持ち身を行はば、夫には良き妻となり、舅(しゅうと)姑(しゅうとめ)には好き嫁となり、後の世には仏となり得るにや教へさせたまへ、と尋ぬければ、僧打ち笑ひて、まことに殊勝の御尋なれば、秘中の秘にはあれど包まず御教へ申すべし、と云ひて、扨女の面を睨みつけ声を励(はげ)しくして、其の問をよく忘れずに日に三度づゝ自分で問はつしやい、と女が三日四日は耳に聾(しひ)るほど、雷(らい)の如くに呵(しか)りけるとぞ」 われわれの日常は、ただ平凡なことどもを実行し続けることにある。それ以外に特別の生き方があるのではない。非凡は平凡の裡にある。 「車夫の妻は車輪の声を聞きたるのみにて、我が夫の帰り来たるか或は然(さ)らぬかを判(わか)ち知り、漁夫の妻は人顔未だ定かならぬに帰帆の影を見て、吾が夫の漁獲(えもの)の多寡を推(すゐ)し知る。これを思へば日ごろの心用ゐだに切ならば、人の力にては能(よく)し敵きほどの事も必ず能く成し出さるべき筈なり、と世に馴れたる人の申しける」 人のこの世に生くる、学ぶべきものは、遠きに求めずとも、手近なところにもあるのである。人からのみではない、飼育する犬や猫から教えられることだってある。心を専らにして、私等は何物からでも、学ぶべきことは学ぼうとするの心懸けがありたい。 『洗心録』所収の文は何れも短い。だからこの書は、その全体が、随筆の書と見ても差支のないものを成している。「作文の境」はすべて六則から成っているが、その六則の一つ一つが、好(よ)き教えならぬはない。ここにその第一則を出して置こう。 「おのれの文を読みて、真に其の拙陋厭ふ可く悲しむべきを感ずるものは幸なり。蓋し自ら省みて真にその拙陋厭ふべく悲むべきを感ずるの時は、其の人の文を作るの手は未だ進まずといふといへども、其の人の文を看るの眼は既に進めるあるを以てなり。眼進めば、手もまた漸く進むべし。日に自ら視て足らずとするものは、其の文は日に漸く進まむ」
なおこの『洗心録』より先に成った露伴の随筆に、『潮待ち草』の一書があり、これは単行本にもなっている。その中の「たけくらべ」の一章など、到れり尽せりともいうべき、行届いたものであるが、ここにそのことを一言するに止める。 なおそれより更に早いものに、「靄護精舎雑筆:あいごしょうじゃぜっぴつ:(折々草)」というものがあり、これは小説『ひげ男』の附録として行われている。その中の「徂徠」の一章は、本稿に紹介した陶器蒐集家のことを書いた一章と、その内容が関聯するのであるから、最後にその全文を載せて結びとしよう。 「徂徠は儒中の漢高楚項なり、其人材を論ずるや唯一言のみ、而して其一言の気象浩大、作用活潑、人をして達者にあらざれば決して説破する能はざるを思はしむ。其言如何。曰く、人才は疵物(きずもの)にあり」 2023.09.11 記す。 |
|
漱石の次には、吉村冬彦博士の随筆ということになるのだろうと、そのことを当てにしていた人も、あったかも知れない。その冬彦博士を取上げる。博士は物理学の方が本職で、その方ですぐれた業績を挙げていられる上に、その上に立派な後進を、数多く養成してもいられる。そうした科学者にして、なお且つ文学者としても一家を成し、俳諧の神髄を解し、自ら俳人としての仕事をしてもいられる。 その上に文章家でもあって、ホトトギス派のk小品文作家を振出しに、大正の文壇に新しい随筆の世界を開いて、ユニークなs地位を確保せられている。多くの随筆を書いて、前にも後にも並ぶ人もない作家とえいてもたたえられているのである。博士の随筆は、科学者としての冷静な眼の輝くものがあるのと同時に、文学者としての温かい心の行渡っているものがあって、他の企及することの出来ない、渾然たる作品を成している。その師の漱石も他の門弟達とは同一視されず、敬意を以て、その人を遇した。そうした事実を通しても、博士のまたと得難い人だったことが知られる。 随筆小品といえば、一般の人々は、これを、小説、戯曲よりも、低いところにあるものとして片付けているのではなかと思われるが、博士の随筆などは、これを、小説、戯曲よりも、更に上位に置かるべきものといってもよく、これを大正文壇の至宝として珍重すべきものというべく、博士の随筆のよさを知らずにいる読書子などは、未だ倶に文を語るに足らざる人々といっても宜しかろうと思われる。
「夜更けの汽車で、一人の紳士が夕刊を見て居た。 其の夕刊の紙面に、犬の欠伸をしてゐる写真が、懸賞写真の第一等として掲げてあつた。 其紳士は微笑しながら其の写真を眺めて居たが、やがて、一つ大きな欠伸をした。 丁度向ひ合わせに乗って居た男も矢張同じ新聞を見て居たが、犬の写真のある頁へ来ると、口のまわりに微笑が浮かんで、さうして、……一つ大きな欠伸をした。 やがて、二人は顔を見合わせて、互に思わぬ微笑を交換した。 さうして、ほとんど同時に二人は大きくのびやかな欠伸をした。 あらゆる『同情』の中の至純なものである」 「脚を切断してしまった人が、時々、なくなって居る足の先の痒みや痛みを感じることがあるさうである。 総入歯をした人が、どうかすると、その入歯がづきづきうずくやうに感じることもあるさうである。 かういう話を聞きながら、私はふと、出家遁世の人の心を想ひ見た。 生命のある限り、世を捨てるとといふことは、とても出来さうに思はれない」 気象学者が cirrus と名づける雲がある。 白い羽毛のやうなのや、刷毛で引いたやうなのがある。 通例巻雲(ケンウン)と訳されて居る。 私の子供はそんなことは無視してしまつて、勝手にスウスウ雲と命名してしまつた」 「人殺しをした人々の魂が、毎年きまつた或月の夜中に墓の中から呼び出される。 さうして、銘々の昔の犯罪の現場を見舞はせられる。 行きがけには誰も彼も、 『正当だ。おれのしたことは正当だ』 とつぶやきながら出かけて行く。 ……併し、帰りには、みんな、 『悪かつた。悪かつた』 とつぶやきながら、銘々の墓場へ帰つて行くさうである。 私は、……人殺しだけはしないことにきめようと思ふ」 「眼は、いつでも思つた時にすぐ閉ぢることが出来るやうに出来て居る。 併し、耳の方は、自分では自分を閉ぢることが出来ないやうに出来て居る。 何故だろう」 「『ダンテはいつ迄も大詩人として尊敬されるだらう。……誰も読む人がないから』 と、意地の悪いウォルテーアが云つた。 ゴーホやゴーガンも何時迄も崇拝あれるだらう。…… 誰にも彼等の絵がわかる筈はないからである」 「油絵をかいて見る、 正直に実物の通りの各部分の色を、其等の各部分に相当する『各部分』に塗つたのでは、出来上つた結果の『全体』はさつぱり実物らしくない。 全体が実物らしく見えるやうに描くには、『部分』を実物とhさちがふやうに描かなければいけないといふことになる。 印象派の起つたわけが、やつと少し分かつて来たやうな気がする。 思つたことを如実に云ひ現はす為には、思つた通りを云はないこおが必要だとといふ場合もあるかも知れない」 「猫が居眠りをするといふことを、つい近頃発見した。 其様子が人間の居眠りのありさまに実によく似て居る。 人間いじゅら年を取つても、矢張り時々は何かしら発見をする機会はあるものと見える。 此れだけは心強いことである」 「コスモスといふ草は、一度植ゑると、それから後数年間は、毎年ひとりで生へて来る。 今年も三四本出た。 延び延びて、私の背丈け程に延びたが、一向に未だ花が出さうにも見えない。 今朝行ゆて見ると、枝の尖端に蟻がニ三疋づゝ付いて居て、何かしら仕事をしてゐる。 よく見ると、なんだか莟(つぼみ:黒崎記)らしいものが少し見えるやうである。 コスモスの高さは蟻の身長の数百倍である。人間に対する数千尺に当るわけである。 どうして蟻が此の高い高い茎の頂上に莟の出来たことを嗅ぎ付けるかヾ不思議である」 「大学の構内を歩いて居た。 病院の方から、子供をおぶつた男が出て来た 近づいっとき見ると、男の顔には、何といふか皮膚病だが、葡萄位の大きな疣が一面に族生して居て、見るもおぞましく、身の毛が悚つやうな心地がした。 背中の子供は、やつと三つか四つの可愛いゝ女の児であつたが、世にもうらゝかな顔をして、此の恐ろしい男の背にすがつて居た。 さうして、『お父ちゃん』と呼び掛けては、何かしら片言で話して居る。 その懐かしさうな声を聞いたときに、私は、急に何物かヾ胸の中で溶けるやうな心持がした」 「大道で手品をやつて居る処kを、其のうしろの家の二階から見下ろして居ると、あんまり品玉がよく見え過ぎて、馬鹿らしくて見て居られないさうである。 感心して見物して居る人達の方が不思議に見えるさうである。 それも其の筈である。 手品といふものが、本来、背後から見下ろす人の為に出来た芸当ではないのだから」 「『二階の欄干で、雪の降るのを見て居ると、自分のからだが、二階と一處に段々空中へ上がつて浮くやうな気がする』 と、今年十二になる女の子がいふ。 かういふ子供の頭の中には、屹度大人の知らない詩の世界があるだらうと思ふ。 併し又、かういふ種類の子供には、何処か病弱なところがあるのでhあンあいかといふ気持ちがする」 「第一流の新聞或は雑誌に連載されて居た続きものが、何時の間にか出なくなる。 完結したのだか、しなかつたのだか、はつきした記憶もなしに忘れてしまふ。 しばらく経てから、偶然の機会に、それの続きが、第二流か三流の新聞雑誌に掲載されて居ることを発見する。 一寸、久し振りで旧知にめぐり会つたやうな気がする。 なつかしくもあれば、又何となく淋しくもある」 「ラジオの放送のおかげで、始めて安来節や八木節などといふものを聞く機会を得た。 暖かな中に暗い絶望的な悲みを含んだものである。 時分は、何となく、霜夜の街頭のカンテラの灯を連想する。 併し、何んと云つても、此等の民謡は、日本の土の底から聞こえて来る吾々の祖先の声である。 謡ふ人の姿を見ないで、拡声器の中から響く声だけを聞く事によつて、さういう感じが却て切実になるやうである。 吾々は、結局ベートヴェンやドビュッシーを拋棄して、もう一度此の祖先の声から出直さなければならないでないかといふ気がするのである」 「うすら寒い日の午後の小半日を、邦楽座の二階の人気の少い客席に腰かけて、遠い異国の華やかな歓楽の世界の幻を見た。さうして、つめたい空ッ風に吹かれて、ふるへながら我家に帰つた。食事をして風呂に入つて、肩まで湯の中に浸つて、さうして手拭を顔に押し当てた瞬間に、つぶつた眼の前に忽然と昼間見た活動女優の大写しの顔が現はれた、と思ふとふつと消えた。 ア メ リ カ は 人 皆 踊 る 牡 丹 か な」 「純白な卓布の上に、規則正しく並べられた銀器の色々、切子硝子の花瓶に投込まれた紅白のカーネーション、皿の上のトマトの」紅とサラドの緑、頭上に廻転する扇風機の羽搏き、高い窓を飾る涼しげなカーテン。 其処へ、美しいウエトレスに導かれて、二人の老人がはひつて来る。 それは芭蕉翁と歌麿とである。 芭蕉は定食でいゝといふ。 歌麿はア・ラ・カルテ(アラカルトとは、献立表から好みに応じて一品ずつ注文する料理のこと。またそうした食事方法のことも指す。日本語としては一品料理、お好み料理とも言う:黒崎記)を主張する。 前者は氷水、後者はクラレット(フランスのボルドー産の赤ぶどう酒:黒崎記)を飲む。 前者は少なく、後者は多く食ふ。 前者は嬉しそうに、あたりを眺めて多くは無言であるが、後者はよく談じ、よく論じながら隣の卓西洋人に、鋭い観察の眼を投げる。 隣室でジャズが始まると、歌麿の顔が急に活々して来る。葡萄酒のせいもあるであろう。 芭蕉は相わらずニコニコしながら、一片角砂糖をコーヒーの中に落して、じつと見つめて居る。 小さな泡が真中へかたまつて四方へ開いて消える。 それが消えると同時に、芭蕉も、歌麿も消えてしまつて、自分は唯一人、食堂の隅に取残された自分を見出す」 「今日神田の三省堂へ立寄つて、ひやかして居るうちに、『性的犯罪考』といふ本が見当つたので、気紛れの好奇心から一本を求めた。 それから、暇つぶしに、あの背の高い書架の長城の前をぶらぶら歩いてゐるうちに、『随筆』と札のかゝつた区劃の前に出た。 背の低い、丸顔の、可愛い高等学校の生徒の一人、古風な薩摩絣の羽織に、同じ絣の着物を着たのが、ひょいと右手を伸ばしたと思つて、其指先の行衛を追跡すると、それが一直線に安倍君著『山中雑記』の頭の上に到達した。 おやと思つて居るうちに、手早く書架からそれを引っこ抜いてから、しばらく内容を点検して居たが、やがて、それをそつと元の穴へ返した、と思ふと、今度はすぐ隣りの吉村冬彦著『藪柑子集』を抽出して、此れもしばらく頁をめくつて居たが、やがて又元の空隙へ押しこんだ。 さうして、次にはそれから少し、十四五冊位おいた左の方へ移つて行つた。 正月の休みに郷里帰省中であつたが、親父からいくらか貰つて、稍懐を暖かくして出京したばかりらしいから、どちらか一冊位は買ふかな、と思つて見て居たが、とうとう失敬して行過ぎてしまつた。 尤も、彼はそれからもう一遍立帰つたどうか、其処迄は見届けないから分からない。 それはどうでもいゝが、兎に角安倍君というものと、自分といふものが、此の可愛い学生の謙譲なる購買力の前で、立派な商売敵となつて対立して居た瞬間の光景に、偶然にもめぐり合せたのであつた。 それよりも、もしあの学生が『藪柑子集』を読んだとしたら、その内容から自然に想像するであらうと思はれる若い昔の藪柑子君の面影と、今此処で、水洟をすゝりながら『性的犯罪考』などをあさつて居る年取つた現在の自分の姿との対照を考へると、甚滑稽でもまり、また少し淋しくもあつた。 哲 学 も 科 学 も 寒 き 嚔 哉 抄出は以上で終えることとする。しかし、一読せられた人々は、『柿の種』の内容がいかなるものであるかの一事は、解って貰われたであろうと思う。 以上に引いた幾章かの内、芭蕉と歌麿とが連れ立って食堂へ現れる一篇は、奇想この上もなく、芭蕉の方はともかくとして、歌麿の方は、江戸時代の浮世絵師風情でない、少し芸術家になり過ぎている嫌いがある。しかし、そんなことをいうのは野暮の骨頂で、歌麿も明治に一度くらい洋行して、すっかり灰汁抜けした歌麿と見て置けばよい。かような思いも寄らぬ一篇が科学を専攻する人の手に成っているのだから、恐入らあるを得ぬのである。 恐入るといえば、冬彦博士は、江戸文學の内でも、その時代を専門とする学者達もあまり見ない黄表紙までも読んで、その面白さを、人に与えた手紙の中で――それは確か京伝の作品だったと思うが――いっている、私等は、世にも得難い人だったと思わずにはいられない。 然し博士は、読書界に人気がある人とまではならず、博士の作品は何れも片々たるものばかりで、小説などには手を染められなかった。博士を随筆家と呼ぶことは出来ようが、普通の文士とは違っていた。文は書いても、その文におは筆でかせいでいる文人の文には求め難い気品が4ある。 私は博士の書きものの持つ気品を、世にも尊いものとする。 2023.10.29記す。 |

森銑三著小出昌洋編「新編明治人物夜話」を読む 「好色一代男」「好色一代女」「好色五人女」「西鶴諸国ばなし」「本朝二十不孝」「日本永代蔵」「世間胸算用」「万の文反古」「西鶴置土産」などなどの作品は井原西鶴が書いたことになっているが、この説に異を唱えた人がいる。森銑三である。森によると、西鶴が自ら書いたのは「好色一代男」だけであるという。 別に「日本永代蔵」や「世間胸算用」が西鶴以外の人が書いたとしてもこれらの作品の質が下がるわけではない。誰が書こうと「日本永代蔵」「世間胸算用」は非常に優れた古典である。 森は90年近い生涯(1895年に生まれて1985年に没している)を読書だけに費やしたといわれている読書家の巨人である。森は、戦争後西鶴の研究を始め、それこそ一字一句を確かめて新説を打ち出したのである。西鶴に関する本にはたびたび森のなが登場する。とにかく森は博覧強記な教養人であった。 森が書いた「明治人物夜話」はタイトルの通り、著名明治の人物について書かれた随筆集というような本である。 これらの人物は大きく分けて2種類の人たちに分けられる。1つは本の世界で知り合った人たちであり、もう1つは直接に森が出会った人たちである。主だった人たちをあげてみると、明治天皇・勝海舟・西郷隆盛・高橋是清・栗本鋤雲・幸田露伴・依田学海・成島柳北・森鴎外・尾崎紅葉・斉藤緑雨・正岡子規・三遊亭円朝・狩野亨吉・永井荷風などである。 どの人物についての記述も含蓄があって、わくわくするようなおもしろさである。教養をベースとした文章というのはやはり奥深い。言葉が生き生きとして魂がこもっているのである。 すべて興味深いものばかりであるが、特に印象に残ったものをあげてみると、まず明治天皇と西郷隆盛のことである。 明治維新になって、西郷隆盛は明治天皇の教育係になった。明治天皇はまだ10代で若いというより幼なかった。ある日、天皇が馬場で馬術の訓練をしていると馬から落ちてしまった。天皇は思わず、「痛い」といった。西郷はその声をきいて、なぐさめるのでなく、「痛いなどという言葉を、どのような場合も男が申してはなりませぬ」といった。これ以来、明治天皇は生涯どんなに痛くても一度も「痛い」といわなかったそうである。いやはや、やはり西郷とはとてつもなくすごい男である。 夏目漱石のこともおもしろい。文部省が文芸を普及させるために文芸賞を創設した。この話を伝え聞いた漱石は新聞で、国が文芸に口を出すとは何事かと反論したそうである。実際に、森鴎外・幸田露伴・徳富蘇峰などが選者となって、文芸賞の候補作を決めた。その中に漱石の「門」もはいっていた。最終的に文芸賞を決めることになったが、結局決められなかった。このことを漱石は喜んだ。そして、国が主導する文芸賞もなくなった。この話には漱石の芸術観が出ている。 漱石の学生時代の同級生の狩野亨吉のこともすばらしい。森が直接狩野に会ったときのことを書いている。狩野は第一高等学校長、京都帝大総長にまでなった人であるが、晩年は護国寺裏の八畳間と三畳間しかない借家に妹と二人きりで住んでいた。狩野は生涯独身であった。その家には本はなく、昔読んだ本のカードだけがあった。ある本の話になるとカードを取り出して、それは読んだといった。清貧そのものである。森は狩野のことを敬愛の念をこめて書いている。私は狩野の偉大さを感じた。偉大なる教育者とは狩野みたいな人をいうのではないだろうか。 どれもこれも興味深い随筆ばかりである。私は「明治人物夜話」を読みながら、古きよき時代を旅した気分になった。以上、「インターネットによる」 平成二十九年十月十ニ日追加。 |

その一 写本と繕写 昭和十八年五月下旬ころの本を読んでいると、 柴田宵曲が「写 本」について一章を書いている。そのなかに 或先輩の話しによると、昔の人が今の人に比べて著しく達者だと思われるのは、道を歩くことと、写本をすることだそうである。これは昔の世の中が不便だったためであるが、一面において昔の人の根気のよかった証左になるであろう。 現代人の多くは写本なるものと没交渉に暮らしつつある。今後はいよいよ縁が遠くなりそうに見える。『あられ酒』の中に「よしわれに著述ありとも、活版本を以て世に伝えふることをなさざるべし、われは唯写本を以て伝へんのみと、著作家ならぬ人の、今の著作家に向かって語りしぞ」と,あるが如きは、今の人から見たら随分かけ離れた意見であるに相違ない。しかし世の中は幾度も回転する。一切を挙げて活字に化するような今の世の中にも、活字にするのに便利でない著作はいろいろある。 活字本に誤しょくがあるように、写本は時に誤写を免れぬ。転写本からの写しは特にそれが甚だしい。 近年まで活字の誤しょくを嫌って、自筆のまま板行せしめた人もあるが、子細に点検した人の話しでは、その自筆にも書誤りが絶無ではないそうである。 「貸 借」の章には「繕写」というみられない言葉に出合った。 藤原 惺窩の時代は兵戈戦乱が全くおさまらず、学を講ずる者も乏しかったが、書物の入手も至って困難であった。『十八史略』を角倉与市に借りて書写したという一事を見ても、その程度は察せられる。 私はこの言葉を知らなかった。 『広辞苑』(昭和三十年五月二十五日 第一刷発行)には記載されていた。 「誤りを直してうつしかえること。うつしなおすこと。」と説明されていた。 ▼写本、活版本と文字に表わす手段が変化する過渡期の人達の気分がよく伝わってくる。 現在、写本などする人は絶無に近いだろう。 ゼロックスのコピー器が発達して、本をはじめとして書類の写しまで手軽にそのままコピーできる。さらに最近は、パソコンのワープロで、打ちこんだ文章に、写真や雑誌の文章を読み込むことのできるスキャナーまで使われている時代である。現在も似たものを感じさせられものがある。 近ごろは、私はすべての手紙、ハガキを書くにもワープロを使用している。手書きでないと、こころが伝わらないと思われる人もいる。私もそんな気持ちがしないでもない。しかし私信の内容が保存される便利さもある。 私信は手書きで書くべきである、いやワープロでもよいといった選択の気持ちの問題である。時の推移とともに、写本がなくなつたとおなじようにワープロ派が多数派になっていくのだろう。 (九年十二月十一日 2019.01.02 |
☆13 山崎闇斎(1,619~1,682年)
|
山崎闇斎 佐藤直方は、闇斎門下の三傑の一人であるが、その直方にしてなほ且つ、「昔、闇斎先生に就いてゐた時には、その家へはひるごとに、内心びくびくして、獄にでも下るやうな気持だつた。辭して表へ出ると、始めてほつとして虎口を逃れたやうな心地がした」と告白してゐる。かやうな威力を有する先生が、さう求められるものはない。 門人の楢崎正員が闇斎に呼ばれてその前へ出た時に、「今日は、よいお天気で」と挨拶したら、忽ちどなりつけられた。「天気などはどうでもよい。何か分からぬことでも聞け」と。しかしまた門下の質問も、分かり切つた訓詁でも問はうなら、すぐにまた「字引にある」と叱られる。 もし闇斎の人物の短所はといつたら、あまりにもゆとりのなかつたことが挙げられるかも知れない。しかしそのゆとりのないのが、一面闇斎の長所であつたのである。崎門に於ては一も學問、二にも學問、三にも學問だつた。書物なども、餘白もないまでに書入してあるのが喜ばれた。聖賢の書からなどと、綺麗なまゝで持つてゐようとしたりすると、却つて叱られた。徹頭徹尾學問本位だつたのである。かやうな教育法に依つて、闇斎の門下からは、佐藤直方が出た。浅見絅斎が出た。三宅尚斎が出た。その他の人々が出た。 三 以上は主として『日本道學淵源録』に據つたのであるが、なほ『貫川記聞』といふ殆ど知られてゐない寫本に、闇斎の言行の一二の記してあるのを、序に紹介して置こう。『貫川記聞』は、闇斎からは孫弟子になる若林強斎の談話を、その門人の筆録したものである。 「崎先生が、俗儒を抱へようよりも、事文類聚を買つて置いた方がよい。扶持をいたゞきたいとも、御加増が願ひたいともいはなくてもよい、と仰せられた。尤もなことぢや」 その一つにかやうにある。たゞ知識を授けることならば、何も活きた人を俟たない。眞儒には――眞の教育家には、それ以上のものがなくいてはならないのである。然も現代にも、死んでゐる書物の受賣だけをしてゐる教師がいかに多いことか。 闇斎が他の儒者達と、会津侯保科正之に侍坐してゐた時のことである。正之が、『論語』の「父母はたゞ其の疾をこれ憂ふ「の章に兩説のあることを擧げて、「一方に片づけたいものだが、いかゞであらうか」といつたのに、闇斎は、「兩説共に一理ありますので、俄かに一方に極めるわけにはまゐりませぬ」と申し上げた。すると儒者の一人が横から口を出して、「嘉右衛門殿は御子がないから御存じあるまいが、拙者などは子供を持つてござれば、子を思ふ情はよく分かつて居ることでござる。父母は病をしようかと憂ふると説く方が適切でござろうと存ずる」と、憚りもなくいつた。それを聴いた闇斎は、静かに答へて、「なるほど拙者は子供を持ちませぬから、その趣は存じませぬが、しかし大勢子供もあつて、殊に長男をなくなされている朱子が、片づけられぬと申されてゐるのを見ますれば、俄かに一方に極めるわけにはまゐりますまい」といつた。その儒者は一言もなくなつた。これを聴いた正之は、「尤ものこと」と仰せられて、それ以上の穿鑿は止められた。――一時の思附を卒然として口にして、すぐにまた閉口した俗儒の様子が見えるやうである。 四 闇斎は、天和二年九月十六日に京都に没した。歳は六十五であつた。 闇斎もその晩年には、言行がよほど穏かになつてゐた。然も闇斎自身は笑つていつた。「己が以前のやうでないないのを、徳が進んだからだと思うたら、間違ひじゃ。まことは鎗の穂先が碎けたのぢや」と。 この小篇は、闇斎を語つてもとより委細を盡さぬが、それを盡さうとしたら際限がなくなるであろう。最後にその門流の人遊佐木斎の言を擧げて、結語に代へる。 「闇斎先生の人となりや、平生他の嗜好なし。一味學に志して、未だ嘗て俗人と交らず。温厚の氣象足らずと雖も、志剛にして、制行苟(いやし)くもせず。専ら斯道を明かにするを以て己が任となし、死して後止む。學んで厭はず、教へて倦まざる者に庶幾き歟。其の志の如きは、則ち藩國に仕へず、王公に屈せず。後學を誘引して、此の學を将来に傅へむと欲する而巳。實に本邦の一人にして、其の程朱に功あることは、則ち世未だ其の比を觀ざる也」 ※参考:程朱は日本で使われる用語であり、中国では、朱熹がみずからの先駆者と位置づけた北宋の程頤と合わせて程朱学(程朱理学)・程朱学派と呼ばれ、宋明理学に属す。
森 銑三著作集 第八巻 人物篇八 儒学者研究 (中央公論社)P.11~15より
|
☆14 浅見絅斎(1,652~1,712年)
|
浅見絅齋 一 承応元年8月13日(1652年9月15日) - 正徳元年12月1日(1712年1月8日) 浅見絅齋は儒者であつた。朱子学者であつた。しかしたゞ朱子学者といつたのでは、ぴつたりしないものがある。絅齋は、儒者は儒者でも、最も日本的な儒者、武人的な儒者だつた。徳川幕府専権の時代に当つて常に大義名分を鼓吹し、足一歩も京都の外へ出ず、諸侯の招に応ぜず、薙刀一柄を床の間に逆に立てかけ、「もし禁庭に御大事があらば、これを小脇に掻い挟んで、お味方に参らう所存ぢや」といつた。佩刀の鎺(はばき:鈨・はばきとは日本刀の部材の一つで、刀身の手元の部分に嵌める金具である)に赤心報国の四字を篆鐫(てんせん:中国で秦以前に使われた書体。大篆と小篆とがあり、隷書・楷書のもとになつた。印章・碑銘などに使用)したのも、またさうした精神の顕現だつた。絅齋は剣道にも達してゐた。毎朝夙に起きて、馬を乗廻すことが数回だつたともいはれてゐる。もとよりたゞ先哲の書を講じて、能事畢れりとする学究ではなかつたのである。 絅齋の皇室尊崇の大精神は、更に凝集して『靖獻遺言』の一書となつたのであるが、絅齋の志は、空言を以て義理を説くも、人を感動せしめない。事蹟を挙示して、読む者をして感奮興起するところあらしめたいといふにあつた。然も徳川の盛世に、本朝の諸忠臣を顕彰することは、幕府に尊して憚らざるを得ぬ。依つて漢土の忠臣義士の内から、最も大義に明らかなる者八人を選び、特にその絶命の詞を挙げ、附するにその行実を以てして、天下の人士に尊王の大義を徹底せしめようとした。そしてこの書は、絅齋の生前に刊行せられて普く流布し、絅齋没後には、ますます廣く行われた。幕末多事の日に至つては、王事に奔走する志士達の競つて愛読するところとなり、つひには王政復古の一大原動力ともなつた。絅齋は嘗て『近思録』を講じて「為萬世開太平」の章に至つて、「」拙者が今日おのおの方のためにこの書を講ずるのも、また萬世のために、太平を開くのでござる」といつたといふ。絅齋の自ら任ずるところは、かくの如くだつた。その『靖獻遺言』を著したのも、また正に萬世のために太平を開くものだつた。 二 然も緑仕を肯んぜず、聞達を求めなかつた絅齋の一生は貧に徹してゐた。清貧の語は、たゞ文章の上に好んで人の用ひるところとなつてゐるが、絅齋ほどの清貧に甘んじてゐた人は、蓋し尠かつたらうと思はれる。その高弟の若林強齋も、貧の一事に於ては師の絅齋に譲らなかつたが、或日大津のその家から、京都の絅齋の許へ通う途中で餅を買つて、土産に持参したら、絅齋は大食の人だつたものだから、その餅を貪るように食べて、「そちも貧乏は貧乏やゃが、この餅が買われるくらゐならまだよいわ」と笑いながらいつた。 また或時は、絅齋が寒中にも綿の入つた物を身に着けてゐないのを見て、強齋は母から仕立てて貰つた正月の晴着を作り直して、先生に差上げた。そうしたことなどもあつたのだつた。 やはり或年の暮に強齋が訪ふと、絅齋はがらんとした空家のやうな家に、擂鉢に酒を盛つたのを傍らに置き、椀の蓋でそれを酌んで飲みながら、「正成その時、肌の守を取出し」と、楠木の謡をうたつてゐる。見渡したところが、まだ正月の餅も搗けてはゐない。強齋は家に帰るとすぐに餅を搗かせて、それをまた持参したなどといふ話も傳えられてゐる。このことは尾張に於ける﨑門の儒者の一人だつた細野要齋が書いてゐる。 楠木の謡といふは、絅齋自ら作つて、その道の人に節附けして貰つたものだつた。絅齋は楠公を以てわが国に於ける忠義の士の第一人者として、その徳を慕うのあまりに、『太平記』の桜井駅訣別の一段を謡としてうたつたのものである。 前の絅齋と強齋とのこおは、強齋の談話をその門下山口春水の筆録した『雑話筆記』に據つたのであるが、同書にはまた絅齋のことを語つて、「先生は大男で、よく肥えたる人にて候が、屋根がもるゆゑ、自分(強齋)を相手にしては屋根へ上らるれば、踏まるゝ處がぬくる。或は講堂のねだが落つると、先生の木遣りで、自分がいつでも其の相手になつたことにて候。それほど清貧にありたれども、先生には其れなりに安んじて、つひに富貴利達を求めらるゝ心なく、世に手出しをなさるゝと云ふことの全然なかりたることにて候」といふ一節がある。 大兵肥満の絅齋が、自身に雨漏りの修繕をするとて、屋根へ上つて、却つて屋根板を踏み抜いて、修繕どころか破搊を大きくしてしまふといふやうな悲しい滑稽をも演じたりしたのである。 三 『雑話筆記』には、絅齋のことを語つてゐるのがまだある。絅齋は三人兄弟の仲で、その家はもともと善かつたのであるが、絅齋が学者として一家を成した頃には、家道がいたく衰えてゐた。ところが絅齋の兄も弟も、一向に働きのなかつた人で、絅齋は自分の生活を維持するだけでも容易でないのに、その上にも實家のことにも頭を使つて、何かにつけて苦労しなければならなかつた。門人達は、何れもそれを痛ましいこととしたといふ。「されども先生には、学問の為方のねうねつな通りに、親類一家のことにも、ずんと思召すまゝにせねばおかれぬ御気象にて、それが勢があればなれども、まことに身の孝養も足らぬ身代で、大気なまゝに、当る障るの世話を、身に引きうけてなされて、何でも来いと云う様な御気質ゆゑに、一ばい御苦労も多かつたことにて候」などとしてある。 ねうねつは聞き馴れぬ言葉であるが、これは今ねついといふのと、恐らくは同義なのであらう。貧すれば鈊するなどといふが、絅齋はいかに貧乏しようと、そのために志を挫くような薄弱な徒ではなかつた。苦しい中からも、矢も鉄砲も一身に引受けようというやうな、めげぬ気象を発揮した。そうした点にも絅齋の剛毅な性格が窺われるのである。 『雑話筆記』には、上についで、絅齋の継母への仕え方のいかにもよかつたことが述べてある。その継母といふは、御幸町松原下ル町に住む絅齋の弟の許にゐられたのであるが、晩年病気になつてからは、絅齋は毎日欠かさず看病に赴いた、それも昼間自宅で講義をし、雑用を済まして、夕方から出かける。そしてその看病を夜通し勤めて、朝になつてから帰る、それが酷暑にも厳寒にも変わらずに、末期まで続いた。道筋の人達は絅齋の通るのを見て、感動せずにはゐられなかつた。絅齋は、忠孝節義をたゞ口先で鼓吹する学者ではなかつたのである。 四 絅齋の畢生の著述『靖獻遺言』は、貞享四年(1687年)に板行が成つたのであるが、絅齋の父はそれを見るに及ばずに、その前年に六十一歳でなくなつた。後に絅齋は、「自分が当世に用ひられるぬのを、親御は常々気の毒がられたが、これほどの書物を仕立てるほどになつたことを聞かれたならば、さぞかし悦ばれたことであらうに」と、しばしば述懐に及んだ。門人達もまた師の心中を及んで、それを遺憾なこととしたといふ。強齋も、「晩年には、侯伯も其のなを称せらて、仙洞様(霊元天皇)にも先生のなを知らせられて、仰せ出されたと云ふことなり。今少し御存命ならばと思うこと大分ありたることにて候」といつてゐる。 最初に絅齋を日本的な、武人的儒者であつたとしたが、それだけではまだいひ足りない。絅齋は正に一個の大丈夫だつた。大丈夫にしてそして儒を兼ねたのである。 絅齋、なは安正、通称は重次郎、近江国高島郡太田村の人である。始め医を業としたが、後ち儒に帰して、山崎闇齋に就いて学んだ。崎門の三傑の一人に数へられる。慶安五年年八月十三日に生まれ、正徳元年十二月朔日に没した。歳六十。京の東郊鳥邉山に葬られた。
浅見 絅斎(あさみ けいさい、承応元年8月13日(1652年9月15日)~正徳元年12月1日(1712年1月8日)は、日本の江戸時代の儒学者・思想家。なは重次郎。諱は安正。筆名として望楠楼。 近江国(現滋賀県高島市)に生まれる。はじめ医者を職業としたがやがて山崎闇斎に師事し、後世、闇斎門下の俊英3人、すなわち崎門三傑の一人に数えられる。後年に至つて、闇斎の垂加神道の説に従わなかつたために疎遠となつたが、闇斎の死後は、神道にも興味を示すようになり、香を焚いて罪を謝し、闇斎の所説を継述するに至つた。門下に、若林強斎(守中霊社)・山本復斎(守境霊社)等がいる。その尊王斥覇論は徹底しており、足、関東の地を踏まず、終生、処士として諸侯の招聘を拒み、明治維新の原動力の一つとなつた。
『森 銑三著作集』第八巻(中央公論社)P.16~20より
参考書:近藤啓吾著『靖献遺言』(国書刊行会):(昭和六十三年三月八日購入している)766ページに及ぶ本である。
|
☆15 仁斎とその子達
|
仁斎とその子達 一 公家の徳大寺公――多分實維( さねふさ)といつたひとであろう――は、時々名聲のある儒者達を招いて、その意見を上下せしめて聴いた。何れも始めは謹んでゐるが、その中には夢中になつて、互に肩を怒らし、聲を張上げ、口角から泡を飛ばして自説を主張する中に、ひとり伊藤仁齋のみは終始少しもその態度を變ぜず、ゆつたりとして物をいふ。その様子がいかにも立派で、誰しも仁齋の前には、おのずから頭がさがるのだつたといふ。 京都所司代は、天皇に拝謁することも出来る、重い職分の役人であるが、その所司代が仁齋を路上に見かけた時、高貴の方と思違へて、馬から下りて挨拶したといふ話もある。關白の近衛公――多分基熈(もとひろ)であらう――は、「仁齋先生は大納言以上の人品だ」と、常々いjつてゐたといふ。 ニ 仁齋の平素の行には、強ひて意を立てたり、奇を衒つたり、われはといふやうな態度を示したりすることがなかつた。節分には自ら上下を着けて、「福は内、鬼は外」といつて炒豆を撒いた。佛教は信じなくても、寺の境内に入れば、本堂に向つて禮拝した。長屋の井戸浚屁に手傳ひに出て、一緒に綱を引いたといふのも有名な話である。 或時、新しい家へ引き越したら、そこは昔から變琴のある家だといふことが知れた。そこで仁齋はまた他へ移つた。「先生ほどの方でも、妖怪などをお信じなさるのですか」と或人が問うたら、仁齋は、「いや、さやうな家にはゐぬ方がよろしい。子供がこはがりませうから」と答へた。 まら或時、京都で毒が降るといつて騒ぎ立てゝ、家の井戸を覆うたりしたことがあつた。伊藤家でも下男があわてゝ蓋をした。門人達がそれを見て、「外の家はともかく、先生のところまでが、そんな愚かなまねをなさるのは見つともないではありませぬか。お取らせになつたらいかヾですか」といつt。 三 仁齋の晩年、火事に遭つて家の頽廃したことがあった。或人が見舞いに行つたら、仁齋は堀川の中に床を置いて、そこへ酒を携へて悠々としてゐた。 「飛んだ御災難で」と見舞の言葉を述べたら、仁齋は、「天災は是非に及びません。老人の癖に騒ぎ立てゝ、怪我などしてはと思ひおまして、始めからこゝにかいしてゐます。まづお一つお上り下さい」と、何のこともないやうな様子で盃を差出した。さすがに仁齋先生だと、見舞いに行「つた人は感じ入つた。 この時の火事だつたであらうか。所司代から焚出しを下さるとのことで、仁齋は自身に上下で頂戴に出た。大家の町人達は、何れも手代を名代に出したのであるが、このことを聞傳へて、恥入つて、また自ら上下着用の上で頂戴に出た。 四 或人が仁齋に會つてから、その感じを述べて、「仁齋といふ人は、何といふことなしに一緒にゐたいい人だ。しかし大山のやうで、なかなかこちらの思ふふやうになど動かされる人ではない」といつてゐる。 仁齋の長子東涯は、また父の名を恥づかしめぬ大儒であつたが、ある書物に、仁齋東涯父子の人物を比較して、かやうにいつてある。仁齋は他から「誰々が先生のことをかやうに申して褒めました」などといつても、「さうですか」とばかりで、顔色一つ動かされなかつた。これはその度量が廣くて、毀誉を問題にせられなかつたからである。東涯はさような場合には、「さうですか」といはれるのが、いかにも嬉しさうだつた。東涯は性質が純良で、心に邪気がなかつたからである。仁齋先生の態度は、仁齋先生としてよいし、東涯先生の態度は、また東涯先生としてよろしい――。 五 赤穂義士の大石内蔵助と小野寺十内とが仁齋の門下であつたりして、義士と伊藤家とは相當に関係が深かつた。復仇の報を聞いて、東涯は日記の中にそのことを書きつけてゐる。それには百人ほどで討入つたなどとしてあつて、話が誇大せられてゐるが、大體に於ては正確といつてよく、最後に東涯は、「前代未聞の働き、忠肝義膽と謂ひつべし」としてゐる。義士中の人々を知つてゐた東涯は、人一倍感慨が深かつたのである。そして義盟に加はりながら、討入前に自害して死んだ菅野三平の傳記を、別に漢文で書いてゐる。 なほいつのことか、熊本の細川家の士が、東涯の許へ来て、「人は大事に臨んだ場合には、平生覚悟してゐることでも、多少は取亂すものと見えます。赤穂の浪士達は、死ぬ覚悟などは始めからついてゐた筈ですのに、切腹の申渡しのあつた時には、みんな幾らか顔色が變りました。少しも變らなかつたのは大石内蔵助一人でした」といふ話をした。 世間には人の美點は措いて問はず、短所や缺點のみを見出して喜ぶ人がある。細川家の士も、或はさうした傾向の人だつたのかも知れぬ。これを聞いた時に、東涯はたヾ一言、「面色までも、とやかくいふべきではありますまい」といつた。 切腹の申渡しを受けた時、たとへ多少は面色を變じたにせよ、義士達は、何れも潔く割腹して果てた。面色までも問題にするには及ばぬのである。 六 仁齋の第二子で、東涯には弟に當る梅宇には、『見聞談叢』といふ随筆があるが、その中にも義士のことが数條記されて居り、その一條に小野寺十内と、その遺族とのことがある。 十内は京都の御留守居を勤めてゐて、塾へも度々来た。父仁齋先生と入魂であつた。歳はその頃四十餘と見えてゐたが、一向に武勇の人とも思はれなかつた。痩せて丈の高い人だつた。諸侯の留守居も大勢家へ来られたが、その内でも十内は、身なりや腰の物などには一向構はぬ人のやうだつた。江戸へ立つ前日に来て、「所用があつて江戸へ行きます」と、挨拶せられたが、その時、兄東涯先生に向つていふのには、「人の生死は計り難うござる。仁齋先生へ今一度御意得たうござるが、私はもう五十に近し、先生も七十でござれば、それも計り難うござる。母親と家内とを、聖護院の森の家に残して参りますれば、もしあの邊をお通りの折には、お尋ねが願ひたうござる」とのことだつた。十内の母堂は、九十を越してゐられた。内室はまだ五十前で、女ばかりの家であるから、折ふし使をやられるだけだつたが、復仇の評判の立つた時、仁齋先生は東涯先生を使として、お祝に出された。この時、内室も母堂も、喜びの色を顔に現して、手の舞ひ足の踏むところを知らぬほどだつた。別して母堂の方がさう見えたたと、東涯先生が帰つて話された。翌年切腹の風聞のあつた時、また弔問かたがた東涯先生が越されたが、その折母堂の申されたには、「これも多少學問に志したしるしで、仁齋先生へ厚く御禮申上げまする。世間には子に先立たれて、早く死にたがる者ございますが、私におきましては、倅が本望を遂げましたので、世間が楽しく、人中へも顔出しが出来るゆやうに思はれます。これからは一層達者になつて、膳など据ゑて菩提を弔つてやりまする」といふことだつた。その後、いづ方へ行かれたか知れなかつたが、大和の龍門に母堂の弟が僧になつてゐる方へ行つてなくなられた。内室の方は尼になつて、家へも絶えず音づれがあつた。――梅宇はかやうに書いてゐる。 七 梅宇は、不義の士の大野九朗兵衛のことをも書いてゐる。それには、仁齋先生は九朗兵衛をも識つてゐたれたが、不忠の人間だから、その家の前を通つても、立寄つたりなどせられなかつた。始めは裕かに暮らしてゐたが、その内に落魄して、その惣領息子は、名を變へて日傭頭といふことうをしてゐた。その息子も九朗兵衛の死後に、人々から爪はじきせられて窮死した、などとしてある。 なほ梅宇は、大石主税のことをも書いてゐるが、主税は梅宇自身もよく識つてゐたので、その外貌を叙して、まだ角前髪で、色が白くて、美少年であつたが、筋骨の逞しいことは人一倍だつたとしてゐる。 主税の江戸へ立つ前に、北野の茶屋で偶然合つたら、「明後日は発足します」と挨拶して、「江戸では大川平馬と名乗りますから、あちらへお出になりましたら、小石川邊でさういつてお尋ね下さい」といつた。それから、「この間拵えさせました」といつて縁頭(ふちがしら)を見せた。地は赤銅で、龍の玉を取るところの彫があつた。後で思ふと、それは取りにくい首を取ろうといふ寓意だつたのであろう、と梅宇は書いてゐる。そしてなほ附け加へて、その性質が、とかいふにいはれぬ温にして厳なる人だつた、としてゐる。 八 仁齋の第四子竹里は、後に江戸へ下つて寺坂右衛門と識り、吉右衛門から義學の顛末を聴いて『枕宇録』といふ書を表してゐる。しかし残念なことには、今その書の存在が知られぬ。幕末近い頃まで傳へられてゐたことは確實で、いづこかにありさうに思はれる、この数年来注意してゐながら、まだ見ることを得ずにゐる。 2023.07.22 記す。 |
☆16 徂徠と春臺
|
徂徠と春臺 一 十四の歳から十年あまり上総国の片田舎にゐて、古葛籠の内から見つけ出した祖父の手写本の『大学諺解』 一部を反覆精讀して学力をつけた荻生徂徠は、二十五歳にして江戸へ歸り、芝の増上寺の門前の」豆腐屋ンの二階に間借りして人々に教へたが、始めの内は一向に門人も出来なくつて、毎日豆腐の糟ばかり食べては、辛くも飢を凌いでゐた。 「下谷の祝言寺さんのお説教にはお参りが多いが、こなたの講釋の日には、聴きに来る人がとんとない」 世話をしてくれる婆さんは、面と向かつてこんなことをいふのであつた。 その借りてゐる二階といふのも、天井につかへさうな、ひどい居間だつた。うつかりすると来る者が頭打ちつけるので、詩を書いた紙を壁にべたべた貼って置いたりした。 然るにそれより十年を經た三十五の歳いは、徂徠は柳澤吉保に仕へて五百石を領する身となつてゐた。もう昔日の窮措大ではない。しかしながら、徂徠は、以前の窮迫時代を忘れなかった。増上寺前の豆腐屋へは月々米を贈つて、舊恩を謝したといふ。 しかし徂徠は、立身出世の手段として學問をしたのではなかった。或時、某蔵書家の書物が一庫六十兩で質物に出たと聞いて大いに喜んで、衣類から、道具類から、殆ど一切を賣拂つて、家中を空にして、それでもなお足らぬところは人から借りて、そに一庫の書を買取つた。 備前の湯浅常山は、その著『文會雑記』の中にこの逸話を記して、『誠に豪傑の仕業なり』と歎賞してゐる。 然もまた徂徠は、さような大量の書をたヾ擁してゐるだけでは勿論なかつた。その日常生活はといふと、朝起きるから夜寝るまで、手から書物を離すといふことがないほどで、夕方暗くなれば、本を手にしたまゝで縁へ出て、また一しきり讀む。その内に燈がともると、また讀みながら部屋へhあひるといふ風だつた。 「書物といふものは、とにかく讀んで置かなくては、いざといふ場合に役に立たぬ。お上の紅葉山の御文庫に和漢の典籍が澤山藏してあるが、讀みたいと思ふ学者達に、あれを幾らでも貸して讀ませるやうにしたい。――」 かうした意見を、徂徠はその著書の中に残してゐるのである。 三 徂徠には学問の外は何もなかつた。或年の元旦に、高弟の服部南郭が禮服で年賀に来たが、徂徠はといふと、頭の髪も亂したまゝで、暮も正月もないといふ様子で、「これはよく来られた」と喜んで迎へて、すぐに兵學の話を始める。南郭はたいとう、「おめでたうございます」をいふことも出来ずに歸つた。 しかしながら人としての徂徠は、決して迂遠ではなかつた。或時初めて訪うた書生が、儒學に關する高遠な質疑をするのに答へないで、「貴公のお國は――」問うて、更にその風土や物産や、その他のことを尋ねたが、満足な答は殆ど得られなかつた。その時徂徠は警めて、「遠い異國のことよりも、まず手前の國のことを精しくせられるがよい」といつた。一部の人々は、徂徠一派の學者が、支那崇拝に陥つてゐたことを批難するが、徂徠は決して支那を知つて、自國あるを知らざる迂僻な儒者ではなかつたのである。 四 常山は徂徠を評して豪傑といつたが、事實徂徠は豪傑儒ともいふべき人物だった。「讀書についでの先生のお楽しみは」とと問はれて、「炒豆をかじつて宇宙間の人物を罵ることだ」といつたといふは有名な話であるが、その晩年に、八代将軍吉宗に拝謁することとなつた時、柳澤家のある人が、「あなたはいつも大きな聲で物をひになるが、お城は格別のところだから、あまり聲高にならぬやうに、お慎み下されたい」と注意した。すると徂徠はからから笑つて、「この年になるまで大聲に物をいひつけて来たのを、俄に低くしようというても無理でござろう」といつた。 徂徠が吉宗の御前で經書を講じた後で、陪聴の加納遠江守久通を通じて、「雷の正體はいかやうなものか」との御下問があった。 徂徠はこれを聴いて、久通に向つていつた。 「そこ許様⒨あで申上げまするが、私儀弱年の頃から持病に疝気を患つて、恐れながら腰中がをりをり鳴りはためきまする。しかしこれはいかやうなわけか、いろいろ考へて見ましてもとんと合點が参りませぬ。わが身の内すらさやうでござれば、ましてや玄妙な天地の間のことが、一々分るものではござりませぬ。あの雷も手前の疝気のやうなもので、何とも正體がつかめませんん」 いひもあへず徂徠は揺すり揚げて笑つた。廉の内の将軍吉宗も、その答に思はずお笑ひになつた。――徂徠の人物は、かやうな逸話の裡に躍動してゐるものがある。 五 また或時、荘内の酒井家の家老で、徂徠の門下であつた水野元郎が、同家の士佐藤某を紹介して入門させせ、「佐藤は剛直な男でござりまするが、何分にも短気で、そのために禍を招かうかと思はれまする。どうかその點を御教諭下されて、人間がおだやかになるやうにお導きが願いひたうござりまする」といつた。 徂徠は笑つて答へた。「わが日本は尚武の國で、進を知つて退くを知らぬのがその國ぶりでござる。短気は武道の害にはなり申さぬ。但し短気にも、誠の短気と偽の短気とがござつて、偽の短気は甚だ悪く、却つて辱めを受け申す。誠の短気は、果敢結構決行して、否といはヾその座を起たせず、一刀に討捨てようといたすのがそれでござる。かやうな火蓋を切つた短気の筒先には、更に向ふ者がござらぬ。随つて災ひも出来申さぬ。佐藤子も偽の短気にならぬやうに、御切磋いたされたうござる」と。 水野大夫は、これを聴いて爽然自失した。 六 今は活字にもなつてゐるが『徂徠先答問書』は、すべて上の水野元郎に与へた書簡を編次としたものであるが、その中にも會心の言が極めて多い。「名将は一癖ある者を好むなり」といひ、「人才は疵物なり」という、「人を採用するには、疵物よりお選びなさるべし」といつてゐるのなど、徂徠にして始めてこの言あるものといつてよいであろう。 徂徠は才を愛した。その門人達を遇するのにも、寛厚宏な態度を以てこれに臨み、鋳型に嵌めるやうな窮屈なことをせず、各自の長所をして飽くまでも伸ばさしめた。それだけに徂徠の門下には、天下の逸材が揃つてゐた。 そのために徂徠派の末派には、素行を検束せずして放縦に流れる幣を生じたが、しかし徂徠自身は、身を持することが極めて方正だった。平素衛生にも意を用ひた。豪放と細心と、兼ね備へてうゐたのである。世の豪傑を以て自任して、締めくゝりのつかぬ人々とはその意味を異にしたのである。 七 太宰春臺は、服部南郭と共に徂徠の門人中の一雙璧であつたが、徂徠が大海ならば、春臺はそゝり立つ巖山だつた。禮儀作法で練り上げて、一言一行も苟くもせぬといふ風だった。それだけに天真爛漫ともいふべき趣には缺けてゐた。 春臺は規則正しいことが好きで、起きてから寝るまでの日課が豫定したつた。朝は六ツ(午前六時)ンい床を離れると、羽箒で机を拂つて讀書する。その書物も最初は何、次は何といふ風に極めてあつた。それから依頼せられた詩文を見、自著の校合をする。夜は四ツ(午後十時)に床に就く。そして月に三回、五の日が面会日としてあつた。 春臺は書物を讀んでも、文字に誤のあるときは一點一畫の缺けたものを訂正する。著述の版下などはすべて自ら律する」ことの厳正であつた春臺は、他をもみだりに許さなかつた。未熟の者も褒め立てたりしては、却つてその将来を毒するといふのだつた。それらの點が、師の徂徠とは違つてゐた。 随って徂徠の學問には十分の敬意を拂つても、徂徠の人物とは、そりの合ひかねるところがあつた。その著書の中では、徂徠に對して忌憚のない批評ををも下してゐる。徂徠を伊藤仁齋と比較して仁齋のいずこへも仕へなかつたこと、その子に東涯を有したことなどを数へて、徂徠先生の及ばざるものとしてゐる。 八 その態度の手厳しかつただけに、春臺は徂徠の他の門人達とも、やゝもすれば調和を缺かうとした。或時徂徠の許で、師匠も弟子もくつろいで酒を飲んでゐるところへ春臺が到つたが、行儀を亂した門人達の様子を見るや否や、苦り切つて、「先生から御酒をいたヾくなら、慎んで頂戴したらどうか。その恰好は何事か」と然りつけた。皆は居ずまいを正したが、春臺が来たために座が白けてしおまつた。 その時徂徠は、つと立つて行つて琴を一面携へて来て、「孔子の弟子の内で、季路は、殊に勇気の人だつたが、それでも琴を弾ずる風雅な一面があつた。これはわしの秘蔵の琴だが、足下に贈ることとしよう」といつて、春臺に渡した。春臺に剛のありあまつて、柔の分子の缺けたことを諷したのである。 春臺は師の言に顧みるとこkろがあつた。そしてその琴を一生身を離さずに所持し、徂徠の没後、それを見る度に涙を流しては、「先生からよいお諫めにあづかつた」といつたといふ。 九 春臺は気節を尊んだ。儒を以て立つてはゐたが、自らは武人を以て任じた。家の玄関には鎗を掛けて置いたりした。徂徠と同じく柳澤家に仕へ、同家の奸臣を斬って一旦徂徠の家に隠れた田中桐江が江戸を逃れようとした時には、途中柳澤家の追手のかゝるのを慮り、同門の一兩人と鎖帷子に身を固めて、桐江を都門の外まで送つて出た。春臺は春臺として、大事を託するに足る、頼もしい人だつたのである。 2023.07.17 記す。 |
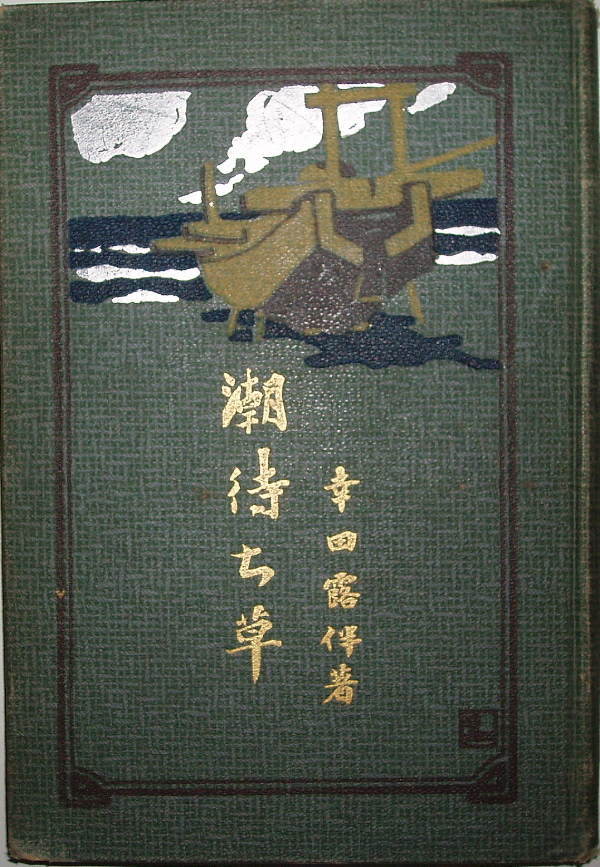 そうした意味で、露伴先生のような、私等の手本となるような文を作って示してくれる先輩のある世は、幸いであったといえよう。先生既に逝いて、文語体の文章らしい文を書いて見せてくれる人は、跡を断ってしまった。百人が百人、口語体の間に合わせの文を書いて、それで済ます世の中になってしまっている。致し方のないことといわなくてはならない。
そうした意味で、露伴先生のような、私等の手本となるような文を作って示してくれる先輩のある世は、幸いであったといえよう。先生既に逝いて、文語体の文章らしい文を書いて見せてくれる人は、跡を断ってしまった。百人が百人、口語体の間に合わせの文を書いて、それで済ます世の中になってしまっている。致し方のないことといわなくてはならない。
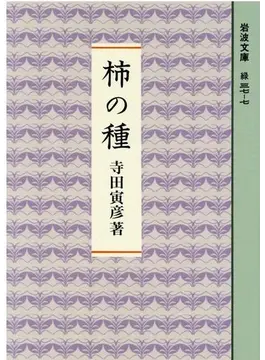 随筆家としての博士をあげつらうには、初め金平糖の変名で発表せられた「丸善と三越」以下の書篇を逸すべきでないかも知れないが、それらは全体があまりにも渾然として居り、その一部分を抄出して、かれこれいおうとするのが困難である。依ってこれには俳誌『渋柿』の題言として連載せられた無題の短文を集めて一冊とした『柿の種』を取上げることとする。博士の随筆は、その量を定めてかかることをせずに、そのテーマとするものを、十分に尽くしたものに、最もよく博士の面目の窺われるものといわれようが、『渋柿』の短文はそれとは別に、短章の裡にその要点を書いて、極めて暗示的な点に特色を有するといってもよく、短文ながらに博士らしい味わいが、その個々に存するのであり、これはこれとして、また私等に親しみの持たれるものを成している。ここにはその中からの何章かを、意に任せて抄出して行くこととする。しかし紙面に限りがあるのであるから、『柿の種』の極一小部分の抄出ということになってしまうのであろうが、その点は予め了解を得て置かなくてはならない。
随筆家としての博士をあげつらうには、初め金平糖の変名で発表せられた「丸善と三越」以下の書篇を逸すべきでないかも知れないが、それらは全体があまりにも渾然として居り、その一部分を抄出して、かれこれいおうとするのが困難である。依ってこれには俳誌『渋柿』の題言として連載せられた無題の短文を集めて一冊とした『柿の種』を取上げることとする。博士の随筆は、その量を定めてかかることをせずに、そのテーマとするものを、十分に尽くしたものに、最もよく博士の面目の窺われるものといわれようが、『渋柿』の短文はそれとは別に、短章の裡にその要点を書いて、極めて暗示的な点に特色を有するといってもよく、短文ながらに博士らしい味わいが、その個々に存するのであり、これはこれとして、また私等に親しみの持たれるものを成している。ここにはその中からの何章かを、意に任せて抄出して行くこととする。しかし紙面に限りがあるのであるから、『柿の種』の極一小部分の抄出ということになってしまうのであろうが、その点は予め了解を得て置かなくてはならない。
 主著『靖献遺言』は、1684年から1687年にかけて書かれた。屈 原、諸葛 亮、陶 潜、
主著『靖献遺言』は、1684年から1687年にかけて書かれた。屈 原、諸葛 亮、陶 潜、