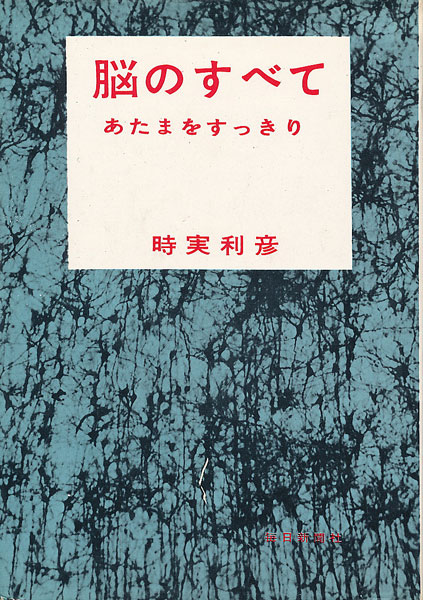
脳のすべて
あたまをすっきり
昭和37年6月5日 初版 昭和37年7月20日 再販 (毎日新聞社)。昭和40年2月3日購入
ウサギに悲恋なし P.111~114
やたらに人を殺したり、傷つけたりするテレビ番組は、子供に悪い影響を与える恐れがあると「暴力番組の追放」が、やかましく論じられたことがありましtヴぁ。
この場合、子供は子供でも、赤ちゃんのことは、ほとんど考えられなかったようでうです。しかし、赤ちゃんだって目はあり、テレビの映像は見えているのです。ただ「赤ん坊になんかわかりゃあしない」というだけでは困ります。
大脳皮質の「分業地図ができるまで」(一〇七ページ)で、運動を起こす場所=運動野と、「見える」とか「聞こえる」という感覚をつかさどる場所=感覚野は、全体からみると、それぞれ、ごく限られた部分であると申しあげました。いいかえxますと、残りの場所の方が広いのです。この一見、あき地のようにみえる場所が、実は人間を人間らしく、「万物の霊長」たらしめている――、つまり、人間ほど広大な?あき地をもって動物はないということです。
たとえば「見える」という感覚を感じる場所の周囲にあるあき地は、「それがなんであるか」内容の判断を下す働きをします。赤ちゃんは、このあき地の働きが発達していないから、内容の判断ができない。こういう"事情"をおとなたちは知りもせず、「わかるものか」とあっさり片づけているのでは……。
 運動野の場合はどうかといいますと、そのすぐ前のあき地で運動の命令計画書が作られます。運動をしようという意志が起こるのは、さらにその前にあるあき地です。これは前頭葉とよばれる部分の一部で、外側からいうと、おでこの上の部分。要するに、運動野は運動の命令をそれぞれの筋肉に伝える役割を果たしているだけ。ピアノでいえばキーに相当し、別のあき血の楽譜と、そのまた前のピアニストにあやつられているといえましょう。
運動野の場合はどうかといいますと、そのすぐ前のあき地で運動の命令計画書が作られます。運動をしようという意志が起こるのは、さらにその前にあるあき地です。これは前頭葉とよばれる部分の一部で、外側からいうと、おでこの上の部分。要するに、運動野は運動の命令をそれぞれの筋肉に伝える役割を果たしているだけ。ピアノでいえばキーに相当し、別のあき血の楽譜と、そのまた前のピアニストにあやつられているといえましょう。
前頭葉の先端から下の方にかけては感情の働きを起こす場所もあり、人間の前頭葉は非常に発達しています。もっとも、化石人類は発達していなかったとみえて、おでこが、そぎとられたようにひっこんでおり、この点では人間失格です。
こころみに、前頭葉が大脳皮質全体全体の面積のどれくらいを占めているか。いろいろ比較してみると
人間(現代人です)=三〇パーセント
イヌ=七パーセント
ウサギ=ニパーセント
喜びも、悲しみも、恋しさも、ねたみ、うらみも前頭葉で生まれます。してみると、ウサギには「喜びも悲しみも幾年月」というような生涯はないし、恋に破れて涙を流すこともありません。反対に、人間は「悲恋にむせぶ」こともある。前頭葉が発達しているおかげです。
前頭葉には意志や創造や感情をつかさどる場所もありますから、ここを切りとる手術を施すと、感情や意志の現われ方が弱まり、創造力が衰え、よくいえば、おとなっしくなり、悪くいえば、ボーッとしてしまいます。
耳の奥の方にあたる側頭葉が発達しているのも人間の特徴です。ここは記憶の働きをつかさどるあき地です。花をみて「赤い」「バラ」と判断を下せるのは、側頭葉に記憶があってこそ、記憶のないところに判断はありません。未開人にはバイオリンとピアノの音色に区別はつけられないでしょう。赤ちゃんがなんでも口へもってゆくのも同じことで、まだ、これは食べてはいけないとか、これは食べられないという記憶がないためです。
あたまのテッペンの頭頂葉のあき地は、ざらざら、すべすべ、あるいは丸い、四角い、青色、色あいなどを知覚し、判別するところです。
人間には広大な?あき地、前頭葉、側頭葉、頭頂葉で、動物にはみられない、知、情、意の高等な精神作用を営んでいると申せましょう。本能の心が古い皮質にやどるのにたいして、知、情、意の心はすべて新しい皮質にやどるものであり、人間はここで「想を練る」ことができるわけです。刺激をうけたからといって、いきなり行動に出るのは"動物的"、核実験の応酬にいとまのない人々の脳の働きぶりは、どう考えても"人間的"ではなさそうです。
2024.04.10 記す
人間の代名詞「口八丁手八丁 P.115~118
「手は外部の脳髄である」ドイツの大哲学者カントは、こういいました。それから、およそ百六十年、この言葉は、大脳生理学の面からみても、疑う余地のない名言であることがたしかめられてきました。
大脳の運動野、つまり、からだのさまざまな筋肉に運動の命令を送りだす脳細胞の集まっている場所は、わずかな場所ではありますけれども、近年、脳科学者ペンフィールィルドは、これをくわしく調べてみたのです。そして彼は、運動野のうちで、手、顔、口、舌への筋肉に命令を送りだす領域はききわだって広く、腰、胴体、肩などの大きな筋肉へ命令を送りだす領域はかえって狭いことをつきとめました。
手、顔、口、舌への運動の命令をだす領域が広ということは、とりもなおさず、これらの筋肉の運動には、たくさんな脳細胞が関係しているということです。したがって、非常にこまかく命令が下され、複雑な運動が行われるということにもなります。
早い話が、手の先、つまり手の指と、足の先、つまり足の指の運動を比べてください。本数は同じでも手の指の器用さは、足のそれとは比較になりません。足の指の運動は下駄をひっかけるとき、鼻緒をはさむのに役立つくらい。
顔にしてもそうです。われわれは、実にさまざまな表情を作ることができる。「無き笑い」などという、ややこしい表情まで、だが、命令を下す領域の狭い胴体やお尻の筋肉は、これほど繊細で機敏にはまいりません。見事なフラダンスを挑発的なツイストにしても、お尻の筋肉の一つ一つまでを、こまかく動かしてはいない。お尻に"複雑な表情"を求めるのは不可能です。
手を使い、表情を作る。このほかに、もう一つ、年限と動物を区別している大きな特徴に、しゃべることがあります。舌、唇などの筋肉がこまかく動かせるからこそ、われわれは複雑な言葉を使えるわけですが、ン隠元の三つの特徴は、そのまま大脳の運動野の"分業地図"にはっきりしめされていると申せましょう。
動物の場合は、区分のあり方が人間とはまったく違います。「サルも木から落ちるといいますがサルはなんといっても、木の上の王者です。そこで、サルの運動野はどうなっているかを調べてみると、足を動かす命令をだす場所が、手のそれと同じくらいあります。サルが木から木へ自由自在に飛び移り、めったにお落ちない秘密の一つは、手と足が同じように働く、」このようなからくりがあるためだといえるのです。
ブタ「といえば、だれでもすぐ鼻を連想します。これは当然で、ブタの運動野の大部分は、鼻の筋肉に命令をだす場所に占められているのですから、ゾウもまた同じたぐいです。
動物に比べてみれば、ことのほか弁舌さわやかで筆のたつ人でなくても、人間は「口八丁手八丁」に作られているというべきでしょう。いいかえれば「口八丁手八丁」とは人間の代名詞です。
とくに手が、われわれの生活のなかで、重要かつ欠くべからざる役割を果たして「いることは、想像以上。手相見が「手にはすべての運命が現われている」としているのはともかく、フランクリンが、人間を「ホモ・ファーベル」(道具を使う人)とよんだのも、手あってのことです。
たしかに、恋人同士が手をつなぐとき、手は交渉の器官となり、手まねでしゃべるときは表現の器官となり、鍬をにぎれば労働の器官ともなります。「手は外部の脳髄である」とは、よくぞ申しましたが、「手のうちをみせる」というのも、手としての密接な関係を物語ってあまりあります。
「手加減」「手なおし」「手しおにかける」「手をうつ」「上手下手」「お手本」「あの手、この手」「お手のもの」……と、手は人間生活ンおいたるところに結びついています。ときには手の指で人間そのものを代表させることがある。親指は主人、だんな――つまり男を意味し、小指を出して「これがね……」といえば、まず女性と決まっています。
2024.04.10 記す
きき手、きき脳 P.119~122
ヤンキースの強打者ロジャー・マリス外野手が、一九六一年に六十一本の本塁打を放ちながら、惜しくも先輩ベーブ・ルースの大記録を破れなかったことは、まだ記憶に新しいスポーツ界ンお話題です。偶然の一致でしょうが、この新旧二人の強打者は、そろいもそろって左打者、つまり左ききです。
一方、同じ年の日本選手権シリーズで、最高殊勲選手の栄冠を射止めた巨人の宮本敏雄選手は、ご存じのとおり右きき。このように、人には右ききもあれば、左ききもあり、きく方の手を、きき手とよんでいます。
ところで、ルースも、マリスも、宮本選手も、生れてしばらくは同じように両手使いだったはずです。右きき、左ききがはっきりしてくるのは、生後七ヵ月くらいからだからです。いいかえますと、このあたりから右ききになる人が圧倒的に多いわけです。そうでなく、いちどは左左ききのようになっても、のちに右ききに転向する人が少なくありません。プロ野球史上、最高の契約金で東映入りした"金の卵"尾崎行雄投手も小さいときは左投げだったそうです。
左ききは小、中学生で八ぱーセント、おとなで五パーセント、という統計がくらいで、転向組が百人のうち三人あり、おとなの右ききと左ききの比は九五対五。数的にみた場合、左ききはまったく劣勢ですが、これは、なにもいまにはじまったことではないようです。以下は史実に現われた右ききの優勢さ――。
七十万年前にいた人類のもっとも古い祖先アウストラロピテクスは右ききだった――有名な人類学者のダート教授は、こういっています。理由はアウストラロピテクスの骨が発掘された場所からは、同時にヒヒの骨も出ていますが、大部分が頭の骨の左側を打たれ、左の脳をこわされている。これはアウストラロピテクスが右ききで、右手に骨のような凶器?をもち、ヒヒの正面からなぐりつけ、殺していたことを物語っているというのです。現在でも、ご主人にぶたれて耳を痛めたと訴える婦人が、どちらの耳をやられているかといいますとほとんどが左の耳といっていいくらいです。
余談はさておき、つぎ、は一九六一年夏、東大西アジア古人類調査団が掘りあてた二十万年のネルアンデルタール人。彼らのいたところには右手向きの石器がたくさん出てきます。
話はぐっと下がってニー三万年前の後期石器時代、南フランスには、この時代に洞窟に描かれた壁画がたくさん残っていますが、壁に指をひろげて押しつけて、それに色素の粉をふりかけて描いたテのあとがみられます。右手と左手の数を比べてみますと、左手のあとがずっと多い。つまり、右手で粉をふりかけたというわけで、こっこでも右ききは圧倒的に多数です。
歴史はさらに浅くなり、エジプト時代の絵画。ここに見られる人物には、左手で物を持っているものが多いようですが、構図を考えての上だとされています。実際には、右ききが多かったに違いありません。ついでながら、チンパンジー、日本ザルにも左ききは少ないといわれています。
では、このように右ききが多いのはなぜか。この疑問に対する答は数多く、諸説フンプン。内臓が左にかたよっているので、バランスをとるために右を使うようになったとか、おなかの中にいるときから、右手の方が動くようになつているためだとか――しかし、どの説も決めテを欠いており、断定できません。比較的はっきりしているのは、左ききには遺伝的要素ががあることです。両親が左ききだと、その子は四六パーセントまで左ききだという調査があります。
さて、大脳の運動野は左右に分かれていて、どうしたことか、左側の運動野はからだの右半分の筋肉に命令を、右側の運動野は左半分の筋肉に命令を出すようにおなっています。したがって、右ききの人は左側の運動野が、左ききの人は右側の運動野が発達していると申せましょう。きおき手に対してきき脳があるというわけになります。
とかく左は右に比べて軽く扱われやすかったようで、昔は「左ききには精神異常者が多い」などといわれちゃほど。けれども、ただ、きき脳の位置が違うだけの「ことです。早い話が、ミケランジェロ、ダビンチ、左甚五郎、梅原龍三郎……と左ききにも偉人、大家は少なくありません。
左ききのお子さんをおもちのおかあさんの中には、強引に右ききになおそうと苦労されている方をみうけますが、むだな努力です。
2024.04.10 記す
人間はオートメの権化 P.123~126
寺田寅彦博士の随筆に
「百足の足を驚嘆しながら万年筆を操ってこんなことを書くという驚くべき動作を何の気もなくて遂
行している」
こんな一節があります。
※参考:随筆「藤棚の陰から」:青空文庫に登録されている。(黒崎記)
たしかにむかでは、よくもまあ、あれほどたくさんの足を整然と動かせるものだと感心させられますが、人間の運動のからくりも複雑にして精巧。たとえ一挙手一投足といったような簡単な動作でも、実際は非常に微妙な仕組みにあやつられているのです。ただ、われわれが意識していないだけのことです。
さて、コーヒー茶わんを手にとってコーヒーを飲むとき、ペンをもってものを書くとき、間違いなく動作を進めるのに、目が役立っていることはたしかです。しかし、目の助けはなくても動作はできる。目のみえない人を見てごらんなさい。普通の人でもよろしい。われわれは、暗やみのなかでさまざまな動作を行なっているではありませんか。鼻の先をかくことも、恋人の手をそっとにぎることも……。
 ところが、脊髄や小脳の病気にかかると、動作はすこぶるぎこちなくなり、目を閉じると「鼻の先をつまんで」といわれても、耳をつかんでしまったり、額をおさえたり……なかなかうまくゆかないものです。
ところが、脊髄や小脳の病気にかかると、動作はすこぶるぎこちなくなり、目を閉じると「鼻の先をつまんで」といわれても、耳をつかんでしまったり、額をおさえたり……なかなかうまくゆかないものです。
われわれが思いどおり運動できる秘密は、脊髄や小脳にあると考えられます。事実、多くの実験によって、脳からの運動の命令だけでhあなく、それによって運動する筋肉から、その瞬間の動き、状態を刻一刻、脊髄を通して脳へ知らせてくる"情報"がたしかでないと、運動は確実にゆかないことがたしかめられました。
この"情報"を筋肉から発するのは筋紡錘という、長さ一ーニみりの感覚器です。筋内のなかに、散らばってうずもれている筋紡錘は、あらゆる運動を的確に行わせるカギをにぎっているといえましょう。小ツブでも役割は大きい。だが、よくしたもので、必要のないところには、たくさんはありません。たとえば、声帯の筋肉にはきわめて少ないのです。この場合は、声の高さ、大きさを、耳がコントロールできるからです。したがって、耳からあやしくなってくると、とんでもない調子のずれた大きな声を出したりすることになってしまいます。
オートメーションには、いま機械がどのように動いているかという"返り情報"が、絶対に必要です。ただ命令を出し放しにおけばすむというものではありません。してみると、人間のからだは立派なオートメーションを備えているわけです。機械のオートメーションなど比べものにならないほど、すぐれたそれをもっています。
人体にはオートメの備えがあるから、われわれは手をあげようとするとき、脳でそういう意志を起こしさえすればいいのです。そうでなかったら、手をあげるためには肩、脳の筋肉を、ときには胴体、腰、脚の筋肉まで、いちいち働かせなければならない。考えただけでもゾッとします。
この際、脳へ返ってくる"情報"が、欠くことのできないものであることは、まことに意味深いと思いになりませんか。こんな"情報"は、われわれの意識にほとんどのぼらない、いわば"声なき声"ですが、無視すれば、運動失調を招きます。
民主主義もも同じ。口にとなえるだけではなく、それに対する下々の声、国民の願いに耳をかさなければ、政治失調は避けられないでしょう。人の上に立つ人々」は、人体のからくりそのものを、もう少し見習ったら、いかがものか。きっと教えられるところ大なるものがあるはずです。
20204.04.10 記す
ネコは落ちても P.127~130
ご存じのとおり、ヒザをポンとたたくと、あげまいとしても止まるものではなく、足の先はピョコンとハネあがってします。われわれのからだには、こういうように意識に関係なく運動や働きを行なう仕組みがそなわっていて、反射とよばれています。
すっぱい梅干しを口にいれると、ツバがやたらにでてくるのも反射なら、熱くやけたものにちょっとでも触れると、さっと手をひくのも反射、この際、熱くやけたものから、どのくらいの速さで何センチ手をはなせばヤケドはしないかときった計算ずくでやってはいません。手は脳の命令によって動いているわけではないのです。
ネコを飼っておられる方、ひとつ、ネコを逆さまにして落としてみてください。ネコは決してあたまから逆さまに転落はしません。空中できれいに立ち直って地面へヒラリ。もちろんネコは頭で考えながら、回転しているわけではなく、いくつかの反射が結びついて演出された動作なのです。
反射波無意識に行われていると申しましても、なにか反射をおこす原動力がなくてはだめ。その原動力は――
▽足がピョコンとあがる反射――筋紡錘からの信号
▽ツバがでる反射――味の感覚器からの信号
▽熱くやけたものから手をひく反射――皮膚の温度や痛みの感覚器からの信号
▽ネコが回転して立ち直る反射――迷路や筋紡錘からの信号
しかも、反射の原動力になる信号は、大脳皮質までゆかないで、脊髄や脳幹部や小脳で、すぐさま運動神経や分泌神経に伝わって、筋肉や睡液腺を働かすわけ。これが反射のからくりです。
「人間はオートメの権化」(一二三ページ)で、手足を動かす場合の筋紡錘の信号は、運動の調節のための"情報"の役目をしていると申しましたが、反射では、むしろ運動の原動力という大役を受けもっているのです。しかも、われわれはそれを意識していませんから、まさに"縁の下の力もち"です。
身近な例をあげましょう。
人間は二本の足で立ち、歩いています。立っているということは、胴や足の百くらいの筋肉がからだをさえるために働いているということ。しかし、どの筋肉をどれだけ緊張さす、なんて考えていません。事実は、脳からの"立っておれ"という命令はほんのわずかで、あとは筋紡錘からでる信号の"縁の下の力もち"と調節のしくみでコトたりているのです。
歩く場合も反射は欠かせません。いつも「右足を進めたから、こんどは左足を前へ」なんて考えていたら、たまったものではありません。
してみると、反射の威力は絶大、実際に、筋紡錘からの信号が脊髄にはいる通路を断ち切ってしまうと、筋肉に故障はなくても、腰抜けのイヌやネコが出現します。
もし、こういうからくりがうまくいかなくなると、脳からひっきりなしに命令を出さねばならず、脳はたちまちクタクタになります。まず一時間とは立っていられませんし、ものの十分間とは歩けないでしょう。
ところで、筋紡錘は筋肉より疲れやすく、早く働きが弱まってくるものです。こうなると、さきにも述べたように、脳からくどく命令をださなければ、前と同じような運動はできなくなります。
脳からの命令が続く状態を、われわれは「疲れた」というのですから、「疲労感」とは「脳の努力感」だといってさしつかえないでしょう。早い話が、「足が重くなった」といっても、目方まで目にみえてふえるようなことはありません。足の筋肉そのものの疲れより、問題は脳が疲れを感じていることですし、その前に筋紡錘の疲れと反射の衰えがあるのです。
運動の選手やトレーナーは「筋肉の疲れ」や、栄養、あるいは心臓の強さばかりを考慮しているようですが、「筋肉の疲れ」とは、まず、「筋紡錘の疲れ」であり、それが脳の働きに結びついていることを考えてのことでしょうか。
2024.04.11 記す
モナ・リザの微笑を解く P.131~134
電車やバスのなかで広告をながめながら、いつも感じていることですが、子供の笑顔と女優さんの笑顔とでは、同じように笑っていても、どこかに違ったところがあるような気がしてなりません。みなさんはいかがでしょうか。
いつてみれば、子供の笑顔にある「あどけなさ」が、ハイティーンの笑顔には、もう見られませんし、商売で笑っている女優さんのそれには「そらぞらしさ」が目だつばかりです。笑いだけではなく、たくさんの小さな筋肉が伸び縮みしてできる顔の表情そのものにも、こういう違いははっきりしています。
赤ちゃんの天真らんまんな表情をおとなに求めるのは無理な注文のようです。なぜ無理なのか。この疑問に答えるには、やはり大脳の二重構造と、それぞれの働きを説かなければなりません。
われわれの筋肉を運動させる命令は大脳皮質、つまり新しい皮質の運動野から出ていますし運動野は左右に分かれ、左からはからだの右の部分の筋肉に、右からは左の部分の筋肉へ命令をだすようにできている――すでに「きき手、きき脳」(一一九ページ)で申し上げたとおりです。
 この新しい皮質は同時に、理性や知性など複雑な心のやどるところであり、赤ちゃんのころは発達していないが、十代末期ともなれば、ほぼ完成します。
この新しい皮質は同時に、理性や知性など複雑な心のやどるところであり、赤ちゃんのころは発達していないが、十代末期ともなれば、ほぼ完成します。
そこで大人は「なに食わぬ顔」をしたり「虫も殺さぬ顔」が作れる。しかも、運動野は左右がたがいに独立して働くので、「色っぽいウインク」も可能なら、「ゆがんだ笑い」もできるわけです。おとなの表情はたしかに複雑ですが、それだけに人工的であり、真の心はうかがいにくいものです。顔色ひとつで、乙女心の底に秘めた燃ゆる思いを看破するのは、親といえども必ずしも容易でないのをみればわかりましょう。
赤ちゃんは違う。おかあさんたちは、ちょっとした表情から、オシメのぬれたことを読みとれます。赤ちゃんは、新しい皮質が発達していないから、筋肉を動かし、表情を作る場合、本能の心がやどる古い皮質にある運動を起こす場所からの命令だけによっています。
赤ちゃんの表情はつねに「腹のうち」を出していると申せましょう。ここにわれわれは天真まんらんさを感じるのです。しかも、古い皮質にある運動を起こす場所は、からだの左右両側に対して、大まかだが、同時に命令をくだすようになっています。したがって、赤ちゃんはウインクはできないけれども、その笑い、その表情には、いつも美しい左右の対称性があります。
「目は口ほどにものをいい」という諺があります。たしかに目もとには表情が現れる。「理知的な目」というくらいですからね。
では、口もとはどうでしょう。高村幸太郎氏は「清正のひげはここに楽にはえ、長兵衛の決意はここでぐっときまり、鷺娘の超現実性もここからほのぼのとたちのぼる」と、口のあたりの表現が大切だと書き残していますし、アメリカの心理学者で、本能に結びついた心は、目もとより口もとによくみられることを研究した人もあります。なるほど「理知的な口」とは申しません。思う存分に楽しもうという夜会では、口もとをかくします。互いに理知の現われるところをおおうのですから、効果はあるはず。
笑いにしても、目もとには新しい皮質にやどるやどる理知的な笑いがでてくるし、口もとには古い皮質にやどる本能的、いいかえれば情的な笑いがでてくるのです。
ダビンチの「モナ・リザ」が傑作だといわれるのは、二つの笑いを巧みに描きだしているからではないでしょうか。とくに目もとの笑いがモデルの内省的な理知をうつしだしているところに「謎の微笑」とよばれる秘密があるようです。
2024.03.31 記す
言葉によってのみ…… P.134~137
「吾輩は猫である。まだ名前はない。……」で、はじまる漱石の名作「吾輩は猫である」に限らず、動物自身がしゃべる形式の小説は少なくありません。だからといって、実際に動物が言葉をもち、しゃべれると思う方はいないでしょう。
日本モンキーセンターの伊谷純一郎氏によると、ニホンザルには言葉があり、ヒソヒソばなしをすることがあるそうですが、その数はわずか二、三にすぎないといいますから、まったくの例外です。
動物は、ほえ、うなり、さえずる……いうなれば声をもっているだけです。これらの声は、すべて、生きること、子孫を残すために役立っています。たとえば、春先ともなれば、きまって、われわれを悩ます。あのネコの奇妙なうなり声――。
人間だって、ときには「うーむ」とうなることはありますが、人間は、ただの声のほかに、生れてから言葉を学び、これをあやつることができます。ウイルヘルム・フォン・フンボルトという有名な言語学者は「人間はただ言葉によってのみ人間である」といって、動物と区別したくらいです。
また、こんなこともいわれています。「言葉は思考の本性を直接、表したものである」(マルクス)、「思考は言語によって自己を形成しなが言語を形成してゆく」(ドラクロア)。ちょっとむずかしそうに聞こえますが「ものを考えられるのは言葉あってのこと」くらいの意味だと思ってください。要するに、言葉はこころの状態を表現したもので、その仕組みはやはり脳の働きにつながっています。
わたしは、NHKの「ことばの誕生」という番組に関係し、昭和三十六年の十月から、赤ちゃんがどのように、言葉を理解し、覚え、しゃべってゆくかを、数人の先生方と研究しています。タレントははじめ零歳4.この子たちが五歳になるまで観察を続けてみようというのです。こんな気長な試みをあえてしようというのも、言葉をしゃべれるようになってゆく過程に、たしかめられていないことが多いからです。もっとも、女の子の方が男の子より早くしゃべりだすことや、口数が多いことは間違いないようです。センダンはふた葉よりなんとやら……。
また、言葉を理解する能力が、しゃべる能力より早く備わることは、脳の発達ぐあいから説明できます。
大脳には筋肉に運動の命令をだす運動野があるように、声と言葉の働きをつかさどる脳細胞の集まり、つまり言語野があります。
言語野は側頭葉の上のほうにあって、言葉を理解する場所と、前頭葉に「あって直接しゃべること=口の筋肉の運動=を支配している場所に分かれていますが、前頭葉の発達は側頭葉よりおそい。これが、理解はできても、しゃべれない時期のある理由です。
近年になって、カナダの脳外科学者ペンフィールドは、前頭葉にもうひとつ、しゃべることをコントロールしている言語野をさぐりあてました。しめて三つの言語野は全部、脳の左半球にあります。したがって、脳の一部がこわれても、左半球さえ無事なら、言葉に支障は起こりません。狂犬病のワクチンを発見するなど輝かしい業績を残したルイ・パストゥールは、中年のころ、脳出血になり右半球をやんで左半身不随になりましたが、言葉には不自由せず、立派に研究も発表も続けていました。
では、運動にみられる「きき手、きき脳」(一一九ページ)ということが、言葉にはまったくないかというと、さにあらず。
左半球の言語野に対応する右半球の一部には、同じような能力が秘められており、左半球の言語野がこわれて失語症になると、ピンチ・ヒッターとして働きだします。ただし、完全にこんなことが望めるのはニ、三歳まで、それにしても不思議な仕組みではありませんか。
2024.04.11 記す
目から火が出る P.138~140
「目から火が出た」ということを申します。暗やみで柱におでこをぶつけたり、剣道でお面をこっぴどくたたかれたりしたとき――多かれ少なかれ、だれでも経験しておいででしょうが、なぜ火のないところに煙ならぬ火が出るのか、ご存じですか。
これにはちゃんと、それだけの理由があるのです。見る、聞く、かぐ、甘い、塩からい、痛い、温かい、冷たい……どんな感覚でも、それが起こるまでには、最初に感覚器が刺激を受けいれ、そこから信号が感覚神経を伝わって、大脳皮質の感覚野へ送り込まれるという段取りが普通で、感覚そのものは終着駅も大脳で起こるものです。
平たくいえば、「脳細胞が感じる」わけですが、目の網膜にある感覚器は光のエネルギーを受けいれて働き、耳の内耳にある感覚器は音のエネルギーを受けいれて働くといったように、それぞれが自分に適した刺激を受けいれる性質をもっています。
と同時に、すべての感覚器はあらゆる刺激を受けいれる性質を兼ね備えています。なんだか矛盾するようですが、自分に適した刺激にはきわめて敏感で、そうでない刺激には鈍感だということなのです。「鈍感である」の裏返しは「きわめて強い刺激なら受けいれる」ということです。
たとえば、目の感覚にとって、頭をしたたかなぐられることは強い刺激であり、当然、働きを起こし視神経経由で信号を大脳へ送り込む――「目から火が出る」つまり、光を感じるのは、こんなからくりがあるからです。
鼻にひどいパンチをくらって、一瞬、火薬の燃えたようなにおいを感じたことはありませんか。相手のゲンコツににおいがあるわけでもないのに、これもまた「目から火」と同じこと。鼻の中にあるにおいの感覚器が強い刺激をうけて働いたためです。
熱いお湯に手を突っ込んだ瞬間「冷たい」と感じるのもそうです。「冷たい」とまで思わなくても、お風呂にはいろうとして、かなり手を深く突っ込んでしまってから、あるいは一回からだごと飛びこんであいまってから「あっちっち……」と、あわてたような覚えならあるでしょう。

皮膚には、冷たさを受けいれる感覚器と、温かさを受けいれる感覚器がありますが、冷たさの方は表面近くに、温かさの方はずっと奥にあるので、熱いお湯につかると、熱さという強い刺激によって、冷たさを受ける感覚器の方が一瞬早く働くわけです。もちろん、温かさの方もついで働きだし、温度が非常に高い場合、痛みの感覚器も同時に働いて、はじめて"熱さ"を感じます。"熱さ"だけを受けいれる感覚器はありません。なんと、このむだのなさ!
ところで、感覚は感覚器ー感覚神経ー大脳皮質の感覚野という「感覚路線」のうち、どの「部分」を刺激しても起こるものです。たとえば、視覚の感覚神経(視神経)に電流をあてれば、目の前が明るくなったような気がします。
この際、感覚は脳細胞は脳細胞で起こっているのに、実際はすべて"眼の前"に感じます。まさか「脳の中が明るくなった」という人はないでしょう。感覚のこのような特徴を「投射」といいます。
一例をあげると「まぼろしのの手」
戦争や事故で手をなくした人が、ないはずの指の先に痛みを感じるとか、ものがさわったようだと訴えるのがそれです。切断された傷跡になにかあって、感覚神経から刺激が大脳へ伝わってゆき、そこで感覚を起こし、かつて感覚神経を起こし、かつて感覚神経や感覚器が分布していたところに「投射」して、あたかもそこに刺激が加わっているように感じている――不思議といえば不思議ですが、感覚とはこういものだとわかれば、納得していただけましょう。
2024.04.18 記す。
聞く稲妻、目から雷鳴 P.141~144
光でも、音でも、見え、聞こえするまでは、それを感覚器が刺激として受けいれ、信号を感覚神経経由で大脳皮質の感覚野に送りこむという段取りがあるわけですが、感覚神経はどうやって信号を伝えているでしょうか。
そのむかし、哲学者デカルトはこんなふうに考えていました。光の感覚は、目の中にはいった光が、視神経の管のなかに張っている細い糸によって脳に達すると起こり、音は聴神経のなかの糸が音波を脳へ運ぶから聞こえるというのです。外界の温度もそのまま脳へ……。つまり感覚器は、はいってくる刺激をそのまま受けいれて、感覚はそのままそっくり脳へ運んでいることになります。いまでは、まったくのお笑いですが、このような考え方は、二十世紀にはいってもまだ大手を振ってまかり通っていたものです。
感覚神経の研究が急速に進んできたのは、きわめて最近のこと。どの感覚神経も同じ神経線維の束であり、構造も働き方も変わらないことがわかりました。
感覚器が刺激を受けいれて働くと、それにつながっている感覚神経に電気的な変化が伝わってゆきます。「シビレエイは物語る」(九六ページ)で申しましたように、細胞が働けば電気が起こる――ここでは感覚器の感覚細胞が働いているわけですが、伝わってくる電気的変化=信号と考えていいでしょう。

ところで、この信号は「ツートン、ツートン」というパルス信号のような性質をもっています。普通、話をする場合、電話線に流れている電流は、つながった波形ですが、感覚神経では、一定の間隔をおいてくり返し送られるもので、電気計算機にも利用されている能率的で、乱れにくいパルス信号方式、それが人間のからだにも、ちゃんとそなわっているのです。
どんな感覚器につながっている感覚神経も、管なんていうものはなく、パルス信号を伝えているにすぎない、ただの電線みたいなものです。そのうえ、どの感覚神経も同じようなパルスをつたえています。
もし、視神経と聴神経を切り離して、視神経を耳の感覚器に、聴神経を目の感覚につないだら、目にはいった光の刺激は、聴神経を通って大脳の音を感ずる聴覚野へ、耳にはいった音の刺激は、視神経を通って光を感ずる視覚野へ到達することになります。
この際、感覚野の方は信号を受けると、どこからこようとおかまいなしに、その場所にもっている感覚を起こしますから、ことはややこしくなってきます。話を具体的にしましょう。われわれは、ピカッとする稲妻を聞き、ゴロゴロという雷鳴を見るということです。
では信号の伝わる速さはどうか。もちろん、限りがありますし、これだけは感覚神経の太さによって違います。太いほど速く、一秒に百メートルくらい、細くなるとぐっと落ちて一、ニメートル。目、耳などの感覚器につながっている感覚神経は太く、痛み、温度、内臓などの感覚器につながっているそれは細い。ただし、痛みの神経は、細いなかにも太い、細いがあります。いきなりピリッとくる痛みと、あとからジーンとくる痛みがあるのは、このためだと申せましょう。
太い神経ほど信号を速く伝える事実を知ってしまうと、「図太い神経の持ち主だ」というのは、ちょっと気にかかる表現です。まして、太いからこそ、こまかく見わけ、聞きわけることができるのですから――。
例を視神経にとりますと、神経線維本数は約百万本。こんなに神経が多いから、さまざまなものの形を見わけ、いろいろな色をしることができます。神経線維が少なくなったら、美しい七色の虹も、色あせて天のカケ橋にすぎなくなってしまうかもしれません。
2024.04.19 記す
痛みと人生 P.145~147
「ポカッ」となぐられると、だれだって痛い。皮膚にある痛みの感覚器が働いて信号を脳へ送り込むからです。ところで、痛みの感覚器にはほかの感覚器にみられない特徴があります。
第一に、皮膚はもちろん粘膜や筋肉、内臓の各器官など、からだのあらゆる部分に分布していること、だから、間違って舌をかむと痛いし、食中毒を起こすとおなかが痛む。
第二に、構造が簡単なせいか、目の感覚器が光に対して、鼻の感覚器がにおいに対していったうように、特定の刺激にだけ敏感だということはなく、あらゆる刺激に対して門戸を開放していることです。ただし、刺激がある程度まで強くないと受けいれません。どんなに弱い刺激でも受けいれるとしたら、光を見ても、音を聞いても、においをかいでも、必ず痛みが伴うわけで、人生は苦痛の連続、たまったものではありません。
どなたも、もうお気づきだと思いますが、問題は「ある程度」とは、どのくらいの刺激なのかという点です。
ここで熱いお湯があるとしましょう、温度が四十五度くらいまでなら、あなたは手をつけていられるはずですが、五十度を越えるともうだめ。とても長くはつけてはいられません。温かさを受けいれる感覚器と、痛みを受けいれる感覚器が同時に働きだして、"熱さ"を感じるからです。ヤセがまんして、つけ続けてごらんなさい、熱さより痛さを強く感じるようになり、果てはやけどです。
 強い音を聞く場合はどうでしょうか。ジェット機が目の前から飛び立つ瞬間、「耳をつんざくような音」に、思わず耳をおおった経験はありませんか。これ以上の音=刺激=は鼓膜や耳のなかの感覚器を破壊しかねないと、鼓膜にある痛みの感覚器が働きだして、われわれに痛みを感じさせ、耳をおおわせるといったぐあいです。
強い音を聞く場合はどうでしょうか。ジェット機が目の前から飛び立つ瞬間、「耳をつんざくような音」に、思わず耳をおおった経験はありませんか。これ以上の音=刺激=は鼓膜や耳のなかの感覚器を破壊しかねないと、鼓膜にある痛みの感覚器が働きだして、われわれに痛みを感じさせ、耳をおおわせるといったぐあいです。
いつぞやテレビを見ていたら、乙羽信子さんが、黒いメガネをかけて出演していました。撮影のとき、強く、明るいライトを目にうけたのが原因だそうです。仕事となれば、少々、明るすぎて痛くても、目を閉じてしまうわけにはいかず、角膜を傷つけてしまったのでしょうが、痛みにあえて抵抗するのは間違いのもとです。
痛みの感覚器は、もしも刺激の強さがわれわれのからだを傷つけ、生命に危害を与える恐れがあると必ず働いて、痛みという危険信号をだしてくれるのです。
痛みとは、「いやな感じ」ですし、もちろん、あって喜ばしいものではありませんが、全然なかったらどうか。たとえば、われわれはおなかが痛いと、薬を飲み、医者にかかり、健康を保つことができます。痛みの感覚がなかったら人生まともには過ごせない――決して大げさではありません。痛みの感覚器は人体防衛の重要なトリデと申せましょう。
それが、かけがえのない器官になるほど多く備わっているのも、よくしたものです。たとえば、とってみると、「なんだ、こんなに小さいゴミか」と思うほど小さいゴミでも、目に飛び込んだときの痛みは格別です。だいたい、口のまわりとか舌など、さわって感じのいいところは痛みも敏感で、指の先も敏感なところで、ヒョウソの手術など受けると気を失ってしまう人があるくらいです。
一方、お尻や背中、腕などには痛みの感覚器は少ない。ですから注射はおもにこういうところにするわけでです。尻切り魔が捕えにくいのも、痛みの感覚がにぶく、切られたときすぐに気がつきにくいためではないでしょうか。
2024.04.18 記す
火も涼しいことがある P.148~150
肌を刺すように冷たい風が吹きだす季節がくると、わたしは「よくも女性は、あの薄いナイロンのストッキングだけで我慢できるものだ」と感心させられます。
こんなことをいうと、「なに、女はにぶいからさ」と、反論される方がありそうですが、皮膚にある温度の感覚器は、男のも、女のも同じ仕組みであり、同じ感度をもっています。また、女性の皮下脂肪が寒さを感じさせないほど厚いわけでもありません。「女はにぶい」とは失礼ないい分です。
では、なにが、女性をして薄い靴下一枚で寒さに耐えさせているのでしょうか。答えは、それほど複雑ではありません。「なによりもスタイル第一」という女性自身がもっている強い意志です。意志の力はたくましい。冷たいとい感覚をぐっと抑えてしまうのですから。
男性だって、温度の感覚は意志の力や、気の持ち方によって、ある程度までコントロールできます。必ずしも女性だけの特性ではないのです。寒中、滝にうたれる行者、あるいは寒中水泳の参加者たち、いずれも気の持ち方で、冷たい感覚を感じなくさせている例です。
天正年間のこと、織田勢のため焼き打ちにされた甲斐の慧林寺の禅僧快川が「心頭を滅却すれば火もまた涼し」という名文句を口に唱えながら、火の中に飛びこんでいったのは有名な話です。燃えさかる火まで涼しく感じるとは、まことに偉大な意志の力というべきでしょう。ここまで徹し切れる人はザラにはありますまい。
 痛みの感覚も、気の持ち方で非常に変って来ます。同じ太さ、同じ量の注射でも、人によってバカに痛がるかと思うと、人によって平気な顔をしていることがあるのはこのためです。ソ連であみだされた無痛分娩も同じ原理で、暗示と説得によって痛いと思わないわけです。「痛いのは痛いんだ」――たしかにそうです。しかし「痛いと思うから痛いんだ」――これにも一理あることがおわかりいただけたと思います。
痛みの感覚も、気の持ち方で非常に変って来ます。同じ太さ、同じ量の注射でも、人によってバカに痛がるかと思うと、人によって平気な顔をしていることがあるのはこのためです。ソ連であみだされた無痛分娩も同じ原理で、暗示と説得によって痛いと思わないわけです。「痛いのは痛いんだ」――たしかにそうです。しかし「痛いと思うから痛いんだ」――これにも一理あることがおわかりいただけたと思います。
話が少々理屈っぽくなりましたが、温度や痛みの感覚は、人それぞれの気の持ち方によって、感じ方が大幅に変ってくるだけに、面倒なことも少なくありません。
大衆浴場でよく起こる「水をうめろ」「うめるな」といういさかいなどは典型的なもので、温度の感覚の仕組みが変わらぬ限り、絶えることはなさそうです。といって、法律でズバリ何度とも決めにくい。いまは衛生的な見地から、何度以上という条例が設けられているようですが――。
われわれの皮膚には、温度の感覚、痛みの感覚のほかに、触覚と圧覚が備わっています。触覚や圧覚は情感をそそりやすい。だからモチハダは"いい感じ"だとされているのです。しかし、温度の感覚はそれ以上に、あるときは煽情的であり、あるときは抑情的です。いくらモチハダがいいといっても、冷たくてはだめで、やはり血がかよっていてこそ情感も起ころうというもの。「氷のように冷たい人」「心あたたまる……」「情熱家、冷血漢」すべて、情の動きに結びついた温度の感覚の特徴を物語っています。
痛みの方は、「胸の痛みに耐えかねて……」というくらい。なにも胸の病気ではありません。つらい、苦しい心情を痛みとと結びつけた表現です。これも情の動きと密接につながっている証拠です。
といったように、温度や痛みの感覚は気分によってコントロールされる特徴をもっていると同時に、気分を左右するすることも大きいという特徴をもっていると申せましょう。
2024.04.19 記す
学校の椅子はなぜ堅い P.151~154
――教室の椅子はなぜ堅いのでしょうか。もう少し楽な椅子にしてもらいたいと思います。
「とんでもない。これは意識の水準を高め、頭をはっきりさせるためです。暖かい思いやりがこもっているものですから、少々お尻が痛いくらいで不服をいうのはおやめなさい」
――すると、お役所などで、えらい人ほど楽な椅子を使っているのはどういことになりますか。
「たしかに、あまり楽な椅子は感心できません。お役所に限らず、仕事の場にソファーなどはもってのほか。即刻、追放といきたいものです」
――おえら方の頭をポ~ッとさせちゃうというねらいかもしれませんね。
「そうだとしたら巧妙なテですが……」
クッションのよい椅子に深々と腰かけて、ふんぞり返っている方々は、そのために、頭の活動がにぶりがちだと思ってもいないでしょうが、筋肉をだらけさせると、意識は明らかに低下します。
わたしの友人のひとりが興味ある体験談をしてくれました。
「徹夜の団体交渉に勝つ秘訣は、決してよい椅子を使わず、相手側と同じ堅い椅子にすることだ」
彼はもちろん使用者側ですが、知らず知らずのうちに、意識をささえるからくりにかなった秘訣を身につけていたのです。
ところで、この問題を正確に理解していただくには、まず意識とはどんなものかを知っていただかなければなりません。
ドイツのある内科の先生は「右の目が見え、左の耳が聞こえるだけで、あとはまったくきかない十七歳の前から、光をなくし、左の目をふさいでみたところ、すやすや眠りだした。――しかし光をあて、音を聞かせたら目ざめた」と報告しています――当然のことというなかれ。
こういうなんでもないような観察がてがかりに、学者たちは得体の知れぬ意識の正体にメスを入れていったのです。一九四九年、アメリカのカリフォルニア大学教授で脳生理学界の第一人者である私の恩師、マグーン先生は、延髄の近くの脳幹部にあり、神経が網の目のようにかみあっているだけで、さっぱり働きのわからなかった網様体をこわすと昏睡状態に陥り、刺激すると目がさめ、さらに意識が高まることをつきとめて、意識の水準を左右する源はここにあることを明らかにしました。意識の正体に、はじめて直接ふれた画期的な実験です。近代脳生理学は、この実験からスタートしたといっても過言ではありません。
※参考:マグンに関するきじについては、時実利彦著「脳の話」P.194を参考に(黒崎記)
感覚器から出た信号は、脳幹部の感覚神経を通って大脳皮質の感覚野にとどき、感覚が起こることは前に申しました。
「ところで、感覚神経は脳幹部で網様体にも枝を出しているので、信号の一部は網様体へ流れこむ。ここで新しい信号が作られて大脳皮質全体へ。網様体経由の新しい信号は、すべての脳細胞の働きを高める役割をもっている」――これがマグーン先生のたどりついた結論です。意識をはっきりさせ、頭をさえさすには"感覚信号を絶え間なく網様体を通して、大脳皮質へどしどし送りこむべし"ということがおわかりでしょう。
もっとも、いくらはいってくる信号が多いほどよいといっても、痛みの感覚信号や、ひどい音の信号であっては、気になって、頭は明せきになるどころではありません。
われわれは気づいていないけれども、網様体の活動を盛んにして、意識をはっきりさせてくれる理想的な信号は、筋肉のなかにうずもれている筋紡錘という小さな感覚器からの信号です。筋紡錘は筋肉が運動したり、緊張したり、強くひっぱられたとき、じゃんじゃん信号を出す性質もっています。
堅い椅子には、ゆったりとは寄りかかれない。どうしてもキチンと姿勢を正すことになり、頸と背中の筋肉はつっぱる。そこで信号がたくさんでる――学校の椅子はやはり堅い必要があるのです。
2024.04.19 記す
アクビ礼賛 P.155~157
近ごろあまり使われなくなりましたが、逍遥という言葉があります。ぶらぶら歩くことです。ギリシャの哲学者アリストテレスは、並木道を歩きながら弟子たちに講義したそうで、この学派には逍遥学派という、またの名がつけられました。
歩くときは足の筋肉が働いていますので、そのなかにある感覚器の筋紡錘からは、しきりに信号が出て大脳へ。「学校の椅子はなぜ堅い」(一五一ページ)で申したとおり、大脳は感覚器から網様体経由でくる信号が多いほどよく働き、意識は高まって、頭ははっきりするようにできています。アリストテレスは合理的な教授法をとっていたわけです。さすがは大哲学者――。
そういえば、なくなったノーベル賞作家ヘミングウェイは、小説を書くとき――おそらくタイプをうっていたのでしょうが――立ったままで、決して腰かけなかったということです。人が立っているときは、意識にはのぼらないけれども、百くらいの筋肉が働いていますから腰かけて筋肉をだらっとさせているときより、頭はずっとさえているはずです。「気をつけ」と"不動の姿勢"をとらせての訓辞は、"休めの姿勢"で聞かすより効果的なのです。
疲れて電車に乗っても、立ったままではなかなか眠れない。それが腰かけると眠ってしまうのも、同じような理由によるものです。では、腰かけるのとすわるのとは、どちらが頭の働きをよくするかというと、ふとモモの緊張がより強くひき伸ばされるよううになるすわる方でしょう。なぜなら、これも「学校の椅子はなぜ堅い」で申しましたとおり、筋紡錘からの信号は筋肉がひき伸ばされたときにも、しきりに出ているものだからです。
頭の働きに活を入れようと思ったら、筋肉をひき伸ばせ! われわれは無意識に、このスローガンを実行しています。俳人高浜虚子先生は"五十ばかりあくびをすると一句が浮かぶ"という特技をおもちになっていたそうです。
あくびが咬筋といって、上あごと下あごの間に張っており、ものをかむのに必要な筋肉を強くひき伸ばすものであることを思えば、もっともなお話。
あくびは血液のなかの炭酸ガスを追い出すための深呼吸だ――と説いている書物が圧倒的ですが、「あくびは頭をはっきりさせるための運動のひとつだ」といい改めるべきではないでしょうか。虚子先生のあくびは、いささか桁はずれで、納得がいかないという方にも、わかっていただけるような例をあげます。
いままで眠っていたネコが目をさまして、行動を起こそうという間際には、きまってあくびをし、ついでに背伸びしています。われわれも、これから起き出そうという際には、伸びをしたり、あくびをする――ともに筋肉を伸ばすことによって、頭をはっきりさせる効果があることは、ご承知のとおりです。
退屈な講演や授業を聞かされると、あくびが出そうになるものです。このあくびが、頭をはっきりさせて、なんとか目をさましていようという、無意識の努力の現われだとしたら、ただ「お行儀が悪い」としかりつけたり、腹をたてたりはできなくなります。
あくびは自然の覚醒剤。したいときにはいつでも堂々とやりたいものです。エチケットに反することになるのは、いかにも残念ですが。
ついでながら、咬筋の収縮を繰り返しても、同じような効果がありますので、ガムをかむのは結構なこと。アメリカの野球選手は例外なくガムをかみながらプレーしています。わたしなども、小学生のころは、よく煎豆をかじりながら勉強したものです。
2024.04.19 記す
心ここにあらざれば…… P.158~161
古代ギリシャの科学者アルキメデスは、シシリア島のシュラクサイをローマ軍の攻撃から守り抜こうと、防備施設の測量や計算に夢中になっていたため、敵が近づいてきたのに気づかず、不意をつかれて殺されてしまったと伝えられています。
エジソンにも、考えごとに熱中していて、時計を卵と間違えお湯の中につつこんでしまった――こんな逸話が残っています。
日本流にいえば「心ここにあらざれば、見れども見えず、聞けども聞こえず」ということでしょう。
われわれは、ひとつのことに注意を集中すると、ほかのことには気がつかなくなります。聖徳太子が十人の相手から同時に訴えを聞いたなどというお話は、人間放れしすぎていて信じられません。それより、アメリカのファングという科学者が書いている、つぎのような例の方がはるかに人間的であり、ほほえましくないでしょうか。
ある小学校で国語の時間に、先生が一人の少年に教科書を読まさせ、一段落したところで「いま読んだ部分の意味をいってごらんなさい」と質問しました。
するとその生徒は「僕にはわかりません。僕は聞いてはいなかったから」と答えたというのです。
注意の集中のからくりは、ずっと「大脳全体の微妙な調整作用によって行われている」と説明されてきました。われわれの感覚器は目のそれを除けば、耳、鼻、皮膚……すべて刺激に対して門戸を開放していますので、大脳にはいろいろな信号がひっきりなしに送りこまれ、種々の感覚がごっちゃまぜに起こりかねませんが、実際には、同時にいくつもの感覚を感じとるなんて不可能です。
したがって、たしかに、どかで、はいってくる信号のうち不必要なものをぼやかし、一つの信号にしぼって、はっきり感じとれるよう調整作用が行われていなければならないはずです。
問題の「どこかで?」を、かつては「大脳全体だ」としていたわけですが、最近の研究の結果、まったく違った答えがでてきました。
ネコを使っての実験です。耳の感覚器と大脳皮質の聴覚野を結ぶ聴神経は、音の信号を運ぶ役割を持っていますので、ここから信号をとりだし記録するような装置を作り、三秒ごとにカチッカチッと音を聞かせると、間違いなく三秒ごとに通過する信号が記録されます。
ところが、音をそのまま聞かせ続けても、目の前にネズミを見せたり、イワシのにおいをただよわせると、途端に信号はとまってしまいます。ネズミの姿が消え、においがなくなれば、また信号は記録される――"動物のあさましさ"と片づけるのは早計。こういった現象は聴覚や視覚にかぎらず、あらゆる感覚についてみられますし、人間にしても同じなのです。
要するに、われわれがあることに注意を集中して、その感覚にだけ焦点をあわせようとすると、不用な刺激によって起こる感覚の信号は、大脳皮質に到着する前に、感覚神経の一部でストップをかけられてしまう。「調整作用が行なわれている。どこで?」。答えは感覚神経の一部です。この際「その信号は必要ない」というストップの命令は、もちろん大脳皮質からでて、網様体経由で各感覚神経へ送りこまれていることも、次第にわかってきました。
こういう、ありがたいからくりがあればこそ、うるさいはずの電車の中でも、人のおしゃべりや、ごう音が気にならず読書ができるわけです。反対に、一度にニつも三つもものごとに、注意は集中できないことをお忘れなく。"運転手には話しかけないでください"――このような注意は堅く守りましょう。
音楽を聞きながら勉強する「ナガラ族」のみなさんも、同時にジャズを鑑賞し数学の難問を解くことはできないものです。これだけ知っておいてください。「ただ音楽が鳴っていればいいんだ、聞いてなんかいない」というならよろしい。さほど勉強の邪魔になっていま
2024.04.19 記す
うらみ海馬に徹す P.162~164
もし、われわれ人間から、記憶がなくなったらどうでしようか。「歌を忘れたカナリア」や、言葉がわからない「青い目をしたお人形」どころのさわぎではすみません。
事態はもっともっと深刻。すべての人が「潮来の伊太郎」のように、風の吹くまま……ゆきあたりばったりの人生を送ることになり、社会は麻のごとく乱れきってしまうでしょう。学問も道徳も、みんな記憶があってこそ存在するのですから。
赤ちゃんにだって記憶はあります。赤ちゃんはママのふところに抱かれていれば安んじて眠るのに、見知らぬ人に抱かれると泣きだすことが多い――ママはよく知っているが。あたまのなかに印象が刻みこまれていない相手だとだめ、これが人見知りというわけです。注射の痛みにしても同じで、年のゆかない子供が注射をして非常に痛いめにあうと、二度目には注射器をみただけでもう泣きだし、よくお母さんを困らさせます。
「痛み」という記憶だけではありません。情に結びついた記憶はなかなか忘れにくいものです。たとえば「うらみ」については「遺恨なり十年一剣を磨す」という言葉があるではありませんか。「うらみ骨髄に徹す」というのも、うらみがよくよく抜きがたいものであることを物語っていると申せ4ましょう。
しかし、残念ながら、これは学問的に正しいとはいえません。骨髄まで徹するのは放射能です。記憶は大脳の古い皮質の一部で海馬とよばれる場所に刻まれていることがわかってきました。
ところで、記憶にはさきにあげたような情に結びついたもの、つまり本能の心がやどる古い皮質の働きだけによって刻みこまれた印象と、理知をつかさどる新しい皮質が発達してから、学習によってえられる知識があります。その場合の印象と知識のいちばん大きな違いは、印象はウノミであって消えにくいことであり、知識はウノミではなく、忘れやすいことです。
イギリスの詩人で文芸評論家でもあったコーリッジは、その著「文学的自叙伝」のなかに、こんな事実を織りこんでいます。
あるとき二十四、五歳の白痴の女性が高い熱にうかされて、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語をはっきりとしゃべりだした。人々は驚いて議論し、結局"悪魔が乗りうつったのだ"と断を下した。ただ一人の医者だけが、彼女の過去を調べて、まず九歳のころから数年間、ある牧師の手元で養われていたこと、そして、その牧師が廊下を歩きながら本を読む習慣があったことを知って、さらに、その蔵書をくってゆき、彼女のしゃべったことが全部のっているのをつきとめた。
知識のほうが忘れやすいのは、くどくど例をあげるまでもなく「記憶術」の本がベストセラーになるのをみれば、容易にわかっていただけましょう。
記憶はよびさますことが出来るからこそ記憶といえるわけですが、カナダの脳外科学者ペンフィールドは、麻酔をかけないで患者の耳の奥のほうにある新しい皮質の一部、側頭葉を電気で刺激してみた実験で、側頭葉が記憶の倉庫ともいうべき海馬から、必要な記憶、とくに知識をだしてくる門番のような働きをしていることを明らかにしました。
※参考:時実利彦「脳の話」(岩波新書)P.175 「記憶の座」を。(黒崎記)
刺激の結果はどうだったかといいますと、患者は「むかし聞いた音楽が流れてくる」といったり「かつて見たネオンが点滅しているのが目の前に浮かんできた」といったのです。
側頭葉は知識がはいってくるときも働いて、海馬へ送り届ける役割も果たしているとみていいでしょう。おとなの側頭葉を二つとも切りとってしまうと、そのときから過去、十五年間くらいの記憶が消えてしまいますし、もちろん新しく記憶することはできません。こんな例がありました。側頭葉を切る手術をうけたあと、奥さんをみて結婚以前の旧姓で話しかけた――。
2024.04.20 記す
赤ちゃんに話しかけよう P.165~167
われわれは「習い性となる」ということを申します。当然のこととして、なにげなしにいっていますが、実は、これが人間と動物を区別する大きな特徴の一つなのですから、ゆるがせにはできません。
こんな実験をした人がありました。生まれたてのニワトリのヒナを二羽もってきて、一羽ははじめから自由に餌をついばめるような状態にし、もう一羽は二日間だけ、餌を人間が口に入れてやり自分ではついばめないようにして、四日目から自由についばませたのです。すると、さきの一羽は一週間でズバリとうまくついばみ、失敗しなくなりましたが、あとの一羽も自由にされてから四日目には、まったく同じようについばめだしました。つまり二羽とも生後一週間で、まったく同様に上達したわけです。
餌をついばむことが経験や学習の結果、身についたものならば、あとのヒナが追いつくには、もう一日かかってしかるべきなのに、事実は反対です。餌をついばむ動作は、脳をふくめた神経系の発達だけによって行えるようにできていると申せましょう。
ニワトリには、「習い性となる」なんて面倒なことは不要、はじめから"性"が備わっているのです。こういう自然に備わった上達の仕組みを成熟とよびますが、下等な動物は成熟だけで、姿も行動も、その動物らしくなります。
生後四十六週目から階段を上る練習をはじめた赤ちゃんは、生後五十三週目からはじめた赤ちゃんより、もちろん早く上れるようになりますけれども、その差の七週間が最後には二週間になってしまう。
 しかし、人間が真に"人間らしく"生きてゆくためには学び、習い、そして記憶することが絶対に必要です。「オオカミ少女の教訓」(四二ページ)で紹介した少女を思い起こしてください。八歳までオオカミに育てられて、人間のなかで育ち、学習する機会をもたなかったこの少女が、いくら周囲で努力してもあまり効果がなく、オオカミの性が抜けきれませんでした。たとえ皮膚や筋肉が一人前に発達していても、これではカオ、カタチだけが人間で、本当に"人間らしい"とは申せません。
しかし、人間が真に"人間らしく"生きてゆくためには学び、習い、そして記憶することが絶対に必要です。「オオカミ少女の教訓」(四二ページ)で紹介した少女を思い起こしてください。八歳までオオカミに育てられて、人間のなかで育ち、学習する機会をもたなかったこの少女が、いくら周囲で努力してもあまり効果がなく、オオカミの性が抜けきれませんでした。たとえ皮膚や筋肉が一人前に発達していても、これではカオ、カタチだけが人間で、本当に"人間らしい"とは申せません。
「カエルの子はカエル」でいいとしても、人の子は生まれ放し、生みっ放しでは人の子らしくもならぬということ、動物だって高等になると教えるー習うー記憶するということがあります。ネコは必ずネズミをとるものと決めこんでいる方があるかもしれませんが、あれは親ネコが教えるから覚えるのであって、もし教えなかったら一生ネズミはとらないでしょう。
ところで、幼いときの学習は理屈ぬき、いわば機械的な学習が行われ、赤ちゃんはウノミするわけです。この場合、大切なのは、第一に反復。最近わたしは都内のA病院をたずねて、つぎのような話を聞かされxました。
「この哺育室では生後一年以内の赤ちゃんを二十人ほど預かって、先生や看護婦たちが親がわりになってよく世話しているが、総体的に言葉の発達だけは悪いのが目立つ。それが、どの赤ちゃんも家庭に帰ると、みるみるうちに言葉の数が多くなるものです」
病院にいる間は、どれほど先生や看護婦さんたちが手落ちなくと心を配っていても、やはり親の元にいるように、つきっきりというわけにはいかないので、言葉の学習についてだけいえば、反復の機会は少ないのではありすまいか。
してみると、赤ちゃんを相手に朝な夕な、しきりに話しかけているお母さんたちの努力?は、きわめて意味のあることなのです。
2024.04.20 記す
親はよく勉強しておけ P.168~171
わたしは勤め先で、昼食をなににしようかと迷うことがしばしばありますが、そんなとき電話器をとりあげ、つい「四五二〇」とダイヤルを回してしまいます。相手は大学の近くにあるソバ屋さん、わたしがソバをきらいでないせいもありましょうが、この番号が覚えやすいために、かけてしまうのです。
ものを記憶しようときは、具体的なことがらに結びつけると、比較的やさしくなります。とくに番地、電話番号、特定の数値など、それだけでは無味乾燥なものほどそうでしょう。そこでコマーシャルには、こういうテがよく利用されています。「カステラは一番、電話は二番」なんていうのは、いやでも覚えさせられてしまう例。もっとも、番号が単純なので覚えやすいともいえましょう。
電話番号には傑作が多いようです。「二四一ー〇〇八七」これは「によい・はな」と読ませるそうで、ある花屋さん。「八八一五=パパ行こう」というのにもお目にかかったことがあります。どこの……と思ったら、料亭でした。
 ところで、相良守次東大教授は、「記憶とは何か」のなかに、つぎのようなことを紹介しています。「筆者が以前住んでいた郊外の電車の駅前に産院の立看板が立っていたのが、その電話番号には"三九八〇"とでていた……」。二十数年前も前にみたのですが、 ところで、「今日にいたるまで忘れずにおぼえている」という記憶の仕組みは、残念ながら、まだはっきりつきとめられておりません。
ところで、相良守次東大教授は、「記憶とは何か」のなかに、つぎのようなことを紹介しています。「筆者が以前住んでいた郊外の電車の駅前に産院の立看板が立っていたのが、その電話番号には"三九八〇"とでていた……」。二十数年前も前にみたのですが、 ところで、「今日にいたるまで忘れずにおぼえている」という記憶の仕組みは、残念ながら、まだはっきりつきとめられておりません。
記憶の倉庫が、大脳の古い皮質の一部、海馬であることは間違いないけれども、そこに一つ一つの記憶がどのようにしてたくわえられているかがわからないのです。
非常にたくさんある脳細胞のうちの、特定のいくつかの細胞の間をぐるぐる回っている状態、これが一つの記憶であり、信号が止まることは、忘れることを意味する――という学説が十五、六年前からもっともらしく、となえられてきました。
しかしながら、信号は、脳細胞が睡眠時や睡眠薬をのんだときのように活動を停止すれば回らなくなるはずです。したがって、この学説では十年も二十年も消えない記憶のからくりは解けません。もし、この学説どおりなら、ひと眠りすれば人はすべてをさらりと忘れてしまい「きのうのない人生」を送ることになりましょう。「きのう」というのも記憶の一つですから――。
記憶のからくりは、どうやら一つ一つの脳細胞そのものなかに秘められているようです。とくに、そのシンともいうべき細胞核やまわりの原形質をかたちづくっている蛋白質の分子構造がカギをにぎっているのではないか――現在ではこういう考えが優勢になっております。
だとすると、細胞核は親から子へ伝わるものですから、記憶の形跡も子に伝わることが考えられましょう。「お父さん、しっかり勉強しといてね」親たるもの、これくらいのことは注文されるまでもなく、考えておきたいもの。
ソ連での実験にこんな例があります。ネズミを相手に、鈴を鳴らしては、餌箱に餌を入れることをくり返してみたところ、二百九十八回目からは鈴を鳴らしただけで餌箱に飛びこむようになった。その子のネズミに試みたら百十四回目から、そのまた子、つまり孫ネズミは三十一回目から、五代目になったら六回目から、もう飛びこむようになった……。
こういう訓練を行う途中で、脳細胞に電気シヨックをかけると、覚えるまでの所要時間や回数に変化が起こります。教えてからのち一時間後にかけ、また教えて一時間後に、というようにかけた場合は、まったくかけなかったのと同様に覚え、十五分にすると、覚えるのに数倍の時間を要し、五分にすると、全然なにも覚えません。
これはネズミの場合ですが、人間でも自動車事故などで強いショックをうけると、事故直前のことを忘れてしまう例はザラにあります。記憶が脳に深く刻みこまれるまでには、最低十五分ー三十分という時間が必要なのです。勉強し終わったばかりのお子さんを、ひどく驚かせたりするのは罪なことだとお心得ください。
2024.04.20 記す
ある物理学者の嘆き P.172~175
メロドラマの決定版「君の名は」(菊田一夫作)のはじめに、いつも「忘却とは忘れ去ることなり……」という意味ありげな文句がついていました。まだ、忘れていらっしゃらない方も多いでしょう。
たしかに、忘却とは忘れることであり、忘れるとは忘却することではありましょうが「忘れる」ことについて、十九世紀の末にドイツの心理学者エッピングハウスがおもしろい研究ををしています。
彼はいろいろな方法で、あまり意味のないこと――たとえば数字の羅列などは一度覚えても、十五分たっと半分、八時間たつと三分のニは忘れてしまうことをたしかめました。ただし、一ヵ月たっても全体の五分の一は覚えている――この結果から、彼は「忘却曲線」という「もの忘れのグラフ」をひねりだしましたが、文字ににかえて表現すると、つぎのようになりましょう。
「どうでもいいことは、すぐにごっそり忘れてしまい、あとは徐々に忘れてゆくが、まったく忘れてしまうことは少ない。記憶の痕跡はなんらかの形で多少は残っている」
なるほど、われわれは忘れたつもりでもでいることを、なにかの拍子にふと思い出したりすることがあります。とはいっても、まったく忘れてしまうことがあるのはどういうわけか?
前にいったとおり、たいしたことがらでなくてさえ、痕跡だけは長く残っています。つまり、記憶は使わなくてもなかなか消え去るものではありません。しかし、新しい記憶が加わってきて、先に刻まれていた記憶を混乱させると、だいたい消滅してしまうものです。これこそ忘却といっていいでしょう。
だとすれば、失恋の痛手――これも記憶です――は、新しい恋人を発見すればより早くいやされましょうし、いとし子を失った親の悲しみも、新しい子をつくれるものならば、この方が「時」よりも早い解決法だということになりますが……。
よく「物忘れをするようになった」と嘆く方があります、が、一度、脳に刻みこまれた人間の記憶は、人工頭脳やソロバンと違って、なかなか"払えばご破算"とはゆかないため、かえって人間自身がくるしまなければンあらない問題も多いのでです。
昭和三十五年に来日したアメリカの有名な原子物理学者オッペンハイマー博士は、大阪での講演会で、こう申しています。
「核兵器の製造を中止したり、使用禁止の取り決めはできるが、もっと大切なことは、原子力の知識を忘れることだ。しかし、悲しいことに、人間は原子力については無知だった二十年前に戻ることはできない」
忘却装置といったものができて、これにかければなんでも「払える」ならば、かけてしまいたいことは少なくありません。恨み、悲しみ、心のウサの数々、さらに戦争に利用されるくらいなら原子力だって――。
もの忘れも考えようによっては自然の忘却装置、いやなことはできるだけ、こいつにかけて大いに忘れましょう。そうすれば心身ともにすこやかになり、健康はうけあい――むかしから「もの忘れは長寿のコツ」というではありませんか。
忘れろ、忘れようという話ばかりになってしまったので、最後に忘れない法を一つ。つまり、もの覚えをよくするにはどうしたらよいか。
2024.04.20 記す
靴音とヨダレから P.176~178
ノーベル賞を受けた人――といえば尊敬すべきすぐれた頭脳の持ち主だと思っても不思議ではありません。ところがここに、ノーベル賞を受けながら、ノーベル賞を受けた人物から"大馬鹿野郎だ"ときめつけられた学者があります。おそらく前代未聞のことでしょう。
一九二五年にノーベル賞を受賞したイギリスの作家バーナード・ショ―は、小説「神を求める黒人の少女」のなかに、つぎのような意味のことを書いています。
「……二つのことがらが同時に起こることによって、動物や人間の心の中に結びつきができて、一つの習慣が作られる――だれでも知っている事実だ。これを"発見"するのに二十年もかかった科学者がいる。こんな馬鹿ものはいない……。エセ科学者の最たるもの……」
ショーがこうまで激しく書いた真の心を探るのはひとまずおくとして、きめつけられた科学者はソ連の生理学者パブロフ(Pavlov)です。パブロフは、ショーが「だれでも知っている事実だ」といった事実=条件反射について研究すること二十五年、偏見と戦いながら、常識として知られていたに過ぎない現象に、はじめて数多くの法則を見出しました。
一九〇四年、消化腺の研究でノーベル医学・生理学賞をうけた彼が、条件反射にとりかかったのは一九〇二年のこと。キッカケを与えてくれたのは一匹のイヌと研究所の小使さんでした。当時、パブロフはイヌを使って、頬から唾液が体外に流れ出るようにし、唾液線の研究をすすめていましたが、ある日、いつも餌をやりにくろ小使さんのコツコツという靴音が聞こえてきただけで、このイヌがだらだらと唾液を出すことに気づいたのです。
ものを食べるとき唾液が出るのは、自然に生まれたときから備わった"反射"だが、こっちは違う。特定の靴音→食べもの→唾液という繰り返しがあって、いつの間にか靴音→唾液という、本来は無関係だった二つのことがらが結びついておこる"反射"だ。よし、このからくりを調べてやろう――彼はそれから調べに調べ、調べ抜きました。その死後、条件反射の新しい法則はまったく発見できなくなったほど――。
つぎに「分化」といって、千サイクルの音を聞かせて餌を与え、さらに五百サイクルの音を聞かせたときは餌を与えないということを繰り返しますと、音は音でも五百サイクルでは絶対に反応を起こさない。いいかえれば見向きもしないということになるのです。
パブロフはもっぱらイヌを使って確かめてゆきましたが、この分化という現象を利用して、われわれはものいわぬ動物たちの感覚を調べることができます。音でも、光でも、色でも、図形でもよろしい。どの点で分化が起こるかをつきとめば、聞きわけ、見わける感覚の能力を知るてがかりとなりましょう。
このほかにもパブロフは、条件反射はできるだけ安静にしてやらないと成立しにくいこと、成功しても放っておくと弱くなり、しまいには消えてしまうこと、大きなショックを与えても同様に消えてしまうなどを明らかにしました。"一九二四年の秋、研究所が出水で水びたしになったとき、条件反射を仕込んだイヌがあっぷあっぷしていたので救いだしたが、そのイヌはすっかり条件反射を起こさなくなっていた"かれはこう書いています。自然の反射にくらべ、条件反射ははるかに不安定なのです。
2024.04.02 記す
まぶしいベルの音 P.179~182
「クマはサーカスには使いにくい」といわれ、事実みられなかったものでしたが、ソ連のボリショイ・サーカス団はみごとにクマの曲芸をみせてくれました。「あれは条件反射を応用して仕込んだのだ」という定評があります。わたしはボリショイのクマを研究したり調べてみたわけではないので、断言はできませんが、おそらくそうだろうと思われます。
とにかく条件反射はいたるところにみられ、応用もされています。
池のフチをコツ、コツたたいて、餌をやる習慣をつけますと、コツ、コツたたいただけでも魚は寄ってくる――音と、餌を食べることは本来まったく関係がありませんが、刺激が繰り返されているうちに結びついて、条件反射が成り立ったのです。
動物の場合"条件"になる刺激は、この例でもわかるとおり、九九パーセントまで感覚刺激、つまり音だとか、光だとか、痛みだとかです。それが人間になると、ずっと抽象的なことでも"条件"をみたす刺激になります。たとえば――
われわれのひとみはまぶしいと縮まって小さくなり、光をさえぎります。そこでベルの音を聞かせてひとみに光線をあてることを繰り返しますと、しまいにはベルの音を耳にしただけで、ひとみは縮まってしまいます。条件反射はここで成立したわけ。これが極端になると、ベルという文字をみただけでも縮まり、もっと極端になると、ベルという文字をあたまのなかに思い浮かべてさえ、ひとみは縮まるのです。
条件反射は内臓にもみられます。胃や腸の運動、心臓の鼓動などについて、パブロフンの弟子のブイコフらが研究しました。
アドレナリンという、心臓に使用する薬をイヌに注射すると、呼吸は荒くなり、心臓の鼓動は激しくなる。何回も注射しているうちに、イヌはこの注射器をみただけで、注射されたときと同じように呼吸をし、鼓動をみせた――と、ブイコフの仲間のひとりは報告しています。
底に金網を張り、電流を通せるようにした箱にネズミを入れ、実際に電流を通せばもちろんネズミはピリピリとする痛みを感じるわけで、逃げだします。電流を通す前に、必ず光をあてたり、音を聞かせたり、これを繰り返すとどうなるか。
いうまでもなく条件反射が成立して、ネズミは光を感じ、音を聞いただけで逃げだしてしまうようになります。この場合、条件反射は痛みを避ける一種の準備運動とでも申しましょうか。条件反射もまたダテに備わった仕組みではなく、生きてゆくうえに欠くことのできないものなのです。
条件反射の法則は「靴音とヨダレから」(一七六ページ)に紹介したパブロフの半生をかけた努力の結果、ほとんどきわめつくされているといいっていいでしょう。そのパブロフが死んでから三十年あまり多くの学者が条件反射のからくり――いいかえれば、これを起こす脳の仕組みの研究に取り組んできました。けれども、残念ながら、まだよくわかっていません。
ただ、はっきりいえるのは、大脳の新しい皮質をとると「分化」できなくなること、古い皮質も大きな役割をはたしていることなのです。この三、四年、とくに古い皮質と条件反射のつながりについて盛んに研究が行われていますので、難問が解ける日も遠くではないでしょう。
※参考:一九六一年一月に打ち上げた宇宙ロケット関連記事は中富信夫 写真/NASA「アメリカ宇宙開拓史」(新潮文庫)P.62に記載されている。(黒崎記)
2024.04.21 記す
人間・ジキル博士 P.183~186
一八七〇年、アメリカのワイオミング州で、恐竜の完全な化石が発掘されて大きな話題になりました。一億五千万年のむかし、地上をわがもの顔に歩きまわっていたにちがいない、全長二〇メートルの大怪獣――しかも関椎骨の形から頭と腰、つまり二ヵ所に脳があることがわかって評判はさらに高くなりました。
当時のシカゴ・トリビュン紙には
……………………………………
もしも、前の脳がこわれたら
後ろの脳がかわりをしただろう。
といった詩が掲載されたくらい、人々の驚き方が察しられます。
ただし、二つの脳が、この詩に歌われたように働いていたかどうかはもちろん疑問で、いろいろと憶が行われた」ようです。たとえば、二つも脳があったら一よりは便利だろうか、いいや、ニつの間にもつれをを生じたら大変だろう?……
などと。
しかし人間の脳も、まったく働きの違う、古い皮質と、それをおおっている新しい皮質という二重構造をもっていることがわかったいまは、さほど驚くにはあたりません。
さきにあげた恐竜についていえば、腰の脳の何分の一という小さなあたまの脳が、新しい皮質だとみていいでしょう。
このように、新しい皮質は人間を人間たらしめている心がやどるところですが、本能的な欲望や、情に結びついた心――怒りとか快、不快などのやどる古い皮質は、脊椎動物ならどんな動物にもあります。つまり古い皮質にやどる心だけは、人にも動物にも共通したものです。
ところで、古い皮質と新しい皮質の間には、どんな関係があるか。アメリカの首都ワシントンの近くにある国立衛生研究所のマックリーン博士はこういっています。
「古い皮質にうごめく心は、競馬のウマみたいなものであり、新しい皮質でいとなまれる精神は、そのウマをあやつる騎手である」
われわれの脳が、もし古い皮質だけだったらどうでしょうか。食うことだけが目的の、みにくい争いに血道をあげ、あるいは欲求のとりこになり、また快楽にうつつを抜かすばかりでしょう。それを、新しい皮質の冷静な思考や判断がぐっと押え、コントロールしているのです。
英国の作家スティブンスンが書いた世にもまれな怪奇小説「ジキル博士とハイドン氏」は、われわれ人間が宿命的にもっている二重性格的な心をズバリ表現したもの――と、わたしには思えてなりません。われわれの心の底に巣食っている古い皮質「ハイドン氏」は、新しい皮質のきびしい監視によって、その姿を表面に現わさず、人間「ジキル博士」としての尊敬を保ち、規律ある社会生活をいとなんでいるといえましょう。
人間行動とはすべて新しい皮質の働きの結果ですから、その働きがにぶったり、よろめいて、手綱がゆるんでしまうと、古い皮質の心がむきだしになります。
新しい皮質は酒やリズムに弱い。だから、酔っぱらうと、どうしても、やることなすことが"動物的"になりがちです。そこで酔っぱらいを「トラ」、とくにひどいのは「大トラ」とよんで、人間と区別することになっているのでしょうか?
といって、新しい皮質のコントロールが極端にきびしすぎると、心のウサが高じてノイローゼの原因になります。手綱はほどよく締めよ――ということ、。その締め加減のいかんによって"人間的"信用が高くなったり、また、なくなったりするものですから――。
※参考:「ジキル博士とハイドン氏」は青空文庫あり。(黒崎記)
202404.21 記す
"気"がむいたら読みましょう P.187~190
われわれはなにげなく、気という言葉を使っております。この"なにげなく"も漢字で書けば
「何気なく」でしょう。
「人生が味気なくなった」
「気が滅入ってしようがない」
「あいつはやま気が多すぎる」
気が早い、短気、気まぐれ、浮気、気心が知れない、気分をだす、気の毒、気にくわない、お気に入り、気のない返事、やる気がない、気おくれ、気勢をあげる……気がつく言葉を全部あげるのには相当な根気がいります。
こんなに使われている気とはいったいなにか――お考えになったことがありますか。
気がかりなことがあると仕事ははかどらず、失敗しやすい。反対に気分がよく、気が乗ると、すらすら運ぶものです。この場合、気は大脳の新しい皮質でいとなまれる理知の働きをささえ、また左右しているといってよいでしょう。
つまり、気とは古い皮質の活力のようなもの。これが盛んなときを、気分がすぐれるとか、意気高揚といい、衰えてきた状態を弱気、あるいは気が沈むなどと申しているわけです。
この事実は、一九六〇年から一九六一年夏にかけ、私たちの研究室で実験的に証明されたばかりjです。
具体的に申しますと、つぎのようなことになります。
古い皮質の働きを左右している脳幹部の視床下部は、同時に、意識のレベルを左右し、新しい皮質の働きのカギをにぎっている。網状にからみあった神経細胞の集まり網様体にも影響を与え、結局は新しい皮質にも働きかけている――。
われわれがなにかをするときは、知力と体力だけではなぜなら、新しい皮質による知力は、古い皮質の状態がすこやかでなければにぶりがちだからです。そこで古い皮質の活力=気力の充実が求められるわけです。
むかしから「知をみがき、心を練る」という言葉がありました。この場合の"知"とは新しい皮質、"心"とは古い皮質をさしているのではないでしょうか。
古い皮質は内臓器官と密接な関係にありますので、これを丈夫にするのは「心を練る」ひとつの方法です。気力のたくましい人を「腹ができている」とか「太っ腹」というのも、うなずけるような気がします。
気が大切であることは、近ごろとみに増加してきた交通事故を見てもわかります。
明らかな酔っぱらい運転、居眠り運転、スピード違反などが原因ならばいざ知らず、注意はしていたつもりだが、なお事故を防げなかった――こういう事故を起こす瞬間は、運転そのものから一瞬、気がそれているとみてよろしい。つまり、古い皮質の働きがにぶったとき、事故はおこりやすい。命が惜しかったら、古い皮質の活力を弱らせるような、気にかかること、気にさわることなどはできるだけなくすべきでしょう。
最近、鉱山や¥一部の工場では、「家族ぐるみの事故防止」というスローガンを大々的に掲げようとしております。働きに出る当人だけがいくら注意していても、出がけに、夫婦げんかや兄弟げんかなど、おもしろくことがあって、あたまにこびりついていますと、なにかの拍子に古い皮質の働きをにぶらせ、注意力を乱して事故を起こすもとになりかねません。職場の安全には施設や技術だけでは解決しきれない精神面の問題もあるのです。
どうも、世間には「知をみがく」言葉ばかり教える本が多いようです。「……に強くなる本」といったたぐいの本を読むのは結構。しかし古い皮質がたくましく、おおらかでないと、せっかくの才知も生かしきれないことにご注意ください。
2024.04.21 記す
色に出にけりわが恋は…… P.191~194
昭和三十四年、ローマ・オリンピックに参加した日本のホープ山中毅選手は、オーストラリアのローズやコンラッズに敗れたとき「自分に負けた」と感想をあらわしておりました。この言葉は意味深長ですが、山中選手ほどのベテランでも堅くなったとか、あるいは多少あがっていたことを示しているといっていいのではないでしょうか。
ことにのぞんで「あがる」とか「堅くなる」というのは、心の奥底=古い皮質が冷静を欠き、働きがこわばった状態です。古い皮質の働きは、習い覚えた知識、技術を発揮させる新しい皮質の働きをバック・アップしていますから、これがこわり、低下しては"日ごろの実力"は出しきれません。
野球でいう「ブルペン投手」、相撲の世界での「けいこ横綱」、いずれも実戦になると"弱い"ところが共通しております。彼らがスターになりきれないのは、いざというとき、古い皮質がふだんのようなおおらかさを失ってしまうためです。試験で知っていることを生かしきれないのも同じこと。知識や技術以前の問題です。
われわれの表情、動作、言葉などは本来、理知をつかさどる新しい皮質の働きに支配されてはいますが、ブルペン投手の例をみれば、動作つまり筋肉の働きにも、古い皮質の働きが影響することがあるのがおわかりましょう。
平家再興の陰謀をはかったカドで捕えた平景清が脱獄したので、ときの判官・秩父重忠は、景清の愛人、阿古屋を責めてゆくえを知ろうとする。しかし「知らぬ、存ぜぬ」の一点張り。これではラチがあかぬとみた重忠は、琴、三味線、胡弓を阿古屋にひかせてみたところ、少しも乱れがない。そこで重忠は「もし知って隠しているならば、演奏に必ず乱れが出よう。これは、まったく知らないのであろう」と、阿古屋を放す……。
南方の未開人種のなかには、酋長の前に容疑者を並べてメシをくわせ、食が進まないものを犯人とする"裁判"があるそうです。
このほか、古い皮質の働きに結びついている血管の伸び縮み、汗の出かた、胃や腸あるいは心臓の動きなども、しばしば理性を越えて、表面に影響をみせます。
忍ぶれど色に出にけりわが恋は
ものや思ふと人の問ふまで
平 兼盛
小倉百人一首におさめられたこの名歌は、理性にとって人にさとられまいと努力しても、おおいきれない心の動きと、その結果、表面に出るものがあることを、よく示していると申せましょう。この"色"が顔色だとすれば、血管の伸び縮みがしからしめたもので、これまた理性でおさえきれないのは当然なのです。
犯罪捜査に利用されているウソ発見器は、"色"に出にけりの原理を科学的に生かした例。ただし、ここで"色"に相当するものは汗です。いくら口をつぐんでいたり、否定してみても、真実をつかれると、古い皮質が刺激をうけ、いやでも自律神経に影響を与えて、汗の出かたは変わる。心臓の鼓動の変化(胸さわぎ)や、呼吸の状態も、汗の出かたと同じからくりなので、同時に記録すれば、ますます確度をますわけです。
いってみれば、機械にドロをはかかせ、本当の心を探る装置であるためか、アメリカあたりでは、トゥルース・ディテクター(真実発見器)ともよんでいます。
人間は新しい皮質にやどる理性が発達しているので、意識的に努力して本心を隠し、表面に仮面をかぶるという、動物にはマネのできない芸当ができます。トボケ面、なにくわぬ顔というやつ。その人間が、新しい皮質にコントロールできない器官の働きをはかって、本心を見抜く装置を作らねばならないとは、人間の特徴もなかなかやっかいです。
2024.04.21 記す
脳にも栄養を P.195~198
生きるためには飯を食わねばならない――脳細胞も生きて働いている以上は"栄養"をとらなければノビてしまいます。
脳細胞は眠っているときや、ポカンとしているときは、働きをやめていますけれども、生きてはいるのです。そして、いつでも働けるように準備オサオサ怠りない。したがって、こんなときにも"栄養"は補給しなければならないわけですが、この際、必要な養分とは酸素とブドウ糖。これは血液の中にまじって脳へ運びこまれます。
大人の脳にはいってくる血液の量は一時間に四五リットル、自動車が同じ時間にに食うガソリンは、多くて一〇リットルぐらいのものでしょう。いかに脳が大量の血液を必要とし、養分を吸収しているかわかろうというもの。ただし、四五リットルのうちに酸素はは三リットル、ブドウ糖は四グラムしかふくまれておりません。
これから成長しようという脳、つまり子供の脳はさらにがめついのです。つまり数字をご覧ください。
まず、体重と脳の重さについて、大人のそれと子供のそれをくらべてみますと
子供=六パーセント
つぎに、体全体を流れている血液のうち何パーセントがいつも脳に流れこんでいるかの比較です。これは、なんと
大人=二〇パーセント
子供=四〇パーセント
むかしは、この量が眠っているときは減るといわれていたものですが、起きているときと変らないことがたしかめられています。
血のめぐりが悪くなるとは、この量が減ることにほかなりません。だいたい、定量の三分のニに減ると、酸素とブドウ糖の不足から脳細胞の働きがおかしくなって、意識はもうろう、さらに減ると気が遠くなり、ついには気を失ってしまいます。
ところで、すゃべったり、考えたり、怒ったり……要するに脳細胞が働くときには、ただ生きているときとはべつの養分が必要です。それは蛋白質ですが、とくに蛋白質を構成している物質のひとつアミノ酸が大切です。
もっとも、一口にアミノ酸と申しましても、これがまた種類が多い。そのうちで欠くことのできないのはグルタミン酸とギャバ、この二つの物質が脳細胞の中で働きを起こすにはビタミンB類の助けををうけているといわれています。
以上の説明で、能の"栄養"といえば、酸素、ブドウ糖、蛋白質グルタミン酸、ギャバ)にビタミンB類に要約されることがおわかりでしょう。酸素は呼吸によって、ブドウ糖は米など澱粉を含むもので、それぞれ満足にに補給されますが、肉類に多い蛋白質と、ビタミンB類は不足しがちです。とくにあたまを使う人は、蛋白質を十分におとりください。一日に五五グラムー六〇グラムはほしいところです。
日本の家庭に広く普及している「グルタミン酸ソーダ」を主体とした白い粉末の調味料を「あたまの働きをよくするから……」といってたくさん使う方があります。残念ながら、これはマトはずれ。グルタミン酸とグルタミン酸ソーダは同じ物質ではないのです。ついでながらグルタミン酸やギャバを服用すれば、あたまがよく働くようになるか? というご質問には
「いささか疑問である。とくにグルタミン酸は……」
とだけ申しあげておきます。
脳細胞と毛細血管の間には、グリア細胞と名づけられた細胞がびっしりつまっており、これが血管内の血液中から、限られた物質だけを通し、また運んでいるものだろうと考えられております。グリア細胞は関門のような役割を果たしているといっていいでしょう。ここを通れない物質だとしたら、いくら服用しても、注射しても無益だということになります。
では、どんな物質をよく通すかといいますと、酸素、ブドウ糖、ペニシリン……。アルコールも通せばこそ脳細胞がよろめいて酔っぱらうわけであり、精神安定剤はことわるまでもないでしょう。
六〇六号で名の通ったサルバルサンは、この関門でストップ。皮膚や骨の梅毒にはきいても、脳梅毒にきかないわけです。ところが幸いなことに、ペニシリンはこの関門をス―ス―通って脳細胞のなかのスピロヘータを殺してくれます。ちかごろ梅毒で脳がいかれる人がすくなった理由は、こんなところにもあるのです。
2024.03.31 記す
精力あって性力あり P.199~102
戦後ひところ、ホルモン・ブームが起こり、あちこちに「ホルモン料理」と書いた看板をみかけました。
あのホルモンという文字からは性ホルモンを連想し、これが精力の増減、強弱のカギをにぎっていると考えた人が少なくないようです。いまでも、性ホルモン=精力のすべてと思いこんでいる人にしばしばぶつかります。しかし、これは少々思いすごしの感があります。
男子は睾丸、女は卵巣にある生殖腺から分泌されるのが性ホルモンの一種であり、からだの健康を保つために大きな役割を果たしているほかのホルモンの働きと両々あいまって、はじめて、たくましい力を発揮させる原動力たりうるのです。
「敗戦の憂き目にあい、捕虜収容所に入れられていたときのこと、食べるのが精いっぱいの状態が続いた。すると口ヒゲ、恥毛がなくなり、乳房がふくれてきた……」という信ずべき体験がありました。
これは、食べ、生きのびることが、子孫を作るいとなみに優先することを物語っており、ギリギリの状態では性ホルモンも出なくなってしまうことを意味します。人間は「食たりて性を知る」とでも申せましょうか。
精力の根源といえば、性ホルモンよりは、むしろ、つぎにあげる四ヵ所から出るホルモンの方ではないかと思いますが、いかがなものか。
脳の底にある視床下部のすぐ下に位する下垂体、喉もとにある甲状腺、膵臓のなかにあるランゲルハンス氏島、腎臓の上に帽子のようにおおいかぶさっている副腎、それぞれが働きの異なるホルモンを出しますが、いずれも健康を保つのに欠かせないものです。どれかひとつでも、出かたが多すぎたり、少なすぎたりすれば、まず"健康"とはいえなくなります。
なかでも、下垂体は成長ホルモンや尿の出かたを押えるホルモンを出し、かつ甲状腺、副腎皮質、生殖腺からホルモンをたくさん出すように刺激するホルモンまで出している――つまりホルモン王国の首相的存在です。もっとも、この下垂体は視床下部から出た神経の支配をうけていることがわかりました。近年ようやく――。
してみると、ホルモンの分泌と、内臓の働きをコントロールして、これも健康の維持に寄与している自律神経とは、ちょっとみたところ無縁のようでいて、事実は同じ視床下部の翼下にあるわけで、切っても切れない仲、互いにあい補い、助けあって、われわれに"健康"を与えてくれるのです。
ホルモン分泌の変化は、脳の働きにまで影響を及ぼすことが、まま、あります。
生理期間中の婦人が、思わず知らず万引きをしてしまうという話をよく耳にしますが、これなどは性ホルモンの分泌が盛んになったために、脳の理知の働きがにぶった例だといえましょう。
発情したウサギやネズミが落ち着きを失い、せわしく動きまわるようになるのも、ホルモン分泌がやはり脳の働きに影響を与えればこそです。脳からの命令が運動神経を伝わって、筋肉へと届かなければ運動は起こらないものですから――。
運動といえばオスのイヌが片足をあげて行なう排尿法も、生後二十週間、いいかえればホルモンの分泌が盛んになり色気づきだすころからみられるものです。
こんな報告があります。「バナナ・テスト」とでも申しましょうか、チンパンジーの集団にバナナを与えると、第一にボスが、続いて強い、地位の上のものから順番にとるが、オスのチンパンジ―を去勢すると、これをとる順番が落ち、メスについても同じ結果をえた――。「動物地位はホルモンによって左右されている」といえそうです。
では人間は? 「英雄、色を好む」というところをみると、動物の場合とまったく違うとばかりはいえないのではないでしょうか。
2024.04.22 記す
人は年期、機械は型 P.203~206
一七四七年、フランスの医者ラ・メトリは「人間はゼンマイ仕掛けの機械である」と説いた「人間機械論」を発表して、ゴウゴウたる世論の非難を浴びました
しかしながら、二百年たったいまは「人間は機械に近づいた」とか「人間と機械の区別はなくなった」という主張が堂々まかり通っています。
こういう主張があたまをもたげてきたきっかけは、一般に人工頭脳とよばれている電子計算機が完成してからでしょう。アメリカの文芸評論家マンフォードなどは「考える機械(電子計算機)を作ることによって、人間は機械への服従の最後の一歩をみずからたどりだした」といっているくらいです。
一九四六年にペンシルバニア大学で誕生した電子計算機は、その後の改良によって、たしかに、すばらしい働きをするものになりました。たとえば計算の能力――
ご存じの円周率です。一九世紀なかごろ、英国の数学者シヤクスは一年以上かかって3.1415……と七百七ケタまで計算しました。これを現在の電子計算機はわずか四秒ですませてしまいます。
さらに相違点をあげると、人工頭脳は真空管やトランジスタ一本こわれても役にたたなくなるのに対して、人間の場合は脳細胞の一つや二つ、いや一万くらいこわれても、脳が全然使いものにならないことはなく、結構、使える点です。
その電源についても同じようなことがいえます。人工頭脳は電流がストップしたら、その場でお手あげ。人間の脳は、すこしくらいの断食ではへこたれないし、貧血しても瞬間的に死ぬようなことはない。エネルギーをストックできるのです。
最後に、わたしが決定的だと思う相違点をあげましょう。人工頭脳は、記憶装置があって、情報を記録はするけれども、一つの計算がすんだら払って「ご破算」にしないと、次の計算が不可能です。
ところが、人間の脳は正反対、どんどん古い皮質に記憶を貯えてゆく。あすの自分はきょうの自分の記憶の上に積み重ねてゆくのが人間であり、個性も、人間らしさも、このようなからくりがあってはじめて形づくられるのです。記憶の積み重ね、すなわち年期とか年の功とか、あるいは経験年齢を重視するのは、まことにもっともなこと。なぜなら、記憶は人間を人間たらしめている最大の要素だからです。機械にはこんなことはありえません。X年型とか○〇式という「型」や「年式」だけが問題にされます。
電子計算機に作曲させた作品?を、ある女流ピアニストに弾かせたところ、「〇〇さんの曲に似ている、計算機はどういうおつもりで作曲したのかしら」と首をかしげたという話をききました。これほど電子計算機は進歩して来ましたが、いかに優秀なものでも、人間があってはじめて電子計算機としての価値が生れるのであって、電子計算機には、人間のような創造力と主体性がないのです。それに、機械の働きはあくまで論理的、合理的なものに限られ、"情"がありません。
人間の脳細胞は百五十億、これに相当する電子計算機のトランジスタは三ー四万、もし人間なみの機械にすると、丸ビルくらいの大きさになり、一億ワットの電力が必要、ところが人間の脳は百ワット以下のエネルギーでたりています。
人工頭脳と人間の脳との距離はまだまだカケ離れています。日本の電子計算機の研究者たちが、ジャーナリズムの作り出した人工頭脳とい名称を使わず、情報処理機とよんでいる気持ちがよくわかります。
核兵器がどしどし作られだしてから「人間と機械の対決」という言葉がしばしば聞かれるようになりました。だが、人間が対決する真の相手はやはり、機械の背後にある人間ではないでしょうか。
2024.04.22 記す
からだのいのちを尊ぼう P.207~210
「朝は四本足で、昼は二本足、夕方は三本足で歩く動物はなにか?」
ギリシャはテーベの郊外の岩にデンとかまえた、顔は処女、胴はシシ、そして翼をもった怪獣スフィンクスが、旅人に向って問いかけた有名な謎であります。
答えられない旅人はことごとく殺されたのですから、おだやかではありません。だが、勇者オイディブスが「それは人間だ。赤ん坊は手足を使ってはい、成長すると二本の足で歩き、老人は杖をつくから」と正解したため、さしもの怪獣も水の中に姿を消した……。「ギリシャ神話」のこの一章は、人間の生涯の外面的変化を見事に描いています。けれども「人間とはなにか」という答えにはならないでしょう。
アリストテレスによれば、人間は「社会的動物」、ソクラテスによれば「理性をもった動物」、パスカルによれば「考える葦」、さらにドイツの哲学者カッシラーによれば「シンボル(言葉)をあやつる動物」だということになります。これを要するに、人間を人間たらしめるのは脳の働きがあり、「人間性」とは脳にあるものだと申せましょう。
※記憶:私が購入した参考書河盛好蔵著『Je sais lire』(白水社)P.22人間は社交的動物である。 L`homme est un animal sociable.とある。
動物に序列をつけた十八世紀の博物学者リンネは、人間を最上位にすえ「ホモ・サピエンス」(知恵ある人)と名づけました。人間はたぐいない脳をもっているようです。ただし、ここにやどる精神の知恵は、偉大な生みだしもするが、文明が進めば進むほど、バランスがくずれやすいという矛盾した特徴をもっていることもお忘れなく――。
賢いはずの人間が形づくっている社会や国家に、暴力沙汰が、殺人が、戦争さえも絶えないではありませんか。
一九一三年にノーベル医学・生理学賞をうけたフランスのシャルル・リシエは「人間論」と題する本をあらわして、救いようのない人間の愚行を徹底的にあばきたて「人間は超愚人であるといいたいところだが、ホモ・スツルツス(愚かなる人)くらいで勘弁しておこう」と結んでいます。なるほどそういわれると、グウのねもでません。
ご承知のとおり、平均寿命はめざましく伸びています。しかし、残念ながら精神年齢の方はさっぱりなのが、人間ではないでしょうか。
たしかに理知のやどる大脳の新しい皮質はすばらしい知識を獲得し、発達してきました。つまり、人間のあたまはよくなってきたのです、といって、それだけで、人間は幸福になれるかと申しますと、はなはだ疑問です。本能の心がやどる古い皮質の働きとの調節を、絶えず考えてください。
古い皮質をたかぶらせ、欲求不満を抱かせますと、新しい皮質の理知では押えきれなくなる状態を招きます。「あたまをすっきり」とは、古い皮質をこのような状態にせず、安らかにたもつことにほかなりません。
民族と民族、国家と国家の間でも、集団的に古い皮質がたかぶり、欲求不満が高じて、ついには戦争という愚劣な挙に出てしまうことがありうるのです。この際、脳の働きは個々さまざまであり、互いに主体性は犯すべからざるものであれば、一方がいかに戦争を回避しようとしても、一方がしかけてくれば避けられないことになりましょう。
平和への道はたしかにけわしくはありますが、人間すべてがもっている真の共通点を、互いに尊重することによってのみ切り開けるのではないかと思われます。
真の共通点とは、首から下のいのち、つまり、からだのいのちです。これがあって脳にもはじめて働きが生じるわけですし、しかも、このいのちは、われわれの意識の外にあって営まれているのですから、理屈なしに尊重しあえる可能性がありましょう。いや、事実、そうしなければならないのです。
この精神は、アフリカの炎熱の地で、黒人の医療に献身しているアルベルト・シュバイツァー博士が信念のように、いつも強調している言葉「生への尊敬」に現れています。
「精神的に健康な人とは、愛や理性や信仰によって生き、彼とそのはらからの人生を尊敬する人である」アメリカの心理学者、E・フロムの「正気の社会」から)――これも忘れたくない教えではないでしょうか。
2024.04.02 記す
時実利彦著「脳の話」(岩波新書)
時実利彦著「人間のからくり」(毎日新聞社)
現代の生物学6「脳と神経系」(岩波書店)
相良守次著「記憶とは何か」(岩波新書)
著者紹介
時実利彦(ときざねとしこ)
1909年、岡山県備前町生まれ、
岡山一中、旧制六高、東京大学医学部卒。
東京大学医学部教授。脳研究所員。医学博士。
私は時実利彦著「脳の話」(岩波新書)を利用しまして、連絡月報昭和四十年リレー随筆を掲載しています。
 パブロフが一代のうちに確認した法則は実におびただしいものがあります。たとえば条件反射の「汎化」です。千サイクルの音を聞かせ、餌を与える――これを繰り返して千サイクルの音→唾液という条件反射が成立すると、八百サイクルの音でも千二百サイクルの音でも、はじめの条件に近いものなら、やはり唾液を出す、つまり脳に同じような反応が起こるということです。
パブロフが一代のうちに確認した法則は実におびただしいものがあります。たとえば条件反射の「汎化」です。千サイクルの音を聞かせ、餌を与える――これを繰り返して千サイクルの音→唾液という条件反射が成立すると、八百サイクルの音でも千二百サイクルの音でも、はじめの条件に近いものなら、やはり唾液を出す、つまり脳に同じような反応が起こるということです。
 アメリカが、一九六一年一月に打ち上げた宇宙ロケットに乗せられたチンパンジー「ハム君」は、条件反射によって、赤、白、青色のランプが点滅するたびに、それぞれ形の違ったボタンを必ず押すように仕込まれていました。こうして、いまでさえ条件反射は無重力状態での動物の脳の働きや、意識の状態を知るのに役立っています。将来はさらに役立つでしょう。同じ条件反射でも、人により成立と消滅の期間が違うことから、パブロフがいったように"人間の性格まで条件反射の個性によってわかる"かどうかはともかくとしても――。
アメリカが、一九六一年一月に打ち上げた宇宙ロケットに乗せられたチンパンジー「ハム君」は、条件反射によって、赤、白、青色のランプが点滅するたびに、それぞれ形の違ったボタンを必ず押すように仕込まれていました。こうして、いまでさえ条件反射は無重力状態での動物の脳の働きや、意識の状態を知るのに役立っています。将来はさらに役立つでしょう。同じ条件反射でも、人により成立と消滅の期間が違うことから、パブロフがいったように"人間の性格まで条件反射の個性によってわかる"かどうかはともかくとしても――。
 理性あるいは知性、それに感情という言葉で代表される、高等な精神作用をいとなむ新しい皮質は、人間がいちばん発達しています。反対に、下等な動物になるほど、脳全体の大きさにくらべて小さく、カエルの脳などになると、新しい皮質に相当する部分はほとんど見当たりません。
理性あるいは知性、それに感情という言葉で代表される、高等な精神作用をいとなむ新しい皮質は、人間がいちばん発達しています。反対に、下等な動物になるほど、脳全体の大きさにくらべて小さく、カエルの脳などになると、新しい皮質に相当する部分はほとんど見当たりません。
 「人間・ジキル博士」(一八三ぺージ)で説明したように、新しい皮質は古い皮質の働きを御しいるとはいいながら、その御する力は古い皮質のあり方にささえられているという、まことにデリケートな関係にあります。
「人間・ジキル博士」(一八三ぺージ)で説明したように、新しい皮質は古い皮質の働きを御しいるとはいいながら、その御する力は古い皮質のあり方にささえられているという、まことにデリケートな関係にあります。
 浄瑠璃「壇浦兜軍記」の"阿古屋の琴責"の段は、このからくりをもとに組み立てられております。
浄瑠璃「壇浦兜軍記」の"阿古屋の琴責"の段は、このからくりをもとに組み立てられております。
 大人=ニ・ニパーセント
大人=ニ・ニパーセント
 計算だけではありません。翻訳、台風の進路判定、病気の診断、お歳暮の品目判定……と、電子計算機は人間の頭脳そこのけの働きをしますが、計算を行なうのにも、判定や決定を下すにも、まず人間に問題を符号に変えて与えてもらう――つまり情報を入れてもらわなければなりません。これだけでも、人間の頭脳と人工頭脳とは大変な違いがあるのがおわかりでしょう。
計算だけではありません。翻訳、台風の進路判定、病気の診断、お歳暮の品目判定……と、電子計算機は人間の頭脳そこのけの働きをしますが、計算を行なうのにも、判定や決定を下すにも、まず人間に問題を符号に変えて与えてもらう――つまり情報を入れてもらわなければなりません。これだけでも、人間の頭脳と人工頭脳とは大変な違いがあるのがおわかりでしょう。
参考図書
あとがきに 昭和37年再販。昭和三十六年の十月はじめから五十七回にわたり毎日新聞に連載したのをまとめたものです。
さしえに加藤芳郎さんの漫画を借用せせててただきました。と記載しています。