(立川書房)1984年7月10日 第6刷発行
| 01 | 秀吉の出生は、結局、謎であるとしかいいようがない(P.42) | 02 | 天性、秀吉は人をひつけずにはおかない人物であった(P.43) | 03 | サルよ、禿ネズミよといわれながら(P.45) | 04 | 人間は五、六歳までにきまる。秀吉はおっかさんのおかげで(P.47) |
| 05 | 士民の子も大金持も、生活の内容は大差なかったから(P.48) | 06 | 始めから天下を望んだやつはみんな駄目になってしまう(P.49) | 07 | 男というものは挫折するたびに大きくなってゆくものだ(P.50) | 08 | 政治家としては秀吉より家康のほうが一枚上だが(P.52) |
| 09 | もし、秀吉に跡継ぎがいたら歴史は一変していたろう(P.53) | 10 | 人間、やることは必然的にその師匠に似てくるものです(P.54) | 11 | 死にざまを見ればその人間がわかる(P.56) | 12 | 芸術文化の大パトロンとして秀吉の名は永遠不滅である(P.57) |
| 01 | 血で血を洗う戦国の乱世に(P.114) | 02 | "信長の妹、お市の方(P.115) | 03 | 戦国の女は気が昂っていた(P.116) | 04 | お市の方の三人の娘たち(P.118) |
| 05 | "しあわせであったかも知れないす(P.120) | 06 | 淀君と寧々(P.121) | 07 | 夫・忠興を狂気に走らせた(P.122) | 08 | 戦国時代に微温湯(P.123) |
| 01 | 長野主膳に出合ったときから、不思議な宿命に行き当たる。(P.260) | 02 | 直弼は水戸藩を恐れた。何せ十四代将軍で争った仲だから(P.261) | 03 | 第二次大戦で本当に戦ったのは、天皇しかいない。(P.264) | 04 | 桜田門外の変もかなり疑問の事件だ。資料に表われない裏側の事情があったはず(P.265) |
| 05 | 昔の大名というのは、政治でも、座興にしても真剣にやった(P.267) | 06 | ****** | 07 | ****** | 08 | ****** |
|
『男の系譜[全]』(立風書房)(1982年4月10日 初版発行)
目次
Ⅰ 戦国篇 織田信長 渡辺堪兵衛 豊臣秀吉 真田幸村 加藤清正 徳川家康 番外・戦国の女たち Ⅱ 江戸篇 荒木叉右衛門 幡随院長兵衛 徳川綱吉 浅野内匠頭 大石内蔵助 徳川吉宗 Ⅲ 幕末維新篇 井伊直弼 徳川家茂 松平容保 西郷隆盛 編者あとがき 以上の内容のものです。 |
|
秀吉の出生は、 結局、謎であるとしかいいようがない…… P.42 秀吉についてはね、貧しい、卑しい生れでありながら立身出世して天下を取った、そういう人物として一般には受け取られている。
天性、秀吉は
秀吉の偉くなりかたというのは、まさに強運の人というのを絵に画いたようだということになっている。けれども運だけで偉くなれるわけじゃないから、それじゃ秀吉があれだけになった一番の原動力は何かというと、天性人心を得るような、そういう天性を持っていたんですね。人の心をひきつけずにはおかない……。
サルよ、、秀吉は
秀吉の偉くなりかたというのは、まさに強運の人というのを絵に画いたようだということになっている。けれども運だけで偉くなれるわけじゃないから、それじゃ秀吉があれだけになった一番の原動力は何かというと、天性人心を得るような、そういう天性を持っていたんですね。人の心をひきつけずにはおかない……。
人間は五、六歳までにきまる。
若いときに、どういう人間に出会うか。それが人柄というものを左右する。その左右することを自然に選んでゆくわけですよ、だれでも。
士民の子も、
秀吉というと、すぐに、成上り者といい、士民の子というでしょう。しかし、昔は、そりゃたしかに大名なり大金持ち、大百姓というものはいるけれども、生活自体はそんなに士民とかわらないですよ。ないんだよ。貧富の差というものが。
始めから天下を望んだやつは
秀吉が、始めからひたすら天下を取りたい一心で、それを目的にしてあれこれやっていたら、とっくに駄目になっていたでしょうね。信長に仕えている間、秀吉はまるでそんな気はなかったといっていい。……ただ、信長が自分にうってつけの主人であり、信長にとっても自分はうってつけの家来だという、そういう感じはあったでしょう。理想的な、双方がピタッと呼吸の合った関係で、その活動の中に主従とも酔っていたんじゃないですか。二人の関係を言えば。
男というものは
いま、現にやっていることに、どれだけ打ち込んでいるかという、その積み重ねが後になってそのときが来たときの差になる……かといって、ただ一所懸命に努力するというのでも駄目だということは、この前にも話したと思うけども。行く先の望みということでどりょくするというのは、その望みが思いとおりにならないと、もう続きませんから。苦痛で。
政治家としては
信長にね、秀吉がこういっていますよ。日本の天下が治まったら自分は朝鮮にやってくれ、朝鮮を自分に治めさせてくれ。そうしたら、お前は大変な大風呂敷だと信長が笑った。秀吉が異国へ目を向けるという感覚は、これはやはり信長の感化でしょうね。
もし、秀吉に跡継ぎがいたら
せっかく天下をとっても、自分亡きあとの天下をだれに譲るかということになったとき、秀吉の心は暗澹としてくる。家康のように将来への展望というものが持てないわけだから。
人間、やることは
信長にね、秀吉がこういっていますよ。日本の天下が治まったら自分は朝鮮にやってくれ、朝鮮を自分に治めさせてくれ。そうしたら、お前は大変な大風呂敷だと信長が笑った。秀吉が異国へ目を向けるという感覚は、これはやはり信長の感化でしょうね。
死にざまを見れば
天下をとった秀吉というのは、朝鮮を攻めとって、そこへ天下様をお迎えするとか、少し誇大妄想気味になる。とうとう狂ってしまわれたと家臣みんなが思った」くらいだからね。家康なんかに、これはもう長いことはないという見きわめをつけられてしまう。もともと朝鮮征伐に賛成した大名はひとりもいないんだからね。みんなはんたいしているわけだ。
芸術文化の大パトロンとして
秀吉の死んだあと、秀吉の時代はたった十年かそらしかなかった。しかし、この十年というものは大変な十年ですよ。
|
|
江戸の「元禄」も「昭和元禄」も、 つまりは戦後の繁栄ということだ…… P.176 もう、一時代前のことになるけれども「昭和元禄」という言葉が流行ったろう。流行らせたのは福田赳夫さんだというけれどね。 江戸の元禄と、昭和の元禄、必ずしもそっくり同じではないが、確かに共通するところがある。それはどういうところかというと、つまり「戦後の社会が繁栄した」ということだ。そこが一番よく似ている。 戦争が始まったあとの国が戦争に費やしていたエネルギーを平和に振り向けることができたために、めざましい勢いで繁栄したということ。その点が非常に似ているんだよ。 元禄時代というのは一六八八年に始まって一七〇三年まで続くわけだが、これは、いわゆる戦国時代の終りから数えて七、八十年たった時期に当る。 関ケ原の天下分け目の合戦が一六〇〇年、徳川家康が江戸に幕府を開いて征夷大将軍となったのが一六〇三年だろう。それが江戸時代の始まりということになるけれども、まだ戦争は完全に終っていない。大阪に豊臣秀頼がいたからだ。家康にしてみれば、これだけが目の上のこぶだった。 それで、無理やりにも豊臣方を戦争に引きずりこんで、ついに完全に息の根をとめる。それが大阪城の攻防だ。冬の陣が一六一四年、夏の陣が翌年の一六一五年。これでようやく徳川幕府の基礎というものが固まったわけだ。 家康が秀頼を亡ぼして後、二代秀忠、三代家光、四代は家綱、それから五代綱吉でしょう。綱吉が将軍位に就いたのは確か一六八〇年だと思ったな。 大阪の陣以後の七、八十年というのは、これはまったく戦争が絶えて、それまでは全部戦争に使っていた物資とか生産力とか輸送力、ひとくちでいえば経済力だな、それがそっくり平和に振り向けられてくるから、当然、そこに繁栄の状態というのが、あらわれてくる。それが元禄時代を現出したということなんだね。 昭和元禄というのも、太平洋戦争が終って三十年近くたって、経済力が全部平和のために振り向けられた結果に他ならない。だから、そこのところが根本的に似ているというわけだ。 日本は敗戦国になったけれども、その戦後の三十年間というものは、まったく戦争をしていない三十年なんだ。これは日本だけじゃないのかな。ドイツもそうか。 世界の各国、主だったところは、この三十年間にも相変わらず戦争のためにエネルギーを使っているでしょう。イギリスだってちょっとやったし、フランスはアルジェリア、アメリカに至ってはベトナムに手を出して大変だったわけだ。こういう国にしてみれば、戦後というのがないわけで、ずっと戦争が続いているということだからね。 ソ連の場合は、自分の国が直接戦争をしていないかわりに、あっちこっちに介入しているから、事実上は戦争をしているのと同じだろう。他のいろいろな国のために武器を生産して提供しているんだからね。中国とも、表向きは冷戦状態ということだけれども、つねに戦時体制にあるわけだ。 だから、文化水準とまではいわないまでも国民生活の水準というものは、ソ連ではいまだに繁栄から遠いわけですよ。 結局、経済力を全部平和に注ぎこんで国民の生活が豊かになったという点では、今度の戦争で負けた日本が一番。この三十数年というもの、まったく無傷でやってきたんだから。従ってこの高度成長になったわけだ。 しかし、反面では、社会にさまざまな歪みというものがあらわれてくることにもなる。政治家がちゃんとしていないから。五代将軍・綱吉の元禄時代もやっぱりそうだった。 ※参考図書:大石慎三郎著『元禄時代』(岩波新書)(黒崎記)
五代将軍・綱吉の生母・桂昌院。
綱吉のことをいうとね、この人は三代・家光の第四男として生まれたんだ。四代・家綱の弟ということになる。 綱吉のおっ母さんというのは桂昌院という人で、もともとは卑しい素性の女なんだが後に偉くなって、ついには江戸城の大奥で幕府を操るほどの権力を発揮したわけだ。 この桂昌院のときにはじめて幕府の大奥に女の権力が生れたんですよ。綱吉の時代に。それまでは、女はほとんど政治にくちばしを入れることがなかった。幕府の閣僚、大老、老中、むろん将軍もそうだが、女には一切口を出せず、全部、男がとりしきってきたものだ。 それが綱吉の時代になって、綱吉の生母である桂昌院が将軍の母親として権力を拡張したがために、ここに大奥の権力というものが生れたわけだ。政治、経済、社会に至るまで、あらゆるところに江戸城大奥の女どもがある程度強い影響力を発揮するようになったのは、この五代将軍・家綱の時代からですよ。
それで、桂昌院だけれども、もとはお玉ということだけで身元がはっきりわからない。俗説には、魚屋の娘だというね、京都の。あるいは京の堀川の八百屋の娘ともいう。 家光がどうしてこれをお妾にしたかというと、自分が三代将軍になったときに、幕府の威勢を京都の朝廷に誇示するために大変な行列を連ねて京都へ乗りこんだ。そうして将軍が天皇と対面したわけなんだ。 これはもう素晴しい行列で、大変豪華なものでね。京都へ行って盛大に金をばらまいているし、つまりはそれによって徳川の威光というものをみせつけたわけです。 そのときにね、向こうに滞在している間になんらかの伝手でお玉が将軍つきの侍女になって入りこんできたんじゃないかと思う。 別の一説では、参議六条有純の娘お万という女性が、寛永十六年、伊勢山寺・慶光院の住持になったお礼言上のため江戸へ下ったとき、お玉はその侍女としてついて行ったというんだな。 お万の美貌に目を奪われた家光は、江戸へ出てきたお万をそのとき還俗させて側室にしちゃった。それで、お玉もそのまま仕えているうちに、今度は家光がお玉にまで手をつけたというわけだ。 まあ、いずれにせよ、魚屋だ八百屋だか、よく身元もわからないような娘が将軍の身近に仕えるようになったということは、後の江戸時代の幕府においては、先ず考えられないことですよ。中期以後は、そういうことは例がないんじゃないか。 だから、そのころはまだ戦国時代のな残があって、割合に闊達な素朴な感じというものがそこかしこに残っていたんだろうね。女であっても、そいうふうに自分の魅力を武器として、ついには将軍の側室になり、後には幕府の政治までも操るところまで行く……そういうことができるだけの、はつらつとした時代だったということでしょう。いいことか悪いことかは別として、つまり男にも女にもチャンスというものがかなり与えられいたわけだ。 とにかくそういうことで、お玉というのは家光の側室になり、後の五代将軍・綱吉を生んだ。家光には長男・家綱のほか腹ちがいの息子が四人いた。次男が亀松、三男が綱重、それから綱吉で、この下にもう一人、鶴松というのが生れている。 兄さんが三人もいて、自分は四男坊だから、まさか将軍になるとは思っていなかったわけだ、綱吉としては。それは全然計算に入れてなかったろうよ。お玉……桂昌院もそういうことは考えていなかったに違いない。それが、四代将軍・家綱に子どもがいなかったために、綱吉のところへ五代将軍がころがりこんできた。
学問だけが趣味で学問に淫した綱吉。
家光は長男の家綱を世子にしたが、弟の綱重を甲府城主、綱吉を館林城主として、それぞれ二十万石を与えた。他の子どもは早く死んじゃったんでしょう、幼いうちに。 ところが綱重という人も早死にしてしまうんだ。で、残っている家光の子どもというのは、上州・館林の殿様になっていた綱吉だけ。 館林の城では、ごくつつましい生活をしていたんだよ、綱吉も。そのころはたとえ将軍自身といえどもきわめて質素に暮していたんだから、家光自身。 そりゃ家光という人はいろいろ噂のある人ですよ。乱暴したとかね。あまり芳しからぬ話もあるけれど、将軍の生活自体はごく質素なものだったんだな。 それはどういうところでわかるかというと、川越に喜多院という寺がある。そこに三代将軍・家光のころの御殿の一部があって、春日局の使っていた部屋がそこに残っているんだ。それを見ると実につつしまやかなものです。そういうところで家光は育っているわけだからね。御殿といっても、あまり御殿という感じはしない。地方のちょっとした庄屋さんのお屋敷程度のものだよ。 そういう質実剛健な生活をしたわけだろう。将軍が。ましてや館林の殿様に過ぎない綱吉がそんなに贅沢な生活ができるわけがないんだよ。 どんな物でも大切にしておいて、いざというときに役立てることをモラルにいしていた時代ですからね、その当時は。そういう根本的な人間生活のモラルを将軍自ら実践していたんだ。筆一本でもちびるまで使う、冬でも足袋をはかない、そういう生活が指導階級にあった。 だから、義理の兄貴である家綱が死んで五代将軍がころがりこんできた当初は、綱吉もまだ割合とつつましくやっているわけなんだ。 家綱という人は生まれつき病弱なほうだったらしい。四十歳で病死している。わずか十一歳で将軍になったから在職期間は長いけれどね。 この家綱に子どもがない。それで弟の綱吉を養子ということにして将軍を継がせたわけですよ。ところで、この綱吉だが、父親の三代将軍・家光という人が、自分が若いころ勉強しないで武術ばかりやって学問しなかったということを悔んでいた。そんなわけで、家光は晩年に桂昌院に、 「自分は学問をきらって今日におよんだことを後悔している。さいわいに綱吉はかしこい性質のようであるから、つとめて聖賢の道を学ばせるように……」 そういう遺言をしたんだね。桂昌院はそれを守って綱吉に子どものころから盛んに学問させた。いい先生をいっぱいつけて。今日でいえば教育ママということだね。 子どもというのは、たいてい勉強なんて嫌いなもんだろう。親がいくら勉強しろ勉強しろといったてね、いやがるのが普通ですよ。ところが綱吉は好きなんだ。 学問することが大好きで、十七、八のころは家来を呼んで〔論語〕の講義をした。下手か上手か、それはまあ別として、綱吉としては家来を集めて講義して聞かせるのが何よりも楽しみなんだよ。 むろん綱吉自身の天性ということもあるだろう、幾分かは。だけど母親のせいだよね、大部分。桂昌院は、もともと身分が卑しい生い立ちでしょう。そのことがコンプレックスになっていて、いつもひた隠しにしてきたに違いない。 その反動でもあるんだろうな。むやみやたらに綱吉を可愛がると同時に、学問でなければ夜もあけぬという育てかたをしたわけだ。子どもの時分からこんな育てかたをされたらたまったもんじゃありませんよ。 学問だけに熱中する子どもというものは、不健全にきまっている。子どものころは、何よりもまずその小さな肉体をフルに使って、躰で万象を確かめるべきなんだよ。 綱吉が家来に講義するのが楽しみだというのは、それをつまらないという奴はいないからね。恐れ入って聞いていなくてはならないわけけだもの。だから綱吉は面白くてしょうがない。自分はこんなに学問ができるんだぞ、自分は学問のある偉い殿様なんだぞ、そう信じこむようになって、それが誇りなんだ。将軍になったときには、それで、学者将軍なんていわれた。 他に何も楽しみを知らなかっただろうと思うね。〔論語〕の講義なんかする以外に、そういう人間、いまでもいるじゃないの。学問が趣味になり、いわば学問に淫してしまって、学問ばかりで世の中のことがまったくわからない……そういうのが。
綱吉が五代将軍になれたのは、ひとえに
綱吉が五代将軍になったすぐのことだ。越後騒動というのがあった、高田に。越後高田城主・松平光永の家中で世継ぎ問題をめぐって騒動が起きた。例の小栗美作の事件だ。 この越後藩の騒動は四代・家綱のころから引き続いていて、なかなか解決できなかったわけだ。延宝七年、これは綱吉が将軍になる前年だが、幕府は一応裁決を下して家老・小栗美作の勝ちということになった。これは当時の大老である酒井忠清が小栗の賄賂を受け取っていたためだというんだけれどね。 その翌年、綱吉は、将軍になるやいなや早速この越後騒動を自ら再審するとういうわけだ。就任早々に出て行って、たちまち解決してしまったものだ。一日か二日のうちに。 御三家以下、諸大名がずらりと居並ぶ中で双方のいい分を聞きとると、その場で大声で判決を下し、翌日には小栗美作に切腹を命じた上、続いて松平光永を改易だ。この綱吉の裁きというのは大したものだった。だから、偉い将軍が出てきた、これで徳川幕府は万々歳だというわけだよ。 そもそも綱吉は、将軍になれるかなれないか、わからなかった。何故かというとね、四代将軍・家綱を輔佐していた大老の酒井忠清が、家綱が間もなく死ぬというときに、皇室から天皇のお子さんをもらってきて将軍に据えようという構想を打ち出したんだ。 酒井忠清というのは、当時、大変な権勢を誇っていて、世間では忠清のことを「下馬将軍」と呼んだくらいだ。忠清の邸が江戸城内大手門外の下馬札の付近にあって、将軍同様の権力をふるったからだ。 その忠清がどうしてそういう考えを起こしたかというと、家綱の弟の綱吉には老中・堀田正俊という人がついている。この堀田正俊に対抗して自分の勢力を維持するためには、家綱に子がいない以上、だれか他のところから候補者を連れて来なければいけないわけだ。それで、いわば窮余の一策だな。「鎌倉幕府の先例にならって……」という大義名分のもとに、京都から有栖川宮幸仁親王を迎えして将軍にしようと提案した。 老中の堀田正俊という人は、下総の国・古河の城主で、三代将軍・家光の乳母として有名な春日局の養子格なんだよ。堀田正俊のお父さんという人も、やはり、春日局の養子格で、非常に春日局に可愛がられた。 春日局といえば、乳母とはいえ家光を育て上げて将軍の位に就けたほどの人で、その養子格だからね。堀田正俊。将軍直属の重臣ということで、その勢力もなかなかあなどりがたいものがあった。 だから、酒井忠清も、うっかりしていると自分が蹴落とされてしまうから、そこで宮様をもらってきて将軍にしようとしたわけですよ。これが実現すれば、自分は将軍のうしろだてとして権力が安泰になるからね。 ところが、大老・酒井忠清を恐れるあまり一人として反対する者がない中で、敢然と反対意見を主張したのが堀田正俊だ。 「館林侯(綱吉)は将軍家の実弟であられる。正統の後嗣まさにこれなり。皇族をわざわざ迎えまつるなどとは、まことにもって不思議千万なことである」 立派な肉親の血を分けた弟というものがありながら何事かというわけだよ。 それで両者の間に、むろん、暗闘がくりひろげられたわけだね。いよいよ家綱が死にそうだというとき、堀田正俊が綱吉を連れて江戸城に入ってきた。正俊はよっぽどうまく事を運んだろうな。忠清の気付かぬうちに綱吉をさっと城内に連れてきて、家綱が寝ている枕元で、次の将軍は綱吉であると家綱に認めさせてしまった。電光石火のごとく。 これでは、さすがの酒井大老も手も足も出ない。結局、そのために酒井忠清は失脚しますね。「陰の将軍」といわれたくらいの酒井は、こうして威勢を失うわけです。堀田正俊に出し抜かれて。 ※令和四年の日本の政治家でも政権の座の主人公のうしろだてとしての権力をえようとしている。2022.04.15記す。
貞享元年八月二十八日、江戸城中にて
だから、綱吉にとっては、堀田正俊は自分を将軍の座に就けてくれた大恩人だ。それで家光が春日局に頭が上がらなかったように、同様に綱吉も正俊に頭が上がらない、少なくとも将軍になった当初は。 堀田正俊という人は。本来、なかなかの硬骨漢でね。幕府閣僚随一の剛直無類をうたわれた人物だった。それでいて馬鹿じゃないしね。綱吉を見事に将軍にした手腕はなみなみではないわけだから。 正俊は、もちろん、酒井忠清のあとをおそって大老になった。こうして五代将軍・綱吉とこれを輔佐する堀田大老との幕政体制がととのえられた。正俊は綱吉を立派な将軍にしようと思っていろいろ進言するし、一方、綱吉も堀田大老の意見をよく聞き一所懸命政務に励む。だから最初のうちはボロが出ない。 ところが、堀田正俊が思いもかけぬ急死をとげてしまう。貞享元(一六八四)年八月二十八日というから、綱吉を輔佐することわずか四年だね。
それは、大石内蔵助が祖父のあとをついで国家老となって五年目のことで、浅野内匠頭がはじめて赤穂へ国入りをした翌年ということになる。もともと堀田正俊と稲葉正休は親類なんだ。それで片一方は若年寄で、堀田は老中だから、幕府の政治のことをしょっちゅう話し合わなければならないわけだ。 その間に、はっきりした理由はわかっていないけれども、お互いに意思の疎通がなくなって行ったようだ。堀田正俊という人は大老になったからといって威張るような人物とも思われないんだが、大老という職掌柄、上から抑えつけるということもあったでしょう。かねてから政治上、意見が合わなくて、いがみあっていたのは事実だな。 その恨みがあったのか、突然、斬りつけて大老を殺してしまった。稲葉もその場で斬られて死んだ。この事件は、その場で喧嘩両成敗になったから、あとに問題が残らなかった。 けれどもね、綱吉自身の立場で考えるとどうなるか。綱吉という人は、自分の在職の間に二度、江戸城中での刃傷事件を經驗しているわけだよ。 これはだれも気が付いていないし、書いた人もいないが、自分がまだ若いときに堀田正俊が殺されたということがね、浅野内匠頭の刃傷事件における綱吉の反応に影響しているのではないかと、おれは思っている。 頼りにしていた、父親とも思っていた堀田正俊を稲葉が殺したわけだろう。憎いよね。そいう思いがあるから、刃傷事件という場合には殺されたほうにどうしても同情的になる。吉良上野介に対しても、あのとき、そういう気持がはたらいたんじゃないかと思うんだ、とっさに。それで、あんな一方的な裁判をすることになった。むろん、それだけでなくていろいろな理由はあるだろうけれどね。この視点から「松の廊下」事件を書いたのはまだないと思うんだが。 ※元禄14年3月14日 (旧暦)(1701年4月21日)、赤穂藩主浅野内匠頭長矩が、江戸城松之大廊下で、高家吉良上野介義央に斬りかかった事に端を発する。 事件当時、江戸城では幕府が朝廷の使者を接待している真っ最中だったので、場所柄もわきまえずに刃傷に及んだ浅野に対し、第五代将軍徳川綱吉は大激怒、浅野内匠頭は即日切腹、浅野家は所領の播州赤穂を没収の上改易されたが、吉良に咎めはなかった。かえってお褒めの言葉さえ賜った。史料によると、老中は将軍の命をふくんで高家詰所に臨み、「上野介儀公儀を重んじ、急難に臨みながら、時節を弁へ、場所を慎みたる段、神妙に思召さる。是に由て、何の御構もなし、手疵療養致す可き上意なり。」と伝達したということである。その後の経過も、まさにこの線に沿ったもので、結局、浅野家は断絶、家来は浪人しなければならないとことに対し、吉良にはもと通りの出仕を許したのである。 この処置はいわゆる喧嘩両成敗の原則に反し、きわめて片手落ちであることの不満が浅野家の側に生じたということである。 ※参考:赤穂浪士と喧嘩両成敗(黒崎記)
齢を取ってから、やったことないことを
堀田正俊が殺されたとき、綱吉はいくつになるかな。正保三(一六四六)年生まれで、将軍の座を射止めたのが三十五歳のときだから、このときすでに四十近いわけだ。もう若いという年齢じゃない。 だから、堀田を失ったことでがっかりしたし、情けなく思ったけれども、その反面、うれしくないこともない。頭を抑える家来がいなくなったんだから。 いよいよこれからは万事、自分の思うままということになったわけだよ。それから急速に綱吉が変になってくる。 親の代からの重臣というのは、頼りになると同時に、なにかにつけて煙たい存在でもある。どこの殿様でもそうなんだ。重臣にいじめられ、鍛えられて一人前になって行くわけだが、鬱陶しいんだな、どうしても。 館林時代からの質素な生活が、堀田正俊の死後、手のひらを返すように一変してしまう。頭を抑えていた堀田正俊がいなくなって、もうなんでも自分の思う通りにできるというので、それまで家綱の内部に鬱積していたものが反動的に出てきた。 それからは、どんどん贅沢しはじめて、あとは贅沢三昧。御殿を建て直したり、毎日のように宴会をやったりしたんじゃないの。役者を招んで踊らせたㇼ、お能に凝ったり……。 若い時分は学問一点張りでしょう。なにもやったことがないんだ。他に、人間、齢をとってから急にやったことないことをやると、どうにもならない。 こういうことをいうと自慢するように取られるかも知れないが、そうではなくて、おれなんかの場合、戦争に行くまでは株屋だろう。ごく短い間で、まあ十年くらいやったような気がするけれども、充実していたからね、いろいろと……。 だから戦後、兵隊から帰って来て、なにもないだろう。だけど、一向に平気なんだ。何を着ていようが気にもならない。西洋乞食みたいな恰好していても平気なんだよ。戦後、おれはついに背広というもの、つくらなった。若い人はみんな月給をやりくりして、食うもの減らして背広をつくっていたよ。靴を買い、ネクタイを買ってね。おれは昭和二十五、六年ごろまで海軍の服だったな。この間死んだ谷中の叔父のお古を一つもらって持っていたけどね。 昭和二十五年ごろには、ほとんどだれでも背広だった。だけど、別段、欲しいと思わない。全然。贅沢なこともなんにもしようと思わない。若いうちに贅沢の限りをしてしまったからだ。 戦争にも行かないで、あのままだったら、どうもこうもならなかったろうね。幸か不幸か大変な経験をして、だれでもそうだけれど、戦争に行ったために前の生活が中断されたから……。 とにかくそれで、戦後になってもいまさら贅沢しようという気が起きないんだ。普通、人がだんだん齢を取るに従って覚えて行く贅沢の味を、おれの場合は十代のうちに圧縮して知っちゃったということかな。 ここで変なふうに自分をどうかしようと思ってもしようがない。そうでしょう。背広だけやっと買ったところで、あとの物はどうなるというんだ。それに似合うワイシャツがない。ネクタイがない。帽子がない。靴がない。コートがない。 そういう物が全部そろえば、買ってもいいけれど、なんにもそろわない。みんなチグハグで、だから買う気になれないんだよ。 家を持つんだって、もともと大した家に住んでいたわけじゃないけれども、戦前でもね。だけど、どこだってきれいな家へ入って、うまいもの食ったり、旅行したりね、いろんなことをしてきてるだろう。 だから、いい家を持ちたいとということもないんだなあ。おれの場合は要するにそういうことなんだけれども、綱吉の場合はそうじゃないからね。 三十過ぎてまで質素、質素とやらされてきて、思いもかけない将軍になって、はじめのうちは堀田正俊なんかが頭を抑えていたからおとなしくしていたけれども、その堀田が死んでしまったろう。そこではじめて贅沢の味を覚えたから大変なんだ。
歴史に残る悪令「生類憐みの令」も、
綱吉がこうして贅沢に溺れて行くと、当然、将軍のおつ母さんである桂昌院も、女ながら大変な勢力を備えるようになる。 というのも綱吉は論語なんか勉強して自分では非常に親孝行のつもりなんだから。ところが、綱吉の親孝行というのは自分の母である桂昌院のみに対してであって、他人の孝行なんかどうでもいいんだな。 それがために、変な坊主が、隆光というんだが、とんでもない権力を持つようになる。これは紀州のどこかで山伏のようなことをしていた一種の予言者なんだ、密教の。千里眼であるとかいってね。この坊主が桂昌院に取り入って、すっかり信頼を得てしまう。 綱吉が将軍になって間もなく重い病気にかかった。すると早速、隆光が祈禱をしてね、偶然にもなおってしまった。むろん偶然に過ぎないけれども、それは昔の人だからね、みんな祈祷のためになおったと信じるわけだ。綱吉もすっかり隆光を信頼するようになる。 そうすると隆光は、ますます気に入られようと思うから、 「将軍家におかせられましては戌の年のお生まれにござります。なれば、無益の殺生を禁じるが肝要。ことに犬をいたわり、これをいつくしむことによって、御家はますます御繁栄。天下は万万歳にござります……」 こういう、愚にもつかぬことをいい出した。実際は、綱吉は最後に死ぬとき自分の子どもはみんな死んでしまって、結局は自分のすぐ上の兄で甲府の殿様になつた綱重、この人の子どもの家宣が六代将軍になったんだからね。 いま、新橋に「御浜御殿」というのがあるだろう、浜離宮、あれは甲府の殿様の下屋敷だった。 そういうことで、悪名高い「生類憐みの令」というのが出るわけだ。手はじめは犬を殺してはいかん、犬を大事にしろという法律だったが、そてがどんどん強化拡大されて動物全部を愛護しろということになった。 江戸城の中で将軍の料理番が魚を料理しているとき蚊が一ぴきとまった。で、パチンとはたいてつぶしたら、それを見ていた同僚がいいつけた。可哀そうな蚊を無惨に殺したというので料理番は島流し、同時に、告げ口した奴も見ていながら制めなかったというのでこれも八丈島送り。 いまの大久保から中野あたりに、十八万坪の犬のアパートをつくって、江戸中の野犬を集めて、うまいものを食わせた。「御犬屋敷」というんだ。八万二千頭もいたそうよ、そこに。 その予算だけでも一年に二十万両とか三十万両とかかった。そういう負担は全部、江戸市民にかかるわけだ。犬医者なんていうのは肩で風切って歩いた。金もたっぷり入るしね。 犬どもは「御犬さま」と呼ばれて傲慢無礼になり民家に入りこんで食いちらす。追っ払うわけには行かないんだ。そんなことをしたらすぐ、犬目付に捕まって牢に入れられる。野良犬が子どもに咬みついてもどうにもできない。 綱吉は手前のために贅沢のしほうだい。犬は全部市民の負担。今日、われわれがやらされているのと同じだよ。われわれが税金払ってトラックのために道路つくっているのとおんなじなんだよ。 現代社会は文明的とかなんとかいっているけれども、われわれの租税でバカみたいな議員どもの高い給料を払っているわけでしょう。結構な話だよね。バカでない政治家なら、いくらでも払って、十二分につかってやってもらいたいと思うけど、バカ議員、バカ政治家ばっかりでしょう。むろん、全部じゃないが。 国民をなめているわけだよ、手前の苗字やな前をひらがなで書くじゃないの。ポスターでもなんでも。あれは、おのれの字を投票者が読めないと思うから、そういうことをするんだよ。ひらがなで書く奴が選挙のたびにふえるな。芸能人みたいに。 だから、そういう意味では元禄時代に似ている。政治家が国民をばかにしているという意味で。あのころも現代も変っちゃいないわけだよ。 元禄時時代は綱吉の独裁時代だから、そもそも綱吉が国民をばかにしているということだな。しかし「生類憐みの令」のような奇怪愚劣な法令に反対する家来が一人としていないという、これも呆れた話だ。媚びへつらう奴ばかりで。 堀田正俊の死後、綱吉の独裁者としての力は物凄かった。もともとバカな人じゃないから。やたらに書物を読んでいて、きれる人なんだから。こわいわけだよ、家来どもは。 2022.04.17記す。
戦争があるとないとではこうも違う。
戦争があるとないとではこうも違う。江戸に蕎麦屋ができ、茶漬家ができ…… 綱吉が一つ法律をつくったことで役人がふえたわけだ。犬のための役人が。犬の収容所の所長もできるし、犬目付という犬のたの警察もできる。それは犬を虐待する者を探して歩くんだ。ちょっと野良犬を蹴飛ばしたりしようものなら、すぐしょっぴかれる。そうすると手柄になるんだから、犬目付の。 そっくりだろう、現在の社会の様子と。いろいろな世の中のことが、封建時代であろうと二十世紀であろうと、やっていることは変っちゃいないんだ。人間のしくみが同じだからね、やることは同じなんだよ。 それでね、こういう悪政が続く中で、綱吉は贅沢をしているわけでしょう。当然、他の大名もこれに習う。将軍といえども真冬に足袋もはかずにあかぎれだらけだったものが、いまや足袋一つでも贅沢な生地でつくるということになる。刀でもただの刀では気が済まないから金とか銀とかで鍔をつくったりする。持ち物すべてが贅沢になってくる。着物にしても、女の下着にしても。食いものだって、昔は外へ出るときに弁当持って行かなければならなかったのが、元禄時代になると、金さえ持っていれば外で食えるようになる。食いもの屋がでできたから。 どうしてそういう店ができるようになったかわかるかい? 戦国時代には「余剰」というものがない。物質の面でも時間の上でも、戦争のためには、食いものだってなんだってできるだけ切り詰めて、武器をつくり大砲の弾つくりをしなければればならないだろう。 人口も少なかった。それが戦争がなくなると、戦争に使っていた人手が余る。人の手があれば土地を開墾できるじゃないの。作物の耕作地帯がひろがる。人手が余っていれば米の他にも何かつくれる。蕎麦だとか。それがどんどんできるでしょう。 食糧事情にゆとりが出てくるわけだよ。米の他にもいろいろつくれるということで。だから、まず、蕎麦屋というものができる、都会では。余った人手の所産だよ、これは。金さえ持って行けば蕎麦が食べられるから大変便利になった。はじめは太く打った黒い蕎麦を箸でちぎるようにして口へ入れ、丹念に噛みしめるものだった。それがしだいに調理のしかたも工夫されてくる。 たとえば、「蒸切蕎麦」などというものができるようになった。これは、湯でさらした蕎麦を水で洗って、それを蒸篭に入れて熱く蒸すんだよ。これを柚子の香りのする汁につけて食べるんだ。 元禄のころは、江戸では蕎麦屋と茶漬屋が大流行だった。米の生産も余剰分ができるようになったからね。ちょっとした盛り場へ行けば三色茶漬、五色茶漬などというものが食べられる。お茶漬けといっても今日のそれとは違うよ。三色というのは三種類のおかずで飯を食わせるということなんだ。 西瓜なんかも、信長、秀吉のころは南蛮渡来で、ポルトガルのものを船底に冷たくして運んできて、日本へ上陸すれば一個いくらか知らないが、とても一般の人は買えない値段だった。千利休なんかが、親指の頭ほどに切って茶会の席で使っているわけだ。 それが人手が余って畑も広くなってくると、蕎麦ばかりじゃない、西瓜なんかもできるから、夏になると西瓜、西瓜と売りに来て、都会なら金さえもっていればどんどん買える。 戦後、われわれが何もないところから、だんだん電気洗濯機だ、電気掃除機だ、テレビ、ステレオだ……こうなってきた。元禄時代から見れば現代は大変な贅沢だけれども、戦国時代から見ると元禄時代はもっと贅沢だった。夢みたいな、とんでもない贅沢だったわけだよ。 それほど戦争というものはエネルギーを食っちゃうんだよ。戦国時代から家光のころまでは宿屋へ行ったって丹前なんか出さない。江戸時代中期になっても出さないな。幕末に近くなってからだ、こういうものを出すようになったのは。 宿屋へ着くと袴ぐらいは脱ぐけれども、ちりを払って部屋に通って、それで金を払って米を買うんだよ、客が。自分で宿屋の台所へ行って鍋釜を借りて自炊するんだ。弁当も自分でつくる。 それが綱吉の時代になれば、人手が余ってきて、金儲けができるから、宿屋へ行っても金さえ出せば全部用が足りるようになる。湯に入っている間に飯ができていて、これを食えばいい。昔の旅と較べたら天地の差だ。生活革命だよ、これは。こういうように世の中がなってくると、いろいろな商売が出てくる。ということは武士の使う金がみんな町人の懐に入ってしまうということだろう。元禄時代になって本当に町人が経済的な実力をつけたんだよ。 そのかわり、綱吉が死んだとき、江戸城の御金蔵はからっぽですよ。祖先の遺した莫大な金を全部使いつくして、そのうえ町人に借金まで残した。それで、みんなも知っている御三家の一人、徳川光圀、例の水戸黄門がずいぶん綱吉に意見したけれども、結局、光圀は怒って隠居しちゃうわけだ。 2022.04.18記す。
なんでも覚えるととめどがなくなる綱吉。
贅沢と慢心が昂じてくると、今度は女に狂い出す。綱吉というのは、はじめは女にあまり興味がなくて学問ばかり。むしろ男色のほうだった。これでは跡取りの子も生まれないし困るというので、牧野成貞、これは綱吉が館林の殿様だったころからの家来で、綱吉が将軍になると抜擢されて側用人になったが、この人がいろいろ考えた挙句、なんとかいうきれいな女を腰元にして将軍に近づけた。そうしたら綱吉、覚えちゃった……女の味を。 この将軍はなんでも一つ覚えるととめどがなくなるんだよ。綱吉というのはそういう性格なんだ。それで、お気に入りの牧野成貞の屋敷へたびたび遊びに行くなんて破天荒のことなんだ。こんなことを始めたのは綱吉が最初だな。牧野のうちじゃ大変だよ。 そのたびに邸内を改築したり、能舞台をこしらえたりして一晩もてなす。そうしたら、綱吉、こともあろうに牧野の女房に目をつけた。きれいな女性だったんでしょう。ある晩、突然、江戸城に呼びつけ、それっきり自分の妾にしちゃった。自分の最も信頼する、最も忠義な家来の細君をですよ。何年かたって牧野のところへ平然と奥さんを返した。普通の神経じゃないね。 そればかりじゃない。今度は牧野の娘・安子に目をつけた。これは一晩か二晩で返された。だけど、このときには安子は結婚したばかりだった。黒田直相の次男が養子に来て牧野成住となっていたわけだよ。 自分の女房のときも、自分の娘のときも、牧野成貞は目をつぶってこらえた。一言の文句もいわずに。気が弱いんだな。けれども成住のほうは黙っていなかった。将軍を斬るわけに行かないから切腹してしまった。狂人のような将軍に対する、これが唯一の反抗だったのだね。安子も翌年死んだ。病死ということになっているが、わからないね。 牧野成貞は実に哀れだよ。まるで生ける化石のようになった奥さんと、死ぬしかなかった娘と、両方を体験しているわけですよ。それで「汝はまことに忠臣である」というような賞をあたえたりしているんだよ。綱吉は、破廉恥のきわみだ。 女色ばかりか、男色のほうも盛んなものだったらしい。綱吉は一生の間に、彼に愛玩された男女は合せて百人をこえるというんだから。そんなことを平気でやっていながら、自分では動物を愛護しているつもり、母親に孝養をつくしているつもりなんだ、綱吉は。 自分は非常に孝行な将軍であるということをつねに自慢していた。仁義礼智信、孝行の道というのがあるでしょう、論語に。それを自分が実行しているつもりである。 だから手前だけの学問なんだ。世の中のことが何もわからない人が学問するとこういうことになってしまう。蚊をつぶして島送りになった侍に親がいて、どんなに悲しむか、そんなことは知っちゃいない。 いまでもいますよ、こういうタイプのインテリが。たとえば、勝手に法律をつくって、他人が自分のつくった法律を破ると容赦しない。それで自分がそれを破るのは一向に平気という……まったく身勝手なんだよ。こういう将軍のために一番苦しんだのは江戸の市民だね。それと直属の家来たち。大名の領地はそれぞれ独立した国だから、将軍といえどもそこまで行ってどうこうすることはできない。 学問をしながら空虚なんだ。つねに。自分が実践しようと思っても機会がないでしょう。夜中に抜け出して町の酒屋で一杯飲みながら他人の話を聞くなんてことはできないよね。将軍になったら、だから自分のできないことを家来に強いる。女房を自分の妾に差し出すことが忠義である、そういうふうに自分で勝手になっ得する、頭の中で。インテリだからね、綱吉は。インテリというのは自分で理屈をつけて自分でなっ得できる。自分でなっ得させちゃう。これが綱吉のようなタイプのインテリの特長なんだ。 女でも、たまたま棄てたりしても、自分で自分に都合のいいようになっ得するんだ。あれを棄てたのはこういう気に食わないことをしたから、これは棄てるのが当然である、自分はちっとも悪いことをしていない、悪いのは女のほうだ……こうなっ得するわけだ。自己弁護の技術にたけているんだな、つまり。
綱吉は六十五歳まで生きた。
綱吉には徳松という子どもがいたんだが、五つのときに病死してしまった。それっきり世継ぎの子が生れない。「生類憐みの令」というのは、もとはといえば跡継ぎ欲しさからだった。 それで、とうとう甲府の綱重の子をやむなく六代将軍にするわけけだが、この六代・家宣に将軍の座をあけ渡す最後のときに、自分が死んでも「生類憐みの令」は撤廃してはいかんと命じたんだよ、遺言として。 ところが家宣は、将軍になるやいなや、一日でもってこの悪令を廃止してしまうんだ。これは先代が最も気にかけておられたものに相違ないが、この禁令に触れて罪を得た者は何十万にも上る、先代の御意志に背くけれども自分はこの禁令を廃止する、そういってね。だから、いかに悪令であったか、どれほど怨嗟の声が巷に満ちていたかわかる。 ※参考:南條範夫著『徳川十五代物語』(平凡社)P.113 参照。(黒崎記) 綱吉が、こんなに恨まれながら六十五まで長生きしたということは、町民の血が入っていたから。母親がえたいの知れない魚屋の娘だったといわれる、その血が入っていたからじゃないかな。そう思うだよ。 それからね、信長の血も入っているんだ。綱吉には、織田信長の血筋なんだよ、考えてみると。 いいかい。信長の妹のお市の方。これが浅井長政に嫁いで三人の娘が生まれたわけだ。長女は例の淀君。次女が初。三女がお江で、これが三度目の結婚で徳川二代将軍・秀忠の夫人になるでしょう。そして秀忠夫人が生んだのが三代・家光で、家光とお玉の間に生まれたのが綱吉というわけだからね。だから、信長と同じ血が入っていることになる。面白いだろう、ちょっと。 ※参考:権力者の不明(黒崎記) 2022.04.19 記す。 |
|
長野主膳に出合ったときから、
徳川幕府崩壊の一番大きな原因を一言でいえば、結局、日本が鎖国をしていたということ。そもそもの遠因はそこにあるんですよ。どうしてだかわかるかい? この戦後の三十数年を考えてみてもわかるようにね、農作物というのは年ごとに出来、不出来があるでしょう。たとえば去年の冷害がいい例だ。今日の日本では、そうした場合に、すぐ貿易で食料を輸入するから、何でもない。ところが江戸時代は鎖国をしていて、外国との交際がない。凶作だったらどうにもならない。 幕末の井伊直弼が大老に就任する前の、田沼時代から天候が定まらなくて飢饉が相次いでいるわけだよ。これは地球の運行によって周期的に繰り返される現象なんだ。いまでも「冷夏」だとか氷河時代に近づきつつあるとか、いろいろいわれている。本当のところはどうなのか、よく知らないけどさ。 ただ、平安朝のころの風俗を見ると、男でも女でも薄い麻の単衣のきもので、冬でもそれを何枚か重ねているだけでしょう。あのころはやっぱり気候が現代よりいくらか暖かったんじゃないのかね。 それが幕末になると、何というのかえ、ちょうど地球の運行からいって気候不順の時期に当たちゃったんだね。冷害が続いて飢饉の年が続く。みんなが騒ぎ出す。 騒ぐということなら、いつの世の中でも政治が悪いということになるわけだよ。それで、もう一方に国学の発達ということがある。本居宣長に発する「日本は神の国である」という、古事記を舞台とした思想だな。これがいつの間にか有力な、幕府政治に対する反対イデオロギーのようなものになってきた。
折りしも世界の交通が発達して、外国人たちが船で日本へやって来る。進んだ武力を背景として日本に対して開国を迫る。しかし、国学が盛んになっている日本では、青い眼の外人たちがこの神国へ入って来るなんてとんでもないことだ、というわけだ。 いろいろな条件が幕末のこの時期に来て全部一緒に重なっちゃたんです。そこに「夷狄を攘」つまり異国の人間を追い払う攘夷思想というものが生まれた。ところが外国側も黙って引込んではいられない。日本という基地が東南アジアの一角にどうしても必要なんだから。現代の日米関係と同じことですよ。まあ、あの当時は貿易のための航路で水や食料を補給したいということでしようけれどね。 アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが軍艦四隻を率いて浦賀へ来航したのが嘉永六(一八五三)年の六月、同じ年の六月。同じ年の八月にはロシアのプチャーチンが、やはり軍艦四隻とともに長崎へ現われた。安政元(一八五四)年にはイギリスの東インドシナ艦隊が来るという具合で、日本の国情は内外ともに騒然たるものになってきた。 ちょうどそういう時代に井伊直弼は大老になったわけです。井伊家はごぞんじのように藩祖・井伊直正以来、徳川家の大名の中でも生え抜きの名家で、井伊直弼という人はその十三代目に当たる。 本当は直弼が井伊家を継ぐはずはなかたんだよ。それというのも十一代藩主・直中の十四男ですからね、それも妾腹の。だから他の大名の養子になるあてもなく、彦根城のそばに小さな家をもらってね。これに、 「埋木舎」 というな前をつけて、そこでひっそりと暮らしていた。自分はもうここで一生埋もれ木で朽ち果てるというあきらめなんだ。いまでも残っていますよ、大名の子どもが住むような家じゃなくてね。まあ、厩はありましたがね。 それで、悶々の日々を過ごしていたところに現れたのが長野主膳なんだ。のちに井伊直弼の懐刀といわれた人物。この人の経歴は詳しくはわかっていないけれども、紀州のね、殿様の御落胤……という感じなんだな、どうも。とにかく紀州藩に縁の深い人ではあるが、やっぱり直弼と同じような境遇で、だからこの二人は意気投合したところもあるんでしょうね。 井伊直弼という人は、何事によらず一心に打ち込んでやる性格だったらしい。文武両道を学んだが、どれも通り一遍ではない。禅は悟道の域に達し、居合は自分で一派を創立したほど、さらに茶道にも熱心で後年「茶湯一会集」という本を著しているんですから。 また直弼は和歌も学んでいた。それで、国学者として、同時に歌人として盛名を馳せていた長野主膳に出合ったときから、主膳の学識に心酔して子弟の契りを結んだ。これが天保十三(一八四二)年のこと。当時はまだ井伊直弼も若かった。三十にもなっていません。むろん、やがて自分が大老になるだろうなんて夢にも思っていない。 ところが不思議な宿命というのか、思いもかけず井伊家の当主になる。兄貴がみんな死んだり他家へ行っちゃったりでね。そうすると、本来井伊家はめぃ藩ではあるし、直弼の持前の賢明さ、頭の切れるところが作用して、それでついに大老に就任ということになったわけだ
直弼は水戸藩を恐れた。
幕末のことを考えるときは、水戸藩の存在というものに注目しなければならないんだ。紀州家、尾張家、水戸家。これは徳川の親族の中でも最大の、いわゆる御三家で、将軍家に跡継ぎがいないときは、御三家から出るというぐらいのものですからね。それほど重要な御三家の一つでありながら、水戸藩というのはかねがね幕府に対して不満を抱いているわけだよ。 そもそも水戸家は、黄門・水戸光圀の時代から、幕府に対する御意見番なんだ。幕府の政治がよくないというとときには、昔から水戸家が意見をいうことになっている。光圀以来ね。 光圀の時代というのはちょうどバカ将軍の五代綱吉の時代で、綱吉が光圀にさんざんやっつけられたものだから、ついに光圀を遠ざけてしまった。それで光圀は隠居して引き籠り、そこで「大日本史」というものを編纂した。そのときから水戸藩というものは、学問の非常に盛んな、日本の歴史というものはどういうものであるかを研究することの盛んな、そういうお国柄になっているわけですよ。 元来がそういう幕府批判の伝統のある水戸藩であるのに加えて、ちょうどそのときの藩主が水戸斎昭。これがンええ、偉い人だったというんだが、まあ何ていうのか一種の過激人物なんだね。大老・井伊直弼とこの水戸斎昭がことごとく激しく対立した。直弼は開港やむなしという考えかたなんだ。とにかく外国側の強硬な申し入れを断ったら大砲でどんどん撃ちかけられて、もう、どうにもならない。勝負にならないとわかっているから、それで井伊大老は、この際、しかたがないから国を開いて外国と交際を始めという政策に踏みきったわけです。 ところが水戸藩にいわせれば、井伊大老はけしからん、外国と交際するなんて何事だ、というわけ。そういう水戸の精神的風土を頼って、攘夷派のグループがいろいろ画策をする。水戸は水戸で彼らに対してひそかに援助をする。 こうなってくると直弼としては、ちょっと捨てておけないことになる。単に過激な革命分子がうろうろして騒いでいるのと違うから。徳川の親藩である御三家の一つでる水戸藩が、そういう不穏分子と結びつくということは、これは大変なことですからね。幕府の大老である井伊直弼は、立場上、何とか思い切った手を打たなければならない。それがつまり「安政の大獄」ですよ。 徹底的に取り締まって、多くの人間を処刑した。このとき直弼の意を受けて働いたのが長野主膳でね。革命分子のアジトがいっぱいあった京都へ長野主膳が行き、いまでも残っている俵屋という旅館を定宿にして、密偵を放っていろいろとお公家さんだの志士だの、あるいは大名家なんかを探索して、それを井伊直弼に報告する。 長野主膳は、紀州藩と深く関係のある人でしょう。ということは元来水戸とは相容れない立場なんだ。将軍家継承問題でも、紀州の徳川慶福か、それとも水戸の一橋慶喜か、争ったばかりのところですからね、結局、このときは紀州藩主慶福が勝って、十四代将軍家茂になる。この陰に主膳の暗躍があった。 そういうこともあって、水戸藩に対する処分が一番過酷なのになった。安政の大獄と呼ばれる弾圧では百人を越える反幕府派が捕えられ、処刑されたけれども、やっぱり徹底的にやられたのは水戸藩。斎昭(慶喜の実父)は国許永蟄居、慶喜は隠居・謹慎。あるいはね、検挙しなくてもいい者までもやってしまったかもしれないんだよ。だけどね、井伊のやったことは、大老としては当然のことをやったまでなんですよ。 ただ、時代が悪かった。もう少し前だったら是認された何でもないことなんだけれども、このときは、かえって火に油をそそぐ結果になってしまった。井伊自身は、よくよく考えて、これはやらなくてはしようがないと思ってしたことだろうと思うんだよ、ぼくは。後になってから、井伊のやりかたは過激だ、もっと他にやりようがあったろうなんていうのは簡単なんだ。だけど、あの当時にあってはね、ちょっといえないと思うね。 ところで、もう一つね、これは歴史家がまだ見逃しているんじゃないかと思うんですがね。人間というのは、年少のころから若い時代に押しひしがれた下積みの生活をしているとね、自分が権力の座に着いたときに、反動的にその力をふるうんだよ。これは井伊大老のみならず、一般の人みんなに当てはまることです。 恐ろしんだよ、これは、年少のころの鬱屈したものが、何かの拍子にパーッとふき出して来る。それは本人でさえ無意識のうちにすることなんだ。 直弼の場合は、別に生活に困るといういうことはないわけです。下積みではあっても一応、藩から金は出ている。しかし、現実には自分の家来たちよりももっとひどいような家をあてがわれてねえ。十七歳から三十二歳で藩主になるまで、わずか三百俵の捨て扶持でしょう。殿様の子でありながら貧乏世帯なんだ。その直弼が井伊藩三十五万石の藩主になり、ついには大老になったとなるとだね。やっぱり、しいたげられていた時代の反動が無意識のうちに出てくるんだよ。 だから、そういう人間のどうにもならない心理というのから見て、安政の大獄に象徴される井伊大老のやりかたに、ある程度年少時代の反動が出たということはいえるんだ。そうでなければ、ああまで激しい弾圧はしなかったんじゃないのかな。他にまだ方法がなかったわけじゃないと思うしね。 幕府の大老としては、あくまで当然のことをしたに過ぎない。井伊が悪いことをしたとは、ぼくは思わないんだ。しかし、もう少しやりかたが他にもあったろう、他の人だったらまた別の方法で解決しようとしただろうということですよ。たとえば、せめて皇女和宮の降嫁の終るまでは事を延ばすとかね。まあ、井伊としては、ここでやってしまわないと見せしめにならないと思ったんでしょうね。何しろ水戸が背後にいるから、革命分子たちの。直弼はその点を一番恐れたんだよ。
第二次大戦で本当に戦ったのは、
当事者というのは、自分のことはわからないものなんだ。自分で自分のことはわからなくても、他人のことはわかる。これが人間ですよ。同時に、渦中にあるときはわからないんだよ。 このことは大東亜戦争自体を見てもわかるでしょう。あの推移を見てもね。駄目だとわかっていながらも引きずられて、結局は戦争をするんだから。駄目だ、駄目だってみんがいっていた。海軍でも到底こんな戦争はできない、やったら敗けると、資材もなくてやったら必ず最後には敗けるんだと海軍がいっているのに、陸軍がおっぱじめるだろう。 だから、動乱のときというのはどうしようもないんだよ。日露戦争のときのように、陸軍と海軍がすっかり肚を割って、相談して、この戦争はやるけれども早くやめなければいけないということで一致してね、そこでお互いに協力して戦争を始める――ということじゃなくてだねえ、もう駄目だとわかっていて引きずりこまれるわけだからね、この前の戦争は。 だから、井伊直弼の場合は、それよりもっと無理からぬことだと思うんですよ。一番バカバカしいのは今度の太平洋戦争ですよ。あの中で、真面目に戦ったのはただ一人だけです。他の、大臣とか政治家、軍人、みんな口では、駄目だ駄目だ、陸軍の横暴を何とかしなきゃいかんっていってましたがね、本当に戦ったのはたった一人しかいない。だれだかわかる? 天皇ですよ。日本の敵・陸軍の横暴というものに対して、たった一人敢然と戦ったのは天皇なんです。ぎりぎりのところまで戦い続けている。政治上の独裁権がないにもかかわらず。だけど、その天皇を援けるやつが一人もいなかったんだ、命賭けでやるやつが。 始めから最後までもう、しっかりとした見通しを持ち、日本の将来というものを賢明に予見して、正しい考えをつらぬいたのは天皇一人だけ。これは、ちかごろいろいろな資料が出るようになってきて、ようやくわかったことです。もし、そういうものの資料が出なければ永久にわからずじまいですよ。天皇はいつも雲の上の存在で、戦争なんかでもみんなまわりのいう通りに動かされて、うんうんっていって戦争になっちゃっと、というふうにしか思えない。 それがこのごろになって、さかんに資料が公開されるようになり、だから、ああそういうことだったのかとわかってきたわけだよ。あれほど英邁な君主がいながら、時の流れというものは結局どうしようもなく、日本はバカバカしい戦争に突入した。このことは、ちゃんと覚えておいたほうがいい。
桜田門外の変もかなり疑問の事件だ。
安政の大獄以来、水戸藩の井伊大老に対する怨みというものは、これは大変なんだ。まあ、あれだけ徹底的にやられたんだから無理もない。で、結局、その不満が爆発して、水戸浪士が桜田門外で井伊直弼を殺すわけだ。 この事件も不思議なんだよね。当然、早くから、何かありそうだ、いつ襲われるかもしれないという噂は入っているわけだし、危険であることは十二分にわかっていたわけですよ、井伊家にも、それにもかかわらず、あんなに簡単にやられちゃうといのが不思議でしょう。いくら雪が降っていたからって、油断をしたといってもねえ。江戸城のところで真っ昼間に襲撃してくるとは夢にも思わなかっただろうな。こういうことが、こういう場所で起こるという、そこにも将軍家というものの権威がいかに落ちていたか、よく表われていますね。 昔の将軍家の威光といったら、それは大したものだからね。考えられないわけだよ、こんな事件が起きるなんて。結局、八代吉宗以降、だんだん将軍家の威光が薄れていったんだ。中には利口な将軍もいたけれどね。それで当然、独裁政権であるだけに、ひとたび威光が薄れだしたらもう、どうにもならないんだ。 やむを得ず合議制になってくるわけだ、政治が。老中、若年寄が集まって相談をし、それを大老が決裁するというような形にね。合議制というものには本来、それなりのいいところがあるわけだが、そこがやっぱり、いまの民主政治と違ってそれぞれ殿様だからね。領国があり、そこへ帰れば絶対君主でしょう。 封建時代の日本は、たくさんの独立国の集合体ですからね。国境がいくつも存在したわけです。国境感覚が日本人にはないなんていう学者がいるけれど、とんでもない話でね。 それでまた桜田門の事件だが、井伊家といえば藩祖・直政以来「赤備え」でなを取ってきた武勇の家柄なんだ。それがわずか十八人の浪士に襲撃されて、大将の首を取られるという醜態をさらしたわけだからねえ。井伊家の江戸屋敷は桜田門から見えるんだよ。いまの国会議事堂のちょっと前のところですからね。ほんのわずかな距離でしかない。しかも真っ昼間なんだ。 この三月三日は上巳の節句といって、殿中でお祝いの儀式があるわけだ。だから各大名がどんどん行列をつくって登城してくる。ちょうど雪が降っていたこともあって、みんな合羽を着て、刀に柄袋をはめている。その柄袋をはずさなければ刀は抜けない。そこへ飛び込んで来られたものだから、たちまちに斬り立てられたんですね。 井伊の家来にも一人や二人、落ち着いているのはいた。柄袋をはずして、たすきを掛けて、それから立ち上がって防いだというものもいました。だけど、そのときにはすでに井伊直弼は腹に鉄砲玉を受けていた。そうでなければ直弼ほどの男があんな死にざまはしませんよ。 映画で観るとみんなおかしいんだ。桜田門外の変。何回も映画になっている。それが必ず血相変えて、いまにも斬り込むぞという格好で近寄っているわけだ。あんなことをしてたら、すぐにバレちゃう。井伊のほうだって柄袋をはずせることになる。だから、柄袋をはずすひまもないような斬り込みかたを見せないとね。あれはアッという間に終っちゃうんだから。まず、五分か十分だろう。 桜田門の近くに集っているのはいいんだよ。みんな武鑑を持って、 「今度の大名は何々様だ。次は何様……。」 と武鑑に出ている紋と行列の紋を照らし合わせて、見物しているわけだ、田舎侍が。それで井伊家の行列がすぐ目の前まで来た瞬間に、水戸浪士の一人、森五六郎っていうのがパッと飛び出し、訴状を捧げて、 「申し上げます!」 「何事だ、退け!!」 そのときにもう、隠れてるやつがドーンと一発撃っている。それが直弼に当たっちゃたんですねえ。実際に見たわけじゃないが、まあ、こうだっただろうと思う。 浪士十八人の中に一人だけ薩摩藩の出がいた。有村治左衛門という。この有村が駕籠から直弼を引きずり出して、首を切り取った。それで有村はその首を持って、少し逃げて、結局重傷のために松平大隅守の屋敷の門前で死んだ。そのために松平家が直弼の首を預かっちゃったんだよ。 井伊家としては、その首を返してもらうのに大変だった。傷口を縫合して、病死ということで幕府へ届け出たわけです。むろん、幕府は委細承知の上で、これを認めた。認めざるを得ませんよ。大老が路上で浪士に殺されたなんていったら、幕府の権威自体が吹っ飛んじゃうもの。そうでなくたって非常時なんだからね。 一説には、前の晩に、 「明日の御登城に浪士たちの襲撃あり」 という投げ文が、井伊家の屋敷にあったというんだ。で、それを直弼に知らせたところが、泰然自若としていたとか、死を予期して、 「死ぬなら死んでもかまわぬ……」 という様子であったとか、そういう話が残っている。だからねえ。資料には表われない裏側の事情が、やっぱり、いろいろあったんじゃないかと思いますね。
昔の大名というのは、政治でも、座興にしても
十二、三年前に、彦根へ講演に行ったんんですよ、頼まれて。講演の後で市長主催の宴会があったわけだ。そのときぼくは市長の井伊さんの三味線で長唄をうたった。「勧進帳」を。ぼくは、どっちかというと、そんなことをしたくないほうなんだ。 小福っていう芸者がね、ぼくに、 「あたし市長さんの三味線、一回も聴いたことがないから、いい機会だから是非聴きたい。だから、勧進帳お願いします」 と、そういうんだ。 ぼくは、そのとき考えたのはね、自分がそういうことやるのはいやなんだけれども、市長がどういうふうに三味線を弾くのか見たかった。殿様だからねえ。それで、 「じゃ、やろう。おまえも手伝ってくれ」 と、いうことになって、小福といっしょに勧進帳をうたった。井伊兄弟の三味線で。市長の弟さんは大学の先生なんだ。学者ですよ。その人も三味線を弾くんですよ。 うたいながら市長の井伊さんを見てるとね、もう真剣なんだねえ。汗びっしょり流して。いわゆるお座敷芸じゃない。もう本当に自分が習ったものを真剣にやるわけですよ。あれはやっぱり大名芸ですね。お大名というのは、それほど真面目な、立派なものなんだ。 この話はもう何べんもしたろうけれど、いいと思うんだ。とにかくぼくは非常に感にうたれてね。ご兄弟を見ていて、 (ああ、昔の大名というのは、こういうものだなあ……) って、感覚としてね、こういうふうに思ったね。それは、どこがどうって、ことばではいい切れませんよ。ただ、昔の大名というのは何事に対しても、たとえ座興の、座興ですよ実は、ぼくなんかの三味線を弾くというのはね、それでも汗びっしょりになって真剣にやるわけだよ。 大名っていうのは、こうだったんだよ。政治でも何でも。むろん、バカ大名もいただろうけれども、だいたいはもう、みんな一所懸命ですよ。 で、井伊さんがね、全国市長会議に行くだろう、当時ね。そうすると一番見すぼらしいんだよ、洋服が、戦前のものをそのまま着ているから。修理に修理を重ねてね。ところがねえ、会議が始まるでしょう。すると、だんだん井伊さんがピカピカ光ってきて、立派に見えてくるんだって。これ、別の市長から聞いた話だ。つまり、大名っていうのはそういうものだよ。 あとでぼくは恨まれたよ、本来ならば彦根藩の殿様である人に三味線を弾かせた、池波正太郎はけしからん、なんてね。 それで、井伊さんは、昔の御下屋敷の一つの小さなほうに、奥さんと二人で暮しているわけだ。奥さんは沖縄の公女ですよ。大変な名流の出なんだ。だけど女中も使わないで掃除から何から全部、奥さんが自分でやっていて、屋敷の一部を何か病気の人たちの施設にして、その世話もしているわけですよ。 そういうことを彦根の市民はみんな知っている。他人によく思われよう、自分が何か得をしようという気が全然なくて、そういうことを一所懸命にやっていることをね。だから、いかに革命派が立っても市長選挙には駄目なんだよ。勝てないんだよ。市民が知っているから。 本当の大名というものはどうであったか、井伊さんを見ているとわかる。自分のことなんか考えていないんです。ところが明治維新で成り上がったやつには、そういところがない。利権を漁る、地位を漁る、名誉を漁る、というやつのほうが多くなっちゃった、明治維新後の政治家は。 昭和のこういう世の中になっても、大名というのはああなんだからね、井伊さんのよくに、金にも名誉にも関心がない、何よりも市民のことが一番大切だと。殿様って、そういうものなんですよ。そういう無私の生きかたが伝統的に血になってつながってきているわけです。そこがわからない人が多いんだねえ。 2022.04.22 記す。 |
 このときの戦いで、秀吉側近の若武者たちが、それぞれ槍を振るって目覚ましい働きをしたわけで、これが世にいう賤ヶ嶽の七本槍。加藤虎之助清正。平野長泰。脇坂甚内安治。加藤孫六嘉明(よしあきら)。福島市松正則。糟谷助右門武則。それから片岡助作且元(かつもと)、この七人。清正は真先かけて飛び出し、一番槍とな乗って、敵の武将拝郷五左衛門隊の鉄砲頭・戸波隼人という者を討ちとったというんだな。
このときの戦いで、秀吉側近の若武者たちが、それぞれ槍を振るって目覚ましい働きをしたわけで、これが世にいう賤ヶ嶽の七本槍。加藤虎之助清正。平野長泰。脇坂甚内安治。加藤孫六嘉明(よしあきら)。福島市松正則。糟谷助右門武則。それから片岡助作且元(かつもと)、この七人。清正は真先かけて飛び出し、一番槍とな乗って、敵の武将拝郷五左衛門隊の鉄砲頭・戸波隼人という者を討ちとったというんだな。


 だから〔八甲田山〕という映画なんか観るとね、つくづく思うだが、少なくとも〔八甲田山〕のころの軍隊がいてくれると頼もしいなあ。かつての日本は、こういう軍人が守ってくれたのかという気がする。
だから〔八甲田山〕という映画なんか観るとね、つくづく思うだが、少なくとも〔八甲田山〕のころの軍隊がいてくれると頼もしいなあ。かつての日本は、こういう軍人が守ってくれたのかという気がする。
 ※南條範夫『徳川十五代物語』(発行所平凡社)P.76 家綱の時代も大奥が政治面に口を出すということがますます盛んになっていく、と書かれている。(黒崎記)
※南條範夫『徳川十五代物語』(発行所平凡社)P.76 家綱の時代も大奥が政治面に口を出すということがますます盛んになっていく、と書かれている。(黒崎記)
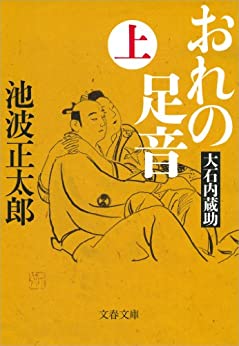
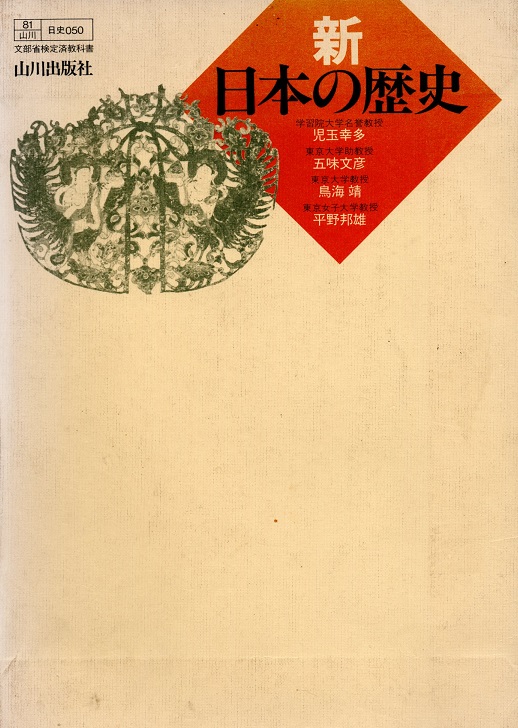 ※参考図書:『新 日本の歴史』(山川出版)P.220(黒崎記)
※参考図書:『新 日本の歴史』(山川出版)P.220(黒崎記)
 また、ある人にいわせれば、孝明天皇が御所で便所へおいでになって、帰りに手を洗ったときにね、縁の下から手槍でもって孝明天皇を突いたやつがいる、と。それが伊藤博文だという説がある。説だよ。本当だっていうんじゃない。本当でないともいえないんだ。天皇のあれをね、拝見したお医者さまの話が伝えられているんです。歴史小説家の村雨退二郎さんが、だいぶ前にこの人は亡くなりましたが、「病死か暗殺か――孝明天皇」とい一文を遺しているんだ。それをぼくも「近藤勇の白書」という小説の中で紹介しておいた。
また、ある人にいわせれば、孝明天皇が御所で便所へおいでになって、帰りに手を洗ったときにね、縁の下から手槍でもって孝明天皇を突いたやつがいる、と。それが伊藤博文だという説がある。説だよ。本当だっていうんじゃない。本当でないともいえないんだ。天皇のあれをね、拝見したお医者さまの話が伝えられているんです。歴史小説家の村雨退二郎さんが、だいぶ前にこの人は亡くなりましたが、「病死か暗殺か――孝明天皇」とい一文を遺しているんだ。それをぼくも「近藤勇の白書」という小説の中で紹介しておいた。
 この悲惨な戦いのことをね、会津の人が書いていますよ、柴五郎という人が。中公新書で出ている。『ある明治人の記録――会津人柴五郎の遺訓』というんだ。やっぱり、ぼくみたいなものは、それを読んでいると涙がでてくるね。ひどい、あまりにもひどい目にあわされているので。
この悲惨な戦いのことをね、会津の人が書いていますよ、柴五郎という人が。中公新書で出ている。『ある明治人の記録――会津人柴五郎の遺訓』というんだ。やっぱり、ぼくみたいなものは、それを読んでいると涙がでてくるね。ひどい、あまりにもひどい目にあわされているので。
 西郷隆盛というと、だれでも上野公園に建っている銅像を思い浮かべるでしょう。現代の若い人たちはそれも知らないかな。六尺に近い巨体で、素晴らしい顔をしている。それは子どものころからだった。無口で純重な感じの少年で、まわりの子どもたちからは、
西郷隆盛というと、だれでも上野公園に建っている銅像を思い浮かべるでしょう。現代の若い人たちはそれも知らないかな。六尺に近い巨体で、素晴らしい顔をしている。それは子どものころからだった。無口で純重な感じの少年で、まわりの子どもたちからは、