| ★習えば遠し | 第1章 生活の中で学ぶ | 第2章 生きる | 第3章 養生ー心身 | 第4章 読 書 | 第5章 書 物 |
| 第6章 ことば 言葉 その意味は | 第7章 家族・親のこころ | 第8章 IT技術 | 第9章 第2次世界戦争 | 第10章 もろもろ |
READING BOOK
有絃の琴琴を弾ずるを知りて、無絃の琴を弾ずるを知らず。
迹を以て用いて、神を以て用いず、何を以てか琴書の趣を得ん。
〔菜根譚 後集 八〕
|
骨董などが本物か偽物かの判断の力を養うには、小さいころから本物しか見せないといわれている。この場合、本物を見なれている人がそばにいることも大事だと思う。判断の付かない人はどこが良いのかわるいのか、着眼点はもちろんその意味さえ分からない。 ▼こんな話を耳にすると思い出すのは昔の古典(多くは論語など)の素読である。少年時代「子曰く……」と大声で暗誦できるまで素読させられたそうである。当然、そのときは、其の意味は分からない。ある年配になっても文章はほぼ記憶していて、其の上、その意味が少しずつ分かってくる。 ▼今は、こんな教育は行われていない。有名大学に入るためには、有名中学・高校一貫の学校へと。また入試に関係ないものは教えてもらわなくてもよいと思う父兄。 ▼人生一貫教育をいまこそ考えなければと思うことしきり。 平成十五年十一月二十日 |

昔は文庫本でも糸綴じであった。近頃のものにはそんな本があるのだろうか? 多くの本は糊付けだけである。 一九八三年(昭和五十八年))八月二十日(約二十一年前)に購入した第47版発行の本である。私の愛読書の一冊の本も糊付けであった。数年前に本が割れたので背中を糊付けして何とか修理した。今年、其の本がさらに割れてページをあわせるに注意しなければならないほどになった。そこで、その文庫本をしっかりとそろえて、クリップにはさみ、表紙から目打ちで穴をあけて糸で五カ所縫いつけた。 ▼珍しいものでも、絶版本でもない。今でも売られている本だから新しく買えば済むことではないか、と思う。しかし、購入以来、何度も繰り返し読み、読んだ時に感じたことなど書き込みをしている。それを読むのも自分の読書の足跡を見る気持ちがして手放したくない気持ちを断ち切れず修理をした。 本があふれる時代、製本のコストからやむをえないのだろうが、私は古典などの良書は少し値段を高くしても糸綴じにして、長期に読み続けても、ばらばらにならない本、さらに、希望としては本の終わりに白紙のメモ欄を数ページを作ってもらえないものだろうか。出版社にお願いしたい。 平成十六年二月十三日 ▼この本を読むにあたって中村 元先生の改版に際しての文章を是非お読みください。 中村 元 一 『正法眼蔵随聞記』の成立 二 岩波文庫本の由来 道元が単にわが国の曹洞宗の開祖としてではなくて、わが国の生んだ偉大な思想家として一般に知られるようになったのは、和辻哲郎博士の力によるところが大きく、そうして道元の人物像がくっきり浮かび上ってきたのは、この『正法眼蔵随聞記』の岩波文庫本による点が多い。 和辻先生は、道元の思想および人格にひかれて「沙門道元」という論文を、大正九年から十二年にわたってまとめ、その初めの部分すなわち約三分の二を雑誌『新小説』に連載し、残りを当時創刊された『思想』誌に掲載されたのである。それが発表直後にどれだけの影響を及ぼしたか、よくは解らないが、この論文がやがて『日本精神史研究』岩波書店、大正十五年十月刊行)のうちにおさめられて刊行されるとともに、道元という思想家・宗教家が一般に非常に注目されるようになった。 その一例として、わたし自身の経験をのべることを許して頂きたい。わたしは東京高等師範学校附属中学校に、大正十四に入学したが、級担任で修身の先生であった原房孝先生が、修身の時間に道元の事蹟を感激を以って伝えられ事を覚えている。それは、求道者たるもの、ひいては勉強を志す者はこれだけの覚悟が要るということを強調されたのである。わたくしが後年研究者になってから知ったことであるが、原先生の講話の内容は、大体「沙門道元」の中に出ていることがらであり、さらに遡れば、『正法眼蔵随聞記』の中に出て来ることがらであった。 岩波文庫本の『正法眼蔵随聞記』が刊行されたのは、昭和四年である。道元に対するブームが漸く起ったので、やがて原典を刊行するという運びになったのであろう。世間でこの文庫本は非常に歓迎され、昭和十三年よりも以前にすでに十一刷を刊行していた。 道元自身の著作である『正法眼蔵』にくらべれば、この『随聞記』のほうは、はるかに内容が読み易いが、しかし当時でも一般の人々には近づき難いものであったらしい。そこでこれに振り仮名をつけようという提議がばされ、わたくしがそれを為すように、和辻先生から仰せつかった。 大変勉強になる好い機会であったが、わたしには、なかなか重荷であった。一般の仏教辞典や禅学辞典にも出て来ない語が沢山見受けられる。そこで旧幕時代からよく読まれた『随聞記』(京都、貝原書院刊)および『永平正宗訓』(同じく、貝原書院刊)に出て来る若干の振り仮なを片はしから検討した。しかしそれらの振り仮なはごく僅かであり、部分的であった。当時はまだ『随聞記』全体についての振り仮名版本は刊行されていなかった。 そこで個々の話の読みくせを知るためには、特に『正法眼蔵』の振り仮なつきの出版に当らねばならぬ、と考えて、当時曹洞宗聖典として振り仮なのつけられて出版(例えば東方書院版、あるいは来馬琢道師編のもの[無我山書房刊、明治四十四年])などをいろいろ参照した。それでもはっきりしないところは、のちに永平寺西堂となられた橋本恵光老師や永平寺東京別院副監院の成河仙嶽老師に教えて頂いた。そのほか宇井伯寿先生にも何かと御教示にあずかったことを覚えている。 そのように諸先輩の一方ならぬお世話に与(あずか)ったにもかかわらず、ここに付した振り仮なでよいかどうか、なお確信をもっていない点がある。例えば、「道」という字が一字だけ出て来るときに、来馬琢道師編の聖典には「どう」と振り仮名がつけてあるが、橋本恵光老師は、提唱のときに、つねに「みち」と読んでおられた。そうして老師に個人的に伺ったところが、ただ「みち」と読むほうが良い」といわれたが、その理由については、別に何も言われなかった。 ともかくこういう道筋をたどって、昭和十三年四月二十五日に振り仮名つきの第十二刷が刊行された。その後もつづけて印刷されている。 ところで一九八一年に、この文庫本の紙型が摩耗してしまったので、新たに組み直すに当って、従前どおり面山本によるべきか、新たに長円寺本によるべきか、ということが、問題となった。 『随聞記』の原形を明らかにするためには、文献学的には長円寺本を重んずべきであろう。しかし現在の岩波文庫本としては、やはり面山本を校訂刊行することにした。そのわけは、 (1)面山が手を加えているから、全体として読み易く、解り易い、内容を把握することが容易である。長円寺本で不明な点が、面山本でよく理解される個所もいくつかある。 (2)面山以後現代に至るまでの、道元思想の理解に、面山本は決定的な重要性をもっていた。曹洞宗は伝統的に面山本を依用しているので、今でも権威がある。 現在の研究者のうちにも、面山本によるべきであるという主張がすくなくない。(ただし長円寺本をとる傾向が徐々に増えていることは否定できないが。) よって精密な研究のためには、読者は「日本古典文学大系」本を参照されたいが、「岩波文庫」としては、その性格上、やはり面山本の印刷を継続することにした。 振り仮なつについては、この機会に曹洞宗の若干の方々に是正を乞うたが、今までには特に挙げられることもなかった。なおこの点については、諸方からの御叱正を願っている。 漢字については、常用漢字の字体を使い得るものについては、それを使って読み易くした。しかし仮なについては旧仮なおよび版本のままの仮な遣いに従った。そのわけは微細な変更が意味の誤解をひき起す恐れがあるからである。[例えば、「ゐる」と「いる」と直すと、もう意味が違って来る。] なお版本は片仮な書きであるが、翻刻に当っては、旧版以来平仮な書きに改めてある。
三十六年二月十三日
参照:このホームページに、『正法眼蔵随聞く記』より引用したもの5件を列記します。 道元の関東下向 生死事大、無常迅速 わたしの読書 道元の二人の弟子 生死事大、無常迅速 平成十九年九月五日 |
『日暮硯』を読む
|
リーダーの読むべき本として『日暮硯』(岩波文庫)をすすめてきた。江戸時代の中期に、信州松代藩の家老恩田木工が、甚だしい窮乏に陥った藩政の建て直しを一任せられ、まず五カ年計画を立て、身を挺してその改革に当り、よくその功を成した事蹟に関する説話の筆録である。歴史年表によると、一七五九年、肥後・松代藩などで藩政改革が行われると記録されている。 樋口清之『うめぼし博士の 逆・日本史2』P.76~78によると
この本によると、御用商人・八田家からの借金だけでも二一万両にのぼり、給料遅配が原因で足軽たちがストライキをしたり、百姓一揆が相次ぎ、彼が家老職を拝命した一七五四(宝暦四)年には、松代藩の財政はほとんど瀕死の重症だった。 だが、この困難な状況を、彼は勇躍、唯一人で乗り切ったとされている。まず、藩の重だった連中から彼の政策に絶対に反対しないという一札を取り、親戚・家臣一同には、「いっさい嘘をいわない」とうことを約束させ、食事は飯と汁、衣類は木綿以外は着ないなどの質素倹約的生活をさせたうえ、領内の百姓には約束事は必ず守り、公表した施策はいっさい変更したりせず、また御用金なども申しつけないなどの善政を敷いたとされる。 一方、藩士には信賞必罰の制度を徹底させ、この善政によってわずか五年で、藩の財政ならびに領地を、まことに豊かに立て直した――これが『日暮硯』に書かれている内容である。 だが、事実はこの記述とずいぶん違っていた。恩田木工が五年間、改革に腐心したのは事実だが、莫大な藩の借金は減っておらず、彼が死んだ次の年、藩主の参勤交代の費用さえ捻出できない状態だったし、彼が農民に約束した政策も、ほとんど守られることがないありさまだった。 つまり、彼の純粋な動機や政策とは無関係に、現実の松代藩の経済は、何一つ改善されることがなかったのだが、彼の人柄の清潔さゆえに『日暮硯』においては、日本的美学が強力に働き、事実を極端にねじ曲げ、"結果"まで、逆に美化されたのである。 これと対比するに、薩摩藩の財政再建に非常な功績のあった調所笑左衛門(広郷(一七七六ー一八四八)の生涯に対する評価は、まことに対照的である。 彼は使番・町奉行などをへて、藩主・島津斉興の側用人・家老に成り上がった人物である。この成り上がり者が、日本社会では必要以上に軽んじられることは『逆・日本史(1)』(73ページ以下)で詳しく述べたとおりだが、かてて加えて、笑左衛門は財政建直しに、個人の徳目などまるで考慮にいれなかった。 一国の経済に個人の美徳、つまり人格や人柄は無関係のはずである。いや、正確には人格とは無関係に、適切で効果的な手が打てる能力があるか否かが、家老としての最初の要件である。そして彼は、じつに有能であった。 たとえば、二五〇年賦償還法(借金の二五〇年分割法)を強引に押し進めたり、砂糖の総買入れや琉球を介して密貿易を行ったりし、ついに、薩摩藩の財政を大幅に建て直すことに成功したのである。だが、その強引さが災いし、幕府の嫌疑を受けるところとなり、最後は自殺に追いこまれれている。 そして、古くから、「恩田木工=善、調所笑左衛門=悪」のイメージが一般に定着しているわけだが、財政建直しという観点から見れば、つまり、家老職としての職責をどちらが全うしたかの判断からすれば、世間の評判とはまったく逆の結論が導き出されるのは言うまでもない。 個人の美徳を優先してきた農耕民族・日本人 では、なぜこんなことが起きるのであろうか。一つには、渡部昇一氏がつとに指摘されたことだが、リーダーに能力がなければ全滅の危機に瀕することがしばしば起る牧畜民族と違い、農耕民族のリーダーは、能力より人徳で人心の掌握を行ってきたため、キラキラとした才能を疎んずる風習のある点が挙げられる。 また、農耕民族は能力による格差を極端に嫌うメンタリティ、つまり、嫉妬心がきわめて強く、やや誇張して言えば、日本社会には「他人の不幸はわが幸せ、他人の幸せはわが不幸せ」というべクトルが、つねに働きつづけていることも忘れてはならない。 さらに大きな要因として、欧米とはちがい社会全体を観察する精緻な学問が、日本社会には発達する土壌がなかったことも挙げられよう。 たとえば、MIT(マサチューセッツ工科大学)の教授であるポール・サムエルソンの代表的な著作である『経済学』の冒頭には、「個人の美徳は集団の悪徳である」という一文が載っている。現在でも、この一文にはじめて接すると、たいていの日本人は一様に驚きと嫌悪感を露(あらわ)にする。
▼奈良本辰也氏は「『図説長野県の歴史』で、古川貞雄さんが、『日暮硯』における名家老恩田木工の事蹟は、『つくられた』面が多いことを指摘されているが、それはまさにその通りであろう「…しかし、木工在世中には、百姓一揆などおきてはいない。とすれば、やはり政治の姿勢によるものだと言うことが出来る。根本にある仁政の思想が、そのような虚構を作り出したのだ。」
※堤 清二訳・解説 現代語で読む『日暮硯』(三笠書房)もある。あとがきに、丸山真男先生にお目にかかった。『日暮硯』の件を申し上げると、「あれは面白いよ。松代藩は僕の郷里だからよく読んでいるが」とのお話であった。と書いている。 ※池波正太郎『真田騒動 恩田木工』(新潮文庫)に「恩田木工」について書かれている。この本は、[信濃大みょう記][碁盤の首][錯乱][真田騒動]および[この父その子]の短編・中編4あわせて五編が収録されている。[真田騒動]は真田騒動――恩田木工―― となっている。 |

《物語》大正八年、冬の吹雪きの夜に烈は生まれた。父の意造は新潟県亀田の地主で、清酒『冬麗』の藏元二代目。妻・加穂は、八人の子を妊り、死産、早逝ですべて亡くしている。烈という、女の子に似わぬ猛々しいなには、この子だけは逞しく生き延びてほしいという両親の深い祈りが込められていた。病弱な加穂に代わっな、烈の養育は、加穂の妹、独身のまま実家にとどまっていた佐穂に委ねられる。その親身の世話で烈はすくすく成長するが、小学校入学直前に烈の目に異変が発見される。夜盲症ーいずれ失明に至る、不治の眼病である。烈と家族の、哀しくとも美しい物語が、ここに始まる。
▼「もともと、仕事に自分の全人生を賭ける人間を見るとすっかり魅了されてしまうたちで、これまでにも琴を弾くひと、絵を書くひと、芝居をするひと、香を焼くひと、などにのめりこんで描いてきました」この小説では眼の不自由な女性・烈を酒造りの世界に置いている。「みなさんもどうぞ、長く長く、烈のこと、佐穂のこと、意造のこと、お胸のうちでいとしんで下さいませね」。
著者あとがき。
▼「火鉢の燠の尉となってはらりと落ちる、そんな音まで聞こえそうな」(文中の表現)など、静寂さをこんな言葉の美しさに私はいつも惹かれている。
「蔵」大正十五年、春まだ浅い二月末。 新潟県中蒲原郡亀田郷・・・ この地の大地主で酒造業を営む田乃内家の奥庭では、新酒の仕込みの祝いを兼ねた梅見の宴が始まろうとしていた。 当主・田乃内意造には、九人の子を次々と亡くした後にやっと恵まれた一人娘・烈があった。 烈は意造の愛情を一身に集め、女子大進学を目指して励んでいる。 意造の妻・賀穂は病弱だったため、烈が十五の歳に亡くなり、妹・佐穂が母代わりとして幼い烈を育てていた。 佐穂の弟・佐野武郎は意造が佐穂を後添にするつもりがないことに不平をもらす。 意造の母・むらも、佐穂が意造の妻となることを願っていたが、意造は曖昧な返事をするだけだった。 新潟古町の置屋、能登屋の女将・昌枝に連れられて、初々しい振袖奴・せきも宴に呼ばれていた。 宴のさなか、突然の吹雪に一同が家の中に入ろうとした時、烈がつまずく。 不審に思い問い詰める意造に、以前から視力が落ち不安に脅えていたことを打ち明ける烈。 意造と佐穂はがく然とする。 目の診察を受けるために東京の帝大病院に烈を連れて行っていた意造と佐穂が、 しょう然として帰ってきた。 烈の病名は「網膜色素変性症」と言い、いずれは失明に至ることを医師に宣告されたのだ。 「私、少しでも光が見えるうちに死んじまいて!「絶叫して叫ぶ烈。 誰もが沈うつな思いに沈む中、むらは賀穂が自分の死後は妹の佐穂に烈の母親になってもらうようにと言い残したことを意造と佐穂に打ち明けた。 とまどう佐穂。 意造は主治医・常石に、烈の目の病の原因に遺伝の可能性があると帝大病院の医師から告げられたことを話す。 意造は賀穂の実家・佐野家の血を疑っていた。 その時、意造はあたりの匂いに酒蔵の以上を知る。 酒造りに致命的な「腐造」を出したのだ。 打ちのめされた意造は能登屋の若い芸者・せきを相手に酒浸りになっていたが、 突然せきを後添いにもらうと言い出す。 意造を密かに慕っていた佐穂は、衝撃を受ける。 意造もまた佐穂の気持ちに気づいていたが、若いせきを妻に迎えることで不幸続きの田乃内家に新しい血を入れたいと考えていたのだ。 婚礼の日、せきを嫁と認めないむらは烈を連れて席を立ってしまう。 烈の目も日ごとに光を失っていた。 昭和四年四月。 田乃内家ではむらが亡くなり、意造とせきの間には丈一郎という息子が生まれていた。 烈はせきに心を開かず、丈一郎が跡取りになれば目の見えない自分は厄介者になると考え、かたくなになっていた。 今や手探りでしか歩けない烈は、ある日女人禁制の酒蔵の中に迷いこみ、若い杜氏・涼太と出会う。 目が見えなくても幸せに生きている人がいると語る涼太。 その言葉に、閉ざされていた烈の心に希望の光が差し込む。 そこに、駆け込んで来た女中が、意造が倒れたと告げる。 中風で倒れた意造も杖をついて歩けるほどに回復してきたある日、母屋から突然悲鳴があがった。 幼い丈一郎が、洗い場の石の角で頭を打ったのだ。 ぐったりとした丈一郎を抱えて半狂乱になるせき。 いたたまれずに庭にでた烈は、突然凍りつく。 「見えね!何しとつ見えね!」。 烈は完全にその光を失ったのだった。 昭和六年元旦。 丈一郎の死、烈の失明と続く不幸にうつひしがれた意造は蔵を閉める決意をしていたが、烈はこれに反対し自分に酒造りをさせてくれるように訴える。 驚いた意造は酒蔵は女人禁制、ましてや烈の目では無理だと説く。 しかし、失明の絶望を乗り越え自分の生きる道を見つけようとしている烈の必死の思いに、ついに意造の心も動かされる再び酒造りに取り組む決意を固め、烈に手伝ってくれるように言うのだった。 翌年三月。 烈が蔵に入って初めての酒造りは順調に進み、酒蔵では仕込みを終えた内祝いの宴が開かれていた。 烈は、涼太から故郷の野積や日本海の話を聞き、名杜氏への夢を熱く語る涼太に魅かれていく。 屋敷の奥では、佐穂が昌枝から重大なことを打ち明けられていた。 それはせきが意造以外の男の子どもを妊娠しているということだった。 佐穂がせきに子どもの父親を尋ねているところへ烈が現れ、相手が涼太ではないかと疑い、せきを問い詰める。 涼太へのほとばしる思いを明かす烈に、佐穂はやさしく声をかける。 目が見えなくたって、好きらって叫ぶことはできるでしょう? 叫んでちょうだい。何一つ叫べなかった私の替わりに。 丈一郎の死以来、意造との仲が冷えていたせきが姿を消した。 心配した佐穂は意造にせきが妊娠していることを告げる。 やがて昌枝に連れられて戻ってきたせきを、意造は激しくなじる。 離縁して田之内家から開放してほしいというせきの哀願をも冷たく拒絶するのだった。 昭和八年春。 田之内家に代々伝わる雛飾りの前で、せきが佐穂に別れを告げていた。 せきの腹の子は死産だった。 何かあったら戻って来るようにと言う佐穂に、せきは「もう後ろは振り返らない」ときっぱり答えて去っていった。 その姿を、意造はただ立ち尽くして見送っていた。 しょう然とする意造に烈は、涼太と結婚していっしょに酒造りをやっていきたいと告げる。 驚き憤る意造に、烈はこれから故郷の野積に戻ってる涼太のもとへ行って結婚を申し込むつもりだと言い放ち、意気揚々と旅立っていく。 せき、そして烈までに立ち去られてがっくりとうなだれる意造のそばには、佐穂がそっと寄り添っていた。 烈と涼太に跡をゆずって自分たちもいっしょになろうと言う意造に、佐穂は答える。 私はあにさまのお側にいられただけで、ほんにしあわせでごぜえました。 それで十分でごぜえますがね。野積の浜辺を烈が転げるように駈けてくる。 驚く涼太に思いをぶつける烈。 とまどっていた涼太も、目の見えなかった涼太の母のために幸せになろうと言う烈の言葉に大きくうなずく。 烈の後を追ってきた新発田の叔父・武朗が、意造が二人の結婚を許したことを知らせ、 仮祝言用に用意してきた純白の打ち掛けを見せる。 幸せに顔を輝かせる烈。 おとっつっぁま!おばさま!私、もう何も怖くはねッ! 私の目の底の闇に、光が見えてきたから。 烈は光に向って歩く!それが生きる歓びだから! 烈は天を仰ぐ。 ふりそそぐ光を両手いっぱいに抱えて。 ★Web Site による。場所が、新潟県中蒲原郡、私はこの地の中条へ何度も訪れている。知人も何人かいる。こんなご縁で読んでも烈に惹かれる。平成29年7月21日、追加。
補足:平成二十七年一月八日:「吉川栄治と宮尾登美子と広辞苑」を検索すると、以上の記事が掲載されていた。 平成五年十月一五日 一〇四号 宮尾登美子『藏』 ...... 作家宮尾登美子さんは、〈広辞苑の愛読者で、美しい言葉にであうと、ノートに書き込んでいます。それが ... 吉川英治氏は、十八、九歳のころ、横浜から上京、本所のある印刷工場の住み込み職工になった。
新聞は一斉に宮尾さんの訃報と作品について報道した。ある新聞の記事を紹介します。 宮尾登美子さん死去:濃密な文章、情感豊かに 構想じっくり温め 女性たちの生きる姿を追い続けた作家、宮尾登美子さんが88歳で亡くなった。2008年、ベッドから落ちて背骨を痛めてから、徐々に執筆から遠ざかり、13年7月、文芸誌に発表した柝(き)の音の消えるまで 追悼市川団十郎丈が最後の原稿となった。同年夏から療養を続けていたが、次女環さんによると先月30日夜、静かに息を引き取ったという。 ◇ ■評伝 生家の「芸妓娼妓(げいぎしょうぎ)紹介業」が、宮尾さんの大きな十字架だった。高等女学校の入試で県立に落ちたのは、家業のせいとうわさされた。早く家を出たかったため私立の女学校卒業後、高知市を離れ山間部の代用教員になり17歳という若さで結婚。 しかし、作家への道をこじ開けてくれたのもまた、忌み嫌った家業だった。 婦人公論女流新人賞でデビューして約10年、ことごとくボツの憂き目にあっていた。「小説は面白く書けばいいと思っていたが、自分自身と血を吐く思いで向き合って書かないといけなかった」。そうして生まれたのが、生家をモデルにした「櫂(かい)」だった。それからはベストセラーを連発。読者はドラマチックな宮尾文学に魅了されていった。 アイデアは10年でも、20年でも長い時間温める。いよいよ向き合っても、例えば「一絃(いちげん)の琴」なら琴を取り寄せることから始まる。1日の執筆量は原稿用紙数枚。それ以上書くと、「内容が薄くなる」。共に上京してくれた元高知新聞記者の夫との生活も大事にした。こうして紡いだ小説からは情感がにおい立ち、文章の密度は濃い。執筆に9年かかった「櫂」は、“手織りの木綿のような文章”と評された。 次に出したい小説の種があった。「櫂」「朱夏」「春燈」「仁淀川」と書き継いできた自伝的小説の続きだった。私のことだから書くとなっても10年くらいかかる。どうなりますことやら。そう笑ったのは08年のこと。宮尾さんには時間が足りなかった。 平成二十六年一月八日 |
|
『わが生涯の記』の一部を拙訳しました。人生のなかで最も忘れ難い日はアン・サリバン先生との出会いである。七歳になる三か月まえの日であった。その日の朝、アンはパーキンズ盲人学校の子供から送られた人形を彼女に与えた。しばらく人形で遊んだ後、アンはヘレンの手のひらに「doll」と綴った。この指つづりが楽しくなりまねをした。ついにその字が正しく書けるようになると子供らしい喜びと誇らしくなりました。二階の部屋から階下にいた母のところにかけおりて、自分の手のひらを上げてdollの字をかいた。単語を綴っていることや言葉があることさえ知らなかったのである。その後、この方法で多くの言葉の綴りを知った。pin~hat~cup。動詞のsit~stand~walkなど。(中略)多くの新しい言葉を学んだ。mother~father~sister~teacherなど。言葉を知って彼女の世界に花が咲いた。その日、ベッドに横たわり喜びをかみしめているとき、私より幸せな子供はいないだろう。明日に速くなればと初めて待ち望んだ。 ▼『D・カーネギー 人生のヒント』から教えられました。(三笠書房) 目が見えなくなる―これが人生最大の不幸だと思っている人がおおいが、ヘレン・ケラーによると、目が見えないよりも耳の聴こえないほうが辛いそうだ。彼女は全くの暗黒と静寂によって社会から隔離されている。最も恋い焦がれているのは友情ある人の声なのである。彼女は全盲である。そのくせ、彼女は大概の目の見える人より遥かに本を読んでいる。おそらく一般人の百ばいは本をよんでいるだろう。その上、著書も七冊まである。その生涯が映画化された時は出演までした。耳も全く聴こえないが、ちゃんと耳の聴こえる大概の人より遥かによく音楽を鑑賞できる。 198号と同じです。 *追加:2008.3.8 Googleで「Three Days to see」を検索しますと、ヘレンケラーの願望が読み取れます。 *追加:2009.10.19 |
|
安岡正篤『照心語録』の中の一つに『真剣に読書することを目耕という。晋の王韶之(しょうし) が若い時、貧乏もかまわず本ばかり読んでいる。家人が「こんなに貧乏なのだから少しは耕したらどうか」とそしると、彼曰く、「我常に目耕せるのみ」と。書斎などに掲げておきたい語だ。』との語録がありました。 ▼私のハガキ通信「三二三号(平成十五年十二月一日)」「色 読」について、近所の日蓮宗のお寺での「日蓮・なぐさめの手紙」について講演を聴いたときである。講演者は「最近、日蓮の手紙を読み始めた。私の手紙の読み方は、通り一遍の、皮相な読み方なのであるが、日蓮の手紙は、襟を正し、本気で読まないと、理解できないことを知った。色読の必要である。」 ▼読書の態度について味わいのある言葉を先人は考えていたものだ。私は目耕・色読をとおして心を耕しているのではないかと思い「心 耕」という言葉を造語した。 ▼インターネットで「心 耕」を検索すると、「心耕」と「耕心」の言葉が使われているのを知った。そのなかに、三宝寺(所在地は記録されていなかった)の記事があった。当寺では「耕心の会」という法話の会を月に1回開催しております。「耕心」の名前の由来は、釈尊が在世中にお悟りを開かれて説法伝導の旅の途中で、田を耕していた農夫に「聖者よ、あなたもそんなことをしていないで田でも耕したらどうだ。」と言われ、釈尊は静かにその農夫の前に行き、そっと農夫の胸に手を当て「私も大切な“心という田”を耕しているのだよ。」といわれた、故事によるものです。 ▼よい言葉を造ったものだと、ひとりで喜んでいたが、お釈尊様以来すでにつくられているのを知り、自分の無知を恥じた。 平成十六年三月二十二日、平成二十三年一月二十四日再読。 |
|
愛読、未読、素読など読む字のつくものは平素よくきく言葉である。色読は知らなかった。近所の日蓮宗のお寺での「日蓮・なぐさめの手紙」について講演を聴いたときである。講演者は「最近、日蓮の手紙を読み始めた。私の手紙の読み方は、通り一遍の、皮相な読み方なのであるが、日蓮の手紙は、襟を正し、本気で読まないと、理解できないことを知った。色読の必要である。」そのとき、全身で読み、行動実践で読むことを意味するでしょう(後略)とある歴史家の解釈を紹介された。 ▼愛読書を持っているだけで幸せである。愛読書にもいろいろあるだろうが、行動実践で読めるものを持っているだろうか? 一つでも持っている者は幸せである。二つ持てば、なお幸せである。現在は価値観の多様化によって自分で色読する読み物を持っているひとは多様化しているのではないだろうか。 ▼色読できるために、まず問われるのは、過去.現在を問わず、この人ならば、実践行動で尊敬できる人を自分が持っているかどうか。そのためには生存されている尊敬できる人がいる者。また、それがない人には、現在にいたるまで読み続けられた古典と呼ばれる著作とその人物の研究がよいのではないだろう。そして、その人たちの言動を真似ること。少しも恥ずかしいことではない。 「自学自得ハガキ通信第二部」323号と同じ。 |
|
OECD国際学習到達度調査(参加国が共同して国際的に開発した十五歳児を対象とする学習到達問題を実施する調査。日本では高校一年生一三〇万人から、層化二段階抽出法で調査する学校うぃお決定し、各学校から無作為に調査対象生徒約四七〇〇人を選定した。) ▼「数学的リテラシー(応用力)」は六位、「読解力」は経済協力開発機構(OECD)平均並みの十四位―十七日公表された国際学習到達度調査の結果で、日本はこの二つの分野で前回より大きく順位を下げた。私も残念に思います。文部科学省や教育専門家の方々が制度や対策をとられるでしょう。最近「ゆとり教育」の反省の言葉を大臣が発言したりしている。 ▼私はかって某企業の社員の研修を担当したことがあります。その方法はいわゆる通信教育法でありました。一定期間、研修生を合宿、指導項目を教えて、職場に帰し、毎月課題を与えて報告を提出、添削して返却する。ある期間するとまた研修所に寝泊りして教育指導・試験をする形式であった。仕事が終わり家庭に帰り通信課題を調べ報告するためには2~3時間は勉強しなければならなかった。大変つらいことであった。それでも彼らは頑張っていました。 ▼あるとき「生活アンケート」を送り調べたことがあります。その中のひとつに「職場の人や家族にほめられましたか」という質問にたいして、職場もさることながら家族からほめられたという回答が意外と多かった。例えば「よくお酒が辛抱できますね」とか「昔よりおこらなくなりましたね」とか「お父さんはよく勉強するね」とか。私が見落としていたのはそこでした。会社での研修でもあると同時に、家庭の研修でもあったのではないか。私はもともと、研修は職場と研修生と研修所の三位一体だと考えていたのですが、実は家族を含めた四位一体だったのです。 ★参考:お父さんの勉強は家族を動かす ▼子供の親も塾に通わせる、よいと思われる学校を選んでいる。しかし、それだけでは人任せになりませんか。私の体験から、読解力を向上するには、子供が本を読む機会がふえることが先決でないでしょうか。そのためには、父母たちが子供のいるところで少なくとも毎日一日五分間(それ以上が望ましい)でも本を読んでは。必ず効果があると信じています。親が想像する以上に子供は親のすることを見ています。 平成十六年十二月二十日 ★補足:2005年07月120日(水曜日)朝日新聞社説 言語力 やはり読書が大切だ 「言語力」という聞き慣れない言葉を盛り込んだ法案が衆議院で可決され、今の国会で成立する見通しとなった。 文字・活字文化振興法案である。与野党の286人から成る超党派の議員連盟がまとめた。 法案では、読み書きだけでなく、伝える力や調べる力なども含めて「言語力」と呼ぶ。言語力をはぐくむことで、心豊かな生活を楽しめるようにする。そんな目的を掲げて、図書館の充実などを国と自治体に求めている。 言葉の力をつけるのをわざわざ法律で定める必要があるのか。そんな疑問を抱く人がいるかもしれない。 しかし、さまざまな学力調査が示すように、児童や生徒の読解力や表現力が低下している。大学生の採用試験で企業が最も重視するのは、コミュニケーション能力である。伝える力や聞く力の乏しい学生が少なくないからだ。 言葉の力をつけるには、言葉と出合う機会を増やすにかぎる。それには本を読むことが欠かせない。 全国学校図書館協議会の04年度の調査では、1カ月間に1冊も本を読まなかったのは、小学生で7%、中学生で19%、高校生では43%にのぼった。 最悪だったころに比べれば、本を読まない中高生はやや減っている。しかし、進学するにつれて、読書から遠ざかる傾向は変わっていない。 大学でも、本を読む学生と読まない学生の二極化が進んでいる。 今はインターネットでさまざまな情報が得られる時代だ。だからといって、読書の意義が薄れたわけではない。 言葉の使い方を知り、漢字や慣用句を覚える。論旨を読み取り、展開の仕方を学ぶ。文化や歴史を学び、思考を伸ばす。想像力を磨く。そうしたことに、読書ほど手軽で効率的な方法はない。 昨年2月の文化審議会は、急速に変化していく今後の社会では、今まで以上に国語力が必要だと答申した。そのために、「自ら本に手を伸ばす子ども」を育てようと提言している。 すでに、いくつかの学校図書館で母親らが児童への「読み聞かせ」を続けている。図書の整理や受付を手伝うグループも多い。家庭で要らなくなった本を集めて学校に配っている自治体もある。 本好きの子どもを増やす取り組みが、もっと広がってほしい。法案をつくった議員は息長く国や自治体に働きかけ、後押しを続けてもらいたい。 言葉の能力の低下というと、大人は若者だけの問題と考えがちだ。しかし、文化庁の世論調査では、年配の人ほど敬語に自信を持っているのに、実際には敬語の使い方を誤っている回答が目立った。「青田買い」などの慣用句でも、50歳以上は若者より間違える人が多かった。 |
|
箱入りの本は本棚にのると読む機会が少なくなる。 辞書も箱入りのものが多い。そのうえ表紙はプラッスチクでカバーされている。
辞書を購入したら箱から取り出して、カバーも外し、箱はメモの入れ物に利用するなど勧めている高校の先生がいた。同じ程度の辞書が数種あれば値段の高いほうを買うように話しているそうだ。
▼つかいふるされているのは勲章をつけているようなものだといわれていた。雑巾も汚れなければ雑巾ではない。 【天声人語】2005年05月09日(月曜日)付を読み率直に驚いた。大学生もここまできたかと。そのまま引用いたします。
ゴールデンウイークが終わって、きょうから大学のキャンパスも活気を取り戻す。講義もそろそろ本格化する頃である。
▼都内の私大で第二外国語のスペイン語を教えている知り合いによると、年々辞書を持たない学生が増えているという。毎年、最初の授業で何冊かの辞書を推薦するのだが、今年3回目の授業で尋ねたところ、クラス30人のうち購入したのは3人だった。かなり前なら、外国語を学ぶのに辞書を買うのは常識だった。いまの学生が辞書を買わない理由「高い」「重い」「引くのが面倒くさい」の三つだという。 別の私大のベテラン教員は、一昔前のこんな話を教えてくれた。辞書の持ち込み可でフランス語を訳す試験を行ったところ、ある学生は仏和辞典だけでなく、国語辞典も持ち込んだ。訳文に正確さを期するためだった。これまた失われた風景だという。 ▼いま書店の外国語コーナーをのぞくと、「超やさしい○○語の入門」「10日でマスター」といったようなタイトルの薄っぺらい本であふれている。詳しい文法は省略だ。辞書を買わない学生もこういう本は購入する。辞書を片手に難解な原書に挑戦するなんてことは今時、はやらないかもしれない。だが、外国語は地道な努力が習得の基本である。それはいつの時代も変わらない。 孫が某大学の文系の学部に入ったので、私の本棚にデンと鎮座していた研究社の英和大辞典、その他にオクスフォードの英英辞典を持ちかえらせた。これを読み、時流に合わなかったのかと、半信半疑。一度、彼女に実情を聞いてみたいものだ。 平成十七年五月九日、平成二十三年五月六日再読。 |
|
其の一 学而第一 子曰わく、学んで時に之を習う、亦た説(よろこ)ばしからず乎(や)。有朋(とも)遠方より来る、亦楽しからずや。人知らずして慍(いか)らず。亦君子ならず乎。 P.7
論語開巻第一章は、学問とは何か、つまり孔子は学問というものをどう考えていたか、を示す。この言葉を後の編纂者が『論語』の最初にすえることによって、孔子学団における学問のあり方を示そうとしたものである。伊藤仁斎がこの一章を「小論語」とよび、ここに『論語』の全精神が集約されてあらわれているとみたのは的確である。また別に、この章は孔子一生の要約であって、彼は「学びて厭(いと)わず」(述而(じゅじ)第七2)という持続的な学習態度によって天下三千の秀才を集めたが、生涯不遇であった、にもかかわらず「天を怨まず」(憲問(けんもん)第十四37)という悟達の境地に達していたことを示す、とする解釈もあるようだが、それは後世の付会であって、私は賛成しない。ただ素直に孔子が学問のよろこびを語ったものとよんでおきたい不
▼私も何度かホームページに『論語』の語句を引用させていただました。この章の桑原先生の説明のように、「生涯学習」の態度を持ち続けたいものです。
子曰く吾(わ)れ十有五(じゆうゆうご)にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順(したが)う。七十にして心の欲する所に従いて矩(のり)を踰(こ)えず。「為政第二」P.37
この章は規範的にも、歴史的にもよむことができる。「吾」という字が冠せられているのだから、孔子が一生を段階的に特色づけて述べた簡潔な自叙伝であることは間違いない。しかし、それが聖人の生涯なのであるから、のちの者にとっては一つの規範ないし模範と受けとられたのは自然である。たとえば、四十代のことを「不惑」と日常語でもいい、四十にもなったのだから、もう人生への態度をはっきりさせなければならない、あやふやな生き方は許されない、といった語感がそこに常にからむのである。この章は、規範的に受けとるのが普通であって、それはそれで正しいと思う。
▼先生が説明されている終わりに、最後に冒涜的に見えることを恐れず私の感想を一つつけ加えると、人間の成長には学問修養が大いに作用するが、同時に人間が生物であることも無視できないであろう。「天命を知る」というのは、自分がこの世で完遂すべき使命を自覚することであると同時に、五十の衰えの感覚から自分としてはこうしかならないのだということを認め、その運命の甘受の中で生きようと思うことでもある。自信であると同時に諦念である。「耳順」は、自覚的努力というより、生理の作用する寛容、あるいは原理的束縛からの離脱であることが少なくないのではないか。よく言えば素直さだが、あくまで突進しようとするひたむきな精神の喪失ともいえる。「心の欲する所に従いて矩を踰(こ)えず」というのは、自由自在の至上境といえるが、同時に節度を失うような思想ないし行動が生理的にもうできなくなったということにもなろう。それは必ずしも羨ましい境地とは言えないのではないか。これ以上飲むと明日頭が痛かろう、と思って、意志的に盃をおくのが立派なのであって、飲んでいるうちにいつのまにか盃が手を離れるというのでは、いささか淋しかろう。そう思うのは、いつまでも悟れない人間の愚かしい感想だろうか。しかし孔子もまた人であって、彼の発言が無意識的に彼の生理的諸段階を反映しているのかもしれないのである。
▼桑原先生のこの作品は昭和四十九年(1974年)である。先生の生年は1904年であるから、七十歳のときにかかれたものである。孔子のなくなられたのは七十三歳である。
桑原先生がフランス文学研究の情熱を孔子の学問に対するそれと重ねあわされての感想だろうか。
読書好きの年配者に過ぎない私には何か生理的に共感するものがあります。
平成十七年十二月二十一日
宮崎市定『論語の新解釈』など参考にして読まれると表現は違うけれどもおなじような説明を知ることができます。
平成二十三年二月七日
桑原武夫『論語』を読んでいると興味深い論が述べられていた。孔子の「子曰く吾(わ)れ十有五(じゆうゆうご)にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順(したが)う。七十にして心の欲する所に従いて矩(のり)を踰(こ)えず。」の言葉に対して、その深い意味を認めた上で、これは単純に孔子が年を取って肉体的に衰えてきたからだとも読みとれる、と言うのである。つまり、六十にして耳順うとか、七十にして矩を越えずとか言うのも、人間は年老いてくると、他人にいちいち逆らったりするのも面倒だし、若いときのような無鉄砲な力もなくなるので、自然にこうなると言うのである。
このような考えが正しいとか正しくない、と言うよりは、このように突き放して「東洋の知恵」を見てみることも必要と筆者には思われる。このことは言いかえてみると、孔子は老年の知の方から発言しているのに対して、それを桑原武夫は壮年の知の側から見ることも可能なことを指摘している。物事は見方によって、いろいろに見えるものであり、どれかひとつが絶対に正しいなどとは、簡単に言えないのである。河合隼雄『日本人とアイデンティティ』P.60より。
2017.10.23
|
|
最近、老化防止のため「簡単な数字の足し算、引き算」、「文字をなどる」、「写経本」また「パズル」の本などが、書店の入り口のよく見える場所におかれている。 ▼私は手元の表題の辞書を読むことにした。分からないものに赤鉛筆で線を引く。1日目はわずか6ページ読んだだけである。 それぞれの説明をあえて割愛した書き込んで自分で確かめると、その意味を思い出せないものがある。私だけででの分類すると 1、読み方を知らなかったもの:あいせい【合婿】 2、読み方は知っていたが、意味を知らなかったもの:あかぎっぷ【赤切符】、あいよめ【相嫁】
3、意味を知らなかったもの:あいえんきえん【合縁奇縁】、あいかた【合方】、あいくち【合口】、いぜん【愛染】
5、書き方を知らない漢字:あいばん【間判・合判・相判】 6、一度も使ったことのない熟語:あいちょう【愛重】、あいもち【相持ち】
7、使っている言葉の漢字を知らなかったも:あかぎれ【皸】
辞書を読めば自分の日本語の力を知ることができる。古今の書籍をいくら読んでいるかの目安にもなるのではないかと。 以上の言葉の多くは出版物にも平素の会話でもあまり使われない言葉であることにも気づいた。 もし本を読んでいるときにこんな言葉に出会ったときに意味がわかる程度にはなりたいと思う。 反面、こんな言葉を辞書が残している利便と私たちの日常の言葉の変化を知ることができた。辞典を読み楽しがあるようだ。
岩波『国語辞典 第三版』より
参考:読まれた方はその意味を試してみてはいかがですか。見出しの下段の最初に書かれている説明を写しましたからご参考までに。
【合婿】…………………「気にいりのむこ」
【合縁奇縁】……………「人の交わりには互いに気がよく合う合わないがあって、それは不思議な縁によるものだということ」 【合方】…………………「歌い手に対し、三味線(しゃみせん)をひく者」 【合口】…………………「つばのない短刀」 【愛染】…………………「煩悩。▽愛着に染まる意から出た」 【赤切符】………………「もとの汽車の三等乗車券の通称。▽赤い色をしていたから」 【相嫁】…………………「夫の兄弟の妻▽その妻どうしで言う」 【愛重】…………………「愛して大事にすること」 【相持ち】………………「いっしょに持つこと。特に、平等に負担すること」 【間判・合判・相判】…「紙の大きさの一種」 【文色】…………………「様子。ものの区別。けじめ」 【青道心】………………「僧になったばかりで仏道を十分におさめていないひと」 【赤鰯】…………………「ぬかづけにしたいわし。それを干したいわし」 【皸】……………………「寒さのために手足の皮が裂けたもの」 平成十九年八月六日 |

本居宣長が加茂眞淵に一生に一度だけ会ったという話が記憶に残っていて、時折、その記録を探していました。 小林 司『出会いについて』(NHKブックス)P.5~P.9で見つけ出すことが出来ました。 以下にその内容を抜き書きします。 松阪の一夜 私が習った戦前の小学校の国語の教科書『小学校国語読本巻十一』の第十三課には、「松坂の一夜」という文章が載っていた。 三重県松阪市殿町にある本居宣長記念館へ行ってみると、この教科書が、いまでもガラスのケースの中に展示されている。読者の多くもたぶん記憶しておられるこの文章を次に引用しておこう。 「本居宣長は伊勢の國松阪の人である。若い頃から読書が好きで、将来学問を以て身を立てたいと、一心に勉強してゐた。」
『どうも残念なことでした。あなたがよく會ひたいとお話しになる江戸の加茂眞淵先生が、先程お見えになりました。』 といふ。思ひがけない言葉に宣長は驚いて、 『先生がどうしてこちらへ。』 『何でも、山城・大和方面の御旅行がすんで、これから参宮をなさるのださうです。あの新上屋にお泊りになって、さつきお出かけの途中『何か珍しい本はないか。』と、お立寄り下さいました。』 『それは惜しいことをした。どうかしてお目にかゝりたいものだが。』 『後を追つてお出になつたら、大てい追附けませう。』 宣長は、大急ぎで眞淵の様子を聞取つて後を追つたが、松阪の町のはづれまで行つても、それらしい人は見えない。次の宿の先まで行つてみたが、やはり追附けなかつた。宣長は力を落して、すごすごともどつて来た。さうして新上屋の主人に、萬一お帰りに又泊られることがあつたら、すぐ知らせてもらひたいと頼んでおいた。 望みがかなって宣長が眞淵を新上屋の一室に訪ふことが出来たのは、それから数日の後であつた。二人は、ほの暗い行燈のもとで対座した。眞淵はもう七十歳に近く、いろいろりつぱな著書もあつて、天下に聞こえた老大家。宣長はまだ三十歳余り、温和な人となりのうちに、どことなく才気のひらめいてゐる少壮の学者。年こそ違へ、二人は同じ学問の道をたどつてゐるのである。だんだん話してゐる中に、眞淵は宣長の学識の尋常でないことを知つて、非常に頼もしく思つた。話が古事記のことに及ぶと、宣長は、 『私は、かねがね古事記を研究したいと思つてをります。それについて、何か御注意下さることはございますまいか。』 『それは、よいところにお気附きでした。私も、実は早くから古事記を研究したい考はあつたのですが、それは萬葉集を調べておくことが大切だと思つて、其の方の研究に取りかゝつたのです。ところが、何時の間にか年を取つてしまつて、古事記に手をのばすことが出来なくなりました。あなたはまだお若いから、しつかり努力なさつたら、きつと此の研究を大成することが出来ませう。たゞ注意しなければならないのは、順序正しく進むといふことです。これは、学問の研究には特に必要ですから、まづ土台を作つて、それから一歩々々高く登り、最後の目的に達するやうになさい。』 夏の夜はふけやすい、家々の戸は、もう皆とざされてゐる。老学者の言に深く感動した宣長は、未来の希望に胸ををどらせながら、ひつそりした町筋を我が家へ向かつた。 其の後、宣長は絶えず文通して眞淵の教を受け、師弟の関係は日一日と親密の度を加へたが、面会の機会は松阪の一夜以後とうとう来なかつた。 宣長は眞淵の志を受けつぎ、三十五年の間努力に努力を続けて、遂に古事記の研究を大成した。有名な古事記傳といふ大著述は此の研究の結果で、我が國文学の上に不滅の光を放つてゐる。 この本居宣長と加茂眞淵の出会いは、一七六三年(宝暦十三年)五月二十五日の出来事であり、これを佐々木信綱が書いた「松阪の追懐」という文章に基づいて小学生向けにわかりやすくリライトしたものである。この教科書の文中には書かれていないけれども、本居宣長は、京都で修業をしたのちに松阪に戻って小児科医を開業していた。したがって、国文学についてはいわば素人である。 このとき、加茂眞淵は六十七歳、宣長は三十四歳であり、加茂眞淵のほうは、『冠辞考』(一七五七)、『萬葉考』(一七六〇)などもすでに完成していて、将軍有徳公の第二子田安、中な言宗武(国学者。江戸幕府第8代将軍・吉宗の次男)に対する国学の先生を勤め、その名前が天下に響いている大家であった。 二十二歳で京都に医学を学びに出てから、医学だけではなく、契沖の著書などを読んで、国学に興味をもっていた宣長は、長い間ぜひ、加茂眞淵に一度会ってみたいと思っていたのであるが、ちょうど加茂眞淵が旅行をしてきたので、幸運にも旅館で会うことができたのであった。 宣長の日記(宝暦十三年五月)には、「二十五日、曇天、嶺松院会也。岡部衛士当所新上屋一宿。始対面」とある。岡部衛士というのは加茂眞淵のことだ。 著者:小林 司は1929年生まれで、私とほぼ同年でありますが。以上のお話は記憶にありませんでした。 こんな立派な人同士のただ一度の出会いと、その後の絶えざる文通による師弟関係は宣長にとっては、研究の力になっただろうと思われます。 私にも、小学校の先生との全く偶然の出会いで忘れられないものがあります。 参考1:教科書に載った松阪の一夜 私にとって非常に参考になりました。
参考2:本居宣長:うひ山ふみ
平成二十年四月二十日、平成二十六年二月二十一日、修正 |
|
★其の一 守屋 洋 新釈『菜根譚』一九八六年十一月十日第一版第三十二刷(PHP) 『菜根譚』について 『菜根譚』の魅力 『菜根譚』は、人生の書である。 こう言えば、青臭い書生論を連想されるかもしれないが、じつはそうではない。人生の円熟した境地、老獪きわまりない処世の道を説いたのが、『菜根譚』である。 私事になるが、初めて『菜根譚』を読んだのは、二十代の時だった。そのときは、なるほどと肯く面もないではなかったが、多くの点で納得がいかなかった。むしろ反発すらおぼえたものである。それから十年すぎた三十代に、また手にしてみた。そのときは、反発はほとんど感じない。むしろ多くの点で、共感すらおぼえた。さらに十年たった四十代、つい二、三年まえに、三たび読む機会があった。すると、どうだろう、思わず小膝をたたきたくなることばに、しばしばぶっかるではないか。 『菜根譚』は、不思議な魅力をもった本である。 中国の古典のなかには、処世の道を説いた本がたくさんある。いや、中国の古典というものは、もともと「応対辞令の学」といわれるように、直接間接に、処世の道を説いたものが主流であった。古典の九〇パーセントがそういう内容の本だと言ってよい。 『菜根譚』は、そのなかにあって、他の本にはない大きな特色をもっている。それは何かと言えば、儒仏道、すなわち儒教と仏教と道教の三つの主張を融合し、そのうえにたって処世の道を語っていることだ。 中国には、むかしから、思想、道徳のうえで、儒教と道教という二つの大きな流れがあった。この二つは、互いに対立し互いに補完しあいながら、中国人の意識を支配してきた。この関係は、現代中国でも生き続けている。 儒教というのは、「修身、斉家、治国、平天下」、すなわち学問を修め、身を立てて国を治めることを説いたエリートの思想であり、「功名を竹帛ニ垂ル」ことをすすめた「表」の道徳である。また、広く人たるの規範を示しているという点では、建て前の道徳と言ってもよい。 だが、表の道徳だけでは、世の中は息苦しい。そこで必要になるのが、それを補完する「裏」の道徳である。その役割をになったのが道教であり、その原型となる老荘思想だった。儒教が競争場裏に功名を求める哲学だとすれば、道教はみずからの人生にのんびり自足する哲学だと言ってもよい。また、儒教が建て前の道徳だとすれば、道教は本音の道徳だと言ってよいかもしれない。 さらに、儒教がエリートの思想であるとすれば、道教は民衆の思想であったともいえる。しかし、エリートでも、公の場では建て前として儒教の規範に従うが、私生活の本音のところでは、むしろ道教の影響を強く受けてきた。 儒教と道教は、このような関係を保ちながら、中国人の意識を支配してきた。だが、儒教にしても道教にしても、中国の古典は、いわゆる「応対辞令」の学であって、人々の心の問題にまではほとんど立ち入らない。中国人の関心は、一貫して厳しい現実をいかに生きるかにあって、悩める心の救済にはあまり関心を示さなかった。その欠を補ったのが、インドから伝わった仏教であり、とくに、それをもとに中国で独自の展開を見せた禅である。禅は一時、在来の儒教や道教を圧倒する勢いで、中国社会に広まった。 『菜根譚』は、この三つの教えを融合したところに特徴があり、そこから独特の味わいがかもし出されている。 たとえば、悠々自適の心境を語りながら、必ずしも功みょう富貴を否定しない。また、きびしい現実を生きる処世の道を説きながら、心の救済にも多くのことばをついやしている。隠士の心境に共鳴しながら、実社会に立つエリートの心得を説くことも忘れない。 だから、『菜根譚』という本は、読む人の境遇によって、受け取り方がずいぶんちがってくるにちがいない。 しかし、それぞれの境遇に応じて、必ずや得るところもおおいはずである。きびしい現実のなかで苦闘している人々は適切な助言を見出すであろうし、ふ遇な状態に苦しんでいる人々はなぐさめと励ましを受けるであろうし、心のいらいらに悩まされている人々は大いなる安らぎを与えられるであろう。 読む人の境遇に応じて、いろいろな読み方ができるところに、『菜根譚』のあやしげな魅力があると言ってよい。 ▼参考:釈 宗演 人生の名著 『菜根譚』 (三笠書房)から出版。 釈 宗演は、1859年、若狭国に生まれ、12歳で妙心寺の越渓(えつけい)について得度し、仏門に入った。その後、越渓の師である備前国曹源寺の儀山のもとで参究を続け、20歳で鎌倉に赴き、円覚寺・洪川(こうせん)和尚の法燈を嗣いだ。夏目漱石や鈴木大拙の師として有めおい。
孔子の人間学――論語からの発想 「論語読み」の愉しみ 実用的な職業訓練の書『論語』 山本七平氏が、『論語の読み方』(祥伝社)で[論語]を現代に生きていくのに役立てようという、きわめて実用的な「読み方」をしています。そして私は、山本氏の読み方は、ひとつの立派な方法だと思う。 もちろん、学問という観点からすると、山本氏の読み方は、第二義的なものにすぎない、とはいえます。そもそも、学問というのは、つき進めていけば、そのまま実用に役立つというものではない。とくに、基礎的な研究になればなるほど、実用とは縁遠くなるものですが、それでも「論語」についていえば、山本氏の読み方は、決して間違っていないと言えるでしょう。 私がこのように言うのは「論語」そのものが、孔子がその弟子に職業訓練をしたときの言行録であって、それはきわめて実用的なものであったからです。 ちなみに、「論語」の冒頭に、「子曰わく、学んで時に之を習う。亦悦(よろこ)ばしからずや」という有名な一句があります。ここでいう「学」とは礼を学ぶことで、孔子は礼を教える職業学校の校長とみてもいい。当時はまだ祭政一致の傾向の強い時代でしたから、伝統的な礼を知っている人材を要求され、孔子は弟子に礼を教えて、諸侯や貴族の下に就職させていたのです。 ところで、礼、あるいは「仕来」というと、最近の人は単なる形式といって軽視するところがありますが、これは大変な間違い。いっさいは、人間関係の処理でエネルギーを節約する重要な方法です。 たとえば、朝、人と会ったとします。「おはよう」という言葉がなければ、どのようにして、相手に自分の好意を伝えるかで、そのたびに考えなければならない。これは、ほんの一例ですが、現在の外交にしても政治にしても、それほど障害のないところは、すべて類型化、形式化して、エネルギーを節約している。 このように人間関係には礼は重要ですが、孔子の時代は祭政一致の傾向が強く、今以上に礼が重視されたのですから、礼の大家である孔子の下に、よい就職先を得るために、多くの弟子が集まってきたのでしょう。 「論語」は、こうして孔子が弟子に職業訓練をしたときに、弟子の質問に答えて話したことを、後になって弟子たちが言行録としてまとめたもので、孔子自らが筆をとって書いたものではない。それで「論語」では、よく「こういう場面で弟子が質問した」という書き方になっている。また「子曰わく」と書いてあっても、孔子がみんなを集めて演壇の上から説教したのではなく、折々に質問に答えて話した言葉です。 「仕来の中から人生を求める」 ところで、「論語」ではもちろん、礼のことについても多少はとりあげていますが、これは全体からみると少ない。何故なら孔子は、ただ昔からの「仕来」をオウム返しにするだけでは満足しなかった。礼の裏には必ず仁とか道とかいう人間性の問題があると考え、その意味も礼とともに弟子に教えたからです。 つまり、「仕来」の中から人生を求めていった。それが「論語」にまとめられたといえます。先の例で言えば、「論語」は職業学校の校長の精神教育の報告書とでもいえましょうか。 このように、孔子には、それまでの習慣を集大成した古い面と、人生の意味を突きとめようとした新しい面とがある。しかし、いずれにしても、彼の動機が職業教育、弟子の就職というところにあったことは疑いない。 だから、山本氏のように「論語」をハウツウもののように読むのは決して間違いではないし、大いにそのように利用していいのです。 ところで、当時は孔子だけでなく、ほかにも礼を教える先生はいたはずなのに、それらの学説は滅びてしまい、孔子だけが残ったという点も無視できない。これは、孔子の学説が、当時の世の中をよくよく反映していたということでしょう。それだけに、当時の社会、教育などが一体どういうものであったか、を知るのは大変参考になる。 [論語]は、山本氏の読み方のほかにも、あらゆる利用の方法がある。ということです。 それでは、このように一般の人にも親しみやすいはずの「論語」が、大変に難解なものとみられてきたのは、何故でしょうか。それを知るには、やはり、「論語」の歩んできた歴史をみる必要があります。 先王の教から孔子の儒教 まず、「論語」は、儒教の最高の経典とみていいのですが、孔子自身は儒教という言葉を一度も言っていない。これは、儒教が孔子の時代から数百年も後の漢代の初期に成立したものですからです。(中略) 宋時代を分岐点(朱子学が成立)として、先王の教であった孔子の教えである儒教にスッキリと形を整えていきました。このことを宋史の「道学伝」では、 「故に曰く、(孔)夫子は堯舜よりも賢(まさ)ること遠し矣」 と書いています。 さらに、こうした儒教の教学上のことだけではなく、官吏登用試験である科挙のやりかたが「論語」をより、広く中国社会に根づかせることになりました。 科挙の試験科目は四書と五経、それに詩をつくらせる詩賦と、策論の四種類。宋時代以降、その中で最も重んじられたのが四書ですが、ことに「論語」は問題が出しやすいこともあって科挙の最重要科目になりました。 それで、何をおいても「論語」だけは、十分に理解しておかなければ絶対に受からない、というので、子供の教育も、まず字の形をおぼえたら、すぐに「論語」を読ませるというようになっていったのです。 以上が、まことに概略だけになりましたが、「論語」の中国の歴史で辿った歩みです。 ▼以上、二人の学者の説明で中国古典の読み方の参考になりました。
「学」と言えば私は現代の学問を思いますが、孔子の時代は「礼」など想像することもできませんでした。宮崎先生に啓蒙させられました。それにしても内藤湖南先生が万巻の書を読まれたと何かで読んだことがあります。その中に、私の記憶では書籍の「前書き」「後記」に目を通しておられたことが印象に残っています。私が本を読む時には、これらはほとんど読まず、すぐに本文を読んでいます。これは反省しなければならないことです。「前書き」「後記」に著者が書きたいことが述べられているものだと思いますので、先ずこれらを読み、概要を知った上で本文を読むのがよいと思います。
★参考:中国の古代思想家4
|

新聞を読んでいると三岸節子と好太郎の記事に出会う。 以前に読んだ画家の名前だったと思った。琵琶湖の余呉に関係があった記憶は残っていた。愛知県とかかれているとは。確かめるために本棚を探すと、梅原 猛『湖の伝説』―画家・三橋節子の愛と死―であった。三岸節子と三橋節子の一字違いの名前であった。 ▼その本の表紙の裏に1977年1月4日と書かれていた。約30年昔、私はかなり熱心に読んだ記憶がよみがえってきた。表紙のカバーに「近江昔話花折峠」の絵が描かれている。その絵にこころ惹かれた。写真を見ればわかるでしょう。 私の印象や感じたことを書いてみます。 赤い着物を着た女性に視点が向く。三分の一くらいの幅の紺色の河とも大地とも思えるところに右肩をしたにして、その腕を左上に向け、仏像の手のひらに見られるように何かを受け取るようなかたちである。(右腕を肉腫で切断した)大きな左手を腹部に置き、左肩辺りは横向きであるが下半身は上向きかげん、ふっくらとした顔は上を向いているようでもあり左を向いているようでもある。両足も大きく踏みしめているように描かれている。画面の下にはいろいろな小さい可憐な花が咲いている。画面の右上には左側から右にのびて、弧をえがいて上にのびてどこまでも続く白い道と思われるものが描かれていて、そのうえにワイン色の着物を着ている子供が両手を高く挙げている。横たわっている女性をしっかりと見送っているような構図に、私には若い母親(一男一女の母親であった)が子供を残して旅立つときの思いと最期を見届けるかのように見送っている子供の気持ちが胸を詰まらせる。この絵を見ているだけで彼女の思いに、本を読むまでもないような気分にさせられて題目のフレーズになった。同時に「お釈迦様の涅槃図絵」を思った。自分でも説明しがたいのですが、こころの底からの声のよう・・・。
▼彼女の略歴は、昭和14年生まれ。36年、現、京都市立美術大学日本画科を卒業。48年、3月、左鎖骨腫瘊のため右腕切断手術。左手にて作品を描き出品をつづける。12月、2度目入院。49年、12月、3度目の入院。50年2月24日転移性肺腫瘊のため死去(35歳)。この絵は左手でかかれたものである。「こころ」を余すことなく無言ではあるが絵にすることにより表現している。私は絵の持つ力に圧倒された。
▼私の中学同級生の一人が廣島高等学校(現広島大学)の生徒であったとき、大腿骨肉腫のため大学病院で左足切断手術。その後、松葉杖をつきながら通学していたが卒業を待たず死去した。今にして思う、彼が死去するまで明るく当時の高校生らしく勉学を続けた原動力はなんだったのだろうかと。 平成十八年六月十八日、2011/02/28再読。 |
|
忘れ物を含めて忘れることが多い。最近の私の例では、バスの中に手提げカバンを忘れて、家に帰って気づき、バス会社に電話すると保管されていた。 ▼身に着けているものでさえ忘れる。以前にもホームページに書いたかもしれない?大学病院歯学部で治療を受けて、そのまま帰り、入れ歯をわすれているのに気づいた。学生さんがわざわざ家まで届けてくださった。 また、ある日、病院での受診診日だと思いこみ、バスに乗り込み、たまたま手帳を見ると1日前であったので、気づいたバス停で降りて、折り返して帰り、翌日、あらためて受診に出かけるなどなど。 自分ではこんなはずではなかったのにとおもっているのだが生理はいかんともなしがたしと。 ▼岩波新書が出版されると、全部買い、読まれているほどの読書家の先輩(HJidesaburou.Kobayashi)との電話。「最近はボケ防止に本を読んでいるが、すぐに忘れてしまう」と、こぼされていた。
本当に防止になるのだろうか?
忘れることの効果はいろいろ言われています。読書についても年配者にとってはまんざらではなさそうだ。反面、研究者などにとっては好ましくないことであろう。然し彼らも所詮は人様であるから、記憶力の減退、忘れを避けることは出来ないでしょう。
▼インターネットで「ボケ防止と読書」を検索すると、本当に多くの人が自分の心がけを書かれている。それほど多くの人が(多くは年配の人だと想像)関心をもたれていると思える。
平成十八年十月十三日 |
|
宇宙体験の内的インパクトは、何人かの宇宙飛行士の人生を根底から変えてしまうほど大きなものがあった。宇宙体験のどこが、なぜ、それほど大きなインパクトを与えたかのか。宇宙体験は人間の意識をどう変えるのか。 そこのところを宇宙飛行士たちから直接聞いてみようと、一九八一年の八月から九月にかけてアメリカ各地をまわり、さまざまの生活を送っている元宇宙飛行士たち十二に取材してきた結果をまとめたのがこのレポート(『宇宙からの帰還』)である。P.36 ▼この本の「むすび」を読むと、本書はここで終わる。はじめは、ここまで紹介した宇宙飛行士たちのさまざまな考えをあれこれ分析し、総括して、結論めいたものを付け加えようとおもっていた。 しかし、ここまでのところ何度か読み返しているうちに、そんなことはしないほうがよいと思うにいたった。ここで語られていることは、いずれも安易な総括をゆるさない、人間存在の本質、この世界の存在の本質(の認識)にかかわる問題である。そして、彼らの体験は、我々が想像力を働かせば頭の中でそれを追体験できるというような単純な体験ではない。彼らが強調しているように、それは人間の想像力をはるかに越えた、実体験した人のみがそれについて語りうるような体験である。そういう体験を持たない筆者が彼らを論評することは、いささか無謀というものだろう。と。 立花隆『宇宙からの帰還』(中央公論社)昭和五十八年十二月十日二十一版 ▼私はこの本を読み、『荘子』の鵬鯤(ほうこん)の物語と共に始まる「逊遥遊篇」をおもった。それは、以下のようなものである。 北の果(は)ての海に魚がいて、そのなを鯤(こん)という。鯤の大きささはいったい何千里あるか見当もつかない。ある時突然形が変わって鳥となった。そのなは鵬(ほう)という。鵬の背中は、これまたいったい何千里あるか見当もつかない。ふるいたって飛びあがると、その翼(つばさ)はまるで大空一ぱいに広がって雲のようである。この鳥は、海の荒れ狂うときになると、(その大風に乗って飛びあがり、)さて南の果ての海へ天翔る。南の果ての海とは天の池である。地(てんち)なり。 鵬が南の果ての海に移る時には、水に撃(うつ)つこと三千里、つむじかぜに羽ばたいて上ること九万里、六月の風に乗って天(あま)がけり去るのだと。 大鵬が九万里の上空から眺めた地上の世界の光景が説明されている。我々の住む地上の世界――野馬(かげろう)はためき、塵埃のたちこめ、生きとし生けるもの犇(ひしめ)きあって呼吸するこの地上の生活――の遥かなる高みにひろがる果てしなき天空のあの深くたたえた蒼(あお)さ、それは天空それ自体の色なのであろうか、それとも天と地との限りなき距(へだ)たりがそれを蒼く見せるのであろうが、今、大鵬が九万里の空の高みから逆に地上の世界を見下ろす時、この世界も亦蒼一色として遠くその眼下にひろがるであろう。地上の世界の矮小(わいしょう)さと雑多さとを超克するもの、それは大鵬の限りなき飛揚であり、その超克のみが、一切の地上的な差別と対立の姿を大いなる一に止揚するのである。
▼西暦前四世紀(現代の宇宙物理・工学では説明できない文明・文化の時代)に書かれた「大鵬」と二十世紀の宇宙船を比較するとき、西暦前四世紀その想像力のすさまじさをおもわずにいられません。二つの本を比較しながら読むと自分なりになにかが得られるとおもいました。
平成十八年十一月三日:「文化の日」に書之。
平成十八年十一月十一日 多くのことを親しく教えていただいている方の、6年前に読まれた感想と参考になる体験を追加いたします。私にも非常に参考になります。 『宇宙からの帰還』(立花 隆著 中公論社)を読んで H.10.05.01 「地球の重力圏から脱出し、宇宙空間や月面から地球を眺めたとき、精神に異常なインパクトが与えられる。」宇宙的体験をすることにより、その後宇宙飛行士達は、NASAの勤めを辞め、特異な生活に入っている人が多い。ある人は、宗教家、ビジネスマン、政治家等になり、またある人は、精神に異常をきたしている。中でも、宗教家になっている人が多い。 ただ一人で、暗黒の宇宙の中でぽっかりと浮かぶ宇宙のオアシス地球を眺めたとき、また自分から猛スピードで遠ざかって行く青く美しい聖なる地球の姿を眺めたとき、「自分が宇宙の中でどんな存在であり、自分とは何か?」と問わざるを得ない根本命題にとらわれると思われるが……。 私も、この宇宙体験に似た体験をしたことがある。アメリカのデイズニーランドで仲間とはぐれ、間違って、ただ一人でスペースシャトル宇宙探検号に乗ってしまった時のことである。異国で暗黒の世界に、ただ一人投げ出された時の恐怖とふ安は言葉で言い尽せない。 ▼宇宙空間で感じることは、その時の状況にもよるが、本人のライフヒストリーや思考傾向にもよると思われる。しかし、考えが次第に自分・人種・人類・地球・宇宙と広がり、そして神とのつながりに思い巡らされるようになるのは、当然であろう。 人は、置かれている立場がより高くなり、総合的視野が増し、抽象度が高くなると、自己概念も自ずと変容をきたし、外的な諸状況に的確に対応出来るようになってくる。この事は、何事に置いてもあてはまると思われる。 現在の自分の立場から離れ、別の立場から物事を眺めてみると、新しい発見がある。別の見方や考え方の中に創造性が宿っている。そうなると、全ては相対的かと思われるかもしれない。そうとばかりは言えない。なぜなら、宗教的根本原理は一義的に存在すると言ってもよい。例えば、「我れ思う故に我れ在り」「太陽は、東から昇り西に沈む」「生は死への近づきである」等、これらは閉じた系であり、論理的には矛盾がない。これらを基として、ふ死の体得・永遠のいのちの目覚めから宗教的教義が出来ていると思う。キリストにしても釈迦にしても孔子にしても根本原理は同じであろう。ただ、自分たちなりに自分たちの宗教的教義を展開しているに過ぎず、教義を導くその具体化の段階で、内容や方法において、その時どきその人々により、千変万化していると思われる。
坐禅は、この千変万化の姿に振り迷わされることなく、根本に立ち返り、本来の自己(スピリチュアル・ワンネス)に目覚めるための一方策である。鋭く自己の内面に働きかけ、心身一如に到達できるまで生活を聖らかにすることである。
|
|
ヒルティ著『幸福論 第一部』草間平作訳 (岩波文庫)1992年7月15日 第71刷発行 仕事の上手な仕方 P.13 仕事の上手な仕方は、あらゆる技術のなかでもっとも大切な技術である。というのは、この技術を一度正しく会得すれば、その他の一切の智的活動がきわめて容易になるからである。それなのに、正しい仕事の仕方を心得た人は、比較的少ないものだ。「労働」や「労働者」についておそらくこれまでになく盛んに論議される現代においてすら、実際にこの技術がいちじるしく進歩したとも普及したともみえない。むしろ反対に、できるだけ少なく働くか、あるいは生涯の短い時間だけ働いて、残りの人生を休息のうちに過ごそうというのが、一般の傾向である。 それなら働きと休息とは、一見両立しない対立物のようにみえるが、果たしてそうであろうか。まず第一に、これを検討しなければならぬ。誰でもがすぐそうするように、勤労をたたえるだけでは、勤労の意欲はわくものではない。それどころか、勤労を厭う心が不幸にもこんなにひろまって、ほとんど近代的国民の一つの病気となって、誰もかれもが理屈の上では称賛される勤労から、実際にはできるだけ逃れようとするかぎり、社会状態の改善などは言うも無駄である。働きと休息とが対立物だとすれば、事実上、この社会の病気はとうていなおる見込みはないであろう。(中略) 今日の社会ではまず第一に必要なことは、有益な仕事は、例外なく、すべての人々の心身の健康のために、従ってまた彼等の幸福のために、必要欠くべからざるものだ、という認識と經驗が広く世に普及することである。 以上のことから必然に次のような結論が出てくる。すなわち、怠惰を業とする者はもはや優秀な「高い」階級とは認められず、その正体通りのもの、つまり、正しい処世の道を失った精神的にふ完全な、ふ健康な人間とみなすべきである。こうした考え方が一度、社会全体のゆるがぬ確信の表現の風習となって現れるならば、そのとき初めて、この地上にも、より良い時代が到来するであろう。それまでは世界は、一方の人たちの過大の労働と、他方の人々の過小の働きのために悩むのある。この両方は互いに因果をなして制約し合っているが、しかし、そのいずれかが真実のところ、より不幸であるかはなはだ疑問である。 ところで、われわれのさらに疑問とするところは、この原則は、人類の数千年来の経験に基づくものであり、また、誰もが働いたり働かなかったりして毎日自分でそれをためしてみることができるし、その上、すべての宗教や哲学が常に教えることなのに、なぜそれが今なお広く世に行われないのか、ということである。たとえば、聖書を大いにありがたがっていながら、聖書にはさほど明らかに記されていない死刑をしごく熱心に弁護する一方、聖書のきわめて明白な命令にそむいて、もっとも全然働かないわけではないが、せいぜい一日くらい働いて、あとの六日は貴夫人業である怠惰のうちに日を送って、ふ思議なほど平気でいられる数千人の「貴夫人」があるのは、なぜだろうか。こういうことになるのは、おもに労働の分配と処理とが適当でないからで、そのために労働はしばしば、まったくの重荷となるのである。そこで、われわれはいま本論の主題にかえることになる。 さて、なんらかの仕事がぜひとも必要だという原理がよく納得できて、しかし、やろうとすると妙に故障が起るがそれさえなければ、喜んで仕事にかかりたいという人たちのために、いま初めて、ある教訓を与えることが出来るのである。 参考:ヒルティ *カール・ヒルティは一八三三年、スイスで生まれた。一八九一年、この本は出版された。約百二十年前であるが、「勤労を厭う心が不幸にもこんなにひろまって、ほとんど近代的国民の一つの病気となっても、誰もかれもが理屈の上では称賛される勤労から、実際にはできるだけ逃れようとするかぎり、社会状態の改善などは言うも無駄である。」との記述は、当時のスイスと現在日本の社会の情勢の背景の違いはそれぞれあると思うが現在の若者に「NEET」があることとなぜか結びついてくる。
ヒルティの著作には『眠れぬ夜のために 第一部 第二部』があります、今後、私の生活に役立つ言葉に出会いましたら、適宜掲載します。
|
|
▼中島敦『弟子』 一 魯《ろ》の卞《べん》の游侠《ゆうきょう》の徒、仲由《ちゅうゆう》、字《あざな》は子路という者が、近頃《ちかごろ》賢者《けんじゃ》の噂《うわさ》も高い学匠《がくしょう》・陬人《すうひと》孔丘《こうきゅう》を辱《はずか》しめてくれようものと思い立った。似而非《えせ》賢者|何程《なにほど》のことやあらんと、蓬頭突鬢《ほうとうとつびん》・垂冠《すいかん》・短後《たんこう》の衣という服装《いでたち》で、左手に雄雞《おんどり》、右手に牡豚《おすぶた》を引提げ、勢《いきおい》猛《もう》に、孔丘が家を指して出掛《でか》ける。雞を揺《ゆ》り豚を奮《ふる》い、嗷《かまびす》しい脣吻《しんぷん》の音をもって、儒家《じゅか》の絃歌講誦《げんかこうしょう》の声を擾《みだ》そうというのである。 けたたましい動物の叫《さけ》びと共に眼《め》を瞋《いか》らして跳《と》び込《こ》んで来た青年と、圜冠句履《えんかんこうり》緩《ゆる》く玦《けつ》を帯びて几《き》に凭《よ》った温顔の孔子との間に、問答が始まる。 「汝《なんじ》、何をか好む?」と孔子が聞く。 「我、長剣《ちょうけん》を好む。」と青年は昂然《こうぜん》として言い放つ。 孔子は思わずニコリとした。青年の声や態度の中に、余りに稚気《ちき》満々たる誇負《こふ》を見たからである。血色のいい・眉《まゆ》の太い・眼のはっきりした・見るからに精悍《せいかん》そうな青年の顔には、しかし、どこか、愛すべき素直さがおのずと現れているように思われる。再び孔子が聞く。 「学はすなわちいかん?」 「学、豈《あに》、益あらんや。」もともとこれを言うのが目的なのだから、子路は勢込んで怒鳴《どな》るように答える。 学の権威《けんい》について云々《うんぬん》されては微笑《わら》ってばかりもいられない。孔子は諄々《じゅんじゅん》として学の必要を説き始める。人君《じんくん》にして諫臣《かんしん》が無ければ正《せい》を失い、士にして教友が無ければ聴《ちょう》を失う。樹《き》も縄《なわ》を受けて始めて直くなるのではないか。馬に策《むち》が、弓に檠《けい》が必要なように、人にも、その放恣《ほうし》な性情を矯《た》める教学が、どうして必要でなかろうぞ。匡《ただ》し理《おさ》め磨《みが》いて、始めてものは有用の材となるのだ。 後世に残された語録の字面《じづら》などからは到底《とうてい》想像も出来ぬ・極めて説得的な弁舌を孔子は有《も》っていた。言葉の内容ばかりでなく、その穏《おだや》かな音声・抑揚《よくよう》の中にも、それを語る時の極めて確信に充《み》ちた態度の中にも、どうしても聴者を説得せずにはおかないものがある。青年の態度からは次第に反抗《はんこう》の色が消えて、ようやく謹聴《きんちょう》の様子に変って来る。 「しかし」と、それでも子路はなお逆襲《ぎゃくしゅう》する気力を失わない。南山の竹は揉《た》めずして自ら直く、斬《き》ってこれを用うれば犀革《さいかく》の厚きをも通すと聞いている。して見れば、天性優れたる者にとって、何の学ぶ必要があろうか? 孔子にとって、こんな幼稚な譬喩《ひゆ》を打破るほどたやすい事はない。汝の云《い》うその南山の竹に矢の羽をつけ鏃《やじり》を付けてこれを礪《みが》いたならば、ただに犀革を通すのみではあるまいに、と孔子に言われた時、愛すべき単純な若者は返す言葉に窮《きゅう》したは底本では「窮《きゅう》しし」。顔を赧《あか》らめ、しばらく孔子の前に突立《つった》ったまま何か考えている様子だったが、急に?と豚とを抛《ほう》り出し、頭を低《た》れて、「謹《つつ》しんで教を受けん。」と降参した。単に言葉に窮したためではない。実は、室に入って孔子の容《すがた》を見、その最初の一言を聞いた時、直ちに雞豚《けいとん》の場違《ばちが》いであることを感じ、己《おのれ》と余りにも懸絶《けんぜつ》した相手の大きさに圧倒《あっとう》されていたのである。 即日《そくじつ》、子路は師弟の礼を執《と》って孔子の門に入った。 二 このような人間を、子路は見たことがない。力|千鈞《せんきん》の鼎《かなえ》を挙げる勇者を彼《かれ》は見たことがある。明《めい》千里の外を察する智者《ちしゃ》の話も聞いたことがある。しかし、孔子に在るものは、決してそんな怪物《かいぶつ》めいた異常さではない。ただ最も常識的な完成に過ぎないのである。知情意のおのおのから肉体的の諸能力に至るまで、実に平凡《へいぼん》に、しかし実に伸《の》び伸びと発達した見事さである。一つ一つの能力の優秀《ゆうしゅう》さが全然目立たないほど、過ふ及《かふきゅう》無く均衡《きんこう》のとれた豊かさは、子路にとって正《まさ》しく初めて見る所のものであった。闊達《かったつ》自在、いささかの道学者|臭《しゅう》も無いのに子路は驚《おどろ》く。この人は苦労人だなとすぐに子路は感じた。可笑《おか》しいことに、子路の誇《ほこ》る武芸や膂力《りょりょく》においてさえ孔子の方が上なのである。ただそれを平生《へいぜい》用いないだけのことだ。侠者子路はまずこの点で度胆《どぎも》を抜《ぬ》かれた。放蕩無頼《ほうとうぶらい》の生活にも経験があるのではないかと思われる位、あらゆる人間への鋭《するど》い心理的|洞察《どうさつ》がある。そういう一面から、また一方、極めて高く汚《けが》れないその理想主義に至るまでの幅《はば》の広さを考えると、子路はウーンと心の底から呻《うな》らずにはいられない。とにかく、この人はどこへ持って行っても大丈夫な人だ。潔癖《けっぺき》な倫理的《りんりてき》な見方からしても大丈夫《だいじょうぶ》だし、最も世俗的な意味から云《い》っても大丈夫だ。子路が今までに会った人間の偉《えら》さは、どれも皆《みな》その利用価値の中に在った。これこれの役に立つから偉いというに過ぎない。孔子の場合は全然違う。ただそこに孔子という人間が存在するというだけで充分《じゅうぶん》なのだ。少くとも子路には、そう思えた。彼はすっかり心酔《しんすい》してしまった。門に入っていまだ一月ならずして、もはや、この精神的支柱から離《はな》れ得ない自分を感じていた。 後年の孔子の長い放浪《ほうろう》の艱苦《かんく》を通じて、子路ほど欣然《きんぜん》として従った者は無い。それは、孔子の弟子たることによって仕官の途《みち》を求めようとするのでもなく、また、滑稽《こっけい》なことに、師の傍に在って己の才徳を磨こうとするのでさえもなかった。死に至るまで渝《かわ》らなかった・極端《きょくたん》に求むる所の無い・純粋《じゅんすい》な敬愛の情だけが、この男を師の傍に引留めたのである。かつて長剣を手離せなかったように、子路は今は何としてもこの人から離れられなくなっていた。 その時、四十而不惑《しじゅうにしてまどわず》といった・その四十|歳《さい》に孔子はまだ達していなかった。子路よりわずか九歳の年長に過ぎないのだが、子路はその年齢《ねんれい》の差をほとんど無限の距離《きょり》に感じていた。 孔子は孔子で、この弟子の際立った馴《な》らし難さに驚いている。単に勇を好むとか柔《じゅう》を嫌《きら》うとかいうならば幾《いく》らでも類はあるが、この弟子ほどものの形を軽蔑《けいべつ》する男も珍《めずら》しい。究極は精神に帰すると云いじょう、礼なるものはすべて形から入らねばならぬのに、子路という男は、その形からはいって行くという筋道を容易に受けつけないのである。「礼と云い礼と云う。玉帛《ぎょくはく》を云わんや。楽《がく》と云い楽と云う。鐘鼓《しょうこ》を云わんや。」などというと大いに欣《よろこ》んで聞いているが、曲礼《きょくれい》の細則を説く段になるとにわかに詰《つ》まらなさそうな顔をする。形式主義への・この本能的|忌避《きひ》と闘《たたか》ってこの男に礼楽を教えるのは、孔子にとってもなかなかの難事であった。が、それ以上に、これを習うことが子路にとっての難事業であった。子路が頼《たよ》るのは孔子という人間の厚みだけである。その厚みが、日常の区々たる細行の集積であるとは、子路には考えられない。本《もと》があって始めて末が生ずるのだと彼は言う。しかしその本《もと》をいかにして養うかについての実際的な考慮《こうりょ》が足りないとて、いつも孔子に叱《しか》られるのである。彼が孔子に心ぷくするのは一つのこと。彼が孔子の感化を直ちに受けつけたかどうかは、また別の事に属する。 上智と下愚《かぐ》は移り難いと言った時、孔子は子路のことを考えに入れていなかった。欠点だらけではあっても、子路を下愚とは孔子も考えない。孔子はこの剽悍《ひょうかん》な弟子の無類の美点を誰《だれ》よりも高く買っている。それはこの男の純粋な没利害性のことだ。この種の美しさは、この国の人々の間に在っては余りにも稀《まれ》なので、子路のこの傾向《けいこう》は、孔子以外の誰からも徳としては認められない。むしろ一種のふ可解な愚《おろ》かさとして映るに過ぎないのである。しかし、子路の勇も政治的才幹も、この珍しい愚かさに比べれば、ものの数でないことを、孔子だけは良く知っていた。 師の言に従って己《おのれ》を抑《おさ》え、とにもかくにも形に就こうとしたのは、親に対する態度においてであった。孔子の門に入って以来、乱暴者の子路が急に親孝行になったという親戚《しんせき》中の評判である。褒《ほ》められて子路は変な気がした。親孝行どころか、嘘《うそ》ばかりついているような気がして仕方が無いからである。我儘《わがまま》を云って親を手古摺《てこず》らせていた頃《ころ》の方が、どう考えても正直だったのだ。今の自分の偽《いつわ》りに喜ばされている親達が少々情無くも思われる。こまかい心理|分析家《ぶんせきか》ではないけれども、極めて正直な人間だったので、こんな事にも気が付くのである。ずっと後年になって、ある時|突然《とつぜん》、親の老いたことに気が付き、己の幼かった頃の両親の元気な姿を思出したら、急に泪《なみだ》が出て来た。その時以来、子路の親孝行は無類の献身的《けんしんてき》なものとなるのだが、とにかく、それまでの彼の俄《にわ》か孝行はこんな工合《ぐあい》であった。 三 ある日子路が街を歩いて行くと、かつての友人の二三に出会った。無頼とは云えぬまでも放縦《ほうじゅう》にして拘《こだ》わる所の無い游侠の徒である。子路は立止ってしばらく話した。その中《うち》に彼|等《ら》の一人が子路の服装《ふくそう》をじろじろ見廻《みまわ》し、やあ、これが儒服という奴《やつ》か? 随分《ずいぶん》みすぼらしいなりだな、と言った。長剣が恋《こい》しくはないかい、とも言った。子路が相手にしないでいると、今度は聞捨《ききずて》のならぬことを言出した。どうだい。あの孔丘という先生はなかなかの喰《く》わせものだって云うじゃないか。しかつめらしい顔をして心にもない事を誠しやかに説いていると、えらく甘《あま》い汁《しる》が吸えるものと見えるなあ。別に悪意がある訳ではなく、心安立《こころやすだ》てからのいつもの毒舌だったが、子路は顔色を変えた。いきなりその男の胸倉《むなぐら》を掴《つか》み、右手の拳《こぶし》をしたたか横面《よこつら》に飛ばした。二つ三つ続け様に喰《くら》わしてから手を離すと、相手は意気地なく倒《たお》れた。呆気《あっけ》に取られている他の連中に向っても子路は挑戦的《ちょうせんてき》な眼を向けたが、子路の剛勇《ごうゆう》を知る彼等は向って来ようともしない。殴《なぐ》られた男を左右から扶《たす》け起し、捨台詞《すてぜりふ》一つ残さずにこそこそと立去った。 いつかこの事が孔子の耳に入ったものと見える。子路が呼ばれて師の前に出て行った時、直接には触《ふ》れないながら、次のようなことを聞かされねばならなかった。古《いにしえ》の君子は忠をもって質となし仁をもって衛となした。ふ善ある時はすなわち忠をもってこれを化し、侵暴《しんぼう》ある時はすなわち仁をもってこれを固うした。腕力《わんりょく》の必要を見ぬゆえんである。とかく小人はふ遜《ふそん》をもって勇と見做《みな》し勝ちだが、君子の勇とは義を立つることの謂《いい》である云々。神妙に子路は聞いていた。 数日後、子路がまた街を歩いていると、往来の木蔭《こかげ》で閑人達《かんじんたち》の盛《さか》んに弁じている声が耳に入った。それがどうやら孔子の噂のようである。――昔《むかし》、昔、と何でも古《いにしえ》を担《かつ》ぎ出して今を貶《おと》す。誰も昔を見たことがないのだから何とでも言える訳さ。しかし昔の道を杓子定規《しゃくしじょうぎ》にそのまま履《ふ》んで、それで巧《うま》く世が治まるくらいなら、誰も苦労はしないよ。俺《おれ》達にとっては、死んだ周公よりも生ける陽虎様《ようこさま》の方が偉いということになるのさ。 下剋上《げこくじょう》の世であった。政治の実権が魯侯《ろこう》からその大夫たる季孫氏《きそんし》の手に移り、それが今や更《さら》に季孫氏の臣たる陽虎という野心家の手に移ろうとしている。しゃべっている当人はあるいは陽虎の身内の者かも知れない。 ――ところで、その陽虎様がこの間から孔丘を用いようと何度も迎《むか》えを出されたのに、何と、孔丘の方からそれを避《さ》けているというじゃないか。口では大層な事を言っていても、実際の生きた政治にはまるで自信が無いのだろうよ。あの手合《てあい》はね。 子路は背後《うしろ》から人々を分けて、つかつかと弁者の前に進み出た。人々は彼が孔門の徒であることをすぐに認めた。今まで得々と弁じ立てていた当の老人は、顔色を失い、意味も無く子路の前に頭を下げてから人垣《ひとがき》の背後に身を隠《かく》した。眥《まなじり》を決した子路の形相《ぎょうそう》が余りにすさまじかったのであろう。 その後しばらく、同じような事が処々で起った。肩《かた》を怒《いか》らせ炯々《けいけい》と眼を光らせた子路の姿が遠くから見え出すと、人々は孔子を刺《そし》る口を噤《つぐ》むようになった。 子路はこの事で度々師に叱られるが、自分でもどうしようもない。彼は彼なりに心の中では言分《いいぶん》が無いでもない。いわゆる君子なるものが俺と同じ強さの忿怒《ふんぬ》を感じてなおかつそれを抑え得るのだったら、そりゃ偉い。しかし、実際は、俺ほど強く怒りを感じやしないんだ。少くとも、抑え得る程度に弱くしか感じていないのだ。きっと…………。 一年ほど経《た》ってから孔子が苦笑と共に嘆《たん》じた。由《ゆう》が門に入ってから自分は悪言を耳にしなくなったと。 四 ある時、子路が一室で瑟《しつ》を鼓《こ》していた。 孔子はそれを別室で聞いていたが、しばらくして傍《かたわ》らなる冉有《ぜんゆう》に向って言った。あの瑟の音を聞くがよい。暴厲《ぼうれい》の気がおのずから漲《みなぎ》っているではないか。君子の音は温柔《おんじゅう》にして中《ちゅう》におり、生育の気を養うものでなければならぬ。昔|舜《しゅん》は五絃琴《ごげんきん》を弾《だん》じて南風の詩を作った。南風の薫《くん》ずるやもって我が民の慍《いかり》を解くべし。南風の時なるやもって我が民の財を阜《おおい》にすべしと。今|由《ゆう》の音を聞くに、誠に殺伐激越《さつばつげきえつ》、南音に非《あら》ずして北声に類するものだ。弾者の荒怠暴恣《こうたいぼうし》の心状をこれほど明らかに映し出したものはない。―― 後、冉有が子路の所へ行って夫子《ふうし》の言葉を告げた。 子路は元々自分に楽才の乏《とぼ》しいことを知っている。そして自らそれを耳と手のせいに帰していた。しかし、それが実はもっと深い精神の持ち方から来ているのだと聞かされた時、彼は愕然《がくぜん》として懼《おそ》れた。大切なのは手の習練ではない。もっと深く考えねばならぬ。彼は一室に閉《と》じ籠《こも》り、静思して喰《くら》わず、もって骨立《こつりつ》するに至った。数日の後、ようやく思い得たと信じて、再び瑟を執った。そうして、極めて恐《おそ》る恐る弾じた。その音を洩《も》れ聞いた孔子は、今度は別に何も言わなかった。咎《とが》めるような顔色も見えない。子貢《しこう》が子路の所へ行ってそのむねを告げた。師の咎が無かったと聞いて子路は嬉《うれ》しげに笑った。 人の良い兄弟子の嬉しそうな笑顔《えがお》を見て、若い子貢も微笑を禁じ得ない。聡明《そうめい》な子貢はちゃんと知っている。子路の奏《かな》でる音が依然《いぜん》として殺伐な北声に満ちていることを。そうして、夫子がそれを咎めたまわぬのは、痩《や》せ細るまで苦しんで考え込んだ子路の一本気を愊《あわれ》まれたために過ぎないことを。 五 弟子の中で、子路ほど孔子に叱られる者は無い。子路ほど遠慮《えんりょ》なく師に反問する者もない「請《こ》う。古の道を釈《す》てて由《ゆう》の意を行わん。可ならんか。」などと、叱られるに決っていることを聞いてみたり、孔子に面と向ってずけずけと「これある哉《かな》。子の迂《う》なるや!」などと言ってのける人間は他に誰もいない。それでいて、また、子路ほど全身的に孔子に凭《よ》り掛かっている者もないのである。どしどし問返すのは、心から紊得《なっとく》出来ないものを表面《うわべ》だけ諾《うべな》うことの出来ぬ性分だからだ。また、他の弟子達のように、嗤《わら》われまい叱られまいと気を遣《つか》わないからである。 子路が他の所ではあくまで人の下風に立つを潔しとしない独立|ふ羈《ふき》の男であり、一諾千金《いちだくせんきん》の快男児であるだけに、碌々《ろくろく》たる凡弟子然《ぼんていしぜん》として孔子の前に侍《はんべ》っている姿は、人々に確かに奇異《きい》な感じを与《あた》えた。事実、彼には、孔子の前にいる時だけは複雑な思索《しさく》や重要な判断は一切《いっさい》師に任せてしまって自分は安心しきっているような滑稽《こっけい》な傾向も無いではない。母親の前では自分に出来る事までも、してもらっている幼児と同じような工合である。退いて考えてみて、自ら苦笑することがある位だ。 だが、これほどの師にもなお触れることを許さぬ胸中の奥所がある。ここばかりは譲《ゆず》れないというぎりぎり結著の所が。 すなわち、子路にとって、この世に一つの大事なものがある。そのものの前には死生も論ずるに足りず、いわんや、区々たる利害のごとき、問題にはならない。侠といえばやや軽すぎる。信といい義というと、どうも道学者流で自由な躍動《やくどう》の気に欠ける憾《うら》みがある。そんな名前はどうでもいい。子路にとって、それは快感の一種のようなものである。とにかく、それの感じられるものが善きことであり、それの伴《ともな》わないものが悪《あ》しきことだ。極めてはっきりしていて、いまだかつてこれに疑を感じたことがない。孔子の云う仁とはかなり開きがあるのだが、子路は師の教の中から、この単純な倫理観を補強するようなものばかりを選んで摂《と》り入れる。巧言令色足恭《コウゲンレイショクスウキョウ》、怨《ウラミ》ヲ匿《カク》シテ其《ソ》ノ人ヲ友トスルハ、丘|之《コレ》ヲ恥《ハ》ヅ とか、生ヲ求メテ以《モッ》テ仁ヲ害スルナク身ヲ殺シテ以テ仁ヲ成スアリ とか、狂者ハ進ンデ取リ狷者《ケンジャ》ハ為《ナ》サザル所アリ とかいうのが、それだ。孔子も初めはこの角《つの》を矯《た》めようとしないではなかったが、後には諦《あきら》めて止《や》めてしまった。とにかく、これはこれで一|匹《ぴき》の見事な牛には違いないのだから。策《むち》を必要とする弟子もあれば、手綱《たづな》を必要とする弟子もある。容易な手綱では抑えられそうもない子路の性格的欠点が、実は同時にかえって大いに用うるに足るものであることを知り、子路には大体の方向の指示さえ与えればよいのだと考えていた。敬ニシテ礼ニ中ラザルヲ野トイヒ、勇ニシテ礼ニ中ラザルヲ逆トイフとか、信ヲ好ンデ学ヲ好マザレバソノ蔽《ヘイ》ヤ賊《ゾク》、直ヲ好ンデ学ヲ好マザレバソノ蔽ヤ絞《カウ》 などというのも、結局は、個人としての子路に対してよりも、いわば塾頭格《じゅくとうかく》としての子路に向っての叱言《こごと》である場合が多かった。子路という特殊な個人に在ってはかえって魅力《みりょく》となり得るものが、他の門生|一般《いっぱん》についてはおおむね害となることが多いからである。 六 晋《しん》の魏楡《きゆ》の地で石がものを言ったという。民の怨嗟《えんさ》の声が石を仮りて発したのであろうと、ある賢者が解した。既《すで》に衰微《すいび》した周室は更に二つに分れて争っている。十に余る大国はそれぞれ相結び相闘って干戈《かんか》の止む時が無い。斉侯《せいこう》の一人は臣下の妻に通じて夜ごとその邸《やしき》に忍《しの》んで来る中についにその夫に弑《しい》せられてしまう。楚《そ》では王族の一人が病臥《びょうが》中の王の頸《くび》をしめて位を奪《うば》う。呉《ご》では足頸を斬取《きりと》られた罪人共が王を襲《おそ》い、晋では二人の臣が互《たが》いに妻を交換《こうかん》し合う。このような世の中であった。 魯の昭公は上卿《じょうけい》季平子《きへいし》を討とうとしてかえって国を逐《お》われ、亡命七年にして他国で窮死《きゅうし》する。亡命中帰国の話がととのいかかっても、昭公に従った臣下共が帰国後の己《おのれ》の運命を案じ公を引留めて帰らせない。魯の国は季孫・叔孫《しゅくそん》・孟孫《もうそん》三氏の天下から、更に季氏の宰《さい》・陽虎の恣《ほしいまま》な手に操られて行く。 ところが、その策士陽虎が結局己の策に倒れて失脚《しっきゃく》してから、急にこの国の政界の風向きが変った。思いがけなく孔子が中都の宰として用いられることになる。公平無私な官吏《かんり》や苛斂誅求《かれんちゅうきゅう》を事とせぬ政治家の皆無《かいむ》だった当時のこととて、孔子の公正な方針と周到な計画とはごく短い期間に驚異的《きょういてき》な治績を挙げた。すっかり驚嘆《きょうたん》した主君の定公が問うた。汝の中都を治めし所の法をもって魯国を治むればすなわちいかん? 孔子が答えて言う。何ぞ但《ただ》魯国のみならんや。天下を治むるといえども可ならんか。およそ法螺《ほら》とは縁《えん》の遠い孔子がすこぶる恭《うやうや》しい調子で澄《す》ましてこうした壮語を弄《ろう》したので、定公はますます驚いた。彼は直ちに孔子を司空に挙げ、続いて大司寇《だいしこう》に進めて宰相《さいしょう》の事をも兼《か》ね摂《と》らせた。孔子の推挙で子路は魯国の内閣書記官長とも言うべき季氏の宰となる。孔子の内政改革案の実行者として真先《まっさき》に活動したことは言うまでもない。 孔子の政策の第一は中央集権すなわち魯侯の権力強化である。このためには、現在魯侯よりも勢力を有《も》つ季・叔・孟・三|桓《かん》の力を削《そ》がねばならぬ。三氏の私城にして百雉《ひゃくち》(厚さ三|丈《じょう》、高さ一丈)を超《こ》えるものに郈《こう》・費《ひ》・成《せい》の三地がある。まずこれ等を毀《こぼ》つことに孔子は決め、その実行に直接当ったのが子路であった。 自分の仕事の結果がすぐにはっきりと現れて来る、しかも今までの経験には無かったほどの大きい規模で現れて来ることは、子路のような人間にとって確かに愉快《ゆかい》に違いなかった。殊《こと》に、既成《きせい》政治家の張り廻《めぐ》らした奸悪《かんあく》な組織や習慣を一つ一つ破砕《はさい》して行くことは、子路に、今まで知らなかった一種の生甲斐《いきがい》を感じさせる。多年の抱負《ほうふ》の実現に生々《いきいき》と忙《いそが》しげな孔子の顔を見るのも、さすがに嬉《うれ》しい。孔子の目にも、弟子の一人としてではなく一個の実行力ある政治家としての子路の姿が頼《たの》もしいものに映った。 費の城を毀《こわ》しに掛かった時、それに反抗して公山ふ狃《こうざんふちゅう》という者が費人を率い魯の都を襲うた。武子台に難を避けた定公の身辺にまで叛軍《はんぐん》の矢が及《およ》ぶほど、一時は危かったが、孔子の適切な判断と指揮とによって纔《わず》かに事無きを得た。子路はまた改めて師の実際家的|手腕《しゅわん》に敬服する。孔子の政治家としての手腕は良く知っているし、またその個人的な膂力の強さも知ってはいたが、実際の戦闘に際してこれほどの鮮《あざ》やかな指揮ぶりを見せようとは思いがけなかったのである。もちろん、子路自身もこの時は真先に立って奮い戦った。久しぶりに揮《ふる》う長剣の味も、まんざら棄《す》てたものではない。とにかく、経書の字句をほじくったり古礼を習うたりするよりも、粗《あら》い現実の面と取組み合って生きて行く方が、この男の性に合っているようである。 斉との間の屈辱的《くつじょくてき》媾和《こうわ》のために、定公が孔子を随《したが》えて斉の景公と夾谷《きょうこく》の地に会したことがある。その時孔子は斉の無礼を咎《とが》めて、景公始め群卿諸大夫を頭ごなしに叱咤《しった》した。戦勝国たるはずの斉の君臣一同ことごとく顫《ふる》え上ったとある。子路をして心からの快哉《かいさい》を叫ばしめるに充分な出来事ではあったが、この時以来、強国斉は、隣国《りんこく》の宰相としての孔子の存在に、あるいは孔子の施政《しせい》の下《もと》に充実して行く魯の国力に、懼《おそれ》を抱《いだ》き始めた。苦心の結果、誠にいかにも古代|支那《しな》式な苦肉の策が採られた。すなわち、斉から魯へ贈《おく》るに、歌舞《かぶ》に長じた美女の一団をもってしたのである。こうして魯侯の心を蕩《とろ》かし定公と孔子との間を離間《りかん》しようとしたのだ。ところで、更に古代支那式なのは、この幼稚な策が、魯国内反孔子派の策動と相《あい》俟《ま》って、余りにも速く効を奏したことである。魯侯は女楽に耽《ふけ》ってもはや朝《ちょう》に出なくなった。季桓子《きかんし》以下の大官連もこれに倣《なら》い出す。子路は真先に憤慨《ふんがい》して衝突《しょうとつ》し、官を辞した。孔子は子路ほど早く見切をつけず、なお尽《つ》くせるだけの手段を尽くそうとする。子路は孔子に早く辞《や》めてもらいたくて仕方が無い。師が臣節を汚《けが》すのを懼れるのではなく、ただこの淫《みだ》らな雰囲気《ふんいき》の中に師を置いて眺《なが》めるのが堪《たま》らないのである。 孔子の粘《ねば》り強さもついに諦めねばならなくなった時、子路はほっとした。そうして、師に従って欣《よろこ》んで魯の国を立退《たちの》いた。 作曲家でもあり作詞家でもあった孔子は、次第に遠離《とおざか》り行く都城を顧《かえり》みながら、歌う。 かの美婦の口には君子ももって出走すべし。かの美婦の謁《えつ》には君子ももって死敗すべし。………… かくて、爾後《じご》永年に亘《わた》る孔子の遍歴《へんれき》が始まる。 七 大きな疑問が一つある。子供の時からの疑問なのだが、成人になっても老人になりかかってもいまだに紊得できないことに変りはない。それは、誰もが一向に怪《あや》しもうとしない事柄《ことがら》だ。邪《じゃ》が栄えて正が虐《しいた》げられるという・ありきたりの事実についてである。 この事実にぶつかるごとに、子路は心からの悲憤《ひふん》を発しないではいられない。なぜだ? なぜそうなのだ? 悪は一時栄えても結局はその酬《むくい》を受けると人は云う。なるほどそういう例もあるかも知れぬ。しかし、それも人間というものが結局は破滅《はめつ》に終るという一般的な場合の一例なのではないか。善人が究極の勝利を得たなどという例《ためし》は、遠い昔は知らず、今の世ではほとんど聞いたことさえ無い。なぜだ? なぜだ? 大きな子供・子路にとって、こればかりは幾ら憤慨しても憤慨し足りないのだ。彼は地団駄《じだんだ》を踏《ふ》む思いで、天とは何だと考える。天は何を見ているのだ。そのような運命を作り上げるのが天なら、自分は天に反抗《はんこう》しないではいられない。天は人間と獣《けもの》との間に区別を設けないと同じく、善と悪との間にも差別を立てないのか。正とか邪とかは畢竟《ひっきょう》人間の間だけの仮の取決《とりきめ》に過ぎないのか? 子路がこの問題で孔子の所へ聞きに行くと、いつも決って、人間の幸福というものの真の在り方について説き聞かせられるだけだ。善をなすことの報《むくい》は、では結局、善をなしたという満足の外には無いのか? 師の前では一応紊得したような気になるのだが、さて退いて独りになって考えてみると、やはりどうしても釈然としない所が残る。そんな無理に解釈してみたあげくの幸福なんかでは承知出来ない。誰が見ても文句の無い・はっきりした形の善報が義人の上に来るのでなくては、どうしても面白くないのである。 天についてのこの不満を、彼は何よりも師の運命について感じる。ほとんど人間とは思えないこの大才、大徳が、なぜこうしたふ遇《ふぐう》に甘んじなければならぬのか。家庭的にも恵《めぐ》まれず、年老いてから放浪の旅に出なければならぬようなふ運が、どうしてこの人を待たねばならぬのか。一夜、「鳳鳥《ほうちょう》至らず。河、図《と》を出さず。已《や》んぬるかな。」と独言に孔子が呟《つぶや》くのを聞いた時、子路は思わず涙《なみだ》の溢《あふ》れて来るのを禁じ得なかった。孔子が嘆じたのは天下|蒼生《そうせい》のためだったが、子路の泣いたのは天下のためではなく孔子一人のためである。 この人と、この人を竢《ま》つ時世とを見て泣いた時から、子路の心は決っている。濁世《だくせ》のあるゆる侵害《しんがい》からこの人を守る楯《たて》となること。精神的には導かれ守られる代りに、世俗的な煩労《はんろう》汚辱《おじょく》を一切|己《おの》が身に引受けること。僭越《せんえつ》ながらこれが自分の務《つとめ》だと思う。学も才も自分は後学の諸才人に劣《おと》るかも知れぬ。しかし、いったん事ある場合真先に夫子のために生命を抛《なげう》って顧みぬのは誰よりも自分だと、彼は自ら深く信じていた。 八 「ここに美玉あり。匱《ひつ》に韞《おさ》めて蔵《かく》さんか。善賈《ぜんか》を求めて沽《う》らんか。」と子貢が言った時、孔子は即座《そくざ》に、「これを沽らん哉《かな》。これを沽らん哉。我は賈《あたい》を待つものなり。」と答えた。 そういうつもりで孔子は天下周遊の旅に出たのである。随った弟子達も大部分はもちろん沽りたいのだが、子路は必ずしも沽ろうとは思わない。権力の地位に在って所信を断行する快さは既に先頃の経験で知ってはいるが、それには孔子を上に戴《いただ》くといった風な特別な条件が絶対に必要である。それが出来ないなら、むしろ、「褐《かつ》(粗衣《そい》)を被《き》て玉を懐《いだ》く」という生き方が好ましい。生涯《しょうがい》孔子の番犬に終ろうとも、いささかの悔《くい》も無い。世俗的な虚栄心《きょえいしん》が無い訳ではないが、なまじいの仕官はかえって己《おのれ》の本領たる磊落《らいらく》闊達を害するものだと思っている。 様々な連中が孔子に従って歩いた。てきぱきした実務家の冉有《ぜんゆう》。温厚の長者|閔子騫《びんしけん》。穿鑿《せんさく》好きな故実家の子夏《しか》。いささか詭弁派的《きべんはてき》な享受家《きょうじゅか》宰予《さいよ》。気骨《きこつ》稜々《りょうりょう》たる慷慨家《こうがいか》の公良孺《こうりょうじゅ》。身長《みのたけ》九尺六寸といわれる長人孔子の半分位しかない短矮《たんわい》な愚直者《ぐちょくしゃ》子羔《しこう》。年齢から云っても貫禄《かんろく》から云っても、もちろん子路が彼等の宰領格《さいりょうかく》である。 子路より二十二歳も年下ではあったが、子貢という青年は誠に際立った才人である。孔子がいつも口を極めて賞《ほ》める顔回《がんかい》よりも、むしろ子貢の方を子路は推したい気持であった。孔子からその強靱《きょうじん》な生活力と、またその政治性とを抜き去ったような顔回という若者を、子路は余り好まない。それは決して嫉妬《しっと》ではない。(子貢《しこう》子張輩《しちょうはい》は、顔淵《がんえん》に対する・師の桁外《けたはず》れの打込み方に、どうしてもこの感情を禁じ得ないらしいが。)子路は年齢が違い過ぎてもいるし、それに元来そんな事に拘《こだ》わらぬ性《たち》でもあったから。ただ、彼には顔淵の受動的な柔軟《じゅうなん》な才能の良さが全然|呑《の》み込めないのである。第一、どこかヴァイタルな力の欠けている所が気に入らない。そこへ行くと、多少|軽薄《けいはく》ではあっても常に才気と活力とに充ちている子貢の方が、子路の性質には合うのであろう。この若者の頭の鋭さに驚かされるのは子路ばかりではない。頭に比べてまだ人間の出来ていないことは誰にも気付かれる所だが、しかし、それは年齢というものだ。余りの軽薄さに腹を立てて一喝《いっかつ》を喰わせることもあるが、大体において、後世|畏《おそ》るべしという感じを子路はこの青年に対して抱いている。 ある時、子貢が二三の朋輩《ほうばい》に向って次のような意味のことを述べた。――夫子は巧弁を忌《い》むといわれるが、しかし夫子自身弁が巧過《うます》ぎると思う。これは警戒《けいかい》を要する。宰予などの巧さとは、まるで違う。宰予の弁のごときは、巧さが目に立ち過ぎる故、聴者に楽しみは与え得ても、信頼《しんらい》は与え得ない。それだけにかえって安全といえる。夫子のは全く違う。流暢《りゅうちょう》さの代りに、絶対に人に疑を抱《いだ》かせぬ重厚さを備え、諧謔《かいぎゃく》の代りに、含蓄《がんちく》に富む譬喩《ひゆ》を有《も》つその弁は、何人《なんぴと》といえども逆らうことの出来ぬものだ。もちろん、夫子の云われる所は九|分《ぶ》九|厘《りん》まで常に謬《あやま》り無き真理だと思う。また夫子の行われる所は九分九厘まで我々の誰もが取ってもって範《はん》とすべきものだ。にもかかわらず、残りの一厘――絶対に人に信頼を起させる夫子の弁舌の中の・わずか百分の一が、時に、夫子の性格の(その性格の中の・絶対|普遍的《ふへんてき》な真理と必ずしも一致《いっち》しない極少部分の)弁明に用いられる惧《おそ》れがある。警戒を要するのはここだ。これはあるいは、余り夫子に親しみ過ぎ狎《な》れ過ぎたための慾《よく》の云わせることかも知れぬ。実際、後世の者が夫子をもって聖人と崇《あが》めた所で、それは当然過ぎる位当然なことだ。夫子ほど完全に近い人を自分は見たことがないし、また将来もこういう人はそう現れるものではなかろうから。ただ自分の言いたいのは、その夫子にしてなおかつかかる微小ではあるが・警戒すべき点を残すものだという事だ。顔回のような夫子と似通った肌合《はだあい》の男にとっては、自分の感じるようなふ満は少しも感じられないに違いない。夫子がしばしば顔回を讃《ほ》められるのも、結局はこの肌合のせいではないのか。………… 青二才《あおにさい》の分際で師の批評などおこがましいと腹が立ち、また、これを言わせているのは畢竟《ひっきょう》顔淵への嫉妬だとは知りながら、それでも子路はこの言葉の中に莫迦《ばか》にしきれないものを感じた。肌合の相違ということについては、確かに子路も思い当ることがあったからである。 おれ達には漠然《ばくぜん》としか気付かれないものをハッキリ形に表す・妙《みょう》な才能が、この生意気な若僧《わかぞう》にはあるらしいと、子路は感心と軽蔑とを同時に感じる。 子貢が孔子に奇妙な質問をしたことがある。「死者は知ることありや? 将《は》た知ることなきや?」死後の知覚の有無、あるいは霊魂《れいこん》の滅ふ滅についての疑問である。孔子がまた妙な返辞をした。「死者知るありと言わんとすれば、まさに孝子順孫、生を妨《さまた》げてもって死を送らんとすることを恐る。死者知るなしと言わんとすれば、まさにふ孝の子その親を棄《す》てて葬《ほうむ》らざらんとすることを恐る。」およそ見当違いの返辞なので子貢は甚《はなは》だ不服だった。もちろん、子貢の質問の意味は良く判《わか》っているが、あくまで現実主義者、日常生活中心主義者たる孔子は、この優れた弟子の関心の方向を換《か》えようとしたのである。 子貢は不満だったので、子路にこの話をした。子路は別にそんな問題に興味は無かったが、死そのものよりも師の死生観を知りたい気がちょっとしたので、ある時死について訊《たず》ねてみた。 「いまだ生を知らず。いずくんぞ死を知らん。」これが孔子の答であった。 全くだ! と子路はすっかり感心した。しかし、子貢はまたしても鮮《あざ》やかに肩透《かたすか》しを喰ったような気がした。それはそうです。しかし私の言っているのはそんな事ではない。明らかにそう言っている子貢の表情である。 九 衛《えい》の霊公は極めて意志の弱い君主である。賢とふ才とを識別し得ないほど愚かではないのだが、結局は苦い諫言《かんげん》よりも甘い諂諛《てんゆ》に欣《よろこ》ばされてしまう。衛の国政を左右するものはその後宮であった。 夫人|南子《なんし》はつとに淫奔《いんぽん》の噂が高い。まだ宋《そう》の公女だった頃異母兄の朝《ちょう》という有名な美男と通じていたが、衛侯の夫人となってからもなお宋朝を衛に呼び大夫に任じてこれと醜《しゅう》関係を続けている。すこぶる才走った女で、政治|向《むき》の事にまで容喙《ようかい》するが、霊公はこの夫人の言葉なら頷《うなず》かぬことはない。霊公に聴《き》かれようとする者はまず南子に取入るのが例であった。 孔子が魯から衛に入った時、召を受けて霊公には謁《えっ》したが、夫人の所へは別に挨拶《あいさつ》に出なかった。南子が冠《かんむり》を曲げた。早速《さっそく》人を遣《つか》わして孔子に言わしめる。四方の君子、寡君《かくん》と兄弟たらんと欲する者は、必ず寡小君《かしょうくん》(夫人)を見る。寡小君見んことを願えり云々。 孔子もやむをえず挨拶に出た。南子は絺帷《ちい》(薄《うす》い葛布《くずぬの》の垂れぎぬ)の後に在って孔子を引見する。孔子の北面稽首《ほくめんけいしゅ》の礼に対し、南子が再拝して応《こた》えると、夫人の身に着けた環佩《かんぱい》が璆然《きゅうぜん》として鳴ったとある。 孔子が公宮から帰って来ると、子路が露骨《ろこつ》にふ愉快な顔をしていた。彼は、孔子が南子|風情《ふぜい》の要求などは黙殺《もくさつ》することを望んでいたのである。まさか孔子が妖婦《ようふ》にたぶらかされるとは思いはしない。しかし、絶対|清浄《せいじょう》であるはずの夫子が汚らわしい淫女に頭を下げたというだけで既に面白くない。美玉を愛蔵する者がその珠《たま》の表面《おもて》にふ浄なるものの影《かげ》の映るのさえ避けたい類《たぐい》なのであろう。孔子はまた、子路の中で相当|敏腕《びんわん》な実際家と隣《とな》り合って住んでいる大きな子供が、いつまでたっても一向老成しそうもないのを見て、可笑《おか》しくもあり、困りもするのである。 一日、霊公の所から孔子へ使が来た。車で一緒《いっしょ》に都を一巡《いちじゅん》しながら色々話を承《うけたまわ》ろうと云う。孔子は欣んでふくを改め直ちに出掛けた。 この丈《たけ》の高いぶっきらぼうな爺《じい》さんを、霊公が無闇《むやみ》に賢者として尊敬するのが、南子には面白くない。自分を出し抜いて、二人同車して都を巡《めぐ》るなどとはもっての外である。 孔子が公に謁し、さて表に出て共に車に乗ろうとすると、そこには既に盛装《せいそう》を凝《こ》らした南子夫人が乗込んでいた。孔子の席が無い。南子は意地の悪い微笑を含《ふく》んで霊公を見る。孔子もさすがにふ愉快になり、冷やかに公の様子を窺《うかが》う。霊公は面目無げに目を俯《ふ》せ、しかし南子には何事も言えない。黙《だま》って孔子のために次の車を指《ゆび》さす。 二乗の車が衛の都を行く。前なる四輪の豪奢《ごうしゃ》な馬車には、霊公と並《なら》んで嬋妍《せんけん》たる南子夫人の姿が牡丹《ぼたん》の花のように輝《かがや》く。後《うしろ》の見すぼらしい二輪の牛車には、寂《さび》しげな孔子の顔が端然《たんぜん》と正面を向いている。沿道の民衆の間にはさすがに秘《ひそ》やかな嘆声《たんせい》と顰蹙《ひんしゅく》とが起る。 群集の間に交って子路もこの様子を見た。公からの使を受けた時の夫子の欣びを目にしているだけに、腸《はらわた》の煮《に》え返る思いがするのだ。何事か嬌声《きょうせい》を弄《ろう》しながら南子が目の前を進んで行く。思わず嚇《かっ》となって、彼は拳を固め人々を押分けて飛出そうとする。背後《うしろ》から引留める者がある。振切《ふりき》ろうと眼を瞋《いか》らせて後を向く。子若《しじゃく》と子正《しせい》の二人である。必死に子路の袖《そで》を控《ひか》えている二人の眼に、涙の宿っているのを子路は見た。子路は、ようやく振上げた拳を下す。 翌日、孔子等の一行は衛を去った。「我いまだ徳を好むこと色を好むがごとき者を見ざるなり。」というのが、その時の孔子の嘆声である。 十 葉公《しょうこう》子高《しこう》は竜《りゅう》を好むこと甚だしい。居室にも竜を雕《ほ》り繍帳《しゅうちょう》にも竜を画き、日常竜の中に起臥《きが》していた。これを聞いたほん物《もの》の天竜が大きに欣んで一日葉公の家に降《くだ》り己《おのれ》の愛好者を覗《のぞ》き見た。頭は《まど》に窺《うかが》い尾《お》は堂に揓《ひ》くという素晴らしい大きさである。葉公はこれを見るや怖《おそ》れわなないて逃《に》げ走った。その魂魄《こんぱく》を失い五色主無《ごしきしゅな》し、という意気地無さであった。 諸侯は孔子の賢のなを好んで、その実を欣ばぬ。いずれも葉公の竜における類である。実際の孔子は余りに彼等には大き過ぎるもののように見えた。孔子を国賓《こくひん》として遇《ぐう》しようという国はある。孔子の弟子の幾人《いくにん》かを用いた国もある。が、孔子の政策を実行しようとする国はどこにも無い。匡《きょう》では暴民の凌辱《りょうじょく》を受けようとし、宋では姦臣《かんしん》の迫害《はくがい》に遭《あ》い、蒲《ほ》ではまた兇漢《きょうかん》の襲撃《しゅうげき》を受ける。諸侯の敬遠と御用《ごよう》学者の嫉視と政治家連の排斥《はいせき》とが、孔子を待ち受けていたもののすべてである。 それでもなお、講誦を止めず切磋《せっさ》を怠《おこた》らず、孔子と弟子達とは倦《う》まずに国々への旅を続けた。「鳥よく木を択《えら》ぶ。木|豈《あ》に鳥を択ばんや。」などと至って気位は高いが、決して世を拗《す》ねたのではなく、あくまで用いられんことを求めている。そして、己等《おのれら》の用いられようとするのは己がために非ずして天下のため、道のためなのだと本気で――全く呆《あき》れたことに本気でそう考えている。乏しくとも常に明るく、苦しくとも望を捨てない。誠にふ思議な一行であった。 一行が招かれて楚《そ》の昭王の許《もと》へ行こうとした時、陳《ちん》・蔡《さい》の大夫共が相計り秘かに暴徒を集めて孔子等を途に囲ましめた。孔子の楚に用いられることを惧《おそ》れこれを妨げようとしたのである。暴徒に襲われるのはこれが始めてではなかったが、この時は最も困窮に陥《おちい》った。糧道《りょうどう》が絶たれ、一同火食せざること七日に及《およ》んだ。さすがに、餒《う》え、疲《つか》れ、病者も続出する。弟子達の困憊《こんぱい》と恐惶《きょうこう》との間に在って孔子は独り気力少しも衰《おとろ》えず、平生通り絃歌して輟《や》まない。従者等の疲憊《ひはい》を見るに見かねた子路が、いささか色を作《な》して、絃歌する孔子の側《そば》に行った。そうして訊ねた。夫子の歌うは礼かと。孔子は答えない。絃を操る手も休めない。さて曲が終ってからようやく言った。 「由《ゆう》よ。吾《われ》汝に告げん。君子|楽《がく》を好むは驕《おご》るなきがためなり。小人楽を好むは懾《おそ》るるなきがためなり。それ誰《だれ》の子ぞや。我を知らずして我に従う者は。」 子路は一瞬《いっしゅん》耳を疑った。この窮境に在ってなお驕るなきがために楽をなすとや? しかし、すぐにその心に思い到《いた》ると、途端《とたん》に彼は嬉しくなり、覚えず戚《ほこ》を執って舞《ま》うた。孔子がこれに和して弾じ、曲、三度《みたび》めぐった。傍にある者またしばらくは飢《うえ》を忘れ疲を忘れて、この武骨な即興《そっきょう》の舞《まい》に興じ入るのであった。 同じ陳蔡の厄《やく》の時、いまだ容易に囲みの解けそうもないのを見て、子路が言った。君子も窮することあるか? と。師の平生の説によれば、君子は窮することが無いはずだと思ったからである。孔子が即座に答えた。「窮するとは道に窮するの謂《いい》に非ずや。今、丘《きゅう》、仁義の道を抱き乱世の患に遭う。何ぞ窮すとなさんや。もしそれ、食足らず体|瘁《つか》るるをもって窮すとなさば、君子ももとより窮す。但《ただ》、小人は窮すればここに濫《みだ》る。」と。そこが違うだけだというのである。子路は思わず顔を赧《あか》らめた。己の内なる小人を指摘された心地である。窮するも命なることを知り、大難に臨んでいささかの興奮の色も無い孔子の容《すがた》を見ては、大勇なる哉《かな》と嘆ぜざるを得ない。かつての自分の誇《ほこり》であった・白刃《はくじん》前《まえ》に接《まじ》わるも目まじろがざる底《てい》の勇が、何と惨《みじ》めにちっぽけなことかと思うのである。 十一 許《きょ》から葉《しょう》へと出る途すがら、子路が独り孔子の一行に遅《おく》れて畑中の路《みち》を歩いて行くと、蓧《あじか》を荷《にな》うた一人の老人に会った。子路が気軽に会釈《えしゃく》して、夫子を見ざりしや、と問う。老人は立止って、「夫子と言ったとて、どれが一体汝のいう夫子やら俺《おれ》に分《わか》る訳がないではないか」と突堅貪《つっけんどん》に答え、子路の人態《にんてい》をじろりと眺めてから、「見受けたところ、四体を労せず実事に従わず空理空論に日を暮《く》らしている人らしいな。」と蔑《さげす》むように笑う。それから傍の畑に入りこちらを見返りもせずにせっせと草を取り始めた。隠者《いんじゃ》の一人に違いないと子路は思って一揖《いちゆう》し、道に立って次の言葉を待った。老人は黙って一仕事してから道に出て来、子路を伴って己が家に導いた。既に日が暮れかかっていたのである。老人は雞をつぶし黍《きび》を炊《かし》いで、もてなし、二人の子にも子路を引合せた。食後、いささかの濁酒《にごりざけ》に酔《よい》の廻《まわ》った老人は傍なる琴を執って弾じた。二人の子がそれに和して唱《うた》う。 湛々《タンタン》タル露《ツユ》アリ 陽《ヒ》ニ非ザレバ晞《ヒ》ズ 厭々《エンエン》トシテ夜飲ス 酔ハズンバ帰ルコトナシ 明らかに貧しい生活《くらし》なのにもかかわらず、まことに融々《ゆうゆう》たる裕《ゆた》かさが家中に溢《あふ》れている。和《なご》やかに充ち足りた親子三人の顔付の中に、時としてどこか知的なものが閃《ひらめ》くのも、見逃《みのが》し難い。 弾じ終ってから老人が子路に向って語る。陸を行くには車、水を行くには舟《ふね》と昔から決ったもの。今陸を行くに舟をもってすれば、いかん? 今の世に周の古法を施《ほどこ》そうとするのは、ちょうど陸に舟を行《や》るがごときものと謂《い》うべし。猨狙《さる》に周公の服を着せれば、驚いて引裂《ひきさ》き棄てるに決っている。云々…………子路を孔門の徒と知っての言葉であることは明らかだ。老人はまた言う。「楽しみ全くして始めて志を得たといえる。志を得るとは軒冕《けんべん》の謂ではない。」と。澹然無極《たんぜんむきょく》とでもいうのがこの老人の理想なのであろう。子路にとってこうした遁世哲学《とんせいてつがく》は始めてではない。長沮《ちょうそ》・桀溺《けつでき》の二人にも遇《あ》った。楚の接与《せつよ》という佯狂《ようきょう》の男にも遇ったことがある。しかしこうして彼等の生活の中に入り一夜を共に過したことは、まだ無かった。穏やかな老人の言葉と怡々《いい》たるその容に接している中に、子路は、これもまた一つの美しき生き方には違いないと、幾分の羨望《せんぼう》をさえ感じないではなかった。 しかし、彼も黙って相手の言葉に頷《うなず》いてばかりいた訳ではない。「世と断《た》つのはもとより楽しかろうが、人の人たるゆえんは楽しみを全《まっと》うする所にあるのではない。区々たる一身を潔うせんとして大倫を紊《みだ》るのは、人間の道ではない。我々とて、今の世に道の行われない事ぐらいは、とっくに承知している。今の世に道を説くことの危険さも知っている。しかし、道無き世なればこそ、危険を冒《おか》してもなお道を説く必要があるのではないか。」 翌朝、子路は老人の家を辞して道を急いだ。みちみち孔子と昨夜の老人とを並《なら》べて考えてみた。孔子の明察があの老人に劣《おと》る訳はない。孔子の慾《よく》があの老人よりも多い訳はない。それでいてなおかつ己を全うする途を棄て道のために天下を周遊していることを思うと、急に、昨夜は一向に感じなかった憎悪《ぞうお》を、あの老人に対して覚え始めた。午《ひる》近く、ようやく、遥《はる》か前方の真青《まっさお》な麦畠《むぎばたけ》の中の道に一団の人影が見えた。その中で特に際立って丈の高い孔子の姿を認め得た時、子路は突然《とつぜん》、何か胸を緊《し》め付けられるような苦しさを感じた。 十二 宋から陳に出る渡船の上で、子貢と宰予とが議論をしている。十室の邑《ゆう》、必ず忠信|丘《きゅう》がごとき者あり。丘の学を好むに如《し》かざるなり。という師の言葉を中心に、子貢は、この言葉にもかかわらず孔子の偉大《いだい》な完成はその先天的な素質の非凡《ひぼん》さに依《よ》るものだといい、宰予は、いや、後天的な自己完成への努力の方が与《あずか》って大きいのだと言う。宰予によれば、孔子の能力と弟子達の能力との差異は量的なものであって、決して質的なそれではない。孔子の有《も》っているものは万人のもっているものだ。ただその一つ一つを孔子は絶えざる刻苦によって今の大きさにまで仕上げただけのことだと。子貢は、しかし、量的な差も絶大になると結局質的な差と変る所は無いという。それに、自己完成への努力をあれほどまでに続け得ることそれ自体が、既に先天的な非凡さの何よりの証拠《しょうこ》ではないかと。だが、何にも増して孔子の天才の核心《かくしん》たるものは何かといえば、「それは」と子貢が言う。「あの優れた中庸《ちゅうよう》への本能だ。いついかなる場合にも夫子の進退を美しいものにする・見事な中庸への本能だ。」と。 何を言ってるんだと、傍で子路が苦い顔をする。口先ばかりで腹の無い奴等め! 今この舟がひっくり返りでもしたら、奴等はどんなに真蒼《まっさお》な顔をするだろう。何といってもいったん有事の際に、実際に夫子の役に立ち得るのはおれなのだ。才弁縦横の若い二人を前にして、巧言は徳を紊るという言葉を考え、矜《ほこ》らかに我が胸中一片の氷心《ひょうしん》を恃《たの》むのである。 子路にも、しかし、師へのふ満が必ずしも無い訳ではない。 陳の霊公が臣下の妻と通じその女の肌着を身に着けて朝《ちょう》に立ち、それを見せびらかした時、泄冶《せつや》という臣が諫《いさ》めて、殺された。百年ばかり以前のこの事件について一人の弟子が孔子に尋《たず》ねたことがある。泄冶の正諫《せいかん》して殺されたのは古の名臣|比干《ひかん》の諫死と変る所が無い。仁と称して良いであろうかと。孔子が答えた。いや、比干と紂王《ちゅうおう》との場合は血縁でもあり、また官から云っても少師であり、従って己の身を捨てて争諫し、殺された後に紂王の悔寤《かいご》するのを期待した訳だ。これは仁と謂うべきであろう。泄冶の霊公におけるは骨肉の親あるにも非ず、位も一大夫に過ぎぬ。君正しからず一国正しからずと知らば、潔く身を退くべきに、身の程をも計らず、区々たる一身をもって一国の淫婚《いんこん》を正そうとした。自ら無駄に生命を捐《す》てたものだ。仁どころの騒《さわ》ぎではないと。 その弟子はそう言われて紊得して引き下ったが、傍にいた子路にはどうしても頷《うなず》けない。早速、彼は口を出す。仁・ふ仁はしばらく措《お》く。しかしとにかく一身の危《あやう》きを忘れて一国の紊乱《びんらん》を正そうとした事の中には、智ふ智を超えた立派なものが在るのではなかろうか。空しく命を捐つなどと言い切れないものが。たとえ結果はどうあろうとも。 由《ゆう》よ。汝には、そういう小義の中にある見事さばかりが眼に付いて、それ以上は判《わか》らぬと見える。古の士は国に道あれば忠を尽くしてもってこれを輔《たす》け、国に道無ければ身を退いてもってこれを避けた。こうした出処進退の見事さはいまだ判らぬと見える。詩に曰《い》う。民|僻《よこしま》多き時は自ら辟《のり》を立つることなかれと。蓋《けだ》し、泄冶の場合にあてはまるようだな。 「では」と大分長い間考えた後《あと》で子路が言う。結局この世で最も大切なことは、一身の安全を計ることに在るのか? 身を捨てて義を成すことの中にはないのであろうか? 一人の人間の出処進退の適ふ適の方が、天下|蒼生《そうせい》の安危ということよりも大切なのであろうか? というのは、今の泄冶がもし眼前の乱倫に顰蹙《ひんしゅく》して身を退いたとすれば、なるほど彼の一身はそれで良いかも知れぬが、陳国の民にとって一体それが何になろう? まだしも、無駄とは知りつつも諫死した方が、国民の気風に与える影響から言っても遥かに意味があるのではないか。 「それは何も一身の保全ばかりが大切とは言わない。それならば比干を仁人と褒めはしないはずだ。但《ただ》、生命は道のために捨てるとしても捨て時・捨て処がある。それを察するに智をもってするのは、別に私《わたくし》の利のためではない。急いで死ぬるばかりが能ではないのだ。」 そう言われれば一応はそんな気がして来るが、やはり釈然としない所がある。身を殺して仁を成すべきことを言いながら、その一方、どこかしら明哲《めいてつ》保身を最上智と考える傾向が、時々師の言説の中に感じられる。それがどうも気になるのだ。他の弟子達がこれを一向に感じないのは、明哲保身主義が彼等に本能として、くっついているからだ。それをすべての根柢《こんてい》とした上での・仁であり義でなければ、彼等には危くて仕方が無いに違いない。 子路が紊得し難げな顔色で立去った時、その後姿を見送りながら、孔子が愀然《しゅうぜん》として言った。邦《くに》に道有る時も直きこと矢のごとし。道無き時もまた矢のごとし。あの男も衛の史魚《しぎょ》の類だな。恐らく、尋常《じんじょう》な死に方はしないであろうと。 楚が呉《ご》を伐《う》った時、工尹商陽《こういんしょうよう》という者が呉の師を追うたが、同乗の王子|棄疾《きしつ》に「王事なり。子、弓を手にして可なり。」といわれて始めて弓を執り、「子、これを射よ。」と勧められてようやく一人を射斃《しゃへい》した。しかしすぐにまた弓を韔《かわぶくろ》に収めてしまった。再び促《うなが》されてまた弓を取出し、あと二人を斃《たお》したが、一人を射るごとに目を掩《おお》うた。さて三人を斃すと、「自分の今の身分ではこの位で充分反命するに足るだろう。」とて、車を返した。 この話を孔子が伝え聞き、「人を殺すの中、また礼あり。」と感心した。子路に言わせれば、しかし、こんなとんでもない話はない。殊に、「自分としては三人斃した位で充分だ。」などという言葉の中に、彼の大嫌いな・一身の行動を国家の休戚より上に置く考え方が余りにハッキリしているので、腹が立つのである。彼は怫然《ふつぜん》として孔子に喰って掛かる。「人臣の節、君の大事に当りては、ただ力の及ぶ所を尽くし、死して而《しこう》して後に已《や》む。夫子何ぞ彼を善しとする?」孔子もさすがにこれには一言も無い。笑いながら答える。「然《しか》り。汝の言のごとし。吾《われ》、ただその、人を殺すに忍《しの》びざるの心あるを取るのみ。」 十三 衛に出入すること四度、陳に留まること三年、曹《そう》・宋・蔡・葉・楚と、子路は孔子に従って歩いた。 孔子の道を実行に移してくれる諸侯が出て来ようとは、今更望めなかったが、しかし、もはやふ思議に子路はいらだたない。世の溷濁《こんだく》と諸侯の無能と孔子のふ遇とに対する憤懣《ふんまん》焦躁《しょうそう》を幾年か繰返《くりかえ》した後、ようやくこの頃になって、漠然とながら、孔子及びそれに従う自分等の運命の意味が判りかけて来たようである。それは、消極的に命なりと諦める気持とは大分遠い。同じく命なりと云うにしても、「一小国に限定されない・一時代に限られない・天下万代の木鐸《ぼくたく》」としての使命に目覚めかけて来た・かなり積極的な命なりである。匡《きょう》の地で暴民に囲まれた時|昂然《こうぜん》として孔子の言った「天のいまだ斯文《しぶん》を喪《ほろぼ》さざるや匡人《きょうひと》それ予《われ》をいかんせんや」が、今は子路にも実に良く解《わか》って来た。いかなる場合にも絶望せず、決して現実を軽蔑せず、与えられた範囲で常に最善を尽くすという師の智慧《ちえ》の大きさも判るし、常に後世の人に見られていることを意識しているような孔子の挙措《きょそ》の意味も今にして始めて頷けるのである。あり余る俗才に妨げられてか、明敏子貢には、孔子のこの超時代的な使命についての自覚が少い。朴直《ぼくちょく》子路の方が、その単純極まる師への愛情の故であろうか、かえって孔子というものの大きな意味をつかみ得たようである。 放浪の年を重ねている中に、子路ももはや五十歳であった。圭角《けいかく》がとれたとは称し難いながら、さすがに人間の重みも加わった。後世のいわゆる「万鍾《ばんしょう》我において何をか加えん」の気骨も、炯々たるその眼光も、痩浪人《やせろうにん》の徒《いたず》らなる誇負《こふ》から離れて、既に堂々たる一家の風格を備えて来た。 十四 孔子が四度目に衛を訪れた時、若い衛侯や正卿|孔叔圉《こうしゅくぎょ》等から乞《こ》われるままに、子路を推してこの国に仕えさせた。孔子が十余年ぶりで故国に聘《むか》えられた時も、子路は別れて衛に留まったのである。 十年来、衛は南子夫人の乱行を中心に、絶えず紛争《ふんそう》を重ねていた。まず公叔戊《こうしゅくじゅ》という者が南子排斥を企《くわだ》てかえってその讒《ざん》に遭って魯に亡命する。続いて霊公の子・太子|蒯聵《かいがい》も義母南子を刺《さ》そうとして失敗し晋に奔《はし》る。太子欠位の中に霊公が卒《しゅっ》する。やむをえず亡命太子の子の幼い輒《ちょう》を立てて後を嗣《つ》がせる。出公《しゅつこう》がこれである。出奔《しゅっぽん》した前太子蒯聵は晋の力を借りて衛の西部に潜入《せんにゅう》し虎視眈々《こしたんたん》と衛侯の位を窺う。これを拒《こば》もうとする現衛侯出公は子。位を奪《うば》おうと狙《ねら》う者は父。子路が仕えることになった衛の国はこのような状態であった。 子路の仕事は孔家《こうけ》のために宰として蒲《ほ》の地を治めることである。衛の孔家は、魯ならば季孫氏に当る名家で、当主孔叔圉はつとに名大夫の誉《ほまれ》が高い。蒲は、先頃南子の讒に遭って亡命した公叔戊の旧領地で、従って、主人を逐《お》うた現在の政府に対してことごとに反抗的な態度を執っている。元々|人気《じんき》の荒《あら》い土地で、かつて子路自身も孔子に従ってこの地で暴民に襲われたことがある。 任地に立つ前、子路は孔子の所に行き、「邑に壮士多くして治め難し」といわれる蒲の事情を述べて教を乞《こ》うた。孔子が言う。「恭《きょう》にして敬あらばもって勇を懾《おそ》れしむべく、寛《かん》にして正しからばもって強を懐くべく、温にして断ならばもって姦を抑《おさ》うべし」と。子路再拝して謝し、欣然《きんぜん》として任に赴《おもむ》いた。 蒲に着くと子路はまず土地の有力者、反抗分子等を呼び、これと腹蔵なく語り合った。手なずけようとの手段ではない。孔子の常に言う「教えずして刑《けい》することの不可」を知るが故に、まず彼等に己の意の在る所を明かしたのである。気取の無い率直さが荒っぽい土地の人気に投じたらしい。壮士連はことごとく子路の明快闊達に推服した。それにこの頃になると、既に子路のなは孔門|随一《ずいいち》の快男児として天下に響《ひび》いていた。片言もって獄《ごく》を折《さだ》むべきものは、それ由《ゆう》かなどという孔子の推奨《すいしょう》の辞までが、大袈裟《おおげさ》な尾鰭《おひれ》をつけて普《あまね》く知れ渡《わた》っていたのである。蒲の壮士連を推服せしめたものは、一つには確かにこうした評判でもあった。 三年後、孔子がたまたま蒲を通った。まず領内に入った時、「善い哉、由や、恭敬にして信なり」と言った。進んで邑に入った時、「善い哉、由や、忠信にして寛なり」と言った。いよいよ子路の邸に入るに及んで、「善い哉、由や、明察にして断なり」と言った。轡《くつわ》を執っていた子貢が、いまだ子路を見ずしてこれを褒める理由を聞くと、孔子が答えた。已《すで》にその領域に入れば田疇《でんちゅう》ことごとく治まり草莱《そうらい》甚だ辟《ひら》け溝洫《こうきょく》は深く整っている。治者恭敬にして信なるが故に、民その力を尽くしたからである。その邑に入れば民家の牆屋《しょうおく》は完備し樹木は繁茂《はんも》している。治者忠信にして寛なるが故に、民その営を忽《ゆるが》せにしないからである。さていよいよその庭に至れば甚だ清閑《せいかん》で従者|僕僮《ぼくどう》一人として命《めい》に違《たが》う者が無い。治者の言、明察にして断なるが故に、その政が紊《みだ》れないからである。いまだ由を見ずしてことごとくその政を知った訳ではないかと。 十五 魯の哀公《あいこう》が西の方《かた》大野《たいや》に狩《かり》して麒麟《きりん》を獲《え》た頃、子路は一時衛から魯に帰っていた。その時|小邾《しょうちゅ》の大夫・射《えき》という者が国に叛《そむ》き魯に来奔した。子路と一面識のあったこの男は、「季路をして我に要せしめば、吾|盟《ちか》うことなけん。」と言った。当時の慣《なら》いとして、他国に亡命した者は、その生命の保証をその国に盟ってもらってから始めて安んじて居つくことが出来るのだが、この小邾の大夫は子路さえその保証に立ってくれれば魯国の誓《ちかい》など要《い》らぬというのである。諾《だく》を宿するなし、という子路の信と直とは、それほど世に知られていたのだ。ところが、子路はこの頼をにべも無く断《ことわ》った。ある人が言う。千乗の国の盟をも信ぜずして、ただ子《し》一人の言を信じようという。男児の本懐《ほんかい》これに過ぎたるはあるまいに、なにゆえこれを恥とするのかと。子路が答えた。魯国が小邾と事ある場合、その城下に死ねとあらば、事のいかんを問わず欣んで応じよう。しかし射という男は国を売ったふ臣だ。もしその保証に立つとなれば、自ら売国奴《ばいこくど》を是認することになる。おれに出来ることか、出来ないことか、考えるまでもないではないか! 子路を良く知るほどの者は、この話を伝え聞いた時、思わず微笑した。余りにも彼のしそうな事、言いそうな事だったからである。 同じ年、斉の陳恒《ちんこう》がその君を弑《しい》した。孔子は斎戒《さいかい》すること三日の後、哀公の前に出て、義のために斉を伐《う》たんことを請うた。請うこと三度。斉の強さを恐れた哀公は聴こうとしない。季孫《きそん》に告げて事を計れと言う。季康子《きこうし》がこれに賛成する訳が無いのだ。孔子は君の前を退いて、さて人に告げて言った。「吾、大夫の後《しりえ》に従うをもってなり。故にあえて言わずんばあらず。」無駄とは知りつつも一応は言わねばならぬ己《おのれ》の地位だというのである。(当時孔子は国老の待遇《たいぐう》を受けていた。) 子路はちょっと顔を曇《くも》らせた。夫子のした事は、ただ形を完《まっと》うするために過ぎなかったのか。形さえ履《ふ》めば、それが実行に移されないでも平気で済ませる程度の義憤なのか? 教を受けること四十年に近くして、なお、この溝《みぞ》はどうしようもないのである。 十六 子路が魯に来ている間に、衛では政界の大黒柱|孔叔圉《こうしゅくぎょ》が死んだ。その未亡人で、亡命太子|蒯聵《かいがい》の姉に当る伯姫《はくき》という女策士が政治の表面に出て来る。一子|悝《かい》が父|圉《ぎょ》の後《あと》を嗣《つ》いだことにはなっているが、名目だけに過ぎぬ。伯姫から云えば、現衛侯|輒《ちょう》は甥《おい》、位を窺う前太子は弟で、親しさに変りはないはずだが、愛憎《あいぞう》と利慾との複雑な経緯《けいい》があって、妙に弟のためばかりを計ろうとする。夫の死後|頻《しき》りに寵愛《ちょうあい》している小姓《こしょう》上りの渾良夫《こんりょうふ》なる美青年を使として、弟蒯聵との間を往復させ、秘かに現衛侯|逐出《おいだ》しを企んでいる。 子路が再び衛に戻《もど》ってみると、衛侯父子の争は更に激化《げきか》し、政変の機運の濃《こ》く漂《ただよ》っているのがどことなく感じられた。 周の昭王の四十年|閏《うるう》十二月|某日《ぼうじつ》。夕方近くになって子路の家にあわただしく跳び込んで来た使があった。孔家の老・欒寧《らんねい》の所からである。「本日、前太子蒯聵都に潜入。ただ今孔氏の宅に入り、伯姫・渾良夫と共に当主|孔悝《こうかい》を脅《おど》して己を衛侯に戴かしめた。大勢は既に動かし難い。自分(欒寧)は今から現衛侯を奉《ほう》じて魯に奔るところだ。後《あと》はよろしく頼む。」という口上である。 いよいよ来たな、と子路は思った。とにかく、自分の直接の主人に当る孔悝が捕《とら》えられ脅されたと聞いては、黙っている訳に行かない。おっ取り刀で、彼は公宮へ駈け付ける。 外門を入ろうとすると、ちょうど中から出て来るちんちくりんな男にぶっつかった。子羔《しこう》だ。孔門の後輩で、子路の推薦《すいせん》によってこの国の大夫となった・正直な・気の小さい男である。子羔が言う。内門はもう閉《しま》ってしまいましたよ。子路。いや、とにかく行くだけは行ってみよう。子羔。しかし、もう無駄ですよ。かえって難に遭うこともないとは限らぬし。子路が声を荒《あ》らげて言う。孔家の禄《ろく》を喰《は》む身ではないか。何のために難を避ける? 子羔を振切って内門の所まで来ると、果して中から閉っている。ドンドンと烈《はげ》しく叩《たた》く。はいってはいけない! と、中から叫ぶ。その声を聞き咎《とが》めて子路が怒鳴《どな》った。公孫敢《こうそんかん》だな、その声は。難を逃《のが》れんがために節を変ずるような、俺は、そんな人間じゃない。その禄を利した以上、その患《かん》を救わねばならぬのだ。開《あ》けろ! 開けろ! ちょうど中から使の者が出て来たので、それと入違いに子路は跳び込んだ。 見ると、広庭一面の群集だ。孔悝のなにおいて新衛侯|擁立《ようりつ》の宣言があるからとて急に呼び集められた群臣である。皆それぞれに驚愕《きょうがく》と困惑《こんわく》との表情を浮《う》かべ、向背《こうはい》に迷うもののごとく見える。庭に面した露台《ろだい》の上には、若い孔悝が母の伯姫と叔父《おじ》の蒯聵とに抑えられ、一同に向って政変の宣言とその説明とをするよう、強《し》いられている貌《かたち》だ。 子路は群衆の背後《うしろ》から露台に向って大声に叫んだ。孔悝を捕えて何になるか! 孔悝を離せ。孔悝一人を殺したとて正義派は亡《ほろ》びはせぬぞ! 子路としてはまず己の主人を救い出したかったのだ。さて、広庭のざわめきが一瞬静まって一同が己の方を振向いたと知ると、今度は群集に向って煽動《せんどう》を始めた。太子は音に聞えた臆病者《おくびょうもの》だぞ。下から火を放って台を焼けば、恐れて孔叔(悝)を舎《ゆる》すに決っている。火を放《つ》けようではないか。火を! 既に薄暮《はくぼ》のこととて庭の隅々《すみずみ》に篝火《かがりび》が燃されている。それを指さしながら子路が、「火を! 火を!」と叫ぶ。「先代孔叔文子(圉)の恩義に感ずる者共は火を取って台を焼け。そうして孔叔を救え!」 台の上の簒奪者《さんだつしゃ》は大いに懼れ、石乞《せききつ》・盂黶《うえん》の二剣士に命じて、子路を討たしめた。 子路は二人を相手に激《はげ》しく斬り結ぶ。往年の勇者子路も、しかし、年には勝てぬ。次第に疲労《ひろう》が加わり、呼吸が乱れる。子路の旗色の悪いのを見た群集は、この時ようやく旗幟《きし》を明らかにした。罵声《ばせい》が子路に向って飛び、無数の石や棒が子路の身体《からだ》に当った。敵の戟《ほこ》の尖端《さき》が頬《ほお》を掠《かす》めた。纓《えい》(冠の紐《ひも》)が断《き》れて、冠が落ちかかる。左手でそれを支えようとした途端に、もう一人の敵の剣が肩先に喰い込む。血が迸《ほとばし》り、子路は倒《たお》れ、冠が落ちる。倒れながら、子路は手を伸《の》ばして冠を拾い、正しく頭に着けて素速く纓を結んだ。敵の刃《やいば》の下で、真赤《まっか》に血を浴びた子路が、最期《さいご》の力を絞《しぼ》って絶叫《ぜっきょう》する。 「見よ! 君子は、冠を、正しゅうして、死ぬものだぞ!」 全身|膾《なます》のごとくに切り刻まれて、子路は死んだ。 魯に在って遥かに衛の政変を聞いた孔子は即座に、柴《さい》(子羔)や、それ帰らん。由《ゆう》や死なん。と言った。果してその言のごとくなったことを知った時、老聖人は佇立瞑目《ちょりつめいもく》することしばし、やがて潸然《さんぜん》として涙下った。子路の屍《しかばね》が醢《ししびしお》にされたと聞くや、家中の塩漬類《しおづけるい》をことごとく捨てさせ、爾後《じご》、醢は一切|食膳《しょくぜん》に上さなかったということである。 (昭和十八年二月) 底本:「ちくま日本文学全集 中島敦」筑摩書房 1992(平成4)年7月20日第1刷発行 青空文庫作成ファイル:このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
子路からはじまっている。 私は論語を読んでいて顔回が尊敬すべき人物であると思う。 論語(岩波文庫)の人名索引で出現する人物の多い順位を調べてみた。 それによると1位は子路(季路・仲由)=43、2位は孔子(仲尼)=40、3位は子貢(賜)=31、四位は子張(師)=19、五位は顔淵(回)=18であった。 ▼また『史記』(筑摩世界文学大系)の「列伝篇」の「仲尼弟子伝第七」には 孔子が述懐して言った。「私の門人で六芸(りくげい)に通暁する者はは、七十七人いるが、みな、すぐれた才能の士である。徳業家としては顔渕(がんえん)・閔子騫(びんしけん)・冄伯牛(ぜんはくぎゅう)・冲弓(ちゅうきゅう)がおり、政治家としては冄有(ぜんゆう)・季路(きろ)、弁論家としては宰我(しが)・子貢(しこう)、文学家としては子遊(しゆう)・子夏(しか)がいる。ただそれぞれぞれに短所もあって、子張(しちょう)は偏屈、曽参(そうしん)は遅鈊、子羔(しこう)は愚直、子路は粗野、顔淵は貧乏で、しばしば米櫃(こめびつ)の空しことがあった。子貢は仕官しないで貨殖し、事をはかってよく的中した。」
顔回(がんかい)は魯の人、字(あざな)を子淵(しえん)といい、孔子より三十歳の年少であった。顔淵が仁について問うたところ、孔子は、「おのれの私欲にうちかち、みずから礼に立ちかえってこそ、天下の人は、みな仁にむかうだろう」と答えた。孔子の言に、賢いかな、回(かい)は。箪一盛の飯、瓢一杯の水に満足し、きたない露地の中に安住している。普通の人なら、憂悶に堪えないのに、回は道を楽しんで改めようとしない。回と話すと、一見愚かもののようであるが、私の前を退いたのち、その私生活を観察すると、やはり道義を啓発するものがある。回はけっして愚かなものではない。登用されれば道をおこない、捨てられれば引きこもる。これは、ただ私とおまえと、二人だけができることだとある。回は二十九歳で、頭髪ことごとく白く若死にした。孔子は慟哭し、回を得てから、門人はますます私に親しんだのに――と言って嘆いた。魯の哀公が孔子に、「弟子のうちでは、だれが学問を好むか」と問うたとき、孔子は「顔回という者がおりまして、學を好み、怒りを人に移さず、過ちを二度とくり返さぬ男でございましたが、不幸にも短命で死にました。いまでは他に學を好むという者はおりません」と答えた。(中略)
以上で「仲尼弟子伝第七」について述べるのを終わります。 論語については非常にたくさんの本があります。しかし、孔子についての小説は少ないのか私はよんだことがありませんでしたが、井上靖氏は『孔子』について小説的に纏められています。 孔子の弟子についの小説についてはさらに少ないのではないかと思います。ありましたらご教示ください。私の手元にあるものは以下のものです。 『論語」その裏おもて』駒田信二(旺文社文庫)1985年1月25日初版発行のなかで、駒田信二は、愛弟子・子路――その「狂狷」の項目 P.187 で、 孔子の弟子たちのなかで『論語』に最もしばしばなのあらわれるのは子路である。子路の言動に触れた章は、三十章を越える。 中島敦(一九〇九~四二)の小説「弟子」は、孔子と子路との師弟愛を描いた秀作であるが、そのなかで作者は次のように語っている。 弟子の中で、子路程孔子に叱られる者は無い。子路程遠慮なく師に反問する者もない。 「請ふ。古い道を釈(す)てて由(ゆう)の意を行はん。可ならんか。」などと、叱られるに決まっていることを聞いてみたり、孔子に面と向かってづけづけと「是(これ)ある哉。子の迂なるや!」などと言ってのける人物は他には誰もいない。それでゐて、又子路程全身的に孔子に凭り掛かってゐる者もないのである。どしどし問返すのは、心から納得出来ないものは表面(うはべ)だけ諾(うべな)ふことの出来ぬ性分だからだ。又、他の弟子達のやうに嗤(わら)はれまい叱られまいと気を遣はないからである。 との文章がある。 ▼次に此の小説の解説者は『弟子』は孔子と子路の性格や運命を書いたといえ、題名がしめすように、門下第一の勇士である子路一人の性格や運命が描かれているといった方がよい。もちろん、孔子の人格が思想とともにみごとな人間像をつくり、生き生きと描きだされているからこそ、弟子の子路の一生がその性向とともに美しく描き出されもするのである。子路の人物・性向を愛して、写しだしている。 私も子路が孔子に学び成長する姿に共感するものがありました。また、論語の読み方について、一節一節について学んでいましたが、中島敦『弟子』のように、この人はと思う人の言行についてまとめて読み通すことにより、その努力を知ることも読み方としてあることを教えられました。 2009/01/1、2011/02/26 |
|
読書論は、読書遍歴と読書の方法に大別できる。今回は読書の仕方にかぎって私が実行しているやり方、これまでに読んだ読書論の中で参考になった方法と自分流にアレンジしたものについて述べます。 ★一冊の本の読み方 私は、本を手にとると、書名・著者名を見る。まえがきはとばして、目次にザーと目を通す。本文を読み終わると、一瞬肩の力がぬけるおもいがよぎり、本をとじ、棚にしまいこむ。こんな繰り返しが、私の読み方であった。しばらくの間、印象に残っているが、ほとんど忘れ去られてしまう。 コップにつがれたビールを手に持ち、口に運び、一気に飲みほす。ゴクゴクとのどごし、胃に入る。ああ、うまい。こんな連想をしてもおかしくなかった。 本は、「まえがき」、「目次」、「本文」、「あとがき」で構成されている。すいせん文、解説がついているものもある。まえがきには、著者がどんな意図で本を書いたかをのべている。意図しないものを書いているはずがない。したがって読者は、これを読めば、作者のメッセージをインプットされる。本文を読み進むと、予想されたものにぶっかる。なるほどとうなづかさせられ、目標地点に着いた感じさへする。 ▼桑原武夫『わたしの読書遍歴』(潮文庫)昭和六十一年四月二十五日発行 この本 P.26 に内藤湖南先生(一八六六~一九四三、元京大東洋史教授)の本の読み方について記載されている。を紹介する。 内藤湖南「(一)は大ていの本は序文・目次・結論だけを精読して見当をつけ、精読派を圧倒することがあった。これは彼がすでに無数の本を読んでいたからである。すべての本を精読しなければ気がすまぬ人もあるが、そういう人は恐らく幅の広い教養はもてまい。ここのところは、実は読書論の一ばん重要で、高級なところだが、うまく説明した本を知らない。もちろん私にも説明できぬが、インタレストの強度ということで説明するより他はなかろうと思っている。」 ※余談:この本のⅢ トルストイ『復活』、アベ・ブレヴォ『マロン・レスコ』、プーシキン『大尉の娘』、アンドレ・ジッド『狭き門』、ヘミングウェイ『武器よさらば』、中江兆民『三酔人経綸問答』、竹越与三郎『二千五百年史』、宮崎滔天『三十三年之夢』、南方熊楠『十二支』、内藤湖南『日本文化史研究』である。 この読み方を参考にして、まえがき・あとがきを私も読むように努めている。更に、読み終わった直後、もう一度まえがきにかえっている。すると、一回目に読みすごしていたものに気づいたり、内容理解の程度が深くなり、著者が強調している点を再認識する。また、内容を重点的に記憶するのに役立つ。
教授の本の読み方というのは一口でいうと、その本の伝えようとしているいるメッセージを直接的に表現した文字を、その本の頁の中から探し出すということである。その直接的に表現した文字が「へそ」に相当する。P.14 鵜飼 信成 本の中のへそをさがすのも読書の楽しみの一つになる。このへそをさがしあてるヒントは、まえがきにも書き込まれていると私は考えている。まえがきを精読した者だけがこのメッセージ、へそを読みとることができる。 ★本の選び方 「読書ができるようになれば半分教育が出来たことになります。読書によっていくらでも勉強できます。読む本ですが、ベストセラー等読ませる必要はありません。十年たっても尚読まれる本はよい本です。五十年たっても読まれる本は尚よい本です。百年たっても尚読まれる本は尚よい本です。(後略)」 基督教独立学園(山形県小国町)鈴木弼美(すけよし)校長先生から教えていただいたものです。十年、五十年、百年と読み継がれた本をキッチリとよまなければならないことを教示されている。
どんな本を選ぶにはどうすればよいかの目安としては立花隆氏『「知」のソフトウエァ』(講談社現代新書)昭和五九年三月二〇日第一刷発行(二) に書かれているものが役立つ。
「同(五)じ本を読むならば、ちゃんとその大道を行くべき本は決まっておる。ほかのものを読むこともさしつかえはないが、少なくとも大道を歩くものをまず修めて後にしてもらわないと困る。漢学のほうでありますれば、昔から言つた四書(『大学』『中庸』『論語』『孟子』)が少なくともそこらを読んでおらなければ始まらないのです。ところがそれさえも読まない。この傾向は、おそらく英文学でも国文学でも同じでしょう。また歴sなどでも同じではないでしょうか。」 諸橋徹次先生は言われている。古典、そして読みつがれた本はちゃんと読んでおきたいものである。『古典の叡智』P.75
「よく万巻の書を読むなどというが、そんなことが人間にできるはずはない。人は一年に一万ページの本を読めば、それでひとかどの人物になれるはずだ。一万ページと言えばびっくりするかもしれないが、一日わずか二十八ページずつ読んでいけばいいのだ。」と草柳大蔵氏は書いている。 一日わずか二十八ページずつは、一週間に二百ページ弱の本を一冊読む計算になり、年間五十二冊になる。一人ひとりの読書量を比較してみるとよい。 一日わずか二十八ぺージ読むことを実行してみることにする。三日間ぐらいは続けることはできる。読みやすい本ばかりを読むわけではない。古典類を読みはじめると、また専門書を勉強すると途端にページ数は進まなくなる。それでも二十八ページと思うと苦しみにさへなる。毎日まいにち二十八ぺージの量はこなさなくても、毎日一日も休まずに平均二十八ぺージを読むことはできる。しかし、これができれば、やはりひとかどの人物だと言えると私も思う。 実践する秘訣はいつ、どこででもよむことである。きまった時間、場所でと思っていてはできない。通勤の電車・バスの中で、けいたいしている本を開くことである。 「一日読まざれば、一日くらわず」と覚悟されている先生がいらっしゃいます。満九十歳になられますが、いまでも毎日読書され、私達に佳書の紹介・指導されています。 ★抜き書き 「読書の楽しみのひとつは、感動した言葉や気に入った詩歌を『抜き書き』して、知的宝石箱を作ることにある」と、草柳大蔵氏は言っている。私は、読んだり、聞いたりしてこれぞと思った言葉をいつもけいたいしている手帳に書きこむようにしている。その際、書き抜いた日付・書名・出典、ページなどをきちょうめんにメモしておくことをすすめる。 抜き書きは実行するのをすすめる。どんな効果があるか、一人ひとりの楽しみにまかせることにしたい。 ★立腰と読書 昨年十月より、起床すると、坐り机をまえにして静坐立腰、読書継続してみた。静坐を始めると即刻読書に打ち込めるのと、寒さを余り感じないことを一冬の期間に体験した。 佐藤一斎の『言志晩録』に「読書と静坐を一時に行う工夫」がある。 「(七四)吾れ読書静坐を把(と)つて打(だ)して一片と做(な)さんとと欲し、因て自ら之を試みぬ。経を読む時は、寧静端座し、巻を披(ひら)きて目を渉(しょう)し、一事一理、必ず之を心に求むるに、乃ち能く之れと黙契し、恍として自得する有り。此の際真に是れ無欲にして、即ち是れ主静なり。必ずしも一日各半の工夫を做さず。」(岩波文庫)P.165 昔、朱子は「半日静座、半日読書」といったが、佐藤一斎は読書静坐とを合わせて一ぺんにしようと試みたと、川上正光氏は説明している。 ★わたしの読書課題 「(一)最愛の著者の全作品を読み、これを全人としてとらえること。」 「(ニ)人の卓れた思想家を真に読みぬく事によって、一個の見識はできるものなり。同時に真にその人を選ばば、事すでに半ば成りしというも可ならむ。」 『森信三先生一日一語』二月二十二日 「(三)自己と縁なき著名人の書を読むより、縁ある同志の手刷りのプリントを読む方が、どれほど生きた勉強になるかわからぬ。これ前者は円周上の無数の一点に過ぎないが、後者は直接わが円心に近い人々だからである。」 『森信三先生一日一語』九月三日 尊敬している人が読まれた本を読み追体験 繰り返し読める本を持つこと。
「参考文献」
一 桑原武夫『わたしの読書遍歴』(潮文庫)昭和六十一年四月二十五日発行 P.26
*1986(昭和六十一年八月)に書いていたものを加筆訂正したものです。 2009.06.06記、2012.12.再読・追加。 ※2009.04.23:再読して。引用書物の中に、著者・発行年月日が記載されていない、また直ぐに何ページに書かれているか分からないものがあった。。 |
|
これは『論語』の冒頭の「学 而 第一」の「子曰く、学んで時に之を習う。亦た悦ばしからずや。朋あり、遠方より来る。亦た楽しからずや。人知らずして慍(いきど)おらず。亦た君子ならずや。」の時についての解釈について、下記の著作から抜き出してみた。 1、宮崎市定『論語の新研究』(岩波書店)P.160:「子曰く、(禮を)学んで、時をきめて(弟子たちが集まり)温習会を開くのは、こんなたのしいことはない。」 2、金谷 治『論語』(岩波文庫)P.17:先生がいわれた、「学んでは適当な時期におさらいする、いかにも心嬉しいことだね。[そのたびに理解が深まって向上していくのだから。]」 3、宇野哲人『論語新釈』(講談社学術文庫)P.14:先覚者に従って聖賢の道を学び、断えずこれを復習して熟達するようにする。そうすると、智が開け道が明らかになって、ちょうど今まで浮くこともできなかった者がたちまち游げるようになったようなもであるから、誠に喜ばしいではないか。「時」については時々刻々少しも間断のないこと。 4、諸橋徹次『論語の講義』(大修館書店)P.1:孔子言う、学問をして、その学んだところを機会ある毎に復習して練習して行くと、学んだところがおのずから真の知識として我が身に体得されて来る。これはまたなんと愉快なことではなかろうか。「時」に之を習ふとは、時に当って幾度も練習実習すること。習の字は、雛鳥が巣立ちをする前にしばしば羽ばたきの稽古をすることで、従って自習を続ければ、学んだことが実行にも移されるのである。 以上四冊の本から「時」の解釈を読みました。 「時をきめて」「適当な時期」「時々刻々少しも間断のないこと」「時にあたって幾度も」である。 宮崎市定『論語の新研究』では、 学はここでは禮を学ぶこと。孔子は禮の師であり、弟子に禮を教えて諸侯や貴族の求めに応じて就職させた。当時はまだ祭政一致の傾向の強い時代であったから、伝統的な禮を知っている者が要求されたのである。習うとは復習の意味であるが、ここでは今日の学校における学芸会のように、皆で集まって実演することを言う。孔子の家は学校であった。集会であるから常に行うわけに行かないで時をきめて挙行する。漢の司馬遷が曲阜へ行き、孔子の廟堂を観たが、数百年を経た当時においても、諸生は恰も孔子の時のように、時をきめてその家で禮を習っていることを聞き、史記孔子世家に、 諸生は時を以て、禮を其家に習う。 と記している。 「時」の一字さえも、こんなに解釈が沢山あるのを知った。宮崎市定氏の「時」の解釈は、孔子のこれほどまでの徹底的研究によるものだろうと思った。 2009.11.3 文化の日 |
| 古代への情熱 |

小林 司『出会いについて 精神科医のノートから』P.28~P.30より引用、紹介します トロヤ文明、ミケーネ文明という二大文明を発見した考古学者ハインリッヒ・シュリーマン(一八二二~九〇)は、八歳のときに、ゲオルグ・ルドウィヒ・イエッラー博士が書いた『子供のための世界歴史』という本を、父親から、一八二九年のクリスマスにもらった。 その書物には、燃えあがっているトロイのさし絵があり、そこには巨大な城壁やスカイヤ門がたつていて、父のアンキセスを背負い、幼いアスカニアの手を引いて逃げていくエーネスが描かれていた。 このさし絵を見て、シュリーマンは大喜びで「おとうさん、あなたは間違っていたよ。イエッラーはきつとトロヤを見たことがあるんだ。でなければ博士がここを書けなかったでしょう」と叫んだのであつた。父親は「いや、そんなことはないさ、これはただの空想で書いたんだよ」と答えたのだが、シュリーマンは、「それなら、古代トロヤには実際にこの絵に書かれているような堅固な城壁があったのでしょうか」と聞くと、父親は「そうだ」と答えた。 そこで「お父さん、もしその城壁が建つていることがあるなら、それがあとかたもなくなるなんてことはないから数百年間の石ころやチリの下に隠れて埋まっているかもしれないでしょう」と主張した。父親はもちろん、「そんなことはないさ」と言ったのだが、シュリーマンが自分の考えを堅く主張してゆずらないので、「そのうちにはいつかトロヤを発掘しよう」ということでその場はおさまった。 この時から四十二年後の一八七一年十月十二日、シュリーマンは、ヒッサリックの丘でトロヤの発掘をはじめ、そして古代文明を発掘することになった。もしも、父が八歳の子どもに『子供のための世界歴史』をくれなかったら、こんなことは実現しなかったかもしれない。 これは、シュリーマンと本との出会いであるけれども、よく考えてみると、シュリーマンは本に突然出会ったから古代の発掘を決めたのではなくて、それまでもすでに古代史に対しては熱情的な興味を持つていた父親から、しばしば、古代ローマの小都市ヘラクラネウムやポンペイの悲劇的な滅亡を聞かされていた。そこで行われた発掘を見物するのに十分な時間とお金を持つ人こそは、もっとも幸福な人間であると思っていたらしい。 この父親は、また、しばしば、シュリーマンに、ホメロスの英雄の働きや、トロヤ戦役の出来事を讃えながら物語ったが、「トロイは完全に破壊されて、あとかたもなく地上から消え失せた」と父親に聞かされて、いつも悲しい思いをしていたのであった。そうした下地があったからこそ、この本に出会ったとき、シュリーマンの一生を決定するような気持ちがわいてきたのに違いない。 この場合の本との「出会い」は、いわばガソリンのある所でマッチをすつたような「火つけ役」をしたのものとかんがえられよう。
※参考1:「ゲオルグ・ルドウィヒ・イエッラー博士」はインタネットで検索しても見つかりません。小林司先生が読まれた原本はいまや知ることができません。
※参考3:トロイの遺跡の場所です。想像の翼を広げてみてください。 ※参考4:トロイの遺跡発掘のシュリーマンは江戸時代の日本に来ていた。 1871年にトロイアの遺跡を発掘したことで知られるシュリーマン。『古代への情熱』だけではなく日本好き。世界周遊の旅の中で江戸時代の日本にやってきていたのだ。江戸時代に訪れた場所は、横浜、八王子、浅草、愛宕山など、外国人への襲撃が繰り返される中での訪問だった。『シュリーマン旅行記 清国・日本』より
※余録 江戸川柳「かやば町手本読み読み舟にのり」と… 毎日新聞2019年12月6日 東京朝刊 江戸川柳に「かやば町手本読み読み舟にのり」とある。江戸・茅場町の寺子屋に渡し舟で通う子どもの様子で、読んでいた手本とは「往来物(おうらいもの)」と呼ばれた教科書だ。進学のない時代にずいぶんと勉強熱心である ▲「教育は欧州の文明国以上に行き渡っている。アジアの他の国では女たちが完全な無知の中に放置されているのに対し、日本では男も女もみな読み書きできる」。これはトロイアを発見した考古学者、シュリーマンの日本観察である ▲「みな読み書き」は言い過ぎにせよ、幕末や明治に来日した外国人はその故国と比べて日本の庶民、とくに女性が本を読む姿に本当に驚いている。歴史的には折り紙つきの日本人の「読む力」だが、その急落を伝える試験結果である ▲79カ国・地域の15歳を対象に3年ごとに行われる国際的な学習到達度調査(PISA)で、昨年の読解力の成績が前回の8位から15位へと低下した。科学や数学の応用力の成績が上位に踏みとどまった中での際だった学力後退という ▲「テスト結果に一喜一憂(いっきいちゆう)するな」と言いたいところだが、この成績低下、思い当たるふしがあるのがつらい。何しろ本を読まない、スマホに没頭(ぼっとう)する、長文を読んで考える習慣がない……止まらない活字離れを指摘する専門家が多い ▲以前はゆとり教育からの路線転換をもたらしたPISAのデータだが、読解力はV字回復の後に再び低落した。川柳子や幕末の外国人を驚かせたご先祖たちに教えてもらいたくなる「楽しく読む力」である。 2012.04.17、2014.09.19、2019.12.6追加 |
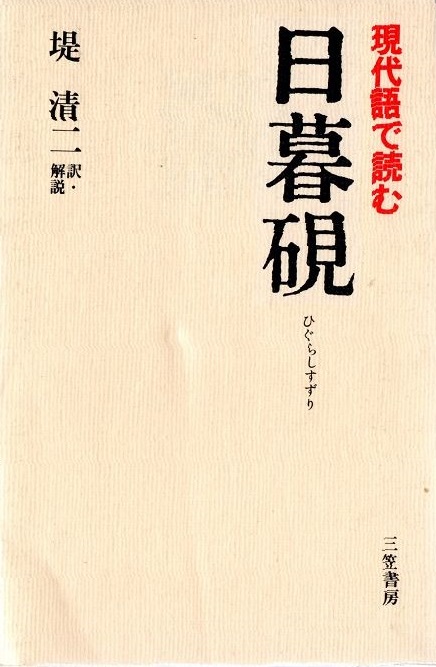 日本人は、「個人の美徳の集積のうえに、集団全体の美徳は発揮される」と考えたがる民族だからである。これも、農耕社会での豊かな収穫は、一人一人が勤勉に働いた結果、ようやく手にできるという素朴な実感が育てた感覚だろう。
日本人は、「個人の美徳の集積のうえに、集団全体の美徳は発揮される」と考えたがる民族だからである。これも、農耕社会での豊かな収穫は、一人一人が勤勉に働いた結果、ようやく手にできるという素朴な実感が育てた感覚だろう。
 ☆補足:「自学自得ハガキ通信第二部」102号と同じです。
☆補足:「自学自得ハガキ通信第二部」102号と同じです。
 或夏の半ば、宣長がかねて買ひつけの古本屋に行くと、主人は愛想よく迎へて、
或夏の半ば、宣長がかねて買ひつけの古本屋に行くと、主人は愛想よく迎へて、
 ▼人体の重心点はへそである。本にも中心になるへそがあると思っていた「図書」編集部編『私の読書』岩波新書1983年11月25日 第2刷発行 で、モーティマ・アドラー教授――(Mortimer Jerome Adler, 1902年12月28日 - 2001年6月28日)はアメリカの哲学者、教育者――の本の読み方は同じ考え方をしている。
▼人体の重心点はへそである。本にも中心になるへそがあると思っていた「図書」編集部編『私の読書』岩波新書1983年11月25日 第2刷発行 で、モーティマ・アドラー教授――(Mortimer Jerome Adler, 1902年12月28日 - 2001年6月28日)はアメリカの哲学者、教育者――の本の読み方は同じ考え方をしている。
 「入門書は一冊だけにせず何冊か買ったほうがよい。その際、なるべく、傾向のちがうものを選ぶ。定評ある教科書的な入門書を落とさないようにすると同時に、新しい意欲的な入門書も落とさないようにする。前者は版数の重ね方でそれと知れるだろうし、後者は、はしがきなどに示された著者の気負いによってそれと知れるだろう。」 P.96
「入門書は一冊だけにせず何冊か買ったほうがよい。その際、なるべく、傾向のちがうものを選ぶ。定評ある教科書的な入門書を落とさないようにすると同時に、新しい意欲的な入門書も落とさないようにする。前者は版数の重ね方でそれと知れるだろうし、後者は、はしがきなどに示された著者の気負いによってそれと知れるだろう。」 P.96
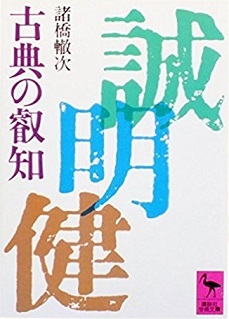 ★どれくらい読むか
★どれくらい読むか
 ※参考2:岩波文庫からも出版されています。以前、これを読みまして感動した記憶だけは残っています。
※参考2:岩波文庫からも出版されています。以前、これを読みまして感動した記憶だけは残っています。