改 訂 版 2022.11.11. 改訂

印刷した賀状の中に、手書きのものがまじっていると、なぜか心ふかれる。今年は先輩O三のものが、とくに心にのこった。 ハガキの上半分に、自分で彫った「賀正」と、「元旦」の朱色のスタンプ。その下に、 『呻吟語』――呂(りょ)新吾、中国明末の人、と註がつけてある。そして、これにつづけて、 「まことに仰せの如くなれども、われ次の愚句を詠みたり。 しようことの あるようでんし 老いの春」 この句が三行に分けて書かれ、「しようこと」に赤マルがつけてあり、上段空白のところに、「広辞苑をみるに『しようことと』はセンコトの転。仕様事と書くのは誤り……とあり」 と註がつけられている。 Oさんは、東大を昭和九年に卒業されているから、多分七十二、三歳であろう。某省付属の研究所に奉職。定年後は悠々自適しておられる。 ときどきお会いすると、じつに柔和な表情で、狂歌のことをたのしげに話され、また碁に熱中される。負ければくやしがる様子は、まことに天真爛漫」、別れたあとも、ほのぼのとした楽しさがいつまでも消えないのである。 この賀状には、そういうOさんの心境が、さりげなく、しかし的確にのべられているようで体温が直に伝わってくる。 ただ「しようことのあるようでなし」には若干心ひっかかるものを感じた。狂歌も、碁も、それぞれ老境の楽しみのひとつにはまちがいないとしも、これとは別に「しようこと」を渇望しているのかの感じ、そのことができないでいるためんい、老いの虚しさを嘆くニュアンスがある。私はここにひjっかかる。
「老いて虚しく生きない」という問題を考えるたびに、よく思い出すのは、山形の守谷伝右衛門というひとである。歌人斎藤茂吉の父親。本名は、熊次郎といった。 二十三歳のとき、守谷伝右衛門の娘、十九歳のkいくの婿として入籍し、明治二十七年四十四歳で家督をつぐと同時に「右衛門」を襲名した。 三十二歳のとき、三男坊として生まれたのが茂吉。茂吉は二十四歳のとき、同郷人で、「青山脳病院」を創立した斎藤紀一の養子となる。これは明治三十八年第一高等学校を六月に卒業し、九月に東京帝国大学医科大学に入る間の七月のことであった。 「茂吉の父」の晩年の逸話がすばらしい。結城哀草果は、「茂吉とその秀歌」(中央公論社)という本で、次のように書いている。 「お父さんは牡丹園をつくろうと思いたたれて、山形市外の元木(もとき)といところの、有名な牡丹園に牡丹の種子を求めにゆかれた。芽で接ぐことによって育てる方法は、簡便で早く花が咲くけれども、それでは真の愛着が起らないばかりでhあなく、それ以上の珍花を求めることができないところに、不満を感じられて種子蒔(ま)いて育てることを思いたたれたのである。 牡丹園の主人は顎に白鬚ののびた老人の姿を目のあたりに見て、 『牡丹は種子で蒔いては少なくとも五、六年を経てようやく花をもつものである。あなたの年頃ではとても骨折損になるだろう』 と真面目に忠告されたのであるが、 『その事なら承知の上だ。十年でも十五年でもかまわない、自分の死後に立派な花が咲いたらそれで本望である。自分は生涯牡丹に丹誠をここめて見たいのだ』 と申されて、種子を求められた。牡丹は生前に立派な花を咲かせていた。肥料から栽培法までしっかり研究しておられたのには、全く驚くの他ないのである」 また、真壁仁の『人間茂吉』(三省堂)には、 「(茂吉の父は)体重十二貫(四十五キロ)ほどの小男だったというが、胆(たん)剛直で意志は強靭であった。 牡丹は根つぎでは育たない。種で蒔いて育てなければならない。元木(現山形市)部落に丹野ときう牡丹屋がある。熊次郎は、そこへ種を買いに行った。すると、 『種子で蒔いてから二十年経たなきゃ花が咲かない。すこしおそすぎはしませんか』 と主人が言う。熊次郎は怒って、 『何を仰言(おつしや)る。私がまもなく死ぬとでも思ってらっしゃるのか』 とやり返す。そして種を手に入れて帰る。それは生前みごとな花をつけた。大正十一年(一九二二)五月、守谷家の庭でうつした熊次郎(七十三歳)の写真がある。茂吉はドイツ留学中で、孫の茂太(七歳)と並んで立っている。そばに背丈より高い牡丹の木が幾株か茂っているのが見える」 と書かれている。 ともあれ、老年に老いて牡丹を愛した茂吉の父は、期せずして「老いて虚しく生きない」人生をつらぬいたのではあるまいか。
茂吉の母いくの死は大正二年、茂吉三十二歳のときである。 このとき茂吉は、歌集『赤光』(斎藤茂吉全集第一巻、岩波書店)のなかにある五十九首もの大作「死にたまふ母」をつくった。 岩澤正二東洋工業会長は茂吉全集ンお愛蔵家であるが、 「茂吉の歌の中から、お好きなのを三百選んでください」 という筆者の希望にこたえて、その一首にこの中の、 わが母よ死にたまひゆく我が母よ我(わ)を生まし乳(ち)足らひし母よ をあげられたことがある。 父伝右衛門の死は大正十二年(七十四歳)で、このとき四十二歳の茂吉はミュンヘン留学中で、一ヵ月おくれてその知らせをうけとった。 上田三四二は、『斎藤茂吉』(筑摩書房)の中で、 「死を知って茂吉の詠んだ歌はわずかに二首である。それも、 わが父が老いてみまかりゆきしこと独逸の国にひたになげかふ 七十四歳になりたまふ父のこと一日(ひとひ)おもへば悲しくもあるか こういう、歌としては誠に通一遍のものにすぎなかった」 と書いている。(註、父を謳った『遍歴』は全集第一巻所載) しかし、大正十四年一月に帰国した茂吉は雑誌『改造』四月号に『念珠集』(註、全集第五巻所載)というエッセイを寄稿した。 このことについて、上田三四二は前掲文章につづけて、 「両者をへだてる十年の歳月、別してその環境の変化が歌を変えたmでであって、永別を前にした茂吉の嘆きが、父において浅かったわけではない。『死にたまふ父』の挽歌は、海の彼方にあった茂吉についに成らなかったが、帰朝後茂吉は直ちに『念珠集』一篇を編んで亡父追慕の念をいたした。十章よりなるこの随筆所は、数ある随筆集の散文のうち、もっとも精彩に富んだものであるb。おそらく文章家としての茂吉の面目は勿論、歌人茂吉の秘密さえそこに明らかに現れていると思われる。(中略)『念珠集』は父恋いの章である」。 と書いている。
茂吉の顔貌は、母よりも父に似るところが大きかったらしい。またその生き方のすべてに、父の影響は色濃く出ているいるようにおもわれるが、とくに「父」をおもわせるのは、晩年の姿である。 戦争下の昭和二十年四月十日、六十四歳の茂吉は、郷里の山形県に疎開した。 はじめ、上山町山城屋に入った。ここは、弟高橋四郎兵衛の経営する温泉旅館である。 ついで四月十四日から金瓶(かなかめ)の斎藤重十衛門宅に居をうつした。ここは、妹なをの婚家である。 ところが、二十一年一月末に、遠く最上川畔の大石田町にうつり、二月一日に、二藤部(にとべ)兵右衛門方の離家にうつり住んだ。この大石田町への疎開を、結城哀草果は「芭蕉への抵抗」であったという(前掲書)。 茂吉は離家に「聴禽書屋」という名をつけて親しんだ。 松尾芭蕉は、この土地で、 五月雨をあつめて早し最上川 の名吟をのこしている。 彼は、元禄二年四十六歳、早春に江戸を発ち、奥羽地方を行脚して、六月ころ大石田にきて泊まり、新庄をへて最上川を船で下り、庄内に出た。上の句は、この時の所産である。 茂吉は、和歌では柿本人麻呂、俳句では松尾芭蕉を高く評価していた。それはいつの間にか、一種のライバルを意識化していたようである。 大石田にうつったのも、芭蕉のこの名義に「抵抗」したためで、その結果、 最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも の秀歌がうまれたのである(歌集『白き山』、全集第三巻所載)。 このころ、茂吉は左肋膜炎にかかり、一時重態になった。しかしそのことをひとにつげることを禁じた。長男茂大にさえしらせてはいけないといった。そうまでしての闘病と作歌精進だったンおである。 この気魄によって、茂吉は元気をとりもどし、昭和二十八年七十二まで生きぬいたのである。再起してから長逝までの間に、 『短歌一家言』(斎藤書店)、『作家実語鈔』(要書房)、『童牛漫語』(斎藤書店)、歌集『遠遊』(岩波書店)――以上六十六歳。 歌集『遍歴』(岩波書店)――以上六十七歳。 『茂吉小文』(朝日新聞社)、『島木赤彦』(角川書店)、新版『赤光』(千日書房)、歌集『小園』(岩波書店)、『幸田露半』(洗心書林)、歌集『白き山』(岩波書店)、『近世歌人評伝』(要書房)――以上六十八歳。 歌集『ともしび』(岩波書店)、『校註金塊和歌集』(朝日新聞社)、歌集『たかはら』(岩波書店)、『明治大正短歌史』(中央公論社)、『伊藤佐千夫』(雄鶏社)、歌集『連山』(岩波書店)――以上六十九歳。 『続明治大正短歌史』(中央公論社)、『歌壇夜叉語』(同)、歌集『石泉』(岩波書店)、歌集『霜』(同)の業績を残した。 茂吉の父親の言葉『その事なら承知の上だ。十年でも十五年でもかまわない、自分の死後に立派な花が咲いたらそれで本望である。自分は生涯牡丹に丹誠をここめて見たいのだ』を読んで、 安岡正篤著『百 朝 集』P.80~81に書かれている下記の記述のあることを思い出した。 太宰春臺の産語は今日の經濟思想の失ってをる根本を説いた好書であるが、その中に衛国の君が蒲という処に出かけて、松の木の苗をうゑをてをる老人に教えられたおもしろい話を引いてをる。衛の君・蒲の野に観る。一老父の多く苗松を栽うる者有るを見る。喘息して拮据す。衛君従つて之に問ひて曰く、老夫罷めよ。女奚なんじなんぞ以て苗松を栽うるを為すか。対へて曰く、将に以て棟梁と為さんとす。衛君曰く、老夫の年幾何か。曰く、八十有五。衛君笑うて曰く、此の松、材と成るべきも、老夫能く之を用ひんか。老夫栽うるを綴やめ、仰いで衛君を視て曰く、樹木は用を百年の後に待つなり。君以て必ず其の世に於て之を用ひんと為すや。噫、君の言何ぞ国を有(も)つ者に似ざるの甚だしき。小人老耄して死に幾ちかしと雖も、独り子孫の計を為さざらんやと。衛君大いに慙ぢ、謝して曰く、寡人われ過てり。請ふ善言を師とせんと。因つて之を労ふに酒食を以てす。詩に云はく、厥その孫謀を胎(のこ)し、以て翼子を燕(やす)んずと。 2023.06.17 記す。 |
|
電力国家管理問題で現役を引退した松永安左エ門が、茶道に打ちこんだ話は世間に知られている。 その松永とお茶との結びつきは、昭和九年五月、数え年六十歳のとき、諸戸清六の麹町別邸における茶会に一子夫人と招かれたことにはじまる。 そしてその年十二月、杉山茂丸から自動車いっぱいの茶道具を贈られた。杉山は筑前福岡藩士の息子で、明治、大正、昭和にわたる右翼浪人である。松永に茶道具を贈った動機はよくわからないが、このとき七十一歳だった。 松永がはじめて茶会を催したのは翌年一月、熱海の別壮小雨荘で、客は杉山茂丸、福沢桃介、山下亀三郎の三人だったが、案内なしで鈍翁益田孝が姿を見せた。これは杉山から連絡があって知っていたものらしい。 その年九月には、青山根津喜一郎、十月には、三渓原富太郎を招いた。こちらはいずれも埼玉県入間郡柳瀬村(現所沢市)の「柳瀬荘内」での茶会である。 これは柳瀬山荘内にその年茶室をつくったからで、織部好三畳台目のその茶室には「耳庵」と名づけた。これは『論語』の、「子いわく、吾十有五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして心の欲する所に従いて矩(のり)をこえず」にもとづくもの。還暦をこえた松永が、その年齢にちなみ、孔子の「耳順(じじゅん)」の「耳」をとり、茶室を意味する庵の上につけ、その名前としたわけである。 すると益田鈍翁は、「耳庵」という文字から、松永自身の風貌の一特徴、耳の大きさを連想したものと見える。 「耳庵か。それは結構。君は耳たぼが大きいから、きっと福がある。長生きするだろう」 といって、枯淡な筆蹟で「耳庵」と書いた扁額を贈ってくれた。やがて松永はこの「耳庵」を雅号として使うようになる。
松永耳庵は、箱根にも「不染(ふせん)庵」という茶室をつくた。 この「不染庵」には耳庵以前の因縁がある。強羅を終点として箱根に電車をつくろうとした実業家(草郷某)が、益田鈍翁の助力を求めた。鈍翁は、公園に面した形勝の地を選び、自分はここに茶室をつくろうとし、他の知友にも、別荘地として買い取りをすすめた。 鈍翁に依頼をうけた仰木敬一郎が非常に苦心のはてにつくりあげた別荘は、大いに鈍翁の気に入って、本席を不染庵、寄附(よりつき:庭園などに設ける簡単な休み所)を白雲洞と命名した。 その後、原三渓が病気となり、年々芦ノ湖に避暑にきていたが、ある日鈍翁が三渓を見舞ったとき、霧の深い湖畔に長く滞在するのはよくない、といって「不染庵」をそのまま三渓に進呈した。 三渓は大いによろこび、それより毎年ここに避暑したが、昭和十四年に世を去り、その遺族は三渓ともっとも親交のあった松永耳庵に、形見わけとして贈ったのである。 耳庵から、不染庵席開きの案内をうけたのは、畠山一清、塩原又策、藤原銀次郎、昭和十五年八月十二日、それぞれ夫人同伴でその茶会にのぞんだ。 ところで、客の一人藤原銀次郎は、このあと『茶道新体制』というエッセイを書いたのである。 耳庵より六歳年上で、「製紙王」の名が高い藤原は茶道にも深く入っており、たとえば昭和十二年刊行の『事業学・人間学』という著書の中でも、いろいろと茶人の心得などを説いている。 その藤原が『茶道新体制』の中では、「何事も新体制の世の中である」と書き出して、耳庵による不染庵席開きのこと茶会を「新体制」の一現象と言おうとしている。しかし「当世はこれが一種の流行なれば、時世に魁(さきがけ)して所謂先端を行こうとするには、なんとしても新体制でなければ夜も日も明けぬというのが今日の日本である。されば茶道の新人の間にも、この新体制が芽を出し、これから繁茂しようとする兆あるは、是また尤も至極」とか、「一同新体制の厚意を謝しつつお暇」などという書き方には、耳庵を茶道の新人=新米あつかいにするばかりか、時代のバスに乗りおくれまいとなりふりかまわぬオポチュ二ストの一人だといわんばかりのニュアンスが感じられる。それは一種の冷やかしといってもよく、千利休のいう「余情残心」とはまったく異質の「俗情」と「底意」が感じられるものだった。 藤原はさらに翌十六年十一月、柳瀬山荘の耳庵炉開きに招かれたあと、「柳瀬荘耳庵の炉開き」というエッセイを書いた。そして、「東西に茶人多しと雖も、徹頭徹尾自家の見を貫通して奔放自在、天馬空を行くが如き感のあるのは耳庵老人」、(作庭は)気取らず、巧まず、自然に出来て、而も数十百年も経たるが如く、宛として韻士高人の幽居を首肯せしむる、此間に悠遊する主人の得意思うべし」、「主人の気性は作庭に於て然り、況や茶事を一貫して鋭鋒現然たり。斯様茶風であればこそ客たるものの楽しみ一層」、「甘い取合わせに嫌味が無く、勢い余って、人の意表に出るという行き方」という微妙な表現をしたのである。賞めているようで、じつは冷やかし、笑っている底意はかくしようがない。 「茶道」の権威者と自他共に認める藤原は、耳庵の茶会、主人公の人柄などを賞めるかの素ぶりをしながら、じつは耳庵の「幽玄」や「侘び」などとの縁のうすさ、つまりは「茶人」としての次元の低さを寓するかのような後味を残したのである。
いうまでもなく、茶に親しみながらも、耳庵の世界は「幽玄」と「侘び」に徹し切っているものではなかった。心機一転、新生への願望、決意があった。 つまり、「茶人」とはいっても、世にいわゆる有閑的遊び人ではなかった。胸中には、祖国の前途を憂慮し、軍人官僚の独善的支配体制を怒る情熱は決して消えていなかった。また、わが事すべておわれりとして、諦念、無為の中に朽ちるよりは、「人間いかに生きるべきか」という道を探求する意欲に燃えていた。 茶をたて、茶を喫しながらも、彼はつねに「隠居」の意味をおのれに問う求道者であり、行の人であった。 戦後二年目、七十三歳のとき公刊した『桑楡録(そうゆ)』には、山荘にこもる自分を反省し、自戒して次のように買いている。 「場所を山林に移し、業務の第一線から退けば隠居であると思うた耳庵なども、頭を剃り法衣を纏い黒谷に引籠り百万遍を唱えた熊谷蓮生坊なども『心の自由』が欠けていたら、隠居にも法師にもなれぬ。宗旦も不審庵を捨て又隠(ゆういん)と号し今日庵と称して懈怠を慎み、外来のものから心の自由を保持することができたので、利休伝統の草庵小座敷の侘び茶の祖となった。隠居して隠居にならず、市井巷間の内に働いて居ても隠居になれる。昔から小隠は山に隠れ、大隠は市にかくれると言っている。 大智禅師に『山中愚作』の偈頌(げじゆ)がある。隠居とはこれだ。 庵内の主人庵外に参(まじ)わる 静中の消息閙中(とうちゅう)に看る 到る処無心便(すなわ)ちこれ山」 贅をつくした別壮をおのれの城塞とし、 「古い句に『さまざまに暮れ行く年の一日かな』と言うのがある。昨日は雨、きょうは西日のkうつくしさ、人みjなそれぞれにお老ゆ、人をしてそのままに現成(げんじょう)せしむるのも、つねにその一と日である」
という心境を『桑楡録』はしがきの結びとするようになったのである。
藤原銀次郎が自他共に認める「茶道」の達人であったことは、今さら異論の立てようがない。しかしながら、あれほど「招客の精神」を人びとに説教したこの人において、たとえば吉野信次の回想録『おもかじとりかじ』の中で、 「工業クラブの膳桂之助が藤原さんとは全産連(全国産業団体連合会)の関係でいちばん親しかった。膳がいっていたが、藤原という人は、一文にもならない人には、決して御馳走しないといっていた」 と書かれているようなことがあったことは、膳桂之助という人がいい加減なことをいう人でないだけに、藤原「茶道」への大きな疑問符であることは否定できない。 耳庵の茶には、この種の功利的、通俗的意図をかれこれいわれるようなところは、いっさいなかった。 その心境が、通俗的、打算的にも一文にもならぬ人――つまりは政治や経済とは何の関係もなく、したがって、職業、価値観、発想法、教養においてまったく「異質」の人びとをその茶席に招くことを可能にしたのである。 しかし、ただ客にできた、という点が尊いのではなかった。その異質の人びとのいうことに、謙虚に耳を傾け、その真髄をおのれの憂国の志とバイブレトさせて、そこに生涯のテーマを見出した点がすばらしいのである。 異質の「人」を、この姿勢によって異質の「友」とすることができた。その友の一人に鈴木大拙がいる。鈴木はあるとき、アーノルド・ジョゼフ・トインビーの話をした。 「日本の敗戦と敗北感につながるコンプレックスが、とくにインテリ的な指導者の間にはなはだしい。トインビーの『歴史研究』が広く日本人に読まれることになれば、こういう傾向に対し良薬になるだろう」 このことばに、耳庵は感動した。そして八十歳のとき、ロンドンにトインビーを訪ね、翻訳権をゆづってもらった。こうして邦訳『歴史の研究』全二十五巻(経済往来社刊)は世に出たが、これは無論耳庵その人にとって「一文にもならなぬ」ことだったのである。 2023.05.21記す。 |
|
年輪思考への疑問・権力者の不明 小島直記『逆境を愛する男たち』第四話 P.16~31 幕末の儒学者佐藤一斎の『言志四録』を、筆者の生涯の本と考えている。噛めば噛むほど味が出る。 「少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず」 なんといういい言葉であろうか。六十歳を過ぎて、この言葉によって励まされたお方が少なくないであろう。 今夏あるトップ・セミナーにおいて、この言葉を引用した。話のあとの質問で、この言葉をもう一度くり返してほしい、というのがあった。その人は、ノートに書かれた。 今後、折にふれ、その人の心の糧となるにちがいない。 ところで、今日とり上げたいのは次の言葉である。 「余自ら視・観・察を翻転して姑(しばら)く一生に配せんに、三十已下(いか)は、視の時候に似たり。三十より五十に至るまでは、観の時候に似たり。五十より七十に至るまでは、察の時候に似たり。察の時候には当(まさ)に知命・楽天に達すべし。而して余の年齢今六十六にして、猶ほ未だ深く理路に入る能はず。而るを況や知命・楽天に於てをや。余齢幾ばくも無し。自ら勵まざる容(べ)からず」 これを現代訳すれば、 「自分は視(現象を見る)観(本質を見る)察(全体の実相を把握する)を一生に配して考えると、三十歳以前は視の時期らしい。三十歳から五十歳の間は観の時期で、五十歳から七十歳の間は察の時期に当るようだ。察の時期には知命・楽天の境地に達し得べきであるが、自分はもう六十六歳になるというのに、深い道理ある境地にいまだ入ることができないでいる。いわんや知命・楽天の境地は望めない。余命いくばくもない現在、自ら励まなくてならぬ」 ということになろう。 一斎先生は八十八歳で逝去されたから、六十六歳で「余命いくばくもない」ということにはならなかった。それはともかくとして、人間の判断には、年齢が大きくモノをいうこと、そして一斎先生が老境に達しても絶えず自分のいたらざるところを反省しておられる謙虚な姿勢、この二つのことがわかる良い言葉でるにちがいない。 関連:佐藤一斎:視・観・察 ただ私は、ときおりこの「年輪思考」の問題に対して疑問をもつことがある。たとえば、「日本資本主義の最高指導者」といわれる渋沢栄一の生涯において、このことを感じるのである。 周知のように、慶応三年(一八六七)十五代将軍徳川慶喜の弟昭武(あきたけ)がフランスの万国博覧会に将軍名代として派遣されたとき、二十八歳(数え)の渋沢栄一は、会計係として二十八人の随員に加わって渡欧した。 その途中、スエズで進行中の、フランス人レセップスによる運河工事を見た。そのとき、そういう大規模の事業ができるのは合本主義(特殊会社経営法)のおかげであるときき、『航西日誌』に、 「すべて西人のことを興す、ひとり一身一個のためにせず、多くは全国全州の鴻益(こうえき)をはかる。その規模の遠大にして、目途の広壮なる、なお感ずべし」 と書きつけたのである。 さらにパリにきて、多くの銀行や会社との交渉を体験してから、この気持ちはますます強くなった。零細な大衆の資金をあつめ、これによって「資本」をつくり、社会的に意義のある大きな仕事をやる仕組み――こういう事実に注目したのは彼一人であった。 他の随員たちも、選ばれた水戸藩の子弟たちだったにちがいない。しかし、スエズ運河や会社についての認識、とくに日本人としての問題意識の点ではまったく石頭にひとしかった。つまり、一斎先生の前述の言葉を用いるならば、彼らはすべて「視」の段階にとどまった。そして渋沢ただ一人は、単なる現象をこえて資本主義的経営理念を直観的に把握し、かつ祖国の将来の課題というテーマの芽としたのである。これは「観」というよりは、むしろ「察」というべき天才的洞察であったと思う。 明治になって、二年一月渋沢は静岡に「商法会所」という事業体をつくった。これは同時期に、福沢諭吉がつくった「丸屋商社」(『丸善』の母体)とともに、日本最初の株式会社だといわれている。 明治維新政府は渋沢をスカウトし、大蔵省に入った渋沢は「合本主義」の啓蒙、育成に力を注ぎ、退官して第一国立銀行監査役(ついで頭取)となってからは、そのトップリーダーとして活躍した。「日本資本主義の最高指導者」という敬称はここに由来している。 自他ともに認める「会社経営」法の権威者として、渋沢はあるとき、三菱の創始者岩崎弥太郎と論争したことがある。 岩崎は、日本で最初に「社則」をつくった人だが、たとえばその第一条は、 「当社ハ姑ク会社ノ名ヲ命ジ会社ノ体ヲ成スト雖モ其実全ク一家ノ事業ニシテ他ノ資金ヲ募集シ結社スル者ト大ニ異ナリ、故ニ会社ニ関スル一切ノ事及ビ褒貶黜陟等都テ社長ノ特裁ヲ仰グベシ」 となっていた。会社という名前をなのり、会社の組織をつくっても「会社」ではない、というすさまじい独裁宣言であって、渋沢の唱導する「合本主義」の精神に全く反している。 そこで渋沢は、岩崎から隅田川の舟遊びに招待されたとき、それに批判を加えたのだ。 「あなたの会社の社則を拝見したが、私としては少々異論がありますな。とくにあの第一条に、会社という名前をなのり、会社としての組織をつくっているがじつは会社ではなく、すべて自分の独裁、という思想がもられているが、それにはもっとも疑問がある。合本主義というのは、単に金だけ集めるのではなく、その出資者たちの知能も結集させて機能させようというものだ。広く衆知を集め、その合議制にもとづく運営をおこなってこそ、会社の特色もウマ味も出てくるわけであって、あなたのような会社の規定では、はじめからその可能性を封じるようなものではあるまいか」 すると岩崎は、猛然と反発した。 「それは屁理屈じゃ。おぬしは、商売というものをちっとも知っとらん。多くの人数がよりあつまって仕事をしては、りくつばかり多くなって、成績はあがるものじゃない。決定にも暇がかかり、責任の所在がはっきりせんようになる。その証拠は、はばかりながらわしの会社の成績と世間の会社の成績を見るとよくわかる。どちらがうまくいっとるかは、事実が証明しとるんじゃ」 ここで渋沢は、ぐっとつまってしまった。岩崎は「世間の会社」といっているが、本音は「渋沢の会社」といいたいところであろう。それをいわれると、渋沢としても頭の痛いところだったのだ。 渋沢の実業界における基盤は、第一国立銀行を第一とし、抄紙会社(のちの王子製紙)を第二とする。 抄紙会社は、渋沢が大蔵省三等出士だった頃、公債証書、紙幣、印紙類の発行をはじめるにあたり、洋紙が必要なので、三井、小野、島田三富豪に出資させて設立したものである。はじめ十万円、明治八年には二十五万円の資本金となっていた。 当時は会社組織の方法を知ったものはいなくて、渋沢は『会社弁』というパンフレットを出して、解説し、抄紙会社はその実物見本といえた。 ところが会社運営は順調ではなかった。まず製紙機械がアメリカからとどいたとき、小野、島田両家が破綻、株の大半は三井が引き受けた。 外人技師を二人やとった。それぞれ二百六十五円という月給で、日本人社員で二十五円以上もらうのは、支配人と副支配人の二人だけにくらべると、まさに破格の待遇である。 しかし、機械は故障属続出、どうにか紙が出たかと思うとすぐに切れてしまう。会社はピンチにおちいった。 渋沢は、他人の前ではグチをこぼさなかった。それは自分の沽券(こけん)(体面、値打ち)にかかわるからだ。しかし、身内の人間、たとえば甥の大川平三郎にむかっては、 「王子製紙にもこまったものだ。どうしたらよいか見当がつかぬ」 と嘆声をもらすことがあった。 つまり、岩崎の反発は、渋沢のもっとも痛い点をついていたわけである。 大川平三郎の母親は、渋沢夫人の姉である。その縁をたよって、大川は明治五年十三歳のとき上京し、渋沢の書生となった。 渋沢はこのとき三十三歳だが、家人に「殿様」とよばせていた。大川少年は朝早く起こされて「殿様」の居間から玄関まで掃除をし、それから本郷の壬申(じんしん)義塾にやってもらった。余暇には英語を独習していた。 大川家は代々剣客で、川越藩主から士分にとり立てられていた。しかし明治になると剣道はすたれ、一家は窮乏した。そこで母親が妹である渋沢夫人のところに金を借りにくる。それが度重なると、夫人もいい顔をしなくなり、十六歳の大川少年にむかって父の無能を口にした。 そこで、一日も早く職業について父母の苦労を少なくしてやらねばならぬと思い、抄紙会社にやとってもらい、月給五円の職工になっていたのである。 それから四年目、大川は「建白書」を提出。会社不振の原因を分析し、自分がアメリカで技術を学べば会社は立ち直ると主張した。そして三年間実地体験を積んで帰国すると、生産実績は五倍増、会社は隆盛に向かったのである。 四十歳の渋沢よりも、二十歳の大川の判断力がまさっていたというこの事実は、思考における年齢の問題について、一斎説への有力な反証といえないであろうか。 参考:大川平三郎(おおかわへいざぶろう)(1860―1936) 日本の近代製紙業の先駆者的企業家。武蔵(むさし)国川越藩(埼玉県)の藩士の次男として生まれる。12歳のときに上京、伯父渋沢栄一の書生となったが、生家の困窮から学業を断念、1875年(明治8)抄紙(しょうし)会社(王子製紙の前身)に入社した。アメリカ留学後、副支配人、専務取締役となったが、98年に退社。その後、独立の製紙企業家として九州製紙、中央製紙、樺太(からふと)工業などを創立して、一時期には国内最大の製紙企業群を傘下に収めた。しかし、第一次世界大戦後に事業拠点であった樺太工業の経営が悪化し、1933年(昭和8)に王子製紙への吸収合併を余儀なくされた。 平成二十九年三月二十五日 |
|
人品について 小島直記『逆境を愛する男たち』 第七話 P.45~50 万事順調で、世の中がおもしろく、楽しくて仕方がない、という人には縁のない話をする。 「現代がいやになった時など、これを読んでいると、とても嬉しくなるこおが少なくない」 と、若き日の安岡正篤老師が書いておられる本の話である。 その「これを」という本は『世説新語』。 劉(りうゆ)宗(六朝時代)の高祖の一門で、臨川に封ぜられた劉義慶という文学好きの王が当時の学者をあつめて、歴世人物のおもしろい説話を選述したもの。私たちは、『不如会』という読書で、安岡老師から講義していただいたことがある。 いろいろと、骨の太い男たちのことが書いてある。その一例。
朱子季は張堪(ちょうかん)と同縣なり。張、大学中に於て文季を見、甚だ之を重んじ、臂を把って語って曰く、妻子を以て朱生に託さんと欲すと。文季敢て対(こた)えず。張亡(し)して後、其の妻子の貧困を聞き、自ら往いて候視(こうし)し、厚く之を賑贍(しんせん:たくさん贈物をする)す。子怪んで問うて曰く、大人は堪と友たらざるに何ぞ忽ち此の如きやと。文季曰く、堪嘗て知己の言あり。吾れ以て心に信ずればなりと。 この原文に、「嬉しいではないか」と、若き日の安岡老師の感想がついている。私が特に珍重するのは、この感想=肉声である。 本屋には『世説新語』の解説書があるかもしれない。しかし、安岡老師の感想=肉声をつけたものは、世の中にただ一冊しかない。 その本こそ『童心残筆』なのである。 『童心残筆』の「序」に、
とある。 つまり、碩学(大学者)の二十代、三十代のエッセイ、漢詩、和歌、俳句集。 本は、内容の上から、「客心」、「世間」、「人品」、「余滴」の四章にわかれる。 「客心」は旅の記録。 「世間」は、学校教育、農村、官界など、時世の問題にふれての断想や会話。 「人品」は、宋の陸象山が、 「諸処方に譊々然(どうどうぜん:がやがや)として学問を論ずる時、我れ唯だ此に在って多く諸生と人品を説く」 といった言葉が深く心に沁んでいて、現代人も人々がイデオロギーだ、指導理論だ、主義だ、学説だと、徒(いたずら)に知識の末に趨(はし)って、一向性命を養うことを知らないのに、ひそかにあきたらずおもう心がさせた一分類。 「余滴」は漢詩、和歌、俳句百首より成る。 『童心残筆』は、昭和十一年二月に初版、一ヵ月後には再販、三版と刊行され、昭和十五年以後は普及版として版を重ねた。今日、古本屋でときたま見るこtヴぉがあるが、市価数万円。 この稀覯(きこう)本が昨年十一月、全国師友会から、原型そのままに、新しく上梓されたのである。
この本の中に、南画家新井洞巌の作品が五枚挿入され、装幀は新井画伯と吉川英治の二人によってなされた。 新井画伯は住友生命新井正明会長の先考。新井会長の「あとがき」によれば、 「安岡先生は人間には『縁』というものがあり、これは最も大切なもので、また尊ばねばならないと、いつも説いておられますが、先生と父洞巌とのご縁は、昭和の初期、吉川英治先生の紹介によるものと記憶しています。洞巌はそれまで、安岡先生の学徳を敬慕し、私淑しておりましたが、親しくお目にかかる機会に恵まれせんでした。ところが一度縁が結ばれてからは、急速にその親交の度が進み、生を終るまで親しく師事しておりました」 とある。 書簡文がのっている。『童心残筆』初版が間もなく刷りあがることになった一月ある夜の清遊のことを、吉川英治が牡丹園ご主人柳沼源太郎に知らせたもの。 「先頃頂戴の牡丹の薪にて、新春一月十三日夜、宿望の一会を催し申候。屋外に焚くは惜う候まま、赤坂の桔梗と申す家の炉部屋を借り申し候て客をいたし候。当夜の客は金鶏学院の安岡正篤氏、元東京府知事香坂昌康氏、南画家新井洞巌の御三名に小生の四人に候て、炉には冬夜の暖をとる大根煮をいたし、酒は灘の吟醸、酌人には牡丹の花と申しても劣りなき赤坂の美妓に候。丹炎誠に美しく、微薫のある煙も、牡丹なる故にや苦になり申さず候。安岡氏の言葉にて暫く灯火を滅し、炉明りのみにて暫時を雑談に忘れ申し候。 本文四百六十五ページ、多忙な実業家には、特に「人品」の一章をおすすめする。内容は、人間論、人物論である。 冒頭にのべた『世説新語』がある。 「わが親友に得たいのはこういう人物だ」 「そうか、そうか、ああそうか、実に愢(はじ)入る」 「有り難い。親の恩ほど測られぬものはないものだ」 「泣かされるではないか。止めどなく涙がこぼれる」 「先輩は唯だ後輩を偉くしてやれば好いのだ」 「此の時声無し声あるに勝る」 「今時の志士国士は皆頭(ず)が高いぞ。大筆で細書する味を知らねばいjかん」 これらは、本文に対する老師の感想=肉声である。 人物論としては、前回登場してもらった八代六郎提督論『八代将軍』がすばらしい。 若き日の安岡老師は、次の点を人間的魅力とされている。 「近年会ったいわゆる名流の士の中で、初対面のとき、ああこれは好い風格だと感ぜしめられたのは、文官では牧野伸顕伯(当時宮内大臣)であった。宮相官邸の奥まった一室に敬虔を極めた態度で時jを移して清談する老伯の眉の動きから眼の閃きを白面の一書生であった私はしみじみ眺め入った。そしてその彫ったような姿、寂びた気分、荘重な会話に始めて国老と語ったという気分がした。武人では何といっても城山(じょうざん:雅号)八代六郎大将である。この人真に風神奕々(えきえき)として人に迫るものがあった。目鼻立ちも明かるく引締って、さぞかし青年士官のときは堂々たる美丈夫であったろう。その面目鬚眉(しゆび)の間に呑牛の気象が生動しておって、風発する議論の機鋒もまた峻烈、惰夫を起たせる慨があった」 八代六郎は「純朴」の人であった。これが彼を知るすべての人の胸を打った。 在職の頃、いかに部下を愛したかは世間周知のこと。閑地についても、よく人を懐(おも)つた。 「その優情に往々私もひそかに涙したことがある。数ならぬ私のことなども始終案じられて、感激したことが多かった。歿なられる幾日か前に、夢に私を見られて、いくら話しかけても書物に対したまま少しも返事がない。何ぞ病気でもしているのではないかと案じられという話を奥さんから聞かされて、衰えられた姿を見ながら涙をのんだ」 知人の子供のこともよくおもいうかべ、その成人のさまなどをたずねた。 ある夜八代宅で対座小酌しているとき、ふと手文庫から一冊のノートを出した。 「これは万(よろず)朝報の俚謡正調からわたしの好きなものを拾いあつめておいたものだが、こんなものがある」 といって、微吟した中に、初盆に母親が、死んだいとし子の竹馬にのってくる姿をおもい浮かべて泣くところを詠んだものがあって、八代も泣き、安岡も落涙した。 小鳥を可愛がっていた。馴染みの訪客に小鳥は奇声を放って家人に告げる。帰りには首を傾けて別れの挨拶らしい鳴声を出す。八代はいつも玄関まで送って出て、この小鳥をうながしながらいっしょに別れの辞儀をした。 この小鳥は、提督より早く往生した。夫婦の面には本当にさびしさの色がただよっていた。 教養が広く、深かったことは、じつに意想外であった。仏教。陽明学。易学。特に日本史には深く眼をさらしていた。系譜や紋章に精通していたのは、家門を尊ぶ武士的精神の所産。史伝に見える名将の言行については、博覧強記、驚くべきものがあった。 「盃をふくんで南朝の忠臣を論じ、戦国の武将を談じ、気あがり、情熱するときは、英風四辺をはらって座客をして壮快禁ずる能わざらしめた。この気魄と情熱と教養とが、あのように朝(ちよう)に当っては色を正して俗流政治家を畏怖せしめ、難に臨んでよく紛を解いて、民衆の手に汗を にぎらしめた所以であろう」 2023.06.14 記す。 |
|
読書による自己形成 小島直記『逆境を愛する男たち』 第九話 P.57~63 近頃の若者に「活字離れ」の傾向があることを、識者は嘆いている。 これはまったく重要な現象には違いないが、しかし本を読まなければダメだ、といくら説教してみたところで、読もうとしない人間に本を読ませることのむずかしさは、馬を水辺につれていくことはできても、水をのませることはできないという昔からの諺のとおりであろう。 そこで便法だが、ドライで功利的な現代の若者の耳に入りやすい実例として、たとえば次のような話をしてやるのはどうであろうか。 山猫書房という本屋から、丸尾長顕著『回想小林一三 素顔の人間像』という本が出ている。著者は小林一三に見出されて宝塚歌劇団の世話をするようになり、のち日劇ミュージックホールの創設に参加したりして、演劇界の重鎮となった人。この本の中に<スターの発掘>という一節がある。 高浪喜代子という生徒がいた。可愛い子であったが、背は高くなく、おきゃんな所があると思うと、また静かな所もある、というタイプだったらしい。その生徒から、 「私はスターになりたいけれども、いっこうにスターになれない。しかし、スターになる方法があったら教えてほしい」 という相談をうけた著者は、机上の本をさして、 「この『ボヴァリー夫人』を読んだら、きっとスターになる」 と、とっさにいった。フロベル原作のこの小説の当時の訳本は、訳が下手で、読みづらいものだった。しかし、彼女がより知的になったらそのときチャンスをつかむ女だと思って、あえてすすめたのた。 「そんなら読んでみます」 といって、彼女はその本をもって帰った。 いつぺん読んできた。が、スターにならない。 二度読んだ。まだスターにならない。著者の目には、まだ輝きが感じられなかった。 三度読んできた。それでも、まだダメ。しかしながら、なんとなく知的な面が感じられるようになった。 「三度読んだけれども、スターにならないじゃないの」 という。 「じゃ、もう一度だけ読んできてください。も一度読めば、かならずスターになる。ならなかったら、私が切腹してみせる」 彼女はそういわれて、真剣になって四度読んできた。そして四度読んできたときにいったのである。 「スターになろうと思って、四度も読んだ。だけれど、もう私はスターにならなくてもよろしい。この本を四度読んで感じたことは、人間の感情というものが、こんなにデリケートなものである、ということを知った。だから丸尾さんにダマされてもいい。もうスターにならなくてもいい。この本を四度読んで、そういうことを理解しただけでも、私は満足することにする。あなたにダマされたけれども、得はとった」 ところが、スターにならなくなってもいい、と言った途端に、彼女はスターになったのである。なぜか? 「それはそうである。彼女はもう以前の高浪喜代子ではなかった。知的に輝きを増した目をしていた。そして鋭くなってきた。それを作者は捨ておくはずはない。すぐ役がついた。目も輝いてきた。肩の力も抜けてきた。こうして高浪喜代子は、大スターのし上がった」 この話を読んで、筆者は夢想するのだ。 「本を読めばスターになる」 このCMを大にやれば、少なくとも若い女性層の読書人がふえるのではあるまいかと。 スターになろうというような、功利的な目的をかかげること自体、<読書>の本旨にそむくものだ、と眼をむく本格派もあるだろう。 けれども、本を読むことによって自分の人間をつくり上げた、という実例はじつに多いのだ。そういう効用があるのだということを強調して、一人でも多くの若者に本を読ませようとすることは、少なくとも、一流大学に入らねばダメだ、という人生指針よりは、よっぽど親切であるし、真実をついていると思う。 英文学者中野好夫に『人は野獣に及ばず』(みすず書房)という本があるが、たとえばこの本の中には、 「徳川期田沼時代の醜聞は近年とみにお馴染みになったが、明治大正の聖代? などにしても、ひどいものである。まずは汚職腐敗の連続と考えてよろしい。 が、筆者のもっと驚くのは近年事件摘発のたびに、その主役大物のまず九割以上というのが、東大法学部出身者という一事である。 巨額の国費を使って、ずいぶんひどい大学を作ったもの。おそらくみん選り抜き特別の秀才なのであろう。だが、問題は性根である。いわば出世志向だけの亡者。ひたすらただ卒業証書だけが目的の蝗群(いなごのむれ)なのだから、教授諸氏としても手のつけようがあるまい。心からのご同情を申し上げる。 節義喪失の秀才ほど、およそ世に始末の悪いものはない。わたし自身も実は東大出身者である。但し、法学部ではない、文学部だ。その文学部でさえ、わたしは定年十年前にやりきれなくて教職をよしたが、あんな連中を教育する法学部の先生たちは、よくまあ我慢してつとまるものとつくづく思う。 もう一度くりかえしいうが国もひどい大学をつくったものである。学部こそちがえ、いまのわたしの心情は、自分がその東大出身者であることに、身のちぢまるほど恥ずかし思いさえする。情けない話だ> という痛烈な一節があるのである。 学歴志向よりも読書による自己形成を―― このことから筆者がすぐ連想するのは、住友の広瀬宰平のことである。 彼が別子銅山勤務の 彼は、雑用に追いつかわれながら、 山の人びとは、 やがて、字がうすれ、紙が破れる。すると新しく『経典余師』を買う。 この一冊の読書が彼の<大学>であり、 浜松市に「金原明善記念館」がある。 その記念館において筆者は『経典余師』を見出した。金原翁もまたこの本によって自己形成を 彼の読書法とは、 「古書を古読せず、雑書を雑読せず」 という味のあることばも生まれている。 金原明善がそういう 一、君国を重んじること。―― 二、財産を>重んじること。―― 三、衣食住に制限を設くること。―― 四、人は 五、家計は一定の年額を設くること。―― 六、家伝二宝のこと。―― 彼はさらに三つの<希望>をあげた。 一、実を先にしてなを後にす 二、行を先にして言を後にす 三、事業を重んじて身を軽んず 平成二十七年九月十九日、令和四年二月二十六日追加。 |
|
獄中の人間学 小島直記著『逆境を愛する男たち』 第十話 P.64~70 奥村綱雄の「野村証券」社長時代は、昭和二十三年四月から、三十四年六月までの十一年二ヵ月。四十五歳から五十六歳までの働きざかりであった。 その社長就任のとき、耳庵松永安左エ門のところへ挨拶に行った。 耳庵はこのとき七十歳、電気事業再編成問題のスタートとして返り咲きをする一年前のことだが、 「人間は三つの節を通らねば一人前ではない。その一つは浪人、その一つは闘病、その一つは監獄だ。君はそのどの一つも経験していない」 といった。これには、意気軒高の奥村もシュンとなったという。 耳庵は、たしかにこの三つの体験者であった。 明治四十年三十二歳のとき、株式大暴落でスッテンテンになり、家まで焼けた。このとき彼は、「人生五十年を標準として、まだ五十までには十七、八年ある。ここで四、五年休んでもよかろう、と思って、灘の住吉の呉田の浜へ家を借りて、二ヵ年分の家賃を前払いして、籠城した」(『自叙伝』玄海出版) キザで、助平で、オッチョコチョイの坊ちゃんが、「実業人」としての自覚に徹することができたのは、まさにこの「浪人」のおかげである。 「闘病」は明治二十三年十五歳、慶應義塾在学中コレラにかかって生死の境をくぐった。 「投獄」は明治四十三年三十五歳。前年に「福博電気軌道」の専務に就任し、共進会に間に合わせるため、突貫工事の先頭に立ち、その年三月八日、県知事から営業開始認可があり、ただちに開通式を行ったが、その前日、「贈賄容疑」で大阪警察に召喚されたのである。 この頃、大阪市民の間に市政刷新の声があがり、それは司直を動かして、市助役など実力者の身辺が洗われた。そして、「箕面(みのお)有馬電軌」の市内引込線問題にからむ収賄事件が発覚し、同社専務小林一三(耳庵より二歳年上)とともに大阪警察に逮捕され、ついで堀河の未決監に放りこまれたのだった。 逸翁小林一三も耳庵とおなじく慶應義塾の学んだが、学生時代には知りあっていない。逸翁が三井銀行につとめ、大阪支店詰となったとき、共通の先輩で、支店長だった平賀敏の紹介で知りあった仲だ。 電車の市内乗り入れには、市会の承認がいる。その実権をにぎる三人のボスを平賀は教え、その三人と親しいのは耳庵だといった。 その工作は成功したが、収賄事件の発覚でくさい飯を食う仲にまで発展(?)したわけである。 ところが、当時の法律では、贈った方は罪にならなかった。もし耳庵と逸翁が、自分のことだけを考える人間ならば、簡単に白状して、解放されたことだろう。 しかし、二人ともそうはしなかった。 「どうだ、贈賄しただろう?」 と係官はせめ立てる。 「はい、やりました」 といえば、助役たちの罪は確定させることになる。二人が口を割らないのはそのためだったが、それが検事を怒らせた。 「証拠はあがっているのだ。当人たちも、もらいました、白状している。それをあくまでも、やっておらぬとシラをきるのであれば、偽証罪だ。これだと、懲役二年だぞ」 とおどす。 が、二人はガンばった。一週間たっても、二週間たってもカタはつかない。 耳庵の兄貴分で、事業のパートナー福沢桃介が東京からとんできた。そして、逸翁の親分岩下清周とともに「代理自白」ということをやった。 「あの二人に、他人をキズをつけるようなことをいわせるのは無理ですから、¥われわれ二人が勝手に自白します。小林と松永がやったにちがいありません。現に会社の帳簿をみても、はっきりとわかることです」 検察側も弁護側も、桃介たちがいったことを認めるように、と二人にすすめる。 「認めぬとあれば、福沢、岩下両名を偽証で逮捕するぞ」 といおどしもついていた。 なお、三日間、二人は考えた。桃介は毎日朝早くからやってきて、耳庵をつつく、耳庵もさとるところがあった。 「考えてみれば、小林としてはいえないことだ。自分が口を割れば、小林も救われるのだ」 耳庵の覚悟はきまって、桃介の証言書に判をおした。そこで監獄を出され、やがて三十分おくれて逸翁も解放されたのである。
松永耳庵は、以上三つの体験をふまえて、奥村に忠告をしたのである。それが何故に重要かという点については、注釈しておらず、奥村も反問をしていない。しかしそれが通じたのは、要するに「極限状態」をくぐりぬけないと、人間はほんとうに鍛えられない、という意味がおのずとふくまれているからであろう。 そういうと「極限状態」、とくに投獄体験がどういうものかについて、最近出た『獄中の人間学』(竹井出版)昭和五十七年三月十二日第一刷発行:が多くの貴重な示唆をあたえてくれる。
この本は、古海忠之と城野宏の対話集である。 古海は東大を卒業して大正十三年に大蔵省に入り、昭和七年満州国政府に派遣、同二十年満州国総務庁次長として逮捕され禁固十八年の刑をうけた。 城野は、昭和十三年東大卒業後、徴兵で中国にわたり、中華民国山西省政府の指導にあたった。終戦後も山西野戦軍を指導して中国人民解放軍と戦闘、首都太原落城で捕虜となり投獄された。 この二人の当時の回顧談は期せずして「人間とは何か」ということを教えてくれる。『獄中人間学』というタイトルがつけられたここにあるだろう。 二人の体験は、耳庵、逸翁の体験とは比較にならぬスゴさである。太原の監獄では、六畳ぐらいの部屋に二十人ばかりがつめこまれて、仰向けに寝られない。目の前に隣の奴の足がある。食事は、太原では粟のかゆ一杯、北京ではトウモロコシの団子で、一日二食、七年半、一度も風呂に入らなかった。 こういう「極限状況」下で、人間の心理はおかしくなる。捕らえられた日本人のうち、神経衰弱になるものが多かった。 「神経衰弱になるやつには特性がありましたね。なにかとゴマすりをする。これでは神経衰弱になる。人に振りまわされるから」(城野) 「神経衰弱になるような連中を見ていると、家族なんかに会いたい思いがつのって、その一事ばかりを考えるようになるんだね。(中略)もう意識がその一事に支配されてしまっているから、他のことには反応しなくなってしまう。人間の脳味噌というのは外部的な刺激には反応しなくなったら、もうおしまいだなと思ったね」(古海)
日本人の中には、ただ帰りたい一心から、共産主義のお先棒をかつぐものがいた。 古海は、ソ連で第十三ラゲールにいた。ここは関東軍の将校ばかりである。彼らとは顔見知りなので、顔を合わせれば挨拶する。ところが連中は、古海の顔を見ると、すうーっと横道に逃げるのである。 当時、ソ連は赤化教育の意味もあって、捕虜や抑留者の間に民主委員会をつくらせ、かつての上官つるし上げをやらせていた。熱心にやれば、早く日本に帰れると信じて、つるし上げはエスカレートしていた。古海は、戦犯、反動の筆頭とみられていたので、あんなのと仲良くしたら大変だ、ということだったらしい。 「そんなとき、瀬島(龍三)中佐と、もう一人の男だけが、『やあ、古海さん、よくきましたね』と平気で声をかけてきて、いろんな話をしてくれたよ。瀬島とはあちこちのラーゲルを転々するうちに何度か一緒になったが、半年くらい一緒だったかな。瀬島は古海のような反動ブルジョアジーと親しくするのはけしからんというわけで、他の連中からものすごいつるし上げにあうんだ。それでも彼のぼくに対する態度は一向に変わらないんだな」(古海) 「語弊があるかもしれませんが、サムライというか、やはりヒトなんですね」(城野) いいにつけ悪いにつけ、その人間の人間性が、ラーゲルのようなところでははっきり見えたね」(古海) 「瀬島さんは、日本に帰ってこられてからちゃんと、ああいう風に日本にプラスになることをやっておられる。やはり、人間というものはそういうものですね。監獄の中でも、自分の信念とか、自分の立場を踏みはずさないでやるということですね。監獄の中でもそれができた人間は、日本に帰ってきてからもそれができる。だから立派にまた仕事ができる。ゴマをするという奴は、どこへ行っても他人の顔色ばかりうかがっているから、なんにもできないんだとおもいますね」(城野) 「人間、作為をやってはダメだということだね。他人の目をバカにしてはいけないよ。馬は人を見るというが、人は人を見ているんだ」(古海) 「古海さんは向こうでも、こちらでも変わらない。生きざまという言葉はきらいだが、態度が言っ一貫している。だから、みんながあなたのまわりに集まってくる」(城野) 「その点は君もそうじゃないか。作為なしに原則を押し通して生きることが、信頼を得る道だと痛感しているよ」(古海) 「その人間の原則で生きていく姿。それが信用となり信頼となって事業などでも伸びていく。作為は通用しない。それほど世の中は甘くないぞということですね」(城野) 「要は、その人の人間性だ。人間性はごまかせないよ」(古海) 投獄体験をへて、人生の達人ともいうべき境地にある二人の対話は、まだまだ多くのテーマにおよび、貴重であるが、あとは読者諸氏のご検討に俟つ。 「投獄」の憂き目など、好んであいたいとはおもう人もあるまいが、せめてこの一書を読むことで、われわれが自分自身を反省し、鍛え直す一つの手がかりになるような気がする・ 20203.05.22記す。
|
|
勇武より徳量の将 小島直記著『逆境を愛する男たち』 第十話 P.71~77 日本経済新聞(昭和五十八年四月三日付)朝刊文化欄に「地域生活に甦る英雄たち」と題する童門冬二のエッセイがのっている。 足利尊氏、上杉鷹山、横井小楠、河上彦齋(げんさい)、加藤清正、坂本竜馬、西郷隆盛など「歴史上の人物」が、足利市、米沢氏市、熊本、鹿児島などの「各地で着実に血を通わせてよみがえりはじめている」というのである。 このうち、 「熊本で、いまも依然として人気があるのは加藤清正だ。人気の淵源は他国人のぼくにはわからないところもあるが面白い」 という一箇所が、いろいろと感慨をさそった。 昔、政友会に小泉三申(さんしん:本名策太郎)という代議士がいた。静岡県伊豆子浦の出身で、新聞記者をへて政治家となり、『政界策士』として知られた人。幸徳秋水の親友である一方、田中義一を陸軍少将時代から着目して、のちに田中が政友会総裁になるときの黒幕的役割を果たした。 ところが友人としても「自他共に認める」存在で、死後二年目の昭和十四年から、岩波書店によって、その全集が刊行されはじめた。これは第四巻まで出て、戦局深刻化のためそのあとは出なかったものの、日本の政治家で、こういう一流出版社から全集が出版された例は他にないだろう。この小泉三申が『加藤清正』を書き、熊本の人びとによろこばれて、「九州新聞」に主筆として迎えられるという縁が生じたのである。 明治三十年頃、日本橋石町の裳華房(しょうかぼう)という本屋があった。 この本がどの程度売れたのか、データは残っていない。 三十年一月に『加藤清正』、同五月に『明智光秀』、同八月に『織田信長』(上)、同十月に『織田信長』(下)と三申の本が出た。すると、おもわぬ反響がおきたのである。 そのことを白柳秀湖は、 「『加藤清正』が好評を博すると、熊本の人々は、その郷土の偉人、それは従来、武弁一途の豪傑としてのみ知られて来た加藤清正が、この年少史論家の筆によってその真骨頂を天下に紹介せられたことをいたく感激し、わざわざ人を介して翁(註、三申のこと)を郷土の新聞(註、九州新聞)に主筆として迎えたほどであった。翁が弱冠筆を載せて熊本に赴任したのもそのためであった」 と書いている。 五十歳でその生涯をおわった清正が、比類のない誠忠勇武の士であったことは、天下周知のことである。 清正は三歳で父を失ったが、母は清正九歳のとき、羽柴秀吉に頼った。それは秀吉の母と従姉妹だった縁による(註、異説もある)。 三申本によれば、秀吉は、清正に異相あるを愛し、月俸七人扶持を給して母子を養った。以後、秀吉の出世とともに、清正の運命も開ける。 天正四年十五歳で元服、百七十石。 十八歳で二百石、翌々年加増百石。 二十二歳、賤ヶ岳七本槍の功名で三千石。 天正十四年二十五歳のとき、秀吉は太政大臣となる。 二十七歳、肥後半国二十五万石に封ぜられる。 文禄元年(一五九二)三十一歳、征明の師に先鋒として出陣。 慶長元年三十五歳。小西行長の中傷で太閤に譴(けん)せられ、伏見に蟄居して罰を待つ。大地震発生のとき、伏見城にかけつけて秀吉を守り、冤(えん)解かれる。 ふたたび朝鮮に行き、蔚山に籠城して苦戦する。 慶長三年三十七歳、秀吉薨去。博多帰着。 同五年、関ケ原の戦いで、清正は徳川につき、肥後全州七十三万石に封ぜらる。 同六年、熊本城を築く。 同八年、江戸城修築、清正その縄張りをなす。家康は、清正の娘を第十子長福丸(のちの紀伊大納言頼宜)に配す。 同十六年(一六一一)、熊本城で卒去、五十歳。 寛永九年(一六三二)、加藤家断絶。 以上のような清正五十年の生涯に対して、三申が強調したのは、 「清正の其の臣下を御するや、其の力に頼らずして寧ろ其の徳を以てす。則ち清正は勇武を以て勝ると言わんよりも、寧ろ徳量を以て勝るの人、其の跡歴々証すべし」 ということであった。
三申の清正執筆それに感激した熊本の人たちによる「九州新聞」招聘は、二十世紀初頭のできごとである。しかし清正のことが今日においても忘れていないことは、たとえば池波正太郎の『男の系譜』(立風書房刊)において、心をこめて語られていることが証明している。 池波は、まず清正の母親をほめている。 「自分の息子も、その友だちも、少しも分けへだてなく可愛がることの出来た、そういう心の温かい、本当に情のある人だった、清正の母親は。ちかごろのいわゆる教育ママなんかとは違いますよ、全然。 この言葉は、おなじ本の中の「渡辺勘兵衛」の章で、 「人間というものは、大体、五歳から十歳くらいの間に全部決定されるわけですよ、そのときの生活環境でその人の一生が」 といい、また「豊臣秀吉」の章で、 「若いときに、どういう人間に出会うか。それが人柄というものを左右する。その左右することを自然に選んでゆくわけですよ、だれでも」 「生れつきといったけれども、これはつまり、うんと小さいころの母親の問題ということです。秀吉のおっかさんという人がえらい人だったんですね。人間の形成というものは、生まれついてから五歳くらいまでが最も大事で、そのときの家庭生活というものが全部、一生影響してきますよ、絶対、そ思う」 といっている言葉にも関連がある。石田三成との対比においてとくにはっきりしている。 「三成の西軍が数こそ多いけれども、まったくの烏合の衆だったということ。それだけ人望がないんですよ、石田三成に。この人のために力を尽くして戦おうという気にだれもならない。ほうびに釣られて味方しただけの軍勢だったということが三成自身にわかっていないんだ」 「三成は秀吉の好調時代に秀吉のそばにくっついていて、つねに権力座にいたけれども、順境しか経験がない。清正みたいに異国の地で生命がけで敵と戦い抜いた、壁土まで食いながら頑張ってのけた。そういう体験をしていないでしょう。こういう、逆境に沈んで苦しみ抜いたことのない人間は、だいたい駄目なんだ。人を見る眼も出来ていないしね」 「これにくらべて、加藤清正は人間の大きさが違っていたな。朝鮮の役から以降、清正は別人のごとく大人物と変貌している」
慶長十五年早春、清正は熊本から名古屋へいった。名古屋城修築のためだが、武装の兵列をひきい、自分も甲冑に身を固めた。まず大阪城で秀頼の機嫌をうかがい、それから大軍をひきいて名古屋入りをしたのだが、家康は本多正信を使者に立てて、三ヶ条の質問をした。 第一、秀頼の機嫌うかがいを堂々とやってから、こちらに出向いてくるとは、大阪方を関東よりも重く見ているのではないか。 第二、天下太平の世に、軍勢を引きつれての道中は、いささか不穏ではないか。 第三、むかしの戦陣の折りのまま、ひげをつけておるのは、時節柄、異風殺伐な感じがする故、剃りおとしてしかるべきではないか。 第一条に、清正は答えた。 「それがしは徳川家にも恩義がござる。なれども新恩のために旧恩を捨てると申すのは、まことの武士のなすべきことではないと存ずる」 池波は、「正論ですよ、堂々たる、本多正信も、こう明快にいわあれては返すことばもなかった」と拍手する。 第二条に対して、わが領国肥後の国は遠い、万一、途中で異変おきた場合、軍兵をよびよせたりしていては、急場の役に立たず、十分のご奉公もできぬ。それで軍勢を、と答えると、 「そのご奉公とは、どなたへの?」 と強くつめよられる。 「無論のこと、天下を治むる徳川家へのご奉公」 といい切った。 第三条の「ひげ」。 「なるほど、剃りおとせばさっぱりといたすことでござろう。なれど、若いころからたくわえたこのひげ、むかし戦陣にあったころ、このひげ面に頬当(ほほあて)をつけ、兜の緒をきりりと締めたるとき、身の内が引きしまるほどのこころよさを、いまもって忘れがたし。このように天下太平の世とはなっても、若きむかしを忘れがたきこの胸中、とくとおくみとりねがいたい」 正信が、その通りつたえると、家康はむしろ機嫌よく、「清正の申すことよ」と笑った。しかし、「口調にそぐわない緊張が、そのとき家康の面上に漂っていたに違いない」 20203.06.16 記す。 |
|
鈍才の大成 小島直記著『逆境を愛する男たち』 第十三話 P.84~90 子供がよくできること、学校の成績がよいことは、世の親にとって最高の望みであろう。 経済学者ジョン・スチュアート・ミルは、三歳でギリシャ語を習いはじめた。父親が導き手であった。ギリシャ語で意味をつけた表をカードに書いてやった。 三歳の坊やは、この単語集を一通り終えると、ただちに訳読にすすんで『イソップ物語』を通読した。 八歳からラテン語をはじめている。 同じく経済学者ジョン・メイナード・ケインズは、四歳半のとき、「利子とは何か?」と問われて、 「僕がお父さんに半ペニーわたし、お父さんがそれを非常に長い間もっていたとすれば、お父さんはその半ペニーと、そのほかにいくらかを加えて僕に返さなければいけないでしょう。それが利子です」 と答えた。 十一歳のとき、クラスで一番。 十三歳のとき、担任教師は、 「学校中のすべての生徒をはるかに抜きんででている。彼はイートンの特待給費生の資格を得るであろう。 と書く。 イートン中学で頭角をあらわす。古典学で首席。「帝国の責務」という論文で満点。上級数学賞。リチャーズ英語論文賞。チェインバレン賞。数学、歴史、英語論文で首席。「数学と古典」で特待給費生に選ばれる。十九歳でケンブリッジ大学入学。 こういう話をきくと、日本の教育ママは羨望のため息をつき、 「あんたもがんばらなきゃダメよ。早く塾へいらっしゃい」 と、嘆くであろう。 だが、学校の成績のいい子が、将来かならず伸びるとは限らない。
「私は算術という学科が一番嫌いだった」 と小出楢重(こいで ならしげ)は書いている。先生や親から叱られても、落第しかかっても好きになれなかった。それというのも、5+5が10で、先生がやっても、生徒がやっても10となる。10とならぬときには落第するのだからつまらない、という理由であった。 5+5を、羽左衛門がやると100となり、延若がやると55となり、天勝がやると消え失せたりするようなことを、大いに面白がる性分なのであった。 算術の問題が、また実に面白くなかった。「大工あり」とくる。「一日に何時間を働く」と書いてある。 しかし、当時十二や十三歳の子供が、大工の生活などに興味がもてるはずがない。賃金の問題だから、なおさら無関係だ。 「大工が何時間働こうと汽車がいくら走ろうと、玄米が何銭であろうと、私の知ったことじゃない」 「いくらの買い物をして釣銭がどうとかこうとか、まつたくそんなケチなことはどうだっていい。釣銭はいらないよ」 「そういう心が横たわり出すと、もはやとうてい私の力でも、先生の力でも、親の力でおいてさえも、この横たわりたるこの心は動いてくれないのだ。したがってこの問題を解こうなどというような従順な気持ちには決してなれないのだった」 普通、算数のできる子供は、頭がよい、といわれる。したがって、算数のできない小出は、頭が悪い、と思われÞふぁであろう。 だが、こういう心理的抵抗で素直にとけこめない子供を、ただ頭が悪いという一言で片づけてよいのだろうか。 「やっとの思いで美術学校へ入学したとき、私は初めて算術から解放された。私の死ぬまで算術がないんだと思ったとき、私の嫌いな世界中の蜘蛛が一時に自殺してくれたような心地jがした」 彼は、算数とは関係のない世界で画家小出楢重となつた。昭和六年四十四歳の若さで死んだが、その名は不滅である。 学校秀才であれば、将来性があり、そうでなければ望みはない、という通念=俗見を打破る例は、たくさんある。 「日本のケインズ」とよばれた元首相石橋湛山は、中学時代、一年生と四年生のときに落第している。卒業して、一高を受験し、二回スベっている。 二浪してようやく早稲田大学に入るのだが、大隈重信を助けてこの学校の基礎を築き上げた小野梓(あずさ)という人も、決して神童的ではなかった。西村真次の書いた伝記には、 「七、八歳になっても学業がすすまず、『唐詩選』の五言古詩の首章『中原還逐鹿』という一遍をおぼえるのに三ヶ月を要し、『大学』の一巻の素読に二ヶ年を要した」 とある。鈍才とはこのことであろう。 もっと上手(うわて)がいる。明治政府草創期に財政担当者となった由利公正である。 由利の父は福井藩士で、近習番として百石をもらっている。そこで生まれた幼名石五郎、三十四歳のpとき八郎と改名、さらに四十歳のとき公正(きみまさ)と改め、四十三歳のとき姓を変えて「由利公正」となっている。 由利は、貧乏にあえぐ藩の財政を建て直した。徳川幕府が倒れ、維新政府ができたとき「参与」として登用されて、五ケ条の誓文を起草した。財政を担当し、また初代東京府知事にもなっている。そういう男が、少年時代、 「あいつ、バカではないか」 といわれた。 「親も親だ」 と、両親までトバッチリをうけている。 その理由を一口でいえば、 「学問をしない」 ということだ。大体サムライの子は、五、六歳ごろから素読をはじめる。 これは、文章の意味には立ち入らないで、ただ文字だけをたどって声を出して読むのである。 これが「学問」のそもそも、とされていた。ところが三岡石五郎は、その「そもそも」のコースがなかなか終わらない。 四書五経がやっとおわったのは、なんと十八歳、元服を終って、一人前のオトナとして扱われる年になって、ようやく幼稚園のコースを終ったわけで、なるほど、これはおそい。おそすぎる。 そこで、バカではないか、といわれ、親も親だ、と悪口をいわれたわけである。鈍才の典型といってよいだろう。 だが、人間の一生には、学校や点数とは別のものも重要である。 石橋湛山の場合、それは第一に「出会い」であった。甲府中学校長大島正健、哲学者田中王堂との出会いは、落第をし、一高に入らなかったために可能となった。 そして第二に、大学を卒業してからの本格的勉強だった。 学校を出て、東洋経済新報社に入った。しかし財政・経済中心の本誌の方ではなく、社会思想誌『東洋持論』の編集者としてであった。 ところが二十八歳のとき、『東洋持論』は廃刊となり、彼は本誌にうつった。ということは、「哲学青年」から「経済記者」に自己改造しなければならぬ、ということである。 彼はそれを、通勤電車の中で、経済学の原書を読了していく、という努力でなしとげた。 いうまでもなく、経済学は、ただ本を読んだからといって、身につきはしない。ましてや、経済記者として現実の経済問題を論じることは、本の知識だけでできるものではない。しかし、それはそれとしても、大前提となるものが、経済学文献の勉強であることはまちがいない。 自ら原典にあたる。降っても照っても、その勉強を続けて次々と古典を読破していく。その根気と情熱が自己改造を可能にした。昭和時代、「金解禁」論争がおきたとき、彼はもじどおりオピニオン・リーダーであった。 小野梓の勉強の歩みはのろかった。だが彼は、自分の頭で考えていった。教師の話をそのまま鵜のみにしなかったから、進み具合はおそかったが、通っていった跡は、自分の思考で踏み固めてあった。 明治二年十七のとき、「自ら士路を脱して平人の籍につく」 「今どき平人でさえ士挌になりたがるのに、お前はわざわざ帯刀をぬきすてて平人になる。まったく心得ちがいだ」 といましめられたが、変えなかった。彼の頭の中には、古くさい封建秩序にたよる考えなど消え失せて、世界的思想ともよぶべき自由闊達な考えが芽生えていた。 十八歳のとき、「救民論」を書いた。その中で、「宇内合州政府の創設」ということをいっている。今日でいえば世界連邦政府の考えである。 やがて『国憲汎論』という独創的な本を書く素地は、こういうコースの所産に他ならなかった。 由利公正の場合も、自分の頭で考える、という点で小野に似ている。ただ彼の場合、これに自分の足が加わった。 福井藩の財政は、ドン底だった。 「それは何故か。どうしなければならぬか」 と彼は考えはじめた。十代の終わりである。そのためには、歳入と歳出を知らねばならぬ。 勘定場の役人にきいたが、誰も知らない。そこで彼は、にぎり飯の弁当をもって、各村別にまわりはじめた。一年、二年、三年、四年とその調査は続いた。 「あいつ、何をしておる?」 といぶかしく思った人々には、陽に焼けて黒くなった外貌しか見えなかった。 「たのもられもせぬのに、あいつはやっぱりバカだ」 と笑った。その実証的調査が、やがて藩を救う、ということを予感したものは一人もなかったのである。 2023.08.15 記す。
|
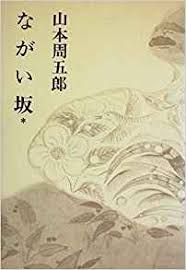
運命を決めた坂 小島直記著『逆境を愛する男たち』 第十五話 P.98~103 人生を坂にたとえる人は少なくない。作家山本周五郎は、三浦主水正の名作に『ながい坂』*、『ながい坂』**(新潮社)というタイトルをつけている。 主水正は胸の中でつぶやく。 「佐佐義兵衛は百二十石の書院番、藩では中流の上位に属する。世間を見る眼や、自分の生き方についても、家柄だけのゆとりと幅をもつことができるだろう。だがおれはそうではない。おれは尚功館(しょうこうかん)へあがったときから、勾配の急な坂道へ足を踏み入れたのだ。この坂は嶮しく、そして長い」 そして、坂道で出会う人々は、それぞれのけわしい道中で実感したことを語る。 「義であることがつねに善ではない」(『ながい坂』山本周五郎小説全集19(新潮社)昭和四十三年十一月五日 五刷) P.177:黒崎記) 「人の一生はながいものだ、一足とびに山の頂点へあがるのも、一歩、一歩としっかり登ってゆくのも、結局はおなじことになるんだ。一足とびにあがるより、一歩ずつ登るほうが途中の草木や泉や、いろいろな風物を見ることができるし、それよりも一歩、一歩をたしかめてきた、という自信をつかむことのほうが強い力になるものだ」 (同書 P.21、黒崎記。以下同じ) 「学問はただつめこむだだけが能ではない。学問だけがどんなに進んでも、おまえ自身がそれについてゆけなければ、まなんだことはなんの役にも立たない、ひとが二年かかるところを四年かけてやっても、それが身についたものならはるかに強いし力があるものだ。おまえのようすを見ていると、なにか目的があってあせりにあせっているようだが、このへんで考えたほうがいいな」 (同書 P.31) 「学問が大切だということはわかりきっている。放れ馬を巧みに避けるよりも、学問にすぐれた才能があるほうがよい。けれども、じつは両者は一体でなければならないのだ」 (同書 P.42) 「自分の眼や耳の届くところだけで判断すると、しばしば誤った理解で頭が固まってしまう」(同書 P.44) 「相手が約束を無視して勝負をいどんできたのなら、是非の判断よりも応じて立つほうが人間らしいという。また、これが正しいという信念にとらわれると、眼も耳もそのほうへ偏向し、『正しい』という固執のため逆に、判断がかたよってしまう、ともいわれた。『よくわからないな』と彼はつぶやいた」 (同書 P.69) 「もの事を避けてばかりいると、その反対のほうに思わぬ災厄や陥穽が待ち構えている」 (同書 P.85) 「人間の一生はそうながくはない、憎んだり嫌ったりするような時間はあまりないんだよ」 (同書 P.121) <人はときによって、いつも自分の好むようには生きられない。ときには自分の望ましくもないことにも全力を尽くさなければならないことがあるものだ> (同書 P.130) 「人間はみながみな順調に成長するとは限らない、二十歳でだめになる者もあろうし、五十歳でなお伸びる才能もある」 (同書 P.136) 「世の中を裏から見ると、人間のやることはたいがい売買でね」 (同書 P.143) 「おとし穴を知らない者は、落ちてからでなければ、そこにおとし穴があることに気がつかない」 P.152 たとえとしての坂ではなく、現実の坂が人間の運命にかかわりをもつ例もある。作家岸田国士の場合がそれであったことを、フランス文学者内藤濯が語っている。 明治四十三年七月、東京帝大を卒業した内藤は、本郷菊坂上に住んで、市ヶ谷の陸軍中央幼年学校に、フランス語の教師として通っていた。 西寄りのつぎの通りに、菊富士ホテルという下宿屋があった。そこにはアナーキストとして危険人物視されていた大杉 栄が、愛人の伊藤野枝と同棲しているというので、ふたりの私服刑事が、朝となく夕方となく、界隈をうろついていた。 大正五年春、岸田国士がとつぜん内藤家を訪ねてきた。夕暮れ近い居間で、ふたりは対座した。 岸田の父は、紀州藩上層武士の出で、近衛砲兵大尉のとき生まれたのが国士である。そして、父のあとをついで職業軍人になるため、幼年学校、士官学校のコースをたどらされた。 幼年学校の生徒だったころ、国語の先生から"わが理想の人物"という作文の題をあたえられた。 そのとき、クラスの誰もが、楠木正成や乃木将軍を礼賛する間にあって、岸田は由井正雪を推奨した。 由井正雪は、江戸幕府の顛覆を企てて失敗した人として知られている。学校当局は、岸田に危険な兆候を感じて、その心事を問い詰めた。すると岸田はひるむことなく、 「一つの時代を切りひらくほどの人でなくては、理想の人とするには足りません」 と答えたという。 士官学校を出ると、久留米四十八連隊に配属。少尉任官、連隊旗手となった。 しかし、在任三年、軍隊のいやな裏面を知り、学校時代からの文学志望やみがたく、父の勘当までうけて退職した。 そして、フランス文学で身を立て直そうと考えながら、とつぜん内藤を訪問したのである。 後年の岸田国士は、ダンディとして有名だった。背広の胸ポケットからハンケチをのぞかせるにも細かい心づかいをした。 しかし、大正五年の訪問のとき、着ている袷の襟は垢だらけだった。はいている袴のヒダは、くずれてしまっていた。 というのも、彼はその服装で労働をしていたからである。その頃、胸突くほど急な勾配だった九段坂で、人力車や荷車のあと押しをして、二銭銅貨一つにありついた。また、小さな活版屋の日雇いになって、文選工のまねごとをしながら、辛うじてその日その日を送っていた。 ところが、そういうひどい貧乏の中にあっても、人間としての凛々しさを失っていなかった。たとえよれよれの袴でも、それをきちんと身につけるたしなみをもっていた。 「貧乏というのはきたならしいものだ」 と、彼はいったことがある。これについて内藤は、 「貧乏の苦しさを身にしみて経験した彼は、貧乏そのものには同情する気持ちをもっていても、貧すれば鈍することのきたならしさには堪えられなかったらしい。それはひとえに、彼の持って生まれた凛々しい心がしからしめたことで、岸田文学のスマートさも、そいう心の至って自然な帰結だったといってはいけないだろうか」 とのべている。 当時白水社が『模範仏和大辞典』の編集をしており、内藤はその編集に助力していた。そこで内藤は編集仲間にはかって、岸田にその一部を担当させることにした。 岸田はその仕事に打ちこんだ。訳語一つひとつの新鮮さに、仲間のだれもが目をみはった。普通の人だったったら"慰められない"としてすますところを、"みかえる者のない"といったような耳ざわりのいい日本語をもちこまなくては、満足できなかった。 その仕事で、六百円の稿料が入った。すると岸田は、 「これでフランスに行く」 と言いだした。 「それは無謀だ。よしたがいい」 と内藤は止めた。しかし岸田はきっとして、 「どうしても行く」 といい、大阪商船の貨物船にのって日本を去ったのである。 岸田は、仏領インドシナのハイフォンで一働きしてマルセイユ行きの船にのり、パリについた。そして大正十一年、父の死で帰国するまで、パリの劇壇に出入りして実地を学んだ。 それをもとにして、帰国後に書いた戯曲『古い玩具』が山本有三の目にとまり、『チロルの秋』、『紙風船』など、今までにない新しさをもったその作品と彼の名前は、いちはやくスターダムに輝いた。やがて『暖流』、『落葉日記』などの小説も書いて、物質的にも安定し、北軽井沢に別荘をもつにいたった。 「高原の清らかな空気を吸いにきませんか」 と誘われて、内藤がその別荘の客となったのは昭和二十五年の頃だった。 二晩泊まって、東京へ用事で行く岸田と二人、軽井沢駅から汽車にのり、向かい合わせに腰をおろした。 碓氷峠を離れた頃だった。それまで何か考えこんでいた岸田は急に口をひらいた。 「いつのことだったかおぼえていますか、はじめて菊坂をお訪ねしたのが?」 内藤は、古い話なのでまるきり見当がつかず、首を横にふった。 といって、目をしばたたいた。 周知のように、大杉は愛人伊藤野枝などとともに、関東大震災のときに、甘粕憲兵大尉に虐殺されている。このとき死ななかったにせよ、大杉の仲間となっておれば、岸田の命もなかったはずである。 それをきいて内藤は、 「そうだったのか。あの坂一つで人間ひとりの運命を決したわけなんだな」 といった。 しかし、遠い昔の経験を、胸ひとつに押し包んで、それが煮つまるのを辛抱づよく待っていた彼の心境から、紛うかたない文学以前の問題を感じたことは、あえて口に出さなかったという(中公文庫『未知の人への返書』)。 2022.03.06記す。
|
|
敗者復活 小島直記著『逆境を愛する男たち』 第十六話 P.104~110 刑事事件で失脚した実業家が、再起して前以上の地位、声望をとりもどすということは、決して容易ではあるまい。だが見事にこれをなしとげた人もいないではない。大日本製糖専務だった磯村音介がその一人である。 人間には、順調に波瀾のない生涯を歩むものと、有為転変の生涯を歩むものとがいる。それが運命ということかもしれないが、磯村音介は無論のこの後者の方だった。 身長四尺八寸五分だったというから、一メートル四十七、日本人としても小兵の方である。ところが身長と反比例して、胆っ玉、決断力、ファティングスピリットは常人を超えていた。 のちの蔵相、首相高橋是清がまだ三十代の農商務省特許局長時代、本人はいやがるのに、ペルー銀山の開発責任者にされたことがある。 このとき、高橋といっしょにペルーに行こうと思って、大学を中退退学したのが磯村であった。だが、あの事業は危険だから止めたがいいといわれて、やむを得ず中学校の先生となった。 英語はペラペラで、電話口で外人と喧嘩をするほどだったという。 先生をしているうち、下郷伝平にスカウトされて江商合資会社の支配人となり、日露戦争後領土となった台湾にわたって、一仕事もくろんだが見事に失敗した。 そこで内地にもどり、就職したのが日本精製糖株式会社である。このとき二十九歳で、月給三十五円。
遠州森(静岡県掛川付近)は清水次郎長の子分石松で人に知られているが、ヤクザだけでなく、有為の人材も数多く出ている。発明家鈴木藤三郎もその一人で、はじめは菓子屋の小僧、ついで茶の商売に転じた。あるとき横浜に行ってみて、茶の輸出額よりも砂糖の輸入額が多いときかされてびっくりし、 「これはいかん。国のため、もとの職業に返って、ぜひ砂糖をつくらねばならん」 と発奮した。 そしてつくったのが氷砂糖製造工場である。これは明治二十八年に資本金三十万円の会社にした。この組織変更のとき、第三十銀行から資本を借りたので、同行から長尾三十郎という人を迎えて社長とし、社名を「日本精製糖株式会社」としたのである。磯村の入社はこのときであった。 同社は、二十九年六十万万円、三十二年二百万万円三十七年四百万円に増資、鈴木は長尾に代わって社長に就任、磯村は支配人に引き立てられた。 この頃、業界の雄としては、大阪に日本精糖(資本金百万)、大里に神戸鈴木商店経営の大里製糖所があった。磯村はこれらを合併して、内地における市場独占をねらって、鈴木社長に進言したのである。 鈴木は、腕一本でたたき上げた人であり、名人肌、職人肌、ワンマン型である。工場で職工をステッキでぶんなぐったこともある。砂糖、醤油、製糸、蒸発罐、燃焼器、煮炊器、乾燥機など、発明特許は百五十九件という一種の天才だが、 「自分以外に砂糖のことがわかってたまるか」 という偏屈なところもある。 自分をさしおいて、部下の分際でコソコソ企てるなどけしからんと、磯村に大目玉を食らわせてしまった。 磯村はへこたれない、相場師鈴久として名高い鈴木久五郎が、ひそかに会社の株を買い占めていることを耳にしていたので、ある日面会を求め、単刀直入に砂糖合同案をもちかけると、鈴久は大賛成。 そこで鈴久と力を合わせて、株の過半数を買い占め、鈴木藤三郎社長を退陣させてしまった。
専務に就任した磯村音介は、財界御御所渋沢栄一を相談役に推戴、間もなく農商務省農務局長、農学博士酒匂常明に社長として天降ってもらった。そして大阪の日本精糖を合併、資本金千二百万円、大日本製糖株式会社と改称した。このとき磯村は四十歳。 磯村は、急激に事業を大きくしようとして、ありとあらゆる積極策をおし進めた。 台湾に工場をつくった。 六百五十万円で大里製糖所を買収した。 明治製糖、台湾製糖の両会社と共同して、名古屋精糖を買いつぶし、さらに東洋製糖も吸収にかかった。 ところが、その急激な拡大政策の中に禍根がはらまれていたのである。 その第一は、資金の大部分が固定し、運転資金が少なくなったことだ。 第二は、大里製糖所、名古屋精糖の買収費や、台湾工場建設費や、社債と借入金で調達したことだ。 第三は、合同後の生産能力は日産八百五十トン、内地市場消費高の約三倍という過剰生産設備となったことだ。 しかも、大里製糖所の買収ができたときは、双方ともに有頂天となり、京都祇園の中村楼で手打ち式。芸妓五十人をはべらせての大宴会で、世話人には一万円ずつ現ナマで贈呈した。 鈴木商店では、この六百五十万をモトにして、この後財界に雄飛するのだが、大日本製糖の方では、この派手なムードが首脳部のやり方から消えてなくなって、ピンチを招く一要因となる。 しかし、内情を知らぬ世間からは「花形株」としてもてはやされ、三十九年下半期には六割四分、その後も一割五分の安定配当を続けるという無理な「蛸配当」を余儀なくされたのである。 もしも当初の見込みどおり、内地市場の独占ができていれば、あるいは価格吊り上げ、政府補助金の増額など、いろいろの手が打てたかもわからない。 それなのに、ライバルとして、神戸精糖、横浜精糖、塩水港製糖、明治製糖など、二十数社にのぼるメーカーが出現して独占の夢は砕けたのだった。 社長酒匂は温和な学者タイプ。ロボットであり、お飾りであって、結局磯村が嵐をのりきるパイロットだった。 彼は、窮地打開の秘策として、代議士を通じての政治工作を考えた。そのネライは三つ。 一、輸入原糖戻税期限延長運動 二、砂糖消費税の増徴反対運動 三、砂糖官営運動 こうして政界に金をバラまき、やがて「日糖事件」として刑事問題化するわけだが、この取調べで、磯村の腹心秋山一裕は、税払戻法改正法律案通貨のため、どう金をまいたかを陳述している。「議員に対する運動費十二万二千二百円ほどのうち、五万五千ほどは政友会所属の議員に、三万二千~三千円をその他の議員に贈りました。長谷川豊吉、荻野芳蔵には一万五千円から二万円を贈りました。両人はじめ十五万円出せといい、次には七万五千円に負けて、磯村を脅迫しましたが、結局こうなったのです」 今日のゼニの値打に直せば四、五億円がバラまかれた、ということだったろうか。
日糖事件で、四十九歳の酒匂社長はピストル自殺を」した。渋沢栄一は、財界引退声明を行った。取締役伊藤茂七は、法廷で発狂した。 四十三歳の磯村は、懲役刑(刑期不詳)をうけ、かつ私財を会社に提出させられて、無一文となった。 ところが彼は、 「人間は三度まで運が向くものだ」 という信念の持主だった。刑期がおわると、 「三度目の運はかならずつかむ」 と決意して再出発したのである。 彼には五人の弟妹がいた。いずれも仲がよく、長兄である音介のために、お互いの金を出しあった。 大正二年、四十七歳の磯村は、弟妹の金で本所区太平町にささやかな苛性ソーダの試験工場をつくることができた。 三井銀行員から富士紡績の経営者となっていた和田豊治が彼を後援し、激励してくれた。その好意で程ケ谷富士紡績工場の隣接地に程ケ谷ソーダ工場をつくったのが四年のことである。ここで電解ソーダ法に成功した。 六年には、液化塩素も製造をはじめた。また同年、郡山に東洋曹達株式会社を創立して、過酸化塩素の製造をはじめた。 十年には、程ケ谷で合成塩酸製造をはじめた。 この頃日本は、対岸の火事第一次大戦で大いにもうけ、産業構造は軽工業から重工業へと質的転換をなしとげた時期である。磯村の事業は大いに当って、化学工業界において押しもおされもせぬ地歩をしめたのである。 けれど、注目しなければならぬのは、そういう経済発展にさきがけて化学工業部門に進出した先見性、さらに事業経営者としての姿勢である。 大正四年資本金八万円の程ケ谷曹達株式会社の社長となっても、決して傲ることはなかった。 和服は綿服しか着なかった。洋服は詰襟である。しかも、材料や製品などを大風呂敷に包み、自ら背負って工場も往復した。 日糖専務時代は花柳界で大いに遊んだが、再出発してからは、茶屋酒は無論のこと、いっさいの社交を絶って、事業だけに打ちこんだ。 一方、部下を非常に可愛がった。いわゆる「食を分かって士を養う」という風であったという。 唯一の道楽は、書生を養うことであった。彼の庇護を受けて世に出たものは少なくないが、たとえば日曹コンツェルンの創始者中野友礼はその一人であった。 磯村の親しい人に、鈴木商店の大番頭金子直吉ががいた。 その機敏な点において、熱心な点において、また辺幅(うわべ)を飾らない点において、まったく同じタイプの人間だったという。 しかし、金子は鈴木商店破綻後再起できず、磯村は一流実業家として、昭和九年六十八歳でその波瀾の生涯を終っている。 2023.03.18記す。 |
|
陰徳をもって本とすべし 小島直記著『逆境を愛する男たち』第二十話 P.111~117 寄附の好きな人はいないだろう。しかし世間に対して、「きらいだ」ということを公言する人はすくないだろう。本心はしたくないけれども、世間体や評判などを考えて、いやいや寄附をするという人が多いのではあるまいか。 ところが、それを公然と表明した人がいる。いわゆる安田財閥の創始者安田善次郎翁であった。「人の寄附などたよりにしているようなことで、なんのまとまった仕事ができるか。寄附は結局人をあやまらせる。自分の汗と血をもって事をなすという方針の上に立った仕事でなければ、物にならない」 といったこともある。寄附を求める人にありがちの、自己責任感のうすい他力本願主義をきらったのである。 山路愛山はその『現代富豪伝』において、 「金持ちの尊ぶべきとと否とは其持高にあらずして、其富の使用法にあり。天下国家を益せず、産業世界の人才を鼓舞せず。単に天下の富を一家に集むるとも是あに我等の感謝に値するものならんや」 と喝破している。 こういう考え方は、社会通念として存在していることは事実だ。だからこそ、寄附はきらいでも、きらいだと公言する人は少なく、いやいやながらも財布をあけるわけである。反面、金を出さないというそれだけのことで、非難、中傷の手がかりともなるわけである。 寄附をきらいだと公言し、寄附をことわった安田に対して、「ケチ」の悪名が高くなるのは自然の成行きであった。
安田にとって不本意だったろう思われるのは、安田銀行など、その事業隆盛ぶりがまた世間の反感を買ったことであった。 明治四十二年といえば彼は七十三歳(数え)だったが、『実業之日本』四月一日号に、「実業界を退隠するに当り余の心事を告白す」という談話筆記がのっている。 この中で彼は「致富(ちふ)」の原因として「分限(ぶんげん)」を守ったことをあげ、 「私はその昔鰹節屋をはじめたときから、わが生活は収入の十分の八と定め、いかなることがあってもこの規則をこえたことがない。今日でも依然これを実行している」 と述べている。 彼は事業経営に六つの法則をつくったという。 第一、目的に向って順序正しく進むこと。 第二、心に誓い立ててこれを実行すること。 第三、善いことを見たら必ず実行し、悪いことを知ったらただちに禁断すること。 第四、真心をもって事にあたるということ。 第五、虚飾を避けて実益を収めるとということ。 第六、身の分限を守り、冗費をはぶいて不時の用に備えること。 こういう法則のもとに事業を運営し、それで栄えたと思っている。それを世間からかれこれいわれては心外だ、という気持ちからであろう。いろいろと反駁したのである。 安田は「乗っ取り」屋だといわれた。これに対しては、 「他人の窮迫に乗じて金を貸し、ついでにその実権を奪うがごとき念は断じてない。担保が流れこみになるので、結果から見ればあるいは右様(みぎよう)に思われるかもしれぬが、私においてことさらにそんな政策をとったのでないということは、ここに明言してはばからぬ」 といっている。 事業の支配権をにぎり、前経営者のクビを斬ることも非難された。これに対しては、 「前の当局者は世人に信用がないから他の者をもってこれに代えることになる。私が自分の信用するものをつかわしてその局に当らしむるのはむしろ当然の成行きで、業務を忠実に執行し、社会に対する私の義務を完全に果たす道と考えているからのことである。その誠意がかえって策略のごとく世人より解せられるのは、はなはだ心外にたえぬ」 といっている。
「ケチ」で通った安田にも、無論「富者の社会的義務」という考えはあった。 「資産を作るにはもとより自身の勤勉努力が、衆人に超ゆるにあらずんば能(あた)wざざるところであるが、また一方より見れば、社会から受くる感化や恩恵もまた大いにあるといわねばならぬ。すなわち、一個人の努力と時勢の変遷と相伴うて資産を作る場合も多いのであるから、富者は社会に対する義務を忘れてはならぬ」 という言葉がそのことを物語っている。 ただこの考え、義務意識がそのまま「寄附」には結びつかないのであった。 何故かといえば、それは、 「社会に迷惑をおよぼさぬため、自分の事業の正当な発達をはかることが第一」 という発想歩をとるからである。それにまた、寄附については、 「陰徳をもつて本とすべし、慈善をもって名誉を望むべからず」 という父の遺訓が胸にあったからだという。 「ケチ」と悪口をいわれていることは、おそらく彼の耳にも入っていたであろう。非難中傷の手紙などが個人的にとどいていたのかもしれない。だが彼は、 「私がなしたことが多くの人の幸福となっていれば、たとえそのことが世間に現れずとも、心中満足に思っている。此世の毀誉褒貶は棺をおおうて事定まると昔からいうが、真にその通りで、社会の表面に立って業を成せば、いろいろの誤解を受け、我が心事と世評と相反することが少なからぬ。しかしかたく「陰徳」ということを信じておれば、さらに不満足を感ずることがない」 と語っているのである。
安田善次郎については竜渓(りゆうけい)矢野文雄『安田善次郎伝』がある。「余は安田松翁(しょうおう:善次郎の雅号)と相い識(し)ること久しく、晩年特に親しかりき、故に翁没して後数月、安田家より伝記編術の嘱(しよく)ありしを以て……」という序文をつけて、大正十四年に刊行されている。今日では「中央文庫」に入っている。 その竜渓もまた、 「氏が一方にて世人から称賛せられる事柄が、一方ではまた暗に恨みを買う種子となっていたのは是非もない事である」 と、冷たい世評の存在を肯定している。 ところで、「寄附」に対する彼の態度、「陰徳」論が決してことばだけのゴマ化しでも、単なる強がりでもないことを証明する記事が、意外な本の中に見出される。鶴見祐輔著『後藤新平』第四巻である。 後藤は世間から「大風呂敷」といわれた人である。その政策、抱負があまりにに大きすぎて、常識でこり固まった世間の理解をはみ出していたからだ。 その後藤が東京市長だった大正九年、東京市政調査会設置の計画を立てた。このとき、後藤の演説をきいて、 「東京市の行き詰まりは、すなわち帝国の行き詰まりであって、首都たる東京は帝国の縮図なれば、東京を救済することは帝国を救済する所以との高説は感服いたしました。ついてはこの事業につき何か私に応分の御用でもあるようならば微力尽くして見たいと存じます」 と申し入れたのが「ケチ」の安田である。しかも彼は、 「俗に申す寄り合い世帯ではとうてい思う存分のことはできるものではありませんから、私がお手伝いすることになれば、はばかりながら、このくらいの資金は私の独力で足ります故、あえて他の助力を借りるにおよびますまい」 といったのである。さすがの「大風呂敷」も、「余はいささかの度肝を抜かれたのであった」と語っている。 資金援助について、安田はいった。 「私はこれまで何れの慈善事業にも、郷里のことにも名前をあらわして出金したことはありません。が慈善の根本から割出された事業ならば微力をつくしてみたい心はもっております。(中略)私の心は神明の知りたまう所とうぬぼれているのです。(中略)あなたが使う人となられれるならば、私は集める人となってお手伝いができると自ら信ずるのであります。しかしあなたが他人の力に依頼せぬとおっしゃればそれまでであるが、わたしはそういう意義のある仕事に向って家産を傾けることを決していとわぬのである。いくら金を集めたとて、死んでいくときは黄金の棺に入るわけには参りません」 彼が単なる口舌の徒でなかったことは、この逸話が証明している。 ところがこれから間もなく、大正十年九月二十八日、大磯別邸にいた安田は、朝日平吾という男に刺殺され、八十四年の生涯を閉じたのである。 朝日は、 「労働ホテルを建てるので、寄附をしてもらいたい」 といってことわれれ、怒って刺殺したんのであった。しかし、安田を殺したあと、自分も命を絶ったそのふところに「斬奸状」と「死の叫び」と題する論文が入っていた。そして「死の叫び」のはしがきには、 「奸富安田善次郎巨富ヲ作(ナ)ストイへドモ富豪ノ責任ヲハタサズ、国家社会ヲ無視シ貪欲卑吝ニシテ民家ノ怨府(エンブ)タルヤ久シ。予ソノ頑迷ヲ愍(アハレ)ミ仏心慈言ヲモツテ訓(ヲシ)フルトイへドモ改悟セズ、ヨッテ天誅ヲ加へ世ノ警(イマシ)メトナス」 と書かれてあった。すなわち朝日は、世間の定評どおり、初めからことわられることを予知し、殺すつもりで安田別邸を訪れたことがこれでわかる。 凶変のあと、安田家では遺言状などを整理し、東京市への寄付金関係の書類出てきたので、嗣子善之助(このあと善次郎を襲名)は後藤市長を訪ね、「三百五十万円」、今日の百億円以上に相当する金と本所横網町所在安田本邸および河岸地を寄附したのである。 2023.06.13 記す。 |
|
雷おやじの魅力 小島直記著『逆境を愛する男たち』第二十話 P.133~138 帝国陸海軍がオールド・ニッポン最強最大の組織体であったことは否定できない。その幹部たちが驕慢になったのは日露戦争後といわれるが、その中のエリート統率者たちを槍玉に上げたのが『薩の海軍・長の陸軍』という本である。 著者は鵜崎鷺城。日露戦争終結後の明治四十三年、三十八歳の鷺城は、雑誌『日本及日本人』にこれを掲載し、翌年政教社から刊行された。今日読みたければ、筑摩書房刊『明治文学全集』の中の一冊、『明治人物論集』におさめられている。 海軍の大ボス山本権兵衛、陸軍の大ボス山県有朋以下、 「なるほど、上原さんは偉かった」 と心からなっ得したのは、今村均著『今村均回顧録』を読んでからである。 周知のように、今村自身大将にまで陸軍のエリートである。しかし私がこの将軍を心から敬慕する理由は二つある。
※写真は角田房子著『責任ラバウルの将軍今村均』(新潮社)にある写真:自宅庭先の三畳の小屋にて。 陸軍の大ボス山県有朋は、西南戦争のとき四十歳の中将で政府軍の指揮をとり、文字どおり命の恩人であった西郷隆盛をはじめ、多くの若者を戦死させた。それは公務上やむを得なかったとしても、東京に凱旋した翌年、何をしたかといえば、目白に椿山荘という豪邸を構え、天下を睥睨したのである。この山県に比較すれば、今村均の人間的美しさがよくわかる。戦の勝敗を超えた心の世界である。
旧職業軍人の自伝として、石光真清『城下の人』、『曠野の花』、『望郷の歌』、『誰のために』の四部作(中公文庫)、水野広徳の『剣を吊るまで』、『剣を解くまで』の二部作(経済往来社)、そしてこの今村均自伝がベスト三だと私は信じている。特に今村均自伝は、組織の幹部とはどうあるべきかを教えてくれる点で、現代のトップマネジメントの好参考というように思う。 陸軍は長州閥であった。その中で、長州閥に属しない宮崎県都城出身でありながら、元帥陸軍大将にまでなったのであるから、上原勇作は確かにタダものではなかったろう。一体、どういう点が偉かったか。 今村均は、大正十年三十五歳の秋、イギリスから帰って参謀本部所属の参謀となり、参謀総長上原勇作の別荘に報告にいった。 それは鎌倉にあったが、"これが別荘か"とおかしくなるほどの簡素な三部屋のバラックにすぎない。 上原は少年時代、旧藩主嗣子の指導役をたのまれ、共に鹿児島の造士館に学んだ。しかし、発奮して上京。家からの送金はないので、薩摩出身野津道貫少佐(のち元帥)の玄関番となり、大学南校(東大の母体)に学んだ。が、中途退学して陸軍士官学校に入り、首席卒業。フランス留学ののち、ずっと中央の要職にあった。今村は、 「直情径行、他がどう思うかなどを、考慮することなしに所信を説く。自然、階級の進むに従い、『雷おやじ』のあだながつき、周囲から煙たがられていた武人だ」 と書いている。 趣味道楽をもたない。たった一つの楽しみは読書で、「読書がなければ上原もない」と、自身もよく口にしていた。 今村がイギリスから送った駐在員報告もくわしく読んでおり、不明の点をコテンパンにたたいたのち質問。 「三年間の駐在で、イギリスの最も良い点と感じたところは、何だった?」 「良い点は、紳士道といいましょうか、実に礼儀の正しいことです。悪いところと申せば、保守主義で、他国のことを学ぼうとしないことです」 「君は三年もおって、まるで逆に見ている。イギリスの紳士道という礼儀は、国内だけの話。国際間のことになると、完全に非紳士的だ、香港をどうして手に入れたか。インドをどう統治しているか。敗將ナポレオンをどうとりあっかったか。アフリカ土人をいかに奴隷として売りさばいたか。君はそれでもイギリス国民を紳士的だというの。またイギリスの悪いところは保守だという。イギリスは外に対しては、あのように、おおっぴらに不作法に利己主義をふるまいながら、国内では全英人の団結保持のため、おおいに国粋と民族の優越性を説いてやまない。この保守こそ、大英帝国を堅持しているただ一つの強みといえる。しかも保守の内容を検討して見給え。彼らのような進歩的な民族が、どこにある。蒸気機関の発明、鉄道の建設、社会施設の改良、議会制度など、みな他国より、一歩も二歩も先に進んでいる。現に将来列国軍がそうなるであろう軍の機械化などでさえ、イギリスが先鞭をつけているではないか。君はもういっぺん、イギリスの歴史や、民族の性格を研究しなおななけりゃいかん」 散々のていらくで退散した。 (せっかくの日曜日を棒に振り、何のことだ、雷おやじ奴!) と思った。が、そのあとから、 (だが、今日はおれの敗けだ。どうだ、あのおやじの本を読んでいることは。それに、おれの報告を本当によく見ていてくれる。やっぱりえらいおやじだ) と思った。 その一年後、上原は元帥として軍事参議官専任となると同時に、前年少佐に進級したばかりの今村は、その副官となった。 元帥には二人の副官がつく。一人は事務副官で、他は参謀の副官である。今村は後者で、主として陸軍軍事に関する現在および将来の計画、わが国軍の情勢等を報告し、その諮問に応じ、また元帥と陸軍三長官との公的連絡にあたる役だ。 「とてもあのおやじの下では、一ヵ月もつとめきれまい」 と、思った。上原六十八歳、今村は三十七歳である。その年の暮、摂政殿下(現天皇、当時二十二歳)から、上原元帥に対し、南洋委任統治諸島の視察報告を行うよう沙汰があった。 赤坂離宮での報告は、一時間半ほどですみ、お茶を賜わった。 「茶の時間がすんだら、わたしの乗馬演習の時間になる。元帥もいっしょにやらないか」 「勇作め本日は乗馬の服装で参上いたしませんでした。お許しを賜わりますなら、御馬術を拝観いたしたと存じます」 「それはいっこうにさしつかえない」 そういう対話があって、 殿下を先頭に、侍従武官X大佐、侍従、主馬寮の者八名が騎乗して馬場に入った。 十周ほど内側を速歩、駈足でまわり、ついで障碍飛越えとなった。主馬寮の者が横木障碍物を中央に備えた。その高さは八十センチぐらいに見える。 「もう少し高く」 と殿下に命じられ、さらに十センチほど高められた。そして、殿下を先頭に、あとの八騎は逐次十五~十六メートルをへだててこれにつづいた。 殿下の馬の足は木に触れて、横木は地におちた。つづいて八騎も、すべて失敗して横木を落す。 第二回も第三回も失敗。 第四回目、殿下は少しいら立っておられ、強く馬に拍車をあてられたが、やはり失敗だった。 他の八騎もすべて失敗。 「横木を低くせよ」 と殿下は命じられ、強く気合をかけ、顔をあかくして突進、見事に跳越された。つづく八騎も成功した。 元帥はわれを忘れ 馬場内にかけこんで、御乗馬の口わきの手綱をおさえ、平手で馬を軽くたたきながら、 「殿下、ただ今は見事でございました。成功するまで、おやめにならなかったことは、うれしく拝し上げました。何事も一度や二度では成るものではありません」 と、まなこを瞬かせながら言上した。 殿下は満足げに微笑して、 「馬はなかなかよくしこまれてあるのだが、今日は最初から少し高くしすぎたので、良くいかなかった」 といわれた。 雷おやじは扈従の侍従武官以下に向かい、 「さてさて、おのおの方は、殿下のお相手のがらではありませんぞ」 と、大きく呼ばわった。そして帰途の自動車の中で、 「X大佐までが、あんな消極のまねをし、わざと障碍をしくじっている。馬術がよいので、武官に選ばれているのに……。殿下の御気分を、悪くしない礼意で、わざとああしていることはわかる。が、あのような礼意は、結局御輔佐をあやまり、御聡明の御伸びを害することになる。人臣のおもねりのはじまりは、あのまちがった礼意の慣習によるものだ」 といかにも不快そうに語った。 X騎兵大佐は、次の異動期、他の職にかえられた。 2022.03.11記す。
|
|
棺を蓋いて事定まる 小島直記『逆境を愛する男たち』第二十一話 P.139~144 戦争のため卒業が半年くり上がり、昭和十八年九月末に学校を卒業した筆者は、十月一日から海軍経理学校補習学生第十期海軍主計見習尉官というものにしてもらった。通称「短現十期生」である。 五ヵ月訓練をうけ、十九年三月一日主計中尉任官。最初の赴任地は、愛知県知多半島の河和(こうわ)海軍航空隊であった。 そこに「短現」の先輩が二人おられた。主計長冨田康次主計大尉(間もなく主計少佐)、分隊長西脇教二郎主計大尉である。戦後、冨田主計長は検察畑に進まれ、公安調査庁長官、な古屋高検検事長など歴任、いま弁護士となっておられる。また西脇分隊長は実業界に進まれ、太陽生命社長として活躍されている。 お二人とも、職務に関しては厳しかったが、私的面ではじつに心温かく、特に非常な読書家であったことが忘れられない。 着任そうそう筆者は入院した。冨田主計長は出張の途次、本屋によって数々の文芸書を買って差し入れしてくださった。また西脇分隊長とは、その愛読書『ラッフルズ伝』を材料に、夜おそくまで語りあったことがある。 両先輩の庇護のおかげで、新米中尉は大きなヘマもせず、また意地悪い老士官たちにいじめられることも少なかった。 そのうち筆者は、河和町とは反対側の、伊勢海に面したの西岸(せいがん)寺のそばに家賃三十五円の家を借り、新所帯をもった。 以来三十九年、往時茫々、いつとはなしに忘れていたが、最近そのことをいろいろとおもい出す機会があった。 「唐人お吉は知多半島生まれだった」 という見出しの記事(昭和五十七年六月一日付け東京新聞)を読んだからである。
「洋妾」と書いて、周知のように「らしゃめん」と読む。辞書には「日本の女で、西洋人のめかけになった女を卑しめていう語」とある。下田の芸者お吉がその一人となり、「唐人」という冠詞がつくのもそのためだが、そのことを前述の記事は、 「安政三年(一八五六)七月、アメリカ領事館が下田柿崎の玉泉寺に置かれ、十七歳で芸者になったお吉は、間もなく下田奉行から説得されてタウンゼント・ハリスに仕えた」 と書いている。ハリスの妾であったことが既定の事実になっていることに注目されたい。 お吉は、明治二十三年三月、下田蓮台寺の稲生沢川に身投げしたが、この薄幸の女性は新聞記事によれば、 「天保十二年(一八四一)十一月、下田坂下町で、船大工市兵衛の二女として生れた――とされているが、お吉の菩提寺『宝福寺』の檀家総代らの調査により、知多半島の内海で生まれ、四歳のとき両親とともに下田へきたことがわかった」 とある。筆者が内海町、知多半島、冨田主計長、西脇分隊長をおもい出したのはこのためであった。それはそれとして、記事はさらに、 「宝福寺十七代目の竹岡範男住職(六十七歳)は、『お吉は下田へ移ってこなければ別の人生もあったろうに、黒船の来航とお吉の存在は、日本の開国の歴史の一ページで、お吉を守りながら真実を伝えることも下田の義務です』」 という談話もかかげている。ここでも、ハリスの妾であったことが既定の事実となっていることに注目されたい。
タウンゼンㇳ・ハリスは、安政三年下田にきたとき五十一歳であった。 幕府は勅許をまたずに日米修好通商条約に調印し、外国奉行をおき、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも修好通商条約を結ぶ。 安政六年五月、公使に昇格したハリスは、下田玉泉寺を引きあげ、六月、麻生の善福寺に公使館を設置した。このとき、外国通弁御用、「宿寺(しゅくじ)詰」といことでおなじ寺に住こんだのが益田徳之進。すなわち、明治になって「孝」と改名し、三井物産初代社長となる人である。 ハリスは、書院を自分の部屋にしていた。前に泉水があり、それをへだてて向うは高い山になっている。樹木がうっそうと茂って、昼でもうす暗く、深山の中にいるようであった。 書記官ポールト゚マンは、寺院内の塔頭、(本寺の境内にあって本寺に従属する小寺)にいた。ハリスは、ポールㇳマンはじめ、公使館員をよく𠮟った。益田の部屋は、書院から二間目なので机をたたいて叱るのがよくきこえた。 ハリスの人柄を物語る話を二つ。 オランダ人ヒュースケンが浪人に斬殺されたとき、イギリス公使はじめ外交団は大いに憤慨し、横浜に引きあげるほかない、ということになったとき、 「バカなことをいってはこまる」 と制止したのがハリスであった。 「あなた方、引きあげるなら勝手に引きあげるのがよかろう。だがわたしは引きあげぬ。この暗殺事件は無論容易ならぬ事件であるが、国交を傷つけるほどの事件ともおもわれぬ。もともと日本は、外国のことを夷荻(いてき)といっているような国だから、外国人が気に入らぬといって殺すような乱暴者のいるのはやむを得ない。こういう未開の国にきて、こういう事件にあうのはやむを得ない。したがって、こういう場合、すみやかに幕府は遺憾の意を表し、加害者を懲罰し、被害者の遺族に十分な賠償をすればよいのである」 ハリスはそういって、翌日から、わざと馬にのって運動に出かけはじめた。麹町から小石川と、江戸城をぐるりとまわるのである。 これには幕府が仰天した。アメリカを代表する公使にまちがいがおこれば、外交上一大難題がおきる。そこで、江原素六(えばら そろく)を隊長とする五十人の騎馬隊がハリスの前後を守るようにしたのであった。江原はのちの代議士。麻生学園をつくる。 ハリスは乗馬は得意でなかった。それなのにこういうことをしたのは、 「これによって日本人に威力を示し、諸外国に範をたれようという深慮に出たものであろう」 と益田は語る(『自叙益田孝翁伝』)。この乗馬行で外交団の動揺はおさまり、事件は落着した。 第二の話。ハリスの身のまわりは、下田からつれてきた滝蔵という者が世話していた。この男は英語はチンプンカンプンなのに、ハリスのいうことだけは何でもわかる。 「真面目なお方じや。日曜日には誰にも会わず、用もきかず、書院にとじこもってお経を読んでおられる」 と彼は話している。お経とはバイブルであろう。こういう見聞、とくに「範をたれよう」という姿勢、「真面目なお方」という滝蔵の評価、バイブル、二部屋へだてて女性の声などきかなかった材料をもとに、 「ハリスは真面目なクリスチャンであった。唐人お吉という女を愛していたといううわさなぞはじつに怪しからん。私は信じない。決してそんな人物ではなかった。どうか冤(えん)(無実の罪)を晴らしたいものである」 と益田は語っているのである。 もし、「既定の事実」が正しいとすると、ハリスは、江戸では謹厳で、下田時代だけお吉を愛したのであろうか。だとすれば、にせクリスチャンだということになる。滝蔵もウソつきだということになる。 下田時代にも、範をたれようという使命感のもと、謹厳であったとすれば、下田奉行所の役人が、ハリスを口実としてお吉と遊んのではだあるまいか。疑問はいろいろ出てくる。
十三年前、今は亡き評論家伊藤肇君と論争したことがある。七歳下の彼は当時四十三歳、某経済誌の記者で、まだ安岡正篤老師の教えをうけていなかった。
「あんたも早く生体解剖をやらにゃダメだよ」 ときめつけたことにはじまる。筆者は二つの点で反駁した。 第一、「伝記」を無条件に「現存実業家人物評」の下位におく価値観の問題。 第二、現存実業家と面識があるということで、その人物を論評できると考えている安易、不徹底な考え方の問題。筆者は、 「中国の古い言葉に、棺を蓋いて事定まる(『晋書 劉毅伝』)というのがある。その意味は、死んでこの世を去ったのち、初めてその人の生前の事業や性行の真価が定まる、というものだ。大体人物評価のポイントは『出処進退』といわれ、とくに『退』が一番重要だが、君はその『退』を見ないで、ゴシップ的なことばかりほじくってもはじまらぬではないか」 と反論した。しかし彼は承服せず、水掛け論となってしまったのである。 だが、ハリスのことをおもうと、筆者には改めて疑問が浮かぶ。 彼は文久二年(一八六二)帰国してニューヨークに住み、明治十一年(一八七八)にこの世を去った。けれども唐人お吉の一件に関しては、問題は解決したとはいえないだろう。すなわち「棺をおおいて事定まる」とはいえないわけだ。そしてそれは一洋妾だけのことではなくて、ハリスその人の人格、全人生を決定する評価のポイントなのだ。 2008.12.26。2022.02.27追加。
|
|
小島直記著『逆境を愛する男たち』第二十二話 P.145~151
第二十一話 引退のタイミング 若き日の伊藤肇君と論争した「死体解剖」と「生体解剖」の問題は、前話でのべたように、「出処進退」の「退」にポイントがあるのであった。 その現役からの退き方について、「日本資本主義の最高指導者」という最大級の賛辞をうけている渋沢栄一が、はなはだ変わったやり方をしている。「第一回引退」と「第二回引退」と、二度やったのである。 明治四十二年六月六日、東京兜町の渋沢事務所では、関係者数名を招き、引退声明が行われた。その声明文の中に、 「余は心身共に尚壮健なりと雖も、一人にて万事に精通すろ能はざるを以て、折を見て退隠せんとは、常に余が胸中に描きたる希望なりき。恰も当年七十歳となりたれば句切りとして愈々財界より隠退する事に決したり。尤も第一銀行は余が財界の人となれる最初の記念なるを以て、臨終の際までは其事務に鞅掌する積りにして東京貯蓄銀行、銀行集会所、銀行倶楽部には第一銀行の関係上従来通りに留職する考えなり」 という文言がある。 これが、「引退」ということについて、さまざまな感想を催させるところだ. 第一に、プロにとって「部分引退」なるものがあり得るだろうか、という疑問をもたせる。それはたとえば、若乃花が引退声明をしたあとも、 「三役との相撲だけは従来どおりやってみせる」 というようなものではないか。 それが許されるどうかは二の次にして、まずはそういう段階的差別をつける心情に、歯切れのわるさ、サッパリしない後味を感じる。 渋沢は『論語』の権威として者、自他共に許していた。 『論語』の境地は、ぐずぐずと意味もなく延引することをよろこばない。「朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり」――一日の充実は、後日に未練を残さないものとする。それでこそ≪道を聞いた≫といえるものである。「その老ゆるに及んでや、之を戒むるは得るに在り」――この「得るとは、「欲念」である。財物、あるいは地位、あるいは長生きして子孫の繁栄を見たいという気持ち。「引退」とは、この「欲念」からの解脱が人間にとって可能かどうかは別として、先ずはその志向があり、その決断があり、そのための励行があってこそ、はじめて意味をもつもの。当初から部分的志向、部分的決断、部分的励行を予定するようなことでは、どうして『論語』の権威者、日本資本主義の最高指導者の進退といえるだろうか。
渋沢の、このときの心情、進退は不可解である。しかしながら、その頃の経済界の出来事と関係させながら考えるとき、その真意、真相なるものが察知せられる気がする。 それは、この物語の十六話でも触れた「日糖事件」の存在だ。 その年の一月五日、万朝報は、「大日本精糖破滅」というセンセーションなる見出しで、その会社の積弊がバクロし、大騒動があったのち、三大工場も停止した、場合によっては、一大疑獄がおこるかもしれぬ形勢だとして、 「事茲に至れるは全く重役等が罪悪を逞うせる結果にして、即ち彼らは毎期の考課状を偽造して不当支出を蔽ひ、或は所有株の預け合ひをなして、制規を瞞着せる等不正行為尠からず而も今や其の不正暴露せるを見るや、来る十四、十五日頃を期し、自ら進んで大株主会を開き、今日迄の罪状を告白して会社を自沈せしむるの計画を立てるに至れり」 と報じたのである。 こうして火のついた事件は、四月に重役たちが拘引され、つづいて代議士たちが収賄容疑で逮捕され、五月予審決定、七月判決があり、農商務省農務局長から天下っていた農学博士の社長酒匂常明がピストル自殺をするという展開となる。 その疑獄の詳細は割愛するが、この背後に渋沢栄一の言動が一つの問題を提起していたのである。 新聞がいろいろ書き立てても、ときの首相桂太郎は、 「一民間企業の私事にすぎない」 として、頬かむりで通そうとした。ところがイギリス大使マクドナルドが日糖の株主で、株に対して、 「こういう背任不徳の重役を見逃し、法律的にも何等の制裁を加えず、そのまま放任されるようなことがありましたならば、一は将来日本の経済界の発展を阻害し、一は海外市場における日本の信用を失墜することは疑いないところで、まことに遺憾に存じます。五、六年前イギリスにおいても類似の事件が起きましたが、その責任者は、ただちに法律の制裁をうけ、懲役二十五年の刑に処せられ、社会的にも勿論葬られ、その背任不徳の行為に対する当然の罰をうけました。他事ながらご参考までに」 という手紙を送ったのである。この手紙に尻をたたかれ、桂首相はあわてて司法権の発動を命じたのであった。 ところが、こういう破局的段階にいたる数年前に、株主の一部は会社の乱脈経理に不審を抱いていた。そこで、四十年十一月の株主総会において、 「調査委員をおいて監査すべきである」 という動議が多数株主から提案されえたのである。ところが、この動議に反対を唱えたのが、会社の相談役渋沢にほかならなかった。 「自分は、現重役の行為が完全無欠であるとは信じませんが、それかといって、調査委員をもうける必要はないとおもいます。調査委員をおくというようなことは、会社が最大の危機にのぞんだ場合のことでありまして、当社の現状は、決してこういう段階にあるとは考えません」 と彼は言ったのである。 ほかならぬ財界の最高指導者、権威者の、確信にあふれた企業診断であり、断定である。いきり立った株主たちも、その権威の前に叩頭して動議を引っこめた。 そしてわずか一年半後のこの事件発生である。 「あのとき渋沢さんが動議に反対していなければ、会社の破綻をくいとめことができたかもしれない」 と株主たちはおもったであろうし、当然、 「あのとき監査に反対した責任はどうしてくれる」 といきまきもしたであろう。 その不平や批判が」ご本人の耳に達したかどうかは別として、そういおう不平や批判とは関係なく、渋沢が普通の人間であれば、あのときの発言を「しまった」とおもい、その責任におもいをいたすのは当然の道すじであろう。 何らかの形で、責任をとらねばならない。そのためには、「財界引退」という進退以外にはなさそうだが、さりとてまだまだ財界には未練がある。 そういう心理的ジレンマの末に考えついたのが「部分引退」声明ではなかったろうか。 これは筆者の単なる推測にすぎないけれども、部分的引退の理由としては、これしか考えつかないのである。 渋沢は、このような進退をしたのち、さらにこのあと、大正五年七十八歳のとき、もう一度引退声明をして、このときようやく、 「実業界と直接関係を絶つ」 ということになったのであった。
英文学者の中野好夫の『人は獣に及ばず』(みすず書房)を先に引用したが、この中に「高風の財界人――伊庭貞剛」という一文がある。 「奇妙注文が飛びこんできたものである。……注文先がどだい、まちがっている」 と書きながらも、中野が協調し、礼賛しているのは伊庭の人柄、特にその進退の「退」のいさぎよさだ。 「老人が老を自覚することほど、世に難しい問題はないらしい。これができたら達人である。逆に、いい年をして、俺はまだ若い、若い者になんぞ負けるもんか、などと口癖にしだしたら、もう末である」 「筆者自身は、財界人などというお偉方とはまず完全に無縁だが、それでも共通の知人ということもあり、年に一、二度くらいは財界人まじりのパーティ類に出ることもある。あるときこんなことがあった。会場の一隅で数人、さかんに大声で気焔を上げている老人群がいた。聞くともなく聞いていると、果たしてこれ、若いものなんぞに負けるもんかの連発であり、そう怒鳴っては肩を叩き合っているのだ。老醜見るにたえなかった」
中野は、伊庭に関する伝記本のうち、西川正治郎著『幽翁』は読んでいないらしい。主として神山誠の『伊庭貞剛』から引用している。 中野の重視するのは、伊庭引退の年(明治三十七年)の二月、『実業之日本』に寄稿した「少壮と老成」である。 「言葉は平易、内容もまた、あるいは平凡と見えるかもしれぬが、なんといっても燦然と光っているのは、『進歩発展に最も害をするものは、青年の過失ではなくて、老人の跋扈である』 とする一行であろう。前後の常識論に比較して、この一節だけは一種の熱気を帯びている」 伊庭は五十八歳(数え)で引退した。無論「部分的」引退などではない。つまり、本当の「引退」であった。そしてなお八十歳まで生き、悠々と人生を味わって美しい大往生をとげたのである。 「もちろん老人のもつ経験は貴重である。だが、それを生かす道は、必ずしも未練がましく、第一線に頑張り続けていることだけにあるわけでないはず。引際というのが大切なのだ。その意味で伊庭の進退は、財界のみならず、すべての人間にとって、実に得難い教訓をのこしてくれているように思う」 中野は、自分の文章を「見当ちがいの駄文」といっている。しかし筆者はまったく同感である。 2023.03.16記す。
|
|
小島直記著『逆境を愛する男たち』第二十三話 P.152~157
第二十三話 被疑者としての身の処し方 書架の片隅に『湘南方丈記』という本がある。著者は三上忠三、昭和十一年八月改造社刊。この本を、いつどこで買ったか、どういう内容であったか、そういうことを完全に忘れていた。ところがこのほど『昭和動乱期を語る』(経済往来社)という新刊書を読んで、はからずもその本のいきさつを知ることができた。 『昭和動乱期を語る』には、「一流雑誌記者の証言」というサブ・タイトルがついている。すなわち、大草実(文芸春秋)、萱原宏一(講談社)、下島連(文芸春秋)、下村亮一(日本評論)、高森栄次(博文館)、松下英麿(中央公論)など、往年のベテラン記者が一堂に会しての回想座談会が内容だった。 文壇、出版界、論壇、陸海軍、政財界の有名人物数百人がとり上げられ、エピソード、秘話は無論のこと、肉眼による痛烈な批判を浴びている。実物を知らなかったわれわれが、いかに「虚像」を本ものとおもっていたかを思い知らされ、あるいは、ある事件の真相を教えられるなど、興味はつきない。現代史に関心を抱くものにとっては必見の名著といえるだろう。 この中で『湘南方丈記』のことが出てくるのだ。 萱原 いまもロッキードで世間が騒いでいますね。戦前に越鉄疑獄とか帝人疑獄、その他いろいろあって、小橋一太、小川平吉、三土忠造といった人々が被疑者になった。僕はいまの政治家と較べて、それらの人々が立派だったと思うのは、いったん被疑者になると、サッと政治の表舞台から退いて、ひたすら謹慎したという一事ですよ。いまの人どうですか、盗人猛々しいじゃないですか。僕は他の人はあまり知らんけれども、三土忠造さんは割合知ってるんです。 『湘南方丈記』執筆の背景は以上のとおりである。 三土忠造は明治四年(一八七一)香川県生まれ。苦学して師範学校を卒業し、小学校教員となった。が、それにあきたらず、東京高等師範学校を卒業、小笠原長幹(おがさわら ながよし)の留学のおともで米国に行き、農政学を学んだ。 ※「米国に行き、農政学を学んだ」記事は要確認。(黒崎記) 帰国後、高等師範学校教授となったが、間もなくやめて「東京日日新聞」記者となり、さらに政界に入って政友会に所属。高橋是清に認められ、高橋内閣の書記官長。昭和二年(一九二七)田中義一内閣の文部大臣、高橋のあとをついで大蔵大臣、犬養内閣の逓信大臣、斎藤内閣の鉄道大臣を歴任した。帝人事件連座は、この鉄道大臣時代である。 「疑獄」というのは中国の言葉で、辞書には(一)犯罪の疑いがあって捜査、審理を受けている事件、一般に、大規模な収賄事件をいう。(二)有罪か無罪か判決しにくい、世上の疑念が集まっている裁判事件、とある。 ところが「帝人事件」は、二百六十六回の公判のあと、藤井五一郎裁判長から、「証拠不充分ニアラズ、犯罪ノ事実ナキナリ」という判決をうけた。つまり「疑獄」という言葉は当てはまらないのだ。 しかし、無実の人々が拘束され、ついに内閣まで瓦解させたほどのこの事件がどうして起きたか、という点では、まったく不審にたえない事件であり、その意味では文字通り「疑獄」だったといえるのである。 「帝人事件」については、筆者も書いている(『疑獄』=昭和五十八年潮出版社)。けれども筆者の知るかぎり、もっとも内容価値があるのは、事件の飛沫をうけ、背任罪で一年二カ月を求刑された河合良成による『帝人事件 三十年目の証言』(昭和四十五年講談社)である。 この本の第三部「瀆職に関する各人の場合」の七に「三土さんの場合」というのがある。 この事件のポイントは帝人株をめぐる贈収賄罪にある。しかし三土忠造は、帝人とは何の関係もなかった。「ところが三土さんを憎んでいたのは、議会その他を騒がせた当時のファッショ連中である。(中略)こういう連中は斎藤総理を憎み、高橋蔵相を憎み、黒田次官を憎んだ。そしてその圏内の一人として、当時の鉄道大臣であった三土さんを憎んだのである」(河合、前掲書) しかし、三土は鉄相なので、仮に帝人株をうけとったとしても、身分関係も職務関係もないので、検事局は収賄罪で告訴できない。そこで犯罪に仕上げるために、「偽証罪」をデッチ上げる。「そのため三土さんを高木君(注、元帝人社長、元台銀理事、高木復亨)及び中島さん(注、元商工大臣、男爵、中島久萬吉)と対質せしめ、高木君(注、元帝人社長、元台銀理事、高木復享)及び中島さん(注、元商工大臣、男爵、中島久萬吉)と対質せしめ、高木君をして『確かにあなたに三百株差し上げた』といわしめ、中島さんには『確かにあなたに二百株を換金してもらった』といわしめる。三土さんはもちろん絶対にその事実を否定するものだから、検事連はこの否定(否定こそ事実である)を捕え、三土さんを偽証罪として約一カ月にわたり収監するのである」(河合、前掲書) すなわち、まったくのトバッチリ、ぬれ衣であった。それなのに、「いったん被疑者になると、サッと政治の表舞台から退いて、ひたすら謹慎した」のである。
「洛北大原の片山陰に、ささやかなる庵を結んで居た鴨長明の昔を、学ぶにはあらずして、余は湘南辻堂なる草廬の傍に、四畳半一室の書斎を造った。椽側までの寸尺をこめて、辛うじて、方丈とも言い得るであろう。 長明は、此の世をば仮の宿り、夢の浮世と観じて、独り塵外に己れを清くし、如来菩薩に仕えて、念仏看経に精進し、糸竹花月を友として、唯静なるを望みとし、愁えなきを楽みとしたという。余は此の世をば、最も楽みの多い世界と見ている。幾度生れ変っても、かかる好い処が、又とあろうとは、想像だにもしない。 仏者の説くが如く、因果応酬の理は、ありとしても、神仏は、自ら助くる者を助けたまう。此の世の生涯に於て、人の為めに、最も多く善根を布く者にして、始めて死後に於ても極楽浄土へは、行かれるものと信じて居る。故に極楽往生の道といっても、多くの人々と共に、相依り相助けて、力の及ぶ限り働くより外はない。働いて働いて働き抜く。さて其の後の事は、あなた任せというのが、余の人生観である。 されば、此の小室の営みも、仏に仕えんが爲めにあらず、穢土の累いを避けんが為めにもあらず、忙中閑を得れば、暫く長安名利の地を去って、静に経史を繙き、思索を凝らして、身を修め、人を導き、国に尽し、世を益するの道を、探らんとするにある」 という言葉ではじまり、最終の「六十小天地」という一篇は、 「草庵は閑静で、読書思索には、最もよい所である。読み飽いた時には、すぐ庭に下り立つ。庭には是等の生物が居て、形色を以て目を慰め、声音を以て耳を楽ませる。松の手入れ、草取り、草木の植換えにも気を転ずる。鋏や鎌や鋸は何時も庭先に置いてある。人間はとかく、自然に技巧を加えることを好む。自然は更に其の上を飾ってくれる。そこに一種の楽みが生ずる。 近い海岸へ出ると、相模灘は、茫々として際涯がない。三浦半島、伊豆半島を左右に望む。江の島は目の前に浮び、大島は雲畑縹渺の間に明滅する。西の空には、雪を頂く富士の高嶺が、魏々として聳え立つ。箱根大山一帯の連山が、其の裾に横わるを見る。本居太平の歌、 〽群山の朝さぎり深ければ さやかに見ゆる富士の芝山 は、写実の妙を得て居る。ここより望み見る富士の姿は、何処よりも美しい。 浜辺は広い。目を遮るものは何もない。汀の砂は、篩にかけたように細かい。夏は朝夕に、洗足でその上を歩く。漁夫はおちこちで、地引網を曳いて居る。何れも潮風に吹かれ、日光に焼けて、赤銅色である。芸術家の涎を垂らすような健康美が多い。相模灘の波は大きくうねって、緩やかに打寄せる。蕪村の秀句、 〽春の海ひねもすのたりのたりかな も、此の浜の実景を、如実に歌って居る。 此の小天地は、余に取っては此の上もない暢神の境である。修養の地である。我々の平素の生活は、繁雑にして心を労することが多い。時には都塵を避け、自然に還って、身を養い心を洗うを要する。又読書研鑽をも怠ってはならぬ。余はここへ来る度に、何時も自然に対して、心から感謝するのである。 という文章をもって終っている。 『昭和動乱期を語る』の座談会で萱原宏一は『湘南方丈記』や『憂幽徒然草』について、 「これがまた、立派な文章でね。世の中の為になる文章です。いまの被疑者の態度どうですか。しかも、あの帝人疑獄なるものは、藤井五一裁判長をして、判決文で『空中の楼閣、水中の月を掬うが如き事件』と言わしめた。まったく根も葉もないデッチ上げ事件なんですよ。それでも退身して深く謹慎した。角栄はどうですか」 といっている。 三土は第二次大戦後、幣原内閣の内務大臣兼運輸大臣となり、昭和二十三年(一九四八)七十七年の生涯を閉じた。 ※2019.05.11写す。 |
|
小島直記『逆境を愛する男たち』第二十四話 P.158~164 越川三郎著『水心随筆』(第九巻、水産タイムス社刊)が出た。私は仕事を放擲して、一巻を読みおえ、非常な感銘を受けた。 著者は安岡正篤門下。中国古典の造詣が深く、その文章には剛直なバックボーンが通っている。深くバイブレイトするのは、そのためにちがいない。 この中に「わが人物観」という一章があって、二・二六事件のときの総理岡田啓介の言葉が引用されている。 「(岡田は)総理大臣になると、三つのものが見えなくなるといった。三つのものとは、第一に金。いつも公金を思うように動かし、自分で金を使うことがないからその価値がわからなくなる。第二は人だ。周囲の取巻きに囲まれて、甘言やら、追従をきくことが多いために、誰が本当の人物か、誰が奸人か、佞人か、その区分けがつかなくなる。第三は、国民の顔がどちらを向いているのか分からなくなる。この三つが見えなくなくなった時は、総理大臣はのたれ死する、と彼は言い切っている」 この個所を読んで、私は以前紹介した池波正太郎の『男の系譜』をもう一度考え直す気になった。 実業界で池波正太郎の作品を愛好する人は多いらしい。私の親しい人では、ブリヂストンタイヤの石橋幹一郎会長がそうである。 『男の系譜』は、『剣客商売』や『鬼平犯科帳』などとは別種のもの。佐藤隆介のあとがきによれば、 「本書はすべて池波正太郎の語り下ろしである。第一回(織田信長)の語りをテープにとるために、編者が恐るおそる東京・荏原の池波邸を訪れたのは、昭和四十九年の夏であったと記憶している。早くも八年という歳月が流れ去ったことになる」 「語り>であるので、小説作品とはまったくちがった味がある。作品の肉声、本音がジカに出てくることだ。たとえば次の箇所――。 「人気作家になるというのはわけない話だ。わけのないというのは才能があればね。だけど、それは、わけないということはテクニックにすぎないことですからね。直木賞とった時点でぼくはエロ小説書けばいっぺんにそのときは出られるかもしれない。パッと、華やかに。しかし、そうしたら、いまのぼくはないわけですよ。直木賞とった時点では、まだまだ小説家としての自分は未熟なところで精一杯のところにいるわけです。だから、それから十年後、十五年後の自分の仕事というものを考えた場合に、やはりそのときには人に華やかに騒いでもらわなくても、蓄積することが大事なんですよね。行く先、自分が流行作家になろうということじゃなしに、自分が小説という仕事を何年か続けねばならないということを考えてみれば、おのずからそうなるわけだ。二年、三年で食いつぶされることは目に見えているのだから。 だけれども、十年十五年、自分で書いて食べていて、家族を養わなければならないということを考えると、十年、十五年、二十年先の自分がどういうものを書くかということを蓄積しておかなければ、とても仕事なんて続けられるものじゃないんだから、そのためには、やはりそうなってゆく、自然にそうなってゆくんですね。自分の力を知れば」 こういう肉声をまじえながら論評された史上の人物は、織田信長、渡辺勘兵衛、豊臣秀吉、真田幸村、加藤清正、徳川家康、荒木又右衛門、幡隨院長兵衛、徳川綱吉、浅野内匠頭、大石蔵助、徳川吉宗、井伊直弼、徳川家茂、松平容保(まつだいら かたもり)、西郷隆盛、番外として戦国の女たち――。おもしろくないはずがない。
こういう肉声をまじえながら論評される史上の人物は、織田信長、渡辺勘兵衛、豊臣秀吉、真田幸村、加藤清正、徳川家康、荒木又右衛門、番隨院長兵衛、徳川綱吉、浅野内匠頭、大石内蔵助、井伊直弼、徳川家茂、松平容保、西郷隆盛、そして番外として戦国の女たち――。おもしろくないはずがない。 以上の人物のうち、岡田啓介総理の言葉と対比しておもいだしたのが、徳川綱吉のことだった。 綱吉は、元禄時代に五代将軍として君臨しているが、生母桂桂昌院というのは、もとはお玉といって魚屋の娘であった。あるいは京の堀川の八百屋の娘ともいう。ともかくも三代将軍家光の手がついて綱吉を生んだのである。 「の桂昌院のときにはじめて幕府の大奧に女の権力が生れたんですよ、綱吉の時代に」 父の家光は、自分が若い頃、武術の修業ばかりやって学問しなかったことを悔んでいた。そこで晩年、桂昌院に、綱吉に聖賢の道を学ばせるよう遺言した。 「(桂昌院)むやみやたらに綱吉を可愛がると同時に、学問でなければ夜も日もあけぬという育てかたをしたわけだ。子どもの時分からこんな育てかたをされたらたまったものじゃありませんよ」 「学問だけに熱中する子どもなどというのは、不健全にきまっている。子どものころは、何よりもまずその小さな肉体をフルに使って、身体で万象を確かめべきなんだよ」 いろいろないきさつがあって、綱吉が将軍の座を射止めたのは三十五歳。このとき堀田正俊が大老となり、綱吉も堀田大老の意見をよくきいて政務にはげみ、最初のうちはボロは出ない。ところが四年後に正俊が死に、様子が変った。 「いよいよこれからは万事、自分の思うがままということになったわけだよ。それから急速に綱吉が変になってくる」 「若い自分は学問一点張でしょう。なにもやったことがないんだ、他に。人間、齢をとってから急にやったことのないことをやると、どうにもならない」 綱吉は、隆光という怪しい坊主を信任する。ロマノフ王朝のラスプーチンみたいな男だ。 ※参考:帝政ロシア末期の祈祷僧。シベリア・トボリスク県ポクロフスコエ村(英語版)出身。 奇怪な逸話に彩られた生涯、勃起していない状態で28cmと言う歴史的な巨根、怪異な容貌から怪僧・怪物・女たらしなどと形容される。ロシア帝国崩壊の一因をつくり、多くの女性と関係を持ち、歴史的な人物評は極めて低い反面、その特異なキャラクターから映画や小説など大衆向けフィクションの悪役として非常に人気が高く、彼を題材にした多くの通俗小説や映画が製作されている。 (黒崎記) 「将軍家におかせられましては戌の年のお生まれでござります。なれば、無益の殺傷を禁じるが肝要。ことに犬をいたわり、これをいつくしむことによって、御家はますます御繁栄、天下は万万歳でござります」 といわれて「生類憐みの令」を出した。 「手はじめは犬を殺してはいかん、犬を大事にしろという法律だったが、それがどんどんエスカレートされて動物全部を愛護しろということになった」 江戸城内の料理番が、料理しているとき、とまった蚊をたたいてつぶした。それを同僚が告げ口したので島流し。また密告した同僚も、見ていながらとめなかった、というので八丈島送りとなる。 「いまの大久保から中野あたりに、十八万坪の犬のアパートをつくって、江戸中の野犬を集めて、うまいものを食わせた。『御犬屋敷』というんだ。八万二千頭もいたそうだよ、そこに」 「その予算だけでも一年に二十万両とか三十万両とかかった。そういう負担は全部、江戸市民にかかるわけだ」 「綱吉は手前のために贅沢のしほうだい。犬は全部市民の負担。今日、われわれがやらされているのと同じだよ。われわれが税金をはらってトラックのために道路をつくっているのとおんなじなんだよ」 「元禄時代は綱吉の独裁時代だから、そもそも綱吉が国民をばかにしているということだな。しかし『生類憐みの令』のような奇怪愚劣な法令に反対する家来が一人としていないという、これも呆れた話だ。媚びへつらう奴ばかりで」 「手前だけの学問なんだ。世の中のことが何もわからない人が学問すると、こういうことになってしまう。蚊をつぶして島送りになった男に親がいて、どんなに悲しむか、そんなこと知っちゃいない」 綱吉にへつらう側用人牧野成貞が、美女を腰元に近づけた。女の味をおぼえた綱吉は、ひともあろうに、牧野の妻を江戸城によびつけ、それきり自分の妾にする。さらには牧野の娘で、結婚したばかりの新妻に目をつけた。これは一晩か二晩で帰されたが、その夫は切服してしまう。その新妻も翌年死ぬ。 「病死ということになっているが、わからないね」 一方、綱吉は男色にも精を出す。 「彼に愛玩された男女は百人をこえるというんだから」 『水心随筆』の筆者越川は書いている。 「(権力者が)この三つの不明からのがれるために、立派な師をもつこと、争臣(正しいことをあえて主張し上司をいさめる部下)をもつことだというのは、古今の明哲が教えているところだ。国に争臣がいなければ、亡ぶというのはよく知られた言葉である> 「元総理の池田勇人は、よく『自分は身辺に三人の知己をおいてこの意見をきく』と語った。三人とは、一人は一流のジャーナリスト、一人は本物の宗教家、一人は名医だそうである」 この一流のジャーナリストが、元西日本新聞記者伊藤昌哉であることは周知の事実。伊藤の名著『池田勇人 その生死』(至誠堂刊)には、二人の人間的結びつき――伊藤がよくアドバイスし、池田がよくそれを容れて努めた姿が活々と書かれている。 昭和三十七年晩秋、池田はヨーロッパ行きをし、伊藤は随行する。エアハルト(当時西独副首相)と会談した池田は、
「アデナウアーがなかなかやめないので、エアハルトはくさっている>
「あと三年たったら、これからお会いになる連中はみんなやめていますよ。総理もどうなっているかわからないが、とにかく若い人に目をつけておいてください」
「池田がつねに成長しているという姿が、池田のまわりの人間を求心的にしていった。政権をとらない前には、人びとは、ひとつの目標に向かって、たえず集団として努力するし、またしなければ政権はとれないものだから、求心的にならざるを得ない。ところがいったん政権をとってしまうと、それぞれがそれぞれのポストについて、下部との関係ができていくので、どうしても各個バラバラの考え方におちいっていきがちなものである。そこからは、人によっては、あるいは環境によっては、腐敗や堕落の生ずる可能性がでてくる」 池田の、努力し、成長しつづける姿勢がそれを防いだ。
|
|
小島直記著『逆境を愛する男たち』(新潮社)昭和五十九年五月二十日発行 P.221~227
第三十三話 魂のバイブレーション 二・二六事件の凶弾で八十三年の生涯をとじた高橋是清(当時岡田内閣大蔵大臣)は、明治四年十八歳のとき、唐津藩英語学校の先生をしたことがある。 このときの生徒に、辰野金吾がいた。東京大学では日本最初の西洋流の建築学講座が「造家学科」というなで開かれたが、辰野金吾は明治十八年その第一回卒業生四人の中の一人として世に出た。日本銀行(旧)本店、東京駅はその代表作で、「辰野式」といわれるように煉瓦に石を巧みに配した特色あるものが多い。 辰野隆(ゆたか)は、金吾の長男で、明治二十一年生まれ、大正五年東京大学で仏文科卒業、同大学で大正十二年のフランス文学の講座を担当した。その門下からは、渡辺一夫、小林秀雄、三好達治、中島健蔵、中村光夫、森有正などが出ている。 昭和二十三年東京大学を定年退職し、あとは中央大学教授となり、明治三十九年七十六歳で世を去った。
その第一回配本は『忘れ得ぬ人々』。その解説を担当した市原豊太は、 「御自分が生涯の時々に出会い、敬愛し、影響を受けられた明治・大正の日本の文化人の思い出」 「諸章を通じて流れている何よりも著しいものは、先生の諸先輩に対する景仰讃歎の純粋さである」 と書いている。 一口にいえば、そこには男と男との魂のバイブレーションがある。この中から、本書の読者に知ってもらいたいものをあげろ、ということであれば、私はためらうことなく、次の話、人物を選びたい。
佐藤正之という人は、山形県か秋田県の大地主の息子だったらしい。中央大学を卒業して、同大学の職員となり、やがて幹事となった。 当時中央大学は財政難で、先生たちの月給が満足に払えない状態が続いていた。佐藤幹事は、「中央大学は法律の学校であるから、一流の法律の先生を呼んでこなければ良くならない」 といって、礼を厚くして東京大学の先生たちを迎えた。他の私大よりも俸給がいい。夜間部の先生に対しては、 「夕飯は学校で食べてください」 といって、それも仕出しの弁当ではなく、神田の近所で恥ずかしくない鰻丼をとるか、ちゃんとしたご馳走をした。俸給をわたすにも、 「天下の学者を会計課に呼んで月給をわたすというのは失礼だ」 といって、いちいち自分が、自分の使っている職員をつかって、家にとどける。自宅にとどけられると、亭主のからくりが露見するので、迷惑する先生もいたらしい。 ところが、その払う金が枯渇した。すると佐藤幹事は、自分の地所を売りはじめた。そうして中央大学のために、いい先生をいい待遇で迎えたばかりでなく、生活の不如意な職員や小使たちまで、あたたかくいたわって生活を助けてやる。そのおやじさんやおふくろさんが死ぬと、 「君、葬式の金があるか?」 といって、自分で出してやる。 こうして、司法官や弁護士など、各界に立派な卒業生を多く出して、中央大学は隆盛になってきた。だが、そのさかんになったときには、佐藤幹事はすべてを売りつくして、一文なしになっていた。しかも彼は、自分のしたことを、自分では一言も話したことはなかったのである。 辰野隆は、中央大学で講義するとき、 「きみたちの先輩には、こういう人が幹事として、大学の運勢に生涯を捧げた。中央大学の発展というのは、佐藤翁に負うところが非常に大きいのだ。こういういい先輩は、官立大学、東大のような学校には、出ようとしても出ないんだ。立身出世も結構だけれども、こういう大先輩のいることは、中央大学の無上の誇りだぞ」 としばしばいったという。辰野は、 「ぼくは、政治家なんかには一人もえらい人はいないと思う。明治、大正、昭和を通じて、政治家はどこの国と比べても、ひどく見劣りがする。腐った世の中には悪臭を放つ政治屋もうじゃうじゃ湧くのであろうけれども、この佐藤翁のような人をいま考えてみると、楽しいと思う。永く忘れたくない人物である」 と書いている。
辰野隆は、府立一中の四年から五年になるときに、教員会議では落第だった。そうしたら、林兼助という若い先生が、 「辰野はスポーツばかりしてできが悪いが、中学の四年くらいで落第すると、それがきっかけになって堕落するおそれの充分ある生徒だから、五年になったらスポーツをやめさせて、自分が激励して教室の仕事を熱心にやらせるようにします」 と弁じてくれた。そこで辰野は、仮及第ということになって一番ビリで五年生になった。 このことは、及第の張り出しのある前に、体操の主任に呼びつけられて、 「お前は非常に成績が悪いから、五年生になったら勉強しろ」 と訓戒をうけ、そのときに林先生のお助け演説の話もきいたのであった。 「あのとき落第すれば、ぼくは庭球、野球、体操、水泳、なんでも好きだっつたから、スポーツが優遇される学校に転校して、なんかの選手になるとか、足が早かったからランニングの選手をやるとか、していたかもしれないが、林先生のおかげで及第させてもらったので、まがりなりにも、そのまま卒業できて、高等学校から東大に行く運命になった」 と辰野は回想する。 林兼助は、辰野が卒業した年に府立一中をやめ、どこかに行ってしまった。そして五十年以上、その消息はまったく知れなった。 いくら探してもわからないはずである。林は、日本各地の中学を転々として数学の教師をしていた上に、養子にいったのであろうか、姓も「松原」と変っていた。その上、辰野は「兼助」というなさえ知らなかったという。 ところが昭和三十四年、岐阜県多治見に辰野は講演に行った。するとはからずも、昔の林先生、いまの松原先生がたずねてきた。 それというのも、辰野は仮及第の件をそれまでにたびたび書いたことがある。それを読んだ人が、 「昔、辰野という生徒を及第にして助けたというのは林先生というけれど、林先生というのは、あなたのことではないですか?」 とたずねたら、 「いま松原だけど、それはぼくだ。あの辰野ならば、かすかにおぼえている」 ということになって、わざわざ講演会場にたずねてきたというわけだ。 「きみの講演をどうしてもきく」 といって、耳が遠いので、公会堂の一番前の席で、両耳に手をあててきいている。辰野は昔話をして、 「じつは非常にぼくは今日はうれしいのです。あのとき先生が助けてくださらなかったら、どうなったかわからない。五十一年、二年ぶりで、しみじみお礼をいうことができました。その先生がじつはぼくの講演をきいてくださる。それがここにおられる松原先生です。さあ先生、壇に上って下さい」 といって、恩師に演壇に上ってもらい、自分の脇に椅子をすえて、そこで講演をきいてもらった。聴衆からのさかんな拍手は、彼らもまた、辰野のよろこびをともによろこんでいたことを物語る。 明治二十六年から三十年までと、同三十八年から大正元年まで、東大総長を二回つとめた浜尾新に、辰野は慈父のようななつかしさを感じたという。 浜尾は、まれに見る訥弁であった。しかもそのまずさが、雄弁にもまして世の敬愛をうけていた。「これを要するに」といって、じつは何も要していなかったり、「諸君は……身体の……健康を……壮健にし……」という珍妙な文句で聴衆を失笑させた。しかもそれをトンネルの中で法螺の貝をならすような音声で語ると、真摯な情熱と愛嬌とがわいてきたという。 また、話しが長かった。教授たちは、浜尾から電話がかかると、まず短くて三十分ときめて、電話室に椅子を持ち出す人も少なくなかった。 その在任中、陸軍当局が「一年志願兵制」廃止の意向を東大へ通告したことがある。浜尾はたちどころに、学生の就業期間が中断されるのは国家のゆゆしき損失だと信じて、自ら陸軍省に出かけていった。そして反対意向を申し入れたのである。 「もし陸軍当局にして、あくまで国家の学制をくつがえすような意向を固辞するなら、帝国大学でも今後一切陸軍の依託学生の修学を拒絶する他はない」 それを力説したわけであるが、それが例の訥弁の雄弁、同じことをいくどとなくくり返して、いっまでも席を立とうとしなかったのだ。 その説くところはきわめて平明、疑いをいれる余地はない。しかし何よりもその終りなき訥弁こそ、欺かざる熱意と、根気の証拠であり、陸軍当局もとうとうしびれを切らして、その主旨を諒とするに至った。辰野は、 「しかも堂々と所信を披歴してはばからなかった浜尾総長が、軍部の怒りも恨みも買わず、軍部は軍部で帝大総長の人格と信念とを容れて、光風霽月の襟度を示した点は、当時、学府と軍部とがその思う所を忌憚なく語り合って、ともに進まんとする美挙として、心ある者に深い感銘を与えたのであった」 と書いている。 2022.04.12 記す。 |
 「本年を以て私も三十代に別れを告げ、所謂不惑に達しようとしている。此の書を読んでいるうち、ふと陽明の帰懐の詩『行年忽五十、頓(とみ)に覚ゆ毛髪の改まるを、四十九年非、童心独り猶、在り』を想起して、十年の差はあるが、妙にしんみり感じられてならぬものであるから、遂に此の書に『童心残筆』と題することにした」
「本年を以て私も三十代に別れを告げ、所謂不惑に達しようとしている。此の書を読んでいるうち、ふと陽明の帰懐の詩『行年忽五十、頓(とみ)に覚ゆ毛髪の改まるを、四十九年非、童心独り猶、在り』を想起して、十年の差はあるが、妙にしんみり感じられてならぬものであるから、遂に此の書に『童心残筆』と題することにした」
 その一つは、戦後自宅の庭の一隅に三畳位の小屋を建てられ、そこに籠って世捨人同様の姿で戦没者の冥福を祈ったという人間的姿勢である。
その一つは、戦後自宅の庭の一隅に三畳位の小屋を建てられ、そこに籠って世捨人同様の姿で戦没者の冥福を祈ったという人間的姿勢である。
 第二は、その自伝のすばらしさだ。ここにいう自伝とは『今村均回顧録』と『続 今村均回顧録』の二冊である。ともに芙蓉書房から刊行されている。これはオールド・ニッポン最強最大の組織体の中で、知能はいうに及ばず、人間的にも最高の境地に達した人物が、よく澄んだ、涙をたたえた眼で人間と出来事を過不足なくとらえた回顧録である。
第二は、その自伝のすばらしさだ。ここにいう自伝とは『今村均回顧録』と『続 今村均回顧録』の二冊である。ともに芙蓉書房から刊行されている。これはオールド・ニッポン最強最大の組織体の中で、知能はいうに及ばず、人間的にも最高の境地に達した人物が、よく澄んだ、涙をたたえた眼で人間と出来事を過不足なくとらえた回顧録である。
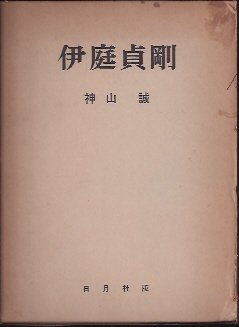

 いまその存在を思い出したのは、『辰野隆随想全集』(福武書店)が刊行されはじめたからである。
いまその存在を思い出したのは、『辰野隆随想全集』(福武書店)が刊行されはじめたからである。