| 日本の本より (享保17年~安政3年) |
日本の本より (明治時代:1) |
日本の本より (明治時代:2) |
日本の本より (明治時代:3) |
|---|---|---|---|
| 日本の本より (明治時代:4) |
★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 日本の本より (大正時代) |
日本の本より (昭和時代) |
★★★★★★ | ★★★★★★ |
| 外国の人々(1868年以前) | 外国の人々(1868年以後) | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
(明治時代:1) |
|---|

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.39~43 團 琢磨 先見の明「鉱山学」に志す 明治四年十一月、条約改正準備交渉のために岩倉大使一行がアメリカ丸でたったとき、公卿、大みょうの子弟、男女学生など五十四人が同行した。この中に旧黒田藩主の嗣子長知(ながとも)がはいっていた。長知には側近の家来を随行させようと重臣たちが考えたとき、父長溥(ながひろ)はその案を一しゅうした。「従来君子の関係のあった者を同行させれば、依然旧習にとらわれ、長知のためにもよろしくない。むしろ平素何の関係もなく、かつ前途有為の秀才を、学友という資格で、随行ではなく、同行させよ。長知は単に外国を見て知見を広めれば十分、少年には他日一技一能を会得させるべきである」 と、まことに新時代の黎明にふさわしい一大見識であったが、このことばによってどれほど大きな可能性が日本の歴史に加えられるか、そこまで正確な予測はできなかったであろう。その言葉によって選ばれた「前途有為の秀才」とは、金子堅太郎、團琢磨の二人であった。金子はハーバード大学で法律学を修め、伊藤博文の秘書官として大日本帝国憲法の起草に関与し、やがて伯爵・枢密顧問官となる。團はマサチューセッツ・インスティチュ―ㇳ・オブ・テクノロジーで鉱山学を修め、三井鉱山の近代的開発に成功して三井財閥のドル箱となし、やがて男爵・日本工業倶楽部理事長として日本財界をリードする。まさに「一技一能を会得」して歴史的存在となったのである。 ※この時、留学した人たちの中に津田 梅子がいた。 しかし、留学生に選ばれたとき、金子は十九歳(数え年)、團は十四歳で、本人たちにも自分の能力はわかっていなかった。ましてや金子の妹を團がもらい、二人が義兄弟になろうとは夢にも思わなかったであろう。 團は馬廻三百石の神屋宅之丞の四男、十三歳のとき元勘定奉行六百石取り團家に養子にいった。ところが秘蔵むすこで実家でもかわいがられていたから、なにか気に入らぬことがあるとすぐ家に帰りたい、という。そこで團家でも宝物のように大事にした。團はつけ物がきらいで、朝から魚がないと食事をしない。養母はいろいろと料理をととのえて、これがいいの、あれがいいのとご機嫌をとる。髪を梳(す)いてやり、着物をきせてやり、ふろにも入れてやる。金子がたずねると、琢磨少年は縮緬(ちりめん)の座ぶとにすわり、家来どもにかしずかれてごちそうを食べているところであった。藩の留学生として上京していたのが廃藩置県で学資を打ち切られ、司法省判事の学僕になって苦学していた金子青年は、團の若殿様ぶりにおどろいてしまった。 黒田長知、金子、團はおなじ船室に入れられ、長知は二段ベッドの上段、金子は下段、團はソファに寝たが、船が揺れて團はころげ落ち、あとは洋服、くつのまま板の間に毛布をかぶって寝た。「三日ほど何も食わない。これまでわがまま者といわれておった人が、西洋の船にのってだれもかすずくものがない。女中もおらなければ家来もおらぬ。わずかに一人ぼっちでしうからよほど苦しんだでしょう。それからだんだん日をふるにしたがって、ようやくはい出て飯を食うようになり洋服も着て歩くようになったが、こまったことには人につかえた経験がない。自分自身のことすら皆人にしてもらって、着物をきせてもらい、髪も梳いてもらたった若殿様であるから、旧君のお供をしておっても、旧君にかしずくということを知らない。僕は貧乏書生で苦労をしておったから、何もかも、くつみがきから着物の世話まで皆私がする。それで私もふ平であるが仕方がない。しかるに團は、僕にはそんなことはできぬというのです。二十五日間船の中で何もかも皆私にやらせて團はへい気でいる……」(『日本工業倶楽部二十五年史』下巻)と、この旅から六十一年たって、團が血盟団員のテロに倒れ、工業倶楽部で追悼晩餐会があった席上で金子は回想している。ノホホンとしている團少年を横目でにらみ、ブースカいいながらくつをみがいている堅太郎青年の姿が目に浮ぶようである。 彼らはボストンで勉強することとなり、長知とは別の下宿屋に一室を借りた。夜はダブルベッドにいっしょに寝る。金子團の無精にに閉口した。ワイシャツ、ハンカチ、くつ下などよごれものをそのまま押し入れにほうりこんでせんたくにも出さない。金子は注意した。 「ここには家来もいなければ女中もいない。自分のものは自分で始末せい。僕もやるから貴様もやれ」> 「そういうものか……」 團はいやいやながら整理にかかった。 大きな机を共同でつかったが、金子は自分の前を掃除し、團はしまい。そしてきたなくなると、何もかも金子の方に押しやる。金子は真ん中に板を立て、境界をつくった。 [これれからこっちは僕が整理する。そっちの方は君が勝手にしろ。これからこっちへはいるべからず」 二人は、旧岩国藩主の弟吉川重吉(十二歳)とその従者田中泰吉(十四歳)とともにグラマースクール(小学校)にはいったが、いずれも首席になった。ところが二年目に團がやめるといいだした。 「やめてどうする?」 「君はどうする?」 「僕はこれからハイスクールへいって、それから法科大学へいって法律をやる」 「僕は工科大学へいく」 「どうして?」 「僕は鉱山学士になる。鉱山堀りになる」 「それはよせ。鉱山堀りは武士のすべきことではない。貴様の父は筑前藩の財政の枢機をにぎる政治家だ。お前も政治学やれ」 「僕は政治はきらいだ。工科大学にはいって、鉱山のことを研究する」 「どいうわけで貴様はそんな考えをおこした?」 「調べてみると、日本は鉱物が多い。僕はアメリカで鉱山の学問をして帰って、金銀を掘ったり、石炭を掘って大いに地下の財宝を世にあらわす仕事をしたいと思う」 金子はびっくりしたが、やがてそのおどろきは尊敬にかわる。ちょうどこの話をしていたころ、故国では政府が三池鉱山を買収していた。それまでは民有で、柳河藩家老小野隆基はじめ、いろいろの人物が鉱区をもち、それがあちこちでたぬき堀りをやっていて紛争がたえず、政府でもこまって、総計四千九十一円六十五銭二厘で買い上げたのである。團はむろんそういうことは知らなかったが、その立志の年と三池鉱山官有の年が一致したのは不思議な偶然といえよう。やがて工学士になって明治十一年に帰国した團に福岡県令渡辺清は三池鉱山の調査をたのんだが、ちょうど流行病蔓延(まんえん)のときだったため團は一週間で逃げ帰ったので、渡辺県令は激怒したという。このときまでは團と三池とは縁がなかった。 ※プロフィル:福岡藩士の家に生れ,明治4四(1871) 年十三歳のとき,岩倉具視ら特命全権大使の欧米視察団に同行。そのままアメリカに在留し,マサチューセッツ工科大学鉱山学科を卒業,一八七八年帰国した。工部省鉱山局に勤務し,官営三池炭鉱に赴任,八十八年三池が三井に払下げられるとともに三井に入り,同炭鉱の近代化に努めた。 一九一四年三井合名理事長となり,三井財閥を工業中心の事業体に発展させた。さらに日本工業倶楽部理事長,日本経済連盟の会長など,昭和初期における財界の最高指導者として活躍したが,三井本館前で血盟団員の凶弾に倒れた。 2019.07.15 |
 元来議会なるものは、言論を戦わし、事実と道理の有無を対照し、正邪曲直の区別を明らかにし、もって国家民衆の福利を計るがために開くのである。しかして投票の結果が、いかに多数でも、邪を転じて正となし、曲を変じて直となす事はできない。故に事実と道理の前には、いかなる多数党といえども屈従せざるを得ないのが、議会本来の面目であって、議院政治が国家人民の利福を増進する大根本は、実にこの一事にあるのだ。しかるに……表決において多数さえ得れば、それで満足する傾きがある。すなわち議事堂はなばかりで実は表決堂である。
元来議会なるものは、言論を戦わし、事実と道理の有無を対照し、正邪曲直の区別を明らかにし、もって国家民衆の福利を計るがために開くのである。しかして投票の結果が、いかに多数でも、邪を転じて正となし、曲を変じて直となす事はできない。故に事実と道理の前には、いかなる多数党といえども屈従せざるを得ないのが、議会本来の面目であって、議院政治が国家人民の利福を増進する大根本は、実にこの一事にあるのだ。しかるに……表決において多数さえ得れば、それで満足する傾きがある。すなわち議事堂はなばかりで実は表決堂である。
(憲政の危機)
11月20日埼玉県に生まれる。新聞記者をへて、第一議会より終生衆議院の議席にあり、つねに軍閥、官僚政治を攻撃し、普選運動・護憲運動の立役者であった。 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.192 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.239~243
八代 六郎 「真の序」知る老提督
小泉三申は「軍人方面に結識する必要を感じ、海軍の八代(六郎)、秋山(真之)、陸軍の田中(義一)、宇都宮(太郎)、この人々に着目して交わりを通じ」たが、この中もっとも親しくなったのは田中義一であった。第一旅団長時代の少将田中を政友会総裁原敬に結びつけ、やがて原内閣の陸相、政友会総裁、田中内閣成立の手引き役をつとめるのは三申である。しかし、どういう理由で田中と特に親密になり、他の人びととはそれほどでなかったかは、三申も語っておらず、推測はむずかしい。 ただ筆者がひそかに思うことは、たとえば田中の過去に、三申自身のものと共通する体験があったことである。田中は十三歳のとき小学校の「授業生」となり、十九歳で他家の玄関番をしながら『資治通鑑』三百五十数巻を読破し、これを抄写した唐紙は六十センチ以上に達したという。三申も授業生をし、教養の基礎、その身につけ方も田中に似ていた。「策士」三申が自ら軍人成長株に近づくのである以上、そこに功利的打算がなかったとはいえないであろうが、しかもなお彼等を結びつけたものは、相似た過去をもつ同志としてのなつかしさ、心のバイブレーションというものではなかったか。 ところで、三申とは浅かった八代 六郎にも「結識」に関する逸話が残っている。大正十二年――といえば、八代は六十三歳、すでに大隈内閣の海軍大臣、第二艦隊司令長官、佐世保市鎮守府司令長官をへて男爵を授けられ、七年海軍大将に昇進、軍事参議官として重きをなしていたときである。ある一夜、青年学者安岡正篤と自宅において酒をくみ交すうち、談たまたま陽明学の問題に及んで、意見が対立した。安岡正篤はこのとき二十六歳、金鶏園内に東洋思想研究所を設立し、後藤文夫、松本学、湯沢三千雄などエリート官僚の来訪も繁くなり、大川周明、永田秀次郎と拓殖大学東洋思想講座講師に招聘され、青年学徒の尊敬を一身に集めていたときである。すでに前年には『王陽明の研究』も刊行されていた。いかに相手が男爵海軍大将という大物であろうとも、学説、所信をまげるわけにはゆかない。堂々と真正面から、老提督の見解に反駁した。 席には酒が出されていた。両者ともに斗酒なお辞せずという酒豪である。酔うどころか、飲めば飲むほど頭がさえて議論いよいよ白熱、夕方五時ころにはじまって十二時になってもおわらない。そのとき八代夫人が姿を見せ、安岡青年に、 「あなた、もうお帰りください」 といった。すでに二人で五升平げており、夫人は老齢の夫の健康を案じたのである。帰ろうとすると、老提督は、 「逃げるか!」 と叱咜した。無論、逃避退散するのではない。一週間後に再会、その間熟慮反省して、まちがっていた方が弟子入りをし、相手を床の間を背にすわらせて奉ろう、という約束になった。 一週間後、八代大正は紋服に改めて安岡家を訪ね、弟子入りをするといった。 「ご冗談でしょう」 「冗談じゃない」 老提督はあくまでも真剣で、それからは三十七歳も年下の安岡を「先生」と呼び、宴席においてもかならず下座につき、昭和五年に死ぬまで師の礼をとりつづけたのであった。「長幼序あり」というのが東洋道徳の基本である。しかし学問、真理の前には階級、職業、年齢など問題にしないことこそ本当の「序」――人間の生き方、結びつき方である。これが老提督の思想であり行動方式であったと思われるが、この壮快な一挿話は、おのずと昭和初年における将軍たちの思想、行動方式を連想させるのである。 昭和六年秋「十月事件」がおきた。中野雅夫著『橋本中佐の手記』によれば、「決行計画は一夜にして政府機能を撲滅し、之れに代るべき政府者に大命降下を奏請するにあり、之が為に各大臣、政党首領、某某実業家、元老、内相、宮相等を一時に殺戩(さつせん、殺しほろぼす)し、陸軍高級者は監禁乃至殺戩し、之に使用する兵力は歩兵二十三連隊、機関銃六十丁、毒瓦斯、爆弾、飛行機等なり……」という物騒なクーデター計画で、少壮軍人有志の桜会リーダー橋本欣五郎、長勇(ちょう いさむ)ら中堅将校が中心となり、大川周明ら民間人も加わり、在京部隊の青年将校も軍隊をひきいて参加することになっていた。 ところがその計画は世間に知れ、橋本日記も「遂に宮内次官陸軍省に来り此旨を告げ、制止を乞ひたるなり。……十月十六日(十七日?)夜八時頃陸軍省陸相官邸に於て三長官其他軍首脳部集り此事件に就いて会議す>と書いている。「其夜予は将来の兵器の分配場所偵察の為各料理屋を転転とし夜三時頃築地金竜に至る。長、田中あり、突然三時過大木憲兵少佐より後刻下士官を貴官等を逮捕に向はすべく伝ふ。……夜三時ころ憲兵曹長以下数名来り憲兵隊へ連行を乞ふ」。 ところが、連行はされたものの、決して「犯人」あつかいでなかったことは、たとえば橋本らのシンパであった内田絹子の談話が物語る。「八時ごろ自動車が家の前で停ったので、そら来た、と思ったところ憲兵隊の小使いが長勇さんの名刺をもってきて、クシとタオルと石けん、それに歯ブラシを三人分持ってこいということである。……(憲兵隊長)官舎前で自動車をおりて門をはいると憲兵が二人ピストルを持って隠れていた。部屋に入ってみると憲兵隊の奥さんとお嬢さんが橋本さんらに給仕をしている。……翌日分散した情報がはいった。数日して金竜亭の女将がきて、橋本さんから芸者を三人つれてこい、と連絡があった。ちょうど松タケをもらっていたので松タケ御飯をたき、芸者をつれて千葉稲毛の海気館にいった。橋本さんは立派な部屋で習字をしていた」(前掲書) そういう優遇だけにとどまらず、彼等首謀者は謹慎させられただけで、処分らしいことは行われなかった。彼等の背景に、社会腐敗、政党の堕落=政治の貧困があったにせよ、天皇の軍隊を私兵化し、首相以下を殺害しようと企てることは、国家の法秩序無視、軍規の紊乱であったにもかかわらず、陸軍首脳部の将官たちは、これほどまでの寛大さ、わけ知りぶりを示したのであった。「問題は事件そのものや処分にあるのではなく、政治的欠陥、腐敗、国民的困窮にあるのだから、この原因をとり除かない限り処分しようがしまいが起るべき事件は起こるものだ」と中野雅夫はいうが、しかしこの無法の容認が、同種事件続発の誘因をなしたことは否定できない。このような法秩序を無視してまでの後進への譲歩、媚態は、八代六郎の親和とは似て非なるもの、「万機公論」の提唱者横井小楠が横死して六十二年目に、「問答無用」のテロリズムを復活させたのであった。老将軍らのわけ知り顔、寛大さ、「理念なき親和」には歴史を後退させる力しかなかったのである。 2019.07.19 |
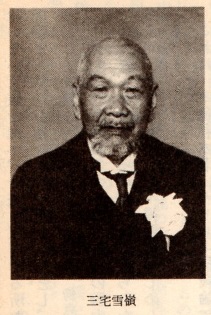
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.224~228 より 三宅 雪嶺 スゴ味のきいた筆誅 『日本』時代の雪嶺三宅雄二郎については、長谷川 如是閑や古島 一雄が語っている。如是閑の入社は、正岡子規の没した翌三十六年というから、このときの雪嶺は四十四歳、原稿は家で毛筆で書き、それを自分でもってきた。いつも角帯の着ながし、羽織をきないことが多く、頬ヒゲをのばし、髪は七分刈。急ぎ足で入ってきて、決して椅子につかず、つっ立って雑誌を読みながらゲラ刷を待っている。彼は校正も自分でやった。ときどきドモった口で、一言二言いって皆を笑わせた。 彼の「不得要領」は評判であった。何をきいても、ことさらドモったように、ウウウというだけで、決してはっきり可否をいわないからである。それをみなは彼の文章の口調をまねて、「何何するも可、せざるも可」といっていた(如是閑『ある心の自叙伝』)。 半面、原稿については厳格をきわめ、一字一句精苦の結晶である。もともと遅筆の上に、想をこらし、句をねるのでときどき締切りに間にあわない。あるとき古島一雄は、他の原稿で間にあわせ、雪嶺のものはデスクにしまいこんでいた。雪嶺は、いくら待ってもゲラ刷が出ないので、しょく字室に催促にいき、そんな原稿はきていないといわれ、古島に原稿の返却をもとめた。 「明日にまわすから、このままにしてあずかっておく」 「いや、明日もってくるからぜひ返してくれ」 その翌日返された原稿には、さらに添削の跡があった。「この苦心惨憺を経ればこそ、あの名文章ができるのだ。いわゆる名工の苦心だ」と古島は感嘆している。 遺憾ながら、筆者にはその「名文章」がむずかしすぎる。雪嶺三十四歳の作『王陽明』に接したときは、鼻血が出るようなおもいをした。とくに縦横に引用された漢文には長大息した。そういうわけで、あまり多くの文章は読んでいないけれども、その一部分にふれた印象だけでも「スゴい」というおもいは誇張でなくて実感である。 かつて、板垣 退助洋行問題というのがあった。自由党結成(明治十五年)直後、出所上明(じつは三井)の旅費をもらって外遊し、党内の馬場辰猪などから猛反撃をうけた。とくにその動機について、たとえば阿部 真之助が戦後において「彼が党の分裂を代価に払ってまで、洋行を固執しなければならないわけは、いまでもわからない」(『近代政治家評伝』)と書いた事件である。 ところが雪嶺は、「各地方における自由党員の鎮圧はいよいよ厳を加へ、寸毫も仮借する所なし。……板垣は政治運動を継続するの困難を感ぜる際後藤より洋行を勧められ、渡りに船とし、旅費の出所の如き、深く問はず……文明の政治を探討せんことを希ふ」(『同時代史』第二巻、傍点引用者)と書いている。「渡りに船と」は、比喩というよりはむしろ心理描写である。板垣の胸中を見透して、そのおく底のものをグイとつかみだいしたような感じがする。その切れ味はこちらをドキとさせる。新聞社内のつきあいにおいて、「するも可、せざるも可」の不得要領をしめしていたのは、まさに対照的、対極的なスゴ味が出ている。 これは、幸徳 秋水著『キリスト抹殺論』に書いてやった序文には、もっとはっきり出ている。秋水は四十三年春、湯河原でこれを書き、六月逮捕、十二月公判終了、原稿完成、翌年一月死刑を執行された。「秋水に死刑の宣告の下つた翌日……序を執筆、内務省より掲載を禁ぜられる」(『同時代史』第六巻、三宅雪嶺年譜)。 大逆事件の首魁の本に序文を書いてやる、ということ自体が、すでに相当の覚悟を要する。雪嶺は五十二歳、思想的には秋水と反対で、同志的義務感に殉ずる必要もなかった。それをあえてした。そして、たとえばその一節に、「秋水は既に国家に在りてはふ忠、剰へ大不忠。家族に在りて不孝、剰へ大不孝。不忠不孝のなに於て死を求めて死に就く。悪とせんか、愚とせんか、誠に適当なる形容詞なきに苦しむも、窮鼠と社鼠と孰か択ぶべしとする」(傍点引用者)という表現は、ズバリと「何か」を斬り捨てている。その「なにか」とは「窮鼠」「社鼠」の用語から、推測もむずかしくない。とくに「社鼠」とは、「やしろに巣くうねずみ」の意味から転じて、「主君の側にいる小人のたとえ」である。「窮鼠」が秋水ならば、「社鼠」は体制側のエリートたち、ぬくぬくと肥えふとる元勲や閣僚たちを諷するものである。そういう連中と秋水を対比した場合、人間の生き方としてどちらが「悪」か「愚」かわからない、といっているのである。まことに痛烈無比、腐敗した特権階級へのいのちがけの筆誅であったといえる。秋水は「先生の慈悲実に骨身にしみて嬉しく何となく暗涙が催された。僕はこの引導により十分の歓喜満足をもって成仏する」と高嶋米峰あての手紙に書いたのである。 大正十二年雪嶺六十四歳のとき、雑誌『我観』創刊(第一号は十月十五日)、十五年一月から同誌上に「同時代観」第一篇「万延元年」をのせ、以後二十年間つづけて「昭和二十年」におよんだ(のち『同時代史』と改めて六巻刊行)。この間に長男の上慮の事故死(六十九歳のとき)、長女(中野 正剛妻)の病死(七十五歳のとき)、妻竜子(花圃)の病死(八十四歳のとき)、女婿中野の自刃(同)のほか、空襲、病気もおそったが、その筆をうばうことはできなかった。そしてライフワークとよぶにふさわしいこの仕事を完成してもなお闘志満々、新たに長篇をはじめようとした。「構想は頭の中に去来して居り、両手で頬を押さえて日当たりの良い所にすわって想を練るのが普通であった」よ孫中野泰雄は書いている。 二十一年二十五日、約二時間、床の上に横臥したまま「文化創造への参照」の冒頭部分を口述し、「十四枚、(注、二百字)もうそんなになったのかと、うれしそうであった。しかし翌日二時ごろから容態一変、深い眠りに入ったままついに覚めなかった。文字どおり眠るような大往生」であった。如是閑は「このように雪嶺の生涯は郷里(注、金沢)の白山を象徴したと思われる雪嶺のなにふさわしい孤高の生涯であったが、彼の周囲からは古島一雄、内藤 湖南、田岡 嶺雲、国府 犀東らの人材が輩出した。かくいう筆者もその一人である。孤高ではあったが、数多い同志、友人後進を、そして愛読者を持った生涯はまた幸福であったといえないこともなかろう」と書いている。「いえないこともなかろう」どころか、これこそ文人の本懐ではないか、と筆者は考える。
谷沢 永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.130~131 人は善くも言われ、悪くも言われるのがよい 三宅 雪嶺『世の中』 三宅 雪嶺の話術は淡々として平易であるが、実は人を鼓舞するところもっとも深い。読者の気宇を高めるというはなはだ難しい効能においては、近代のあらゆる著作家を見渡したところ、三宅雪嶺と幸田露伴をもって双璧と見做してよいであろう。 雪嶺は世の『毀誉褒貶』に思いを致し、「毀誉褒貶の巷に立ち、善くも言われ、悪くも言われるのは性格を鍛錬するに与かって居る」と断言する。 そして「評判は何でも宜い、俺は俺のなす所さえ為せば宜いと云うのは、其(その)評判が利害に関係せぬ限りに於てである。一旦、利害に関係すれば其恐るる事、虎よりも甚だしい」という調子で、雪嶺の真骨頂は温和の辛辣にある。 雪嶺の一大特色は人間の生涯を、有為転変の連続として見る視野の大きさである。――「人は善くも言われ、悪くも言われるのがよい。善くも言わるる事に慣れたものは少しばかり悪く言われて腹立て愚を現す事がある。悪く言われ続いた者は僻んで善い事を為なくなる」 しかし「人の一生は種々の波瀾がある、己一身は同一種の人物であるが、世間との関係が様々に変ずる」。この「世間との関係」こそが褒貶問題の起源なのだ。 結局のところ人間は誰でも、「時として善く言われ時として悪く言われる」ものなので、悪く言われるのをわれるのを完全に防ぐ方法は見出し難い。 だが、「人の噂も七十五日、善く言われたとて当てにならず、悪く言われたとて当てにならぬ。が、煙の起るのはただでは起きぬ、当てにならぬ所に何事かある」。それは自分が無意識のうちに、煽いだ火種に基くに違いない。 恐らく人間は初め悪く言われて、当初は不可解であった理由を探り当てようと、努力するうちに成長するのであろう。同時にまたいかなる悪口にも退かず、毅然として動かぬ度胸も必要である。「評判ばかり心配するのも変なものである」と見る雪嶺は、「錬磨に錬磨する間に自然に兼合(かねあい)が出来る」のだと説く。
プロフィル:(1860年~1945)哲学者・評論家。歌人三宅 花圃(みやけ かほ)の夫。石川県生。なは雄二郎。東大卒。志賀重昂(しが しげたか)らと政教社を結成し、雑誌「日本人」を創刊。国粋主義に基づく社会批判を行なう一方、哲学的な著述でもなをあらわし、「中央公論」等諸誌に多彩な論説を発表した。のち政教社を離れ、中野 正剛と「我観」を創刊した。文化勲章受章。回想録『同時代史』等著書多数。
※参考図書:小島 直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.182~187 第二十七話 いのちがけの筆誅
谷沢永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.160~161 兵は拙速を尚ぶと云うが、兵のみでなはない。多くの事は拙速を貴んで居る。巧みでも遅くては必要がなくなって仕舞う。熟考の上でとか、篤と考えてとか云う事はせぬ方に慣れを作るが宜い 三宅 雪嶺『世の中』
参考:「兵は拙速なるを聞くも、未だ巧久なる賭ざるなり。」(読み下し)。 戦争には拙速――まずくともすばやくやる――というのはあるが、巧久――うまく長びく――という例はまだ無い。(口語訳) 『孫 子』(岩波文庫)金谷 治訳注 1984年6月20日 第24刷発行 P.28
「熟考と速断」と題するこの文章は、「考え過ごしては事は出来ぬ」との小見出しを掲げて、次の如く悠然と雪嶺調に説き始める。 ――「無鉄砲とか、盲滅法とか云う事は、皆な悪い事になって居る。後悔先に立たぬとも謂う。或は此類の事を板鼻主義となづける。板塀に鼻が閊えるまで先が分からぬのを意味するのである。向う見ずは実に危険至極である。が、危険として考え過ぎると、事が出来なくなる。熟考の上でとか、篤と考えてとか云う事を言うが、其割合に事が能く行くとも限らぬ」。つまり「熟考」は、要するにわが国で特に頻用される逃口上で、"当り障りなく"を第一に念じての拒絶である。個人間の場合だったら有無相通じて結構でもあろうが、この牢固たる習慣が公機関に持ち込まれると支障を来たす。 ――「役所の事務の運ばぬのは様々の事情もあるが、是等の事が与って居らぬとはせぬ。漢字等閑(なおざり)にせぬと云うのではあるが、成る可く判断を避けようと云うに過ぎぬ」。出来れば難題を自分以外の者に押しつけ、判断の責任を慎重に免れようと企る。仮にある判断が正しくて効果を挙げても、役所の機構ではどのようにも顕彰されず、失敗のみが大きく取り上げられるのだから、誰もが石橋を叩いてそれども渡らぬ。 いずれにせよ「判断を延ばすのは悪い習慣である。速かに判断を下すと重味がないような懸念をする」。そのような「慎重の態度」よりも、事態を打破するための巧みな方法が別に控えている。 ――「無鉄砲だの盲滅法だのと云うのは悪い事になって居るが、時に依るとそれで勝つ事もある。あれの無鉄砲には適わぬ盲蛇に怖じぬで致し方がないとか言って、開けて通すような場合もある」。人間の長い一生にうちには、何回か「無鉄砲」で事を裁決せねばならず、その勘が働かなくては進歩も成功も望めぬであろう。 2010.03.02 |

▼後世への最大遺物 ▼デンマルク国の話(以上は岩波文庫一冊にまとめられています。
はしがき この小冊子は、明治二十七年七月相州箱根駅において開設せられしキリスト教徒第六夏期学校において述べし余《よ》の講話を、同校委員諸子の承諾を得てここに印刷に附せしものなり。 事、キリスト教と学生とにかんすること多し、しかれどもまた多少一般の人生問題を論究せざるにあらず、これけだし余の親友京都便利堂主人がしいてこれを発刊せしゆえなるべし、読者の寛容を待つ。 明治三十年六月二十日 東京青山において 内村鑑三 再版に附する序言 一篇のキリスト教的演説、別にこれを一書となすの必要なしと思いしも、前発行者の勧告により、印刷に附して世に公《おおやけ》にせしに、すでに数千部を出《いだ》すにいたれり、ここにおいて余はその多少世道人心を裨益《ひえき》することもあるを信じ、今また多くの訂正を加えて、再版に附することとはなしぬ、もしこの小冊子にしてなお新福音を宣伝するの機械となるを得ば余《よ》の幸福何ぞこれに如《し》かん。 明治三十二年十月三十日 東京角筈村において 内村鑑三 この講演は明治二十七年、すなわち日清戦争のあった年、すなわち今より三十一年前、私がまだ三十三歳の壮年であったときに、海老な《えびな》弾正《だんじょう》君司会のもとに、箱根山上、蘆の湖の畔《ほとり》においてなしたものであります。その年に私の娘のルツ子が生まれ、私は彼女を彼女の母とともに京都の寓居に残して箱根へ来て講演したのであります。その娘はすでに世を去り、またこの講演を一書となして初めて世に出した私の親友京都便利堂主人中村弥左衛門君もツイこのごろ世を去りました。その他この書成って以来の世の変化は非常であります。多くの人がこの書を読んで志を立てて成功したと聞きます。その内に私と同じようにキリスト信者になった者もすくなくないとのことであります。そして彼らの内にある者は早くすでに立派にキリスト教を「卒業」して今は背教者をもって自から任ずる者もあります。またはこの書によって信者になりて、キリスト教的文士となりて、その攻撃の鉾《ほこ》を著者なる私に向ける人もあります。実に世はさまざまであります。そして私は幸いにして今日まで生存《いきなが》らえて、この書に書いてあることに多く違《たが》わずして私の生涯を送ってきたことを神に感謝します。この小著そのものが私の「後世への最大遺物」の一つとなったことを感謝します。「天地無始終《てんちしじゅうなく》、人生有生死《じんせいせいしあり》」であります。しかし生死ある人生に無死の生命を得るの途が供えてあります。天地は失《う》せても失せざるものがあります。そのものをいくぶんなりと握るを得て生涯は真の成功であり、また大なる満足であります。私は今よりさらに三十年生きようとは思いません。しかし過去三十年間生き残ったこの書は今よりなお三十年あるいはそれ以上に生き残るであろうとみてもよろしかろうと思います。終りに臨《のぞ》んで私はこの小著述をその最初の出版者たる故中村弥左衛門君に献じます。君の霊の天にありて安からんことを祈ります。 大正十四年(一九二五年)二月二十四日 東京市外柏木において 内村鑑三 夏期演説 後世への最大遺物 第一回 時は夏でございますし、処《ところ》は山の絶頂でございます。それでここで私が手を振り足を飛ばしまして私の血に熱度を加えて、諸君の熱血をここに注ぎ出すことはあるいは私にできないことではないかも知れません、しかしこれは私の好まぬところ、また諸君もあまり要求しないところだろうと私は考えます。それでキリスト教の演説会で演説者が腰を掛けて話をするのはたぶんこの講師が嚆矢《こうし》であるかも知れない(満場大笑)、しかしながらもしこうすることが私の目的に適《かな》うことでございますれば、私は先例を破ってここであなたがたとゆっくり腰を掛けてお話をしてもかまわないと思います。これもまた破壊党の所業だと思《おぼ》し召されてもよろしゅうございます(拍手喝采)。 そこで私は「後世への最大遺物」という題を掲げておきました。もしこのことについて私の今まで考えましたことと今感じますることとをみな述べまするならば、いつもの一時間より長くなるかも知れませぬ。もし長くなってつまらなくなったなら勝手にお帰りなすってください、私もまたくたびれましたならばあるいは途中で休みを願うかも知れませぬ。もしあまり長くなりましたならば、明朝の一時間も私の戴いた時間でございますからそのときに述べるかも知れませぬ。ドウゾこういう清い静かなところにありまするときには、東京やまたはその他の騒がしいところでみな気の立っているところでするような騒がしい演説を私はしたくないです。私はここで諸君と膝を打ち合せて私の所感そのままを演説し、また諸君の質問にも応じたいと思います。 この夏期学校に来ますついでに私は東京に立ち寄り、そのとき私の親爺《おやじ》と詩の話をいたしました。親爺が山陽《さんよう》の古い詩を出してくれました。私が初めて山陽の詩を読みましたのは、親爺からもらったこの本でした(本を手に持って)。でこの夏期学校にくるついでに、その山陽の本を再《ふたた》び持ってきました。そのなかに私の幼《ちい》さいときに私の心を励ました詩がございます。その詩は諸君もご承知のとおり山陽の詩の一番初めに載《の》っている詩でございます、「十有三春秋《じゅうゆうさんしゅんじゅう》、逝者已如水《ゆくものはすでにみずのごとし》、天地無始終《てんちしじゅうなく》、人生有生死《じんせいせいしあり》、安得類古人《いずくんぞこじんにるいして》、千載列青史《せんざいせいしにれっするをえん》」。有名の詩でございます、山陽が十三のときに作った詩でございます。それで自分の生涯を顧みてみますれば、まだ外国語学校に通学しておりまする時分《じぶん》にこの詩を読みまして、私も自《おのず》から同感に堪《た》えなかった。私のようにこんなに弱いもので子供のときから身体《からだ》が弱《よお》うございましたが、こういうような弱い身体であって別に社会に立つ位置もなし、また私を社会に引ッ張ってくれる電信線もございませぬけれども、ドウゾ私も一人の歴史的の人間になって、そうして千載青史に列するを得《う》るくらいの人間になりたいという心がやはり私にも起ったのでございます。その欲望はけっして悪い欲望とは思っていませぬ。私がそのことを父に話し友達に話したときに彼らはたいへん喜んだ。「汝にそれほどの希望があったならば汝の生涯はまことに頼もしい」といって喜んでくれました。ところがふ意にキリスト教に接し、通常この国において説かれましたキリスト教の教えを受けたときには、青年のときに持ったところの千載青史に列するを得んというこの欲望が大分なくなってきました。それで何となく厭世的《えんせいてき》の考えが起ってきた。すなわち人間が千載青史に列するを得んというのは、まことにこれは肉欲的、ふ信者的、heathen《ヒーゼン》 的の考えである、クリスチャンなどは功みょうを欲することはなすべからざることである、われわれは後世になを伝えるとかいうことは、根コソギ取ってしまわなければならぬ、というような考えが出てきました。それゆえに私の生涯は実に前の生涯より清い生涯になったかも知れませぬ。けれども前のよりはつまらない生涯になった。マーどうかなるだけ罪を犯さないように、なるだけ神に逆らって汚《けが》らわしいことをしないように、ただただ立派にこの生涯を終ってキリストによって天国に救われて、未来永遠の喜びを得んと欲する考えが起ってきました。 そこでそのときの心持ちはなるほどそのなかに一種の喜びがなかったではございませぬけれども、以前の心持ちとは正反対の心持ちでありました。そうしてこの世の中に事業をしよう、この世の中に一つ旗を挙げよう、この世の中に立って男らしい生涯を送ろう、という念がなくなってしまいました。ほとんどなくなってしまいましたから、私はいわゆる坊主臭い因循的《いんじゅんてき》の考えになってきました。それでまた私ばかりでなく私を教えてくれる人がソウでありました。たびたび……ここには宣教師はおりませぬから少しは宣教師の悪口をいっても許してくださるかと思いまするが……宣教師のところに往《い》って私の希望を話しますると、「あなたはそんな希望を持ってはいけませぬ、そのようなことはそれは欲心でございます、それはあなたのまだキリスト教に感化されないところの心から起ってくるのです」というようなことを聞かされないではなかった。私は諸君たちもソウいうような考えにどこかで出会ったことはないことはないだろうと思います。なるほど千載青史に列するを得んということは、考えのいたしようによってはまことに下等なる考えであるかも知れませぬ。われわれがなをこの世の中に遺《のこ》したいというのでございます。この一代のわずかの生涯を終ってそのあとは後世の人にわれわれのなを褒め立ってもらいたいという考え、それはなるほどある意味からいいますると私どもにとっては持ってはならない考えであると思います。ちょうどエジプトの昔の王様が己《おの》れのなが万世に伝わるようにと思うてピラミッドを作った、すなわち世の中の人に彼は国の王であったということを知らしむるために万民の労力を使役して大きなピラミッドを作ったというようなことは、実にキリスト信者としては持つべからざる考えだと思われます。有名な天下の糸平が死ぬときの遺言《ゆいごん》は「己れのために絶大の墓を立てろ>ということであったそうだ。そうしてその墓には天下の糸平と誰か日本の有名なる人に書いてもらえと遺言した。それで諸君が東京の牛《うし》の御前《ごぜ》に往《い》ってごらんなさると立派な花崗石《かこうせき》で伊藤博文さんが書いた「天下之糸平」という碑が建っております。それは、その千載にまで天下の糸平をこの世の中に伝えよというた糸平の考えは、私はクリスチャン的の考えではなかろうと思います。またそういう例がほかにもたくさんある。このあいだアメリカのある新聞で見ましたに、ある貴婦人で大金持の寡婦《やもめ》が、「私はドウゾ死んだ後に私のなを国人に覚えてもらいたい、しかし自分の持っている金を学校に寄附するとかあるいは病院に寄附するとかいうことは普通の人のなすところなれば、私は世界中にないところの大なる墓を作ってみたい、そうして千載に記憶されたい」という希望を起した。先日その墓が成ったそうでございます。ドンナに立派な墓であるかは知りませぬけれども、その計算に驚いた、二百万ドルかかったというのでございます。二百万ドルの金をかけて自分の墓を建ったのは確かにキリスト教的の考えではございません。 しかしながらある意味からいいますれば、千載青史に列するを得んという考えは、私はそんなに悪い考えではない、ないばかりでなくそれは本当の意味にとってみまするならば、キリスト教信者が持ってもよい考えでございまして、それはキリスト信者が持つべき考えではないかと思います、なお、われわれの生涯の解釈から申しますると、この生涯はわれわれが未来に往く階段である。ちょうど大学校にはいる前の予備校である。もしわれわれの生涯がわずかこの五十年で消えてしまうものならば実につまらぬものである。私は未来永遠に私を準備するためにこの世の中に来て、私の流すところの涙も、私の心を喜ばしむるところの喜びも、喜怒哀楽《きどあいらく》のこの変化というものは、私の霊魂をだんだんと作り上げて、ついに私は死なない人間となってこの世を去ってから、もっと清い生涯をいつまでも送らんとするは、私の持っている確信でございます。しかしながらそのことは純粋なる宗教問題でございまして、それは私の今晩あなたがたにお話をいたしたいことではございません。 しかしながら私にここに一つの希望がある。この世の中をズット通り過ぎて安らかに天国に往き、私の予備学校を卒業して天国なる大学校にはいってしまったならば、それでたくさんかと己れの心に問うてみると、そのときに私の心に清い欲が一つ起ってくる。すなわち私に五十年の命をくれたこの美しい地球、この美しい国、この楽しい社会、このわれわれを育ててくれた山、河、これらに私が何も遺さずには死んでしまいたくない、との希望が起ってくる。ドウゾ私は死んでからただに天国に往くばかりでなく、私はここに一つの何かを遺して往きたい。それで何もかならずしも後世の人が私を褒めたってくれいというのではない、私の名誉を遺したいというのではない、ただ私がドレほどこの地球を愛し、ドレだけこの世界を愛し、ドレだけ私の同胞を思ったかという記念物をこの世に置いて往きたいのである、すなわち英語でいう Memento《メメント》 を残したいのである。こういう考えは美しい考えであります。私がアメリカにおりましたときにも、その考えがたびたび私の心に起りました。私は私の卒業した米国の大学校を去るときに、同志とともに卒業式の当日に愛樹を一本校内に椊えてきた。これは私が四年も育てられた私の学校に私の愛情を遺しておきたいためであった。なかには私の同級生で、金のあった人はそればかりでは満足しないで、あるいは学校に音楽堂を寄附するもあり、あるいは書籍館を寄附するもあり、あるいは運動場を寄附するもありました。 しかるに今われわれは世界というこの学校を去りまするときに、われわれは何もここに遺さずに往くのでございますか。その点からいうとやはり私には千載青史に列するを得んという望みが残っている。私は何かこの地球に Memento を置いて逝《ゆ》きたい、私がこの地球を愛した証拠を置いて逝きたい、私が同胞を愛した記念碑を置いて逝きたい。それゆえにお互いにここに生まれてきた以上は、われわれが喜ばしい国に往くかも知れませぬけれども、しかしわれわれがこの世の中にあるあいだは、少しなりともこの世の中を善くして往きたいです。この世の中にわれわれの Memento を遺して逝きたいです。有名なる天文学者のハーシェルが二十歳ばかりのときに彼の友人に語って「わが愛する友よ、われわれが死ぬときには、われわれが生まれたときより、世の中を少しなりともよくして往こうではないか」というた。実に美しい青年の希望ではありませんか。「この世の中を、私が死ぬときは、私の生まれたときよりは少しなりともよくして逝こうじゃないか」と。ハーシェルの伝記を読んでごらんなさい。彼はこの世の中を非常によくして逝った人であります。今まで知られない天体を全《まった》く描いて逝った人であります。南半球の星を、何年間かアフリカの希望峰椊民地に行きまして、スッカリ図に載せましたゆえに、今日の天文学者の知識はハーシェルによってドレだけ利益を得たか知れない。それがために航海が開け、商業が開け、人類が進歩し、ついには宣教師を外国にやることが出き、キリスト教伝播の直接間接の助けにどれだけなったか知れませぬ。われわれもハーシェルと同じに互いにみな希望 Ambition《アムビション》 を遂《と》げとうはございませぬか。われわれが死ぬまでにはこの世の中を少しなりとも善くして死にたいではありませんか。何か一つ事業を成し遂げて、できるならばわれわれの生まれたときよりもこの日本を少しなりともよくして逝きたいではありませんか。この点についてはわれわれ皆々同意であろうと思います。 それでこの次は遺物のことです。何を置いて逝こう、という問題です。何を置いてわれわれがこの愛する地球を去ろうかというのです。そのことについて私も考えた、考えたばかりでなくたびたびやってみた。何か遺したい希望があってこれを遺そうと思いました。それで後世への遺物もたくさんあるだろうと思います。それを一々お話しすることはできないことでございます。けれども、このなかに第一番にわれわれの思考に浮ぶものからお話しをいたしたいと思います。 後世へわれわれの遺すもののなかにまず第一番に大切のものがある。何であるかというと金です。われわれが死ぬときに遺産金を社会に遺して逝く、己の子供に遺して逝くばかりでなく、社会に遺して逝くということです、それは多くの人の考えにあるところではないかと思います。それでソウいうことをキリスト信者の前にいいますると、金《かね》を遺すなどということは実につまらないことではないかという反対がジキに出るだろうと思います。私は覚えております。明治十六年に初めて札幌から山男になって東京に出てきました。その時分に東京には奇体《きたい》な現象があって、それをなづけてリバイバルというたのです。その時分私は後世に何を遺さんかと思っておりしかというに、私は実業教育を受けたものであったから、もちろん金を遺したかった、億万の富を日本に遺して、日本を救ってやりたいという考えをもっておりました。自分には明治二十七年になったら、夏期学校の講師に選ばれるという考えは、その時分にはチットもなかったのです(満場大笑)。金を遺したい、金満家になりたい、という希望を持っておったのです。ところがこのことをあるリバイバルに非常に熱心の牧師先生に話したところが、その牧師さんに私は非常に叱られました。「金を遺したい、というイクジのない、そんなものはドウにもなるから、君は福音のために働きたまえ」というて戒《いまし》められた。しかし私はその決心を変更しなかった。今でも変更しない。金を遺すものを賤《いや》しめるような人はやはり金のことに賤しい人であります、吝嗇《けち》な人であります。金というものは、ここで金の価値について長い講釈をするには及びませぬけれども、しかしながら金というものの必要は、あなたがた十分に認めておいでなさるだろうと思います。金は宇宙のものであるから、金というものはいつでもできるものだという人に向って、フランクリンは答えて「そんなら今拵《こしら》えてみたまえ」と申しました。それで私に金などは要《い》らないというた牧師先生はドウいう人であったかというに、後で聞いてみると、やはりずいぶん金を欲しがっている人だそうです。それで金というものは、いつでも得られるものであるということは、われわれが始終持っている考えでございますけれども、実際金の要《い》るときになってから金というものは得るに非常にむずかしいものです。そうしてあるときは富というものは、どこでも得られるように、空中にでも懸っているもののように思いますけれども、その富を一つに集めることのできるものは、これは非常に神の助けを受くる人でなければできないことであります。ちょうど秋になって雁《かり》は天を飛んでいる。それは誰が捕《と》ってもよい。しかしその雁を捕ることはむずかしいことであります。人間の手に雁が十羽なり二十羽なり集まってあるならば、それに価値があります。すなわち、手の内の一羽の雀は木の上におるところの二羽の雀より貴い、というのはこのことであります。そこで金というものは宇宙に浮いているようなものでございますけれども、しかしながらそれを一つにまとめて、そうして後世の人がこれを用いることができるように溜《た》めて往かんとする欲望が諸君のうちにあるならば、私は私の満腔《まんこう》の同情をもって、イエス・キリストの御な《みな》によって、父なる神の御なによって、聖霊の御なによって、教会のために、国のために、世界のために、「君よ、金を溜めたまえ」というて、このことをその人に勧めるものです。富というものを一つにまとめるということは一大事業です。それでわれわれの今日の実際問題は社会問題であろうと、教会問題であろうと、青年問題であろうと、教育問題であろうとも、それを煎《せん》じつめてみれば、やはり金銭問題です。ここにいたって誰が金が不要だなぞというものがありますか。ドウゾ、キリスト信者のなかに金持が起ってもらいたいです、実業家が起ってもらいたいです。われわれの働くときに、われわれの後楯《うしろだて》になりまして、われわれの心を十分にわかった人がわれわれを見継《みつ》いでくれるということは、われわれの目下の必要でございます。それで金を後世に遺そうという欲望を持っているところの青年諸君が、その方に向って、神の与えたる方法によって、われわれの子孫にたくさん金を遺してくださらんことを、私は実に祈ります。アメリカの有名なるフィラデルフィアのジラードというフランスの商人が、アメリカに移住しまして、建てた孤児院を、私は見ました。これは世界第一番の孤児院です。およそ小学生徒くらいのものが七百人ばかりおります。中学、大学くらいまでの孤児をズッとならべますならば、たぶん千人以上のように覚えました。その孤児院の組織を見まするに、われわれの今日《こんにち》日本にあるところの孤児院のように、寄附金の足らないために事業がさしつかえるような孤児院ではなくして、ジラードが生涯かかって溜めた金をことごとく投じて建てたものです。ジラードの生涯を書いたものを読んでみますると、なんでもない、ただその一つの目的をもって金を溜めたのです。彼に子供はなかった、妻君も早く死んでしまった。「妻はなし、子供はなし、私には何にも目的はない。けれども、どうか世界第一の孤児院を建ってやりたい」というて、一生懸命に働いて拵《こしら》えた金で建てた孤児院でございます。その時分はアメリカ開国の早いころでありましたから、金の溜め方が今のように早くゆかなかった。しかし一生涯かかって溜めたところのものは、おおよそ二百万ドルばかりでありました。それをもってペンシルバニア州に人の気のつかぬ地面をたくさん買った。それで死ぬときに、「この金をもって二つの孤児院を建てろ、一つはおれを育ててくれたところのニューオルリーンズに建て、一つはおれの住んだところのフィラデルフィアに建てろ」と申しました。それで妙な癖があった人とみえまして、教会というものをたいそう嫌ったのです。それで「おれは別にこの金を使うことについて条件はつけないけれども、おれの建ったところの孤児院のなかに、デノミネーションすなわち宗派の教師は誰でも入れてはならぬ」という稀代《きたい》な条件をつけて死んでしまった。それゆえに、今でもメソジストの教師でも、監督教会の教師でも、組合教会の教師でも、この孤児院にははいることはお気の毒でございますけれどもできませぬ(大笑)。そのほかは誰でもそこにはいることができる。それでこの孤児院の組織のことは長いことでございますから、今ここにお話し申しませぬけれども、前に述べた二百万ドルをもって買い集めましたところの山です。それが今日のペンシルバニア州における石炭と鉄とを出す山でございます。実に今日の富はほとんど何千万ドルであるかわからない。今はどれだけ事業を拡張してもよい、ただただ拡張する人がいないだけです。それでもし諸君のうち、フィラデルフィアに往く方があれば、一番にまずこの孤児院を往って見ることをお勧め申します。 また有名なる慈善家ピーボディーはいかにして彼の大業を成したかと申しまするに、彼が初めてベルモントの山から出るときには、ボストンに出て大金持ちになろうという希望を持っておったのでございます。彼は一文なしで故郷を出てきました。それでボストンまではその時分はもちろん汽車はありませんし、また馬車があっても無銭《ただ》では乗れませぬから、ある旅籠屋《はたごや》の亭主に向い、「私はボストンまで往かなければならぬ、しかしながら日が暮れて困るから今夜泊めてくれぬか」というたら、旅籠屋の亭主が、可愛想だから泊めてやろう、というて喜んで引き受けた。けれどもそのときにピーボディーは旅籠屋の亭主に向って「無銭《ただ》で泊まることは嫌《いや》だ、何かさしてくれるならば泊まりたい」というた。ところが旅籠屋の亭主は「泊まるならば自由に泊まれ」というた。しかしピーボディーは、「それではすまぬ」というた。そうして家を見渡したところが、裏に薪がたくさん積んであった。それから「御厄介になる代りに、裏の薪を割らしてください」というて旅籠屋の亭主の承諾を得て、昼過ぎかかって夜まで薪を挽《ひ》き、これを割り、たいていこのくらいで旅籠賃に足ると思うくらいまで働きまして、そうして後に泊まったということであります。そのピーボディーは彼の一生涯を何に費《ついや》したかというと、何百万ドルという高は知っておりませぬけれども、金を溜めて、ことに黒人の教育のために使った。今日アメリカにおります黒人がたぶん日本人と同じくらいの社交的程度に達しておりますのは何であるかというに、それはピーボディーのごとき慈善家の金の結果であるといわなければなりません。私は金のためにはアメリカ人はたいへん弱い、アメリカ人は金のためにはだいぶ侵害されたる民《たみ》であるということも知っております、けれどもアメリカ人のなかに金持ちがありまして、彼らが清き目的をもっを溜めそれを清きことのために用うるということは、アメリカの今日の盛大をいたした大原因であるということだけは私もわかって帰ってきました。それでもしわれわれのなかにも、実業に従事するときにこういう目的をもって金を溜める人が出てきませぬときには、本当の実業家はわれわれのなかに起りませぬ。そういう目的をもって実業家が起りませぬならば、彼らはいくら起っても国の益になりませぬ。ただただわずかに憲法発布式のときに貧乏人に一万円……一人に五十銭か六十銭くらいの頭割をなしたというような、ソンナ慈善はしない方がかえってよいです。三菱のような何千万円というように金を溜めまして、今日まで……これから三菱は善い事業をするかと信じておりますけれども……今日まで何をしたか。彼自身が大いに勢力を得、立派な家を建て立派な別荘を建てましたけれども、日本の社会はそれによって何を利益したかというと、何一つとして見るべきものはないです。それでキリスト教信者が立ちまして、キリスト信徒の実業家が起りまして、金を儲《もう》けることは己れのために儲けるのではない、神の正しい道によって、天地宇宙の正当なる法則にしたがって、富を国家のために使うのであるという実業の精神がわれわれのなかに起らんことを私は願う。そういう実業家が今日わが国に起らんことは、神学生徒の起らんことよりも私の望むところでございます。今日は神学生徒がキリスト信者のなかに十人あるかと思うと、実業家は一人もないです。百人あるかと思うと実業家は一人もない。あるいは千人あるかと思うと、一人おるかおらぬかというくらいであります。金をもって神と国とに事《つか》えようという清き考えを持つ青年がない。よく話に聴きまするかの紀ノ国屋文左衛門が百万両溜めて百万両使ってみようなどという賤しい考えを持たないで、百万両溜めて百万両神のために使って見ようというような実業家になりたい。そういう実業家が欲しい。その百万両を国のために、社会のために遺して逝こうという希望は実に清い希望だと思います。今日私が自身に持ちたい望みです。もし自身にできるならばしたいことですが、ふしあわせにその方の伎倆は私にはありませぬから、もし諸君のなかにその希望がありますならば、ドウゾ今の教育事業とかに従事する人たちは、「汝の事業は下等の事業なり」などというて、その人を失望させぬように注意してもらいたい。またそういう希望を持った人は、神がその人に命じたところの考えであると思うて十分にそのことを自から奨励されんことを望む。あるアメリカの金持ちが「私は汝にこの金を譲り渡すが、このなかに穢《きた》ない銭《ぜに》は一文もない」というて子供に遺産を渡したそうですが、私どもはそういう金が欲しいのです。 それで後世への最大遺物のなかで、まず第一に大切のものは何であるかというに、私は金だというて、その金の必要を述べた。しかしながら何人も金を溜める力を持っておらない。私はこれはやはり一つの Genius《ジーニアス》(天才)ではないかと思います。私は残念ながらこの天才を持っておらぬ。ある人が申しまするに金を溜める天才を持っている人の耳はたいそう膨《ふく》れて下の方に垂れているそうですが、私は鏡に向って見ましたが、私の耳はたいそう縮んでおりますから、その天才は私にはないとみえます(大笑)。私の今まで教えました生徒のなかに、非常にこの天才を持っているものがある。ある奴《やつ》は北海道に一文無しで追い払われたところが、今は私に十倍もする富を持っている。「今におれが貧乏になったら、君はおれを助けろ」というておきました。実に金儲けは、やはりほかの職業と同じように、ある人たちの天職である。誰にも金を儲けることができるかということについては、私は疑います。それで金儲けのことについては少しも考えを与えてはならぬところの人が金を儲けようといたしますると、その人は非常に穢《きた》なく見えます。そればかりではない、金は後世への最大遺物の一つでございますけれども、遺しようが悪いとずいぶん害をなす。それゆえに金を溜める力を持った人ばかりでなく、金を使う力を持った人が出てこなければならない。かの有名なるグールドのように彼は生きているあいだに二千万ドル溜めた。そのために彼の親友四人までを自殺せしめ、アチラの会社を引き倒し、コチラの会社を引き倒して二千万ドル溜めた。ある人の言に「グールドが一千ドルとまとまった金を慈善のために出したことはない」と申しました。彼は死ぬときにその金をどうしたかというと、ただ自分の子供にそれを分け与えて死んだだけであります。すなわちグールドは金を溜めることを知って、金を使うことを知らぬ人であった。それゆえに金を遺物としようと思う人には、金を溜める力とまたその金を使う力とがなくてはならぬ。この二つの考えのない人、この二つの考えについて十分に決心しない人が、金を溜めるということは、はなはだ危険のことだと思います。 さて、私のように金を溜めることの下手なもの、あるいは溜めてもそれが使えない人は、後世の遺物に何を遺そうか。私はとうてい金持ちになる望みはない、ゆえにほとんど十年前にその考えをば捨ててしまった。それでもし金を遺すことができませぬならば、何を遺そうかという実際問題が出てきます。それで私が金よりもよい遺物は何であるかと考えて見ますと、事業です。事業とは、すなわち金を使うことです。金は労力を代表するものでありますから、労力を使ってこれを事業に変じ、事業を遺して逝くことができる。金を得る力のない人で事業家はたくさんあります。金持ちと事業家は二つ別物のように見える。商売する人と金を溜める人とは人物が違うように見えます。大阪にいる人はたいそう金を使うことが上手であるが、京都にいる人は金を溜めることが上手である。東京の商人に聞いてみると、金を持っている人には商売はできない、金のないものが人の金を使《つこ》うて事業をするのであると申します。純粋の事業家の成功を考えてみまするに、けっして金ではない。グールドはけっして事業家ではない。バンダービルトはけっして事業家ではない。バンダービルトは非常に金を作ることが上手でございました。そして彼は他の人の事業を助けただけであります。有名のカルフォルニアのスタンフォードは、たいへん金を儲けることが上手であった。しかしながらそのスタンフォードに三人の友人がありました。その友人のことは面白い話でございますが、時がないからお話をしませぬけれども、金を儲けた人と、金を使う人と、数々あります。それですから金を溜めて金を遺すことができないならば、あるいは神が私に事業をなす天才を与えてくださったかも知れませぬ。もしそうならば私は金を遺すことができませぬとも、事業を遺せば充分満足します。それで事業をなすということは、美しいことであるはもちろんです。ドウいう事業が一番誰にもわかるかというと土木的の事業です。私は土木学者ではありませぬけれども、土木事業を見ることが非常に好きでございます。一つの土木事業を遺すことは、実にわれわれにとっても快楽であるし、また永遠の喜びと富とを後世に遺すことではないかと思います。今日も船に乗って、湖水の向こうまで往きました。その南の方に当って水門がある。その水門というは、山の裾をくぐっている一つの隧道《ずいどう》であります。その隧道を通って、この湖水の水が沼津の方に落ちまして、二千石|乃至《ないし》三千石の田地を灌漑しているということを聞きました。昨日ある友人に会うて、あの穴を掘った話を聞きました。その話を聞いたときに私は実に嬉しかった。あの穴を掘った人は今からちょうど六百年も前の人であったろうということでござ」ますが、誰が掘ったかわからない。ただこれだけの伝説が遺っているのでございます。すなわち箱根のある近所に百姓の兄弟があって、まことに沈着であって、その兄弟が互いに相語っていうに、「われわれはこの有難き国に生まれてきて、何か後世に遺して逝かなければならぬ、それゆえに何かわれわれにできることをやろうではないか」と。しかし兄なる者はいうた。「われわれのような貧乏人で、貧乏人には何も大事業を遺して逝くことはできない>というと、弟が兄に向っていうには、「この山をくり抜いて湖水の水をとり、水田を興してやったならば、それが後世への大なる遺物ではないか」というた。兄は「それは非常に面白いことだ、それではお前は上の方から掘れ、おれは下の方から掘ろう。一生涯かかってもこの穴を掘ろうじゃないか」といって掘り始めた。それでドウいうふうにしてやりましたかというと、そのころは測量器械もないから、山の上に標《しるし》を立って、両方から掘っていったとみえる。それから兄弟が生涯かかって何もせずに……たぶん自分の職業になるだけの仕事はしたでございましょう……兄弟して両方からして、毎年毎年掘っていった。何十年でございますか、その年は忘れましたけれども、下の方から掘ってきたものは、湖水の方から掘っていった者の四尺上に往ったそうでございます。四尺上に往きましたけれども御承知の通り、水は高うございますから、やはり竜吐水《りゅうどすい》のように向こうの方によく落ちるのです。生涯かかって人が見ておらないときに、後世に事業を遺そうというところの奇特《きとく》の心より、二人の兄弟はこの大事業をなしました。人が見てもくれない、褒めてもくれないのに、生涯を費してこの穴を掘ったのは、それは今日にいたってもわれわれを励ます所業ではありませぬか。それから今の五ヵ村が何千石だかどれだけ人口があるか忘れましたが、五ヵ村が頼朝《よりとも》時代から今日にいたるまで年々米を取ってきました。ことに湖水の流れるところでありますから、旱魃《かんばつ》ということを感じたことはございません。実にその兄弟はしあわせの人間であったと思います。もし私が何にもできないならば、私はその兄弟に真似たいと思います。これは非常な遺物です。たぶん今往ってみましたならば、その穴は長さたぶん十町かそこらの穴でありましょうが、そのころは煙硝《えんしょう》もない、ダイナマイトもないときでございましたから、アノ穴を掘ることは実に非常なことでございましたろう。 大阪の天保山を切ったのも近ごろのことでございます。かの安治川《あじがわ》を切った人は実に日本にとって非常な功績をなした人であると思います。安治川があるために大阪の木津川の流れを北の方に取りまして、水を速くして、それがために水害の患《うれい》を取り除いてしまったばかりでなく、深い港を拵《こしら》えて九州、四国から来る船をことごとくアソコに繋《つな》ぐようになったのでございます。また秀吉の時代に切った吉野川は昔は大阪の裏を流れておって人民を艱《なや》ましたのを、堺と住吉の間に開鑿《かいさく》しまして、それがために大和川の水害というものがなくなって、何十ヵ村という村が大阪の城の後ろにできました。これまた非常な事業です。それから有名の越後の阿賀川《あがのがわ》を切ったことでございます。実にエライ事業でございます。有名の新発田《しばた》の十万石、今は日本においてたぶん富の中心点であるだろうという所でございます。これらの大事業を考えてみるときに私の心のなかに起るところの考えは、もし金を後世に遺すことができぬならば、私は事業を遺したいとの考えです。また土木事業ばかりでなく、その他の事業でももしわれわれが精神を籠《こ》めてするときは、われわれの事業は、ちょうど金に利息がつき、利息に利息が加わってきて、だんだん多くなってくるように、一つの事業がだんだん大きくなって、終りには非常なる事業となります。 事業のことを考えますときに、私はいつでも有名のデビッド・リビングストンのことを思い出さないことはない。それで諸君のうち英語のできるお方に私はスコットランドの教授ブレーキの書いた“Life《ライフ》 and《アンド》 Letters《レターズ》 of《オブ》 David《デビッド》Livingstone《リビングストン》”という本を読んでごらんなさることを勧めます。私一個人にとっては聖書のほかに、私の生涯に大刺激を与えた本は二つあります。一つはカーライルの『クロムウェル伝』であります。そのことについては私は後にお話をいたします。それからその次にこのブレーキ氏の書いた『デビッド・リビングストン』という本です。それでデビッド・リビングストンの一生涯はどういうものであったかというと、私は彼を宗教家あるいは宣教師と見るよりは、むしろ大事業家として尊敬せざるをえません。もし私は金を溜めることができなかったならば、あるいはまた土木事業を起すことができぬならば、私はデビッド・リビングストンのような事業をしたいと思います。この人はスコットランドのグラスゴーの機屋《はたや》の子でありまして、若いときからして公共事業に非常に注意しました。「どこかに私は」……デビッド・リビングストンの考えまするに……「どこかに私は一事業を起してみたい」という考えで、始めは支那《しな》に往きたいという考えでありまして、その望みをもって英国の伝道会社に訴えてみたところが、支那に遣《や》る必要がないといって許されなかった。ついにアフリカにはいって、三十七年間己れの生命をアフリカのために差し出し、始めのうちはおもに伝道をしておりました。けれども彼は考えました、アフリカを永遠に救うには今日は伝道ではいけない。すなわちアフリカの内地を探検して、その地理を明かにしこれに貿易を開いて勢力を与えねばいけぬ、ソウすれば伝道は商売の結果としてかならず来るに相違ない。そこで彼は伝道を止めまして探検家になったのでございます。彼はアフリカを三度縦横に横ぎり、わからなかった湖水もわかり、今までわからなかった河の方向も定められ、それがために種々の大事業も起ってきた。しかしながらリビングストンの事業はそれで終らない、スタンレーの探検となり、ペーテルスの探検となり、チャンバーレンの探検となり、今日のいわゆるアフリカ問題にして一つとしてリビングストンの事業に原因せぬものはないのでございます。コンゴ自由国、すなわち欧米九ヵ国が同盟しまして、プロテスタント主義の自由国をアフリカの中心に立つるにいたったのも、やはりリビングストンの手によったものといわなければなりませぬ 今日の英国はエライ国である、今日のアメリカの共和国はエライ国であると申しますが、それは何から始まったかとたびたび考えてみる。それで私は尊敬する人について少しく偏するかも知れませぬが、もし偏しておったならばそのようにご裁判を願います、けれども私の考えまするには、今日のイギリスの大なるわけは、イギリスにピューリタンという党派が起ったからであると思います。アメリカに今日のような共和国の起ったわけは何であるか、イギリスにピューリタンという党派が起ったゆえである。しかしながらこの世にピューリタンが大事業を遺したといい、遺しつつあるというは何のわけであるかというと、何でもない、このなかにピューリタンの大将がいたからである。そのオリバー・クロムウェルという人の事業は、彼が政権を握ったのはわずか五年でありましたけれども、彼の事業は彼の死とともにまったく終ってしまったように見えますけれども、ソウではない。クロムウェルの事業は今日のイギリスを作りつつあるのです。しかのみならず英国がクロムウェルの理想に達するにはまだズッと未来にあることだろうと思います。彼は後世に英国というものを遺した。合衆国というものを遺した。アングロサクソン民族がオーストラリアを従え、南アメリカに権力を得て、南北アメリカを支配するようになったのも彼の遺蹟といわなければなりませぬ。 第二回 昨晩は後世へわれわれが遺して逝くべきものについて、まず第一に金のことの話をいたし、その次に事業のお話をいたしました。ところで金を溜める天才もなし、またそれを使う天才もなし、かつまた事業の天才もなし、また事業をなすための社会の位地もないときには、われわれがこの世において何をいたしたらよろしかろうか。事業をなすにはわれわれに神から受けた特別の天才が要《い》るばかりでなく、また社会上の位地が要る。われわれはあるときはかの人は天才があるのに何故なんにもしないでいるかといって人を責めますけれども、それはたびたび起る酷《こく》な責め方だと思います。人は位地を得ますとずいぶんつまらない者でも大事業をいたすものであります。位地がありませぬとエライ人でも志を抱《いだ》いて空《むな》しく山間に終ってしまった者もたくさんあります。それゆえに事業をもって人を評することはできないことは明かなることだろうと思います。それゆえに私に事業の天才もなし、またこれをなすの位地もなし、友達もなし、社会の賛成もなかったならば、私は身を滅ぼして死んでしまい、世の中に何も遺すことはできないかという問題が起ってくる。それでもし私に金を溜めることができず、また社会は私の事業をすることを許さなければ、私はまだ一つ遺すものを持っています。何であるかというと、私の思想です。もしこの世の中において私が私の考えを実行することができなければ、私はこれを実行する精神を筆と墨とをもって紙の上に遺すことができる。あるいはそうでなくとも、それに似たような事業がございます。すなわち私がこの世の中に生きているあいだに、事業をなすことができなければ、私は青年を薫陶《くんとう》して私の思想を若い人に注いで、そうしてその人をして私の事業をなさしめることができる。すなわちこれを短くいいますれば、著述をするということと学生を教えるということであります。著述をすることと教育のことと二つをここで論じたい。しかしだいぶ時がかかりますからただその第一すなわち思想を遺すということについて私の文学的観察をお話ししたいと思います。すなわちわれわれの思想を遺すには今の青年にわれわれの志を注いでゆくも一つの方法でございますけれども、しかしながら思想そのものだけを遺してゆくには文学によるほかない。それで文学というものの要はまったくそこにあると思います。文学というものはわれわれの心に常に抱いているところの思想を後世に伝える道具に相違ない。それが文学の実用だと思います。それで思想の遺物というものの大なることはわれわれは誰もよく知っていることであります。思想のこの世の中に実行されたものが事業です。われわれがこの世の中で実行することができないからして、種子《たね》だけを播《ま》いて逝こう、「われは恨みを抱いて、慷慨《こうがい》を抱いて地下に下らんとすれども、汝らわれの後に来る人々よ、折あらばわが思想を実行せよ」と後世へ言い遺すのである。それでその遺物の大《おお》いなることは実に著しいものであります われわれのよく知っているとおり、二千年ほど前にユダヤのごくつまらない漁夫や、あるいはまことに世の中に知られない人々が、『新約聖書』という僅かな書物を書いた。そうしてその小さい本がついに全世界を改めたということは、ここにいる人にはお話しするほどのことはない、みなご存じであります。また山陽という人は勤王論を作った人であります。先生はドウしても日本を復活するには日本をして一団体にしなければならぬ。一団体にするには日本の皇室を尊んでそれで徳川の封建政治をやめてしまって、それで今日いうところの王朝の時代にしなければならぬという大思想を持っておった。しかしながら山陽はそれを実行しようかと思ったけれども、実行することができなかった。山陽ほどの先見のない人はそれを実行しようとして戦場の露と消えてしまったに相違ない。しかし山陽はソンナ馬鹿ではなかった。彼は彼の在世中とてもこのことのできないことを知っていたから、自身の志を『日本外史』に述べた。そこで日本の歴史を述ぶるに当っても特別に王室を保護するようには書かなかった。外家《がいか》の歴史を書いてその中にはっきりといわずとも、ただ勤王家の精神をもって源平以来の外家の歴史を書いてわれわれに遺してくれた。今日の王政復古を持ち来《きた》した原動力は何であったかといえば、多くの歴史家がいうとおり山陽の『日本外史』がその一つでありしことはよくわかっている。山陽はその思想を遺して日本を復活させた。今日の王政復古前後の歴史をことごとく調べてみると山陽の功の非常に多いことがわかる。私は山陽のほかのことは知りませぬ。かの人の私行については二つ三つふ同意なところがあります。彼の国体論や兵制論についてはふ同意であります。しかしながら彼山陽の一つの Ambition《アムビション》 すなわち「われは今世に望むところはないけれども来世の人に大いに望むところがある」といった彼の欲望は私が実に彼を尊敬してやまざるところであります。すなわち山陽は『日本外史』を遺物として死んでしまって、骨は洛陽|東山《ひがしやま》に葬ってありますけれども、『日本外史』から新日本国は生まれてきました。 イギリスに今からして二百年前に痩ッこけて丈《せい》の低いしじゅう病身な一人の学者がおった。それでこの人は世の中の人に知られないで、何も用のない者と思われて、しじゅう貧乏して裏店《うらだな》のようなところに住まって、かの人は何をするかと人にいわれるくらい世の中に知れない人で、何もできないような人であったが、しかし彼は一つの大思想を持っていた人でありました。その思想というは人間というものは非常な価値のあるものである、また一個人というものは国家よりも大切なものである、という大思想を持っていた人であります。それで十七世紀の中ごろにおいてはその説は社会にまったく容《い》れられなかった。その時分にはヨーロッパでは主義は国家主義と定《き》まっておった。イタリアなり、イギリスなり、フランスなり、ドイツなり、みな国家的精神を養わなければならぬとて、社会はあげて国家という団体に思想を傾けておった時でございました。その時に当ってどのような権力のある人であろうとも、彼の信ずるところの、個人は国家より大切であるという考えを世の中にいくら発表しても、実行のできないことはわかりきっておった。そこでこの学者は私《ひそ》かに裏店に引っ込んで本を書いた。この人は、ご存じでありましょう、ジョン・ロックであります。その本は、“Human《ヒューマン》 Understanding《アンダスタンディング》”であります。しかるにこの本がフランスに往きまして、ルソーが読んだ、モンテスキューが読んだ、ミラボーが読んだ、そうしてその思想がフランス全国に行きわたって、ついに一七九〇年フランスの大革命が起ってきまして、フランスの二千八百万の国民を動かした。それがためにヨーロッパ中が動きだして、この十九世紀の始めにおいてもジョン・ロックの著書でヨーロッパが動いた。それから合衆国が生まれた。それからフランスの共和国が生まれてきた。それからハンガリアの改革があった。それからイタリアの独立があった。実にジョン・ロックがヨーロッパの改革に及ぼした影響は非常であります。その結果を日本でお互いが感じている。われわれの願いは何であるか、個人の権力を増そうというのではないか。われわれはこのことをどこまで実行することができるか、それはまだ問題でございますけれども、何しろこれがわれわれの願いであります。もちろんジョン・ロック以前にもそういう思想を持った人はあった。しかしながらジョン・ロックはその思想を形に顕《あら》わして“Human Understanding”という本を書いて死んでしまった。しかし彼の思想は今日われわれのなかに働いている。ジョン・ロックは身体も弱いし、社会の位地もごく低くあったけれども、彼は実に今日のヨーロッパを支配する人となったと思います。 それゆえに思想を遺すということは大事業であります。もしわれわれが事業を遺すことができぬならば、思想を遺してそうして将来にいたってわれわれの事業をなすことができると思う。そこで私はここでご注意を申しておかねばならぬことがある。われわれのなかに文学者という奴がある。誰でも筆を把《と》ってそうして雑誌か何かに批評でも載《の》すれば、それが文学者だと思う人がある。それで文学というものは惰《なま》け書生の一つの玩具《おもちゃ》になっている。誰でも文学はできる。それで日本人の考えに文学というものはまことに気楽なもののように思われている。山に引っ込んで文筆に従事するなどは実に羨《うらやま》しいことのように考えられている。福地源一郎君が忍ばず《しのばず》の池のほとりに別荘を建てて日蓮上人の脚本を書いている。それを他から見るとたいそう風流に見える。また日本人が文学者という者の生涯はどういう生涯であるだろうと思うているかというに、それは絵艸紙《えぞうし》屋へ行ってみるとわかる。どういう絵があるかというと、赤く塗ってある御堂のなかに美しい女が机の前に坐っておって、向こうから月の上ってくるのを筆を翳《かざ》して眺めている。これは何であるかというと紫式部の源氏の間である。これが日本流の文学者である。しかし文学というものはコンナものであるならば、文学は後世への遺物でなくしてかえって後世への害物である。なるほど『源氏物語』という本は美しい言葉を日本に伝えたものであるかも知れませぬ。しかし『源氏物語』が日本の士気を鼓舞することのために何をしたか。何もしないばかりでなくわれわれを女らしき意気地なしになした。あのような文学はわれわれのなかから根コソギに絶やしたい(拍手)。あのようなものが文学ならば、実にわれわれはカーライルとともに、文学というものには一度も手をつけたことがないということを世界に向って誇りたい。文学はソンナものではない。文学はわれわれがこの世界に戦争するときの道具である。今日戦争することはできないから未来において戦争しようというのが文学であります。それゆえに文学者が机の前に立ちますときにはすなわちルーテルがウォルムスの会議に立ったとき、パウロがアグリッパ王の前に立ったとき、クロムウェルが剣を抜いてダンバーの戦場に臨《のぞ》んだときと同じことであります。この社会、この国を改良しよう、この世界の敵なる悪魔を平《たい》らげようとの目的をもって戦争をするのであります。ルーテルが室《へや》のなかに入って何か書いておったときに、悪魔が出てきたゆえに、ルーテルはインクスタンドを取ってそれにぶッつけたという話がある。歴史家に聞くとこれは本当の話ではないといいます。しかしながらこれが文学です。われわれはほかのことで事業をすることができないから、インクスタンドを取って悪魔にぶッつけてやるのである。事業を今日なさんとするのではない。将来未来までにわれわれの戦争を続ける考えから事業を筆と紙とにのこして、そうしてこの世を終ろうというのが文学者の持っている Ambition《アムビション》 であります。それでその贈物《おくりもの》、われわれがわれわれの思想を筆と紙とに遺してこれを将来に贈ることが実に文学者の事業でありまして、もし神がわれわれにこのことを許しますならば、われわれは感謝してその贈物を遺したいと思う。有名なるウォルフ将軍がケベックの市《まち》を取るときにグレイの Elegy《エレジイ》 を歌いながらいった言葉があります、すなわち「このケベックを取るよりもわれはむしろこの Elegy を書かん」と。もちろん Elegy は過激なるいわゆるルーテル的の文章ではない。しかしながらこれがイギリス人の心、ウォルフ将軍のような心をどれだけ慰めたか、実に今日までのイギリス人の勇気をどれだけ励ましたか知れない。 トーマス・グレイという人は有名な学者で、彼の時代の人で彼くらいすべての学問に達していた人はほとんどなかったそうであります。イギリスの文学者中で博学、多才といったならばたぶんトーマス・グレイであったろうという批評であります。しかしながらトーマス・グレイは何を遺したか。彼の書いた本は一つに集めたらば、たぶんこんなくらい(手真似にて)の本でほとんど二百ページか、三百ページもありましょう。しかしそのうちこれぞというて大作はありませぬ。トーマス・グレイの後世への遺物は何にもない、ただ Elegy という三百行ばかりの詩でありました。グレイの四十八年の生涯というものは Elegy を書いて終ってしまったのです。しかしながらたぶんイギリスの国民の続くあいだは、イギリスの国語が話されているあいだは Elegy は消えないでしょう。この詩ほど多くの人を慰め、ことに多くの貧乏人を慰め、世の中にまったく容れられない人を慰め、多くの志を抱いてそれを世の中に発表することのできない者を慰めたものはない。この詩によってグレイは万世を慰めつつある。われわれは実にグレイの運命を羨むのであります。すべての学問を四十八年間も積んだ人がただ三百行くらいの詩を遺して死んだというては小さいようでございますが、実にグレイは大事業をなした人であると思います。有名なるヘンリー・ビーチャーがいった言葉に……私はこれはけっしてビーチャーが小さいことを針小棒大にしていうた言葉ではないと思います……「私は六十年か七十年の生涯を私のように送りしよりも、むしろチャールス・ウェスレーの書いた“Jesus《ジーザス》, Lover《ラヴァー》 of《オブ》 my《マイ》 soul《ソール》”の讃美歌一篇を作った方がよい」と申しました。チョット考えてみるとこれはただチャールス・ウェスレーを尊敬するあまりに発した言葉であって、けっしてビーチャーの心のなかから出た言葉ではないように思われますけれども、しかしながらウェスレーのこの歌をいく度か繰り返して歌ってみまして、どれだけの心情、どれだけの趣味、どれだけの希望がそのうちにあるかを見るときには、あるいはビーチャーのいったことが本当であるかも知れないと思います。ビーチャーの大事業もけっしてこの一つの讃美歌ほどの事業をなしていないかも知れませぬ。それゆえにもしわれわれに思想がありまするならば、もしわれわれがそれを直接に実行することができないならば、それを紙に写しましてこれを後世に遺しますことは大事業ではないかと思います。文学者の事業というものはそれゆえに羨むべき事業である。 こういう事業ならばあるいはわれわれも行ってみたいと思う。こう申しますると、諸君のなかにまたこういう人があります。「ドウモしかしながら文学などは私らにはとてもできない、ドウモ私は今まで筆を執ったことがない。また私は学問が少い、とても私は文学者になることはできない」。それで『源氏物語』を見てとてもこういう流暢《りゅうちょう》なる文は書けないと思い、マコーレーの文を見てとてもこれを学ぶことはできぬと考え、山陽の文を見てとてもこういうものは書けないと思い、ドウしても私は文学者になることはできないといって失望する人がある。文学者は特別の天職を持った人であって文学はとてもわれわれ平凡の人間にできることではないと思う人があります。その失望はどこから起ったかというと、前にお話しした柔弱なる考えから起ったのでございます。すなわち『源氏物語』的の文学思想から起った考えであります。文学というものはソンナものではない。文学というものはわれわれの心のありのままをいうものです。ジョン・バンヤンという人はチットモ学問のない人でありました。もしあの人が読んだ本があるならば、タッタ二つでありました、すなわち『バイブル』とフォックスの書いた『ブック・オブ・マータース』(“Book of Martyrs”)というこの二つでした。今ならばこのような本を読む忍耐力のある人はない。私は札幌にてそれを読んだことがある。十ページくらい読むと後は読む勇気がなくなる本である。ことにクエーカーの書いた本でありますから文法上の誤謬《ごびゅう》がたくさんある。しかるにバンヤンは始めから終りまでこの本を読んだ。彼は申しました。「私はプラトンの本もまたアリストテレスの本も読んだことはない、ただイエス・キリストの恩恵《めぐみ》にあずかった憐れなる罪人であるから、ただわが思うそのままを書くのである」といって、“Pilgrim's《ピルグリムス》 Progress《プログレス》”(『天路歴程』)という有名なる本を書いた。それでたぶんイギリス文学の批評家中で第一番という人……このあいだ死んだフランス人、テーヌという人であります……その人がバンヤンのこの著を評して何といったかというと「たぶん純粋という点から英語を論じたときにはジョン・バンヤンの“Pilgrim's Progress”に及ぶ文章はあるまい。これはまったく外からの雑《まじ》りのない、もっとも純粋なる英語であるだろう」と申しました。そうしてかくも有名なる本は何であるかというと無学者の書いた本であります。それでもしわれわれにジョン・バンヤンの精神がありますならば、すなわちわれわれが他人から聞いたつまらない説を伝えるのでなく、自分の拵《こしら》った神学説を伝えるでなくして、私はこう感じた、私はこう苦しんだ、私はこう喜んだ、ということを書くならば、世間の人はドレだけ喜んでこれを読むか知れませぬ。今の人が読むのみならず後世の人も実に喜んで読みます。バンヤンは実に「真面目なる宗教家」であります。心の実験を真面目に表わしたものが英国第一等の文学であります。それだによってわれわれのなかに文学者になりたいと思う観念を持つ人がありまするならば、バンヤンのような心を持たなくてはなりません。彼のような心を持ったならば実に文学者になれぬ人はないと思います。 今ここに丹羽さんがいませぬから少し丹羽さんの悪口をいいましょう(笑声起る)……後でいいつけてはイケマセンよ(大笑)。丹羽さんが青年会において『基督《キリスト》教青年』という雑誌を出した。それで私のところへもだいぶ送ってきた。そこで私が先日東京へ出ましたときに、先生が「ドウです内村君、あなたは『基督教青年』をドウお考えなさいますか」と問われたから、私は真面目にまた明白に答えた。「失礼ながら『基督教青年』は私のところへきますと私はすぐそれを厠《かわや》へ持っていって置いてきます。」ところが先生たいへん怒った。それから私はそのわけをいいました。アノ『基督教青年』を私が汚穢《きたな》い用に用いるのは何であるかというに、実につまらぬ雑誌であるからです。なにゆえにつまらないかというに、アノ雑誌のなかに名論卓説がないからつまらないというのではありません。アノ雑誌のつまらないわけは、青年が青年らしくないことを書くからです。青年が学者の真似をして、つまらない議論をアッチからも引き抜き、コッチからも引き抜いて、それを鋏刀《はさみ》と糊とでくッつけたような論文を出すから読まないのです。もし青年が青年の心のままを書いてくれたならば、私はこれを大切にして年の終りになったら立派に表装して、私の Library《ライブラリイ》(書函)のなかのもっとも価値あるものとして遺しておきましょうと申しました。それからその雑誌はだいぶ改良されたようであります。それです、私は名論卓説を聴きたいのではない。私の欲するところと社会の欲するところは、女よりは女のいうようなことを聴きたい、男よりは男のいうようなことを聴きたい、青年よりは青年の思っているとおりのことを聴きたい、老人よりは老人の思っているとおりのことを聴きたい。それが文学です。それゆえにただわれわれの心のままを表白してごらんなさい。ソウしてゆけばいくら文法は間違っておっても、世の中の人が読んでくれる。それがわれわれの遺物です。もし何もすることができなければ、われわれの思うままを書けばよろしいのです。私は高知から来た一人の下女を持っています。非常に面白い下女で、私のところに参りましてから、いろいろの世話をいたします。ある時はほとんど私の母のように私の世話をしてくれます。その女が手紙を書くのを側《そば》で見ていますと、非常な手紙です。筆を横に取って、仮名で、土佐言葉で書く。今あとで坂本さんが出て土佐言葉の標本を諸君に示すかも知れませぬ(大笑拍手)。ずいぶん面白い言葉であります。仮なで書くのですから、土佐言葉がソックリそのままで出てくる。それで彼女は長い手紙を書きます。実に読むのに骨が折れる。しかしながら私はいつでもそれを見て喜びます。その女は信者でも何でもない。毎月|三日月様《みかづきさま》になりますと私のところへ参って「ドウゾ旦那さまお銭《あし》を六厘」という。「何に使うか」というと、黙っている。「何でもよいから」という。やると豆腐を買ってきまして、三日月様に豆腐を供《そな》える。後で聞いてみると「旦那さまのために三日月様に祈っておかぬと運が悪い」と申します。私は感謝していつでも六厘差し出します(大笑)。それから七夕様《たなばたさま》がきますといつでも私のために七夕様に団子だの梨だの柿などを供えます。私はいつもそれを喜んで供えさせます。その女が書いてくれる手紙を私は実に多くの立派な学者先生の文学を『六合雑誌』などに拝見するよりも喜んで見まする。それが本当の文学で、それが私の心情に訴える文学。……文学とは何でもない、われわれの心情に訴えるものであります。文学というものはソウいうものであるならば……ソウいうものでなくてはならぬ……それならばわれわれはなろうと思えば文学者になることができます。われわれの文学者になれないのは筆が執《と》れないからなれないのではない、われわれに漢文が書けないから文学者になれないのでもない。われわれの心に鬱勃《うつぼつ》たる思想が籠《こ》もっておって、われわれが心のままをジョン・バンヤンがやったように綴ることができるならば、それが第一等の立派な文学であります。カーライルのいったとおり「何でもよいから深いところへ入れ、深いところにはことごとく音楽がある」。実にあなたがたの心情をありのままに書いてごらんなさい、それが流暢なる立派な文学であります。私自身の経験によっても私は文天祥《ぶんてんしょう》がドウ書いたか、白楽天がドウ書いたかと思っていろいろ調べてしかる後に書いた文よりも、自分が心のありのままに、仮な《かな》の間違いがあろうが、文法に合うまいが、かまわないで書いた文の方が私が見ても一番良い文章であって、外の人が評してもまた一番良い文章であるといいます。文学者の秘訣《ひけつ》はそこにあります。こういう文学ならばわれわれ誰でも遺すことができる。それゆえに有難いことでございます。もしわれわれが事業を遺すことができなければ、われわれに神様が言葉というものを下さいましたからして、われわれ人間に文学というものを下さいましたから、われわれは文学をもってわれわれの考えを後世に遺して逝くことができます ソウ申しますとまたこういう問題が出てきます。われわれは金を溜めることができず、また事業をなすことができない。それからまたそれならばといって、あなたがたがみな文学者になったらば、たぶん活版屋では喜ぶかもしれませぬけれども、社会では喜ばない。文学者の世の中にふえるということは、ただ活版屋と紙製造所を喜ばすだけで、あまり社会に益をなさないかも知れない。ゆえにもしわれわれが文学者となることができず、またなる考えもなし、バンヤンのような思想を持っておっても、バンヤンのように綴ることができないときには、別に後世への遺物はないかという問題が起る。それは私にもたびたび起った問題であります。なるほど文学者になることは私が前に述べましたとおりヤサシイこととは思いますけれども、しかし誰でも文学者になるということは実は望むべからざることであります。たとえば、学校の先生……ある人がいうように何でも大学に入って学士の称号を取り、あるいはその上にアメリカへでも往って学校を卒業さえしてくれば、それで先生になれると思うのと同じことであります。私はたびたび聞いて感じまして、今でも心に留《と》めておりますが、私がたいへん世話になりましたアーマスト大学の教頭シーリー先生がいった言葉に「この学校で払うだけの給金を払えば学者を得ることはいくらでも得られる。地質学を研究する人、動物学を研究する人はいくらもある。地質学者、動物学者はたくさんいる。しかしながら地質学、動物学を教えることのできる人は実に少い。文学者はたくさんいる、文学を教えることのできる人は少い。それゆえにこの学校に三、四十人の教授がいるけれども、その三、四十人の教師は非常に貴《とうと》い、なぜなればこれらの人は学問を自分で知っているばかりでなく、それを教えることのできる人であります」と。これはわれわれが深く考うべきことで、われわれが学校さえ卒業すればかならず先生になれるという考えを持ってはならぬ。学校の先生になるということは一種特別の天職だと私は思っております。よい先生というものはかならずしも大学者ではない。大島君もご承知でございますが、私どもが札幌におりましたときに、クラーク先生という人が教師であって、椊物学を受け持っておりました。その時分にはほかに植物学者がおりませぬから、クラーク先生を第一等の植物学者だと思っておりました。この先生のいったことは植物学上誤りのないことだと思っておりました。しかしながら彼の本国に行って聞いたら、先生だいぶ化《ばけ》の皮が現われた。かの国のある学者が、クラークが椊物学について口を利《き》くなどとは不思議だ、といって笑っておりました。しかしながら、とにかく先生は非常な力を持っておった人でした。どういう力であったかというに、すなわち植物学を青年の頭のなかへ注ぎ込んで、植物学という学問の Interest《インタレスト》 を起す力を持った人でありました。それゆえに植物学の先生としては非常に価値のあった人でありました。ゆえに学問さえすれば、われわれが先生になれるという考えをわれわれは持つべきでない。われわれに思想さえあれば、われわれがことごとく先生になれるという考えを抛却《ほうきゃく》してしまわねばならぬ。先生になる人は学問ができるよりも――学問もなくてはなりませぬけれども――学問ができるよりも学問を青年に伝えることのできる人でなければならない。これを伝えることは一つの技術であります。短い言葉でありますけれども、このなかに非常の意味が含まっております。たといわれわれが文学者になりたい、学校の先生になりたいという望みがあっても、これかならずしも誰にもできるものではないと思います。 それで金も遺すことができず、事業も遺すことができない人は、かならずや文学者または学校の先生となって思想を遺して逝くことができるかというに、それはそうはいかぬ。しかしながら文学と教育とは、工業をなすということ、金を溜めるということよりも、よほどやさしいことだと思います。なぜなれば独立でできることであるからです。ことに文学は独立的の事業である。今日のような学校にてはどこの学校にても、Mission《ミッション》 School《スクール》 を始めとしてどこの官立学校にても、われわれの思想を伝えるといっても実際伝えることはできない。それゆえ学校事業は独立事業としてはずいぶん難い事業であります。しかしながら文学事業にいたっては社会はほとんどわれわれの自由に任《まか》せる。それゆえに多くの独立を望む人が政治界を去って宗教界に入り、宗教界を去って教育界に入り、また教育界を去ってついに文学界に入ったことは明かな事実であります。多くのエライ人は文学に逃げ込みました。文学は独立の思想を維持する人のために、もっとも便益なる隠れ場所であろうと思います。しかしながらただ今も申し上げましたとおり、かならずしも誰にでも入ることのできる道ではない。 ここにいたってこういう問題が出てくる。文学者にもなれず学校の先生にもなれなかったならば、それならば私は後世に何をも遺すことはできないかという問題が出てくる。何かほかに事業はないか、私もたびたびそれがために失望に陥ることがある。しからば私には何も遺すものはない。事業家にもなれず、金を溜めることもできず、本を書くこともできず、ものを教えることもできない。ソウすれば私は無用の人間として、平凡の人間として消えてしまわなければならぬか。陸放翁《りくほうおう》のいったごとく「我死骨即朽《わがしこつすなわちくつるも》、青史亦無な《せいしにまたななし》」と嘆じ、この悲嘆の声を発してわれわれが生涯を終るのではないかと思うて失望の極に陥ることがある。しかれども私はそれよりモット大きい、今度は前の三つと違いまして誰にも遺すことのできる最大遺物があると思う。それは実に最大遺物であります。金も実に一つの遺物でありますけれども、私はこれを最大遺物となづけることはできない。事業も実に大遺物たるには相違ない、ほとんど最大遺物というてもようございますけれども、いまだこれを本当の最大遺物ということはできない。文学も先刻お話ししたとおり実に貴いものであって、わが思想を書いたものは実に後世への価値ある遺物と思いますけれども、私がこれをもって最大遺物ということはできない。最大遺物ということのできないわけは、一つは誰にも遺すことのできる遺物でないから最大遺物ということはできないのではないかと思う。そればかりでなくその結果はかならずしも害のないものではない。昨日もお話ししたとおり金は用い方によってたいへん利益がありますけれども、用い方が悪いとまたたいへん害を来《きた》すものである。事業におけるも同じことであります。クロムウェルの事業とか、リビングストンの事業はたいへん利益がありますかわりに、またこれには害が一緒に伴《ともの》うております。また本を書くことも同じようにそのなかに善いこともありまた悪いこともたくさんあります。われわれはそれを完全なる遺物または最大遺物となづけることはできないと思います。 それならば最大遺物とはなんであるか。私が考えてみますに人間が後世に遺すことのできる、ソウしてこれは誰にも遺すことのできるところの遺物で、利益ばかりあって害のない遺物がある。それは何であるかならば勇ましい高尚なる生涯に白丸傍点]であると思います。これが本当の遺物ではないかと思う。他の遺物は誰にも遺すことのできる遺物ではないと思います。しかして高尚なる勇ましい生涯とは何であるかというと、私がここで申すまでもなく、諸君もわれわれも前から承知している生涯であります。すなわちこの世の中はこれはけっして悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信ずることである。失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという考えをわれわれの生涯に実行して、その生涯を世の中への贈物としてこの世を去るということであります。その遺物は誰にも遺すことのできる遺物ではないかと思う。もし今までのエライ人の事業をわれわれが考えてみますときに、あるいはエライ文学者の事業を考えてみますときに、その人の書いた本、その人の遺した事業はエライものでございますが、しかしその人の生涯に較《くら》べたときには実に小さい遺物だろうと思います。パウロの書翰《しょかん》は実に有益な書翰でありますけれども、しかしこれをパウロの生涯に較べたときには価値のはなはだ少いものではないかと思う。パウロ彼自身はこのパウロの書いたロマ書や、ガラテヤ人に贈った書翰よりもエライ者であると思います。クロムウェルがアングロサクソン民族の王国を造ったことは大事業でありますけれども、クロムウェルがあの時代に立って自分の独立思想を実行し、神によってあの勇壮なる生涯を送ったという、あのクロムウェル彼自身の生涯というものは、これはクロムウェルの事業に十倍も百倍もする社会にとっての遺物ではないかと考えます。私は元来トーマス・カーライルの本を非常に敬読する者であります。それである人にはそれがために嫌われますけれども、私はカーライルという人については全体非常に尊敬を表しております。たびたびあの人の本を読んで利益を得、またそれによって刺激をも受けたことでございます。けれども、私はトーマス・カーライルの書いた四十冊ばかりの本をみな寄せてみてカーライル彼自身の生涯に較べたときには、カーライルの書いたものは実に価値の少いものであると思います。先日カーライルの伝を読んで感じました。ご承知の通りカーライルが書いたもののなかで一番有名なものはフランス革命の歴史でございます。それである歴史家がいうたに「イギリス人の書いたもので歴史的の叙事、ものを説き明した文体からいえば、カーライルの『フランス革命史』がたぶん一番といってもよいであろう、もし一番でなければ一番のなかに入るべきものである」ということであります。それでこの本を読む人はことごとく同じ感覚を持つだろうと思います。実に今より百年ばかり前のことをわれわれの目の前に活きている画のように、ソウして立派な画人《えかき》が書いてもアノようには書けぬというように、フランス革命のパノラマ(活画)を示してくれたものはこの本であります。それでわれわれはその本に非常の価値を置きます。カーライルがわれわれに遺してくれたこの本は実にわれわれの貴ぶところでございます。しかしながらフランスの革命を書いたカーライルの生涯の実験を見ますと、この本よりかまだ立派なものがあります。その話は長いけれどもここにあなたがたに話すことを許していただきたい。カーライルがこの書を著《あら》わすのは彼にとってはほとんど一生涯の仕事であった。チョット『革命史』を見まするならば、このくらいの本は誰にでも書けるだろうと思うほどの本であります。けれども歴史的の研究を凝《こ》らし、広く材料を集めて成った本でありまして、実にカーライルが生涯の血を絞って書いた本であります。それで何十年ですか忘れましたが、何十年かかかってようやく自分の望みのとおりの本が書けた。それからしてその本が原稿になってこれを罫紙《けいし》に書いてしまった。それからしてこれはモウじきに出版するときがくるだろうと思って待っておった。そのときに友人が来ましてカーライルに遇《あ》ったところが、カーライルがその話をしたら「実に結構な書物だ、今晩一読を許してもらいたい」といった。そのときにカーライルは自分の書いたものはつまらないものだと思って人の批評を仰ぎたいと思ったから、貸してやった。貸してやるとその友人はこれを家へ持っていった。そうすると友人の友人がやってきて、これを手に取って読んでみて、「これは面白い本だ、一つドウゾ今晩私に読ましてくれ」といった。ソコで友人がいうには「明日の朝早く持ってこい、そうすれば貸してやる」といって貸してやったら、その人はまたこれをその家へ持っていって一所懸命に読んで、暁方《あけがた》まで読んだところが、あしたの事業に妨《さまた》げがあるというので、その本をば机の上に抛《ほう》り放《はな》しにして床《とこ》について自分は寝入ってしまった。そうすると翌朝彼の起きない前に下女がやってきて、家の主人が起きる前にストーブに火をたきつけようと思って、ご承知のとおり西洋では紙をコッパの代りに用いてクベますから、何か好い反古《ほご》はないかと思って調べたところが机の前に書いたものがだいぶひろがっていたから、これは好いものと思って、それをみな丸めてストーブのなかへ入れて火をつけて焼いてしまった。カーライルの何十年ほどかかった『革命史』を焼いてしまった。時計の三分か四分の間に煙となってしまった。それで友人がこのことを聞いて非常に驚いた。何ともいうことができない。ほかのものであるならば、紙幣《さつ》を焼いたならば紙幣を償《つぐな》うことができる、家を焼いたならば家を建ててやることもできる、しかしながら思想の凝《こ》って成ったもの、熱血を注いで何十年かかって書いたものを焼いてしまったのは償いようがない。死んだものはモウ活《い》き帰らない。それがために腹を切ったところが、それまでであります。それで友人に話したところが、友人も実にドウすることもできないで一週間|黙《だま》っておった。何といってよいかわからぬ。ドウモ仕方がないから、そのことをカーライルにいった。そのときにカーライルは十日ばかりぼんやりとして何もしなかったということであります。さすがのカーライルもそうであったろうと思います。それで腹が立った。ずいぶん短気の人でありましたから、非常に腹を立てた。彼はそのときは歴史などは抛りぽかして何にもならないつまらない小説を読んだそうです。しかしながらその間に己《おのれ》で己《おのれ》に帰っていうに「トーマス・カーライルよ、汝は愚人である、汝の書いた『革命史』はソンナに貴いものではない、第一に貴いのは汝がこの艱難《かんなん》に忍んでそうしてふたたび筆を執《と》ってそれを書き直すことである、それが汝の本当にエライところである、実にそのことについて失望するような人間が書いた『革命史』を社会に出しても役に立たぬ、それゆえにモウ一度書き直せ」といって自分で自分を鼓舞して、ふたたび筆を執って書いた。その話はそれだけの話です。しかしわれわれはそのときのカーライルの心中にはいったときには実に推察の情|溢《あふ》るるばかりであります。カーライルのエライことは『革命史』という本のためにではなくして、火にて焼かれたものをふたたび書き直したということである。もしあるいはその本が遺っておらずとも、彼は実に後世への非常の遺物を遺したのであります。たといわれわれがイクラやりそこなってもイクラふ運にあっても、そのときに力を回復して、われわれの事業を捨ててはならぬ、勇気を起してふたたびそれに取りかからなければならぬ、という心を起してくれたことについて、カーライルは非常な遺物を遺してくれた人ではないか。 今時《こんじ》の弊害は何であるかといいますれば、なるほど金がない、われわれの国に事業が少い、良い本がない、それは確かです。しかしながら日本人お互いに今要するものは何であるか。本が足りないのでしょうか、金がないのでしょうか、あるいは事業がふ足なのでありましょうか。それらのことのふ足はもとよりないことはない。けれども、私が考えてみると、今日第一の欠乏は Life《ライフ》 生命の欠乏であります。それで近ごろはしきりに学問ということ、教育ということ、すなわち Culture《カルチュア》(修養)ということが大へんにわれわれを動かします。われわれはドウしても学問をしなければならぬ、ドウしてもわれわれは青年に学問をつぎ込まねばならぬ、教育をのこして後世の人を誡《いま》しめ、後世の人を教えねばならぬというてわれわれは心配いたします。もちろんこのことはたいへんよいことであります。それでもしわれわれが今より百年後にこの世に生まれてきたと仮定して、明治二十七年の人の歴史を読むとすれば、ドウでしょう、これを読んできてわれわれにどういう感じが起りましょうか。なるほどここにも学校が建った、ここにも教会が建った、ここにも青年会館が建った、ドウして建ったろうといってだんだん読んでみますと、この人はアメリカへ行って金をもらってきて建てた、あるいはこの人はこういう運動をして建てたということがある。そこでわれわれがこれを読みますときにアア、とても私にはそんなことはできない、今ではアメリカへ行っても金はもらえまい、また私にはそのように人と共同する力はない。私にはそういう真似《まね》はできない、私はとてもそういう事業はできないというて失望しましょう。すなわち私が今から五十年も百年も後の人間であったならば、今日の時代から学校を受け継いだかも知れない。教会を受け継いだかも知れませぬ。けれども私自身を働かせる原動力をばもらわない。大切なるものをばもらわないに相違ない。しかしもしここにつまらない教会が一つあるとすれば、そのつまらない教会の建物を売ってみたところがほとんどわずかの金の価値しかないかも知れませぬ。しかしながらその教会の建った歴史を聞いたときに、その歴史がこういう歴史であったと仮《かり》定《さだ》めてごらんなさい……この教会を建てた人はまことに貧乏人であった、この教会を建てた人は学問も別にない人であった、それだけれどもこの人は己のすべての浪費を節して、すべての欲情を去って、まるで己の力だけにたよって、この教会を造ったものである。……こういう歴史を読むと私にも勇気が起ってくる。かの人にできたならば己にもできないことはない、われも一つやってみようというようになる。 私は近世の日本の英傑、あるいは世界の英傑といってもよろしい人のお話をいたしましょう。この世界の英傑のなかに、ちょうどわれわれの留《と》まっているこの箱根山の近所に生まれた人で二宮金次郎という人がありました。この人の伝を読みましたときに私は非常な感覚をもらった。それでドウも二宮金次郎先生には私は現に負《お》うところが実に多い。二宮金次郎氏の事業はあまり日本にひろまってはおらぬ。それで彼のなした事業はことごとくこれを纏《まと》めてみましたならば、二十ヵ村か三十ヵ村の人民を救っただけに止《とど》まっていると考えます。しかしながらこの人の生涯が私を益し、それから今日日本の多くの人を益するわけは何であるかというと、何でもない、この人は事業の贈物にあらずして生涯の贈物を遺した。この人の生涯はすでにご承知の方もありましょうが、チョット申してみましょう。二宮金次郎氏は十四のときに父を失い、十六のときに母を失い、家が貧乏にして何物もなく、ためにごく残酷な伯父に預けられた人であります。それで一文の銭もなし家産はことごとく傾き、弟一人、妹一人持っていた。身に一文もなくして孤児です。その人がドウして生涯を立てたか。伯父さんの家にあってその手伝いをしている間に本が読みたくなった。そうしたときに本を読んでおったら、伯父さんに叱られた。この高い油を使って本を読むなどということはまことに馬鹿馬鹿しいことだといって読ませぬ。そうすると、黙っていて伯父さんの油を使っては悪いということを聞きましたから、「それでは私は私の油のできるまでは本を読まぬ」という決心をした。それでどうしたかというと、川辺の誰も知らないところへ行きまして、菜種《なたね》を蒔《ま》いた。一ヵ年かかって菜種を五、六升も取った。それからその菜種を持っていって、油屋へ行って油と取換えてきまして、それからその油で本を見た。そうしたところがまた叱られた。「油ばかりお前のものであれば本を読んでもよいと思っては違う、お前の時間も私のものだ。本を読むなどという馬鹿なことをするならよいからその時間に縄を綯《よ》れ」といわれた。それからまた仕方がない、伯父さんのいうことであるから終日働いてあとで本を読んだ、……そういう苦学をした人であります。どうして自分の生涯を立てたかというに、村の人の遊ぶとき、ことにお祭り日などには、近所の畑のなかに洪水で沼になったところがあった、その沼地を伯父さんの時間でない、自分の時間に、その沼地よりことごとく水を引いてそこでもって小さい鍬《くわ》で田地を拵《こしら》えて、そこへ持っていって稲を椊えた。こうして初めて一俵の米を取った。その人の自伝によりますれば、「米を一俵取ったときの私の喜びは何ともいえなかった。これ天が初めて私に直接に授けたものにしてその一俵は私にとっては百万の価値があった」というてある。それからその方法をだんだん続けまして二十歳のときに伯父さんの家を辞した。そのときには三、四俵の米を持っておった。それから仕上げた人であります。それでこの人の生涯を初めから終りまで見ますと、この宇宙というものは実に神様……神様とはいいませぬ……天の造ってくださったもので、天というものは実に恩恵の深いもので、人間を助けよう助けようとばかり思っている。それだからもしわれわれがこの身を天と地とに委《ゆだ》ねて天の法則に従っていったならば、われわれは欲せずといえども天がわれわれを助けてくれる>というこういう考えであります。その考えを持ったばかりでなく、その考えを実行した。その話は長うございますけれども、ついには何万石という村々を改良して自分の身をことごとく人のために使った。旧幕の末路にあたって経済上、農業改良上について非常の功労のあった人であります。それでわれわれもそういう人の生涯、二宮金次郎先生のような人の生涯を見ますときに、「もしあの人にもアアいうことができたならば私にもできないことはない」という考えを起します。普通の考えではありますけれども非常に価値のある考えであります。それで人に頼らずともわれわれが神にたより己にたよって宇宙の法則に従えば、この世界はわれわれの望むとおりになり、この世界にわが考えを行うことができるという感覚が起ってくる。二宮金次郎先生の事業は大きくなかったけれども、彼の生涯はドレほどの生涯であったか知れませぬ。私ばかりでなく日本中幾万の人はこの人からインスピレーション>を得たでありましょうと思います。あなたがたもこの人の伝を読んでごらんなさい。『少年文学』の中に『二宮尊徳翁』というのが出ておりますが、アレはつまらない本です。私のよく読みましたのは、農商務省で出版になりました、五百ページばかりの『報徳記』という本です。この本を諸君が読まれんことを切に希望します。この本はわれわれに新理想を与え、新希望を与えてくれる本であります。実にキリスト教の『バイブル』を読むような考えがいたします。ゆえにわれわれがもし事業を遺すことができずとも、二宮金次郎的の、すなわち独立生涯を躬行《きゅうこう》していったならば、われわれは実に大事業を遺す人ではないかと思います。 私は時が長くなりましたからもうしまいにいたしますが、常に私の生涯に深い感覚を与える一つの言葉を皆様の前に繰り返したい。ことにわれわれのなかに一人アメリカのマサチューセッツ州マウント・ホリヨーク・セミナリーという学校へ行って卒業してきた方がおりますが、この女学校は古い女学校であります。たいへんよい女学校であります。しかしながらもし私をしてその女学校を評せしむれば、今の教育上ことに知育上においては私はけっしてアメリカ第一等の女学校とは思わない。米国にはたくさんよい女学校がございます。スミス女学校というような大きな学校もあります。またボストンのウェレスレー学校、フィラデルフィアのブリンモアー学校というようなものがございます。けれどもマウント・ホリヨーク・セミナリーという女学校は非常な勢力をもって非常な事業を世界になした女学校であります。何故《なぜ》だといいます(その女学校はこの節はだいぶよく揃ったそうでありますが、このあいだまではふ整頓の女学校でありました)、それが世界を感化するの勢力を持つにいたった原因は、その学校にはエライ非常な女がおった。その人は立派な物理学の機械に優《まさ》って、立派な天文台に優って、あるいは立派な学者に優って、価値《ねうち》のある魂《たましい》を持っておったメリー・ライオンという女でありました。その生涯をことごとく述べることは今ここではできませぬが、この女史が自分の女生徒に遺言した言葉はわれわれのなかの婦女を励まさねばならぬ、また男子をも励まさねばならぬものである。すなわち私はその女の生涯をたびたび考えてみますに、実に日本の武士のような生涯であります。彼女は実に義侠心に充《み》ち満《み》ちておった女であります。彼女は何というたかというに、彼女の女生徒にこういうた。 他の人の行くことを嫌うところへ行け。 他の人の嫌がることをなせ これがマウント・ホリヨーク・セミナリーの立った土台石であります。これが世界を感化した力ではないかと思います。他の人の嫌がることをなし、他の人の嫌がるところへ行くという精神であります。それでわれわれの生涯はその方に向って行きつつあるか。われわれの多くはそうでなくして、他の人もなすから己もなそうというのではないか。他の人もアアいうことをするから私もソウしようというふうではないか。ほかの人もアメリカへ金もらいに行くから私も行こう、他の人も壮士になるから私も壮士になろう、はなはだしきはだいぶこのごろは耶蘇《ヤソ》教が世間の評判がよくなったから私も耶蘇教になろう、というようなものがございます。関東に往きますと関西にあまり多くないものがある。関東には良いものがだいぶたくさんあります。関西よりも良いものがあると思います。関東人は意地《いじ》ということをしきりに申します。意地の悪い奴はつむじが曲っていると申しますが毬栗頭《いがぐりあたま》にてはすぐわかる。頭のつむじがここらに(手真似にて)こう曲がっている奴はかならず意地が悪い。人が右へ行こうというと左といい、アアしようといえばコウしようというようなふうで、ことに上州人にそれが多いといいます(私は上州の人間ではありませぬけれども)。それでかならずしもこれは誉《ほ》むべき精神ではないと思うが、しかしながら武士の意地というものです。その意地をわれわれから取り除《の》けてしまったならば、われわれは腰抜け武士になってしまう。徳川家康のエライところはたくさんありますけれども、諸君のご承知のとおり彼が子供のときに川原《かわら》へ行ってみたところが、子供の二群が戦《いくさ》をしておった、石撃《いしぶち》をしておった。家康はこれを見て彼の家来に命じて人数の少い方を手伝ってやれといった。多い方はよろしいから少い方へ行って助けてやれといった。これが徳川家康のエライところであります。それでいつでも正義のために立つ者は少数である。それでわれわれのなすべきことはいつでも少数の正義の方に立って、そうしてその正義のために多勢のふ義の徒に向って石撃をやらなければなりません。もちろんかならずしも負ける方を助けるというのではない。私の望むのは少数とともに戦うの意地です。その精神です。それはわれわれのなかにみな欲《ほ》しい。今日われわれが正義の味方に立つときに、われわれ少数の人が正義のために立つときに、少くともこの夏期学校に来ている者くらいはともにその方に起《た》ってもらいたい。それでドウゾ後世の人がわれわれについてこの人らは力もなかった、富もなかった、学問もなかった人であったけれども、己の一生涯をめいめい持っておった主義のために送ってくれたといわれたいではありませんか。これは誰にも遺すことのできる生涯ではないかと思います。それでその遺物を遺すことができたと思うと実にわれわれは嬉しい、たといわれわれの生涯はドンナ生涯であっても。 たびたびこういうような考えは起りませぬか。もし私に家族の関係がなかったならば私にも大事業ができたであろう、あるいはもし私に金があって大学を卒業し欧米へ行って知識を磨いてきたならば私にも大事業ができたであろう、もし私に良い友人があったならば大事業ができたであろう、こういう考えは人々に実際起る考えであります。しかれども種々のふ幸に打ち勝つことによって大事業というものができる、それが大事業であります。それゆえにわれわれがこの考えをもってみますと、われわれに邪魔のあるのはもっとも愉快なことであります。邪魔があればあるほどわれわれの事業ができる。勇ましい生涯と事業を後世に遺すことができる。とにかく反対があればあるほど面白い。われわれに友達がない、われわれに金がない、われわれに学問がないというのが面白い。われわれが神の恩恵を享《う》け、われわれの信仰によってこれらのふ足に打ち勝つことができれば、われわれは非常な事業を遺すものである。われわれが熱心をもってこれに勝てば勝つほど、後世への遺物が大きくなる。もし私に金がたくさんあって、地位があって、責任が少くして、それで大事業ができたところが何でもない。たとい事業は小さくても、これらのすべての反対に打ち勝つことによって、それで後世の人が私によって大いに利益を得るにいたるのである。種々のふ都合《ふつごう》、種々の反対に打ち勝つことが、われわれの大事業ではないかと思う。それゆえにヤコブのように、われわれの出遭《であ》う艱難《かんなん》についてわれわれは感謝すべきではないかと思います。 まことに私の言葉が錯雑しておって、かつ時間も少くございますから、私の考えをことごとく述べることはできない。しかしながら私は今日これで御免《ごめん》をこうむって山を降《くだ》ろうと思います。それで来年またふたたびどこかでお目にかかるときまでには少くとも幾何《いくばく》の遺物を貯えておきたい。この一年の後にわれわれがふたたび会しますときには、われわれが何か遺しておって、今年は後世のためにこれだけの金を溜めたというのも結構、今年は後世のためにこれだけの事業をなしたというのも結構、また私の思想を雑誌の一論文に書いて遺したというのも結構、しかしそれよりもいっそう良いのは後世のために私は弱いものを助けてやった、後世のために私はこれだけの艱難に打ち勝ってみた、後世のために私はこれだけの品性を修練してみた、後世のために私はこれだけの義侠心を実行してみた、後世のために私はこれだけの情実に勝ってみた、という話を持ってふたたびここに集まりたいと考えます。この心掛けをもってわれわれが毎年毎日進みましたならば、われわれの生涯は決して五十年や六十年の生涯にはあらずして、実に水の辺《ほと》りに椊えたる樹のようなもので、だんだんと芽を萌《ふ》き枝を生じてゆくものであると思います。けっして竹に木を接《つ》ぎ、木に竹を接ぐような少しも成長しない価値のない生涯ではないと思います。こういう生涯を送らんことは実に私の最大希望でございまして、私の心を毎日慰め、かついろいろのことをなすに当って私を励ますことであります。それで私のなお一つの題の「真面目ならざる宗教家」というのは時間がありませぬからここに述べませぬ。述べませぬけれども、しかしながら私の精神のあるところは皆様に十分お話しいたしたと思います。己の信ずることを実行するものが真面目なる信者です。ただただ壮言大語することは誰にもできます。いくら神学を研究しても、いくら哲学書を読みても、われわれの信じた主義を真面目に実行するところの精神がありませぬあいだは、神はわれわれにとって異邦人であります。それゆえにわれわれは神がわれわれに知らしたことをそのまま実行いたさなければなりません。こういたさねばならぬと思うたことはわれわれはことごとく実行しなければならない。もしわれわれが正義はついに勝つものにしてふ義はついに負けるものであるということを世間に発表するものであるならば、そのとおりにわれわれは実行しなければならない。これを称して真面目なる信徒と申すのです。われわれに後世に遺すものは何もなくとも、われわれに後世の人にこれぞというて覚えられるべきものはなにもなくとも、アノ人はこの世の中に活きているあいだは真面目なる生涯を送った人であるといわれるだけのことを後世の人に遺したいと思います。(拍手喝采) 底本:「後世への最大遺物 デンマルク国の話」岩波文庫、岩波書店 1946(昭和21)年10月10日第1刷発行 1976(昭和51)年3月16日第30刷改版発行 1994(平成6)年8月6日第64刷発行 青空文庫作成ファイル:このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。 ▼後世への最大遺物の最後に述べられている言葉です。 2008.4.30
▼デンマルク国の話 信仰と樹木とをもって国を救いし話 曠野《あれの》と湿潤《うるおい》なき地とは楽しみ、 沙漠《さばく》は歓《よろこ》びて番紅《さふらん》のごとくに咲《はなさ》かん、 盛《さかん》に咲《はなさ》きて歓ばん、 喜びかつ歌わん、 レバノンの栄《さか》えはこれに与えられん、 カルメルとシャロンの美《うるわ》しきとはこれに授けられん、 彼らはエホバの栄《さかえ》を見ん、 我らの神の美《うる》わしきを視《み》ん。 (イザヤ書三五章一―二節) 今日は少しこの世のことについてお話しいたそうと欲《おも》います。デンマークは欧州北部の一小邦であります。その面積は朝鮮と台湾とを除いた日本帝国の十分の一でありまして、わが北海道の半分に当り、九州の一島に当らない国であります。その人口は二百五十万でありまして、日本の二十分の一であります。実に取るに足りないような小国でありますが、しかしこの国について多くの面白い話があります。 今、単に経済上より観察を下しまして、この小国のけっして侮《あなど》るべからざる国であることがわかります。この国の面積と人口とはとてもわが日本国に及びませんが、しかし富の程度にいたりましてははるかに日本以上であります。その一例を挙《あ》げますれば日本国の二十分の一の人口を有するデンマーク国は日本の二分の一の外国貿易をもつのであります。すなわちデンマーク人一人の外国貿易の高は日本人一人の十倍に当るのであります。もってその富の程度がわかります。ある人のいいまするに、デンマーク人はたぶん世界のなかでもっとも富んだる民であるだろうとのことであります。すなわちデンマーク人一人の有する富はドイツ人または英国人または米国人一人の有する富よりも多いのであります。実に驚くべきことではありませんか。 しからばデンマーク人はどうしてこの富を得たかと問いまするに、それは彼らが国外に多くの領地をもっているからではありません、彼らはもちろん広きグリーンランドをもちます。しかし北氷洋の氷のなかにあるこの領土の経済上ほとんど何の価値もないことは何人《なんびと》も知っております。彼らはまたその面積においてはデンマーク本土に二倍するアイスランドをもちます。しかしそのなを聞いてその国の富饒《ふにょう》の土地でないことはすぐにわかります。ほかにわずかに鳥毛《とりのけ》を産するファロー島があります。またやや富饒なる西インド中のサンクロア、サントーマス、サンユーアンの三島があります。これ確かに富の源《みなもと》でありますが、しかし経済上収支相償うこと尠《すくな》きがゆえに、かつてはこれを米国に売却せんとの計画もあったくらいであります。ゆえにデンマークの富源といいまして、別に本国以外にあるのでありません。人口一人に対し世界第一の富を彼らに供せしその富源はわが九州大のデンマーク本国においてあるのであります。 しかるにこのデンマーク本国がけっして富饒の地と称すべきではないのであります。国に一鉱山あるでなく、大港湾の万国の船舶を惹《ひ》くものがあるのではありません。デンマークの富は主としてその土地にあるのであります、その牧場とその家畜と、その樅《もみ》と白樺《しらかば》との森林と、その沿海の漁業とにおいてあるのであります。ことにその誇りとするところはその乳産であります、そのバターとチーズとであります。デンマークは実に牛乳をもって立つ国であるということができます。トーヴァルセンを出して世界の彫刻術に一新紀元を劃《かく》し、アンデルセンを出して近世お伽話《とぎばなし》の元祖たらしめ、キェルケゴールを出して無教会主義のキリスト教を世界に唱《とな》えしめしデンマークは、実に柔和なる牝牛《めうし》の産をもって立つ小にして静かなる国であります。 しかるに今を去る四十年前のデンマークはもっとも憐れなる国でありました。一八六四年にドイツ、オーストリアの二強国の圧迫するところとなり、その要求を拒《こば》みし結果、ついに開戦のふ幸を見、デンマーク人は善く戦いましたが、しかし弱はもって強に勝つ能《あた》はず、デッペルの一戦に北軍敗れてふたたび起《た》つ能わざるにいたりました。デンマークは和を乞いました、しかして敗北の賠償《ばいしょう》としてドイツ、オーストリアの二国に南部最良の二州シュレスウィヒとホルスタインを割譲しました。戦争はここに終りを告げました。しかしデンマークはこれがために窮困の極に達しました。もとより多くもない領土、しかもその最良の部分を持ち去られたのであります。いかにして国運を恢復《かいふく》せんか、いかにして敗戦の大搊害を償《つぐな》わんか、これこの時にあたりデンマークの愛国者がその脳漿《のうしょう》を絞《しぼ》って考えし問題でありました。国は小さく、民は尠《すくな》く、しかして残りし土地に荒漠多しという状態《ありさま》でありました。国民の精力はかかるときに試《た》めさるるのであります。戦いは敗れ、国は削《けず》られ、国民の意気鎖沈しなにごとにも手のつかざるときに、かかるときに国民の真の価値《ねうち》は判明するのであります。戦勝国の戦後の経営はどんなつまらない政治家にもできます、国威宣揚にともなう事業の発展はどんなつまらない実業家にもできます、難いのは戦敗国の戦後の経営であります、国運衰退のときにおける事業の発展であります。戦いに敗れて精神に敗れない民が真に偉大なる民であります戦いに敗れて精神に敗れない民が真に偉大なる民であります、宗教といい信仰といい、国運隆盛のときにはなんの必要もないものであります。しかしながら国に幽暗《くらき》の臨《のぞ》みしときに精神の光が必要になるのであります。国の興《おこ》ると亡《ほろ》ぶるとはこのときに定まるのであります。どんな国にもときには暗黒が臨みます。そのとき、これに打ち勝つことのできる民が、その民が永久に栄ゆるのであります。あたかも疾病《やまい》の襲うところとなりて人の健康がわかると同然であります。平常《ふだん》のときには弱い人も強い人と違いません。疾病《やまい》に罹《かか》って弱い人は斃《たお》れて強い人は存《のこ》るのであります。そのごとく真に強い国は国難に遭遇して亡びないのであります。その兵は敗れ、その財は尽《つ》きてそのときなお起るの精力を蓄うるものであります。これはまことに国民の試練の時であります。このときに亡びないで、彼らは運命のいかんにかかわらず、永久に亡びないのであります。 越王|勾践《こうせん》呉を破りて帰るではありません、デンマーク人は戦いに敗れて家に還ってきました。還りきたれば国は荒れ、財は尽き、見るものとして悲憤失望の種ならざるはなしでありました。「今やデンマークにとり悪しき日なり」と彼らは相互に対していいました。この挨拶《あいさつ》に対して「否《いな》」と答えうる者は彼らのなかに一人もありませんでした。しかるにここに彼らのなかに一人の工兵士官がありました。彼のなをダルガス(Enrico Mylius Dalgas)といいまして、フランス種のデンマーク人でありました。彼の祖先は有名なるユグノー党の一人でありまして、彼らは一六八五年信仰自由のゆえをもって故国フランスを逐《お》われ、あるいは英国に、あるいはオランダに、あるいはプロイセンに、またあるいはデンマークに逃れ来《きた》りし者でありました。ユグノー党の人はいたるところに自由と熱信と勤勉とを運びました。英国においてはエリザベス女王のもとにその今や世界に冠たる製造業を起しました。その他、オランダにおいて、ドイツにおいて、多くの有利的事業は彼らによって起されました。旧《ふる》き宗教を維持せんとするの結果、フランス国が失いし多くのもののなかに、かの国にとり最大の搊失と称すべきものはユグノー党の外国脱出でありました。しかして十九世紀の末に当って彼らはいまだなおその祖先の精神を失わなかったのであります。ダルガス、齢《とし》は今三十六歳、工兵士官として戦争に臨み、橋を架し、道路を築き、溝《みぞ》を掘るの際、彼は細《こま》かに彼の故国の地質を研究しました。しかして戦争いまだ終らざるに彼はすでに彼の胸中に故国|恢復《かいふく》の策を蓄えました。すなわちデンマーク国の欧州大陸に連《つら》なる部分にして、その領土の大部分を占むるユトランド(Jutland)の荒漠を化してこれを沃饒《よくにょう》の地となさんとの大計画を、彼はすでに彼の胸中に蓄えました。ゆえに戦い敗れて彼の同僚が絶望に圧せられてその故国に帰り来《きた》りしときに、ダルガス一人はその面《おも》に微笑《えみ》を湛《たた》えその首《こうべ》に希望の春を戴《いただ》きました。「今やデンマークにとり悪しき日なり」と彼の同僚はいいました。「まことにしかり」とダルガスは答えました。「しかしながらわれらは外に失いしところのものを内において取り返すを得《う》べし、君らと余との生存中にわれらはユトランドの曠野を化して薔薇《バラ》の花咲くところとなすを得べし」と彼は続いて答えました。この工兵士官に預言者イザヤの精神がありました。彼の血管に流るるユグノー党の血はこの時にあたって彼をして平和の天使たらしめました。他人の失望するときに彼は失望しませんでした。彼は彼の国人が剣をもって失ったものを鋤《すき》をもって取り返さんとしました。今や敵国に対して復讐戦《ふくしゅうせん》を計画するにあらず、鋤《すき》と鍬《くわ》とをもって残る領土の曠漠と闘い、これを田園と化して敵に奪われしものを補わんとしました。まことにクリスチャンらしき計画ではありませんか。真正の平和主義者はかかる計画に出でなければなりません。 しかしダルガスはただに預言者ではありませんでした。彼は単に夢想家《ゆめみるもの》ではありませんでした。工兵士官なる彼は、土木学者でありしと同時に、また地質学者であり椊物学者でありました。彼はかのごとくにして詩人でありしと同時にまた実際家でありました。彼は理想を実現するの術《すべ》を知っておりました。かかる軍人をわれわれはときどき欧米の軍人のなかに見るのであります。軍人といえば人を殺すの術にのみ長じている者であるとの思想は外国においては一般に行われておらないのであります。 ユトランドはデンマークの半分以上であります。しかしてその三分の一以上がふ毛の地であったのであります。面積一万五千平方マイルのデンマークにとりましては三千平方マイルの曠野は過大の廃物であります。これを化して良田沃野となして、外に失いしところのものを内にありて償《つぐな》わんとするのがそれがダルガスの夢であったのであります。しかしてこの夢を実現するにあたってダルガスの執《と》るべき武器はただ二つでありました。その第一は水でありました。その第二は樹《き》でありました。荒地に水を漑《そそ》ぐを得、これに樹をうえて植林の実を挙ぐるを得ば、それで事《こと》は成るのであります。事《こと》はいたって簡単でありました。しかし簡単ではあるが容易ではありませんでした。世に御《ぎょ》し難いものとて人間の作った沙漠のごときはありません。もしユトランドの荒地がサハラの沙漠のごときものでありましたならば問題ははるかに容易であったのであります。天然の沙漠は水をさえこれに灑《そそ》ぐを得ばそれでじきに沃土《よきつち》となるのであります。しかし人間の無謀と怠慢とになりし沙漠はこれを恢復するにもっとも難いものであります。しかしてユトランドの荒地はこの種の荒地であったのであります。今より八百年前の昔にはそこに繁茂せる良き林がありました。しかして降《くだ》って今より二百年前まではところどころに樫の林を見ることができました。しかるに文明の進むと同時に人の欲心はますます増進し、彼らは土地より取るに急《きゅう》にしてこれに酬《むく》ゆるに緩《かん》でありましたゆえに、地は時を追うてますます瘠せ衰え、ついに四十年前の憐むべき状態《ありさま》に立ちいたったのであります。しかし人間の強欲をもってするも地は永久に殺すことのできるものではありません。神と天然とが示すある適当の方法をもってしますれば、この最悪の状態においてある土地をも元始《はじめ》の沃饒に返すことができます。まことに詩人シラーのいいしがごとく、天然には永久の希望あり、壊敗はこれをただ人のあいだにおいてのみ見るのであります。 まず溝を穿《うが》ちて水を注ぎ、ヒースと称する荒野の植物を駆逐し、これに代うるに馬鈴薯《じゃがたらいも》ならびに牧草《ぼくそう》をもってするのであります。このことはさほどの困難ではありませんでした。しかし難中の難事は荒地に樹をうゆることでありました、このことについてダルガスは非常の苦心をもって研究しました。植物界広しといえどもユトランドの荒地に適しそこに成育してレバノンの栄えを呈《あら》わす樹はあるやなしやと彼は研究に研究を重ねました。しかして彼の心に思い当りましたのはノルウェー産の樅《もみ》でありました、これはユトランドの荒地に成育すべき樹であることはわかりました。しかしながら実際これを試験《ため》してみますると、思うとおりには行きません。樅は生《は》えは生《は》えまするが数年ならずして枯れてしまいます。ユトランドの荒地は今やこの強梗《きょうこう》なる樹木をさえ養うに足るの養分を存《のこ》しませんでした。 しかしダルガスの熱心はこれがために挫《くじ》けませんでした。彼は天然はまた彼にこの難問題をも解決してくれることと確信しました。ゆえに彼はさらに研究を続けました。しかして彼の頭脳《あたま》にフト浮び出ましたことはアルプス産の小樅《こもみ》でありました。もしこれを移しょくしたらばいかんと彼は思いました。しかしてこれを取り来《きた》りてノルウェー産の樅のあいだにうえましたときに、奇なるかな、両種の樅は相いならんで生長し、年を経るも枯れなかったのであります。ここにおいて大問題は釈《と》けました。ユトランドの荒野に始めて緑の野を見ることができました。緑は希望の色であります。ダルガスの希望、デンマークの希望、その民二百五十万の希望は実際に現われました。 しかし問題はいまだ全《まった》く釈けませんでした。緑の野はできましたが、緑の林はできませんでした。ユトランドの荒地より建築用の木材をも伐り得んとのダルガスの野心的欲望は事実となりて現われませんでした。樅《もみ》はある程度まで成長して、それで成長を止めました、その枯死《かれること》はアルプス産の小樅《こもみ》の併しょく《へいしょく》をもって防《ふせ》ぎ得ましたけれども、その永久の成長はこれによって成就《とげ》られませんでした。「ダルガスよ、汝の預言せし材木を与えよ」といいてデンマークの農夫らは彼に迫りました。あたかもエジプトより遁《のが》れ出でしイスラエルの民が一部の失敗のゆえをもってモーセを責めたと同然でありました。しかし神はモーセの祈願《ねがい》を聴きたまいしがごとくにダルガスの心の叫びをも聴きたまいました。黙示は今度は彼に臨《のぞ》まずして彼の子に臨みました、彼の長男をフレデリック・ダルガスといいました。彼は父の質《たち》を受けて善き植物学者でありました。彼は樅《もみ》の成長について大なる発見をなしました。 若きダルガスはいいました、大樅がある程度以上に成長しないのは小樅をいつまでも大樅のそばに生《はや》しておくからである。もしある時期に達して小樅を斫《き》り払ってしまうならば大樅は独《ひと》り土地を占領してその成長を続けるであろうと。しかして若きダルガスのこの言を実際に試《ため》してみましたところが実にそのとおりでありました。小樅はある程度まで大樅の成長を促《うなが》すの能力《ちから》を持っております。しかしその程度に達すればかえってこれを妨ぐるものである、との奇態《きたい》なる植物学上の事実が、ダルガス父子によって発見せられたのであります。しかもこの発見はデンマーク国の開発にとりては実に絶大なる発見でありました、これによってユトランドの荒地|挽回《ばんかい》の難問題は解釈されたのであります。これよりして各地に鬱蒼《うっそう》たる樅の林を見るにいたりました。一八六〇年においてはユトランドの山林はわずかに十五万七千エーカーに過ぎませんでしたが、四十七年後の一九〇七年にいたりましては四十七万六千エーカーの多きに達しました。しかしこれなお全州面積の七分二厘に過ぎません。さらにダルガスの方法に循《したが》い植林を継続いたしますならば数十年の後にはかの地に数百万エーカーの緑林を見るにいたるのでありましょう。実に多望と謂《いい》つべしであります。 しかし植林の効果は単に木材の収穫に止《とど》まりません。第一にその善き感化を蒙《こうむ》りたるものはユトランドの気候でありました。樹木のなき土地は熱しやすくして冷《さ》めやすくあります。ゆえにダルガスの植林以前においてはユトランドの夏は昼は非常に暑くして、夜はときに霜を見ました。四六時中に熱帯の暑気と初冬の霜を見ることでありますれば、しょく生は堪《たま》ったものでありません。その時にあたってユトランドの農夫が収穫成功の希望をもって種《う》ゆるを得し植物は馬鈴薯、黒麦、その他少数のものに過ぎませんでした。しかし植林成功後のかの地の農業は一変しました。夏期の降霜はまったく止《や》みました。今や小麦なり、砂糖大根なり、北欧産の穀類または野菜にして、成熟せざるものなきにいたりました。ユトランドは大樅《おおもみ》の林の繁茂のゆえをもって良き田園と化しました。木材を与えられし上に善き気候を与えられました、うゆべきはまことに樹であります。 しかし植林の善き感化はこれに止《とど》まりませんでした。樹木の繁茂は海岸より吹き送らるる砂塵《すなほこり》の荒廃を止《と》めました。北海沿岸特有の砂丘《すなやま》は海岸近くに喰い止められました、樅《もみ》は根を地に張りて襲いくる砂塵《すなほこり》に対していいました、 ここまでは来《きた》るを得《う》べし しかしここを越ゆべからず と(ヨブ記三八章一一節)。北海に浜《ひん》する国にとりては敵国の艦隊よりも恐るべき砂丘《すなやま》は、戦闘艦ならずして緑の樅の林をもって、ここにみごとに撃退されたのであります。 霜は消え砂は去り、その上に第三に洪水の害は除かれたのであります。これいずこの国においても椊林の結果としてじきに現わるるものであります。もちろん海抜六百尺をもって最高点となすユトランドにおいてはわが邦《くに》のごとき山国《やまぐに》におけるごとく洪水の害を見ることはありません。しかしその比較的に少きこの害すらダルガスの事業によって除かれたのであります。 かくのごとくにしてユトランドの全州は一変しました。廃《すた》りし市邑《しゆう》はふたたび起りました。新たに町村は設けられました。地価は非常に騰貴《とうき》しました、あるところにおいては四十年前の百五十倍に達しました。道路と鉄道とは縦横《たてよこ》に築かれました。わが四国全島にさらに一千方マイルを加えたるユトランドは復活しました、戦争によって失いしシュレスウィヒとホルスタインとは今日すでに償《つぐな》われてなお余りあるとのことであります。 しかし木材よりも、野菜よりも、穀類よりも、畜類よりも、さらに貴きものは国民の精神であります。デンマーク人の精神はダルガス植林成功の結果としてここに一変したのであります。失望せる彼らはここに希望を恢復しました、彼らは国を削《けず》られてさらに新たに良き国を得たのであります。しかも他人の国を奪ったのではありません。己れの国を改造したのであります。自由宗教より来る熱誠と忍耐と、これに加うるに大樅《おおもみ》、小樅《こもみ》の不思議なる能力《ちから》とによりて、彼らの荒れたる国を挽回《ばんかい》したのであります。 ダルガスの他の事業について私は今ここに語るの時をもちません。彼はいかにして砂地《すなじ》を田園に化せしか、いかにして沼地の水を排《はら》いしか、いかにして磽地《いしじ》を拓《ひら》いて果園を作りしか、これ植林に劣らぬ面白き物語《ものがたり》であります。これらの問題に興味を有せらるる諸君はじかに私についてお尋ねを願います。 * * * * 今、ここにお話しいたしましたデンマークの話は、私どもに何を教えますか。 第一に戦敗かならずしもふ幸にあらざることを教えます。国は戦争に負けても亡びません。実に戦争に勝って亡びた国は歴史上けっして尠《すくな》くないのであります。国の興亡は戦争の勝敗によりません、その民の平素の修養によります。善き宗教、善き道徳、善き精神ありて国は戦争に負けても衰えません。否《いな》、その正反対が事実であります。牢固《ろうこ》たる精神ありて戦敗はかえって善き刺激となりてふ幸の民を興します。デンマークは実にその善き実例であります。 第二は天然の無限的生産力を示します。富は大陸にもあります、島嶼《とうしょ》にもあります。沃野にもあります、沙漠にもあります。大陸の主《ぬし》かならずしも富者ではありません。小島の所有者かならずしも貧者ではありません。善くこれを開発すれば小島も能く大陸に勝《ま》さるの産を産するのであります。ゆえに国の小なるはけっして歎《なげ》くに足りません。これに対して国の大なるはけっして誇るに足りません。富は有利化されたるエネルギー(力)であります。しかしてエネルギーは太陽の光線にもあります。海の波濤《なみ》にもあります。吹く風にもあります。噴火する火山にもあります。もしこれを利用するを得ますればこれらはみなことごとく富源であります。かならずしも英国のごとく世界の陸面六分の一の持ち主となるの必要はありません。デンマークで足ります。然《しか》り、それよりも小なる国で足ります。外《そと》に拡《ひろ》がらんとするよりは内《うち》を開発すべきであります。 第三に信仰の実力を示します。国の実力は軍隊ではありません、軍艦ではありません。はたまた金ではありません、銀ではありません、信仰であります。このことにかんしましてはマハン大佐もいまだ真理を語りません、アダム・スミス、J・S・ミルもいまだ真理を語りません。このことにかんして真理を語ったものはやはり旧《ふる》い『聖書』であります。 もし芥種《からしだね》のごとき信仰あらば、この山に移りてここよりかしこに移れと命《い》うとも、かならず移らん、また汝らに能《あた》わざることなかるべし とイエスはいいたまいました(マタイ伝一七章二〇節)。また おおよそ神によりて生まるる者は世に勝つ、われらをして世に勝たしむるものはわれらの信なり と聖ヨハネはいいました(ヨハネ第一書五章四節)。世に勝つの力、地を征服する力はやはり信仰であります。ユグノー党の信仰はその一人をもって鋤《すき》と樅樹《もみのき》とをもってデンマーク国を救いました。よしまたダルガス一人に信仰がありましてもデンマーク人全体に信仰がありませんでしたならば、彼の事業も無効に終ったのであります。この人あり、この民あり、フランスより輸入されたる自由信仰あり、デンマーク自生の自由信仰ありて、この偉業が成ったのであります。宗教、信仰、経済に関係なしと唱《とな》うる者は誰でありますか。宗教は詩人と愚人とに佳《よ》くして実際家と智者に要なしなどと唱うる人は、歴史も哲学も経済も何にも知らない人であります。国にもしかかる「愚かなる智者」のみありて、ダルガスのごとき智《さと》き愚人がおりませんならば、不幸一歩を誤りて戦敗の非運に遭いまするならば、その国はそのときたちまちにして亡びてしまうのであります。国家の大危険にして信仰を嘲り「国家の大危険にして信仰を嘲り」、これを無用視するがごときことはありませんこれを無用視するがごときことはありません。私が今日ここにお話しいたしましたデンマークとダルガスとにかんする事柄は大いに軽佻浮薄《けいちょうふはく》の経世家を警《いまし》むべきであります。 底本:「後世への最大遺物 デンマルク国の話」岩波文庫、岩波書店 1946(昭和21)年10月10日第1刷発行 1976(昭和51)年3月16日第30刷改版発行1994(平成6)年8月6日 第64刷発行 青空文庫作成ファイル:このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
今、ここにお話しいたしましたデンマークの話は、私どもに何をおしえましすか。 ▼第一に戦敗かならずしもふ幸にあらざることを教えます。国は戦争に負けても亡びません。実に戦争に勝って亡びた国は歴史上けっして尠(すくな)くないのであります。国の興亡は戦争の勝敗によりません、その民の平素の修養によります。善き宗教、善き道徳、善き精神ありて国は戦争に負けても衰えません。否(いな)、その正反対が事実であります。牢固たる精神ありて戦敗はかえって善き刺激となりてふ幸の民を興します。デンマークは実にその善き実例であります。 ▼第二は天然の無限的生産を示します。実は大陸にもあります、島嶼(とうしょ)にもあります。沃野にもあります。砂漠にもあります。大陸の主(ぬし)かならずしも富者ではありません。小島の所有者かならずしも貧者ではありません。善くこれを開発すれば小島も能く大陸に勝さるの産を産するのであります。ゆえに国の小なるはけっして歎くに足りません。・・・。 ▼第三に信仰の実力を示します。国の実力は軍隊ではありません、軍艦ではありません。はたまた金でがありません、銀ではありません、信仰であります。・・・。よしまたダルガス一人に信仰がありましてもデンマーク人全体にに信仰がありませんでしたならば、彼の事業は無効に終わったのであります。このひとあり、この民あり、フランスより輸入されたる自由信仰ありて、この偉業が成ったのであります。宗教、信仰、経済に関係なしと唱うる者は誰でありますか。宗教は詩人と愚人とに佳くして実際かと智者に要なしなど唱うる人は、歴史も哲学も経済も何にも知らないひとであります。國にももしかかる「愚かなる智者」のみありて、ダルガスのごとき「智(さと)き愚人」がおりませんならば、不幸一歩を誤りて戦敗の悲運に遭いますならば、その国はそのときたちまちにして亡びてしまうのであります。国家の大危険にして信仰を嘲り、これを無用視するがごときことはありません。私が今日ここにお話しいたしましたデンマークとダルガスに関する事柄は大いに軽佻浮薄(けいちょうふはく)の経世家のを警(いまし)むべきであります。 2011.04.18 内村鑑三著作:中江藤樹 |
 小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.29~33
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.29~33
岡 倉天心 牛鍋囲んで逍遥らと文学論 日本橋蛎殻町松平家下屋敷の一隅をかりてはじめた岡倉勘右衛門の宿屋は、福井県から上京するものがほとんど例外なしに泊まってくれ、開店早々から繁盛したらしいが、勘右衛門をもっともよろこばせたのは、せがれのできのよさであったろう。長男は早死にしたが、次男覚三(天心)は抜群の秀才で、十二歳で官立外国語学校にはいり、十四歳で官立東京開成学校にうつった。これはその二年目に東京大学と改められたから、覚三は十六歳の若さで東大生となったわけである。同学年には井上哲次郎(のち文学博士)、牧野伸顕(のち内大臣、伯爵)などがいた。 文学部の覚三は、政治学、理財学などのほか、中村正直(敬宇と号す)の漢文教室、ウイリアム・ホートンの英文学教室に親しんだ。中村は、明治十年四十六歳で文学部嘱託となったが、もとは幕府の儒官。慶應二年から明治元年まで英国に留学し、四年にスマイルス『セルフ・ヘルプ』の訳を『西国立志編』と題して出版し、ベストセラーとなった。もと幕府の騎兵頭だった益田孝が、井上馨にスカウㇳされて造幣頭として大阪にいったとき泊まった宿屋のむこ養子が馬越恭平(のち大日本麦酒社長)で、「馬越はタスキをかけておひつをあらっておった。細君はビンズケで髪をてかてかにして、襟にちり紙を当てておった。だんだん馬越の様子を見るとなかなか見こみのある男だから、これを読みたまえというて中村敬宇の西国立志編をやった。馬越はそれで大いに志を立てた」(『益田孝翁伝』)と益田は語っている。やがて馬越は宿屋をとびだして益田の部下となり、三井物産横浜支店長となるのである。 ところで岡倉覚三の方は、とくに英米文学を耽読した。ある日、同級生の福富孝季と小石川の牛肉屋の二階にあがり、牛鍋をつつきながら外国文学論を戦わしていると、隣の席に二人の学生がやってきて、これまた外国文学論をやりはじめる。そこでいっしょになって、大いに語ろうではないかということになった。 二人とも東大生だ。一人は江戸深川の高田早苗、もう一人は美濃大田出身の坪内友蔵(のち逍遥と号す)である。大学では、高田は岡倉より二年後輩で、坪内はさらに一年おくれて卒業するが、年齢は逆で、その会合を明治十一年と推定すれば、坪内は二十歳、高田十九歳、岡倉十七歳ということになる。しかし岡倉がもっとも早熟で、翌年十八歳で妻帯、十九歳で文学士、月給四十五円の文部省御用掛となるのである。 「だれの作品がいちばん好きか?」ということになり、 「ウオルター・スコツㇳの『アイヴァンホー』が好きですね」 と高田が言った。福富は、アレキサンドル・デューマの『モンテ・クリスト伯』をあげ、岡倉はヴィクトール・ユーゴ―の『レ・ゼラブル』をあげる。このとき、のちの逍遥坪内青年がひとり沈黙していたのはふにおちかねるが、京口元吉によれば、」「当時、逍遥先生にはまだチンプンカンプンで、目を丸くしてきき入るばかり。それを勧めて、逍遥先生にスコツㇳの『湖上の佳人』を読み合わせ、『春窓綺話』と題して、共訳出版するに至らしめて、後年の大英文学者に仕立てあげたのも、わが高田早苗先生>(『高田早苗伝』)だったわけである。もっとも門外漢だった逍遥ただ一人プロの英文学者になったところに、人生の面白さがあるようだ。 四人のうち、学問にもっとも縁が深かったのは高田といえる。彼の父は定職をもたず、家計窮迫、給費生としてようやく学業をつづけていたけれども、もとは江戸屈指の豪家であった。紀州和歌山の藩主徳川吉宗が八代将軍となったとき、随従して江戸にうつり住んだ御用商人高田茂右衛門友清がその先祖。 友清は府内に二十六ヵ所もの宅地をもつ富豪となったが、自費をもって下総(千葉県)手賀沼で二万石、武藏大宮(埼玉県)の見沼で一万石の新田を開発し、さらに利根川の水を荒川へおとす運河工事をして、産を失った。幕府ではその功績を認め、二千石の旗本にしようとしたのを友清はことわり、利根川・荒川間の通商営業を許してもらって、代々通船問屋として巨富を貯えた。六代六郎左衛門與清は学究で博覧強記、蔵書十万冊に達し、平田篤胤、伴信友とならんで江戸時代後期における国学の三大家と仰がれた。その血は曽孫の早苗にもっとも濃く伝わったようである。 高田家は、天保改革によるふ況期から左前となり、とくに早苗の父小太郎清常は十九歳で幕末の動乱期に当主となり、やがてそのすべてを失った。早苗には二人の兄があったが、いずれも他家に養子となり、三男坊の早苗が九代当主となっている。「種々の事情で、と先生はボカしているが、想像をたくましくすることが許されるならば、おそらくは傾く家計を補うための口減らしのためであったのではなかろうか」(京口・前掲書)。 しかし、家は窮迫しても、早苗の才能は光った。小室樵山という書家について書道と漢籍の素読をならっていた十二歳のとき、樵山がその日の米塩にも事欠きながら藩閥をきらって就職口をことわったのを知ると、数日前にならったばかりの「蒙求」の一節――「父母ノイマストキハ、官ヲエラバズシテ仕フ」を引用して、中風の老父を貧苦に悩ませておいてせっかくのご用をことわるとは心得ませぬ、とやりこめて、先生の目を白黒させたことがあったという。 このすぐれた友人によって文学的開眼をした逍遥は、やがて『当世書生気質』を書いたとき、主人公小山田燦爾のモデルに高田をつかつた。スラリとした長身の、気品のある美男子だった早苗はどこでも大もてにもてたので、モデルとしてはうってつけであったわけだ。 ところで、岡倉と高田の縁も、牛鍋の文学論議だけではおわらない。明治三十一年岡倉天心が日本美術院を創立したとき、開院式にのぞんで祝辞をのべた文部省高等学務局長が高田だったのである。ただその友情は、大正二年九月、五十二歳の天心の死によって断たれる。高田は七十九歳まで長命し、この間、法学博士、貴衆両院議院、文部大臣、早稲田大学総長となった。また逍遥も七十七年の生涯があった。福富孝季は、外相大隈重信の条約改正に反対した頭山満、杉浦重剛などのメンバーの一人に名前が出てくるが、斎藤隆三は「いくばくならず福富は自決して亡くなった」(『岡倉天心』)と書いている。天心は二首の弔詩を献じたという。 人物1、福富孝季:(1857~1891) 明治時代の教育者。安政4年11月生まれ。明治19年イギリスに留学し,心理学,教育学をおさめる。帰国後は高等師範教授となった。臨淵の号で劇評家としても知られ,著作に『私撰浄瑠璃年代記』などがある。明治24年4月9日死去。35歳。土佐(高知県)出身。東京大学卒。 人物2、高田早苗:(1860~1938)政治家,教育家。江戸深川出身。小山田与清の孫。東大卒。号は半峰。大隈重信に協力し立憲改進党,東京専門学校(のちの早大)の創設に参画。1890年以降衆議院に当選6回。大隈の腹心,改進党・進歩党の幹部として活躍。第2次大隈内閣の文相を勤め,教育調査会総裁として1918年公布の大学令立案に努めた。1923年早大総長。 人物3、坪内逍遥:(1859~1936)小説家,劇作家,評論家。本みょう勇蔵のちに雄蔵。美濃国生れ。東大政治学科卒。1885年『小説神髄』を書き『当世書生気質』を発表して写実による近代文学の方向を示した。二葉亭四迷をはじめ,逍遥の近代文学論は広く大きな影響を与えたが,自身は1889年の『細君』を最後に小説の筆を折った。1890年,東京専門学校(早稲田大学の前身)に文学科を設け,翌年《早稲田文学》を創刊し,後進の育成に努めた。また同誌を発表の場として森鴎外との間に没理想論争を展開した。また演劇革新を志して戯曲『桐一葉』『牧の方』『沓手鳥(ほととぎす)孤城落月』等を発表,『新曲浦島』などの舞踊劇をも創作した。演劇研究所を作って俳優の養成に努め,早稲田大学演劇博物館を建設し,『シェークスピア全集』の翻訳を完成するなど,日本近代文学,演劇の発展史上に大きな功績を残した。 2019.05.24

アジアは一つだ。ヒマラヤ山脈は、二つの強力な文明――孔子の共同主義のシナ文明と、ヴェーダの個人主義のインド文明とを、ただこれを強調せんがために分つ。しかしながら、この雪の障壁をもってしても、あの窮極と普遍とに対する広い愛の拡がりを、ただの一時もさえぎることはできないのだ。この愛こそは、全アジア民族共通の相続財産ともいうべき思想なのだ。この愛こそは、彼らに、世界のすべての大宗教を生み出すことを得させたものなのだ。(東洋の理想)
12月26日生まれた美術評論家。東京美術学校長をつとめ、日本美術院を設立するなど、明治美術の父と称せられる。主著『日本の目覚め』『茶の本』 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.213
小林司著『出会いについて』精神科医のノートから (NHKブックス)P.20 から 『茶の本』や『東洋の理想』を書いた岡倉天心(一八六二~一九一三)の父親は、越前福井藩の藩士であり、横浜で藩が経営していた貿易店の支配人をしていた関係上、岡倉天心は、七歳頃からアメリカ人に英語を習っていたために英会話がひじょうにうまかった。 そして、東京大学の文学部の学生だったときに、米国人アーネスト・フェノロサ(一八五三~一九〇六)に通訳として雇われたのである。 フェノロサは、その前の年、一八七八年に東京大学の教員として日本に着任し、日本の絵や彫刻を見て、日本の古美術を研究したいと考えていたのである。そして、フェノロサといっしょに画家や画商に会って通訳をしたり、ほうぼうを訪ねて絵や彫刻を見ているうちに天心自身も、古美術に強く魅力を感じるようになった。西洋美術にはない、独特の美がある日本美術の伝統を活かして、新しい日本の美術を生み出したい、と天心は考えた。その後、ヨーロッパで西洋美術を研究して、日本の美術がすぐれているという確信うをもち、一八八九年にはフェノロサと協力して東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)を開設させた。そして、岡倉天心は、校長兼日本美術史の教授になったのである。のち、一九〇四年にはアメリカに招かれて、ボストン美術館の東洋部長になっている。 天心とフェノロサとの出会いもまた、初めて出会った瞬間に火花を散らしたというようなものではなくて、むしろ知合ってから長い期間にしだいに感化された、と考えるべきであろう。
司馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版 雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。「ますらおぶり」「たおやめぶり」忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 第六章 日本にきた外国人 フェノロサ、チェンバレン、サンソム P.136~ 司馬 サトーは後年イギリスに帰りますが、日本のことを全然言いたがらなかったそうですな。懐しそうにも語らないし、読む本は、ひじょうに古典的なオーソドックスなヨーロッパのものばかり読んでいたといいます。これは萩原延壽さんのイギリスで得た成果で、私が聞いた萩原さんの解釈を受け渡しするので、少しずつ間違いがあると思いますけれども……。 ※萩原延壽は東京都台東区浅草出身。旧制三高(現・京都大学総合人間学部)卒業後、練馬区立開進第一中学校教員を務める。東京大学法学部政治学科へ進学。卒業後、同大学院で岡義武に師事。修了後、国立国会図書館調査立法考査局政治部外務課に勤務。米国ペンシルベニア大学・英国オックスフォード大学に留学。英国留学中、丸山眞男の知遇を得る。帰国後、著述活動に専念し、『中央公論』など論壇で活躍。各大学からの教員職を断り、在野の歴史家として生涯を通した。 英国滞在中、英国国立公文書館に保管されていた英国外交官アーネスト・サトウの1861年から1926年までの45冊の日記帳を調べ上げ、サトウの幕末期から明治初期までの活動を描いた大作『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』(全14巻)を、朝日新聞に休載をはさみつつ約14年間連載、完結刊行を見届け2001年(平成13年)10月24日逝去、享年75。なお同年には、執筆生活を支え続けた夫人に先立たれており、後を追うように生涯を終えた。 ※アーネスト・サトウ著『一外交官の見た明治維新上・下』坂田精一訳(岩波文庫)昭和四七年二月二十日 第一四刷発行 それはなぜかということなんですが、とにかくサトーは一大構想があって日本を動かしたわけでしょう。自分では、明治維新は自分の作品だと思っています。じじつ彼が西郷に匹敵するほどの志士として存在したことは確かです。けれども、明治維新政府の大官たちがもうサトーを必要としなくなっいたということですね。それに腹が立っている。これはぼくはひじょうにわかる。おれになぜいろいろありがとうございましたと言わないのか、ということですよ。それはあるでしょう。サトーのほうが日本にたいする思い入れは強いのですからね。明治維新政府の大官たちには、サトーの果たした役割をよく知らない人が多かったと思う。それがやっぱり悲しかったことと、それから中国公使になったときもう一度やってやろうと思ったのですね。日本で成功したことをもう一度義和団の乱のあとの中国でやってやろうと思ったが、向うは国が大きくて、とてもややこしく、北京公使としての仕事があまり思わしくいっていなかったというがあるようです。 それからもう一つは、サトーには天才のもっている病理学的な性質があったでしょうね。これは私自身のかってな見方ですけれども、分裂症的な性格でもって、ひとつ熱中したら凝り性で、うんと凝って、凝ったあとはケロッと忘れているタイプの人があるでしょう。あれもあっいたかもしれない。 キーン しかし、そういう傾向は、日本に来たあらゆる外人の場合にも認められると思います。サトーだけのことじゃなかったようです。たとえばフェノロサ(明治十一年来日)もそうだったし、チェンバレン(明治六年来日)もそうでした。そしてだいたい理由は同じじゃないかと思います。ともに日本で相当大きな仕事をやって、日本人に尊敬されました。しかし日本に弟子をつくって、弟子がだんだん自分のやったこともできるようになった。もう日本ではその人は必要でなくなるわけです。 フェノロサの場合は明らかにそうだったですね。彼がはじめて日本に来たときは、日本は国宝が売られている時代だった。いま京都に住んでいる私の親しい友人の祖父にあたる人が、明治五年に宣教師として京都に来たとき知恩院のお坊さんに、「大きな鐘があるがいりませんか。売りたい」と言われたそうです。それがあとで国宝になった有名な知恩院の鐘です。その人は「結構なものですけれども、うちとしては大きすぎます」とおことわりしたそうですが……(笑い)。あの時代は、だれも日本の古きよきもののよさを認めていなかった。なんでも新しい西洋的なものを喜んだ時代でした。フェノロサは、なるべく日本人に自分たちのだいじな過去の美術のよさを教えたかった。だから弟子もつくったのでしょう。一番の弟子はなんといっても岡倉天心です。フェノロサは何かの用事でアメリカへ帰ったのち、二度めに日本にやって来ましたが、もうだれも彼を雇わなかった。日本人で同じような仕事をする人がすでにいましたから、わざわざお雇い外人さんに高いお金を出す必要はなかったのです。 2010.06.08、2019.06.01追加。 |
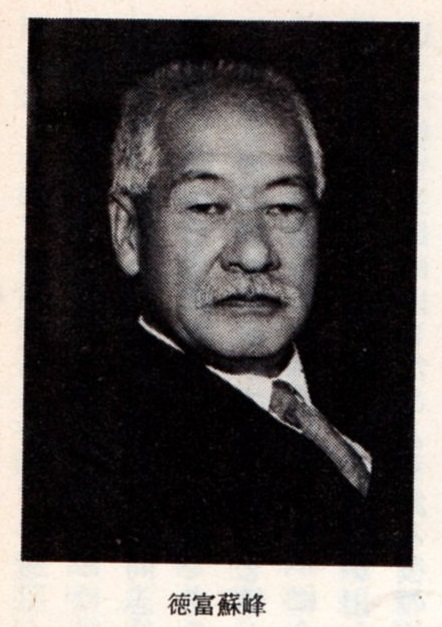
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.134~138 徳富 蘇峰 福地 桜痴を慕い記者志す 昭和四十二年夏に出た『京都二十景』という本は旅情を大いにそそる。ことに空気のうまさ、町をとりまく山なみの稜線の目を洗うようなあざやかさ、舗装した道の下をながれる溝のせせらぎが耳につくほどの静けさ、鷹ヶ峰、下六丁峠、苔寺のほとり、鞍馬街道、今熊野の泉涌寺、嵯峨野の上の菖蒲谷池、山科の疎水べりなど、「恋を語る散歩道」という形容詞をつけられたあたりは、一人でもいいから歩いてみたい衝動を感じる。 今日においてもこういう自然環境なのであるから、約九十年前、同志社入学を思い立った徳富猪一郎が訪れたころはどんなによかったかと思われるが、『蘇峰自伝』には、その印象をつたえる文章は一行もなく、明治十三年十八歳のときつくった「京都」とい詩は、「春帰春去遂如何。五歳星霜容易過。恥汝東三十六峰。屏顔依旧翠烟多」というもので、明治青年の一タイプらしく立身出世を思う気持が強く出ている反面、詩的情熱という面は淡いように感じられる。 それはそれとして、徳富が東山三十六峰を眺めて感慨にひたるまでには、いくたの迂路(うろ)をたどっている。郷里水俣を出たのは明治三年、八歳の秋で、彼をつれていったのは横井小楠未亡人、すなわち母の妹津世子(つせこ)であった。 そして熊本時代がはじまる。いくつかの塾を転々として熊本洋学校にはいったのが十歳のときで、このときは成績が上がらず、年齢不足の名目で退校させられ、八年夏、再入校した。九年一月、小楠の忘れ形見時雄、金森 通倫(みちとも)、海老な 喜三郎(弾正)、浮田 和民など有志三十五名による「花岡山事件」がおきた。彼らは熊本の西南にある花岡山にのぼり、円坐して「奉教主意書」を朗読し、神に祈り、誓約署名したが、その中に徳富の名前もある。ただ彼は、「予の真意は深くキリスト教を研究して、それを信じたのではなかった。もとよりキリスト教のために一生を捧ぐるという了見は露ほどもなかった」(『自伝』)と述懐している。 学校のキリスト教化は大問題となり、彼らは父兄たちに猛烈な圧迫をうけた。徳富も自宅によびもどされ聖書と讃美歌を焼かれ、父一敬にきびしく折檻(せつかん)されたあと、上京して勉強しなおすことになったのである。 一方熊本洋学校は閉鎖され、学生の一部は外人教師の紹介で、前年十一月に開設されたばかりの、京都の同志社英学校にはいった。彼らは「熊本バンド」といわれ、その学力とまじめな素行を創立者新島 㐮に高く評価されたが、彼らも新島に建白書を出し、酒、タバコはもとより、買い食いしない、料理屋へ行かないなどの塾則案を示し、採用された。 東京で神田一ッ橋の東京英語学校に入った徳富は二月ほどで絶望し、京都に金森通倫を文通したあと、親戚の反対を押しきって同志社入学を決行した。「予は学校は書物を読むところというよりも、むしろ師について学ぶ処であるという考えをもっていたから、その場所を東京において見出さず、京都において見出さんと欲したのである」。 しかし、同志社には絶望した。第一に食事に閉口した。麦飯がきらいで、親戚にとまって麦飯が出ると一日ぐらいは絶食し、麦飯が出ないと「今度は麦飯これなく、ご安心下され候」という手紙を父母に出したこともある彼の前に、麦の中に牛肉の塊を入れて煮たものがほとんど毎日出された。肉は引き出して細かく切り、菜っ葉とともにスープにし、麦は茶わんにもって食べるのであるが、「麦飯ともつかず、ただザラザラに煮たものをすすりこむことは、予にとって少なからざる苦役であった」。 その上、学費がなくなった。東京をたったときもってきた三十円は次第になくなったが、無断転校をしたため、郷里にいってやるわけにはゆかない。「絶望の倹約」で、着物も一度きたらそれが切れてなわのようになるまで替えない。しかし、とくに必要ないかぎりは帯もとかずに起臥(きが)し、ふろにもほとんどはいらないため、学生たちは彼のそばに近づくのをいやがるようになった。旅の途中に彼とあった従兄は「猪一郎さんはまるで乞食のような風をしている」という報告書を送ったほどだ。 徳富の心を苦しめたのは貧乏ではなく、「何事もアメリカ、アメリカといい、日本の事を全く忘れているような」学校内の空気であった。明治十年、新島の説教のあと、外国の飢饉(ききん)にたいする救助金募集があったとき、たまりかねた徳富は声をふるわせて立ちあがり、「今わが国には戦争があり、私の郷里熊本には、これがために非常な不幸に陥っているものがある。それらにたいして救助することをせず、縁もゆかりもない他方の人の不幸を救うのは、前後緩急をあやまったことで、いかに結構でも私一人として賛成できない。故に私は寄付をことわる。しかしもし西南の役において不幸になったものを救うならば、自分だけのことはするつもりです」と叫んだ。 宗教書を読むことよりも、彼は新聞雑誌をむさぼり読んだ。自分で買う余力はなかったが、同志社には、東京のものでは『東京日日新聞』、『報知新聞』『朝野新聞』が、大阪のものでは、『大阪日報』がきていた。福地 桜痴、犬飼 毅、成島 柳北など、ジャーナリズムの花形の存在も、「花形」として心にきざまれたが、とくに福地の人間像は、徳富の人生に大きな影響をのこしたようである。福地はこのとき三十七歳、各社とも社長級の大物を動員したにもかかわらず、報知の矢野竜渓、朝野の成島柳北とともに京都にとどまって南下しなかったのに、東京日日新聞社長たる福地は、自ら特派員となって現地にのりこみ、「戦報採録」で好評嘖々(さくさく)、紙数を激増させた。そのころ、道楽者として聞えた彼は「池の端の御前」としてぜいたくなくらしをしていたが、従軍にあたっては、家族に後事を託し、愛妓にも手当をして出発したといわれる。そういう裏面をしらぬ福富は福地を敬慕し、ことに木戸孝允の要望に京都御所に伺候し、戦況報告をした一事は、「一布衣(ほい:無位無官)の身をもって謁見仰せつけられ……此事の如きは予の頭脳に少なからざる刺激をあたえたように覚えている」(『自伝』)と彼自身も文章にしている。 同年五月二十六日、内閣顧問木戸 孝允が京都で病死した。享年四十五歳。福地は戦地から電報で原稿を送り、五月二十八日から六月四日まで「木戸小伝」として連載された。「公ノ病ニ在ル、一眼覚ル毎ニ則チ曰ク、某ニ遇ヘリ、曰ク、某来レリㇳ。(中略)一日奄然ㇳシテ睡ニ就キ、将ニ逝カンㇳスル者ノ如ク、而シテマタニㇵカニ大呼シテ曰ク、"西郷モー大抵ニセンカ"。コレヨリ二日ヲ経テ薨ズルㇳ云フ」というこの連載を、徳富は「もっとも愛読した」。そして福音を説く説教師ではなく、一管の筆に慷慨(こうがい)の志を述べる新聞記者になろうという志が、まさにこの京都の時代に確立したのである。 2019.06.29 |
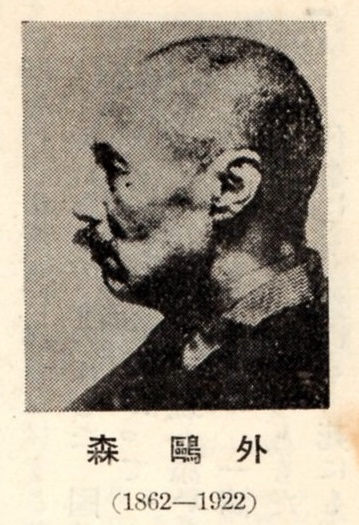
「きようなり。きようなり。きのうありて何かせん。あすも、あさても空しきなのみ、あだなる声のみ。」この時、二点三点、粒太き雨は車上の二人が衣を打ちしが、またたくまに繁くなりて、湖上よりの横しぶき、あららかにおとずれ来り、紅を潮したる少女が片頬に打ちつくるを、さしのぞく巨勢の心は、唯そらにのみやなりゆくらん。少女は伸びあがりて、「御者、酒手は取らすべし。疾く駆れ。一策加えよ、今一策。」と叫びて、右手に巨勢がくびを抱き、己はうなじをそらせて仰ぎみたり。 7月9日この日死んだ近代日本の古典的文学者。医科大学を出て軍医総監となったが、文学により大きな仕事を残した。『鴎外全集』 *桑原 武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.114
※本棚にある森 鷗外の本
平成二十九年六月十六日 |
|
「(岡田は)総理大臣になると、三つのものがみえなくなるといった。三つのものとは、第一に金。いつも公金を思うように動かし、自分で金を使うことがないからその価値がわからなくなる。第二は人だ。周囲の取巻きに囲まれて、甘言やら追従をきくことが多いために、誰が本当の人物か、誰が奸人か 佞人か、その区別がつかなくなる。第三は、国民の顔がどちらをい向いているか分からなくなる。この三つが見えなくなった時は、総理大臣はのたれ死する、と彼は言い切っている」 参考:軍人・政治家(総理大臣) *小島直記『逆境を愛する男たち』(新潮社)P.158 「第二十四話 権力者の不明」より。 2010.12.19 |
10 上山英一郎 鶏口となるも牛後となる勿れ(1,862~1,943)
|
社是、社訓といえば企業の"旗"だが電通の「鬼十則」のように行動規範をずばりと打ち出したような個性的なものは、意外にすくない。たいていはその文脈も似たりよったりで、誠意、信用、創意工夫などといった常套句を織りまぜたものや、どこまで本気なのか、建前ばかり謳いあげたものが多い。 先ごろも「大口顧客への損失補填」という證券スキャンダルが台風のごとく通りすぎたあと、有名証券数社の"社是"をゆっくり眺めてみると、 《顧客と共に栄える》 《顧客と共に~信頼と発展~》 《顧客と共に繁栄しよう。信用を重んじ、誠実に奉仕する》 《證券業の使命を認識し顧客への奉仕を第一とする。信用を重んじ勤勉誠実を旨とする》 というのだから、その白々しさに破顔ってしまう。 こうした建前ばかりのフレーズにくらべると、上方商人の血をうけつぐ大阪の老舗に伝わる家訓などは、虚飾がなく、 《良い暮しを望むなら、一所懸命に働け》(書画材料の『丹青堂』) 《商いは牛のよだれ》(すき焼きの『北むら』) と、みずから信じるところの商人道を語って直截である。 飾り気がないといえば、創業一四〇五年の蒼古たる来歴をもつ社寺建築業、金剛組の家訓もまた質朴をきわめている。 その金剛家第三十七代、金剛喜定が残した「遺言書」に『職家心得之事』がある。要約すると、 一、曲尺の使いかたなど、基本的な技術の修得に励んだ上で仕事に当る事。 一、読み書き、そろばん等の稽古は専ら致す事。 一、世間の人々の交わりいたすとも、物事を頼み過ぎてはいけない。 一、大酒は、いたさない様つつしまなかればならない。 一、身分に過ぎた華美な衣服をまとうな。 一、門人、弟子に至る迄、目下の人には厚い心で接しなければならない。 一、何事も人とあらそってはならない。 一、どんな人にでも、いんぎんに接しなければならない。 一、諸事取引する相手とは無私正直に面談する事。 ――という。 海を越えてきたといえば、中国古典の故事を創業者の経営信条とし、社訓にしている企業がある。 《鶏口となるも牛後となる勿れ》(『史記』蘇秦列伝・『戦国策』韓策) 除虫剤の事業を興した上村英一郎は、商品の品質、信用、経営などの方面からみても、つねに業界のトップメーカーとして立つという自負のもとに、
黄金の鶏(金鳥)》
を社のシンボルマークにした。
寧 為鶏口、 無為牛後》むしろ鶏口となるとも、牛後になるなかえれの意は、紀元前四世紀末、諸国を遊説していた論客蘇秦が韓の宣恵王に
「大きなものの尻尾(尻の穴という説もある)になるより、小さくちぇも頭になれ」
と説った有名な言葉からきている。
この、黄金の鶏を心意気とした上山は、和歌山県の有田箕島に生まれた。箕島は、有田川の河口にひらけた、両岸の山々をうずいめつくす壮大な蜜柑畑に囲まれた町である。
除虫菊発祥の地であるこのあたりは、戦前まで、初夏になると雪のような白い花におおわれた除虫菊の一大栽培地であった。
この除虫菊の、白い可憐な花にふくまれている強力な殺虫成分に着目したのが上村英一郎である。有田地方で一、二といわれる豪農の家に生まれた英一朗は、上京して慶應義塾に学ぶが病を得て、帰郷、家業の蜜柑農に励む。
そんな英一朗の蜜柑国に福沢諭吉の紹介状をもらったアメリカ人、植物輸出入会社のH・E・アーモア社長がやってくる。英一郎がアーモアから貰った一つまみの除虫菊ビューハクの種子を山田原の地に蒔くのは明治十九年(一八六六)のことである。
この除虫菊が、やがて全国にひろがっていくのだが、その背後には除虫菊が国家事業として有力なことを、四国、中国から北海道まで全国を巡回し講演会をひらいて力説し、希望者には無料で種子を配って播種栽培を奨励し、奔走した英一朗のふ断の努力がある。
「除虫菊は、農家の裏作として麦よりも有利で、山畑や荒蕪地にも簡単に栽培できる」
と、英一郎は熱っぽく説いてまわった。
後年、この英一郎のひたむきな指導に感謝した岡山、広島、香川、愛媛など除虫菊の生産地の人びとは、尾道の千光寺公園に頌徳碑を建て、対岸の向島に除虫菊神社(祭神・上山英一朗)を建立し、英一郎を神として祀つている。
ともあれ、自宅付近に工場を建て、兵庫県尼崎に分工場、大阪をはじめ北海道から遠くニューヨークにまで支店を置き、総生産量の六割をアメリカに輸出するまでになった英一郎は、明治二十九年、シベリア鉄道の終点ウラジオストックで三階建てのビルを支店にし、巨大な看板をかかげてロシア人を仰天させるなど、派手な活躍ぶりをみせる。が、明治三十八年、朝鮮の支店に赴いたとき、何物かに狙撃されたり、翌三十九年、戒厳令下のシベリアを旅行中にスパイ容疑で逮捕され、銃殺されかけたり、死に直面したこともしばしばであったという。
除虫菊の栽培に成功した英一郎も、渦巻き式蚊取り線香の型式に定着させるまで幾つかの苦難に直面している。カイロ灰式から仏壇線香にヒントを得た棒状蚊取り線香が開発され、輸送中の破搊が減少したという大正期から昭和十年代までが蚊取り線香の黄金期であった。昭和十年の除虫菊の干花三十九万九千貫、わが国除虫菊生産の最高記録である。殺虫剤開発に生涯を賭けた情熱の人、上山英一朗、昭和十年天寿を全うして逝く。八十歳であった。
英一朗が、白い除虫菊の花に託した夢は、戦後、大輪の花を咲かせる。
アメリカ軍によってもたらされたDDTが過大に宣伝されたため、一時は除虫菊産業は消滅してしまうのではないかと憂慮されたが、防疫用除虫菊乳剤の製造によって立ち直り、日本経済が好転しはじめた昭和二十六年、除虫菊の輸出もまた本格化した。
英一朗が興した除虫菊栽培は、やがて除虫薬品の原料が化学品となって時の流れのなかに姿を消していった。が、新しい家庭用殺虫剤、農薬、除草剤、各種防疫剤などを開発した彼の後継者たちは、《為鶏口、無為牛後》の旗じるしのもとに更なる躍進をつづけておる。もちろん、茶の間におくりこまれている、華やかな"金鳥"のテレビ・コマーシャルなど、彼が知ろう筈もンいのだが。
神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.208~212
2021.06.01記
|

『武士道』
新渡戸 稲造著 矢内原忠雄訳(岩波文庫)1985年5月16日 第29刷 発行 「武士道」はその表徴たる桜花と同じく、日本の土地に固有の花である。*こう説きおこした新渡戸は以下、武士道の淵源・特質、民衆への感化を考察し、武士道がいかにして日本の精神的土壌に開花結実したかを解き明かす。「太平洋の架け橋」たらんと志した人にふさわしく、その論議は常に世界的コンテクストの中で展開される。表て紙に書かれている文章。 *『岩波文庫』表て紙に書かれている文章。 第一章 道徳体系としての武士道 武士道はその表徴たる桜花と同じく、日本の土地に固有の花である。それは古代の徳が乾からびた標本となって、我が国の歴史の腊用集中に保存せられているのではない。それは今なお我々の間における力と美との活ける対象である。それはなんら手に触れうべき形態を取らないけれども、それにかかわらず道徳的雰囲気を香らせ、我々をして今なおその力強き支配のもとにあるを自覚せしめる。それを生みかつ育てた社会状態は消え失せて既に久しい。しかし昔あって今はあらざる遠き星がなお我々の上にその光を投げているように、封建制度の子たる武士道の光はその母たる制度の死にし後にも生き残って、今なお我々の道徳の道を照らしている。ヨーロッパにおいてこれと姉妹たる騎士道が死して顧みられざりし時、ひとりバークはその棺の上にかの周知の感動すぺき讃辞を発した。いま彼れバークの国語〔英語〕をもってこの問題についての考察を述べることは、私の愉快とするところである。 極東に関する悲しむべき知識の欠乏は、ジョージ・ミラー博士のごとき博学の学者が、騎士道もしくはそれに類似の制度は古代諸国民もしくは現代東洋人の間には嘗て存在しなかったと、躊躇なく断言していることでも解る。しかしながらかかる無知は恕すべき点が大である。何となればこの善き博士の著書の第三版は、ペリー提督が我が国鎖国主義の戸を叩きつつあったと同じ年に発行せられたのであるから。その後十年以上をへて我が国の封建制度が最後の息を引き取ろうとしていたころ、カール・マルクスはその著『資本論』において、封建制の社会的政治的諸制度研究上の特殊の利便に関し、当時封建制の活きた形はただ日本においてのみ見られると述べて、読者の注意を喚起した。私も同様に西洋の歴史および倫理研究者に対し、現代日本における武士道の研究を指摘したいと思う。 ヨーロッパと日本の封建制および騎士道の歴史的なる比較論は興味あることではあるが、詳細にわたりてこれに立ち入ることは本書の目的ではない。私の試みはむしろ第一に我が武士道の起源および淵源、第二にその特性および教訓、第三にその民衆に及ぼしたる感化、第四にその感化の継続性、永久性を述ぶるにある。これら諸点の中第一はただ簡単かつ大急ぎに述べるに止める。然らずんば私は読者をば我が国史の紆曲せる小路にまで連れこむことになるであろう。第二の点はやや詳細に論じよう。けだしそれは国際倫理学および比較性格学の研究者をして我が国民の思想および行動のやり方について興味を覚えしめるだろうから。残りの点は余論として取扱うであろう。 私が大ざっぱにシヴァリー Chivalry と訳した日本語は、その原語においては騎士道というよりも多くの含蓄がある。ブシドウは字義的には武士道、すなわち武士がその職業においてまた日常生活において守るべき道を意味する。一言にすれば「武士の掟」、すなわち武人階級の身分に伴う義務である。かく字義を明らかにした以上、これから原語でこの語を用うることを許してもらいたい。原語を使用することはまた別の理由からも都合がよい。このように截然として独自的であり、特異なる考え方と性格の型を生み出し、かつこれほど地方的なる教訓は、その特殊性の徽章を面上に帯びておらねばならない。それ故、民族的特性を極めて顕著に表現する二、三の語は国民的の音色ねいろをもつのであって、最善の翻訳者といえどもその真を写しだすことは困難であり、場合によっては、積極的にふ当ふ正を加えることさえなきを保し難い。誰かドイツ語のゲミュート Gemüt の意味を、翻訳によりて善く現わしえようか。英語のゼントルマン gentleman とフランス語のジャンティオム gentilhomme とは、言語的には極めて近接している。しかしこの二つの語のもつ持ち味の差を、誰か感じないであろうか。※noblessoblige 武士道は上述のごとく道徳的原理の掟であって、武士が守るべきことを要求されたるもの、もしくは教えられたるものである。それは成文法ではない。精々、口伝により、もしくは数人の有名なる武士もしくは学者の筆によって伝えられたる僅かの格言があるに過ぎない。むしろそれは語られず書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法たることが多い。ふ言ふ文であるだけ、実行によって一層力強き効力を認められているのである。それは、いかに有能なりといえども一人の人の頭脳の創造ではなく、またいかに著名なりといえども一人の人物の生涯に基礎するものではなく、数十年数百年にわたる武士の生活の有機的発達である。道徳史上における武士道の地位は大憲章もしくは人身逮捕令に比較すべきものさえないのである。十七世紀初めにおいて武家諸法度が制定せられたことは事実である、しかし武家〔諸〕法度十三カ条は概ね婚姻、居城、徒党等に関するものであって、教訓的規則はほんの僅かだけ触れられているに過ぎない。それ故に我々は明確なる時と場所とを指して、「ここに泉の源がある」と言うことができない。ただそれは封建時代において自覚せられたものであるから、時に関する限りその起源は封建制と同一であると見てよかろう。しかしながら封建制そのものが多くの糸によって織り成されているのであり、武士道もその錯綜せる性質を享けている。イギリスにおいて封建制の政治的諸制度はノルマン征服の時代に発していると言われるが、日本においてもその興起は十二世紀末、源頼朝の制覇と時代を同じくするものと言いうるであろう。しかしながらイギリスにおいて封建制の社会的諸要素は遠く征服者ウィリアム以前の時代に溯るがごとく、日本における封建制の萌芽もまた上述の時代より遥か以前から存在していたのである。 ヨーロッパにおけるがごとく日本においてもまた、封建制が公式に始まった時、専門的なる武士の階級が自然に勢力を得てきた。これらはサムライとして知られた。その字義は英語の古語のクニヒト cniht(knecht,knight) と同じく、衛士もしくは従者を意味するものであって、カエサルがアクィタニアに存在すると録したるソルデュリイ soldurii、もしくはタキトゥスによればゲルマンの首長に随従したるコミタティ comitati、もしくはさらに後世に比を求むればヨーロッパ中世史に現わるるミリテス・メディイ milites medii、とその性質が似通っている。漢字の「武家」もしくは「武士」という語も普通に用いられた。彼らは特権階級であって、元来は戦闘を職業とせる粗野な素性であったに違いない。この階級は、長期間にわたり絶えざる戦闘の繰り返されているうちに、最も勇敢な、最も冒険的な者の中から自然に徴募せられたのであり、しかして淘汰の過程の進行するに伴いふ怯懦柔弱の輩は捨てられ、エマスンの句を借用すれば、「まったく男性的で、獣のごとき力をもつ粗野なる種族」だけが生き残り、これがサムライの家族と階級とを形成したのである。大なる名誉と大なる特権と、したがってこれに伴う大なる責任とをもつに至り、彼らは直ちに行動の共通規準の必要を感じた。ことに彼らは常に交戦者たる立場にあり、かつ異なる氏に属するものであったから、その必要は一層大であった。あたかも医者が医者仲間の競争をぱ職業的礼儀によって制限するごとく、また弁護士が作法を破った時は査問会に出なければならぬごとく、武士もまた彼らの不行跡についての最終審判を受くべき何かの規準がなければならなかった。 戦闘におけるフェア・プレイ!野蛮と小児らしさのこの原始的なる感覚のうちに、甚だ豊かなる道徳の萌芽が存している。これはあらゆる文武の徳の根本ではないか?「小さい子をいじめず、大きな子に背を向けなかった者、というなを後に残したい」と言った、小イギリス人トム・ブラウンの子供らしい願いを聞いて我々はほほえむ(あたかも我々がそんな願いをいだく年輩を通り過ぎてしまったかのように!)。けれどもこの願いこそ、その上に偉大なる規模の道徳的建築を建てうべき隅の首石であることを、誰か知らないであろうか。最も柔和でありかつ最も平和を愛する宗教でさえこの願求を裏書きすると私が言えば、それは言い過ぎであろうか。トムの願いの基礎の上に、イギリスの偉大は大半打ち建てられたのである。しかして武士道の立つ礎石もこれより小なるものでなきことを、我々はやがて発見するであろう。友教徒の正しく証明するごとく、戦闘そのものは攻撃的にせよ防禦的にせよ蛮的(ばんてき)でありふ正であるとしても、我々はなおレッシングと共に言いうる、「我らは知る、欠点いかに大であるともそれから徳が起こる(1)』」と。「卑劣」といい「臆病」というは、健全にして単純なる性質の者に対する最悪の侮辱の言葉である。少年はこの観念をもって生涯を始める。武士もまた然り。しかしながら生涯がより大となり、その関係が多方面となるや、初期の信念はおのれを是認し、満足し、発展せしむるため、より高き権威ならびにより合理的なる淵源による確認を求める。もし戦闘の規律が行なわれただけであって、より高き道徳の支持を受けることがなかったとすれば、武士の理想は武士道に遥か及ばざるものに堕したであろう。ヨーロッパにおいてはキリスト教が、その解釈上騎士道に都合のよき譲歩を認めたにかかわらず、これに霊的素材を注入した。「宗教と戦争と名誉は、完全なるキリスト教武士の三つの魂である」とラマルティーヌは言っている。日本においても武士道の淵源たるものが幾つかあったのである。
(1)補注 ラスキンは最も心柔和にして平和を愛する人の一人であった。しかし彼は奮闘的生涯の崇拝者たる熱心をもって、戦争の価値を信じた。彼はその著『野の橄欖(かんらん)の王冠』の中でこう言っている―戦争はあらゆる技術の基礎であると私の言う時、それは同時に人間のあらゆる高き徳と能力の基礎であることを意味しているのである。この発見は私にとりて頗(すこぶ)る奇異であり、かつ頗る怖(おそろ)しいのであるが、しかしそれがまったく否定し難(がた)き事実であることを私は知った。簡単に言えば、すぺての偉大なる国民は、彼らの言の真理と思想の力とを戦争において学んだこと、戦争において涵養(かんよう)せられ平和によって浪費せられたこと、戦争によって教えられ平和によって欺かれたこと、戦争によって訓練せられ平和によって裏切られたこと、要するに戦争の中に生まれ平和の中に死んだのであることを、私は見いだしたのである。
第二章 武士道の淵源 まず仏教から始めよう。運命に任すという平静なる感覚、ふ可避に対する静かなる服従、危険災禍に直面してのストイック的なる沈着、生を賎しみ死を親しむ心、仏教は武士道に対してこれらを寄与した。ある剣道の達人〔柳生但馬守〕がその門弟に業の極意を教え終った時、これに告げて言った、「これ以上の事は余の指南の及ぶころでなく、禅の教えに譲らねばならない」と。「禅」とはディヤーナの日本語訳であって、それは「言語による表現の範囲を超えたる思想の領域に、瞑想をもって達せんとする人間の努力を意味する(1)」。その方法は瞑想である。しかしてその目的は、私の領解する限りにおいては、すべての現象の底に横たわる原理、能うべくんば絶対そのものを確知し、かくして自己をばこの絶対と調和せしむるにある。かくのごとく定義してみれば、この教えは一宗派の教義以上のものであって、何人にても絶対の洞察に達したる者は、現世の事象を脱俗して「新しき天と新しき地」とに覚醒するのである。 仏教の与え得ざりしものを、神道が豊かに供給した。神道の教義によりて刻みこまれたる主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、ならびに親に対する孝行は、他のいかなる宗教によっても教えられなかったほどのものであって、これによって武士の傲慢なる性格にふく従性が賦与せられた。神道の神学には「原罪」の教義がない。かえって反対に、人の心の本来善にして神のごとく清浄なることを信じ、神託の宣べらるべき至聖所としてこれを崇め貴ぶ。神社に詣ずる者は誰でも観るごとく、その礼拝の対象および道具は甚だ少なく、奥殿に掲げられたる素鏡がその備えつけの主要部分を成すのである。鏡の存在は容易に説明ができる。それは人の心を表あらわすものであって、心が完全に平静かつ明澄なる時は神の御像を映す。この故に人もし神前に立ちて拝礼する時は、鏡の輝く面に自己の像の映れるを見るであろう。かくてその礼拝の行為は、「汝自身を知れ」という旧きデルフィの神託と同一に帰するのである。しかしながら己れを知るということは、ギリシヤの教えにおいても日本の教えにおいても、人間の身体的部分に関する知識、すなわち解剖学や精神物理学を意味するのではない。この知識の性質は道徳的であり、人の道徳的性質の内省たるべきである。モムゼンがギリシヤ人とローマ人とを比較して論ずるところによれば、ギリシヤ人は礼拝するとき眼を天にあげるが、ローマ人はその頭を物で被う、前者の祈りは凝視であり、後者のそれは内省であるという。我が国民の内省は、本質的にはローマ人の宗教観念と同じく、個人の道徳的意識よりもむしろ国民的意識を顕著ならしめた。神道の自然崇拝は国土をば我々の奥深きたましいに親しきものたらしめ、その祖先崇拝は系図から系図へと辿って皇室をば全国民共通の遠祖となした。我々に取りて国土は、金鉱を採掘したり穀物を収穫したりする土地以上の意味を有する―それは神々、すなわち我々の祖先の霊の神聖なる棲所である。また我々にとりて天皇は、法律国家の警察の長ではなく、文化国家の保護者でもなく、地上において肉身をもちたもう天の代表者であり、天の力と仁愛とを御一身に兼備したもうのである。ブートミー氏(2)がイギリスの王室について「それは権威の像たるのみでなく、国民的統一の創造者であり象徴である」と言いしことが真であるとすれば(しかして私はその真なることを信ずるものであるが)、この事は日本の皇室については二倍にも三倍にも強調せらるべき事柄である。 神道の教義には、我が民族の感情生活の二つの支配的特色と呼ばるべき愛国心および忠義が含まれている。アーサー・メイ・クナップ曰く、「へブル文学においては神の事を言っているのか国の事を言っているのか、天のことかエルサレムのことか、救主のことか国民そのもののことか、これを見分けることはしばしば困難である(3)」と。真に然りである。同様の混同は我が民族的信仰〔神道〕の語彙の中にも見られる。然り、その用語の曖昧なるにより、論理的なる頭脳の人からは混同と思われるであろうが、それは国民的本能・民族的感情を入れた枠であるから、あえて体系的哲学もしくは合理的神学たるを装わないのである。この宗教―或いはこの宗教によって表現せられたる民族的感情と言った方が更に正確ではあるまいか?―は武士道の中に忠君愛国を十二分に吹きこんだ。これらは教義としてよりも刺激として作用した。けだし神道は中世のキリスト教会と異なり、その信者に対しほとんどなんらの信仰箇条をも規定せず、かえって直截簡単なる形式の行為の規準を供給したのである。 厳密なる意味においての道徳的教義に関しては、孔子の教訓は武士道の最も豊富なる淵源であった。君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友間における五倫の道は、経書が中国から輸入される以前からわが民族的本能の認めていたところであって、孔子の教えはこれを確認したに過ぎない。政治道徳に関する彼の教訓の性質は、平静仁慈にしてかつ処世の智慧に富み、治者階級たる武士には特に善く適合した。孔子の貴族的保守的なる言は、武士たる政治家の要求に善く適応したのである。孔子に次いで孟子も、武士道の上に大なる権威を振った。孟子の力強くしてかつしばしばすこぶる平民的なる説は、同情心ある性質の者には甚だ魅力的であった。それは現存社会秩序に対して危険思想である、叛逆的である、とさえ考えられて、彼の著書は久しき間禁書であったが、それにかかわらず、この賢人の言は武士の心に永久に寓ったのである。 孔孟の書は青少年の主要なる教科書であり、また大人の間における議論の最高権威であった。しかしながらこれら聖賢の古書を知っているだけでは、高き尊敬を払われなかった。孔子を知的に知っているに過ぎざる者をば、「論語読みの論語知らず」と嘲る俚諺)がある。典型的なる一人の武士〔西郷南洲〕は、文学の物識をば書物の蠹と呼んだ。また或る人〔三浦梅園〕は学問を臭き菜に喩え、「学問は臭き菜のようなり、能く能く臭みを去らざれば用いがたし。少し書を読めば少し学者臭し、余計書を読めば余計学者臭し、こまりものなり」と言った。その意味するところは、知識はこれを学ぶ者の心に同化せられ、その品性に現われる時においてのみ、真に知識となる、と言うにある。知的専門家は機械であると考えられた。知識そのものは道徳的感情に従属するものと考えられた。人間ならびに宇宙は等しく霊的かつ道徳的であると思惟せられた。宇宙の進行は道徳性を有せずとなすハックスレーの断定を、武士道は容認するをえなかったのである。 武士道はかかる種類の知識を軽んじ、知識はそれ自体を目的として求むべきではなく、叡智獲得の手段として求むべきであるとなした。それ故に、この目的にまで到達せざる者は、注文に応じて詩歌名句を吐きだす便利な機械に過ぎざるものとみなされた。かくして知識は人生における実践躬行と同一視せられ、しかしてこのソクラテス的教義は中国の哲学者王陽明において最大の説明者を見いだした。彼は知行合一を繰り返して倦ところを知らなかったのである。 この問題を論ずるに際し、しばらく余論に入ることを許してもらいたい。それは最も高潔なる武士中、この哲人の教訓によって強き影響を受けた者が少なくないからである。西洋の読者は、王陽明の著述の中に『新約聖書』との類似点の多いことを容易に見いだすであろう。特殊なる用語上の差異さえ認めれば、「まず神の国と神の義とを求めよ、さらばすべてこれらの物は汝らに加えらるべし」という言は、王陽明のほとんどいずれのページにも見いだされうる思想である。彼の門弟たる一人の日本人三輪執斎は言っている―「天地生々の主宰、人にやどりて心となる。故に心は活物にして、常に照々たり」と。また曰く、「その本体の霊明は常に照々たり。その霊明人意に渡らず、自然より発現して、よくその善悪を照らすを良知という、かの天神の光明なり」と。これらの言は、アイザック・ペニントンもしくは他の神秘哲学者らの文章とじつによく似た響きをもつではないか。神道の単純なる教義に表現せられたるごとき日本人の心性は、陽明の教えを受けいれるに特に適していたと思われる。彼はその良心無謬説をば極端なる超自然主義にまで押し進め、ただに正邪善悪の差別のみならず、心理的諸事実ならびに物理的諸現象の性質を認識する能力をさえ良心に帰している。彼は理想主義に徹入することバークレイやフィヒテに劣らず、人知の外に物象の存在するを否定するにまで至った。彼の学説は唯我論について非難せらるるすべての論理的誤謬を含むとしても、強固たる確信の力を有し、もって個性の強き性格と平静なる気質とを発達せしめたるその道徳的意義は、これを否定しえざるところである。 かくのごとく、その淵源の何たるを問わず、武士道が自己に吸収同化したる本質的なる原理は少数かつ単純であった。少数かつ単純ではあったが、我が国民歴史上最もふ安定なる時代における最もふ安なる日々においてさえ、安固たる処世訓を供給するには十分であった。我々の祖先たる武人の健全純朴なる性質は、古代思想の大路小路より抜き集めたる平凡かつ断片的なる教訓の穂束から彼らの精神の十分なる糧を引き出し、かつ時代の要求の刺激のもとに、これらの穂束から新しくかつ比類なき型の男性道を形成したのである。鋭敏なるフランスの学者ド・ラ・マズリエール氏は十六世紀日本の印象を要約して日く、「十六世紀の中頃に至るまで、日本においては政治も社会も宗教もすべて混乱の中にあった。しかしながら内乱、野蛮時代に返るごとき生活の仕方、各人が各自の権利を維持する必要―これらはかのテーヌによりて『勇敢なる独創力、急速なる決心と決死的なる着手の習慣、実行と忍苦との偉大なる能力』を賞讃せられたる十六世紀のイタリー人に比すべき人間を、日本においても作り出した。日本においてもイタリーにおけると同様、中世の粗野なる生活風習は、人間をば『徹頭徹尾闘争的抵抗的なる』偉大なる動物となした。しかしてこの事こそ日本民族の主要なる特性、すなわち彼らの精神ならびに気質における著しき複雑性が、十六世紀において最高度に発揮せられた理由である。インドにおいて、また中国においてさえ、人々の間に存する差異は主として精力もしくは知能の程度にあるに反し、日本においてはこれらのほか性格の独創性においても差異がある。さて、個性は優秀なる民族ならびに発達せる文明の徴しるしである。ニイチェの好んだ表現を用うるならば、アジア大陸においてはその人を語るはその平原を語るのであり、日本ならびにヨーロッパにおいては特に山獄によって人を代表せしめる、と言いうるであろうと。 ド・ラ・マズリエール氏が評論の対象としたる人々〔日本民族〕の一般的諸特性について、吾人はこれから筆を進めよう。私はまず「義」から始めるであろう。
(1)ラフカディオ・ハーン『異国的および回顧的』八四ページ。 (2)ブートミー『イギリス国民』一八八ページ。 (3)クナップ『封建的および近代的日本』第一巻一八三ページ。
第三章 義 義は武士の掟中最も厳格なる教訓である。武士にとりて卑劣なる行動、曲りたる振舞いほど忌むべきものはない。義の観念は誤謬であるかも知れない ― 狭隘きようあいであるかも知れない。或る著名の武士〔林子平〕はこれを定義して決断力となした、曰く、「義は勇の相手にて裁断の心なり。道理に任せて決心して猶予せざる心をいうなり。死すべき場合に死し、討つべき場合に討つことなり」と。また或る者〔真木和泉は次のごとく述べている、「節義は例えていわば人の体に骨あるがごとし。骨なければ首も正しく上にあることを得ず、手も動くを得ず、足も立つを得ず。されば人は才能ありとても、学問ありとても、節義なければ世に立つことを得ず。節義あれば、上骨上調法にても、士たるだけのこと欠かぬなり>と。孟子は「仁は人の心なり、義は人の路なり」と言い、かつ嘆じて曰く「その路を舎て由らず、その心を放って求むるを知らず、哀しい哉。人雞犬の放つあらば則ちこれを求むるを知る、心を放つあるも求むるを知らず」と。 ※参考:孟子が言うに仁は人の心に本来からあるいもの、即ち人の本心であり、義は人の踏むべき正路である。踏むべき道をしうてて、それに由らず、その本心を放ち失って、それを探し求めることを知らないという事は、実になさけないことである。人は自分の飼っている鶏や犬がどこかへ行ってしまうと、すぐにそれを追いかけ探すことを知っているのに、自分の本心が何処かへ放失されてしまっていても、それを探し求めて、再び自分にとりもどすことを知らない。学問というのは、外ではない。ただこの失った本心をとりもどそうと求めることにあるのみである。『孟子』新釈漢文大系 4 内野熊一郎著 P.402 彼に後るること三百年、国を異にしていでたる一人の大教師〔キリスト〕が、我は失せし者の見いださるべき義の道なりと言いし比喩の面影を、「鏡をもて見るごとく朧」ながらここに認めうるではないか。私は論点から脱線したが、要するに孟子によれば、義は人が喪れたる楽園を回復するために歩むべき直くかつ狭き路である。 封建時代の末期には泰平が長く続いたために武士階級の生活に余暇を生じ、これと共にあらゆる種類の娯楽と技芸の嗜を生じた。しかしかかる時代においてさえ、「義士」なる語は学問もしくは芸術の堪能を意味するいかなる名称よりも勝れるものと考えられた。我が国民の大衆教育上しばしば引用せられる四十七人の忠臣は、俗に四十七義士として知られているのである。 ややともすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代にありて、この真率正直なる男らしき徳は最大の光輝をもって輝いた宝石であり、人の最も高く賞讃したるところである。義と勇とは双生児の兄弟であって、共に武徳である。しかし勇について述ぶるに先だち、私はしばらく「義理」について述べよう。これは義からの分岐と見るべき語であって、始めはその原型から僅かだけ離れたに過ぎなかったが、次第に距離を生じ、ついに世俗の用語としてはその本来の意味を離れてしまった。義理という文字は「正義の道理」の意味であるが、時をふるに従い、世論が履行を期待する漠然たる義務の感を意味するようになったのである。その本来の純粋なる意味においては、義理は単純明瞭なる義務を意味した ― したがって我々は両親、目上の者、目下の者、一般社会、等々に負う義理ということを言うのである。これらの場合において義理は義務である。何となれば義務とは「正義の道理」が我々になすことを要求し、かつ命令するところ以外の何ものでもないではないか。「正義の道理」は我々の絶対命令であるべきではないか。 義理の本来の意味は義務にほかならない。しかして義理という語のできた理由は次の事実からであると、私は思う。すなわち我々の行為、たとえば親に対する行為において、唯一の動機は愛であるべきであるが、それの欠けたる場合、孝を命ずるためには何か他の権威がなければならぬ。そこで人々はこの権威を義理において構成したのである。彼らが義理の権威を形成したことは極めて正当である。何となればもし愛が徳行を刺激するほど強烈に働かない場合には、人は知性に助けを求めねばならない。すなわち人の理性を動かして、義ただしく行為する必要を知らしめねばならない。同じことは他の道徳的義務についても言える。義務が重荷と感ぜらるるや否や、ただちに義理が介入して、吾人のそれを避けることを妨げる。義理をかく解する時、それは厳しき監督者であり、鞭を手にして怠惰なる者を打ちてその仕事を遂行せしめる。義理は道徳における第二義的の力であり、動機としてはキリスト教の愛の教えに甚しく劣る。愛は「律法」である。私の見るところによれば、義理は偶然的なる生まれや実力に値せざる依怙(えこ)ひいきが階級的差別を作り出し、その社会的単位は家族であり、年長は才能の優越以上に貴ばれ、自然の情愛はしばしば恣意的人工的なる習慣に屈服しなければならなかったような、人為的社会の諸条件から生まれでたものである。正にこの人為性の故に義理は時をへるうちに堕落して、この事かの事 ― 例えば母は長子を助けるために必要とあらば他の子どもをみな犠牲にせねばならぬのは何故であるか、もしくは娘は父の放蕩の費用を得るために貞操を売らねばならぬのは何故であるか等々を、説明したり是認したりする時によびだされる漠然たる妥当感となったのである。私見によれば、義理は「正義の道理」として出発したのであるが、しばしば決疑論に屈伏したのである。それは非難を恐れる臆病にまで堕落した。スコットが愛国心について、「それは最も美しきものであると同時に、しばしば最も疑わしきものであって、他の感情の仮面である」と書いていることを、私は義理について言いうるであろう。「義しき道理」より以上もしくは以下に持ちゆかれる時、義理は驚くべき言葉の濫用となる。それはその翼のもとにあらゆる種類の詭弁と偽善とを宿した。もし鋭敏にして正しき勇気感、敢為堅忍の精神が武士道になかったならば、義理はたやすく卑怯者の巣と化したであろう。
第四章 勇・敢為堅忍の精神 勇気は、義のために行なわれるのでなければ、徳の中に数えられるにほとんど値しない。孔子は『論語』において、その常用の論法に従い消極的に勇の定義を下して、「義を見てなさざるは勇なきなり」と説いた。この格言を積極的に言い直せば、「勇とは義しき事をなすことなり」である。あらゆる種類の危険を冒し、一命を殆くし、死の顎に飛びこむ ―― これらはしばしば勇気と同一視せられ、しかして武器をとる職業においてはかかる猪突的てき行為 ― シェイクスピアが呼んで「勇気の私生児」と言えるもの ―― が、上当に喝采せられた。しかしながら武士道にありてはしからず、死に値せざる事のために死するは、「犬死」と賤しめられた。プラトンは勇気を定義して、「恐るべきものと恐るべからざるものとを識別することなり」と言ったが、プラトンのなを聞いたことさえなかった水戸の義公も、「戦場に駆け入りて討死するはいとやすき業にていかなる無下の者にてもなしえらるべし。生くべき時は生き死すべき時にのみ死するを真の勇とはいうなり」と言っている。西洋において道徳的勇気と肉体的勇気との間に立てられた区別は、我が国民の間にありても久しき前から認められていた。いやしくも武士の少年にして、「大勇」と「匹夫の勇」とについて聞かざりし者があろうか。 剛毅、不撓不屈、大胆、自若、勇気等のごとき心性は、少年の心に最も容易に訴えられ、かつ実行と模範とによって訓練されうるものであって、少年の間に幼時から励みとせられたる、いわば最も人気ある徳であった。小児はいまだ母の懐を離れざるに、すでに軍物語を繰り返し聞かされた。もし何かの痛みによって泣けば、母は子供を叱って「これしきの痛みで泣くとは何という臆病者です! 戦場で汝の腕が斬り取られたらばどうします? 切腹を命ぜられた時はどうする?」と励ました。『先代萩』の千松が、「籠に寄りくる親鳥の、餌ばみをすれば子雀の、嘴さしよるありさまに、小鳥を羨む稚心にも、侍の子はひもじい目をするが忠義じゃ」と、いじらしくも我慢したる昔話は、人のあまねく知るところである。我慢と勇気の話はお伽ばなしの中にもたくさんある。しかし少年に対し敢為自若くの精神を鼓吹する方法は、決してこれらの物語に尽なかった。時には残酷と思われるほどの厳しさをもって、親は子供の胆力を錬磨した。「獅子はその児こを千仭の谷に落す」と彼らは言った。武士の子は艱難の嶮き谷へ投ぜられ、シスュポス的苦役に駆り立てられた。時としては食物を与えず、もしくは寒気に曝すことも、忍耐を学ばしむるに極めて有効なる試煉であると考えられた。幼少の児童に用を命じて全然未知の人に遣わし、或いは厳寒といえども日出前に起き、朝食前素足にて師の家に通って素読の稽古に出席せしめた。また月に一、二度天満宮の祭日等に、少数の少年が集まって徹宵声高く輪講した。あらゆる種類の物凄き場所 ―― 処刑場、墓場、化物屋敷等に出かけることは、少年の好んでなした遊戯である。斬首の刑が行なわれた時は、少年はその気味わるき光景を見にやられたのみでなく、夜暗くなってから単身その場所を訪れ、梟首に印をつけて帰ることを命ぜられた。 この超スパルタ式なる「胆きもを練る」方法(1)』は、現代の教育家を驚かせて戦慄と疑問を抱かしめるであろうか ―― このやり方は、人の心の優しき情緒をば蕾のうちに摘取る野蛮の方法であるまいかとの疑問を、抱かしめるであろうか。我々は次章において、勇気について武士道のもつ他の諸観念を考察しよう。
(1) 補注 勇気が人のたましいに宿れる姿は、平静すなわち心の落ちつきとして現われる。平静は静止的状態における勇気である。敢為の行為が勇気の動態的表現たるに対し、平静はその静態的表現である。真に勇敢なる人は常に沈着である。彼は決して驚愕に襲われず、何ものも彼の精神の平静を紊さない。激しき戦闘の最中にも彼は冷静であり、大事変の真中にありても彼は心の平静を保つ。地震も彼を震わず、彼は嵐を見て笑う。危険もしくは死の脅威に面しても沈着を失わざる者、例えば差し迫る危険のもとに詩を誦、死に直面して歌を吟ずる者、かかる人は真に偉大なる人物として吾人の賞嘆するところであり、その筆蹟もしくは声音従容としてなんら平生と異なるところなきは、心の大なることの何よりの証拠である ―― 吾人はこれを「余裕」と呼ぶ。それは屈託せず、混雑せず、さらに多くをいるる余地ある心である。 信ずべき史実として伝えらるるところによれば、江戸城の創建者たる太田道灌が槍にて刺された時、彼の歌を好むを知れる刺客は、刺しながら次のごとく上の句をよんだ、 かかる時さこそ生命の惜しからめ これを聞いてまさに息絶えんとする英雄は、脇に受けたる致命傷にも少しもひるまず、 かねてなき身と思ひ知らずば と、下の句をつづけた。 勇気にはスポーツ的の要素さえある。常人には深刻な事柄も、勇者には遊戯に過ぎない。それ故昔の戦においては、相戦う者同士戯言のやりとりをしたり、歌合戦を始めたことも決して稀ではない。合戦は蛮力の争いだけではなく、同時に知的の競技であった。 十一世紀末、衣川の合戦はかかる性質のものであった。東国の軍は敗れ、その将安べ貞任は逃げた。追手の大将・源義家が彼に迫って声高く、「きたなくも敵に後を見するものかな、しばし返せや」と呼ばわりしに、貞任の馬を控えたるを見て、義家は大音に 衣のたてはほころびにけり と詠よみかけた。その声終るか終らざるに、敗軍の将は従容として 年を経へし糸のみだれの苦しさに と、上の句を付けた。義家は引きしぼりたる弓を俄かに弛て立ち去り、掌中の敵の遁ぐるに任せた。人怪しみてその故を問いたれば、敵に激しく追われながら心の平静を失わざる剛の者を、恥ずかしめるに忍びず、と答えたという。 ブルトゥスの死に際しアントニウスおよびオクタヴィウスの感じたる悲哀は、勇者の一般的経験である。上杉謙信は十四年の間、武田信玄と戦ったが、信玄の死を聞くや「敵の中の最も善き者」の失せしことを慟哭した。謙信の信玄に対する態度には終始高貴なる模範が示された。信玄の国は海を距ること遠き山国であって、塩の供給をば東海道の北条氏に仰いだ。北条氏は信玄と公然戦闘を交えていたのではないが、彼を弱める目的をもってこの必需品の交易を禁じた。謙信は信玄の窮状を聞き、書を寄せて曰く、聞く北条氏、公を困むるに塩をもってすと、これ極めて卑劣なる行為なり、我の公と争うところは、弓箭にありて米塩にあらず、今より以後塩を我が国に取れ、多寡ただ命のままなり、と。これはかの「ローマ人は金をもって戦わず、鉄をもって戦う」と言いしカミラスの言に比してなお余りがある。ニイチェが「汝の敵を誇りとすべし、しからば敵の成功はまた汝の成功なり」と言えるは、よく武士の心情を語れるものである。実に勇と名誉とは等しく、平時において友たるに値する者のみを、戦時における敵としてもつべきことを要求する。勇がこの高さに達した時、それは仁に近づく。
*『自分をもっと深く掘れ!』新渡戸稲造著 竹内均解説 三笠書房p19 より
平民道
先達中本誌の余白を借りてデモクラシーに関して一言するところがあった。今回計らずもデモクラシーの本家本元なる米国に渡るを好機会として、自分の述べた事が他人の、ことに先輩の説くところとどれほど符合するか、また背馳するかを見たい心掛である。 横浜を出帆する際、親類を見送りに来られた文学博士遠藤隆吉君に甲板上で遇うたら、同君が『社会及国体研究録』の第一号を手渡しつつ「デモクラシーは国体と相反するような考を抱く人があるので誠に嘆かわしいから、今度このような研究録を出して大に世の惑を釈こう」といわれた。この一言は深く吾輩を感激せしめた。僕は同君には日頃親しみはないけれども、君の手を執て打振るほど漢字悦ばしく思った。しかし口に発したのはただ「ドーゾやってくれたまえ」と繰返すのみであった。 デモクラシーは平民道 しばしば紙上に述べた通りデモクラシーは現時世界の大勢である、これに背く民はその末甚だ憂えられる。ただに流行なるが故にこの勢に乗ずべしとは吾輩の主張するところでない。吾輩の主張は今回に始った事でなく二十年已来の所信であった。たまたまこの事を述べてもとかく誤解を来し勝であるために遠慮をしておった位な事であるが、吾輩の所信は已に数多き著書の中にあちらこちらに漏らしてある。かつて十余年前大阪で演説した時の如きは聴衆の中にあった米国のウエンライト博士が演説後僕に言われたことに「君は武士道の鼓吹者とのみ思っていたに、今日その反対の説を聴いて驚いた」と。その時僕は同博士に拙著『武士道』の巻末を熟読せられたなら、吾輩の真の主張が理解されるであろうと答えた。この一話によっても読者は察せられるであろうが、今日僕の論ずるデモクラシーは決して今日に始った事ではない。デモクラシーなる字が如何にも流行語になったからこれを説くものも流行を追うものの如く思われ、またこの字を民主主義とか民本主義とか訳するから国体に反くような心配を起すけれども、僕はこれを簡単に平民道と訳してはドーであろうかとの問題を改めて提議したい。 武士の階級的道徳を武士道という、しかもこの名詞は昔一般に用いなかった。士道なる言葉は素行も松陰もまたその他用いていた人が衆多ある。これと同時に武士なる語も言うまでもなく古くから使用さるる語である。然るに武士道と三ツ並べた熟字は一般に用いられなかった。僕は度々この文字の出所を尋ねられたけれども、実は始めて用いた時分には何の先例にも拠った訳ではなかった。然るに今日は武士道といえば誰一人この字の使用を疑うものはない。元来武士道は国民一般に普遍的の道徳ではなく、少数の士の守るべき道と知られた。しかし武士の制度が廃せられて士族というのはただ戸籍上の称呼に止る今日には、かくの如き階級的道徳は踏襲すべくもない。これからはモー一層広い階級否な階級的区別なき一般民衆の守るべき道こそ国の道徳でなくてはなるまい。また国際聯盟なんか力説される世の中に、武に重きを置く道徳は通用が甚だ狭い。また仮りに国際聯盟が出来ないにしても武に重きを置かんとするよりは、平和を理想としかつ平和を常態とするが至当であろう。しかのみならず先に言う如く士は今日階級としてはない、昔の如く「花は桜木、人は武士」と謳った時代は過ぎ去って、武士を理想あるいは標準とする道徳もこれまた時世後れであろう。それよりは民を根拠とし標準とし、これに重きを置いて政治も道徳も行う時代が今日まさに到来した、故に武に対して平和、士に対して民と、人の考がモット広くかつ穏かになりつつあることを察すれば、今後は武士道よりも平民に道を主張するこそ時を得たものと思う。 平民道は武士道の延長 かく言えば僕は時代とともに始終考えを変えて行くように聞えるであろうが、時代について用語が異なったりまた重きを置く所も異るのは至当の事である。根本的の考えは更に変らない、恐らく昔の聖人といえども時と場合によって説きようを自在に変えたであろう。人を見て法を説くとは即ちこの謂である。同じ文字を使っても内容を変えれば一見貫徹している如く見えても意味が異る。その反対に用語を違えても思想に至っては一貫していることもある。 今日とても士道なる文字をそのままに書いてなおその内容に従来の意味と異る思想を含めることは甚だ容易い。たとえば明治になって新に士籍とはいわれまいが、広い意味に於ける士の族に昇格したものが沢山ある。学士を始として代議士もあれば弁護士もある。モット広く用ゆれば国士もあれば弁士もある、即ちこの新らしき士族は昔のそれと違って武芸を営むものでない。然るにいわゆる平民なる一般国民に比してより高き教育を受けた輩である、随って彼らは名誉ある位置を占め、社会の尊敬を受けるものであるから、誰人も士たらんことを望むであろう。さすればやはり「花は桜木、人は士」なりと歌っても、あな勝ち時代錯誤ではあるまい。しかし今日のいわゆる士字は昔の武士のように狭い階級ではない、各自の力によって自在に到達し得る栄誉である。かくの如く同じ文字を使っても内容を全然変えれば外部は一貫してもその趣旨に於て大差を来たす。それと同然に別の文字を用いて趣旨を一貫する事も出来る。僕のいわゆる平民道は予て主張した武士道の延長に過ぎない。かつて拙著にも述べて置た通り武士道は階級的の道徳として永続すべきものではない、人智の開発と共に武士道は道を平民道に開いて、従来平民の理想のはなはだ低級なりしを高めるにつけては、武士道が指導するの任がある。僕は今後の道徳は武士道にあらずして平民道にありと主張する所以は高尚なる士魂を捨てて野卑劣等なる町人百姓の心に堕ちよと絶叫するのではない、已に数百年間武士道を以て一般国民道徳の亀鑑として町人百姓さえあるいは義経、あるいは弁慶、あるいは秀吉、あるいは清正を崇拝して武士道を尊重したこの心を利用していわゆる町人百姓の道徳を引上げるの策に出でねばなるまい。丁度徴兵令を施行して国防の義務は武士の一階級に止まらず、すべての階級に共通の義務、否権利だとしたと同じように、忠君なり廉恥心なり仁義道徳もただに士の子弟の守るべきものでなく、いやしくも日本人に生れたもの、否この世に生を享けた人類は悉く守るべき道なりと教えるのは、取りも直さず平民を士族の格に上せると同然である、換言すれば武士道を平民道に拡げたというもこの意に外ならない。 武士があって武士道が興るのは歴史的の順序と思われるが少しく歴史の隠れたる力を研究したなら、たとえそのながなくとも武士道あって始めて武士が出現したと言うのが過言であるまい。道の道とすべきは常の道にあらずとやら、武士の道を武士道とな付ける間はまだ武士の守るべき常道を穿ったものではあるまい。いわゆる武士道なるものはそのなの起る前に忠君の念、廉恥心、仁義、人道なる思想が少数の先覚者に現われて彼らはいわゆる士となって、その後武士の階級が起り以て武士道が鼓吹されたものであろう。今日この武士の階級が廃せらるるといえども、根本のいわゆる常道は決して失わせることなく広く施されて万民これを行えばこれが少数の武士階級に行わるるより遥に有力な、かつ有益な道徳となるに違いはない。して万民|普くこれを行えば最早武士道と言われない、これが即ち僕の平民道と命名をした所以である。 デモクラシーは国の色合 デモクラシーといえば直ちに政体あるいは国体に懸るものと早合点する人が多い。僕はしばしば繰返してこの誤解を明かにせんことを求めたが、デモクラシーは決して共和政体の意味にのみ取るべきものでない。もっとも共和政体とデモクラシーと関係の近いことはいうまでもない、けれどもこの両者が同一物でない、我国体を心配するものは右両者の関係近きがためであるけれども、近いがために危険視するのは取越苦労であって、君主国と専制国と関係甚だ近い、それ故に君主国を危険視するならばそれこそ危険の極でないか。僕の見る所ではデモクラシーは国の体でもないまたその形でもない、寧ろ国の品性もしくは国の色合ともいいたい。であるから共和政治にしてもデモクラシーの色彩の弱い処もある、現に羅馬の歴史を見てもオクタヴィアスの時代にはその政体の名実が符合しない感がある。また近きは奈翁三世の時代の仏蘭西も果して共和国であったか帝国であったか判断に迷う位である。またなは君主国であってもその実デモクラシーの盛に行われる英吉利の如きは、なも形も君主国にして、その品質と色彩は漢字確にデモクラシーである。僕のしばしば言うデモクラシーは我国体を害しないものとはこの意味であって、この意味を解さないものは、吾国体を世界の趨勢、人類の要求、政治の大本より遠ざからしむる危険なるものと言わねばならぬ。前に武士に先って武士道の大義が存在したと述べたと同じ理由によりて、僕は政治的民本主義が実施さるるに先って道徳的といわんか社会的といわんか、とにかく政治の根本義たる所にデモクラシーが行われて始めて政治にその実が挙げられるものと思う。モット平たく言えば民本思想あって始めて民本政治が現われる。して民本思想とは前に述べた平民道で、社会に生存する御互が貧富や教育の有無や、家柄やその他何によらず人格以外の差別によって相互間に区別を付けて一方には侮り、一方は怒り、一方は威張り一方はヒガみ、一方は>我儘振舞あれば一方は卑屈に縮むようでは政治の上にデモクラシーを主張してもこれ単に主張に終りて実益が甚だ少なかろう、といって僕は然らば政治は圧制を旨としても思想的のデモクラシーを主張すれば足れりとは信じない。政治的の平等と自由を主張する事は思想の上にデモクラシーを実現する助ともなることなれば、政治的民本主義も鼓吹すべきであるけれども物の順序より言えば一般人民の腹の中に平民道の大本を養ってその出現が政治上に及ぶというのこそ順序であろう。 米国がデモクラシーの国というのは共和政治なるが故ではない、彼らがまだ独立をしない即ち英国王の司配の下に椊民地として社会を構成した時に社会階級や官尊民卑や男尊女卑の如き人格以外の差違を軽んじ、また職業によりて上下の区別をなしたり、家柄、教育を以て人の位附を定める如き事なく、人皆平等、随って相互に人格を認め、相互の説を尊重する習慣があったれば、今日米国のデモクラシーが淵源深く基礎が堅いと称するのである。 〔一九一九年五月一日『実業之日本』二二巻一〇号〕 このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。
農業経済学者,教育者。南部藩士の子として盛岡に生まれる。札幌農学校に入り,W.S.クラークに導かれてキリスト教に入信。欧米に留学して農業経営学を修め,帰国後,1906年一高校長,その後東大教授,東京女子大学長等をつとめて学生に大きな影響を与えた。 |
|
「天命に安んじ 人事を尽くす」 参考:明治時代の真宗大谷派の僧侶、哲学者・宗教家。 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.119~123 小室 三吉 買われたその愛社精神 松平春嶽は、幕府の政事総裁、明治政府初代民部卿などをつとめたが、その政治活動の基盤は、横井 小楠のようなすぐれた学者を招いて賓師とし、原理原則を教えてもらうと同時に、各地にバラまいた多数の情報係に、さまざまの出来事を報告させることにあったようである。 情報は、ごく薄手の紙に「一ミリの空白をもむだにせず、ごく細字で隙間なく書きこまれて」(小池 藤吾郎編『幕末覚書』)あったというが、その一つとして、京三条大橋より南一町ほどの河原に、三つの木像の首がさらされていることが報告されたのは文久三年二月、小栗忠順が梟首(きゅうしゅ)される五年前のことであった。 木像は、等持院におさめてあった足利尊氏、同義詮のものである。人間の生首ではないがほかならぬ足利三代の首となると、単なるいたずら、いやがらせをこえた深刻な意味をもっていた。小池 藤吾郎によれば「足利三代の木像は、実に将軍家を代表する。これは徳川将軍家にとっても、たまらない一種のふ𠮷の前兆にみえたであろう。連想は徳川 家康、秀忠、家光三代のそれに及ぶ。足利家の冒涜であるとともに、徳川将軍家の抹殺……」という意味がある。この意味から、幕府は木像梟首を重大視し、京都守護職松平 容保(まつだいら かたもり)の家来たちは嫌疑者十四名を逮捕し、うち五名は無罪で釈放した。逮捕された中に、烏丸三条下ル、小室 雄太郎手代十蔵(四十歳)がおり、やがてその主人の小室 信夫(しのぶ:二十六歳)も検挙されて、阿波藩につながれ、在獄五年、慶應四年正月に釈放された。 彼の実家は丹後国(京都府)の豪農兼縮緬(ちりめん)生糸問屋であり、信夫は京都支店の監督をしているうち、尊皇攘夷運動に加わったのである。 信夫は、明治新政府になって岩鼻県知事をしたあと、民権議院設立建白書の署名者の一人となったが、「家業にして振るわざれば富国の基礎立たず」という考えから実業界に進出し、大阪築港、小倉製糸、奥羽鉄道、六九銀行、北海道製麻会社、京都鉄道会社に関係した。また、明治十六年、三菱に対抗するため、三井系で設立された共同運輸会社では、創立委員をへて理事となった。三井物産社長益田孝と親しくなったのはそのためであろう。やがて信夫のせがれ三吉は、英国留学のあと三井物産に入社し、上海支店長上田安三郎の下に配属された。 上田寿四朗氏(安三郎四男)からお借りした益田孝と上田安三郎の往復書簡を見てみると、明治十八年以降の分に小室三吉の名前が出てくる。上田支店長は小室を非常に信任したようである。 ちょうどこのころ、益田の弟英作も物産にいたようで、上田はその上海支店配属を希望したらしく、「令弟英作氏を当地に御派出下されたく御所望申上げ候ところ御許容云々「と感謝しているが、社長の弟よりも小室の方を高く評価したことは、十八年末、本社に提出した「社員昇等ならびに増額願」を見れば明らかである。上田の下には九名の部下がいたようで、そのうち手代二等月給二十五円の福原栄太郎がトップで、これを「手代一等銀貨四二十円」にしたい、と上田は書いている。「手代三等十五円」というのが小室三吉と益田英作の二人であったが、小室を「手代二等銀貨三十円」に、益田を「手代二等銀貨二十五円」にというのが上田案である。五円の格差をつけたわけである。 この「格差」、ことに社長の弟を低くしたことについては、社長自身に釈明の要がある、と上田支店長は考えたようで、十九年二月、益田個人への親書において、二人の人物論がのべられている。 「……小室三吉と益田英作とは、益田の方古参にして事務も充分出来候ことは承知まかりあり候へども、当方ではさしあたり小室の方、当方の商業に馴れ、別してこのたび香港に派出後、本人の動作をとくと注目いたし候ところ、諸事取扱方いたって深実にして、労をおしまず勉強にして人に功をゆずり、事の細大となく会社の得失を思考して要点に着目し、つねに人にまじはるに温和にして礼譲あつく、なかんづく身の品行は一点の申し条もこれなく、その会社のためにつくすの精神は勿論じつに感心まかりあり候。この人この姿にて末ながく会社に従事するものなれば、まことに当社にとりて大なる幸福にこれあり。かかる人物はなるべく重く登用して本人には倍々その童心を(?)くせしめ、一つは他の標準とも致し候方しかるべく存じ奉候。英作氏、小室に劣るにあらざれども、不幸にして当地にくることおそく、いまだこれまで充分智才を示すの機会を得られざりしことに候間、必ず成すことあるは存じながらも、私としては小室の方を一歩進めざるを得ず勘考申し候。……」 まことに条理をつくした名文という気がする。上田はこのとき三十二歳でもとより経営学などの学問はなかった。しかし、見知らぬ異国で一軒一軒「三池炭」を売りこんでいくという血のにじむ体験が、人間をどこでどう評価すべきか、を学ばせたようである。勤務評定をどうすべきか、上田は「知識」ではなくて「生活体験」としてわかっていたようである。その上田にこれほどの評価されたのであるから、小室三吉ももって瞑すべし、ということになろうが、反面、社長の血族関係よりも個人的能力を優先させた支店長、それを容認した社長がいてこそ、会社は本当に伸びたのであろう。戦前における「三井物産」発展のかげにはいろいろの原因が数えられるであろうが、この「昇等増額願」一件の人事政策こそ、その重要なキメ手ではなかったろうか。 さて、益田孝は、弟に格差をつけた上田を、その年「元締役」に抜擢した。これは「平重役」ということらしく、それまでは馬越横浜支店長、拝司長崎支店長の二名だけで、上田といっしょに松岡譲(函館支店長)、宮本新左衛門とが元締役になったらしい。 明治二十五年四月、上田は「三井物産会計委員」(役員)に任ぜられ、本社の「専務委員外国部受持」となり、後任支店長に小室が昇格した。 小室がとくに信任して身辺から離さなかった部下が山本条太郎である。山本は、前にのべたいきさつで頼朝丸に左遷されていたが、明治二十一年三月、上海支店勤務と、小室が支店長になったときは二十六歳であった。山本が商法上英文をしたため小室に提出すると、ときどき筆を加えて訂正された。山本のは頼朝丸での独学、小室はロンドン仕込みでそこには格段の差がある。山本はこの訂正をうけたときはそのままにせず、必ず別紙に写しとって大切に保存した。傲岸ふ遜(ごうがんふそん)といわれた山本にも、このような謙虚さ細心さがあったが、それは小室の人間的魅力があったらこそ、とも思われる。 2019.07.30 |

何かを始めることは優しいが、それを継続することは難しい、成功させることはなお難しい。 教育者。佐倉藩士の子として江戸に生まれた。8歳のとき、日本最初の女子海外留学生として米国にまなび、帰国(1882)後、華族女学校、女子高等師範学校教授を歴任したが、1900年、英語によって女子の国際的知見を広め、また中等諸学校の英語教員の養成を目的とした女子英学塾(現在の津田塾大学)を創立、塾長となった。塾は、中流以上の子女に英語および近代的教養を与える学校として発展した。 *『国民百科辞典』による。
ふしぎな運命でわたしは幼いころ米国へ参りまして、米国の教育を受けました。帰朝したならば――これという才能もありませんが――日本の女子教育に尽したい、自分の学んだものを日本の婦人にもわかちあいたいという考えで帰りました。(津田梅子) 明治二十三年(一九〇〇年)の九月十四日、津田 梅子(三十五歳)は女子英語塾(後の津田塾)を開く。 *青木 雨彦監修『中年の博物館』P.132

伊藤博文と子どもたち 日本最初の女子留学生として渡米した津田梅子は、帰国後、二十二年伊藤の世話で華族学校に奉職、伊藤家の家庭教師となる。『明治天皇と元勲』TBSブルタニカ P.268 2009.10.14,2019.06.12,2019.08.19追加。 |
☆15留岡幸助(1,864~1,934年)

高瀬善夫著『一路白頭ニ至ル』(岩波新書)1984年1月10日 第2刷発行
岡山県高梁(たかはし)は、倉敷から伯備線のどん行列車に揺られて、高梁川沿いに一時間近くさかのぼったところに位置する静かな山間の町である。昭和二十九年に市制が施行されたが、人口は次第に減少し、今では二万七千人が住むに過ぎないが、もとはといえば備中松山藩の城下である。
▼明治五(一八七二)年は、小学校が開設された年である。この年、留岡幸助は士族屋敷のある新町の寺小屋へ通いはじめた。
*参考:明治初年、法律によって、華族・士族・平民の身分制度が出来ました。土地役人のような下っ端が決められるはずがなく、政府が決めたのです。武家時代の公卿や大みょうが「華族」、一般武士が「士族」、その他の農工商が「平民」に分けられました。昭和22年(1947)戸籍法が改正になるまで、戸籍には「士族」とか「平民」とかが明記してありました。 町人の子の幸助は士族の子と口論になり、左手に噛みつき歯型を残して、米屋の留岡金助は喧嘩した武士の家から」「きょうより出入りを差し止める」仕打ちを受けた。 ▼人間の平等の最初のきっかけ
明治十三(一八八〇)年、彼が十六歳のとき、高梁の町に珍しい講釈の一行が乗り込んできた。説教するのは、外人宣教師のケリーと牧師の:金森通倫である。金森は同志社神学校の第一回卒業生で、この年に岡山基督教会をつくった。ケリーは、岡山士族の中川横太郎に神戸から招かれて説教会を開いて以来、岡山伝道に力を注いできた人物である。その説教の一節が幸助の心を大きく揺さぶった。
明治十五年に創立された高梁教会には「迫害石」なるものが保存されている。信者は町の冠婚葬祭に参加できない。教師になれない。官吏になれない。女は嫁にもいけない。そういう町に生きる金助は、息子がキリスト教に深入りしていくのを座視してはいられなかった。
丹波への牧師をしている留岡のもとに、金森通倫牧師からの一通の手紙が届けられた。「北海道空知集治監の大井輝前典獄から、同志社出身で教誨師になってくれる者をさがしてくれないかと頼まれた。私は君が適任の人だと思う。どうか奮発して、行く気になってほしい」
▼精神の開拓者
丹波第一教会から辞表を受理された留岡は、いったん高梁へ帰った後、神戸から横浜へ渡り、そこから後から来る妻子を待った。そして明治二十四年(一八九二)年四月三十日、生後わずか六ヵ月の長男をかかえ留岡夫妻は、下等船室の乗客となり、まつたく未知の北海道へと旅立った。札幌→手宮(小樽)→幌内太駅→市来知(現三笠市)の空知集治監に着く。自分が赴任する空知集治監の正門にもいたらぬ前に、留岡はまっさきに、囚人たちが酷使されている状態をみた。「おれは監獄のことを書物で読み、頭のなかであれこれと考えてきたけれども、来てみればズブの素人にすぎない。日本の監獄はとはこういうところであったのか」
▼流刑の山野を行く 幌内外役所からもどった留岡は、その日の午後三時幌内太発の汽車に乗って長い旅に出た。主要な目的は標茶の釧路分監で教戒することであったが、そのほかにも大事な用事があった。全行程を踏破すれば千三百九十二キロに及ぶはずである。その大部分を自分の足と馬の背と小船に頼ってひとりで行くのである。(中略)彼はいかなる罪人も感化しうるという信念があった。しかも他方では、囚人たちの生歴を丹念に調べていた。非常に早い犯罪社会学的調査といってもいいものである。その仕事を通じて、彼は一つの結論に達する。調べた在監三百人のうち、八割近くまでか十四、五歳のころ非行少年であった。犯罪の初発年令は低い。もとを正そうとすれば、この少年たちに手をさしのべることふぁ緊要な課題であろう。少年感化の問題を考えれば、留岡はアメリカへ渡って、そのやり方を学んできたいとと思いつめるようになった。
▼留岡はどうしてもアメリカへ渡って、日本にいては思いつかないような精度をつぶさに勉強してこなければならないと思い立った。一介の貧乏教戒師がどうもがいたら渡航の費用が捻出できるだろうか。ほとんどふ可能に近い。しかし、一旦決心したら、がむしゃらにでもその目的に向かって突き進まねばやまないのが、彼の流儀である。
▼アメリカへ行く 留岡幸助とうとうやってきた。P.126
念願の地であるニューヨーク州のエルマイラへ。明治二十八年五月十九、彼は丘の上にまるでお城のように立っているエルマイラ感化監獄を訪ね、ブロクウェー典獄と面会した。この人に学ぶことこそが、彼の渡米の最大の目的である。
人から愚かといわれようと時代おくれといわれようと、自分はそういう仕事をしよう、留岡の決意は固まった。ブロックウェーのこの一言を彼は「一路到白頭」と意訳して、それをみずからの座右銘とする。
▼計画の難航 二年間のアメリカ留学を終えて、留岡は横浜に帰ってきた。彼の頭のなかは日本に感化院をつくることでいっぱいだ。「私の社会思想は大学や専門学校で学んだものではない。監獄は私にとっては一の大なる大学であり、囚人は私の為には社会学の教師であり、先生であった」そういう思いにかられる彼は、これまでに学び身に付けたことを生かして、おのれが一生をかける事業を自覚したのだ。
彼は空知で親しくなった野広中の紹介で、内閣官邸(いまの帝国ホテルのところ)に板垣退助を訪ねた。監獄改良を叫んでいた内務大臣板垣は、内務次官の三好退蔵と相談するのがよかろうといった。三好は一大感化院をつくる構想を胸に抱いていたのである。会いに行くと、彼は留岡に心の底を打ち明けてくれた。感化院設立のために奔走する共同計画がはじまり、設立向かって積極的に動きはじめた。
▼家庭学校への道
巣鴨三千六百坪の所有者は山本忠次郎であった。その地主が留岡にたずねた。
▼家庭学校
明治三十二年三月、巣鴨に新しい校舎ができた。これを留岡は「第一家族」となづけた。学校概則の第一条には、「本校ヲ家庭学校ト称ス」とある。そう呼ぶからには、それなりのはっきりした理由があるはずである。
▼北海道家庭学校については、「 北海道家庭学校」参考にしてください。2019.02.12 新規引用。
▼ 留岡幸助年譜 元治元年(一八八四)備中國高梁(現在の岡山県の高梁)に生まれる。父吉田万吉、母トメ。間もなく留岡金助・勝夫妻の養子となる。 明治十六年(一八八三)養父らの迫害を受け、一時、同志社の三十番教室に潜伏。発見されてつれもどされたが、さらに愛媛県今治へ脱出。 明治十八年(一八八五)同志社英学校別科神学科邦語神学課に入学。新島襄の教えを受ける。 明治二十一年(一八八八)同志社を卒業。福知山の丹波第一教会牧師となる。 明治二十四年(一八九一)北海道来知の空知集治監に教悔師として赴く。 明治二十七年(一八九四) 北海道冬期学校を開く。監獄学の研究視察のため、エンプレス・オブ・インディア号で横浜を出港、アメリカへ遊学。コンコルド感化監獄で実習をしながら学ぶ。 明治二十八年(一八九五)エルマイラ感化監獄でブロックウェーに師事。 明治三十二年(一八九九)社会学研究科に入会。警察監獄学校教授になる。東京府北豊島郡巣鴨村に土地を購入して、家庭学校を創立。十一月二十三日、生徒一人を収容。 明治三十九年(一九〇六)家庭学校を財団法人として、理事長兼校長となる。 大正三年(一九一四)内務省地方局嘱託を辞任。北海道上湧別村社な淵に分校と農場を開設(当初は七百十六町歩)、八月二十四日、開場式を行う。 大正十二年(一九二二)家庭学校茅ヶ崎分校を創設する。水平運動に共感。関東大震災で茅ヶ崎分校は倒壊。 昭和九年(一九三四)死去。七十歳。 昭和四十四年(一九六九)谷昌恒、第五代校長に就任。
留岡の死から三日後の東京日日新聞の随想欄「日日だより」に、徳富蘇峰は「日本の忠僕留岡幸助君を悼む」という文章を載せた。
以上の記事は、ほとんど「岩波新書」の抜き書きであることをお断りしておきます。
参考までに、谷 昌恒氏には、評論社の教育選書『ひとむれ』数集の著作に「北海道家庭学校」の実践活動が詳しく述べられている。
平成二十一年六月十六日 平成二十二年九月十五日:追加した。また、筆者が少し変更している個所もあることをおことわりします。 追加1:平成二十三年に「大地の志」の題名の映画化の予定で、準備されています。 追加2:「大地の詩(うた)―留岡幸助物語」上映始まる
高梁市出身で、わが国児童福祉の先駆者として知られる留岡幸助(1864〜1934年)の生涯を描いた映画「大地の詩(うた)―留岡幸助物語」の上映が23年2月19日、岡山、倉敷市内の映画館で始まった。
▼2019.02.12、岩波新書をひらいて、修正。 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.59~64 山路 愛山 終生変わらぬ蘇峰との友情 幕府天文方という役職があった。役高百俵の微禄ではあるが、農耕その他行事の基本となった暦編さんの役目は重大であった。その天文方に山路 弥左衛門がなったとき、部下の天文方手附に田口 樫郎という人物がいた。弥左衛門の曾孫は弥吉といい、愛山と号した。樫郎のせがれは卯吉といい、鼎軒と号した。つまり明治期の代表的評論家二人が、天文方の系譜から生まれたといことになる。 田口鼎軒(たぐちていけん)についてはすでに『日本さらりーまん外史』でのべたことがある。山路愛山は田口よりも九歳年下で、五歳おとき幕府の瓦解にあい、祖父母とともに無禄移住で静岡にうつった。父一郎は榎本武揚に加わって家を出奔、母けい子はすでに二年前に死亡していた。静岡時代のことはくわしくわからないが、生活苦をなめたようで、月給二円の代用教員の県庁雇員だったという。 森 鴎外に『渋江抽斉』という傑作があるが、この抽斉の嗣子保は、明治十九年に私立静岡英語学校教頭となり、弥吉はこの保に英語を習った。このころ愛鷹(あしたか)山にちなんで「如山」と「愛山」という二つの号をつくり、如山はすぐやめて、以後は愛山で通した。 明治二十年二月、二十四歳のとき、徳富 蘇峰が創刊した『国民之友』を読んで感動し、蘇峰に手紙を出した。横井小楠の甥にあたる蘇峰はこのとき二十五歳、前年に一家をひきて上京、「予はただ自己の運命を信ずる以外には、何等の確定した考えもなかった」(『蘇峰自伝』)と書いているように、背水の陣をしいて『国民之友』創刊にふみきったときである。愛山の心をこめた手紙は何よりもうれしかったであろう。 二人の終生変わらぬ情はこの手紙に端を発したが、同時にそれは愛山の人生を決定したともいえる。愛山の業績は何よりも史論において傑出しているが、その仕事の基礎固め、第一期の作品は、明治二十五年(二十九歳)から三十年(三十四歳)まで、蘇峰の創刊した『国民新聞』の記者時代に生まれたからである。一本の手紙の縁というものの、それが単なる手紙ではなかったこと、読後感を書いた愛山も真剣であり、うけとった蘇峰もその雑誌にいのちを張っていたこと、この両者の心の世界、波動の一致を見落としてはならないだろう。 評論家愛山については諸家の論評があるが、 彼は酒を飲まず、子供をしからない人であった。説教めいたことをいうのは年に一度。元旦のときでだけである。このときは祖先の画像を床の間に掲げ、子供たちをその前に正座させて、このおじいさんはどんな人で、どういうことをした人だといろいろ説いて聞かせ、昔の武士は卑怯の振る舞いをするのをいちばんの恥とした、お前たちも、どんなことがあっても卑怯の振る舞いだけはするな、と教訓したのである。 反面、「立身出世」を要求しなかった。子供たちには弥生、金次郎、しの、久三郎、平四郎という平易な名前をつけた。そこで、 「本読みの先生が、どうしてむすこさんたちに、平凡なやさしい名前ばかりつけられるのですか?」 とたずねられた。愛山は答えた。 「何にでもむくようにだ。一ぜん飯屋のおやじがあまりえらそうな名前では、商売にもさわろうではないか」 後年、この話を母からきいた平四郎は「わたしは心を安んじた」と書いている。便所の壁に世界地図がはりつけてあった。痔のわるい愛山は、それをゆっくりながめていたらしいが、平四郎はそれに落書をした。すると、地図の横に、「平ちゃん、いたずらするなかれ」と書いただけで、しからなかった。 読んでいなければ、書いていた。ぬるい風呂が好きで、それがわくまでゆっくりとつかっている。そのとき必ず本を手にしていた。ブッブッ声を出して読んでいた。これが唯一最高の楽しみだったらしい。暑いときはもろはだぬぎで、水をガブガブのみ声を出して調子をつけながら書いていた。非常な達筆で、ひとには読めない字であった。(筑摩書房刊、明治文学全集三五巻『山路愛山集』の扉にその筆跡がある。ご覧になれば「その記するところ、蠅頭(ようとう)の細字、他人弁別する能わず」という蘇峰の嘆きが誇張でないことをおわかりいただけるはず)。 貧乏なくせに、落剝(らくはく)した旧幕人を見ると助けてやる。そのつど勝手向きの苦しさを夫人が訴え、口論となった。 「武士は相見互身(あいみたがいみ)だ」 「今どき、武士だ武士だなんてかつお節の方がよっぽどいい」 と夫人も負けてはいない。愛山は、 「おたねェ(夫人のな)、おれは出てくるぞォ」 と大声でいい、ステッキで門や扉をガンガンたたきながらとびだすが、一時間もするケロリとした顔でもどってきて、 「おたね、おれがわるかった。勘弁しろよ」 といって書斎にはいり、またせっせと原稿書きに精出すのであった。 頼山陽を尊敬していたが、その山陽よりも一年だけ長生きして、五十四歳で永眠した。生涯が努力の連続であり、「君は孤立援なく、学閥なく、藩閥なく、生れて地に落ちし以来、自から養い、かつ家を養わざるを得ず。その硯田筆耕の際に半生を消磨したるも、もとより無理からぬ次第なり」という蘇峰の追悼文を読むと、売文を業とする筆者など身につまされて、思わずまぶたが熱くなる。 2019.07.17 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.104~108 郷 誠之助 道楽から一転、会社再建の名人に 仲間奉公をふりだしい、薩長土肥の出身者で要職を独占していた明治政府において大蔵次官までになったのであるから、郷純造が頭のいいヤリ手であったことはいうまでもないが、とくに精力絶倫といわれた。十三歳のとき、肥桶一荷をかついでほめられたことがある。普通、二十歳ぐらいでないとかつげないものであった。また、四十代になっても芽が出ないので、成田不動に二十一日間の断食祈願をしたあと、三日後には江戸に帰り、しかもみやげに芋を一荷かつでいった。常人ならば満願となって宿へ下がると、最初は重湯、それからお粥、つぎにご飯を食べて、しだいに元気づくには一週間か十日はかかるものであった。 多数の女性を愛し、八男二女を生ませたが、最終の子は七十歳のときに生れ、「すなわち終り初物の意を表し朔雄となづけたり」とある。このバイタリティーは子供たちにうけつがれ、さまざまなデフォルメをうけて表現されたが、跡とりとなった誠之助の場合、不羈(ふき)奔放の行動となってあらわれた。 小学生時代の楽しみといえば、屋根の引き窓にのぼり、女中たちが働いている台所へ小便をすることだった。というのであるから、栴檀(せんだん)は双葉(ふたば)より芳しかったわけだ。十三歳のとき父の乾分(こぶん)である宮城県大書記官の家にあずけられたが、肩上げのついた着物をきて、上級生の悪太郎にくっついて紅灯の巷(ちまた)をさまよう。これではいかぬと中学の寄宿舎に入れられると、毎晩ぬけだして遊郭に通い一升酒をたいらげて「あんたというひとは……」と、アバズレ女郎のどぎもをうばった。 十五歳で東京に帰り、十六歳のとき無銭旅行に出かけた。手を焼いた父親からアメリカにやられそうで、アメリカに行ったのでは人間がますます軽薄になるばかりである。俺も日本人だ。日本人は日本固有の方法で修養しなければならぬ。それには日本全国を広く行脚して、その土地土地の志士とか、偉い人物に面会し、議論を戦わすのが一番よろし>と考えたからである。 辞書などを売って旅費二十円を工面したが、これは川崎の遊郭で使いはたし、一面識もない静岡県知事に借金に行った。玄関で「郷誠」と書いた名刺を出すと、「忙しいから会えない」という。そこで、「郷純造男誠之助」と書き直すと、慇懃(いんぎん)な態度で会ってくれた。誠之助は腰にさした太いきせるでスパリスパリやり、カチンカチンと火ばちのふちをたたきながえあ、旅の目的などをしゃべった。県知事は「ちょっとお待ちください」といって奥に引っこもり、やがて紙に包んだものをさしだした。五円札が二枚はいっていた。 しかし、県知事の注進で純造は烈火のように怒り、勘当状をわたした。「汝不幸ふ仁にして余の訓戒に悖戻(はいれい)し……」ととても丁寧な字で書いてあったという。 勘当されて京都に行き、同志社にはいった。そのうち薬の行商に加わり、若狭の小浜まで行った。「本家は江州安土町、その又薬の効能は、腹痛、頭痛、胸つかえ……」と宣伝文句をとなえ、軒なみに押し売りしていく商法だったが、誠之助は新法をあみだし、裁判所、中学校に押しかけた。中学校では授業中の教室にはいりこんで、教師をつかまえて薬の効能を説くだけでなく、「あなた方のような一般人より一段知識の進んでいる人から、まずこの有用なる薬を試して普及してくれなくてはこまる」と文句をつけて、学生に買わせたところに、そのあつかましさとユニークな才能があらわれていたといえよう。 十九歳のとき、未来を誓った恋人が自殺し、ショックをうけた。二十歳のときから二十七歳のときまでドイツ留学。「ドイツでは我輩も道楽もしたが、初めの三年間は真面目に、真剣に、ミッシリ勉強をした」という述懐は語るに落ちる。ちょうど森鴎外も留学中でその「独逸日記」には「郷誠之助と相見る。誠之助はハルレにありて経済学を修む。……快活の少年にて、好みて撞球戯をなす」と、プレイボーイぶりが記されている。仲間には、井上哲次郎(のち文学博士)、和田継四郎(八幡製鉄所長官)、松方巌(正義長男、十五銀行頭取)、田村恰与造(たむら いよぞう:参謀本部次長)、都築馨六(つづき けいろく:井上馨の女婿、枢密院書記官長)、青山胤道(あおやま たねみち:医科大学長)、佐藤三吉(同東京帝国大学医科大付属医院長)など将来の大物たちがいる。 帰国旅費は三回送らせ、三度とも遊びに使ってしまったため、フランス船で帰国したときは、「ドミノ(西洋賭博)で小遣銭を稼ぎながら帰ってきた」。 帰国して農商務省嘱託(無給)となり、それをやめてから数年間、前回のべた「本当の道楽」で父からもらった金をきれいに使ってしまうのである。父も心痛したであろうが、親類の連中も心配して、何とか「正業」につかせたいと考えた。しかし、「もともと気位の高い奴だから、サラリーマンなどでは承知もせず、できもしないだろう」というので、いきなり社長のポストにつけてやったのである。父は草履とり、せがれは社長が人生のスタートだったことになる。ただ「社長」とはいってもボロ会社の典型で、資本金二十万円、払い込み四万五千円、七年間に社長が六人も変ったという日本運輸会社の社長であった。 誠之助は、職についたのであるから借金の跡始末をしようと考え、抵当にはいっていた麹町六番地の住宅を売りにだした。これを四千円で買ったのが横浜税関長有島武郎、有島生馬、里見弴の父親である。 さて、借金を片づけた誠之助は、三年間一歩もお茶屋に出入りしなかった。そして繰り越し欠そん四万円の業績を立て直して、八分配当にまでこぎつけた。今まで道楽者あつかいして信用しなかった世間も、いささか認めはじめてきた。「ボロ会社」再建の名人という評判が立つて、日本メリヤス、日本鉛管製造、入山採炭、王子製紙、日本火災保険、日本醤油、帝国商業銀行、東京製絨など、つぎつぎと問題会社がもちこまれてきた。このうち、最も成功したのは、三十六歳のとき社長になった入山採炭である。反対派は、「東京へ刺客を送る」といつておどしにかかったが、そこは単なるお坊ちゃんではない、逆に自分から鉱山に出かけて、ただ一人ブラブラ山もとを歩きまわった。そうなると、だれも手をだせなかった。 在職十七年で、資本金は倍額、配当は無配から一割となった。社長をやめると退職金に三十万円もらったが、半分の十五万円は従業員に分配し、腹心の鉱務所長に二万円、その他記念品をつくって関係先にくばるなどして、ご自身は二万円しかうけとらなかった。二代目はケチだ、とか、若いときの道楽者はシブチンになる、とかいわれるが、彼はその通説を見事にくつがえしたのである。そういう「男」になったせがれに満足しつつ、純造は八十五歳で永眠した。 2019.07.28 |

小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)昭和六十年三月二十日発行 P.61~67 出 会 い 教育論議がさかん、中曽根内閣も教育問題に意欲をしめしている。 いいことにちがいない。しかし、論議がさかんなのは、弊害が目にあまるからだともいえる。また、議論の多くに「教育」と「学校」とをほとんど同一視したものがある。「教育は教師の仕事」という考え方もある。 そこに疑問と不満が残る。現代日本の頽廃、モラルの欠如、拝金拝物宗、人間の卑弱さなど、すべて「学歴社会」の当然の産物だが、それをつき破るエラン・ヴィタール(フランス:élan vital)が忘れられているのである。 明治・大正・昭和三代の言論史を通じて、スターと見られる人びとは何人かいるが、その中の一人、古島一雄は、 「学歴は?」 ときかれると、 「小学校だけ」 と答えていた。この人を、のちの言論史上のスターに仕上げたのは、まさしく学歴ではなかった。では何か? 第一に、「出会い」をあげねばならない。 前話でも書いた通り、十五歳のとき上京して、同郷の先輩、浜尾新のところにあずけられた。「出会い」の第一号は浜尾ということになる。 ところが、浜尾と古島の関係は必ずしもピッタリいかなかった。浜尾の書生になると、 「貴様学校へ行け、どこにするか」 という。そこで神田の共立学校にいくことになった。のちの総理・大蔵大臣高橋是清が英語の先生であった。ところがすぐ退校にになったので、高橋との縁は生じなかった。
それから二、三転校するが、行くところすぐ又退校退校。 「浜尾という人は温厚の君子で、その時分文部省の権大書記官、大学の総理補か何かしていたが、その人が保証人になって入学する。入学して片っ端から退学をくらう、どうもこまりきっていた。浜尾にしたら実際にこまっていたろうと思う」 この浜尾の書生時代、古島には「官僚ぎらい」の下地ができた。 「来る奴はみな官僚だ。それがみな頭をピョコピョコ下げておるのに、片っ方はふんぞり返っておる」 そのうち、浜尾の上司九鬼隆一がきた。 「これに対する浜尾の態度は慇懃を極める。どうしてこういう階級の差があるのだろうか。(中略)浜尾自身の上に対する態度と下に対する態度には非常な差がある。どうもいやなものだ」 そのうち、浜尾の親友杉浦重剛がイギリス留学から帰ってきた。浜尾は杉浦に古島を引きあわせ、 「こいつをどうかよろしくたのむ」 といってくれた。杉浦は承諾。これが「出会い」の第二号で、浜尾が第一号となったのは、この第二号の出会いの原因をつくってくれたからだといえる。 杉浦については別章でのべる。 杉浦のところに通っているうち、浜尾の家をとび出して田舎に帰るという事件がおきた。それは、 「お前はこれから何になるつもりだ?」 と浜尾にきかれ、古島が答えられずにいると、 「人間というものは志を立てるということが大事だ。それがなくてただ学問してもだめだから一つの目的をたてろ。日本で今一番大きな仕事は鉄道だ。鉄道ということについて誰もほんとうに学問した者はない。だからお前それをやれ」 といわれ、鉄道技師など、たまったものではない、と考えて家出をしてしまった。 やがて、見つけ出されると、日ごろ温厚な浜尾が非常な剣幕でどなりつけた。 「貴様のような奴はおれはよう世話をせんから国へ帰れ!」 浜尾はおどしただけだったかもしれない。だから、そのときあやまればよかったのだ。しかし古島は、 「帰れというなら帰りましょう。明日帰ります。金はありませんから金をください」 といって、あやまらずに郷里に帰ってしまった。 家へ帰ったが、父は婿養子で、おとなしい人だったから、こわくはない。ただ祖父だけがこわかった。 祖父は旧幕時代、但馬豊岡の京極飛騨守につかえ、勘定奉行であった。明治になってからは、藩主と士族の株をあつめ、「宝林社」という銀行のような事業を主宰していた。母親は、 「お前おじいさまのところへいってあやまりなさい」 という。あやまったところで仕方がないから、 「ただ今帰りました」 といった。すると祖父は別に叱らない。 「そちは論語を読んだことがあるだろう。論語の中に«君子は既往をとがめず»ということがある。おれはなにもいわん。遠路のところ帰ったのであるから、そっちで休息しやれ」 といっただけだった。 ※参考1:宮崎市定『論語の新研究』(岩波書店)P.191 61「哀公、社を宰我に問う。宰我、対えて曰く、夏后氏は松を以い、殷人は柏を以い、周人は栗を以う。民をして戦慄せしむるを曰うなり、と。子これを聞いて曰く、成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず」。 そのうち、母親から、家が経済的にこまってきている、ときいて、小学校の代用教員となった。 そして月給をもらうと、いろいろと新しい文房具を買ってきて、机の上に並べてたのしんでいた。ある日、祖父がそれに注目した。 「貴様それはどこから買ってきたか」 「こういうところで買ってきました」 「どうも貴様は、おれと同じ性分でこまる」 眉をひそめて、祖父はことばをつづける。 「これは骨董癖のようなもので、一つの趣味だ。貴様はどうもそれになりそうだ。たとえば一つの掛物をもつ。そうすると間もなくそれに飽いて、もっといい物が欲しくなる。ところが貧乏武士だから金はなし、仕方がないからそれを売ってからさらに新しい物を買う。こういうことを自分も今日までやってきた。しかし、こういうことをしていると、自然にそこに売買の気が生じる。いわゆる掘り出し物とか、売買によって利益を得ようとして、人間が非常に卑しくなる。いわゆる玩物喪志になる。若い者がそんなことになってはいかんから、よく考えろ。おれの家は勘定奉行で、殿様の株や士族の株を集めて金貸しをしているが、これは決しておれのものではない。すべて人のものだ。それをまちがえてはならん。おれの死後には一文の財産も残さんから、それだけ貴様にきかしておく。おやじにもそれをいうておけ」 おやじは養子なので、まるきり無視されていた。 祖父が死んだとき、十円足らずの金と、古い証文だけが残っていた。証文には棒が引いてあった。 「僕はそのとき祖父はえらい人だったと子供心に痛切に感じた」(前出、『一老政治家の回顧』) 小学校の代用教員では将来性がない。考えこんでいるところに、杉浦重剛から手紙がきた。開いてみると、 五月雨にしばし濁れる山の井の底の心は汲む人ぞ知る という和歌がただ一つ書いてある。 「僕はこれを読んで無限の感慨をおぼえた。人生知己の恩を感じた第一歩である」 当時、父は裁判所の書記をしていた。その友人が松江の裁判所にいた。父にいわれて、松江にいって採用試験をうけることとなった。 東良三郎という判事が試験官。古島は、問題にはすべて〇を書いて出した。ただ、他に書くことがないから、 「一体裁判の趣旨とするところは、論語にいう«必ずや訟えなからしめん»という、これが裁判の極致であって、法を論ずるのはそもそも末である」 ※参考2:宮崎市定著『論語の新研究』(岩波書店)P.287 291「子曰く、訟を聴くは、吾は猶お人のごときなり。必ずや、訟えなからしめんか」。 ※宮崎市定著『論語の新研究』で、該当の句に到達するには、他の『論語』の本の索引を調べて、論語二十篇のどの章にあるかを確認してからである。 という議論を書いて出した。すると東判事は、 「これは満点だ」 といって所長に報告、書記官に採用された。 裁判所長富永冬樹は、矢野二郎(東京高等商業学校初代校長)の兄である。古島を、娘と息子の英語の家庭教師にたのんだ。 富永は、古島を属官あつかいにしない。いっしょに食事をしたり、大いに優遇する。 すると、はじめは書記だと見向きもしなかった連中が、古島にお世辞をいうようになる。 「あなたの洋服はいい洋服ですね。これは新型ですか」 という判事までいた。 「何というゲス野郎かとおもって、それからいっそう官僚というものはイヤになってしまった」(前出、同書) 態度が変わらなかったのは、東判事ただ一人であった。 その頃、徳富蘇峰の『将来之日本』というのが出版された。こういうものを読むと、こんなところにくすぶっていてもしょうがない、という気持が強くなる。 裁判所長は好意的だから、ひょっとすると昇進させてくれるかもしれない。そうなると恩義が生じて出ていくことができない。早く見切りをつけるにかぎる、とおもった。 それから月給をためた。そして、「さすがに悪いとおもったから、東判事にも誰にも相談せず、いきなり辞表をぶっつけて、一路神戸へ飛んだ」 そして杉浦に手紙を書いた。すぐ来い、といってきた。 「今からどうするか?」 「わたしはもうおくれてしまった。これから大学に入る気はない。すぐ世の中に出たいとおもう」 杉浦は古島の性格を考えて「新聞記者」をすすめたのである。 ※関連:浜尾新の記事内容とほぼ同じ。 2019.08.13 |
|
内藤湖南『日本文化史研究』(講談社学術文庫)昭和58年3月18日 第6刷発行 ―内藤湖南によって論じられた日本文化論の名著―日本文化史研究 大正13年(1924)初版が出され、昭和5年(1930)増補版が出された。 現代日本を知るには、応仁の乱以後を知れば十分だと喝破する「応仁の乱について」などがとくに有名である。 そのほか、「日本文化とは何ぞや」「日本文化の独立」「維新史の資料について」など秀逸な論文を収める。 本書は日本文化論の名著であるばかりではなく、「歴史とは何か」「日本とは何か」という点まで追求した名著であると言える。 ▼『日本文化史 上』 たとえば忠孝という事がある。忠孝という名目はもちろんシナより輸入した語であるが、忠孝という事実は元来日本国民が十分に具えていて、自分が所有せるものにシナから輸入した名目を応用したものということに解釈しようと欲する傾きがある。しかしながらこれを根本より考えてみると、すでに国民がもっておった徳行の事実があり、しかしてまた地方に固有の国語がある以上、なにかそれに相当した名目がなければならぬはずである。(中略)特別な家族的なならびに君臣関係の言葉としての忠孝ということが、すでに古代にその言葉がなかったとすれば、その思想があったか否やが大きな疑問とするに足るではないか。(P.18) 従来日本史の研究は、いずれの時代を問わず、本国の側からするのが常であった。 たまに松下見林(まつしたけんりん)の『異称日本伝』のごとく、他国の側からこれを見たものがあるけれども、これはごく稀な例であって、殊に徳川の中世以後、国学が発達してから、その研究法が当時の漢学者に比してむしろ進歩しており、学術的に近いために、その日本中心主義の研究法をますます一般に是認せしむる傾向を強めた。(P.33) ▼『日本文化史研究(下)』 私は応仁の乱(1467~1477年)について申し上げることになっておりますが、私がこんな事をお話するのは一体他流試合と申すもので、ちょっとも私の専門に関係ないものであります、が大分若いときに本をなんということなしにむやみに読んだ時分に、いろいろこの時代のものを読んだことがありますので、それを思い出して少しばかり申し上げることにいたしました。それももう少し調べてお話するといいのですが、ちょっとも調べる時間がないので、頼りない記憶で申し上げるんですから、間違いがあるかも知れませぬが、それは他流試合だけにご勘弁を願います。 とにかく応仁の乱というものは、日本の歴史にとつてはよほど大切な時代であるということだけは間違いのないことであります。しかもそれは単に京都におる人がもっとも関係があるというだけでなく、すなわち京都の町を焼かれ、寺々神社を焼かれたというばかりではありませぬ。それらはむしろ応仁の乱の関係としてはきわめて小さな事であります、応仁の乱の日本の歴史にもっとも大きな関係のあることはもっとほかにあるのであります。 大体歴史というものは、ある一面から申しますると、いつでも下級人民がだんだん向上発展して行く記録であるといっていいのでありまして、日本の歴史も大部分この下級人民がだんだん向上発展して行った記録であります。この中で応仁の乱というものは、今もうしました意味においてももっとも大きな記録であるといってよかろうと思います。一言にして蔽えば、応仁の乱というものの日本歴史におけるもっとも大事な関係というものはそこにあるのであります。(P.61~62) そういふ風でとにかくこれは非常に大事な時代であります。大体今日の日本を知るために日本の歴史を研究するには、古代の歴史を研究する必要は殆どありませぬ、応仁の乱以後の歴史を知っておったらそれでたくさんです。それ以前の事は外国の歴史と同じくらいにしか感ぜられませぬが、応仁の乱以後はわれわれの真の身体骨肉に直接触れた歴史であって、これをほんとうに知っておれば、それで日本歴史は十分だと言っていいのであります、そういう大きな時代でありますので、それについて私の感じたいろいろな事をいってみたいと思います。がしかし私はたくさんの本を読んだというわけでありませぬから、わずかな材料でお話するのです、その材料も専門の側からみるとまたうさんくさい材料があるかも知れませぬが、しかしそれも構わぬと思います。事実が確かであってもなくても大体その時代においてそういう風な考え、そういう風な気分があったという事が判ればたくさんでありますから、しいて事実を穿鑿する必要もありませぬ、ただその時分の気分の判る材料でお話してみようと思います。しかし私の材料というのは要するにこれだけ(本を指示して)ですから、これを見てもいかに材料が貧弱であり、きわめて平凡なものであるかという事が分ります。(P.64) かくのごとく応仁の乱の前後は、単に足軽が跋扈ばっこして暴力を揮うというばかりでなく、思想の上においても、その他すべての智識、趣味において、一般にいままで貴族階級の占有であったものが、一般に民衆に拡がるという傾きを持って来たのであります。これが日本歴史の変り目であります。仏教の信仰においてもこの変化が著しく現われて来ました。仏教の中で、その当時においても急に発達したのが門徒宗であります。 門徒宗は当時においては実に立派な危険思想であります(笑声起る)。一条禅閤兼良などもその点は認めているようでありまして「仏法を尊ぶべき」と書いてある箇条の中に、「さて出家のともがらも、わが宝を広めんと思う心ざしは有べけれど、無智愚痴(ぐち)の男女をすゝめ入て、はてはては徒党をむすび邪法を行ひ、民業を妨げ濫妨(らんぼう)をいたす事は仏法の悪魔、王法の怨敵(おんてき)也、」と書いてある。一条禅閤兼良は門徒宗のようなむやみに愚民の信仰を得てそれを拡めることに反対の意見をもっておりますが、其当時においてすでにそういう現象があったということが分ります。それは兼良が直接そういう状態を見ておりましたところからそう感じたのだと思いますが、引きつづき戦国時代において門徒の一揆によってしばしば騒動が起り、加賀の富樫などこれがため亡んでしまい、家康公なども危く一向門徒の一揆に亡ぼされるところでありました。単に百姓の集まりが信仰によって熱烈に動いた結果、立派な大みょうをも亡ぼすようになりました。非常に危険なものであって、門徒宗が実に当時の危険思想の伝播に効力があったといっていいのであります。ただし世の中が治まると、危険思想の中にもちゃんと秩序が立って紊まり返るもので、今の真宗では危険思想などといふ者がどこにあったかというような顔をしていますが(笑声起る)なかなかそんなわけのものではなく、少し薬が利き過ぎると、どこまで行くか分らぬほどの状態でありました。かくのごとく応仁の乱というものはずいぶん古来の制度習慣を維持しようとしております側――一条禅閤兼良などのような側から見ると、堪えられないほど危険な時代であったに違いありませぬ。 それが百年にして元亀げんき天正になって、世の中が統一され整理されるというと、その間に養われたところのいろいろの思想が後来の日本統一に非常に役に立つ思想になりまして、今日のごとくもっとも統一の観念の強い国民を形造って来ているのであります。しかしこの後も騒ぎがあるたびに必ず統一思想が起るかというとそれはお受け合いができませぬ。今日の日本の労働争議についても保証しろといわれてもそれは保証しませぬ。ただ前にはそういうことがあったというだけであります。何か騒動があればそのたびごとにその結果としてなにか特別なことができるということは確かであります、ただどういうことができるかということは分らない。一条禅閤のごときも当時の乱世の後に結構な時代が来るとは予想しなかったのであります。歴史家が過去のことによりて将来の事を判断するということはよほど慎重に考えないと危険なことであります。 とにかく応仁時代というものは、今日過ぎ去ったあとから見ると、そういう風ないろいろの重大な関係を日本全体の上に及ぼし、ことに平民実力の興起においてもっとも肝腎な時代で、平民のほうからはもっとも謳歌おうかすべき時代であるといっていいのであります。 それと同時に日本の帝室というような日本を統一すべき原動力からいっても、たいへん価値のある時代であったということはこれを明言して妨げなかろうと思います、まあ他流試合でありますからこれくらいのところでご免を蒙っておきます。(大正十年八月史学地理学局同攻会講演) (P.84~87)
内藤湖南先生風貌
内藤湖南といえば、わが國のシナ学の創始者であること、そして何よりもその蔵書のことが念頭にうかぶ。その数五万部、しかも書庫において「暗がりでも目的の書物が探り出せる」(森鹿三『内藤湖南』第九巻付録月報)というのであるからまったく頭が下がる。 昭和四十一年にその伝記が出た。著者は青江舜二郎、タイトルは『竜の星座』。この名著によりながら、とくに蔵書五万部の由来を探ってみたい。 本名虎次郎。慶応二年七月(1866年)秋田県鹿野郡毛馬内に生まれ、昭和九年(1934年)京都府村相楽郡瓶原現在加茂町)で永眠した。六十九年におよぶ生涯で、本との関係は三歳に始まる。 十三歳上の兄が、炉ばたでおもしろ半分に漢詩を教えると、すぐおぼえて、もっともっととせがむ。本箱から本をもちだして、読んで、読んでという。『二十四孝』を読んでやると間もなく暗記した。友だちとかくれん坊をしても、大声で『唐詩選』の暗誦をしていたからすぐ見つかった。おそるべき神童ぶりである。 小学生時代、自分のもっている本を全部ふろしきにつつんで、背おって出かける。じつは継母に原因があった。生母は四歳のとき死別し、つぎつぎと継母がきては去り、小学生のときは四番目の継母であつたが、虎次郎はこの酒飲みの女をきらった。授業がおわり、家にもどっくて顔を合わせるのが苦痛なので、放課後ひとり教室にのこって読むために、すべての本を持参したのだ。すでに幼少の身でおぼえた”悲しき逃避”である。 十七歳、県立師範学校中等科師範科に九十五点、首席で入学。まわりのものはほめそやしたが、彼は継母とはなれて自由になれるほうがずっとうれしかった。そして、普通なら七年かかるところを三年半で卒業、北秋田郡綴子小学校の首席訓導となる。月給十円、下宿代三円、実家送金四円、のこり三円で本を買いはじめた。蔵書五万部の出發点はこのあたりらしい。 翌年(二十一歳)無断上京、『明教新誌』の編集者に採用された。月給八円で生活はくるしく、いろいろな懸賞に応募した。このころは炳卿というペンネーム。このほか、不擬不慧主人、冷眼子、落人後子炳卿、潜夫、黒頭尊者などを用い、二十五年(二十六歳)はじめて湖南鷗侶というのが活字になった。 郷里の十和田湖にちなむものであろうが、青江舜二郎は、父の号が「十湾」であり、その親近感から「十湾」と同義の「湖南」を号にしたのではないか、という。 大同新報をへて三河新聞にはいった。最大の魅力は月給三十円で、すでにこのころ「いい本を手に入れるということはほとんどマニアに近く、しかも一方、親身になって他人のめんどうを見ることもやめない」。三河新聞は三月でやめ、三宅雪嶺主宰の『日本人』にはいり高橋健三に認められてその秘書となった。高橋は官報局長をやめて大阪にうつり、大阪朝日新聞の客員となった。湖南も同行して大阪朝日記者となり、翌年高橋が松隈内閣の書記官長に就任したので朝日をやめて上京、この引きあげのとき、すでに蔵書は一千部に達していた。このあと、台湾日報主事、万朝報論説記者となる。ひるごろ人力車で出社し、二時間ばかりで帰宅すると、二階にこもる。夕食に下りてきてもほとんどモノをいわず、すむとすぐ二階にもどって夜明けまで読書。起きるのは十時ごろ、という生活で、蔵書は三千部に達していた。 三十四歳のとき万朝報をやめ、大阪朝日新聞社に再入社。四十歳までつとめ、翌年京都帝国大学文学部講師、「東洋史講座」を担当、四十三歳で教授。この京都時代に蔵書は五万部にふくれた。家中いたるところに本、本。庭に大きな穴がいくつも掘られが、これは火事のとき本を助けるためである。渉猟範囲もひろく、木村泰治は犬に関するあらゆるシナの文献を読み「犬の文献では朝野群戴にまさるものはないと思います。この本は上野図書館にありません」といったところ「いやもっといいのがある。それは『国語』(書名)だ」と即座にいわれて、とてもかなわないとおもった。あれだけの蔵書をはたしてみんな読んだろうかと多くの人が疑問にした。あるひとにたづねられた湖南氏は「序結はていねい、目次はななめ、本文指でなでるだけ」と、笑いながらドドイツ調で答えた。 徳富蘇峰が訪ねてくるというので、なるべく彼がよろこびそうな本を一室にあつめておいた。ところが、さすがに蘇峰はシナの典籍にくわしく、宋版『史記』十四冊、『宋本毛詩正義』十七冊、唐の写本『説文』一巻の三つを見ただけで大満悦、他の本は見ないで帰った。 湖南は三十歳のとき、十七歳の田口郁子と結婚した。小柄で、色白で、まる顔の肉感的な美人で、初対面で参ったらしい。郁子を女手ひとつで育てた女丈夫の未亡人は、湖南の家によく泊まりに来たが、彼はこの義母もニガ手であった。ムッツリとして終日書斎にこもっていたのは、小学生時代と同様、"悲しき逃避"の一面もあったのである。 近くに同県人の松田家があり、未亡人はそこでよばれては酔いつぶれた。そのつど、松田家に下宿している京大工学部学生石田熊吉は、彼女をおぶって湖南宅へ運んだ。そのせいか、石田青年はつくづく酒はこんなふうにのむべきでないと身にしみて感じ、のちせがれの博英(現代議士)には、十七、八歳ごろから、どんなにのんでもみだれないように実地鍛錬を行ったという。湖南は生涯酒をたしまなかったが、それは多分に心理的なもので、継母と義母の酔態に嫌悪感をもったためらしい。 大正十五年、定年で京都大学をやめ、翌年瓶原村の恭仁山荘にうつる。このころは学者としてよりも、蔵書家、書家、書画鑑定家として有名で、加茂駅の三人の人力車夫は、湖南まいりの客のおかげで生活できた。 ところで、ここで師事した門弟たちは、一つの珍風景を目撃している。 彼はいつも夫人といっしょに風呂に入った。それほど熱くない湯で、出たりはいったり、ちゃぶちゃぶの音の合間には笑い声を立てたりして、二時間ぐらいかかる。入浴の途中、何かで夫人が出てきて書斎を横切ったりするようなときでも、腰をかがめたり、タオルでかくしたりせず、まことに無邪気なありのままの姿。白くふっくりとつややかで、五十の女性とはおもわれない。そこであわてて目を伏せる弟子たちの、よこしまな心がしきりに恥じられるような天真爛漫さであった。「湖南は恐らく、解放された青春を、そしてセックスのうつくしさを、瓶原ではじめて体験したのではなかった>。(青江、前掲書) 「本ばかり読んでいて、いつこどもをつくるのだろう?」とカゲ口をたたかれていた。 ところがどうして、長男乾吉、次男耕次郎、長女百合子、次女ヒナ子、三男戊申、四男茂彦、五男夏五、三女早苗(早世)四女祥子と、常人以上の子宝にめぐまれていたのであるから、まことにおめでたい。 ※黒崎記:よく万巻の書を読むなどというが、そんなことが人間にできるはずははない。人は一年に一万ページの本を読めば、それでひとかどの人物になれるはずだ。一万ページと言えばびっくりするかもしれないが、一日わずか二十八ページずつ読んでいけばいいのだ。と、草柳大蔵氏は書いている。 毎日読むには相当の覚悟しなければならない。 森 信三先生は〈一日読まざれば一日くらわず〉と書かれている。 平成二十年四月一日 追加:貝原益軒『養生訓』(岩波文庫)をよまくてはならいくなり、その本を探すこと2日。2日目にフト2階の本棚にあるのではと思い、そこに見つけることが出来た。 平成二十一年十月二十一日
黄丕烈【こうひれつ】(1763~1825)
「黄丕烈」について調べると、
清朝はその初頃から有名な藏書家が多く、錢謙益及その族孫錢曾、又は季振宜などは、順治より康煕の初年に有名であるが、併し藏書家の最盛期は乾隆の中頃以後にあるので、乾隆の末から嘉慶を經て、道光の初頃まで居つた蘇州の黄丕烈は最も有名で、殆ど清朝を通じて第一の藏書家と言つてよいのである。 ▼黄丕烈は宋版の本百餘種を得て、百宋一廛と號した。この頃の藏書家は、單に收藏の多きに誇るのみでなく、又多く古版の本を得ることを努めて、而もその上に古版を以て通行の本を校勘することを努めた。この黄丕烈は、その點に於ても最もな高い人であるが、この人の刻した士禮居叢書は、多くは宋版その他古版の本を飜刻して、精巧を極めたので、清朝に出版された叢書の中でも最も善い本と言はれ、今日に於てはその値の高きことも、殆ど古版の本に匹敵するほどで、我國に傳來したものは恐らく二部位に過ぎない。
▼この人達は又藏書の事に就て色々の趣味あることを企て、百宋一廛については、當時古書の校勘に於て第一人者と稱せられた顧廣圻は、百宋一廛賦といふものを作つてその藏書の富んでゐることを褒め立てなどしたので、當時の藏書家の間にもてはやされた事であるが、黄丕烈は又嘉慶年間に、十年ほど引續いて祭書といふことを始めた。即ち黄氏には讀未見書齋といふ書齋があつたが、其處で祭書をやつた。その後になつて、士禮居で祭書をしたこともある。その祭をする毎に必ず圖を作り、その友人なる學者達に、圖説を作らせたのであるが、前に言つた顧廣圻も、士禮居祭書の詩といふものがあつて、今に傳つてゐる。昔唐の賈島は、年の終に、一年間作つた詩を自ら祭つたといふ事が傳へられて、一つの文壇の佳話となつてゐるが、祭書といふことを始めたのは黄丕烈からで、これも文壇の佳話に相違ない。この人の藏書は、その後展轉して今日支那・日本に於ける藏書家の中にも傳はつてゐるものがあるが、これはその人が死んだ後に散亂したのは勿論なるも、死んだ後ばかりでなく、其人の生存中に既に人手に渡つたものもあるのである。支那人の藏書などを好む人は、多くは黄丕烈の如く讀書家で、又校勘の好きな人であつて、日本などの如く、金があつて、讀めない本を澤山蒐めるのとは違つてゐるので、多少財産のある人でも、全力を擧げて書籍を蒐める結果、晩年には多く貧乏になつて、自然に書籍を賣らねばならなくなる。黄丕烈なども、五十歳以後は大分金に窮したらしく、當時(嘉慶の末頃に)新に起つて來た藏書家、汪士鐘に色々な珍本を賣つたことがその年譜に見えてゐ、後に自分が賣つた本を、汪士鐘から借りて校勘したりなどしてゐる。勿論然うかといつて、古書を蒐めることを絶尊に止めてゐるのではないが、一方賣りながら、一方買ひ集めてゐるのである。ごく晩年(道光五年)その六十三歳の時には、自分で本屋を開店してゐるが、到頭この年に亡くなつた。
▼藏書家の中で張金吾は最も晩年不幸になつた一人であるが、大體藏書家といふ者は、自ら好んで讀み、且蒐める人に限りて、支那でも數代相續した人の殆どないといふ事、それから又讀みもしない藏書家は、却て數代相續してゐるといふ事は、一種の非常なる皮肉なことである。併し前にも言つた如く、支那人は自分の好むところを滿足しさへすれば、そのために財産を失はうが、晩年藏書が散亂しようが、そんなことを豫め考へずに、全力をつくして集め、藏書志を作り、或は又善本を飜刻し、藏書の效力を後世に貽すといふ事は、むしろ藏書家としての本望に叶つた事かも知れぬ。かういふ不思議の趣味は、近代の支那に於て發達したところであるが、日本に於ける藏書の趣味も、斯ういふ風に發達することを希望して善いか惡いかは別問題として、吾々が目前見るところでも、最近藏書の集散が激しくなるところから考へると、矢張支那の近代の跡を追ふものと考へられない事もない。(談話筆記)「青空文庫」による。 |
|
南方熊楠『十二支考』 桑原武夫『わたしの読書遍歴』(潮文庫)昭和六十一年四月二十五日発行 P.199~204 十二支に一二の動物を配当した最初の文献は、後漢の王充(おうじゅう)の『論衡(ろんこう)』だといわれるが、これは日本にもはやくから伝わり、いまなお勢力を失わぬことは、今年は寅年(とらどし)だから阪神タイガースが優勝した、などといわれることにもあらわれている。 南方熊楠は一九一四年から、雑誌『太陽』に毎年の干支(えと)の動物について、古今東西の説話をふまえたエッセイを執筆した。寅年からはじまって子年まで一一年間にわたるが、丑についてはついに書かなかった。いま『南方熊楠全集』の第一、第二巻に収められているのがそれである。一〇歳で『文選(もんぜん)』を暗記したといわれる希代の記憶力をもったうえに、十数カ国語に通じる語学力をそなえた、ものすごい読書家であった南方は、かれ自身が百科全書そのものであったといえる。その知識を総動員して書かれた『十二支考』は、それぞれの動物についての世界で最も豊富な文献といってもよい。 猿についていえば、まずその世界各国語による名称を列挙し、英語では古くはすべてエープ(「まねをする」という動詞 ape から出たともいう)といったが、一六世紀ごろからモンキーという言葉ができ、前者は尾のない人間に近い猿どもをさし、後者はその他を一括するなどと述べたあとで『本草啓蒙(ほんぞうけいもう)』によって猿の和名を一二あげる。コノミドㇼ、ヨブコトㇼ、イソノタチハキ、イソノタモトマイ、コガノミコ、タカノミコ、タカ、マシラ、マシコ、マシ、スズミノコ、サル。木の上に棲むからトリという。老猿はよく人の不浄を嗅ぎわけるというので、これに帯刀させ、神前に不浄のまま出てくる連中を追っぱらわせたところからイソノタチハキという。マシラは梵語の摩頭羅から出たらしいが、この外来語がサルより多く使われたのは、サルが「去(さ)る」ときこえるのに反してマシラは「優(まさ)る」に通じるからだといった調子である。言葉のせんさくにすぎぬ、などというひとがあるかもしれない。しかし、そういってしまうことは、古代中世の文献はすべて無用だということにつらなる。『今昔物語』の読解力においては、南方の右に出るものがなかったことを知らねばならない。『今昔物語』は無用だというわけにはいかぬのである。また、類音による言葉への好悪は世界のどこの国にもあることである。言葉を無視して文化の研究はありえないのだ. 南方の書くものによって、わたしたちは日本人の生活における文化的・感情的なるものの根源にさかのぼることができる。しかし、それがわたしたちが思いこんでいるほど、わが国独自なものでなく、日本がどのように世界につらなっているかをも教えれてくれるのである。 ウサギとカメの話を知らぬひとはない。イソップ物語から出たとされているが、これはもちろん後世の附会である。同じような形式の話は南洋のフィジー島にツルとチョウがトンガ島まで競争するというのがあり、マダガスカル、セイロン、シャムなどにもあると知るのは、なんと楽しいことであろうか。田原藤太秀郷(たわらとうだひでさと)が三上山のムカデを退治して竜宮へ招かれる説話も周知のことだが、南方はこれが『今昔物語』に類話があり、中国、インドその他にその起源があることを考証する。 ギリシア神話に出てくるメデュサはだれしも知っているであろう。この妖怪の眼でにらまれた人間は、たちどころに石となる。賢いペルセウスが鏡の反射を利用してその首を斬るという話だ。このように特定の人間または怪物に見られただけで害をうけることを、英語ではイヴィル・アイ、東洋では悪眼、眼毒、見毒などともいうが、いま日本でふつう「邪視」というのは南方の造語である。メルメの小説『コロンバ』を読んだひとは、その女主人公が邪視とされたことをおぼえているであろう。蛇を論じたところで南方は、この民間信仰が世界いたるところにみられることを、豊富な文献によって明らかにしている。こんにちもなお田舎の家の入口にザルをかけるところがある。高天原でアメノウズメが女を隠すべきところを見せたのは、猿田彦の邪視をおさえるためで、古建築や大切なものを入れた箱などにワイセツな像や絵をそなえておくのも、このためだという。 好事趣味のひまつぶしと思われるかもしれないが、こうした知識なしには古い文化は説明できぬのであり、また歴史解釈にも大切な道具となりうる。たとえば『三国志』に出てくる魏の曹操が呂伯奢(りょはくしゃ)を殺したという事実は、この英雄の性格決定上重要なきめ手の一つだが、ここにも南方の知見は有用性を発揮する。曹操が的に追われて逃げたとき、旧知の呂の家に一泊した。主人が酒を買いに出ていったあと、剣を研ぐ音がするので、耳をすますと、「しばって殺せ」というささやきが聞える。先んずれば人を制す。家人を皆殺しにしてみれば、台所に料理用の豚が一頭つないであった。おりから帰ってきた主人をも斬ったという話である。これを不仁と咎められたさい、曹操は「むしろ我をして天下の人にそむかしむとも、天下の人をして我にそむかしむるをやめよ」といったという。岡崎文夫博士は、この言葉をふまえて曹操の性格を決定しようされたが、そのさい、一六世紀の女王マグリットの『エプタメロン』第三四話に同型の話があり、またイタリアのカラブリアにもまったく同じ民話があり、日本では悪七兵衛景清にも、これは南方はふれていないが、明智光秀の重臣斎藤内蔵助にも同じような話がまつわっていることを知るならば、解釈はおのずと変ってくるであろう。 南方熊楠は、このようにあまねく世界にわたる知識をもっていたが、コスモポリタンではなく、日本古来の文化を尊重する愛国者であった。かれは好んで「国のため」という表現を使う。ロンドン滞在中、孫文に会い、「願わくは、われわれ東洋人は一度西洋人をあげてことごとく国境外へ放逐したし」といって中国の革命家を驚かせたことがある。これはもちろん、相手のどぎもをぬいてやろうというイタズラの気分もあるが、同時に明治の学者に共通な国家民族意識のあらわれでもあるだろう。 かれは、近代合理主義の立場から由緒正しい神社を合併整理しようとする時の政府に、猛烈な抵抗をこころみたが、けっして現在の僧侶や神官を尊重するようなことはなかった。「無学無頼」なかれらを人民の精神的指導者にしようなどというのは「娼妓は烈女伝を説かしめる」ようなものだとまでいっている。 実用の学をなにより尊重するかれは、もちろん迷信を尊重したりはしない。ただ古くからつづいた迷信には、いつもその存在を必然とした理由があるのであって、これを無視して一挙につぶそうというのは無意味でもあり得策でもないというのである。当時の日本人は西洋文明国には迷信などないものと思いこんでいたが、南方は、最近まで西洋がどのようにバカげた迷信に満ち満ちていたかをつねに指摘する。ローマにはキリストのヘソの緒(お)と割礼された前皮があり、カタロニアには聖母マリアの経水をふいたという布切れがあり、オーグスプールには聖バルテルミの男根が鎮座して、「おのおの随喜恭礼されたなど、こんな椿事は日本にまた有るかな」などと書いている。かれは好んで男女愛欲のことを記し、それがかれの考証論文に一種のユトリをあたえているが、ここにもかれの反官学的庶民性があらわれているといえよう。 とにかく面白い本である。 2019.05.18 記す。 附記。本書は平凡社(東洋文庫)におさめられている。
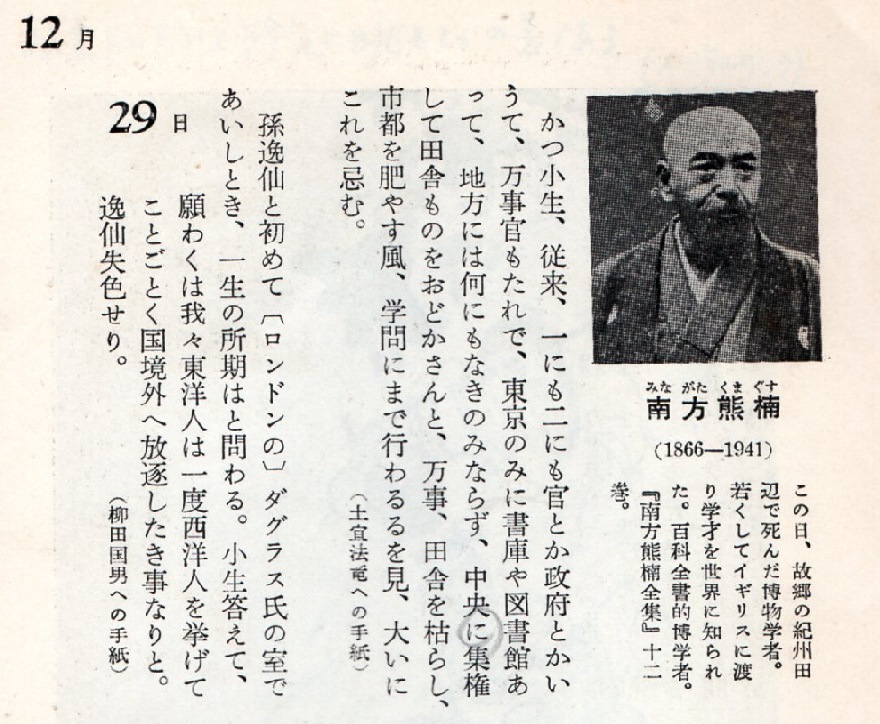
かつ小生、従来、一にも二にも官とか政府とかいうて、万事官もたれで、東京のみに書庫や図書館あって、地方には何もなきのみならず、中央に集権して田舎ものをおどかさんと、万事、田舎を枯らし、市都を肥やす風、學問にまで行わるるを見、大いにこれを忌む。(土宜法竜への手紙)
孫逸仙と初めて〔ロンドンの〕ダグラス氏の室であいしとき、一生の所期はと問わる。小生答えて、願わくは我々東洋人は一度西洋人を挙げてことごとく国境外へ放逐したき事なりと。孫逸仙失色せり。(柳田国男への手紙)
12月29日、故郷の紀州田辺で死んだ博物学者。若くしてイギリスに渡り学才を世界に知られた。百科全書的博学者。『南方熊楠』十二巻。 *桑原武夫編『一日一言』――人類の知恵――(岩波新書)P.215 ※神坂次郎『縛られた巨人』南方熊楠の生涯(新潮社)一九八七年八月十五日 五刷 手元にある。
※神坂次郎『縛られた巨人』南方熊楠の生涯(新潮社)一九八七年八月十五日 五刷 手元にある。 2010.05.31 |
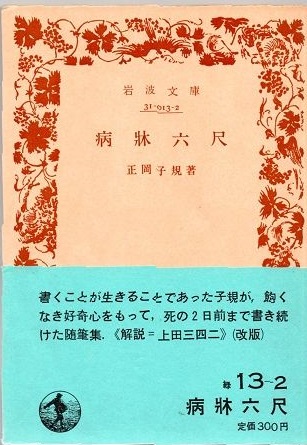
▼『病牀六尺』正岡 子規著 (岩波文庫) 1984年7月16日 第26刷改版発行 一
●病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余りにも広すぎるのである。僅かに手を延ばして畳に触れる事はあるが、布団の外へまで足を延ばして体をくつろぐ事も出来ない。甚だしい時は極端の苦痛に苦しめられて五分も一寸も体の動けない事がある。苦痛、煩悶、号泣、麻痺剤、僅かに一条の活路を死路の内に求めて少しの安楽を貪る果敢(はか)なさ、それでも生きて居ればいひたい事はいひたいもので、毎日見るのは新聞雑誌に限って居れど、それさへ読めないで苦しんで居る時も多いが、読めば腹の立つ事、癪にさわる事、たまには何となく嬉しくてために病苦を忘るるやうな事がないでもない。年が年中、しかも六年の間世間も知らずに寐て居た病人の感じはまずこんなものですと前置きして(以下略)P.7~
(五月五日)
二十一(P.43) ●余は今まで禅宗のいはゆる悟りといふ事を誤解して居た。悟りといふ事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思って居たのは間違ひで、悟りといふ事は如何なる場合でも平気で生きて居る事であった。 ●因に問ふ。狗子に仏性ありや。曰、苦。 また問ふ。祖師西来の意は漢字奈何(いかん)。曰、苦。
また問ふ。……………………………………。曰、苦。
(六月二日)
参考:「因に問ふ。狗子に仏性ありや。」は『無門関』の「趙州の狗子(くし)」からの引用である。
四十五 ●写生といふ事は、画を画くにも、記事文を書く上にも極めて必要なもので、この手段によらなくては画も記事文も全く出来ないといふてもよい位である。これは早くより西洋では、用ゐられて居つた手段であるが、しかし昔の写生は不完全な写生であつたために、この頃は更に進歩して一層精密な手段を取るやうになつて居る。しかるに日本では昔から写生といふ事を甚だおろそかに見て居つたために、画の発達を妨げ、また文章も歌も総ての事が進歩しなかつたのである。それが習慣となつて今日でもまだ写生の味を知らない人が十中の八、九である。画の上にも詩歌の上にも、理想といふ事を称(とな)へる人が少くないが、それらは写生の味を知らない人であつて、写生といふことを非常に浅薄な事として排斥するのであるが、その実、理想の方がよほど浅薄であつて、とても写生の趣味の変化多きには及ばぬ事である。理想の作が必ず悪いといふわけではないが、普通に理想として顕(あらわ)れる作には、悪いのが多いといふのが事実である。理想といふ事は人間の考を表はすのであるから、その人間が非常な奇才でない以上は、到底類似と陳腐を免れぬやうになるのは必然である。固(もと)より子供に見せる時、無学なる人に見せる時、初心なる人に見せる時などには、理想といふ事がその人を感ぜしめる事がない事はないが、ほぼ学問あり見識ある以上の人に見せる時には非常なる偉人の変つた理想でなければ、到底その人を満足せしめる事は出来ないであろう。これは今日以後の如く教育の普及した時世には免れない事である。これに反して写生といふ事は、天然を写すのであるから、天然の趣味が変化して居るだけそれだけ、写生文写生画の趣味も変化し得るのである。写生の作を見ると、ちよつと浅薄のやうに見えても、深く味はへば味はふほど変化が多く趣味が深い。写生の弊害を言へば、勿論いろいろの弊害もあるであろうけれど、今日実際に当てはめて見ても、理想の弊害ほど甚だしくないやうに思ふ。理想といふやつは一呼吸に屋根の上に飛び上らうとしてかへつて池の中に落ち込むやうな事が多い。写生は平淡である代りに、さる仕搊ひはないのである。さうして平淡の中に至味を寓するにものに至つては、その妙実に言ふべからざるものがある。 (六月二十六日) 八十七 ●草花の一枝を枕元に置いて、それを正直に写生して居ると造化の秘密が段々分かって来るような気がする。 (八月七日) 参考:『この世 この人生』の著者:上田三四二さんが、書くことが生きることであった子規が、飽くなき好奇心をもって、死の2日まで書き続けた随筆集《解説=上田三四二》 その解説の最後の部分に、『病牀六尺』の最後の回の載った翌九月十八日、覚悟の子規は妹律らにたすけられて辛うじて筆を持ち、画板に貼った唐紙に辞世の句を書付けた。「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」。痰を切り、ひと息いれて、「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」。またひと休みして「をとゝひのへちまの水も取らざりき」。そこで、筆を投げた。穂先がシーツをわずかに汚した。そしてその日のうちに昏睡におちいった子規は、越えて十九日の午前一時に、息を引き取る。三十六歳。いまふうに数えて、三十五歳になる直前であった。 追加:子規の著作に『仰臥漫録』(岩波文庫)がある。子規が死の前年から明治34年9月から死の直前まで、俳句・水彩画等を交えて赤裸々に語った稀有な病牀日録。現世への野望と快楽の逞しい夢から失意失望の呻吟、絶叫、号泣に至る人間性情のあらゆる振幅を畳み込んだエッセイであり、命旦夕に迫る子規の心境が何の誇張も虚飾もなくうかがわれて、深い感動に誘われる。(表紙の文章)
参考1:小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中央文庫)昭和五十八年八月十日 P.179 より。 正岡子規 露伴の評で小説を断念し俳句に 伊予松山の正岡升は、明治十六年十七歳のとき上京し、第一高等中学校在学中二十三歳で喀血して「子規」と号した。子規はほととぎす、杜鵑、杜宇ともいう。蜀の国王であった望帝(杜宇)は、自分の徳が宰相に及ばないと思い、帝位を譲って他国に亡命した。のち帝は死し、その魂は化して子規となり、蜀に飛来して血を吐きながらなきつづけたという故事の因む。 翌年、文化大学にはいり、国文科を修めることとなったが、学業よりは俳句に打ち込んだ。たまたま幸田露伴の『風流仏』に感心した。自分もこのような作品を書きたいと思い、うるさい寄宿舎をでて本郷駒込の借家にうつり、小説『月の都』を書き上げて露伴を訪ねたのが二十六歳のときである。 露伴も同年の二十六歳で『風流仏』は二十三歳の作品であった。(子規、露伴の生まれた慶応三年には尾崎紅葉、石橋忍月、夏目漱石などの文人が生まれている)。子規は露伴に、「この小説の趣向は『風流仏』から盗んだところがある。それは『風流仏』を喜ぶからである。周囲の人のすすめにしたがって上梓しようと思うが、君の諒解を得ておきたい」とのべ、座に客があったので、二十分ぐらいで原稿をおいて帰った。 一日たって原稿が送り返され、ざっとした批評がついていた。子規はもっとくわしい批評をききたいと思って、かさねて訪問した。露伴はこの作品に「文章の骨は得ているが肉はいまだし」とか、「覇気強し」という評語をあたえたようである。この一作を世に問い、小説家として立とうとした子規の野望は挫け、小説は断念して俳句の道に専念することとなった。 陸羯南の親友加藤恒忠は子規の叔父にあたる。子規は在学中から新聞社にはいりたいと思い、叔父を通じて申しに入れていた。古島一雄が「加藤の親戚の者で、正岡という青年が入社したいというから、会ってくれ」と陸にいわれたのはそのためである。古島が合ってみると、紺がすりの着流しで、顔色蒼白の男である。「目下帝大にいるが、退学して入社したい」という。「あと一年で卒業するなら、入社はそれからでも遅くあるまい」とさとすと、「実は、もはや試験のための学問はイヤになった。ことに井上哲次郎の哲学の講義など、この上きかされてはたまらない。自分は元来病身だから、一日も早く所信を実行したいのだ。それは俳句の革新だ」と正岡青年はいった。古島は俳句のことは何も知らなかったが、試験のための学問がイヤになったという意気に共鳴して、ただちに入社を予約して、まず作品の寄稿を求めた。 そこで子規が書いたのが「かけはしの記」という俳句まじりの紀行文で、これが社中の認めるところとなり、九月に大学を退学した子規は、十二月に日本新聞社にはいった。入社して初めて書いたのが『獺祭書屋俳話』で、俳句界革新の暁鐘となった。ついで「岐蘇三十首」という漢詩をのせ、この方面では自信家ぞろいの社中を驚倒させた。 『日本』は、伊藤内閣の発行停止処分にそなえて『小日本』を出すこととし、その編集責任者に子規が抜擢された。推薦者は古島で、論説は古島が一時間ずつ出張して兼務するという条件になっていた。それから毎日一時間ずつ机をならべているとき、子規は古島に「俳句をやってみないか」とすすめた。 「タカが知れた十七のチョンノマ文学だ、一夜百句ぐらいワケはない」 と古島はうそぶいた。子規は「梅」という題を出し、翌日、百句をつくってみせると、子規は一笑した。 「これはまるで漢詩の翻訳じゃ。俳句には俳句の作法もあれば、材料もある。こんなものは俳句でも何でもない。まずは古人の俳句を詠むことだ」 子規は『古人五百題』という本と、かねて自ら分類していた材料の「種本」をくれた。それは、「大」の例句としては、「荒海や佐渡に横たふ天の川」(芭蕉)が、「美」の例句としては、「狩衣の袖の浦這う蛍哉」(蕪村)が、「奇の」例句としては「日の光今朝や鰯の頭より」(蕪村)が掲げてある。その他、「雅」としては、「時雨るるや黒木つむ家の窓明り」(野沢凡兆)、「繊」としては、「つかむ手の裏を這ふたる蛍哉」(蕪村?)、「比喩」としては、「しだり尾の長屋々々のあやめ哉」(嵐雪)、「即事」としては、「文もなく口上もなし粽(ちまき)五把」(嵐雪)などがあげてある。 作句の模範であると同時に、子規の鑑識による選句集として貴重な入門ガイドとなるはずであった。さらに子規は「古州」という俳号まで選んでやった。また「達磨さんこちら向かん花も候」という古州の句を紙上にのせたりして奨励したが、「無縁の衆は済度しがたく、こちらの方でサジを投げてしまった」古島は、晩年になって、「もしあのとき勉強しておいたら、老後の楽しみになったろうものをと、今になって後悔している」とひとに語ることになる。「古州」という子規直選のゆかりの号の代わりに「古一念」という別号が世に知られるゆえんでもある。 それはそれとして、古島は子規の絶倫の精力におどろいた。肺病だというのに連載小説を書き、材料の取捨、原稿の検閲、絵画の注文、募集俳句の選、艶種の雑報まで、自ら筆をとって朝から晩まで努力したのである。しかし、病いは次第に進み、二十九歳のとき従軍記者となって大連から帰る船中で喀血がやまず、翌年から歩行の自由を失い、病床につくこととなった。三十一歳のとき腰部疼痛がはげしくなり、重体に陥ったこともある。三十二歳のとき自ら墓碑銘を書いた。 「正岡常規又ノなハ処之助又ノなハ升又ノなハ子規又ノなハ獺祭書屋主人又ノなハ竹ノ里人伊予松山ニ生レ東京根岸ニ住ム父隼太松山藩御馬廻加番タㇼ卒す母大原氏ニ養ハル日本新聞社員タリ明治三十□年□月□日没ス享年三十□月給四十円」 というもので、空欄の個所はそれから四年目に埋まった。すなわち「明治三十五年九月十九日没ス享年三十六歳」となったのである。 森鴎外は「遺言には随分面白いものが有るもので、現に子規の自筆の墓誌抔(など)も愛敬が有って好い。樗牛の清見潟は最高だろう。我々なんぞとは趣味が違ふ。西洋の昔の人の中で、最も面白く感じたのは、第十三世紀に死んだ独逸詩人 Walther von der Vogelweide の遺言だ。それは西洋の風習どほり、地面と平らにひらたい石を置いて、其石に窪みを四つ彫り込ませて、それに麦と水とを入れさせて、鳥に飲ませたり食わせたりしてもらひたいといふのであつた」(『妄人妄語』)と書いた。 ※参考1:広辞苑によると、し-き【子規】ほととぎす。しき【子規】→まさおかしき(正岡子規)。なは常規となっている。 ※参考2:最近、司馬 遼太郎『坂の上の雲』でNHKで放映されて多くの人が視聴されたようです。子規は(1867~1902)、秋山真之は(1868~1919)である。 ★プロフィル:正岡 子規は、日本の俳人、歌人、国語学研究家。なは常規。幼名は処之助で、のちに升と改めた。 俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面に亘り創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治時代を代表する文学者の一人であった。死を迎えるまでの約7年間は結核を患っていた。 2009.10.27,2011.01.02追加。 |

日本の現代の開化を支配している波は西洋の潮流で、その波を渡る日本人は西洋人ではないのだから、新しい波が寄せる度に自分がその中で食客をして気がねをしているような気持ちになる。新しい波はとにかく、今しがた漸くの思いで脱却した旧い波の特質やら真相ゆあらも弁えるひまのないうちに、もう棄てなければならなくなってしまった。……こういう開化の影響を受ける国民はどこかに空虚の感がなければなりません。またどこかに不満と不安の念をいだかなければなりません。……我々のやっている事は内発的でない、外発的である。これを一言でいえば、現代日本の開化は皮相、上滑りの開化である。(現代日本の開化)
1月5日生れた明治大正期の文豪。当時の自由主義運動のそとにあり、余裕派と呼ばれた。『坊ちゃん』『明暗』『文学論』 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.4 |
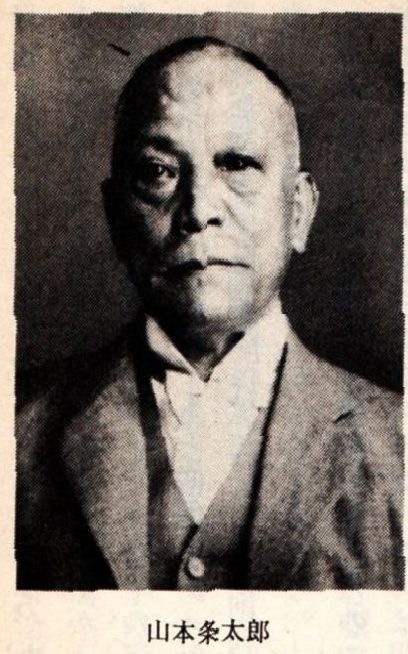
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.24~28 山本丈太郎 吉田茂とは従兄弟同士 明治四年の廃藩置県によって武士階級は崩壊し、流離落剝(らくはく)の境遇におちたものも少なくなかったが、越前藩で十石二人扶持(ぶち)だった山本条悦(のち武と改名)は旧藩主松平家の家従に採用されて、明治五年家族とともに越前をたった。このとき両親につれられて、北国街道から近江路、東海道の十数日におよぶ長旅をしたのが六歳の長男条太郎である。 主人は松平茂昭、その父が横井小楠を招聘した慶永(春嶽)である。小楠をむかえた松平父子の態度は「御父子様ともにつぎの間まで御送迎、かつ痛足のことも御承知にて、しとねを敷き候よう仰せつけられ、ひとへに御断りに及び候へども、御聞入れに相成り申さず、御自身様御立ちなされ候間、いたしかたなくその通りにいたし候」という小楠の手紙が語るように、まことに礼儀正しいものであったらしい。こういう一家の家従に選抜されたのであるから、山本条太郎の父親の人柄もしのばれるところである。すなわち、単に能筆で算数に巧みであったという以上に、折り目正しい誠実の士であったであろう。 上京した山本一家は、日本橋蛎殻町(にほんばしかきがらちょう)にあった松平家下屋敷の一隅に居を定めた。すると彼らよりもわずかにおくれて、横浜から同じ下屋敷の一隅にきた一家がある。岡倉 勘右衛門とその家族たちであった。 岡倉も旧越前藩士で、勘右衛門は計算の力を買われて紊戸(なんど)方をつとめたことがある。越前藩が小楠の指導によって貿易に力を入れ、開港直後の横浜に商店を出すことになったとき、経営をまかされたのが勘右衛門であった。 その店は「石川屋」と称し、越前国産の生糸、絹紬(つむぎ)を外国商館に売りこむ仕事で、開業十五年目に廃藩置県ちなり、閉店のやむなきにいたったもである。勘右衛門は店をたたむと上京し、旧藩主の下屋敷の一隅で旅館をはじめることとなった。 ところが岡倉家には覚三、由三郎という兄弟がいた。兄が十二歳で、弟が六歳、山本家の七歳になる条太郎と遊び友だちになるのは自然の勢いである。今日からは想像もつかないが、当時の蛎殻町には、草原や水たまりが多かった。覚三、条太郎、由三郎の小童たちが、そこでトンボとりや水遊びに熱中したことはいうまでもない。ところが、運命の手は間もなくこの竹馬の友を引きはなし、それぞれにまったく異質の人生コースを進ませるのである。 転変はまず丈太郎の身の上におきた。九歳のとき、母親を失ったのである。十五歳のとみ、九歳の条太郎、上京後生まれてようやく三歳になったばかりのさく――男手に三人の子供をかかえて途方にくれた山本 武は、姉妹を福井の祖母に、条太郎を亡妻の姉で宏(ひろし)家にとついでいたその子にあずけた。 その子の夫は宏仏海、もと僧侶であったが還俗して東京に出、出版界に活躍した人物である。『明教新誌』、『万朝報』はこのひとの創刊にかかり、また佐久間 貞一らと組んで秀英社(のち大日本印刷)を創立した。 明治九年、山本武は後妻をむかえたので子供たちはふたたび父のもとにかえり、条太郎はやがて神田の共立学校にはいった。これは明治四年佐野鼎が創立したもので、一時は生徒二百四名を教える盛況をみたが、佐野の死とともに衰えていた。十一年、校長になって、学校の目的を大学予備門への入学養成に改めたのが高橋 是清(のち首相、蔵相)である。明治十四年度の修学者名簿には、山本条太郎のほか、小笠原 長生、黒田 清輝、松方 幸次郎などの名前がある。 しかし、条太郎は間もなく肋膜炎で退学したため、これらの人びととの縁はうすかった。ただ、これからちょうど五十年たち、実業界から政界入りをした山本が政友会において高橋と親交を結んだのをみれば、不思議な運命の糸が結びつけていたというほかはないようである。肋膜炎がなおっても条太郎は復学せず、亡母の弟吉田 健三の紹介で、三井物産横浜支店の小僧にやとわれた。月手当一円五十銭。 吉田健三は、十六歳のとき大阪に出て医学を学び、二十歳のとき英国軍艦に便乗してヨーロッパにわたり、明治元年二十二歳で帰国すると、横浜の英一番館ことジャーディン・マジソン商会にやとわれた。その後貿易商として頭角をあらわし、五年には『東京日日新聞』の創刊に参画し、十五年には『絵入自由新聞』を創刊した。政界における交友関係も広く、板垣 退助、後藤 象二郎、林 有造、竹内 綱、大江卓などと親交をむすんだ。 両国の伊生(いぶ)村楼という料亭で政談演説会があったとき、その階上では箏曲(そうきょく)の会がひらかれていた。なやかな旋律にさそわれてのぞいてみると、そこに絶世の美女がいる。きいてみると、幕末の儒者佐藤 一斎の孫娘だということで、吉田はそのあと佐藤家をたずね、妻にむかえたい、と申し入れた。これが夫人士(こと)子であるが、子宝にめぐまれなかったので、友人竹内 綱の五男茂(このとき四歳)をあとつぎにもらいうけた。これがのちの総理大臣吉田茂になろうとは健三夫婦もよそうしなかったことであろうが、おなじように、従兄弟同志となった山本条太郎と吉田茂が昭和二年、前者が満鉄総裁、後者が奉天総領事として、おなじ満州の赤い夕日を見ることになったとは、まさに奇縁というほかはあるまい。 さて松平家下屋敷では竹馬の友であった岡倉兄弟のうち、兄の覚三は文部省の役人をへて東京美術学校の校長になった――というよりも、英文の『東洋の理想』『茶の本』の著者として不朽のなをのこす岡倉 天心となった。また弟の由三郎は、東京師範学校、立教大学の教授になった――というよりも、英語教育界の第一人者となったのである。 その後、岡倉兄弟と山本条太郎の友情が復活したかどうか、筆者は知らない。ただ、三人ともに見上げるような一流の人材となったということよりも、「英語」がそれぞれの生活の中心となっていた事実に心ひかれるのである。 三井物産社員山本丈太郎が、いかにして英語をマスターするにいたったかは、かって拙著『日本さらりーまん外史』で物語ったことがある。正規の学校こそ出なかったが、山本もまた英語の達人となった。実業家、政治家としての多忙な日常においても常に英米の新刊書をもとめ、熱読した。たとえば堀切 善兵衛は「シーグフリート氏が『英国の危機』を書いて非常に好評を博したときだ。私はこの本を読みたいと思ったがまだ手にはいらなかった。ところがある日山本氏を訪ねて雑談し、帰りがけに本棚を見わたすとそこにその本が……」(『山本 条太郎追懐禄』)と書いている。岡倉兄弟、山本たちは、竹馬の友であると同時に英語の友でもあったといえよう。 2019.07.05 |

人は三ッの愛の中に生き、一ッの愛無きに至って死す 幸田露伴「ひとり言」 谷沢永一『百言百話』(中公新書)昭和60年2月25日発行 P.116~117 幸田露伴は数年四十八歳の大正三年、「ひとり言」を書き連ねて次の一文を草した。 ――「人は三ッの愛の中に生き、一ッの愛(さえも)無きに至って死す。いとけなきほどは、親の愛の中に養われて生く。父の力、母の情、春の天の暖むるが如く、夏の地の蒸すが如く、弱き身を扶けられて、さてわずかに人となる。既に長じては、男は妻の愛の泉に涵されて、苦しき世にも心の乾き枯れざるを得、女は夫の陰に擁かれて、たまり無き身の生命安らかなるを得。又老いての後は子の愛を思いの綱として、これに索かれて生く。親の愛、配偶の愛、子の愛、此の三の愛あればこそ、人も生甲斐ありて、生き居りもするなれ。親は無くても子は育つと云えど、親の愛にはぐくまれぬ児を見れば、痩せたる山の拗れたる樹を見るが如し。力ありても優しからずざんがん生立つ。妻無き男を見れば、巉巖(高くそびえ立つ山)に雲断え、怪石(きがん)の水を失いたるが如く、其の好きものも、古画の半破れたるを観るに似、其の悪きものは、鏽刀の室無きを望むがごとし。夫無き女の老いたるは、薔薇の花すでに謝して(しぼみ落ちて)刺いたずらに硬きが如く、猶若きは、山の禽の雨にしおたれて翼悲しく窄るを見るが如く、忌わしく、又あさまし。(中略)およそ此等のさまを思うに、愛執は仏の呵(叱る)ところなれども、まことに人の世の味はただ愛の鹹によりて調えられ、愛の鹹気失すれば羹臛(野菜の吸物と肉の吸物)皆敗るる(あじがなくなる)なり。古き諺に生(生命あるもの)相憐み、死(生命を失ったもの)相捐つ(捨てる)とあり。人は相憐み相愛して生き、生きては相憐み相愛し、相憐み愛せずして相棄て捐つるに至りては死し、死しては相棄て相捐つるなり。(中略)風止みては火おのずから滅えんとし、雨遠くしては草ようやく枯れんとす。愛のある間にのみこそ人の世はあるべけれ>。 露伴は南蕃渡来のキリスト教風ではない、わが國びとの伝統おみび常識の延長線上に愛を説いた。社会の構成員がいかに富もうと、それぞれの人間の愛が濃くならずして何の喜びぞ。 ※関連1:大倉 喜八郎 ※関連2:安田 善次郎

捨てることの大切さ 鎌田茂雄『正法眼蔵随聞記講話』(講談社学術文庫)P.162~163より 現代の世の中は、あまりにも多くの情報や物に溢れている。少しでも情報を減らしたり、物も余分なものを持たぬことが、現代における施しであり、供養であると私は思う。私自身も、新聞は毎日とっていない。時たま必要ならば買うが、あまり読まない。大きな事件は朝の六時のラジオのニュースで大体分かる。洪水のように溢れる情報から心を守らなければ仕事ができないからである。幸田露伴氏の『閑窓三記』のなかに「捨」という随筆があるのでここにかかげておく。 取ることを知りて、捨つることを知らぬは、大なる過ちなり。雑草破瓦などを除き捨つれば、庭のおもむきはおのずからに成り、紙片糸屑などは掃き捨つれば、家の内はおのずからに整ひ、莠は捨つれば稲は肥え、蕾を多く摘み捨つれば、菊の花はいと大きく咲くなり。天地もと人を悩まさず、人ことさらに要無きものを取りて、自ら累らはし、自ら苦しむのみ。捨てなむ捨てなむ。烟管も捨つべきなり。酒杯(さかずき)も捨つべきなり。無くてぞ有る可き此等の物を捨つれば、要なきわづらひは大方去るなり。おもへば捨つべきものの猶多くも有る哉。無くて事欠かぬほどのものを悉く捨てて、袂の風のただ清く、心は水のただ平らかなるに至らば、人は望もおのずから成りて、徳もおのずから進みつべきなり。さは云へ、さは云へ、捨てかぬることよ。 取ることだけを知って、捨てることを知らないのは大きな過ちであるという。「天地もと人を悩まさず」であって、天地の書かれざる経は、春になれば花を咲かせ、秋になれば紅葉する。天地の運行はもともと人を悩ますものではない。それは「至誠の用(はたらき)」であるからである。しかるに人はことさらに必要のないものを取って、自らを苦しめている。たしかに現在は不必要なものがあまりに多い。天地の流れにそわないものばかりである。そこで露伴氏は「捨てなむ捨てなむ」というのである。烟管も捨てるべきだし、酒杯も捨てるべきだという。なくてもよい。これらの物を捨ててしまえば、わずらいごとも大部分は去ってしまうにちがいない。 このように「捨てる」ことをひたすら実行すれば、「袂の風のただ清く、心は水のただ平らかなるに至らば、人は望もおのずから成りて、徳もおのづから進みつべきなり>と喝破する。あらゆる物を捨て去ってしまえば、まさしくそれは清風流水の境地になるのである。 ここまでは何とか分かる。しかしいざ捨てようとする時、どんなものでも捨てられなくなるのが人情である。露伴氏も「さは云へ、捨てかぬることよ」といっているではないか。 「捨」というのはできるようでできない。供養でも布施も捨の思想が貫徹していなければできるものではない。栄西が貧乏人に仏像の材料を平気でやれたのも、まさしく「捨」の思想を淡々と行じたからにほかならない。 ※参考:幸田露伴の樹相学。
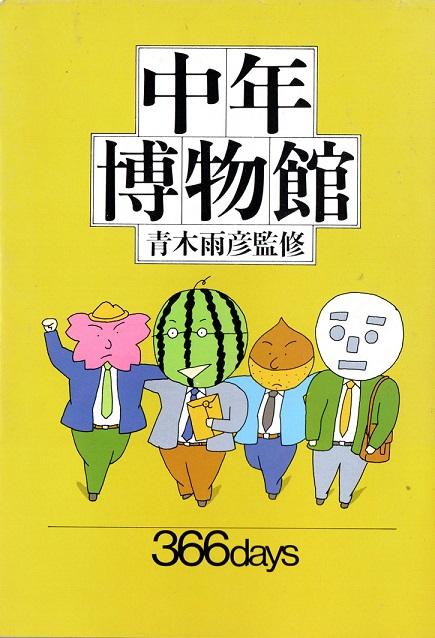
★五月三十一日 人の常情、敗れたる者は天の命を称して嘆じ、成れる者は己れの力を説きて誇る。二者共に陋(ろう)とすべし。(幸田露伴)明治三十八年(一九〇五年)のこの日、読売新聞に連載されていた幸田露伴の『天うつ涙』が日露戦争勃発にあって中絶した。これ以後、露伴は小説を絶ち、学者への道を歩み始める。三十八であった。京都大学講師となる。青木雨彦『中年 博物館』による。 2011.10.06、2019.05.31追加。 |
人の使ひ方、我慢のしどころ

(戦前、戦中にかけての三井財閥の大黒柱。日銀総裁、大蔵商工大臣、枢密院顧問官歴任)
▼『私の人生観』五十五章構成(文藝春秋新社)(昭和二十六年三月二十五日初版)定価二三〇圓
自 序(遺稿) 請はるゝまゝに何回か昔話をした。それが積り積つて一書を成したのである。最初の注文は處世談といふことであったが、此の本の中でも話してある様に、教訓めいたことは一切性分に合はないので――昔話が何かの足しになつたら處世談と云ふもよからう、人生談とな付くるも苦しからず、たゞ住みみくい世の中をいくらか住みよくするよすがにもと、人の質問に、思ひ出すまゝに答へたままでゝである。もとより閑人の閑文字には相違ないが、年甲の龜の甲に勝るもの幾許かあらば幸甚である。 大 磯 に て 著 者 十五章 人 の 使 ひ 方 P.78~83 "人を使ふといふ言葉は封建的かも知れませんが、仕事をやる上にはどうしても多くの人に働いて貰はなければならない。その働かせ方なのですが、人は十人十色ですから仲々一様にはいかないでせうが、大別して二つの型がある様に思ひます。一つはすべて他人まかせのやり方、もう一つは自分手づからやらねば気のすまない人――さういふ點で、いろんな先輩のやり方や貴方のお考へ等をお伺ひ致したいと思ひます"。 仕事をまかせるといつてもそれは程度問題ではないかと思ふ。例へば、鐘紡をあれまでにした武藤山治君などは、自分で何もかもやるといふのではないけれども、抑へるところは、ちゃんと抑へて居て、スキやユㇽミがなかつた。この間も松永(安左衛門氏)が来ての話だが、松永君は電力に辿りつくまではいろんなことをやつた男で、一時石炭の賣込みをやつたことがある。その當時のことだから相當に激しい商賣だつたのであらうが、鐘紡の武藤さんだけは騙せなかったと白状して居る。あとはいゝ加減に誤魔化して、悪い石炭を押付けたといふ意味にとれるが、……とにかく武藤君はあれだけの大會社だけれども、抑へるところは抑へて居たからいゝ加減のことは出来なかつたのだと思ふ。さういふ風に、武藤は人を使ふのにコセコセしないけれども末端の方まで目が行き届いて力が行き渡つて居たのである。 そこへ行くと、朝吹英二といふ人は朝から晩まで會社のひとを怒鳴りつけて居る。つまり癇癪もちなんだ。その上ひどく勿祖(そゝつ)かしい人で、物を忘れたり、間違へたりする。一日中それで騒いで居る。或る時、會社から何處かけへ出かける時眼鏡がないから探して呉れといつて、ガンガンやつて居る。入口の自動車の前で、朝吹さんヂリヂチして煮えくり返つて居るが、秘書が出て来て「どうしてもありませんが……」と言ふ。「そんな馬鹿なことがあるか、どこを探して居るのぞ!」と、朝吹さんが怒鳴りつける。秘書がヒョイと見ると、先生自分で手に持つて居る――「あなたが、御自分で手にもつてるぢやありませんか」朝吹さんが見ると成程自分で持つて居る。大概の人なら「済まん済まん」というところだが、先生いよいよ怒りくるつて「なぜ、それを早く言はんか」と怒鳴とたといふ。ガミガミ云ふのもこゝまで来れば愛嬌であるが、朝吹さんのは年がら年中怒鳴つて居て、理屈も何もないことで人を叱つて居る――それで人気があつた。誰も恨まない。私など家内をたまに怒鳴つたりすることはあつたが、滅多に人を怒鳴つたことがない。若し私が朝吹さんの様に人を叱つたり、怒鳴りつけしたら忽ちに反感を買ふだらう。けれども朝吹さんの場合は𠮟られても恨む人はない、それならば平生可愛がつて物でもやつたりするのかと思ふとさうでもない。人徳といふのか、何かそこに人間のうまみがある。人を惹きつけるものがあるのである。 ところが、益田孝といふ人は前にも話した様に気持の練れた人であるが、それでも怒ると机の上のインキ壺をぶつつけたりする。これをやられたのが岩原謙三で、彼がまだ下ッ端の時分益田さんの横に居てインキ壺をぶつつけられた、然し突嗟の気轉で何かコッケイなことをしてみせたので、益田さんも御機嫌が直つて笑はれたといふ――さういふことがある。有賀長文などゝいふ人も、普段はへェへェ云つてるが、怒ると下の者にインキ壺をぶつつけたさうだ。人はいろいろなものである。 細かい點では格務謙吉がある。彼人は自分で仕事が出来るから人のは歯がゆくて見て居られない、英文なども達者で、外國へ出す手紙は自分で見てみんな直す、簡単にやれるからでもあらうが、相當細かいところまで叱言を言つたらしい。太ッ肚に見えて案外細かいのは郷誠之助だつた。郷の机の上には必ず三本か五本鉛筆を置いてある、一本か二本でよさそうなものだが必ず三本か五本位は置いてあつて、自分で計算をする。人に物を贈るにも贈られるにも、自分で名刺を書く。私などは家内まかせにしてあるが、吉田君(茂氏)などもその様だ――つまり、「苟もしない」という譯である。郷の家などへ行つてみるとキチンとしたもので、大きな待合にでも行つた様な整つた暮し方をして居る。神經が行き渡つて居る、細君は新橋の藝者だつた人で、家のきりもりをして居るのは郷の姉さんか妹さんであつた。その人が偉かつたのかどうか分らぬが、私らの見たところ相當贅澤をして居る様に思はれるのに、郷は「池田君、僕は月に二千圓でやつて居る」言つて居た。當私の家で毎月いくらかゝたか覚えて居ないが、二千や三千でないことだけは確かだ。だからあれだけ堂々たる構へで二千圓というのは餘程の倹約で、郷の姉妹も偉かつたかも知れぬが、郷自身細かいところがあつたからと思ふ。然し郷はさう言つた後で、もつとも妾宅は別だと>と附加へるのを忘れなかつた。然し人間が豪放と見えるのは表)面だけであつた。 ほんとうの太ッ肚と云へば和田豐治などはさうだつたらうが、それでも任せきりといふことはない。渋澤さんは第一銀行の頭取であつたが、これは殆んど専務の佐々木さん(勇之助氏)に一任して居つた。渋澤さんは他の仕事が忙しくて、銀行の日々の仕事はとてもやつて居られない、そこで佐々木さんが全権をもつてやつて居たのだが、そこはよく出来たもので、佐々木といふ人は細心の人で渋澤さんに相談なしでやれる人ではなかつたから、大きなことになると矢張り渋澤さんが決裁したと思ふ。 さういふ風に自分がやつて居る以上、まるで任せるといふことは出来ない。また自分では小さいことには干渉しないつもりでも、立場を變へて見ると必ずしもさうではないといふ場合もあり得る。結局、大きな重要な仕事は自分がやることになるので、私などもその點では人に任せきりといふことはなかつた。大體の結論を示しておいて案を作つたりすることは任せる、その案を見て気にいれば通すし、気にいらねば直させる、誰でもさうなのではないかと思ふ。たゞ自分などは各務の様に細かいところまではやらなかつたつもりだ……勿論、これも自分だけの考へで人はどういふか分らない。 たゞ、私が人を使ふ上に一つ言ひたいことは、第一番にその人の人格を重んじて人を使はなければならぬといふことである。これはもう女中を使ふ場合でも同じことで、人に仕事をやつて貰ふにも自ら限度といふものがあつて、人にやらすべき仕事と、さうでない仕事とある。例へば、自分の秘書として使つて居る人は銀行の秘書なのだから、銀行の仕事にはその人を使ふのは差支へないけれども、自分の家でお客をする場合にはその人を使ふべきではない。世間ではさよくさういふ例を見るが、私はさういふことはやつたことがない。やるべきことではないと思ふ。いくら秘書でも人格を無視して仕事をして貰ふことはよろしくない。その點話でも日本人はルーズで、これ位のことは何も人格がどうかうといふほどのことではあるまいという譯で、安直に物を頼んだり、人を使つたりする……これはいけない。やはり眞ン底からその人の人格を尊重して居ればさういふことはない筈なのである。 2022.03.26 記す。 四十五章 我 慢 の し ど こ ろ P.243~249 "貴方のことを、よく人は「禪坊主」だと言ひますね。然しお會ひしてみたところ、坊主臭いところは全然ないし、貴方御自身も宗教にはまるで關心をお持ちになって居られない様です。そこで、どこから禪坊主といふことが出て来るのかといふと、矢張り貴方の捉はれのないお人柄から来ると思はれます。貴方には第一、金銭や地位のみょう利の慾がない、それから詰まらない事にくよくよしない、そして一寸お見かけしたところ怕いけれども別にお怒りになる様なこともない、尤もこれは怒らないから怕いのかも知れませんけれども……とにかく、容易なことではお怒りにならない様ですね。ところで仏教では、貪、瞋、痴といふことを非常に重視する。やはり慾と怒りと愚痴、竟り非現実的な思考ですね……此の三つが原因で諸諸の悪業が造られる。だから結局のところ「忍」といふことが大事だと言つて居ります。これは仏教ばかりでなく、キリスト教でも儒教でも、新興宗教は知りませんが……大抵の宗教が強調している點だと思はれます。宗教ばかりでなく、一般道徳としても「ならぬ勘忍するが勘忍」とか「石の上にも三年」とか種々(いろいろ)ありますね。西洋にも「世界は忍耐強き者の為に存す」といふ諺がある位――ですから、我慢といふことは古来最も偉大な徳の一つ、殆んど凡ゆる美徳の根源ではないかとさへ考へられてゐるのです。そこから自然に宗教的な感じが出て来て、禪坊主といふ印象になるのだと思ひます……然しそれはまあいづれにしても、今はいろいろの意味で我慢といふことが大切の時だと思ふのですが、それについて、貴方の先ず「お怒りにならない」といふことから……。"
そんなことはありませんよ……いくらぼんやりでも、怒ることだってありますからね。 先ず怒鳴った經驗から言ふと、ヨーロッパへ旅行した時、大矢知君(昇氏)を一遍怒鳴つた。これは今でも、悪いことをしたと思つて、思ひ出しては後悔して居るが……。 あれは、オランダからドイツへ行く時であつた。 大矢知君が随行で来て呉れて居つて、荷物のことや時間のことは、全部同君にやって貰つて、私はただ停車場へ行けばいゝといふ約束になって居つた。そこで、そろそろ時間が来たからホテルで自動車を呼んで、停車場へ駆けつけてみると、どうも大矢知君の言ふ時間に汽車は出そうにもない。そこでだんだん訊き合してみると、驛が違って居る……。 東京だつて、新橋驛もあれば品川驛もある――そこで、カツとなつて大矢知君を怒鳴ってしまった。下の者に對してあんなに怒鳴つたのは私として初めてであつた。悪いことをしたと思つたから、それからはあまり怒鳴ることはしなかつたと思ふ。 元来、私は人を怒鳴ったり、人と喧嘩したりすることはあまり好まない。大矢知君の外には團さんと一ペンやつた位だと思ふ。この時は、卓を叩いてゆあり合つたので私としては一寸珍しい例である。 そのきつかけといふのは、三井合名で使ふ機密費の問題で、合名の機密費は銀行でいくら、物産でいくらと持ちよつて出すことになつて居つた。例へば銀行では半期に二十萬とか三十萬とかちゃんと割當てがきまつて居る。ところが、三井の事業というものが、三井一家でけやつて居る間はそてでよかつたと思ふが、その時代の様に他の株主も入つて来て居ることになると、三井一家だけの合名の機密費に、他の株主も参加している率で會社の金を出すといふことは理屈にあはない。さういふ誰が考へても不合理なことはするべきでない。三井にとつて面白くない。これが銀行を代表する私の意見であつた。その時原嘉道君はいゝといふ意見で、青木君はいけないと言ふ……けれども、これは他はどうでも私の方は絶対に駄目だと言つた。 すると、團さんは「君は三井の為を考へて呉れないのか」――ハツキㇼさうは言はなかつたかも知れないが、さういふ意味のことを言つた。そこで、私は卓を叩いてやあつた。私は三井の為を考へるから先程から理屈を説いて反對して居る。三井の為を考へないとは、一體貴方は何んてい不失敬なことを言ふか、三井がどうでもよいならば、私は何を好んで貴方に反對する必要があるだらう。銀行がこの問題で法律上の問題を起こす様なことでもあつたら、貴方はどうするのか、三井はどういふ立場になるか、貴方はそれを考へたことがあるか――實に失敬千萬のことをいふといふ譯で、私はやつたものだ。すると流石におしゃべりの團さんも黙つていまつた。 團さんは、その頃もう七十を越して居ったと思ふ。私も六十幾つかであつた。何しろ、こんなに人とやり合つたといふのは、私としては後にも先にもない。一生に一度きりである。 無論、三井合名で使つた機密費といふものは、間接には三井銀行に何程かの利益をもたらして居るであらう。これは分る。然しそれだからと云つて、たゞ漫然と金を出すといふ譯にはいかない。だから銀行としては絶對に出さないといふのではないので、書出しの出来る様なものにして貰ひたい。例へば、何處かの寄附金で、誰が見ても納得する寄附といふのがある。さういふ寄附は、銀行がいくら、物産がいくらときめて割りふりする。これは銀行として、何んの寄附として何萬何千何百圓と分る様につけて置く。私は決算報告といふものを重役會に出すのだから、どこへ出しても立派に通るものでなくてはならない。……これは、誰が考へても當然なことではないかと思ふ。それを團さんが三井の中での非國民みたいなことを私に言つたから、私は怒つたのである。 だから、いくら鈍でも、人間である以上は私だつて怒ることもある。肚の中には癪に障ることもある。ただ、少し「鈍」いから他の人の様に度々は表面に出ないけれども、不愉快なことは同じだと思ふ。たゞ心の中で怒つて居ると、矢張り顔色に出るものと見えて、額に皺がよるらしい。今は年齢をとつてしまつたので普段でも皺が出来て居るけれども、「またお父さんの皺がよつた」と家内からよく言はれた。さういふ時はふ機嫌な時である。それだからして、怒るといふことで私も人並みだと思ふ。 たゞ、ここまで来た時、呑みこむか、呑みこまないか、これが問題ですよ……。 こゝまで来た時……こゝのところが我慢のしどころですね。……さういふ點では、私は確かに人よりは我慢強い――自分でさう思つて居る。いまの年齢になつても、随分女房を怒鳴りつけてやりたいと思ふことがある。然し結局我慢してしまふ。腹がたつて、こゝまで来た時、その三分間か五分間……そこで我慢する。爆発するかしないかは、この三分間か五分間だ――こゝを過ぎると不思議に腹がたゝなくなる。却つて、莫迦々々しくなることもある。怒らなくてよかつたと思ふ ……この三分間か五分間が境目だと思ふ。 一生の永い間を見ると、随分自分の思ふ通りにいかないこともある。折角かうして呉れと頼んであつて、さうならないものであるに、結果はまるで逆になつて居る、理屈にも何にも合つて居ない……といふことだつて四六時中起きて来る、けれども腹をたてて怒鳴つて居たからとて格別どういふこともない。喧嘩口論みな同じで……私はどこかが痛い時には、「痛いといふことはどういふことなんだ」「痛いといふことが何んだ」それだけのことぢやないか……さう思つて我慢する。私には哲学もなにもないけれども、それに似たものがあるとすれば、さうして我慢することではないかと思ふ。この我慢ということについては、私は東北人の無神經で、相當の忍耐力をもつて居ると思ふ。 國民性として忍耐強いのは、矢張りイギリス人であろう。今次の世界大戦で、ドイツの敵前上陸が今日か明日かといふ時のあの落着き払つた態度は流石に大國民のなに恥ぢないものであつた。あの時に國内で騒ぎたてたらイギリスはそれまでではなかつたらうか、それれを騒がず、恐れず、ヂツともち耐へたといふことは一寸眞似が出来ないと思ふ。日本人など、その點はどうであらうか……。 2010.03.31 ※送り仮なは旧送り仮な、漢字は旧漢字で書かれている。原文のまま写す。 |
|
司馬 遼太郎『坂の上の雲』が出版された時、よく読まれた。 平成二十二年、NHKが、この原作を放映しています。主要人物として秋山真之・秋山好古・正岡子規・広瀬武夫のおりなす内容である。 秋山真之は日露戦争の時、連合艦隊長官東郷平八郎の下で作戦参謀であった。 島田謹二(1901~1993年)の『アメリカにおける秋山真之』『ロシアにおける広瀬武夫』(いずれも朝日新聞社)の二冊が手許にあります。 『アメリカにおける秋山真之』は主としてアメリカでの研究について書かれている。そのP.9に(海軍大将 山梨勝之進)は書いている。 秋山真之〔教官〕のこと 私が海軍大学生のころ、教官に秋山真之(さねゆき)中佐がおられました。戦略、戦術、戦務を体系づけた、飛びつきたくなるような魅力的で、筋が通って胸のすくような講義ででありました。 アメリカ海軍の空気と感情とを、日本海軍に導入されたのは、秋山教官の力であります。 ジョミ二ありクラウゼヴィッツ、孫子等が、口をついて出て来る。川中島の戦史を説く時(甲越の軍書にいわゆる)車懸(くるまがか)りの戦法とはこういうものだと詳しく説明して下さいました。 ※関連:二つの「戦争論」 「二十閲月(ニツゲツ)ノ征戦已ニ往時ト過ギ……」という連合艦隊解散の辞など一遍でなぐり書きをしたといわれますが、世界の名文ですが、普通の人ではありませんでした。のべつ頭が活動しているのですね。兄さんの好古(よしふる)将軍も偉い人でしたが、頭の方は弟さんの方が上でした。
秋山真之中将のこと
秋山さんが生まれたとき、ご両親が困って、「また男の子がうまれた。困ったなあ、坊さんにしようかな、他に育てようがない」と。聞いておったのが、兄さんの好古将軍で、陸軍大将になった人である。「どうか、弟を坊さんにするのはやめてくれ。自分がなんとかして、あれを育てて、両親には心配をかけんようにするから」と。それで、兄さんの方が士官学校にはいって、少尉になって、貧乏少尉でもいくらか金が入る。それで弟を東京へ呼んだ。行ったところが、ご飯を食べる茶碗が一つしかない。兄さんが食べているときは、それがすむまで、秋山将軍は待っているわけです。下駄も一つしかなかった。そういう貧乏をした。頭がいいんだが、東大で上の方まで行くには学費がないから、海軍にはいった。坊さんになるのはやめたわけである。
それから、アメリカに留学した。マハンに会って、アメリカの海軍大学校に入ることを希望したが、アメリカ海軍は許可せず、はいれない。マハンが「海軍大学校へ入らんでもよい。お前は、本が読めるだろう。戦史を読め。戦史を読んで、ひとりで考えれば、海軍大学校にはいる以上である。それにはこいう本がある」と。それで勉強した。非常に本を読んだ。小村寿太郎さんが、そのとき公使でワシントンに来ていた。非常に二人が気が合って、おれ、貴様で喜んで話しあっていたが、貧乏なことは、二人に勝ち負けはない。 小村さんも非常な貧乏であった。親から借金を引き継いでいた。「ところが、秋山君。今、日本には政党なんていうものがあるが、あの政党なんていうものは、野次馬の集まりだ。外国の政党では、主義があって、多年の訓練によって、政党というものができている。日本の政党では、デマゴーグの集まりで、主義もへったくりもありゃせん。あんなのは、今にいきづまる。国家に大事がある場合に、今の政党なんていうものは、なにもならない。その場合に、君だの、われわれだのは立って、本当に、日本のためを思って、働くべき時機がそのとき来るのだ」。こういうことを、小村さんが、秋山さんに言って、おたがいに許しあった仲だという。そして、読んだ、読んだ。大使館においてあらゆる本を、かたっぱしから、秋山さんが読んだのである。そして、鋭くて、周到で、米西戦争について本省に出した報告には、みな舌をまいて驚いた。こまかいことは、時間がないので申されないが、とにかく着眼が極めて鋭く、また周到で、砲台なんかについても、みなこまかい表がついていた。まあ、そういうふうにして、アメリカの留学をすまして、日本に帰って来た。 私も秋山さんといっしょに旅行したことがあるが、シベリア鉄道で、長いトンネルがあると、ちゃんと図面をもっていて、すぐそこへマークする。非常にすばやい鋭利な人で、ちょっとあの頭というものは、どんな頭なんだろう。 フォシュ元帥が、ナポレオンを批評して「頭に体操させるようなものだ」と言ったが、ちょっと図面を見て、作戦計画をすぐ立てて、そうすると、こういう点、こういう点などというものは、ぐるっとまわる。秋山さんも頭の働きかたが、われわれには、わからんところが《あった。 ロシアに行ったときに、今計画中の一等戦艦の図面を出して、極秘註の極秘のものを、拡げて見せてくれた。わたしと鳥巣玉大佐、米内、三宅など五、六人で見ているわけです。鳥巣は、私の級の人で、非常に頭のよい人であった。私などは、こうして見て帰ってくると、なにも覚えていない。ところが秋山さんは、帰ってくるとすぐ便所にはいる。そして、しばらく考えている。便所から出てきてから紙を出せという。そこへ図面を書く。長さと幅の比例とか、曲線の具合とか、断面の鋼鉄の具合とか、よく覚えている。 「だいたい今日見たロシアの計画の線、どうかね、みんな覚えているかね」というと、だれも覚えていない。あの一分か三十秒の間に、ナポレオンみたいに、秋山さんの頭がくるっとまわって、体操するようなものだろうと思うのである。 あの頭の働き具合は、われわれの知っている海軍の先輩のうちでは、秋山さんひとりの持ちものであった。要点が五つか六つあるのを、それをくるっと頭の中で電燈のようにまわすのである。そして覚えていて、図を書くのである。 それから、ドーバー海峡に、戦争中に防潜網が敷設されていた。ドーバーに司令部があって、ヴィコンテー中将がいた。ここの防備設備はイギリスの現役の将官でもはいれなかった。秋山さんとわれわれもはいれない。ところがヴィコンテー中将というのは、わたしらが「三笠《で少尉で行ったときに大佐で、はじめてイギリスが潜水艦五隻をヴィカースで造ったときの監督官だったから知っていた。そこでドーバー海峡の防備図面を出して見せてくれた。ほんの一分か二分。帰ってから、これを秋山さんが書いた。この辺から曲がって、こっちを向いてと、あの頭の働き具合というものは、ちょっと普通の人は、まねのできることではない。そのような頭の働き具合であった。 秋山さんは本当に偉いりっぱな人でして、そして、アメリカの海軍から、図上演習、兵棋演習を学び、それから海の上にスクエヤーを書いて地点を作る、ああいったようなやり方を導入して、日本の海軍の兵術の基礎を椊えた人であった。 (昭和四十一年十一月二十一日講和)
「表面はそんをしたようにみえて、裏面で得をしている。これは、賢かったとあとで気がつくようであれば、まずまず成功」 2009年11月21日 朝日新聞より。 ほんとうに社会に貢献した人は自分を輝こそうとしないから無名に埋もれている。山梨勝之進がそうである。海軍軍人。小説『坂の上の雲』で有名な秋山真之は海軍大学校で、天才的頭脳からほとばしり出る戦略思想を少数の後輩将校に授けた。なかでも山梨が優秀。秋山思想を受け継ぐ者として将来を期待されていた。 参考:秋山 真之:海軍兵学校第17期(明治19年入校)、山梨勝之進:海軍兵学校第25期(明治28年入校)。 ★山梨 勝之進(1877~1967年)プロフィル:日本の海軍の軍人。最終階級は海軍大将。従二位勲一等。 主だった軍歴を軍政部門に歩み、左近充隼太・山本権兵衛・加藤友三郎の系譜を継ぐと目されていた、いわゆる条約派の1人。また帝国海軍の77人の大将のうち、艦隊司令長官職を経験していない9人のうちの1人である。 2009.11.21 参考:「人智ノ発達ト機械ノ進歩ハ、江戸長崎ノ行軍時間ヲ東京倫敦(ロンドン)ノ行軍時間ト同一ニシタルコトヲ忘ルベカラズ」 この言葉は秋山が米国留学中、本に落書きした「天剣漫録」30カ条の27条目。(朝日新聞:21.12.05による) 島田謹二(1901~1993年)『アメリカにおける秋山真之』の中に、「天剣漫録」がP.550~P.555に詳しく全条が記載されていた。引用させて頂くことにした。 一、細心焦慮ハ計畫ノ要能ニシテ、虚心平気ハ実施ノ原力也。 二、敗ケヌ気ト油断セザル心アル人ハ、無識ナリトモ、用兵家タルヲ得。 三、大抵ノ人ハ、妻子ヲ持ツト共ニ片足ヲ棺桶ニ衝込ミテ半死シ、進取ノ気象衰ヘ退歩ヲ始ム。 四、金ノ経済ヲ知ル人ハ多シ。時ノ経済ヲ知ル人ハ稀ナリ。 五、手ハ上手ナリトモ、力足ラヌトキハ敗ル、戦術巧妙ナリトモ、兵力少(スクナ)ケレバ勝ツ能ハズ。 六、一身一家一郷ヲ愛スルモノハ悟道足ラズ。世界宇宙等ヲ愛スルモノハ悟道過ギタリ。軍人ハ満腔ノ愛情ヲ君国ニ捧ゲ、上下及ばざるナキヲ要ス。 七、本年ノ海軍年鑑ヲ見ルニ、吾国海軍モ幕ノ内(ウチ)ニ入レリ。精励息(ヤ)マザレバ、大関ニモ横綱ニモナラン。勉強セザレバ、又三段目ニ下(サ)ガラザルベカラズ。 八、ネルソンハ戦術ヨリモ愛国心ニ富ミタルヲ知ルベシ。 九、人生ノ万事、虚々実々、臨機応変タルヲ要ス、虚実機変ニ適当シテ、始メテ其ノ事成ル。 十、吾人ノ一生ハ帝国ノ一生ニ比スレバ、万分ノ一ニモ足ラズト雖モ、吾人一生ノ安(ヤスキ)ヲ偸メバ、帝国ノ一生危シ。 十一、成敗は天に在りと雖、人事ヲ尽クサズシテ、天、天ト云フコト勿レ。 十二、敗クルモ目的ヲ達スコトアリ、勝ッモ目的ヲ達セザルコトアリ、真正ノ勝利ハ目的ノ達ふ達ニ存ス。 十三、平時常ニ智ヲ磨キテ天蔵ヲ発(アバ)キ置クニアラザレバ、事ニ臨ミテ成敗ヲ天ニ委(イ)セザルベカラズ。 十四、苦キトキノ神頼ミハ、元来無理ナル注文ナリ。 十五、教官ノ善悪、書籍ノ良否等ヲ口ニスル者ハ、到底啓発ノ見コミ無シ。 十六、自啓自発セザルモノハ、教ヘタリトモ実施スルコト能ハズ。 十七、岡目ハ八目ノ強味アリ。責任ヲ持ット、大抵ノ人ハ八目ノ弱味ヲ生ズ。宜ク責任ノ有無(ウム)ニ拘(カカ)ハラズ、岡目ナルヲ要ス。唯是レ虚心平気ナルノミ。 十八、虚心平気ナラントト欲セバ、靜界動界ニ修練工夫シテ人欲ノ心雲ヲ払ヒ、無我ノ妙域ニ達セザルベカラズ。兵術ノ研究ハ心気鍛錬ニ伴フヲ要ス。 十九、天上天下唯我独尊ハ軍人ノ心剣ナリ。 二十、進級速カナレバ、速カナル程吾人ハ早足ニテ勉強セザルベカラズ。何トナレバ一定ノ距離ヲ行クニ少キ時間ヲ与ヘラレタレバナリ。 二一、吾人ノ今後三十年、其ノ打十五ハ寝テ暮ラスト思ヘバ、何事ヲ為ス遑モナシ。 二二、治ニ居テ乱ヲ忘ルベカラズ。天下将(マサ)ニ乱レントスト覚悟セヨ。 二三、世界ノ地図ヲ眺メテ日本ノ小ナルヲ知レ。 二四、世界ヲ統一スルモノハ大日本帝国ナリ。 二五、家康ハ三河武士ノ赤誠ト忠勤トニ依リテ天下ヲ得タリ。小大、此理ヲ朊膺スベシ。 二六、元亀天正ノ小天地ハ、目下世界ノ前面ナリ。 二七、「人智ノ発達ト機械ノ進歩ハ、江戸長崎ノ行軍時間ヲ東京倫敦(ロンドン)ノ行軍時間ト同一ニシタルコトヲ忘ルベカラズ」 二八、三月ニナルト早ヤ冬ノ寒サヲ忘レテ陽気ニ浮カルル様ノ事ニテハ、次ノ冬ノ防寒ハ覚束ナシ。 二九、咽下(ノドモト)過グレバ熱サヲ忘ルルハ凡俗ノ劣情ナリ。 三十、観(カン)ジ来レバ、吾人ハ緊褌)キンコン)一番セザルベカラズ。 余談:彼は海軍兵学校(十七期)において試験問題に「やまをかける名人」だった。友達がその秘訣を聞いた。「教官は大事な事柄を教える時は声が大きいから、そこをメモしておけば、大抵、試験問題になるのだ」と。 追加:このホームページを読んでいた広島の親しくメールを戴いているかたから、海戦のときに旗艦三笠で戦われました祖父のお話をメールでいただきました。私も海軍に短期間ではあるが籍をおいたものとして当時の海戦の様子をうかがうことができました。以下の文章でした。有難う御座います。 実は、私の祖父が日本海海戦に〔三笠〕へ乗艦して参戦しているのです。この海戦時、祖父は艦砲射撃で、発射の合図を出す役を務めていたということで射撃が始まって、はじめは発射音で数を数えることが出来たが、おしまい頃は音が 聞こえなくなり、振動と硝煙で数を記録したと話してくれたこともありました。これが原因で片方の耳は鼓膜が破れ、その後も日々の生活では少々ふ自由をしていましたが東郷元帥、秋山参謀長の艦に乗艦出来たことを誇りに思っていて時々自慢話をしていました貴殿紹介の秋山真之の話の中で、アメリカ留学中に本に落書きしたという三十か条からなる箴言はとても感銘深いものばかりで、一つ一つ頷きながら読ませて戴きました。 ★プロフィル:秋山 真之は、日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。位階勲等功級は従四位勲二等功三級。勲二等旭日重光章、功三級金鵄勲章を授与された。幼名は淳五郎。 三兄は「日本騎兵の父」と云われた陸軍大将の秋山好古、次兄は朝鮮京城電気重役の岡正矣。子は4男2女。元参議院議員・大石尚子は、真之の孫。 2010.12.13。
淮陰生 完本『一月一話』――読書こぼればなし――(岩波書店)〔ある二発の砲弾〕の章 P.114~115 日本海海戦といえば、いくらいまの若い人たちでも、多少は知ってもいようが、その約一年近く前の明治三十七年八月十日にあった黄海開戦となると、知る人ははるかに少ないのではなかろうか。もっとも、近年司馬遼太郎氏が『坂の上の雲』を書き、それには当然、この海戦のことも詳細に出ているが、なにしろあの厖大な伝記小説、果して何人の読者が、こんな一海戦のことなど記憶の中にのこしてくれただろうか。だが、少なくとも淮陰生にとっては、とうてい忘れえぬ神秘な運命の啓示が、この一日の出来事の中にうかがえるように思う。だから、その点だけを紹介してみる。 黄海開戦とは、一言でいえば、旅順口からウラディボストックへと遁入をはかったロシア東洋艦隊に対し、わが連合艦隊がこれを阻止、できれば撃滅を企図して起った一戦であった。大まかにいえば、この日の海戦は二つの合戦に大別される。一つは午後一時過ぎにはじまった第一合戦であり、いま一つはほぼ五時半ごろから開始された第二合戦である。第一合戦でわが方は転針に小過誤をやり、戦機を逸したために、その後は追蹤だけで実に三時間を空費した。やっと追いすがって砲火を再開したのが第二合戦。勝つには勝ったが、戦果はきはめてふ満足なものに終わった。 ところで、表題の二発の砲弾とは、それぞれこの両合戦の最中(さ なか)で起こったものである。まず第一次合戦時であった。敵の放った一発の十二インチ砲巨弾が、見事わが旗艦「三笠」の大檣を打ち抜いた。大穴のあいた大檣は、危うく舷外に倒れそうになり、やっとのことでのこった。さて次は第二次合戦である。午後六時も半過ぎだが、こんどはわが十二インチ主砲の一弾が、てきめん敵旗艦「ツェザレウィッチ」の司令塔に命中し、長官ウィトゲフト以下幕僚はもちろん、ついでに操舵手まで一挙に仆してしまったのである。旗艦は当然盲目航法になった。たちまち敵戦列は支離滅裂となり、勝敗の数は一瞬にして決まった。 問題は以上の二弾である。もしこれが逆になっていたとしたらどうだろうか。いや、もし敵弾に打ち抜かれた「三笠」の大檣が、事実舷外に倒れていしたら――追蹤はとうていふ可能だったであろう。先任参謀として作戦の全責任を負っていた秋山真之が、戦後九年にして書いている一文がある。彼はいうのだ、「砲術の巧拙と云えば夫(それ)迄だが、現時の人智で作り出した大砲は、一分一厘狂ひ違はぬ様に出来て居らぬのだ。斯の如きが即ち戦運で、吾人は何処迄も皇軍の天祐を確信せざるを得ない」と。そして「怪弾」とまでこれを呼んでいる。 名将秋山の晩年は必ずしもよくなかった。奇矯な行動が多く、心霊学に凝ったり、大本教に深入りしたり、一時は発狂説まで飛んだ。が、開戦以来日本海海戦まで、終始国の命運への全責任を一人で背負った形であった彼としては、なにか運命の神秘を信じないわけにはいかなかったのではあるまいか。一種の運命論者になるのも、わかるような気がするのだ。(74.8) |
|
★司馬 遼太郎『坂の上の雲』が出版された時、よく読まれた。 私は昭和42年、友人がこの本を貸してくれて読むようにと勧められたられたのである。 平成二十二年、NHKが、この原作を放映しています。主要人物として秋山真之・秋山好古・正岡子規・広瀬武夫のおりなす内容である。 秋山真之は日露戦争の時、連合艦隊長官東郷平八郎の下で作戦参謀であった。 ★令和4年4月、児島直記〚出世を急がぬ男たち〛 (新潮文庫)昭和五十九年四月二十五日発行 P.10~14 を読むと、 渡部昇一『ドイツ参謀本部』(中公新書)昭和49年12月20日初版 をトップ・マネジメントの好参考としておすすめしたい。 理由はいくつもあるが、その一つとして「二冊の本がフランスとドイツの運命を、つまりヨーロッパ大陸の運命を決定した」箇所(一一二ページ以下)がある。それらの本とは、一冊はアンㇳワーヌ・アンリ・ジョミニ(仏: Antoine-Henri Jomini)の『戦争術概要』、もう一冊はカール・フォン・クラウゼヴィッツ(独: Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (Claußwitz)の『戦争論』。 を読んで戦争論を知った。 ★そこで少し戦争論に関連記事をしらべることにした。
アメリカにおける秋山真之――明治期日本人の一肖像―― 秋山真之をかく見る P.7
一、少尉時代 俊 才
秋山真之〔教官〕のこと P.9 私が海軍大学生のころ、教官に秋山真之(さねゆき)中佐がおられました。戦略、戦術、戦務を体系づけた、飛びつきたくなるような魅力的で、筋が通って胸のすくような講義でありました。 アメリカ海軍の空気と感情とを、日本海軍に導入されたのは、秋山教官の力であります。 ジョミニありクラウゼヴィッツ、孫子等が、口をついて出て来る。川中島の戦史を説く時(甲越の軍書にいわゆる)車懸(くるまがか)りの戦法とはこういうものだと詳しく説明して下さいました。
「二十悦月ノ征戦已ニ往時ㇳ過ギ……」という連合艦隊解散の辞など、一遍でなぐり書きをしたといわれますが、世界の名文ですな。普通の人ではありませんでした。のべつ頭が活動しているのですね。兄さんの好古将軍も偉い人でしたが、頭の方は弟さんの方が上でした。
山梨勝之進著『歴史と名将』歴史に見るリーダーシップの条件(毎日新聞社)P.358~ 秋山将軍は、海軍大学校で、私たちの教官でした。ジョミニのなはよく出されましたがクラウゼヴィッツの話は、されたことがありませんでした、書かれている。 ※『アメリカにおける秋山真之』と『歴史と名将』における山梨さんのクラウゼヴィッツについての話はどうなるのだろうか。『アメリカにおける秋山真之』の本文をしらべてみていたところ、クラウゼヴィッツについての記事は見つかっていません。(2022.04.14) これは、ジョミニの言葉なんですが、「ひとことで言えば、戦争は、学(science)ではなくて、術(art)である。笛を吹いたり、相撲をとったり、テニスをやったりする『わざ』と同じである」、くどく言っております。 さらにもうひとつ、よいことを言っておりまう。「知識というものと、熟練というものは、まったく違った二つのものである」。例えば相撲をとるのに、こういう手を使えば、うまくいくということは知識であるが、やってみて、うまくいくか否かは、能力ではなく技であるというのです。 ジョミニは、「野球でもテニスでも、こうやればこうなるというのは、知識(knoelege)であって、それが、そのとおりうまくいくかどうかということは、熟練による技(skill)であり、これは、まったく別個のものである」。簡単なことですが、ジョミニの言葉はなかなか味があります。 ところで、ジョミニも、クラウゼヴィッツも歩いた道は、よく似ておりまして、両方とも本国では、あまり重用されませんでした。 ジョミニは、ナポレオンの参謀長のペルティエときう人と非常に仲が悪く、両人とも知恵があって、偉いのですが、検挙さがなく、お互い張り合って対抗していたので、ナポレオンも仲直に困りぬいていたものでした。 ジョミニは、フランスでは少将以上には昇進できないと思い、中途からロシアの陸軍に行き、ロシアの陸軍大学校の創始者になり、ロシアの位では大将にまでなったのであります。(渡部昇一著『ドイツ参謀本部』P.114参照) クラウゼヴィッツもまた、プロシャの軍隊では偉いところまでいかず、ジョミニと同じ時期にロシアに行き、ロシアの軍隊に入ったのであります。クラウゼヴィッツの師は、ドイツの名将シャルンホㇽスㇳです。クラウゼヴィッツは、『戦争論』という本を書きました。これは、彼が書きためてしまってあったものを、夫人が夫の死後に、その本を発表して、全世界に{センセーションをまき起こしものです。(渡部昇一著『ドイツ参謀本部』P.114参照) ジョミニはクラウゼヴィッツの本を批判して、「この本には、哲学や心理の研究があまり多く入り過ぎていて、要するに、説明がくどい、もう少し簡単にはっきりしないと、読む人のためにならない。ところで、自分の本には、ことを決めるのに、こうすればよいのだという説明には、必ず"what" と "why" がついている。だから、私の本を読んだ人は、得るところが多いのではないかと思う」と言っております。ジョミニは、「戦争には、兵器がいかに変化し、時代が変わり、場所が変わったとしちぇも、ふ変の基礎的原則(Fundamrntal Principale) があり、それによって戦争の勝敗が決まるのである」と言っていますが、これはフォッシュ元帥が言ったこととおなじであります。 アメリカの参謀思想や、組織、テキニックというものは、ジョミニの教訓のたまものだといわれております。アメリカ海軍の、後方連絡(Communication)という思想は、ジョミニの陸上戦の教訓から来ているものであります。マハンは、ジョミニの著書をずいぶん勉強して、ジョミニの理論は、海軍戦略にも適用できるものであると言っております。 ジョミニは、フランスのネー将軍の参謀長をしました。この、ネー将軍は、フランス政府から、ナポレオンの逮捕を命ぜられて派遣されたのですが、途中からナポレオンにつき、ワーテルローの戦いのときは、近衛騎兵隊の大将として勇戦奮闘しましたが、(渡部昇一著『ドイツ参謀本部』P.116では第二軍団の参謀長であったとかかれている)武運つたなく敗れたのであります。戦争が済んで、ネー将軍が絞首刑になりましたが、そのときジョミニは、ウェリンㇳン将軍などに頼って、ネー将軍の助命にずいぶん骨を折りましたが、成功しませんでした。 ジョミニは、ナポレオンの戦法に自説を加えて、次のように言っております。すなわち「敵の右翼・左翼・中央或は背後の弱点と思われるところに、迅速にわが全力をそそいで、攻撃を加える。これが戦略(strategy)である。戦略でそういう備えをして、いよいよ戦闘の場で、いかなる時期に、いかなるところを、いかなる方法でうまくぶっかっていくかというのが、戦術(tactics)である」と、このように戦略と戦術の区別しておりました。「軍隊の大部分を、必要と思う場所に集めるという技が戦略であって、集中した部隊を適当な時期に、適当な場所に攻撃を加え、。敵を制するのが戦術である」というのが、ジョミニの解釈であります。 さらにジョミニは、仮にウェリントンや、世界中の戦の上手を集めて、用兵作戦の要訣について研究会を開いたとしても、この世の中には完全というものはないので、これは完璧だという結論は生まれるものではないということを、断言しております。 以上、フォッシュのナポレオン批評、計画と実行、賭博性と合理性のかねあい、あるいはジョミニ、クラウゼヴィッツのことなどについてお話ししましたが、結局は、一方にのみ片寄ってはいけないということかと思います。(後略)(昭和四十一年一月二十六講話)
明治30年6月、秋山大尉は米国留学を命ぜられるが、これは、明治17年の斉藤実以来13年目になる。秋山の留学目的は、米海軍の戦略・戦術の研究にあった。秋山は、米海大に入学を拒否され、4年前まで校長を務めた、『海上権力史論』(明治25年刊)で世界的になを馳せていた、マハン大佐に師事することとなる。ここで、米西戦争が勃発し、秋山は観戦武官として、米海軍の作戦・実戦を詳細に観察する機会を得た。この経験が、後の日本海海戦に大いに役立ったことは言うまでもなく、その後の明治海軍に大きな影響を与えた。 ニューヨークの西区八六丁目のセントラル公園の静かな住宅街にあるマハンの住宅を訪問。 ――海軍大学に入れないとすると、自力で海軍戦術を研究するということになりますが、それにはよいものでしょうか。御忠告ををお聞かせ下さい。『アメリカにおける秋山真之』(『アメリカにおける秋山真之』四四頁) ――そうだな、まずジョミニ、"Art of War",(兵術要論)と、マハンはその書名を教えて、もとはフイランス語で書かれたものですが、英訳があります。戦争の生きた原理を実例で示すのに、こんないい本はありません、とつけくわえた。それに著者は実戦の体験をもった後に書き出しました。ただ机の上の理屈で書いた本でないのですよ。とダメをおした。(四四頁) 米西戦争を観戦,戦史戦書を渉猟して戦略家マハン大佐に接したことは,秋山流戦略論の形成に資するところ大であった。33年帰国。35年海軍大学校教官となり,兵棋演習を取り入れ,戦略,戦術,戦務に組織化した系統的な講義は帝国海軍兵学の基礎となった。 ジョミニの伝統は、日本では幕末に一度流れ入りかけて、十分形を成さず、それがアメリカ経由で秋山に伝わり、日本海軍の中で有力な戦術思想に変形するのだろう。(頁六八三) ※関連:二つの「戦争論」 『歴史と名将』P.368 アメリカに留学した。マハンに会って、アメリカの海軍大学校に入ることを希望したが、アメリカ海軍は許可せず、はいれない。マハンが「海軍大学へ入らんでもよい。お前は、本が読めるだろう。戦史を読め。戦史を読んで、ひとりで考えれば、海軍大学校にはいる以上である。それには、こういう本がある」と、それで勉強した。非常に読んだ。 余談:丁字戦法について
会田雄次著『決断の条件』(新潮選書) 6〔指導者を欠く大衆は烏合の衆である マキアヴェㇼ)
日露戦争における日本海軍の基本戦法の一つは、敵旗艦に全力を集中し、指揮者を倒して敵陣を混乱させるというのがある。それこそ日本古来の海賊戦法だったのだ。それを鬼才秋山真之参議が近代戦に合致するように工夫し、完成したのである。 『歴史と名将』P.349 1、山屋他人さんが、いわゆる丁字戦法を編みだしました。敵の艦隊の頭を押さえて、手中砲火をあびせるといった戦法です。またそのころ、秋山真之さんがアメリカから帰ってきて、アメリカの戦略・戦術・戦務の考え方をとり入れて、日本海軍の戦略・戦術・戦務というものの基礎を築いたものであります。私は、山屋さんが丁字戦法の最初の主唱者であったと記憶しております。 丁字戦法もしくは、丁字作戦とは、砲艦同士の海戦術の一つで、敵艦隊の進行方向をさえぎるような形で自軍の艦隊を配し、全火力を敵艦隊の先頭艦に集中できるようにして敵艦隊の各個撃破を図る戦術をいう。 山屋他人(慶応2.3.4(1866.4.18)~昭和15.9.10(1940) 明治大正期の海軍軍人。盛岡藩(岩手県)藩士山屋勝寿とヤスの長男。明治19(1886)年海軍兵学校を卒業,巡洋艦「高千穂」水雷長などを務め,29年海軍大学校へ入学。卒業とともに砲術練習所教官,海大教官に起用された。戦術家として評価は高く,いわゆる「T字戦法」は,山屋の考案した〔円戦術〕の発展改良であった。また海大教官として多用した兵棋盤による図上演習はその後の戦術教育の主流となり,鋭い戦術感覚を持つ多くの士官を生み出したという。海大校長などを歴任,大正8(1919)年大将,連合艦隊司令長官。皇太子徳仁親王の妃となった小和田雅子の曾祖父。 ★東郷平八郎との出会い(『アメリカにおける秋山真之』P.545) わが生涯に一期をかくした光栄(はえ)ある兵学校卒業式の時、――七月十日だというのに、江田島は梅雨で、小雨がシトㇱㇳ降っていた。首席卒業だから、秋山は、なみいる高官の前にすすんで、水雷に関する講演を行なった。いくらか準備があったし、たいしておめもせずおくせずもせず、予定通り終わった。語り終わった時、きらびやかな服装をした大官たちのうちに、へンな将校が一人いるのに気づいた。年はもう四十をこえているだろう。冬の外套を着て、顔色が青い。ただ黙黙としている。ふしぎに落着いているその人は、他の士官たちとは一風変っていた。あとで聞いてみると、呉鎮守府参謀長東郷平八郎大佐だった。胸の病で血をはいているが、長官の代理で来ているのだと消息通が教えてくれた。うれしい卒業式のはずなのに、その梅雨の日のことwぞ思うと、きっとあの老人のへンに落着いたおもかげが一緒に浮かんでくる。 ※参考図書 1、島田謹二著『アメリカにおける秋山真之』(朝日新聞社) 2、山梨勝之進著『歴史と名将』歴史に見るリーダーダシップの条件(毎日新聞社) 3、渡部昇一著『ドイツ参謀本部』(中公新書) 4、会田雄次著『決断の条件』(新潮選書) 2022.04.16 記す。 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中央文庫)昭和五十八年八月十日 P.129~133 より。 石原真清 軍人やめて諜報活動 年代職業などの区別をこえて、旅をする人の記録は心にしみるものがあるが、この数年間に読んだもののなかでもっとも心に残ったものは『菅江真澄遊覧記』(東洋文庫)と、石原真清の手記による『城下の人』『曠野の花』『望郷の歌』『誰のために』(いずれも竜星閣)であった。つまりその記録を残した菅江真澄(本名は白井秀雄)と石原真清の、旅にその大半を消費した生涯の哀れさに強く胸をうたれた、ということである。
これにくらべれば、石原真清の旅の原因は明白であった。三井物産横浜支店員の兄真澄に迎えられて東京の土を踏んだ真清は、明治十六年に陸軍幼年学校にはいった。五十一名の生徒は二班にわけられ、真清は第一班にはいったが、第二班の取締生徒(三年生)橘周太(のち軍神橘中佐とうたわれた人物)を敬慕し、そのいうことなら何でもそむくことがなかった、というところにその人柄を示すものがある。橘もその真情に打たれ、二十二年に士官学校を卒業した真清が近衛歩兵第二連隊付きになったとき、卒業祝いとして伝家の宝刀一文字を贈った。 やがて三弟真臣(のち中将)も士官学校にはいり、連隊づとめの真清とともに、日曜祭日の休みには兄真澄の社宅を訪ねた。真澄は馬越恭平にたのまれて恵比寿麦酒会社の再建に打ちこんでいた。そこで弟たちも軍服を仕事着にかえて一日中工場の古クギ拾いや箱造りをしたという。真清は兄に人力車をプレゼントした。一台二十五円、少尉の俸給は二十九円五十銭。「私には少々骨が折れた。兄は涙を流さんばかりに悦んで、毎日この車に乗って活躍していた」(『城下の人』)。 兄を訪ねない日は橘を訪ねた。彼は紺がすりの着物の前をキチンと合わせて机に向かい、寸暇をおしんで兵の教育指導要綱を起草中であった。「……兵汗を拭わざれば拭うべからず。兵休まざれば休むべからず。兵食わざれば食うべからず。兵と難苦を同じうし、労逸を等しうする時は、兵も死を致すものものなり。信用は求むるものに非ず。得るものなり……」。そういう文章に感動する真清は、やがて職業軍人としての栄進とは関係のないところで、国のためにつくそうと考えるようになる。 日清戦争では台湾に出征した。新橋駅まで送りにきた真澄は、真清が宇品から輸送船にのる前日、急性肺炎で死亡した。悲しみを胸に秘めて転戦し、やがて凱旋して功五級金鵄勲章勲六等瑞宝章を賜った。だが彼の心は、三国干渉でその野心を露骨にしたロシア帝国にひかれ、ロシア研究の必要を感じ、ロシア語を学びはじめた。三十歳で妻を迎えてもその決心はかわらず、参謀本部田村怡与造大佐の了解のもとに、休職願とロシア留学願(私費)を出し、三十二年六月、許可がおりた。このときをもって、真清の軍人生活は事実上終わったのである。 最初の留学地はブラゴペシチェンスク。菊地正三という仮名の真清は、在留シナ人三千名が、子供にいたるまで殺されたアムール川の濁流に葬られる惨事に直面したあと、ハルピン潜行の命をうける。いのちがけのその旅で彼のいのちを救ったのは日本女――馬賊の妾などになっている薄倖の娼婦たちであった。真清は予備役となり、写真館を開いて諜報活動を行う道を選ぶ。「国につくす道に現役と予備役のちがいはない。軍人としての栄誉を捨てて国家のため生涯を捧げてくれ」と伊地知少将にいわれたとき、 「銃声こそ聞えませぬが私にとって満州は激しい戦場であります」 とかれは答えた。しかし、そのための旅がいかに大きな犠牲をしい、しかも報いられることのないものであったかは、晩年においてはじめて悟るのである。 三十七年早暁、ロシア憲兵にたたき起され、日露開戦による国外退去を命ぜられて、無一文で日本にもどったものの、すぐに招集されてまた満州にわたった。 凱旋後、また満州に行ったのは参謀本部の田中義一大佐(のち大将、首相)にたのまれたが、四十年八月、無一文で帰国せねばならなかった。ロシアに勝って国際的地位も向上し、官界も軍部も自信をもって近代国家への組織化に急であったが、それは反面、軍の官僚化となり、原住民への威圧と変っており、真清の心は痛んだ。 真清は今度も日本におちつくことはできなかった。叔父野田豁通(男爵)を中心につくられた会社の仕事に、半ば強制的に引きこまれたためだ。しかしこれも失敗して帰国した彼は、四十二年から世田谷村の三等郵便局長としての静穏な生活にはいり、ようやく妻子との日常生活に人間としてのしあわせを味わうことができた。だがその喜びもつかの間、またもや大陸行きの仕事が彼を引きずりだした。満蒙貿易公司の満州商品陳列館経営が表面の名目、実は英国の利権侵略に対抗するため、陸軍が立てたプランで、その仕事について間もなく、すでに少将となっていた同期の生高公通(都督府参謀長)から、黒竜州アレキセ゚―フスク付近の諜報勤務命令をうけとった。「シベリアの冬は暮れやすく、人の生涯は移ろいやすい。青年将校の軍服をぬいでブラゴペシチェンスクに初めて留学した日から二十年……この貴重な歳月の二十年をいつしか過して私は五十歳の身を久しぶりにこの地に運んだ」「『誰のために』と彼は書いている。そしてソビエト革命下の動乱にまきこまれ、いのちがけの体験にもとづく献策も司令官大井中将に一蹴され、君は一体だれのために働いとるんだ、ロシアのためか、と罵倒された。 帰国したあと、郵便局を失い、愛妻の死、借金の山に押しひしがれ、失意のうちに七十六年の生涯をとじるときは、おのれの過去を嫌悪していたという。私心なく奉公した彼には何の報償もなく、くだらぬ男たちが勲章と爵位で胸をそらしたのが、帝国日本の一面でもあった。上記四冊の本はその手記をもとに一人むすこの真人が編んだものだが、「一国の歴史は、一民族の歴史は英雄と賢者と聖人によって作られたかのように教えられたが、野心と打算と怯懦と誤解と無知と情性によって作られたことはなかったか」と、血を吐く思いの疑問が書き留められている。 ※プロフィル:石光 真清(眞清)(いしみつ まきよ、慶応4年8月30日(1868年10月15日)~昭和17年(1942年)5月15日)は、日本陸軍の軍人(最終階級陸軍少佐)、諜報活動家。明治から大正にかけてシベリア、満州での諜報活動に従事した。 明治元年(1868年)熊本に生れる。少年時代を神風連の乱や西南戦争などの動乱の中に過ごし、陸軍幼年学校に入る。陸軍中尉で日清戦争に参加し台湾に遠征、ロシア研究の必要を痛感して帰国、明治32年(1899年)特別任務を帯びてシベリアに渡る。 日露戦争後は東京世田谷の三等郵便局長を務めたりしたが、大正6年(1917年)ロシア革命の後、再びシベリアに渡り諜報活動に従事する。 帰国後は、夫人の死や負債等、失意の日を送り、昭和17年(1942年)76歳で没した。没後に石光真人が編み完成させたのが手記(遺稿)四部作『城下の人』『曠野の花』『望郷の歌』『誰のために』である。この四部作は、毎日出版文化賞を受賞し、また伝記作家の小島直記など、多の識者が自伝の名作と評価している。 ※参考:森銑三著作集 続編 第5巻 森銑三/著 中央公論社 出版年月 1993年6月 に掲載されている。 |

幸徳(秋水)君らは時の政府に謀反人(むほんにん)と見なされて殺された。諸君、謀反を恐れてはならぬ。自ら謀反人となるを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀反である。「身を殺して魂を殺す能わざる者を恐るるなかれ。」肉体の死は何でもない。恐るべきは霊魂の死である。人が教えられたる信条のままに執着し、言わせらるるごとく言い、させらるるごとくふるまい、型から鋳出した人形のごとく形式的に生活の安をぬすんで、一切の自立自信、自化自発を失う時、すなわちこれ霊魂の死である。我らは生きねばならぬ。生きるために謀反せねばならぬ。(明治四十四年二月一日、一高における講演) この日(9月18日)死んだロマン主義文学者。熊本県に生れ同志社に学んだ。キリスト教的自由主義にたち『上如帰』『黒汐』などで大衆をつかんだ。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.156 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.229~233 福沢 桃介 体験からの処世術を説く偽悪派 三宅雪嶺の書いた序文で異色とおもわれるのが、福沢桃介著『桃介式』に書いたものであった。 この本は、「予が処世観」、「羨むなかれ世のいわゆる成功者」、「金儲けは株にあり」、「憎まれていやがられて世を渡れ」、「どうすれば金持ちになれるか」、「出世の秘訣」の六篇からなっている。 第一篇は明治三十九年、桃介は三十九歳で、北海道炭礦鉄道会社の社員であった。第二篇は四十歳、一月に日清紡績を設立して専務取締役となり、三月に持株を処分、「いよいよ実業界に入る」(『福沢桃介翁伝』年譜)中間の二月のもの。第三篇は同年六月、第四篇は同年七月のもの。 第五篇は四十一歳、後輩松永安左エ門にかつがれて福博電気軌道会社発起人となり、また豊橋電気の取締役、高松電気軌道の発起人となった年のもの。第六篇は四十四歳、すでにな古屋電燈大株主の地位を拠点に中京財界に進出し、また日本瓦斯を創立して社長となったあと、四国水力電気社長、浜田電気社長、野田電気社長、唐津軌道取締役となった年のもの。翌年五月には千葉県から衆議院議院選挙に立候補して当選、政友会公認となるふうで、公私ともいよいよアブラののってきた時期の所産であり、考え方の反映であった。 ただその内容は、自ら桃介式と自負するほど天下独歩の創見ではないようにおもわれる。むしろそのユニークな味は、あくまでも自分の体験をふまえ、歯に衣をきせぬやり方でズバズバいうという表現法にあるようである。たとえば第一篇には「人に可愛がられる方法を教えてあげます」といって、「人に面と向っていろいろなことはいわなくても、カゲにおってあの人は善い人だ、まことに利口な人だ、というように、つねにほめていると、いつかその人にわかる。以心伝心、自然とそれが先方の人に通じて喜ばれる。ひっきょうするに、人をそしるということは、自分の無能を表明するものだから、よくよく慎まなければならぬ」とか、「金というものは、もってみるとそれほど楽しいものではないのです。ただ金をこしらえてみたい、金をこしらえてこういう家に住んでみたいとか、うまいものを食ってみたいとかいう、その道中が楽しみなのである」、「いまだ衣食の足らざる会社の社員などは、相互に送別会を催すとかなんとか、そんな交際や礼儀にお金を出すには及ばない……炭礦会社の寄生虫として桃介は、一銭一厘たりともそういうお金は使わない」と語っている。自ら「寄生虫」という一種の偽悪趣味がその味のようでもある。 第二篇では、世の中の金持ちは「偶然今日の結果を得たくせに、かしこぶってホラをふくので、先見の明とは真赤のウソだ」、「人を見たらたいがい泥棒だと思えばまちがいない」といっている。第三篇では、「三井、三菱が儲けるのに諸君が儲けられぬというはずはない。ただ彼は一万株を売り、諸君は一株を売るというだけの差である」、「若い人はどうしても金をためなければならぬ。人間は独立して生計ができてのちはじめて大胆に自己の意見をのべられる。どうかすれば免職され、翌日から飯が食えぬといううような、パン問題を争うている中は、おもいきって意見を述べられなければ、よい考えも出ぬ」といっている。 第四篇では、「憎まれていやがられて世を渡れという……これ世渡りの一秘訣」、「歴史を見るに、古来貨殖に成功した者は、多くは世の中をいやがられて渡りたる者にして、可愛がられる人は、下について働く側の人にして、頭立ちたる人になれるの例はあまり見受けざる処なり」、「妻子眷属、朋友知己の前に傲然としていばっていても、助けられたる人の前にピョコピョコ頭を下げざるにおいては、決して男子の快事にあらざるなり」、「天は人の助けざる者を助く」という。 第五篇では「私はケチが自慢」、「世間の人のごとく森村(市左衛門)さんが貿易に成功し外国の金を日本にもってきた点において尊敬しているのではない。あの人は片意地の強い人である。私の取る所はここだ」という。第六篇には、サラリーマンの処世法が書いてある。要約すると「味」がぬけるが、紙数の関係で要点を列挙すれば、(一)入社先の社風に従え。善かろうが悪かろうが、ただ盲従せよ。(二)上役の性質を知り、その人の気に入るように仕事をしていけ。上役は、敬い奉れば必ず喜ぶ。(三)月給で暮らせ。(四)表を絹にし、裏を木綿にする態度で生きよ。(五)勉強を見せかけよ。メクラ千人の世の中では、自分が正しければ、その正しいことを人に知らせる必要がある。(六)上役より先に帰るな。(七)利口らしく見せかけるともに正直らしく見せかけることも必要。(八)病気と失職にそなえ、貯蓄せよ。「上役は、世の中の呼吸をのみこんでいるから、なるべくタダのお世辞でゴマ化し、実質をあたえずして人を使おうとする。前途に希望をもたせておく。働くのはわるくないが、ただ正直に一生懸命に働けば、それで必ず立身出世すると思うと大まちがいである」という。 引用してゆけば、キリもないが要するにこういうふうで、その桃介的姿勢に興味をもったのか、雪嶺の序文も、「面白い」、「愉快である」ということばを使っている。雪嶺は「偽善めかぬ所がよい」と、そこに男らしさを見た。 けれども、ただベタぼめしないところが「雪嶺式」である。この本の出版元は実業之世界社で、野依秀市にたのまれてお義理で書いたようではあっても、そこに一本のスジを通し、いうべきことはいう、というところがいい。「桃介君をもって快男子とするは当らぬかもしれぬ。さほど愉快な男でもなかろう、が、言う所行う所すこぶる愉快」という表現にもそれがうかがえる。 ポイントは養子問題である。桃介は川越の提灯屋岩崎家の次男坊、在学中諭吉に見込まれ、二十歳で入籍、アメリカ留学をおえて二十二歳で諭吉次女ふさと結婚した。しかし福沢家には四人の息子がおり、「養子は諭吉相続の養子にあらず、諭吉の次女お房へ配偶して別居すること>と申しわたされていた。そういう限定をしてまで養子として何ほどかの便利を得来たったったであろうか、もし今後大いに手腕をのばし、一個の桃介となって社会に存在するようになれば、養子とならんだった方が、よかったように思われるかもしれぬ。尋常人では翁の眼鏡にかから、君が養子に選ばれのは人物を見ぬかれたのであって、祝すべきであるが、独立独行という点よりせば余計の事……福沢の家に養子になったとて何程の事がある」。 桃介が愛人川上貞奴との仲を公然化したのはこの前後である。「福沢」コムプレックスのせいかどうかは、よくわからない。 2019.08.07 |
|
銀行家、政治家。明治2年3月25日日田県(大分県日田市)に生まれる。帝国大学法科大学卒業後、日本銀行に入る。営業局長、ニューヨーク代理店監督役などを経て、横浜正金銀行常務副頭取、ついで頭取、1919年(大正8)から日本銀行総裁。関東大震災直後、経済救済のため第二次内閣の蔵相となり在任4か月で辞任。のち貴族院議員に勅選され、在野で財界の世話役を務めたが、1927年(昭和2)金融恐慌後の財界救済のため、再度日銀総裁に就任。 1929年浜口雄幸内閣が成立すると、民政党の経済政策の要である金解禁を実施するため、首相に請われて蔵相に就任し、民政党に入党した。井上は緊縮財政とデフレーション政策を推し進め、金解禁の準備を整え、翌年1月、金本位制復帰を実現した。しかし、世界恐慌の深刻化と井上財政のデフレ政策が重なって、日本は大ふ況にみまわれ(昭和恐慌)、輸出は振るわず、金は流出し、日本経済は破綻に瀕した。大正以来財界のトップを歩んだ自信家の井上は、円を買い支え、金本位制維持に努めたが、1931年12月政変で井上が下野すると、日本の金本位制は終焉した。翌昭和7年2月9日、民政党総務として選挙運動中、右翼テロリスト血盟団員の小沼正に狙撃されて没した。 インターネットより引用。 2021.08.17記す |
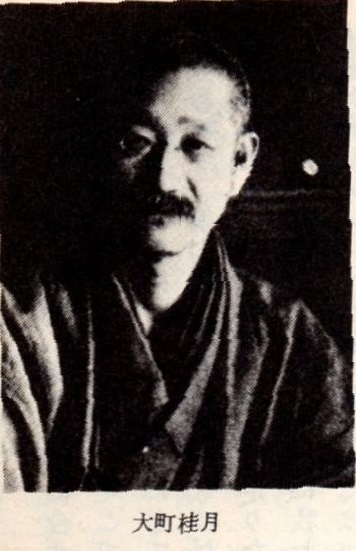
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.164~168 大町 桂月 酒客・中毒で筆動かぬ時も 飲酒喫煙のレコードを伝記で探ったことがある。タバコは『続さらりーまん外史』でのべたように、住友総理事中田錦吉の五歳からというのがいちばん早いようであったが、酒は西園寺公望ではなかったろうか。養育にあたった老女に相模というのがいて「男は酒をのまぬといけませぬ」といって五歳から食膳に酒をつけたので、子供のくせにちびりちびりとやったのである。 高橋是清も、はじめた年は不明だが、十三歳のころにはひとかどの酒客で、横浜の外国銀行のボーイになっていたが、馬丁やコックなどと朝夕のんでいた。さかなはねずみとりで捕えたねずみを、支配人のビフテキ焼きで焼いたものであった。慶應三年十四歳のときコロラード号で渡米したときは、旅費としてもらっていた二十ドルをウイスキーで使いはたし、同行の友人の分までのんでしまったので、サンフランシスコに着いたとき、引率者の富田鉄之助に「君はこの船で帰れッ」と大変な剣幕でしかられた。 第一回の総選挙で当選しながら「アルコール中毒の為、評決の数に加はり兼ね辞職仕候」という辞表を書いてやめてしまった中江兆民も、酒客列伝からおとすわけにはゆくまい。もっともアルコール中毒は一口実で、予算問題で政府側に寝返った板垣退助ら四十数吊名にたいする怒りが原因であった。 兆民には『三酔人経綸問答』という評論があって、主人公南海先生の酩酊ぶりを書いている。南海先生は生まれつき酒が好きだが、わずか一、二本のときは気持ちよく酔っぱらい、気分もふわりと、宇宙を飛びまわるようで、見るもの聞くもの楽しい。この世に憂いなどがあろうとは思えぬほどだ。さらに二、三本のむと、精神がにわかにたかぶる。思想がしきりにわきおこり、身は小部屋の中におりながら、眼は全世界を見通し、一瞬間に千年前にさかのぼり、千年後にまたがり、世界の進路を示し、社会の方針を教え、「自分こそ人類の社会生活の指導者である」と思うようになる。さらにもう二、三本のむと、耳は鳴り、目はくらみ、腕をふりまわし、足をふみならし、昂奮のはてはひっくり返って前後ふ覚となる。おそらくはご自身の体験にもとづく記述であったろう。 天台道士杉浦重剛の周辺には、とりわけ酒客がそろっていたようだ。その門下生からは巌谷小波、大町桂月、江見水蔭、近藤紅緑などの文人が出たが、桂月と水蔭に酒の上の逸話がある。桂月は高知のひとで、天台道士の稱好塾に学び、東京大学国文科を卒業したが酒を讃える詩として、「一杯陽気発し、二杯寒温を忘れ、三杯慮尽き、四杯世喧を絶し、五杯六杯多々益々弁じ、唯だ一身の乾坤に合するをお覚ゆ」というのをつくった。 五十歳のとき、アルコール中毒。そこで一年半ばかり酒を断ち、酒毒はなくなったが、筆が動かない。そこで「節酒」ということにして、非難攻撃の声があつまった。そのなかで天台道士はひとり非難せず、頼山陽の菅茶山のものだという瓢箪に酒をつめて贈った。桂月は感激し、容量をはかると、三合八勺、四合に足りない。そこで四合を酒豪に引っかけて、「しゅごうには好し成らずとも御情のこもるひさごに我は酔はなむ」という歌をつくった。 水蔭は岡山の人。十七歳で稱好塾にはいったが、あるとき吉原に遊びに行き、しこたま酒をのんで泥酔のあげく、町角で菰をかぶって寝こんでいるところを新聞社の写真班にうつされ、翌日新聞にのった。塾生一同は激怒し、体面を汚したから即時退塾処分にして下さい、と師に申し入れたが、このときの天台道士のことばがいい。「いやそれはならん。君たちはあの江見にくらべ品行方正、学業優等だからどこへ放り出しても何とかなる。しかし江見は、ここにおいてもあのようなふ始末なやつだ。いまここを出してしまえば、どんな悪党になるかもしれん。だから出すわけにはゆかん。もし君たちが不服なら、君たちに出てもらうより外はない」。一同、この慈心に打たれ、返すことばもなかった。 天台道士には、「酒を詠ずるの詩」がある。「之れ無くして礼楽全うする能わず。笑ふを休めよ七賢と八仙とを。誰か道ふ禹王亡国を戒しむと。国家の命脈実に焉に存す」というものである。しかし本人はむしろ愛煙家であった。ところがある日から、タバコを口にしない。周囲が理由をきいても笑って答えない。しっこくたずねると、今にわかるとだけいった。禁煙一年におよぶと、今日からはのむ、と宣言した。 この禁煙のいきさつはあとでわかった。彼の親友に福富孝季がいる。この物語の第五話に岡倉天心の親友として登場した人物である。六尺余の巨漢で、ケンブリッジ留学時代、下宿屋の主人が「日本のジャイアント」とよんでいた。まだ三十代はじめなのに、満頭房々とした白髪。東京師範学校教授であったが、とりわけ酒が強い。いつからはじめたかは不明だが、あるとき友人たちの前で、日本酒を七升、ビールを二十四本のみほしてみせたことがある。千頭清臣は、土佐藩の貢進生として天台道士とともに学び、のちその妹楠緒は杉浦夫人となった人だが「余は君(福富)の酒量を知れり。君嘗て一呼吸して一瓶のウイスキーを傾け尽したることあり」と書いている。 天台道士は、この福富の酒を心配したのであった。彼はかつて『講学雑法』というのを出して、穂積陳重(のち法学博士)とならんで「飲酒の利害」という論文をのせたこともある。化学者としてアルコールの害を説く知識をもっていたが、それをことばだけで説こうとはしなかった。親友に忠告して酒をやめさせるには、まず自分で好きなタバコをやめてから、と考えた。そして禁煙一年、ようやく忠告の資格ができたとして、いったのである。 「タバコをあれほど好きだった僕でも、やめようとすればこのようにキッパリとやめることができるのだ。君も将来国家のために尽くそうという精神があるならば、どうか酒をやめてくれよ」福富は親友を思うその誠実さに打たれて、あびるほどのんでいた酒をピタリとやめた。それからしばらくして、福富はのどを斬って自殺した。ときに三十三歳。天心は二首の弔詩を献じた。天台道士は、「あんなことになるなら酒をとめるではなかった」と涙を流した。 2019.08.10 |
|
評論家・小説家・社会運動家。長野の生まれ。キリスト教徒となる。普選運動・社会主義啓蒙運動に奔走。また、日露戦争の際には非戦運動を起こす。小説「火の柱」「良人 (りょうじん) の自白」など。 ひのはしら【火の柱】 木下尚江の小説。明治37年(1904)発表。日露戦争前後、非戦論を唱え、資本家・軍人・政治家らの虚偽とふ正をあばくキリスト教社会主義者の行動を描く。 りょうじんのじはく〔リヤウジンのジハク〕【良人の自白】 の解説 木下尚江の長編小説。明治37年(1904)から明治38年(1905)にかけて毎日新聞に断続的に連載、3編に分けて刊行されたのち、明治39年(1906)に続編刊行。家族制度の批判を企図して書かれた作品。
大臣大将の胸に光るは何ですエ、 金鵄勲章? イエイエ違います、 可愛い兵士のしゃれこうべ! ポコ、ポンポコポコ、ポン お金持衆のコップに光るは何ですかエ! シャンぺーン? イエイエ違います、
ポコ、ポンポコポコ、ポン (『良人の自白』社会糖売りの歌) 9月08日この日松本に生まれる。明治時代の社会主義文学運度の先駆者の一人。社会主義小説もかいた。のち運動から離脱した。代 表作『火の柱など。』 桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.150 2020.05.20 |

「人はいうシナ国民は古を尊ぶ国民なり、故に進歩なしと。これ思わざるの甚しきものなり。……彼ら古をしたう所以(ゆえん)のもの、すなわちまさに大に進まんと欲する所以にあらずや。……願わくば共に一生を賭(と)してシナ内地に進入し、心をシナ人にして、英雄を収攬(しゅうらん)してもって継天立極の基を定めん。もしシナにして復興して義によって立たんか、インド興すべく、シャム、安南振起すべく、ヒリッピン、エジブㇳもって救うべきなり。」……余はこれ[兄の言葉]を聞いて起って舞えり。余が宿昔(しゅくせき)の疑問ここに破れたればなり。然り、余が一生の大方針は確立せり。(三十三年の夢) この日(12月6日)に生れ、また同日に死す。自由民権論から出てアジアの解放に想到、孫文らとともに戦う。志やぶれ浪花節語りなる。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.202 |
|
大正・昭和期の政治家。明治3年4月1日高知県で山林官水口胤平(たねひら)の三男として生まれ、同県の豪農浜口義立の養子となる。1895年(明治28)東京帝国大学政治学科を卒業後、大蔵省に入り、山形、松山、熊本など地方の税務管理(監督)局長を長く務めたのち、1904年(明治37)に本省に戻り、専売局に勤務した。第三次桂太郎(かつらたろう)内閣の逓信(ていしん)次官就任まで、もっぱら専売局にあって、専売事業の確立に努め、1907年には初代専売局長官に就任、専売局の基礎固めをした。その誠実な人柄と仕事ぶりを見込まれ、住友から重役就任を請われたこともあった。また後藤新平からは、後藤の台湾総督府民政局長就任のおりに台湾行きを、満鉄総裁就任のおりには満鉄入りの誘いを受けたが、断り続けた。 しかし1912年(大正1)後藤の三度目の招きに応じ、第三次桂太郎内閣の逓信次官に就任した。翌1913年後藤とともに桂の立憲同志会の結成に参加、政界入りした。1914年、第二次大隈重信(おおくましげのぶ)内閣の蔵相若槻礼次郎(わかつきれいじろう)のもとで大蔵次官に就任した。1915年の総選挙に初出馬で当選したが、1917年の総選挙では落選、1919年の補欠選挙で当選した。以後4回の総選挙に連続当選。1924年の護憲三派内閣、ついで第二次加藤高明(かとうたかあき)内閣、第一次若槻内閣の蔵相に就任し、税制整理案の成立に努めた。内閣改造で内相に転じ、1927年(昭和2)内閣総辞職により辞任した。 同年憲政会・政友本党の合併による立憲民政党の結成に際して初代総裁に就任。1929年、田中義一(たなかぎいち)政友会内閣が総辞職したため、かわって民政党内閣を組織し、蔵相井上準之助(いのうえじゅんのすけ)に財政緊縮、産業合理化を進めさせ、金解禁を断行した。また外相幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)のもとで協調外交を推進し、対中国関係の改善とイギリス、アメリカとの協調に努めた。1930年、ロンドン海軍軍縮会議に全権団を派遣し、海軍軍令部の反対を押し切って軍縮条約を締結した。内閣打倒をねらう政友会は条約調印直後の議会で統帥権干犯論を掲げて激しく政府を攻撃し、軍部右翼の統帥権干犯論をあおりたてた。枢密院での条約批准も難航したが、元老西園寺公望(さいおんじきんもち)の後押しで切り抜けることができた。 同年11月14日東京駅で右翼青年佐郷屋留雄(さごうやとめお)に狙撃(そげき)され、重傷を負った。政友会は第59議会でふたたび統帥権干犯論をかざして激しい政府攻撃を展開し、浜口の出席を執拗(しつよう)に求めた。無理を押しての議会出席がたたって、病状が悪化したため、1931年(昭和6)4月首相を辞任した。同年8月26日死去。その重厚で誠実な人柄については国民の信頼が厚く、その容貌(ようぼう)から「ライオン首相」とよばれた。民政党内で重きをなしていたため、その死は党内に後継者をめぐる対立を引き起こすことになった。 2021.10.13記す。
42 男 子 の 本 懐 '92 冬の号(朝日新論説委員室)+株式会社英文朝日 1993年3月25日 第1刷 P.100 (1992.11.17) 浜口雄幸首相が東京駅で狙撃されたのは、一九三〇年(昭和五年)十一月十四日だった。当時六十歳。重厚、誠実な人柄で人々の信望を集め、顔立ちからライオン首相とあだななされていた民政党の政治家である。 襲ったのは愛国社員、佐郷屋留雄とな乗る右翼青年だ。乗車の直前をねらって、すぐ近くから短銃で撃った。弾丸は腹部に入って止まった。回復手術で一命をりとめる。「男子の本懐だ」と言ったといわれるのは、狙撃の直後に、駅で手当てを受けた時のことだ。 腹膜炎を起こすことが懸念された。ガスが出ればその心配は消えるというので、国中が気をもむ一幕があった。十七日午前一時十五分、期待されたしろものの第一発。「ガスが出た」という連絡がとびかった。「秋の夜や天下に轟く屁一つ」は、主治医の喜びの句だ。 浜口内閣は海軍軍縮条約を結んだ。野党の政友会は、これを、統帥権をおかすものだと攻撃していた。軍部や右翼にも同様の議論があり、狙撃犯人も「統帥権干犯」を襲撃の理由の人一つにあげていた。首相に登院を求める声が強まる。翌年二月、病を押して登院した。 無理な議会出席がたたり、病状は悪化した。四月に首相を辞任、八月に死ぬ。無念だっただろう。狙撃の後、官邸で歩行訓練などをして議会に出る練習をしていた。三月十日の登院の前に家族や近親者が思いとどまるように頼むが、その時の首相の言葉が残っている。 「大丈夫だ、政治家は、うそを言ったり言い抜けをしたりするものではない。いったん三月上旬に登院すると言明した以上、生命を賭しても、十には登院せねばならぬ。世人が政治家の言を疑うようになっては政治は行われない。浜口は東京駅で死んだと思えば何の未練もないではないか」。 こういう政治家の言葉を、近ごろ、聞いたことがない。本懐も覚悟も責任感もなし、だ。 2021.10.11記す。岸田文雄首相の所信表明に対する10月11日の衆院本会議での代表質問が行われた日。
42. A SPIRIT LACKING IN TODAY'S POLITICKS It was on Nov. 14, 1930, that Prime Minister Osachi Hamaguchi was shot at Tokyo Station. At that time he was 60 years old. He was popular because of his serious and sincere character. A politician of the Minseito(Democratic Party), he was given the nickname "Lion Premier" because of his features. His attacker was a young rightist, who identified as Tomeo Sagoya, a member of the Aikokusya. He fired a pistol at close range just when Hamaguchi was getting on the train. The bullet lodged in Hamaguchi's abdomen. His life was saved by an abdominal operation. He reportedly said, "This is a man's deepest satisfaction," when he received first-aid treatment at the station immediately after being shot. There were worries that he would develop peritonitis. Since it was said such worries would disappear if he could release the gas in his intestines, the whole nation worried. "The first hoped for release occurred at 1:15 a.m. on Nov. 17. The report, "Gas was released," was relayed everywhere. The following happy was penned by the physician in charge: "In the autumn night/One fart resounds/Across the whole country." The Hamaguchi Cabinet signed the London naval disarmament treaty. The opposition party, Seiyukai, attacked this as among rightist, and the man who shot Hamaguchi listed "infringement of the supreme command as one of the reason for his attack. Voices demanding that Hamaguchi appear in the Diet grew stronger. In March the following year, he went to the Diet despite his illness. His forced appearance in the Diet resulted in his condition worsening. He resigned as prime minister in April and died in August. He must have been extremely vexed. After being shot, he underwent rehabilitation, such as walking practice, in his official residence so that he could go to the Diet. Prior to his appearance in the Diet on March 10, family members asked him to desist from going. At that time he uttered the following words. "I'm all right. A politician must not lie or make excuses. As long as I have stated that I would appear in the Diet in the first 10 days of March, I must appear on March 10 even at the risk of my life. If the public comes doubt the statements of politicians, government cannot be carried out. If you think that Hamaguchi died at Tokyo Station, there is no regret whatsoever." We have not heard such words by a politician recently. Today's politicians have neither satisfaction nor resolution nor sense of responsibility. Copy on 2012.10.12 参考図書:城山三郎著『男子の本懐』(新潮文庫)昭和五十八年十二月二十五日 二刷 緊縮財政と行政整理による「金解禁」。これは近代日本の歴史のなかでもっとも鮮明な経済政策と言われている。第一次世界大戦後の慢性的ふ況を脱するために、多くの困難を克服して昭和五年一月に断行された金解禁を遂行した浜口雄幸と井上準之助。性格も境遇も正反対の二人の男が、いかにして一つの政策に生命を賭けたか、人間の生きがいとは何かを静かに問いかけた長編小説。
|
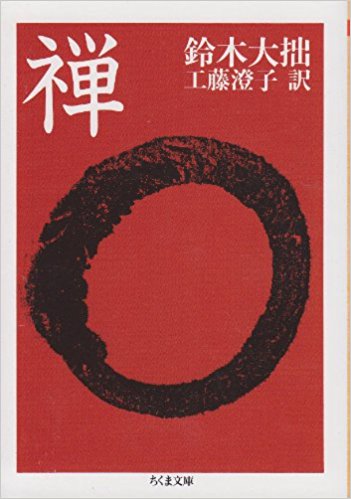
▼鈴木大拙の「公案」について 「理屈というものを理屈としないで、事の上に取り扱うもの、そのことそのこと一事一事の上に理を明きらめて行くと言うふうに考えてはどうかと思う。物を通して行かぬと、どうしても物はわからぬものであるから、その物を通すというそのことが公案であると言ってもいい。」
*2000.10.16 『無門関』をよんでいるから参考になる。
▼ソネット 尊敬している方から鈴木大拙さんが、兄弟を亡くした親友である西田幾太郎へ送ったソネット教えられて。 A sonnet to Nishida who lost his brother in the siege of Port Arthur O human life, what a fragile thing thou art! A drop of dew on a weather -beaten leaf, By passers’ feet down-trodden; and how brief Thy glitter! Too soon fated to depart To a region, who perhaps didst thou first start. The mornful thought doth follow us like thief; Heavily opressed we are without relief; Eternal void, would thou allay our heart! And yet ours is to strive, to weep, to bear; Human are we, with fire in our veins burning; To Reason’s hollow talk let’s not concede. Our tears run free, the heart its woes declare! From every grief endured life’s lesson learning Into the depths of Mystery we read.
ああ、人の命よ、汝はなんと儚いものか 風雨に晒された木の葉の上の露の一滴 行く人に踏まれ、そしてかくも短き 汝の輝き!あまりにはやく逝く定め おそらくは汝の来たりし初めの場所に 弔う思いは秘やかに我らに従い 打ち沈む我らに安息はない 〈永遠の空〉よ我らの心を癒やし給え しかし我らの心は、苦しみ、泣き、忍び 人の子なる我らには血潮がたぎる 理性の空虚な話には耳を貸さぬように 涙を存分に流し、心は悲しみを叫ぶ 耐えた一つ一つの悲しみから人生の教えを学び 〈不可思議〉の奥底にそれを深く読みとる ★説明1:ソネット(十四行詩、Sonnet)は、14行から成るヨーロッパの定型詩。 ルネサンス期にイタリアで創始され、英語詩にも取り入れられ、代表的な詩形のひとつとなった。 ★説明2:sonnet:A sonnet is a poem that has 14 lines. Each line has 14 syllables, and the poem a fixed pattern of rhymes. by Collins COBULD ENGLISH DICTIONARY 2008.4.13
真理とは外にあるもので、感知する主体によって感知されるべきもののように思うのは二元的な考え方で、その理解は知性によることになる。ところが、禅が言うには、われわれは真理の只中に、真理によって生きているのであって、それから離れることはできない。玄沙(げんしゃ)は言う、「われらは大海の中で、頭も肩も水に浸っているようなものである。しかもなお、われわれは、さも悲しげに、水を求めて両手を差しのべているのだ」と。だからある僧が「わたしの自己とは何でしょうか」と問うた時、かれはただちに答えた。「自己をもって、何をしようというのか」。これを知的に分析するならば、かれの意味するところはこうである。自己について話しはじめる時、われわれは必然的に、すぐさま自己と非自己の二元論を打ち立てて、もって理知主義の誤りに陥る。われわれは水の中にいる……これが事実である。だからそのままでいようではないか、と禅は言う。なぜならば、水を求めはじめる時、われわれは自己を水と外的な関係におき、これまで自分のものだったものを取り上げられてしまうからである。 玄沙が韋(い)という武官を茶に招じた時、韋はたずねた、「われわれはそれを毎日持っているにもかかわらず、それを知らないのだと言いますが、これはどういうことでしょうか。」玄沙は質問には答えずに、菓子を一きれ取ってかれにすすめた。それを食べ終って、武官はふたたびたずねた。すると師は言った、「われわれは毎日それを使っていながら、ただそれを知らないだけだ」。明らかにこれは、実地教示である。また、ある時ひとりの僧がかれの許にやって《きて、いかにして真理の道に入るべきかの指示を乞うた。玄沙はたずねた、「おまえには、あの小川のせせらぎが聞えるか。」「はい、聞えます。」玄沙は答えた、「そこから入るがよい。」 鈴木大拙 工藤澄子訳『禅』(ちくま文庫)P.15215~1533 ★プロフィル:鈴木 大拙は、禅についての著作を英語で著し、日本の禅文化を海外に広くしらしめた仏教学者である。著書約100冊の内23冊が、英文で書かれている。梅原猛曰く、「近代日本最大の仏教学者」。1949年に文化勲章、日本学士院会員。 なの「大拙」は居士号である。 2009.08.01
春秋 2018/7/15付 およそ偉人のなを冠した記念館のたぐいで、これほどモノのない場所は珍しい。金沢市の鈴木大拙館である。世界的な仏教学者として知られ、著作も数多い。しかし、モダンな建物内には書斎での写真や自筆の書が点々と配され、来訪者は意外の感を持つかもしれない。 ▼ほの暗い通路から、明るく広々とした人工池のほとりに出ると、誰の足も止まる。「水鏡の庭」という。まわりの木々の緑が映えるみなもでは数分に一度、魚がはねたような音がして波紋が広がり、やがては消えてしまう。ひたすら見入っているヒゲもじゃの若者も、タンクトップの女性2人も海外からの旅行客のようだ。 ▼2011年秋に開館、昨年末までに30万人が訪れた。今も年7万人ペースの来館者があり、4割は海外からという。SNS(交流サイト)などで評判になっているらしい。「長い時間、滞在されるのはたいてい外国の方」と館の人が教えてくれた。確かに、ここには自国第一主義の遠ぼえも貿易をめぐるきしみも届かない。 ▼水や風の音を耳にし、自分を包むゆったりとした時間と向き合うとき、国や宗派を超え、感じ取れる何かがあるのだろう。折しも12日は大拙の命日。館に近い生誕地では胸像への献花があった。ノーベル平和賞の候補にもながあがった「東西のかけ橋」は自らの思いの広がりを、長い眉で控えめに誇っているように見えた。 ★関連:鈴木大拙随門記 |

国木田 独歩(くにきだ どっぽ)(1,871~1908年)6月23日)は、日本の小説家、詩人、ジャーナリスト、編集者。千葉県銚子生まれ、広島県広島市、山口県育ち。 幼名:を亀吉、後に哲夫と改名した。筆名は独歩の他、孤島生、鏡面生、鉄斧生、九天生、田舎漢、独歩吟客、独歩生などがある。 田山花袋、柳田國男らと知り合い『独歩吟』を発表。詩や小説を書き、次第に小説に専心した。デビュー作 『愛弟通信』(1894年) 、『武蔵野』(1898年)『牛肉と馬鈴薯』(1901年)『運命論者』(1903年)『春の鳥』(1904年)『竹の木戸』(1908年)といった浪漫的な作品の後、『春の鳥』『竹の木戸』などで自然主義文学の先駆とされる。また現在も続いている雑誌『婦人画報』の創刊者であり、編集者としての手腕も評価されている。夏目漱石は、その短編『巡査』を絶賛した他、芥川龍之介も国木田独歩の作品を高く評価していた。ロシア語などへの翻訳がある。
富と功みょう! これ実に誘惑なり。吾は日々この誘惑に出あう。 人は人の奴隷にあらざるか。 独立自由のわが一個の吾、何を苦しんで他の誉れを求むること、餓えたる犬が肉を追うて走るがごときぞや。
この自由天来の霊、何を苦しんで窮屈なる日を体裁よきなのもとに、その実、功みょうの念にあふられて送らざるべからざるか。……人生の悲恨は人が人の奴隷となりて、自ら苦しみ、わが霊をただちに大自然のうちに大自由の翼を求めざるにあり。(欺かざるの記)
この日(6月23日)死んだ文学者。自然主義文学の先輩とされるが、キリスト教徒としての思想性と詩人としての抒情性にとむ。好短編が多い。『武蔵野』『酒中日記』『愛弟通信』 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.108 2022.01.13記す。
一 「武蔵野の俤《おもかげ》は今わずかに入間《いるま》郡に残れり」と自分は文政年間にできた地図で見たことがある。そしてその地図に入間郡「小手指原《こてさしはら》久米川は古戦場なり太平記元弘三年五月十一日源平小手指原にて戦うこと一日がうちに三十余たび日暮れは平家三里退きて久米川に陣を取る明れば源氏久米川の陣へ押寄せると載せたるはこのあたりなるべし」と書きこんであるのを読んだことがある。自分は武蔵野の跡のわずかに残っている処とは定めてこの古戦場あたりではあるまいかと思って、一度行ってみるつもりでいてまだ行かないが実際は今もやはりそのとおりであろうかと危ぶんでいる。ともかく、画や歌でばかり想像している武蔵野をその俤ばかりでも見たいものとは自分ばかりの願いではあるまい。それほどの武蔵野が今ははたしていかがであるか、自分は詳わしくこの問に答えて自分を満足させたいとの望みを起こしたことはじつに一年前の事であって、今はますますこの望みが大きくなってきた。 さてこの望みがはたして自分の力で達せらるるであろうか。自分はできないとはいわぬ。容易でないと信じている、それだけ自分は今の武蔵野に趣味を感じている。たぶん同感の人もすくなからぬことと思う。 それで今、すこしく端緒《たんちょ》をここに開いて、秋から冬へかけての自分の見て感じたところを書いて自分の望みの一少部分を果したい。まず自分がかの問に下すべき答は武蔵野の美《び》今も昔に劣らずとの一語である。昔の武蔵野は実地見てどんなに美であったことやら、それは想像にも及ばんほどであったに相違あるまいが、自分が今見る武蔵野の美しさはかかる誇張的の断案を下さしむるほどに自分を動かしているのである。自分は武蔵野の美といった、美といわんよりむしろ詩趣《ししゅ》といいたい、そのほうが適切と思われる。 二 そこで自分は材料不足のところから自分の日記を種にしてみたい。自分は二十九年の秋の初めから春の初めまで、渋谷《しぶや》村の小さな茅屋《ぼうおく》に住んでいた。自分がかの望みを起こしたのもその時のこと、また秋から冬の事のみを今書くというのもそのわけである。 九月七日――「昨日も今日も南風強く吹き雲を送りつ雲を払いつ、雨降りみ降らずみ、日光雲間をもるるとき林影一時に煌《きら》めく、――」 これが今の武蔵野の秋の初めである。林はまだ夏の緑のそのままでありながら空模様が夏とまったく変わってきて雨雲《あまぐも》の南風につれて武蔵野の空低くしきりに雨を送るその晴間には日の光|水気《すいき》を帯びてかなたの林に落ちこなたの杜《もり》にかがやく。自分はしばしば思った、こんな日に武蔵野を大観することができたらいかに美しいことだろうかと。二日置いて九日の日記にも「風強く秋声|野《や》にみつ、浮雲変幻《ふうんへんげん》たり」とある。ちょうどこのころはこんな天気が続いて大空と野との景色が間断なく変化して日の光は夏らしく雲の色風の音は秋らしくきわめて趣味深く自分は感じた。 まずこれを今の武蔵野の秋の発端《ほったん》として、自分は冬の終わるころまでの日記を左に並べて、変化の大略と光景の要素とを示しておかんと思う。 九月十九日――「朝、空曇り風死す、冷霧寒露、虫声しげし、天地の心なお目さめぬがごとし」 同二十一日――「秋天|拭《ぬぐ》うがごとし、木葉火のごとくかがやく」 十月十九日――「明らかに林影黒し」 同二十五日――「朝は霧深く、午後は晴る、夜に入りて雲の絶間の月さゆ。朝まだき霧の晴れぬ間に家を出《い》で野を歩み林を訪う」 同二十六日――「午後林を訪《おとな》う。林の奥に座して四顧し、傾聴し、睇視し、黙想す」 十一月四日――「天高く気澄む、夕暮に独り風吹く野に立てば、天外の富士近く、国境をめぐる連山地平線上に黒し。星光一点、暮色ようやく到り、林影ようやく遠し」 同十八日――「月を蹈《ふ》んで散歩す、青煙地を這《は》い月光林に砕く」 同十九日――「天晴れ、風清く、露冷やかなり。満目黄葉の中緑樹を雑《まじ》ゆ。小鳥|梢《こずえ》に囀《てん》ず。一路人影なし。独り歩み黙思|口吟《こうぎん》し、足にまかせて近郊をめぐる」 同二十二日――「夜|更《ふ》けぬ、戸外は林をわたる風声ものすごし。滴声しきりなれども雨はすでに止みたりとおぼし」 同二十三日――「昨夜の風雨にて木葉ほとんど揺落せり。稲田もほとんど刈り取らる。冬枯の淋しき様となりぬ」 同二十四日――「木葉いまだまったく落ちず。遠山を望めば、心も消え入らんばかり懐《なつか》し」 同二十六日――夜十時記す「屋外は風雨の声ものすごし。滴声相応ず。今日は終日霧たちこめて野や林や永久《とこしえ》の夢に入りたらんごとく。午後犬を伴うて散歩す。林に入り黙坐す。犬眠る。水流林より出でて林に入る、落葉を浮かべて流る。おりおり時雨しめやかに林を過ぎて落葉の上をわたりゆく音静かなり」 同二十七日――「昨夜の風雨は今朝なごりなく晴れ、日うららかに昇りぬ。屋後の丘に立ちて望めば富士山真白ろに連山の上に聳《そび》ゆ。風清く気澄めり」。 げに初冬の朝なるかな。 「田面《たおも》に水あふれ、林影|倒《さかしま》に映れり」 十二月二日――「今朝霜、雪のごとく朝日にきらめきてみごとなり。しばらくして薄雲かかり日光寒し」 同二十二日――「雪初めて降る」 三十年一月十三日――「夜更けぬ。風死し林黙す。雪しきりに降る。燈をかかげて戸外をうかがう、降雪火影にきらめきて舞う。ああ武蔵野沈黙す。しかも耳を澄ませば遠きかなたの林をわたる風の音す、はたして風声か」 同十四日――「今朝大雪、葡萄棚《ぶどうだな》堕《お》ちぬ。 夜更けぬ。梢をわたる風の音遠く聞こゆ、ああこれ武蔵野の林より林をわたる冬の夜寒《よさむ》の凩《こがらし》なるかな。雪どけの滴声軒をめぐる」 同二十日――「美しき朝。空は片雲なく、地は霜柱白銀のごとくきらめく。小鳥梢に囀ず。梢頭《しょうとう》針のごとし」 二月八日――「梅咲きぬ。月ようやく美なり」 三月十三日――「夜十二時、月傾き風きゅうに、雲わき、林鳴る」 同二十一日――「夜十一時。屋外の風声をきく、たちまち遠くたちまち近し。春や襲いし、冬や遁《のが》れし」 三 昔の武蔵野は萱原《かやはら》のはてなき光景をもって絶類の美を鳴らしていたようにいい伝えてあるが、今の武蔵野は林である。林はじつに今の武蔵野の特色といってもよい。すなわち木はおもに楢《なら》の類《たぐ》いで冬はことごとく落葉し、春は滴《したた》るばかりの新緑|萌《も》え出ずるその変化が秩父嶺以東十数里の野いっせいに行なわれて、春夏秋冬を通じ霞《かすみ》に雨に月に風に霧に時雨《しぐれ》に雪に、緑蔭に紅葉に、さまざまの光景を呈《てい》するその妙はちょっと西国地方また東北の者には解しかねるのである。元来日本人はこれまで楢の類いの落葉林の美をあまり知らなかったようである。林といえばおもに松林のみが日本の文学美術の上に認められていて、歌にも楢林の奥で時雨を聞くというようなことは見あたらない。自分も西国に人となって少年の時学生として初めて東京に上ってから十年になるが、かかる落葉林の美を解するに至ったのは近来のことで、それも左の文章がおおいに自分を教えたのである。 「秋九月中旬というころ、一日自分が樺《かば》の林の中に座していたことがあッた。今朝から小雨が降りそそぎ、その晴れ間にはおりおり生《な》ま暖かな日かげも射してまことに気まぐれな空合《そらあ》い。あわあわしい白《し》ら雲が空《そ》ら一面に棚引《たなび》くかと思うと、フトまたあちこち瞬《またた》く間雲切れがして、むりに押し分けたような雲間から澄みて怜悧《さか》し気《げ》にみえる人の眼のごとくに朗らかに晴れた蒼空《あおぞら》がのぞかれた。自分は座して、四顧して、そして耳を傾けていた。木の葉が頭上でかすかに戦《そよ》いだが、その音を聞いたばかりでも季節は知られた。それは春先する、おもしろそうな、笑うようなさざめきでもなく、夏のゆるやかなそよぎでもなく、永たらしい話し声でもなく、また末の秋のおどおどした、うそさぶそうなお饒舌《しゃべ》りでもなかったが、ただようやく聞取れるか聞取れぬほどのしめやかな私語《ささやき》の声であった。そよ吹く風は忍ぶように木末《こずえ》を伝ッた、照ると曇るとで雨にじめつく林の中のようすが間断なく移り変わッた、あるいはそこにありとある物すべて一時に微笑したように、隈《くま》なくあかみわたッて、さのみ繁《しげ》くもない樺《かば》のほそぼそとした幹《みき》は思いがけずも白絹めく、やさしい光沢《こうたく》を帯《お》び、地上に散り布《し》いた、細かな落ち葉はにわかに日に映じてまばゆきまでに金色を放ち、頭をかきむしッたような『パアポロトニク』(蕨《わらび》の類《たぐ》い)のみごとな茎《くき》、しかも熟《つ》えすぎた葡萄《ぶどう》めく色を帯びたのが、際限もなくもつれからみつして目前に透かして見られた。」 あるいはまたあたり一面にわかに薄暗くなりだして、瞬《またた》く間に物のあいろも見えなくなり、樺の木立ちも、降り積ッたままでまた日の眼に逢わぬ雪のように、白くおぼろに霞む――と小雨が忍びやかに、怪し気に、私語するようにバラバラと降ッて通ッた。樺の木の葉はいちじるしく光沢が褪《さ》めてもさすがになお青かッた、がただそちこちに立つ稚木のみはすべて赤くも黄いろくも色づいて、おりおり日の光りが今ま雨に濡《ぬ》れたばかりの細枝の繁みを漏《も》れて滑りながらに脱《ぬ》けてくるのをあびては、キラキラときらめいた」 すなわちこれはツルゲーネフの書きたるものを二葉亭が訳して「あいびき」と題した短編の冒頭《ぼうとう》にある一節であって、自分がかかる落葉林の趣きを解するに至ったのはこの微妙な叙景の筆の力が多い。これはロシアの景でしかも林は樺の木で、武蔵野の林は楢の木、植物帯からいうとはなはだ異なっているが落葉林の趣は同じことである。自分はしばしば思うた、もし武蔵野の林が楢の類《たぐ》いでなく、松か何かであったらきわめて平凡な変化に乏しい色彩いちようなものとなってさまで珍重《ちんちょう》するに足らないだろうと。 楢の類いだから黄葉する。黄葉するから落葉する。時雨《しぐれ》が私語《ささや》く。凩《こがらし》が叫ぶ。一陣の風小高い丘を襲えば、幾千万の木の葉高く大空に舞うて、小鳥の群かのごとく遠く飛び去る。木の葉落ちつくせば、数十里の方域にわたる林が一時に裸体《はだか》になって、蒼《あお》ずんだ冬の空が高くこの上に垂れ、武蔵野一面が一種の沈静に入る。空気がいちだん澄みわたる。遠い物音が鮮かに聞こえる。自分は十月二十六日の記に、林の奥に座して四顧し、傾聴し、睇視《ていし》し、黙想すと書いた。「あいびき」にも、自分は座して、四顧して、そして耳を傾けたとある。この耳を傾けて聞くということがどんなに秋の末から冬へかけての、今の武蔵野の心に適《かな》っているだろう。秋ならば林のうちより起こる音、冬ならば林のかなた遠く響く音。 鳥の羽音、囀《さえず》る声。風のそよぐ、鳴る、うそぶく、叫ぶ声。叢《くさむら》の蔭、林の奥にすだく虫の音。空車《からぐるま》荷車の林を廻《めぐ》り、坂を下り、野路《のじ》を横ぎる響。蹄《ひづめ》で落葉を蹶散《けち》らす音、これは騎兵演習の斥候《せっこう》か、さなくば夫婦連れで遠乗りに出かけた外国人である。何事をか声高《こわだか》に話しながらゆく村の者のだみ声、それもいつしか、遠ざかりゆく。独り淋しそうに道をいそぐ女の足音。遠く響く砲声。隣の林でだしぬけに起こる銃音《つつおと》。自分が一度犬をつれ、近処の林を訪《おとな》い、切株に腰をかけて書《ほん》を読んでいると、突然林の奥で物の落ちたような音がした。足もとに臥《ね》ていた犬が耳を立ててきっとそのほうを見つめた。それぎりであった。たぶん栗が落ちたのであろう、武蔵野には栗樹《くりのき》もずいぶん多いから。 もしそれ時雨《しぐれ》の音に至ってはこれほど幽寂《ゆうじゃく》のものはない。山家の時雨は我国でも和歌の題にまでなっているが、広い、広い、野末から野末へと林を越え、杜《もり》を越え、田を横ぎり、また林を越えて、しのびやかに通り過《ゆ》く時雨の音のいかにも幽《しず》かで、また鷹揚《おうよう》な趣きがあって、優《やさ》しく懐《ゆか》しいのは、じつに武蔵野の時雨の特色であろう。自分がかつて北海道の深林で時雨に逢ったことがある、これはまた人跡絶無の大森林であるからその趣はさらに深いが、その代り、武蔵野の時雨《しぐれ》のさらに人なつかしく、私語《ささや》くがごとき趣はない。 秋の中ごろから冬の初め、試みに中野あたり、あるいは渋谷、世田ヶ谷、または小金井の奥の林を訪《おとな》うて、しばらく座って散歩の疲れを休めてみよ。これらの物音、たちまち起こり、たちまち止み、しだいに近づき、しだいに遠ざかり、頭上の木の葉風なきに落ちてかすかな音をし、それも止んだ時、自然の静蕭《せいしょう》を感じ、永遠《エタルニテー》の呼吸身に迫るを覚ゆるであろう。武蔵野の冬の夜更けて星斗闌干《せいとらんかん》たる時、星をも吹き落としそうな野分《のわき》がすさまじく林をわたる音を、自分はしばしば日記に書いた。風の音は人の思いを遠くに誘う。自分はこのもの凄《すご》い風の音のたちまち近くたちまち遠きを聞きては、遠い昔からの武蔵野の生活を思いつづけたこともある。 熊谷直好の和歌に、 よもすから木葉かたよる音きけは しのひに風のかよふなりけり というがあれど、自分は山家の生活を知っていながら、この歌の心をげにもと感じたのは、じつに武蔵野の冬の村居の時であった。 林に座っていて日の光のもっとも美しさを感ずるのは、春の末より夏の初めであるが、それは今ここには書くべきでない。その次は黄葉の季節である。なかば黄いろくなかば緑な林の中に歩いていると、澄みわたった大空が梢々《こずえこずえ》の隙間からのぞかれて日の光は風に動く葉末《はずえ》葉末に砕《くだ》け、その美しさいいつくされず。日光とか碓氷《うすい》とか、天下の名所はともかく、武蔵野のような広い平原の林が隈《くま》なく染まって、日の西に傾くとともに一面の火花を放つというも特異の美観ではあるまいか。もし高きに登りて一目にこの大観を占めることができるならこの上もないこと、よしそれができがたいにせよ、平原の景の単調なるだけに、人をしてその一部を見て全部の広い、ほとんど限りない光景を想像さするものである。その想像に動かされつつ夕照に向かって黄葉の中を歩けるだけ歩くことがどんなにおもしろかろう。林が尽きると野に出る。 四 「十月二十五日の記に、野を歩み林を訪うと書き、また十一月四日の記には、夕暮に独り風吹く野に立てばと書いてある。そこで自分は今一度ツルゲーネフを引く。」 「自分はたちどまった、花束を拾い上げた、そして林を去ッてのらへ出た。日は青々とした空に低く漂《ただよ》ッて、射す影も蒼ざめて冷やかになり、照るとはなくただジミな水色のぼかしを見るように四方に充《み》ちわたった。日没にはまだ半時間もあろうに、モウゆうやけがほの赤く天末を染めだした。黄いろくからびた刈株《かりかぶ》をわたッて烈しく吹きつける野分に催されて、そりかえッた細かな落ち葉があわただしく起き上がり、林に沿うた往来を横ぎって、自分の側を駈け通ッた、のらに向かッて壁のようにたつ林の一面はすべてざわざわざわつき、細末の玉の屑《くず》を散らしたように煌《きらめ》きはしないがちらついていた。また枯れ草《くさ》、莠《はぐさ》、藁《わら》の嫌いなくそこら一面にからみついた蜘蛛《くも》の巣は風に吹き靡《なび》かされて波たッていた。 自分はたちどまった……心細くなってきた、眼に遮《さえぎ》る物象はサッパリとはしていれど、おもしろ気もおかし気もなく、さびれはてたうちにも、どうやら間近になッた冬のすさまじさが見透かされるように思われて。小心な鴉《からす》が重そうに羽ばたきをして、烈しく風を切りながら、頭上を高く飛び過ぎたが、フト首を回《めぐ》らして、横目で自分をにらめて、きゅうに飛び上がッて、声をちぎるように啼《な》きわたりながら、林の向うへかくれてしまッた。鳩《はと》が幾羽ともなく群をなして勢いこんで穀倉のほうから飛んできた、がフト柱を建てたように舞い昇ッて、さてパッといっせいに野面に散ッた――アア秋だ! 誰だか禿山《はげやま》の向うを通るとみえて、から車の音が虚空《こくう》に響きわたッた……」 これはロシアの野であるが、我武蔵野の野の秋から冬へかけての光景も、およそこんなものである。武蔵野にはけっして禿山はない。しかし大洋のうねりのように高低起伏している。それも外見には一面の平原のようで、むしろ高台のところどころが低く窪《くぼ》んで小さな浅い谷をなしているといったほうが適当であろう。この谷の底はたいがい水田である。畑はおもに高台にある、高台は林と畑とでさまざまの区劃をなしている。畑はすなわち野である。されば林とても数里にわたるものなく否《いな》、おそらく一里にわたるものもあるまい、畑とても一眸《いちぼう》数里に続くものはなく一座の林の周囲は畑、一頃《いっけい》の畑の三方は林、というような具合で、農家がその間に散在してさらにこれを分割している。すなわち野やら林やら、ただ乱雑に入組んでいて、たちまち林に入るかと思えば、たちまち野に出るというような風である。それがまたじつに武蔵野に一種の特色を与えていて、ここに自然あり、ここに生活あり、北海道のような自然そのままの大原野大森林とは異なっていて、その趣も特異である。 稲の熟するころとなると、谷々の水田が黄《き》ばんでくる。稲が刈り取られて林の影が倒《さか》さに田面に映るころとなると、大根畑の盛りで、大根がそろそろ抜かれて、あちらこちらの水溜《みずた》めまたは小さな流れのほとりで洗われるようになると、野は麦の新芽で青々となってくる。あるいは麦畑の一端、野原のままで残り、尾花野菊が風に吹かれている。萱原《かやはら》の一端がしだいに高まって、そのはてが天ぎわをかぎっていて、そこへ爪先《つまさき》あがりに登ってみると、林の絶え間を国境に連なる秩父《ちちぶ》の諸嶺が黒く横たわッていて、あたかも地平線上を走ってはまた地平線下に没しているようにもみえる。さてこれよりまた畑のほうへ下るべきか。あるいは畑のかなたの萱原に身を横たえ、強く吹く北風を、積み重ねた枯草で避《よ》けながら、南の空をめぐる日の微温《ぬる》き光に顔をさらして畑の横の林が風にざわつき煌《きらめ》き輝くのを眺むべきか。あるいはまたただちにかの林へとゆく路をすすむべきか。自分はかくためらったことがしばしばある。自分は困ったか否《いな》、けっして困らない。自分は武蔵野を縦横に通じている路は、どれを撰《えら》んでいっても自分を失望ささないことを久しく経験して知っているから。 五 自分の朋友がかつてその郷里から寄せた手紙の中に「この間も一人夕方に萱原を歩みて考え申|候《そうろう》、この野の中に縦横に通ぜる十数の径《みち》の上を何百年の昔よりこのかた朝の露さやけしといいては出で夕の雲花やかなりといいてはあこがれ何百人のあわれ知る人や逊遥《しょうよう》しつらん相|悪《にく》む人は相避けて異なる道をへだたりていき相愛する人は相合して同じ道を手に手とりつつかえりつらん>との一節があった。野原の径を歩みてはかかるいみじき想いも起こるならんが、武蔵野の路はこれとは異り、相逢わんとて往くとても逢いそこね、相避けんとて歩むも林の回り角で突然出逢うことがあろう。されば路という路、右にめぐり左に転じ、林を貫き、野を横ぎり、真直《まっすぐ》なること鉄道線路のごときかと思えば、東よりすすみてまた東にかえるような迂回《うかい》の路もあり、林にかくれ、谷にかくれ、野に現われ、また林にかくれ、野原の路のようによく遠くの別路ゆく人影を見ることは容易でない。しかし野原の径の想いにもまして、武蔵野の路にはいみじき実《じつ》がある。 武蔵野に散歩する人は、道に迷うことを苦にしてはならない。どの路でも足の向くほうへゆけばかならずそこに見るべく、聞くべく、感ずべき獲物がある。武蔵野の美はただその縦横に通ずる数千条の路を当《あて》もなく歩くことによって始めて獲《え》られる。春、夏、秋、冬、朝、昼、夕、夜、月にも、雪にも、風にも、霧にも、霜にも、雨にも、時雨にも、ただこの路をぶらぶら歩いて思いつきしだいに右し左すれば随処《ずいしょ》に吾らを満足さするものがある。これがじつにまた、武蔵野第一の特色だろうと自分はしみじみ感じている。武蔵野を除いて日本にこのような処がどこにあるか。北海道の原野にはむろんのこと、奈須野にもない、そのほかどこにあるか。林と野とがかくもよく入り乱れて、生活と自然とがこのように密接している処がどこにあるか。じつに武蔵野にかかる特殊の路のあるのはこのゆえである。 されば君もし、一の小径を往き、たちまち三条に分かるる処に出たなら困るに及ばない、君の杖《つえ》を立ててその倒れたほうに往きたまえ。あるいはその路が君を小さな林に導く。林の中ごろに到ってまた二つに分かれたら、その小なる路を撰《えら》んでみたまえ。あるいはその路が君を妙な処に導く。これは林の奥の古い墓地で苔《こけ》むす墓が四つ五つ並んでその前にすこしばかりの空地があって、その横のほうに女郎花《おみなえし》など咲いていることもあろう。頭の上の梢《こずえ》で小鳥が鳴いていたら君の幸福である。すぐ引きかえして左の路を進んでみたまえ。たちまち林が尽きて君の前に見わたしの広い野が開ける。足元からすこしだらだら下がりになり萱《かや》が一面に生え、尾花の末が日に光っている、萱原の先きが畑で、畑の先に背の低い林が一|叢《むら》繁り、その林の上に遠い杉の小杜《こもり》が見え、地平線の上に淡々《あわあわ》しい雲が集まっていて雲の色にまがいそうな連山がその間にすこしずつ見える。十月小春の日の光のどかに照り、小気味よい風がそよそよと吹く。もし萱原のほうへ下《お》りてゆくと、今まで見えた広い景色がことごとく隠れてしまって、小さな谷の底に出るだろう。思いがけなく細長い池が萱原と林との間に隠れていたのを発見する。水は清く澄んで、大空を横ぎる白雲の断片を鮮かに映している。水のほとりには枯蘆《かれあし》がすこしばかり生えている。この池のほとりの径《みち》をしばらくゆくとまた二つに分かれる。右にゆけば林、左にゆけば坂。君はかならず坂をのぼるだろう。とかく武蔵野を散歩するのは高い処高い処と撰びたくなるのはなんとかして広い眺望を求むるからで、それでその望みは容易に達せられない。見下ろすような眺望はけっしてできない。それは初めからあきらめたがいい。 もし君、何かの必要で道を尋ねたく思わば、畑の真中にいる農夫にききたまえ。農夫が四十以上の人であったら、大声をあげて尋ねてみたまえ、驚いてこちらを向き、大声で教えてくれるだろう。もし少女《おとめ》であったら近づいて小声でききたまえ。もし若者であったら、帽を取って慇懃《いんぎん》に問いたまえ。鷹揚《おうよう》に教えてくれるだろう。怒ってはならない、これが東京近在の若者の癖《くせ》であるから。 教えられた道をゆくと、道がまた二つに分かれる。教えてくれたほうの道はあまりに小さくてすこし変だと思ってもそのとおりにゆきたまえ、突然農家の庭先に出るだろう。はたして変だと驚いてはいけぬ。その時農家で尋ねてみたまえ、門を出るとすぐ往来ですよと、すげなく答えるだろう。農家の門を外に出てみるとはたして見覚えある往来、なるほどこれが近路《ちかみち》だなと君は思わず微笑をもらす、その時初めて教えてくれた道のありがたさが解《わか》るだろう。 真直《まっすぐ》な路で両側とも十分に黄葉した林が四五丁も続く処に出ることがある。この路を独り静かに歩むことのどんなに楽しかろう。右側の林の頂《いただき》は夕照|鮮《あざや》かにかがやいている。おりおり落葉の音が聞こえるばかり、あたりはしんとしていかにも淋しい。前にも後ろにも人影見えず、誰にも遇《あ》わず。もしそれが木葉落ちつくしたころならば、路は落葉に埋れて、一足ごとにがさがさと音がする、林は奥まで見すかされ、梢の先は針のごとく細く蒼空《あおぞら》を指している。なおさら人に遇わない。いよいよ淋しい。落葉をふむ自分の足音ばかり高く、時に一羽の山鳩あわただしく飛び去る羽音に驚かされるばかり。 同じ路を引きかえして帰るは愚《ぐ》である。迷ったところが今の武蔵野にすぎない、まさかに行暮れて困ることもあるまい。帰りもやはりおよその方角をきめて、べつな路を当てもなく歩くが妙。そうすると思わず落日の美観をうることがある。日は富士の背に落ちんとしていまだまったく落ちず、富士の中腹に群《むら》がる雲は黄金色に染まって、見るがうちにさまざまの形に変ずる。連山の頂は白銀の鎖《くさり》のような雪がしだいに遠く北に走って、終は暗憺《あんたん》たる雲のうちに没してしまう。 日が落ちる、野は風が強く吹く、林は鳴る、武蔵野は暮れんとする、寒さが身に沁《し》む、その時は路をいそぎたまえ、顧みて思わず新月が枯林の梢の横に寒い光を放っているのを見る。風が今にも梢から月を吹き落としそうである。突然また野に出る。君はその時、 山は暮れ野は黄昏《たそがれ》の薄《すすき》かな の名句を思いだすだろう。 六 今より三年前の夏のことであった。自分はある友と市中の寓居《ぐうきょ》を出でて三崎町の停車場から境まで乗り、そこで下りて北へ真直《まっすぐ》に四五丁ゆくと桜橋という小さな橋がある、それを渡ると一軒の掛茶屋《かけぢゃや》がある、この茶屋の婆さんが自分に向かって、「今時分、何にしに来ただア」と問うたことがあった。 自分は友と顔見あわせて笑って、「散歩に来たのよ、ただ遊びに来たのだ」と答えると、婆さんも笑って、それもばかにしたような笑いかたで、「桜は春咲くこと知らねえだね」といった。そこで自分は夏の郊外の散歩のどんなにおもしろいかを婆さんの耳にも解るように話してみたがむだであった。東京の人はのんきだという一語で消されてしまった。自分らは汗をふきふき、婆さんが剥《む》いてくれる甜瓜《まくわうり》を喰い、茶屋の横を流れる幅一尺ばかりの小さな溝で顔を洗いなどして、そこを立ち出でた。この溝の水はたぶん、小金井の水道から引いたものらしく、よく澄んでいて、青草の間を、さも心地よさそうに流れて、おりおりこぼこぼと鳴っては小鳥が来て翼をひたし、喉《のど》を湿《うる》おすのを待っているらしい。しかし婆さんは何とも思わないでこの水で朝夕、鍋釜《なべかま》を洗うようであった。 茶屋を出て、自分らは、そろそろ小金井の堤を、水上のほうへとのぼり初めた。ああその日の散歩がどんなに楽しかったろう。なるほど小金井は桜の名所、それで夏の盛りにその堤をのこのこ歩くもよそ目には愚《おろ》かにみえるだろう、しかしそれはいまだ今の武蔵野の夏の日の光を知らぬ人の話である。 空は蒸暑《むしあつ》い雲が湧《わ》きいでて、雲の奥に雲が隠れ、雲と雲との間の底に蒼空が現われ、雲の蒼空に接する処は白銀の色とも雪の色とも譬《たと》えがたき純白な透明な、それで何となく穏やかな淡々《あわあわ》しい色を帯びている、そこで蒼空が一段と奥深く青々と見える。ただこれぎりなら夏らしくもないが、さて一種の濁《にご》った色の霞《かすみ》のようなものが、雲と雲との間をかき乱して、すべての空の模様を動揺、参差《しんし》、任放、錯雑のありさまとなし、雲を劈《つんざ》く光線と雲より放つ陰翳とが彼方此方に交叉して、ふ羈奔逸の気がいずこともなく空中に微動している。林という林、梢という梢、草葉の末に至るまでが、光と熱とに溶けて、まどろんで、怠けて、うつらうつらとして酔っている。林の一角、直線に断たれてその間から広い野が見える、野良《のら》一面、糸遊《いとゆう》上騰《じょうとう》して永くは見つめていられない。 自分らは汗をふきながら、大空を仰いだり、林の奥をのぞいたり、天ぎわの空、林に接するあたりを眺めたりして堤の上を喘《あえ》ぎ喘ぎ辿《たど》ってゆく。苦しいか? どうして! 身うちには健康がみちあふれている。 長堤三里の間、ほとんど人影を見ない。農家の庭先、あるいは藪《やぶ》の間から突然、犬が現われて、自分らを怪しそうに見て、そしてあくび[をして隠れてしまう。林のかなたでは高く羽ばたきをして雄鶏《おんどり》が時をつくる、それが米倉の壁や杉の森や林や藪に籠《こも》って、ほがらかに聞こえる。堤の上にも家鶏《にわとり》の群が幾組となく桜の陰などに遊んでいる。水上を遠く眺めると、一直線に流れてくる水道の末は銀粉を撒《ま》いたような一種の陰影のうちに消え、間近くなるにつれてぎらぎら輝いて矢のごとく走ってくる。自分たちはある橋の上に立って、流れの上と流れのすそと見比べていた。光線の具合で流れの趣が絶えず変化している。水上が突然薄暗くなるかとみると、雲の影が流れとともに、瞬《またた》く間に走ってきて自分たちの上まで来て、ふと止まって、きゅうに横にそれてしまうことがある。しばらくすると水上がまばゆく煌《かがや》いてきて、両側の林、堤上の桜、あたかも雨後の春草のように鮮かに緑の光を放ってくる。橋の下では何ともいいようのない優しい水音がする。これは水が両岸に激して発するのでもなく、また浅瀬のような音でもない。たっぷりと水量《みずかさ》があって、それで粘土質のほとんど壁を塗ったような深い溝を流れるので、水と水とがもつれてからまって、揉《も》みあって、みずから音を発するのである。何たる人なつかしい音だろう! “――Let us match This water's pleasant tune With some old Border song, or catch, That suits a summer's noon.” の句も思いだされて、七十二歳の翁と少年とが、そこら桜の木蔭にでも坐っていないだろうかと見廻わしたくなる。自分はこの流れの両側に散点する農家の者を幸福《しやわせ》の人々と思った。むろん、この堤の上を麦藁帽子《むぎわらぼうし》とステッキ一本で散歩する自分たちをも。 七 自分といっしょに小金井の堤を散歩した朋友は、今は判官になって地方に行っているが、自分の前号の文を読んで次のごとくに書いて送ってきた。自分は便利のためにこれをここに引用する必要を感ずる――武蔵野は俗にいう関《かん》八州の平野でもない。また道灌《どうかん》が傘《かさ》の代りに山吹《やまぶき》の花を貰ったという歴史的の原でもない。僕は自分で限界を定めた一種の武蔵野を有している。その限界はあたかも国境または村境が山や河や、あるいは古跡や、いろいろのもので、定めらるるようにおのずから定められたもので、その定めは次のいろいろの考えから来る。 僕の武蔵野の範囲の中には東京がある。しかしこれはむろん省《はぶ》かなくてはならぬ、なぜならば我々は農商務省の官衙《かんが》が巍峨《ぎが》として聳《そび》えていたり、鉄管事件《てっかんじけん》の裁判があったりする八百八街によって昔の面影を想像することができない。それに僕が近ごろ知合いになったドイツ婦人の評に、東京は「新しい都」ということがあって、今日の光景ではたとえ徳川の江戸であったにしろ、この評語を適当と考えられる筋もある。このようなわけで東京はかならず武蔵野から抹殺《まっさつ》せねばならぬ。 しかしその市の尽《つ》くる処、すなわち町|外《は》ずれはかならず抹殺してはならぬ。僕が考えには武蔵野の詩趣を描くにはかならずこの町|外《はず》れを一の題目《だいもく》とせねばならぬと思う。たとえば君が住まわれた渋谷の道玄坂《どうげんざか》の近傍、目黒の行人坂《ぎょうにんざか》、また君と僕と散歩したことの多い早稲田の鬼子母神《きしもじん》あたりの町、新宿、白金…… また武蔵野の味《あじ》を知るにはその野から富士山、秩父山脈|国府台《こうのだい》等を眺めた考えのみでなく、またその中央に包《つつ》まれている首府東京をふり顧《かえ》った考えで眺めねばならぬ。そこで三里五里の外に出で平原を描くことの必要がある。君の一篇にも生活と自然とが密接しているということがあり、また時々いろいろなものに出あうおもしろ味が描いてあるが、いかにもさようだ。僕はかつてこういうことがある 家弟をつれて多摩川のほうへ遠足したときに、一二里行き、また半里行きて家並《やなみ》があり、また家並に離れ、また家並に出て、人や動物に接し、また草木ばかりになる、この変化のあるのでところどころに生活を点綴《てんてつ》している趣味のおもしろいことを感じて話したことがあった。この趣味を描くために武蔵野に散在せる駅、駅といかぬまでも家並、すなわち製図家の熟語でいう聯檐家屋《れんたんかおく》を描写するの必要がある。 また多摩川はどうしても武蔵野の範囲に入れなければならぬ。六つ玉川などと我々の先祖がなづけたことがあるが武蔵の多摩川のような川が、ほかにどこにあるか。その川が平らな田と低い林とに連接する処の趣味は、あだかも首府が郊外と連接する処の趣味とともに無限の意義がある。 また東のほうの平面を考えられよ。これはあまりに開けて水田が多くて地平線がすこし低いゆえ、除外せられそうなれどやはり武蔵野に相違ない。亀井戸《かめいど》の金糸堀《きんしぼり》のあたりから木下川辺《きねがわへん》へかけて、水田と立木と茅屋《ぼうおく》とが趣をなしているぐあいは武蔵野の一領分《いちりょうぶん》である。ことに富士でわかる。富士を高く見せてあだかも我々が逗子《ずし》の「あぶずり」で眺むるように見せるのはこの辺にかぎる。また筑波《つくば》でわかる。筑波の影が低く遥《はる》かなるを見ると我々は関《かん》八州の一隅に武蔵野が呼吸している意味を感ずる。 しかし東京の南北にかけては武蔵野の領分がはなはだせまい。ほとんどないといってもよい。これは地勢《ちせい》のしからしむるところで、かつ鉄道が通じているので、すなわち「東京」がこの線路によって武蔵野を貫いて直接に他の範囲と連接しているからである。僕はどうもそう感じる。 そこで僕は武蔵野はまず雑司谷《ぞうしがや》から起こって線を引いてみると、それから板橋の中仙道の西側を通って川越近傍まで達し、君の一編に示された入間郡を包んで円《まる》く甲武線の立川駅に来る。この範囲の間に所沢、田無などいう駅がどんなに趣味が多いか……ことに夏の緑の深いころは。さて立川からは多摩川を限界として上丸辺まで下る。八王子はけっして武蔵野には入れられない。そして丸子《まるこ》から下目黒《しもめぐろ》に返る。この範囲の間に布田、登戸、二子などのどんなに趣味が多いか。以上は西半面。 東の半面は亀井戸辺より小松川へかけ木下川から堀切を包んで千住近傍へ到って止まる。この範囲は異論があれば取除いてもよい。しかし一種の趣味があって武蔵野に相違ないことは前に申したとおりである―― 八 自分は以上の所説にすこしの異存もない。ことに東京市の町外《まちはず》れを題目とせよとの注意はすこぶる同意であって、自分もかねて思いついていたことである。町|外《は》ずれを「武蔵野」の一部に入《い》れるといえば、すこしおかしく聞こえるが、じつは不思議はないので、海を描くに波打ちぎわを描くも同じことである。しかし自分はこれを後廻わしにして、小金井堤上の散歩に引きつづき、まず今の武蔵野の水流を説くことにした。 第一は多摩川、第二は隅田川、むろんこの二流のことは十分に書いてみたいが、さてこれも後廻わしにして、さらに武蔵野を流るる水流を求めてみたい。 小金井の流れのごとき、その一である。この流れは東京近郊に及んでは千駄ヶ谷、代々木、角筈《つのはず》などの諸村の間を流れて新宿に入り四谷上水となる。また井頭池《いのかしらいけ》善福池などより流れ出でて神田上水《かんだじょうすい》となるもの。目黒辺を流れて品海《ひんかい》に入るもの。渋谷辺を流れて金杉《かなすぎ》に出ずるもの。その他名も知れぬ細流小溝《さいりゅうしょうきょ》に至るまで、もしこれをよそで見るならば格別の妙もなけれど、これが今の武蔵野の平地高台の嫌いなく、林をくぐり、野を横切り、隠《かく》れつ現われつして、しかも曲《まが》りくねって(小金井は取除け)流るる趣《おもむき》は春夏秋冬に通じて吾らの心を惹《ひ》くに足るものがある。自分はもと山多き地方に生長《せいちょう》したので、河といえばずいぶん大きな河でもその水は透明であるのを見慣れたせいか、初めは武蔵野の流れ、多摩川を除《のぞ》いては、ことごとく濁っているのではなはだ不快な感を惹《ひ》いたものであるが、だんだん慣れてみると、やはりこのすこし濁った流れが平原の景色に適《かな》ってみえるように思われてきた。 自分が一度、今より四五年前の夏の夜の事であった、かの友と相|携《たずさ》えて近郊を散歩したことを憶えている。神田上水の上流の橋の一つを、夜の八時ごろ通りかかった。この夜は月|冴《さ》えて風清く、野も林も白紗《はくしゃ》につつまれしようにて、何ともいいがたき良夜《りょうや》であった。かの橋の上には村のもの四五人集まっていて、欄《らん》に倚《よ》って何事をか語り何事をか笑い、何事をか歌っていた。その中に一人の老翁《ろうおう》がまざっていて、しきりに若い者の話や歌をまぜッかえしていた。月はさやかに照り、これらの光景を朦朧《もうろう》たる楕円形《だえんけい》のうちに描きだして、田園詩の一節のように浮かべている。自分たちもこの画中の人に加わって欄に倚って月を眺めていると、月は緩《ゆ》るやかに流るる水面に澄んで映っている。羽虫《はむし》が水を摶《う》つごとに細紋起きてしばらく月の面《おも》に小皺《こじわ》がよるばかり。流れは林の間をくねって出てきたり、また林の間に半円を描いて隠れてしまう。林の梢に砕《くだ》けた月の光が薄暗い水に落ちてきらめいて見える。水蒸気は流れの上、四五尺の処をかすめている。 大根の時節に、近郊《きんごう》を散歩すると、これらの細流のほとり、いたるところで、農夫が大根の土を洗っているのを見る。 九 かならずしも道玄坂《どうげんざか》といわず、また白金《しろがね》といわず、つまり東京市街の一端、あるいは甲州街道となり、あるいは青梅道《おうめみち》となり、あるいは中原道《なかはらみち》となり、あるいは世田ヶ谷街道となりて、郊外の林地《りんち》田圃《でんぽ》に突入する処の、市街ともつかず宿駅《しゅくえき》ともつかず、一種の生活と一種の自然とを配合して一種の光景を呈《てい》しおる場処を描写することが、すこぶる自分の詩興を喚《よ》び起こすも妙ではないか。なぜかような場処が我らの感を惹《ひ》くだらうかは。自分は一言にして答えることができる。すなわちこのような町外《まちはず》れの光景は何となく人をして社会というものの縮図でも見るような思いをなさしむるからであろう。言葉を換えていえば、田舎《いなか》の人にも都会の人にも感興を起こさしむるような物語、小さな物語、しかも哀れの深い物語、あるいは抱腹《ほうふく》するような物語が二つ三つそこらの軒先に隠れていそうに思われるからであろう。さらにその特点《とくてん》をいえば、大都会の生活のな残《なごり》と田舎の生活の余波《よは》とがここで落ちあって、緩《ゆる》やかにうずを巻いているようにも思われる。 見たまえ、そこに片眼の犬が蹲《うずくま》っている。この犬のなの通っているかぎりがすなわちこの町外《まちはず》れの領分である。 見たまえ、そこに小さな料理屋がある。泣くのとも笑うのとも分からぬ声を振立ててわめく女の影法師が障子《しょうじ》に映っている。外は夕闇がこめて、煙の臭《にお》いとも土の臭いともわかちがたき香りが淀《よど》んでいる。大八車が二台三台と続いて通る、その空車《からぐるま》の轍《わだち》の響が喧《やかま》しく起こりては絶え、絶えては起こりしている。 見たまえ、鍛冶工《かじや》の前に二頭の駄馬が立っているその黒い影の横のほうで二三人の男が何事をかひそひそと話しあっているのを。鉄蹄《てってい》の真赤になったのが鉄砧《かなしき》の上に置かれ、火花が夕闇を破って往来の中ほどまで飛んだ。話していた人々がどっと何事をか笑った。月が家並《やなみ》の後ろの高い樫《かし》の梢まで昇ると、向う片側の家根が白《し》ろんできた。 かんてらから黒い油煙《ゆえん》が立っている、その間を村の者町の者十数人駈け廻わってわめいている。いろいろの野菜が彼方此方に積んで並べてある。これが小さな野菜市、小さな糶売場《せりば》である。 日が暮れるとすぐ寝てしまう家《うち》があるかと思うと夜《よ》の二時ごろまで店の障子に火影《ほかげ》を映している家がある。理髪所《とこや》の裏が百姓|家《や》で、牛のうなる声が往来まで聞こえる、酒屋の隣家《となり》が紊豆売《なっとううり》の老爺の住家で、毎朝早く紊豆《なっとう》紊豆と嗄声《しわがれごえ》で呼んで都のほうへ向かって出かける。夏の短夜が間もなく明けると、もう荷車が通りはじめる。ごろごろがたがた絶え間がない。九時十時となると、蝉《せみ》が往来から見える高い梢で鳴きだす、だんだん暑くなる。砂埃《すなぼこり》が馬の蹄《ひづめ》、車の轍《わだち》に煽《あお》られて虚空《こくう》に舞い上がる。蝿《はえ》の群が往来を横ぎって家から家、馬から馬へ飛んであるく。 それでも十二時のどんがかすかに聞こえて、どことなく都の空のかなたで汽笛の響がする。 底本:「日本文学全集12 国木田独歩 石川啄木集」集英社、1967(昭和42)年9月7日初版 青空文庫作成ファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。2018.10.27 |

軍備を誇揚することをやめよ。徴兵の制を崇拝することをやめよ。我は兵営が多数無頼(ぶらい)の遊民を産出することを見たり。多くの生産力を消糜することを見たり。多くの有為の青年を蹉跌(さてつ)せしむることを見たり。兵営所在の地方の風俗が多く壊乱せらるることをみたり。行軍の沿道の良民が常に彼らに苦しめららるるをみたり。いまだ軍備と徴兵が国民のために一粒の米、一片の金をだに産するを見ざるなり。いわんや科学をや、文芸をや、宗教道徳の高遠なる理想をや。いな、ただこれを得ざるのみならず、かえってこれを破壊し尽くさんとするにあらずや。(廿世紀の怪物帝国主義) この日(1月24日)この日天皇暗殺未遂と称せられた大逆事件のやめ死刑となる。明治時f代の社会主義運動の指導者。のち無政府主義にかたむいた。著書『社会主義真髄』 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.15 |
|
堺利彦は福岡県の士族に生まれた。明治維新で父が家禄を失い公債証書700円の「五十円足らずの利子」今の150万円ほどの年収で暮らした。成績は優秀で第一高等中等学(いまの東京大学教養学部)に入学。そのまま行けば知事や次官になったはずだが「宇宙の絶大、人間の微小」を感じ、放蕩をはじめ月謝礼能(あたわ)ずで除名となる(自伝『堺利彦伝』)。その後、小学校教員を経て新聞記者。当時珍しかった社会主義運動を始めたため弾圧され入出獄を繰り返す。ただ堺の文章力のすごさは有名。筆一本で生きのびた。 1915年、名著『文章の速達法』をかき、文章の上達の秘訣を述べている。 「素人の作文者はまず決して玄人に怯(お)じてはならぬ」。職業小説家や記者は文章の商売人。その文章は綺麗にみえても長年文章を売るうちに人の心をうつ力を喪失している。「玄人の整頓した文章よりも、正直な素人の疵(きず)の多い文章の方が、はるかに味もあり、力もあり、光もある」といった。作文の第一要件は「真実を語ること」。感じたこと知ったことを率直にかけ、それがないときは「文章を書くべきでない」といった 書く前に「腹案」は立てるのがコツ。書く内容をどの順序で書くか事前に整理してから書く。 そして重要なのが「気乗り>」だ。「よく寝る、散歩する。旅行する。場合相応の本を読む。他の仕事を片付ける」などして「自分の頭の機嫌を取って」調子のよい時に筆をとる。具体的に読み手を想像して書くといい。文章は無駄を嫌う。事柄・理窟・言葉・句法の四つの無駄を省く。これが達意の文を書く要点であるという。 引用:朝日新聞:2010.07.17:磯田道史「この人、その言葉」より

社会主義の主張する所は、ひっきょう善良なる家庭に行われるがごとき共同生活を、社会全般に行いたいというのである。男子が多く外にあって繁劇ななる事務にに従い、女子は多く内にあって家事を努め、老人は老人、小児は小児、皆それぞれ才力に応じたる労働をなし、しかして銘々の必要に応じて公平なる分配をなし、常に相扶(たす)けて生涯を送る、これがすなわち善良なる家庭の生活であって、社会主義の主張は実にこの外にないのである。故に社会主義の実行を……望む者は、必ずまず多くの力を家庭の改革に用い、十分なる社会思想、共同思想を此間に、養う事を努めねばならぬ。(『万朝報』論説)
この日(1月22日)この日死んだ日本社会主義運動の長老。マルクス主義の紹介者。言文一致体の普及、家庭の民主化をとなえた先覚者でもあった。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.14
★プロフィル:堺 利彦は、日本の社会主義者・思想家・歴史家・著述家・小説家。号は枯川、別名は、貝塚渋六。
|
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.209~213 深井 英五 牧師志し同志社へ、しかし 徳富蘇峰の民友社に、明治二十六年の末ごろから深井英五という二十三歳の青年が加わった。青年は「金蘭簿」という社員名簿の指定項目のところに、「得意は無し、趣味は無し、主義は厭世、希望は寂滅」と書きこんだ。いかにもニヒルな感じであるが、深井自身は「少し茶目気分もまじったのであろうが、自棄に傾いた懊悩の心境があらわれている」と回想している(『回顧七十年』)。 彼は上野国高崎藩士の四男坊である。家系が苦しく、中学への進学をあきらめて小学校の「授業生」になっていた。これは小泉三申も郷里でなったことがある助教員のような仕事で、若干の月給がもらえたから本代ぐらいにはなった。そして十六歳のとき、米国人ブラウン夫人の奨学金をうけて同志社普通学校に入ることができた。 そのころ同志社には、普通学校と神学校があった。神学校はキリスト教の牧師を養成するところで、普通学校(五年)を卒業したものを収容する仕組みであった。すでに十四歳のとき洗礼をうけてていた英五は、この神学校をへて牧師になるつもりであった。「同志社教育は広汎にして深厚なる影響を私の一生にあたえた。もっとも重しとすべきは、新島襄先生の感化による人生観の育成である」(前掲書)と彼は書いているが、新島は淡々とした態度しか示さないので、自分にたいして格別関心がないのかとさえ思ったことがある。ただ、新島は、とくに訓戒するというような態度はとらず、むしろ自分の体験を語るという形で静かに人生への心構えを説いたのであった。 それには、三つのポイントがあった。第一は自己の信念に立脚しなけばならぬ、付和雷同やゴマかしてはいけないということ、第二は、単に自己生活のためではなく、世の中のためになるように心がけねばならないということ、第三は、何か仕事しなければならないということ、である。 「それが訓戒ではなく、先生の胸中を吐露されるがごとく聞えたので私は一層深く感動した。神を父とし、人間を同胞とする教理の応用として、私の実践的人生観の基礎ができた>。ところが、自分独自の思索を深めてゆくにしたがい、英五は教理にたいする疑惑をつぎつぎと感じた。たとえば処女受胎という奇蹟につまづいた。「しかしながら信仰は思想にあらずして、心の熱である。熱の源たる伝統の権威がなくなって、その教理を単なる思想として検討すれば、矛盾またはふ合理らしく見ゆる点にたいしてふ安が拡大される」。 ※関連:椎な麟三著『私の聖書物語』。 「宗教と理性を調和せんことを期したところの思索は逆の結果を生じ、私の数年間心にいだきたる念願は破壊した」。普通学校を卒業したとき、もはや牧師になる気持ちはなく、神学校入りはやめ、「真理および人生価値の標準について全然懐疑におちいってしまった」。それと同時に生計をどうするか、の問題でもあり、神経衰弱になるか、大脱線をするかもしれぬ境界に立っていた。それを見て、同志社の学友で、早くから新聞記者を志して『国民新聞』に入っていた平田久(ひさし)が徳富蘇峰に助力を乞うたのである。 蘇峰はこのとき三十一歳で、深井青年に哲学への執着があるのを見て、東大で心理学を講じていた元良勇次郎に庇護と指導をたのんでやった。深井は元良の学問に深い影響をうけたけれども生活費をかせぐ道は見出せなかった。そこで蘇峰は、外国新刊書の要領をパンフレットにし、毎月一冊ずつ民友社から出版して生活費をかせがせる方法を考えてやり、これが約一年つづき、そのあと『国民新聞』に入社しないか、とすすめたのである。それも、普通の記者ではなく、後方にあって政治、法律などの学問を研究するという仕事で「いわば捨扶持の読書生の如きもの……月給は少ないが、書物を多く買ってもらった」。深井は感激して蘇峰の好意をうけた。 蘇峰自身は、「君を予の理想的の新聞記者につくり上げようと思ったが、その方面では予はいささか予の考えがまちがいであることを悟った」(『蘇峰自伝』)と回想している。「君は小心に過ぐるというべきほど、堅実性に富んだ人であって、山気たる事とか、冒険的な事とかは好まない。頭脳は全く倫理的にできていて、自らまず酔うて、しかして後人を酔わしむるなどという手際は、望むべきでなかった」。ただ、その英語と調査能力が抜群であることを見ぬいた蘇峰は、七年後、大蔵大臣松方正義(薩摩藩士)、にその能力を推薦し、深井はその秘書官となって、別個の人生が開けるのである。 深井は、「一生懸命に努力したつもりだが、成績からいえば自分でも甚だ不満足であった。ただ私自身のために得るところはすこぶる多かった」という。 それは第一に、「世間表裏の臭いをかいだ」こと、第二に、「国家本位の現実主義」を心にうえつけたことである。蘇峰のスタッフであった七年間の、特に重要な事件として彼は三つをあげる。第一は、日清戦争のとき、大本営地広島で通信員となり、ついで従軍記者として関東州にわたったことである。このとき徳富のスタッフとして、参謀次長川上操六中将の庇護をうけ、その人間味に接したことは大きかった。それまでは蘇峰も川上に好意をもってなかった。ところが「一見旧のごとし」「会ってみて、日本の陸軍の脈はここにあり」と感じた。川上は、「徳富君に何一つ不足はないが、こまったものは例の平民主義……これさえ止めてもらえばまことに結構である」といった。しかし蘇峰は「彼(川上)は薩摩の生地にドイツのメッキをした男で、ついに平民主義の真諦はわからなかったが、しかしその考え方も、その態度も、彼は自らしらず覚えざるに平民的であった」と評している。 第二は、二十九年春から三十年夏にかけて蘇峰が欧米を巡遊したとき、その随行をしたことである。ロンドンでは、タイムズ紙の編集次長を数十年やって特異の経歴をつくったキャッパ―と蘇峰は「一見して意気投合」、深井も「共通の接遇」をうけた。ところがこれから十年後、日露戦争の外債募集で高橋是清がロンドンにきたとき、深井は高橋に随行し、キャッパ―を紹介して便宜をうけることになる。 第三は、英文雑誌『THE FAR EAST』を編集したことである。 松方の秘書官となり、徳富と深井の関係は一段落となったが、深井の心情においては依然として「門下生」の意識がつづき、それは終生変わらなかった。国民新聞社をやめるとき、蘇峰は「春鴻秋燕人力に非ず明月清風我に随いて長し」ということばを書いて贈ったが、深井は自分の心境を道破したものとして書斎に掲げた。昭和十四年、すでに日銀総裁、枢密顧問官の顕職をつとめた深井が、病気療養中に蘇峰にもらった手紙を整理装幀させると、十一巻二帖の大部数になったという。 ※昭和十二年に総裁職を辞任しました。
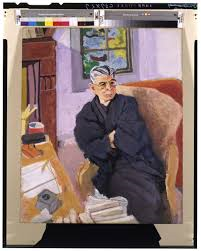
安井曽太郎の「深井英五氏像」 六月十一日まで、東京・京橋のブリジストン美術館で「生誕九十年記念 安井曽太郎展」が開いている。NHKテレビでは「日曜美術館」でこの内容を紹介し、日本経済新聞は五月二日の教養読書特集で、同画伯の「深井英五氏像」と、嘉門安雄の解説を掲げた。 この「深井英五氏像」は、昭和十二年に描かれたもので、肖像画の代表的傑作であるという。 なにが代表的傑作たらしめた要因であろうか。 「深井さんの普段の姿を描きたいと思って、その書斎での深井さんを絵にすることにした。深井さんの書斎は余り広くなく、そのうえ大き過ぎるくらいのテーブルが置かれてあり、床には沢山の書物が積み重ねてあって、やっと画架が置けるくらいであった……」 とは安井の述懐である。 「私はこの絵を見るごとに、やや斜めに構えて微動だにせず、じっと日銀総裁の深井さんをまともから見据えている安井曽太郎のきびしさを思う。だからこそ、このような素晴しい肖像が、人間像が描かれるのである。豊かに深く、さわやかに温かい絵である」 と嘉門は賞めている。たしかにそのとおりであろう。 ただこの画像をじっと見つめていると、おのずと別の感慨がわいてくる。 深井英五は、昭和十六年第十三代日銀総裁となった。その前には、パリ講和会議、ワシントン軍縮会議に、全権随員となった。ロンドン国際経済会議には、全権として列した。貴族議員、枢密顧問官にもなっている。 ところが安井は、そいうステイタスに何の関心を示さず、「普段の姿」を描こうと志向している。そして深井も、和服にくつろいで描かれている。その書斎が余り広くなく、床に沢山の書物を重ねてあるというのも好ましい。そこに、とりつくろわぬ素顔、日常生活が露呈されており、スノピズムの侵入する余地はない。そして、じっと見据えるきびしい画家の眼にこたえているのは、深井自身の、ウソのない人生である。 ※参考:スノビズム(snobbism)は俗物根性と訳される。 多くの場合「知識・教養をひけらかす見栄張りの気取り屋」「上位の者に取り入り、下の者を見下す嫌味な人物」「紳士気取りの俗物」といった意味で使われる。 安井の眼と、これにこたえる深井の年輪。 その激突と均衡の上にこそ、豊かで、深く、さわやかな人間像が温かく形成されたのであろうとおもうが、腕を組み、室内の一点を凝視する深井の姿に、向学心に燃えていた青少年期の原型が感じられてならない。 深井は、上野国高崎において、百五十石取だった旧藩士の第五男として明治四年(一八七一年)に生れている。 父は、前代の遺臣として固く自ら持し、まつたく世間から退隠してくらした。寡言沈重、学問および立志の方向について希望をしめすことはほとんどなく、ただ体格の弱小を心配して護身のために少し武芸をならえ、と注意した。情操、行状などについて訓戒をあたえることは少なかった。ただ貧乏生活がせがれの心境に悪影響をおよぼすことを憂慮し、武士らしい気節を伝えるため、身をもって模範を示した。 高崎は連隊所在地で、そこに所属する将校の子供たちゃ、別の階級のように優遇され、「坊ちゃん」と呼ばれていた。 深井も別に深い理由もなく、周囲の風習にしたがっていると、父からきびしくとがめられた。 「坊ちゃんというのは、主筋に対してのみ使うべきことばである。我家貧なりといえども、卑屈の心になってはいけない」 と父は訓戒したのである。「これは私が六、七歳の頃のことで、その深き印象は一生を通じて種々の場合に私の意気を動かした」と語っている(『回顧七十年』)。 上級学校に進学できない深井に、そのチャンスをあたえたのは新島襄である。新島は、高崎の隣の安中出身で、元治元年(一八六四年)国禁を犯してアメリカにわたり、アムハースト大学のアンドヴィァ―神学校で学び、明治七年(一八七四年)帰国し、翌年京都に同志社を創立した。 その新島が群馬県に帰省したとき、奨学金を支給して同志社に入学させるべきものを物色し、深井がその選にあたったのである。 「同志社教育は広汎にして深厚なる影響を私に与えた。最も重しとすべきは、新島先生の感化による人生観の生成である」 と深井は語っている。また、「当時の同志社教育は、教師と生徒の気分に就いていえば、単なる授業ではなく、心と心との接触による切磋琢磨であった」 とものべている。 深井は、毎月奨学金を新島から手わたされるので、他の学生よりも多く接触した。彼はこれを幸いに、鼓吹激励をうけたいと期待した。が新島は、かねて評判のように熱烈の態度を示さなかった。 「温情は感受したが、談話は概して淡々たるものであった」 一生は長いから急がずにやれとか、健康をそこねないように注意しろ、というような話が多かった。庭の果物を、枝つきのまま手折ってくれたり、休暇の旅費をあたえたりしたこともある。 賄食(まかないしょく)に甲乙の区別ができたとき、深井は乙を選び、その月は先生からいただく学費をそれだけ減らしてもらいたいと申出る、それはまちがっている、健康には栄養が大切だと注意された。 「先生は特に私を訓戒するごとき態度をもってせず、むしろ自己修養の体験を語るように人生の心構えを説き示された」 深井はその印象を三つに要約している。 第一は、自己の信念に立脚しなけばならぬ、付和雷同やゴマかしてはいけないということ。 第二は、単に自己生活のために働くのではいけなく。世の中のためになるように心がけねばならぬ。世のためになるというのは、必ずしも大事業をなすのみに限らない。分に応じてそれぞれの途(みち)がある、といった。 第三は、何か仕事しなければならなければいけない。その趣旨は、仕事の種類をとわず、世の中との接触を必要とし、独善高踏をいましめることにあったらしい。 深井は、以上の三つをしばしばきかされた。それも訓戒ではなく、その胸のうちを吐露するようにきこえたので、深井はいっそう深く感動した。 「神を父とし、人間を同胞とする教理の応用として、私の実践的人生観の基礎ができたのである」 安井の「深井英五氏像」には、この人間的原型が、清潔で、明澄な強さとして、よくとらえられているようにおもう。 (昭和五十三年六月) 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.263~267より 2019.08.04 |
|
香川県大内郡水主村(現在の東かがわ市)出身。 長年立憲政友会の衆議院議員として党内にて重きをなし、内閣書記官長を振り出しに文部大臣・大蔵大臣・逓信大臣・鉄道大臣・枢密顧問官・内務大臣(一時運輸大臣も兼務)を歴任した戦前政界の重鎮である。 出生時以来の姓は宮脇であったが、1895年(明治28年)に三土(「みつち」、みと・みど等は誤り)家に婿養子として入ったために三土姓をな乗った。この婿入りにともない本籍地が香川県阿野郡西庄村(現在の坂出市内)に移ったため、衆議院議員選挙では故郷を含む香川一区ではなく、香川二区から立候補していた。 香川県観音寺市の、日本で唯一の石積みアーチ式ダム豊稔池のな付け親である。また、1912年に制定された「高松市歌(その一)」の作詞者でもある。 「モッタイナイ」を教えた三土忠造の母 数年前、佐藤義亮の『明るい生活』(新潮社、一九三九)という本を入手した。読んでみると、これが意外に興味深い。全編がいわゆる「訓話」であるが、素材が実に多様であり、語り口も巧みである。もちろん、今日の視点から見て、時局に迎合しすぎているようなものも散見されるが、それらを除けば、今日でも十分、読むに値する訓話が多いように思う。 本日は、そうした訓話のうちから、三土忠三土忠造・宮脇長吉宮脇長吉の兄弟が、その母から、「モッタイナイ」ということを教えられた話を紹介する。 ◇まづ家庭の教化から 今の政冶家中、三土忠造氏(元鉄相)は、質素な堅実な人として聞えてゐます。さういふ気風はどこから来たのかといふに、主として家庭の教化によるのださうで、氏の令弟宮脇長吉氏(代議士・陸軍中将)は、次のような話をされました。 私たち兄弟の小さな時分、物を大事にしなければならないといふ母の教はとても厳しかつたもので、御飯粒などこぼして平気でゐると、それはそれはひどく叱られました。ある朝小学校へ行く時間が遅れたので、丁度母が見てゐなかつたのを幸ひ、急いで御飯をかつこみ、茶碗に二粒三粒残つてゐたのをそのまゝにして飛びだしました。二丁ばかり行つた頃、後から私のなを呼ぶ声が聞えます。母が追つかけて来たのでした。 なぜ、御飯粒を残して行くのです。勿体ないといふことを忘れたのかね。すぐ帰つてお食べなさい。言葉つよく叱られた私は、返す言葉もなく、茶碗に残つてゐる御飯粒をたべに渋々引返へ〈ヒッカエ〉さなければなりませんでした……> 宮脇氏はこう話されてから、子供の時分よく聞かされた「勿体ない!」といふ言葉は、今もなほ頭に響いて来るやうな気がすると一言ひ添へられました。三土一家の質素、堅実の気風は、決して偶然にできたものでないことがわかります。 三土忠造は、小学校教員を振り出しに、衆議院議員を経て、大臣を何度も経験した異色の政治家であるが、その旧姓は宮脇である。したがって、引用文中、「三土一家」とあるところは、宮脇一家とすべきところであった。なお、旅行作家として知られた宮脇俊三は、宮脇長吉の三男にあたる。
三土 忠造(みつち ちゅうぞう、1871年8月11日(明治4年6月25日) - 1948年(昭和23年)4月1日)は、明治から昭和にかけての日本の政治家。
小島直記著『逆境を愛する男たち』(新潮社)昭和五十九年五月二十日発行 P.152~157 第二十三話 被疑者としての身の処し方 書架の片隅に『湘南方丈記』という本がある。著者は三上忠三、昭和十一年八月改造社刊。この本を、いつどこで買ったか、どういう内容であったか、そういうことを完全に忘れていた。ところがこのほど『昭和動乱期を語る』(経済往来社)という新刊書を読んで、はからずもその本のいきさつを知ることができた。 『昭和動乱期を語る』には、「一流雑誌記者の証言」というサブ・タイトルがついている。すなわち、大草実(文芸春秋)、萱原宏一(講談社)、下島連(文芸春秋)、下村亮一(日本評論)、高森栄次(博文館)、松下英麿(中央公論)など、往年のベテラン記者が一堂に会しての回想座談会が内容だった。 文壇、出版界、論壇、陸海軍、政財界の有名人物数百人がとり上げられ、エピソード、秘話は無論のこと、肉眼による痛烈な批判を浴びている。実物を知らなかったわれわれが、いかに「虚像」を本ものとおもっていたかを思い知らされ、あるいは、ある事件の真相を教えられるなど、興味はつきない。現代史に関心を抱くものにとっては必見の名著といえるだろう。 この中で『湘南方丈記』のことが出てくるのだ。 「萱原 いまもロッキードで世間が騒いでいますね。戦前に越鉄疑獄とか帝人疑獄、その他いろいろあって、小橋一太、小川平吉、三土忠造といった人々が被疑者になった。僕はいまの政治家と較べて、それらの人々が立派だったと思うのは、いったん被疑者になると、サッと政治の表舞台から退いて、ひたすら謹慎したという一事ですよ。いまの人どうですか、盗人猛々しいじゃないですか。僕は他の人はあまり知らんけれども、三土忠造さんは割合知ってるんです。 『湘南方丈記』執筆の背景は以上のとおりである。 三土忠造は明治四年(一八七一)香川県生まれ。苦学して師範学校を卒業し、小学校教員となった。が、それにあきたらず、東京高等師範学校を卒業、小笠原長幹(おがさわら ながよし)の留学のおともで米国に行き、農政学を学んだ。 「米国に行き、農政学を学んだ」記事は要確認。 帰国後、高等師範学校教授となったが、間もなくやめて「東京日日新聞」記者となり、さらに政界に入って政友会に所属。高橋是清に認められ、高橋内閣の書記官長。昭和二年(一九二七)田中義一内閣の文部大臣、高橋のあとをついで大蔵大臣、犬飼内閣の逓信大臣、斎藤内閣の鉄道大臣を歴任した。帝人事件連座は、この鉄道大臣時代である。 「疑獄」というのは中国の言葉で、辞書には(一)犯罪の疑いがあって捜査、審理を受けている事件、一般に、大規模な収賄事件をいう。(二)有罪か無罪か判決しにくい、世上の疑念が集まっている裁判事件、とある。 ところが「帝人事件」は、二百六十六回の公判のあと、藤井五一郎裁判長から、「証拠不充分ニアラズ、犯罪ノ事実ナキナリ」という判決をうけた。つまり「疑獄」という言葉は当てはまらないのだ。 しかし、無実の人々が拘束され、ついに内閣まで瓦解させたほどのこの事件がどうして起きたか、という点では、まったくふ審にたえない事件であり、その意味では文字通り「疑獄」だったといえるのである。 「帝人事件」については、筆者も書いている(『疑獄』=昭和五十八年潮出版社)。けれども筆者の知るかぎり、もっとも内容価値があるのは、事件の飛沫をうけ、背任罪で一年二カ月を求刑された河合良成による『帝人事件 三十年目の証言』(昭和四十五年講談社)である。 この本の第三部「瀆職に関する各人の場合」の七に「三土さんの場合」というのがある。 この事件のポイントは帝人株をめぐる贈収賄罪にある。しかし三土忠造は、帝人とは何の関係もなかった。「ところが三土さんを憎んでいたのは、議会その他を騒がせた当時のファッショ連中である。(中略)こういう連中は斎藤総理を憎み、高橋蔵相を憎み、黒田次官を憎んだ。そしてその圏内の一人として、当時の鉄道大臣であった三土さんを憎んだのである」(河合、前掲書) しかし、三土は鉄相なので、仮に帝人株をうけとったとしても、身分関係も職務関係もないので、検事局は収賄罪で告訴できない。そこで犯罪に仕上げるために、「偽証罪」をデッチ上げる。「そのため三土さんを高木君(注、元帝人社長、元台銀理事、高木復亨)及び中島さん(注、元商工大臣、男爵、中島久萬吉)と対質せしめ、高木君(注、元帝人社長、元台銀理事、高木復享)及び中島さん(注、元商工大臣、男爵、中島久萬吉)と対質せしめ、高木君をして『確かにあなたに三百株差し上げた』といわしめ、中島さんには『確かにあなたに二百株を換金してもらった』といわしめる。三土さんはもちろん絶対にその事実を否定するものだから、検事連はこの否定(否定こそ事実である)を捕え、三土さんを偽証罪として約一カ月にわたり収監するのである」(河合、前掲書) すなわち、まったくのトバッチリ、ぬれ衣であった。それなのに、「いったん被疑者になると、サッと政治の表舞台から退いて、ひたすら謹慎した」のである。
「洛北大原の片山陰に、ささやかなる庵を結んで居た鴨長明の昔を、学ぶにはあらずして、余は湘南辻堂なる草廬の傍に、四畳半一室の書斎を造った。椽側までの寸尺をこめて、辛うじて、方丈とも言い得るであろう。 長明は、此の世をば仮の宿り、夢の浮世と観じて、独り塵外に己れを清くし、如来菩薩に仕えて、念仏看経に精進し、糸竹花月を友として、唯静なるを望みとし、愁えなきを楽みとしたという。余は此の世をば、最も楽みの多い世界と見ている。幾度生れ変っても、かかる好い処が、又とあろうとは、想像だにもしない。 仏者の説くが如く、因果応酬の理は、ありとしても、神仏は、自ら助くる者を助けたまう。此の世の生涯に於て、人の為めに、最も多く善根を布く者にして、始めて死後に於ても極楽浄土へは、行かれるものと信じて居る。故に極楽往生の道といっても、多くの人々と共に、相依り相助けて、力の及ぶ限り働くより外はない。働いて働いて働き抜く。さて其の後の事は、あなた任せというのが、余の人生観である。 されば、此の小室の営みも、仏に仕えんが爲めにあらず、穢土の累いを避けんが為めにもあらず、忙中閑を得れば、暫く長安みょう利の地を去って、静に経史を繙き、思索を凝らして、身を修め、人を導き、国に尽し、世を益するの道を、探らんとするにある」 という言葉ではじまり、最終の「六十小天地」という一篇は、 「草庵は閑静で、読書思索には、最もよい所である。読み飽いた時には、すぐ庭に下り立つ。庭には是等の生物が居て、形色を以て目を慰め、声音を以て耳を楽ませる。松の手入れ、草取り、草木のうえ換えにも気を転ずる。鋏や鎌や鋸は何時も庭先に置いてある。人間はとかく、自然に技巧を加えることを好む。自然は更に其の上を飾ってくれる。そこに一種の楽みが生ずる。 近い海岸へ出ると、相模灘は、茫々として際涯がない。三浦半島、伊豆半島を左右に望む。江の島は目の前に浮び、大島は雲畑縹渺の間に明滅する。西の空には、雪を頂く富士の高嶺が、魏々として聳え立つ。箱根大山一帯の連山が、其の裾に横わるを見る。本居太平の歌、 群山の朝さぎり深ければ さやかに見ゆる富士の芝山 は、写実の妙を得て居る。ここより望み見る富士の姿は、何処よりも美しい。 浜辺は広い。目を遮るものは何もない。汀の砂は、篩にかけたように細かい。夏は朝夕に、洗足でその上を歩く。漁夫はおちこちで、地引網を曳いて居る。何れも潮風に吹かれ、日光に焼けて、赤銅色である。芸術家の涎を垂らすような健康美が多い。相模灘の波は大きくうねって、緩やかに打寄せる。蕪村の秀句、 春の海ひねもすのたりのたりかな も、此の浜の実景を、如実に歌って居る。 此の小天地は、余に取っては此の上もない暢神の境である。修養の地である。我々の平素の生活は、繁雑にして心を労することが多い。時には都塵を避け、自然に還って、身を養い心を洗うを要する。又読書研鑽をも怠ってはならぬ。余はここへ来る度に、何時も自然に対して、心から感謝するのである」 という文章をもって終っている。 『昭和動乱期を語る』の座談会で萱原宏一は『湘南方丈記』や『憂幽徒然草』について、 「これがまた、立派な文章でね。世の中の為になる文章です。いまの被疑者の態度どうですか。しかも、あの帝人疑獄なるものは、藤井五一裁判長をして、判決文で『空中の楼閣、水中の月を掬うが如き事件』と言わしめた。まったく根も葉もないデッチ上げ事件なんですよ。それでも退身して深く謹慎した。角栄はどうですか」」 といっている。 三土は第二次大戦後、幣原内閣の内務大臣兼運輸大臣となり、昭和二十三年(一九四八)七十七年の生涯を閉じた。 ※2019.05.11写す。 |
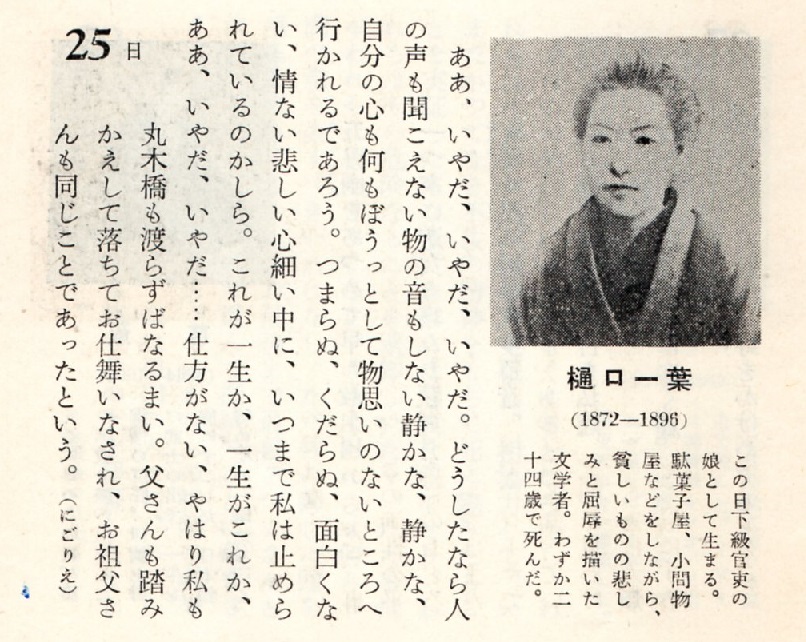
▼『にごりえ』 ああ、いやだ、いやだ、いやだ。どうしたなら人の声も聞こえない物の音もしない静かな、静かな、自分の心も何もぼうっとして物思いのないところへ行かれるであろう。つまらぬ、くだらぬ、面白くない、情けない悲しい心細い中に、いつまで私は止められているのかしら。これが一生か、一生がこれか、ああ、いやだ…仕方がない、やはり私も丸木橋を渡らずばなるまい。父さんも踏みかえして落ちてお仕舞いなされ、お祖父さんも同じことであったという。(にごりえ) 参考:お力(遊郭の女)と二人の遊び人の物語の中でのお力の言葉。 3月25日下級官吏の娘として生まる。駄菓子屋、小間物屋などしながら、貧しいものの悲しみと屈辱を描いた文学者。わずかに二十四歳で死んだ。
*桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)より
2010年3月27日(土)付朝日新聞「天声人語」より
|
|
一 毎日掃いても落ち葉がたまる これが取りもなおさず人生である。 田山 花袋(たやま かたい、1872年1月22日(明治4年12月13日) - 1930年(昭和5年)5月13日)は、日本の小説家。本名、録弥(ろくや)。群馬県(当時は栃木県)生れ。 尾崎紅葉のもとで修行したが、後に国木田独歩、柳田國男らと交わる。『蒲団』『田舎教師』などの自然主義派の作品を発表し、その代表的な作家の一人。紀行文にも優れたものがある
褐色の道路――砲車のわだちや靴の跡や草鞋の跡が深く印したままに、石のように乾いて固くなった路が前』長く通じている。……何処まで行ったらこんな路は歩かなくてよくなるのか。(中略)
軍隊生活の束縛ほど残酷なものはないと突然思った。……この病、この脚気、たといこの病は治ったにしても戦場は大いなる牢獄である。いかにもがいても焦っても、この大いなる牢獄から脱することはできぬ。(一兵卒)
5月13日死んだ日本の自然主義文学運度の主唱者、その代表的作家。しかもロマンチックな一面があった。主著『布団』『田舎教師』、『生』、『妻』など。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.81 ※参考:一兵卒 2020.05.13 ★プロフィル:田山 花袋は、日本の小説家。本名、録弥。群馬県生れ。 尾崎紅葉のもとで修行したが、後に国木田独歩、柳田國男らと交わる。『蒲団』『田舎教師』などの自然主義派の作品を発表し、その代表的な作家の一人。紀行文にも優れたものがある。 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.219~223 田中 義一 三申の影響で政界へ 結識とは「近付きになる、交際する」ことを意味するらしい。したがって、一人の人間にとって結識の相手は数多くあるともいえそうだが、たとえば小泉三申の場合、このことばを使っているのは、筆者の見たかぎりでは、二回きりのようである。一つは、幸徳(秋水)とは年齢感情での他共通点が多いものだから、自然親密になったのだろうが、これぞ私が江湖に結識した最初の一人である>(『暖窓漫談』、三申全集第四巻)で、もう一つは、「(明治四十五年春)私は初めて代議士となったが、その三、五年前から、軍人方面に結識する必要を感じ、海軍の八代(六郎)、秋山(真之)、陸軍の田中(義一)、宇都宮(太郎)、この人々に着目して交わりを通じ、毎月一回、赤坂の三河屋で宴集……」(『懐往時談』、全集に入らず)である。 小泉三申は、明治二十七年二十三歳のとき、自由党機関誌『自由新聞』の記者となった。社長の板垣退助は毎日出勤してきて社員を集めて『孫子』の講釈をする。ところが古参記者たちはききあきていて、よりつかない。結局、新米の三申と、もう一人の青年記者がきき役にまわった。 その色が黒く、背が低く、風采のあがらない男が幸徳伝次郎、かつては玄関番をしたことのある中江兆民から「秋水」という号をもらっていた。秋水は三申よりも一歳年長で話が合う。ともに文学青年で、つれ立って牛肉屋で飲み、烏丸の地獄屋で女遊びをした。月給はともに七円で、下宿代が六円、二人は収支のバランスをとるため、社の宿直を引きうけ、一晩一人前十六銭をかせぎ、また連載小説を引きうけて一回分二十五銭をかせいだ。 二人の『自由新聞』時代は一年ほどしかつづかなかったが、職場を異にしても親交はつづいた。やがて三申は『九州新聞』主筆として熊本に去り、秋水は『万朝報』につとめているうちに二人の思想的断層は深くなった。秋水が左傾化したのである。 明治三十六年、三十二歳の三申が『九州新聞』をやめて上京し、財界進出を意図して米相場などに手を出したとき、秋水は『万朝報』をやめて平民社を創立した。『週刊平民新聞』第一号には賛助執筆者の一人として三申のながあり、三十七年一月十日号の同紙に「病床噡語」(全集第四巻)を寄稿して「平民新聞を手にして覚えず落涙の滂沱たるを禁じ得なかった」と書いているが、同志的関係にはいたらず、むしろ背を向けて相反する立場に人生の座標をおいた。軍人と知り合う必要を感じたのもその路線における必然といえるかもしれない。上述した数名のうち、もっとも深く結ばれたのが田中義一である。 明治四十五年の「三、五年前」とはばく然としているが、五年前の四十年とすれば、田中は四十四歳、五月に歩兵第三連隊長、十一月に歩兵大佐となった年である。三年前の四十二年にすれば、一月に陸軍省軍事課長となった年で、その翌年に、大逆事件で秋水が逮捕され、田中は思想の悪化に対する方策として在郷軍人の創立をなしとげ、陸軍少将、歩兵第二旅団長となったのである。 三申の「結識」は、この左と右の両巨頭に対するもので、しかもそれは表面上、矛盾なくつづけられた。「今春君の忠告に従って一切の世事を抛ち著述の生活に入ろうと決心したときは、今思えば既におそかった……」という秋水の三申宛書簡は、この時期における両者の関係を物語る。三申は秋水に『通俗日本戦国史』の執筆をすすめ、この仕事によって「主義者」から立ち直らせようとした。秋水もこの気持ちをうけて湯河原の宿にこもり、その仕事を進めた。ただ、どういう理由からか、小泉は約束の金をわたさず、秋水は中途で中止して『キリスト抹殺論』を書いた。そして湯河原駅でつかまり、翌年一月死刑になるのである。秋水は刑執行の三日前にも三申に手紙を書き、三申は『キリスト抹殺論』の出版許可の意向を警視総監からきいて秋水に知らせてやり、また、墓碑銘を書いてやり、遺品遺稿は彼のもとにとどけられた。 一方、三申は田中を政治と結びつけることに努力した。「四谷の拙宅で橋渡しをして、二人(注、原敬と田中)を逢わせたのが、やがて田中が原内閣の陸軍大臣となり、後年政友会の総裁となる機縁ともなった」』(『懐往時談』)あるひは「度々赤坂辺に席を設け、党内の要人と田中との接近を図った」(同)と三申も語っている。決定的な事件は高橋是清の後任として、田中を政友会総裁に引っぱりだしたことである。田中の正伝は、「一体誰が彼を引きずりだしたか? 政界に引入れた張本人は三浦観樹、久原房之助(くはら ふさのすけ)であり、さらにこれを政友会に引っぱり高橋総裁の後任にもってくる道筋をつけたのは横田千之助といわれ、小泉策太郎といわれる。ルートは一つではなかったろう」(『田中義一伝記』下巻)というが、横田は小泉の親友であり、田中引き出しの策源地が三申にあったことはまちがいない。これが大正十四年五月のことで、田中は六十三歳、三申は五十二歳であった。そして二年目に、田中は内閣総理大臣になり、外相を兼任する。三申の喜びも察しられるが、意外にもその翌年、両者は離反し、三申は政友会を去ったのである。 原因は久原房之助の入閣問題にあった。「しかるに同氏(注、久原)登用に関し閣内の一部及び与党政友会内に異論が起った……党内に閣僚候補多数存在するにもかかわらず政界の一年生、商売人上りの久原を登用するのは情実に流れすぎるというのであって……反対論者は小泉策太郎」、「小泉の機知、文章は当時政界第一であったろが、首相は久原氏の人物をより高く評価した」というのが『田中義一伝記』の記述である。はたしてそうであったか。かつて鮎川義介は『日本経済新聞』紙上で、首相になった田中が「いずれは久原を総理にするつもりだから」と語り、「まず外相に擬したが……逓相の椅子があてがわれてあって、外相は田中が兼摂した」「その後、田中の動きは……どうやら外相の椅子のすわり心地が気にいったらしい……それに気づかぬ久原ではない、ある日、久原は私に同行を求めて田中邸を訪ねた。三人鼎座して話しているうち、久原は……田中の食言を責め……言いわけをきこうとせず椅子を振り上げて肉薄した」(『私の履歴書』第二四巻)と回想している。 一国の宰相に、椅子をふりあげて肉薄するという狂態の原因が、田中の「食言」にあるのか、あるいは多年のスポンサーだった事実をふまえての脅迫であるのか、その真相は不明だとしてもこういう関係の中に純粋の「人物評価」だけをもちこむのは無理である。一方、大逆事件はデッチ上げだといわれる、ということは、三申の結識と離反の中に、彼自身の人物のみならず、それぞれの時期におけるわが国の権力を解くてがかりがある、ということであろう。 2019.08.02 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.204~208 小泉 策太郎 『国民之友』読み開眼 小泉 策太郎が「三申」という雅号をもったのは十二、三のころだという。このころ俳句をはじめ、小学校の先生につけてもらったのである。この先生は元幕府につかえた漢学者で、幕府瓦解のあと天城山をこえて南伊豆に入り込んだ。そして子浦に安住し、小学校ができたたとき、その初代訓導になった。「三申」というのは、小泉少年の生まれた明治五年十一月三日午後四時というのが、申(さる)の年、申の日、申の刻にあたるところからつけたものだが、のち少年が政友会代議士となってからは、見ざる、聞かざる、言わざるの「三猿」の意にうけとられることもあった。政治家として、大いに見、大いに聞き、大いに言うくせに、あえて「三猿主義」を標榜するところが策士らしい、という見方による。 それはともかく、三申少年は大変な読書家であった。十三、四歳になると、為永春水や滝沢馬琴の作品を愛読した。小学校を出たとき、家が貧しいので進学できなかった。蘭学塾にはいろうにも、月十銭の謝礼を払う余裕がなかった。そこで子守をアルバイトにしながら、子供をおんぶしたまま塾の縁側の方から室内の講義の声に耳をかたむけるという工夫までした。東京に徒弟奉公にいったが一年でやめて帰校し、母校の先生となった。このとき生涯を決定する大事件がおきたのである。 二十五歳の徳富蘇峰が『国民之友』を創刊したのがこの年(明治二十年)二月である。これを読んで感激した静岡県庁の雇員山路愛山は蘇峰に手紙を出し、やがて蘇峰の庇護のもとに史論家としての人生コースが開けた話はのべた(六〇ページ)。小泉三申も、蘇峰に手紙こそ出さなかったが、大きな影響をうけた。のち岩波書店から『小泉三申全集』が出たように小泉三申は政治家という以上に史論家であり、文人であったが、その文書的開眼をしてくれたのが『国民之友』なのである。そして三申は手紙を書かず、個人的に恩顧をうけるということはなったのに、二人は不思議な糸に結ばれる運命にあったのである。 三申は、二十二歳のとき村上浪六の居候となり、作家を志して、『新小説』の懸賞小説に一等入選したこともある。ところが百円はもらえるものと考えた原稿料が十円だったため、これでは生活できぬと断念して三十三歳のとき『自由新聞』記者となった。このとき同僚に幸徳秋水、堺枯川、斎藤緑雨らがおり、とくに秋水とは終生の交りを結んだ。三申はこの新聞に『慶安騒動記』を連載して史論家として注目され、これを改題した『由比正雪』以下、『加藤清正』、『明智光秀』、『織田信長』が『偉人史叢』シリーズとして公刊された。このうち、とくに『織田信長』の一巻は徳富蘇峰の注目するところであったが、三申本人はそのことを知らなかった。彼にとって生涯の目標は政治家になることであり、文章は余技にすぎなかった。財界進出に転換して、新聞記者から米相場、石材売りこみにかわったのが三十二歳、衆議院議員になったのが四十一歳のときである。そして五十歳のとき、逗子の老竜庵にはじめて蘇峰を訪ねた。『国民之友』以来三十五年、『織田信長』以来二十四年の歳月が流れていた。 蘇峰はにこにことして迎え、 「いやもう先生のことは、よく知っています。先生の『織田信長』を熟読、敬朊しています」 といった。三申はびっくりし、これをお世辞だとうけとった。(さすがに蘇峰先生は老熟大成の域に達していられる。人をそらさぬ、ほどのいいことをいわれるものかな)と感心したのである。ところが蘇峰はふいと起って、ぎっしり本のつまっている書架から、さがしもせずに一冊抜きだしてきた。 「この通りですよ」 と示されたのをみて、三申はおどろいた。偉人史叢の一冊『織田信長』で、しかもところどころに付箋して、何か細かく書きいれてある。蘇峰は、そのような熟読、評価の体験をふまえて三申を「先生」とよんだのである。この真面目さが「文人」蘇峰の真骨頂であったわけだが、どこまで三申がそのことを理解したかは疑問であった。 「蘇峰翁は僕を叱って、何故文章に精進せずして、ろくでもない政治家になったかといわれます」ということを三申は「痴遊に寄す」という文章の中に書いている。この蘇峰のことばに自分が何と答えたかは書いていないが、文章全体はおのずとその回答となっている。三申は伊藤痴遊(仁太郎)が講談師として有名となり、政治家として世にあらわれなかったことを、余技が本技をしのいだ例として遺憾の意を表している。三申において人生の「本技」とは「政治家」となることであり、その意味において「文人」としての生涯は、第二義的な、余技の世界への陥没に他ならず、蘇峰の忠言もその意味では「片腹いたい」ということだったかもしれないのである。 しかし蘇峰の真意は「政治家」と「文人」の相互比較において、後者を高しとする価値体系から、三申に文章への精進をアドバイスしたのではなかったであろう。政友会代議士としての三申は「政界の黒幕」、「策士」のなを喧伝されている。そういうマキャベリ的世界への没入は、経国済民を本旨とする「政治」の邪道であり、そこに三申の才能が消耗することを愛惜したのではなかったか。 三申は、昭和三年五十七歳のとき、田中義一首相と所見を異にして、政友会を脱党した。この二年後の総選挙のとき、非常な苦戦をしたが、このとき蘇峰は応援のため、沼津、三島の演説会場に姿を見せたのである。「私もくだらぬ顔ですまされない。潜行して楽屋まで礼に出たついでに、先生の演説をぬすみ聴きしたのだったが、先生は昔山田武甫(やまだ たけとし)――熊本の自由党の開山です――の選挙応援をした後、二十年来か三十年来か、政治演説に出たことがないが、小泉が負けそうだときいて、久しぶりに出て来たというので、天下独歩の快弁をふるわれ、自分が小泉を相知ったのは、古今稀れなる英雄に紹介された。その人はすなわち織田信長である。信長がわれわれを親しくさせたと説きはじめられたのが、おかしくもあり、こそばゆくもあった」と三申は語っている。 この選挙は、政治家三申にとって最後のものであった。「政界風雲の策源地」として注目された往年の華やかさは消えて、書画、仏像に親しみ、文筆を友とする日常と変わった。彼はとくに西園寺公望に近づき、『随筆西園寺公』などを書いたが、やがてその仕事は中断した。策士の接近を警戒する園公側近が、彼の訪問をよろこばなかったためで、「本技」が「余技」の成就を妨げた、ともいえそうである。 2019.07.30 |

私たちの不安は、何一つ自発的に働きかけるようなものを持たないで、ただただ受身の位置にあることを暗示せらるところからくる。鋭いと思う言説の多くに接することはできても、真に私たちの心を動かしてくれるような、強い総合の力に遭遇しないところからくる。(板倉だより) 過ぐる半世紀を振りかぇつて見ると、封建時代の過去のものは、まだまだ私たちの内にも外にも活きている。……ある意味からいえば、私たちの眼前にある多くのものは封建時代の遺物の近代化に過ぎなかった。(板倉だより) この日大磯で死んだ文学者。「文学界」を創刊して、ロマン主義の先駆者として詩を書き、のち自然主義的な小説に移った。『破戒』 *桑原武夫編編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.139 2019.07.30 |

いまやらねば、いつできる、わしがやらねば、だれがやる 「こだわるな、こだわるな。人間本来、住むところなし。どこに住んでも心は一つ。仕事ができればそれでよい。 悲しいときには泣くがよい。辛いときにも泣くがよい。涙流して耐えねばならぬ。耐えた心がやがて薬になる。 わからなくても困る。わかりすぎても困る。百を越えても青二才。勉強勉強、人生すべて師なり。 七十、八十は鼻たれ小僧、人間ざかりは百から百から。わしらの人生、これからこれから。」 参考:井原市立 田中美術館
★日本の彫刻家。本名は平櫛倬太郎(ひらくし たくたろう)。旧姓は田中。岡山県井原市名誉市民(1958年)、福山市名誉市民(1965年)、小平市名誉市民(1972年)。
|
|
一 バラ二本、一本は花大にして、一本は小。大大をほこらず、小小をはぢず、力のかぎり咲けるが美しい。 『実践人四六〇号』より。 〈聞き手は聞いて育ち、話し手は聞いてもらって育つ〉 竹下 哲『心のうた』の中に引用されていた言葉より。 参考1:明治から昭和の教育者。兵庫県出身。 明治6年1月8日生まれ。小学校代用教員から東京高師付属小学校訓導となる。樋口(ひぐち)勘次郎に師事し、随意選題による綴(つづ)り方を提唱。大正14年公職をしりぞき、全国教壇行脚をして実践教育をつづけた。昭和26年12月9日死去。78歳。兵庫県出身。旧姓は小笠原。号は恵雨。著作に「綴り方教授」「恵雨自伝」など。 【格言など】自己生活内に題材を求めて自己に満足の出来るように書く、それ以外の何物もありません(「小倉講演綴方教授の解決」) 参考2:芦田教式(七変化(しちへんか)の教式とも呼ばれる)を創始。この数式を西山啓子先生が修士論文にされた。
「共に育ちましょう」
|
|
一 金がないから何も出来ないという人間は、金があっても何も出来ない人間である。 阪急グループ創始者である。
宝塚少女歌劇も始めた。小林は宝塚の舞台に惜しい女優でもその結婚引退を引き留めなかった。働く女性の結婚を考慮することが女性の関与してゐる事業を成功させる要訣(ようけつ)とみて、良い結婚相手の選び方まで指南している。
良人(おつと)を選ぶなら、自分の職業を楽しんで、邪念なく、朗(ほがら)かに働く青年を選びなさい。
|

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.114~118 蜷川 新 反体制精神を貫き維新をえぐる 小栗 忠順夫人道子の妹、すなわち播州林田藩主建部内匠頭の三女はつは、旗本蜷川 親賢にとついだ。 蜷川家は五千石の大身である。神田川小川町に上屋敷があり、敷地千七百坪、馬場五百坪、建坪七百六十坪で、三十畳の広間をはじめ部屋数は五十九もあった。小石川には下屋敷があり、敷地五千坪、ここに中二階の家屋があった。 維新の変動を迎えたとき、親賢は三十六歳、はつは三十一歳。小栗家に長女が生まれたのと軌を一にして蜷川家にも長女あかが生まれた。 将軍慶喜が退隠、徳川宗家を五歳の田安 亀之助(徳川 家達:いえさと)がつぎ、駿河、遠江、陸奥の一部を合わせた七十万石の大みょうとなった。亀之助が百人ほどの家来に守られて東京(西暦一八六八年七月十七日改称)を出発し、駿府(静岡)についたのが八月十五日である。 江戸占領軍が旧幕臣の屋敷没収命令を出したのは七月十六日である。このとき蜷川家の上屋敷は没収され、さらに十月下屋敷も没収されることとなった。武士としての親賢には、二つの道しかなかった。「帰順」して「朝臣」となるか、駿河に「無禄移住」するかである。親族の大みょう、高級旗本の中には「朝臣」となって没収を免れるものが多かったが、親賢は「旗本としての意地に生きることを決意した」(坂井誠一『遍歴の武家』)。 駿府移住を決意して家財道具を売ったところ、八千両になったというが、これは大したことである。騎兵頭の益田孝は、「帰商」を決意して小石川の家を売ろうとしたが一文にもならず、ようやくへっついの銅壺が三両二分に売れて、それをもって横浜へ行った、と語っている(『自叙益田孝翁伝』)。こういうドサㇰサで、二束三文にたたかれやすい情勢下に古道具で八千両にもなったということは、いかに蜷川家が裕福であったか、道具類が上等のものであったかを物語るようである。 蜷川家が裕福になった一つの理由は、側用取次の職にあったことらしい。大みょうたちが将軍のご機嫌伺をするには、この側用取次を通じなければならなかった。そこで大みょうたちは、定期的に進物をとどけた。目録には「御太刀一腰」とか「御馬一匹」とか書かれ、内容は黄金であったという。この「役得」によって蜷川家の財産はふくれたのであった。 親賢が使用人をつれて総勢二十人、東京を出発したのは明治元年十一月七日である。無禄移住者は総数三万余といわれるがそのほとんどは三千石以下の旗本、御家人、徒士であり、駿河藩の役人になった者をのぞくと、三千石以上の旗本は、蜷川と阿部邦之助(三千石)だけであった。 静岡で二女かつが生まれ、明治六年一月に初めて男の子新がうまれたが、誕生五日前目に親賢は熱病で急死した。未亡人はつは、あか、かつ、新の三児をつれて上京、神田五軒町の建部家に寄留した。すでに小川町の上屋敷はこわされて小学校が建っていたし、下屋敷は大学の植物園となっていた。旧幕臣の子女で、芸者、茶くみ女などになったものも多かったし、市ヶ谷見附の土手では首くくりが絶えなかった。こういう暗い雰囲気の中に、新は成長していった。少年の日、隣の一狂人が欅の大木の切り口を棒でたたきながら、 「天子の畜生! 日本政府の畜生!」 と叫ぶのを見て異様な感銘をうけた。 静岡の財産管理者から毎月二十円ほど送金してきたが、明治二十年突然打ちきられた。未亡人は十五歳の新たちと六畳、三畳二間しかない借家にうつった。新は苦学しながら第一高等中学校、帝国大学のコースを進んだが、同時に独特の反体制=反骨の精神も育っていった。一高時代、親友渡辺千冬(のち浜口内閣法相)、五来欣造と「真面目」という回覧小冊子をつくり、新は「華族論」を書いたが、その中には「余ㇵクロームウエルヲ愛シ、又足利尊氏ヲ愛ス……」という一節がある。それを評して渡辺千冬は「豈(あに)計ランヤ、幕下ふ平ノ士ハ、岳南(新の雅号)其ノ人ノ如キふ平児ヲ生マンㇳハ。……岳南ニススム、君ノ一生ヲ通ジテ之ノ主意ヲ忘ルルナカレ。注目シテ我ㇵ君ノ為スㇳコロヲ見ル」と書いた。まことに新の人生は、此の基本的姿勢で貫かれたのである。 大学生となった新は、内務大臣西郷従道に「国有土地下戻申請書」を提出し、没収された小石川下屋敷の返還を求めたが却下されたので、今度は内務大臣を相手に行政訴訟を起こし、これは八年目に棄却された。すでに韓国政府財政顧問となっていた新は、この判決をふ満とし、「全然事実ㇳ法理ㇳニ背反スルモノ……形式ハ裁判宣告ナリㇳ雖モ、実質ハ政略ニ基ㇰ行政処分」という批判文を知友に送った。 新は外交官試験をうけたことがある。試験官は石井菊次郎(のち大隈内閣外相)でフランス文を読まされた。新がスラスラと読むと、石井はその意味をたずねる。 「わかりません」 「何故か?」 「単語が二つわかりません。それで意味がとれないのです」 「教えてやろう」 「試験場に出てきて、知らない文字を教えられては私の不名誉です」 石井は怒っていった。 「それならば、もうよろしい」 不合格であったが、「いかにも旗本の子孫らしい気骨のある行動」と坂井誠一はほめている(前掲書)。 外交官にならなかった新は、国際法学者となり、法学博士となった。大正以降は、徳富蘇峰に望まれて同志社大学教授となり、国際法・外交史を教えるかたわら、国際赤十字連盟の仕事に貢献した。 昭和五年以降、駒沢大学教授以外の公職を退いて大磯の吉田元首相邸隣に閑居し、著述に専念し、敗戦を迎えた。そして沈黙を守ること七年、七十九歳のとき神田共立講堂で「国防の声と憲法蹂躙」という講演を終わったあと、猛然と著述活動をはじめた。わずか五年間に『愛国者への道』『天皇』『維新正観』等、十数冊出したのであるから、その仕事ぶりは壮者をしのぐというよりも何か異常な狂熱を感じさせる。無論、仕事の量でそうであるとともに、その内容のはげしさが目をみはらさせるのである。 ことに『維新正観』は、反国定教科書的立場で維新の醜悪さをあばき、「彼等は薩長藩閥政府を作ることによって、慶喜が自ら進んで放棄した権力を、天皇のなにかくれて詐取したにすぎない。彼等の眼中には天皇もなく、国もなく、人民もなかった」と書いている。頼山陽は、上杉謙信の心情を「遺恨十年」とうたったが、蜷川新の場合は「遺恨八十年」の感じがする。どうやら「明治百年」の背後には、「遺恨百年」があるようだ。 2019.07.30 |
|
文学者、評論家、啓蒙家、翻訳家。多くの外国語に通じて名訳を残した。号で、「上田柳村」とも呼ばれる。「山のあなたの空遠く 『幸』(さひはひ)住むと人の言ふ」(カール・ブッセの「山のあなた」)や、「秋の日の ヴィオロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し」(一般には「秋の歌」)などの訳詞は、今なお、広く知られている。 ▼山のあなた カール・ブッセ 上田敏訳 『海潮音』より 山のあなたの空遠く 『幸』(さひはひ)住むと人のいふ。 噫ああ、われひとと尋とめゆきて、 涙さしぐみ、かへりきぬ。 山のあなたになほ遠く 『幸』(さひはひ)住むと人のいふ。 ▼『落ち葉』 ポオル・ヹルレエヌ(上田敏訳) 秋の日の ヴィオロンのため息の 身にしみてひたぶるにうら悲し 鐘の音に胸ふたぎ色かえて涙ぐむ 過ぎし日の思い出や げにわれはうらぶれて ここかしこさだめなく 飛び散らう落葉かな 2013.04.09 |
|
渡辺教育総監(渡辺錠太郎大将):1936(昭和十一年)2月26日、所謂二・二六事件で陸軍将校に殺害された。次女の渡辺 和子さんは目撃されている。 ▼教育総監の次女、渡辺 和子さんも、犬養毅(元首相)さんの孫、道子さんもキリスト教を信仰されている共通点に五・一五事件、二・二六事件に関連が彼女たちに影響を与えたのでははないかと私は感じます。
関連:渡辺 和子
|
|
青い眼鏡をかければ、世の中がすべて青く見え、赤い眼鏡をかければ、すべてが赤く見える。 世の中は自分の心の反応である。 人を憎めば人もまた自分につらく当たり、人を愛すれば人もまた自分に親しむのである。 参考:精神医学者―森田療法で有名。 |

「幸と云ひふ幸と云ふも皆比較的のもので、自分以上に幸福のもの、ふ幸のもののある事をほんほんうに体得せよ。」 小平波平(おだいらなみへい)は日立製作所の創立者。電気立国の基礎を築いた。小平は学生時代から「模倣」が嫌い。「模倣で満足する限り日本の工業は論じるに足りない」と「自力で作る」ことにこだわった。 明治は、日本人が、未来は変わる、自分の手で変えると、信じていたじだいである。(中略) 小平波平は世話焼き。結局、日本の電気産業なりたちの世話を焼いたといっていい。「人を世話するなら徹底的に気持よくしなくては駄目。飼い犬に手を噛まれたなどと泣き言をいうくらいなら初めから世話せぬがよい」といっている。長生きの秘訣は「人に迷惑をかけるな。出来る丈けの世話をせよ。何処までも親切に徹底せよ。恩は忘れてはならぬが恩を売ってはならぬ」を守ること。 ▼冒頭のように幸福と不幸を達観できれば「諦めの修養も出来る。厭な奴に頭を下げずに安眠が出来て長生きが出来る」と語った。(『小平さんの想い出』)。日立も今年で100年になる。
*「磯田道史の この人、その言葉」朝日新聞2010.08.07 より。
|
|
1、「教師の真の偉大さは、その完成した人間学問になくて、向上して止まざる不断の努力と情熱とにある。教師の権威は、この努力から生じてくるのである。」 2、「書物を買うにあたつては、十年経つてもその値打ちの変わらぬ書を――。」 3、われわれは、何をもって同志としての共通的な実践ケ条と考えたらよかろうか (1)「人生二度なし」 (2)「ハガキ活用の練達者」 (3)「一日読まざれば一日喰はず」 (4)「一人雑誌」(ハガキ通信) (5)「下坐行を怠らぬこと」 4、「人間五十にもなったら、何らかの意味で、この世に必要な人物とならねばならない」 ★プロフィル:三浦 修吾は、日本の教育者である。 福岡県浮羽郡吉井町若宮出身。 福岡師範を卒業後、東京高等師範に進学し、その英語科を卒業。鹿児島師範を経て、姫路師範に転出。鹿児島師範当時の教え子に、玉川学園を創立した小原国芳がいる。同付属小学校主事となる。姫路師範在職2年で結核に罹り、1915年退職。『生を教育に求めて』。 |
|
柳田 國男 東京帝国大学法科大学政治科卒業 代表作:『遠野物語』(1910年)、『蝸牛考』、『桃太郎の誕生』、『海上の道』 主な受賞歴:文化勲章受勲(1951年)、正三位勲一等旭日大綬章受勲 柳田 國男は、日本の民俗学者・官僚。明治憲法下で農務官僚、貴族院書記官長、終戦後から廃止になるまで最後の枢密顧問官などを務めた。1949年日本学士院会員、1951年文化勲章受章。1962年勲一等旭日大綬章(没時陞叙)。 〔日本人とは何か〕という問いの答えを求め、日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行した。初期は山の生活に着目し、『遠野物語』で〔願わくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ〕と述べた。日本民俗学の開拓者であり、多数の著作は今日まで重版され続けている。 以下、余技の世界小島直記『伝記にみる 風貌姿勢』(竹井出版) P.91~96 より 柳田柳叟、小倉簡齊、江口香邨(こうそん)というなじみがうすいとおもわれるならば、それは雅号ののせいだろう。柳叟柳田 國男は農務省にはいり、貴族院書記官長をやめたあと、朝日新聞客員などをしながら〔日本民俗学〕を創建した。柳叟は俳号である。 簡齊小倉正恒は、山口県参事官をやめて住友にはいり、総理事をへて第二次近衛内閣国務大臣、第三次近衛内閣大蔵大臣、南京国民政府経済最高顧問をした。漢学にかけては財界最高、川田順は〔若きらよ聞きておどろけ先生は郭沫若を友としたまふ〕とよみ、貝塚茂樹は[中国をはじめアジア諸国と文化的な親縁関係を維持し、理解を深めねばならないといい、慨然として、郭沫若旧蔵書をもとに『アジア文庫』を創設された簡齊先生の信念ははるかに時流を抜いていた。われわれは実業界における最後の漢詩人にして最上の漢学の理解者を失って愛惜にたえない](『日本と日本人』)と書いた。『小倉正恒談叢』一巻が残っている。 香邨江口定條は、東京高商で教鞭をとったあと第百十九国立銀行にはいり、三菱に転じ、総理事をへて満鉄副総裁。満州事変、そしてその直後に上海事件がおこると〔これはナポレオンのモスコーだ。とてもものにならん〕といって辞職した。このあと沼津の香貴山下の別荘で、とくに〔万巻の書を蒐めて好書に目をさらし〕〔«平生愛する所青山故人名草奇書»という好語が剣掃にあるが、翁の共鳴禁ぜぬもの〕(安岡正篤『東洋的志学』)で、悠々自適の晩年を送った。 すなわち、三人とも読書を余技としたひと、わが敬愛の理由は第一にここにある。ところが、柳田国男の場合だけ〔余技〕は変じて〔本技〕となった。その〔民族学者に転進した〕(長谷川如是閑)いきさつ、事実の奥にあるものを諸家のことばによって探ってみたい。[先生のような頭のもち主と先生ような境遇がなければ、こういう学問と趣味が完成されなかったであろう](西脇順三郎)。その〔頭〕の内容に絶倫の記憶力がある。[たった一度しか訪れない土地の事情を、手にとるように話される](村治夫)。[何百というそうした人がいたろうものを、名刺を一見したばかりで、ずばりその人をなざされた]。(奈良環之助) 加えて抜群の努力家であった。[先生の読書は、どんな本でも一頁から全部読むという方法だった](宮良当壮)。[何十巻もある大日本資料などみておられたが二日に三、四冊読んで抄出されるすばらしさ、その本を拝見するとその本はすでに読破されていて、どの頁にも記号や紙が貼られているではないか。それをまた読まれ、抄出される](大月松二)。 [私がなにより驚いたのは、その本のはしがきから索引まで、二二三頁のその一頁残さず、赤インキで、――とか、?とか△とかVのしるしがついていたことだった](富本一枝)。〔一番敬服したのは、その一刻もおろそかにしない研究態度だった。成城の家が新築されたのは昭和二年の夏の終わりだった。国男氏が夫人に向って、≪ぐずぐずしていては勉強ができない。ぼくだけ独り先へ引越すよ≫といわれているのを傍できいて私は一寸びっくりした。その言葉通り、氏は家族達より五、六ケ月早く引越された〕(飯島小平)。〔日本中で足跡を印しない"村"は五つくらいだという"神話"を先輩から聞かされた〕(荒垣秀雄)。
〔貴族院書記官長を徳川さんと喧嘩をしてやめたりした挿話を、故伊沢多喜男さんからうかがったこともあった〕(飯島衛)。〔上役というのは徳川第十六代将軍(徳川家達)といわれた人で貴族院議長であった。その上役が大まかに鞄持ちを命じたので≪自分は柳田国男である≫という誇りをもって鞄を持つことを断って辞職した〕(井伏鱒二)。わが国には〔民俗学〕ということばすらないという状況の下で孤軍奮闘がはじまる。〔学問は誰のため何のためにするのか……日本の同胞、一般常民のためにするのだという心に徹していられた〕(和歌森太郎)。その精進は、すぐれた若者たちの心に灯をともした。〔当時私は落語にとりつかれていて、よく四谷のきよし亭に小勝をききに出かけたが、その帰り途に、道路から一つ空地を隔てた向うに先生の書斎の電灯がついていて、その電灯の下に御勉強中の先生の頭が浮かぶように、窓越しに見えているを、何か気がとがめる思いをして眺めながら通り過ぎた〕(池上隆祐)。〔先生の書斎はまだ明りがついていて……いつものように、窓ごしに先生の横向きの姿が見えていたので、言葉は悪いが≪いるな≫と思った。この≪いるな≫というのは自分も勉強をしなければならないという意味と結びついていた〕(中村哲)。 〔大正十年一月は此為にも永く記念せられる〕(『妹の力』の〔此為〕は、位階勲等でも別荘新築でもなく、沖縄にわたって〔オナリ〕ということばが〔姉妹〕を意味することを知ったからであった。ここにこの人の真骨頂、そして〔余技〕が〔本技〕にならざるを得なかった理由があるようだ。 昭和三十七年八月八日、壮大な生涯に幕がおりた。米寿祝いの三月後のことであった。 2022.02.22記す。 |
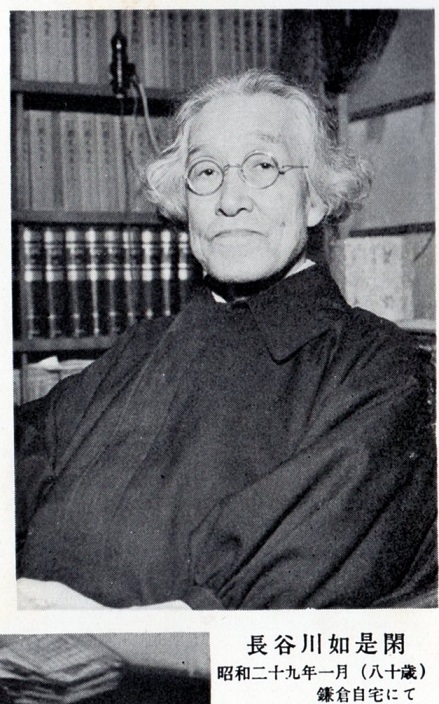
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.154~158 長谷川如是閑(1875~1969) 記者時代に羯南の影響を受ける 「羯南の識見と文章は『羯南文録』によってその思想の根底をも窺うことができるが、僕の最も遺憾に思うことは、彼をして最もふ得意なる経営のことまで引き受けて、その記者たる本分に専念せしめ得ざりし一事である。彼はみょう利に恬淡(てんたん)というよりも、みょう利を卑しむ孤高の国士である。それが社長であり、主筆であるために、彼の天分を十分に発揮することができなかった「と語ったのは古島一雄である。 羯南の文業については二つの見解があった。「僕は子供のとき、日本新聞を愛読したが、陸実という人は全集なんか読んでみると、どうも後世に残るようなものを書いたかどうか知らんと思うな。時事論文はあるけれども、これといってまとまつたものはないですね「と否定的だったは馬場恒吾である。(『三宅雪嶺博士と明治・大正・昭和を語る』日本評論社、昭和十一年十一月号)。 これにたいして、「私はそのころそういう種類の本を広く読んだのではないが、そのころまでの新聞記者や学者の本で、羯南のこの数冊(注、『近時政論考』『近時憲法考』『国際論』)に匹敵するほど学問的のものは、小野梓の『国憲汎論』の他には見た覚えはない。……全く独自の見地……その後の祖述学者のそれとはちがって、たしかに羯南自身のもの」と高い評価をしたのは長谷川如是閑であった(『ある心の自叙伝』)。 このほか彼は「青年の私は羯南のこの『憲法考』と『政論考』とを読んで、『日本』一派の立場に自分を置くようになったのであったが、もし羯南に自由主義にたいするそのような理解がなかったら、私はあこがれの『日本』であったにしろ、恐らくその一派におのれを投じることを躊躇したであろう」と書き、また「私がもしも『日本』にはいる前に、その羯南の『国際論』を読んでいたら、その論旨よりも、そのニュアンスが、私の当時の気分と合わないために、私は『日本』の同人たることを躊躇したであろう」とも書いている。 評価は二つにわかれたようであるが、これは前書を高しとし、後書を低しとするものとはいえないであろう。前書(『政論考』等)と後書(『国際論』)の執筆時点には、約三年のズレがあり、その思想的推移についてゆけなかった、ということであって、原理原則に忠実であろうとした若き如是閑の潔癖感と批判力を示すものであったとしても、羯南の本がつまらない、という意味ではないであろう。価値があると思えばこそ、それを相手としたはずであった。 さて、この如是閑こと長谷川万次郎が東京・深川木場の材木商の次男として生まれたのは明治八年であるから、羯南よりは十五歳下、古一念(古島)よりは十歳下、馬場とは同年だったことになる。病身で、三十歳までのいのちと医者にいわれたが、その如是閑ひとり今なお健在であるのだから、人間の寿命はわからぬものである。 万次郎の父は、論説を主とする「大新聞」をとり、「小新聞」はいかがわしい記事があるから、というのでとらせなかった。そこで子供の万次郎も、ほとんどふりがな新聞を読まず、反面、羯南、雪嶺などの名前には親しみをおぼえていた。 杉浦重剛の東京英語学校(のち日本中学)をへて、東京法学院(今の中央大学)にはいったが、弁護士を目標にしないで、新聞記者を目標に勉強した。学校は半日なので、半日は図書館――それもおもに上野図書館に通った。マルクスの〚資本論〛(英訳)も借りてみたが、歯が立たなった。 そのころ、浅草花屋敷まで経営していた父が事業に失敗した。万次郎は一時休学して、日給四十銭の海軍省雇員となったが、肋膜にかかって、これをやめ、しばらく療養したのち、二年の編入試験をうけて法学院にもどった。学生時代は、名刺の肩書に「飲食の交際はお断申候」と刷りこんで友人にわたすほど、つきあいぎらいであった。 卒業しても、四年間ブラブラしていた。父は、弁護士の試験準備をしているものと思いこんでいたが、彼自身は「借家のありもせぬ床の間を背にして一日中父は端座し、その二階では、飯の種にもならぬことを考えながら、椅子にかけて一日中海を見ていた」(前掲書)と書いている。じつは歴史と古典に打ちこんでいたのである。日本の古典は博文館の普及版によったが、「直ちにボロボロになるので、二十銭の安本でも、新しく買う余裕もない生活だったので、私はその数十冊を、一々和装の表紙をつけて、自ら製本した。……それを見ると、いつも当時の貧苦と闘いながらの読書を思い出して、涙に目が曇る」という述懐は胸を打つ。 彼はのちに、「万葉集における自然主義」という論文を書き(『改造』八年一月号)、「進歩的な史学者も進歩的な国学者もまだこの領域ではどれほども活動するにいたっていない時期に、これだけ鋭い古代社会批判をこめた万葉集把握はほとんだ例がなく(津田左右吉はべつとして)、読者にきわめて強烈新鮮な刺激を与えた」(小田切秀雄『現代文芸評論集』(一)解説)といわれる業績の背後に、こういう努力が積み重ねられていたのであった。 就職運動は何もせず、友人はこれを評して、「君という男は、弓を引いたって、的をねらんじにゃねえ、いつまでもただ満を持するてやつで、引っぱったまま的が矢の先にくるのを、いつまでも待っているんだと」といわれた。 浪人二、三年目ごろ、匿名で『日本』に投書した中間読物が縁となって古島一雄らに知られ、三十六年の秋、打ちあわせのために社をたずねると、「いよいよ君に社にきてもらうことになった」と古島にいわれた。 「それはどうも」といったものの、その帰途、あともどりしてことわろうかと迷い、そのままとなった。 入社翌年に、羯南は欧州漫遊から帰ってきた。「文章も文章だが、何よりも羯南の人をひきつけたのは、その人柄だった」「久しく別れていたおじさんか何かに出会ったような、なつかしさを感じて、それだけで『日本』の記者になった幸福をさえ感じ、あのときあともどりしないでよかったと、帰りがけにあらためて思った」。 明治三十九年、羯南は病気で倒れ、『日本』を伊藤欽亮に譲渡し、翌年九月、鎌倉で長逝した。 伊藤新社長は、時事新報編集局長のキャリアもあり、自信満々三宅雪嶺の文章にまで加筆したため、社員は承服せず、古島上在中に表題『日本』を勝手に変更するにおよんで連結辞職し、雪嶺の雑誌『日本人』にうつって『日本及び日本人』と改題した。如是閑が行をともにしたことは書くまでもない。 参考:『昭和文学全集・第三十七巻』長谷川如是閑集・大内兵衛集・笠新太郎集(角川書店版)昭和二十九年五月三十日 初版発行 「ある心の自叙傳」「日本新聞のころ」 の記事あり。 2019.06.10記す。 |

▼渡辺淳一『遠き落日(上)(下)』(角川文庫)より 一九一五(大正四年)野口英世は帝国学士院恩賜賞の受賞が決まった。日本で授賞式があるから出席されるようにというアメリカにいた彼に連絡があった。まさに故郷に錦をかざる絶好のチャンスであった。血脇守之助はじめ、日本にいる知人たちは、みな、英世は喜び勇んで帰国するものと思っていた。 だが英世は帰らなかった。理由は、単に忙しくて時間をとれない、というだけのことである。英世はそれを守之助に報らせ、お祝いにきた日本記者クラブの面々にも伝えた。 ▼この恩賜賞受賞が決まった翌月、石塚三郎はは猪苗代湖の撮影会のあと、三城潟(さんじょうがた)によって、英世の母シカの写真を撮った。石塚はかつて高山歯科医学院で、英世と一緒に玄関番をしていたが、学院を卒(お)えたあと越後長岡で歯科医院を開業し、その地方の有力者となり、代議士になっていた。 石塚はこの写真を、近況報告をかねて英世に送った。 「是非一度帰ってきたらいい、お母さんもこんなに年齢をとられた」 写真の母はつぎはぎだらけの袷(あわせ)に、モンペをはき背を丸めて写っていた。英世が別れた当時より瘠せて小さくなり、髪の半ば以上が白くなっている。このときシカは六十二歳になっていた 「お母さんは相変わらず苦労している。この写真を見て、誰が医学博士・理学博士野口英世氏の母と思うだろうか。このお母さんのためにも、ぜひ帰ったらどうです。人々のあいだに恩賜賞受賞の記憶が新しいいまこそ、故郷に錦をかざる絶好の機会です」 この写真とともに母シカが自ら書いた手紙が同封されていた。 おそらくチビた鉛筆で、一字一字たしかめながら書いたのであろう。平仮なと片仮なまじりの稚拙な文章である。だがそのなかに母の子を思う真実があふれている。母からの子に宛てた手紙として、まさに名文中の名文といえる。
▼英世は迷った。正直いって、母の写真にはショックを受けた。まだまだ元気だろうと思っていたのが、老いて子供のように小さくなっている。青年期から壮年期に向けて、英世が逞しくなったのに対して、母はその分だけ確実に老いたようである。
「帰ったほうがいいだろうか」英世はメリーに相談してみる。
「会いたいのなら帰ったほうがいいわ。でもお金はどうするの」
このとき年収五千ドルも貰いながら、ノグチ家は相変わらず余裕がなかった。ときにメリーがヒステリーをおこしてビールを飲んだり、手当たり次第に買い物をすることがあるが、そんなことは知れていた。問題なのは、やはり英世の浪費癖だった。五千ドルももらい、差し当たり債鬼に悩まされることもないだけに、英世はますます気が大きくなっていた。友人とレストランなどに行っても、メニューもろくに見ずに、のっている料理すべてをもってこいなどと注文する。(中略)
感想:この文章では「野口英世の母」を取り上げました。
▼私も会社勤めをしていたとき、めったに家に帰らなかった。あるとき、たまたま帰郷したとき、伯母から「お前のお母さんは帰ってこないので淋しがっているよ」と、言われた。どなたのお母さんも、自分の子供にいつでも会いたがっている気持ちは変らないと思います。
参考1:野口英世記念館 記念館のご好意によりリンクのお許しをいただきました。
参考2:恩賜賞の野口英世とノーベル受賞者利根川進の二つの研究所
私事:アメリカ旅行ー第一回目ー
関連:奥村鶴吉
★プロフィル:野口 英世は、日本の細菌学者。福島県耶麻郡三ッ和村出身。 猪苗代高等小学校卒業、済生学舎修了後、ペンシルベニア大学医学部を経て、ロックフェラー医学研究所研究員。細菌学の研究に主に従事し、黄熱病や梅毒等の研究で知られる。
2013.7.12。
|
薄田泣菫「自然随筆」

薄田泣菫 略歴 「インターネット」 浅口郡大江連島村(現倉敷市)出身の詩人。1877(明治10)年5月19日~1945(昭和20)年10月9日。本名は薄田淳介。岡山中学を中退し、1894(明治27)年上京、上野の図書館で独学する。1897(明治30)年、雑誌「新著月刊」に『花密蔵難見』を発表し文壇に認められる。1899(明治32)年には第一詩集『暮笛集』(金尾文淵堂)を出版し好評を得、その後も相次いで詩集を出版した。1906(明治39)年に出版された『白羊宮』(金尾文淵堂)は、古典浪漫主義の詩の絶頂に達したと評価され、日本詩壇史上にそのなをふ滅のものとした。 ほかに『ゆく春』(金尾文淵堂書店 1901年)、『二十五弦』(春陽堂 1905年)、『泣菫詩集』(毎日新聞社 1925年)などの詩集がある。1915(大正4)年から大阪毎日新聞夕刊に連載した随筆『茶話』が好評を博し、以後随筆家として活躍する。 主な随筆集として『泣菫文集』(大阪毎日新聞社 1926年)、『艸木蟲魚』(創元社 1929年)がある。戦争末期に疎開していた郷里連島の生家でその生涯を閉じた。
『薄田泣菫全集』(全8巻 創元社 1938-1939年)が刊行されている。
厄神社(倉敷市連島町西之浦)と長法寺(津山市井口)に詩碑があるほか、倉敷市連島の生家は「薄田泣菫生家」として整備されている。 泣菫の由来 明治30年20歳の時、文芸雑誌『新著月刊』に「花密蔵難見〈はなみつにしてみえがたし〉」と題して長短13編の詩を発表、高い評価を得ています。この時、初めて泣菫の号を用いています。 「インターネット」 松浦澄恵著「薄田泣菫―詩の創造と思索の跡―」を読んで、「泣菫」という雅号の由来がオスカー・ワイルド作「キーツの墓」という詩にあることを知りました。 オスカー・ワイルドといえば、アイルランド出身の詩人、作家、劇作家。 彼の戯曲『ウィンダミア卿夫人の扇』を原作として、舞台を美しい景色のアマルフィに移した映画『理想の女』は感動ドラマでした。 また『幸福な王子』という童話も書いているのですが、このお話は須賀敦子さんや皇后美智子様が愛読された山本有三編『日本少国民文庫 世界名作選(二)』に収められています。 さて松浦澄恵著「薄田泣菫」の「キーツの墓」からです。 オスカー・ワイルドは尊敬していたキーツの墓に詣で、キーツの死を悼んで「キーツの墓」を作詩しました。その詩で墓を取り巻くように朝な夕なに露を含んで咲くすみれを次のように謡っています。 “ いま その墓をおおう糸杉も 葬いのイチイもないが 露にぬれて すすり泣く やさしのスミレが 白骨のうえに織る とわに 花咲く環を ” 熱烈なキーツのファンであった泣菫は、英詩集の中からワイルドの「キーツの墓」をみつけ、深い共感から泣く菫(すみれ)と書かれた泣菫を雅号としたようであると述べられています。 この「キーツの墓」の詩が生まれた年は、奇しくも泣菫の生まれた明治十年でした。泣菫はこの不思議な縁に自分はキーツの生まれ代わりになろう。和製キーツになって日本の近代詩をキーツに倣って完成させようとしたそうです。 最後に 「泣菫の雅号の重要な発見は、成城大学 松浦暢名誉教授の半世紀を越える長い、キーツと泣菫の、研究の中で成されたものである」 と記されていました。 参考:薄田泣菫「自然随筆」 2017.08.30。
薄田泣菫「自然随筆」
長い文章なら、どんな下手でも書く事が出来る。文章を短く切り詰める事が出来るようになったら、その人は一ぱしの書き手である。 『艸木虫魚』 柚の木の梢高く柚子の実のかかっているのを見るときほど、秋のわびしさをしみじみと身に感ずるものはない。豊熟した胸のふくらみを林檎に、軽い憂鬱を柿に、清明を梨に、素朴を栗に授けた秋は、最後に残されたわびしさと苦笑とを柚子に与えている。苦笑はつよい酸味となり、わびしさは高い香気となり、この二つのほかには何物をももっていない柚子の実は、まったく貧しい秋の私生児ながら、一風変った秋の気質は、外のものよりもたっぷりと持ち伝えている。 柚子は世間のすねものである。超絶哲学者の猫が、軒端で日向ぼこりをしながら、どんな思索にふけっていようと、また新聞記者の雀が、路次裏で見た小さな出来事をどんなに大げさに吹聴していようと、彼はそんなことには一向頓着しない。赤く熟しきった太陽が雑木林に落ちて往く夕ぐれ時、隣の柿の木の枝で浮気ものの渡り鳥がはしゃぎちらしているのを見ても、彼は苦笑しながら黙々として頭をふるに過ぎない。そこらの果樹園の林檎が、梨が、柿が、蜜柑が、一つ残さずとりつくされて、どちらをふり向いて見ても、枝に残っているものは自分ひとりしかないのを知っても、彼は依然として苦笑と沈黙とをつづけている。彼は自分の持っているのは、さびしい「わび」の味いで、この味いがあまり世間受けのしないことは、柚子自らもよく知っているのである。 むかし、千利休が飛喜百翁の茶会で西瓜(すいか)をよばれたことがあった。西瓜には砂糖がかけてあった。利休は砂糖のないところだけを食べた。そして家に帰ると、門人たちにむかって、 「百翁はもっとものがわかっている男だと思っていたのに、案外そうでもなかった。今日西瓜をふるまうのに、わざわざ砂糖をふりかけていたが、西瓜には西瓜の味があるものを、つまらぬことをしたものだ。」といって笑ったそうだ。もののほんとうの味を味おうとするのが茶人の心がけだとすると、枝に残って朝夕の冷気に苦笑する柚子が、彼等の手につまれて柚味噌となるに何の不思議はない。「わび」を求めてやまない彼等に、こんな香の高い「わび」はないはずであるから。 徳川八代将軍吉宗の頃、原田順阿弥という茶人があった。あるとき、老中松平左近将監の茶会に招かれて、懐石に柚味噌をふるまわれたことがあった。その後幾日か経て、順阿弥は将監にあいさつをした。 「こないだの御味噌は、風味も格別にいただきました。さすが御庭のもぎ立てはちがったものだと存じました。」 「庭のもぎ立て。」将監は不審そうにいった。「なぜそんなことがわかった。」 順阿弥は得意そうに微笑した。 「外でもございません。お路次へ上りましたときと、下りましたときと、お庭の柚子の数がちがっておりましたものですから。」 それを聞くと、将監は 「油断もすきも出来ない。」 といって、にが笑いしたそうである。 ものごとに細かい用意があるのはいいものだが、路次の柚子を数えるなどは、柚味噌のわびしい風味をたのしむ人の振舞とも覚えない。こんなことを得意とするようでは、いつかは他人のふところ加減をも読みかねなくなる。P.11~13 とうがらし(2) 青紫蘇、ねぎ、春菊、茗荷(みょうが)、菜っ葉――そういったもののみが取り残されて、申し合せたように青い葉の色で畑の健康を維持しているなかに、一株の唐辛が交って、火のしずくのような赤い実を点在させているのが眼についた。 「舞台では、なるべく赤い花をつかわないようにする。――これは脚本家が何よりも先に心がけなければならぬことである。強い赤の色は、どうかすると観客の注意を乱していけないから。」 これは舞台監督として聞えたダヴィッド・ベラスコの言葉であるが、この監督が折角そういって気をつけているのにもかかわらず、唐辛は平気でトルコ人のような赤い帽子を被って舞台に立っているので、青一式の周囲の平和が、お蔭でどのくらい引っかきまわされているかしれない。 唐辛は怒っているのだ。 唐辛よ。お前は何をそんなに怒っているのか。もっと平和な気持になって、御近所の衆と一緒に静な秋を楽しんだらどうだろう。トルコ人の被りそうなそんな赤帽子は腋の下にでもそっとおし隠したらいいではないか。 唐辛はむっとしている。 唐辛は皮肉家だ。生れつきするどい皮肉家だ。彼は自分にさわるものには、誰にでも容捨なく持前の皮肉を投げつける。彼には「わさび」や「からし」のようなユウモリスト達が、相手に辛い皮肉を味わせながらも、同時にまた眼がしらに涙を浮べて笑いころげさせる滑稽味が欠けている。彼はどこまでも単純だ。感情が激越だ。単純で感情が激越なればこそ、皮肉家なのである。 自然界のあらゆるものは性格をもっている。その性格にはそれぞれ変化があり、打開がある。たとえば柿や栗などは、初めのうちは渋いが、終いには甘くなる。蜜柑や杏のようなものは、初めのうちは酸っぱいが、終いには甘くなる。これらはそれぞれの性格の成長であり、飛躍である。悔悟であり、新生である。そんななかにたったひとり唐辛のみは、最初から終りまで同じ「からさ」の持ち続けである。何の変化もなく悔悟もない一本調子の生活ほど、気をいらだたせるものはない。日を重ねるにつれて唐辛の癇癪がいよいよ手におえなくなり、その皮肉がますますするどくなるのに何の不思議があろう。 かくして唐辛は、いつもあんなにぷんぷん怒りどおしに怒っているのである。そして偉大なる太陽もそれをどうすることが出来ないのだ。 今はもう三十年のむかしにもなろう。私が二十歳足らずの頃、早稲田鶴巻町のある下宿屋に友達を訪ねたことがあった。狭い廊下を通りかかると、障子を明けっ放しにした薄ぎたない部屋に、一人の老人が酒を飲みながら、声高に孟子を朗読しているのがあった。机の上には、小皿に唐辛を盛ったのが置いてあって、老人は時々それをつまんで、鼠のように歯音をたててかじっていた。 「誰かね、あの老人は。」 「あれが田中正造だよ。鉱毒事件で名高い……」 私はそれを聞いた瞬間、あの爺さんのはげしい癇癪を、唐辛のせいのようにも思ったことがあった。P.14~16 かまきり(3) 秋草のなかにどかりと腰をおろして、両足を前へ投げ出したまま日向ぼっこをしていると、かさこそと草の葉を伝って、私の膝の上に這いのぼって来るものがある。見るとかまきりだ。かまきりはたった今生捕ったばかしの小さな赤とんぼを、大事そうに両手でもって胸へ抱え込んでいる。 哀れな犠牲だ。私はかろく指さきでその赤とんぼの羽に触ってみた。あわよくば助けてやりたかったのだ。かまきりは立ちとまった。要らぬおせっかいを癪にさえたらしく、胸をそらして身構えた。私はまたとんぼの尻尾に触ろうとした。それを見たかまきりは、一足しさって高く右手の鎌をふりあげた。私はまたとんぼの頭を小突いた。その一刹那かまきりは赤とんぼをふり捨てて、両手の鎌をふりかざして手向って来た。私は指さきでその草色の背を押えた。処女(きむすめ)が他人に肌を弄られたような無気味さと恥辱とに身をふるわしながら、かまきりはいきなり私の指に噛みつこうとした。私はかろくそれを弾き飛ばした。よろよろとよろけた虫は、両脚をつよくしっかりと踏みはだかって、やっと立ち直ったかと思うと、すぐまた鎌を尖らして来た。 「なかなかしぶとい奴だな。それじゃ、こうしてくれる……」 私はすきを見て、相手の細っこい首根っこを両指につまみあげようとして、その瞬間自分が今争っているのは、草色の背をした小さな秋の虫ではなく、私自身の胸の奥に巣くっている反抗心そのものであるような気がしたので、そのままそっと指を引っこめてしまった。 「反抗」の精霊よ。押えれば頭をもち上げたがる「反動」の小さな悪魔よ。澄みきった清明な秋の心の中にすみながら、お前は生れおちるとから死ぬるまで、一瞬の間も反抗と争闘との志を捨てようとはしない…… 馬を見よ。馬はあの大きな図体をしながら、人間にはどこまでも従順で、いいつけられたことにはすなおに朊従している。ある学者の説明によると、馬があんなに人間に従順なのは、ひとえにその眼の構造によることで、馬の眼は人間の眼よりも二十二パアセントだけものを大きく見せるように出来ているので、五尺五寸の人間は馬の眼には六尺七寸以上に映ることになる。それゆえにこそ馬は人間におとなしいので、もしか馬が人間のほんとうの大きさを知ることが出来て、芝居の「馬」のように自分の背で反身になっているものが、必ずしも主役の一人とは限らないことを知ったなら、馬は主人を鞍の上からゆすぶり落して、足蹴にかけまいものでもないということだ。馬にこんな不思議な眼を授けた自然は、かまきりにはかなり鋭利な二つの鎌と一緒に、しぶとい反抗心を与えてくれた。これあるがゆえに、お前はあらゆる虫と戦い、草の葉と戦い、風と戦い、お前の母である清明な秋と戦い、はては大胆にも偉大なる太陽に向ってすら戦をいどもうとするのだ。百舌鳥もお前に似て喧嘩ずきな鳥だが、あの鳥の慾望は征朊の心地よさにあるので、征朊出来そうにもない相手には、滅多に争いを仕かけようとはしない。それに較べると、お前は何という向う見ずな反逆気(むほんぎ)だろう。あの太陽に向って喧嘩をしかけるとは。それにしてはお前の身体はあまりにひ弱すぎる。 「お前は結局自分の反逆気に焼かれて死ぬより外はないのだ。」 私が小声でそっと耳打ちしようとすると、かまきりはもうそこらにいなくなっていた。それでも構わなかった。私は自分の胸に巣くっている、今一つのかまきりに呼びかけることが出来たから。P.17~19 蜜 柑(4) 黄金色の蜜柑がそろそろ市に出るころになった。 むかし、善光という禅僧があった。あるとき托鉢行脚に出て紀州に入ったことがあった。ちょうど秋末のことで、そこらの蜜柑山には、黄金色の実が枝もたわむばかりに鈴なりになっていた。山の持主は蜜柑取に忙しいらしく、こんもり繁った樹のかげからは、ときおり陽気な歌が聞えていた。 蜜柑山に沿うた小路をのぼりかかった善光は、ふと立ちとまった。頭の上には大粒の蜜柑のいくつかがぶら下っていた。善光は不思議なものを見つけたように、眼を上げてその枝を見つめた。そしてときどきいかにもふ審に堪えないように小首をかしげては、何やら口のなかで独言をいっているらしかった。 しばらくすると、程近い樹のかげから一人の農夫がのっそりと出て来た。 「坊さん。あんたそんなところで何してはりまんね。」 善光は手をあげて頭の上の枝を指ざした。 「あすこに変なものがぶら下っている。あれは何というものかしら。」 「変なもの。どれ。どこに。」 農夫は善光の指ざす方角を見あげた。そしてはじけるように笑い出した。 「はははは。あれ知んなはらんのか。蜜柑やおまへんか。」 「蜜柑。」善光はいぶかしそうに農夫の顔を見た。「何ですか、蜜柑というのは。」 「蜜柑を知んなはらんのか。」農夫はおかしそうな表情をして善光を見かえした。旅の坊さんは牛のようなとぼけた顔をして立っていた。農夫は爪立ちをしながら手を伸ばして、枝から蜜柑の一つをもぎとった。 「まあ、あがってごらん。おいしおまっせ。」 善光は熟しきった果物を手のひらに載せられたまま、それが火焔のかたまりででもあるかのように眼を見張った。 「食べられる、これが……」 善光のもじもじしている容子を見た農夫は、おかしさに溜らなさそうにまた笑い出した。 「坊さんなんて、ありがたいもんやな。蜜柑の食べ方一つ知んなはらん。どれ、わしが教えてあげまっさ。」 農夫は蜜柑の皮をむいて、あらためて中味を善光の手にかえした。 善光はそれを一口に頬張った。その口もとを見つめていた農夫はいった。 「なかなかおいしおまっしゃろ。」 善光はそれには答えないで、蝦蟇(がま)のような大きなおとがいを動かしながら、じっと後口(あとくち)を味っていたが、まだ何だか腑に落ちなさそうなところがあるらしく、ちょっと小首をかしげた。 「申しかねますが、今一ついただけないでしょうか。」 農夫は黙ってまた二つの蜜柑を枝からもぎとった。善光はそれを二つとも食べてしまって、初めて合点したようにいった。 「なるほど蜜柑というものはうまいものですな。」 旅の僧に初めて蜜柑を味わせたその喜びをもって、農夫がもとの樹かげに帰って往くと、善光は手を伸ばして道に落ちている蜜柑の皮を、残らず拾いとってふところに収めた。 「これ、これ。そんなもの拾うたかて、食べられやしまへんぜ。」 農夫の声が樹かげから聞えた。善光は声のする方にふりむいた。 「いや、持って帰って陳皮にするのです。」 善光め。何も知らない顔をしていて、実は蜜柑の皮を食うすべまで知っていたのだ。――禅というものは、いろんな場合に役に立つものである。P.20~23 柿(5) 今日野道をぶらついていると、一軒の田舎家の裏口に出た。そこには柿の木が立っていて、枝には柿の実の幾つかが、午後三時頃の日光を受けて紅玉のように光っていた。柿の木の上には、雨あがりの青磁色をした深い秋の空が、たとえようもない清明な姿をして拡がっていた。 燃えるような柿の色に暗示されて、赤絵を焼いたという柿右衛門の陶器には、器の一方に片寄せて花鳥をえがき、それに対する他の一方は素地の清徹をそのまま残して、花鳥の花やかな配色と対照させているのがよくある。ちょうどそのように柿の実の紅玉を見て楽むにも、それをもぎ取って手のひらに載せたり、果物籠に盛ったりしたのでは感興が薄い。やはり大空を陶器皿の見込に見たてて、深い空の色を背景として見あげるに越したことはない。柿右衛門の製作には、そのまま残された素地に、ちぎれ雲とか小さな鳥とかを描き込んで、その器の向きを示しているのがよくあるが、頭の上の柿の実に見とれる折にも、慾をいえば、雲の一片か小鳥かが空を飛んでいてくれたら、どんなにかおもしろかろうとも思うが、世のなかのことは、そうそう注文通りにはゆきかねるから仕方がない。 柿右衛門に限ったことではないが、陶器の絵には、自然界ではとても見つかりそうにもない変な形をした禽獣や草木がよく描かれてある。鍋島にうずまきの花をもった草が描かれているのは、人の皆知っているところで、むしろあすこの製作の特徴のようにさえなっているが、あんな草がどこに見出されるだろうか。また古陶のな高いものに頭でっかちな鳥や、すばらしく尻っ尾の長い鳥の染付をよく見ることがあるが、あんなぶ恰好な鳥はどこの森をさがしても、ねっから見つかりそうには思われない。 むかし、宋の徽宗皇帝が、画院の画工たちに孔雀が丘に上ろうとする様を描かせたことがあった。画は出来上って上覧に供せられたが、皇帝はどれを見ても一向気に入らぬらしかった。皇帝はいった。「孔雀が丘に上るときには、きっと左脚から先にするものなのだ。それなのにお前たちの画は、皆右脚から先に踏み出している。こんなに事実に違っていてはとても駄目だ。」 すべてに生動の真をつかもうがためには、精厳な写生によらなければならないとした院態写生画のこうした主張からすると、あの陶器画のあるものは、何という気まま勝手な、反自然な、しかしまた何という自由な精神に富んだものだろう。彼等は右脚を先にするは愚なこと、はでな孔雀の羽の代りに、じみな牛の尻尾をつけかえまいものでもなさそうだ。そこに笑うべき稚拙がある。しかしまた快活な自由さがないではない……。 柿の木と柿の実とのあの素朴な厚ぼったい感じは、どの材料をつかうよりも、一番よく陶器画として表現出来そうだ。私をして描かしむれば、鍋島の陶器師があのうずまきの草花を選んだような自由さをもって、私は紅玉の実を支える枝という枝に、雄鶏の脚に見るような、するどい蹴爪をかき添えるかも知れない。 なぜといって、今気がついたことだが、あすこに真赤に熟しているのは、まがうようもない渋柿だからである。P.24~26 蓑 虫(6) 1 空は藍色に澄んでいる。陶器のそれを思わせるような静かで、新鮮な、冷い藍色だ。 庭の梅の木の枝に蓑虫が一つぶら下っている。有合せの枯っ葉を縫いつづくった草庵とでもいうべきお粗末な住家で、庵の主人は印度人のような鳶色の体を少しばかし、まだ開けっ放しの入口の孔から突き出したまま、ひょくりひょくりと頭をふっている。何一つする仕事はなし、退屈でたまらないから、閑つぶしに頭でもふってみようかといった風の振方である。 そっと指さきで触ってみると、虫は急に頭をすくめて、すぽりと巣のなかに潜り込んでしまうが、しばらくすると、のっそりと這い上って来て、またしてもひょくりひょくりと頭をふっている。 2 むかし、支那の河南に武億という学者があった。ある歳の冬、友人の家に泊っていて除夜を過ごしたことがあった。その日の夕方宿の主人がこんなことをいい出した。 「旅に出て歳を送るのは、さだめし心細いものだろうと思うな。その心細さを紛らせるのに何かいいものがあったら、遠慮なくいってくれたまえ。」 すると、武億は答えた。 「有難う。じゃ酒を貰おうかな。酔ってさえいれば除夜も何もあったものではない」 主人は客の好みに応じて蒙古酒一瓶に、豕肉と、鶏と、家鴨と、その外にもいろんな珍らしい食物を見つくろって武億をもてなした。客はその席に持ち出されたものはみんな飲みつくし、食べつくして、いい機嫌になっていたが、何となくまだ物足りなさそうにも見えるので、主人が気をきかせて、 「まだ欲しいものがあるなら、何なりともいってくれたまえ。」 というと、武億はとろんこの眼を睡そうに瞬きながら、 「何もない。ただ泣きたいばかりだ。」 といいも終らず、いきなり声をあげて小児のようにおいおい泣き出したそうだ。 武億が声をあげて泣き出したのは、したたか酒に食べ酔った後の所在なさ、やるせなさからで、蓑虫がひょくりひょくりと円い頭をふり立てているのも、同じ所在なさやるせなさの気持からだ。虫は春からこの方、ずっと青葉に食べ飽きて、今はもう秋冬の長い静かな眠りを待つのみの身の上だ。ところが、気紛れな秋は、この小さな虫に順調な安眠を与えようとはしないで、時ももう十月半ばだというのに、どうかすると夏のような日光の直射と、晴れきった空の藍色とで、虫の好奇心を誘惑しようとする。木の葉を食うにはもう遅すぎ、ぐっすり寝込むにはまだ早過ぎる中途半端な今の「出来心」を思うと、虫は退屈しのぎの所在なさから、小坊主のような円い頭をひょくりひょくりと振ってでもいるより外に仕方がなかったのだ。 3 むかしの人は、虫となのつくものは、どんなものでも歌をうたうものと思っていたらしく、蚯蚓(みみず)や蓑虫をも鳴く虫の仲間に数え入れて、なかにも蓑虫は 「父こいし。父こいし。……」 と親を慕って鳴くのが哀れだといい伝えられているが、ほんとうのことをいうと、蚯蚓と蓑虫とは性来のむっつりやで、今日まで一度だって歌などうたったことはないはずだ。蚯蚓が詩人と間違えられたのは、たまさかその巣に潜り込んで鳴いている螻蛄(けら)のせいで、地下労働者の蚯蚓は決して歌をうたおうとしない。黙りこくってせっせと地を掘るのが彼の仕事である。 それと違って、蓑虫が歌をうたわないのは、彼がほんとうの詩人だからだ。むかしの人もいったように、ほんとうに詩を知ることの深いものは、詩を作ろうとはしないものだ。声に出して歌うと、自分の内部が痩ることを知っているものは、唯沈黙を守るより外には仕方がない。――だから蓑虫は黙っているのだ。 支那の周櫟園の父はなかなかの洒落者で、老年になってから自分のために棺を一つ作らせて、それを邸内に置いていた。天気のいい日などに酒に酔っぱらうと、 「いい気持だ。こんな気持をなくしないうちに、今日は一つ死んでのけよう。」 といいいい、ごそごそその棺のなかに潜り込んで、ぐっすり寝入ったものだ。そして眠りから覚めると、多くの孫たちを呼び集め、懐中に忍ばせておいたいろんな果物を投げてやって、孫たちがそれを争い拾うのを眺めて悦んでいたということだ。――死の家から、若い生命の伸びてゆくのを見る娯しみである。 枯っ葉でつづくった蓑虫の草庵は、やがてまたその棺であり、墓である。そのなかで頭をふりふり世間を観じている蓑虫の心は、むかし周氏の父が味ったような遊びに近いものではなかろうか。 私にはそんなことが考えられる。P.21~27 参考:周櫟園 (しゅうれきえん) . …中国,清初の文人。字は元亮,櫟(れき)園と号し,河南祥符(開封)の人。明末崇禎13年(1640)の進士。清朝に降った,いわゆる弐臣(じしん)で,福建左布政使・戸部右侍郎などを歴任,有能な官僚で実務の才があった。詩文をよくし,篆刻(てんこく)にもくわしく,特に書画の鑑識にすぐれた。著に《頼古堂集》《因樹屋書影》《印人伝》などがある。なお,幸田露伴は,周亮工とその愛姫王氏の交情を〈狂濤艶魂〉(《幽情記》所収)に作品化している。…「インタネットより」 松 茸(7) 1 西日のあたった台所の板敷に、五、六本の松茸が裸のままでころがっている。その一つを取り上げてみると、この菌(きのこ)特有の高い香気がひえびえと手のひらにしみとおるようだ。 ものの香気ほど聯想を生むものはない。松茸の香気を嗅いですぐに想い浮べられるものは、十月の高い空のもとに起伏する緑青色の松並木の山また丘である。馬には馬の毛皮の汗ばんだ臭みがあり、女には女の肌の白粉くさい匂いがあるように、秋の松山にはまた松山みずからの体臭がある。日光と霧と松脂(まつやに)のしずくとが細かく降注ぐ山土の傾斜、ふやけた落葉の堆積のなかから踊り出して来たこの頭の円い菌こそは、松山の赤肌に嗅がれる体臭を、遺伝的にたっぷりと持ち伝えた、ちゃきちゃきの秋の小伜である。 2 私たちの母国ほど、松の樹にめぐまれている土地は少かろう。高い山、低い山、高原、平野、畷道、または波うち際の砂浜に至るまで、どこにでも、松の樹の存在は見出される。遠いむかしに生きていたという蛟龍のような、鱗だらけの脊をして、偶に一人ぽっちで立っていないこともないが、多くの場合互に手を取り肩を並べて群生している。それも杉や樅(もみ)などと異って、群生したからといって、同じ高さで同じ恰好に成長するのではなく、集団的生活を営みながらも、持って生れた自分の本性を搊わないで、めいめい勝手にわが欲するがままに背を伸ばし、手を振りかざしている。全体として緑青と代赭(たいしゃ)との塊りとしか見えない松木立も、そのなかに入ってよく見ると、それぞれの樹が性向と姿態とを異にしているのに驚くことがよくある。多くの樹木が女の顔立と同じように、老齢の重みに圧されると、唯もう醜くなるのみなのに較べて、松の樹は男の容貌と同じように、歳とともに鍛錬せられゆく性格の重みを加え、環境との争闘から生じた痛ましい創痕(きずあと)を、雄々しくもむき出しに見せつけている。 松はこうした際立った性格のために、人間に愛敬せられるとともに、また松脂くさいその葉の呼吸で、あたりの大気に新鮮さを放散し、人間の気分に一味の健かさを与えている。私はこれまで自分の心に憂鬱の雲がかかると、いつもきまったように松木立のなかに入って行くことにしているが、松脂の香気に充ちた空気を胸一杯に吸い込むと、憂鬱は影もなく消えてゆき、心はいつのまにか気力と新鮮さとを取り返している。 むかし、足利尊氏は洛西等持院の境内にあった一本の松をこの上もなく愛していた。それはほととぎすの松といって、ほととぎすが巣をかけたことのある名木だった。実をいうと、この鳥はどんな場合にも、自分では巣を組まないで、鶯の家へこっそり卵を産み落し、雛をかえさせるので知られているほどだから、ほととぎすの巣だというのも、詮じてみれば鶯のそれだったかも知れないが、そんな詮索はどうでもいいとして、尊氏は愛賞のあまり、鎌倉へ下向の折にも、この樹のみはわざわざ持ち運ばせるのを忘れなかった。すると、鎌倉滞在中は樹に何となく生気がぬけていたが、主人の上洛とともに等持院に帰って来ると、急にまた元気づいて、葉の色も若やいで来たということだ。 私が松木立のなかに立って、持病の憂鬱がとみに軽くなるのを覚えるのは、ちょうどこのほととぎすの松が、寺の境内に帰って来て、生気を回復するのと同じように、ここに一つの郷土を感ずるからなのではあるまいか。ともかくも、それほどまでに松脂のにおいは、私たちの生活の奥深く滲み透っているように思われる。 3 松茸の蒸すようなにおいは、私をしてこんなことまでも聯想させた。だが、私は今病をいだいて、起居さえふ自由な境涯にある。松木立のなかで感じられる大気の辛辣さ新鮮さが、どんなに私を誘惑して、軽い動悸をさえ覚えさせるものがあろうとも、さしあたって私はどうするわけにもゆかない。 近江の石山寺に持ち伝えられた古文書を見た人の話によると、そのむかし、京都のある公卿が、一度ほととぎすを聞こうとは思うが、どうしても聞かれないので、霊験のあらたかな観世音に願って、都の空でこの鳥を鳴かせてほしいと、所望して来たことがそれに載っているそうだ。観世音に祈って、居ながらほととぎすが聞かれるものなら、病に居ても松木立のそぞろ歩きが出来ないこともなかろう。だが、それが出来ないというなら、そこにはまた想像と幻想というものがある。私はその自由な翼に乗って、どことなく松脂の匂いのする私の郷土へ飛ぶことが出来ようというものだ。P.35~32 影(8) 1 閉(た)てきった障子に、午後三時頃の陽があかるくあたって、庭さきの木芙蓉の影が黒くはっきりと映(うつ)っている。 枝のたたずまい。花のさかずき。ぎざぎざの入ったもみじ形の葉。――そういうものが、くっきりと浮び出したように、白い障子のおもてにその横顔を投げている。 かまきりが一つ、高脚を踏ん張って、葉の裏にすがりついている。 雀が一羽、どこからか飛んで来て枝にとまると、そのはずみに枝が揺れ、葉が揺れ幹がかすかに揺れている。 小さな蜜蜂が、矢のように真っすぐに来て、蕊の高い花びらのなかに隠れたかと思うと、すぐにまた飛び出して往ってしまう。 いそがしい生活の動きだ。 木芙蓉がだしぬけに顔を、肩を、胸を、――、身体じゅうを皺くちゃにして笑い出した。風が吹いて来たのだ。 一瞬の間もじっとしていない自然の動きは、絶えず障子の影絵にその脈搏を伝え、影は刻々にその以前の姿態と心持とを塗抹し、忘却し、喪失して、それに更る新しい姿態と心持とを生み出している。その一刹那の影を捉えて、それにふさわしい形を与えることは、とても無駄な思いつきだろうか。 むかし、前蜀のなにがし夫人は、秋の夜長のつれづれに、ひとり室に籠って考え事に耽っていたが、ふと何かを見つけると、声に出して叫んだ。 「まあ、竹があんなところに……」 平素夫人が愛していた庭さきの竹が、仙女のような瘠せた清らかな影を、紙窓にうつしていた。いつのまにか空には月があがっていたのだ。 絵心の深かった夫人は、早速筆をとって窓の影そのままを一気に墨に染めた。かりそめの出来心がさせた戯れとのみ軽く思っていたこの竹の画は、後でよく見ると、幹も、枝も、葉も、溌溂として生意に富んだ、すばらしい出来だったそうだ。 夫人のこの画こそ、墨竹の初まりのようにいう人もあるが、そんなことはどうでもよい。忘れてはならないのは、夫人が少しの躊躇もなく、自然の一刹那の姿態を捉えたことによって、はちきれるばかり豊富に生意を画面に盛り得たことだ。 2 自分の姿を見て満足を覚える人は、世間にざらにあるだろうが、自分の影を見て限りもない楽みを感ずる人は滅多にあるまい。 明末四公子の一人として、風流のなをほしいままにした冒巣民の愛妾小苑のごときは、その僅なうちの一人に相違なかった。 小苑が紅熟した桜桃(さくらんぼ)をつまんで食べる時には、桜桃(さくらんぼ)と唇との見わけがつかなかったというほどだから、どんなに美しい女だったかはほぼ想像することが出来る。二十七の若盛りで亡くなったので、冒氏は哀惜のあまり、自分の手でこの女の思い出を書き残しているが、それによると、小苑は自分の影を見ることが好きで、月夜には、ああか、こうかといろんな立姿を月あかりにうつして、興に入っていたものだそうだ。 あるとき、菊を贈ってよこした人があった、花のひかり、葉のつや、枝のたたずまいなど、見るから眼のさめるようなうつくしい花だった。そのおり小苑は病気で床に臥っていたが、やおら起きあがって、白地の六面屏風に花の三方をとりまかせた。そして自分も花の側に座を設けて、灯火が屏風へ投げる二つの影をいろいろと試み直していたが、いくらか疲れが出たらしくぐたりとなって、誰にいうともなく、 「菊の花はほんとうによく出来ているんだが、人間の方がこんなに痩っちまって……」 と悲しそうにつぶやいたということだ。 自分の姿態と、影と、心持とを、花のもつそれらと交錯させ、諧和させようとする試みは、多くの人が花を自分の好みにねじ曲げるようにするそれとは異って、確におもしろい行き方だと思う。P.36~39 さすらい蟹(9) 1 今日蛤(はまぐり)を食べていると、貝のなかから小さな蟹が出た。貝隠れといって、蛤や鳥貝の貝のなかに潜り込み、つつましやかな生活を送っている小さな食客だ。蟹という蟹が持って生れた争闘性から、身分ふ相応な資本(もとで)を入れて、大きな親爪や堅い甲羅をしょい込み、何ぞといっては、すぐにそれを相手の鼻さきに突きつけようとする無頼漢(ならずもの)揃いのなかにあって、これはまた何という無力な、無抵抗な弱者であろう。 そうした弱者であるだけに、こっそりとそこらの蛤の家に潜り込み、宿の主人といがみあいもしないで、仲よく同じ屋根の下で、それぞれの本性に合った、異った生活を営むことも出来るので、こんな貧しい、しかしまたむつまじい生活を与えてくれる自然の意志と慈愛とは、感嘆に値いするものがある。 この小さな蟹の第二指と第五指とが、人間のそれと同じように、第三指や第四指に比べて少し短いのは、どうした訳であろうか。自然はこんな目で測られないような小さなものにまで、細かい意匠の変化を見せて、同じものになるのを嫌っているのではなかろうか。 2 他人の軒さきを借りて生活をする貝隠れとは打って変って、広い海の上を漂泊することの好きな蟹に「おきぐらぷすす」がある。胆の太い航海者が小さなぼろ船に乗って、平気で海のただ中に遠出をするように、この蟹はそこらに有合せの流れ木につかまって、静かな海の上を波のまにまにところ定めず漂泊するのが、何よりも好きらしい。この小さな冒険者に不思議がられるのは、彼が広い海の上を乗り歩く娯しみとともに、また新しい港に船がかりする悦びをも知っているらしいことだ。磯打つ波と一緒に流れ木がそこらの砂浜に打ちあげられると、蟹は元気よく波に濡れた砂の上におり立ち、まるで自分が新しい大陸の発見者ででもあるように、気取った足どりでそこらを歩き廻るそうだ。 3 漂泊好きなこの蟹のことを考えるたびに思い出されるのは、年若くして亡くなった詩人増野三良氏のことだ。増野氏は生前オマア・カイヤムやタゴオルの訳者として知られていたが、そんな飜訳よりも彼自身のものを書いた方がよかりそうに思われるほど、詩人の気稟(きひん)に富んだ男だった。 増野氏が大阪にいる頃、私は梅田駅の附近でたびたび彼を見かけたので、あるときこんなことを訊いたことがあった。 「よく出逢うじゃないか。君のうちはこの近くなの。」 増野氏の答は意外だった。 「いや、違います。僕は毎日少くとも一度はこの停車場にやって来るんです。自分が人生の旅人であることを忘れまいとするためにね。」 私は笑いながらいった。 「それはいいことだ。少くとも大阪のような土地では、旅人で暮されたら、その方が一等幸福らしいね。」 「僕は時々駅前の料理屋(レストオラン)へ入って食事をしますが、そこの店のものに旅人あつかいをされると、僕自身もいつの間にかその気になって、この煤煙と雑音との都会に対して旅人としての自由な気持をとり返すことが出来るんです。僕はどんな土地にも、人生そのものにも、土着民であることを好みません。旅人であるのが性に合ってるんですよ。」 増野氏はこういって、女にしてみたいような美しい大きな眼を輝かせた。私はその眼のなかに、一片の雲のような漂泊好きな感情がちらと通り過ぎるのを見た。 4 それから二、三日して、私は友人を見送りに、梅田駅の構内に立っていた。下りの特急列車が今着いたばかりで、プラットフォオムは多数の乗客で混雑していた。 ふと見ると、そのなかに増野氏が交って、白い入場券を帽子の鍔(つば)に、細身のステッキを小腋に抱込んだまま、ひとごみをかき分けかき分け、気取った歩きぶりで、そこらをぶらぶらしているのが眼についた。その姿を見ると、長い汽車旅行に飽きて、停車時間の暫くをそこらに降り立っている旅人の気持がありありと感じられた。 「人生の旅人か。」 私は増野氏のいった言葉を思い出して、この若い、おしゃれな「おきぐらぷすす」の後姿をいつまでも眼で追っていた。P.79 参考:私の手持ちの「岩波文庫」(1998年9月16日)第一刷 とは記述が異なる。 糸 瓜(10) 1 「これは驚いた。糸瓜(へちま)の奴め、いかにもぶらりと下っていますね。のびのびと何の屈託もなさそうなあの姿を見ると、全くもって羨ましい。」 今日訪ねて来た医者のM氏は、応接室の窓越しに菜園の高棚にぶら下っている糸瓜を見つけて、さも感心したようにいった。 「全く苦労知らずの奴ですね。」 私がいうと、M氏は大きく頷いて、 「そうですよ。ほんとうに苦労知らずですよ。私もこの頃病院の仕事があまり多過ぎるので、過労のせいか、身体が思わしくないものですから、自宅に帰っているうちだけでも、仕事を忘れて暢気に暮したい。それには糸瓜でも眺めて、そののんびりした気持を娯んだらよかろうと思って、今年の夏は裏の空地へ糸瓜の種を蒔いてみました。ところが……」 「どうでした。出来ばえは。」 「お話になりません。生(な)る糸瓜も、生る糸瓜も、小指のように細い、おまけに寸の伸びない、まるで胡瓜のような奴ばかりなんです。毎日糸瓜でも見て、その暢気そうな気持を味いたいと楽しんでいただけに、栄養ふ良の瘠っぴいを見ると、どうも気が気でなく、毎日いらいらさせられるばかりなので、何事も予期通りにはゆかないものだと思いました。」 「どうしたわけでしょう。土でも合わなかったかな。」 「土が合わない。あんな暢気な奴でも、そんな選り好みをしますか。」 M氏は不思議そうにいった。 「するでしょうな。それからまた糸瓜を長めに作ろうとするには、根を深く耕さなければならぬといいますが、ほんとうのことのようですね。」 「根を深く。なるほどそんなものかも知れませんな。ところで、お宅のあの糸瓜ですが……>M氏は椅子から少し腰を浮けて、窓外を覗き込むようにした。「あれは随分長いようじゃありませんか。どれほど寸がありましょうな。」 「さあ、どれほどありますかな。一向測ってみないもんですから……」 「へえ、折角あんなに伸びてるものを、それでは少し無関心に過ぎるじゃありませんか。しかし、ほんとうのことをいうと、糸瓜を椊えて楽しもうという心は、寸を測るなどは、無用の沙汰とするかも知れませんね。」 M氏の言葉には、自然物に親んで、自分の心を癒そうとするもののみが知る愛と抛擲とがあった。 2 私が糸瓜の長さを測ってみようともしないのは、今年のものは去年のに較べて、一体に出来が悪く、寸が短いからでもあった。 去年のものはすべて出来がよく、おまけに素直で、どれ一つ意地くね悪く曲りくねろうとはしないで、七尺豊なものが背筋を並べて、すくすくと棚からぶら下っていた。 なかに一番長いのは、尖った尻のさきが土にとどきそうになっていたので、まさかの時の用意に、家のものが摺鉢形に地べたを掘窪めていたことがあった。 ある日、たずねて来た若い英文学者のI氏は、それをみるとにやにや笑い出した。 「ほう。糸瓜の下が円く掘下げられていますね。あれを見ると、僕うちの親父が上野の動物園にいた時分のことを思い出しますよ。」 「おとうさんは、動物園にもいられたんですか。」 I氏の父はな高い老博士で、日本で誰よりも先にダアウィニズムを紹介した動物学者であった。私も二、三度会ったことがあって、学者らしい学者として尊敬の念を抱いていた。 「それはずっと以前のことで、こんなことがありました。――」 といって、I氏は次のようなことを話し出した。 I博士が動物園をあずかっていた頃、世間に何か目出度いことがあって、その記念として、動物園では夫婦者の麒麟(きりん)を購うことに決めた。人も知っているように、麒麟は多くの動物のうちでも、とりわけ首と脚とが長く、有合せの檻で辛抱させる訳にもゆかないので、どうしても新しいものを新調する必要があった。その設計書と経費の明細書とが、博士の上役にあたる博物館長あてに差出された。館長は生物のことなど少しも知らないKという老人だったので、経費は無雑作に半分方削られてしまった。 「いくら麒麟だって、こんなに費用をかけるのは勿体ない。第一、檻の高さがべら棒に高いじゃないか。」 老館長は眼鏡越しに年若な博士の顔を見ていった。 「いえ、それだけの高さのものが是非とも必要なんです。一体麒麟という獣は……」 博士はこの獣について事細かに述べ立てようとした。 「わかっとる。わかっとる。麒麟は生草を踏まず、生物を食わずといって、世にも有難い獣じゃ。」 館長は麒麟をアフリカ産のジラフだと知ろうはずがなく、名前を訊いただけで、すぐに支那人の想像から生れた霊獣を思い出しているらしかった。 「そんな霊獣でいて、おまけに背が高いんですから……」 「まあ、待ちなさい。君にいいことを教える。檻はこの設計書の半分の高さにこしらえなさい。」館長は大切な内証事を話すので、出し惜みをするらしく、一語一語金貨を数えるように、ゆっくりした調子でいった。「そして麒麟の頭が天井につかえるなら、床の地べたを幾らでも掘下げるんだ。いいかえ、天井を低くこしらえる代りに、地べたを深く掘下げるんだよ。」 博士はそれを聞いて苦笑するより外に仕方がなかった。P.45~50 
茶の花(11) 1 茶の花が白く咲いた。 茶は華美(はで)好きの多い草木のなかにあって、ひとり隠遁の志の深い出世間者である。裏庭の塀際か、垣根つづきに椊えられて、自分の天地といっては、僅に方丈の空間に過ぎないことが多いが、唯いたずらに幹を伸し、枝を拡げるのは、自分の性分に合わないことを知っているこの灌木は、いかにも隠遁者らしい恰好で、まるまると背を円めて地べたにかいつくばっている。春から夏へかけて、多くの草木が太陽の「青春」と「情熱」とに飽酔しようとして、てんでに大きな、底の深い花の盃を高く持ち上げている頃には、彼は心静かに日向ぼっこをして、微笑を続けているばかしだ。そしてその騒々しい草木が、花を閉じ、葉を振い落してしまうと、この謙遜な隠遁者はやっと自分の番が来たように、厚ぼったい葉の蔭から小さな盃を持ち出して来る。それは白磁作りの古風なもので、彼はそれでもって初冬の太陽から水の滴りのような「孤寒」「静思」とをそっと汲み取るのである。 渡鳥は毎日のように寒空を横切って、思い思いの方角へ飛び往くのが見られるが、みんな自分の旅にかまけていて、誰ひとり途の通りがかりに空地に下りて来て、この隠遁者を見舞おうとはしない。訪いもせず、訪われもせぬ閑寂な日が二、三日続いて、あるうすら寒い日の夕ぐれ前、灰色の着付をした小さな旅人がひょっくりと訪ねて来る。長めの尻尾を思いきり脊に反しているので、誰の眼にもすぐにそれがみそさざいであることが分ろうというものだ。 みそさざいは灰色の翼を持っていながら、空高く飛ぶことを心がけないで、絶えず物かげから物かげへと、孤独をもとめてさすらい歩くひとり者である。このひとり者はさびしい裏庭の茶の木が目につくと、自分の好みにそっくりな好い友だちが見つかったように、いきなり飛んでいって、厚ぼったい葉なみを潜りぬけたり、小枝につかまってとんぼ返りをうったりする。 2 画禅室随筆の著者董其昌は、茶を論じてこういったことがあった。 「茶は眼にとっては色である。鼻にとっては香である。身にとっては触である。舌にとっては味である。この四のものは皆茶の正性ではない。これを合せばあるが、これを離せばなくなってしまう。ありというのは種々法生で、なしというのは種々法滅である。色は眼をもっては観えない。香は鼻をもっては嗅げない。触は身をもっては覚れない。味は舌をもっては知れない。法界の茶三昧とはこれである。」 随分と気取った物のいいようであるが、それにしても茶を味わう場合には、この灌木の閑寂な生活を心頭より忘却しないようにしなければならぬ。 3 むかし、宋の書家として聞えた蔡襄が、その友歐陽修のために頼まれて、集古目録の序に筆を揮ったことがあった。その返礼として鼠鬚筆(そしゅひつ)数本と、銅緑の筆架と、好物の茶と、恵山泉の名水幾瓶とを歐陽修から贈って来たものだ。蔡襄はそれを見て、 「潤筆料としては、少しあっさりし過ぎてるようだ。しかし、俗でなくて何よりだ。」 といって笑ったそうだが、その恵山泉の水で茶を煮ると、すっかりいい気になって、 此泉何以珍 適与真茶遇 在物両清純 於予独得趣 ………… ………… と詩を作って歌ったということだ。 4 すべて茶を煮るには、炭加減と水の品とを吟味することが肝腎で、むかしの数寄者は何よりもこれに心をつかったものだ。わざわざ使を立てて、宇治橋の三の間の水を汲ませた風流も、こうした細かな吟味からのことだったが、大阪ではむかしから天王寺逢坂の水が茶にいいといって、一般に尚ばれたようだ。逢坂の水といえば、それについてこんな話が残っている。 俳優二代目嵐小六の家に、ながく奉公をしている女中の父親で、女房に死別れて娘と一緒に身を寄せているのがあった。小六はこの男が仕事もなくては、定めし居つらかろうと、毎日逢坂の水を一荷ずつ水桶で家に運ばせることにした。それを聞いた世間はよくはいわなかった。 「役者風情が贅沢な沙汰じゃないか。あんなに遠くまで人をやって、わざわざお茶の水を汲ませるなんて。まるでお大みょうのすることだ。」 この噂が弟子の口から師匠の耳へ伝えられた。すると、小六は 「それはもっての外の取沙汰というものだ。お前たちも聞いてるだろうが、むかし阪田藤十郎は、大阪の芝居へ勤める折には、わざわざ京の賀茂川の水を樽詰にして送らせたものだそうだ。ちょっと聞くと大層贅沢なようだが、藤十郎の考えでは、芝居に出ているうちは、自分の身体は銀主方と見物衆のもので、自分ひとりのものではないはずだから、つねに飲みつけない水を飲んで、腹をこわしてもとの用心から、賀茂川の水を取り寄せたまでのことなのだ。わしが逢坂の水を汲ませるのも、それと同じわけで、つまりは銀主方と見物衆とを大切に思うからのことなんだ。」 と顔色を変えて言訳をしたそうだ。 5 むかし、大阪の備後町に、河内屋太郎兵衛という商人があった。財(かね)があるにまかせて、随分思い切った振舞をするので、その度に世間の人たちから、 「また河内屋のいたずらか。何を仕出かすかもわからない男だな」と評判を立てられるようになった。 あるとき、紀州侯を備後町の屋敷に迎えて、茶を献じたことがあった。紀州侯はその日の水が大層気に入ったらしかった。 「いい水質だ。太郎兵衛、ついでがあったら余も少しこの水を貰い受けたいものじゃて。」 太郎兵衛はかしこまった。 「お口にかないまして、太郎兵衛面目に存じます。早速お届け致すでござりましょう。」 紀州侯は間もなく和歌山へ帰った。そして太郎兵衛の茶席で所望した水のことなどはすっかり忘れていた。すべて人の頭に立とうというものは、昨日あったことを今日は忘れてしまわねばならない場合が多いものだが、紀州侯は誂え向きにそういう質に生れ合わせていたらしかった。 ある日のこと、側近くに仕えている家来の一人が、慌てて紀州侯の前へ出て来た。 「殿、只今大阪の商人河内屋太郎兵衛と申すものから、かねてのお約束だと申しまして、水を送って参りました。」 「ほう、河内屋太郎兵衛から……水を……」紀州侯は忘れていた約束を思い出した。 「それならば早速受取ってつかわし、大事に貯えおくようにいたせ。」 「さあ、貯えると申しましたところで、あんなに沢山な水樽では……」 家来は当惑したようにいった。 「そんなに沢山持って参ったか。」 殿は物好きそうに眼を光らせた。 「はい、お城前はその水樽で身動きが出来ぬほどになっております。まだその上に次から次へと荷車が詰めかけて参りまして……」 家来は城のなかはいうまでもないこと、紀州侯の領地という領地は、すっかり水樽で埋ってしまうかのように、気味悪さに肩を顫わせた。 「そうか。河内屋めがまたいたずらしおったな。 紀州侯はからからと声を立てて笑った。P.51~58 仙人と石(12) 支那の唐代に、張果老という仙人がありました。恒州の中条山というところに棲んでいて、いつも旅をするときには、驢馬にまたがって一日に数万里の道程(みちのり)を往ったといいます。旅づかれで家に帰って休もうとでもする場合には、驢馬の首や脚をぽきぽきと折り曲げて畳み、便利な小型(こがた)に形をかえて持ち運んだそうです。そんなおりに、思いがけなく川に出水(でみず)があって、徒渉(かちわた)りがしにくいと、この仙人は手にさげた折畳み式の馬に水を吹きかけます。すると、驢馬は急に元気づき、曲げられた四つの脚を踏みのばして、もとの姿にかえったといいます。 あるとき、張果老が長い旅にすっかり疲れはてて、驢馬から下りて野なかの柳の蔭で憩(いこ)っていたことがあります。驢馬はその傍でうまそうに草の葉を食べ、時おり長い尻尾をふって羽虫を追っていました。 「おい、仙人どの。仙人どの。」 誰だか呼ぶ声がしたので、張果老はうつらうつらする眼をひらいてあたりを見まわしました。十月の静かなあたたかい日ざしはそこいら一杯に流れて、広い野原には自分たちの外に、何一つ生物(いきもの)の影は見えませんでした。張果老はまた睡りかけようとしました。 「おい、仙人どの。仙人どのってば。」 またしても自分を呼ぶらしい声がするので、仙人はふ機嫌そうに眼をさましました。 「誰だ。わしを呼ぶのは。」 「わしだ。お前のまえに立っている石だよ。」 「なに、石だって。」 仙人はずっと向うを見ていた眼を、急に自分の脚もとに落しました。そこには白い石が立っていました。仙人は気むつかしそうに言いました。 「お前か。さっきからわしを呼んでるのは。わしは今睡りかけているところなんだ。」 「それはすまなかった。お前に逢ったら、一度訊いてみたいと思うことがあるもんだから。」 どこに口があるとも分らなかったが、白い石はしっかりした声で言いました。 「何か。お前が訊きたいというのは。」 「ほかでもない。わしは随分ながくここに住んでいるが、よくお前が驢馬に乗って、そこらを駆けて往くのを見ることがある。おそろしい速さだね。」 「速いはずだ。一日五万里を往くのだから。」 仙人は得意そうに驢馬を見かえりました。馬は主人の顔を見て、にやりと笑いました。 「五万里。それは驚いた。」石はびっくりして少し肩を動かしたようでした。「そんなに速力(あし)の出る馬をどこから手に入れることが出来たのだ。」 張果老は仙人らしい白いあご髯を、細い樹の枝のような指でしごきました。 「どこからでもない。わしが自分の法力でこしらえたのだ。わしはそういう馬が是非一頭ほしく思ったから。」 「なぜまたそんな途方もない馬をほしがったのだ。」 長年同じところにじっとしている石は、仙人のそんな気持が腑に落ちないらしく訊きました。 「わしは幸福の棲む土地をたずねて、方々捜し歩きたかったからだ。」仙人は昨日見た夢を思い出すような眼つきをしました。「わしはあれに乗って、毎日毎日どこという当もなしに、暴風(あらし)のように駆けずり廻ったよ。わしが尋ね残した国は、どこにもないほどだ。この原っぱも今日まで幾度通ったか覚えきれない……」 「そうして、その幸福とやらはうまく見つかったのか。」 白い石は待ち切れないように口を出しました。 「まだ見つからない。そしてわしはすっかり年をとってしまった。」仙人はこう言って、自分の姿を今更のように見返りました。「髯はこの通りに白くなるし、手は痩せて枯木のように細くなった……」 「わしはむかしからずっとここに立っているが、別段それをふしあわせだとも、退屈だとも思ったことはない。わしがお前のように方々飛び廻りたく思わないのは何故(なぜ)だろうな。」 石の言葉は他人(ひと)に話すでもなく、独語(ひとりごと)のようでした。 仙人はそれを聞くと、深く頷きました。 「わしもこの頃になって、やっとそう思い出したよ。幸福というものは外にあるものじゃない。ここぞと思うところに落ちついて棲んでいれば、初めてそこに幸福というものが……」 「それはお前にしては出来過ぎたほどの思いつきだ。どうだい、いっそここに落ちついて、わしと一緒に棲んじゃ。お前にしても、もう一生のつづまりをつけてもいい歳だよ。驢馬の始末なら、明日にでも通りがかりの旅商人(たびあきんど)に売り払ったらいいじゃないか。」 白い石が無遠慮にこう言うと、驢馬は長い耳でそれを立聞きして、癪にさえたらしく、いきなり後脚(あとあし)を上げて、そこらを蹴飛ばしました。 「いや。わしにはそこまでの思いきりがない。人間というものは、みんなこれまで自分のして来た仕事に、引きずられて往くものなのだ。 ――ああ、お前につかまって、つい長話(ながばなし)をしすぎた。わしはもう出かけなければならない……」 張果老は哀しそうに言って、自分の膝の上に落ちた砂埃を払いながら立ち上りました。石は見えぬ眼でそれを感づいたらしく、 「やっぱり幸福を求めて……」 「そうだ。幸福を求めて。……こんなにして方々駆けずり廻って、やがて死ぬのが、わしの一生かも知れない。でも、わしは出かけなければならない。」 仙人は静かな足どりで、驢馬のいる方へ歩み寄りました。馬はそれと気づいて、元気そうに高くいななきました。 「そんならもうお別れだ。」 張果老はひらりと驢馬の背にまたがりました。そして一鞭あてたかと思うと、馬は嵐のように飛んで、またたくうちに広野のはてに点のように小さくなりました。 「とうとう往ってしまった。……わしはやはり一人ぽっちだ。」 白い石は低い声で独語(ひとりごと)を言って、そのまま黙ってしまいました。 秋の日はそろそろ西へ落ちかかりました。途を間違えたらしいこがね虫が、土をもち上げて、ひょっくりと頭を出しましたが、急にそれと気づいたらしく、すぐにまた姿を隠してしまいました。P.59~64 春の魔術(13) 春が帰って来た。そしてその不思議な魔術がまた始まろうとしている。 欧洲航路の途中、シンガポオルに立ち寄ったことのある人は、あそこへ泊る船という船へよく訪ねて来る土人の魔術師のことを知っているだろう。鳶色の肌をしたこの魔法使は、皆の見る前で砂を盛った椊木鉢のなかに、一粒の向日葵(ひまわり)の種子を蒔く。そして暫く呪文を唱えていると、その種子から小さな芽がむくむくと頭を持ち出し、すっと双葉を開いたと思うと、やがて黄ろい花がぽっかりと眼をあけかかるのだ。その手際のあざやかさは、見ている誰もが心から驚嘆させられるが、春の魔法使は、この鳶色の肌をした土人のそれよりももっと巧妙に、もっと秘密に、その魔術の企(たくら)みを仕おおせるだけの技巧と敏慧さとをもっている。 私はこの頃の野道を歩くとき、自分の足の下にしかけられている春の魔術を思って、足の裏をくすぐられるようなこそばゆさを感じることがよくある。そこらの石ころの下、土くれのかげ、または置き腐れになった古蓆(むしろ)のなか――といったような、ついこないだまで霜柱に閉じられていた「忘却」と「睡眠」との国から、いろんな草が、小さな獣のような毛むくじゃらな手や、または小鳥のように細めに開けた怜悧そうな眼を覗けているのを数知れず見つけるではないか。こうした生物の、産れてまだ間もない柔かい生命が、私の注意な足に踏まれて、どうかするととりかえしのつかない傷を負わされまいものでもないのを思うと、滅多に外を出歩くこともできないような気持がする。 自分におっ被(かぶ)さっているいろんな邪魔ものを手で押しのけ、頭で突き上げて、地べたの上に自分を持ち出して来た草という草は、刻々に葉を伸し、茎を伸して、ひたすらに太陽の微笑と愛撫とに向って近づこうとする。 その意気込みの激しさ。巻鬚や葉のひとつびとつが、感情をもち、霊魂をもっているかのように、地べたから大空を目ざして躍り上りそうに いている。もしかそれぞれの根が、土底深く下りていなかったならば、春の草という草は、鳥のように羽ばたきして太陽を目あてに飛び揚ったかも知れない。 それはひとり草のみではない。冬中ファキイル僧のように仮死の状態にあったそこらの木々の瘠せかじけた黒い枝には、また生命が甦って、新しい芽を吹き出しているではないか。寒さのうちは老予言者ででもあるように、寂しい姿をして、節くれだった裸の枝で意味ありそうに北極星の彼方を指さしていた公孫樹までが、齢にもふ似合な若やぎようで、指さきという指さきをすっかり薄緑に染めておめかしをしている。 そしてその成長の早さ、変化の目まぐるしさは、実際驚かれるばかりで、春の魔術には、ただ一つの繰返しすらもない。全く飛躍の連続である。 この魔術の主調をなすものは、生の歓喜であり、生命の不思議である。p.65~67 まんりょう(14) 夕方ふと見ると、椊込の湿っぽい木かげで、真っ赤なまんりょうの実が、かすかに揺れている。寒い冬を越し、年を越しても、まだ落ちないでいるのだ。 小鳥の眼のような、つぶらな紅い実が揺れ、厚ぼったい葉が揺れ、茎が揺れ、そしてまた私の心が微かに揺れている…… 謙遜な小さきまんりょうの実よ。お前が夢にもこの夕ぐれ時の天鵝絨(ビロード)のように静かな、その手触りのつめたさをかき乱そうなどと大それた望みをもつものでないことは判っている。いや、お前の立っているその木かげの湿っぽい空気を、自分のものにしようとも思うものでないことは、よく私が知っている。 お前はただ実の赤さをよろこび、実の重みを楽んでいるに過ぎない。お前は夕ぐれ時の木蔭に、小さな紅提灯をともして、一人でおもしろがっている子供なのだ。 持って生れたいささかの生命をいたわり、その日その日をさびしく遊んで来たまんりょうよ。 またしても風もないのに、お前の小さな紅提灯が揺れ、そしてまた私の心が揺れる。P.68~69 小 鳥(15) 春の彼岸過ぎのことだった。 どこをあてどともなく歩いていると、小さな草の丘に出て来た。丘は新芽を吹き出したばかりの灌木に囲まれていて、なかに円く取り残された空地に、かなり大きな桜の老木が一つ立っていた。 それを見ると、私は思いがけないところでむかし馴染に出あったような気持で、邪魔になる灌木を押し分けながら、足を早めてその樹の側に近寄って往った。そして滑々した樹の肌をひとしきり手で撫でまわした後、私はそっと自分の背を幹にもたせかけた。 枝という枝は、それぞれ浅緑の若葉と、爪紅をさした花のつぼみとを持って、また蘇って来た春の情熱に身悶えしている。冬中眠っていた樹の生命は、また元気よくめざめて、樹皮の一重下では、その力づよい脈搏と呼吸とが高く波うっている。 その道の学者のいうところによると、野中に立っている一本の樺の木は、一日に八百ポンド以上の水分を空中に向って放散している。普通の大きさの水桶でこれだけの水を運ぼうとするには、まずざっと三十二度は通わなければならぬ。もしか人が地べたから樺のてっぺんまでそれを持ち運ぶとして、一度の上り下りに十分かかるものとすれば、それだけの水を運んでしまうには、五時間以上も働かなければならぬことになるといっている。 樺にしてからがそうだ。桜にしてもそうでないとはいわれまい。とりわけ春は再び樹にかえって来て、枝という枝は数知れぬしなやかな葉を伸ばし、みずみずしい花を吹いている昨日今日、樹の内部では一瞬の休みもなく、夥しい水分が、根より吸い上げられて、噴き上げの水のようなすばらしい力をもって、幹から枝の先々にまで持ち運ばれていることだろう。――私はその激しい動揺を、自分の背に感じて、思わず 「春だな。」 と、心のなかでそういった。そして眼をあげて、頭の上に垂れかかっている枝を見た。 その瞬間、深い紺色の空の彼方から、小石のようなものが一つ飛んで来て、ひょいと上枝にとまって、身軽に立ちなおったのを見ると、それは一羽の小鳥であった。鳥は黒繻子のような縁をとった灰色の羽をしていた。私はなも知らないこの小さな遊び仲間を眼の前に迎えて心より悦んだ。 むかし支那に焦澹園という儒者があった。多くの学者のなかから擢んでられて東宮侍講となったが、あるとき進講していると、御庭の立木に飛んで来て、ちろちろと清しい声で鳴く小鳥があった。東宮は眼ざとくそれを見つけて、枝移りするその身軽い動作に心を奪われているらしかった。それに気がついた焦澹園は快からず思って、いきなり進講をやめてしまった。侍講の熱心な言葉が急に聞えなくなったのに驚いた東宮は、自分の仕打に気づいて、残り惜い思いはしながらも、またもとのように居ずまいを直した。侍講はやっと安心したように再び講義を続けたということだ。 儒者焦澹園のつもりでは、かりにも聖賢の道を聞いている途中で、東宮ともあろうものが、小鳥の素振に気をとられるなどとは、怪しからぬことだというにあるらしいが、しかし、ほんとうのことをいうと、東宮はいいものを見つけたので、侍講は何をさしおいてもそれをほめなければならないはずなのだ。堅苦しい聖賢の道を聞きながら、小鳥の流れるような音律に耳を傾け、溌溂たる動作に眼を奪われるというのは、規律と形式との生活のただ中にいても、なお自然物と戯れ、自然物と楽もうとする、ほしいままな心を失わない証拠で、侍講が今少し賢いか、今少し愚かのどちらかであって、東宮が小鳥に見とれているのをそのまま見遁すことが出来たなら、この年若な貴公子はしかつべらしい聖賢の道よりも、もっと自由で、もっと明るいものを見つけることが出来ただろうと思われる…… そんな他人のことを考えるひまがあったら、私は自分の見つけた小鳥と遊んだ方がよかった。――小鳥は今持前の身軽さで、枝から枝へととんぼがえりを試みている。その拍子に私は不思議なものを見つけた。 小鳥は赤いふんどしを締めていた。その尻っぺたにある赤いさし毛は、私をしてそんなことを思わせた。 「何だ。漁師の小せがれのように、赤いまわしなんか締めてさ……」 私は思わず声を出して笑った。小鳥は臆面もなくまだとんぼがえりを続けている。 見ているうちに、いつのまにか私の心もとんぼがえりをしていた。P.70~73 参考:焦 こう(しょう こう、1540年-1620年)は明代中国の儒学者、歴史家。字は弱侯。たん園またはい園と号す。たん園先生またはい園先生、焦太史と呼ばれる。 桜 鯛(16) 1 春はどこから来る。 春は若草の萌えた野道から来るともいい、また都大路の女の着物の色から来るともいうが、津軽海峡をへだてた北海道の平野に、久しく農人の生活を送って来た人の話によると、あちらの春は、野からも山からも来ない。言葉どおりに天そのものから下りて来る。それも一歩ごとにその足跡から花がほほ笑むという、素足の美しい女神ではなく、雄々しい行進曲に合せて、馬を躍らせて来る男性の神様である。強い光に満ちあふれた大空から、黄金の鎧をきらめかせ、ラッパの音高く下りて来るのが、あの雪国の春だそうだ。 それとは違って、私の知っている春は、広い野原からも来たが、それと同じ頃を見はからって、砂丘のあなたの青い海からもまたやって来た。私の生れ故郷は、瀬戸内海の波の音のきこえる小村で、春になると、桜鯛がよく網に上った、それを売り歩く魚商人の声が、陽気に村々に聞えて来ると、村人は初めて海の春が、自分たちの貧しい食膳にも上るようになったのを喜んだものだ。 麦の茎が伸び、雲雀が空でちろちろ鳴いていても、海に桜鯛がとれ出したという噂を聞かないうちは、春も何となく寂しかった。 2 桜鯛よ。 網から引あげられて籠に入ったお前は、タニスで発見せられたな高いニイル河神の石像に彫りつけられた河魚のように、いつも横向きになっていて、つぶらな唯一つの眼しか見せていない。そのむかし、アレキサンドル大王の部将として聞えていたアンチゴノスは、自分の横顔(プロフィル)を描かせた最初の人だといわれているが、それはこの男が生れつきのめっかちだったので、その醜さを人に見られまいための用意に過ぎなかった。鯛はアンチゴノスと違って、眼は二つともいい分はなかったが、魚のならわしとして、一つの側面に一つの眼をしか持っていなかったから、籠のなかに寝かされたのでは、その一つの眼でものを見るより外に仕方がなかった。 イギリスに小説家として、また下院の議員として相当聞えた A. W. Mason という人がいる。この人はいつも片眼鏡(モノクル)をかけていて、好きな水泳をする場合にも、滅多にそれをはずさないそうだ。あるとき汽車のなかで、その眼鏡を壊したことがあった。すると、片眼が急に風邪をひいてしまったそうだ。鯛もしおっぱい海の水を出て、じかに空気に触れるので、よく風邪でも引いて充血したように、真っ赤な眼をしているのがよくある。 鯛よ。お前の眼は、これまで外界の自然を、自分の行動と平行してしか見なかった。お前の見る外界は、お前が鰭(ひれ)を動かして前へ進むときには、同じように前へ進み、お前が脊後へ退くときには、同じように背後へ退いた。正面から来て、お前の口さきにぶっつかるものは、お前の眼で見た外界ではなかった。お前は前に立っているものを永久に見ることが出来ないのみならず、左の眼で見たものは、右の眼で見たものとはすっかり違っていた。一つの眼が神を見て、それと遊んでいる同じ瞬間に、今一つの眼は悪魔を見て、その醜い姿に怖れおののくこともあったに相違ない。 鯛よ。お前は海から引きあげられて、籠に入れられた一刹那、初めて高い空のあなたに、紅熟した南瓜のように円い大きなものを見て、びっくりしたことだろう。あれは太陽といって、多くのものにとって光明と生命との本源であるが、お前がまのあたりあれを見たときは、やがてお前にとっては死であった。 鯛よ。お前が一つの眼で、そういう不思議な太陽を見ていたときも、今一つの眼は何かつまらぬものを見て、こっそり微笑していたらしかった。それは悲しいことだが、鯛にとっては免れることの出来ない運命であった。 3 むかし、支那に張風という老画家があった。仏道に帰依して、二、三十年の間は、少しもなまぐさいものを口にしなかったが、あるとき、友だちの一人が松江の鱸(すずき)を煮ているところへ往き合せたことがあった。張風は皿に盛られた魚の姿を一目見ると、 「忘れもしない。これはうちにいた鷹の子が好いて食べたものだ。」といって、いきなり箸をとって、うまそうに食べ出した。そしてそれからというものは、平気で肉食をしつづけたということだ。 私は張風のように、別になまぐさいものを断っているわけではないが、春になって、そこらの海がぼんやり霞んでいるのを見ると、生れ故郷の瀬戸うちの海を思い出して、そこで捕られた魚の金粉を吹いたような鱗をなつかしがることがよくある。P.74~78 蟹(17) 1 雨の晴れ間を野路へ出てみた。 ずぶ濡れになった石のかげから、蟹が一つひょっこりと顔を出していた。 「いよう。蟹か。暫くぶりだったな。」 私はそう思って微笑した。それが春になって初めて見る蟹だったことは、私がよく知っていた。 暫く立ちとまって見ていると、蟹は石の下からのこのこと這い出して来た。そして爪立するような脚どりで水溜を渉り、髪を洗う女のように頭を水に突っ伏している雑草の背を踏んで、少し高めになっている芝土の上へあがって来た。 ふと何かを見つけた蟹は、慌てて芝土に力足を踏みしめ、黒みがかった緑色の甲羅がそっくりかえるばかりに、二つの真赤な大鋏(おおばさみ)を頭の上に振りかざしている。 怒りっぽい蟹は、一歩(ひとあし)巣から外へ踏み出したかと思うと、じきにもう自分の敵を見つけているのだ。 彼は傍に立っている私を、好意のある自分の友達とも知らないで、その姿に早くもふ安と焦燥とを感じ出し、持前の喧嘩好きな性分から急に赫となって、私に脅迫を試みているのだ。 万力(まんりき)を思わせるような真赤な大鋏。それはどんな強い敵をも威しつけるのに充分な武器であった。 そんな恐ろしい武器を揮って、敵を脅かすことに馴れた蟹は、持ち前の怒りっぽい、気短かな性分から、絶えず自分の周囲に敵を作り、絶えずそれがために焦立っているのではなかろうか。 その気持は私にもよく分る。すべて人間の魂の物蔭には、蟹が一匹ずつかくれていて、それが皆赤い爪を持っているのだ。 私がこんなことを思っていると、蟹は横柄な足どりで、横這いに草のなかに姿を隠してしまった。 2 海に棲むものに擁剣蟹(がざみ)がいる。物もあろうに太陽を敵として、その光明を怖れているこの蟹は、昼間は海底の砂にもぐって、夜にならなければその姿を現わそうとしない。 擁剣蟹は、脚の附け際の肉がうまいので知られているが、獲られた日によってひどく肉の肥痩が異うことがある。それに気づいた私は、いつだったか出入の魚屋にその理由を訊いたことがあった。魚屋はその荷籠から刺(とげ)のある甲羅を被(き)たこの蟹をつまみ出しながら言った。 「奴さん。こんな姿はしていますが、大の明るみ嫌いでしてね。夜分しか外を出歩かない上に、満月の夜のあとさきは、海が明るいので昼だと思って、じっと砂にもぐっていて、餌一つとろうとしないそうですから、多分その故(せい)かも知れませんよ。」 魚屋の言葉を真実だとすると、擁剣蟹は白熱した太陽の正視を怖れているのみならず、また青白い満月の流盻(ながしめ)をすらも嫌がっているのだ。 こんな性分の擁剣蟹にとっては、一月でもいい、月のない夜が、せめて満月の出ない夜が、どんなにか望ましいことだろう。一月でもいい、満月の出ない夜が。そんなことが果して有り得るだろうか。――いや、それはあるにはあった。天文学者の言うところによると、紀元八百六十六年の二月には、月は一度も顔を見せなかった。 月が顔を見せないことはなかったが、満月の夜は一度もなかった。こんなことは世界の開闢以来初めてで、その後も二百五十万年の間に、まず二度とはあるまいといわれているが、そんなことになったのは、前の一月中に満月の夜が二度もあり、続いて三月になってからもまた二度あったので、二月には一度も見られないことになったのだということだ。 してみると、擁剣蟹がどんなに嫌がったところで、青白い顔をした満月は、月に一度はきっと海の上を見舞うにきまっているので、明るみを好まないこの蟹は、そんな夜になると、静かな波の響にも、青ざめた光のぶ気味さに怯えつつ、海底の土にでもこっそり潜っている外はなかった。 やがて闇の夜が来ると、擁剣蟹は急に元気づいて活躍を始める。そして波底の暗がりにまぎれて、大勢の仲間を誘い合せ、海から海へとはてしもない大袈裟な旅を続けることがよくある。夜の海に網を下す漁師たちが、思いがけないあたりでこの蟹を引き揚げて、その遠出に驚くのも、こんな時のことだ。 3 潮の退いた干潟を歩いていると、底土の巣から這い出したままの潮招蟹(しおまねぎ)が、甲羅に泥をこびりつけて、忙しそうに食物をあさっているのがよくある。蟹は時々立ち停って、片っ方のずば抜けて大きな大鋏(おおばさみ)を、しかつめらしく上げ下しをしている。自分の身体の全体よりもずっと重そうな大きな脚だ。 それを見ると、蟹は自分の周囲に、何かしら自分に好意をもたないもののあるのを感じて、それに対って威嚇と侮蔑とを試みているようだ。その相手が海賊のように毛むくじゃらな泥蟹であろうと、狡猾な水禽であろうと、または無干渉な大空そのものであろうと、そんなことは蟹にとってどちらでもいいのだ。 蟹は唯反抗し、威嚇さえすれば、それで充分なのだ。P.79~83 海 老(18) 1 潮干狩の季節が来た。 潮干狩に往って、貝を拾い、魚を獲るのは、それぞれ異った興味があるものだ。海の中もふ景気だと見えて、いつもしかめっ面をしている蟹をからかったり、盗人のように夜でなければ出歩かない擁剣蟹(がざみ)を砂の中から掘出したり、富豪(かねもち)のように巣に入口を二つ持っていて、その一つを足で踏まれると、きっと裏口から飛び出す蝦蛄(しゃこ)を押えたりするのもおもしろいものだが、それよりも私の好きなのは、車海老を手捕りにすることだ。 遠浅な海では、引潮の場合にあまり遊びが過ぎて帰り遅れた魚や、海老などが、そこらの藻草や、砂の窪みにかいつくばって、姿を隠しているのがあるものだ。そんなのを何の気もつかずに踏むと、足の下から海老があわてて跳出すことがよくある。 海老は弾き豆のように勢いよく飛出すが、あまり遠くへは行かないで、きっとまたそこらの砂の窪みに落ちつくものだ。水影に透してじっと見つめていると、海老は尻尾から先に、浅く砂や藻草にもぐって、やがて背全体をも隠してしまうが、鼻眼鏡のような柄のついた二つの眼だけは外に出して、それとなく自分を驚かせた闖入者を見まもっている。やがて闖入者に他意がないらしいのを見極めると、海老は安心したように、しずかにお洒落の鼻眼鏡の柄を畳んでしまう。 海老はもう何も見えない。見えないから安心している。 私たちはそこを狙って、よくこの海の騎士を生捕にしたものだ。 海老を海の騎士だと呼ぶのに、何の不思議があろう。彼は強い魂をもっている。死ぬまで飛躍を止めようとしない。それにまた彼は兜をかぶっている。その兜は彼にとって少し重過ぎるほどいかめしい拵えだ。 2 海老が好きで、その頭を兜として立派に飾りたてたものに、蒔絵師の善吉があった。善吉は羽前の鶴岡に住んでいた人で、明治の初年頃までまだ生きながらえていた。 「俺の家に来て見ろ。金の兜をきた海老がいるぜ。」 善吉は人を見ると、得意そうによくこんなことをいったものだ。 それを聞いた人たちのなかには、物ずきにも善吉の家をたずねてゆくのがあった。 家には、縁端に大きな水盤がおいてあった。なかを覗いてみると、なみなみと盛られた水の底に、青い藻草が漂っていて、そのなかを数知れぬ川海老が、楽しそうに泳ぎまわっていた。 驚いたことには、海老はいずれも金の兜と金の鎧とを身につけて、きらきらと光っていた。 皆は呆気にとられて、こんな綺麗な海老をどこで捕って来たかを善吉に聞いた。 善吉は笑ってばかりいて、それには答えなかった。 黄金の海老は、善吉が商売道具の絵具をもって、こまめに金蒔絵したものであった。 善吉の妻は、海老のために、毎日餌をやることと、水盤の水を取りかえることとを夫にいいつかっていたが、内職仕事の織物の方にかまけていて、どうかするとそれを忘れがちだった。 そんな折には、夫の機嫌はとりわけよくなかった。一度などそれが原因で、夫婦のなかに大喧嘩が持ち上ったこともあった。 その翌日だったか、妻は夫の留守を見計らって、水盤の海老を家の前を流れる小川のなかにすっかりぶちまけてしまった。 外から帰って来た善吉は、水盤が空になっているのを見て、留守中の出来事を察したらしかった。 見ると、薄暗い土間に、半ば織りさした木綿機があった。妻は近所あるきでもしているらしく、そこらに姿を見せなかった。 気味悪くにやりと笑って、善吉はすばしこく土間へ飛び下りた。そしてそこにあった鋏をもって、織さしの布をむざむざとつみ切ったかと思うと、それを一くるめにくるめて、前の小川にぽいと投げ捨ててしまったそうだ。 3
この老和尚を描いたものに、渡辺崋山の作品がある。それは禿頭の和尚が、幾らか屈み腰に、左手に持った網を肩にかたげたまま、右手の指の間にぴちぴち跳ねまわる海老を捉えている図で、脚下(あしもと)に芦の葉が少し描き添えてあるのみなのが、枯淡な老和尚の面目にふさわしかった。 「贅沢な老人だな。こんな採りたての、活(いき)のいい海老を食べるなんて。」 私はその絵を見ているうちに、和尚の無一物の生活の豊かさが羨ましくなって、ついこんなことを思ったことがあった。P.84~88 ★参考:蜆子和尚は唐末の禅僧。居所を定めず,常に一衲をまとい,河辺で蝦や蜆をとって食べ,夜は神祠の紙銭中に寝たという。可翁は十四世紀前半に活躍したと推測され,初期水墨画の代表的画人であるが,詳しい伝記は分からない。 魚の憂鬱(19) 池のほとりに来た。蒼黒い水のおもてに、油のような春の光がきらきらと浮いている。ふと見ると、水底の藻の塊を押し分けて、大きな鯉がのっそりと出て来た。そして気が進まなさそうにそこらを見まわしているらしかったが、やがてまたのっそりと藻のなかに隠れてしまった。 私はそれを見て、以前引きつけられた支那画の不思議な魚を思い出した。 私は少年の頃、よく魚釣に出かけて往った。ある時、鮒を獲ろうとして、小舟に乗って、村はずれの池に浮んだことがあった。 その日はどうしたわけか、釣れが悪かった。私はやけになって、すぐそこを游いでいる三寸ばかりの魚を目がけて鉤を下した。そして無理やりに餌を魚の鼻さきにこすりつけようとして、ふと物に驚いて、じっと水の深みを見おろした。 今まで雲にかげっていた春の陽(ひ)は、急にぱっと明るくそこらに落ちかかって来た。ささ濁りに濁った水の中に、青い藻が長く浮いていて、その蔭から大きな鯉が、真っ黒な半身(はんみ)をのっそりと覗けているではないか。鋼鉄の兜でも被(かぶ)ったようなそのしかめっ面。人を恐れないその眼の光り。私は見ているうちに、何だかぶ気味になった。 「池のぬしかも知れない。」 そう思うと、水草の蔭に、幾年と棲みながらえて、岸を外へ、広い天地に躍り出すこともできないで、絶えず身悶えして池を泳ぎまわり、絶えず限られた池を呪って来た老魚の生活の倦怠と憂鬱とが、私の小さな心を脅(おびや)かすように感じられて来たので、私は魚を獲ることなどはすっかり思いとまって、そこそこに舟を岸に漕ぎ戻したことがあった。 河魚といえば、いずれも新鮮な生命にぴちぴちしていて、その姿をしなやかな、美しいものとのみ思って、友達のような親みをもって遊び馴れて来た私に、この古池の鯉は、彼等の持つ冷たいぶ気味さと憂鬱との半面を見せてくれるに十分であった。 私はその後、どうしたわけか、魚の画が好きになって、出来る限りいろんな画家のものを貪り見たことがあった。画院の待詔で、游魚の図の名手として聞え、世間から范獺子と呼ばれた范安仁をはじめ、応挙、蘆雪、崋山などのな高い作物をも見たが、その多くは軽快な魚の動作姿態と、凝滞のない水の生活の自由さとを描いたもので、あの古池の鯉が見せてくれたような、淡水に棲む老魚の持つ倦怠と、憂鬱と、暗いぶ気味さとは、どの作品でも味うことができなかったのを、幾らか物足らず思ったものだ。たった一度、呉霊壁のあまりすぐれた出来とも思われない作品に、あり来りのそれとはちがって、鯉を水の怪生か何かのように醜く描いてあるのを見て、おもしろいと思ったことがあった。作者はどんな人かよく知らないが、多くの画家が生命の溌溂さをのみ見ているこの魚族を取り扱うのに、彼みずからの見方に従って、グロテスクの味をたっぷりと出したのが気に入って、いまだに忘れられないでいる。P.89~91 苺(20) 苺の花がこぼれたように咲いている。 白い小さな花で、おまけに地べたにこびりついて咲くので、どうかすると脚に踏まれそうだ。 女にも娘のうちは、内気で、きゃしゃで、一向目にも立たなかったのが、人の妻となって、子供でも産むと、急にはしゃいで、おしゃべりな肥大婦(ふとっちょ)になり、どうかすると亭主の頭に手をやりかねないようになるのがあるものだ。苺もそれで、花のうちはあんなにつつましいが、一度実を結ぶと、だんだん肥えて赤ら顔になり、よそ事ながら気恥かしくなるほど尻も大きく張って来るものだ。 その苺もやがて紅く熟して来る。 むかし、江蘇の汪 が清朝に二度勤めをして、翰林編修になっていた頃のことだった。あるとき客と一緒に葡萄を食べたことがあった。葡萄は北京の近くで採れたもので、大層うまかった。北の方で生れた客は、ところ自慢から にむかって、 「うまいですな。お故郷(くに)の江蘇にも、何かこんな果物のいいのがおありでしょうか。」 と訊いたものだ。すると、汪 は、 「私の故郷にですか。故郷には、夏になると楊梅(やまもも)が、秋になると柑子(こうじ:うすかわみかん)が熟しますよ。こんなことを話してるだけでも、口に唾(つばき)が溜ろうという始末で……もしか自分でそれをちぎった日には……」 といって、夢でも見ているような眼つきをしていたそうだが、それから暫くすると、急に病気だといって、役を罷めて故郷に帰ったということだ。 それを思うと、上方(かみがた)地方に住んで、朝夕を採り立ての苺を食べ馴れている人達は、P.92~93滅多に土地を離れて、天国にも旅立ちが出来ないわけだ。なぜというのに、天国にはそのむかしエバが盗んだ林檎の樹が立っている。もしかその実を見て、汪 のように、故郷へ帰りたくなっては大変だから……P.92~93
草の汁(21) この頃野へ出てみると、いろんな草が芽を出し、葉を出している。長い間つめたい土にもぐっていたものが、久しぶりに明るい暖かな世界へ飛び出して来たので、神経の先々まで喜びに顫えているようだ。太陽が酔っ払いであろうが、無頼漢(ならずもの)であろうが、そんなことには頓着なく、草はみな両手を差し上げている。 春の朝、生れたばかりのこの雑草が、露に濡れているのを見ていると、どの葉も、どの若芽もが、皆生(なま)のままで食べられそうに思われるものだ。物好きの人達のなかには、そんなことから思いついたものか、春の遊びの一つとして、よく草の葉を食べあるく催しをしたものがあった。 それにはまず、味噌を盛った小皿を用意しなければならない。それが出来ると、彼等は列をつくって野道に出かける。そして先達がこれと思う草を摘み、それに味噌をつけて食べると、後について往く人達は、順々にそれに倣って同じことをする。どんなことがあっても、それを嫌がってはならない約束なのだ。春の雑草でも食べようという人達は、牛のように無頓着で、牛のように従順でなければならないことは、彼等自身よく知っているはずだった。 一、二度違った草を噛むと、次の人が代って先達になることになっているが、こうして幾度か繰返しているうちには、それと知らないで、毒草を口にすることも少くない。そんな場合には、皆の唇は紫色に腫れあがり、胸先がちくちく痛むようなことがないでもなかったが、仮にも仲間を組んで、悪食(あくじき)の一つもしようという輩は、そんなことには一向驚かなかった。 こんな遊びをした仲間で、私の知っている人が一人あるが、その人はいっていた。 「遊びとしてはちょっと変なものですが、そんなことをやったおかげで、大分物知りになりました。私はその後大抵の草は一目見て、それが食べられるか、どうかということが分るようになりました。」P.94~95 木の芽(22) 1 勝手口にある山椒の若芽が、この頃の暖気で、めっきり寸を伸ばした。枝に手をかけて軽くゆすぶって見ると、この木特有の強い匂が、ぷんぷんとあたりに散らばった。 何という塩っぱい、鼻を刺すような匂だろう。春になると、そこらの草や木が、われがちに太陽の光を飽飲して、町娘のように派手で、贅沢な色で、花のおめかしをし合っているなかに、自分のみは、黄色な紙の切屑のようにじみな、細々(こまごま)した花で辛抱しなければならず、それがためには、大気の明るい椊込みのなかに出ることも出来ないで、うすら寒い勝手口に立っていなければならない山椒の樹は、何をおいても葉で自らを償い、自らを現すより外には仕方がなかった。そして葉は思いきり匂を撒き散らしているのだ。 Smithsonian Institution の McIndoo 博士は、嗅覚の鋭敏なのでな高い人だが、いつだったか、五、六ヶ月の実験の後、同じ巣に棲っている女王蜂と、雄蜂と、働蜂とをそれぞれ嗅ぎ分けることが出来た。博士はまた数多くの蜂蜜を集めて、その匂の差異を少しも間違わないで、嗅ぎ知ることが出来た。こうした実験の成功から博士は確信をもって、同じ巣に棲んでいる蜂という蜂は、それぞれちがった体臭をもっているので、彼等は暗い巣のなかで、やや離れていても、お互によく相手を嗅ぎ知ることが出来るのだといっている。 何の別ちもなく見えるこんなものの匂にも、味いわけようとすれば、味いわけ得られるだけの微かな相違はあるのだ。自然がかくばかり細かな用意をもって、倹約(しまつ)して物を使っているのに、この木の芽の塩っぱい匂は、あまりに濫費(むだづかい)に過ぎ、あまりに一人よがりに過ぎはしないだろうか。――とはいうものの、自然に恵まれないものは、しょうことなしに溜息でもつくの外はなかった。こうして洩らされた葉の溜息は、その静かな情熱を包んで、麝香猫のようにぷんぷんあたりを匂わせているのだ。 2 春さきに勝手口の空地に顔を出しているものに、山椒と蕗の薹とがある。蕗の薹は辛辣な皮肉家だけに、絶えず苦笑をしている。巧みな皮肉も、度を過ごすと少しあくどくなるように、蕗の薹の苦い風味を好む人も、もし分量が過ぎると、口をゆがめ、顔を顰めないわけにはゆかなくなる。皮肉家は多くの場合に自我主義者(エゴイスト)で、どうかすると自分の持味で他の味をかき乱そうとするからだ。それに較べると、山椒の匂は刺激はあるが、苦味がないだけに、外のものとの折れ合も悪くはない。 筍といういたずらものがある。春になると、土鼠のように、土のなかから産毛(うぶげ)だらけの頭を持出して来る奴だが、このいたずらもののなかには、えぐい味のがあって、そんなのはどうかすると、食べた人に世の中を味気なく思わせるものだ。また小芋という頭の円い小坊主がいる。この小坊主にもえぐいのがあって、これはまた食べた人を怒りっぽくするものだが、こんな場合に木の芽がつまに添えてあると、私たちはそれを噛んで、こうした小さな悪党達の悪戯(いたずら)から、やっと逃げ出すことが出来る。 3 イギリスのある詩人がいった。―― 「万人の鼻に嗅ぎつけられる匂が二つある。一つは燃える炭火の匂。今一つは溶ける脂肪の匂。前のは料理を仕過ぎた匂で、後のは料理を仕足りない匂だ。」 と。私は今一つ、木の芽や、またそれと同じような働きをするものをこれに附け加えて、料理の風味を添える匂としたいと思う。P.96~99 物の味(23) 1 「どんな芸事でも、食物の味のわからない人達に、その呼吸がわかろうはずがありませんよ。庖丁加減にちっとも気のつかない奴が、物の上手になったためしはないのですからな。」 四条派の始祖松村呉春は、人を見るとよくこんなことをいったものだ。 呉春は、『胆大小心録』の著者上田秋成から、「食いものは、さまざまと物好みが上手じゃった。」といわれたほどあって、味覚がすぐれて鋭敏な人で、料理の詮議はなかなかやかましかった。 呉春は若い頃から、暮し向がひどくふ自由なのにもかかわらず、五、六人の俳人仲間と一緒に、一菜会という会をこしらえて、毎月二度ずつ集まっていた。そしてその会では、俳諧や、絵画の研究の外に、いろいろ変った料理を味って、この方面の知識を蓄えることも忘れなかった。 2 呉春は困った時には、島原の遊女が昵懇客(なじみきゃく)へおくる艶書の代筆までしたことがあった。そんな苦しい経験を数知れず持っている彼も、画名があがってからの貧乏は、どうにも辛抱が出来なかった。 師の蕪村の門を出てから後も、呉春の画は一向に売れなかった。彼は自分の前に一点のかすかな光明をも見せてくれない運命を呪った。そしてとうとうわれとわれが存在を否定しようとした。生きようにも生きるすべのないものは、死ぬより仕方がなかった。 物を味うことの好きな呉春に、たった一つ、死ぬる前に味っておかねばならぬものが残されていた。 彼は一度でいいから、心ゆくまでそれを味ってみたいと思いながら、今日まで遂にそれを果すことが出来なかったのだ。 それはこの世に二つとない美味いものだった。しかし、それを食べたものは、やがて死ななければならなかった。彼はその死が怖ろしさに、今日までそれを味うことを躊躇していた。 それを味うことが、やがて死であるとすれば、いま死のうとする彼にとって、そんな都合のよい食物はなかった。 その食物というのは、外でもない。河豚(ふぐ)であった。 呉春は死のうと思いきめたその日の夕方、めぼしいものを売った金で、酒と河豚とを買って来た。 「河豚よ。今お前を味うのは、やがてまた死を味うわけなのだ。お前たち二つのものにここで一緒に会えるのは、おれにとっても都合が悪くはない。」 呉春は透きとおるような魚の肉を見て、こんなことを考えていた。そしてしたたか酒を煽飲(あお)りながら、一箸ごとに噛みしめるようにしてそれを味った。 河豚は美味かった。多くの物の味を知りつくしていた呉春にも、こんな美味いものは初めてだった。彼は自分の最期に、この上もない物を味うことが出来るのを、いやそれよりも、そういう物を楽しんで味うことによって、安々と死をもたらすことが出来るのを心より喜んだ。 暫くすると、彼の感覚は倦怠を覚え出した。薄明りが眼の前にちらつくように思った。麻痺が来かかったのだ。 「河豚よ。お前は美味かった。すてきに美味かった。――死もきっとそうに違いなかろう……」 呉春はだるい心の底で夢のようにそんなことを思った……。 柔かい闇と、物の匂のような眠とが、そっと落ちかかって来た。彼はその後のことは覚えなかった。 3 翌朝、日が高く昇ってから、呉春は酒の酔と毒魚の麻痺とから、やっと醒めかかることが出来た。 彼は亡者のような恐怖に充ちた眼をしてそこらを見まわした。やがて顔は空洞(うつろ)のようになった。彼が取り散らした室の様子を見て、昨夜からの始末をやっと思い浮べることが出来たのは、それから大分時が経ってからのことだった。 まだ痛みのどこかに残っている頭をかかえたまま、彼はぼんやりと考え込んでいたが、暫くすると、重そうに顔をもち上げた。そして 「死んだものが生きかえったのだ。よし、おれは働こう。何事にも屈託などしないぞ。」 と呻くように叫んだ。彼は幾年かぶりに自分が失くした声を取り返したように思った。 その途端彼は自分を殺して、また活かしてくれた河豚を思って、その味いだけは永久に忘れまいと思った。P.100~104 食 味 通(24) 1 物事に感じの深い芸術家のなかには、味覚も人一ばいすぐれていて、とかく料理加減に口やかましい人があるものだ。蕪村門下の寧馨児(ねいけいじ)として聞えた松村月渓もその一人で、平素よく、物の風味のわからない人達に、芸事の細かい呼吸が解せられようはずがないといいいいしていて、弟子をとる場合には、画よりも食物のことを先に訊いたものだそうだ。 だが、物の風味を細かく味いわけなければならない食味などいうものは、得てして実際よりも口さきの通がりの方が多いもので、見え坊な芸術家のなかには、どうかするとそんなものを見受けないこともない。ロシアの文豪プウシキンなども、自分が多くの文人と同じように詩のことしかわからないと言われるのが厭さに、他人と話をするおりには、自分の専門のことなぞは噫(おくび)にも出さないで、馬だの骨牌だのと一緒に、よく料理の事をいっぱし通のような口振で話したものだ。だが、ほんとうの事を言うと、プウシキンはアラビヤ馬とはどんな馬なのか、一向に見わけがつかず、骨牌の切札とは、どんなものをいうのか、知りもしなかった。一番ひどいのは料理の事で、仏蘭西式の本場の板前よりも、馬鈴薯を油で揚げたのが好物で、いつもそればかりを旨そうにぱくついていたという事だ。 2 そんな通がりの多い中に、日根対山は食味通として、立派な味覚を持っている一人だった。対山は岡田半江の高弟で、南宗画家として明治の初年まで存(ながら)えていた人だった。 対山はひどい酒好きだったが、いつもな高い剣菱ばかりを飲んでいて、この外にはどんな酒にも唇を濡そうとしなかった。何かの会合で出かける場合には、いつも自用の酒を瓢に詰めて、片時もそれを側より離さなかった。 ある時、土佐の藩主山内容堂から席画を所望せられて、藩邸へ上った 事があった。画がすむと、別室で饗応があった。 席画の出来栄(できばえ)にすっかり上機嫌になった容堂は、 「対山は酒の吟味がいこう厳しいと聞いたが、これは乃公の飲料(のみしろ)じゃ。一つ試みてくれ。」 といって、被布姿で前にかしこまっている画家に盃を勧めた。 対山は口もとに微笑を浮べたばかしで、盃を取り上げようともしなかった。 「殿に御愛用がおありになりますように、手前にも用い馴れたものがござりますので、その外のものは……」 「ほう、飲まぬと申すか。さてさて量見の狭い酒客じゃて。」容堂の言葉には、客の高慢な言い草を癪にさえるというよりも、それをおもしろがるような気味が見えた。「そう聞いてみると尚更のことじゃ。一献掬まさずにはおかぬぞ。」 対山は無理強いに大きな盃を手に取らせられた。彼は嘗めるようにちょっと唇を浸して、酒を吟味するらしかったが、そのまま一息にぐっと大盃を飲み干してしまった。 「確かに剣菱といただきました。殿のお好みが、手前と同じように剣菱であろうとは全く思いがけないことで……」 彼は酒の見極めがつくと、初めて安心したように盃の数を重ね出した。 3 あるとき、朝早く対山を訪ねて来た人があった。その人は道の通りがかりにふとこの南宗画家の家を見つけたので、平素のぶ沙汰を詫びかたがた、ちょっと顔を出したに過ぎなかった。 対山は自分の居間で、小型の薬味箪笥のようなものにもたれて、頬杖をついたままつくねんとしていたが、客の顔を見ると、 「久しぶりだな。よく来てくれた。」 と言って、心から喜んで迎えた。そしていつもの剣菱をギヤマンの徳利に入れて、自分で燗をしだした。その徳利はオランダからの渡り物だといって、対山が自慢の道具の一つだった。 酒が暖まると、対山は薬味箪笥の抽斗(ひきだし)から、珍らしい肴を一つびとつ取り出して卓子に並べたてた。そのなかには江戸の浅草海苔もあった。越前の雲丹もあった。播州路の川で獲(と)れた鮎のうるかもあった。対山はまた一つの抽斗から曲物(まげもの)を取り出し、中味をちょっぴり小皿に分けて客に勧めた。 「これは八瀬の蕗の薹で、わしが自分で煮つけたものだ。」 客はそれを嘗めてみた。苦いうちに何とも言われない好い匂があるように思った。対山はちびりちびり盃の数を重ねながら、いろんな食べ物の講釈をして聞かせた。それを聞いていると、この人は持ち前の細かい味覚で嚼みわけたいろんな肴の味を、も一度自分の想像のなかで味い返しているのではあるまいかと思われた。そして酒を飲むのも、こんな楽みを喚び起すためではあるまいかと思われた。 客はそんな話に一向興味を持たなかったので、そろそろ暇を告げようとすると、対山は慌ててそれを引きとめた。 「まあよい。まあよい。今日は久しぶりのことだから、これから画を描いて進ぜる。おい、誰か紙を持って来い。」 彼は声を立てて次の間に向って呼かけた。 画と聞いては、客も帰るわけには往かなかった。暫くまた尻を落着けて話の相手をしていると、対山は酒を勧め、肴を勧めるばかりで、一向絵筆をとろうとしなかった。客は待ちかねてそれとなく催促をしてみた。 「お酒も何ですが、どうか画の方を……。」 「画の方……何か、それは。」 酒に酔った対山は、画のことなどはもうすっかり忘れているらしかった。 「さっき先生が私に描いてやるとおっしゃいました……。」 客が不足そうに言うと、やっと先刻の出鱈目を思い出した対山は、 「うん。そのことか。それならすぐにも描いて進ぜるから、今一つ重ねなさい。」 と、またしても盃を取らせようとするのだ。 こんなことを繰り返しているうちに、到頭夜になった。そこらが暗くなったので、行灯が持ち出された。 へべれけに酔っ払った対山は、黄ろい灯影(ほかげ)にじっと眼をやっていたが、 「さっき画を進ぜるといったが、画よりももっといいものを進ぜよう。」 独語のように言って、よろよろと立ち上ったかと思うと、床の間から一振の刀を提げて来た。そしていきなり鞘をはずして、 「やっ。」 という掛声とともに、盲滅法に客の頭の上でそれを揮りまわした。 客はびくりして、取るものも取りあえず座から転び出した。 戸外の冷っこい大気のなかで、客はやっと沈着を取り返すことが出来た。そして朝からのいきさつを頭のなかで繰り返して思った。 「あの先生の酒は、物の味を肴にするのじゃなくて、感興を肴にするのだ。私というものも、つまりは八瀬の蕗の薹と同じように、先生にとって一つの肴に過ぎなかったのだ――たしかにそうだ。」P.105~111 徳富健次郎氏(25) 1 徳富健次郎氏が歿くなった。重病のことだったし、どうかとも思う疑いはあったが、いつも看護の人達にむかって、 「生きたい。まだ死にたくない。」 と、力強い声で叫んでいたということを聞き、因縁の深い、好きな伊香保へ往って、湯に浸りながら療養を尽しているということを聞くにつけて、この分ならば遠からずきっと快くなるだろうと思っていたのに、とうとう歿くなってしまったのは、残念の限りである。 徳富氏と私との交遊については、二、三年前刊行した私の『泣菫文集』に書いたことがあるから、ここにはなるべくそれに洩れた事柄を断片的に記して、この老文人がありし日の面影をしのびたいと思う。尤も話の都合上、前後聯絡のあるものは、記述が文集のそれと多少重複するかも知れないが、その辺は止むを得ないこととして、どうか大目に見てもらいたい。 私が初めて徳富氏に会ったのは、明治三十四、五年の頃で、その頃氏が住っていた東京の郊外渋谷の家でだった。三宅克己氏の水彩画がたった一枚壁にかかった座敷で、二月の余も鋏を入れないらしい、硬い髪の毛がうるさく襟筋に垂れかかるのを気にしながら、氏はぽつりぽつりと言葉少に話しつづけた。言葉つきも、態度も、極めて謙遜だったが、談話のところどころに鋭い皮肉が刃物のように光るのもおもしろかった。しかし、それよりもなおおもしろかったのは、百姓のそれを思わせるような大きな右手の人差指で、話をしいしい、気忙しく畳の上に書きものをする癖で、それとなく気をつけて見ていると、その書きものは、いろはとなり、ロオマ字となり、漢字となり、時には大入道の頭になったりした。 ちょうどその頃『ふ如帰』が出版せられて、大層評判が立っていたので、話はおのずとその方へ向いていった。 「こないだも喜多村緑郎君がやって来て、あれを芝居に仕組みたいからと相談を受けましたが、あれが芝居になるかしら、なると思うなら、あなたの方でいいように仕組んで下さいと返事すると、そんなら私の方で芝居にするから、舞台にかけたら是非一度見に来てくれというのです。自分の恥を大勢の中へわざわざ見に往くものがありますかというと、喜多村君変な顔をして帰って往きましたっけ。」 徳富氏は両手を胸の上に組んで、とってつけたように笑った。しばらくすると、氏はだしぬけに 「島崎藤村君が、こないだ国木田独歩君などと一緒に訪ねて来てくれて、久しぶりに大層話がはずみましたよ。」 といって、こんなことをいい足した。 「ところが、その後島崎君がある雑誌記者に向って、 「徳富君もこの頃では、玄関をこしらえるようになりましたね。」と話していたそうです。私は玄関など設けたことはありません。私にはそんな必要がありませんから。」 言葉の調子に、どこか不平らしいところがあった。私はどういって返事をしていいかわからなかった。 2 徳富氏の『黒潮(こくちょう)』第一巻が公にせられたのは明治三十六年だった。この小説は作そのものよりも、兄蘇峰氏に投げつけた絶交書のような序文の方でな高かった。 その年の夏、徳富氏は大阪へ遊びに来て、私を訪ねてくれたことがあった。ちょうど博覧会が天王寺に催されていた頃で、その賑いをあてこみに、難波で東京大阪の合併相撲があって、かなり人気を引立てていた。 徳富氏も私も相撲は好きだった。尤もあの前後に生れ合わせていて、それで相撲を好かなかったという人があったら、そんな人は人生のどんな事柄に対しても、興味が持てなかったに相違なかった。それほどまでにあの頃の相撲は溌溂としていた。伸びゆく生命そのものを見るような感じがあった。 二人の話はおのずと好きな方へ向いて往った。徳富氏は黒い大きな塵よけ眼鏡の奥から、眼を光らせながらいった。 「昨日一日合併相撲を見ましたが、大阪方の若島は強いですね。手もなく荒岩を投げつけましたよ。荒岩の一生にあのくらい手綺麗に投げられたことは、二度とないかも知れません。ことによると、常陸山なぞもやられないにも限らない……。」 「若島はいい力士ですが、常陸山に勝とうなどとは思われない。」 私は客の言葉に承引が出来なかった。 「いや、勝つかも知れない。」 「分でゆくと、まず七三かな。」 「いや、そんなことはない。五分五分だ。」 「まさか……。」 二人は暫くそんなことをいい争っていたが、ちょうどそこへ外の来客があったので、話はそれなりになってしまった。 その場所での両力士は預りで、誰が見ても八百長の臭みが高かったということだった。 すると、その翌月だったか、合併相撲の顔触をそのまま京都へ持ち込んで、花見小路で興行したことがあった。その楽(らく)の日に若島は常陸山につり出されて負けたが、若島としてはなかなか分のいい相撲をとったので、ひいき客のある人が祇園下の料理屋へこの力士を招いて、言葉を極めてその日の相撲ぶりを賞めたてたものだ。若島は気恥かしそうに頭へ手をやった。 「いや。そうお賞め下さるがものはありません。今度こそ初めて常陸関のずばぬけて強いのに驚きました。実は私五日も前からあの人が、今日の相撲につりに来るということを聞いて知っていましたのです。」 「ほう、誰の口から。」 「常陸関自身の口から。あの人は決して嘘を言いません。つると言ったが最後、外の手が出せる場合でもそれをしないで、つりぬくという気象ですから、私は安心してそれを防ぐ工夫ばかしをこらしました。顔が合って四つに組むと、常陸関はすぐにつりに来ました。私はかねての工夫通り外掛で防ぎました。二度目にまたつりに来ました。今度もどうやら持ちこたえました。すると、三度目のあのつりです。とうとう牛蒡(ごぼう)抜きにやられてしまいました。いやはや、強いのなんのといって、とてもお話になりません。」 私はその話を座敷に居合せた友人から聞いたので、早速それを認めて徳富氏に手紙を出した。氏からは何の返事もなかった。 3 徳富氏が最初の聖地巡礼に出かけるときのことだった。私と懇意なK書店の主人は、見送のためわざわざ神戸から門司まで同船することにした。 船が門司近くの海に来ると、書店の主人は今まで興じていた世間話を急に切上げにかかった。 「先生。私に一つのお願があるんですが……。」 「願い。――」徳富氏は急に更まった相手の容子に眼を光らせた。 「実は今度の御紀行の出版は、是非私どもの方に……。」 その言葉を押えつけるように、徳富氏は大きな掌面(てのひら)を相手の鼻さきでふった。 「待って下さい、その話は。私暫く考えて返事しますから。」 徳富氏はこういい捨てておいて、大跨に船室の方へあるいて行った。 ものの一時間も経つと、徳富氏はのっそりとK氏の待っている室へ入って来た。 「Kさん。あなたさっき門司からの帰りには、薄田君を訪ねるといってましたね。」 「ええ、訪ねます。何か御用でもおありでしたら……。」 「じゃ、御面倒ですが、これをお渡し下さい。」徳富氏はふところから手紙を一通取出した。「それから、あなたには……。」 K氏は何かを待設けるもののように胸を躍らせた。 「あなたにはいいものを上げます。私の原稿よりかもずっといい……。」 「何でしょう。原稿よりかもいいものというと……。」 K氏は顔一ぱいに微笑をたたえた。それを見下すように前に立ちはだかった徳富氏は、宣教師のようにもの静かな、どこかに力のこもった声でいった。 「神をお信じなさい。ただそれだけです。」 「神を……。」書店の主人は、その神をさがすもののように空虚な眼をしてそこらを見廻した。 船は門司の沖に来かかったらしく、汽笛がぼうと鳴った。 海近い備中の郷里の家で、私がK氏の口からこんな話を聞きながら、受取った徳富氏の手紙には、次のような文句があった。 ふ図思ひ立ちてキリストの踏みし土を踏み、またヤスナヤポリヤナにトルストイ翁を訪はむと巡礼の途に上り申候。神許し玉はば、一年の後には帰り来り、或は御目にかかるの機会ある可く候。 大兄願はくば金玉に躯を大切に、渾ての点において弥々御精進あらんことを切に祈上候。 一九〇六、仏誕の日関門海峡春雨の朝
徳富健次郎
4 私は一度K書店の主人と道づれになって、今の粕谷の家に徳富氏を訪ねたことがあった。門を入って黄ばんだ庭木の下をくぐって往くと、そこに井戸があった。K氏はその前を通りかかるとき、小声で独語のように、 「そうだ。労働は神聖だったな。」 と、口のなかでつぶやいたらしかった。私はそれを聞きのがさなかった。 「何だね、それ。」 K氏は何とも答えなかった。二人は原っぱのよう名前栽のなかに立っている一軒家に通された。日あたりのいい縁側に座蒲団を持ち出してそれに座ると、K氏はにやにや笑い出した。 「さっき井戸端を通るとき、私が何か言ったでしょう。あれはね、以前私がこちらにお伺いしたとき、先生が、自分の代りに風呂の水を汲んでくれるなら、面会してもいいとおっしゃるので、仕方がなく汲みにかかりました。こちらの井戸は湯殿とは大分遠いところにあるので、なかなか容易な仕事じゃありません。やっと汲み終えて、客間へ通ると、先生が汗みずくになった私の顔を見られて、 「Kさん。労働は神聖ですな。」 と言って笑われましたっけ。今あすこを通りかかって、それを思い出したものですから……。」 「いつぞやの「神を信ぜよ。」と同じ筆法だ。徳富君一流の教訓だよ。」 私がそういって笑っているところへ、主人がのっそりと入って来た。そしてそこらを眺め廻しながら、「この家いいでしょう。土地の賭博打がもてあましていたのを、七十円で買い取ったのです。時々勝負のことから、子分のものの喧嘩が初まるので、そんなときの用意に、戸棚なぞあんなに頑丈に作ってありますよ。」 といって、家の説明などしたりした。 その日はいろんなことを話合った。夕方になって帰ろうとすると、徳富氏は、 「あなた方にさつまいもを進ぜましょう。私が作ったのです。これ、こんなに大きいのがありますよ。」 と言って、縁の下から小犬のような大きさのさつまいもを、幾つも幾つも掘り出して、それを風呂敷に包もうとした。私達は帰り途の難渋さを思って、幾度か辞退したが、頑固な主人はどうしても承知しなかった。 やっと上高井戸の停留所についた頃には、私達の手は棒のようになっていた。P.112~122 芥川龍之介氏の事(26) 今は亡き芥川龍之介氏が、大阪毎日新聞に入社したのは、たしか大正八年の二月末だったと思う。話がまとまると、氏は早速入社の辞を書いてよこした。原稿はすぐにしょく字場へ廻されて活字に組まれたが、ちょうど政治季節で、おもしろくもない議会の記事が、大手をふって紙面にのさばっている頃なので、その文章はなかなか容易に組み入れられようとしなかった。あまり日数が経つので、私はとうとう気を腐らして、頑固な編輯整理に対する面当(つらあて)から、芥川氏の同意を得て、その原稿を未掲載のまま撤回することにした。そのゲラ刷が一枚残って手もとにあったのを、今日はからずも見つけた。読みかえしてみると、皮肉好きな故人の面目が、ありありと文字の間にうかがわれる。それをここに掲げるのは、故人を愛する人達のために、一つでも多くの思い出を供したい微意に外ならぬ。
入社の辞
予は過去二年間、海軍機関学校で英語を教えた。この二年間は、予にとって決して不快な二年間ではない。何故と云えば予は従来、公務の余暇を以て創作に従事し得る――或は創作の余暇を以て公務に従事し得る恩典に浴していたからである。 予の寡聞(かぶん)を以てしても、甲教師は超人哲学の紹介を試みたが為に、文部当局の忌諱(きい)に触れたとか聞いた。乙教師は恋愛問題の創作に耽ったが為に、陸軍当局の譴責を蒙ったそうである。それらの諸先生に比べれば、従来予が官立学校教師として小説家を兼業する事が出来たのは、確に比類稀(ひるいまれ)なる御上(おかみ)の御待遇(ごたいぐう)として、難有く感銘すべきものであろう。尤もこれは甲先生や乙先生が堂々たる本官教授だったのに反して、予は一介(いっかい)の嘱托(しょくたく)教授に過ぎなかったから、予の呼吸し得た自由の空気の如きも、実は海軍当局が予に厚かった結果と云うよりも、或は単に予の存在があれどもなきが如くだった為かも知れない。が、そう解釈する事は独り礼を昨日の上官に失するばかりでなく、予に教師の口を世話してくれた諸先生に対しても甚だ御気の毒の至(いたり)だと思う。だから予は外に差支えのない限り、正に海軍当局の海の如き大度量に感泣して、あの横須賀工廠の恐る可き煤煙を肺の底まで吸いこみながら、永久に「それは犬である」と講釈を繰返して行ってもよかったのである。 が、不幸にして二年間の経験によれば、予は教育家として、殊に未来の海軍将校を陶鋳(とうちゅう)すべき教育家として、いくら己惚れて見た所が、到底然るべき人物ではない。少くとも現代日本の官許教育方針を丸薬の如く服膺(ふくよう)出来ない点だけでも、明(あきらか)に即刻放逐さるべきふ良教師である。勿論これだけの自覚があったにしても、一家眷属(けんぞく)の口が乾上(ひあが)る惧がある以上、予は怪しげな語学の資本を運転させて、どこまでも教育家らしい店構(みせがま)えを張りつづける覚悟でいた。いや、たとい米塩(べいえん)の資(し)に窮さないにしても、下手は下手なりに創作で押して行こうと云う気が出なかったなら、予は何時(いつ)までも名誉ある海軍教授の看板を謹んでぶら下げていたかも知れない。しかし現在の予は、既に過去の予と違って、全精力を創作に費さない限り人生に対しても又予自身に対しても、済まないような気がしているのである。それには単に時間の上から云っても、一週五日間、午前八時から午後三時まで機械の如く学校に出頭している訳に行くものではない。そこで予は遺憾ながら、当局並びに同僚たる文武教官各位の愛顧に反(そむ)いて、とうとう大阪毎日新聞へ入社する事になった。 新聞は予に人並の給料をくれる。のみならず毎日出社すべき義務さえも強いようとはしない。これは官等の高下をも明かにしない予にとって、白頭(はくとう)と共に勅任官を賜るよりは遥に居心(いごこち)の好い位置である。この意味に於て、予は予自身の為に心から予の入社を祝したいと思う。と同時に又我帝国海軍の為にも、予の如きふ良教師が部内に跡を絶った事を同じく心から祝したいと思う。 昔の支那人は「帰らなんいざ、田園将(まさ)に蕪(ぶ)せんとす」とか謡った。予はまだそれほど道情(どうじょう)を得た人間だとは思わない。が、昨(さく)の非を悔い今の是(ぜ)を悟っている上から云えば、予も亦同じ帰去来(ききょらい)の人である。春風は既に予が草堂の簷(のき)を吹いた。これから予も軽燕と共に、そろそろ征途(せいと)へ上ろうと思っている。 同じ年の五月上旬、芥川氏は氏の入社と同時に、東京日々の方へ迎えられた菊池寛氏と連立って、初めて大阪に来たことがあった。新聞社へ来訪したのが、ちょうど編輯会議の例会のある十日の夕方だったので、私は二氏に会議の席へ顔出しして、何かちょっとした演説でもしてもらおうとした。演説と聞いて、菊池氏は急に京都へ行かなければならない用事を思い出したりしたので、芥川氏はふ承ぶ精に会議に出席しなければならなくなった。 その晩、芥川氏が何を喋舌(しゃべ)ったかは、すっかり忘れてしまったが、唯いくらか前屈みに演壇に立って、蒼白い額に垂れかかる長い髪の毛をうるさそうに払いのけながら、開口一番、 「私は今晩初めてこの演壇に立つことを、義理にも光栄と心得なければならぬかも知れませんが、ほんとうは決して光栄と思うものでないことをまず申上げておきます……」と氏一流の皮肉を放ったことだけは、いまだに覚えている。この演説にはさすがの芥川氏も閉口したと見えて、東京へ帰ってから初めての手紙に、 「しかし演説には辟易しました。演説をしなくてもいいという条件がないと、ちょいと編輯会議にも出席出来ませんな。」といってよこしていた。P.123~127 哲人の晩年(27) 三十年間、The Ladies' Home Journal の記者として名声を馳せた Edward Bok が、小新聞の速記者として働いていたのは、まだ十五、六歳の少年の頃だった。その頃彼は思い立って、ボストンへ名士の訪問に出かけて往ったことがあった。 彼はそこで、詩人の Oliver Wendell Holmes や、Longfellow や、宗教家の Phillips Brooks などに会った。これらの名士たちは、幾分のものずきも手伝って、みんな親切にこの少年をもてなした。そしていろいろ有益な談話をしてくれたり、少年の差出した帳面に、それぞれ署名をしてくれたりした。こんなことで、少年のボストンにおける滞在は、譬えようもない楽しいものだった。 少年は、最後に Emerson を訪問しようとした。この文豪こそは、少年が最も尊敬もし、また一番会いたくも思っている人だった。 少年は途中で、Emerson の家近く棲んでいる女流文学者の Louise Alcott を訪ねて、あたたかい煖炉の傍で、いろんなお饒舌を取換わした。少年の口からその日の予定を聞いた女史は、気づかわしそうに言った。 「さあ、あの方を訪ねたところで、会ってもらえるかしら。この頃は滅多にお客さまにお会いにならないんですからね。どうもお弱くてお気の毒なんですわ。――でも、折角ですからお宅までぶらぶら御一緒に出かけてみましょうよ。」 女流文学者は、外套と帽子とを身につけて、気軽に先へ立って案内した。 長い間、コンコオドの哲人として、中外の人から崇められていたこの老文豪が、ちょうど死ぬる前の年のことであった。 Emerson の家に着くと、入口に老文豪の娘さんが立って迎えていた。Alcott 女史が少年の希望を述べると、娘さんはつよく頭を掉った。 「父はこの頃どなたにもお目にかかりません。お目にかかりましたところで、かえって気難しさを御覧に入れるようなものですから。」 少年は熱心に自分の渇仰を訴えた。その純真さは相手を動かさないではおかなかった。 「じゃ、暫く待ってて下さい。私訊いてみますから。」 娘さんは奥へ入った。Alcott 女史も後について往った。暫くすると、女史はそっと帰って来た。見ると、眼は涙に濡れていた。 「お上り。」 女史の言葉は短かかった。少年はその後について、室を二つ通りぬけた。三つ目の室の入口に、先刻の娘さんが立っていたが、眼は同じように潤んでいた。 「お父さま――」彼女は一言いった。見ると、机によりかかって Emerson がいた。娘の言葉に、彼は驚くばかり落着き払った態度で、やおら立上ってその手を伸した。そして少年の手を受取ると、俯(うつ)むき加減につくづくとこの珍らしい来客に見入った。それは悲しい柔和な眼つきだったが、好意といっては少しも感じられなかった。 彼は少年を机に近い椅子に坐らせた。そして自分は腰を下そうともしないで、窓際近く歩いて往って、そこに衝立ったまま口笛を吹いていた。少年は腑に落ちなさそうに、老文豪のこうした素振に見とれていたが、ふと微かな啜泣(すすりな)きの声を聞きつけて、あたりを見廻すと、それは娘さんのせいだとわかった。娘さんはそっと室から滑り出た。少年は救いを求めるように Alcott 女史の方を見た。女史は脣に指を押しあてて、じっとこちらを見つめていた。黙っていよという合図なのだ。少年はすっかり弱らされた。 暫くすると、老文豪は静かに窓際を離れた。そして前を通るとき、ちょっと少年に会釈をして自分の椅子に腰を下した。二つの悲しそうな眼は、おのずと前にいる少年の顔に注がれた。さきがたからつき穂がなくて困りきっていたこの小さな客人は、もう黙っていられなくなったように思った。 少年はここの主人の親友 Carlyle のことを語り出した。そしてこの人の手紙があったら、一通いただけないかと言った。 Carlyle のなを聞くと、主人は不思議そうに眼をあげた。そしてゆっくりした調子で、 「Carlyle かね。そう、あの男は今朝ここにいましたよ。あすの朝もまたやって来るでしょう。」 と、まるで子供のように他愛もなく言っていたが、急に言葉を改めて、「何でしたかね、君の御用というのは――」 少年は自分の願いを繰返した。 「そうか。それじゃ捜してあげよう。」主人は打って変って快活になった。「この机の抽斗(ひきだし)には、あの男の手紙がどっさりあるはずだから。」 それを聞くと、Alcott 女史の潤んだ眼は喜びに輝いた。口もとには抑えきれぬ微笑の影さえ漂った。 室の容子ががらりと変って来た。老文豪は手紙と書類とが一杯詰っている机の抽斗をあけて、中を捜し出した。そしてときどき眼を上げて少年の顔を見たが、その眼はやさしい情味に溢れていた。少年がわざわざそのために紐育(ニューヨーク)から出かけて来たことを話すと、「そうか。」と言って、明るく笑っていた。 老文豪は、少年が期待したような何物をも捜し出さないで、そろそろ机の抽斗を閉めにかかった。そしてまた低声で口笛を吹きながら、不思議そうにじろじろと二人の顔を見まわした。 少年はこの上長くはもう居られまいと思った。のちのちの記念になるものが何か一つ欲しかった。彼はポケットから帳面を取出した。 「先生。これに一つお名前を書いていただけませんでしょうか。」 「名前。 「ええ、どうぞ。」少年は言った。「先生のお名前の Ralph Waldo Emerson ってえのを。」 その名前を聞いても、文豪は何とも感じないらしかった。 「書いて欲しいと思う名前を書きつけて御覧。すれば、私がそれを見て写すから。」 少年は自分の耳を信ずることが出来なかった。だが、彼はペンを取上げて書いた。―― Ralph Waldo Emerson, Concord; November 22, 1881 ――と。 老文豪は、それを見て悲しそうに言った。 「いや、有難う。」 それから彼はペンを取上げて、一字ずつゆっくりとお手本通りに自分の名前を書き写した。そして所書きの辺まで来ると、仕事が余り難しいので、もじもじするらしく見えたが、それでもまた一字一字ぼつぼつと写し出した。所書きには、書き誤りが一つ消してあった。やっと書き写してしまうと、老文豪は疲れたようにペンを下において、帳面を持主に返した。 少年はそれをポケットに蔵(しま)い込んだ。老文豪の眼が、机の上に取り残された先刻(さっき)少年が書いたお手本の紙片に落ると、急に晴やかな笑がその顔に浮んで来た。 「私の名前が書いて欲しいのだね。承知した。何か帳面でもお持ちかい。」 びっくりさせられた少年は、機械的にも一度ポケットから帳面を取出した。文豪は手ばやく器用に紙をめくって、ペンを取上げたかと思うと、紙片を側におしのけたまま、一気にさっと註文通りの文句を書き上げてしまった。 二人が礼を言って、暇乞いをしようとすると、主人の老文豪はにこにこしながら立ち上って、 「まだ早いじゃないか。こちらにいるうちに、も一度訪ねて来ないかね。」 と、愛想を言った。そして少年の手を取って握手したが、それは心からの温い力の籠ったものだった。 「往くときと、来たときと、こんなに気持の違うのは初めてだ。」 少年は子供心にそう思った。P128~134 盗まれぬように(28) 1 世の中に茶人ほど器物を尚ぶものはあるまい。利休は茶の精神が侘びと寂との二つにある。価の高い器物を愛するのは、その心が利欲を思うからだ。「欠けたる摺鉢にても、時の間に合ふを茶道の本意。」だといった。本阿弥光悦は、器物の貴いものは、過って取毀したときに、誰でも気持ちよく思わないものだ。それを思うと、器は粗末な方がいいようだといって、老年になって鷹ヶ峰に閑居するときには、茶器の立派なものは、それぞれ知人に分けて、自分は粗末なもののみを持って往ったということだ。また徳川光圀は、数奇な道に遊ぶと、器物の欲が出るものだといって、折角好きな茶の湯をも、晩年になってふっつりと思いとまったということだ。こんな人達がいったことに寸分間違いないとしても、器物はやはり立派な方がよかった。器がすぐれていると、それに接するものの心までが、おのずと潤いを帯びて、明るくなってくるものだ。 2 天明三年、松平ふ昧は希代の茶入油屋肩衝(あぶらやかたつき)を自分の手に入れた。その当時の取沙汰では、この名器の価が一万両ということだったが、事実は天明の大飢饉の際だったので、一千五百両で取引ができたのだそうだ。一国の国守ともある身分で、皆が飢饉で困っている場合に、茶入を需めるなどの風流沙汰は、実はどうかと思われるが、ふ昧はもう夙くそれを購ってしまったのだし、おまけに彼自身らももう亡くなっているので、今更咎め立てしようにも仕方がない。*だが、これにつけても真実(ほんとう)だと思われるのは、骨董物は飢饉年に買いとり、娘は箪笥の安いときに嫁入りさせるということである。 不昧はこの肩衝の茶入に、円悟の墨蹟をとりあわせて、家宝第一ということにした。そして参勤交代の折には、それを笈(おい)に収めて輿側(かごわき)を歩かせたものだ。その愛撫の大袈裟なのに驚いたある人が、試しに訊いたことがあった。 「そんなに御大切な品を、もしか将軍家が御所望になりました場合には…」 「その代わりには、領土一箇国を拝領いたしたいもので。」 あるとき、某の老中がその茶入の一見を懇望したことがあった。不昧は承知して、早速その老中を江戸屋敷に招いた。座が定まると、ふ昧は自分の手で笈の蓋を開き、幾重にもなった革袋や箱包をほどいた。中から取り出されたのは、胴に珠のような潤いををもった肩衝の茶入だった。ふ昧はそれを若狭盆に載せて、ずっと客の前に押し進めた。 老中は手に取りあげて、ほれぼれと茶入に見入った。口の捻り、肩の張り、胴から裾へかけての円み、畳付のしずかさ。どこに一つの非の打ちどころもない、すばらしい出来だった。老中はそれをそっと盆の上に返しながら、いかにも感に堪えないようにいった。 「まったく天下一と拝見いたしました。」 その言葉が終わるか、終わらないかするうちに、ふ昧は早口に、 「もはやおよろしいですか。」 といいざま、ひったくるように若狭盆を手もとに引き寄せた。まるで老中が力ずくで、その茶入を横取しはしないかと気づかうかのように 3 The Ladies' Home Jornal の記者として、三十年も働いていた Edward Bok が、まだ十五、六の少年だった。名士訪問を志して、ボストンに牧師としてな高い Phillips Brooks を訪ねたことがあった。牧師はその当時蔵書家として聞こえた一人だった。 訪問の前日、この牧師の友人である Wendell Philips に会った。少年の口から明日の予定を聞いたこの雄弁家は、笑い笑い言ってきかせた。 「明日は Brooks を訪ねるんだって。あの男の書斎にはぎっしり本がつまっていて、それにはみんな記号と書入れがしてあるんだよ。訪ねて往ったら、是非その本を見せてもらいなさい。そしてその男がよそ見しているときに、二冊ばかりポケットに失敬するがいい。何よりもいい記念になるからな。なに、どっさり持合せがあるんだ。発見(みつけ)られる心配だなんかありゃしないよ。」 少年は Brooks に会うと、すぐにこの話をした。牧師は声を立てて笑った。 「子供に与える大人の助言としては、随分思い切ったことをいったものだな。」 Brooks はこの幼い珍客を、自分の書斎に案内するとことを忘れなかった。そこには世間の評判通りに、沢山の書物がぎっしり書棚に詰っていた。 「ここにある書物には、それぞれ書入れがしてあって、中にはそのために頁が真黒になっているものもある。世間にはこの書入れを嫌がる人もあるようだが、しかし、書物が俺に話しかけるのに、俺の方で返事をしないわけには往かんじゃないか。」 こういって、牧師は書棚から一冊のバイブルを引出して見せた。それは使い古して、表紙などくたくたになっている本だった。 「俺のところにはバイブルは幾冊もあるよ。説教用、儀式用とそれぞれ別々になっているが、この本は俺の自家用というわけさ。見なさい、こんなに書入れがしてある。これはみんな使徒パウロと俺との議論だよ。随分はげしい議論だったが……さあ、どちらが勝ったか、それは俺にもわからない。」 少年の眼が、どうかすると細々した書入れよりも、夥しい書棚に牽きつけられようとするのを見てとって Brooks は、 「お前さんも、本が好きだと見えるな。何ならボストンへやって来たときには、いつでも家へ来て、勝手にそこらの本を取出して見てもかまわないよ。」P.115~139 女流音楽家(29) プリマ・ドンナの Tetrazzini 夫人が演奏旅行をして、アメリカの Buffalo 市に来たことがあった。夫人の支配人は、土地で聞えた Statler ホテルへやって来て、夫人のために三室続きの部屋を註文した。その当時、ホテルには二室続きの部屋は幾つかあったが、註文通りの部屋といっては、一つも持合せがなかった。だが、ホテルの主人は、このな高い女流音楽家をほかの宿屋にとられることが、どれだけ自分の店の估券にかかわるかをよく承知しているので、平気でそれを引受けた。 「承知仕りました。夫人はいつ頃当地にお着になりますお見込で……」 「今晩の五時には、間違いなく乗込んで来るはずです。」 主人は時計を見た。ちょうど午前十時だった。 「よろしうございます。それまでにはちゃんとお部屋を用意いたして、皆様のお着をお待ちうけ申すでございましょう。」 支配人の後姿が見えなくなると、ホテルの主人は大急ぎで出入の大工を二、三人呼びよせた。そして二室続きの部屋と第三の室とを仕切っている壁板をぶち抜いて、そこに入口の扉をつけた。削り立ての板には乾きの速い塗料を塗り、緑色の帷(カアテン)を引張って眼に立たぬようにした。汚れたり傷がついたりしていた床の上には、派手な絨氈を敷いて、やっと註文通りの三室続きの部屋が出来上った。それは約束の午後五時に五分前のことだった。 それから暫くすると、支配人を先に、美しく着飾った Tetrazzini が入って来た。そしてホテルの主人から新しく出来上った部屋のいきさつを聞くと、満足そうにほほ笑んだ。 「まあ、そんなにまでして下すったの。ほんとうにお気の毒ですわ。」 だが、Tetrazzini よ。そんなに己惚れるものではない。女という女は、どうかすると相手の男の胸に、第二第三の新しい部屋をこしらえさせるもので、男がその鍵を滅多に女に手渡ししないから、女がそれに気づかないまでのことだ。――唯それだけのことなのだ。P.141~142 演説つかい(30) バアナアド・ショウは、その脚本の一つで、英雄シイザアの禿頭を、若いクレオパトラの口でもって思う存分に冷かしたり、からかったりしている。どんな偉い英雄でも、クレオパトラのような美しい女に、折角隠していた頭の禿を見つけられて冷かされたのでは、少々参るに相違ない。 アメリカの法律家で、長いこと下院の雄弁家として聞えた男に Thomas Reed というのがあった。この男があるとき、まだ馴染のない理髪床へ鬚を剃りに入って往ったことがあった。 黒ん坊の鬚剃り職人は、髪の毛の薄くなった客の頭を見遁さなかった。そしてあわよくば発毛剤(けはえぐすり)の一罎を客に押しつけようとした。 「旦那。ここんところが少し薄いようだが、こんなになったのは、随分前からのことでがすか。」 「禿げとるというのかね。>法律家は石鹸の泡だらけの頤を動かした。「わしが産れ落ちた時には、やはりこんな頭だったよ。その後(ご)人が見てうらやましがるような、美しい髪の毛がふさふさと生えよったが、それもほんの暫くの間で、すぐにまた以前のように禿げかかって来たよ。」 黒ん坊はそれを聞くと、鼻さきに皺をよせて笑っていたが、発毛剤のことはもうあきらめたらしく、黙りこくって剃刀を動かしていた。 客が帰って往った後で、そこに待合せていた男の一人が、今までそこで顔を剃らせていた客は、議院きっての雄弁家だということを話した。すると、黒ん坊は厚い唇を尖らせて、喚くようにいった。 「雄弁家だって。そんなこと知らねえでどうするものか。わしら誰よりもよくあの旦那が演説遣いだってえことを知ってるだよ。」P143~144 名 前(31) 1 劇場監督として聞えた Charles Frohman が、あるとき友人の劇作家 J. M. Barrie と連れ立って、自分の関係しているある劇場の楽屋口から入ろうとしたことがあった。 そこに立っていた門番の老人は、胡散そうな眼つきをして、先きに立った Frohman の胸を突いた。 「ここはあんた方の入る所じゃござりません。」 それを聞いた劇場監督は、すなおに頷いて後へ引き返した。 その場の様子を見た Barrie は、腑に落ちなさそうに訊いた。 「何だって君、あの爺さんに君な名前を打ち明けないんだね。」 「とんでもない。」劇場監督はびっくりしたように言った。「そんなことでもしてみたまえ。爺さん、おっ魂消(たまげ)て死ぬかも知れないぞ。あれは御覧の通りの善人で、唯もう仕事大事に勤めているんだからね。」 2 アメリカの俳優として聞えた Joe Jefferson が、あるときデトロイトの銀行で、持って来た小切手の支払を受けようとしたことがあった。 出納係の若い男は、小切手から離した眼を、窓の外に立っている男に移して、じろじろとその顔に見入った。 「失礼ですが、あなたが Jefferson さん御当人だとおっしゃるのは。」 俳優はそれを聞くと、ちょっと眼をぱちくりさせたが、急に舞台に立っている折のように声に抑揚(めりはり)をつけて、 “If my leedle dog Schneider was only here, he'd know me.” と流れるように言った。 「いや、間違いはございません。」 出納係は喜ばしそうに叫んだ。そして小切手はすぐに正金に換えられた。 3 明の詩画家許友は、ぶくぶくに肥った背低(せひく)で、身体中に毛といっては一本も生えていなかった男だが、人が訪ねて来ても、それに答礼するでもなく、そんな交際(つきあい)には一向無頓着であった。あるとき客が来て、詩だの画だのいろんな話をして帰って往ったが、その後で許友は家の者に、 「今のは何という男だったかな。」 と訊いたので、 「あなたの御存じない人が、私に判ろうはずはありません。」 というと、許友は禿げた頭に手をやりながら、 「俺には一向覚えがないでな。」 と呟くように言ったということだ。P.145~147 返 辞(32) 1 新入学生が、初めて学校の校庭を踏むときには、地べたを護謨毬(ゴムまり)か何ぞのように感じるほど、神経質になるものだが、ある年の新学期にエル大学に入って来た若い人たちのなかに、とりわけ神経質な学生が一人あった。 部長 Jones は、その学生の家族たちと懇意にしていたので、学生が訪ねて来ると、愛想ぶりに連れ立って学校のなかを方々案内して見せた。 その時ちょうど教会堂の鐘が鳴り出していた。さきがたからしきりと話の題目を捜していた若い学生は、やっときっかけを見つけたように言葉をかけた。 「あの鐘は、すてきによく鳴るじゃありませんか。」 部長はずぼんの隠しに両手を突っ込んだまま、他の事でも考えているらしく、何一つ答えてくれなかった。新入生は胸に動悸を覚えた。 「あの鐘はよく鳴りますね。僕気に入っちゃった。」 彼は半分がた自分に話すもののように言った。部長は何とも答えなかった。 「鐘の音が、たまらなくいいじゃありませんか。」 新入生は泣き出しそうになって、やけに声を高めた。 「何かお話しでしたか。」部長はやっと気づいたように、今まで地べたに落していた考ぶかい視線を、若い道連れの方へさし向けた。「あの地獄の鐘めが、いやにうるさく我鳴り立てるもんだから、つい……」 2 な高い提琴家ミイシャ・エルマン氏が、初めて大阪に来て、中之島の中央公会堂で演奏を試みたときのことだった。ずかずかと楽屋へ訪ねて往ったある若い音楽批評家は、そこにおでこで小男の提琴家が立っているのを見ると、いきなりまずい英語で話しかけた。 「すばらしい成功ですね。ところで、どうです。この会場(ホオル)のお感じは。別に悪くはないでしょう。」 熱心な聴衆を二千あまりも収容するこの立派な会場を持っていることは、若い批評家の土地(ところ)自慢の一つだった。彼はこの名誉ある音楽家から、それに折紙がつけてもらいたかったのだ。 エルマン氏は、禿げ上った前額に滲み出る汗を無雑作に手帛で拭きとりながら、ぶっきらぼうに答えた。 「ここは音楽会をする場所じゃないね。大砲をうつところだよ。大砲をね……」P.148~150 慈善家(33) 男というものは、郵便切手を一枚買うのにも、同じ事なら美しい女から買いたがるものなのだ。――故ウィルソンの女婿 Mcadoo 氏はよくこの事実を知っていた。 あるとき Mcadoo 氏が、自分の関係しているある慈善事業のために、慈善市(バザア)を催したことがあった。氏はその売子のなかに、幾人かの美しい女優を交えておくのを忘れなかった。 その日になって、氏が会場の入口を入ろうとすると、そこには紀念の花束を売りつけようとして、四、五人の若い女たちが客を待っていた。そのなかに一人ずばぬけて美しい女優が交っていたが、その女はかねて顔馴染な Mcadoo 氏を見ると、顔一杯に愛嬌笑いを見せながら、いち早く歩み寄って来た。そしてきゃしゃな指さきに露の滴るような花束をとり上げて、 「あなた、お一つどうぞ……」 と、押しつけようとした。 Mcadoo 氏はあぶなくそれを受け取ろうとして、ふと第二の売子の足音を聞いてその方にふり向いた。それは顔立も、朊装も、見るから地味な婦人だった。氏は急に考をかえて、その婦人から花束を一つ買い取った。 「あなた、なぜ私のを買って下さらないの。」 女優はわざとぷりぷりした顔をしてみせた。以前にも増してそれは美しかった。地味な姿の売子が、新しい来客の方へと急ぎ足に往ったのを見てとった Mcadoo 氏は、低声で女優に言った。 「でも、あなたはあまりお美しいから。僕は今日はいっぱし慈善家になりおおせたいつもりだから、わざと地味な方のを選んで買いました。」 この言葉は覿面(てきめん)だった。女優はそれを聞くと、胸に抱えた花束をそっくりそのまま買い取られでもしたように、顔中を明るくして満足そうに笑った。 間違い(34) 牧師 Phillips Brooks が、あるとき宗教雑誌から訊かれた問題について、ちょっとした返事を書き送ったことがあった。そのなかに、 “We pray too loud and work too little.” という文句があったのを、椊字工はそれを拾う場合に、うまい間違いをした。刷り上った雑誌に現われた文句は次のようになっていた。 “We bray too loud and work too little.” Bray は「驢馬のように啼く」という言葉だ。それを見た牧師は、心から微笑(ほほえ)まぬわけに往かなかった。そして感心したように人に話した。 「植字工のしたことは、全くほんとうですね。正誤など書き送る気は更にありませんよ。」P.153~153 救 済(35) 滑稽作家マアク・トウェンのところへ、ふだん懇意にしているある娘から、近頃身体の加減がよくないことを訴えて来たので、作家は保健用の電気帯でも買ってみたらどうかと知らせてやったことがあった。 すると、暫く経ってから、その娘から手紙が来た。なかに次のような文句があった。 「お言葉に従いまして、私は電気帯を一つ求めました。ですが、一向に助かりそうとは思われません。」 作家はすぐに返事を認めた。 「私は助かりました。会社の在庫品が一つ捌(は)けましたので。」(154~154) 良人改造(36) 会社官衙(かんが)の昼間の勤めをすませて、夕方早く家に帰って来べきはずの良人が、途中でぐれて、外で夜更しをするということは、うちで待っているその妻にとっては堪えがたい苦痛に相違ない。 そういうだらしのない男に連れ添った米国婦人の一人が、良人のそんな癖を治そうとして、いいことを思いついた。良人の穿き古した靴が破けかかって、別なのを新調しなければならないのを見てとった妻は、「これまでのあなたの靴はあまり大き過ぎて、まるでお百姓さんのようにぶ恰好でしたわ。こん度お誂えになるのは、も少し小ぶりになさいよ。きっと意気でいいから。」 といって、わざと文(サイズ)の小さいのを靴屋に註文させたものだ。 このもくろみは確かに成功した。一日外で文(サイズ)の小さな靴を穿かされている良人は、足の窮屈なのにたまりかねて、勤めがすむが早いか、大急ぎで家に帰って来た。そして窮屈な靴をぬいで、スリッパに穿きかえるのを何よりも楽しみにした。 こんな日が重なるにつれて、良人の悪い癖はいつのまにか治っていたそうだ。 女の抜目のない利用法にかかったら、どんな男でも羅紗の小片(こぎれ)と同じように、ただ一つの材料に過ぎない。女はそれが手提袋を縫うのに寸が足りないと知ったら、代りに人形の着物を思いつこうというものだ。――滅多にあきらめはしない。P.155~156 マッチの火(37) これは露西亜の片田舎にある一軒屋で起きた事柄だ。―― ある独身者の農夫が、寝しなに自分の義歯(いれば)をはずして、枕もとのコップの水に浸しておいた。すべて義眼や義歯をはめている人たちは、よくこうしたことをするものなのだ。 その夜はひどく寒かった。朝起きてみると、戸外は大雪だった。農夫は義歯を取り上げようとして、初めてコップの水がなかに歯を抱(いだ)いたままで、堅く凍りついているのに気がついた。 氷を溶すには、さしあたり火をおこすより仕方がなかった。彼は台所に下りてマッチを捜したが、間が悪いときには悪いもので、唯の一本もそこらに見つからなかった。 ちょうど暁の五時で、農夫は義歯のない口では、朝飯を食べることもできなければ、また人と話をするわけにも往かなかった。 彼は厩に入って馬を起した。そして町はずれに住んでいる友人を訪ねようとして、六哩(マイル)の間雪の道を走らせた。 友人は入口に立ったその訪問客が、急に齢(とし)とって皺くちゃな、歯のない頤をもぐもぐさせながら、手ぶりで何か話そうとするのを見てびっくりした。やっとのことで彼はその訪問客がマッチ箱をもとめに来たことが解って、涙が出るほど大笑いをした。 農夫は大事なマッチ箱を一つ貰い受けて、また大急ぎに馬を駆って帰って来た。そして氷を溶して、やっと義歯を口のなかに頬張ることができたそうだ。 これを思うと、何をさしおいても、マッチの一箱は枕もとにおいておくべきものだ。マッチは義歯の凍ったのを溶すに役立つのみならず、寝起きに喫(の)みたくなる煙草にも火をつけることができる。しかし、それよりもいいのは、近くに眠っている人の寝顔を、それと知られないでこっそり見ることができることだ。人の寝顔を見ると、いろいろな意味で自分を賢くすることができるものだ。P.157~159 左(38) 「どちらでもいいから、片眼を閉じるか、または瞬きしてみせたまえ。」 こう言うと、誰もが決ったように自分の弱い方の眼でそれをするが、男は一般に左の方を使う。耳も男は左が弱いので、耳が遠いとか何とかいう場合は、男なら大抵左に決っている。ところが女にはこんな傾向が見えない。女はどんな場合にでも健全だ。もしか女が片眼で笑ったら、それは彼女が自分の身近くで、何かふ健全なものを見つけたからだと思って間違はない。P.159~159 天下一の虚堂墨蹟(39) 1 今日新聞紙を見ると、紀州徳川家では家什整理のため、四月上旬東京美術倶楽部で書画骨董の売立入札を催すはずで、出品数は三百点、大変の前景気だそうだ。呼物の主なものとして、虚堂墨蹟、馬麟寒山拾得、牧渓江天暮雪、大名物瓢箪茶入などが挙げてあった。 虚堂墨蹟といえば、足利の初めから茶人仲間に大層珍重がられたもので、松平ふ昧なども秘蔵の唐物(からもの)茶入油屋肩衝(あぶらやかたつき)に円悟墨蹟を配したのに対して、古瀬戸茶入鎗(やり)の鞘(さや)には虚堂墨蹟を配し、参覲交代の節には二つの笈に入れ、それぞれ家来に負わせて、自分の輿側(かごわき)に随行させなければ承知しなかったものだそうだ。 不昧の鑑識で、虚堂墨蹟に配せられた鎗の鞘の茶入は、もと京都の町人井筒屋事河井十左衛門の秘蔵で、その頃の伏見奉行小堀遠州は、京へ上るときには、いつもきまって井筒屋を訪ねて来て、 「京へ上って来る楽しみは、たった一つ鎗の鞘を見る事じゃ。」と言って、この茶入を前に、いつまでもいつまでも見とれていたものだそうだ。そんなだったから、井筒屋の主人がこの茶入に対する愛し方はまた格別なもので、店にいるときは、いつでもこの茶入を箱に入れて側に置き、縋りつくようにしてその箱に手をかけていたということだ。後に家運が衰えて、止むなく三井八郎右衛門に譲渡さねばならなくなったが、せめて箱だけはと言って、そのまま残しておいたのを、とてももともと通りに家が栄えそうにもないので、いつまでも引き離しておくのも本意ないわけだと、その箱をも三井家に送って、久し振に茶入にめぐり合せたのはな高い話である。 そんな名器に配するように考えられたところを見ても、虚堂墨蹟がむかしからどんなに重んじられたかが、よくわかろうというものだ。 2 紀州家の虚堂墨蹟は、同家の祖先大紊言頼宣が、父家康から授ったもので、これについてはいろいろな逸話が伝えられているが、その中で最も興味多く考えられるものを、一つ二つここに思い出してみることにする。 虚堂禅師の筆が、家康の手から紀伊大紊言に下されたことを聞いた当時の老中方は、かねて噂にのみは聞いたことのある名品である。何とかして拝見させていただくわけには往くまいかと、口を揃えて頼宣に頼んだものだ。きさくな頼宣は気持よくそれを承諾して、日をきめて茶会を開くことにした。 その日になって、赤坂喰違(くいちがい)の紀州家の邸では、数寄屋の床の飾りつけから道具万端ちゃんと用意が出来ているはずだった。 出迎のものの口から、お客の老中方が揃って数寄屋に入ったことを聞いた頼宣は、挨拶に出かけようとして、居間を出て黒書院を通りかかった。ふと気がつくと、違棚の上に箱から取出したばかりの懸物が一つ置いてあった。頼宣はもしやと思って検めてみた。それは紛う方もない、虚堂の懸物だった。 頼宣は胸に動悸を覚えた。道具奉行の鴨居善兵衛と茶道の千宗左とが呼び出された。頼宣はきっと二人の顔を見据えた。「あれほど申しつけておいたのに、何故あって数寄屋にこれを掛けぬのじゃ。今日の茶事を何と心得おるか。」 主人の手に虚堂の懸物を見た二人は、はっと恐縮して、亀の子のように頭をすくめるより外に仕方がなかった。 「恐れ入りました。全く手前どもの粗相から、お数寄屋には他のお軸を掛けましたような次第で……」 愚しい粗忽者をいくら叱ったところで、さしあたっての間違をどうすることも出来ないのを知っている頼宣は、長くは二人を相手にしていなかった。彼は家来中での老巧者として知られた渡辺若狭守直綱を呼んで、何か小声で耳打をした。 若狭守はいそいそと数寄屋に入って往った。そこには老中方が膝を押並べて、いずれも腑に落ちなさそうな顔をして、床の間の懸物に眼をやっていた。若狭守は主人に代って手短に挨拶をした。 「かねて御所望になりました虚堂禅師の墨蹟は、御案内の通り権現様お直々に賜わりました品ゆえに、床に懸けておいてお待ちするのは勿体なく存じますので、皆様のお入を待って、主人自ら懸けて御覧に入れたい所存にござります。しかし、それまでの間を素床(すどこ)のままに致しておくのもどうかと存じまして、代りのものを御覧に入れましたような次第で……」 それを聞くと、客人達は言葉を揃えて感心した。 「御用意のほど、御尤に存じます。」 「しからば御免を蒙って……」若狭守はその機会をはずさなかった。そして声を高めて次の間に呼びかけた。「茶道。これに参って床の軸物をはずしなさい。」 次の襖がさっと開いて、千宗左の姿が現われたかと思うと、床の懸物は手早く取りはずされて、千宗左はまた影のように消えてしまった。すると、入違いに左手に懸物を、右手に矢筈竹を持った主人頼宣が入って来た。皆はその態度の水のような静かさに、覚えず心を惹きつけられてしまった。 懸物は流れるように床の間にかけられた。虚堂禅師の筆は、石のような重みをもって客人達の上に落ちかかって来た。皆はその重みに堪えられないように、思わず頭を下げた。 3 紀伊大紊言頼宣は、茶道の稽古は古田織部正(おりべのかみ)や織田有楽斎を師匠として励んでいたから、利休七哲として有楽斎と肩を並べていた細川三斎から見れば、ちょっと後輩だった。 虚堂禅師の懸物が、家康の手より頼宣に伝えられてから間もなくの事だった。江戸から西国の所領に帰ろうとした三斎は、何かの席上で紀州家の重臣渡辺若狭守直綱に会った。四方山の話のついでに、三斎はこんな事を言った。その頃彼はもうかなりの老年だった。 「今度権現様より御拝領になりました虚堂の御懸物は、天下一と承りますにつけて、一度拝見いたしたいと存じながら、今日までその折がなくて過しましたことは、残念至極でなりませぬ。もしお骨折により、拝見が叶いますならば、今生の面目この上もない事かと存じます。何分御覧の通り、老年の身の上、この度帰国いたしました上は次の参府はとても望まれないことかと存ぜられますので……」 三斎の言葉には、生のあるうちに一つでも多く傑れたものを観て、その風格を味おうとする茶人の謙遜が溢れていた。若狭守はそれに動かされないわけに往かなかった。 「さほどまでの御執心、何とかお取計いいたすでござりましょう。」 若狭守は帰って、このことを頼宣に告げた。頼宣はこころよく承諾した。 「それはいと易いことじゃ。早速案内したがよかろう。」 約束の日が来た。今日こそ生涯の望が達せられて、天下一の虚堂が見られるのだと思うと、三斎は自分の身のまわりが急に明るくなったように感じた。赤坂喰違にある紀州家の門を潜ったときには、胸に動悸をさえ覚えたように思った。 三斎は案内せられて、数寄屋に入った。何よりもさきに床の間を見た彼は、自分の眼を疑わずにはいられなかった。そこに懸けられたのは、清拙派のある僧侶の書いたもので、墨の匂も爽やかには出来ていたが、自分の見たいと思っていた天下一の虚堂ではなかった。 「何か仔細があっての事だろう。」 不思議には思いながらも、三斎はそんな気振も見せないで、静かに席についた。 やがて主人の頼宣が出て来た。彼は自分で茶を立てて、客にすすめた。そして言葉丁寧に挨拶した。 「御所望により、虚堂の墨蹟を御覧に入るべく御招きはいたしたが、都合あって、今日はその運びに参りかねた。前以ってそれを申したら、お入りはなかろうかと存じて、わざと隠し立してお招きいたした次第、なにとぞ悪しからず……」 三斎はそれを聞くと、はっとなって、急に眼の前が暗くなったように思った。だが容子には少しもそんなところは見えなかった。 「ぶしつけな御願を申上げましたのに、お叱りはなくて、かえって御丁寧な御挨拶痛み入ります。御秘蔵の禅師の墨蹟、今日拝見が叶いませぬのは、まことに残念至極に存じますが、また重ねての折をお待ちすることにいたしましょう。」 四方山の雑談の後、三斎は礼を述べて立上った。そして黒書院と白書院とのなかにある廊下に来かかると、そこの杉戸の前に、若狭守が一人立っていた。若狭守は箱から取出した懸物を、蓋の上に持ち添えたまま、先刻から何ものかを待っているらしく思われた。三斎が近づくと、彼はそこに跪(ひざまず)いた。 「お口上にござります。」 三斎もぴたりと歩みを止めて、廊下に跪いた。若狭守は言った。 「先日のお言葉に、御老年の御身、次の御参府も望まれないによって、虚堂の墨蹟御覧になりたいとのことでござりましたが、この後とも引続き御参府をお待ちいたせばこそ、わざと今日はお目にかけるのを差控えたのでござります。この次に御参府の節には、きっとお約束を果しますが、しかし、たっての御所望ならば、書院にて御覧に入れよとのことでござりますが……。」 若狭守が箱の蓋に持ち添えた懸物は、長年の間三斎が夢にも忘れ得なかった虚堂禅師の墨蹟だった。彼が一言所望さえしたなら、その場で直に天下一の禅師の風格に接することが出来るはずだった。実を言えば、彼はもう年をとり過ぎていた。どんな事があって、次の年の参府が出来なくなるかも知れなかった。それを思えば、彼は今生の思い出としても、飽かずその懸物に見入りたかった。彼は思わず、 「しからば、お言葉にあまえまして……。」 と言おうとして、急に口を噤(つぐ)んだ。 そんなことが言われるべき義理はなかった。かたい約束に背いてまでも、彼の息災を祈ってくれる若い大紊言の心遣いを思えば、そんなことは 気にも出せるわけではなかった。実際大紊言の誠心は身に沁みてありがたかった。その心遣いの細かさの前には、懸物を見る機会が、一年遅れようとも、二年遅れようとも、よしまた百年遅れようとも、そんなことを詮議立することは、とても恥かしくて出来なかった。 「有難き仰せには、お礼の申上げようもござりませぬ。お言葉に従いまして、この後も度々参府仕るべく、御懸物はその節あらためて拝見いたすでござりましょう。」 三斎はこう言って、虚堂の墨蹟を手にとって、丁寧に頭にいただいた。そしてそれを若狭守に返すと、急ぎ足に廊下をすたすたと彼方へ去った。 4 聞くところによれば、紀州家では今度の売立で相続税を産み出すとのことだが、虚堂禅師の墨蹟を初め、重だった書画骨董は、それぞれこうした逸話をもっていないものはないはずだから、逸話や伝説を珍重する茶人仲間では、たいした附値を見ることだろうと想像せられる。紀州家の当主は、まず何を措いても、所蔵の書画骨董にこんな逸話を添物にして残しておいてくれた、祖先頼宣に対して感謝しなければなるまい。 頼宣が老年になって、家を嫡子光貞に譲るとき、次男左京大夫には、茶入や懸物などの家康伝来の名品を幾つか取揃えて譲ったものだ。それを見た渡辺若狭守はふ審そうに訊ねた。(この三つの話を通じて、いつでも渡辺若狭守が顔を出すのを、不思議に思う人があるかも知れないが、こういう役はいつも相手を引きたたせて、大きく見せるために存在する、言わば冬瓜の肩にとまった虫のようなもので、それが髯を生やした蟋蟀(こおろぎ)であろうと、若狭守であろうと、どちらにしても少しも差支がない。) 「御次男様へ、茶の湯のお道具、さように数々お譲りになりましたところで、さしあたりお用いになるべき御客様もござりますまいに。」 すると、頼宣は、 「左京は小身のことゆえ、時には兄に金銀の借用方を申込むこともあろう。その折これを質ぐさに入れたなら、道具は本家にかえり、左京はまた金子を手に入れることが出来ようと思うからじゃ。」 と言ったということだ。してみると、紀州家の当代が、相続税を産みたさに、伝来の重宝を売ったところで、頼宣はただ笑って済ますぐらいのことだろう。P.160~170 遺愛品(40) 小説家M氏は、脳溢血で懇意の友人にも挨拶しないで、突然歿くなった。毎日日課として、八種ほどの田舎新聞の続き物を何の苦もなく書上げ、その上道頓堀の芝居見物や、古本あさりや、骨董いじりなどに、一日中駈けずり廻って、少しの疲労をも見なかったほど達者な人だったが、歿くなる折には、まるで朽木が倒れるように、ぽくりと往ってしまった。 入棺式の時刻になると、故人の懇意な友人や門下生達は、思い出の深い書斎に集って、この小説家の遺骸と一緒に、白木の棺に紊めるべき遺愛品の撰択について協議を始めた。M氏には子供らしい妙な癖があって、自分に門下生の多いのを誇りたさの念から、一度物を訊きに自分を訪ねて来たものは、誰によらず門人名簿に書き加えていたから、その日そこに集った人達のなかにも、本人はいっぱし懇意な友達のつもりでいても、その名前がちゃんと門人名簿のなかに見つからないとも保証出来なかった。 「井伊大老の短冊などはどんなものでしょう。たしか一、二枚あったように覚えていますが――。>門下生のHという新聞記者は、寝ふ足な眼をしょぼしょぼさせながら皆の顔を見た。「××新聞に載っていた、大老についての記述が、先生最後の絶筆となったようなわけですから、その縁でもって……。」 「あれは、たしか未完結のままでしたね。」 故人と同じ古本道楽で、豆本の蒐集家として聞えた、禿頭の銀行家は、円っこい膝の上で、指の節をぽきぽき鳴らしながら、誰に訊くともなしにこんなことを言った。 「そうです。未完結のままで。」 「そりゃいかん。そんなものを棺に納めたら、かえって故人が妄執の種となるばかりですよ。」 銀行家は、取引先の担保にいかさまな品書きを見つけた折のように、皮肉な笑を見せた。Hはそれなり口を噤んでしまった。 「義士のものはどうだっしゃろ。Mはんの出世作は、たしか義士伝だしたな。」 故人と大の仲よしで、その作物を舞台にかけては、いつも評判をとっていた老俳優の駒十郎は、こんなことを言うのにも、台詞らしい抑揚(めりはり)を忘れなかった。 「さあ……。」 誰かが気のない返事をした。 「いけまへんやろか。」 駒十郎は、てれ隠しに袂から巻煙草を一本取出して、それを口に銜(くわ)えた。身体を動かす度に、香水の匂がぷんぷんあたりに漂った。 「可愛らしい玩具か何かないものかしら。来山の遊女(おやま)人形といったような……。」 胡麻白頭の俳人Sは、縁なしの眼鏡越しに、じろじろあたりを見廻した。自分の玩具好きから、M氏をもその方の趣味に引込もうとして、二、三度手土産に面白い京人形を持って来たことがあるので、それを捜すつもりらしかったが、あいにくその人形は物吝みをしないM氏が、強請(ねだ)られるままに出入の若い女優にくれてしまっていたからそこらに影を見せなかった。 「十万堂の遊女人形は、あれは女房の代りじゃなかったんですか。」故人がかかりつけの医者で、謡曲好きのGは、痺(しびれ)が切れたらしい足を胡坐に組みかえた。「すると、Mさんには、かえって御迷惑になるかも知れませんな。」 皆は意味あり気な眼を見交した。 先刻から襖を開けて、押入に首を突込んだまま、そこに山のように積重ねてある書物を、あれかこれかと捜していたらしい、脚本作者のWは、そのなかから八冊ばかりの大型の和本を取出すと、 「これだ。これだ。これだったら、誰にも異存があろうはずがない。」 と、頓狂な声を立てながら、得意そうに頭の上にふりかざして、皆に見せびらかした。それは西鶴の『好色一代男』で、どの巻も、どの巻も、手持よく保存せられたと見えて、表紙にも小口にも、汚れや痛みなどの極めて少い立派な本だった。 「なるほどね。一代男とはいい思いつきだ。Mさんは夙くから西鶴の歎美者だったしそれに一代男というと……。」 銀行家は、禿げた前額を撫上げながら、ちょっと言葉を切って、にやりとした。 「一代男というと……。」皆は頭のなかで、この草子の主人公世之助が、慾望の限を尽した遊蕩生活を繰返してみた。そして人情のうらおもて、とりわけ女心のかげひなたを知りぬいていたM氏にとって、こんなに好い道づれはまたとあるまいと思った。 「それはいい。Mさんと世之助とでは、きっと話が合うから。」 皆は口を揃えて『好色一代男』を棺に紊めることに同意した。そして生前懇意だった人のために、死後好い道づれを見つけることが出来たのを心から喜んだ。 「それじゃ、どなたも御異存はございませんな。」 脚本作者のWが『一代男』八冊を手に取上げて、やっとこなと立上ろうとすると、急に次の間の襖が開いて、 「異存がおまっせ、わてに。」 と、呼びかけながら、いが栗頭の五十恰好の男が入って来た。大阪にな高い古本屋の主人で、M氏とは至って懇意な仲だった。 古本屋の主人は、脚本作者の側に割込むと、ちょっと頭を下げて皆に挨拶した。そして懐中からぺちゃんこになった敷島の袋を取出すと、一本抜取ってそれに火をつけた。 「どなたのお言葉か知りまへんが、一代男をとは殺生だっせ。これを灰にして見なはれ。世間にたんとはない西鶴物が、また一部だけ影を隠すわけだすからな。それにこんな手持のよい一代男は、どこを捜したかて、滅多に見られるわけのものやおまへん。わてがこれを先生に紊めたのは、つい先日(こないだ)のことだしたが、その時の値段が確か千五百円だしたぜ。」 「ほう、千五百円。そない高い本とは知らなんだ。どれ、どれ……。」 駒十郎は、喫みさしの煙草を、火鉢の灰に突込んで、その手で脚本作者の膝から、本の一冊を取上げた。あたりの二、三人は、首をのばしてそれを覗き込んだ。 「そんなに高くなったかな。五百円の値を聞いて、びっくりしたのは、つい二、三年前のように思ったが。」古本好きの銀行家は、書物の値段が自分に相談なしに、ぐんぐんせり上っているのが、幾らかふ機嫌らしかった。「ともかくも、そんなに高価なものを灰にしてしまっては、遺族の方々にも申訳がないから。」 「じゃ、一代男は思い止まりましょう。」 「外に何か見つかればいいが。」誰かがこんなことを言った。 駒十郎は先刻から挿絵の一つに見とれて、側に坐った新聞記者のHを相手に、自分の出る芝居の番附だけは、どうかしてこんな風に描かせたいものだといったようなことを、小声でひそひそ話していた。 「いいものがおます。也有の『鶉衣』だす。」古本屋の主人は、勢よく立上ったかと思うと、かねて勝手を知った書棚に往って、四冊本の俳文集を取出して来た。 「この本だしたら、也有の名著で、先生のこの上もない愛読書だしたし、それに……。」 皆は後を聞かないでも満足した。そして一代男の代りに鶉衣四冊を棺に紊めることに同意した。 「ああ、そうだったな。>医者のGが、拍子ぬけのしたように呟いた。「也有もMさんも同じ尾張人だったから、途々な古屋弁でもって仲好く話して往くことだろうて。」 皆はそれを聞くと、故人の特徴のあるな古屋訛を思い出した。そしてそれももう二度と聞かれなくなったのだと思って、覚えずほろりとした。P171~177 暗 示(41) 1 こういう話がある。 ある時、山ぞいの二また道を、若い男と若い女とが、どちらも同じ方向をさして歩いていたことがあった。 二また道の間隔は、段々せばめられて、やがて一筋道となった。見ず知らずの二人は、一緒に連立って歩かなければならなくなった。 若い男は、背には空になった水桶をかつぎ、左の手には鶏をぶら提げ、右の手には杖を持ちながら、一頭の山羊をひっぱっていた。 道が薄暗い渓合に入って来ると、女は気づかわしそうに言葉をかけた。 「わたし何だか心配でたまらなくなったわ。こんな寂しい渓合を、あなたとたった二人で連立って歩いていて、もしかあなたが力ずくで接吻でもなすったら、どうしようかしら。ほんとうに困っちまうのよ。」 「え。僕が力ずくであなたを接吻するんですって。」男は思いがけない言いがかりに、腹立ちと可笑さとのごっちゃになった表情をした。 「馬鹿をいうものじゃありません。僕は御覧の通り、こんなに大きな水桶を背負って、片手には鶏をぶら提げ、片手には杖をついて、おまけに山羊をひっぱってるじゃありませんか。まるで手足を縛られたも同然の僕に、そんな真似が出来ようはずがありませんよ」 「それあそうでしょうけれど……。」女はまだ気が容せなさそうにいった。「でも、もしかあなたが、その杖を地べたに突きさして、それに山羊を繋いで、それから背の水桶をおろして、鶏をそのなかに伏せてさえおけば、いくら私が嫌がったって、力ずくで接吻することくらい出来るじゃありませんか。」 「そんなことなんか、僕考えてみたこともありません。」 男は険しい眼つきで、きっと女の顔を睨んだが、ふとその紅い唇が眼につくと、何だか気の利いたことの言える唇だなと思った。 二人は連立って、薄暗い樹蔭の小路に入って往った。人通りの全く絶えたあたりに来ると、男は女が言ったように、杖を地べたに突きさし、それに山羊を繋ぎ、背の水桶をおろして、鶏をそのなかに伏せた。そして女の肩を捉えて、無理強いに接吻したということだ。 2 この場合、若い男は初めのうちは何も知らなかったのだが、女の敏感な警戒性が思わず洩した一言に暗示せられて、それを実行に移したのである。善行にせよ、悪業にせよ、すべて男の勇敢な実行の背後には、得てしてこうした婦人の暗示が隠れているものだ。P.178~180 詩人の喧騒(42) 支那の西湖に臨んで社廟が一つ立っている。廟の下手は湖水に漁獲(すなどり)をする小舟の多くが船がかりするところで、うすら寒い秋の夜などになると、篷(とま)のなかから貧しい漁師達が寝そびれた紛れの低い船歌を聞くことがよくある。 月の明るいある夜のことだった。そこらに泊り合せた多くの船では、漁師たちはもう寝しずまったらしく、あたりはひっそりして何の物音も聞えなかった。その中に皆の群から少し離れて、社廟のすぐ真下(ました)に繋いだ小舟では、若い漁師がどうしたものかうまく寝つかれないで、唯ひとりもぞくさしていた。 若い漁師は所在なさに篷を上げて外を見た。水銀のような青白い光の雫は、細かく湖の上に降り注いで、そのまま水に吸い込まれているようだった。時々小さな魚が水の面に跳ね上るのが見られたが、水泡の爆(は)ぜ割れる微かな音一つ立てなかった。 「静かな夜だなあ。」 若い漁師は寒そうに首を竦(すく)めて、覚えずこう呟こうとして、そのまま口を噤んでしまった。少しでも声を立てて深い寂黙(しじま)を破るのが、何だか気味悪く感じられたのだ。 漁師はまたもとのように篷の下に潜り込もうとしたが、ふと近くに何だか得体の分らない、怪しい騒めきが始まったのを聴きつけて、覚えず半身を舷から乗出すようにして聴耳を立てた。騒めきは掠めるような人声で、すぐ頭の上の社廟のなかに起きていた。何でも五、六人の人たちが、二組に分れて言い争っているらしかった。その一組は呼吸の通っている人達とみえて、声柄に何の変りもなかったが、今一つの組が肉身を具えたこの世の人たちでなかったのは、その物言いぶりが何よりもよく語っていた。紛れもない幽魂(たましい)そのものの声で、それを耳にすると、掘りかえされた墓土の黴臭い呼吸と、闇に生れた眼なし鰻の冷さが気味悪く感じられた。恐いもの見たさの物好きが強く働いていなかったら、若い漁師はそこそこに舟を漕いで、遠くへ逃げ出したかも知れなかった。 「すると、お前たちが心静かに月に見とれていると、そこへこちらの二人が無理に入って来たというのだな。」 だしぬけにこういう声が聞えた。その声には、口喧嘩(いさかい)をし合っている輩(てあい)のものとは似てもつかない重々しい力があった。若い漁師はすぐにそれを社廟の神様のお声だなと気づいて、軽い身顫いを覚えた。 「さようにございます。手前どもが永い間閉じ籠められた常闇(とこやみ)の国から抜け出して来て、久しぶりに見たのが今夜の満月でございましょう。手前どもはあの青白い光を見ると、むかしのいろんなことを思い出して、唯もう夢のような気持で、水際の草の上に蝗(いなご)のように脛(すね)を折り曲げて、じっとあたりの静かさを楽しんでいたものでございます。そこへいきなり理ふ尽に割り込んでござらしたのがこの旦那衆で……。」 喧嘩の片われは、下様(しもざま)な雑人(ぞうにん)だと見えて、言葉つきにどことなく自ら卑下したところがあった。他の一人がすぐ後を引取った。 「いさかいは、そこから始まったのでございます。手前どもの団欒(まどい)に、そこのお二人が割り込んで見えなければ、悶着(もめ)は起らなかったはずです。どうか正しいお裁きが願いたいもので……。」 「それはいかん。」神様は苦々しそうに相手をたしなめた。「おまえ達は、相当な身なりをしているくせに、何故あってそんなぶ作法な真似をするのだ。一体何者なのか。おまえ達は……。」 「詩人です。二人とも。」 相手の一人は得意そうに言い放った。その声にはみだらな女と酒とのにおいがぷんと籠っているように感じられた。若い漁師はそれを聞いて、この人たちは詩を作ることを、魚を獲ることと同じように、立派な職業(しごと)だと考えているらしい。魚は市場に持って往けば、いつだって金に替えることが出来るが、詩と来たらてんで引取手(ひきとりて)があるまいに、可笑しな勘違いだと思って、口もとに軽い微笑を浮べた。 「そうか、詩人か。」神様は二人の男が詩人だと聞いて、いくらか気持が更(かわ)ったらしく、急に調子を荒らげて相手の雑人を叱りつけた。「何だ。貴様たち。こちらは文字のある先生方じゃないか。下衆のくせに寄ってたかって、先生方に反抗(はむか)うなんて、恥知らず奴(め)が……。」 「滅相な。手前どもがこの旦那衆に反抗(はむか)うなんて、そんな……。」相手の一人がびっくりしたように言った。持病の喘息で生命を捨てたものらしく、言葉を急き込む度に、ぜいぜい息切れがするのが手に取るように聞えた。「そんな間違ったことはございません。喧嘩(いさかい)の種を蒔いたのはこの旦那衆です。静かに月を見ている手前どものなかへ割り込んで来るなり、鵞鳥のような声でもって、何だか、へい、訳も解らないことを、ぎゃあぎゃあ我鳴り立てなすったものだから……。」 「そんな高声で、何をまた議論し合ったのだ。」 社廟の神様は、詩人たちに訊いたらしかった。 「無論詩のことでございます。」きっぱりと返事をするのが聞えた。「その他(ほか)のことは、何一つ論ずる値打がありませんから。」 「ほう、詩のことか。詩のことなら、議論の題目として何不足はないはずだ。」神様も恋をする若い人達と同じように、詩は大の好物らしかった。「お前達も、黙って聴いていればいいじゃないか。」 聴いてはいませんでしたが、黙ってはいました。なぜと申しまして、聴いたところで手前どもにはあまり難かしくて、とても解りようがなかったのですから。すると、この旦那衆は、黙っているのが気に喰わないと見えて、また一段と声を張り上げて喚き散らしなさいます。これでもか、これでもかといった風に。それを辛抱(がまん)しかねた仲間の一人が、 「どうか少しお静かに願います。」 といったものです。すると、こちらの旦那衆が、 「何っ。」 と、いいさま、いきなり起上って拳(こぶし)を振り上げなさいましたので……。 「何でも、へい、世間の噂には、江都の詩人汪先生は、友達が宋代とやらの詩を貶(けな)したからといって、えらく腹に据えかねて、いきり立って議論を吹っかけたので、近くの樹にとまっていた小鳥が、みんな逃げてしまったそうに聞きました。一体詩人というものは、みんな牛のように吼えるものと見えまして……。」 雑人の一人が、横合から冷かし気味にこんなことをいったものだ。すると、神様は陽気に笑い出した。 「は、は、は、は。詩人達が牛のように吼えるものかどうかは知らぬが、確かに牛のように角突き合いはよくするものらしいね。ところで、先生方――。」神様の詩人達に対する言葉は皮肉になった。「先生方の詩論とやらは、いずれは高尚で結構ずくめなものだろうが、それも処と相手とを吟味した上でなくっては。今夜のところはこのままさらりと水に流そう。が、その代り以後はちと場所柄をわきまえるようにしてもらいたいものだて。」 それを聞くと、雑人方は、草の枯葉が共擦れするような、微かな気配を立ててひそめき出した。若い漁師は眼をつぶらにして社廟をふり仰いで見た。青白い月明りが薄絹のようにたよたよと顫えている後壁の隙間から、魚の腹のような冷い燐火が、三つ四つ続けさまにふらふらと飛び出したかと思うと、その瞬間、 「き、き……。」 と二十日鼠の笑うような声が低く聞き取られたように思った。 その後から、青と赤との衣を着た人がのっそりと二人出て来た。詩人だなと思って、若い漁師は伸び上るようにしてその顔を見ていたが、それが誰だったかに気がつくと、慌てて首をすくめて眼を伏せた。 「何だ。那奴(あいつ)じゃないか。こないだ鳶が空から取落した奴を、松江の鱸だといって、うまく騙して売りつけてやった、あの露次裏の老ぼれじゃないか。」 詩人二人は、そんなことに気がつこうはずがなく、口の中で何かぶつくさぼやきながら、霧の中に見えなくなってしまった。P.181~187 樹木の不思議(43) 1 今日久しぶりに岡山にいる友人G氏が訪ねて来た。そして手土産だといって梨を一籠くれた。梨は一つずつ丁寧に二重の薄紙に包まれていたが、その紙をめくってみるとなかからは黄熟した肌の滑っこい、みずみずしい大粒の実が現われた。 梨好きな私は、早速その一つを皮をむかせて食べてみた。きめの細かい肉は歯ざわりがさくさくとして、口の中に溶け込むように軽かった。 「うまいね、この梨。ことしの夏は京都、奈良、鳥取と方々の果樹園のものを食べてみたが、こんなうまいのは始めてだよ。」 「実際うまいだろう。皆がそう言っている……。」と客はさも満足そうにいって、口もとに軽い微笑の影を漂わせた。「うまいはずだよ。これには不思議な力が籠っているんだから……。」 「不思議な力。」私はいぶかしそうにG氏の顔を見た。 「まったく不思議なんだ。それはこう言う訳なんだがね。」 G氏は落ついた句調で、ぽつりぽつりと次のようなことを話した。 2 岡山を西へ一里半ばかり離れた田舎に、かなり広い梨畑をもった農夫があった。どうしたものか、いつの年も咲き盛った花の割合に、実のとまりが極く少く、とまった果実もそれが熟れる頃になると、妙に虫がついて、収穫として畑よりあがるものは、ほんの僅かしかなかった。年毎の搊つづきに気を腐らした農夫は、いっそ梨畑を掘り返して、そのあとに何か新しいものを椊えつけてみたらと思った。で、いつもこんな場合に、いい分別を貸してもらうことになっている神道――教会の教師を訪ねて、その相談をもちかけた。いうまでもなく、農夫はその教会のふるい信徒の一人だった。 農夫の口から委細を聞いた教師は、気むつかしく首をふった。 「梨畑を掘り返すにはまだ早い。もっと御祈念を積みなさい。」 「御祈念はいたしとります。」 農夫の言葉つきには、どこかに不足らしいところがあった。 「何と言って御祈念している……。」 「神様。どうぞ私の梨畑を……。」 気後れがするらしく、口のなかで言う農夫の言葉を、教師は皆まで聞かなかった。 「私の梨畑だと。お前さんにそんなものはないはずだ。何もかも一切神様にお返ししなさい、といって聞かせたことをもう忘れているね。」 それを聞くと、農夫は両手を膝の上へ、頭を垂れたまま、悄気(しょげ)かえったようにじっと考え込んでいたが、暫くすると、 「いや、よくわかりました。私が間違っておりました。」 と、丁寧に教師に挨拶をして帰って往った。 その日から農夫の心は貧しくなった。彼は一切のものを神に返した。毎朝鋏と鍬とをもって梨畑へ出かけると、いつもきまったように樹の下に立って、 「神様。これからあなたの畑で働かせていただきます。もしか梨の実がみのって、少しでも余分のものがおありでしたら、そのときには盗人や虫におやりになる前に、まず私にいただかせて下さいますように」と、真心を籠めて祈念した。そして自分の畑を自分の手で処理するといったようなこれまでの気儘な態度をあらためて、自分はただこの畑の世話をするために雇われた貧しい働き人の一人に過ぎないような謙遜な気もちで、一切を自然にまかせっきりにして、傍からそっと草を抜き、肥料を施しなどした。 こうは思いあらためたものの、農夫は心の奥でその結果について幾らかのふ安を抱かないわけではなかったが、次の夏が来て、梨の実がみのる季節になると、彼は不思議なものを見せつけられて、心の底から驚嘆した。 一度は掘り返して火に焼いてしまおうと思った、やくざな梨畑の樹という樹は、枝も撓(たわ)むばかりに大きな果実を幾つとなくつけているのであった。 3 「その不思議な梨畑に出来たのが、実はこれなんだよ。」 客のG氏はこう言って、自分が持って来た果物籠から、梨の実の一つを取出したかと思うと、皮をもむかないで、いきなりそれに噛みついた。 4 こんな話がむかしにも一つある。 足利時代に又四郎という庭造りの名人があった。庭造りというと、今も昔も在り来りの型より外には、何一つ知らぬ輩のみ多いが、又四郎はそんなのとは異って、文字もあり、する仕事にも、それぞれちゃんとした典拠があったようだ。 あるとき又四郎が、さる寺方から頼まれて、築山を造ったことがあった。その仕事振を見ようとして、住職がぶらりと庭へ出てみると、不思議なことには滝頭(たきがしら)が西へとってあった。 住職は合点が往かなかった。 「滝頭を西にとったのはおかしい。すべてどんなものでも、頭は東にあるのが、本当じゃなかろうか。」 「ごもっともさまで。……すべて滝頭を東にとりますのは、庭造りの極った型でございます。」又四郎は答えた。「が、それは在家の庭のことで、寺方のになりますと、滝頭を西にとった方が、かえって本当かと思われます、むかしから仏法東漸と申しまして……。」 「仏法東漸か。なるほどそう聞けば、それも尤なようだて。」 住職は笑って紊得するより外には仕方がなかった。 同じ頃に、蘭坡和尚という禅僧があった。和尚は自坊の境内に一段の風致を加えるために、枝ぶりのいい松を五、六株椊えたことがあった。程経て気がついてみると、松の葉は赤く枯れかかっていた。和尚は衰えた松の薬には酒がいいことを聞いていたが、酒は自分にも二つとない好物だったので、いくら松のためとは言い条、それを譲るわけにはゆかなかった。和尚はかねて懇意な間柄だったので、又四郎に相談をもちかけた。 「見らるるとおり、あのように松が枯れかけて来た。何かいい薬はないものかしら」 「薬はいろいろあるにはあります。が、どれもこれもあまり効力(ききめ)といってはないようです……。」 又四郎は赤ちゃけた松の葉を見上げながら冷やかに答えた。 「あまり効力がない。それは困ったものだな」 和尚はさも当惑したように円い頭をふった。頭の上では松の樹が勢のない溜息をついて、同じように枝をふったらしかった。又四郎は言った。 「そんな薬よりも、ずっと効力が見えるものが一つあります。もっともこれは私の秘伝でございますが……。」 「そうか。秘伝と聞けば、なお更それを聞きたいものだて。」 「それは、和尚さま、お経にある文句なのです。」 又四郎は口もとに軽い微笑を浮べて言った。 「お経の文句。それはどのお経にある。」 和尚の眼はものずきに燃えていた。 「観音経のなかの、 澍甘露法雨 滅除煩悩焔 という文句です。あの文句を紙に書いて、そっと樹の根に埋めておきますと、霊験はあらたかなものです。枯れかけた樹の色が、急に青々と若返って来ます。」 又四郎は枯れかけた当の松の樹にも、立ち聞きせられるのを気遣うように、声を低めて言った。 「いかさま。これはいいことを教えてもらった。」 和尚のよろこびは一通りではなかった、彼はいそいそと自分の居間に帰って往ったが、暫くすると、折り畳んだ紙片を掌面に載せてまた出て来た。 「又四郎どの。御面倒だが、それじゃこの紙片を土に埋めて下さい。」 又四郎は受取った紙片をそっとおし拡げてみていたが、すぐまたそれを和尚の手に返した。 「和尚さま。 甘露法雨の澍の字が樹になっていますよ。」 「ほい。わしとしたことが、これは失敗ったな。」 和尚は頭を撫でて高く笑った。 文字はすぐに書きあらためられて、又四郎の手で松の根もとに埋められた、そしてそのまま捨ておかれた。 枯れかけた松の色は、やがてまた青くなり出した。 5 何事も自然にまかせて、あまりおせっかいをしないのが、一番いいようだ。P.188~196 蔬菜の味(44) 1 元の道士として聞えた画家張伯雨が、あるとき蔬菜の画を描き、それに漢陰園味と題名をつけたことがあった。というのは、むかし、子貢が、丈人と漢陰に出合ったことがあった。そのとき丈人が圃(はたけ)に水をやるのに、御苦労さまにも坑道をつけた井のなかに降りて往き、そこから水甕を抱いて出て来るのを見て、子貢がひどく気の毒がって、そんなまだるっこいことをするよりも、いっそこうしたがよかろうと、槹(はねつるべ)の仕方を伝授したものだ。すると、丈人はむっとした顔をして、ひどく機嫌を搊じたらしかった。丈人の嫌がったのは、子貢が心安だての差出口よりも、そんな便利な機械を使う事だった。すべて土に親しんで、蔬菜でも作って楽もうというには、そんな調法な機械をいじくるよりも、どこまでも甕で水を運ぶまだるっこさに甘んじて、その素人くさい労役を味うだけの心がけがなくてはならないが、伯雨はその心持を汲みとって自分の作画になづけたものだった。後に明の姚雲東がその蔬菜の画を手に入れて、ひどく感心したあまりに、自分でも屋敷のまわりに圃を作り、雑菜の種子を播いて、日々そのなかを耕すようになった。 そして明暮(あけくれ)蔬菜の生長を見て楽んでいるうちに、雲東は自分でも伯雨のまねをしてみずから土に親んで得た園味を思うさま描き現わしてみたいと思うようになった。 九箇月を費してやっと出来上ったのは、な高い雑菜の図で、自分の圃に作ったいろんな野菜の写生画と詩文とに、溢れるような田園の趣味を漂わせたものだった。 伯雨の漢陰園味も、雲東の雑菜の図も、今はどこに伝わっているか知る由もなく、いくら玩賞したいと思ったところで、そんな機会がとても得られるわけのものではないが、私は秀れた作家の手になった蔬菜の図には、ある程度の情熱をさえ感じる。自分の身近くにころがっている、極めてありふれたものを更に見直して、そのなかに隠れている美に気づき、それに深い愛着をもつのは、誰にとっても極めていいことに相違ない。 2 肥り肉(じし)の女が、よく汗ばんだ襟首を押しはだける癖があるように、大根は身体中(からだじゅう)の肉がはちきれるほど肥えて来ると、息苦しそうに土のなかに爪立をして、むっちりした肩のあたりを一、二寸ばかり畦土の上へもち上げて来る。そして初冬の冷い空気がひえびえと膚にさわるのを、いかにも気持よさそうに娯しんでいるようだ。畑から大根を引くとき、長い根がじりじりと土から離れてゆくのを手に感じるのは悪くないものだが、それよりも心をひかれるのは、土を離れた大根が、新鮮な白い素肌のままで、畑の畦に投げ出された刹那である。身につけたものを悉く脱ぎすてて、狡そうな画家の眼の前に立ったモデル女の上気した肌の羞恥を、そのまま大根のむっちりした肉つきに感じるのはこの時で、あの多肉根が持つなだらかな線と、いたいたしいまでの肌の白さと、抽き立てのみずみずしさとは、観る人にこうした気持を抱かせないではおかない。唯大根の葉っぱに小さな刺があるのは、ふっくらした女の手首に、粗い毛の生えているのを見つけたようなもので、どうかすると接触の気味悪さを思わしめないこともない。 銭舜挙の筆だと伝えられたものに、大根と蟹とを配合して、鋭い線で描き上げた小幅を見たことがあった。怪奇な蟹の形相に顫えている、白い純潔な肉の痛々しい恐怖が、いまだに頭に残っている。 3 玉菜が、そのむかし海岸植物として、潮の香のむせるような断崖に育ち、終日白馬のように躍り狂う海を眺めて暮していたのは、真っ直に土におろした根の深さと、肉の厚い葉の強健さとでも知られることだ。あの大きな掌面(てのひら)をいくつもいくつも重ね合せて、大事そうに胸に抱いた円い球のなかには、一体何がしまわれているのだろう。静脈の痕ありありと読まれるその掌面を、一つ一つ丹念にめくってゆくと、最後に小さな貝殻のような葉っぱの外には、何一つ残されていないのに気がつくかなしさ。上の葉は下の葉に無理強いにおっかぶせようとし、下の葉はそれを跳ね返して、明るい太陽の方へ手を伸そうとする希望はもちながらも、ある強い力に支配せられて、自分より下の葉には、また同じようにおっかぶせようとしている。その重みと力とが互に咬み合い、互に抱きあって、なかに閉じ込められた葉は、永久に太陽を見ぬいらだたしさ。――私は玉菜を見る度に、いつもそうした胸苦しさを、何よりも先に感じないわけにゆかない。 4 里芋は着物を剥がれて、素っ裸のまま、台所の片隅に顫えている時よりも、親芋と一緒に土から掘り出されるおりの方が、ずっとおどけていて、趣きがあるようだ。親芋の大きな尻をとりまいて、多くの兄弟たちが、てんでに毛だらけなからだをすり寄せているのを見ると、小さな生物のような気がして、尻っ尾のないのが不思議なくらいのものだ。 土だらけの里芋の皮を削り落そうとするとき、どうかすると指先が痒くてたまらなくなるのは、玉葱や辣薤(らっきょう)を手にするときに、眼のうちが急に痛くなるのと同じように、土から生れたものの無言の皮肉である。 今から二十四、五年前に、私は徳富健次郎氏と連れ立って、大阪道頓堀の戎橋の上を通っていたことがあった。大跨に二、三歩先を歩いていた徳富氏は、急に立ちとまって背後をふり返った。 「薄田さん。あなたお弟子をお持ちですか。」 「弟子――そんなものは持ちませんよ。」 その頃やっと二十五、六だった私に、弟子などあろうはずがなかった。 「それで安心しました。どうかなるべく弟子なぞもたないようにして下さい。子芋が出来ると、とかく親芋の味がまずくなるものですからね。」 徳富氏はこう言って、またすたすたと歩き出した。 私はその後、それと気づかないでえぐ芋を口に含んだときには、すぐに徳富氏のこの言葉を思い出して、 「青道心(あおどうしん)の小坊主め。お前一人は親の味をよう盗まなかったのか。気の毒な奴だな。」 と、苦笑いさせられたことがよくある。 5 籠に盛られた新鮮な白菜をみるとき、私はまず初冬の夜明の空気の冷さを感じ、葉っぱの縮緬皺にたまった露のかなしい重みを感じ、また葉のおもてをすべる日光の猫の毛のような肌ざわりの柔かさを感じるが、その次の瞬間には、すぐこの野菜が塩漬にせられた後の、歯ざわりの心よさを感じぬわけにゆかない。 ちょうど赤楽の茶 を手にした茶人が、その釉薬のおもしろみに、火の力を感じると同時に、その厚ぼったい口あたりに、茶を啜るときの気持よさを感じるのと同じようなものだ。 どうにも仕方がない。 栗(45) 今日但馬にいる人のところから、小包を送って来た。手に取ると、包みの尻が破けていて、焦茶色の大粒の栗の実が、四つ五つころころと転がり出した。 「いよう。栗だな。丹波栗だ……。」 私は思わず叫んだ。そしてその瞬間、子供のように胸のときめきを覚えた。 どれもこれも小鳥のように生意気に嘴(くちばし)を尖らし、どれもこれも小肥りに肥って、はち切れそうに背を円くしている。 焦茶色の肌は、太陽の熱をむさぼるように吸って、こんがりと焼け上った気味だ。 唐木机の脚、かぶと虫の兜、蟋蟀の太腿――強健なものは、多くの場合に焦茶色にくすぶっている。 夏末に雑木林を通ると、頭の上に大きな栗の毬(いが)がぶら下っているのを見かけることがよくある。爆ぜ割れた毬の中から、小さな栗の実が頭を出してきょろきょろしているのは、巣立ち前の燕の子が、泥の家から空をうかがっているようなもので、その眼はもの好きと冒険とに光っているが、燕の母親がその雛っ児たちを容易には巣の外へ飛出させないように、胸に抱えた子供たちの向う見ずな慾望を知っている栗の毬は、滅多に自分のふところを緩めようとはしない。 殻(から)のなかに閉じ籠って、太陽を飽食している栗の実は、日に日に肉づいて往って、われとわが生命の充実し、内圧する重みにもちこたえられなくなって来る。 実(み)が殻から離れゆく秋が来たのだ。内部の強い動きから、毬はおのずと大きく爆ぜ割れる。 向う見ずの栗の実は、「まだ見ぬ国」にあくがれて、われがちに殻から外へ飛び出して来る。焦茶色の頭巾をかぶった燕の子の巣立ちである。 あるものは静かに枯葉の上に落ち、あるものは石にぶっつかり、かちんと音を立てて、跳ねかえりざま、どこかに姿をかくしてしまう。――どちらにしても、親木の立っている場所から八尺とは離れていない。彼らはそれを少しも悔まない。彼らにとって、ともかくもそこはまだ見ぬ国なのである。焦茶色の外皮の堅さは、こんな場合にもかすり傷一つ負わさない。 私はこんなことを思いながら、栗の実の二つ三つを噛んで、それを火鉢の灰に埋めた。灰のなかからぷすぷすと煙がいぶり出して来た。 老 樹(46) 1 南メキシコの片田舎に、世界で一番古いだろうと言われる老木が立っている。それはすばらしく大きな糸杉(サイプレス)で、幹の周囲が百二十六呎(フィート)、樹齢はごく内輪に見積っても、まず六千年は請合だと言われている。 私の住んでいる西宮をあまり離れていない六甲村に、今度天然記念物となった大きな樟樹がある。幹の周囲三十八尺六寸、根もとの周囲六十四尺にあまるすばらしいもので、樹齢はざっと千三百年にはなるだろうということだ。その附近に住んでいる、今年七十二才の前田某という老人の言葉によると、今から六十年ほど前、老人が十二、三才の頃には、この木の幹に張るしめ縄の長さが、五尋(ひろ)くらいで足りたものが、今では六尋も要るので、千幾百年も経ってこんな大きさになっていながら、まだ成長をやめないのかと、唯もう驚かれるばかりだということだ。 六千年といえば、長い人類の歴史をも遥か下の方に見くだして、その頭は闇い「忘却」のかなたに入っている。その間樹は絶えず成長を続けて来たのだ。その脚の下には大地を踏(ふま)え、肩の上には天を支えて微塵の動ぎをも見せない巨柱のように衝っ立ってはいるが、樹は一瞬の間も休みなく変化を続けて、その大きさを増しているのだ。すべての草花は、その短い一生の間に、自分の全重量のざっと二百倍もの水分を土のなかから吸収するといわれているが、この巨木が六千年の間昼夜をすてず、大地のなかから吸い上げた養いが、どれほど大きなものであったろうかは、誰にも思いやられることだ。その養いは数知れぬ青い葉となって日光に呼吸し、すぐよかな枝となって空に躍り、また鯨の背のような厚ぼったい樹皮となり、髄となりして、今も尚六千年のむかし、土から柔かい双葉を持ち上げた、その頃の生命の新鮮さを失わないでいる。 人間はものの数ではない。神よりも強健で、神よりも生命が長い。――そんなものが一つ、まだ見ぬメキシコの森林に存在することを思うだけでも、私の心は波のように踴躍する。P.207~208 台所のしめじ茸(47) 1 十月中頃のある日の午後二時過ぎ、水が飲みたくなって台所へおりて往った。天気が好いので、家のものたちは皆外へ出て往った後で、そこらはひっそりとしていた。 窓を洩れる西日が、明るく落ちている板敷に、新らしい歯朶(しだ)の葉を被せかけた笊(ざる)がおいてあるのが眼についた。そっとその葉をとりのけてみると、朽葉のかけらを頭に土ぼこりを尻っぺたにこびりつけた菌(きのこ)が、少し前屈みになった内ぶところに、頭の円い小坊主を幾つか抱え込んで、ころころと横になっていた。 「おう。しめじ茸か。しばらくだったな。」 私は久方ぶりに友達に逢ったようにこう思って、その一つを取り上げてみた。冷たい秋の山のにおいが、しっとりと手のひらに浸み入るようだった。 私はよく雑木山のなかで、しめじ茸を見つけたことがあった。この菌は狐のたいまつなどが、湿っぽい土地に一人ぽっちで立っているのと違って、少し乾(かわ)いたところに、大勢の仲間と一緒に出ている。私は黄ばみかかった落葉樹の下で、この菌の胡粉を塗ったような白い揃いの着付で、肩もすれずれに円舞を踊っているのを見たことがあった。また短い芝草の生えた緩い傾斜で、勢揃いでもしているように、朽葉色の蓋(かさ)を反らして、ずらりと一列に立ち並んでいるのを見たこともあった。どんな場合にも、一つびとつ離ればなれに孤独を誇るようなことがなく、いつも朋輩のなかに立ち交って、群居生活を娯んでいるのが、このしめじ茸の持って生れた本性であるらしい。私はそれを思って、この菌を採る場合には、あとに残されたものの寂しさを憐んで、頭の円い小坊主だけは、出来るだけ多くそのままにしておいたものだが…… 蟋蟀が鳴いている。竈のうしろかどこかから、懶そうな声が途切れ途切れに聞えて来る。 「それ、虫が鳴いている。お前と俺と二人にとって、那奴(あいつ)はむかし馴染だったな。」 私はもとのように歯朶の葉をそっと菌に被せかけた。そして日光のこぼれている板敷から、少し側の方へ笊を押しやった。 2 いつだったか、渡辺崋山の草虫帖の一つに、菌をとり扱っているのを見たことがあった。枯木の幹を横さまに、その周囲に七つ八つの椎茸を描いたもので、円い太腿をした蟋蟀が二つ配(あしら)ってあった。画面の全体が焦茶色の調子でひきしめられていたが、枯れ朽ちた椎の木の上皮に養いを取って、かりそめの生を心ゆくばかり娯しんでいる菌の気持が、心にくいまでよく出ていたことを覚えている。 客室の南瓜(48) 1 南瓜――といえば、以前は薬食いとして冬まで持ち越し、または年を越させたものだが、米国産の細長いつるくび南瓜や、朱色の肌をした平べったい金冬瓜や、いろんな恰好をしたコロンケットなどが、娯みに栽培せられるようになってから、南瓜は秋から冬を通じて、客間の装飾としても用いられるようになった。 私は奈良興福寺にあるな高い木彫の天灯鬼が、左肩に載せた灯を左手で支えて、ぐっと身体をひねっている姿や、その相手の龍頭鬼が龍を首に巻きつかせたまま、灯を頭に載せ、両手を組み、白い眼をむいているのを見るのが好きだ。鬼というものをこんなにまで写生風に取扱って、それに溢れるばかりの感情を盛った作者の腕前に心から驚歎させられるが、それと同時に、この小鬼たちに対して友だちのような心安さから、その肩に盛り上った肉塊(ししむら)を撫で廻し、その臍のあたりを小突いてみたくなることがよくある。私が南瓜を愛するのはそれと同じ気持で、瘤のようにでこぼこした、または縮緬皺の細かい肉つきの手触りと色つやとに、その生みの親である太陽と土との、怪奇な意匠と秀れた仕上げとを味いたいからに外ならぬ。実際南瓜こそは、情熱に焼け爛れた太陽と黒土との間に生れた、鼻っ欠けの私生児に過ぎないかも知れないが、この私生児は、日の熱と土の力とを両つとも立派に持ち伝えた、碌でなしのえらものである。 2 円い瓜、長目な瓜、細長い瓜、またはでこぼこの瓜――それがどんな形であろうと、私が瓜の実を好む気持に少しも変りはない。高麗焼の陶器に、朝鮮民族の呑気な、しかし、また本質的な線の力強さを味い得るように、私たちは瓜の実の持ついろいろな線や、恰好や、肌触りに、見かけは間伸びがしたようで、どこかにちゃんと締め括りがあり、大まかなようで、実は細かい用意があるのに驚かされることがよくある。 瓜のおもしろ味は、蔓や巻髪を切離してはならない。最も力の籠っているのは、蔓と瓜の実とをつなぐ臍(ほぞ)の柄(え)で、生(な)り物全体の重みを支えなければならぬだけに、秀れた茶壺の捻り返しを見るような、力と鮮やかさとを味わされることが多い。この臍を起点として、瓜の肌に沿うて流れる輪廓の線は、真桑瓜や雀瓜のように、こぢんまりと恰好よく纏っているのもあるが、どうかすると、長糸瓜のように、線と線とが互に平行したまま、無謀にも七尺あまりも走った後、やっと思い出したように、いくらか尻膨れになってつづまりをつけるのや、または冬瓜や西瓜のように、図外れに大きな弧線を描いて、どうにも始末におえなくなっているのがある。そのなげやりに近いまでの胆の太さは、芸術家と実行者とを、愛と放棄とを、両つながらその意図に有っている自然翁でなくては、とても出来ない放れ業である。 いつだったか、元末の画家呂敬甫の『瓜虫図』の写しを見たことがあった。長い蔓に生った大きな青い瓜に、火の雫のような赤蜻蛉を配ったものだった。また小栗宗湛の『青瓜図』をも見たことがあった。蔓につながった二つの大きな瓜を横たえ、それに二疋の螳螂を添えたもので、瓜の大きさと葉の緑とが、いまだに記憶に残っている。二つの絵に共通の点は、こうした自然物に対する深い愛と、大きな瓜に小さな昆虫を配したところにあるが、軽い羽をもった赤蜻蛉も、反抗心に燃えている螳螂も、どっかりと横に寝そべったあの青瓜の大頭(おおあたま)の前に出ては、何となく気圧(けお)されがちに見えるのもおもしろいと思った。 3 夜半亭蕪村の描いた真桑瓜と西瓜の化物を見たことがあった。すべての想像に画のようなはっきりとした輪廓をもたせないではおかなかったこの芸術家は、絶えず幻想を娯み、また幻想に悩まされていたのではあるまいかと疑われるほど、妖怪変化について多くの記述と絵画とを遺している。私が見たのもその一つで、遠州見付の夜啼婆、鎌倉若宮八幡の銀杏の樹の化物などと一所に描かれたものだった。山城駒のわたりの真桑瓜の化物が、左手に草履を掴んで、勢よく駆け出そうとする奴姿は、朝露と土とに塗れている軽快な真桑瓜の精として上出来だった。が、それよりもいいと思ったのは、大阪木津の西瓜の化物で、二本差で気取ってはいるが、大きな頭の重みで、俯向き加減にそろそろと歩いている姿には、覚えず心をひかれた。図はずれに大きくなり過ぎた頭の重みから、絶えず生命の悩ましさと危さとを感じて、慢性の脳神経衰弱症にとりつかれている、この幼馴染の青瓜を思うと、私は実際気の毒でならない。 4 出来の悪い冬瓜の末生(うらなり)を見ると、じき思い出されるのは、風羅念仏の俳人惟然坊の頭である。この俳人は生れつき頭が柔かいので、夜寝るのに枕の堅いのが大嫌いであった。ある時師の無名庵に泊って、木枕にぐるぐる帯を巻きつけていたのを、芭蕉に見とがめられて、 「お前は頭に奢を持っている男だな。貧乏したのは、そのせいかもしれないぞ。」 と冷かされたのはな高い話だ。私は襤褸屑(ぼろくず)のように破けた葉っぱを纏った、貧乏な、頭痛持らしく額に筋を立てている青瓜を見る度に、あの蝋色の胡粉を散らした歪形(いびつがた)な頭の下に、せめて枕だけは柔かいのをあてがってやりたく思うことがよくある。 5 太閤記を見ると、秀吉が朝鮮征伐のために、陣を進めた九州の旅先で、異形(いぎょう)の仮装をして、瓜売になったことが載っている。広く仕切った瓜畑に、粗末な茶店など設け、太閤自ら家康、利家といったような輩と一緒に瓜商人に装って、 「瓜はどうかな。味のよい瓜を買うてたもれ。」 と声まで似せて売り歩いたものだ。すると、旅僧になっていた織田有楽斎が呼びとめた。 「もし、もし。瓜売どの。老年の修行者に瓜をお施し下され。」 秀吉が自分の荷のなかから、瓜を二つ取出して、その手に載せてやると、有楽斎はそれを見てちょっと眉をしかめた。 「折角じゃが、これは熟れていぬようじゃ。もっと甘そうなのを……。」 と押が強く所望するおかしさに、居合す人達は皆笑いくずれたということだ。闊達な秀吉の気質と真桑瓜の持味とは、うまく調和しそうに思われる。P.212~217 秋が来た(49) また秋がやって来た。 空を見よ。澄みきった桔梗色の美しさ。一雨さっと降り上った後の初夏の青磁色の空の新鮮さもさることながら、大空そのものの底の知られない深さと透明さとは、この頃ならでは仰ぎ見るべくもない。私は建詰った市街の屋根と屋根との間から、ふと紫色の空を見つけて、 「おう、秋だ。」 と思わずそこに立停ったことがよくある。何という清澄さであろう。すぐれた哲人の観心の生涯を他にしては、この世でまたと見られない味である。桔梗色に澄み切ったままでもよいが、ときおり白雲の一つ二つが、掠めたように静かに行き過ぎるのも悪くはない。哲人が観心の生涯にも、どうかすると追懐のちぎれ雲が影を落さないものとも限らない。雲はやがて行き過ぎて、いつの間にかその姿を消してしまう。残るものは桔梗色の深い清澄さそのものである。偶に雲の代りに小鳥の影が矢のように空を横切る事がある。陶工柿右衛門の眼は、すばしこくこれを捉えて、その大皿の円窓に、こうした小鳥の可愛らしい姿を描き残している。 山の寂黙(じゃくもく)そのものを味うにも、この頃が一番よい。感じ易い木の葉はもうそろそろ散りかかって、透けた木の間から洩れ落ちる昼過ぎの陽の柔かさ。あたりのものかげから冷え冷えと流れて来る山気(さんき)をかき乱すともないつつましやかさを背に感じながら、落葉の径をそことしもなく辿っていると、ふとだしぬけに生きた山の匂をまざまざと鼻さきに嗅ぎつけることがよくある。ちょうど古寺に来て、薄暗い方丈で老和尚と差向いに坐ったとき、黙りこくった和尚その人の肌の匂を感じた折のように、こうした場合には何一つ言葉やもの音を聞かないのが、かえって味いが深いものだ。 畑には果実が枝も撓むばかりに房々と実のっている。憂鬱な梨、葡萄、女の乳房のように ぎ口から絶えず乳を滴らす無花果、蜜柑、紅玉のような柿。――支那花鳥画の名手徐熙の孫で、花卉を描くのに初めて没骨法を用いたというので知られている徐崇嗣は、豊熟した果実の枝を離れて地に墜つる状を描いて、その情趣を髣髴せしめたということだが、私は果実の大地に墜ちる音を聞くのが好きだ。人気もない林の小径に立って、笑み割れた落栗の実が、一つ二つ枯葉の上に落ちるのを聞くのは、秋に好ましいものの一つである。 日が暮れると、青白い月が顔を出して来る。安住の宮を求めて、東より西へと絶えずさすらい歩く天上の巡礼者が、足音も立てず静かに森の上に立つと、そこらのありとあらゆるものは、行いすました尼の前に出たように、しっとりと涙の露に濡れながら、昼間見て来たことをも一度心のうちに繰り返し、繰り返して、それぞれ瞑想に耽るのである。P.218~220 秋の佗人(50) 二日二夜の間びしょびしょと降りつづけた秋雨は、三日目の朝になって、やっと霽(は)れあがった。樹々の葉からは、風もないのに雨のしずくがはらはらとこぼれかかった。石灯籠の下にある草柘椊(くさつげ)を少し離れて、なも知らない小さな菌(きのこ)が二かたまり生えているのが眼についた。昨日の夕方、雨の庭を眺めたときには、それらしい影も形も見えなかったのに……。 京都の三条大橋の東に檀王法林寺というお寺がある。そこの境内から川端へ抜けるところに赤門があり、夕方になると閉されるが、いつ締まるのか誰もそれを見かけたものがない。川向うの上木屋町あたりで若い妓(おんな)たちが、この門の締まるのを見ると、有卦に入るといって、欄干にもたれてじっとそれを待っているが、見ているときには締まらないで、ちょっと眼を外(そ)っ方(ぽう)に逸らした時に、ちゃんと閉じられているということだ。 ちょうどそのように、誰の眼にも気づかれないうちに、菌はひょっこりと地べたに飛出している。うるさい人間の「おせっかい」と「眼」との隙を見つけて、そこにほっと呼吸をついているといったように。 このわび人たちは、仲間にはぐれないように互に肩をくっつけ合い、蓋(かさ)を傾け合って、ひそひそ声で話している。時偶庭木の葉を洩れて、日光がちらちらと零(こぼ)れかかると、菌たちはとんでもない邪魔ものに闖入せられたかのように、襟もとを顫わせて嫌がっている。わび人はわび人らしく、じめじめした湿地と薄暗がりとを娯しんでいるのだ。 そこらに着飾って立つ花のように、縞羅紗のズボンをはき、腰に剣をさした若い騎士の蜂が、ちょくちょく訪ねて来るのでもない。誰一人その存在を気づかず、偶にそれと知っても、その微かな呼吸に籠る激しい「毒」を恐れて、それに近づこうともしない。こうして与えられた「孤独」を守って、彼らはそこに自分たちの生命をいたわり、成長させている。 いたずら盛りの子供が、幾度か棒切を持って、この小さなわび人たちを虐げようとしたことがあった。その都度私は彼をたしなめて、その「孤独」を庇ってやった。 二、三日してまた雨が降った。雨の絶間にふと気づくと、菌はもう見えなかった。揃いの着付に揃いの蓋を被っていたこのわび人たちの姿は、どこにも見られなかった。 彼らは誰にも気づかれないで来たように、誰にも気づかれないで去ったのである。P.221~222 草の実のとりいれ(51) 収穫(とりいれ)といえば、すぐに晩秋の野における農夫の労働生活が思われる。これは激しい汗みずくな、しかしまた楽みにも充ちたものである。草の実の採入れは、それとは趣の異った、暢気な、間のぬけた、ほんのちょっとした気慰みの仕事に過ぎないが、それでも、そのなかに閑寂そのものの味が味われないこともない。 秋の彼岸前後になると、懐妊した女の乳のように、おしろい花の実が黒く色づき初める。それを撮み取ろうとすると、円い実は小さな生物か何ぞのように、こざかしく指の間を潜りぬけて、ころころと地べたに転がり落ちる。人間の採集がほんの気紛れからで、あまりあてにはならない事をよく知っている草の実は、こうして人間のおせっかいから遁れて、われとわが種子を保護するのである。それを思うと、落葉の下、土くれの蔭までもかき分けて、落ちたおしろいの実の行方をさがすなどすまじき事のように思う。 おしろいの実を掌に取り集めると、誰でもがその一つ二つを爪で割ってみたくなるものだ。中には女が化粧につかうおしろいのような白い粉が一ぱいにつまっている。小供の時もよくそうして割ってみた。大人になって後もなお時々割ってみる事がある。自然はいかさまな小商人(こあきんど)のように、中味を詰め替える事をしないので、今もむかしのものと少しも変らない、正真まざりっ気なしのおしろいの粉が、ほろほろとこぼれかかる。この小さな草の実にこうした誘惑を感じるのも、不思議なことの一つである。 鳳仙花の種子を採集するには、蟋蟀を捉えるのと同じ程度の細心さがなくてはならない。なぜかというに、この草の実は苞形(つとがた)の外殻(から)に包まれていて、この苞の敏感さは、人間の指さきがどうかした拍子にその肌に触れると、さも自分の清浄さを汚されでもしたかのように急に爆ぜわれて、なかに抱いている小坊主の種子を一気に弾き飛ばしてしまうからだ。苞ぐるみ巧くそれを ぎとったところで、どうせ長もちはしないに極っているが、手のひらのなかで苞の爆ぜるのを感じるのは、ちょっとくすぐったいもので、蟋蟀のように刺(とげ)だらけの脛(すね)で、肌を蹴飛ばしたりしないのが気持がいい。 のっぽな露西亜種の向日葵が、野球用の革手袋(ミット)を思わせるような大きな盤の上に、高々と大粒な実を盛り上げて、秋風に吹かれているのは哀れが深い。秋から冬へかけて、シベリヤを旅行した人の話を聞くと、あの辺の子供たちは、雪の道を学校への往き復りに、隠しの中からこの草の実の炮じたのを取り出しては、ぽつりぽつりと噛っているそうだ。そろそろ粉雪のちらつく頃になると、好きな虫けらも見当らないので、そこらの雀という雀は、余儀なく菜食主義者とならなければならない。脂肪の多い向日葵の実は、この俄仕立(にわかじたて)の青道心(あおどうしん)のこのうえもない餌となるので、それを思うと、私はこの種子を収める場合に、いつも余分のものをなるべく多く貯えなければならなくなる。 けばだった鶏頭の花をかき分けて、一つびとつ小粒の実を拾いとるのは、やがて天鵞絨(ビロード)や絨氈の厚ぼったい手ざわりを娯むのである。からからに干からびた紫蘇の枝から、紫蘇の実をしごきとる時、手のひらに残ったかすかな草の香を嗅ぐと、誰でもが何とはなしにそれと言葉には言いつくし難い哀愁を覚えるものである。枯れた蔓にぶら下って、秋を観じている小瓢箪の実が、いつのまにか内部に脱け落ちて、おりふしの風にからからと音を立てながらも、取り出すすべのないのも、秋のもどかしさである。 糸瓜の実が尻ぬけをしたあとを、何心なく覗き込み、細かい繊維の網から出来上った長い長い空洞が、おりからの秋天の如く無一物なのに驚いて、声を放って哄笑するのも、時にとっての一興である。P.223~225 【青道心】 の意味 1: 出家したばかりで仏道にうとい者。今道心。新発意(しんぼち)。 2 :よく考えもせずに起こした信仰心。なま道心。 赤土の山と海と(52) 私の郷里は水島灘に近い小山の裾にある。山には格別秀れたところもないが、少年時代の遊び場所として、私にとっては忘れがたい土地なのだ。 山は一面に松林で蔽われている。赤松と黒松との程よい交錯。そこでなければ味われない肌理(きめ)の細かい風の音と、健康を喚び覚させるような辛辣な空気の匂とは、私の好きなものの一つであった。 メレジュコオフスキイの『先駆者』を読むと、レオナルド・ダ・ヴィンチが戦争を避けて、友人ジロラモ・メルチの別荘地ヴァプリオに泊っている頃、メルチの子供フランチェスコと連れ立って、近くの森のなかを見て歩く条がある。少年は若芽を吹き出したばかりの木立のかげで、この絶代の知慧者から、自然に対する愛と知識とを教えられているが、こういう指導者を持たなかった私は、いつもたった一人でこの松山を遊び歩いた。そして人知れず行われている樹木の成長と、枯朽とを静かに見入ったり繁みの中から水のように滴り出る小鳥の歌にじっと聴きとれたりした。一葉蘭(いちようらん)が花と葉と、どちらもたった一つずつの、極めて乏しい天恵の下に、それでも自分を娯しむ生活を営んでいるのを知り、社交嫌いな鷦鷯(みそさざい)が、人一倍巣を作ることの上手な世話女房であるのを見たのも、この山のなかであった。フランチェスコは森の静寂のなかで、レオナルドの鉄のような心臓の鼓動を聞きながら、時々同伴者の頭の縮れっ毛や、長い髯が日に輝いているのを盗み見て、神様ではなかろうかと思ったということだが、私も偶に自分の背後や横側で、黒い大きなものが、自分と同じような身振で物に見とれ聞きとれているのを見て、思わずびっくりしたことがあった。それは山の傾斜に落ちている私の影だった。 私はそんなことにも倦むと、山のいただきにある大きな岩の背に寝転んだ。そして自分の上に拡がっている大きな藍色の空をじっと見入った。空にはよく鳶の二、三羽が大幅な輪を描いて舞っていた。私のとりとめない空想は、その鳶の焦茶色に光った翼に載せられて空高く飛んだものだが、どうかすると鳥の描く輪は、次第々々に横に逸れて、いつのまにか私の視野から遠ざかってしまうことがないでもない。振り落された私の空想は、あぶなくもんどりうってまた私のふところに帰って来た。 私はまた海にもよく往った。多くの場合水島灘の浪は女のように静かだった。私は岸の柔かい砂の上に腰をおろして、眼の前を滑って往く船の数をよんだりした。船はいずれも白鳥の翼のような白い帆を張っていた。そして少年のとりとめのない夢を載せて、次から次へと島々のかげに隠れて往った。 海が遠浅なので、私はよく潮の退いた跡へおり立って、蝦や、しゃこや、がざみや、しおまねぎや、鰈や、いろんな貝などを捕った。私はこれらのものの水のなかの生活に親しむにつれて、山の上の草木や、小鳥などと一緒に、自分の朋輩として彼らに深い愛を感ずるようになった。そしてこの世のなかで、人間ばかりが大切なものでないことを思うようになった。 あの小高い赤土の松山と遠浅の海と。――思えばこの二つは、私の少年時代を哺育した道場であった。P.226~228 糸瓜と向日葵(53) 八月――日。畑に椊えた長糸瓜は、釣上げられた鰻のように、長いからだをだらりと棚からぶら下げている。地べたとすれすれに尖った尻をふっている。一番剽軽で、そして一番長そうな奴を手で押えて、物尺であたってみたら、七尺近くもあった。 糸瓜棚の上に、一、二尺も長い首を持ち上げて、お盆のように大きな花を咲かせていた向日葵は、いつの間にか金の花びらをふるい落して、その跡にざらざらの実を粒立たせているのが見える。立秋からもう十日も経っているのに、相変らず暑い。 K氏来訪。開け放った応接室の窓越しに、ちらと畑の方へ眼をやりながら言った。 「あの向日葵はロシヤ種でしょう。あの実をロシヤ人が噛み割る方法を御存じですか。」 「いや、知りません。どんなにします。」 「それがおかしいんです。まず向日葵の実を一つ歯の間に噛んでおいて、そして……。」K氏は大きな両手でもって妙な恰好をしてみせた。「左の手で頭のてっぺんを押えつけて、右の掌面でいきなり強く下顎をこづき上るんです。こうやって。いかにもロシヤ人らしい食べ方でしょう。」 私はそれを見て、思わず噴き出した。 「まさか……。」 「いや、ほんとうのことですよ。」K氏は不足らしく言った。「私は独逸(ドイツ)の田舎の停車場で、若いロシヤの労働者が、柵にもたれてそれをやっているのを見たんです。嘘だとお思いなら、その時一緒にいた私の友人の独逸人に訊いてみて下さい。」 「その独逸人は、どこにいるんです。」 私は物ずきにも訊いてみた。 「今伯林(ベルリン)にいますよ。」 K氏が帰った後へ入れかわりにB夫人来訪。夫人は信神の念のあつい妙好人である。 午すぎの室のうちは、息苦しいほどに熱かった。私は夫人と差向いに四方山の話をしているうちに、夫人が時々それとなく窓の方へ眼をやって、いかにも楽しそうに、 「どうもありがとうございます。」 と、口のなかで小声に言って、ちょっと会釈しているのに気づいた。それが私の談話に対するうけ答えでないのはいうまでもないこと、どうかすると、私の存在をも忘れさせるような、眼に見えない第三者が窓越しに立っていて、それに対する挨拶とも見えるようで、何だかちょっとぶ気味だった。私は訊いてみた。 「何を言ってらっしゃるの。さっきから。」 「お礼を申し上げてるんですわ。」夫人は小娘のようにちょっと含羞んだ。「あまりお涼しい風が、吹き込んでまいりますもんですから。」 「そんなことまで一々言葉に出して、お礼を言わなければならないんですか。黙って感謝していてもよかりそうなものだのに。」 「いいえ。私達の神様は、人間の感謝が歓喜(よろこび)の声となって、大げさに告白されるのを、大層およろこびになりますよ。」夫人はきっぱりと言った。「黙っていたのでは、かえってお気に召さないんです。神恩(おかげ)は小さくとも、大よろこびでお礼を申上げますと、次にいただけますものは、もっと大きうございます。」¥ 「そこに多少の虚偽が含まれてはいないでしょうか。」 「多少の虚偽はあっても構いません。おかげを喜ぶ度合が強くさえありましたら、嘘から真実が生れ、二二が五ともなれば、七ともなるのでございますよ。」 B夫人はこう言って、ふと窓越しに外へ眼をやったが、糸瓜棚にだらりとぶら下った長糸瓜を見ると、思わず声を高めた。 「まあ、長い糸瓜ですこと。たんとおかげをいただいてますのね……。」P.229~232 落梅の音(54) 今年は梅雨前には、雨がひっきりなく降り続いたが、肝腎の梅雨に入ってからは毎日の好天気で、自分の住まっている近くの水田なども水ふ足で、田椊が延びがちになり、宵ごとに聞く蛙の声も何となく力がなかったが、六月も末になってから雨は降り出した。 初めはしとしとと降り出した雨が、やがて底を抜いたような土砂降りとなり、それが二日も三日も四日も五日も、どうかすると九日も十日も降り続くと、天地は雨の光と影と響とに圧倒されて、草も、木も、鳥も、獣も、野も、山も、また人間も、まるで小さな魚のように、押流されてしまいそうな、危っかしい気持を抱かせられる。この危っかしさを孕んでいるのが梅雨の雨の特徴で、芭蕉の さみだれを集めて早し最上川 という句を読んで、岸を浸さんばかりの濁り水が、矢のように早く走っているのを想像して、眼が眩いそうになるまでに水の力に驚くのも、この危さの気持を感ずるからである。蕪村の さみだれや大河を前に家二軒 も、またこの危さの美を外にしては味われぬ句である。いつの年でも梅雨に入ってどしゃ降りの大雨に、ふ安な危っかしさを抱かせられる度ごとに、私は喩えがたい一種の快感を覚えぬわけには往かない。 幾日か降り続いた雨が、やがて降りくたびれた頃は、凡兆のいう この頃は小粒になりぬ五月雨 で、長雨と大雨の憂鬱とふ安とから救い出された、激情の後のぐったりした疲れから産れる明るさといったようなものが、分毎に、秒毎に度を加えて来るのもこうした時である。 また降り続き、降り暮らした雨が、いつか夜になって人の寝静まった後に、こっそり霽れて、それがちょうど月のある頃で、庭木の影が水のように窓障子に浮んでいるのを、ふと眼が覚めて見る驚きなども、梅雨でなくては得られない趣である。 月の無い、まったくの闇の一夜、夜が更けて寝つかれないでいると、さきがたから降り細った雨はいつしか止んで、草木という草木は、雫のたれる濡れ髪を地べたに突伏したまま、起き上る力もなく、へとへとになっている静かさの底で、ぽたりと何物か地べたに落ちるのを聞きつけることがよくある。 熟梅(うみうめ)の一つが枝を離れた音である。 私はどんなときでもこの音を聞きつけると、梅の実が自分の心の深みに落ちて来たかのような、驚きとなつかしみとを感ずる。なに一つ動かない閑寂そのものの微かな溜息が、樹の枝を離れて、真っ直に私の生命の波心にささやきに来たような感じである。 むかし小堀遠州は、古瀬戸の茶入「伊予すだれ」を愛玩して、これを見ると、心はいつでも「わび」を感じるといって、暫くの間も座右を離さなかった。その子権十郎はまたその小壺に書きつけをして、 「昔年亡父孤蓬庵主小壺をもとめ、伊予すだれとなづけ、その形たとへば編笠といふものに似て、物ふりて佗し。それ故に古歌をもつて あふことはまばらに編める伊予すだれいよいよ我をわびさするかな 我が愚かなる眺めにも、これを思ふに忽然としてわびしき姿なり。また寂寞たり。まことなるかな、青苔日々にあつくとあるも然り。年月をふるといへども、こと訪ふ人もなく、安閑の境界は却つて楽を招き、富貴を願はず、我が惑はぬ年をこそ、秋の夜の長きに老の寝覚のつれづれに思ひ出してしるし侍る。」 といっている。これで見ると、孤蓬庵父子はこの小壺に対すると、その形を見ただけで、もう「わび」の心持に入ることが出来たものと思われる。 私が梅の実の熟(つ)えて落ちる音を好むのもつまりそれで、その音を聞くと、忽然として閑寂のふところに佗びの心持を味うことが出来るからである。私が梅の樹に取り囲まれた郷里の茅屋に、いまだに断ちがたい愛着を感じているのもそれ。一本の梅の木もない今の借家に絶えず物足りなさを抱かせられているのもそれ。また軒端の梅は実を採るものでなく、音を娯むものとしているのもそれゆえである。P.233~236 参考:野沢 凡兆は、江戸時代前期の俳諧師。姓は越野、または宮城、宮部とも。加賀国金沢の出身と言われる。京都に出て医者になり、そのときに松尾芭蕉と出会い、師事したが後に離れた。晩年は零落したという。妻の野沢とめも俳諧師である。写実的な句を得意とした。 『猿蓑』を向井去来と編集した。 ウィキペディア 菱(55) 1 どこをあてどともなく歩いていると、そそけた灌木にとり囲まれた池のほとりに出て来た。池にはところどころに細かい水草が浮いていて、片眼で笑うような午過ぎの日ざしが一杯に落ちかかっている。 草の路に沿うて池のまわりを歩いていると、ふと菱の実が食べたくなって来た。 何の故ともわからない。 支那湖州の菱湖鎮の菱は、味がうまいので聞えたもので、民船であの辺を旅をすると、舷を叩いてよくそれを売りに来るそうだが、私はまだそんなうまい菱の実を味わったことがない。私が少年のころ食べ馴れたのは、自分たちが小舟に乗って、村はずれの池から採って来た普通(ただ)の菱の実で、取り立てて言うほど味のいいものではなかったが、いかつい角を生(はや)した、その堅苦しい恰好がおもしろい上に、歯で噛むと、何とも譬えようのない仄かな匂が、ぷんと歯ぐきに沁み透ったものだ。 秋が来ると、私がときどき菱の実を思い出すのも、ひとえにその匂をなつかしむからのことだ。 一わたり池のおもてをあちこちと見わたしても、見覚えのある菱の葉はそこらに見つからなかった。 ふと小蝦か魚かの白く水の上に跳ねあがるのが見えて、泡のつぶやきのような微かな音が聞かれた。 その瞬間、私は菱の実の殻を噛み割ったような気持を私の前歯に感じた。 2 菱の根は池の底におりて泥のなか深く入っているが、蔓は長く伸びて水の面を這いまわっている。葉柄の腫れ上った三角形の葉は、水の面が皺む度に、たよたよと揺れ動いて、少しの落つきももたない。葉と葉との間にこぼれ咲いた小さな白い花は、真夏のものとは思われないほど佗しいもので、水底からわざわざ這い上って来て、あんなに小さい質素な花で満足しているその遠慮深い小心さは、贅沢好き、濫費好きの夏の太陽から、侮蔑の苦笑をもって酬いらるるに過ぎないかも知れない。 だが、その小さな、謙遜な花から、兜虫のように、鬼のように、いかつい角を生した青黒い顔の菱の実が生れるのだ。P.237~238 くろかわ(56) くろかわという菌がある。二、三寸あまりの黒い蓋を着て、そこらの湿地に立っている。下向きに巻いた蓋をそっと傾けてみると、そこには白羅紗のような裏がついている。京都人はこれを料理につかう場合には、生(なま)のを茹(う)でて、それを熱湯のなかから取出すと、いきなりぴしゃりと板の間に投げつけるのを忘れない。 「なぜそんなことをするのだ。」 と訊くと、 「投げつけられると、菌がびっくりして、その拍子に苦味(にがみ)が幾らか取れるようですから。」 という返事だ。 こうして残された少しの苦味は、この菌を酢のものにして味わう場合に、唯一つのなくてかなわぬものである。P.240~240 山茶花(57) 山茶花は泣き笑いをしている。十一月末のいじけ切った椊込みのなかに立って、白に、薄紅に、寂しく咲いたその花には、風邪に罹った女の、眼の縁の上気(のぼせ)は、発熱のせいかも知れないと、そっと触ってみると、肌はしっとりと汗ばんで、思いの外冷えきっている、そのつめたさが感じられる。途の通りがかりに飛び込んで来た風来坊の泥棒蜂が、その大きな百日鬘を花びらのなかに突っ込んで、すぐにまたつまらなさそうに引返して往くのは、その蕊の匂があまりに低く、冷いのによることかもしれない。 これまで薄暗い庭の片隅で、日光に向いた一方にだけ花をもっていた山茶花を、ことしの春先に日当りのいい中央(まんなか)どころに移し椊えたことがあった。いつも室の片隅から客に応対することしか知らない「女」を、大勢の群集のまんなかに引張り出すと、「女」は自分の背後を気にして、しきりと帯の結び目のあたりを撫まわしたりするものだが、ちょうどそのように、庭の片隅から日光のただなかに引越して来た山茶花は、小枝の少い自分の背後を気にして、出来合いの見すぼらしい花を三つ四つつけて、やっとばつを合わせているような恰好だ。 寂しい花だ。P.241~242 魚の旅(58) 魚の水を離れたようなものだ。――とは、頼りを失って、手も足も出ない場合に用いる言葉だが、しかし魚のなかには、水を離れても、ある期間は立派に生き存えているのがある。南アメリカの熱帯地方に棲んでいるある魚族は、池が狭くて、やけくそな太陽の熱に遠からず水が干上ろうというおそれがある場合には、あらかじめそれを感づいて、もっと広く、もっと冷い水をもとめて、漂泊の旅に上る。そして森の湿地から湿地へと、幾百という魚が群をなして、夜を日に継いでぞろぞろと動いているということだ。 私も一度山越しの夜道に、草鞋の底で長い縄片のようなものを踏えたことがあった。手にさげた提灯の明りをさしつけて見ると、それは砂まみれになった鰻だった。 「あ、びっくりした。足の裏がぬるっとして滑りそうだったから、てっきり長虫(ながむし)だろうと思ったが……。>私は後から来る連の男に呼びかけた。「何だってまた、鰻がこんなところにまごまごしているんだろう。」 「すっかり秋だな。もう落鰻(おちうなぎ)の時節に入ったのだ。」 連の男はそこらをのたくっている鰻に落した眼をあげて、暗い空を見た。 空には星がきらびやかに瞬いて、銀河が白く帯のように落ちかかっていた。 「秋だな。」 と、連の男はも一度繰返していって、秋になると鰻は卵を産みに、山の上の湖から、高原の池から、沼から、小流から、てんでに這い出して来て、あらゆる困難に堪えつつ、河を下って海に入り、長い旅を続けて、遠くフィリッピンあたりまで行くらしいが、その生活の細々したことは、まだはっきり判らないのだというようなことを話して聞かせてくれた。 「奴さん、もうそろそろ旅に出たくなって、そこらの池から、闇にまぎれてぬけ出して来たのさ。」 「へえ、それじゃ、お前もそんな長旅をしている一人なのか。そうとは知らないで、草鞋で踏みつけてすまなかったな。」 私は砂まみれになった身体のどこかに、傷でも負わせはしなかったろうかと、気がかりになって、提灯の明りでそこらを捜し廻ったが、鰻はもう地べたに姿を見せなかった。 道の片側には、夜露を帯びた雑草の葉が茂り合い、その蔭をあるかないかの水がちょろちょろと流れていた。遠い海への長旅に絶えず気をとられている鰻は、私たちの気づかないうちに、いつの間にか草をもぐって、そのなかに滑り込んだらしかった。 「まあ、よかった。」 私は口のなかでそういった。そしてあの粘り強い生命の力さえ失わなかったら、ちっとやそっとの傷はあっても、それはすぐに癒えついて、自分に負わされただけの旅の役目は、きっとしおおせるだろうと思った。 私たちはまた夜道を急いだ。P.243~245 潔 癖(59) 1 「自分の描く竹は、唯もう胸の逸興を写しただけで、葉や枝の恰好がどうかということはあまり詮議しない。麻としようが、蘆としようが、それは見る人の勝手だ。」 竹を描く度にこういった元の倪雲林は、竹が好きだっただけに、竹によく似た魂のすがすがしさと潔癖とを持っている画人だった。 その潔癖といえば、まるで病気かと思われるほどひどいもので、いつも水を盛った盥を側において、自分にも日に幾十度となく顔を洗い、手を濯ぎ、偶に訪ねて来る客人にも、座敷に通る前に、一々手を洗わせなければ承知しなかったものだ。 あるとき雲林の家に、客が一人泊ったことがあった。主人は自分が手にかけて綺麗に掃除をした庭の椊込みが、そんなことに無関心な客人によって、汚されはしまいかとびくびくものでいた。雲林は人間の臭みが自然に沁み込むのをおそれて、自分の描く山水の画幅には、どんなことがあっても、人物を描き添えないというほどな泉石好きだった。 主人は夜が更けて、客が咳き込むのを聞いた。 「きっとそこらに唾を吐き散らしているかも知れない。」 そう思うと、この清潔好きな画家は、気に懸ってろくろく睡るわけにゆかなかった。朝になると、彼は早速召使を叩き起して、客が窓外に吐き捨てたらしい唾の痕を捜させた。 召使はそんなことには馴れていた。彼は露に湿った一枚の桐の葉を折って来た。 「見つかりました、旦那さま。葉の面がこんなに濡れております。」 雲林は顔をしかめた。そしてその一枚の葉を捨てさせに、遠い村境まで召使を急がせた。 2 またあるとき、倪雲林の母が大病にかかったことがあった。雲林は出来ることなら、医者というものは招きたくなかった。病人があれば、どんな汚い家にでも訪ねて往かなければならない医者のからだは、決して安心の出来る客人ではなかった。しかし、親孝行の彼は、母の病が治したさの一念から、目をつぶって某という医者を迎えることにした。 医者は町に住んでいた。雲林はそれを迎えに自分の愛馬を送った。馬は主人の清潔好きな癖から、毎日洗い清められて、雪のように白く輝いていた。 平素から雲林が他人を汚いもの扱いにする癖を知っていて、それをにがにがしいことに思っていた医者は、馬に跨るが早いか、道のぬかるみを選って歩かせ初めた。 その日はちょうど大雨の後だったので、道のところどころには汚い水溜があった。そんなところへ来ると、医者はわざわざ飛び下りて馬の腹や、尻っぺたを思いきり泥水で汚した。 医者が雲林の家に着いた時には、馬はどぶ鼠のように汚くなっていた。出迎えた雲林は尻目にそれを見て苦りきっていたが、大事な場合だったので、じっと辛抱していた。医者は導かれて病室に通ったが、出入にそこらの道具に衝き当ったり、主人が大事の文房具を見ると、わざわざ立停って汗だらけの手でいじくりまわしたりした。 診察がすんで、医者の姿が見えなくなってしまうと、倪雲林の怒りは噴水のように迸り出した。 「お母さま。あなたに治っていただきたさの一念から、私は出来ぬことを辛抱しました。もしか私が病気だったら、死んでもあんな医者は迎えませんよ。」 倪雲林は、その後五、六日というものは、毎日のように馬を洗い洗いしたということだ。お蔭で泥にまみれた馬の毛は雪のように白くはなったが、一旦傷つけられた主人の潔癖は、長く歪められたままで残っていた。P.246~249 鶏(60) むかし、福井藩に高橋記内という鍔(つば)作りの名人があった。藩主をはじめ、家中のものたちは、その手で作られた鍔を、自分の腰のものにつけていることを誇として、ひどくそれを欲しがっていた。しかし、名人気質の記内は注文があったからといって、おいそれとすぐには仕事にとりかかろうとはしないで、毎日酒ばかり飲んでいた。記内は大の酒好きだった。 あるとき、殿様からのいいつけで、お側近く仕えている小役人の一人が記内を訪ねて来て、鶏の鍔を注文した。記内は早速承知して殿様お手飼の鶏の拝借方を申し出た。この鍔師が細工はすべて写生をもととして、物の形なり、動作なりを生きているように写し取るところに妙味があるのを知っている役人は、もっともな申出だとして、御鶏を貸し与えた。御鶏は羽の色が純白で、そこらに見られない高価な珍らしいものだった。 記内は大喜びで、その鶏を仕事場の近くに放った。鶏はしかつめらしい顔つきで、餌を拾いながら、気取った足どりであちこち歩き廻った。 「おい、そんなに気取るなよ。御殿のお庭より、こちとらの門先の方がどんなにか気儘でよかろうというものだ。もっとのんびりとしていてくれよ。」 記内はこんな冗談口をききながら、わき眼もふらないで鶏の動作を見つめていた。側にはいつものように酒徳利が置いてあった。記内は楽しそうにちびりちびりそれを飲みつづけていた。 肝腎の鍔が出来ないうちに、記内は毎日飲み溜めた酒の払いに困るようになった。きびしい酒屋の催促に、記内は堪りかねて、持前のずぼらな性分から、御貸下の鶏を売り飛ばしてしまった。 珍しい純白な鶏は、間もなくまた殿様のお手もとに買い戻されていた。記内の仕業はお上を憚らぬふ敵な振舞だというので、厳重に謹慎をいい渡された。 ある日、役人の一人がその後の様子を見に記内の家を訪ねた。この鍔作りの名人は戸を閉て切った仕事場のなかで、相も変らず酒に酔っぱらってごろ寝をしていた。 「これは何というざまだ、ほんとうに呆れ返ってしまう。」役人は酒臭い記内を揺り起こしながらいった。「これ、そんなに寝てばかりいないで、早く眼を覚まさんか。お上のお免しを得るには、御注文の品を打ち上げるより外にはないということが、お前には分らんか。」 「寝る、寝るといわれるが、遠慮を申しつけられたのでは、寝るより外には仕方がないのじゃからな。」 記内は独語のようにぼやいて、やっと起き上った。そしてとろんこの眼で役人の顔を見つけると、ふ足そうな微笑をうかべた。 「そんなにいわれるなら、これから仕事に取りかかろうから、もう一度あの鶏をお貸下げが願いたいものだな。」 「それはならぬ。お前のことじゃもの、また御鶏を酒手に代えまいものでもない。」 記内は大声で笑い出した。 「は、は、は、は。そんなに心配だったら、お前様が附添になってござらっしゃればいいじゃないか。」 「なるほどな……」 役人はいわれた通りに、まさかの時の用意に、自分が附添って御鶏を記内の仕事場に連れ込んだ。御鶏は油断のならぬ顔つきで、横眼で記内の方を盗み見ながら、横柄にそこらを歩きまわっていた。 記内は腕を拱んで、側眼もふらずじっとそれに見とれていたが、気に入った鶏の姿態が眼に入ると、 「あ、これだ。これだ。」 ようにいって、眼の底に焼きつけられた形をそのまま、すぐに仕事にとりかかった。 間もなくすばらしい鶏の鍔が出来上った。御褒美の一つとして、羽の白い鶏の一つがいが記内のもとに下げられた。記内はそれを見向うともしなかった。 「鶏か。折角だが、お前にはもう用はないのだ。」P.250~253 驢 馬(61) 1 驢馬は愛すべきものの一つだ。馬のように気どらないで、薄のろなところが愛嬌があっていい、脚の運びが遅いのも、小児や老人の乗ものとして、恰好でこそあれ、少しも非難すべきいわれはない。とりわけ都合がいいのは、馬に比べて背が低いので、どうかした拍子に誤って落馬するとき、腰などしたたかに打つ心配がないことだ。落馬のときのことなど心配すると、今の人はおかしがって笑い出すかも知れないが、むかし池大雅は、旅行のとき、宿場宿場でよく馬に乗ることがある。そんな時に落馬の心がけがなかったら、ものの拍子で怪我をするかも知れないといって、わざわざその道の人について、馬から落ちる法を稽古したものだ。それを思うと、私が驢馬のことにつけて、すぐに落馬の場合を思いついたのに、少しも間違がないことが解るだろう。 2 支那の明代の末に、徐枋という気品の高い画家があった。節義のために死んだ父の遺言を守って、一代に肩を比べるもののないほどの学才を持ちながら、役にもつかないで、一生を門を閉じて暮した人だったが、この人が飼っていた驢馬は、大変もの分りがよく、 「あの馬は、すっかり人間のいうことが分るようだ。」 という評判をとったほどのものだった。 寡慾で、貧乏だった徐枋は、家に食うものといっては何一つなくて、ひもじい目をすることがよくあった。そんな折にはこの画家は、即興の画なり書なりをしたため、それを籠に入れて、しっかりと驢馬の背に結びつけたものだ。すると、この評判の怜悧ものは、門を出るなり、側目もふらないで、一散に程近い町の方へ走って往った。そして巧みにひとごみのなかを分けながら、市場の前まで歩いて来て、ぴたりとそこへ立ちとまった。 「ほら、徐先生のお使が来た。きっとまたお急ぎの御用だぞ。」 それを見つけた町の人は、いつものことなので、てんでに走り寄って、籠のなかから書画を持ち出し、自分たちの気に入ったものを選び取った。そしてその代りに米や魚や野菜を、しこたまそのなかに運び入れることを忘れなかった。 籠が一杯になると、驢馬は市場を後に、もと来た道を道草も喰わないで、静かに帰って往った。P.254~256 参考:吉田松陰、野山獄(のやまごく)に在(あ)る時、友人土屋松如(つちやしょじょ)、居易堂集(きょいどうしゅう:明の遺臣俟斎徐枋(しさいじょほう)の著)を ... 孟子本文 私が野山獄にいる時、友人である土屋松如が、〚居易堂集』〈明の遺臣侯斎徐坊の著〉を貸してくれた。 遊 び(62) 1 すべて画家とか、彫刻家とかいう人たちのなかには、いろんな動物を飼って、その習性なり、形態なりを研究し、写生するのがよくある。 与謝蕪村の門弟松本奉時という大阪の画家は、ひどく蛙が好きで、方々からいろんな種類を集めて、それを写生したり、鳴かせたりして喜んでいた。それだけに、長い間には珍らしいのを見つけることも少くはなかったが、あるとき、三本足と六本足の蛙を見つけて、これこそ後の世に伝えなければならぬと、筆をとってこくめいに写生したものが、今に残っているということだ。 2 長崎東福寺の住職東海和尚は、画の方でもかなり聞えた人で、よく河豚を描いて人にくれたりしていたが、ほんとうのところは、まだ一度もこの魚を見たことがなかった。 あるとき、和尚は海辺を通って、潮の引いたあとの水溜に、二、三びきの小魚を見つけたことがあった。 「何だろう、可愛らしい小ざかなだな。」 和尚は水溜の側にしゃがんで、暫く魚のそぶりに見とれていたが、ふとちょっかいが出してみたくなって、手を伸べて魚の尻っ尾を押えようとした。魚は怒って山寺の老和尚のように、腹を大きく膨らませたかと思うと、急に游ぎがむつかしくなって、水の上にひっくりかえって、癲癇持のように泡をふき出した。その恰好は自分がいつも画に描きなれている河豚にそっくりだった。 「河豚だ。河豚だ。こいつおもしろい奴だな。」 和尚は笑いながら、はち切れそうな魚の腹を指先でちょっと弾いてみたりした。 「和尚さま、何してござるだ。そんな毒魚(どくうお)いじくって……。」 だしぬけに肩の上から太い声がするので、和尚はうしろを振り返った。そこにはこのあたりのものらしい漁師の咎め立てするような苦い顔が見つかった。 「わしか。わしはちょっと仲のいい友達と遊ばしてもらっていたばかりじゃ。」 和尚はこういって、河豚と遊ぶのを少しもやめなかった。その態度には、好きな遊戯に夢中になっている小児の純一さがあった。P.257~259 古本と蔵書印(63) 本屋の息子(むすこ)に生れただけあって、文豪アナトオル・フランスは無類の愛書家だった。巴里(パリ)のセイヌ河のほとりに、古本屋が並んでいて、皺くちゃな婆さん達が編物をしながら店番をしているのは誰もが知っていることだが、アナトオル・フランスも少年の頃、この古本屋の店さきに立って、手あたり次第にそこらの本をいじくりまわして、いろんな知識を得たのみならず、老年になっても時々この店さきにその姿を見せることがあった。フランスはこの古本屋町を讃美して、「すべての知識の人、趣味の人にとって、そこは第二の故郷である。」と言い、また「私はこのセイヌ河のほとりで大きくなった。そこでは古本屋が景色の一部をなしている。」とも言っている。彼はこの古本屋から貪るように知識を吸収したが、そのお礼としてまたいろいろな趣味と知識とを提供するを忘れなかった。――というのは外のことではない。彼が自分の文庫に持てあました書物を、時折この古本屋に売り払ったことをいうのだ。 一度こんなことがあった。――あるときフランスは来客を書斎に案内して、自分の蔵書を一々その人に見せていた。愛書家として聞えている割合には、その蔵書がひどく貧しく、とりわけ新刊物がまるで見えないのに驚いた客は、すなおにその驚きを主人に打ちあけたものだ。すると、フランスは、 「私は新刊物は持っていません。方々から寄贈をうけたものも、今は一冊も手もとに残していません。みんな田舎にいる友人に送ってやったからです。」 と、言いわけがましく言ったそうだが、その田舎の友人というのが、実はセイヌ河のほとりにある古本屋をさしていったのだ。 そのフランスを真似るというわけではないが、私もよく読みふるしの本を古本屋に売る。家が狭いので、いくら好きだといっても、そうそう書物ばかりを棚に積み重ねておくわけにも往かないからである。 京都に住んでいた頃は、読みふるした本があると、いつも纏めて丸太町川端のKという古本屋に売り払ったものだ。あるとき希臘(ギリシャ)羅馬(ローマ)の古典の英訳物を五、六十冊ほど取揃えてこの本屋へ売ったことがあった。私はアイスヒュロスを読むにも、ソフォクレエスを読むにも、ピンダロスやテオクリトスを読むにも、ダンテを読むにも、また近代の大陸文学を読むにも、英訳の異本が幾種かあるものは、その全部とは往かないまでも、評判のあるものはなるべく沢山取寄せて、それを比較対照して読むことにしているが、一度読んでしまってからは、そのなかで自分が一番秀れていると思ったものを一種か二種か残しておいて、他はみな売り払うことにきめている。今Kという古本屋に譲ったのも、こうしたわけで私にはもうふ用になっていたものなのである。 それから二、三日すると、京都大学のD博士がふらりと遊びに来た。博士は聞えた外国文学通で、また愛書家でもあった。 「いま来がけに丸太町の古本屋で、こんなものを見つけて来ました。」 博士は座敷に通るなりこう言って、手に持った二冊の書物をそこに投り出した。一つは緑色で他の一つは藍色の布表紙だった。私はそれを手に取上げた瞬間にはっと思った。自分が手を切った女が、他の男と連れ立っているのを見た折に感じる、ちょうどそれに似た驚きだった。書物はまがう方もない、私がK書店に売り払ったなかのものに相違なかった。 「ピンダロスにテオクリトスですか。」 私は二、三日前まで自分の手もとにあったものを、今は他人の所有として見なければならない心のひけ目を感じながら、そっと書物の背を撫でまわしたり、ペエジをめくって馴染のある文句を読みかえしたりした。 「京都にもこんな本を読んでる人があるんですね。いずれは気まぐれでしょうが……」 博士は何よりも好きな煙草の脂(やに)で黒くなった歯をちらと見せながら、心もち厚い唇を上品にゆがめた。 「気まぐれでしょうか。気まぐれに読むにしては、物があまりに古すぎますね。」 私はうっかりこう言って、それと同時にこの書物の前の持主が私であったことを、すなおに打明ける機会を取りはずしてしまったことを感じた。 「それじゃ同志社あたりに来ていた宣教師の遺愛品(ビクエスト)かな。そうかも知れない。」 博士は藍表紙のテオクリトスを手にとると、署名の書き入れでも捜すらしく、前附の紙を一枚一枚めくっていたが、そんなものはどこにも見られなかった。 私は膝の上に取残されたピンダロスの緑色の表紙を撫でながら、前の持主を喘息か何かで亡くなった宣教師だと思い違いせられた、その運命を悲しまぬわけに往かなかった。 「宣教師だなんて、とんでもない。宣教師などにお前がわかってたまるものかい。――だが、こんなことになったのも、俺が蔵書印を持合さなかったからのことで。二度とまたこんな間違いの起らぬように、大急ぎで一つすばらしい蔵書印をこしらえなくちゃ……」 私はその後D博士を訪問する度に、その書斎の硝子戸越しに、幾度かこの二冊の書物を見た。その都度書物の背の金文字は藪睨みのような眼つきをして、 「おや、宣教師さん。いらっしゃい。」 と、当つけがましく挨拶するように思われた。 私はその瞬間、 「おう、すっかり忘れていた。今度こそは大急ぎで一つ蔵書印のすばらしく立派な奴を……」 と、いつでも考え及ぶには及ぶのだったが、その都度忘れてしまって、いまだに蔵書印というものを持たないでいる。P.260~264 ある日の基督(64) 1 西班牙(スペイン)の ALPUJARRAS 山には、人間の顔をした梟が棲んでいるそうです。それについて土地の人達のなかに、むかしからこんな事が言い伝えられています。 あるとき、キリストがヨハネとペテロとを連れて、この山の裾野を通りかかったことがありました。師匠も弟子もひどく腹がすいていました。折よく山羊の群を飼っている男に出会(でくわ)したので、ペテロがその男を呼びとめて、 「村の衆。私達は旅の者だが、ひどく腹が減って困っている。どうか私達のためにお前さんの山羊を一つ御馳走してはくれまいか。」 と頼んでみました。羊飼はひどく吝(しわ)い男でしたから、初のうちはなかなか承知しそうにもありませんでしたが、三人が口を揃えてうるさく強請(せが)むので、ぶつくさ呟きながらも引請けるには引請けました。 だが、羊飼は自分の山羊を使おうとはしないで、代りに猫を殺して、それでもって客を振舞いました。キリストは食卓につくなり、変な眼つきをしてその肉片を見ていましたが、暫くすると口のなかで、 皿のなかの油揚(フライ) 山羊ならよいが 小猫の肉(み)なら やっとこさで逃げ出しゃれ と、二、三度繰り返して言いました。すると、皿のなかの油揚が急に立ちあがり、窓越しに外へ飛び出して、そのまま姿を隠してしまいました。 「不埒な羊飼だ。こんな男はいっそ梟にでも生れ代るといいのに……」 キリストは腹立まぎれに独語のように呟(ぼや)きました。すると、その次の一刹那には、羊飼の姿がそこから消えてしまって、人間のような顔をした梟が一羽、の上にとまっていましたが、二、三度羽ばたきをしたかと思うと、ついと家の外へ飛び出してしまいました。 「ほう、羊飼が梟になりおった。気の毒なことをしたな。だが、あれよりも可憫(かあい)そうなのは私だよ。無駄口一つきく事が出来ないのだからな。」 キリストはそれを見て、心のなかでこんなことを思いました。そして神の子に生れて、摩訶不思議な力を持っているものの世間の狭さ、窮屈さを思って、微かな溜息をもらしました。 2 その後、キリストはまた多くの弟子達を連れて、ユダヤのある村を通りかかった事がありました。村端れには柳の並木の美しい野原が続いていました。 その日はぽかぽか暖か過ぎるほどの上天気だったので、キリストは上衣を脱いで、一本の柳の枝に掛けました。そして彼は村人の多くがこの救世主の説教を聴こうとして待合せている野の傾斜をさして歩き出しました。 説教のすばらしい出来に満足したキリストは、足どりも軽く柔い草を踏んで、柳の並木に帰って来ました。しかし、いくら捜しても、彼の上衣と、その上衣を掛けておいた柳の木はそこらに見つかりませんでした。 「てっきり柳の木があの上衣を持逃げしたのだ。あれはある信者の女が、自分の手で織ってよこしたもので、極上等の織物だったからな。だが、この時候に上衣なしに外を出歩かねばならないなんて……」 キリストはそう思うと、忌々しくて溜りませんでした。彼は眼を上げて柳の並木を見ました。柳の木はこの若い救世主をなぶるように、長い下枝をゆらゆらと揺り動かせました。 「ひとの物を持逃げするなんて。そんな木は一本残らず消えてなくなればいい。」 キリストはうっかり口を滑らしました。すると、その瞬間そこらの柳の並木は、急に葉も、枝も、萎れかえってすっかり立枯となってしまいました。 「おう、柳の木が枯れてしまった。――可憫そうなことをしたな。だが、ほんとうのことをいうと、あの木よりも私の方が可憫そうなんだ。うっかり口もきけないという仕末なのだからな。」 キリストは以前西班牙の山の中で羊飼を梟にした失敗(しくじり)を思い出して、自分がふ用意に洩した言葉がそのまま実現せられてゆくのに驚きました。自分がつぶやくように言った言葉を、すぐにその仕事の一つに取入れる神の慈愛に驚くよりも、その神を動かすあるものが自分の内に隠れているのに驚きました。そしてまたしても神の子に生れて、摩訶不思議な力を身に具えている自分の世間の狭さ、窮屈さを心から悲しんだという事です。P.265~269 老和尚とその弟子(65) な高い西宮海清寺の住職南天棒和尚の弟子に、東馬(とうま)甚斎という居士があった。満洲に放浪していた頃は、馬賊の群に交って、相応な働をしたと言われるほどあって、筋骨の逞しい、鬼のようにいかつい恰幅をした壮士で、日本に帰って来てからは、そこらの電車に乗るのにいつも切符というものを持たないで、車掌がそれを喧(やかま)しく言うと、 「俺は東馬だ。顔を見覚えておけ、顔を……」 と獣のようなぶ気味な顔を、相手の鼻先に突き出すので、車掌も運転手も度胆をぬかれて、ぶつくさ呟きながらも、大抵はそのまま見遁していたものだった。 あるとし、満洲から帰って海清寺に落ちついた甚斎は、僧堂に自分の気に添わない雲水が二、三人いることに気がついた。 「あんなのは、一日も早く追い出さなくちゃ。和尚の顔にもかかわることだ。」 甚斎は腹のなかでそう思ったらしかった。彼はその翌日から庫裡(くり)へ顔を出した。そして雲水たちの食事の世話を焼きだした。 ある朝、雲水たちは汁鍋の蓋を取ってびっくりした。鍋のなかには、無造作にひきちぎられた雑草の葉っぱの上に、殿様蛙の幾匹かが、味噌汁の熱気に焼け爛れた身体を、苦しそうにしゃちこ張らせたまま、折重って死んでいた。 「気味が悪いな。一体どうしてこんなものが……」 雲水の一人は咎めだてするように、そこに突立っている甚斎の顔を見た。 「俺の手料理さ。肉食の好きな君たちには、あまり珍らしくもあるまいが、まあ遠慮せんで食べてくれ。俺もここでお相伴(しょうばん)をするから。」 甚斎はこう言って、皆の汁椀にそれぞれ雑草の葉っぱと蛙とを盛り分けた。そして鍋に残った蛙の死骸の一つをつまみ上げて、蝦蟇(がま)仙人のように自分の掌面(てのひら)に載せたかと思うと、いきなり唇を尖(とが)らせてするするとそれを鵜呑にしてしまった。 皆は呆気にとられた。そしてぶ気味そうに自分たちの椀のなかを覗き込んでじっと眉を顰(ひそ)めていたが、眼の前にいっかい膝の上で石のような拳(こぶし)を撫でまわしている甚斎の姿を見ると、悲しそうにそっと溜息をついた。 皆は不承不精に椀を取り上げた。そして犬のように臭気(くさみ)を嗅ぎながら、雑草の葉っぱを前歯でちょっぴり噛ってみたり、蛙の後脚をそっと舌でさわってみたりした。 そんなことが度重るうちに、自分の身にうしろ暗いところのある雲水は、後々(あとあと)を気遣って、いつの間にか寺から姿を隠してしまった。甚斎は手を拍(う)って喜んだ。 そのことが南天棒の耳に入ると、甚斎は方丈に呼び出された。他人のなかでは荒馬のように粗暴な甚斎も、和尚の前へ出ては猫のようにおとなしかった。和尚はいった。 「東馬、お前は雲水たちをいびり出したそうじゃな。乱暴にも程があるじゃないか。」 「はい。別に追出したというわけではありませんが……」甚斎は雄鶏のように昂然と胸を反(そ)らせた。「彼等から出て往きました。雲水にもあるまじき所業の多かった輩(てあい)でしたから、あとに残ったものは、実際救われましたようなわけで……」 老和尚は相手の得意そうな顔をじろりと見返した。 「後に残ったものは救われたかも知れんが、出て往ったものは救われたじゃろうかな。」 ……甚斎は壁に衝き当ったようにどぎまぎした。 「救われないかも知れませんが、それにしたって、あんなふ行跡者は仕方がありません。」 「それはいかん。」和尚はこう言って、側の本箱から一冊の写本を取出した。そして紙に折目のついているところを繰り開けて、甚斎の鼻先に突きつけた。「ここのところを読んでみなさい。声をあげて。」 甚斎は和尚の手から本を受取った。そして紊所坊主(なっしょぼうず)がお経を読む折のように、声を張り上げてそれを読み出した。 「下谷高岸寺に、ある頃弟子僧二人あり。一人は律義廉直にして、専ら寺徳をなす。一人は戒行を保たで、大酒を好み、あまつさへ争論止まず、私多し。ある時什物を取出し売るを――ひどい奴があったものですな。まるで此寺(こちら)の雲水そっくりのようで……。」 「むだ口を利(き)かんと、後を読みなさい。」 和尚は媼さんのような口もとをしてたしなめた。甚斎はまた読み続けた。 「あるとき、什物を取出し売るを、一人の僧見て諫(いさめ)を加へけるに、聞入れざれば、この由住持に告げ、追退(おいの)け給はずば、ために悪しかりなんと言ふ。住持先づ諭し見るべしとて、厳しく戒めたるままにて捨て置きぬ。又あるとき仏具を取出し売りたるに、いよいよ禍ひに及び、わが身にもかからん間、彼のものに給はずんば、我に暇給はるべしと頻りに言ひける程に、住持涙を浮べ、さあらば、願ひのままにその方に暇をつかはすべし。悪僧は今暫し傍におきて諭すべしといふに――これは手ぬるい。ねえ、老師。少し手ぬるいじゃござんせんか。」 「どうでもいい、そんなことは。早く後を読み続けなさい。」 和尚はわざと突っ放すように言った。甚斎は亀の子のように首をすくめた。 「この僧大いに怨み、われ暇のこと申さば、悪僧を追出し給はんと思ふものから、それを却つて罪なきわれに暇給はること、近頃依怙(えこ)の心に非ずやといへば、住持答へて、さにあらず、御身は今この寺を出でたりとも、僧一人の勤めはなるものなり。悪僧は今わが傍(かたえ)を離るれば、忽ち捕はれて罪人とならんも計り難し。さすれば……」 甚斎は間(ま)が悪いように段々と声を落して、くどくどと口のなかで読み下した。 「もっと声を大きくして……」 和尚は注意をした。甚斎の声は灯(ひ)をかきたてたように、またぱっと明るくなった。 「わが徳も捨たれて、一人の弟子を失ふなり。故に傍(かたえ)に暫し置きて、彼が命をも延ばし、且は厳しく教戒をもせば、善心に立ち返ることもやありなんと思ふが故なり、と言へば、悪僧このことを聞き、師の厚恩に感じ、やがて本心に飜(か)へりしとぞ。」 読み終った甚斎が、幾らかふ足そうな顔つきで書物を膝の上に置くと、和尚はそれを受取って、大事に本箱に蔵い込みながら言った。 「どうじゃ、わかったか。修業の足りない雲水が、悪いことをしたからというて、寺を追い出すのは、それは罪を重ねさすようなものなんじゃ。」 「どうも相済みません。」 甚斎は不満と後悔とのごっちゃになったような表情をした。 「いや。俺にあやまってくれても、俺はどうするわけにもゆかんて。」和尚はさも当惑したもののように言った。「折角俺を頼って来た仏弟子を、修業半ばに追い返したんじゃ、仏様に対して俺が相済まんわけじゃ。でお前には気の毒じゃが、一まずここを引き取ってもらいたい。」 「それはあんまりなお言葉です。老師が御承知の通り、私には家というものがありません。」 甚斎はいかつい顔を歪めて、鼻を詰らせたような声を出した。 「いや、家がないことはない。お前には世間というものがある。しかし寺を追い出された雲水には、何も残っていないのじゃ。」 「これからはきっと慎みますから、今度ばかりはどうぞ……」 甚斎は蛙のように両手をついてあやまった。 「いや、ならぬ。」 和尚はきっぱりと言い切った。甚斎は恨めしそうな顔をして、すごすごと庫裡の方へ引取って往った。 暫くすると、甚斎はいつもに似ずつつましやかに方丈に入って来た。その顔は蒼味を帯びていた。和尚は机にもたれて、何か読みものをしていた。 「老師。心からお詫のしるしを、ここにお預けいたしますから、今度のことばかりは、どうぞ大目にお見遁しを……」 こう言って、彼は手に持った小さな紙包を机の端においた。和尚は黙々としてその包を開けてみた。なかには真赤な血にまみれた、なまなましい小指が一つ転っていた。和尚はじろりと尻目に甚斎の左手を見た。小指の附根には、無造作に繃帯がしてあった。和尚はまた黙々としてそれをもとのように包みなおした。 和尚の眼は何物にも妨げられなかったように、またしずかに読み本の上に注がれた。甚斎はもどかしさに堪らぬように、 「老師。これでお免(ゆるし)が願われましょうか。」 和尚はきっと相手の顔を見た。その言葉の調子は低かったが、石のような重みと、石のような冷さとをもって、甚斎のひしがれた心の上に落ちかかった。 「お前に用のないものが、俺に入用なとでも思っとるのか。うつけもの奴(め)が。」 師家のお役に立たなかった小指は、またもとの持主に帰らねばならなかった。甚斎とその小指とは一緒に、海清寺のかかりつけの医者のもとへ送られた。そして小指は器用にもとの附根に縫いつけられた。 「どうだ、痛くはなかったか。」 手術が済んだ後、甚斎に訊いたものがあった。すると、この乱暴者はにやりと笑ったのみで、何とも答えなかった。P.270~277 参考:中原南天棒( なかはら なんてんぼう) 臨済宗の僧。長崎県生。諱は全忠、字は鄧、別号に白崖窟。11才で得度、隠山惟?・卓洲胡僊両派下の24人の老師に師事する。禅風の高揚に努め、乃木希典、児玉源太郎らも参禅した。晩年は西宮海清寺に住す。自ら山中で切り出した南天の一棒を携え人に接したことから、南天棒と呼ばれた。近世稀にみる豪僧として知られる。大正14年(1925)寂、87才。 名器を毀つ(66) 1 勧修寺大紊言経広は心ざまが真直で、誰に遠慮もなく物の言える人だった。 時の禁裏後西院天皇は茶の湯がお好きで、茶人に共通の道具癖から井戸という茶碗の名器を手に入れて、この上もなく珍重させられていた。 あるとき経広が御前にまかり出ると、主上はとりわけ上機嫌で、御自分で秘蔵の井戸を取り出されてお茶を賜ったりなどした。経広は主上の御口からその茶碗がな高い井戸だということを承ると、驚きと喜びとに思わず声をはずませた。 「井戸と申しますと、名前のみはかねて聞き及びましたが、眼にいたすのはまったく初めてのことで、ついては御許を蒙って、篤と拝見いたしたいと存じますが……」 主上からお許しが出ると、経広はいそいそと立ち上って南向きの勾欄に近づいて往った。ちょうど秋の曇り日の午過ぎだったので、御殿の中は経広の老眼にはあまりに薄暗かった。彼は明りを求めて勾欄の上にのしかかるようにして茶碗を眺めた。いかにも感に堪えたように幾度か掌面(てのひら)にひねくり廻しているうちに、どうしたはずみにか、つい御器(おうつわ)を取り落とすような粗忽をしでかした。茶碗は切石の上に落ちて、粉々に砕けてしまった。 主上はさっと顔色を変えられたらしかった。座に帰って来た経広には、悪びれた気色も見えなかった。 「過失とは申しながら、御秘蔵の名器を毀ちました罪は重々恐れ入ります。しかし、よくよく考えまするに、名器とは言い条、これまで数多の人の手にかかりたるやも知れざる品、むかし宋の徽宗皇帝は秘蔵の名硯を米元章に御貸与えになり、一度臣下の手に触れたものは、また用い難いとあって、そのまま元章にお下げになりましたとやら。さような嫌いのある品を御側近うお置きになりますのはいかがかと存ぜられます。してみれば、唯今の粗忽もかえって怪我の功みょうかと存じまして……」 この一言を聞かれると、主上の御機嫌は直ったが、しかし何となく寂しそうだった。 心ざまの真直な経広は、茶器の愛に溺れきっていられる主上を諫めようとして、向う見ずにもその前にまず肝腎の茶器を壊してしまったのだ。 2 伊達政宗があるとき家に伝えた名物茶碗を取出していたことがあった。 太閤秀吉が自分の好みから、また政略上の方便から煽り立てた茶の湯の流行は、激情と反抗心との持主である奥州の荒くれ男をも捉えて、利休の門に弟子入をさせ、時おりは為(しよ)う事なさの退屈しのぎから、茶器弄りをさえさせるようになったのだった。 茶碗は天目だった。紺青色の釉(くすり)のなかに宝玉のような九曜星の美しい花紋が茶碗の肌一面に光っていた。政宗は持前の片眼に磨りつけるようにして、この窯変の不思議を貪り眺めていたが、ついうっとりとなったまま、危く茶碗を掌面(てのひら)より取り落そうとした。 政宗ははっとなって覚えず胆を潰した。 「金二千両もしたものじゃ。壊してなるものか。」 こんな考えが電光のように頭のなかを走った。仕合せと茶碗は膝の上で巧く両手の掌面(てのひら)に抱きとめられていた。政宗は冷汗をかいた。胸には高く動悸が鳴っている…… 「おれは娘っ子のようにおっ魂消たな。――恥しいことじゃ。」 政宗はその次の瞬間そう思って悔しさに身悶えした。突嗟の場合器の値段を思い浮べて、胸をどきつかせたのが何としても堪えられなく厭だった。 いつだったか、政宗は徳川家康に茶の饗応(ふるまい)を受けたことがあった。そのおり家康は湯を汲み出そうとして何心なく釜の蓋へ手をやった。蓋は火のように熱していた。あまりの熱さに家康は小児のように、 「おう、熱う……」 と叫んで、釜の蓋を取り離したかと思うと、慌ててその手を自分の耳朶へやった。その様子がいかにも可笑しかったので、政宗は覚えず 「うふ……」 と吹き出してしまった。 家康はそれを聞くと、また気をとり直して、前よりは熱していたらしい釜の蓋を平気で撮み上げた。そして何事もなかったように静かに茶を立てにかかった。 政宗はいつに変らぬ亭主のねばり強さに感心させられたが、それでも腹のなかではもしか俺だったら、初めに手にとり上げたが最後、どんなに熱くたって釜の蓋を取り落すような事はしまいと思った。 政宗は今それを思い出した。あんなに心上りしたことを考えていたものが、今の有様はどうだったかと思うと、顔から火が出るような気持がした。誰だったか知らないが自分の耳近くにやって来て、 「うふ……」 と冷かすように吹き出したらしい気配(けはい)を政宗は感じた。 逆上(のぼ)せ易いこの茶人はかっとなってしまった。彼は鷲掴みに茶碗を片手にひっ掴んだかと思うと、いきなりそれを庭石目がけて叩きつけた。茶碗はけたたましい音を立てて、粉微塵に砕け散った。 「は、は、は、は……」 政宗は声高く笑った。彼はその瞬間、金二千両の天目茶碗を失った代りに、自分の心の落着きをしかと取り返すことが出来たように思って、昂然と胸を反らした。 3 泉州小泉の城主片桐貞昌は、茶道石州流の開祖として、船越吉勝、多賀左近と合せて、その頃の三宗匠と称えられた名誉の茶人であった。 貞昌があるとき、海道筋に旅をして宿屋に泊ったことがあった。ちょうど冬のことだったので、宿屋の主人(あるじ)は夜長の心遣いから、溺器(しびん)を室の片隅に持運んで来た。それは一風変った形をした陶器だったが、物の鑑定(めきき)にたけた貞昌の眼は、それを見遁さなかった。彼は主人に言いつけて、器を綺麗に洗い濯がせた後、あらためて手にとって見直すことにした。 洗い清められた溺器(しびん)の肌には、古い陶物(やきもの)の厚ぼったいぶ器用な味がよく出ていた。愛撫に充ちた貞昌の眼は労わるようにその上を滑った。 「亭主。この器が譲り受けたい。価は何程にしてくれるの。」 暫くしてから、貞昌は主人の方に振り向きざま言葉をかけた。 「お気に召しましたらお持ち帰りを願いますが、旅籠屋が溺器をお譲りして代物(だいもつ)をいただきましたとあっては……」 主人は小泉一万石の城主ともあるものが、ものもあろうに旅籠屋の溺器を買い取ろうとするなぞ、風流にしてはあまりに戯談に過ぎ、戯談にしてはあまりに風流に過ぎるとでも思っているらしかった。 「他人から物を譲り受けて、代物を払わぬという法はない。」 貞昌は半は自分の供のものたちへ言いきかせるようにいって、何程かの金を主人の手に渡させた。 貞昌は静かに立って夜の障子を開けた。薄暗い内庭に踏石がほんのり白く浮んで見えた。彼は手に持った溺器を強くそれに叩きつけた。居合せた人たちはびっくりした顔を上げた。 何事もなかったような気振(けぶり)で貞昌は座に帰った。そして静かな声でいった。 「わしの見たところに間違がなければ、あれは立派な古渡(こわたり)じゃ。今は埋れて溺器に用いられているが、もしか眼の利く商人(あきんど)に見つかって掘り出されでもしようものなら、どんなところへ名器として紊まらぬものでもない代物(しろもの)じゃ。そんなことがあってはならぬと思うから、可惜(あたら)ものをつい割ってしもうた。」 4 三人は三様の心持と方法とで、世の中から三つの陶器を失った。失われたのは、いずれも秀れた名器だったが、彼等はそれを失うことによりて、一層尊いあるものを救うことが出来たのだ。P.278~284 利休と丿観(67) 山科の丿観(へちかん)は、利休と同じ頃の茶人だった。丿観は利休の茶に幾らか諂(へつら)い気味があるのを非難して、 「あの男は若い頃は、心持の秀れた人だったが、この頃の容子を見ると、真実が少くなって、まるで別人のようだ。あれを見ると、人間というものは、二十年目ぐらいには心までが変って往くものと見える。自分も四十の坂を越えて、やっと解脱の念が起きた。鴨長明は蝸牛のように、方丈の家を洛中に引っ張りまわし、自分は蟹のように他人の掘った穴を借りている。こうして現世を夢幻と観ずるのは、すべて心ある人のすることだが、利休は人の盛なことのみを知って、それがいつかは衰えるものだということを知らないようだ。」 と言い言いしていたが、利休は別に自分のすばらしい天地をもっており、それに性格から言っても、丿観よりは大きいところがあったから、そんな非難をもあまり頓着しなかったようだ。 あるとき、丿観が茶会を開いて、利休を招いたことがあった。案内にはわざと時刻を間違えておいた。 その時刻になって、利休は丿観の草庵を訪れた。ところが、折角客を招こうというのに、門の扉はぴったりと閉っていた。 「はてな。」 利休は門の外で早くも主人の趣向にぶっつかったように思った。丿観はそのころの茶人仲間でも、一番趣向の気取っているので知られた男だった。利休はその前の年の秋、太閤が北野に大茶の湯を催したときのことを思い出した。その日利休は太閤のお供をして、方々の大みょうたちの茶席を訪れた。そして由緒のある高貴な道具の数々と、そんなものを巧く取合せていた茶席の主人の心遣とを味って、眼も心も幾らか疲労を覚えた頃、ふと見ると、緑青を砕いたような松原の樹蔭に、朱塗の大傘を立てて、その下を小ぢんまりと蘆垣で囲っているのがあった。主人は五十ばかりの法体で、松の小枝に瓢をつるし、その下で静かに茶を煮ていた。 ものずきな太閤が、ずかずかと傘の下に入って往って、 「どうだ。ここにも茶があるのかい。」 と大声に訊かれると、主人はつつましやかに、 「はい。用意いたしております。」 と言いざま、天目茶碗に白湯をくみ、瓢から香煎(こうせん)をふり出して、この珍客にたてまつった。その法体の主人こそ、別でもない山科の丿観で、その日の高く取り澄した心憎さは、いまだに利休の心に軽い衝動を与えずにはおかなかった。 利休は潜り戸を開けて、なかに入った。見ると、すぐ脚もとに新しく掘ったばかしの坑があり、簀子をその上に横たえて、ちょっと見に分らぬように土が被せかけてあった。 「これだな、主人の趣向は。」 客はその瞬間、すぐに主人の悪戯(いたずら)を見てとった。平素から客としての第一の心得は、主人の志を無駄にしないことだと、人に教えもし、自分にも信じている彼は、何の躊躇もなく脚をその上に運んだ。すると、簀の子はめりめりとへし折れる音がして、客はころころと坑のなかに転げ込んだ。 異様なもの音を聞いた主人の丿観は、わざと慌てふためいて外へ飛び出して来た。坑のなかには利休が馬鈴薯のように土だらけになって、尻餅をついていた。 「これは、これは。宗匠でいらっしゃいましたか。とんだ粗相をいたして、まことに相済みません。」 「丿観どの。老人(としより)はとかく脚もとが危うてな……」 客としての心得は、主人の志を無駄にしないことだと思っていた利休も、案外その志と坑とが両つともあまりに深く、落込んだままどうすることも出来ないで、困りきっていた場合なので、丿観が上から出した手に縋って、やっとこなと起き上って坑の外へ這い出して来た。二人は顔を見合せて、からからと声をあげて笑った。 客は早速湯殿に案内せられた。湯槽には新しい湯が溢れるばかりに沸いていた。茶の湯の大宗匠はそのなかに浸り、のんびりした気持になって頭のてっぺんや、頸窩(ぼんのくぼ)にへばりついた土を洗い落した。 浴みが済むと、新しい卸し立ての衣裳が客を待っていた。利休は勧めらるるがままにそれを着けて、茶席に入った。 「すっかり生れかわったような気持だて。」 利休は全くいい気持だった。こんな気持を味うことが出来るのも、自分が落し坑だと知って、わざとそれに陥(はま)り込んだからだと思った。これから後も落し坑には精々落ちた方がいいと思って、にやりとした。 丿観は、客が上機嫌らしいのを見て、すっかり自分の計画が当ったのだと考えて、いい心持になっていた。それを見るにつけて利休は、主人の折角の志を無駄にしなかったことを信じて、一層満足に思ったP.286~290。 参考:丿貫(へちかん、べちかん、生没年不詳)は、戦国時代後期から安土桃山時代にかけての伝説的な茶人。なの表記は、丿恒、丿観、別貫などとも。なお「丿(ヘツ、ヘチ)」は、カタカナの「ノ」ではなく、漢字である。 京都上京の商家坂本屋の出身とも、美濃の出とも言われる。一説に拠れば医師曲直瀬道三の姪婿だといい、武野紹鴎の門で茶を修めたという。山科の地に庵を構えて寓居し、数々の奇行をもって知られた。久須見疎安の『茶話指月集』(1640年)によれば、天正15年(1587年)に豊臣秀吉が主催して行われた北野大茶湯の野点において、丿貫は直径一間半(約2.7メートル)の大きな朱塗りの大傘を立てて茶席を設け、人目を引いた。秀吉も大いに驚き喜び、以後丿貫は諸役免除の特権を賜ったという。
探幽と松平伊豆(68)
探幽は名画家の多い狩野家でも、とりわけ画才が秀れているので聞えていた人でした。 この探幽があるとき松平伊豆守信綱に招かれて、その屋敷に遊んだことがありました。主人の信綱はその日の記念として、雲龍の図を探幽に求めました。 雲龍の図だというので、墨汁は家来たちの手でたっぷりと用意せられました。探幽は画絹を前に、しばらくは構図の工夫に思い耽っていましたが、やがて考えが決ったと見えて、筆をとり上げようとしますと、そこへ次の間から信綱が興奮したらしい顔を現わしました。そしてまだ何一つ描き下してない画絹を見ると、 「何じゃ、まだ一つも画いてないのか。さてさて絵師というものは鈊なものじゃて。」 わざと聞えよがしに言ったかと思うと、いきなり足の爪先でそこにあった硯を蹴飛ばして、そのまま次の間に姿を隠しました。墨汁は画絹は言うに及ばず、探幽の膝から胸のあたりまで飛び散りました。まるで気の狂った泥鼠が乱暴を働いた後のようでした。探幽はむっとしました。 「あまりといえば乱暴ななされ方だ。」 真青に顔の色を変えて、そのまま立ち上って帰ろうとしました。それを見た松平家の家来たちは、てんでに言葉をつくして平謝りに謝りました。このまま探幽を帰しては、居合す家来たちの大きな手落となると聞いては、探幽もむげに我を通すわけには往きませんでした。彼はしぶしぶ座に帰って、また画絹の前に坐りました。 伊豆守の無礼だけは、どうしても免すわけに往かぬと探幽は思いました。膝から胸のあたりに飛び散った生々しい墨汁の痕を見ると、彼は身内が燃えるように覚えました。このいらいらしい気持から遁れるには、湧き返る憤怒をそのまま、画絹へ投つけるより外にはありませんでした。探幽は顫える手に絵筆を取り上げて、画絹と掴み合うような意気込で、雲龍の図にとりかかりました。 程なく画は描き上げられました。それはすばらしい出来でした。探幽はそれを見て、憤怒のまだ消え切らない口もとをへし曲げるようにして、ちらと微笑しました。先刻から探幽の恐しい筆使いを見て、どうなることかと気遣っていたらしい松平家の家来たちは、お互いに顔を見合せて、腹の底より感心したらしい溜息を洩しました。 そこへ主人の信綱が、以前と打って変って慇懃なものごしで、にこにこしながら出て来ました。 「先刻はいかい失礼をいたした。気持に感激がないと、いい絵は出来難いものじゃと聞いたので、ついその……」 探幽は初めて信綱が自分に無礼を働いたわけに気がつきました。それと同時に、知慧自慢の伊豆守がこの画の前に立って、誰彼の容赦なく、作者を怒らせて描かせた吾が趣向を語って聞かせるだろう、その得意らしい顔つきが、気になってなりませんでした。で、負けぬ気になって次のように言いました。 「素人衆は一途に感激のことを申されますが、画家にとって大切なのは感激よりも、その感激に手綱をつけて、引き締めて往く力でございます。この絵もそれを引き締めるのに大分骨が折れましたが、まあ、どうかこうか……」P.291~293
人間というもの(69)
1 むかし、支那に馮幼将という、竹の画がすぐれて上手な画家がありました。この画家がある人に頼まれて、その家の壁に得意の筆で五、六本の竹を描いたことがありました。 画が出来上ったので、作者が墨に塗れた筆をもったまま壁の前に立って、満足そうにその出来ばえを眺めていますと、だしぬけに騒々しい羽音がして、三羽五羽ばかしの雀が、その肩越しにさっと飛んで来ました。そして先を争って若竹の枝にとまろうとして、幾度か画面にぶっつかっては落ち、ぶっつかっては落ち、終いには床に落ちたまま羽ばたきもせず、不思議そうに円(まる)い頭を傾(かし)げて、じっと考え込んでいました。 また童二如という画家がありました。梅が好きで、梅を描くことにかけては、その頃の画家に誰ひとりこの人に肩を並べるものがありませんでした。 あるとき、童二如が自分の書斎の壁に梅を描きました。すると、それが冬の寒いもなかだったにもかかわらず、五、六ぴきの蜜蜂が寒そうに羽をならして飛んで来ました。そして描かれた花の上にとまって、不思議そうにそこらを嗅ぎまわっていましたが、甘い匂いといっては、ただの一しずくも吸い取ることが出来ないのを知ると、 「何だ。画にかいた花だったのか。ひとを調弄(からか)うのも大概にするがいいや。」 とぶつぶつ呟きながら、ひどく腹を立てて飛び去りました。 2 ある日のこと、画家にあざむかれた雀の小坊主と蜜蜂とは、人間に立ち聴きせられないように、わざと木深い森の中に隠れて、何がな復讐(しかえし)の手段はないものかと、ひそひそ評議をこらしていました。 「人間って奴、何だってあんなにまやかし物が作りたいんだろうな。みんな神様の真似ごとじゃないか。」 癇癪持の蜜蜂は、羽をならしながら憎々(にくにく)しそうに言いました。曩(さき)の日のことを思うと、今になってもまだ腹に据えかねるのでした。 「そうだよ。みんな神様の真似ごとさ。唯仕事がすこしばかりまずいだけなんだ。」 第一の雀が片脚をあげて、毛深いぼんのくぼの附近(あたり)を掻きながら、こんなことを言いました。 「巧くもないくせに、何だってそんなことに手出しなぞするんだろうな。」 「小(ち)っちゃな神様になりたいからなんだよ。」第三の雀が貝殻のような嘴をすぼめて、皮肉な口をききました。「現におれ達をかついだあの二人の画かきだね。あいつらはおれ達の眼をうまくくらまかしたというので、たいした評判を取り、おかげであの画は途方もない値段である富豪(かねもち)の手に買い取られたそうだ。何が幸福(しあわせ)になるんだか、人間の世の中はわからないことだらけだよ。」 「そうだとも。そうだとも。」 残りの雀は声を揃えて調子を合せました。 「ほんとうに忌々(いまいま)しいたらありゃしない。ひとの失敗(しくじり)を自分の幸福(しあわせ)にするなんて。今度出逢ったが最後、この剣でもって思いきりみなの復讐(しかえし)をしてやらなくっちゃ。」 蜜蜂は黄ろい毛だらけの尻に隠していた短剣をそっと引っこ抜いて、得意そうに皆に見せびらかしました。剣は持主が手入れを怠けたせいか、古い留針(とめばり)のように尖端(さき)が少し錆びかかっていました。 「お前。まだ分ってないんだな。画を描くことの出来る手は、また生物(いきもの)を殺すことも出来る手だってことがさ。」第一の雀は蜜蜂の態度に軽い反感をもったらしく、わざと自分のぶ作法を見せつけるように、枝の上から白い糞(ふん)を飛ばしました。「お前、その剣でもって人間の首筋を刺すことが出来るかも知れんが、その代り、とても生きては帰れないんだぞ。」 「じゃ、どうすればいいんだ。復讐(しかえし)もしないで黙って待っていろというのか。」 蜜蜂は腹立たしくて溜らないように叫びました。頭の触角と羽とが小刻みにぶるぶると顫えました。 「復讐(しかえし)は簡単だよ。これから人間の画かきどもが何を描こうとも、おれ達はわざと気づかないふりをして外(そ)っ方(ぽう)を向いているんだ。そうすれば、おれ達がいくらそそっかしいにしたって、以前のように騙かされようがないじゃないか。騙かされさえしなかったら、どんな高慢な画かきにしても、手前味噌の盛りようがないんだからな。」 「」大きにそうかも知れんて。じゃ、そうと決めようじゃないか。」 「よかろう。忘れても人間に洩らすんじゃないよ。」 「これでやっと復讐(しかえし)が出来ようというもんだ。」 皆は吾を忘れて悦び合っていました。すると、だしぬけに程近い草のなかから、 「へっ、復讐かい。それが。おめでたく出来てるな。」 と冷笑する声が聞えました。 皆はびっくりして声のした方へ眼をやりました。日あたりのいい草の上で、今まで昼寝をしていたらしい一匹の黒猫が、起き上りざま背を円めて、大きな欠伸(あくび)をするのが眼につきました。 「いよう、黒外套(くろがいとう)の哲学者先生。お久しぶりですな。」剽軽者(ひょうきんもの)の一羽の雀は心安立(こころやすだて)と御機嫌とりとからこんな風に呼びかけました。「先生は唯今私達の仲間がみんなおめでたく出来てるようにおっしゃいましたね。」 「いったよ。確かにいった。実際そうなんだから仕方がない。」 黒猫の眼は金色に輝きました。 「何がおめでたいんだか、そのわけを聞かしてもらおうじゃないか」 雀の二、三羽が、不平そうにそっと嘴を突らしました。 「望みならいって聞かそう。」黒猫は哲学者の冷静を強いて失うまいとするように、長い口髭を一本一本指でしごきながらいいました。「お前達は人間の描いたものには、もう一切目を藉(か)さない。そうすれば欺かれる心配がなくなるから、自然画の評判も立たなくなるわけだと思ってるらしいが、それがおめでたくて何だろう。画の評判ってものは、お前達が立てるのじゃなくて、ほんとうは世間のするしわざじゃないか。」 「世間。おれはまだ世間ってものを見たことがない。」 第一の雀は不思議そうな顔をして、第二の雀をふりかえりました。 「世間ってのは、人間の仲間をひっくるめていう名前なんだよ。」黒外套の哲学者は、今更そんな講釈をするのは退屈至極だといわないばかりに大きなあくびをしました。 「人間を活(い)かすも殺すも、この世間の思わく一つによることなんだが、もともと人間って奴が妙な生れつきでね。多勢集まると、一人でいる時よりも品が落ちて、とかく愚(ばか)になりやすいんだ。だからお前達のようなもののしたことをも大袈裟に吹聴して、うっかり評判を立てるようなことにもなるんさ。」 「じゃ、その世間とやらを引き入れて、そいつに背(せな)を向けさせたらどうなんだ。」癇癪持の蜜蜂は、やけになって喚(わめ)きました。 「どんな高慢ちきの画かきだって、ちっとは困るだろうて。」 「それが出来たら困るかも知れん。また困らぬかも知れん。なぜといって、人間の腹の中にはそれぞれ虫が潜(もぐ)っていて、こいつの頭(かぶり)のふりよう一つで、平気で世間を相手に気儘気随をおっ通したがる病(やまい)があるんだから。そうだ。まあ、病(やまい)だろうね。尤もそんな折には誰でもが極って持ち出したがる文句があるんだよ。 ――今はわからないんだ。やがてわかる時が来るだろう。 といってね。文句というものは、またたびと同じようになかなか調法なものさ。」 黒猫は口もとににやりと微笑を浮べたかと思うと、そのまま起き上って、足音も立てず草の中に姿を隠してしまいました。 「腹の中に虫が……。変だなあ。人間って奴、どこまで分らないずくめなんだろう。」 知慧自慢の第二の雀が焦茶色の円い頭を傾(かし)げて、さもさも当惑したように考え込むと、残りの雀も同じように腑に落ちなさそうな顔をして、きょろきょろしていました。 短気ものの蜜蜂は、悔(くや)しまぎれに直接行動でも思い込んだらしく、誰にも言葉を交わさないで、いきなり小さな羽を拡げて、森から外へ飛び出しました。P.294~300
肖像画(70)
むかし、天保の頃に、二代目一陽斎豊国というな高い浮世絵師がありました。 あるとき、豊国は蔵前の札差(ふださし)として聞えた某(なにがし)の老人から、その姿絵を頼まれました。どこの老人もがそうであるように、この札差も性急(せっかち)でしたから、絵の出来るのを待ちかねて、幾度か催促しました。ところが、多くの絵師のそれと同じように、豊国はそんな註文なぞ忘れたかのように、ながく打捨ておきました。 やっと三年目になって、姿絵は出来上りました。使に立った札差の小僧は、豊国の手から、主人の姿絵を受取って、それに眼を落しました。 「これはよくにていますな。うちの御隠居さんそっくりですよ。」 と思わず叫びながら、つくづく見とれていましたが、暫くするとその眼からはらはらと涙がこぼれかかろうとしました。すぐ前で煙草をふかしていた豊国は、それを見遁しませんでした。 「おい、おい。小僧さん。何だって涙なぞこぼすのだ。御隠居のお小言でも思い出したのかい。それならそれでいいが、絵面を濡らすことだけは堪忍してくんな。」 「いいえ、違います。」小僧は慌てて手の甲で、涙を受取りました。 「私にも国もとにこの御隠居様と同じ年恰好のお祖父様(じいさま)があります。小さい時から大層私を可愛がってくれましたので、江戸へ奉公に出て来ても、一日だって忘れたことはありません。今これを見るにつけて、私のお祖父様をもこんな風に描いていただきましたら、どんなにか嬉しかろうと存じまして」 「ふうん。そんな訳だったのか。お前、祖父さん思いだな。」豊国は口にくわえていた煙管を、ぽんと畳の上へ投げ出しました。「その孝心にめでて、お前の祖父さんを描いてやりたくは思うが、でも、遠い国許に居るのじゃ、そうもいかないし、ここで一つお前の姿絵を描いてやるから、それを国許へ送ってやったらどんなものだい。そんなに可愛がってくれた祖父さんだ。今も何かにつけて、お前を思い出しているだろうからな。」 「ありがとう存じます。」 小僧は感に余って、丁寧に頭を下げました。 「それじゃ、すぐ始めよう。まあ、こっちへ上んな。そして涙でも拭きねえ。」 豊国はすっかり上機嫌で、絵筆を取上げました。小僧は気恥かしそうにその前に坐って、きちんと膝の上に両手を揃えました。 絵は程なく出来上りました。豊国はそれに彩色まで施してやりました。 「さあ、これを送ってやりねえ。吾ながらよく出来たよ。」 「ありがとう存じます。お祖父様がどんなにか喜ぶことでしょう。」 小僧はこれがほんとうに自分の姿なのかと、不思議そうに絵に見入りました。そして遠い国にいる老人が、これを見るときの驚きと喜びとを胸に描いてみました。 自分の姿絵を小僧の手から受取った札差の老人は、 「よく出来た。そっくり俺に生写しだよ。これだったら三年かかったのに、少しも無理はないはずだ。」 と言って、大喜びに喜びました。しかし、小僧が半ば得意そうに、半ば言訳がましく、先刻のいきさつを話しながら、ふところから取出した今一枚の姿絵を見ると、また気むつかしくなりました。そしてやくざなものを扱うようにそれをそこに投げ出しました。 「何だ。つまらない。お前にちっとも似てやしないじゃないか。」P.301~303
道風の見た雨蛙(71)
細かい秋の雨がびしょびしょと降りしきる朝でした。久しぶりの雨なので、雨蛙はもう家にじっとしていられなくなって、上機嫌で散歩に出ました。濡れそぼった無花果の広い葉からは、甘そうな雫がしたたり落ちていました。雨蛙は竹垣の端からその葉の上へひょいと飛び移るなり、自慢の咽喉で、 「け、け、け……」 と一声鳴いてみました。すると、だしぬけにどこからか、 「先生。上機嫌ですな。」 と、声がかかりました。雨蛙はその声の主が誰であるかをすぐに感づきました。こんな雨の日に外を出歩こうというものは、自分を取り除けては、蟹と蝸牛(かたつむり)の外には誰もいないのに、蟹はあの通りの気むつかしやで、滅多に他人と口をきこうともしませんでしたから。 雨蛙はこっそり無花果の葉の裏をのぞき込みました。そこには柄のついた雨除け眼鏡をはめた蝸牛がいました。この友達は今日もいつものように大がかりに自分の家を背にしょっていました。 「や。お早う。やっぱりお前だったな。」 蝸牛は老人のように眼鏡越しに相手を見ました。 「お早う。上機嫌ですな、先生。」 「先生だって。おいおい、何だってそんなにあらたまるんだい。今朝に限って。」 雨蛙はからかわれでもしたようにいやな顔をしました。 「気に触ったらごめんなさい。じゃ、やっぱりこれまで通り、お前と呼ばしてもらおうか。」 蝸牛の態度には、どこかにあらたまったところがありました。きさくな雨蛙は、それが気に入らないように頬をふくらませていました。 「お前で結構さ。もともとおれたちは長い間の朋輩つきあいで、お天気嫌いな癖も、お互いにもってる仲じゃないか。」 「そう言ってくれるとうれしい。実はさっきお前も知っているあの従弟のなめくじから、お前の噂を聞いて、すっかり感心したもんだから、つい、その……」蝸牛はてれかくしに眼鏡をはずして、雨の雫を拭きとりました。「ところで、だしぬけに変なことを訊くようだが、お前、人間に近づきがあるそうだな。」 「人間にか。人間には幾人(いくたり)か近づきがあるよ。」雨蛙は相手の気色を見てとって、すっかり機嫌をなおしたようでした。「おれが歌の稽古をつけてもらったのも、やっぱり人間だったよ。」 「ほう、歌の稽古を……」 雨蛙は以前山に棲んでいた頃、程近い人家にまぎれ込んで、竹製の刀架(かたなかけ)の孔のなかにもぐり込んでいたことがありました。ちょうど春雨の頃で、雨の音を聞きながら、口から出まかせの節で歌を唱っていると、急に座敷の方から美しい笛の音が流れて来ました。それにつれて歌を合わせていると、自分の咽喉がびっくりするほど滑らかに調子に合って来たことを、雨蛙は気づきました。そんなことを四、五日繰りかえしているうちに、雨蛙はだんだん芸が上達して、その刀架の孔から、広い世間へ這い出して来た折には、もういっぱしの歌唱いになっていました。 雨蛙は今その話を蝸牛にして聞かせました。雨除け眼鏡をはめた友達は、すっかり感心しました。 「そしてその家の主人の名前は……「 「柳田将監という笛の名人だったよ。日光山に住んでいる……」雨蛙は自分の師匠のなを自慢そうに言って聞かせました。 「それじゃない。もっと外にもあるだろう。」 「あるとも。俳句の上手な一茶という男も知ってるよ。」 「その男はどこで知ったのだ。」 蝸牛は持ち重りのする背(せな)の家を揺ぶってみました。家のまわりから雨の雫が落ちかかりました。 「信濃路(しなのじ)の小さな田舎でだったよ。おれはその頃将監さんに仕込まれた咽喉でもって旅芸人を稼いでいたのだ。柏原という村へ来て、くたびれ休めにそこにあった小屋の縁側に腰をかけたものだ。気がつくと、暗い家のなかに貧乏くさい男が、じっとわしを見つめているじゃないか。気味が悪かったものだから、おれも苦りきっていてやったよ。すると、その男がうめくように一句詠(よ)むじゃないか。 われを見て苦い顔する蛙かな といってね。」 「へえ、変に気のひがんだ奴だな。」 「そうだよ。実際気のひがんだ奴らしかった>雨蛙はまた話をつづけました。お金を貸せとでも言われたら困ると思って、おれはそこそこに逃げ出しちゃった。すると貧乏爺(びんぼうおやじ)め、追っかけるようにまた一句投げつけるじゃないか。 薄縁(うすべり)に尿(いばり)して逃る蛙かな といってね。相手怖さからおれが縁側にうっかり持病の小便をもらしたのを見つかったんだね。」 雨蛙は申訳がなさそうに滑(すべ)っこい頭をかきました。 「は、は、は、は。こいつは笑わせるよ。は、は、は。」蝸牛はたまらぬように笑いこけました。その拍子に雨除け眼鏡があぶなくはずれかかろうとしたのをやっともとへ直しながら、「一茶という奴、おかしな野郎だな。だが、もっと外にもあるはずだが……たしか小野道風とかいった……」 「小野道風……」雨蛙は忘れた名前をふるい出すように、二、三度頭を横にふりました。 「そんな人は知らないよ。ねっから記憶(おぼえ)がないようだ。」 「記憶(おぼえ)がないはずはない。あの人のお名前を忘れられたら、大変なことになる……」 蝸牛はこう言って、先刻従弟のなめくじに聞いたことを話して聞かせました。 それは小野道風といったな高い書家が、まだ修業盛りの頃、どうも一向芸が上達しないので、すっかり嫌気がさして、雨の降るなかを、ぶらぶら散歩に出かけました。ふと見ると、途ばたのしだれ柳の下に雨蛙が一匹いて、枝に飛びつこうとしています。幾度か飛んで、幾度か落ちしている末、とうとう骨折のかいがあって、枝に縋りつきました、それを見た道風はすっかり感心しました。 「何事も努力だな。あの蛙がわしにそれを教えてくれたのだ。」 と思った彼は、家に帰ってから夜を日についで、みっちり勉強を重ねました。やがて書道のえらい大家になったという話なのでした。 「何でもその道風とやらは、公卿(くげ)の次男坊だそうだから、お冠でも着ていたかも知れない。そんな男の記憶はないかしら」 「ある。ある。やっと思い出した。ずっと以前にそんな男に出あったことがあったっけ。」雨蛙はだしぬけに大きな声で叫びました。「だが、話が少しほんとうのことと違っているようだ。おれは何も道風とやらに教えようと思って、そんなに骨を折っていたわけじゃないよ。」 「これ。そんなに大きな声を……」 蝸牛は慌てて眼でとめました。そして声をひそめて、この頃世間の噂によると、人間は雨蛙が道風を感化して、すぐれた書家をつくり上げた手柄を記念するために、今度銅像を建てようと目論んでいるという事を話しました。 「そんな場合じゃないか。話が違っているなどと、余計な口をきくものじゃないよ。」 銅像――と聞くだけでも、雨蛙は喜びました。彼は秋になると、鋭い嘴(くちばし)をもった鵙(もず)がやって来て、自分たちを生捕りにして、樹の枝に磔(はりつけ)にするのを何よりも恐れていました。あの癇癪(かんしゃく)もちの小鳥が、赤銅張(しゃくどうば)りの自分をどうにもあつかいかねている姿を想像するのは、雨蛙にとってこの上もない満足でした。 「だが、おれは着物を着ていない。すっ裸だ。こんな姿(なり)でもいいのかしら。」 雨蛙は心のなかでそう思うと、急に自分の姿が恥かしくなって、両手をひろげてふくれた腹を隠しました。腹には臍(へそ)がありませんでした。 「おれには臍がない。困ったなあ。臍のない銅像を見ると、皆が噴き出すだろうからな。」 雨はざあざあ降りしきって来ました。雨蛙は両手で腹を抱えたまま、ずぶ濡れになって腑抜(ふぬ)けがしたようにぼんやりとそこに立っていました。 「えらい降りだな。」蝸牛はどうかすると、滑り落ちそうな無花果の葉っぱをしっかりとつかまえました。「おい、おい。何をそんなに考え込んでるんだ。」 「おれは銅像になぞしてもらいたくない。」雨蛙は哀しそうにいいました。「おれの腹には臍がないし、それに話が大分喰い違っているようだ。おれはあの折人にものを教えようとも思っていなければ、そんなに骨を折って柳の枝に飛びつこうともしていたわけじゃないんだよ。」 「じゃ、何をしてたんだ。正直に言いなさい。」 蝸牛は険しい顔をしました。友達のそんな気色を見てとった雨蛙は、気おくれがしたように声を低めました。 「ほんとうのことをいうと、おれはぶらんこをしていたんだよ。道風さんにはすまないけど、唯それだけのことなんだ。」 「ぶらんこ……」 蝸牛は呆気にとられたようにいいました。そして柄(え)のついた雨除け眼鏡を持ちなおして、しげしげと相手の顔を見入っていましたが、こんなせち辛い世のなかに、のん気にぶらんこをして遊ぶような、そんな友達なぞ持ちたくないといったように、顔をしかめたまま、黙って向をかえました。 仲のいい友達を一人失くした哀しみを抱きながら、雨蛙はぐしょ濡れになって、無花果の上葉から下葉へと飛び下りました。 そこには皺くちゃな蟇蛙(ひきがえる)がいて、待っていたように悪態を吐(つ)きました。 「慾のない小伜(こせがれ)めが。一家(いっけ)一族の面目ってことを知りくさらねえのか」 「それは知っている。だが、おれは嘘は言いたくないのだ。それに買いかぶられるのが何よりも嫌なんだ。」 そういった雨蛙の言葉には、何となくある明るさと力強さとがありました。P.304~312 *彼は現在の倉敷市連島の生まれ。 *この本の解説は杉本秀太郎である。その一部は、「冴えた眼力で自然と人事を観察し、端正な文章で愛情こまやかにつづる清澄な心境随筆。とりわけ、幼少時から親しんだ身近な動植物に注ぐ著者のまなざしはあたたかく、時に共感をこめて語りかける。枯淡と洒脱の円熟味ゆたかなエッセイの数々(71)は、どこかなつかしくまたさわやかな読後感を呼ぶ。」である。 参考:薄田泣菫 2010.02.24、2017.07.11~08.19追加。 |
|
谷沢永一著『百言百話』(中公新書)昭和60年2月25日 発行 P.200~201 やってみなはれ 鳥井信治郎「やってみなはれ みとくれなはれ」より 明治三十五年の某日、寿屋(現・サントリー)の創設者であり、今は川西市雲雀ケ丘の自宅で静養している鳥井信治郎の枕頭に、長兄が早世したため家業を継いだ次男の佐治敬三が静かに坐って、ビール製造の決意と企画をうちあけた。 開高建の厳粛な描写によれば、「信治郎はしばらく考えこんでいたが、やがて低い声で、自分はこれまでサントリーに命を賭けててきた。あんたはビールに賭けようというねンな。人生はとどのつまり賭けや。わしは何もいわない。〈……やってみなはれ〉といった。細心に細心をかさね、起り得るいっさいの事態を想像しておけ。しかし、さいごには踏みきれ。賭けろ。賭けるなら大きく賭けろ。賭けたらひるむな。徹底的に食いさがってはなすな。鳥井信治郎の慣用句"やってみなはれ"にはそういうひびきがあった。八十三年の生涯にもっともしばしば使った日本語はこれである」。 人生はとどのつまり賭けや――この信念をもって鳥井信治郎は生涯を貫いた。賭けの瞬間は孤独で淋しくて辛い。だが賭けという難関を自ら設定し、それを突破する勇気なくして、人間の一生に輝きはないのだ。賭けこそ人間をとことんまで鍛え上げて苦しめるのだが、賭けを恐れる人間に栄光と生き甲斐は恐らく訪れぬであろう。
では人生の門口に立つ青年の場合はどうか。伊藤整の名エッセイ「青春について」が事態の真実を示す。青春期にあって「本当に力が必要なのは、単に耐えることでない。目標を持たずに耐える、ということである。何時、どのようにして、自分に、ある事が満たされ、あることが成就し、この空しさから抜け出すことが出来るか、ということが、あらゆ青年のひそかな、そして心からの願いであり、期待である。しかし誰も、何人も、その青年に確約してやることができない」のだ。人生とは、青春期にあっても熟年期にあっても、「やってみなはれ」と、自分自身に言い聞かせるしかない未知の航路である。
※佐治敬三著『洋酒天国』世界の酒の探訪記 (文藝春秋社)昭和35年12月20日初版 スコッチをたずねて(イオギリス)キアンチの国(イタリー)黄金の丘(フランス)古城と酒(オーストリア)日光を飲む(スイス)ラインとモーゼル(ドイツ)ビールづくりのモラル(デンマーク)ジンとリキュール(オランダ)カクテルの国(アメリカ)の章の編成。 2019.09.16 |

 退校の原因は他でもない。外務大臣などをした陸奥宗光の嗣子広吉がそこで学んでいた。「きれいな着物を着て、なんとなくのさぼっておるので、こいつやってしまえと、陸奥の頭を殴ったりし、それが原因で退校させられた」(『一老政治家の回顧』)
退校の原因は他でもない。外務大臣などをした陸奥宗光の嗣子広吉がそこで学んでいた。「きれいな着物を着て、なんとなくのさぼっておるので、こいつやってしまえと、陸奥の頭を殴ったりし、それが原因で退校させられた」(『一老政治家の回顧』)

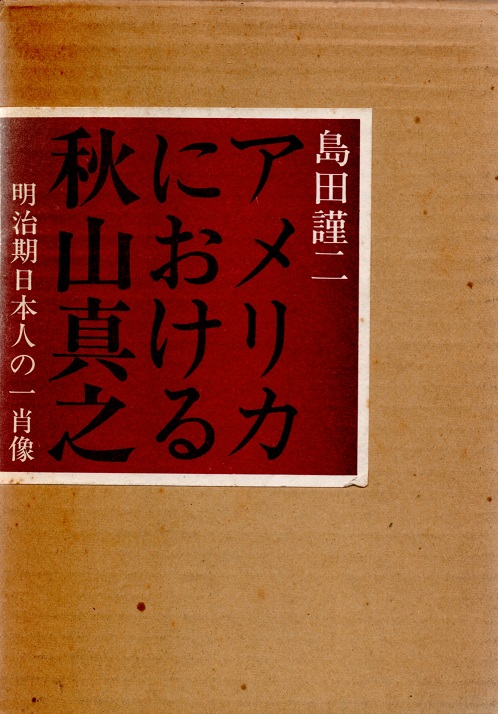 島田謹二(1901~1993年)の『アメリカにおける秋山真之』(朝日新聞社)(1972年12月10日 第12刷)調べる。
島田謹二(1901~1993年)の『アメリカにおける秋山真之』(朝日新聞社)(1972年12月10日 第12刷)調べる。
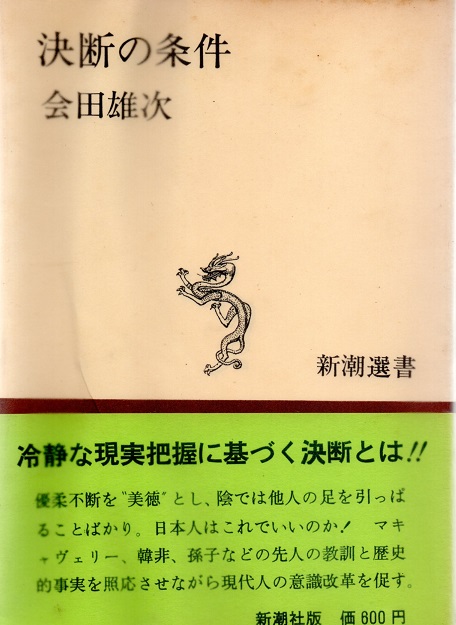
 菅江については、「天明の初年に二十八で、故郷の三河国を出てしまってから、出羽の角館で七十六歳を以て没するまで、四十八回の正月を雪国の中で、次々に迎えて居た人」(『雪国の春』)という柳田国男の叙述にもっともフィーリングがあるようだ。「どうして斯ういふ寂しくも又骨折な生涯の旅行が始まったか」はわからない。「真澄の目的は、いままで学んできた国学・本草の知識をもって、当時ほとんど知られることのなかった辺境の地、陸奥――北海道をふくめた東北地方――の風物をすべてにわたってたしかめてみたところにあるように思われる」(内田武志『菅江真澄というひと』:黒崎確認:『菅江真澄遊覧記』(東洋文庫)P.16)という解説も、二十八歳から七十六歳まで郷里に帰らず、みちのくを歩きつづけた孤独な魂の秘密まではときあかしてくれない。
菅江については、「天明の初年に二十八で、故郷の三河国を出てしまってから、出羽の角館で七十六歳を以て没するまで、四十八回の正月を雪国の中で、次々に迎えて居た人」(『雪国の春』)という柳田国男の叙述にもっともフィーリングがあるようだ。「どうして斯ういふ寂しくも又骨折な生涯の旅行が始まったか」はわからない。「真澄の目的は、いままで学んできた国学・本草の知識をもって、当時ほとんど知られることのなかった辺境の地、陸奥――北海道をふくめた東北地方――の風物をすべてにわたってたしかめてみたところにあるように思われる」(内田武志『菅江真澄というひと』:黒崎確認:『菅江真澄遊覧記』(東洋文庫)P.16)という解説も、二十八歳から七十六歳まで郷里に帰らず、みちのくを歩きつづけた孤独な魂の秘密まではときあかしてくれない。

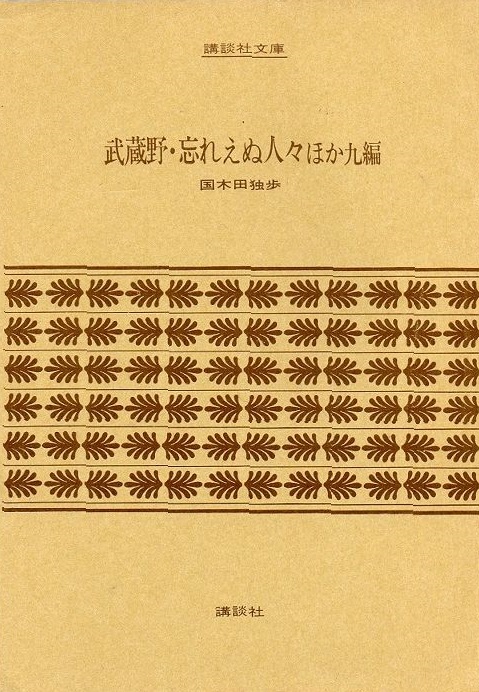 ▼『武蔵野』
▼『武蔵野』


 これらに、空想力と情感が働いた。〔餠が丸いのは、心臓の形に似せてつくったのではないか、という如き大胆な仮説をたてられる、奔放な想像力の躍動が、その文章に華やかさを添えているのだと思う〕(白井浩司)。〔≪雪国の春≫のなかに、どこか東北地方の浜で、旅人が、村の女たちに話しかけてからかわれる情景の出てくる話がある。≪清光館哀史≫というので、月かげも、女たちのふくんだような笑い声も、津波なぞの自然の荒さも、貧しいハタゴヤの没落も、よその部屋でやっている蓄音機をきくようなやさしさでひびいていた〕(中野重治)。〔氏が民俗学の形で大成した仕事の背後には、天地の広大と、人間の生命の脆さを対比した詩人の憂鬱が横たわっているのではないか〕(中村光夫)。この稟質の上に、確固とした問題意識が生れた。田山花袋、国木田独歩等、新進作家とグループをつくり〔青年時代文学者となる状態から発足させられた。しかし先生が文壇的文学者になれなかったのは、当然だったと思う〕(保田与十郎)。エリート官僚の出世コースを自ら外れ、余技を本技としたのもおなじ理由である。明治三十三年二十六歳のとき、東大法学部を出て農商務省にはいった。〔官僚の道を農商務省にえらんだというのも当時としては変わり種であって、学究的な関心があったことを示している。役人といえば内務官僚というのが常道であった時代である〕(中村哲)。ご本人は〔飢饉といえば、私自身もその惨事にあった経験がある。その経験が、私を民俗学の研究に導いた一つの理由ともいえるのであって、飢饉を絶滅しなければならないという気持が、私をこの学問にかり立て、かつ農務省にはいる動機にもなったのである〕(『故郷七十年』)と書いている。
これらに、空想力と情感が働いた。〔餠が丸いのは、心臓の形に似せてつくったのではないか、という如き大胆な仮説をたてられる、奔放な想像力の躍動が、その文章に華やかさを添えているのだと思う〕(白井浩司)。〔≪雪国の春≫のなかに、どこか東北地方の浜で、旅人が、村の女たちに話しかけてからかわれる情景の出てくる話がある。≪清光館哀史≫というので、月かげも、女たちのふくんだような笑い声も、津波なぞの自然の荒さも、貧しいハタゴヤの没落も、よその部屋でやっている蓄音機をきくようなやさしさでひびいていた〕(中野重治)。〔氏が民俗学の形で大成した仕事の背後には、天地の広大と、人間の生命の脆さを対比した詩人の憂鬱が横たわっているのではないか〕(中村光夫)。この稟質の上に、確固とした問題意識が生れた。田山花袋、国木田独歩等、新進作家とグループをつくり〔青年時代文学者となる状態から発足させられた。しかし先生が文壇的文学者になれなかったのは、当然だったと思う〕(保田与十郎)。エリート官僚の出世コースを自ら外れ、余技を本技としたのもおなじ理由である。明治三十三年二十六歳のとき、東大法学部を出て農商務省にはいった。〔官僚の道を農商務省にえらんだというのも当時としては変わり種であって、学究的な関心があったことを示している。役人といえば内務官僚というのが常道であった時代である〕(中村哲)。ご本人は〔飢饉といえば、私自身もその惨事にあった経験がある。その経験が、私を民俗学の研究に導いた一つの理由ともいえるのであって、飢饉を絶滅しなければならないという気持が、私をこの学問にかり立て、かつ農務省にはいる動機にもなったのである〕(『故郷七十年』)と書いている。
 猪苗代湖の野口記念館には、その原文が保存されているが、文句の形は修正して、文章だけを記しておく。
猪苗代湖の野口記念館には、その原文が保存されているが、文句の形は修正して、文章だけを記しておく。
 海老をまた好いた人に、蜆子和尚という老僧が唐代にあった。和尚は身のまわりに何一つ物らしい物を蓄えないで、夏も冬もたった一枚の衣でおっ通したほど、無慾枯淡な生涯を送ったものだった。腹が空くと、衣の裾をからげて水に入り、海老や、貝といったようなものを採って、うまそうに食っていた。僧かと思えば僧でもなく、俗かと見れば俗でもなさそうで、一向そんなことに無頓着で、出入自在、その日その日の生命に無理な軛(くびき)を負わせないで、あるがままに楽み、唯もう自然と遊戯しているつもりで暮していたらしかった。
海老をまた好いた人に、蜆子和尚という老僧が唐代にあった。和尚は身のまわりに何一つ物らしい物を蓄えないで、夏も冬もたった一枚の衣でおっ通したほど、無慾枯淡な生涯を送ったものだった。腹が空くと、衣の裾をからげて水に入り、海老や、貝といったようなものを採って、うまそうに食っていた。僧かと思えば僧でもなく、俗かと見れば俗でもなさそうで、一向そんなことに無頓着で、出入自在、その日その日の生命に無理な軛(くびき)を負わせないで、あるがままに楽み、唯もう自然と遊戯しているつもりで暮していたらしかった。
