| 日本の本より (享保17年~安政3年) |
日本の本より (明治時代:1) |
日本の本より (明治時代:2) |
日本の本より (明治時代:3) |
|---|---|---|---|
| 日本の本より (明治時代:4) |
★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 日本の本より (大正時代) |
日本の本より (昭和時代) |
★★★★★★ | ★★★★★★ |
| 外国の人々(1868年以前) | 外国の人々(1868年以後) | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
(明治時代:3) |
|---|

小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.33~37 忘れられた海軍大将・山梨勝之進 「山本権兵衛大将の前にたつと、爛々とかがやく灼熱の太陽の前にあるおもいがする。加藤友三郎大将の前に立つと、何物をも一点の狂いなく映し出す明鏡の前にたつたおもいがする。斎藤実大将とともにあるときは、美しいサロンに坐しウイスキ―を杯に酌み、静かに語るおもいがする」 人物評言としてまことに見事なものといえるが、それでは、これを語った山梨勝之進自身はどいう人物であったか。 彼については、ほとんど知られていないが、それでは肩書だけの、内容のない二流、三流の人物だったのであろうか。
山梨勝之進は明治十年仙台市に生れ、海軍兵学校(海兵25期次席/25人)を出て、二十代の艦隊勤務のほか、「比叡」副長、「香取」艦長を歴任したが艦隊勤務は少なく、海軍省副官、大臣秘書官などを経て、軍務局第一課長、人事課長、海軍艦政本部長など軍政の中枢を歩き、海軍次官、佐世保および呉の鎮守府司令長官となって、昭和八年満五十六歳になる前、予備役になった。その後昭和十四年から二十一年まで学習院長、昭和四十二年満九十歳で永眠。 世間的に有名でなかった理由は、第一に、枢要な軍政の機勤にふれながらも、世間的に派手な立場にたつことがなかったこと、第二に、ご本人が、自己宣伝はもちろんのこと、自己顕示感に乏しく、文字どおりサイレント・ネイヴィの典型だったことによる。 早く海軍を退いたのは、ロンドン軍縮会議(昭和五年)の余波であった。このとき、英米の国力をよく知り、国際協調を維持することが日本を救う道と考えて努力した当路者は、「条約派」としてうとまれ、つぎつぎと予備役に編入された。海軍次官として心血を注いだ山梨もその犠牲者の一人、当時首席全権だった若槻(わかつき)礼次郎は、 「こういう人たちは、あまり私のところへなど来ないが、一ぺん山梨に会った。私は山梨に対して、あんたなどは、当たり前に行けば、連合艦隊の司令長官になるだろうし、海軍大臣になるべき人と思う。それが予備になって、今日のような境遇になろうとは、見ていて、じつに堪えられん、と言った。すると山梨は、いや、私はちっとも遺憾と思っていない。軍縮のような大問題は、犠牲なしには決まりません。誰か犠牲者がなければならん。自分がその犠牲になるつもりでやっただけですから、私は海軍の要職から退けられ、今日の境遇になったことは、少しも惜しむべきことではありません、と言った。これを聞いて私は、今更ながら山梨の人物の立派なことを知ったのであった」(『古風庵回顧録』) と語っている。 山梨は、後年このことについて語ることを好まなかったが、これについて橋口氏は、他人の語るにまかせるものの自己は語らずと心にきめたことは、あくまでも守りとおす強靭(きょうじん)な「寡黙の精神」と評価している。 山梨は、晩年海上自衛隊幹部学校で講演を行った。その間、資料の整備、原稿作成、外国公館への照会、原書の読破など、一回の講話の準備に三ヵ月をついやした。昭和三十四年九月八十二歳のときにはじめ、おえたのが四十一年十一月、満八十九歳をこえ、数えで九十一歳の正月を迎えんとするときであった。原稿は大学ノート四十冊に及んだ。 ※山梨勝之進著『歴史と名将』歴史に見るリーダーシップの条件(毎日新聞社)昭和56年10月30日第1刷 橋口氏は、「自己のいっさいを後人に捧げつくす教育の要諦を身をもって実践しておられる」、「また後人としての人間にたいするかぎりない愛情と負託がないかぎり、よわい八十歳をこえてから、あれほどの情熱と苦行が生まれるはずはない」と書いている。 橋口氏は名エッセイストのなが高いが、本書の中で語っている人物は、山梨勝之進と吉田茂の二人にすぎない。 「忘れられた海軍大将」と、吉田を書いた「素顔の総理大臣」とは、分量的に大差があるが、本質的に共通するものは、ともに著者と面識があったという点である。 これは橋口氏の人物評伝の重要な特色であり、期せずしてユニークな内容価値を保証する条件ともなっているようだ。 評伝は、資料だけでは書けない。ましてや、レトリックで処理できるものではない。では何が必要か、といえば、人間との出会いをおろそかにしない、という人間的姿勢であろう。 橋口氏の評伝は、そのことをはっきり示している。彼が書いたのは、単なる海軍大将、総理大臣ではなかった。一人は、学習院長として、自分を教え、アドバイスしてくれた人。一人は内閣参事官時代、欠席した閣議の決済をうけるため、大磯の自邸で二人きりで会っており、二回に一回は機嫌がわるく、五回に一回は機嫌がよかった人だ。 橋口氏は、この人たちと会うとき、人間いかに生きるべきか、という命題を片ときも放していない。すなわち、山梨も吉田も、位階勲等、スティタスよりは、いかにいきているか、という一点にしぼって見つめている。つまりは、人間の誠実さで対決している。 私心がないから、その眼はつねに澄んでいる。そして、根本には深い愛情がある。 これらのものを融合したものを「肉感」とよぶならば、橋口氏の評伝はまさしく肉感の産物。氏はおのれの肉感のほかは一切世評を信ぜず、先人の評価のうち、その肉感とバイブレーションをおこすものだけを正しい評価として受け入れている。若槻の回顧録が二回にわたって引用されるのは、若槻が大蔵省の大先輩だからではなくて、山梨勝之進への高評価が橋口氏自身の肉感を裏づけているからである。吉田が老いてなお仏和辞典を片手に外国新聞を読む姿に感銘するのは、氏自身がそういう勉強家であったからに他ならない。 私事をいえば、筆者は橋口氏と大学、海軍の同期。拙著『無冠の男』を贈ると、「精読した」と冒頭に書いて、くわしく、率直にその読後感を送ってきた、その冒頭の一語にこそ、氏の人柄、人生観、そして本書を貫く根本の精神が表れていると思う。 (昭和五十一年十一月四日)) ※橋口 收(はしぐち おさむ、1921年9月 - 2005年7月13日)は、学習院初等科、中等科(旧制)、高等科を経て、1943年に東京帝国大学を卒業、大蔵省に入省する。大蔵官僚としては主計局長に就任、事務次官に昇格する者と思われたが、田中角栄内閣下で編成した1974年度予算が首相の指示で放漫財政になったためこれに反対、角福戦争に半ば巻き込まれる形で事務次官に就任できず、新設の国土庁事務次官に押し込まれた(事務次官に就任したのは、田中角栄が推した大蔵省同期の高木文雄主税局長)。主計局長になりながら事務次官の座を逃したのは、福田赳夫以来のことであった。 退官後は、公正取引委員会委員長、広島銀行頭取、同会長を歴任した。広島銀行会長在任中に、広島に本社のあるマツダとフォードとの提携事業をまとめた。 2019.08.07 |

吉野 作造(よしの さくぞう)は、大正時代を中心に活躍した日本の政治学者、思想家である。東京帝国大学で教壇に立ち、大正デモクラシーの立役者となった。初なは[作蔵]、1917年5月[作造]に改みょう。号は[古川学人]。弟は商工官僚・政治家の吉野信次。
何よりも第一に現時の学生に対して希望したきは、真理に対する従順な態度です。真理を求めてこれを我が主義とせんとする熱情はなかなか盛です。しかし、一たん何物かを真理と思い込んだが最後、彼らは盲目となるのが常です。故に外により正しいものがあると教うるものがあっても、これに耳を傾けません。学生の真理探究の態度は多情でなくてはなりません。無節操なくてはなりません。無節操といっては誤解を誤解をまねくかも知れませんが、常により正しからんとして、いつでも態度を改めうるように用意していなくてはなりません。 (学生に対する希望) この日(3月18日)死す。東大の政治教授。大正時代の民本主義運動の理論的指導者。普選の実行、政治の民衆化のためにたたかった。晩年『明治文化全集』を編纂 桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.47 2021.12.30記す。 |
03 寺田 寅彦(1878~1935年)

▼寺田寅彦随筆集 (岩波文庫)第2巻(昭和二十四年十月三十日 発行)P.265 科学の高塔は未だ曾て完成した事がないバベルの塔である。此れでもう大體出来上がったと思ふと、實は出来上がって居ない証據が脚元から発見される。職工達の言葉が混亂して分からなくなる。併し、凡ての時代の學者はその完成を将来に夢みてきた。現在がさうであり、未来も恐らくさうであらう。

一 車上 (岩波文庫)第2巻(昭和二十四年十月三十日 発行)P.144~145 「三上(さんじょう)」という言葉がある。枕上(ちんじょう)鞍上(あんじょう)厠上(しじょう)合わせて三上の意だという。「いゝ考えを発酵させるに適した三つの環境」を對立させたものとも解釈される。なかなかうまい事を言ったものだと思う。併しこれは昔の支那人か余程閑人でないと、現代では言葉通りには適用し難い。 三上の三上たる所以を考えてみる。まずこの三つの境地はいづれも肉體的には不自由な拘束された余儀ない境地である事に気が付く。この三上に在(あ)る間はわれわれは他の仕事をした度くても出来ない。併し又一方から見ると非常に自由な解放された有難い境地である。なんとならばこれらの場合にわれわれは外からいろいろの用事を持ちかけられる心配から免れている。肉体が束縛されているかわりに精神が解放されている。頭脳の働きが外方へ向くのを止められているので自然に内側へ向かって行くせいだと言われる。 現代の一般の人について考えてみるとこの三上には多少の変更を要する。まず:「枕上(ちんじょう)」であるが、毎日の仕事に追われた上に、夜なべ仕事でくたびれて、やっと床につく多くの人には枕上は眠る事が第一義である。それで眠られないという場合は病気なのだからろくな考えは出ないのが普通である。 「厠上(しじょう)」のほうは人によると現在でも適用するかもしれない。自分の知っている人の内でも、たぶんそうらしいと思われるほどの長時間をこの境地に安住している人はある。しかし寝坊をして出勤時間に遅れないように急いで用を足す習慣のものには、これもまた瞑想(めいそう)に適した環境ではない。 残る一つの「鞍上(あんじょう)」はちょっとわれわれに縁が遠い。これに代わるべき人力(じんりき)や自動車も少なくも東京市中ではあまり落ち着いた気分を養うには適しないようである。自用車のある場合はあるいはどうかもしれないが、それのない者にとっては残る一つの問題は電車の「車上」である。 電車の中では普通の意味での閑寂は味わわれない。しかしそのかわりに極度の混雑から来た捨てばちの落ち着きといったようなものがないでもない。乗客はみんな石ころであって自分もその中の一つの石ころになって周囲の石ころの束縛をあきらめているところにおのずから「三上」の境地と相通ずる点が生じて来る。従って満員電車の内は存外瞑想に適している。机の前や実験室では浮かばないようないいアイディアが電車の内でひょっくり浮き上がる場合をしばしば経験する。 「三上」の三上たるゆえんの要素には、肉体の拘束から来る精神の解放というもののほかにもう一つの要件があると思われる。それはある適当な感覚的の刺激である。鞍上(あんじょう)と厠上(しじょう)の場合にはこれが明白であるが枕上(ちんじょう)ではこれが明白でないように見える。しかしよく考えてみると枕(まくら)や寝床の触感のほかに横臥(おうが)のために起こる全身の血圧分布の変化はまさにこれに当たるものであると考えられる。問題の「車上」の場合にはこの条件が充分に満足されている事が明白である。ただむしろ刺激があり過ぎるので、病弱なものや慣れないものには「車上」の効力を生じ得ない。この刺激に適当に麻痺(まひ)したものが最もよく「車上」の能率を上げる事ができるものらしい。 ▼私見:「湯川秀樹博士のエピソード」に「枕上」の言葉がつかわれています。私は、かねがね誰が、何時、この言葉をつくったのだろうか? 上の文章を読んでもわからない。インターネットで調べても分かりませんでした。 関連:扇谷正造 2011.03.31
科学者とあたま (岩波文庫)第4巻(昭和二十四年十月三十日 発行)1950年03月30日購入 P.246~252
頭のいゝ人は云はヾ富士の裾野まで来て、此處から頂上を眺めたたヾけで、それで富士の全体體を呑込で東京へ引返すという心配がある。富士は矢張り登って見なければ分からない。 頭のいゝ人は見透しが利くだけに、あらゆる道筋の前途の難關が見渡される。少くも自分でさう云ふ気がする。その為にやゝもすると前進する勇気を沮喪し易い。頭の悪い人は前途に霧がかかつてゐる為に却つて楽観的である。さうした難關に出遭つても存外どうにかしてそれを切抜けて行く。どうにも抜けられない難關というのは極めて稀だかれである。 それで研學の徒は餘り頭のいゝ先生にうつかり助言を乞うてはいけない。屹度前途に重畳する難關を一つ一つ蝨潰しに枚挙されてさうして折角楽しみにしてゐる企圖の絶望を宣告されるからである。委細構うはず着手して見ると存外指摘された難關は楽に始末が付いて、指摘されなかった意外な難點ンい出逢うこともkある。 頭のよい人は、餘りに多く頭の力を過信する恐れがある。其の結果として、自然が吾々に表示する現象が自分の頭で考へたことゝ一致しない場合に、「自然の方が間違つてうゐる」かのやうに考へる恐れがある。真逆それ程でなくても、さう云つたやうな傾向になる恐れがある。此れでは自然科學は自然の科學でなくなる。一方で又自分の思つたやうに結果が出たときに、それが實は思つたとは別の原因の為に生じた偶然の結果でありはしないかといふ可能性を吟味するといふ大事な仕事と忘れる恐れがある。 頭の悪い人は、頭のいゝ人が考へて、はじめから駄目にきまってゐるやうな試みを、一生懸命につヾけてゐる。やっと、それが駄目と分かる頃には、併し大抵何かしら駄目でない他のものゝ絲口を取り上げて居る。さうしてそれは、そのはじめから駄目な試みを敢てしなかった人には決して手に觸れる機會のないような絲口である場合も少なくない。自然は書卓の前で手を束ねて空中に畫を画いて居る人からは逃げ出して、自然の眞中へ赤裸で飛込んで来る人にのみ其の神秘の扉を開いて見せるからである。 頭のいゝ人は戀が出来ない。戀は盲目である。科學者になるには自然を戀人としなければならない。自然は矢張り其の戀人にのみ眞心を打明けるものである。 科學の歴史は或る意味では錯覚と失策の歴史である。偉大なる迂遇者の頭の悪い能率の悪い仕事の歴史である。 頭のいゝ人は批評家に適するが行為の人にはなりにくい。凡ての行為には危険が伴ふからである。怪我を恐れる人は大工にはなれない。失敗を怖がる人は科學者にはなれない。科學も矢張り頭の悪い命知らずの死骸の山の上に築かれた電動であり、血の河の畔に咲いた花園である。一身の利害に對して頭がよい人は戦士にはなりにくい。 頭のいゝ人は他人の仕事のあらが眼につき易い。其の結果として自然に他人のする事が愚かに見え従つて自分が誰よりも賢いといふやうな錯覚に陥り易い。さうなると自然の結果として自分の向上心に弛みが出て、やがて其人の進歩が止まってしまふ。頭の悪い人には他人の仕事が大抵みんな立派に見えると同時に又えらい人の仕事でも自分には出来さうな気がするのでおのづから自分の向上心を刺激されるといふこともあるのである。 頭のいゝ人で人の仕事のあらは分かるが自分の仕事のあらは見えないいとふ程度の人がある。さういふ人は人の仕事をくさしながらも自分で何かしら仕事をして、さうして學会に幾分の貢獻をする。併しもう一層頭がよくて、自分の仕事のあらも見えるといふ人がある。さういふ人になると、何處迄研究しても結末が付かない。それで結局研究の結果を纏めないで終る。即ち何もしなかつたのと、實證的な見地からは同等になる。さういふ人は何でも分かつてゐるが、唯々「人間は過誤の動物である」といふ事實だけを忘却してゐるのである。一方では又、大小方圓の見さかひも付かない程に頭が悪いおかげで大膽な實験をして大膽な理論を公にし其の結果として百の間違ひの内に一つ二つの眞を見付け出して學会に何かしかの貢獻をして又誤つて大家の名を博する事さへある。併し科學の世界では凡ての間違ひは泡沫のやうに消えて眞なものゝみが生残る。それで何もしない人よりは何かした人の方が科学學に貢獻する譯である。 頭のいゝ學者は又、何か思ひ付いた仕事が」あつた場合にても、其の仕事の結果が價値といふ點から見ると折角骨を折つても結局大した重要なものになりそうもないといふ見込みをつけて着手しないで終る場合が多い。併し頭の悪い學者はそんな見込みが立たないために、人からは極めてつまらないと思はれる事でも何でも我武者らに仕事に取付いて脇目もふらずに進行して行く。さうして居るうちに、始めには豫期しなかつたやうな重大な結果に打つかる機會も決して少なくはない。此の場合にも頭のいゝ人は人間の頭の力を買被つて天然の無際限の奥行を忘却するのである。科學滴研究の結果の價値はそれが現はれる迄は大抵誰にも分からない。又、結果が出た時には誰も認めなかつた價値が十年百年の後に初めて認められることも珍しくはない。 頭がよくて、さうして、自分を頭がいゝと思ひ利口だと思ふ人は先生になれても科學者にはなれない。人間の頭の力の限界を自覚して大自然の前に愚な赤裸の自分を投出し、さうした唯々大自然の直接の教えのみ傾聴する覚悟があつて、初めて科學者にはなれるのである。併しそれだけでは科學者にはなれない事も勿論である。矢張り観察と分析と推理の正確周到を必要とするのは云う迄もないことである。 つまり、頭が悪いと同時に頭がよくなくてはならないのである。 ★プロフィル:寺田 寅彦は、戦前の日本の物理学者、随筆家、俳人であり吉村冬彦、寅日子、牛頓、藪柑子の筆名でも知られる。高知県出身。 2008.06.03 |
04 河上 肇(1879~1916年)

眼の前にはいかなる黒雲が渦を巻いていようとも、全人類の上によりよき世界が年一年、早足で近づきつつあることには、寸毫(すんごう)の疑いもない。私は牢獄のうちに繋がれていながらも、この偉大なる新社会の近づいてくる足音を刻々に聞くことができる。 私はもう六十に近い老人だが、しかし、もし幸いにも天が私に、私の祖母や父や母やの長寿を恵んでくれるならば、私は、私の最も愛するこの日本に、私の愛する娘たちや孫たちの住んでいるこの日本の社会に、私が涙をこぼして喜ぶであろうような変化が到来する日を、生きた眼で見ることができるであろう。(自叙伝) この日(10月27日)この日死んだ。日本におけるマルクス主義経済学の開祖。京大教授。無我愛運動をへて、のち、共産党に入り、運動に献身した。『貧乏物語』『自叙伝』 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.18 |
05 正宗 白鳥(1879~1962年)
|
誰にでも人に言えぬ秘密がある *自分の秘密は天知る、地知る、吾れ知る。「黙 養」の心がけこそ試される。 ★プロフィル:正宗 白鳥は、明治 から昭和にかけて活躍した小説家、劇作家、文学評論家。本名は正宗 忠夫。 2008.11.11 |
06 唐牛 敏世(1879~1979年)
|
来てみればさほどでもなし白寿かな みちのく銀行唐牛敏世氏の近作である。氏は昭和五十三年の八月十五日で満九十九歳を迎えた。白寿である。しかも現役の頭取である。 いったい、六十五歳以上の老人は、何をもって現役、非現役の目安とするかといえば、どうも、つぎの三つのようである。 一、テーブル・スピーチを五分以内にまとめることが出来る。 一、三十分間の会話の中で、同じ話を二度くりかえさない。 一、ココまでは自分はわかっている。しかし、ソレカラ先は分からないと自分の知識と理解力の限界を知っている。それ故、自分の知らないソレカラ先のことは謙虚に学ぼうとする。 胸に手をあてて考えてみると、いちいち思い当ることばかりである。仙崖和尚は「くどくなる 気短になる 愚痴になる 出しゃばりたがる 世話をやきたがる」を老人の兆候としているが、これは行為にあらわれた現象で、これをチェックできるのは、前記の三条件に対する心掛けであろう。 駿河銀行の岡崎喜太郎氏もかって百歳をこえた現役頭取といわれたが、先年死去した。いま経済界では、現役の最長年者は唐牛氏だけであろう。 その『みちのく銀行』から講演をたのまれた(八月八日)。この機会にと唐牛頭取と対談することにした。テープで三時間。はじめは、私も時々合の手を入れていたが、そのうち、これは独演会の方がはるかに面白くミがあり、諸君に喜ばれるだろうと思い、ただただ拝聴することにした。 対談は二つの部分に分かれた。長寿法と波爛万丈の巻である。若いころ、ずいぶん、いろいろな事をやられたらしい。七転び八起きで、みちのく銀行の前身『弘前相互無尽』をはじめたのは四十六歳の時であった。中高年のスタートにしてもいいところである。 氏の長寿法はひと口にいえば
〽この秋は雨か嵐かしらねども
という信条であるという。あすのことを思い患っても仕方がない。まずきょうのことである。つまり「足ルヲ知ル」の境地で、それが定まって進取の精神が生まれてくる。あすの老醜や老衰をくよくよ考えても仕方がない。自分で是とする健康法を、毎日毎日持続して行うこと、これである。 小食粗食。これはまあ、どの長寿法にも書いてあり、唐牛氏も同じだが、その外に二つの新しいことをやられている。一つは頭の体操である。頭の体操というと、参議院議員の源田実氏の高等数学、あるいは亡くなった石田礼助翁のように株でもやるのかと思ったら、そうではなく文字通りの体操である。 八十歳ぐらいから時々、頭がボケるのに気がついた。年のせいで仕方がないと思ってはみたものの、せめて退化はふせぎたい。それには頭の血液の循環をよくしたらどうか、とふと思いついた。それから朝夕二回、顔を洗うたびに頭にタオルをのせて六十回ぐらい頭を摩擦する。これを続けていたら、頭が今までよりクリアにはならないけれども、以後、ボケるということがなくなってきた。 もう一つは、正寝法(せいしんほう)というのかも知れない。夜、床についたら、ゆったりする。それにはまず゛寝方゛である。あおのけになり、両手両足を大の字型にして寝る。深呼吸を何回もやる。両手はのばして、その間指を何度ものばしたり曲げたりする。つまり握っては開き、開いては握る。同様に足指にもこれを行う。手足の指を動かすことはそれが末端だけにとどまらない。実は中枢の部分にも運動は及ぶのである。 「セガレはさすがに駄目ですが、あとの部分は若い者と変わりはない。ま、今は耳がすこし遠いくらいで、これにはちょっと困っている」
という。支店長会議など、一時間立ちっ放しでレクチャーをする。支店長たちの方で、お許しをねがって椅子に腰かけるということだ。
扇谷正造『現代ビジネス金言集』P.212~より ★プロフィル:唐牛 敏世(かろうじ びんせい、1879年(明治12年)8月15日 - 1979年(昭和54年)1月19日)は、日本の銀行家。みちのく銀行初代頭取。勲四等旭日小綬章1978年(昭和53年)。 2010.07.18 |
07 大原 孫三郎(1880~1943年)

私はクラレの社員であった。昭和二十五年入社以来の社長は大原總一郎氏であり、そのご尊父が大原孫三郎氏であった。 『大原孫三郎伝』(大原孫三郎伝刊行会)昭和五十八年十二月十日発行(非売品)は通読していた。 ところが、平成二十五年(2013年)二月十五日(金)急性感染症で、岡山大学病院泌尿科・歯学部受診。総合内科受診。即入院となりました。 入院中、医師の一人に倉敷からの方が居られて、雑談していますと兼田麗子著『大原孫三郎━━善意と戦略の経営者』(中公新書)2012年12月20日発行が最近出版されている。大変、感激されて読み通した、と話された。
私は退院後、この本をを購入して読みました。 このたび、読み返しましたので、冒頭の言葉を紹介します。 はじめに 大原孫三郎とは 大原孫三郎とはどのような人物か、と尋ねてみたら、どんな回答があるだろうか。孫三郎について聞いたことのある人は、金持ちの道楽息子で社会事業にもお金を使った人と答えるかもしれない。また、ある人は大原美術館をつくった人物と言うかもしれない。 このように、大原孫三郎は様々な視点から語られるが、岡山県倉敷の大地主と倉敷紡績の経営者の地位を父親から継承し、美術館や科学研究所、病院の創設など、社会や教育などのためにも尽力した実業家である。 小作人に臨時の利益還元 一九一九年(大正八年)三月、孫三郎は、小作人の一年限りの利益分配を行った。その理由は、「昨年は風水害のため凶作に近い年柄(としがら)であったが、地主側としては米価が非常に高値を示せるためにその懐具合は決して悪い年柄ではなく、寧ろよい年柄であったというのが実情」だったからであった。 地主であるだけではなく、産業資本家でもあったことが有利に働いたことは確かであるが、小作争議が起こっていた時期に、孫三郎は地主として、一種のボーナスのようなものを小作人に提供していたのであった。 経済社会的格差の拡大によって労働運動や社会運動が頻発するようになった時代、孫三郎は、地主と小作人、労働者と資本家の利害は一致する、随って共存共栄を目指さなくてはならないと考えた。そして、社会をよくするための対策を孫三郎は考え、積極的に講じていった。 孫三郎は青年期に使命感に目覚め、「余がこの資産を与えられたのは、余の為にあらず、世界の為である。余に与えられしにはあらず、世界に与えらたのである。余は其の世界に与えられた金を以て、神の御心に依り働くものである。金は余のものにあらず、余は神の為、世界の為に生まれ、この財産も神の為、世界の為に作られて居るのである」と考えるようになった。そして、このような理想や使命感を孫三郎は生涯持ちつづけたのである。 「片足に下駄、もう片方に靴を履いて」 しかし、孫三郎は「自分の一生は失敗の歴史であった」とよく語っていた。「片足に下駄、もう片方に靴を履いてと自ら表現したような、本業の経営活動(経済性、理)と社会的事業活動(倫理性、情)の両立は、不況による経済事情の側面からも相当難しかった。このあたりのことを息子の總一郎(一九〇九-六八)は次のように振り返っていた。「もう投げだそうと思ったことも再三あった、と後で父の関係の人達から聞かされたが、それでも私に対して弱音を吐いたり、困惑したという表情をみせたことは殆んどなかった」。 反抗の精神 それでも、孫三郎が「下駄と靴」の両立を放棄しなかった理由は、単に理想主義者的な側面だけでは説明できない。反抗の精神が大きな力となっていた。幼少期から金持ちの息子だということだけで色眼鏡で見られてきたため、強い人間でなければならないと悟ったことによって、孫三郎は、負けることが嫌いな、反抗の精神が強い人物となっていった。 そのような孫三郎は、設立した施設の運営を放棄するのではなく、本来は会社から出してもよさそうな経費までも自分の財布から出して維持を図ったりした。 また、自らの過ちを反省し、生涯それを背負いつづけたことも下駄と靴。の両方を放棄しなかった理由であろう。孫三郎は、東京に出て、東京専門学校(現早稲田大学)に籍を置いたが、もっぱら実社会での勉強に終始して、大借金をつくるなど大きな失敗を犯してしまった。孫三郎と親しかった倉敷協会の牧師、田崎健作(一八八五-一九七五)曰く、生涯の呵責に孫三郎はさいなまされつづけたのであった。 一九〇二年(明治三十五年)四月十一日の孫三郎の日記には、「旧約を読了。さらに旧約を再読するか、新約聖書の三読にかかるか(中略)聖書の研究はまだまだ、これから益々勉強しようとの決心。聖書を反復熟読するようになって、反省、天職を見つけた」と書かれている。 また五月十四には、「昨夜聖書研究にて馬太(マタイ)伝四章を読んだ。余は丁度この悪魔の試みにあったのである。この悪魔の為全く失敗したのであった。併しその悪魔の手から救い出され、救い出されて初めて全く失敗であり罪である事を、やっと知ったのであった。罪であることを知る事が出来たから、悪魔から離れることも出来たのである。これは全く御心に反して居ったのだが、その救われたることによりて、余の盡すべき天職、神の命じ賜う天職を教え賜うたのである。キリストは悪魔の大誘惑に打勝ち賜うた。余は悪魔に誘惑されて其手に陥ったが、幸にその悪魔たる事を教え賜い、而して余の天職を教え賜うたのである。嗚呼神は余を全く救い賜うたのである」と綴っていた。 「正しく理解されなかった人」 このような孫三郎について總一郎は、次のように回顧していた。「父の残した事業は今では形態上変貌したが、内容的には存続しているものもかなり多いので、それらの業績から父に対する現在の評価はむしろ恵まれていると思う。しかし、生前は必ずしも今のようには評価されていなかった。それは非常に分かりにくい性格の持ち主だったからであろう。その分かりにくさは茫洋として捕え難いという類のものではなかった。尖鋭な矛盾を蔵しながら、その葛藤が外部に向かってはいろいろな組み合わせや強さで発散したから、人によって評価はまちまちだった。むずかし人だったという人もあれば、親しみ易い人だったという人もあり、冷たい人だったという人もあれば、温かい人だったという人もある。要は正しく理解されなかった人であったと思う」。 大原美術館が創設され、正面玄関の両脇にはロダンの洗礼者ヨハネの像とカレーの市民の像が置かれた。このとき、このヨハネの像を見た倉敷の人のなかには、孫三郎が父親の裸体像をつくらせた、なにも裸にしなくてもよいだろうと陰口をたたいた人もいたという。また、左翼の運動家が演説で、資本家の搾取の見本だと槍玉に挙げたこともあったと伝えられている。 孫三郎は、「仕事を始めるときには、十人のうち三人が賛成するときに始めなければいけない。一人も賛成がないというのは早すぎるが、十人のうち五人も賛成するようなときには、着手してもすでに手遅れだ、七人も八人も賛成するようならば、もうやらない方が良い」と言っていた。 また、「わしの目は十年先が見える。十年たったら世人にわしがやったことがわかる」と孫三郎は冗談めかしてよく言ったいたという。この孫三郎の言葉から十年をはるかに超えた今、「下駄をはいてあるこうとした」孫三郎を正しく評価する機は熟しているだろう。 以上で「はじめに」の文章は終わっている。しかし、本書には、本業の経営活動(経済性、理):倉敷紡績と倉敷絹織そして社会的事業活動(倫理性、情):地域の企業経営ー中国銀行・中国電力・『山陽新聞』:地域社会の改良整備ー倉敷中央病院の設立:三の科学研究所:芸術支援などなど活躍されている記事が網羅されている。 著者の参考文献の多いのにおどろかされた。よく研究されている。 参考2:『渋沢栄一』 ★プロフィル:大原 孫三郎は日本の実業家。倉敷紡績、倉敷絹織、倉敷毛織、中国合同銀行、中国水力電気会社の社長を務め、大原財閥を築き上げる。 社会、文化事業にも熱心に取り組み、倉紡中央病院、大原美術館、大原奨農会農業研究所、倉敷労働科学研究所、大原社会問題研究所、私立倉敷商業補習学校を設立した。 2015.12.19 |
08 奥村鶴吉(1881~1959年)日本の医学者。専門は細菌学。東京歯科大学学長・理事長であった。

人は四十になるまでに〔土台〕を作らねばならぬ 奥村鶴吉編『野口英世』より ★渡辺淳一さんは『遠き落日(下)』P.311、「野口英世について書かれた伝記は、各種の児童ものを含めて四十冊に達するが、そのうちで、一応信頼がおけるものは、奥村鶴吉編『野口英世』、エクスタイン著『ノグチ』、筑波常治著『野口英世』など数冊に過ぎない。」と記述している。 ★関連:野口英世 人は四十になるまでに〔土台〕を作らねばならぬ 野口英世「奥村鶴吉編『野口英世』より」 『論語』第二百二十七章。子罕第九を想起しよう。――子曰く、若い学徒に大きな期待をもつべきだ。どうしても後輩がいつまでも先輩に及ばないでいるものか。併し四十歳、五十歳になって芽のふかぬ者には、もう期待するのは無理だろう。(宮崎市定訳文)。 人にはそれぞれ境遇や性格の差があるので、機械的に融通性なく律してはならぬであろうが、生涯の半ばを越えない時期に、揺るがぬ〔土台〕を築くべきであるのは、蓋し鉄則として銘記すべきであろう。孔子が五十歳までを勘定に入れたのは、その寛容な期待はむしろ感嘆に値しよう。 四十さいまでに作りあげねばならぬ〔土台〕については、やや粗雑ながら二種類を数え得る。 第一には当該人物が生涯を通じて、専らとすべき中心の主題である。理工科系と文科系では大きく異なり、文科系がちょっと見には遅鈍であるのも止むを得ぬが、それでも四十歳前後は大きな節目であろう。いわんや理工科系は他の何に比しても、迅速で俊敏な一応の成就が要求される。いずれにせよ学窓を出て十年以内に堅牢な基礎を築きあげねばならない。もっとも孔子が第二百二十六章で言う如く、「芽を出して成長しても、穂を出さぬことがある。穂をだしたと思っても、實の熟さぬことがある。」(宮崎市定訳文)のだから、達成がかならずしも第一義ではなかろう。なかには芽が出ぬうちに薹(とう)が立つ輩(やから)も少なくない。問題は過不足のない成熟であろう。 そして忘れてはならぬのがもうひとつの〔土台〕である。もし専門分野にのみかかずらわっていれば、視野狭窄症にもなりかねない。もうひとつの「土台」とは広範な好奇心である。森羅万象のことごとくまでは言わぬにしても、頑(かたく)なではない柔軟な受信の姿勢を、可能な限り保ってゆく訓練がなければ、発想の貧困は掩うべくもなく露呈する。人が真先に衰弱し始めるのは、専門以外に対する好奇心であるようだ。万事に敏感で多角的な触覚も、また必要不可欠の〔土台〕であるのではなかろうか。 *谷沢永一著『百言百話』明日への知恵 (中央新書)P.48~49より 2010.02.02 |
09 岩波 茂雄 (1881~1946年)
|
岩波 茂雄 重剛に直談判し特別入学(1881~1946年)小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.169~173。 長野県の長野中学は松本中学校の分校であったが小阪順造(のち枢密顧問官、日本発送電総裁)は本校に進まないで、東京の日本中学に転校した。同級生仲間で雑誌『日本及日本人』をとつて輪読していたので、三宅雪嶺、陸羯南、杉浦天台道士の文章に親しみ、とくに天台道士に感銘があったためである。そのとき、同県諏訪の人間で、丸坊主の眼のクリクリした岩波茂雄という少年がおなじ転入者の一人にいた。 岩波は諏訪実科中学に学んでいたが、明治三十一年十七歳の春杉浦重剛に「請願書」という一文を送ったのである。「謹呈ス我大日本ノ教育家/杉浦先生閣下/茲(ここ)ニ信陽ノ一寒生泣血傾首再拝シテ自己ノ境遇ヲ述ベ胸中ヲ吐露シテ敢テ閣下ニ誓願スル所アラントス/拙劣ノ文閣下ノ耳目ヲ瀆フニ止マルト雖モ伏シテ希クハ一読ノ栄ヲ賜ランコトヲ」という書きだしで、片親(父)を失った自分の境遇を述べ「童心無邪気ナル時ノ死別ハ悲シミヲ感ズルコト少シトスルモ漸ク父母ノ為ニ其身ヲ成長シ之ヨリハ少シク孝道ヲ致サントスル暁ニ際シ突然父君ニ後レ給フノ悲傷如何/嗚呼余ハ実ニコノ悲境ニ沈ミタル可憐児ナリ」と書く。 しかし、いたずらに哭泣くするよりも、奮励刻苦、身を立て名を挙ぐるにしかず、と発奮した。そして、「力ノ及ブ限リ学識ヲ磨励シ社会ニ出ヅル暁ニハ至誠一貫以テ現今腐敗セル社会ヲ改革シ国家ノ為ニ身骨ヲ捧ゲ大事業ヲナシ一ハ亡父ノ霊魂ヲ慰メ聊(いささ)カ孝道ノ終リヲ為サンㇳスル>志望を立てた。だが、その志望を果すには障害がある。「夫レ我家ハ母ト余ㇳニ妹アルノミ。故ニ余ハ家ヲ襲ヒテ母ヲ養フノ義務ヲ有ス。故ニ東都遊学ハ容易ニ母ノ許シヲ得ザリシ也」。「余ハ斯カル境遇ヲ脱出シテ都ニ遊学シ其目的ヲ達セントス」るが、学資がない。そこで「真正ノ大人物ノ家ニ請ヒテ身ヲ托シ己ノ管督ヲ請ヒ……今書生タラントスルニ付イテ其人ヲ求ムルコト急也。側カニ聞ク、閣下英邁卓識磊落奇偉超然トシテ脱俗シ大ニ教育ノ為ニ尽力セラルルㇳ……先生願ハクハ余ノ愚鈍ヲステ給ハズ不幸ナル可憐児ガ至誠ナル心ヲ哀ミ我ヲシテ書生タラシメヨ。先生許可セラルルヤ否ヤ。……先生豈ニ許サザルノ理アランヤ。至誠ノ発動スル所威尊ヲ冒涜シテ恐懼已ムナシ。撓首屈指命ノ下ルヲ待タンノミ。若シ忝ナクモ返書ヲ恵マレバ何ノ栄カ之ニ過ギシ。頓首百拝」。 これについて安倍能成は「《……後レ給フノ悲傷如何》という敬語の置き損ないの如きは、晩年の彼の会話にも往々あることで、如何にも岩波らしい」といい、また、「この文章は幼稚ではあるけれども、恐らく晩年の彼の宣言文章の如く、実にしつこい苦心彫琢の末になったものであろう」(『岩波茂雄伝』)ともいぅている。ともかく、生一本の情熱とまごころは行間にあふれており、杉浦も動かされて、書生におくことはできないが、とにかく上京せよという意味の返事を書いた。 そこで三月下旬、岩波は友人の「男子志を立てて郷関を出づ、学もし成らずんば死すとも還らず」の詩吟に送られながら、肌寒い湖畔の暁風をついて出発したのである。 四月四日、岩波は五年の編入試験を受けたが、英語のできがわるくて不合格であった。彼は大いに憤慨し、「けしからん、けしからん」と連呼し、「おれがこれほど杉浦先生を慕ってきて入れないというなら、おれはもう死んでしまう。死ぬ死ぬ」とダダをこねた。 そして結局、杉浦校長に直談判したが、「不合格では仕方がない」という返事である。そこで岩波は、「自分はいなかから出てきて外の学校へはいろうという気は毛頭ありません。日本中学に入れてもらえなければ死ぬよりほかに道はありません。家にもおめおめと帰れません。何とか入れてください」と泣いて訴え、「入れていただかねば、ここを動きません」とまでいった。「それではおれが再試験をしよう」ということで、その結果、特例中の特例として入学を許されたのである。 日本中学は明治十八年にできた東京英語学校が二十七年に名称と組織を改めたもので、杉浦は二十三年七月、三十六歳で衆議院議員に当選したおなじ月から、校長になっていた。どこの学校にも、退学、停学、説諭という三つの処罰法があるが、日本中学には停学がなかった。これは「悪いことをした学生でも改悛の見込みがあれば何度でも説諭するがよい。到底改悛の見込みがないとあれば、保証人をよんで引き取ってもらうがよい。しかし停学というのはいけないよ。元来なまけたいものを停学にすれば、本人はむしろよろこんで、親の目をかすめて遊び歩くだろう。それも決してよい所には遊びに行かない。停学のためにかえってますます本人を悪くするだけだ」という杉浦の考え方によるものであったが、しかし、生徒にはほとんど干渉しなかった。 小坂たちが入学して間もなく四年の組と五年の組とが大げんかをした。椅子がとび、机は倒れ、窓ガラスは破れる大騒ぎで、一番広い廊下で格闘していると、「ああ、校長さんがやってきた」と叫ぶものがあり、たちまち大風が静まったようになって、鼻血をふいたり、コブだらけの頭をなでたりしている生徒たちの前に半白のアゴひげを生やした、痩せた、目の光る和服の校長は上がってきたが、「オイ、こうやられると、頭の上にホコリが落ちてこまるから、やめてくれ」といったきりで悠々と降りていった。それきりで何のとがめもなく、「なるほど、こう行くべきだ」と小坂はしみじみ感じた(藤本尚則『国師杉浦重剛先生』序)。 ある冬三年生が教室で机をこわし炭俵を積み、床の上で火をたいたことがある。生徒取締はカンカンに怒って校長に訴え、即時退校処分に願います、といった。すると杉浦は、「君らは教室で火をたいたそうであるが、君らも子供ではない。もしあやまったらどんなことになるか、わかりきっているだろう。これからはそんなつまらないことをしてはならん。今度は許してやる」といった。生徒たちは感涙にむせんだ。そいう光景を壁の上の軸が見下ろしていた。それは杉浦の親友河上謹一が自ら揮毫して贈ったもので、「待人寛、持身厳」の六文字が墨痕淋漓と書かれてあった。 小坂が浜口内閣の拓務政務次官となったとき、事務次官は中学同級生小林欣一、そして外務次官吉田茂も一年半ほど在学したことのある同窓生であった。 ※参考図書:小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.89~95 第十三話 育英の名人 ※関連:岩波書店のマーク 2010.03.04 |
10 脇本 楽之軒(わきもとらくしけん)(1883~1963年)
|
鑑賞の立場からいえば、芸術は全く個人的な我れというものを標準として、その芸術的価値を問うわけで、全然他人の容喙をゆるさない。芸術が自己以上を語り得ない如く、鑑賞も自己以上に出で得ない 脇本楽之軒『日本美術随想』 楽之軒はただちに言葉を続けて「耳鑑」を罵る。耳学という語があってつまり耳学問、聞きかじりのあやふやな知識を指すのに対して、我れというものを「標準」とはせず、偽の権威や浮薄な輿論に追随的な、鸚鵡の如き囀りを「耳鑑」と蔑むのであろう。 ――「葡萄の実には葡萄独自の味があり、柿の実には書き独自の味があるわけで、それを佳とするのも、ひとえに自己の味覚の判断に拠るわけで、どうすることも出来ない。人に教えられて柿よりも葡萄を佳として、これを柿以上の嗜好物とすれば、それは耳鑑であって、衷に顧みてうたた恥ずべく、うたた悲しみを覚えざるを得なかろう」。いやむしろ耳鑑を恥じて悲しむ者は、極度に稀少であるのかも知れない。 そして楽之軒は勿論のこと「輿論」なるものを顧みない。――「輿論というも畢竟かかる耳鑑の人達が相寄って作り上げるものらしく、もし計画的に、あらぬ方向に輿論を転換しようとすれば、それもまた不可能ではない。かくの如く観じ来れば芸術に対する世間的評価も、浮雲のようなもので、歯牙にかけるに足りないことがわかる。そうして一世に卓越した評論家が如何に大切であるかかがわかる」。 そこで楽之軒は畏敬の念をもって岡倉天心を想起する。「一世に卓越した評論家は、一世の世間を見ない。彼はただ自家の心眼一つに基づいて言議する。岡倉天心は西洋の批評家が古典主義、浪漫主義、写実主義の分類法を掲げて、芸術を分類し、批評するのを見て、およそ一人の作家でその三つを兼ねないものがあるかといって呵々大笑した」(『東洋の思想』)。可いかな天心の言や。古典、浪漫、写実と指摘して、得々たる輩こそ、また実に多くは耳鑑の人であるから。芸術の世界は生やさしいものではなく、ただ心、心を知る」。 ※引用:谷沢永一『百言百話』(中公新書)昭和60年2月25日発行 P.144~145 2010.03.04 、2019.05.06追加。 |

▼孔子・老子・釈迦『三聖会談』(講談社学術文庫) 「吾未だ行う有ること能わざるも、乃ち願う所は則ち孔子を学ばん」 「わたしがいま考えている仁者の一つの風貌は『論語』にある。「仁者は山を楽しむ」というときの姿ではなかろうかと思う。P.83 *諸橋轍次碩学百歳にして言っている言葉である。
▼『論語の講義』 口耳四寸の学(耳に聞いたことを直ちに口に出す口耳四寸の学) 憲問第十四〔四五〕に「東洋教学の特質」についての『論語』の記述があります。
▼『古典の叡智』(講談社学術文庫) 人生修養の根本義を説く。著者の多年にわたる研究・教育生活の経験から、人間の理想の徳として導き出されたのが、「誠・明・健」の三徳である。その内容と修養法について易しく語る。 孟子は「人は為さざるあり、しかるのちに為すことあり」といっています。私は断じてやらない、そんなことは決してしないぞというがんばりがあってこそ、初めて為すことあり。それがほんとうの有為なる人間だというのです。「為さざるあり。しかるのちに為すことあり」その為さざるありの勇気を実際ほしいと思うのですが、今日の世はその人を求めることはむつかしい。 私見:孟子の言葉は私にはむつかしいと実感しています。どのページを開いても参考になります。ご承知のとおり先生は六十年も中国文学の教育にたずさわれた方であり、『大漢和辞典』の編者であります。
2008.5.15
東洋教学の特質 一口に申しますと、私どもの学んだ東洋の学問はすべて己れというものを主としております。その点は今日の教育方針とまったく同じであります。『論語』のなかにある門人が、君子というものはどんな者かという質問をしたことがある。いうまでもなく君子というものは人間の一番完成した者に与えられる称号であります。その君子は何をするかという質問をした、それについて孔子は何と答えるておるかとというと「己を修む」というたった一言でありました。 それを聞いた子路はちょっと不満に思う。ただ己を修むるだけで君子か。それならだれでもできるじゃないかとの疑いがあったんです。そこで子路は「わずかそれだけですか」と質問いたしました。すると孔子は「人を安んず」とつけ加えました。人を安んずるためには、己を修むることが先決であります。また己を修むるということの終局の目的は人を人を安んじ、人を治むるところまでゆかねばなりません。だから修己と安人は本来一系の思想であります。孔子は人を安んずるといっていますが、後の学者はこれを人を治むと書きかえまして修己治人の四字を定め、これが儒教の一大目標、一大精神であるとしたのであります。要するに儒教の最も尊んでいるのは己であります。P.104 ★プロフィル:諸橋 轍次は、漢字の研究者で大著『大漢和辞典』や『広漢和辞典』の編者。文学博士。東京文理科大学名誉教授。都留短期大学および都留文科大学の初代学長。本人によると直江兼続の子孫である。号は止軒。 同郷の社会学者建部遯吾は従兄にあたる。 三男の諸橋晋六は静嘉堂文庫理事長のほか三菱商事社長・会長も務めた。 2009.01.07 |
12 山本五十六海軍大将(1884~1943年)

一、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かぬ 一、苦しいこともあるだろう。 二、言いたいこともあるだろう。 三 不満なこともあるだろう。 四 腹の立つこともあるだろう。 五 泣きたいこともあるだろう。 これらをじっとこらえていくのが、男の修業である。
山本五十六 百戦百勝も一忍にしかず 連合艦隊司令長官、山本五十六は、男くさい魅力をもったリーダ~である。渾身、気魄に満ちた五十六は、その強烈な個性のゆえに感情の振幅も大きい。 感情の人であり、ときには情愛の人といわれ、茶目っ気もあった。身長百六十センチメートル足らずで躯幹短小、目の玉も躰もきびきびとよく働いた。その五十六が、海軍省の正面階段を大股で、どんどん駆け上っていく姿はまるで堀部安兵衛が高田の馬場へ走りこんでいくような風情であったという。 五十六の家系は、雪深い越後長岡藩四千石牧野家に仕える槍術指南役、儒者として百二十石を食んでいる。その長岡藩に、藩祖牧野忠成(ただなり)が家臣に示した『参州牛久保の壁書』という十七条の蕃訓がある。侍の恥辱というのは、戦場でおくれをとることではなく、その他にも数々あると、忠成は説(いう)。 第一 虚言又は人の中を悪(あ)しく言いなす事。 第二 頭をは(殴)られても、はりても恥辱の事。 第三 座敷にても路地にても慮外(ぶしつけな振舞)の事。 第四 親兄弟の敵をねらわざる事。 第五 堪忍すべき儀を堪忍せず、堪忍すまじき儀を堪忍する事。 ……(以下、略)…… 父祖たちの出自の地、三河国牛久保での草創の頃の苦しさを忘れるな、という藩祖の言葉を、三百年近く愚直に守りつづけてきた藩士の骨の硬さは、越後長岡に地に住みながら、遠い故郷の三河言葉を使いつづけてきたことをみてもわかる。 幕末の風雲のなかで長岡藩は、越後長岡独立、武装中立」を叫び、黒いつなみのように殺到した北陸道鎮撫軍を迎撃。長岡藩軍事総督、河合継之助の下知をうけた五十六の祖父、高野秀右衛門は火縄銃六挺を交互に使って群がり寄せる敵十数人を射殺し、弾丸がつきると敵中に斬込み闘死。父の高野貞吉も銃士隊小隊長として転戦、会津若松城で負傷している。 が、長岡戦争は敗北し、河合継之助戦死のあとを守って長岡藩の総司令官になった二十三歳の若き家老、山本帯刀は降伏勧告を拒んで斬首、山本家は廃絶。明治新政府の「逆賊」河合、山本家への処断は苛烈である。朝敵の汚名が両家から消えるのは、五十六が生まれた明治十七年(一八八四)であった。そして、罪名消滅した山本家を、旧藩主牧野忠篤から望まれて五十六が相続するのは、そのまた遥か後年の大正五年(一九一六)、五十六が海軍少佐のころであった。 五十六はその相続の日を五月十九日、長岡落城の痛恨の日に決めたのも、無念の思いを罩(こ)めたのであろう、この頃から五十六は、無法な官軍をを相手に六砲口に三百六十発元込め式連射機関銃ガトリグガ三門をぶつ放し、死闘を展開した河合継之助に、はげしく心を傾斜させている。継之助が、 《一忍以支百勇(一忍をもって百勇を支えうべし》 と、よく書いたのに倣(なら)って五十六も 《百戦百勝不如一忍(百戦百勝も一忍しかず》 と書いたという。 海軍兵学校に入ったとき教官から、お前の信念は、と訊かれた五十六は、 「痩我慢であります」 と応えている。十八歳のこの五十六のの横顔から、苦汁に満ちた「長岡魂」が泛びあがってくる。作家の山本周五郎が、その作品の中で「自分の傷が痛いから、おれは人の傷の痛さがわかるんだ」といっているが、五十六の身辺には、そうした心の翳(かげ)りががみえる。嬉しいにつけ悲しいにつけ、五十六はよく泣いた。にんげんとしての情が、常人よりもはるかに多量であったのであろう。 五十六が部下に接したとき、喜びをわかちあう場合よりも、悲しみを噛みしめた時のほうに彼の真面目が光を放っている。丹精し手塩にかけて育て上げた海鷲のエース、白相(しらそう)が飛行機事故のために死んだという知らせをうけたとき、五十六は海軍省詰めの記者たちと歓談していた。と、その瞬間五十六は、にわかに大粒の涙をこぼし、手放しで涙を流し、あまりの嘆きに怺(こら)えかね、部厚い唇を結んだまま、涙をしたたらせながら無言で部屋を出ていったという。 また、白相らと三羽烏とうたわれていた南郷少佐の戦死を弔うため、南郷の父を訪ねた五十六は、悔みを述べているうちにこみあげてくる悲しみに堪えなくなり、声をあげて泣き、さらに悲しみをつのらせて号泣し、隋随の者に助けられて南郷家を辞去するという有様であった。 五十六の部下への愛情を伝えるエピソードに、こういうのがある。"赤城"の艦長時代、波荒い飛行甲板に着艦しようとした一機が、目測を誤った。このままでは海中に転落すると思った瞬間、五十六は駆け寄り、その尾翼にしがみついた。が、それくらいで止まる筈はない。「あっ、艦長が!」。叫びをあげて士官や下士官、兵たちは主翼や尾翼に縋りつき転落寸前の飛行機を引き止めた。「山本長官の部下思いは、単なる人情ではなく命がけの迫力を感じました」と、部下であった山口多聞(たもん)中将は語るが、多くの将兵が五十六を「ウチの長官」と称(よ)んで慕ったのは、こういうことからであろう。 もちろん、連合艦隊司令長官としてのリーダーシップを構成しているのはこうした"情"ばかりではない。強烈な行動力、勝負師としての度胸と決断力。大艦主義の海軍のなかで、誰よりも早く、航空主力、戦艦無用論を唱え、飛行機による艦船攻撃の優位性を説いた。それも精鋭主義よりも、 「艦船攻撃は絶対に量だね」 と主張しつづけた五十六の先見性。鬱屈したときなど、ずしりと重い特製の竹刀を掴んで道場に出、越後人特有のせかせかした動きで全身から精気を噴射するよに飛び込み、火をふくような斬撃をくり返している五十六。そんな気魄に将兵たちは魅(ひ)かれていたのであろう。 その五十六の趣味にギャンブルがある。無類の勝負好きの五十六は、暇さえあればルーレット、トランプ、花札、玉突き、麻雀(マージャン)と、あらゆる賭けごとに挑んでいる。これくらいギャンブル好きな男も珍しかった。かつて欧米視察の旅の途中、モナコに立寄った五十六は目の色をかえてカジノで遊び、連戦連勝、勝ちに勝ちまくり、あまりの勝負運の強さに、「カジノへの入場を拒否された"世界で二人目のの男"の記録をつくった」 という風評がたった。その噂が五十六の生涯の自慢であった。 「若い士官はブリッジ(トランプ)をやれ、賭けごとに打ち込むと、先が見えるようになる」 そう言って五十六は、つねに「勝負ごとの三徳」を若い士官たちに語っている。 一 賭けごとは勝敗の有無にかかわらず、冷静にモノを判断する修練ができる。 一 機を狙って相手を撃破する修練ができる。 一 大胆にして細心、その習慣を身につけることができる。 「但し、私欲をはさんではいかぬ。熱中してはいかぬ。冷静に局面を観察していれば、かならず勝つ機会がわかる。それを辛抱して待つのだ」 疾風迅雷ともいわれる山本作戦の起爆薬になり、その行動の炸薬(さくやく)になったのは、こうした五十六独特のギャンブル哲学であったのかもしれない。 ※神坂次郎『男このことば』(新潮文庫)P.71~76。 参考1:小林虎三郎 参考2:第26、27代連合艦隊司令長官。海軍兵学校32期生。最終階級は元帥海軍大将。栄典は正三位大勲位功一級。1943年に前線視察の際、ブーゲンビル島上空で戦死。旧姓は高野。 戦死された時、私は中学4年生であった。全国民が悲しみに包まれれていた記憶が鮮明に残っている。 2016.01.07 |
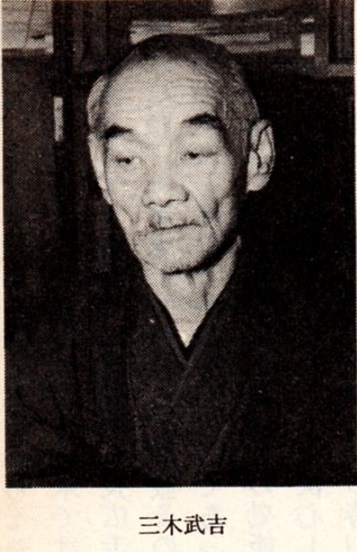
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.139~143 三木 武吉 山県家門前で毎晩演説ぶつ 京都同志社にはいりながら、キリスト教の信仰にはいらなかった徳富蘇峰も、創立者新島襄の人格に魅了され、終生師と仰いだ。新島は明治二十三年四十八歳の若さで世を去った。このとき二十八歳であった蘇峰には、昭和三十二年に永眠するまで、なお六十七年の人生があったわけだが、遺言によって京都若王寺三頭の新島の墓石のかたわらに自分の分骨の墓を建てさせたほどであるから、その敬慕の念がいかに深かったかを思わせるのである。ひとり蘇峰だけではなく、新島の死後もその遺風を慕う青年は全国から集まったというが、その中にうどん食い逃げ事件で高松中学から退校処分をうけた十七歳の三木武吉がいた。 退校させられて郷里を出る前に、武吉は易者に見てもらうと、後年有名になっ三白眼たを注視した易者は、 「この目をもっているいる者は天下をねらうものだと古来いい伝えられている。豊臣秀吉も由比正雪もこの双瞳だ。楚の項羽もこれだったと物の本に書いてある。お前は出世するぞ」 と激励した。このあと、同志社中学部の編入試験をうけるまで大阪の親戚のうちにあずけられた。武吉は勉強にあきると市内を歩きまわり、道頓堀の芝居や見世物小屋では、絵看板だけ見て中にはいらなかった。腹がへると、すうどんを食った。 「二銭だったナ。そのときの念願は、一杯五銭のしっぽくを腹いっぱい食うことだった。出世したら、これを食ってやろうと思ったことだ」とは彼の述懐である。 二年の編入試験をうけ、合格して入学してみると、五年生に永井柳太郎という暴れん坊の旗頭がいる。眉目秀麗の長身、剣道は免許皆伝と呼号し、とりすましているところが三木にはカチンときた。ある日、永井は級友・下級生たちにとりかこまれているとき、 「僕はようやく無我の境に達することができた」と自慢しはじめた。いきなりきりつけられても、間髪をいれず身をかわせる。ぼんやりしているようでじつはしからず、八方に構えがある。「これが無我の境地というものだ」、といい気になっていると、 「それは無我の境地とはいえない。有我の境というものだ」と水をさしたものがいる。二年生の三木だ。永井と三木はさっそく口論をはじめたが、そのうち三木は脳貧血でよろめいた。医者にみてもらうと、ひどい胃弱症にかかっているので、長期間の療養が必要だ、という。口論がきっかけで仲よしとなった永井も、からだをつくり直して再起を期すべきだ、という。三木もついに涙をのんで休学帰国を決意した。彼の同志社時代はこうしてわずか数ヵ月でおわる。 翌年六月、胃弱を直して三木は東京に向った。有名な政客星亨の法律事務所で書生にやとわれることになっていたのでる。ところが明日から事務所に住みこむという日、星は東京市会議事堂で伊庭想太郎に斬殺され、このため武吉の運命もまた大きな余波をうけることとなった。※明治三十四年(一九〇一年)六月二日午三3時過ぎ斬殺された。 彼は神田の駄菓子屋の二階三畳を一月一円の部屋代で借り、昼は大成中学に通い、夜は製本屋で働いた。五時間働けば十銭になる。一ぜんめし屋は一食四銭であったから、一日二食はどうにか食えるという計算であった。すると父の知人である郷士出身実業家中野武英(なかの ぶえい:東京商業会議所会頭)が早稲田にある東京専門学校の学監高田早苗に紹介状を書いてくれ、その縁故で早稲田の学生となることができた。喜んだ郷里の父は、毎月八円の郵便為替を送ってくれるようになり、武吉はようやく愁眉(しゅうび)を開いた。灰色の苦学生とも別れて、人なみに青春を味わえるようになった彼は、まず野球に関心をもった。当時は学習院、一高が野球界の王座についていた。 「学習院や一高が、国の費用で勉強しているくせに、一段偉いような顔をしているのはけしからん。野球でも、やつらの鼻をたたきおるんだ」 と、武吉は五歳年長の学友橋戸信(はしど しん/まこと:文献により一定していない:頑鉄)をたきつけて野球部をつくらせた。橋戸は選手生活をへて野球評論家として世に知られる存在となるが、三木の方は、「彼の将棋におけると同じように、腕前よりはヤジの方がすぐれていた。舌戦というところだ。だから自然ヤジの方にまわることになり、応援団の方に力を入れることになったんだ」と永井は語っている。後年のヤジ将軍は、まず早稲田の森の応援からそのキャリアをはじめたことになる。 だが、単なるヤジで満足できる三木ではなかった。アメリカきっての雄弁家といわれるブライアンが来日して大講堂で二時間余も長広舌をふるったことがある。ぎっしりと場内を満たした七百の学生は、セキとして声なく、静寂そのもので聞き入ったが武吉もその一人であった。はっきりわかったことばは十か二十くらいであったが、なんとなく論述の趣旨はのみこめた。彼は、語学の境界をこえて意思を伝える雄弁の効能に打たれ、自分も魂のはいった弁舌、ことば以上に魂のこもった弁舌のけいこをしようと決心した。 川をへだてた目白には、山県有朋の椿山荘があった。夕食をすませて夜になると、武吉は椿山荘まで散歩に出かけ、豪勢な大みょう門の前にたつと、藩閥政治の非をたたく演説をはじめる。請願巡査が出てきてとがめると、 「天下の公道で演説するのがなぜいかんのだ」と逆ネジをくらわせた。議論となると、巡査は法律学生がニガ手だ。だが、腕ずくでも止めさせることはできたであろうに、それをしなかったのは、武吉の演説が面白く、内心では(その通り!)と拍手していたためかもしれない。追っぱろうとして苦心しているふりはするが、本気でとめようとはしないのである。三木は、表門からだけでは効果がうすいとさとると、横手にまわり、さらに裏口にまわってガナリ立てた。山県は三十二年九月に立憲政友会総裁伊藤博文に内閣をゆずって以来、表面に出ていないが、長閥、陸軍を背景とし、宮中、府中に隠然たる勢力をもつ公爵である。その山県と対決する意気ごみであるから、三木としても政治、政策について真剣に勉強し、それを十分にたたきこんで原稿なしでしゃべりまくった。ある夜、寺内正毅(陸軍大将、のち首相)が訪問していてこの演説をきき、「うむ、狂人か。面白いぞ。狂人でもなかなかスジの通ったことをいうわい」と感心したらしい。しかし毎晩やられる山県の方はカンカンに怒りだし、岡部半蔵伝来の槍術で一刺しとばかり長押(なげし)の長槍に手をかけたこともあったという。 権威にいどむ青春の狂熱とはいえ、山県邸にほえ立てる三木青年の姿は、ヘルメットにふくめん、角材をもち、徒党を組まなければ交渉の場にも出られないような、現代の一部学生よりよっぽど男らしいというべきでないか。 2019.08.05 |
14 長谷川 伸(本名・伸二郎)(1884~1963年)
|
▼「瞼の母」 一 逢いたくなったら俺あ、眼をつぶろうよ。 嘉永元年の春、若き博徒、金町の半次郎は下総の飯岡の親分を襲撃したあと母と妹のいる武蔵国南葛飾郡の実家に逃れていた。そこへ飯岡の子分、突き膝の喜八と宮の七五郎が敵討ちにやってくる。半次郎を気にかけ、後を追ってきた旅の博徒番場の忠太郎が二人を斬り倒す。常陸の叔父のもとへ旅立つ半次郎に忠太郎は堅気になれと見送り、自身は生き別れた母を捜しに江戸へ向かう。江戸では息子と生き別れたという三味線弾きの老婆と出会うが人違いだった。忠太郎は母親を背負って歩く男とすれ違い、うらやましく思う。 嘉永二年の秋、柳橋の料理茶屋「水熊」の前では無頼漢、素盲の金五郎が後家のおかみの婿に入って「水熊」を乗っ取ろうとたくらんでいた。店から元夜鷹の老婆おとらが叩きだされるのを見た忠太郎は声をかけ、店のおかみが江州に子を置いてきたと聞き出す。 「水熊」のおかみおはまの居間では娘のお登世が着物を着替え客の前に出て行くところ。店のおかみに会いたがる男と板前が喧嘩している声がおはまの耳に入る。強情な男を追い出してやろうとおはまは男を部屋に入れる。おはまと対面した忠太郎は、江州阪田郡、醒が井の磨針峠(すりはりとうげ)の宿場、番場のおきなが屋忠兵衛という旅籠屋について尋ねる。おはまはそこへ嫁いでいたこと、息子の忠太郎が五つの時に家を出たことを認めるが、息子は九つで死んだと言ってきかない。金目当てだと疑うおはまに、忠太郎はもし母親が困窮していた時のために貯めていたという金百両を胴巻から出すが、おはまの冷たい態度は変わらない。忠太郎は落胆して店を去る。すれ違いにおはまの元へ戻ってきたお登世はおはまを説得、おはまは娘可愛さに邪険にしたことを後悔して泣き出す。素盲の金五郎が恩を売るため浪人の鳥羽田要助と忠太郎を追ったと聞いたおはまとお登世は駕籠で追いかける。夜明けの荒川堤、忠太郎は鳥羽田に襲撃されるが斬り倒す。おはまとお登世が忠太郎の名を呼び探すが忠太郎は返事をしない。二人があきらめて去ったあと忠太郎は反対方向に歩き出す。「俺あ、こう上下の瞼を合せ、じいッと考えてりゃあ、逢わねえ昔のおッかさんのおもかげが出てくるんだ――それでいいんだ。逢いたくなったら俺あ、眼をつぶろうよ。」忍び寄ってきた金五郎を斬り倒し、忠太郎は再び旅に出る。「インターネットによる」 |
15 阿部真之助 (1884~1964年)

新聞社の平均的読者像ということ 阿部真之助氏の教え さて、平均的読者像ということですが、この問題に私が初めてふれたのは、いまから三十何年か前のことです。当時私は東大新聞の学生でありました。花森安治、田宮虎彦、岡倉古士郎、杉浦民平君などといっしょにつくっていた。 ▼そのころ、年に何回か学外から名士を呼んで勉強会をした。ある年、講師に阿部真之助氏をお招きした。阿部さんは当時東京日日新聞(毎日新聞の前身)の学芸部長でした。大宅壮一、高田保、木村毅という三人の方を嘱託として抱え、名学芸部長をうたわれていた。さて政界や文壇のお話を聞き、阿部さんが何か質問は? という。一人の学生が質問した。
そしたら、阿部さんはふふんと笑って、 「そうだね、小学校六年卒の読み書き能力プラス人生経験十年というところかね」 これには、私たちは、あっとおどろいた。もっともっと高いと思っていた。つづいて第二問。
――それじゃ、ついでにお聞きしますけど、読売新聞はどうですか?
――朝日新聞は?
▼この゛中学一年中退というのが、いかにも阿部さんらしくって、いまでも私の記憶に残っている。しかし、とにかく、私たちは三大新聞とも意外に腰ダメが低いのにガクゼンとした。 しかし、阿部さんの腰ダメは、実に正しいのですね。なぜなら当時、昭和七、八年のそのころの教育の普及度をあとで調べてみると、義務教育を受けて、中学、もしくは女学校に行くのは、一八%なんですね。当時朝日、毎日、読売三社とも、おそらく発行部数は百五十万から二百万ぐらいじゃなかったか。とすると、それくらいの大部数を維持していくには、平均的読者の水準は、ちょうどこの辺のところとなる。後年ジャーナリズムの世界にはいってから私はあらためて、このことばの真実さをつくづく感じたものでありました。 "人生経験十年の読解力" さて、この"阿部方式"についてわからぬところが一つある。"人生経験十年の読解力"という点です。一人の学生がその点についてたずねた。すると阿部さん、にやっと笑って、 「うん、君たちはどこへ飲みに行く」
――そうですね、われわれはだいたい上野かいわいです。あのへんのカフェーか、飲み屋です。
「君たちが行きつけのカフェーに、一か月ぶりぐらいに行く。すると女給君は、まあしばらくね、とかなんとかいう。飲んでいるうち、テキは、「ほんとうにこの人にくいわ」とかなんとかいって、君たちのひじをキュッとつねったとする。その場合、この女給さんの゛にくい゛ということばをどううけとるか? 君は彼女から憎悪されているとは、まさか思うまい。ささやかながら君たちの経て来た人生経験は、これは、女のコビまたは愛情の一種の表現と受けとるだろう。こういうのを人生経験十年の読解力という」 実に明快な(笑)説明をされたものであります。(笑)。 ▼しかし、考えてみると、このことばは、非常に深味のあることばだと私は思う。深川に工場を持っている中小企業の社長さんがいるとする、年齢は五十五、六である。彼は事情があって小学校は四年までしか行けなかった。しかし、一生懸命に努力奮闘したかいあって、今日では資本金何億かの二部上場の社長さんになっている。彼はよくムジュンということばを使う。『君はムジュンしていますよ』とか『その件はどうもムジュンしていただけない』とか上手に、正確にムジュンということばを使いこなしている。 これはご承知のように、昔、中国の楚の国に盾と矛をつくる武具師がいた。ある時、自慢をして、私のつくったホコなら、いかなるタテをも突き破ることができる。同時にまた、私のつくったタテならば、いかなるホコをもこれを防ぐことができるといった。すると、そばで聞いていた人が、それじゃおまえのつくった矛で、お前のつくった盾を突いたならば、どうなるかと聞かれて、返事に窮した。シドロモドロになったという故事から来ている。中小企業の工場主であるこの社長さんはもちろん、そんな故事を知らない。またムジュンという字は矛盾と書くなんてことも知らない。しかし、彼の経てきた人生経験はムジュンということばが、どういうことを意味するのか、また、どういう場合に使うかを正確に教えている。こういうのをまた゛経験こそわが師゛というのでしょう。 *扇谷正造『経験こそわが師』P.253~より引用。この本は、昭和46年初版発行されている。昭和22年、6.3.3.4制になっている。本文は昭和16年以前に書かれているので、学校教育は旧制度であった。
参考:こしだめ 【腰だめ】 (1)銃を腰の辺りに当てて、大まかな見当で撃つこと。 (2)準備や計画が十分整わない状態で、物事を始めること。 私見:外来語が満ち溢れて、その部数は、ある新聞社では1000万近くなっている現在の記事は平均的読者像はどうなのかうかがってみたいものです。 ★プロフィル:明治から昭和にかけて活躍したジャーナリスト、政治評論家、随筆家。 2012.06.17。 |
16 杉浦重剛 (1885~1924年)

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.159~163 明治三年、政府は各藩に命じて貢進生を選ばせ、学力品行ともに抜群の秀才三百人が大学南校に入学した。大学南校は明治二年にでき五年に第一番中学、六年に開成学校、七年に東京開成学校、十年に東京大学となるが、九年に学生たちが「有名三幅対」として、仲間の中からベストスリーを選んだことがある。 「算数家」としては仙石貢、増田礼作、木場貞長があがった。「書家」としては、河上謹一、高橋健三、内田三省が選ばれた。「遠足好き(ただし無銭)」は増田六一郎、仙石貢、杉浦重剛であり、「貧乏」には杉浦重剛、宮崎道正、磯野徳三郎のながあった。この他「入浴ぎらい」、「放屁家」、「慷慨家」、「漢学家」、「短」、「詩好き」、「近世史好き」、「植物好き」、「芝居ぎらい」等いくつもの部門があった中で、総合得点のトップに立ったのは杉浦重剛であり、河上謹一(のち住友理事)、仙石貢(のち満鉄総裁)がこれにつづいた。 杉浦は琵琶湖畔の膳所(ぜぜ)藩から選ばれた貢進生である。梅が好きで、長女に梅路(夭折)、二女に梅子というなをつけたほか、雅号を梅窓とした。この他、天台道士、破扇子、鬼哭子、礫川、無了居士、安政居士などの号も用いた。このうち天台道士がもっとも世に知られたが、謹一の息子河上弘一が「杉浦先生は少壮の頃より夙に高士の風があったので「杉浦はまるで天台の道士のようだ》と言った父の言葉をそのまま先生がうけ納れて一生《天台道士》と号して通されました」(藤本尚則『国師杉浦重剛先生』序)というように、親友河上謹一の命名によるものであった。杉浦の郷里は比叡山に近く、ここは天台宗の開祖最澄・伝教大師が延暦寺を建て、その本拠としたので天台山の異称がある。杉浦は十六、七歳のころ、すでに山僧の風格をもっていたということであろう。 天台道士は、四年の廃藩置県で貢進生制度がなくなり、県費生となったが、これまた五年にやんだので、借金して学問をつづけ、給費制度ができたので、「貧窮願」を出して給費生となっていた。しかし、ふところは寂しくても学問はよくできて、「幅対」金メダルの投票数をあつめたこの年、海外留学生にも選ばれた。この制度は八年からで、第一回は小村寿太郎、鳩山和夫、斎藤修一郎、古市公威、長谷川芳之助、松井直吉、原口要、安東清人、菊地武夫、平井晴二郎、南部救吾の十一人、九年の第二回は杉浦重剛、穂積陳重、沖野忠雄、関屋清景、増田礼作、岡村輝彦、山口半六、桜井錠二、谷口直貞、向坂兌(さぎさか なおし)の十人で、それぞれ専門で一流人となり、歴史になをとどめたが、このうち杉浦の専門は化学であった。 はじめはロンドンにおり、ここは日本人がたくさんいるので、英語を学ぶには日本人のいないところをというわけで、マンチェスターのオーエンスカレッジに学んだ。このときの恩師ロスコ―博士の自叙伝には、「杉浦という男は非常に勝気な性質でつねに首席であったが、あるときの試験に二番に落ちたのを憤り、余のもとを去った」と書かれた(大町桂月、猪狩史山共著『杉浦重剛先生』)。 十三年二十六歳で帰国。このあとの職歴をたどると、同年東京大学理学部博物場掛取締、十四年文部省准奏任御用掛、十五年東京大学予備門(のち一高)長、十八年辞職、二十一年文部省参事官兼専門学務局次長、二十三年六月依願免官、同七月衆議院議員当選。洋行帰りの希少価値で、出世街道をまっしぐらというふうに見えるけれども、じつはこの前後から、天道道士らしい本領が発揮されるのである。 彼は議員たちの腐敗に我慢ができず、病気を理由に辞職した。このあと、松方内閣のとき文部次官をことわり、また芳川顕正文相時代、「称好塾」頭として、じつに多くの人材を育てたのである(これは後述)。その門弟の一人が古島一雄で、もっとも尊敬する四人として、三浦梧楼(観樹)、杉浦重剛(天台道士)、犬飼毅(木堂)、頭山満(立雲)をあげ、四人の寸評を求められて「直言断行は観樹也、立言断行は木堂也。聖言躬行は天台也。不言実行は立雲也」と書いた。この四人の間で、おたがいに深く尊敬しあったのは杉浦と頭山で、頭山は「杉浦のすることなら、なんでもヨカ」と無条件で賛成した。 「決して人の悪口をいわない人」天台道士には無数の逸話があるが、自分の貧乏をよそに、親友小村寿太郎を高利貸しから救った話は光っている。名外交官小村は、父の事業の失敗で巨額の負債に苦しんでいた。これを見かねた天台道士は、学友数人の連帯保証で救おうと思い、まず河上謹一をたずね、そのことわりをいった。河上はかねて連帯保証の危険を説いていたからである。河上は、「それは結構なことじゃ、僕も一口加入する」といい、長谷川芳之助、高橋健三、菊地武夫なども加わって、一人一月十円掛けで七口、数年かけつづけて小村の急を救った。やがて河上は杉浦に「君も貧乏の中からもう三年もつづけたのだから、あとはオレが引きうける」といい、結局、河上、菊地でかたをつけたのである。 杉浦はあまり丈夫でなく神経衰弱が持病で、二十五歳のとき一年間、四十五歳のとき四ヵ月間、四十八歳から五十五歳まで八年間病臥(びょうが)したことがある。この最後の八年間でほとんど世に忘れられ『万朝報』には「故杉浦先生云々」の記事が出た。一方、急迫の度も加わって文字通り柱は傾き、屋根は破れ、寝ていて青天井が見えた。彼は職人をよんで新聞紙を三、四枚張らせ、その上にコールタールを塗らせた。米屋は、米代がたまったので米をもってこなくなった。ある人は見かねて、すでに侯爵となっている小村寿太郎に助力を求められたら、とすすめると、 「小村はいやしくも国家の柱石をもって自らを任ずる男である。それにたいしてわが一家の私事をもって心配をかけてはならぬ。のみならず、かつて小村の貧窮時代、自分は彼を援助したことがあるから、その小村にたいして無心をいうのは、彼に当時の報償を求めるような観がする。断じていかん」 と承知しなかった。數多い知人、門弟で彼のことを思うものがなかったとき、頭山満から五百円がとどいた。「頭山氏天野氏を使いとして五百金を贈らる。我深く頭山氏の厚誼に感ず」と彼は日記に誌(しる)した。 病気は四十二年に全快。そして、ほとんど彼の存在を忘れていた性急にして薄情な世間が、あっとおどろくことが起きた。大正三年、東宮(皇太子)御学問所ができ、帝王学の根幹となるべき倫理ご進講の大役が彼に課せられたからである。一部では「博士でもないのに」と首を傾けるものもいたというが、笑止千万とはこのことであろう。
東京大学予備門長、日本中学校長、東宮御学問所御用掛を歴任した国粋論者で教育家の杉浦重剛(1855-1924)が側近に語った談話録。帯封から。 ※杉浦重剛氏は大正天皇が皇太子のとき、御進講の大任に当っている。大正天皇の皇孫:明仁天皇退任の日。写す。 ※参考図書:小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.89~95 第十三話 育英の名人 2019.04.30。 |
17田辺 元 (1885~1962)
|
私は道元の思弁の深さ綿密さに打たれて、日本人の思索能力に対する自信を鼓吹せられた。私は道元に対する感激と驚嘆とを広く世に伝えることを以って自分の義務であると感ずる 田辺 元 参考:田里亦無『道元禅入門』(産能大学出版部刊)より知った。田里亦無は1993年4月ご逝去。 日本の哲学者。旧字体で表記した場合は田邊 元となる。西田幾多郎とともに京都学派を代表する思想家。元京都大学教授、京都大学名誉教授。1947年帝国学士院会員、1950年文化勲章受章。 |
18出光 佐三(さぞう) (1885~1981年)
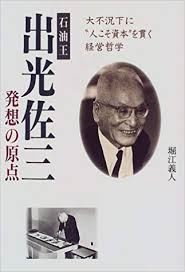
「出光興産社長 出光佐三 の七つの奴隷解放宣言」 堀江義人著『石油王 出光佐三 の発想の原点』(三心堂出版社) p235~ 「人間尊重」を旗じるしに 一、黄金の奴隷になるな 一、学問の奴隷になるな 一、組織・機構の奴隷になるな 一、権力の奴隷になるな 一、数・理論の奴隷になるな 一、主義の奴隷になるな 一、モラルの奴隷になるな これらはすべて、「人間尊重」「大家族主義」「独立自治」など、創業以来の主義・方針が、そのときどきの時代環境のなかで、自戒のことばとして生んだものである。 〝黄金の奴隷〃にならないこと、〝学問の奴隷〃にならないことは、すでに神戸高商時代に自戒していた。 「出光がつぶれるなら世間がまちがっている」佐三には、自分の「人間尊重」のための戦いの歴史をふり返ったとき、こういい切れるだけの自信があった。 「自分が死んだくらいでは出光は変わらない。変わらない出光がつぶれ季となどあり得ない」「人間尊重」は、だれもが納得する普遍的な真理だからである。 自分が死んだら出光はどうなるかと新聞記者たちに聞かれたとき、佐三はこう答えた。 「出光の支店長や主任が口やかましくいって指導しているか、黙って身をもって率いているか調べてみたまえ。みんなが身をもって仕事をし、若い社員がそれに共鳴してついていっていることがわかるはずだ。私が死んだって変わりはせんよ」と聞いた記者は、本当に出光の支店や出張所のあり方を調べたらしく、その後は「佐三が死んだら……」などとは聞かなくなったと語っている。 「人間がしっかりしていれば、なにものをも恐れることはない」 そのしっかりした人間が見すえなければならないのは、「人間尊重」という理想の実現にいたる道である。 「大所高所に飛躍してものを考えよ。近視眼的にならず、遠く先を見よ。一部にとらわれず、全体を達観せよ」 仙厓の画軸『橋流れて水流れず』を示しながら、大局を悟り、現代を超越して社会に示唆を与えなければならないと佐三が社員に訓示したのは、昭和二十二年一月のことであった。 流れないはずの橋はいずれ朽ち果てるが、流れ失せるはずの水は海にそそいで雲となり、雨となり、また川にそそぐことで永久に存在する。動のなかに静を見、静のなかに動を見ることの大切さ。 「われわれは自信たっぷりに、流れざる水の力を信じ、これを利用すべきである。眼前の水にとらわれてはいけない」と。 平成二十五年五月十八日 |
19大杉 栄(1885~1923年)

諸君の芸術は老人の芸術である。われわれがわれわれの晩年にわれわれの任務を果たし、われわれの共同行為の義務をつくした後に、公平無私の芸術や、ゲーテの晴朗や、純粋の美を望むのは、善いことでもあり、自然のことでもある。それは人生の旅の至上の理想でであり究竟である。しかし、そこへ行くだけの功績もなしに、あまりに早くそこに到達する人や民族は、悲しむべきものである。それらの人々やそれらの民族には、その晴朗は、無感覚すなわち死の前兆に過ぎない。(新しき世界のための新しき芸術) この日(9月16日)この日、関東大震災の混乱中、甘粕大尉に虐殺された無政府主義者。労働者の自主的運動を激励し、ボルシェヴィキとの共同戦線をとく。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.154 |
20野上 弥生子(1885~1985年)
|
▼『随筆 一隅の記』新潮社 昭和五十三年四月十五日 夏目先生の思い出ーー漱石生誕百年記念講演ーー 先生がお亡くなりになったということを聞いて、そのころ住まっておりました染井から、早稲田の南町のお宅まで、夢中でかけつけた時から、もう五十年経ってしまつたのかと思いますと、いまさらに”往時茫々として夢に似たり”ということばが思い出されます。(中略) 夏目先生は、修善寺での大患のあと、ひとつの転機を迎えたようにいわれております。それで、修善寺の達磨山にございます詩のこころが、先生の新しい心境のごとくにも解釈されます。「仰臥の人唖の如し、黙黙として大空(だいくう)に対す、大空雲動かず、終日遥として相同じ」〈仰臥人如唖 黙黙対大空 大空雲不動 終日遥相同〉しかし、先生が戦後まで生きていらして、こういう気持ち、ただ悠然と地上の転変に対していらっしゃったでしょうか。また、「天に則(のつと)って私を去る」(則天去私)は先生の到達した哲学であり、新しい悟りだとも申されているようでございます。P.109 補足:1:夏目漱石の門下生上野豊一郎野と結婚。2:夏目漱石(1867~1916年) 2008.6.5
あらすじ 利休(千宗易)は堺の商家の出で、若いときから茶の湯を学んで秀でており、四十代のころ信長に仕え、その茶頭として重用された。信長が本能寺の変で亡くなった後は、秀吉の茶頭を務めることになる。秀吉はほぼ十歳下であった。 利休は秀吉の依頼で幾つもの茶室を建てていく。一切の余分なものを取り払った簡素な二畳の茶室、待庵。意表をつく組み立て式の黄金の茶室。 また秀吉のために聚楽第で多くの茶会を行い、茶の湯の指導をする師弟関係が築かれていくが、一方政治に関しても意見を言い、相談に乗るような間柄であった。 利休の一の弟子、山上宗二は秀吉と対立して、北条氏に身を寄せていたが、秀吉の小田原討伐の際に、密かに抜けてきて師の利休のもとを訪れる。利休のとりなしで秀吉に面会するが、宗二は秀吉の怒りを買い、その場で惨殺されてしまう。 秀吉に重用される利休には敵も多かった。あるとき利休が宴席でふと漏らした「唐御陣が明智討ちのようにいけばでしょうが」の言葉を、日ごろ利休の存在を快く思っていなかった石田光成は、朝鮮出兵に反対する傲慢な意見として、これを咎めだての材料にと考える。 大徳寺(臨済宗大徳寺派大本山)三門に、親友の僧、古渓(大徳寺住持)、の発案で利休像を置いたことも、不遜であると非難された。 楼門修復に利休が尽力し、資金を寄付したので、寺側の謝意の木像だったのだが、怒った秀吉は利休に堺での蟄居を言い渡す。秀吉に侘びを入れて、復帰する機会を無視する利休に、秀吉は苛立ち、遂に切腹を申し付ける。利休の首は獄門にかけられて市中に晒され、木像も引き降ろされて磔刑となった。 多重視点の、かなり重い文体である。内容も重たい話なので、決して読みやすい作品ではないが、いろいろなことを考えさせられるという点で、深いものを持っている。 通常多重視点を使って書くと、読者には異なった人物の目が与えられて、そこから作品世界を見られるので読みやすくなるものであるが、この作品は逆に登場人物の複雑な心理が、多くの歴史的事象と絡み合って、心理描写が錯綜し、屈折し、読み進む上で非常に努力を強いられる。 利休、秀吉の二大主要人物の他に、石田三成、古渓和尚、秀吉の弟秀長、大政所、北政所、山上宗二、利休の妻りき、紀三郎、ちか、など多くの登場人物(創作人物を含む)があり、作者の筆はどの人にも万遍なく愛情が注がれていて、おろそかでなく非常に丁寧である。 そこには手抜きもなければ省略もない。せっかく登場させるからには、という訳だろうか、できうる限りの目配りと配慮で、どの人物も最大限に作品中に生かされ続けようとする。 そのため膨大な資料を駆使し、エピソード満載ということになってしまい、結局作品はこの分量を抱え込んで、膨張し続けていったのだろう。おそらくは作者としては割愛するに忍びない個々の愛着ある場面を、網羅していった結果であると思われる。 印象的な場面は幾つもあるが、とりわけ利休一の弟子であった山上宗二が、秀吉の怒りを買って、見せしめのようにむごい殺され方をする場面は衝撃的である。それは作品中に重苦しい伏線となっており、利休の心に不吉な影を落とし、やがて最後の切腹の場面へと繋がっていく。読み手の心の中にも不安な予感、恐怖感を共有させていく、効果的で巧みな構成であると思う。 利休の死の原因には諸説あって、自分の木像を三門に置いた不遜行為がよくいわれるが、朝鮮出兵に反対したからという説、茶頭としての慢心説、娘を側室に差し出さなかったからという説、茶席である人物の毒殺を命じられたが断ったからという説や、秀吉に対する毒殺未遂説まであるそうだ。 その死の真相が分からず、いろいろな説が出るのも、秀吉に信頼が厚かった側近の突然の切腹、木像の磔刑という処罰の形があまりにも異常であったからだろう。 今東光の小説「お吟さま」では側室説が採用されている。利休の娘が秀吉の側室にと望まれたが、利休がそれを拒否したことによる悲劇、というある意味では分かりやすい話になっていて、物語はまた別の様相を帯びている。 利休は二度結婚していて、先妻の娘は三人あったようだが、当時の彼女たちの年齢をみてみると、皆若くはなく既婚で子もあり、そのうちの一人(末娘)は寡婦であったそうだ。 「秀吉と利休」では、利休の娘の側室の話は一切絡まない。そういう話とはまた別の、違う角度から試みた作品なのである。 秀吉は、機を見るに敏ではあったが、成り上がり者で、真の芸術など何一つ解さない現実的な絶対権力者として描かれる。 それに対して、利休は内心で反発しながらも恭順の姿勢をとり、茶道を深化させる一方で、冷静に時代を眺める目を併せ持った知的人物として描かれている。 主点は利休の心の描写にあり、いってみれば心の底で軽蔑している相手に、日々屈服しつつ生きていかなければならなかった一人の人間の、苦衷の内面が、豊富なエピソードとともに綴られていくのである。 トラブルが起きる晩年までは、利休はうまく時流に乗って、生き抜いていくしたたかさも持っていたようで、そのことも作品中に織り込まれている。そして秀吉と利休の対立、というテーマは、この作品では、政治家と芸術家の相克、対立という構図で捉えられている。 作品ではさまざまに揺れ動くその心理的葛藤が中心に据えられている。石田三成ら、側近の嫉妬や反発や策謀に翻弄された結果、自らの矜持ゆえに悲劇的な死を選び取っていく、という経緯が「唐御陣……」の言葉が発端となったという作者の創作で、具体的に説明され、気を許してうっかり吐いた言葉が独り歩きをしていく恐ろしさが如実に描かれる。 秀吉に頭を下げ、非を認め、皆の前で謝罪さえすれば、また元の茶頭に復帰できるとわかっているのに、最後までそれをしなかった利休の意地というか、誇りの高さが、秀吉の中の強固な意地と正面からぶつかり、潰れていくさまは、むしろ淡々とした調子で描写されている。 利休があくまで自己を貫くのなら、もうその先に予想されるものは宗二と同じ死しかなかったはずであったからだろう……。 利休の家は豪商ではなかったが、堺で魚、海産物を扱う中程度の商家であった。 信長が堺を制圧しようとした折、堺の人々は初め結束して信長に抵抗しようとしたらしい。それが話し合いで決着していったのは、双方のさまざまな利害関係によるものであった。 茶の湯をたしなむ堺の裕福な貿易商人でもあった今井宗久、津田宗及たちは、宗易(利休)とともに、信長に茶頭として召抱えられていく。 信長は仕舞、小鼓をよくし、茶の湯にも通暁し、その膝下で茶頭を務めていた彼らは、信任されて次第に高い地位を得ていった。派手好みの信長は、安土城内に黄金ずくめの茶室を作らせもした。 茶の湯は当時の武士のたしなみであったが、単なる文化的な趣味の範囲を超え、小さな密室である茶席では、武器弾薬を扱う堺の貿易商人たちとの商談が行われ、さまざまな軍事、政治の情報交換の場としての意味も合わせ持つようになっていった。茶道政治といわれる所以である。 信長は大みょうたちを集めて盛んに茶会を開き、その一方では、茶道具を収集することにも熱心で、戦乱で散逸していた天下の名器といわれる室町時代の茶道具類を買い取って手元に置き、褒賞として家臣に与えることもした。このような茶道の隆盛につれ、武将たちは信長に倣って茶会を開くことを望み、優れた茶器を手に入れたがったが、信長は並みの武将には茶会を開くことを許さなかったという。 本能寺での信長の横死後、信長に仕えていた茶頭たちは、そのまま引き続き秀吉に仕えることになった。信長の茶の湯による政治的文化政策はもうしっかり根付いていて、それを切り離したり否定したりすることは、最早できなかったのだろう。 信長が生きていた頃、利休のほうが秀吉よりも身分は上であった。本能寺の後、秀吉の時代になったが、天下人の秀吉といえども、茶の湯の世界では、利休が師匠であり、秀吉は弟子の立場である。その辺りは、秀吉は複雑な心境であったかもしれない。 利休はじめ宗久や宗二など、信長に仕えた茶頭たちは、二人の主君を比較し、皆口には出さなかったが、内心できっとその差を絶えず思ったに違いない。性格的には恐ろしい面を持つカリスマ君主ではあったろうが、どこか洗練された鋭い感覚の持ち主であった信長、そういう信長の茶の湯に対し、秀吉のそれはおそらくはかなり劣るものであったことは充分想像できる。 秀吉は信長のようになりたかったかもしれない。信長がしたように自分も大坂城に黄金の茶室を作らせ、人々を驚嘆させた。得意だったことだろう。黄金の茶室を組み立て式にし、持ち運び可能としたのは秀吉の新しいアイデアだったろうが、金の茶室という思い切った発想自体は、本来信長のものであった。 秀吉はまた信長のように能も稽古した。けれども能も茶の湯もうわべには真似できても、なぞれることには限界があり、真の上達に至るにはほど遠いものがあったろう。秀吉は信長という理想のモデルに自分を近づけようとし、単に模倣したに過ぎないともいえる。 秀吉は事あるごとに信長と比べられ、蔑まれる自分を感じていたはずである。悔しかっただろうことは想像がつく。 この作品中にはあまりはっきりとした形では出てこないが、目に見えない、信長という強大で魅力的で、決して乗り越えられない壁のような存在が、秀吉と利休の間には重く介在していたことは当然考えられるし、秀吉の苛立ちや怒り、意地悪さ、猜疑心に含まれる感情には、信長の姿が絶えずちらつき影を落とし、信長を超えられない焦燥感があったこと、また秀吉の芸術的なものに対する憧れや劣等感をもっと強調すれば、この作品は更に理解されやすくなったのではないだろうか、と思うのだがどうだろうか。 秀吉は大坂城を居城としたが、大坂城を築城するまでは、光秀を破った山崎合戦の地、天王山の山頂に山崎城を築いて、一時期そこで政治をとっていた。 今は山崎城の遺構は何もなく(土塁、石垣も見られない)僅かに礎石らしいものが幾つか山頂に残っているが、何の整備もされていないので、ハイキング客が弁当を広げてごみを散らかすだけの場所となっている。そこにかつて秀吉の城があったということは、地元でももう忘れられかけているようだ。 山崎城があった頃、利休は秀吉に命じられて、天王山の山麓にある妙喜庵の中に、小さな茶室を建てた。これが今に残る有名な待庵である。当時は秀吉の来客のもてなし、密談、商談など、さまざまに茶室は用いられたことだろう。 JR山崎駅前に今も妙喜庵跡が残っている。妙喜庵は室町時代の連歌師、俳人である山崎宗鑑の庵であった。 そこに利休の待庵というシンプルなたった二畳の茶室が、今も当時のままに保存されている。それは拝観もできるのだが、一ヶ月前に葉書で申し込まないとならないので、思いついて出かけて行って、その場ですぐ見せてもらうことはできない。ただ近くの阪急大山崎駅前にある、大山崎町資料館にはレプリカがあり、こちらのほうは随時見学できる。 私は以前この複製された茶室のほうを見学したことがあった。それは実に簡素極まりない空間であった。 照明を落とした一隅に原寸大の茶室が拵えてある。にじり口の正面に床があり、左手に炉。床の間の壁は黒っぽい土壁。本当に質素な無の空間である。ほとんど虚無的な感じのする、でもここで真に豊かなものが生み出され、それを心に感じる人のみが、味わうことが可能な、そういう精神的な空間なのである。 利休は禅の世界にも深く入っていたとよくいわれるが、確かにこの虚無に近い空間をみていると、禅の何らかの影響下にある空間と考えても差し支えないだろう、という気持ちになる。 質素な中にもてなしの心と気持ちを尽くそうとする精神、利休のいう草庵路地の侘び茶の世界が、金ぴかの黄金茶室と方向を逆にすることについての作者の考察はどうだろうか。その点をみてみたい。「秀吉と利休」ではこのように表現されている。 「……妙喜庵内の待庵によって、いっぽう無にまで圧しつくした美の創造に悦びを見出したに劣らない意欲を、他方黄金の茶座敷にもそそいだまでであった。火焔に消滅したことで、いっそ活き活きと眼に残る安土の七重の天守閣、それの再現にほかならぬ大坂城のけんらん、華麗が象徴する限りなく豊満で、過剰な、美の時代感覚を、畳三ひらの黄金の空間に横溢させてみようとした試みでもあった。 はなはだしく異質なる建物も、それ故に別種のものではなく、利休の利休らしい独創が、たまたま極の両端に表現されただけで、その意味からは、二つは一つのものに過ぎなかった。同時に黄金の茶室で金の茶道具を用いつつも、待庵の侘び茶を味わうに変わらず、その粗ら壁をまえにして座っても、百畳敷きの大広間で、永徳、山楽の障壁画の間にあるに等しく、溌剌とおおらかな美意識に浸りえないならば、結句はそれを枯れかじけさせた侘び数奇にも、徹することはできないはずだ、と利休は考えたかった……」。 長く引用してしまったが、利休は茶湯とて別事ではなく、ただ湯を沸かして飲むまで」と言い切り、素朴な日常の生活用品である竹筒や、魚を入れるびく、手籠などに、山野に咲く草花を、それも一日でしおれる可憐な花を、何ら技巧を加えず「花は野にあるよう」に生けることをよしとしていた。 侘び茶の世界に生き、やがて権力の前に呑み込まれていくそのような利休の葛藤と逡巡と覚悟の姿勢を、作者は手探りしつつ、作品中に描いては削りまた描いて、あたかも彫刻刀で丹念に刻みつけていくのに似た文体で、しっかりと書き進めるのである。 七十代後半に達して、それまで溜めた思いを一気に溢れさせるかのような作者の筆の勢い、そのエネルギーに、読み手は最初から最後のページまで、ずっと圧倒され続けるだろう。
野上弥生子は明治十八年、大分県臼杵生まれの人である。九十九歳という長寿で没したが、晩年に至っても旺盛な文学活動を続けたことで知られている。 『秀吉と利休』は女流文学賞を受けた作品だが、実に作者七十九歳のときの受賞、というからそのパワーに驚いてしまう。 若いころから夫を通じて夏目漱石、寺田寅彦、芥川龍之介らと交流があり、文学への関心は人一倍強かったようだ。二十八歳のとき翻訳『ギリシャ・ローマ神話』を出している。 『ギリシャ・ローマ神話』は同様のタイトルで、その後他の作家の方もいろいろ工夫して翻訳されており、いわば複数の書き手の競作の形にもなっていると思うが、私は中でも野上さんの文章が好きで、ひもとく度に彼女の紡ぎ出す世界に引き込まれてしまう。丁寧で細部にまで神経の行き届いた、作者の性格がそのまま表れたような気品のある文体なのである。 創作への情熱と、家庭の主婦としての葛藤もあったに違いないと思われるが、三人の子を育て、家庭生活を大切にしたので、本格的な創作、文筆活動は五十歳を過ぎてからスタート、やがて次々と大作を発表、文化勲章受章まで登り詰めるという、恐るべき大器晩成、努力型の人であった。 以上インターネットによる
春秋 2018/9/6付 てんか。1585年、関白となった秀吉は以降、手紙にこう自署したという。乱世をほぼ平定、天皇から国の支配を任されたとの自負がにじむ。しかし、この後の高慢は史書や小説が示す通りだ。野上弥生子「秀吉と利休」はささいな言葉が側近に災いした経緯を描く。 ▼「唐御陣(からごじん)は明智討ちのようにはいくまい」。朝鮮半島への出兵を危ぶむ利休の感想である。漏れ聞いた秀吉は呼びつけて、ただした。「おれを、それほど非力と見ているのだな」。目玉として打ち出した国策へのふ安とひけめの分、怒りも激しい。「面も見たくない」。権力の座をつかんだ者のおごりがあらわなひと幕だ。 ▼自民党総裁選があす告示される。安倍晋三首相と石破茂元幹事長の一騎打ちの様相で、8日は討論会も予定されている。現状では、安倍陣営の優位は揺るぎそうにない。先日、5派閥合同で選挙対策本部が発足したと報じられた。圧勝ムードの中、政策論争より内向きの忠義立てや猟官が目立ってしまうようではさびしい。 ▼「3年で雇用と社会保障の改革を進める」。安倍首相は本紙に述べた。これまで放った矢の行方も見えませぬ、とお友達なら諭してもよさそうだが、党内にものを言えない空気が漂っているのだろうか。同調圧力ならば闊達な議論のため除かねばなるまい。来秋の首相在職日数の最長記録がレガシーでは困るのだ。いちい。 20018.9.6 |
21山本 有三 (1887~1974年)

▼『米百俵』小林虎三郎 発 刊 の こ と ば 長岡市は、戊辰戦争(一八六八)から七十年余後、昭和二十年八月一日、米機の空襲にあい、再び全市が焦土と化し、多くの尊い犠牲者をだした。それから三十年、いま、太陽も空気も水も緑も美しい地方中核都市に発展している。 私は、昭和四十一年十一月、市長就任当時から健康で、清潔な、文化の香り高い都市づくりに専念してきた。しかし、真に、自然と人間が調和できる市民生活には、豊で美しい自然的風土と整備された環境も、もちろん大切なことであるが、同時に、人間の心の中の精神的風土(教育・文化)の形成も極めて大切である。 戊辰戦争の敗戦のすえ、人心荒廃しはてたとき、焼け野原に立って、小林虎三郎は、人物をつくれ、教育こそ人間形成、長岡復興の要諦であるという永遠の理想を掲げ、極貧のなかから国漢学校を設立し、みごとに長岡を立ち直らせて、多くの偉材、傑物を輩出させる基をつくった。時代は変わったが、現代の高度経済成長によって生じた物質中心主義は、逆に、人心の頽廃をまねいているようにみえる。 いまこそ、たちどまって「照顧脚下」の反省をし、脈々と生き続けてきた小林虎三郎の精神を想起し、教育尊重の市民性をさらに高めて、文化の香り高い都市にするために、『米百俵小林虎三郎の思想』を出版することにした。 いうまでもなく、原作『米百俵』は、山本有三氏のふ朽の名作であり、長岡市という地方自治体が、小説家の戯曲を出版するということは、きわめて異例の事業なので、私は、この機会に、なぜこの出版にふみきったかということを簡単に説明することにしたい。 長岡市が、全国的にも稀な長岡ニュータウン計画をはじめとして、多くの現代的地方中核都市形成事業を積極的に推進していることは、世人の注目しているところである。そしてその次元の高い構想と、積極的姿勢を支える精神はなにかということも識者の関心事である。私のお会いした多くの方々は、この精神を『米百俵小林虎三郎』の思想」の精神であると指摘されている。しかし、この往年の名作戯曲の真の意図については、しらない方も多いようである。したがって、さきほど述べたとおり、精神的風土(教育・文化)の形成のために『米百俵小林虎三郎の思想』を出版頒布し、多くの方に知っていただくことにしたのである。 原作『米百俵』がつくられた経緯にについては、ちょっとしたエピソードがある。 昭和十四年の晩春、旧制長岡中学校で私と同級生であった星野慎一氏(ドイツ文学者)は、ヘルタ・ヤーン婦人と一緒に「真実一路」を独訳する許可を得るため、山本有三氏を訪れた。いくたびか訪れるにつれて、話題は、北越戊辰戦争や、薩長諸藩の新政府軍と激闘した軍事総督河合継之助のこと、長岡の落城と敗戦などに移っていった。ところが、星野氏が、ふと明治の夜明けを予見し、参戦に反対して、恭順を説き、領内の平和を強く主張した小林虎三郎のことにふれると、山本氏は驚くほど異常な関心を示し始めた。実は、山本氏はかねがね、長岡が、戊辰戦争で徹底的に小藩にもかかわらず、偉材、傑物が多く排出するのを不思議に思っていたのである。当時、日中戦争は、泥沼の様相を呈し、やがて二年後には、米・英国等を敵として太平洋戦争に突入するという狂乱の時代であった。それから後、山本氏は、つぶさに虎三郎に関する資料を集め、珠玉ともいうべき「米百俵」(戯曲)を書き上げ、小林虎三郎に関する研究とあわせて『米百俵』は一冊の本にまとめられ、昭和十八年六月新潮社から出版された。しかも初版五万部という当時としては破天荒の出版であった。さらに、同年六月には、井上正夫演劇道場によって、築地の東京劇場で上演された。当時、私もこれを観劇し、胸の迫る思いがしたが、多くの観客もまた深い感動を与えられたようであった。 だが、太平洋戦争はいよいよ熾烈化して、わが国は断末魔の苦しみにあえぎ、青少年の学校教育はほとんど中止され、軍需生産工場に動員されたり、学徒兵として戦場へかり出されて行った。 このような暗たんたる状況下で、この教育と平和の理想で裏打ちされた「米百俵」は、当時の軍部や政府から「反戦戯曲」だと強い弾圧をうけて絶版となり、自主回収の憂き目をみたのである。 今回の出版に当っては、先覚者小林虎三郎の思想について、さらに一層の理解を求める意味から、虎三郎に関する資料を博捜し、解説を加えて読者の便に供した。この出版が、「人間復興」の教育・文化の形成を願う私の真意の一端から出たことを、少しでもご理解いただければ幸いである。 最後に、山本有三氏のご遺族と新潮社から深いご理解とご承諾を賜り、また国立国会図書館からもいろいろご助言をいただき、長岡市役所から出版できたことについて、衷心より感謝の意を表する次第である。 なお、本書の『米百俵』は昭和二十五年に新潮社から出版された山本有三文庫「生きとし生けるもの」の中の『米百俵』を底本とし、「注」『隠れたる先覚者小林虎三郎』「そえがき」は昭和十八出版の隠れたる先覚者小林虎三郎」によった。 昭和五十年七月十五日 長岡市長 小 林 幸 平
参考:小泉首相が五月の所信表明演説で引用した山本有三の戯曲『米百俵』を、中村吉右衛門が主人公の長岡藩士、小林虎三郎役で九月の東京・歌舞伎座で上演する。 『米百俵』は一九七九年十月に歌舞伎座で吉右衛門の実父、松本白鸚(はくおう)の虎三郎、吉右衛門の伊東喜平太(長岡藩士)役で上演されている。松竹が再演を考えていたところに小泉首相の演説が重なった。 虎三郎は江戸時代末期、佐久間象山の門下生で吉田寅次郎(松陰)と並んで「二虎(こ)」と称された有望な人物だった。虎三郎は象山の意を受け長岡藩の老中、牧野備前守に「開港するなら下田よりも横浜がいい」と説いたが、時の大老、阿部伊勢守の怒りを買い、国元に戻された。 長岡藩は官軍に敗れ、禄高は三分の一に減らされて貧窮にあえいでいた。そこに三根山藩から米百表が見舞いに送られてきた。大参事(家老に相当)だった虎三郎は、「食べてしまえばそれでおしまいだが、長岡の将来を託す人材育成のため学校を作るべきだ」とその米を売って建設資金とした。」 山本有三の戯曲は戦時下の四三年」に井上正夫らが東京劇場で上演したのが初演。「人物を作って、新しい日本を立ち上がらせるのだ」と虎三郎は言ったが、日本は人物を得ず戦争に突入していったともいえるだけに、このせりふはどう受けとめられたのだろうか。
(2001年7月30日:日経の文化往来より)
2010.06.20 |
22さすがは校長先生
海軍中将新見 政一(1887~1993年)小伝
|
歴史を深く研究した者は洞察を得る事ができる
もう五十五年もまえの話になるが、私が江田島の海軍兵学校に学んだときの校長先生・新見政一中将もまたこのタイプの「英国型学将」であった。
1 海軍士官への道を歩む 新見政一は明治20年に広島県安佐郡に徳川時代初期から続いた庄屋の家に生まれた。小学校を卒業してから廣島に出て県立中学を受験したら、アッケなく落第したが、それは彼が田舎育ちのために「競争試験」というものを全然知らなかったからで、これに発奮した新見は猛勉強をつづけて明治38年12月に忠海(ただのうみ)中学から優秀な成績で海軍兵学校(海軍兵学校第36期)に入校した。忠海中学というのは当時セーラー服を制服にしていた異色の中学である、女学校のセーラー服はまだ日本に定着していなかった。 時代は日本海海戦大勝利の直後であるから、この年の海兵の競争率は三十五人に一人ほどのきびしいなかで、新見の入校後の成績は200人ちゅう第二位だった。第一位は佐藤市郎、この人は佐藤栄作・岸伸信介の長兄でズバ抜けた俊才であったという。 新見は在学中に学業に励んだが、しばらくして右足に湿疹ができ、軍医の治療ではなかなかよくならずにだんだん悪化して、ついには屋外の訓練に参加できなくなり、これがハンモック・ナンバー(卒業席次・遠洋航海の時に与えられるハンモックの番号)の足を引っぱって、結局192人ちゅう14番で明治41年に海兵を卒業、明治43年に海軍少尉に任官した。 2 砲術士官となる 海軍における初級士官の根幹は、人事配置・学校教育と密接にリンクされたOJT(実務訓練)で、半年おきくらいの頻繁な転勤(配置換え)を行って各種の実務をひろく習得さえながら本人の視野を広げて行き、これと平行して砲術・水雷・航海・通信などの「術科学校」へ派遣して専門的な理論的な技術をマスターさせる……という方式となる。 新見はこのようなコースのなかで数年をへながら、砲術学校(高等科)を卒業して砲術士「僕としては大尉(32歳)で15サンチ砲20門の指揮をとることに非常な誇りを感じたものである」と述懐している。 3 軍令部参謀となり、わが国海軍組織の大欠陥を指摘 しかし海軍はそのご彼に別の才能のあることを見抜き、歴史研究の道を歩ませた。大正11年に軍令部参謀となり、「海軍作戦機関の研究」という課題を与えられて約半年研究した結果、新見は日本海軍の組織のなかに既存する次のような二つの大欠陥を発見・指摘したのである。 ① 最高統帥組織について 国の防衛は軍隊だけで行えるものでなく、近代戦は国家総力戦になることが明らかなのに、日本の最高統帥機関は文民優位になっていない。 (これは第一次大戦の顕著な教訓であったが、日本は結局日清・日露戦役と同様の旧式な「大本営組織」をもって大東亜戦争に突入してあの惨害を招いた) ② 海上交通線の防御組織について 第一次大戦では英・独両国がたがいに相手の交通線を遮断し、必死の経済線をやって勝負をつけた。そのために、たとえば英国の軍令部は「商船行動・通商・対潜・掃海」など本来の海戦以外の通商保護の領域になんと百名以上の海軍将校を配員して、大がかりな研究・準備を進めているのに、日本では対米洋上決戦の準備にかまけてここがガラあきとなっている。 50年たった現在の目で、75年前に提示されたこの指摘を見れば、それがきわめて鋭利にわが国の弱点をついたことは、誰の目にも明らかなことだ。 4 英国に駐在、つぶさに第一次大戦を研究 このレポートはおおいに当時の軍令部長・山下源太郎大将の注意を引いた。そこで新見は軍令部参謀の身分のまま英国に駐在を命ぜられ、第一次大戦の詳細な研究に従事することとなる。 渡英した新見はしばらくオクスフォードに居住して国際法の講義を聴き、その後ロンドンに移って首相官邸のまんまえにある「大英帝国国防会議・戦史部」のなかに大きな机をもらって、そこへ通勤しながら理想的な環境のもとで戦史を研究した。これは英国海軍当局の特別の好意によるもので、彼はおおくの軍事機密書類を含むナマナマしい資料を自由に閲覧することを認められていた。新見の研究は海軍固有の戦略・戦術にかかわるもので、専門的かつ多岐にわたるが、マクロの国家戦略の視角から見れば特に注目すべき点が二つある。
③ 将来米国を敵にまわしてはならないこと 第一次大戦は有史いらい最大の戦争であったが、「連合国は豊富な国内資源と大規模な工業力を持つアメリカの参戦によってかろうじて勝利をおさめることができた」のである。アメリカが、その国民性である「パイオニァ精神」や「アメリカ第一主義」を発揮してさらに強大な国家に成長することは疑いない。今後の日本の国策はこの現実を念頭に置きアメリカを敵とするような行動を慎重に避けねばならぬ。
④ ドイツはトップの意思統一ができない国であること 第一次大戦におけるドイツ軍は最後の段階に至るまで本土に敵一兵も入れないほど善戦したが、統帥部は支離滅裂で、政治家は世論の指導もせず、政略と戦略はチグハグで、陸海軍は別の方針によって行動し、結局あの敗戦をまねいた。将来注意を要する点である。 新見は大正15年初頭に帰国し、2年間の研究成果を取りまとめた膨大な報告書を提出したが、彼を英国に派遣した軍令部長・山下大将はすでにその職を去り、献策はそのごの海軍によってほとんど利用されるところがなかった。しかしこの研究業績をつうじて新見の研究者ならびに教育者としてのてきせい適性は正等に評価されたといえる。 5 第二次大戦の発生と帰趨を的確に予言 帰国後の彼は艦長・艦隊参謀長などのほか長期にわたって海軍大学校の戦史教官をつとめたのち、海軍省教育局長・海軍兵学校長(1939年)として部内教育の本道をあゆむこととなる。 最も劇的であったのは昭和12年秩父宮殿下の渡英に随行ののち、ドイツ・アメリカを視察して帰ったときの報告で、彼は国際情勢に関する深い知識と公正な史観にもとづき、第二次大戦の勃発とその帰趨、わが国のとるべき道を次のように的確に予言した(要旨)。
⑤ ヨーロッパでは遅かれ早かれ(ドイツがフランスを攻撃して)戦争が起こる。 ⑥ 独伊との関係にこれ以上深入りしてヨーロッパ政局にの渦中にまきこまれてはなならない、フリーハンドを保つのが有利だ。 ⑦もし日本が独伊に見方すれば、英・仏・米を敵とする結果となる。
⑧ 第一次大戦の教訓からすれば、日本がどちらの道をとるべきかは明らかなことだ。 以上の①~⑧の指摘は、これを別の側面から要約すれば「歴史を深刻に研究したものは洞察を得ることができる」と言う事である。 そのご彼は多数の後輩を教育し、機会あるごとに以上の論点を強調したが、けっきょく「親独・反英米・大陸進出・陸軍主導」の世の潮流を食い止める事はできなかった。つまりは「平家・海軍・国際派」の道を歩んだわけだ。 開戦時は第二遣支艦隊司令長官として皮肉にもホンコン占領作戦の指揮をとる運命を担ったが、先行きの読めていた新見の心中はムジュンにみちたものであっただろう。昭和十七年舞鶴鎮守府司令長官を最後に現役を去った。 6 戦後一〇六歳まで生き抜き大著を遺す そのご半世紀をへてわれら往事の悪童共もすでに老境に入り、同期の生存者もだんだん少なくなってきた。ここまで辿りついて思い当たるのは、人間の一生は「社会とどんな関係を結び、どのように受け入れられてきたか(客観・他者評価)」ということのほかにもう一つ、「自分の信念をどのように貫き、自分らしい人生をいかに生きてきたか(主観・自己評価)」という観点がきわ立って重要であることを知る。 新見は戦後の混乱期を生き抜いて強靭な生命力を示し、106歳というまったく例外的な高齢に達して平成5年4月に世を去った。その長寿の精神的な原動力となったものは、海軍時代から引き続いた「戦史研究」と、それを支える旺盛な知識欲・達成意欲である。 彼は終戦後「第二次世界大戦の研究」に着手し、昭和37年(75歳)から始めて55年(93歳)に至るまで、実に19年間にわたり、海上自衛隊幹部学校において連続的に戦史を講じ、その成果をまとめて昭和59年(97歳)のとき『第二次世界大戦戦争指導史』(原書房)を出版した。680ページにわたる大冊、超老年期に収穫された終生研鑽の結実で、この時に至るまで彼の頭脳がまったく衰えを見せなかったのは多くの人々の証言するところである。 「平家・海軍・国際派」などというのはしょせん評論家・傍観者のセリフであって、人間はギリギリのところ「自己評価(主観)」に頼らなければ生き抜けず、成仏できない。この意味で新見中将の戦後の足跡は健全で、名利にかかわらず、首尾一貫してわが道を歩み、幼児から百年間積み上げた素養を余すところ無く活用して、三角形の最終頂点を完成したという点で教え子たちの模範となるものが多い。今は亡きわれらの校長先生に心からなる感謝と敬意を表して本稿の結びとします。 (引用書 『日本海軍の良識・提督・新見政一』原書房) *補足:平成16年11月25日、海兵75期 広島県立忠海中学 山本道廣君から送ってくださったものを4年と少しの本日写しました。 参考:海軍兵学校歴代海軍兵学校長をご覧ください。 平成21年1月6日 |
23 小泉 信三(1888~1966年)

▼父 小泉信三を語る 2008年5月21日 ある新聞に表題の本の広告があった。 小泉 妙著(山内慶太・神吉創二・都倉武之編) 良き家庭人として素顔から、娘がいま見た学者・教育者としての小泉、そして吉田茂、古今亭志ん生ら幅ひろい交友を愛情をこめて語る。東宮御教育常時参与として、皇太子殿下(今上陛下)とのご親交を記した日記も初公開。と説明されていた。
この本の文頭 信吉戦死の報が来たのは昭和十七年十二月四日夕のことでである。五時頃、私は外出先で家からの電話をきき、すぐに電報を見た。 コイズミカイグンシュケイチュウイ一〇ツキ二二ヒミナミタイヘイヨウホウメンニオイテメイヨノセンシヲトゲラレタリトリアヘズゴッウチカタガタオクヤミモウシアグナホセイゼンノハイゾクカンセンブタイメイトウハキミツホジゼウオモラシナキヨウイタサレタシカイグンセウジンジキョウクテウ (小泉信吉主計中尉十月二十二日南太平洋方面に於て名誉の戦死を遂げられた。取り敢へず御通知旁々御悔み申上ぐ。なほ生前の配属艦船部隊名等は機密保持上お漏らしなきよう致されたし。海軍省人事局長) 彼は年二十五、慶応義塾を卒業して三菱銀行に勤務すること四箇月、海軍々人となった一年二箇月、父母と祖母と妹二人を後に遺した。 この本の最終は下記の文章で結ばれていた 親の身として思えば、信吉の二十五年の一生はやはり生きた甲斐のある一生であった。信吉の父母同胞を父母同胞として、その他凡ての境遇を境遇として、そうしてその命数は二十五年に限られたものとして、信吉に、今一度この一生をくり返すことを願うかと問うたなら、彼は然りと答えるであろう。父母たる我々も同様である。親としてわが子の長命を祈らぬ者はない。しかし、吾々両人は、二十五年の間に人の親としての幸福を享けたと謂い得る。信吉の容貌、信吉の性質すべての彼の長所短所はそのままとして、そうして二十五までしか生きないものとして、さてこの人間を汝は再び子として持つを願うかと問われたら、吾々夫婦は言下に願うと答えるであろう。
信吉は文筆が好きであった。若し順当に私が先に死んだら、彼は必ず私の為に何かを書いたであろう。それが反対になった。然るにこの一年余り、私は職務の余暇が乏しかったので、朝夙(はや)く起きて書いたり、夜半に書いたりしたこともあるが、筆の運びは思うに任せず、出来栄も意の如くならなかった。しかし信吉は凡てそれを恕(じょ)するであろう。彼の生前、私はろくに親らしいことがしてやれなかった。この一編の文が、彼に対する私の小さな贈り物である。
2008.5.24 補足:宮本 進 先生の一通のメールから、小泉信三・信吉親子について思い出し、この記事を讀み、本を取り出してページをめくっていると、本の中に下記の手紙が挟まれていた。
前略
参考:小泉信三 平成二十六年十一月十二日。 |
24 里見 弴(とん)(1888~1983年)
|
道元についても、禅宗についても「幼児に等しい無智」であった著者が、ふとした機縁でこの巨人の生涯に格闘することになる。文献を渉猟し、自分の頭で読み解いてゆく――。禅師七百回忌の「饅頭本」で終らせないためにも「見て来たような嘘」だけはつかないと、と語る作家里見弴(1888~1983)の描いた道元禅師像。 『道元禅師の話』(岩波文庫の帯封より。)
▼「日常の起居自ら掟なきは心情未だ熟せざれば也 心情未熟にして芸術のみの完成を希(ねが)う 是木によっ倚(よ)って魚覓(もと)むるの儔(ともがら)也」
|
25岡本 かの子 (1889~1939年)
|
年年にわが悲みは深くしていよよ華やぐ命なりけり ★プロフィル:岡本 かの子は、大正、昭和期の小説家、歌人、仏教研究家。本カノ。東京府東京市赤坂区青山南町生まれ。跡見女学校卒業。漫画家岡本一平と結婚し、芸術家岡本太郎を生んだ。小説家として実質的にデビューをしたのは晩年であったが、生前の精力的な執筆活動から、死後多くの遺作が発表された。 |
26柳 宗悦(1889~1961年)

序 無学ではあり貧しくはあるけれども、彼は篤信な平信徒だ。なぜ信じ、何を信ずるかをさえ、充分に言い現せない。しかしその素朴な言葉の中に、驚くべき彼の体験が閃ひらめいている。手にはこれとて持物はない。だが信仰の真髄だけは握り得ているのだ。彼が捕えずとも神が彼に握らせている。それ故彼には動かない力がある。 私は同じようなことを、今眺ながめている一枚の皿についてもいうことが出来る。それは貧しい「下手げて」と蔑さげすまれる品物に過ぎない。奢おごる風情もなく、華やかな化粧もない。作る者も何を作るか、どうして出来るか、詳しくは知らないのだ。信徒がみょう号みょうごうを口ぐせに何度も唱えるように、彼は何度も何度も同じ轆轤ろくろの上で同じ形を廻しているのだ。そうして同じ模様を描き、同じ釉くすり掛けを繰返している。美が何であるか、窯藝とは何か。どうして彼にそんなことを知る智慧ちえがあろう。だが凡てを知らずとも、彼の手は速やかに動いている。みょう号は既に人の声ではなく仏の声だといわれているが、陶工の手も既に彼の手ではなく、自然の手だといい得るであろう。彼が美を工夫せずとも、自然が美を守ってくれる。彼は何も打ち忘れているのだ。無心な帰依きえから信仰が出てくるように、自おのずから器うつわには美が湧わいてくるのだ。私は厭あかずその皿を眺め眺める。 一 雑器の美などいえば、如何にも奇を衒てらう者のようにとられるかも知れぬ。または何か反動としてそんなことを称えるようにも取られよう。だが思い誤られやすい聯想を除くために、私は最初幾つかの注意を添えておかねばならない。ここに雑器とはもとより一般の民衆が用いる雑具の謂いいである。誰もが使う日常の器具であるからあるいはこれを民具と呼んでもよい。ごく普通なもの、誰も買い誰も手に触れる日々の用具である。払う金子きんすとてもわずかである。それも何時何処においても、たやすく求め得る品々である。「手廻りのもの」とか「不断遣(ふだんづかい)」とか、「勝手道具」とか呼ばれるものを指すのである。牀ゆかに飾られ室を彩いろどるためのものではなく、台所に置かれ居間に散らばる諸道具である。あるいは皿、あるいは盆、あるいは箪笥たんす、あるいは衣類、それも多くは家内うちづかいのもの。悉ことごとくが日々の生活に必要なものばかりである。何も珍しいものではない。誰とてもそれらのものを知りぬいている。 二 しかし不思議である。一生のうち一番多く眼に触れるものでありながら、その存在は注視されることなくして過ぎた。誰も粗末なものとのみ思うからであろう。さながら美しきものが彼らの中に何一つないかのようにさえ見える。語るべき歴史家でさえ、それを歴史に語ろうとは試みない。しかし人々の足許から彼らの知りぬいているものを改めて取上げよう。私は新しい美の一章が今日から歴史に増補せられることを疑わない。人々は不思議がるであろうが、その光は訝いぶかりの雲をいち早く消すであろう。 しかしなぜかくも長くその美が見捨てられたか。花園に居慣れる者はその香りを知らないといわれる。余りに見慣れているが故に、とりわけ見ようとはしないのである。習性に沈む時反省は失せる。まして感激は消えるであろう。それらのものに潜ひそむ美が認識されるまでに、今日までの長い月日がかかった。私たちは強あながちそれを咎とがめることは出来ぬ。なぜなら、今までは離れてそれらのものを省みる時期ではなく、まだそれらのものを産み、その中に生きつつあったからである。認識はいつも時代の間隔を求める。歴史は追憶であり、批判は回顧である。 今や時代は急激にその方向を転じた。凡てのものが今日ほど忙しく流れ去ることはまたとないかもしれぬ。時も心もまたは物も、過去へと速かに流れた。因襲の重荷は下ろされたのである。私たちの前には凡てが新しく廻転する。未来も新しくまた過去も新しい。慣れた世界も今は不思議な世界である。吾々の眼には、改めて凡てのものが印象深く吟味される。それは拭ぬぐわれた鏡にも等しい。一切が新しく鮮かに映る。善きものも悪しきものも、その前には姿を偽いつわることが出来ぬ。いずれのものが美しいか。それを見分くべきよき時期は来たのである。今は批判の時代であり意識の時代である。よき審判者たる幸が吾々に許されてある。私たちは時代の恵みとしてそれを空むなしくしてはならない。 塵ちりに埋もれた暗い場所から、ここに一つの新しい美の世界が展開せられた。それは誰も知る世界でありながら、誰も見なかった世界である。私は雑器の美について語らねばならない。またその美から何を学び得るかを語ろうとするのである。 三 毎日触れる器具であるから、それは実際に堪たえねばならない。弱きもの華やかなもの、込こみ入りしもの、それらの性質はここに許されていない。 分厚ぶあつなもの、頑丈がんじょうなもの、健全なもの、それが日常の生活に即する器である。手荒き取扱いや烈はげしい暑さや寒さや、それらのことを悦んで忍ぶほどのものでなければならぬ。病弱ではならない。華美ではならない。強く正しき質を有もたねばならぬ。それは誰にでも、また如何なる風にも使われる準備をせねばならぬ。装うてはいられない。偽ることは許されない。いつも試煉を受けるからである。正直の徳を守らぬものは、よき器うつわとなることが出来ぬ。工藝は雑器において凡ての仮面を脱ぐのである。それは用の世界である。実際を離れる場合はない。どこまでも人々に奉仕しようとて作られた器である。しかし実用のものであるからといって、それを物的なものとのみ思うなら誤りである。物ではあろうが心がないと誰がいい得よう。忍耐とか健全とか誠実とか、それらの徳は既に器の有つ心ではないか。それはどこまでも地の生活に交わる器である。しかし正しく地に活くる者に、天は祝福を降すであろう。よき用とよき美とは、叛そむく世界ではない。物心一如であるといい得ないであろうか。 彼らは勤め働く身であるから、貧しく着、慎ましく暮している。しかしそこには満足が見える。彼らはいつも健すこやかに朝な夕なを迎えるではないか。顧みられない個所で、無造作に扱われながら、なおも無心に素朴に暮している。動じない美があるではないか。わずかの接触で戦おののくほどの繊細さにも、心を誘う美しさがある。しかし強き打撃に、なおも動ぜぬ姿には、それにも増して驚くべき美しさが見える。しかもその美しさは日毎ひごとに加わるではないか。用いずば器は美しくならない。器は用いられて美しく、美しくなるが故に人は更にそれを用いる。人と器と、そこには主従の契ちぎりがある。器は仕えることによって美を増し、主は使うことによって愛を増すのである。 人はそれらのものなくして毎日を過ごすことが出来ぬ。器具とはいうも日々の伴侶はんりょである。私たちの生活を補佐する忠実な友達である。誰もそれらに便たよりつつ一日を送る。その姿には誠実な美があるではないか。謙譲の徳が現れているではないか。凡てが病弱に流れがちな今日、彼らのうちに健康の美を見ることは、恵みであり悦びである。 四 そこにはとりわけて彩りもなく飾りもない。至純な形、二、三の模様、それも素朴な手法。彼らは知を誇らず、風に奢おごらない。奇異とか威嚇いかくとか、少しだにそれらの工たくらみが含まれない。挑いどむこともあらわな態さまもなく、いつも穏かであり静かである。時としては初心な朴訥ぼくとつな、控目がちな面おももちさえ見える。その美は一つとして私たちを強いようとはしない。美を衒てらう今日であるから、わけてもそれらの慎ましい作が慕したわしく思える。 それらの多くは片田舎の名も知れぬ故郷で育つのである。または裏町の塵にまみれた暗い工房の中から生れてくる。たずさわるものは貧しき人の荒れたる手。拙つたなき器具や粗あらき素材。売らるる場所とても狭き店舗てんぽ、または路上の蓆むしろ。用いらるる個所も散り荒さるる室々。だが摂理は不思議である。これらのことが美しさを器のために保障する。それは信仰と同じである。宗教は貧の徳を求め、智に傲おごる者を誡いましめるではないか。素朴な器にこそ驚くべき美が宿る。 作は無慾むよくである。仕えるためであって名を成すためではない。丁度労働者が彼らの作る美しき道路に名を記さないのと同じである。作者はどこにも彼の名を書こうとは試みない。悉ことごとくがななき人々の作である。慾なきこの心が如何に器の美を浄きよめているであろう。ほとんど凡ての職工は学もなき人々であった。なぜ出来、何が美を産むか、これらのことについては知るところがない。伝わりし手法をそのままに承うけ、惑うこともなく作りまた作る。何の理論があり得よう。まして何の感傷が入り得よう。雑器の美は無心の美である。 なも無き作であるから、私たちは作者の歴史を綴つづることは出来ぬ。作る者は優れた少数の個人ではなく、あの凡夫と呼ばれる衆生しゅじょうである。あの驚くべき器の美が民衆より生れたとは何を語るであろう。かつて美は凡ての共有であって、個人の所有ではなかった。私たちは民族のなにおいて、時代のなにおいて、その労作を記念せねばならぬ。知に劣る民衆も、作においては秀ひいでた民衆である。今は個人のみ活きて時代は沈む。しかしかつては時代が活き、個人は自からを匿かくした。わずかな作者から美が出るのではなく、美の中に多くの作者が活きた。雑器は民藝である。 五 注意さるべきは素材である。よき工藝はよき天然の上に宿る。豊かな質は自然が守るのである。器が材料を選ぶというよりも、材料が器を招くとこそいうべきである。民藝には必ずその郷土があるではないか。その地に原料があって、その民藝が発足する。自然から恵まれた物資が産みの母である。風土と素材と製作と、これらのものは離れてはならぬ。一体である時、作物は素直である。自然が味方するからである。 原料が失われたら、むしろその工房は閉じられねばならぬ。材料に無理がある時、器は自然の咎とがめを受ける。また手近くその地から材料を得ることなくば、どうして多くを産み、廉やすきを得、健すこやかなものを作ることが出来よう。一つの器の背後には、特殊な気温や地質やまたは物質が秘められてある。郷土的薫かおり、地方的彩り、このことこそは工藝に幾多の種を加え、味わいを添える、天然に従順なるものは、天然の愛を享うける。この必然性を欠く時、器に力は失せ美は褪あせる。雑器に見られる豊かな質は、自然からの贈物である。その美を見る時、人は自然、自からを見るのである。 これのみではない、凡ての形も、模様も、原料に招かれるのだというべきであろう。その間にはいつも必然な縁ゆかりが結ばれてくる。よき化粧とは身に施すものではなく、身に従うものであろう。原料をただの物資とのみ思ってはならぬ。そこには自然の意志の現れがある。その意志は、如何なる形を如何なる模様を有つべきかを吾々に命じる。誰もこの自然の意志に叛そむいて、よき器を作ることは出来ぬ。よき工人は自然の欲する以外のことを欲せぬであろう。 このことはよき教えではないか。神の子たるを味わう時、信の焔ほのおは燃えるであろう。同じように自然の子となる時、美に彼は彩られるであろう。詮せんずるに自然に保障せられての美しさである。母のその懐に帰れば帰るほど、美はいよいよ温められる。私はこの教えのよき場合を雑器の中に見出さないわけにゆかぬ。 六 日々の用具であるから、稀有けうのものではなく、いつも巷間こうかんに準備される。毀こぼたれるとも更に同じものがそれに代る。それ故生産は多量でありまた廉価である。これは数量のことに過ぎぬと思うであろうが、この事実こそは工藝の美に不思議な働きを投げる。時として多産は粗雑に流れる恐れもあろう。しかしこのことなくして雑器の美は生れてこない。 反復は熟達の母である。多くの需要は多くの供給を招き、多くの製作は限りなき反復を求める。反復はついに技術を完了の域に誘う。特に分業に転ずる時、一技において特に冴さえる。同じ形、同じ絵、この単調な循環じゅんかんがほとんど生涯の仕事である。技術に完まったき者は技術の意識を越える。人はここに虚心となり無に帰り、工夫を離れ努力を忘れる。彼は語らいまた笑いつつその仕事を運ぶ。驚くべきはその速度。否、速かならざれば、彼は一日の糧かてを得ることが出来ぬ。幾千幾万。この反復において彼の手は全き自由をかち得る。その自由さから生れ出づる凡ての創造。私は胸を躍らせつつ、その不思議な業を眺める。彼は彼の手に信じ入っているではないか。そこには少しの狐疑こぎだにない。あの驚くべき筆の走り、形の勢い、あの自然な奔放ほんぽうな味わい。既に彼が手を用いているのではなく、何者かがそれを動かしているのである。だから自然の美が生れないわけにはゆかぬ。多量な製作は必然、美しき器たる運命を受ける。 それは驚くべき円熟の作である。あの雑器と呼ばれる器の背後には、長き年月と多くの汗と、限りなき繰返しとが齎もたらす技術の完成があり、自由の獲得がある。それは人が作るというよりも、むしろ自然が産むとこそいうべきであろう。「馬の目」と呼ばれる皿を見よ、如何なる画家も、あの簡単な渦巻うずまきを、かくも易々やすやすと自由に画くことは出来ないであろう。それは真に驚異である。凡てが機械に帰る近き未来においては、かつて人の手が如何なる奇蹟をなし得たかを信じ難くさえなるであろう。 七 民藝は必然に手工藝である。神を除いて、手よりも驚くべき創造者があろうか。自在な運動から、全ての不可思議な美が生れてくる。如何なる機械の力も、手工の前には自由を有たぬ。手こそは自然が与えた最良の器具である。この与えられた恵みに叛そむいて、何の美を産み得るであろう。 不幸にも経済的事情に強いられて、今はほとんど凡てが機械の業に委ゆだねられる。そこからもある種の美は生れてこよう。強あながちそれを忌いみ嫌ってはならぬ。しかしその美には限りがある。人は無制限に無遠慮にその力を用いてはならぬ。それはいつも規定の美に止まるであろう。単なる定則は美の閉塞へいそくに過ぎない。機械が人を支配する時、作られるものは冷たくまた浅い。味わいとか潤おいとか、それは人の手に托されてある。その雅致を生み、器の生命を産む面の変化、削けずりの跡、筆の走り、刀の冴さえ、かかるものをまで、どうして機械が作り得よう。機械には決定のみあって創造はない。今のままなら、ついに人の労働から自由を奪い、喜びを奪うであろう。かつては人が器具を支配し得たのである。この主従の二が正しい位置を保つ時、美は温められ高められた。 手工藝の終りが近づいて来た今日、祖先が作った雑器こそは、貴重な遺品である。民藝が手工である時期は、今や過去に流れようとしている。苦しい事情はかかるものの復興を阻止している。今日の不合理な勢いの許もとでは、一度廃すたれると、民藝として栄える日は二度とは戻り難いであろう。ただ伝統を守り続ける地方のみが、今も正しい手工藝の道を歩む。そうしてわずかばかりの個人がそれを助けようと努力している。しかし「手工に帰れよ」という叫びは、いつも繰返されるであろう。なぜならそこにこそ最も豊かに、正しき労働の自由があり、正しき工藝の美が許されているからである。かくて手工のしるしである今日までの民器が、愛を以て顧みられる日は来るにちがいない。歴史は傾くとも、その美に傾きはない。時と共にその光はいや増すであろう。 八 この世界に来る時、作る心も作られる物も、または用いる手法も凡てが至純である。この単純さこそは要求せられた器の性質である。人はこの言葉を粗野という字に置き換えてはならぬ。この性質にこそ美の保障がある。よき藝術で単純さを欠いたものがあろうか。または錯雑が美を産んだ例が沢山あろうか。単純を離れて正しき美はない。物は雑器と呼ばれてはいるが、純一なその姿にこそかえって美の本質が宿る。人は藝術の法則を学ぶために、むしろ普通な誰も知るこれらの世界に来ねばならぬ。 悟得ごとくするものは無碍(むげ)である。自然に任ずるこれらの作も自由の境に活きる。よき手工の前に、単なる掟おきては存在を有たない。物に応じ心に従って、凡てが流れるままに委ねられる。如何なる形も色も模様も彼らの前に開放される。どれを選ぶべきか、定められた掟はない。それが何の美を産むか、かかることに拘こだわる心さえ有たぬ。しかし誤りはない。彼が気儘きままに選ぶのではなく、自然が選ぶ自由に、彼を托しているからである。 この自由こそは、創造の母であった。雑器に見られる極めて豊かな種類と変化とは、このことを如実に語る。変化は作為が産むのではない。作為こそは拘束である。凡てが天然に托される時、驚くべき創造が始まる。技巧の作為が、どうしてあの奔放ほんぽうな味わいを産み得よう。またはかくまで豊かな変化を発し得よう。ここにはいたずらな循環がなく、単なる模造がない。常に新たな鮮かな世界への開発がある。 あの「猪口(ちょこ)」と呼ばれる器を見よ。その小さな表面に、画き出された模様の変化は、実に数百種にさえ及ぶであろう。しかもその筆致の妙を、誰か否むことが出来よう。ありふれた縞しまものの如きでさえ、同一のものはかえって見出し難いのを知るであろう。民藝は驚くべき自由の世界であり創造の境地である。 九 不断遣いのものであるから粗略にされて、遠い過去のものはわずかより残らぬ。残るともその種類は乏しいであろう。日本において工藝が特に多様になったのは、ここ二、三世紀の間である。漆器、木工はもとより、あるいは金工、あるいは染織、下っては陶磁器。それらは多種な調度に適応せられた。雑器のよき歴史が漸ようやく傾き始めて、正しい手工が終りに近づいたのは明治の半頃である。だが匿かくれた地方には、まだ手法や様式の伝統が支持されて、古格を保つものが少くない。今日残る雑器は、江戸時代のものが多いのであるから、種類もあり数も乏しくはない。 徳川の文化は平民の所有であった。文学においてそうであり、絵画においてそうである。残された雑器も、民衆によって保持された文化のよき一部を占める。ただそれは浮世絵の如き、都みやこびた繊細な文化を語るのではない。素朴な確実な郷土の風格を保有する。優美な姿はなくとも、悉ことごとくが便りになる篤実な伴侶はんりょである。もし共に暮すなら、日に日に親しみは増すであろう。それらのものが傍にある時、真に家に在る寛くつろぎを覚えるであろう。 概して見るならば、美の歴史は下り坂であった。昔に競い得る新たなものは稀まれであろう。時代が下降するにつれて技巧は無益な煩雑を重ねた。手工はその重荷に悩んで、生気は次第に失せた。丹念とか精巧とか、それらの特質はあるかもしれぬ。だが単純に包まれる美の本質は殺されてしまった。自然への信頼は人為的作法に虐しいたげられて、美には凋落ちょうらくの傾きが見える。だがこの悲しい歴史に交わって、ひとりこの流れに犯されなかったのは、実に雑器の類である。ここには病原が少い。美術の圏外に放置せられたためか、作る者は美の意識に煩わずらわされずしてすんだ。末期においても健全な美を求めようとするなら、私たちはこの領域に来ねばならぬ。姿は貧しくはあろう。しかし何ものの間に伍しても、その確かな存在が破れる場合はない。試みに一個の焼物を選んで、その裏を見られよ。よく支那や朝鮮のあの高台こうだいの強さに比べ得るものは、かかる雑器においてのみである。この世界に弱さはない。否、弱きものは日々の器たるに堪えることが出来ぬ。 一〇 しかし力はこれに止まらない。固有な日本の存在がそれによって代表される。もとより絵画において彫刻において、日本自からの栄誉を語る幾多のものがあろう。しかし概していうならば、唐土の遺風を脱し得たものは少く、韓土の影響を離れ得たものも乏しい。ましてそれらに拮抗きっこうし得る力と深さとに充みちるものは稀まれだといわねばならぬ。偉大である支那の前に、優雅である朝鮮の前に、私たちは私たちの藝術を無遠慮に出すことが出来ぬ。 しかし雑器の領域に来る時、その稀な例外の一つの場合に来るのである。そこには独自の日本がある。充分な確実さと、充分な自由と、充分な独創とがここに発見される。それは模倣もほうではない、追従ではない。世界の作に伍して、ここに日本があると言い切ることが出来る。故国の自然と風土と、感情と理解との、まちがいもない発露である。真に一格の創造である。人は雑器と呼びなすものに、独自な日本を語ることを、遠慮がちに感ずるであろうか。ゆめそう思ってはならぬ。広く日本の民衆から、かかる作が生れたことをこそ誇ってよい。ましてそれらの器を日々の友としていたことを喜び合わねばならぬ。その栄誉は個人の所有ではなく、民族の共有である。民藝において日本の美が見出されることほど、力強い事実はないではないか。もし民衆の生活にかかる美の基礎がなかったなら、如何に心もとなく思えるであろう。私は日本民族の栄誉のためにも、積る塵の下から雑器を取上げねばならぬ。 一一 無学な職人から作られたもの、遠い片田舎から運ばれたもの、当時の民衆の誰もが用いしもの、下物と呼ばれて日々の雑具に用いられるもの、裏手の暗き室々で使われるもの、彩りもなく貧しき素朴なもの、数も多く価も廉やすきもの、この低い器の中に高い美が宿るとは、何の摂理であろうか。あの無心な嬰児みどりごの心に、一物をも有たざる心に、知を誇らざる者に、言葉を慎しむ者に、清貧を悦ぶ者たちの中に、神が宿るとは如何に不可思議な真理であろう。同じその教えが、それらの器にも活々いきいきと読まれるではないか。 しかも奉仕に一生を委ねるもの、自みずからを捧ささげて日々の用を務むるもの、倦うむことなく現実の世に働くもの、健康と満足とのうちにその日を暮すもの、誰もの生活に幸福を贈ろうと志すもの、それらの慎ましい器の一生に、美が包まれるとは、驚くべき事柄ではないか。しかもよく用いられて手ずれを受ける時、その美がいや増すとは何の天意であろうか。信仰の生活も、犠牲の生活であり奉仕の一生ではないか。神に仕え人に仕え自からを忘れる敬虔けいけんな者のその姿が、主に仕える器にも見られるではないか。現実に即するものに、現実を越えた美が最も鮮かに示されるとは、如何に微妙な備えであろう。 自からは美を知らざるもの、我に無心なるもの、名に奢おごらないもの、自然のままに凡てを委ねるもの、必然に生れしもの、それらのものから異常な美が出るとは、如何に深き教えであろう。凡てを神の御なにおいてのみ行う信徒の深さと、同じものがそこに潜むではないか。「心の貧しきもの」、「自からへり下るもの」、「雑具」と呼びなされたそれらの器こそは、「幸あるもの」、「光あるもの」と呼ばるべきであろう。天は、美は、既にそれらのものの所有である。 跋 過去の時代においてかかる雑器の美を認めたのは、初代の茶人たちであった。彼らには並ならぬ眼があった。人々は忘れ去ったのであろうが、今日万金を投ずるあの茶器は、「大名物(おおめいぶつ)」は、その多くが全くの雑器に過ぎない。かくも自然な、かくも奔放な彼らの雅致は、雑器なるが故だといい得よう。もし彼らが雑器でなかったら、決して「大名物」とはなり得なかったであろう。人はあの「井戸」の茶碗を省みて、七個の見処みどころがあるという。後にはついにそれが美の約束とまで考えられた。だがもとの作者にそれを聞かせたら、如何ばかり困却するであろう。その約束で作られる後代の模作品に、たえて優れた作がないのも無理はない。既に雑器の意を離れて、美術品として工夫されたに過ぎないからである。人々はあの深く渋き茶器が、無造作な雑器であったことをゆめ忘れてはならない。 今は茶室を造るにも数寄すきをこらすが、その風格は賤しずが家やに因るものであろう。今も田舎家は美しい。茶室は清貧の徳を味わうのである。今は茶室において富貴を誇るが、末世の誤りを語るに過ぎぬ。今や茶道の真意は忘れられて来たのである。「茶」の美は「下手げて」の美である。貧の美である。 史家もあの「大名物」を讃美する。だが少しも他の雑器については語らない。さながら他には何もないかのように考えている。だが茶碗や茶入は夥おびただしい雑器の中のわずか一、二種に過ぎない。美の王座についているそれらのものの姉妹が、まだ限りなく塵ちりの下に埋もれている。かかる雑器に美を認めないのは、彼らが茶器の美についても既に知るところがないからであろう。 許されるならば、私は片田舎の忘れられた民家において、塵につつまれる雑器を取上げ、新しく茶をたてよう。この時こそ道の本に返って、初代の茶人たちと心ゆくばかり交わることが出来よう。 (一九二六年):『民藝四十年』の中の「雑器の美」 |
|
一 〽秋風や忘れてならぬなを忘れ ★プロフィル:久保田 万太郎は、浅草生まれの大正から昭和にかけて活躍した俳人、小説家、劇作家。生すいの江戸っ子として伝統的な江戸言葉を駆使して滅びゆく下町の人情を描いた。俳人としては岡本松浜、松根東洋城に師事、戦後に俳誌「春燈」を主宰し文人俳句の代表作家として知られる。俳句の別号に暮雨、傘雨。 |
28內田 百閒 (1889~1971年)
|
內田百閒は、夏目漱石門下の日本の小説家、随筆家。本名は内田 榮造。 戦後は筆名を内田 百閒と改めた。別号は百鬼園。 「百閒」は、故郷岡山にある旭川の緊急放水路である百間川から取ったもの。別号の「百鬼園」を「借金」の語呂合わせとする説もあるが、本人は一応のところ否定している。 迫り来る得体の知れない恐怖感を表現した小説や、独特なユーモアに富んだ随筆などを得意とした。後輩の芥川龍之介に慕われたほか、師である夏目漱石の縁故から夏目伸六と親交が深かったことでも有名。 |
29田中 良雄『職業と人生』(1890~1964年)
|
▼『職業と人生』 一隅を照らすもので 私はありたい 私の受けもつ一隅が どんなにちいさい みじめな はかないものであっても わるびれず ひるまず いつもほのかに 照らして行きたい *伝教大師の「照干一隅」を散文詩にしたもの。
本棚の一隅にあった。ところどころ鉛筆の線が引かれていることから一度は読んだ跡が残っていることになる。 現在でも活きているお話ばかりであるが、今回はその中の「照于一隅」のお話を抜き書き紹介します。P.73 江州彦根の近在に、豊郷という村があります。そこには昨年六十幾歳を一期として此の世を去って行かれた、世にも殊勝なる豆腐屋さんがいました。彼は毎日たった三箱の豆腐をつくること、それを終生の仕事としていた。来る日も来る日も、三箱の豆腐に自分の全心を打ちこんで、気に入ったものを作り上げることに、無上の楽しみと喜びとを感じていた。さすがに味がよいので直ぐに売り切れてしまうが、いくら売れても、三箱以上は決して作ろうとしなかった。これだけ作らせて戴いたら、之で私の力一杯であり、これ以上に手を拡げると、自分の意に満たぬ粗末なものを作ることになる。自分は冥加をおそれる。まあまあ三箱に止めて置こう、というのが爺さんの一貫した心持であった。 そこで爺さんは、自分の力相応の仕事をして、皆からうまいうまいと褒められて喜びながら、自分のなりわいを立てさせて貰って、乏しいながら、自分も妻子も何不足なく家業に養われて行く、それがただ有り難く、勿体ない。彼は日々家族のものと共々に報恩の行として日々の仕事にいそしみながら、彼の道心を静かに養いながら、その素朴にして麗しき一生を終わって行ったのであります。彼は少しも世間に知られることなく静かに彼の生涯を終わって行ったのでありますが、この爺さんの如き真に「一隅を照らすもの」と言うべきであると思うのであります。 「照于一隅」という言葉は、伝教大師の山家学生式(さんげがしょうしき)というものの中に、大師が古人の言として引かれたものです。山家学生式というものは何であるかと申しますと、伝教大師が叡山に於て、国民の指導者を養成されるため学則を定めて、嵯峨天皇に上って勅裁を請われた式文(しきもん)であります。あの鎮護国家の大理想に燃えておられた大師が、いよいよ将来、我が国民指導の任に当たるべき青年学生を養成する具体案を樹て、その指導精神を明らかにせられた宣言書といってもよいのであります。しかも、これは弘仁九年の五月に出されたので、弘仁十三年の六月には大師は五十六で遷化して居られますから、五十二の時のことで、謂わば大師の晩年に書かれたものであります。大師は式文の最初に
国宝とは何物ぞ。宝とは道心なり。道心あるの人を名づけて国宝と為す。故に古人の言はく径寸十枚是国宝に非ず、一隅を照らす、此れ即ち国宝なりと。 古人というのは斉の威王のことで、径寸十枚というのは一寸もあるダイヤモンドという程の意味でありましょう。かつて魏の王様が斉の威王に向かって「私の国にはこのような大きなダイヤが十個もある、これが私の宝だ」と誇り顔にいうと、威王は「私の国では一隅を照らす人が沢山いる、それが私の国の国宝だ」といった。それを大師は引かれたのであります。大師の養成されようとする学生も亦、この一隅を照らすものになったのであります。 然らば、一隅を照らすとは如何なる人であるか、それは即ち「道心あるの人」をいうのであります。道心を以て明るく一隅を照らしている人の謂いであります。そして、これこそ真に国の宝あるとせらるるのでありましょう。国の宝は、決して財宝ではなく、人である。道心あるひとである。国家の構成分子は人であるが、その人の、複雑を極めた日常生活が何よりも先ず、道心によって統一されなくてはならない。その道心を基礎とし、道心に統一せられ、道心に照らされて行く人、そういう人が国家にとっては何よりの宝である。そいうしっかりした人を先ず叡山の自分の手元で育てて、その学生を全国にやって、日本国民の一人一人が一隅を照らすものにすること、それを大師は理想とせられていたのであります。でありますから、大師のお心持からすれば、仮令、名僧知識というような、名声天下に轟く人でなくてとも、軍人であれ、官吏であれ、商人であろうと、大工であろうと、百姓であろうと乃至は豆腐屋さんであろうと、紙屑屋さんであろうと、苟も内に深く道心に燃えつつ、朗らかにその日その日の仕事にいそしみ、その職業をよろこんで果たしているならば、それが、即ち、「一隅を照らすもの」だと申します。ここに国の宝といわれる更に深い意味があると思うものであります。 参考1:昭和五十三年四月二十日発行 住 友 修 史 室 参考2:田中良雄さん履歴:住友本社常務理事:写真の本は、昭和59年10月8日、住友生命保険相互会社よりいただいた。 参考3:住友電工
親しくしている方から、下記のメールがおくられてきました。 この最澄の書き残した言葉と言われます「照于一隅」は、本当は違う意味だということらしいです。 長いこと、『照干一隅 此則国宝』と読み解釈されてきましが、最澄の真筆を見ますと、『干』ではなくて『千』だそうです。すると解釈が、「一隅にありながら千里を照らす逸材こそが国の宝である」となります。 最澄が参考とした中国の出典の原義も、「千里を照らす優れた才」の意味だそうです。さらに、「一隅」は隅っこの意味でなく「今存在するその場所」という意味のようです。 新しい解釈だと、『照千一隅』の元の意味は、多分「千里を照らす才」となり、『照千一隅 此則国宝』は、「どこにいても才能のある人はその才能で千里を照らす、そういう人こそ国の宝である」となります。謙虚な意味は、無くなります。 最澄は、中国人が望んでいる立身出世の「偉人が千里を照らす>の理想を日本人に伝えたかったのでしょうが、日本人は、思いに反してこの言葉を自分たち心の琴線にふれるように、「社会の片隅でこつこつと自分の職務を精一杯遂行することこそ、実は最も尊いのだ」というふうに改訳してしまったのではないでしょうか。 ありがとうございました。 |
30河井 寛次郎 (1890~1966年)

河井寛次郎さんの作品が大原美術館に沢山展示されている。 一 眼聴耳視 「眼で聴き 耳で視る」 「眼で見て、耳で聴くのではなく 眼で聴いて、耳で視よ」という。 これはすなわち、視覚や聴覚が大事なのではなく、心で感じることこそが肝要なのである、ということであろう
略歴 1890(明治23)年8月24日島根県安来に生まれる。 松江中学校卒業ののち、東京高等工業学校窯業科に入学。 1914(大正3)年、京都陶磁器試験所に入所。 大正9(1920)年、現在の記念館の地、五条坂に住居と窯を持ち独立、つねと結婚。大正13年には娘・須也子をもうける。 大正10(1921)年、「第一回創作陶磁展」を開催、以降生涯にわたり、作品を発表。 作風は 大きく、三期に分けられる。中国古陶磁を範とした初期、「用の美」の中期、「造形の後期」。 昭和12(1937)年に、自らの設計により自宅を建築(現在の記念館)。 昭和41(1966)年11月18日、76歳で亡くなる。 |
 これについて、その真実を浮彫りにした名著が上梓された。橋口収著『饒舌と寡黙』。周知のように、著者は国土庁初代次官として現職にある人。かねて名エッセイストの名が高い氏は、この本の「忘れられた海軍大将」という一章においてこの提督の生涯を描くとともに、「ソフィスティケイテッド・ソフィスティケ―ション」という心からの賛辞を呈している。
これについて、その真実を浮彫りにした名著が上梓された。橋口収著『饒舌と寡黙』。周知のように、著者は国土庁初代次官として現職にある人。かねて名エッセイストの名が高い氏は、この本の「忘れられた海軍大将」という一章においてこの提督の生涯を描くとともに、「ソフィスティケイテッド・ソフィスティケ―ション」という心からの賛辞を呈している。
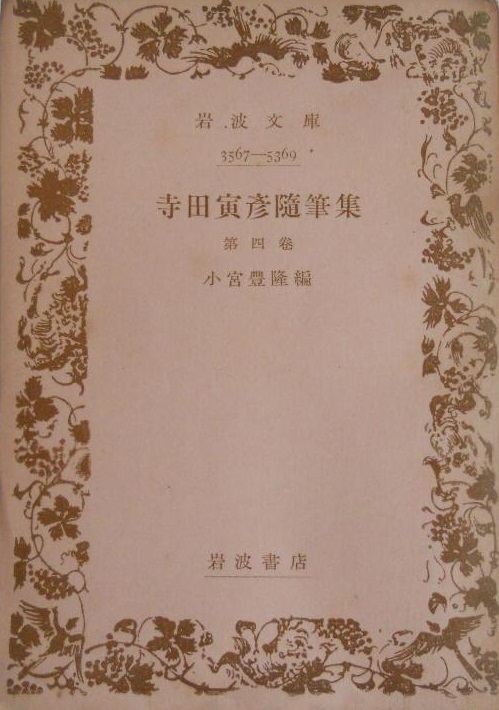 所謂頭のいゝ人は、云はば脚の早い旅人のやうなものである。人より先に人の未だ行かない處へ行き着くことも出来る代りに、途中の道傍或は一寸した脇道にある肝心なものを見落す恐れがある。頭の悪い人脚ののろい人がずつと後からおくれて来て譯もなく其の大事な寳物を拾って行く場合がある。
所謂頭のいゝ人は、云はば脚の早い旅人のやうなものである。人より先に人の未だ行かない處へ行き着くことも出来る代りに、途中の道傍或は一寸した脇道にある肝心なものを見落す恐れがある。頭の悪い人脚ののろい人がずつと後からおくれて来て譯もなく其の大事な寳物を拾って行く場合がある。
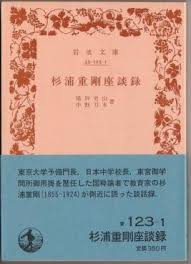 『杉浦重剛座談録』猪狩史山(いがり しざん)中野刀水(なかの とうすい)著(岩波文庫)1986年4月4日 第9刷発行
『杉浦重剛座談録』猪狩史山(いがり しざん)中野刀水(なかの とうすい)著(岩波文庫)1986年4月4日 第9刷発行
 ▼『秀吉と利休』中央公論社 昭和三十九年二月二十日
▼『秀吉と利休』中央公論社 昭和三十九年二月二十日

 私の本棚には小泉信三『海軍主計大尉小泉新吉』(文春文庫)があった。購入日:1975.1.31と記載していた。(2017.10.21も現存)
私の本棚には小泉信三『海軍主計大尉小泉新吉』(文春文庫)があった。購入日:1975.1.31と記載していた。(2017.10.21も現存)