改 訂 版 2022.11.11. 改訂
| 01 | 〔サヨナラダケガ人生ダ(P.48)〕 | 02 | 〔出 会 い(P.61)〕 | 03 | 〔將に將たる器(P.131)〕 | 04 | 〔悲運の総理大臣(P.164)〕 |
| 05 | 〔「見てくれ」の処世術(P.195)〕 | 06 | 〔己の何を捨てるか(P.227)〕 | 07 | ****** | 08 | ****** |
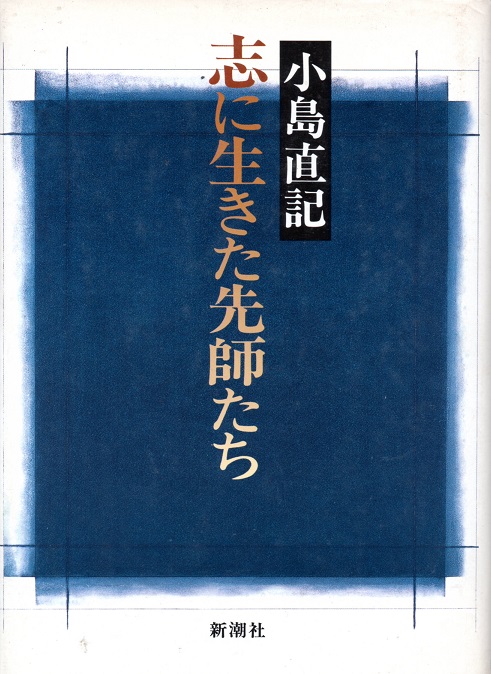
第七話 サヨナラダケガ人生ダ 小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)(昭和五六十三五月二十日発行)P.48~54 テレビで井伏鱒二の特集があった。画面を見ながらある旧友のことを思い出したのは、その友人がこの作家を「ドジョジ」とよんでいたあからである。「鱒」をドジョウと読むものと思いこんでいたらしい。 彼は歯科医専で東京。筆者は旧制高校で福岡。毎週手紙をやりとりしていた。筆者が上京すると、同じ下宿でくらしはじめた。 筆者が海軍に入ったとき、彼は天津で開業していたが、筆者の母のために、学生時代の手紙を集めておいてくれたという。戦死するかもしれぬと思い、その形見にというつもりだったろう。 そのうち、彼も海軍にとられた。はじめ通信兵で、内地の通信学校にいた。しかし、やがて歯科専門の軍医となり、巡洋艦にのりこんだ。そしてフィリピン沖で艦と運命を共にした。 井伏鱒二の面影は、友人「ドジョジ」君とオーバラップしてなつかしくてたまらない。終ってから『井伏鱒二集』をとり出して、『集金旅行』などの名作を読んだ。 どれもすばらしく、なつかしい作品ばかりだが、とくにその夜は、詩作品が心にしみた。その中でも、中国の詩の翻訳がとくによかった。たとえば于武陵の「勧酒」は、 勧君金屈巵(きみにすすむきんくつし) 満酌不須辞(まんしゃくじするべからず) 花発多風雨(はなひらいてふううおおく) 人生足別離(じんせいべつりにみつ) というのが原文だが、井伏訳では コノサカヅキヲ受ケテクㇾ ドウゾナミナミツガシテオクレ ハナニアラシノタㇳヘモアルゾ 「サヨナラ」ダケガ人生ダ となっている。翻訳の域を超えた絶妙の作品と思うがいかがなものか。 地方講演に行くとき、筆者は小型のテープ・カセットをもって行く。テープは、モーツァルトの交響曲四十番。見知らぬ土地の夜ふけのホテルで、じっとこの局に耳をかたむける味はたとえようがない。ところが、 「どうしてその曲か?」 と従兄がいった。 「自分の葬式のときの曲だから」 と答えると、 「縁起でもない!」 と一喝されたわけである。 縁起とは関係なく、自分の死のことを考える人は、昔からいっぱいいる。それを端的に示すのは「遺言」だ、森鷗外は、 「遺言には随分面白いのが有るもので、現に子規の自筆の墓誌抔も愛嬌が有つて好い。樗牛の清見潟は崇高だろうが、我々なんぞは、趣味が違ふ。西洋の昔の人の中で、最も面白く感じたのは、第十三世紀に死んだ独逸詩人 Watlther von Vogelweide の遺言だ。それは西洋の風習どほり、地面と平らに匾い石を置いて、其石に窪みを四つ彫り込ませて、それに麦と水とを入れさせて、鳥に飲ませたり食はせたりしてもらひたいというのであつた」 と書いたことがある(『妄人妄語』)。 ところが本人が書いた遺言は、まるきり別のものだった。 大正十一年七月九日、森鷗外没(六十一歳)。その三日前、親友に口述筆記させた遺言状は、 「余ハ少年ノ時ヨリ老死ニ至ㇽマデ一切秘密無ク交際シタル友ハ加古鶴所君ナㇼ。ココニ死ニ臨ンデ加古君ノ一筆ヲ煩ㇵス 死ハ一切ヲ打チ切ㇽ重大事件ナリ 奈如ナル官憲威力ㇳ雖モ此ニ反抗スㇽ事ヲ得ズト信ズ 余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス 宮内省陸軍皆縁故アレドモ生死別ルル瞬間アラユル外形的取扱ヒヲ辞ス 森林太郎トシテ死セントス 墓ハ森林太郎墓ノ外一字モホル可カラズ 書ハ中村不折ニ委託シ 宮内省陸軍ノ栄典ハ絶対ニ取りヤメヲ謂フ 手続ハソレゾㇾアルベシ コレ唯一ノ友人ニ云ヒ残スモノニシテ何人ノ容喙ヲモ許サズ」 というものであった(段落、句読点は原文とちがう)。これを要するに、ここに示されているのは、自分の死と葬式とを、世間が形式上どう取り扱うかに対する何人の容喙も許さぬ本人の指図である。 つまり、死と葬式に対する世間的形式上取り扱い、これが文豪のこの世にかけた最後にして最大の気がかりごとであったことを示している。 われら在野の売文業者からいえば、そんなことが気になるほどなら、さっさと陸軍などはやめてしまって、ペン一本で生きればよかったじゃないか、といいたくなる。世間がどう取り扱おうと、そんなこと関係ないじゃないか、と不思議である。 その死を世間がどう扱うか。 たとえば山縣有朋は、鷗外と同じ大正十一年二月に八十五年の生涯を閉じた。そのときの肩書は、「枢密院議長元帥大将従一位大勲位功一級公爵」 位人臣をきわめた彼には「国葬」の勅令が公布され、二月九日日比谷公園で国葬の儀が行われた。これについて阿部慎之助は、 「私は新聞記者として、いくつかの国葬というものを見てきた。国葬となると元勲と称せられる人々は、本来的に民衆の友ではなかった。それでも私は山縣の国葬ほど、寂莫たるものを見たことがなかった。葬場は日本の国の内にある。だが民衆の国境から遠くかけ離れた、離れ島にあるような感じがした。山縣という人間は、民衆からこんなにも縁のない、むしろ憎しみの的となっていたのである」 と書いている。 片や、鼎軒田口卯吉は、明治三十八年四月、五十一歳で世を去った。 本郷春木町中央公会堂で告別式がいとなまれ、谷中墓地に葬ることになったが、当日はあいにくと雨天であった。ところが途上、葬列にあったものは、田口の棺だときくと、みんな雨の中に脱帽して敬意を表したのである。 田口はどういう人だったか。 幕臣の家に生まれ、維新の変動で逆境に立った。家計を助けるため、横浜で夜店の番人となったこともある。 官費の大蔵省翻訳局上級生徒となり、二十歳のとき十一等出仕、月給三十円。役所でお雇い役人シャンドに、エコノミストのことで質問し、日本の国力ではとてもダメだといわれて、発奮した話は前々話でのべた。 彼は経済雑誌を出すため、役人をやめた。はじめは渋沢栄一のバックアップで、銀行業界の資金援助をうけたが、間もなくこれを辞退した。やがて「三菱」への政府援助の可否をめぐり、犬養毅との間に日本最初の経済論争を行う。 田口のレッセ・フェール(laissez-faire:自由放任)説、犬養のマーカンティリズム(重商主義、保護主義)説、それぞれに一理ある。 犬養はしきりに英語まじりの衒学趣味を発揮した。田口は額面どおりうけとって、 「犬養は豊富な外国の原典を渉猟して自分に対抗している」 と考えた。それに負けないよう、自分も原書をそろえたい。けれどもスポンサーとは縁を切って、雑誌の経営は苦しく、その余力はない。 「犬養は、三菱の金力を背景にして蔵書山のごとし」 と慨嘆した。 この思いちがい、滑稽だと笑えるだろうか。むしろ、この思いちがいこそ、評論家としての本質が出ている。 「論争とは、そういう研究と蓄積の上でするもの、すべきものだ」 と信じていたのである。 生前、大蔵大臣松方正義から、次官就任を懇望された。彼はことわった。死んでから、勲四等をもらった。山縣の勢力、位階勲等とくらべたら、まったく問題にならない。それでいて世間の人は、田口の棺だときくと、雨の中に帽子をとつたのである。 山縣有朋は、目白台の椿山荘にいて、天下をへいげいした。今日、田中角栄邸に集まる政客のように、文豪鷗外も目白もうでにはげんだ。 山縣は、歌人でもある。鷗外としては、山縣とのつながりを、あくまでも和歌の関係、文学上の問題だけだ、といいたかったかもしれない。 しかし彼は軍医総監、陸軍省医務局長になったあと、『古稀庵記』を書いている。 古稀庵は、山縣が古稀すなわち七十歳に達した明治四十年、彼の第七番目の別荘として、小田原に建てられた一万坪の豪邸。一説では、その愛人同士が姉妹関係にあった三井物産初代社長益田孝が建ててやったものといわれる。 鷗外の『古稀庵記』は全文およそ九百八十字、文中いたるところに山縣讃美の言葉がある。 「願はくは公爵の気高くををしきみ姿を猶年久に此山水の間に見てしかなと思ふ心をいささか書いつくるになむ」はその一例。文学も和歌も関係がなく、ただ山縣へのお世辞が羅列されているのである。 このため、死んでからもそのことをいわれる。辰野隆は武林無想庵との対談で、 「鷗外先生に会いにいったときに、ホンの茶呑み話のつもりで、むかし斎藤緑雨が文壇の寿命ということをいって、山寺の灯の如く明滅しながら命長かるべし、と鷗外のことをいった。それをいうと、鷗外先生、ブーッと怒っちゃってネ。(中略)そこでぼくは、なんだ、けちくせえナ、茶のみ話じゃねぇか、それを怒るなんて、なんだ、山縣の腰巾着奴と思いましたよ。とにかく料簡のせまい人だな、少くとも官僚だ。露伴とくらべると人間としてはずっと落ちますね」 といっている。「山県の腰巾着」といわれることを、鷗外は予測したかどうか。 2022.03.15記す。
|

第九話 出 会 い 小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)昭和六十年三月二十日発行 P.61~67 教育論議がさかん、中曽根内閣も教育問題に意欲を示している。 いいことにちがいない。しかし、論議がさかんなのは、弊害が目にあまるからだともいえる。また、議論の多くに「教育」と「学校」とをほとんど同一視したものがある。「教育は教師の仕事」という考え方もある。 そこに疑問と不満が残る。現代日本の頽廃、モラルの欠如、拝金拝物宗、人間の卑弱さなど、すべて「学歴社会」の当然の産物だが、それをつき破るエラン・ヴィタール(フランス:élan vital:黒崎記)が忘れられているのである。 明治・大正・昭和三代の言論史を通じて、スターと見られる人びとは何人かいるが、その中の一人、古島一雄(1,865~1,952年)は、 [学歴は?」 ときかれると、 「小学校だけ」 と答えていた。この人を、のちの言論史上のスターに仕上げたのは、まさしく学歴ではなかった。では何か? 第一に、「出会い」をあげねばならない。 前話でも書いた通り、十五歳のとき上京して、同郷の先輩、浜尾新のところにあずけられた。「出会い」の第一号は浜尾ということになる。 ところが、浜尾と古島の関係は必ずしもピッタリいかなかった。浜尾の書生になると、 「貴様学校へ行け、どこにするか」 という。そこで神田の共立学校にいくことになった。のちの総理・大蔵大臣高橋是清が英語の先生であった。ところがすぐ退校にになったので、高橋との縁は生じなかった。
それから二、三転校するが、行くところすぐ又退校退校。 「浜尾という人は温厚の君子で、その時分文部省の権大書記官、大学の総理補か何かしていたが、その人が保証人になって入学する。入学して片っ端から退学をくらう、どうもこまりきっていた。浜尾にしたら実際にこまっていたろうと思う」 この浜尾の書生時代、古島には「官僚ぎらい」の下地ができた。 「来る奴はみな官僚だ。それがみな頭をピョコピョコ下げておるのに、片っ方はふんぞり返っておる」 そのうち、浜尾の上司九鬼隆一がきた。 「これに対する浜尾の態度は慇懃を極める。どうしてこういう階級の差があるのだろうか。(中略)浜尾自身の上に対する態度と下に対する態度には非常な差がある。どうもいやなものだ」 そのうち、浜尾の親友杉浦重剛がイギリス留学から帰ってきた。浜尾は杉浦に古島を引きあわせ、 「こいつをどうかよろしくたのむ」 といってくれた。杉浦は承諾。これが「出会い」の第二号で、浜尾が第一号となったのは、この第二号の出会いの原因をつくってくれたからだといえる。 杉浦については別章でのべる。 杉浦のところに通っているうち、浜尾の家をとび出して田舎に帰るという事件がおきた。それは、 「お前はこれから何になるつもりだ?」 と浜尾にきかれ、古島が答えられずにいると、 「人間というものは志を立てるということが大事だ。それがなくてただ学問してもだめだから一つの目的をたてろ。日本で今一番大きな仕事は鉄道だ。鉄道ということについて誰もほんとうに学問した者はない。だからお前それをやれ」 といわれ、鉄道技師など、たまったものではない、と考えて家出をしてしまった。 やがて、見つけ出されると、日ごろ温厚な浜尾が非常な剣幕でどなりつけた。 「貴様のような奴はおれはよう世話をせんから国へ帰れ!」 浜尾はおどしただけだったかもしれない。だから、そのときあやまればよかったのだ。しかし古島は、 「帰れというなら帰りましょう。明日帰ります。金はありませんから金をください」 といって、あやまらずに郷里に帰ってしまった。 家へ帰ったが、父は婿養子で、おとなしい人だったから、こわくはない。ただ祖父だけがこわかった。 祖父は旧幕時代、但馬豊岡の京極飛騨守につかえ、勘定奉行であった。明治になってからは、藩主と士族の株をあつめ、「宝林社」という銀行のような事業を主宰していた。母親は、 「お前おじいさまのところへいってあやまりなさい」 という。あやまったところで仕方がないから、 「ただ今帰りました」 といった。すると祖父は別に叱らない。 「そちは論語を読んだことがあるだろう。論語の中に≪君子は既往をとがめず≫ということがある。おれはなにもいわん。遠路のところ帰ったのであるから、そっちで休息しやれ」 といっただけだった。 参考1:宮崎市定『論語の新研究』(岩波書店)P.191 61「哀公、社を宰我に問う。宰我、対えて曰く、夏后氏は松を以い、殷人は柏を以い、周人は栗を以う。民をして戦慄せしむるを曰うなり、と。子これを聞いて曰く、成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず」。(黒崎記) そのうち、母親から、家が経済的にこまってきている、ときいて、小学校の代用教員となった。 そして月給をもらうと、いろいろと新しい文房具を買ってきて、机の上に並べてたのしんでいた。ある日、祖父がそれに注目した。 「貴様それはどこから買ってきたか」 「こういうところで買ってきました」 「どうも貴様は、おれと同じ性分でこまる」 眉をひそめて、祖父はことばをつづける。 「これは骨董癖のようなもので、一つの趣味だ。貴様はどうもそれになりそうだ。たとえば一つの掛物をもつ。そうすると間もなくそれに飽いて、もっといい物が欲しくなる。ところが貧乏武士だから金はなし、仕方がないからそれを売ってからさらに新しい物を買う。こういうことを自分も今日までやってきた。しかし、こういうことをしていると、自然にそこに売買の気が生じる。いわゆる掘り出し物とか、売買によって利益を得ようとして、人間が非常に卑しくなる。いわゆる玩物喪志になる。若い者がそんなことになってはいかんから、よく考えろ。おれの家は勘定奉行で、殿様の株や士族の株を集めて金貸しをしているが、これは決しておれのものではない。すべて人のものだ。それをまちがえてはならん。おれの死後には一文の財産も残さんから、それだけ貴様にきかしておく。おやじにもそれをいうておけ」 おやじは養子なので、まるきり無視されていた。 祖父が死んだとき、十円足らずの金と、古い証文だけが残っていた。証文には棒が引いてあった。 「僕はそのとき祖父はえらい人だったと子供心に痛切に感じた」(前出、『一老政治家の回顧』) 小学校の代用教員では将来性がない。考えこんでいるところに、杉浦重剛から手紙がきた。開いてみると、 〽五月雨にしばし濁れる山の井の底の心は汲む人ぞ知る という和歌がただ一つ書いてある。 「僕はこれを読んで無限の感慨をおぼえた。人生知己の恩を感じた第一歩である」 当時、父は裁判所の書記をしていた。その友人が松江の裁判所にいた。父にいわれて、松江にいって採用試験をうけることとなった。 東良三郎という判事が試験官。古島は、問題にはすべて〇を書いて出した。ただ、他に書くことがないから、 「一体裁判の趣旨とするところは、論語にいう≪必ずや訟えなからしめん≫という、これが裁判の極致であって、法を論ずるのはそもそも末である」 ※参考2:宮崎市定著『論語の新研究』(岩波書店)P.287 291「子曰く、訟を聴くは、吾は猶お人のごときなり。必ずや、訟えなからしめんか」。 宮崎市定著『論語の新研究』で、該当の句に到達するには、他の『論語』の本の索引を調べて、論語二十篇のどの章にあるかを確認してからである。 という議論を書いて出した。すると東判事は、 「これは満点だ」 といって所長に報告、書記官に採用された。 裁判所長富永冬樹は、矢野二郎(東京高等商業学校初代校長)の兄である。古島を、娘と息子の英語の家庭教師にたのんだ。 富永は、古島を属官あつかいにしない。いっしょに食事をしたり、大いに優遇する。 すると、はじめは書記だと見向きもしなかった連中が、古島にお世辞をいうようになる。 「あなたの洋服はいい洋服ですね。これは新型ですか」 という判事までいた。 「何というゲス野郎かとおもって、それからいっそう官僚というものはイヤになってしまった」(前出、同書) 態度が変わらなかったのは、東判事ただ一人であった。 その頃、徳富蘇峰の『将来之日本』というのが出版された。こういうものを読むと、こんなところにくすぶっていてもしょうがない、という気持が強くなる。 裁判所長は好意的だから、ひょっとすると昇進させてくれるかもしれない。そうなると恩義が生じて出ていくことができない。早く見切りをつけるにかぎる、とおもった。 それから月給をためた。そして、「さすがに悪いとおもったから、東判事にも誰にも相談せず、いきなり辞表をぶっつけて、一路神戸へ飛んだ」 そして杉浦に手紙を書いた。すぐ来い、といってきた。 「今からどうするか?」 「わたしはもうおくれてしまった。これから大学に入る気はない。すぐ世の中に出たいとおもう」 杉浦は古島の性格を考えて「新聞記者」をすすめたのである。 ※関連:浜尾新の記事内容とほぼ同じ。 2019.08.13 |
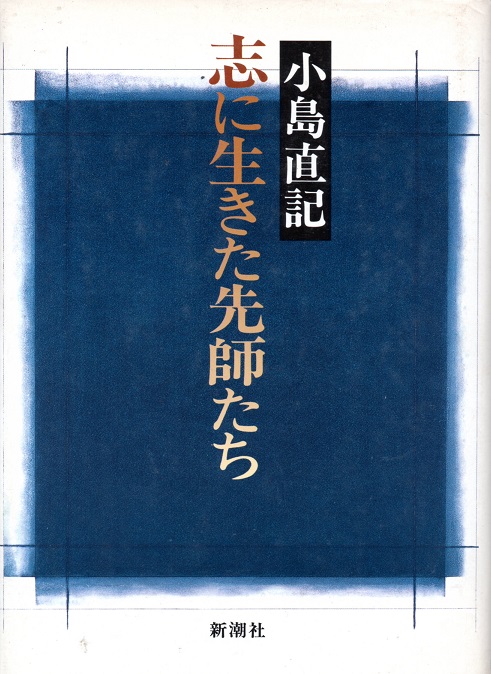
第十九話 將に將たる器 小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)昭和六十年三月二十日発行 P.131~137 児玉源太郎(1,852~1,906年)は五十五歳で若死にしたけれども、明治・大正・昭和三代の陸軍軍人中、もっとも優秀な人物であったという定評は動かない。 鵜崎鷺城の『薩の海軍・長の陸軍』は、再三くり返すように、海軍の山本権兵衛、陸軍の山県有朋以下、ときめく将星をコテンパンにやっつけている本だが、児玉に対しては変わった形で讃辞を呈している。 すなわち、桂は総理大臣に三度なるなど、出世頭といえるけれども、鵜崎によれば、その原因は二つあるという。 第一は、山県という大ボスの庇護をうけたこと。そして第二は、児玉が早死にしたことだというのだ。 また鶴見祐輔の『後藤新平』は、後藤の生涯、業績をのべながらも、おのずと児玉の偉大さを浮び上らせている。特に児玉その人を誉めようという意図をもたないでも、軍人世界とは別個のところで生きた人物の歩みに、おのずとその人柄が光るということは、決して誰にでもあることではないのだ。 日清戦争の結果、台湾は日本の領土となった。総督府がおかれ、初代樺山資紀、二代桂太郎、三代乃木希典と軍人総督が就任した。ところが、台湾行政の実体は土匪討伐で、拓地植民の仕事は何一つできなかった。 そこで、台湾放棄論、あるいは一億円でフランスに売却すべし、などの論を公然ととなえるものすらあったのである。 この難局処理の大任をおびたのが四代総督児玉源太郎であった。そして、その女房役の民政局長に選んだのが後藤新平である。 これには世間がアッといった。後藤は医者で、内務省の衛生局長である。 「うまくいって宮崎県知事ぐらいか」 とおもわれていた存在だ。それが、 「台湾統治というような、政治百般にわたる広汎な行政的経営の大任に堪え得るであろうか」(鶴見、前掲書) 「児玉以外にない」ということは「朝野の間に異論がなかった」が、後藤新平は、世間すべてからその適格性に疑問をもたれた。 その後藤が、歴代民政局長官中のベストという存在になったのは、本人自身の能力もさることながら、彼を信任し、能力を最大限に発揮させた児玉総督のおかげである。一口にいえば「将に将たる器」、それが児玉という人であった。話は明治時代の植民地台湾のことといいながら、児玉がいかにしたかは、トップ・マネジメントの好参考といえるだろう。 後藤新平は後年、つねに近親者に語って、 「人間は仕事をはじめるときは、いつも最悪の場合を考えておかなくてはいけない。戦にしても、進むのはやさしい。本当にむずかしいのは引けどきだ」 と語ったという。 スカウトされて台湾にいったのは四十二歳だが、後藤はいつも机のひき出しに三百円入れておいた。なぜか。 「その時分は役人が免職になって帰るときには、三月たたないものには帰る旅費をくれなかったものです。それでおれも覚悟していったんだから、いつ免職になってもいいように、机の引き出しにはいつも旅費として三百円入れておいたものだ。それを妻が見てね。あの金はどうするんだというから、あれはおれが免職になったときに使う金だ、といって、それだけは使わずにおいたのであった」 と後藤は語っている。在台十年間、彼はつねに「最悪の場合」を覚悟して仕事をした。そして、ついにその場面が生じなかったのは児玉のおかげである。 後藤はもとより凡才ではない。しかし、頭のよさという点では、児玉の方がはるかにまさっていたらしい。 「港湾の修築のことでも、殖産のことでも、製糖のことでも、藍の栽培のことでも、そういう技術的な話をしても、児玉さんに話をすれば十分でわかることならば、後藤さんはやはり二十分ぐらいはかかった。私ならどうしても二時間ぐらいはかかるとおもう。児玉さんは、まるで電光のようにピカピカする鋭さを呈していて、身体全体が花火であるかのごとくピカピカしておって、その話の整然としておることおどろくほどであった」 と新渡戸新渡戸稲造の言葉である。 こういうカミソリのような頭脳の持ち主は、たいてい部下のやることは気にいらないだろう。「陸軍きっての干渉家だ」といううわさを後藤もきいていた。 ところが現実はちがっていた。児玉総督は着任して間もなく、後藤民政局長に対して、施政方針演説の草稿をつくるよ命じた。後藤は、 「そんなものは、やらん方がいいでしょう」 という。児玉は理由をきく。 「それは今まで樺山さんもやりました。桂さんもやりました。乃木さんもやりました。それは詩人が詩をつくるようなもの。つまらないから、やらん方がいいでしょう。施政方針の演説をなさらぬことを、不審におもってききにきたら、おれは生物学の原則にしたがってやる、とおっしゃればいい」 「生物学というのは何じゃ?」 「それは、慣習を重んじること。ひらめの目をにわかに鯛のようにしろといったて、できるものじゃありませ。慣習を重んじなければならんというのは、生物学の原則からきています」 「そうかそうか。そんなことか。よしよし、それじゃ止めよう」 児玉は後藤の意見を採用した。それは、施政演説をしないということの、二つの理由をピシリとつかんだからだった。 それは第一に、植民政策の要諦は、不言実行にあるということだ。どんなに美辞麗句をつらねても、実現されない政策に対して、原住民は馬耳東風である。 第二に、すべての植民政策は、その植民地の民度、風俗、習慣に従わねばならぬ。それを後藤は「生物学」と表現したのだ。 児玉は知っていた。日本政府の根本的弊害の一つは、法律制度だけを中心とする形式的政治である。それは日本の官僚、政治家の大半が、法律科出身にしめられていることによる。台湾統治の第一着手は、法律万能主義の打破でなければならぬ。 児玉は、後藤の真意を正しく洞察していた。
児玉と後藤が赴任したとき、台湾領有以来二年半たっていた。しかし、統治はまだ手をつけたばかりで、総督官邸も地方の三等郵便局程度の貧弱のものだった。 そこで後藤は、まず総督官邸の建築にとりかかった。彼はいった。 「台湾総督は我国の南方経営の王座である。その官邸は善美をつくすべきである。わが輩は直属のオペラを設けたいとおもったのであるが、それは時節柄遠慮したのだ。これくらいの官邸をかれこれいうのは、わが南方経営を解せぬものの言である」 後藤の考え方は、統治しようとする本島人の性格をもととしていた。彼等は物質的人種で、黄金と儀礼と、社屋と宏園とが尊崇の的である。宏壮な官邸は、民の心服を買う一方便だと考えたのだ。 児玉は、その言葉を理解して、総督官邸の建築には反対しなかった。しかし完成しても、壮麗な総督室を居室としないで、階下につくられた民政長官宿泊用の小室を使った。そのため民政長官は、さらに小さい秘書官室に泊まるほかはなかった。 それをみた竹越与三郎(歴史家、政治家)は、「質素なる総督は……」というふうに書いたが、児玉自身はそうはいわなかった。 「乃木のは、倹素自ら身を持しているのじゃが、わしのはちがう。あんなピカピカした部屋は、わしの趣味に合わんからじゃ」 当時、台湾日日新報にいた尾崎秀真は、 「政治家としての児玉さんは、実に厳格そのもので、官邸にいるときはかならず勲章をさげて、厳然として本島人に接していましたが、日曜日になると、粗末な着ながしにわらぞうりをはいて、農民を相手に路傍で打ちとけた話をするというふうでした」 と語っている。 児玉総督にすべてをまかせられて、後藤民政局長(のち長官)は、無能怠惰な千八十人の役人をクビ切るなど、バリバリと革新政策を推し進めた。当然これは敵を多くつくった。 「台湾の統治は、今の民政長官がわるいから、あと三十日は保たない」 と総理大臣山縣有朋に直訴したものもいる。 ところが、かんじんの児玉が、 「後藤がわるいことはないのだ」 といって、全然とり合わないため、後藤には何も影響はなかった。 しかし、難問は別のところにもあった。 台湾領有は、日清戦争の結果。そこで、 「この島はおれたちがとったんだ。またおれたちが守るんだ」 という意識をもって、軍人たちの鼻息が荒かった。後藤は、陸軍参謀長立見少将、台北旅団長内藤少将、台中旅団長松村少将、台南旅団長高井少将などを清涼館という料亭に招待したことがある。 そのとき、後藤は公務のため、招待した時間におくれ、七時すぎにかけつけた。すると客のなかの松村少将が、 「なぜ主人たるものがおくれてきた」 とネチネチからみはじめたのだ。その遠因は、軍人の腹の中にあった文官政治=児玉の威を借りて大きな顔をしている民政長官への反感にある。 あまりしっこいので後藤は腹を立て、売り言葉に買い言葉、口論どころか、少将の頭をポカポカとなぐりつけてしまった。 その晩、辞表を書いて、翌朝、後藤が前夜のことを報告すると、 「それはよかった」 と児玉はいって、とがめなかった。その晩総督はまた陸軍将官たちを招いて、 「国家の柱石たる軍人が、台湾の新版図において酔い倒れるとか、文官と軋轢するとか、格闘するとかいうような行動をとられることは、はなはだ遺憾に感ずる」 と一本きめつけた。民生部に対する軍部の圧迫は、このとき以来なくなった。 2019.08.16 |
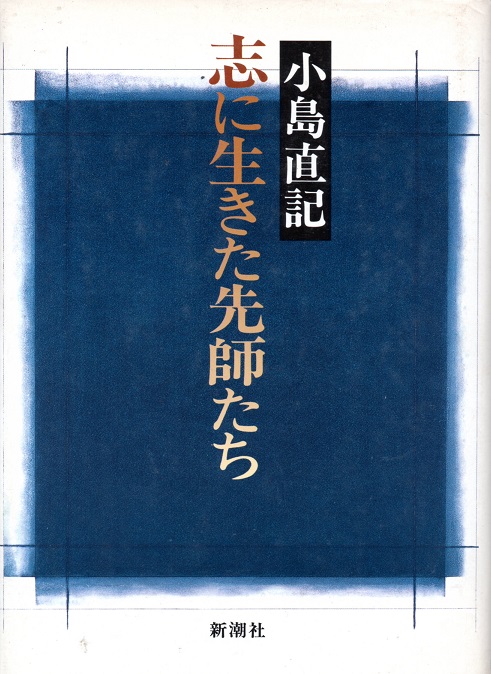
第二十四話 悲運の総理大臣 小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)昭和六十年三月二十日発行 P.164~169 明治十八年内閣制発足のときから、海軍大臣のポストはほとんど西郷従道が独占していた。彼以外には樺山資紀と仁礼景範の二人がわずかの期間、その席にあったにすぎない。 それが明治三十一年第二次山県内閣のとき山本権兵衛にかわった。 山本海相は次官に齊藤実大佐をばってきした。 これが「異例の人事」といわれたのは、第一に西郷五十六歳、前次官伊藤嶲吉(またはしゅんきち)五十九歳だったのに、山本が四十七歳、斎藤が四十一歳と、大幅若返りが実現したからだ。 第二は、西郷が元帥海軍大将侯爵、伊藤が中将男爵という肩書だったのにくらべ、山本も齊藤も爵位がなかったことである。ことに斉藤は一大佐、しかも大佐になってから一年にも満たなかった。当時の海軍省では、軍務局長が少将諸岡頼之、水路部長が少将肝付兼行で、斎藤次官は一大佐の身で、これら先輩将官の上に出たわけである。 二人はやがて海軍の頂点に立つ。 海軍大将で、のちに学習院長となった山梨勝之進は、 「山本権兵衛大将の前に立つと、爛々とかがやく灼熱の太陽の前にあるおもいがする。加藤友三郎大将の前に立つと、何物をも一点の狂いなく映し出す名鏡の前に立ったおもいがする。斎藤実大将とともにあるときは、美しいサロンに坐し、香り高いウイスキーを杯に酌み、静かに語るおもいがする」 と語ったことがある。 関連:山梨勝之進 それぞれの個性のちがいをとらえた見事な人物評であるが、この評言が語るように、山本と齊藤とはまったくちがっていた。 まず山本が南国薩摩の出身であるのに対して、斎藤は東北岩手の出身である。 ただ二人の人生に共通して感じられるのは、常人にくらべて運命の影がとくに色濃いということである。
山本権兵衛は明治七年二十三歳、海軍兵学寮在学中に、学校をやめて郷里にもどり、西郷隆盛を中心につくられた私学校に入ろうとしたことがある。同級生の左近充隼太が行動を共にすることになった。 「母病気看護のため」という口実で休暇をもらい、本や衣類を売って大阪までの旅費にあてた。大阪には、鹿児島出身の五代友厚がいる。二人は三十円の借金を申し入れたが、 「お前たちの行動は、西郷に対する私情にとらわれた軽挙妄動である。ただちに帰校せよ」 と五代は説教して、金は貸さなかった。しかし二人が宿で寝ていると、まくらもとに「餞別」と書いた紙包みがあり、名前はなかったが五十円入っていた。 鹿児島に着いて西郷隆盛に会うと、西郷もまた五代と似たことをいって、二人の行動をいましめた。山本はその真意をさとり、 「今日から他を顧みず、一意海軍の修業にはげみます」 と誓った。 左近充は承知せず、いったん山本ともどったものの、また考えを変えて、鹿児島に帰った。 明治十年二月、私学校生徒一万数千人は反乱、三月には熊本城を包囲した。この頃、山本は艦務研究のため、ドイツ軍艦ピネタ号にのりこんでいた。そして南米沿岸を航行中、敗退した西郷軍はわずか三百人で城山にこもった。そして九月二十三日に総攻撃をうけ、西郷は自刃、左近充もこの間に討ち死していた。 このころ、ピネタ号はサルバルド港を抜錨し、大西洋を北上していた。その航路のはるか彼方に、帝国海軍の最高ポストが待っていたのである。 関連:左近充隼太
斉藤実は、幼名富五郎。実とは、明治八年十八歳、海軍兵学寮在学中に改名したものである。 その富五郎時代、近所の後藤新平と水沢の小川でよくいっしょに泳いだ。 新平は、自分で器用に髪を結いなおして、何くわぬ顔で帰ったが、富五郎はうまく結えないで、家に帰ると泳いだことがバレて母親から叱れた。 二人はやがて県庁の給仕となった。新平、富五郎、山崎周作の三人は「水沢の三秀才」といわれ、やがて志を抱いて上京することとなった。 富五郎は明治五年十五歳、大参事嘉悦氏房一行に加わって上京し、翌年二月、陸軍幼年学校を受験し不合格となった。 翌年八月、海軍兵学寮受験、合格した。六期生。 この入学試験の微妙なちがいが、のちの一生を決定したわけである。 海軍兵学寮は、明治二年創立の海軍操練所にはじまる。三年三月海軍兵学寮と改称、さらに九年八月海軍兵学校と改称された。 富五郎が入校したとき、イギリスから海軍少佐ダグラス(のち大将)以下三十四人の士官下士官水兵が招かれて、教授・訓練に関するいっさいの責任をおっていた。 したがって、教科書は原書、数学・砲術の講義から艦船の操縦、航海の練習など、すべて英語で行われる。 これは富五郎にとって大変なハンディキャップであった。入学試験は、漢文か英語か、各自の選択の自由にまかせられていた。英語を知らない富五郎は、漢文だけで入学できたのだが、ABCも知らぬ身には、イギリス人の講義、原書の教科書はチンプンカンプンである。 クラスメートで、のちに艦隊司令長官となった中将寺垣猪三の回顧談はその姿をのべている。 「記憶力が最も強かったが、一番感心したことはその勉強ぶりのいかにも緻密なことであった。 英人教師はときどき生徒をつれて実習場に出かけるのであったが、途中いろいろ説話しながら行くことが多かった。われわれ生徒の多くは教場の講義でないから気にもとめずにいたが、斎藤だけはそんなことを聞き逃さずにチャンとノートに控えておくという調子であった。あるときの試験に習ったことのない問題を出されたので、生徒一同辟易し、中には怪しからんなど憤慨するものもあったが、斎藤君はすまして答案を書いて出していた。あとで聞くと、そのとき出された問題は宿舎から実習場までの説話が課されたものであったから、斎藤君以外のうっかり連中は答案をかけなかったのである。 こんな風だから斎藤君は英語教師の口授は片言隻語も聞きもらさず、しかもその日のうちに必ず筆記しておくのであったから、英語の進歩もっともいちじるしく、在学中はいつも級長であったとおもう。 また斎藤君はすこしでも腑におちないことがあると、ノートを携えて教官のところへ出かけ、ことばの足らぬところは手マネで聞いてキチンと調べあげているのだった。だからクラスの連中は何かわからないことがあると、斎藤にきけというように、斎藤君のノートはクラスで有名なもので、私たちはそのノートにかなり厄介になったものである> この勉強の時代から三十数年たった明治四十三年十月から四十四年十月にかけて鵜崎鷺城は『薩の海軍・長の陸軍』を雑誌「日本及日本人」に連載した。ちょうど斎藤実が五十三歳から五十四歳のとき。この間彼は、四十一歳海軍次官、四十三歳少将、四十七歳中将、四十九歳海軍大臣(第一次西園寺内閣)、五十歳男爵となり、第二次桂内閣の海軍大臣をしているときだ。 鵜崎のこの評論は、日露戦争のあと、とくにいばりはじめた陸海軍将星をコテンパンにやっつけるところに特徴をもつ。ところがその毒舌評論でありながら、斎藤については、 「語学の才に至っては今の海軍将官を通じて恐らく第一人とすべし。かつて外国艦隊の来朝するやその招待席上において試むべき英語演説の原稿をわずかに二三時間にして草し、しかも字句の妥当を得て文法に適いしは専門語学者の驚嘆したる処なりき。彼の議会に臨むや一見茫洋として何等光彩を放たざるも、一たび口を開けば語簡にして要領をつくす。けだし彼は能ある鷹は爪をかくすの類か」 と賞めているのである。
山本権兵衛は、明治三十七年五十三歳、海軍大将となり、大正二年六十二歳、総理大臣となった。そして海軍大臣は五十六歳の斎藤実大将(前年大将となる)である。 しかし山本内閣はシーメンス事件のために倒れる。 参考:シーメンス事件:1914年に起こった日本海軍の収賄事件。独のジーメンス会社の元東京支店員のベルリンでの裁判中,海軍首脳の同社からの収賄が発覚,野党同志会の島田三郎らによる責任追及をはじめ世論の攻撃を受け,海軍首脳および三井物産の関係者が検挙され,第1次山本権兵衛内閣は総辞職した。(黒崎記) 山本がカムバックして第二次山本内閣を組織するのは大正十二年七十二歳のとき。しかし虎の門事件のため、わずか四ヵ月で退陣のやむなきにいたる。 参考:虎ノ門事件は、1923年(大正12年)12月27日日本の東京市麹町区虎ノ門外において、皇太子・摂政宮裕仁親王(後の昭和天皇)が無政府主義者の難波大助から狙撃を受けた暗殺未遂事件である。(黒崎記) 一方斎藤は、シーメンス事件の年、予備役となったが、大正八年六十二歳で朝鮮総督に就任。 着任のとき、京城駅頭で爆弾を投げられたが、無事であった。かつて中尉時代の二十七歳の時、アメリカのロチェスター付近で汽車が衝突し、山階宮、八田、坂本、森友、大久保などが重軽傷を負ったなかで、寝台車の上段ベッドにとじこめられて、あやうく窒息しそうになりながら助け出されたことがある。ともに彼の強運を物語るかのようである。 朝鮮総督辞任が昭和六年七十四歳。翌七年五・一五事件で倒れた犬養内閣のあとを受けて斎藤内閣を組織した。しかし、事実無根の事件といわれた帝人疑獄のため総辞職。 その後、十年末七十八歳で内大臣に任ぜられたが、その三月後の十一年二月二十六日、「二・二六」事件の凶弾によって殺害された。 「異例の人事」で世間の注目をあつめた海軍の両チャンピオン、山本権兵衛と斎藤実はともに総理大臣になったものの、ついに悲運をまぬがれることがなかった点でも似ているのである。 2019.08.15.終戦記念日。七十四年目。 |
|
第二十九話 「見てくれ」の処世術 小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)(昭和六十年三月二十日発行)P.195~201 テレビなどで売れっ子の某評論家が、 「もうこれからは《見てくれ》の時代だ。なかみよりも、表面を飾って、ひとを引きつけたものが勝つ」 というような趣旨のことをある雑誌に書いていた。自分自身の人気を背景に、世間――とくに次代の若者に教えてやる、という調子が感じられた。 ご本人は、人気もの、成功者としての高みから、新しい時代を先どりして警鐘を打ちならしたつもりかもしれない。 しかし、これはいささかも新しくなく、ましてや独創的な見解でもないのだ。 「東京の昔、すなわち江戸時代においてもっとも粋な人は、表を木綿にして裏に絹をつけた。渋いおしゃれとして今なお通人社会にもてはやされている。私はこれと反対に、表を絹にし、裏を木綿にすることをすすめる」 「勉強は、ただ勉強するばかりでなくて、勉強することを見せかけなければいえない。人によっては、俯仰天地に恥じず、おのれの心さえ正しければ、いかに非難をうけてもやましいことはないという。これは道理ある言葉である。けれども、単に自分の良心をなぐさめるだけならそれでよいが、出世の秘訣としてはとるべき手段ではない。メクラ千人の世の中には、自分が正しければ、その正しいことを人に知らせる必要がある」
ところで、福沢桃介も某人気評論家も、「見せかけの必要性」をいっているところは似ているが、根本においてはちがっている。
某評論家は、なかみ軽視の見せかけ論だ。しかし桃介式は、「見せかけ」が効果をあげるための条件を忘れずに書いているのである。 たとえば「出世の秘訣」という一章があって、そこに人を訪問するときの心得が書いてある。それは単にニュールックのスタイルでパリッとしていけばよいようなアサハカなものではない。 「初対面の人と会うには、その人のもっともヒマなときを選ばねばならぬ」 といっている。 そしてさらに、人によっては、いつ忙しいか、ヒマなのか、本人でもわからぬ場合がある。いつヒマかを知るのはむずかしいが、さりとて前もって電話で打ち合わせておくのは、友だち同士、平生交際している間柄ならばよいが、初対面で、しかもものをたのみにいくのは失礼にあたる。ヒマかどうか、どうして判断したらよいか。 これには、取次を擒にするがよい。取次(たとえば秘書)に、 「お客さんはたくさんありますか?」 「ご主人(あるいは社長さん)はお忙しうございますか?」 ときくべきである。 なお、きくばかりでなく、 「今日はお寒うございます」 「あたたかでございます」 などと挨拶する。なるたけ取次と懇意になるがよい。 「世の中でもっとも安いものはなんだ。タダである。タダより安いものはない。一銭の金よりも安い。言葉――お世辞というものはタダだ。タダのお世辞をいって人を擒にする。これが秘訣だ」 そして、忙しいということであれば、ただ名刺をおいて帰らなければならない。 桃介はさらに、応接間での心得をいう。 やっと面会を許されて、応接間に通される。しかし、先方がおかけなさいというまでは、決して椅子にかけてはならぬ。 それまでは立つているのが礼である。立ってモノをいう。またかけよといっても、かけない。再三いわれてからかける。 日本座敷の場合、下座にいて、主人がくるまで座布団の上にすわらない。 初対面の挨拶がすめば、まず一番先に、 「今日は何分間ほどお話したいのですが、よろしいでしょうか」 と都合をきいてみる。 自分(桃介)のような露骨な人は、今日は忙しいから、二分間話したらすぐ帰れというが、多くの人はそんなことはいわぬ。 いわぬは礼儀である。言葉をかえていえば、人心を収攬せんがためである。 [大官連中や、会社の重役等はみんな人心収攬を心得ている。いかにして人を悦服せしむべきかということに怠らず注意している。その人心収攬の秘訣はなんであるかというと、おのれを空しうして、人のいうことをきくにある」 ここで桃介は、大隈重信と福沢諭吉の実例をあげる。 大隈は、「聞くことの下手な人で、しゃべることの上手な人」であった。 福沢は、「聞くことの上手な人で、しゃべることも上手な人」であった。 この聞くことの上手なところこそ、福沢に大隈以上の徳望があった理由だ、という。 訪問客が大隈にモノをいうと、こっちのいうのを聞いたのか聞かないのか、要領を得ないうちに、大隈はしゃべり出す。 「だから、偉い人ではあるが、なつかしい人ではない」 福沢は、田舎のつまらぬおやじがきても、チャンとそのいうことを聞いてやる。そして「なるほど」、「うん」、「それからどうした」というふうに、ていねいに、熱心に聞く。 だから一つのことをいおうとおもっても、つい五つも十もいうようになる。そこでその人は、「福沢先生は、私のようなもののいうことを聞いて下さった」 というので、非常に敬慕される。 福沢にしても、くだらぬことを、一時間も二時間もしゃべられるのは、心持がよくないにちがいない。けれども、克己心が強い。それを忍んで聞いたのである。 また、非常に忙しい人だった。それなのに、くだらぬ話を、熱心に、力をこめて聞くというのは、じつに苦痛であったろう。それを忍んで聞いただけ偉いのである。 そのほか、桃介は教えている。 「決して長居すべからず」 「先方に多くしゃべらせよ」 「主人の見送りをことわれ」 主人は送りたくもなんともない。ただ、初めての人だから、敬意を表するために、いやいやながら送ってくる。いやと思うことをやらせるものではない。そこで、送ることは絶対にことわらねばならぬが、大切なのはそのときのセリフだ。 「私は今後もたびたびうかがわせていただくつもりでございます。一々お送り下さってはまことにあいすみません」 というのがいい。そうすると、次に行ったときは、先方が気やすくなる。こっちも気やすくなる。 「先方に用のできたときは速かに帰れ」 時間をあたえてもらって話しているうちに、電話がかかってくるとか、他の客がくるとかしたときは、話をやめてすぐ帰るがとい。 「先方に、不意の用ができたのを妨げるのはいけない」 要するに、ニューモードのスタイルなどではないのだ。「挙動をつつしみ、言葉を少なくし、できるだけ相手に対して好感情をあたえ、少しもいやなおもいをさせず、そしてなるたけ早く切り上げて、こっちの欠点を先方に知らせないというのが初対面の秘訣である」 「勉強を見せかけよ」といっているが、これよりもまた、単に見せかけるだけでは不十分だ、と桃介はいう。これと並行してやるべきことがいくつもある。 「上役より先に帰ってはならぬ」 「馬鹿らしく見えることが得であると同時に、また利口らしく見えることも得である」 都会人は、利口であると同時に利口らしく見せることを好む。ところが世間では、利口さよりも正直さを重く見る。「馬鹿でも正直の方がよろしい」 「上役の気風をのみこんで、それに同化せよ」 そしてここに桃介独自の人生観、処世術ともいうべき「金銭」のことが出てくる。 「上役に盲従するのは必要だが、盲従するにしても、その良心を鋭敏にして、一身をつつしみ、貯蓄することを忘れてはならぬ」 前話で書いたように、彼は、埼玉県川越の提燈屋の次男坊であった。貧しいために、学校にはだしで通った。 「友だちは笑うけど仕方がない。大きくなったら金をもうけて、今の貧乏を忘れたいと子供心にもしみじみおもったことがある」 と回想している。 しかし、この体験は幼い魂に陰影を残した。 「私は貧乏人の家に生まれたから、富者に対する反抗心が強く、金持ちになって倒してやろうと実業界に発心したことの、そもそもの原型はこのときにつくられた」 そういうことから、彼は油断をしない、工夫をこらす少年になった。それでなくては、友だちに勝てない、と思ったからだ。 処世のテクニック、絹を表にし、見せかけるという《見てくれ》戦術はその延長線上に生まれたものといえる。しかし、それをささえる内実のものを、決していいかげんにしないところが見事であった。 《見てくれ》だけで品物を買ってくれても、そのひとはイチゲンのお客でおわる。お得意の形成となる出会いの原因は、見てくれの奥に光る真実である。ごま化しのきかぬ品質である。 ※小島直記著『人材水脈』(中公文庫)P.229~233 「福沢桃介 体験からの処世術を説く偽悪派」参考。(黒崎記) 2022.03.17記す。
|
|
己の何を捨てるか 小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)(昭和六十年三月二十日発行)P.227~232 日本経済新聞昭和五十九年四月二十一日朝刊文化欄に、作家秦恒平の「わが脱サラの師・華岳」というエッセイがのっている。最近もっとも感動し、共鳴した一文であった。 筆者は、もと出版社の管理職にあったが、その社は昭和四十九年の春闘で揺れていた。五十人の管理職が社外へ退避して、都内を連日転々としたあげくに、ある朝社屋へ突入したものの、逆に組合員の袋叩きにあったりした。 筆者も叩かれた側の一人で、叩かれ叩かれながら、画家村上華岳の人と芸術を主題に、日々、小説『墨牡丹』を書いていた。それは三百三十枚の長編として完稿した。 争議のあと、自分の課で担当している月刊誌の遅れをとりもどしたあと、老社長退職の日に、未練なく社を退いた。 『墨牡丹』は、季刊誌「すばる」の巻頭に一挙掲載され、のち集英社の単行本となった。おなじ月に、別の社からも、六百枚の長編書き下ろし作品が出版された。 こうして、脱サラによる作家生活がはじまったわけだが、筆者の心にあったのは、村上華岳の生き方だった。 華岳は、これは「けっして隠遁ではない」といったそうである。 華岳は、国画創作協会の展覧会に秀作を出品しつづけていたが、五回展までで「懊悩熟考の結果、昭和二年からは決然として退」いた。「以後は神戸花隅の家に籠って、いわゆる官展や画壇との交渉をみずから断ち切ってしまった。三十八だった」 華岳は、これを「けっして隠遁ではない」といったそうである。 「よりよい自身の藝術を創り出すために断熱《淘げ》たまでで、むしろ《真の活動》に繋がると言っている。《淘げる》とはけだし淘汰するの意味であって、より本質的な道を選択して進むという、実践の意欲を籠めていた。また《世投げる》という批評も籠めていた」 華岳には、親がのこしてくれた「数軒のボロ家」があった。その家賃が、 「乏しいながらも、心静かに絵に打ち込ませる、有難い経済の支え」だった。 筆者は、こつこつ書きつづけよう、文壇という気ぜわしい世界のことは、意識しないでいい、と決めていた。経済の支えとなる「数軒のボロ家」もなかったけれども、 「淘げて淘げて、常にいつも《華岳》の決意が生きて残るならいい」 とおもった。そして、今もそうおもっている、大学から客員教授の招きがあり、好条件なのでかなり迷った。しかし、結局、うけなかった。 「第学側の好意に重々感謝はしながらも、断りの手紙を投函した瞬間、胸の底から清々した」というのである。 近頃、講演を求められるたびに、「勝負の仕方」というものに力点をおいた話をしている。 人生を「戦場」にたとえる人は多い。男は一歩敷居をまたいで外に出れば、七人の敵がある、といった人もいる。 そういう人生で、敗者とならぬためにはどうしたらよいか。 「剣道」の例を見よう。 剣をとって敵と相対したとき、一番大事なものは何であろうか、大衆文学の名手たちは、「構え」に力点があるとする。佐々木味津三の『旗本退屈男』、早乙主水之介が強いのは「双羽流晴眼くずし」のせいである。柴田錬三郎の眠狂四郎は、「円月殺法」によって強敵を斬り倒す。 しかし、その道の達人にきいたところ、大切なのは「構え」でなく、「間合い」、すなわち、敵と自分との間隔であるという。 斬られまい、として間合いをひろげれば、敵を斬ることができない。斬ろう、として間合いをちぢめれば、敵から斬られる危険性が大となる。 斬ると斬られるという絶対に矛盾するものの自己同一、生と死との表裏一体の境地に自らをおいて、「皮を斬らして肉を斬り、肉を斬らして骨を斬る」という紙一重の必殺戦法をとらないかぎり、敵は斬れないとのことである。 要は、「斬らして」という境地、自分の何を捨てるか、ということになる。人生にはパーフェクト・ゲームはないのである。 「伝記」の世界において、私がもっとも興味をひかれるのは、その人が、どういうとき、どういう勝負をしたか、ということである。世にあふれるいわゆる成功美談なるものは、この一点を見つめるとき、おのずとメッキがはげてゆく。 ましてや、単なる地位、肩書だけでそりくり返る人、いばる人の浅さ、おろかさも露呈する。地位、肩書は、剣道でいえば「構え」である。上段、中段、下段、晴眼、それぞれの構えにすべて意味がある。重要でないものはない。しかし、構えでは敵は斬れない。地位、肩書で斬れるのは、つまらぬザコにきまっている。 達人、本ものの強者は、間合いを大切にし、必殺の気合いで敵を斬る。そのナカミはテーマである。いのちをかけたテーマが、おのずと生み出すテクニックのもとに、喰うか喰われるかのきわどい一瞬、勝ちを占めるのである。前述のエッセイの例を引けば、「淘げる」こと、「より本質的な道を選択して進む」こと、「世投げ」の姿勢をとること以外に、生き残れる道はないはずでらる。 すぐれた先人には、いずれもそのことがある。たとえば藤原銀次郎の「脱サラ」の跡――。 参考:信頼できる男は誰か? 彼は、すぐれたサラリーマンであった。 慶應義塾を出て、二十六歳のとき三井銀行員となった。翌年、深川出張所所長。 行員たちは、唐桟の着物に角帯、前だれという服装で、格子の中にすわって事務をとっていた。 藤原は、内部を椅子、テーブル式にあらためた。 そのころ、第一銀行も三井銀行も、東京には本店があるだけで、支店はなかった。深川出張所は、深川に倉庫があり、そこにある米や肥料を担保に金を貸すだけで、預金業務はやらなかった。 深川の商人たちは、預金をするため、人力車をやとって本店までいく。千葉方面からも、わざわざ人力車で本店までいっている。 「預金の取りあつかいをしたら、お客さんはよろこばれるだろう」 と藤原はおもった。それまでの歴代所長は、だれ一人としてそう考えたものはいない。このアイデアは、本店の中上川彦次郎専務理事の理解、支持のもとに実施され、得意先に大いによろこばれた。 このあと、倉庫品担保の貸しつけ金利に新機軸を打ち出した。それまでは、すべて同一の金利をとっていたが、その中には、いつでも売って金になるもの、売るのに骨が折れ、危険がともなうものなど、いろいろ格差がある。この格差に応じて、倉敷料や利息に段階をつけたのだ。今日、倉庫業界はすべてこの式となっている。 月給は四十円からいっぺんに六十円となった。 二十八歳、富岡製糸所の、支配人となり、月給九十八円となった。 ここでは、女工の賃金が「家柄」と「美貌」で決められていた。藤原はそれをピース・ワークの出来高払い制に変え、合理化を達した。 三十歳、人事交流で三井物産に入った。三十二歳、台北支店長。三十八歳、木材部長となり、改革に大ナタをふるって、四十歳のとき、赤字を転じて黒字となった。四十一歳、南樺太の森林地帯を踏査して、パルプ会社創立を進言した。 そして四十二歳。いわゆる「厄年」に、王子製紙再建のため、出向を命じられたのである。 王子製紙は、その頃ドン底にあえいでいた。親会社の三井銀行にまで見放され、資金を融通してくれない。五十円払込の王子株は、五円台に落ちこんでいた。 「厄年にボロ会社を引きうけてどうなるか」 と引きとめる人が多かった。 しかし藤原は、尊敬する朝吹英二の説得をうけると、決然として王子行きにふみ切ったのである。ただこのとき、別の重大な行為もあわせ行っていることが見のがせない。 三井物産はボーナスの多い会社であった。物産の社員たちは、そのボーナスで派手な生活をしていた。ところが藤原は、そのボーナスには手をつけず、全部貯蓄して、毎月の月給だけで生活していた。 すなわち、王子製紙にいくことを決意したとき、かなりの金額の貯金ができていた。 常識から見れば、ボロ会社の再建は容易ではない。三井銀行でも見放した会社が、うまく立ち直る見こみは少ない。 となれば、その再建に失敗したあとの生活問題がある。貯金は、その備えとしてとっておく――それが普通のやり方であろう。 ところが藤原は、その貯金をすべてボロ株だという王子株に投入したのだ。そして、貯金がなくなると、家屋を担保にして借金し、その金をまた王子株に投入した。それからさらに、これらの株券を担保にして金を借り、それでまた王子株を買ったのである。 藤原は、失敗したあとのそなえを自ら捨てたのである。文字どおり、背水の陣。王子製紙の再建に生死をかけた。ボロ会社と生命を共にする覚悟、それがサラリーマンぐらしと決別し、経営者として新しく生きるための第一歩だったのだ。 まさに、間合いを心得た必殺剣法。 藤原は再建に成功した。株価は数十倍となって大きな財産ができるとともに、彼自身は「製紙王」として、日本実業界を代表する大物になったのである。 2022.03.19記す。
|
 退校の原因は他でもない。外務大臣などをした陸奥宗光の嗣子広吉がそこで学んでいた。「きれいな着物を着て、なんとなくのさぼっておるので、こいつやってしまえと、陸奥の頭を殴ったりし、それが原因で退校させられた」(『一老政治家の回顧』)
退校の原因は他でもない。外務大臣などをした陸奥宗光の嗣子広吉がそこで学んでいた。「きれいな着物を着て、なんとなくのさぼっておるので、こいつやってしまえと、陸奥の頭を殴ったりし、それが原因で退校させられた」(『一老政治家の回顧』)
 この言葉は、じつに七十四年も前の明治四十四年に本に出ている。書いた人は、実業家福沢桃介(1868~1938年)で、『桃介式』(実業之世界社)というのがその本である。
この言葉は、じつに七十四年も前の明治四十四年に本に出ている。書いた人は、実業家福沢桃介(1868~1938年)で、『桃介式』(実業之世界社)というのがその本である。