改 訂 版 2022.11.11. 改訂

『山』は不思議に相性がいい。柳田国男の作品では『山の人生』が一番好きだし、このところ山崎安治著『日本登山史』(新橋、白水社)を座右において楽しんでいる。 山と日本人との」かかわりあいをのべた本なので、当然古い昔のことから、現代の登山のことまで書いてある。千枚をこす大著であるから、忙しい人は一気に読了とまではいくまい。そのつど、何かのことをポイントにしてその部分の記述をたどるという味読法があり、私はそうしている。一昨年山形で羽黒山に行ったあと、この本の「中世の登山」の章にある「諸峰開山の伝説」を読んで感銘があった。 今年(一九八八年)は忙しくて、毎年行っているヨーロッパの旅も実現しない。そのかわり、いろいろと旅行記などを枕元に積んでおいて、手当りしだいに楽しんでいるが、田中尚四著『ヨーロッパ・アルプスの旅』(大学生協事業センター刊)でアイガーの美しい写真を見ていると、この登山史の「アルピニズムの勃興」の章の中の「槙有恒のアイガー東山稜登攀」を再読したくなったのである。 * 一昨年の秋、グリンデルワルトのホテルで休んでいるとき、槙氏が初めてここに来られたのは、自分の生れた大正八年であったことを思いだしたが、登山史の著者山崎氏も大正八年生れ、そこにいい知れぬ御縁を感じて愛着が深まる。 槙氏は明治二十七年宮城県生、大正六年慶応義塾大学法律科を卒業、七年アメリカのコロンビア大学に留学、八年イギリスにいった。同年十一月ジュネーブ、ベルンを経て十二月はじめグリンデルワルト村のホテル・アドラーに投宿。 ここでドイツ語と登山技術を学び、翌年夏、かねてからの計画を実行にうつした。エミールとフリッツのシュトイリ兄弟をガイドに、ヴェッターホルン(3700M)、ユングフラウ(4158M)、メンヒ(4099M)、アイガー(3970M)を踏破したのである。 「この夏の登山によって、雪線以上のアルプスの高峰がどれほどきびしいものであることを学び、岩と雪と氷と、低い気圧と気温、強い紫外線と激しい天候の変化のなかで、一本のロープに結びあい、互いに協力して自分の能力を最高度に発揮するには、難い意志をもって、敢然と山の持つ危険に立ちむかねばならぬことを身をもって知ることができた。そしてそこに新しい喜びが見いだされたのであった」(『日本登山史』) * アイガーは一八七四年ハート礼以来誰も登っていない。すでにイギリス、ドイツ、オスとリア、スイスの一流登山家が十二回も失敗していた。 大正十(一九二一)年九月九日、槙氏はアマタ―、フリッツ・シュトイリ、プラバンドを従えてユングフラウの鉄道のアイスメイアで下車し、アイガーの東山稜に取りついた。ジャンダルム(3500M)のわずか200メートルの岸壁を登りきるのに朝の九時から午後五時まで八時間を要した。十日午後六時四十五分、ついに頂上を極めた。 地元では花火をあげ、一行は胴上げされ、肩車にかつぎあげられた。村長は祝辞を述べ、着飾った娘たちは花束を贈った。 * この成功は、すでに鉄の時代を迎えていたヨーロッパ・アルプス登山史の幕開けを飾る成果であり、日本の登山家も新しい局面を迎えることができた。「槙の帰国によって、はじめて日本にアルプス的な登山の実態が理解されるようになった」(『日本登山史』)
* 『日本登山史』の著者山崎氏も『山男』であったという。巻末の「略歴」には、「一九一九年生~一九八五年没。一九四一年早大法学部卒。元日本山岳会常務理事」にあり、「著書」として『穂高 星空』、『剣(つるぎ)の窓』、『山の序曲』、『登山の基礎』、『登山史の周辺』があげられ、また「主要記事」としてマーリ『はるかなエヴェレスト』、ウエストン『日本アルプスの登山と探検』、ノートン『エヴェレストへの闘い』、セイヤ―『エヴェレストへの四人』、ボニントン『アンナプルナ南壁』があげられている。 また近藤信行氏の「巻後に」によると、山崎氏は小田原に生まれ、横浜に育った。早大在学中、山岳部員として大きな足跡を残した。復員後、日刊スポーツ新聞社で文化部長、整理部長、編集委員などを歴任。「日本登山史の研究という未知の領域に足をふみいれるのは、戦後まもなく大患にみまわれたからであった」という。 療養生活一年半、日本山岳会の機関紙『山岳』をはじめ、各大学の部報類を丹念に読みながらノートをとる、ということが登山史家山崎氏を生んだのである。 * 四十年近い研究の成果をふまえて二十巻の『日本登山記録大成』が完成したのは昭和五十八年。「いよいよ本格的な、密度の高い『日本登山史』の筆をとるときになった」と書いたのが五十九年五月。その年の暮、近藤氏の山の家に一泊したときは、集まった山仲間にむかって、気力に満ちた表情で一千枚を書き上げたこと、あと二、三ヵ月で完成すると語った。 それは昭和四十四年六月刊行『日本登山史』をもとに大幅な補正を行ない、詳細な註をほどこしていたものである。
「これ、のどにとおらないんだ、奈落の底におちていくようだ」 といって身を横たえた。そしてついに六十五年の寿命は尽き、続稿はならなかったのである。これは山の遭難ではなかった。だがこれまた「山男」の山に捧げた壮烈な死であることはまちがいない。 ※参考:「アイガー東山稜登攀」について、槙 有恒著『わたしの山旅』(岩波新書)Ⅴ章……P.64~86 を参考。 写真:アイガー東山稜 2023.05.25記す。
|
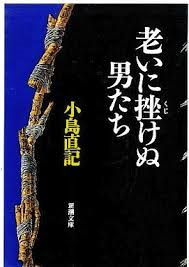
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.41~45 『中川一政全文集』全十巻(中央公論社)の出版が完了した。机上に全巻を重ねて、ホクホクしている。 「宝の山」といういい方をすれば、物質的期待感のニュアンスを持つようで語弊があるが、そういう卑俗なソロバンの次元を越えた、純乎として純な豊穣さが眼前に展開していて、胸が弾むのである。
「そんなバカな――」 と腹を立てることの多い六十代の末期だが、この本の前では『耳順』の気持ちになってしまう。 無論、自分の今の背丈では、よく理解できたというわけにはゆかない。しかし、素直な気持ちで鼓舞される魅力に満ち満ちているのである。 九十年に及ぶその広大な世界を、「ヨシのズイから覗く」楽しさだ。 * 『年輪』ということを学ぶのにいい、と思う。 第一巻から、アンダーラインを引き、ノートに書き写していったのは、まさに『年輪』の姿にほかならない。
『三十代』の言葉―― ――深い美を見ている画家は自分を未熟だと思っているものである。 ――芸術家は作品を作るが、一方に於(おい)ておのずからその顔を作ってゆくものである。 ――考うることは平生のこと。画(え)に臨んでは当意即妙であるべし。 ――負くべきものには負けては如何(いかが)。 遇うべきものには遇っては如何。 之に依って妄想無し。 画は物を愛することからはじまる。 ――男でもそうでありますが、女では尚更いろいろの目前にひかれて度胸を据える場所を浅い所で間にあわせます。 ――広く見るという事は大将の心、深く見るという事は参謀のする事。この分別と思慮を備えるのがよい鑑賞家です。一方は人の云う事に素直な態度で、一方は自分の心に素直な態度です。 ――何か心に持っている人は表面で見せかけません。 * (以上第一巻より) ――黄土(おうど:オークルジョウヌ)と黒(ノアル)とは極めて安価な色である。そして変色退色にじょいて最も堅固な色である。そればかりではなく、ただの黄土がルノアール(Renoir)によって金色に用いられる。また黒がただの黒色にあらずしてティチアールによって銀色に用いられたということだ。明君の人を用うる、その財能を見て長ずる所に従うというが、ルノアール、ティチアーノの如きは明君たるに違いない。 それと反対に金色を使って黄色に使い、銀色を使って黒にしか使えぬ画家あらばまさしく玩物喪志というべきだ。 ――応挙は家を見に行って、玄関を見てかぇって来たのである。 ――腹に力がない時画をかくと肩がはります。 ――私は一年の四分の一は旅行します。良い山や川を眺めるのは古人に逢うような思いがします。 ――私は文章を書くことで外から画の勉強をしていたと思う。画だけかいていたら職人になってしまったろう。 ――画かきを断念しようと幾度か思った挙句が、自分の才能など考えず、出来るだけの事をするより仕方がないと思った。腹がきまってきた。今思うと、短距離選手の走法をやめて長距離選手の走法をやり出したのである。 ――私はその腰のおろし方の深さによってその人間の資格も芸術の資格も決まると思う。
『四十代』言葉―― ――自分は「鉢の木」の主人公の如く鎧櫃(よろいびつ)に鎧を用意して、いざ鎌倉の時に武士たる事を得る武士だ。 ――私は諸国を歩く。 そして私の立っている処が安房の国の田圃の中だったり、陸中の山の上だったりする。と感じる。此の孤独を旅愁と云うのだろう。 ――病院から棺(森田氏の)と共に自宅へ運ばれたカンバスの中に、自分の葬式の次第をかくせよと図面まで描(か)いた紙片が出てきた。 ――森田恒友(つねとも)さんは知っていて、我々と生きている世界の話をしたのである。 ――森田さんは描く所よりも描かない所に気を籠(こ)めた。されば平凡な一片の水、一塊の土を描いてあの奥行きを示したのである。 ――木村荘八は林檎等を配した静物を岸田劉生に見せた。劉生は近視であったから手にとって見ていたが、これはここから切りとった方が構図がいいと無雑作に批判を下した時に、木村荘八は声を上げて泣いたのである。 ――木村荘八は特別の構えはなくとも、必要があれば立所に演説をし、手紙を書き、画を描くが、それは彼の多忙がさせたに違いないが、そこに彼の江戸っ子的禅機があるように思われる。 ――私は秩父へ写生に行った。 山の中は遅く日が出、早く日が没するのである。そして毎日同じコンニャク畑の画架を立てかけて仕事をするのである。 私は地平に落ちる日を絶えて久しく見ない。私はなかなか出来上がらない仕事を夜長と寒さに悩まされて、肩の骨が縮む気がする。 私の仕事は三月二日になった。南風が此の渓谷に入って天気が変わるようである。私は一先(ひとま)ず家に帰って来ようと画架を荷造りした。夜飯能(はんのう)駅へ着いた。
翌(あく)る日は雪であった。私は恐る恐るに荷物を開いて自分の労作をアトリエで眺めた。私は自分の仕事に失望して物も云えなかった。私には乾坤一擲の仕事だが、まだ一生懸命がたらぬのだろうか。 妻は、 「また敵討ち?」 と私の顔を覗きこんで悲しそうな顔をした。 私の心のかなしさを誰が知るか。 ――人の一生には焦点がある。学問も経験も才能もそこに集まって燃える時がある。その時を標準にしなければその一生はつまらない。 (以上第二巻より) 2023.05.23記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.51~56 その人は天草出身で、日本海海戦の夜、日本赤十字社の従軍看護婦として博愛丸に乗り組んだ。博愛丸は消灯し、従軍看護婦は盛装し、万一の場合を覚悟していた。 すると、闇夜を突いて後ろから二隻の駆逐艦が迫ってくる。バルチック艦隊の脱走艦ではないかと思って、博愛丸は全速力で逃げた。二隻とも全速力で迫ってくる。とうとう二隻に挟まれて、左右からサーチライトを浴びた。そして日本の病院船だと知ると、駆逐艦はサーチライトを点滅させて信号を送ってきた。 「バルチックカンタイゼンメツ」 甲板に整列していた従軍看護婦たちはいっせいに「バンザイ」を叫んだ。 * そのことが生涯に大きな影響を残し、ときには愛敬のタネともなる。次男坊が悪童にイジメられてきて、 「それでもわしの子か。すぐ行って仕返しをしてこい。それもできんようななら家に帰るな」 と叱りつける夫に、 「そうよ、そうよ。敵ハ幾万アリトテモ、烏合ノ衆ナルゾ。罪ハソレ正ニ勝チ難ク、味方ニ正シキ道理有りというじゃないの」 と相槌を打つ。 夜の暗がりで、柱に額をぶっつけると、物置から金槌を下げてきて、ボコッとへこむほど柱を打つ。痛さのあまりそうしなければいられないほど、腹が立ったのである。 中学に入った長男が外人教師のもとに通わされる。挨拶かたがたその人がついてくる。何冊かリーダーを読んで、いくらかわかるはずなのに、長男は外人教師に言葉が出てこない。するとサンキュウ、ノウサンキュウ、エックスキューズ・ミイ、プリーズ・シッダウンくらいの単語しか知らないその人が、その単語を駆使してペラペラとやる。ついに外人教師が笑って、日本語で言う。 「お母さん、イングリッシュ大変上手。貴方イングリッシュ下手ね」 その人は上機嫌で得意になっていいう。 「母さんは初めてサンキュウって言葉を覚えたきには嬉しくって。早く使ってみたいと思っていたら、外国人が通りかかったの。走っていって頭を下げて、サンキュウといったら外国人は目を丸くして驚いていたのよ。だから、またサンキュウといって頭を下げて逃げてきたの。あの頃は、私も大胆だったわね」 * 長男が中学三年生のとき主人が死ぬ。一高を志望する長男が、 「東京の予備校の模擬試験を受けたい。そうしなければ一高に入るのが難しい」 というと、その人は身を乗り出して、 「そうだね。そうおし」 と賛成する。息子が合格すると、歓喜のあまり、だれかれとなく、 「奥様。奥様は『嗚呼玉杯』を知っていられるでしょうか。ええ、そうです。一高の寮歌です。どうしたことか、うちのバカがその一高にはいりましてね」 と宣伝する。 その長男が文学かぶれで、一高を一年生の中途で退学する。するとその人も文学ばあさんになって、新潮社の『世界文学全集』のどれを読めばいいかと聞く。 「まあ、ドストエフスキーの『罪と罰』とフローベルの『ボヴァリー夫人』かな」 といわれ、天眼鏡を持ってきて昼となく夜となく読みつづける。大いに感動して横光利一を訪ねる、と言い出す。もどってきたので聞いてみる。 「なんといったの?」 「ドストエフスキー<の『罪と罰』は世界一ですね、といった」 「そしたら?」 「横光さんは『そうです。世界一です』と言われたよ。しかし、フローベルの『ボヴァリー夫人』も世界一ですねと言ったら、『そうです。それも世界一です』とおっしゃったよ。私もまんざらではないね」 長男が徴兵検査に行くとなると、「勝ってくるぞと勇ましく」と、まるで出征でもさすような勢い。 検査にハネられると、喜ぶどころかひどく心配して、どこか悪いのかもしれない、自分もついていくから病院で診てもらえという。 先ず日赤で、何の心配もないといわれる。その人は、伝研をはじめつぎつぎと大病院につれて行き、 「お母さんは、何としても息子さんを結核だと言ってもらわなければ、承知できないのですね。誰にも誤診というものはあるもんですよ。恐らく、息子さんは結核だと誤診されたんでしょう」 と医者に笑われるまではやめようとしなかった。 * 長男が真冬の樺太に行くと言い出すと、その人はわがことのように勇み立つ。「どうせ樺太に行くなら、果ての果てまで行っておいでよ。でも、松本だってこの寒さだろう。少々のことじゃ駄目よ。二、三日は待てるだろう」 たちまちひと抱えほども極太の毛糸を買ってきて、茶室を締め切り、食事の用意もそこそこに、二日二晩一睡もせず、二本合わせてセーター、ズボン下から靴下まで編みあげた。 * 戦後、長男が酒田にいるとき、今までは少なかったその人の手紙が多くなる。それにはいつも<私のことは心配することはない。お二人が幸福にしていられると思うだけでも、私は楽しい>という言葉が書いてある。 長男は、手紙の字がいつもと違うことに気がつく。おかしいと思って上京して弟の家に行ってみると、高血圧で倒れている。そして言うのだ。 <「んなからだになって哀しい。こんなからだになりさえしなければ、私はなにをしてでも、敦(あつし:註。長男)だけには好きなことをさせてやりたいと思っていたのに」 これはいけない、と思った長男は母を紀州に連れていくことにする。その人は大喜びをするが、容態急変して帰らぬ旅に旅立ってしまう。
* 森敦著『十二夜――月山注連寺にて』(実業之日本社刊)は、活字が大きくて読みやすく、心に余韻が残るいい本であった。 内容は、お寺で行われた十二夜連続の講演で、著者が自分の生涯を回顧するという形をとっている。その中でもっとも印象的だったのが『その人』母堂の姿であった。 ※参考:森敦著『月 山』(河出書房新社) 令和四年五月十日 |

小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.70~75 石光真清(まきよ)の自伝『城下の人』、『曠野の花』、『望郷の歌』、『誰のために』の四部作は、『自伝』のべスト5に入れるべきめぃ作だと信じている。 近頃、その四部作を一冊におさめた本が『石光真清の手記』(中央公論社)というタイトルで刊行されたのを機会に、久々に読み直す機会に恵まれた。そして、初めて読んだときと変らぬ感動をおぼえ、そのことを書かずにはいられない。それを一口で言えば、心が洗われた。最近、そういう本と出会うことが少ないだけに、一冊本の刊行によって生まれた新鮮な再会が実に有難い。 * 周知のように、『自伝』の傑作といわれるものに、ジャン・ジャック・ルッソオの『コンフェッション』がある。字義からいけば『告白』と訳したがよさそうに思われるこのタイトルの邦訳は、なぜか『懺悔録』となっていて、その一種の宗教臭がきらいだが、さらにきらいなのは内容だ。
ルッソオは「人権擁護」の戦士だということになっているが、実は情婦に生ませた私生児を捨てた男である。 フランス・ロワール河の沿岸にいくつもある城のうち、シュノンソオは特に見事だが、ルイ十五世の徴税請負人デュパンがその持主になったことがある。そこでデュパン夫人は二十六歳の若さでこのシャㇳオの女主人となり社交界の花形となったが、彼女の秘書として雇われたのがルッソオであった。 ルッソオが初めてやってきたとき、デュパン夫人は化粧部屋で引見した。そのとき、夫人は双腕(もろうで)をあらわに、髪をとき、長くくずしたまま、バス・ロープの前ははだけていた。 初めてそういう女性の姿を見たルッソオは、「頭から血が引き、めまいがして、そこに立つていることができなかった。ふるえだして、気が遠くなった」 と『告白』している。つまり、いかにウブであったかを強調しているのだが、実は十九歳のとき、すでにヴァラン夫人の若いツバメとなって、いわゆるただれた愛欲のお相手もつとめていた。したがって、あられもないデュパン夫人の姿をみて、<めまいがし、ふるえだし、気が遠くなる>ほどウブであったはずがない。カマトトとはこのことだ。 ルッソオ自伝には、こういうウソがある。『石光真清の手記』には、そういうウソがない。そればかりか、人間の真実、運命の過酷さ、大日本帝国発展過程の<縁の下の力もち>になった人々の哀れさを描きながら、その温かさで読者をつつんでくれる。読後感のすがすがしさが貴重である。 * 主人公真清(四男坊)は、陸軍幼年学校に入るため、船で横浜につく。出迎えてくれた長男真澄は、三井物産横浜支店に勤め、月給八円をもらっている。双子(ふたこ)木綿の着物に角帯、前だれかけというスタイルに、『士族』意識の弟は驚いて軽蔑の念がわき、「そのような服装で外国語で応対するのですか。外人が馬鹿にしませんか」 とたずねる。 「この服装は日本商人の正しいふく装だ。日本人が日本のふく装をするのに外人が笑うはずがないじゃないか」 と兄は答える。彼は誠実無比、曲がったことができない人物。支店長馬越恭平(まごしきょうへい)は自分のカンちがいで、帳簿がまちがいだと怒って、筆で黒々と線を引いたことがある。その担当が真澄で、 「商店の会計帳簿は神聖にしておかすべからざるもの、いかなる地位のものでもこれを毀そんし、無視することはできません。あなたがその無理を押し通すつもりなら、私にも覚悟があります」 と開き直る。閉口した馬越があやまっても聞かない。ついに馬越は、帳簿を神棚にそなえ、柏手を打っておじぎをすること三回、やっと許してもらった。 主人公たちの父真民は、西南戦争後間もなく死に、母守家(もりえ)は熊本にいた。それが病気になり、長男の結婚を見届けなければ死んだ夫に顔を合わせられないと言い出し、上京する。 真澄はその意向を受けて結婚するが、それは一ヵ月で解消。母は帰国すると言い出す。真澄は物産を退社して熊本に同行する。郷里で結婚するが、花嫁は結婚前に約束した男がおり、挙式後十日目に家出して行方ふ明となる。三度目の結婚をする。 真澄はなれぬ百姓仕事に精を出し、人力車を求め、それに母をのせ毎朝、毎夕散歩する。その前途を心配した叔父などの勧告で母も譲歩し、家族をつれて上京した真澄は、物産に復職する。三月後に妻がコレラで死に、物産も重役と衝突して退社する。その後、なすことすべてに失敗して、負債に苦しむ。 その真澄をスカウトするのが馬越だ。馬越は物産をやめ、恵比寿麦酒(えびすびーる)の再建を引き受けるについて、真澄を支配人として迎えたが、そのとき母守家にいうのである。 <良いご子息をお持ちです。人は勉強によって術を得ることはできます。しかし誠意を得ることはできません。生れながらに備わった誠意というものは、数万貫の鉱石のなかから掘り当てた宝石のように貴いものです> 真澄は、その仕事に心血を注ぐ。連隊勤めの主人公も、士官学校在学中の末弟(五男)も、日曜祭日の休みには兄の社宅を訪ね、軍ぷくを作業着に着替えて一日中、古釘ひろいや箱づくりを手伝う。 会社が軌道にのりはじめた三年目、日清戦争がはじまり、主人公は出征。宇品港まで送ってきた真澄は、弟がまだ船中にあるうちに急死した。 その四年後、ウラジオストックで主人公は馬越に出合う。宿で食事を共にしながら、馬越は言う。自分の今日あるは、真澄とその叔父二人のおかげである。 世の中を渡る人――私のような商人には二つの型がある。利害の判断によって渡る人、善悪の判断よって渡る人――私のような商人の道に育ったものは、とかく利害に拘泥(こうでい)しやすい。私はお二人と近づきになって、商人の新しい道を発見したように思う。人間一人の力量に物を言わせて渡世する商いとはちがって、多くの人と、多額の資金を集めて経営するこれからの事業には、正しさに対する勇気と信念が必要であることをしみじみ感じました。そして初めて信用が得られるのです。信用が何よりも大きな資本になります。 馬越の真澄遺族に対する厚情は、明治、大正、昭和の三代にわたってつづいた。このエピソード一つにも、人間の真心の世界が見事に描かれていて、忘れることができないのである。 ※関連事項:ルッソオ ※関連事項:石光真清 令和四年五月九日 |
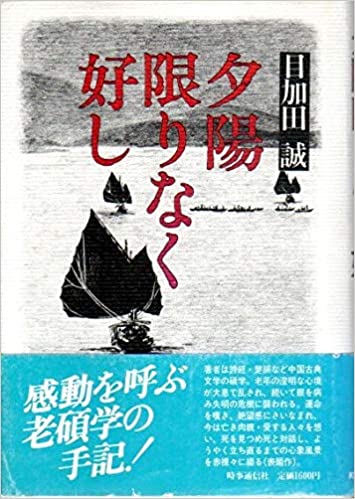
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.75~79 机上の二冊、目加田誠著『夕陽限りなく好し』と同『唐詩散策』を見ていると、五十年ほど前のことを思い出す。 当時、旧制福岡高校生だったが、先輩に目加田誠二という人がおられた。その人に、学校の受付子が、新聞の寄稿文を見て、 「最近ご活躍ですね」 といったそうである。ところがその筆者は、九州帝大の目加田教授で、受付子は「誠」と「誠二」の区別をうっかり見逃して、先輩がその文章の筆者であると誤認していたのである。 その文章がどんなものであったかは忘れた。また、目加田教授にお会いすることもついになかったが、今その著書を机上に置いていると、その頃の思い出がおのずと胸に浮かぶのである。 * 『夕陽限りなく好し』にその生涯のことが書いてある。『詩経』、『楚辞』など中国古典文学のこの碩学が、実に寂しい境遇であられたことに驚く。それは、「私は昭和四年に東大を卒業後、一年半ほど研究所におり、それから京都の三高に三年、九大に三十四年、早稲田大学に七年、教師をつとめた」(「教師生活」)という記述だけからは想像もできない。 明治三十七年岩国生れ、父は陸軍軍人。大男で典型的な明治の武人。同僚の家のことを、「彼奴はは毎月貯金をしているそうだ」 と、噛んで吐きだすように言ったことがある。自分たちは国家から毎月使うために必要な俸給をもらっている。死ねば家族には扶助料があるから、飢えはしない。余ったら若い士官にご馳走してやれ。 「しかるに何ぞや、貯金するなどとは、というわけである」(〔父〕) 母は「極めて小柄で、いつも丸まげ」、「父とは十二も年の違うやさしい、美しい、武人の妻」(「母」)。 祖母が八十歳で死んだとき、火葬場で棺を炉に入れた瞬間、父はわっと号泣した。すさまじい泣き方であった。<私は男が泣くのを、まして父が泣くのを初めて見て、粛然とした>。その翌年、あとを追うようにして父は死ぬ。享年四十四歳。 三十二歳で未亡人となった母は、六人の子供をつれて郷里に帰り、小さな家を建てて住む。「母は髪を短くきり、それからは全く毅然とした女になった。着物など少しも持っていなかったから、父の形見の羽二重の紋付を仕立て直して、何か事あるときにはそれを着て出かけていた。そういう時の端然たる姿を子供心にも自慢にした」。 第一次大戦後の物価騰貴で苦労したためか、夫に五年おくれて、母は病気で死ぬ。享年三十六歳。中学四年の長男誠を枕元に呼び、遺言状を書き写させた。残していく子供たちの身の上をそれぞれ親戚に頼んだのである。親類はみな立派に暮らしていた。しかし、遺言状に書き残した頼みは一つも聞いてくれない。<私が生涯、親類という関係を一切認めようとせぬ人間になったのはそのせいである。そして母の最期の言葉にこたえようとして、弟妹の親代わりになり、そのため私の青春時代には、何一つ華やかな想い出もない>。 高校時代、休みになって寮が閉鎖されても帰る家がない。夏休みは、二年生のときは友人の世話で九十九里浜の網元の家、三年生のときは大洗海岸で暮す。そして関東大震災直後、肋膜炎で入院、ついで肺尖カタル。「ついに高校を休学して、それから千葉県や山口県の海岸を二年間、一人で転々とした。将来の見通しもない、情けない青春の日」(「関東大震災」)。 * 三高に勤めているとき、北京留学。それを終えて帰国すると、留学中病んでいた夫人が死亡。三歳になる娘を親類にあずけてひとり九州大学に赴任する。「初めての土地に一人下宿して、大学の様子も分らず、話す相手もなく、寂寥は身に沁みた」(「暗い旅」)。 終戦の翌年、住む家を失って、福岡の郊外、津屋崎の、とある丘の上の鶏舎に畳をしいて、一家六人がそこに住む。「食べるものもろくになく、(再婚の)妻もその小屋で病に倒れた」。鶏舎生活二年、その間に夫人死亡。「ある粉雪の降る日、リヤカーの上に四つになる末の男の子をのせて、農家にバレションをもらいに行く途中、郵便局に寄ったところ、局長さんがあとを追ってきて、自分は方面委員をしているから、もし必要なら、生活保護の手続きをしてあげよう、といってくれた。私は恥ずかしさと、情けなさと、見知らぬ人の親切に、涙をぬぐいながら車をひいて歩いた」(「波の音」)。 七十歳で公の勤めは一切止めた。七十五歳――心不全で入院。退院してまもなく網膜剥離で入院。手術して退院すると、今度は急性肝炎でまた入院。「私は全く死にかけていました。(中略)死んで自分が消えるということは、自分が無になってしまうということで、あとには感覚も何もない。遺体が残るだけで、焼かれようが、埋められようが、ただ朽ちた枯れ木のようなもので何も分かるはずがない。あの世もなければ霊魂が残ることもない。自分という存在が無くなるだけで、自分が死んでも地球は相変わらず回転しているし、道路に車は充満しているし、春は桜が咲き、秋は紅葉が散って、この世の中は何ら変わることなく悠々と動いてゆく。その間を、長い歴史から見れば、ほんの一時期、時の流れに浮かんでいた泡がそのときふっと消えるようなものです。あとの供養も、墓参りも、ただ残った者の心遺りです。死者は何も知らない。知る主体がないのだから」。 七十八歳の夏、右の眼球がひどく痛みだし、頭のなかに響き、頭をかかえて転がるほどになった。虹彩内膜炎といわれた。 痛みとともに右の眼はいよいよ見えなくなり、左の眼もかすんできた。暮れから入院。手術してもよくは見えない。 「まっ暗な世界から、ともかくも光の世界に立ち戻った」 「これだけでも見えれば、全盲の人からみれば、天と地の相違ではないか。私はこの眼が僅かでも見えている限り、心を明るく保って自分に出来るだけのことをして人生のつとめを果たしてゆこう」 「私は今やもう、そのような侘びしさから抜け出さねばねばならぬ。もう一度頭を上げて見るがいい。沈みゆく太陽のあの美しさ。空を紫金に染める夕映えの見事さはどうだ」 「私は影を長く曳きながら沈む陽を迫って、どこまでゆくのか分からない。しかし、黄昏がひたすら迫っておればこそ、夕陽は限りなく美しい」 ※関連:目加田誠 2022.04.24 記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.89~93 子供の教育 『子供の教育』のなかでモンテーニュは、 「人間の学問のうちでもっとも困難で重大な問題は子供の養育と教育にある」 といっている。私はこの言葉で、日本では、佐藤一斎さん、鈴木大拙さんという大学者が、いずれも自分の子供の教育でてこずり、失敗しておられる実例を思い出す。 一斎先生の長男は慎左衛門さん。長男であるのに父のあとをつがず、幕府御家人の田口家に婿養子にいった(いかされた)。田口家は徒士(かち)組で、これは歩いて主君のお供をする歩卒である。 一方、佐藤家は美濃巌邑藩の家老の家柄。一斎先生は大学頭林述齊の塾長で、のち昌平黌の儒官(今日ならば東大学長)になられた。そういうめい家のあととり息子が徒士組の家に婿入りするのは、当時のしきたりにないことである。 慎左衛門の孫の鼎軒(卯吉は、未完の『自叙伝』のなかで、 「生来のあらあらしきお方にて、文をきらい武をたしなみ、相撲、鳶の者などを大路にて打ちこらしたまひしことなどありしかば、儒家の家を継ぐべからずとて、御徒なる我家に婿入りせられぬ」 と書いている。田口家はそれまで富裕だったが、慎左衛門は放蕩に身をもちくずし、貧しくなった家に十一歳の一人娘町子を残して早死した。 『言志四録』の最後の巻『耋録』は、一斎先生八十歳~八十一歳の作である。そのなかの<老人の養生五則その三>には、 「児孫団集すれば養を成し、老友聚話すれば養を為す。凡そ吉慶事を聞けば、亦皆養を成す」 ※『言志四録』(岩波文庫):この文庫本のP.90に『老いに挫けぬ男たち』P.90と記入していた。 とある。児孫団集のなかで、一斎先生の胸のなかを、若くして世を去ったふ肖の長男へのニガく哀しい思いが吹き過ぎていかなかったであろうか。あるいは孟子の、 「丹朱は不肖にして、舜の子も亦ふ肖なり。(中略)其の子の賢ふ肖は、皆天なり」(万章句上) という言葉が浮かんではいなかったであろうか。 * 鈴木大拙博士は十一年間のアメリカ生活を切り上げて明治四十二(一九〇九)年三十九歳のとき帰国、学習院高等部中等部教授となり、英語を教えた。その二年後にピアトレス・レーン嬢と結婚し、やがてアランという子供が養子となった。 博士は大正十年(一九二一)年大谷大学教授となり、そこの学生で、のち作家となる岩倉正治がアランの家庭教師に選ばれた。 ある夏岩倉は大拙先生にたのまれて、富山県の実家にアランをつれていき、野良仕事の手伝いをさせることになった。 「やつはなァ、このままじゃダメになるよ。夜勉強しているかと思うと、いつの間にか、二階の窓から綱をおろして、おもてへ遊びに行っている。西部劇だな。わしはまだよいとして、心配する家内がかわいそうでな」 と大拙先生はいわれた。(『鈴木大拙禅選集』別巻『鈴木大拙の人と学問』、<アラン君をめぐってのふ幸>) 当時アランは小学四、五年生、眉目秀麗、早熟で、オートバイを乗りこなし、乗馬をやり、カウボーイの投げ縄などの芸当を愛し、得意であった。 岩倉はアランを田舎の生家に「軟禁」して、炎天下の田の草とりや草刈りで鍛えようとした。 アランは抗議し、町の乗馬クラブから馬を借りて鎌倉あたりへ脱走するといった。岩倉は泣いて説得し、思いとどまらせた。 「先生がその後義絶されたアラン君のことについてはあまりふれたくない」 として、 「成人するにつれてアラン君に落ち着きができ、私も蔭ながらよろこんだが、結局幸福な和解はできなかったようである。先生の生涯におけるふ幸の一つであろう」といっている。 * 以上の話は、子供の教育のむずかしさを物語る典型的な例と思われるが、しかし、幸福な例も少なくない。 『英領インド史』の著者ジェイムズ・ミルは、長男が三歳のときから、ギリシャ語を教えはじめている。息子は父の期待にこたえてのちに大成し、経済学者ジョン・スチュアーㇳ・ミルとなるのだ。 ケンブリッジ大学講師のジョン・ネヴィル・ケインズは、長男ジオン・メイナードの成長ぶりを日記につけるほどの子煩悩ぶりである。そして長男も両親の期待にそむかず、わずか四歳半のとき、 「利子」とは何か、と問われて、 「僕がお父さんに半ペニーわたし、お父さんがそれを非常に長い間もっていたとすれば、お父さんはその半ペニーとそのほかにいくらかを加えて僕に返さなければいけないでしょう。それが利子です」 と応える早熟ぶりを示す。やがて大成して『雇用・利子及び貨幣の一般理論』を代表作とする経済学者として世界に知られるのである。 だが、親が子供の教育には無頓着で、子供は親とはまったく関係なく成長して大物になる例も少なくはない。石橋湛山、福沢桃介、内藤湖南、小野梓等々。 内藤虎次郎(湖南)さんの場合、生母と四歳で死別。次々と継母がきて、小学生の頃は四番目の継母であった。 少年はこの酒のみ女をきらい、授業がおわっても家にもどって顔をあわせるのが苦痛なので、放課後一人教室に残って読むために、自分の持つすべての本を風呂敷に包んで背負ってでかけた。 やがて、小学校訓導、雑誌編集者、新聞記者などをへて、京都大学講師、四十三歳で教授、我国シナ学の創始者、蔵書五万冊の大学者となる。 あれだけの蔵書をはたしてみんな読んだろうかと多くの人が疑問にしたが、ご本人は、「序結はていねいに、目次はななめ、本文指でなでるだけ」 と都都逸調で答えたという。 ※山陽新聞夕刊(昭和62年7月20日:月曜日)のインタビューを受けたとき、愛読書は小島直記の伝記ものといっていた。 あらためて読むとまた違った記事にバイブレイㇳ(小島さんがよく使われている言葉)するものがあるのではと思い、まったく久しぶりに本棚から小島さんの著作数冊のなからこの文庫本を引き出した。思ったとおり<子供の教育>の記事があった(一度は読んでいた)。 2022.02.15記す。 |
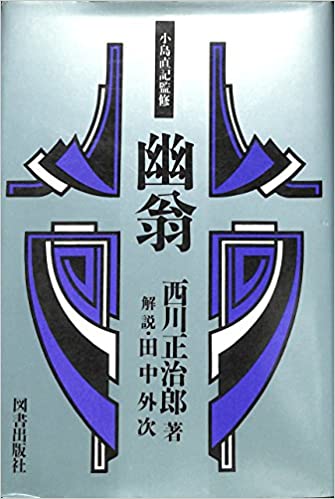
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.98~103 『臨済録』――文庫本④ 二十六年前『日本さらりーまん外史』というのを日本経済新聞に連載してもらったとき、その中で初めて伊庭貞剛さんのことを書いた。文庫本で『臨済録』を読んだのはそのときである。 それは伊庭さんに関係がある。別子銅山の争議をおさめに行くことになって、死を覚悟した。西川正治朗さんの名著『幽翁』には、 新居浜行きの汽船中、翁は余念もなく、ふるびた和本を懐中より取りだして読みふけってゐた。それは大阪を出るとき、峩山老漢からおくられた、『臨済録』であった。翁が何か山で読むものがほしいがといつた時、当時禅門無双と呼ばれた魁偉の老漢は、『何も読まんがよい、が、読みたければ』と云って、選みだされたのが、この本であった」 とある。そこで私もこの本と格闘したのkであったが、よくわからぬ、tヴぉいうのが当時の感想 一九八九年夏、直腸癌の手術を受け、長い間ベッドに寝ていて読書だけが楽しみというとき、読んだ文庫本の中に『臨済録』があって、いろいろと思うことがあった。 アンダーラインが懐かしい。赤と緑と二色の跡があるのは、二度読んだ証拠である。ペン一本になろうかと思い惑っていた四十五歳、はたして何がわかったか? 伊庭さんが『臨済録』で危機をのり切られたことは『幽翁』に書かれている。 老漢は、読むべきところと読まずともよいところを区別し、読まずともよいところは紙撚りをひねって閉じていた。 難解、難透、まるっきり歯の立たない書物であることが次第にわかりだす。 雨に、風に、はた雪に、年を重ねて、不退転の精進が続くと、少しずつ解けてくる。 寒灯のひかり、空しく明滅するいくとき、はっとわれに返った。その刹那、忽然として「あるもの」が電光のごとく奔って、翁を躍り起たしめる。「これだ!」と翁は思わず号乎する。 かくも烈しく感動せしめた「あるもの」を翁は「正精の気」と呼ぶ。 私はこういう事実を『幽翁』の文章で知っただけで、それ以上深く思うことはなかった。そして『幽翁』にも、そのことはこれ以上深く追求されてはいない。だが、そこにテーマを見出すのが伝記の仕事ではないかと問題意識がその頃はなかった。今は、そのことが反省される。 翁が『臨済録』を読まれたという事実を、記述を知っただけで、それで満足し、安心してはいけなかった。もっと具体的に、射場さんがもっとも感銘された箇所はどこであったか、『臨済録』そのものの細部に入りこんで、その心のヒダを推測すべきだったのだ。 * 推理小説のナゾ解きに似ている。難しいのは、臨済義玄の言葉を平明な現代文に直して、文意を解釈したところで何もならないということだ。 答えが出ても、その当否をいえるのは亡き翁だけ。闇の中の自問自答である。 読む必要のあるところ、ないところはどの部分か、紙撚りで閉じた箇所もわからない。カギは「危機」への対応ということだけである。 歓迎会の席で職員から脅かされる。家には多人数で押しかけ、執拗にからんでくる。この中で、心の平静を保ち、死の恐怖から逃れるにはどうするか。 翁はもと大阪上等裁判所の判事、法律の専門家である。ところがこの場合、自己防衛のためにはどういう法規があり、司法・警察当局にどういう保護を期待できるか、それについては最初から全く配慮していない。法の保護をみずから離れている。 この争議をかたづけて手柄にし、昇進しようというような野望もない。失敗して死ぬことが、おのれのために天のあたえた唯一の道である。「翁はそう信じた」と西川さんは書いている。 山の散歩と謡曲を日課とし、『臨済録』に没頭する。人に会えば「や、ご苦労さん」と声をかける。来るものはこばまわず、いつでも家に通して話に耳を傾ける。その態度にも顔にも、殺気や怒りはなく、平静と温和そのもの。人心はいつの間にか鎮静して、騒ぎもしだいにおさまってしまった。 この「危機」の間における最大感銘の一節との出会いとは? * 争議の調停と山暮し、ともにその体験はない。ただ「危機」をいうならば、癌という死病を越えてきた。 癌の場合、退院してもそれは無罪放免ではなく「保釈」であるという。つまり、いつ再発するかわからぬ、ということだそうだ。 したがって当分抗癌剤の世話にならねばならぬ。だがその効果は疑問、という人もいる。ある医者の随筆には、癌の退院患者の五年先における死亡率は四十パーセント、とあった。その意味で死の恐怖はまだまだ去っていないけれども、その「危機」を踏まえた今こそ、それを唯一の手がかりにするほかはないように思われた。 ところで本を読むのが楽しみといっても、耳の奥で絶えず「死」を予告する曲が聞えていて、本に熱中できるはずはない。面白さにのめりこむには恐怖を忘れる必要があるが、それはどういうときかと考えた。 家内が四ヵ月間看病していて、入院中二回(退院後五回)倒れた。命がけの看病である。また、多忙の中に、わざわざ横浜まで見舞って下さった方々、さらに病室に入り、激励して下さった横山剛院長、ベストを尽して下さった石井忠弘主治医と看護婦さん。こういう人々の好意によって自分は生かされている。 臨済義玄は、 「随処に主と作れば立処皆真なり」 といっているが、そのことであろう。 恐怖におののく「患者」から、生きるよろこびと有難さに支えられ、まっすぐ立つ「人間」にもどること、ここにこそ、病苦との訣別があったのだ。
この推測は、時間の経過とともに、確信と変ってきている。 ※参考:「随処に主と作れば立処皆真なり。境来るも回換することを得ず」。(岩波文庫)P.50~61に〔その場その場で主人公となれば、おのれの在り場所はみな真実の場となり、いかなる外的条件も、その場を取り替えることはできぬ〕。(黒崎記) 2022.04.02 記す。
|
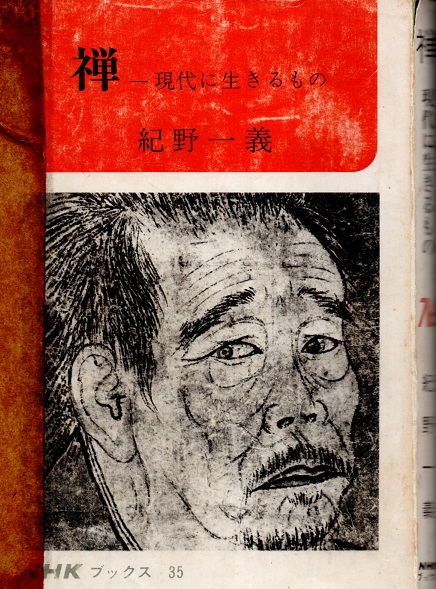
南無地獄大菩薩 小島直記『老いに挫けぬ男たち』P.126~132
白隠禅師に「南無地獄大菩薩」という書があることは、紀野一義『禅 現代に生きるもの』で知った。
A氏とB氏の俳句を通じた交遊は二十年に及んでいた。そのB氏が事業に失敗し、万事休してA氏に金策を頼んだ。 「大金です。私の手もとにそれだけの金は遊んでいません。困りましたね」 と言ったきり、A氏は沈黙した。そしてしばらくして、
翌日B氏が通されたのは茶室で、床の間に一軸が掛けられている。それが白隠の「南無地獄大菩薩」であった。 心の底に毒気を浴びせかけるかのようで、うす気味が悪く、見たくない。それでいてひきつけられる。B氏の心を占めている「破産」、「自殺」、それが「南無地獄大菩薩」と重なって、耐えがたい苦汁となって胃の腑(ふ)を突き上げた。
B氏はいつの間にか、「南無地獄大菩薩 南無地獄大菩薩」
「地獄を嫌うのは人間の情である。しかし、地獄を厭い避けようとすればするほど、地獄は盛大となり、頭のうえから覆いかぶさってくる。この厭わしい地獄に対してそのまま南無と帰命し、大菩薩と合掌礼拝したら一体どういうことになるのか」 B氏はそのとき、今まで経験したことのないような一条の光を見出した。 「逃げられるような地獄ならそれは地獄ではない。地獄というものは絶体に逃げられないのだ。逃げられないのなら、どこまでもその地獄を背負っていくほかはない。背負うのなら、南無地獄大菩薩、ありがたいご縁だ、とことんまで一緒に参りましょうと腹を据えるほかはない。そうだ、地獄の中で、自分の能力の限りを尽くして死ぬまでやるのだ」 白隠の太い文字が、そう語りかけているように思われた。人の好意にすがって地獄を逃れようとしたおのれの甘さ、卑劣さにむしろ悲しみを覚えて、やっとB氏は落ちつきをとりもどした。 地獄に体当たりをしようと決意したB氏は、金子(きんす)融通の件を改めて願い下げにしてA氏邸を辞去したのである。 「一幅の書の中に、これほどまで起死回生の力を打ち込んだ白隠禅師の禅定力に、わたしは怖れさえ覚えるのである」 と紀野氏は書いておられる。 人の好意にすがって地獄を逃れようとしたおのれの甘さ、卑劣さにむしろ悲しみを覚えて《の言葉を読むと、B氏の心の転機におしえられるものがありました。 ※紀野一義『禅 現代に生きるもの』(NHKブックス)(昭和四一年二月一〇日第二刷・発行)P.184~参考。 ※本当にB氏が事業に失敗して追い込まれ、自殺まで思うまでにいたったのと比べて、現在はとっくに退職しています私にも、会社勤務中には色々なことがありました。工場に勤務していたとき、仕事場での事故により、現場の指導者としての責任を感じて退社を真剣に考えました。私は身体障碍者として定年まで会社のご配慮もあり、研究開発や工場勤務、研修所に勤めさせていただけたのに感謝しなければならないと思います。 2012.02.01 * 白隠の生涯を調べていて、先ず興味を引くのはその健康法である。生まれたのは、貞享(じょうきょう)二年(一六八五)年、三歳でやっと立ち上がることができたほど弱い子供であった。成長しても病身で、ことに二十六歳のときは「心火逆上し、肺金焦枯(黒崎記:心火逆上―激しいふ安のために頭に血が上る。肺金焦枯―胸がざわざわして落ち着かず。)して国手(医者)も手を拱く」 という状況になった。 そういう病身でありながら、実に八十四歳まで生きたのである。その理由は独特の「健康法」を考え出し、実行したからで、彼はその秘法を、『夜船閑話』、『遠羅天釜(お ら て がま)』、『鵠林尺牘(こくりんせきとく)』などの書き物に書き残している。それは「内観の法」、「軟輭(なんそ)の法」、「独り按摩」などであるが、私はこの中の「独り按摩」を自家薬籠中(じかやくろうちゅう)のものにしたいと考えた。それは、次のようなものである。 一、手の平を摺(す)る。 二、指を組む。 三、揉み手。 四、拇(おやゆび)にて揉む。 五、手の平、指の筋を揉む。 六、指を引く。 七、腕を逆にこき上げる。 八、頬を逆に摺り上げる。 九、鼻の左右を摺る。 十、額を横にする。 十一、眉下を逆に摺る。 十二、耳を左右の手の平にて摺り下る。 十三、耳を上中下へ引く。 十四、耳へ人差し指を入れて一度ぬきて打つ。 十五、こめかみを両手にて摺る。 十六、脳を揉む。頭の中渦巻きよりヒヨメキを襟にかけ揉む也。 十七、頭を左右へ振る。 十八、身左右三度。 十九、九拝。 二十、左右の二の腕を掴み上下す。 二十一、同所にて肩を廻す。 二十二、指を組み、鼻の通りへ上げ膝を打つ。 二十三、左右のコブシを以て臍裏背肩を打つ。 以上初伝。 一、胸をさする左右。 二、腹を左右よりさする。 三、手を上げて左右の耳を撮み捨つ如くす。 四、左右の耳朶(みみたぶ)をつまみ、手を左右へ大いに開く。 五、足を以て尻を打つ。手を組み合わせて胸を打つ。 六、足を以て頭を打つ。 七、足首をふる。 八、かかと爪先を以てふる。 九、左右のコブシにて足の裏を打つ。 十、手の中指を合わせ土フマズにて踏み、目を眠り、歯を叩く十二返、唾をのむ三度。 十一、足の甲を揉む。 十二、足の指を引く。 十三、足の指のマタを揉む。 十四、足の甲を裏へちぢめる。 十五、サンリの筋を揉む。 十六、ももの内外を揉む。 十七、サンリを左右のコブシにて打つ。 十八、左右の手を背に組み合わせ腰骨を打つ。 十九、向臥(こうが)して足を開く一尺。息三度。 以上後伝。伝しおわる。銘にいわく、長生は長息也。 * 簡単に見えるが、容易ではない。試みてもらえばわかるが、根気がつづかないのである。 六月末に入院したときも、これをつづけようとした。予定された手術では、成功した場合が、顔面の肉を削りとるので、顔が歪み、まぶたが閉じぬようになり、胸の肉をとって顔面に植皮するため、右腕が上がらなくなるといわれ、覚悟した。独り按摩もその日までかと思うと、急に自分の五体がいとしくてならなくなった。ところが、冒険的手術は避けようということで化学療法となり、顔面も、右腕もつつがないことになったのである。 「南無地獄大菩薩!」 私が思ったのはこの言葉であった。 平成二十九年十一月十日。2022.03.14.補正。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.132~136 入院生活の最大の慰めは読書である。そのために自宅から本を運び、さらに友人たちからの差し入れであった。 差し入れの本のそれぞれに友情がこもり、ありがたかったが、特に友人田舞徳太郎氏から贈られた本、田里亦無(たざとやくむ)著『道元禅入門』は心にしみる思いがあり、病室四十五日間をかけてじっくりと味読した。 人口肛門(こうもん)のため毎日一時間余りをかけて洗腸をする。そのとき、トイレの明りが暗くて本は読みづらいが、この本には『正法眼蔵』の「現成公案」の原文が大きな活字で、行を分けて、散文詩のような形でおさめてあり、読むのに都合がよく、夢中になって朗読するよろこびを味うことができた。 これは生涯初めての体験で、十年来格闘を続けている『正法眼蔵』の世界に一歩か二歩、わけ入ることができたという手ごたえを腹のそこから感じさせられたのである。 この著者については、巻末に「学歴なし、職歴なし、禅歴も亦なし」とあるだけで何も分からないが、まえがきに「扉の題字は恩師法学博士、常盤敏太郎先生にお願いして」とある個所から、その学歴は探れるであろう。田舞氏はその教えを受けておられることを耳にした。 五年ほど、前、吹田(すいた)市のあるホテルで、田舞氏のつくられた(株)日本創造教育研究所発会式のとき、控室でちょっとお会いし、鎌倉にお住いということだけを聞いたことがある。質素な服装で、余分なものは何一つ身にも心にもつけていないという感じが漂っていたことが印象に残る。 * その著『道元禅入門』は、二三九ページの略装本で手軽なものだが、中身は濃厚だ。丹精こめた手造りの名人芸というべきか、さりげない形で、読者がよく理解できるよう、きめ細かい配慮がなされている。 巻頭にシモーヌ・ヴェイユの、 「与えるというものではないが人に是非渡しておかねばならぬ大切な預かりものが自分の内にある」 とう言葉が掲げてある。 私ははシモーヌ・ヴェイユという人を知らない。フランス文学事典によれば、 「一九〇九年パリに生まれ、高等師範学校を卒業、二十二歳で哲学教授資格を取得。明晰な頭脳と神秘的な魂の資質に恵まれた彼女は、その短い生涯の間、不幸な人々への慈愛と圧迫者への怒りを身をもって示した。 地方の高等中学校に奉職したが、その後ルノー自動車工場に女工として働き(一九三四)、スペインの人民戦線に参加した。国籍はユダヤ人の父母とともにいったんアメリカにおもむいた(一九四二)が、抵抗運動に加わるため、単身ロンドンに渡り、同胞の窮乏を分かとうとして食を絶ち、衰弱の極アッシュ・フォードのサナトリウムで客死(一九四三)。 ロンドン滞在中、ド・ゴールの『戦うフランス』運動に加わり、『解放後のフランスの将来』に関する考察を書いた。これが、一九四九年カミュの主宰する『エスポワール叢書』中に『根をおろして』という題で出版されるや、歴史、文明、革命、労働問題、宗教などについての意見は注目を浴び、遺稿刊行の進むにつれて識者の関心はますます高まった。 死後発表された主な著作は『重苦しさと恩寵』(一九四七)、『神への待望』(一九五一)、『超自然的認識』(一九五〇)、『労働者の現状』(一九五一)、『ノート』(一九五一)、『ギリシアの源泉』(一九五三)、『圧迫と自由』(一九五五) とある。 田里氏は、これらうちどれから先ほどの言葉を見つけて、というよりバイブレイトするものを感じて、引用されたのであろう。すなわちペダントリーの結果ではなく、やむにやまれぬ信条告白といえるとおもう。それは、高所から、難解をもって聞こえる『正法眼蔵』=『道元禅』の神髄を教えてやるぞという態度ではなく、おなじ平面に立って、「与えるというものではないが人に是非渡しておかねばならぬ大切な預かりものが自分の内にある」、それをこの本で渡そうとしているのです、といっておられるのである。 「多くの学者学僧に難解難入の書なりとされた大著『正法眼蔵』九十五巻(岩波文庫版で約一二〇〇ページ)(中略)の一巻に『現成公案』がある。その一巻こそ道元禅の核心を示すもので、他の九十四巻はこれらの展開に過ぎない。本書はこの『現成公案』を中心に、道元禅の核心を説きあかすものである。したがって入門書とはいえ、単なる案内書ではない。中に入って、道元禅の核心をつかみ取り、出門させることを予定する」 という文章は、挫折(ざせつ)体験にあえぐものを強く鼓舞するものがある。 * 本書末尾にある「参考書について」も容易ならぬ配慮がめぐらされている。 「『正法眼蔵』の解説書もまた多くあるが、推奨できる書は少ない」 という断定の切れ味がいい。 「各界の人々により、いろいろと高く評価されているが、それらを一言にしていえば『それは燃え上がる生命の詩であり、格調は高いが難解の思想の書である』。詩は情緒的であり、思想は論理的である。情緒をそこなうことなく、論理を正確に展開することは、困難なことである。ここに解説者を困惑させるものがあり、かつ多くの解説書が不完全な理由がある。情緒に力を入れすぎる解説者は、道元の思想を正確に伝えることができない。また、道元の思想のみを伝えようとする解説者は、道元の生き生きとした情熱を全く死物化してしまう。しかもそこに伝えられるものは、道元の思想とはおよそかけ離れたものである」 著者の推奨される参考書の筆頭に橋田邦彦(くにひこ)著『正法眼蔵の側面観』(大法輪閣刊)がある。 私はこの名前を見て、一瞬のうちに五十年の歳月がまったく新しい意味を帯びてよみがえるような思いをした。 橋田氏は、東大医学部の教授から一高校長(昭和十二年、五十五歳)、近衛内閣(第二次)の文部大臣(十五年、五十八歳)、戦後戦犯者として指名され(二十年、六十三歳)、青酸カリ服毒、自決された人である。 私は昭和四十五年に初版を出し、六十三年に第七刷を出したこの書を幸いに手に入れた。そのはしがきに、 「『眼蔵』は、志操堅尚の士にあらずんば、決してこれを読破することは出来ない] という言葉がある。 平成二十七年九月二十三日 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.137~142 高杉晋作 味覚を失った半病人の老人に楽しいことが少ないのは当然かも知れぬ。その上連日の新聞は政治家のスキャンダル記事だ。愈々楽しくない。高杉晋作の辞世の歌を思い出すのはそのためで、彼は、 面白きこともなき世を面白く 住みなうものは心ンありけり その高杉の活躍の舞台となったのは下関だが、ここは私たちの学生時代、東京から帰省するときの鬼門であったという暗い思い出があって、面白くない。 下関に近づくと列車の中に憲兵が乗ってきて、学生の荷物の本を調べ、危険分子とにらめば有無を言わさず引っ張られるとのことで、できるだけ堅い本や文学書などは持っていかないようにした。私も一度調べられたが、そのときは佐藤通事次の『皇道哲学』という本だったので、文句のつけようはなかったらしく、無事だったのである。 *
この本は八年前に読み、すでに伝記文学館に寄贈しているのだが、せっかく辞世の歌を思い出したときでもあるし、再読したいという思いが強くなって、本を借りに静岡県愛鷹山麓まで行ってきた。 今ていねいに読み返して、あらためて新鮮な、深い感銘を受けたので、面白きこtヴぉもなき世を面白くする一方法かもしれぬとおもい、この本の魅力について語ることにしたい。 特色の第一は、主人公晋作登場までに多くの頁が費やされいることだ。 大急ぎで断りたいのは、これは寄り道ではなく、この前置きがあるからこそ、主人公の理解が正確なものになる、ということだ。 特色の第二は、著者の態度は学究的冷静さで、極めて客観的な書き方をしながら、しかも晋作に対する愛情がおのずと流露するような記述となっていること、端的にいえばロゴスとパトスとが見事に調和を保ち、両々あいまつて幕末風雲児の生涯を、その時代的背景とともに見事に描き切っていることである。 まずは全体の構成を見よう。 「序章」として、「幕末慕情」というタイトルのもと、城下町・萩を訪ねた旅のことから筆は起こされている。 著者は京都から山陰路へ向い、まず松江に一泊して、次の日に萩に泊る。そして城址、松下村塾、松陰生家、毛利家菩提寺東光寺、明倫館跡とその武道館有備餡、野山獄、武家屋敷、町の家並みなど見て、 「佇(たたずま)いがひっそりとして、あまり人間のぬくもりを感じさせない。おそらく萩の町は、維新という台風が過ぎ去ったあと、抜け殻になってしまったのではないか」 という感想を持つ。 武家屋敷の中で、木戸孝允(きどたかよし)と高杉晋作の生家を見て意外に思う。 木戸は二十石取の藩医の息子であり、高杉は百五十石取りの上士の息子である。ところが、木戸の家は庭も広々として結構も立派、高杉の家は練塀超しに家の中がのぞけそうなこぢんまりとした小屋にすぎない。そこで、 「幕末のころ、すでに家格と富裕さは別の紋おだったのであろう。それは、はるか城下町をはなれた農家を思はせる松陰の生家の貧しさほどではないにしろ、日々つましい生活を想像させるのに十分である」 と考えるのである。 著者が衝撃を受けたのは、毛利家菩提寺東光寺であった。毛利家の歴代の墓と共に、いくつもの灯籠が並ぶ広い境内を一巡して、土産物の売店に煙草を買おうとして近づいた。 するとさまざまな土産物に混じって、萩の風景を染め込んだ手ぬぐいがぶらさがっており、その余白に、 面白きこともなき世を面白く 住みなすものは心なりけり という晋作の辞世の歌が染めこまれている。著者は、「面白きこともなき世を面白く」という文句を反芻しているうちに、油然として晋作への興味が湧いてきたという。 それは、幕末の志士が詠んだにしては、奇妙に新しい響きをもっている。 「<面白きこともなき世>と感じていながら、<なき世を面白く>と反転させる発想が、ちょっと他にみられない独特の情感と論理ではないか」 * 当時の著者は、四十歳にとどこうという年齢で、 「まだまだ、暑い夏の盛りを歩んでいる感じではあったが、ときとして、ふっと世間の人間の空隙を垣間(かいま)みることがないではなかった。この三十歳にもならずに世を去った男は、なにを観(み)て、"面白きこともなき世"と思ったのであろうか。そう感じた上で、それを面白くさせ、自らの生を活性化させようとした、その心意気は何であったのか――」 晋作は、文久三(一八六三)年三月、十年の暇(いとま)乞いを願って髪を剃り落とし、「東行(とうこう)」と称した。 それは、京都において公武合体論に引きずられる藩論に対して、割拠論ともいうべき独特の戦略を主張して容れられず、 「その議論は十年早い」 といわれたからである。 そのとき歌を詠んだ。 西へ行く人を慕ひて東行く わが心をば神ぞ知るらん というものだが、著者はいう。 「号・東行の由来である。この歌もまた、辞世の歌と発想に共通性がある。 「西へ行く人を慕ひて東行く」と反転していることである。晋作の気持のなかには、つねにものごとの両面性、両義性を観る視点が秘んでいる。隠棲した西行への思慕を晋作は終生もちつづけていたらし。 "面白きこともなき世"はその隠棲につながる。しかし"ンあき世を面白く"と反転することは、"東行く"ことを決意する晋作の態度と軌を一ににする――」 以来、晋作のことはつねに著者の胸中にあった。そして、いよいよ書くことにして下関に向ったのは、初めて萩を訪ねてから十二年目、昭和五十六年十月のことである。 著者はゆかりの場所を巡り、やがて桜山招魂社に行く。文久三年、攘夷戦で多くの戦死者が出たとき、晋作の主張でできたもので、その建立のとき彼は詠んだ。 おくれてもおくれても又君たちに 誓ひしことをあに忘れめや 弔(とむら)はる人に入るべき身なりしに 弔ふ人となるはづかし 「晋作の真情が溢れた歌」と著者はいう。 2023.06.03記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.142~146 至芸――高杉晋作② 粕谷一希氏が高杉晋作に興味を感じたのは昭和四十四年(一九六九)年五月である。そしてそれが『面白きこともなき世を――高杉晋作遊記』(以下単に『高杉晋作遊記』と書く)として月刊雑誌に二年間連載ののち、単行本となったのが昭和五十九(一九八四)年七月である。 スタンダールのいう「結晶作用」に十五年かかっているわけであるが、このうち、まず多くの時間は関係文献の熟読に費やされたであろう。著者はその内容を「主観的感想と批評をまじえて」というサブタイトルのもとに公表されている。 「この書物は私自身のための『維新入門』である」 とは「あとがき」の言葉だが、われわれ読者にとっても貴重な「維新入門案内」として、ここに晋作関係の書名だけでも再録いたしたい。私は、特に今日の日本で、明治維新の再検討が必要だと痛感している。 「学問的には当然参照すべき原資料や基本文献で見落としているものも多い。また図書館通いの苦手な私は、個人で収集できた範囲でこれを書いた」 とのことであるが、以下のように実に豊富なものであると同時に、「イメージ豊かな作品に吸い寄せられるのを怖れたため」執筆に当たり参照しない、というような周到な配慮もなされている。 『高杉晋作全集』(上・下、昭和四十九年・新人物往来社) 『東行高杉晋作』(昭和四十一年・高杉東行先生百年祭奉賛会) 古川薫『高杉晋作』(昭和四十六年・創元社) 「古川氏は長府在住の作家として、他に小説や少年向きの高杉晋作を書かれ、愛着と造詣において第一人者である」 と著者は注釈している。 古川氏は『天辺の椅子』という作品の著者。主人公は児玉源太郎。この武将についていままでロクな文献はなかった。小説ではあるが、実録的の色合いが濃く、伝記的作品として私は愛読した。 著者がかつて愛読し、執筆に当って参照しなかったものは、奈良本辰也『吉田松陰』(昭和二十六年・岩波新書)、同『高杉晋作』(昭和四十年・中公新書)、司馬遼太郎『世に棲む日日』(全三巻、昭和四十六年・文藝春秋)。 他に、福田善之(ふくだよしゆき)『維新風雲録・高杉晋作』(昭和四十二年・大和書房)、のち『歴史講談・高杉晋作』(昭和五十一年・角川文庫)、大岡昇平『高杉晋作』(中央公論社全集第六巻)。 「出来るだけ現像に近づきたいために、敢て入手しなかった」ものとして林房雄、尾崎士郎、村上元三、山岡荘八、池波正太郎、南条範夫、早乙女貢の作品。 「入手、参照した戦前の伝記」として、 村田峰次郎『高杉晋作』(大正三年・民友社)。 横山健堂『高杉晋作』(大正五年・武侠世界社)。 森本覚円『高杉晋作』(昭和十八年・高山書院)。 「手引書として便利なもの」 古川薫編『高杉晋作のすべて』(昭和五十三年・新人物往来社) 筆者が書き上げたあと刊行されたもので、「ほぼ今日考えられる最高の映像化となっている」もの 「高杉晋作写真集」(昭和五十九年・新人物往来社) この他「主要人物関係」、「幕末史関係」、「辞典」など数多くの文献があげられてあるが、紙幅の都合で割愛する。 * これら文献の研究こそ、主人公登場までに多くの頁が費やされ、また学究的冷静さで客観的な書き方がされた理由だが、しかもロゴスとパトスとが見事に調和を保ち、両々あいまって幕末風雲児の生涯が見事に描かれている場面が数多くあることに感服するのである。 その一例に坂本竜馬、桂小五郎、高杉晋作鼎談の場面(二七七頁)がある。 「おそらく、三者の会合は、竜馬の漂々たる口調による薩摩の内情と天下の形勢報告が中心となったことであろう。それに対して、桂は端然たる姿勢を崩さず、時として、短い質問を発する。(中略) これに対し、晋作は終始無言で二人の会話に聞き入り、いつか、疲れたのか、脇息によりかかっていた身体(からだ)が足を伸ばし、やがて肘枕で眼をつぶっていまったかもしれない。時として薄眼を開けると、潮風と共に入ってくる室外の、見なれた馬関の海を眺めたことだろう。そして、二人の会話がつきかけたころ、むっくり起き上がり、『坂本さん、長州人は理屈が多うてのう、西郷どんのように腹芸とは参りかねるのじゃ』とカラカラ笑う。晋作にこう言われるとと桂も苦笑する他はない。おそらく、二言、三言で、竜馬は自分と同じ自由児である晋作のえもいわれぬ魅力を了解したにちがいない。 ――この男は長州では他にない型の男だ。 竜馬の眼が一瞬光った。すると、晋作は間髪を入れず、懐から黒光りのする短銃を取り出し、卓上に置いた。 ――僕の愛用のものだ。坂本さんに進呈しよう。刀よりも役に立つ。 竜馬も晋作も、そして桂も、生涯、人を斬っていない。危機に際しては逃げる。逃げるしかないのだ、という鉄則を、三人は一様に心得ていたようだ。 おそらく、小道具を偏愛した晋作は、それを進呈することで、最高の親愛の情を示したのである。生涯において数回の邂逅しかなかった二人であるが、相許した間柄は他にはない独特のものであったにちがいない」 * もう一つの例(二九五頁)。 「臨終間際の晋作は、『面白きこともなき世を面白く』と書きつけて、そこで気力を失って後がつづかなかった。枕許にいた望東尼(もとに)に筆と色紙を託すると、望東尼が、『住みなすものは心なりけり』と下の句をつけた。 晋作はそれをみて、『面白いのう』とつぶやいて息を引きとったという。 しかし、ここのところは、最期の晋作の心の内を走った想念を見落としているように思えてならない。 この望東尼の下の句はせっかくの上の句の発想の面白さを消してしまって教訓めいたものに堕している。 ――この尼さん、どうも整いすぎ、取り澄ましすぎてつまらん。おれが元気なら、エロ話でもしてからかってやるのだが。 蕩児晋作は胸中をよぎった想念に、幽界に引きずりこまれながら、フト笑い出していたにちがいない」 2023.06.04 記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.142~146 女と酒――高杉晋作③ 粕谷一希著『高杉晋作遊記』の中に注目すべき一節がある。「ある架空の情景」と題する二ぺージ半の文章である。 幕末の青年たち、あるいは志士たちのすべては野心勃々、功業心の固まりであった、とみるの方が自然である。しかし、安政四、五年(西暦一八五七、五八年。黒船来航二年目、晋作は十九歳、松下村塾に入ったのが四年、文学修業を命ぜられて江戸に行ったのが五年)の吉田松陰、久坂玄瑞の間のドラマを想像するとき、晋作ひとり異質であり、直情径行の二人にに対して、畏敬の念と共に、どこかで違和感を隠していたのではないかと思われる。そこで著者は「架空の対話」を挿入しているのである。 * 時勢をめぐって激論がつづいた後、若者たちは松下村塾を去って行く。玄瑞と晋作は一緒に塾を出る。途中で、 ――玄瑞よ、ちょっと暖まってゆかんか。 晋作は懐から取り出して振ってみせ、ニヤリと笑う。その笑いに相手を吸い込むような温和力があって抗し切れないものがある。 晋作は返事を待たずに、雑木林に入って、器用に焚火をおこして瓢箪を暖め出す。 ――仕様のない奴じゃ。 玄瑞は大きな体をゆさぶるように晋作と共に腰を下す。 ――婚儀も間近なことじゃの、玄瑞。 ――む。 ――ところで、貴公は女をしっているか。 ――何を貴様、下らんことをいう。 ――下らんことではないがな。 一月ほど前、晋作は萩を抜け出して、馬関の裏町(花街)に一人で出かけていたのである。 ――女の体は柔らかく、そこに顔を埋めていると、天下も、黒船もない。それだけで深々と天国におる気分になってきよる。とにかあんなやすらかな場所はないがな。 無垢な玄瑞は言葉を見いだせずに、当惑顔になる。晋作は優越感を覚えて、さらに意地悪な質問を思いつく。 ――先生はどうなのかいな。 ――何を失敬な、天下のために東奔西走されてきた先生は、とうから女など念頭にあるまい。妻帯を断念されていることは、日ごろのお言葉からでも察しはつく。 さあ、そこだ。先生や君の議論は純粋すぎて、息がつけん。他人を説得するのも、女を口説くのも、なかなか機微を要する。世を動かすも、女を口説くのも、時と場所を選らばねば、いかん。そうは思わんか。 玄瑞は何も言えない。 ――弁の立つ玄瑞でも、答えの出ないこともあるな、ウフ、ウフ、アッハッハ――。 晋作は初めて、玄瑞をやりこめたことを、心から満足したように、大きく哄笑すると、焚火の火を踏み消し、茫然と佇む玄瑞を尻目にスタスタと歩き出す。 * 博引傍証 資料的に厳正をきわめたこの本の中のこの「架空の情景」こそ著者のパトスの現れである。しかし、それが少しも突飛でも、遊離的でも、遊びでもなく、むしろ高杉晋作を理解する貴重な手がかりであることに私は感嘆する。この本に対する「ロゴスとパトスの調和」という賛辞が、決して過褒(かほう)でないことkを諸賢も納得して下さるにちがいない。 * プレイボーイ晋作は、女と共に酒も愛した。 「萩で覚えた酒を、江戸の地でまた始めていた。酒だけではない。酒と女に溺れ始めていた。<心中糸の如く乱れ>ていた晋作、日々、外圧は切迫し、幕府・諸侯に覇気はなく、自らも為す術(すべ)もない身で、迂遠な学問を続ける気にもならず、機をまぎらわすには、酒色にふけるよりなかった。また、そこへ逃避しながら、彼には根っから好色な体質が潜んでいたのかもしれない」 「彼は、ヴィジョンを透視する直観の鋭い男である。しかしまた、酒を好むことは、ときとして、ヴィジョンをイリュージョンに変える場合がある。自己の願望や観念が酒によって誇大にふくらむ場合がある。そしてまた、酒は人間を自己暗示にかける。晋作の度肝をぬく行動は、ある意味で、まず自分自自身を自己暗示にかけての自己催眠行動であったといえなくもない――」 こういう記述は、「緊迫した状況のなかで、晋作の一見、不可解な行動」をじっと考えているうちに、著者がおのずと誘い込まれた「空想と推理」であろうが、私は、今までにこれほど周到な、味のある解説に接したことはない。これまた「ロゴスとパトス」の見事な調和である。 * 晋作は五尺二寸(一五八センチ)の小男で、馬面(うまづら)だった。しかも幼児疱瘡にかかり、顔にアバタが残って「あずき餅」というアダ名をつけられた。どう見ても「水も滴る好男子」とはいえない晋作は、一体女性にモテたであろうか? 満二十七年八ヵ月の短い生涯において、固有名詞として登場する女性は三人。 一人は二十二歳(数え)のとき迎えた六歳年下の妻、山口奉行の娘雅子。 一人は愛人おうの。赤間関(あかませき)の芸者で、生国その他不詳。無口な女。 も一人は、野村望東尼。晋作より三十三歳年上の尼槽だが、「一個の母性として登場している。しかし未亡人であり歌人であり、勤王家であった望東尼の、晋作に対する甲斐々々(かいがい)しさ、そして晋作の反応のなかには、諧調を乱さない形での好情があり、ひょっとすると、いたずら者の晋作は、この老婦人に淡い色気を感じていたのではないかと空想させる余地がある」。 晋作は「生涯において、吉田松陰と主家毛利家と高杉家という三つの鬼門をもっていた。この三者に対するときだけ、彼は襟を正して糞まじめになるほかはなかった」 「妻の雅子は、その家に属する嫁であった。晋作自身、雅子の筋目正しい美しさに惚れていたと思われるが、それは神聖な領域の一部」 晋作は、「この世界に対し、人間に対して、虚飾をはいで本質を洞察する男」。「形式的な知ではなく、身についた智を重んずる男」。「無知で愚鈍にみえるおうのの、無垢な魂を見抜いた」。 パトロン白石家に愛人といるとき、雅子と息子が訪ねてきて「妻妾同居」、桂小五郎への手紙で「子供のように泣き言」を並べた。ツケが回ってきた、と著者は言う。 2023.06.05 記す。 |

小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.170~174 回 顧 録 七年前(一九七九年)のあわただしい旅の途中だったから、店名も町名も忘れたが、ロンドンのある古本屋に立ち寄ったことがある。 中に入ると、右隅の机に一人の店員がかけていた。学校の先生という感じの上品な女性で、「サー」の敬称をつけて、「どんな本をお探しですか?」 と尋ねる。 「伝記本を――」 と答えると、椅子から立ってきて、奥の左隅に案内し、 「どうぞ――」 とニッコㇼした。商売気はまつたくなく、しかも何か買わないと悪いな、と思わせるような、親切で、上手なサービスぶりなのだ。 天井まである大きな本棚を前にして私は弱ってしまった。その膨大な古書がすべて「評伝」、「メモアール」類で、そのタイトルを読むだけでも大変な仕事だ。そのうえ参ったのは、評伝の対象、メモアールの筆者が、まったく知らない人ばかりなのである。 いかに自分がイギリス関係の勉強をしていなかったか、そのことを強く思い知らされた。と同時に、野村総研中川幸次社長の、 「イギリス人は現役を去るとメモアールを書き残す人が多いが、日本人はどうもその点足りないようだね」 という言葉を思い出した。なるほど、本棚にあるのはそういう類いのものにちがいなかった。 そのうちくたびれてしまったので、 「また来ます」 といって店を出た。 「どうぞおいで下さい」 という返事に、いわゆるひやかし客に対する冷やかでおざなりなぞんざいさはまったく感じられない。この本屋の店員の応対の仕方も大英帝国の底力の一つといっていいのではないか、とおもいながら、翌日もでかけてみた。 著者についてはよくわからないが、丁寧にその何冊かを読んでいけば、面白い展望が開けるようにおもわれる。だが本の大きさ、重さが、旅の荷物には不適である。やむなく買うのはやめて、また手ぶらで帰ることになり、その店員には、 「残念だが……」と断りをいった。するとニコニコしながら、 「お役にたてずに、すみませんでした」 と、反対にあやまたれてしまったのである。イギリスについてのいい思い出の一つとして忘れられない。 ところで、日本人のメモアールの件である。そういうものを残したいたいとおもいながらも、多忙のためや、ためらいや、書くのはニガ手などに理由で、あえて実行できないお方もおられるのではあるまいか。そんな場合には参考になるのが、池田成彬の『財界回顧』、『故人今人』の作成の仕方である。
※私のユーヨークでの本屋の思い出。 平成4年07月30日木曜日(4日目) マンハッタンへ出掛ける。長男が住んでいたアパートからバスで往復できる。
*本を探す…Trevelyan G.M. Shortened History of England Penguin Bellで聞くと Brentano で探してみろと言う。Brentano では New York University の近くの本屋が歴史書は豊富だと教えてくれた。 本屋の information Counterで“Can I get this book?”と尋ねるとすぐ調べてくれる。 日本と違って本屋の従業員が他の本屋を照会するなど、想像できなかった。
戦前文人外交官として有名だった柳沢健(やなぎさわけん)という人がいた。この人が池田回顧録を出したいと思ったのは、戦後間もなくのことだが、それは単に池田が有名人だからというようなことではなかったらしい。柳沢が戦争中にタイの日本文化館館長になるとき、タイの全権大使坪上貞二が麻生永坂の池田邸に連れていってくれた。当時池田は枢密院顧問官(昭和十六年十月就任、七十五歳)で、これが初対面だった。 その後柳沢は、バンコックに大建造物を建て、日タイ文化の交流センターにしようという大プランをもった。大蔵省は二百五十万円出してくれることになっが、その倍額五百万円は民間寄附によらねばならない。その世話役を池田に頼むつもりであった。 「『石橋居士』の池田さんは、私のこんなおおげさなプランにすぐとのられるはずはなかった。(中略)こっちがあくまで粘るとそろそろ『石橋』を叩き始められた。大蔵大臣に会う。大東亜大臣に会う、民間の主な人びとに打診してみる、――それが約半歳もかかったろう。そしてとうとう、旗振り役を引き受けようというご返事が貰えたのである。しかもこの旗振りの見事さは大したもので、一堂に会した東西財界のお歴々を一言片句の文句を言わせずに承諾させたもので、その実況を見た私は、ただ壮観というほかはなかった」 それ以来の敬愛の気持ちが、回顧録出版企画の底にある。昭和二十年に池田はパージとなったが二十一年五月その指定は解除された。それでもなかなかウンといわない。ようやくウンとうに至る心境を、彼は、大磯の家に柳沢と同行した小汀利得に物語った。 「一年以上も前に柳沢さんがやって来られて、今度独特の企画で出版事業を始めようというので、結構な企てだと思ってそのことは口にしたものです。そのおり柳沢さんは一例として、私の昔話もそれに加えたいなず言われたことは事実ですが、当時私にはそんなつもりは毛頭無かったものです。ところがその叢書が一、二冊出るうちに、予告として私の本が出るようなことがチャンと載っているじゃありませんか。こうなると、私がやらぬことに柳沢さんを困らせることになると思ったので、とうとうおひきうけすることになってしまったのです」 こうして、この作業は昭和二十三年、池田は八十二歳のときに行われた。 「従来過去の手柄話なり自慢話なりを人前で「やるような興味をまるで持たぬ、謙遜そのもの、謹直」そのものといっていい池田さんなのに、いざそれをやらねば」ならぬとなると、逆にこっちが」まごつく」ほどの積極性を示されるのである」 東京から二時間はかかる大磯の自宅で、朝九時半から口述を始めようというので、柳沢たちは八時前に汽車にのらねばならぬ。午餐時の小休止をすますと、早速また口述に取りかかり、それが夕方五時近くまで休みなしにつづいた。それが十回に亘った。しかも、事柄により、これに関係のあった人を呼んで、口述の際の共働者として立ち会わせた。小汀の他に、名取和作(富士電機社長)、松永安左エ門、金子堅次郎(東芝電器副社長)、大矢知昇(東横百貨店社長)などが、そのときどきに同席した。出来上がった膨大な速記録を、池田は一々朱を入れて添削した。不明確な箇所は前記の人々に問い合わせる。小田原の松永にわざわざ自身で出向くこともあった。 こうして成った『財界回顧』『故人今人』の二冊は二十四年に出版され、池田はその翌年二十五年八十四歳、腸潰瘍でなくなった。まさに貴重な証言、宝物は、危機一髪のときに成ったといえるのである。 2022.04.01 記す。
|

小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.174~178 昭和四年――回顧録② 「あなた(池田)が初めてお母さんに連れられて生国の米沢から東京に出てこられ、日本橋をお通りになったところ、そこの河岸に転がっている鮪を御覧になり、『あれはやはり唇がしびれるのか?』と聞かれたので、お母さんが袖を引っ張って、『大きな声を出してそんなことを言ってはいけませんよ』とたしなめられたお話、――あれはお幾つの時でしたか?」 という柳沢健の質問を受けて、 「十三の時です」 と答えるところから池田成彬の『財界回顧』ははじまる。全編は十章にわかれており、その第四章が「夫人同伴の欧米旅行」というタイトル。 「一九二九年(昭和四年)正月のすえに日本を発ったのです」 というこの旅のとき池田は六十三歳、明治四十二年四十三歳で常務取締役、大正八年五十二歳で筆頭常務となって十年目、金融恐慌の嵐を乗り切って二年目のことである。 船でマルセイユに上陸、ニースで十日間ほど休養、イタリーを見、パリにもどって一月、ベルリンに一月、スイス、オーストリア、ハンガリーを回ってまたパリ、それからロンドン一月、オランダにいってまたロンドン、そのあとベルギーに行き、アメリカについたのは九月であった。 旅の目的は二つあった。金融恐慌後、預金は大銀行に集中、一方、景気は冷えきっていて、設備投資などはほとんどない。つまり、今日いう「過剰流動性」のなかで、有力な外国投資の可能性を探ることが一つ。も一つは、懸案の金解禁に対する意見を聞くことで、外国投資の安全性ということからも、為替安定の問題は第一の目的と裏腹の関係にある。 アメリカは空前の繁栄にある、という印象をもってサンフランシスコから帰国の途についたとき、船にとどいた電報はニューヨーク株式の大暴落をつげていた。日本では蔵相井上準之助が訪ねてきて、 「実は君が帰るのを待っていた。ヨーロッパ、アメリカでは日本の金解禁をどう思っておるか? 欧米の話をきいてから何時から実行するということを公布しようと思っていた」 という。池田は、 「アメリカやイギリスではあまり問題にしていない」 などと旅の印象をのべて、 「『日本で金解禁をすれば我々銀行は援助する』ということを話して、翌日か翌々日に、来年の一月からやるということを決めたのが当時の事実です」 と回顧しているのである。 「今年(昭和六十一年)は昭和四年に似ている、昭和四年に学べ」という声があったが、これはこの「ニューヨーク株式の暴落に学べ」という警告に力点があった。それは確かにそのとおりであろうが、それ以上の問題性、教訓性を示すのがこの『財界回顧』の第四章なのだ。 あの金解禁断行が、完全に間違っていたこと、その基底にあるのが、井上、池田など、当時のトップ・リーダーたちの判断の間違いにあったことは、今日でははっきりしている。ニューヨークの株式大暴落が、世界経済の構造的矛盾のあらわれであり、したがってそのあと世界的恐慌がつづいたのに、当時の日本では、 「これは米英の金利低下となって、これまで我が金解禁をはばんでいた海外の金利高を解消するものであって、わが財界に有利である」 などと目先だけを見た楽観説がしたり顔に唱えられ、また金解禁趣旨徹底のため全国に派遣された委員のなかに、 「解禁さえすれば好景気がきます」 といって拍手喝采を浴びたものが多かった、とうこともはっきりしている。それに似たことが、今日はたして皆無であるかどうか。そのことがドル安=円高現象に対する大蔵省、日銀幹部、経済評論家、ジャーナリズムなどのそのときどきにおける発言、予測とその責任という点を中心に、徹底的に追求されているかどうか。 そこにこそ「昭和四年」を今取り上げる意味があるのではないか。
「この二十九年という年は、前後に世界に何も問題のない年でしたね。不思議な年でしたね。政治上にも経済上にも何も問題はない」 と池田はいっているが、これには唖然となるほかない。
これは、昭和三年六月四日張作霖が北京から奉天に引き上げる途中、満鉄付属地内で日本軍の列車爆破の陰謀によって即死した事件で、関東軍の河本大作大佐によって仕組まれたものだったことが明らかになっている。しかし当時真相は発表されず、これを野党(民政党)が議会で追求、特に中野正剛の攻撃がきびしかった。 「どこまでも調査の一点ばりで、深甚の憂慮をもってこの問題の推移を日本国のために考えている国民の代表のまえに何も言わず、ただそれだけでおし通そうとという御態度を私は奇怪に思う。あなたがたは、内地の新聞に出せば発売禁止、国民がこれを言えばお前は売国奴、議会でものをいわさぬ、これがあなた方の態度である。しかも外国の世論、外国の新聞にたいしては、何等の対抗手段も取らぬ。世界の主張のまえには袋叩きにあっても、日本の汚名を晴らすためには何等の努力をもなさず、なす気概もない」「我が軍隊を政略のために動かした政友会内閣が責めを負わずして、司令官に責任を負わして総理大臣が責めをまぬかれんとするごときは、無責任のはなはだしきものであります」 この二ヵ月後田中は急死したが、日頃頑健であっただけに、死因について疑問をもたれ、自殺説も一部にながれたのである。 外遊中の池田がこれを知らなかったとしても、しかし回顧談は昭和二十三年になされている。この事件こそ、軍部独走のハシリであり、それは敗戦につながる問題でもあった。その議会追求、内閣瓦解、総理急死の歴史的問題性を、彼はついに認識しなかったのであろうか。 2022.03.30 記す。
|

小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.179~183 故人今人――回顧録③ 『故人今人』というタイトルの本は、池田成彬の『財界回顧録』の、続編である。編者柳沢健は、「一方は池田さんの関係された事業の変遷史、他方は池田さんの親炙された財界人やら政界人やらの噂話さては月旦ということになった」 と「後書」に書いている。要するに、両書共に捨て難い記録というわけだが、とくに後書は、人物論の見地から、語られる対象の人物とともに、語る人その人をも語っていて、こたえられぬ面白さを感じる。人間は、どこでほめられ、どこで悪口を言われるか、その参考にもなるだろう。あるいは有名人の実像と虚像にも、大きな示唆を与えてくれるようだ。 先ず、福沢諭吉。 「三田を出た人は福沢先生を神様のようにいうが、これは同志社の人は新島先生を、早稲田の人は大隈さんを、完全な人のように思っておるのと同じで……」 と池田がいうのを小汀利得がさえぎって、 「早稲田の人間の大隈観は違うようですがね」 と異論をいうところが面白い。しかしそれだけに、前章で指摘した池田の昭和四年観――「この二九年という年は、前後に世界に何も問題のない年でしたね。……政治上にも経済上にも問題ない」 という発言のとき、そこに同席していた小汀が、それを正さなかったのがわからない。 それはともかく、池田は、福沢をやや冷たく、客観的に見ていたことは、 <偉い人には違いないし、年をとってからそれもよくわかったが、三田出の多くの人ほど私は先生を絶対的には見ていない」 とい言葉で明らかだ。この点、福沢を絶対的に見ていた松永耳庵と対照的である。その池田が福沢を「偉い」といっているのは次の点だ。 池田はハーバードを出て帰国すると、先ず『時事新報』に入った。 「この記者時代ですが、我々のような初めて入った者は、今から考えると随分乱暴なことを書きなぐっていたようだが、先生はなかなかよく見てくれました。今でも覚えておるが、当時私は外交論を書いた。それがことごとく強硬論です。そうしたら先生から、『外交論を書くのだったら外務大臣になったつもりで書かなければいかん、こんな強硬論ばかりで外務大臣がつとまるか』と叱られました。そうして書いたもので少しでも取るべきものは、真赤になるまで直すので、ほとんど私の文章ではなくなっている。偉いものですよ、根気のいいことは」 批判するのは次の点だ。 「月給が足りないからやめるといったときに、懇々と諭されたところまではよかったが、今度は俸給令を社内に張り出したものの、ただ張り出したというだけで実行しようとはしないのだから、そんなことで社員の不満を抑えられるわけに行きませんん。どうも先生としては余りにあさはかで、学者というものはあんなものかと思うような、――今でも何のためにあんなことをしたのかわかりませんね」 同席者名取和作の、 「先生は裕福だが、一面細かいところもあった。例えばお寺へお墓参りにいって一厘五毛のお釣りをとったという話もある」 というのは初耳であった。 次は西園寺公望。 池田はただ一度会っている。昭和五年、民政党が金解禁をやって、世間が騒がしくなったとき、西園寺秘書の原田熊雄が来て、 「是非あなたに会いたいといっておられるから、会ってくれないか」 といった。池田は、 「嫌だよ。第一私は西園寺さんを知らない。それに、民間の銀行屋が西園寺詣りをするなんて、嫌なことだ」 と断った。すると大蔵大臣の井上準之助がやって来て、 「是非君に会いたいといっておられるから、是非あってくれ」 という、今度は、 「興津に行くのは嫌だが、東京に来られたら会おう」 と返事して、六年六月に会った。西園寺は、金解禁のことについて解説を求める。池田は三時間ぐらいしゃべった。 「そのとき私が西園寺さんに敬服したのは、当時八十幾つかになっていましたが、普通老人は人の話を黙って傾聴はしないものなのに、西園寺さんは私のしゃべっている間一言も言わずにしまいまで黙って聞いてくれたということです」 この言葉のあと、 「大体公卿というものは人の悪いもので、西園寺さんなんかも蔭でせせら笑う分でも、一応真面目な顔をして聞くという修養がつんでたじゃないですか?」 と小汀がいうところが面白い。 次は原敬。 池田は原が総理大臣のとき、旧米沢藩主上杉死亡のとき頼まれて、位階を上げる相談に行った。 「原さんは恐らく私の名を一寸聞いて知っていたという程度でしょうが、すぐ上れということで客間に通されましたが、そこには掛物は何かつまらぬ新画がかかっており、火鉢といえば一円五十銭くらいの瀬戸物のでね、他に装飾は何もない、すこぶる質素な部屋でした」 正二位を従一位にしてもらいたいというと、宮内省では正二位になって五、六年経たないと従一位にしないから、勲章ではどうかという。 そして、何か他の人と違ったことはやらなかったかと聞き、留学生教育を奨励した話を聞くと、 「それでよい。それではこういうふうに書いてもらいたい。余程うまく書かないとむずかしいですよ」 と知恵を授け、やがて勲二等にしてやった。 「原という人は、人から頼まれれば、それだけの努力をする人だと思いました」 と池田はほめる一方で、 「高遠な理想をもって政治をやっていくという考え方の人ではなく、非常に実際的で、何でも力で行くという人でしたね」と批判し、 「しかし個人としては実に清廉な人」とほめているのである。今日、そういう政治家は――? という余韻を感じる人も少なくはあるまい。 2022.03.22 記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.183~188 毀誉一套――回顧録④ 佐藤一斎は『言志耋録』のなかで「毀誉四則」ということをいっている。その第一が「毀誉は一套なり。誉はこれ毀の始め、毀はこれ誉の終りなればなり。人はよろしく誉を求めずして、その誉を全うし、毀を避けずしてその毀を免かるべし。これを尚(たつと)しとなす」ということである。「毀誉一套」とは、「悪口いわれることと誉められることとは一揃いのもの」という意味である。 池田成彬の回顧録第二部『故人今人』で論評されている人たちに聞かせたかった言葉であり、同時に現在ときめく人たちに考えてもらいたい言葉である。 ※「毀誉四則」は『言志耋録』二一三、二一四、二一五、二一六である。『言志四録』の中の『言志耋録』(岩波文庫)P.269~270に記載されている。(黒崎記)
この章は、加藤高明、尾崎行雄、山本悌三郎などの政治家が「気取る」、「いばる」という視点から論じられている話。 池田は八日会の幹事だったとき、加藤さんを呼んでくれ、という注文が会員から出た。そこで何の気なしに電話をかけてお目に掛かりたいというと、 「だれかの御紹介をお持ちですか?」 という。気取るのだな、と思ったが、紹介なしでは会わないということなので或る人の紹介で会うことができた。 ところが加藤は、会の翌日、池田の家の玄関に名刺をもって御礼をいいにきたのである。「つまり、初めての人には紹介なしには会わない。節目というものはちゃんと立てる。しかし一遍でも呼ばれたら、翌日はちゃんと挨拶に来る。紳士としてはそれが当然だという理屈です。あの人は原敬とはちがう。理屈詰めでした。よくあれで、苦節十年到頭離れないでおったものだなあと思うのですが、選挙の金なんかを作って皆を相当に助けたでしょうね。そうでもないと、十年の間党を握っていくというのは余程困難じゃないかと思う。話しておると、なかなか普通の大臣連中とは違っておりましたね。どうしても近代の政治家のなかでは原、加藤でしょうね」 と池田は註釈をつけている。言外に、理屈詰めでは人はついていかないもの、加藤の場合、金の力で人がついていったのだ、といっているように感じる。 池田のその話を名取和作が承ける。 松本行きで加藤とおなじ汽車であった。名取が別なところにおったら、 「こっちへきたまえ」 と向うから話しかけてきて、 「武藤(山治)と和田(豊治)がどうして仲が悪いのかな」 などといった。 「別に気取ってはいませんでしたよ」 という名取の印象だ。 そこで小汀利得が、 「最初は気取っていたが、段々くだけたのですね」 と註釈し、さらに池田が、 「大分変ったのでしょうね。前は官僚臭が強かった」 と註釈を加える。 「気取る」、「いばる」のは「官僚臭」だということだが、だとすると、今の財界は実に「官僚臭が強い」というのがわれわれの実感である。 ここで名取は尾崎行雄をとりあげる。尾崎は、司法大臣をやめたばかりになっておったとき、一人で一等車に乗っておった。大変な混雑だったが、尾崎一人っきり、ふんぞり反っており、名取が立っておるのに、こっちへ来い、ともいわない。 「一人で気取っておりましたね」 名取は尾崎が嫌いだったそうだが、その原因はこのような尾崎の体臭にあったというわけだ。 すると小汀が、 「山本悌二郎という人がそうでしたね」といい出す。そのときから三十年近く前というから、大正十年代のことだろう。小汀は砂糖係の記者であった。山本は目黒の競馬場のところに四千坪の広い屋敷をもっていた。当時糖業連合会長、台湾製糖社長だったので、小汀は何度か訪ねたことがある。 目黒の駅で電車をおり、行きは人力車に乗るが、それを待たせるというわけにいかないから返してある。そこで、話が終ってから駅までてくてく歩いて帰らねばならない。すると小汀がまだ門を出ないうちに、山本は自動車で屋敷を出ていく。 「先生の行き先は工業倶楽部です。僕は別に乗りたくはないけれども、同じ道なんだから『君一緒に乗っていこう』ぐらい言ってもよさそうなものだが、決して言わない。気取った人間でしたね」 ここで話題は変って、近衛文麿のことになる。近衛は三回組閣した。池田は第一次(昭和十一年六月四日~十四年一月五日)の大蔵大臣兼商工大臣に、十三年五月二十六日に就任した。「聡明な人だが頼りのない人で、どうもまことにふわふわした、一口に言うと頼りにならない、という気がしたのでしたのです」 という。それを承けて小汀は、 「重大なときにああいう経験のない公卿なんか出したということが、間違いのもとですね」 ところが柳沢健が、後藤隆之助に直接聞いた話というのを披露する。近衛は死ぬということを後藤に打ち明けた。後藤は、 「そんな犬死にはおよしなさい。ぜひ国際裁判所の法廷において堂々と今までのあなたの平和的信念を吐露し、世界の世論に訴えてからのことになさい」 と説いた。近衛は、 「それはできない。何故かというと、自分が正しかったとか、平和工作に終始したとか言い出すと、結局陛下に迷惑を及ぼすような結果にならぬものでもない。そんなことはどんなにしても僕としてはできない。それを考えると、事前に死ぬ以外に方法はない」 といった。後藤は返す言葉がなく、 「それでは死になさい。しかし、東条みたいな醜態をさらしちゃいけませんよ」 というと近衛は笑って、 「その点は大丈夫」 と答えたという。 二十年十二月十六日午前六時頃、寝室にいつになく灯(ひ)がついているのをみて、千代子夫人は部屋にはいったが、すでに近衛は毒を飲んで死んでいた。 武人の東条陸軍大将が、ピストルの引き金をひきそこねてMPに引立てられる写真にくらべると、従容と目的を果して永眠する写真は、犯し難い美しさが感じられ、へナへナの公卿もバカにはならぬ、と思ったことを思い出した。 2022.03.20記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.188~192 朝吹英二――回顧録⑤ 「人の評判は、半分聞けばいい」ということを、佐藤一斎は『毀誉四則』の第三に上げた。 ※「毀誉四則」は『言志耋録』二一三、二一四、二一五、二一六である。『言志四録』の中の『言志耋録』(岩波文庫)P.289~270に記載されている。(黒崎記) 博学の彼は、中国前漢時代の学者劉向の、 「人を誉めるのに、その優れたところをおおげさに言わないと、聞き手は面白く感じない。人をそしるにも、その悪い点を増大して話さないと聞き手は満足しない」 という言葉を引用して、 「この言、人情を尽すというべし」 といっている。 しかしこれは、話が誇張されやすい、という傾向の指摘として参考になるものの、逆に、「言葉が足りない」という思いをさせられる場合もあるのである。 『故人今人』における朝吹英二の例がそれである。
『故人今人』に取り上げらた人は、程度の差こそあれ、池田邸に集まった人々から大体ケチをつけられている。すなわちその人物をめぐる一種の欠席裁判の趣もあるが、ただ一人の例外が朝吹英二。彼はその席のすべての人から褒められているのである。いかに人徳のあった人かは、これだけからもうかがえるが、それだけに、 (一)言われていることが事実と違っていたり、(二)事実が知られていないということがあるので驚く。同時に、せっかくそこまで褒めるならば、それを、(三)我が身に照らして考えた発言があってもよさそうなものだ、という思いを押え切れないのである。 事実と違う発言は、 「(失敗して困ったところを)中上川(彦次郎)さんが三井へ来いといってくれた。(中略)そういう具合で、中上川さんに拾われて三井に入り、鐘紡を引き受けたのです」 というもので、これが、そのとき池田邸に集まった人々のなかでもっとも朝吹に近いはずの、朝吹の女婿名取和作の発言だからこまるのだ。 明治二十一年、朝吹は尾崎行雄の外国行の旅費を工面してやった。窮乏洗うがごとき内情だったが、朝吹はそれを口にして人への援助を断ったことは一度もない。 その朝吹のことをじっと考えていたのが日銀総裁川田小一郎である。二人はかつて三菱で働いた仲間であった。 「ときには顔を見せにこい」 という手紙を出し、やって来た朝吹にその日もらったばかりでまだ封も切らない月給袋を、 「持っていけよ」 と渡してやった。そして、 「ところで君は、ここいらで一応方針を変えて、どこぞつとめてみる気はないか?」 と尋ねたのである。 朝吹は、「あります」という。 「そうか、そんならワシに考えがある。万事任せてくれるだろうな」 朝吹が帰ったあと、ただちに三井銀行に使いを出して、中上川を呼びつけた。 「朝吹は君の義弟じゃないか。放っておくということがあるもんか。三井で何とか面倒を見ろ」 中上川としては、放っていたわけではなかった。ただ義理の弟(妹澄が朝吹夫人)だけに、自分から三井に入れにくいという事情があったのだ。 川田総裁のお声がかりということであれば、話は別である。三井物産の益田孝と相談して鐘紡に入れ、専務にしたのである。 名取は、岳父朝吹の恩人川田のことをまったくオミッㇳして知ったかぶりをしているのである。 「事実を知らない」のは池田成彬で、 「(朝吹は)天才的な人だね。それなのに、どういうわけで横浜で失敗したのか知らないが……」 といっている。 「日本の対外貿易に、外国銀行が為替を取り扱い、利益を独占されるのはつまらぬ。日本人の為替銀行をつくったらどうか」 と福沢諭吉が言い出し、大蔵卿大隈重信がこれを容れて、横浜正金銀行(東京銀行の前身)が明治十三年にできた。福沢門下生からは、中村道太、小泉信吉が幹部となった。 「せっかく銀行をつくっても、為替と取り組む人間が西洋人では、仏つくって魂を入れぬようなもの。為替と取り組む日本人の貿易機関をつくらねばならぬ」 これも福沢の意見で、貿易商会が誕生した。このとき幹部として、門下生から早矢仕有的、朝吹の二人が選ばれたのである。 このとき朝吹は三菱の東京店支配人、安定したポストを動きたくはなかったが、恩師福沢、社長岩崎弥太郎の期待を受けていると聞くと、 「知己のために身を投げ出すのが男の道だ」 と取締役支配人に就任したのである。 ところが、十四年政変(大隈追放)のトバチㇼで、「糧道を断って大隈を干ぼしにせよ」との政策から、政府は正金銀行に命じて、貿易商会のためにする為替取組を禁止、輸出業務を不可能にした。そして、商会の帳尻は、産業奨励、輸出奨励の補助として、すべて大蔵省にひきつぐ規定であったのを改め、これまでの支出を貸付金に計上して、「さあ返せ」とせまったのである。 このとき、他の重役はみな逃げて、責任を取ろうするものはいなかった。負債を全部引き受けたのが朝吹で、そのための窮迫だったのである。 ここに朝吹の神髄がある。その事実を知らないで、朝吹の人物批判など、やろうとすること自体がおこがましい、といわねばならぬ。 朝吹は子供の頃天然痘にかかり、そのアバタが大人になっても残っていた。富士登山をした福沢桃介は感想を語る会で、 「遠くから見た富士は美しいが、登ってみるとまったく違い、登山道など浅ましいまでに汚い。富士は朝吹君の顔といったものです」 といった。 この醜男が、しかも貧乏のドンゾコで飛び切りの美人たちに本気で惚れられたのである。 「あれはなぜであったか?」 そのことについて話し、ついでに自分たちのことを反省すれば、この人物評は完璧であったのに……。 2022.03.21 春分の日、記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.193~198 外 国 語 昔流にいえば「古希」の年。正月に読む本は特に良いものを、と念じていると感応があった。 昨年『鞍馬天狗のおじさんは』を探して送ってくれたS君が、今度は忙しいなかに『思想のドラマトゥルギー』(林達夫・久野収対談集、平凡社選集)を探して送ってくれたのである。 おかげで久々に学問の香気に包まれた。おのれの生ぬるい勉強ぶりを痛切に反省させられるのはつらいことだが、しかしそういうことを含めて、読み終わるまで充実した数日を送ることができたのは幸せであった。心からS君の好意に感謝した。 先ず思いだしたのが、林達夫の『思想の運命』を読んだ東京・中野の下宿のことだ。 だが、本の内容については、関根秀雄の『モンテーニュ随想録』の誤訳をコテンパンにやっつけてあって、その語学力のすごさに驚嘆したことしか思いだせない。 『思想のドラマトゥルギー』には、林がそのすごい語学力の由来を語る箇所があって、まずはそのあたりが楽しかった。 * 「一生舞台で精力と時間とを使い果たした男、と墓碑銘に書いてもらってもいい」 稽古が好き、昔流のある種の修行のように、五年たっても十年たっても、成果があがったのかどうか、自分では測りにくいもの――語学もその一つ。 「語学は西洋をやる『問』で(中略)結局、英語から始まって、独、仏、伊、それからスペイン、ロシアという順でやり、肝腎のギリシア語は、シェクスピア御同様、 "Small Latine and Lesse Greeke" 『少しのラテン語、より少ないギリシア語』で終わってしまいそうなのが心のこり」 「無駄に無駄を重ねた、その最たるものが実は『英語』かもしれない」 * 外交官の息子。数えで三つから七つ頃までシヤトルの領事館兼官舎で育つ。 洋菓子がきらいでチョコレートなどおしげなくくれてやるので近所の餓鬼どもの小ボス。米語がペラペラなのは当り前である。 父のボンベイ転任。達夫だけが福井の叔父の家にあずけられる。 そこの小学校で「異人」あつかいされてイジメられる。 * 帰国した両親は、京都吉田山に家を新築。達夫もそこにうつる。 乗馬、テニスなど、万事ハイカラな家で、福井弁の田舎者になった彼だけが異邦人。双方違和感だらけで、家族たちと反目する。 大きな使い古しの薄汚いウェブスター大辞典を父がくれるが、 「そんなもの要らなん」 と拒否したため、激怒した父からこっぴどい平手打ちをくらって、ひっくり返った。 以来、口もきかない仲違(なかたがい)い。親元から通学できる三高に行かず、一高にいくのもそのためである。 * 京都一中では、ABCからのやり直し。はじめいやいゃやっているうちに、いつの間にかおもしろくなってきて、クラスで一番できるようになる。 「読み、書き、話す、この三拍子そろった語学ができた唯一のものは、後のあらゆる語学を通じて、この中学の四、五年頃の英語だけだったでしょうか」 好人物の米人教師に可愛がられ。その家のパーティにつれていかれたり、夏に比叡山にできる外人のテント村に呼ばれて、寺などのガイド役をやらされる。「英語という『特技』を持ったおかげで、見世物にされたり、そういうことがあれこれ重なって、またしても英語アレルギーの再発さね、英語とはもうきれいさっぱり縁を切ろうと、英語では口も利かなく、ものも書かなくなってしまった。まあ読む方だけは続けたけれどね。僕の大事な『西洋への窓』だったから。それからというもの、『語学』とは、僕には沈黙の中の一方通行の作業になった次第です」 * 中学の一年上に、のちの画家そして詩人の村山槐多(かいた)がいた。 「『全校オンチ』というのがどこの学校にもいるでしょう。村一番の阿呆(あほう)みたいな。衆目の見るところ、槐多はそれだったんです」 林はある日、岡崎の図書館にいった。洋書のカタログでゴードン・クレイグの On the Art of Theatre を借りた。ところが、序文からさっぱりわからない。ガックリきて、目次をみて、ちょっとパラパラと頁をめくって、それから返しにいった。そこに槐多がヒョロヒヨロと現れてきて、堂々たる貫禄のある洋書を一冊返すのだ。 「何を読んでいるの」 「プラトンを読んでいる。えらくおもしろい」 五冊か六冊あるうちの、今は何冊目かだといった。 「中学の時のことでしょう、驚きましたね。こっちは中学生の手にとる本だなんて思ってもいない。その同じ『プラトンン全集』が、僕が五年後京都大学へ入って最初に買った本なんです。それを槐多の奴、中学の時に読んでいやがった。しかし、何の先入観もなしに読むと、槐多のように中学生でも、面白い、面白いと言って読める。ギリシアでは青少年の読み物だったということも、彼、誰にも知られず実践していたわけです」 * その後、「語学では全くの食違いの連続で、(一高の)独法に入って、半年にもならぬうちにドイツ語がいやになって、フランス語の講習会へ通ったり……そうして大学を出て口すぎの教師になる段になると、英語の教師しかない。またしても英語さ。そして戦後の、英語、英語、英語。いや、米語、米語、米語。僕の英語は、中断、再開、中断、再開……それを四回もやるという、退化とその回復というものを含めた精力と時間の無駄使いの連続であったわけです」 「この頃はもっぱらスペイン語とロシア語を(ラジオ)聴いている(中略)。毎朝、目がさめると、枕元のラジオにスイッチを入れて、目ざまし時計代わりに、この頭の体操をやる。つい、その前後のドイツ語もフランス語も聴いてしまう時があって、ひどい時は独、露、仏、西と、その順序にぶっ遠し一時間二十分聴く時だってある。どうしても読み一辺倒になる僕たち学徒には、ある意味で一番ためになる柔軟体操の時間だ」 2023.05.27記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.198~203 ギリシャ人一人とローマ人一人を選んでそれぞれの生涯をのべたあと、「比較」という一章であいめくくりをし、二十一組の対比を試み、関係者をふくめて七九七名の人物を登場させたのが「ブルターク英雄伝」である。 この対比という方法を「戦後日本の出立に深く関わる世代に限定」して、「小林秀雄と丸山真男」、「馬場恒吾と石橋湛山」など十一組を論じた卓越した労作が粕谷一希著「対比列伝」(新潮社刊)である。 この一組として、「知の形態について」といタイトルのもとに、安岡正篤と林達夫が対比されている。二人は旧制一高の同級生であった。 粕谷氏の名著を読み、そして「思想のドラマトゥルギー」(林達夫・久野収対談集)や林繁之著「安岡正篤先生随行録」を読んでいると、安岡、林両人に関係があった人物として井上哲次郎の名が出てくる。 井上(安政ニ~昭和十九、一八五五~一九四四)は福岡県出身。東大卒、ドイツ留学、のち東大教授。ドイツ系哲学を移植、また日本主義を唱導。 「安岡正篤先生随行録」の筆者林繁之氏は、永年その信を受けて側近におられた誠実無比の人。この本は、その人柄がおのずとにじみ出ている好著である。 ただ、客観的には、いくつか首をかしげるところもあるのではあるまいか? たとえば、「早朝の電話」の話がそうである。 時として先生からお電話を頂戴してしまうことも多い。(中略)先生は受話器の向こうから、一、ニのことを私に命じられた後、一瞬の合間をおいてから、 「どうしたことか、明けがた夢を見てネ、それが僕の大学時代のことなんだ。井上哲次郎先生と話しているんだよ」 そして、「不思議なものだ」と電話切れた。 井上哲次郎博士は、安岡先生が東京帝国大学に在学当時の教授で、先生より四十三歳年上の斯界の大家であった。わが国近代における東洋哲学史研究の先覚者であり、「日本朱子学派の哲学」「日本陽明学派のてつがく」「日本古学はの哲学」という三部作は特に有名である。 先生はこの老教授に、学生と教授の分を越えて親炙した。講義のほかにも、研究室やお宅に伺って、遠慮ない議論をされたことがあったそうである。井上教授はまた先生のその議論をすでに一家をなしているものとして熱心に傾聴され「安岡君は畏材だ」と大学の同僚に語られていたと伝えられている。 安岡先生の「井上先生と激論している夢を見てネ」という電話のお声を聞いて、私はとっさに(以下略)」 この文章において、電話は、 「井上哲次郎先生と話している」 「井上先生と激論している」 と二通りに書かれている。 私はこれにこだわる。こだわる理由は二つある。一つは、単なる「話」と「激論」ではまったく違うからである。そして第二の理由は、以下のことがあるからである。 * 帝国大学生正岡常規(つねのり:俳号子規)は、中途退学して「日本」新聞社に就職しようとした。面接したのが古島一雄である。 「あと一年で卒業するなら、入社はそれからでも遅くはあるまい」 と古島がいうと、 「実はもはや試験のための学問はイヤになった。ことに井上哲次郎の哲学の講義など、この上きかされてxはたまらない(攻略)」 そう子規は語ったと、古島は回顧している(古一念会編「古島一雄」)。 山路愛山は明治二十六年二十九歳のとき「明治文学史」を書き、その中で当時の花形学者たちをたたいた。 「外山正一(とやままさかず)は実に一たび我が文学界にボルテアのごとき嘲罵の鉄槌(てつつい)をふるいたりき。彼はその学識を衒(てら)いて、ミル、スペンサー,ペンタム、ハックスレー、何でもござれと並び立てて傲然たること、なお井上(哲次郎)博士が仏人、独逸(ドイツ)人、魯(ロ)人、以太利(イタリー)人、西班牙(スペイン)人の名を並べて下界の無学者を笑うが如くなりき」 「天下の人、指を学者の屈すれば必ず哲次郎君を称し、必ず高橋五郎君を称す。吾人は幸いにして国民乃友紙上においてニ君の論争を拝見するを得たり。井上君ラテン語b、イタリア語、イスパニア語を引証せられるば、高橋君一々その出処を論ぜらられる。無学の拙者どもには御両君の博学ありあり見えてなんと申しあげようなし。さりながら、博学ひっきょう拝むべきやいなや。もしもシェクスピーアを読まずんば戯曲の消息を解すべからずとせば、シェクスピーアは何を読んでシェクスピーアたりしや7(以下略)」 和辻哲郎はキエルケゴルの「人生行路の諸段階」を井上に借りにいった。 井上は読んだと称して、とうとうまくしたてたが、実際に読んでみるとその話は全然見当違い。 和辻先生、こんなホラ吹きが大学教授をしているとは何ともな情けないと絶望して、逆にそれが自分自身で自主的に勉強に身を入れるはげみになったというんですがね」 久野収にこの話を聞いた林達夫は、中学生の頃、井上の講演を聞いたことを思い出す。 井上は、人間のなかにはシャロ―・マインド(浅薄な心)の奴とディープ・マインド(深刻な心)の奴と二ついる、という話からはじめたのであった。 後で考えてみると、夫子(ふうし)自身シャロ―・マインドの代表であったというわけです」(「思想のドラマトゥルギー」) * そういうのが東大教授、文学博士井上哲次郎の正体であった以上、彼に知遇を得たということは、「事大主義」を信奉するならばともかく、少しも安岡青年の「権威」づけにならないはずである。 むしろ俊敏にして潔癖な安岡青年としては、井上のインチキ性を見破って「激論」するしかさなかったはずだ、と私は考えたい。 2023.08.18記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.203~208 上田 敏 徳川末期の幕臣に、乙骨太郎乙(おつこつたろういつ)というおもしろい名前の武士がいた。「華陽」と号し、英学者で漢学者、沼津兵学校の教官、駿府藩校英学塾の教頭、明治になって大蔵省翻訳局の教頭をつとめたというが、早く父を失った田口卯吉(鼎軒:ていけん)を親代わりとなって育てた人として忘れがたい。 このひとの弟が絅二(けいじ)。慶應三(一八六七)年パリ大博覧会参加の徳川民部大輔(たゆう)に従い、渡欧したとき写した写真が、嘉治隆一(かじりゅういち)著「人物万華鏡」の巻頭にのっている。 太郎乙は、旧友や知人に並々ならず尊敬され、子供の名前をつけてくれと頼まれることがしばしばであった。 親友の英学者外山正一の長男には「岑作(みねさく)」。 政治学者河津祐之(すけゆき)の長男には「邁(すすむ)」(この人は後に東大教授。学生はたわむれに河津シャムと呼んでいた)。 田口卯吉の長男には「文太」。 そして自分の長男には「敦」。これはアンクル・トムス・ケビンからとったもので、「とむ」と読ませた。 また弟絅二の長男には「敏」。これはビンジミン・フランクリンのビンからとったものだ。 その敏が幼くして父を失ったので、田口卯吉が引きとって十年間世話してやった。これが上田敏である。 * 上田敏は明治七(一八七四)年十月東京築地に生れ、大正五(一九一六)年七月、萎縮腎で世を去った。
秋の日の ギオロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し。
鐘のおとに 胸ふたぎ 色かへて 涙ぐむ 過ぎし日の おもひでや。
げにわれは うらぶれて ここかしこ さだめなく とび散らふ 落葉かな。
は、青春期の大事な記念碑である。 * 矢野峰人(ほうじん)は京都大学で、大正四年から敏の亡くなるまで教えを受けた。 のちに「上田敏先生の思い出」(筑摩書房。現代日本文学全集58)のなかで書いていることは、大学教授としての敏のすばらしさをうかがわせて心に残る。 「(前略)上田先生の講義の妙味は何処(いずこ)にあったか? 第一にそれは、借物でなく、俄仕込み(にわかじこみ)でなく、久しきに亙(わた)って自分の血となり、肉となつて居るものを、機に臨み時に応じて自由自在に吐き出す所にある。先生にあつては、一切のものが渾然と融合して一つの有機的統一体と成つて居た。中世の抒情詩人トマス・ド・ヘイルズ作に『パリス・ヘレンいづくにかある?』とあるのを見れば、必然的に、ヴィヨンがいにしえの麗人をならべて『こぞの雪いづくにありや?』とうたつた名吟を併せ想ひ、それにつれてはスティヴンスがこの盗賊・殺人の詩人を描いた短編『その夜の宿』の事にも触れざるを得ないという調子である」 * 菊池寛は、敏の死後『新思潮』に、「先生の講義は豚に与えた真珠である」と書いた(『上田先生のこと』)。 また矢野への手紙に、 「これで日本には詩のわかる学者がなくなった」 と書いた。 * まったくちがった視点で、敏の人柄の温かさを活写しているのが林達夫の「父と息子の対話」(『思想の運命』)である。 中学五年生の達夫は、ひそかに尊敬していた敏を訪ねたことがある。自分の将来の志望について助言を得たい、と思ったからであった。 初めての、しかも突然の訪問だったのに、敏はこころよく面会してやった。そして文科をやりたい、という志望をきくと、自分自身、いまいかに政治的関心が強まっているかを語り、フランスの政治家=文士の活動の例をいろいろあげて、とにかく法科に一度入ったらどうかといった。 「この先生の忠言に従って、私は一高の法科へ進むことになったのですが、そこまではまあ無鉄砲とは見ないでしょうが、その先がどうもいけないのです。 「では、先生、試験までどうか英語を教えて下さいませんか」。 当時、わが国における最も有名な英文学教授にむかって高等学校受験準備の語学を教えろなんて、どうしてそんな大それたことがいえたのであるか、よくわかりません。私はそのとき、そんな申し出が、お門違いな無礼なものとは夢にも思っていなかったのです」 ところが敏はそんな無茶な言葉をきいても、まるで当たり前のことかのように、いかにも気の毒そうに、せつかくだが多忙で見て上げられないから、そのかわりにそういうことにもっと適任者である友人に頼んであげよう、といった。 それが厨川白村(くりやがわはくそん)。 「不幸にして年少の客気ゆえに厨川氏などは軽蔑しきって眼中になかったので、その場でこれは黙殺してしまいましたから、語学の一件はそれっきりになりましたが、考えてみると、先生が、中学生だからといって少しも私を子供扱いせずに大人並みに応対してくだすった態度には、実に細かい心づかいがあったと思い、いまだに感謝しているとともに、自分の言動のはなはだ礼儀を欠いていたことを今更恥じ入る次第です」 この話は、胸にジンとくる。林自身が上田敏に匹敵する、といえそうな『語学の達人』になったことはすでにのべた。その林の人生に、ときおりこのときの敏のことが思い浮かんだことだろう。そしてそれは、彼の人生におけるもっともなつかしく、うれしい思い出ではなかったろうか。 2023.05.26記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.213~218 高藤太一郎 藤沢善郎という未知の人から手紙をもらったのは五月中旬、体調が最低に落ちこんで、ついに入院する一月前のことであった。その手紙は、高藤太一郎という人物の消息について書かれていたが、それは二十年来の私の願望に対する親切な教示に他ならなかったのである。 * 緒方竹虎は好きな政治家だが、友人としても一流で、昭和二十五年六十四歳のとき『人間中野正剛』が、六十八歳のとき『一軍人――回想の米内光政』が出版されている。 いずれも伝記としての傑作だが、後書に出てくるのが高藤太一郎である。 米内の父は、盛岡市長の前身である盛岡戸長を四年つとめ、初代市長にも当選した人物であった。しかし、潔癖な人であり、政治生活は文字通り<井戸塀で資産を失ってしまった。この息子の光政も少年時代から貧乏の味をなめさせられたのである。 緒方は書いている。「盛岡中学二年生のとき授業料滞納者の氏名を掲示されたことがあった。米内光政という名もその中に書かれている。これを見た他の生徒は冗談半分に米内をとらえてからかう。これにはさすがに閉口していると、通りかかった五年生の級長高藤太一郎が、 『なんだ、なんだ、このくらいのことを大袈裟に騒ぐんじゃない』 とみんなを戒めて米内を救出した」。 それだけではなかった。高藤は学校の帰りに五年生担当教師の冨田小一郎宅を訪ねる。冨田は校内きってのやかましや。生徒からは煙たがられ、訪問しても玄関先で用事をすまして、座敷などには上がりもしないし、上げもしない。 高藤はその富田家に上りこんで、授業料滞納者掲示について談判する。 緒方は書いている。「家庭から渡された授業料を使いこんで滞納していないというような生徒なら、掲示して他の生徒のみせしめにするのもよかろう。しかし家庭の事情によって滞納しているものまで、同列に扱うことは教育者としていかがなものであろうかと攻め立てたらしい。冨田先生も高藤の義侠と米内の事情を知り、翌日すぐ米内光政の名は掲示板から消された。 親身な上級生の同情に感激した米内は、その後海軍に入って、昇進したり勤務先が変る毎に、いつも高藤の許には消息を寄することを忘れなかったという」。 * 私はこの話に感動した。緒方の筆=目と心は、本当に英雄的行為とは何か、を教えてくれている、と思った。 世に英雄伝なるものはあふれており、また英雄の出現を待望する声もある。しかし、凡百の「英雄伝」は、ともすれば、覇業、功名談、位階勲等、の世界に力点がある。英雄的行為の中身は、立身出世主義と肩書の尊重だ。無名の市井人は、伝記に書かれることもなく、ましてや英雄伝とは無縁の存在とされている。 これは私の伝記、英雄伝に対する根本的不信感、不満足感の原因となっていた。ところが緒方のこの文章は、そういう俗見にとらえられぬ肉眼で、ほんものの英雄をとらえている。こういうことのできるのが英雄的人物であり、肩書をもって英雄だと思いこんでいるようなのは英雄ではない。 それだけに、この中学生がその後どういう人生を送ったかは、気になるところである。しかし、いわゆる伝記は有名人のものしかなく、高藤少年のことを知る手掛かりがないのが残念でたまらなかった。私はその無念さを伝記への不信感として強めた。 ちょうど「今週の日本」から一年間の連載を頼まれていたので、私はそのことを一章に書き、のちに単行本『風貌姿勢』(竹井出版)におさめた。そしてさらに十九年たった昨年、東京での講演会で触れ、その講演録『伝記に学ぶ人間学』におさめた。 藤沢善郎氏は、『伝記に学ぶ人間学』を読まれて、私に手紙を下さったのである。 ※『風貌姿勢』P.259〔えの章 英雄伝〕に記載されている。なおこの本には黒崎昭二様 小島直記と署名までされている。小島伝記文学館(伝記作家・小島直記) * その要点を抜粋させていただく。 「私は亡兄信朗(大正十年三月生)が昭和八年四月、当時の第二東京市立中学(通常イチㇼツ二中と呼ばれ、現在の上野高校)に入学しましたおり、小学校五年生でありましたが兄が学校から持ち帰るもののなかに校友会誌(学校報?)のごときものがあり、その巻頭の写真(眼鏡をかけて頭髪は五分刈り、がっしりした体格)並びに一文があり、その何れにも『校長 高藤太一郎』と記されていたのを覚えております」 高藤氏は、信郎氏が昭和十五年三月卒業されるまでの五年間、ずっと同校の校長であったらしい。「自主協調の精神」を教育のモット―に掲げ、それは校歌、応援歌にも盛りこんであった。夏休み中には生徒たちを、埼玉県所在「平林寺」(小島註=松永耳庵夫妻の墓がある)の林間学校で鍛錬した。 「同校の卒業生や関係者が数多く居られますので、先生の御著書を読んで情報を寄せられる方々も多いかと推察いたしますが、『選択』五月号で橋口収氏の一文『私の読書日記』を読んであらためて『伝記に学ぶ人間学』を拝読し、連絡申し上げた次第でございます」 * 藤沢善郎氏は大正十一年六月生まれ。旧制麻生中学、旧制山口高校を経て東北大法文学部法科三回生の昭和十八年十二月、第一次学徒動員により海軍兵科四期予備学生となり、人間魚雷「回天」搭乗員として、山口県光市で敗戦を迎えられた。戦後は、二十一年八月、農林中金をふりだしに東京銀行に五十五歳の定年まで勤め、その後アメリカの生命保険会社、野村投資顧問を歴任、現在(株)日本格付研究所の嘱託として元気でおられるという。 なるほど、旧イチㇼツ二中の卒業生や関係者は数多いであろうが、それまで、どなたからも情報をいただいたことはなかった(私の著書がそう多くの人に読まれているはずもないことから、それは当然である。仮に読まれた方がいくらあったとしても、わざわざ手紙で知らせるということはなかなか出来にくいことだと思う)。だがそれだけに、藤沢氏のご好意は身にしみて有難く、真の英雄「高藤太一郎少年」が教育者としての道を進んだことを、読者各位に知らせたいという思いが強かった。しかしそのときは衰弱していて気力がなく、果たせなかった。 それから五ヵ月、私は「直腸癌」の手術をしてようやく退院し、最初の仕事としてこのことを書くことができた。「命なるかな」の感を抑え難い。 2022.02.17記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.218~223 熱い血――高藤太一郎少年・その後 中学時代、米内光政に義侠の手をさしのべた高藤太一郎のことを雑誌『選択』に書くと、盛岡の一方井卓郎氏、東京の俵伸一氏から懇切なお便りをいただいた。また旧「第二東京市立中学校」同窓会有志の手によって出版されていた『高藤太一郎先生を追憶する』という本が『選択』編集部の好意で手に入った。 二十年来気がかりであった人物の実像が、にわかにはっきりしてきてうれしいかぎりである。 太一郎は明治九(一八七六)年南部藩士族鈴木清令、妻シゲの次男として生まれた。五歳年長の長兄、三歳年長の姉、三歳年下の妹、五歳年下の弟、八歳年下の弟、十二歳年下の弟、十六歳年下の弟の七人兄弟姉妹。高藤と姓が変わったのは、熊本県鹿本中学教師時代。 二十九歳のとき、二十一歳の高藤ハツと結婚したが、日露戦争に従軍したハツの父(陸軍中佐、五十四歳で戦死)の遺言で高藤家の家督を相続し、姓を改めたのである。 ハツとの間に長女民(三十歳のとき)、長男土佐夫(三十二歳)、次女桂子(三十四歳)、次男正典(三十七歳)と四人の子宝が恵まれる。 米内のためにしたことについては、異説がある。すなわち、授業料滞納の掲示から、米内の名を抹消させたというのが緒方竹虎著『一軍人の生涯』の記述だが、これとはちがう話だ。 光政の父は、盛岡の筆頭の有力者であったが、政争に巻きこまれ、事業にも失敗し、妻子を残して東京に出て苦心奔走したが、なかなか再起できなかった。 残された母は子弟二人の子供をかかえて、夫から送金はなく、高利貸から家屋敷をとられ、裏長屋で針仕事をして暮らしていた。 高藤は、冨田教諭から二円借りると、その足で米内家を訪ね、母に渡したのだという。「当時、月謝は一ケ月五十銭、滞納三ケ月分が一円五十銭、あとの五十銭は、学用品代ということであった」(山崎正一・東大名誉教授。旧二期) * 海軍士官にあこがれたが、近眼のために兵学校受験をあきらめ、東京高等師範学校文科に入って、教育家を志した。これは、海軍士官になる子弟を育成し、果たせなかった自分の夢を間接に達成したかったからだという。 教育家としての経歴は次の通り。 明治三十三(一九〇〇)年、二十五歳、東京高師卒業。同校研究科入学。 三十四年、二十六歳、研究科卒業。 熊本県鹿本中学校教諭。月俸六十五円。修身担当。 三十七年、二十九歳、結婚(前述)。 三十九年、三十一歳。四月、熊本県師範学校教諭。九級俸(ただし当分の間八百四十円)。十二月、高知県師範学校教諭。教頭をつとめる。 大正二(一九一三)年、三十八歳。茨木県師範学校長。 八年、四十四歳。三重県師範学校長。 十二年、四十八歳。和歌山県師範学校長。 十四年、五十歳。上野二中夜間中学長兼任。 十五年、五十一歳。二級俸(三千六百円)。 昭和二年、五十二歳。高等官三等。 四年、五十四歳。一級俸(三千八百円)、年功加俸(百二十円)。 五年、五十五歳。満州出張。 六年、五十六歳。七月、欧米各国へ出張。 七年、五十七歳。四月帰国。 十二年、六十二歳。勲四等瑞宝章。 十八年、六十八歳。七月、郡制実施による校めい変更で、郡立上野中学校長兼都立上野(夜間)中学校長となる。八月、依願退職。 三十七年、八十七歳。六月永眠。 * 全生涯を通じてもっとも個性的な逸話は、三十七年(二十九歳)鹿本中学教頭として生徒数十名を率い、江田島の海軍兵学校を見学したときのものだろう。 呉で盛岡中学の先輩相羽恒三(海軍少佐)に会った。 相羽は、「頭脳明敏、人格すぐれ、気力充実の人として、太一郎がかねて尊敬していた人物。少年の日、海軍志願をしたのも、相羽の個人的感化によるものであった」(山口正一)。 その相羽が、この戦争中に第一線に行かず、軍港勤務になっている。不審に思ってたずねると、 「高利貸に借金があり、陸に足止めを受けておるのだ」 という返事。 太一郎は帰校するとすぐ上京して、その高利貸に会い、事情を聞いた。そして、新婚間もない国もとの夫人に連絡して金策を命じたのである。 夫人は行李いっぱいの嫁入り衣装を送ってきた。それは五百円で売れた。その五百円をもって高利貸を訪ね、相羽の借金を千円のうちの五百円を返却し、残額は自分が責任をもって返済することにして借用証文を取り返し、呉軍港に行って相羽にその証文を返した。 相羽少佐はこれで自由となり駆逐艦長として出征した。日本海海戦では、僚艦とともに、敵艦隊司令長官ロジェストベンスキー提督を捕虜とする武勲をたてている。 このとき太一郎は九級俸(年額八百四十円)で、五百円の高利の借金は大変な負担であった。それをその後十余年、返済しつづけた。 ついに高利貸は、 「もうこれ以上返却してもらわなくても結構です。私はもう十分儲けさせてもらいました。あなたのように義理固い人は当今珍しい。記念にひとつ差し上げます」 といって、黒光りのする木造の観音菩薩像を送ってきたのである。 この観音像を、太一郎は永い間床の間に安置していたという。 その追憶の書一冊を読み終えて先ず打たれることは、このような逸話である。 米内の逸話、相羽の逸話の他にも、たとえば、 「退職後までも友人の遺族の方のためにどなたかに借金をし恩給を返済にあてておりました」 と次男正典はのべている。このように他人の難儀を見過ごすことのできない太一郎の「熱い血」が、老いた私の心を感奮させるのである。 2022.02.18記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.228~233 宮本武蔵を知ろうよする人が先ず直面するのは、その経歴の不確かさ――そのことを伝える資料がいろいろのことを伝えていて、どれが本当であるか、見当がつかなくなることだろう。 一刀流宗家高野弘正氏の『日本武芸譚』によれば、 「幼名を弁之助といって、当時天下一の十手の名人新免無二斎の子として、作州(今の岡山県)英田郡讃甘村大字宮本で生まれた。しかし、武蔵の出生地は、彼の自著『五輪書』で、――自分は播州(兵庫県)の産である――とみずから述べているとおり、播州揖東郡鵤宮本村であると主張する人も数多くいるので、この二説のどちらが正しいか、今のところ断定はできないが、両宮本という在所が作州と播州の国境の山一つ越えたきわめて近いところにあるので、両方の武蔵信仰者はともに譲らないのである」とある。 ※参考:宮本武蔵著 渡辺一郎校註『五輪書』(岩波文庫)P.9(黒崎記) 小山竜太郎氏の『真説・日本剣豪伝』によれば、 「宮本甚右衛門家貞の三男として、天正十二(一五八四)年――一説に天正十年生れともいう――播州宮本村(今の兵庫県揖保郡大字太子町宮本)に生れ、赤ん坊のうちに新免無二斎の未亡人にもらわれて養子になった。義理の姉が一人いる>」とある。 出生地、父親が違うというのは決定的な相違である。その他いろいろあってはっきりしないのに、われわれの間に一つの定説となった武蔵像が、吉川英治氏の『宮本武蔵』であることに異論のある人はあるまいと思う。 この現象について、たとえば桑原武夫氏は、 「宮本武蔵の説話は、延享三(一七四六)年に八文字屋自笑(はちもんじやじしょう)の書いた戯作本(げさくほん)『花筏巌流島』をはじめとして、それにもとづく幾種類の講談が出ているが、吉川英治は、こうした民間の伝承に生きている武蔵像とは異なったものを提出しようという意図をもって、この『宮本武蔵』を書いたのである。そして、現在、日本人の間に支配的になっているのは、吉川英治の造型した宮本武蔵像であって、すでに別の像はほとんど消滅してしまっている」と書いておられるほどだ。(『〔宮本武蔵〕』と日本人』) この桑原氏の文章が書かれたのは一九六四(昭和三十九)年だが、このことは九〇(平成二)年の現在も同じと見てよいだろう。 *
記録を見ると、これが東京と大阪の『朝日新聞』の夕刊に連載されたのは、一九三五(昭和十)年八月二十三日から三六(昭和十一)年九月十日まで、『前編』(地の巻、水の巻、火の巻)三二七回。 三六(昭和十一)年九月十二日から三七(昭和十二)年五月二十日まで、『後編』(風の巻)二一三回。 三八(昭和十三)年一月から三九(昭和十四)年七月十一日まで、(空の巻)、(円明の巻)四七二回。 合計一〇一二回にわたっていた。 時代的背景としては、 (昭和十一年) 二・二六事件。 寺内陸相の自由主義排撃声明。 軍部大臣現役復活。 中野正剛、東方会結成。 スペイン内乱が起きる。 (昭和十二年) 日華事変起きる。 日独伊防共協定。 第一次人民戦線事件。 中ソ不可侵条約。 国共合作宣言。 文部省『国体の本義』配布。 (昭和十三年) 「国民政府を相手にせず」の近衛声明。 第二次人民戦線事件。 国家総動員法成立。 張鼓峰(ちょうこほう)事件。 ヒトラーのオーストリア併合。 (昭和十四年) ノモハン事件。 国民徴用令。 フランコが政権につく。 チェコ併合。 第二次世界大戦がはじまる。 などがあげられる。日本が太平洋戦争に傾斜していく息苦しい、いやな時期であった。 これは『宮本武蔵』に対して読者が何を求めていたか、なぜ歓迎されたという事情、そして作者吉川氏の心の世界の微妙な動きを探る手掛かりである。 * 歴史学者松島栄一氏の回想には、 「もえば、そのころの夕刊を待ちかねて読んだわたしは、まだ学生として上京したてであった。(これを毎晩老いたる母に読んでやるのが、そのころのわたしにできた、ただ一つの親孝行であったのだから)」 とある(中央公論社刊、全画挿入 愛読愛蔵版、第一巻付録)。 作家源氏鶏太氏の回想には、 「文学青年であった私にとって、『宮本武蔵』は、自分が文学青年であることを、完全に忘れさせてしまった。それほど、愛読したのである。愛読というよりも熱狂したといった方が当っている。 しかし、それは私だけではなかった。会社中が、いや、大阪中が、『宮本武蔵』のために沸き立っていた、といっても過言ではない。 毎日の夕刊を待ちこがれて読み、明日はどうなるだろうか、と話し合ったものである。時には、この話し合いが議論にまで進んだこともしばしばであった。 その頃、私は東京へ出張して、ここでも、同じことがくりひろげられていることを知って、おどろきを深くした。 お通さんが可哀そうだとか、お杉婆さんが憎らしいとか、話はいつでも具体的であり、それぞれにひいきがついていた。 大阪と東京がこうなのだから、恐らく、日本中がそういう状態であったにちがいない」とある(同、第二巻付録)。 私は中学生から旧制高校生の頃で、『少年倶楽部』の「神州天馬峡」のファンとして、その延長線の上でこの作品に引きずりこまれていた。しかし、配属将校のいばり方にささやかな抵抗を試みたりしたものの、数年後には軍隊に行き、死と直面するという運命を切実に感じることもなかった。 したがって、吉川武蔵に「求道者」、「剣聖」の典型を認め、これを自分の生き方の手本にするという気持は希薄であった。 令和四年五月十三日 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.233~238 「芥川賞」、「直木賞」は文学賞としてもっともポピュラーなものかもしれない。ところで、前者が芥川龍之介、後者が直木三十五を記念するための名称であることを知る人は少ないだろうが、その作品が、今日どれだけ読まれているか、という疑問をもっている。 直木(明治二十四~昭和九)は大阪生まれ。家は古物商で、本名は植村宗一。その「植」の字を二つにして「直木」とし、三十一歳のときにその年齢をよって「直木三十一」とした。以後、年ごとに数をふやし、三十四をとばして三十五としてからは「直木三十五」で通した。 逸話が多い。市岡中学時代は、試験のとき教師から、 「字が小さい」 と注意された。翌日、たくさんのわら紙をもってゆき、一枚に一字ずつ、大きな字を書いて答案を出した。 早大英文科予科に入学して、月謝未納で除名された。それでも登校をつづけ、卒業式の記念撮影にも加わった。 春秋社、冬夏社、元泉社、プラトン社など、出版事業はすべて失敗。マキノ省三と組んでの映画製作にも失敗、 着のみ着のみのまま親子四人で上京して、貧乏しうながら、昭和四年『週刊朝日』に「由比根元(こんげん)大殺記」を書いて作家として認められ、『大阪毎日』、『東京日日』に「南国太平記」を連載して流行作家tヴぉなった。 七年、ファシズム宣言。 九年、前からの肺結核に脊椎カリエスが加わり、四十三歳で世を去った。 「直木の功績は、大佛次郎とともに、時代小説を知識階級の嗜好ンいまでひきあげたことであり、文壇文学にすぎないとする純文学に対し、『大衆文学の理想は、ホメロスと近代作家との融合が到達点である』と豪語し、大衆文学への過小評価を訂正さえようとした理論的指導者であったことである。その奇行、喧嘩腰の論争、愛国者的姿勢で有名である」 と小松伸六は書いている。 * その「喧嘩腰の論争」の中に「宮本武蔵評価」の問題がある。そして、武蔵を高く評価する作家菊池寛、剣道家高野佐三郎、同斎村五郎、歴史家中村孝也(こうや)、同笹川臨風(りんぷ)が直木に斬られた(『武勇伝雑話』)のである。 * 「菊池寛は江戸時代における武蔵への陰口が、私に伝わった「ものだと、私の武蔵への非難を、解釈している。しかし武蔵に対する私の攻撃は、武蔵を偉人とする「宮本武蔵顕彰会」の『宮本武蔵伝』によったものであって、私の解釈が正しいか、どうかは、後に、武蔵の匹夫的行動を列挙して、これを論ずることにする」 ここでは先ず菊池の、「江戸時代における武蔵への陰口が、私に伝わったものだ」という意見の浅薄さが叩かれる。 もし、単に陰口云々のみに対して反駁するなら、「何が陰口であるか」を聞かぬとわからない。 「他の剣客に、武蔵のように非難されている例があるか」ということも、聞かなくはならぬ。 自分の引用する書物『宮本武蔵伝』(前掲)が、「陰口を伝えているか」、「当時の正しい話を伝えているか」、「武蔵に有利なこととともに、不利なものをも加えているか」。「武蔵を顕彰する会から出た本ゆえ、武蔵に有利なことのみ伝えて伝えている、不利な記録を収録していないか」……ここまで調べてみなくてはならぬ。 吉岡の試合のごとき、武蔵伝と、吉川家の記録とはまったく違っている。ところが『武蔵伝』には、吉岡の記録を全然収録していない。これで、公平に、考えることができるかどうか。 それとも、両者を比較して絶対に『武蔵伝』の方が正しいとでもいう人があるなら、「その研究ほ方法を、聞きたいたいものでである」。 武蔵は、いろいろと自分でも書き残している。『宮本武蔵顕彰会』などというものまでできている。せがれが小笠原の家老であっがゆえに、碑も立派にたっている。芝居となり、講談となる「、広く、人の頭に残されている。 「これは、その人が、残されない他の人よりも、数段えらかったのではなく、一つの偶然である」 由比正雪は、だれでもが知っているが,別木庄左衛門の名はだれも知らない。忠臣蔵は、残らず日本人が知っているが、浄瑠璃坂の仇討ちは少数の人しか知らない。維新の剣客にしても、千葉周作や近藤勇はよく知られているが、剣聖と称させれていた男谷下総のことはだれも知らない。 「これら人々の事績が、有名と無名と、そんなに格段の差があるかと云えば、大したことではない。ジャーナリズムが宣伝したか、せぬかの差のみである」 武蔵は、芝居となり、講談となり、一般化されている。そして、事実においても第一流の剣客であるから、多少研究した人は、なるほど、武蔵は偉い人だと感心する。 だが感心した人は、他の剣客の偉さを調べて、感心しているのか。武蔵だけを見て感心しているのか。こういう人々は、武蔵伝一冊見ただけで感心してしまって余の人の事績は、少しも研究していないらしい。また、するにしても、本もない。剣客の中で、ちゃんとした伝記の出ている人は、武蔵と、斎藤弥九朗、千葉周作ぐらいのもであろう。 「この点において、いささか、私は、余人のことをも、研究しているから、武蔵を、一流の中へ加えるが、ナンバーワンには、決してしない」 * 菊池寛はさらに、武蔵の試合の回数は六十三度、名は試合でも実は果し合い、といって誉めた。直木はこの点も叩く。 「試合は、必ずしも、果し合いではない。(中略)武蔵は、果し合い的試合もした。と同時に、傷つかぬ試合的試合もした。ことごとくを、果し合いに見るのは当時の法令を知らぬからである」 「試合において誇るなら、一つでもいいから、天下第一の人と試合をして、打ち勝つことである。天下第一を避けて、六十三人の弱い奴に勝ったとて、何の誇りにもならない」 塚原卜伝は、十七のとき、京の清水で真剣勝負をして以来、「真剣勝負」のみ十九度、場の働き三十七度、木剣の試合数百度、矢キズ六ヵ所、敵を討ち取る数、二百二人。 松本備前守、高名の首百二十五、並みの百七十六。 「武蔵は戦場へ六度出ているが、一向に戦場で働いていたという話は伝わっていない」 2023.05.30記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.238~242 直木三十五は、 「(宮本)武蔵のことは、次の五点を論じると、よくわかる」 として、 第一、その人物の、傲岸不遜 第二、その著作の価値 第三、剣道上の邪道としての二刀流 第四、当時における武蔵の社会的地位と名声 第五、門人に傑物の出ざること をあげている。 そして第一の例として九つの逸話をあげているが、武蔵の生涯は『自伝』、『他伝』ともに不備であって、後世の人間にとって、くわしいことはよくわからない。そのなかから逸話をひろってきてもそれは伝間証拠の域を出ず、根拠とするには弱すぎるのである。 動かぬ証拠、明確な客観的事績というものに、有名な『五輪書』がある。が直木はこれからも、 「みずからの勇を恃み、猛獣のごとく、うそぶいている」 と、酷評している。 「五輪書の冒頭にそれがある」 と書いて、次のような引用、例証の仕方をしている。 「兵法(ひようほう)の道二天一流と号し、数年鍛錬の事、初めて書物に書き顕(あら)はさんと思ふ。時に、寛永二十年十月上旬の頃(小島註。以下、岩波文庫卯で二十七字脱落)生国播磨の武士、新免武蔵藤原玄信、年つもりて云ふ(小島註。原文は、年つもりて六十)。我、若年の昔より、兵法の道に心をかけ、、十三歳にいして初めて勝負をなす。そのあひて、新当流有馬喜兵衛といふ兵法者に打ち勝ち、十六歳にして、但馬国秋山という強力jの兵法者に打ち勝ち、二十一歳にして都に上り、天下の兵法者に逢ひて、数度の勝負を決すと雖も勝負を得ずという事なし。その後国々所々に至り、諸流の兵法者に行逢ひ、六十余度まで勝負すと雖も、一度もその利を失はず……」 以下、あとで指摘する重要部分(小島註。岩波文庫で十四行分)を脱落させたまま、 「これは、人の書くことであって、自ら書くべきことではないようである。もし菊池寛が、「吾十三歳にして、文章世界に投書して一等賞をとり、十六歳にして、大学首席に出(い)で、二十一歳、"啓吉物語"を書いて、文壇を震撼し、四十六歳の今日まで、作するところ六十四余冊、一冊と雖も、売れざるものなし」と、自叙伝に書いたら、人々は何というであろうか」 と言うのである。 一見、武蔵の非を言うために都合のいい、当を得た解釈のようであるが、実はこれには大きな問題点が秘められている。それが「脱落の部分」であって、これを完全にネグレクトすればいかにも直木説のように武蔵の『自慢』となるかもしれない。しかし、原文すべてに目を配り、虚心にその真意を探れば、決してこのような曲解は生れないはずだと私は考える。
脱落の部分は、何を語るところであるのか。最初の脱落「二十七字」は、「九州肥後の地岩戸山に上り、天を拝し、観音を礼し、仏前にむかひ」というところである。すなわち『五輪書』執筆の場所、時刻、心の姿勢をのべている。 「熊本市の西方、有明海に面して金峰山(きんぽうさん)という山塊がある。最高峰でも六六メートルほどの高さだが、東は熊本平野の彼方に阿蘇の噴煙を見、西は有明海をへだてて島原の雲仙岳をながめることができる(中略)。この金峰山の中腹に雲巌寺がある。寺の奥にある洞窟を霊巌洞といい、石体四面の観音をまつっている。岩戸観音という。武蔵が参籠して『五輪書』を書いたのはここである。周囲には、うっそうと古木が茂り、奇巌の上に五百羅漢がこけむし、文字通り深山の気を感じさせてくれる。『神仏は尊し、神仏を恃まず』(独行道)という武蔵が、静かに波乱の生涯をふりかえり、勝負の道をまとめあげるのに絶好の場所だったであろうことがうなずける」(神子侃:かみこただし、『宮本武蔵五輪書』) この場所で、「十月上旬」(あとの脱落の箇所には「十月十日の夜寅の一点」とある。すなわち「十月十日午前四時三十分」)に、「天を拝し、観音を礼し、仏前に向って」書きはじめているのである。 「すでにこのことが重要な意味をもっているように思う。物事には、志と決意が大事(中略)、時や場所に託して決意を肝に銘ずることが大切(中略)、天・観音・仏という絶対者を拝して仕事を始めている。このことは、私心のないことを物語る(中略)、山鹿素行は、戦略は朝たてたものでなければ戦わずして負けだという。会社の会議などでも、本当は朝がよいそうである。茶の湯でも早朝に汲んだ水を使う。これらはみな、朝の陽気を尊ぶのであろう。(中略)『陽気を発するところ金石もまた透る』とは、嘘ではない」(寺山旦中(たんちゅう)、『五輪書、宮本武蔵のわざと道』) 神子、寺山両氏のこの文章に、「場所、時刻、心の姿勢」の重要性が指摘されている。 われわれも、早朝、誰もいない山林、神社、寺院の静寂のなかにたたずんだことはある。その場合、われわれの心中を去来するものは、打算、自慢、憎悪、出世欲など、いわゆる『俗情』を脱した清冽、恭倹、厳粛なものではないだろうか。まっしてやそこで、絶対者を拝む気持ちになっているとき、そのような俗情の忍び寄るスキなど、あろうはずはないのである。 武蔵もまさにそうであった。そこで観音像の前にひれ伏して、おのれの凄惨、真剣そのものだった決闘の生涯を回顧した。そして自分がどのような武芸者であるかを、包まずのべたのである。 「私はこのような体験をして参りましたもの。万事において師匠もなかった必死のその道を、神仏御照覧のもと、書きつづってみようと思います」 と、その絶対者に告白した。だからこそ、後半の脱落の部分が大きな意味をもつのである。 「万事において、我に師匠なし。今此書を作るといえども、仏法・儒道の古語もからず、軍記・軍法の古きことをももちいず、この一流の見たて、実の心を顕す事、天道と観世音を鏡として、十月十日の夜寅の一点に、筆をとって書初め(かきそ)むるものなり」 直木はこれを無視した。故意か。だとすれば卑劣である。そういうことに無感覚だったのか。だとすればつまらぬ作家である。 2023.05.31 記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.242~247 宮本武蔵評価のポイントは五つ、と直木三十五が書いたことは前章で述べた。 この章はその第五点、 「門人に傑物の出ざること」 についていろいろ書きたいと思っていたが、中川一政(かずまさ)の『腹の虫』(中川一政全文集、第九巻)に、じつに適切なことが書いてあるのでそれを引用する。 「ゴッホの後にセザンヌ、ルオーのあとにピカソ。予想もしない違った顔をして出てくるものである。禅師も画(え)かきもそうであろう。 一休も身後法度で、自分の真似するものを厭がり、これを仏法の盗賊といっている。 一休も書いているが沢庵も書いている。 『我に嗣法の弟子なし、老僧の身後に、もしわが弟子と称するものがあるときは、まさしく仏法の賊である。よろしく官に告げて大罪に処するがよい』 沢庵が一休をまねして云っているのではない。『我を学ぶものは死す。』という根本を云っているものである。根本から出たものではなくては本物ではなく花咲くことができない。画かきもそのとおりである」 剣士もそのとおりであろう。 * 吉川英治の『宮本武蔵』は、新聞連載のときの挿絵がよかった。 挿絵は、『地の巻』、『水の巻』、『火の巻』、『風の巻』を矢野橋村(きようそん)が描き、『空の巻』、『二天の巻』、『円明の巻』を石井鶴三(つるぞう)が描いた。 その鶴三のことを、一政は何度も書いている。『庭の眺め』(昭和十一年、一政四十三歳、全文章第三巻)の「強飯(こわめし)」には「友達」という云い方で出てくる。一政の誕生日に先輩友達を招いて、強飯を出した。 「私の隣りに座った友達は箸をとって暫く黙っていた。どうしたのかと思っていると、『何年ぶりのことでしょう』と感慨深い顔をしました」 そして後日、「友達」は身の上を語る。一政は「彼」という云い方で「友達」に聞いたその過去を書く。 彼が二十三歳のとき、兄が失明した。彼は美術学校の学生だったが、月給二十円のアルバイトを見つける。その二十円で、父なき兄病む一家を支えなければならぬ。家に稼いだ金を入れ、自分に渡される金は一日三銭であった。 朝飯を食べて学校に行き、八時から九時までいて、それから会社まで徒歩で行く。三銭ではソバも食べられない。強飯が三銭であったので、それが唯一の糧(かて)であった。 その三銭も紙筆に代えれば、その日一日食わないでいねばならない。 彼は、人の家のゴミ箱を開けた。動物質の肉や魚は悪臭がしたが、植物質のものは洗えば汚くないからそれを食べた。 どんな厳寒も、制服と一枚のシャツだけ。夜、外堀を帰ると空腹と寒さのために幾度も倒れそうになった。 路上に眠るときは、砂利をつんだ陰に身を横たえると温かい。風は身体(からだ)の上を通って行くから。 「ルンペンをした人でなければわからない」 と彼は云った。 兄の失明が治ったときにはホッとした。が、家の者は兄を助けて早く世の中に出さねばならぬという考えで、彼はその生活から三十になってようやく放免された。そして結核になっていた。 医者は、 「うまいものを食べて転地しなければ助からぬ」 といったが、彼はその言葉を聞かず、石にかじりついても生きて見せると決意した。ちょうど同輩に同病の人がいて、これが死んだのである。 「あのとき医者の云うとおりになっていたら私は死んだろう」 と彼は云った。 一政と識るようになってからも、 「画で食えなければ労働で私は食える自信がある」 とよく云った。 そして今日、次のように云う。 「いくら自分が画家であると威張っても駄目だ。世間から選手として選ばれなければ、選ばれるまで勉強しろ。世間は選手として選んだ以上は餓死させない。私は今日私を選んで食べさしてくれる世間に不誠実な画をかいてはすまない」 また、こうも云う。 「私は金は持っていない。しかし世間にあずけてある。その金をどれだけ使えるかはその人の力である」 * 一政は、この「強飯」の末尾に、 「その名を挙げることはその時でないから挙げません」 と書いた。しかし、次の年に書いた「石井鶴三」という随筆(全文集第三巻、『顔を洗う』)のなかで、その名前を挙げたのである。 一政、鶴三の出会いは、大正九年、一政二十七歳のとき、神田神保町(じんぽうちょう)の兜屋画廊で一政の個展があったとき、鶴三が見に来たことからはじまる。 一政は、いろいろと鶴三のことをほめている。そのうち、鶴三の画を描く態度を、『宮本武蔵』の挿絵でなく、武蔵その人に結びつけてほめているのが印象的である。 二人は奈良の博物館に行った。義演和尚(ぎえんわじょう)の像を喜んで、鶴三はその彫刻の木の継目などの細部を綿密に調べてからスケッチをはじめた。 「誰もいないガランとした室の中で、足を少しく開き腹に力を入れ眼を心持ち細目にして、たっぷりした形で描いていた。どっちかと云えば剣術つかいに似ている。 後で宮本武蔵の兵法(ひようほう)を読むに及んで、うらやかな眼というのはあの心であろうと思った」 この「うらやかな眼」については「庭の眺め」の中にも次のように書いている。 「にぎやかな二科会! 沢山の出品を残暑と人いきれの中でどう見て歩いたらよいだろう。(中略)石井鶴三はうらやかな眼をして壁面を伝わってゆくそうである。よい画には特別の空気があってそこへ来ると自ら足が停まるとうのである。うらやかな眼と私が云うのは、それが宮本武蔵が説いた兵法三十五個条の眼付であるからである」 参考のため兵法第三十五条の第六を掲げる。 「目を付けると云所、昔は色々在ることなれ共、今伝る処(ところ)の目付は、大体顔に付るなり。目のおさめ様は、常の目より少し細き様にして、うらやかに見る也(なり)。目の玉を不動、敵合近く共、いか程も、遠く見る目なり。(以下略)」:岩波文庫 宮本武蔵著『五輪書』P.143 ⑥一 目付の事(黒崎記) 2023.06.01記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.247~251 吉川英治『宮本武蔵』では、沢庵が重要な役割を果している。 登場するのは『地の巻』の第四章「花御堂」である。播州滝野口に近い宮本村の寺に、孤児で十七歳の娘が世話になっている。本位田又八の許嫁で、のちに武蔵を恋い焦がれるようになる薄幸の美女お通である。 前の年、関ケ原の戦があり、又八と武蔵は、手柄を立てに出ていった。ところが、それきり今にいたるまで何の消息もない。 「なぜ男は、戦など行くのだろう。あんなに止めたのに――」 お通が縁側で物思いにふけっているところに、真っ裸の男が井戸のほうから歩いてくる。 「まるで煤しにかけた羅漢である。三年か四年目には、寺へ泊る但馬の国の雲水で、三十歳ぐらいな若い禅坊主なのだ」 と吉川が書いているのが沢庵宗彭であり、作品初登場の場面である。 関ケ原合戦の翌年ということであれば慶長六(一六〇一)年である。『沢庵和尚年譜』(東海和尚紀念録)によると、この年沢庵は二十九歳である。 また、『五輪書』の「年つもって六十」という記述が正しいとすれば、武蔵の生年は天正十二年(一五八四)年ということになり、小説のこの時点では数えで十八歳である。 武蔵が村に帰ってくる。まだ求道の武芸者「武蔵」ではなく、腕力だけの「たけぞう」である。暴れまわる「たけぞう」を捕まえて千年杉の梢をぶら下げて曝すのが沢庵だ。そして、 「怖いものの怖さを知れ」 「暴勇は児戯、無知、獣の強さ」 「もののふの強さであれ」 「生命は珠よ」 と教えて、武蔵に求道の出発点を用意してやるのである。 沢庵は、以下『地の巻』、『水の巻』、『火の巻』、『風の巻』、『空の巻』、『二天の巻』と毎巻登場したあと、大坂城の工事現場で捕えられた又八を救った後は、どういうわけかこの小説の世界から姿を消してしまう。最後の『円明の巻』に禅僧が登場するが、これは沢庵ではなくて愚堂という別人である。 なぜ沢庵が姿を消し、愚堂にバトンタッチをしたかについては、吉川は一言も書いていない。 * しかし、沢庵は死んでしまったのではない。彼の生涯のもっとも輝かしい事蹟は、このあとにこそ示されるのだ。 彼は慶長十四(一六〇九)年三十七歳のとき、後水尾天皇の詔を受けて大徳寺に住持(第一五三世)となる。 大徳寺、妙心寺は皇室にかかわる寺なので、幕府の管理する五山とは別格である。出世入山は「紫衣出世」といい、天皇の綸旨が必要である。五山派の寺は幕府の公帖によって「黄衣」出世という。「紫衣」を賜わることは、僧侶としての最高位について「高僧」として待遇されたことになる。だが沢庵はわずか三日でその地位を辞退して大徳寺を去ったのである。 この行動、心理は、一休宗純の故事を思わせる。一休が後土御門天皇の詔によって大徳寺の住持(第四七世)になったのは、文明六(一四七四)年八十一歳のときであった。 このとき作った詩の一節に、 「五十年来蓑笠客、 慙慚今日紫衣僧」 というのがある。 「五十年間も破れた衣に身を包み、名もなき一坊主で過してきたのに、今では高僧ともてはやされている。なんと恥しいことか」 彼はたった一日しか大徳寺内に住まなかった。もっぱら薪村の酬恩庵に引き籠って、のっぴきならぬ用事のときだけわざわざ八里の道を輿に乗って京まで通ったという。 * しかし、自らを黒衣の無名僧と意識し、行動する気持は、「紫衣」を無視するということではない。 寛永四(一六二七)年沢庵五十五歳のとき「紫衣事件」が起きた。幕府は「妙心寺、大徳寺法度をつくり、両寺に布達した。それは将軍の公帖を有せざる紫衣は、元和以後のものはこれを許さぬ、というものである。 このとき沢庵は、幕府の権威を恐れず、抗議の文書を提出してスジを通そうとし、その罪で出羽国(山形県)上山に流されたのである。 流寓生活足かけ四年、寛永九(一六三二)年徳川秀忠が死ぬ。彼はすでに元和九(一六二三)年に将軍職を家光に譲っていた。 かねてから沢庵に好意を抱く将軍家剣術師範柳生但馬守宗矩などが家光にとりなしてくれたので、許されて江戸に戻ったのが六十歳のときである。 家光は、沢庵を尊敬するあまり、江戸に寺を建ててやり、宗教界を取り締まる最高の地位をあたえようとした。しかし、沢庵はこれを辞退して京都にもどり、やがて但馬に隠棲した。 家光の命で江戸に出たのが寛永十二(一六三五)年六十三歳のときである。沢庵は柳生但馬守の麻生別邸に寓居した。 そして但馬守に手紙を書く。「不動智神妙録」として今日まで伝えられたもので、四百字詰原稿用紙に直して十四枚の長さである。このなかで沢庵が力説していることは、 「自分が自分になりきる、自分に徹しきるにはどうすべきか」 ということだ。そこに、剣禅一如の境地が説かれている。 しかしそれだけではない。 「唯今寵臣たるにより、諸大名より賂を厚くし、欲に義を忘れ候事、度々不可有候。貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり。上の唱は猿楽の様に申し候由。また挨拶のよき大名をば、御前においても強く御取成しなさる由、重ねて能々御思案可然歟」 自分に好意をもつ人物だからこそ、直言したのである。 令和四年五月十四日 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.252~256 剣道の流派はいろいろとあるあ、チャンバラ映画のドル箱は柳生流のようである。最近テレビではÞヴゃんバラ映画の根強い人気に応えて多くの番組が登場しているが、『柳生武芸張』はじめ柳生関係が圧倒的に多いように思える。 この『武』の家門柳生家が『文』の本家とみられる菅原道真の後裔だというのであるからおもしろい。 宇治関白藤原頼道が大和国四箇(しか)の荘を春日神社に寄進したとき、道真の裔(すえ)永家がその一つである小柳生荘を預かった。そして彼の子孫がそこに定住して地名を氏(うじ)にしたのだという。 戦乱の時代、当然柳生家にも浮沈があった。 永珍(ながよし)のとき累代の所領を失ったが、兼武中興のとき本領を安堵された。 その七世宗厳(石舟斎:せきしゅうさい)は豊臣秀吉のため、隠田(おんでん)の科(とが)で所領を没収された。しかし関ケ原の役で宗厳は、その第八子宗矩とともに徳川家康に従い、その功によって旧領柳生の地に二千石を賜わり御家人となった。 こののちたびたび加増、寛永九(一六三二)年一万二千五百石を領し、明治になって華族に列「し子爵となっている。 * 累代の人物中、チャンバラ小説、映画の花形となっているのは先ず石舟斎宗厳と、その息子宗矩、宗矩の長男十兵衛三厳(みつよし)の三人である。 宗厳は、はじめ筒井順慶に属し、ついで松永秀久に従い、やがて徳川家康に見出されて一族繁栄の芽が吹いたが、この間二つの重要なことが伝えられている。 一つは、上泉秀綱(こういずみひでつな)に新陰流(註=河出書房版『日本歴史大辞典』)は「神陰流」とし、直木三十五は「新陰流」と書いている)を学んでその奥義を極め、新陰流を創始して家康にこれを伝授したということ。 第二は、関ケ原役のときは、家康のスパイとして大阪方の動静を探ったということである。 第一の点については、直木三十五が『剣法夜話』において書いた逸話が記憶に残る。 「当時、柳生流の元祖、柳生宗厳は、近畿第一と称されていた。この人のところへ、上泉がきたとき、試合となって、上泉は『まず』お、門人、疋田文五郎を出した。宗厳が、立ち向かうと、文五郎、『右をとる』と、いうと、ぽんと、右が入る。『左をとりますぞ』ぽんと、左が入る。段違いだ。宗厳と、門人の疋田で、これだ」(「武勇伝雑話」) 直木はまた『武功雑記』という書物の一節を引く。 「兵法つかひの上手に、上泉伊勢という虎珀(こはく:疋田文五郎小伯のこと)という弟子を召しつれ和州へ行く。時に柳生氏、上方(かみかた)にて兵法無類の上手なり、幸ひと思はれ、上泉を呼んで木刀を所望し見て、心をかしく思ふて上泉と試合を望む。家泉さらば、まず虎伯と遊ばせよと、再三辞退す。柳生即ち、虎伯とつかひしに、虎伯、それにては悪(あ)ししとて三度まで柳生を打つ。そこにて是非上泉と仕合を致したしと望む。上泉辞退しかねて向かふといなや、其(その)太刀にては取り申すとて取る。之によって柳生大いに驚き、上泉を三年まで留置し、しんかげの秘伝を伝授す……」 これで見れば、柳生宗厳の腕前は大したものではなかったことになる。それが一流派を創始し、徳川家康に伝授するほどの自信と信用が生れるまでに、どのような精進が重ねられたか。このことについて具体的に書いたものに、何があるだろうか。 第二のスパイ説をもとに一編の物語を書いたのが五味康祐である。それが『柳生武芸張』であることは周知の通りで、何度も映画化され、ついこの間もその新作がテレビで放映された。 徳川家康は、そのとき柳生石舟斎、山田浮月齋、霞幻竜齋など三スパイを使った、というのがその作品の設定である。 しかし役目が終ると、家康は山田、霞幻竜齋にはわずかな金を与えただけで縁をきり、柳生石舟斎ひとり重用するようになる。 霞は死ぬが、山田は生き残り、その復讐を企てる。彼がそのためにねらうのは『柳生武芸張』といわれる三巻の巻物で、それは徳川打倒をねらう大名たちの連判状。もしそれが世に出れば、天下は二分され徳川体制も倒壊の危機におちいるという。 その争奪に、山田一味と柳生一族、特に石舟斎の孫の十兵衛三厳が血みどろの戦いをくりひろげ、それに霞の遺児がからむという筋立てだ。 吉川英治の『宮本武蔵』では、『水の巻』に石舟斎が出てくる。スパイの一件は書かれていない。上泉伊勢守のことは書かれている。 上泉の訪問は、石舟斎三十七、八歳の頃。お供は、甥の疋田文五郎と、老弟の鈴木意伯。立ち会うのは疋田でなく上泉で、第一日、第二日、第三日とも、指定したところに打ち込む。 小柳生城に引きとめられて教えたあと、立ち去るときに一つの『公安』を授ける。 「無刀の太刀如何(いかん)?」 石舟斎は寝食忘れて研鑽、のち再会して立ちあった上泉は一目見て、 「もうあなたと太刀打はむだなことである。あなたは、真理をつかまれた」 といって、印可、絵目録四巻を残して去る。 さて、石舟斎の晩年。 訪ねてきた吉岡伝七郎一行とは会わないで、その宿に芍薬一本を届けさせる。その使いがお通である。 伝七郎は枝の切口に目もとめず、むっと色をなして、 「ば、ばかな。芍薬は京にも咲いているといってくれい」 と突き返す。その報告を聞いて、 「やはり会わんでよかった。会って見るまでもない人物、吉岡も、まず拳法一代じゃ」 と石舟斎はいう。 ところが、持ちかえられたその花の切口に目を止め、自分も芍薬を切ってみて、自分の腕がはかに劣るのが武蔵である。 だが、切り口で何が分かるか、という反論があった。武蔵が箸で蠅を捕まえるところとともに、つまらぬ作者の思いつきだ、という声もあった。 そうであるかもわからない。しかし、この挿話はいまでも鮮やかに心に残っている。 そういうものだろうと、心のどこかで深くうなずくものがある。 2023.05.29記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.256~260 柳生家第七世石舟齋宗厳は子沢山だったらしい。彼とともに徳川家康に従い、やがて第八世として家をつぐことになる但馬守宗矩は、石舟宗厳の第八子(直木三十五によれば第五子)だという。 だとすれば、その上に少なくとも七人の息子がいたはずだが、夭折したのか、凡庸、軟弱だったのか。 ところで、柳生父子が家康につかえはじめたという文禄(一五九四)年に、石舟斎は六十八歳、宗矩は二十三歳「であった。関ケ原賤のあった慶長五(一六〇〇)年には、石舟斎七十四歳、宗矩三十歳、この前後、彼らの役目が家康のスパイだったとする説をとれば、父の力はすでに老齢、肉体的にスパイ活動は無理と思われる。したがってその役目は、せがれ宗矩が主につとめたのではなかったのか。 このあと、その功によって柳生の本領に二千石を与えられた。そして関ケ原戦の翌年(慶長六年)、宗矩は家康の第二子秀忠(二十三歳)から入門誓紙を受け、柳生流を伝授しはじめた。これは徳川幕府成立の二年前である。 同十一(一六〇五)年には秀忠は二代将軍に就任、宗矩も将軍家兵法師範となり、地位も高まり、千石加増されている。そしてさらに二年後、宗矩三十七歳のときに待ちに待った長男が生まれた。これが「のちの十兵衛三厳である。石舟斎は、その孫の生れる一年前、八十歳で世を去つていた。 * 元和七(一六二〇)年宗矩五十歳のとき、二代将軍秀忠の第二子家光(十七歳)の兵法師範となった。 家光は稽古に熱中した。一方、技術、心法のことについても疑問をぶちまけた。性急でわがままな将軍家御曹司のねだりにこたえて、宗矩は文筆でそのことを書き出そうとした。のちに『兵法家伝書』として完成する柳生新陰流の基本的伝書は、ここにその端緒をもつ。 なお、このようなことで、家光の信任はいよいよ厚くなっていった。その三年後に家光は三代将軍となる。信任厚い宗矩の声望もこれとともに倍加する。 寛永六(一六二九)年宗矩(五十九歳)は従十五位下・但馬守に叙任される。。同九年、大御所秀忠が五十四歳で世を去り、名実ともに家光時代となる。 八月はじめ、「紫衣事件」で羽州(山形県)上山に流されていた沢庵(六十歳)が許されて江戸にもどったが、これは日頃彼に好意を持っていた宗矩が家光にとりなしたからだという。 沢庵が江戸にもどった翌九月、多年書きつづけていた兵法書が『兵法家伝書』として完成した。これは「進履橋」、「殺人刀 上」、「活人剣 下」の三部から成る。 「進履橋」は中国の古典『史記』にある故事に基づく。張良の青年時代、土橋の上で老人(黄石公)に出会った。老人は橋の下に履(くつ)を落とし、張良はこれをとってきて、はかせてやった。この縁で兵法を授けられ、のち漢の高祖を助けて項羽を滅ぼし、天下平定に貢献した。 「みずからを張良に比し、その兵法をもって平天下の礎としようとした宗矩の自負心をうかがうことができる」
と渡辺一郎はいう。(『兵法家伝書』岩波文庫本、甲註) 『兵法家伝書』には、この三年後、沢庵が宗矩にあてた書簡(『不動智神妙録』)にも出てくる次の言葉がある。 「はじめは何もしらざる故」 「念(ねん)に渉(わた)って無念」 「なす心を外へちらさずして」 「無心」 「わが身へもとめかへせ」 「心を放ちかけて」 「敬の字」 「行ふ間の心(しん)なり」 「始終治まりたる心(しん)」 「間(ま)に髪(はつ)を容(い)れず」 「着(ぢやく)」 「本心・道心」 「本心かくれて妄心となる」 「至極向上にはあらず」 宗矩は、「法の師の示しをうけてここに記(しる)すものなり」と書いている。この「師」が沢庵を意味することはいうまどもない。甲註者・渡辺一郎は、 「沢庵と宗矩との緊密な接触は、寛永九年八月、沢庵が羽州上山における三年の流謫(るたく)生活から赦(ゆる)されて江戸に滞留するようになってからと考えるのが妥当であり、この『兵法家伝書』の成立年代である寛永九年九月との間は、せいぜい二ヵ月しかない。この時点で、宗矩の手許にはある程度の草稿ができあがっており、そこに使われているh禅の古語や老儒の語句の用法に沢庵の批判を乞い、疑義を正し、助言をうけて加筆訂正したと見る方が妥当ではなかろう」 という。 『兵法家伝書』完成とおなじ九月、宗矩は将軍側近として御使番のシンボルの「五の字」の旗指物を許され、十月には三千石加増、十二月には総目付(大監察)となり、次いで一万二千五百石の大身(たいしん)となった。 これは、兵法師範から行政官僚への転身であり、彼の勢威は一段と増したが、またおのずから傲(おご)り、油断も生じたのであろう。三年後、江戸に出た沢庵が、のちに『不動智神妙録』と呼ばれる手紙で彼を叱責したのがその証拠である。 「(前略)、ご子息(十兵衛三厳)の素行の定まらぬことについて申します。親の心がけ、行動が正しくないのに、子供の悪を責めるのは誤り。あなたがまず身を正しく持し、その上で意見されれば、自然素行も改まり、弟内膳殿(宗冬)も兄の行動を見習って正しくなるでしょう。こうなれば父子共々に善人、まことにめでたい。(中略)あなたは寵臣で、各大名から賄賂(まいない)も多く、欲に目がくらんで義を忘れておられるようだがとんでもないこと。また、乱舞を好み、自分の能に思い上がって諸大名のところに押しかけて能を見せるということは、もう病気としかいいようがない。さらに御上(おかみ)の唱を猿楽だというではありませんか。また御世辞のよい大名を、将軍御前において大いに引き立てられるとのこと、重ね重ねよく考えていただきたい。 歌に『心こそ心迷わす心なれ、心に心心許すな』とあります」 このとき沢庵は、宗矩の別邸に滞在した。これこそ両者の親交を物語るものだが、親友であるだけに、沢庵は宗矩の傲りを天下のために許さず、真正面から打ち据えた。 柳生新陰流の家元は、その真実、道念によって一刀両断されたのである。 2023.05.28記す。 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.261~265 年が改まってもテレビでは時代劇ブームで、」そのうち「柳生もの」が大きなウエイトを占めている。演ずる俳優は代わっても、ドラマの主役は但馬守宗矩、十兵衛三厳父子であり、父は政略、せがれは武闘とその役割は決まっている。 十兵衛三厳は刀の鍔を眼帯代わりにかけた独眼竜ながら、その強さはまさに無敵、山村聡(やまむらそう)が宗矩、松方弘樹が三厳に扮した番組では鹿児島まで乗り込んで、実に薩摩示現流の達人たち五十人を一気に斬り捨ててしまった。 荒唐無稽もここにきてはご愛嬌の感があるが、それにしてもこの三厳という人物、私は柳生一族のなかではもっとも興味があり、劇映画小説上の取り扱い方に不満、疑問をもっている。すなわち、単に強いだけの荒武者ではなかったと見るのである。 父親の宗矩という人物は、沢庵和尚の『不動智神妙録』を読むかぎり、出脊主義でギララのスノッブだと思われる。柳生の里の無名の地位から、将軍家兵法師範として頭角を現わしはじめたおのれの家を、いよいよ栄えさせたいという願望も強烈であったろう。ところが、その柳生家をつぐべき息子がなかなか生まれなかった。これは彼にとって最大の心痛事であったに違いない。 慶長六年、宗矩三十一歳のとき徳川家康の第二子秀忠(二十三歳)から入門誓紙を受け、柳生流を教えはじめた。 四年後、秀忠は二代将軍に就任、宗矩は将軍家兵法師範となり千石加増、計三千国となった。 その喜びを浮世の土産として、翌年石舟斎宗厳が八十年の生涯を閉じた。 そしてさらに一年後、待ちに待った長男が生れたのである。幼名七郎、すなわちのちの十兵衛三厳である。 * 七郎は、天稟の素質を持ち、石舟斎の再来といわれた。宗矩の喜びも察するに余がある。 十三歳のとき、将軍世子家光の小姓として出仕、三歳ちがいの恰好の兵法相手として重用されはじめる。 その翌年、宗矩は家光の兵法師範となり、生涯の密接な交わりがはじまる。 これは、せがれ七郎の身分、将来にとって、つまりは柳生家の家運にとって、確実な保証ができたことを意味していた。当然、父親にとっては跡取り息子がさらに大事な存在に思われてきて、目を細めて自慢の息子を眺めたことであろう。 ところが意外な成り行きとなった。七郎、元服して十兵衛三厳となった長男が、寛永三年二十歳の秋、家光の勘気を蒙って致仕したのである。 翌年、宗矩は病気で倒れた。それは剣術が好きではあるが、反面性急でわがままな家光のねだりによって、柳生流の神髄を文章の形にするため、『兵法家伝書』の執筆に心魂を傾けていた。その積年の過労から胃潰瘍となったのである。希望の星、長男の失寵、致仕という思わぬ事件についての心痛も、その病気のもとになったのではなかったか。 * 三厳がどういう理由で家光の勘気を蒙ったのか、これははっきりしない。「素行不良」というのが定説になっていたようで、沢庵もその手紙に、 「ご子息の素行の定まらぬことについて申します。親の心がけ、行動が正しくないのに、子供の悪を責めるのは誤り」 と書いているのである。 しかし、「親の心がけ、行動が正しくない」ということの中身である。 宗矩の素行がどうであったか、その議論はあえて二の次としてもよいだろう。素行不良でなかったとしてもかまわない。息子の心を傷つけ、身をあやまらせるもととなったのは、おやじの人生観、価値観、人柄であったろうと思う。 「おやじ殿は『兵法家』だ。『剣士』として、剣の道ひとすじに生きる人間でなければならぬ。しかるに、おやじ殿には出世欲、権力欲の体臭が強すぎる。『すべては柳生家の繁栄のために』などという次元をうろついていて、どうして剣の奥義に達することができようぞ」 幼にして石舟斎の再来といわれた天才であっただけに、青年三厳は『剣』の道に真剣であり、純粋であった。 その故に俗物根性の固まりのようなおやじの生き方、そういう家の跡継ぎとして、お家大事に主君につかえる生き方が面白くないようになった。 その憂さを酒、遊離によってまぎらわそうとし、それが「素行不良」として家光の恩寵を失い、罷免されるもとになった。 こういう道筋ではなかったか。 * このような推測を可能にするのが、その後の三厳の精進、成長である。 彼は致仕したのち、不機嫌なおやじのもと、江戸を離れて、柳生の里にこもった。それからの幾年月、ひたすら『剣』一筋の道に打ち込んだ。 そして寛永十四年三十一歳のとき、夏稽古のはじまる五月一日に江戸にもどり、父の道場で稽古の総仕上げを行なった。そして、その成果をまとめた一巻をもって沢庵の校閲加筆を乞い、初めて父より印可を受けたのである。
このタイトルのつけ方、武骨一辺倒でないところが注目を要する。単にタイトルの文字趣味だけではなくて、たとえば『悒(ゆう)貫書』には、 「一、秘する花を知る事。秘すれば花なり。秘せざれば花なるべからずとなり」 と世阿弥の『風姿花伝』を引用しながら、 「兵法秘すべき事、我兵法の仕覚たる所をば、一子にも其者の心持を見届けざる以前は、相伝有るべからず」 と書いているところをみても、ただ木剣を振るだけでなく、能の道にも思いを潜めた心の姿勢、教養がうかがわれるのである。おやじの『兵法家伝書』についても「秘伝どもみなつくせり。重畳sり。丁寧なり」と最大級の評価を与えた。理屈や親子の情からでなくて、孤独の武芸者としての血みどろの修練から得た評価である。宗矩もうれしかったであろう。 四十四歳のとき、柳生に近い山城村で遊猟中に急逝した。 病気か、暗殺されたのか、その詳細は知るべくもない。 2023.05.29記す。
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.308~312 ワインで有名なこの港町には前から良い感じを持っていたが、実際に行ってみてさらにその気持が強くなった大きな理由に、カンコンス広場の印象がある。
これは十二万六千平方メートルあってヨーロッパ最大の広場だという。だが単なる広さなどナンセンスだ。カンコンス広場の特徴は、王や将軍の世俗的で生臭い彫像など一つもなく、東西向かい合う形でモンテスキューとモンテ―ニュの彫像があることだ。すなわち、記念すべき代表人物として、片や『法の精神』の著者、片や『随想録』の著者――ともに世界的『思想』の権威者を公園の彫像に選ぶことの素晴しさ=その土地にそういう人がおり、またそいう人を選ぶ市民がいるという二重の意味において、ボルドオの格調があり、気品がある文化的、精神的豊かさを示していることだ。 * はじめモンテスキュー、次にモンテ―ニュの彫像の下に立って、何枚も写真を写しながら、いろいろの思いが浮かんで、この公園と別れるのがつらい。公園なるものに、これほどの愛着をもったのは生涯初めてのことである。 モンテスキューは一六八九年に生まれ、一七五五年に六十六歳で死んでいる。 モンテ―ニュは一五三三年に生れ、一五九二年に五十九歳で死んでいる。 二人とも意外に早死、というより、自分がいつの間にか、すでに二人の没年を過ぎた老齢に達していることが胸に波紋を起す。彼らの著作を机において、胸のおどるような高揚を感じた青春の日のことが走馬燈のように浮ぶ。 その回想から一つの決定的な疑問―― 「しかし、自分は一体何を学んだろうか? ことにモンテスキューに」 *
「モンテ―ニュを若いとき読んでもわかるはずはない」 という意味のことをツヴァイク(Zweig:黒崎記)も言っている(『三人の巨匠』)。正確には、「生涯のどんな時期にも、どんな年齢のときにも、誰でもがすぐに親しむことのできる数少ない何人かの作家がいる。ホメロス、シェークスピア、ゲーテ、バルザック、トルストイなどである。しかしその反面、一定の時期にいたって、初めてその意味深い胸うちを、すっかり開いてみせてくれる作家がいる。モンテ―ニュがその一人である。あまり若すぎて、人生の経験も浅く、絶望を味わったこともないようでは、モンテ―ニュを正しく評価することはできない」
たとえば『随想録』第一巻「第二十章哲学するのはいかに死すべきかを学ぶためであること」というのがある。 モンテ―ニュはこれを三十九歳で書いた。若い日の私がこの一章で理解できたのは、この事実一つではなかったのか? だがそれにしても、そもそも死について語る年齢は、何歳ごろが適当か。三十九歳で死の意味をのべるということは、はたしてどういう問題をもつものであろうか? これは、古稀になって死の切実さを感じているものにとって、どうでもよい問題とは思えない。 三十九歳といえば、アミエルが「老いるということは死ぬことよりも難しい」と日記に書きつけた年齢でもある。彼は六十歳で死んだから、『老い』の難しさを十分に体験したとはいえまい。ただ、すでに彼より十年長く生きたものとしては、その言葉の深い意味、洞察の鋭さが若い頃よりもよくわかる気がする。 モンテ―ニュが三十九歳で死について語ったとしても、別に支障がないことは、アミエルの例を見ればよくわかる。 * この文章を書いた頃モンテ―ニュの眼には、『死』は急激に突如として襲う人生最大の不幸として映っていた。ところが四十一歳頃落馬して失神するという経験をし、四十四歳以後はしばしば腎臓結石の発作に見舞われた。そこで『死』というものは、むしろゆっくりと静かに近寄ってくるものだということをさとったという。それにしても、彼がごく若いときから死ぬときまで、生涯『死の思想』(『死の恐怖』とはちがう)にとりつかれいたことは事実である。 『生老病死』、『生者必滅』という人間の宿命=必然を、彼は『ユメーヌ・コンディシオン(humain Condition:黒崎記』(人間の分際または人間の境遇)として、それをありのままに、たじろがずにうけとめて、強く、楽しく、生き抜き生き終るためには『哲学する』必要があると考えた。この文章のタイトルはそこから来る。 その言葉で心に残るものは二つ。 ①「すべて一度きりのことは苦しくありえない。あれほど束の間のことをあんなに長い間こわがるのは道理だろうか。長い生涯も短い生涯も死んでしまえば全く一つになる。まったく、もはやないものの中に長い短いはないのである。アリストテレスが言ったが、ヒュパニスの河辺にはただ一日しか生きない小さい虫がいる。朝の八時に死ぬのは若死である。夕の五時に死ぬのは老衰して死ぬのである。こんなわずかの時の長い短いを幸せだとか不幸だとか考えるのを見て、我々のうちに笑わないものがいるだろうか>
孟子は、
岩波文庫『孟子』(下)の小林勝人の注によれば、
「殀は短命、寿は長命。不弐はたがわず。
天命の至る(寿命の尽きる)のを待つのが、天命を尊重する道である」
とある。
※参考:中国古典選9『孟子』(下)(尽心篇第七上篇)P.218 の金谷 治によれば、
「殀と寿とに弐(疑)わず、身を修めてこれを俟つは、命を立んずる所以なり。」 (黒崎記)
穂積重遠は『新釈孟子』において、
「天命の至るのを待つのが安心立命というもの」
と解釈している。
モンテ―ニュと孟子の考え方が似ていることに驚く。
②「どこでお前たちの命が終わっても、それはそれで全部なのだ。人生の利益は、その長さにはなく、その用い方にある。あるものは長く生きはしたが、ほとんど生きなかった。お前たちがこの世にある間は、ただ生きることに意を用いよ。お前たちが十分に生きたかどうかは、かかつてお前たちの意志にある。年数にはない」
*
逗子時代の囲碁の仲間に、SさんとYさんという人がいたが、二人ともに、仲間と碁を打ちながら、相手に気づかぬうちに、眠るように亡くなられた。
モンテ―ニュは第二十章の最後に書いている。
「そいう物々しい支度をする暇もなく死ねたら我々はどんなに幸福だろう!」
私は、SさんとYさんのことを思いだし、心から羨望に堪えない。
令和四年六月二十一日
|
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.332~336 病後を養う私にとって、見果てぬ夢が二つある。一つはヨーロッパの旅をすること、二つはうまいものを食べたいということである。 二年前の直腸癌手術と放射線治療の影響で、縫合した尻の肉が盛りあがらず、長時間すわることに耐えられない。せいぜい三、四時間までで、片道十時間以上の飛行機の座席など我慢できるわけがない。 それにこの夏の耳下腺腫瘤(悪性)に対する化学療法と放射線治療で味覚を失った。何を食べても味がせず、文字通り味気ない生活である。 以上の理由で、ヨーロッパの旅とうまいものにあこがれる気持の切実さはご賢察いただけるだろう。 ところで、その旅と料理の両方からいえば、 「最高のところはローマだったな――」 と考えるうち、そのローマの宿で『言志四録』を読んだことが思いだされてきた。 十一年前の一九八〇年十月二十二日午後八時二十一分、畏友伊藤肇君が亡くなった。 十一月六日に青山葬儀所で友人葬が行われ、その三日後に私は成田を出発してロンドンに向かった。そして十六日の日記に、 「第七日。五時に起床。快晴。五時十五分、通りで人声がする。『言志四録』を読む」 と書いている。 その宿はレオナルド・ダ・ヴィンチ・ホテル、読んだ箇所は『言志後録』の一七六、 「その老ゆるみ及んでや、これを戒むるは得にあり」(論語、季氏編) についての記述からであった。 ※参考:『言志後録』一七六(岩波文庫)P.121 (黒崎記) ※参考:(論語巻き第八 季氏第十六)『論語』金谷治訳注(岩波文庫)P.230 (黒崎記) 佐藤一斎先生は、若い頃はこの「得」という字が何事を指しているのかわからなかったという。だがすでに老年となり、自分の心をもってこれを検証すれば次の通りだと言われる。 「往年血気盛んなりしときは、欲念もまた盛なりき。今に及んで血気衰耗し、欲念かえってやや淡泊なるを覚ゆ。ただこれ年歯をむさぼり、子孫を営む念頭、これを往時に比するにやや濃やかなれば、『得』の字あるいはこの類を指し、必ずしも財を得、物を得るを指さじ」 以下は現代訳する。 「生きるも死ぬも天命である。いま老年になって、強いて養生し、長生きをしようとするのは、天命を知らないやり方である。子孫の幸福も、自ずから天の与える分限がある。いま子孫のために殊更に配慮しようとするのもまた天命を知らないからだ。こういうことは、老いぼれて、心の乱れた者のすることで、すべて『得』をいましめる条件でる。ただ以上のことは自分の考えで、他の老人たちはどう思っているか知らない」 そこから読みはじめて、二四五「毎旦鶏鳴いて起き、心を澄まして黙座すること一晌(ひととき)、自ら夜気の存否如何を察し、然る後蓐を出でて盥嗽し、経書を読み、日出でて事を観る。毎夜昏刻、人定(午後十時)に至りて、内外事了し、間有れば則ち古人の語録を読み、人定後にまた心を澄まして黙座すること一晌、自ら日間行なひし所の当否如何を省みて、然る後寝に就く。余近年此れを守って以て常度(日常の規則)と為さんと欲す。然るにこの事易きに似て難く、常常是くの如くなること能はず」 ※参考:『言志後録』二四五(岩波文庫)P.138(黒崎記) まで読んだとき八時になっていた。日記には次のように書いている。 「八時に朝食、食欲なし。十時のチェツクアウㇳ前に二回勘定に行くが、十時すぎでないとだめだという。他に客はだれもいないし、ちょいと記録を見ればすぐ済むことなのに融通の利かない官僚的体臭は、モスコー空港の売り子によく似ている。客のためという配慮をまったくしない。(以下略) * そのとき私は六十一歳で、それから今日までの十一年間、さらに『言志四録』との縁は深くなった。塩見氏の経営研究所(大坂)、田舞徳太郎氏の日本創造教育研究所(吹田)、松下政経塾(茅ヶ崎)などの講義で教材に使い、それぞれの世代の人々を相手に語りながら、実はそれは自分自身がこの書物と結んだ五十年の縁の意味、理解の程度などを省みる機会にほかならなかったような気がする。 『言志四録』は「四録」という文字が意味するように、四つの記録(随想)からなっている。 第一の記録は一斎先生が四十二歳から五十二歳にかけて書いた二百四十六編(条)の文書を集めたもので、これに『言志録』というタイトルがつけられた。 第二は五十七歳から六十七歳までに書いた二百五十五編の文章を集めたもので、『言志後録』という。 第三は六十七歳から七十八歳に及ぶ二百九十二編で『言志晩録』 第四は八十歳のときに書いた三百四十編の『言志耋録』で<耋>とは<八十歳>という意味である。 したがって全部で千百三十三編(条)あるわけだが、長年読んできて、七十二歳のいま、もっとも自分を支え、心に残る言葉は何であろうかと考えると、次の二編(条)であることはまちがいない。 「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈を頼め」(『晩録』一三) ※『言志晩録』一三(岩波文庫)P.140(黒崎記) 「少にして学べば、則ち壮にして為すところあり、壮にして学べば則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず」(『晩録』) 自戒の言葉としながら、ついに実行できなかったのが次の言葉である。 「凡そ事を作(なす)には、須(すべ)らく天に事うるの心有るを要すべし。人に示すの念有るを要せず」(『言志録』三) ※『言志録』三(岩波文庫)P.11 (黒崎記) 「天に事うる」とは「天を相手にする」という意味にとればわかりやすい。 私は、ここまで悟りきることはついにできず、つねに第三者の評価ということを念頭に置き、こだわってきた。 周知のように西郷南洲翁は『言志四録』を教養の源泉とした。今に残る『私抄言志録』には彼自ら大事と思う言葉を選んである。その中から選ばれたのはわずか百一編、その一つにこの「三がある」。 『西郷南洲遺訓』の「人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして、己を尽して人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」 ※『西郷南洲遺訓』二十五(岩波文庫)P.13(黒崎記) はこの言葉(「三」)を熟考することによって得た悟りであろう。南洲翁の大きさ、おのれの小ささを知るのに、これほど明確な証拠はないのである。 令和四年五月十一日 |
|
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮文庫)P.337~341 『言志四録』の中の、 「少にして学べば、則ち壮にして為すところあり。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老にして学べば、則ち死して朽ちず」(『晩録』六〇) ※参考:『言志晩録』六〇(岩波文庫)P.162 (黒崎記) はれわれを鼓舞する。ところでこの「学ぶ」とは学歴=大学教育などとは関係のないものであろう。実例としては、西郷隆盛と吉田松陰がまず脳裏に浮かぶが、ここでは前者のみをとりあげる。 西郷南洲が『言志四録』の中から、特に気に入った言葉を選んで『私抄言志録』をつくった話は知られている。
どういう言葉を不要とし、どういう言葉を座右の銘としたか、その個別的検証は興味あることだが、本稿では紙幅がないので、ここではその配列の順序についてだけ、私見をのべることにしたい。 『言志四録』は、『言志録』、『後禄』、『晩録』、『耋録』の四部からなっている。もし南洲「私抄」の記述=選択がその順序においてなされているならば別に問題はない。ところがその順序がちがうところに、まさに「私抄」の「私抄」たる所以、選択=プロフェション・ド・フォアたる所以が見られるのである。「私抄」百一条すべての順序については、おなじく紙幅の関係でのべない。ここでは、冒頭三条がすべて『四録』としては最後尾の『耋録』から選ばれいることのみを問題にしたい。 『四録』の各々は、執筆年齢にちがいがある。『言志録』は四十一歳から五十二歳、『後禄』は五十七歳から六十七歳、『晩録』は六十七歳から七十八歳、『耋録』は八十歳のときの執筆である。 すなわち、執筆年齢としては八十歳の佐藤一斎最晩年の三条にもっとも関心、問題性を見出しているが、その価値観、あるいはこれを武士として生きる上での第一義とする南洲の動きがあらわれていた。 * 冒頭の一条は、 「遊惰を認めて以て寛裕と為すこと勿れ。厳酷を認めて以て直諒と為す勿れ。私欲を認めて以て志願と為すこと勿れ」(〔耋録〕二一〇) ※『言志四録』〔耋録〕二一〇(岩波文庫)P.269、『西郷南洲遺訓』(岩波文庫)P.27 (黒崎記) である。 「遊びなまけているのを見て、心が広くこせつかない人間だと思うな。厳しく容赦しないのを見て、真直ぐでいつわりがない人間だと思うな。利己的欲望を見て、志を立ててその実現を望み計る人間だと思うな」 とは、ニセモノをホンモノと誤認してはならぬという教えである。これは薩摩隼人のリーダーとして、彼がもっとも痛感するところであったろう。 第二番目の一条は、 「毀誉得喪は、真に是人生の雲霧、人をして昏迷せしむ。此の雲霧を一掃せば、則ち天青く日白し」(〔耋録〕二一六) ※『言志四録』〔耋録〕二一〇(岩波文庫)P.270、『西郷南洲遺訓』(岩波文庫)P.27 (黒崎記) である。 「悪口、名誉、成功、失敗は本当に人生の雲や霧のようなものだ。これが人間の心を暗くし、あるいは迷わしめる。この心の雲や霧である毀誉得喪にこだわる気持ちをさらりと一掃すれば、天が青く日が白く輝くように人生は明るいものなのだ」 佐藤一斎はこのほかにも書いている。 「名誉ある人間は、その名誉を自慢してはならない。自分の日常の行いをその名誉にふさわしいものであるようにつとめよ。また世間から悪く言われる人間は、その非難を避けてはいけない。どうして悪く言われるようになったか、原因を自分で考え求めなければならぬ。こういう工夫をつめば、名誉も不名誉もともに自分にとって利益がある」 「虚名をわざとらしく見せびらかして、実績ありと世を欺くな。実績のある名声を辞退して、本来なかったものとするがいい。いや、実績のある名声を辞退して、本来なかったものとしては良くない。虚名も実名も両方ともに忘れ、自然に来るのにまかせることだ」 一斎はまた「毀誉四則」というものを書いている。 その一は、「悪口を言われることとほめられることは、一揃いのものだ。ほめられることは悪口を言われることの初めであり、悪口を言われることはほめられることの終りであるからだ。人間はまず、ほめられようとしないで、ほめられる元になる行いを完全にし、また悪口を言われることを避けようとしないで、根本的に悪口を言われないようにつとめるがいい。これが一番いいやり方なのだ」 その二は、「むやみに自分をほめたり、悪口を言ったりするものがいても、喜んだり、怒ったりするには足らない。ほめ言葉がその通り当っているものは、自分の友というべきだ。勤めてそれに値するよう実績をあげなければならぬ。悪口がその通り当っているものは、自分の師匠と尊敬してその教えに従わねばならぬ」 その三は、「人が悪口を言ったり、ほめたりするときは、その半分が事実だと思って聞け。劉向(りゅうこう)という人は、『人をほめるのに、そのすぐれたところを大げさに言わないと、聞き手はおもしろく感じない。悪口を言うのにも、その悪い点を増大させて言わぬと聞き手は満足しないものだ』といっている。この言葉は人情をうがっている」 その四は、南洲が「私抄」の第二条に選んだものだ。 ※「毀誉四則」は『言志耋録』二一三、二一四、二一五、二一六である。『言志四録』の中の『言志耋録』(岩波文庫)P.269~270に記載されている。(黒崎記) さらに一斎は、「鏡中の影」ということも書いている。 「自分の顔形がいいか悪いかは自分ではわからぬ。鏡に映してはじめてわかる。他人から、悪口を言われたり、ほめられたりするのは、鏡に映る自分の影法師のようなもので、自分にとって利益がある。ただ、今は老境に入ったので、どういわれようと気にしないから鏡中に映る自分の影も認めない」 というものだ。 さて、「私抄」の第三条目は、「唐虞の治は只是情の一字なり。極めて之を言へば、万物一体も情の推に外ならず」(〔耋録〕二五一)である。 ※『言志耋録』(岩波文庫)P.280 (黒崎記) 堯帝、舜帝の理想的政治の要諦は『情』の一字だ、ということである。 冒頭三条には、今日のトップ・リーダーにこそ、もっとも必要な教訓があると思われるが、役人が序列を決める勲章に涙を流す人々に、はたして謙虚に耳を傾ける心があるかどうか。 南洲が冒頭にもってきた意味もここにあろうか。 令和四年五月十二日 |
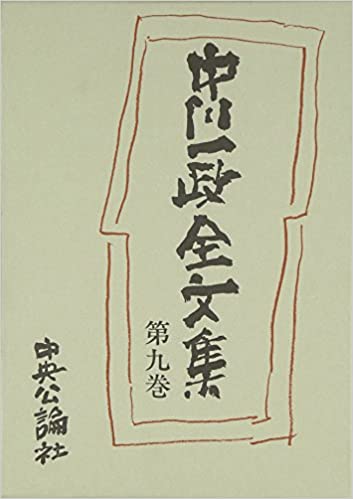 孔子は六十にして耳順(したが)う」といった。私としては、聖人と違って、
孔子は六十にして耳順(したが)う」といった。私としては、聖人と違って、

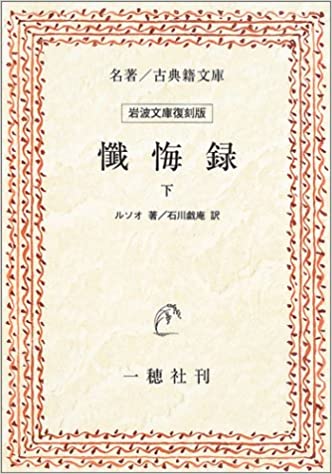
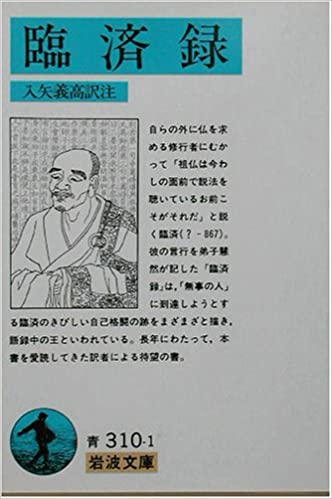 伊庭翁が出会ったのもこの一節にちがいない。
伊庭翁が出会ったのもこの一節にちがいない。
 「明日九時にご足労願います。そのときご返事させていただきます」
「明日九時にご足労願います。そのときご返事させていただきます」
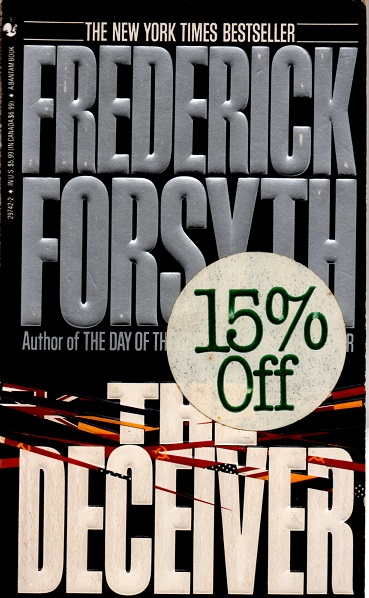 本屋(5th Ave )Brentanoで FREDERICK FORSYTH “The Deceiver”の本1冊購入。15%off 、New York Tax 8.25%(本の販売システムが日本と違う)
本屋(5th Ave )Brentanoで FREDERICK FORSYTH “The Deceiver”の本1冊購入。15%off 、New York Tax 8.25%(本の販売システムが日本と違う)

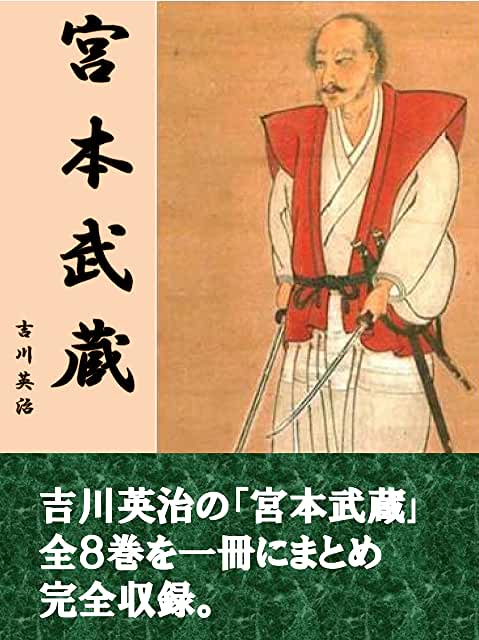 吉川英治氏の『宮本武蔵』は、われわれの世代には特になつかしい。
吉川英治氏の『宮本武蔵』は、われわれの世代には特になつかしい。




