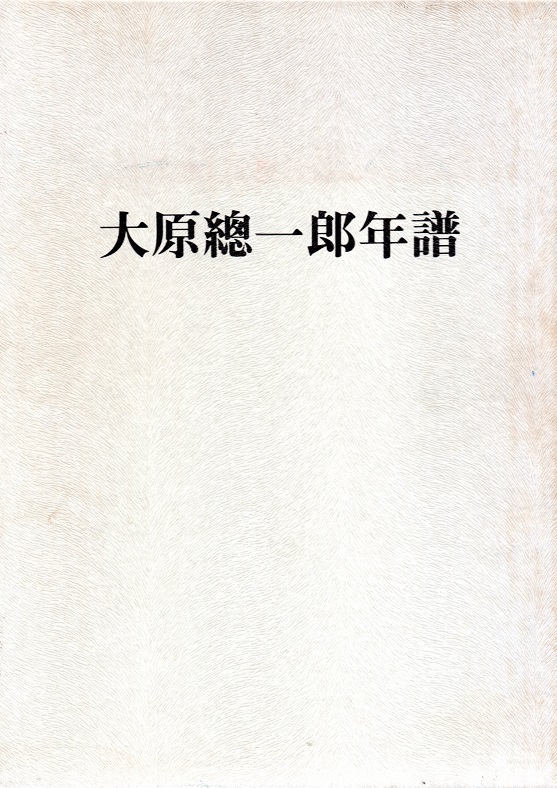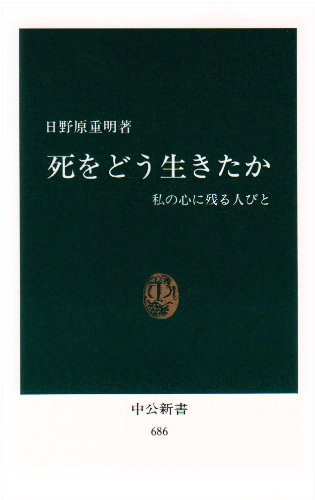| 日本の本より (享保17年~安政3年) |
日本の本より (明治時代:1) |
日本の本より (明治時代:2) |
日本の本より (明治時代:3) |
|---|---|---|---|
| 日本の本より (明治時代:4) |
★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 日本の本より (大正時代) |
日本の本より (昭和時代) |
★★★★★★ | ★★★★★★ |
| 外国の人々(1868年以前) | 外国の人々(1868年以後) | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
(明治時代:4) |
|---|

「岸本英夫先生」の死生観:元東大宗教学教授「死を受け容れ」から抜粋 (上田VS脇本)の対話 これは、昭和六十一年九月七日に、NHK教育テレビの「こころの時代」で放映されたものです。 歌人・医師:上 田 三四二(みよじ) 大正十二年、兵庫県生まれ。第三高等学校、京都大学医学部卒業。医師、歌人、文芸評論家、作家。平成元年没。著書に、歌集「黙契」「雉」「湧井」「遊行」「上田三四二全歌集」、評論集「西行・実朝・良寛」「この世この生」「徒然草を読む」、創作集「深んど」「惜身命」ほか 駒沢大学教授:脇 本(わきもと)平 也(つねや) 大正十年岡山県生まれ。昭和十九年東京帝国大学文学部宗教学宗教史学科卒。東京大学教授、駒沢大学教授を歴任、のち国際宗教研究所理事長、日本宗教学会会長を務める。著書に「評伝清沢満之」「宗教を語る―入門宗教学」 脇本:今お話を伺って、また思い出しますのは、岸本先生のことなんですがね。岸本先生が、先ほど言いましたように、癌に罹られて、それで、「今の一瞬を充実して生きる」ということをお考えになって、そこで私なんかは、学生の時からずっと、あと助手になり、ずっと可愛がって頂いたんですけれども、その間に病気になられる前と、なられた後とでは、われわれ、学生、教え子に対する姿勢も全然変わってこられるんですね。それは非常に太ったまるまるとした身体つきの方で、だから身体つきと同じように、「非常に円満な穏やかな先生だ」というふうに言われていましてね。われわれに非常に優しくいろいろ接しておられたんですが、病気になった後からは、」脇本君、今この一瞬が真剣勝負だよ>という、そういう形で、今まで私が書いた論文やなんかヘマがあっても、「ここんとこ、おかしいじゃないかな」というのが、それが違うんですよ、「これは何だ!」というようにね、真剣勝負なんです。そういう姿勢で学生にも接せられましたから、その他の点でも仕事をどんどんなさったですね。クリエーティブとおっしゃいましたが、クリエーティブな仕事をなさったんですけれども。それが癌の方は普通五年経って再発しなければ少し安心だといわれていますね。 上田:十年だともう安心だという。 脇本:五年過ぎて、その間に皮膚癌―黒色腫(メラノーム)ですから、額のようなところへポツッとニキビのようなものができるんですね。これを取って調べると、やはり癌なんですね。ですから、頭辺りですが、それを二十回ぐらい小さなほくろのようなものを取る手術をしましてね。それでその取った跡は穴が開きますから、太股(ふともも)から皮膚を取って埋めるという。ですから、「脇本君、僕の太腿は切られの与三郎だよ」というふうなことをおっしゃっていましたがね。そういう激しい癌と闘いながら、大学の教授としての他に、図書館長というふうな大きな仕事をお引き受けになられたり、非常にクリエーティブに仕事をなさるんですね。それが非常に激しく、もう一瞬一瞬燃えて燃えて生きるという。それをご自身でも、「イノシシのように突進する」というふうな書き方で顧みておりますけど。そういう生き方をなさっていたのが、七年、八年ぐらい過ぎた辺りでしょうかね、「少し人生というものに対する姿勢が、どうも自分の中で変わってきたような気がする」とおっしゃるんですね。 上田:それはなんか緩やかに、 脇本:ええ。非常に緩やかになりましてね。そして激しく充実して生きるということの他に、今生かされているその命を―これは「心身(しんじん)永く閑(しず)かなり」という兼好がいうみたいな、生かされてある今を、ある意味でゆったりと受け容れて、そして楽しみとまではおっしゃらなかったかも知れませんが、そういうゆとりのある、という姿勢になってこられましてね。その時にお考えになったのが、要するに、「死というのは別れである」と。「別れというのは、つまり死というのは何もかも無くなっちゃう、と思っていたけども、そうじゃない。自分は死んでも、死ぬのは自分が死ぬのであって、死んだ後に世界は残っている。自分が生まれる前に世界はあったはずだ。そういう意味では、要するに、自分がな残惜しいけれども、後ろ髪を引かれながら、みんなと別れていく。その別れということは、この世に生きている限りは旅行に行ったりなんかで絶えずやっている。その絶えずやっている旅行、それの別れを今度は大いなる別れで別れるんだ。別れた後、宇宙の生命に戻って永遠の休息に入る」というお考えになってこられたんですね。それでわれわれも十年近くになりましたから、回復なさるのかなあと思っていたら、そうはいかなかったんですけどね。脳の全体にメラノームが広がっていた、ということで亡くなられたんです。そういう一方で、死を目前に見ながら、そこの「生きている間の一瞬一瞬を激しく燃焼して生きる」という。それの他に、「今生きている命、それを楽しく受け容れていこう」というふうな、そしてその後は、「宇宙の生命の中へ戻って安らう」というふうな考えをされておられましたね。われわれの個々の命が生きている、その命の全部をこう支えているといいますか、上田さんの言い方でいうと、宇宙全体の電磁波というんですか? 岸本先生は、「死というのは別れである。別れというのは、つまり死というのは、何もかも無くなっちゃう、と思っていたけれども、そうじゃない。自分は死んでも、死ぬのは自分が死ぬのであって、死んだ後に世界は残っている。自分が生まれる前に世界はあったはずだ。そういう意味では、自分がな残り惜しいけれども、うしろ髪を引かれながら、みんなと別れていく。その別れということは、この世に生きている限りは、旅行に行ったりなんかで絶えずやっている。その絶えずやっている旅行、それの別れを、今度はおおいなる別れで別れるんだ。別れた後、宇宙の生命に戻って永遠の休息に入る」。と、述べておられます。 参考:上 田 三四二 2016.09.12
『死について考える─岸本英夫の「生死観四態」』 岸本英夫氏の『死を見つめる心』(講談社文庫、1973 年) 死の問題に古来から多少ともかかわってきたのは、宗教とよばれる分野でした。死んだらどうなるのか。死とは何であるのか。死後の世界はあるのか。あるとすればどのようなものなのか。どのような死に方ができるのか。…これらは、今どのように生きていくべきなのかという問題と密接にかかわりながら説かれることも多くありました。 岸本氏は「生死観四態」(同書、99 頁~ 119 頁)の中で、「死が人生の重大関心事となるのは、それが生の終焉であるからである。(中略)人間の生に対する執着、どうしても死なねばならぬという事実、死後の運命の不可知、この三つの事実が激しい激流となって、互いに相打ち、相噛み合って、大きな渦巻をつくる。その渦巻から立ち昇る水煙りの如く、さまざまな生死観が湧き上がって来る」(同書、100 頁)けれど、そのような「多様なる生死観を通観すると、限りなき生命、滅びざる生命の把握の仕方について、いくつかの類型に概括することができるように思われる」(同書、101 頁)として、以下の4態を挙げています。 1.肉体的生命の存続を希求するもの 2.死後における生命の永存を信ずるもの 3.自己の生命を、それに代る限りなき生命に托するもの 4.現実の生活の中に永遠の生命を感得するもの 1は、「死にたくない」という思いの最も素朴な表れで、「当面の死の克服と、暫定的な肉体的生命の存続」(同書、102 頁)とが問題になるといいます。2.3.4.は、肉体の死だけで、人間の死を終わりにしないという点で共通するかもしれません。 2017.06.01 :追加
岸本先生は、『死を見つめる心』岸本英夫著 講談社文庫 の中で、 「死というのは別れである。別れというのは、つまり死というのは、なにもかも無くなっちゃう、と思っていたけれど、そうじゃない。自分は死んでも、死ぬのは自分が死ぬのであって、死んだ後に世界は残っている。自分が生まれる前に世界はあったはずだ。そいう意味では、自分がな残り惜しいけれども、うしろ髪を引かれながら、みんなと別れていく。その別れということは、この世に生きている限りは、旅行に行ったりなんかで絶えずやっている。その絶えずやっている旅行、その別れを、今度はおおいなる別れで別れるんだ。別れた後、宇宙の生命に戻って永遠の休息に入る」。と、述べておられます。 2018.01.16 :追加 |
02 星野 立子(1903~1984年)
|
〽時ものを解決するや春を待つ―高浜虚子
この父の句は、私の生活にいつも大きな力を与えてくれます。仕事に追われている時、悲しい時、苦しい時はいつもこの句を心に浮かべてはそれらを耐えていきます。 ▼父がまだ元気だった頃、こんな会話をかわしたことがありました。 「正岡のおじさん(子規)が亡くなった時、お父さん、心細くならなかった?」 「それは、頼る人が目の前から消え去ったんだから心細くもあり、どうしていいかわからなかった。だが、これからは自分でしなければならない、勉強しよう、と心にきめて、それまでと同じ心で勉強し、努力してきた。そうしているうちにいつとはなしにきょうになったと今は思える」 「私もお父さんがいらっしゃらなくなったらもっと困るに違いないわね。でも"時ものを解決するや……"ですね」 父が亡くなって七年たちました。歳月はさまざまな形をもちながら、来てはまた過ぎていきます。 ▼父は時おりこんなこともいいました。 「おばあさん(父の母のこと)がいつも父さんの身近にいてまもってくださっていると信じている。父さんが死んだら、おばあさんと一緒におまえたちをまもるよ」 父の死後、私は困った時にはいつも小声で"父さん"といいます。そして努力をしているうちに、やがて何とはなしにいい考えが浮かんできます。 信じることのしあわせをしみじみと感じます。 「近くのものから手をつけて整理をはじめること」 これも父のことばですが、だんだんと用事が重なってくると、古い方から始末をつけていこうと思いながらも、つい手をつけかねてどうにもならなくなってしまうことがあります。そんなときには、いちばん手じかなものから手をつけていけ、と父は教えてくれました。そのとおりにしてみると、机の上に積み重なっていたものが、いつかしだいに崩れていき、やがてきれいにかたずいてしまいます。 父は私にとって、父親であると同時に師でもあり、また信仰なのです。 ※:扇谷正造編『私をさせた一言』(青春新書)P.158~159より。 ▼星野 立子の代表句 〽ままごとの飯もおさいも土筆かな 〽囀(さえずり)をこぼさじと抱く大樹かな 〽朴の葉の落ちをり朴の木はいづこ 〽しんしんと寒さがたのし歩みゆく 〽雛飾りつつふと命惜しきかな
参考:愛媛県温泉郡長町新町(現・松山市湊町)に旧松山藩士・池内政忠の5男として生まれた。9歳の時に祖母の実家、高濱家を継ぐ。
人物:星野 立子(ほしの たつこ:昭和期の俳人。高浜虚子の次女。虚子の一族で評価の高い人物の一人ある。 2012.11。
春秋 2020/5/1付 カエデやケヤキの若葉にすがすがしい風が吹き渡る。風薫る5月である。「五月来ぬ心ひらけし五月来ぬ」(星野立子)。新緑の生命力に癒やされる美しい季節がめぐってきた。心ひらけし、とは陰りのない、真っすぐな言葉だ。晴れ晴れとした気持ちが伝わってくる。 ▼去年の今時分、何をしていたのか。覚えておられる方も多いはず。平成の30年余りの時代が終わり、5月1日から令和に元号が改まった。東京・渋谷のスクランブル交差点には、雨がそぼ降るなか、改元カウントダウンで盛り上がる人波が寄せた。ネット上の動画を見ると、ハチ公前は身動きができないほどの密集だった。 ▼恐ろしい。と、感じてしまうのは、すっかり巣ごもり暮らしになじんだせいか。去年は10連休だった。2400万人以上が帰省や国内外の旅行を楽しんだ。昭和から平成の代替わり当時の重苦しい自粛ムードは、みじんもなかった。思い思いに休日を楽しんでいた。わずか1年前のことだが、はるか昔のように感じられる。 |
03 池田 潔(いけだ きよし(1903~1990年)

日本のイギリス文学者、評論家、随筆家である。 三井財閥の最高指導者で日銀総裁を務めた池田成彬の二男として東京に生まれる。母方の祖父は、福澤諭吉の甥で三井銀行理事の中上川彦次郎。旧制麻布中学4年次を終えてから17歳で渡英し、パブリックスクールのリース校(The Leys School)を卒業。1926年にケンブリッジ大学を卒業後、渡独してハイデルベルク大学に学ぶ。 自由と規律 岩波新書の池田潔著『自由と規律』(発行日=2003年04月) を読みました。この本は、戦前イギリスのパブリックスクール、リース・スクールからケンブリッジ大学に学びその後ドイツのハイデルベルグ大学で学んだ著者の経験に基づき、戦後間もないころに書かれたものですが、当時同様に教育再生議論が盛んなわが国において、今日的意味のあるめい著だと思います。 戦前におけるイギリスのパブリックスクールは特権階級のエリート養成校であり、ほとんどの生徒がケンブリッジかオックスフォードに行きました。この両大学は800年の歴史を持ち、日本における東京大学、アメリカのハーバード大学と比べても別格の超めい門大学といえます。 このような極めて特異な環境での経験が、今の日本の一般的な教育に参考にはならないのではないか、別世界のお話ではないかと思われる向きもありましょうが、教育の原理・原則を見事に言い表わしており、豊饒の海に溺れそうになっている現代日本のわれわれにこそ学ぶべき示唆に富んでいると思います。 ワーテルローの戦いでナポレオンのフランスを破ったウエリントン公爵の有めいな言葉、「ワーテルローの戦勝はイートン校の校庭において獲得された」が、パブリックスクールへの最大の賛辞と言えましょう。パブリックスクールの生活は全寮制で規則も厳しく、勉学とスポーツの文武両道がモットーです。池田氏は慶應義塾大学の教授でしたが、「かく厳格なる教育が、それによって期するところは何であるか。それは正邪の観念を明らかにし、正を正とし邪を邪としてはばからぬ道徳的勇気を養い、各人がかかる勇気を持つところに、そこに始めて真の自由の保障がある所以を教えることに在ると思う。」と言う恩師、小泉信三氏の言葉を紹介しています。 同じくパブリックスクールのハロー校の博物学教師ピーター・ブレナンの自叙伝から、第一次大戦時の次のようなエピソードが紹介されています。ブレナンが教え子の英伯爵の一人息子と自転車旅行に出かけた途中、宣戦布告の報に接するやいなや、二人はロンドンに取って返し、入隊を希望します。生徒はまだ16歳であったため一旦は入隊を認められませんが、何度も申請の列に並び、ついには入隊を許されます。それから四年後、一人は片脚となって帰り、一人は遂に還らなかった。ここに社会的に恵まれ指導的立場に立つべき人間の果たすべき義務、即ちノーブレス・オブリージの精神を見て取ることができます。池田氏は言います。「彼らといえども、もとより進んで苦痛を求めるものではない。事情が許せば安楽な道を選ぶことは勿論である。ただ、常に百年の利害を冷静に判断して、空しく一日の苟安を偸む愚を知り、知れば万難に打克って困難な道をゆく決断をもっているのである。」 イギリス人はスポーツ、それも団体競技を好みますが、パブリックスクールにおいてもスポーツはふ可欠の要素です。彼らは忠誠心を涵養する手段を運動競技に求めており、個人的な利害、肉体的苦痛を犠牲にして自分の属するティーム全体の利益に奉仕することがスポーツの真の精神だと考えられています。 トラファルガー海戦に臨んだネルソン提督は、将は将として、兵は兵として、各々与えられた任務を忠実に遂行すること。「如何なる」ではなく「如何に」仕事をするかを求めたと言います。 パブリックスクールの教師は自らもパブリックスクールの教育を受け、オックスブリッジに学んだものが多いと言います。決して高い給料ではありませんが、それを一生の仕事として終わるそうです。「混乱の時代、小人は小金を作る夢をみ、大丈夫は時代を作る夢をみる」とは、まさにこのことを指すのでしょう。 「正直であれ、是非を的確にする勇気をもて、弱者を虐めるな、他人より自由を侵さるるを嫌うが如く他人の自由を侵すな。」これを教え込むのがかれらの役割です。自らリース・スクールで六年間を過ごした池田氏は、パブリックスクールを動かすものは、独裁者による善政であり、校運の興廃は校長の人に懸かっており、優れた学校には必ず優れた校長がいるといわれる所以であると述べています。 「スポーツマンシップとは、彼我の立場を比べて、何かの事情によって得たふ当に有利な立場を利用して勝負することを拒否する精神、すなわち対等の条件でのみ勝負に臨む心掛けを言うのだろう。」「自由は規律を伴い、そして自由を保障するものが勇気であることを知る。」という池田氏の言葉は、なんとも含蓄深いものではありませんか。 平成28.8.06 |
04 目加田 誠(1904~1994年)
|
目加田 誠(めかだ まこと、1904年(明治37年)2月3日 - 1994年(平成6年)4月30日)は、古典中国文学者、九州大学めい誉教授、日本学士院会員。
七十歳で公の勤めは一切止めた。七十五歳―心ふ全で入院。退院してまもなく網膜剥離で入院。手術して退院すると、今度は急性肝炎でまた入院。
▼七十八歳の夏、右の眼球がひどく痛みだし、頭のなかに響き、頭をかかえて転がるほどになった。虹彩(こうさい)内膜炎といわれた。 痛みとともに右の眼はいよいよ見えなくなり、左の眼もかすんできた。暮れから入院。手術してもよくは見えない。 「まっ暗な世界から、ともかくも光の世界に立ち戻った」 「これだけでも見えれば、全盲の人からみれば、天と地の相違ではないか。私はこの眼が僅かでも見えている限り、心を明るく保って自分に出来るだけのことをして人生のつとめを果たしてゆこう」 「私は今やもう、そのような侘(わ)びしさから抜け出さねばねばならぬ。もう一度頭を上げて見るがいい。沈みゆく太陽のあの美しさ。空を紫金に染める夕映えの見事さはどうだ」 「私は影を長く曳(ひ)きながら沈む陽を迫って、どこまでゆくのか分からない。しかし、黄昏(たそがれ)がひたすら迫っておればこそ、夕陽は限りなく美しい」 文献:児島直記『老いに挫けぬ男たち』(岩新潮社)P.78~79
参考1:森 信三『一日一語』 十一月九日
どんな地位にある人でも、一旦盲目になったら、あんまになる他に途はない。それ故一刻も早くそこまで身を落とさねばならぬ一一
参考2:この文章を書き込む以前に全盲になられた先生の記事を朝日新聞の「天声人語」¥で知っていました。 山口県生まれ。東京帝国大学支那文学科卒。第三高等学校教授を経て、九州大学教授。昭和39年(1964年)九大退官後、早稲田大学教授。昭和60年(1985年)学士院会員。文学博士。詩経、唐詩などの著書が多数ある。自宅がある福岡県大野城市で没した。 2012.11
誠よ、もうよいではないか、早くおいで、皆待っているよと、母の声する(目加田 誠さん遺稿):足利 孝之『帰っておいで』より。 2013.05.24 |
|
ひとを差別することへの怒り 人間を差別することぐらい罪悪はないと私は思う。人間はいつ、どこでも平等でなければならないからだ。 ▼私の幼い頃、私の隣の家は素封家であった。近所のひとはそこの子供のな前を決して呼び捨てにしない。しかし子供の間ではそうしたことにいっこう無頓着で子供同士そうするように呼び捨てにしていた。 ある時、その子の母親が私の呼び捨てにした声を聞いて、激こうしながらこう叱りつけた。 「うちの子はあんたみたいに貧乏人の子ではない、坊ちゃんですよ。それを呼び捨てにするとは何事です。ちゃんと"さん"をつけてよびなさい」 私にとってたいへんなショックだった。「家が貧乏だからといって、そう差別しなくてもいいじゃないか」と、内心はおおいに不服だった。この一件が、私の耳に現在までへばりついているところをみると、この時の心の傷痕はよほど大きかったものと思われる。 しかし、このふ愉快な体験が、後年私に差別を最も軽蔑する確固とした信念と背骨を椊えつけてくれたようだ。つまり貧乏であるなしにかかわらずひとをを差別してはいけないという強い信念を持つようになったのである。これは、私の人生における大きな収穫であった。 ▼私の会社の組織など、他の大企業に比較すると、足もとにも及ばない。その機構も、また社員にもそれほど卓越した者はいないと思っている。しかし、ただひとつ、私がどこの大企業に対しても誇れるのは、私の会社では社員のすべてが平等で、働き甲斐のある会社であるということだ。雇員とか臨時職員といった差別はつけない。採用した以上は社員である。 アプレだといわれ、叩かれ攻撃されながらここまで成長できたのは、叩かれたことによって反省したこともあるが、それよりも若いひとがいたからだと思う。その若いひとに対しても本当の気持ちをくみ取り、みんなにふるい立って働いてもらったということが、現在の繁栄をもたらしたものだと思う。 戦争直後はまったくの無めい会社であった本田が「よく伸びた」といわれる背景には、こうした平等主義が音高く流れているのだ。 ひとのうえにひとはなし――公平無私という私の信条は、今後もますます強固なるものだろうし、生涯貫いていきたいと思っている。
本田技研工業の創業者。「モノ作りのロマンチスト」と呼ばれた技術者型経営者。自由奔放な性格、明るい人間性、ホンダイズムと称されるチャレンジ精神などから幅広いフアンがいる。自動車修理工から身を起こし、オートバイ「ドリーム号」「スーパーカブ号」などを次々に開発し、二輪車で世界のトップメーカーとなる。その後、四輪車に進出、藤沢武夫とともに一代でホンダを世界的な企業に成長させた戦後を代表する技術型経営者。日本人として初めて米国の自動車殿堂入りを果たす。 創業者の彼は、会社を家族に引き継がせていない。多くの会社創業者は一族に継承させている。皆様よくご存知だと思います。本田さんの行動と比較してどう思いますか。 2012.11.
追加:2014.09.09、NHKのTVを視聴していると、本田宗一郎について放映されていた。私は彼のめい言をメモ書きましたので紹介します。 1、「やってみませんで何がわかりますか」 2、「石橋をたたかないでわたれ」 3、「チームの中で権威をつくるな」 4、「エリートでなければ作れないならこんな車はつくらないでよい」¥
春秋 2016/12/20付 報告義務ナシ、返済ふ要。ただし基金に拠出したのが誰かは絶対に教えない。かつてこんなユニークな奨学金制度があった。運営する財団は約20年にわたり理工系の若手研究者1735人を支援した。奨学生らの謎が解けたのは1983年、財団が解散したときである。 ▼足長おじさんはホンダの創業者、本田宗一郎氏と、そのめい参謀として知られた藤沢武夫氏だったことが明かされた。それでも匿めいへのこだわりは強かったようで、本紙がこのエピソードを報じた際にも、掲載する直前になってなお関係者から、「やはり謎のままにしておくべきなのだろうか」との苦悩の電話が入ってきた。 ▼とことん匿めいにこだわる。実めいを出してメッセージを込める。どんな形にしろ、他者を思いやっての行いを知れば心が温まる。漫画タイガーマスクの主人公「伊達直人」を名乗り、児童施設にランドセルを届けた前橋市の河村正剛さんは自ら仮面を脱ぎ捨てた。「僕が出ることで支援拡充につながれば」と呼び掛けている。 ▼東京都内では「子ども食堂」の案内を目にすることが多くなった。NPO法人や近所のおじさん、おばさんが食事をこしらえ、居場所のない地域の子どもたちと食卓を囲む場だ。それぞれの立場で、できることは何かと考えてみる。だれもが気負わず、本田宗一郎や伊達直人になる社会であれば、希望は失われないと思う。 2016.12.20 89歳 |
06 亀井 勝一郎(1907~1966年)
07 和田 重正 (1907~1993年)
|
「達人は食事、掃除、読書、何でも重大だと思い、バカモノは一生重大なことに出会わない」
|
08 松本 清張(1909~1968年)
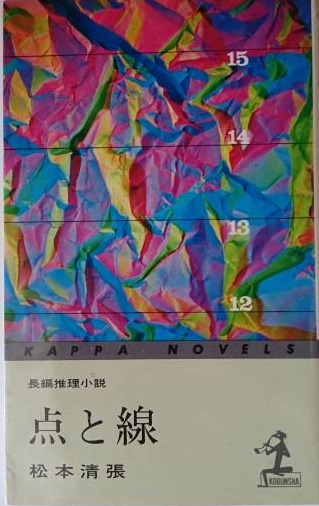
小説〚点と線〛 あらすじ この事件の謎は昭和32年、福岡市の香椎という小さな街の海岸で男女の死体が発見されたことから始まる。亡くなった男の方は官僚、女は料亭の女中。地元警察はこの2人を朊毒による心中と断定し、事件は解決したかに思えたが、一人の老刑事 鳥飼重太郎はこの男女の死に疑問を持った。それは死んだ男の所持品の中に“お一人様”と、書かれた列車車内食堂の領収書があったことからだ。「東京から2人できたはずなのになぜ“二人”ではなく“お一人様”なのか?この男女は本当に心中なのか?」という疑問からストーリーが展開していく。 当時、死亡した官僚の男の部署に、汚職の疑惑がもたれていた。汚職と心中の関係を調べるため、東京警視庁より若い刑事 三原紀一が福岡に送られた。こうして地元老刑事鳥飼と若手刑事三原がこの事件に乗り出したのだが、二人に早速大きな壁が待ち受けていた。 心中説を有力にする目撃証言が出たのだ。事件当日、香椎の駅前を男女が歩いていたというもの、更には東京駅で停車中の、博多行き夜行列車あさかぜに二人が乗っていたというのも目撃されていた。だが三原は、奇妙なことに気付いたのだ。 東京駅で目撃された博多行きの夜行列車は15番ホームに停車していた。目撃者は13番ホームから二人を見たというのだが、この2つのホームの間にはひっきりなしに列車が行き交い、見通すことが難しかしいということだ。三原は調べていくうちに1日の内で17時57分から18時01分までの4分間。たった4分間だけ見通すことのできる時間があることに気付いた。三原は「意図的に目撃者をつくりあげた奴がいる」と、推理したのだ。 そして浮上してきたのが、機械工具商の安田という人物だった。安田は汚職疑惑のある省庁の出入り業者だった。三原は安田に疑惑の影を追うのだが、調べれば調べるほど安田のアリバイは完璧であった。心中事件のあった日、安田はなんと北海道に出張しているのだ。しかし周到な安田のアリバイも三原の執念によって、もろく崩れたのだ。 ある日、三原が何気なく立ち寄った喫茶店でのことだ。偶然入り口で一緒に入った見ず知らずの女性と、二人連れの客だと店員に勘違いされたのだ。この時三原に事件の全てが見えた。 「目撃された男女は、本当に心中した男女だったのか?」 三原は事件の核心に迫っていく。そして判ったことは、心中だと思われていた男は、官僚汚職の口封じの犠牲者だったのだ。一方女は、安田の行き付けの料亭の女中で、安田の愛人でもあった。また、犯人は安田一人ではなく共犯者がいることも判った。それは鎌倉で病に伏していた安田の妻であった。偽装心中はこの夫婦によってつくられたものだったのだ。病気の妻は、出張の多い夫 安田の時刻表を眺め遠い地に思いを馳せていた。夫に愛人がいる事を認めながらも憎悪に膨れ上がっていた妻は、時刻表を使った犯罪を計画したのだった。 しかし、事件は詳細の真相が判らないまま、安田夫婦の心中によりあっけない結末を迎えたのだ。 最後に三原から鳥飼重太郎に宛てた三原紀一の手紙で小説は終わる。 H.29.07.28
松本清張略歴 松本 清張(まつもと せいちょう、1909年(明治42年)12月21日 - 1992年(平成4年)8月4日)は、日本の小説家。 1953年に『或る「小倉日記」伝』で芥川賞を受賞。以降しばらく、歴史小説・現代小説の短編を中心に執筆した。1958年には『点と線』『眼の壁』を発表。これらの作品がベストセラーになり松本清張ブーム、社会派推理小説ブームを起こす。以後、『ゼロの焦点』『砂の器』などの作品もベストセラーになり戦後日本を代表する作家となる。その他、『かげろう絵図』などの時代小説を手がけているが、『古代史疑』などで日本古代史にも強い関心を示し、『火の路』などの小説作品に結実した。緻密で深い研究に基づく自説の発表は小説家の水準を超えると評される。また、『日本の黒い霧』『昭和史発掘』などのノンフィクションをはじめ、近代史・現代史に取り組んだ諸作品を著し、森鴎外や菊池寛に関する評伝を残すなど、広い領域にまたがる創作活動を続けた。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 |
09 大原 總一郎 (1909~1968年)

▼倉敷絹織(株)ビニロンの研究を開始 わが社が合成繊維に関する一般的基礎調査を開始したのは、昭和10年の10月であった。その後13年に至ってカーバイドを原料とするビニル系合成繊維を中心とする一連の研究に着手したが、その着手は同年の4月であった。同じ年の7月、鐘紡もまたビニール系合成繊維の研究に着手した。 これらの研究は京都大学において、喜多、桜田両教授の指導のもとに李、川上氏等によって進められ、14年10月ポリビニールアルコール繊維の湿式紡糸に関する研究が發表され、この繊維に「合成1号」の名称が与えられた。この研究が実るまでには、京都大学内でも、むしろ酢酸繊維素系の研究に向かおうとする傾向が見られたが、わが社の友成博士は終始外部から協力激励して、ポリビニールアルコール繊維の研究完成に対する推進力となった。同年12月、鐘紡も矢沢博士のもとで同様の繊維の製造方法を公にし、翌年1月これに「カネビアン」と命名した。 わが社は、14年12月より、合成1号の一貫的製造技術確立のための研究を開始し、翌15年10月には岡山工場内中央研究所にポリビニールアルコールおよび繊維の日産10キロの中間試験設備を設置して研究の推進を計った。 また、日本合成繊維研究協会も高槻試験場に合成1号日産50キロの中間試験設備を建設して工業化試験に着手したが、これは当時、工業化に最も進んだ技術者が、主として設計にあたった。 当時は戦争の初期に当り、繊維原料の自給が強く要望されて、強力な推進体制が期待される空気もあったが、戦争の進行にしたがって、いっさいの繊維の研究は、技術・資材・資金のあらゆる面で極度の制約をうけるに至った。 わが社の研究は岡山の研究所内で基礎技術に関する研究を終了し、昭和17年10月には、日産200キロの工業化試験工場の建設に着手するまでになった。この設備は翌18年12月に完成を見たが、当時は繊維工業に対して軍需産業への徴用などによって技能者が得難く、また技術も低下していたのでふ測の災害を招くという結果となった。すなわち20年1月、アセチレンタンクに溶接の火が入って大爆発が起こり、工員3人が即死し、友成研究所長は研究所の椅子に腰をかけて執務中であったが、爆風に押し倒されて負傷するという惨事を招いた。当時のことだったので、憲兵隊からはスパイによる戦力破壊工作ではないかとの疑いをうけ、小南課長が検事局で取調をうけたりなどするという事件ともなった。 これによって研究は挫折し、その後再び再建に着手したが、繊維の研究はもはや休止のやむなきに至り、ポリビニールアルコールのみ航空用塗料などとして、ある程度の生産を続けるるという結果となった。これは昭和19年3月、日本合成繊維研究協会が「高分子協会」とめい称を変更して合成物一般の研究に目標を移したことに現われているように、当時においては繊維工業はもはや問題とされる段階にはなかった。そして4月、ポリビニールアルコールは同協会により「ポバール」と命名された。 このような最小限度の研究も、昭和20年の6月、岡山市を襲った空襲によって試験工場が全焼するとともに中止のやむなきに至り、その後2ヵ月にして終戦を迎えた。(以下略) (連絡月報、昭和36.6月号) *大原總一郎年譜「資料編」より。 ▼ビニロン企業化を決意 昭和24年1.18 「ビニロン工業化の思い出」(講演)より (前略) やがてポバールおよびビニロンのパイロットプラントが動き始めましてから約半年以上たちまして昭和24年になりましたが、この昭和24年もいぜんとしてインフレは進行しておりまして、繊維製品はもとより食料もふ足であり、物価は月とともに上がっていくという状態でありました。 (中略) そういう時に試運転を始めまして、ビニロンの工場は漸次安定の条件を発見するような段階に向かっておりました。製品も試作品ができて、それが織物に織られ靴下に編まれたりして、物量試験の段階にはぃっておりました。 24年の1月に父の命日に郷里に帰っておりました私は、風邪をひいて寝込みましたが、もうそろそろ工業化の決心をすべきであろうと考えたのは、そのころのことでありました。私の父は昭和18年、ちょうど岡山工場の例の爆発事故を起こした試検設備が完成した年に亡くなったのでありますが、風邪寝の病床で考えておりまして、おやじが死ぬ前に、こういういっておった。まあ、いろんなことを言っておったのでありますが、それらの中で、役に立つと思いますことをお話ししますと、人間というものは経験ということが非常にたいせつだということを人はいうけれど経験にもいろいろあると、1ぺんやったことを何回でもくり返してやるというのは動物でもなんでもやる経験であって、人間らしい経験ということとはいえないのだと、いままでほんとうにやったことのないことをやって失敗するというのがほんとうの人間の経験であって、いままでやったことをもう一ペンまちがってやるというようなことはだれでもやることで、経験のある人間ということとはいえないのだということをいっている。それからまた10人の人間がいて、その中の5人が賛成するようなことをいったらたいていのことは手おくれだと、7、8人もいいというようなことをいったらもうやらないほうがいいのだと、せいぜい10人のうち、2、3人ぐらいがいいということをいった時に仕事をやるべきものだと、1人もいいといわない時にやるとそれも危ないと、(笑声)2、3人ぐらいはいいというのを待てばよかったのに、その前にやったから失敗したということをいっておった。ずいぶん死ぬ前にも自信のあることをいっておった……ということを思い出したのであります。 余談でありますが、父は大原社会問題研究所というものをつくりました。資本主義に対して批判的な東京大学の宇野弘蔵さんなどもこの1人でありました。そのような反資本主義的な研究所をつくって日本の資本主義に対して反逆的なことをいるとずいぶん非難されました。おそらくそういうことも死ぬ前に思い出しておったんだろうと思いますが、まあそういったようなことを私も思い出しまして、いよいよ病気が治ったら、これをやる決心をしようかと思って、少しよくなってから研究所の人たちにうちへきてもらい、いよいよ工業化したいと思うのだが、そういうことを決心してもいいような技術的段階にきたかどうかということをたずねてみましたら非常に自信のあるような返事でありました。その自信が果たしてほんとうの自信であったかどうか、いまはわからないのですが、私は自信が仮にないといっても、やろうと思っておったわけで、いよいよ工業化といういうことを決心いたしました。そのほうに会社を挙げてまい進するという方針を決定いたしました。 (後略) (昭和36.12,東北大学における講演より「化学工業」昭和44.11月号) *大原總一郎年譜「資料編」より。 以上の二つの資料は、昭和25年にビニロンの生産工場に入社した私には、技術の開発のかげに、社長の決断、技術者の努力の側面を知ることができましたことを後輩たちに伝え残したいものです。 ★大原總一郎著作:随想集 |
10 宮崎 輝 (1909~1992年)
|
企業は実力の範囲内で健全な赤字部門を持たなくてはいけない 「大野誠治評伝『宮崎 輝』」 旭化成の宮崎 輝が、あえて「経営多角化の経営哲学」を説く真意を、大野誠治は次の如く推測しながら敷衍する。 ――「この思想の基礎になっているのは、企業はどの部門でも黒字になったら、もう発展性はなくなったということである。この場合、赤字とか、黒字とかいうのは、あくまで好不況の波に左右されない平常の時のことである。さらに宮崎のいう赤字というのは、その事業が未成熟のために生まれるものであって、成熟した事業の赤字というのは、この中に入れてはいけない。むしろ成熟した事業の赤字は、その赤字をどうするか、場合によっては成熟した事業そのものを切り捨てなくてはいけないことを意味している。」 ――それはともかく、宮崎は "赤字部門"を企業発展の原動力にしようとしているのである。企業が持っているいろいろな事業のうち、一つか二つは、まだ未成熟の事業であって、将来夢を持てる事業を一人前の事業にしようとすることによって発展する、というわけである。もし、企業が持っている事業をすべて黒字にしたら、その企業は新たに夢を持てるような事業の芽を持たなくては発展しない、というのである。このため、企業は常に新しい事業の芽を求めて、活動しなくてはいけない。> 宮崎 輝が身をもって説く "経営哲学"は、移してもって人生一般に適用し得るであろう。当面の課題を追うのに精一杯の馬車馬型は、必ずマンネリに陥って活力を失う。差し当たり目下は必要に迫られていないにしても、自分が興味を持てる主題を見出し、その研鑽を怠らない意欲と余裕が、次第に人格形成に幅をもたらし、近い将来に思わぬかたちで、生きる時が来ると信じなければならぬ。宮崎 輝は"捨てる経済"よりも"やり直す経済"に重きを置く。人生に必要な赤字の期間を、身をちぢめて恐れる臆病者には、稔り多き黒字が決して訪れぬであろう。 谷沢永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.198 プロヒール:宮崎輝(みやざき かがやき、1909年(明治42年)- 1992年(平成4年)は、昭和・平成期の企業経営者。旭化成中興の祖と呼ばれた。勲一等瑞宝章受章。没後従三位追贈。吾妻町吊誉町民及び延岡市吊誉市民。 長崎県南高来郡山田村(現:雲仙市吾妻町)出身。長崎県立島原中学校に入学、同中学時代は市内の曹洞宗の禅寺晴雲寺で5年間寄宿生活を送った。第五高等学校を経て東京帝国大学法学部英法科卒業後、日本窒素肥料に入社。旭ベンベルグ絹糸(後の旭化成工業、現:旭化成)に配属となる。 1961年(昭和36年)52歳で社長に就任した。 社長在任時には「ダボハゼ経営」、「いもづる式経営」と呼ばれる積極果敢な多角化に乗り出したほか、日米繊維交渉では日本化学繊維協会会長として業界側代表として楠岡豪ら通産省の現場らと連携した。 1985年(昭和60年)6月から死去するまで同社代表取締役会長。この間、1981年(昭和56年)から1983年(昭和58年)まで第二次臨時行政調査会委員を務めた。1992年(平成4年)4月17日、国内出張中に急逝。享年82。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ※クラレ、大原社長と同時代の人。 |
11 森 有正 (1911~1976年)
|
『木々は光を浴びて』というエッセー集のなかで、森は経験とは何かを語りつつ、北海道の支笏湖を訪れ、湖畔の原生林をあるいたある印象について記している。 人間がつくったな前と命題とに邪魔されずに、自然そのものが裸で感覚の中に入って来るよろこび、いなそれは「よろこび」以前の純粋状態だ。あとになってから、私のこの状態に「よろこび」というなをつけるのだ。 『経験と思想』のなかでは森は「経験」を自己と他者との関わりの問題と結びつけて論じているが、ここでは、言語が介入する以前のどこまでも純粋な感覚状態が「経験」という言葉のもとに理解されている。自然がな前をもたず、裸のままで私を満たした状態こそ森の言う「経験」である。この森の理解が、西田の「純粋経験」を理解するための一つのよすがになるであろう。 *藤田正勝『西田幾太郎』(岩波新書)P.39より 2010.07.11 |
12 徳永 康起先生 (1911~1979年)
|
▼『徳永康起先生のことば』―まなこを閉じて―編集・発行:寺田一清 よろこびとかんしゃの中に わが命を何にもやし いかに刻むべきか これわが生涯の公案なり 「人さまの子を大切に――」 わたしが教職につくとき 「母」の言ってくれたこの一言 眼を閉じて トッサに 親の祈り心を 察知し得る者 これ 天下第一等の人材なり 「稚心を去る」第一歩として、誕生日には両親にお礼を申し上げる人間になって頂きたい。 参考:明治期の志士橋本佐内の「啓発録」の第一条に、「稚心」を去る――とあります。 *超凡破格の教育者 『徳永康起先生 の人生と教育』(徳永先生回想録刊行会)の本があります。 一人でよいから、先生にめぐりあえたお蔭で人生の生き甲斐を感じるようになりました―と、いってくれる人が、たとえ一人でもいてくれたらと願う。 参考:医学部S.T教授が学生の指導にあたり、「あの先生に命を救われたという患者さんが一人でもいるような医師になりなさい」と指導された話を思い出しました。 20.11.20 徳永康起先生略歴 明治四十五年(一九一二)のお生まれです。熊本県芦北町大字大野で次男として生れました。 昭和二年、県立熊本師範学校卒業。四月短期現役兵として歩兵第十三連隊に入営。八月末 陸軍伊長として退営。九月 熊本師範附属小学校六年生を担任。 熊本県の徳永康起先生についてまず思われるのは、その師、森 信三のコトバをかりれば、「超凡破格」の教育者ということです。凡人ではなしえない型やぶりのことをやってのけたということです。熊本県人の性格を肥後もっこすといいますが、徳永先生のその情熱と徹底ぶりはまさに、教育界の代表的肥後もっこすと言えましょう。それは35歳で校長就任、五年間の校長職を自らなげうって、平教員に降格願いをし、念願通り、平教員として再出発。受持ったのが太田郷小学校の五年五組の生徒51人で、これが「ごぼくの子」卒業記念に校庭の五本の椊樹以後教え子をこのように呼ばれたのです。卒業後も師弟交流の涙ぐましい佳話がうちつづくのでした。 学級担任がしたくて、平教員になれたのは五年あまりで、その後の教員生活は、ずっと中学校の教頭職でした。そして色々のタイプの校長さんに接し仕えられました。 昭和二十九年(一九五四)四十三歳 上甲子園における夏季研修会に初参加。はじめて森信三先生を拝す。 昭和四十一年(一九六六)五十五歳 森先生の命により複写ハガキ第一冊目を使用しはじめる。 昭和四十六年(一九七一)六十歳 退職願を発送。三十八年間の教職を去る。 昭和五十四年(一九七九)六十八歳、腎臓の病気で逝去。 この略歴は『徳永康起先生のことば』より、主として抜粋させていただきました。 2008.11.22 |
13 鈴木 清一 (1911~1980年) ダスキンの創業者
|
子心から親心へ脱皮 私が悪かったのです(鈴木清一) 相手を悪く言うて 解決できることは、 ほとんどない。 なんとなれば 相手にも理窟があるからだ。 そんなことより、 自分が反省することだ。 くやしけれども 自分のこれからの道を 自分でみつけ出すことだ。 できれば 「私が悪かったのです>」と お詫びのできる 大きな人間になることだ! この詩に「くやしけれども」とあるが、みんな腹の中にくやしさはある。本当につらいけれども、自分の道は自分で見つけなければならない。そじて、大きい人間に飛躍するためには、「私が悪かったのだ」という、自分に対する厳しい自覚を持つ。それが階段を一段上がったことになる。そして、さらにもう一段上がるためには、いままでの体験を含めて、「お役に立ててください」という願いを持ってほしい。 出典:石川 洋『人生逃げ場なし』(PHP) P.96~97 参考:鈴木清一 1911(明治44)年、愛知県碧南市に生まれる。 東京・中央商業学校を卒業後、川原商店に入社。 肋膜を患い養母の愛情に救われてからその影響で金光教に入信。1938年、一燈園に身を投じ托鉢求道の生活に入る。1958年、(株)ケントクの前身となる(株)ケントク新生舎を創立。以後「道と経済の合一」を願う祈りの経営について生涯を通じて追求する。 1963年、ダスキン創業。フランチャイズシステムによって画期的な流通組織を確立、おそうじ用具のレンタル事業を全国展開する。1971年、ミスタードーナツ事業の導入をはじめとする多角化によって、わが国初の複合フランチャイズ企業の道を開き、ダスキン企業集団を率いた。1980年、68歳で死去。 2011.03.06 、2017.08.15追加。 |
14 日野原 重明 (1911~2017年)

▼日野原重明『生き方上手』1 「習慣に早くから配慮した者は、おそらく人生の実りも大きい。人はいくつになっても生き方を変えることができます。」 ▼日野原重明『○続生き方上手』2 『どのような困難に直面しても〈ここから始まるのだ〉ととらえ直すことができれば、私たちはかならず前進できます。』 *小沢『本日ただいま誕生』を思い出す。 ▼90歳現役医師〈生き方上手〉が贈る、しあわせの処方箋 ● 60歳は人生の折り返し地点にすぎません ● クヨクヨしたときは、とにかく歩く ● 若いころ好きだったことを、もう一度再開してみるのもいい ● 60歳からは、体の使いすぎよりも・使わなさすぎる・の心配を ● 病気とのつき合い方は〈恐れすぎず〉〈あなどらず〉 ● 自分の気持ちの持ちようで補聴器はイヤリングにもなる ● 「20年後ああなりたい」と憧れるモデルを探す ● その週にためた疲れはその週のうちにとる ● 静かな自然の中より、ストレスの多い都会に住む ● 若い友人をつくることで・二度の人生・が生きられる ● 子供に見返りを求めず、生きがいを探す ● 肩書きを失うことで、新しく得られるものもたくさんある ●「死」を意識してこそ、充実した老いの人生計画もたてられる *:日野原重明『人生百年 私の工夫』の新聞広告より *:聖路加国際病院理事局長・同めい誉院長) ▼『長生きすりゃ いいってもんじゃない』日野原重明 多湖 輝 共著(幻冬社) 九十八まで生きてしまい、さらに百歳まで、などと言っている私がこんなことを言うのはおかしいのですが、生きることの価値を考えたときに、どれだけ長く生きるかではなく、どれだけ深く生きるかが大切です。死や老いに対して成熟することがあるのではないかと思います。 生きることは、成熟に向かって努力することであり、死によって平和な永遠の眠りを与えられるのではないかと考えているのです。 ●師がいれば人は老いません ●生年月日を求める履歴書の陳腐 ●ユーモアさえあれば人生は豊にできる ●家も生き方も「段差をなくす」 ●弱者を助ける人は強者である必要がない ●人生の「分かれ道」でどちらをえらぶ ●わずかな「戦争体験」でも伝える意味がある ●新しいチャレンジが命を延ばしてくれる ●政治家や若者にもっとハッパをかけよう ●病気と恐怖が人生の意味をわからせてくれた ●周囲に期待しすぎる人は幸せになれない ●五十点と五十点の夫婦、あわせて百点でいい ●医者の私も検査値にはあまり拘泥せず ●理想的なダイエット法は普段の食習慣にある ●死にたくとも身体が許してくれない ……など 参考:新聞広告より 2010.06.12
『老いを創める』
紹介して戴きました日野原先生の『老いを創める』を読んだことがあります。その一部をお送りします。 若く生きるにはどうしたらよいか 『老いを創める』日野原重明著(朝日文庫)P.46-47 ▼若く生きる秘訣は、若く生きている人に出会うこと、そのように生きた友や師をもつこと。そして、つとめて命のあふれた幼子に触れることである。生涯を若く生きた尊敬すべき人々に作品を通して出会うこともできよう。若さに会って、暗い、錆びついた老いのイメージから自分を脱出させることがまず必要である。 ▼私が今日までお世話した数多い老人の中で、若さを持ち続けた方々というと、それは何といっても芸術家である。芸術家は、必ず何かのビジョンをもち、いつも何かを創作し続けているからであろう。ビジネスの世界で働いてきた人が急に病気で倒れると、今まで働いてきた組織の地盤が失せ、その人は急に老化する。ビジネスに従事している間は目標があったかもしれないが、一人となった引退生活の中ではビジョンがなくなり、ものを創り出す原動力が失せてくる。そこで、人は、利益を離れて自分以外のものに自分を献げるという習慣がないと、引退後は、ただ孤独になる。 老いて病に倒れた役者の中には、もう一度舞台に立ちたいとの悲願から、強烈な精神力を活力にして、病から立ち上がられた人がある。文楽の人間国宝・二代目野沢喜左衛門さんは、七十四歳の時に心筋梗塞で倒れられたが、生きている限り三味線を弾き続けたいという強烈な願望は、発作四カ月後に再び高座に姿を現させるほどの回復力をもたらしたのである。 人は、老いてから大病すると、体力だけでなく精神力が急速に落ちる。心身を積極的に使うことよりも、用心のために過度の安静に傾き、それがかえって悪循環となる。老人は病んでも、自らを老いの中に幽閉してはならない。 P.43 老いた者が若い世代に遺すべきものは何か。 それは、長い人生の営みの中で得た ① 生活の智慧 ② 人との交わりのマナー ③ よい食習慣、よい生活習慣 ではなかろうか。とありました。 P.89 「自分のものといえるのは、精神と強い意志だけだ。」(ゲーテ) 矢内正一先生は、ヒルティの、人間の誰にもある「怠惰をおさえて仕事に向かわせるもっとも効果的な手段として役立つのは、習慣の大きな力である。・・・・また勤勉、節制、正直、寛大の習慣をも養うことができる。・・・・どんな人間的美徳も、それがまだすっかり習慣となってしまわない限り、たしかにわが物とはいえない。」(『幸福論』第1部 草間平作訳 岩波文庫) などのすばらしいことが載っていました。 25年2月12日、尊敬している方からのメールから。ありがとうございました。文責は私にあります。 平成二十五年四月二日
日野原重明さん死去 105歳 聖路加国際病院めい誉院長 「生涯現役」として著作や講演など幅広く活動してきた聖路加国際病院めい誉院長の日野原重明(ひのはら・しげあき)さんが、2017年7月18日午前6時半、呼吸ふ全で死去した。105歳だった。通夜・お別れの会は関係者で行う。葬儀は29日午後1時から東京都港区南青山2の33の20の東京都青山葬儀所で
日野原重明『死をどう生きたか』
私の心に残る人びと 禅学学者鈴木大拙の最後ーー刻々を大事にされた人 P.78 私の扱った数多い患者さんのなかで最長者は、九十五歳九ヵ月で急逝された禅学学者の鈴木大拙先生である。その先生の晩年の生き方と静かな死の受容を主治医として語ってみたいと思う。 「東洋の哲学を西洋に紹介 先生の本めいは貞太郎。明治三年十月十八日に金沢で生まれ、医師であった父君が六歳のとき死亡。母の手一つで育てられた。第四高等中学校に入学に入学したものの、貧しくて学資がつづかず、中途退学し、一時小学校高等科の英語の先生をされた。その後上京して、東京帝国大学文学部の哲学科選科に入学。二十一歳のとき、鎌倉円覚寺に参禅、今北洪川に師事した。明治三十年、二十七歳でアメリカに渡り、十二年滞在した。いったん帰国後も、しばしば欧米の大学に招かれ、大乗仏教思想や「禅と日本文化」の講義を行い、四高時代の同窓の西田幾多郎博士が西欧の哲学を日本に紹介したのと反対に、東洋の哲学を西欧に紹介し、世界的な仏教学者として活躍された方である」 先生に私がはじめて接したのは昭和三十五年六月で、先生が九十で聖路加国際病院で人間ドック入りされたときである。そのときの先生のドック質問表には、職業は著述業、もと学校の先生とあり、睡眠は午後十一時から朝五時までと、一、二時間の午睡、とある。住居は北鎌倉の東慶寺境内の松ヶ岡文庫になっていた。 九十歳での検査 九十歳の先生の人間ドック入りでは、動脈硬化性高血圧、白内障、難聴などが発見されている。その六年後に、急に腸閉塞で急逝される前日までは、一日四時間は書きものをつづけらたと、秘書が語っている。 先生はなにかのことで、夜中に目がさめてしまうと、仰向けになったまま書きものをされることが多かった。先生は、ニューヨーク市のコロンビア大学教授を長いあいだ勤めておられたし、また四十一歳のとき、アメリカの婦人ピアトリス・レーンと結婚されたので、英語は母国語のようにこなされており、横書きの英文で著述をされることが多かったのである。仰向けに寝て、原稿を横書きにされたという話を、私は大拙先生から聞いて面白く思い、理屈では、体は横にしたほうが、脳の血行がよいはずですと申したら、紊得されていた。その会話のさい、先生は次の面白い思い出を語られた。 先生が八十歳代のころ、欧州を旅して、たまたまフライブルグに住んでいた哲学者、ハイデッガーのお宅を訪ねられたときの話である。坐禅の体位に話がおよんできたとき、ギリシャの哲人は、どんな姿勢でものを考え、論議したかという質問を先生がされると、ハイデッガーは、当時はカウチ(寝椅子)に体を横たえて論議したようだ、と答えられたという。 私は、「大拙先生は、坐禅の体位でも、ギリシャ型の体位でも、体位の両刀使いですね」と冗談を申し上げたことがある。 大拙先生は、ドックで受診されるまでは、高血圧のあることをご存じなかった。私は、老人の血圧はかなり動揺するので、毎年のドック入院のほか、二ヵ月に一回ぐらい、鎌倉から東京に出て受診されることをおすすめした。先生は、むりをしないで上京したいということから、前日、日比谷の日活ホテルに一泊され、翌朝、聖路加の外来にこられるのが常であった。 秘書のかくれたケア 先生は、岡村美穂子さんという、ニューヨーク育ちの若い二世の秘書を連れて、いつも行動されていた。先生の奥さんは癌のため聖路加国際病院で亡くなられたが、其の後先生は、アメリカに住われていたあいだも、また帰国されてからも独身を通された。秘書の岡村さんは、まだ少女のときにニューヨークで先生に出会い、先生にひじょうな感銘をおぼえ、二十歳のときに、ニューヨークの大学を中退して、先生に教えを請いながら、秘書になることを決心し、日本に帰られる先生について単身来日され、その後、先生が逝くなられるまでの十四ヵ年間、先生の著述の助手、そのほか秘書の仕事をしていたのである。 先生の血圧は一八〇/六〇から二四〇/八〇にまで上昇することがよくあった。私は軽い降圧剤(セルベンチナ)を朊用してもらっていたが、血圧の調節がひじょうにむつかしく、困っていた。しかし血圧の測定のために先生がわざわざ頻繁に上京されることはたいへんだと思ったので、秘書に、水銀血圧計を買い求めてもらって、これで朝夕の血圧を測って私に報告してもらうことにした。 先生のような世界的仏教学者でも、診察室での血圧は、家庭内で測った血圧を上廻るという事実を発見したことから、私は高血圧患者の血圧の自己測定にひじょうな関心を向け、以後、高血圧のない一般人にも、血圧を自分で測るという運動を、昭和五十年五以来展開している。 父ゆずりの向学心と節制 先生は教育熱心な医師の家庭に生まれ、五歳のとき母君の膝に抱かれながら見た、読書し著述する父の姿から好学の精神を与えられた。 その父君は、毎朝食事前に、小さい子供たちを集め、自分の書いた「修身十二歌」や「衛生十二字歌」」を読んできかせたという。この本は、それぞれ身を修める法則と健康法を教えた本であった。「わしも(大拙先生は、自分のことをお国言葉で「わし」と呼ばれていた)こういう本が書きたいな、と子供のころから思うようになった因縁で、自分も著作を専門にするようになった>と先生は回顧されている。 そして子供のころから、「衛生十二字歌」に書かれてある文章を暗誦し、 「生ヲ衛ルニ定期アリ、人健康ヲ保ッニハ其ノ定則ヲ守ルベシ。多病ト無病ノ根元ハ、大概食フㇳ飲ムㇳニ法アレバ、健康自然ニ妨ゲナシ……」 私は先生が著述に専念して、長時間坐りっきりになられる時間が長すぎると、足腰が弱くなるので、散歩を毎日定期的になさることをあるときすすめたところ、その後先生は毎日境内の石畳の道にコースをきめて、行ったり来たりされ、運動の距離を確かめるため、一往復ごとに小石を拾い上げて、一列に石畳の上に並べたりされていたという。 救急車で入院 昭和四十一年七月十一日、先生があと三月あまりで、九十六歳の誕生日を迎えられようとしていた日のことである。聖路加国際病院での外来診療の始まる九時に、鎌倉から私の診察室に、先生急病の電話連絡があった。先生はその前夜は遅くまで、あくる日に鎌倉を発って、例年のごとく軽井沢へ避暑に出かけるための長期の旅行の準備をされていたところ、翌朝早く激しい腹痛に目をさまされ、嘔吐が始まった。そこで、近医の処置を受けたが、腹痛が止まらず、苦しみは増す一方だという秘書からの電話であった。 私は午前中の外来診察が終わってから往診に出かけるのでは、タイミングを失するという予感がしたので、内科の五十嵐医師に、鎌倉まですぐに往診してもらうことにした。一時間あまりのち、往診先から連絡があり、腸閉塞の心配があるとのこと。そこで私は近くの病院で、責任をもって手術できるところはないかといくつかの病院に折衝してもらったところ、手術をひきうけるところはないということなので、仕方なく、五十嵐医師に付き添ってもらって、救急車で東京に急行してもらうことにした。 救急車は、お巡りさんに先導されて鎌倉を出たが、途中の道が交通渋滞のため、三時間もかかってやっと聖路加国際病院に到着された。そのときの先生の意識はまだ明瞭ではあったが、一見、きわめて重篤な状態であった。「どんなふうに痛いのですか」とおうかがいしたところ、「どうということはないが、痛いのはかなわんです」と答えられた。診察するbと、腸閉塞状況が見られたあ、老人にときおり見られる腸間膜動脈血栓症も疑われたので、さっそく腹部レントゲン写真を撮ったが、いずれとも判別がむつかしく、そのころより血圧が下がりはじめ、開腹手術をすることはきわねて危険と考えられた。内出血症状に対しては輸血をくり返したが、血圧はどんどん下がる一方であった。 私は、「病気はずいぶん重いのです」と率直に申し上げたら、うなずかれ、私が「最善をつくしますよ」というと、苦しいいなかにもうなずいて、感謝の気持を示された。 なりひどい腹痛の様子がうかがわれたので、私はモルヒネなどの注射をくり返した。先生は痛みを訴えることにははひじょうに控え目であったが、私は「苦しいでしょうね」ときくと、うなずかれるのであった。 臨終のひと時 夜の十一時すぎに、円覚寺の朝比奈宗源管長がお見舞いに病室に入られ、しばらく枕元に黙して坐しておられた。 先生の容態がますます悪化し、輸血や昇圧剤の静注がくり返され、酸素テントが用意された。そこで秘書と少数の方以外は面会をことわって、種々の救急処置が行われた。翌朝の午前三時、死亡の二時間くらい前に、私は「お寺の要職の方々が心配して部屋の外で待っておられるのですが、お会いなさいますか」とたずねやところ、「誰にも会わなくてよい。一人でよい」と答えて、眼を閉じられた。 秘書の岡村さんは、酸素テントの中で息をひきとられる大拙先生の病床のそばの椅子に、まんじりともせず、坐っておられた。 京都大学の文学部教授の西谷啓治先生は、大拙先生の遺体が鎌倉に帰宅した夜の、岡村さんとの対話を次のように書いておられる。 「岡村さんは、病院で息をひきとられた先生のそばに、付き添っていながら”先生がそこに動かずに横たわっていられたことが、生きていられることの続きのように思えて、生きている先生と死なれた先生の間に、さほどの大きな変化の起こったような気がしなかった。”と、岡村さんが何気なくいわれた言葉が深く心に留まった」 岡村さんには大拙先生の禅のエッセンスが伝授されていたことを示す一文である。 先生の急病は、解剖の結果、拘緊性腸閉塞と診断された。腸間膜にヒモンのようなものができており、それがからんで小腸を絞め、腸閉塞をおこし、腸壁に出血と壊死が見られたのである。 あと四年で百歳という良き日を、多くの先生の弟子たちが強く望み、ご自身もそこまで生きて著述をつづけたいと願い、「たえず前進」と自分で号令をかけておられた先生、若い夢見る眼をもって人びとに接し、仕事に励まれた先生。 九十歳を過ぎてからも、浄土真宗の親鸞聖人の『教行信証』という経典の英訳にとりかかられた先生。 その先生が九十歳を超えたとき、岡村さんに、「九十歳にならんとわからんこともあるんだぞ。長生きするものだぞ」といわれた。刻々を大事にされ、今に全力投球をされた、老いても若い世界的仏教学者といえよう。 先生は、西田幾多郎先生とは逆に、東洋の思想を西洋に伝えることに生きがいを感じておられた哲学者であり、東洋の心の紹介者でもあった。 「先生は心の中に野心なく淡々と生きつづけ、長い人生のはせ場を走り通された長距離ランナーであった」と、岡村さんは私に語られた。 先生の生の終焉は、静謐そのものであった。その先生の晩年に親しく接しえたことは、私にとって大きな心の収穫である。 私の書斎の壁には「無事」と書かれた先生の力強い書の額がいまもかかっている。 |
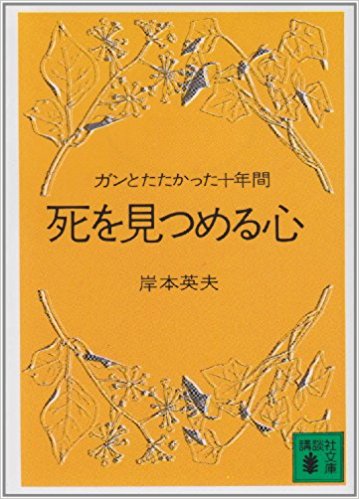
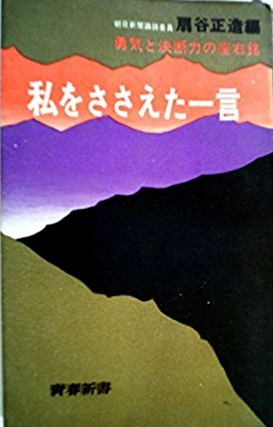

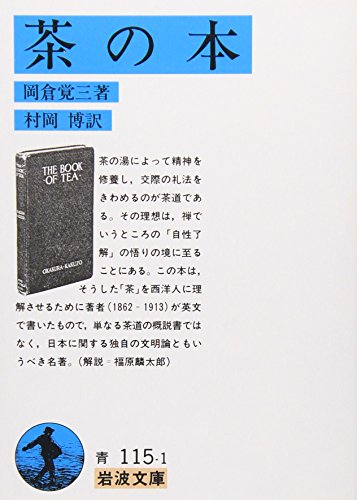 ※参考:岡倉覚三著 村岡 博訳『茶の本』(岩波文庫)P.73 第六章 花
※参考:岡倉覚三著 村岡 博訳『茶の本』(岩波文庫)P.73 第六章 花