改 訂 版 2022.11.11. 改訂
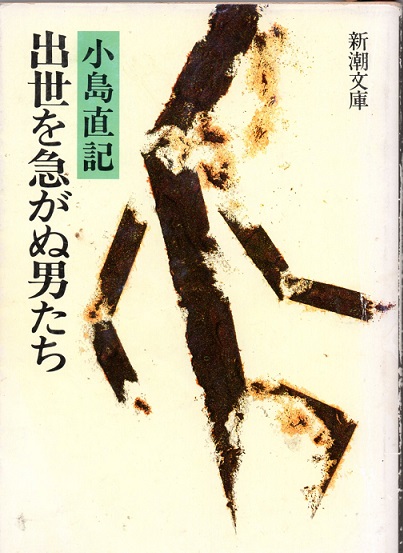
児島直記〚出世を急がぬ男たち〛 (新潮文庫)昭和五十九年四月二十五日発行 P.10~14 渡部昇一『ドイツ参謀本部』(中公新書)昭和49年12月20日初版 をトップ・マネジメントの好参考としておすすめしたい。 理由はいくつもあるが、その一つとして「二冊の本がフランスとドイツの運命を、つまりヨーロッパ大陸の運命を決定した」箇所(一一二ページ以下)がある。それらの本とは、一冊はアンㇳワーヌ・アンリ・ジョミニ(仏: Antoine-Henri Jomini)の『戦争術概要』、もう一冊はカール・フォン・クラウゼヴィッツ(独: Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (Claußwitz)の『戦争論』。 ジョミニは、いろいろな戦闘の実例をあつめ、分類した。そして戦術と補給問題を切り離し、単なる戦術を越えた戦略構想の重要性を強調し、その根本原則を抽出した。 「その取扱いと結論をひき出す明快さの故に、直ちに絶賛を受けることとなった。彼はナポレオン戦争を扱いながらも軍事における天才を重視しなかったところに特徴がある」 ジョミニは、戦争を混乱状態とも混沌とも見なかった。その現象の下には普遍的な法則を見出せると考えた。 したがって、ナポレオンの天才というのは、芸術的天才というよりは科学的天才に近いこととなる。 ナポレオンは、戦争の背後にある諸原理を巧妙に利用したのだ。その勝因は、戦術的先制、敵の連絡や補給路の遮断、決戦場への大軍の集中、先制攻撃、高機動力性、急迫撃等々である。 ジョミニは、これ等を戦争で勝つための原則とし、ナポレオンをその巧みな応用者と見た。そして同時に、他の軍人も、これを勉強すればすぐれた司令官になれる、と考えたのである。 この本は大反響をよび、ヨーロッパ各国の軍隊で争って読まれた。ジョミニは、作戦のラインに注意を向け、図解を重んじ、戦術があたかも幾何学のような様相を呈した。戦争をサイエンス(科学)あるいはアート(技術)として把握したため、ナポレオン戦争の解釈も、フランス革命、産業革命、武器革命、散兵戦の出現など、複雑な要素に対する十分な洞察なしに、行われることになった。
バロック・ロココ時代(十八世紀)の戦争は、今日の「制限戦争」といわれるもの。相手を皆殺しにしたり、徹底的にたたきのめしたりはしない。市民生活には無関係で、戦争は双方の軍隊だけに限られ、非戦闘員は自由に相手国内を旅行することもできた。君主も将軍もこのルールを守ったのである。 ジョミニが、いわばベストセラー的人気に迎えられたのにくらべ、別の一冊、クラウゼヴィッツの『戦争論』は、くすんでいた。プロイセン参謀本部以外ではほとんど知られなかったのである。 ところが、ジョミニが読まれ、クラウゼヴィッツが読まれなかったことの決算が三十年後にあらわれた。普墺(ふおう)戦争と普仏戦争。クラウゼヴィッツを読んだプロイセンは勝ち、ジョミニを学んだオーストリアとフランスは、完膚なきまでに破れたのである。なぜか? クラウゼヴィッツは「哲学」があり、ジョミニにはそれがなかったからである。 クラウゼヴィッツは、ベルリンの士官学校長をつとめた十三年間、公務の余暇には一人とじこもって古今の戦史を読み、それについて沈考を重ねた。そしてコツコツと書きためたものを、その死後、未亡人が出版した。 彼はまず「戦争とは何ぞや?>を問うた。そして、「戦争とは敵を屈服せしめて、自己の意志を実現するために用いられる暴力行為である」と定義した。 暴力の内容は、技術上、科学上の発明である。その暴力行為には、いかなる限界もない。一方の暴力に対するに、他方も暴力をもって応ずるから、概念上、戦争の相互作用は無限定性に導く。 「これこそ十八世紀の制限戦争の概念の対蹠点にある考え方であり、フランス革命以後の徴兵制にもとづく近代戦の本質であったのだ。ジョミニはナポレオンの戦術の現象面に目をうばわれて、まさにこの時代の変化にもとづく戦争の本質を見落したのである」 ※参考:以上の記事については渡部昇一『ドイツ参謀本部』(中公新書)P.113~ を参考。(黒崎記) クラウゼヴィッツはいった。国際法上の慣例は、戦争という名の暴力に対する制限であるが、それはいうに値しないほど無力だ。戦争は他の手段をもってする政治の継続にほかならぬ。 「戦争は政治である」。この戦争観こそ、戦史を理解するカギとなり、戦略を確立するための基礎となる。 「これこそ近代の《全体戦争》あるいは《総力戦》の理論の出発点であり、それ以前の戦争論と決定的に袂を分かつところなのである。同じ戦争に従軍した同時代人でありながら、片やジョミニは戦術を幾何学的ゲームの理論に還元し、片やクラウゼヴィッツは全体戦争への展望を示したのである。ジョミニの本は直ちに喝采を受けたインスタント・サクセスの本だったのに、クラウゼヴィッツのものは、プロイセン以外ではほとんど注目をひかず、一種の時限爆弾となって参謀本部将校の頭脳の中に埋めこまれたのである」 著者渡部昇一のこの記述を読みながら、私の脳裏に浮かんだのは一九二九年(昭和四年)の世界恐慌前後の様相だ。 レイトンの『アスピリン・エイジ』によれば、その前年アメリカでは大統領選挙戦が行われ、候補者フーヴァーは国民に対して、台所にはいつも鶏が二羽用意されており、ガレージには自動車が二台ある。これがどこの家庭でもあたりまえの生活水準と考えられるようになろう、と断言した。ウォール・ストリートの空気も、こうした楽観的気分に同調していた。 十一月の選挙日が近づくにつれ、株式相場は高騰。フ―ヴァーが当選すると、ダウ・ジョーンズ経済通信社の報道する工業株指数は三〇〇に高騰した。ところが、大統領就任式(三月四日)から七ヵ月にして、"暗国の火曜日"一九二九年十月二十九日がやってきた。パニックの幕あけだったのだ。 しかるに日本政府は、「明年一月一日を期して金輸出解禁を断行する」と発表。東京、大阪、名古屋の銀行家たちは金本位体制維持支援を声明した。 アメリカ恐慌についての判断、認識の度合は、 「ニューヨーク株式の崩落は米英の金利低下となって、これまでわが金解禁をはばんでいた海外の金利高を解消するものであって、わが財界に有利である」 などという目先だけを見た楽観論が、したり顔に唱えられいた事実が物語る。趣旨徹底のため全国に派遣された委員の中には「解禁さえすれば好景気がきます」と説いて、拍手喝采をはくしたものが多かった。 「複雑な要素に対する十分な洞察」もなく、「時代の変化にもとづく事態の本質を見落した」考え方が、社会通念、常識として横行した姿は、まさにジョミニを連想させる。 判断も、そしてその対策も根本的誤謬を犯したのは必然の成行であったが、さてそれでは、今日の不況に対する判断と対策のジョミニはいないと断言できるか? (昭和五十年三月) 付記:私は渡部昇一『ドイツ参謀本部』(中公新書)P.195 〔おわりに〕が太平洋戦争における日本のリーダーとスタッフの状態を考える一つの視点だと思ったから記載する。 プロイセン=ドイツ参謀本部は、近代史の動向を左右するほどの意味を持つ組織上の社会的発明であった。しかし、それはビスマルクという強力なリーダーとモルトケという有能なスタッフの組合せの時だけ、めざましい効果を示したにすぎない。その盛りの時には奇蹟を生むほどの力を示したのに、それは極めて短い期間しか続かなかった。強力な大組織におけるリーダーとスタッフのバランスの難しさ示して余すところがない。 第一次大戦ではリーダーが弱くスタッフが強いというアンバランスでドイツは敗北した。第二次大戦にはその反省と反動から、逆にリーダーが強すぎてスタッフが消されてドイツは完全に崩壊した。 スタッフの養成法のノウ・ハウをドイツ参謀本部は完成したが、リーダーは偶然の発生を待つだけだった。これがドイツの悲劇であった。そしてリーダーの養成法はスタッフの養成法とは違う原理に立つたもののようである。 今日の日本にどのようなリーダーが扱われるかは、われわれの関心事でなければならない。 2022.03.25記す。
|

小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.33~37 忘れられた海軍大将・山梨勝之進 「山本権兵衛大将の前にたつと、爛々とかがやく灼熱の太陽の前にあるおもいがする。加藤友三郎大将の前に立つと、何物をも一点の狂いなく映し出す名鏡の前にたつたおもいがする。斎藤実大将とともにあるときは、美しいサロンに坐しウイスキ―を杯に酌み、静かに語るおもいがする」 人物評言としてまことに見事なものといえるが、それでは、これを語った山梨勝之進自身はどういう人物であったか。 彼については、ほとんど知られていないが、それでは肩書だけの、内容のない二流、三流の人物だったのであろうか。
山梨勝之進は明治十年仙台市に生れ、海軍兵学校(海兵25期次席/25人)を出て、二十代の艦隊勤務のほか、「比叡」副長、「香取」艦長を歴任したが艦隊勤務は少なく、海軍省副官、大臣秘書官などを経て、軍務局第一課長、人事課長、海軍艦政本部長など軍政の中枢を歩き、海軍次官、佐世保および呉の鎮守府司令長官となって、昭和八年満五十六歳になる前、予備役になった。その後昭和十四年から二十一年まで学習院長、昭和四十二年満九十歳で永眠。 世間的に有名でなかった理由は、第一に、枢要な軍政の機勤にふれながらも、世間的に派手な立場にたつことがなかったこと、第二に、ご本人が、自己宣伝はもちろんのこと、自己顕示感に乏しく、文字どおりサイレント・ネイヴィの典型だったことによる。 早く海軍を退いたのは、ロンドン軍縮会議(昭和五年)の余波であった。このとき、英米の国力をよく知り、国際協調を維持することが日本を救う道と考えて努力した当路者は、「条約派」としてうとまれ、つぎつぎと予備役に編入された。海軍次官として心血を注いだ山梨もその犠牲者の一人、当時首席全権だった若槻(わかつき)礼次郎は、 「こういう人たちは、あまり私のところへなど来ないが、一ぺん山梨に会った。私は山梨に対して、あんたなどは、当たり前に行けば、連合艦隊の司令長官になるだろうし、海軍大臣になるべき人と思う。それが予備になって、今日のような境遇になろうとは、見ていて、じつに堪えられん、と言った。すると山梨は、いや、私はちっとも遺憾と思っていない。軍縮のような大問題は、犠牲なしには決まりません。誰か犠牲者がなければならん。自分がその犠牲になるつもりでやっただけですから、私は海軍の要職から退けられ、今日の境遇になったことは、少しも惜しむべきことではありません、と言った。これを聞いて私は、今更ながら山梨の人物の立派なことを知ったのであった」(『古風庵回顧録』) と語っている。 山梨は、後年このことについて語ることを好まなかったが、これについて橋口氏は、「他人の語るにまかせるものの自己は語らずと心にきめたことは、あくまでも守りとおす強靭(きょうじん)な「寡黙の精神」と評価している。 山梨は、晩年海上自衛隊幹部学校で講演を行った。その間、資料の整備、原稿作成、外国公館への照会、原書の読破など、一回の講話の準備に三ヵ月をついやした。昭和三十四年九月八十二歳のときにはじめ、おえたのが四十一年十一月、満八十九歳をこえ、数えで九十一歳の正月を迎えんとするときであった。原稿は大学ノート四十冊に及んだ。 山梨勝之進著『歴史と名将』歴史に見るリーダーシップの条件(毎日新聞社)昭和56年10月30日第1刷 橋口氏は、「自己のいっさいを後人に捧げつくす教育の要諦を身をもって実践しておられる」、「また後人としての人間にたいするかぎりない愛情と負託がないかぎり、よわい八十歳をこえてから、あれほどの情熱と苦行が生まれるはずはない」と書いている。 橋口氏は名エッセイストの名が高いが、本書の中で語っている人物は、山梨勝之進と吉田茂の二人にすぎない。 「忘れられた海軍大将」と、吉田を書いた「素顔の総理大臣」とは、分量的に大差があるが、本質的に共通するものは、ともに著者と面識があったという点である。 これは橋口氏の人物評伝の重要な特色であり、期せずしてユニークな内容価値を保証する条件ともなっているようだ。 評伝は、資料だけでは書けない。ましてや、レトリックで処理できるものではない。では何が必要か、といえば、人間との出会いをおろそかにしない、という人間的姿勢であろう。 橋口氏の評伝は、そのことをはっきり示している。彼が書いたのは、単なる海軍大将、総理大臣ではなかった。一人は、学習院長として、自分を教え、アドバイスしてくれた人。一人は内閣参事官時代、欠席した閣議の決済をうけるため、大磯の自邸で二人きりで会っており、二回に一回は機嫌がわるく、五回に一回は機嫌がよかった人だ。 橋口氏は、この人たちと会うとき、人間いかに生きるべきか、という命題を片ときも放していない。すなわち、山梨も吉田も、位階勲等、スティタスよりは、いかにいきているか、という一点にしぼって見つめている。つまりは、人間の誠実さで対決している。 私心がないから、その眼はつねに澄んでいる。そして、根本には深い愛情がある。 これらのものを融合したものを「肉感」とよぶならば、橋口氏の評伝はまさしく肉感の産物。氏はおのれの肉感のほかは一切世評を信ぜず、先人の評価のうち、その肉感とバイブレーションをおこすものだけを正しい評価として受け入れている。若槻の回顧録が二回にわたって引用されるのは、若槻が大蔵省の大先輩だからではなくて、山梨勝之進への高評価が橋口氏自身の肉感を裏づけているからである。吉田が老いてなお仏和辞典を片手に外国新聞を読む姿に感銘するのは、氏自身がそういう勉強家であったからに他ならない。 私事をいえば、筆者は橋口氏と大学、海軍の同期。拙著『無冠の男』を贈ると、「精読した」と冒頭に書いて、くわしく、率直にその読後感を送ってきた、その冒頭の一語にこそ、氏の人柄、人生観、そして本書を貫く根本の精神が表れていると思う。 (昭和五十一年十一月四日) 橋口 收(はしぐち おさむ、1921年9月 - 2005年7月13日)は、学習院初等科、中等科(旧制)、高等科を経て、1943年に東京帝国大学を卒業、大蔵省に入省する。大蔵官僚としては主計局長に就任、事務次官に昇格する者と思われたが、田中角栄内閣下で編成した1974年度予算が首相の指示で放漫財政になったためこれに反対、角福戦争に半ば巻き込まれる形で事務次官に就任できず、新設の国土庁事務次官に押し込まれた(事務次官に就任したのは、田中角栄が推した大蔵省同期の高木文雄主税局長)。主計局長になりながら事務次官の座を逃したのは、福田赳夫以来のことであった。 退官後は、公正取引委員会委員長、広島銀行頭取、同会長を歴任した。広島銀行会長在任中に、広島に本社のあるマツダとフォードとの提携事業をまとめた。 (黒崎記) 2019.08.07 |
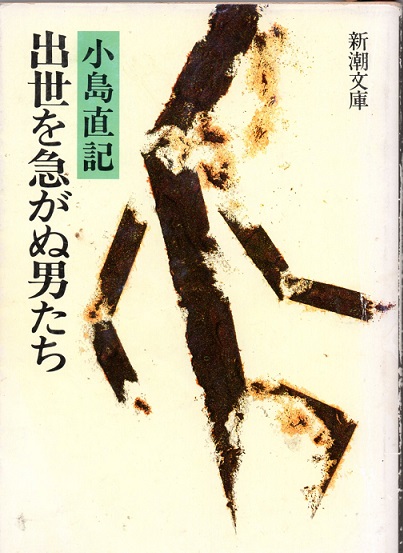
児島直記〚出世を急がぬ男たち〛 (新潮文庫)昭和五十九年四月二十五日発行 P.41~46 田中角栄逮捕(昭和51年7月27日)の時期と並行して、『高橋是清自伝』が中公文庫として上梓された(昭和51年8月10日初版)。無論、逮捕と出版とは何の関係もないのである。「並行して」とおもわしめるもの、あるいは、おもいたくなる関連性がそこにあるのである。 たとえば、逮捕後の田中についていろいろの批評がマスコミにあふれたが、その中に、彼は出世を急いだ男だ、というのがあった。その一事が端的に高橋とは対照的なのである。高橋は、出世を急がぬ人であった。明治二十五年三十九歳のとき、第三代日銀総裁川田小一郎が「山陽鉄道の社長に推薦しよう」といったことがある。高橋はその好意に感謝しつつも、社長のポストを辞退し、新築中の日銀建築事務所で事務主任にやとってもらったのだ。 山陽鉄道は、当時におけるビッグ・ビジネスの一つ。その社長の椅子と、建築事務所の事務主任とどちらがよいか、どちらが出世であるかは、田中角栄のみならず、現代日本人にとっては自明のことであろう。現代の常識、あるいは当世流処世術からは、高橋の行動は愚行以外の何ものでもあるまい。 しかし、まさにその点において、日本人は反省すべきではないのか。現代日本の混迷と腐敗は、出世を急がぬことを愚行とする精神的風土の産物ではないのか。 「社長」と「事務主任」との選択にこそ、高橋是清の全人生はかかっていたわけだが、それがはたして「愚行」であったかどうかを判断するためには、その選択にいたるまでの経緯を見る必要がある。 周知のように、高橋は「ダルマ」といわれた。このアダ名は、高橋の頭がツルツルにはげ、白い頬ヒゲ、あごヒゲをはやした顔つきが似ているところから生じた国民の愛称である。 ダルマ(達磨)というのは、南インドの王子で、九年間も壁に向って座禅を組み、そのため足は腐ったが、悟りをひらくことができたという禅宗の始祖という。ここから、ダルマとは「法」、「真理」、「軌範」などの意味となり、さらにその座禅をした姿をまねして、赤く塗って底を厚くし、倒してもすぐ立つように作った張り子の玩具「不倒翁」のことをいうようになつた。 高橋八十三年の生涯は波瀾万丈、その浮き沈みのはげしさは、総理大臣から芸者の箱屋(三味線運び)、アメリカでの奴隷にいたるまで、最上層から最下層にまで及んでいる。普通の人間ならば、二度と起きあがれないドタン場まで転落しながら、またのこのこ浮かび上った。七転び八起きとは、まさに彼のためにできたことばだといえる。そういう意味で、外見だけでなく、生涯そのものがダルマにふさわしいものだった。
明治十四年二十八歳のとき、新設の農商務省につとめた。そして二十二年三十六歳のとき、初代特許局長に任命された。このとき、農商務次官前田正名のところに耳よりな話がもちこまれた。南米ペルーのカラワクラ銀山が未採掘のまま捨てられてあるが、見本の鉱石を分析してみると純銀に近い良鉱で、大いに有望だ、という話。前田は、三浦梧楼、牧野伸顕などの有力者を説き、五十万円の資本金で日秘鉱業会社を創立し、いやがる高橋を無理矢理説いて、日本側代表として現地に行かせたのである。 ところがこれがインチキで、山は廃山だったもの。事業は完全に失敗した。そして深い事情を知らぬ世間では、彼をインチキのボスだと誤解した。いのちからがら引きあげてきた彼は、もともと責任はなかったのに、家屋敷を売りはらい、債務の弁償に投げだした。一家はその屋敷裏の汚い長屋に引っ越して生活苦に直面することになった。 ※参考:『高橋是清自伝』(上)P.296 「ペルー銀山の失敗とその後の落魄時代」。(黒崎記) 事情を知る人は同情して、就職口を探してくれた。県知事、郡長などの口があったが、高橋はみんなことわった。「衣食のために官途にはつかぬ。食うにこまって役人になったのでは、上官のいうことがまちがっていても従わねばならんからね」というのが彼の言い分だった。 日銀の川田総裁が、山陽鉄道社長のポストにつけようとしたのはこのときである。 高橋はこれを断った。そのときのセリフは、 「それは意外なことをうけたわります。私は官界を断念して実業界に転ずるについては、丁稚小僧からたたき上げねばならぬと考えております。私はこれまで鉄道には何の経験も知識もありません。したがって私は社長として過ちなくやって行く信念がありません。もし万一その職をはずかしめるようなことがあっては、推薦者たるあなたにご迷惑をかけるばかりでなく、私自身も信念なきにその地位にすわることは良心が許しません。どうせ実業界にお出し下さるなら、やはり丁稚小僧から出してください」 というのであった。これこそまさに「スジを通した」のだといえる。 日銀建築事務所で指揮をとっていたのは建築家辰野金吾。東京駅も彼の設計だが、高橋は辰野とは古い縁があった。 アメリカから帰って、明治二年十六歳のとき大学南校(東大)の教官三等手伝になったが、芸者をつれて芝居を見に行き、女の長襦袢をきて桟敷で酔い痴れている現場を外人教師に見られ、辞表を出して芸者の居候兼箱屋になった。だが、「男一匹、こんなことではいかぬと、自分で自分に愛想がつきて、ある夕方、その家の前で、天を仰いで考えこんでいると」、友人が声をかけてくれ、重津英語学校の先生の口を世話してもらった。辰野はそのときの教え子。そして今や、その教え子の部下となったわけである。 だが、川田総裁は社長の椅子を断った高橋の人物に惚れ、間もなく正社員に採用した。そして、西部(馬関)の支店長(四十歳)、正金銀行本店支配人(四十二歳)、同副頭取(四十四歳)、日銀副総裁(四十六歳)と昇進し、やがて日銀総裁、大蔵大臣、総理大臣とその道はひらけるのである。
筆者は、伝記本の傑作はどれかときかれるたびに、この自伝をあげていた。しかしその本は昭和十一年千倉書房刊で、簡単に入手できないのを残念におもっていた。それが今中央公論社の英断で、文庫本として多くの読者に読まれるチャンスがつくられたことをよろこぶ。そして、腐敗、混迷の時世に疲れ、あるいは怒る人びとが、「急がぬ男」の人生を味読され、蘇生のおもいをされるよう祈ってやまない。 (昭和五十一年九月) ※参考:『高橋是清自伝』(下)P.11~「実業界に入る(三十九歳の頃)」参考。(黒崎記) 2022.03.24記す。
|
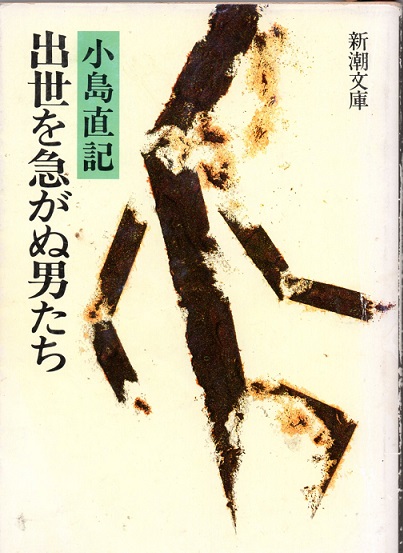
児島直記〚出世を急がぬ男たち〛 (新潮文庫)昭和五十九年四月二十五日発行 P.46~50 昭和五十三年秋から「東京新聞」(中日・北陸中日、北海道)に長野広生氏の『波乱万丈―高橋是清 その時代』の連載がはじまり、三六〇回で完結したあと、このほど単行本として出版された。その上・下二冊本を読み返しながら、改めて高橋是清のことを考えている。 周知のように、彼には〚高橋是清自伝〛がある。いわゆる自叙伝も数多いいが、その中からベスト・テンを選ぶとなると、福沢諭吉の『福翁自伝』や川上肇の〚自叙伝〛などとならんで、この高橋自伝が入るにちがいないと私は信じ、ひとにもそう語ってきた。ところが何分にも昭和十一年(千倉書房刊)の本なので、簡単に手に入れて読み、確認してもらうわけにゆかない。残念におもっていたところ、昭和五十一年に「中公文庫」として再刊されたので、恐らく多くの方がこの本のおもしろさを味わわれたにちがいないとおもう。 高橋自伝はそのように、おもしろさの点では太鼓判がおせるが、ただ一つ根本的なところに問題があった。それはこれが、明治三十八年暮まででおわっていることである。このとき高橋は五十二歳。昭和十一年二・二六事件の凶弾によって八十三年の生涯をおわるまで、なお三十一年におよぶ後半生がブランクとなっているのである。 しかもこの後半生こそ、七回におよぶ大蔵大臣就任と、第四代政友会総裁時代であって、政治家、財政家として歴史に残る仕事をした時期であった。つまり、人間の生涯をのべる自伝としては、本命といわねばならない。その本命のない伝記にすぎないともいえるのである。 その後、全生涯をのべた伝記が出なかったわけではない。たとえば昭和三十三年には、時事通信社から『三代宰相列伝』全十五巻が出て、その一冊として今村武雄著『高橋是清』も書かれている。 この今村本は、まことによくできた高橋伝である。ただ、このシリーズは、新書版で二四〇ページ前後という制約を課せられていた。いくつもの事業が割愛され、また記述も簡略化されざるを得ない条件下に、よくもこれまでまとめたと感嘆させられるものが今村本にはある。しかしそれだけに、紙数の制限なく、自由に書かせたらどんなに立派な高橋伝ができたであろうか、と嘆息させられるのだ。 その意味において、長野広生著『波乱万丈』は、B6版上下六五六ページ、今村本よりも大きな本であることが、まず無条件に高橋伝としてのメリットを与えている。しかしそれも相対的なものにすぎない。長野本もまた紙数が足りないのである。 大ざっぱにその理由をいえば、全部で六五六ページのうち、〚高橋自伝〛に相応する個所が上巻全体と、下巻二一五ページに書かれている。つまり、全体の八二・一パーセントが五十二までに費され、本命の部分が一七・五パーセントの分量しかないわけである。 この点、今村本は全二四一ページのうち、高橋自伝の分は七二ページ、全体の二九・六パーセントを使い、本命の部分に七割をあてており、構成の面からだけいえば、この方がよいといえるだろう。 ただ、あえて推測をのべれば、長野本は、当初から「本命の部分はわずかでよい」という考えのもとに書き進められたものではない気がする。新聞の連載であるから、大体の回数はあらかじめ決められいたであろうが、連載がはじまってしばらく読むうちに、これは相当の回数をあたえられているな、とおもわせるものがあった。叙述の仕方が丁寧で、筆者の眼がよくディテールまで行きとどいていた。したがって物語のテンポは大河の流れをおもわせるゆるやかさであり、腰の落ちついた立派な仕事ぶりだと感心させるものがあった。波瀾万丈の八十三年をこの調子でたどるには、たとえば司馬遼太郎〚胡蝶の夢〛(全五巻)の紙数であるいは不足するかもしれないのである。 それを三六〇回でおわるのは、明らかに無理であり、惜しいことであった。一般的に「三六〇回」というのが新聞連載としては「適当な回数」ということかもしれない。しかし新聞社の幹部の中に、この連載を真剣に読み、その内容価値を理解される方がおられたならば、これはもっと多くの回数があたえられるべきであった。そうすれば、高橋是清伝の決定版ともいうべき見事な成果があげられたはずである。 外債募集のとき、のちの日銀総裁深井英五が随行した。深井は、文章の起草、代理応接、暗号電信などから微細の事務にいたるまで手当たり次第にとりさばいた。徹夜にちかいこともしばしばで、食卓で居眠りをするほどに疲れたこともあった。懇意になった英国人たちは、深井を「過労望郷の可憐児」とよんで同情してくれた。 深井は、ときどき自分の意見も主張した。ただ、高橋という人は反対意見を猛烈に撃退する人だから注意せよ、と出発前に注意されていたとおり、深井の異論は即座に反撃をうけたが、時をあらためて別の角度から進言すれば、前言を忘れたかのように冷静にきき、採るべきものは採った。それまで高橋は、人に紹介するのに深井をセクレタリーとよんでいたが、やがてアシスタントとよぶようになった。辞令の文言が変ったのでなく、高橋の深井評価が変ったのである。 ところが〚波瀾万丈〛では、深井随行の事実は無論記述してあるが、上の逸話はのせられていない。 ことわるまでもあるまいが、この逸話は、深井の手柄話ではあっても、じつは、高橋その人の、部下に対する態度を示すいい話である。〚波瀾万丈〛には、そのプロローグに、高橋が大蔵省の部下の名前を、ほとんどおぼえずに終わったのではないか、という話が出てくる。「この失念をただの性癖といっても、それだけでは片のつかない、底の深いものがあるように思える。失念の彼方に、いったいなにがあったのだろうか」と著者は書いている。このこととも関連が深く、要するに高橋という人間をよりよく示すための大事なところで、オミットするには惜しいのである。 著者は無論、この逸話を熟知いたはずなのに、それを文字どおり「割愛」しなければならなかった。その理由は他でもなく、回数の制限である。指定回数の半ばをすぎてもまだ本命の部分に達しない焦慮が、そうさせたのであろう。私はそう信じ、同情にたえない。 だが一方で著者は、高橋自筆の未公開文書を一族に見せてもらっている。この点「日記も提出するから」ということで『松永安ヱ衛門伝』を引きうけたのに、ついに見せてもらえなかった私よりは、非常にめぐまれていたというべきで、うらやましくて仕方がない。(昭和五十五年三月)
|

『ブリューゲルへの旅』の意味 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日 発行)P.50~54 中国の詩人李白は、「天地は万物の逆旅、光陰は百代の過客」といった。これをデフォㇽメして、俳人芭蕉は「月日は百代の過客にして……」と『奥の細道』の冒頭に書いている。 ところで、旅を意味する英語のトラベル(travel)ということばの語源は、骨折りとか苦役とかいう意味の語だそうだ。同系の語であるフランス語のㇳラヴァイユ(travailler)という語には、仕事とか労働という意味のほかに、苦しい仕事という語感を今でも残しているという。つまり、昔は旅というものは難行苦行であったのである。 トラベルという英語を知らなかった芭蕉にとっても、旅は決して楽なものであるはずはなかった。麻生磯次の『芭蕉物語』によると、ほかほかと温かい大川端の芭蕉庵で、門弟の杉風は師の旅立ちが心配で引きとめようとするが、芭蕉の決意は固く、また門弟の曾良がおともするときいて、
「曽良さんが一緒でございますか。それは結構です。曾良さんなら身体
というのである。その旅が安楽なものであれば、剣術の心得など必要のはずはなかった。
現在では、物見遊山の旅についてツーリスム(tourisume)という語がよく使われる。これは単に回るという意味で、いのちがけという意味はないらしい。無論、交通事故やハイジャックの危険性はあるが、これは語源そのものに含まれるものではあるまい。毎年数百万人の日本人が外国旅行にいくというのも、そのトラベルよりもツアーの性格を多くもつからであろう。ただそれらの多くの旅に共通する一つのパターンは、忙しさ、あわただしさであろうとおもわれる。日本人は、ツアーにおいてもやたらと急ぐ。進歩の旗印の下に、大都市化と工業化を急いできたように、町から町へ、名所から名所へ、点と線の構図を描くことをもって旅としているかのようである。
もっとも、少数の日本人はこれとは「別の旅」をしているはずである。近頃読みおえた中野孝次の『ブリューゲルへの旅』は、まさにそのような「別の旅」の仕方、その意味深い世界を、教えるものであった。
ブリューゲル(一五一八~六九)は、ネーデルランドの画家で、北欧ルネッサンスの代表的存在である。中野のその旅は、ブリューゲルの作品を見て歩く旅に他ならぬが、それは一九六六年春ウィーンではじまっている。
中野はそれまでこんな絵を見たことがなかった。白と緑青と濃褐色の深い色合いで描かれたこの絵は、「いわば《もの》の存在感だけで語った」。それはいろいろ考えさせ、それからそれへと連想をうかばせる。いつの間にか中野は、自分自身の半生と会話をかわしている。
昭和初年、千葉県市川市で少年時代を送った。そこはすでに東京のベッドタウンであり、すべてが変貌の大きなうねりのなかにあった。町を流れる真間川だけは変らぬように見えたが、その川さえいつか工場排水で赤茶けた沈殿物を川底や杭にためている。町がつねに変化変貌の過程にあり、変るということだけがたしかに現実のように感じられた。現在自分たちがいる貧しい平凡な日常は、これも変らなければならないもので、変るとしたら必ずいい方に上っていくはず。現状への不満が、現在を不安定な仮の状態と見なすことで、進歩や向上という希望によって緩和されるようである。向学心は学校で賞讃される最大の美徳で、野心に裏づけられた努力さえあれば道はひらけるというすすめは、不安定なサラリーマン子弟の多い土地柄では現実的であった。しかしその雰囲気は、周囲の自然を手ごたえたしかな実在とし、現在も自分の背骨にしっかりと存在するサムシングにしてくれる一番大事なものを、決定的に失わせた。
そしてこれにつづく高校の教養主義的雰囲気。その中で芸術は、日常的な生活とちがう異次元の価値にたかめられた(中野孝次『ブリュゲールへの旅』(河出文庫P.24)黒崎記)。
だがブリュゲールの絵には、無名の人びとの日常生活が、あるがままの姿でほとんど聖性にまで純化されている。それを見ていると、自分が途方もなくまちがった道を歩いてきたような気がした。目の前に疑いもなく存在していたものを見ないために、ばかばかしいほどの迂路を通って、抽象的な観念世界をつくりあげてきたような気がした。連想の中に、あざけるような一つの声があっ「身を立て、名を挙げ、やよはげめよ」
「結局われわれはこの百年間、この掛声に駆りたてられて盲目的に走ってきただけなのかもしれない
それ以来、ほぼ一年にわたって、中野は古ぼけたフォルクスワーゲンを運転して、ブリューゲルの絵のある都市――ナポリ、ベルリン、ブリュセル、ロンドン、マドリッド、パリなど――を、つぎつぎと追いかけることがヨーロッパ滞在の目的のようになってしまう。
この旅のはじまる前、留学という名目の旅で中野はヨーロッパを訪れ、ウィ―ンに滞在していた。そこで『ブリュゲールへの旅』とは、ヨーロッパ滞在中、ブリュゲールの絵を鑑賞するため、各地を旅行したことだ、といえそうだが、こういういい方では、外国旅行中美術館を訪れ、そこのコレクションを見るわれわれの旅と大差ないことになる。だが本質的にまったくちがうのだ。中野は「絵を媒介として自分のこれまでの生を問うという作業」をしたのである。
それは、ことばとしては一つの「鑑賞法」というほかはないだろう。しかし、鑑賞ということばが内包する一種の遊び、余裕、ひまつぶし、のんきさ、よその国の昔の美術品という無責任な異物感、作品と自分との間の傷つくことのない距離、断絶はないのである。
世界美術館巡り、というような旅の企画は、日本の旅行業者によって立てられている。そういう旅も結構にちがいないが、それらはこちらの嗜好、賞味の仕方とは関係なくつくられた「定食」であり、そしてまちがいなく、一つ美術館からつぎの美術館へと、あわただしく移動する急ぎの旅であるだろう。
急がぬ旅を考えねばなるまい。(昭和五十二年四月)
2022.03.03記す。
|
|
星新一の経済小説 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日 発行)P.69~73 経済小説の売れ行きがよいという。 これは、不況による危機感の現われ、一方では安直にストレス解消となるためなど解説する人もいる。ともかく、恥部をさらけ出しただけのポルノ小説や、ドギつく、残虐な劇画ブームよりは、はるかにまっとうなおとな社会の現象にちがいない。 ところでここでは、いま売れているものの品評ではなく、「経済小説」としての正当な、高い評価をうけないでいる傑作を推薦いたしたい。
星新一はショート・ショート文学界の最高峰。その評価はとくに外国で高い。 反面、それが定評となりすぎて、すぐれた伝記小説や経済小説をも書いているのに、それがあまり評価されていない感じがする。『人民は弱し 官吏は強し』も、ショート・ショートの大家という公式的定評の影におおわれて、経済小説としての優秀性が賞揚されない傾きがあるようだ。 また、在来の経済小説の主流がいわゆるサラリーマンものであり、その味に馴れてしまった読者にとっては、まったく歯ごたえのちがう、硬質・異種の小説ということで、経済小説のワクの中に入れられなかったのかもしれない。 しかし、この作品の卓越性は、その歯ごたえの相違、硬質・異種の中にこそある。いいかえれば、いままでの経済小説が現実の経済機構、経済戦にくらべるとじつに他愛もないものであったことに気づかせてくれるのである。
大正時代の疑獄事件といえば、長浜銀行破綻(頭取岩下清周失脚)事件、シーメンス事件、星製薬破綻(社長星一失脚)事件の三つである。 星新一の『人民は弱し 官吏は強し』は、この第三の疑獄事件を描いている。
福島県に生まれた星青年がアメリカに渡り、そこでさまざまな苦労をなめながら、独特の合理主義と正義感を身につけた一本立の男となるまでが描かれている。すなわち明治時代の星一、それがこの本の主題である。 これにつづく大正時代の星一を描いたのが『人民は弱し 官吏は強し』だが、作品としては前者よりも九年早く世に出た。 なお、以上につづく昭和時代の星一は『祖父・小金井良精の記』のなかで描かれている。これは四年前に本になった。
サラリーマンの哀歓、あるいは出世物語もわるくはない。しかし、そのサラリーマンが生きる場所、経済界の性格、政治と経済の接点、組織と人間の関係などを捨象した私小説的手法で、本当のサラリーマンが描けるわけがない。星新一のこの小説は、権力にさいなまされる私企業という形で、恐るべき日本の深淵、いわば悪の根源を描ききっている。
北浜銀行頭取岩下清周は、大正四年大隈内閣時代に起訴された。そして大正十年の最終審において懲役三年の判決をうけ服役、北浜銀行への弁償金支払いのため、全財産を手放した。 『岩下清周伝』は、 「大隈内閣時代議会操縦の主将大浦(兼武)内相はずいぶん思いきった手段をも取りかねぬ人であったので、原(敬、政友会総裁、岩下の親友)攻撃の一手段として先ずその馬を倒せという戦法が用いられ、奇禍ついに君に及びたるなり、との観測を下せし人もあった」 と書いている。これは婉曲な表現法だが、事件の経過はまさしくその陰謀を露呈している。 星一の場合、後藤新平との人間的結びつきがにらまれ、後藤の失脚を画策する憲政会のターゲットにされた。これに星の独創的経営に繁栄する星製薬をねたむ同業者が荷担し、運動資金を提供する。 当時の医療行政の元締めは内務省衛生局だが、この役人たちが表面の加害者として理不尽のかぎりをつくすのは、内務大臣に憲政会の切れ者大浦兼武がなっていたこと、星が他の業者のようにペコペコせず、官民同等の立場で正々堂々と立場をのべ、理非曲直を明らかにさせようとする《お上をおそれぬ男》であったこと、そして第三に業者提供の運動資金の効き目による。内務省だけでなく、あらゆる国家権力の手先きも似たようなものである。 正当な申し入れ、異議については、 「上司に伝えて相談してみる」 「自分の権限ではなんとも返答できない」 と逃れる。反面、いきり立って、 「会社のひとつやふたつが、つぶれようが、そんなことは法の前には問題ではない」 と本音を吐く。 デッチ上げ事件で、星は警察の取調をうける。全国の各銀行には、 「星に関する預金の明細を報告せよ」 という通達が出される。 「この種のことに神経過敏で臆病な銀行関係者は、決してただの事務的な連絡とはうけとらない」 そこで通達の意味を、 「星は近く有罪となるであろう。星の関係者に金を貸すと回収不能になる。貸してあるのなら早く引きあげるべきであろう」 というように解釈する。銀行からの金融はピタリと停止される。 取調室では、N警部補はドアのすきまを作ってやり、各社の写真班に撮影の便宜をはかってやりさえする。
デッチ上げ裁判は、星を刑務所におくることはできなかった。しかし、無罪ではあっても、刑事被告になったということだけで、事業は致命傷をうける。一方、官吏は、国家的には損失をまねくことまであえてして一企業をつぶし、しかも役所独特の無責任体制のため、その責任追及もできないのである。 図式的には、日本民主化のおくれ、使い古された表現では「官尊民卑」的心理地帯、そこに置かれた孤立無援のすぐれた経営者、すぐれた企業がいかに無力であったかを描きつくすことによって、著者は大正時代の父の受難を語りながら読者には今日の日本・協調経済の実体を考えさせる。それは、私憤が公憤となっているからである。私情に溺れず、愛情の涙でくもらぬ眼が、父を語ることでじつは日本の権力機構をえぐり得たからである。 (昭和五十三年八月) ※関連:谷沢永一著『百言百話』(中公新書)(昭和60年2月25日発行)P.102
表現が無用に長くなるのは、もちろん第一に言わんとする内容の核心を、本人が煎じ詰めて把握していない場合であろう。恐らくは語彙がはなはだしく貧困で、それらを思いつくまで無秩序に並べているうち、先方がなんとか察知してくれるであろうと、もっぱら甘えの根性から依頼心に流れ、いたずらに時間を空費するのみならず、相手を苛々させるのが落ちだ。 表現が饒舌に流れる場合の第二は、胸に一物あって計画的に先方を疲れさせ、軽重の差はあれ欺そうとする場合であろう。真意を察知されては元も子もないから、出来るだけ華やかに言葉を飾る。余計な話題を持ち出して興味が拡散するように、出来れば相手を前後左右に引きまわす。常にもっぱら先方の意を迎えるために上手下手は別にして阿諛追従の限りを尽くす。落語の<子ほめ>(<年ほめ><赤子ほめ>とも)みたいな失態を演じても意に介さない。そのうち肚の底を漸く見透かされて、追い立てられるに決まっているのがこの型である。 話がしつこく容易に果てない場合の第三は、なんらかの宗教およびイデオロギーの布教であろう。これがもっとも厄介難儀で、うっかり相手になろうものなら始末が悪い。第一や第二の単純な型なら、一喝し追っ払い退け得るかも知れぬが、説得癖に凝り固まっている信者の場合は、効果が乏しいと見定めると却って元気になり、張り合いを感じてねばりねばる。こういう場合の対策は最初が肝心で、天から話に乗らぬしかない。 要約とは反対をゆく冗漫の第四は、対象への感情移入があまりにも度が過ぎるため、ひたすら自己陶酔に耽る迷惑型だ。文芸雑誌が載せる謂うところの文芸評論の、ほとんどは手を替えこの型に属するが、ただし筆者が言葉通り本当にお誠心から、のめり込んでいるのか否かは判定が困難で、大抵の場合は昂奮を演技し、人目を惹こうと努めているのかも知れない。 愚劣な冗長を恥じともせぬ冗漫の第五は、高等学校や大学で書かせる無益なレポートで、指導する側が要約の手腕を持たぬのだから、支離滅裂に陥るのも無理はない。そして現在のところもっとも要約の努力を欠くのは、人文社会科学系の大学教員が書いている珍論文である。 星新一はショート・ショート文学界の最高峰と言われている人の記録である。 2022.04.10記す。 |
|
ウィーンの日本人 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日 発行)P.140~144 ウィーンでホテルは郊外のツーロテルだったため、オペラ前で市電に乗って三十分もかかった。しかしそれだけに、何度か往復するうちに、この町の姿もやや明確になってくるよな気がした。 第二次大戦後のこの町の荒廃は、映画『第三の男』でわれわれは知っている。しかし町はすでに復興し、うすっぺらな東京と比較にならぬ重厚さで、旅人の胸にいろいろと感慨をそそるのだ。 私は敬愛する作家シュテファン・ツヴァイクの回想を思い出した。『ジョゼフ・フーシェ』の作者ツヴァイクは、一八八一年(明治十四年)この町に生まれ、一九四一年(昭和十六年)六十歳のとき、亡命先のアメリカで回想録『昨今の世界』を書いたのである。 ツヴァイクによれば、当時のウィーンでは、軍事、政治、商業は、個人の生活でも社会の生活でも、優位を占めるべき事柄ではなかった。 市民が毎朝の新聞に最初の一瞥を注ぐのは、議会の論争に対してでもなければ、世界の出来事に対してでもなく、ほかの都市ではほとんど理解できぬような重要さを公けの生活に帯びている。劇場の上演曲目に対してであった。 総理大臣や最も富める有力者が街を通っても、誰もふり向くことがない、ということはあった。ところが宮廷俳優やオペラの女流歌手は、どんな売子や貸馬車の馭者にでも見わけがついたという。 このような気風、生活の基調、価値体系が完全に姿を消したのは、第一次、第二次大戦のために他ならない。しかしながら、すでによみ返った町の、たとえばモーツァルトの像のある王立公園から、リンク(馬蹄型の環状道路)をぶらぶらと東に歩いて、ケㇽンㇳナー通りとの交叉点に建つ国立オペラ劇場などをながめていると、ツヴァイクの語るその頃の、華麗で、落ちついて、のどかで、シュニツラ―風にやや淫蕩的な雰囲気も、かすかながら匂ってくるような気がした。 けれども、こういう感慨に絶えず黒い影を投げるものがあった。ヒットラーの亡霊である。 アドルフ・ヒットラーは一八八九年(明治二十二年)オーストリアとバヴァㇼアとの国境を流れるイン河畔の小さな町ブラウナウに生まれた。つまりツヴァイクよりも八歳若いことになる。 ヒットラーは、青春の野望を託してこのウィーンにやってきた。一九〇九年(明治四十二年)から一九一三年(大正二年)までの足かけ五年間、彼自身の記述によれば「生涯で一番不幸な時期」(『わが闘争』)をすごしたのである。 初めは臨時労働者、つぎには、なんでも屋の絵描きとして日々の糧をかせぐ彼の宿は、ドナウ河に近いメㇽデマン街にある浮浪者収容所であった。つねに飢えていて、華麗な市民たちのプチブル的生活を横目でにらみながら、なんとかしてドン底からはい上ろうとしていた。「およそ人が到達したいかなる決勝点も、その人間の独自性プラス野獣性のおかげだ」という思想を身につけたのもこのときである。 彼の伝記を書いたアロン・バロックは、「抜け目のないこと、不正直、欺瞞とへつらい、残酷性に味方して感情と誠実を投げうつこと、これらこそ、立身出世をするためにとりわけ必要であり、つまり意志の力ということになる。ウィーンで過ごした歳月から、ヒットラーの学びとった原理はかくのごときものであった」といっている。 「政治家とウソ」という問題を考えているとき、作家吉岡達夫氏の訪問をうけた。吉岡氏は、ライフワーク執筆のため、数ヵ月前から明春までの予定でチロル地方の小村に滞在中だが、私と語るためウィーンまできてくらたのである。私の出発前にもらった留守番中の夫人の手紙によると、氏は日本人の一人もいない村に住んでいるのに、密度の濃い会語に飢えているようです、とのことであった。 目抜き通りのカフェのテラスでいろいろと話をした。たまたま、日本留学生上田浩二君のうけた被害のことがあった。 昨年秋、N参議院員を団長とする民社党の議院団約五十名がウィーンにきたとき、上田君ともう一人が二人で十日間通訳をした。到着そうそう女を世話しろという人物も数人いたりして、なかなか気骨の折れる仕事だったらしい。ところがその報酬は、手金として十万円ほどだけであったそうだ。 相場は、一人が一日で三万円から五万円、一人が二十人以上の通訳をする場合、少なくとも一日五万円だそうである。 十万円きりで、あとはウンともスンとも音沙汰はない。あまりのことに、大使館にかけあってもらおうとして話したが、館員はニガ笑いをしただけで、何の力にもなってくれず、結局泣き寝入りとなってしまった。
それは、「無理強いされた約束は守る必要はない」というマキアヴェリの言葉を掲げた一章だ。この百年間、日本人はヨーロッパに学び、近代化に熱中してきたが、この近代化は、その近代を生み出した地下の根とは無関係だった、と会田氏はいう。日本の近代化は、だから、まだ着物、せいぜい肌着ぐらいのところで、肉体化するまでにいたっていない。近代化社会における人間の結合の基本である契約についても同様である。我々は、結んだ契約を守ることが、近代社会成立のための絶対的な前提と教えられ、その通りに信じ、実行している。しかしそれだけしか知らないのを、イミテーション近代主義者だ、と会田氏はいう。契約は、まさにマキアヴェリが教える通り、破られる場合も、破ってよい場合もあるのだ。ただ、そこに条件がある。「無茶な環境のもとに、脅迫や詐欺などによって結んだ契約は破っても毫も差支えない。むしろ破るべきだ。これがヨーロッパの近代の根である。その根を知らないところに日本人の誤認も、甘えも、責任転嫁も、偽善も、あらゆる近代的悪徳が存在するのである」という。 会田氏の胸のすくような文明批判に感嘆した気持ちからいえば、通訳料問題はあまりにも寒寒としている。世情にうとい留学生たちは、頼まれたから通訳をしたが、それは「契約」として表面化、具体化されていなかったようだ。ただ、当時の期待として、世間並の相場で使ってくれるだろう、という期待感をもっていたのであろう。そこで裏切られて腹を立てている。せっかく外国で暮らす以上、そういう取引を「契約」としてはっきりさせる西洋風リアリズムを学ぶべきだった。だが、それを傍観するだけの大使館員もひどい。しかし私には特に民社党議員団が情無い。せっかく国際会議に多数の人を送るのに、党内部にしゃべれる人材がおらず、現地で相場も知らずに通訳をやとうような、そういう人材不足、調査不備で、現代の大政党といえるのか。 (昭和五十年九月) ※参考:会田雄次著『決断の条件』(新潮選書)P.97 〔無理強いされた約束は守る必要はない。マキアヴェリ〕(黒崎記) ※シュテファン・ツヴァイクについて、 会田雄次は同著P.157~ 〔人主は心を己が死を利とするものに加えざるべからず。日月は外に暉囲するも、その賊は内にあり。その憎む所に備うるも、禍は愛する所にあり〕韓非子の章で下記のように書いている。 これは恐ろしい言葉である。いくら外的に備えて見ても、敵は実は内部にいる。その内部の敵だって憎むものだけを用心しても駄目だ。災禍は実に愛する者から発する。そういうことである。
フランス王ルイ十五世が死ぬ。寵妃をはじめ重臣たちは悲しみに沈んでいる。だがその王宮の一角からかすかなどよめきが、悲しみの静まりをおびやかすように伝わり、やがて大きな波動となって来る。皇太子つまり今やㇽイ十六世となった新王の近臣たちがおもわず漏らす万歳の叫びだ。奇妙な対照、最大の悲しみの中に最高の歓喜がおさえ切れずにほとばしる。だが、この両者は別に対決していたわけではない。ルイ十五世は陰謀によって倒されたわけではない。利の動きに人の動き、人の気の働きが従って流れているだけのことである。ツヴァイクは、その天才の筆で淡々と、しかも冷酷無残、この上なく鋭利に、この間の情勢をえがき出して見せてくれたのである。 ※さらに吉野 秀雄『やわらかなこころ』(講談社文庫)に 盤珪在世の当時、姫路に一人の盲人あり、ひとの音声をきいてその心事をさとる天才をもっていた。盲人のつねにいうには、
賀詞にはかならず愁いのひびきを帯
と、さらに盲人は語を継ぎ、人心の機微はこうしたものであるが、盤珪和尚だけはべつで、師の音声を聞くに、得失・毀誉・尊卑・上下のどういう場合にも異色を容れず、やわらぎにみちた妙音声であって、師に接する者、その声を聞いただけで信に入ることもむべなるかなである。といったという。 記述も参考になる。人の心事を言い表わしていると思える。 2022.04.10記す。 |
|
新田次郎の仕事 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日発行)P.189~193 ある文芸誌で毎月、「新人賞」作品をつのっている。応募者の年齢は年々高くなり、前回はみな四十歳以上だった。ところが今回は、二十代が圧倒的に多くなった。おそらく村上龍の『限りなく透明に近いブルー』が芥川賞をもらった影響だろう。ただし、その応募作にロクナものはなかった――数日前、某誌編集者にきいた話である。 こういう現象は、決して今日だけのものではないだろう。古くは大正時代の島田清次郎、戦後では石原慎太郎のヒーローぶりに刺激され、原稿紙をひろげた若者はたくさんいたとおもう。 若者たちをかり立てたのは、金銭欲、名誉欲ばかりではなかっただろう。既成の秩序や価値に対するモダモダを吐きつくしたい衝動、憤怒が、まがりなりにも一篇の物語を書き上げるという苦しい作業にたえさせたにちがいない。 しかし、その志向とエネルギーは評価するとしても、応募作がロクでもなかったということは重要な問題を示している。
この本の末尾に「アラスカ取材紀行」がおさめられている。この作品執筆のいきさつ、現地旅行などを記録したものだが、これによると、作者がフランク安田に興味をもったのは昭和三十年。そして「北極光」という七十余枚の作品にして「小説新潮」三十年四月号に発表した。 発表したものの、なんとなくもの足りない。とくにアラスカを踏まずに書いたという安易な姿勢に反省がおきた。「私はいい加減な仕事をやったという心の重荷を十六年も背負って歩いた」 四十八年六月半ばにアラスカに行った。約一ヵ月の取材をおえると、安田の出身地石巻に行き、生家などを見た。そのあと資料整理に没頭し、十一月に入ってようやく筆をおこし、まる三ヵ月を費して脱稿した。 「この作品は、海外取材を基礎としたものであり、短期的に力を集中したものとして、私の作品の中では、特異な存在となるであろう。作品のよしあしは読者の判定に任せる以外にないが、いままで、この仕事ほど、書かねばならないという自意識に取り憑(つ)かれたものはなかった。フランク安田こと安田恭輔という人物に惚(ほ)れこんでしまったからであろう この淡々としたことばこそ、どうして『アラスカ物語』が傑作となり、インスタント懸賞作家の作品がくだらないか、そのポイントを示している。
今年の九月、おなじ作者の『小説に書けなかった自伝』という本が出た。
これは、新田次郎全集全二十二巻の月報として、昭和四十九年六月より昭和五十一年三月に至るまでの二十二ヵ月間にわたり、「私の小説履歴」と題して書きつづけたものに、およそ百枚ほど書き加えたものという。文字どおり、飾らぬ自伝だが、前述の問題に対する貴重な示唆が、作者の血と汗の匂いをにじませながら語られている。(同書あとがき P.206 に記載) 小説を書くようになった「そもそもの動機は『筆の内職(アルバイト)』をしたいということから発生した生活上の要求にあって、文学とか小説とかいうものとはなんのかかわりもない出発だった」 「サンデー毎日」の懸賞小説に応募しようとおもった。一等は二十万円、「昭和二十六年の二十万円は現在の五百万円ほどの価値があった」。友人も競争相手になることが予想される。「玄人と勝負して勝には、まずその手の内を研究せねばならない。流行作家の小説を原稿用紙にそのまま書き写してみた」 作者は、中央気象台の課長補佐だったつとめをおえて、その筆写を毎晩つづけるのは大変な苦労だった。しかし、これをやってみて、「既成作家がそれほど恐るべき競争相手ではないと思った」、「私は私で好きなように書けばいいのだと分ると、もうなにものにも恐れなかった」。 「強力伝」八十枚を書き、それが一等当選した。電車の中にビラが下がり、新田次郎の名が麗麗しく印刷されてあった。「なにか自分はもう作家の登龍門をくぐり抜けてしまったように感じた」が、「懸賞小説に一度ぐらい当選したところで、誰も問題にしてくれないのだということがわかった」 それから「投稿作家の四年間」がつづく。「講談倶楽部」は何回出しても、予選にも通過しない。「オール読物」新人賞も落ちた。「サンデー毎日」には二回当選した。 この頃、つとめ先でも注目される。同僚との共同研究による発明が運輸大臣賞をうけ、実用化されると、「小説的発想」によって作られた機械がさて実用になるかなあ」と皮肉をいわれ、針に刺されたように痛い。小説のことはおくびにも出さないようにし、仕事も人一倍つとめた。 「マージャンで夜更かしして、翌日の会議で居眠りしている人は許されても、もし、私が居眠りをしたら、おそらく許されないだろうと思っていた」 「強力伝」で直木賞。石原が「太陽の季節」で芥川賞をとったときである。 それから十年間、作者は役人作家の座を守った。退庁は夕五時。国電で吉祥寺(きちじょうじ)の自宅にもどるのが六時すぎ、食事をして、七時のニュースをきくと、二階の部屋にこもる。階段をのぼりながら、「戦いだ、戦いだ」とよくいった。そして十一時までみっちり書く、四時間以上書くことはできなかった。 仕事で気象レーダー室に入ると、 「若い文豪、取材かね」 といわれた。その時分からひそかに役所をやめようとおもいはじめる。 「週刊新潮」の連載で、「労作必ずしも佳作ならず」ということも体験させられた。 昭和三十八年四月、測機課長。四十一年三月退職。独立しても、さらにきびしい努力の日が一日の休みもなくつづいた。アラスカ取材旅行が六十二歳(!)のときである。
新田次郎の作品、自伝は何を語っているか。それは要するに、「モトデをかけない仕事にホンモノはない」ということである。インスタント作家はもって肝に銘すべきであるが、しかし以上の教訓は、なにも小説の世界だけに限る話ではない。 (昭和五十一年十一月) ※参考:『アラスカ物語』について「杉山吉良のアッツ島再訪」の章『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.205~に引用されている。 ※『アラスカ物語』、『小説に書けなかった自伝』、ついでに『八甲田山死の方向』をよみながら以上の記事を写す。 2022.03.05記す。 |

信頼できる男は誰か? 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月二十五日発行)P.208~212 会田雄次の近著『日本人材論 指導者の条件』(講談社)(昭和51年11月22日 第一刷発行)はまことにおもしろかった。 そのおもしろさの内容は複雑だが、たとえばつぎのような一節がある。
課長が何かの用事で席をはずした。鬼の居ぬ間ということで、みんなストーブの前に集まってプロ野球か競馬かの話に夢中になっている。そこへ突如その恐ろしい課長が入ってきた。そのとき、各人がとった対応の仕方はさまざまであった。 Aは、「じゃあ、明日のその会合のこと、打ち合わせた通りにやってくれよ」と仕事の話をしていたようにうまく逃げた。 Bは、「バレたぁ」と笑いながら、頭をかきかき机にもどった。 Cは、「課長、すみませんでした」と率直にあやまり、さっと仕事にとりかかった。 Dは、強情を張って、なおしばらく雑談をつづけた。 Eは、「課長、課長もこんどの有馬記念、ハイセイコーだと思われますか」と、上司も雑談にまきこもうとした。 Fは、バツが悪そうな顔をして、もぞもぞと仕事にもどった。 Gは、自分だけ雑談に加わっていなかったような顔をして、黒板をながめ、メモをとったのである。
もしあなたが課長だったら、どのタイプの人間を一番信頼できると思い、どれを不可と思われるだろうか。 この問いに対して、人びとは圧倒的に「良」としたのはC、そして「不可」としたのは、強情を張るDと、うまくごま化そうとしたAとGであったという。 しかし会田は、Cを「良」とする多数意見に反対している。その根拠は、 「Cは本当に反省していただろうか」 という疑問だ。
鬼の居ぬ間に、ちょっとサボることは人間性の常である。サボりたいのは、男女を問わず、つとめ人のふつうの感覚である。見つかったら、しまったとは感じるだろうが、心の底から悪かった思うものではあるまい。 昔の人は、そういうときの感情を、バツが悪いとか、きまりが悪いという適切な言葉で表現していた。 「その感情を表現するのに、《課長、すみませんでした》というのは大げさすぎる。一見正直で良心的なように見えるが、内実は偽善的ハッタリ屋であろう。うまくごま化した男と同種の人間」 と会田の指摘はするどい。
では、本当に信頼できる男は誰か? Fである。いたずらを母親に見つけられた子供のように、ブスッとした表情、半ベソをかいた子供のような顔で、いいわけもごま化しもせず仕事にもどる男なのである。 だが、問題はこれからなのだ。今日の社会状況では、このFを選ぶ人はゼロのはずである、と会田はいう。 「戦後の日本の民主化の最大の誤りの一つに、奇怪な懺悔主義の大流行と、それと表裏一体につらなっている責任転嫁主義と、《私は正直者で被害者だとする卑劣極まる主張》の奔流がある」 「自分で自分は純情だなどという奴は偽者である。小器用に口先だけでゴマ化すこともできず、うまく被害者ぶることもできぬ本当の正直者が反動とか体制派だとかいわれ、社会の核になるどころか、排斥されつくしてしまったところに、今日の日本の社会の救い難い病弊が存在する」 ※参考:以上の記事は、『日本人材論 指導者の条件』のP.132~136に記載されている。(黒崎記)。
「日本の今日的状況」に気持ちを重くしながら、筆者は昔の人選びの一例をおもいうかべる。藤原銀次郎のやり方だ、 三井物産木材部長だった藤原が、王子製紙の経営をまかされたのは四十二歳の厄年であった。 「厄年にボロ会社を引きうけてどうなるか」 と引きとめる人もいた。たしかに、王子製紙はボロ会社の代表と見られていた。系列につながる三井銀行でさえ金を貸さなかった。原料も、現金でなければ買えなかった。株価は、旧株五十円払込のものが十円から十五円、新株二十五円払込のものが二円五十銭前後に下がっていた。 藤原は、この再建策の第一に人材登用を考えた。まず前の同僚と部下の中から、高島菊次郎、井上憲一、足立正を起用した。しかし、これは定石的手法であり、本当の創意はここからはじまる。 各工場をまわって、係員にいろいろ質問したのがそのやり方だ。通りいっぺんのことを聞くのでは、よしあしのカンどころはつかめない。答弁の盲点をつくには、担当者以上の知識がいる。むしろ、試されるのは質問者自身の能力だといっていい。藤原はそれだけの勉強した上で、質問に当ったのだ。 人を選ぼうとするには、まず選ぶ本人が第一に選ばれるべき人材であることを要する。人選びとは、じつは自己鍛錬の苦行であり、その反応にすぎない。 質問した相手のうち、ほとんどが落第した。ただその中に、一人だけ光りを放つ人物がいた。中部工場で下積みになっていた無名の一山林係。中部工場から気田工場への二十八キロの山道を話していきながら、藤原は心から感嘆した。何をきいても知っているのだ。いや、仕事の上の知識だけでなく、人生、世間についても深く考えている。その男をさっそく係長にばってきした。これがのち副社長、そして北海水力電気社長の田中治郎である。 こういうやり方を重ねて、藤原は多くの人材を登用した。これが彼の最大の武器となった。同じ製紙業界には、最強のライバルとして大川平三郎がいた。石山賢吉(ダイヤモンド社創業者)は二人を比較して、「大川氏は、偉大な天才児であった。一人の大川と一人の藤原と戦っては、とうてい、かなわない。それでもって、藤原さんは大川氏を征服した。それはなぜか。人材を登用したからだ。一人の藤原は百人の大川をつくって戦った。これで大勝を博し、大川氏の事業を自己の傘下(さんか)に納めた。藤原さんの人材登用を事業家の学ぶべき重大事項である> と、書いている(『藤原銀次郎氏の足跡』)。 だがここで、見逃されてはならぬ一事がある。それは、ボロ会社にうつってから、藤原が自分の貯蓄をそのボロ株に投じたことである。背水の陣をしいて勝負に出たとき、人選びも本当の迫力をもったのである。真剣にならねば、人は見えない。時代がどう変わろうとも、このことだけは決して変らぬはずである。 (昭和五十二年二月) ※会田雄次著『日本人材論 指導者の条件』(講談社)(昭和51年11月22日 第一刷発行)は昭和51年12月13日(月)購入していた。傍線を引いたりしている。 2022.03.08記す。
|
|
ある総理大臣の逸話 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日発行)P.222~226 テレビに写った閣僚たちの顔を見ているうちに、ふと別の人物の顔が脳裏にうかんだ。 その人の郷里は高知県の田舎で、代々お山方をつとめた。これは微禄の端役で、俗にいう足軽。その人の父親はこのお山方をつとめて明治維新を迎えた。そして明治三年に三男坊として生まれのがこの人である。 三男坊は、小心で臆病な少年だった。雷が鳴りだすと、教室にいるときでも両手で頭をおおい、ふるえていた。しかし成績は抜群だった。ただ、決して才気渙発というのではなく、物事に熱心で、やりだしたら倦(う)むことを知らなかった。 明治十八年高知中学校に入った。学校まで八キロの道を黙々と歩いて通った。三年生のとき、学年試験があまりにもよい成績だったので、いちはやく五年生に編入された。 この秀才に反感をもつ連中が陰謀をくわだてた。弁当の中身をとり出して、かわりに砂をつめたのである。昼休になり、彼が弁当の包をときにかかると、重苦しい沈黙が教室を占領した。弁当箱をあけた彼は、眉ひとつ動かさず、しずかにフタをし、包みおえると、何事もなかったかのように外に出ていった。悪童どもは、その底のしれない大きさに打たれてしまった。 漢文の教師が生徒の人物評をしたことがある。彼に対しては「雲くさい」といった。それは天性茫漠として大きいところがあり、その将来を端倪(推測)することができないという意味であった。 卒業がせまった頃、土地の旧家から養子に望まれた。彼は中学を卒業してこの家に入り、第三高等中学(三高の前身)在学中に家付き娘と結婚した。 東大法科の同級生には、小野塚喜平治、土方久徴(ひじかたひさあきら)、高野岩三郎、幣原喜重郎、勝田主計、伊沢多喜男、下岡忠治などがいた。首席は小野塚で、のちに東大総長となる。その人は次席だった。卒業生の多くは、卒業試験がおわると書物など見向きもしなかったが、その人は翌日からアダム・スミスの『国富論』と取り組んだ。財政政治家を基調とする実際的政治家になろうと、考えていたのである。 やがて大蔵省に入ったが、大臣の威光をカサにいばる秘書官の頭をぶんなぐって、山形県収税長に飛ばされた。つぎは四国松山で、そのつぎは熊本。そこでは税務監督局長(いまの国税局長)で、一種の出世にはちがいないとしても、もはや地方まわり十年間、大蔵主流から完全に見放されていたといってよい。ようやく中央にもどされたものの、ポストは専売局の部長で、大蔵官吏としてはアウトサイダーなのである。 不遇の彼にとって、唯一の慰安所は家庭だった。酒、タバコは無論、芸者買いも知らぬヤボ天の彼は、家で本を読むか、愛妻と碁を打っていた。 その彼に注目し、スカウトしようとした人物がいる。後藤新平である。 南満州鉄道初代総裁となった後藤は 「満州は午前八時の人間でやるのだ」 と宣言した。鶴見祐介は 「その意けだし人生の盛りを過ぎたる名前倒れの人物を登用せずして、全然未成品たる若年の人材を集めて仕事をするというのであった。……『な高かの骨高かはダメだ』。つまり、声名を天下に売って、すでにその全盛期を過ぎたる人物は、実際の役に立たぬ人間多しとの意である。いま満鉄の首脳部を組織するに当たり、伯(後藤)は思いきって若年無めいの人物を起用した」 と書いている(『後藤新平』第二巻)。 後藤はまず副総裁に数え年四十歳の中村是公をばつてきした。そして理事の人選をすべて中村にまかせ、ほとんど干渉しなかった。理事のうち、山県有朋の推薦による野々村金五郎一人をのぞいて、あとは全部中村が選び、後藤が承認した。営業担当として三井物産から田中清次郎と犬塚信太朗、経理・金融担当として日本銀行から久保田勝美、付属地の行政・土木担当として内務省から久保田清周と清野長太郎、鉄道担当として鉄道技師の国沢新兵衛、法律担当として京都大学から岡松参太郎、そして対大蔵省担当として、専売局事業部長のその人があがったのである。 収入は十倍となり、将来性もあるポストなのだ。ところがその人はことわった。その理由は他でもなかった。 「専売局の事業はようやく緒についたばかりで、自分が去ることはせっかくのその仕事を紛糾させることになる。そういう無責任なことは自分にはできないから、今しばらく専売局においてもらいたい」 というのである。 後藤は、金銭や地位に眩惑されないその人に、いっそう惚れこんでしまった。 第二次桂内閣が生れたとき、後藤は逓信大臣になった。そのとき、次官にはその人を迎えようとした。 本命コースとはいえない専売局長から、逓信省とはいえ、いちやく次官になれるというのはまさに破格の昇進である。凡百の役人は、自分を冷遇した役所に後足で砂をかけ、一も二もなくとびつくところであろう。 ところがその人は、この口もことわったのである。後藤という人物がきらいだというのではない。 「まだ専売局の方がすっかりカタづかないので、今ここを去ることは、九仞の功を一簣にかくようなものですから、ご辞退したい」 というのだった。後藤はいよいよ惚れこんだ。 この内閣は第二次西園寺内閣とかわり、これが倒れて第三次桂内閣が成立すると、後藤はふたたび逓信大臣となって、またもやその人を次官にと望んだのである。文字通り「三顧の礼」であった。その人も感激した。そのときは専売局長官となっていたが、専売局の仕事は一段落している。その人は、大蔵省の先輩で、第三次内閣の大蔵大臣になっていた若槻礼次郎に相談した。若槻は、 「うけるように」 とすすめた。 その人が、のちに第二十八代総理大臣となる浜口雄幸である。浜口を論じるには、金解禁政策の論議がふ可欠である。しかしその前に、この人には、不遇の地位にありながら、うまい話にはすぐ飛びつこうとしなかった逸話である。 逸話にはちがいないが、それはその人の本質を示すもの――たとえばいまの閣僚に、こういう逸話があるだろうか、というのが私の脳裏を去らぬ疑問であった。 (昭和五十二年六月)
近くの鉄道病院から、医師がかけつけた。その医師がおもわず、 「総理、たいへんなことに」 とつぶやくと、浜口は目を開けていった。 「男子の本懐です」 苦痛ははげしかったが、意識は明瞭であった。 「時間は何時だ」 などとも訊いた。 浜口は、ホームからかけつけてきた幣原にも、 「男子の本懐だ」 と漏らし、 「予算閣議もかたづいたあとだから、いい」 といった。 銃弾は左下腹部にとどまり、内出血がひどく、内臓を圧迫する。医師は話を禁じた。 浜口は苦痛をまぎらすように、愛誦していた「夜深同看千巌雪」の句をくちずさんだ。 周囲の人には、「千巌雪」だけが、聞きとれた。 2022.03.06記す。 |
|
安田善次郎の「運命」 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日発行)P.231~235
安田財閥の創始者安田善次郎は、大正四年七十八歳(数え)のとき「運命」について語った。(『実業之日本』二月一日所載)。 彼は、「この世にはやはり運というものは確かにある」と語っている。 「しかしその運の神は先方から自分の方へ来てくれるものか、または自分からその運をとりに行くものか、この二つの事の判断のしかたによって、人生の成功と失敗とがおのずからわかれる」 「運は⦅ハコブ⦆なりである。すなわち我身で我身を運んで行かなければ、運の神にあうことも運の神に愛せられることもない。運は確かにこの世に存在しているものとすれば、そこまで自分が行ってそれを取る。それがすなわち⦅運はハコブなり⦆である」 安田はこの処世訓を、自分の生涯に対比させ、その結論として、確信をもって語ったのであろうとおもわれる。
「江戸を去る百里の僻境に生まれ、陋巷の寒家に人と為り、寺小屋の外は、高等の教育を受くるの機会なく、赤手単身にて郷関を出でたる一少年が、その一代に於て、二億円と称せらるる資産を積み得たるは、我が国数百年の財界を通じて、蓋し稀覯(きこう)の事に属す」 と書いている。 天保九年、越中国富山の町外れに生まれた。父は苦心して金を貯め、下士の株を買って茶坊主にとりたてられたが、内職をしなければ家族をたべさせられない。善次郎も七、八歳頃から花売りをして家計を助けた。十二歳以後は、天秤棒をにない、野菜の行商をして歩く。夜は『太閤記』の写本をつくり、これを売った。そのうち、売薬行商で全国を歩く若者たちから話をきき、広い天地で大いにもうけたいと志すにいたった。 江戸に行くつもりで家出。江戸についたものの、家につれもどされた。親を説得しその許しを得てまた江戸にもどり、両替店に奉公し、ようやく独立したのが二十六歳である。両替店ではあるが資本金はわずか五陵両。日本橋小舟町の四辻で、戸板の上に小銭をならべただけのあわれな露店である。 しかし、幕末から明治維新のドサクサに大いにもうけた。 「最初の目的は千両の身代になりたいとの希望で、できるかぎりの勤倹を実行して二十八歳のとききその目的を達したから、このさいさらに第二次の希望をおこして、一ヵ年千両のくらしをするような身代になりたいと望んで、四十二、三歳の頃首尾よく目的どおりになった」 と彼は語っている。 安田銀行の開業が明治十三年、四十二歳のときであった。貧家に生まれて日本の代表的富豪になるその一生は、棚からボタ餅の幸運を夢みてのんびり待っていたものでなく、まさに刻苦精励、我身で我身を運んで運をとりにいったものとというほかはない。 そのかぎりにおいて、安田の談話はいささかもウソをついていなかった。しかし、その「ハコビ」そのものが別の運を招くものだったことが恐ろしい。それは「ケチ」という悪名が世間にひろまったことによる。 それは矢野の『安田善次郎伝』が、「氏が一方にて世人から称賛せられる事柄か、一方にはまた暗に恨みを買う種子となっていたのは是非もない事である」 と書いたところである。 「ケチ」という悪名の原因は「寄附ぎらい」にある。しかし彼には無論、社会に対する富者の義務の意識はあったのであのである。ただその意識は、第一に「陰徳をもって本とすべし。慈善をもって名誉を望むべからず」という父の遺訓にしたがった。第二に、「人の寄附などをたよりにしているようなことで、なんのまとまった仕事ができるか、結局は人をあやまらせるh。自分の汗と血をもって事をなすという方針の上に立った仕事でなければモノにならない」という彼のことばが示すように、寄附を求める者の、自己責任なき他力本願主義を嫌悪していた。金を出すことを絶対いやがったのではなかったのである。 その証拠は、東京市長後藤新平が大東京市開発のため「八億円計画」をつくったときに示された。世間は大風呂敷と嘲笑したのに、安田は正しく評価した。そして、その計画はちいさすぎはしないかといったあと、 「私はこれまでいずれの慈善事業にも、郷里のことにも名前を現わして出金したことはありません。が慈善の根本から割出された事業ならば、微力をつくしてみたい心はもっております。(中略)私の心は神明の知り給う所とうぬぼれているのです。(中略)あなたが使う人となられるならば、私は集める人となってお手伝いができると自ら信ずるのであります。しかしあなたが他人の力に信頼せぬとおっしゃればそれまでであるが、私はそういう意義のある仕事に向って家産を傾けることを決していとわものである。死んでいくときは黄金の棺に入れるわけでも参りません」 といったのである〔鶴見祐輔著『後藤新平』第四巻〕。
この申し入れをして間もなく、大正十年九月二十八日朝、大磯の安田別荘に一人の面会強要者があらわれた。 男は、まず労働会館建設のための寄附金を申しこみ、ことわられると短刀を出して、安田の顔を二ヵ所刺し、さらに庭に逃げようとする背後からおどりかかって、咽喉にとどめをさした。男は、自分も咽喉を刺して自殺した。 男は朝日平吾三十二歳。ふところに斬奸状を書いたものをしのばせており、その冒頭には、「奸富安田善次郎巨富ヲ作(ナ)ストイへドモ富豪ノ責任ヲハタサズ、国家社会ヲ無視シ貪欲卑吝ニシテ民家ノ怨府(エンブ)タルヤ久シ。予ソノ頑迷ヲ愍(アハレ)ミ仏心慈言ヲモツテ訓(ヲシ)フルトイへドモ改悟セズ、ヨッテ天誅ヲ加へ世ノ警(イマシ)メトナス」 とあった。朝日は寄附がことわられることをあらかじめ予測し、殺すつもりで会ったのだ。 安田善次郎八十四年の不屈の生涯が、そういう凶変で閉じられたことはいたましい。七十八歳で「運命」を論じた彼にも、六年後のそのことは予期できなかったところに人間の限界があるのだろう。 (昭和五十二年八月) 20203.06.05 記す。 |
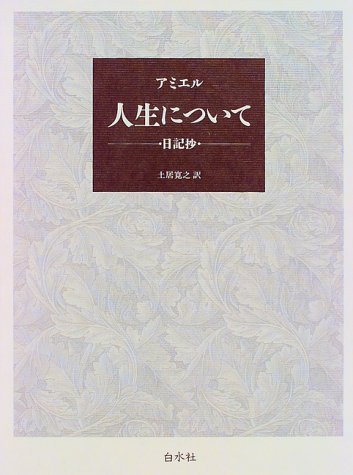
アミエル、浅野総一郎、伊庭貞剛の晩年 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日発行)P.226~231 「画龍点睛」ということばがある。人の人生にとって、老年こそまさにその時期にあたろうが、老人のさまざまの生きざまを見るにつけ、それは容易なことではなさそうだ、という気がする。 『アミエルの日記』(河野与一 訳 )に、「年をとることは死ぬことよりもむずかしい」という一行があった。この含蓄のある文句をおもいだし、一体アミエルはいくつのときにこれを書いたのか、調べてみるとなんと三十九歳のときである。 ※参考:「年をとること……」の文句 は『アミエル 人生について――日記抄――』土居寛之訳(白水社)P.53。「老衰」 一八六〇年五月五日(三十九歳)の冒頭に記載されている。 その若さで「老年」におもいをいたしていたとはあっぱれだとおもうが、その周到な配慮にもかかわらず、彼の晩年が平穏でも幸せでもなかったことは、おなじ日記に歴然と記録してある。 アミエルは六十歳で生涯を閉じた。老いることはむずかしい、と書いてからちょうど二十一年間生きていたことになる。今日の常識からいえばそれは早死に以外の何ものでもない。 ただ、老年の意義は単に長短の問題ではなさそうである。いたずらに馬齢を加えること自体、その人と縁故者にとっては大事なこととはいえ、ロンガー・ザ・ベターとならぬところに「老年」のむずかしさが示されている。 アミエルの晩年が幸せでなかったというのは、その早死のせいではない。三十九歳の日記は、年をとることは死ぬことよりもむずかしい、ということばにつづけて、 「一つの宝をひとまとめにして一度であきらめることは、その宝を毎日なしくずしに新しく犠牲にすることほどつらくはない、という理由によってである。わが身の衰えに耐え、わが身が小さく弱くなってゆくことを受け容れることは、死を物ともしないこと以上に苦く稀な徳である。悲劇的な夭折には栄光がある。つのりゆく老衰には長い悲しみがあるばかりである。しかしもっとよく考えてみよう。すると、苦痛を耐え忍ぶ宗教的な老年のほうが、若い時代の英雄的な激情よりも胸を打つものがわかってくる。魂の成熟はいろいろな能力の輝きや力のゆたかさよりも価値がある。そしてわれわれの裡(うち)の永遠なるものは"時"の猛威によって加えられる損害のかずかずを利用するにちがいない。そう考えると慰められる」 と書いた。 しかし現実は、「考えると慰められる」という二十一年前の予想を裏切った。 「恐ろしい夜。引きつづき不眠にさいなまされて第十四夜を迎える」 「意気消沈。……肉体と精神とのものうさ。生きるというのは何と困難だろう。おお、私の疲れた心よ!」 痛ましい苦悩の連続だったことがこれでわかる。 このアミエルの晩年とちがった様相を示している人に、実業家ではたとえば浅野総一郎や伊庭貞剛がいる。 浅野は人一倍の精力家であった。五十八歳のときには、「自画自賛に類するが、私は、確かに人の三人前は働いていると信じている。若い時分から職務のために徹夜したことがいくらもあるが、私は人は三時間眠れば沢山と思っている。貴重な時間をむなしく睡眠のためについやしてしまうのは惜しいことだと思う」 八十一歳のときには、「私は百二十五歳まで働く」と語った。 「その日その日によって、日程はちがうが、宅にいるときは毎朝四時起床、五時入浴、ただちに食堂にはいり、その間例によって前日あらかじめ呼び来たった社員二、三めいに面談し、午前七時から同八時まで、浅野セメント、造船所、その他直系会社の各重役の相談を受け、午前八時宅を出て、諸方を歴訪会談し、午前九時半ないし十時、丸の内の事務所に出勤し、十二時まで同事務所にあって、各会社担当者の相談を受ける。零時半ないし午後一時食事をおわり、鶴見、川崎、関係工場視察におもむき、一ヵ所の工場に一時間ないし一時間半ずつ費やす。各工場はいずれも何万坪という広い面積をもっているから、各工場を巡視するには、相当に長い時間を要する。こうして日々プラット・フォームを上下すること六回、毎日二、三里は徒歩し、午後五時か六時には東京の事務所にもどる。晩には二つ三つぐらいの会があり、帰宅するのは午後九時か九時半、帰宅してから、さらになお関係各会社の社員に面談し、午後十時か十一時に就寝する」 浅野はこの談話の中で、天海僧正の長寿法を紹介した。天海は百二十一歳まで生きたといわれるが、その秘訣は、第一が正直に働く、第二が日湯、すなわち毎日風呂に入ること、第三が粗食、第四が「だらり」、いわゆる物を苦にしない心の持ち方であった。 浅野は、自分もおなじ長寿法を実行している、といった。ただし食事については、菜食だけでは腹がへってたまらず、精力がつづかない、だから肉食もやり、大食もする。朝はオートミールに牛乳一合、味噌汁に生卵三個、日本食一杯、水菓子、チーズ、紅茶。昼はうなぎ丼か天丼一個食って、なお足らぬときは釜あげ一つ平らげることもある。夜は多く洋食。 このように長寿法を実行し、ことに第一の「正直に働く」ということは人後に落ちない、と誇った。 だが、この話をしたつぎの年に永眠したため、「百二十五歳まで働く」は画餅におわった。とはいえ、八十歳をすぎてなお現役第一線にあり、ベストをつくして戦った姿は壮絶の一語につきる。<近頃ゴルフをやらぬので身体がナマったよ>などという若い経営者を見たら、この老翁は何といったであろうか。 生涯現役の浅野とはちがって伊庭貞剛は、すでに五十八歳で現役を去った人であった。 引退の十七年前から用意していた石山の別荘「活機園」(所在地:滋賀県大津市田辺町10番14号)に隠棲し、そこで静かに老いていった。 はじめは、日常の動静を語るのに「悠々自適」のことばを用いていた。ところが七十八歳のときから「曠然自適」というようになった。その理由は他でもない。「悠々」にはまだどこかにアカのぬけきらないところ、自力をたのんで得々然とした趣が残っている。「曠然」は、何ものにもとらわれぬ無礙自在の境である。 伊庭は八十歳のとき、子女を集めて遺言し、財産を分けてやった。それから五月後、「ああ、こんな悦びはない。この徹底した悦びとして笑ってお別れしたい」 といい、家族順々に末期の水をふくませてもらった。幼い孫が二度ふくませようとすると 「お前はさっき、くれたではないか」 といって微笑し、やがて大往生をとげたのである。 (昭和五十二年七月) ※どんな生き方が好きかと思うに私は、浅野総一郎氏のそれが好きであると……。 2022.03.05記す。 |
|
文化大臣アンドレ・マルロオ 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.254~258
と書いたのはアンドレ・マルロオである(『反回想録』)。 一九〇一年(明治三十四年)に生まれ、一九七二年(昭和五十一年)七十四年の生涯をとじたマルロオが、ド・ゴール内閣の情報大臣となったのは一九四五年(昭和二十年)十一月、四十二歳のときである。それまでの彼は『征服者』、『侮蔑時代』、『王道』、『人間の条件』などの作品をもつ作家であり、スペイン人民戦線に参加したことが端的に示すように、あきらかに「左翼」作家であった。 その左翼作家がレジスタンス運動をへてフランスの勝利を迎え、ブーロニュのオランダ風家屋に住んでいるとき、夜の十一時軍用自動車が門前にとまった。それはド・ゴール将軍の使者であった。アトリエの敷居をまたごうともせず、「ド・ゴール将軍は、フランスの名において、あなたが将軍にご協力くださるお気持ちがおありか否か、自問せられたいとのことであります」 といった。妙な口上である。 「もちろん、論議にはおよびません」 とマルロオは答えた。 こうしてド・ゴールとの最初の会見が実現するのだが将軍は、 「ダーボール、ル・パッセ」(まず、過去を) とマルロオにいった。当然である。ド・ゴールとしては、マルロオの左翼的経歴、そういう人物の協力関係にまず疑問があったはずだ。質問に答えて、 「しごく単純です。きょうの日まで私は挺身してきておりますが、いわばそれは社会的正義のための闘争であった、と言ってさしつかえなかろうかと思います――」 以下、滔々とのべたマルロオのことばと、その後のいきさつは『反回顧録』上巻一三九頁以下にゆずる。ともかくこうしてマルロオはド・ゴールと結びつき、サルトルはじめ、左翼知識人と絶縁状態になったのである。
一九四五年(昭和二十年)八月十六日、日本降服の翌日、マルロオはド・ゴール内閣の技術顧問となり、十一月に情報大臣として入閣した。 マルロオは新聞、出版物の刊行認可と用紙割当の仕事のほかに、美術品の複製の配布に力を入れた。そして複製の画廊をフランス各地の市役所につくろうと考えた。しかし、ド・ゴール内閣瓦解のため、情報大臣在任はわずか八週間、その仕事は挫折した。
第五次共和国の閣僚は、首相以下つぎつぎと変ったが、ド・ゴールは大統領として、そしてマルロオは文化大臣として十年間変らなかった。「私の右にアンドレ・マルロオがいる。彼はつねにそこにいるであろう。この天才的な友人、気高い生き方にとりつかれたこの人物がそばにいることで、卑俗さから自分が守られているという気持を、私は抱いた。この比類ない証人が私についてつくりあげる理念が、私を激励して決心かためさせるのである>とド・ゴールは回想録(『希望の回想』)に書いている。
※余談:写真説明:オペラ座の前。 平成04年08月10日(月曜日)ヨーロッパ旅行でのパリ市内宿泊・見物。 ホテルの朝食 100F(100F= 2,500円 400F=10,000 円)の定価。 ☆市内見物 バスツアー(シチラマ)4人(私たち夫婦、長男夫婦)でのる。ear-phone ではフランス語、英語、ロシア語など数カ国語で聞ける。私は、これまでの2度の訪問の記憶を辿りながら車上から見物した。 コンコルド広場、シャンゼリゼ通りを見物。ジャンヌダークの騎馬像を遂に見つけることができなかった。残念。歴史の勉強は現地でじっくり生活しなければ身につかない。 ※参考:渡部昇一『日本発見』渡部昇一 対談集 (講談社) P.48 石炭で黒くなった建物 一九六〇年(昭和三十五)から建物を洗いはじめた。圧力で砂と水をかけて削れる汚れを取っていく。五十九年、建物は真っ黒で、オペラ座の正面なんか緑青がダラダラ青くたれてきたないものだった。 ド・ゴール政権の初めごろ、アンドレ・マルロオが文化大臣で、これを洗っちゃおうという法案を出して、結局のところ通った。建物のも地主で洗わない人は何年か後には罰金を取られ、洗う人は補助金が出るわけですね。と書かれている。 「文化の家」が各地につくられた。これは音楽会場、美術館、劇場、成人学校を兼ねた施設で、中世にカテドラルがはたした役割を、世俗化された現代社会で演じさえようとしたものである。ここは<人びとが彼らの最良のものと会うために、出会う場所なのだ>と彼は国会で答弁した。この構想に類似するものとして、日本には久留米市に石橋文化センターがある。ブリヂストン創立者石橋正二郎が創案し、私財を提供して実現したものである。 官庁、学校その他公共建築物をつくる場合、彫刻家、画家、壁掛職人などを必ず顧問として依頼すること、全予算の一パーセントを彼等に支払うことも、マルロオは法制化した。これによって、工業化の波の中に古い伝統的な職人芸が亡びることを防いだのである。「自由世界で唯一の、真の機能を果している文化大臣」とは「ニューズ・ウィーク」誌の評言である。 マルロオは日本を三回訪れた。
一九三一年(昭和六年)二十九歳のとき。一九五八年(昭和三十三年)五十六歳のとき。一九六〇年(昭和三十五年)五十八歳のとき。その三度目の来日でブリヂストン美術館を訪問したとき、筆者は彼の風貌姿勢に接する機会にめぐまれた。 文化大臣の背後には、文化省官房長、駐日フランス大使、日仏会館長、文部省の役人などが金魚の糞のようについてきていた。形だけを見れば、いかにも文化大臣の公式訪問くさい。けれども石橋コレクションを一点ずつ、くい入るように見ていくマルロオの態度からは、そういう官僚臭、公式日程をこなしている儀礼的なそぶりはまったく感じられなかった。彼は、熱中し、陶酔していた。文化大臣という肩書も、その公用ではるばる東京にきていることも、そして、この美術館のあとに学士会館の午餐会に招かれていることも、忘れはてていたかのようである。
日本に、そういう文化大臣が誕生するのはいつのことであろうか。 (昭和五十三年四月) 2022.05.03 記す。 |
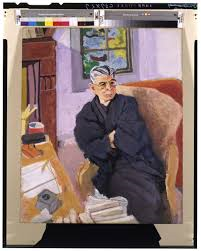
安井曽太郎の「深井英五氏像」 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.263~267 六月十一日まで、東京・京橋のブリジストン美術館で「生誕九十年記念 安井曽太郎展」が開いている。NHKテレビでは「日曜美術館」でこの内容を紹介し、日本経済新聞は五月二日の教養読書特集で、同画伯の「深井英五氏像」と、嘉門安雄の解説を掲げた。 この「深井英五氏像」は、昭和十二年に描かれたもので、肖像画の代表的傑作であるという。 なにが代表的傑作たらしめた要因であろうか。 「深井さんの普段の姿を描きたいと思って、その書斎での深井さんを絵にすることにした。深井さんの書斎は余り広くなく、そのうえ大き過ぎるくらいのテーブルが置かれてあり、床には沢山の書物が積み重ねてあって、やっと画架が置けるくらいであった……」 とは安井の述懐である。 「私はこの絵を見るごとに、やや斜めに構えて微動だにせず、じっと日銀総裁の深井さんをまともから見据えている安井曽太郎のきびしさを思う。だからこそ、このような素晴しい肖像が、人間像が描かれるのである。豊かに深く、さわやかに温かい絵である」 と嘉門は賞めている。たしかにそのとおりであろう。 ただこの画像をじっと見つめていると、おのずと別の感慨がわいてくる。 深井英五は、昭和十六年第十三代日銀総裁となった。その前には、パリ講和会議、ワシントン軍縮会議に、全権随員となった。ロンドン国際経済会議には、全権として列した。貴族議員、枢密顧問官にもなっている。 ところが安井は、そういうステイタスに何の関心を示さず、「普段の姿」を描こうと志向している。そして深井も、和服にくつろいで描かれている。その書斎が余り広くなく、床に沢山の書物を重ねてあるというのも好ましい。そこに、とりつくろわぬ素顔、日常生活が露呈されており、スノピズムの侵入する余地はない。そして、じっと見据えるきびしい画家の眼にこたえているのは、深井自身の、ウソのない人生である。 ※参考:スノビズム(snobbism)は俗物根性と訳される。 多くの場合「知識・教養をひけらかす見栄張りの気取り屋」「上位の者に取り入り、下の者を見下す嫌味な人物」「紳士気取りの俗物」といった意味で使われる。 安井の眼と、これにこたえる深井の年輪。 その激突と均衡の上にこそ、豊かで、深く、さわやかな人間像が温かく形成されたのであろうとおもうが、腕を組み、室内の一点を凝視する深井の姿に、向学心に燃えていた青少年期の原型が感じられてならない。 深井は、上野国高崎において、百五十石取だった旧藩士の第五男として明治四年(一八七一年)に生れている。 父は、前代の遺臣として固く自ら持し、まつたく世間から退隠してくらした。寡言沈重、学問および立志の方向について希望をしめすことはほとんどなく、ただ体格の弱小を心配して護身のために少し武芸をならえ、と注意した。情操、行状などについて訓戒をあたえることは少なかった。ただ貧乏生活がせがれの心境に悪影響をおよぼすことを憂慮し、武士らしい気節を伝えるため、身をもって模範を示した。 高崎は連隊所在地で、そこに所属する将校の子供たちゃ、別の階級のように優遇され、「坊ちゃん」と呼ばれていた。 深井も別に深い理由もなく、周囲の風習にしたがっていると、父からきびしくとがめられた。 「坊ちゃんというのは、主筋に対してのみ使うべきことばである。我家貧なりといえども、卑屈の心になってはいけない」 と父は訓戒したのである。「これは私が六、七歳の頃のことで、その深き印象は一生を通じて種々の場合に私の意気を動かした」と語っている(『回顧七十年』)。 上級学校に進学できない深井に、そのチャンスをあたえたのは新島襄である。新島は、高崎の隣の安中出身で、元治元年(一八六四年)国禁を犯してアメリカにわたり、アムハースト大学のアンドヴァ―神学校で学び、明治七年(一八七四年)帰国し、翌年京都に同志社を創立した。 その新島が群馬県に帰省したとき、奨学金を支給して同志社に入学させるべきものを物色し、深井がその選にあたったのである。 「同志社教育は広汎にして深厚なる影響を私に与えた。最も重しとすべきは、新島先生の感化による人生観の生成である」 と深井は語っている。また、「当時の同志社教育は、教師と生徒の気分に就いていえば、単なる授業ではなく、心と心との接触による切磋琢磨であった」 とものべている。 深井は、毎月奨学金を新島から手わたされるので、他の学生よりも多く接触した。彼はこれを幸いに、鼓吹激励をうけたいと期待した。が新島は、かねて評判のように熱烈の態度を示さなかった。 「温情は感受したが、談話は概して淡々たるものであった」 一生は長いから急がずにやれとか、健康をそこねないように注意しろ、というような話が多かった。庭の果物を、枝つきのまま手折ってくれたり、休暇の旅費をあたえたりしたこともある。 賄食(まかないしょく)に甲乙の区別ができたとき、深井は乙を選び、その月は先生からいただく学費をそれだけ減らしてもらいたいと申出る、それはまちがっている、健康には栄養が大切だと注意された。 「先生は特に私を訓戒するごとき態度をもってせず、むしろ自己修養の体験を語るように人生の心構えを説き示された」 深井はその印象を三つに要約している。 第一は、自己の信念に立脚しなければならぬ、付和雷同やゴマかしてはいけないということ。 第二は、単に自己生活のために働くのではいけなく。世の中のためになるように心がけねばならぬ。世のためになるというのは、必ずしも大事業をなすのみに限らない。分に応じてそれぞれの途(みち)がある、といった。 第三は、何か仕事しなければいけない。その趣旨は、仕事の種類をとわず、世の中との接触を必要とし、独善高踏をいましめることにあったらしい。 深井は、以上の三つをしばしばきかされた。それも訓戒ではなく、その胸のうちを吐露するようにきこえたので、深井はいっそう深く感動した。 「神を父とし、人間を同胞とする教理の応用として、私の実践的人生観の基礎ができたのである」 安井の「深井英五氏像」には、この人間的原型が、清潔で、明澄な強さとして、よくとらえられているようにおもう。 (昭和五十三年六月) 2019.08.04 |
|
桜井忠温と水野広徳(一) 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月二十五日発行)P.304~308 夏目漱石の『坊ちゃん』に、「乗り込んでみるとマッチ箱の様な汽車だ。ごろごろと五分許り動いたと思ったら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった三銭である」と書いてある。子規堂のある松山市正宗寺の庭で、その実物の想像を絶した小ささに驚きながら、 「読んだのは中学一年生だったな」 とおもった。過ぎ去った四十八年もの歳月が嘘のようである。 松山城の天守閣から絶景をたのしんだとき、子規の「春や昔十五万石の城下かな」について、 「石川啄木のようには、その故郷に対し複雑な屈折をもたず、伊予松山の人情や風景ののびやかなままにうたいあげている点、東北と南海道の伊予との風土の違いといえるかもしれない」 と書いている司馬遼太郎の『坂の上の雲』をおもい出した。この本も、読んですでに十一年もたっているのだ。 「光陰矢の如し、少年老いやすし」 の感慨を噛みしめながら、講演会場につくと、書店が出張して、拙著をあれこれならべている。すると、主催者南海放送の門田圭三社長、稲田新常務、大内信也取締役、野本達局長が、それぞれにその何冊かを買われる。講演者への挨拶の意味もあろうが、もともと本が好きだからということが、その自然な動作、表情でわかる。私が感動したのは、それが自著であったからではない。学問芸術を愛する土地柄ということが、肌からわかったように感じられからだった。 司馬文学の影響で、秋山好古、真之兄弟のことしか念頭になかったが、 「桜井忠温、水野広徳が出ています」
大内氏から『反骨の軍人・水野広徳』を贈られた。水野は三十五歳のとき、大内モリエと結婚しているが、この大内氏の一族であろう。その本を、空港、機中、東京から逗子までの横須賀線の中で読みつづけた。眼が痛むぞ、とわかっていても本をおくことができない。これほどの迫力をもつ名著と出会ったのは久々のことである。 これは自伝で、「前編 剣を吊るまで」、「後篇 剣を解くまで」の二部より成る。はじめに島田謹二の、懇切をきわめた、というより、全身全霊をこめて書いた解題があり、まずここで読者の胸は感動でふるえる。
※参考:島田謹二の著作に『アメリカにおける秋山真之』明治期日本人の一肖像、『ロシアにおける広瀬武夫』武骨天使伝。いずれも朝日新聞社発行所、がある。 この「剣」とは海軍士官が吊していた短剣のことで、前編は海軍兵学校に入るまで、後篇は海軍を去るまで、という内容になる。 『坂の上の雲』には、「信さん」と呼ばれた秋山信三郎好古(よしふる)(のち陸軍大将)が少年時代、家が貧しいため銭湯の風呂焚きをした話が、のびのびと、たのしく書いてある。貧しいけれども、両親があり、五人の子供がいる秋山家は、当主(もと十石とりの下士)の生活能力のなさそのものを含めて、浄福に包まれていて明るい。 五番目の子を間引きはできないから寺にやるときいて、十歳の信さんは 「あのな、そら、いけんぞな」 と両親にいう。 「あのな、赤ん坊をお寺へやってはいやぞな。おっつけ、ウチが勉強してな、お豆腐ほどお金をこしらえてぁげるぞな」 たとえ貧しくとも、家族には心が通っており、助け合って生きていく。 これにくらべると、水野広徳の幼少時代は、文字どおり悲惨である。 両親のもとに、水野家も五人の子宝があった。広徳はその第五子で、生まれた翌年生母が死亡する。さらに数えで六歳のとき父も死亡する。家に資産はなく、遺子五人は分散して、一人ずつ親戚に引きとられる。 広徳は母方の伯父の家に引き取られるが、その家の子供との明らかな差別待遇などでいつしか心がねじれ、手のつけられぬ悪童となって、十六歳のとき伯父の家から追い出され、兄光義と同居する。兄はてんかんで足が不自由であり、アンマを業として爪に火をともすようなくらしをしている。食いざかりの広徳が、空腹と戦う情景などの描写に水野の文才が光る。 金のかからない陸軍幼年学校を志望するが、秋山好古の弟真之(まさゆき)(のち海軍中将)の海軍兵学校姿にあこがれて兵学校志望に変る。兄は三十歳で病死する。広徳は、両親と兄を失い、孤独の境遇におかれるが、屈せず勉強して二十二歳のとき入校を許される。同級生六十二名、なかには野村吉三郎、小林躋造(せいぞう)(のち海軍大将)などがいた。兵学校は二十四番で卒業する。 明治三十六年九月海軍大尉となり、三十八年五月の日本海海戦には、秋山真之中佐は東郷司令長官の参謀として、水野大尉は水雷艇長として参加する。そして四十三年(三十六歳)に書いたのが『此一戦』であるが、 「わずかに百トンあまりの水雷艇に至っては、輾転動揺箕(み)を翻すが如く、艇の傾斜は実に六十七度に及び、怒涛艇首を呑めば、人諸共に水中に没し、激浪艇尾を襲へば、湧波、上甲板に漲り、汽機は絶えず空転して、船体砕くるかと疑れ、潮水は煙突内に奔入して汽罐の火消ゆるばかり、既に死を待って居る」 という情景は、彼自身の体験である。
「兵は凶器なり」という言葉ではじまり、「国大と雖も、戦を好む時は必ず亡び、天下安しと雖も、戦を忘るる時は必ず危し」という言葉でおわるこの物語は、帝国海軍の勝利を讃える記録である。 しかし、記録であり、職業軍人の筆になるとはいっても、文中、たとえば、 「ロ提督は多数の給炭船を準備し、駆逐艦は運送船をして之を曳航せしめ、洋中戴炭を行ひつつ、決然印度洋に浮んだ。山中暦なきも、花信尚ほ春を報ず、独り海洋ばかりは春来れど花咲かず、秋去れど紅葉散らず、時は是れ艶陽四月の春半とは云へ、苦熱肉を爛らす赤道の直下、舷(ふなばた)に砕くる潮の飛沫(しぶき)を花と見て、明日さへ知れぬ戦場に向ふ、露艦隊將士の心中感無量であろう」 などの文学的表現に満ち、期せずしてこの物語は「戦争文学」の代表作品となり、洛陽の紙価を高めたのである。 しかし、本当の問題はそこにはなかった――。 2022.03.08記す。
|

桜井忠温と水野広徳(二) 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮社)(昭和五十九年四月二十五日発行)P.309~313 正岡子規、高浜虚子が出たことで、伊予松山は日本文学史上、俳句のメッカというべき土地となったが、同様に、桜井忠温、水野広徳が出たことで、戦争文学の上でも大事な場所となっている。 桜井忠温は明治十二年(一八七九年)に松山市唐人町に士族の子として生まれた。安倍能成の生家と隣同士であった。三十四年(一九〇一年)陸軍士官学校卒業、翌年歩兵少尉任官、三十七年四月歩兵第十二連隊(松山)の連隊旗手として日露戦争に従軍、八月中尉、旅順口望台において、左上腿脚斬創、右腕関節貫通銃創骨折粉砕、左手軟部貫通銃創、左手盲管銃創、右膝頭盲管銃創、左前膊盲管銃創、右下腿骨折貫通銃創、脛腓両骨骨折等の重傷を負った。この体験をもとに『肉弾』を書いて刊行したのが三十九年二十八歳のときである。 この作品は数年にして千版を突破しただけでなく、英、独、仏、伊、露、ギリシャ、中国語の諸国訳が出て、ルーズベルトは子供や知人に読ませ、カイゼルはこれを全連隊に配布して日本精神の研究を命じ、イギリスでは陸軍の副読本に採用された。 著者桜井は昭和五年(一九三〇年)五十二歳で陸軍少将になり、予備役に編入されたが、ジャーナリズムで活躍、昭和四十年(一九六五年)八十七年の生涯をおわっている。軍人作家として一節を貫き得た幸福な人だった。 これにくらべると、『此一戦』によってベストセラー作家となり得た海軍の水野広徳には、大きな波瀾が待ちかまえていた。 大正二年(一九一三年)三十九歳のとき中佐となり、五年七月私費留学の許可を得て、第一次大戦下のヨーロッパを見るため、イギリス、フランス、イタリーを旅した。この旅費は『此一戦』の印税と、友人からの援助によったという。 この旅の印象で、水野の胸の中に苦悶の火が燃え出した。それは現代戦争の大規模なことを実感、日本のように経済的貧困の国では、とうてい堪えられぬとおもい、愛国的見地から戦争を否認、軍国主義、帝国主義的思想に動揺をきたして、職業軍人として生きることに矛盾を感じたためである。 七年(一九一八年)四十四歳で大佐に進級、翌八年ふたたび私費留学の許可を得て、戦後のヨーロッパ視察に出発した。 その旅の様子は、自伝の『剣を解くまで』にくわしいが、ロンドンに着くまでの軽快な筆致は、北フランスの戦場を見て次第に苦渋の色が濃くなる。「二十世紀における科学文明の精神を集めて満四年の間、破壊と殺戮とをほしいままにしたる戦の傷は、見るも悲惨、聞くも悲哀、誠に言語の外である。村落は壊滅し、田園は荒廃し、住民は離散し、家畜は死滅し、満目これ荒涼、満地これ蕭条、惨として生物を見ない」 スイスからドイツへ行く。スイスではユングフラウにアルプス登山鉄道で向かうが、「峡気爽涼、心気清快、同行の電力王Y・M氏等同行人三人『キㇾイだ』、『ステキだ』と、右の窓に走り、左の窓に就き、観賞の応接に暇がない」。この電力王とは松永安左ェ門で、当時代議士だった。 バーゼルからラインの橋を渡ってドイツの地を踏む。超満員で暗い列車にのってベルリンへ。そこで彼が見たものは、われわれ日本人が戦後味わったあの頽廃、屈辱、貧困の生活。「僕は先に北仏戦場の惨状を見て現代戦争の恐るべく、忌むべく、呪うべくを知り、戦争に対する道徳観念に大なる動揺と疑惑とをました。勝った連合国はその得るところ、その失うところを償うに足らず(中略)、戦争を以て国家発展の最良手段とさえ心得たる自分の軍国主義思想は根本から覆された」 どうしたら戦争は防げるか。「軍備の縮小は戦争の発生を緩和するの効果はあるかも知れぬが、決してこれによって戦争を防止し、戦争を絶滅することはできない。元来有効なる軍備の量は自国限りの絶対的のものでなく、常に必ず他と相対的のものでなければならぬ。既に相対的である以上そこには必ず自国の兵力量を定むべき仮想の敵国がなければならぬ。既に仮想の敵国である以上そこに自ら猜疑の念を招き、敵愾の心を生じ、延いては戦争の危険を醞醸することとなる」 「国際公法における交戦法規ぐらい人間の虚栄を示したものは稀である。毒ガスの使用はヘーグの平和条約で禁ぜられいたではないか。商船の武装は海戦法規によって禁ぜられていたではないか。ドイツの潜水艦戦を人道違反として攻撃した連合軍は、海上封鎖によってドイツの老幼を餓死せしめたではないか。戦争に何の人道ぞ! 戦争をして益々残忍酷虐ならしめよ、これ戦争を絶滅に導く一つの途である」 「軍人が政治の実権を握る国にはつねに戦争の危険がある」 「もしも世界の明日が平和であると信ずるならば、或は平和であらんことを欲するならば、いやしくも平和の成立を妨げ、平和の成立を脅かす一切の予約を排斥除去する勇気がなければならない。然るに戦争の撲滅を公然する勇気もなく、さりとて平和に邁進するの英断もなく、武装平和のなに隠れ表に平和を唱えながら、裏に軍備の必要を説く者に至っては、卑怯者の偽善にあらざれば偽善者の卑怯である」 もはや軍人としての前途に希望を失った彼は、十年(一九一一年)四十七歳で予備役編入。軍事および社会評論家として立つたが、「左傾的思想」として危険視され、特に満州事変以後、執筆の自由を奪われ、そして戦争中愛媛県越智郡津倉村、すなわち瀬戸内海中の一島、大島に疎開して、二十年十月七十一年の生涯をおわっている。 軍事評論家松下正寿が松山市正宗寺に建てた歌碑には、安倍能成の筆で、 世にこびず、人におもねらず、我れは我が、正しと思う道を進まん と書かれている。また安倍は自伝『我が生ひ立ち』の前がきの中で「よく見れば薺花咲く垣根かな」という芭蕉の句を引用して、 「人にきづかれぬ薺の花にも牡丹の花と同じく存在理由、存在価値がある、自分が薺の花としてつつましく目立たず咲くか、牡丹の花として玉堂富貴のあたりまばゆい光彩を放つかは自分の努力によってできるのでなく天の与へる賜である。(中略)自分が薺に生まれるのも牡丹に生まれるのも天の道であり、誠である。この天の道、誠の道を自分の努力によって実現して、薺と咲き牡丹と咲くは人の道である。牡丹を羨まないと共に薺を恥ぢないというのが、私の三十歳頃に得た一種の悟りであつた」 と書いている。将軍、提督となって『坂の上の雲』のヒーローにされた秋山兄弟に水野広徳を対比したとき、なぜか安倍の文章が胸に沈んできた。 (昭和五十五年十一月、十二日) 2022.03.10記す。 |
 「このような戦争の技術を学習することは、プロの軍人にはむしろやりやすい。肌に合ったことであった。ジョミニの人気はそこから出たわけであるが、図式化された戦術を学習するという快適さは、バロック・ロココ時代の戦争に通じている」
「このような戦争の技術を学習することは、プロの軍人にはむしろやりやすい。肌に合ったことであった。ジョミニの人気はそこから出たわけであるが、図式化された戦術を学習するという快適さは、バロック・ロココ時代の戦争に通じている」
 これについて、その真実を浮彫りにした名著が上梓された。橋口収著『饒舌と寡黙』。周知のように、著者は国土庁初代次官として現職にある人。かねて名エッセイストの名が高い氏は、この本の「忘れられた海軍大将」という一章においてこの提督の生涯を描くとともに、「ソフィスティケイテッド・ソフィスティケ―ション」という心からの賛辞を呈している。
これについて、その真実を浮彫りにした名著が上梓された。橋口収著『饒舌と寡黙』。周知のように、著者は国土庁初代次官として現職にある人。かねて名エッセイストの名が高い氏は、この本の「忘れられた海軍大将」という一章においてこの提督の生涯を描くとともに、「ソフィスティケイテッド・ソフィスティケ―ション」という心からの賛辞を呈している。
 その波瀾のディテールは『自伝』にゆずる。事実は小説より奇なり、というけれども、彼の自伝は小説よりもおもしろい。
その波瀾のディテールは『自伝』にゆずる。事実は小説より奇なり、というけれども、彼の自伝は小説よりもおもしろい。
 ウィーンには美術史館があり、そのコレクションはハプスブルグ王朝(黒崎挿入:オーストリアの旧帝室で、中世以来ヨーロッパ随一の名家。スイス北部出自の貴族の家系で、家名は山城ハプスブルクHabsburg〔鷹〕の城の意)に由来する)がその権威をかけてあつめたものだ。「ウィ―ンにきて美術史館を見ないで帰るのは、パリに行ってルーブルを見ないで帰るのと同じことだ」といわれている。ここにブリューゲルの代表作十五点があり、中野はとくに「雪中の狩人」にひきつけられた。
ウィーンには美術史館があり、そのコレクションはハプスブルグ王朝(黒崎挿入:オーストリアの旧帝室で、中世以来ヨーロッパ随一の名家。スイス北部出自の貴族の家系で、家名は山城ハプスブルクHabsburg〔鷹〕の城の意)に由来する)がその権威をかけてあつめたものだ。「ウィ―ンにきて美術史館を見ないで帰るのは、パリに行ってルーブルを見ないで帰るのと同じことだ」といわれている。ここにブリューゲルの代表作十五点があり、中野はとくに「雪中の狩人」にひきつけられた。
 星新一著『人民は弱し 官吏は強し』十三年前に出版された本である。
星新一著『人民は弱し 官吏は強し』十三年前に出版された本である。
 著者は、星製薬社長星一の長男。別の作品『明治・父・アメリカ』で父親像を描いている。これは三年前に本になった。
著者は、星製薬社長星一の長男。別の作品『明治・父・アメリカ』で父親像を描いている。これは三年前に本になった。
 したがって、『人民は弱し 官吏は強し』は、伝記小説のジャンルに入れてもさしつかえない。しかし、会社社長となった父の生涯を描くうち、それが期せずして経済小説としての性格をおびたところに、この著者の客観的な眼、冴えた眼を実証するものがある。
したがって、『人民は弱し 官吏は強し』は、伝記小説のジャンルに入れてもさしつかえない。しかし、会社社長となった父の生涯を描くうち、それが期せずして経済小説としての性格をおびたところに、この著者の客観的な眼、冴えた眼を実証するものがある。
 世の中には短く要約できないものはない 星新一『明治の人物誌』
世の中には短く要約できないものはない 星新一『明治の人物誌』
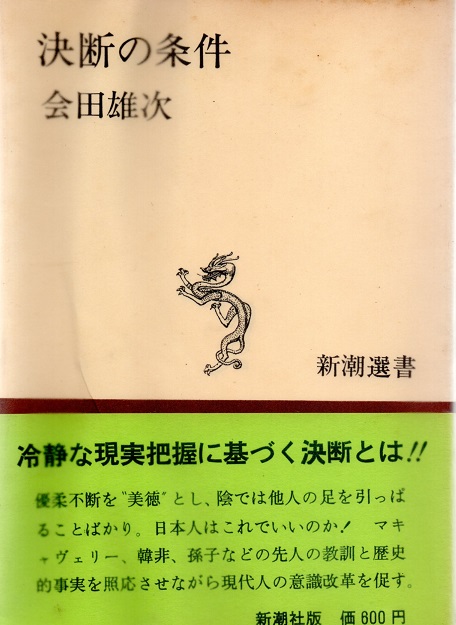 「ひどい話じゃないか。僕は義憤を感じるよ」と吉岡氏は激した。私も同感であったが、たまたま出発前に読んだ会田雄次著『決断の条件』をおもいだしたのである。
「ひどい話じゃないか。僕は義憤を感じるよ」と吉岡氏は激した。私も同感であったが、たまたま出発前に読んだ会田雄次著『決断の条件』をおもいだしたのである。
 ステファン・ツヴァイクの名著『マリー・アントワネット』を思い出される方も居られるだろう。
ステファン・ツヴァイクの名著『マリー・アントワネット』を思い出される方も居られるだろう。
 新田次郎著『アラスカ物語』(昭和四十九年五月二十五日発行)を読まれたであろうか。二年前に出た本だが、もしまだであれば、特に管理職にご一読をすすめる。エスキモーのリーダーとなり、アラスカの救世主と呼ばれた実在の日本人「フランク安田」の生涯を書いたものだが、まずはそのすばらしい自然描写で、読者の心を洗ってくれる。筆者は、志賀直哉の『暗夜行路』を超えた現代文学の傑作だと信じて疑わない。
新田次郎著『アラスカ物語』(昭和四十九年五月二十五日発行)を読まれたであろうか。二年前に出た本だが、もしまだであれば、特に管理職にご一読をすすめる。エスキモーのリーダーとなり、アラスカの救世主と呼ばれた実在の日本人「フランク安田」の生涯を書いたものだが、まずはそのすばらしい自然描写で、読者の心を洗ってくれる。筆者は、志賀直哉の『暗夜行路』を超えた現代文学の傑作だと信じて疑わない。

 ※参考:城山三郎『男子の本懐』には上記の逸話の記載はない。P.308に以下のような記述がある。
※参考:城山三郎『男子の本懐』には上記の逸話の記載はない。P.308に以下のような記述がある。
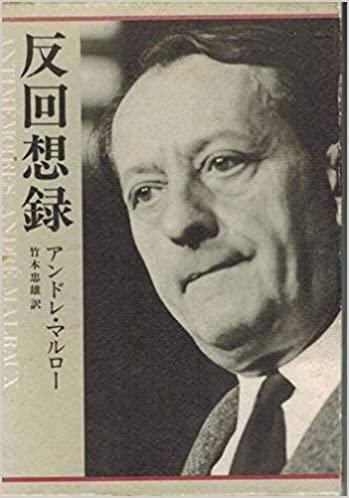 「政治とは、自分にとっては、創造と、ついで国家の活動を意味する。国家なくしていかなる政治も浮草となるほかはなく、多かれ少なかれ一個の倫理と化するほかはない」
「政治とは、自分にとっては、創造と、ついで国家の活動を意味する。国家なくしていかなる政治も浮草となるほかはなく、多かれ少なかれ一個の倫理と化するほかはない」
 一九五八年(昭和二十三年)ド・ゴールは政界に復帰し、マルロオは六月一日に情報担当国務大臣に就任、翌九年一月、第五次共和国大統領となったド・ゴールの下で新内閣が発足し、マルロオは文化問題担当大臣となった。
一九五八年(昭和二十三年)ド・ゴールは政界に復帰し、マルロオは六月一日に情報担当国務大臣に就任、翌九年一月、第五次共和国大統領となったド・ゴールの下で新内閣が発足し、マルロオは文化問題担当大臣となった。
 一作ごとの鑑賞に時間をかけるため、予定時間をはるかにオーバーしたらしく、おともの文部省役人が何度も時計を見、心配そうに私語しあったが、マルロオは平然と黙殺していた。ようやく一巡して、役人衆はホッとしたらしかったが、マルロオはふたたび彫刻室にもどって、今度はライトを要求し、自分はそれをもって、ギリシャのアルカイック時代、"少女像"と"哲人の顔"をあちこちから照らしながら、いつまでもいつまでも鑑賞しつづけたのだ。これこそまさに"文化"のなにそむかぬ「文化大臣」であることを、無言のうちに納得させてくれる情景だったとおもう。
一作ごとの鑑賞に時間をかけるため、予定時間をはるかにオーバーしたらしく、おともの文部省役人が何度も時計を見、心配そうに私語しあったが、マルロオは平然と黙殺していた。ようやく一巡して、役人衆はホッとしたらしかったが、マルロオはふたたび彫刻室にもどって、今度はライトを要求し、自分はそれをもって、ギリシャのアルカイック時代、"少女像"と"哲人の顔"をあちこちから照らしながら、いつまでもいつまでも鑑賞しつづけたのだ。これこそまさに"文化"のなにそむかぬ「文化大臣」であることを、無言のうちに納得させてくれる情景だったとおもう。
 と大内取締役に教えられて、おもわずアッと膝をたたいた。桜井(のち陸軍少将)の『肉弾』、水野(のち海軍大佐)の『此一戦』、ともに少年時代に愛読したもの。あの『戦争文学』のチャンピオンたちが秋山兄弟の光の影にかくれてしまっていた。
と大内取締役に教えられて、おもわずアッと膝をたたいた。桜井(のち陸軍少将)の『肉弾』、水野(のち海軍大佐)の『此一戦』、ともに少年時代に愛読したもの。あの『戦争文学』のチャンピオンたちが秋山兄弟の光の影にかくれてしまっていた。
