| 日本の本より (享保17年~安政3年) |
日本の本より (明治時代:1) |
日本の本より (明治時代:2) |
日本の本より (明治時代:3) |
|---|---|---|---|
| 日本の本より (明治時代:4) |
★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 日本の本より (大正時代) |
日本の本より (昭和時代) |
★★★★★★ | ★★★★★★ |
| 外国の人々(1868年以前) | 外国の人々(1868年以後) | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
(大正時代) |
|---|
|
われを待つ灯はひとつ 東 井 義 雄
黒 崎 昭 二 様

百千の灯あらんも われを待つ 灯は一つ
私が、校長のときでした。朝、子どもたちが登校するときは、きまり正しく、いきいきした姿で登校することは、よく見てきましたが、帰りのようすはどうだろうかと、昇降口から百三十メートルばかり離れた街角に立って、帰りのようすを見たことがありました。 ところが、その百三十メートルばかりのところを二十分も三十分もかかって帰る子がいるのです。 私は、これは、学校の仕事が多くて、子どもが疲れすぎているのだ、これは、学校として、そのあり方を検討し直す必要があるぞ、と思いました。 学校に帰って職員の皆さんにこのことを告げたのですが、そのとき、 「校長先生、学校のせいじゃなくて、家庭のせいらしいんです。学級の中で半分以上の子どもが『家に帰ったってつまらん』『家なんかおもしろくない』といっているんです」 と皆さんがいうのです。 どの家も、どの家も、りっぱになりました。外から見ても立派であるだけではない、中にはぃつてみても、ほんとうに立派になりました。家庭そのものあり方が、魅力を失っているらしのです。意外でした。 ところが、これは私たちの地域だけのことではないらしいのです。広島県に出向きましたとき、先生方がいろいろな面について調査なさったものを見ていると、その中にも、子どもたちが、家に帰る楽しみを失っていることがはっきり出ているのです。 私は、 「百千の灯あらんも われを待つ灯は一つ」ということばを思い出しました。そして、その「われを待つ灯」が、今の家庭にはともっていないのではないかと考えました。「われを待つ灯」それを家にともす人は「お母さん」です。いや「お母さん」それ自身が「灯」なのです。 昔だって、どの家も貧しかったから、子どもが家に帰ったとき、お母さんが待つていてくれるようなことは、ほとんどありませんでした。しかし、お母さんの「心」が待っていてくれました。 あめ 学校から帰ってみると母はるすだった 家の中がガラーンとしてさびしかった みると ぼくののら着に母の手紙がおいてあった いそいで読んでみた 「出石に浩の運動靴買いにいきます。戸棚にあめがあるから、たべもって山にたき木とりにいきなさい。母」 戸棚に ほんとうにあめがあった のら着に着かえて あめをたべながら山にいった 母のちちをなめているようだった。 次のようなお母さんもありました。
* きょうもお母ちゃんははたけだろうとなと思いながら学校から帰ってくると、やっぱり、うちの大戸がしまっていました。つまらないなあとおもって、大戸を『よいしょ』とあけました。すると、わたしはびっくりしました。にわじゅういっぱいに何かかいてあります。よくみると、それはけしずみでかいたおかさんのかおでした。かおのところのそばに「おかえり。やき山のはたにいるよ」とかいてありました。わたしは、けしずみでかいたおかあさんがまってくれたので、さみしくないとおもいました。 わたしは、かばんをおろしてから、けしずみを一こもってきました。そして、おかあさんのかおのところのそばに、小さいわたしをかきました。リボンをつけたわたしにしました。そして、おかあさんのほうに手をのばして、かたたたきをしているところにしました。「かあちゃんたたいてあげるよ」とかきました。はんたいがわに「あしたもまっててね」とかきました。 すっかりかきあげたので、手をあらっておやつをたべてから、わたしは、おかあさんのかおのところのそばで、ゆうがたまで、いっぽんふみをしてあそびました。
すばらしいお母さんではありませんか。子どもが、どんな思いで帰ってくるかを、ちゃんと、わかってくださるのです。まるで仏さまです。お母さんが「灯をともす人」というよりは「灯そのもの」であってくださっているのです。
自分は自分の主人公 P.278~279
世界でただ一人の自分を 光いっぱしの自分にしていく責任者 少々つらいことがあったからといって ヤケなんか おこすまい ヤケをおこして 自分を自分でダメにするなんて こんなバカげたことってないからな つらくたって、がんばろう つらさをのりこえる 強い自分を 創っていこう 自分は自分を創る 責任者なんだからな。
追加:東井義雄先生の詩・私の10選
平成二十九年二月十六日 |
|
親と教師の魂の琴線にふれる書! いまの日本の教育は、子どもたちの「いのちの根」を腐らせている、と著者はいう。目に見える能力の伸展よりも、土中深くはる根を養うことが教師の使命だ―これが著者の教師道40年の結論だ。危機に立つ日本を救う真の教育書が誕生した。
神戸大学教授 伊 藤 隆 二
目 次
Ⅰ もみじあおいを育てているつもりで
Ⅱ 「大いなるいのち」を生きる
Ⅲ いのちを生み育てるもの
Ⅳ 男の子・男の先生・お父さん
2008.06.16 |

峠のお地蔵さま 私は、中国山脈の山の中の貧乏寺に住んでいます。よそへバスに乗って出かけるとき、たいてい、バスの停留所まで六キロばかり自転車で出かけることになるのですが、出かけるとき、いつも、私自身に聞かせることがあります。それは、 「地蔵峠のお地蔵さまの前を通るときには、忘れぬように挨拶するんだぞ」ということです。 ところが、お地蔵さんのところが坂道になっているものですから、ペタルを踏まなくても、自転車が風を切って走ってくれます。その風の気もちよさにふれると、私はすっかりいい気持になってしまいます。オートバイに乗った気持ちはこんなのかもしれないぞと、ブレーキもかけずに走ってしまいます。暴走族の若者たちの気もちが、何だかわかるような気がしながら、ハッと気がついてみると、お地蔵さまへのご挨拶を忘れてしまっているのです。 大体、スピードというものは、どこか人間を狂わせてしまう魔力のようなものをもっているように思われます。 神戸大学にいらっしゃった伊藤隆二先生がいま、横浜市立大学にお勤めですが、最近、お書きになったものを読んでいましたら、先生はこれまではやく歩くのが自慢で、きょうは何人追い越したとか、きょうは昨日より一人多く追い越したというように、早足を自慢していらっしゃったのだそうです。ところが最近、腰を痛められ、早足ができなくなってしまった。が、早足を自慢していたときには全然気がつかなかった世界が見せてもらえるようになったと書いていらっしゃるのです。道ばたに、こんな可憐な草花が、こんなに力いっぱいに咲いていたのかと、川のせせらぎが、こんな美しい音を奏でていたのかと、驚かせてもらえるようになったとお書きになっているのでした。 自転車はまだ、風を切って走る快さを味わさせてくれますが、急ぎの用事でハイヤーを頼んできてもらい、それに乗って出かけるようになるときには、お地蔵さまへのご挨拶を忘れてしまったという申しわけなさの思いさえ忘れてしまって過ぎてしまいます。どうも、私という人間は、スピードを警戒しなければいけない人間らしいのです。 さて、今度は、バスを降りて帰るときです。地蔵峠と呼んでいる坂道は、とても自転車のペダルを踏んでは走れません。自転車を押して坂道を登ることになります。そしてお地蔵さまの前までくると、いつもハッとします。お地蔵さまが合掌して、私をおがんでくださっているからです。私が、ご挨拶を忘れて、風を切って走り過ぎたときも、お地蔵さまはおがんでくださっていたにちがいないのです。ハイヤーに乗って、「ご挨拶」とも考えず、ふんぞり返っていたときにも、お地蔵さまは、おがんでくださっていたにちがいないのです。 そんなことに気がついて、申しわけない思いで、こちらが掌を合わせるよりも先に、お地蔵さまは、おがんでくださっているのです。 拝まれない者も おがまれている 拝まないときも おがまれている そういう申しわけなさとしあわせを味わさせてくださるのが、地蔵峠のお地蔵さまなのです。 でも、地蔵峠のお地蔵さまは、なぜ、私などをおがんでくださるのでしょうか。 私は、いつも、親鸞聖人のご和讃を思い出します。 五濁(ごじょく)悪時 悪世界 濁悪邪見(じゃあくじゃけん)の衆生には 弥陀のみょう号(みょうごう) 与えてぞ 恒沙(ごうじゃ)の諸仏勧めたる というご和讃です。 濁りに濁り、汚れに汚れたいまの世に生まれた濁悪邪見の東井が救われる道は、お念仏以外にはないぞと、ガンジス河の砂の数ほどのたくさんな仏さまが、私に、お念仏を勧めてくださっているという、このご和讃を思い出させてもらうのです。すると、スキッとお釈迦さまのお心が、私の胸の奥まで届いてくださるのです。お地蔵さまは「わしへの忘れてもいいが、十劫の昔から念じずめに念じ、願いずめに願ってくださっている阿弥陀さまのお呼び声、お念仏だけは忘れないにようにしておくれよ」と、掌を合わせてくださっているのだと、気付かせていただくのです。
静かに/平穏に/しかし 確実に/その日が/近づいてくる ○
静かに
このことばを私に届けてくれたのは、親友太田正一君でした。
太田君は、私がテレビをみる時間もない程あわただしい毎日を過ごしていることをよく知っていて、これを届けてくれたのです。
「東井君よ、忙しく生きることも君の生きがいかもしれないと思いはするが、それだけでは空しいといえるのではないか。どうかどうか、この人生にとって、一番急がねばならぬこと、どんなに忙しくとも、忘れてはならないことだけは忘れないでくれよ」。 その思いをこめて、太田君は、このことばを届けてくれたのだと思います。太田君は、師範学校の時の同級の友なのですが、私は、彼を「友」としてよりも「先輩」として「師」として仰いできました。 ▼太田君が校長のときでした。個人文集を送ってくれました。その文集のな前が「燼」でした。どうよませるつもりだろうかと思いながら字典を出して、この字のいろいろな読み方を調べてみました。「じん」と読ませるつもりかな、それとも「もえさし」と読ませるゆもりかな、しかし、どう読むにしても、彼は、なぜわざわざこんなつまらんな前をつけただろうかと思いながら、本文を読んでハッとしました。太要、次のようなことが書いてあるのです。 ○ 私は、きょう、五十七歳の誕生日を迎えた。近ごろ日本人の寿命がのびて、男子でもだいたい七十二歳までは平均生きられるようになったという。私も七十二歳まで果たして生きさせてもらえるのであろうか。明日の日もわからない身の上である。が、仮に七十二歳まで生きさせてもらえるとしてみても、計算してみると残り極めて僅かである。うっかりしてはおられない。 私は、ふと、日本人の平均寿命七十二歳を一日二十四時間にあてはめてみることを考えついた。七十二歳の半分三十六歳が正午ということになる。五十七歳は午後の何時に相当するのであるか。考えてみると自分の年齢を三で割ると十九ということになる。すると、私は、きょう、ちょうど十九時、つまり午後七時になったということになる。私はギクッとした。私の人生はすでに日が暮れてしまっているということにだ。大事なところはすでに燃えてしまって、僅かな「もえさし」が残っているに過ぎないわたしだということだ。 私「もえさし」なのだ。ウカウカしてはおれないのだ。今までのようなボンヤリしたいいかげんな生き方をしていては、「もえさし」もまたたく間に燃え尽きてしまうということだ。ウカウカしてはおれない。 一日々々どころか、一刻々々を真剣に生きさせてもらう以外ない。そのためにはどうすればいいか、せめて一か月毎にでも必ず私の生きざまを総点検して文集にまとめ、先輩知友のご批判を仰ぐことを決意した。 その個人文集のなまえをどうするか。私はいま「もえさし」の身の上である。そのことを銘記して生きさせてもらうためにも「もえさし」「燼」こそふさわしことに気付かせていただいた。 お粗末この上もない個人文集ではあるが、どうか、ご縁の深い皆さん、私の残り僅かな人生のために、いままで以上のきびしいお叱り、お導きをお願い申し上げます。 というような文章でありました。実に彼らしい考え方であり、生き方であることに、改めて頭が下がったことでした。 と同時にギクッとせざるを得ませんでした。彼が「もえさし」であるということは、私も「もえさし」だということだからです。彼がいま「午後七時」だということは、私も「午後七時」だということです。 私も、既に、日は暮れてしまっているのです。どうすればいいのでしょうか。「もえさし」を大切に生きるということは、具体的にいうとどう生きることなのでしょうか。 太田君のことどころか、これは、私の問題です。太田君の「もえさし」の火は、すっかり私に燃え移ってしまいました。 ちょうど、そのとき、私は八鹿(ようか)小学校の校長を勤めさせてもらっていました。自宅から通勤は不可能です。学校から少しばかり離れたところに町営住宅の小さいのを借りて自炊をしていました。 夜の食事が終わって食器類を洗ったり等をし終わると、学校の職員の皆さんが書いてくれている教育記録を読ませてもいらうのが、その頃の私の日課になっていました。記録を読んでは、ひとりひとりの記録に、私の感想を書かせてもらいます。その間は「もえさし」の身の上であることも忘れているのですが、気がついてみうると夜半になってしまっています。 お内仏の前で夜のお勤めをさせてもらい、寝床を敷いて横たわると同時に頭に浮かんでくることは「もえさし」の身の上にある私のことです。 「〚もえさし〛がいま寝ようとしている」 そう気がつくと、「もえさし」の身の上が、如何にもあわれに思われて、とても眠りになんかはいれません。 「〚もえさし〛を大事にするというのは具体的にどうすることなのか」 「わたしは、どう生きればよいというのか」 そう考えはじめると、いよいよ目は冴えてきます。 しかし、元来がぼんやり者ののきな私です。やはり、いつの間にか眠ってしまいます。 翌朝、目を覚まし、寝床を片付けるとまず排便。しゃがみ込もうとしてハッとします。 「〚もえさし〛がいましゃがもうとしている」 「〚もえさし〛を大事にするというのは具体的にどうすることであるのか」 「……」 こうして、私は、すっかり「もえさし」のとりこになってしまいました。 ▼学校からの帰りには、必ず書店に立ち寄って、私の問題に答えてくれそうな書物を探すことが、毎日のくせになってしまいました。 そうしているうちに、私は、ほんとうに尊い本にめぐりあいました。 当時、若い人たちの間で、たいへん問題になっていた大島みち子という娘さんが書いた『若きいのちの日記』でした。 大島みち子。この人は私とおなじ兵庫県の娘さんです。師範学校の時の同期生M君は当時、兵庫県の織物の町である西脇市で西脇中学の校長をしておりましたが、若い頃、大島みち子さんの担任だったといいます。いつか西脇中学のPTAの講演にいったとき、大島みち子さんのことを聞かせてくれました。 子どもの頃から、ほんとうにかわいい子で、頭がすばらしくよく、心のやさしい女の子だったといいます。 それが、高校に入学すると間もなく、何とかというたいへんむずかしい病気にかかってしまいました。M君の話によると、顔のあちこちにある軟骨がつぎつぎに腐っていくのだということでした。でも、一時よくなって五年かかって高校を卒業、京都の同志社大学の文学部に進んだということでした。ところが、大学に進んで間もなく、その難病が再発してしまい、長い病院生活をしなければならなくなりました。その間に河野誠という学生と知りあうようになり、真剣な愛情を感じあうようになっていったわけですが、二人は遂に結ばれることなく、みち子さんは、病院のベッドの上で、短い生涯を終わってしまったのでした。 が、その間に、みち子さんは日記を書いていたのです。その純情日記をあつめたのが「若きいのちの日記」なのです。 M君からこの話を聞くと、私もじっとしておれなくなり、M君に案内してもらい、みち子さんのお家を訪ねお参りをさせていただき、みち子さんのお父さんから、いろいろお話を伺うこともできたのでしたが、私は、こうしして「若きいのちの日記」にめぐりあったのでした。そして、これによって、「これこそ私が探していた問題の見事な答だ」というものにであったのでした。 ○ 病院の外に 健康な日を三日ください 。(一年ともいわず、一か月ともいわず、十日間ともいわず、一週間とみいわないところがいじらしいではありませんか。でも、その三日間を、みち子さんは、どうしようというのでしょうか) 一日目
わたしはとんで故郷に帰りましょう。
二日目
わたしはとんであなたのところへいきたい
三日目
わたしは
何というつつましやかな願いでしょうか。一日目は、とんで故郷に帰って、かわいがっていたおじちゃんに、ありがとうの思いをこめて、肩をたたいてあげたいというのです。お母さんといっしょに台所に立ってお炊事をすることの中に、お母さんの娘に生まれたしあわせを味わいたいというのです。ご苦労ばかりかけっ放しのお父さんに、お父さんありがとうと、熱いおカンを一本つけさせてもらいたいというのです。 二日目は、とんであなたのところへいきたいといいます。はじめて愛を感じた人なんでしょうけれども、この人との別れを、二日目にしていることにも、この娘さんの人柄のつつましやかさというようなものが感じられる気がします。生まれてから、ずっとずっと慈愛をかけてもらったおじいさんや両親、妹などのことなんか、見向きもしないで恋人のところへ突っ走ってしまう人だってたくさんある気がするのですが、みち子さんという人は、そういう人ではなかったようです。 しかも、「あなたと遊びたいなんていいません」と、まず最初に言い切っているのです。そして、愛する人のお部屋のお掃除をすることに、女に生まれたしあわせを噛みしめようというのです。愛する人のワイシャツに、心をこめてアイロンをかけてあげることの中に、女に生まれさせてもらったよろこびを味わせてもらいたいというのです。 人間の生まれがいは、山の彼方・海の彼方にあるのではなかったのです。人間に生まれさせてもらった者なら、誰でもがしている、つまらなく見えている事柄、そのひとつひとつを、心をこめて、大切に生きさせてもらうこと、そのなかに「もえさし」を大事にするという問題の答えがあったのです。それを大島みち子さんは、私に、はっきり、具体的に教えてくれたのです。 その後、私は、宿から学校までの二〇〇メートル程の間を、 ○ 明日がある あさってがある と考えている間は なんにもありはしない かんじんの 「いま」がないんだから。 と、つぶやき ○ きょうが 本番 「いま」こそが 本番。 と、自分に言い聞かせながら、出勤の歩みを運びつづけることになりました。 学校に着きますと、玄関に立ちます。玄関の正面に、私が字のうまい先生に頼んで書いてもらった、イギリスの詩人ローズ・ワスースの詩の中のことば ○ こどもこそは おとなの父 を黙読します。そして ○ 私のあずかっている七二〇の子どもの中から、七二〇のおとなが生まれてくる。この子どもたちの中から、次の八鹿の町が生まれてくる。この子どもたちから、新しい日本が生まれてくる。この子どもたちから、次の新しい世紀が生まれてくる。子どもこそおとなの父。 と自分に言い聞かせます、 校長室に入ります。詩人高村光太郎の書を黙読します。 ○ いくら まわされても 針は 天極を 指す と書かれています。きょうもいろいろなことがやってくるにちがいない。しかし、どういうことがやってきても、この学校が子どものためにあるということ、子どものために私がお世話になっているということだけは、狂わせはしないぞ、と自分に言い聞かせます。 職員室に出向いていきます。そして、 「きょうも、子どもたちが、いろいろとお世話になりますが、どうかよろしくお願いします」と、心の中でつぶやきながら、「おはようございます」と、挨拶します。校長が、校長室で逆立ちしてがんばってみても、それは子どもを伸ばすエネルギーには、直接、つながってくれません。結局、先生方のひとりひとりが「やるぞ!」ということになってくれなければ、子どもをどうしてやることもできません。先生方を信頼し、お願いする以外道のないことを、自分に言い聞かせます。 用務員のおばちゃんの部屋にいきます。「きょうも、子どもたちが、いろいろお世話になりますが、どうかよろしくお願いします」と、心の中でつぶやきながら「おはようございます」と挨拶します。校長なんかの見えないところで、忘れものをした子どもから、おなかを壊して汚した子ども、いろいろな子どもがどれだけお世話になっていることでしょう。このおばちゃんが、半日いなかったら、学校の歯車は、あちらでもこちらでも、きしみはじめるにちがいありません。私のようなできのわるい校長なんか、三日いなくても、一週間いなくても、学校はビクともしませんが、おばちゃんが半日いないとしても…… と思いはじめると、この学校にとって、なくてはならないのは、私などより、おばちゃんではないかと思われてきます。 おばちゃんへの挨拶が終わると、十九の教室を廻って、子どもたちに朝の挨拶をします。子どもたちが、私を見つけると、廊下にいる子どもたちも、 「校長先生、おはようございます」 と挨拶してくれます。 「ああ、おはようございます。あなたはきょう、何をがんばってくれるのかな?」 「算数をがんばります」 「君は何をがんばってくれるのかな?」 「体育をがんばります」 「うれしいな、しっかり頼むよ」 と、肩をたたいて励まします。 一年生の教室の廊下にさしかかると、どの子どもの子も、 「校長先生、おはようございます」 といって、廊下に頭を突き出して待ってくれます。私に、頭をなでてもらうのを待ってくれるのです。 「おお、おはよう。きょうは、どんなことがんばってくれるのかな?」 といいながら、頭をなでてやります。子どもの頭のぬくもりが、「もえさし」の私のやせた胸につたわってきます。二十一世紀をつくるエネルギーがつたわってくると思いますと、「もえさし」はいっぺんにうれしくなっていのちが燃えてくるのを感じるのです。 一年生の子どものお母さんが、 「子どもが、毎朝、『まだ始まるまでにはずいぶん間があるから、そんなに急がないでゆっくりしなさい』といっても、『校長先生に頭をなでてもらわんならもん』といってとんでいくんです」 といってくれたことがありますが、高学年の子どもたちまでもが、 「きょうが本番。今こそが本番」 を、合ことばにしてくれはじめたのはうれしいことでした。 ▼関連:大島みち子『若きいのちの日記』 P.95~113 2008.6.21、2019.02.26追加。
「雖近而不見」
隠岐の島には、尊い先生がおられます。横田武先生と申します。隠岐の島に渡ることがあったら、ぜひお目にかかりたいと、かねてから念願していた私でした。
雖近 而 不見 ※参考:「雖近 而 不見」は、『法華経 下』(岩波文庫)P.50に記載されている。
の書を拝見したいという思いもありましたので、話題も、自然この「雖近而不見」になってきました。
〇 妻 でも、そういう私であることを知らせていただいたおかげで、こんな私が生かされていた、こんな私であるのに赦されていた、守られていた、包まれていた、ということが、ただごとでないこととして仰がれるのです。 P120~131 参考1:「道雖近、不行不至。事雖小、不爲冨成>。 *『荀子』: 道は近しといえども、行かざれば至らず。事は小なりといえども、為さざれば成らず。どんなに近い所に目標があっても向かって行かなければ目標に届かない、どんなに小さい事でも真剣に取り組まなくては出来ない 参考2:雖近 2010.07.08
『拝まない者も おがまれている』のカバー絵(合掌童子)ー佐久間顕一 NHKこころの時代「祈りを描」 年に五千体描く。一体でもおろそかにしないようにしている。ノートに番号をひかえている。 二十年間、いろんなものを描き、それから二十年間、合掌童子を描いている。一切を捨てた良寛は四十六歳、五合庵に定住した年齢に私は借金。五十までに返済し、それから無の生活。 捨ててからいろんなものがくるようになった。捨てたとき描いていたから空虚さはなかった。「私を使ってこんなものを描かせていらっしゃる」と思う。 インドにも合掌童子の友ができたと喜んでいる。 「反対の証拠があるまでやめるな」。私のような鈊根を見捨てられなかった。 くり返すことはいつも新鮮であるから。 念仏もおまかせしていることで描いていて、あとはおまかせ。 描かせていただいている。 私が贈るものがあるとすれば、純なる心一つである。 ※昭和613年6月22日の日記の記録から。2020.03.23記す。 |
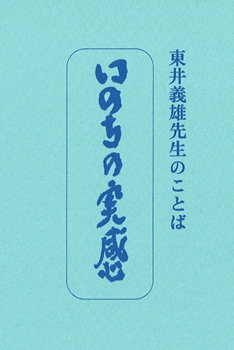
生きていることは、死ぬいのちをかかえているということ 静かに、平静に、しかし、確実にその日が近づいて来る 自分は自分の主人公。自分をりっぱにしあげていく責任者。 九(苦)を越えなければ十の喜びに到り得ない 「聞く」は話すことより消極的なことのように考えられがちですが、これくらい積極的な、全身全霊をかけなければできないことはない。 20.11.19
東井義雄先生略歴 明治45年(一九一二)のお生まれです。兵庫県出石郡の但東長(たんとうちょう)・佐々木にある東光寺(浄土真宗)の長男としてこの世に生を享けられました。 小学校一年生の時母上(33)と死別され、26歳のとき、敬愛する父上と死別されました。 姫路師範学校を卒業。直ちに教職に就かれてより、定年まで四十年間、教育界で尽力なされ、数多くの著述と数々の「教育功労賞」を受賞されました。 父上の跡をつがれて東光寺の住職でした。朝に夕に親鸞上人の「正信偈」をたなえられ、そのお経の生命(いのち)を身に体認せられました。 先生が一代かけて書きのこされた著書は、百冊をこえましょう。その他、寄稿論文は三十篇をこえるとと想像されますが、森 信三先生がいみじくも言われたように教育界における民族の至宝となれば、やはり東井先生の『培基根(ばいきこん)』を第一に挙げたいと思います。 八鹿小学校校長として最後の六年間に発行された集録で、先生自ら手書きの謄写刷りのものでです。先生の気息が感ぜられものです。職員の実践記録や児童の作文を上段に、校長所感を最下段に記載されました。 教職最後の下坐行のあり方が惻々と実感されるもので、先生の人間観・教育観・学力観・授業観が、具体的にうかがえるものです。題して『培基根』とは心にくい限りで、心根を培う親情切々たるものです。 *私は残念ながら『培基根』は読む機会がありませんでした。この略歴は『東井義雄先生のことば』より抜粋させていただきました。 2008.11.21 |
02 矢野 健太郎 数学者(1,912~1,993年)
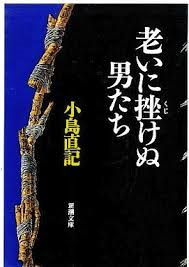
小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮社文庫)P.225より 関東大震災のあと、東京市長後藤新平、「帝都復興」のためには、建物の復興もさることながら、真の復興のためには立派な東京市民を育てることが先決だという意見をもち、市議会もこれに賛同した。 しかしその実現前に後藤は退き、後任の永田秀次郎がその仕事を継いだ。 こうして大正十三(一九二四)年四月中学校二校と女学校一校が新設された。 中学校の一つは九段に新設されれ、第一東京市立中学校と呼ばれ、もう一つは上野公園内に創立され、第二東京市立中学校と呼ばれた。女学校は深川に創立され、東京市立女学校と呼ばれ、さっそく三校の生徒募集が行われた。 そのとき、のちの数学者矢野健太郎はある私立中学校に入学していたが、彫刻家である彼の父は、滝野川町上中里から通学するのに便利な第二東京市立中学校へ行くほうが息子の将来のためによいと考えて、この入学試験を受けることをすすめてくれた。矢野は無事入学することができた。 学校は上野公園内の東京市自治会館を仮校舎として四月二十七日開校、四つの教室を設けるのがやっとで、約二〇〇名の生徒は公園内の共同便所を使用せざるをえなかった。 五月三日、和歌山師範学校から、新任の初代校長高藤太一郎(四十八歳)が着任して一週間一回の終身の時間を担当した。 「背丈は一六〇センチにも足らず、男としては低かったが、骨太のがっちりした体格だった。巾着頭で、ガニ股、ふ動の姿勢をとると足の角度が一二〇度にも開いているのもなつかしい。粗削りの男らしい風格でいて、人情はすこぶるこまやか。動作は敏捷で歩く速さは生徒に負けない。(中略)人柄は、単純率直、真実を愛し、嘘を憎んだ。経済観念希薄なところは多くの逸話の生ずる温床だった。口を開けば音吐朗々、その雄弁は人を魅了せずにはおかない。生徒後援会で話を聞くや父兄は一度で先生のファンになり、尊敬と共に信頼をかちえてしまう。但し故人との対談においても、地声は同じで、傍の者をまま喧嘩とあやまらしめる」(初代同窓会長、旧一期、吉川時哉) 「私がいまでも感心し、感謝していることの一つは、この高藤校長先生が二〇〇名に及ぶわれわれ中学一年生全部の顔とな前、しかも家庭の事情まですべて覚えてしまわれて、折あるごとにわれわれ一人一人に話しかけてくださったことである」(旧一期、矢野健太郎) 「校長の修身の時間というと、今の道徳教育を連想しますが、高藤先生の場合は、自分の体験をきかせる、いわば為になる漫談で、面白くて、あきませんでした」(旧二期、福田恒存(つねあり)) Dale Carnegie の "How to win friends and influence" という本のなかに出てくる人たては、リンカーンー、ディケンズ、ロックフェラー、カーネギー、ロイドジョジなど、世界的に優れた人たちで、この人たちの優れた点を、事例をそえて説いてあるのです。 ①人間関係の調整の大切さ。 ②みずから動き出したくなる気持ちをおこさせること。 ③誠実な関心をよせる。 ④笑顔を忘れない。 ⑤握手に心をこめる。 ⑥な前を覚える。 ⑦聞き手にまわる。 ⑧関心のあり方を見抜く。 ⑨心からほめる。 等であって、高藤先生お一人が私共の目の前で実行されたことばかりで、高藤先生のことを書いた本ではないかと思われるものでした《(旧一期、白井実) * 大正十一年十一月、ドイツの理論物理学者アインシュタインが日本を訪れて、各地で「相対性理論」に関する講演をおこなった。 当時小学校五年生の矢野健太郎は、 「相対性理論は非常に難解な理論であって、その真の意味を理解しうる人は、世界中にも数人しかいない」 といううわさを耳にした。しかしこのことを話してくれた彼の父は、 「それがどんなに難しいものであるとしても、それは人間の考えたことだ、お前だって、よく勉強すればきっとそれが解かるようになるさ」 とはげましてくれたのである。 あるとき、高藤校長から、 「矢野、君は大きくなったら、どんな人物になりたいと思っているかね」 と聞かれた。このとき、どうしたわけか、突然父の言葉を思い出して、 「大きくなったら、アインシュタインと相対的理論について議論ができる人間になりたいと思います」 と答えた。 別に深い考えがあっていったのではない。 ところがその答えは大いに高藤校長のお気に入ったものと見えて、 「そうか、そうか。望みは、大きいほどよろしい。しっかり勉強したまえ」 と、その大きな手で矢野の小さい手をにぎりしめてくれたのである。 「それ以来、私が高藤先生に対して持った感情は、何と表現したらよいのであろう。敬愛の情とでもいうのであろうか」(中略) 矢野は東京高等学校理科、東京大学数学科を卒業して、戦前にパリに二年間留学した。そして「相対性理論」に関する論文をフランス科学院に提出することができた。 また戦後二年間、アメリカのプリンストン高級研究所で過ごすことができたが、このちときには、アインシュタイン博士のオフィスの前にオフィスをもらい、アインシュタインと、その新しい理論について話をする機会をたびたびもつことができたのである。 「これらの話を、高藤先生へ書き送って、先生に大変よろこんでいただくことのできたのは、小さなご恩返しであったと、それができたことを、いまでも喜ばしく思っている」
みなさんは、「ツェノン」が言いだしたといわれる、アキレスと亀に関する有名なパラドックスをご存じでしょうか。P.46~ それは、ギリシャの韋駄天アキレスが、その前方を歩いていく亀を追いぬこうとしても、アキレスは絶対に亀を追い抜くことはできないことを主張するものです。 ▼そしてそれを主張する根拠はつぎの通りです。 まず、アキレスがその前方を歩いている亀を追いぬくためには、アキレスはともかく、もと亀のいた場所まで達しなければなりません。ところが亀は、とまっているわけではないのでですから、アキレスがもと亀のいたところまでくる間に、いくらかは前進しているわけです。 このように、アキレスがもと亀のいたところまでくれば、亀はいくらか前進しているのですから、亀はあい変らずアキレスの前方にいるわけです。 そこでまた前と同じ議論をくり返します。つまり、まだ亀はアキレスの前にいるのですから、アキレスがこの亀を追いぬくためには、アキレスはともかく、もと亀のいた場所へ達しなければなりません。ところが亀は、とまっているわけだはないのですから、アキレスがもの亀のいたtころまでくる間に、いくらかは前進しているわけです。 このように、アキレスがもと亀のいたところまでくれば、亀はいくらか前進しているわけですから、亀はあい変わらずアキレスの前方にいるわけです。 このことを何度くりかえしても、亀はいつまでたってもアキレスの前方にいることはたしかであるから、アキレスは絶対に追い抜くことはできない。 これが有名なツェノン(紀元前四〇〇年頃の人)のパラドックスです。 参考:インターネットで「ツェノン」で検索解答をお読みください。 41 双六の数学 P.147~156 この記事の中に、「いまここに、10本のくじがあって、そのうちの2本が当たりくじであるとしてみます。このくじを2人の人が順番にひくとき、最初にひく方がとくか、あとからひく方がとくかという問題です。」があります。 2008.5.23、2009.11.04、2012.10.26読。2021.11.09追加。 |
03 川上 正光 (1912~1996年)
|
▼『禅の源泉 信心銘 花開く悟りの世界』 まえがき 本書は中国禅の第三祖先鑑智禅師の『信心銘』をわかり易く説明しようとするものである。この『信心銘』は形式的には韻をふんだ美事な哲学詩のようであるが、その内容は禅の神髄を道破して余す所がない。 ▼関連:三祖鑑智僧璨
だいぶ昔のことだが、吉川英治さんの随筆にこんなことが書いてあった。その概要は、 「戦時中などには、僕に吉田松陰を書いてくれという人があった。だが、僕は松陰の偉大さは認めるが書く気はなかった。どうしてかというと、松陰じゃ若かったからやむを得なかったわけだが、儒学の尖鋭的な処を学びとった。儒学の奥の奥に、なお大人の学問としての老荘や易学があるわけだ。だから、松下村塾的な思想はあの時代によかったけれども、時代によっては危険なんだ。」 ということであった。それを読んで筆者は、これは立派な見識であると思った。 ここで『老子』を述べるいとまはないので省略するが、『荘子』は、本書の主眼とする禅にきわめて関係が深い。それで『荘子』のなかにある禅的思想を述べておぅことは、『信心銘』を理解するためにきわめて有効と思うのである。 |
04紅林茂夫(1912~2004)

カイコだけが絹を吐くー問題意識とは何か……P.26 たしかダイヤモンド社の『エグゼクティブ誌』だったと思う。富士銀行の紅林茂夫氏が、読書に関する座談会で、このことばをいった。きれいなことばだな、とさっそくメモした。 紅林さんのいうのは、こういうことである。この地上には、何千何万となく昆虫がいる。それらは、みんな木の葉っぱや草の茎を食べて生きている。しかし、大部分の昆虫は、それを青いまたは黒い糞として体外に排泄しているにすぎない。カイコだけは、それを体内でで消化し、燃焼し、やがて美しい絹糸として吐き出す。読書も、まったく同じである。 コトゴトク書ヲ信ズレバ、書ナキニ若カズ という孟子のことばがある。読む本、読む本を信じて行くようだったら、むしろ、この世には、本がない方がいいという意味である。一代の物知りといわれた長谷川如是閑翁(文化勲章受章者)は、なるだけ自説に反する本をあつめて読んだ。それによって逆に見聞を広くし、自説を補強したといわれるが、本読むということは活字を追うということではなくて、行間に書かれている意味を読み取る、ということである。つまり考えながら読むということであり、ひろげていえば、問題意識をもって接するということである。しかし、それは何も読書に限らない。広く、人生一般についていえることかも知れない。 このごろ、しきりに「問題意識をもて」ということばが叫ばれている。有能な社員とは、問題意識をもつ社員だなどということもいわれている。考え方はいろいろあろうが、私は、これを (イ)、いつも自分の心に課題を持つ。 (ロ)、自分の頭で煮つめて考えてみる。 (ハ)、煮つめて――ということは、いろんな角度から問題を攻めてみる。あるいは次元を変えた発想を試みてみる。 この三つと考えている。こうやってある日、ある時パット突破口が見つかる。カイコが絹を吐いたのである。 商売柄、ジャーナリズムの上で有名な例をあげてせつめいしてみたい。
デモクラシーの不朽のことばといわれる。リンカーンの「人民の、人民による、人民のための政府」ということばは、一八六三十一月十九日、ゲッティスバーグの曠野で行われた南北戦争の北軍慰霊祭の時、述べられたことばである。将兵一万余人を前にして、はじめ、エドワード・エベットという有名な雄弁家が立って演説をした。彼の美しいことばや、大げさなゼスチャー入りの熱弁は、そこに参集した将兵の胸をうった。そのあとで、リンカーンは、低くまるで神に祈るようなことばを二分間ばかりしゃべつた。 翌日の新聞には、エベットの雄弁が、全米の新聞を飾った。わずかに、(ワシントンポストだったと思う)一紙だけが The goverment of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. (人民の、人民による、人民のための政府は、永遠に生き続けねばならぬ)のことばをのせた。そのために、このことばは歴史に残ることばになったというのである。 リンカーンのこのことばは、そこに列席した新聞記者はみんな聞いていたはずである。しかし、彼等は、前座をつとめた雄弁家の美しい弁舌に酔い、リンカーンのことばの意味する深い思想とその内容とを洞察することができなかった。その一つには記者のセンスの問題でもあるが、つきつめていえば、デモクラシーに対する日ごろの考え方の深浅の問題ではあるまいかと、私には思われる。この戦い(南北戦争)の意味は? デモクラシーとは? と、絶えず、自分自身に問い続けたものにして、はじめて、リンカーンのことばの意味するものを汲みとれるのである。ジャーナリストがよく”現代史の目撃者”などといわれもし、いいもしているのだが、本人に、それをみきわめる”目”がなければ、見れども見えずである。 この話はまた、一説によると、この of the people, by the people, for the people ということばは、そのころ、かなり有名な文言だったという説もある。リンカーンは、それを、その時、援用しただけだという説だが、援用だとしても、それが今日に残っているのはリンカーン自身が、デモクラシーということをいつも自分に問いかけており、たまたまタイミングよく、うち出されたということではあるまいか、と私は推察している。 *参考:紅林 茂夫(くればやし しげお、1912年5月2日~2004年3月30日)は、経済評論家。
東京出身。1936年東京商科大学(現一橋大学)卒業、安田銀行入行、戦後改称して富士銀行調査部長、67年常任監査役。経済評論で活躍。のち創価大学教授、90年退職、国際経済研究センター理事長。
2010.08.02、2011.01.13。 |
05 扇谷 正造(1913~1992年)
|
▼『経験こそわが師』(昭和46年2月27日 初版発行) 「問題意識を持つとは」の章P.206 の末尾 ーー私の好きなことばに『人生は教訓に満ちている。しかし、どの一つをとってみても万人にあてはまるものはない』(山本周五郎『赤ひげ診療譚』)というのがある。経験はだれでもする。しかし、その中から鉱石をつかみとるのは、君だ。と、援用している。
▼『現代ビジネス金言集』(1979年1月31日第一刷発行) 「5W1H」――ビジネスの文法 P.74
ある日、何かの本で、このことばの出典を知った。これは、イギリスのキップリングの詩の一節だという。一九〇七年ノーベル賞を受賞した海洋詩人、ジョセフ・ルドヤード・キップリング(Joseph Rudyard Kipling=一八六五~一九三六)の詩にこういうのがある。
昭和四十三年、私は朝日新聞社を退社した。つまり浪人である。仕事はある時もあればない日もある。今までとちがって、手足はない。何もかも一人でやらねばならない。(私も、会社を退社した時、同じことを体験した。そこで、ワープロ使用法を身につけた)。 あなた任せはできない。 根があわて者の、無精者で、土地カンときたらゼロなんて甘えていたひにゃ、オマンマの食いあげとなる。仕事の一つ一つのたびに私は、六人の賢者を傍によびよせる。 「日付はまちがいないか」「お迎えさんと待ち合わせは、東京駅から進行方向右の××駅出口。よし、O・K」「きょうの新郎新婦の名前は?」「いまの時間帯で万一、渋滞でもあったら飛行機に乗り遅れる。モノレールだ」「×日×時、〇〇君との会見、要談のポイントは?」「きょうの会場はホテル・オークラか、ニュー・オータニか」などなど、前夜か、あるいは家を出る前に私は、いつもチェックすることにしてきた。 おかげで、どうやら、何とか、他人様にめいわくもかけずにやってこれた。今の私にとって、そういう意味では5W1Hは”六人の賢者”ということになるかも知れない。それは、いわば、一つの物事を行うにあたっての確認の手続きということである。”生活の文法”のことばはそこから出た。 5W1Hと関連して、私の体験では生産会社に入社してから、アメリカのデミング博士の品質管理法が日本に導入されて、その方法を実行し、手品質の向上・生産性の改善にやくだてたものであっります。それは、Plan・Do・Check・Actionでありました。品質管理の大事な言葉として活用したものです。 2008.3.17
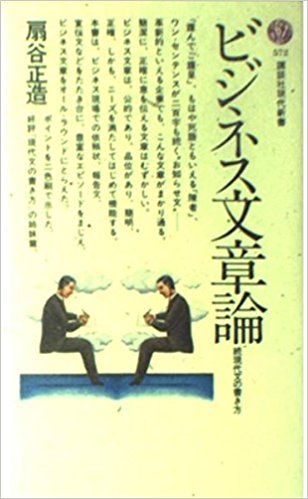
▼『ビジネス文章論』(昭和五十五年三月二十日第一刷発行) 車中でP.146 所用をすませて、熊谷から列車に乗り込んだ。ちょっと疲れていた。ボンヤリ窓外の景色をに見とれていると、 「扇谷先生じゃありませんか」 と呼びびかけられた。さし出された名刺を見ると、「ホテル塩原ガーデン玉屋旅館番頭 大内和郎」とある。今どき”番頭”などという肩書は珍しいな、と思っていると、相手はちょっとテレくさそうにして注釈した。 「肩書に支配人だの、取締役などを刷りこむと、お客様に申しわけない。お客様の中には主任さんや係長さんもいるかも知れないが、大半は平の社員さんたちです。それらの方々が、こちらの名刺の取締役などという肩書を見て、いやな感じを持たれては、と思いまして…………」
という。いいセンスだなと思った。これこそ、私の好きなあの文字? の気持だな、と思った。下のこの奇妙な文字は何と読むか。
「人ハ大キク上ニ置キ、己ハ小サク下二シテ、腹ハ立テズ二横二シテ、気ハ長ク、心ヲ丸クスルコソヨケレ」と読む。この場合、人というのはお客様ということで、この文字は客扱いの心得をいったものである。
新聞記事は 戦前(昭和七、八年ごろ)故阿部真之助氏は、朝日、毎日、読売の三紙の平均的読者像について、つぎのようにいった。 朝日=中学一年中退プラス人生経験十年の読解力。 毎日=小学六年(義務教育)終了プラス人生経験十年の読解力。 読売=小学四年修了プラス人生経験十年の読解力。 人生経験十年というのは、人生で学んだ知恵という意味である。三紙の読者の知的水準はもっと高いものと思っていた私は驚いたことであったが、そのころの中・女学校進学率は、わずか十八パーセントであったことを考えると、うなずけないことはない。しかも当時の新聞はふりがなつきであった。 今はどうか?**高校進学率は九十パーセントを越えている。だが、ルビはなく、国語力が低下していることを考えると、三紙とも高校一年修了プラス人生経験十年というあたりか、平均的読者のメドということになるかも知れない。
「三上」 鞍上 厠上 枕上 参考:《欧陽脩「帰田録」の「余、平生作る所の文章、多くは三上に在り。乃(すなは)ち馬上・枕上(ちんじゃう)・厠上(しじゃう)なり」から》文章を考えるのに最も都合がよいという三つの場面。馬に乗っているとき、寝床に入っているとき、便所に入っているとき。
 ▼『吉川英治先生におそわったこと』(六興社)(昭和47年9月7日 初版発行)
▼『吉川英治先生におそわったこと』(六興社)(昭和47年9月7日 初版発行)
「立ちどまってモノを考える」あるいは「自分の頭でモノを考える」ということは、企業のことばでいえば、とりあえずチェック(check)ということになる。確認であり、吟味であります。 会社や銀行の仕事について、管理職の心得として、よく plan-do-check あるいは plan-do-see ということばがあげられます。企業は、これを細分化してみると、結局はどの仕事も plan-do-check (計画ー実行ー吟味)の、この過程で行われる。三つのうち、 plan と do は、放っておいてもオートマチックにやられて行く、しかし、 check は、立ちどまって考えてみなければ、わからない。それは管理職の仕事というより、今日ではむしろ、企業内の個々の社員の仕事ではあるまいか、と私は考えます。 というのは、現代は、あまりにも機構が複雑化し、とても管理職一人では、目が届きかねる状態になってきている。権限も大幅に個々のメンバーに委譲され、個人の責任が相対的に大きくなってきている。なるほど機械はオートメ化された。むかしにくらべて仕事は単純化されたかも知れないけれども、その代り、ホンのちょっとしたミスが、大きな混乱と、時には昔とはくらべものにならない位の公害や災害を生んで行く。 たとえば、先日、起った大阪のプーレタウン⦅*千日デパート火災(せんにちデパートかさい)は、1972年(昭和47年)5月13日夜、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光経営)で起きたビル火災である。死者118人・負傷者81人の日本のビル火災史上最悪の大惨事となった。⦆における災害事件なども、つきつけてみると、たった一本のたばこの吸いがらが原因となって百何名という死者を出した。というのは、現代生活の快適といい、便利というものは、いつも安全と危険とのバランスのうえにあがなわれているからです。新建築材は安くて快適だ、しかし、火事になると有毒なガスを出す。自動車は便利だ。しかし、その代償としてわれわれは大気汚染というものを払わされている。だから、昔の災害の規模はせいぜい 1+2+3+4+5……というような算術級数的にしか増えて行かなかったが、現代では、それは 1×2×3×4×5……と幾何級数的に増えて行く。ホンの小さな注意(checkする能力)があるかないかが、企業や、われわれの日常生活をおびやかしているともいえる世の中です。注意力というものが、今日ほど相対的に高いウェートを持っている時代は人類の歴史はじまって以来ともいえるでしょう。ところが、われわれの若い世代は、むしろ、その逆の方向の性格が強く働いている。そこに一つの問題があると思うのです。 南カルフォルニア大学の教授で、生化学賞と平和賞の二つのノーベル賞をもらったL・C・ポーリング博士の講演をかって、アメリカで聞いたことがあります。その時、教授は、こんな寓話を話された。 「…いま、原爆を積んだ飛行機が、ヨーロッパの上空を飛んでいる。のどが、かわいたので、飛行士が、コカコーラをのうもと思って、ボタンをおした。ところが、彼は、まちがえて、原爆の方のボタンをおしてしまった。原爆は、東ドイツと西ドイツの境界におち、それがキッカケとなって、第三次大戦がはじまらないと、だれが保証できようか…今日ほど、理性とそして、確証とが、強く強く要求される時代はない」 この話を、私は、いつも思い浮かべるのです。 だから、私はいつも会社の管理職のみなさんにはいう。 仕事をいいつけたら、部下に復唱させてごらんなさい。復唱ということばが、旧軍隊のひびきがあって、いやだと思うなら、いま、私が命じたこと、いってごらんと聞いてみる。そうすると、若い人はたいてい、こちらのいった意味の半分か、あるいは3/5ぐらいしか理解していないことがわかる。その時、あなたの意図と若い社員の理解との間のギャップを埋めて、もう一回、ていねいに説明してやる。企業内教育の本流は、実は、そこにあるのではないか。 もう一つは、日ごろから、何か、フにおちない点、わからない点は聞きかえせ、というしつけをしておくことです。 聞くは、一時の恥、知らざるは一生の恥ということです。
尼ノモノ、大海ノゴトシ 人の生き死について、何とはなしにふれましたのは、たしか昭和三十三、四年ごろの夏、軽井沢においてでした。吉川英治先生は,毎夏、軽井沢へいらっしゃる。ある夜、たまたまそのことに話がはずんでいった。これも亡くなられた朝日の論説主幹、笠信太郎がたまたま、第二次大戦のあと、イタリアのムッソリーニの惨殺について、話をされた折のことと思います。先生のいわく、 禅家には三つの死に方があるという。もっとも普遍的なのは坐脱である。これは坐禅を組んで大往生をとげることをいう。第二は火定(かじょう)である。火中の中にあって坐禅を組みながら死んで行く。 世に有名なのは甲斐の恵林寺の快川和尚である。織田信長に敗れた武田勝頼の残党が、和尚をたよって恵林寺にやって来た。快川は死んだ信玄とは盟友である。で、勝頼をかくまったら、激怒した信長は恵林寺に火をかけた。快川が「心頭滅却スレバ火モマタ涼シ」という偈(げ)をのこして、大勢の弟子たちとともに火中の中に坐禅を組み死んで行ったというのです。 補足:快川和尚は高弟二人はのがれさせている。岡山市にある曹源寺でお聞きした話。 もう一人、女性では慧春尼という尼さんがゆうめいであります。この尼さんは小田原の生まれで、あとで鎌倉に庵を結んだ。聡明で美貌のほまれが高かった。いろいろな伝説のある尼さんです。 ある夜、慧春尼が、一人、山路を歩いて庵に向かった。月夜の晩である。一人の雲水が、向うからやって来る。尼の姿をみて、彼、ムラムラとフィーリングを出した。しかし、彼もさる者です。近くへ歩みよった時、いきなり、彼は裾をまくりあげ、意気盛んなり、彼のシンボルを示した。いわく、
「老僧ノモノ、コレ三尺」
立亡というのは、立ったまま往生をとげる。これは妙心寺の関山和尚が有名であります。長い患いで床に臥せていた関山和尚が、ある日、弟子たちにいった。 「どうやらお迎えがまいったようじゃ、いろいろお世話になった。では、旅にでかけるとしようか」 こういって、起きあがり、墨染の衣に着かえ、ワラジをはき、 「では行ってくるぞ」 と、寺の門を出た。そして三十歩ばかり、歩いたのち、杖を胸にしたまま動かない、弟子たちが、バラバラッとかけよってみると、関山和尚、すでに事切れおったというのです。 この三つの話をしたあと、先生はいわれた。 「しかし、いずれにしても、死に方というのは、むつかしいものだネ。僕には、どうも天龍寺の峨山和尚の死に方に気がひかれる」 とこういわれる。名僧といわれた峨山和尚の死というのは、こうなのです。 長い患いのあと、いよいよ臨終かという時、この名僧は弟子どもを、枕頭に集め、
「やい、みんな見ておけ、死ぬというのものは辛いものじゃ、苦しいもんじゃ、ああ死にとうない、死にとうないわい」
「しかし、何だネ、扇谷君、この間程ヶ谷で聞いたのだが…」 といって、先生は、また、こういう話もしてくれた。 ある老ゴルファーの死(以下略) *扇谷正造『吉川英治氏におそわったこと』(六興出版)より 2010.07.28 |
06 篠田 桃紅(しのだ とうこう) (1,913~2,021年)

『墨を読む』ーー一字ひとこと 桃 P.8 桃 大昔の、中国の隠れ里、桃源郷。 そこの住人は、世の移り変わりを一切しらず、桃の花をながめて、何代も暮していたという。 私のベランダの小さな桃の木に、それでも春毎に花が咲く。 濃い緋の枝垂れ桃の、方三尺の桃源郷に、七八日は夢を見て、私も暮す。 2008.3.2 桃の節句の前日 青 P.16 青は春、朱は夏、秋が白、冬は玄、という。 中国のひとが生み出した。青い墨の色、それは、ひとが、夢を託すために、生み出した色かと思うほどに、仄かな青を、うす墨のにじみに、見せる。 むしろ、青い色というより、透明だという感じを、色にしたようなものではないか、と思ふことがある。 そして、青春とは、透明な季節、ということではないかと思う。 かみ P.28 「かみ」と平仮名で書いて見る。 紙は大事な仕事の道具、「神」でもあり、お守りの「守」かもしれない。 「かみ」と書けば、それは「上」「佳味」「加味」「髪」などに当る意味にもとれる。 「醸」の訓にも「かみ」がある。 日本の紙は昔から楮(こうぞ)や三椏でつくったが、中国の竹で作る画仙紙などにも私はお世話になる。 水 みず P.30 「水」という字は、水の絵のようである。 水はただ思ふだけでも、心が潤う。心がいつも渇いているからなのか。 そして、青春とは、透明な季節、ということではないかと思う。 琴 P.44 「素琴一張酒一壺」 好きな七字で時々書いて見る。 おなじような意味の、 「一壺の酒と傍に君ありて歌えば、あゝ荒野もまさにパラダイス」 という詩も読んだことがある。 そのほか酒ほがいの歌もいろいろあるが、おなじようなことでも日本語だと何となく書きにくい。(酒ほがい:酒▽祝ひ/酒▽寿ひ:黒崎記) 日本人が日本語を書くのはあたり前のことだが、それだけに却って、自分のことば、でないものは書きにくい。 「素琴一張……」のように、具体的ないい方でないほうが、楽器一つ鳴らせない私でも、書けば心に音が流れ、あたりに芳醇な香りも漂うような気がする。 上 うえ P.46 横に線を一本引いて、上に点々としただけで、昔は「上」だった。点と線でよかった。書き方もいろいろだった。今は「上」も「下」も「ㇳ」ひといろになってしまった。
晨 あさ P.58
朝五時十分前だった。 窓を開けると、不二(ふじ)の傾きの少し上に月があった。うすい橙色の、満月か、あるいは十六夜か、ぐらい。 不二はうすい雲に掩われていたが、見るうちに、雲が西側に動いていき、山肌が朱色に輝いた。日が出たのだ。今の今、今日の日が射したのだ。 朱色は一瞬、一瞬にその濃さを増していく。山襞を埋めている影も、刻々に緑を強くして、朱を際立たせていく。 いつの間にか月がいなくなっていた。代りにさっきの月の色に似た色のうすい雲が、これ程の優しさはないという柔らかさで、裾野一帯を包んでいる。 やがてすぐ目の前の谷まで陽の光りが届き、樹々の葉が光りはじめる。ついさっきまで足許を這うように流れていた霧も霽(は)れた。 空気はまだそよとも動かずチ、チッと、遠慮がちな鳥の声が、却ってこの静かさを深める。 不二の朱は、次第に褐色になり、襞々の緑は紺青になり、空は、しんじつの空色になる。 まもなく、動物たちはや人間の、にぎやかな夏の一日が始まるとは信じがたい程、今、この一ときは静かである。 卜 ぼく P.96 亀の甲羅を火で焙って出る割れ目で卜(うらな)いをしたので、そのままそのかたちを「卜」はうらないという字になり、割れる鬨のボクボクという音が、字の音になった。 それから何十世紀もたったが、まだ人間はあしたのことがわからない。 |
07 神谷 美恵子(1914~1979年)

▼『生きがいについて』 自分の道を選ぶ 『生きがいについて』を書いた神谷美恵子の一生も自己実現の好例である。彼女は、津田塾の学生だった時に多摩全生園でハンセン氏病患者をみてから、医師になってこうした人の支えになりたいと思っていたが、両親がそれに反対した。しかし、彼女はプラトンの『国家論』を読んで啓示を受け、「あらゆる障害を越えて、自分の道をえらぼう」と決心した。コロンビア大学の大学院で学部長の説得にもかかわらず、ギリシャ文学から医学コースへ移ったのは二〇代後半である。帰国してから東京女子医学専門学校(現在の東京女子医大)で勉強して医師となる。結婚、育児のほかに、フランス語を教えて家計を支えつつ医学研究を続け、四六歳で医学博士となった。六五歳で亡くなるまでハンセン氏病専門の療養所である愛生園で精神科医として働き、G・ジルボーグの『医学的心理学史』(みすず書房)という膨大な本を訳したり、ヴァージニア・ウルフを日本に紹介した他に、多くの著作を残した。 参考:小林 司「生きがい」とは何か (NHKブックス)P.128 より。 2009.11.01、2010.10.08:写真を挿入
あるいは痴呆に陥った老人でも、そのような姿で存在させられているそのことの中に、私たちにはよくわからない存在の意義を発揮してるのであろう。私たちは人間の小さなあたまで、ただ有用性の観点からのみ人間の存在意義を測ってはならないと思う。何が有用であるか、ということさえ、ほんとうには人間にはわからないのでなかろうか。たとえば学問でも、「人の役に立つ」とみえるもののみが価値ある、と私は決して思っていない。 生命への畏敬ということをシュバイツァーは言ったが、私は、宇宙への畏敬の念に、このごろ、ひとしお満たされている。 2012.02.16:追加。 |

▼『日本故事物語』(河出書房新書) 月日の立つのは早いもの P.204~206 いかにも平凡な、ありふれた感想でありながら、折にふれては誰しもその感を新たにせざるを得ないといったことばである。「月日の立つのは早いもの」ということばなど、古来何千何万回となく人の口に上がっていながら、時として痛切にその感をいだかせられることがある。「熊谷陣屋」の熊谷が敦盛卿を助けんがためにわが子を手にかけ、無常を感じて軍陣を去ってゆく。 十六年はひと昔、アア夢だ夢だ。 と花道を駆け込む心中など、その感慨の代表と言うことができよう。 中国でも昔から時の速さを、 光陰箭(や)の如し と言っている。現代の人間が時の経過を実感するのは時計の針によってであろうが、時計の最も原始的なものは日時計であり、古代人が時が時を感じるのは日影の長さによってであった。それを端的に表わしたのが光陰という語である。朱熹の詩に有名な、 少年老い易く、学成り難し。一寸の光陰軽んずべからず。未だ覚めず、池塘春草の夢。階前の梧葉已(すで)に秋風 とあって、人生の老い易さを嘆いている。西洋の諺にも、「芸術は長く、生命は短し」と言っているが、まことに學問・藝術に志した者にとって、その道の高遠なことに較べて人間の一生はあまりに短いものであった。みずから「無能無芸にして只此一筋につながる」と言って、俳諧一筋を生命とした芭蕉も、この嘆きを繰り返したに違いない。「奥の細道」の冒頭に、 月日は百代の過客にして行きこう年もまた旅人なり。舟の上に生涯をうかべ、馬の口をとらえて老いを迎うるものは、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。 と言っているのは、李白の、 それ天地の万物の逆旅、光陰は百代の過客にして、浮生夢の如し。 を原典としているが、芭蕉はここに、とどまることなく、移り過ぎ行く時を実体として捉え、その推移の中に安住の境地を見出すという一つの悟りを示している。この、旅すなわち人生の姿と見たことばの通り、芭蕉はこの後数年にして、大阪の旅寓御堂前の花屋の裏座敷において、 旅に病んで、夢は枯野をかけめぐ の句を辞世として生涯を終えている。 光陰という語のほかにも、日月を意味する烏兎という語があって、「烏兎怱々」などと用いられるが、これは太陽の中に烏、月の中にうさぎが住むという古代中国の神話によっているものである。月日の速さを譬えては、 駟(し)の隙を過ぐる如し という語がある。駟は四頭立ての馬車のことで、その走り去るのを戸の隙からちらっと見る。それほどの速さだと言うのである。これは「礼記」に出ている語だが、「史記」にも人の一生を、 白駒の隙を過ぐる如きのみ と言っている。これがわが国においても普遍的な知識となって、和歌の上では「隙ゆく駒」「隙過ぐる駒」」という語が常用され、「太平記」には、「隙行く駒の足はやみ」という形容が用いられている。 古今集では、月日の速さを言っている歌は、みな老人の述懐の歌である。歳というなは、その来ることが早いから「疾(と)し」だというようなるしゃれもある。
数うればとまらぬものを とし(歳・疾)と言いて、ことしはいたく老いぞしにける
桜花 散りかい曇れ。おいらくの来んというなる道まがうかに(在原業平)
おいらくの来んと知りせば、門鎖(さ)して「なし」と答えて 会わざらましを
月日の道に関守なし で、老いの到ることの速さばかりはとどめるすべがない。さて、もとにもどって―― 雷様が日と月と一緒に旅をした。宿に着いて一泊し、翌朝目が覚めてみると、日と月の姿が見えない。女中を呼んできくと、「もうお二人様はとっくにお立ちになりました」という返事。
「なに、もう立ったか。さてさて月日のたつのははやいものだ」
トップページの言葉のようにいきたいものです。 平成二十六年十月十三日訂正。 |
09丸山 真男 (1914~1996年)

▼『日本の思想』 いわゆる「伝統」思想と「外来」思想 しばしば、儒教や仏教や、それらと「習合」して発達した神道や、あるいは江戸時代の国学などが伝統思想と呼ばれて、明治以後におびただしく流入したヨーロッパ思想と対比される。この二つのジャンルを区別すること自体は間違いないし、意味もある。けれども、伝統と非伝統というカテゴリーで両者をわかつのは重大な誤解に導くおそれがある。外来思想を摂取し、それがいろいろな形で私達の生活様式や意識のなかにとりこまれ、文化に消し難い刻印を押したという点では、ヨーロッパ産の思想もすでに「伝統化」している。たとえ翻訳思想、いや誤訳思想であるにしても、それなりに私達の思想の枠組を形づくって来たのである。紀平正美から鹿子木 員信まで、どのような国粋主義思想家も『回天詩史』や『靖獻遺言』の著者たちの語彙や範疇だけでその壮大な所論を展開することはできなかった。蓑田胸喜の激越な「思想闘争」すらW・ヴントやA・ローゼンベルクの援用で埋められていた。 私達の思考や発想の様式をいろいろな要素に分解し、それぞれの系譜を遡るならば、仏教的なもの、儒教的なもの、シャーマニズム的なもの、西欧的なもの――要するに私達の歴史にその足跡を印したあらゆる思想の断片に行き当るであろう。問題はそれらがみな雑然と同居し、相互の論理的な関係と占めるべき位置とが一向判然としないところにある。そうした基本的な在り方の点では、いわゆる「伝統」思想も明治以後のヨーロッパ思想も、本質的なちがいは見出されない。近代日本が維新前までの思想的遺産をすてて「欧化」したことが繰り返し慨嘆される(そいう慨嘆もまた明治以後今日までステロタイプ化している)けれども、もし何百年の背景をもつ「伝統」思想が本当に遺産として伝統化していたならば、そのようにたわいなく「欧化」の怒涛に呑みこまれることがどうして起りえたであろうか。 参考1:紀平正美は哲学者・文学博士。三重県生。東大卒。ヘーゲル哲学の弁証法の研究の先駆者で、西洋哲学の方法により東洋哲学の再編を試みた。のちに国家主義的傾向を深め、皇道哲学を打ち立てた。著書に『行の哲学』等。昭和24年(1949)歿、75才。 参考2:鹿子木 員信(かのこぎかずのぶ)は、日本の哲学者、海軍軍人。最終階級は海軍機関中尉。大日本言論報国会の事務局長として国粋主義思想運動をリードし、戦後はA級戦犯容疑者として逮捕された。 妻はポーランド系ドイツ人で教育者の鹿子木コルネリアである、息子にベルリンオリンピックに出場したバスケットボール選手、鹿子木健日子がいる。 参考3:蓑田胸喜(みのだ むねき)1894*1946 大正-昭和時代前期の国家主義者。明治27年1月26日生まれ。慶大,国士舘専門学校の教授。熱烈な皇室中心主義をとなえ,大正14年三井甲之(こうし)と原理日本社を創設。京都帝大,東京帝大の自由主義的な学者を攻撃して滝川事件,天皇機関説事件の口火をきった。昭和21年1月30日自殺。53歳。熊本県出身。東京帝大卒。著作に「学術維新原理日本《など。 丸山真男著『日本の思想史』(岩波新書)1975年6月10日 第25刷発行。P.8
谷沢永一『五輪書の読み方』人生いかに勝つか (ごま書房)昭和57年10月5日 初版第1刷発行 P.120 による 丸山真男の最大の業績は荻生徂徠を題材にした『日本政治思想史研究』(東京大学出版会)ということになっているが、フランクフルト学派の影響から変形マルクス主義を応用しているにすぎぬ。 ※インターネットにによると、谷沢永一氏は丸山を批判している。 |

▼『新ちょつといい話』(文春文庫) □ 池田勇人元首相がエケチットといった評判があつたが、日銀総裁・大蔵大臣をした一万田尚登さんのは、もっと凄かったらしい。 「海山千山(うみやませんざん)」「腹三寸」「一鳥二石の名案」「プラトン輸出」「ロード公団」「ダザンカイ」「神鬼出没」「予正補算」 ある時は「レオナルド・ダヴィンチの壁画」を「ボナパルトの壁画」といった由。 谷村さんの「大蔵省の便所」という本に列記されている。P.14 □ 森鴎外の「即興詩人」の初版は、四号活字で組んである。 鴎外が大きな活字を使ったのには、こういう考えがあった。 「私はこの本を母親に読んでもらいたいんです」P.60 *私は「即興詩人」の初版で「私はこの本を母親に読んでもらいたいんです」で読みました。鴎外も人の子、母親に対する気持ちの深さは変らないものだと、自分を納得させました。 □ 文藝春秋の初代社長、菊池寛は、色紙によく、こう書いた。 「読書随処浄土」 二代目の社長、佐々木茂索さんは、時々こう書いた。 「ひとみなものいのちほろばばほろぶべし おのがいのちにつつがあらすな」P.74 □ 光文社の神吉晴夫社長が、廉価版の新書を出そうと思い、シンボルマークに、鳳凰だの、キリンだの、いろいろ考えたが、どうも満足しない。 ある日、家に帰ると、清水崑さんが絵を送って来ている。鳥居の前で合掌している河童が「神吉大明神たのみます。もうしばらく待って下さい」と書いた色紙である。「よし、これでゆこう」というので、カッパ・ブックスができた。 角笛を吹く河童、神吉さんは、「ラッパのかわりにカッパ」とよくいった。P.107 □ 矢内原伊作さんはもと東大の総長だった矢内原忠雄さんの長男である。 何しろ、聖書に関する権威だから、伊作は旧約に出て来るイサクからとったのだろうと思って、尋ねたら、悲しそうな顔で、伊作は答えた。 「そうじゃないんだ。生まれたのが松山、親が伊予の国で作ったから」P.109 □ 遠藤周作さんが講演で、こういった。 「私は慶応の仏文科を二番で出ました」 シーンとして聴いている。 「卒業したのは二人です」 拍手がおこった。P.110 □ 正岡子規は、夏目漱石の親友であった。 牛込喜久井町に漱石が住んでいる時に、子規が訪ねて、早稲田から関口あたりを二人で散歩したことがある。 その時、漱石は、水田を見ながら、 「あの苗の実はいったい何だね」と尋ねた。米のなる木を知らなかったのだ その後、漱石は、ロンドンに留学した。子規が死ぬ十ヵ月前、それは明治三十四年十一月ということになるが、漱石に送った手紙が残っている。 「モシ書ケルナラ僕ノ眼ノアイテイルウチニ今一便(イチビン)ヨコシテクレヌカ」と書き、そのあとに、こう書いてある。 「ロンドン焼イモノ味ハドンナカキキタイ」P.135 □ 内田百閒さんと、銭湯の話をしていた。 「湯ぶねの隅で、昔は湯をすくって口に入れ、ウガイをした人があったものです」という。 「ずいぶん、非衛生的ですね」と顔をしかめたら、百閒さんは、キツとなって、 「当人が汚いと思わなければいいのです。衛生とは、そういうものです」P.239 □ 内田百閒が、横須賀の海軍機関学校につとめることになった。着任の日、礼服を着て登校した百閒は、教室の壇に上がるとき、足をすべらして尻餅をついた。 立って教官を迎えていた学生は、このアクシデントに、何の反応も示さず、眉も動かさずに、直立不動の姿勢をとっている。しつけがゆ届いているのに、おどろいた。 それからしばらくして、百閒が鼻の下にたくわえていた八の字ヒゲを、ある日、急に剃りおとした。そして、翌日、教室にはいってゆくと、生徒はこんども、まじめな顔で迎えた。 しかし、誰かがクスンといった拍子に、全員が笑い出して、ひっくり返るようなさわぎになった。 「風船が破裂したようだっ」と、百閒は、ぼくに直接語った。 百閒がある時、その海軍機関学校の近くに間借りをした。通うのに便利だからだが、どうも朝、遅刻する。 それについて百閒は、こう説明している。 「遠くから通っていると、途中で遅れをとり戻すことができる。しかし、近すぎると、それができない。遅れをとり戻す時間がないんです」.254 □ マイクのテストの時に、「本日は晴天なり」という。天気が悪くても、そういうが、これは、英語を直輸入したらしいという説を聞いた。 It's fine today. というフレーズの中に、発音のパターンがもりこまれているから、伝声機関の実験に用いられるとかいう話だ。 数学会の巨匠だった岡潔さんは、よく講演をたのまれたが、会場に行って、聴衆の態度が気に入らないと、たいそう機嫌を悪くしたという。 ある時、町の中学校に招かれたが、岡さんの好まれない雰囲気であった。 定刻、壇上にのぼったこの学者は、マイクを手に持つと、本日は晴天なり、本日は晴天なりといっただけで降壇、さっさと帰ってしまった。P.242 □ 芥川龍之介が若い作家に、自作の俳句を聞かせては批評をさせる。 一句、二句と披露すると、「いいですね」「しかし、二句目のは、あまりよくない」といった。 「じゃアこれは」と、また一句。 「まァですね」というと、芥川はニヤリと笑って、 「これは、芭蕉だよ」P.255 □ 室生犀星が、堀達雄夫人と話している時、突然こういった。 「俳句を作るのをやめました」 「まァ、なぜですの」 「何だか、このごろ、うまくなりすぎたから、おもしろくなくなった」P.272 □ 高峰秀子さんが、かいがいしい娘の役を演じている時、監督は山本嘉次郎さんだった。 娘が立っていると、うしろを通る男がその尻をスーッとなでるというアクションがあって、シナリオは、「ふり返ってにらみつける」である。 「デコ、自分でセリフ考えていってごらん」と監督がいった。本番になった。男が尻をさわる。高峰さんが肩越しにどなった。 「何だい、色気づきやがって」 一同ゲラゲラで、本番を撮りなおした。P.276 □ 淡島千景さは、空を飛ぶのが嫌いで、絶対に飛行機に乗らない。 「なぜ、嫌いなんですか、こわいです」という人があった。 「だって、トイレにはいると、下から見られているような気がするんですもの」P.276 □ 大正時代に、カルピスのキャッチフレーズに「甘くてすっぱいカルピスは、初恋の味」というのがあって、たいへん評判がよかった。広告文案としては画期的だろう。 社長の三島海雲が、新聞記者から、「初恋の味って何ですかと子供に訊かれたら、どうしますか」と質問された時、即答した。 「何でもないことです。初恋の味はカルピスの味と答えれば、いいのだから」P.282 ※私感:閑話としてどのページを開いても、戸板さんと多くの人との交流の逸話が書かれているので暇なとき読むと参考なります。一読されてはいかがですか。 |
12池見 酉次郎(1915~1999年)心療内科医師

池見 酉次郎(いけみ ゆうじろう、大正4年(1915年)6月12日 ~平成11年(1999年)6月25日)は日本の心身医学、心療内科の基礎を築いた草分け的な日本の医学者。福岡県糟屋郡粕屋町生まれ。甥に池見陽がいる、。 旧制福岡中学(現福岡県立福岡高等学校)、九州帝国大学医学部卒業。戦後、アメリカの医学が日本に流入した際、心身医学の存在を知る。昭和27年(1952年)にはアメリカミネソタ州のメイヨー・クリニックに留学し、帰国後、日野原重明、三浦岱栄(みうらたいえい:明治34(1901)年12月3日~ 昭和期の精神神経科学者。慶応義塾大学教授)らと共に昭和35年(1960年)日本心身医学会を設立し、初代理事長になる。翌昭和36年(1961年)九州大学に国内最初に設立された精神身体医学研究施設(現在の心療内科に当たる)教授に就任し、内科疾患を中心に、心と体の相関関係に注目した診療方法を体系化、実用化に尽力した。 九州大学医学部名誉教授、自律訓練法国際委員会名誉委員長、日本心身医学会名誉理事長、国際心身医学会理事長、 日本交流分析学会名誉理事長などを歴任。 平成11年(1999年)6月25日肺炎のため、福岡市内の病院で死去。84歳。
著書
(一) 私は多年、心身一如のセルフ・コントロール法、とくに体をととのえ心をととのえる方法について研究し、それを健康増進や治療の目的で活用してきました。ところが、実際問題として、忙しい現代人に時間のかかるセルフ・コントロール法を実行させるには、いろいろと困難が伴うものです。私自身も、自分でやってみて、どの方法でも長続きしにくいことを体験していました。 そのようなとき、たまたま森信三先生の「立腰道」に出合いました。 先生は、かって神戸大学の教授であり、独創的な哲学者で、教育についても深い見識を持つておられますとはかねてより熟知しておりました。 ところが、先生の「立腰教育入門」を一読して、私が長い間、求め続けてきたセルフ・コントロール法の秘伝が、いとも簡潔に「立腰道」の中に凝縮されているのに感嘆しました。東洋の坐禅や静坐法のエッセンスが、本法の中に見事に抽出されており、まさに現代の易行道として、いつでも、だれでもが、日常生活の中で実行できる方法になっておりますのに敬朊いたしました。 五十三年五月に、産業医大の本多正明教授の紹介で、じかに森先生にお目にかかり、私どものセルフ・コントロール法の考え方と立腰道の接点について、親しく談合する機会に恵まれました。当時、先生は八十三歳でしたが、カクシャクとしておられ、先生の情熱をこめた明快な口調がまことに印象的でした。 それ以来、私の唱えるセルフ・コントロール法に関心を抱く人たちには、セルフ・コントロール法の入門として、いつも「立腰道」をすすめることにしております。また、近頃、急にふえてきた教育関係者のための講演でも、必ず「立腰道」を紹介することにしています。 (二) 福岡市の仁愛保育園では、森信三先生の立腰教育の理念と方法を、園の保育に導入して、めざましい成果をあげておられます。 昭和四十八年、石橋園長が、森先生の講演録に感動し、立腰教育を保育にとり入れられて以来、園長をはじめとする全職員が立腰教育に打ち込まれ、今日に到っております。当代きっての哲学者であり教育者である森信三先生が「仁愛教育の方針」として、
一、つねに腰骨を立てる人間に
という、先生の揮毫が大理石に刻みこまれ、この人間教育の基礎として「躾の三大原則」を保育指導の根本方針として掲げておられます。これをみましても、石橋園長のなみなみならぬご傾倒と情熱ぶりには目を見張らせるものがあります。
1、職員みづから、立腰を習得する。
等々のことが、職員の実行目標となっており、職員が園児と共に学ぶ態度が、ここの保育を支えており、職員自身の人間的な成長につながっているようです。 このように仁愛保育園は、森信三先生の「立腰教育」や「躾の三原則」をはじめとし「心情教育」にも大いに力を注がれ、全国的にもめずらしい成果をあげておられますが、これも(一)園長と職員が一体となっての熱意と、それに(二)父兄の信頼関係が確立されているためであると思いますが、この根本にある心身相即の原理にもとづく「立腰教育」の威力ともいえると思います。 (三) 私は数年来、「セルフ・コントロールの医学」を提唱し、とくに心身一如のセルフ・コントロール法を、健康増進や治療に活用することを、機会あるごとに、広く一般に呼びかけてきております。ところが坐禅などの東洋的な行法を実践できる人は限られており、また、やり出しても長続きしにくいものです。そこで、ちかごろは私自身が実行している立腰道を、この種のセルフ・コントロールの入門として実行していただくことを誰にでもおすすめしております。 (福岡市南区塩原三丁目十三*二十五) 平成二十八年四月十七日 文献:森 信 三 先生 提唱 新版 「立腰教育入門」 P.43~48 より。
天地一切のものと和解せよ 心療科という科はむかしは大学病院などにはなかった。これを日本に最初に作られたのは言うまでもなく九州大学の池見酉次郎先生である。 先生は従来の医学が心と体とを別々なものとして、いわゆる生理的な肉体的疾患治療だけを重視していたのにたいして、我々の肉体と心とは一体をなしていること、ストレスや心の苦しみが時として肉体的な疾病としてあらわれることを研究され、戦後九州大学医学部にはじめて今日の心療科の前身を設立されたのである。 別に医学者でもない、一介の作家である私が知ったかぶりにこんなことを書くのは、先生の御著作がいつも心をひくからである。 もちろん、読むのは先生の学術的な論文ではなく、我々素人にもよくわかるような心の話の本なのだが、昨日たまた書棚から『心身セルフ・コントロール法』(主婦の友社)という本をだして再読し、はじめて読んだ時と同じような深い感銘を受けた。 この本の中には実に率直に、実に赤裸々に、御自分の育った境遇や御母堂との間の心理関係、御自身の御家庭の内側まで語っておられる。こんなことまで読者に発表されていいのかねと思うほど御家庭や御夫婦間の出来事を告白されている。 それは━━━先生がどんな人間にも欠点や醜いマイナスの面があることを人間の心を研究する医者として御存じだからにちがいない。そして先生はそうしたマイナスの面は御自分にもあることを自覚され「それを語ることは決して恥ずかしいことではない」と悟られたからにちがいない。「 この本のなかには私に考えさせた言葉や話が幾つも出てきたが、そのひとつに先生が友人で自律訓練法の第一人者ウルフガング・ルーテ教授からさまざまなものを学びながら、更にそれをこえた考えを持たれた挿話があった。 ルーテ教授は色々な方法をつかって、患者個人の体の奥にある自然治癒力を引き出した人である。しかし先生はこの個人だけの自然治癒力を引き出すだけでは心と体の問題のすべては解決するものではないと考えるようになる。 天理教の信者だった母堂を持たれた先生はこの時、この宗教の「天地一切のものと和解せよ」という言葉を憶えておられた。この言葉の通り、人間は自分をとりまき、自分を生かしてくれる大きな生命(いのち)、つまり御母堂のいう天地一切のもの━━━と調和することが最終の治療法だという結論にたっした。そして母と妻を失って苦しんでいたルーテ教授にこう言われたのである。 「あなたが、かねがね唱えている自己正常化の治療は、実母を失い、奥さんを失った今、傷心の状態にあるあなたの心を癒すことができますか」 そしてルーテ教授はこの時、黙っていたという。 こうしたさまざまな挿話や人間の心の底を語ったこの本は先生の人生体験に裏づけられているだけに、なまじかの思想書などより、はるかに読むものに迫ってくる。読み終わり、ああいい本だと思った次第である。 遠藤周作『生き上手 死に上手』(文春文庫)P.98~100 より。 平成二十八年四月二十六日 |
13 西村 公朝 (1919~2004年)

夢を実現する生き方 青春の夢が自分の人生のなかで成就されながら、年を重ねてゆく。そんな人生は素晴らしい。 こんなときの「夢」は希望とか理想とかいう意味で言われるのだが、文字どおり、ほんとうに見た「夢」が成就されてゆくという話がある。 京都愛宕(あたご)念仏寺住職の有名な西村 公朝(にしむら こうちょう)師の『千の手・千の眼』(法蔵館)によると、公朝師は第二次世界大戦のとき、兵士として中国に渡り、行軍中の極度の疲労のなかで、歩きながら眠っているとき、次のような夢を見たという。 簡単に紹介するとーー 行軍中の自分の側に、破搊した仏像が何百何千と悲しそうな表情で並んでいる。その仏像は手足の無いもの、頭が割れているもの、などすべて哀れな姿となっている。 そこで、「あなた方は、私に修理をしてほしいのなら、私を無事に帰国させてください」と言ったところで目が覚めた。 その後、公朝師は不思議に危険に遭わずに終戦とともに帰国した。そこで、仏像との約束を想い起こし、美術院国宝修理所において、多くの仏像を修理し、後に同所の所長となり、東京芸大の教授ともなって、仏像の修理と研究に力をつくしてこられた。 この夢のことを知って、私はその夢に傷だらけの姿として現れた仏像は、戦いによって傷ついた人々のたましいをも表していたのではないかと思った。 現在の公朝師は、念仏寺の住職として人々の心の傷を癒すことをしておられる。(現在形で記述されている):添付の写真は、公朝師が、「祈り」となづけられた像である。 ★河合隼雄『「老いる」とは どういうことか』P.234より *プロフィル:西村 公朝(にしむら こうちょう、1915年(大正4年)6月4日 - 2003年(平成15年)12月2日)は、仏師・仏像修理技師・僧侶・東京芸術大学名誉教授。勲三等瑞宝章。 平成二十九年十一月二十三日勤労感謝の日 |
14 水上 勉 (1919~2004年)

▼『禅とは何か』 二入四行の理論。 真理にいたる方法に、二つの立場と四つの実践が要るというのである。 二入の一つは、原理的ないたり方で、経典をよく学んで、仏法の大意を知って、生きとし生きるものすべては、平等な真実をもっているい るけど、外来的な妄想にさえぎられて、本質を実現できないでいることを確信せよ、というのである。 もう一つの実践的ないたり方には四つの実践方法がある。
第一は前世の怨みに報いる実践である。
参考:1、「無 記」(indifferent)形而上学的な問題について判断を示さず沈黙を守ることである。無用な論争の弊害からのがれ、苦しみからの解放という本来の目的を見失わないためにとられた立場である。 2、「無 為」自然のままで作為するところのないこと。 |
15松永 市郎(海軍兵学校68期)(1919~2005年)
|
▼『先任将校』(光人社刊) 軍艦な取短艇隊帰投せり
まえがき
航海長小林英一郎大尉(当時二十七歳)は、先任将校として、カッター三隻および生存者百九十五名をもって、軍艦な取短艇隊を編成した。しかし、食料(乾パン少々はあった)も真水もなく、また磁石とか六分儀などの航海要具も何一つ持たなかった。先任将校は、カッターが洋上で発見される機会はきわめて少ないからと、十五日間も橈(かい)を漕いで、独力でフィリピンに向かうと宣言した。総員が救助艦を待つようにとこぞって提言したが、先任将校は所信を変えなかった。 そして十三日目の早朝、短艇隊はついにミンダナオ島の東北端スリガオにたどり着いた。食事も休養も十分とらずに、毎日十時間カッターを漕いでいたので、接岸したときは体力の限界点だった。短艇隊の成功は、先任将校の早期決断と隊員一同がいったんは反対したものの、断行と決定するや命をかけて漕ぎつづけたからである。
しかし、戦後の戦友会で、隊員たちが先任将校の殺害を、蜜かに企てていたことを知り、いまさらながら驚いた。食べ物も水もない、狭いカッターの中で、大勢の人が押し合いへし合いしている。前途に、明るい見通しはまったくない。命令を出す指揮官に、前後に見境もなく凶行に及ぼうとしていたことは、当時の状況がいかに切迫していたかを物語っている。 戦後の私は、海難を調査、けんきゅうしてみた。戦時、平時を問わず、毎年、世界各地で、大勢の人たち(ある調査では二十万人)が海難事故に出会い、相当数の人たちが死亡していることを知った。そしてその原因が、海難事故そのものによることもあるが、前途を悲観しての自殺とか、ふ間内の争いによるものが、相当数にのぼっている。人間は、ビタミン・カロリー等の不足による肉体的条件では、世間の常識を上回って生きつづけることができる。その反面、自信を失ったり、失望したりの精神的ショックには、きわめてもろいことを、体験的に知った。 な取短艇隊が、食量も真水もなく、航海要具も持たず、三百マイルも漕いで接岸を目指すことは、海軍常識ではまず不可能だった。しかし先任将校の断固たる決心と隊員の渾身の努力により、ついに不可能を可能にした。諦めずに努力して運命を切り開き、「神は自ら助くる者を助く」という言葉を、身をもって体験することができた。平時でも戦時でも、団体行動をする人たちにとって、とくに生命の危険にさらされたときに、なんらかの御参考にになれば、筆者望外の喜びである。 本書の独断や偏見に遠慮のない御叱正と、読者諸賢の海難事故など御教示たまわれば幸いです。 松永市郎 補足1:この本の中での松永市郎さんの言葉。 「変事にさいしては、部下はだれでも指揮官の顔を見る」 「可愛らしき犬と思えば犬もまた、尾を振って近寄ってくる。小憎らしい猫と思えば猫もまた険しい目付きでにらんでくる。」 「事が起こってから全力で統率に当たっても、立派な統率力ができるものではない。事に当たって立派な統率ができるためには指揮官たるものは、平生から部下の尊敬と信頼を受けていなければならない」 「諸君は、まだ実兵を指揮した経験がない。だから諸君は、理想的な指揮官とは、理解力に富んだ円満なる常識家と思っているだろう。しかし、指揮官とは、ときには、物わかりの悪い頑固物でなければならない」 補足1:私は、生前の著者にお目にかかり、お話をきくことが出来ました。 ※『先任将校』 軍艦な取短艇隊帰投せり 松永市郎(な取短艇隊次席将校)の読者の感想 下手なリーダーシップ論の本よりよほど役に立つ1冊。 昭和19年フィリピンからパラオへ向かう軽巡洋艦な取はアメリカ潜水艦により撃沈される。 3隻のカッターに搭乗した195名。海難では遭難現場に留まれという常識を超えて、27歳の若き大尉に率いられた195名は、15日間かけて300マイル先のフィリピンに生還する。 筆者はな取の通信長、艦長、副長が戦死し、生き残った艦員の先任将校の航海長の次席将校となる。 先任将校の小林英一大尉の言動についての記述を筆者の視点からとらえた内容。良くある自慢話でないところが良い。シーアンカーや天測など道具がほとんどない中、工夫を重ねるところ、筆者が出身の佐賀県で育ててくれた祖母の言葉を、漂流の中で思い出し、役立てていく場面も多々あり。 自分の中で印象に残った場面は大きく2つ。 昼は帆走と休息、夜は漕走という決め事を、ようやく島が見えたことで、昼も漕ぎ、たどりつけず疲れた後、先任将校が予定通り夜の漕走も行わせる場面。「指揮官は理に富んだ円満な常識家ではなく、時には物分かりの悪い頑固者でなければならない。」ようやくフィリピンにたどり着き、陸軍の焼玉船に曳航してもらうようになり、先任将校と次席将校の筆者が、カッターの部下達より先に焼玉船に移乗した先で、つい水を飲んだ時に小林大尉に、「先憂後楽を忘れたか。それでも指揮官と言えるか。」 先任将校は焼玉船に用意されたお粥を、部下達に与えた後、ようやく自分も口にする。 小林大尉の統率力があったからな取搭乗員が生還できたことは間違いない。 理論も必要だが、行動で示す姿勢は大いに参考にしなければならない。 リーダーシップの参考書としてはもちろん、単なる海難ものの1冊としても絶対に楽しめる1冊です。 戦前日本の海軍兵学校などのエリート教育(現在の日本で消滅しているが)も間違っていなかったとも思いました。
★第8回岡山海軍連合クラス会 61.04.20 講師 68期 松永市郎氏 〒857 佐世保市福石町16-6 出席者:55名。43期~78期。61期:板倉光馬。75期10名:小坂二度見、広木重喜(奥村長生君の知人:裁判官)、堀田 昭等。76期15名。77期10名。78期8名。 2008.6.10 |
16豊田 良平(1920~2002年)
|
▼平沢 興先生との対話の抄録ー人に喜びと希望を ・かしこすぎると燃えない。燃えるためには偉大な愚かさがいる。愚かさは知からである。 ・一事を通して、真にものの深さを知ると、その目、その頭で万事を考えてものの真実に近づける。 ・人生にむだはない。むだとしか見えないような目では成長できない。 ・人生において喜びを与えることは、最高であります。 ・あなた方は自分自身が知るよりも数ばいもの知らない素晴しいものを心の中に持っておられるのです。 ・人間として成長することでは、、誰にも遠慮はいらぬ。 ・一流の人は明るい。 ▼『致 知』より掲載 「誠実というのは、嘘をつかんということではなくわが道を貫くということです」 「口で教育論をいうような母では駄目だ。そうではない。事もなげに酒を飲むおやじと一緒に酒を飲みながら、おやじを本当に尊敬しているんだったら、いくら飲んべえの家庭でも悪い子はできない」 「いっぱい水の入ったコップにお湯を注ぐと両方ともにこぼれる」 カリアッパ 一人芝居をしませんか 「俺がお前に、ハウ・ドゥ・ユウ・ドウ(元気か?)と聞いたら、どんなことがあってもアイ・クワイト・ウエル(最高だ)といえ。>」 ※関西師友協会の豊田良平副会長が平成14年10月10日、82歳で逝去した。 |
17梅棹 忠夫(1920~2010年)
18 山本 七平(やまもとしちへい)(1921~1991年)山本書店店主。評論家
|
▼『日本人とユダヤ人』イザヤ・ペンダサン著 (山本書店) 人間はなぜ創造の第六日目に造られたのか。これはもしおまえが傲慢で身をふくらなませたら、蚤だって創造においてはお前より先んじていた、と言いうるためである。 タルムドより 賢者とは? すべて人から学びうる人 強者とは? 自己の情熱を統御しうる人 富者とは? 自らのくじ(運命=分け前)に満足を感じうる人 尊い人とは? 人間を尊ぶ人 ベン・ゾーマ その人の行いがその人の知識より偉大なときは、その知識は有益である。 しかし、その人の知識がその人の行いより大になるときは、その知識は無益である。 ラビ・ハニナ・ベン・ドーサ
日本人とユダヤ人
一 安全と自由と水のコスト
もう二十年以上昔のことである。日本人K氏は貿易再開に備えて渡米した。当時はまだ対日感情の悪いころで、列車の中で、日本人とわかると集団リンチを受けかねまじき情況だった。K氏はニューヨークで、有名なアストリア・ホテルに宿泊し、出張所開設に飛びまわっていたが、人びとの悪意ある態度や冷たい応対には全く神経をすりへらし、ホテルの私室だけが唯一の憩いの場所になってしまった。格式あるホテルだけに、たとえ営業上当然とはいえ、顧客へのサービスは十分だったからである。 少し落着くと、両隣りの部屋にいるのがユダヤ人で、しかも彼らは宿泊しているのでなく、ここに住んでいるのに気がついた。「なるほどユダヤ人てやつは金持ちだなあ、こちらはホテル代まで、本社から、やかましく言われているのに」と思いつつ、それとなく、この両隣りのユダヤ人を観察していた。彼らは確かに貧乏とはいえない。しかし生活は実に質素であり、文字通り一銭一厘といえどもおろそかにしないし、朊装といい、身の回りといい、ふ必要なものは一切身につけていない。しかもその持物には、なに一つとして贅沢品はない、帽子、背広、靴、ライター、時計、万年筆、どれも目立たぬ普通の品である。食堂で顔を合わせるとき彼らのメニューをそれとなく眺めれば、これも節約という感じが強かった。「なるほど、けちでしまり屋で金にきたないのか」。K氏はユダヤ人に対する批評を裏書きする思いで、それを眺めていた。 ただこのユダヤ人たちは、別に、日本人に悪感情をもつていないように見えた。否、むしろ親しげであった。滞在が長びくにつれて、K氏は、いつしか、両隣りのユダヤ人家族と親しくなり、渡米以来の孤独感と人なつかしさから急速に親しさを増していった。ついに家族同様の口をきくまでになった。 ある日のことK氏は、初めて彼らに接して以来、心の底にもっていた一つの疑問を口にした。「あなた方御一家は、どうしてこのホテルにお住いなのですか。ここの部屋代その他を考えれば、快適な立派な郊外の住宅で、もっともっと豊かに楽しく生活できるでしょうに」と。実際、一杯の紅茶も一枚のトーストも、一般の家庭生活それと比べれば、話にならぬほどハイコストである。何がゆえにここに住んで質素な生活をする必要があろう。普通の住宅を借りて、大いに豪勢にやった方がずっと良いはずではないか。当然の疑問であった。だが、ユダヤ人の答えは、全く彼が予期せぬものだった。ここは安全ですからと。K氏は、この『安全』という意味を突差に理解しかねた。ユダヤ人は彼の顔を見ると静かに続けた。「ここは安全ですから」と。K氏は、この『安全』という意味を突差に理解しかねた。ユダヤ人は彼の顔を見ると静かにつづけた。「このホテルは常時特別に警戒してますし、その上連邦政府の秘密警察が絶えず警戒しています。さらに、ホテル側でも、外国の賓客などに事故があったらそれこそ大変ですから、超一流のの警備会社と契約して、最も有能な制朊・私朊のガードマンに絶えず警戒させていますし、ホテル自身にも警備員がいます。その上、フロントその他も、警備という点では絶えず教育され、訓練され、行とどいていますから、ここより安全なところはないわけです。安全にはコストがかかります。しかし、この世のあらゆるることは、生命の安全があってはじめて成り立つわけで、もし生命を失えば、その人にとっては、この世のすべてのことは全く無意味です。もちろん、あなたのおっしゃる郊外の豪邸も豪奢な生活もすべて無意味になってしまいます。ですから、まず、自分の生命の安全を第一に考えて、この安全のためには、たとえ他の支出を削れるだけ削ったとしても、当然のことではないでしょうか。」。 日本にもホテル生活をしている人はいる。しかしそれは、あるいはステイタス・シンボルのゆえ、あるいは優雅な生活と便益もしくは虚栄のためであっても、身の安全のためでははない。P.9~11 この章はP.9~25まで続き、少ししか写しませんでした、関心のあるかたは原文をお読み下さい。 22.08.21 |
19三浦 綾子(1922~1999年)

▼『新約聖書入門』 愛する人から贈られた聖書P.12~13 私がはじめて聖書を手に取ったのは、日曜学校に通った小学校三年生の時である。が、この時、私が日曜学校に通ったのは、神に求められたからではない。私の家は、当時十二人もの大家族で、しかも男の子が多かったから、日曜日というと、家の中はどったんばったんと騒ぎまわる子供たちでうるさかった。なにしろ、八畳二間六畳一間の、たった三部屋しかない家だった。雨の日や冬の寒い日は、どうしても家の中で遊ぶことになる。どちらかというと、本を読むのが好きだった私は、そんな喧噪な世界はうとましかった。それで、友だちに誘われるままに教会に通ったまでである。 だから、この時聖書をひらいたということも、私にはそれほど大きな影響を与えなかった。長じて、聖書を読んだのは、もう年齢も二十七歳になった療養中のことである。その時も私は、聖書を心から読みたいんとは思っていなかった。 他の本にも書いたが私は戦時中、他の教師たちと同様に、ただ徒(いたず)らに熱心な教師だった。その七年目に敗戦に遭った。日本はアメリカ軍の占領下に入った。アメリカ軍の指令で、教科書はかなりのページを墨でぬりつぶさなければならなかった。そうした作業を、生徒に指示しながら、まだ若かった私の胸は、耐えがたい屈辱感にさいなまれた。昨日まで胸を張って教えていた教科書に、墨をぬらせるという、この異様な体験の中で、私は坂をまっさかさまに転がり落ちるような速さで、虚無の淵におちこんだのである。 詳しくは自伝『道ありき』に書いてあるが、それからの私はもはや熱心な教師ではなかった。それまで熱心であっただけに、教科書に墨をぬらせた教師の私は、子供たちの前に顔を上げ得ない思いで教壇に立った。もはや私は、きびしく叱る教師ではなかった。授業中生徒たちが私語しようと、宿題を忘れて来ようと、そんなことはどうでもよかった。どこもかしこも墨だらけの教科書、そのどこをひらいて、一体何を教えようというのか。昨日まで正しかったことが、なぜ正しくないか。果たして今日正しくないとするものが、本当に正しくないのか。私は教えることの重さに、その時ようやく気づき、かつおびえた。そして私は、教室で洗濯をしながら生徒に自習を命ずるような教師になってしまった。こんな中で私は、二人の男性とほとんど同時に婚約し、退職し、その直後発病し、結核療養所に入った。 そして三年の月日が流れ、私は相変わらず虚無的な投げやりな日々をくり返しながら、療養していた。そんな前に現われたのが、幼馴染じみの前川正という医学生であった。彼も療養中であったが、彼は私と違ってクリスチャンホームに育ったキリスト信者であった。その彼に新約聖書を贈られたのは、その一年後であった。彼が読み古したその新約聖書の扉には、 「汝ら互いに重きを負え」 というサインがしてあった。その聖書を私に手渡すとき、彼は言った。 「ぼくと一緒に、毎日最初から、聖書を読んで見ませんか」 私はうなずいた。このうなずくまでの一年のことは長くなるので省略するが、私は彼を愛しはじめていたのである。 私見:太平洋戦争での敗戦後の学校教育の現場の状態の一つとして記録にとどめておきます。 補足:三浦綾子を読む *道ありき *東京ミレニアム・チャーチ 牧師 長谷川 与 志充 三浦文学をこのコーナーでは順に紹介させていただきますが、三浦文学を読むために必読書がここでご紹介する「道ありき」です。この本は三浦綾子の自伝で、それ以前の教師時代話も含まれていますが、その中心は24歳から37歳までの彼女自身の人生が赤裸々に描されています。これから様々な書をこのコーナーでご紹介させていただきますが、すべてのがこの書を土台として書かれていることをまずは覚えておいて下さい。 さて、この書で必ず知っておかなければならない重要人物は、前川正と三浦光世の二人ですが、以下に多くの人々が感動したこのお二人の言葉を書き記しておきます。 「綾ちゃん、ぼくは今まで、綾ちゃんが元気で生きつづけてくれるようにと、どんなに激しく祈って来たかわかりませんよ。綾ちゃんが生きるためになら、自分の命もいらないと思ったほどでした。けれども信仰のうすいぼくには、あなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから、ふ甲斐ない自分を罰するために、こうして自分を打ち付けてやるのです。」(前川正) 「綾ちゃん お互いに、精一杯の誠実な友情で交わって来れたことを、心から感謝します。綾ちゃんは真の意味で私の最初の人であり、最後の人でした。綾ちゃん、綾ちゃんは私が死んでも、生きることを止めることも、消極的になることもないと確かに約束して下さいましたよ。万一、この約束に対しふ誠実であれば、私の綾ちゃんは私の見込み違いだったわけです。そんな綾ちゃんではありませんね!一度申したこと、繰返すことは控えてましたが、決して私は綾ちゃんの最後の人であることを願わなかったこと、このことが今改めて、申述べたいことです。生 きるということは苦しく、又、謎に満ちています。妙な約束に縛られてふ自然な綾ちゃんになっては一番悲しいことです。」(前川正) 「神様、わたしの命を堀田さんに上げてもよろしいですから、どうかなおしてあげてください。」 (三浦光世) 「ぼくの気持ちは単なるヒロイズムや、一時的な同情ではないつもりです。美しい人なら職場に も教会にも近所にもいます。でもぼくは、それよりもあなたの涙に洗われた美しい心を愛しているのです。」(三浦光世) 「あなたが正さんのことを忘れないということが大事なのです。あの人のことを忘れてはいけません。あなたはあの人に導かれてクリスチャンになったのです。わたしたちは前川さんによって結ばれたのです。綾子さん、前川さんに喜んでもらえるような二人になりましょうね。」(三浦光世)「インターネット」より。2017.09.28
「うちにはテレビがないけれど、三浦が、歌が上手なものですから、テレビなどいらないんです」 (三浦 綾子)
三浦綾子さんの「愛すること、信ずること」(講談社新書)の中で驚いた言葉です。「三浦がうたってくれると、ウットリと三浦の顔を眺め、悲しい歌は涙をこぼして聞いてしまう。人から見ると、いい年をして馬鹿な女と笑われるかも知れない。だが、夫の歌がこの上なく楽しいことは、べつだん他人様の迷惑にはなるまいと思う。夫婦なんて、それでいいんじゃないかと思う。何もよその人に聞いてくれとわけでもではない。……」とあります。ここに夫婦といもののあるべき姿のちょっとしたコツがあるように思います。 私の反省を元にして言わせてもらえば、身近な者のアラはすぐ目につきにゃすい。そして、すぐそれを言い立てる。このくりかえしでは実はけっしていい結果につながらないということです。ああ、こんな単純な過ちを今でも私はくりかえしている。 寺田清一「一粒一滴」より 2017.09.26
三浦綾子『塩狩峠』
地に落ちて死ななければ、 一粒のままである。 だが、死ねば、 多くの実を結ぶ。 (新約聖書 ヨハネ伝 第一二章 二四節)
▼明治十年の二月に永野信夫は東京の本郷で生まれた。
父の永野貞行は温厚であった。旗本七百石の家に生まれたというよりは、公家の育ちのような、みやびかな雰囲気の人柄であった。信夫を勝気な母のトセにまかせきりで、ほとんど信夫には干渉することもなかった。だから、信夫は父が恐ろしいとか恐ろしいとも、やさしいとも思わなかった。 信夫は近所の子供と屋根の上で遊んでいるとき屋根からおちて幸い、足首の捻挫だけで骨折はなかった。 お父さんは「そうか、お前がひとりで落ちたのか」 「そうです。ぼく町人の子なんかに屋根から落とされたりするものですか」 信夫の言葉に貞行の顔色がさっと変った。 「信夫っ! もう一度今の言葉を言ってみなさい」 凛とした貞行の声に信夫は一瞬ためらったが、そのときりんりときかん気に結ばれた唇がはっきりと開いた。 「ぼく、町人の子なんかに……」 みなまで言わせずに貞行の手が、信夫のほおを力いっぱいに打った。信夫には何で父の怒りを買ったのかわからない。 「永野家は士族ですよ。町人の子とちがいます」 祖母のトセはいつも信夫に言っていた。 信夫の父貞行は言う「どこもちがっていない。目も二つ、耳も二つだ。いいか信夫。福沢諭吉先生は天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず、とおっしゃった。わかるか、信夫」…………。 父貞行は一度「菊」という女性と結婚。彼女はクリスチャンであり、貞行のお母さん「トセ」はそれが理由で別れさせた。だが貞行は菊を別の家に住ませていた。女の子供もできていた。
それがわかり祖母トセは
(中略) ▼著者は信夫がキリスト信者になったいきさつを詳しく述べている。 その初期段階の経緯の中で、私は中村春雨の少説『無花果』に書かれている言葉に非常に惹かれました。それは「義人なし、一人だになし」である。非常に重い言葉と感じました。キリスト教での原罪を意味しているのではないかと。 *この言葉は『聖書』中の「ローマ書3*10」に「正しい者はいない。一人もいない。」と尊敬する先生からおしえられました。 ▼「雪の街角」の章の記述では、 信夫はキュッキュッとなる雪の道を歩きながら、駅前通りにであた。暮れもおし迫って、人通りもいつもよりにぎやかである。馬橇がリンリン鈴を鳴らしながら、いく台も通る。赤煉瓦で有名な興農社の所までくると、何か大声で聞えた。みると、一人の男が外套も着ないで、大声で叫んでいる、だれも耳をかたむける者はない。信夫は、ふと耳にはいった言葉にひかれて立ちどまった。
「人間という者は、皆さん、いったいどんな者でありますか。まず人間とは、自分をだれよりもかわいいと思う者であります」
「しかしみなさん、真に自分がかわいいということは、どんなことでありましょうか。そのことを諸君は知らないのであります。真に自分がかわいいとは、おのれのみにくさを憎むことであります。しかし、われわれは自分のみにくさを認めたくないものであります。たとえば、つまみぐいはいやしいとされておりましても、自分がつまんで食べるぶんには、いやしいとは思わない。人の陰口をいうことは、男らしくないことだと知りながらも、おのれのいう悪口は正義のしからしむるところのように思うのであります。俗に、泥棒にも三分の理という諺があるではありませんか。人の物を盗んでおきながら、何の申しひらくところがありましょう。しかし泥棒には泥棒の言いぶんがあるのであります」 信夫は驚いて男をみた。男の澄んだ目が、信夫にはまっすぐに注がれている。 (まるでこの人は、いまのおれの気持ちを見とおしてでもいるようだ) 信夫は、自分がどこに立っているのを忘れて、男の話にひきいれられていった。 「みなさん、しかしわたしは、たった一人、世にもばかな男を知っております。その男はイエス・キリストであります」 男はぐいと一歩信夫の方に近よって叫んだ。 「イエス・キリストは、何ひとつ悪いことはなさらなかった。生れつきの盲(めしい)をなおし、生れつきの足なえをなおし、そして人々に、ほんとうの愛を教えたのであります。ほんとうの愛とは、どんなものか、みなさんおわかりですか」 信夫はこの男がキリスト教の伝道師であることを知った。立ちどまっているのは、信夫だけである。 みなさん、愛とは、自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものはとは何でありますか。それは命ではありませんか。このイエス・キリストは、自分の命を吾々に下さったのであります。彼は決して罪を犯したまわなかった。人々は自分が悪いことをしながら、自分は悪くないという者でありますのに、何ひとつ悪いことをしなかったイエス・キリストは、この世のすべての罪を背負って、十字架にかけられたのであります。彼は、自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くない者が、悪い者の罪を背負う。悪い者が悪くないと言って逃げる。ここにハッキリと、神の子の姿と、罪人の姿があるのであります。しかもみなさん、十字架につけられた時、イエス・キリストは、その十字架につけた者のために、かく祈ったのであります。 『父よ、彼らを許し給え、そのなす所を知らざればなり。父よ、彼らを許し給え、そのなす所を知らざればなり』 聞きましたか、みなさん。いま自分を刺し殺す者のために、許しためと祈ることのできるこの人こそ、神の人格を所有するかたであると、私は思うのであります…… このあたりで話が長くなりますので中断しますが、信夫は伝道師の伊木一馬をともなって自分の下宿で話し合いました。 伊木一馬はいく度か大きくうなずきながら聞いていたが、ふところから聖書を出した。 「わかりました。永野君、これはぼくも試みたことなんだが、君もやってみないかね。聖書の中のどれでもいい、ひとつ徹底的に実行してみませんか。徹底的にだよ、君。そうするとね、あるべき人間の姿に、いかに自分が遠いものであるか知るんじゃないかな。わたしは、『汝に乞う者に与え、借らんとする者を拒むな』という言葉を守ろうとして、十日目でかぶとを脱いだよ。君は君の実行しようとすることを、見つけて見るんだね」 伊木一馬は、夕食を食べ、そして帰って行った。 私が思うに信夫はクリスチャンとしての信仰をつかんだの時が与えられたのではないかと。 ▼最終の章は「峠」である。 信夫はふじ子と結婚することになり、結納を持参するためにな寄の駅から汽車で札幌へ向かう。親友吉川の妹ふじ子は、(長く結核を患いカリエスになりその上、足がふ具合であった。しかしキリスト教信者で笑顔を絶やさず、病気を克朊していた。) 汽車はいま、塩狩峠にの頂上に近づいていた。この塩狩峠は天塩(てんしお)の国と石狩の国の国境にある大きな峠である。旭川から北へ約三十キロの地点にあった。深い山林のの中をいく曲りして越える、かなりけわしい峠で、列車はふもとの駅から後端にも機関車をつけ、あえぎあえぎ上るのである。…… 一瞬客車がガクンと止まったような気がした。が、次の瞬間、客車は妙に頼りなくゆっくりとあとずさりを始めた。体に伝わっていた機関車の振動がぶっつととだえた。と見る間に、客車は加速度的に速さを増した。いままで後方に流れていた窓の風景がぐんぐん逆に流れていく。 「あっ、汽車が離れた!」 だれかが叫んだ。さっと車内を恐怖が走った。 「たいへんだ! 転覆するぞ――!」 「皆さん、落ちついてください。汽車はすぐとまります」 信夫はドアの外のデッキのハンドブレキーに手をかけて力いっぱいに回し始めた。次第に速度がゆるんだ。しかし止まることはなく、たったいまの速度なら、自分の体でこの車両をとめることができると、信夫はとっさに判断した。ふじ子(結婚しようとしている女のひと)、菊(自分のお母さん)、待子(自分の妹)の顔が大きく目に浮かんだ。それをふり払うように、信夫は目をつむった。と、次の瞬間、信夫の手はハンドブレーキから離れ、その体は線路を目がけて飛びおりていた。 客車は不気味にきしんで、信夫の上に乗り上げ、遂に完全に停止した。 この知らせは吉川に知らせられた。 その後の話を書き続けるのは、私にはできない。 じっくりとこの本を読んでください。 ▼死後、ふじこは兄と塩狩峠の事故の現場を見に行く。 ふじ子は、ふだん信夫が語っていた言葉を思った。
「ふじ子さん、薪は一本より二本のほうがよく燃えるでしょう。ぼくたちも、信仰の火を燃やすために一緒になるんですよ」
やがて向こうに、大きなカーブが見えた。その手前に、白木の柱が立っている。大方受難現場の標(しるべ)であろう。ふじ子が立ちどまり、雪柳の白い束を線路の上におくのが見えた。が、次の瞬間、ふじ子がガバと線路に打ち伏した。吉川は思わず立ちどまった。吉川の目に、ふじ子の姿と雪柳の白が、涙でうるんでひとつになった。と、胸を刺すとうなふじ子の泣き声が吉川の耳を打った。 塩狩峠は、雲ひとつない明るいまひるだった。 以上で、この本の内容の紹介を終わります。
*尊敬している先生が退職されたキリスト系の学校の校訓は「心を清くして 愛の人であれ」であり、生徒の一人が感想文に「『塩狩峠』の主人公のような生き方をしたい」と書かれていたとのことでした。読んでいなかったので読みました。インターネットでもその概略を勉強もしました。 信夫の言葉「ぼくは毎日を神と人のために生きたいと思う。いつまでも生きたいのは無論だが、いついかなる瞬間に命を召されても、喜んで死んで行けるようになりたいと思いますね」。また神父マクシミリアン・コルベ神父、洞爺丸事故における外国の神父さんが自分の命まで捧げる献身的行為はどこから生まれるのでしょうか。 お断りします。大部分のものは著者の本からの抜き書きになりました。
一九四一年(昭和16年)七月のある日、アウシュビッツ強制収用所からひとりの脱走者がでました。ナチスは、見せしめとして無差別に十人を選び、餓死刑を課した。指名され、死を宣告された十人の中のひとりが「かわいそうな妻と子どもたちに、もう一度会いたい。」と叫んだ。 すると突然、ひとりの男が進み出て身代わりを申し出た。ポーランド生まれの神父マクシミリアン・コルベである。囚人番号一六六七〇号と呼ばれる彼は、約十日後餓死牢の中でその一生を閉じた。 われわれは不思議な縁で教育者となった。われわれの前には、かわいい子どもたちがいる。この子どもたちのために身を捨てる覚悟をしたらどうであろうか。かき集める方向ではなく、身を献げる決意で行動したらどうであろうか。コルベ神父のような崇高な行為はできないににしても――。 以上の原文をフランクル『夜と霧』で一応探してみたが見当たらりませんでした。 ▼また、洞爺丸事故における外国人の献身的行為を思い出していました。 インターネットに記載が沢山ありますからお読みください。 三浦綾子『新約聖書入門』を読んでいると、次の記事がありました。 小説『氷点』の中にもかいたことだが、昭和二十九年秋、青函連絡船の洞爺丸が、台風に襲われて座礁転覆した。乗客何千人のうち、千十一人がこの夜の遭難で死んだ。この洞爺丸には二人の外人宣教師が同乗していたが、救命具を持たない男女に、自分たちの救命具を与えて死んでいった。 最近ある読者から、それは事実か創作かという問い合わせがあった。むろん事実で、二人のうち、ストーン宣教師の写真が、今も私の部屋に飾ってある。 彼らが救命具を与えたのは、人に見せるためではない。転覆という非常事態の中で、誰もが必死だった。他人のことなど、見ている暇はなかった。いわば誰一人見る者のない中で、彼らは自分の命ともいうべき救命具を、人に与えたのである。 私はこの宣教師たちが、生まれながらに神のみを仰ぐ人物であったと思わない。私たちと同じ弱さを持ち、またある時は、人に賞賛にも心ひかれ、人にも認められたい誘惑も、持ったことであろう。だが、神の言葉によって生きるうちに、ついには、自分の救命具を人に与えて、喜んで死んでいける境地になり得たのではないかと思うのである。 ともかく、この二人の行為は、人にほめられたいからという行為ではなく、誰が見ていても、見ていなくても、見ていてくださる神への信頼のもとになし得た行為であると思う。神を仰ぐ生活自体、大きな報酬なのである。 (三浦綾子『新約聖書入門』光文社P.58参照) 平成二十年五月二十五日
作品舞台巡る…北海道町おこしにひと役 毎日新聞2016年3月6日 19時58分 三浦綾子さん 北海道旭川市出身の小説家、故三浦綾子さんの記念文学館を運営する三浦綾子記念文化財団(旭川市)は、代表作「塩狩峠」「泥流地帯」「氷点」の舞台となった和寒、上富良野、旭川の各市町と協力して「三浦文学でまちおこし」事業を始めることになった。実行委員会を設置し、ゆかりの地を巡る散策路(フットパス)の選定などを通して地域の観光や文化の振興を図る。 今年が「塩狩峠」の雑誌連載開始から50年となることを記念した事業で、「氷点」は映画化50年、「泥流地帯」は題材となった十勝岳の噴火から90年と、いずれの作品でも節目の年にあたるという。 まず散策路として、4月中に和寒町の塩狩峠やJR塩狩駅周辺、旭川市の外国樹種見本林など、作品ゆかりの地を巡る6?8キロのコースを選定する。 また、作品やコースなどを解説する冊子を作り、実際に歩くイベントも随時、実施する。さらに作品に関する特別展や朗読会、講演会などを予定。9月にはイベント列車の運行も検討している。 事業にあわせ、財団は和寒、上富良野両町に、絶版になり入手困難な本も含めた三浦さんの作品を文庫として寄贈する。 文学館と作品の舞台の地元住民、自治体が協働する事業は全国でも珍しいという。実行委は「地域の振興だけでなく、優れた文化的財産を地元に根付かせ、若い世代にも伝えていきたい」としている。【横田信行】 平成二十八年三月九日 |
20押田 成人(1922~2003年)カトリック司祭(新潮社)
|
▼『地下水の思想』 「(前略)彼女の心から、社会への虚栄心が遠く消え去って行った。世間を気にしていた彼女のそれまでの人生は夢のようなものだ。」 「涼風は彼岸の窓から吹く。欲望、虚栄、野心は、この窓を閉じさせる。日本を去りたいと想う。しかし、地球を去ることは出来ない。」 「断食の後では、味の神秘が新鮮に現われる。」 「木造校舎では、窓が壊れたといっても、自分達で直せる。それは大事なことだった。先生と生徒が、手をつかって、心をこめてかかわることは、かけがえのないことだった。これからは、それが出来ない。」 「知性の有無は、地位とか職業とかによって判断されるものではない。本当の知性というものは生命がけで生きている人に与えられる。」 |
21紀野 一義(1922~2013年)
|
▼『わが親鸞』(PHP) 『横川法語』P.36 この恵心僧都の書かれたものに『横川法語』がある。これは、仮なで書かれた浄土往生の教えとしては日本最初のものである。それまでの浄土の教えは、すべて漢文で書かれていたのである。 それ一切衆生、三悪道(さんなくどう)をのがれて、人間に生きること大いなるよろこびなり。身はいやしくとも、畜生におとらんや。家まづしくとも、餓鬼にはまさるべし。心におもふことかなはずとも、地獄のくるしみにはくらぶべからず。世のすみうき(住むみ憂き)は、いとふたよりなり。人かずならぬ身のいやしきは、菩提をねがふしるべなり。このゆえに人間にうまるゝことを悦ぶべし。信心あさくとも、本願ふかきがゆゑに、頼めばかならず往生す。念仏ものうえけれど、唱ふればさだめて来迎にあずかる功徳莫大なり。このゆゑに、本願にあふことをよろこぶべし。 また妄念はもとより凡夫の地体なり。妄念の外に別の心もなきなり。臨終の時までは、一向に妄念の凡夫にてあるべきぞとこゝろえて念仏すれば、来迎にあづかりて蓮台にのるときこそさとりとはなれ。妄念のうちより申しいだしたる念仏は、濁(にごり)にしまぬ蓮(はちす)のごとくにして、決定(けつじよう)往生うたがひあるべからず。妄念をいとはずして信心のあさきをなげき、こゝろざしを深くして、常にみょう号を唱ふべし よき人ととの出会いP.48 親鸞が山を下りたのは、二十九歳の年である。そして恵信尼消息第三通に書かれてあるように六角堂に百日籠り、九十五日目の朝示現をこうむったのである。その消息文はこうである。
「山をいでゝ、六角堂に百日こもらせ給て、後世を祈らせ給けるに、九十五日のあか月、聖徳太子の文を結びて、示現にあずからせ給て候ければ」
「横顔にその人の本然の姿が出てくるのであろう」
「親鸞はここまで心の行き届いた人間であった。彼は『悲しみをよく知る人』であった。悲しみをよく知る人でなくては、大ぜいの人を幸せになど出来ないのである。」
「前略 一人居て喜ばば二人と思ふべし、二人居て喜ばば三人と思ふべし、その一人は親鸞なり」:御臨末御書
「人によく思われたいと思っている人間の言葉が、人の心を打つのは自然法爾の人か、おのれを極悪人と自覚した者のみである。」
「自然といふは、自はおのずからといふ行者のはからひにあらず、然といふはしからしむるといふことばなり。如来のちかひてあるがゆへに法爾といふ。法爾といふは、この如来の御ちかひなるがゆへにしからしむるを法爾といふなり」。 P.223
|
22瀬戸 内寂聴(1922~2021年)
|
▼老人六歌仙 しわがよるほくろがでける腰曲がる 頭がはげるひげが白くなる 手はふるう足はよろつく歯は抜ける 耳は聞こえず眼はうとくなる 身に添うは頭巾襟巻き杖眼鏡 たんぽおんじやくしゆびん孫の手 聞きたがる死にとむながるさびしがる 心はまがる欲深くなる くどくなる気短になる愚痴になる 出しゃばりたがる世話やきたがる 又しても同じ話に子を褒める 達者自慢に人はいやがる 「古人の歌」 これは、江戸の仙崖義梵(1750-1837)の老人六歌仙人である。東京出光美術館に所蔵されている。老人六人の絵と、この六つの歌が、賛として書かれている。 仙崖は八十九才まで生きたからりっぱな老人である。
「仙崖さん、あんまり笑って、おしっこちびりましたよ。年をとるってほんとにいやですね。年よりの体のことを、こんなに具体的に書ききる、相当な意地悪ジイサンね。でもこれ、自画像でしょ。江戸時代に老眼鏡があったなんて知らなかった。さぞ高価だったでしょうね。ほくろは老人のしみ。」
五十代の嫁がこの歌にゲラゲラ笑っていましたよ。すぐ自分だってこうなるのに、ハハハ。八十四歳、平成の老婆より
|
23 三好 守(1923~1945年)
|
三好 守(みよし まもる、1923年(大正12年)5月24日 - 1945年(昭和20年)3月20日)は、日本の海軍軍人。海兵73期。太平洋戦争末期、人間魚雷[回天]の搭乗員として訓練中、事故により殉職した。殉職による一階級特進で最終階級は海軍大尉 経歴:1923年(大正12年)5月24日、東京府(現、東京都)で生まれる。1944年(昭和19年)3月22日に海軍兵学校(海兵73期)を卒業すると、同年9月6日に人間魚雷[回天]を創案した黒木博司・仁科関夫と共に第一特別基地隊光基地に着任、[回天]搭乗員として出撃までの時間を訓練にて過ごす。 1945年(昭和20年)3月20日、小雨が降る荒天の中、[回天]特別攻撃隊多々良隊長として出撃する直前の基地発進訓練を光基地沖で行っていたところ、目標艦の艦底中央を全速30ノットで通過する際、下まで降り切っていなかった特眼鏡が艦底に激突して根元から破搊、特眼鏡を見ながら進んでいったために三好は眉間を割られて失神している際に艇は浸水し沈没、溺死・殉職した。享年21。目標艦に接近しすぎていたからか、設定した深度が浅すぎたのが原因と思われる。訓練中の殉職のため、一階級特進で海軍大尉に昇進した。 三好の没後、柿崎実は三好の遺骨を抱いて、同年5月2日に沖縄県海域で特攻・戦死した。 関連:回天特別攻撃田/光基地柿崎実さんの記事もある。
この日太平洋戦争開始。軍閥が無謀にはじめたこの戦争で、多くの青年の命が祖国のためと称してうばわれた。写真は本郷新作「わたつみ像」。 *桑原武夫『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.208 2010.12.08
[わだつみ]とは、[わたのかみ]と同義で[海をつかさどる神]を意味します。[わだ(わた)]は朝鮮語の[パタ(海)]に由来します。 1949年10月20日、東京大学協同組合出版部から『きけわだつみのこえ』という戦没学生の手記が刊行され、広く普及されました。[わだつみ像]はこの刊行収入をもとに戦没学生記念会(通称「わだつみ会」)が計画したもので、本郷新氏の作品です。当初、東京大学構内に設置する予定でしたが、朝鮮戦争さなかの1950年12月4日に評議員会が拒否、その背景には日本を占領していた連合軍の意向も働いたと言われています。東大では「わだつみ像設置拒否反対集会」が開かれましたが、結局、設置場所は定まらず、「わだつみ像」は本郷氏のアトリエに置かれることになりました。1951年、立命館大学の末川博総長が[わだつみ]>を引き受ける意思を表明したことをきっかけに、学内外からの強い支持も寄せられ、1953年12月8日、太平洋戦争開戦の記念日に立命館大学での建立除幕式を迎えるに至りました。翌1954年からは、12月8日前後に「わだつみ像」の前で[ふ戦のつどい]が開かれるようになり、立命館の伝統行事として今日まで続いています。 2017.09.06 |
24 上田 三四二 (1923~1989年)
|
この世 この生 西行・良寛・明恵・道元 (新潮社)一九八五年二月五日八刷 目 次 花 月 西 行 遊 戯 良 寛 顕 夢 明 恵 透 脱 道 元 地 球 浄 土 * 地上一寸ということ――あとがきに代えて―― 以上の構成になっている。 この本を読みながら、それぞれの章でのこれぞと思うところに傍線を引いた箇所を抜書きします。したがって文章の体裁をなしていないと自分でもかんじていますから、この本に関心をもたれましたらご自身で読まれますよう。 その一として「花 月 西 行」を取り上げる。 ウラジミル・ジャンケレヴィッチ(1903~1985フランスの哲学者)「死」。 白地のカバーに、不吉な黒の一字を浮かび上がらせた五百ページにおよぶ訳書(中沢紀雄訳、みすず書房)を前に、呆然としている。 うまい言葉がみつからないまま、呆然などと言ってみたが、そこには、或るうとましさの思いもないわけでない。 なぜ、おぞましい死についてかくも雄弁に、時にはほとんど楽しげに、多くの言葉を費やさなければならないのか。そこで言葉は死の舞踏病を病んでいるかのようだ。死にたいするこんなにも深い、嗜虐的なまでの心入れは、日常感覚にとってなにか異様なもののようにおもわれる。 日常感覚は死の隠蔽の上にはたらく。マンホールの上を歩く足は足下に空洞のあるのを忘れている。知っていてもそのために立竦むことはない。日常感覚も死の空洞の上に鉄板を張って、落ち込むことのないものとして生きている。人間が笑うことが出来るのは、死を忘れているからだ。死の際(きわ)まで死を思わないで生きることは人間の生き方のもっとも健全なものにちがいない。たいていの人はそのように生きており、尿路の結石に苦しんだ十六世紀フランスのモラリストも、たしかそういう生き方を推奨していたと記憶する。 しかし結石の痛みが我慢ならぬほど強くなれば、人はいやでも意志のそとにある身体というものに思いいたる。またその痛みが生命のふ安を誘い出せば、いつまでも死をよけて通ることも出来なくなる。そしてそのとき、人は、死とは身体の消滅であるというわかりきった事実の前に駭然(がいぜん)とする。一人の人間にとって、彼自身の死だけが唯一正真の死だが、人はいつか、目隠しを解かれて、そういう自分の死と対面しなければならない。 私がジャンケレヴィッチの「死」に惹かれるのは、私自身、結石ならぬもっとずっと予後の悪い病気によって、早々とその目隠しを解かれたことによる。この書物があまりにも死を淫していると見えることから、或るうとましさの思いのないわけでもないことは言ったとおりだが、総じて、私はこのふ𠮷な主題の書物から大きなものを得たような気がしている。 ジャンケレヴィッチは死を三つの面から見ている。 一つは「死のこちら側の死」、すなわち生きている時間にとって死とは何かという問いである。死ぬものだけが生きている。この当たり前すぎる事実には、真剣に生きようとするものにとって汲みつくせないほどの含蓄がある。 いま一つは「死の瞬間における死」。ここでは死の刹那が問われる。一回きりの、やり直しのきかない、そして取り返しのつかない死というもの。その最初にして最後の、体験を超えた体験の相が照らし出される。 最後は「死のむこう側の死」である。死のむこう側に、後世(ごせ)というものがあるのだろうか。それとも虚無があるだけなのだろうか。後世というものはなく、虚無があるだけでもないとするのがジャンケレヴィッチの立場であるようにおもわれる。いや、死後は絶対の無だが、生きたという事実そのものが光芒を曳いて無の上に懸かっていると、彼はこの最後の章ばかりは楽しげどころか額に脂汗さえ滲ませながら、生のために、生にとっては絶対のふ条理である死に向かって、つよく主張している。(中略) こうして、死後はすでに考慮の外である。死を避けることは出来ないが、死後はないと思い定め、思い定めた上は死後の救済に心を救済に労することなく、滝口までの線分の生をどう生きるかに思いをひそめればよい。 以上が死にたいする私のこれまでの考え方であった。そしていまもその考え方を変えていない。私は魂の持続を信じることが出来ず、身体の消滅のときをもって私という存在の消滅するときと観じて、その死までのさし迫った生をどのように生きるかに関心を振り向け、或る偶然から、と言った方がよいほどちょっとした選択の機をとおし「徒然草」にちかづき、その一種静寂主義ともいうべき隠遁の人生哲学に共感を見出してきたのである。(中略) 兼好は死後に何の関心も寄せていない。先途ちかき思いはひしひしと彼をせめているが後世は――後世の語は二、三「徒然草」に見えているにもかかわらず、彼の視野に入っていない。兼好は滝口までの線分的生のうちに自己を生き切ろうとする。その生き切り方が、徹底した外界に対する無欲と自己にたいする無為であり、その無欲と無為をとおして、自己の外部の時間よりずっと遅い刻みをもつ一個の内部時計とするところに、心身永閑の思想とかって私が要約したような兼好の行き方の独自性があった。(中略) 西行を兼好から区別する最大の目じるしは何か。 兼好が後世抜きであるのに対して、西行には後世が信じられている。兼好の生は「死の瞬間における死」で終る滝口に終わる。身の終りがすなわち魂の終わりである。しかし西行の魂は身の終りの後まで生きのびて、滝口は絶望的な存在の消滅を意味しない。死の瞬間は西行にとってももちろん劇的であり、西行の場合とりわけ劇的であったといわねばならないが、しかしそれは悲劇的でも絶望的でもなかった。 西行に本当に後世は信じられていたか。信仰の深さのほどはしかと定めがたいが、西行が死後にたいして或るイメージを抱いていたことだけはたしかと思われる。兼好とちがって西行は、「死の向こう側」を視野のうちに取り込んでいるのである。(中略) 晩年の一時期を伊勢に過ごした西行の言行を伝える「西公談抄」に、「歌のことを談ずとても、其隙には、一生幾ばくならず、来世近きにありといふ文を口ずさみにいはれし、あはれに貴くぞおぼえし」とあるのは、西行がつねに後世を念頭に置いていたことの一つの証拠といえよう。「来世(後世)近きにあり」の語気には、後世への期待さえ感じられないことはない。 また西行の和歌―― 来む世には心のうちにあらはさむあかでやみぬる月の光を 仏には桜の花をたてまつれ我が後の世を人とぶらはば 二首とも、自分の死後を歌っている。生涯、月と花に心を労した歌人にふさわしく、あの世でも円光の月に思いをひそめ、桜の花に逢うことによろこびを見出そうと言っている。ここで、死後は現世のつづきのようなものとして意識されている。すくなくとも、現世への未練として歌われている。西行は、来(きた)るべき世においても、依然として現世の景物である花月への情が彼の心を占めるであろうと予告しているのである。 このような西行の「死のむこう側の死」への視線は、「死の瞬間における死」を歌うありにも有名な次の歌を梃子としていることは見やすい。 願はくは花のしたにて春死なむそのとききさらぎの望月のころ 一首は「山家集」に出ている。「山家集」は西行が伊勢に移る以前に成立したと推定されるから、どんなにおそく見積つてもこれは死に先立つこと十年の作である。定義のうえからは辞世であるわけはないが、しかし作者の心に分け入ってみれば、これが辞世の歌でなければ話ははじまらないだろう。西行は実際の死より十年以上も前に辞世の歌を詠み、以後、春くるごとに望月の花の下で――如月十五日は釈迦入滅の日にあたるが、この世における花の爛漫、月の清明を仏道成就の道しるべとして、彼岸に渡ることを心に期してきたのである。ちなみにこの歌は「続古今集」では二句が「願はくは花のもとにて」となっている。これも一つのかたちで、一般にはこの方がよく通っている。 この歌は美しい玉の砕けるような衝撃力をもっている。死はここで西行の憧れの完成だが、その憧れの完成が、西行という現身消滅を意味するゆえに衝撃は大きいのである。 まして、よく知られるように、文治六年(建久元年)二月十六日、西行が河内弘川寺においてこの願いを実現し、七十三歳で示寂したとあっては、一首の歌、一人の歌人の死が世人に与えた衝撃のほどははかり知れないものがあった。(中略) 西行の場合、「死のむこう側の死」すなわち死後は、彼の「死の瞬間における死」すなわち死際の栄光に光被されている。これは時人の眼にそう映ったというだけではない。西行の意識そのものにおいても、死の瞬間の高揚が死後を照らしていることが思われる。「願はくは花のしたにて春死なむそのとききさらぎの望月のころ」――この哀切というよりは豊潤に、死に向ってというよりは花月に向って、憧れわたる魂のかたちをみせて歌い上げられた「死の瞬間における死」の歌の美しさにくらべれば、「来む世には心のうちにあらはさむあかでやみぬる月の光を」の月の歌も、「仏には桜の花をたてまつれ我が後の世を人とぶらはば」の花の歌も、これら「死のむこう側の死」を歌う声のひびきは、西行の作のなかでも上の部に属するといっても、何程のことはない。死後は死の瞬間におよばないのである。 西行に死後の信じられていたことは、二種の歌を見るとおりであっただろう。しかし西行にとって、死後は死の瞬間におよばない。西行の死後は、死の瞬間に揚がる美しい花火の、尾を曳いて闇に懸かり闇を渡る、その光芒の余勢のようなものではなかったかと思われる。 世に後世者流というのがある。後世人、ごせもの、とも呼ばれる彼らは、現世を穢土と観じて、後世にその望みのすべてを託そうとする。彼らにとって現世に生きることは何の価値もなく、それはただ極楽往生のための準備期間にすぎない。今生は死後のためにのみあり、この世において死急(しにいそ)ぎにまさるよろこびはないのである。一例として、「一言芳談」はそういう後世者たちの生を厭い死に憧れる言葉に満ちている。 西行に死後は念持されている。信じられていると言ってもいいことは、これまで見てきたとおりである。しかし、彼は後世者流ではなかった。西行は死に憧れたか。彼は花月に憧れたのであって、死に憧れたのではなかった。「死の瞬間における死を歌った「願はくは」の一言は、死への憧れを語っているのではない。死をも輝かしいものとする月と花――この現世の景物でありながら現世のものともおもわれぬ感動を呼びおこすもの、それに対(むか)うとあやしい浮遊感につれてゆかれ、陶酔に誘われるもの、美感としかなづけようがないために仮にそう言っておくが、人のこころを至美、至純、至極の境(さかい)にむかって押しあげ、昇りつめさせるもの、そしてそこでは時間が空虚ではなく充ちており、充ちることによって時間を忘れさせるもの、そいう蠱惑の源としての月と花への憧れを、語っているのである。(中略) 死後のことはわからない。死後はないとする私の直観をやわらげて言えば、せいぜいのところ、死後のことはわからないと言うほかはないが、死後の有無如何にかかわらず死は確実に到来する。その到来する死をふ可知の死後につないで、そこに希望があるにしろ、ないにしろ、現世と現世における生の超自然性に目覚めることは、生きる上での果報にちがいない。「死によって、この世ですべての存在は、街かどのコーヒー店主にいたるまで、超自然的存在なのだ。」――これまで、目に見えてこなかったあたらしい認識の地平が、私の前に、開かれているのを、覚える。~P.29 私感:著者上田氏は病魔により死の滝口に確実に向かっていると自覚させられている。そこで思い出されるのは、『修證儀』の冒頭の語句「生(しょう)を明(あき)らめ死を明らむるは仏家一大事の因縁なり。」であります。 2008.6.15 |
|
▼『歴史の中の日本』(中公文庫)一九九五年八月三十日改訂再販 P.149~152 ある胎動 ――「新井白石とその時代展」によせて 日本人がやった歴史的軽わざというのは、明治以前の学問文化の遺産をすてることによって明治以後の文化をつくりあげたことだろう。 明治政府は、東京大学に西洋諸学の学科をはやくからつくったが、漢学の講座はそれよりもおくれた。しかし「日本漢学科」というようなものはついどこの大学にもおかれずじまいで、こんにちにいたっている。 こういう制度上の空白が、たとえば室町期の五山文学のようなものを忘れさせた。五山文学が日本人によっておこなわれたいわば模倣の中国詩文であるため、中国文学者の対象にならず、また一種の日本文学ではあっても漢学であるため国文学者の研究対象にならない。 五山文学のような極端な運命におちていないにしても、江戸時代、おもに漢文によって思想や感情を表現した学者や文学者の業績は右とおなじようななりゆきで、ほとんど見すてられた。新井白石、荻生徂徠、富永中基といったな前は、われわれにとってヨーロッパや中国の先哲よりもはるかになじみにくい感じをもつのは、明治維新という文化大革命が、いまの中国のそれにおとらないほどにすさまじいものであったことをおもわせる。 隣国の疝気(せんき)をとやかく憶測する必要はないが、その文化大革命の本旨らしものから想像しておそらく百年はかかるかもしてない。 日本は、幸い(でもないが)百年たつた。 ようやく明治のエネルギーが落ちてきて、われわれは自分の国の先哲を、錠のおりた古いトダナからひきだして陽の下でさらしてみるという気になったらしい。そういう余裕ができたという意味では幸いということがいえそうだし、でなければあいもかわらずエネルギシュな日本人は、中国からヨーロッパにかけてあさりにあさった知的欲求のはたらきのすえついにフロンティアを、日本そのものに発見した、ということもいえるかもしれない。この場合はさかんなるかな、という形容をつかうべきかもしれず、いずれにしてもこういう日本文化のあたらしい機運のなかからなにごとか大きなものがうまれてきそうな気もする。 こういう傾向のなかで、私のような門外漢がおもしろくかんずるのは、このような処女地の発掘者のなかに、在来の漢文読みや国文学者がまじっていることがすくなくないということである。 五山文学については、アメリカの大学の中国文学者でそれを研究しているひとが何人かいるという。あるいは作家で仏文学者でもある中村真一郎氏が、頼山陽とその時代の知識人のすぐれたエッセイを雑誌に連載している。また河上徹太郎氏がさきに『吉田松陰』を書き、小林秀雄氏が本居宣長━━これは国学者であるにしても━━の考察をつづけている。いずれもその著作以前にはなかったすぐれたものだが、それらに共通しているものは、地球をまわってついにここを発見したという発見者の熱気である。吉川幸次郎氏が夏目漱石の漢詩についてわれわれに教えてくれた事もこの一群のなかに入るであろう。 こんど、フランス文学者の桑原武夫氏が、新井白石の数多い著作のなかから、こんにちの文明や文化の課題に交差しうるものをえらんで、現代語訳された。桑原氏は白石について、十七世紀末から十八世紀にかけて日本がもちえたもっとも偉大な百科全書的文化人であるとし、さらに「徳川日本のおかれた条件のふ利にもかかわらず、当時の世界の代表的百科全書的文化人、たとえばをヴォルテル、フランクリン、ライプニッツ、ロモノーソフ、顧炎武など、十人のうちに当然数えこまるべき視野の広さと思考の独創性をもった先駆者であった」としている。このみじかい文章が単に紹介文にとどまっていないのは、はるばるヨーロッパ的教養世界からやってきた者が明治以前の文化の灰のなかから輝くものを発見した。発見者のわかわかしい驚嘆と熱気がふくまれているからであろう。 東京では、デパートで新井白石の遺品展ももよわされるという。明治、大正の文化人がきけば目をこすっておどろくであろう。デパートで「白石」が展示されるということになると、その意味では一つの流行現象のようにもとれるが、しかし流行というには根がありすぎるるようであり、一つのまったくあたらしい文化がはじまろうとしているとおもったほうが理解しやすいかもしれない。むろんそのことは、日本回帰とか国粋賛美といったふうな多分に心理的現象のものではなく、明治以来の日本人の教養感覚というものが一つの総合期をむかえようとしているといったふうのそういう歴史的段階を感ずるのだが、これは世間のすみで風聞のみをきいて暮らししている閑人の錯覚だろうか。 平成二十七年十二月十三日、全文を読む。
坂の上の雲
1968年(昭和43年)から1972年(昭和47年)にかけ『産経新聞』に連載。単行版全6巻(文藝春秋、初版1969年~1972年)、文庫版全8巻(文春文庫、初版1978年、島田謹二解説)で刊行。 秋山好古、真之兄弟が明治13年から15年まで下宿していた旧旗本佐久間正節屋敷が存在していた場所。麹町区土手三番町(現:千代田区五番町) 司馬遼太郎は、自身の太平洋戦争末期の体験から日本の成り立ちについて、深い感慨を持つに至った。戦後新聞社勤務を経て昭和30年代に作家となったが、題材として振り返るには、資料収集も含め時間を要した。近代日本の定義を明治維新以後に置くとするなら、本作品は長編作品としては初の近代物である。 『坂の上の雲』とは、封建の世から目覚めたばかりの日本が、登って行けばやがてはそこに手が届くと思い登って行った近代国家や列強というものを「坂の上の雲」に例えた、切なさのこもった題名である。作者が常々問うていた日本特有の精神と文化が19世紀末の西洋文化に対しどのような反応を示したか、を正面から問うた作品である。作者は、そのため事実のみを書く、という方針を持っていたと述べたが、これについては様々に問題点も指摘されている。 当初は秋山好古、秋山真之の兄弟と正岡子規の3人を主人公に、松山出身の彼らが明治という近代日本の勃興期を、いかに生きたかを描き、青春群像小説の面が強調されている。 前半は、秋山好古が小学校助教試験を受けに大阪に渡り、堺県の合格証を元に小学校教師をした後、官立の大阪師範学校を経て陸軍士官学校に学び、フランス留学を経て日本騎兵を作り上げてゆく様子を基点にしている。秋山真之は、松山中学から実兄の好古を頼り上京する。帝国大学進学を目指し、共立学校にて正岡子規とともに高橋是清に英語を学び、共立学校を経て大学予備門(のちの一高)に在籍する。正岡子規に遅れ上京した真之との交友関係は、読者には楽しく、明治初期の青年の志や情熱について理解を深める材料ともなる。夏目漱石が彼達の友人に属し、子規との交友関係を綴るくだりは、明治特有の時代風潮を映し出している。子規は帝国大学文学部へ進学。真之は海軍兵学校へと異なる道を歩む。 この時点での重要なモチーフの一つは、羸弱(るいじゃく)な基盤しか持たない近代国家としての日本を支えるために、青年たちが自己と国家を同一視し、自ら国家の一分野を担う気概を持って各々の学問や専門的事象に取り組む明治期特有の人間像である。好古における騎兵、真之における海軍戦術の研究、子規における短詩型文学と近代日本語による散文の改革運動など、それぞれが近代日本の勃興期の状況下で、代表的な事例として丁寧に描かれている。 後半は、日露戦争の描写が中心となり、あたかも「説日露戦争」の雰囲気が強くなる。作者が日露戦争そのものを巨視的かつ全体的に捉えることを意図し、後半部分では本来の主人公である秋山兄弟の他に児玉源太郎、東郷平八郎、乃木希典などの将官や、各戦闘で中心的な役割を果たした師団と日本海海戦についての記述に紙幅が割かれている。読者に理解しやすいよう軍事的な記述も時系列的に述べられている。本作も、日露戦争の終結と共に締められる。 私は、昭和四十二年、この本を同じ会社に勤めていた松林さんから借りて毎日読み続けて、読み通した。
最近、司馬遼太郎著『歴史の中の日本』(中公文庫)の中で『坂の上の雲』を書き終えてP.102~116 を見つけて、私たちが置かれていた日本国の風潮を知ることが出来た。記述の一部を残して、以下に、その要点を抜き書きすることにした。 書き終えてあらためておもうことは、明治末年から大正初年までに刊行されたあのぼう大な『日露戦史』(参謀本部編集)のばかばかしさである。歴史というものは時間関係と位置関係でできあがっているという立場で書かれたもので、事実は羅列されていても一行の真実も書かれておらず、また一つの軍隊運動についての価値観も抜きで、まして戦術上の批判も書かれていない。ただ戦況ごとの地図が五百枚ほどもあって、この地図をたよりにあらためて価値をきめてゆかねばならなかった。 「日本陸軍の神秘的大勝」 という神話が成立したのは、日露戦争のあとである。満州における陸軍の戦いには負けてはいないが、決して勝ってはいなかった。戦いにおける勝利の定義はむずかしく、何をもって勝ちとするかはいまだに決まっていないが、もし角界(すもう)のように敵を土俵の外に押し出す━━つまり敵の陣地を奪った━━ということが勝ちの定義とするならば日本軍はたしかに勝った。しかし、戦場には土俵がなく、とくにロシア軍の伝統的戦術思想として土俵がない。ロシアはナポレオンと戦うにあたってどんどん退却した。ナポレオンは追撃に追撃という一見連戦連勝のかたちをとりつつ、補給線がのびきってついにモスクワで自滅的な大敗北を喫し、軍隊そのものが蒸発したような状況になり、ナポレオンは身ひとつでのがれざるをえなかった。ロシアはその国家的経験をもっているだけに、満州における基本的戦略はそれであった。 ただナポレオン戦争の場合は世界の世論がロシアに同情的であり、ナポレオン軍の衰弱してゆくのを根気よく待った。 しかし日露戦争の場合は、国際世論はロシアに対して冷たかった。ロシアの強盗じみた極東侵略はとくに英国の利益に反し、その英国が世界の情報の主導力をもっていたし、さらにはどの国もロシアが極東を併呑してかつてのモンゴル帝国のような世界帝国になることを好まなかったために、満州においてロシア軍が土俵をすてて北方へ退却するのをいちいち「ロシア軍の大敗北」というかたちで報道し、喧伝した。国際世論が一戦局ごとに勝敗の行司役になり、つねに日本軍に軍配をあげた。国際世論が勝敗の基準をつくった。 実際の真相は、児玉源太郎が開戦の前に、 「観測としてはうまく行って五分五分である。そこをなんとか戦術に苦心をして六分四分にもってゆきたい」 といったとおり、結果としてもそうであった。その満州における凄惨な陸戦を、戦争という大きな場において一挙に勝利へ締めくくってしまったのは、黄海と日本海におけるロシア艦隊の全滅にある。まったく全滅した。日本艦隊は戦艦、巡洋艦、駆逐艦の一隻も敵の砲弾に沈められることなく無傷であった。戦争はすでに世界史にとっても古典的現象になってしまったが、侵入軍がまったく全滅したという歴史は人類はこの例以外にもったことがない。 しかし戦争は勝利国においてむしろ悲惨な面が多い。日本人が世界史上もっとも滑稽な夜郎自大の民族になるものであり、さらに具体的にいえば上の『日露戦史』で見られるようにこの戦争の科学的な解剖を怠り、むしろ隠蔽し、戦えば勝つという軍隊神話をつくりあげ、大正期や昭和期の専門の軍人でさえもそれを信じ、以下は考えられぬようなことだが、陸軍大学校でさえこの現実を科学的態度で分析したり教えたりしたことがなかったということである。日本についての迷蒙というものは、日露戦争までの日本の指導層にはなかった。なかったからこそ、自分の弱さを冷静に見つめ、それを補強するための戦略や外交政略を冷静に樹立することができた。もし、日露戦争がおわったあと、それを冷静に分析する国民的気分が存在していたならばその後の日本の歴史は変わっていたかもしれない。(中略) 「戦勝国の歴史はあてにならない。戦敗国の戦史こそより多く戦争の真相を教える」ということばがある。 戦敗国のロシア側の資料はじつに役に立った。たとえばステッセルやロジェストウェンスキー、それにネガトフなどは戦後、裁判にかけられ、かれらが最善をつくしたかどうかについて軍事的な討議がたたかわされているだけに、戦勝国の場合よりも局面局面の事態や両軍がとった処置についての価値観がよりくっきりしている。ロシア側の従軍者たちの手記はじつに客観的態度に富んだすばらしいものがいくつかあって、それらを読んでいるうちに当時のロシア人の民度についてわれわれの既成概念を是正しなければならないと幾度もおもったかわからない。 当時のロシアの状態というのは、たとえば日本の文学青年にとって永遠の存在であるかもしれないドストエフスキーでさえ、ロシアのアジア侵略の支持者で、ただしその理由はすこし風変りであった。 「ロシアはヨーロッパ圏においてはばかにされる。しかしアジアへゆけばりっぱにヨーロッパ人で通る」 という意味のことをどこかに書いていた記憶があるが、しかしこの戦役に参加した記録を残した士官たちとなるとべつで、かれらは自分たちの軍隊にたいして、すくなくとも昭和期になって国家感覚がペリー来航当時に逆行してしまった日本の陸軍軍人たちよりは客観的であり、国家という存在に対して昭和期の軍人よりも知的なとらえかたをしていた、 だからロシアは敗けたのだということは通らない。当時のロシアはあらゆる国家機構が老朽しきっていた段階で、日本は逆にこの戦役より三十数年前に革命をおこし「国民」が成立し、すべてが新品の国家だったわけであり、自然ひとびとは国家に対してロマンの最高の源泉をもとめていたし、国家機構も機能的に作動していた時期であった。戦敗の原因をもっと大ざっぱにいえといわれればそう答えるしかない。日本人がとくにすぐれていたわけででもなく、ロシア人がとくに愚どんであったわけでもないのである。ただロシア国家は老朽化しているいるために愚どんであった。信じられなことだが、ロシア帝国は相手の日本帝国に対して無知であった。日本の内閣の良否や司令官たちの個々の能力、国民の意識や社会制度、あるいは陸海軍の練度や戦術上の得手、ふ得手もしくは慣用癖などをほとんど調査していない。 「信じられないことだが」と書いたが、世界史のなかですくなくとももう一例、帝政末期のロシアとそっくりの愚どんさを示した国家がある。太平洋戦争をやった日本である。上のようなことを昭和期の日本は敵国であるアメリカについてほとんど調査することなく対米宣戦を布告した。そして負けた。日露戦争前あるいは戦中においてあれほど慎重きわまりない手配りをやったおなじ日本とはとても思えないほどのことだが、国家機構というのは三十数年であれほど老朽化するものだろうか。老朽化した国家機構というのは、みなそのように愚にかえってしまう運命をもつのかもしれない。 レニンは日露戦争についての世界史的評価を最初にやった人であった。 ところが、レニンを革命の父とするその後のソ連にあっては、おそらくスターリンがそれをやったのであろうが、日露戦争をロシアの歴史からほとんど抹殺した。教科書でも数行書かれているだけだということであり、国立海軍博物館でも、ロシア国家が経験した海軍の歴史を図式化したり、物品を展示したりしているが、世界の海軍史上最大の海戦である日本海海戦というのは消されてしまっている。年代表においても展示物においても日本海海戦がまったくないそうである。 私はこの作品を書いているときソ連に取材しにゆこうとおもいつつ果たせなかった。他の取材手段によって海軍博物館や教科書の現状を知ったのだが、要するにソ連のすくなくとも海軍博物館においては、昭和前期の日本にノモハンの敗北が"存在しなかった"ように日本海海戦が存在せず、いまも存在していないのである。 国家というものはまことに奇妙なものである。それが社会主義国であろうがなかろうが、体制に変わりなく奇妙なものであるらしい。私はこの作品を書くにあたって日露いずれもえこひきせず、人類がもった一時期の一局面という立場で公平に見ようとしたつもりである。戦前ならこのように書くことは困難であり、いまソ連で書かれることも困難であろう。私も日本の現実に多くのふ満をもっているひとりだが、その意味での現状には満足している。(中略) 日本は維新後、西洋が四百年かかった経験をわずか半世紀で濃縮してやってしまった。日露戦争の勝利が、日本をして遅まきの帝国主義という重病患者にさせた。泥くさい軍国主義も体験した。それらの体験と失敗のあげくに太平洋戦争という、巨視的にいえば日露戦争の勘定書というべきものがやってきた。 日本人が幕末から維新という、はじめて国際環境に参加したときの反応は、社会全体が一個の精神病にかかったような状態だった。攘夷的ヒステリーも開国論的臆病意識も、夜郎自大的な徳川社会人が、にわかに国際環境を知ることによって日本の意外な脾弱(ひじゃく)さを知らされたための病的現象であったとみたほうがいいかもしれない。その脾弱感という国家をあげての病的意識からのがれるための唯一の道が『富国強兵』というものだった。国是というよりも多分に国家をあげての信仰というべきものだった。 その信仰が、維新後三十余年で、当時世界最大の軍事国家のひとつでであるロシアと戦い、勝つことによって信仰のあかしを得た。帝政ロシアの極東侵略に対し日本がそれを戦争のかたちではねかえすことができた最大の理由をあげよというならば、日本政府も国民も、幕末以来つづいてきた日本の脾弱感をもっていたためであり、このため弱者の外交という、外交としてはもっとも知恵ぶかいものをやり、他の列強の同情を得べく奔走し、同情と援助を得ることに成功した。要するに脾弱感が勝利の最大の原因であった。 ただし、勝ったあと日本がいかにばかばかしい自国観をもつようになったかは、すでに知られているところである。脾弱感の裏返しは、現実的事実認識をともわない強国意識であった。やはり国家的な病気がつづいた。日本はたとえば帝国主義という、西洋が数世紀かかってやったものを、その終末期においてわずか半世紀でばたばたとやってそのあげくが太平洋戦争であった。われわれはヒトラーやムソリーニを欧米人なみにののしっているが、そのヒトラーやムソリーニをすら持たずにおなじことをたった昭和前期の日本というもののおろかしさを考えたことがあるだろうか。政治家や高級軍人もマスコミも国民も、神話化された日露戦争の神話性を信じきっていたし、自国や国際環境についての現実認識をうしなっていた。日露戦争の勝利はある意味では日本人を子供にもどした。その勝利の勘定書が太平洋戦争の大敗北としてまわってきたのは、歴史のもつきわめて単純な意味での因果律といっていい。 日本人は、事実を事実として残すという冷厳な感覚に欠けているのだろうか。時世時節(ときよじせつ)の価値観が事実に対する万能の判定者になり、都合のわるい事実を消す。日露戦争後の陸軍戦史もそうであった。太平洋戦争後も逆ながらおなじことがおこなわれ、いまもおこなわれている。事実は、文献の面でも、物の面でも、すべて存在したというものは残すべきである。いやな事実も、それが事実であるがために残しておくというヨーロッパの国々でみられる習慣に対しわれわれは多少の敬意をはらってもよさそうに思える。
ともあれ、機関車は長い貨物の列を引きずって通りすぎてしまった。感傷だとはうけとられたくないが、私は遠ざかってゆく最後尾車の赤いランプを見つめている小さな駅の駅長さんのような気持でいる。
平成二十八年二月二十八日 |
26 司馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版
|
雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。「ますらおぶり」「たおやめぶり」忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 忠義と裏切り 馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版 雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。「ますらおぶり」「たおやめぶり」忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 忠義と裏切り P.66~69 キーン 前から司馬さんにうかがいたいと思っていたのですが、日本史を読んでおりますと、源平時代から戦国時代まで、いろいろな合戦がありましたが、だいたい何によって勝負の結果がきまったかというと、裏切りだったようです。中国の場合ならば、こちら側が孫子の兵法に従って攻撃し、巧妙な方法だったから勝った、ということになるわけですが、日本の場合は、いちばん決定的な瞬間にだいたい裏切者がいて、反対側に寝返ったために勝ったり敗けたりということになるように思われるのです。壇ノ浦とか関ケ原とか、みんなそうではありませんか。私にはその日本人の戦の勝ち方、敗けっぷりがどうも理解できないところがある。どう納得したらよいのでしょうね。ただ、一つの歴史的な事実として認めるほかないのですが、これにはなにか意味があるかもしれない。 司馬 そのとおりです。合戦のいちばんピークの段階で必ず裏切者が出てくる。その裏切者が裏切者として、のちのちまで非難攻撃されるかというと、されていないですね。おっしゃった壇ノ浦の戦いでも、いまの大分県あたりの武士たち――緒方党など――が、はじめは平家についていて、次に壇ノ浦の段階では源氏に寝返っている。だから、舟の数が源氏のほうがおおくなったんです。関ケ原だってご存じのように裏切りでしょう。 これはやっぱり同族社会で、たいてい親類か縁者になっている。時節時節の何らかの理由で敵味方に分かれているが、そのわかれ方も明快な理由じゃないのですね。日本人の場合には、たとえばそこに宗教ががんとあって、あいつはカトリックで、おれはプロテスタントだというような、そういう明快な戦争というものはないのです。一向一揆があったというけれども、あれはちょっとちがうもので、これはこの話の主題の中に入ってこれないものです。ですから、一般にこっち側の親類縁者のグループと、あっち側の親類縁者のグループが戦争する場合に、だんだん状況が白熱してきて、どっち側が内部的に切り崩したほうが得だというときがくるんです。すると、「それじゃおまえ裏切るか」ということで裏切っちゃう。同じ基盤でやっているんですね。ですから、ほんのすこし前の時代まで、たとえば昭和初期の左翼運動だって、検事が左翼の青年か共産党員を検挙して、いろいろしゃべっているうちに、「おれとおまえとは高等学校はおなじだったな」というようなことで、だんだんうちとけて、なんでもなくなってしまうというようなことが、ままあった。妙な例ですが、そういったことがだいたい日本の戦争に多いです「 たとえばヨーロッパで、ウオーターローで大きな戦いがある。あれは結局プロシァ軍がイギリス側についていて、プロシァ軍がどこに現れるかということで勝負がきまるわけです。結局プロシァ軍が現れて、ナポレオンは切り崩されるわけですけれども、あれも明快ですね。プロシァ軍は裏切っていないわけですから、これはウェリントンの同盟軍でって、しかも隠してある軍隊だと、戦術的にじつに明快です。 ところが、関ケ原の役というのは、ウオーターローの戦いと較べてみても、世界史的に見ても相当大きな合戦です。だから、大いにやればいいのに、午前中までは西軍の勝ち、午後になったら東軍が勝つ。その間に裏切りがあるということですから、そういう意味では合戦としてのおもしろみがない。ところが、日本人にとっておもしろいのは、つまりそれに至る舞台裏の話であって、関ケ原合戦そのものはページェンㇳ (pageant)にすぎない。すでに小早川秀秋は、秀吉の未亡人北の政所(まんどころ)から、東のほう、家康さんのほうへおつきなさいと耳打ちされておって、どうしょうかと思っているうちに、家康のほうから強硬な使いが来て、おまえ、裏切るという約束をしていたけれども、いっこうに裏切らないじゃないか、とせまられて、それじゃしようがないといって裏切っちゃう、ということであって、要するに戦争そのものはページェンㇳなんです。話の筋は前日までにきまっている。むしろドラマは戦争そのものよりも、戦争の楽屋裏にある。 これは私がよくしゃべっていることで、もう一度しゃべるのはテレくさいのですけれども、明治十七年だったかに、モルトケの愛弟子でメッケル少佐というプロシァ陸軍の参謀将校が、日本に招かれてやってくる。それで日本でドイツ式の参謀本部を作ったわけです。それが関ケ原の古戦場に行って参謀のための現地教育をしたときの話です。メッケルはだいたい両軍の布陣を聞いて、「石田方の勝ち」と言うんですよ(笑い)。メッケルはもちろん日本史の知識はまったくないわけですね。そこで他の日本人が、「いや、じつは石田方は負けているんです」。「そんな馬鹿なことは考えられない。この配置からいったら、石田方は勝つ態勢をもっているから、石田方の勝ちだ」と言う。「いや、じつは負けているんです」。「それはどういうわけだ」と言っていろいろ質問するので、「舞台裏がこうだった」と説明すると「それならしようがない」とはじめて納得したそうですけれど、日本人にとってだいじなのは、いわゆる舞台裏なんですね。根まわしみたいなものです。 |
|
たまたま書棚に「朝日新聞 天声人語’92秋[英文対照]原書房」をめくっていると、「大山康晴 十五世名人の将棋人生」の記事があったので紹介します。 将棋の十五世名人、大山康晴:1923年(大正12年)3月13日 - 1992年(平成4年)さんが六十九歳で亡くなった。名人、王将位などのタイトルを通産八十期獲得、『受けの大山』と評され、最後まで現役だった。 岡山県の西阿知という、今は倉敷市の一部になっている町の生まれだ。自伝によると勝負ごとの盛んな土地で、小さい時から将棋で遊んだ。本将棋を覚えたのは、七歳の時。父親は才能を伸ばそうとした。 小学校一年の三学期に近くの平井先生の家に将棋を習いに通い始めた。真に強くなるためには、基本定跡を覚える。これが先生の方針で、城跡を暗記して勉強した。四年生の時、担任の教師から「将棋をやめて勉強したらどうか」と言われた。 算数の成績がよい、勉強すればそろばんの先生になれる、とも言う。そいうものか、と将棋を休んだ。それを知った父親が、怒って教師の家に飛んでゆく。将棋を覚えるのに今が最も大事な時期だ、あなたは教師として勉強しろと注意すればよい……。 卒業と同時に大阪の木見金治郎八段に弟子入りした。学友が駅頭に送りに来た。立てたのぼりに「大山少年入門」「行く先は花がある春の山」。入門した日に大山さんは五歳上の内弟子、升田幸三二段と角落ちで三番さして全敗する。 木見八段の方針は、私は教えない、自分で調べてわからぬところがあれば聞きに来い、だった。升田さんとはそれ以来の仲で、ともに競った。よき理解者としての父親と確固とした方針をもつ師、そして腕を磨き合う格好の相手に恵まれていた。 それに自らの不屈の精神と精進を合わせたのものが大山さん将棋人生だろう。新しいタイトルに挑戦することを「苦しみではなく、喜びであるはず」と考え「頂上に登りつめれば、いずれは下がることときがくる」と不断の努力を自分に強いた。 「将棋史上、最強の棋士といってもいい」と中原誠名人はきっぱり評している。
GRAD MASTER OKAYAMA The 15th grand master of shogi, Yasuharu Oyama, died at the age of 69. He won titles such as grand master and king a total of 80 times. He was called "Oyama of defense" and was on the active list until his death. He was born in Nishiachi, which is now a part of Kurashiki City in Okayama Prefecture, According to his autobiography, games of skill were very popular in the town, and he played shogi from time he was small. He began learning real shogi when he was seven, and his father tried to develop his talent. In the third semester of his first year in the primary school, he begun going to the home of teacher Hirai nearby to learn shogi. In order to become really strong, one must commit to memory all the set moves. This was teacher's policy, so Oyama memorized the set tactics and studied hard. When he was in the fourth grade in primary school, his home teacher said, "You should stop shogi and concentrate on your studies." The teacher also said that since his arithmetic grades were good, he could become an abacus teacher if he studied hard, Consequently Oyama stopped to learn shogi. Learning about this, his father angrily rushed to the teacher' home and said, "Now is the most important time for learning shogi. As a teacher, all you have to do is tell him to study." As soon as he graduated from primary school, he became a pupil of 8th dan Kinjiro Kimi of Osaka. Classmates came to the train station to send him off. They carried banners which said, "Boy Oyama Becomes Pupil," and, "Where he goes/There are flowers/Spring mountain" The day he became Kimi's pupil, he played three matches with 2nd dan Kozo Masuda lacking a bishop, and lost all three matches. Kimi's policy was, "I do not teach. Check yourself and if there is something you cannot understand, then come and ask me." He has been friends with Masuda ever since, and they competed with each other. He was blessed with a father who really understood him, a firm teacher and a suitable opponent with whom he could mutually hone skills. The combination of his indomitable spirit and diligence probably defines the shogi life of Oyama. He felt that challenging a new title "was not a hardship, but should be a joy." Considering that "if you rise to the top, the time will eventually come when you will come down," he forced himself to exert efforts every day. 朝日新聞 天声人語’92秋[英文対照]原書房
棋士と棋風 いまの、棋士と棋風の話からはじめますか。もっとも将棋は、その人の人格がでますから、人間の話になるかもしれんが。 いま名人をやっとる中原誠君、強い人ですから大山康晴君とよく似とるが、ただ、自然体といいますかーー大山君のは将棋にたいする意地みたいなものがありますが、中原君のは素直というのか、おとなしい。将棋の理屈だけを追求するというタイプです。 だから大山君の将棋の場合は、数手みただけで、”これは大山だ”ということがわかるんですが、中原君の場合は規則どおりーー規矩に従った学者的な将棋ですから、それがみんな、自然流というておる。自然の法則に従うということです。 だからすべて、会議にしてもなんにしても、意をだした発言はありません。 これは元来、頭のいいところへ加えて、家庭環境ということでしょうか。家庭をのぞいたことはありませんが、そうだと思う。お父さんが郵政省だかのお役人でーー電話のほうだというから今は公社で役人とはいわんが、鳥取か島根のほうで生まれて、小さいときにお父さんの転勤で仙台へこられた。だから宮城県出身というが、単なる素朴な東北人というわけでもない。西日本も入っておる。東北も入っておる。そして東京にも長く住んでおる。そういう家庭環境ですね。 中原君の師匠は、高柳敏夫君(八段)です。いや、師匠のクセなどというものは、全然ありません。 これはね、ぼくの場合も、師匠の棋風というものはなにもない。大山にもない。支障がウンと強けりゃその棋風を学んだかもしれんが、弱いんだから、そんなものを学んだらもうあかんヮ。 いや、弟子は師の半芸にも及ばずとかいいますが、たとえいくら師匠が強くても、それはぼくの将棋であり、大山の将棋であり、中原の将棋でなけりゃいかん。そして師匠というのは、大橋宗桂(初代名人、慶長年間=一五九六~一六一〇)や坂田三吉や、その他いろんな先輩の将棋が師匠になっとるわけで、ほかのふ純物はいらんのだから。 まあね、棋士にとっては、あらゆる先人が残してくれた棋譜が師匠になりますが、しかし師匠には弟子運というのがあります。師匠が強いかたといってもかならずしも弟子が強くなるとは限らない。むしろ逆の場合が多い。 これはつまり、横綱でなく、小結とか関脇で終わった親方が、自分の果たせなかった夢を弟子にたくして、稽古なんかも必死に教えこむ、そういうのと同じことが、われわれの世界にもありますから。人間の心は、将棋の世界でも相撲でもその他でも、あまり変わらん。ただ、師匠がえらいと、その顔とヒキで弟子もえらくなれる、という社会のことはどうか知りませんが、われわれの世界にはそんなものは通じない、自分の実力だけだから話が簡単だヮ。 ま、強い弱いじゃなくて、弟子に自信をもたせて個性をのばしてくれる師匠、これがいい。師匠運がいいというのは、それですね。 升田幸三『王手』”ここ一番”の勝負哲学(サンケイドラマブック)昭和五十年九月より 将棋ソフトと将棋名人の勝負 将棋ソフト、佐藤名人を破る 電王戦第1局 、また囲碁の世界でもAIとの勝負が話題になっている。下記の記事をご覧ください。 参考:AI人工知能(Artificial Intelligence)について 平成二十九(2017)年四月十七日
(天声人語)14歳棋士の快進撃 2017年4月30日05時00分 公開中の映画「3月のライオン」の主人公は10代の棋士だ。家族を交通事故で失うも、中学在学中の15歳でプロとなる。孤独とふ振を乗り越え、棋界のトップに挑戦する。 ▼親子ほど年の離れたベテランを、涼しい顔で打ち負かす。その姿を映画館の客席で見て思い浮かべたのは中学生棋士、藤井聡太四段である。昨年暮れ、62 歳上の加藤一二三(ひふみ)九段を打ち負かした。非公式戦とはいえ、棋界の第一人者羽生善治三冠も破った。現実がフィクションを追い越してしまった。 ▼愛知県瀬戸市の中学3年生。5歳で祖母に駒の動かし方を教わり、小4で棋士養成機関の奨励会に入る。史上最年少の14歳と2カ月でプロに。「タイトルを取りたいが、いまはまだ棋力をつける時期。もっと精進して強くなりたい」。受け答えも頼もしい。 ▼ふだんは、学校から帰ると朝日新聞を開く。時事問題に関心があり、お気に入りは「特派員メモ」や「患者を生きる」と聞くと、新聞を作る側としては励まされる。愛読書は司馬遼太郎や沢木耕太郎だそうだ。 ▼その沢木氏に「神童 天才 凡人」という短編がある。神童と言われた中原誠十六世名人が高校時代に直面した苦悩を描く。勝負の世界ではどんな逸材も一度は壁にぶつかる。乗り越えた者だけが真の天才と呼ばれるのだろう。 ▼破竹の勢いの藤井四段だが、いつかはつまずく日もあろう。映画の主人公も失意の淵(ふち)をさまよった末に再起する。タイトル戦に挑む目は、冬に耐えた者特有の光をたたえていた。 平成二十九(2017)年四月三十日
余録 プロデビューしたころの将棋をふりかえって…毎日新聞2017年12月6日 東京朝刊 プロデビューしたころの将棋をふりかえって羽生善治(はぶ・よしはる)さんは「無理が通れば道理引っ込む」と評している。実に荒っぽい感覚だけで勝っていたという。1手の水面下に潜む膨大な思考に思いが及んだのは後年だった ▲「盤面が大海原(おおうなばら)に見える」と語ったのは将棋界の7大タイトルを手にした後のことである。指し手とは「大海原」のなかのただ一本、ある場所からある場所へ行く航路を一つ見つけただけで、他の道は実際行ってみないと分からない ▲将棋の局面変化は実に10の220乗通りで、大海原どころか全宇宙の原子の数よりはるかに多いという。その宇宙でただ一つの航路を描き続けてたどりついた前人未到(ぜんじんみとう)の永世7冠の頂点である。竜王戦七番勝負を制しての快挙だった ▲羽生さんが永世6冠となったのは9年前だ。この偉才にして永世7冠までにたどった道のりの長さは、成しとげたことの至難を示す。またそれは将棋界が人工知能(AI)に挑戦された9年間だった ▲羽生さんはかつて「神様と将棋を指して勝てますか」と聞かれ、「神様が角落ちなら勝てる気がする」と答えたことがある。ここで言われているのは互いに手の内をさらす理詰めのゲームである将棋は神も人もAIも特別扱いのない透明で対等なゲームということだ ▲盤上の宇宙に知力と霊力を尽くす棋士、そのたたずまいの美しさを自ら示してきた羽生さんの永世7冠への歩みだった。いつの日かAIは「力」と「品位」が一体化した永世7冠を夢見るのだろうか。 |
29外山 滋比古 (1923~年)
30 竹下 哲(1923~年)
|
▼『心のうた』長崎出版文化協会(昭和55年9月30日 初版) この本よりごく一部を抜粋します その一 せんせい はしがあるよ 「無財の七施」ということがある。何をもたなくれも、無一文でも、七つの施しができるのである。たとえば「眼施」がある。あたたかい、やさしい目をすることである。とげとげしい、冷たい目をしないことである。これなら、財産がなくても、だれでも直ちにできる。また「顔施」というのがある。なごやかな、にこにこした顔をするbことである。明るい笑顔は、まわりの人々をあたたかくする。無一文でできる施しである。 この「七施」のなかに「捨身施」というのがある。友のために、みんなのために身を捨てることである。コルベ神父の生涯は、この「捨身施」の典型とも言うべきであろう。 第二次世界大戦中のナチス・ドイツの残虐ぶりは、人類史上最大の汚点として永遠に残るであろう。そのうちでも、アウシュビッツ強制収容所の言語を絶する殺りくは、われわれの心を寒々とさせるものである。 一九四一年(昭和16年)七月のある日、アウシュビッツ強制収用所からひとりの脱走者がでました。ナチスは、見せしめとして無差別に十人を選び、餓死刑を課した。指名され、死を宣告された十人の中のひとりが「かわいそうな妻と子どもたちに、もう一度会いたい。」と叫んだ。 すると突然、ひとりの男が進み出て身代わりを申し出た。ポーランド生まれの神父マクシミリアン・コルベである。囚人番号一六六七〇号と呼ばれる彼は、約十日後餓死牢の中でその一生を閉じた。 われわれは不思議な縁で教育者となった。われわれの前には、かわいい子どもたちがいる。この子どもたちのために身を捨てる覚悟をしたらどうであろうか。かき集める方向ではなく、身を献げる決意で行動したらどうであろうか。コルベ神父のような崇高な行為はできないにしても――。 せんせい はしがあるよ せんせい はながさいているよ せんせい はんからおとしちゃった せんせい おべんとうにしてよ せんせい バナナはんぶんあげるよ 小学校一年生の「えんそく」と題する詩である。こんな純情な子どもたいを前にしながら、なおかつ拱手傍観している者があるなら、それは人生の生きがいというものを知らない人であろう。 捨身・献身ということを、しきりに思うこのごろである。P.9~11
(47.11.15)
以上の原文をフランクル『夜と霧』で一応探してみたのが見当たらなかった。 感想:この文章を読みながら、尊敬している先生が公立学校を退職され、再度、教鞭をとられたキリスト教系の学校の校訓は「心を清くして 愛の人であれ」であり、生徒の一人が先生への感想文に三浦綾子『塩狩峠』の主人公のようなひとになりたいと書かれていたとのことでした。 参照:『塩狩峠』三浦綾子 また、洞爺丸事故における外国人の献身的行為を思い出しました。 インターネットに記載が沢山ありますからお読みください。 参考:カルネアデスの板の記事の中に「洞爺丸事故」での捨身の行為をされたアメリカ人宣教師・ディーン・リーパーがいました。 2008.4.15、2017.04.19追加。 その二 一枚の紙片 宮崎での会議を終えて、今朝、飛行機で帰ってきました。宮崎では、M会館に宿泊しました。 昨夜は、別室で懇親会があるというので、部屋にカギをかけて、その会に臨みました。会がすんで部屋に帰ってみると、すでに布団が敷いてあります。見ると、卓上に一枚の紙片が置いてあります。それには次のようなことばが書いてありました。 お留守でしたので、失礼して合カギであけ、お床をのべさせていただきました。 おやすみなさい。 一読して、ほのぼのしたものが胸の中にあふれてくるのを覚えました。ひとことばのあたたかさ、重さをしみじみと感じました。 それにつけても思い出すのは、広島大學の藤原与一先生の次の一文です。 ほんのわずかなことばづかいによっでもずいぶん、心のこまやかさを表現することができるものである。友人から聞いた話だが、かれが旅から帰ってのこと、「あさっては、ぼくの誕生日だね。」と言ったそうである。それに答えて細君は、「そうですよのよ。」と言ったという。聞いた私は、いいことばだなあと思った。「そうですよ。」でも、ひとかどの返事ではあったはずだが、「そうですのよ。」と答えたのは、やはり、その細君の心づかいのこまやかさ、しぜんの深い愛情であった。「のよ」がまさに、「愛のことば」だおと思われる。━━ひとことばが、だいじである。> いいお話ですね。こまやかな心づかいですね。 ことばなどに神経を使わないでも、と言う人がいます。でも、ひとことばが重大なのです。道元禅師は、「愛語よく回天のちからあることを学すべきなり。」と言っています。ひとことばが、世間の他の大きな事業と比べて軽いなどと、どうして言えるでしょうか。 福井市に住む医師の米沢英雄さんは、「桜や牡丹は花の中の王者であって、雑草はつまらないというのは、あくまで人間の判断であり評価である。大宇宙からみれば、あるいは、人間を超えた仏の立場からみれば、ひとしく生きとし生けるものであって、その間に優劣はないのだ。雑草は、桜や牡丹に対して卑下したりしてはいない。」と言っています。 そうです。雑草と桜や牡丹との間に優劣はないのです。おなじように、ひとことばが他の事業よりも軽い、ということは決してないはずです。 ひとことばの重みを大切にする――そこに、国語教育のかなめがあります。そこに、真の意味の「人間教育」があります。P.73~75 (54.1.19 高校国語教育研修講座で) その三 愛惜の心 『遺愛集』という本がある。島秋人という死刑囚の詩集である。島秋人は昭和九年に生まれ、幼少を満州で育った。病弱で結核やカリエスになり、七年間もギブスをはめて育った。そのため、小学校、中学校を通じて、成績は一番下であった。周囲からうとんじられ、バカにされて、性格も次第にすさんでいった。幼年院にも入れられた。 昭和三十四年のある雨の夜、空腹にたえかねて、ある農家に押し入り、二千円を奪った。その際、争って家の人を殺し、死刑囚として入獄。昭和四十二年十一月二日、小菅刑務所で処刑された。わずか三十三歳であった。 獄中、ふとしたきっかけで短歌を作るようになり、作歌を通じて心境も次第に深まっていった。 その歌は、当然に、罪をわび、世のために償いをしたいという歌が多いが、それとともに、毎日の生活をいとおしみ、いつくしむ歌が極めて多い。 愛に飢えし死刑囚われの賜りし菓子地に置きて蟻を待ちおたり まみ細め換気孔よりもるる陽を格子にのぼり顔に当てゐき 獄灯の下に病みゐて時をりの排水管の音に聴き入る 死を目前にして、一匹の蟻をいつくしみ、「換気孔よりもるる陽」や、「排水管の音」をいとおしむ切ない心が、これらの歌の底流にある。物質的な豊かさに幻惑されて、私どもが次第に忘れ去ろうとしている心である。 高度経済成長は、私どもの生活に物質的な繫栄をもたらした。しかしその繁栄は、もともと大量生産、大量消費であり、私どもに「使い捨て」を強いるものであった。その結果、ものをいとおしみ、いつきしむという、いわゆる愛惜の心が急速に失われていった。 『暮しの手帖』の第五十二号に、評論家の花森安治(1944~1978)さんが一つの意見を述べている。
もう五十年も六十年も昔の話ですが、ぼくが小学校に通っていたころには、サッカーのボールでも、二コしかありませんでした。それを大切にゆずりあって使い、終ったらきれいにふいて、元へもどせ、としつけられたものです。(中略) そんなにたくさんボールがあれば、遠くへけとばしたした場合、いちいち拾うのがめんどうで、またべつのボールを出して使う、ということはないでしょうか。━━ まことに傾聴すべき意見である。ものは多ければ多いほどいい、というわけではない。少ないボールを、「大切にゆずり合って使い、終わったらきれいにふいて、元へもどす」ことの中で、ボールに対する愛惜の心、ひいては敬虔の情が自然にわいてくるのであろう。私どもが、豊かな物質的繁栄と引き換えに、こういう心情を失ったとするならば、ことはまことに重大である。それは、人間が人間らしい心を失うことだから。 参考:とと姉ちゃん花森安治さんと関連して。 木村無想さんの「自炊」と題する詩に、 たなの上で ネギが 大根が 人参が じぶんの 出を待つように ならんでいる こんな おろかな わたしのために━━ というのがある。ネギや大根や人参を単なる「食料」とは見ないで、それらをいとおしみ、むしろそれらに合掌する心━━敬虔の情が、この詩の底辺を色濃く流れている。 また、榎本栄一さんは「ぞうきん」という詩で、 ぞうきんは 他のよごれを いっしょうけんめいに拭いている 自分はよごれにまみれている
とうたっている。
華やかな物質的繁栄に酔って、一切のものを利用価値でしか見ず、使うだけ使って「使い捨て」にしてきたところに、恐るべき心の荒廃が始まった。深刻な「人間喪失」が始まった。 もう一度、人間らしい心の原点に立ち還ろう。一輪の花、一粒の米をもいとおしむ愛惜の心━━敬虔の情を取り戻そう。そこから「人間」が始まる。P.125~129 (55.6.18 『長崎新聞』) 2008.4.15、2017.04.19追加。 長崎県社会教育長 竹 下 哲(さとる) 大正十二年長崎市生まれ。広島高等師範学校(現広島大学)卒業。長崎県教育長、県立長崎図書館長、県教育センター所長、県立諫早高等学校長、県立長崎西高等学校長、長崎県社会教育委員長を歴任。著書に「心のうた」「いのちのうた」「くらしのうた」他。 竹 下 哲 と金 光 寿 郎 対談 金光:今日は長崎市にお住いの竹下哲先生にお越し頂いております。竹下先生は長い間、県の教育委員会のお仕事や高等学校の校長先生などのお仕事をなさっておいでになった方で、その間に探求され実践されてきた人間の生き方について、いろいろお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 竹下:どうぞよろしく。 金光:今日のテーマは「二度、生まれる」ということになっているんでございますが、その一度目のお生まれは、いつ頃、どちらでお生まれになったんでございましょう? 竹下:大正十二年、長崎市で生まれました。それでもう六十九歳になってしまいました。 金光:お生まれになったご家庭は、どういうご家庭だったんでございましょうか? 竹下: 私の家は四人兄弟でございまして、私が長男でございます。父は国鉄に勤めておりまして、駅長なども致しておりました。そういうことで、大変質素な堅実な家庭でございました。父も母も念仏者でございまして、そのために家庭には宗教的な雰囲気が漂っていた、と思います。それが大変有り難いことだ、と今にして思うのです。 金光:しかし、子どもの頃はあんまりそういうのが、あまり有り難いとも、おそらくお感じにはならなかったと思いますが、子どもの頃の竹下哲少年はどういう少年だったんでございましょう? 竹下:そうですね。腕白で遊ぶのが好きで、山や川を跋渉(ばっしょう)してですね、そんな生活を致しておりました。 金光:だんだん大きくなられて、自分はこういう方向にいけばいいんじゃないか、というふうにお考えになるようなきっかけがいくつかおありだったと思うんですが、最初にどういうところで、よし、こういう方向にいってみよう、とお考えになったんでございましょうか。 竹下:中学校三年生の時に、母が、「今日は偉い方がおいでになって、仏教の講演会があるから、お前、学校の帰りに聞きに行きなさい」というのです。それで、私、カバンを小脇に抱えて、半ば義理で講演を聞きに行ったのです。その時の講師が山本晋道(やまもと しんどう)という先生でいらっしゃいまして、大変頭の切れ味の鋭い、情熱的なお話をなさいました。今思いば、『歎異抄』の第二章のご講義だったのです。私は、内容は十分には勿論理解できませんでしたけれども、先生のお人柄、直向(ひたむ)きなそのお姿、そしてご承知の通り、『歎異抄』第二章は、「おのおの十余(じゅうよ)か国のさかいをこえて、身命(しんみょう)をかえりみずして、たずねきたらしめたまう御(おん)こころざし、ひとえに往生極楽のみちをといきかんがためなり。」で始まりますね。「身命(しんみょう)をかえりみずして」―命懸けで、というところに強く打たれまして、その一言が少年の私の心を貫いた、とこういってもいいかと思います。その時何か人生の方向が定まったという、そういう実感が致しました。 金光:山本晋道という方はどういう方だったんでございますか? 竹下:この方は、在家の方で、東大の英文学科をご卒業になりまして、旧制中学校の英語の先生だったんです。頭のいい、情熱的な、また正義感の強い先生でした。しかし、人生は正義感が強いとか、情熱だというようなことでスムーズにいくわけじゃありませんで、いろいろなことで行き詰まられたんですね。その時に、川を隔てて、お寺から鐘が鳴り響いてまいりまして、その鐘の音を聞いて、「あ、お寺があるな。そこで自分の悩みを解決してくれるかも知れない」ということで、お寺に行かれたんです。そこの老僧にお会いされて、諄々とお話を聞かれて、その時に心が開けまして、そして、「そうだ。この道一筋に行こう」ということで、中学校の先生を辞めて、そしてお坊さんになって、山本晋道(やまもとしんどう)とな乗られたんです。中学校の先生をお辞めになったものですから、たちまちに家計が困難になります。一家路頭に迷うということになりました。先生はそれで野菜を担いで、野菜の行商をされたんです。それほど徹底した方でしたね。やがて梅原真隆(うめはらしんりゅう)(1885-1966)先生に師事されて、そこで勉強されまして、そして福岡とか長崎とか、或いは熊本なんかに聞法(もんぽう)道場をお作りになりまして、そこでお説教をなさっておりました。私はたまたま福岡で生活を致しておりまして、福岡で始めて先生のお話を聞いた、というふうなことでございます。 金光:そういういわば体当たりで道を求められる方のお話だっただけに、非常に印象が深かった、ということだと思いますが、その中学校で、「ああ、こういう生き方があるんだな」ということをお感じになった後、今度は大学はどちらへお行きになったんでしょうか? 竹下:広島の高等師範学校に学びまして―今の広島大学の教育学部でございますが、そこでまたいろいろと先生方のお教えを頂きました。 金光:どういう先生方がその当時お出でになったんでしょうか? 竹下:広島はご承知の通り安芸門徒(あきもんと)の本拠地でございまして、念仏の声が町中に響き渡っているというふうな町でございました。そこで金子大栄(かねこだいえい)(明治十四年~昭和五十一年:仏教学者・真宗僧侶)、藤秀すい(しゅうすい)(明治十八年~昭和五十八年:広島文理科大学講師・真宗僧侶)、白井成允(しらいしげのぶ)(明治二十一年~昭和四十八年:倫理学者・元京城帝大教授)がおられました。(註:」「藤秀すい」の「すい」は、「王」偏に「翠」と書く) 金光:いずれも非常に有名な学徳兼備な方でございますが、その金子先生の講義は学校でお受けになったんでございますか? 竹下:いいえ、そうではありません。私は国文学の専攻なものですから、直接に先生の正式の講義に座ってお話を承ったということではなくて、随時仏教の講演をなさっておられまして、そのご講演を拝聴した、ということでございます。 金光:藤秀すい(しゅうすい)先生は講師をなさっていたそうですが、藤先生とはどういうご関係であるんですか? (註:「藤秀すい」の「すい」は、「王」」偏に「翠」と書く) 竹下:藤先生のお話も、学校でも随時伺いましたけれども、特に先生のお宅に何度もお伺いして、いろいろと懇切に教えて頂きました。今思うと、ほんとに若造の私に懇切に教えで下さいまして有り難かったなあ、と思うのです。 金光:白井成允(しらいしげのぶ)先生も非常にたくさん感化を受けた方がお出でになる方でございますが、白井先生とはどういうご関係であったんでございましょう? 竹下:白井先生も仏教の講演をあちらこちらでなさっておられまして、まだお若い先生でした。特に『歎異抄』の講義をなさっておられまして、そのご講義を胸を躍らせて伺ったものであります。思えば、いろいろの先生方のご縁に出会わせて頂いた、という思いがしきりにするんです。 金光:そういうご経験の後で、いわば決定的な影響をお受けになったのは、弟さんのご病気のことだ、と伺っておりますが、それはどういうことだったんでございますか? 竹下:弟は昭寿(あきひさ)と言っておりまして、私どもは「昭(あき)ちゃん、昭(あき)ちゃん」と言っておりました。昭和三十四年に体の調子が悪くなりまして、食欲がありません。それで、「昭ちゃん、どうしたんだ」と言いますと、「どうも食欲がないんだ。力がないんだ」とこういうのです。それで長崎に是真会(ぜしんかい)病院という病院がありまして、そこの院長先生が高原憲(たかはらけん)先生で、念仏者でいらっしゃいました。その先生に診て頂きました。胃を切り開いてみましたら、驚くことに、ガンは胃の全体を冒して、もう手遅れだ、というのです。後は死を待つばかりなんですね。家に連れて帰りまして、家で療養することになりました。刻々痩せ細っていきます。忘れもしませんが、昭和三十四年三月二十五日に、先生がお出でになりまして、ガンの宣告です。それこそ死の宣告をなさいました。「昭寿さん、あなたの病気は胃ガンなんだ。手遅れなんだ。どうかお念仏を申してくれ」とこういうお話でありました。 金光:しかし、言われた昭寿さんはまだ三十歳の若さでしたね。 竹下:ええ。三十歳でした。弟は静かに先生のお話を聞いておりまして、先生のお話がすんだ時に、「先生、有り難うございました」と。しみじみとお念仏を申すようになりました。そして、四月十七日に亡くなるんですけども、それまでの生活の見事なことですね。輝くばかりの生活を致しました。そして、四月十七日にだんだん呼吸が切迫してきます。母が弟の手を握りまして、「昭ちゃん、このまんまよ、このまんまよ。もうすぐ楽にさせて頂けるのよね。・・・ナンマンダブツ」とお念仏を申しますと、弟は目にいっぱい涙をたたえて母の顔を見つめておりました。やがて呼吸が衰えてきます。そして手を合わせて、かすかに呟くように、「ナンマンダブツ、ナンマンダブツ」とお念仏を申して亡くなりました。見事な往生でした。その弟が死の宣告を受けたその日から、「兄ちゃん、僕たちは『歎異抄(たんにしょう)』を今まで勉強して良かった。今から毎朝兄ちゃんが出勤する前、僕の枕元で『歎異抄』を読んで頂戴」というのです。私は毎朝弟の枕元で『歎異抄』を広げて読みました。悲しくてですね、な残惜しくてですね、三十歳の弟ともう別れるのかと思うと、涙が溢れてなかなか先に進みませんでしたけども、梅原真隆先生の現代語訳を読みまして、弟はとても喜びまして、頷いて聞いてくれました。 金光:その場合、弟さんは、いわば『歎異抄』の世界というのは、お浄土の世界ということだと思いますが、今日のテーマの「二度、生まれる」という、その実感というものをもう味わっていらっしゃったんでございましょうか。 竹下:ええ。そういうお浄土に目覚めて生きていったんだと思います。ですから、胃ガンですから、体の苦痛は酷いです。ですけど、心は安らいで、実にほんとに輝くような日々を送っておりました。弟ながら見事だ、と私は思いました。 金光:人間というものは、一度はどうしても死ぬという、そういう性質をもって生まれてきているわけでございますが、やっぱりその中でほんとに人間らしい生き方ができるようになるのには、ただ生まれて食べて亡くなるだけじゃ、ほんとの人間にはなれないということでございましょうか。 竹下:そうですね。人間以外の動物は、犬でも猫でも牛でも馬でも一回生まれただけで、間違いなく犬であり猫であり牛であり馬であるのです。ただ不思議にも人間だけは、一回生まれただけでは本当の人間にならない、と思うのです。二回目の誕生が必要だと思うのです。その二回目の誕生というのは、私に言わせれば、「仏法にご縁があって、お念仏を申す身にならせて頂くことだ」とこう思います。第一回の誕生はいうまでもなく、お母さんのお腹からオギャと生まれることです。それは生物学的には人間でしょうけども、まだ本当の人間になっていないんだ、と思うのです。第二回目の誕生が必要ですね。第二回の誕生で、「念仏申す身になるということは、本当の人間に生まれ変わることだ」と思うのです。もっというならば、目覚めてこの人生を生きていくんだ、と思います。よく宗教というのはうっとりして恍惚状態になるんだ、というふうに誤って言われておりますけども、そうではなくて、目覚めて生きていくんだ、と。是非そういう二度目の誕生が必要だ、と私は思っております。 金光:竹下先生にとっては、弟さんのガンの宣告を受けられて亡くなられるまでのご生活を見ながら、一緒に、しかも『歎異抄』などを読まれて生活なさったそのことが、その後の生き方というのに大きな決定力を持っていた、ということでございますか。 竹下:はい。今申しましたように、小さい頃から宗教的な雰囲気の家庭に育ちました。山本晋道先生によって点火されました。そして、金子先生、その他の先生方から導いて頂きました。そして決定的にしたのは弟の死ですね。弟が命を懸けて私に教えてくれたんだ、と思います。それで、二回目の誕生と言いましたが、さらに言いますならば、三回目の誕生があると思うんです。それは今生の命が終わって、お浄土に往生にして仏になして頂く。それが三回目の誕生であろう、というふうに私は思っております。 金光:今日は、二度の誕生ということがテーマになっているわけでございますが、じゃ、そういうお話を聞いて、自分もそういう人間になりたいと思う場合に、どういうふうに目覚めて生きていけばよろしいでしょうか。 竹下:それはなかなか難しいですけども、仏法に出会って、お念仏申す身にならせて頂くと、いろいろなことに目覚めることができるように思うのです。三つ差し当たってあげることができると思うんですが、その第一番目は、自分一人で生きているんじゃないんだ。みな一緒に助け合い、保ち合って生きているんだ、という目覚めを与えられるんだ。そういう目覚めを賜るんだ、というふうに私は思うのです。 金光:「みんな一緒」というと、人間みんな、という意味でございますか。 竹下:勿論人間も、あの人この人と一緒にだし、それだけではなくて、草木虫漁と言いますね。草も木も虫も魚も、馬も牛も諸(もろ)ともに一切万物が助け合いながら一緒に生きている、こういうふうに私は思うのです。そういうことになんか目覚めさして頂いた、という感じが致します。 金光:たしかに人間というのは、人間同士だけではなくて、空気にしても太陽にしても、いろんなものの中で頂いて生かされているということでございますね。 竹下:よく仏教で「重重無尽」の因縁(「華厳経」)と言いますね。それぞれ重なり合い繋がり合って助け合いながら生きている。それを「重重無尽(じゅうじゅうむじん)」というお言葉があります。そういう存在として、私も生き、あなたも生きているんだ。それの自覚というものが大事ではないでしょうか。 金光:そういう自覚があれば、草や木も人間の都合のいい時にだけ勝手に使ってしまうということにはならないわけでございますね。 竹下:そうだと思いますね。今どんどん木が切られております。「地球温暖化」というふうに言われております。やっぱり木を大事に、花を大事に、動物を大事に、一緒に手を握って生きていく、ということが大事だと思うんですね。 金光:これは現代たしかにその通りだと思うんですが、もっと以前にもそういうことにちゃんと目覚めて述べていらっしゃる方も当然お出でになるわけでございましょうね。 竹下:仏教の先覚者はみんなそうなんですけども、近いところでは有名な宮沢賢治ですね。宮沢賢治も仏教に生きた方ですけれども、宮沢賢治(1896-1933)の言葉に、 世界がぜんたい 幸福にならないうちは、 個人の幸福は あり得ない (宮沢賢治) 参考:論文『農民芸術概論』の序論には、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」いう有名な文章がここにあります。 こういう有名な言葉があります。自分一人幸福になることはないのですね。世界全体が幸福になって、はじめて自分の幸福もあるんだ、と。ですから、例えばベトナムとかカンボジアで難民があるということは、私たちもやっぱりふ幸でもある。或いはアフリカで飢えている人がいる、ということは、私どもの痛みでもある。みんな一緒に生きているんだ。そういう自覚が大事なことだ、と思っております。 金光:「重重無尽」という言葉を、今の言葉で言い換えられたのが、「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない」というふうに考えてもいいわけでございますね。 竹下:はい。そうだと思います。 金光:今、宮沢賢治の例が挙げられたんですが、他の方も随分おっしゃっているわけでございましょうね。 竹下:ええ。たくさんの方がおっしゃっていまして、例えば広島時代に学びました金子大栄先生はこうおっしゃっています。 露しげき雑草の土に帰することなくば 巨木も生い立つにところがない というお言葉があります。露をいっぱいはらんでいる雑草ですね、やがて土になります。その土を土台として大きな巨木が亭亭(ていてい)と聳えているんですね。だから巨木は雑草に手を合わせる必要があると思うんです。また雑草も巨木が葉を茂らせて秋になると葉を落とします。それが土に帰って養分になります。その養分を頂いて雑草も生きるんですね。お互いに保ち合って、お互いに合掌しあって生きていく、ということが道理のある世界ではないでしょうか。 金光:そういう目でみると、草も木もそうですけれども、いろんな新しい気付きというのがあるわけでございましょうね。 竹下:卑近な例ですけども、ご承知の通り長崎は坂が多いのですね、石段が多いのです。先だって、石段の上の空き地に家が建ちまして、新築工事が始まっているんです。ふと見ておりましたら、馬が―小さな馬なんです。対馬(つしま)で産する馬なんですけども、忍耐力が強くて従順で力も強いのです。その馬が建築用材の砂利を運び、材木を運び、瓦を運んでいるんです。それを見たとき、グッといましたですね。朝暗いうちから、陽が暮れるまで、黙々として、上り下り、上り下り・・・何十回じゃありませんよね、何百回も材木を運び、砂利を運んでいるんです。黙々としてですね。思わずその馬の額を撫でてあげました。馬よ有り難う、と。そうなんですね。私ども立派な家に住んでいる。それは快適でいいでしょうけども、自分の力ではないのであって、例えばそういう馬が一生懸命働いてくれている。馬の汗も涙も滲んでおるんだ。そういうことを感じて生きていく、ということが人間らしい生き方だ、と言えるんじゃないでしょうか。 金光:これは、しかしそういうふうにお話を伺うと、そうだと思いますが、大人でなくても、子どもでもそういう感じをちゃんと感じている場合もあるわけでございますね。 竹下:そうですね。むしろ子どものほうが純情ですから感受性が強いんじゃないでしょうか。それで先だって子どもの詩集を読んでおりましたら、小学校一年生の男の子が、「風になって」という詩を作っているんです。 「かぜになって」 かぜになったら かあちゃん かせいでっとこさいって あせひっこめてやるんだ すっと うんとかせがれっぞい (小一男子の詩) という言葉です。私、爽やかな風になったら、お母さんが、―「かせいでっとこ」というのは、稼いでいるところ、ですね。働いているところに風になって飛んでいって、お母さんの汗を引っ込めてやるんだ。「すっと」というのは、「そんなら」「そうすると」でしょうね。そうするとお母さん稼がれるぞい。ウンと仕事ができるでしょう。素晴らしい純情な詩ですね。お母さんと一体となっています。風と一体となっています。そういう感覚というものは非常に大事なことだ、と私は思うんです。 金光:先生は長年教育の畑で仕事をなさっていらっしゃるわけですが、今のお話を教育の場で考えますと、どういうことになりますですか。 竹下:そうですね。いろいろなことが言いますけども、例えばよく聞かれるんです。「先生、叱るのはどう叱ったらいいでしょうか?」とかね、「誉めるのはどんなふうに誉めればいいでしょうか?」と。誉め方叱り方をよく聞かれるんですね。誉めることも必要だし、叱ることも必要です。ですけども、そのもっと根底に、叱るのではなくて悲しむのだ、と思うのです。 金光:相手がなんかしくじった場合に、叱るんじゃなくて一緒に悲しむ。 竹下:「どうしてそんなことをしたの?」と悲しむのですね。誉めるのではなくて喜ぶんだと思うのです。「よくやってくれたね。先生、嬉しいよ!」。そういう悲しむ、喜ぶという一体感ですね。子どもと一緒になる。そこからはじめて、叱るということが意味を持ち、誉めるということも意味を持つんだと思うので、ただ叱る誉めるだけだったら、自分は安全地帯におって、「お前はダメだ」「お前は良かった」というだけのことだと思うのです。教育というのは、子どもと一体になる、ということが原点ではないでしょうか。 金光:そういういろんな場所で、そういうふうに周りの者と共感を持って生活できるというと、これは毎日の生活が非常に厚みを持って、といいますか、味わいが非常に深くなるということでございましょうね。 竹下:そう思いますね。ですから一人だけで生きているんじゃなくて、あの方、この方、あの人、この人、草や木とともに生きているということは、そういうもののお蔭で生きているということなんですね。それで思い出したけども、佐々木信綱(のぶつな)(1872-1963)という先生がいらっしゃいます。 金光:有名な歌人の方ですね。 竹下:有名な国文学の第一人者であり、また有名な歌人でいらっしゃいます。その佐々木信綱先生のお歌に、こういう歌がございます。 ありがたし今日の一日(ひとひ)もわが命 めぐみたまへり天(あめ)と地と人と (佐々木信綱) という歌ですね。思えば、朝目を覚ましてみると有り難いことである。今日の一日(ひとひ)も、私のいのちも恵んで頂いた。恵みたまえりですね。それは天、例えば太陽の光、或いは雨が降ってくださる。大地。いろいろの穀物、野菜を作ってくださる人、いろいろ額に汗して働いてくださって、例えば一杯のご飯でも炊いてくださる。お米でも作ってくださる。そういうお歌があります。やっぱり第一人者にしてこの言葉あり、と私は思うんですね。 金光:そういうことはもっと昔の方も気が付いていらっしゃったことだと思いますが、そういう言葉が残っているものでございましょうか。 竹下:ええ。『浄土論』と言いますけども、天親菩薩(てんじんぼさつ)という方が、そういうご本を作っておられまして、棒読み致しますと、 普共諸衆生(ふぐしょしゅじょう) 往生安楽国(おうじょうあんらくこく) (天親菩薩「浄土論」) と棒読みで読みます。読み下しますと、「普」というのは「あまねく」ですね。あまねく諸々(もろもろ)の衆生とともに、安楽国に往生せん、ということです。「あまねく」ということは、みんなですね。特にあなたもあなたのままで、私も私のままで、みなさんもみなさんのままで、それがあまねくです。おしなべてではないですね。おしなべてはもう平均してしまいます。あなたはあなたのままで、私も私のままで、みんなもろもろの衆生とともに一緒に安楽国に往生致しましょう、という天親菩薩の『浄土論』のお言葉です。そういう世界なんですね、仏法の世界というのは。 金光:天親菩薩(四世紀頃の西北インドの僧)という方はたしか世親菩薩(せしんぼさつ)とも訳される方で、世親菩薩というと、唯識という仏教を確立された方ですが、その方にこういう言葉があるわけでございますか。 竹下:ええ。 金光:ただなかなか「みなともに」というのが難しいことでざいますね。 竹下:私どもエゴで生きておりますので。やっぱりお念仏申させて頂く時に、エゴのこの身は変わらないけども、いつの間にか広い世界に出させて頂く。広い世界を賜るとでも言いましょうか、そういうふうに私は思います。 金光:そういう世界に生きますと、やっぱり自分だけではなくて、いろんな人間、いろんなものと一緒に、ともに生きていくという、そういうことができるようになるわけでございますか。 竹下:ええ。だんだんそういうふうな味わいを深くさせて頂くんじゃないでしょうか。 金光:何かそういうことを表現して言葉がございますでしょうか。 竹下:第二番目に申し上げたいと思っておることですけども、『大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)』というお経の中に、 各各安立(かくかくあんりゅう) (「大無量寿経」) という言葉があります。各々ですね、あなたもあなたも私も、―「安立」の「安」は、自分というものに安んじて、「立つ」というのは、自分の花を咲かせる。 金光:めいめいが自分に安んずる、ということですね。 竹下:それは能力とか性別だとか、或いは歳をとっておる、若い、そういうこといっさい関係なく、それぞれみんな存在の意味を持って生きておるんだ、と。それが「各各安立」という言葉だ、というふうに私は頂いております。 金光:たしかにそういうふうにできればいいんですが、なかなか現実に直面すると、総論としては賛成でも、自分がその場にいくとなかなかできにくい、という面があるんじゃないかと思いますが。 竹下:ええ。そういう「各各安立」ということが道理ですから、日常生活もいろいろのことで思い当たると言いますか、そうさせて頂いております。神谷美恵子(1914-1979)さんがいらっしゃいます。 金光:有名な方ですね。精神科のお医者さんで、 竹下:長い間、長島愛生園(ながしまあいせいえん)の精神科医長をなさって、或いは津田熟大学の教授もなさった方ですけども、その方のお言葉にこういうのがあります。 痴呆(ちほう)におちいった老人でも、そのような姿で存在させられているそのことの中に、私たちにはよくわからない存在の意義を発揮しているのであろう。私たちは人間の小さな頭で、ただ有用性の観点からのみ人間の存在意義をはかってはならないと思う。 こうおっしゃっています。でも有用性を問題にするんですね。役に立つか、役に立たないか。頭が良いかどうか。或いは仕事ができるかどうか。有用性も必要でしょうけど、もっと根元的には寝た切りの老人でも、そうしてこの世におるということは、私どもにわからんけども、存在意義を発揮しているんだろう、と。神谷美恵子さんはおしゃっています。大変含蓄の多いお言葉だと思います。 金光:先生は随分教育畑で長くお過ごしになっていらっしゃるわけですが、そういう普通の人が考える有用性だけで考える世界と違う「各各安立」の実例をいくつかご存じだと思うんですが、一、二ご紹介して頂けませんでしょうか。 竹下:有用性だけでいくと、子供たちは育たないのですね。それでせっかくそういうお尋ねですから、東井義雄(とういよしお)(1912-1991)先生から承ったお話を思い出しました。それは、広島県のある高等学校の話です。大変荒れた高等学校だったそうです。夏その高等学校で学級対抗の水泳の競争が、四人一組で競争があたんだそうです。あるクラスで三人はすぐ選手が決まったんです。後の一人がなかなか決まらなかったそうですね。その時にその学級の番長が、「Aにしよう」と言ったんです。Aさんというのは女の子で、しかも小さい時に小児麻痺を患っていて、身体が十分でないのです。泳げるんですけども早く泳げないんです。その子をどうして指名したかというと、みんなで笑い者にしよう、という魂胆なんですね。いよいよ当日がやってきました。Aさんの出番がやってきました。Aさんはプールに飛び込みましたけども、何しろ小児麻痺を患った身体ですから、一生懸命泳げば泳ぐほど滑稽なんですね。みんながドッと笑いました。その時にです、一人の男の人が背広を着たままプールに飛び込みました。その学校の校長先生だったんです。その校長先生は背広のままその子と泳ぎながら、「しっかりね!しっかりね!校長先生も泳ぐからね!我慢してしっかりね!」涙を流して一緒に泳がれたそうです。その光景に全校生徒が粛然とし、その二人が長い時間をかけてやっとゴールインした時に、みんな泣きながら拍手をしたんだそうです。そのことがあって、次第にその学校は平静さを取り戻したということです。それは運動神経がにぶいいからダメだではなくて、小児麻痺なら小児麻痺の子どもとして輝いて生きていっているんだ。それを認めた校長先生の偉さ素晴らしさでしょうね。それが全校生徒を感泣させたんだ、と私は思うのです。 金光:多少身体がふ自由な生徒さんの場合も一生懸命やっている。その姿が非常に感動を与える。やっぱり身体が十分動かなくても、人間というのはいろんな働きができる。先ほど神谷先生の言葉にもあるように、そういう働きが人間にはあるわけでございますね。 竹下:頭が良い悪い、仕事ができるできない、ということだけで切り捨ててしまいますけども、そうでなくて寝た切りの老人もいつの間にかお役に立たして頂いているんじゃないでしょうか。実は先だって、ある方のご本を読みまして大変感銘を受けました。その方は七十歳近い方です。心筋梗塞で倒れて寝た切りに―しばらくの間ね―その時に看護学校から実習生が派遣されて来た。十九歳の女の子だそうですよ。その少女が三週間その方の看病をしたんだそうです。とても親身で、三度の食事、それから熱がありますから氷枕を取り替えてくれる。親身に世話してくれるんだそうです。そして五日間通じがなかったそうですけども、やっと通じがあったんだそうですね。粗相(そそう)してシーツを汚してしまった。大変恐縮していると、その子が飛んで来て、奇麗に拭いてくれて、「おじさんよかったですね。気持がスーッとしたでしょう」とこういうんです。あんまり親切に言うものですから、「あなた親切ね、どうしてそんなに親切にしてくれるの」とこう聞いたら、「おじさんが役に立って下さっているんです」と、その子が言うんだそうです。「へぇ、どうして?」と言いましたら、「私におじさんぐらいの歳の父が故郷(くに)にいます。ガンなんです。看病したいけども、私、学校におりますので看病できません。おじさんを見ると、父親みたいな感じがします。父親と思って看病させてもらっています。おじさんのお蔭で、私、親孝行させてもらっています。ありがとうございました」というんだそうです。そして、三週間の実習が済んだ時に、看護のレポートを持って来て見せるんだそうです。「おじさんのお蔭で、こうして立派なレポートを作ることができました。ありがとうございました」というんだそうです。その方はとても感銘した、と。そして、一つのことを覚(さと)ったというんですね。「おれは役に立っているんだ。役に立つんだ、と。頑張るのもいいかも知れんけれども、しかし寝た切りのこの私であっても、いつの間にかみなさんのお役に立たせて頂いているんだなあ、ということを私実感しました」と、その本に書いてございました。そうでしょうね。役に立っているんだ。ある意味で傲慢ですものね。あの人がおるんで上手くいかん。あの人がおらんならもっと上手く仕事ができるのに、と人を傷つけ、人間関係をダメにするんじゃないでしょうか。よく若い人たちで、「おれはもうダメだ」なんていう人多いです。それはむしろ賜ったいのちに対する冒涜(ぼうとく)だと思いますよ。人それぞれに生きる意義を与えられて生きているんじゃないでしょうか。自分の花を咲かせることが大事なこどではないでしょうか。そういうことを思うのです。 金光:これは、例えば花の場合ですと、タンポポに「バラのようになれ」とはどんな人だってそういうことは言わないと思いますが、人間の場合には、どうもそれに似たことが、「羨ましいと思うような人に自分の子どもをしたい」とか、そういうところがあるようでございますね。 竹下:草花のような世界が本当の道理でしょうね。バラも美しいです。タンポポも地味であるけど味わい深い花ですよね。そのタンポポに向かって、「お前ダメだ。バラみたいになれ」と言ったって、それは無理です。またその必要もありません。また教育において、「なんかタンポポに対してバラになれ」と言っているんじゃないでしょうか。言うならば、「タンポポよ、立派ね。立派なタンポポの花を咲かせてね」というふうに激励することが大事なことではないでしょうかね。タンポポもタンポポでいいんですよ。そしてまた卑近なことで大変恐縮ですけども、先だって家内が台所で野菜料理を作って、野菜を刻んでいるんです。そして、誰にいうともなく、「野菜は奇麗な素晴らしい色をみんなしていますね」というんですね。人参の赤さ、大根の白さ、ジャガイモのあの黄色、或いはネギの緑ですね。それぞれに素晴らしい色でしょう。そして野菜料理を引き立てていますものね。家内がいうのは、「人参の赤いのを刻んで、野菜料理の中にいれると、お料理全体が華やかになりますね。野菜全体を引き立てますね」と、家内がいうんですね。私もははた心を打たれました。そうなんだ。各各安立です。人参を人参でいいのです。人参はあんまり好まれませんけども、人参はあの味でいいのです。あの赤さでいいのです。人参に向かって「白くなれ」と言ったって、それは無理だし、ネギみたいに「緑になれ」って無理です。赤でいいのです。ということは、やっぱり君は君でいいんだよ、ということではないでしょうか。 金光:そういうそれぞれの持っている世界で花を咲かせることが、それで十分なんだ、と。そういう世界が、言葉を換えると、「お浄土の世界、二度生まれで感ずる世界」ということでございましょうか。 竹下:そうだと思いますね。お念仏を賜って、お念仏申す身にならさせて頂くと、「ああ、私は私で良かったのね。あなたもあなたで良かったのね。自分の花を咲かせましょう」。なんか安堵感といいますか、自分に安心して生きていくことができるんじゃないでしょうか。 金光:お経本の中にもそういう言葉がございますですか。 竹下:『阿弥陀経(あみだきょう)』というお経がありまして、私の大変好きなところなんですけども、こういうお言葉があります。 池中蓮華(ちちゅうれんげ)、 大如車輪(だいにょしゃりん)。 青色青光(しょうしきしょうこう)、 黄色黄光(おうしきおうこう)、 赤色赤光(しゃくしきしゃっこう)、 白色白光(びゃくしきびゃっこう)。 微妙香潔(びみょうこうけつ)。 (「阿弥陀経」) というのですね。お浄土の池の中に蓮の花が咲いています。大きさは車輪のようです。そして青い蓮の花は青い光を放っています。黄色い蓮の花は黄色い光を放っています。赤い蓮の花は赤い光を放っています。白い蓮の花は白い光を放っています。その光がお互いに反射して荘厳なお浄土の風景であり、また言いも言えぬ香りが辺りに漂っています。こういう大変美しいところですね。私はこの経文を読みまして、「ああ、それぞれの花が自分の花を咲かせているなあ」ということに感心しました。それを一歩進んで、「君は君でいいんだよ、という世界だ」と思うのですね。青い花に向かって、「青い花はダメだよ。白い花を咲かせなさい。赤い花を咲かせなさい」それは無理です。必要ないのです。青い花は青い花を咲かせて、それでいいのです。十分お役に立っているんです。赤い花もそうです。黄色い花もそうですね。各各安立の世界だ。そしてお互いに助け合っている世界だ、というふうに私は思うのです。 金光:そうすると、学校の場合ですと、英語が得意な生徒はそのままでいいし、数学が得意な子どもはそれでいいし、あなたはそれでいいんだよ、君はそれでいいんだよ、ということになるわけですか。 竹下:いや、そういうことではないのですね。例えば数学ができない、それでいいんだよ、昼寝しておればいいんだよ、そうではないんです。「それでいいんだ」というのは、根底的に、君は君のために役目・使命と言いますか、そういうものをちゃんと持ってきているんだよ。自分の花を咲かせるんだよ。自分の花を咲かせる養いとして、「英語も勉強しなさいよ、数学も勉強しなさいよ」ということでしょうね。 金光: 安立して、進歩がない、ということでは勿論ないわけですね。 竹下:そうなんですね。そうじゃなくて、ただ上の学校に、偉くなるために、そういうことだけのために尻を引っぱたいて、「勉強、勉強、勉強」というのは、子供たちも可哀想、親もやっぱり可哀想じゃないでしょうか。 金光:それだと、「青い花に白くなれ」というのと同じようなことになるわけですね。 竹下:同じことですね。このままでいいんですけども、立派な青い花を咲かせてね、という世界ですね。それで、私は高等学校の校長なんかしておりましたけども、千五百人の生徒がおります。生徒みんなに言ったことは、「君は君でいんだよ。君も君でいいんだよ。自分の花を咲かせるんだよ」と、いつも言い続けておりました。そういう意味で、「勉強もしっかりしなさいね。運動もしっかりしなさいね」というと、生徒が安心するんですね。私は、今の教育において大事なことは「安堵感(あんどかん)の教育だ、安堵する教育だ」。別の言葉で言うならば、「存在の肯定の教育」ですね。「あなたの存在を頷くという教育」が根底にないといけないんじゃないでしょうか。 金光:「君はダメだよ、ダメだよ」ということでないんですね。 竹下:じゃなくてね。そういうふうに生徒に語り掛けると、生徒が、「先生、私でいいんでしょうか」というので、「そうだよ。君がいないと世の中成り立たないんだよ。しっかりね」というと、安心して、自分の花を咲かせるようになるのは、大変そういう意味において楽しい教育生活をさせて頂きました。 金光:そういうふうな目で、みんながそれぞれ安堵して、安心した世界で自分の花を咲かせようとしていると、やっぱりそういう世の中の周りの見方と言いますか、景色も自然に変わってくるわけでございましょうね。 竹下:ええ。お念仏申す身にならさせて頂きますと、自然に周りのものが仏さまとして拝まれてくる。そういう世界を賜るんだ、と私思うんです。ご承知ですね、宇野正一(うのまさかず)先生がいらっしゃいます。宇野正一先生のことを今思い出すのですけども、宇野先生は、おじいさん、おばあさんに育てられたんですね。おじいさん、おばあさんが篤信(とくしん)の念仏者でいらっしゃって、いつも、 食べものさまには 仏がござる。 (宇野正一) とおっしゃったそうですね。「食べ物様には仏がござる。拝んで食べなさい」と、いつもおっしゃっておったそうです。そして、その宇野先生が小学校に上がって、小学校五年生の時に、理科の時間に顕微鏡で物を観る時間があったんだそうです。宇野先生は、ああ、おじいちゃん、〝いつも食べ物様には仏がござる〟と言っておった。ご飯の中に、顕微鏡で見たら仏があるだろうか、と。弁当箱の一粒のご飯粒を取り出して顕微鏡で覗いたんだそうです。ところがボウッと白く霞んで、仏さまは見えなかったんだそうですよ。それで先生に尋ねたんだそうですよ。「おじいちゃんは、〝食べ物様には仏がござる〟といつもいうんですけど、先生、ご飯の中に仏が見えませんでしたけども、仏いるでしょうか?」と聞いたんですね。学校の先生が、「そんな馬鹿な話があるか」と。「お前のおじいさんは迷信だ。ご飯の中には含水炭素とタンパク質と澱粉と水があるんだ。仏なんかあるもんか」とおっしゃったそうですよ。宇野先生は家へ帰りまして、「おじいちゃん、嘘ついた」と。おじいちゃんをなじったんですね。おじいちゃんは、孫のいうことを黙って聞いておられて、しばらくしてから仏さまの前に坐って、長い間涙を流して坐っておられたそうです。その姿が宇野少年の心を貫いたんですね。食べ物様には仏がござる。そうですよ。今の問題は、食べ物を単なる栄養補給源と考える。ビタミンCがどうだ、タンパク質がどうだ、それだけのことなんですね。その底に食べ物がいのちを持っている。いのちあるものである。仏さまである。そういうことが今一番欠けておるんじゃないでしょうか。 それで篤信の念仏者であられました木村無相(きむらむそう)さんの詩に「自 炊」という題の詩があります。 「自 炊」 たなの上で ネギが 大根が 人参が じぶんの出を待つように ならんでいる こんな おろかな わたしのために (木村無相) 自炊生活をしておられます。棚の上に、ネギとか大根とか人参が、自分の出を待つように並んでいる、というんですね。何のためにか。こんな愚かな私のために、自分のことしか考えないエゴの私のために、大根も人参もネギも自分のいのちを捧げてくれる。こう木村無相さんが詠まれる時には、ネギを拝み、大根を拝み、人参を仏さまとして拝んでおられたんじゃないでしょうか。そういうひろやかな世界が開けてくるんだと思うんです。 金光:しかし、大根、人参なんかはよくな前を知っておりますけれども、魚なんかになると、我々、これは美味しいとか、ふ味いとか、な前なんかほとんど知らないのが普通なんですが、なんか先生のお宅で奥さまに一本取られたお話があるようでございますが。 竹下:大変恥ずかしい話ですけども、先だってですね、夕食のお膳につきましたら、お皿に焼き魚が載っているんです。箸でちょっと突いて、口に含んでみました。とても美味しいです。とろけるように美味しいです。それで家内に、「この魚、美味しいね。なんという魚?」と聞きましたら、家内が、「時々あなた食べているでしょう。な前ぐらい知って食べないと、罰が当たりますよ」というんですよね。「そうね、じゃ、ちょっと考えるから」と。暫く考えてから、「そうそう、わかった。このお魚はアジだろう」と言ったんです。そうしたら家内が笑い出しまして、「アジじゃないですよ。これはカマスじゃないですか」というんですね。一本取られまして、家内が、「名前も知らないで食べては、罰が当たりますよ」というのです。ごもっともです。ほんとにその通りです。カマスは自分の体を捧げているんですものね。自分の体を捧げて、私の身体を支えて下さっているんですから、カマス菩薩ですよ。カマスを拝まないと申し訳ないんじゃないでしょうか。 金光:そういうふうに、そこに働いているいのちといいますか、仏さまといいますか、そういうものに気が付くというのは、いろんな場合にあるわけで、こういうお話を聞いて感じる場合もありますが、子どもさんなら子どもさんでまたそういうことを感じる、そういう場合も当然あるわけでございますね。 竹下:実は先だって長崎にお住いの、ほんとに念仏の薫り高いご家庭ですけれども、そこの小学校四年生のお嬢ちゃんが、―此処に持って参っておりますが―「先生、読んでください」と言って、小学校四年生ですから十歳でしょう。その女の子が作文を私に送ってくれたんです。題は「愛犬リー」というので、ちょっと読まして頂きましょう。 昭和五十六年十二月六日。これは私の誕生日だ。私が生まれた時、もう既にリーは生まれ、家の家族となっていた。私はリーより二歳年下だった。まだ幼い私は、リーが家の犬だと知らなかった。私が四歳になった時、リーと見つめ合いながら写った写真が今でも残っている。世界中みな生きとしいけるものたくさんの生き物が生きている。その中で人間に生まれた私、犬に生まれたリーが出会いたのだ。とても不思議だ。その時はまだ若くて元気だったリーであった。しかしだんだん衰えていくリーの姿は不思議でならなかった。一日餌をやり忘れたこともあった。しかしリーは何一つはぶてなかった。―「はぶてなかった」というのは文句を言わなかった。苦情を言わなかったという意味でしょうね。―そんなリーを見ていると、自分がとても恥ずかしかった。ちょっと嫌なことがあるとすぐはぶてる自分。なんと我が儘だ。ついにリーは目が見えなくなった。今までは目が見えていて小屋の中にウンチをすることもなかった。しかし目が見えなくなってからは、小屋の中にウンチをすることもたびたびあった。その目が見えないまま、三ヶ月が過ぎた。平成三年十二月二十三日。この日は天皇誕生日だ。朝なんともなく動き回っていたリー。それが夕方の四時十六分頃、私が見ていると、倒れてもがいていた。私はそんなに苦しんでいるリーをジッと見つめて、「リー頑張れ」と小さな声で叫んだ。リーは目は見えなくても、耳だけはかすかに聞こえていた。しばらくすると、リーは起きあがった。私は良かったと思った。そして私はしばらくその場を離れていた。そしてもう一度来て見た。するとリーは石段に首を垂らし、舌を出して息を引き取っていた。私はそのとき、何がどうなっているのかわからなかった。驚きのあまり腰を抜かしてしまった。リーが死んだのは四時二十分ぐらいだった。あんなに朝まで元気だったリーが死んだとはとても信じられない。私はリーが死んでからやっと気付いた。リーは私に「お念仏をしなさい」と教えてくれた。本当は仏さまなんだ。リーは自分の体を犠牲にしてまで教えてくれた。そのためにもリーの死をムダにしないためにも、お念仏でリーを思い出し、リーに厚く感謝しなければならない。私は今になってこう思う。リーはきっと死ぬ時に私を求めたに違いない。リー、ほんとにすまなかった。私はお念仏でリーとまた会いたい。リー、また親さまのもとで会おうね。さらばリーよ。 こういう作文です。 金光:小学校四年生の方がちゃんと「親さまの世界」ということをおっしゃっていらっしゃるわけですね。「親さまの世界」なんていうのはなかなか目にも見えないし、形も見えないし、そういう意味ではわかりにくいですが、ちゃんとここにはその世界が出ているわけでございますね。 竹下:そうですね。犬が身を犠牲にして、私に知らせてくださった。仏として拝んでいる。有り難い。そういうご家庭がやっぱり素晴らしいんだと思いますね。それで親鸞聖人のお言葉なんですけども、『唯信鈔文意(ゆいしんしょうもんい)』というのがありまして、その中に、 法身(ほっしん)は、 いろもなし かたちもましまさず。 しかれば、 こころもおよばれず、 ことばもたえたり。 (「唯信鈔文意」) というお言葉があります。「法身(ほっしん)」というのは仏さまです。私ども目に見える色もありません。形もありません。ですから想像することもできないし、表現もできませんですね。じゃ、我々と無関係の存在かというと、そうではなくて、続いて『一念多念文意(いちねんたねんもんい)』という中に、 この如来、十方微塵(じっぽうみじん)世界にみちみちたまえるがゆえに、無辺光仏(むへんこうぶつ)ともうす。 というお言葉があります。十方微塵世界に充ち満ちていらっしゃる。だから無関係ではなくて、ご飯となり、お魚となり、いろいろのものになって働いてくださる。 金光:見えないけれども我々に充ち満ちている、ということでございますね。そのことが先ほどの作文にもありますし、それからこれまでのずっと話して頂いたお話の中でも、その充ち満ち給える如来様の働きというものをいろんな例で実証して頂いた、ということになるわけだと思いますが、今日はいろいろと大変貴重なお話を聞かせて頂きまして有り難うございました。 竹下:有り難うございました。 これは平成四年三月八日に、NHK教育テレビの 「こころの時代」で放映されたものである 平成二十九年七月十八日追加。 |
30草柳大蔵(1924~2002年)
|
「よく万巻の書を読むなどというが、そんなことが人間にできるはずはない。人は1年に1万ページの本を読めば、それでひとかどの人物になれるはずだ。1万ページと言えばびっくりするかもしれないが、一日わずか28ページずつ読んでいけばいいのだ。」 20.7.12 |
31 中野 孝次 (1925~2004年)
『現代人の作法』・『自分が生きる時間』・『道元 断章』
| ★『清貧の思想』 | 鴨長明と方丈の庵 | 越後五合庵での良寛 嚢中三升の米、炉辺一束の薪 |
良寛圓通寺に来る | 良寛圓通寺を去る |
| 橘 曙覧 雨の漏る陋屋に万巻の書 |
橘 曙覧と松平春嶽 | 『現代人の作法』 むやみに空き缶を捨てるな | 自由と規律 | |
| 自己が万法に証せられるるがゆえに | 道元とエックハルㇳ | 『自分が生きる時間』 人間は生きるために何が本当に必要なのか |
『道元 断章』 |
|
中野孝次『清貧の思想』発行:草思社(1992年9月16日初版) まえがき いま国外旅行をすると、どの国でも日本及び日本人に対する感心が高いように感じられる。むろん理由の第一は、クルマ、電気機器、エレクトロニクス、時計、カメラなど、日本製品の大量進出にあるだろう。日本が非常に高度な工業技術と生産性を持つことはこれらの製品でわかるが、これらを作った日本及び日本人とは一体いかなるものか、物は見えても人間の顔が見えないというのが、関心を高める理由になっているようである。実際わが国の政府は海外に対する自己宣伝を怠りすぎているから、そういう要求が起こるのももっともだと思われる。 理由の第二は、しかしそれと相反するもので、逆に日本人の大量の海外渡航に由来するもののようである。史上かつてなかったほどの数の日本人ツーリストが各地各国に出掛けるし、また企業の長期滞在者の数も少なくない。かれらの行動をじかに見て「これが日本人か?」という疑問を抱く。その疑問は概して否定的な性質のものだが(本文第十六章:清貧の思想――日本文化の一側面 利に惑ふは愚かなる人なり)、それもまた日本及び日本人への関心を高める理由になっているのは皮肉である。日本人とはただホモ・ファーベル(物を作る人)であって、物を作って売るだけの者なのか、それ以外の文化を持たないのか、というわけだ。 それ以外にもまだ理由はあるだろうけれども、わたしが受けた印象ではほぼその二点によるようであった。そして何かにつけて日本及び日本人について質問されるわけである。 わたしは話を求められるたびにいつも「日本文化の一側面」という話をすることに決めて来た。内容は大体日本の古典――西行・兼好・光悦・芭蕉・池大雅・良寛など――を引きながら、日本には物作りとか金儲けとか、現世の富貴や栄達を追求する者ばかりでなく、それ以外にひたすら心の世界を重んじる文化の伝統がある。ワーズワースの「低く暮し、高く思う」という詩句のように、現世での生存は能うかぎり簡素にして心を風雅に遊ばせることを、人間としての最も高尚な生き方とする文化の伝統があったのだ。それは今の日本と日本人を見ていてはあまり感じられないかもしれないが、わたしはそれこそが日本の最も誇りうる文化であると信じる。今もその伝統――清貧を尊ぶ思想と言っていい――はわれわれの中にあって、物質万能の風潮に対抗している。それは現代の日本の主たる潮流ではないからあえて「一側面」と遠慮しておくが、実はわたしはこれこそが日本文化の精髄だと信じているのだと、古典の詩歌を引きつつ、わたしの「清貧の伝統」と考えるところを話して来たのだった。 かつて明治時代に『日本及び日本人』という国粋主義の雑誌があり、戦時中の皇国主義的国粋主義の支配下に青年期を送ったわたしには国粋主義くらい嫌悪すべきものはなかったのに、そのわたしが齢をとってこうして結果的には、かれらと同じように『日本及び日本人』の宣伝をすることになったのは、これもまた皮肉な成行きであった。 ただ、講演では話がどうしても大雑把になる。充分に意をつくせぬことの方が多い。話そうと思っていながら話せなかったこともある。またそれ以上に、話しているうちに自分の認識や知識のふ充分さに気づくこともある。これはたんに外国人向けの文化案内に留まらぬ、と感じて来たということもある。 そいう気持ちが嵩じて来て、いつかはこれを書くとことで確かめておかねば、と思っていた。が、こういうことは内心で思っていても機会がないとなかなか実行できないもので、そのままに打過ぎていたところ、たまたま草思社からその話を書くようすすめられた。いい機会だと思ったが、これをそのままにしておいた。ところが今年の正月元旦、何か書き初めをと思い立って原稿用紙に向かったとき、ふとこれを書く決心がついて書き出したら、思いがけず自分でも興が乗って、以後毎日、他の仕事を全部放擲して書きつづけることになったのは、われながら驚きであった。こんなことはわたしとしても初めての体験である。 「Ⅰ」と名付けた十五章に書いたのは、わたしがそのつど話して来たこと、ないし話そうと思いながら充分に話せなかったことである。日本の読書人には周知の事柄で珍しくないこともあえて記してあるのは、話す相手が外国人だったためととっていただきたい。 そしてこの十五章でとりあげた話を材料としてかれらに何を訴えようとしたか、わたしがそれをどう思うかを記したのが、「Ⅱ」と題した部分で、むろん主眼はここにある。これはあえて言えば私の祈りのごときものである。そうあってほしいという話である。そのためにいささか美化している向きもあるだろうが、それがわたしの念願であることは間違いがない。 いま地球の環境保護とかエコロジーとか、シンプル・ライフtこいうことがしきりに言われだしているが、そんなことはわれわれの文化の伝統から言えば当たり前のの、あまりにも当然すぎて言うまでもない自明の理であった。という思いがわたしにはあった。かれらはだれに言われるより先に自然との共存の中に生きて来たのである。大量生産=大量消費社会の出現や、それに対する新しいあるべき文明社会の原理は、われわれの先祖の作りあげたこの文化――清貧の思想――の中から生まれるだろう、という思いさえわたしにはあった。 一個の文士の夢と嗤うなら嗤え。わたしはそんな夢のような願いをこめてこれらの話して来た、ということだけが事実である。 参考:ウィリアム・ワーズワース は 1770年から1850年まで生きた英国詩人である。“低く暮らし、高く思う”は、英語では、Plain living and high thinking で、原詩の該当部分の訳は次の様になる。「質素なる生活、高遠な思想は既になく昔ながらの善き主張の飾り気なき美はさり、われらの平和、われらの敬虔に充つる天真、家法となる宗教もすべて失せたり」 これは、『ワーズワース詩集』 田部 重治 (翻訳)、(岩波文庫)のロンドン一八〇二年(一)に出てくる一節である。
鴨長明と方丈の庵P.34~41 三界は只心ひとつなり 人の心がゆたかでであるか貧しいかは、大邸宅を営んで富貴であることでもなく、権勢を誇ることでもなく、もっぱらその人の心情の高雅であるか卑陋(ひろう)であるかによるというこの考え方は、そもそもはやはり仏教に由来するのだろう。わたしはその方面は素人でまったくの見当で言うのだが、どうもそんなふうに思われてならない。 自然のまま放っておけば、原始形態では、物を持たぬその日暮らしの貧乏人よりも、家屋敷を持ち大勢の使用人を持った長者のほうが尊ばれ、人の生殺与奪の権を握った権力者が崇められるだろう。所有は多ければ多いほどよしとするのは、ごく当たり前の成行きである。その自然な(この場合は原始的な)感情に対して、それ以外に人間には大事な価値があると最初に教えたのが、日本では仏教だったと思われる。 現世の価値――他人より多くの富や権力を持つ者が崇められるーーに対して、目には見えないもう一つの価値の世界があるのだ、それはブッダの教える心の救済にかかわる世界である。人が真に幸福になるかならぬかは、現世での成功や失敗によってではなく、心という誰でもが与えられていながら日ごろは欲望に覆われているために雲らされている、その世界にかかわることだと、形而上的な体系と教えたのが日本では仏教であった。 仏教は現在では見るかげもないほど堕落してしまって、葬式仏教といわれるくらい、僧侶は魂の救済能力を失った存在になってしまっているが、かつてはこれが何よりも尊ばれる人びとであった時代があった。かれらは魂の救済者だった。現世の中に彼岸の価値体系をもたらし、人に心の世界を教える使徒であった。 十世紀に源信という僧が著した『往生要集』にすでに、 足ることを知らば貧といへども富となづくべし、財ありとも欲多ければこれを貧となづく。 という文言が見える。これは彼の説いた内のほんのカケラのカケラのような言葉だが、このような考え方があるということは、当時この教えに初めて接した人びとには目の醒めるような新鮮な発見だったろうと思う。この一言によってかれらの富貴観は革命的な衝撃を受けたにちがいないのである。 ここで日本仏教史の話をしてもしかたないし、わたしにはその資格も能力もないが、中世初めに出現した日本仏教の教組ーー法然・親鸞・道元・日蓮など――の影響力の大きさは、ヨーロッパ社会におけるキリスト教のそれに匹敵すると言っても過言ではあるまい。 要するに当時の人びとはかれらによって、欲望の支配する現世の価値のほかに、もっと人間にとって大きな魂の救済にかかわる一大世界があることに目を開かれた。教義は各派それぞれに違ったが、日本人が形而上的な世界の価値を知ったのは仏教によってだった。これはまさしく精神世界の革命といっていい出来事で、中世から近世にかけての人びとは最も熱烈に、犠牲となることをも怖れず、仏教を信じたのだった。 神仏と日本ではいうが、このようなある絶対的な見えぬ存在を信じ、それに対する垂直の関係を第一としたことが、大変なことだったと私は信じる。現代は仏教がそういう役割を完全に失い、形骸化し、それともふつうの生活者もこういう目に見えぬ存在を畏れる心を失った。絶対的な存在がなくなれば、法律とか評判とか、世俗の横の関係ばかりになって、内にみずから律するものをもたなくなる。 この「心」というものが信じられない時代の、一人の知識人の生き方をよく示している古典に『方丈記』というのがある。これは鴨長明(一一五五?~一二一六)という歌人が、当時の戦乱の窮乏の世の中で隠者となって世を捨てて生きた記録だが、悟道といにはほど遠いけれども、いかにも人間の本音がよくあらわれているため、のちのちまで日本人に愛読されて来た。 長明は元久(一二四〇)年、五十歳のときに出家遁世した。つまり人生五十年といわれていた時代に彼はぎりぎりの最後まで現世に執着しぬいて、それから世を捨てた。捨てたというより世からはじき出された格好で、めんめんたる未練とうらみをもって出家した。そして山中の方丈(一丈四方の住居)に住んだときの記録が『方丈記』だけれど、彼がどうして方丈の暮しをよしとしたかを知るためにも、そいの一部を引いてみよう。(『方丈記 徒然草 新日本古典文学大系 岩波書店』) おおかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思いしかども、今すでに五年(いつとせ)を経たり。かりの庵もややふるさととなりて、軒に朽(く)ち葉(ば)ふかく、土居(つちい)に苔むせり。おのずから、ことの便りに都を聞けば、この山にこもり居てのち、やんごとなき人のかくれ給えるもあまた聞こゆ。ましてその数ならぬたぐい、尽くしてこれを知るべからず。たびたびの炎上(えんじょう)にほろびたる家、またいくそばくぞ。ただ仮の庵のみ、のどけくしておそれなし。ほどせましといえども、夜臥す床あり、昼居座あり。一身をやどすにふ足なし。かむな小さき貝を好む。これ身知れるによりてなり。みさごは荒磯に居る。すなわち人をおそるるがゆえなり。われまたかくのごとし。身を知れれば、願は走(わし)らず。ただしずかなるを望(み)とし、憂(うれ)へ無きをたのしみとす。惣(すべ)て世の人のすみかをつくるなひ、必ずしも、身(み)のためにせず。或は妻子・眷属(けんぞく)の為につくり、或は親昵(しんじつ)・朋友(ほういう)の為につくる。或は主君・師匠、および財宝・牛馬のためにさえこれをつくる。われ、今、身のためにむすべり。人の為につくらず。ゆえいかんとなれば、今の世のならひ、この身のありさま、ともなうべき人もなく、たのむべき奴(やっこ)もなし。縦(たとひ)、ひろくつくれりとも、誰(たれ)を宿(やど)し、誰(たれ)をか据(す)えん。 それ、人の友とあるものは、富めるをとうとみ、ねんごろなるを先とす。必ずしもなさけあると、すなおなるとをばふ愛(あいせず)。只、糸竹(しちく)、花月を友とせんにはしかじ。ひとの奴たるものは、賞罰はなはだしく、恩顧あつきをさきとす。更に、はぐくみあわれむと、安くしずかなるとをば願はず。只、わが身を奴婢とするにはしかず。いかが奴婢とするとならば、若(もし)、なすべき事あれば、すなわちおのが身をつかう。たゆからずしもあらねど、人をしたがえ、人をかえりみるよりやすし。若(もし)、ありくべき事あれば、みずからあゆむ。苦(くる)しといえども、馬・鞍・牛・車と、心をなやますにはしかず。今、一身をわかちて、二(ふたつ)の用をなす。手の奴、足の乗り物、よくわが心にかなえり。心 、身の苦しみを知れれば、苦しむ時休めつ、まめなれば使ふ。使ふとても、たびた過ぐさず。もの憂しとても、心を動かす事なし。いかにいわんや、つねにありき、つねに働くは、養生なるべし。なんぞいたずらに休み居らん。人をなやます、罪業なり。いかが他の力を借るべき。衣食のたぐい、またおなじ。藤の衣、麻のふすま、 得るにしたがひて、肌(はだへ)をかくし、野邉のおはぎ、峰の木の実、わずかに命をつぐばかりなり。人にまじわらざれば、すがたを恥ずる悔(く)いもなし。糧ともしければ、おろそかなる報(むくい)をあまくす。惣(すべ)て、かようの楽しみ、富める人に対していうにはあらず。只、わが身ひとつにとりて、むかしいまとをなぞらうるばかりなり。 夫れ、三界は只心ひとつなり。心若やすからずば、象馬(ぞうめ)・七珍(しつちん)もよしなし、宮殿・楼閣も望みなし。今、さびしきすまひ、一間の庵、みづからこれを愛す。おのづから、都に出でて、身の乞匃(こつがい)となれる事を恥づるといへども、帰りてここに居る時は、他の俗塵に馳(は)する事をあはれむ。若、人このいへる事を疑はば、魚(いを)と鳥とのありさまを見よ。魚は水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は林をねがふ。鳥にあらざれば、その心を知らず。閑居の気味もまたおなじ。住まずして誰かさとらん。 長明氏はこんなふうに、この世で一番大事なのは心が安らかであるかどうかである。もしたえず安らかならぬ心の状態なら宮殿・楼閣に住んだとて空しく、もし草庵にいても心安らかならその方がずっといい、と言っているのだ。語調にまだ世間への未練といった気味合いが残るとしても、方丈の住居を彼が本当に愛し満足していたのは事実だろう。 鴨長明という人は、彼もまた出家遁世したわけだが、その境界(きょうがい)はさきほど言ったように真の悟道とは言いがたいかったように思われる。たとえば『徒然草』を読んでいると、そこに一人のおそろしいほどよく目の見える醒めた人物がいるのを感じるが、『方丈記』を読んでそいう感じは受けない。そこにいるのは悟道とはほど遠い、世間と人間への関心を最後まで捨て切れないでいる煩悩の人である。最後まで世の中への未練、恨み、貪婪(どんらん)な好奇心、執着を捨て切れず、捨てきれない自分に忠実に生きた人で、『方丈記』の面白さはその人間臭さによる。 長明氏が出家遁世したのは五十のとしで、これは二十三歳で世を捨てた西行、三十ごろには沙弥(しゃみ)になっていた兼好とくらべてもずいぶん遅い。遅いばかりでなくその遁世も、自分から仏道に志したためでなく、執着しぬいた世の中からはじき出されるようにして山に入ったのだ。『方丈記』には、 ――五十の春を迎へて、家を出て世を背けり。 と、あっさりきれいごとに書いてあるが、実際は年来の宿願(彼はいつかは下賀茂社の正禰宜惣官になりたいと願っていた)がついに叶えられなかったので、ふくれて家に籠り、和歌所への出仕をやめ、ついに山に遁世するしかなくなったのだ。彼に好意をもつ源家永もその日記にそういう長明氏の心持を、 「こはごはしき心」 と評して、そのロバのような強情さにあきれかえり、サジを投げている。 そんなふうにして心ならずも五十歳で山中に遁世せざるを得なくなったのだが、ひとたび方丈の住居を始めるとそれを全面的に肯定し、いわば方丈の哲学といったものを作ってしまうのが鴨長明だった。己を貫くためついに山中方丈の住居にまで自己の社会的生存形態を縮小しきって、そこでのみ、 ――ただ、仮の庵のみ長閑けくして、恐れなし。 と安心できることを誇っている。仏法のためでもなく、すべては己れ一個のためにしたことだというのである。 わたしはこういう文章を読むとそこに、この国の中世初めにすでにこれほどはっきりした自己認識を持つ人がいたという事実に感嘆せずにいられないのである。 これを現代のこととして言えば、会社人間としてひたすら会社のために働きつくして来た人が、社内の人事や組織と衝突して、そのままならぬことに絶望し、会社勤めのごときことに望みをかけることなく、一念発起してどこか過疎村の廃屋にでも住み、だれにも拘束されぬ自給自足の百姓生活を始めるようなものだろうか。別に仏道修行しようというものでない。ただ気ままに、己れ一人の心身の自由と安心とのために、世間一般とちがう生活を始めるのである。そのとき果して、この長明氏のように、 ――ただ、仮の庵のみ長閑けくして、恐れなし。 と言い切れるかどうか。そう言い切れる人がいたら、わたしはその人を尊敬する。それこそ真に人間らしい生を選んだ人だと思うからだ。長明氏ではないが、人が幸福かどうかは外見ではわからぬ、物の見方のコペルニクス的転回さえ行えば、人に拘束されぬ山中の貧しい暮しにこそ真の平安があるかもしれないのだ。 そしてこのように、 ――三界は只心ひとつなり。 衆生が活動する全世界は「心ひとつ」の持ちよう如何で価値が逆転する、自分はもし安らかな心が得られないのであれば宮殿・楼閣も望まぬ、いまは乞食同様の身となったのであるが、山に帰ってここにいるときは世間の人がみょう利の世界にあくせくしているのを憐れむ気になると、こういう価値の逆転を行わせた原動力が仏教であったわけだ。鴨長明は決して他の出家者のように仏道修行一途の者ではなかったけれど、それでもこういう心境をたのしむことが出来た。 人間が自己をまっすぐに支えるには、こういう目に見えない存在に対する畏れを持つことが必要なのかもしれない。 昔わたしは高等学校で哲学者カントの「天にあっては星の輝き、地にあっては心の律」という言葉を知り、感動したものであったけれども、洋の東西を問わず天を畏れる心と己が心の律を守る心とは、たがいに相通ずるものであろうか。 前回取上げた光悦とその母 妙秀とは、熱烈な法華経門徒であったが、法華宗とは限らぬ、神仏と呼ばれる存在を敬い畏れる心が、かれらに人間としての品位を与えるのだとしたら、それを失ったことが現代人を支えのない存在にしてしまったのかもしれぬという気がする。 とにかく鴨長明は、方丈という最小限の空間に住みながら、そこで音楽をたおしみ、利得にあくせく奔走しないでいられる生活を誇りとしたのだった。またその心境をよしとする人がいたからこそ、彼の『方丈記』は今日まで読みつがれて来たのであろう。こういうふうにして人から人へ目に見えない糸で伝えられて来たもの、それをもし文化の伝統というなら、その伝統をわたしは尊いもに思うのだ。 平成29(2017)年5月4日
★越後五合庵での良寛 嚢中三升の米、炉辺一束の薪P.42~54 わたしはいま年を逐うごとに年々ますます良寛(宝暦八~天保二 一七五八~一八三一)が尊ばれ好かれ愛されてゆくようなのを、現代の七不思議の一つに思っている。彼の生き方や思想は現代の大方のそれと正反対であって、それが好まれる理由がわからないからだ。良寛はなぜいま好まれるのだろうか。 八〇年代後半から九〇年初めにかけてすべてバブルだったということになっているけれども、過去数年財テクなどといういやな言葉が横行し、猫も杓子も株をやって財テクをしないのは人ではないというような風潮があった。大新聞までが財テク欄などもうけて金儲けをけしかける有様なのを、わたしは終始にがにがしく思っていたが、あんなふうな現象が起こるというのも一般に金があることだけをよしとする風があるからだろう。すべては数字ではかられ、数字であらわせぬ価値は目もかけられないのである。 そんな風潮が現代の風だとすれば、良寛はまさにそれとはまったく反対の生き方をした人で、生涯金なぞにはまるで無縁、住もうところは草庵で、乞食をして暮した人だ。その人がこの時代になぜもてはやされるのか不思議でならないが、あるいは時代全体があまりにも実利主義一辺倒だから、かえってその反対の清らかな生き方に憧れるのだろうか。 騰々 天真に任(まか)す 嚢中 三升の米 炉辺 一束の薪 誰か問わん 迷悟の跡 何ぞ知らん みょう利の塵 夜雨 草庵の裡(うち) 雙脚(そうきゃく) 等閑に伸ばす 良寛の代表作といわれるこの詩を口ずさんでいると、それだけでなんとなく悠々としたいい気分になってくるが、ちょっと考えてみればこんな暮しはとうていわれわれに出来るわけがないとわかる。自分は立身だの出身だの、金儲けだの栄達だの、そういうことに心を労するのがいやで、すべて天のなすままに任せて来た。いま自分には、この草庵の頭陀袋(ずだぶくろ)の中には乞食でもらって来た米が三升あるだけで、炉辺には一束の薪があるだけ。そういう極限のふ安な状態にあるのだけれども、これだけあれば充分、迷いだの悟りだのということは知らん、ましてや名声だのリ利得などは問題ではない、わたしは夜の雨がしとしんとと降る草庵の裡にあって、二本の脚をのどかに伸ばして満ち足りている、というのだから。 われわれにはとうていこんな心境になれるわけもなく、それに耐えきれまいが、それにもかかわらずこの詩にはみごとな一つの境界が示されていて、それがわれわれをひきつけるのである。それは一体なぜか。現代の良寛流行はそのなぜかにかかっている。われわれは現代の奉職時代にいるからかえってそんな心にひかれるのだろうか。 わたしはいつかの冬、越後の国上の五合庵跡をたずね、そこに再建されている庵を見て、老杉の下に建つ一間きりの寒々tこした粗末な住居に自分ならtこうてい耐えられまいと思った。あまりにも簡素で、あまりにも貧しすぎるのである。そうしてこういうところに粗衣粗食で暮した人はよほど精神の強靭な人だったのろうと想像するともに、現代文明に甘やかされたわれわれの脆弱さを省みずにいられなかった。 考えてみればしかしわれわれだって、いまや知る者も少ない遠い昔になってしまったが、東京はじめ日本中の都市が空襲で焼かれたあとの焼野原でこれと似たり寄ったりの生活をしていたのである。夜具tふぉてもろくになく、食糧は配給制のまさに「嚢中三升の米」の状態で、それでも雨露をふせぐ屋根の下に住み、食うものがあることを感謝していた時期があったのだ。とすれば現在この五合庵を見て「なんという貧しさ、よくこんなところで暮らせたものだ」と感じること自体、われわれが甘や化されて、いつのまにか精神が脆弱になっていることを示すものかもしれない。 そして結局われわれがそのように考えるのは、良寛のその貧寒たる生が彼自ら選んだ生の形態だったのにたいし、戦後のわれわれの窮乏状態はやむなく強いられた状態であったからであろう。われわれはあの窮乏状態からなんとか這い上がってゆたかな生活をしようとあくせく働きつづけてたが、良寛においては始めから腹いっぱい食べようとか生活をゆたかにしようとか、ましてや立身出世しようというような願望はさらさらなかった。 生涯 身を立つるに懶く 騰々 天真に任す 立身出世など考えもせず万事なるがままに任せて来たのである。そしてその結果たる現在の草庵の暮しで、それに満足し「雙脚(そうきゃく)等閑に伸ばす」ことができるのを、これ以上ない至福の心持でいるというのだ。 われわれには真似はできないが、しかし良寛のその心境を想像することはできる。 食い物がいくらでも手に入る飽食の時代に、食があること自体をありがたがる気持ちは起こらない。つねに飢餓すれすれの、食のないことが常態であるからこそ、三升の米のあることがありがたいのである。 暖房のきいた暖かい部屋がふつうであればそれをとくにありがたく思うことはないが、寒気のきびしい外での乞食から帰って炉に焚くべき一束の薪があれば、その暖に感謝せずにいられない。 ないことが常態であるとき初めて人は物のあることに無上の満足と感謝を覚える。あるのが常態ならば、ないことにふ満こそ感じても、決してありがたがる心持は沸かないであろう。とすれば、身辺をつねに欠乏の状態すれすれに置くことは、それ自体が感謝をもって生きることの工夫であるかもしれないのだ。良寛が草庵の生を選んだのはそういうことであったろうとわたしは想像する。 そして現にその貧しい草庵の暮しぶりを歌った良寛の詩や和歌に、ある言いようもない優遊たる心境があらwざれているから、われわれはその人にひきつけられるのだと思う。たんに貧しい暮しをしたというだけならば誰もその人にひきつけられはしない。 『良寛禅師奇話』という本の冒頭 良寛禅師は常に黙々として、動作閑雅、余有るが如し。心広ければ体ゆたかなりとは、この事ならん。 良寛は孤独なひとり暮しをしていたばかりでなく、生来口数少ない寡黙の人であったらしい。そこにさらに自ら選んだ内省的な生活のためいよいよ言葉は少なかったが、それでいてた立居振舞にはまことに閑雅なものがあって、ゆったりと内から溢れてくるものがあるようであった。心が自由でとらわれなければ体がゆたかであるとはこれをいうのであろう、というのである。 いかにも良寛という人の人となりが目に見える思いがする。良寛の書を見てもそうだが、何にもとらわれず実にのびやかで、しかも高雅な書体であって、あれは良寛の人柄ンおあらわれそのままであるのだろう。そして乞食草庵の暮しという最低限の生存の下にありながら、そういうゆったりと満ち足りた高雅な心事を保っている人だったから、彼はいまますますわれわれをひきつけるのであろう。 『良寛禅師奇話』を書き遺したのは解良栄重(けらよししげ)という人だが、この人はよほどに良寛に私淑すること深かった人で、良寛という人から発する香気をよく書きとめている。 師、余ガ家ニ信宿(しんしゅく)日ヲ重ヌ。上下自(おのずか)ラ和睦シ、和気家ニチ、帰去ルト云ドモ、数日ノ内、人自ラ和ス。師ト語ル事一夕スレバ、胸襟清キ事ユ。師、更ニ内外ノ経文ヲ説木、善ヲ勧ムルニモアラズ、或ハ厨下(ちゅうか)ニツキテ火ヲ焼(た)キ、或ハ正堂ニ坐禅ス。其話、詩文 ニ倭ワタラズ、道義ニ不及(およばず)、優遊ぶ(ゆうゆう)トシテ名状スベキ事ナシ。只道義ノ人ヲ化スノミ。 良寛もまた解良の家に親しみ、ときに二晩どまりで泊まってゆくこともあったのだ。そのときの印象を栄重は書きとめているのだが、いかにも良寛という人から発する香気のようなものが伝わってくる文章である。 良寛がその家にいるというだけで、しかもとくに説教するのでもなく、詩や和歌の話を講釈するわけでもないのに、家の中に和気が満ちるようだった、台所に来て火を焚くのを手伝ったり、奥座敷で黙々と坐禅を組んだり、ごく自然にいつもとおりにふるまっているだけなのだが、なんでもないそのふるまいに接し、炉辺で世間話わおしているだけで、胸の内が清らかになってくるようだったというのである。、 良寛とはいかにもそういう人であったのだろう。五合庵に住みこんだ乞食坊主が、ただ惨めったらしいだけで何の魅力もない人物であったら、人びとは憐れみはしてもこのように心から崇め親しみ尊みはあいなかったはずだ。良寛がかくも人に愛されたのは、貧しい草庵暮しの乞食僧にもかかわらず、その最も簡素な生活にあって常人の及ばぬ高雅な心持の、いかにもかぐわしい人柄であったからだ。 良寛は詩を作り和歌を詠む。書をよくする。しかしその詩は漢詩人の作る専門家の詩でなく、和歌は桂園流(けいえんりゅう)の常套歌(じょうとうか)ではなく、書は書家の書ではなかった。どれもが良寛の内的生活を表現するためのものであって、専門家臭は一つもない。経文にも通じているはずであるのに坊主のように経を説かず、それを知識として所有をも所有として斥け、すべてはただ行住坐臥、日々を新たに充実させるための手だてなのであった。 参考:桂園 香川景樹の号。桂園派香川景樹を中心とする和歌の一流派。平易を尚び、声調を重んずるを旨とした。 師、神気内に充て秀発す。其の形容、神仙の如し。長大にして清癯(せいく)、隆準(りゅうせつ)にして鳳眼(ほうがん)、温良にして厳正、一点香火の気なし。(略)今、其の形状を追想するに当り、今似たる人を見ず。鵬斎(ほうさい)曰く、喜撰(きせん)以後此人なしと。 良寛は胸中にきよらかな精気が満ちていて、それがおのずから溢れ外にあらわれていた。その姿形はは神仙のようであった。背は高く痩せ、鼻の柱が高く、切れ長の目をしていた。温良であってしかも厳正、抹香くささがまったくなかった。いまその人となりを追想してみるに、あのような人はほかにまるで思いつかない。江戸の儒者亀田鵬斎は三十六歌仙の一人喜撰以後あのような人はいないといったが、そうであるかもしれぬ。 わたしはこれを解良栄重が敬愛のあまりに誇張して良寛を美化したとは思わない。良寛はまさにそういうひとであったに違いないのである。 この栄重の証言を読むにつけてもわたしは、良寛がこのむおうな人間になったことについてその草庵生活がどうかかわっていたか、言葉を変えれば、無所有の草庵の乞食生活なしにこのような良寛は生まれなかったのではないか、という想像に駆られる。草庵生活は良寛にとって必然でぁり、草庵生活なしにこのような良寛が可能であったかどうか、と。 それにはその反対を思い浮かべてみるのがいいかもしれない。良寛がどこかの寺の、なんなら彼が修行した備中玉島の国仙和尚の跡を継いでいたと考えてみる。それには彼がその円通寺で作った詩を読んでみるのが一番いい。 円通寺に来たってより 幾度か冬春を経たる 衣垢(いあか)づけば 聊か自ら濯(あら)い 食尽くれば 城闉(じょういん)に出づ 門前 千家の邑(いう) 更に一人を知らず 曽(かつ)て高僧伝を読む。 僧は清貧を可とす可(べ)し 自分がこの備中円通寺に越後を去って遠くからやって来てから、幾度の春秋を経たことであろう。衣が垢じみてくればかりそめに自分で洗濯し、食うものがなくなれば巷(ちまた)へ出て托鉢して来た。寺の門前には玉島の町家が百千tふぉなく連なっているが、そこに住む人を自分は一人も知らない。むかし梁(りょう)の慧皎(けいこう)の著した『高僧伝』という書物を読んで、僧侶たる者はすべからく清貧えあれと説かれているのを知った。自分も孤独に堪え、清貧を旨として、坐禅弁道に務めよう。 ここにうたわれた修行僧良寛の姿はずいぶん孤独な印象を与える。玉島の町に千戸の邑(ゆう)があっても自分はそれを一つも知らない。ただ寺にあって坐禅弁道にはげむのみだ、というのである。 円通寺は岡山藩主の菩提寺で、岡山の西の玉島にある。良寛が国仙和尚に参ずべくここに来たのは二十二歳のとしで、師の大忍国仙が遷化(せんげ)したのは良寛三十四歳のときだ。十二年間も良寛はそこで修行生活をしながら、おそらくきわめて口数の少い、人と交わらない孤独な修行をつづけていたのであろう。円通寺のころをうたったもう一つの詩に、さらにその心境が述べられている 憶在(おも)う円通の時 常に吾が道の孤なるを嘆ぜり 柴を搬(はこ)んでは 龐公(ほこう)を懐(おも)い 碓(うす)を踏んでは 老盧(ろうろ)を思う 入室 敢えて後るるに非ず 晩参 恒に徒に先んず 一たび席を散んじてより 倏忽(しゅつこつ)として三十年 山海 中州を隔て 消息 人の伝うるなし 旧を懐うて 終に涙あり 之を水の潺湲(せんかん)たるに寄す 柴を運んでは龐居士を偲び、米搗き台に上っては盧行者(ろ あんじゃ)のことを思った。師に参ずるには人に後れまいとし、晩の講義にはいつもまっさきに駆けつけた。そうやって修行一途「常に吾が道の孤なるを嘆ぜり」というのである。 この一句はふつうにとれば、禅家の常套として「仏道のさびれることを心配していた」ということだろうが、わたしは言葉のひびきから、そこにもっと個人的な灌漑の気配が感じられるような気がする。すなわち同じ修行仲間の中にあってさえ良寛の行道ぶりは他と違って「孤」だったのではないかったかと思うのだ「孤」とはその修行の仕方と心持が他とはまったく異なっていて、良寛はひたすら純粋な仏道修行を志していたのに対し、ほかの修行僧たちはいずれどこかの寺の住持となるために修行していたというような、その心の違いを言ったのかもしれぬ。 良寛は大忍国仙の死後すぐに玉島を去ってしまうのだが、良寛研究家北川省一氏の説によると、これは後継者の玄透即中(げんとうそくちゅう)が幕府の権力をかさにきて宗門改革に乗り出そうとしたのに対し良寛が反対した、そこで玄透は幕府の悪僧追放令を適用して良寛を追い出したのではないか、という。わたしはことの是非を判断すべくもないものの、もしそういうようなことがあったとしたら、それは師の大忍国仙生存中から存在し、体制側につく玄透即中と、政治権力にかかわりない仏道修行一本でゆく良寛とのあいだに、いま言ったような生き方の根本的な違いがあって、玄透はかねて良寛を憎んでいたのかもしれないと思うのだ。 当時円通寺には三十人に近い先輩がいたらしいが、大忍国仙にとっては末席に近い良寛こそがその中で自分の法嗣(ほうし)たるべき人物と考えていたのかもしれぬ。国仙が良寛に与えた印可の偈(げ)の文言を読むと、国仙のその気持ちがわかるような気がするのである。 良寛庵主に附す 良也愚の如く道転(うた)た寛(ひろ)し 騰々任運 誰を得てか看せしめん 為に附す 山形の爛藤杖(らんとうじょう) 到る処 壁間に午睡 閑(のびや)ならん 寛政二庚戌冬 水月老納(ろうのう)仙大忍 柳田聖山氏はこの偈をこう訳してている。 「良よ、おまえは馬鹿みたいに、ゆけばゆくほど、足の下が寛(ひろ)がりつづける、大道の子だったわい。のほほんのほんと、足にまかせてゆくおまえを、いったい誰が監視できるものか。さあ、山から切りだしたままの、このまっくろな藤の杖を授ける。これをもって何処(どこ)へなりとゆけ、何処かの岩かげででも、ぐっすり午睡(ひるね)するがよい。」 良也、というこの呼びかけの言葉からして、いかにも良寛にたいする親しみの気持ちが感じられるが、柳田氏はこの「良也如愚」という言い方は『論語』為政第二の、孔子が顔回についていう言葉から来たのであろうと推測し、どえらい弟子がいたものよとの思いをそれによってあらわしたのだと言っている。国仙は純粋に求道一筋でみょう利に関係ない良寛にわが道を託したのだろうと見ている。 良寛の「常に吾が道の孤なるを嘆ぜり」は、そういう自分の生き方の孤独を嘆ずる気持から出た言葉だという気がする。そいう良寛には、出家しても寺というもう一つの世間の中でみょう利を求めるような生き方は、端(はな)からする気もなかったし出来なかったろうと思うのだ。 参考:行者(あんじゃ)とは、仏教寺院において僧侶のように出家をせず、俗人のまま、米搗きや薪拾いなど寺の雑務を行う労働者の事である。特に中国禅宗に多く見られ、禅宗六祖の慧能が、五祖の弘忍のいた黄梅山で「盧行者」として米搗きに従事していた時に弘忍から六代目として認められた事例が有名である。 ★良寛、山中の沈黙行 独り奏す没弦琴(P.54~57) 大忍国仙の死後、寺を出て玉島を去ったあとの良寛の足跡はよくわからない。九州や四国にも渡ったことがるともいうが、ともかく諸国の名僧知識を訪ね、自己の心境を深めるため、永い諸国行脚の道についたものらしい。そのころの良寛ンいついての信頼しうる報告が、たまたま江戸の近藤万丈(こんどうばんじょう)という国学者の手記にある。これは良寛の修行ぶりを知る上にいろいろと示唆を与えてくれる貴重な証言だから、吉野秀雄が現代語に訳したものを以下に掲げる。(中の解説も吉野秀雄、ただ仮な遣いは改めた。) 自分の若い頃(近藤万丈の若い時分)、土佐の国へいった時、城下から三里ばかりこっちで(これは高知の東三里のことであろう)、雨もひどく降り、日も暮れた。道から二丁目ほど右手の山の麓に、みすぼらしい庵(いおり)が見えたので、そこへいって宿を乞うと、色青く顔の痩せた坊さんが(これぞ良寛である)、ひとり炉を囲んでいたが、食いものも風をふせぐ夜着も何もないという。この坊さん、はじめに口をきいただけで、あとは一言も物をいわず、坐禅するでもなく、眠るでもなく、口のうちに念仏唱えるでもなく、こっちから話しかけてもただ微笑するばかりなので、自分はこいつぁてっきり気狂いだと思って、その夜は炉端にごろ寝をしたが、明け方目ざめてみると、坊さんもやはり炉端に手枕をしてぐっすり寝込んでいた。あくる朝も雨がひどくて出かけられないので、今しばらく宿を貸して下さらぬかといえば、いつまでなりともと答えてくれたのは、きのうにまさってうれしかった。巳の刻すぎ(正午近い頃)、麦の粉を湯がいて食わせてくれた。さてその庵の中を見廻すと、ただ木仏が一躯立っているのと、窓の下に小机を据えて本を二冊おいてある外は、何一つ貯えを持っている様子もない。机の上の本は何であろうかと開いてみれば、唐本の『荘子』である。その中にこの坊さんの作と思われる詩を草書で書いたのが挟んであった。自分は漢詩は習わぬので上手下手は分からぬが、その草書は目を驚かすばかり見事なものであった。そこで笈(おい):(背中に負う脚のついた箱)の中から扇子を二本取り出して、梅に鶯の絵と富士山の絵とに賛さんをもとめたところが、たちどころに筆を染めてくれた。その賛は忘れたが、富士の絵の賛のしまいに、「かくいう者は誰たぞ。越州(越後)の産了寛(良寛の書き搊じか、記憶違い)書す」とあったのを覚えている。 これは近藤万丈が相手を何者とも知らずに体験だけを書いているので、貴重な証言でもあり、また凄みがある。良寛はそのときみずからに沈黙の行を課していたのであろうが、それにしてもその暮しぶりの徹底した無一物ぶり、沈黙ぶりは凄じい。吉野秀雄はそれについてこう言っている。 「良寛は、今や肉削そげ、肩ゆがみ、顔面蒼白の壮年乞食僧と化したが、しかもあくまで沈黙を守り抜こうととしている。この沈黙は無気味だ。じいんと静まり返ったこの沈黙は恐ろしい。なぜなら、彼の沈黙はおのずから彼の真理追及の難行苦行がいかに充実し、透徹していたかを現示する以外のなにものでもないからだ。>」 実際そうであろうと思う。旅人の目によってちらりと垣間見られた良寛の姿は、その小さな映像を通じてその向うに当時の良寛の課した修行のきびしさと、内的生活の充実を感じさせるに充分である。良寛といえども一日にして成ったのではなかった。大忍国師に印可を授けられたあとも、ひたすらこういう己が心をのみ凝視する修行をつづけて、ようやくわれわれが見る良寛を作りあげていたのだ。外から見ればただの乞食坊主にすぎないが、内にはゆったりと清らかな水が流れ、没絃琴ぼつげんきんの調べに聴き入っている透徹の人に。 静夜 草庵の裏うち 独り奏す 没絃琴(ぼつげんきん) 調べは風雲に入りて絶え 声は流れに和して深し 洋々 渓谷(けいこく)に盈(み)ち 颯々(さつさつ) 山林を度(わた)る 耳聾漢(じろうかん)に非ざるよりは 誰か聞かん 希声(きせい)の音 何もない貧しい草庵にあって、良寛の心の中にはそいう音のない琴の音がひびき、風に飛んで消え、流れと和して妙なる諧調をなしていたのである。解良栄重のいう「神気内に充て秀発す」とは、そういう内的充実のことを言うのであろう。この没絃琴の調べは山中孤独の草庵だからひびいたのであって大伽藍に住む金襴の僧には決して聞こえない性質の音であった。 僧になるとは、云うまでもなく世俗の社会を捨て、仏道修行に生涯をささげる生を選ぶことである。そこに俗塵の入る余地はないはずだが、法界もまた一つの人間の社会であれば、そこにも他人を出しぬいていい寺の住職になりたいとか、権勢に重んじられて権力の端に連なりたいとか、およそ仏法に反する欲望もさかんだったのだ。あるいは大方の僧がそうであったかもしれぬ。江戸時代三百年は、仏教が幕府権力に操縦され最も堕落した時代だったから、そういう徒がおおかったに違いない。 その中で仏道修行を純粋に心の修行とした良寛のような修行僧は、まさに「孤」たらざるを得ず、その純粋性を貫きには寺院制度からはみ出して、どこにも所属しない「個」であるしかなかっただろう。あるのは己れひとりの心の世界だけである。乞食の中でその心をみがいた良寛だから、いまなおその生き方がわれわれの心をひきつけてやまないのであろう。 平成29(2017)年5月10日
橘 曙覧、雨の漏る陋屋に万巻の書 P.96~106 歌よみて遊ぶほかなし吾はただ 橘 曙覧(たちばなあけみ)(1812~1867)といっても今は日本人でも知る人はほとんどいないだろうが、幕末の歌人で、明治になって正岡子規がその万葉調の歌を評価して以来有名になった。わたしはこの人の素直な生活の歌が好きで、前々から親しんできた。その曙覧の『志濃夫廼舎歌集(しのぶのやかしゅう)』に、大雅とその妻玉瀾と、玉瀾の母百合女を詠んだ歌がある。 祇園百合女 一つある葉かあげの蕾かき抱き身を野に朽たす姫ゆりの花 池無名 勢田の橋その人とほく去りて後すてし扇を見ひしがる哉 玉瀾女 此の筆は眉根つくろふ筆ならず山水(やまみず)かきて背に見する筆 わざわざこうやって大雅とそのまわりの人びとを詠んだことにも、曙覧がいかにその風を慕っていたかが察しられるが、これらの歌には大雅にんついての逸話が元になっている。 大雅は若いころまで世に知られず一向に画が売れないので、扇子に画をかいて祇園の境内で売っていたことがあった。売るといっても筵を敷いてその上に扇子を並べておくだけの話だが、幾日たってもまるで売れない。そのとき祇園社に茶店を出していたのが百合女で、茶店は母の梶という女からひきついだものであった。梶も娘の百合も風流の人であって、梶には『梶の葉』、百合には『佐遊李葉(さゆりば)』という歌集がある。その百合女が見かねて何くれと親切にしてやり、それから縁が生じ、結局は百合の娘町うを池無名に嫁がせることになったのだ。 その大雅は文人画を柳里恭(りゅうりきょう)や祇園南海(ぎおんなんかい)に学び、相当な域に達していても無名では画で生きていくことができない。そこで扇子に絵を画いて近江のほうへ売りにいったがまったく売れず、帰りに瀬田の橋まで来たとき、売れぬものならせめて竜神に捧げてしまえと、扇を全部川の中に投げてしまったというのである。 そいう逸話を曙覧は知っていたから、百合女には娘の町をかき抱いていつくしみ育てる歌を、大雅にはあなたの捨てたというその扇がみたいものですという歌を、玉瀾にはあなたが大雅とむつまじく絵を描くところこそ慕わしいという歌を、それぞれ詠んだのであろう。 玉瀾という人もまことにその人柄の慕わしい人であって、彼女が夫とともに暮らして少しもその貧乏を苦にせず、絵の世界にのみ遊ぶ人だったことは前に記したが、彼女の絵も実にみごとなものだったらしい。森銑三が『雲烟琑淡(うんえんさだん)』という本の中の逸話を紹介しているので、それを訳してみる。 閨秀で南画をよくした者を挙げるならばまず玉瀾をもって第一としなければならないとは、ひとり田能村竹田の説ばかりでなく、ほとんど古来の定説と言っていい。玉瀾はその身が百合の子であり、また大雅の妻だというそのことだけでも、すでになんとなく慕わしい気がするが、ましてその人品が高雅で、その筆墨の技が精妙なのであるからなおさらである。世人が彼女の遺墨を珍重してやまないのも尤もというべきである。 ところで自分が見ることを得た玉瀾の真蹟の中で最も賞翫したのは、小雲氏所蔵の摺扇(しょうせん)であった。これは無造作に描きだした山水の画だが、そこにかえって無限の興趣があった。左の上方に大雅の筆で『泉臨香澗落(いずみはこうかんにのぞみておち)、峰入翠雲多(みねはすいうんにいりておおし)』という沈佺期(ちんせんき)の句が記されており、その書もまた実にいいものだった。 この摺扇はもと司馬江漢(しばこうかん)が所有していたもので、その箱に江漢の筆で『大雅書、玉瀾画』と認(したた)め、その下に例のローマ字で江漢のなを記してあるばかりか、扇の裏面に次のような文章が記してあった。 『三浦侯の大夫九津見氏は俗に人呼んで唐人吉左衛門という風流の第一人者であったが、信州から京都にいつたったおり、玉瀾女の茶店で扇を買い、それを持って大雅を訪ねて字を書いてもらった。そして江戸に来て自分にこれを贈ってくれたのである。大事に蔵することほとんど三十年になる。いま脇坂氏が切にこれを求めるので与える次第である。文化元年甲子暮、春波楼主人認む』と。 見るにたしかに玉瀾の画、大雅の書である、まことに貴重なものだ。ましてや江漢が久しく珍翫して来たというのだからなおさらである。この摺扇のような逸品は、世間にもめったにないであろう。 この九津見吉左衛門とは森銑三氏の注によれば荻生徂徠門で才名の高かった源京国、九津見華岳(くずみかがく)という人だそうで、その人が扇を手に入れた次第といい、それを貰ったのが司馬江漢であったことといい、扇一つを通じて文人の心が伝えられていったさまがなんとも好ましいのである。 つまり橘曙覧は、玉瀾がそういう人であることを知って、かの歌を詠んだわけだ。 曙覧は福井の人で、三十代半ばに決心して「祖先相伝の家業財産を挙げて弟宜に譲り、飄然として城南の足羽山(あしばやま)に退去し、専(もつぱ)ら文学に従事>したのであった。以後五十七歳で没するまで、まさに「専ら文学に従事」し、貧乏暮しも意に介せず歌を詠んで生きた。その歌が明治になって子規に、 「曙覧の歌想は万葉より進みたる処あり、曙覧の歌調は万葉に及ばざる処あり。」 と評価されて世に知られたのである。 うつくしき蝶ほしがりて花園の花に少女の汗こぼすかな 人臭き人に聞かする歌ならず鬼の夜ふけて来ばつげもせむ 若葉さすころはいづこの山見ても何の木見ても麗しきかな 生活の中の感情を歌っていて、実感があり、そこが子規には気に入ったのだろう。これらの歌にはほとんど明治人が詠んだと言っていい新鮮な感覚がある。 曙覧の歌で最も有名なのは「たのしみは」に始まる『独楽吟』であろう。この時代にこんなふうに自由に生活歌を作っていた新しさに驚かされるのである。 たのしみは珍しき書(ふみ)人にかり始め一ひらひろげたる時 たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどひ頭ならべて物をくふ時 たのしみはそぞろ読みゆく書の中に我とひとしきひとを見し時 どれもみな貧乏生活の中での生きるよろこびの一瞬を詠んだもので、現代のわれわれにもじかに通じる歌ばかりである。彼は何十首もこういう歌を作りつづけている。 この無名の歌人を高く評価したのは福井藩の家老中根雪江(なかね ゆきえ)で、雪江は初めは曙覧に歌を教えたのだが、後には「余は始めの程こそ先達(せんだつ)めきて物しつれ、いまはかなわぬ」といい、曙覧の歌についてこう言っている。 「その歌風は次第に境を高めていって、世のありきたりの風を抜ん出て、何よりも上世の心ばえを主んじ、世間に起る事や意表に思うことどもを、ただそのままに詠みあげている。」 と、曙覧の歌の新しさ、高さをほめ讃えているのである。 そしてこの中根雪江の推奨によって主人松平春嶽も曙覧を重んじ、安政の大獄に連坐して春嶽が江戸の邸内に幽居していたときは、曙覧に命じて万葉の秀歌を選んで書かせ、それを部屋の四周に貼って心の慰めとしたという。また元治二(一八六五)年には中根雪江の案内で曙覧の陋屋を訪ね、その貧しさ、いぶせきに驚いたことをみずから文章に書き遺している(「橘曙覧の家にいたる詞」)。この文章は貴顕から見た陰士の生活の記録としても面白いから、次に訳してみる。 かねて自分よりすぐれた物事を知る人には、身分の高下を問わず会って物を尋ね、あるいは物語を聞きたいものだと思っていたが、今日はこのころには珍しく日影あたたかに、久かたの空晴れてのどかな日和だったので、こんな日には山川野辺の景色もよかろうと、巳の刻(午前十時)の鼓を打つころから野遊びに出かけ、三橋(みつはし)という所に行った。そこに見える家をさして中根師賢(雪江)が、あれが曙覧の家でございますと言うのを聞いて、急に訪ねてみる気になった。 行ってみると小さな板屋の惨めな家で、囲いもなく、片付けもしないのか、そこかしこに塵埃が山をなしている。柴の門とてなく、心許ない気持で家に入っていった。師賢が気ぜわしくなく『参議の君のお成りぞ』と大声で呼ばると、中から膝折り伏せるようにして家の者が這い出て来た。 少し広いところに入ってみると、壁は落ちかかり、障子はやぶれ、畳は切れ、雨の漏るような有様であるけれども、机の上にはおびただしい書物が積んであって、あやしげな厨子に人丸(ひとまる)の御像なぞも飾れていた。自分は着物を脱いで、賤(しず)の着る粗末な衣に着かぇた。そして扇一本を侍医の半井保(なからいたもつ:福井藩の侍医、諱は保、通称元沖)に渡し、これを曙覧に与えよと伝え、あらためて曙覧にむかって言った。 ーーそなたの屋のなを『わらや』と呼ぶのはふさわしくない。橘という姓の縁もあることゆえ、今日からは『忍ぶの屋』とあらためるがよい。 とはいうものの家の中の汚いことはたとえようもない。虱という虫なども這い出てくるのではないかと思われるほどであった。 だが、形はこのように貧しく見えるとも、その心の雅びこそまことに慕わしいものだったのである。自分は富貴の身で大厦高楼(たいかこうろう)に住み、何ひとつ足らぬものとてない身上であるけれども、その屋に万巻の書の蓄えもなく、心は寒く貧しく、曙覧に劣ること言うまでもないから、自然とうしろめたく顔が赤くなる気持ちがしたことであった。これからは曙覧のうたばかりでなく、その心の雅びを慕い学ばねばならぬ、と思った。 さようの次第であるから、日ごろの心の汚れを洗い、浮世の外の月花を友とするよう、子孫の者も心がけるがよい。 かく申すは参議正四位、大蔵の大輔源朝臣慶永(よしなが)、元治二年(きさらぎ)末の六日、館に帰って記す。 松平春嶽は幕末の名君といわれているが、その人でも曙覧の住居の汚さに辟易しているさまがよくうかがえる。これが鴨長明の方丈庵とか兼好法師の庵を訪れたのなら、かれらは独身で身奇麗に住なしていたろうから貧しさに驚いても気味悪がったりはしなかったろうに、曙覧は子沢山で汚すうえ、散らかし放題なのでそのひどさに呆れかえったのだ。しかしひとたび曙覧と話してみると、相手の高雅な心根はすぐわかり、貧しい曙覧にくらべたら高貴の身の自分のほうがどんなに「心寒く貧しく」劣っているかと気づいたというところがいい。 曙覧が『独楽吟』四十五首を書きつけて春嶽の家臣勝沢愿(かつざわげん)に与えたことがあったらしい。勝沢が当直のおりにそれを春嶽にさしあげたところ、春嶽は、 「予これをみれば、おかしくおもしろく、はた人情のきはみ其外の興さまざまなりけり。下情しらぬ予これをみて、いかにとおもひあたりし事もありしなり。予もこれにならひて五十首をよみて、西施之傚顰(せいしのひそっみにならう)にちかしとひとり笑ひて、かくはしがきけるなり。」 自分も曙覧のまねをして五十首詠んでいるのである。そんなことからも春嶽は、こと風雅の道においては自分がいかに劣っているかを身をもって知っていたのであろう。春嶽のその歌も『志濃夫廼舎歌集』に載っていんるが、これはまあ紹介するに及ぶまい。興味のある人は歌集について看られよ。 春嶽は曙覧の閑居を訪問したあと、侍臣を派遣して曙覧に、城中への伺候と図書の進講とをすすめたようだが、曙覧はそれを固辞して受けなかったことが「歌集」からもうかがえる。
二月廿六日(元治二年乙丑)
賤夫(しづのを)も生けるしるしの有りて今日君来ましける伏屋(ふせや)の中に
其後、御館にまうのぼばるべう、川崎致高主を御使として仰せごと
花めきてしばし見ゆるもすずな園田盧(たぶせのいほ)に咲けばなりけり この川崎致高というのは春嶽の侍士で曙覧の門人、風雅の士であったが、讒(ざ)に遭って明治二(一八六九)年、自刃したそうである。 すずなはあの春の七草の鈴菜で、こんな青葉が花めいて見えるのも田舎家に咲いているからでありまして、御殿でも花と見えるわけではありませぬ、と固辞しているのだ。曙覧の心根はあくまでも野にあって心のまま自由に生きるところにあった。 たのしみは 意(こころ)にかなふ 山水の あたりしづかに 見てありくとき たのしみは 書(ふみ)よみ倦(う)める をりしもあれ 声(こゑ)知る人の 門たたく時 たのしみは 客人(まれびと(まらうど))えたる 折しもあれ 瓢(ひさご)に酒の ありあへる時 こういうたのしみは宮仕えしても叶わず、あくまでも誰にもたよらぬ独立独歩の貧しい暮しにのみあることを曙覧はよく心得、自分の風雅はそういうところにおいてのみありうると知っていたに違いない。 彼が死んだのは明治と改元された年の八月で、幕末の激動期に数奇(すうき)なその歌人の生を終えたのだった。彼の志はこんな歌によくあらわれていると思われる。 歌よみて遊ぶ外なし吾はただ天(あめ)にありとも土(つち)にありとも 幽世(かくりよ)に入るとも吾は現世(うつしよ)に在るとひとしく歌をよむのみ 参考:常世(とこよ)、かくりよ(隠世、幽世)とは、永久に変わらない神域。死後の世界でもあり、黄泉もそこにあるとされる。「永久」を意味し、古くは「常夜」とも表記した。日本神話や古神道や神道の重要な二律する世界観の一方であり、対峙して「現世(うつしよ)」がある。変化の無い世界であり、例えるなら因果律がないような定常的であり、ある部分では時間軸が無いともいえる様な世界。ウィキペディアより。
中野孝次『現代人の作法』(岩波新書)(1997年4月11日 第1刷発行)
あるポスター ある日わが街の駅のプラットホームで、たくさんの絵入りポスターの中に字だけのこんなポスターがまじっていた。 わたしは興味を覚え早速手帳に写し始めたが、写していてこんなポスターを作らざるを得なかった担当者の苦汁の顔が見えるように思い、なんとなくおかしくなった。 むろんこんな事態が起こらぬようにするには、あらゆる駅のプラットホームに缶ジュースの販売機を置かなければいいのである。簡単な話だ。それでは鉄道共済会(と今でもいうのかどうか)か何か、とにかく業者が困るのであろう。そこでマナーに訴えるこういう一種の意見広告を作ったわけだろう。空しいことは重々承知の上で。 実際いま電車に乗っていて、空缶があっちへころころ、こっちへころころ転がりつづけ、乗客はみな知らん顔をしているというふ愉快な体験は、誰もがしている。それどころか缶ジュースをちびちび啜りりながらマンガ雑誌を読み、やがて平気でその空缶を床に置いて出てゆく若者も後を絶たない。が、それに対しても誰も注意しない。たまに見るに見かねた老人が(わたしもその一人)降りるときふ快そうにそれをつまんで、駅のゴミ箱に捨てるぐらいのものだ。 我慢ができない 缶ジュースの自動販売機なんてものが出現する以前は、もちろんこんな問題は生じなかったわけである。が、いつごろかそれが発明され設置され、街のいたるところに見かけだしたときから、人はそれなしではいられぬようになったらしい。わたしの住む郊外の街でも駅の周辺に無数の自動販売機が立っていて、見ていると駅からぞろぞろ出て来た乗客の何人かはそこから缶を出し、飲みながら帰ってゆく。自宅までの十分か十五分家へつくまで我慢できないのか、と昔者のわたしなどは歯がゆく思うが、そのわずかの距離でも我慢できないでただちに欲望を充足させるのが、今の日本人なのだ。 しかも彼らは飲み終わると他人の家であろうと何であろうとお構いなく、飲み終わったところにそれを捨ててゆく。駅から三、四分のわたしのところなどちょうど飲み終わる時らしく、塀ぎわにそれの捨てられていない日はない。わが住む街横浜市でもさすがにそれを見かねたか、先年「ポイ捨て禁止法」なるものを作ったが、事態は一向に変わらない。 人が物を追いかける時代 わたしはそこに現代特有の病を見るような気がしている。つまり、まず新しい企業の製品が世に出現し、それが人間の健康や教育のためにいにのか悪いのか、生きるために必要なのかどうか検討することもなく、その新しさ、便利さ、快適さ、安易な欲望充足性のゆえに受け入れられ、流行し、誰もがそれにどっぷりつかってしまう。物が先に世に表れ、人は無批判にその流行に従って、それを使うマナーなんてものの生じるひまがないのである。ある日気がついたら、草むらは空缶だらけになってしまっていたというだけだ。 それに対して社会が合意して認める取扱い基準、行動基準が出来上がらぬうちに、新しい物だけが先に横行し始め、人の側が事態に追いついいけないということが、いろんな面で起こっているのである。といって今さらその物を社会から廃棄させるわけにもいかないから、やむを得ず遅まきながら駅のポスターのように「マナーって、なんだろう」と人間のふるまい方を問うことになる。こんな例はほかにもいくらもある。いや、現代はすべて物の方が先行して、人間はあとから物を追っかけつづけている時代だ、と言ってもいいかもしれない。 昔からあるものならば、人はそれに対しどう対処すべきかを知っている。何はいい何は悪いと言うことができる。何に対してどうすべきかというきまりがある。ことに対する作法が決まっている。 たとえばお茶ならば、これには昔から茶道というものがあって、その淹(い)れ方、のみ方、道具の扱い方、立居ふるまいの仕方など、すべてきちんと作法がつくられている。人はそれに従って行動すれば笑い者にもならず、人と和し、同じ一つの世界に遊ぶことができる。が、缶ジュースなんてものはここ数十年間に初めて出現したものだけに、どうとり扱っていいか決まりもなく、ただ欲望のままそれに手を出し、用が終われば捨てる。扱いは人それぞれの良識にまかされているわけで、結果をみれば缶ジュース愛用者には良識ある連中はめつたにいないことが判明しただけである。ともかく今や街中いたるところ空缶がポイ捨てされている有様なのだから、それに対しては駅のポスターのように生ぬるくでなく、 むやみに空缶を捨てるな とでもいうしかないのである。P.2~6 ★リンク:アメリカメイン州のバーハバーへの旅 16 「自由と規律」 見るに見かねる若者の行状 ここまで来てわれわれは、作法とは倫理観が形にあらわれるものであり、従って自分の価値体系を持たぬ者には作法はありえない、と結論づけてもいいように思う。見方をひろげれば無作法とは無倫理のことなのであった。 若者には作法がないという。たしかに無礼で無作法で自分たちのことしか念頭にないような若者が多いことは、多くの人の指摘するとおりだ。わたしも見るに見かねることが多い。 いつか朝日新聞の「天声人語」が報道して大いに話題になったものに、電車の中で老婦人が譲られた座席に坐ろうとしたら、自分が腰かけようと予定していたらしい高校生に「ババア死んでしまえ」等々のひどい罵声を浴びせられたという事件があった。事実ひどい話で、わたしも読んだとき怒りがこみあげてきたけれども、これはいわば氷山の一角であろう。昔は想像できなかったような精神状態に、現代の若者に一部はいるらしいのである。この文章の初めの方にもいくつか挙げたが、街中で見ただけでも彼らの行状にはあまりにも見るに見かねるものが多い。 ◇大股ひろげて座席を占拠し、自分が他の乗客に迷惑かけているという自覚がまったくない若者。 ◇シルバーシートに掛けて老人が前に立ってもぜんぜん席を譲る気のない若者。 ◇大きなスポーツバッグを肩からさげて、それが他の乗客にふ快感と苦痛を与えていることに気付かぬ若者。 ◇入口にかたまって「ウッソ!」「ヤダー!」などとあたりままわぬ嬌声をあげ、そのかしまさがどんなふ快感を与えていつかに気づかぬ女子高生たち。 ◇入口につっ立っておしゃべりに夢中になったまま、ドアの開閉、乗客の乗り降りにも平気でいる女子高生ども。 ◇電車の中ですぐしゃがみこむ若者、道ばたや広場でウンコ坐りしたまま話しこんでいる若者。 そういう例を列挙したらきりがないだろう。彼らの姿は見て醜いし、みっとっもないし、どん感だし、はた迷惑きわまりないが、肝心なのは彼らがそれらのことに気がついていない、自覚していない、他人に迷惑をかけているという意識がまったくないらしいことだ。街中で見かけるだけでもそうなのだから、彼らの家庭や学校における行状は想像に余りあるが、わたしがいま運命に感謝していることの一つは、こんな若者どもと教場や家庭で付き合わずにすむということなのである。わたしの年下の友人は高校教師として彼らと日常接しないわけにゆかず、ときどきその話をするが、それは聞くだにすさまじいものであった。 とにかくこういう連中は、国内でこそ何とか存在を容認されていても、とても外国に出せるものでなく、出したらそれこそ昔の右翼用語にいう「国辱もの」であろう。日本の高校や大学でやっていけない連中が欧米の学校にゆく例がふえ、彼らの現地の家庭にホームスティするようだが、日本でのこんな行状をそのまま持ちこんでそれが許容されるわけもなく、鼻つまみ者になり、たちまち追い出されてしまうという。その男女交際のふしだらさからイェローキャプなどと蔑称される女子大生なども出ている。 だれの責任か とにかくごくあたり前のたしなみ、作法がないのだから、外国で通用するはずもないのだ。が、そういう目に遇うのは彼らの勝手であり、こちらの知ったことじゃないのだが、こういうけじめもわからぬ、物の善悪も知らぬ、自己本位の若者が出現したことに対しては大人の側にも責任なしとしないのではないか。つまり大人が━初めは生んだ親が、ついで学校の教師が、さらには社会で彼らに接した第三者が━彼らに物事のけじめ、善し悪しの判断力、美醜の感覚を、すなわち作法を、子供のときからしっかり叩きこんでこなかった結果が、現在見るが如き若者の行状となって現れているのであろう。とすればこの本源的責任は大人にあるということになる。 戦後の子供観 生まれてきた子供はそのまま善である。天使のような存在だ、無邪気だ、可愛いい、だからいかなる強制も行わず、自由にのびのびと成長させるがいい、自由放任させておけば子供は自然にいい子に育つだろうといった子供観が、戦後ずっとこの国では支配的であったようにわたしは感じている。少なくとも昔のようにスパルタ式教育がいい、武士道的躾が必要だ、などという者は、親にも教師にも一人もいなかったように覚えている。 その結果大抵の家庭が、自由放任を以て家における子供教育方針にした。子供をのびのび育てるのが善とされた。子供の欲望や要求はなるべく叶えてやり、命令せず、強要せず、できるかぎり叱らず、好きなようにさせとくのがいいとされた。 わたしの世代の時分は大抵の家の子が、家では掃除、整理整頓、雑巾がけ、子守り、あるいは水汲み、庭仕事、風呂たきをさせられた。家の周りの掃除のできぬ子はいなかった。そうやって親に命じられた仕事をすることで子供は掃除や雑巾がけや、薪割り、風呂の火焚き、刃物の扱いなど覚えたのだ。 しかし戦後は、とくに都会では、ほとんどの家庭で子供はそういう家庭での手伝いをさせられなかったように見える。現に掃除をどうしたらいいか知らない子、ナイフでものを削れない子まで出てきているのだから、そう判断して間違いあるまい。正しい箸の持ち方、正しい鉛筆の持ち方のできない子にいたっては無数である。 それらをさせないことが、子供の能力の開発を妨げている、というふうには親たちは考えなかった。子供には楽をさせ、その代りになるべくたくさん勉強させるがいいとされた。学習塾へ行くのは善であり、とにかくすべてが受験勉強のために捧げられたのだから、子供の精神的訓練、躾、徳育、人格の陶冶といったことはてんで問題にされなかった。子供らは欲するものは何でも与えられたから我慢を知らず、物にふ自由したり欲望が叶えられぬ状態を知らない。 『自由と規律』の世界 昔の日本では武家ばかりでなく農民、商家、職人の家でも、暖衣飽食は子供の教育によくないとされ、欲望を抑えること、我慢すること、忍耐すること、総じて質実な生活をするのがいいとされた。これは前にもちょっと紹介した英国のパブリックスクールの暮しも同じで、名著といっていい池田潔『自由と規律』(岩波新書、一九四九年)によると、それは食事一つとっても実に想像を絶する質実さである。
朝は、オートミール少量、燻製にしん、またはソーセージ一片など、日曜日の卵一個は最大の御馳走である。キャベツの小量がつくこともある。菓子一皿、パン一片、お茶は、パン三斤、マーガリン少量、紅茶。夜食というものは全然ない。 質も量もともに実に粗末なもので、これでは食い盛りの十二歳ー十九歳の若者をとうてい満足させることはできない。生徒たちはだから昼飯が終わるとこれで翌朝まで何も食べれないかと寂寥感に陥ったというが、さもあろう。しかしこの粗食は長いあいだの教育の経験から導きだされた方針なのである。裕福な家庭で育った子供たちはこのような忍耐生活に放りこまれて、初めは地獄の苦しみを味わう。ひもじさを味わい、それを我慢する。そのことが大切な体験なのだ。住居たる寮の生活もこれと同じである。 室の南北に十個ずつ大きな窓があり、四季を通じて夜も昼も開け放たれている。毛布は夏一枚冬二枚、掛布団はなく、教師の室と病室を除いては学校中に暖房設備というものがない。室内を 吹き荒(すさ)ぶ木枯に一夜が明けて、朝、目が覚めると毛布の裾に薄く雪が積っていることがある。洗面器の水も、堅く栓をした瓶の中の髪油も、バリバリ凍りついている。しかし、そんな朝でも彼等は一斉にピジャマの上衣を脱ぎ捨てて、顔から首すじ上半身をまっ赤になるまで洗いたてる。 まるで戦前の日本の軍隊を思わせるような過酷な生活環境だが、暖房も何もないこの生活も教育上の必要と見做されたのだった。なんのためにそうするか。著者の池田潔は、もと慶応大学学長だった小泉信三の「自由と訓練」という文章を引用している。 生徒は多く裕福な家の子弟であるから右のような欠乏が経済的必要から来たものでないことは明らかである。食物量の制限hあ思春期の少年の飽食をふ可とする考慮に出たといんふ説を聞いたことがある。何れにしても何事も少年等のほしいままにさせぬことは、自由を尊ぶイギリスの学校としてわれわれの意外とすべきものが多い。しかし、ここに長い年月の経験と考慮とが費されてゐることを思わねばなるまい。 かく厳格なる教育が、それによって期するところは何であるか。それは正邪の観念を明らかにし、正を正とし邪を邪としてはばからぬ道徳的勇気を養ひ、各人がかかる勇気を持つところに始めて真の自由の保障がある所以を教へることにあると思ふ。 少年たちはこういう過酷な耐乏生活を克朊することで精神をきたえ、苦痛の先にこそ本当の満足があること、耐乏生活なしに身心の訓練はないことを学ぶ。欲望を抑制し、質朴な日常に耐えることで意志を強くし、善を善、邪を邪とする「心の磁石」を養う。それが人間教育にとっても最も大事だというのである。 ◇何事も子供のほしいままにさせることは、子供のたちのためになるどころか子供たちを搊なう所以である。 ◇厳格なる教育によってのみ、正を正とし邪を邪とする道徳的勇気は養成される。 ◇そして各人がそういう勇気を持つところにのみ真の自由が保障される。 池田潔『自由と規律』が英国のパブリックスクールを範として説くところは上の三条につづめられようが、省みて戦後日本の家庭教育、学校教育はまさにこの反対だったのではあるまいか。家庭でも学校でも社会でも、自由を放任と誤解し、子供の好き勝手にさせておくことが民主主義と思いこんだのではなかったか。 ◇だが、自由とは甘やかしのことではない。厳格なる教育によってのみ子供は人格を要請される。人格とは正邪、善悪を正しく判断し、正しいもののために戦う道徳的勇気をもつ人間のことである。 この親たちにしてこの子らあり 戦後の日本の教育を誤らせたのは、結局戦後社会を作った大人たちだということになる。彼らが自由を誤解し、規律を守る必要を教えこまなかったために、どう見ても甘ったれた、我慢のない、他者への思いやりを欠く子供たちが多くできてしまったのだというしかないだろう。 甘ったれとは、どうなってもいつかは他人が助けてくれるだろう、cという根性のことだ。自分のしたことは自分が責任をとる、というきびんしい覚悟を欠くことだ。一度も授業に出ないで単位だけもらおうと土下座してたのみこむ大学生や、個人破産者が 五万件をこえるなどという事態は、その一つのあらわれであろう。 毎年とくに冬になると、中高年登山者の遭難事故が起こる。ここ十数年来登山はほとんど中高年者の行うところとなって、若者はそんなきつく苦しいだけのスポーツをしないが、その中高年登山者にも甘えがある。未経験、未訓練なのに危険なところへも平気でのこのこでかけ、しかも装備、食料もふ十分で、滑落したり、道に迷ったり、雪崩に巻きこまれたりする。そしてそのたびに山岳救助隊に助けをもとめるのである。充分なる訓練と調査と準備がないからそうなるのだが、遭難しも誰かが助けてくれるだろうという甘えがあるからそれをしない。山に対する作法がなっていないのである。 ◇甘えがあるとは、いくつになっても精神的に未熟なことである。未成熟とは人間になり切っていないということである。 ◇どんな事柄でも成しとげるためには規律の学習と訓練とが要る。心身ともの鍛錬、訓練なしに何事もなせるわけがない。 しかし戦後の日本社会はたまたま未曽有の経済的成功をなしとげ、物質的にゆたかになったために、どんな事柄でも金さえだせばできるのだという錯覚に陥ったように見える。いまの日本は食料自給率三〇パーセントあるかなしという慢性的な食糧ふ足国だが、金さえ払えばどこからでも輸入できると安心しきって、自足をはからない。これもまた甘えであり、世界中の貧しい食料ふ足国に対する傲慢である。世の中には金では買えないものがある、かってはならぬものがあるということを日本人は忘れてしまったかのようだ。 とくに、人間としての能力の養成は、心身ともにいかに金があっても自己訓練なしに達成されるものでないという単純な事実さえ、とかく今はかえりみられなくなっている。登山などはその最たるもので、きびしい鍛錬と充分な準備なしに甘ったれた気持で山へ入ったりするから、山の神はただちに死をもって罰するのである。山には山の規律が、社会には社会のきびしい規律がある。社会の方はただ山の神のようにただちには罰を与えないだけである。だが甘ったれた未熟者に対し、罰はいつかは必ず下されるのである。 Link:『自由と規律』
17 自己が万法に証せられるるがゆえに 「テレビドラマの中の作法」
老父清左衛門が畳に正坐して話しているのに、三十にもなる伜が刀を持ったままでつつ立って聞いているなんてシーンが、平気でながなが放映される。こんなのは、ディレクター氏がほんの僅かでも想像力があれば、ありうべからざる行為であるぐらいすぐわかるはずだ。武士の子供は幼児から親の話しを聞くときはきちんと正坐し、両手を膝にのせて、親の目をしっかり見つめながら聞くように躾られている。そのごく当り前のことさえわからないのは、つまり彼は親からその常識的作法を教えられたこともなく、ふだん自分もつつ立ったままやりとりしているからであろう。 一事が万事、当然心得ているべき作法の一つ一つがなっていないから、見るだけで腹が立つのである。 しかし顧みるに、作法のこの当然の常識と非常識のあいだの落差にこそ、戦後五十年の日本社会があるのだろう。 結局すべての原因は、一九四五年の敗戦で自信喪失し、価値基準を見失った親の世代が、権威と自信を以て子供たちに是非善悪、正邪の見きわめを教えてこなかった、人間のあるべきようについて自分の信念を伝えられなかったところにあるということであろう。親自身が信念を持てなくなったのだから仕方がないが。そしてその親から何も教えられなかった子が親になっても、結局は親と同じく真の自信と権威をもって人間はこうふるまうべしという基準を子らに伝えられず、その繰り返しが、今日のこの無作法の時代を将来してしまったのだと思われる。 普遍的価値観の存在 そうなった大元には、天皇中心国家から民主主義社会への大変換が行われた過程で、民主主義や自由や個人の権利といったことへの誤解が横たわっていたにちがいない。個人の権利には社会の秩序とルールへの尊重の義務が対としてあり、自由には規律尊重が対としてあるという、その当然の反面が見えず、自由は野放しの放任となり、個人の権利はエゴイズムに歪曲された。何をしても自由という社会など成立ちうべくもないのに、なんとなく「自分がしたいことをして何が悪い」という雰囲気のみが支配的になってしまった。 そして親たちはいまでも、人間こうあるべしについて本当の自信を持つにはいたっていないのではないか。前にも言ったように子供は無知なのである、人間となるためには人間として躾けられ教育されねばならぬものである。子供は馴致されねば人間とならぬ存在であり、その子供を本当に教育するには、親は権威と自信と、時には体罰をふくむ強制を以てしなければならぬであろう。いまもそういうきびしい態度で子に対している国は地球上どこにでもある。日本も昔の親はそうした。その当たり前の教育が戦後行われなくなったところに、今日のこの事態が生じたのだ、と考えるしかないのであるまいか。 では、そういうきびしい態度で子に対し教育できた昔の親には何があったのか。彼らの自信と権威を支えていたのは何であったのか。 それは、このことは、一個の自分が勝手に私の意見として言うのではない、これは人間として当然そうすべき決まりだから言うのだ、これが人間の道だから言うのだ、という心持であったろうとわたしは信じている。 その親に、では人間の道とはどういうものだ、どうしてそれが絶対に正しい人間の道だとわかるんだ、と質問したら、恐らく大多数の親はうまく答えられなかったことだろう。彼らはそれを親からそうすべきだと教えこまれたから信じている、世間一般がそれを人間の道だとしているからそうしている、だけのことかもしれない。が、とにかくそういう個をこえた普遍的な価値があることだけは、誰も疑はなかったであろう。普遍的な価値がなければ人間社会が成立っていかぬことは、誰一人として疑わなかったであろう。 日本人はその普遍的価値を「道」あるいは「法」という言葉であらわしてきたように思われる。法は仏法の法である。道は茶道、華道、弓道という道である。それは自分がその中にあり、それに従ってふるまい、己を正すべき、ある目に見えない原理である。目に見えないが厳としてそこにあり、武道や芸道の場合にはそれを究(きわ)めることによって究極の境地に達することができ、仏法の場合にはそれにひたすら従うことで自己脱落した末に悟りに達する、そういうもののことである。 個己であって個己をこえる人たち わたしにはうまく言えないから、鈴木大拙『日本的霊性』(岩波文庫、一九七二年)を引用する。 感覚や感情も、それから思慮分別も、もともと霊性のはたらきに根ざしているのであるが、霊性そのものに突き当たらない限り、根無し草のようで、今日は此の岸、明日は彼の岸という浮動的境涯の外に出るわけにいかない。これは個己の生活である。個己の深底にある超個の人(にん)にまだお目通りが済んでいない。こういうと甚だ神秘的に響き、また物の外に心の世界を作り出すようにも考えられようが、ここに明らかな認識がないと困る。普通には個己の世界だけしか、人々は見ていない。‥‥‥超個の人は、既に 超個であるから個己の世界にはいない。それゆえ、人と言ってもそれは個己の上に動く人ではない。さればと言って万象を撥(はら)って、そこに残る人でもない。こんな人はまだ個己の人である。超個の人は、個己と縁のない人だということではない。人は大いに個己と縁がある。実に離れられない縁がある。彼は個己を離れて存在し得ないと言ってよい。それかと言って、個己が彼だとは言われぬ。超個の人は、そんな不思議と言えば不思議な一物である。「一無位の真人(しんにん)」である、「万象之中独露身」である。‥‥‥この超個の人が本当の個己である。 モラエスやハーンが日本に来て、まだ西欧式高等教育の”毒”に当っていない昔ながらの日本人を(多くはろくな教育もうけていない)見たとき、彼らが何よりもまず尊いものに感じとったのも、この鈴木大拙がいう個己でありながら個己をこえた人というものである。無私無我で、しかも神仏を信じ、その信ずる人間の道に従って生きている人々のいることであった。たとえばモラエスはその「日本精神」(明治文学全集49、筑摩書房)という論文でこう言っている。
日本人は宇宙のあらゆる部面にーー太陽に、月に、星に、山に、川に、森に、稲妻に、虫に、花にーー、いたるところに、神を見る。 そしてそれが西洋人の自然と対立する精神のあり方といかにちがうかを論証すれる。 何れにしろ、日本人の精神は、文明世界の他のすべての人々と比較して、没個人性の特徴を最もはっきり示している。その宗教的概念、それは、神と創造者自然とを、その宗教的概念から来る没個人性によって、一つの物に、同じ物にしているのであるが、それこそ、偉大なる基本的原理であって‥‥‥ つまり百数十年前まではこういう心のありよう、無我とか、宗教的諦念とかがあって、人々は個をこえて存在する普遍的な自己に生きていたことがわかるのだ。彼らは真に全身心をもって個をこえたそういう尊い価値のあることを信じていた。だから、教育がなくとも、無知でも、権威と自信をもってそのみずからを信ずる価値を子供に伝えることができたのだ。 戦後五十年間に日本人が失ったのは、かつては誰もが深く信じ持っていたそいう普遍的価値への信仰である。 近頃そういう状況へのあきたらなかさか仏教を、たとえば道元の『正法眼蔵』に近づく人が多いようである。わたしもその一人で、この難解な仏典に魅せられて過去十数年たえずそばに置いて親近しているが、たとえばこういう言葉にわたしは身心を揺さぶられるように感ずるのである。
仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするゝなり。自己をわするゝといふは、万法に証せらゝなり。万法に証せらゝといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。(『正法眼蔵』(一)現成公案) よくわからぬながら道元が力強い言葉で説くこういう精神のありように、なにか人間を救済する真の原理があるように感じているのである。道元は同じところで、
自己をはこびて万法を修証するを迷いとす。万法すゝみて自己を修証するはさとりなり。 と言っているが、自己が我執を離れて(自己脱落して)そこに透明で空虚で充実した精神の場が出来するとき、おのずから神がその中に影向(ようごう)して(万法すゝみて自己を修証する)、自己は個己でありながら万法に証せられ人(にん)となる。そんなことが可能であるように思い、その境地にあこがれているのである。 道元や鈴木大拙が説くこの霊魂のはたらきの機微は、中世ドイツの神秘主義者マイスター・エックハルトが説くこんな言葉ととひびきあっているように思われる。エックハルトは聖書にいう「幸いなるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなり」にふれて精神の貧しさはとはどいうものかを説き、究極の貧しさとはたんに人がすべての被造物と自分自身にとらわれることがないだけでなく、神の存在そのものさえ忘れるほど無心にならなければならぬとして、こいう。
そうではなく、神が魂の内で働かそうとする場合、神自身がその働きの場となるほどに、ーー神はもちろん喜んでそうするがーー、人が神と神のわざすべてにとらわれなていないとき、それを精神における貧しさというのである。なぜならば、人がそれほどに貧しくなったのを神が見出すtこき、そのときに(はじめて)神は神自身のわざをなすのであって、人はそのような神を自分の内に受け、かくして、神が働くのは神自身のうちであるという事実から、神は神のわざ固有の場となるのである。ここに至り、つまりこのような貧しさにおいてこそ、人は、彼がかつてあったし、今もあり、そしてこれからも永遠にそうありつづけるような、永遠なる有を再び取り戻すのである。(『エックハルト説教集』、岩波文庫、一九九〇年) わたしにはいつも、道元のいうところとこのドイツ中世の神秘主義者のいうところは、宗教的境地においてぴたりと合致しているように思われた。 要するにそういう、人間を個我をこえて 普遍的ンあ人たらしめるところの何かがあると信じたとき、人は初めて 人となるのだと思われる 。我に執われているあいだはそれは見えなかった普遍的な価値、目に見えないないが天地の間、人間の中にたしかに存在しそれを導いてゆく道であり法であるものがあるのである。それが信じられてきたから人間の世は成立ってきたのだ。 個己としての自分が自分一個のはからいでこのこのことを言うのではない。自分の中にある普遍的な法が自分をして代弁させているのであるから、自分はかくも権威をもって言うことができるのだ。おれは従って普遍なる者からの命令である。汝、心して聞け。
「姦淫するなかれ」と云へることあるを汝等きけり。されど我は汝らに告ぐ、すべて色情を懐きて女を見るものはも、既に心のうち姦淫したるなり。「マタイ伝 27」 西欧の社会では教会がこの役を果たす一つの機関だった。とにかくいかにふるくさくとも、耳にタコができるまでこのことを子供の時から吹き込まれていれば、売春をして「自分が自分の自由でしているのに何が悪い」という科白は、少なくとも出てこないだろう。今の日本社会に欠けているのは、こういうあたり前の道理を権威をもってとく者の存在である。今の日本の仏教はその役を果していない。学校の先生もそれを行なっていない。 人間として生きる決意 ではどうするか。結局そういう無権威の世にあっては、一人ひとりの個己が、みずからの全精神をもって普遍的価値と信ぜられるものに到達すべく努力し、自己の全人格を賭けてそれを行うしかないのか。行うとはみずからがそれによって行動し、子があれば子にそれを伝え、その価値に反するものと衝突したときは全力をもってそれと戦うということである。しかし、人間として生きようと願うならば、それはいつの世にもしてきたことであろう。 ーー汝殺すなかれ。 ーー汝の 父母を敬え。 ーー汝姦淫するなかれ。 ーー汝盗むなかれ。 よその国の律法であっても、こういったものは人間の普遍的な原理として、どこの国、いっの世にも人の道でありつづけよう。 正座して物を言う父の前につっ立って聞く息子は、たんに作法に外れているだけでない、人の道、倫理の外にあらわれた形であることがわかる。 毎週卑猥な写真をのせて色情を煽ることで売り上げをのばそうとする週刊誌などは、「既に心のうち姦淫したるなり」で、人間の道にそむくことをすすめているも同然である。出版倫理にも作法にもとるやり方だが、それがまかり通っているところに現代の倫理的退廃がある。
『自分が生きる時間』

車の中でお話しました「保守的なこと」とは、最近読みました本『自分が生きる時間』 中野孝次著 三笠書店 から感じ取ったことです。一人ひとりの個人的問題のみでなく、ある面では、文明や文化に対する反省と自覚の問題を含め、これからの日本に対する問題提起の意味を込めています。 「人間は生きるために何が本当に必要なのか」(p.128-133) ▼ひとは人間として生きるために何を必要とし、何を必要としないのか。われわれは戦後から今日まで半世紀以上、もっぱら快適性を求めつづけ、今「先進国」の仲間入りができたうぬぼれ、過剰な商品の山の中で欲望をさらに刺激されながら暮している。欲望にはきりのなさを利用して新たに次から次へ欲望をかきたててくるのが商業資本である ▼わたしの家のそばに新しく保育所ができて、若い両親が朝晩送り迎えする。近くだからいやでもその光景が目に入ってしまうが、見ていると貧困と困窮からやむなく子どもをあずけている親たちというふうには見えない。ほとんどの親がピカピカの新車で乗り付け、しゃれた格好のママが「○○ちゃん、お利巧にしてましたか」と、子どもを助手席にのせて帰ってゆく。一体彼女たちは日中どこでどうしているのだろう、と考えずけにいられぬ光景が毎日繰返されているのである。 ▼彼女たちはおそらくより快適な生を実現すべく、住宅資金のために、あるいは車とかピアノとかを買うために働きに出ているのだろう。なかにはむろんどうしても夫婦で働かねば生活を維持できない人もいるのだろうが、少なくとも外から見たかぎりでは一体何のために生き、人間として生きるために本当に何を必要とするのか、彼女たちは考えたことがあるのだろうかと、わたしの想像は彼女らの暮しぶりに向かってしまう。 己れを知ることは、己れ自身のなかに共存する世界像を戦わせ、世の常の罪や掟を成り立たせる世界像を破つて、より深い自己が見出した世界像を現前させることである。己を知ることは、遠心的であると同時に求心的な作業である。戦後文学の時期は、人が飢えて丸裸かで廃墟に投げ出された時期であり、あらゆる秩序、あらゆる組織が寸断され、いわば気をまぎらわせるどんな中間物もなしに、人が赤裸々に己れと世界との関係に直面せざるをえなかった時期である。無飾の戦後文学が、人間存在の究極の意味を問い、一転険しい相貌を帯びたのは、瓦礫の市にふさわしかったといえる。(本多秋五『物語戦後文学史』) そういう、一切の余計なものを剥ぎとった末に残る最後の人間的なものを追求したのが、戦争直後のあの時期の文学であった。今、生活のさまざまな局面がすべて制度化され、管理され、あたかもきまりきった軌道をゆくようにしかひとが生きられない時、必要なのはもう一度あのころのようにどんな中間物もなしに、人が赤裸々に己れと世界との関係に直面することであろうし、そこから自分と自分の生の現在を見ることではないかと思う。戦争体験こそ、その点で最も有効な視点を与えてくれるはずである。 ▼「地上に一人でも飢えに苦しむ者がいるかぎり、わたしの食事はこれで充分だ」と言ったインドの聖者はだれだったか。たしかその人はそのように宣言して、弟子たちがととのえる美味佳肴(かこう)を斥け、生涯ふつうの農民が食うのと同じ粗末なものにしか手をつけなかったのだった。想像力な働きとはそういものであろう。 わたしもときおり文学関係のパーティに出かけることがある。出版社のパーティだから贅沢といったってたかがしれているのだが、それでも中央のテーブルに料理の山が食いちらかされたまま残されているのを見ると、昔の人の言い方どおり、これではいつかバチが当るのではないかという気になる。食堂で子どもたちがあれもこれもと注文しながら、あらかた汚らしく食い残しているのを見た時もそう思う。 ▼先だってもわたしはそういう場面に行き合わせて、インドで見たある光景を反射的に思い浮かべずにいられなかった。わたしが乗っていたのはインドが誇るダージ・エクスプレスの一等車だった。冷房はないが座席は広く、車内食事のサービスがある。わたしの前に坐っていたのは腹のつき出た実業家らしい中年インド人で、紙皿に盛って運ばれてきた食事をまずそうに食い始めた。 ちょうど彼が食事を終えようとしかけた時を見はからって、暗いプラットホームから、か細い少年の声がして、それと同時に汚い黒い手がさし出された。紳士は皿の中の残り物を(それともあらかじめ取りわけておいたのだろうか)ナプキンに包んで渡した。少年は別に礼も言わず受け取ってのろのろ離れ、すりよってきたもじやもじや頭の妹らしい少女と立ったままそれをわけて食べ始めた。 プラットホームは薄暗く、そのあちこちにたくきんの男たちが、一晩ここで寝るのであろう、ごろんごろんころがっている停車場であった。 ▼『自分が生きる時間』 “現在を見る”別の目を持て わたしは一人の七十代半ばの老文学者を知っているが、彼は自らのうちにきびしく自らを律する原理のようなものを持っているらしく、たとえ外がどのように変ろうと頑固にその戒律を崩さない。彼の生活はおそろしく簡素で、外から見れば、いまやそんな言葉ききえなくなってしまったようだが、質素というしかない。接客用の椅子なども、大正時代にでも流行ったような、籐の古びた椅子である。 彼は、世の中が彼を求めようが、求めまいが、毎日早くから北向きの窓ぎわの古机に向かい、人間の根源に関わるような問題ばかり考えている。その文章は雄勁(ゆうけい)で厳密、どの一行をとっても充分時間をかけて考えぬかれたことの歴然とわかる緻密さを持っている。彼の日々はほとんど昔の無欲な禅僧に似ていると言っていいだろう。 すなわち彼のすべてはもっぱら精神の自由を保つために捧げられているのである。わたしが文化という言葉を考えるのは、こういう人にたいしてだ。「食は文化なり」と広言して美味を追いまわす小説家ではないし、また知的生活の方法とやら称してあやしげな文章を書きまくる手合いにたいしてでもない。それではあまりにも文化という言葉があわれではないか。 ▼以上は尊敬する方からのメールでいただいたものです。お許しを得ましたので掲載します。文責は黒崎です。 平成二十四年三月八日
中野孝次『道元 断章』(岩波書店)(2000年6月15日 第1刷発行)
まえがき
いま道元を読むとはどういうことか。
わたしにとってそれは『正法眼蔵』の文章を読み、ひたすらその言葉の力を味わいつづけることであった。
『正法眼蔵』は恐ろしく難解だ。わたしは生涯のすべてを読書に捧げてきた人間で、読書のプロだとうぬぼれているが、その私でも読んでただちに理解できるというわけにいかない。こんな体験ははじめてだ。が、わかってもわからなくても読む。わたしはしばしば音(こえ)を出して読んだ。
するとふしぎなことに、理解できずとも、その言葉の迫力、文章の勢い、声調を通じて、道元の言わんとすることはこれなのだと、なにかがわたしに伝わってくる。言葉では表現できない魂の世界の秘儀が、素人なりにわかるような気がするのだった。それはわたしを力づけ、生きる力を与えた。そしてそれに元気づけられてさらに『正法眼蔵』に親しむということが、ここ十五年ほどつづいた。今もつづいている。
なぜ自分はこんなに『正法眼蔵』に惹かれるのか、わたしはときどき自問したものである。
第一に思い浮かぶのは、これは自分を救うように作用する、ということだった。『正法眼蔵』のある章句を、たとめば「全機」のなかの、
――しるべし、自己に無量の法あるなかに、生あり、死あるなり。
を、歩きながら口ずさむと、それだけで生死のふ安から解放されるような気がした。そいう力づける章句がだんだん増えていくのがうれしく、わたしは『正法眼蔵』を読みつづけてきたことがわかった。
つまりわたしにとって『正法眼蔵』を読むとは、そのなかから自分の気に入った章句を発見することだったのである。滑稽なことに、その全体を理解しようとする欲求さえ起らなかった。訴えてこない章は読みとばし、好きな章だけ何度でも読むという、非常にわがままな読み方をしてきたのであった。その結果、わたしが頼りにしたのは水野弥穂子校註の岩波文庫本だったが、そのある所は赤青の傍線、付箋、感想の書きこみ、関連ページの記入などでにぎやかに汚れたのに、ある所はまっさらのまま残ることになった。
つまりわたしは、『正法眼蔵』を全体のなかから自分の気に入った章句のみ集めるという、ひたすら利己的な要求から読んできたことになる。
わたしは『正法眼蔵』を文学として読んだ、と言ってもよさそうだ。わたしが惹きつけられてきたのは、ただ道元の文章の力、によつてだったのだから。
わたしは道元の全部を理解しようという要求さえ持たなかった。人みなが推奨する『正法眼蔵随聞記』も、『永平広録』も、わたしには参考書にとどまった。
第二に、しかし、そういうたいへん片寄ったわたしの読み方でも、道元の言葉を現代日本のなかで読むというのは、それだけで何事かである。
たとえば道元の説く生死観は、死を日常生活から追放した現代日本社会にこそ、もろに働きかけ、その欠陥を衝く、とわたしには思われた。死を正しく見ない社会では生の姿もあいまいになる。死をしっかり見据えてはじめて生が生となる、と道元は言っているように思われた。また、現代人はもっぱら、カレンダーや時計の作りだす機械的な時間をのみ時間と思いこんでいるが、はたしてそんな時間観念は生の実際に照らして正しいか、と道元を読んでわたしは疑うようなった。道元を読むことでわたしが受けた最大の衝撃は、この時間についての道元の考えであった。
空間もまた、数量でとらえるたんなるひろがりではなく、無限大に拡延したかと思うと極微小にまで縮小する。「拳頭一尺」が宇宙全体に匹敵する、そういう大小、距離、遠近にとらわれぬ生きた何者かだった。
さらに、われわれが子供のときからなじんでいる認識の仕方は、はたして正しいか、とも道元は言っていた。われわれはヨーロッパ伝統の、主観・客観二分した世界観になじみ、対象化して物を見、論理的、因果論的、相対的、科学的、概念的にしかものを考えない。が、世界はそれだけでない、と道元はものすごいことを言っているのだった。一二三四五という数でとらえられぬ、という。これは思考の、というより思考以前の覚知を迫るが、そういう世界がたしかにあると、道元を読んでいるわたしは信ずるようになった。
わたしのひたすら利己的に読んだ道元でも、そういう人間存在の最も根本的な事柄について、わたしの精神革命を促し、迫り、ある程度はそれを実現させたのだった。現代に生きる一人としてそのことを報告するのも、まんざら意味のないことではあるまいと思う。わたしは道元の研究者でも、『正法眼蔵』全体を理解しようとする者でもなく、道元にわがままな近づき方をしている一介の素人にすぎない。が、素人が道元に刺激されて考えたことでも、現代を考える上では役に立つのではないか。そう思って、図々しくもこの道元読書報告を書くことにした。『道元断章』とした所以である。
むろんこれが人さまの道元理解に役立つなどとは、わたしはぜんぜんきたいしていない。これは道元を学んで、そのことによってふだんとちがう角度から現代日本を考えてみようという、それだけの試みである。主眼は「今ココニ」生きるわたしの生の確認にある。
ただわたしはかねがね、古典を専門家の占有に任せておくのは間違っている、ふつうの読書子こそ遠慮なくわがものとして利用すべきだ、それが古典を再生させる道であり、またわれわれのためである、と思っている。古典をカルチャー・センターなどよそ行きの場所に置いてあがめるだけではいけない、自分の日常生活の中に取入れなければ意味がないものである。
参考:だんしょう【断章】:文章の断片。「断章取義」の略。他人の文章の一部を、そこの文脈にかかわらずに取って使うこと。
参考:音読の効用を参加にしてください。
▼中野孝次さんプロフィール:千葉県生まれ。昭和19年旧制第五高等学校入学。東京大学文学部独文科卒。国学院大学教授を経て、小説、評論、随筆、翻訳と多彩な活動を続ける。
|
|
女性史家 「人は、その人の持つ心の器に応じてしか、人にも本にも出会えぬものらしい」 参考:「もろさわようこ」は、女性史研究家。 本みょうは両沢葉子。 長野県生まれ。 本名・両沢葉子。 生家が没落し、女中奉公をしながら小学校を卒業。 陸軍士官学校の事務員、地方紙記者などを経て、女性史研究家となり、庶民世界での近代女性史に関する著書多数、女性解放運動に力を注ぐ。 1969年、『信濃のおんな』で毎日出版文化賞受賞。 |
|
「タテ社会の人間関係」などの著作で知られる社会人類学者で、東京大名誉教授の中根千枝(なかね・ちえ)さんが2021年10月12日午前4時、老衰のため東京都内で死去した。94歳だった。 女性で初めて東京大教授に就任するなど、女性研究者の草分けとして活躍した。地域社会に住んで社会構造を明らかにする手法でアジアや西欧と日本を比較、アジアの国々を中心に国際交流に貢献した。 序列偏重の日本社会を考察した1967年の「タテ社会の人間関係」が100万部を超すベストセラーとなり、各国で翻訳された。東京大東洋文化研究所所長や東京女学館大学長を歴任。95年に日本学士院会員。 93年文化功労者、2001年文化勲章。他の著書に「家族の構造」「社会人類学」「タテ社会と現代日本」など。
手持ちの図書 1、「タテ社会の人間関係」(講談社現代新書) 1973.06.10 購入。
「場」を強調し「ウチ」「ソト」を強く意識する日本的社会構造にはどのような条件が考えられるか。「単一社会の理論」によりその本質をとらえるロングセラーを続ける。 [ウチ]の者以外は人間にあらずの感 [ウチ][ヨソ]の意識が強く、この感覚が尖鋭化してくると、まるで[ウチ]の者以外は人間でなくなってしまうと思われるほどの極端な人間関係のコンストラストが、同じ社会にみられるようになる。知らない人だったら、つきとばして席を獲得したその同じ人が、親しい知人――に対しては、自分がどんなに疲れていても席を譲るといった滑稽なすがたがみられるのである。――本書より 2、「タテ社会の力学」(講談社現代新書) 1978.06.03購入。 日本社会では法的規制はきわめて弱い。 人々の行動を律するのは法ではなく、個人あるいは集団間にはたらく力学的規制なのである。 無原則のまま外界の変化に柔軟に対応する日本社会は、「柔軟動物的構造」をもっている。本来の意味での権力が存在せず、小集団におけるリーダーの力が弱いのも、この特殊な社会構造によるのである。 本書は、タテ社会内部にはたらくダイナミズム・動的法則を、[全人格的参加][無差別的平等主義][儀礼的序列][とりまきの構造]など、興味深い事例を引きながらあざやかに分析し、現代人一人一人をとりまくネットワークを明示する。『タテ社会の人間関係』と対をなす必読の名著。 法規制でなく社会的規制――私たちの社会生活に規制が働き、全体の治安が維持されているのは、個々人が小集団規制に従い、全体が力学的にバランスをとろうとする動きををもっているからとうえよう。こうした社会に育まれた私たち日本人は、法規制にてらして行動するなどということはなく、まわりの人々にてらして、あるいはあわせて行動することに習慣づけられいる。いいかえれば、規制というものを肌で感じながら行動しているといえよう。 日本社会においては、社会的規制が法規制の機能まで包含していると解釈できる。こうした世界になれていると、法のきびっさを忘れがちである。否、知らないで過ごすことも可能である。――本書より 2、「適応の条件」日本的連続の思考(講談社現代新書) 1973.06.27購入。 異なる文化に接した場合の[カルチュア・ショック]は、日本人において特に大きい。そこには、日本社会の[タテ]の原理による人間関係と、ウチからソトへの[連続]の思考が作用している。 本書は、欧米・インド・東南アジアなど、ソトの場での日本人の適応と、そこに投影された[ウチ]意識の構造を分析し、[強制]と[逃避]という二つの顕著な傾きを指摘する。 著者のゆたかなフィールド・ワークをもとに、国際化時代の日本人の適応条件を考察する本書は、ベストセラー「タテ社会の人間関係」につづく必読の好著である。 システムの発見――ゴムの産地としてな高いマレーシアでは、英国統治時代からいわれてきた[ラバー・タイム]というのがある。ゴムのように伸びる時間の感覚である。 熱帯ではどの国でも多少こうした傾向があるのがつねである。 これに対して、約束した日時を守らないといって二年間も憤慨しつづけて過す日本人などがある。 何度か同じように日時を守らなかった経験をもった場合には、怒るよりも、まず「なぜだろう」と考えるべきである。 必ず何か理由があり、そのおくれ方自体に一定のシステムがみつかるものである。 たとえば、一ヵ月といった場合はだいたい二ヵ月を意味するとか。 表現というものは必ずしも実際の数を意味しないということは、どこの文化にもあることである。――本書より 2021.11.07記す。 |

 『セルフ・コントロール入門法』 池見酉次郎
『セルフ・コントロール入門法』 池見酉次郎
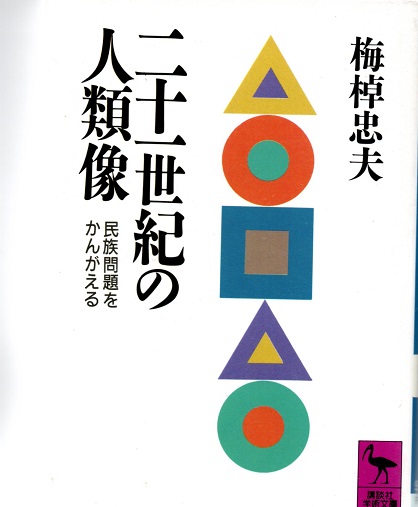 ▼『二十一世紀の人類像』民族問題を考える(講談社学術文庫)
▼『二十一世紀の人類像』民族問題を考える(講談社学術文庫)
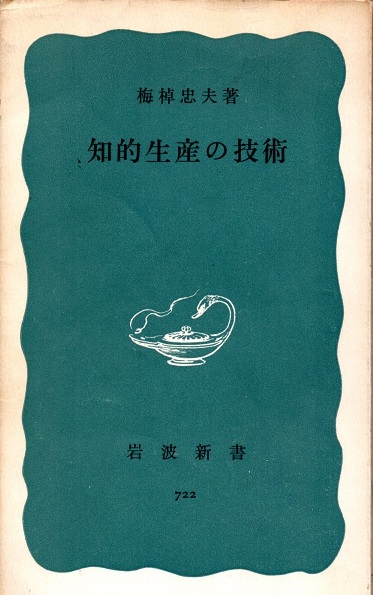
 一粒の麦は、
一粒の麦は、

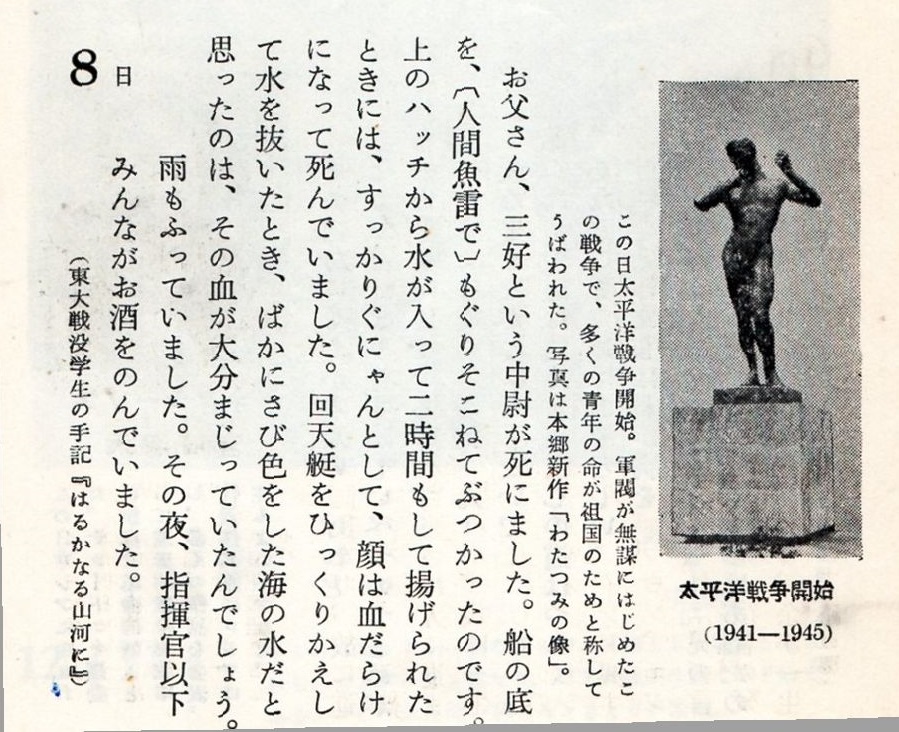 お父さん、三好という中尉が死にました。舟の底を、〔人間魚雷で〕もぐりそこねてぶつかったのです。上のハッチから水が入って二時間もして揚げられたときには、すっかりぐにゃんとして、顔は血だらけになって死んでいました。回天艇をひっくりかえして水を抜いたとき、ばかにさび色をした海の水だと思ったのは、その血が大分まじっていたでしょう。雨もふっていました。その夜、指揮官以下みんなが酒をのんでいました。
(東大戦没学生の手記『はるかなる山河に』)
お父さん、三好という中尉が死にました。舟の底を、〔人間魚雷で〕もぐりそこねてぶつかったのです。上のハッチから水が入って二時間もして揚げられたときには、すっかりぐにゃんとして、顔は血だらけになって死んでいました。回天艇をひっくりかえして水を抜いたとき、ばかにさび色をした海の水だと思ったのは、その血が大分まじっていたでしょう。雨もふっていました。その夜、指揮官以下みんなが酒をのんでいました。
(東大戦没学生の手記『はるかなる山河に』)

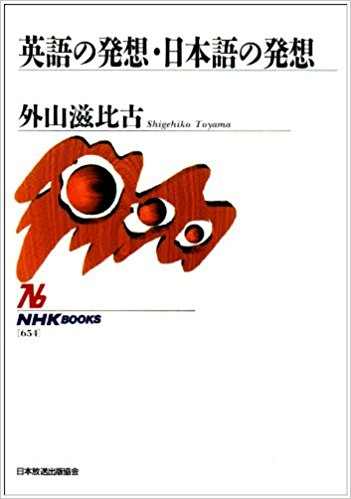


 ━━ぼくはここでは、まず、ほとんどの学校がもっている、このボールの数の多さが気になるのです。一人に一コ以上のボールをもっている、ということはどういうことでしょうか。本当の教育からいって、果してそれだけのボールの数がいるのでしょうか。
━━ぼくはここでは、まず、ほとんどの学校がもっている、このボールの数の多さが気になるのです。一人に一コ以上のボールをもっている、ということはどういうことでしょうか。本当の教育からいって、果してそれだけのボールの数がいるのでしょうか。
 日本社会の人間関係は、個人主義・契約精神に根づいた欧米とは、大きな相違をみせている。
日本社会の人間関係は、個人主義・契約精神に根づいた欧米とは、大きな相違をみせている。