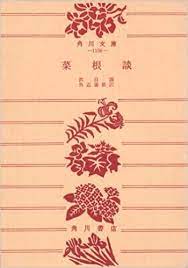| わが人生の師を語る | 01 | 「人は一代 名は末代」 | 02 | 「ボーイスカウトの心得」 | 03 | 「古渓の三か条」 | 04 | 浜口雄幸の『随感録』 |
| 05 | 懲らされてこそ教育である | 06 | 学びて思わざれば則ち罔く | 07 | 苦しみを通じて喜びへ | 08 | 安岡正篤先生の思い出 | |
| 09 | 「忘の説」 | 10 | ****** | 11 | ****** | 12 | ****** | |
| わが体験的古典論 | 01 | 君子は豹変す | 02 | 君子は器ならず | 03 | 変至らざるなし、応当時たらざるなし | 04 | 其の身正しからずば令すと雖も従わず |
| 05 | 性相近し、習相遠し | 06 | ****** | 07 | ****** | 08 | ****** | |
| 『孟子』私論 | 01 | 孟子の人となり | 02 | 『孟子』はなぜよく読まれるか | 03 | 天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず | 04 | 人の選び方、用い方 |
| 古典に学ぶ経営哲学 | 01 | 日々新たならんことを欲す | 02 | 「鍛錬」ということ | 03 | 自らに勝つ者は強し | 04 | 武道の極意 |
| 05 | 功の成るは成るの日に成るに非ず | 06 | 人を樹うるに如くはなし | 07 | 倦まずたゆまず | 08 | 「忠恕」の精神 | |
| 09 | 常に心に喜神を持つく | 10 | 実践あっての学問 | 11 | 独りを慎む | 12 | ****** |
「人は一代 名は末代」
|
人は一代 名は末代 P.22~24 病院では私の同室の兵隊が、大変な痛みのために泣いたりわめいたりするのですが、私はここで泣いたりわめいたりしたのでは名がすたる、というような時代がかった考えを持っていたのです。従って、包帯交換のときなど、非常に痛くて耐えられないような状態であっても、冷汗を流しながら我慢をしていたようなわけです。
また、こんなこともしきりに思い出しました。それは私の実母が、私がまだ幼いころ、いつも聞かせてくれた言葉です。それは「今に見ていろ僕だって、見上げるほどの大木に、なって見せずにおくものか」という歌です。あとでこれは尋常小学校国語読本巻四に「椎の木と樫の実」という歌の中にあることがわかりました。私はその前のほうの文句は覚えていないで、「今に見ていろ僕だって、見上げるほどの大木に、なって見せずにおくものか」だけが頭にこびりついていたものいとみえます。それは貧乏な生活の中で母親のひそかな願いが子供に響き、なんといはなしに覚えたものと思われます。 その全文を次に挙げておきましょう。なかなかいいことが書いてあります。 思う存分はびこった 山の麓の椎の木は 根本へ草も寄せつけぬ 山の中からこりおげ出て 人に踏まれた樫の実が 椎を見上げてこう言った。 「今に見ていろ僕だって 見上げるほどの大木に なって見せずにおくものか」 何百年が経った後 山の麓の大木は あの椎の木か樫の木か 2023.01.09記。 |
「ボーイスカウトの心得」
|
ボーイスカウトの心得 『古教、心を照らす』 P.27~30 私は小学校では、珠算とか算術が得意でしたが、絵も割合に上手でした。それで、子供心に絵描きのところへ養子に行くのだから、将来は絵描きになるのかな、とちょっぴり考えておりました。しかし、父の新井洞巌は私の素質をちゃんと見抜いていたのでしょう。 私を絵描きにする意思は全くなく、そんな程度ではとても絵描きにはなれない、また、絵描きになったところで、食うのが大変だから、絵など描かないで、学校の勉強のほうを一生懸命にやれ、ということでした。今になってみると、少しは絵を習っておけばよかったなと思っていますが、その当時は、絵など習ってはいけないということでした。 東京へ出て、六年生の一年間だけ巣鴨の仰高小学校へ通いました。大正十四年二月のことですが、この小学校でボーイスカウトの幹部研修会が催されました。そこへ後藤新平伯爵が出席され、生徒たちを前に一場の講話をされました。それを私は今でもよく覚えています。 それはボーイスカウトの心得で、 一、 人の世話にならないように 二、 人の世話をするように 三、 その報いをうけないように という三か条です。この言葉は少年の私の心に強く響いて、後々までもこの精神でやり抜きたいと思ったことでした。 ところが、この東京の小学校では、唱歌の時間に五線譜の読み方、つまりおたまじゃくしを教えておりました。田舎の小学校では習ったこともありませんから、私には全くできません。それである唱歌の時間に、先生はそのおたまじゃくしの譜を読んでみろ、といわれたのです。私は習っておりませんから、即座に、「読めません」といいました。そうすると、その学期の唱歌の成績が乙になってしまったわけです。それまで、成績はすべて甲をもらっていました。そうしたところへ唱歌だけが乙になってしまったのですから、これが一生私に響いて、自分は唱歌は下手なんだと思い込むようになってしまいました。 今はカラオケが大変に流行していますが、私はいまだにカラオケはやれいません。それでも、ときどき「そんなことはないでしょう。なかなか声が大きいじゃないですか」といってくれる人がありますが、声が大きくても、節回しが悪くては歌になりません。 とにかく、六年生のときに乙をもらって以来、唱歌というものは好きでないのです。 中学校は家のすぐ近くの京北中学に入りました。入学のときの校長は湯本武比古先生、先生が亡くなられてから笹川臨風先生になりました。国語の先生は林古渓先生でした。林先生は、あの有名な「あした浜辺をさまよえば、昔のことぞしのばるる」という『浜辺の歌』の作詞者です。ここ歌詞やメロディだけを聞いていますと、優しいスマートな先生のようですが、実物はさにあらずで、髭面で眉毛は濃く、池上本門寺のおられたこともあり、仏教によって育った方なのです。 ※参考:歌詞全部を記載:インターネットによる(黒崎調べる)
あした浜辺を さまよえば
ゆうべ浜辺を もとおれば
はやちたちまち 波を吹き
われわれは中学の生意気盛りでしたから、先生のことをその風貌から「達磨」と呼んでいました。この達磨先生に教わった国語は、どうも点数が悪かった。というのは、今でこそ大きな声だといわれますが、当時の私は声が小さかったのです。それで、国語の時間に先生から名指しをされて読まされると、「聞こえない、もう一度読め」などといわれたりしました。 それに、当時は作文は毛筆で書かされましたが、これもそう得意ではありませんでしたので国語、作文ともにあまり点数はよくありませんでした。父が父兄会に行って、「林先生はお前のことをほめていなかったよ」といわれたことを覚えていおます。 この林先生は私が四年生になったとき、旧制松山高等学校に転勤されました。去られたあとで、先生が偉いということがわかってきて一生師事しました。 2023.01.09記す。 |
「古渓の三か条」
|
「古渓の三か条」 『古教、心を照らす』 P.30~33 林先生は、よく「骨を惜しむな、気をつけろ、気をきかせろ」といわれていました。これは、いわゆる「古渓の三か条」といわれるものですが、これをいわれると、いたずら盛りの生徒たちは達磨さんまた例の話を始めた、とはなはだ失礼な言を吐いていたものでした。私もその一人で、中学生時代にはその意味を十分理解しませんでしたが、だんだん成長して会社勤めをするようになると、この「骨を惜しむな、気をつけろ、気をきかせろ」という言葉は非常にいい言葉だなあ、と思うようになりました。 林先生が、「骨を惜しむな、気をつけろ、気をきかせろ」という言葉を入れてつくられた歌があります。 1 ころんだらすぐはねおきろ 骨を惜しむな 名を惜しめ 2 堅固な土手の蟻の穴 油断大敵 気を付けろ 3 無駄骨折らずにとくをとれ 見る目聞く耳 気をきかせ 4 面壁九年それもよい 我慢辛抱実が結ぶ と、こういうものです。 もともと林先生は和歌の道にもたけておられ、また漢詩もつくられるし、それに関連した本も出しておられる。当時の私は生意気盛りで、真剣に聞いていなかったのですが、三年生になるまでに何度か聞いたこの言葉も、やはりその後の私の人生に大きな影響を与えています。 中学を出て、旧制一高を受けましたが、落ちてしまい、仕方なく一年浪人をすることになりました。会社でこの話をすると、会長も浪人をしたかとみんなが喜んでくれました。ともあれ、、浪人するのであれば、今なら予備校へ行くところでしょうが、私は東京府立一中の補修科というところへ入りました。現在の日比谷高校ですが、当時一高へ一番多く入学者を出していたのは、この一中でした。 補修科に入るのにも試験はありましたが、こちらの方は無事入ることができました。そして一学期の通信簿をもらったとき、数学の先生がにこにこしながら、「お前は入れるぞ」といってくれたのです。一中の先生の言葉でしたから、これはいい励みになって、より一層勉強しなくては、と心に誓ったものでした。 一中の校長は川田正澂先生といって、土佐の出身の方でした。当時府立中学校の校長の中では最右翼といわれた人で、人格見識ともに優れた有名な教育者でした。後に東京府立高等学校の校長にもなられました。 この校長先生がちょっと変わっていて、式辞とか訓辞をされるときは、必ず原稿を手にして読むのです。われわれ生徒から見ると、校長先生が原稿を手に持ちながら訓辞をするというのは、どうもおかしいと思ったのですが、先生にいわせると、くだらないことを思い付きで長々喋るよりは、本当に立派に推敲した文章を一字一句間違いなく読んだほうがよい、ということでした。これは一理あると思います。 この川田先生がいわれた言葉の中で、今でも覚えているのは、「頭山満翁はいいました。男に惚れられる男になれ云々」という言葉です。これが浪人中の私の心に響きました。当時の私は、。人との付き合いが悪く、もちろん人と話をするのも嫌いで、いつもむっとした内向的な男でした。ですから、女に惚れられるなどということは考えてみたこともない。そこへ頭山満翁が「男に惚れられる男になれ」といっているのを聞いたものですから、少なくともそういう男を目指そうという気持ちなりました。 ※参考:頭山 満 2023.01.09記す。 |
浜口雄幸の『随感録』
|
浜口雄幸の『随感録』 『古教、心を照らす』 P.33~36 この年、東京駅の駅頭で、浜口雄幸首相が、右翼の佐郷屋留雄(さごうや とめお)に狙撃されるという事件がありました。そいのとき、浜口首相は「男子の本懐だ」だということをいったということです。これが城山三郎の『男子の本懐』という小説になっているわけですが、この事件のあったのは、昭和五年十一月十四日のことです。この方も川田先生と同じ土佐出身で、私がもっとも尊敬する政治家の一人です。 浜口さんが狙撃されたのは、ロンドン軍縮条約締結に関してですが、その後ずいぶん苦しい闘病生活を送られました。その療養中に『随感録』という書物を書かれています。『随感録』は修学時代の学生の精神修養上の参考の一端だと思って書かれたものだけあって、大変ためになる本で、私に非常な感銘を与えてくれました。その当時から浜口首相の写真を自分の部屋に掲げていました。今でもライオン首相といわれた浜口さんの写真を大切に保存しております。 『随感録』の一節を引いてみましょう。 「非社交的な性格の矯正と言い、弁論の矯正と言い、一、二の例に過ぎないけれども、其の他余の性格上の欠点は一々ここには言わぬけれども多々あったのである。これらのことは親兄弟にも知れぬように、ほとんど血の出る如き大努力をなして、自分自身これが矯正に努めた。而してその努力にはそれぞれ相当な効果があったと信ずる」 「余の信ずる所によれば、人格は努力と修養とによって完成せられないまでも、少くも或る程度において向上発達せられ得べきものであり、又向上発達せしめなければならないものである」 「余は生来極めて平凡な人間である。ただ幸にして余は余自身のまことに平凡であることをよく承知しておった。平凡な人間が平凡なことをしておったのでは、この世において平凡以下のことしか為し得ぬこと極めて明瞭である。修業と努力とは、自覚したる平凡人の余生活であらねばならぬ。而して努力の効果如何であったかということは別問題であるが、兎も角も余の今日あるは、この努力のお陰であると信ずる」 そしてまた、かつては非常に無口で人と話をするのが嫌いだ、お辞儀をするのはいやだと思っていたけれども、今日ではさしたる支障がないようになった、というようなことも書いてあります。 当時私自身も平凡な人間であり、そして非社交的な人間であり、内気で、人に対してすぐ口をきくことができない、お辞儀をすることもできないような人間であると自覚していました。その私にとって、とくに中学校を出たばかりの私にとって、浜口首相のこのような言葉は、浜口雄幸でさえこうだったのであれば、この私も努力と修養によってなんとかなるものであろうという気持ちにさせるものでした。努力と修養が、何よりも尊いということを深く考えさせられ、また教えられのです。 翌年、昭和六年の四月、一高に入学することができました。新井家では、私は養子で一人息子ですから、家族はどうしても東京の学校へ行け、といいます。一年浪人したあとでもあるし、この年は失敗するわけにもいかないので、一高のほかに早稲田も受験しました。当時、早稲田では学科試験のほかに口頭試問があって、「お前、両方受かったら、どちらへ行くか」と訊きますから、「一高へ行きまさう」と答えました。すると、試験官が「そうだろうな」と笑ったを、印象深く覚えています。 四月八日に両方から入学許可の通知がきました。最初から一高と決めていましたから、一高へ進みましたが、入ってみて驚いたのは、世の中にはこんなにもできるやつがいるのか、ということでした。入学してきたとき、すでに高等学校で習うドイツ語なんかはマスターしていて、自分は教科書は買わず、人の教科書をちょっと貸せといって借りて、それで試験は一番という男、また学校へはさっぱり出席しないのによくできる男などなど。 私はつくづく自分が平凡であることを悟り、こういう男たちと競争しなければならないとすると、よほど努力しなければならない、と痛感したものです。読んだばかりの浜口雄幸の『随感録』の言葉が、より一層心に響いたわけです。一高は、当時天下の秀才たちが集まった学校でしたが、今の進学校とは違って割と自由な雰囲気が漂っていました。 ※参考:浜口雄幸 2023.01.10記す。 |
懲らされてこそ教育である
|
懲らされてこそ教育である 『古教、心を照らす』 P.39~36 また、夏目漱石の親友で、菅虎雄というドイツ語の先生がいました。東大のドイツ文学科を三番で出たというので、当時生徒が何人いたか、というと三人だったということです。 その菅先生は和服に袴姿で、ドイツ語の本を懐に入れて、椅子の上に座って講義をされる。そして、われわれにはドイツ語のどの本を読めなどということはあまりいわないで、白隠禅師の『夜船閑話』とか『遠羅天釜』とかを読むとよろしいというようなことをいわれた。 漱石の『虞美人草』の冒頭に宗近君と甲野君の二人が、叡山に登る文章がありますが、これは漱石がこの菅先生と二人で登ったことを参考にして書いたものだそうです。漱石の話になると、先生は授業そっちのけになるので、われわれは先生が教科書を進めるのを遅らせようとして、「先生が漱石と比叡山にに登ったときはどうだったんですか」などと訊きますと、「うん、そうじゃった。漱石と一緒じゃった」とか何とか話を始められる。 そして、「今日は進めなかったな」などといわれるのですが、われわれは大喜びでした。 菅先生だけでなく、他の講義のときも何とかして先生に無駄話をさせようという風潮があったのですが、あるとき、「ここの学生は講義が進まないといって喜ぶけれども、私立の大学で、夜働いて通っている人なんかは、逆に進まなかったら文句をいう。折角月謝を払ってきているのに、先生もっと進んでくれというんだよ。お前たちもそういうことにもっと見習え」と菅先生ではありませんが他の先生にいわれたことを覚えています。 漱石の書翰集に菅先生に宛てたものがあります。菅先生はドイツ語の先生でありましたが、当時、書では日本一でもあったのです。それで、漱石が、「君から貰った紙へ君から貰った筆を以て君から授かった法を実行してかくと斯様なものが出来る。才子は違ったもので一時間許り稽古するとすぐ此位になる。うまいものでしょう。ほめてくれないと進歩しない……」と明治三十七年七月十八日附菅先生宛ての手紙を書いています。親友同士ですから、半ば冗談でもありましょうが、漱石はそんなことも書いているのです。 ドイツ語の先生では、そのほかに漱石の『三四郎』に出てくる哲学者・広田先生のモデルといわれる岩本先生という方もいました。この先生は非常に点数が辛くて、山本有三が一高に入って、無理解なドイツ語の教師がいて、そのために三十何人かが落第をさせられ、自分もその一人りになって一高をやめたということを何かに書いていますが、この「無理解なドイツ語の教師」というのが、岩本先生のことなのです。 岩本先生は、ゲーテの『わが生活より』、また『詩と真実』という七百頁の自伝的小説を、私の高等学校二年から三年にかけて、講義をされました。その『詩と真実』の扉にギリシア語で「懲らされてこそ教育である」という言葉が載っています。つまり、教育というものは懲らされるもので、今のように自由にさせられるという教育ではないということです。 ゲーテという人は大変な天才でありますが、そのゲーテが学生時代にお父さん宛に手紙を出しますと、ゲーテのお父さんはその手紙を全部一つ一つ、字の書き方や文章の綴り方などについて直して返しているのです。これを読んでゲーテでさえ真剣に努力し修業したのだと感じました。これは先に書いた浜口雄幸の努力と修養に一脈通ずるものがあると考えます。 2023.01.12.記す。 |
|
学びて思わざれば則ち罔く、思うて学ばざれば則ち殆し 新井正明著『古教、心を照らす』 P.41~44 大学は法学部を受けました。当時の受験科目は二科目でした。私は一高時代ドイツ語をやっていましたので、ドイツ語の和訳と日本語の作文の二科目でした。ドイツ語ンおほうはどういう問題だったかもう忘れてしまいましたが、作文のほうはよく覚えています。「学而不思則罔、思而不学則殆」という『論語』ンお文章が白文で出て、これについて所感を述べよ、という問題でした。 このときの法学部長は穂積重遠先生でした。この先生は渋沢栄一さんのお孫さんに当たります。渋沢さんといえば、「論語と算盤」を標語としたほどの大の論語信者で、その論語講義は立派なものです。そのお孫さんですから、法学博士でありますが、非常に『論語』に造詣が深く、著書も多い。現在も講談社文庫で、先生の『論語』と『孟子』が出ています。そういう方ですから、『論語』の中から試験問題を出されたのも不思議ではありません。これは、、私は大変いい問題であったと思います。 私が大学に入ったのは昭和九年ですが、その年に、戦後総理大臣になった芦田均さんが大学に講演にこられたことがあります。芦田さんは自由主義者でしたから、戦争中はほとんど言論を封じられるような状態でしたが、このとき、芦田さんはお話の中で、「今年の入学試験に『学びて思わざれば則ち罔く、思うて学ばざれば則ち殆し』という題が出たそうだが、その答案の中で、学びて思わざれば則ち左傾し、思うて学ばざれば則ち右傾す、故にわれは中道を行く、というのが一番傑作の答案であった」といわれました。
これは、芦田さんの創作ではないかとも思いますが、穂積先生の『新訳論語』を読むと、左翼は「学ビテ思ワザル」もの、右翼は「思イテ学バザル」ものといった答案があった、と書いておられますから、あながち芦田さんだけの創作でもなかったのでしょう。たとえば、マルクスの学説を学んでも、日本の国柄というものをよく思えば、左傾するということはないでしょうし、また逆に、日本の国は神国だと思うだけで広く学ばないと、右傾することになる。だから、学習と思索との伴わざるべからざること、両々相またねばならないことを述べたものであります。※参考:『新訳論語』P.四十(黒崎記) これについて、穂積先生の前記『新訳論語』の中で愉快な答案があったといって次のように述べられております。「自分は高等学校時代水泳選手で、初心者をコーチしていて、どうしても泳げるようにならぬ者に二種類あるのを発見した。第一は、教えられるとおり手足を動かしていながら、自分で泳ごうという気のないものだ。これは学びて思わざるものである。第二は、浮こう、泳ごうと焦って盛んに手足をばたばたたさせるが、少しも教えたとおりにならない。これは思うて学ばないものである。いずれも水泳が上手にならない。豈にそれ水泳のみならんや云々」ということです。:『新訳論語』P.四十(黒崎記) この「豈にそれ水泳のみならんや」といったところがなかなかきています。われわれの職業でも全く同じことがいえます。学生時代にはそれほどまでに思いませでしたが、最近になってこの言葉を大変深く感ずるようになりました。 また、穂積先生は、ドイツのオットー・フォン・ギ―ルケという人のいった、「人の人たる所以は、人と人の結合にあり」ということを何度か紹介されました。これもなかなか味のある言葉で、長く会社生活をしておりますと、この言葉が真実であることをしみじみと思い知らされます。 2023.01.28 記す。 |
|
苦しみを通じて喜びへ 新井正明著『古教、心を照らす』 P.55~61 こうして主に安岡先生の著作を読みながら、一年間、陸軍病院におりました。この間、いろいろな方の励ましを受けました。先に書いたように丸山君と堀切君が見舞ってくれたことや北澤専務が大阪からわざわざきて下さったことや、みな実にありがたい思い出として残っています。 丸山君は私が内地に帰るとすぐ病院にこういう一枚の葉書をくれました。普通なら「拝啓 君は勇敢に戦って、名誉の負傷を負われた由……」と書くところなのでしょうが、彼の文面は、 「Duruch Leiden Freude――L.V.Bethoven」:「苦悩を突き抜けて歓喜へ」と和訳されています。 「苦しみを通じて喜びへ――ベートベン」とだけ書いてありました。それはいかにも丸山君らしい葉書ではあったのですが、私にとっては一生にわたって自分を支えてくれる言葉になったのです。私は、座右の銘は、と聞かれたとき、この言葉をあげることが多いのですが、昭和十四年以来、私の人生を支えてくれた心の柱といっても過言ではありません。 義足を引きずって歩くのはいやだと思いました、マイナスの人生でもあります。北澤専務が引き合いにに出した重光葵氏は、そういう人生のことを「赤字の人生」だといっています。しかし、このように励みになる言葉に支えられていると思うと、これをプラスに変えられるような感じがしてきたのです。同時に、こうした心の中の戦いが知らず知らずのうちに、自分でいうのも変ですが、私を非常に強くしてくれたように思います。 私は今でこそ、われわれ生命保険業界で"暴れん坊"などというあだ名を頂戴したこともありますが、自分ではおとなしい人間であると思います。高等学校のクラス会などに行くと、友人たちが、「あのおとなしかった新井が生命保険会社に勤めているというのはいまだに不思議だ」というほどです。そういうことから見ると、結局、私自身、生まれつきは決して気の強いほうではなかったのですが、自ら背負っている宿命を克服するためには、強くあらねばならない、負けてはいけない、自分を叱咤してきたことによって、精神的な強さが身に付いたように思います。 それから、堀切君のお母さんがバラの花を届けてくれたことは前に書きましたが、そのときこういうことをいわれました。 「うちの真一郎は小さいときから足が悪いので慣れていますが、新井さんは急にご不自由になられたので大変でしょう」 このお母さんの言葉は大変に私の胸を打ちました。考えてみれば、堀切君は運動会にも出られず、遠足にも行けず、ずいぶんつらい思いをしたのでしょう。それに比べれば、私は一通りやってきました。それだけでもありがたいことだ、私は心の底からそう思うことができたのです。 ちょっと余談になりますが、この堀切君とも私はその後ずっと付き合いをさせていただきました。堀切君は残念ながら、昭和六十二年三月他界されました。葬儀のとき、友人代表として私は弔辞を読みましたが、彼の人柄といいますか、人となりがよくわかると思いますのでここにそのときの弔辞を紹介させていただきます。
弔 辞 堀切君、こうして私が弔辞を申し上げることになろうとは夢にも思いませんでした。併し悲しい現実はどうしようにもありません。手厚いご看護をなさいました奥様はじめご家族の皆様方のご悲嘆如何ばかりかと拝察申し上げます。 昭和六年四月、君は四年終了で一高文科乙類に優秀な成績で入学されました。私も同じクラスの一員でありましたので、それ以来今日まで五十六年の永い間おつきあいをさせて頂きました。明晰な頭脳の持ち主であった君は生来の明朗闊達さにより入学早々からクラス全員の人気の的になり、若干の茶目っ気もあったので君の周囲には常に笑い声が絶えず、クラス全体の和合の中心となりました。脚がご不自由であったにも拘らず、そのことを傍の者に全然意識させませんでした。この良いお人柄は立派なご両親より受けつがれた天性の素質と良いご家庭のご薫陶の賜物に間違いありません。 昭和十二年私は大阪の会社に就職、東京を去りましたが、翌年応召満州ハイラルの国境守備隊に配属されました。翌十四年に起きたノモンハン事件に参戦、砲弾破片創にてついに隻脚の身になったのであります。同年秋、牛込の第一陸軍病院に転送されて参りますと、早速君は級友丸山真男君の肩につかまりながら私の見舞いに来てくれました。「おい靖国神社に行かなくてよかったなあ」というのが二人の口から最初に出た言葉でした。嬉しかったですね。死すべかりし身が生きて親しい友達に会えた喜びは何物にもかえがたいものでした。日ならずして御母上様がご丹誠の美しいバラの花を沢山もってお見舞いに来て下さいました。花ってこんなに綺麗なものかと強烈に感じました。生きていて良かったなあとしみじみ思いました。其の時御母上様は「うちの真一郎は小さい時から脚が悪いのでなれていますが、新井さんは急にご不自由になられたのでさぞ大変でしょうね」と心暖まるお慰めの言葉をかけて下さいました。私は「真一郎君は子供の時からご不自由で運動会にも出られず、遠足にも行けず随分つらい思いをされたでしょう。私は一通りやって来ましたから真一郎君よりましですよ」とお答えしたのがついこの間のように思いますが、はや四十八年前のことになります。私はよく人にも話すのですが、あの時の堀切君の言葉と御母上様の暖かいお心使いが、私に生きていることの喜びと生きることへの励ましを与えて下さいました。感謝に耐えない次第です。 学生時代君は小型自動車に乗って通学された時がありました。その頃私どもは君の自動車であっちこっちと連れて行って貰ったことがありました。君の屈託のない様子に甘え、遠慮することもなくそうしたのですが、私は脚を失ってからあの当時堀切君に心ないことをしたものだと自責の念にかられて仕方がありません。脚の不自由なことがどんなにつらいかを知らなかったとはいえ、本当に申し訳ないことでございました。 東京で行われるクラス会の内では常に君が一番若く見受けられました。会が終わると夜をついで福島まで自動車で帰るのだと聞き、外観だけでなく体も本当に健康なのだと感心いたしたものでした。併し或る時私にしみじみお互いに脚が悪いのだから体だけは大事にしようと例のおだやかな口調で語りかけてくれました。ほのぼのとしたものを感じ、ここまで生きて来たのだから元気でもっと永生きし時々こうして会って話をしようと言ったものでした。 去る二月五日、同期生の大来佐武郎氏の叙勲祝賀会の折、谷村祐さんから君が入院中とお聞きし驚きました。早速お宅にお電話いたしましたところ、快方に向かっておられる由にて幾分安堵しその内にお見舞いに上がろうと思っていたところでした。ところがついに不帰の客になられたとの訃報に接し、悲しみの極みであります。淋しさで一杯であります。堀切君に会う喜び、堀切君と語る楽しみは永遠に失われてしまいました。併し怪我をして以来今日までずっと堀切君の朗かさ暖かさ親切さを手本として及ばずながら見習って生きて参りました私には、今日以降も君は私の心の中に生き続け私の生活を導いて下さるでしょう。 堀切君本当に永い間有難うございました。クラスの世話人から友人を代表して弔辞を捧げるよう依頼を受けましたが、私は堀切君からあまりにも大きな影響を受けました為、つい個人的なことに片寄り過ぎた感がいたします。不悪御諒承願います。 思い出はつきませんが、以上を以って弔辞を終わらせていただきます。堀切君どうか安らかにお休み下さい。 昭和六十二年三月七日 新 井 正 明 2021.01.26 記す。 |
安岡正篤先生の思い出
|
安岡正篤先生の思い出 『古教、心を照らす』 P.82~88 私の父と安岡先生のお付き合いは、実際は二十年足らずでしたが、子の私のほうは、先生が亡くなられる昭和五十八年まで、実に五十年近いお付き合いをさせていただくことができました。 安岡先生は学生時代に『王陽明研究』という非常にすぐれた内容の書物を書かれました。先生が東京大学を卒業されて徴兵検査を受けられたとき、司令官が、「『王陽明研究』の著者、安岡正篤先生とどういうご関係ですか」と聞いたので、先生が、「私です」と答えたら、司令官が驚いたという話があります。 あるいは、当時いろんな人が先生を訪ねましたが、応対に出られた先生ご本人に、「安岡先生はご在宅ですか」といいます。先生が、「はい」と答えると、「先生にお目にかかりたい」という。それで、「私が安岡です」と答えるのですが、誰も信じなかったという話もあります。お若いころから、それほど高名な方だったわけです。 まだ先生が小学生だったころ、担任の先生が休んだために、安岡先生が代わりに教えられたことがあったそうです。安岡先生は、旧制中学まで大阪でしたから、関西雌雄協会の講演で大阪へこられると、小学校時代の先生の同級生たちが集まります。私は関西雌雄協会の会長をしておりました関係で、同席したことがありますが、そのときに、「安岡先生に教わったほうがよくわかった」と同級生がいっておられました。 東京大学に『国家学会雑誌』というのがありました。まだ学生であった先生が、そこへ論文を書きますと、それを読んだ中国の学者が、教授クラスの人物が書いたものだろうと思ったという話もあります。そのように本当に偉い先生でした。 私の父は、先生の本を早くから読んでおりまして、「大先生がおるな」ということをよくいっていました。ちょうど吉川英治先生が安岡先生とお知り合いだった、という幸運もあってお近づきになれたことは、前に記したとおりです。本で知るかぎり、老先生だろうと思っていたのに、実際お目にかかってみると、自分より三十二歳も若かった、と父はいっておりました。 先生は世間一般から陽明学者といわれておりました。それは先生が幼少のころから王陽明の人と学に親しみ、大学生のときに書いた「王陽明研究」が東大卒業の年、大正十一年に出版され、当時洛陽の紙価を高からしめ先生の名が一躍世に出たためでしょう。先生は陽明学者といわれると、「そういう具合に規定してもらっちゃ困る」ともいっておられました。 私の家内の祖父は、山崎闇斎の系統を受けている朱子学者で内田遠湖といいます。私の結婚式に、安岡先生にご臨席を願い、祝辞をいただきましたが、そのとき、家内の祖父は、「安岡の説には半分賛成で、半分反対」などといっておりました。 陽明学者と朱子学は非常に仲の悪い学問だからです。しかし、先生は朱子の伝記も書いておられますし、陽明学とか朱子学というもにに限定されたいないのです。非常に広い視野を持った方なのです。 「帝王学」とは「上に立つ者がどうしても身につけていかなければならない学問」つまり「エリートの人間学」であるとし」、その基本は「原理原則を教えてもらう師をもつこと」、「直言してくれる側近をもつこと」「よき幕賓をもつこと」の三つの柱から成り立っているといわれたのは先年亡くなった伊藤肇さんですが、安岡先生は私にとってまさに「原理原則を教えて下さる師」であり、精神的支柱でありました。
先生の魅力は何かと改めて問われますと、それこそ「曰く言い難し」で簡単に申せませんが、高潔な人格、該博な学識、卓越せる識見ということになりましよう。 『呻吟語』の中に「深沈厚重なるは是れ第一等の資質」とあり、また「安重深沈なるは是れ第一等の美質なり。天下の大難を治むる者は此人なり。天下の大事を弁ずるものは此の人なり」とありますが、先生はまさに深沈厚重、安重深沈なる人と申せましょう。(参考:安岡正篤『東洋思想十講 人物を修める』P.251) ※参考:呂新吾『呻吟語』) 顔淵が孔子の人格をたたえて「これを仰げば彌々高く、これを鑽れば彌々堅し云々」(論語 子罕第九の十一:黒崎記)と感嘆しておりますが、私どもにとって先生はこのように申すべき方だと存じます。 先にもいいましたように先生の学は陽明学に止まらず広く東洋学全般に及び、更には西欧の思想文学にも深い造詣をもっておられました。先生ご自身、自分の専門は何だかわからないとよくいっておられましたが、本当に行くとして可ならざるなく、私どもの想像を絶した広範囲にわたっておりました。
※参考:志向の三原則 常にこういう観点に立つて問題を解明されていかれますので、先生の講義は普通一般の訓話の学とはほど遠いものがありました。中国古典を講じても先哲の遺訓を説いても、その精神を現在の状況にあてはめ、将来への見通しを示されます。 先生はまた憂国慨世の心情を強くもっておられ、常に国家社会という公の立場に立って物事を見ておられますので、その先見性には何時も驚かされます。一例を挙げますと十数年前でしょうか、我が国朝野を挙げて中国一辺倒のときがありました。先生は当時、時流にとらわれず毛首席や毛青夫人その他要人の人物を痛烈に批判し、中国国情に鋭いメスを入れられておられました。世間は先生の説にくみしない方が多かったと思いますが、その後の状況をみると先生が適格な判断を下しておられたことがよくわかります。 こう書いて参りますと、先生はなかなか近寄りがたい存在のようにみえますが、先生ご自身は「たしかに私の育ちは孔孟派で形もそうできているらしいが、どうも本来本来はそして自分の好みは多分に老荘的だ。几帳面なようで万事に注意深いかと思うと、おおざっぱで無頓着で、なるようにしかならぬという楽天的な無精さがある。人一倍苦労性で始終人からいろいろな相談をもちかけられてうるさくてたまらぬくせに決して棄てておけない」といっておられます。ここに先生の暖かい人間味を感じます。先生はいつも悠揚迫らず端然としておられます。その点は酒席においても変わりません。一盃一盃と杯をかわしておるうちに、えもいわれぬ独特の風韻を醸し出されるのが常です。これが私どもにとって、また格別の魅力となります。こうなりますと、いささか気が楽になり、弟子どもが日頃疑問に思っていることや気にかかっていることを、何やかや次々と質問いたします。先生には随分迷惑なことと思いますが、孔子の所謂「人を誨えて倦まず」で少しも厭わず、杯を傾けながら、静かな口調で諄々と教えて下さいます。漸く陶酔の境に入ると、色紙に筆を走らせこともときにありますが、かつて 良夜相酔 杯酒相楽 酔心相語 明日清風 と格調の高い書体で書いて下さったことがありました。 安岡先生の書は随分沢山頂戴しております。それぞれ思い出に残るばかりですが、現在私の書斎に掲げてあるのは清の曽國藩の四耐四不、すなわち耐冷耐苦対煩耐閑不激譟不不競不随可以成事(冷に耐え苦に耐え煩に耐え激せず譟がず競わず随わず以て事を成すべし)であります。 他に先生の六中観、すなわち死中有活。苦中有楽。忙中有閑。壺中有天。意中有人。腹中有書。明の崔後渠の六然、すなわち自處超然。處人藹然有事斬然)。無事澄然。得意澹然。失意泰然。 ※参考:百朝集 これらは私の日々の行動の規範となっているものであります。 2023.02.01記す。 |
「忘の説」
|
「忘の説」 『古教、心を照らす』 P.88~ 私が安岡先生の本を読んで深く感じ、今までに何回となく人にお話ししたことがあるもののうちに、『続・経世瑣言』の中にある「忘の説」があります。 「一体人間に忘れるということのあるのは、いかにも困ったことでもあるが、また実に有り難いことでもある。造化の妙は我儘勝手な人間の到底窺知することの出来ないものがある。老荘者流は頻に『忘』の徳を説いているが、肩の凝りを解くものがある。是非を忘れ、恩讐を忘れ、生老病死を忘れる、これ実に衆生の救いでもある。どうにもならぬことを忘れるのは幸福だとドイツの諺にもいっているが、東西情理に変わりはない。忘却あるところに記憶がある。それでまた妙である。『忘却は黒いページで、その上に記憶はその輝く文字を記して、そして読み易くする。もしそれ悉く光明であったら、何も読めはしない』とカーライルはうまいことを言っている。我々の人生を輝く文字で記すためには確かに忘却の黒いページを作るがよい。いかに忘れるか、何を忘れるかの修養は、非常に好ましいものである。『寵愛すべて(都)忘却し、功名ことごとく(尽)すでに(已)抛つ』などもよい。論語の中に、孔子の人物を現わして非常によい処がある。ある人が子路に孔子はどういう人かと問うた。子路は対へなかった。対へられなかったのかも知れぬ。これを聞いて孔子は曰った。お前は何故かう言わなかったのか――その人となりや、憤を発して食を忘れ、楽むで以て憂を忘れ、老いの将に至らんとするのを知らず、しかりと。(論語 述而第七:黒崎記)それでこそ孔子という人はうれしいひとである。偉いひとである。前に忘年の交ということを説いたが、孔子のやうな人であってこそ、どんなにも忘年の交である。 この「忘の説」読んで、私は、「ああ、これだな」と思いました。つまり、「自分は兵隊に行って怪我をした。もとには戻らない。それならば、どうにもならないことを忘れるのが幸福だ」と考えなければいけないのではないかということです。過去の、どうにもならないことを悔やんでも仕方がないと思うようになりました。 つまり昭和十四年八月二十日に、怪我をしなければよかったといくら思ってみてもしようがない。また、招集令状がこなければよかった、戦争に行っても弾の当たらないほうにいればよかった、ということをいくら思ってみてもどうにもならない。それよりも、現在自分がおかれているところから、将来に向かって人生を切り拓いていかなければならない、とそう思ったのです。 過去のどうにもならぬことを忘れて、現在、唯今から将来に向かって人生を切り開いていくのが、私に与えられた道なんだと痛切に感じた次第でした。 ゲーテの「処世のおきて」というのに、「気持ちよい生活を作ろうと思ったら、済んだことをくよくよせぬこと、滅多なことに腹立てぬこと、いつも現在を楽しむこと、とりわけ人を憎まぬこと、未来を神にまかせること」といのがあります。また、「明日のことを思い煩うな、明日は明日自ら思い煩らわん、一日の苦労が一日にて足れり」という聖書のことばもあります。
※参考:処世のおきて
私自身も、過去のどうにもならぬことを忘れて、現在、唯今から人生を切り拓いていくという考えに立つことが出来たのは、安岡先生のお陰であり、また北澤さんや芦田さん、そして実に多くの人びとのお陰であると思って感謝している次第です。 2021.01.30記す。 |
君子は豹変す
|
君子は豹変す 『古教、心を照らす』 P.92~94 私のこれまで歩いてきた足跡を振り返りながら、その間に私を育み、導き、そして支えてくれた数々の言葉、先輩、友人たちとの出会いについて語ってきましたが、私の七十余年の人生において精神的バックボーンの役割を果たしたのは、やはり中国古典を中心とする先哲の教えでした。いかに自分の生き方、仕事上のあり方というものが、古典の教えにおうところが大きかったかということに思い至ります。 私はこれまでずいぶんといろいろな言葉に出会い、その都度、勇気を鼓舞されて、今日まで生きて来たなと改めて感ぜずにはおれません。 そういった、私の体験を基に、中国の古典などが説いている人生の英知、上に立つ者の心得といったものを私なりに語ってみたいと思います。 昭和三十一年、私が人事部長から業務部長の時代になつたとき人事部長の時代にいったことと業務部長になってからいうことが違うということで豹変したといわれたものでした。もっとも、それは以前労組の委員長から人事課長、人事部長になったときもよくいわれたことですが。 私自身は心底から、会社良くなればもっと月給をあげてやりたい、またそういう会社にしなきゃいかんと思っていましたが、「部長はそんなことをいって誤魔化す」とか「嘘をいう」とかいう。保守反動だとか頑迷固陋という悪口は決まり文句だから平気でしたが、誠心誠意やっているのにこちらの人格を疑うような非難というものは辛いものでした。 とにかく、私はそのときそのとき会社のために適切な意見を述べているつもりおですがよく「豹変したね」とかいわれました。 そこで「豹変」という言葉が気になって、辞書にあたってみました。「字源」には「豹変とは豹の斑紋の明らかなる如く君子の旧悪を改めて善に遷るの著しき義」とありました。他の辞典も大同小異です。私は君子でないから豹変はおぼつかないが、辞書の厳密な解釈のように「旧悪」を改めて、善に遷ることができればいいなと思っていました。 「君子豹変」の原典は『易経』です。これは難しい本ですから、なかなか分かりにくいのですが、その中の「易経革卦」に「君子豹変、小人革面」という言葉があり、その前に「大人虎変」という言葉もあります。「大人虎変」というのは、ほぼ「君子豹変」と同じ意味だと解釈していいと思いますが、「小人革面」となると非常に手厳しい言葉です。小人は外面のみを革めるだけで、「その心未だ尽く化する能わず」とあります。苟に小人なるかな、です。表面だけ改めたふりをして、内心は改まらいというのです。 第三者の批判はどうあろうとも、そこで到達した結論は、あまり七面倒臭い詮索はしないに如くはなし、現在自分に課せられた任務に最善を尽くし、もしそれが豹変と見れば豹変ですし、豹変せずと解されば、これまたよし、ということで一応の解決がつきました。 その考えはいまも変わっておりません。まさに『易経』の言葉通り、リーダーというのは変に応じて、どんどん虎変豹変していかなければならないと思っています。 ※参考:君子豹変
九五。大人虎変。未占有孚。
2023.02.09記す。 |
君子は器ならず
|
君子は器ならず 『古教、心を照らす』 P.94~96 この「君子は豹変す」と似た言葉が『論語』の中にもあります。それは「君子は器ならず」という言葉です。器というのは型があって使い道が決っているが、君子はあらゆる場合において、それに対応する才能、識見を発揮しなければならない。それが「君子は器ならず」という言葉です。 経営者や会社幹部の中には、「俺はこうやって成功してきたんだから、俺のいうことに間違いはない」という人がいます。そういうことを言うこと自体間違いであり、限界がきているといえるのではないでしょうか。 あるとき、読売新聞の務台光雄さんから、吉川英治先生が読売新聞に太閤記を書いたときのエピソードを聞かされたことがあります。それによりますと、吉川先生はなかなか書くとはいってくれず、六か月くらいしてからやっと条件付きで承諾したのですが、その条件というのは、天下を取ってからの太閤は面白くない、天下人になるまでの太閤を書きたい、ということだったそうです。 一つの目標に向かって進んでいるときには、あらゆる事態に柔軟に対応し、適切にやってきたが、天下を取ってしまったあとの秀吉はその柔軟さが消えて、器が固まってしまった代表例であり、人間としての面白味がなくなったことを、吉川先生はいいたかったのだと思います。 天下人秀吉ばかりではありません。企業の中でも、取締役になってめきめき力を付ける人と、そこで成長が止まってしまう人というのが確かにいるのです。これはやはり、器量の違いではないかと私は思っています。 また『論語』には「性、相近し、習えば相い遠し」という言葉もあります。人間は誰でも生まれたときは似たりとったりなのですが、その後、習うことによって、また、習慣によって大きな隔たりができるということです。この習うとう字ンお「白」はひよこの身体を表し、それに「羽」が付いています。ひよこが何回も何回も同じことをやると、やがて飛べるようになる、ということです。 会社の中でいろいろな人を見ていますと、この習いをやり続けられる人とそうでない人がいます。それが続けられるかどうか、それが問題なのですが、これは器量であると思います。続けられる人には器量というものがあるのです。 もちろん、その人そのものは立派でも、いろいろな客観的な条件がうまくかみあわないということがありますが、その人が伸びていくかどうかは、結局は、一生人間の修練をしていくという気持ちがあるかないか、ということではないかと思うのです。 それから、また、ある地位のときは大変力を発揮したが、一段上に上がると、それほどでもないという人もいます。これも、結局は器量、心の持ち方の問題です。だんだん地位が上がるにつれて、たくさんの人を使うようになります。一人の人の知識、技術というのは限られていますが、たくさんの人の心をつかんで、その人たちが力を発揮できるようにすれば、より大きな仕事ができる。それができるかどうかは心の問題で、ですから、器量を大きくしていくには、やはり自分の心を修練していくこと以外にはないのではないかと思います。 2023.02.13記す。 |
変至らざるなし、応当らざるなし
|
変至らざるなし、応当らざるなし 『古教、心を照らす』 P.100~104 変に応ずる心得はこれだと感じ入った言葉があります。 それは 変無不至(変至らずなし) 応無不当(応当らずなし) という句であります。 これは、金森徳次郎先生がお書きになった言葉です。変化というものは至らざるなしで、どういう具合にやって来るかわからない。しかし、それに対する対処はきちっととらなければならない、ということです。 金森先生にこの「変無不至、応無不当」という色紙を書いていただいたのは、昭和二十六年のことです。この年、先生が静岡へ講演にこられました。当時、私は静岡支社長をやっていました。そのころ金森先生は、国会図書館長をやっておられたと思います。ちょうど、私の中学校時代の同級生で、上智大学の教授をしていた品田豊治という友人が、先生の秘書をしておりました。先生が宿屋に泊まられたときに、一筆色紙をお願い申し上げたいといいましたところこの言葉を書いて下さったのです。 この言葉の出典は何であろうかと安岡先生をはじめいろいろな人にお訊きしましたが、今日までわからずじまいです。金森先生にお訊きしておけばよかったと思いますが、故人になられましたので、そういうこともできません。この言葉は、多分金森先生の体験からご自身でお作りになった言葉ではないかと思っています。 昭和十年に天皇機関説問題というのが起こりました。この天皇機関説を唱えたのはご存じのように東京都知事をされた美濃部亮吉さんのお父さんの美濃部達吉という憲法学者です。この方が国家法人説というのを唱えました。これは、主権は擬制的人格である国家に帰属していて、天皇は主権を行使する機関にすぎない、という学説であり、当時は一般の通説でした。この説に反対していたのが、穂積八束博士であり、上杉慎吉博士でした。お二人の説というのは、天皇は主権を行使する機関ではない、天皇そのものが主権者であるというのです。そして筧克彦博士などは天皇は神様だ、日本は神道(かむながら)の国であるから、天皇陛下というものは国家と同じだ、こういうことをいっておられました。 ところが、岡田内閣のときに国体明徴問題、あるいは天皇機関説問題ともいいますが、国家法人説が右翼のある人たちから大変な攻撃を受けました。そのときに金森先生は法制局長官で、この天皇機関説を支持しておられました。また、もう一人枢密院議長一木喜徳郎という方、この方も立派な学者でしたが、天皇機関説を主張しておられました。金森先生はこのときの攻撃に遭って、法制局長官を辞任されたのです。 この金森先生が、戦後新憲法の専任国務大臣となって、現在の新しい憲法を創られたのです。ちょっと前には攻撃を受けた人が、新しい憲法を創る担当者になりました。ご承知のように、それ以前の憲法は大日本帝国憲法といって、欽定憲法です。これは天皇が発案して発布されたものです。この憲法にも改正の手続きをするための条文はありますが、これはしかし、今後絶対に変えることはできないだろうとして、不磨の大典として発布されたのです。第一条には、大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す、とあって、第三条には、天皇は神聖にして侵すべからず、とあります。 ところが、新しい憲法は、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である、と規定されています。金森大臣がいろいろ答弁したなかに、天皇は国民の憧れの中心であるという説明があって、これは有名になりました。 金森先生は学説的には、天皇は統治の主権を行使する機関であるという説を支持しておられましたが、まさか敗戦で、ご自分が新しい憲法にかかわるいようなろうとは思われなかったろう、と私は思います。そして、その当時の議会での先生の答弁、片方ではGHQの指示もありました。そういうことを踏まえながらガラリと違った憲法を創る、ずいぶんご苦労をなさったのではないかと思います。そこで、変化というものは至らざる無しで、どういう具合にやってくるかわからない。しかし、それに対する対応はきちっととらなければならない、ということだと思うのです。 現在から見ると、あの変化というのは大変な変革でありました。けれども、いい憲法を創って、そして敗戦後の日本の政治というものをその憲法でやってきたということは、適切であったと私は思います。
昭和二十年から今日まで、日本の政治経済その他ずいぶん変わってまいりました。現在の政治がいいか、あるいは経済がうまくいっているかというと、これも議論百出でしょうが、戦後ずっと平和で自由な国家が形成されているということは事実です。従って、金森先生の大きな変革に対する対応は間違っていなかったということがいえると思います。
われわれが仕事をしている上においても、どういう変化がやってくるかわからない。これに対して、常に真正面からぶっかって、どういう対応をすればいいかということを、日頃勉強しておかなければならないと思います。会社でもずいぶん変革が起こります。けれども、そのときどきで適切な施策を講じて、これを乗り切っていかねばなりません。平穏無事であってくれればいいけれども、なかなかそうはいきません。何が起きるかわかりませ。その何かが起こったとき、あわてふためいてしまって、対応策が取れないとうのではいけないのじゃないかと思います。 ※参考:利根川 裕『私論・天皇機関説』(學藝書林):(黒崎記) 2023.01.30記す。 |
其の身正しからずば令すと雖も従わず
|
其の身正しからずば令すと雖も従わず 『古教、心を照らす』 P.106~112 政治に関する問答を、『論語』から拾ってみましょう。子路第十三に「葉公問政、子曰、近者説、遠者来」という言葉があります。 「葉公、政を問う。子の曰く、近き者説び遠き者来たる。 つまりこれは近くにおる者が喜ぶようになれば、遠方におる者もそれを聞き知って、みんな寄って来るということです。 泰伯第八には「子の曰く、民はこれに由らしむべし。これを知らしむべからず」という言葉があります。安岡先生は、この「由らしむべし。これを知らしむべからず」の解釈について、「一般の人は今は民主主義の世の中であるから『民は由らしむべし。これを知らしむべからず』ではいけないのだというが、それはその人の解釈が間違っている。『民は由らしむべし』というのは、上に立つものがしっかりして立派であるならば、みんなが安心して寄って来る。知らしむべからず『というのは、政策のすべてを民に知らしめることはほとんど不可能である』といわれています。 ※関連:安岡先生は、この「由らしむべし。これを知らしむべからず」の解釈については、安岡正篤著『朝の論語』(明徳出版社)P.169~172。 『論語』は二千数百年前の語録でありますから、知らしめることはなかなか難しかったでしょう。今は新聞あるいはラジオ・テレビ等がありますが、それでもなかなか難しい。会社の中でさえそういうことがあります。 私は先に書きましたように、「三者総繁栄」という方針立て何回となく話をしておりますので、みんな知っているだろうと思っていましたが、数年たったあるとき女子職員に聞いてみたことがあります。そうすると、「はあ、そんなことは聞いたことがありません」とあっさりといわれました。これだけ口を極めていっても、まだ駄目か、と思いました。 ことほど左様に物事というのは知らしむることは難しいのでありますから、上に立つ者はあの人の下におれば間違いない、という具合に信用される行動を取ることが大切じゃないかと思います。 そういう考え方からしますと子路第十三にある「その身正しければ令せざれども行われる、その身正しからざれば令すと雖も従わず」という章句が心にひびいて来ます。 亡くなられた経済評論家伊藤肇さんがいろいろとかかれたご自身の著書の中に、「住友生命の新井さんが好きなのは『子の曰く、その身正しければ、令せざれども行わる。その身正しからざれば、令すと雖も従わず』という言葉だ」と何度も書いて下さったことがあります。確かに私はこの言葉が大変に好きです。ところいが「その身正しければ、令せざれども行わる」とはいうものの、現実はなかなかそうはうまくいきません。
「其の身正しければ令せざれども行わる」というのは、自分が正しい行動を一生懸命にやっておれば、命令せずとも人はその通り行う、ということでありますが、本当のところ、こちらがいわなければなかなかやってくれません。しかし「その身正しからざれば令すと雖も従わず」というのは、私は真理だと思います。 私が社長になったとき、やはり、上の者が率先垂範しないといけないということで、朝は早く出てくるようにしました。そうすれば、重役も皆早く出てくるだろうと思ったのです。けれども、必ずしもそうではありませんでした。社長は血圧が高いから早く目が覚めるので早く出勤するが、俺は夜型の人間で血圧が低いから朝は遅いのだ、といって遅く出勤する者もいたようです。このように「その身正しければ、令せざれども行わる」わけではないのですが、「その身正しからざれば令すと雖も従わず」というほうは、これは確かなのです。 私がそのことを痛切に感じたのは、昭和十九年から二十年にかけて、大阪の空襲が始まった時分のことです。ある日、人事課長が職員を集めて、「こういう非常時だから、皆早く出てきて仕事をしてくれ」と訓示をしました。ところが、そういうことをいった課長本人はどうかというと、ご本人は早くは出てこないのです。なぜこないかというと、決してズルをしていたわけでありません。心臓の病気を持っていたのです。心臓が弱いから、なかなか早くは出てこられないのです。しかし、影の声は何というでしょう。「自分出てこないで、人に出てこいといったって、それは話が通じない」とこういうことをいいます。私はそのころ人事課長代理で課長の心臓が弱いということは承知していました。だから、課長が職員にそういいながら、自分は出てこないということは困るけれども、仕方がないと思っていました。心臓が弱いということがどういうことなのか、心臓の丈夫な方にはおわかりにならないのです。 私が遅くきたら、それは私を見て私の足が悪いからだろうと思うでしょう。それは足が悪いということは目に見えるからです。現実に当時住友生命の専務だった北澤敬二郎さんは、「遅くきて早く帰ってよろしい」といわれました。当時の会社の最高責任者のお墨付きですから、そうしても誰も文句はいいません。けれども、もし私がいわれたことに甘えていたら、「あいつは足の悪いことをいいことに、楽をしている」と誰からともなくいい出したに違いないと思います。 足が悪いことは見ればわかりますが、それがどのくらい不自由なんだか、どれくらい痛いのかということは、経験したことがなければわからないと思います。戦時中、戦争直後は電車などで「傷痍軍人がきたら席をゆずりなさい」ということになっていました。実際に傷痍軍人記章をつけている私を見かけて、すっと席を立って下さる方もありました。しかし、多くの人は、私がこういう格好で電車に乗ると、目をつむってしまう。目をつむれば見えないのだから、立つ必要はないのです。 皆疲れている時代でした。その中で立って下さる方が現実にあったということは、きっとそういう方は心の優しい方なのです。あるいは身内に足の悪い人がいるか、自分がかつて怪我をしたことがある方だろうと思います。 このように人に気持ちが通じないという話は、それこそたくさんあります。 満州事変のとき作戦本部作戦課長として作戦指導にあたった今村均大将という人がいますが、今村さんは太平洋戦争中は第八方面軍司令官となって、オーストラリア軍に降伏し、ジャワ島の獄中にいたのですが、そこで書いた『今村均大将回想録』という本があります。その中に次のような話があります。
副官室にいた当時中尉の今村さんはすかさず、 「元帥、それを取ってくれませんか。元帥がしていると、ほかの連中までが元帥さえ金の指輪をしているんだから、ということになります。華美に流れていけません」 といいますと、 「君の僕の指輪を見る目つきがおかしいと思っておったが、今日初めていったな。実はこれは陸軍士官学校を首席で卒業の時、恩賜の品を頂き郷里に帰ったら、母が非常に喜こんで、自分が嫁入りの時親から贈られた金指輪を手渡され、常にこれを身につけ、金の錆ないようにいつも心を錆つかせぬよう心掛けなさいといわれたものなのだ」 というわけですが、今村中尉は、 「わかりました。しかし、一般の者はそういうことをしりません。それだったら、書斎の机の上において、毎日眺めて下さい」 といったそうです。 上原元帥の考え方は実に親孝行ですし、国家のために尽くそうと思って、常に心を錆びないように磨くというのですが、世間はそういうようにはなかなか解釈してくれないということです。 ところで、別の解釈の本では「其の身正しければ、令せざれども行われる」を「およそ民の行いは、身をもってこれに先んずれば、すなわち令せずして行われる」といっています。これは南宋の時代の朱熹が残した『集注』の解釈ですが、民のことは上に立つ人が自ら苦労してやるようにすれば、下の者は何もいわなくともその通り行う、というのです。こうなると、『論語』の「子路問政」の「これに先んじ、これを労す」と全く同じような意味になってきます。「およそ民のことは、上に立つ人が自ら苦労してやるようにすれば、下の者はいくら働かされても、怨みには思わないというのです。 私は会社の中で、「いくら働いても疲れない会社」にしようではないか、といってきましたが、これは肉体的」なものではありません。一生懸命に働けば、誰だって肉体的には疲れます。それをいくら働いても精神的には疲れないで、気持ちよく働いたというような会社にしなくてはいけない、と思っています。 私、黒崎は、勤務していた会社の研修所長の時、構内の草抜きを研修生と一緒にしました。研修生は北から北海道、新潟県、福井県、茨木県、東京、大阪、岡山、倉敷、玉島、福岡、愛姫県の工場・事務所に勤務している者たちでであった。スクーリングで倉敷にある研修所で教育を受けていた。その機会を利用して、授業の始まる前、毎朝、掃除をしながらお互いに交流するようにさせました。私も彼らの話を聞きながらでした。彼れらからは一言の苦情をきくことはありませんでした 2023.02.16 記す。
|
性相近し、習相遠し
|
性相近し、習相遠し 『古教、心を照らす』 P.135~138 そういう実力、あるいは能力を養うためには衛霊公第十五にあるように「吾れ嘗て終日食(くら)わず、終夜寝ねず、以て思う。益なし。学ぶに如かざるなり」です。結局は勉強しなければならないということです。陽貨第十七に「性相近し、習相遠し」といわれているように、人間というものは生まれたときには似たりよったりなのです。しかし、その後の勉強努力によって遠く相隔たってしまうのだというのです。 ところが、「性相近し、習相遠し」の次には「唯上知と下愚は移らず」という言葉があります。吉川幸次郎先生の講義によれば、『漢書』を書いた班固(はんこ)の『古今人評』では、人間を九つの段階に分けているということです。 それによると、上知というのは上の上の人という意味で、聖人あるいは絶対の善人のことです。孔子の弟子の顔回という人などはその一人で、あまり勉強や努力をしなくても、初めから偉い人でだったわけです。また下愚というのは下の下で、絶対の悪人ともいうべき人で、そういうものはどんなに教育してもだめだというのです。 それに対して、孟子は「人は皆堯舜となるべし」といっています。「舜も人なり、われも人なり」ともいっています。教育論としては孟子のほうが、一生懸命に勉強すれば堯舜になれるというのですから、嬉しいのですが、孔子のほうがやはり現実的といえるかもしれません。 そこで長たる者は何が一番大切かといいますと「能なきを患う」とありますように、力がなければいけませんが、しかし、力があればそれでいいかというと、そうではなく、徳がなければならないのだと思います。 ※参考:『論語』憲問第十四の三十二「人の己を知らざることを患えず、己の能なきを患う」(黒崎記) その徳を備えるためにはどうしたらいいかといいますと、「吾れ嘗て終日食(くら)わず、終夜寝ねず、以て思う。益なし。学ぶに如かざるなり」と孔子がいっておりますが、「学ぶ」ことです。同じ学ぶのであれば、安岡先生のいわれた活学を学ぶべきでしょう。ただ、一番大切なのは、学ぼうという志を立てて、それを実践することであると思います。そういう気持ちになれば、あらゆることが勉強になります。 『論語』の述而第七に 「我れ三人行なえば必ず我が師を得。その善き者を択びてこれに従う。その善からざる者にしてこれを改む」 とあります。三人行動したら必ず立派な師をみつける。そして自分もそういう人になりたいとそれをみならい、また、悪い人を見れば自分を省みて、あんなふうになってはいけないと思うわけです。 王陽明の弟子が、あるとき、「先生、私は仕事が忙しくて勉強ができません」といいましたら、王陽明は「今やっている仕事を一生懸命にやりなさい。それが本当の実学です」といって諭したという有名な話があります。その弟子は裁判所の書記をしていましたので、それをつまらない仕事だと思ったのでしょう。 この「実学」が大切だと思います。私も若いときは、会社の同僚が、研究的な仕事に携わったり、論文を書いたりしているのを見ると、彼らが非常にいい仕事をしているように見え、それに引き換え、一日中汗まみれになって雑用に追いまくられ、伝票の書き方さえわからないといっている自分は、遅れをとっているように感じられて、ただ羨ましいと思ったものでした。 ところが、王陽明の実学の訓というものを読むと、学問というものはそのようなものであると知らされ、今、自分に与えられている仕事を一生懸命にやることが、本当に生きた学問であると考えるようになったのです。 20.23.11.記す。 |
孟子の人となり
|
孟子の人となり P.140~142 先に戦時中『孟子』を読むことによってずいぶん勇気づけられた、ということを書きました。若いころは、その気魄あふれる威勢のよい文章に惹かれたものです。ところが年を経るにしたがって経営の参考となる言葉が多くあることに気づくようになりました。そこで、『孟子』を中心に一章を設けて、私なりにこういうことを経営の参考にしたらいいのではないか、ということを書いておきたいと思います。 ご存じのように、『孟子』は天命が革まると、天子が交代するという革命是認の思想があり、それがわが国の国体に合わないところから、徳川時代のは、『孟子』を積んでくる船は、日本に着く前に沈んでしまうといわたり、本居宣長は国学者の立場から、『孟子』は悪い書物で、人臣たる者の読むべき書ではないといったりしています。しかし、『孟子』にはなかなか良いことがたくさん書かれております。 その良い所を選んで、私のように学問の世界におられない者が、どう解釈し、どういう具合に経営に応用しているか、そういう事を書いてみたいと思います。 『孟子』は『論語』『中庸』『大学』と並んで四書の一つに数えられ、昔からよく読まれてきたことはご存じのとおりです。 『孟子』という書物は孟軻とその弟子によって書かれたといわれていますが、広く読まれたその理由の第一は、孟軻という人の人柄の立派さにあるということが挙げられます。「孟子」というのは孟軻を尊敬しての呼び名ですが、彼は紀元前三七二年に生まれ、紀元前二八九年に八十四歳で亡くなったといわれています。 この孟子については、「孟母三遷」という有名な話があります。お父さんが早く亡くなったので、お母さんは孟子を一生懸命に教育したのです。初めお墓の傍らに住んでいると、孟子がお葬式の真似ばかりする。それはよくないというので、今度は市場のそばに移ると、今度は商売人の真似ばかりする。これもよくないというので」、今度は学校のそばに移った。そうすると、孟子は勉強の真似をするようになった、というのです。 「隣の家の豚」という話もあります。隣家で豚を殺しているので、孟子が、「お母さん、あれをどうするの」と訊きます。お母さんはついうっかり、「お前に食べさせるつもりだ」といってしまいます。お母さんは、胎教までして孟子を立派に育てようと思っていたので、今まで孟子に嘘をいったことがありません。それで、大変高価ではあったが、無理をして隣家に行き、その豚肉を買って食べさせたということです。 また、「孟母断機」という話もあります。孟子が遠方に遊学して帰ってきたとき、お母さんがどれだけ学問が進んだかと尋ねると、孟子が「以前と同じで変わったことはありません」と答えたので、お母さんはそれまで織りかけてきた織物を切断してしまった。そして、「こうして織物を切断してしまえば、これ以上に織ることはできない。これと同じく、勉学しても進歩しないのであれば、そのかいがないではないか」と厳しく諭したというのです。このように偉大な母親に育てられた孟子は、亞聖といわれるような大思想家になったわけです。 孔子は聖人といわれ、非常に円満な大人格者ですが、孟子は孔子に次ぐという意味で亞聖といわれ、また、聖人ではなく、賢人であるといおわれます。孔子と比べると、孟子は激しい気性の人で、また、雄弁でした。それで、しばしば、感情的に走る嫌いがあったためでしょう。 孟子は諸国を巡って、自分の理想とする倫理と道徳に基づいた政治をしよう、それによって世界を平和にしようと考えて、理想主義的な歩みを続けましたが、どこの国においても用いられませんでした。そして、七十歳のころ故郷に帰って、弟子たちとともにこの『孟子』を作ったといわれています。 2023.01.22 記す。 |
『孟子』はなぜよく読まれるか
|
『孟子』はなぜよく読まれるか P.142~144 孟子は、孔子の「仁」という教えのほかに「義」を加えて、「仁義」ということを説いています。孟子が活躍した戦国時代には、孔子の教えの流れは汲んでいても、実にいろいろな思想家が排出しています。 墨翟という人はすべての人を無差別に愛さなければならないと説いています。この説によると、自分の父親も他人の父親も同じだということになります。従って、自分の父親を無視することにもなる、といって孟子は反撃を加えています。また楊朱という人は、為我主義という今の利己主義のようなことを説いていますが、それに対しても、孟子は反論しています。 孟子は、どちらかというと、当時の制度を認めて、その上に立って理想的な社会を作ろうということで、親子とか長幼の序というものを重んじる考え方です。結論的には、孟子という人物が、立派であるとということ、そいれが『孟子』の中には随所に現れているから、現代に至るまで『孟子』がよく読まれている第一の理由だということができると思います。 次に、孟子は保守的な考え方でありながら、反面、常に進歩的な考え方を持ち続けています。治者の立場を擁護する説き方をする一方、被治者の立場にも立ち、究極的には人民を大切にする、民衆の幸福を考えることが第一だと説いているのです。つまり、民衆の不平を取り除くとか、貧富の差をなくすとか、人民の苦痛や飢餓をなくさなければならないとかいっていますが、それは結局、経済的安定を一般の国民に与えなければならないということです。 しかし、経済の安定だけではいけないので、精神の安定をはかるために、教育を大切にすいることも、孟子は力説していれうのです。こうした面から見ると、普通孟子といえば、封建的、保守的思想家と思われているにもかかわらず、孟子は大いに近代的意味が含まれていることがわかるのです。これが、今日私たちが『孟子』を読んでも、理にかなっているなと思い、大いに共鳴する原因であり、また、『孟子』が現代においてもよく読まれる第二の理由だと思います。 第三の理由は、文章が非常にすばらしいということです。ここにはとても『孟子』の全文を掲載することはできませんが、私が選んだ文章を読んでみるだけでも、それが非常にリズミカルで、故事を引用したり、エピソードを挟んだり、また一見縁遠いような比喩を持ってきて議論をつづけているうちに突然、問題の核心に入り、相手の関心を引きつけて自らの主張をクローズアップさせるといううまさがあります。 ときにはこれはずいぶん強弁だと思われることをも、激しい勢いで議論していくこともあり、その非常に巧みな弁論術にはしばしば感心させられます。 2023.01.23 記す。 |
天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず
|
天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず P.175~176 以下、孟子の中から枢要な考えを述べている項目を抜き出してみます。 まず「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」ということです。 「孟子曰く、天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず、三里の城、七里の廓、環(囲)みて之を攻むるも勝たず。夫れ環みて之を攻むれば、必ず天の時を得る者あるべし、然り而して勝たざる者は、是れ天の時は地の利に如かざればなり。城高からざるに非ず、地深からざるに非ず、兵革堅利ならざるに非ず、米粟多からざるに非ざるも、委(棄)てて之を去るは、是れ地の利は人の和に如かざればなり。故に曰く、民を域(止)むるに封彊の界を以てせず、国を固むるに山谿の険を以てせず、天下を威すに兵革の利を以てせずと。道を得たる者は助け多く、道を失える者は助け寡し。助け寡きの至りは、親戚も之に畔き、助け多きの至は、天下も之に順う。天下の順う所を以て、親戚の畔く所を攻む。故に君子は戦わざるを有(貴)ぶも、戦えば必ず勝つ」(公孫丑章句下) この章も有名な文章で、およそ戦争をするには天の時、地の利、人の和と三つの大切な条件があるが、天の時はどんなによくとも地の利には及ばないし、地の利はどんなによくとも人の和には及ぼない、ということを説いております。「民が他国に逃げ出さぬよう国境を固めたりするな。国を守るのに山や谷などの要害をたのんだりするな。また天下を威嚇するのに武器や甲冑などをそろえたりするな」と昔からいわれているが、まことにもっともなことで、正しい道にかなった人には自然と味方が多いし、正しい道にかなわぬ人には味方が少ない。従って正しい道にかなった有徳の君子は戦わないことを尊ぶが、やむなく戦うときには必ず勝つものであると、孟子は民和ということを尊重力説しています。 2023.01.24 記す。 |
人の選び方、用い方
|
人の選び方、用い方 P.177~180 「孟子斉の宣王に見えて曰く、所謂故国とは、喬木の謂を謂うに非ざるなり。世臣累世修徳の臣)有るの謂なり。王には親臣なく、昔者進めし所も、今日その今日その亡かるべきを、[さえ]知らざる[様]なり。王曰く、吾何を以てその不才を識りて之を舎てんや。曰く、国君賢を進むるには、已むを得ざるが如くす[べし]。将に卑をして尊に踰え、疎をして戚に踰しめんとす、慎しまざるべけんや。左右賢しと曰うも、未だ可ならざるなり、諸大夫賢しと曰うも、未だ可ならざるなり、国人皆賢しと曰い、然る後に之を察、[その]賢しきを見て、然る後に之を用いよ。左右皆不可しと曰うも、聴く勿れ、諸大夫皆不可しと曰うも、聴く勿れ、国人皆不可と曰い、然る後に之を察め、[その]不可きを見て、然る後に之を去れ。左右皆殺すべしと曰うも、聴く勿れ。諸大夫皆殺すべしと曰うも、聴く勿れ、国人皆殺すべしと曰い、然る後に之を察め、[その]殺すべきを見て、然る後に之を殺せ。故ば国人之を殺すというべし。此の如くにして、然る後に以て民の父母たるべし」(梁恵王章句下) 「古い由緒ある国というのは、その国に大木があるからではなく、国と運命をともにする忠義な譜代の家臣がいるというのです。宣王、あなたには譜代の家臣どころか信頼する家臣さえおりません。昨日登用したばかりの者が次の日にいなくなってもご存じないような有様です」と孟子がいいますと、王様が「では人物を見抜くにはどうしたらよいのですか」と問いますので、それに対し孟子は次のように答えております。「人材を登用するときには万全を期さねばならない、身分の賤しいものを抜擢したり、血縁のうすい人間を重用したりする場合もあるのだから、よほど慎重な態度が必要です。 側近が全部ほめても不十分、大臣が推薦してもまだ不十分、国中の人が皆ほめてもそれだけではいけない。自分でよく見きわめ、これなら大丈夫だと確信してはじめて登用するのです。やめさせる場合も同様、側近が全部あれは駄目だといっても聴き入れてはいけません。大臣の進言があっても取り上げてはなりません。国中の人が皆よくないといってもそれだけではいけません。自分でよく調べてみて、これはよくないと自信がついたところではじめてやめさせるのです。 死刑のときも全く同じです。こういう順序をふんで刑を執行いたしますと王様が殺したのではなく『国中の人が皆で殺したのだ』ということになるわけです。このように人の採否・刑罰等すべて慎重にやることによってはじめて人民の父母たることが出来るのです」 側近政治の弊害とか国民総意を正しくみることの重要性を説いておるわけですが、国の政治のみならず、会社経営においても人事の重要性が痛感されます。 人の観察法についても、孟子はいいことをいっています。どういう人間がいい人間か、悪い人間かということを見分ける知才というものが必要になってきます。それには「離婁章句上」に次のような文章があります。 「孟子曰く、人を存(察)るには眸子より良きはなし。眸子はその悪を奄(掩))う能わず。胸中正しければ則ち眸子瞭らかなり。胸中正しからざれば則ち眸子眊し。その言を聴きて其の眸子を観れば、人焉んぞ廋さんや」(離婁章句上) 瞳ほどよく人物の善悪をあらわすものはない。瞳は人の心の悪を掩いかくすことは出来ない。だから相手の言葉をよく聞きながらその瞳をよく観察すれば人はその心の中をかくすことは出来ない、と説いておるのですが、私ども会社生活をしていても人観ることは大変重要なことです。 松下幸之助さんは人を観る眼がある。あの人が選んだ人ならば間違いがないといわれていますが、瞳だけでなく、ほかのところも無論見ておられると思いますが、孟子は瞳が非常に大切だといっているわけです。 2023.01.25 記す。 |
日々新たならんことを欲す
|
日々新たならんことを欲す 『古教、心を照らす』 P.196~198 ここでは、これまでに私が親しんできた古典の中からいくつか好きな言葉を選んで書いてみたいと思います。 脈絡もなく列挙するようですが、これらはすべて私にとっては感慨の深い言葉ばかりです。読んでいただくと、これは私の日々の生活での、経営の上での一貫した姿勢、信条を汲み取っていただけるものと思います。 「勇往向前、一日は一日より新たならんことを欲す」 これは伊藤仁斎の『古学先生文集』の中にある言葉です。「人間は昨日より今日、今日より明日と、日々新たに勇ましく前へ前へと進むことが肝要である。勇往邁進、一日一日新たならんとする意欲と行動があってこそ何事も達成することができる」ということです。『大学』の中に、中国古代の殷の湯王が毎日使う洗面の盥に「苟に日に新たに、日々に新たに、又日に新たなり」と彫り付けたという有名な話があります。われわれは日々新たに変化し進歩してゆかねばならない、常に旧来の陋習を去ってゆかねばなりません。 ※参考:湯の盤の銘に曰く「苟に日に新にせば、日々に新に、又日に新なり」と。中国古典選6 『大学・中庸 上』(朝日新聞社)P.84(黒崎記) この「新」という字は安岡正篤先生に教わったところによると、木と斤辛とで成り立っており、木を斤(斧)で切る、そうすると新しいものが生まれてくる。それはなかなか辛いので、辛苦の辛という字が付いているのだ」、ということです。朝日新聞の題字を見ると、新聞の新の字が「𣂺」となっています。新の字の成り立ちの元の字を使っているのです。(偏の部分の横画が1本多く、「木」の部分が「未」になっている:黒崎記) 新しいものを作るときには苦労がつきものだということを字そのものがあらわしているわけです。 伊藤仁斎はご承知のように徳川初期の儒者であり、堀河学派の創始者です。江戸時代の思想家の中でもっとも独創的でかつ社会に大きな影響力を及ぼしたのは、伊藤仁斎と荻生徂徠、それに本居宣長であると説く学者がおります。 中国学の泰斗吉川幸次郎先生はその『論語』の講義の中でさかんに伊藤仁斎のことを述べ、荻生徂徠の説を取り入れておられます。 ある日、一高時代の友人丸山真男君と久しぶりに杯を交わしていたときに、たまたま吉川幸次郎先生の『論語』に話が及びました。「吉川先生は、伊藤仁斎の説、荻生徂徠の意見をずいぶん取り上げておられるね」と私がいいましたところ、彼は「あれは僕が教えたんだ」といいます。吉川先生は「日本には本当の学者がいない。中国の学者でなければ、尊敬に値しない」といって、支那服を着たりして、すっかり中国の人のようになさっておられた方だそうです。ところが、丸山君が、吉川先生に伊藤仁斎、荻生徂徠の学問のことを話して以来、吉川先生は仁斎・徂徠の思想学問について研究するようになったのだということです。吉川先生の書かれた本を読んでも、丸山君がそういうことをいったということは全然出ておりませんから、私は全く知らラかったのですが、聞いてみてなるほどと思いました。 丸山君は日本政治思想史が専門の学者ですが、その学問の中で一番有名なのは「近世儒教の発展における徂徠学の特質並びにその国学との関連」というものです。これは荻生徂徠と本居宣長の思想と学問を実によく研究したもので、彼が東大を出て助手をしている間の研究を論文にまとめたものです。 丸山君がそういう勉強をしている間私は何をやっていたかというと、北満に行き、ノモハンで怪我をして帰国し、陸軍病院に入院です。そこへ彼が堀切君を連れて見舞いにきてくれたことは前に書きました。 私が陸軍病院にいるころ彼の論文が国家学会の雑誌に載っていましたので、私には難しいところがたくさんありましたが、ベッドの上で一生懸命に読んだものです。こちらは兵隊にいっているうちに、彼はかくも立派な学者になったか、と感心するばかりでした。 私の本立てに丸山真男「日本の思想」「現代政治の思想と行動」がある。 2023.02.09記す。 |
「鍛錬」といいうこと
|
「鍛錬」ということ 『古教、心を照らす』 P.200~202 「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」 宮本武蔵の『五輪書』の、「水の巻」の最後のところにこの言葉が出てきます。 武蔵は剣聖と仰がれ、剣の道では無双の達人でした。天性優れた資質の持ち主であったに違いないが、彼ほどその一生を通じて工夫を凝らし、精進に精進を重ねた人は少ないといわれています。「今日は昨日のわれに勝ち、明日は下手に勝ち、後は上手に勝つと思い」といって刻苦工夫の重要性を説いている不断の努力、倦まず撓ゆまず一歩一歩鍛錬することのみが剣の奥義を究める唯一の道であるとしました。その鍛錬も生やさしいものでなく千日の稽古を鍛とし、万日の稽古をもって錬とする。ですから万日というば三十年です。三十年稽古をして初めて鍛錬になるという。ですから五年や十年では鍛錬の域に達しないのであって、修業とは極めて厳しいものであることを教えています。 『五輪書』というのは、宮本武蔵が熊本の西、有明海に面した金峰山の中腹にある雲巌寺の洞窟で執筆したといわれています。これは地水火風空の仏教思想によって五巻からなっております。宮本武蔵は「一芸一道、万芸に通ずる」といって、一つの道を極めればあらゆる芸に通ずるということをいっています。だから、剣道だけではなく、書とか、絵とか、彫刻とか、あらゆるものに往くとして可ならざるものはないのです。 宮本武蔵といえば、吉川英治先生を思い出します。吉川先生と私の父が親しかったということは、現在の私に非常に大きな意味をもたらしています。私が吉川先生とお近づきになれたこともそうですが、安岡先生と会えたのも、まさにこのお陰なのです。ただ、この出会いをもたらしたのは、父の弟子で岸大洞という人でした。 昭和の初めごろ、吉川先生は小説を書くためにいろいろな文献を探しておられました。岸さんはいつのころか吉川先生のところへ出入りするようになっていて、頼まれていろいろな古い資料を吉川先生のもとにお届けしていました。そのうちに私の父と吉川先生が知り合いになりました。 あるときたまたま安岡先生の話が出て、吉川先生は安岡先生とご昵懇であることがわかりました。私の父はそれ以前から安岡先生の書物を読み、ずいぶん偉い先生がいらっしゃるといっておりましたが、まだお目にかかっていませんでした。安岡先生のお住まいは小石川の白山御殿町で、私の家はその隣の原町です。原町には金鶏学院のある酒井伯爵の御屋敷もあります。先生のお宅と私の家とはすぐ近くでありましたが、当時は知り合う機会がなかったのでしょう。それが吉川先生のご紹介によって父は安岡先生とお近づきになりました。父は安岡先生より三十以上も年上でしたが、安岡先生に大変尊敬の念をもって師事したのです。それで、私にも先生の本を読むように、先生のところへ講義を聴きに行くようにと勧めていましたが、私はまだ生意気な盛りであった上に先生のあまりの偉さにおそれをなし講義を聴きに行くことはありませんでした。 そういうご縁がありますので、宮本武蔵のこの言葉を読むと、いつも吉川先生、そして安岡先生のいろいろな思いが湧いてくるのです。 2023.02.13記す。
|
武道の極意
|
武道の極意 『古教、心を照らす』 P.204~205 「刀剣短くば一歩を進めて長くすべし」 これは柳生但馬守宗矩の言葉です。敵と相対峙したとき、敵の剣より自分の剣のほうが短かったならば、その短くて不利な分だけ積極的に踏み込んで間合いを詰める。そして有利な体勢を展開する。彼の日常剣法練磨の体験からにじみ出た言葉で日本の武道の極意を示した教えであると思います。 柳生宗矩という人が生まれたのは足利末期ですが、死んだのは徳川三代将軍家光の」時代です。この人は関ケ原の戦いで大変功績がって、郷里の柳生之庄一万三千石の大名に取り立てられました。将軍家光の剣道の先生であり、また沢庵禅師を家光に推挙したという経歴の持ち主です。 これは単に剣法に於ける真理であるばかりでなく実社会の物事はすべて積極的にやらねばならないということのいい教訓だと思います。 2023.02.13記す。
|
自らに勝つ者は強し
|
自らに勝つ者は強し 『古教、心を照らす』 P.202~203 「自らに勝つ者は強し」――これは私の一番好きな言葉のうちの一つです。『老子』の弁徳第三十三にあります。 「人を知る者は智、自らを知る者は明なり。人に勝つ者は力あり、自らに勝つ者は強し。足るを知る者は富み、強めて行う者は志あり。其の所を失わざる者は久しく、死して滅びざる者は寿し」というものです。その中で、力ある者は人に勝つことができる、けれども本当に強いのは、自らに勝つ者である、というのです。 ※参考:中国古典選10『老子 上』(朝日文庫)P.236 これは説明するまでもないでしょう。王陽明が、「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」といっておりますが、やはり自らに勝つということは大変に難しいということになるわけですが、これはなかなか難しい。まずそういう決意をすることが大切でしょう。そしてあらゆる困難にぶっかっても、自分の欲に迷わされることなく立ち向かって行く、こういうことだと思います。 2023.02.12記す。 |
功の成るは成るの日に成るに非ず
|
功の成るは成るの日に成るに非ず 『古教、心を照らす』 P.205~210 「功の成るは成るの日に成るに非ず。蓋し必ず由って起るところあり。禍の作るは作るの日に作らず、亦必ず由って兆すところあり」 これは蘇老泉の『管仲論』の中にある言葉です。 管仲というのは、春秋時代の斉の国の人で、斉の公子糾という人に仕えておりましたが、親友である鮑叔の仕える公子小白と糾とが斉侯の位を争い、小白が勝ちます。この小白がのちの桓公です。鮑叔は管仲を桓公に推薦し、管仲はその宰相となって大変立派な国作りをしました。富国強兵も達成しました。そして桓公を覇者の地位につけました。 そういう管仲の政治的手腕は誰もが認めるけれども、自分が仕えていた糾を殺した桓公の宰相となったことなど、徳義の点で問題にする人があります。 この蘇老泉は、蘇東坡(軾)、蘇潁濵(轍)のお父さんで、親子三人ともに文名が高く、当時三蘇の文名は洛陽の紙価を高からしめたといわれています。 つまり、何事も一朝一夕に達せられるのではなくて、すべて平素の努力の集積によって成功するのです。一方、禍が起こるのも、その日になって急に起こるのではなく、前から必ずその萌芽があるというのです。 従って、私たちは普段から努力を重ねていかなければならないわけです。毎日毎日慎重にやっていかないと禍が起こるということを戒めたものですが、これはなかなかいい文章です。 この『管仲論』の中に、次のような文章があります。 「一国は一人を以て興り、一人を以て亡ぶ。賢者はその身の死するを悲しまずして、その国の衰えんことを憂う。故に必ず復賢者ありて、而る後に以て死すべし。彼の管仲なる者は何を以て死せるや」 管仲の後任になつた人たちがあまりよくなくて、そして国が滅びてしまった。それを蘇老泉が批判しているのです。 「一国は一人を以て興り、一人を以て亡ぶ」――だから、よほどしっかりしなければなりません。「賢者はその身の死するを悲しまずして、その国の衰えんことを憂う」――賢者は自分が死ぬことは悲しまないが、後に残った国が衰えるということを憂うるものである。「故に必ず復た賢者ありて、而る後に以て死すべし」――だから後継者として立派な人を残してはじめて死ぬことができるのである。「彼の管仲なる者は何を以て死せるや」――管仲はそういうことをしなかったのだから、何に安心して死んだのであろうか、と。 この蘇老泉の『管仲論』については、少し手厳しすぎるという批判もあるそうですが、われわれは会社を立派にしたから後は誰でもいいというのではなくて、やはり後にも立派な人を残してその会社が永遠に繁栄するようにしなければいけないという具合に私たちは考えなければならないわけです。 ※参考:「衣食足って礼節を知る」。管仲の著書と伝えられる『管子』のなかの一句で、人間の生活の安定があって、始めて道徳が維持されることを主張する。中国の正統思想である儒教では、道徳が経済より大切だと考えられており、物質的生活の重要さを説くのは、異端思想の法家の理念にぞくする。農業を重視する儒教にたいして、商工業を奨励する『管子』の学説はこの点でも異端である。個人がじぶんの思想を著書として公にするのは、管仲の時代より三百年以上もたった戦国時代に始まった。『管子』は戦国時代末期、そのころ斉国に行われていた政治経済学説を管仲の名のもとに寄せ集めてできた本である。管仲がこの通りの言葉を述べたとは限らないけれども、こういう経済が道徳より急務だという思想はこの大政治家の言としてうけとられ、中国の政治に深い影響をあたえた。貝塚茂樹著『中国の歴史 上』P.106(黒崎記) 松下幸之助さんは松下政経塾の塾長をしておられたときにある塾生が、松下さんに「塾長、政治と会社の経営とはどう違うんですか」と尋ねたのに対して、「政治と経営とは同じものである。政治というものは国家を経営するものであり、われわれは会社を経営するものである。その考え方は一体のものである」と答えておられます。これを聞いたとき、私はまさに我が意を得た、という思いがしました。 私は資本家でありませんし、特別能力があるわけでもありませんが、たまたま会社の経営をする地位に就きました。そのとうおりに会社の経営もできないものだろうかと考えました。 『論語』の中に「政は正なり」(『論語』顔淵・第十二)、政治を正しくしなければならないという章句を前に紹介いたしましたが、ある法務大臣などは、政治家に徳目を求めるのは、八百屋で魚を買うようなものだといったことがありますがこれは随分乱暴な意見だと思います。また、政治に清潔だけを求めては政治はできない、とおっしゃる政治家もおります。政治家に清潔だけを求めるべきではないかもしれません。だけれど、政治家には立派な徳目がなければいけないのではないかと私は思います。 安岡先生からかつて、山鹿素行の「修己治人の訓」というものを教えられました。己を修めてはじめて人を治めるということで、山鹿素行はその要諦として「威・愛・清・簡・教」の五つを挙げています。安岡先生はこういうことが、政治家の徳目としてなくてはならないということを私たちに教えて下さったのですが、全くそのとおりだと首肯されます。 威というのは、威厳のことで威張ることではありません。立派な人格者であれば、おのずと威厳が出る、という当然のことです。愛というのは愛情です。国民のすべてに愛情を傾ける。愛情を傾けるについてはいろいろな方法があるでしょうが、国を富ませ、国民を豊かにするということが愛情ではないでしょうか。それから、税金をあまり取らないということも愛情ではないでしょうか。つぎは清ですが、これは清廉・清潔の清で、政治はクリーンでなければならないということをいっているのです。政治に金がかかるというのは事実で、これを認めないわけにはいかないでしょうが、そのかねをどういう方法で調達するかということについて、政治家としてはしっかりとした考えを持ってやらなければいけないのではないかと思います。その次は簡ですすが、簡易・簡明ということです。あまりごたごたしていてはいけないということです。最後は教えですが、これは教化のことで、教育もここに入れて考えていいでしょう。 以上の五つが政治家に必要な徳目だということです。政治家にはこういう政治をしてもらわなければならないと思いますが、一方で、これは政治の世界だけではなく、会社の経営においても、大切な問題であると思います。 現実はなかなかそうはいかないかもしれませんが、理想としてはそうでなければいけないのではないかと私は思います。会社の経営も、やはりそういうことを追求すべきではないかというのが、私の経営理念です。 2023.02.07記す。 |
人を樹うるに如くはなし
|
人を樹うるに如くはなし 『古教、心を照らす』 P.218~220 「一年の計は穀を樹うるに如くはなし。十年の計は木を樹うるに如くはなし。終身の計は人を樹うるに如くはなし」 この原典は『管子』ですが、安岡先生が『百朝集』の中に「三樹」として取り上げておられますから、すでに広く知られていると思います。この『百朝集』には次のような話が紹介されています。 ※参考:『百朝集』P.80(黒崎記) 昔中国の衛という国で君主が猟に出かけたときに、一人の老人が、「はあはあ」いいながら、松の苗木を植えていました。そこで、衛の君主が、「おじいさん、いくつかね」と尋ねたら、「八十五になる」と答えました。衛の君主はそれを聞いて笑いながら、 「なるほどこの松はいずれ立派な材木になるだろうけれども、それではおじいさんの生きている間には使えないじゃないかないか」 と申しました。これを聞いた老人は松を植える手を止めて、衛の君主の顔をじっと見て、「木は植えててから百年後にこれを用いて役立てるものである。自分が生きている間に用いられないから無駄ではないかという王様は、とても国を治める方の言葉とは思えない。こんなことで国が治められますか」 そして、 「私は年老い、先の短い身でありますけれども、子孫のために木を植えているのです」 ということをいいました。これを聞いた衛の君主はすっかり恥じ入って、「自分が間違っていた」といって酒を出し、食事をさせて老人をねぎらったということです。 この話はもともと太宰春台の『産語』という本の中に書いてあります。これは大変に難しい本で、現在、手に入るかどうかわかりませんが、昭和四十六年に明徳出版社から刊行されています。これには神谷正男という方が解説を付けておられます。神谷先生の本『産語――人間の生き方』という題で、解説と訳文がついており、それだけ読めば、原漢文を読まなくとも大変ためになると思います。 太宰春台は信州飯田の人です。荻生徂徠の門人で、経世済民の実学をやったということです。しかし、この『産語』を自分で書いたということはいわないで、こういう書物がどこかにあった、というようなことをいっていたのだそうです。 これは吉田松陰が松下村塾で教科書として使い、松陰の弟子の品川弥二郎が、松陰からこの書の講義を受け、大変な影響を与えられたということです。以後、品川弥二郎は終生『産語』を欠くべからざる珍書として愛読し、自ら全文を邦訳して刊行したと伝えられています。 こういう考えは事業においても大切なことです。『管仲論』のところで、管仲自身功績はあったけれども、遺憾ながら立派な後継者を残すことができなかったという批判を紹介しましたが、この『産語』の主旨もやはり立派な人材をあとに残さなければならないということなのです。 2023.02.05記す。 |
倦まずたゆまず
|
倦まずたゆまず 『古教、心を照らす』 P.229~231 『中庸』にこういう文章があります。 「人一たびにして之を能くすれば、己れ之を百たびし、人十たびにして之を能くすれば、己れ之を千たびす」 私がこれを知ったのは中学のときです。私は田舎の小学校五年終了で東京に出まして中学も東京の中学校に入りました。郷里の小学校で同級生の親類のものもやはり東京で中学校に通っておりましたので、その家によく遊びに行きました。そこのおやじさんは、当時民政党の代議士でした。 その彼のところへ遊びに行くと、机の前の壁に『中庸』のこの文句を書いた紙がはってあるわけです。代議士である父親が自身で書いてくれたものです。どちらかというと、あまり勉強好きでなかったその友人に対し、一生懸命にやれという父親の戒めであったことはいうまでもありませんが私には強く印象に残りました。 その頃の私はこれが『中庸』にあることを知らなかった。だからもちろんのこのあとにつづく文章も知りませんでした。この後に「果して此の道を能くすれば、愚と雖も必ず明らかに、柔と雖も強なり」とあります。 一生懸命、人より余計何回も何回もやればよくなるということであります。 この『中庸』というのは改めていうまどもありませんけれども『大学』と同じく『礼記』の一篇であったのを、朱子が四書に加えて単行本にして盛んに読まれるようになったものです。 その作者は孔子の孫の子思であるといわれますが、この中に「誠は天の道なり、これを誠にするは人の道なり」という有名な文句があります。 「誠は天の道なり。これを誠にするは人の道なり。誠なる者は勉めずして中り、思わずして得、従容として道に中る、聖人なり。之を誠にする者は善を択んで固く之を執る者なり。博く之を学び審らか之を問い、慎んで之を思い、明らかに之を弁じ篤く之を行う。学ばざる有れば之を学び、能くせざれば措かざるなり。問わざるあれば之を問い、知るらざれば措かざるなり。思わざる有れば之を思い、得ざれば措かざるなり。弁ぜざる有れば之を弁じ、明らかにせざれば措かざるなり。行わざる有れば之を行い、篤くせざれば措かざるなり」 この次に前掲の「人一たびにして云々」が続くのです。 ※参考:中国古典選7 『大学・中庸(下)』(朝日新聞社)P.147 中庸 宋朱熹章句 第二十章。(黒崎記) 私はまた『中庸』の中で「至誠息むことなし、息まざれば則ち久し、久しければ則ち徴あり、徴あれば則ち悠遠なり」という言葉が好きです。 やっぱり誠の道を倦まずたゆまずやってゆけば必ず効果があって、それが悠遠に通ずるということで、大変感銘している言葉です。 ※参考:中国古典選7 『大学・中庸(下)』(朝日新聞社)P.162 中庸 宋朱熹章句 第二十章。(黒崎記) 2023.02.06記す。 |
「忠恕」の精神
|
「忠恕」の精神 『古教、心を照らす』 P.236~240 行路難 水に在らず 山に在らず 只だ人情反覆の間に在り これは、白楽天の「新楽府五十篇」のうちの一つ「太行の路」の中にでてくる句であります。 白楽天(七七二~八四六)は中唐の詩人で、名は居易、楽天は字(あざな)であります。盛唐時代の李白・杜甫と並び称せられ、中国ではもちろん、わが国でも古来最も親しまれた詩人であります。彼の作品「長恨歌」とか「琵琶行」などは名詩として日本にもよく知られております。 新楽府というのは、唐代の新しい歌謡曲で、その内容はすべて当時の政府または世相に対する批判であります。風刺詩であります。広く大衆に愛され、各地で盛んに歌われていたといわれております。 この詩の意味するところは、人生の行路の辛いこと、世渡りの険しいことは、水の深いことでもなく、山の高いことでもなく、人情の反覆常ならざることにあるということであります。 この"太行の路"というのは、夫婦に譬を借りて君臣の関係の始終変わらないことの難しいことを歌った詩であります。この詩の初めの方に夫婦の譬を借りてということで"生まれて婦人の身となる莫れ、百年の苦楽は他人による、行路難 山より難く、水より険し"と歌っております。つまり人間と生まれて婦人の身となるものではない、人生百年の苦楽は他人である夫によるものである。そしてその人生のきびしさは、山より難く、水より険しい。しかし、人情反覆の間にあって、人と人の間柄がうまくいけば、それが一番幸せだということを言っているのであります。 それからもう一題。 「子の曰く、参よ、吾が道は一以て之を貫く。曾子の曰く、唯。子出ず、門人問うて曰く、何の謂いぞや。曾子の曰く、夫子の道は忠恕のみ。(論語里仁第四) ※参考:宮崎市定著『論語の新研究』(岩波書店)P.225 81/499 孔子曰く、参よ、私の道はただ一筋の道だ。曾子曰く、わかりました。孔子が去ったあと、門人が曾子に尋ねた。どいう意味だったのでしょうか。曾子曰く、孔先生の道は真心の一本道なのだ。 孔子が「参よ」と呼びかけて、「私の思想なり、行動なりは、一つのことで貫かれている」と弟子の曾子に語った言葉です。参というのは曾子の名前です。曾子は、「はい」とだけ答えました。ほかの弟子たちは何のことかわからず、孔子がその場を去られると、「さっきの対話はどういう意味ですか」と尋ねました。曾子は説明して、「うちの先生の道は忠恕、つまり、誠実と思いやりだけですよ」といったのです。 この文章は、「夫子一貫」の章といって『論語』の中でも古来有名です。 私が社長の時に、ある新聞記者から、「社長、どういう会社にしたいんですか」と問われました。それに対して私は、答えの一つに、「忠恕」の精神で会社を経営したいと申しました。これは安岡先生から『論語』の一番の眼目は「忠恕」で忠恕の道は徹底した人道主義であると教わっていたからであります。 この「忠恕」について安岡先生は、「忠とは理想を追求し、進歩向上を求めてやまぬ精神・努力を申します。恕はそれに伴って一切を包容し育成してゆく仁愛の寛容であります。恕はゆるすと読むのが普通であります。ゆるすというのは寛容のことであります」と『朝の論語』で説かれており、その場に立って赦すということですから、まあ愛といってもよいと思います。
ただ会社の経営は忠恕の精神だけでやるといっても、それだけでは十分でないと考え、私はそれに勇気を加えて忠恕と勇気ということを言ったのであります。 これは私は今でも間違っていないと思っております。何しろ「夫子の道は忠恕のみ」といって孔子が一生貫いた道でありますから、この孔子さんの道を私なんかがやり通せるかどうか分からないけれど、理想としては、そういうことをやっていきたいと思いました。 しかし、忠恕というのは一般の職員に馴染みが薄く、恕という字を、ジョと読まないで怒と読んでしまう者もおりいささか困りました。そこで途中から、忠は誠、恕は愛として、誠と愛と勇気dさということに致しました。そうしますと皆よく分かってくれました。 それはそれとししまして、新聞記者に問われたときのいま一つの答は「いくら働いても疲れない会社にしたい」ということでありました。これはどういうことかといいますと、働けば肉体は疲れます。肉体は疲れますが、人と人との関係がうまくいきさえすれば、精神は疲れません。一日勤めていても、早く終業時間が来ないかなあといって時間ばかり気にしている、こういうのはかえって疲れます。 それよりも仕事を一生懸命にやって、気持ちよく仕事をしておれば、ああもうこんな時間になったのかということで、肉体は疲れるけれども、精神は疲れない。心に充実感がみなぎる、そういう会社にしたいなあと思いました。 そういう会社になったかどうかは分かりませんが、少なくとも理想はそうでありました。それは、上と下との関係・同僚との関係、私は人間関係という言葉はあまり好きではありませんが、人間関係がうまくいくと疲れません。 それで、「行路の難きは水に在らず、山に在らず、只人情反覆に在り」というと、ああそうなんだな、人と人との関係がうまくいけば、万事うまくいくんだなという具合に思ったわけであります。 2023.02.02記す。 |
常に心に喜神を持つ
|
常に心に喜神を持つ 『古教、心を照らす』 P.242~246 次は『菜根譚』の文章です。 これは明の洪自誠の著になる『菜根譚』の一節です。洪自誠は儒学・老荘・仏教に通じた哲人で、処世の道だけでなく文雅風流まで幅広く説いています。 「耳中、常に耳に逆うの言を聞き、心中、常に心に払るの事あれば、わずかに是れ徳に進み、行を修むるの砥石なり。若し言々耳を悦ばし、事々心に快ければ、すなわち此の生を把って鴆毒の中に埋在せん。
※参考:菜根譚 前集 二二二句あり
人間は平素、常に耳には聞きづらい忠言を聞き、常に心には思い通りにならぬことがあって、それでこそ徳に進み行を修めるための砥石となる。(これと反対に)、もしどの言葉も耳を喜ばせ、すべての事が心を満足させるようであっては、それではこの人生を鴆毒の中に埋め沈めてしまうことになる。岩波文庫P.29 2020.02.03追加。
六 疾風怒風には、禽鳥も戚々たり、霽日光風には、草木も欣々たり。見るべし、天地は一日も和気なかるべからず、人心は一日も
暴風豪雨の日には、非情の小鳥まで憂え恐れて悲しげである。(これに反して)天気晴朗で穏やかな風の日には、草木も生き生きとして喜んでいるようである。してみると、天地には一日たりとも和気がなければならない。(これと同じく)、人の心にも一日たりとも喜び楽しむ気持ちがなければならない。岩波文庫P.30
参考:新井正明『古教、心を照らす』(竹井出版)p.246
これは昭和十二年の夏のころでしょうか、春のころでしょうか、私が寮の図書室でこの『菜根譚』を見つけて読みだしたところ、割合初めの方にこういう文章がありました。
これに大いに感じたのはどうしてかというと、学校を出て住友に入って大阪に来ました。そうしますと住友は大阪では、住友さん、住友さんといわれ大事にされておりまして有難く思ったわけです。しかし飲み屋に行くときは井桁のマークは引っくり返して行け、なんて先輩にいわれて身を慎しまなければならないということも教わりました。
けれども会社は私には甚だ住み心地が悪かった。なぜかというと私は裕福な家に育っておりません。当時は、お金持ちの家か、商売人の家以外には電話なんかありませんでした。従って私の家には電話はありません。ところが会社員になりますというと、電話を聞かなければならない。私は電話のベルが鳴ってもなるべく把りたくないのでですが、しかし新人社員でありますから私が電話を把らなければならないわけです。
それで私が電話を把りまして、誰々さん、電話ですというと、その先輩がすぐに替ってくれればいいのに把ってくれない。そして誰からだというから、相手の名前を訊いて渡そうとすると、どういう用件だというわけです。
これが甚だ私には辛かったのです。今では大阪弁、関西弁はラジオやテレビで普及してきておりますけれども、当時私のように関東で生まれ、そして東京で育ったものには奇異に感じました。まことに大阪の方には、申し訳ありませんけれど。
中学校のときに、軍人さんでありましたけれどもこちら出身の先生が「えろうなったら休んでもええ」というと、えろうなったらという本当の意味がわからない。それは疲れたら休んでもいいということです。それで生意気ざかりの中学生が「えろうなったら休んでええですか」というと「ええ」というと喜んでわあっと笑う。先生の方は、なんで笑っておるのかわからない。そういう時代でありましたので、電話がなかなか苦手でありました。
また手紙を書くときは候文で書かされるのでありますが、その候文がどうも具合が悪い。しかし私は真面目に取り組んだつもりです。それで先輩が直してくれた候文をとっておいて次のときにその通り書いて出す。すると先輩は自分が直したそれをまた直すわけです。
私はこれは一体どういうことであろうかと思うわけでありますけれども、考えてみますと出す相手が違うんですね。「御座候」と「有之候」というように違います。そして役所に出す手紙に「伏して懇願奉り候」ということを書かねばならない。
そんなわけでどうも会社が面白くない。終業時間になったらさっさと帰る。ところでそのころは居残りすると月末にいくらかお金が貰えるんです。先輩の方々は月末になるとお金を貰っておるのに私はなんにも貰えないから、どういうわけかと思ったら全然居残りをしなかったわけです。ところが折角いい会社に入ったのに毎日毎日面白くないというのは、これまた具合が悪いので、自分の心に楽しみを持たなければいけないと思っていた矢先、たまたま出遭ったのがこの『菜根譚』の「耳に逆らうの言」であります。
これについて魚返善雄(おがえりよしお:黒崎記)先生がこういうことをいっております。
「耳には耳の痛いことばかり、胸には無念なことばかり、それがわが玉を磨く石となる。おだてられたり、いいことばかりでは、われとわが身に毒を盛るようなものだ」と。
ああこれだな、毎日毎日嫌なことばかりだけれども、これは砥石で砥がれているようなもんだな、これじゃ少し心がけを変えなければいけないという具合に思ったわけです。
ですからこれは昭和十二年から今日に至るまで約五十年間、私が嫌なこと、辛いことがあったときに、この言葉が甦ってきて、ああ、ここのところを堪えていかなければならない、これは人間を磨く所以ではないかという具合に考えたわけであります。
安岡先生から健康の三原則として、まず第一に喜神を持つということ、第二に感謝するということ、第三に陰徳を積むということを学びましたが、その喜神という言葉が『菜根譚』の中にありますので、ここに引用しておきます。
※参考:健康の三原則について、安岡正篤『東洋思想十講 人物を修める』(竹井出版)P.247~248(黒崎記)
「疾風怒風は、禽鳥も戚々たり、霽日光風には草木も欣欣たり。見るべし、天地は一日も和気なかるべからず、人心は一日も
これも魚返善雄先生の名訳をあげておきます。
「風雨の日には鳥さえ悲しむ。晴れた天気には草木も喜ぶ。つまりこの世はいつも和やかなのがよく、人間は何時もにこやかなのがよい」
どんなことがあっても、へこたれないで、どんな嫌なことがあっても、常に心に喜神を持つということが健康の三原則のうちの第一であるということです。
これはまた「耳中、常に耳に逆うの言」と同じような具合に何か事があったときには、そいうことに思いを致して堪えてきたのであります。
2020.02.04記す。2023.02.03追記。
|
実践あっての学問
|
実践あっての学問 『古教、心を照らす』 P.246~248 次は荀子です。 荀子は戦国趙の人です。時代は紀元前三世紀ごろで、ご承知のように孟子の性善説に対して性悪説を唱えた人です。 人の性はあるがままに放っておけば必ず自己中心の利欲をほしいままにし他の利害を顧みなくなり、そこに争奪が起こるので礼を以て抑制しなければならないと説いています。
この『荀子』開巻第一に勧学篇というのがあり、最初に出てくるのが、「君子曰く、学は以て已むべからず。青は之を藍に取りて、藍より青し。氷は水之を為して、氷より寒し」です。 学問は中道でやめては絶対にいけない。青は藍より作るけれども藍よりも青い。氷は水で作るけれも水より冷たいということでありますが、これが「出藍の誉」という語源であります。これはすべて天性あるがままに放っておいたならば、自己中心になるけれども、これは矯正することによって立派になるということであります。 それから「木は縄を受けて則ち直く、金は礪に就いて則ち利し、君子は博く学びて日に己れを三省せば、則ち知明かにして行い過ちなからん」――木は墨縄(大工が木を挽いたり削ったりするとき直線の印をつけるために使用するなわ)を用いて初めてまっすぐに切ることが出来、金は砥石にかけられることによって鋭くなる。人もまた博く学んで日々に何度も反省すれば、智も明晰で行為にも過失がなくんなるということであります。これは一生懸命勉強しなければならないということを説いたものと思います。 儒効篇にこうあります。 聞かざるは之を聞くに若かず 之を聞くは之を見るに若かず 之を見るは之を知るに若かず 之を知るは之を行うに若かず 学は之を行うに至りて止む ※参考:『荀子』 中国の思想 4(徳間書店)P.282(黒崎記) これは聞見より実行、天性より後天的積習を説いたものであります。 「聞かぬは聞くに及ばず、聞くは見るに及ばず、見るは知るに及ばず、知るは行うに及ばない。学問は実践する事を究極の目標として努力すべきものである。すなわち学問はこれを実行することに至って最上に達したというべきだ」と説いております。 2023.02.04記す。 |
独りを慎む
|
独りを慎む 『古教、心を照らす』 P.246~248
『大学』章句伝六章にこういう章句がありまさう。
「所謂其の意を誠にすとは、自ら欺く母きなり。悪臭を悪むが如くし、好色を好むが如くす。此を之れ自ら謙くすと謂う。故に君子は必ずその独を慎むなり。
小人間居して不善を為せば、至らざる所無し。君子を見て后厭然として其の不善を揜いてその善を著わす。人の己を視ること肺肝を見るが如く然れば、則ち何の益かあらん。此れ中 曽子曰く十目の視る所、十手の指す所、其れ厳なるかな、と。 富は屋を潤し、徳は身を潤す。心広く体胖かなり。故に君子は必ずその意を誠にす」 これは自ら欺かぬようにせよということを述べておるのです。悪をにくむ場合は悪臭をにくむが如く真心からにくみ、善を好むときには好色を好むが如く真心から好むようにせよ、そうすれば心の中に一点のやましいこともなく自分で満足することが出来る。だから君子は自ら欺くことなく独り慎むのである。小人は独り居って悪いことをして人に知られないだろうと思うが到底かくしおおせるものではない。 曽子も人の考や行動は沢山の人が注視していたり、あまたの人の手が指さしているから、おそれつつしまねばならない。自ら欺き人を欺くようなことをせず、誠の道理をはなれず、徳をわが身に修めてゆけば富が屋を潤す如く徳は身を潤し、自然心は広く、体は胖かになるものである。 ※参考:中国古典選6『大学・中庸(上)』(朝日新聞社)P.111(黒崎記) ※私は研究所へ異動するとき、上司から「人間はあらゆる角度から知らないと思っている人からも評価されている。みている人はみているから注意すること。」と言われた。また、母親からは後ろ指をさされるな、といわれていた。 ※参考:中国古典選6『大学・中庸(上)』(朝日新聞社)P.111(黒崎記) 『貞観政要』という書物には、唐の太宗が常に緩みがちな緊張感を引き締めていたという話が出てきますが、最高の地位についていると表立って文句をいう者もいないだけに、自ら独りを慎まなければならない。自分で自分に緊張を課することが大切であります。 そういう意味で、この「独りを慎む」というのは大変慈味深い言葉です。とくに上にたつ者に不可欠の心得、条件といってよいかと思います。前に老子の「自らに勝つ者は強し」ということにつき述べましたが「自らに勝つ」基本には「独り慎む」ということがなければならないと思います。 古典のなかには、まだまだ汲めども尽きない、素晴らしい教えの言葉がたくさんあるのですが、いずれにしましても、私が実業の世界でそれなりの歩みをしてこれたのは、こういった先人の教えが大きな支えになっているからだと信じています。 2023.02.04記す。 |
 これを見て看護婦が涙を流していたそうです。このことは当時の私の上司であった伊藤軍曹ときう人から聞いて知りました。結局、女々しいことをして名を汚してはならないということで、子供のころの書き初めの言葉が、ずっと私の心の支えとなり、強くしていたのだろうと思います。
これを見て看護婦が涙を流していたそうです。このことは当時の私の上司であった伊藤軍曹ときう人から聞いて知りました。結局、女々しいことをして名を汚してはならないということで、子供のころの書き初めの言葉が、ずっと私の心の支えとなり、強くしていたのだろうと思います。
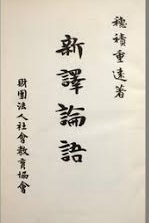
 ※参考:伊藤肇著『現代帝王学』(講談社文庫)(昭和59年2月15日第1刷発行):第一章、第二章、第三章。(黒崎記)
※参考:伊藤肇著『現代帝王学』(講談社文庫)(昭和59年2月15日第1刷発行):第一章、第二章、第三章。(黒崎記)
 象曰、大人虎変、其文炳也。
象曰、大人虎変、其文炳也。

 ※参考:伊藤肇『十八史略の人物学』(プレジデント社)P.146 住友生命会長、「新井正明の自戒の言葉は、やはり『論語』の一節である。其ノ身、正シケレバ、令セズシテ行ナワレ、其ノ身、正シカラザレバ、令ストイえドモ従ワズ。」とか書かれている。(黒崎記)
※参考:伊藤肇『十八史略の人物学』(プレジデント社)P.146 住友生命会長、「新井正明の自戒の言葉は、やはり『論語』の一節である。其ノ身、正シケレバ、令セズシテ行ナワレ、其ノ身、正シカラザレバ、令ストイえドモ従ワズ。」とか書かれている。(黒崎記)
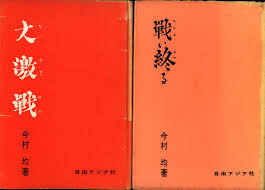 今村さんは日清・日露戦争で活躍した上原勇作元帥の副官をしていたこといがあります。この上原元帥は金の指輪をしていたということですが、あるとき、右翼的な一人の宗教家が、「金の指輪なぞをしているのはけしからん」といったそうです。
今村さんは日清・日露戦争で活躍した上原勇作元帥の副官をしていたこといがあります。この上原元帥は金の指輪をしていたということですが、あるとき、右翼的な一人の宗教家が、「金の指輪なぞをしているのはけしからん」といったそうです。
 五 耳中、常に耳に逆うの言を聞き、心中、常に心に払るの事ありて、纔に是れ徳に進み行を修むるの砥石なり。若し言々耳を悦ばし、事々心に快ければ、便ち此の生を把って鴆毒の中に埋在せん。
五 耳中、常に耳に逆うの言を聞き、心中、常に心に払るの事ありて、纔に是れ徳に進み行を修むるの砥石なり。若し言々耳を悦ばし、事々心に快ければ、便ち此の生を把って鴆毒の中に埋在せん。