改 訂 版 2022.12.08 改訂

心の怒りを絶ち、おもての怒りをすて、人のたがうを怒らざれ。人みな心あり。心おのおの執ることあり。彼よみすれば、すなわち我非なり。我よみすれば、すなわち彼非なり。我必ずしも聖にあらず。彼かならずしも愚にあらず。共にこれただひとのみ。是非の理)、いずれか定むべき、相ともに賢遇なり。鐶の端なきがごとし。これをもって彼の人はおもて怒るといえども、かえって我があやまちを恐れよ。我ひとり得たりといえども、衆に従って同じくおこなえ。(憲法、第十条) 4月3日、太子によって『憲法十七条』が制定された。太子は大陸文化の移入に熱心で、仏教を盛んにして、日本文化に新しい方向を開いた。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.57 補足:(憲法、第十条)は「他人と意見が異なっても腹を立てないようにしなさい」と解釈されている。 2010.04.03
『菩提心を発しましょう』 「和を以つて貴しと為す」 第30号 2016.7.31発行 今日、宗教色を背景にした国際テロが罪もない庶民を殺害し、それに対応して、政治色を以て、行きどころもない弱者を国外に排除する摩擦が一層激しくなっています。人間が人間にたいする寛容性を失い前世紀に逆行している感が有ります。今私たちは勇気をもって、我らは複雑なる宗教の組織を超脱し、煩(はん)瑣(さ)なる教学を放(ほう)擲(てき)して、一人ひとりが信頼し合える平等の人間性に目覚め、世界の人々が互いに手を把りあって、人類恒久和平の為に精進努力すべき時ではないでしょうか。 仏陀は、生誕されると、直ちに周行七歩、右の指は天を指し、左の指は地を指して、「天上天下唯我独尊」と叫ばれたと伝えています。おそらく、私たち誰でも生まれたとき、「オギャア、オギャア」と大声を張り上げて生まれてきました。周りに気兼ねもなく、酷(ひど)いこの世界に迷うこともなく、純粋な生命そのものを「天上天下唯我独尊」と頂けるのが仏教ではないでしょうか。この生誕の説話は、仏陀の生涯の「自覚に即した教えの内容」を、端的に生誕に託して表されたものと思います。仏陀は生まれるとすぐ立って、周行七歩を歩かれ、右の手は天を指さしたということは、天に人間を支配するような、人間を奴隷あつかいにするような神はないぞということでありましょう。左の手で地を指さされたのは、人間の下に誘惑的魔障もおらんぞ。人間こそ絶対の尊厳者であることを表現されたものと言わねばなりません。七足歩かれたのは、仏陀の教えの根本思想が、人間の一人ひとりをして、自由にして尊厳なる、「智慧と慈悲」を内包する絶対的主権者としての自覚を持たしめるものであることを思うとき、そう解釈をせざるを得ません。お釈迦さまは哲学者ではなく、苦行によって人間性の真実に目覚められた第一人者であります。其のとき「奇なるかな、奇なるかな、一切衆生悉「皆な如来の智慧徳相を具有す」、「皆生まれながらに仏の智慧によって悟っていたのに、生まれて後、外の世界に迷うがために苦しむのだ」と、だから、汝、自らに内在する一念の邪念もない純粋な心を拠り所として外の世界に騙されるではないぞ」と、はっきり示しておられます。「汝ら輾転(てんてん)してこの法を行ぜば、そこに私は永遠に生きているぞ」と、力強示しておられます。今こそ一人ひとり一個の求道者として、仏子として、世界の仏教徒が手を把りあって、人類恒久和平の為に精進する時であると信じます。 平成二十八年七月 曹源寺住職 原田正道 合掌 輾転(てんてん):釈迦の教え、真実を正しく体得し、自ら実践して、正しく伝える。仏法:純粋な心で事物現象を照らすこと。 「和を以つて貴と為す」 これは、論語に由来しています。 「子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」「論語」 孔子は明確に君子は「和」して「同」ぜず、小人は「同」じて「和」せずと同と和を「別々のもの」として言っています。 つまり「和を以って貴しとなす」の「和」を「同」と捉えている時点で「小人」=つまらない人物とまで言っています。 聖徳太子が発布した十七条の憲法 そこには、「和を以て貴しと為す」という言葉があります。 孔子曰わく、礼の和を用(もっ)て貴(たっと)しと為すは、先王の道も斯(これ)を美と為す。小大(しょうだい)之に由れば、行われざる所あり。和を知りて和すれども礼を以て之を節せざれば、亦(また)行うべからざるなり。(学而第一・仮な論語7頁) 孔子が言われました。 「礼において和を貴いとするのは、私一人の考えではない。昔の聖王の道もそれを美しいことと考えた。だからといって、和だけですべての人間関係を行おうとすると、うまく行かないことがある。和の貴いことを知って、和しても礼(敬謝謙譲等の心)を以て調節しないと、うまく行かないのである。」 和する事には礼が必要。正に「親しき仲にも礼儀あり」所詮外向けに虚飾に塗れているだけで、内向きには横柄になっているようではダメです。 この「和を以つて貴しと為す」の精神的支柱は、日本の伝統分化として、富国強兵時代に至るまで受け継がれてきましたが、現在は、取って代わって個人主義が謳歌しています。 聖徳太子の仏教思想 私たち凡夫は自性清浄心として如来蔵を宿しています。しかし、それはまだ如来の胎児であり、数多の煩悩に覆われ、如来としての働きはありません。衆生が如来の蔵を開いて仏の命を輝かそうとするには、如来への絶対的信と菩薩行(仏となるための修行)を実践することが大切となります。 菩薩行の実行により、争乱の絶えない現実社会は次第に浄化され、「和の精神」に立脚した安寧がこの世に実現され、菩薩行の成就の暁には仏国土が現出します。 「このように太子が、常住真実なる法身如来への帰依信順こそ行善の本であり、直控の道であることを開顕せられたことは、正しく仏教を出家聖者から解放して、広く一般庶民のものとせられたものと言ってもよく、それはまた、一切衆生を平等に仏果に入れしめることを究極の理想とする仏教の宗教性を如実に開顕せられたものと言うことが出来るのである。」 太子の仏教思想は一言で言えば「捨身思想」です。捨身思想とは即ち「他人のために死ぬ」ことです。 これは法隆寺にある国宝の玉虫厨子にも現れています。そこには釈迦が前世で行った善行をまとめたとされる「釈迦本生譚(ジャータカ)」に出て来る2大捨身(自殺)話の「捨身飼虎(しゃしんしこ)」と「施身聞偈(せしんもんげ)」が描かれています。 *捨身飼虎・・・釈迦が前世である国の王子だった時、修行中に虎の親子が飢えに苦しんでいるのを見かねて、自ら虎の餌となって 命を捨てる話。 *施身聞偈・・・釈迦が前世で雪山修行をしていた時、仏教の真理である「偈(げ)」の後半を知るために悪鬼に命を捧げる話。 私たち凡夫は自性清浄心として如来蔵を宿しています。しかし、それはまだ如来の胎児であり、数多の煩悩に覆われ、如来としての働きはありません。衆生が如来の蔵を開いて仏の命を輝かそうとするには、如来への絶対的信と菩薩行(仏となるための修行)を実践することが大切となります。 十七条憲法はそのための手引き書であり、三経義疏はその理論的根拠なのです。 菩薩行の実行により、争乱の絶えない現実社会は次第に浄化され、「和の精神」に立脚した安寧がこの世に実現され、菩薩行の成就の暁には仏国土が現出します。 「このように太子が、常住真実なる法身如来への帰依信順こそ行善の本であり、直控の道であることを開顕せられたことは、正しく仏教を出家聖者から解放して、広く一般庶民のものとせられたものと言ってもよく、それはまた、一切衆生を平等に仏果に入れしめることを究極の理想とする仏教の宗教性を如実に開顕せられたものと言うことが出来るのである。」また、太子が書いた仏教の解説書である「三経義疏(さんきょうぎしょ)」の三つの経、法華経・維摩経・勝鬘経のうち、勝鬘経の中心となる考えも「捨身」です。仏教の真の教えを知るためには身・命・財の3つを捨てなければならないとされているのです。 聖徳太子が亡くなったのは推古30年(622年)2月22日、妃の膳部夫人との心中(自殺)です。これも捨身思想から出たものです。そしてその思想は息子の山背大兄王に引き継がれて行きます。山背大兄王は蘇我入鹿が自分を殺そうとした時、「自分が軍を率いて入鹿を討てば勝つだろうが、自分はそのようなことで人民を殺したくはない。いっそこの身を入鹿にくれてやろう」と一家もろとも心中しています。 2016.08.03 |

送春不用動舟車 唯別残鶯與落花 若使韶光知我意 今宵旅宿在詩家 (春を送るに舟車を動かすを用いず ただ鶯と落花と別るるのみ もし韶光(春の光)をして我が意を知らしめば 今宵の旅宿は詩家(詩人である私の家)にあらん)
こちふかば にほひ おこせよ 梅の花
君がすむ やどのこずゑを ゆくゆくと
2月25日九州の大宰府で死んだ。和漢の学に通じた平安朝の代表的文学者。右大臣になったが藤原氏に憎まれて左遷された。天満宮は彼をまつる。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.33 参考:写真は岸和田市土生町:「土生神社 御祭神」 2010.02.25 |

▼『枕草子』(一〇〇一ころ) 〔一〕 春はあけぼの。やうやうしろくなり行く、山ぎはすこしあかりて、むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。 夏はよる。月の頃はさらなり、やみもなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただひとつふたつなど、ほのかにうちひかりて行くもをかし。雨など降るもをかし。 秋は夕暮れ。夕日のさして山のはいとちかうなりたるに、からすのねどころへ行くとて、みつよつ、ふたつみつなどとびいそぐさへあはれなり。まいて雁(などのつらねたるが、いとちひさくみゆるはいとをかし。日入りはてて、風の音むしのねなど、はたいふべきにあらず。 冬はつとめて。雪の降りたるはいふべきにあらず、霜のいとしろきも、またさらでもいと寒きに、火などいそぎおこして、炭もてわたるもいとつきづきし。晝になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶(の火もしろき灰がちりになりてわろし。(岩波文庫)P.19 「つとめ」という言葉は、『万葉集』では、自力で骨を折って事をするという意味である。「明らけきなに負ふ伴(とも)の男(を)心つとめよ」(りっぱななを背負っている家来たちよ、心をはげまして一生懸命やりなさい)と使う。また、『源氏物語』などでは、朝夕の仏道の勤行を「つとめ」といっている。しかし『枕草紙』の有名な「春はあけぼの。夏は夜」の続きには、「冬はつとめて」と書いてある。「つとめ」とは、朝早くの意味であり、雪の朝など寒いときに、急いで火をおこして、炭を持って廊下を渡っていくのも、いかにも冬の早朝にふさわしい景色だと清少納言は言っている。つまり「つとめて」は、一方では自力で骨を折って精を出すことを意味し、他方では、朝早くという意味になっている。:大野 晋著『日本語の年輪』(新潮文庫)P.134P.134:23.01.12に追加 〔四十二〕 あてなるもの あてなるもの 薄色に白襲(の汗衫(。かりのこ。削(り氷(にあまづら入(い)れて、あたらしき金鋺(に入れたる。水晶(の数珠(。藤の花。梅の花に雪の降りかかりたる。いみじううつくしきちごの、いちごなどくひたる。P.75 [現代語訳] 上品なもの。薄紫の袙(上着と肌着の間に着る内着)の上に白い汗衫をかさねたの。 カリの卵。 かき氷に甘いつゆをかけて新しい金の器に入れたの。 水晶の数珠。フジの花。ウメの花に雪が降りかかっているの。 とてもかわいらしい子供がイチゴなどを食べているの。 〔一六五〕 讀經は不斷經 P.223 読経は、不斷經(がもっとも尊い。 不斷經というのは、ある期間、多数の僧侶が交代で日夜途切れることなく経典を読み続ける修法(ズホウ)のことをいいます。願の軽重により、七日、二十一日、三十日などがあったようです。 想像しますと、凄まじいまでの願掛けです。 枕草子を見る限り、冷静理知的な部分が多くみられる少な言さまですが、このような神や仏と接しあっているような社会に生きていたのです。 |
 ▼『方丈記』(日本古典文学大系)(岩波書店)
▼『方丈記』(日本古典文学大系)(岩波書店)
一 ゆく河の流(れは絶(た)えずして、しかも、もとの水にあらず。淀(よど)みに浮(うか)ぶうたかたは、かつ消(き)えかつ結(むす)びて、久しくとゞまりたる例(ためし)なし。世の中にある人と栖(すみか)と、またかくのごとし。
四 夫(それ)三界は只心ひとつなり。心若(もし)やすからずは、像目(ぞうめ)・七珍(しつちん)もよしなく、宮殿・楼閣も望(のぞ)みみなし。今さびしきすまひ、一間(ひとま)の菴(いほり)、みづからこれを愛す。 P.43 五 抑(そもそも)、一期の月影(かげ)かたぶきて、余算、山の端(は)に近(ちか)し、たちまちに三途(さんず)の闇(やみ)に向(むか)はんとす、何(なに)のわざをかかこたんとす。仏(ほ)の教(おし)へ給ふおもむきは、事にふれて執心(しゅしん)なかれとなり。今、草菴(さうあん)を愛(あい)するともとがとす。閑寂(かんせき)に著(ぢやく)するもさはりなるべし。いかゞ要(えう)なき楽(たの)しみを述べて、あたら時をすごさむ。 P.44
▼当時は、京の街は戦乱につぐ戦乱で焼き払われ、その上に二回もの大震災に合い、疫が流行り、悲惨な情況が続き、人々の心は荒廃しきっていました。。街は無数(4~万人)の死骸から発生する異臭で、満ちていたと記されています。さながら地獄の情況を呈していたと思われます。
長明の父祖は代々鴨の社の神官であった。長明は、早くからこの社の禰宜になりたい希望を持っていた。しかし庇護者の二条天皇の中宮高松女院が亡くなり、つづいて父長継(ながつぐ)を失い、希望はかなえられなくなった。
尾場暢殃 加藤中道館『方丈記精釈(全)』から抜粋、参照。 ★リンク:鴨長明と方丈の庵 ※関連:田辺聖子『文車日記』―私の古典散歩―ゆく河の流れ(方丈記)
春秋 2016/12/28付 鴨長明は『方丈記』に、平安京を襲った大火のありさまを生々しく描いている。1177年4月、強風すさぶ夜の記録だ。都の東南から出た火はあっという間に官庁街に及ぶ。空は真っ赤に染まり「吹き切られたる焔(ほのお)、飛ぶがごとくして一、二町を越えつつ移りゆく」。 ▼炎は建物を次から次へとのみ込んでいくだけでなく、風に乗って「飛ぶ」。その恐ろしさを長明は克明に記したわけだ。火の玉が100メートルも200メートルも遠くに飛び、あちこちで新たな出火を引き起こしたのだろう。それと同じ光景を新潟県糸魚川市の大火は見せつけた。焼失面積4ヘクタール。「飛ぶ炎」の目撃証言が少なくない。 ▼そういう魔物の襲来にひとたまりもない木造建築の密集ぶりも、往時とあまり変わらないのかもしれない。消防能力は平安時代とはまるでちがうはずだが、入り組んだ細い路地は消火活動を妨げて災いを広げた。同様の場所は日本中にあるという。東京では山手線の外側がドーナツ状の巨大な木造住宅密集(木密(もくみつ))地域だ。 ▼そこに住むのは生身の人間だから、あれこれ対策は練られていても簡単には進まない。とはいえ放っておけば、将来どんな災厄を招くことだろう。『方丈記』はその前半が当時のさまざまな災害のルポであり、作者が無常観を深めていく背景をなす。800年余を経た現代の社会が、よもやそんな諦念を抱いてはなるまい。 2016.12.19、89歳 |
☆05『平家物語』(1,221年以前)
|
一、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり、沙羅雙樹の花の色、盛者必衰の理(をあらはす。驕れる者久しからず、ただ春の夢の如し。猛(たけ)き人もつひに滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。 二、あはれ、弓矢取る身ほどくちおしかりける事はなし。武芸の家に生まれずば、なにしに、たゞ今かゝる憂き目をば見るべき。情なうも討ち奉つたるものかな。敦盛最後の事(『平家物語下巻』(角川文庫)P.105)
あることのはじまりは、あることのおわりであり、逆もまた然りとするなら、私が予感とともに待ち受けているのは、まさしくこの世の無常の姿、いのちを享(う)けたものすべてがたどる一栄一落の有様以外のものではない。『平家』を読む。このとき、かすかな胸さわぎが絶えないのは物怪(もつけ)の幸いである。 『平家』冒頭の誰でも知っているくだりは、これから語り出されるものをよく聴き給えということを、ああいう喩(たと)えで語りだしたのである。天竺というおそろしく遠い国の、奥も知れない林のなかに埋もれてしまって、たしかめようもなくなった祇園精舎から、どこからとも吹く世外の風に乗り、はるばる鳴りわたってくる鐘の声。どんなものより近い自分の肉体という場にたしかめることのできる胸のざわめき。相隔たる最も甚だしいこのふたつが、時として、ひとつにかさなるのは、念仏を唱える人の両のてのひらが合わされるのと同じくらいに自然なことではないでしょうか。いま、耳の底にかすかに鳴っているものを「祇園精舎の鐘の声」と思うなら、たしかにそれは「諸行無常の響きあり」である。私の胸のなかにあって、瞬時も鼓動してやめないものも、いずれは停止する。これほどたしかなことはない。胸の鼓動が諸行無常の音となって聞こえはじめたにしても、わが耳を咎め立てることはない。いずれ、ほどなく、諸行無常という唱え声よりも、もっと耳をそばだてて聴かずにいられないものが、琵琶の響きとともに次から次にとあらわれてくるだろう。耳をせいぜい敏感な状態に保っておくこと。この用心を忘れぬことにしよう。 だが、聞こえてくるものに聴き入れる用意をととのえていると、も一方では、見えてくるものに目をとめよという声もまた耳に入る。動くものはいうまでもない。動不動にかかわらず、色あるものの色、彩りに目をとめるべし、とその声は告げている。冒頭のくだりを念のために引き写すと、 祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰(じょうしゃひつすい)のことわりをあらわす。 おごれる人も久しからず、只春の夜(よ)の夢のごとし、たけき者も遂にはほろびぬ、偏(ひと)へに風の前の塵に同じ。 はじめに音を言い、諸行無常を言ったあとで、色を言い盛者必衰を言うのは、勿論、対句にもとづいてのことである。仏教説話によれば、釈迦がクシナガラで二本の沙羅の木のあいだに横臥して涅槃(ねはん)に入ったとき、淡黄色の沙羅の花が白変した。そこで釈迦の入滅の地を白鶴に喩て鶴林と称する。いのちの果てで白く色あせたものも、もとはそれぞれのいのちの色に燃えていたのに、と対句後半は言いたいらしい。 白が地の色として布(し)かれたことが大事なことである。この白地は、のちの物語に、あでやかな色、きらびやかな色、猛々しい色、しっとりと落ちついた色、物さびた色、重く沈んだ闇の色が、それぞれに映え出す用意なのだとなつ得される。のちの物語を絵巻物のように楽しむつもりなら、霧にとざされた冬の朝のように白いだけの世界を、つとめて思いえがくに限るだろう。しかし『平家』が昔の絵師たちを誘惑し、近代、当代の画家たちに格好の画題を提供し、えがかれた絵が人を魅了するのも、あるいは白変した沙羅の花の色が、われわれの眼底に染みとおっているからなのかも知れない。自然界が人界の異変に感染して示した一瞬裡の白変は、いつしかわれわれに無常を悟らせ色となり、すべて色あるものの示す色はやがて無常の白変を蒙り、ただ追憶のなかに再生する限りにおいて、もとのいのちの色を回復する。この経緯に注目すれば、『平家』が絵巻物あるいは大小の画面よりも能舞台に、もっと多くの主題を提供し、あんなに多くの主人公たちを幽明の境に出没させるにいたったことに、何ら不思議はないように思われる。
『平家』巻頭の「祇園精舎」は、ほどなく調子をあらためて、天下の乱れを招き「ひさしからずして、亡じにし」高位高官の例をまずは「遠く異朝」にたずね求めて中国の諸例を挙げ、次いで近く本朝をうかがふに、承平の将門(まさかど)、天慶(てんぎょう)の純友(すみとも)、康和の義信(ぎしん)、平治の信頼(しんらい)と並び立てたあとに、「まぢかくは、六波羅の入道前太政(さきのだいじょう)大臣平朝臣(あそん)清盛公ともうしし人のありさま、伝え承るこそ心も詞も及ばね」と、話題を清盛のことに絞る。この人、桓武天皇の第五皇子を祖とし、それより九代の後胤になるという。祖父は讃岐守正盛、父は刑部卿忠盛。「かの親王の御子高見の王、無官無位にしてうせ給ひぬ。その御子高望(たかもち)の王の時、初めて平の姓をたまはつて、上総介(かずさのすけ)になり給ひしより、忽ちに王氏を出でて人臣につらなる。」高望の王の子よりのち、清盛の祖父正盛にいたるまで「六代は諸国の受領たりしかども、殿上の仙籍をばいまだ許されず。しかるを」と一転した物語は、これより清盛の父忠盛が昇殿を許された次第に移る。撥(ばち)の音にわかに高く、息使い切迫して、せわせわしい。
参考:『平家物語を読む』 ※関連:田辺聖子『文車日記』―私の古典散歩―知盛最後(平家物語) 2015.09.17 |
☆06 兼好法師(1,283~1,350年)
|
▼『徒然草』(日本古典文学大系) つれづれ草 上 序 段 つれつれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるはしけれ。 平成二十年二月十日 第三十段 人の亡きあとばかり悲しきはなし。中陰のほど、山里などにうつろひて、便あしく狭(き所にあまたあひゐて、後のわざども営みあへる、心あわたゝし。日かずのはやく過(ぐ)るほどぞ、ものも似ぬ。はての日は、いと情なう、たがひに言ふ事もなく、我賢(かしこ)げに物ひきしたゝ、ちりぢりに行(き)あかれぬ。もとのすみかに帰りてぞ、更に悲しき事は多かるべき。「しかしかのことは、あなかしこ、跡のため忌むなる事ぞ」など言へるこそ、かばかりのなかに何かはと、人の心はなほうたておぼゆれ。 第三十五段 手のわろき人の、はばからず文書をちらすはよし。見ぐるしとて、人に書かするはうるさし。 第六十二段 延政門院いときなくおはしましける時、院へ参る人に御言つてとて申させ給ひける御歌、 ふたつ文字牛の角字直ぐな文字 歪文字とぞ君は覚ゆる 恋しく思ひ参らせ給ふとなり。 ※参考;淮陰子、愛誦歌あれこれ(五) 第七十四段 蟻のごとくに集まりて、東西に急ぎ、南北に走(わし)る。高きあり、賤きあり。老いたるあり、若きあり。行く所あり。帰る家あり。夕に寝(い)ねて、朝(あした)に起く。いとなむ所何事ぞや。生(しよう)をむさぼり、利を求めて止む時なし。 身を養ひて何事をか待つ。期(ご)する處、たゞ老と死とにあり。その来る事速やかにして、念々の間に止まらず、これを待つ間、何のたのしびかあらん。惑(まど)へるものはこれを恐れず。みょう利に溺れて先途(せんど)の近き事をかへり見ねばなり。愚かなる人は、またこれを悲しぶ。常住(じょうじゅう)ならんことを思ひて、変化(へんげ)の理(ことわり)を知らねばなり。 第七十五段 つれづれわぶる人は、いかなる心ならん。まざるゝかたなく、たゞひとりあるのみこそよけれ。 世にしたがへば、心、外の塵に奪はれて惑ひやすく、人に交(まじは)れば、言葉よその聞きに随ひて、さながら心にあらず。人に戯(たはぶ)れ、物に争ひ、一度(ひとたび)は恨み、一度は喜ぶ。その事定まれる事なし。分別みだりに起りて、得失止む時なし。惑ひの上に酔へり。酔の中に夢をなす。走りて急がはしく、ほれて忘れたる事、人皆かくのごとし。 いまだ誠の道を知らずとも、縁を離れて身を閑(しずか)にし、事にあづからずして心やすくせんこそ、暫く楽しぶとも言ひつべけれ。「生活・人事・伎能・学問等の諸縁を止めよ」とこそ、摩訶止観(まかしくわん)にも侍れ。 第九十三段 「されば、人、死を憎まば、生(しやう)を愛すべし。存命(ぞんめい)の喜び、日々に楽しまざらんや。愚かな人、この楽しびを忘れて、いたづがはしく外の楽しびを求め、この財(たから)を忘れて、危ふく他の財を貪るには、志、満つ事なし。生ける間生を楽しまずして、死に臨みて死を恐れば、この理あるべからず。人皆生を楽しまざるは、死を恐れざる故なり。死を恐れざるにはあらず、死の近き事を忘るゝなり。もしまた、生死の相にあずからずといはば、実(まこと)の理を得たりといふべし」といふに、人、いよいよ嘲る。 第百八段 されば道人は、遠く日月を惜しむべからず、ただ今の一念、むなしく過ぐることを惜しむべし。 第百九段 高みょうの木のぼりといひしをのこ、人を掟(おき)てて、高き木にのぼせて梢を切らせしに、いと危(あやふ)く見えしほどはいふ事もなくて、降るゝ時に、軒長(のきたけ)ばかりに成りて、「あやまちすな。心して降りよ」と言葉をかけ侍(り)しを、「かばかりになりては、飛(び)降るとも降りなん。如何(いか)にかく言ふぞ」と申し侍りしかば、「その事に候(さうらふ)。目くるめき、枝危きほどほどは、己が恐れ侍れば申さず。あやまちは、やすき所に成りて、必ず仕る事に候」といふ。 第百十七段 友とするにわろき者、七つあり。一つには、高くやん事なき人。二つには、若わかき人。三つには、病ひなく身強き人。四つ)には、酒を好む人。五つには、たけく勇(め)る兵(つはもの)。六つには、虚言(そらごと)する人。七つには欲ふかき人。 よき友三つあり。一つには、物くるゝ友。二つには医師(くすし)。三つには、知恵ある友。 参考:朋友 第百二十三段 無益(むやく)のことをなして時を移すを、愚(おろか)なる人とも、僻事(ひがこと)する人とも言ふべし。国のため、君のために、止やむことを得ずして為すべき事多し。その余りの暇(いとま)、幾(いくばく)ならず。思ふべし、人の身に止むことを得えずして営(いと)なむ所、第一に食ふ物、第二に着る物、第三に居(ゐる)所なり。人間の大事、この三つには過ぎず。饑(う)ゑず、寒からず、風雨に侵(をか)されずして、閑(しづか)に過すを楽(たのしび)とす。たゞし、人皆病あり。病に冒をかされぬれば、その愁忍び難し。医療を忘るべからず。薬を加へて、四つの事、求め得ざるを貧しとす。この四つ、欠けざるを富めりとす。この四つの外を求め営むを奢おごりとす。四つの事倹約ならば、誰の人か足たらずとせん。 私見:年配者はこの四つで十分であると思う。それが難民などに求めることが出来ない人たちをなんとかしたいものである。 ※小島直記著『回り道を選んだ男たち〔養生の本〕に中野孝二次著『神々の谷』を紹介している。その中の記事に142段が記載されている。2022.03.01記す。 2010.03.16 つれづれ草 下 第百三十七段 若きにもよらず、強きにもよらず、思いかけぬは死期なり。 第百四十段 身死して財(たから)残る事は、知者(ちしゃ)のせざる処なり。よからぬ物たくはへ置(き)たるもつたなく、よき物は、心をとめけんとはかなし。 第百八十八段 一事を必ずなさんと思はば、他の事のやぶるゝをいたむべからず。人の嘲りをも恥ずべからず。 第百五十五段 死期(しご)はついでをまたず。死は前よりしも来たらず、かねて後ろに迫れり。人皆死ある事を知りて、まつことなし、しかも急ならざるに、覚えずして来る。沖の干潟(ひかた)遥かなれども、磯より潮の満つるが如し。 第二百二十六段 後鳥羽院の御時、信濃前司行長(しなのぜんじゆきなが)、稽古の誉ありけりが、楽府の御論議(みろんぎ)の番(ばん)にめされて、七徳(しちとく)の舞をふたつ忘れたりければ五徳の冠者(くわじゃ)と異名をつきにけるを、心うき事にして、學問をすてて遁世(とんせい)したりけるを、慈鎮和尚(じちんおしょう)、一藝あるものをば、下部(しも べ)までも召しおきて、不便にさせ給(ひ)ければ、この信濃(の)入道を扶持(ふじ)し給(ひ)けり。 この行長入道、平家物語を作りて、生佛(しやぶつ)といひける盲目に教(へ)て語らせけり。さて、山門のことを、ことにゅゝしく書けり。九朗判官(くろうほうがん)の事はくはしく知(り)て書(き)のせたり。蒲冠者(かばのくわんじゃ)の事は、よく知らざりけるにや、多くのことゞもしるしもらせり。武士の事・弓馬(きゅうば)のわざは、生佛、東国の者にて、武士に問(ひ)聞(き)て書かせけり。かの生佛が生まれつきの聲を、今の琵琶法師は學びたるなり。 私見:『平家物語』の作者を知ることができた。2015.09.27 第二百四十三段 八つになりし年、父に問ひて云はく、「仏は如何なるものにか候ふらん」といふ。父が云はく、「仏には人のなりたるなり」と。また問ふ「人は何として仏には成り候ふやら」と。父また、「仏のをしへによりてなるなり」とこたふ。またとふ、「教へ候ひける仏をば、なにがをしえ候ひける」と。また答ふ、「それもまた、さきの仏のをしへへによりて成り給ふなり」と。またとふ、「その教へはじめ候ひける第一の仏は、如何なる仏にか候ひける」といふ時、父、「空よりやふりけん、土よりやわきけん」といひて、笑ふ。「問ひつめられて、え答へずなり侍りつ」と、諸人にかたりて興じき。 2000.02.10 |
☆07 足利尊氏文武両道は、車輪の如し(1,305~1,358年)
|
足利尊氏といえば、戦闘を終えて凱旋してしてくる勇壮な武将ぶりを描いた画像が伝えられている。尊氏の子義詮の花押(のあるこの画像のなかの尊氏は、大鎧を着て兜をぬいだ乱髪で、逸(りたつ黒馬にまたがり、抜き放った大太刀を右肩にかついでいる。背の箙((矢を入れる具)の六本の矢のうち一本が折れているのも、戦いの激しさを物語っている。見る者を魅(きつけるのは、その表情である。馬上で揺れる髪、ひろい額の下の太い眉、精悍な大きな目、黒々とした口ひげ、顎ひげ、大きく見ひらいたその眼差しは、なにを瞶(めているのであろうか。 
足利氏の祖は、八幡太郎源義家の第三子、源義国の晩年、足利の別業(別荘)にこもり、その次男の源義康が足利の庄を伝領したことからはじまる。 のちに室町幕府の創設者になる尊氏(別名を高氏)はこの直系、足利貞氏(さだうじ)の嫡男として生まれている。 こ足利氏の氏寺である鑁阿寺(は、 「天下を取れなかった八幡太郎義家が、七代目の子孫に生まれかわって、かならず天下を取る」 といった『鑁阿寺の置文((遺言状)』 そしてその義家から数えて五代目の足利義氏のとき、機会がやってきた。鎌倉の三代将軍源実朝が、鶴岡八幡宮で暗殺され、頼朝系の血統が絶えた。源氏の嫡流から後継者を選ぶとすれば、足利義氏こそ最有力の候補者であろう。 しかし、その期待は空しかった。 頼朝の外戚でしかない北条氏が、名目だけの将軍を京都から迎え、その実権を握り、みずから執権(幕府長官)として勢威大いにふるったのである。 こうして足利一族の不満のうちに時が流れ、七代目の足利家時の代になったとき、北条氏い膝を屈しているわが身に堪えられなくなった家時は、 「わが命にかえて、三代目の子孫に天下を取らせしめたまえ」 と置文して、割腹して果てた(『難太平記』今川了俊)。 高氏はその家時から三代目にあたる。 鎌倉幕府の御家人(直属の臣)として歴々の陽のあたる場所にいたとはいえ、高氏というそのなも、執権、北条高塒から一字与えられたものだ。 この足利一族の「源氏再興」の悲願を背負った高氏が、動乱の『太平記』の世界に登場してくるのは、二十七歳の時である。 「天皇ご謀反!」 皇居を脱出して笠置山にたてこもった後醍醐天皇討伐のため、高氏は幕府の大将軍として出陣。世にいう元弘の変でる。
以来、高氏の行動は背信、変節いとまない騒乱のなかで転々とする。 昨日の味方が今日の敵となり、一門一族のなかでも我欲おもむくままに裏切り、殺し合い、血で血を洗うような修羅の世界であった 当時のこの武士たちの向背、去就ただならぬ世相を語るものに《降参半分ノ法》というのがある。いったん裏切っても、状況不利とみれば降参すればよいのだ。「降参人は、所領の半分または三分の一を差出して詫びを入れれば、首まで取られることはない」という慣習が立法化されていたから、簡単に裏切り、寝返りをくり返していた。 元弘三年、笠置で捕えられ隠岐(島根県)に流された後醍醐帝はふたたび脱出。後醍醐帝軍を討つことを命じられた高氏は、ひそかに後醍醐帝の綸旨((みことのり)を得て丹波、篠村八幡宮で鎌倉幕府に反旗をひるがえして、軍を反転して六波羅探題を討ち、北条一族を滅亡にみちびいた。高氏は、殊勲第一の者として鎮守府将軍に任ぜられ後醍醐帝の尊治(の一字を賜わり尊氏と改名する。 けれど、尊氏はほどなく後醍醐帝と対立し、持明院の豊仁(親王をかつぎ皇位につけ、光明天皇として遂に足利十代にわたる悲願であった足利幕府を樹立する。 尊氏の来歴を駆け足で眺めてくると、いかにも乱世の梟雄(といった面だましが泛びあがってくるが、現実の尊氏は、名門の嫡男らしい、どこか芒洋としたところのある御曹司であった。 尊氏をよく知る臨済宗の禅僧、夢窓疎石の尊氏評によると、かれのすぐれたところが三つあり、 「第一に、戦場にのぞんで咲((微笑)をうかべて畏怖する様子がない。第二に、生まれつき慈悲ぶかく、人を憎悪するところがない。怨敵でさえ、わが子に接する如くおだやかな目でみる。第三は、お心大きく、国でも所領でも、金銀や武具、馬でも惜しげもなく人びとに与えた」 という。 そんな尊氏のやさしさと教養の深さをうかがわせるのが、光明天皇を即位させた二日後、清水寺におさめた見事な筆跡の「願文」である。 《この世は夢のごとくに候。尊氏にだう(道)心たば(賜)せ給(候て、後世たすけさせ在(しまし候べく候。猶々(とく(疾)とんせい(遁世)したく候。だう(道)心たば(賜)せ給候べく候。今生(のくわほう(果報)にか(代)へて、後生たすけさせ給候べく候て、直義あんをん(安穏)にまもらせ給候べく候。》 建武三年八月十日 尊氏 (花押)清水寺》 この修羅の世はまさに悪夢のようだ、と嘆じた尊氏は、せめてあの世に赴いたとき、迷い多い私を救うてくだされ、この世での果報というものがあれば、弟の直義に与え、直義を穏やかにすごさせてくだされ……という尊氏の念(いはやさしい。
(等持院(尊氏)殿百首) こうした尊氏の魅力は、勝ち戦よりも退却の場合に、より濃くあらわれてくる。当時の、欲望をぎらつかせた将兵たちは、ひとたび退却するとなると雲散霧消、まるで春の大潮が引いていくように、数万あった軍団もたちまち、わずか十数騎などといった惨憺たる有様になるのが常であった。が、戦いに利なく尊氏が九州へ落ちていった時など、その悠々たる態度と、勝利に逆転した場合の「呉れっぷり」のよさが人心を集め、やがて九州から巻き返しにでて東上し、逆寄(する尊氏軍は、各地から駆けつけた将兵で雪だるまのようにふくれあがり、これが湊川で楠木正成を打ち破り大勝利になったことは、すでに世間周知のことであろう。 尊氏は最晩年の延文二年(一三五七)二十一箇条からなる『等持院御遺言殿』を書き残している。 《文武両道は、車輪の如し。一輪欠ければ人を度(さず》 国を治めるものは学問を身につけるべきである。とはいえ、戦だけを働きとする武者には学問などは無用である。 《五兵にたずさわる者に、文学は無用なるべし》 刀など五種類の武器をもって戦う男たちに学問は無用。生かじりの学問をもてあそべば、口先ばかり達者で心正しからざる《侫者(》となる者多し、心得るべきことだと、尊氏は説(う。》 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.176~181 2021.05.24記 |

1、秘すれば花なり。秘せずば花なるべからず。 ▼田中 裕 校註『新潮社古典集成:世阿弥芸術論集』(新潮社)養和五十一年九月十日 発行 『風姿花伝』より このころの能、盛りの窮めなり。ここにて、この條々を窮め悟りて、堪能になれば、さだめて、天下に許され、名望を得(う)べし。もし、この時分に、天下の許されも不足に、名望も思ふほどなくは、いかなる上手なりとも、いまだ、まことの花を窮めぬ為手と知るべし。もし窮めずんば、四十より能は下がるべし。それ、後の證據なるべし。 さるほどに、上がるは三十四、五までのころ、下がるは四十以来なり。かへすがへす、このころ、天下の許されを得ずば、能を窮めたりとは思ふべからず。 ここにてなほ慎むべし。このころは、過ぎしかたをも覚え、また行くさきの手だてをも悟る時分なり。このころ窮めずば、この後天下の許されんを得んこと、かへすがへすかたかるべし。P.20 一 この別紙の口伝、当芸において家の大事、一代一人の相伝(そうでん)なり。たとへ一子たりといふとも、無器量(ぶきりょう)の者には伝ふべからず。「家、家にあらず、次ぐをもて家とす。人、人にあらず、知るをもて人とす」といへり。これ、万徳了達(ばんとくれうだつ)の妙花を窮むるところなるべし。 *『風姿花伝』の最後に記録されている。P.98 ▼『花 鏡』より 1:動十分心 動七分身(十分に心を動かして、身を七分に動かせ)。 「心を十分に動かして、身を七分に動かせ」とは、習ふところの手をさし、足を動かすことは、師の教えのままに動かして、その分をよく為(し)窮めて後、さし引く手をちちと、心ほどには動かさで、心よりうちに控ふるなり。これは、必ず舞・はたらきにかぎるべからず。立ちふるまふ身づかひまでも、心よりは身を惜しみて立ちはたらけば、身は体になり、心は用(ゆ)になりて、面白き感あるべし。P.118 2:劫之入(る)用心之事 この芸能を習学して、上手のなを取りて、毎年を送りて、位の上がるを、よき劫(こふと申すなり。しかれどもこの劫は、住所によりて変るべきことあり。 名望を得ること、都にて褒美を得ずはあるべからず。さようの人も在国して、田舎にては、都の風体を忘れじとする劫ばかりにて、結句、よきことを忘れじ忘れじとするほどに、少な少なとよき風情の濃くなるところを覚えねば、悪き劫になるなり。これを住劫と、きらふなり。(中略) しかればよきほどの上手も、年寄れば古体になるとは、この劫なり。人の目にはみえて、きらふことを、われは昔よりこのよきところを持ちてこそなを得たれと思ひつめて、そのもまま、人のきらふことも知らで、老の入舞(いりまひ)を為搊ずること、しかしながらこの劫なり。よくよく用心すべし。
*:1、劫…もともと仏語で、計りしれない遠大な時間のことであるが、これは転じて長年月にわたる修練の成果。年功の意。
3:初心忘可ず
老後の初心を忘るべからずとは、命には終はりあり、能には果てあるべからず。その時分時分の一体一体を習ひわたりて、また老後の風体に似合うことを習ふは、老後の初心なり。老後、初心なれ、前能(ぜんのう)を後心(ごしん)とす。五十有余よりは、「せぬならでは手だてなし」といへり。せぬならでは手だてなきほどの大事を老後せんこと、初心にてはなしや。 さるほどに一期(いちご)初心を忘れずして過ぐれば、上がる位を入舞(いりまひ)にして、つひに能下がらず。しかれば能の奥を見せずして、生涯を暮すを、当流の奥義(おうぎ)、子孫家訓(ていきん)の秘伝とす。この心底(しんてい)を伝ふるを、初心重代相伝の芸案とす。初心を忘れずして、初心を重代すべし。P.159 舞は音声(おんじやう)より出でずれば、感あるべからず。一声(いつせい)のにほひより舞へ移る堺(さかひ)にて、妙力(めうりき)あるべし。また舞ひをさむるよころも、音感へをさむる位あり。(中略) また舞に、目前心後といふことあり。「目を前に見(つけ)て、心を後に置け」となり。これは以前申しつる無智風体(ふうてい)の用心なり。見所(けんじょ)より見る所の風姿は、わが離見(りけん)なり。しかればわが眼(まなこ)の見るところは、我見(がけん)なり。離見の見(けん)にはあらず。離見の見にて見るところは、すなはち見所同心の見なり。その時は、わが姿を見得するなり。P.124
上手にもわるき所あり。へたにもよき所かならずあるものなり。これをみる人もなし。主もしらず。上手はなをたのみ、達者にかくされてわるき所しらず。へたはもとより工夫なければ、わるき所をもしらねば、よきところのたまたまあるをわきまえず。されば上手も下手も、たがいに人にたずぬべし。(花鏡)
この日(6月17日)*日本能楽の完成者。観阿弥の子。天才的演技者で、同時にすぐれた作者として現行曲の過半数をつくった。ほかに理論書が多い。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.100 ▼世阿弥、佐渡に流される:世阿弥が佐渡に流されたのは永享(一四三四)五月のことで、理由はやはり分からないが、おそらく元重(世阿弥の弟で観世座の庶流であった四郎の子であるが、早くから世阿弥に認められて、その指導をうけた)に対してその後も変らない狷介(けんかい)さが、ついにこの偏執狂的な将軍(足利義教)の勘気にふれたのであろう。在島の作品としては、配流途上の風物や謫所(たくしょ)の生活・感情を謡った小謡(こうたい)集『金島書(きんとうしょ)』が残っており、ほかに金春氏信に送った自筆書簡一通も現存する。(中略)やがて赦免をうけて帰洛したという伝えもある。 参考:吉田東吾の業績としては、ほかに能楽研究がある。この方面でも『花伝書』を含む世阿弥の遺著十六部を発見、甲注本を出すなどの巨歩を残した。紀田順一郎『知の職人たち』P.38 |
|
にんげんには、誰でも口癖がある。 古典落語の名人といわれる桂文楽は機嫌のよいときはいつも、 「あぱらかべっそん」 などと意味不明の言葉を呟いたというし、洋酒の寿屋の創業者鳥井信次郎は、「やってみなはれ、やらなわかりしまへん」 が口癖であった。 サムライの世界では、柳生家の高弟、高田三之丞などはちょっと変っている。道場にでて試合相手に袋竹刀をかまえると、 「おいとしぼう、おいとしぼう」 と叫んで斬撃した。 」 高田の尾張方言を訳してみると、「おいたわしや、おいたわしや!」だから、対峙した相手にすれば嫌な気分になる。 鎌倉幕府の執権、北条泰時の口癖は、 《道理ほど面白きものはなし》 であり、感激したときや嬉しい時など、しばしばこの言葉を口にしていたという。そして驚いたことに泰時は、この口癖である「道理」を中心にして、日本最初の『貞永式目』をつくりあげてしまったのである。 これから述べようとするのも、中央政界きっての傍若無人ぶりを発揮し、あくのつよさで室町幕府の政所執事から殿中惣奉行にのしがり専横をきわめた伊勢貞親(一四一七~七三)が、口癖のように洩らしつづけ、書き残した『為愚息教訓一札』である。 高望王の後裔伊勢氏は足利尊氏の父、貞氏から一字を与えられるほどの家系で、代々この"貞"の一字を継いで室町幕府に出仕し、故実(昔の伝統、作法、習慣など)師範として将軍家嫡子の養育係をつとめている。 貞親もまた家職をついで六代将軍足利義教に仕え、伊勢家で育てた義成(のち義政)が八代将軍になるに及んで、 《幕府(義政)貞親を呼びて父と云い其の妾を母と称すと云う》(『続本朝画史』) と信任されたことをよいことに、義政夫人、日野富子らと結んで専横をきわめ、将軍家の後嗣問題に介入、足利義視の暗殺をくわだてる。 この事件が応仁の大乱の点火薬になる。貞宗が父の、あまりの横暴ぶりを見とがめて泣いて諫言し、かえって怒りをかい勘当されるということがあったのは、この時である。 はたして、貞宗が危惧したように貞親は山な宗全に憎まれ、 《貞親(は山なを)懼れて遁走し蹤(蹤跡・ゆくえ)を晦ます》(『同前』) という破目になる。貞親失脚のあと貞宗は、おだやかで堅実な人柄と穏健な政治力をかわれ、義政の命をうけて政所執事となり、かねてから養育の任にあたっていた義政の子、九代将軍義尚を後見し、応仁の乱とその後の難局を乗りきった功績は大きい。この貞宗はまた、伊勢流武家故実の大成者としての評価も高い。 だが、器量ゆたかな貞宗でも、父の貞親の眼からみれば、世間知らずで頼りなげに思われたのであろう。前述の"愚息"のための三十八ヵ条にも及ぶ教訓を語り授けている。その中から幾つかを抜き書きしてみると、 《一、いずくよりも珍物到来せば多少によらず進上いたすべき也。殊に初物などは一ツ二ツ(だからこそ)其の興あり。予、若年の比小笠原大中に或る人茄子の初物を数十送りしを則進上す。十の中を三つ進上したるを、同名(の)備前(という人が)何と十ながら進上なきぞといいければ、初物などは多く進上せぬもの也。少を興にすると申し、尤もの事也》 たくさん手元にあっても初物などは少量進呈するほど珍重されるものだ、というところなど、贈物のコツを語って見事である。
《一、人に酒などすすむる事、第一にちかづく媒となるなり、あながち其(酒)にふける心はなけれども、風情あれば人もこぞり無音も知音に(近づきのなかった人とも親しく)成、友(として)したしむ。外聞もよき也。汝(貞宗)ごときの者は、ただ上意(将軍)を始め奉り田夫に至迄わろ(悪)くいわれぬ第一詮
数多い訓 《一、上意のよきもの(将軍の覚えよき人)又は(将軍と)くちなどきくものとは常によんで(招待して)知音(親しく)して物をもとらす(贈り物をする)べき也。かようなればいうべき事をもいわずかたうどになる物なり(だまっていても味方になってくれるものだ)》
《一、いかなる不肖の者尋来ともかろがろ出 とるにたらない身分の者が訪ねてきても、気軽に会ってやれ。わざわざ訪ねてきて、会えずに帰るは残念に思うものだ。このようなことをつづけておれば、大事な人も疎遠になっていくものである。そうした人たちが世間に悪評をふり撒き、またそれを小耳にはさんで悪い噂をひろげていく。たとえ病床にあっても、寝巻のままでも会ってやれば人というものはよろこぶものだ。
《一、いかに気にあわざる者来たり共可対面
《一、人と知音するには、兼好法師がいえるごとく無能なる者と寄合う事何の詮かあらん。雑談にもかようの者は人の上さ(噂)や賤 無能だと言っても、極心(誠実)な者は自分の鏡ともなるし、又、酒宴などで座持ちのよい男も大事ゆえ、目をかけてやるがよい。 こうした貞親の訓戒は三十八ヵ条の中には、平成の時代にも通用するような事例が多い。貞親はすべてを語りおえたあと、次のように結んでいる。 《右条々、子を思う心の闇にくらまされて暁のねぶり(眠り)をすますごとにおもい出る事どもつくすなる心に、猶おろかなる筆にまかせて貞宗に与え侍る。もとよりいましめのためなれば他人の一覧におよぶ事あるべからず。 子をおもう親の心の闇晴ていさむる道にまよわずもがな
于時 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.261~265 2021.06.18記 |
|
戦国乱世の"下剋上"ぶりを絵に描 当時、敏景のために所領を掴み取られた都の公卿たちは、黒けむりをあげんばかりの悪罵酷評を敏景に浴びせかけている。
「このたび、朝倉弾正左衛門尉
《越前国足羽御厨
《年貢六千五百疋
《七千疋の東郷荘も、四千三百疋の清弘みょうも、四千疋の次田名も、すべて弾正左衛門が押領》(『桃花蘂葉
「呵責 と、兼良の子、奈良興隆寺の尋尊も、口をきわめて罵りつづける。
が、それが乱世なのである。下剋上というが、"上"が傲慢で下民を虐げ搾取するばかりで"徳"のない支配階級に対して《天が命を革 「時こそ、いたれり!」 それにしても、新興勢力の旗手、敏景の蹶起ぶりはすさまじい。
朝倉家は代々、越前の守護大みょう斯波
敏景が出世のきっかけをつかんだのは、主家である斯波家を二つに割り裂いた、義敏と義廉 ※関連:"応仁の乱"について、内藤湖南著『日本文化史研究』(講談社学術文庫)昭和58年3月18日 第6刷発行の中に 現代日本を知るには、応仁の乱以後を知れば十分だと喝破している。 このとき敏景は義廉を擁立して西軍(山な宗全)に属した。が、東軍の実力者、細川勝元からの、 「われに加担すれば、越前守護職に任ぜよう」 との一言で、ころりと気が変った。守護大みょうになるというのは、長いあいだの夢であった。 「応!」
とばかり、目をかがやかせた敏景は、昨日までの主人
戦国大みょうの先がけとして、応仁の乱という嵐のなかで《一孤半身より》身を起して、《不思議に国を》持つ身になったと述懐する敏景と同じ思いを、子の教景
生涯、合戦にあけくれた教景 《武者ハ犬ㇳモイエ、畜生ㇳモイエ、勝ツ事ガ本ニテ候》 生涯、合戦にあけくれた教景は、乱世の生き難さを『宗滴話記』八十三ヵ条のなかで、しみじみと語る。 武者たるもの、たとえ犬畜生とののしられようと、勝つことが本分……だという。実力主義の世界の、血と汗と涙のなかで培われたプロの言葉だ。 ともあれ、あるじの斯波義廉をしのいで、足利一門の有力者でなければなり得なかった越前守護職に、将軍義政から任ぜられた敏景は、勇躍、西軍を討伐し、越前の地に勢威をふるった。
晩年、入道した英林宗雄と号した敏景は、子孫のために家訓十七箇条(『朝倉敏景十七箇条』(群書類従本)、『英林壁書』(黒川本)、『朝倉英林入道子孫へ一書』(新井白石本)とも称 《於朝倉之家宿老を不可定。其身の器用忠節によりて可申付之事》(一) 朝倉の家においては家老を定むべからず。その身の能力、忠勤によりて申しつくべき事。 以下、興味ぶかい箇所を読みくだして列記してみると、
「先祖代々門閥の家格であっても、実力のともわない者に団
《名作の刀脇指など、好ませられまじく候。そのゆえは、仮令、万疋の太刀を持ちたりといえども、百疋の鑓 《京都より猿楽(能楽の旧称)などたびたび呼びまねき、見物を好ませられまじく候。その金額を領内の猿楽上手の者に与え、京にのぼらせ、猿楽を習わせれば、領内の文化も栄え、末々までよろこばしき事》(五) 《朝倉一族はじめ家中の者ども、年の始めの出仕は布子(ふだん着)たるべき事。高禄の者、軽輩の者、いずれも華美を慎しみ布子を用いるべき事》(八) 「家臣のなかで、みにくい顔つきにて風采あがらぬ者であっても真面目に勤める者には情をかけるべし。また、臆病な男であっても容儀や立居振舞の見事な者は行列の供や、他家への使者に使うがよい。この二つにはずれる者は召し抱えておっても無駄である」(九) 「おのれの役職に精勤するものと、怠ける者とを同格に扱ってはならぬ。精勤な者まで怠け心を抱くようになる」(十)
「さほど不自由でなければ、他国から流れてきた牢人などに右筆 他国者に機密文書を扱わせるということぐらい、危険なものはない。 「年に三度ぐらいは、正直で才覚のある者を選んで国じゅうを歩かせ、四民それぞれの口謁(申し立て)を聞き、それを報告させること。機会をみて当主自身、巡検にまわるべき事」(十四) 「勝とうとする戦、取ろうとする城攻めに際して、殊更に吉日を選び、方角などを考え、いたずらに時日を空費してはならぬ。いかに吉日とて大風の日に船を出したり、大軍に唯一人にて向えば、如何なることか。たとえ悪日悪方角であろうとも、情報をあつめよくよく虚実を考察し、臨機応変に対処すれば必ず勝利を得るものぞ」(十三)
戦国のこの当時、出陣するにも吉日を選び方位を選び、酒を飲むにも馬に騎るにも数々の作法があった。甲冑を着用するにも一定の順序と方式があり、"八幡殿ノ殿"というのがある。下帯 だが、合理主義者敏景の冷徹な目は、そのような故実に惑わされてはいない。 「いかにすればこの乱世を生きぬけるか」 そのため敏景は、この十七箇条の奥書に、 《昼夜眼をふたぐ(とじる)ことなく、工夫を致し、ある時は諸々の名人をあつめ、その語るを耳にはさみ、思案を致しおるゆえ、いまにかくの如く(安泰)に候》
《あいかまえて子孫の者ども右之条々よくhuku
膺し、昼夜相勤めて、長く胎闕 |

その一 「七重八重 花は咲けども 山吹のみの一つだに なきぞ悲しき」
参考:「花咲きて実はならずとも長きけに思ほゆるかも山吹の花」
資長( *岡谷繁実著『名将言行録』(岩波文庫)一冊/八冊 P.72 少し詳しく述べると、 遠乗りにでかけたある日、突然のにわか雨にあった道灌は蓑を借りようと、たまたま側にあった農家にかけこんだ。農家に入り、声をかけると、出てきたのはまだ年端もいかぬ少女であった。貧しげな家屋ににあわず、どこか気品を感じさせる少女であったという。 ▼「急な雨にあってしまった。後で城の者に届けさせる故、蓑を貸してもらえないだろうか?」道灌がそう言うと、少女はしばらく道灌をじっと見つめてから、すっと外へ出ていってしまった。蓑をとりにいったのであろう、そう考え、道灌がしばし待っていると、少女はまもなく戻ってきた。 しかし、少女が手にしていたのは蓑ではなく、山吹の花一輪であった。雨のしずくに濡れた花は、りんとして美しかったが、見ると少女もずぶ濡れである。だまってそれを差し出す少女は、じっと道灌を見つめている。この少女は頭がおかしいのであろうか、花の意味がわからぬまま、道灌は蓑を貸してもらえぬことを悟り、雨の中を帰途についた。 ▼その夜、道灌は近臣にこのことを語った。すると、近臣の一人、中村重頼が進み出て次のような話をした。そういえば、後拾遺集の中に醍醐天皇の皇子中務卿兼明親王が詠まれたものに、七重八重花は咲けども山吹の実の(蓑)ひとつだになきぞかなしき、という歌がございます。 その娘は、蓑ひとつなき貧しさを恥じたのでありましょうか。しかし、なぜそのような者がこの歌を……。そういうと、重頼も考え込んでしまった。 ▼道灌は己の不明を恥じ、翌日少女の家に、使者を使わした。使者の手には蓑ひとつが携えられていた。しかしながら、使者がその家についてみると、すでに家の者はだれもなく、空き家になっていたという。 道灌はこの日を境にして、歌道に精進するようになったという。 その二 短慮不成功
父親に「短慮不成功」を平易な言葉で述べよ、と言われた大田資長 「急がずば 濡れざらましを 旅人の後より晴るる 野路の村雨」 *日本経済新聞より 平成二十四年七月十八日:追加。 |
☆12 北条早雲 万民に対し、一言半句にても虚言申すべからず(1,456~1,519)
|
桶狭間に出陣する信長が、「人間五十年……」と幸若(わか)の『敦盛(あつもり』を三度舞ったというのも五十を一生と考えてのことで、彼自身もまた四十九歳で戦火のなかに消え、越後の上杉謙信も四十九歳、甲斐の武田信玄は五十三歳で病没している。
が、伊勢新九朗長氏、のちに早雲庵宗瑞
かれの妹が海道随一の守護大みょう、今川義忠の室となり寵愛をうけて北川殿とよばれ、義忠とのあいだに生まれた竜王丸
後に早雲、妹の北川殿を頼って駿府
この居候
これが発端となって今川家は、四歳の嗣子竜王丸(のち氏親)派と、跡目を狙う一族の今川範満 「危ういかな。いま、今川家が真二つに分れて争えば、近隣諸国の思う壺となりお家滅亡は必定」 と調停に乗りだし、範満を討って 紛争解決に奔走し、その功労によって長享二年(一四八八)氏親(竜王丸)から駿河、富士十三部を与えられ興国寺城(沼津市根小屋)の主となる。このとき早雲数えて五十七歳。
新九朗長早雲の人生の見事さは、老人にありがちな性急さを微塵も見せなかったことであろう。軍
《齢 興国寺城主になった早雲は、当時の武将たちが五公五民の年貢、ひどいところでは七公三民(税率七〇%)の酷税を課していたのを、 《年貢過分の故、百姓つか(疲)れ苦しみ餓死に及ぶ。以後(わが領分では)年貢四ッ(四〇%)収むべし》 と布告した。 《此人(早雲)慈悲の心ふかくして百姓をあわれみ是によって百姓共「かく慈悲なる地頭殿にあいぬる物哉」とよろこび「此君の情には命の用にもたつべし。あわれ世に久しくさか(栄)えかし」と、心ざしをこばずという者なし》(『北条五代記』)
こうした早雲の政治が爆発的な戦力に化 と口ぐちに叫んだという。
いっぽう、早雲軍が急襲した敵方の土豪や百姓たちも、かねてから早雲の善政にあこがれ、「われらが国も早雲殿の国にならばや」と、たちまち呼応し、堀越公方足利茶々丸は自刃 日本史の区分によると、早雲進撃のこの延徳三年(一四九一)から「戦国時代」が始まる。 ともあれ、こののち早雲が小田原城乗っ取り、念願の相模国を平定し後北条五代の覇権の基を築きあげ、永正十六年(一五一九)八十八歳で老衰死するまで、現役として戦国街道を全力疾走する経緯は司馬遼太郎の歴史小説『箱根の坂』などの諸書によって、すでに世間周知のことであろう。
早雲は生命力の勁 早雲という男は、日頃は針のようなささやかな物まで蔵に仕舞い込むほどの倹約家だが、いざ合戦ともなれば貴重な宝石さえ惜しげもなく打ち砕くという思い切った使い方をする――と、早雲の細心さと果断な実行力を激賞している。
早雲は晩年、わが越し方をふり返って彼の人生観とも家訓ともいうべき日常の心得を『早雲寺殿廿一
《朝はいかにもはやく起
《少しの隙 明日をも知れぬ乱世のなかで、懐中の書物を読みふける。それは、ひょっとすると若き日の早雲の姿であったのかもしれない。
《御通 《正直を憲法にした上たるをば敬い下たるをばあわれみ、有るをば有るとし、無きを無きとし、有りのままなる心持、仏意冥慮にもかなうと見えたり》
この二十一箇条は、きわめて日常的な訓
《上下万民に対し、一言半句にても虚言申すべからず。かりそめにも有
の条 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.50~54 2021.05.31記 |
☆13 山本勘助(1,493もしくは1,500~1,561年)
|
日本のなかの"戦国"というのは、中国の周の威烈王から秦の始皇帝の天下統一までの群雄割拠の時代を"戦国時代"と称
この激動の時代、世にこころざし
かれらは、しかるべき武将のもとに身を寄せ、知謀あるものは軍略を、腕におぼえのある男は、"陣借り牢人 戦国武者というのは一種の自由労働者で、 「武士は二君に仕えず」 どころか「七たび牢人せねばオトコ(一人の武士)ではない」といわれ、その人間市場でオトコを売るのが稼業であった。 槍をかざして一番乗りをするのも敵の首を叩き切るのも、出世のため金のため、というのがサムライの本心であった。後年の、"禄"をもらって寝て暮らすだけの遊民、世襲制公務員に変身したサムライとは、生き方、考え方がちがう。 《君ニ仕エテ忠ヲ尽サンニハアラズ、(戦に出るのは)なヲ立テ家ヲ発セン(興そうとする)バカリ也》 《合戦ノハタラキニ心ヲ尽スハ、子孫ノタメㇳモ申スベシ》
こうして、一介の素牢人から関東の王にのしあがった伊勢新九郎こと北条早雲、油の行商人となって諸国を歩きまわった"戦国の蝮 武田騎馬軍団の軍師(参謀)とともいわれる山本勘助もまた、その一人である。 武田晴信の謀臣、山本晴幸(勘助)。三河国牛窪に生まれ、二十歳のころから諸国を遍歴し三十有余年、甲斐国に辿りつき晴信に仕える。このとき勘助、すでに五十二。 放浪中の辛酸について『続武将感状記』は、こう語る。 《山本勘助、室町将軍家に仕官を望みけるが》 事ならず京を立去る。わが身を托するのは、 《安芸の大江(毛利)元就に如くはなし》 そう思い定めて旅立つたものの、人生というのは、おもしろい。
途中、葛井寺
で、この地にとどまること数年。ようやく安芸に辿りつき、厳島に詣で知人の棚守謀に挙 「ああ、あの牢人めなら要らぬわ。用いざれば他国へ走り、安芸の毛利などとよからぬ噂を立てるにちがいない。されば一日も早よう此処から立退かすべし」 と元就はいう。かくして勘助、失意を抱いて、また、旅に出るしかなかった。 勘助が武田家に仕えたのは、一説によると武田の重臣、板垣信方の推挙によったのだというが、 《丈短く色黒く》 ながい放浪と、各地での「陣場稼ぎ」の戦闘で、満身創痍の有様であった。 が、これを見て晴信(信玄)大いによろこび、 《かくの如き醜容貌をして、なお盛名あるというは、その能もって知るべし》 と知行二百貫を与え、足軽大将に任じた。そののち勘助、晴信の旗本五人の内に加えられ、晴信の参謀として、抜群の"軍略"で敵城を落とすこと九ヵ城。諸戦での功を賞せられ、禄八百貫。 晩年、勘助は、あるじ晴信が信玄を号するにおよんで自分もまた剃髪し、道鬼斎と号した。 永禄四年(一五六一)上杉謙信との川中島第四度目の会戦で激闘、全身に八十六ヵ所の傷を負い、壮絶な戦死を遂げる。享年六十九.(『甲斐戦国志』『甲陽軍艦』)。 ――というのが山本勘助の来歴だが、"信頼すべき文献に見当らない"として架空の人物視する人もいる。が、最近はその関係書などが発見され、ようやく勘助の実在が認められるようになってきた。 ともあれ、この勘助が語った戦国武者の心得を、信玄が家臣に命じて記録させたと伝えられる聞書き『山本道鬼入道百目録』が遺されている。
《一、嗽
地の恩は、わが住所居し、五行 文中にある"五行"というのは、古代中国の学説で、天地の間に循環流行している人間や動しょく物に大事なもの、万物組成の元素の意味である。 以下、その百二ヵ条のなかから戦国武者の教訓としてユニークなものをアトランダムに四、五ヵ条を抜き書いてみると、
「武士たるもの、驚破 戦国乱世というのは、生きていられるということ自体、異常な幸福であった。 「この世にもう何の未練も、望みもない、などという者を近づけるな。なんとなれば、にんげん、身分の上下にかかわらず、みな、明日という日に望みを託しているからこそ、その勤めに出精し、身を正しておれるのだ。人の世に希望を持たぬ者など、なにをしですかわかったものではない」(第八十条) 《人食すといえども一升の米に過ぎず座して三尺、寝るは六尺を以って足る》(第十条) 飯を喰うといっても、一度に二升も三升もの飯が喰えるわけでなし、金にまかせて贅沢な普請をしてみても、寝るのに必要なのはたった六尺。 「嫁をとるときには、相手の美醜などどうでもよいが、日頃の評判を近所で聞いて、よくよく調べておけ。つましい娘か派手好きな娘か、親に孝行か、家来たちをいたわるか、どうか、それが大事だ。仲人の言葉など信じてはならぬ」(第九十条) と、戦国という修羅をくぐりぬけてきた勘助は、しずかに語りつづけている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.92~96
神坂次郎は、――というのが山本勘助の来歴だが、"信頼すべき文献に見当らない"として架空の人物視する人もいる。が、最近はその関係書などが発見され、ようやく勘助の実在が認められるようになってきた。 新田次郎はその著作『武田信玄 火の巻』あとがき、 信玄と云えば、その影に添うごとく軍師の山本勘助が出て来る。ところが、この山本勘助なる人物は、山県昌景の組下にいた身分の軽い武士で川中島の戦のときには物見をやったていどのことしか分っていない。山本勘助の子が、妙心寺派の僧となったが、この男が学があって、武田信玄の事蹟を集めて、これを物語風にまとめたものに、小幡景憲が加筆し高坂弾正が遺したと称して江戸初期に出版したものが『甲陽軍鑑』だと云われている。原本を山本勘助の子が書いたとすれば、父親を軍師に仕立てるのは当然であろう。軍師山本勘助という人物は、他の信用置ける資料には全く出て来ないから、山本勘助が実在の人であったとしても軍師でなかったことは確実と見てよいだろう。だが、なんと云っても、武田信玄のことになると、この『甲陽軍鑑』の影響力が大きく、軍師山本勘助が出ないとおさまりがつかない。そのために、武田信玄の側近の一人であった、駒井高白齋のような人物が蔭にかくれてしまったのであろう。 2021.05.20記 |
|
骨肉相食むというが、武田信玄とその父、信虎との争いほど凄まじいものはない。信虎は、わが身によく似たはげしい長男の信玄を嫌い、かねてから信玄の廃嫡をたくらみ、温和な次男信繁を愛し、後嗣にと考えていた。勇猛をうたわれた荒武将の信虎だけに、その偏愛ぶりは目にあまるものがあった。 ある年の正月などは、信玄を黙殺して、これ見よがしに祝儀の盃を信繁だけに与えたという。 「いまに見ておれ」 信玄が、信虎追放の計画を練りはじめたのはこの日からである。天文十年(一五四一)六月、その機会がついに来た。 おりから信虎は、娘婿の今川義元を訪ねて駿河に出かけていた。その留守を狙って行動を起した信玄は、駿河に通じている甲斐国境を封鎖し、信虎の供をした家臣の家族を人質にとり、信虎を捨て甲斐に帰れと呼びかけた。あわれなのは信虎である。従臣たちはみな、信玄の呼びかけに応じて帰国し、信虎はただ一人、駿河にとり残され、八十一歳で亡くなるまでの二十五年間、今川家の食客となり、やがてその今川からも追われ、欝々と世を過ごすことになる。 父を追放し武田家を掴み取った信玄は、次いで信濃に出兵し、妹婿にあたる諏訪頼重を討滅。信濃になだれこんだ武田軍団は、さらに上田城の村上義清を撃破し、信濃の守護大みょう、小笠原長時を越後に追い落し、甲斐一国をわが物にし、駿河の今川義元、相模の北条氏康と三国攻守同盟を結んだ。 こうして背後を固めた信玄は、越後国境に迫り、上杉謙信と川中島で五度の合戦をかわしたが勝敗決するに到らず。のち剽悍天下に鳴る甲信二万五千の武田騎馬軍団をひきいた信玄は、天下への夢を抱き西上の途につく。
頼 山陽(らい さんよう/1781-1832)の漢詩「不識庵機山を撃つの図に題す」に基づく詩吟『川中島』。
題名のとおり、武田信玄と上杉政虎(のちの謙信)の「川中島の戦い」を題材としている。歌い出しは「鞭声粛粛 歌詞・読み方 鞭声粛粛 夜河を過る(べんせい しゅくしゅく よる かわをわたる) 曉に見る千兵の 大牙を擁するを(あかつきにみる せんぺいの たいがを ようするを) 遺恨なり十年 一剣を磨き(いこんなり じゅうねん いっけんを みがき) 流星光底 長蛇を逸す(りゅうせい こうてい ちょうだを いっす)
信玄は勇猛であったが、その軍事行動は細心で緻密であった。軍を進めるにさいしても、さまざまな情報を掻き集め、行く手の山や川、池の一つ一つまで調べあげて絵図をつくらせ、それをもとに計画をたて、突撃にあたっても一騎駈けはゆるさず、隊伊を組ませて組織的な行動をとらせていた。 すぐれた民政家でもあった信玄のすばらしさは、在世中ひとりの叛臣もださなかったというその人間管理、卓絶した家臣統率力であろう。それを語ったものに、
《法度
という五ヵ条の訓
《第一条、大将の人をよく目利 大将たるもの、家老や家臣たち個々の人柄を掌握し、その得手を知って職務を命じなければならぬ。これらの人材を果物にたとえれば、梅や桃などは先に花が咲き、のちに実がなる。また、ザクロや瓜などは、まず実なりてのち花咲くものなり。さてま蓮花という物は、花も実も一度なるものなり。 「この三様は、人間も同じである」 国持大みょうは、こうした家臣の特性を生かした使い方をせねばならぬのだ。
また家臣たちもよく聞け。わが身に音信
もともと、贈物ばかりして上役の歓心を買おうと、慇懃な面 《第二条、》武士たらん者の手柄、無手柄を上中下によくわけて、鏡にて物の見ゆる様に、大将の私なくなさる事》 大将たる者、家臣の忠節忠勤に応じて与える恩賞は、よくよく心得たうえで私心なく、誰の目にも依怙贔屓なく鏡でも見るように公平に与えなければならぬ。 また、上役が下役の手柄を横取りしたり、大功(大手柄)をたてたのを軽く扱ったりすると、家臣たちはどれがよいのかわからなくなり、忠節忠義をつくす考えがなくなるものだ。
《第三条、兵 兵どもの手柄への恩賞については、かならずその手柄に応じて上位の恩賞、中位の恩賞、下位の恩賞を与えねばならぬ、上位の手柄の者に中位の恩賞が与えられたり、下位の手柄に上位の恩賞に対するようなねぎらいの言葉などかければ、忠節な者ほど落胆し、張合いをなくして忠誠を尽くそうという者がいなくなる。辻斬りや喧嘩、辻相撲、粗暴な振舞いをする者などは本物の勇気ではないから、戦場にでてロクな働きができるわけはない。こうした家臣が多くなれば、誰も法度を守らなくなる。 《第四条、大将、誰も慈悲なさるべき儀肝要なり》 大将は慈悲心をもって家臣に接することが大事である。 慈悲の心がなければ、世の有為無常もわからず、重臣で贔屓の者ばかりを重くもちい、軽い身分の者の勤務ぶりを評価しようとしないから、軽輩微禄の者や不弁者(貧乏人)は、いかにすぐれていても忠節や忠義のつくしようがない、それらが全軍にひろがり、わが身大事とばかり誰も進んで忠節をつくそうとしなくなるものだ。 そうなると口先だけの世間巧者や追従者ばかり横行し、道理も義理もわからなくなってくる。そうした家臣じゃ出世をしても、それを主君のおかげだとも思わず、みなみなおのれの力だけで立身したと思いこみ、主君のことなど考えようとしなくなる。
《第五条、大将のいかり給う事、余りなければ、奉公人油断ある物なり。油断あれば自然に分別ある人も背 大将たる者は温和なだけでは駄目で、必要なときは血相を変えて怒気をみなぎらせて、家臣たちの心をひきしめる事が大事だ。 ただ、その場合の怒りかたに思慮分別をはたらかせねばならぬ。家臣の罪科の軽重を誤ったりすれば、逆効果で、そのような大将の"法度"を誰も守らくなる。法度を守らなければ軍規が乱れ、戦場に出ても勝ことなどない。仮りに、まぐれで勝ったならば、かえって油断を生じ、やがては大敗に通じるものだ。
《一城を構え、人数引き廻す侍大将ども、その工夫専ら有るべき事肝要なり。右五ヶ上の理 こうした信玄の言行を書き伝えた『甲陽軍鑑』は、 《信玄公右(五ヶ条の訓)の趣、善悪の沙汰、黒白のごとくわかり、賞罰明らかなること、天のごとく、地のごとくあそばし、よく法度をたて、よくさいはいを取って、味方をいさめ、敵をおかしかすめ給う》 と述べ、家臣たちを、"適材適所"に差し向け、馬上の戦さにすぐれた関東の敵には、馬と足軽用兵にすぐれた家老の内藤修理を……、こがえし(小返し・軍勢の退却後に一部の兵が引き返して戦うこと)をよくする徳川家康へは、小いくさを能くする山県三郎兵衛を差し向けるなど、
《敵の行 と記している。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.202~207
参考:新田次郎著『武田信玄』全四巻(文藝春秋)昭和四十九年六月十日 第十三刷
新田次郎著『武田信玄 風の巻』あとがきによると、 信玄と云えば、その影に添うごとく軍師の山本勘助が出て来る。ところが、この山本勘助なる人物は、山県昌景の組下にいた身分の軽い武士で川中島の戦のときには物見をやったていどのことしか分っていない。山本勘助の子が、妙心寺派の僧となったが、この男が学があって、武田信玄の事蹟を集めて、これを物語風にまとめたものに、小幡景憲が加筆し高坂弾正が遺したと称して江戸初期に出版したものが『甲陽軍鑑』だと云われている。原本を山本勘助の子が書いたとすれば、父親を軍師に仕立てるのは当然であろう。軍師山本勘助という人物は、他の信用置ける資料には全く出て来ないから、山本勘助が実在の人であったとしても軍師でなかったことは確実と見てよいだろう。だが、なんと云っても、武田信玄のことになると、この『甲陽軍鑑』の影響力が大きく、軍師山本勘助が出ないとおさまりがつかない。そのために、武田信玄の側近の一人であった、駒井高白齋のような人物が蔭にかくれてしまったのであろう。
私は武田信玄を書くに当って、なるべく史料に忠実であることを願った。それが、歴史小説の使命のように思えてならない。人物の設定にもいろいろ気を配った。山本勘助が使い番衆になったり、間者になったり、敵地に入って工作活動をする細作
新田次郎著『武田信玄 火の巻』あとがきによると、 火の巻でもっとも力を入れて書いたものは太郎義信の事件である。太郎義信は父信玄に逆心を抱いたが為に座敷牢に入れられ、ついには自害して果てたということは『甲陽軍鑑』に書いてある。品十二には、永禄十年御自害候。病死とも申也。と書いてあり、品卅三には、其年の春、三十の御歳、太郎義信公御自害也。と書いてある。同じ『甲陽軍鑑』でも、自害説の他に病死説を取り上げているところを見ても。真相は伝えられていなかったに違いない。川中島のの大会戦のときから信玄と義信とが中違いうをしていたとか、義信が飯富兵部と共に信玄を追放しようとしたなどということはおそらく俗説で、真相は信玄の駿河進攻作戦に対して義信が反対したから自害させられたという歴史家の見方が正しいであろう。ただ自害したか病死したかについては全くわからない。分らないところが小説になるのである。私が自害説を取らずに病死説を取ったのは、私の史観であって、ここで自害説を取れば、私の中の信玄像は根底からひっくりかえってしまうことになる。昭和四十六年五月 2021.05.18記 |
|
利 休の辞世
人生七十
力囲希咄
吾這宝剣
祖仏共殺
提
一太刀
天に 拋 天正十九年仲春 廿五日 利休宗易居士 それは、白日青天怒電走の一句とともに、利休の劇的な死にふさわしい、気迫のこもった辞世であった。この辞世はいまも裏千家に伝えられている。 力囲希咄 は(ええなんじゃいの)といった意味である。 囲の中の(井)は(力)です この字はつかわれていません。 岡倉覚三 『茶の本』にも記載されています 村井康彦著〚千利休〛(NHKブックス)昭和60年12月10日第10刷発行 P.255 参考: 松原泰道、全国青少年教化協議会において
白日青天怒雷走 「白日青天」は、晴れわたった日和。白日はくもりのない太陽・白昼。転じて少しも包み隠すところのない明白さや、無罪である事実が明らかになるときなどに使われる。「怒雷」は烈しい雷鳴で、同義語に青天の霹靂(へきれき=にわかに起こる雷鳴)がある。また、ときとして人間感情の激変をいう。これで辞書的な説明は尽きよう。
千家流茶道の祖、千利休(宗易(そうえき))は京都紫野の大徳寺の古渓 利休は秀吉の厚い信頼を得ていたが、利休が自分の木像を大徳寺の山門上に置いたことなどから、秀吉の激怒を買い自刃(じじん)して果てた。その死の直前に、古渓と利休が別離の茶事をもつ。茶を喫しつつ、古渓は「末期の一句(覚悟の一言)は如何に」と、この場に臨んでの平素の禅のこころを尋ねる。利休が全身を挙げて師に答えたのが「白日青天怒雷走」であった。古渓もその心境に満足して、二人して最後の別れの茶味を喫し終わった(古渓、補庵稿)。 白日青天怒雷走の字義の解釈は最初に記した。利休の答えも、常識的にはどの項にもあてはまる。秀吉の心境の変化・利休にとっては環境の突然の変異・利休の無実や怒りの心情等のすべてがこの語に盛られよう。
しかしそれでは古渓が満足するわけがない。利休があえてこの語を末期の窮極の一句としたのは、字義を超える命の躍動がなければならぬ。恩讐
雷は、利休の怒りではなく晴天白日の清涼さの助詞だ。この例に「一鳥啼山更幽(一鳥啼 参考: 一、茶の湯とは ただ湯をわかし 茶をたてて のむばかりなる事と知るべし。 |
☆16 上杉 謙信(1,530~1,578年)

上杉家(謙信)の家訓16ケ条「宝在心」 01、 心に物なき時は心広く、体やすらかなり。 02、 心に我慢(慢心のこと)なき時は愛敬失はず。 03、 心に欲なき時は義理を行ふ。 04、 心に私なし時は疑ふことなし。 05、 心に驕(おご)りなき時は人を敬ふ。 06、 心に誤りなき時は人を畏れず。 07、 心に邪険なき時は人を育つる。 08、 心に貪りなき時は人にへつらふことなし。
09、 心に怒りなき時は言葉
10、 心に堪忍あるときは事を調 11、 心に曇りなき時は心静かなり。
12、 心に勇ある時は悔 13、 心賎しからざる時は願ひ好まず。 14、 心に孝行ある時は忠節厚し 15、 心に自慢なき時は人の善を知る。 16、 心に迷ひなき時は人をとがめず。
引用:松下幸之助著『商売心得帖』(PHP研究所)昭和48年2月20日発行。P.98
辞 世 「極楽も 地獄も先は 有明の 月の心に 懸かる雲なし」 「四十九年 一睡の夢 一期の栄華 一盃の酒」
上杉謙信公の名言 わしは国を取ることは考えず、後の勝利も考えず、目前に迫っている一戦を大事にするのみである。 信玄の兵法に、のちの勝ちを大切にするのは、国を多くとりたいという気持ちからである。自分は国を取る考えはなく、のちの勝ちも考えない。さしあたっての一戦に勝つことを心掛けている。 手にする道具は得意とする業物でよい。飛び道具を使っても、相手が死ねば死だ。鉄砲で撃っても、小太刀で斬っても、敵を討ったことには変わりはない。 戦場の働きは武士として当然のことだ。戦場の働きばかりで知行(報酬)を多く与え、人の長(おさ)としてはならない。 人の上に立つ対象となるべき人間の一言は、深き思慮をもってなすべきだ。軽率なことは言ってはならぬ。 上策は敵も察知す。われ下策をとり、死地に入って敵の後巻に入る。 一期の栄は一盃の酒 四十九年は一酔の間 生を知らず死また知らず歳月またこれ夢中の如し。 生を必するものは死し、死を必するものは生く。
争うべきは弓箭(ゆみや)にあり、米・塩にあらず
|

毛利元就の三男で、兄弟に同母兄の毛利隆元・吉川元春などがいる。竹原小早川家を継承し、後に沼田小早川家も継承して両家を統合。吉川元春と共に毛利両川として戦国大みょう毛利氏の発展に尽くした。毛利水軍の指揮官としても活躍している。豊臣政権下では豊臣秀吉の信任を受け、文禄4年(1595年)に発令された「御掟五ヶ条」と「御掟追加」九ヶ条において秀吉に五大老の一人に任じられた。実子はなく、木下家定の五男で豊臣秀吉の養子となっていた羽柴秀俊(小早川秀秋)を養子として迎え、家督を譲っている。特に豊臣秀吉の信頼は厚く、事実上毛利氏の主導者であった。 言行録――『名将言行録』(一)岡谷繁実著(岩波文庫)P.209~
○ 隆景曰く異見をして見るに直ちに請合う者に、其異見を保つ者なし、異見をする人の詞 ○ 隆景、常に若者共に謂て曰く、我心に合いたることは皆身の毒と思ふべし。我心に六ケ敷ことは皆薬となるべきことゝ思ふべし。若き者は萬づ一人嗜むべきことなり。如何となれば、年の若きは末久しからん間、嗜み餘りあることなるべし。如何となれば、年の若きは末久しからん間、嗜みても餘あることなるべし、老たるは猶以て嗜むべし、末近ければ嗜む間久しきことにあらざれば、嗜みよからん。一生は夢の間なれば、人々能く言はるゝことこそならずとも、悪く言はるべきは人にあらず、と度々一門の者共に申聞かされしとなり。
○ 隆景曰く、人たる者は不斷門には、磔
○ 隆景、嘗て茶事を好めり。或時人に語て曰く、茶の湯の翫
○ 隆景、嘗て黒田孝高(よしたか:如水として知られる)に語て曰く、貴殿は事を決斷して後悔み給ふことあるべし、何となれば、貴殿の才智甚だ敏にして、一を聞いて二を知る程の聡明なれば、人の言を聞くと等しく即時に善悪を決斷し給ふこと、水の卑 ○ 隆景曰く、孝高の智は甚だ敏にして、是非を決するに造作もなきこと利刀にて竹を二ッに割るが如し、天下に及ぶ者なし。然るに只才覚武略の誉れはありて、思慮の誉れはなし。我孝高の才智には遙に劣れり、孝高の思慮せずして即時に決斷することを、我は返す返す思案して漸く孝高の即時の智に及ぶ。然れども世上の人我を却て思案ありと言ふは、才に鈊きにより決斷することならずして、思案を好む故なるべし。 ○ 黒田長政、隆景に向ひ、分別は如何したるが能く候やと問ふ。隆景、別の子細なし。只久く思案して遅く決斷するに、仁愛を本として分別すれば、萬一思慮理に當らざることありとも遠からず。仁愛なき分別は才智巧なりとも、皆僻事なりと知り給ふべしと答へけり。 ○ 隆景、平生人の善言を取り用ふ、士は申に及ばず、下部にも其者の知るべきことをば尋ね問て、其者の申所然るべきことあれば取用て行ひける。故に人々進みて言を獻ぜしとぞ。 ○ 隆景、初め堪忍の二字を書きて壁に掛けしが、後には思案の二字に書替られたとぞ。 ○ 隆景、或時急速のことありて、右筆に物を書かするに、急用のことなり、静かに書すべしと言われしぞ。 ○ 隆景、資性廉直、信義を重んじ、苟も戯言なし。若し一たび出言すれば、聊かも變改せしことなしとぞ。 ○ 隆景、奸人と交はりても之が為に混濁せず、常に弱を以て強を制し、柔を以て剛を制す。故に當時之を楊柳に比せり。元就嘗て曰く、仁を施し、民を愛し、国家を保つことは、我、隆景に及ばずとありて、常に治国のことをば委任せられけり。 隆景、三原(広島県)に退老す。 ○ 隆景、學を好み、平生著書多しと雖も、移りに臨み意に満たずと言て、悉く之を火にせり。 ※関連:天下は地方の積み重ね 2021.05.04記 |
☆18 豊臣 秀吉(1,537~1,598年)主人は無理を云うなるものと知れ
|
にんげんは、その長い生涯において身を引き裂かれる思いで決断を迫られる場合がある。 歴史は、そんな人生の岐路に立って、決断というなのサイコロを投じた男たちの明暗とさまざまな表情を描きだしている。
一瞬の決断に賭 歴史は、そんな男たちの、人生の転機に賭けた成敗を、淡々とわたしたちに語りかけてくる。 主君、信長の死という悲運を逆手にとって、天下人への"運"を秀吉が掴むのは、わずか一時間余の決断であった。
だが、その一時間余こそ秀吉が一世一代、脳漿
このとき秀吉は、中国遠征軍の司令官として備中(岡山県)高松城攻めの本陣で、毛利・吉川 「しかし……」 本能寺の変を知った瞬間、秀吉は思った。 「それが、どうしたというのだ」 遠征軍をひきいて各地に布陣している織田家の武将たちの誰よりも速く、光秀討滅に駆けのぼれば、ナンバー1になれる。
秀吉の決断は早い。すぐさま毛利家と和睦を結んだ。間一髪であった。この和議の誓紙 この後の行動は機敏をきわめている。
こうして中国撤退の秀吉軍二万余の軍団は、連日の雨と洪水で泥の海と化した山陽道を凄まじい速度で駆けぬけて行った。これが後のちまで秀吉の「中国大返
篠 備中高松を出て姫路まで行程六十キロ。ここまでくれば毛利軍から追撃される懸念もない。 姫路に着いてからの秀吉の行動は、なんとも豪快で底抜けに明るく、天下取りの面目躍如たるものがある。城に入った秀吉はすぐさま風呂に入って汗と泥を落し、湯殿にすわりこんだまま、小姓を呼び、一切の軍令を発している。世にいう「お湯殿の号令」である。 陣立てを下知すると秀吉は、次に金奉行や蔵奉行を呼びよせ、姫路城にあるだけの黄金、銀、銭から八万五千石の米一粒残らず秀吉軍団の武将から足軽、小者にいたまで知行(石高)に応じて全員に分け与えてしまったのである。
その夜、秀吉はじめ全軍の将兵は泥のごとく眠って、翌、払暁 「者ども、駈けよ!」
戦いには、「機」というものがある。いかに大軍を抱いていてもその機をはずしては玩具 尼崎での秀吉は、全軍の将兵におびただしい魚や獣肉を振舞って精気を充満させ、天下分け目の決戦の地、山崎にむかった。このとき、各地から従軍をもとめて加わる諸大みょう軍のため秀吉軍団は雪だるまのごとくふくれあがった。
後日譚になるが、このとき秀吉の家臣で足腰も立たぬ病のため行軍に加わっていない男がいた。山崎の合戦のあと秀吉は、この家臣を斬罪 秀吉軍の進撃の予想外の速さに、光秀軍は動揺した。秀才型の光秀は、こうした不測の事態への対応が不得手であった。
動揺するといえば、娘婿の細川忠興 こうした秀吉の、天下取りとしての「英雄的資質」のあらわれの一つは、この(姫路城でみる)呉れっぷりのよさであろう。呉れっぷりのよさが人を動かすのは、戦国の世も平成の現在の「政治」の世界もかわりはない。 こうした秀吉の「人たらし」「カネくばり」は、こののちの諸戦場でも、よく見られる。敵の首を掻き切って駆け戻ってくる武者たちに、本陣の秀吉は、 「あつぱれ、ようやった」
と傍 《多くの金銀を土蔵に積んでおくのは、有能な人間を牢に押し込めておくに等しい》 という秀吉の、生涯最大の大盤振舞は、天正十七年(一五八九)聚楽第で徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝ら大みょうたちへのカネくばりであろう。 このとき秀吉が、家康らに与えたのは金五千枚、銀三万枚、これだけ貰えば、誰だって「粉骨砕身」を誓ってしまう。 秀吉が日ごろ、近臣たちによく語っていたという処世訓が幾つか伝えられている。
《一、朝寝すべからず
秀吉が一代の栄をきわめた絢爛豪華な聚楽第が完成したとき、その門の扉に誰かが、 「奢るもの久しからず」 と落書きして貼り付けていた。
それをみた秀吉はにやりと微笑 《奢らずとも久しからず》 と、書きくわえたという。
大気者
*神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)P.182~187
|
☆19 本多正信堪忍は身を立つるの壁(1,538~1,616年)
|
人の世の人それぞれの浮沈は、巨木な"時"の流れのなかにある。関ケ原の合戦は、三河以来の戦場の血と汗のなかの徳川氏を築きあげてきた武功派譜代の輝ける舞台の幕切れでもあった。やがて時代は、徳川氏が戦国大みょうから江戸幕府創設という流動する政治、社会の変化のなかで、家臣団の実権は"武功派"から"吏僚派
こうした時代の潮流の中で、戦場での武勲もない、鷹匠 文治派の謀臣、本多の台頭は、あたらし武士像の出現でもあった。 「百姓は財のあやまらぬよう不足なきよう治めること道なり」(『本左録』)の言葉で有名な本多佐渡守正信。祖父の代から松平(徳川)家に仕えた本多の家系とはいえ、正信の家の本多は、徳川四天王といわれた本多平八郎忠勝家のような名門本多とは別の、低い位置にあった。 《鷹師、会計の小吏より出身して馬上の武功なしといえども、吏務は慎察にして、文筆の志ありければ漸く登康》(『台徳院御実紀』》 など記されているように、戦国のこの当時、貴賤とみられていた下級役人であった。 正信の前半生は紆余曲折をきわめている。幼い頃から家康に仕えた彼が、三河の一向一揆に加わり叛乱軍の参謀役として主君に弓を引き、やがて故郷を出奔して京に走り、松永久秀のもとに身を寄せる。松永は一目で正信の器量才覚を見ぬいて、
《人に語りていわく、久秀、松平家より来る侍を見ること少なからず、多くはこれ武勇の輩
と思ったが、正信はその久秀のもとにも長くはとどまらず、加賀や越後を転々とし流偶 その正信が家康に詫びを入れ、帰り新参の鷹匠として食禄四十万石を与えられたのは永禄十二年(一五六九)、正信三十二歳のとき。後年、正信が幕閣の要職にありながら民政への鋭い感覚をもっていたのは、この民情探索の役目でもあった鷹匠や、彼にとって冬の時代ともいう三河出奔後の諸国放浪の時代の体験からきている。
武田討滅後、甲斐の国の動揺を治めるため行政官として目ざましい活躍をみせた正信は、にんげん通 「れからは、火を発した者に切腹を命じよ」 と言いつけた。翌朝、正信が出仕するのを待ちかねて、 「昨日申しつけたこと、みなに達したか」 と訊く。すると正信は、
「上様のお言葉、昨晩よくよく考えてみましたるところ、もし誤って三河以来の譜代高禄の屋敷から火がでました場合、切腹を仰せつけることは出来ますまい。と、軽い身分の者のみを切腹させ、譜代大身の者なら赦 言われてみると、正信のいうとおりである。 また、映像や小説などでみると家康は温厚、忍耐をわきまえた武将……となっているが、それは外交上の"顔"で、本来は極めて短気、時には近習たちの過失を口汚く罵倒し、怒りに目を吊りあげ今にも手討ちせんばかりの形相をみせる時がしばしばあった、 そんな時に正信は、家康の御前へにじり寄って、 「何ごとに候や」 と家康に訊く。と、いきり立った家康は口に泡を噛んで、 「こ奴(やつ)めが、かような振舞を致しくさって」 それを聞くなり正信は、 「上様のお怒り、ご尤もでござる」 そういうと叱りつけられている近習を睨みつけ、家康も驚くほどの大声で、
「汝 正信は矢継ぎ早に、手討ちにされようとする近習の家代々の忠勤ぶりを(家康に聞かせるように)大声で叫びあげ、
「汝もその心がまえによって、今日よりいよいよ相勤めよ、上様にもさよう思 正信が激しく長々と喋っているあいだに、家康の怒りはとっくに冷めてしまっている。
「これ、何をしておるか、お声をお出しなされたゆえ、上様には咽喉
こうした正信の配慮によって、近習たちもお咎
一介の鷹匠から、江戸幕府の最高頭脳に立身しながら、正信はつねに質素であった。俸禄は相模(神奈川県)玉縄(たまなわ)三万石、それ以上の加増を正信は辞退しつづけている。その正信の壁書
《一、淫酒 二、堪忍は身立つるの壁
三、苦労は栄華の礎 四、倹約は君に仕うるの材木 五、珍膳(ちんぜん)珍味(を好む)は貧の柱
六、多言慮外(無礼)は身を亡 七、人情は家を作るの畳
八、法度 九、花麗(華麗、派手)は借金の板敷
十、我儘は朋友に悪
生涯、清貧に甘んじ無欲に徹し、家康政権を推進してきた正信の最後の仕事は、豊臣討伐の大坂ノ陣であった。「やるか!」かねてから社寺の修造に事よせて豊臣家の財力を蕩尽 おりから家康は病臥していたが、その知らせを耳にした途端、 《大坂討滅コソ本望ナリ》 と叫び、枕頭(ちんとう)の刀を抜き放ち、床の上に飛びあがったと伝えられている。
この後、冬ノ陣では、「総堀 正信の死は、あるじ家康の死の五十日目である。
家康が正信をみること朋友のごとくであったと伝えられる本多佐渡守正信、元和 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.116~116 2021.06.02記 |
☆20 島井 宗室(1,539~1,615年)
|
口がましく、言葉おゝき人は、人のきらう事候。我ためににもならぬ物ニ候。 *朝日新聞:2009.10.24より引用。
*島井(嶋井) 宗室
私見:古今東西の人物は、発言について、同様なことに触れている。
|
☆21 徳川家康(上) 生涯座右の銘とした失意の自画像(1,543~1,616年)
|
戦国の世とはいえ、松平竹千代(のち徳川家康)ほど過酷な運命にもてあそばれた子は、またとあるまい。幼児として母のふところで甘えられたのは、まだ物ごころもつかないあいだで、三歳の時にはその母とも生別している。理由は、母の実家である水野家の動向が、強大国家、今川家の不興をかうことを父の広忠が恐れたからである。 あわれなのは竹千代であった。三歳で母と生き分れ、六歳の幼さで人質として駿府の今川家に送られていく。が、その途中、広忠が後添いに迎えた妻の父、戸田宗光(康光ともいう)に欺かれ、その身柄を永楽銭百貫文(『三河物語』大久保彦左衛門)で敵方の織田家に売りとばされる。 これが家康七十五年の人生の中で遭遇した最初の"大難"であった。家康の悲運は、そんな想像を絶した"四度の大難"と"六度の大戦"に見舞われていることであろう。 "四度の大難"というのは、 一、織田へ売られたとき(六歳) 二、三河の一向一揆のとき(二十二歳) 三、三方ヶ原の大敗戦のとき(三十一歳) 四、本能寺の変のとき(四十一歳) であり、また"六度の大戦"というのは、 一、姉川の戦い(二十九歳) 二、三方ヶ原の戦(三十一歳) 三、長篠の戦い(三十四歳) 四、小牧長久手の役(四十三歳) 五、関ケ原の合戦(五十九歳) 六、大坂ノ陣(七十三歳) そしてこの大難と大戦の両方に出てくるのが三方ヶ原の一件である。
――元亀 「時こそいたれり」
風林火山の軍旗をはためかせた三万五千の遠征軍は、一路、京を目指して進撃の途についた。信玄の上洛をはばむものはない。尾張の織田信長にしても、所詮、信玄の敵ではない。織田同盟の最前線基地にある家康から援軍を懇願された信長は、三千の兵を差し向けたものの、出発する武将たちに「信玄と戦うてはならぬ」と、強く言いふくめている。信長は、戦国の古豪ともいう信玄と戦う愚を知っている。この巨大な敵に向かうには時機 「三河殿も、いまは息をひそめて時を稼がれよ」 と信長はいう。それはそうである。家康の手元にあるのは徳川八千の軍兵と、義理で出向してきている織田援軍三千である。全兵力を投入して兆戦してみたところで、百に一つの勝算もない。ところが、浜松城での戦評定の場で家康は、思いも寄らぬ下知を下した。 「翌朝、全軍出撃!」 日ごろ、石橋を叩いて叩いて、なお渡ろうとしない慎重な家康が、敗けるとわかった戦に、みずから飛び込んでいったのである。
「いかに信玄が勇猛とはいえ、よもや鬼神ではあるまい。それが、人もなげにわが屋敷うちを踏通ろうとするのじゃぞ、汝
と家康は、土肌色の顔をひきつらせて言いつのったという。この夜の家康は、常になく強引であった。武将たちは口ぐちに無謀さを説いて思いとどろませようとしたが、家康はまるで人変りしたような険しい表情で家臣たちを睨 しかし決断したあとの家康は、心の動揺を抑えるように、しきりに爪を噛んでいたという。
アメリカの軍事医学によると、爪を噛む癖のある兵は、戦闘にのぞむと発狂すると説 西洋史上巨大な権力を握った男のひとりであるアドルフ・ヒトラーにしても、その心理の底流には余人の窺い知れぬ臆病さが秘められていたという。ヒトラー研究の古典というヘデインの『ヒトラー伝』や、バロックの『ヒトラー・独裁政治研究』によると、素顔のかれは《月の光が怖くて》《すこしでも不安をおぼえると小指をしゃぶった》という。とすれば、戦場でふ安に襲われた時、いつも爪を噛みつづけたという家康のそれと酷似している。 ともあれ、三方ヶ原の大地をとどかせて黒つなみのように進撃してくる武田騎馬軍団三万五千にむかって、突撃を敢行した徳川軍は、瞬時にして四散、馬の平首にすがりついて遁走した家康は、背中にすがりついてくる武田軍の叫喚を振り払うように浜松城に逃げ込んだ。恐怖のあまり家康が、鞍壺に脱糞したといわれるのも、この時のことだ。
ところが、いまにも発狂するのではないかと思うような形相で逃げ帰った家康が、がらりと音をたてるほどに人変わりするのは、城の搦手 この瞬間から家康の行動は、いままど表情が嘘のように、不敵なくらいの豪胆さを発揮する。家康は、怒涛のように押し寄せてくる武田軍に防戦するため、城門を閉めようとする城兵を制して、
《城門ハ閉ル事アルベカラズ(略)門ノ内外ニ大篝 と命じ、そのまま城内に入って奥女中に湯漬けを持って来させ三杯掻き込み、その場にごろり横になって高いびきをかいて眠りこんでしまった。 いっぽう、浜松城に迫った武田軍は、真一文字に開かれた大手門、あかあかと大かがり火が燃えたつ城外、城内は、打ち水をして掃ききよめられ、深として人かげもない。この、不敵な無防備ぶりに遅疑し、気を呑まれた武田軍は、 「やぁ、徳川めらは、よほどの計略をたて待ちうけておるぞ」 と、為すところなく引きあげていったという。
こうした家康の"負
徳川美術館に現存するその中の家康は、逃げ帰ったばかりで片方の籠手
家康はこの薄気味悪い画像を、生涯(絵で描 2012.06.05記 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.121~126 |
☆22 徳川家康(下) 我一人の天下とは思うべからず(1,543~1,616年)
|
徳川家康の言行や逸話と伝えられるもののなかに「戦場における指揮官の心得」といった話がある。 《一軍の將たるものは、味方諸人のぼんのくぼばかり見て合戦に勝てるものにてはなく》(『駿河土産』『武功雑記』) 戦闘部隊の將たるものは、(兵士の後頭部ばかり見える)後方の安全地帯にいて口さきばかりの下知(指揮)をしていては、とても戦闘に勝てるものではない。將みずからが勇気をふるいたたせ、敵に突進していくのがよいのだ。 勝敗というものは、その時どきの運次第。勝とうと願っても勝てぬときもあるし、また、思わぬときに勝ちを得ることもある。戦場にのぞんで、いたずらに思案するは、かえって不利をまねくものと心得よ……と家康はいう。 戦場での家康が勇敢であったのは、『徳川実紀』などに登場する次のエピソードを見ればよくわかる。晩年、彼は指の中節にできたタコのために指の屈伸も思うようにならなかった。
これは、若いころから数知れぬ戦場にのぞんだ家康が、最初のうちは采配をかざして指揮しているが、戦いが白熱化してきて 切所
と、身をのりだし、右の拳を固めて鞍の前輪を叩きつけ、その激しさのあまり皮肉が破れて血が流れ、そのようなことが数限りなくあったあらだと説 その野戦の名手であった家康に、「武将」から「政治家」への転換を決断させたのが、豊臣秀吉を敵にまわして戦った小牧長久手の役である。
この戦闘で家康は、神速ともいうべき機動作戦を縦横に駆使して、秀吉軍に強烈な打撃を与え後手 しかし、戦争というのは総力戦である。武力闘争のほかに、政治、外交、経済など、さまざまな要素がふくまれている。家康は局地戦としての"戦闘"に勝ったが、大局的な"戦争"には完膚なきまでの痛撃をうけている。
じじつ、小牧の役ほど覇者への道を驀進 秀吉のこの機略には、一種、商人に似た流動感がある。これは、謀略というよりも「取引」にちかい。秀吉の見事さは、陰に陽に相手の目さきに利をちらつかせて、人を多く殺すことなく味方にひきこんでしまったことだ。 おどろいたことに秀吉は、家康がかついでいた小牧の役のめぃ目人の代表ともいうべき織田信雄までを懐柔し、家康の気づかぬあいだに単独講和をむすんでしまったのである。
こうなると家康の立場はあわれだ。いままで唯一のものとして掲げていた"盟友信長の遺児を守る"という大義名分の旗じるしが、あっ、と気づいたときはすでに秀吉が担
「おのれ、府甲斐 この小牧の役での敗北は、家康の視座を武力から政治へと大きく変換させた。家康の動向はこの頃から「政治」にむかって激しい傾斜をみせる。
家康はふたたび、かつて信長との盟約に無類の律儀 《内府(家康)の律儀さよ》 と信頼をよせられるほどの実直さで恭順ぶりをしめし、忠実にその命を奉じた。 《人は、上下、大小に限らず、事の道理を分別し、知ること専要なり》(『故老諸談』)
防御本能がつよい家康は、自分を守るために、自分を空 《万事、用心のなきというはなく》(『岩淵夜話別集』) そうした家康の「律儀」の上に歳月が流れていく。その年月のあいだ家康は、秀吉から権謀術数や政治の仕組みについて多くのことを学びとっている。家康は、この屈辱に満ちた辛酸の日々を無駄にすごしてはいない。一度懲りれば二度と同じ過失を返さない男である。
「いまに見ておれ、豊臣の奴輩 家康の凄味は、かつて自分に苦汁を飲ませたものを、そっくりそのままのかたちで相手に投げ返し、酷烈きわまりない報復をとげていることだ。
三方ヶ原で信玄に惨敗
豊臣を討滅して天下を掴むというのは、家康の執念でもあった。家康はその一事に、ながい生涯の果ての命の一しずくまでを賭
その大坂(豊臣)が家康挑発にのって軍 こうして関ケ原、大坂冬・夏ノ陣と豊臣方を断滅し、すべての事をなしおえた翌年家康は、しずかに死を迎えている。
死にのぞんだ家康は、なん戸 「まことに、水もたまらぬ斬れ味にて」 そう家康に告げると、家康は皺ばんだ頬に微笑をうかべて、その血刀を手にとり二度、三度、声をあげて素振りをくれ、 「われ、この剣をもってながく徳川の天下を鎮護せん」 といったという。戦国武将の最後を物語るにふさわしい、凄絶なエピソードである。
この時期、家康に迫ってくるおのれの死を予期していたのであろう。最後にのぞんで将軍秀忠(家康の三男)をまねき、老臣の誰彼を呼びよせ、いかにも人生の惨苦ことごとく嘗 《天下は天下之人の天下にして、我一人の天下とは思うべからず。国も又、一国之人の国にして、一人の国にはあらず》(『武蔵燭談』) 日本国六十余州は、そこに住む人びとの天下であって、われ(将軍)ひとりの天下などと思ってはならぬ。諸大みょうたちの領国や、家もまた藩主や家長ひとりのものではない、と人の上にたつ者の独断や専横な振舞いをいましめ、
儂亡 こうして、戦国の長距離ランナー家康は、いかにも実際家の老人らしい訓戒をのこして逝く。安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士。享年七十五.
家康の死後、朴質な三河者たちは、亡主の下知をまもり、その訓 2012.06.06記 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.127~131
人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し。 急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし。
心に望み起こらば、困窮
堪忍 勝つ事ばかり知りて、負くること知らざれば害その身に至る。 己を責めても人を責めるな。及ばざるは過ぎたるより勝れり。 先に行くあとに残るも同じこと 連れて行けぬをわかれぞと思う
「滅びるときには自らの力で滅びよ」
万一徳川家に一大事が起こったときに見るようにと遺した密書が、水戸家に保存されていた。
石川 洋『一燈園法話:人生逃げ場なし』(PHP)P.84
|
☆23 山上 宗二(1,544~1,590年)
|
「一期と一度の会」(『山上宗二記』に「茶湯者覚悟」に書かれている言葉)。これが井伊直弼の「一期一会」の由来と言われている。 *堺の豪商、千利休の高弟。茶の湯の上手で物知りであったが、秀吉にさえお耳にする事申して耳鼻をそがれて惨殺された。 2009.10.24 |
☆24 黒田 如水(1,546~1,604年)分別過ぐれば大事の合戦はなし難し
|
かつて秀吉が近臣たちに、
「この秀吉が死ねば、儂 と、たわむれて言ったことがある。訊かれて近臣たちは困った。応えようがないのである。で、皆がもじもじしていると、秀吉は声をかさねて、 「これは座興ゆえ、思うままに言うてみせよ」 そう促されて近臣たちは、やむなく重い口をひらいたが、かれらの挙げた大みょうのなは、いずれも五大老の徳川家康、前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元といったものであった。 「なにを言うておるか」 秀吉は薄く嗤って、近臣たちをじろりと見、
「ただ一人、天下を掴む者がある。わからぬか、あの瘡 「は?」 近臣たちはいぶかしげな表情をした
秀吉のいうカサ頭は、黒田官兵衛孝高
「わずか十二万二千石の黒田が、どうして天下を奪 近臣たちは口ぐちのそう言うと、秀吉は、 「なんの、なんの、その方らにはまだカサ頭めの根心が読めぬとみえ」 かの高松を攻めしとき、右府(信長公)の訃報をうけ、夜を昼についで東上し、明智光秀を討滅して以来、交戦大小数度におよんでいるが……と秀吉はいう。
それらの大事にのぞんではこの秀吉も、呼吸 「世に怖ろしきものは徳川と黒田よ。されど徳川は温和なり。黒田のカサ頭こそ、なんとも心をゆるし難きものなり」 そう言うと秀吉は、いまいましげに舌を鳴らしたという。
――その黒田孝高(一五四六~一六〇四)。幼名を万吉といい、播磨国(兵庫県)御著 黒田家の出自は、戦国大みょうの多くがそうであるように、はっきりしたものではないが、近江国伊香郡黒田だといわれている。その近江から黒田氏が備前国福岡に転じたのは永正の頃で、戦乱を逃れて更にそこから播磨の御著の地で黒田家は、家伝の目薬「地味膏」を商い、財をふとらせ、小地主になった。 それが運の開けるもとで、孝高の父の頃になると近隣に鳴りひびくほどの大地主にのしあがった。当時、黒田家にあつまる郎党、下男は二百人に及んだという。おりから乱世、大みょうになる基盤はできている。やがて孝高は、小寺官兵衛のなで歴史の舞台に登場する。 中国攻めの軍をひきいて下向した秀吉を姫路城に迎えた孝高は、秀吉に三つの策を献じている。いずれも卓越した策であった。この智謀に舌を巻いた秀吉は、孝高と誓書を交換して兄弟の約を結んだという。
以来、孝高は秀吉の参謀の竹中半兵衛と共に、帷幄 史書によると、そのくだりを、
(此時、秀吉変を聞き、未だ何とも詞
という、本能寺の変の飛報をうけて秀吉が呆然としていると、傍にいた孝高が秀吉の膝をほとほとたたき、微笑をうかべて「ご運の開かせ給うべき時が来たのでござりまする。この機を逃さず、巧 のちに孝高は、このことを秀吉が側近の者に洩らしたという噂を耳にするや、 「南無三宝!わが家に禍い迫ったわ」 と髪をおろして隠居し、如水を号し、家督を嫡子の長政にゆずってしまった。 そしてなお孝高は、秀吉の疑心を避けるために側近を離れず、参謀として、小田原征伐、朝鮮の役に従っている。こんなところははいかにも孝高らしい、芸の細やかな行動である。 秀吉の死後、孝高は家康に与したが、心底では「あわよくば天下を」と虎視眈々、野心を燃やしつづけている。
と、運よく関ケ原である。けれど、そんな孝高の心術 「あの阿呆めが」 と、苦りきったという話しがある。 この、関ケ原の騒乱に乗じた孝高のみごとさは、豊前中津を打って出て、豊後、筑前など手当りしだいに攻略しわが手におめるという怪物ぶりを発揮したことであろう。 孝高の心中は、こうして九州全土を制圧したうえ、家康と三成が戦い疲れた頃を見はからって中央に進出し、天下を取ろうという魂胆であった。 (関ケ原の時、家康と三成と取合、百日も手間取らば(二人が戦いに疲れたところで)我九州より攻登り、勝相撲に入りて(漁夫の利を得て)天下を掌の中に握らんと思いたりき) と孝高は後年、臨終の床で長政にそう述懐している。 (その時は、子なる汝も打ち捨て、捨殺して一博打打たんと思いしぞかし。天下を望む(者)は、親も子も顧みては叶わぬなり)
言うと孝高は、紫の袱紗 «軍(いくさ)は死生の界なれば、分別過ぐれば大事の合戦はなし難し》 戦は生きるか死ぬかの大ばくちゆえ、思慮が過ぎては大事の戦はできぬ。時によっては草履と木履を片々にはいても駈け出す心がまえがなくてはならぬ。食物がなければ何事もできぬものなり。ゆえに金銀をつかわず、兵糧をたくわえ一旦緩急の軍陣の用意を心がけておけ、そういったという。 話が前後したが、戦国の勝負師、黒田如水のしぶとさは、関ケ原の戦後、いままでの謀反気など何處吹く風といった顔つきで、ぬけぬけと家康に祝いを述べ、息子の長政のために筑前福岡五十二万石をちゃっかりせしめていることであろう。 ※参考:黒田如水 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.251~255 2021.05.16記 |
|
戦国時代というのは「七たび牢人せねば武士
その戦国の世に、それを絵に描
こうして「渡り武者」となった高虎は、槍をかつぎ具足を背にして戦国の野を放浪する。高虎は不運であった。近江の阿閉淡路守
やがて高虎は手づるを得て織田信長の弟、信行の子、織田七郎兵衛信澄に仕える。ところがこの織田信澄も、妻が明智光秀の女
次に高虎は、秀吉の弟、羽柴秀長に仕え、禄三百石を振り出しに、播州別所攻め、九州の島津攻めで奮迅し、やがて二万石、従五位下
さすがの高虎も、六度目のこの不運にはがっくりした。しかし、後年「戦国の寝業師」と称 この高虎の懸命の「賭け」は当った。かれの遁世を知った豊臣秀吉は、その志をあわれみ、「予に仕えよ」 と高虎の翻意をうながした。召喚の命をうけた高虎は伏見城に赴き、秀吉に拝謁し、伊予七万石の封をうける。秀俊の死から、わずか二ヵ月のことである。
こうしてピンチをチャンスに活 「戦国を生きるに必要なのは、戦場働きよりも、処世の巧妙さであろう」 そのため高虎は、大恩のある秀吉にさえも容赦ない目をむけ、観察しつづけている。 「豊臣の世も、所詮は秀吉一代か」 秀吉の老齢、朝鮮出兵の濫費は諸大みょうと領民を疲弊させ、豊臣政権への魅力を失わしめている。 「となると、次の天下は?」 それは云うまでもなく、関八洲に広大な所領をもつ徳川家康である。高虎は、身をすり寄せるように家康への接近をはかった。そしてやがて秀吉が死病の床につく頃になると高虎は、豊臣色の濃い反徳川派の大みょうたちの動向を探って、その情報を細大もらさず家康のもとに運びこんだ。ほどなく秀吉が死に、家康と反徳川の石田三成党とのあいだに不穏な気がただよいはじめた。ある夜、三成らの家康打倒の陰謀を察知した高虎からの急報によって、家康は大坂の高虎邸に難を避け、危機を脱した。 「佐渡守(高虎)殿は奇特の仁じや」 そんな高虎の行為が、徳川家の重臣たちに不愉快な筈はない。後年、高虎は徳川家に"大忠"の者として外様大みょうでは真っ先に"松平"の姓を許され譜代同然の扱いをうけたのも、諸侯に先んじてわが身を売り込んできた高虎の行動を徳川家が賞したからであろう。 家康が石田党討滅の軍をひきいて天下分け目の関ケ原にむかったのも、開戦前から、時々刻々ちょ変化する諸大みょうたちの動向を細かに報告しつづけた高虎からの諜報によってである。この時期、舞台裏での高虎の活躍は巧妙をきわえている。関ケ原の合戦は小早川秀秋らの裏切りによって形勢は逆転する。が、この裏切り大みょうたちは、開戦直前、家康の密命をうけた高虎が、ひそかに裏面工作をしていたものだ。 関ケ原の陣ののち、これら一連の"功みょう"によって高虎は、一足跳びに二十万万石の大みょうになり、それがやがて二十二万万石……二十七万石……そして伊賀および伊勢半国に山城、大和の一部を加えて三十二万千九百五十石の身上にのしあがっていく。 こうした高虎の処世法を物語るエピソードがある。あるとき、二条城の改築を命じられた高虎は、設計図を二通りつくった。 「このわけが、わかる」 高虎は近習にいった。二種類というのは、誰の目にも不備な図面と、見事にすぐれたもの二種類である。その二つの図面を家康に差し出せば、よい方を家康が採る。当然であろう。で、不備な図面を選ぶのは、もちろん高虎である。こうしてあるじの選んだすぐれた図面をもとに仕事をすすめていく。
「万事、善 と高虎は言ったという。ゴマすりの権化と化したような、世間功者の高虎らしい言葉である。だが、このゴマすりの、名人芸ともいう保身術が、藤堂藩三十二万三千九百五十石を、徳川三百年のあいだ一粒の減封も国替もなく安泰にすごさせたのである。 その高虎が、嫡男高次に遺した全文二十一ヵ条からなる、藩主としての心得がある。それらの中から幾つか掲げてみると、
《一、常によき友と咄し、異(意)見をも請
《一、家中の者共奉公の道、忠こそあらば、小忠を大忠になし、加増をも遣
《一、家中の者、武道の上、傍輩 家臣のどんな小さな手柄でも、それを大きく賞して俸禄を増やしてやるがよい。藩士の中でずばぬけた忠節の士があれば、これを他国の評判になるほどの褒美を与え家来をつけてやるなど、他藩よりも家臣を重用して召使うがよい。
《一、代官物賄
藩士たちの仕事の中でも、徴税や経理、または食糧、弾薬の運搬補給を役目とする者も、戦闘部隊同様に目をかけてやれ。戦場に出て戦う藩士も、後方にあって作戦のため軍需品の補給、輸送やその事務にたずさわる藩士も、車の両輪である、と高虎はいう。いかにも人生の辛苦を甞めてきた、苦労人らしい訓 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.165~169 2021.06.12記 |
☆26 真田幸村 われに挑む一人の男もなきか (1,567~1,615年)
|
戦国騒乱の世というのは、生ぬるい根性では生きられる時代ではなかった。慶長五年(一六〇〇)天下分け目の関ケ原合戦に真田家は"家"を保つため真っ二つに分かれ、幸村は父の昌幸と共に西軍、石田三成に加担、兄の信之は東軍、徳川家康に属して、親子兄弟が袂を分かって戦いにのぞんだ。 が、関ケ原で西軍が壊滅し、戦後、昌幸、幸村父子は罪を得て紀州高野山の久度山に配流の身となる。そして、天下に比類のない軍略で秀吉の舌を巻かせ家康に二度までも苦汁をなめさせ、徳川軍を翻弄した謀將、昌村も、十一年後の慶長十六年(一六一一)、失意のうちに久度山で死ぬ。 以来、幸村は妻子やわずかな家臣とともに更に三年の歳月をこの地で過ごすことになる。久度山での幸村の暮しは困窮をきわめたものであった。 現在も真田家の菩提寺、高野山蓮華定院に残る無心状のなかで幸村は、 「その後ごぶさたを致しております。さて、(使いの者に持たせた)この壺に焼酎をお詰めくだされ。一杯詰めてこぼれぬよう壺の口をしっかり目張りしてくだされ。壺二つに焼酎の件よろしく願いまする」 と、酒を愛した貧しい日々を語り、また、老いのしのびよる身の歎きを姉婿の小山田壹岐守に、しみじみと書き連ねている。
《とかくとかく年のより申し候こと、口惜しく候。我らなどもにわかに年より、殊の外、病者 この手紙からは、テレビや映画などでよく見る、百万の兵馬をひきいて天下を切り取りかねまじき風貌をした印象とはうらはらな、歯がぬけ髭も白くなり、病がちな小男といった幸村の表情が泛びあがってくる。これが現実の幸村であった。現実といえば、幸村は柔和で心やさしい人物であったと、兄の信之の追懐の言葉にある。
九度山での不遇の時代の幸村の見事さは、終始柔和で、わが身を腐らせなかったことであろう。逆境にあっても落ちこまず、心を荒
こうして慶長十九年(一六一四)十月、久度山で朽ち果てるのかと半ば諦めていた人生の涯 「行こうぞ、大坂へ」 決断した瞬間から、幸村は豹変する。
大坂に入城し五千の軍兵を預けられた幸村は、将兵の軍装を燃えたつような赤一色に統一した。風になびかせた真田の旗はもとより、のぼり差物から甲冑にいたるまで、ことごとく真っ赤に染めあげた真田隊の、赤備
《真田左衛門(幸村)赤のぼりを立て一色赤装束にて》(『山口休庵咄
《真田が赤備え、躑躅
赤という色は人の心を昂奮させる色であり、戦場にのぞんだ将兵たちを奮いたたせる色でもあった。幸村自身も、緋おどしの鎧に鹿の角の前立
こうした演出ぶりは、現代にも通用する。人びとの心を目的にむかって直進させるために、軍隊での軍服、工場での制服のような工夫も必要なのである。すぐれたリーダーとしての資格は、いかに部下たちをおのれの統率のもとに魅 にんげん幸村の魅力を語るエピソードの一つに、大坂入城の供をした高野山の庄官(庄屋)の地侍ら百五十四人の男たちがある。久度山幽居十五年のあいだ、幸村の人となりに接した男たちが吸い寄せられるように集まってきたのである。 そして彼らは、この風采のあがらない小柄の老人に嬉々として奮迅し、全員燃えたつ火の玉となって雲霞のような徳川軍団に突撃すること数度、幸村討死の後も、その場を去らずことごとく死んでいくのである。この中には、高野山の奥から鉄砲を肩にやってきた猟師たち三十余名もいる。主将が討死した場合、将兵たちは戦場から落ちのびていくのが戦国の世の常であって、全員戦史というのは異例のことだ。
《真田日本一の兵 そして戦場での幸村は、こうした部下からの信頼に見事に応えている。
翌、元和
《関頭軍勢百万も候 と大声で罵倒し、悠々と引きあげていった(大坂陣『北川覚書』)。
このときの幸村の、あまりに不敵な、惚
戦闘指揮官幸村のすばらしさは、機略縦横の作戦ぶりはもとより、死ぬための戦いでしかなかった夏ノ陣の悪戦苦闘の中にあっても悲愴感さえ泛べていなかったことであろう。肩ひじを張ったり、まなじりを吊りあげたりすることなく自然体で、それどころか最後の突撃に入る前日など、どこで死んだら一番分
世に人使いの名手というのがある。傍 それにしても、河内の野をうずめつくすような徳川軍団の前に進み出た幸村が、「関東軍百万もあれど、われに挑む一人の男(武士)もなきか」と叫んだという光景は、事にのぞんだ際のリーダーのあるべき姿を描きだしている。
戦国の世に残すべき"家"をもたなかった幸村が、歴史のなかで遺 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.77~81 2012.05.26記 |
☆27 伊達 政宗 仁に過れば弱くなる、義に過れば固くなる(1,567~1,636年)
|
戦国の梟雄といわれた伊達政宗は、晩年、波瀾をきわめたみずからの生涯を振り返って一つの詩を詠んでいる。 馬上少年過ぐ 世平らかにし白髪多し
残躯
楽しまざるをこれ如何
少年と書いて、わかき年とよむのであろう。この清々
正宗は、その誕生からして劇的であった。母は出羽山形城主、最上修理大夫義守の娘、義子で、戦国の世のならいで米沢城の伊達輝宗のもとに輿入れしたが、この美貌の新妻は"鬼婆"とよばれたほど勝気で驕慢であった。嫁して五年、子宝にめぐまれず、やがて伊達家の老臣たちから離別ばなしがもちあがり、輝宗に側室をすすめよという話がでてきた。
この噂を耳にして目を吊り上げた義子は、高名な和尚を湯殿山に籠らせ、わが身も白衣をまとい護摩を焚き、死物狂いの祈願をつづける。こうして懐妊した義子は、世子、梵天丸(正宗)を生み落した。梵天丸は勝気な母の意地と執念が生ませた奇蹟の子であった。
だが、こうした稚
美貌でわがままな母は、みにくい正宗を嫌い、正宗の弟竺丸を溺愛し、夫の輝宗に再三、正宗を廃嫡し竺丸を跡継ぎにしようと働きかける。そして輝宗が同意しないとみると、刺客を正宗の寝所におくりこみ、眠りこんでいる正宗を絞殺しようとくわだてるが、事は未然に破れる。
しかし、こんなことで断念する義子ではない、次には毒殺をはかるが、これもまた未遂におわる。危険を感じた父の輝宗は、家督争いの根を絶つため、天正十二年(一五八四)正宗に伊達家十七代の当主の座をゆずり、隠居してしまった。ときに正宗十八歳である。
のち正宗は、父の輝宗が敵方の畠山義継に拉致されたのを知って駈けつけ、畠山を銃撃して殺すが輝宗はそのとき義継から刺殺されるという、正宗生涯最大の悲劇が起こっている。
ともあれ、輝宗の死によって伊達家中に完全な独裁権力を築いた正宗は、以来、二万三千余騎の伊達軍団をひきい奥羽の覇者街道疾駆しつずける。
父の死の翌日、芦な、佐竹、岩城、石川ら連合軍三万を相手に激戦をくりひろげ、剽悍無類の武みょうを天下にひびかせ、やがて、仙道七郎を征服し、さらに出羽国に進撃し所領百万石。二十三歳にして、かつての藤原三代と肩を並べるほどの広大な領土をわが手に掴んだ。
天正十八年(一五九〇)豊臣秀吉が小田原の北条氏討伐の軍をおこし、奥羽の諸大みょうに小田原参陣をもとめたとき正宗は、
「いまは と形勢を観望して、出兵をしぶっていた。
その後、戦況は北条氏に不利とみた正宗は、ようやく重い腰をあげた。このときの正宗の演出ぶりは見事である。秀吉に謁見するにあたって、髪を水引で結び、白衣の死装束で諸大みょうの居並ぶなかを、秀吉の前に膝行 これが効を奏したのか、旧芦な領は没収されたものの七十余万石は安泰であった。 正宗の二度目の危機は、戦国の葛西大崎の一揆を正宗が背後から煽動しているという疑いをかけられた時である。※葛西大崎一揆(かさいおおさきいっき)は、天正18年(1590年)に発生した、豊臣秀吉の奥州仕置により改易された葛西氏・大崎氏らの旧臣による新領主の木村吉清・清久父子に対する反乱である。
この時も正宗は、行列の先頭に金箔を貼りつめたわが身の磔
こうして一歩踏みはずせば奈落に転落しようという修羅を踏みこえてきた正宗に、次のような
《一、仁に過ぐれば弱くなる
義に過ぐれば固くなる
礼に過ぐれば諂
智に過ぎれば嘘をつく
信に過れば搊をする
一、気長く心穏やかにして、万
一、朝夕の食事はうまからずともほめて食ふべし。元来客の身になれば好嫌ひは申されまじ
一、今日行
仁・義・礼・智・信の五常、五倫(りん)を政宗流に解釈し、苦しいことや不自由なることがあっても「この世に客にきた」と思えばよいのだ。たとえ、朝夕の食事がまずくとも、「この世に客にきた身だ」と思って喰ってやれ、と政宗は説
おさない頃から辛酸をなめてきただけに、正宗には人に接する時の気くばりがある。
《かりそめにも人に振舞うとあらば、料理第一と心得よ》
人に馳走するときは、家人だけにまかせず、主人も目くばりしてその人の好むものを品よく出すべきである。
相手の身分にかかわらず、正宗が心くばりをしたという例が、次のエピソードの中に読みとることができる。
――あるとき伊達邸へ、友人の毛利長門守がきた。長門守は違い棚に置かれていた「香匙火箸」
これは模様のよい香匙でござる、いずれ拝借して写したいものよ」
「いつにても、お持ちな」
何日か経ったある日、長門守から
「いつぞや約束の香匙を借りてまいれ」
と家臣のひとりが使者を仰せつかった。その家臣は、聞きなれぬ品物のなに、それから先、馬に乗るのにも降りるのにも、口のなかでもごもご、
「香匙火箸、香匙火箸」
と呟き呟き、伊達邸へ着いた。そして取次に出た伊達の家臣に、早速、香匙火箸の借用を申し入れた。
「香匙火箸?」
そういうと伊達の家臣のほうも耳なれない品のなを呪文
ところが、数多い部屋の唐紙を開け閉めし、立つたり坐ったりしているちに、ころりと「借用の品物」のなを忘れてしまった。
「ええい、いま一度訊いてくるか」
と、小走りに使者の前まできて、
「さて、先ほどお伺い申しましたあの品のなは?」
だが、運の悪いことに使者の方も、取次の者に述べた途端、吻
その手紙には「今日の使者ぶり、あつぱれ日本一の者、よき褒美(を与え)なされたし」と書かれていた。正宗は、借用の品のなを失念し苦しまぎれに「わが(毛利)家の作法」と胸を張った使者の、その武辺者らしい負けぬ気を愛したのであろう。使者の家臣は即日、長門守から加増されたという。
神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.188~194
|
|
小人は縁に出会うて縁に気づかず。 中人は縁に出会うて縁を生かさず。 大人は袖触れおうた縁。 (徳川家の剣術指南を担当した柳生家の家訓) 【覚書き|才能の無い人間はチャンスに気づかない。中の才能の者はチャンスに気づいているが飛びつかない。とても才能のある人間は、袖が触れるほどの些細なチャンスも逃さない。大物になる人物はチャンスに敏感であるという意味の言葉】 |
|
『五 輪 書』 宮本武蔵著 渡辺一郎校註(岩波文庫)
一 千日の稽古を鍛 独 行 道 解 説 P.164 一、世々の道をそむく事なし。 一、身にたのしみをたくまず。 一、我事のおゐて後悔をせず。 一、仏神は貴し、仏神をたのまず。 私見:自分の仕事:自分の仕事は、自分がやっている自分の仕事だと思うのはとんでもないことで、ほんとうは世の中にやらせてもらっている世の中の仕事である。ここに仕事の意義がある。 一 我以外皆我師 参考:『宮本武蔵』で知られる作家の吉川英治が、その著書の中で記した言葉である。武蔵の言との説もあるそうだが、実際は、吉川氏が好んで使っていたという。
|
|
銭
唸る……といえば、いまから千年ほど昔の中国に袁
「ああ、それはカネが友(金
と破顔 で、そのカネの話だが、戦国のころ、金銀に異常な執着をもつ武士がいた。
《陸奥の国、蒲生氏郷
つねに角栄螺 ところがこの左内、世にもまれな金銀好きで、並はずれた倹約家で家来にも常に口ぐせのように、
「銭を蓄 と倹約、貯蓄を奨励し、自分から率先して、 《常に草履をつくり、売る》(『土稿会談』)
という、なりふりかまわぬ蓄銭癖をみせ、せっせと銭を貯
この左内の唯一の愉
《一月 と、稼ぎためた大判や小判、銀貨などを座敷中に撒き散らし、ふんどし一つの裸になってその上でころげまわることぐらいだ。
「あような呆気
という家中の侍たちの陰口も耳に入ってくる。が、いかに吝嗇野情と称
《あるとき、いつもの如く金銀を並べて居りしに、近きあたり(近所)の士あらそいをし出し、方人 座敷いっぱいに撒き散らした金銭をそのままに、喧嘩を仲裁して左内が帰ってきたのはその翌日であった。その間、左内は、金銀のことをすこしも気にする様子はなかったという。
左内の馬の口取りをしている中間
《金の徳は天下の人をも従えつべし。汝 手文庫のなかから小判十枚を取りだし、中間に与えたとう。
上田秋成の『雨月物語』のなかの「貧福論」によると、その夜、黄金の精が左内の夢枕にあらわれて、夜っぴて左内と金銭論、経済、処世、貧福論をかわし、遠寺の鐘が五更 ※参考図書:『雨月物語巻之五』「貧福論」日本古典全書〚上田秋成〛(朝日新聞社)P.162~ 後年、蒲生家が減封されて宇都宮に移っていったため、会津に土着した左内、新領主の上杉家に召し抱えられて知行千石。
そののち、上杉家が石田三成と呼応し、反徳川の軍を挙げたとき左内は、「軍費の御用意のため、永 当時、新領土会津に移ってから二年という上杉家の財政は"戦争"をするにしても窮迫のどん底にあった。主家でさえそんな状態だから、家臣たちの貧寒ぶりはあわれなものだ。にわかの出陣の支度に狼狽した同僚の一人が、守銭奴と陰口していたにもかかわらず、左内の前に低頭して、泣くような声で借金を申しこんだ。 「ああ、よろしゅうござる」
吝嗇だと思っていた左内が、案に相違して明るい顔つきで、きりだした額そのまま貸してくれたので喜び、踵 「なるほど、かねてから左内殿が金を大事にしろというたのは、この時の備えがためであったのか」 以来、家中の者は誰ひとり左内の悪口を言わなくなった。
そのうえ、このときの伊達政宗軍との合戦、摺上川 その左内に、背後から迫った黒革おどしの鎧、三日月の前立物をした兜をかぶった黒武者が、背中めがけて一太刀斬りつけた。一瞬、振り返りざま左内は、片手なぐりに相手の兜の真っ向から鞍の前壺まで斬りつけ、返す二の太刀で兜のシコロを斬り飛ばし相手の太刀を斬り折り、三太刀目で右の膝口を斬撃し、黒武者を遁走させている。 「おのれ卑怯なり馬を返して勝負せよ!」 と左内は呶号した。その黒武者が、じつは敵将、伊達正宗であった。 左内の奮戦にもかかわらず上杉家は、関ケ原ののち家康から国替えと減封に処せられている。左内はふたたび牢人。その後、左内があの時の荒武者だと知った政宗は、その武勇を愛し三万石をもって招こうとした。だが左内は辞退し、会津若松六十三万石に返り咲いた旧主、蒲生家に一万石で仕えた。 帰り新参として蒲生家に出仕した左内の蓄銭癖は、更に昂じている。
金
後年、みずから死期を覚った左内は、病床から主君、忠郷
この左内の弟、岡備中守の娘と山鹿六右衛門のあいだに生れたのが、山鹿流軍学の祖で赤穂藩家老、大石内蔵助の師、山鹿甚五左衛門、素行 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.278~282 2021.06.29記 |
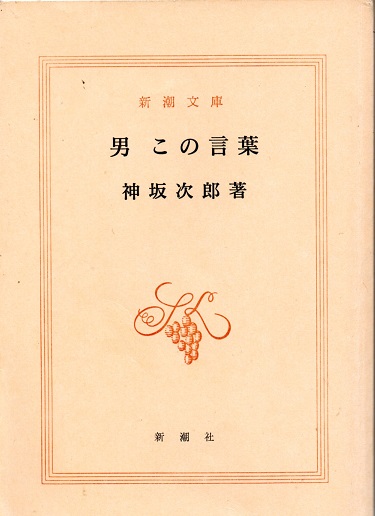
いつの世の"戦争"でも、どの時代の"商売"にしても、いち早く情報をつかんで素迅 いまから三百年ほど前の天和・貞享年間、これに気づいて実行したのが柏屋こと柏原家初代の三右衛門である。 柏原家の系譜によると、初代の三右衛門は肥後熊本の加藤家の臣、柏原郷右衛門の後裔で京都の人(『柏原洋紙店八十年史』)。京の問屋町、五条下ル三丁目で呉huku や小間物の仕入販売をおこなっていたが、堅実な商いぶりによって三右衛門は、京都人が理想とする、全国の諸大みょうが集まってくる江戸に店舗をかまえる「江戸店持ち京商人」に成長し、豪商への道を歩きはじめる。
新興商人として登場した柏屋の特徴は、従来の大商人たちがその『家訓』のなかで、《新儀停止 《一業専心》
と経営の多角化を戒め、それを忠実に守りつづけたのと逆に、小間物諸色 この柏屋商法の特色は、既成の大商人たちが米を中心にした大みょうや裕福な町人たちのみを得意先にしていたのを尻目に、江戸という世界第一の消費地に住むおびただしい数の庶民大衆を"商売"の相手に、かれらが必要とする品物を売りさばいたことであろう。
柏家のこの多角経営のシステムは、各業種各店の搊失、危険をたがいに支えあい扶 それまでの商人たちと生き方を異にした柏屋は、こうして京に本店(柏原本家)をすえ、柏屋グループの陣頭に立った柏原家の当主は、諸店の資金運用、商品仕入れに専念し、これらを集中管理するための決算書を作成、経営の合理化をはかっている。 つまり、江戸の諸店は年間の純利益を本店におさめ、次の年度の資金を本店から借り入れるという方法をとり、また、この運営の安全をはかるため、江戸店から番頭が絶えず京都本店と連絡をとり、本店の指示をうける。なかでも、商品相場や市場の情報には金額を惜しまず超特急の「仕立便」を用いるよう本店から厳命されていた。 当時の『江戸飛脚便仲間定制』によると、江戸・大坂間の飛脚便の種類は「並便」「幸便」「仕立便」の三つからなっている。並便は便をまとめて一定の日に発送するのでおよそ二十五日。幸便というのは、定日にまとめて発送するのだが、飛脚は昼夜兼行で走行するため所要日は十日。超特急便の仕立便になると、即刻、飛脚が突っ走って大坂まで三日半から五日というすさまじい速さで書状が届けられていた。この三日半便になると、百匁の重さの書状で七両二分。仮りに一両を現在の十万円とすると七十五万円になる。が、 《(相場の)高下に付き存じ入りこれ有り候節は……》(柏原家『家内定法帳』十八箇条) という家訓をみれば、柏原家がいかに情報を"商人のいのち"として重視していたかかがわかる。そしてその通信文も、金額や日時、商品名なども極秘を守るため秘密の符号を使っていた。数字にしても、 《一(き)二(や)三(う)四(の)五(ね)六(江)七(と)八(て)九(み)十(る)》 と記した。この符号を一から十まで連ねてみると、 《京の値江戸で見る》 と、いかにも京商人らしい符牒になる。 柏屋グループが江戸で扱う商品の大部分は、京、大坂に集結する西国物で、土佐や伊予の紙、河内の木綿、京呉服や扇、小間物、紀州黒江の漆器などであった。これらの商品のなかでも、江戸へ海上輸送された大衆向きの河内木綿は、木綿問屋としての柏屋を一躍、天下第一の太物(木綿)問屋の地位に押しあげてしまった。(『江戸呉服問屋長者番付』寛政期)。 だが、柏屋の後継者たちは細心であった。それでもなお気をゆるめず、いかにすれば柏屋が安泰に存続できるかという心をくだいていた。この勢いに乗じて増資をし、どれだけ店舗を増やすか、などというよりも、いかに手堅く柏屋を守るかというほうが大事であった。 大みょうなら、よほど重大な失態かふ始末さえなければ御家安泰の保障はされるが、商家はどれほど豪商になっても、明日の安泰を保障してくれるものは何もないのだ。安心も油断もできぬ日が、来る日も来る日もやってくるのだ。初代三右衛門……二代孫左衛門……三代助右衛門……四代孫左衛門……五代三右衛門と、柏屋の当主たちは、絶えず危機意識を抱きながら"豪商"としての道を踏みしめていった。 当主といっても、考えてみれば、柏屋の"家"を守り、次代へゆずり渡すための、 「家を預かっている奉公人」 にすぎないのであった。その"家"の運営にしても、当主の独断専制ではない。柏屋に長く勤めた功労多い番頭の中から"別家"にとりたてられた人びとや、その別家のなかの古参の"老分"などが、本家当主を中心にした会議に加わる、一種の合議制なのだ。 老分や別家の人びとは、主人よりも主家の家業を優先させる権限を柏原本家から与えられていた。まんいち、主人に素行不良や独断経営の行動があった場合、その行状を詰問し糾弾し、当主の座から追放することさえもできたという。 こうした柏原家歴代の主従の心の根にあるのは、人よりも家、主人よりも店という強烈な経営思想であり、冷徹なまでの家業意識であった。
《一、店の商売
《一、自分商売 《一、ふ働き(怠け者)又は我儘致し候やから之あり候わば、相共に意見申すべく候、再三不得心の上は暇(解雇)遣し申すべき事》
《何事によらず惣じて大事は小事より発 柏原家におけるこのファミリ・コントロール要綱『家内定法帳』は、年ごとに激化する経済競争に対処し、商業経営における安定基礎おつくるため柏屋主従のあいだで強く守りつがれていた。こうして京、江戸の巨商として発展をつづけていく柏原家に、さまざまな豪商の血が流れこんでくる。
京都第一の富商といわれた那波屋から迎えた養子、八代目孫左衛門のもとに三井家、宗睦の娘が嫁し、さらに九代目孫左衛門のところに松坂屋、伊藤次郎左衛門の愛娘 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.82~86 2021.06.13記 |
|
「紀州は南海に突出して、西のかたは阿波、淡路を制し、北は京都、近畿をひかえ、東方は大和、伊勢につらなり西国第一の要衝である。ゆえに至親の者に守らしめよ」 との家康の遺命をふくんだ頼宣は、駿河、遠江(静岡県)五十万石の地を離れて紀州に入国する。 これが俗にいう"駿河越え"である。このとき頼宣に従ってお国入りをしたのは家臣ばかりではない。おびただしい数の百姓や商工業者も加わり、ちょっとした民族の大移動の観があったという。そのせいか、城下町和歌山の方言は、いまも三河方言の残欠を尾骶骨のようにとどめている。こうして徳川御三家の一、紀州一国と伊勢の一部をくわえて五十五万五千石の紀州徳川家が誕生する。 頼宣の向う気の強さは、十四歳で大坂の陣に初陣したときの話からもうかがえる。先陣をゆるされず、その不満を茶臼山の本陣にいる家康に訴え、涙をこぼして口惜しがった(『藩翰譜』)。 と、傍にいた松平右衛門大夫が慰め顔に、 「若君はこの先、まだ幾度か先陣の機会もござりましよう」 そういうと頼宣は、 「おのれ、この頼宣に十四歳が二度あるか」 と睨みつかたという。
そんな頼宣の覇気を、家康は愛していたようであった。そしてそのような頼宣であればこそ《紀州の地、治世し難し》と、諸国でも治めにくい国の一つとされていた紀州を懐柔し、あるいは恫喝し、よくおのれの掌中のものとし得たのであろう。当時の紀州は寺領七十万石を豪語する根来 頼宣はその不穏の気の充ち満ちた紀州に武を備え、産業の振興に力をそそぎ、新領土の国づくりに非凡な才腕をふるう。そうした治世のなかで、ひときわ目につくのが、万治三年(一六六〇)の正月、みずから筆をとってしたため、領民たちに公布した『父母状』であろう。これにまつわる一つのエピソードがある。 ある年、山ふかい熊野の奥で、父親を殺害した男が捕まった。
捕縛された男は、すぐに調べられたが、目を吊り上げて役人をにらみつけ、「なにを、吐 と、うそぶき、悔いる様子もない。これには、役人も手を焼いた。言葉をつくして、親殺しがどのような大罪であるかを説いても、諭しても、この男には通じないのである。 始末に困った役人は、思いあぐねた末、上役に報告した。 その報告が、やがて頼宣のもとにとどけられた。 おりから夏のことで、扇子をつかいながら聞いていた頼宣は、やがてぱちりと扇子をたたみ、頬づえをついたまま、ながいあいだ考えこんでいた。 「おそろしいことだの」 しばらくして頼宣は、溜息した。 「いかに熊野の山中とはいえ、わが領内でかように禽獣(鳥や獣)にも劣る者を出したのは、すべて予の不徳のいたすところ。かというて、わが罪を知らぬそやつを、そのまま罰することもなるまい」 人いちばい孝行心のつよい頼宣には、親殺しなどとは想像することもできなかった。 頼宣は、その男の身柄を和歌山城下の獄舎に移させると、儒者の李梅渓に命じて牢獄の中で孝経の教えを説かせた。 こうして梅渓の牢獄通いがはじまる。 しかし、それは徒労であった。 大学者、李梅渓の心をこめた孝経の講義も、熊野山中で自儘に生きてきた男の耳には遠いようであった。 そして一年たち、二年たち、三年目に入った。 そんなある日、いつもは挙措おだやかな梅渓が、あわただしい足どりで登城し、頼宣の前に進みでた。 梅渓は、唇をふるわせた。
「か、かの男め……はじめて涙をこぼし"いままで人の道もわきまえず生きてきたわが身が恐ろしい。このうえは一刻も早う、御成敗くだされ"と頭 梅渓の報告に、頼宣はゆっくりうなずいた。 「おのれの非を悔い、にんげんの道理をわきまえたなれば、ふびんながら"法"にしたがわせよ」 で、ほどなく男は処刑されたと『大人雑記』にいう。 この事件があった後、頼宣はふたたびこのような心得ちがいの者が出ぬようにとの思いで書きあげたのが、『父母状』である。
《父母に孝行に 法度 頼宣はこの文字を李梅渓に書かせ、謄本をとらせて広く領内の士庶に配布した。以来、この六十余字が紀州藩の道徳教育の教科書となり、明治のころまでつづいた。
剛毅快闊で、みずからを南海の竜 その頼宣に、寛永寺の長老が 「南竜公と申された頃とは、ずいぶんお変りなされました」
そう言うと頼宣は、自嘲するような口吻 「なんの、睡竜(眠り竜)とてまだ夢をみる」
と嗤 頼宣は晩年、『紀伊亜相頼宣卿訓論』として、「若き大将の心得べき事」「老職(重役)の若き輩の心得べき事」「頭職の心得べき事」など、さまざまな訓
《一、御感 一、物ごとになずみ(馴れしたしみ)うばれる(心奪わる)べからず 一、心の留守之なき様に仕るべし》
そして主人たる者もまた、知恵才覚のある家臣の意見によく耳を傾け、これをわが身の役に立てれば、自分はひとりであっても《家老、大身 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.195~200 2021.06.26記 |
☆33中江 藤樹(1,608~1,648年)
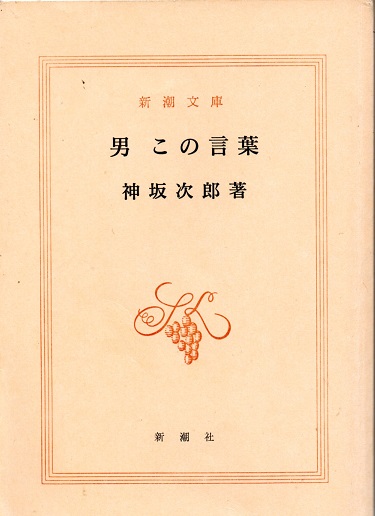
なもない車曳きから天下の巨富を掴んでのしあがった元禄の開発事業家 通称を十(重)右衛門。生活の道をもとめて十三歳で江戸にむかう。が、生き馬の目をぬくという江戸での車力(車曳き)暮しに絶望した彼は、やがて都落ちをする。 その失意の道中の小田原で、十右衛門は旅の僧から、 「惜しいのう、おぬしの人相には立身、富貴の相がでておるに、それを江戸に捨ててきたのか」 そう言われて十右衛門は、ふたたび江戸へ引き返していく。そして品川の海岸まできたとき、おりから盂蘭盆すぎて浜辺には仏前に供えた胡瓜や茄子がおびただしく打ちあげられていた。 「これだ、これだ」
それをみた十右衛門は、近くにいた乞食たちに銭をやり、それを拾い集めさせ漬物にして売りだし、大もうけをした。こうして稼いだ金を資金に、大八車を買い求め車曳きたちを集め事業としての車力業の第一歩を踏みだした。おりから江戸は、市街地造成の真最中で、建設現場は活況を呈し、普請場に運ばれていく土石や木材の車や、河岸
大江戸開発ブームの花形である車両運送の親方になった十右衛門は、稼ぎ集めた金を投入して材木商となり、深川霊巌島に住む。当時の材木商というのは普請と作事 こうして車力の親方十右衛門から材木商土木建築業河村瑞賢(瑞賢は号)へと転身した彼の前に、明暦三年(一六五七)江戸城をはじめ江戸市街の大部分を焼きつくすという未曽有の大火、本郷の本妙寺で娘の供養のため振袖を焼いたのが原因となった「振袖火事」がおこる。 「いまだっ!」 瑞賢は機を見るに敏であった。 わが家に迫る火の手を尻目に、手元にあった十両を懐中につっこむとまっしぐらに木曾へ走った。
瑞賢は素迅
江戸大火の風評
子供が貰った小判の玩具におどろいた主人は、瑞賢をよほどの分限者(富豪)と思ったのであろう。あとから金をもってくる番頭をを待っているという瑞賢に、持ち山すべての材木を売り渡す証文に印を捺した。そして、瑞賢が傭 が、すでに遅い。かれらはみな瑞賢から彼の言い値で高価な材木を買うしかなかった。材木商たちに売却した代金で山林王への支払いをすませ、残りの大量の材木を江戸に運んだ瑞賢は、他の材木商よりはるかに安い材木を売りだし、すべて売りつくして巨利を博した……という。
当時、江戸の町では、「抜群の知恵者」ということを人びとは「瑞賢ぶり」と言い囃
あるとき、芝、増上寺本坊の大屋根の棟瓦 「なんの、造作もないこと。まあ、御覧じあれ」
そいうと瑞賢は、大凧をつくり、本坊の前で空高くあげた。凧は、長い凧糸をつけたまま本坊の屋根を越えて、本坊の裏手に降りた。瑞賢がその糸を手繰ると、凧糸はやがて紐 江戸の巷で語られたこれらの瑞賢の工夫や出世譚の信憑性はさておき、瑞賢が万人にぬきでた知恵働きと、みごとなばかりの決断(実行)力の持ち主であったことは明白である。 デベロツパーとしての瑞賢の偉大さは「幕府御用」の金看板のもとに海運界の地方分権(諸国大みょう領)を解体し、幕府のお声がかりの事業として奥州(福島、宮城、岩手、青森)からの東廻りの航路、そして近世海運史上画期的ともいう出羽(山形)からの西廻り航路を開発したことであろう。 従来、東廻りの場合、那珂湊(茨木)や銚子で陸揚げし、江戸に向い、西廻りなら敦賀(福井)などで陸揚げして陸路をとらねばならぬという不自由さがあった。
陸上輸送といえば、仮に大坂から江戸へ千石の米を運ぶとすれば馬千二百五十頭、馬子 瑞賢のこの陸路を併用しない本州一周航路の出現によって、経費や日数は激減し、米俵の荷くずれや損耗もなく、その他の物産も安価に輸送され、江戸、大坂はもとより諸国の都市に飛躍的な繁栄をもたらした。 瑞賢はこの新航路開発の功績によって幕府から三千両を与えられ、その後、大坂安治川の開削や、 《銀千貫目を一息(一瞬)に儲けた》(『商売記』三井高治) という京都御所の入札や、採掘銀の入札や、採掘銀半分を与えられるという幕府銀山の経営など、国家規模の開発事業家として巨万の富をたくわえている。 元禄十一年(一六九八)、将軍綱吉に謁見をゆるされ、旗本となった瑞賢は、河村平太夫を称して立身をきわめ、翌年、波瀾に満ちた人生の幕をとじている。享年八十二. 瑞賢は晩年、その著のなかで、
《夢幻の身を以て夢幻の身を育て夢幻の身を厭
と説う。徒手空拳で天下一の政商となり、旗本にまでのしあがった瑞賢にも似ぬ、気弱な、無常感に満ちた語である。功成りな遂げた彼が、人生の涯 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.228~232 2021.06.09記 |
☆35 山崎 闇斎(1,619~1,682年)
|
一
幼少の頃の山崎闇斎は、手に負へないいたづらッ子であったらしい。京都の下立賣で生まれて、そこで育ったのであるが、六つ七つで、竿を持つて堀河橋へ出て、通行人の脛を打つては、水中へ落して面白がる。悪戯もよほど悪性だつたのである。
二 最初に闇斎の少年の逸話を叙したが、それらの逸話に現われた闇斎の性格の烈しさは、一生涯附いて廻つてゐた。闇斎は正に烈火の如き教育家だつた。何者をも灼き盡さずんば止まぬ概があつた。 その面に、常に怒気を帯びてゐたとかと思はれる闇斎が、果して理想的な教育者型かどうかに就いては、疑問の余地があるかも知れぬ。しかし少なくも闇斎は、活きたる教育者であった。門人が、途上に美色を見て心の動いたりする時に、一念先生のことに及べば、忽ちにして心が引き締まるといつたといふ。かやうな強い教育力を持つた先生を、またいづこに求めようか。 佐藤直方は、闇斎門下の三傑の一人であるが、その直方にしてなほ且つ、「昔、闇斎先生に就いてゐた時には、その家へはひるごとに、内心びくびくして、獄にでも下るやうな気持だつた。辭して表へ出ると、始めてほつとして虎口を逃れたやうな心地がした」と告白してゐる。かやうな威力を有する先生が、さう求められるものはない。
門人の楢崎正員
もし闇斎の人物の短所はといつたら、あまりにもゆとりのなかつたことが挙げられるかも知れない。しかしそのゆとりのないのが、一面闇斎の長所であつたのである。崎門に於ては一も學問、二にも學問、三にも學問だつた。書物なども、餘白もないまでに書入してあるのが喜ばれた。聖賢の書からなどと、綺麗なまゝで持つてゐようとしたりすると、却つて叱られた。徹頭徹尾學問本位だつたのである。かやうな教育法に依つて、闇斎の門下からは、佐藤直方が出た。浅見絅斎 三 以上は主として『日本道學淵源録』に據つたのであるが、なほ『貫川記聞』といふ殆ど知られてゐない寫本に、闇斎の言行の一二の記してあるのを、序に紹介して置こう。『貫川記聞』は、闇斎からは孫弟子になる若林強斎の談話を、その門人の筆録したものである。 「崎先生が、俗儒を抱へようよりも、事文類聚を買つて置いた方がよい。扶持をいたゞきたいとも、御加増が願ひたいともいはなくてもよい、と仰せられた。尤もなことぢや」 その一つにかやうにある。たゞ知識を授けることならば、何も活きた人を俟たない。眞儒には――眞の教育家には、それ以上のものがなくいてはならないのである。然も現代にも、死んでゐる書物の受賣だけをしてゐる教師がいかに多いことか。 闇斎が他の儒者達と、会津侯保科正之に侍坐してゐた時のことである。正之が、『論語』の「父母はたゞ其の疾をこれ憂ふ「の章に兩説のあることを擧げて、「一方に片づけたいものだが、いかゞであらうか」といつたのに、闇斎は、「兩説共に一理ありますので、俄かに一方に極めるわけにはまゐりませぬ」と申し上げた。すると儒者の一人が横から口を出して、「嘉右衛門殿は御子がないから御存じあるまいが、拙者などは子供を持つてござれば、子を思ふ情はよく分かつて居ることでござる。父母は病をしようかと憂ふると説く方が適切でござろうと存ずる」と、憚りもなくいつた。それを聴いた闇斎は、静かに答へて、「なるほど拙者は子供を持ちませぬから、その趣は存じませぬが、しかし大勢子供もあつて、殊に長男をなくなされている朱子が、片づけられぬと申されてゐるのを見ますれば、俄かに一方に極めるわけにはまゐりますまい」といつた。その儒者は一言もなくなつた。これを聴いた正之は、「尤ものこと」と仰せられて、それ以上の穿鑿は止められた。――一時の思附を卒然として口にして、すぐにまた閉口した俗儒の様子が見えるやうである。 四 闇斎は、天和二年九月十六日に京都に没した。歳は六十五であつた。 闇斎もその晩年には、言行がよほど穏かになつてゐた。然も闇斎自身は笑つていつた。「己が以前のやうでないないのを、徳が進んだからだと思うたら、間違ひじゃ。まことは鎗の穂先が碎けたのぢや」と。 この小篇は、闇斎を語つてもとより委細を盡さぬが、それを盡さうとしたら際限がなくなるであろう。最後にその門流の人遊佐木斎の言を擧げて、結語に代へる。
「闇斎先生の人となりや、平生他の嗜好なし。一味學に志して、未だ嘗て俗人と交らず。温厚の氣象足らずと雖も、志剛にして、制行苟(いやし)くもせず。専ら斯道を明かにするを以て己が任となし、死して後止む。學んで厭はず、教へて倦まざる者に庶幾 ※参考:程朱は日本で使われる用語であり、中国では、朱熹がみずからの先駆者と位置づけた北宋の程頤と合わせて程朱学(程朱理学)・程朱学派と呼ばれ、宋明理学に属す。
森 銑三著作集 第八巻 人物篇八 儒学者研究 (中央公論社)P.11~15より
|
☆36 三井高利 単木は折れ易く、林木は折れ難し(1,622~1,694年)
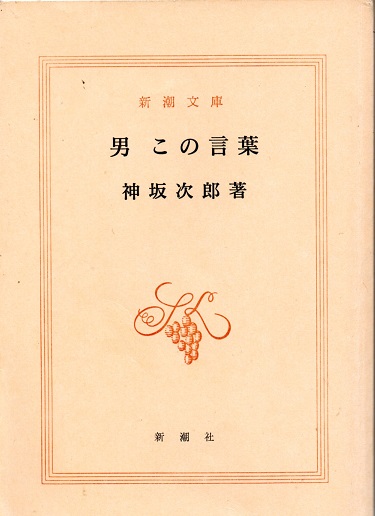
伊勢松坂の越後屋、三井高俊の女房(法名を殊法 この四男が、三井財閥三百年の繁栄の基礎を築いた三井八郎兵衛高利(一六二二~九四)である。少年期の高利は、この松坂の店で母から、商家の丁稚として厳しくしつけられていた。
当時の商人の理想は「江戸店 「お前も、江戸の兄の店で商売を習うてくるがいい。その路銀に、これを持ってお行き」 そういうと殊法は、十両分の松坂木綿を馬の鞍につけた。道中、これを売り旅費を稼いで行けというのだ。こうして江戸にむかった高利は、道々それを売りながら旅費を稼ぎだしたばかりでなく、たっぷり小遣銭まで懐中に入れて江戸に着いた。 長兄の俊次は、高利の商才を試すつもりで、ある日、三貫文の銭を高利の前に置き「これを元手に、今日一日いくら稼げるか、やってみるか」という。うなずいた高利はは、その銭で草鞋を買い、江戸で一番人出の多い日本橋のたもとに立ち、通りすがりの百姓や商人、人夫に売りつけ、夕方、五貫文の銭をかついで帰ってきた。 以来十年、長兄から店をまかされた高利は、銀百貫目ほどであった江戸店の資金を千五百貫目(約二万五千両)に増やしている。
高利の商才に舌をまいた俊次は、このように智恵のよくまわる弟が空おそろしくなってきた。将来、高利が独立して商売仇にでもなれば、俊次の店はおろか、わが子たちはみな高利に圧 「で、お前は松坂に帰って、母上に孝養をつくしてくれ」 そういう俊次は、厄介払いをしたような顔つきで銀百貫目を高利に与えて、江戸から追い落した。 以来、高利は老母に仕え店を守り、江戸での独立の夢を抱きながら欝々といて二十余年の歳月を逸している。江戸の俊次が死んだとき、高利はすでに五十二歳であった。が、高利は、「待っていたり!」 と老いた顔に血のいろをみなぎらせて躍りあがった。かねてからこの日のために、高利は三人の息子を江戸におくり、俊次の店で修業させていた。その息子たちを呼び集めると、本町一丁目に呉服、太物(綿織物)の店をひらき、故郷の屋号をとって越後屋となづけた。 後年の三井財閥の基礎となる巨富は、晩年の高利のこの店で稼ぎ出されたものである。 こうして雌伏二十余年、高利が練りに練った、当時としては誰も思いつかなかった卓抜な商法が次から次へと打ち出されるのである。 その頃の"本町通り"の商人は、大みょうや上級武士、金持ちの町人や大百姓を相手に、得意先をまわって品物を見せて売り、盆暮二度に支払いをうけるという掛売り商売をしていた。 ところが、高利が考え実行したのは"本町通り"で売られているのと同様の呉服を、安く大量に一般庶民大衆を相手に売ろうという斬新な商法であった。 それは「現金掛値なし」つまり定価による現金販売の実施である。そして得意先をまわる人件費を節約した「店売り」であり、いままで一反を単位として売っていたものを、庶民も買えるように「切り売り」をしたことであり、さらに各地の同業者相手に薄利多売を実行した「諸国商人売り」であった。 こうした高利の経営の合理化と顧客への奉仕を徹底した"安くて、掛値なしの現金払い"の店頭売り商法は大当りに当った。
が、これをみて面白くないのは"本町通りの老舗"商人たちである。得意先の大みょう家までが越後屋に注文をしはじめるという始末に腹をたてて、越後屋の台所先の敷地へ惣雪隠 「そのかわり……」 後継者である高平(八郎右衛門)のなで江戸八百八町に引札(広告チラシ)をくばり、"現金、安売り、掛値なし"の駿河町の三井越後屋(三越)のなを世間に撒きひろげていった。 高利のこの商法は、江戸の人びとをよろこばせ、元禄元年(一六八八)、井原西鶴の『日本永代蔵』に《毎日金子百五十両ずつならしに(平均して)商売しける》とあるのが享保年間(一七一六~三六)、新井白石の『石書』では《一日千両ずつ平均に商い有るなり》となり、さらに下って文化十三年(一八一六)の『世事見聞録』に《千人余の手代を遣い、一日千両の商いあれば祝いする》と書かれるほどに繁盛をきわめている。 『三井八郎併兵衛高利 遺訓』
《単木は折れ易く、林木は折れ難し、汝等相協戮輯睦 一本の木は折れやすいが、林となった木は容易に折れないものだ。わが家の者は仲むつまじく互いに力をあわせ家運を盛りあげ固めよ。 《各家の営業より生ずる総収入は、必ず一定の積立金を引去りたる後、始めて之を各家に分配すべし》 一族各分家の商いにおいて得た利益金は、一定の積立金を差し引いた後はじめて各分家に分配すること。
《各家の内より一人の年長を挙げ、老分 一族各分家のなかから一人の年長者を選んで、各分家はみな老分の命をきくこと。 三井家には京都六家のような、独特の結社組織があるが、《老分》の制度をもうけ、一族の和合をはかり、各分家の主人たちは、 《凡そ一家の事、上下大小の区別なく、之に通暁する事に心懸くべし》 と、一家の中のことは、どのようなことでも主人たる者知り尽くておき、
《賢者能者 能力のある者の活用に最大の注意を払い、下の者の中から不平や恨みを抱くようなことのないよう、注意せよ。 《堅く奢侈を禁じ、厳に節倹を行うべし》 天和三年(一六八三)、高利は駿河町南側の地を東西に分けて、東側を呉服屋、西側を両替店とした。これが後の三越百貨店、三井銀行となったことはいうまでもない。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.213~217 2021.05.22記 |
☆37 伊藤 仁斎(1,627~1,705年)
☆38 徳川光圀 苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし(1,628~1,701年)
|
天下の副将軍こと水戸黄門(中な言)が家来の助さん、格さんと共に全国各地を旅し、行く先々で悪をこらしめる話は、江戸のころから有名である。その漫遊記のストーリイは、いつに変らぬワン・パターン、同工異曲そのものながら、平成の現代もなお、助さん格さんが一しきり大あばれしたあと、金蒔絵 「一同ひかえい! この葵の御紋が目に入らぬか。ここにおいでのお方様をどなたと心得る。おそれ多くも前(さき)の天下の副将軍、水戸のご老公なるぞ」 と印籠がアップになれば、テレビの視聴率もグ―ンとあがる。 ついでながらこの「水戸黄門」のテレビ第一回目の放映はいまから二十三年前の昭和四十四年(一九六九)だから、テレビ界きっての人気番組である。
こうしたエピソードをもつ水戸光圀は、徳川御三家の一つ、水戸藩頼房の十一男十五女の第七子に生まれた。母の、谷左馬介の娘久子は、大奥に仕える老女の娘でもあり、一目で心を奪われた頼房は、側室として邸 《水(堕胎)ニナシ申ス様ニ》 と命じたのである。 が、気骨のある三木は、闇から闇へ流してしまう前に頼房の母、英勝院に相談したうえ、ひそかに久子を自分の屋敷に引取り、そこで生み落させた。その子が、光圀であった。
《英勝院、御父ㇵ頼房公、第三ノ御子(三男)御母ハ谷佐馬介ノ女
こうして生れた光圀(当時は長丸)は、五歳のとき、英勝院のお声がかりで頼房の子と認知され、水戸城に入り千代丸をな乗る(長男頼重はこの時期まだ披露(正式認可)がなく、次男亀麻呂 少年時代の光圀の行状は、そのいのちの誕生を父から拒絶されたという反抗の揺り返しのように、藩主の世子にあるまじき粗野な振舞が多かったという。
御三家のなかでも水戸家は江戸定府
《ソノ返(度)数多キニ御コマリナサㇾ、御筆ヲ二、三本ヅツ束ネ、御握リ御書キ遊バサㇾ候ニ付キ、御反故 父から云いつけられた宿題を早く片付けようと筆二、三本握って書いたと、晩年、光圀自身も告白しているが、反抗期の光圀少年の肝の太さは、七歳のときの生首一件をみてもわかる。 ある夜ふけ、頼房は光圀の度胸を試すため、斬首した罪人の首をさらしている刑場へ取りに行かせた。うなずいた光圀は、気おくれした様子もなく出かけて行き、死首が重いのでもとどり(髪の毛を束ねたところ)をつかんでずるずる引きずって帰ってきたという。
光圀の身辺には、つねに三人の傅役 悪所通いといえば、、某夜、例の如く屋敷を脱けて娼家に泊まっていたところ、小石川の水戸屋敷の近くで火事が発生、急いで帰ってくると屋敷の門前は、
《挑
門前を家臣たちが固めて入る隙間
おりから、水戸家へ出入りの商人たちが水籠 「海北孫右衛門の(家の)者にて候」 と声をかけ、すまし顔で入っていったという。
こうした放埓 江戸時代の殿様というのは不自由なもので、寝所では毎夜、枕元や廊下、次の間に小姓が不寝番をし、側室と寝るときも同じ部屋のなか老女控えてい、便所に行くにも御供つきであった。隠居の身であっても、自由気ままな旅など出来よう筈はない。 光圀の無頼な行状がおさまるのは、頼房の強い意見があっての事からとも、十八歳のとき、『史記』の『伯夷伝』を読み、兄の頼重をさしおいて自分が相続人になっていることの順逆に悩んだ事だともいう(『桃源遺事』)。 のちに光圀は、兄頼重の子を養子にして、水戸家三代目をその宗淳に継がせている。
六十三歳で隠居して常陸太田の西山荘にこもった光圀は、助さんこと佐々木助三郎、格さんこと渥美格之丞のモデルともいう佐々木宗淳
晩年、光圀は子孫のために九ヵ条の訓戒『徳川光圀壁書』をのこしている。いかにも彼らしい、野人の趣のある訓 《一、苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし 一、主人と親は無理(を言う)なるものと思え、下人は(頭の働きの)たらぬものと知るべし
一、掟に怯 一、欲と色と酒をかたきと知るべし
一、朝寝すべからず。咄 一、(ものごとは)九分(どおりしてのけても)にたらず、十分はこぼるる(やりすぎてもいけない)と知るべし 一、子ほど親を思え、子なきものは身にくらべ(くらべ)て、ちかき手本と知るべし
一、小さき事は分別せよ、大なる事に驚くべからず(小さいと思える事でも、よく考えて処理せよ、大きな事であっても慌 一、(思慮)分別(する)は堪忍にあるべし(堪忍に勝るものはない)と知るべし》 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.246~ 2021.06.03記 |
☆39 貝原 益軒(1,630~1,714年)

貝原 益軒著 石川 謙校訂『養生訓・和俗童子訓』 (岩波文庫)1990年5月25日 第33刷発行 運動して健康を増進しておくこと 身体は日々少しづつ労働すべし。久しく安座すべからず。毎日飯後(はんご)に、必ず庭圃(ていほ)の内、数百歩しづかに歩行すべし。雨中には室屋(しつおく)の内を、幾度も徐行すべし。如此、日々朝晩(ちょうばん)運動すれば、針・灸を用ひずして、飲食・気血の滞なくして安楽なるべし。 人生は百歳を以て上寿とする 人の身は百年を以(て)期(ご)とす。上寿は百歳、中寿は八十、下寿は六十なり。六十以上は長生なり。世上の人を見るに、下寿をたもつ人すくなく、五十以下短命なる人多し。人生七十古来まれなり、といえるは虚語にあらず。長命なる人すくなし。五十なれば不沃(ふよう)と云(いい)て、わか死(じに)にあらず。人の命なんぞ如此みじかきや。是(これ)皆、養生の術なければなり。短命なるは生れ付て短きにはあらず。十人に九人は皆みずからそこなへるなり。ここを以(て)、人皆養生の術なくんばあるべからず。(岩波文庫 P.31~32)
★2021.12月7日(金) 余録 「人の身は百年を以て期とす」…
「人の身は百年を以(もっ)て期(ご)とす」。江戸時代の儒学者、貝原益軒(かいばらえきけん)は晩年の著作「養(よう)生(じょう)訓(くん)」で、適切に生きれば100歳までの長寿が可能と説いた。寿命の短い時代に83歳で亡くなるまで執筆活動を続けた人の言葉だから説得力がある
言葉を少なくすることの効用についての医学的意味:言葉をつつしみて、無用の言(ことば)をはぶき、言
つばきを吐くな:津液 津液をばのむべし。吐べからず。痰をば吐べし、のむべからず。痰あらば紙にて取べし。遠くはくべからず。水飲津液すでに滞りて、痰となりて内にありては、再(び)、津液とはならず。痰、内にあれば、気をふさぎて、かへつて害あり。此理をしらざる人、痰を吐ずしてのむは、ひが事也。痰を吐く時、気をもらすべからず。酒多くのめば痰を生じ、気を上(のぼ)せ、津液をへらす。(岩波文庫:P.51)
言葉を少くせよ:心はつねに従容としづかに、せはしからず、和平なるべし。言語はしづかにしてすくなくし、無用の事いふべからず。是尤 飲食ともに控えめにせよ:飲食は飢渇をやめんためなれば、飢渇だにやみなば其上にむさぼらず、ほしゐままにすべからず。(同書:P.65) 心たのしく残躯を養へ:老後は、わかき時より、月日の早き事、十ばいなれば、一日を十日とし、十日を百日とし、一月を一年とし、喜楽して、あだに日をくらすべからず。つねに時・日をおしむべし。こころしづかに従容として余日(よじつ)を楽み、いかりなく、欲すくなくして、残躯をやしなふべし。老後一日も楽しまずして、空しく過ごすはおしむべし。老後の一日、千金にあたるべし。人の子たる者、是を心にかけて、思はざるべけんや。(同書:P.159) 関連:谷沢永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書)P.96 老後は、若き時より月日の早き事十ばいなれば、一日を十日とし、十日を百日とし、一月を一年とし、喜楽して、あだに日を暮らすべからず
統計的に平均寿命が延びているからと言って、中年以後に為すべき事柄が緩やかになったのでない。誰でも四十を過ぎれば身辺が慌 人間は短い寿命のうちに、悔いなく充実した生活と、生涯の主題と念ずる仕事とを、可能な限り一段階ずつ果してゆかねばならぬ。若い時には何から手をつけてよいやら、漠然としているゆえに無駄な時間を過ごす。ある種の人はその無駄を将来の養分とするのだが、いずれにせよ長い時間を将来に持つ若年時と、分別ざかり以後とでは条件が異なる。 人生の経験を積むにしたがって、第一には自分の資質が生来どのようであるのかに気付く。いたずらに無駄な抵抗を重ねず、各自に生来の向き向きを、早く悟って有効に生かさなければならない。そのためには是非とも集中力が必要となり「一日を十日と」する日ごとの努力が必要であろう。
第二に人生経験は否応なく、各自それぞれわが足で立つ以外にないと悟らせる。青年時に特有の甘えも今は許されない。頼るべきは現在の自分のみである。そのとき無用の回り道をしている閑はない。人生にもっとも大切で不可欠なのは、目的地へ導く最短コースの発見である。下手な芸術家気取りのボヘミアンスタイルは、単なる気弱な懶惰 第三に人生が与えてくれる本当の喜び楽しみは、無為とは逆の心に張りのある忙しさ、困難な目的を明確に持ち続ける者にのみ、与えられるのである事情が自得できよう。そしてわれ亡き後への手配りが済めば、まさしく老後を仕出かしたりと申すべきであろう。 関連:■躰が寒く感じた 2009.10.20 |
☆40 大村 彦太郎(1,636~1,689年)
|
商いは高利によらず、正直によき物を売れ 戦前、三越、松坂屋、高島屋などと肩を並べたデパート業界の名門であった東京、白木屋おなが、全国浦々浦々に知れわたったのは、昭和七年(一九三二)歳末の大火によってである。 《白木屋大火のいましめ 外出時には必ずズロースを 同デパートの専務語る》(朝日新聞7.12.23) 《今度の火災で痛感した事は女店員が折角ツナを或いはトイ(樋)を伝わって降りてきても、五階、四階と降りて二、三階のところまでくると下に見物人(野次馬)が沢山雲集して上を見上げて騒いでいる。若い女の事とて(着物の)裾の乱れているのが気になって、片手でロープにすがりつきながら片手で裾をおさえたりするため、手がゆるんで墜落してしまった。(略)今後女店員にはこうした事のないよう全部強制的にズロースを用いさせる積りですが、お客様の方でも万一の場合の用意に外出する時にはこの位の事は心得て頂きたいものです。尊い犠牲者が教えてくれたこの教訓を無駄にせぬよう努力する積りです》 この、十四人の女店員の墜落が、日本人の女性にパンティをはかせるきっかけになるのだが、白木屋百貨店の来歴は、湖国近江(滋賀県)の片ほとりからはじまる。 寛永十三年(一六三六)長浜で生まれた大村彦太郎(初代)は、幼くして父道与と死別し、母親の実家、河崎家に引きとられた。河崎家は、飛騨の材木を京、大坂で売りさばく材木商、白木屋をひらいた。 一説によると、彦太郎が京へ出立する時、日頃から学んでいた長浜、良疇(りょうちゅう)寺の法山和尚から、 「くじけることなく(商売に)励むためには信仰が大事じゃ」 と小さな観音仏を与えられ、 「成功したら、十年後この寺を訪ねてこい」 と励まされたという。 京にでた彦太郎は、材木商のかたわら綿布などの行商に出精すること十年。相当な財を蓄積した彦太郎は、約束通り長浜の法山和尚を訪ねる。 よくやった。が、さらに十年、世に知られる商人になって訪ねてこい? 法山の言葉にふるい立った彦太郎は、これを機会に投機性が強くて不安定な材木商をやめ、小間物、呉服の分野への進出をはかり、江戸に赴いてお江戸随一の繁華街、日本橋通二丁目に小さな店をかまえた。 しかし、彦太郎は慎重であった。開業当初は、多額の資金を寝せねばならない呉服扱いを避け、ひたすら、 商内(あきない)は高利をとらず 正直に 末は繁盛(彦太郎の道歌) と、正直と奉仕に徹する商法を展開した。 彦太郎が念願の呉服に手をだし、羽二重(純白の絹布)を売りだしたのは、開業六年目のことである。白木屋、大村彦太郎の地道で堅実なこの商法は、やがて彼を銀五百二十余貫(純資産)の大商人の座に押しあげていく。 こうして彦太郎は十年後、ふたたび長浜に法山和尚を訪ねる。 「よくやった、あと一息じゃ彦太郎、こんど来る時は日本一の商人になってこい」 法山の激励をうけた彦太郎は以来十年、江戸きっての商人、小間物類から呉服を扱う大呉服店にのしあがって、三たび良疇寺の法山和尚を訪ねるが、その時すでに法山は世を去っていた。彦太郎はその、人生の師ともいうべき法山の墓石にすがりつき、声を放って哭(な)いたという。 彦太郎が大番頭に命じて家法をつくらせたのは、創業八年目の寛永十年(一六七〇)のことである。この、五項にわたる簡潔な家法は、その末尾に番頭以下使用人十四人がそれぞれ署名し、大番頭の中川治兵衛に差出した一種の誓約書ともいうべき異色の『白木屋定法』であった。 《一、御公儀様より仰せ出され候御法度の旨相守り申すべく候事 一、衆中(人びとの中で)誰に寄らず悪事(を働く者)は申すに及ばず非儀申さる者御座候わば、見付け次第少しも隠し立てず早速申し出べく候、(略)合点参らざる(なつ得いかぬ振舞のある)者御座候わば、議事(誰彼)に寄らず申し進む(出る)べき事 一、諸事非儀(よからぬ振舞)之なき様に人々我(わがまま)を慎み正直に相勤め偽なる儀申すまじく候。殊に他所に於いて女さばくり(おんな道楽)仕り申すまじく候事 右の趣相守り申すべく候。少しも違背仕るまじく候、仏神は(この)紙面に及び候。 仍 如 件 寛文十年九月晦日 横田太兵衛 高田又兵衛 (以下十四人) 中川治兵衛 殿》 元禄二年(一六八九)大村彦太郎逝く。 彦太郎が、法山和尚と約束して三度目に長浜を来訪した日から十年目、二代目彦太郎は、亡父にかわり良疇寺を訪れ、法山と彦太郎の冥福を祈って銀五十貫を寄進している。 創業者彦太郎の商いに対する《商いは高利によらず、正直によき物を売れ》という堅実と倹約を家訓とした姿勢は、二代目彦太郎以降の彦太郎代々に受け継がれ、三井家の越後屋に迫るほどの大呉服店となり、当時の商人たちの理想である、京都に本店を持った、いわゆる「江戸店(たな)持ち京商人」として繁栄の一途を辿っていった。 大村家の家法は、こののち、白木屋中興の祖といわれる四代彦太郎によって享保八年(一七二三)に改訂、増補されている。 《一、酒は商人衆(取引先の商人を)饗応(接待)の為に候処、手前に過ぎ(自分で酩酊)候えば商人衆へ無挨拶(失礼)、他所(よそ)にて酒用い(宴席を設け)候事無用たるべく候。酒の上にて宜しからざる事も之れ有る物に候間、堅く相守り申さるべく候事。 一、諸式(諸商品)商事の儀、地田舎集衆(地方の得意先に限らず商人衆(取引先)を大切に致すべく候、少しの買物致され候衆中を尚以て懇篤に致し遣し申すべく候。大商人衆中の分は自然大切に成候間、買物多少に限らず、客衆を随分懇意に遊ばされ何とか相調え帰り申候みぎりは、見世端(みせばた)まで成べく腰をかがめ懇に挨拶致(せば)又重て買物に被来候(こられ)。》 お客様が買物をして帰るときは、買物の多少にかかわらず、店の表まで出て腰をかがめ、心をこめてお礼を申しあげれば、また、買物に来てくださるものである。 ――こうして白木屋は、江戸から東京へと三百年にわたる風雪を乗り越え、明治三十六年(一九〇三)わが国最初の洋式建築百貨店として登場。デパート業界に新風を吹き込む。 が、歳月というのは酷薄である。白木屋代々の人々が営々と築きあげてきたこの百貨店も、戦後、横井英樹の乗っ取り騒動に捲きこまれ、東急百貨店に吸収。現在の東急百貨店日本橋店からは、かつてのイ白木屋の面影は偲ぶよしもない。
神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)P.170~P.175
春秋 2016/10/10付 老夫婦とベテラン店員が心から別れを惜しんでいる。「またいつか、どこかでお会いしたいわね」と客の婦人。「ありがとうございます」と頭を下げる店員。先月末、千葉県で「そごう柏店」が43年の歴史に幕を閉じた。最終日まで数日という売り場で見たやりとりだ。 ▼入り口近くでは開業した頃の街並みを写真展で紹介していた。今でこそ周りには大小のビルが立ち並んでいるが、昔の写真は平屋や2階建ての木造民家が目立つ。少し離れればもう農地だ。駅前再開発で誕生した巨艦店は人々の憧れであり、自慢でもあったろう。大きな百貨店があるから柏の街に住むと決めた人もいよう。 ▼この店だけでなく、百貨店は長く全国各地で街の顔を務めた。しかしバブル崩壊から長いトンネルが続く。セブン&アイグループは神戸市三宮駅前などのそごうや西武を売却し関西での百貨店事業を大幅に縮小すると決めた。流通業界の雄であり華でもあった百貨店は、グループ経営の足を引っ張る存在になってしまった。 ▼地元の人は愛着を持っている。店員は閉店を前にしても礼儀正しく真面目に働く。そうした人たちに支えられてきた店の数々が、それでも傾いてしまった。景気の停滞、専門店チェーンの台頭、ネット通販の普及と、私たちの「買い物」を取り巻く環境はめまぐるしく変化した。波にさらされ続ける小売業界の苦難である。 |
☆41 池田 綱政(1,638~1,712年)
|
能楽、和歌、絵画、蹴鞠等を愛好した公家的文化大みょうで、現在国指定特別名所となっている後楽園(岡山市)を造影したのも綱政であった。光政は和意谷墓所(吉永町)を造営、儒式によって祖父輝政、父利隆及び自らの墓所を営ませたが、綱政は仏教に心を寄せ、元禄十一年(一六九一)に上坂外記に命じて児島郡村の永昌庵を移して曹源寺を造立し、その菩提寺とした。 これが曹源寺の草創であり、現在小方丈に「永昌」の額が掲っているのは、永昌庵を移したためである。元禄十一年といえば、綱政が還暦をを迎えたとしであり、曹源寺の造立は、高祖父信輝の位牌をまつる護国院(京都・妙心寺内)の壊廃を嘆き、信輝の位牌を移して、その菩提を弔うとともに、自らの冥福を祈らせようとしたものであった。綱政が妙心寺の絶外和尚を招請して曹源寺開山とし、寺領二六〇石を寄進するとともに、自影を描かせて、自ら讃を書いておさめているのもこのためであった。 |
☆42 大道寺友山 一ぷくの茶を啜るに付いても、其さま拙からざる様に(1,639~1,730年)
|
元禄という世は、町人の時代であった。諸国で城下町の建設がおわり、都市に人口が集中し、貨幣価値が浸透して商品の流通にたずさわる町人たちの生活は急上昇し、いっぽう、関ケ原からすでに百年、サラリーマン化した武士は、泰平のなかで禄を貰って寝て暮らすだけの遊民になってしまい、役所に出ても、
《我も人も畳の上の奉公斗 《畳の上を這いまわり、互いに手の甲をさすり舌先三寸の勝負をあらそうのみの善悪にて、身命をかけての働きとては之無き事に候》 という時代であった。
そんな、息のつまりそうな役所の中で、ときには古参たちの憂さばらしとして、陰湿な、後輩や新参者いびりがはじまる。わざと事務を複雑にしてみたり、書類の不備を言いたて突き返したり、御番入りの振舞(初出仕の挨拶)と称
こうした風潮のなかで、泰平の世のサムライの心得、"期待される武士 友山のこのサムライ訓五十六条は、のちに信州松代藩十万石真田家の国家老、恩田公準によって四十四条に削られ、天保五年(一八三四)江戸の書店、和泉屋吉兵衛によって松代版『武道初心集』上中下三巻として刊行されている。
余談になるが、この恩田は松代藩の財政再建と『日暮硯』の著で高名な恩田木工
仮なまじりの平易な文章でつづられた『武道初心集』は、一世紀ちかい人の生
この中で友山は、組織の中に生きるための心がまえ、行住坐臥、言語対応など当世の武士としての処世の法を語りおえたあと、その項の末尾を必ず《初心の武士心得のため、よって件 「にんげんというものは」
友山はそう説
「誰もが"死"という存在を忘れて、この世に何日 ゆらい武士というは、正月元旦の朝、雑煮を祝って箸をとる瞬間から、大晦日の除夜の鐘が鳴るまで、日夜常に心に"死" を思い抱き、
《朝夕、手足を洗い、湯風呂にも入って身を潔 という心がけが大事である。人間のあさましさは、その"死"を忘れるからこそ、
《つねに大酒、淫欲 そして、また友山は「択友」のくだりで、 「奉公する武士にとって最も必要なのは、心をゆるせる友」 だという。多くの同僚の中から、勇気すぐれ道理を重んじ思慮ふかく、言うべき時にわが意見をはっきりと述べる、そのような朋輩とは日頃から親しく深いまじわりを結んでおくことだ。こうした友が一人でもおれば、いざというときに強い味方になる。 「にんげん関係のなかで用心すべきはお互いの"弱さ"で結びつくことである」
酒や博打や遊びの仲間なら、すぐに何人でもできる。小唄や浄瑠璃を唸
《貌 武士が生涯の交わりを結ぶ友、生死をともにする友人を得るためには、ながい歳月にわたって互いの心を見届けあうことが必要なのである。 また、勤務についても、この先、いつ迄も勤められると思い、その歳月のながさに退屈し、心もゆるみ、目の前の仕事にしても、「なあに、それは明日にしよう、これは次にまわしておこう」と、投げやりな仕事ぶりで、あげくの果てには、その仕事も同僚間で、
《彼方へはね此方へぬり(あちらにまわし、こちらへ押しつけ)誰一人身に引懸け(責任をもって)世話のやき手もなければ、諸事いやが上にかさなり(仕事が山積し)つかえて、不埒 というのも、厄介なことはすべて翌日、翌月、翌年と、行く先の歳月を頼みにするからである。 役所への出勤にしてもそうだ。いつもぐずぐず出そびれ、
《(まず)茶を一ぷく、煙草を一ぷくと申て、ふよつき(ぶらつき)女房や子供と一口ずつの雑談に時を移して、宿(業)を遅く出ては俄かに狼狽
こうした友山の教訓は、平成に生きる私たちにも立派に通用するのだが、友山の『武道初心集』が刊行された後、さらに世俗的な処世心得で懇切丁寧、噛んでふくめるように詠 《近辺の相番(同僚)または古番(古参者)へはつねに親しく付届(贈物)せよ》 《頭衆へ見舞(挨拶と贈物)は月に一度なり寒暑、非常の見舞は(この)外なり》 《番頭、組頭、または伴頭の子ども(や)親類(にも)近づいていよ》 上役に逆らわず、勤番先では次の言葉だけ使っておれば、わが身は安泰である。そこで、 《世の中は諸事ご尤もありがたい御前ご機嫌さて恐れいる》 《手れん(人あしらいの方法)とは左様でござるご尤も御意(仰せ)の通りおめでたい事》
先ごろ、不肖の息子のため大学へ裏口入学をはかって発覚、マスコミを騒がせたタレントがいたが、今も昔も親馬鹿ぶりは渝 《近年は惣領どもの御番入り、親がかわって願書出すなり》 とはいえ長男はまだいい。二男三男の厄介人が部屋住のまま老いて、なお養子先を求めている姿は悲惨である。 《部屋住も五十(歳)以上に至りては(藩庁へ)養子願の伺いをせよ》 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.66~70 2021.06.04記 |
☆43 芭 蕉(1,644~1,694年)
|
▼おくのほそ道
一 冒 頭
|
☆44
浅見 絅斎
|
一 承応元年8月13日(1652年9月15日) - 正徳元年12月1日(1712年1月8日)浅見絅齋は儒者であつた。朱子学者であつた。しかしたゞ朱子学者といつたのでは、ぴつたりしないものがある。絅齋は、儒者は儒者でも、最も日本的な儒者、武人的な儒者だつた。徳川幕府専権の時代に当つて常に大義名分を鼓吹し、足一歩も京都の外へ出ず、諸侯の招に応ぜず、薙刀一柄を床の間に逆に立てかけ、「もし禁庭に御大事があらば、これを小脇に掻い挟んで、お味方に参らう所存ぢや」といつた。佩刀の鎺(はばき:鈨・はばきとは日本刀の部材の一つで、刀身の手元の部分に嵌める金具である)に赤心報国の四字を篆鐫(てんせん:中国で秦以前に使われた書体。大篆と小篆とがあり、隷書・楷書のもとになつた。印章・碑銘などに使用)したのも、またさうした精神の顕現だつた。絅齋は剣道にも達してゐた。毎朝夙に起きて、馬を乗廻すことが数回だつたともいはれてゐる。もとよりたゞ先哲の書を講じて、能事畢れりとする学究ではなかつたのである。 絅齋の皇室尊崇の大精神は、更に凝集して『靖獻遺言』の一書となつたのであるが、絅齋の志は、空言を以て義理を説くも、人を感動せしめない。事蹟を挙示して、読む者をして感奮興起するところあらしめたいといふにあつた。然も徳川の盛世に、本朝の諸忠臣を顕彰することは、幕府に尊して憚らざるを得ぬ。依つて漢土の忠臣義士の内から、最も大義に明らかなる者八人を選び、特にその絶命の詞を挙げ、附するにその行実を以てして、天下の人士に尊王の大義を徹底せしめようとした。そしてこの書は、絅齋の生前に刊行せられて普く流布し、絅齋没後には、ますます廣く行われた。幕末多事の日に至つては、王事に奔走する志士達の競つて愛読するところとなり、つひには王政復古の一大原動力ともなつた。絅齋は嘗て『近思録』を講じて「為萬世開太平」の章に至つて、「」拙者が今日おのおの方のためにこの書を講ずるのも、また萬世のために、太平を開くのでござる」といつたといふ。絅齋の自ら任ずるところは、かくの如くだつた。その『靖獻遺言』を著したのも、また正に萬世のために太平を開くものだつた。 二 然も緑仕を肯んぜず、聞達を求めなかつた絅齋の一生は貧に徹してゐた。清貧の語は、たゞ文章の上に好んで人の用ひるところとなつてゐるが、絅齋ほどの清貧に甘んじてゐた人は、蓋し尠かつたらうと思はれる。その高弟の若林強齋も、貧の一事に於ては師の絅齋に譲らなかつたが、或日大津のその家から、京都の絅齋の許へ通う途中で餅を買つて、土産に持参したら、絅齋は大食の人だつたものだから、その餅を貪るように食べて、「そちも貧乏は貧乏やゃが、この餅が買われるくらゐならまだよいわ」と笑いながらいつた。 また或時は、絅齋が寒中にも綿の入つた物を身に着けてゐないのを見て、強齋は母から仕立てて貰つた正月の晴着を作り直して、先生に差上げた。そうしたことなどもあつたのだつた。 やはり或年の暮に強齋が訪ふと、絅齋はがらんとした空家のやうな家に、擂鉢に酒を盛つたのを傍らに置き、椀の蓋でそれを酌んで飲みながら、「正成その時、肌の守を取出し」と、楠木の謡をうたつてゐる。見渡したところが、まだ正月の餅も搗けてはゐない。強齋は家に帰るとすぐに餅を搗かせて、それをまた持参したなどといふ話も傳えられてゐる。このことは尾張に於ける﨑門の儒者の一人だつた細野要齋が書いてゐる。 楠木の謡といふは、絅齋自ら作つて、その道の人に節附けして貰つたものだつた。絅齋は楠公を以てわが国に於ける忠義の士の第一人者として、その徳を慕うのあまりに、『太平記』の桜井駅訣別の一段を謡としてうたつたのものである。 前の絅齋と強齋とのこおは、強齋の談話をその門下山口春水の筆録した『雑話筆記』に據つたのであるが、同書にはまた絅齋のことを語つて、「先生は大男で、よく肥えたる人にて候が、屋根がもるゆゑ、自分(強齋)を相手にしては屋根へ上らるれば、踏まるゝ處がぬくる。或は講堂のねだが落つると、先生の木遣りで、自分がいつでも其の相手になつたことにて候。それほど清貧にありたれども、先生には其れなりに安んじて、つひに富貴利達を求めらるゝ心なく、世に手出しをなさるゝと云ふことの全然なかりたることにて候」といふ一節がある。 大兵肥満の絅齋が、自身に雨漏りの修繕をするとて、屋根へ上つて、却つて屋根板を踏み抜いて、修繕どころか破搊を大きくしてしまふといふやうな悲しい滑稽をも演じたりしたのである。 三 『雑話筆記』には、絅齋のことを語つてゐるのがまだある。絅齋は三人兄弟の仲で、その家はもともと善かつたのであるが、絅齋が学者として一家を成した頃には、家道がいたく衰えてゐた。ところが絅齋の兄も弟も、一向に働きのなかつた人で、絅齋は自分の生活を維持するだけでも容易でないのに、その上にも實家のことにも頭を使つて、何かにつけて苦労しなければならなかつた。門人達は、何れもそれを痛ましいこととしたといふ。「されども先生には、学問の為方のねうねつな通りに、親類一家のことにも、ずんと思召すまゝにせねばおかれぬ御気象にて、それが勢があればなれども、まことに身の孝養も足らぬ身代で、大気なまゝに、当る障るの世話を、身に引きうけてなされて、何でも来いと云う様な御気質ゆゑに、一ばい御苦労も多かつたことにて候」などとしてある。 ねうねつは聞き馴れぬ言葉であるが、これは今ねついといふのと、恐らくは同義なのであらう。貧すれば鈊するなどといふが、絅齋はいかに貧乏しようと、そのために志を挫くような薄弱な徒ではなかつた。苦しい中からも、矢も鉄砲も一身に引受けようというやうな、めげぬ気象を発揮した。そうした点にも絅齋の剛毅な性格が窺われるのである。 『雑話筆記』には、上についで、絅齋の継母への仕え方のいかにもよかつたことが述べてある。その継母といふは、御幸町松原下ル町に住む絅齋の弟の許にゐられたのであるが、晩年病気になつてからは、絅齋は毎日欠かさず看病に赴いた、それも昼間自宅で講義をし、雑用を済まして、夕方から出かける。そしてその看病を夜通し勤めて、朝になつてから帰る、それが酷暑にも厳寒にも変わらずに、末期まで続いた。道筋の人達は絅齋の通るのを見て、感動せずにはゐられなかつた。絅齋は、忠孝節義をたゞ口先で鼓吹する学者ではなかつたのである。 四 絅齋の畢生の著述『靖獻遺言』は、貞享四年(1687年)に板行が成つたのであるが、絅齋の父はそれを見るに及ばずに、その前年に六十一歳でなくなつた。後に絅齋は、「自分が当世に用ひられるぬのを、親御は常々気の毒がられたが、これほどの書物を仕立てるほどになつたことを聞かれたならば、さぞかし悦ばれたことであらうに」と、しばしば述懐に及んだ。門人達もまた師の心中を及んで、それを遺憾なこととしたといふ。強齋も、「晩年には、侯伯も其のなを称せらて、仙洞様(霊元天皇)にも先生のなを知らせられて、仰せ出されたと云ふことなり。今少し御存命ならばと思うこと大分ありたることにて候」といつてゐる。 最初に絅齋を日本的な、武人的儒者であつたとしたが、それだけではまだいひ足りない。絅齋は正に一個の大丈夫だつた。大丈夫にしてそして儒を兼ねたのである。 絅齋、なは安正、通称は重次郎、近江国高島郡太田村の人である。始め医を業としたが、後ち儒に帰して、山崎闇齋に就いて学んだ。崎門の三傑の一人に数へられる。慶安五年年八月十三日に生まれ、正徳元年十二月朔日に没した。歳六十。京の東郊鳥邉山に葬られた。
浅見 絅斎(あさみ けいさい、承応元年8月13日(1652年9月15日)~正徳元年12月1日(1712年1月8日)は、日本の江戸時代の儒学者・思想家。なは重次郎。諱は安正。筆名として望楠楼。 近江国(現滋賀県高島市)に生まれる。はじめ医者を職業としたがやがて山崎闇斎に師事し、後世、闇斎門下の俊英3人、すなわち崎門三傑の一人に数えられる。後年に至つて、闇斎の垂加神道の説に従わなかつたために疎遠となつたが、闇斎の死後は、神道にも興味を示すようになり、香を焚いて罪を謝し、闇斎の所説を継述するに至つた。門下に、若林強斎(守中霊社)・山本復斎(守境霊社)等がいる。その尊王斥覇論は徹底しており、足、関東の地を踏まず、終生、処士として諸侯の招聘を拒み、明治維新の原動力の一つとなつた。
『森 銑三著作集』第八巻(中央公論社)P.16~20より
参考書:近藤啓吾著『靖献遺言』(国書刊行会):(昭和六十三年三月八日購入している)766ページに及ぶ本である。
|
☆45 新井 白石(1,657~1,720年)

徳川家宣(1,662~1,712年)と白石 家宣、第六代将軍となる。 この時すでに四十八歳であった。 強烈な印象を与える綱吉と吉宗との間に挟まれて、些か影の薄い思いがするが、永い間、隠忍してようやく将軍職についただけに、老成したところもある。よく人の言を聞いて平凡ながら失政の少なかった将軍である。 家宣は、父綱重が十九歳の時、お保良(おほら)という二十六歳の女中に生ませた児で幼名虎松と云った。綱重が甲府の国守となり、二条家の娘を正室に迎えることになると、外聞を憚って、虎松は綱重の重臣新見備中守正信の養子にされた。 新見は、万一の時を考えて、大老酒井忠清に、虎松が綱重の第一子であることを確認しておいて貰ったが、とに角、少年虎松は新見左近と名乗って陪臣の身として人生の出発をはじめた。 しかし、綱重にその後男児が生まれないので左近即ち虎松が九歳の時、これを再び自分の世嗣に戻そうと考えた。新見と対立していた島田淡路守・太田壱岐守の両人が、これに反対し、 ――主君綱重の落胤である虎松はすでに死亡した。新見はそれを秘して自分の児を虎松として主家を嗣がせようとしている、主君はこの頃、乱心気味でそれが分からないのだ、 と、幕府に訴え出た。 老中久世大和守、綱重に対面して事実を調べてみたが、乱心の様子もないし、虎松が本物であることも間違いない。島田・太田の陰謀は砕かれ、延宝四年(一六七六)十二月、虎松は元服して網豊と称した。 延宝六年、綱重が死亡したので家督を嗣ぎ、同八年、十九歳で正三位となった。 綱吉に世嗣が生まれない以上、当然この綱豊が世嗣となるべきだが、お伝の方以下大奥は必死になって反対し、吉保もまたこれに加担したため、綱豊の世嗣は容易に決らなかった。
ようやくそれが決った宝永(一七〇四)には、綱豊は四十三歳であった。その二十数年に亘る永い間、この男はひたすら読書につとめ、能楽に心をまぎらせていた。間部詮房 この新将軍家宣は、綱吉の遺体を収めた柩の前で、柳沢吉保を呼んではっきりと宣言した。 ――生類憐みの令は、先代が最も気にかけられたものに違いないが、この禁令に触れて罪を得たものは何十万にも上る、先代の御遺志には背くが自分はこの禁令停止することとする、 何らの反対も許さぬ断乎たる態度であった。そしてこの愚劣な法令は一月二十二日、綱吉葬儀の二日前に廃止された。 上下を問わず歓呼してこれを迎えたことは云うまでもない。罪を宥されたもの八千六百人に上った。施策の第一歩は成功であった。 次に行ったのは吉保を政権の座から退けることである。 吉保が、家宣に向って、
――私は亡き上様に特別の御高恩を頂いた者故、殉死仕るべき筈でございますが、御禁制故それもできず、せめて髻 と申し出ると、家宣はすかさず、 重い地位にある者が髻を払って葬送の供をするという先例はない。強いて落髪したければ、先ず御役御免を願い、葬送の済んだ後で隠居した上、落髪するがよかろう、 と、ぴしゃりとやりこめた。 これでは厭でも、御役御免を願って隠居する他はない。さすがの吉保も、政治の舞台を退き、落髪して保山と号し、駒込の下邸に引込んでしまった。 生類憐みの令の廃止といい、吉保追落しといい、家宣はその性格に似合わぬ鋭さを示している。恐らく、綱吉と吉保とに対する深く長い怨恨のためであろう。 家宣の政治顧問として活躍したのは新井白石である。 家宣の時代、及びこれに続く家継の政権の中心になったのは間部詮房であり、政治顧問として活躍したのは新井白石である。 間部の父、西田嘉兵衛は甲府家に仕え、詮房は家宣に仕えたが、姓を間部と改めた。小姓から用人、更に側衆となり、家宣が将軍職に就くと若年寄格、老中格となって政権を一手に握った。宝永七年には上州の五万石、高崎城主となっている。 不遇時代の家宣はこの間部と新井の二人に非常に慰められているため、間部に対する信任も非常に厚く、政治はすべてこの間部に相談し、間部の口を通じて行わせていた。老中でも将軍の前に出ることは五日に一ぺん、十日に一ぺんくらいしかなかったといわれるくらいである。 このい詮房と一体同心になって家宣の政治をたすけたのが新井白石である。 白石は三十七歳の時、甲府藩に仕え、綱豊の侍講となって以来、その絶対的信頼を獲得していた。
従来、将軍の侍講として政事顧問の役をつとめるのは林道春 しかし白石の該博な知識と、透徹した論理とは、常に白石に勝利をもたらしたようである。 白石が最も重要視したのは、朝鮮来聘使の待遇問題、貨幣改革、そして長崎の通商貿易に関する問題であった。 朝鮮來聘使は、将軍の代替えの毎に祝賀の為にやってくる朝鮮国王の使節でさるが、その一行は三百数十人から四百人に及び、接待に要する費用は莫大なものであった。 白石は従来の待遇が余りに厚きに過ぎたものとして大いに簡略化したので、使節は頗る不満らしかったが、費用は六〇パーセントも節約することができた。 また将軍が事実上、日本の主権者であることを明確にするため、従来は朝鮮からの国書の宛名が「日本国大君殿下」とあったのを、「日本国王」と改めるよう要求し、幕府の返書に用いた「日本国源某」という署名も「日本国王」とすることにした。先方も「朝鮮国王李某」と署名していたからである。 更に大きな問題は、幕府が直面していた財政難の解決と、元禄の貨幣改鋳に伴うインフレーションの収束である。 この点については白石は、綱吉時代の財政を一手に担当していた荻原近江守重秀と、真向から対立した。 二人の対立は根深い。 家宣が将軍職についた時、幕府の財政状態について、荻原重秀に説明を求めると、 ――幕府の収入は金にして年およそ七十六、七万両、その中、旗本の給料として三十万両が差引かれて、残りは四十六、七万両、これで一年の経常費を賄わなければならない。一方前年度の総支出は約百四十万両、今年は京都御所の修繕に七、八十万両かかるから、予算の不足は百七、八十万両に上る。このような赤字は例年相つづいてきたのだが、先年、改鋳によって五百万両の利益を得たので、辛うじて何とかやってこられた。それにしても、その残金も今は三十七万両しかない。さし当り前将軍の葬儀、新将軍の宣下等のための費用を考えると、到底足りない。又、改鋳をやるよりほかあるまい。 と云う。 家宣以下、老中たちも呆然とした。 しかし、白石が、綿密に調査してみると、秀重の説明にはおかしいところがある。 ――今、五百万両の残金三十七万両しか残っていないと云うが、去年の収入は現実に今年になってはいってくる。それが七十六万両ある筈だ。従って今年使用できる金は百十万両あまりとなる勘定だ。これだけあれば何とかやれる筈、それに何もかも一時に払う必要はない。足りないところは、延べ払いでもよい、 と白石が論駁したので、ようやく一同はほっとするという一幕もあった。 白石は又、重秀の財政運用に疑惑の目をもち、勘定所吟味の設置を要請した。この勘定役は前代まであったのだが、重秀が勘定奉行となってから、その独断専行の邪魔になるので廃官になっていた。それを再び復活させたのである。 白石と重秀とは、性格的に全く相容れぬものがあったらしく、白石の重秀に対する論難には、かなり強い感情的なものがまじっている。 白石は重秀が財政困難打破のため貨幣改鋳という最も安易な、しかも弊害の多い方法を選んで、貨幣価値の暴落、物価冒頭を招いたことを痛烈に非難した。 重秀も必死の抵抗を試みたが、ついに正徳二年(一七一二)九月、職を罷めさせられた。しかし一度失われた貨幣への信頼は容易に回復せず、さすがの白石も貨幣問題には手を焼いたようである。 綱吉時代には貿易収支も赤字つづきで、長崎を通じてわが国の金・銀・銅が大量に海外に流出していた。白石の調査によれば、慶安元年(一六四八)から宝永五年(一七〇八)までに、金二百三十九万七千六百両、銀三十七万四千二百貫が海外に流出しており、また寛文三年(一六六三)から宝永四年までの間に、銅一億一千百四十五万斤が流出している。そのため、この頃に至って交易用の銅が著しく不足するようになっていた。 白石は長崎貿易を制限するほかなしと考え、オランダ船は年間二艘、貿易額銀三千貫、唐船は年間三十艘、銀六千貫を超え、銅の輸出は年間四百五十万斤を超えてはならぬものとした。 また唐人やオランダ人との間に、抜荷取引が盛んに行われていることを指摘し、役人が外国人に遠慮してその取締りをいい加減にしていることを不可とし、厳重な取締りを要求した。 新井白石という男は功名心や自負心が強く、しかも非常に闘争的であったため多くの政敵をつくり、吉宗の登場とともに失脚してしまった。しかし白石は少なくとも柳沢吉保のような迎合一点張り、将軍の意思に対していつもイエスマンである、というような立場ではなく、あくまでも自分の学問的な理想を政治にいかそうとして、必要があればいつでも家宣に進言したことは高く買ってやらなければならない。 また家宣のほうも、長い間、将軍になれそうでなかった不遇時代から白石を自分の師匠として、学問の上の師匠ばかりではなく政治の上の師匠として、非常に高く評価していた。従って君臣一体という状況で、『折りたく柴の記』にある白石の言葉をかりれば、
――わが心に思うところは申さずということなく、上 というくらいだった。自分は何でもいいたいことをいったし、将軍も自分のいった言葉は全部用いてくれたといっているのである。 ※参考:日本の名著15『新井白石』(中央公論社)P.173(黒崎記) 家宣の政治は割合に成功だったといわれているが、その政治の成功の基礎には、恐らく白石の進言というものが大きく力があったと思われる。 白石は天下有用の学を理想とし、将軍を堯・舜たらしめようとしたが、その実際の効果は乏しかったとみてよい。 白石の本領はあくまで学者である。学者としての研究を犠牲にして、将軍の最高顧問として精魂をつくしたが、現実は彼の手に余るものであった。 白石の業績の中、後代まで残ったものは結局、彼の学問である。彼が明治以前における最大の歴史家であることは、万人の認めざるを得ないところであろう。 古代史研究としての『古史通』『古史通或門』、中世史としての『読史余論』、当時の現代史であり且つその自叙伝でもある『折りたく柴の記』は、いずれも傑れた著述である。わずかに百余日で書上げられた関ケ原以降家綱に至る大名三百三十七家の家伝『藩翰譜』も名著といってよい。 白石がその生涯を著述に専念していたら、われわれは更に多くの傑れた歴史書を読むことができたであろう。 歴史を総合的に、その発展の過程においてとらえたこと、日本古代とくに神代についての科学的実証的に追及し、 ――神はヒトなり、 と喝破したことなど、時流を遥かに擢んでている。 その言語学者としての才能も『采覧異言』『西洋紀聞』『東雅』『同文通考』などに充分に見られるし、『折りたく柴の記』は自伝文学の最高峰の一つを示すと云ってよいであろう。愕くべき博学の人でもある。つまらぬ権力意思にあやつられることなく学究生活に打込んでいたら、更に偉大な存在となったに違いない。 大奥の乱脈 家宣は正徳二年の夏、病を得たが、秋になると、次第に悪化したので、間部詮房、新井白石に、その継嗣について相談した。 この時、一子鍋松は、わずか四歳である。 家宣は、第七代将軍として尾張中納言吉通(よしみち)を立て、第八代を鍋松に譲らせるか、或いは鍋松に次代を譲り、吉通をその後見人として西の丸に入れるかどちらかにしたいと考えていたのであるが、白石は断乎としてそのどちらにも反対し、鍋松を立てて将軍とし、間部以下の側近がこれを守り立ててゆけばよいと主張した。 十月十四日、家宣は五十一歳で死んだ。 鍋松が後をついで第七代将軍となり、家継を名乗る。 四歳の童児であるから、実際上政権を握ったのは間部詮房であり、白石は依然としてその顧問格として活躍した。間部は、家継の生母月光院と非常に親密であり、しばしば大奥に入って、月光院の部屋を訪れ、さし向いて炬燵にはいったりしていたので、幼年の家継でさえ、 ――間部は上様のようじゃ、 と、云った。二人の間の醜聞が囁かれたのも当然であったろう。 月光院は、浅草唯念寺の僧侶の娘であるが、大奥に奉公する中に、家宣にその美貌と才気とを愛されて側室となり、左京の局と呼ばれたが、宝永六年に鍋松を生んだ。 家宣はそれまでに二人の男子を失っているので、鍋松は大切に育てられ、いささか過保護の虚弱児でもあったらしい。 家宣が死んで、左京の局は月光院と称したが、新将軍の生母として、大奥第一の権力者となった。 政務に熱心なあまり妻も妾も持たなかった間部が、この美貌の未亡人の許にしげしげと通ったのであるから、噂がたったのは当然であろうが、その真偽は別として、大奥全体に何となく自由な放恣な色っぽい気配が漂ってきたことは否めぬところであった。 そうした雰囲気の背景として起ったのが、絵島生島事件である。 正徳四年(一七一四)一月十二日、木挽町の山村長太夫座で、美男で知られた生島新五郎の狂言がかかっていた。それを見物に来たのが、大奥の年寄絵島の一行であった。絵島は増上寺の前将軍家宣の廟に代参に行っての帰りであるが、こうした公けの外出を機会に、芝居見物をすることは公然の秘密となっていた。 絵島は二階の桟敷に席をとり、幕間には生島以下の役者たちも姿をみせて接待したので、思わず時を過し、夜に入ってから帰城した。 御錠口の門限にぎりぎり間に合ったが、七つ口の扉は閉まっており、それの開かれるの待っているこの一行がひどく浮ついた色っぽい様子であったので、忽ち色々な噂が乱れ飛んだ。 あまり噂が高くなったので放置することができず、絵島と、同行した宮路とは一応、親戚の家に謹慎となった。 更に取調べの手は芝居各座に及び、役者たちの生活がかなり乱れていることが明らかになったため、役者生島新五郎、狂言作者中村清五郎は入牢を申しつけられ、処罰者は十七人に上った。 この絵島は御家人白井平右衛門の娘であるが、大奥に奉公すると忽ちその才気を認められて左京局に愛され、年寄の地位に上って四百石を受け、大きな権勢を振うようになっていた。 自然、放縦な行いが多くなり、代参や宿下りの時など、物見遊山・芝居見物にふけるようになる。 大奥に出入りする御用商人たちは、そんな機会に絵島に接近してその好意を獲得しようと試みた者が少くない。
浅草に住む材木商の栂 絵島と生島とが、この頃から深い関係になっていたことは推察できる。この頃の劇場には二階三階があり、桟敷には簾がかかっていたし、桟敷から楽屋や座元の家に間道が作られていたらしいから、どんなことでも可能だった筈である。
取調べの結果、大奥女中の乱脈ぶりが明白になったので、絵島は遠流 この事件に関係したものは千五百人にも上ったが、それを一ヶ月足らずで処分し終わっている。 奥山交竹院も、生島新五郎も、中村清五郎も、座元の山村長太夫も伊豆諸島に流罪、山村座は取潰し、絵島の豈白井平右衛門は絵島の不行跡を諫めることなく、吉原見物などにもついていったのは不届として死罪を申し渡された。 この」事件の取調べに当ったのは、御目付の丸毛五郎兵衛と稲生次郎左衛門であるが、稲生は峻烈な裁判をもって知られていた人物である。 忽ち事を大ぴらにし、殊更に手を拡げてしまったので、月光院も間部も白石も、公けに口を挟むことができず、当惑している中に、稲生は恐るべきスピードで裁判を完結してしまった。 月光院はやっと、その時になって絵島のために減刑運動を行い、遠流から信州高遠の内藤駿河守へお預けということにして貰った。
絵島は高遠城に近い火打平の松林の中の囲 生島の方は、三宅島で流人生活を送ること二十九年、寛保三年に許されて江戸に戻ったが、あわれ美貌を誇った役者も、その時は七十三歳であったという。 大奥の乱脈ぶりは、月光院その人に最も多くの罪があったかも知れない。幼少の将軍を抱えて、独身の宰相間部と、何人も怪しむような親密関係を持っていたとすれば、大奥の女たちの所業について、声を大にして叱正することはできなかっyたであろう。 将軍家継は、正徳六年四月三十日、わずか八歳で死んだが、それも月光院に責があったように思われる。 一般に流れた噂によれば、生来虚弱な家継を、月光院と間部が庭園での酒宴の席に連れ出して、風邪をひかせたりしたことがしばしばあったという。
家継が死ぬと、後継者を誰にするかが問題になった。候補に挙げられたのは、尾張中納言継友、水戸中納綱條 月光院と間部とが、ほとんど無為に過していた間に、天英院と結んだ老中筆頭土屋正直らが、大いに暗躍して、反間部派を結集して吉宗を担ぎ出したのだという説もある。 南条範夫『徳川十五代物語』(平凡社)による。 20232.02.12記す。
▼『折りたく柴の記』の序を紹介します。日本の名著『新井白石』(中央公論社)P.45~46による。 むかしの人は、言うべきことははっきり言うが、そのほか無用の口をきかず、言うべきことも、できるだけ少ないことばで意をつくした。私の父母であった人びともそうであった。
父であられた人は、七十五になられたとき、はげしい熱病にかかり危篤におちいられた。医者(江馬益庵
そういうふうだったから、お尋ねしてみたいことも言い出しかねて暮らすうちに、なくなられたので、それっきりなってしまったことが多い。世間一般のことならば、それでもよかろう。父親や祖父のことがくわしくわからないのはくやしいが、いまはもう尋ねる人もない。このくやさしさから、私の子どもたちもまた、私と同じようになることもありうると悟った。
補注:独参湯 気つけの妙薬。水一合に朝鮮人参二匁を入れ、半合に煎じて服用する。しょうがゆを加えることもある。 補注:散位 位だけがあって官職のないもの。白石は従五位下に叙せらていたが、正徳六年(享保元)五月十二日、隠退したので、この称を用いたのである。
外交内政の両面で新井白石は難題に挑んでいく。朝鮮使節への対応、南蛮人の取調と海外新知識の吸収、そして綱吉時代に乱れた経済立直しのために通貨改革……正論を吐く白石に敵も増えて家宣の死で運命は大きく変わる。市井から出て多大な業績を残した白石を描いた歴史小説。(解説・伊集院静) 2010.06.13 |
☆46 室 鳩巣(1,658~1,734年)
|
江戸時代中期の儒学者。鳩巣は号。医師草庵の子として江戸の谷中に生まれた、15歳で加賀藩主前田綱紀に仕え、京都で木下順庵に学んだ。1711年同門の新井白石の推薦で8代将軍徳川吉宗の侍講となり享保の改革の教学政策に貢献、荻生徂徠、伊藤東涯の古学両派に対し朱子学を維持した。江戸駿河台に住んだところから「駿台雑話」を著したほか、幕府への上書「献可禄」、詩文集「鳩巣文集」などがある。
『国民百科事典』(平凡社)による。
|
☆47 徳川家宣(1,662~1,712年)と白石

家宣、第六代将軍となる。 この時すでに四十八歳であった。 強烈な印象を与える綱吉と吉宗との間に挟まれて、些か影の薄い思いがするが、永い間、隠忍してようやく将軍職についただけに、老成したところもある。よく人の言を聞いて平凡ながら失政の少なかった将軍である。 家宣は、父綱重が十九歳の時、お保良(おほら)という二十六歳の女中に生ませた児で幼名虎松と云った。綱重が甲府の国守となり、二条家の娘を正室に迎えることになると、外聞を憚って、虎松は綱重の重臣新見備中守正信の養子にされた。 新見は、万一の時を考えて、大老酒井忠清に、虎松が綱重の第一子であることを確認しておいて貰ったが、とに角、少年虎松は新見左近と名乗って陪臣の身として人生の出発をはじめた。 しかし、綱重にその後男児が生まれないので左近即ち虎松が九歳の時、これを再び自分の世嗣に戻そうと考えた。新見と対立していた島田淡路守・太田壱岐守の両人が、これに反対し、 ――主君綱重の落胤である虎松はすでに死亡した。新見はそれを秘して自分の児を虎松として主家を嗣がせようとしている、主君はこの頃、乱心気味でそれが分からないのだ、 と、幕府に訴え出た。 老中久世大和守、綱重に対面して事実を調べてみたが、乱心の様子もないし、虎松が本物であることも間違いない。島田・太田の陰謀は砕かれ、延宝四年(一六七六)十二月、虎松は元服して網豊と称した。 延宝六年、綱重が死亡したので家督を嗣ぎ、同八年、十九歳で正三位となった。 綱吉に世嗣が生まれない以上、当然この綱豊が世嗣となるべきだが、お伝の方以下大奥は必死になって反対し、吉保もまたこれに加担したため、綱豊の世嗣は容易に決らなかった。
ようやくそれが決った宝永(一七〇四)には、綱豊は四十三歳であった。その二十数年に亘る永い間、この男はひたすら読書につとめ、能楽に心をまぎらせていた。間部詮房 この新将軍家宣は、綱吉の遺体を収めた柩の前で、柳沢吉保を呼んではっきりと宣言した。 ――生類憐みの令は、先代が最も気にかけられたものに違いないが、この禁令に触れて罪を得たものは何十万にも上る、先代の御遺志には背くが自分はこの禁令停止することとする、 何らの反対も許さぬ断乎たる態度であった。そしてこの愚劣な法令は一月二十二日、綱吉葬儀の二日前に廃止された。 上下を問わず歓呼してこれを迎えたことは云うまでもない。罪を宥されたもの八千六百人に上った。施策の第一歩は成功であった。 次に行ったのは吉保を政権の座から退けることである。 吉保が、家宣に向って、
――私は亡き上様に特別の御高恩を頂いた者故、殉死仕るべき筈でございますが、御禁制故それもできず、せめて髻 と申し出ると、家宣はすかさず、 重い地位にある者が髻を払って葬送の供をするという先例はない。強いて落髪したければ、先ず御役御免を願い、葬送の済んだ後で隠居した上、落髪するがよかろう、 と、ぴしゃりとやりこめた。 これでは厭でも、御役御免を願って隠居する他はない。さすがの吉保も、政治の舞台を退き、落髪して保山と号し、駒込の下邸に引込んでしまった。 生類憐みの令の廃止といい、吉保追落しといい、家宣はその性格に似合わぬ鋭さを示している。恐らく、綱吉と吉保とに対する深く長い怨恨のためであろう。 家宣の政治顧問として活躍したのは新井白石である。 家宣の時代、及びこれに続く家継の政権の中心になったのは間部詮房であり、政治顧問として活躍したのは新井白石である。 間部の父、西田嘉兵衛は甲府家に仕え、詮房は家宣に仕えたが、姓を間部と改めた。小姓から用人、更に側衆となり、家宣が将軍職に就くと若年寄格、老中格となって政権を一手に握った。宝永七年には上州の五万石、高崎城主となっている。 不遇時代の家宣はこの間部と新井の二人に非常に慰められているため、間部に対する信任も非常に厚く、政治はすべてこの間部に相談し、間部の口を通じて行わせていた。老中でも将軍の前に出ることは五日に一ぺん、十日に一ぺんくらいしかなかったといわれるくらいである。 このい詮房と一体同心になって家宣の政治をたすけたのが新井白石である。 白石は三十七歳の時、甲府藩に仕え、綱豊の侍講となって以来、その絶対的信頼を獲得していた。
従来、将軍の侍講として政事顧問の役をつとめるのは林道春 しかし白石の該博な知識と、透徹した論理とは、常に白石に勝利をもたらしたようである。 白石が最も重要視したのは、朝鮮来聘使の待遇問題、貨幣改革、そして長崎の通商貿易に関する問題であった。 朝鮮來聘使は、将軍の代替えの毎に祝賀の為にやってくる朝鮮国王の使節でさるが、その一行は三百数十人から四百人に及び、接待に要する費用は莫大なものであった。 白石は従来の待遇が余りに厚きに過ぎたものとして大いに簡略化したので、使節は頗る不満らしかったが、費用は六〇パーセントも節約することができた。 また将軍が事実上、日本の主権者であることを明確にするため、従来は朝鮮からの国書の宛名が「日本国大君殿下」とあったのを、「日本国王」と改めるよう要求し、幕府の返書に用いた「日本国源某」という署名も「日本国王」とすることにした。先方も「朝鮮国王李某」と署名していたからである。 更に大きな問題は、幕府が直面していた財政難の解決と、元禄の貨幣改鋳に伴うインフレーションの収束である。 この点については白石は、綱吉時代の財政を一手に担当していた荻原近江守重秀と、真向から対立した。 二人の対立は根深い。 家宣が将軍職についた時、幕府の財政状態について、荻原重秀に説明を求めると、 ――幕府の収入は金にして年およそ七十六、七万両、その中、旗本の給料として三十万両が差引かれて、残りは四十六、七万両、これで一年の経常費を賄わなければならない。一方前年度の総支出は約百四十万両、今年は京都御所の修繕に七、八十万両かかるから、予算の不足は百七、八十万両に上る。このような赤字は例年相つづいてきたのだが、先年、改鋳によって五百万両の利益を得たので、辛うじて何とかやってこられた。それにしても、その残金も今は三十七万両しかない。さし当り前将軍の葬儀、新将軍の宣下等のための費用を考えると、到底足りない。又、改鋳をやるよりほかあるまい。 と云う。 家宣以下、老中たちも呆然とした。 しかし、白石が、綿密に調査してみると、秀重の説明にはおかしいところがある。 ――今、五百万両の残金三十七万両しか残っていないと云うが、去年の収入は現実に今年になってはいってくる。それが七十六万両ある筈だ。従って今年使用できる金は百十万両あまりとなる勘定だ。これだけあれば何とかやれる筈、それに何もかも一時に払う必要はない。足りないところは、延べ払いでもよい、 と白石が論駁したので、ようやく一同はほっとするという一幕もあった。 白石は又、重秀の財政運用に疑惑の目をもち、勘定所吟味の設置を要請した。この勘定役は前代まであったのだが、重秀が勘定奉行となってから、その独断専行の邪魔になるので廃官になっていた。それを再び復活させたのである。 白石と重秀とは、性格的に全く相容れぬものがあったらしく、白石の重秀に対する論難には、かなり強い感情的なものがまじっている。 白石は重秀が財政困難打破のため貨幣改鋳という最も安易な、しかも弊害の多い方法を選んで、貨幣価値の暴落、物価冒頭を招いたことを痛烈に非難した。 重秀も必死の抵抗を試みたが、ついに正徳二年(一七一二)九月、職を罷めさせられた。しかし一度失われた貨幣への信頼は容易に回復せず、さすがの白石も貨幣問題には手を焼いたようである。 綱吉時代には貿易収支も赤字つづきで、長崎を通じてわが国の金・銀・銅が大量に海外に流出していた。白石の調査によれば、慶安元年(一六四八)から宝永五年(一七〇八)までに、金二百三十九万七千六百両、銀三十七万四千二百貫が海外に流出しており、また寛文三年(一六六三)から宝永四年までの間に、銅一億一千百四十五万斤が流出している。そのため、この頃に至って交易用の銅が著しく不足するようになっていた。 白石は長崎貿易を制限するほかなしと考え、オランダ船は年間二艘、貿易額銀三千貫、唐船は年間三十艘、銀六千貫を超え、銅の輸出は年間四百五十万斤を超えてはならぬものとした。 また唐人やオランダ人との間に、抜荷取引が盛んに行われていることを指摘し、役人が外国人に遠慮してその取締りをいい加減にしていることを不可とし、厳重な取締りを要求した。 新井白石という男は功名心や自負心が強く、しかも非常に闘争的であったため多くの政敵をつくり、吉宗の登場とともに失脚してしまった。しかし白石は少なくとも柳沢吉保のような迎合一点張り、将軍の意思に対していつもイエスマンである、というような立場ではなく、あくまでも自分の学問的な理想を政治にいかそうとして、必要があればいつでも家宣に進言したことは高く買ってやらなければならない。 また家宣のほうも、長い間、将軍になれそうでなかった不遇時代から白石を自分の師匠として、学問の上の師匠ばかりではなく政治の上の師匠として、非常に高く評価していた。従って君臣一体という状況で、『折りたく柴の記』にある白石の言葉をかりれば、
――わが心に思うところは申さずということなく、上 というくらいだった。自分は何でもいいたいことをいったし、将軍も自分のいった言葉は全部用いてくれたといっているのである。 ※参考:日本の名著15『新井白石』(中央公論社)P.173(黒崎記) 家宣の政治は割合に成功だったといわれているが、その政治の成功の基礎には、恐らく白石の進言というものが大きく力があったと思われる。 白石は天下有用の学を理想とし、将軍を堯・舜たらしめようとしたが、その実際の効果は乏しかったとみてよい。 白石の本領はあくまで学者である。学者としての研究を犠牲にして、将軍の最高顧問として精魂をつくしたが、現実は彼の手に余るものであった。 白石の業績の中、後代まで残ったものは結局、彼の学問である。彼が明治以前における最大の歴史家であることは、万人の認めざるを得ないところであろう。 古代史研究としての『古史通』『古史通或門』、中世史としての『読史余論』、当時の現代史であり且つその自叙伝でもある『折りたく柴の記』は、いずれも傑れた著述である。わずかに百余日で書上げられた関ケ原以降家綱に至る大名三百三十七家の家伝『藩翰譜』も名著といってよい。 白石がその生涯を著述に専念していたら、われわれは更に多くの傑れた歴史書を読むことができたであろう。 歴史を総合的に、その発展の過程においてとらえたこと、日本古代とくに神代についての科学的実証的に追及し、 ――神はヒトなり、 と喝破したことなど、時流を遥かに擢んでている。 その言語学者としての才能も『采覧異言』『西洋紀聞』『東雅』『同文通考』などに充分に見られるし、『折りたく柴の記』は自伝文学の最高峰の一つを示すと云ってよいであろう。愕くべき博学の人でもある。つまらぬ権力意思にあやつられることなく学究生活に打込んでいたら、更に偉大な存在となったに違いない。 大奥の乱脈 家宣は正徳二年の夏、病を得たが、秋になると、次第に悪化したので、間部詮房、新井白石に、その継嗣について相談した。 この時、一子鍋松は、わずか四歳である。 家宣は、第七代将軍として尾張中納言吉通(よしみち)を立て、第八代を鍋松に譲らせるか、或いは鍋松に次代を譲り、吉通をその後見人として西の丸に入れるかどちらかにしたいと考えていたのであるが、白石は断乎としてそのどちらにも反対し、鍋松を立てて将軍とし、間部以下の側近がこれを守り立ててゆけばよいと主張した。 十月十四日、家宣は五十一歳で死んだ。 鍋松が後をついで第七代将軍となり、家継を名乗る。 四歳の童児であるから、実際上政権を握ったのは間部詮房であり、白石は依然としてその顧問格として活躍した。間部は、家継の生母月光院と非常に親密であり、しばしば大奥に入って、月光院の部屋を訪れ、さし向いて炬燵にはいったりしていたので、幼年の家継でさえ、 ――間部は上様のようじゃ、 と、云った。二人の間の醜聞が囁かれたのも当然であったろう。 月光院は、浅草唯念寺の僧侶の娘であるが、大奥に奉公する中に、家宣にその美貌と才気とを愛されて側室となり、左京の局と呼ばれたが、宝永六年に鍋松を生んだ。 家宣はそれまでに二人の男子を失っているので、鍋松は大切に育てられ、いささか過保護の虚弱児でもあったらしい。 家宣が死んで、左京の局は月光院と称したが、新将軍の生母として、大奥第一の権力者となった。 政務に熱心なあまり妻も妾も持たなかった間部が、この美貌の未亡人の許にしげしげと通ったのであるから、噂がたったのは当然であろうが、その真偽は別として、大奥全体に何となく自由な放恣な色っぽい気配が漂ってきたことは否めぬところであった。 そうした雰囲気の背景として起ったのが、絵島生島事件である。 正徳四年(一七一四)一月十二日、木挽町の山村長太夫座で、美男で知られた生島新五郎の狂言がかかっていた。それを見物に来たのが、大奥の年寄絵島の一行であった。絵島は増上寺の前将軍家宣の廟に代参に行っての帰りであるが、こうした公けの外出を機会に、芝居見物をすることは公然の秘密となっていた。 絵島は二階の桟敷に席をとり、幕間には生島以下の役者たちも姿をみせて接待したので、思わず時を過し、夜に入ってから帰城した。 御錠口の門限にぎりぎり間に合ったが、七つ口の扉は閉まっており、それの開かれるの待っているこの一行がひどく浮ついた色っぽい様子であったので、忽ち色々な噂が乱れ飛んだ。 あまり噂が高くなったので放置することができず、絵島と、同行した宮路とは一応、親戚の家に謹慎となった。 更に取調べの手は芝居各座に及び、役者たちの生活がかなり乱れていることが明らかになったため、役者生島新五郎、狂言作者中村清五郎は入牢を申しつけられ、処罰者は十七人に上った。 この絵島は御家人白井平右衛門の娘であるが、大奥に奉公すると忽ちその才気を認められて左京局に愛され、年寄の地位に上って四百石を受け、大きな権勢を振うようになっていた。 自然、放縦な行いが多くなり、代参や宿下りの時など、物見遊山・芝居見物にふけるようになる。 大奥に出入りする御用商人たちは、そんな機会に絵島に接近してその好意を獲得しようと試みた者が少くない。
浅草に住む材木商の栂 絵島と生島とが、この頃から深い関係になっていたことは推察できる。この頃の劇場には二階三階があり、桟敷には簾がかかっていたし、桟敷から楽屋や座元の家に間道が作られていたらしいから、どんなことでも可能だった筈である。
取調べの結果、大奥女中の乱脈ぶりが明白になったので、絵島は遠流 この事件に関係したものは千五百人にも上ったが、それを一ヶ月足らずで処分し終わっている。 奥山交竹院も、生島新五郎も、中村清五郎も、座元の山村長太夫も伊豆諸島に流罪、山村座は取潰し、絵島の豈白井平右衛門は絵島の不行跡を諫めることなく、吉原見物などにもついていったのは不届として死罪を申し渡された。 この」事件の取調べに当ったのは、御目付の丸毛五郎兵衛と稲生次郎左衛門であるが、稲生は峻烈な裁判をもって知られていた人物である。 忽ち事を大ぴらにし、殊更に手を拡げてしまったので、月光院も間部も白石も、公けに口を挟むことができず、当惑している中に、稲生は恐るべきスピードで裁判を完結してしまった。 月光院はやっと、その時になって絵島のために減刑運動を行い、遠流から信州高遠の内藤駿河守へお預けということにして貰った。
絵島は高遠城に近い火打平の松林の中の囲 生島の方は、三宅島で流人生活を送ること二十九年、寛保三年に許されて江戸に戻ったが、あわれ美貌を誇った役者も、その時は七十三歳であったという。 大奥の乱脈ぶりは、月光院その人に最も多くの罪があったかも知れない。幼少の将軍を抱えて、独身の宰相間部と、何人も怪しむような親密関係を持っていたとすれば、大奥の女たちの所業について、声を大にして叱正することはできなかっyたであろう。 将軍家継は、正徳六年四月三十日、わずか八歳で死んだが、それも月光院に責があったように思われる。 一般に流れた噂によれば、生来虚弱な家継を、月光院と間部が庭園での酒宴の席に連れ出して、風邪をひかせたりしたことがしばしばあったという。
家継が死ぬと、後継者を誰にするかが問題になった。候補に挙げられたのは、尾張中納言継友、水戸中納綱條 月光院と間部とが、ほとんど無為に過していた間に、天英院と結んだ老中筆頭土屋正直らが、大いに暗躍して、反間部派を結集して吉宗を担ぎ出したのだという説もある。 南条範夫『徳川十五代物語』(平凡社)による。 20232.02.12記す。 |
☆48荻生徂徠(1,666~1,728年)

[朱子の『通鑑綱目』]にこれあり候歴代の人物の評判をよく覚えて候て、評判いたし候分にては、悉皆(しつかい)覚え事にて人のうわさばかりに候。人のうわさをいたし候を学問と存じ候ゆえ、人柄のよき人も学問いたし候えば、人柄悪しくなり候こと多くござ候。 学問は飛耳長目(ひじちょうもく)の道と荀子も申し候。この国にいて見ぬ異国の事をも承り候は、耳に翼できて飛びゆくごとく、今の世に生れて数千戴の昔の事を今日見るごとく存じ候ことは長目なりと申す事に候。されば見聞広く事実に行きわたり候を学問と申す事に候ゆえ、学問は極まり候。 2月16日生れた儒学者。朱子学を排して古学に帰ろうとし、そのために古代の言語をよく研究した。役に立つ学問、「実学」を推進した。図はその印鑑。 桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.28 2020.07.31 |
☆49太宰春台(1,680~1,747年)

古くよりそうじて、位高き人に、ものの上手はなきものにて、上手はいつも賤しき者に出来るなり。歌の道にても、人丸、赤人は貴人にあらず。『古今集』を選びたる人々も……皆、地下(じげ)の賤しき者どもなり。この輩みな歌道に達せし故に、選集の勅を受けたり。歌の盛なりし時だに、高位の人はまれなり。いわんや、今の世、歌道衰微の時に、公家(くげ)の高位の人に何として上手あるべき、我に眼なきが故に、公家の名家にて、歌所(うたどころ)と定められたる人をば、必ず上手ぞとおもいて、その添削批判を受くるは、あさましき事なり。。 5月30日江戸で死んだ信濃飯田出身の儒学者。荻生徂徠に師事し、宋学と孟子を排激し、また仏教批判ををこころみた。『聖学問答』など。 桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.90 2020.07.31 |
☆50 徳川吉宗 九分は足らぬ、十分はこぼるると知るべし(1,684~1,751年)
☆51
石田梅岩
|
石門心学とは江戸時代に石田梅岩が創始した庶民のための生活哲学です。石門とは、石田梅岩の門流という意味です。陽明学を心学と呼ぶこともあり、それと区別するため、石門の文字を付けました。梅岩は、儒教・仏教・神道に基づいた道徳を、独自の形で、そして町人にもわかりやすく日常に実践できる形で説きました。そのため、「町人の哲学」とも呼ばれています。 石門心学の思想 17世紀末になると、商業の発展とともに都市部の商人は、経済的に確固たる地位を築き上げるようになります。しかし、江戸幕府による儒教思想の浸透にともない、商人はその道徳的規範を失いかけていました。農民が社会の基盤とみなされていたのに対して、商人は何も生産せず、売り買いだけで労せずして利益を得ると蔑視されていたからです。 梅岩が独自の学問・思想を創造したのも、そうした商人の精神的苦境を救うためでした。彼は、士農工商という現実社会の秩序を肯定し、それを人間の上下ではなく単なる職業区分ととらえるなど、儒教思想を取り込むような形で庶民に説いていきました。倹約や正直,堪忍といった主な梅岩の教えも、それまでの儒教倫理をベースとしたものでした。また、商人にとっての利潤を、武士の俸禄と同じように正当なものと認め、商人蔑視の風潮を否定しました。 これらの新しさとわかりやすさを兼ね備えた梅岩の思想は、新しい道徳観を求める町人の心を次第にとらえていきました。 石門心学はその後、組織化が進み、18世紀末には全国に普及していきました。ただ梅岩の死後は、思想的・学問的意義を失い,民衆のための教化哲学や社会運動という意味を徐々に深めていきます。
石田梅岩は貞享2(1685)年,丹波国桑田郡東懸村 次男であったため、京都に出て上京の呉服商黒柳家に約20年間奉公しました。その間に、市井の隠者小栗了雲(おぐりりょううん)と出会い,思想を深めていきます。梅岩は正式な学問を修めたわけではありませんが、奉公の経験と了雲との出会いが、経済と道徳の融合という独特の思想を生み出す基礎となったと思われます。 梅岩は享保14(1729)年,車屋町通御池上る東側の自宅で講義を始めました。そこで彼は聴講料を一切取らず、また紹介者も必要としない誰でも自由に聴講できるスタイルをとりました。初めのうちは聴衆も数人という状況でしたが、出張講釈などを続けることで次第に評判は高まっていきました。 また講義とは別に、毎月3回月次会(つきなみえ)と呼ばれる研究会を開き、その中で多数の門弟を育てました。その月次会での問答を整理したものが、元文4(1739)年に出版された『都鄙問答』(とひもんどう)です。田舎から京都へ出てきた者の質問に、梅岩が答える形式をとっており、教学の基本理念が記されています。
延享元(1744)年には彼の主張の中核である「倹約」を説いた『斉家論』
手島堵庵 梅岩亡き後,石門心学の中心的存在となったのが手島堵庵(1718~86)です。堵庵は京都の商家に生まれ、18才で梅岩の門に入ります。44才の時に家督をその子和庵(かあん)に譲り、以降は心学の普及につとめました。 梅岩を,真理を求める求道者的存在とするならば、堵庵は庶民を教え導く指導者的存在でした。そして、組織の改革や教化方法の改善に手腕を発揮しました。
明和2(1765)年には富小路通三条下るに、最初の心学講舎である五楽舎
また、女性だけの特別講座や、年少者のために日中行う「前訓」 その結果、民衆に広く受け入れられた心学は、天明・享和(1781~1804)の頃には、京都を中心に社会的一大勢力に発展しました。その背景には,都市部における寺子屋の定着によって、教育の必要性が庶民に浸透したことが挙げられるでしょう。ただ一方で、梅岩の思想の哲学的側面は薄れ,その教えは平易で単純なものになっていきました。
柴田鳩翁
もとは講談師であった柴田鳩翁(1783~1839)は、文政4(1821)年時習舎の薩徳軒
特にこの頃になると、心学も一般に浸透したため、大みょうや代官に依頼され各地を巡回することが多くなりました。越前大野、美作 それらの場で語られた話を、養子である遊翁がまとめたものが『鳩翁道話』です。天保6(1835)年に出版され、明治時代にはベストセラーにもなりました。 また彼は実践を重んじ、自ら復興した脩正舎を中心に飢饉時の救援活動を推し進めました。天保の大飢饉の折には,長期にわたり施粥を行い,彼の没した翌年の天保11(1840)年には町奉行所より表彰されています。 京都の富商と心学 大黒屋三郎兵衛家屋三郎兵衛家は越後屋(三井家)や大丸(下村家)とともに、江戸時代、京都有数の呉服屋でした。その第四代当主杉浦利喬(1732~1809)は石田梅岩の門に入り、心学を修めました。利喬は店の者に、『家内之定』や『家業之定』とともに『石田梅岩語録』を読み聞かせていたことからも、心学の思想を経営の理念に取り入れていたことがうかがえます。またその『家内之定』に、, 家業専に仕、常に倹約を守るべき事などとあり、明らかに心学の影響が見て取れます。 文化6(1809)年に利喬は亡くなりますが、以降も心学は大黒屋の家訓として受け継がれていきました。現在、杉浦家には石田梅岩の肖像画が残されています。 大黒屋以外にも、心学に傾倒した商家は多く、講舎の運営資金の大半は、そうした商人達によって賄われていたようです。
また、心学の説く倹約や正直、堪忍 小学校と心学 明治2(1869)年に日本で最初に発足した京都の小学校では、住民を対象とした社会教育として、儒書の講釈とともに心学の講義が行われていました。小学校には心学の道話師が置かれ、月に6回の講義の席が設けられていました。これは、江戸時代に心学が果たした役割が,明治に入ってもある程度評価されていたからだと思われます。ただ文明開化の流れには対応できず、この制度も明治(1871)年には廃止されます。 ※インターネットによる。 2021.05.26記 |
|
世に、これほど痛快な男はない。徳川宗春、さきのなを通春 この宗春の、思いもかけぬ幸運ぶりは、のちに生涯の政敵となる八代将軍吉宗(紀州徳川家二代光貞の第四子で、越前丹生三万石。が、父の光貞はじめ三代、四代とつづく兄たちの突然死のため五代藩主にのぼる)の運命と酷似しているから、歴史というものは皮肉なものだ、 藩主の座についた宗春の胸中には、幕府憎しの思いが黒けむりをあげている。反感の理由は、将軍職候補として最短の距離にあった尾張徳川家が、そのチャンスを二度までも流したことであろう。 それにしても尾張徳川家は不運つづきであった。六代将軍家宣の病状が悪化したとき、病床の家宣は、わが子家継の幼少さと病弱を危ぶみ、 「予の跡目は、尾張吉通に……」 と遺言して死んだ。尾張家は、次期将軍への期待に目をかがやかしたが、幕府閣老たちの反対によって、家宣の世子家継が将軍となる。だが、家継は三年後に病没。 「さて、このたびこそ将軍に……」
と、二度目の好機到来に尾張徳川家は胸はずませたが、次期将軍と家宣から望まれていた四代吉通は二十五歳の若さで急死してしまう。不運はそれだけではなかった。五代藩主をついだ三歳の五郎太も就任二ヵ月で世を去り、さらに六代藩主継友までが《暴 こうした悲運の尾張徳川家にかわって、颯爽と八代将軍に就任したのが紀州藩主徳川吉宗であった。思いもかけぬ紀州徳川家の登場に、尾張徳川家は愕然とした。そしてやがて尾張領内では、 「じつは……」 藩主たちの死は、吉宗がひそかに差しむけた隠密によって毒殺されたのだという噂がささやかれ、誰もがそれを強く信じた。 「お殿様、ご残念!」 兄、継友のあとを嗣いで尾張徳川家のあるじになった宗春は、そんな藩士や領民たちの憎悪を一身に抱いて、吉宗という巨大な独裁者の君臨する幕府に抵抗し、挑みかかっていく。標的は将軍吉宗の「享保の改革」であった。
おりから吉宗は、五代将軍綱吉の頃から疲弊の度を深めてきていた幕府財政の建直しに取組んでいた。元禄以来の華美の風を矯 それは、なんとも異様な光景であった。行列の先頭を、長大な、真紅のキセルがゆるゆると進んでいく。長さ二間(約三・六メートル)。そのキセルの先端から、時折、ぷかりぷかりと白いけむりが立ちのぼっているのである。
行列のあるじは、いうまでもなく徳川宗春だが、それにしては行装 享保十六年(一七三一)江戸を発してな古屋にむかった宗春は、入国と同時に、領民たちにおどろくべき改革を申し渡した。 「遊芸、音曲、芝居興行も自由、遊郭も設けよ」 宗春の政治は、厳しい上にも厳しく締めつけ鬱陶しい緊縮政策をとっている吉宗の「享保の改革」の引っくり返しであった。長い歳月にわたって疲弊し破綻に瀕している財政が、吉宗のいう"倹約"だけで切り抜けられようとは、宗春は思っていない。 「考えてみよ」
宗春は、お国入りするにあたって、藩主としての抱負と施策方針を二十一ヵ条にまとめた自著『温知政要(尾張亜細相宗春卿 家訓)』のなかで説
《省略倹約の義は、家を治むるの根本なれば、尤も相勤むべき事なり、第一、国の用縮まり不足しては、万事さしつかゆる(差支える)のみにて、困窮の至極となる。さながら(とは申せ)めったに省略するばかりにては、慈悲の心うちくもりて、覚えずしらずむごく(酷く)不仁になる仕方出来 いたずらに倹約を叫んで締めつけるだけでは為政者としての慈悲の心薄くなり、庶民を苦しめるばかりではないか、と宗春はいう。 《国に法令多きは恥の基なり(略)諸令多くなれば、破る者また多し、法令多く過ぐれば人のこころいさみ(活発さ)なく、せばく(狭く)いじけ、道を歩くにも後光を見まわし》 という状態になるものだ。 宗春のこの『温知政要』のなかには、平成の現在でもそのまま適用しそうな言葉が多い。
《たとえ千金をのべたる物にても、軽
という条
《万 この、人それぞれ各人の用を知って使えとう条など、わが身の趣味嗜好を最高のものと信じている吉宗への、そしてまた峻烈な法治主義をかかげて幕府にのぞんでいる吉宗の政治姿勢への痛烈な批判である。 ともあれ、宗春の大改革でな古屋の城下は空前の繁盛ぶりをみせる。日本国中が貧寒とした緊縮ムードに喘いでいるなかで、な古屋だけが開放的で活気に満ちた別天地であった。それまで藩法で禁じられていた遊郭が十二の町に拡がり、歌舞伎芝居の常設劇場が十四町に設けられ、それぞれの周辺に見世物小屋、料理屋などの商売店が軒をつらね、この繁華の地を求めて諸国から遊芸人や商売女たちが稼ぎを目当にどっとながれこんできた。宗春が打ち出した「民と共に楽しむ」積極策は見事に当った。 が、この『禁令無視』の行状が吉宗の怒りをかい、幕閣から隠居謹慎を命じられた宗春は、な古屋三ノ丸の角屋敷に幽閉されること二十三年。没後もなお幽閉を解かれず、かれの墓石は金網をかぶせられたままであった。その罪がゆるされ、金網が取り払われるのは死後七十六年目の天保十一年(一八四〇)。政治というものは残酷なものである。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.233~238 2021.06.26記 |
|
江戸期のサラリーマン武士の処世心得といったものに、大道寺友山(一六三九~一七三〇)の『武道初心集』がある。『葉隠』語録が《武士はいかに死すべきか》を書いたものとすれば、この『武道初心集』はサムライの新人たちに、現世を《いかに生くべきか》説いた書である。 ちょっとユニークな武士学入門書は、諸藩の武士たちの家庭に普及し愛読され、藩が消滅した後の明治末年ごろまで読まれていた。おどろいたことにこの本は海を越えて英国に渡り、イオギリス人A・K・サドラーの手によって翻訳され、武士道のテキストとして、 『The Beginer's Book of Bushido』 と題され、一九四一年に国際文化振興会から刊行されている。
この本で友山は、組織のなかに生きる新人のサムライたちのために筆を走らせ武士道を語り、微に入り細をうがって書きつづけていくのだが、家庭でのサムライの心得《妻に対して如何に対処するか》という条
怒りにまかせて女房を拳骨で殴りとばしたりするなど言語道断、夫たるもの《如何なる事あるも、ただただ堪忍せよ》と友山は説く
これを読んでいると、いまも昔も、女房族の手ごわさ、したたかさに手を焼いて途方にくれているサムライたちの表情が泛 女といえば、わが女房のすさまじさに手を焼いた男たちの例が幾つかある。
戦国きっての暴れ大みょうの福島正則でさえも、浮気が発覚して正室(妻)から大薙刀
「さてもさても、女の悋気したる勢いほど恐ろしきはなし、悪鬼羅刹 と溜息したというが、猛妻たちの壮大な悋気の余韻はこの時期まだ残っている。
松江二十六万石の京極若狭守は、幼い頃から叔母(二代将軍秀忠の妻)の超ヤキモチぶりを見て恐妻ノイローゼになり、正室の目をおそれるあまり妾腹のわが子の出生を公儀に届けずひた匿
小倉藩の家老、長岡佐渡の妻おこまは、細川忠興とその妻ガラシア玉の娘だけに気が強い。が、このおこまの方の侍女に思いをかけた佐渡は、老女(女長官)を掻きくどいてようやく首尾をとげ、以来、なにくわぬ顔で逢う瀬を重ねていた。ふたりの密会がばれたのは、細川家伝来の天下の名香、白菊の伽羅 「あな憎や!」 とばかり、手元の焼け火箸をとって侍女の胸を突き刺し、三度突き刺して殺してしまつた。
唐津八万三千石の大みょう、寺沢兵庫頭 兵庫頭の度重なる浮気に逆上して実家に帰ってしまった正室おせんの方におどろいた兵庫頭は、慌てて呼び戻すための使者を走らせたが、おせんの方は冷やかに、 「もはや、過ぎたる夢でありますゆえ」 と、素気ない言葉を返すばかりである。これを気に病んだ兵庫頭は、思いつめたあまり菩提寺に入って、切腹してしまった。 《正保四年十一月十八日、兵庫頭発狂シ浅草海禅寺ニ入リ自刃シテ封除セラル、三十九歳》 こうした"勇気凛々"の女房族の話ならザルに盛りあげるほどある。江戸時代の爛熟期、文化・文政の庶民の世界を覗いてみて
《今、軽キ裏店 と『世事見聞録』の筆者はいう。 以下、現代風に読みくだしてみると、 ――近ごろ、裏長屋に住む人びとの様子をみると、親は苦しいやりくりをしてその日その日を送っているのに娘の方は親たちにおかまいなく、べっったりと化粧し晴れ着をきて男たちと遊び暮らし、女房のほうもまた娘に負けず、夫が働きに出かけた留守をさいわいに、隣近所の女房寄り集り、みなみな亭主の甲斐性のなさを言いちらし、花札など博打に興じ、あげくの果ては若い男を相手に酒を飲み、芝居見物や料理茶屋に出かけ、夕方疲れて帰ってきた亭主を顎の先でこきつかい、酔ざめの水を持ってこさせるなど、
《女房ハ主人ノ如ク、夫ハ下人ノ如クナリ、懈逅
――この時期、商家の女房たちの勁
《妻は内(家庭)を守り、勝手廻り(台所)を能くするが身の役目なり、商いごときにつき談合せらるることありとも、智慧顔に善悪を分け、勝手不勝手いいなすは却って身代の妨げなり。牝鶏晨
と、世の亭主たちを代弁して"女房訓"に説
《家内を見廻り、(無駄な)費
《物妬み、中言 《下女丁稚を使い者(使用人)と侮ることなかれ。別して心付(チップ)、それぞれに致すべし》 《仮にも男体したる者と囁き小話(などする事を)忌むべし》 《己が器量を鼻にかけ、不埒の所存あるべからず》 《夫の家、始め貧にして後栄えたりとも、高慢無用たるべし》
《夫の家、始宜しく後零落
《身代不相応の衣装、櫛、笄 《芝居見物、遊山等々度々出て、世間に顔見らるること慎むべし》
《右の条々、女房たるもの朝夕忘れず嗜む者は、女夫喧嘩の物言なく家栄え子孫多く、女の鑑 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.45~49 2021.06.15記 |
☆54山本 常朝(1,716年頃)
|
▼『葉 隠』 聞 書 第一 二 武士道といふは、死ぬ事と見つけたり。 『葉隠 上』(岩波文庫)P.23 一四三 武士は假にも弱氣のこと云ふまじ、すまじと、兼々心がくべき事なり。かりそめの事にて、心の奥見ゆるものなり。 P.73 森信三『一日一語』: 肉体的苦痛や精神的苦悩は、なるべく人に漏らさぬことー。 人に苦痛や不幸を漏らして慰めてもらおうという根性は、甘くて女々しいことを知らねばならぬ。 ※海軍兵学校での教えでもあった。 一五四 世に教訓する人は多し、教訓を悦ぶ人はすくなし。まして教訓に従ふ人は稀なり。年三十を越したる者は、教訓する人もなし。教訓の道ふさがりて、我儘なる故、一生非を重ね、愚を増して、すたるなり。道を知れる人には、何卒馴れ近づきて教訓を受くべき事なり。P.75 説明:『葉隠』の筆録者田代又佐衛門陣基(ツラモト)、文中に出てくる常朝(ジャウテウ)居士はすなはち『葉隠』の口述者山本神右衛門常朝(ツネトモ)である。
岩波文庫は(上・中・下3冊)
2009.07.12 |
|
徳川期における最も偉大で進歩的な政治家とも称
紀州藩の軽輩であった田沼の家が、歴史の表面に浮びあがってくるのはこの意行の代である。紀州徳川家から徳川宗家に入って八代将軍の座に就いた吉宗に随従して江戸にくだった意行は、三百俵御小なん戸役 いっぽう、将軍の世子、家重の小姓としてスタートした意次は、天下の人士を瞠目させた空前絶後ともいう出世ぶりをみせるのだが、それを年表風に列記すると、 元文二年(一七三七)十九歳、主殿頭に叙任。 延享三年(一七四六)二十八歳、小姓頭取となり、御役料百両。 延享四年(一七四七)二十九歳、二千石に加増。 寛延四年(一七五一)三十三歳、九代将軍家重の御側御用取次となる。 宝暦五年(一七五五)三十七歳、五千石に加増。 宝暦八年(一七五八)四十歳、遠州(静岡県)相良一万石を拝領し、大みょうに。 やがて家治に将軍職をゆずって隠居した家重は、その臨終の枕頭に家治を呼んで、 《主殿はまとうど(完全な人物)なり、ゆくゆく心を添えて召使わるべきよし御遺言ありしにより》(『徳川実紀』) 十代将軍家治はその遺言をまもり、意次を一万五千石に加増。以来、意次は家治の側近ナンバー1の官僚政治家として卓越した才腕をふるう。 四十九歳で御用人となり加増二万石、相良城主となる。五十一歳、側用人兼老中格に列し三万石という破格の立身をとげる。 老中職といえば、将軍綱吉の寵臣、柳沢美濃守吉保でさえ、正式の老中にはなれなかったのである。この一事をみても意次の出世は、信じられないほどの幸運に包まれていたといえる。 意次の幸運は、なおもつづく、 五十九歳、三万七千石……六十三歳、加増をうけ四万七千石となる。 信じるべき資料によると意次は、細面の美男で才気渙発で、切れ者の官僚にありながら驕ったところがなく挙措おだやかで謙虚な人柄であったという。下僚に対しても物腰低く、人間関係の達人で、政治家としても当時の猫の目のように移り変る経済社会を広い視野で眺め、鎖国いらい立ち遅れている日本を開国に転じ、沈滞の底にある経済の活性化をはかろうとしていた。 「そのためには……」
海外貿易の道をひろげ、国内でも北海道に百十六万町歩の開拓、七万人移住の計画や、千島、樺太開発の大構想など、現実を凝視
海外貿易といえば、意次の嫡男の山城守意知
――だが、こうした意次父子の心にくいばかりの仕事ぶりに、諸大みょうや旗本たちは黒けむりをあげるほどの妬 「あの、成り上り者めが」 そんな彼らの目に、軽輩微禄の意次が将軍家重・家治のお声がかりで天下第一等の権力者にのしあがり、古い因習を次から次へと破って政治の世界に新風を吹きこませている姿ほど憎々しいものはない。 だが、心の中ではそう思いながらも彼らは、猟官運動のために田沼邸に日参じ、意次、意知に世辞を振り撒き、阿諛(へつらうこと)し、追従の限りをつくしている。それは意次の前に平身低頭した松平定信や、肥前平戸城主、松浦静山の例をみればわかる。 が、好事魔多し。政治家としての意次の晩年の不運は、明和七、八年(一七七〇、七一)の全国的な大旱魃から、天明三年(一七八三)にいたる数々の天変地異である。うちつづく飢饉、災害、疫病、伊豆大島三原山の大噴火、浅間山の爆発に民衆は戦慄した。この災禍の原因は意次父子の奸悪な政治を天が懲らしめているのだ、という噂がささやかれ、そうした黒い風説に追打ちをかけるように、山城守意知が江戸城内で旗本、佐野左衛門に斬りつけられ横死するという事件が起っている。この刃傷の原因はいまも不明だが、すでに老境にある六十六歳の意次にとって、嫡男である政治改革の唯一の同志でもあった意知の死は致命的であった。
だが、意次は父である前に政治家であった。五体を引き裂かれるような思いを怺 この日から、意次の運命は逆転する。
失脚後の意次に浴びせかけられた、いわれなき中傷の殆どは「成り上り者」意次の卓越した政治手腕に対する保守派門閥大みょう、旗本たちの嫉妬と憎悪である。反田沼派の彼らが振り撒いたデマに踊らされた巷の人びとは奸悪の侫人として意次父子を罵倒し、讒謗(誹謗)の限りをつくしている。従来の諸資料や文献のなかにみる"賄賂伝説"もその一つである。田沼事件は、幕府を舞台にした一種の「お家騒動」であり、欲望芬々 みずからについて語らず、記録も残すことのなかった意次だが、唯ひとつ子孫のための家訓ともいうべき遺書(田沼道雄氏蔵)を残している。意次の処世信条であるこの七ヵ条の訓は、忠義、孝行、武芸、学門といったもののほか、 《交誼に裏表なきよう心掛くべし》 《家人(使用人)をあわれみ、賞罰に依怙の沙汰あるべからず》 《百姓、町人に無慈悲なる扱いなすべからず、(わが)家の害、これに過ぐるものなし》 といった要旨のものの他、財政問題については、 《勝手元不如意にて貯えなきは、一朝事ある時の役に立たず,御軍用に差しつかえ、武道を失い、領地頂戴の身の不面目、これに過ぐるものなし 》 と述べ、捌紙までつけ格別の注意を与えている。武士の収入というのは予定以上に増えることはない。凶作による収入減、不時の出費、それらが重なれば憂うべき結果を招くものだ。借金をした場合、利息は十分の一、千両借りれば知行百両減じたものと同じゆえ、利子の支払いと元金の返済に窮し、更に借金し、遂には大借財となりたる例、世間に極めて多し。ゆえに、 《常に心を用い、いささかの奢りもなく、油断せず要心すべし》 と意次は、その遺訓のなかで声を重ねている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.273~277 2021.06.10記 |
☆56 本居 宣長(1,730~1,801年)
|
「……初心のほどは、かたはしより文義を解せんとはすべからず、まず大抵にさらさらと見て、他の書にうつり、これやかれやと讀みては、又さきによみたる書へ立かへりつゝ、幾遍 本居宣長著 村岡典嗣校訂『うひ山ふみ 鈴屋答問録』(岩波文庫)P.19より。 関連図書:『本居宣長』日本の名著 21(中央公論社)昭和59年3月20日初版発行 P.36。
この本によると、『宇比山踏』 関連:松阪の一夜 |
☆57 杉田 玄白(1,733~1,817年)
 医は生涯の業として、迚
医は生涯の業として、迚
若狭国小浜藩医。玄白は通称。江戸生まれ。
漢学を宮瀬竜門 山脇東洋の解剖観察に刺激され、オランダ通詞にオランダ流外科について質問、蘭書の入手につとめた。 明和8年(1771年)小塚原こづかっぱら刑場で屍体の解剖を観察。 携帯したオランダ語解剖書『ターヘル・アナトミア』の内景図が実景と符合していることに驚嘆し、同志と翻訳を決意する。 安永3年(1774年)『解体新書』5巻として公刊し、蘭方医書の本格的翻訳の先駆となった。 以後、診療と後進の育成に尽した。多趣味で、社会批判の書などもある
あとがき 江戸末期の医学者杉田玄白らが、オランダの解剖学書「ターヘル・アトミア」を翻訳して『解体新書』と名づけて出版したのは、一七七四年でした。二百年記念の一九七四年、わたしたちは、玄白の偉業をしのんで日曜版の『みんなの健康』のページに『新・解体新書』という連載記事を始め、二年続けて、一九七五年末までにちょうど百回に達しました。 この本は、それをまとめたもので、さし絵も、作者のご好意により、そのまま採録しました。取材にあたってお世話になった解剖学者やお医者さん、そのほかのかたがたに、心からお礼を申し上げます。連載を始めた当時の科学部長・広田哲士氏、同次長坂根巌夫氏の指導と助言を忘れることができません。 一九七六年一月 朝日新聞東京本社科学部長 木村 繁 2017.11.03 記録 |
☆58 伊能 忠敬(1,745~1,819年)
|
家 訓 第一 仮にも偽をせず、孝悌忠信にして正直なるべし 第二 身の上の人ハ勿論、身下の人にても教訓意見あらば急度相用堅く守べし 第三 篤敬謙譲にて言語進退を寛裕ニ諸事謙り敬ミ、少も人と争論など成べからず 参考:1 ■佐原 伊能忠敬記念館
参考:2 ■Yagiken Web Site
私は伊能忠敬については知っていましたが、あらためて上記参考資料により、後半生の生き方に感動致しました。
江戸時代に全国を測量し日本地図を作り上げた伊能忠敬の墓は、東京・上野の源空寺にある。隣に眠るのは19歳年下の暦学の師匠、高橋至時(よしとき)だ。忠敬は遺言で、若くして病に倒れた師の横に自らを葬るよう求めた。享年73歳。超高齢化の今、生き方に学ぶところは多い。 ▼酒造や米取引をなりわいとする下総国佐原村(現・千葉県香取市)の伊能家に忠敬が養子に入ったのは17歳の時。家業をもり立てる一方、村な主として飢饉(ききん)の対応に当たった。この間もひとりで天文学や数学を学び、隠居後、50歳で高橋に入門している。幕府の許可を得て、北海道の測量に着手した時は55歳になっていた。 ▼最後の遠征となった九州では持病を押し、ほとんど歯のない状態のなか、古希に近い体にむち打ち現場で指揮をとっている。途中、片腕と頼む副隊長が40代で病死し、忠敬は「鳥が翼をもがれた」と嘆いた。実はこれに先立ち、家督を継いだ長男の景敬も世を去っている。家族は遠方の忠敬にあえて知らせなかったようだ。 ▼まさに「一身で二生を経た」と言うにふさわしい。持ち前の向学心と根気で歴史を切り開いたのだが、逆縁や逆境に耐え抜いた姿にも敬服する。人生一世紀の時代は近そうだ。長く働くにしろ、学び直すにしろ、思いもかけぬ悲嘆や苦難が待ち受けるかもしれない。乗り越える勇気と知恵を忠敬の生涯から学んでおきたい。 春秋 2017/8/20付
余録 彼は地球の大きさを知りたかった…毎日新聞2018年1月4日 東京朝刊 彼は地球の大きさを知りたかった。測ってみたかった。家業を息子に譲り、天文学や測量技術を学ぼうと江戸に出る。50歳の手習いだ。伊能忠敬(いのうただたか)の日本地図作りがこうして始まった ▲実測は「蝦夷地(えぞち)」と呼ばれた北海道に始まり、10次にわたる。旅は苦闘続きだった。入り組んだ海岸線の踏破にてこずり、現地案内人が藩の機密漏れを恐れて地名を言わないこともあったと記録にある ▲61歳の春には、今の山口県でマラリアにかかり長く療養した。晩年になると「歯がすっかり抜け、奈良漬けも食べられない。悲しい」という手紙を娘に送っている。約4万キロを歩いて測量を終えた時、忠敬は71歳だった ▲その陰には、宿を提供したり、現地で作業を手伝ったりした人たちの存在もあった。測量日記には1万2000人のなが残る。そこで伊能忠敬研究会は2年前、彼らの子孫たちにな乗りをあげてほしいと協力者の名前を公開した ▲これまで約100人の申し出が寄せられている。先祖が歴史的な取り組みにかかわったことを初めて知った人も多い。新たな記録や品物も見つかった。忠敬の没後200年を迎え、4月には東京都内で式典を開いて子孫に感謝状を贈る ▲研究会の戸村茂昭(とむら・しげあき)さんは「協力者あっての偉業でした。そうした人たちにも光をあてたい」と話す。年齢や困難を乗り越えて奮闘する姿が、多くの人々を手助けへと動かしたのだろうか。自らの探究心や好奇心にふたをせず、挑み続けた忠敬の姿勢は今の時代も色あせていない。 毎日新聞:余録2018年1月4日 |
☆59 塙 保己一(1,746~1,819年)
|
『史記』読んでいますと、中国では「左丘(さきゅう)」は失明して『国語』を作つています。日本でも七歳にして失明して学問に励んだ塙保己一(クリックしてください) がいることを思い出しました。インターネットで検索しますと、上記の記事が検索されました。早速リンクさせていただくお許しをお願いいたしますと、快諾を頂きました。ヘレン・ケラーとの関連のお話も掲載されていますから、十分にお読みくみください。 追加:「命かぎりにはげみなば、などで業のならざらんや」朝日新聞(2010.02.06)磯田道史の「この人、その言葉」より |
|
江戸後期の大阪で、「大みょうであれ旗本であれ、借金をせねば暮らしていけぬ者は、"貧民"だ」と言い放った男がいる。升屋小右衛門、町人学者としてのなを山片蟠桃 「仙台藩などというても、(こちらは)年貢米をカタに返済できぬほどの金を貸しておるのだから、仙台六十二万石は升屋の物も同然だ」
と小右衛門は辛辣
百姓が年貢に出した残りの米を藩が「米札」(一種の私製紙幣)で買いあげ、江戸に運んで売った現金を両替商にまわしてその利息を稼ぎ、藩財政再建に充 「それなら、手前どもで一万五千両ほど御用だていたしましょう」 これで資金の方は都合がついたが、東海廻し(太平洋)で江戸へ運ぶために仙台、銚子、江戸と三ヵ所に役所を設ける必要がある。
「その費用も升屋がお出ししましょう。が、これらの役所の雑費
と小右衛門はいう。だが、いつの場合にも役所というのは融通のきかない石頭ばかりで、前例のない金は一両も出せない。もともと「算用 「なるほど、それなれば」 小右衛門はうなずいた。その二百両のかわりに、 「一俵一合のサシ米をおゆるしくださらぬか」
サシ米というのは、俵の米の品質をチェックするとき、俵へサシ(刺 「おお、それならやすいことじゃ」 と役人は、快諾した。
「サムライどもの阿保 小右衛門は、心の中で舌をだした。
当初、二百両支給せよと切りだしたのは作戦である。二百両を升屋に支出して、もし小右衛門の施策が失敗した場合、その責任は係役人が背負わされてしまう。だが、一俵につきたった一合のサシ米が減ったところで係役人には痛くも痒
ところがこの一俵一合が莫迦
この六千両が、以後、升屋の金蔵
このサシ米や買米、回米で、傾きかけていた升屋や仙台藩を立て直した大番頭の小右衛門に、当主の重芳(升屋四代目山片平右衛門)は感謝の意を罩 小右衛門が町人学者、山片蟠桃としてなをあらわしてくるのはこの頃からである。号の蟠桃は、升屋山片の番頭、をなぞらえたものである。
学問を好んだ蟠桃は、《書生の交りは貴賤貧富を論ぜず》と四民平等をうたった町人の学問所、懐徳堂に学び、朱子学を中井竹山、履軒 《太陽ハ天地ノ主ナリ、地ハ主ニアラズ、太陽動カズシテ(略)》
と、日本最初の地動説とも思える一節もある。天文学に興味をもつ蟠桃は、観測器械をつかって天体観測をしたり、奇児
《紅毛ナドノ国ハ、国王元ヨリ商売ノ大将ナリ。万国ニ奔 そして蟠桃は、外国と交易をするには、天文、地理の知識が必要だと述べる。
《先年(松平定信の寛政改革)諸 《経済ハ民ヲシテ信ゼシムルニアリ。民信ゼズシテ何ヲカナサン。民ヲ信ゼシムルハ唯ソノ身ノ行イアルノミ》 商いとえば、物価は需要と供給が決定するもので、政治権力が介入したところでどうなるものでもない。かえって高騰をあおりたてるばかりである。
蟠桃はまた、神仏や迷信は人間の心がつくったもので、霊魂などというものは存在しないと言い、日本の神々が生まれ、国土草木を生む……という(本居宣長などの)学者たちの愚陋
《今ノ巫祝 もともと神や霊魂など有りはしないのだ。
《死シテ何
《ソノ魂魄 《人ノ生ズルは草木ノ萌生スルガゴㇳク、ソノ死スルㇵ枯ルルガ如シ、又ソノ子アルㇵ種実ヲ蒔テ生ズルガ如シ、スベテ一種一衰ノ道理生ㇾテ、グングンㇳ陽気盛ンニナリテモ、亦ツヒニオトロエ、命尽キ死シ、消散シテテ土ニ帰ス》
ある時蟠桃の友人が重病になった。が、祈禱師
「儂 そう詰め寄ると、祈禱師は仰天して逃げて行ってしまったという。実学家蟠桃の面目躍如たる逸話である。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.256~260 2021.06.07記
|
|
ずいぶん以前のことなのだが、アメリカ大統領ジョン・F・ケネディに、「大統領閣下、あなたが尊敬する日本人は?」と日本人記者が質問したことがある。そのときケネディは、信長でも秀吉、家康でもなく、徳川中期の地方の一大みようにすぎない、 「ヨーザン・ウエスギ」 のなをあげて記者団をおどろかせた。
――上杉鷹山
が、十歳の直丸(鷹山)が赴く以前の米沢藩は、財政のどん底に喘いでいた。もっとも上杉家の貧困ぶりは今に始まったものではない。謙信以来の歴々の名家も、関ケ原合戦で西軍、石田三成に加担したため、会津若松百三十万石から米沢三十万石に減封処分されるが、不運は更に続く。嗣子に恵まれなかった三代藩主の急逝によって、家名断絶、米沢藩取潰しの瀬戸際に立たされるが、三代藩主夫人の父、保科正之 それからが地獄であった。現在の企業なら経営の枠組みが縮小されれば、それに応じて減量し、従業員の人員整理にかかる。ところが、上杉家ではそれをしなかった。当時、幕府が定めた大みょう家の軍役は、平時では一万石につき約二百人。十五万石に半減された上杉家の場合なら三千人でいい筈だが、家臣団は従来のままの六千人。かれらの俸禄だけでも、十三万万五千石が必要である。 こうした放漫経営に拍車をかけたのが、吉良上野介に嫁いだ三代藩主綱勝の妹と、上野介の子、三郎が上杉家四代藩主になるという、吉良家との二重縁故であった。諸事、豪奢が家風ともいう吉良家出身の、派手好みの浪費狂の四代藩主の行状と、その実家である吉良家へ年々送りつづけた莫大な経済援助が、ただでさえ苦しい上杉家の財政を破綻させ涸渇させた。
江戸藩邸へは、売掛金の催促に連日、町人たちが詰めかけ、それらの借金の清算もできず、やがては藩主が登城する行列に必要な経費にも事欠き、やむなく重臣たちが甲冑刀槍
「鍋釜のなかに"上杉弾正大弼 と噂される始末であった。 借金と言えば、江戸の豪商三谷(みたに)家をはじめ出羽酒田の本間家など、借りられるところはすべて借りつくし、藩士たちからは俸禄の借りあげ、領民からは過酷な搾取と、火の車財政のやりくりをしてきた米沢藩が、 絶対絶命の窮乏の極に立たされたのは、宝暦三年(一七五三)。幕府から上野、寛永寺中堂普請を命じられての出費、五万七千四百両余と、同年洪水による領内の被害三万七千七百八十余石、そしてその翌年の凶作被害そん耗高七万五千八百二十余石の減収であった。だが、それに追打ちをかけるように宝暦五年、六年と奥羽地方一帯に大凶作が襲来する。領内の窮士貧民は小ぬか藁だんご)、松皮だんごや木の根を喰って飢えをしのいだが、その顔色はすでに、《人間の色合にて之無く候》という有様であった。 「もはや、自滅か」 万策尽きた重定は、藩主の地位を放棄し、十五万石の領土を幕府に返上しようと前代未聞の決断をした。 この、重定の封土返上は尾張中な言徳川宗勝に諭されて中止し、明和四年(一七六七)重定隠居。かわって鷹山、九代藩主になる。時に十七歳。家督をついだ鷹山はこのとき、 受次ぎて国のつかさの身となれば 忘るまじきは民の父母
今日からは家臣や領民の父となり母となり、かれらをいつくしむ政治 しかし、この時期の鷹山の立場は、前社長が投げ出した倒産同然の老朽会社を、若い養子の社長が懸命になって再建しようというのに似ている。 鷹山の施策第一弾は、従来の諸儀式、仏事、祭礼、祝事を取り止め、または延期し、五十人の奥女中を九人に減らし、藩主以下全員、食事は一汁一菜、綿服の着用、贈答の品は一切廃止……と十二ヵ条に及ぶ倹約令の公布であった。そしてその徹底を図るために『志記』と題した一文を書いて、その意とするところを重臣たちに伝えた。だが、「死にかかっている魚は頭から腐っていく」というが、若い藩主に対する重臣たちの反応はつめたい。 「けッ、かよう貧乏くさい倹約令など、武威を天下にふるって隠れもない不識院(謙信公)さま以来の面目を汚す気か」 と、贅沢に狎れた家臣たちは鷹山の倹約令を嘲弄し、なかでも正面から非難蔑視した奉行職の千坂対馬、色部修理、江戸家老の須田満主など七重臣は病気と称して出仕しなかった。 「やむを得まい」
鷹山の処断は峻烈であった。重臣たちに、切腹、隠居閉門と採決を下したあと鷹山は、大倹約令を実施し、竹俣当綱
鷹山のすばらしさは、奇蹟にちかい再建をなし遂げたあとも、自分は一汁一菜、綿服という質素な生活を守り続けたことであろう。天明五年(一七八五)米沢藩を黒字財政にのせたあと、鷹山は前藩主の実子、治広 そのとき鷹山が、藩主の心得として治広に与えたのが『伝国之辞(譲封之詞)』である。
《一、国家ハ先祖より子孫へ伝候国家にして、我私 一、人民ハ国家に属し足る人民にして、我私すべき物にㇵ無之候 一、国家人民の為に立たる君にて、君の為に立たる国家人民には是なく候
右三条、御遺念有間敷 天明五巳年二月七日
治広殿 机前 治憲(花押 ここでいう国家とは米沢藩、人民とは領民のことだが、「君主は国家、人民のためにたてられたもので、君主のための国家、人民があるのではない」という愛民の思想は、はるか後世の海の彼方のアメリカで《人民による、人民のための、人民の政治》と叫んだリンカーンの言葉を思い出させる。 日本人記者から質問お受けたときケネディは、wざれわrでとは逆に、ヨーザン・ウエスギの言葉を思い泛べたのであろう。 鷹山の『伝国之辞』は、ゲティスバーグのリンカーンのあの有名な演説より、八十年も前に書かれている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.18~22 2021.06.21記 |
|
なせばなる なさねば成らぬ何事も 成らぬは人の なさぬなりけり
▼うわさによりますと、故ケネディがアメリカの大統領に就任したとき、日本の新聞記者たちが、祝いに行き、ぶしつけに〈日本の政治家のうち誰を一番尊敬されますか〉と聞いたところ、即座に「上杉鷹山」と答えられ新聞記者達は、意外さにおどろいたということです。余りにもうがった話のように聞こえますが、静かに考えて見ますと、やはりあり得ることだと思います。
▼それは明治二十七年内村鑑三先生の名著(英文)『日本及び日本人』のなかに「新日本の建設者 西郷隆盛」「封建領主 上杉鷹山」「農民聖人 二宮尊徳」「村落教師 中江藤樹」「仏教僧侶 日蓮上人」と、代表的日本人として紹介されました。これが欧米人の間に、大変な評判になりました。この本はわが国の主要人物をただしく評価し、日本人特有の多くの美点、特質を外国の人々に知らせようとしたもので、盲目的な忠誠心や好戦的愛国心をもつ国民として海外に誤って伝えられているのを正し、さらに進んで、世界の人々は、クリスチャンを含めて、むしろ日本人に学ばねばならぬと説こうとしたものであります。
*上杉鷹山公小伝(編集発行 御堀端史跡保存会)より引用。 2008.4.03、2011.09.05再読。
参考1:上杉鷹山
私見:ケネディ大使が父親の故ケネディ米国大統領が日本の政治家で一番尊敬している人は 平成二十六年九月二十八日 |
|
「男一匹、本気で相手にしてよいほど値打ちの確かなものは、この世でひとつしかない、それは金のことさ」 と言ったのは文豪、オノㇾ・ド・バルザックだが、その金についてアメリカの経済雑誌『フォーチュン』(一九九〇年九月十日号)が発表した恒例の"世界の長者番付"によると、世界一の金持ちは四年連続して産油国のブルネイ第二十九代国王サルタン・ハサナル・ボルキァ・ムイザデン・ワダウラで総資産は二百五十億ドル(約三兆六千二百五十億円)、その殆どが石油、天然ガスの輸出と、おびただしい国外投資で稼いだ利益で、一日あたりの収入は約四十八億円だというから、気が遠くなるほどの金額である。 第二位はサウジアラビアのファㇵド国王とその王室で百八十億ドル、第三位が製菓で有名なアメリカのフォレスㇳ・マーズ氏とその家族の百二十五億ドル。第四位がイギリスのエリザベス女王の不動産など百十七億ドル。日本人では西武鉄道のオーナー、堤義明氏の七十三億ドル(一兆九百五十億円)が第七位に顔をみせている。
《世ニアルㇹドノ願イ、何ニヨラズ銀徳(金の力)ニテ叶ワザルコト天 この五ツというのは、地水火風空の五つの原素から成り立っている生命をさしているのだが、そのイノチ以外のものは、すべて金の力で解決のつかないものはこの世にない。にんげん万事金の世の中と、偶然ながら符合しているのがおもしろい。そして西鶴は、そのお金持ちの資格を、
《銀百貫目ヨリシテ是ヲ分限
だと定義している。以前この西鶴の定義を平成の現在の銀の地金相場に換算して「一千貫ならたったの一億円、それくらいの小金持ちなら掃いて捨てるほどいる」と力説していた人もいるが、歴史の中の金勘定はそんな単純なものではない。元禄のその当時といえば大坂心斎橋ちかくで間口六、七間の家が銀一貫三百七十匁 ともあれ、そんな"分限"や"長者"になるために西鶴は、暮しの処方箋として、 《朝起五両、家職二十両、夜話八両、始末十両、達者七両》
この妙薬を朝夕服用すれば、かならずお金持ちになれると説 この商都大坂に住む分限、長者といわれた銀主(諸大みょうの金貨)の家に、 《貧乏払い》
という奇妙な風習があった。毎月晦日 《口ヲワンㇳアクヨウニシテ、口ヲヒロゲテ》 と、茶碗か壺のような形につくり、それを両手に捧げ持って旦那のいる居間から奥座敷、小座敷や店、倉庫、台所の隅まで、どたどたと走りまわる。 貧乏神の大好物は焼味噌だから、いい匂いに誘われ、焼味噌のなかに飛びこんでくる。こうして店じゅうに巣くっている貧乏神を焼味噌の中に入れてしまうと、しっかりと口を封じ、貧乏神のいっぱい詰ったその焼味噌を持ったまま番頭は往来に走り出、川の中へ投げこむ。 「こうした風習を児戯にひとしいと嗤うかもしれないが」 と、近世異色の経営コンサルㇳ海保青陵(一七五五~一八一七)はいう。
青陵は、荻生徂徠 ああ、こんな子供だましのような真似までして旦那や番頭が"貧乏"を嫌うのかと思わせるのが経営者としての知恵である。 《大坂ノ貧ヲニクミテ富ヲコノムコㇳハ天性ナリ》
《旦那の第一ニコノムモノハ金銀ニテ第一ニイヤガルモノハ貧乏神也ㇳ思 こうした、低成長下の経済を凝視する青陵の現実尊重の視線は強烈である。
《金ㇳ言ウコㇳヲ言葉ニモ言 から、武士が貧乏から脱けだせないのだと青陵はいう。
《阿蘭陀 考えてもみよ、君臣の関係にしても「売り買い」ではないか、青陵の語気は鋭い。
《古
《卿 天皇と公卿や藩主と家臣の関係にしても、すべて「売り買い」である。この売り買いこそが、天地の理だと青陵は声を重ねる。 百年一日のごとく、農民から米を収奪することだけに明け暮れ、商品経済の大切さに目をむけようとしないのは無能な家臣たちの"俸禄"の食いつぶしであり、能力のある家臣から見れば暗愚な藩主は生涯の不作、折角の知恵も宝の持ち腐れ、骨折り搊である。 《食イツブシハ君ノ損ナリ、骨折リ損ハ臣ノそんナリ、ㇵナハダ不算用(勘定にあわない)ナリ》 そう言うと青陵は、諸藩の重役たちに藩営の商業を勧め、武士もまた経済の大事を知り、他国に特産品を売りつけ大いに稼ぎ、利に利を積み、藩財政の建て直しをはかるべきだという。 《一体、天理ハ理ヅメ也。ウリカイ利息ハ利ヅメ也。国ヲ富サンㇳナラバ、理ニカエルコト也》 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.87~91 2021.06.22記 |
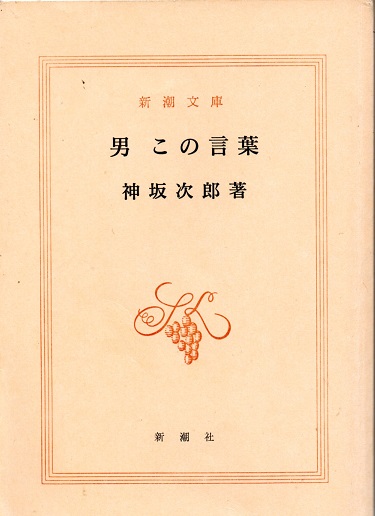
甘い清涼飲料を与えた実験室の二十日鼠 「にんげん生涯の吉凶ことごとく"食"によって左右される」
と説
水野南北。もとのなを鍵屋の熊太、巷の無頼漢である。五歳の頃、両親を亡くした熊太は。大坂阿波座で鍵職人をしている叔父弥助に引き取られ、鍵や錠前づくりを仕込まれるが、十歳のとき盗み飲みした酒が彼の人生を狂わせる。やがて酒代に窮した熊太は、叔父が稼ぎ貯めた有金をつかんで、出奔し、無頼遊侠の群れに身を投じる。性、凶暴。刃傷沙汰 その日、ネギ畑に囲まれた難波村の土橋ですれちがった老僧は、熊太の顔をまじまじと見て、 「ああ、いかんな。死相が出ておる」 と嘆息した。これを聞いて顔色をかえた熊太は食ってかかったが、
「まぁ聞け、いま三眼六神
腹をたてた熊太は、老僧の頭を殴りつけて帰った。が、老僧の観相はおそろしいほどに適中した。北浜の材木河岸 こうして五ヵ月たったある日、熊太は思いがけなく大坂の町角で、あの"死"を予告した老僧に出逢った。老僧は穴のあくほど熊太の顔をみつめて、 「奇妙じゃ、死相がきえておるわ」
と首をかしげた。そして老僧は「この五ヵ月のあいだ何があったか」と訊いた。熊太が瑞竜寺の和尚との食事のことを告げると、「それじゃ、人には天禄
老僧がこのとき熊太に、節食が寿命を延ばしたといったことばは、現代人の目からみても理に適っている。だいたい、熊太のような極道無頼の生活は放埓で不規則で、女色におぼれ血の気の多い魚や鳥獣の肉を啖
ともあれ、こうして老僧、水野海常の観相学に傾倒した熊太は、海常に弟子入りし、人間の運、不運や生死を予告する"顔"というものの相
「よいかな、観相というのは、ものの貌 師の海常から"水野南北"のなを与えられた熊太は、やがて「千人観相、万人観相」の悲願をたて、南は長崎から北は青森へと数年、巡歴をつづづけた後、ふたたび大坂に帰って、さらに人々の"顔"を観るため床屋の下働きとして三年……次いで"にんげんの躰"を観るため風呂屋の三助として三年……そして更に"相"を失くしたにんげんを観るため、難波千日前の火葬場で死者の顔や躰を観ること三年。
こうして、観相家として大坂の巷に立った南北の(観相術)は、すさまじいばかりに人間の"相 「だまって坐れば、ぴたりと当たる」
そんな南北の風説 「しかし……」 当代随一の観相家として世に躍り出た南北にも、なお心迷うことがある。誰彼の運命を当てたところで、それが何であろう。命を運ぶというその"運命"を予知し、凶運を吉運に導いてこそ真の相法というものではないか。そして"食"に注目した南北は、食うというもっとも素朴な営みを運命学にまで昇華させていく。 《禍を福に転ずるの道は食に在り》 そのことは彼の著『南北相伝』全十巻、『相伝極意、修身録』全四巻にくわしい。 《生涯の吉凶ことごとく食より起る。怒るべきは食なり、慎むべきは食なり。(略)常に大食暴食の者、たとえ(人相学的に)相貌大いによろしくとも、身分しかと治まりがたし》
南北のこの「慎食の教え」、食の相法は、南北自身の世間放浪の経験と見解から発した独創的なものであった。唐
《食の多少を以て富貴貧賤寿夭
《凡そ心身を養うの本は食なり、それを厳重に養わざれば心身厳重ならず、身を治まること能
百発百中と称 それはもはや相学だけのものではなく、すでに一つの思想であった。
南北が実証によって理を極め、集大成した希代 晩年、南北は光格天皇より《天下一》の号を賜わり、従五位出羽之介に叙せられている。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.154~158 2021.06.08記 |
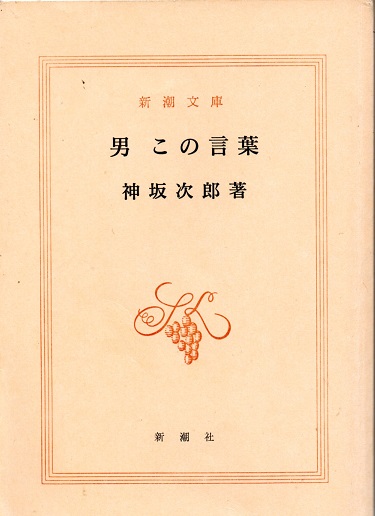
旧
《屏風と商人はすぐ(真っ直ぐ)に立たぬという事あり、しかし屏風は、下のゆがみし所へはたゝぬものなり。商人もその通りにて、五歩と一割の利は、極
商人と屏風は曲がらねば立たぬ、などと世間では誤解して莫迦
この記述などを読んでいると、まるでロッキード事件から最近の泡沫
《我が金の有
《いかに銀儲 この商人訓のなかで岩垣は、自力本願の商人の道を説き、日常の生活から商家の運営、金融に関する教えや商業手形の扱いなど、こと細かに極めて具体的に語りつづけている。 残念なことに著者、岩垣光定の来歴は不明だが、巻末の、
《宝暦 丁丑春
をみれば、宝暦七年(一七五七)ごろの京都あたりに住んでいた人物で心学(平易な言葉と通俗な譬喩で説いた庶民学)者か、また跋文(あとがき)などを読むと、心学をまなんだ商家の主人かとも思える。心学といえば、京都の儒者で経済学者でもある岩垣月洲の父、岡田南涯 ※参考:石田梅岩
ともあれ、当時の京の巷で岩垣が見聞し、体験した『商人生業鑑』五巻のなかから興味ぶかい条
《身過
岩垣がこの商人訓を書いた時代は、従来の「貴穀賤金 そうした風潮のなかで岩垣は、 《町人は禄(収入)なき事を常に忘れず》 利を稼ぎ生計を立てるのが本分だと言ってのける。
「商人というものは」百姓のように田畑も持たねば、武士のように定禄 《(わが店に)出入る人の影にて商いをし、妻子を養い渡世するゆえ貧なる人いやしき人にても、売買用にて来る人を主人のごとくおもってつとむべし》
《金銀の儲けは多くてもあてにはならず、始末(倹約)にて溜るは少なくても、積れば多く確かなり、(略)纔
《世には盗人という者、人の財宝を奪取て世をわたるは実に悪業なれど、今日の暮しならぬゆえ、命を捨てものにしてすること是非もなし。人の子として幼少よい親の介抱によりて(一人前の)人となり、芸能、。商い道残る所習得 世間には自分より利口な人がいくらでもいるということ、おぼえておけ。まことに賢い人は、賢ぶった顔をしない。例えて言えば、酒がいっぱいつまった樽は、音をたてたりはしないものだ。 《万事、時節の勢いを知りて進むときは進み、退くべき時は退くを(まことに)かしこき人というンあり》
《世渡りの業 商いというのは傘のようなものだ。(商機というなの)雨が降れば傘(商い)をひろげ、雨がやめば傘をすぼめて(慎重に)商いを堅めてゆけ。 著者の岩垣光定は、いかにも長い歳月、京の町家ぐらしをし、商人たちの生きざまを見聞きしてきた苦労人らしくやわらかな語り口で、「屏風」ではじめたこの商人訓を「傘」商法のくだりで結んでいる。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.132~137 2021.06.30記 |
☆66 平田篤胤(1,776~1,843年)

国学者平田篤胤の著作に『気吹颫』(または気吹於呂志〔いぶきおろし〕)と題された一本がある。文化八年、彼が三十六歳のときに行った、さしずめ今でいえば公開有料講義を、門人たちが筆記板行しただけのものであり、もとより代表作などといえるほどの著作ではない。内容もまた例によって儒仏を排し、復古神道を宣揚する型通りのもの。しかし、ただ講説筆記というだけに、いわば脱線、言いたい放題の怪気焔までがそのままの形でのこされており、このいささか難物国学者の講釈ぶりを目のあたりに聞くようで愉快なのだ。とりあえずその一つを紹介することにする。
儒仏邪を併せて攻撃する彼の筆鋒は、ついでに当時興隆期にあった蘭学にまで八当りするのである。災難なのはオランダ人、以下のような名誉毀そん、人身攻撃に近いものにまでなるのだから、これはもう奇説珍説を通り越してひどい。そこで話は多少下 腰より下は長く、足の細やかなる所も獣に似て、溲尿実はこのあとまだオランダ人の淫乱ぶりについての珍講釈がつづくのだが、謹直な本誌読者のお叱りを受けるおそれもあるので、一応これで切り上げることにする。戦前出版の全集ですら伏字なしに収めているくらいだから、熱心な読者はそれについて見られるがよろしい。それにしても、国学者型破りの珍放談であることだけはまちがいない。 篤胤の洋学知識がどの程度だったか、淮陰子などには判定しかねる。西川如見の『天文義論』『長崎夜話草』あたりから、杉田玄白『解体新書』、桂川甫周『北槎聞略』等々くらいまでは、ある程度知っていたらしい形跡もあるが、初手から偏見で接しているのだからお話にならぬ。かの藤田東湖すらが、「奇男子に御座候。其性妄誕にはこまり申候共、気概には感服仕候」と、いささかもてあまし気味に見えるほどの篤胤という人物、この珍説もまた同じ東湖書簡にいう「付会の説をまじめに弁ずるはあきれ申候」とある、せいぜいその程度の興味で読めば、まずは一場のお笑い種、とりたてて世道人心をなどと大きく出る必要もあるまい。 (78・6) 淮陰生著『完本一月一話――読書こぼればなし――』 P.202~203 〔ある国学者のある珍説〕より孫引きそのもの・ 令和4年(2022)5月28日。 |
☆67 佐藤 一斎(1,772~1,859年)

佐藤一斎という人物 佐藤一斎先生と申しますと、現代流に一言にしていえば幕府の大学総長であったわけです。一斎先生は美濃の岩村藩の家老の子息で、少年のころから非常によく出来た人でした。そのころ岩村藩主の御曹子(ぞうし)で林衡(こう)(後の述斉)という大変英邁な公子がいまして、一斎先生はその人の学友として形影相従ったと申してよい人です。 この人は後に幕府の総理であった松平定信(一七五八*一八二九)に見込まれて林家を嗣ぎ、述齋と称し、皆さんもよくご承知のの幕府の大学長になりましたが、一斎先生はその縁にひかれて述齋が亡くなった後、学頭を継承し、安政六年に、八十八歳で亡くなりました。 一斎先生は当時天下各藩の志ある者で先生の人物、学問に傾倒し教を受けなかったものはないといわれたほど、非常に広い感化を世に及ぼした人です。しかもこの人はいわゆる儒者、ただの学者、教育家というものといささか異なる人でありまして、非常に自由な、そして風格に富んだ文字どおり碩学というべき人でした。 一斎先生には、読者の間に特に知られている面白い逸話、先生の風格をよく伝えたいろいろの伝説があります。 その一つを申し上げますと、諸藩の志しある人物、学問を好む人物が、多くこの一斎先生の門を叩いて教えを受けておりますがその中に幕末の志士で不羈(ふき)奔放な佐久間象(しょう)山(一八一一=一八六四)がいました。 この人について一寸脱線しますが、この間もある学会の雑談の席で象(しょう)山のことについて話が出ました時に、いやあれは象(ぞう)山が本当だという人がいまして議論になったことがありあした。ちょうどそこへ私が入って行きまして、「しょうざん」「ぞうざん」どっちが本当かなんて聞かれたことがありあす。あれは言ううまでもなく象(しょう)山の故郷である信州の山の名称でありまして、普通は「しょうざん」と言い、本人も「しょうざん」と言っていたそうです。その山は、いまでもそのままのなで残ってますが、土地の人は象(ぞう)山と言いならわしてきているそうです。従って佐久間 象(ぞう)山というのは、土地の人が言いならわしている呼び方で、象(しょう)山とは、他国の人が自然に呼びならわした呼び方です。彼の叔父さんは甥のことを「ぞうざん」といわず「しょうざん」と言っていたそうです。 土地の人は象(ぞう)山といい、叔父さんは象(しょう)山という、だからどっちでもいいのですが、学者はとかく「しょうざん」が本当だ、いや「ぞうざん」が本当だなどといろいろ論議をいたします。しかし世間一般には、象(ぞう)山ではなく象(しょう)山といいならわしております。 そんな事はさしおきまして、象山とよく並び称せられます山田方谷という人がいます。この人は、あまり知られておりません。しかしこの人は、もし大藩に出ていたならば非常に偉くて、後世にもなを残したと思う人傑ですが、今は高梁(はし)といっております備中松山というところのたった五万石の小藩板倉藩の家老でした。しかも藩公は幕末に老中をいたしまして、徳川幕府と運命を共にした人です。方谷も運命を藩公と共にして早く隠遁してしまいました。 しかしそれでもこの人の業績は、識者の間に非常によく伝わっています。あの備中の高梁なんて本当に山の中の小さな町ですが、旅人が一度、この高梁、つまり松山藩に足を入れますと、すぐに「ああ、これは板倉藩だ」ということに気づくというほど、実によく善政の効果が見えており、その風俗、流風余韻というものが永く残っていたそうです。後世にまで伝わるような、すぐれた風習。 ※「流風」は昔の人から伝えられているすぐれた風習、美風。「余韻」は事の後に残る味わいのこと。 この藩公板倉勝静(きよ)が老中をしていたある時、控の間で老中のお供の人々が雑談にふけっておりました。段々話が微妙になり、時局論になった。その時たいていの者は、「何、我が幕府の威力をもってすれば、この時局などは問題ない」という意見だったのですが、その中で山田方谷だけは、襟を正して、 いや、方今(ほうこん)、徳川将軍の治世というものは、荒い風濤(風が荒れ、波が高い)に竿さしている舟のようなもので、非常に危うい、この時局と幕府というものをたとえて考えてみるならば、衣服のようなものである。 家康神君が仕立てられた衣服を家光将軍、綱吉将軍、代々の将軍が洗い張り、湯のしをし、仕立直しをいくども試みて今日に至った。率直にいうともう仕立直しがきかんくらい弱っている。これは大変なことだ。我々はちょうど風濤に竿さす扁舟(一葉の舟)のようなものだ と非常にきつい言葉で評しました。 一座の者は、かたちを改め、色をうしなったという話があります。山田方谷という人は、そういう見識の高い、そしてまた、非常に気概のある珍しい人傑でした。 その人がやはり一時、佐藤一斎の門下におりまして、たまたま佐久間象山と一緒でした。実は塾の中に寄宿舎がありまして、そこに他の塾生と象山と方谷も泊まっていたのですが、毎晩夜がふけますと象山と方谷が議論を始める。段々議論が激しくなって、やかましくて仕様がない。 そこで他の塾生が迷惑がり、代表者が一斎先生のところへまかり出て、「実は毎晩夜がふけ、我々が寝ようと思うころになると、やかましく激論をする奴がいて困ります。先生から一つお叱りを願いたい」と申し出たそうです。すると一斎先生は、「何者か」「方谷と象山であります」「そうか」としばらく考えておられて、「あの二人がやるならば、お前達はがまんせい」と言われたので、皆しゅんとなってしまった。 これは大変面白い逸話であります。たいていなら「それはけしからん、私から言うてやる」といわれるところなんですが、象山と方谷の議論ならがまんせいと言ったところなどは、一斎先生もただ者ではない、なかなか線の太い、豪邁な人であるということをよくあらわしている話だと思います。 この一斎先生は、そういうわけですから人物、学識(学問、見識)をもってその及ぼした感化というものは、今日、静かに検討してみますと、驚くべきものがあります。 ※安岡正篤著『重役心得箇条』(致知出版社)平成七年四月三十日第一刷 P.12~21より。
「言志録」
二七 真に大志有る者は、克く小事を勤め、真に遠慮有る者は、細事を忽 2009.11.09
四四 得意の時候は、最も當に退歩の工夫を著くすべし。一時一事も亦皆亢龍
四八 天尊く地卑くして、乾坤定まる。君臣の分は、既に天定に属す。各その職を尽くすのみ。故に臣の君に於ける、當に畜養
五三 家翁、今年、齢八十有六、側ら人多き時は、神気自(おのづか)ら能く壮実なれども、人少なき時は、神気頓に衰脱す。余思ふ、子孫男女は同体一気なれば、其の頼んで以て安んずる所の者固よりなり。但々此れのみならず。老人は気乏し。人の気を得て以て之を助くれば、蓋し一時気体調和すること、温補 一二二 本然の真己有り。躯殻(くかく)の仮己有り。須く自ら認め得んことを要すべし。
一二九 需は雨天なり。待てば則ち霽る。待たざれば則ち沾濡 一三六 釈老の徒の如き、死に處するに頗る自得有り。然れども其の学畢竟死を畏るるより来る。
一四〇 経を読む時に方りては、須らく我が遭う所の人情事変を把りて注脚と做 一四四 博聞強記は聡明の横なり。精神入神は聡明の竪なり。 二一九 一物を多くすれば斯に一事を多くし、一事を多くすれば斯に一累を多くす。 「言志後録」 P.77~
一 此の学は吾人一生の負担なり。當に斃れて後已むべし。道は固と窮り無く、堯舜の上にも善尽くる無し。孔子は志学より七十に至るまで、十年毎に自ら其の進む所有るを覚え、孜々として自ら彊め、老の将に至らんとするを知らざりき。假
三四 克己の工夫は一呼吸の閒に在り。
三八 一の字、積の字、甚だ畏る可し。善悪の幾も初一年に在りて、善悪の熟するも積累の後に在り。
四七 易は天を以て人を説き、書は人を以て天を説く。 八七 仮己を去って真己を成し、客我を逐うて主我を存す。是を「其の身を獲ず」といふ。 九八 人は皆身の安否を問ふことを知れども、而も心の安否を問ふことを知らず。宜しく自ら問ふべし。「能く闇室を欺かざるか否か。能く衾影に愧ぢざるか否か。能く安穏快楽を得るか否か」と。時時是くの如くすれば、心便ち放れず。 一〇七 人の事を做すは、目前に粗脱多く、徒らに来日の事を思量す。
一〇八 老人は衆の觀望して矜式 一六〇 「忘るること勿れ。助けて長ぜしむること勿れ。」子を教ふるも亦此の意を存すべし。厳にして慈。是も亦子を待つに用ひて可なり。
二四〇 余自ら視・観・察を翻転して姑く一生に配せんに、三十已下は、視の時候に似たり。三十より五十に至るまでは、観の時候に似たり。五十より七十に至るまでは、察の時候に似たり。察の時候には當に知命・楽天に達すべし。而して余の今六十六にして、猶ほ未だ深く理路に入る能はず。而るを況や知命・楽天に於てをや。餘齢幾ばくも無し。自ら勵まざる容
二四五 毎旦鶏鳴いて起き、心を澄まして黙坐すること一响 「言志晩録」 P.147~ 九 「憤を発して食を忘る」とは、志気是くの如し。「楽んで以って憂を忘る」とは、心体是くの如し。「老の将に至らんとするを知らず」とは,命を知り天を楽しむこと是くの如し。聖人は人と同じからず。又人と異ならず。 一三 一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂ふること勿。唯々一燈を頼め。 参考:法句経「おのれこそ……」
四九 著書は只々自ら怡悦 五八 顔淵・仲弓は「請ふ斯の語を事とせん」と。子張は「諸は紳に書す」子路は「終身之を誦す。」孔門に在りては、往々にして一二の要語を服膺すること是くの如き有り。親切なりと謂ふ可し。後人の標目の類と同じからず。 五九 余は年少の時、学に於て多く疑有り。中年に至るも亦然り。一疑起る毎に、見解少しく変ず。即ち学の稊々進むを覚えぬ。近年に至るに及びては、則ち絶えて疑念無し。又学も亦進まざるを覚えぬ。乃ち始めて信ず、「白沙の云はゆる疑は覚悟の機なり」と。斯の道は窮り無く、学も亦窮り無し。今老いたりと雖も、自ら励まざる可けんや。 参考:陳献章(ちんけんしょう)(1428―1500)中国、明(みん)代中期の思想家。字(あざな)は公甫(こうほ)、号は石斎、白沙(はくさ)先生とも称される。追諡(ついし)は文恭。広東(カントン)省新会県白沙里の人。・・・ 人間の心が本来具有している能力を信頼し、心のあり方に人間の主体性の確立を求める学問を心学とよぶが、王陽明とともに心学の先駆をなした。著に『白沙子全集』がある。 少にして学べば則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰へず。老いて学べば、則ち死して朽ちず。(岩波文庫による) ※:年輪思考への疑問 *安岡正篤著『百 朝 集』P.78 安岡正篤先生はこの句を次のように説明されている。 若い者の怠けて勉強せぬ者を見るほど不愉快なものはない。ろくな者にならぬことは言うまでもないが、まあまあ餘程のろくでなしでなければ、それ相応に勉強する志くらゐはあるものである。 壮年になると、もう学ばぬ者、学ぼうともせぬ者が随分多い。生活に逐はれて忙殺されてをる間に、段々志まで失ってしまうのである。さうすると案外老衰が早く来る。所謂若朽である。肉体だけは頑健でも、精神が呆けてしまふ。反対に能く学ぶ人は老来ますます妙である。但し学も心性の学を肝腎とする。雑学ではだめである。古詩にいふ通り、「少壮、努力せずば、老大、徒に傷悲せん」こと間違ひない。でなければ呆けたのである。之に反して老来益々学道に精進する姿ほど尊いものはない。細井平洲も敬重した川越在の郷長老奥貫(ぬき)の歌に、「道を聞く夕に死すも可なりとの言葉にすがる老の日暮らし」。かうありたいものである。そして「老檜・晴天に参す」るようなのは実に好いのではないか。 2008.11.2 一〇三 彼れを知り己を知れば、百戦百勝す。彼れを知るは、難きに似て易く、己を知るは、易きに似て難し。 一六九 我が言語は、吾が耳自ら聴く可し。我が挙動は、吾が目自ら視る可し。視聴既に心に愧ぢざらば、則ち人も亦必ず服せん。
一七五 心は現在なるを要す。事未だ来らざるに邀 *孟子告子篇に、「学問之道無也。求其放心而已矣」 とある。 二〇八 武人は多く是を胸次明快にして、文儒郤って闇弱なり。禅僧或は自得有りて、儒者に自得なし。並びに愧ず可し。 二六一 人は老境に至りて儘ゝ善く忘る。唯ゝ義のみは忘る可からず。 「言志耋録」P.219~ 一五 学を為すの初は、固と当に有字の書を読むべし。学を為すこと之れ熟すれば、宜しく無字の書を読む可し。 一六 源有るの活水は浮萊も自ら潔く、源無きの濁る沼は蓴(じゅん)菜(さい)も亦汚る。 三七 学を為すには、人の之れを強ふるを俟たず。必ずや心に感興する所有つて之を為し、躬に持循する所有つて之れを執り、心に和楽する所有つて之を為す。「詩に興り、礼に立ち、楽に成る」とは、此れを謂ふなり。 *脚注:(持循)すなほに持ちつづくること。 四〇 真の己を以て仮の己に克つは、天理なり。身の我をもって心の我を害するは、人欲なり。 五〇 端坐して内省し、心の工夫をなす做(な)すには、宜しく先ず自ら其の主宰を認むべきなり。省(せい)する我れか。省せらるる者は我れか。心は固と我れにして、躯も亦我なるに、此の言を為す者は果たして誰か。是れを之れ自省と謂う。自省の極は、乃ち霊光の真の我れたるを見る。 一〇五 人を知るは、難くして易く、自ら知るは、易くして難し。但々當に諸れを夢寐に徴して以て自ら知るべし。夢寐は自ら欺く能はず。 一一三 人は須らく忙裏に閒を占め、苦中に楽を存する工夫を著くべし。
二一七 世には、未だ見ざるの心友有り。日に見るの疎交有り。物の睽合 *脚注:【睽合】そむくと合ふとをいふ。 参考:加茂真淵と本居宣長は、松坂の僅かの出会いで、終生の契りを結んだ。結局は、心と心のふれ合いであり、感応のないところには心友は得難い。 2010.04.15 二二二 文章は必ずしも他に求めず、経書を反復し、其の語意を得れば、則ち文章の熟するも、亦た其の中に在り。 二七七 教えて之を化するは、化及び難きなり。化して之を教ふるは、教入り易きなり。 私の記憶:広島大学工学部長が竹内先生(恩師)の送別の辞に使われた。 三二二 清忙は養を成す。過閑は養に非ず。
三二八 人生は二十より三十に至る、方に出づるの日の如し。四十より六十に至る、日中の日の如し。盛徳大業、此の時候に在り。七十八十は、則ち衰頽蹉跎 三三二 少者は少に狃るること勿れ。壮者は壮に任ずること勿れ。老者は老を頼むこと勿れ。 |
☆68 『重職心得箇条』
|
「重職心得箇条」という書 P.21 佐藤一斎先生が自分の出身の岩村藩のために選定しました藩の十七条憲法、これが「重職心得箇条」です。 これは、段々有名になりまして、伝え聞く諸藩が続々と使いを派遣してこの憲法を写させて貰ったということです。 それが、どうしましたか、明治以来すっかり世に忘れられてしまいまして、自然、「重職心得箇条」というものの原稿の所在も不明になっていました。確か大正になりまして、ふとしたことから東京帝大の図書館の中から発見され、改めて識者の間に注意を引くようになったという歴史があります。 これを読んでみますと実に淡々として少しもこだわらずに極めて平明に重職の心得べき憲法を叙述しています。聖徳太子の十七条憲法なども非常に優れたものですが、この心得箇条も非常にくだけた文章で、しかも高い識見のもとに、国政にあずかる重要な職務にあたるものはかくしなければならんということを、実に要領よく把握している名作だと思います。 全然わからずになっていたものが、大正になって世に出て参りまして、終戦前、私も大分紹介いたしまして東京でも大阪でも志ある人々に知られるようになりました。 これは現在でも大変参考になるものです。皆さんは会社の重職でありますから、皆さんの為に大いに参考になるだろうと思い、この「重職心得箇条」をご紹介する次第です。
一 重職と申すは、家國の大事を取計べき職にして、此重の字を取失ひ、軽々しきはあしく候。大事に油断ありては、其職を得ずと申すべく候。先ず挙動言語より厚重にいたし、威厳を養うべし。重職は君に代るべき大臣なれば、大臣重ふして百事挙るべく、物を鎮定する所ありて、人心をしつむべし、斯の如くにして重職のなに叶ふべし。又小事に区々たれば、大事に手抜あるもの、瑣末を省く時は、自然と大事抜目あるべからず。斯の如くにして大臣のなに叶ふべし。凡そ政事なを正すより始まる。今先ず重職大臣のなを正すを本始となすのみ。
二 大臣の心得は、まず諸有司の了簡を尽さしめて、是を公平に裁決する所其職なるべし。もし有司の了簡より一層能き了簡有りとも、さして害なき事は、有司の議を用るにしかず。有司を引立て、気乗り能き様に駆使する事、要務にて候。又些少の過失に目つきて、人を容れ用る事ならねば、取るべき人は一人も無之様になるべし。功を以て過を補はしむる事可也。又賢才と云ふ程のものは無くても、其藩だけの相応のものは有るべし。人々に択 三 家々に祖先の法あり、取失うべからず。又仕来仕癖の習あり、是は時に従て変易あるべし。兎角目の付け方間違ふて、家法を古式と心得て除け置き。仕来仕癖を家法家格などと心得て守株せり。時世に連れて動かすべきを動かさざれば、大勢立たぬものなり。 四 先格古例に二つあり、家法の例格あり、仕癖の例格あり、先ず今此事を処するに斯様斯様あるべしと自案を付、時宜を考へて然る後例格を検し、今日に引合すべし。仕癖の例格にても、其通りにし、時宜に叶はざる事は拘泥すべからず。自案と云ふもの無しに、先ず先格より入るは、当今役人の通病なり。
五 応機と云ふ事あり肝要也。物事何によらず後の機は前に見ゆるもの也。其機の動きを察して、是に従うべし。物に拘
六 公平を失ふては、善き事も行われず。凡そ物事の内に入ては、大体の中すみ見へず、姑 七 衆人の厭服する所を心掛べし、無利押付けの事あるべからず、苛察を威厳と認め、又好む所に私するは皆少量の病なり。 八 重職たるもの、勤向繁多と云ふ口上は恥べき事なり。仮令世話敷とも世話敷と云はぬが能きなり、随分手のすき、心に有余あるに非れば、大事に心付かぬもの也。重職小事を自らし、諸役に任使する事能はざる故に、諸役自然ともたる所ありて、重職多事になる勢 あり。
九 刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是を預るべきなり、倒 十 政事は大小軽重の弁を失ふべからず。緩急先後の序を誤るべからず。徐緩にても失し、火急にても過つ也、着眼を高くし、惣体を見回し、両三年、四五年乃至十年の内何々と、意中に成算を立て、手順を逐て施行すべし。
十一 胸中を豁大寛広にすべし。僅少の事を大造に心得て、狭迫なる振舞あるべからず。仮令才ありても其用を果さず。人を容るヽ気象と物を蓄 十二 大臣たるもの胸中に定見ありて、見込たる事を貫き通すべき元より也。然れども又虚懐公平にして人言を採り、沛然と一時に転化すべき事もあり。此虚懐転化なきは我意の弊を免れがたし。能々視察あるべし。
十三 政事に抑揚の勢を取る事あり。有司上下に釣合を持事あり。能々弁
十四 政事と云えば、拵 十五 風儀は上より起こるもの也。人を猜疑し、蔭事を発き、たとへば、誰にも表向斯様に申せ共、内心は斯様なりなどゝ、掘出す習は甚あしゝ。上に此風あらば、下必ず其習となりて、人心に癖を持つ。上下とも表裡両般の心ありて治めにくし。何分此六かしみを去り、其事の顕れたるまゝに公平の計ひにし、其風へ挽回したきもの也。 十六 物事を隠す風儀甚あしゝ。機事は密なるべけれども、打出して能き事までも韜み隠す時は却て、衆人に探る心を持たせる様になる もの也。
十七 人君の初政は、年に春のある如きものなり。先人心を一新して、発揚歓欣の所を持たしむべし。刑賞に至ても明白なるべし。財幣窮迫の処より、徒に剥落厳沍
*佐藤一斉「重役心得箇条」を読む 安岡正篤 (致知出版社)平成七年四月三十日第一刷発行より。
|
☆69 徳川 家斉(1,787~1,837年)
|
▼将軍家斉の人物
徳川十五代の将軍の内でも、初代の家康や、二代の秀忠は、人物がはっきりしていて、問題がない。しかし三代の家光となると、もう面倒になる。三宅雪嶺など、家光をもって一の英雄漢とする。その反対に、三田村鳶魚はこれを低脳児だったとして、頭からこき下している。
「楽翁公、閣老の職を辞して、水野羽州代わりて政権を握りたる後、十一代将軍の左右に出入りする者は、すべて阿諛佞曲の俗吏のみにて、将軍に向ひ直言諷諌を申上ぐるもの一人だになく、これに因りて、将軍の驕傲は日に募り、天下の政治は無為にさへあれば泰平なりとの誤解を、将軍に起さしめたり。近年凶荒打続きて、米価騰貴し都鄙の別なく、餓莩
最後に付記してある羽倉用九は、すなわち簡堂である。「想古録」の著者は、簡堂先生より聴くところを、そのまま筆録して置いてくれたのであった。簡堂はそれを勘定奉行の岡本近江守より聴いたのだったことが明記せられている。近江守、なは成、花亭の号で知られているが、別に豊洲とも号している。右の文中に「豊洲翁」とあるのは、すなわち近江守なのである。「想古録」の著者は、まだその人が突止められていないが、その人はまた信頼の置かれる士人だったところから、簡堂も、心置きなく、かような秘話を洩らしたものと思われる。「想古録」に記すところは、一夕の談話というに過ぎなかったかも知れないが、それが岡本花亭より出た話ということを考える時は、その内容には、相当の信憑性の存することを認めてよいのではないかと思われる。
引用:森 銑三著『史伝閑歩』(中央公論社)P.10
補足:22.04.24付の朝日新聞「天声人語」では第11代将軍徳川家斉 |
☆71 大塩平八郎(1,793~1,837年)

……天災流行、ついに五穀飢饉 参考:湯武とは、殷の湯王と周の武王のことで、湯王が夏の桀王を放ち、武王が紂王を伐ちしことをのべている。 天保8年(1837年)2月19日貧民救済のため大阪で挙兵した。大阪町奉行の与力。陽明学者として多くの門下をもった。乱は一日でやぶれ、やがて自殺。写真の図は当時の檄文。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.30 参考:幸田成友著『大塩平八郎』(中公新書)P.195 〔五 檄 文〕の中の P.196~197の記事より部分的に切り抜きしたものである。(202.05.29.黒崎記) 2010.02.19 |
☆72 大原 幽学(1,793~1,837年)
|
大原幽学 このよく似た経世家であるふたりの出自は、尊徳翁が農民の子、幽学先生は武家の生まれだったようで、幼少の境遇にも極端な差があります。 また人生の最期も極端に違いますが、このふたりの中にはなにか共通するものが流れているように思われます。 大原幽学の最期について、森本哲郎氏はつぎのように描写しています:
安政五年(1858年)三月八日の未明、六十二歳になるひとりの浪人が、黒絹の着物に白い帯、小倉の袴をつけて、下総
新暦に直すと四月二十一日の朝まだきのころになる。おそらく、あたりは松籟 ********** 大原幽学をこのような自刃に至らしめたものについて、森本哲郎氏はつぎのように書いています: 房総地方の農村の改革に力を尽くしたあげく、その活動が幕府、勘定奉行の疑惑を呼び、江戸へ呼び出されて吟味を受けたことにあった。幽学が南総、北総各地の農村をまわって「聖学=性学」を説き、寺子屋ともいうべき教導所を設けて農民を集め、教育にカを注いでいた天保期は、折りも折り、「天保大飢縫」で、農民一揆が頻発し、日本全国が騒然たる有様だった。 それだけに幕府は神経をとがらせ、幽学のこうした行動を、農民煽動の画策のようにみなしたのも、とうぜんだったのであろう。凶作で米価は高騰し、餓死者続出という世情のなか、天保八年(1837)には大阪で大塩平八郎の乱が起きている。
だが、幽学は農民の反乱をそそのかしたわけではなく、あくまで農村の改革、農民の教育に専念していただけであった。農業技術を指導し、相互扶助のための基金を設け、農業協同組合の雛形ともいえる「先祖株組合」をつくり、大いに実績をあげて、領主からの表彰さえも受けていたのである。荒廃していた村々は、つぎつぎに立ち直っていった。だが、その功が逆に仇
「お上 さらに嫌疑を深めたのは、幽学がおのれの出自を秘し、ただ「尾張藩浪人」とだけな乗っていたことである。なぜ彼が身元を黙して語らなかったのかは不明だが、十八歳のとき何かのあやまちを犯して勘当された、その何か、にあったのではあるまいか。以後、彼は日本の各地を流浪すること十数年に及んだ末、北総の長部村を本拠として農民の教導に後半生を費やすことになるのである。 が、当時、幕府は身元不明の人間を泊めたり、世話をしたりすることを固く禁じていた。浪人といえば大目にみられたようだが、そのためには士分であったことを、はっきり証明できなければならない。けれど、彼は自分の過去をけっして明かさなかった。
そこで、門人のひとりが、自分の親戚筋にあたる高松彦七郎という御家人に頼んで、幽学を彼の実弟に仕立て、「浪人」であることを保証したため、五年以上にもわたったという吟味の結果は、意外に軽い「押込め 村民に多大の迷惑をかけたこと・・・五年以上に及ぶ吟味のあいだ、江戸滞在の費用その他の金額はかなりにのぼり、それを村民が負担したのである・・・も彼の心を激しく痛めたのだが、それ以上に、自分が不在のあいだに村民のなかには再び「不孝、不正に帰る者」が数多いのを知って、愕然としたことが何よりの動機だったようである。 ・・・以上森本哲郎著『サムライマインド』より・・・
谷沢永一著『百言百話』明日への知恵 (中公新書) 己れ人を愛すれば、人も亦我を愛して則ち和す。己れ人を悪(に)くめば、人も亦我れを悪くんで、則ち破災となる 大原幽学 『微味玄考』 人間は群れをなしてしか生きられぬ。そして自分が否応なく所属する小集団、またその延長線上にある中集団および大集団のなかにおいても、可能な限り自分の存在を際立たせたい。人間は四六時中を通じて無言のうちに、自分を認めてくれ、然るべく待遇してくれと、まわりに向けて乞い縋っているのだ。もともと人間は淋しい存在である。人間は他の人間の情愛に飢えているのだ。 そのくせ人間は生来の利己主義者であるから、常に求めるところ多く与えること少ない。そこで意志力の戦略的戦術が必要となる。 自分がそれほど認めて欲しければ、自分の周囲にいる他人を積極的に評価しその長所を見出すべく努める必要がある。人間の情愛関係を律しているのは、勝負にたとえるなら先手必勝の原理なのだ。自分が情愛に飢えている如く、あるいはそれ以上に自分を囲繞する多くの他人は、淋しさのあまり氷のように冷えきっているに違いない。このとき自分から先に情愛を放射し、相手を心の底から温めてやれば、相手もまた情愛の発動を禁じ得ないであろう。 もちろん急に不自然な好意を示せば、相手は逆にはなはだしく警戒するに決まっている。しかし第一段階で引き下っては反対の結果を生み、いたずらに相手の猜疑心を強めるに終る。しかし最初の拒絶的態度をなんとか和らげようと、重ねて根気よく情愛を持ち続ければ、よほど鋭角的な非社会的人間でない限り、効果は次第に顕れて来るはずだ。 現代日本の若者は自尊心のみ非常に強く、そのため自閉的で実は小心翼々、社交性のいちじるしく欠如した独特の型となっている。社会が豊かであり人間関係が平等であるのを、天下の当然な条件と考え、内心の欲求ばかり強く広く、そういう自分をむしろ持て余している。傲岸に見えるのは薄皮一枚の外見だけ、内実は情愛に餓えている甘え坊だと、見極めをつければ処遇法も、おのずから明白になるのではあるまいか。 ※私が大原幽学を知ったのは、越川春樹先生を訪ねてである。 2019.05.03 記す。 |
☆73
幸若舞
|
1、人間五十年化天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり。舞曲「敦盛」 *室町時代の曲舞の一種 |
☆74 南坊 宗啓(生没年不詳)
|
▼『南方録』 利休の茶の湯を伝える書で有名。利休の高弟・南坊宗啓が書き留めたものを黒田藩の立花実山が利休百回忌となる1690年に写本したという型をとって書かれている。 徳川幕府の元禄時代。封建制度真っ直中に、茶の湯の精神は平等で素直な人間関係が何より大切と説いている。 「滅後」の章に次のように書かれている。「賞客ト云ハ、貴賎ニヨラズ、申入レタル人ヲ上客トアシラフ也。平生ノ高下ニヨラズ」、「草庵ノ作法、天下ノ人、カクノゴトク休ノ清風ニシタガイ、貴賎一同、露地ノ本意ヲ行ワレシコト、寺院ノ清規ニマサリテ尊カリシ」。 以上はインターネットによる。 一 水を運び、薪をとり、湯をわかし、茶を立ててゝ、仏にそなへ、人にもほどこし、吾ものむ。 参考:露地とは茶室に附随する庭園の通称。「露地ノ本意ヲ行ワレシコト、寺院ノ清規ニマサリテ尊カリシ也」の意味が私には分かりません。 |
|
家訓や人生訓といったものは、かくかくしかじかの辛酸辛苦の果てに我が家をここまで築きあげた、よって子孫たるもの儂
あまりの放埓、無頼の行状が問題になったので三十七歳の春、隠居して夢酔
《息子(勝海舟)がしつまい(まじめな)故に益友をもととし悪友につき合わず、武芸に遊んでいておれに孝心にしてくれて、よく兄弟をも憐 と言い、さらに声を重ねて、
《(男たるもの)身を立てなをあげて、家をおこす事がかんじんだ。たとえばおれを見ろよ。理外にはしりて人外(無法)なことばかりしたから、祖先より代々勤めつづいた家だが、おれひとり勤めないから家にきず(疵)を付た。是がなによりの手本だわ。今となり醒めていくら後悔をしたからとてしかたがない。(略)人間になるにも其通りだ。どんよく(貪欲)迷うとうわべ(表面)は人間で心は犬猫どうよう(同様)になる。真人間になるように心懸るが専一だ。文武諸芸みなみな学ぶに心を用いざれば不残
天保十四年寅 左衛門太郎入道 夢酔老》 と述懐する。 ――この、勝海舟の父、小吉(夢酔)の波瀾に満ちた、自叙伝とも、喧嘩の自慢話ともいうべき家訓の書『夢酔独言』の中の、彼の人生を覗いてみよう。 ※参考図書:『夢酔独言』*勝子吉自伝*(角川文庫)
越後国小谷郷から江戸へ出て検校
養子縁組をするためには、支配役と組頭に挨拶をして承認を得なければならないので、七歳の亀松が大人髷 「なは小吉、年は当年とって十七歳」
だというと、支配役の石川右近将監
「十七歳か、それにしてはちと老 ということで、無事認めて貰った。 町内きっての暴れ者の小吉は、この年、年長の悪がき二、三十人を相手に大げんかをして手下にしてしまい、八歳のとき、本所亀沢町に屋敷が移ると、飼犬同士の噛みあいが原因で小吉ら侍の子グループと職人のせがれたち四、五十人が大げんかにになり、小吉はなまくら脇差を抜いて奮迅。仕立屋の悪たれの弁次の眉間に一太刀、「ぎゃつ!」と尻餅をついた弁次が溝の中へ転げこみ這いあがるところを二の太刀で顔を切る。ということで小吉ら八人は勝ちどきをあげて帰ってきた。
こうしてチンピラの世界になをひびかせた小吉は、九歳から柔術、十歳で馬、十一歳で剣術の道場通いをする。苦手だったのは十二歳から林大学頭 文化十二年(一八一五)十四歳の五月、養家の祖母《ばばぁどのにいびられ》腹をたてて、七、八両盗みだして家出を決行。上方をめざして東海道をのぼるが、途中の宿でゴマの灰(旅人などの財物を欺き盗む者)に着物も大小も金も持ち逃げされ、襦袢一枚で乞食になり、伊勢大神宮に詣でようとするが、鞠子の宿では博奕打ちに頼まれ、賭場への銭運びをしたり、病気になって行き倒れているところを旅の僧に助けられたり、惨憺たる放浪をつづけていく。あるときなどは狼の出るという山中で野宿し、寝返りをうった途端に崖から落ち、金玉を打って気絶し、それが原因で金玉が腫れ、おかしな恰好で辿りついた小田原の漁村では人のよい漁師に救けられた。漁の手伝いをしているうちに見込まれ、三十娘を貰って養子に入らぬかという話がもちあがってくる。が、 《おれも武士、こんなところに一生いてもつまらねぇから、江戸へ帰って》 と、帰心矢の如く、漁師の娘の機嫌をとって喜ばせ《浜の仕事に行く》からと弁当をつくらせ、戸棚にあった銭三百文と娘の着物一枚を失敬して夜八ツ(午前二時)遁走。かくして放浪四ヵ月で、ぼろぼろになった小吉は江戸に辿り着く。が、まさに危機一髪。 「今月帰って来なければ、月末には期限切れで家名断絶するところであったが、間にあって帰ったのは、まずまずめでたい」 と支配役の石川から言われて、小吉は冷汗をかいた。
冷汗といえば、十六歳で組頭の屋敷へ《逢対
以後、直心影流 十八のとき世帯を持つが、借金山積し、出奔。甥の新太郎に連れ戻され、座敷牢に閉じ込められること三年余。この牢ぐらしのあいだに、小吉はちゃっかりと、新妻に嫡男の麟太郎(海舟)を生ませている。 小吉の行状は、隠居した後もなお改まる様子はない。 《一生不動にて朽ちける事、子孫に面目なき事いわん方なし、ああ恥ずかしきかな》 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.218~222 2021.06.27記 |
☆76 山田 方谷(1,805~1,877年)
|
▼山田方谷・三島中洲 叢書:『日本の思想家41』(明徳出版社) 序 山田方谷とはどんな人物だったのか、どのような学問をして、そしてどんな仕事をしたのか。そんなことはすべて、現代では歴史の裏側に埋没したかのようである。しかしながらいま一度発掘して、その存在を問いなをしてみる意義のある人物である。 学問について言えば、方谷が江戸の佐藤一斎の塾長をしていて、同門生の上に立っていたことの一事によっても、その識見のすぐれていたことがわかる。 またその政治的業績について言えば、備中松山藩の財政の窮乏を救い、政治の改革をみごとに成しとげたことによって、その経世家としての手腕がわかる。 幕末維新の際の日本の政治上の変革期において、風塵にもまれ泥にまみれて、幕政の改革に智力を傾けて老中板倉勝静を補佐したその努力がわかっていただけるであろう。 さてしかしながら、維新を機としてにわかに歴史の表舞台に乗り出した人たちと、その裏にかくれた人々があったのは、またやむを得ないことであった。方谷はみずから幕を引いて外に出るのをきらった。このような方谷の心の軌跡を、本書では追求してみたつもりである。 山田 琢
略 年 普
1805年:備中松山藩領の西方村(現在は高梁市に編入されている)に生まれる。山田安五郎(号は方谷)
この理財論は単なる議論ではなく、板倉藩が非常に貧乏で、もうどうにも手がつけられないほど疲弊しておったのを徹底的に改革し、特に財政を豊かにして生産をあげ、風俗を正しましたので、旅人が一たび板倉藩にはいるとすぐ分かったというくらい治績をあげました。したがって、この理財論は単なる政治家や経済学者の論と違って、その人の実力が証した名論であり、権威ある議論であります。 理財について非常に緻密に調査をしておることは、板倉藩の歴史始まって以来今日が最高であって、口をひらくと金、金と言っておるのだから、少しは暮らしが楽になったかと思うと、相変わらず貧乏で疲弊のどん底にある。農民がおさめる税金、海や山からとれる産物、あるいは通行税・取引税などは必ずとれるだけとりたてている。 また支出の面では、徳川幕府から賦課される費用、外交祭礼の費用、その他乗り物、建築費はできるだけ節約して数十年になるが、藩の貧乏はますますひどくなり、借金は増えるばかりで、米倉も空となり、救済することができない状態となってしまった。これは理財にあたる人間の知識の不足が原因であるのか、それとも技術が未熟であるためか、あるいはどこかに手ぬかりや欠陥があるためだろうか。 いやそうではない。 天下の事件や問題を処理する者は、事件や問題の外に立って、事件の内にちぢこまらぬことが大切である――夫れ善く天下の事を制する者は、事の外に立って、事の内に屈せず――。
これが理財論の全編を通じて方谷が言わんと欲する根本的見識であります。
『倫 風』令和元年4月号
嫌な男の凄い自信
山田方谷は、幕末の学者だ。かれの出身は農民だったが、領主がその才能を見抜いて江戸に留学させてくれた。学んだ場所は昌平坂学問所(大学頭 昌平坂学問所は、やがて幕府の直轄になるが、その頃は林家の経営する私塾で、しかし大学頭のポストを持っているので、全国から集まる門人は多かった。 この学問所に、佐藤一斎という学者がいた。学問所では、孔子などの正学を教えることを旨としていたが、一斎は他に王陽明の学問も教えていた。陽明学は、幕府の禁ずるところで、"異学"と呼ばれていた。方谷が熱心に学んだのがこの陽明学だった。孔子の教えは少し物足らなかったのだ。 宿舎に、相部屋の青年がいた。信州(長野県)松代藩の者だという。佐久間象山といった。理論好きな男で、また自分に異常な自信を持っている。鼻の先にそれがぶら下っていた。一目見て方谷は、(嫌な奴だ)と思った。ところが言う事が振るっている。 「山田君、君は備中岡山(岡山県高梁市)の地方人だが、同時に日本国民でもある。さらに、また世界人でもある。つまり君は、三つの人格を持っている。大々の面に対して、勉強しなければ駄目だよ」 方谷は面食らった。 「君は一体何が言いたいのだ?」 「君を含めて、今江戸にいる若者の多くは攘夷攘夷と叫んでいる。しかし、攘夷をする相手の例えばアメリカが、一体どれだけの国力を持っているのか、軍隊はどの位の規模か、あるいは産出する石油の量が一体どの位あるのか、そういうことは誰も知らない。つまり、相手国の力を勉強せずに、ただ攘夷攘夷と言っても仕方がないと言っているのだ」 「……」 方谷は圧倒された。見るからに嫌な自信過剰な男だとは思ってはいるが、言う事は当を得ている。正しい。方谷は以後、佐久間象山に対して二通りの考え方を持つようにした。つまり、 「人間的には好きになれないが、その意見の正しい所には耳を傾けよう」という考えである。 山の海防隊
江戸から戻って来た方谷を、藩主はしばらく経ってから家老に抜擢した。そして、 「藩の改革を行ってほしい。時が時だから、藩の武士に海防の知識をうえ付けてほしい」と告げた。方谷は喜んだ。 すぐ藩の武士たちを集め、外国からの攻撃に備える組織を編成した。 「海防隊」となずけた。武士の一人が訊いた。 「御家老、こんな海から遠い山の中にいて、海防というのはどういう意味ですか?」 「日本を襲う外国は強い。船から上がれば、この山の中にも進入してくる。その時に備えるのだ」 「外国が、こんな山の中にやって来ますかね」 「やって来ないと考えるのは間違っている。我々の外国に対する認識はみんないい加減な情報だ。たとえば、アメリカでも必ずやって来る。その日に備えよう」 外国の知識は、佐久間象山から仕込んだものだ。しかし方谷は本気で象山の言ったことを信じていた。 (自分は、必ずしも象山を嫌いだったのではないな。案外、あの嫌な男が好きなのかもしれない) そう思った。そして象山がよく、
「俺は日本のナポレオンだ。俺の頭脳に敵
と大法螺 2020.03.30記す |
☆77 橘 曙覧(1,812~1,868年)
 中野幸次『清貧の思想』(草思社)の中の一章「橘 曙覧、雨の漏る陋屋に万巻の書 歌よみて遊ぶほかない吾はただ」P.96~106 より私の好みで抜き書きした文を紹介します。
中野幸次『清貧の思想』(草思社)の中の一章「橘 曙覧、雨の漏る陋屋に万巻の書 歌よみて遊ぶほかない吾はただ」P.96~106 より私の好みで抜き書きした文を紹介します。
橘 曙覧(たちばなあけみ)(1812~1867)といっても今は日本人でも知る人はほとんどいないだろうが、幕末の歌人で、明治になって正岡子規がその万葉調の歌を評価して以来有名になった。わたしはこの人の素直な生活の歌が好きで、前々から親しんできた。 ▼曙覧は福井の人で、三十代半ばに決心して「祖先相伝の家業財産を挙げて弟宜に譲り、飄然として城南の足羽山(あしばやま)に退去し、専(もつぱ)ら文学に従事」したのであった。以後五十七歳で没するまで、まさに「専ら文学に従事」し、貧乏暮しも意に介せず歌を詠んで生きた。その歌が明治になって子規に、
「曙覧の歌想は万葉より進みたる処あり、曙覧の歌調は万葉に及ばざる処あり。」
▼曙覧の歌で最も有名なのは「たのしみは」に始まる『独楽吟』であろう。この時代にこんなふうに自由に生活歌を作っていた新しさに驚かされるのである。 〽たのしみは珍しき書(ふみ)人にかり始め一ひらひろげたる時 〽たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどひ頭ならべて物をくふ時 〽たのしみはそぞろ読みゆく書の中に我とひとしきひとを見し時 どれもみな貧乏生活の中での生きるよろこびの一瞬を詠んだもので、現代のわれわれにもじかに通じる歌ばかりである。彼は何十首もこういう歌を作りつづけている。 ▼この無名の歌人を高く評価したのは福井藩の家老中根雪江(なかね ゆきえ)で、雪江は初めは曙覧に歌を教えたのだが、後には「余は始めの程こそ先達(せんだつ)めきて物しつれ、いまはかなわぬ」といい、曙覧の歌についてこう言っている。 「その歌風は次第に境を高めていって、世のありきたりの風を抜ん出て、何よりも上世の心ばえを主んじ、世間に起る事や意表に思うことどもを、ただそのままに詠みあげている。」 と、曙覧の歌の新しさ、高さをほめ讃えているのである。 ▼彼が死んだのは明治と改元された年の八月で、幕末の激動期に数奇(すうき)なその歌人の生を終えたのだった。彼の志はこんな歌によくあらわれていると思われる。 歌よみて遊ぶ外なし吾はただ天(あめ)にありとも土(つち)にありとも 幽世(かくりよ)に入るとも吾は現世(うつしよ)に在るとひとしく歌をよむのみ 参考:常世(とこよ)、かくりよ(隠世、幽世)とは、永久に変わらない神域。死後の世界でもあり、黄泉もそこにあるとされる。「永久」を意味し、古くは「常夜」とも表記した。日本神話や古神道や神道の重要な二律する世界観の一方であり、対峙して「現世(うつしよ)」がある。変化の無い世界であり、例えるなら因果律がないような定常的であり、ある部分では時間軸が無いともいえる様な世界。ウィキペディア転送。 感想:歌よみとして覚悟のほどにうたれる。 2012.04.22 |
☆78 浜口梧陵 財は末なり、信は本なり、本末を明らかにすべし(1,820~1,885年)
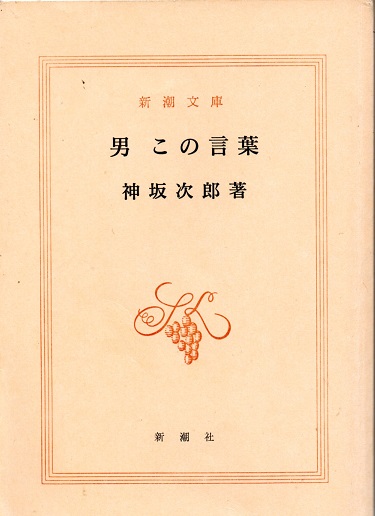
安政元年(一八五四)十一月五日七ツ刻 世にいう安政の大地震である。 南海道沖を震源地とするこの地震は、後年の史料によるとマグニチュード八・四。関東大震災の七・九よりはるかに強烈なものであった。 その激しい揺り返しに、悲鳴をあげて逃げまどう広村(和歌山県有田郡広川町)の人びとの混乱の中で浜口儀兵衛(七代目)は、海をみた。 と、その眼のなかに、くろぐろと底をみせて沖に退いていく海水がみえ、その海水が、はるか沖合に長い堤のようにぶ気味に盛りあがっていくのが見えた。 「津波だ……津波がくるぞ」 儀兵衛は叫んだ。 が、その声も、ごぼう色の夕闇の中に散乱する瓦礫に気をとられ、逃げ場を失って右往左往する村びとたちの耳には届かないようであった。
しかし、猶予はならない。儀兵衛は声を叫
そこには、もう獲りいれられるばかりになった、浜口家の財産というべき数百数千の稲束が架けられていた。儀兵衛に命じられた番頭や下男たちは、その稲束の群に火を放 「大旦那の稲塚が燃えちょる!」
消火に駆けつけた村じゅうの若者や老人や、女や子供たちは息を喘 稲束を焼いて村びとを大つなみから救った儀兵衛の行為は、日本に帰化したギリシャ生まれの英人、ラフカディオ・ㇵーン(小泉八雲)を感動させた。ハーンはそれを『生ける神』として著述し、その作品は海外に紹介されて感動の波紋をひろげた。戦前、小学校教科書に掲載されていた『稲むらの火』の話は、ハーンの原作を逆輸入して日本語に訳したものである。
ㇵ―ンの書いたこの『生ける神』について、エピソードがある。英国に留学していた儀兵衛の末子、浜口擔 そのあと、ステラというイギリス夫人が立って「いま講演したㇵマグチは、ハーンの書いた『仏田の落穂拾い』の中にある"生ける神"のあの偉大なㇵマグチと同じなだが、なにか関係あるのでしょうか」と司会のアーサーに訊ねた。アーサーが、「いかにも、このㇵマグチこそ彼の実子である」というと会場は、一瞬、声にならない感動でどよめき、次の瞬間、割れるような拍手と歓声が湧きあがり、しばらく鳴りやまなかったという。
浜口儀兵衛。文政三年(一八二〇)、紀伊半島の中央部にあたる有田郡広村に生れる。儀兵衛は通称でなを成則、号は梧陵
醤油といえば七百四十年前の建長元年(一二四九)、源実朝の菩提をとむらうため宋(中国)に渡った覚心 その醤油を天文四年(一五三五)大坂に輸送販売したのを皮切りに、江戸期に入ると販路は更に拡がり、紀州徳川家の御仕入醤油として特別の庇護をうけ、浜口家はじめ湯浅醤油醸造業者たちの関東進出がはじまる。 こうして紀州藩御用船同様の特権を与えられ、気候、原料、水と三拍子そろった銚子に工場(ヤマサ醤油、ヒゲタ醤油の前身)を建て、江戸日本橋に店をかまえた浜口家の醤油は、世界最大の消費都市江戸にむかって陸続と運ばれていく。
が、山に高低があり海に干満があるように、豪商と称 《祖先の勤労を常に心に銘ぜよ》 《財は末なり、信は本なり、本末を明らかにすべし》
《綿ぷく咬菜 《雇人を持つ(扱う)に家族(同様)を以ってし、主人と雖も奉公人同様に心掛くべし》 《奉公人にも商売上の利潤を分ち、その労に酬ゆべし》 《春帰秋行。毎年、春を待って帰り、秋に至り江戸に赴くべし》 当主は、仕事の暇な春を待って帰郷し祖先を祀り、寒仕込みの準備のため忙しくなって秋から江戸に引きあげてくること。 《国許に帰りたる時は(当主としてではなく)客分の待遇を受くべき事》
《妻を娶 妻の実家は浜口家より財産、地位など、より下位であることを守ること。これは質素勤勉の家風をまもるためである。 《(当主たる者)徒手飽食して家産を受くるを許さざる事》 《自ら忍びて時の至を待ち、かまえて訴訟を起す勿れ》 他と紛争がが起こっても短慮な振舞いをしてはならぬ。よくよく我慢をして相手の理解を待て。訴訟沙汰に勝つても得るところは何ひとない。
《進んで田畑購 《同族間の縁組(結婚)は厳禁すべし》 《同族相救うに就いては深くその原因を糾明し区別するところあるべし》 同族血縁の情にひかされて家業の運営を誤ってはならぬ。
《家督相続ならびに分家は軽忽
余程の理由のない限り、当主の都合だけで隠居することは許さない。本家、分家を嗣
ともあれ、七代目儀兵衛、江戸では勤王の志を抱いて洋学者、佐久間象山に師事し、勝海舟、福沢諭吉と親交をかさぬ開国論を主張。明治元年、和歌山藩勘定奉行、学習館知事、明治政府の駅逓頭 明治十七年(一八八四)、海外巡礼の途中、ニューヨークにて客死。六十七歳。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.60~64 2021.06.05記 |
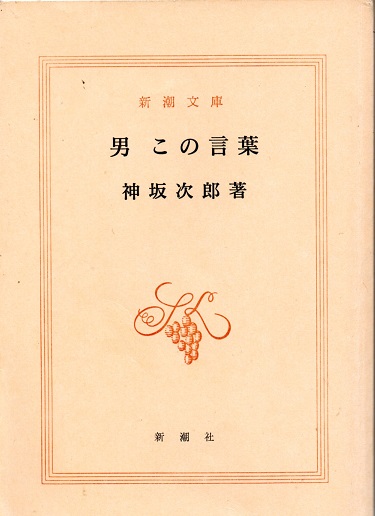
三井財閥草創期の大番頭、三野村利左衛門の前半生は、伝説の霧の中にある。 一説によると、信濃(長野県)または出羽(山形県)に生まれたとも、いやそうではなくて、出羽の浪人を父に、江戸で生まれたのだ、ともいう。が、いずれも確証があっての事ではない。 《三野村利左衛門は、幕末から明治の初年にかけての大変動に際し、天下の富豪が相ついで倒れてゆくなかに、三井家二百年の家運を一再ならず危機を救い、新時代に即応する三井の基礎を建てた殊勲のひとりたるのみならず、幕府及び明治維新政府の枢機に参画して幾多の放れ業を演じた覆面の功労者である》(『自叙益田孝翁伝』長井実編刊)
父と共に京、大坂そして九州日向へと放浪する利左衛門は、その旅先で父とも死別し、天涯の孤児となり、放浪無頼の生活をつづけたのち、天保十年(一八三九)江戸にくだり、干鰯
その才覚を認められ旗本、小栗家(十一代)の中間 当時、ペリーの黒船来航で日本は大きく揺れ動き、豪商三井家もまた、再三にわたり幕府から、 《元治元年(一八六四)、御用金上のう百万両》 《慶應元年(一八六五)、御用金上のう一万両》 と、巨額の御用金を申しつけられ、破産の危機に直面していた。
《(またしても)御勘定奉行小栗上野介(十二代・忠順 という有様であったと、江戸三井両替商番頭の齋藤専蔵は語る。
こうした御用金上のうを拒否すれば、そのシッぺ返しに幕府は三井家に「闕所 「どうしたものか?」 頭をかかえてしまった三井家では、減額を嘆願することにした。このとき浮びあがったのが、出入りの脇両替屋の利八のなである。小栗家二代にわたって信頼をうけていた利左衛門なら、 「うまく、小栗を説いて……」 こうして三井家から小栗説得を依頼された利左衛門は、勘定奉行所にむかった。結果は大成功であった。 「ええっ」 利左衛門の報告に、三井家重役たちは歓声をあげた。それはそうであろう。減額どころか、利左衛門は、 《御用金一件ハ河流ㇾㇳナリタルナリ》 つまり利左衛門は、三井家への御用金は免除、そのうえ幕府が江戸市中への金融緩和政策として行っている、貸付金の取扱い業務「江戸勘定所貸付金御用」まで貰ってきたのである。
こうして三井家重役の絶大な信頼を得た利左衛門は、三井家当主、三井八郎右衛門高福 《利八コト三野村利左衛門ヲ御用所限、通勤支配格》 と破格の扱いをうけ、三井入りをする。利左衛門、四十六歳。 以来、利左衛門は幕末維新の"金融"争乱の真っ只中を奔走する。 その第一の危機は、王制復古を宣言する新政府からの軍資金の要求である。新政府に加担するか、幕府に与するか。激動する経済の動きのなかで、右するか左するか、迷いに迷っている重役たちを尻目に利左衛門は、 「新政府を……」 と、幕府勘定奉行小栗忠順の恩情に目をつぶる思いで、決断をくだしている。 このとき、三井家同様新政府への軍資金をもとめられた豪商たち、平野屋、加島屋は、徳川三百年の情義にひかれ、新政府の申出を拒否している。 これは一種の大ばくちであったが、利左衛門は、かねてから目をつけていた京都を本拠とする御為替御用達の小野組、小野善五郎や、おなじ御用達の島田八郎左衛門(蛭子屋)の動向をみて、踏みきったのであろう。 利左衛門のこの情報分析は、的中した。 幕府に賭けた平野屋、加島屋は脱落し、明治新政府の"官金為替御用達"を掴んだ三井、小野、島田の豪商三家は、政府金融業務の一切を取扱い、富の上に富を重ねていった。 が、新政府への傾斜を深めていきながら三井大番頭の利左衛門は、すでに次なる"政商"への階段をのぼりはじめている。 その手はじめは、政府高官や大蔵省の高級官僚たち、時の権力との癒着であった。 この間の利左衛門の八面六臂の活躍ぶりについて三井両替店の番頭、斎藤専蔵は、
「(利左衛門は)いつも麻裏草履をはいて、木綿の着物に、皮色木綿の打裂 と述懐している。 そして、旋風のように奔走をつづけながら、三野村もまた、 《凡百の事、繁を省き、事用は立ちどころに弁じ、重複を煩わすなかれ、長幼を論じ礼節に拘るなかれ。業を捨てて礼するなかれ。時機を失するなかれ。平常よく断の一字を守れ》
と使用人たちに説 利左衛門と当時の政府高官との接触ぶりについて、こんな逸話がある。
明治四年(一八七一)十月、新政府の岩倉具視、木戸孝允 「れはこれ、三井の番頭さん、一杯いかがでごはすか」 とからかったという。 ともあれ、こうした三井の布石が、やがて三井を新政府最大の御用商人の座に押しあげていく。 この時期、利左衛門の腹案のなかに、 「政府金融業務の独占」 がある。長州出身の井上にしても、薩摩閥の息のかかった小野組などの政商を叩き潰し、金融関係を三井ひとつにすれば、すべて好都合である。 明治七年十月、新政府は政府金融業務にたずさわる者は、公金相当額の抵当を用意すべし、という命令を通達した。そんな巨額の抵当が、にわかに用意できる筈はない。かくして、小野、島田は失格、脱落。 こうして利左衛門は、政府金融の独占に成功した。 三井家における利左衛門の最後の仕事は、大蔵卿大隈重信の庇護の下、日本最初の民間銀行(現さくら銀行)、三井物産を発足させたことであった。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.97~102 ※関連:三井財閥三百年の繁栄の基礎を築いた三井八郎兵衛高利(一六二二~九四)。 2021.06.11記 |
☆80 岩崎弥太郎 会社の利益、搊失は社長の一身に帰すべし(1,835~1,885年)
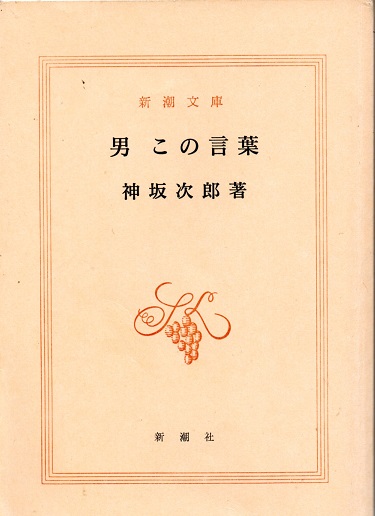
三井財閥の富は、江戸期を通じて二百数十年の歳月と伝統のうえに築かれたものだが、徒手空拳、一代にしてわが国二大富豪の一つにのしあがった男がいる。三菱財閥の創始者、岩崎弥太郎である。 いま、一代にして……と書いたが、正確にいえば明治初年から彼が死を迎える明治十八年(一八八五)まで、わずか十八年間に、こういうべきであろう。 岩崎弥太郎。 天保五年(一八三四)土佐国安芸郡井ノ口村の地下浪人、つまり郷土株を売り払って半農民になった家に生まれた。幼い頃から勉学への思いは強く、頭も人いちばい切れるのだが、直情径行型で激しやすい性格が災いして、立身への足がかりは容易に掴めなかった。 安政五年(一八五四)藩士、奥宮慥齋(ぞうさい)の従者という名目であこがれの江戸にむかい、念願の安積根齋(あさいこんさい)の塾に入門する。しかし、この勉学生活は一年も続かなかった。父が喧嘩騒ぎを起して、重傷を負ったのである。学問を中断して帰郷した弥太郎は、 「かかる偏頗(へんぱ)(不公平)が許されてよいのか」 と、この喧嘩の裁きをつけた役所の非を鳴らし罵倒し、投獄されること七ヵ月、親戚や縁者たちが八方手をつくして出牢はさせたが、《居村追放、高知城下四ヶ村禁足》の処分をうけた。
この追放が赦された後、弥太郎は親戚であり友人でもある後藤象二郎(明治維新、大政奉還の仕掛人の一人)の紹介で、土佐藩きっての有力者、有田東洋の門下生となり、彼の推挙によって下横目 ところが、長崎に着いた弥太郎は、調査などそっちのけで花街に入りびたり、連夜ドンチヤン騒ぎをくりひろげ、またたく間に公費を使い果たして無断で帰ってきた。かくして弥太郎は、役職を取りあげられ罷免。 が、これくらいのことを気にする弥太郎ではない。また後藤象二郎に泣きつき、慶應三年(一八六七)藩営の土佐商会長崎出張所主任として再び長崎に赴任、外国商館を相手に大いに才腕をふるう。ところが、このときも亦上役と衝突し辞職届を叩きつけて帰国する。しかし、後藤象二郎に説得され、三たび長崎にむかう。 こうした長崎での藩営の商事会社"土佐商会"時代におぼえた資金操作の妙が"商売"というものの醍醐味を弥太郎に教えた。
《我は別段に一商会を経営し、往々 この時期、弥太郎は外国商館を相手に手当りしだい外債を借り集め、十九万両からの資金をつかんでいる。
弥太郎のこの資金操作の見事さを後年、政治家であり文人であり、改進党の中心人物の一人であった矢野龍渓 《三菱会社の社長たる者はなかなかの策士である。あの業(海運業)をはじめた時、先ず入用もないのに金を借り、期限の来る前に利息をつけてチャンと返す。しばしばこれをやって貸し方の信用を増して置いて、今度は大口の借款を諸方に申し込み、大金を掻き集めた、それが回転資金の大部分になったというのである。これは世上の噂にすぎぬが、そういう噂を産むくらい、奇抜に見られていたと見える》 と、『龍渓閑話』で述べている。 ともあれ、商務官僚を志した弥太郎の前に、倒幕の嵐が吹き荒れ、明治新政府が誕生、廃藩置県が行われた。 「時こそ来れり!」 弥太郎は目をかがやかした。それはそうだ。土佐藩の命令をうけ"土佐善兵衛"をな乗り土佐開成社を預けられ、経営していた弥太郎の前から土佐藩が消えてしまったのである。 「いっそ、商人になって天下の金を掴んでみるか」
この千載一遇のチャンスに遭遇した弥太郎は、藩営の土佐開成社(資金と建物、六艘の汽船と二艘の曳舟)を「九十九 《機会というものは、人間一生の内に一度や二度は必ず来る。けれどもそれを捉えそこねたら、その人はもうそれなりになってしまう。河や海に魚が群を成してくることがあるが、機会の来るのもそれと同じだ。それっ、魚が集まったといって網を作ろうするのでは間にあわぬ。いつ魚が来ても、すぐに捕えられるように、不断に準備していて、その場になって、まごつかぬようにしておかねばならぬ》 弥太郎は晩年、"機会"についてそう語っている(『随想録』高橋是清)。 こうして三菱蒸気汽船会社をひっさげて出発した弥太郎は、明治新政府の要人となった後藤象二郎や、大隈重信、大久保利通らの強力な援助のもとに"政商"として発展をつづけていく。なかでも明治十年(一八七七)の西南戦争では政府軍の兵士や軍需物資の輸送を一手にひきうけ、一年たらずのあいだに百四十万円もの大金を稼ぎ、三菱財閥の基礎を築いた。 海運業を独占して天下の政商にのしあがった弥太郎は、 《およそ事業をするには、まず人に与えることが必要である。それは、必ずより大きな利益をもたらすからである》 と言い、つねに政府高官をまねいて豪華な酒宴をひらいていたという。
弥太郎のワンマン体制のもとに設立されたこの大三菱の「立社大栽 《会社ノ利益ハ全ク社員ノ一身ニ帰シ》 と強調したり、事業不振の際は 《月給ノ幾分ヲ減少シ、且、傭ヲ止ムルコトアルベシ》
などと減給、解雇をぬけぬけと明示しているところなど、まったく異色の「社則」で、微笑 その社則三ヵ条(明治十八年改正)を列記してみると、
《第一条 当会社ハ姑 第二条 故ニ会社ノ利益ハ社長ノ一身ニ帰シ、会社ノそ失モ亦社長一身ニ帰スベシ。 第三条 前条ノ如シㇳ雖モ、会社盛大ニ相成リ利益ヲ得ルコト多分ナル時ㇵ、一体ニ月給ノ幾分ヲ増加スルコトアルベシ。又会社ノ事業興ラズ多分ノ搊失アルㇳキハ、一体ニ月給ノ幾分ヲ減少シ、且、傭ヲ止ムルコトアルベシ。》 弥太郎が育てた大三菱の見事さは、錚々たるビジネス・リーダーの中から三人の日銀総裁、二人の首相を生んだことだ。 参考:第3代総裁:川田小一郎、第4代総裁:岩崎彌之助、第5代総裁:山本達雄。 参考:岩崎弥太郎の娘を妻とした第24代首相加藤孝明、第25・28代首相若槻礼次郎、岩崎家の縁戚である第44代首相幣原喜重郎と歴代首相が3人も住んでいる(以上故人)。 神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.116~120 2021.05.21記 |
|
土佐海援隊、坂本竜馬
紀州藩勘定奉行、伊達宗広の六男に生まれた陸奥は、藩の政変によって父は幽閉、陸奥も家族らと共に城外十里四方追放の身となる。当時、牛麿とな乗っていた十歳のころである。この時の藩庁への恨みは深く陸奥の胸に灼 いらい陸奥は、久度山、高野山、奈良などの農家を転々としながら勉学に打ちこんだが、打ちこめば打ちこむほど屈辱の思いがこみあげてくる。遂に思いを決した陸奥は、
朝 飄身漂泊難船に似たり 他事争い得ん鳳翼の生ずるを
一挙に雲を排して九天に翔 の詩をのこして出奔、江戸にむかう。このとき陸奥、十五歳。この、紀州藩憎しの思いが、いつか陸奥を勤王思想に突き進ませていく。 こうして幕末風雪のなかを江戸から京にのぼった陸奥は、ここに居を移していた父、宗広と再会。この父の家で土佐の坂本竜馬を知る。 やがて勝海舟の神戸操練所から坂本竜馬の海援隊に入った陸奥は、長州の伊藤俊輔(博文)、土佐の後藤象二郎らと勤王の革命運動に奔走する。が、陸奥の行動は世の常の志士からみれば異色であった。 《他の連中が討幕とか挙兵とか目を吊りあげて議論している時でも、しずかに本を読み考えているようであった。》 と、大江卓の後日譚にいう。 頭のよさで定評があったが、あまりにも理知的で冷静さを失ったことがない陸奥の評判は、海援隊でもあまりよくない。誰よりも陸奥の見識と才幹を愛し将来を期待していた隊長の竜馬でさえも、 「こいつは他日ひとかどの人物になるにはちがいないが、あまり才幹を弄すと同志に憎まれ、殺されるかもしれん」 と案じたという。
坂本が心配するのもむりはない。当時の志士たちの写真をみても、いずれも眼光けわしく、手にピストルや太刀を摑みすえた殺伐としたものばかりだが、その中で若き日の陸奥は、まるで映画で見る鞍馬天狗そのまま、黒頭巾に黒ちりめんの紋付をぞろりと着流し、腰の大小は落し差し、白たびに舞妓のはくような木履
もっとも、こんなところは世間より一歩進んだ現実と抱負を論じて、土佐勤皇党の首領、武市半平太から「ほらふき竜馬」と冷やかされた坂本の、よれよれの袴に洋靴、ふところ手をして写真におさまっている姿と似ていなくもない。似ているといえば、坂本の「ほらふき竜馬」と同様に陸奥もまた、めまぐるしく変転する現実の先々を読みながら、巧みに身を処していくその変貌ぶりを「うそつき小二郎」と称
陸奥の第二の出発は、この坂本竜馬の死を乗り越えた時からはじまる。王政復古が成って明治新政府が生まれると陸奥は、岩倉具視の推挙を得て徴士 このあと陸奥は、備前藩士による外人殺傷事件(神戸事件)、土佐藩士にによるフランス人殺傷事件(堺事件)、イギリス公使の遭難事件などの外交問題を処理して、のち摂津、兵庫など諸県知事を歴任。明治四年、神奈川県知事、同五年、陸奥が主唱する地租改正問題に取り組み地租改正局長となる。同八年、元老院議官。 しかし、陸奥ほどの《衆を超えた見識と才略》の持ち主が薩長閥で占められた新政府に満足できる筈はない。おりからの西南戦争に乗じて土佐立志社と語らい政府転覆をくわだてる。が、事は未然に破れ、投獄されること五年。 明治十五年、特赦出獄した陸奥は、伊藤博文のすすめで欧州諸国を巡歴し憲法を調査。帰国後、不死鳥のごとく新政府に返り咲いた陸奥は、駐米大使、山県内閣の農商務大臣、枢密顧問官となり、第二伊藤内閣の外務大臣として列強諸国、メキシコ、イギリス、清国(中国)、ロシアを相手に、鮮やかな外交手腕をふるう。
明治のジャーナリスト鳥屋部春汀 《奇才、術策に富み、人よんでカミソリ大臣》 と評した陸奥の、そのカミソリが凄まじい斬れ味をみせるのは、明治新政府の大きな課題であった条約改正を見事に成し遂げた瞬間である。 卓抜した政治手腕で強国イギリスと対等で通商条約を結んだ陸奥は、ロシアの干渉を拒絶、日清講和条約、三国干渉などの外交面の難局を切りぬけると、日本の外交史上忘れることのできない足跡を残している。しかもそれが薩摩や長州の藩閥政治のなかで、藩閥のバックもない一匹狼の彼が、それだけの功業を成したのである。並々ならぬ見識と力量といわねばならない。 しかし、その陸奥を評して、
《彼は理想もあり目先も見えたが、権略家だけに人にたいしては現金であった。朝 と『当世策士伝』にいう。 だが、それが政治の本質ではないだろうか。陸奥は感情に走ったり思想的な立場によって左右される男ではなかった。 つねにそれを冷然と凝視している現実家であった。事をなすに当っては細心に考慮し、断行すれば手段を選ばなかった。このため陸奥の"策"には違算がすくない。だが、この陸奥の合理精神は、近代の夜明を迎えたばかりの日本で理解される筈はなかった。この時代、陸奥ほどの近代感覚をそなえた政治家は大久保利通ぐらいのものであろう。
辛酸に満ちた人生をくぐりぬけ、冷徹な眼で現実を瞶 《諸事堪忍すべし 堪忍のできるだけ堪忍すべし 堪忍のできざることに会すれば決して堪忍すべからず》 と、よく言ったという。そしてまた陸奥は、 「日本人にはNOといえる者がすくない。どうしてもYESということができぬ場合は、敢然としてNOと言え」 と、声を重ねている。 が、世間は時として軽率である。 陸奥が誠実の行為と信じた、勇気のある「NO」が、冷淡、不親切などの批判をうけ、そのため陸奥は数多くの政敵をつくった(『陸奥宗光伯』)。 陸奥が広吉に語った「NOという気魄」が、平成日本の、腑抜けたような外交に最も欠けているものであろう。明治三十年八月、伯爵、陸奥宗光死す。五十四歳。欧米列強と骨身を削るような外交の辛苦が、いつか胸を冒していたのである。死の直前、友人の一人に陸奥は、ぼそりと言った。 「皆と離れ、家族と別れて逝くのを淋しいとは思わないが、もう政治ができなくなると思うと、それが滅法かなしいよ」 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.159~164 2021.06.24記 |
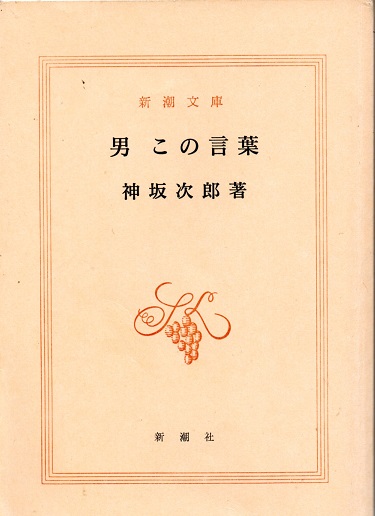
幕末から明治にかけて稼ぎに稼いだ大富豪に、諸戸清六という男がいた。 その先祖というのは伊勢国(三重県)揖斐川沿岸で加路戸新田を開拓し大地主にのしあがったが、祖父の代に家運傾き、父の清五郎は塩問屋、米穀、肥料の仲買商など、さまざまな仕事に手を出したがいずれも失敗、失意のうちに世を去る。 この大借金の加路戸屋を六千百二十円という負債もろとも引きついだのが、清六、十七歳のとき。一円で米が約三斗(四十三キログラム)買えたという時代である。清六は、押しかけてきた債権者と話しあい、十年間無利子で毎月五十一円四十銭ずつ、つまり十年間で借金を返済するという契約をかわした。 「いまに見ちょれ。儂ア、天下一の金満家になつちゃる」 加路戸を去って桑なにでた清六は、ちいさな搗米屋を開業し、大借金返済のため二十ヵ条の自家訓をおのれに課し、猛烈きわまりない働きぶりをみせた。 清六の、その自家訓というのは、 《第一条 今日よりは酒、煙草一切厳禁のこと。 第二条 従来自分の食糧は一日八合なれど、借金皆済までは必ず六合に減ずること。 第三条 温かき飯は手間どり時間を空費す。今日以後、借金皆済まで冷飯たるべきこと。それも茶漬たるべきこと。 第四条 忙しき時は、むしろ食わざること。二度くらいの欠食で空腹をおぼえるようでは、金はたまらぬと心得べし。 第五条 飯を盛り替える時間は惜しきゆえ、二個の椀を用意しておき一杯に盛りおくこと。 第六条 昼飯は必ず帳場で食すべきこと。それも一口にて食し得べき握り飯を二個ずつ用意しておき、用の合間に食すべきこと。 第七条 飯の菜は生ミソの中へ鰹節と生姜を入れて煮詰め、それを少しずつ冷飯の上へのせ、茶漬にして食うこと。 第八条 字は仮な書きがよし、手紙、帳面、すべて人より早く書くべきこと。 第九条 ソロバンは通常がよし。ただ書くこと早く、間違いなきよう稽古すること。 第十条 家裏の空地は一坪にても利用し、茶、大根、すべて野菜をうえ込み、汗の実は必ず他より買うべからず。 第十一条 家の付近に竹木縄類が落ちておれば、それを拾いあつめ宅に持ち帰って何かに利用すること。 第十二条 冬季、火鉢へ炭を入れるを廃し、薪を長さ五寸程に切り、縄を巻いて灰の中へ入れておくこと。 第十三条 下駄、草履三、四足ずつ家の各所の上がり口に並べおき、いつ何処にても上り下り自由になし、時間を省き得ること。 第十四条 道をゆく時は、後足を先へ先へと歩くよう練習すべし。人が一里歩く間に一里半歩くべし。 第十五条 買い出しの場合は、夜行をして相手の家へ早朝に着くこと。早朝なれば先方必ず在宅なり。 第十六条 買い出しは必ず日の暮れまでに片付け、船、車に乗りても、その夜のうちに帰宅し、決して宿屋に泊まらぬこと。 第十七条 旅行具の道具は常に一ところにまとめておき、イザといわば、すぐさま飛び出し得るよう用意のこと。 第十八条 遠出の際は小石多き道のみ草鞋で歩き、通常の道は草鞋をぬぎ、はだしで歩くこと。
第十九条 道に草鞋が落ちておれば拾い来たり、水で洗い、日に干しておき、夜業 第二十条 渡し賃は一厘一毛(銭貨の最低の単位)にても払うことは無易なり、寒中の他は衣類をまとめて泳ぎ渡るべきこと。。 ――といった条々である。 諸戸清六が偉大なのは、この二十ヵ条を作ったことではない、すべて実行したことである。 こうして約束の十年目、血のにじむ思いで大借金の返済を成し遂げた清六は、以来、近隣の農村で買付けた米を美濃や尾張方面に船で運んで売りさばき、帰りの船には薪や雑穀などを積んでくるという稼ぎぶりで、明治初年、すでに数万円の財産を掴んでいたという。 その清六のうえに、思いもかけぬ幸運が舞い込んでくる。明治十年(一八七七)の西南戦争であった。 「やるか!」
清六は素迅 米価の高騰を予測し、全財産を投じて米を買い占め、巨利を掴んだ清六は、おりから新政府が、西南戦争でがたがたになった赤字財政を補填するため濫発に濫発をかさねていた紙幣に目をつけた。 この時期、巷に氾濫する紙幣と正金(銀貨)のあいだに大きな価値のひらきがでていた。正金を銀貨と書いたのは、当時のわが国保有の正貨のほとんどが銀貨であったからだ。 ともあれ、この新政府の紙幣に視線をむけた清六は、
《(紙幣が)銀貨に対して八十五銭の打歩 という。 おそらく清六は、大蔵卿、松方正義が「兌換銀行条例」を公布したその瞬時の潮どきに乗じて、紙幣と正貨との兌換(引き換え)によって荒稼ぎをしたのであろう。 これと同様の例は、安田善次郎の場合にもある。
善次郎は、新政府が強行した「紙幣と正貨の等価通用」の布告を一日前に察知し、三十八円で買い占めに奔走、そのボロ紙幣が翌日には三ばいに化
諸戸清六が蓄財をかさねていく経緯
ある晩、所用の帰りに清六が、桑なの近くの坂道に通りかかると、ひとりの車曳きが坂道を登り悩んでいた。清六はその車の後押しをして坂を登らせてやった。そして、夜まで働いている車曳きをねぎらうように、財布をとりだして「車力どん、夜遅くまで働いて感心だねぇ」と、一枚の銭を与えた。その一枚の銭に車曳きは妙な顔をした。「仮にも天下の金満家といわれる諸戸の旦那とあろうお人が、文久銭一枚とはねぇ」。鼻先で嗤うと車曳きは清六の掌 「ああ、要らないのかぇ車力どん。文久銭一枚でも儂が汗を流して稼いだ大切なお金だよ。お前さんは一生、車を曳いておわるのだねぇ」
そういうと清六は、背を返して歩きだした。以来、土地の人びとはこの坂を、諸戸の「文久坂」と称 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.33~37 2021.06.16記 |
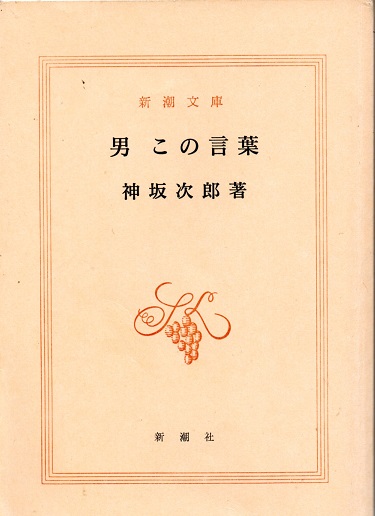
西南戦争による米価の高騰と、明治新政府が濫発した紙幣と正貨の打歩 《明治二十年(一八八七)木曽川工事に着工せらるるや其の水利の便を洞察して沿川の荒蕪地を廉価に買入れ、美田を得、またしょく林事業に着手して巨万の富源を作る等々その画策するところをみな成功せざるはなし》(『大日本人名辞書』) 《(彼の)財産の主なるものは土地にして伊勢、伊賀、紀伊の三国に跨り莫大の面積に渉り地租(土地税)実に二万円以上に達す》 清六は終生、松坂木綿の衣服をまとい粗食に甘んじていたが、吝嗇ではない。諸戸家に勤める丁稚の中で有望と認めた少年には学資を給し学校教育をうけさせ、飲料水に悩む桑なの町民のため十五万円投じて水道を敷設してみたり、また、日本帝国海軍に軍艦建造費を献のうするなど、豪快な金の使いぷりをみせている。
奇行の多かった清六のエピソードの一つに、文明開化の岡蒸気こと"汽車"が登場する。当時の鉄道は、料金は高いし、鉄道頭 《何人によらず鉄道の列車にて旅行せんと欲する者は、まず賃金を払い手形(切符)を受取るべし、然らざれば列車に来るべからず》 《乗車せんと欲する者は遅くとも十五分前にステションに来り切手(切符)を買うなり、手都合を為すべし》 そんなある冬の日。 東海道を走る列車の一等車に、素足に草鞋脚絆といったみすぼらしい身なりの老人が乗っていた。検札にきた車掌が、 「おい、ここは一等車だ、お前などの乗るところじゃない」 そう咎めると、老人は袂から一枚の白い一等切符をとりだし、 「れがあっても、駄目かね」
と微笑
こうして列車が桑なに近い小駅に停 「あの爺さんは?」 乗客の一人がそう訊くと、 「ご存じないのか、天下の千万長者、諸戸清六様を」 「なるほど、桑名の諸戸なら、一等切符どころか、この列車を全部買切ったところでふしぎはない」 乗客たちは、たがいに頷きかわした。
このとき、一等乗客が言った言葉どおり、清六は後日、愛娘 その日、桑なの町民たちは国旗をかかげ、花火を打ちあげ、諸戸家万歳をとなえて見送ったという。 清六と親交のあった東京の実業家、森村市左衛門は、 「彼の汽車旅行は、いつも赤切符(三等)だったといわれているが、そうではない。車中は有益な話を聞く耳学問の勉強の場だと考えていた彼は、一等に乗ってもよい話が聞けそうもないと思えば、すぐに二等車に移り、二等で話しが尽きると、こんどは三等にという場合が多かった。もちろん、彼が喜んで聞いたのは経験談で、車中を見渡して大工でも左官でも、なにか経験のありそうな顔を見かけると、すぐにその人に話しかけるという風だった」 と、述懐する。
清六は、この森村(維新後真っ先に対米貿易の道を開き、森村組を創業。男爵)の家をよく訪ねたが、無益な雑談などはしないで、自分の用事だけをどんどん喋って、それが終ればすぐに帰っていくのだが、時には「もっと活 そんな清六の手紙も変っていて、 「それでいて要領を得ていること、驚くばかりであった」 と森村は語っている。 この森村とともに親しかった大隈重信(政治家、侯爵)は、招かれて二度、桑なの諸戸邸を訪ねている。
《その低はさながら一城郭をなしているが、強盗を防ぐ方法として、見上げるばかりの高土塀の内側に濠
大隈と清六の関係
晩年、諸戸家の家法、家訓をつくることを思い立った清六は、全国の富豪たちの間 《(一)時間は金、忘れてはならぬ。 (二)顔をよくするより金を儲けよ、金儲かり家富まば自然と顔もよくなる。
(三)どこまでも銭のない顔をせよ、銭のある顔をせば贅費 (四)派手にすべからず出来るだけ質素にせよ、衣服は垢の付かぬ木綿服にて充分なり。 (五)身代を減らさぬ考をするには平素交際する人を選べ。 (六)一銭の金を骨折って儲けよ、楽して儲けた金は落とし易し。 (七)無益の道具類は買うな、買えば他人に見せたくもなり、自然と自分の職業を怠り、時間を費す可し、慎まざる可からず。 (八)身代を減らす者は大抵、口先はよくて尻結びの無い、先の見込みの付かぬ者なり。 (九)多く人に会して多く知恵を得よ。 (十)馬鹿になれば悧口、悧口になれば又馬鹿、馬鹿になって物事を尋ね、馬鹿になって商売せよ。 (十一)できるだけ人の下風に立ちて、頭を下げる者は必ず勝を占む。 (十二)人と商売の話をなすもおのれの見込とする。所謂「キキメ」(ここ一番の決め手)一つは決して人に洩らす可からず。
(十三)二年先きの見留 (十四)商取引をなすには先方の掛引を見分けるが肝腎なり、之ができぬ者は商売をするな。
(十五)身代を大きくしたいならば、丁稚下女の為 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.38~44 2021.06.24記 |
|
家訓というと、どうにも肩肱
「深酒はいかぬぞ、博奕なども所詮は"場(賭場)朽ち"、白粉くさい妓
と口癖のように掻きくどいていたようなのが、ひょっとすると後の世の末裔
《酒
などと鹿爪らしい表現で書き留められ、それがいつか「ご先祖さまご遺訓」となって伝えられたという例もないではない。しかし、そいう家訓というのは、一応の体裁を整えてはいても、ナマの肉声がもっていた説得力やバイタリティが希薄になっている場合が多い。
こうした凡百の家訓群のなかで、ときたま、いきいきした語り口の、ひどく人間臭い家訓などに出逢うと、妙に吻
その一つに幕末から昭和二十年ごろ播磨(兵庫県)十一郡にまたがって田畑をもっていた千町長者こと、今村村の伊藤家の家憲がある。小作人三千を擁して関西一と称
それらをここに紹介してみたいのだが、現代風な解釈など加えると、せつかくの雰囲気が伝わらない。原文のまま味わっていただこう。
《一、朝は随分と早く起るべし、(大切な時間をうかうかと寝ていては)勿体ない事なり。
一、心得違いでビンボーしては先祖代々の汗アブラも水の泡にして子孫も女房も難儀、又我身も難儀して人に嗤われㇳンㇳツマラズ。
一、医者には常に気を付けよ(ふだんから親しくしておけ)生身の事故、火急な病人も有るものなり。
一、寺とは随分仲よくせよ。敬せよ。布施は我身分相応に上げよ、(お)経を値切る(のは)罪なり。
一、禍福は門ならず、ただ人の招く処に在りと云えり、此の招き塩梅
一、仁、義、礼、智、信を喩
一、シマツ(倹約)はその家々によりて致し様があるものなり、兎角
一、不調法(あやまち)致した人を見て慎しみ、手柄致した人を見てまねすべし、さすれば世間に笑う人はなし、不調法する人も我が師匠なり。
一、女の美なるは傾国
一、食事は大食わるし、又先の食事の消えざるにその上に喰うはわるし、とかく腹八合(分)に喰え。食より病を起すなり、病は口より入り、禍は口より出
一、酒は朝より九ツ(真昼の十二時ごろ)迄わるし、又一合位を度々飲むは吉、大酒は至って悪し、唯よく働く人は一合位いつもよし。
一、四十歳迄の無事仕合せ(倖せ)は役に立たず、若い時は難儀して老いては仕合わせが大いに吉、依って衆も武家も難儀した程大徳(大きな得)なり、末を思うてシンボせよ。
一、仕合せは務めとシンボの報いと知れ、外に仕合せも運もなし。
一、朝早く起き、よく勤めたら八百万
一、半麦飯の香の物を食べ、その上は驕奢
一、其の道を勤めずして禄を貪り、故無くして宝を得るのは禍の基なりと云えり、拾いものすな(するな)、無理な儲けをすな、不義の富貴はうかべる雲とも云えり。
一、むそう(汚たく)儲け清う喰えと云えり、たとえ牛馬の糞を手でこねても、家業ならばよく勤めよ、また清う喰えとは、いげ(隠元)豆一勺でも盗みし物を喰うな。
一、家内上下ともに同じ菜(副食)に致すべし、別に菜を拵
一、菜は一日一度なり、一人前に三文より四文のもの、その上はおごりなり。
一、おごりさえせずば安穏にはくらされる。身の上(自分が)奢りて躰をいためるはアホ。
一、喧嘩は致すべからず、家内喧嘩は、一匁(一両の六十分の一)より安き事出来申さず。搊なり。
一、わが身(の)勤め(に)てくしゃくしゃ云うな。
一、我が子には慈愛は深く致して稽古又仕事などはキッㇳ申し付くべし、やだくさ(ぐうたら)に致すべからず。
一、仕事は昼夜きっと致すべし、大家も小家もその家々の仕事あるものなり、ぶしょうもわるし。
一、若い時は雪霜雨露を受けずば老いてよろしからず。若いときは難儀せよ。
一、運は拵えるが大いに吉、運次第運次第と云うべからず、倹約して能く働けば必ず必ず運来るべし。
一、倹約は則ち道なり、倹とは糾
一、人は皆勤め(努力)も働きもせずに此の世も未来も楽にやる積りにする。依って両方とも叶わず。
一、口に喰うと云うは中々無きものなり(自分の稼ぎで喰っていくというのは並たいていの事ではない)二百貫匁の身代でも親より預りたるものをへらしては口に喰うとは云わず(親から貰った財産を)へらさぬ人は稀なり、依って古き人も基を拵える人はあっても、保つ人は稀れなりといえり。
一、今日より驕奢(をしようと)思う人は一人もなし、是丈の事(ぐらい)は大事なし、是れ丈は大事なしとじりじりといつの間にやら驕奢となる、万事分限せよ(身の分際を考えよ)。》
この家訓を読んでいて愉快なのは、突然(近郷の住人らしい)「四六瓦屋の旦那」なる人物が登場するくだりである。
「身をもつというのは、高価な着物を着るということではない四六の瓦屋の旦那をみよ。よき身代というのは調子の低い(倹
神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.138~142
2021.06.28記
|



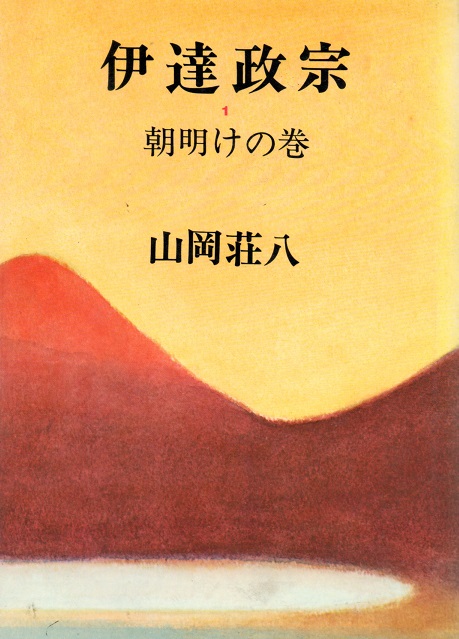 ※参考図書:山岡荘八『伊達政宗全六巻』(毎日新聞社)昭和四十五年九月二十日 第三刷
※参考図書:山岡荘八『伊達政宗全六巻』(毎日新聞社)昭和四十五年九月二十日 第三刷
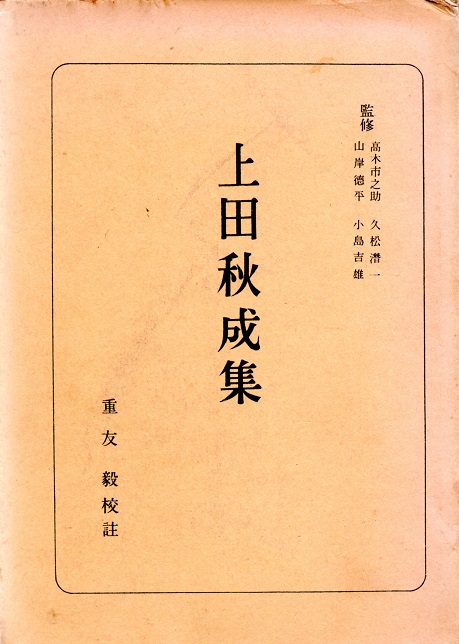 ※参考図書:日本古典全書〚上田秋成〛(朝日新聞社)P.161~
※参考図書:日本古典全書〚上田秋成〛(朝日新聞社)P.161~



 主著『靖献遺言』は、1684年から1687年にかけて書かれた。屈 原、諸葛 亮、陶 潜、
主著『靖献遺言』は、1684年から1687年にかけて書かれた。屈 原、諸葛 亮、陶 潜、 徳川綱吉のあと6代家宣
徳川綱吉のあと6代家宣

 金といえば、《この世で唯ひとつ》の信ずべきものとバルザックが言ったのと同じことを、元禄時代の文豪、井原西鶴
金といえば、《この世で唯ひとつ》の信ずべきものとバルザックが言ったのと同じことを、元禄時代の文豪、井原西鶴 補足:安岡正篤著『先哲講座』(竹井出版)P.58~に、山田方谷が三十歳頃に書いた「理財論」にふれています。
補足:安岡正篤著『先哲講座』(竹井出版)P.58~に、山田方谷が三十歳頃に書いた「理財論」にふれています。
 嫌な奴のよい意見 山田方谷と佐久間象山
嫌な奴のよい意見 山田方谷と佐久間象山