改 訂 版 2023.02.20 改訂

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.9~13 横井小楠 実学説き弾圧受ける 曲者とは、ひとくせあるもの、悪党、あやしいもの、盗賊という意味だそうだが、すばらしい条件でスカウトされようとしたとき、あいつは曲者だから中止されるように、と妨害をうけた人物がいる。肥後の学者横井小楠(一八〇九-一八六九)がその被害者であった。 小楠は、百五十石どりの肥後藩士の二男坊である。なは時存、通称を平四郎といった。畏斎、小楠、沼山という三つの号があるが、小楠がもっとも有めい。これは楠木正行(父正成を大楠公、正行を小楠公と称す)の人物を慕ってつけたものといわれる(他に、家塾が横丁に面していたので小楠塾となづけ、それを号にしたという異説あり)。 十歳のころ藩学時習館に入学し、十五歳のとき成績優秀でほうびをもらい、二十五歳で居寮生にばってきされた。これはめい家の子弟と秀才を二十五人前後選び、藩費で寮生活させながら勉学させる制度で、その将来を約束されたことになる。二十八歳で講堂世話役、二十九歳で居寮長(塾長)、その三年後に江戸留学を命ぜられた。エリートコースの仕上げである。 しかるに、小楠は藩当局の期待するような型にはまった優等生ではなかったのである。当時の肥後藩では、学者(儒者)を幇間(たいこもち、おとこげいしゃ、ごきげんとり)ないし逃避者として飼育し、酷政批判の矛先をくだき、すすんでその協力者に仕立て上げようとしていた。そこで、大半は生活のために御用学者となり、良心的なものは詩文の世界に逃避した。御用学者は字句の解釈だけを重んずる。<けしつぶの中くりほぎて館たて、ひと間ひと間に細注を読む>という狂歌がよまれたほどである。秀才の平四郎青年は、現実の政治と無関係な官学にあきたらず、当然、知行合一をとく陽明学を独習した。したがってその学問的なながれからいえば、中江 藤樹、熊沢 蕃山、佐藤 一斎、大塩 平八郎(中斎)、佐久間 象山、高井鴻山などの人脈につながる。江戸に出ても、官学派の本山昌平黌(東大の前身)でおとなしく講義をきくというよりは、さかんに一流人士と往来した。 そのとき彼がもっとも評価したのは、水戸藩の藤田 東湖、幕臣では川路聖謨の二人である。その東湖が忘年会を催して同志を招待したとき、平四郎も迎えられた。彼は漢詩一編をつくり、一座の人びとに訴えた。<わが輩従来文士にあらず……治乱にただこれわが心をつくし、群小と黒白をあらそわず……なんぞ風月をといて文墨を弄せん、諸君まさにおのおの思うところあるべし、こころみに肝隔をひらきて、座に向って投げうて>という激烈なもので、夜を徹して痛飲し、胸襟を開いて天下の政治を論じようではないか、というのである。 これが肥後藩邸留守居役の耳にはいった。こいう手合いは俗吏にきまっており、事なかれ主義を最上の実践倫理とする。平四郎の言動によって災いがおきることをおそれ、酒失(酒の上の失態)があったとして熊本帰還を命じてしまった。 平四郎青年はそのときエリートコースからはずれてしまったのである。いや、ただ出世しなくなったというだけでなく、いみきらわれ、憎まれ、弾圧されたのである。まず逼塞(門をとざして白昼の出入りを許されない)七十日の処分をうけ、これまでの給与をとり上げられた。三十二歳にして長兄の居候となるほかはなかったのである。兄は知行百五十石で手取りは米五十石の貧乏ぐらし、平四郎が食客となっていよいよ窮迫した。 しかし、彼は節をまげず、その「実学」に打ちこんだ。そこから「治国安民の道、利用厚生の本をあつくして決して知術功みょうの外に馳せず、眼を第一等につけ、聖人以下には一歩もくだらず、日用常行孝弟忠信より力行して、ただちに知道をおこなうべし」という政治理念を確立した。彼を中心に、長岡監物(のち家老、当時二十四歳)、元田 永孚(のち明治天皇侍講、二十四歳)、荻昌国、下津休也などの青年読書グループができ、実学党とよばれ、藩庁、保守派から敵視された。 はじめて私塾を開いたのが三十五歳のときで、これからが「小楠」時代となる。入門第一号は惣庄屋のせがれ徳富一敬(このとき二十一歳)、第二号は矢島 源助。徳富は矢島の妹久子を妻にむかえ、猪一郎(蘇峰)、健次郎(蘆花)の文人兄弟を生んだ。また久子の妹せつは、小楠四十八歳のときに後妻にむかえられたので、小楠と蘇峰、蘆花兄弟は叔父・甥の関係に結ばれる。 さて小楠は、四十三歳のとき諸国遊歴の旅にのぼり、越前の福井を通った。このとき藩首脳を心腹させたことがのちの結びつきの端緒となる。翌年、越前藩では学校創設にあたって小楠の意見をもとめ、その人材教育に関する卓見に藩主松平慶永(春嶽、このとき二十五歳)は魅了されてしまった。春嶽はその後、黒船渡来後の人心動揺を心配して幕府に数回建言する一方、領内の海防兵備に心をくだき、適当なアドバイザーを求めていたが、たまたま安政三年、家臣村田 氏寿にきた小楠の手紙を見るにおよんで、彼こそ自分の求めていた人だと確信し、その招聘を決意したのである。 順序として、熊本にいる藩主細川斉護にその希望を手紙で申し入れ、自らは江戸の肥後藩邸に家老をたずね、家老不在のため藩主夫人(春嶽夫人の母)に会ってそのことをたのみ、さらに翌日は側近に書面をもたせて家老に申しこませた。ところが家老は尻の穴が小さい。家中の人物が他藩に評価され、いいチャンスにめぐまれたことをよろこばず、「とにかく曲者ゆえしきりに他人と取りあい絶交などつかまつり、はなはだもって困り入り申し候……右ようの者ご承知なく御請待に相なり、後日不都合のことなど出来候ては、御大切の御先がらさまゆえ、はなはだもって当惑」と打ちこわしにかかった。手紙だけでなく、越前藩邸をたずね、ボロクソにこきおろした。 ところが、このときの春嶽が見事である。もともと小楠は肥後藩の日かげ者、肩書き、知めい度など外的権威などゼロに近い田舎塾のあるじであった。それを自分の肉眼で見ぬいた上での招聘だ。不都合があってもそれは当方のこと、そちらの知ったことではあるまい、と押しきり、ついに賓師(客人あつかいの先生)としてまねいた。小楠もまた知遇に感じ、動乱期のめい指導役をつとめるとともに、多くの人材を育成した。今日の熊本大学教授を福井大学学長にむかえることとは本質的にちがう人間血盟、心と心の結びつきが、このスカウト人事を成功させたようである。 ※小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公文庫)の表紙に<業半ばにして凶刃に斃れた幕末の思想家横井 小楠の開明的な精神を受け継ぎ、世界的視野を以て維新から現代まで日本の近代化に努めてきた四十七人の男たちの人生に、人間の生き方の根源をさぐる>と書かれている。 2010.03.15、2019.05.02追加。 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.14~18 由利公正 (御誓文起草に小楠の影響 横井 小楠の薫陶をうけたものは、熊本、柳川、福井にいた。このうち福井の門弟では三岡八郎(のち由利公正)が光っている。小楠自身は、「君子と俗流を区別せず、おのおのその情をつくさせ、公平無私・一視同仁の態度で接した」(『北越土産』)と書いているが、やはりできる人物をかわいがったようだ。弟の死亡通知で安政五年十二月、熊本に帰省したとき、小楠の従者二人のほか、二人の越前藩士がおともをした。 その一人が三十歳の三岡八郎で、後年この旅について、「さて道中で、先生のわれにことさらに注意された忘れられぬことがある。宿へつくと一統を呼ばれて言はるるには、いづれも雪中でつかれたろう、早く食事を仕舞うてぢきに寝るから手配りせよ。おのれは酒を呑まぬと言ひつけられたゆゑ、みなみな早々風呂に入り、食事をしたが、早く寝るべしと言ふことで床に入ると、しばらくして三岡と呼ばれる。われ前にでれば、いはく、酒を温むべし手配せよと言はれて、それから講習せられて夜半をこえた。大坂にいたるまで毎夜同様のことでずい分疲れもしたが、その親切はじつに厚いことであった」(『由利公正伝』)と回想している。 「公平無私・一視同仁」どころか、極端な差別待遇だ。しかしこれはとがめるべきでなく、こいうエコヒイキの姿にこそ、材を愛し、期待した小楠の心情、体温が感じられてほほえましいと筆者は感じる。 はたして三岡は恩師の期待にこたえた。それまで越前藩は、節倹だけを唯一の富国策としてきたが、三岡はそのケチケチ根性を打ちこわし、積極的な殖産、貿易策に切りかえたのである。それは小楠の教のままであった。 三岡は、恩師を熊本におくりとどけ、二月ほど講義をきいたあと、長崎に向った。そこで外国貿易、物資の集散状況、その運輸方法などを調査研究し、土地一町歩を買って越前藩蔵屋敷を建て、オランダ商館との間に貿易契約をむすんで帰国した。 出発前、勘定奉行長谷部甚平に、殖産資金五万両の調達をたのんでいた。長谷部も小楠門下生で「越前藩第一の人材、才力敏鋭、談論人を圧し、なかなかむつかしき男」という小楠の評もあるほどで、ただのネズミではない。しかし、節倹第一の藩方針をくつがえす決断はなかったと見え、五万両をい準備していなかった。 三岡は大憤慨でくってかかり、結局小楠の仲裁で、切手(不換紙幣)五万両を増発してこれにあてることとした。三岡は有力者をあつめて新計画を説いたが、彼らもまた藩当局とおなじ消極主義で、ついてこない。三岡は村々をまわり、庄屋、年寄、老農などを説得し、ようやく物産総会所を設置するところまでこぎつけた。。 物産総会所は、会計監督に藩士一人をつけただけで、すべて商人の自治にまかせた。土地の産物である糸、布、木綿、蚊帳地(かやじ)、生糸、しょう油、茶などをオランダ商館に売りこみ、初年度百万両、次年度二百四十万両、四年目の文久元年には三百九十九万両に達した。こうして殖産、貿易策は成功し、藩札は正貨に切りかえられ、藩の倉庫にはつねに五十万両もの小判がたくわれるに至ったのである。 やがて三岡は明治新政府に登用されて参与となり、由利公正と改名してからの最初の仕事は、新政府の基本方針を示す「五箇条の御誓文」の起草であった。彼の試案では、その第五条に「万機公論に決して、私に論ずるなかれ」というのがある。これ坂本 竜馬が、山内容堂に大政奉還のことを具申するため長崎から海路上京したとき起草した「船中八策」の中の、「万機公儀によって決定すべきこと」と酷似している。 坂本は、文久二年七月、幕府の政事総裁となっていた越前藩主松平 春嶽に面会をもとめ、勝安房(海舟)と横井小楠への紹介状を乞うた。このとき坂本は二十七歳、コチコチの攘夷論者であり、開国論をとなえる勝と小楠を説得し、きかない場合はこれを刺殺する覚悟であった。 春嶽は、その気配をさとりながら、あえて紹介状を書いてやった。というのも「人を見る目」に卓越する彼は、勝、横井の力量を信ずるとともに、この若者の明敏な判断力を見ぬき、共鳴必至と判断したのである。はたして竜馬は開眼翻意し、勝について海軍のことを教わるとともに、小楠にも深く傾倒して死ぬまで指導をうけたのである。すなわち両人とともに、その抱懐する「万機公論」の思想は横井小楠に発するのである。 さて由利の試案に福岡 孝悌が加筆訂正をし、くだんの箇条は「列侯会議を興し、万機公論に決すべし」となって冒頭におかれた。これにはさらに木戸孝允が手を加えて「広く会議を興し、万機公論に決すべし」ときまり、明治元年(一八六八)四月六日、文武百官をしたがえた明治天皇は、神前において誓約されたのである。 そのころ小楠は熊本の自宅で貧窮に苦しめられていた。文久二年十二月、肥後藩江戸留守居役の別邸をたずねたとき刺客におそわれ、そのとき小楠ははしご段の近くにすわっていたため、床の間においた大小をとりに行く余裕がなく、そのまま逃げたのである。するとかねがね彼を憎む藩当局は、「士道忘却」としてこれをとがめ、知行召し上げ、士籍剥奪(はくだつ)の罪を科したのである。 しかし、人材を求める新政府からは、小楠召命の達しがきた。首脳部は、病気だといつわってこれをことわったが、岩倉 具視の一喝でようやく新政府出仕を認める始末。小楠は制度局判事をへて参与となった。おなじ参与には、小松 帯刀、大久保 利通、木戸 孝允、後藤 象二郎、広沢 正臣、福島 種臣、由利 公正、福岡 孝悌とえりぬきの人材がそろっていたが、この中で新日本建設のビジョンをもつのは小楠一人だったといわれている。しかし、その大経綸を行う日は来なかった。明治二年一月五日、太政官から帰る途中を待ちぶせされて刺殺されたからである。 凶徒たちは、世界の大勢を知らず、公論の場で事を進めてゆくことを好まず、「問答無用」の直接行動しかとり得ないコチコチの反動的石頭であったが、政府内部には進歩的な小楠を憎み、その凶徒の無罪を主張するものもいたのである。「五箇条の御誓文」の「公論」が「列侯会議」を意味し、近代的立憲主義でなかったという説もあるが、ともかく「問答無用」の暴力的直接行動よりも「公論」による政治的運営を基軸においたところに、明治百年の基本的パターンがあった。 そのほかならぬ設計者がテロに倒れたところに運命の皮肉――というよりも日本の悲劇があったといわねばなるまい。明治百年の歴史は、「問答無用」と「公論」の両輪をめぐってゆれ動いたともいえようが、その意味において、明治二年正月の小楠の死は、まことに象徴的な事件であった。 ※参考:五箇条御誓文 2019.05.29 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.19~23 安場 保和 小楠塾へ通わせた母 横井小楠の熊本における門下生では「三秀才」として、徳の山田 武甫、学の徳富 一敬、知の嘉悦 氏房が有めいであった。また「四天王」として徳の山田 武甫、誠の嘉悦 氏房、知の安場 保和、勇の宮川房之の四人があげられた。最大のお気に入りは徳富で、「小楠のかたわら、一日も徳富なかるべからず」というふうであったらしい。彼は「まじめであり、正直であり重厚質実」であったが「今少し大胆者であり、横着気があったなら、必ず世間的に成功者として今少し幅をきかしただろう」(『蘇峰自伝』)とせがれが書いているように、中央でなを上げるにはいんたらなかった。そのかわりに、せがれの猪一郎(蘇峰)、健次郎(蘆花)兄弟がジャーナリズムの花形となった。 世間に出たのは安場保和(男爵、北海道庁長官)である。その母久子が偉いひとでせがれを小楠にむすびつけたのも彼女の見識による。安場家は二百五十石取り、世俗的立身を大事とする親族たちはすべて小楠塾入門に反対したが、彼女はこれを押しきった。小楠塾への圧力が強くなると、砂で目つぶしをつくって反対派の襲撃にそなえ、むすこの通学を護衛してやった。安場は十九歳で父を失ったが、それからはどんなにおそく帰っても、母のまくらもとで酒をのみ母にも杯を献じ、そのあとやすむという独特の習慣を守った。彼の特徴は大酒と大声で、その大声になやまされた藩主細川侯は会議になると、 「おい、安場参事はなるべくスミの方に席をとってくれ、やかましいから」 と敬遠した。 安場は恩師からとくに「人を見る目」を学んだらしい。胆沢県(のち岩手県に編入)大参事時代、給仕として地もとの少年五めいを採用した中で、一人がのちの総理大臣斎藤実、もう一人が後藤新平であり、後藤とはとくに深い縁でむすばれた。後藤ははじめ安場の玄関番となり、のち阿川光裕にあずけられた。そのとき安場は、 「この子は、将来参議になるだけの資格をそなえているように思われる。自分の家におくよりは君に世話をねがった方がよいように思うから、何分よろしくたのむ。ただ彼の性格を変えないで、本然(ほんねん)のまま育て上げてもらいたい」 明治四年、安場は大蔵大丞、租税権頭となり、岩倉具視を大使とする政府使節に加わって欧米に出張することとなったが、生来語学をニガ手とする彼は、サンフランシスコに上陸し、つぎの駅についたころにはがまんできなくなって、帰国を申し出た。日本に帰って、地方官をやる気なら帰国してもよろしい、と地方官就任を条件に許されたが、その約束で福島県令となったとき、医学校生徒の後藤新平と再会したのである。 福島県令から愛知県令に転じた。すると愛知病院の医師に採用されて後藤はな古屋にやってきた。愛知県令から元老院議官となり、な古屋の地を去ったあと、後藤との縁はさらに深まる。安場の二女和子が後藤の妻となったからである。和子には、はじめ本山彦一(のち大阪毎日、東京日日新聞社長)との縁談がもちこまれた。本山は安場とおなじ肥後藩士のむすこで、慶應義塾で福沢諭吉の薫陶をうけ、時事新報社会計局長をへて兵庫県庁の役人になっていた。安場はのり気になったが、本山は、役人をやめて大隈重信の改進党にはいるつもりですと言う。安場は不賛成で、官にとどまることをすすめたが、本山はきかない。結局、本山の身分がきまるまで、ということで縁談は無期延期となりやがて後藤新平に白羽の矢がたったのである。 安場と後藤との間はすこぶる円満にいった。後藤はとくに岳父の清廉潔白に敬意をいだき、ともに杯をもって快談する夜も多かった。議論が白熱すると、両方ともに人一ばいの大声でどなりあい、人びとはけんかではないかと心配した。後藤は、事あるごとに安場のところにかけつけて相談した。後藤の七十三年の生涯において、「真実に心から相談するという人は、安場一人であったかも知れない」(『後藤 新平』第一巻)と鶴見佑輔は書いている。 後藤は、陸軍の知能といわれた児玉源太郎に信任されて台湾民政長官、満鉄総裁となり、さらに逓信大臣、外務大臣、東京市長などを歴任した。和子はそういう夫の栄進のかげでつつましく家を守り、驕慢なめい流夫人とはならなかった。 家族の旅行はいつも三等車で、後藤が鉄道院総裁となり、夫人の出入りにも駅長などが送迎するようになってやむなく二等車にした。民政長官時代、家族のものの東京での食膳には、魚肉はめつたにのぼらぬ倹約ぶりで、長女愛子は麻布新網町から麹町平河町の学習院女学部への一時間あまりの徒歩通学、つぎのあたった着物なので、体操の時間などに羽織をぬがされると、それがわかって閉口した。長男一蔵も、つぎのあたった制服で学習院に通学した。家庭内ではそのように倹約を守り、主人の公の生活には思いきり金をつかわせた。資産もパトロンもない後藤が、金銭に淡泊であると好評だった裏に、そういう妻の苦心がひめられていたのである。 しかも単なるケチケチ女房族ではなく寸暇をおしんで勉強した。愛読書はアービングの『スケッチ・ブック』(黒崎調べ:1819~1820年に発表した34編の短編を含む小説集である)、ゴールドスミスの『ウエークフィルドの牧師』(黒崎調べ:オリヴァー・ゴールドスミス(Oliver Goldsmith, 1730年11月10日? - 1774年4月4日)は、英国の詩人、小説家、劇作家。アイルランド生まれ)で、むろん原書で読んだのである。後藤にスカウトされて台湾に赴任した新渡戸稲造(のち一高、東京女子大校長)は、「(熱体しょく物に関する)その質問が単に好奇心のみでなく、まじめにして、かつ実用の考えより出ることが明らかであって、わが輩は彼女の頭脳の細やかなることに注意をひかれた」と書いている。 夫のために、台北停車場に黒山のような出迎え人が出てひしめく光景を車中から指さして、 「あれをご覧なさい。あの大ぜいのお出迎えの方々は、お父様をお出迎えにいらっしゃったと思ったら大まちがいですよ。あれは台湾民政長官をお出迎えにいらっしゃったのですよ」 と子供たちにさとしたというエピソードに、めい流夫人の座に酔い痴れることのなかった彼女の叡智が光っている。主人が役所や会社の部長や課長になると、奥さんの方も鼻高天狗となり、まるで自分の召し使いでもあるかのように主人の部下を私用にこきつかう例は少なくないようだが、それはおのれの浅はかさを露呈すると同時に、主人の公的生活に汚点をつけ、足を引っぱることとなる。後藤新平の多彩な活躍と成功は、公私の別をわきまえた夫人和子の内助の功の賜物にほかならなかったのである。 長女愛子は鶴見佑輔にとつぎ、鶴見夫妻には俊輔、和子が生まれた。
参考:鶴見 和子:1918*2006 昭和後期-平成時代の社会学者。鶴見 祐輔の長女。昭和21年丸山 真男,弟の鶴見 俊輔と「思想の科学」を創刊。44年上智大教授。比較常民学の研究をすすめ,柳田国男,南方熊楠(みなかた-くまぐす)らの民俗学を分析,継承。内発的発展論をとなえた。平成18年7月31日死去。88歳。東京出身。津田英学塾(現津田塾大)卒。著作に「社会変動と個人」「漂泊と定住と―柳田 国男の社会変動論」「南方 熊楠―地球志向の比較学,歌集に「回生」。インターネットによる。
|
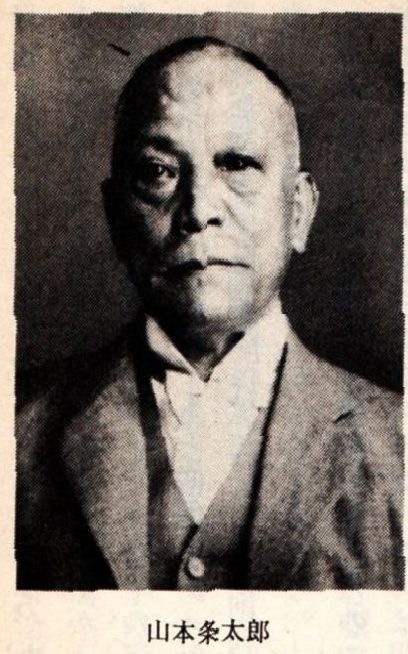
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.24~28 山本丈太郎 吉田茂とは従兄弟同士 明治四年の廃藩置県によって武士階級は崩壊し、流離落剝(らくはく)の境遇におちたものも少なくなかったが、越前藩で十石二人扶持(ぶち)だった山本条悦(のち武と改名)は旧藩主松平家の家従に採用されて、明治五年家族とともに越前をたった。このとき両親につれられて、北国街道から近江路、東海道の十数日におよぶ長旅をしたのが六歳の長男条太郎である。 主人は松平茂昭、その父が横井小楠を招聘した慶永(春嶽)である。小楠をむかえた松平父子の態度は「御父子様ともにつぎの間まで御送迎、かつ痛足のことも御承知にて、しとねを敷き候よう仰せつけられ、ひとへに御断りに及び候へども、御聞入れに相成り申さず、御自身様御立ちなされ候間、いたしかたなくその通りにいたし候」という小楠の手紙が語るように、まことに礼儀正しいものであったらしい。こういう一家の家従に選抜されたのであるから、山本条太郎の父親の人柄もしのばれるところである。すなわち、単に能筆で算数に巧みであったという以上に、折り目正しい誠実の士であったであろう。 上京した山本一家は、日本橋蛎殻町(にほんばしかきがらちょう)にあった松平家下屋敷の一隅に居を定めた。すると彼らよりもわずかにおくれて、横浜から同じ下屋敷の一隅にきた一家がある。岡倉 勘右衛門とその家族たちであった。 岡倉も旧越前藩士で、勘右衛門は計算の力を買われて紊戸(なんど)方をつとめたことがある。越前藩が小楠の指導によって貿易に力を入れ、開港直後の横浜に商店を出すことになったとき、経営をまかされたのが勘右衛門であった。 その店は「石川屋」と称し、越前国産の生糸、絹紬(つむぎ)を外国商館に売りこむ仕事で、開業十五年目に廃藩置県ちなり、閉店のやむなきにいたったもである。勘右衛門は店をたたむと上京し、旧藩主の下屋敷の一隅で旅館をはじめることとなった。 ところが岡倉家には覚三、由三郎という兄弟がいた。兄が十二歳で、弟が六歳、山本家の七歳になる条太郎と遊び友だちになるのは自然の勢いである。今日からは想像もつかないが、当時の蛎殻町には、草原や水たまりが多かった。覚三、条太郎、由三郎の小童たちが、そこでトンボとりや水遊びに熱中したことはいうまでもない。ところが、運命の手は間もなくこの竹馬の友を引きはなし、それぞれにまったく異質の人生コースを進ませるのである。 転変はまず丈太郎の身の上におきた。九歳のとき、母親を失ったのである。十五歳のとみ、九歳の条太郎、上京後生まれてようやく三歳になったばかりのさく――男手に三人の子供をかかえて途方にくれた山本 武は、姉妹を福井の祖母に、条太郎を亡妻の姉で宏(ひろし)家にとついでいたその子にあずけた。 その子の夫は宏仏海、もと僧侶であったが還俗して東京に出、出版界に活躍した人物である。『明教新誌』、『万朝報』はこのひとの創刊にかかり、また佐久間 貞一らと組んで秀英社(のち大日本印刷)を創立した。 明治九年、山本武は後妻をむかえたので子供たちはふたたび父のもとにかえり、条太郎はやがて神田の共立学校にはいった。これは明治四年佐野鼎が創立したもので、一時は生徒二百四めいを教える盛況をみたが、佐野の死とともに衰えていた。十一年、校長になって、学校の目的を大学予備門への入学養成に改めたのが高橋 是清(のち首相、蔵相)である。明治十四年度の修学者めい簿には、山本条太郎のほか、小笠原 長生、黒田 清輝、松方 幸次郎などの名前がある。 しかし、条太郎は間もなく肋膜炎で退学したため、これらの人びととの縁はうすかった。ただ、これからちょうど五十年たち、実業界から政界入りをした山本が政友会において高橋と親交を結んだのをみれば、不思議な運命の糸が結びつけていたというほかはないようである。肋膜炎がなおっても条太郎は復学せず、亡母の弟吉田 健三の紹介で、三井物産横浜支店の小僧にやとわれた。月手当一円五十銭。 吉田健三は、十六歳のとき大阪に出て医学を学び、二十歳のとき英国軍艦に便乗してヨーロッパにわたり、明治元年二十二歳で帰国すると、横浜の英一番館ことジャーディン・マジソン商会にやとわれた。その後貿易商として頭角をあらわし、五年には『東京日日新聞』の創刊に参画し、十五年には『絵入自由新聞』を創刊した。政界における交友関係も広く、板垣 退助、後藤 象二郎、林 有造、竹内 綱、大江卓などと親交をむすんだ。 両国の伊生(いぶ)村楼という料亭で政談演説会があったとき、その階上では箏曲(そうきょく)の会がひらかれていた。なやかな旋律にさそわれてのぞいてみると、そこに絶世の美女がいる。きいてみると、幕末の儒者佐藤 一斎の孫娘だということで、吉田はそのあと佐藤家をたずね、妻にむかえたい、と申し入れた。これが夫人士(こと)子であるが、子宝にめぐまれなかったので、友人竹内 綱の五男茂(このとき四歳)をあとつぎにもらいうけた。これがのちの総理大臣吉田茂になろうとは健三夫婦もよそうしなかったことであろうが、おなじように、従兄弟同志となった山本条太郎と吉田茂が昭和二年、前者が満鉄総裁、後者が奉天総領事として、おなじ満州の赤い夕日を見ることになったとは、まさに奇縁というほかはあるまい。 さて松平家下屋敷では竹馬の友であった岡倉兄弟のうち、兄の覚三は文部省の役人をへて東京美術学校の校長になった――というよりも、英文の『東洋の理想』『茶の本』の著者として不朽のなをのこす岡倉 天心となった。また弟の由三郎は、東京師範学校、立教大学の教授になった――というよりも、英語教育界の第一人者となったのである。 その後、岡倉兄弟と山本条太郎の友情が復活したかどうか、筆者は知らない。ただ、三人ともに見上げるような一流の人材となったということよりも、「英語」がそれぞれの生活の中心となっていた事実に心ひかれるのである。 三井物産社員山本丈太郎が、いかにして英語をマスターするにいたったかは、かって拙著『日本さらりーまん外史』で物語ったことがある。正規の学校こそ出なかったが、山本もまた英語の達人となった。実業家、政治家としての多忙な日常においても常に英米の新刊書をもとめ、熱読した。たとえば堀切 善兵衛は「シーグフリート氏が『英国の危機』を書いて非常に好評を博したときだ。私はこの本を読みたいと思ったがまだ手にはいらなかった。ところがある日山本氏を訪ねて雑談し、帰りがけに本棚を見わたすとそこにその本が……」(『山本 条太郎追懐禄』)と書いている。岡倉兄弟、山本たちは、竹馬の友であると同時に英語の友でもあったといえよう。 2019.07.05 |
 小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.29~33
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.29~33
岡 倉天心 牛鍋囲んで消遥からと文学論 日本橋蛎殻町松平家下屋敷の一隅をかりてはじめた岡倉勘右衛門の宿屋は、福井県から上京するものがほとんど例外なしに泊まってくれ、開店早々から繁盛したらしいが、勘右衛門をもっともよろこばせたのは、せがれのできのよさであったろう。長男は早死にしたが、次男覚三(天心)は抜群の秀才で、十二歳で官立外国語学校にはいり、十四歳で官立東京開成学校にうつった。これはその二年目に東京大学と改められたから、覚三は十六歳の若さで東大生となったわけである。同学年には井上哲次郎(のち文学博士)、牧野伸顕(のち内大臣、伯爵)などがいた。 文学部の覚三は、政治学、理財学などのほか、中村正直(敬宇と号す)の漢文教室、ウイリアム・ホートンの英文学教室に親しんだ。中村は、明治十年四十六歳で文学部嘱託となったが、もとは幕府の儒官。慶應二年から明治元年まで英国に留学し、四年にスマイルス『セルフ・ヘルプ』の訳を『西国立志編』と題して出版し、ベストセラーとなった。もと幕府の騎兵頭だった益田孝が、井上馨にスカウㇳされて造幣頭として大阪にいったとき泊まった宿屋のむこ養子が馬越恭平(のち大日本麦酒社長)で、「馬越はタスキをかけておひつをあらっておった。細君はビンズケで髪をてかてかにして、襟にちり紙を当てておった。だんだん馬越の様子を見るとなかなか見こみのある男だから、これを読みたまえというて中村敬宇の西国立志編をやった。馬越はそれで大いに志を立てた」(『益田孝翁伝』)と益田は語っている。やがて馬越は宿屋をとびだして益田の部下となり、三井物産横浜支店長となるのである。 ところで岡倉覚三の方は、とくに英米文学を耽読した。ある日、同級生の福富孝季と小石川の牛肉屋の二階にあがり、牛鍋をつつきながら外国文学論を戦わしていると、隣の席に二人の学生がやってきて、これまた外国文学論をやりはじめる。そこでいっしょになって、大いに語ろうではないかということになった。 二人とも東大生だ。一人は江戸深川の高田早苗、もう一人は美濃大田出身の坪内友蔵(のちしょう遥と号す)である。大学では、高田は岡倉より二年後輩で、坪内はさらに一年おくれて卒業するが、年齢は逆で、その会合を明治十一年と推定すれば、坪内は二十歳、高田十九歳、岡倉十七歳ということになる。しかし岡倉がもっとも早熟で、翌年十八歳で妻帯、十九歳で文学士、月給四十五円の文部省御用掛となるのである。 「だれの作品がいちばん好きか?」ということになり、 「ウオルター・スコツㇳの『アイヴァンホー』が好きですね」 と高田が言った。福富は、アレキサンドル・デューマの『モンテ・クリスト伯』をあげ、岡倉はヴィクトール・ユーゴ―の『レ・ゼラブル』をあげる。このとき、のちのしょう遥坪内青年がひとり沈黙していたのはふにおちかねるが、京口元吉によれば、「当時、しょう遥先生にはまだチンプンカンプンで、目を丸くしてきき入るばかり。それを勧めて、しょう遥先生にスコツㇳの『湖上の佳人』を読み合わせ、『春窓綺話』と題して、共訳出版するに至らしめて、後年の大英文学者に仕立てあげたのも、わが高田早苗先生」(『高田早苗伝』)だったわけである。もっとも門外漢だったしょう遥ただ一人プロの英文学者になったところに、人生の面白さがあるようだ。 四人のうち、学問にもっとも縁が深かったのは高田といえる。彼の父は定職をもたず、家計窮迫、給費生としてようやく学業をつづけていたけれども、もとは江戸屈指の豪家であった。紀州和歌山の藩主徳川吉宗が八代将軍となったとき、随従して江戸にうつり住んだ御用商人高田茂右衛門友清がその先祖。 友清は府内に二十六ヵ所もの宅地をもつ富豪となったが、自費をもって下総(千葉県)手賀沼で二万石、武藏大宮(埼玉県)の見沼で一万石の新田を開発し、さらに利根川の水を荒川へおとす運河工事をして、産を失った。幕府ではその功績を認め、二千石の旗本にしようとしたのを友清はことわり、利根川・荒川間の通商営業を許してもらって、代々通船問屋として巨富を貯えた。六代六郎左衛門與清は学究で博覧強記、蔵書十万冊に達し、平田篤胤、伴信友とならんで江戸時代後期における国学の三大家と仰がれた。その血は曽孫の早苗にもっとも濃く伝わったようである。 高田家は、天保改革による不況期から左前となり、とくに早苗の父小太郎清常は十九歳で幕末の動乱期に当主となり、やがてそのすべてを失った。早苗には二人の兄があったが、いずれも他家に養子となり、三男坊の早苗が九代当主となっている。「種々の事情で、と先生はボカしているが、想像をたくましくすることが許されるならば、おそらくは傾く家計を補うための口減らしのためであったのではなかろうか」(京口・前掲書)。 しかし、家は窮迫しても、早苗の才能は光った。小室樵山という書家について書道と漢籍の素読をならっていた十二歳のとき、樵山がその日の米塩にも事欠きながら藩閥をきらって就職口をことわったのを知ると、数日前にならったばかりの「蒙求」の一節――「父母ノイマストキハ、官ヲエラバズシテ仕フ」を引用して、中風の老父を貧苦に悩ませておいてせっかくのご用をことわるとは心得ませぬ、とやりこめて、先生の目を白黒させたことがあったという。 このすぐれた友人によって文学的開眼をしたしょう遥は、やがて『当世書生気質』を書いたとき、主人公小山田燦爾のモデルに高田をつかつた。スラリとした長身の、気品のある美男子だった早苗はどこでも大もてにもてたので、モデルとしてはうってつけであったわけだ。 ところで、岡倉と高田の縁も、牛鍋の文学論議だけではおわらない。明治三十一年岡倉天心が日本美術院を創立したとき、開院式にのぞんで祝辞をのべた文部省高等学務局長が高田だったのである。ただその友情は、大正二年九月、五十二歳の天心の死によって断たれる。高田は七十九歳まで長命し、この間、法学博士、貴衆両院議院、文部大臣、早稲田大学総長となった。またしょう遥も七十七年の生涯があった。福富孝季は、外相大隈重信の条約改正に反対した頭山満、杉浦重剛などのメンバーの一人に名前が出てくるが、斎藤隆三は「いくばくならず福富は自決して亡くなった」(『岡倉天心』)と書いている。天心は二首の弔詩を献じたという。 人物1、福富孝季:(1857~1891) 明治時代の教育者。安政4年11月生まれ。明治19年イギリスに留学し,心理学,教育学をおさめる。帰国後は高等師範教授となった。臨淵の号で劇評家としても知られ,著作に『私撰浄瑠璃年代記』などがある。明治24年4月9日死去。35歳。土佐(高知県)出身。東京大学卒。 人物2、高田早苗:(1860~1938)政治家,教育家。江戸深川出身。小山田与清の孫。東大卒。号は半峰。大隈重信に協力し立憲改進党,東京専門学校(のちの早大)の創設に参画。1890年以降衆議院に当選6回。大隈の腹心,改進党・進歩党の幹部として活躍。第2次大隈内閣の文相を勤め,教育調査会総裁として1918年公布の大学令立案に努めた。1923年早大総長。 人物3、坪内しょう遥:(1859~1936)小説家,劇作家,評論家。本みょう勇蔵のちに雄蔵。美濃国生れ。東大政治学科卒。1885年『小説神髄』を書き『当世書生気質』を発表して写実による近代文学の方向を示した。二葉亭四迷をはじめ,しょう遥の近代文学論は広く大きな影響を与えたが,自身は1889年の『細君』を最後に小説の筆を折った。1890年,東京専門学校(早稲田大学の前身)に文学科を設け,翌年《早稲田文学》を創刊し,後進の育成に努めた。また同誌を発表の場として森鴎外との間に没理想論争を展開した。また演劇革新を志して戯曲『桐一葉』『牧の方』『沓手鳥(ほととぎす)孤城落月』等を発表,『新曲浦島』などの舞踊劇をも創作した。演劇研究所を作って俳優の養成に努め,早稲田大学演劇博物館を建設し,『シェークスピア全集』の翻訳を完成するなど,日本近代文学,演劇の発展史上に大きな功績を残した。 2019.05.24

アジアは一つだ。ヒマラヤ山脈は、二つの強力な文明――孔子の共同主義のシナ文明と、ヴェーダの個人主義のインド文明とを、ただこれを強調せんがために分つ。しかしながら、この雪の障壁をもってしても、あの窮極と普遍とに対する広い愛の拡がりを、ただの一時もさえぎることはできないのだ。この愛こそは、全アジア民族共通の相続財産ともいうべき思想なのだ。この愛こそは、彼らに、世界のすべての大宗教を生み出すことを得させたものなのだ。(東洋の理想)
12月26日生まれた美術評論家。東京美術学校長をつとめ、日本美術院を設立するなど、明治美術の父と称せられる。主著『日本の目覚め』『茶の本』 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.213
小林司著『出会いについて』精神科医のノートから (NHKブックス)P.20 から 『茶の本』や『東洋の理想』を書いた岡倉天心(一八六二~一九一三)の父親は、越前福井藩の藩士であり、横浜で藩が経営していた貿易店の支配人をしていた関係上、岡倉天心は、七歳頃からアメリカ人に英語を習っていたために英会話がひじょうにうまかった。 そして、東京大学の文学部の学生だったときに、米国人アーネスト・フェノロサ(一八五三~一九〇六)に通訳として雇われたのである。 フェノロサは、その前の年、一八七八年に東京大学の教員として日本に着任し、日本の絵や彫刻を見て、日本の古美術を研究したいと考えていたのである。そして、フェノロサといっしょに画家や画商に会って通訳をしたり、ほうぼうを訪ねて絵や彫刻を見ているうちに天心自身も、古美術に強く魅力を感じるようになった。西洋美術にはない、独特の美がある日本美術の伝統を活かして、新しい日本の美術を生み出したい、と天心は考えた。その後、ヨーロッパで西洋美術を研究して、日本の美術がすぐれているという確信うをもち、一八八九年にはフェノロサと協力して東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)を開設させた。そして、岡倉天心は、校長兼日本美術史の教授になったのである。のち、一九〇四年にはアメリカに招かれて、ボストン美術館の東洋部長になっている。 天心とフェノロサとの出会いもまた、初めて出会った瞬間に火花を散らしたというようなものではなくて、むしろ知合ってから長い期間にしだいに感化された、と考えるべきであろう。
司馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版 雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。<ますらおぶり><たおやめぶり>忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 第六章 日本にきた外国人 フェノロサ、チェンバレン、サンソム P.136~ 司馬 サトーは後年イギリスに帰りますが、日本のことを全然言いたがらなかったそうですな。懐しそうにも語らないし、読む本は、ひじょうに古典的なオーソドックスなヨーロッパのものばかり読んでいたといいます。これは萩原延壽さんのイギリスで得た成果で、私が聞いた萩原さんの解釈を受け渡しするので、少しずつ間違いがあると思いますけれども……。 ※萩原延壽は東京都台東区浅草出身。旧制三高(現・京都大学総合人間学部)卒業後、練馬区立開進第一中学校教員を務める。東京大学法学部政治学科へ進学。卒業後、同大学院で岡義武に師事。修了後、国立国会図書館調査立法考査局政治部外務課に勤務。米国ペンシルベニア大学・英国オックスフォード大学に留学。英国留学中、丸山眞男の知遇を得る。帰国後、著述活動に専念し、『中央公論』など論壇で活躍。各大学からの教員職を断り、在野の歴史家として生涯を通した。 英国滞在中、英国国立公文書館に保管されていた英国外交官アーネスト・サトウの1861年から1926年までの45冊の日記帳を調べ上げ、サトウの幕末期から明治初期までの活動を描いた大作『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』(全14巻)を、朝日新聞に休載をはさみつつ約14年間連載、完結刊行を見届け2001年(平成13年)10月24日逝去、享年75。なお同年には、執筆生活を支え続けた夫人に先立たれており、後を追うように生涯を終えた。 ※アーネスト・サトウ著『一外交官の見た明治維新上・下』坂田精一訳(岩波文庫)昭和四七年二月二十日 第一四刷発行 それはなぜかということなんですが、とにかくサトーは一大構想があって日本を動かしたわけでしょう。自分では、明治維新は自分の作品だと思っています。じじつ彼が西郷に匹敵するほどの志士として存在したことは確かです。けれども、明治維新政府の大官たちがもうサトーを必要としなくなっいたということですね。それに腹が立っている。これはぼくはひじょうにわかる。おれになぜいろいろありがとうございましたと言わないのか、ということですよ。それはあるでしょう。サトーのほうが日本にたいする思い入れは強いのですからね。明治維新政府の大官たちには、サトーの果たした役割をよく知らない人が多かったと思う。それがやっぱり悲しかったことと、それから中国公使になったときもう一度やってやろうと思ったのですね。日本で成功したことをもう一度義和団の乱のあとの中国でやってやろうと思ったが、向うは国が大きくて、とてもややこしく、北京公使としての仕事があまり思わしくいっていなかったというがあるようです。 それからもう一つは、サトーには天才のもっている病理学的な性質があったでしょうね。これは私自身のかってな見方ですけれども、分裂症的な性格でもって、ひとつ熱中したら凝り性で、うんと凝って、凝ったあとはケロッと忘れているタイプの人があるでしょう。あれもあっいたかもしれない。 キーン しかし、そういう傾向は、日本に来たあらゆる外人の場合にも認められると思います。サトーだけのことじゃなかったようです。たとえばフェノロサ(明治十一年来日)もそうだったし、チェンバレン(明治六年来日)もそうでした。そしてだいたい理由は同じじゃないかと思います。ともに日本で相当大きな仕事をやって、日本人に尊敬されました。しかし日本に弟子をつくって、弟子がだんだん自分のやったこともできるようになった。もう日本ではその人は必要でなくなるわけです。 フェノロサの場合は明らかにそうだったですね。彼がはじめて日本に来たときは、日本は国宝が売られている時代だった。いま京都に住んでいる私の親しい友人の祖父にあたる人が、明治五年に宣教師として京都に来たとき知恩院のお坊さんに、「大きな鐘があるがいりませんか。売りたい」と言われたそうです。それがあとで国宝になった有めいな知恩院の鐘です。その人は「結構なものですけれども、うちとしては大きすぎます」とおことわりしたそうですが……(笑い)。あの時代は、だれも日本の古きよきもののよさを認めていなかった。なんでも新しい西洋的なものを喜んだ時代でした。フェノロサは、なるべく日本人に自分たちのだいじな過去の美術のよさを教えたかった。だから弟子もつくったのでしょう。一番の弟子はなんといっても岡倉天心です。フェノロサは何かの用事でアメリカへ帰ったのち、二度めに日本にやって来ましたが、もうだれも彼を雇わなかった。日本人で同じような仕事をする人がすでにいましたから、わざわざお雇い外人さんに高いお金を出す必要はなかったのです。 2010.06.08、2019.06.01追加。 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中央文庫)昭和五十八年八月十日 P.34~38 元田 永孚 明治天皇に論語を講ずる 大久保利通は安場保和をよんで、「天子さまの侍講には、いったいだれがよかろうか?」と相談したことがある。 明治四年の四月から五月のはじめのことというから、このとき大久保は四十二歳で大蔵卿、安場は三十七歳で大蔵大丞であった。 明治天皇が慶應四年七月に即位されたとき、十七歳の若さであり、三条、岩倉、西郷、木戸、大久保たちが、いわゆる「聖徳玉成」に心を砕いた。 彼らの念じたことは、その環境を「清浄、剛健、質直」にすることで、聡明にしてかつ骨の太い一個の快男児をつくり上げようとしたようである。そのため、吉井友実、島義勇、高島鞆之助、米田虎雄、村田新八、山岡鉄舟など、およそ「口舌の徒」とは正反対の剛直の士宮内省に入れた。また、その年八月には、女官ことごとくを免職にし、その中より適宜ピックアップするという荒療治を行い、吉井のごときは「これまで女官の奉書など諸大名へ出せし数百年来の女権、唯一日に打消し、愉快限りなし」と日記に書きつけている。けれども、もっとも重要視されたのは、君側にあって書を講じ、原理原則を説く侍講の選定に他ならなかった。 安場は、「熊本の学者元田永孚がよろしいと思います」と答えた。 元田は、横井 小楠のつくった青年読書グループのひとりである。このとき二十代の若者だった彼は、かって小楠がそうであったように、世間的にはいっこう有めいでなく、ステイタス、肩書もないまま、すでに五十四歳になっていた。 大久保は、安場の進言をとり入れ、三条実美につたえて元田起用にふみきったのであるが、冷徹無比の大久保のことだ。ことは簡単に運ばれたかに見えて、じつはベストがつくされていたはずである。単に役所の上司が部下の意見を採用したという簡便安易な処置ではなく、まず意見をきく相手の選択に周到な熟慮がなされたであろうし、それを採択するところに安場への評価、信任があったと思われる。言い方をかえれば、ここに安場の人となりがあらわれている。 六月四日、元田永孚ははじめて進講した。テキストは、前任者のあとをうけて、「論語」の公冶長(こうやちょう)篇参考からである。 本篇は、孔子による人物評価論といってもよい。はじめに出てくる公冶長という弟子は、かつて罪人として獄につながれていた。しかるに孔子は、 「公冶長は、娘を嫁にやってもよい人間だ。罪人として入獄したことがあったが、無実の罪であったのだ」 といって、自分の娘をとつがせたのである。 つぎに登場する南容という弟子については、 「国家が正しい政治を行っているときは放っておかれることなく、国家が正しい政治を行っていないときも刑罰にかかることはないだろう」 といって、自分の兄の娘をとつがせたのである。 元田は、以上の文章の字句を解説したあと、自分の意見をつけ加えた。 「聖人(孔子)が人物を判断し、才を選ぶやり方は、公平正大、世間の評判などにこだわらず、かならずその中核を見ぬいております。まことに人物を判断し、才を選ぶやり方の模範とすべきであります。およそ人君の道は、任用賢を得るより大なるはありません。またその徳は、聡明人を知ることを第一とすべきであります。今日、天下の人物を判断されます場合、孔子が公冶長や南容にしたようにされますならば、官に棄才なく、野に遺賢なく、天下の民は心からよろこんで従うことでありましょう。そもそも人君の聡明さというものは生得のもので、学んでどうなるものでもないようでありますが、いやしくも智をたのんで自己流に用いるときは、その知るところは狭小で、かならず過ぶ足のあやまりをさけることはできません。このゆえに昔の聖帝明王はかならず自ら進んで聖人を師とし、その原理原則によって動かれたものであります。上代、応神天皇が王仁を師とせられ、論語を学ばれたように、日本でもシナでもその実例は少なくありません。今日の盛代にあってまたこの論語を学ばれ、聖人の模範をとらせたまうことは、真に祖宗の遺訓を御継述されるの美挙で、臣は心からよろこびにたえません……」 帰宅した元田は、つぎのように日記にしるした。「嗚呼この日何の日ぞや。明治辛未六月四日なり。余二十二歳にして、長岡温良、横井先生、下津大人、荻子とともに程朱の学を講じて、聖人の道を信じ、道徳経世この実学にありと自ら任じて疑わざりしも、藩俗の忌嫉するところとなり、世に否塞することほとんど三十年。ここに至りてはじめて天廷に坐し、天顔に咫尺してこの学を講じ、親しく天聴に達することを得たり。何の慶幸かこれに過ぎんや……」 これについて徳富蘇峰は、「五十四歳にしてはじめてその処を得た。元田の運命もまた不思議であるが、彼が感激禁ずる能はなかったのも、決して偶然ではない」(『近世日本国民史』第八十三巻)と書いているが、筆者はとくに、「人物の判断」をテーマとする[公冶長篇」がその第一講の内容となっためぐりあわせにに、運命の不思議さを思わずにはいられません。 元田自身、世俗的地位、肩書、評判などとは関係ない「原理原則」=肉眼・心眼の世界で選ばれた人間であり、そのことを深く肝に銘じていたがゆえに、この進講のことばには全人生をかけた必死の気持がこもっていたであろう。それは学識や頭のよさから生まれる単なる弁舌とは別ものの、人間の魂の叫びともいうべきものにちがいなかった。 そして、このような良師を得て、魂のバイブレーションという貴重な人間的体験を積み重ねれたらこそ、明治天王先天の稟質はいよいよみがかれ、不世出の大統治者たるべき原型が鋳られていったのであろうと思う。 さて、以上の物語で<帝国日本>の亡霊を思い出されることは筆者の真意ではない。このときから今日まで、約百年の歳月をかけて、われわれ日本人はいったいどれほど「人を見る明>を加えたか、世評にたよらぬ原理原則の世界を築きあげたか、ということである。もっと卑近な例えをいえば、はたして今日、要職に「棄才」なく、日の当らぬ場所に「遺賢」なき人事が、役所や会社で実行されているだろうか、ということである。 ※参考:宮崎市定『論語の新研究』(岩波書店)一九八四年八月三十二日 第一一刷発行 P.204 93 訓:子、公冶長を謂う。妻(め)あわすべきなり。縲絏(るいせつ)の中に在りと雖も其の罪に非ざるなり、と。その子を以て之に妻あわす。子、南容を謂う。邦に道あれば廃せられず、邦に道なきも、刑戮より免れる、と。其の兄の子を以て之に妻あわせたり。 93 新:孔子が公冶長について言った。彼は婿にしていい青年だ。いま未決監に収容されているが、無実の罪で嫌疑を受けただけだ、と。自分の娘と結婚させた。孔子が南容について言った。世の中が治まっている時には重く用いられれ、世の中が亂れた時でも、刑罰にひっかからない人物だ、と。自分の兄の娘と結婚させた。 「平成」の時代が「令和の時代へと改元された。憲法発布記念日2019年5月3日、写した。 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.39~43 團 琢磨 先見の明「鉱山学」に志す 明治四年十一月、条約改正準備交渉のために岩倉大使一行がアメリカ丸でたったとき、公卿、大みょうの子弟、男女学生など五十四人が同行した。この中に旧黒田藩主の嗣子長知(ながとも)がはいっていた。長知には側近の家来を随行させようと重臣たちが考えたとき、父長溥(ながひろ)はその案を一しゅうした。「従来君子の関係のあった者を同行させれば、依然旧習にとらわれ、長知のためにもよろしくない。むしろ平素何の関係もなく、かつ前途有為の秀才を、学友という資格で、随行ではなく、同行させよ。長知は単に外国を見て知見を広めれば十分、少年には他日一技一能を会得させるべきである」 と、まことに新時代の黎明にふさわしい一大見識であったが、このことばによってどれほど大きな可能性が日本の歴史に加えられるか、そこまで正確な予測はできなかったであろう。その言葉によって選ばれた「前途有為の秀才」とは、金子堅太郎、團琢磨の二人であった。金子はハーバード大学で法律学を修め、伊藤博文の秘書官として大日本帝国憲法の起草に関与し、やがて伯爵・枢密顧問官となる。團はマサチューセッツ・インスティチュ―ㇳ・オブ・テクノロジーで鉱山学を修め、三井鉱山の近代的開発に成功して三井財閥のドル箱となし、やがて男爵・日本工業倶楽部理事長として日本財界をリードする。まさに「一技一能を会得」して歴史的存在となったのである。 ※この時、留学した人たちの中に津田 梅子がいた。 しかし、留学生に選ばれたとき、金子は十九歳(数え年)、團は十四歳で、本人たちにも自分の能力はわかっていなかった。ましてや金子の妹を團がもらい、二人が義兄弟になろうとは夢にも思わなかったであろう。 團は馬廻三百石の神屋宅之丞の四男、十三歳のとき元勘定奉行六百石取り團家に養子にいった。ところが秘蔵むすこで実家でもかわいがられていたから、なにか気に入らぬことがあるとすぐ家に帰りたい、という。そこで團家でも宝物のように大事にした。團はつけ物がきらいで、朝から魚がないと食事をしない。養母はいろいろと料理をととのえて、これがいいの、あれがいいのとご機嫌をとる。髪を梳(す)いてやり、着物をきせてやり、ふろにも入れてやる。金子がたずねると、琢磨少年は縮緬(ちりめん)の座ぶとにすわり、家来どもにかしずかれてごちそうを食べているところであった。藩の留学生として上京していたのが廃藩置県で学資を打ち切られ、司法省判事の学僕になって苦学していた金子青年は、團の若殿様ぶりにおどろいてしまった。 黒田長知、金子、團はおなじ船室に入れられ、長知は二段ベッドの上段、金子は下段、團はソファに寝たが、船が揺れて團はころげ落ち、あとは洋服、くつのまま板の間に毛布をかぶって寝た。「三日ほど何も食わない。これまでわがまま者といわれておった人が、西洋の船にのってだれもかすずくものがない。女中もおらなければ家来もおらぬ。わずかに一人ぼっちでしうからよほど苦しんだでしょう。それからだんだん日をふるにしたがって、ようやくはい出て飯を食うようになり洋服も着て歩くようになったが、こまったことには人につかえた経験がない。自分自身のことすら皆人にしてもらって、着物をきせてもらい、髪も梳いてもらたった若殿様であるから、旧君のお供をしておっても、旧君にかしずくということを知らない。僕は貧乏書生で苦労をしておったから、何もかも、くつみがきから着物の世話まで皆私がする。それで私も不平であるが仕方がない。しかるに團は、僕にはそんなことはできぬというのです。二十五日間船の中で何もかも皆私にやらせて團はへい気でいる……」(『日本工業倶楽部二十五年史』下巻)と、この旅から六十一年たって、團が血盟団員のテロに倒れ、工業倶楽部で追悼晩餐会があった席上で金子は回想している。ノホホンとしている團少年を横目でにらみ、ブースカいいながらくつをみがいている堅太郎青年の姿が目に浮ぶようである。 彼らはボストンで勉強することとなり、長知とは別の下宿屋に一室を借りた。夜はダブルベッドにいっしょに寝る。金子團の無精にに閉口した。ワイシャツ、ハンカチ、くつ下などよごれものをそのまま押し入れにほうりこんでせんたくにも出さない。金子は注意した。 「ここには家来もいなければ女中もいない。自分のものは自分で始末せい。僕もやるから貴様もやれ」 「そういうものか……」 團はいやいやながら整理にかかった。 大きな机を共同でつかったが、金子は自分の前を掃除し、團はしまい。そしてきたなくなると、何もかも金子の方に押しやる。金子は真ん中に板を立て、境界をつくった。 「これからこっちは僕が整理する。そっちの方は君が勝手にしろ。これからこっちへはいるべからず」 二人は、旧岩国藩主の弟吉川重吉(十二歳)とその従者田中泰吉(十四歳)とともにグラマースクール(小学校)にはいったが、いずれも首席になった。ところが二年目に團がやめるといいだした。 「やめてどうする?」 「君はどうする?」 「僕はこれからハイスクールへいって、それから法科大学へいって法律をやる」 「僕は工科大学へいく」 「どうして?」 「僕は鉱山学士になる。鉱山堀りになる」 「それはよせ。鉱山堀りは武士のすべきことではない。貴様の父は筑前藩の財政の枢機をにぎる政治家だ。お前も政治学やれ」 「僕は政治はきらいだ。工科大学にはいって、鉱山のことを研究する」 「どいうわけで貴様はそんな考えをおこした?」 「調べてみると、日本は鉱物が多い。僕はアメリカで鉱山の学問をして帰って、金銀を掘ったり、石炭を掘って大いに地下の財宝を世にあらわす仕事をしたいと思う」 金子はびっくりしたが、やがてそのおどろきは尊敬にかわる。ちょうどこの話をしていたころ、故国では政府が三池鉱山を買収していた。それまでは民有で、柳河藩家老小野隆基はじめ、いろいろの人物が鉱区をもち、それがあちこちでたぬき堀りをやっていて紛争がたえず、政府でもこまって、総計四千九十一円六十五銭二厘で買い上げたのである。團はむろんそういうことは知らなかったが、その立志の年と三池鉱山官有の年が一致したのは不思議な偶然といえよう。やがて工学士になって明治十一年に帰国した團に福岡県令渡辺清は三池鉱山の調査をたのんだが、ちょうど流行病蔓延(まんえん)のときだったため團は一週間で逃げ帰ったので、渡辺県令は激怒したという。このときまでは團と三池とは縁がなかった。 ※プロフィル:福岡藩士の家に生れ,明治4四(1871) 年十三歳のとき,岩倉具視ら特命全権大使の欧米視察団に同行。そのままアメリカに在留し,マサチューセッツ工科大学鉱山学科を卒業,一八七八年帰国した。工部省鉱山局に勤務し,官営三池炭鉱に赴任,八十八年三池が三井に払下げられるとともに三井に入り,同炭鉱の近代化に努めた。 一九一四年三井合めい理事長となり,三井財閥を工業中心の事業体に発展させた。さらに日本工業倶楽部理事長,日本経済連盟の会長など,昭和初期における財界の最高指導者として活躍したが,三井本館前で血盟団員の凶弾に倒れた。 2019.07.15 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.44~48 上田 安三郎 三池炭販売に奔走 ボストンには、金子 堅太郎、團 琢磨などのほかにも日本の若ものたちが留学していた。この町はマサチューセッツ湾にのぞむ風光明媚な米国最古の都市で、独立運動の発祥地である。二人が住み《はじめた一八七二年(明治五年)は南北戦争がおわって七年目、新興気分がもりあがり、やがて電灯がともった。物質文明の進歩に目をまるくしながら、暇を見つけてあつまっていたそのグループは、森明善、菊地武夫、平岡熙、伊沢修二、小村寿太郎、栗野慎一郎、上田安三郎、斎藤脩一郎、三岡丈夫、朝比奈一、土屋静であったことを、筆者は鎌倉の上田寿四郎氏(安三郎四男)にお借りした資料で知ることができた。 森は鉄道技師、菊地は日本最初の法学博士で中央大学初代学長、平岡は鉄道技師――というよりも野球を輸入し、日本最初のチームをつくったスポーツ界のパイオニア、伊沢は電話発明中のグラハム・ベルの助手をして発音を学び、視話法によるドモリのきょう正、音楽体操教育、聾唖教育などに貢献し小村は外相、ポーツマス条約日本全権、侯爵、栗野は駐仏大使、枢密顧問官、子爵になるなど、いずれも日本の人材であった(他の四氏は上詳)が、この中では上田と團が不思議な縁によって結ばれていた。ただボストン時代の二人はその因縁を夢にも知らない。 上田は團よりも三歳年長、柳川藩士池田安道の三男として長崎の柳川藩邸で生まれ、三歳のとき上田家に養子にいったが、十二歳のとき養家が倒産したため、諸所を転々とし、十五歳のときロバート・アルウイン(初代ハワイ公使、のち三井物産顧問)につかわれた。 アルウインはこの少年の英才を見ぬき、海外留学希望を実現させた。彼がボストンについたのは明治六年十月、十九歳のときである。このあとコ―マルス商業大学に学び、九年三月からヨーロッパを経由して八月に横浜についたから、團よりは一年おそく米国にいき、二年早く帰国したことになる。ともあれ上田がヨーロッパにたったとき、二人の交友はいちおう終わったかに見えた。 上田は、旧主アルウインの紹介で、創立直後の三井物産にはいり、翌十年一月本採用、月給八円のサラリーマンとなった。七月、上海にわたり、十一月正式に上海支店詰、十三年三月二十六歳の若さで上海支店支配人に任ぜられ、二十五年四月に帰国するまで、一貫して三池炭の販路開拓をテーマとしたのである。 政府が三池炭鉱を買収して工部省所管としたのは六年四月である。それまでは大牟田から小船で瀬戸内海の塩浜(製塩所)に売るだけで、現炭は燃えにくいというので、わざわざ砕いて粉炭にして売っていた。この石炭を輸出して国庫収入をふやそうと考えたのが工部伊藤博文である。彼は九年六月、上海総領事品川忠道に、上海市場における石炭需要量等の調査を命じ、上層塊炭、盤下塊炭、コークスをそれぞれ百斤あて現物見本として送った。これが上海送炭のはじめで、実際の輸出は、口銭(手数料)および益金半額下付金をやることとし三井物産にあたらせることにした。 三池鉱山分局年報によると、石炭一トンの経費と代価は、八年七月から九年六月までが九十一銭三厘と一円四十銭九厘、九年七月か十年六月までが一円三十八銭八厘と一円三十銭となっている。(経費が代価をオーバーしているのはこの期だけで、おそらく西南戦争の影響であろう)。 三池炭は、大牟田の海が浅いため、長崎県島原半島の口ノ津から貨物船につみ、上海では広東路の事務所の二階を借りている上田ら四人のものが一軒一軒売りこみをして歩いた。当時、アメリカン、アンスラサイト、ニュカスル、カーティフ、キーランなど外国炭が出回っており、その二割安にしたとはいえ、臭気と油気の多い三池炭でくいこむのは容易なことではなかった。しかし、そういう苦労はあったにせよ社員としての身分は安定し、益田孝社長の信任を得て、慰労金だけでも上海時代に計六千二百七十五円ももらっている。当時の金の値打ちからいえば、今日の数千万円にあたりはしないか。 これに反して團 琢磨は安定しなかった。帰国早々福岡県知事にたのまれて調査した三池鉱山を一週間で逃げだしてからは、専門で飯が食えず、大阪専門学校助教、大阪中学校訓導、東京大学助教授をへて工部省御用掛となり、三池に赴任するまで六年間も空費している。しかも三池では、高等官から判任官への降格をも忍んで鉱山開発に打ちこんでいたのに、明治二十一年欧米出張中に三井に払い下げられ、團は旅行先においてその職場を失ったのである。 義兄金子 堅太郎はその身のふり方を安場 保和に相談した。安場は、かつてアメリカ丸で渡米したとき、租税権頭として同船した因縁があり、そして今は金子、團の故郷である福岡県の県知事であった。安場は、福岡県技師として採用することを約束した。これをきいた益田が金子の門をたたき、 「とんでもないことをしてくださった。三井組は炭鉱に四百五十万円も出しましたが、この中には團技師の値打ちもはいっています」 と文句をつけて、強引に安場との話を打ちこわし、三井にいれた話はすでに『続日本さらりーまん外史』でのべたことがある。 このころの益田と上田の往復書簡を見てみると、「とにかく十二年の夢もさめて一朝の煙と化し遺憾やる方なきは申すまでもこれなく候へどもいかんとも致し方なくこれなく候。而して今更どのやうな愚痴を申してもその詮なし……>(二十一年四月)とか、<さて三池を買入候ことにいたり候へば、これをすすめたる当会社はその責大に、商売の具合も明年より改革しようほど奮発をいたしたく……」(二十一年八月)とか、益田の憂慮、決意などはうかがえるけれども團の名前は出てこず、また上田がその受け入れのためどれほど益田に働きかけたかは明らかでない。だが、それぞれちがった形で<石炭>をテーマとしていたことにより、ボストン時代の旧交を暖めただけでなく、同じ釜の飯を食べる仲間となって双方ともに感慨無量ではなかったかと推測される。ただ、運命は復活したその友情の永続を許さなかった。『中外商業新聞』(『日本経済新聞』の前身)三十四年七月十三日号は、第三ページの大半をさいて貿易界のパイオニアに追悼記事をささげた。大正七年六月の新聞は、上田の第十七回追悼会があったことを報じ、上田の信任する部下だった小室三吉の追悼談をのせている。この年、團は六十一歳、三井合名会社の理事長に就任し、三井コンツェルンの統率者となっている。 2019.07.16 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.49~53 頭山 満気骨の知事安場と意気投合 安場保和が元老院議官から福岡県知事になったのは、内務大臣山縣有朋から、 「福岡というところは、玄洋社一派の本拠で、なかなか治めるのに骨が折れる。一つぜひ出かてもらいたい」 と懇願されたためである。 筑前福岡の人びとは、その風土的条件もあって、古くから万里の波濤をおそれずに外国と交易し、豪邁・進取的でかつ権力に叩頭せぬ反骨・在野の精神をつちかってきた。明治十四年二月、箱田六輔、進藤喜平太、平岡浩太郎、頭山満などの士族を中心に組織された<玄洋社>も、その精神の所産といえる。彼等はくどくどと規則をつくることをせず、「憲則」としてわずかにつぎの三条のみを掲げた。 第一条 皇室を啓載すべし 第二条 本国を敬重すべし 第三条 人民の権利を固守すべし このいわゆる「法三章」のもと、「金もいらぬ。ただ男らしい死所を得たい」と腕を撫している浪人たちは、いつ反体制のテロリストに変るかもしれぬ無気味な存在で、政府としても無関心でおられなかった。ただいわゆる能力型の人間ではどうにもならぬ相手である。しかるに安場という人は、横井小楠の薫陶をうけて識見があり、とくに「清廉潔白、かつ斗酒なお辞せず」、いかにも明治維新の豪傑らしい風格をそなえている。みょう利や威圧では動かぬ浪人と対決できるのは、そういう風格しかなく、それを官界に求めるとすれば安場しかない、と山県は考えたのである。侍講の相談をした大久保利通の場合と合わせ、いかに安場の評価が高かったかを物語る例である。 このとき安場は四十二歳。福岡に着任してじっと玄洋社の親玉たちを観察した。箱田六輔は、「剛直で正直、親切、つねに表面立って忠実、献身的に働いた」(頭山の批評)人物でことに寝酒一升の大酒家だったから、安場にとって絶好の酒友となったであろうが、すでに前年三十九歳で他界していた。進藤喜平太は三十六歳、謹厳寡黙、「九州侍所別当」のアダ名があり、古武士的風格で徳望をあつめている。平岡浩太郎は三十五歳、のちに代議士になり、炭鉱資本家としても羽ぶりをきかす才子で西南戦争のときは福岡で挙兵し、そのやめ懲役一年をくらったという経歴もある。頭山満は三十一歳、西南戦争の前年に「大久保暗殺、政府転覆の陰謀」を企てた疑いで一年投獄されていた。一番の年少で、昼アンドンのようでありながら、もっとも衆望がある。玄洋社外の人間も頭山をもっとも買っていて、たとえば侠客大野仁平は、「平岡が進む勢いは敵の千軍万馬をものともせず、一挙にして蹴散らすような武者ぶりだが、さてあとをふり返ってみると、大将ひとりいい気持になっているばかりで、あとに従うものはいくらもない。これに反し、頭山の進むのはノソリノソリとまるで牛の歩むようで、いかにも間がぬけているが、あとからあとから軍勢がつづいてゆく」と批評していた。 安場は頭山に最大の関心をもった。さらに、酒は一滴ものまない、非常に腕力が強いのに蚊一匹殺せぬようなやさしさがある、親孝行者だ、ということがわかった。もっとも感心したのは人助けのやり方である。平岡は、人に金をやる場合、百円を二百円と輪をかけて他人に吹聴し、とくに第三者の見ているところで出した。ところが頭山は助けるにもかくれてやる。もらった本人kら聞いた第三者がそのことをたずねても、「ハアそうか」とㇳボけている。「頭山一顧すれば幾百の子弟響きのごとくに来り応じ、平岡大声呼号するも一人の身を挺して来る者なし」という批評もそこから生まれていた。安場は会う前ゕら好きになっていたが、頭山も安場と会ったあと、 「きょうは役人という者にはじめて会ってみたが、存外話せるぞ」 と語った。しかもなお、官権ぎらいの彼は、安場とつき合うことでではかなり思案をこらしたらしい。 「その位にあってその事を行わざる者は尸位素餐(才徳なくして官位におり、いたずらに禄をはむ)の徒なり。その位にあらざるもその事を行い、殊に自家の米塩を憂えずして、君国の経綸に志すものは浪人なり。国士なり。すなわち浪人は政府または人民より頼まるるにあらず、また一紙半銭の報酬を得るにあらずして自ら好んで天下の事にあたる>のをその本領と考えている。県知事などと仲よくすべきでない、と考え、炎天下の道百二十キロをはだしで歩いて熊本に行き、かねて尊敬する前田案内子父子の意見を聞いた。前田下学は、「何も官吏と有志家との別を問うことはあるまい。安場は決して俗吏でなく、国家のためにという志士はだの男だ。二人の意見さえ投合すればほかのことはどうでもよかろう」 と言い、その父案内子も、 「その通りじゃ。安場はわしと剣術友だちでいっしょに宮本の二刀流を学んだことがある。普通の役人とちがい、気骨のある男じゃよ」 と、太鼓判を押してくれた。 こうして二人の親交がはじまる。安場は、上京してくるとすぐ頭山に知らせ、頭山もすぐやってきて話をきく、話がおわると、 「早く日傭取り(県庁づとめをひやかしたもの)に出かけるがええ」 といって、安場が登庁したあと、座敷の寝ころんだまま、安場夫人に土産の菓子をもってこさせ、ムシャムシャ平らげて帰って行く。そういうつき合いとなった。 このころ炭鉱をやれ、とすすめたのが杉山茂丸である。頭山はギロリと杉山をにらみ、 「おれに山師になれとや?」 と眉をひそめた。玄洋社の資金源として必要だといわれてようやく承知し、海軍の予備炭鉱となっていた鉱区の払い下げを願い出た。そのとき最大の便宜をはかってやったのが安場である。これからしばらく、「炭鉱所有者」という一時期が浪人頭山の生涯にあらわれる。夕張炭鉱の一鉱区を四万円で買収したこともあったが、これはのちに井上角五郎の仲介で北海道炭鉱鉄道会社に売却した。頭山が百五十万円で売ろう、といい、井上が、少しまけてほしい、とたのむと、<ケチなことをいうな。しいてまけろというなら、半分まけてやる> と、いきなり七十五万円にしてやった。しかもその金は、井上のコミッションに十五万円、借金ばらい(すべてばい額)、同志にわけてやるなどで、わずか一月で消えてしまった。しょせん、<炭鉱資本家>になれない本質的浪人だったのである。それにしても、安場は娘婿の件では本山彦一とは縁がなく、後藤新平と縁があり、炭鉱の件では團琢磨と縁がなく、頭山満と縁があった。こういう有縁無縁にも不可思議な人生の姿がのぞいている――。 2019.05.30 |
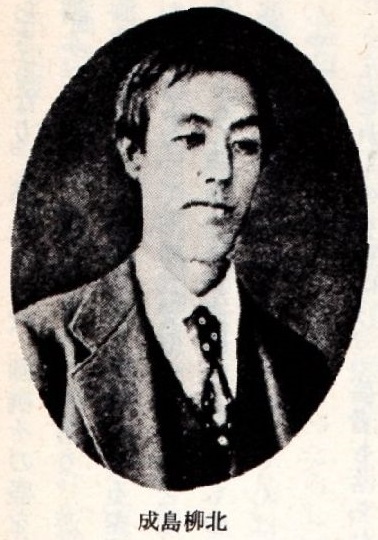
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.54~58 成島 柳北 『柳橋新誌』で藩閥政府を批判 東京の花柳界は、維新のドサクサで不況にあえいだが、明治二年二月「東京府芸者司仲間一同」の名で新政府にさしだした建白書を見ると、「昨春伏見事件以来、家業衰替、難渋ツカマッリ候処、天運循環、御政体一新ニ相成リ、ハカラズモ当春以来は積鬱モ一洗シテ大イニ繁昌……」と、 建白書の要旨は、サービス改善の宣伝である。芸者を三等級にわけ、最上等は高貴の方の秘書的役割をはたさせ、「第二等ハ万石以上へ差シイダシ、第三等は中大夫以下諸家ノ議員、公議人、公用人等、ソノ外富豪、遊冶ノ集合」にさしだしてサービスさせる。「万一私ドモ微忠ト、彼女ドモノ尽力トヲ御賞美ニテ、大ニ月給等仰セツケラレ候ハバ、イササカモ御辞退申シ上ゲズ候。イヨイヨモッテ冥加至極、有難キ仕合」に存じます、というのである。ついこの間まで交際場のスターは遊女が占めていたが、いまや「芸者」がその王座を奪おうとする転形期の荒さと虫のヨサも感じられる。 こういう新興景気を横目に見て、面白くなかったのが旧幕臣である。たとえてみれば、社用で羽ぶりをきかせていた重役さんが、会社倒産で遊べなくなり、総評幹部たちの豪遊のうわさに痛憤やる方なし、というところであろう。成島 柳北の『柳橋新誌』第二編は、こういう背景のもとに明治四年刊行された。 柳北は、「隠士生れで人に短なる所少からず。色を好むこと甚し。酒を嗜むことまた甚し。百般の遊戯好まざる所なく……」と自伝(『濹上隠士伝』)に書いているし、末広鉄腸も「柳北は元来緑酒紅灯の遊びを好み、毎夜必ず酒楼に上り、飲めば必ず妓を聘するをもって常とす……」(『新聞経歴談』)と書いている。いわゆる「自他共に認める」プレーボーイで、早くも二十三歳のとき『柳橋新誌』初編を出していたのであるから、その第二編を出すのは当然の成り行きだったとしても、その間の十二年には、体制上、身分上の激動があり、花街のエピソードをつづりながらも、行間おのずと旧幕臣としての感慨、新秩序への余憤がもれている。 「柳橋往日の妓は、姿色無くんば即ち技芸あり、技芸無くんば則ち才識あり。三者一無くして、婢女と致を同じうするもの甚だ希なり。今は則ちしからず。姿なく芸なく才なし、徒らにその面を粉にしその身を錦にす」 「ああ、柳橋声妓の風一たび壊れ、その醜や言ふべからざるなり。然れば則ちその盛を往日に加ふると雖も、しかもその実、大いに衰ふる者と謂ふべけんか。柳も客もまた罪あり。遊戯その道にあるを知らず。風流の何物たるを弁ぜず、沈湎耽溺して、その妓たらざるを問うはず、濫転を喜んでもっておのれを恋すとなす。巧衒を信じてもっておのれを愛するものとなすもの甚だ多し。たまたま淑良にして軽浮ならざるものあり。よく柳橋往時の遺風を存するものあらば、則ち皆ののしるに痴頑にして事を解せざるの老婆となす。その客にしてかくの如くんば、則ちいずくんぞよく妓輩の日に淫風に趨るをとどめ得んや」 ……これらの文章には、「芸者も落ちたが、その元凶は藩閥政府の田舎漢ではないか」という痛烈な批判が出ている。 エピソードを一つ。ある日柳北が飲んでいると、隣室で客を待つ芸者二人の対話が聞えた。A子は「おごりなさいよ」といっている。そのわけは、B子のだんなが奏任官一等となり、月給も三百をこえた以上、ぜいたくは思いのままではないか、というわけだ。ところがB子は「とんでもない」という。そのわけは、男の昇進は阿諛の結果なのだ。大変なケチで、船頭や箱屋にチップをやったことがなく、ともすれば他人にシリをぬぐわせる。しかもいばりくさって、いつもひとを見下している。ご本人がお祝いはしても、わたしは絶対に祝わない、というわけだ。さらにそのB子は自分の人生哲学を語った。柳北の表現によると、「真の情は情を要す、仮の情は利を要す。もし利を要すれば則ちよろしく勅任以上を選ぶべし。しからざれば知事か華族か。かの奏任官は、貴と雖もいまだもって吾曹の腹を飽かすに足らずと」というリアリズムである。 それから約百年、いまや墨水は汚濁し、役人の王座は経営者にとって代わられたともいわれるが、「濫転を喜んでもっておのれを恋すとなし巧衒を信じてもっておのれを愛するものとなす>」蛮風が浄化せられたかどうか――。 ところで柳北という人物は、二十歳で奥儒者となり、将軍家定に講義をしたというのであるから、単なるプレーボーイではない。二十九歳のとき、千石取りの騎兵頭並、三十一歳のとき、二千石取りの騎兵奉行にばってきされた。このころ、のちに三井物産初代社長となる益田孝と交渉をもつ。柳北よりも十一歳年下の益田は、英語を学ぶため、横浜の横浜駐留軍、通称「赤隊」に加わって訓練をうけ、幕府がフランスの士官を招いて歩、騎、砲三兵の訓練をはじめたとき、騎兵を志願して尉官待遇の差図役になっていた。 益田たちは、柳北に反感をもったらしい。柳北は顔の細長いひとで、馬に乗ると「馬は丸顔」と内田百閒が喜びそうな恰好であった。それでいたずら心をかき立てられたのかどうか「よく馬から落としてやった」(『自叙伝益田孝翁伝』)と彼は語っている。 柳北はさらに会計副総裁に栄進したが、鳥羽伏見の戦いのあと、職禄を返上し、隅田川のほとりに隠棲した。ときに三十二歳。「濹上隠士」の自称はここにはじまる。その「松菊荘」(別名「海裳園」)という別荘はなかなか完成しなかったが、大工左官がなまけたわけでなく、柳北の資金ぐりが渋滞したためである。 「二、三月遊ぶのをやめたらすぐ建築費はできるでしょう」 と来客がいうと、柳北は答えた。 「遊ばないで部屋をつくるより、むしろ部屋を売って遊ぶ方がいいね」 プレーボーイもここまで徹してこそ『柳橋新誌』を書くにふさわしい資格をもてたのだというべきであろう。 維新後、柳北はジャーナリズムに身を投じた。幕臣としては、柳河春三、栗本鋤雲についで第三番目の新聞記者である。第四番目が福地桜痴であった。柳北、桜痴、ともに雅号に植物をとり放蕩児であった点は共通しているが、言論人の立場は正反対であった。体制べったりの桜痴に反し、反政府的であった柳北鍛治屋橋監獄で四ヵ月の刑をくらってる。 松菊荘は借金の抵当となり、抵当流れで三井銀行のものとなっていたが、鐘紡支配人となった三十三歳の和田豊治が六千五百円で手にいれた。明治二十六年のことで、すでに柳北はその九年前、四十八歳で長逝していたのでる。 2019.07.17 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.59~64 山路 愛山 終生変わらぬ蘇峰との友情 幕府天文方という役職があった。役高百俵の微禄ではあるが、農耕その他行事の基本となった暦編さんの役目は重大であった。その天文方に山路 弥左衛門がなったとき、部下の天文方手附に田口 樫郎という人物がいた。弥左衛門の曾孫は弥吉といい、愛山と号した。樫郎のせがれは卯吉といい、鼎軒と号した。つまり明治期の代表的評論家二人が、天文方の系譜から生まれたといことになる。 田口鼎軒(たぐちていけん)についてはすでに『日本さらりーまん外史』でのべたことがある。山路愛山は田口よりも九歳年下で、五歳おとき幕府の瓦解にあい、祖父母とともに無禄移住で静岡にうつった。父一郎は榎本武揚に加わって家を出奔、母けい子はすでに二年前に死亡していた。静岡時代のことはくわしくわからないが、生活苦をなめたようで、月給二円の代用教員の県庁雇員だったという。 森 鴎外に『渋江抽斉』という傑作があるが、この抽斉の嗣子保は、明治十九年に私立静岡英語学校教頭となり、弥吉はこの保に英語を習った。このころ愛鷹(あしたか)山にちなんで「如山」と「愛山」という二つの号をつくり、如山はすぐやめて、以後は愛山で通した。 明治二十年二月、二十四歳のとき、徳富 蘇峰が創刊した『国民之友』を読んで感動し、蘇峰に手紙を出した。横井小楠の甥にあたる蘇峰はこのとき二十五歳、前年に一家をひきて上京、「予はただ自己の運命を信ずる以外には、何等の確定した考えもなかった」(『蘇峰自伝』)と書いているように、背水の陣をしいて『国民之友』創刊にふみきったときである。愛山の心をこめた手紙は何よりもうれしかったであろう。 二人の終生変わらぬ情はこの手紙に端を発したが、同時にそれは愛山の人生を決定したともいえる。愛山の業績は何よりも史論において傑出しているが、その仕事の基礎固め、第一期の作品は、明治二十五年(二十九歳)から三十年(三十四歳)まで、蘇峰の創刊した『国民新聞』の記者時代に生まれたからである。一本の手紙の縁というものの、それが単なる手紙ではなかったこと、読後感を書いた愛山も真剣であり、うけとった蘇峰もその雑誌にいのちを張っていたこと、この両者の心の世界、波動の一致を見落としてはならないだろう。 評論家愛山については諸家の論評があるが、 彼は酒を飲まず、子供をしからない人であった。説教めいたことをいうのは年に一度。元旦のときでだけである。このときは祖先の画像を床の間に掲げ、子供たちをその前に正座させて、このおじいさんはどんな人で、どういうことをした人だといろいろ説いて聞かせ、昔の武士は卑怯の振る舞いをするのをいちばんの恥とした、お前たちも、どんなことがあっても卑怯の振る舞いだけはするな、と教訓したのである。反面、「立身出世」を要求しなかった。子供たちには弥生、金次郎、しの、久三郎、平四郎という平易なな前をつけた。そこで 「本読みの先生が、どうしてむすこさんたちに、平凡なやさしいな前ばかりつけられるのですか?」 とたずねられた。愛山は答えた。 「何にでもむくようにだ。一ぜん飯屋のおやじがあまりえらそうなな前では、商売にもさわろうではないか」 後年、この話を母からきいた平四郎は「わたしは心を安んじた」と書いている。便所の壁に世界地図がはりつけてあった。痔のわるい愛山は、それをゆっくりながめていたらしいが、平四郎はそれに落書をした。すると、地図の横に、「平ちゃん、いたずらするなかれ」と書いただけで、しからなかった。 読んでいなければ、書いていた。ぬるい風呂が好きで、それがわくまでゆっくりとつかっている。そのとき必ず本を手にしていた。ブッブッ声を出して読んでいた。これが唯一最高の楽しみだったらしい。暑いときはもろはだぬぎで、水をガブガブのみ声を出して調子をつけながら書いていた。非常な達筆で、ひとには読めない字であった。(筑摩書房刊、明治文学全集三五巻『山路愛山集』の扉にその筆跡がある。ご覧になれば「その記するところ、蠅頭(ようとう)の細字、他人弁別する能わず」という蘇峰の嘆きが誇張でないことをおわかりいただけるはず)。 貧乏なくせに、落剝(らくはく)した旧幕人を見ると助けてやる。そのつど勝手向きの苦しさを夫人が訴え、口論となった。 「武士は相見互身(あいみたがいみ)だ」 「今どき、武士だ武士だなんてかつお節の方がよっぽどいい」 と夫人も負けてはいない。愛山は、 「おたねェ(夫人のな)、おれは出てくるぞォ」 と大声でいい、ステッキで門や扉をガンガンたたきながらとびだすが、一時間もするケロリとした顔でもどってきて、 「おたね、おれがわるかった。勘弁しろよ」 といって書斎にはいり、またせっせと原稿書きに精出すのであった。 頼山陽を尊敬していたが、その山陽よりも一年だけ長生きして、五十四歳で永眠した。生涯が努力の連続であり、「君は孤立援なく、学閥なく、藩閥なく、生れて地に落ちし以来、自から養い、かつ家を養わざるを得ず。その硯田筆耕の際に半生を消磨したるも、もとより無理からぬ次第なり」という蘇峰の追悼文を読むと、売文を業とする筆者など身につまされて、思わずまぶたが熱くなる。 2019.07.17 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.64~68 五代 友厚 グラバーが決定したその運命 「江戸の仇を長崎で討つ」ということばがあるが、これからのべようとすることは方向も、内容も正反対である。すなわち、長崎での縁が東京において深められ、地理的・時間的移動がその人たちの人間的形成、テーマの成熟につながり、それが日本資本主義創成期の決定的要因になったという話である。その結縁の場所というのが、長崎ではトーマス・グラバー邸なのであった。
※写真説明:冠鍋山から長崎港を見る。 トーマス・グラバーはスコットランドのアバジーン生まれ、安政六年(1859年)秋二十一歳のとき長崎にきてグラバー商会をつくり、はじめは微々たる存在であったが、西南諸藩への武器艦船売り込みで巨富を築いた。また、これらの藩の俊秀たち――五代才助(友厚)、松方助左衛門(正義:孫春子、ライシャワー夫人)、桂小五郎(木戸孝允)、井上聞多(馨)、伊藤俊介(博文)、高杉晋作坂本竜馬などと接触をもち、その人生に大きな影響をあたえた。幕吏の監視をくぐってグラバー邸を訪問し、あるいは滞在した彼らが、お蝶夫人の酌に陶然となり、大いに談論風発する光景は想像するだにたのしいが、グラバーが遊女ツルを身うけして西小島に囲い、トムというむすこを生ませたあと、問題の邸すなわち南山手三番の高台に住まわせたのは明治十三年のことというから、これらの志士が往来した時期とは大分ズレている。 それはそれとして、これらの人材たちに門を開いたことは、単に貿易上の取り引きがなされたというにとどまらず、日本の歴史をつくる大事件であった。 たとえば、グラバーともっともウマが合ったといわれる五代 友厚の場合を見てみよう。彼は薩摩の町奉行のせがれで、十四歳のとき藩主に命じられた世界地図の模写を父に代わってやり上げ、一枚を藩主に献上し、一枚を書斎の壁にかけて朝夕ながめ、さらに直径三尺の地球儀までつくったというのであるから、その国際感覚、問題意識は抜群であったといえる。 十六歳のとき、薩摩が世界の大勢におくれをとらぬための方策として、 一、汽船をもつこと 二、紡績業をおこすこと 三、海外留学生を派遣すること の「三策」を進言した。これら三策の実現に決定的役割をはたすのがグラバーである。 文久三年(一八六三年)、イギリス艦隊が鹿児島を砲撃したとき、五代は松本弘安(寺島宗則)とともに天祐丸にのっていて捕虜となり、横浜で釈放されたあとは刺客の追及をのがれるため、変めいして各地を転々とした。このときグラバーと知りあったというから、このときグラバーは二十五歳、五代は二十七さいだったことになる。 グラバー低にかくまれた五代は、日々もたらされる国際情報で知見を広め、深めるとともに、藩主に対する建言書の執筆に熱中した。その内容は割愛するが、「いま見ても、驚くべき内外知識であり、詳細な数字の裏づけがあった。薩摩藩の富国強兵策を、体系的に総合的に、具体的に論じた大論文であり、そして藩主や藩重役が食指をそそられそうな、"長期経済計画書"であった」(久保統一著『鹿児島百年』幕末篇)。 この中にはとくに海外留学生派遣のことがあり、藩当局はこれをいれて、元治元年末から準備にかかった。やがて選抜された十七めいの秀才たちは慶応元年一月中旬鹿児島を出発し、三月下旬、串木野から英国船オーストラリア号にのりこんだ。この船を世話したのがグラバーであり、五月下旬ロンドン停車場に一行を出迎えたのがグラバーの兄であった。この密航船にリーダーとして五代がのりこんでいたことはいうまでもない。彼は若者たちの修学の手配などをすませたあと、マンチェスター、バーミンガムなどの工業都市をたずね、マニュファクチュアから工場制生産へと転化したイギリス資本主義の実力に目を見はった。藩のために一万ポンドの木綿紡績機械と二千八百丁の小銃を買い入れ、さらにベルギーのブリュッセルにおいて、コント・デ・モンブランという人物と会社設立の契約を結んだ これは薩摩・ベルギー合弁の会社で、製糖、製糸、綿糸紡績、修船、製蝋その他の機械を製作し、造船局、小銃製作局、大砲製作局、米搗機関、鋸機関、ブランデー製局、鉄製局、金山、銅山、錫山、石炭山、鉛山などを開くほか、大阪を中心に動物館、川堀機関、蒸気船、蒸気車、電信などを開設しようという雄大なプランであった。彼がのちに明治新政府の役人をやめて「大阪」の開発に打ちこみ、東の渋沢と並んでわが国財界の二大リーダーとされるライフワークの青写真はここにあるようである。 帰国した五代は、グラバー、小松帯刀らと共同出資という形で、長崎に小菅修船場をつくった。これは四年後の明治元年に完成、二年新政府は十二万ドルで買い上げ、長崎製鉄所とともに工部省の所管とし、十七年三菱会社に貸与、二十年同社に払い下げ、その後三菱造船会社長崎造船所となるのである。 グラバーの世話で留学した若者の中からは、フランス公使鮫島尚信、オランダ公使中村博愛、文部大臣森有礼(初代文部大臣)、枢密顧問官吉田清成、元老院議官町田久成、海軍中将市来和彦、米国のブドウ王磯永彦助ンあどの人材が輩出した。mあたこれにつづいて慶應二年に派遣された米国留学生からは、初代日銀総裁吉原重俊、貴族議員湯地定幹(その妹静子は乃木希典夫人)、海軍大臣・枢密顧問官仁礼景範、東京馬車鉄道社長・東京株式取引所所長長谷元道之などが出た。 この他グラバーが佐賀藩と合弁で経営した高島炭鉱につながる人間の結びつきも見のがせない。これは六年に官有、七年に後藤象二郎に払い下げ、十四年、福沢諭吉の口ぞえで岩崎弥太郎の所有となり、二十一年坑夫虐待事件で現地を調査した警保局長清浦奎吾、朝野新聞記者犬養毅の二人は、のちにそろって内閣総理大臣になったのである。グラバー自身は明治二、三大阪の生糸相場で失敗してからは落ち目となり、ツルに生ませたトムは倉場富三郎として長崎漁業会社をつくったが、終戦直後自殺した。 2019.07.19 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.69~73 井上 馨 長崎で新式銃を購入 洋行体験をもつ井上馨、伊藤博文の英語力がどの程度であったかはわからないが、文久三年五月、二十九歳の井上は「ナビゲーション」という一語しかしらず、三十三歳の伊藤は一語もしらなかったことだけははっきりしている。ただ井上が、これを「航海」ではなく「海軍」とあやまっておぼえたばかりに、とんでもない災難にあうことになる。 彼らが野村弥吉(のち子爵井上勝)、遠藤謹助、山尾庸三たちとロンドンに密航するため、英国船の石炭庫にかくれて横浜を出たのはその年五月十二日であった。途中、上海に上陸し、ジャーディン・マディソン商会支店長の世話をうけたが、支店長のしゃべることがさっぱりわからない。野村は函館で少しかじったことがあったので、 「どうやらオレたちの渡航目的をきいとるようだぞ」 と井上にいった。そこで井上が、 「ナビゲーション!」 と、とっておきの英語を発したのである。支店長はそこで当然ながら「航海術を学ぶこと」が目的だと判断し、ロンドンに帰る帆前船の船長に実地訓練をたのみ、井上、伊藤組は三〇〇トンのペガサス号に、あとのものは五〇〇トンのホワイトアッダー号にのりこむことになった。そして出航するやいなや、帆綱ひっぱり、ポンプ作業、甲板掃除と、きびしくきたえられはじめたのである。他の水夫たちも彼らをけいべつしてさかんに雑用にこきつかった。客員のつもりだった彼らはこの酷使に大憤慨したが、英語を知らぬため、抗弁の方法がない。 ことに哀れだったのが下痢症にかかった伊藤で、船内に水夫用便所はなく、船側の横木にまたがって用をたすのであるが、インド洋をすぎ、マダガスカルから喜望峰に向ったところ大防風雨となり、三〇〇トンの小船は木の葉のようにほんろうされた。伊藤はその嵐の中でも便意をおさえることはできず、井上はやむなく伊藤をなわでしばってそのはじを柱につけ、用便の間、波にさらわれないように守ってやらねばならなかった。まさに「ナビゲーション」という英語をつかったための悲劇にちがいなかったのである。 攘夷さわぎ、外国船砲撃のことを英国新聞で知って、井上、伊藤は半年で帰国したが、それでも英語力はかなりついていたらしい。これから一年半して、彼らはグラバー邸を訪ね、ケーベル銃購入契約を結んだのであった。この武器購入には、歴史的に二つの意義があった。第一は、購入を薩摩藩名義にしたことで、これは坂本竜馬などの奔走により、小松帯刀(こまつ-たてわき)が了承したもの。蛤御門の変(1864年:元治1)以来、犬猿の中となった西南二雄藩が歩み寄り、「雪どけ」、提携の実を示すステップとなったからである。第二に、この新式武装によって長州軍は面目一新し、征討にきた幕軍を鎧袖(がいしゅ)一触、幕府倒壊の重大なモメントとなったからである。 井上、伊藤の名コンビが、そういう先のことまで読んでいたかどうか疑わしいけれども、ともかく当時としてはきわめて至難のワザとされていた外国人相手の契約締結に成功したのであるから、得意満面、さっそく丸山遊郭にしけこんで、 「あのときはナビゲーションしかしらないで失敗したのう」 「お主が糞(くそ)をたれるときの、あの泣き面は忘れられんぞ」 などと往時を回想し、大いに娼妓(しょうぎ)たちを笑わせたであろう、と推測される。 その井上が、二度目にロンドンを訪れたのは明治九年のことであった。彼はすでに四十二歳になっていたが、変化は歳月だけではなかった。三年前に大蔵大輔をやめ、前年に元老院議官となり、政府部内における財政通として自他ともに認める存在。洋行の目的も「財政経済研究のため」となって、夫人ならびに従者の随行も許可せられるという大名旅行であった。 第二の変化は、井上が得意になって英語をふりまわしたことで、それは旅においてばかりでなく、たとえば芳川顕正(よしかわ あきまさ)への手紙にも、 「我国もただ祈る、ポルチシアンを止め、インダスリーに心を用いざれば日々神経の高上を起すのみ。なおヒゲおやじ沢山雇入れ、ついに給金だけの利益を生ずるやいなや、人あえて知らざるなり。我思う、金を奪われなお外に害を残す多からん。其故はカクテルの相違とコストムの遠来を思考すべし」 とあり、木戸孝允への手紙には 「福沢書生三人まかりあり候ところ、いたって行跡等もよく勉強まかりあり候。人物もよろしくかつ従来日本の時は、フルイばかりをロジカルに唱え候ものに候ところ、近来は大いに改悟候て、いたつてコンソルペ―チープとあいなり、民選議院などもなかなか行われがたきこともあいわかり、ブラックチースにこれなくては、国の第一たるウエルスを増殖する等できずという説を起し、毎サチューデーごとに生の居処へ集合候て、ポリチカルエコノミーの書を輪講つかまつり候て、それよりその書を日本の実事いあてはめ論じ、大なる益と存じ奉候くらいに候故、真の学問を志す人、また実に憂国心ある人は、追々コンソルペ―チープに趣き、中々あい楽しみおり候。いよいよもって急進することはよろしからずよう相考え候>とある。 わずかに「ナビゲーション」一語だけしか知らなかった井上が、手紙の行間いたるところに英単語をバラまいている状況は、壮観というよりもあまりにキザという感じがする。とりわけこのころいよいよ「コンソルペ―チープ」化しつつあった木戸孝允など、 「目ざわりだ」 と舌打ちして読んだのではなかったか。 この「福沢書生三人」のうち、一人は中川彦次郎、も一人は小泉信三の父小泉信吉であった。二人は七年暮れにロンドンにつき、文部省留学生菊地大麓(のち東大総長、文相、男爵)の世話する下宿におちついて、『英国商業史』の著者レオン・レビーの事務所に通い、法律、経済、財政、保険、倉庫、貿易などの個人教授をうけていたのである。 最後の一人は、馬場辰猪(ばば たつい)ではあるまいかと萩原延寿氏にたずねてみたが、馬場の「日記」にはそのことに関する記述がないから、馬場ではあるまいということであった。十年五月には小幡篤次郎がロンドンについているので、あるいはこちらかもわからない。 それはそれとして、四十の坂をこした井上がなお若者のような情熱をもって経済学に必死にとりくみ、ことに慶應義塾出身の三秀才と輪読、論争を試み、ついには太政官採用方を本国に稟請(りんせい)するなど、若い人材を引き立ててやろうと努めていた姿勢、心情には好感がもてる。 今日、外国に行く政治家、高官と日本の若者との間に、これだけの接触、こころのつながりあるだろうか。 2019.07.20
井上 馨 (1,835~1,915年)
長州藩出身、明治の政財界に重きをなした元老。 海外知識を得ようとして、伊藤俊輔(博文)ら五人で横浜から英国へ渡ったのが文久三年(一八六三)。四国聯合艦隊の下関砲撃事件を知って俊輔とともに急ぎ帰り、講和のために努力し、のち討幕運動に奔走した。 明治十八年(一八八五)、組閣にあたって首班を決める選考会議で、血気な井上は、「これからの総理は、赤電報(外国電報)が読めるものでなくてはだめじゃ」と、きめつけた。留学の体験があって、英語にも通じている伊藤を盛り立て、一座のなりゆきを決定的にした。井上は終始、伊藤の盟友としてその政治活動を支えた存在だった。 明治四年、新政府の大蔵太輔をつとめて、地租改正、秩禄処分を進めた。だが予算問題で司法卿江藤新平と衝突し、三等出仕渋沢栄一を誘って辞職した。 明治十一年に政界にもどり、参議・工部卿を兼ね、翌年に外務卿となった。 外交については、かつて江華島事件で黒田全権とともに朝鮮に渡り、修好条規を結んだ実績があったが、彼の政治生命を決したケースは、第一次伊藤内閣の外相時代における条約改正問題であった。 井上は明治十九年五月から、各国公使と正式な談判をはじめた。いっぽう、徳川幕府が列強と不平等条約を結んでしまったのは、日本が世界にたちおくれたからだという見地から、伊藤とともに極端な欧化主義をとった。 官設の鹿鳴館を建てて国際的交歓の場とし、各国外交官を招いて盛んに夜会を開催したのもそのためである。これが世間の非難を浴びたばかりか、改正原案の裁判管轄条約にある外国人裁判官の採用という項目が日本の国辱と批判され、井上は努力のかいなく辞任に追い込まれた。 次の黒田内閣の農商務相、第二・第三次伊藤内閣ではそれぞれ内務相・大蔵相をつとめたが、もう彼の政治生命は終わっていた。後年は元老となり、後見者的役割りに本領を発揮した。覇気と情味を兼ねそなえた人物として信望が厚く、財界の発展のためにも尽力した。 政界をしりぞいてからは三菱財閥の顧問格として、日本の実業界を指導した。 参考:元老:日本近代史上,明治中期の内閣制度創設から昭和初期まで存在した政界の超憲法的重臣。天皇の下問に答えて内閣首班の推薦を行い,国家の内外の重要政務について政府あるいは天皇に意見を述べ,その決定に参与するなどの枢機を行なった。成文法で定められた役職ではなく,慣習上の制度としてつくられ,明治憲法下における支配体制維持のための機能を果した。元老と呼ばれれたのは伊藤博文,山県有朋,井上馨,黒田清隆,西郷従道,大山巌,松方正義,桂太郎らで,1940年最後の元老であった西園寺公望の死とともに消滅した。 2019.09.07 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.74~78 大隈重信 人間くささが呼ぶ魅力 大隈 重信は、明治元年三十一歳のとき外国事務局判事から外国官副知事(外務次官)となり、翌年会計官副知事(大蔵次官)を兼任し、間もなく大蔵大輔(次官)兼民部大輔になり、三十三歳のとき参議(大臣)となった。大隈にかぎらず、明治初期の政府高官が若い連中だったことは周知のとおりだが、この中には、本人の実力というよりは藩閥のおかげでそのポストについたものもかなりいて、必ずしも実力はこれに平行しなかったようである。 ところが大隈の場合、なるほどもとは佐賀藩士であり、佐賀藩は海軍力でニラミをきかせて薩長に次ぐ有力藩であったということはあるけれども、そういう背景とは関係なく、その実力をもってその地位をしめた、といえそうである。 その実力をだれより早くも認めたのが井上 馨であった。彼らは維新前後、長崎府判事として親交を結び、井上は「彼(大隈)をこのまま西陲の地に跼蹐せしめることを公私のために惜しみ、木戸に彼を推薦」(『世外井上公』第一巻)した。けれども推薦よりモノをいったのは、キリスト教処分問題で英公使バークスと談判した大隈自身の実力にほかならない。 バークスは四十一歳。フランス公使ロッシュは徳川方にかけ、バークスは討幕派にかけた天下のバクチで勝った上に、列国に先んじて明治政府を承認した功労者である。反面、このことを恩にきせて、ことごとに先輩面、保護者面、指導者面で横車をおそうとするところがあり、三条、岩倉、木戸などの大物たちもみんな閉口していた曲者であった。ところが、フルベツキ宣教師についてすでにキリスト教と万国公法を学んでいた大隈はいささかもたじろがず、昼食ぬきで六時間もの大激論をやりぬいた。このとき通訳をつとめたシーボルトは、 「バークスも、きょうの談判には驚いていました。これまで日本において、大隈のような男と談判したことはない、といって、日本の外交官について少し尊敬の気持を加えたようです」と、三条、岩倉たちに語ったのである。そこで彼の評価が高まり、いちはやく外国官副知事(外務次官)に抜擢されたのも不思議ではなかった。 中央にでた大隈は、二年二月もと旗本三枝家の娘綾子と結婚し、四月には築地本願寺のそばに屋敷をもらって新居をかまえた。ここはもと戸田藩播磨守のもので敷地五千坪、派手好みの大隈にふさわしい豪邸で、四年に有楽町に転居するまで、約三年間を過ごすのである。 この築地時代は、外交官としてデビューした大隈が、横井小楠の愛弟子由利 公正の財政政策の批判者となり、やがて財政家として重きをなすにいたるテーマ交代、転進のときにあたる。反面、五代 友厚、井上 馨、伊藤 博文等々、多くの人材にかこまれていた人気の時期でもあった。 伊藤は、大隈邸の隣の小さな旗本屋敷を買い、その門内に井上が住み、何かといえば大隈のところにあつまったが、彼らばかりでなく、少なくとも三十人ぐらいの食客がいつもごろごろしていた。五代 友厚もその年譜を見れば「二年四月政府の召命により東上し、大隈 重信の邸に滞留し財政上のことを議す」とある。このほか、山縣 有朋、前田 正命、山口 尚芳、土居 通夫、古沢 滋、大江 卓、中井 弘など、ひとくせもふたくせもある豪傑たちがあつまっていた。シナの小説「水滸伝」には、悪徳官僚に反抗した豪傑たちが山東省の山塞にたてこもり、これを「梁山泊」と称したとあるが、中井はこれになぞらえて大隈邸を「築地梁山泊」と命名した。事実、木戸 孝允や大久保 利通などは、ここにあつまる連中の動向を大いに気に病んでいたという。 ともかく、これほどの人物を引きよせるだけの魅力があったことは大したことである。それは第一に主人の大隈が客好きであったからであろうが、それ以上に夫人綾子の客あしらいがうまかったからであるまいか。というわけは、客の多寡は、その主人のステイタス、世俗的利害関係とは必ずしも平行しないからである。たとえば幸田露伴の場合、幾美子夫人を四十四歳のとき失い、児玉八千子を後妻に迎えると、友人たちはだれもたずねてこなくなった。その弟子で、露伴が京都の三条大橋で、 「このギボシは、高山 彦九郎や牛丸若や弁慶の手アカがついているギボシだから、なめてみろ」といわれ、愚直にもなめてみるほど随従した漆山又四郎ですら、わずかひと月で顔を見せなくなった。それというのも、八千子が希代の悪妻だったからで、お客がきらいな人はイヤな女を女房にするにしかず、ということになろうが、築地梁山泊の場合、綾子夫人がよかったのであろう。 そのお客のうち、五代や井上の場合は、長崎グラバー邸につながる縁といえる。すなわち「江戸の仇を長崎で討つ」を、内容的にも方向の上でも逆にしての、人間関係の発展にほかならなかった。 大隈が渋沢栄一を起用したのもこの時代だ。渋沢は一度ことわりにいったが、大隈は、 「あんたは、八百万の神たちの神議にはかりたまえとという祝詞を知っているか?> 「今日の日本は幕府を倒して王政に復したのであるが、これだけではまだまだわれわれの任務をはたしたとはいえない。さらに進んで新しい日本を建設する重大な任務がある。いま新政府に参与しているものは、すなわち八百万の神たちである。あんたもその神様のひとりになりなさい」 と説得して、大蔵省入りを承諾させて話は『さらりーまん外史』でのべたことがある。この大隈的発想によれば、築地梁山泊の客人たちも、八百万の神々にちがいなかった。 ただ面白いのは、主人の大隈をはじめ、それぞれに多くの美点、欠点をそなえていた点で、その人間くささからいえば、彼らはむしろギリシャの神々に近い。そしてとくに興味をそそられるのは、これらの神々の後年における結びつき方で、たとえば渋沢は、自分を起用した大隈とは結びつかずに井上馨を親分に選び、井上・伊藤コンビは、明治十四年の政変において、大隈とは不倶戴天の敵となるのである。そういう成り行きを考えると、築地梁山泊とは、呉越同舟した神々たちの、はかない蜜月時代だったといえるようだ。
▼大隈 重信プロフィル:明治~大正時代の政治家。 天保(てんぽう)9年2月16日生まれ。肥前佐賀藩士大隈 信保の長男。長崎でフルベッキに英学をまなぶ。維新後、明治政府の徴士参与職,外国官副知事,大蔵卿,参議などを歴任。秩禄処分、地租改正などを推進した。明治十四年の政変で官職を辞し、翌年立憲改進党を結成し、総裁。同年東京専門学校(現早大)を創立。21年第1次伊藤内閣、ついで黒田内閣の外相となり、条約改正にあたるが、反対派の来島恒喜(くるしま-つねき)に爆弾をなげつけられ右足をうしなう。31年板垣 退助と憲政党を結成して日本初の政党内閣(隈板(わいはん)内閣)を組織。大正3年第2次内閣を組織して第一次大戦に参戦,4年には対華二十一ヵ条要求を提出した。大正11年1月10日死去。85歳。 2019.05.28
新島先生を憶う 二十回忌に際して 大隈重信 我輩の知れる二大教育家 この春は京都同志社の創立者たりし故新島襄君の二十回忌に当るのである。我輩は君と相知ること深かりしにはあらねどまた因縁浅しということを得ない。況んや我輩もこの三十年間学校教育の事では苦労をしているのであるから、君の如き立派な人格と一定の主義を有する教育家が早世した事を憶い出すと実に残念で堪らぬ。 明治年間に功労ありし教育家は少なくない。しかし我輩の最も推ふくしているのは福沢先生と新島先生の二人である。福沢氏は大なる常識を備えてもっぱら西洋の物質的智識の教育を施し独立自尊の倫理を説き且つ実行した人、また新島氏は基督教主義の精神的教育を施した人で、遣り方はよほど異っていたけれども、両者共に独立上羈にして天下の徳望を博したる点に於ては他に比ぶ者がない。 我輩と新島氏との関係 福沢氏とは昔からの知合いで頗る懇意であったが、新島氏とは久しく会う機会もなく、初めて会ったのは明治十五年であった。この時は我輩も既に政府を退いて、学問の独立を図るという目的から東京専門学校(早稲田大学前身)を設立した頃で、新島君の初めて宅へ来られたのはあたかもこの建築中の頃であった。 この時はただ普通の会談で君は同志社の事を話され、我輩は学問独立の必要を説き、共に民間教育のために尽力しようという位の話であった。 我輩が人と交際を結ぶのは、いつも何か事ある時にその事に関係してそれから知合いになった場合が多い。新島君ともやはりそうで十五年学校建築中に初めて会い、後間もなく建築が終った頃再び訪ねて来られたのでまた会ったが、爾来別に交際を進めるという事もなく数年を過ぎ、明治二十一年に至って初めて我輩も君の事業に対して及ばずながら一臂の力を添える様な関係になった。 我が国最初の私立大学計画者 君が同志社を京都に創立されたのはたしか明治八年頃と聞いているが、君は非常なる苦心を以て漸次これを発展せしめ、ついにこれを基礎として私立大学を設立するの計画を立てて、明治二十年頃よりその準備運動に着手せられた様である。 元来同志社の創立は新島君の非常なる決心とその決心に対する米国人の同情とによりて出来上がったのであるから、学校の資金も大部分は米国人の自由寄付並びに米国伝道会社の寄付に依るものであった。これは同校の主義が基督教の徳育を施すというのであったからである。 かく基督教を以て徳育の基礎とせられたのであるが、その教育の理想とせられたところはいわゆる「人はパンのみにて活くるものにあらず」、真に生命あり、活気あり、真理を愛し、自由を愛し、徳義を重んじ、主義を重んじ、なおその上に日本国のために身命を擲って働くところの真の愛国者を養成したいというのであったらしい。 我が子はなるべく自分の乳で育てるのが至当である。いつまでも米国人の同情のみに依頼しているのは新島君の屑しとするところでない。日本人自ら金を出して自国に必要なる人材を作らねばならぬという考えから基金募集に着せられたらしい。 井上侯と新島氏との関係 明治二十年頃、今の井上〔馨〕侯が外務大臣をしていた時、侯は条約改正の必要上我が社会の各方面の改良を企て、いわゆる文明的事業に対しては極力尽力せられた。依って新島君はまず井上侯に向ってその目的と計画とを話されて尽力を請われたそうである。井上侯は君の精神に感動して大いに尽力するつもりでいたが、二十年の暮に突然内閣を退くこととなり、翌二十一年の春その代りとして我輩が外務大臣となった。 ひとたび引受けたら中途で曖昧に終る事の出来ないのが井上侯の美なる性質である。その種々なる事務引続と共に新島君の依頼された件を我輩に紹介し、君が非凡の人物なる事、教育に対して熱烈なる精神を有する事、私立大学設立の計画を立てた事などをことごとく我輩に話して、かくの如き人物によりて企てられたるかくの如き事業は是非とも成功せしめたいから、共に尽力してくれという話であった。 新島氏のために名士を官邸に集む 我輩は既に十五年以来数度会ってその人物も知っている。ことに教育は我輩生来の嗜好でもあり、且つ我輩も当時は既に数年間東京専門学校経営の経験があったので深く新島君に同情し、直ぐにこれを承諾して大いに尽力しようという事を約した。 依って井上侯と相談の上、我輩の官邸にともかく当時の実業界で最も有力なる人々を集める事になった。その重なる面々は渋沢栄一君、故岩崎弥之助君、益田孝君、原六郎君その他大倉喜八郎、田中平八などの諸君十数めいも見えたが、井上侯も我輩と同様主人役として列席せられた。 そこで我輩は新島君の計画を一同に紹介し、詮ずるところ教育は個人の事業にも非ず、政府の事業にも非ず、国民共同の事業であるから資力のある人は率先してこれを援助せられんことを望む旨を凛烈陳べ、次いで新島君はこの事業を企つるに至った精神を話されたが、その熱誠と凛烈たる精神には一座感動せざるを得なかった。 新島氏の熱誠一座を感動せしむ 列席の人々はこれに動かされて直ぐに応分の寄付を約した。井上侯も我輩までも寄付する事になった。頗る少数の人であったが、それで即座に三万円近くも集った。 今日でこそ教育事業もよほど国民的となって国民は争って学校に寄付し、早稲田大学の如きは新設文科の資金百五十万円を全部寄付に拠らんという計画で既に三分の一以上も集っておるという様な時勢になったが、新島君の奔走された二十余年前の時勢では、民間の教育事業に金でも出そうという事はほとんどなかった。当時の一千円は今日の数千円に当る価値がある。それがとにかく即座に三万円近くも集ったというのは新島君の至誠が人を動かしたというより外はない。 当夜新島氏の容貌風神 当夜の光景は今なお眼の前に見える様である。新島君は当時より既によほど健康を搊じておられたものと見えて、顔色蒼白体躯羸痩という風が見えた。屡々咳をしておられたのが今なお耳に残っている。 しかしその脆弱な病躯中には鉄石の如き精神が存在していた。君は終始儼然として少しも姿勢を崩さず、何となく冒すべからざる風があった。主客が飲み且つ食う時に煙草を盛んに吹かしたので、室内は煙で漢字濛々《もうもう》と霞むくらいになっていた。新島君は無論酒を飲まず、煙草を喫まず、生理的からいってもこの煙は定めて難儀であろうと思うて、給仕に命じて窓を明けさした事を記憶している。 病床にて君の訃を聞く 然るに二十二年の秋には我輩は爆裂弾で足を取られて動けなくなり、新島君も病を得て活動意の如くならず、ついに明治二十三年の一月二十三日、大磯で歿するという残念な事になった。 我輩は最初大手術を行ったがそれが癒えず、却って化膿して来たので更に第二の手術を行い、なお病床に横たわっているうちに新島君の訃報に接したのである。久しく重傷に悩んだ後であるから神経は興奮している。君の死を聞いて誠に感慨に堪えなかった。 日本にまだ一の私立大学なかりし時代に於て、君が同志社を基礎として君が私立大学設立の計画を立てられたのは洵《まこと》に壮挙といわねばならぬ。我輩が応分の尽力を辞さなかったのも君の志を壮なりしとしたからである。 君は大磯に病でほとんど半死の人となっておっても、君の精神はなかなか壮なものであったらしい。歿する二十日あまり前の明治二十三年の正月には病中ながら尚抱壮図迎此春という詩を作ってその志をのべ、盛んに理想を画いて死の既に迫れるを知らなかったそうだ。 我輩の敬服する新島氏の人格 君は青年時代に於て完全なる武士的教育を受け、維新前国禁を犯して密かに米国に航し、同地に於て基督の感化を受けたのであるから、日本武士の精神と基督教の信仰とを併有する一種精神上の勇者であった。 従って炎々たる愛国の忠誠、教育に対する奪うべからざる主義と、熱心火の如き精神と、死を以て事を成さんと欲する気象とがあった。これ我輩の最も君に敬服する点である。 君が教育上に於ける感化もこの点に在ったかと思う。即ち福沢氏の如く広くはなかったが、濃厚であった様である。我が早稲田大学教授たる浮田〔和民〕博士、安部磯雄氏なども直接新島君の感化を受けた人々であるそうだが、いずれも人格の立派な学者である。これらは二氏の天分にも因る事であろうが、新島君の感化もよほど与って力ある事と思う。 君死するの時年僅かに四十八、せめて六十までも生きられたらその感化は更に偉大なものがあったであろう。 今日まで継続する我輩と同志社との関係 明治二十一年新島君のなお在世中我輩は関西に遊んで京都に立寄り、同志社にも案内せられて家内と共に行ってみた。なかなか立派な建築で地所も広く生徒も随分多かった。 新島君の死後同志社も一時紛紜のために頗る悲況に陥ったが明治二十九年我輩が再び外務大臣になった時にまた偶然にもその処置調停に関係する事となり、爾来また種々なる相談までも受け<社友>というものになって同志社女学校の世話までも頼まれるなど、関係は今に連続している。なんだか親類の様な気持がしている。二十一年以後毎度行って演説もした。京都へ行けば必ず演説をする事になっている。またしなければ同志社の方も承知しないという様子である。 新島君逝きてよりここに二十年、一時微にして振わざりし同志社も昨今は一千余めいの校友校員一致発奮の結果、普通学校、(高等)専門学校、神学校、女学校等に分れおいおい盛んになって生徒も増加し、再興の気運に向っている。果して然らば新島君の壮図の実現される日もいつかは来るであろう。我輩は国家のためことに右に述べた様な関係からかかる日の速やかに来らんことを切望する者である。 底本:「大隈重信演説談話集」岩波文庫、岩波書店 2016(平成28)年3月16日第1刷発行
青空文庫作成ファイル:このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
2019.08.21
|

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.79~83 土居 通夫 鴻池の家政改革を実現 築地梁山泊のメンバー中、上思議な縁で結ばれたのが中井弘(のち京都府知事)と土居 通夫(のち大阪商工会議所会頭)である。二人は大隈邸訪問の八年前中井二十六歳、土居二十七歳のとき宇和島ではじめて会った。 中井は本めい横井休之進、薩摩藩士で、脱藩して田中幸助となのり、閣老安藤対馬守暗殺計画に加わり、幕吏の追及を避けて長崎滞在中の五代友厚に庇護(ひご)を求めた。ちょうどこのとき宇和島藩家老がきてミュニエル銃購入のことを五代にたのみ、五代は中井の保護を求めたので、宇和島でその家老邸にかくまわれた。 この邸で退屈をもてあました中井は、ある日商人に変装して藩御用達の紀伊国屋に立ちより、砂糖の取り引きを申し込んだがすぐに主人に化けの皮をはがれ、頭をかかえて退散した。その翌日、家老のむすこと馬で紀伊国屋の前を通ったとき主人が気づき、前日の無礼をわびて、自宅に招待したのである。 そのとき、主人にたのまれて相伴役をつとめたのが土居 通夫であった。彼は足軽の子であったが、十二歳からはじめた剣道で頭角をあらわし、二十二歳で田宮流剣法の免許皆伝となっていた剣士である。前年、武者修行と称して宇和島を訪れた土佐の剣客才谷梅太郎なる男と試合した。これがじつは坂本竜馬で、このときの勝敗は明らかでないが、坂本の熱弁に感奮して、土居の心に勤王討幕の志が生まれた。そして今、紀伊国屋の座敷で薩南の行動派と杯くみ交わし、初対面でありながら意気投合、さながら竹馬の友と再会したかのようであった。 慶應元年、二十九歳の土居は脱藩して大坂に行った。志は勤王討幕にあるが、生活の方便で高利貸の手代となった。この手代時代、十三歳の少年を基盤の上に立たせたままぐいともち上げてみせたり、強盗を追っぱらったりして腕っ節が評判になったのはいいが、新選組から加盟を求められ、これはことわった。なお俳諧をはじめ、これは生涯を通じての趣味となる。 この間、中井は宇和島の政情視察係となって大阪にきたが、花柳界で湯水のように金を使ったため、藩留守居役がキモをつぶし、藩当局にご注進に及んで解職された。このあと後藤象二郎が土佐藩の金でロンドンにやってやり、しばらく滞在して、また大阪にもどってきた。 そのことを聞いて土居は中井をたずね、二人は打ちつれて坂本をたずね、大いに歓談した。やがて坂本は新選組にきられ、二人もまたその追及をのがれて潜伏した。 この年の暮れ、後藤にたのまれて神戸に行ったことがある。それは英商ウオールドが、後藤と約束した土佐の樟脳(しょうのう)の受け渡しがおくれているため、長崎から英国汽船がやってきたので、その話をつけるためであった。早駕籠(かご)で行ったが、途中尼崎に番所がある。中井は無事に通りぬけたが、土居の駕籠は番士にとめられ、尋問を受けた。 「いずれの藩士か?」 「土佐藩士」 「しからば、姓名を書かれたい」 帳面をつきつけられた土居は、とっさに偽名を考え、中井については「中井功蔵」自分は「石井新一郎」だと記入した。 横井休之進は、脱藩して田中幸助、京都では後藤久次郎となのっていたが、ここに土居の思いつきで中井功蔵となった。このあと、中井は「中井功蔵」として明治政府につかえ、のち<蔵>を削って<中井弘>ということになったから、土居 通夫はなづけ親だということになる。 名前は、土居もいくつか変わっている。幼めいは大塚万之助、五歳で養子に行って杉村保太郎、十七歳で元ぷくして杉村彦六、二十四歳で実家にもどり、間もなくよそに婿養子となって中村彦六、脱藩して大阪で手代となったときは真一、やがて土居真一郎と改名し、尼崎番所では石井新一郎、明治五年三十六歳のとき「土居 通夫」と称することとしたのである。 名前だけでなく、職業も転々とした。維新後、五代友厚の下で大阪運上所(月給五両)でつとめ、外国事務局御用掛助勤(七十五両)をへて大阪府権少参事(百両)となったのが明治三年のことで、東京出張中に築地梁山泊をたずねたのである。このときはまだチョンまげを結っていて、断髪するのは二年あとであった。 その「日誌」には、九月二十八日の項に「伊藤(博文)へ行き大阪神戸間の事情相談致し、伊藤同伴にて大隈へ行く……」の記述がある。このとき大隈と伊藤は、鉄道掛土居のために、大阪、神戸両駅の敷地買い上げ問題を大いにしゃべったようで、「両先生の論にては一豪(いちごう)も撓まず潔よき見こみに候事」というのが土居の印象であった。 官制改革で大阪府をやめた土居は、五年五月から半年ほど、大隈邸内の長屋で浪人生活をおくったが、これは築地ではなく、日比谷の新邸の方である。 やがて司法省七等出仕、十年四十一歳で大阪上等裁判所の判事をしているとき、三十一歳の伊庭貞剛伊庭貞剛がおなじく判事となってきた。伊庭はその翌年辞表を出し、叔父広瀬宰平のすすめで住友家にはいり、本店支配人となったあと、別子銅山の争議を収拾したいきさつは『日本さらりーまん外史』で書いたことがあるが、土居も十七年四十八歳のとき、鴻池家の家政改革をたのまれ、官を辞して顧問に就任した。このとき、 「土居は司直の府にあった者だ。必ずや鴻池のため法律をつくり、一々成文によって取りさばこうとするだろう」 いやいや、彼は剣客だったし、今もその気質はぬけない。そこで快刀をふるって乱麻を断ち、鴻池のため、目ざましい大改革を決行するだろう。しかし、断っても断っても乱麻は断ちきれず、結局力つきてとびだすのがオチだろう> などとうわさされたといわれる。 ところが土居は、法律ずくめにもしなかったし、快刀の鞘をはらうこともなかった。ただ鴻池の人びとと俳諧をたのしみ、悠々自適するうちに、しらずしらずのうちに人間的感化をあたえ、やがて方針を明示すると、改革は徐々に実現していったのである。 住友、鴻池という大阪の二名家がともに司法官出身を改革者としてスカウトしたというのも奇縁であろうが、そのことよりも、ともに法律の専門家である伊庭、土居の両人が、<規則>にたよるよりは、裸になって人の<こころ>によびかけ、それによって難事をなしとげたという発想法は、今日においても再検討されてしかるべき問題ではあるまいか。 2019.07.21 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.84~88 中井 弘 別れた妻は井上馨と…… 土居 通夫の「日誌」、明治三年八月二十七日の項に「……中井 弘先頃より当地へ参り居り、今夜山口(料亭)に来る。……井上聞多(馨)、新田満二郎娘婚姻致し引きつれ帰阪の由……」という記述がある。字面だけを見れば格別のこともないけれども、「中井が上京していた」ということと、「井上が新田の娘と結婚した」ということに重大な関連があったことを語っているのが『大隈侯昔日譚』である。 『世外井上公伝・第一巻』は、「公は明治初年に新田義貞の裔(えい:しそん)である新田俊純の女を娶った。即ち武子夫人がこれである」と書いているが、この武子はじつは中井の妻だった。中山は、もと薩摩藩士横井休之助だが、派閥に容(い)れられず、そのふ遇時代を大隈の築地梁山泊に寄せていた。派閥に容れられなかった理由として、「父の代から島津久光の側近だった関係」(『明治の政治家たち』下巻)とはつ部之総はいうが、むしろ中井の政治思想が憎まれていたのではないか、というのが私見である。 中井は後藤象二郎の後援でイギリスに行き、帰国後、土佐藩主山内容堂が徳川慶喜に政権返上をすすめる建白書にあたったが、そのポイントは「政権返上よりも政権返上後の政治体制としてイギリスの議会制度を採用する」(『原敬』)ことにあった、と前田蓮山(まえだ れんざん)はいう。保守性濃くしていた鹿児島の西郷党が、こういう急進的思想の持ち主をよろこぶはすはなかった、と思うのである。 中井には方々に「女」がいた、といわれる。新田武子を妻としたいきさつ、年度などは知らないが、ともかく妻にして間もなく、西郷党から鹿児島にもどってこい、といってきた。 「帰ったが最後、切腹だろう」と中井は考えた。そこで武子に離縁状をわたし、大隈夫人綾子に、「どうか良いところがあったら縁づけてくだされ」 と、武子をあずけていった。 ところが、二十歳の武子と相思相愛の仲になったのが三十五歳の井上馨である。井上は二十一歳のとき志道家の養子になり、芳子という娘も生まれたが、のち離縁して井上姓にもどっていた。年譜によれば、明治元年三十四歳の項に「九月、聞子生る」とあり、これが二番目の娘ということになるが、その生母に関する記述は見当たらない。ただ「その頃井上が何でも変な女と同棲していたが、それがドモも豪傑連中にヒドクふ人望で、ㇳウㇳウ皆で追出すかドウカしてしまった」(『昔日譚』)と大隈は語っているから、あるいはこれがその女性かとも思うが確かではない。 ともかく問題は「そのうち井上という男はなかなか素早い男で、いつの間にか、我が輩の預かり物と相思の仲という始末」(『昔日譚』)という箇所だ。その様子に気づいた大隈夫人が武子にたずねると 「井上さんは大好き……」 という返事である。 それならというわけで伊藤博文、山縣有朋などがあつまって「マア粋な捌き」で築地梁山泊で正式見合いということになった。するとその見合いの日に、切腹したはずの中井がひょっくり顔を出したのである。「のちに聞くと何でも中井は薩摩へ帰ってから、やはり才幹な男で、何とか軍人達の心を和げて死なずにすみ、軍隊の部下となって、軍隊と一緒に上京してきた」(『昔日譚』)のであった。土居日誌の「中井弘先頃より当地へ参り居り」は、このことを指すのである。したがってこの中井上京の時期について「(軍隊と一緒に上京)とあるから、ことは明治四年二月、西郷率兵上京のせつであろう」というはつ部之総の推定がまちがいであることは明らかだ。 上京した中井が、まず一番に梁山泊を訪れた心情は察しられる。離縁状こそわたしはしたものの、新婚ホヤホヤのところで泣きの涙で別れた武子のことが忘れられず、結婚生活をやり直そう、と考えたのであろう。ところが、その日が選りに選って正式見合いの日であったことは、まことに人の運命、女の心はわからない。 玄関で中井とバッタリ会ったのが山縣有朋であった。彼は大隈と同年でこのとき三十三歳、兵部少輔(次官)であった。 「(山県の)このときのあわて方ったらなかった。『マァ、マァ、マァ……』というわけで、中井を一室に押しこめてしまって、女を隠すやら何やらで大騒ぎ、妻なども大分色を失った。トウㇳウ伊藤が情を明かして中井を説伏しようとしたが、中井は恬淡な男で畸人(きじん)である。『マァさうか、どうかよろしく頼む』と云ふた限りであった」(『昔日譚』)。 こうして新田武子は、大隈綾子の妹分ということにして、井上と正式の結婚という段取りになった。土居「日誌」――「井上聞多、新田満二郎娘婚姻致し引きつれ帰阪の由……」の事実は、このあとにつづくわけである。 このころ、井上の生活の根拠は大阪にあった。大隈が築地梁山泊に転居したのは二年四月。井上は「四月二日、長崎出張、中旬上阪、五月二十八日に木戸孝允とともに東京に入る」が「六月二十一日、会計官判事、大阪府在勤」、「三年五月四日、造幣頭兼任」、「八月二十四日、東京を発して下阪……」と、ほとんど東京にはいない。そのくせ、新田武子をモノにしたのであるから、大隈の「井上という男はなじゃなか素早い男で、いつの間にか……」ということばもまことに意味深長であることがわかるようだ。 ところで、中井と別れて大隈邸の世話になったころ、武子には二歳の娘貞子がおり、これが母とともに井上家にひきとられ、十六年十五歳で原敬にとつぐまで井上の娘分としてそだてらたのだから、原敬の運命は長閥の婿養子として開けたのだ、、と阿部真之介が断定しているので、服部之総はこの断定の上に立ち「中井が武子と別れたときすでに生まれていた勘定で、当座は梁山泊の大隈夫妻がが養っていたのであろう。大隈の放談は、隠すべきところはチャンと隠して、なかなか義理がたいところがある」と書いているが、これはどうか 前田蓮山はこれを否定し、その証拠として『原敬日記』の一節――「東京なる伊集院兼常よりの報知を落手せしが、余の妻貞子の実母にて、中井家より離別後、印刷局の技師今村なる人に嫁したるが、今回病死せりとのことなりき。伊集院に依頼して、今村に香典二十五万円送ることを托せり」を掲げている。はつ部のいうように、阿部の断定が正しく、大隈がこの件で義理がたったとすれば、原敬はダマされた、ということになる。どちらが正しいだろうか? 2019.07.22 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.89~93 左近充 隼太 西郷軍に加わり散る 明治七年五代友厚は四十歳で、資本金五十万円で創立した鉱山会社「弘成館」の経営で多忙をきわめていた。これは大阪に本店、東京・築地に出張所をおき、社員三百人、鉱夫などの現業員二万人という当時のビッグ・ビジネスであった。 二月半ばごろ、二人の青年が訪ねてきて、面会を求めた。五代が会ってみると、いずれも鹿児島県出身の海軍兵学寮生徒で、一人は山本権兵衛(二十三歳、のち海軍大将、首相)、もう一人は左近充 隼太となのった。「病気看護のため」という口実で休暇をもらい、帰省中のところであるが、その口実はウソで、じつは兵学寮はそのまま退学し、鹿児島の私学校にはいるつもりであった。 征韓論に敗れた西郷隆盛が、参議兼近衛都督を辞して郷里に向ったのは前年十月。西郷のあとを追って、板垣退助、副島種臣、後藤象二郎、江藤新平がやめ、近衛将校百余めい、下士官六百人などがこれにつづいた。この形勢を見てジッとしておれなくなった山本が、同級の左近充をさそったのである。左近充はただちに同意したが、旅費の工面をどうするか、とたずねた。 「本や衣類を売れば、大阪までの道中はなんとかなる。大坂まで行けば五代ドンがおられるから、同郷のよしみで鹿児島までの旅費を貸してもらう」 というのが山本の計画で、二人はその目的で訪ねてきて、 「三十円貸してください」 と申し入れたのある。ところが、五代の返事は「ノー」であった。 「ばかなマネをしてはいかん。各藩えりぬきの秀才を教育している立派な兵学寮から、どうして設備のふ十分な私学校にはいる必要があるか。君たちの行動は、西郷に対する私情にとらわれた軽率妄動である。ただちに帰校せよ」 と五代はきびしかった。意外な成り行きで、山本たちはスゴスゴと宿屋に引き返した。ところが翌朝目をさましてみると、まくらもとに紙包みが投げこまれている。「餞別」と書いてあるだけで、な前はなかったが、一円札が五十枚もはいっており、五代の好意にちがいなかった。二人は押しいただいて、郷里に向った。 西郷に会ってみると、彼もまたおなじことをいう。「……君等年少の頃より海軍に従事し、その業いまだ半ばにも達せず前途お遼遠なり。それ国家倊々盛大におもむけばますます多事ならん。故に従来海軍にたのむこと多大なるべきを覚ゆるのみならず、わが国はシナ及びロシア等ンい隣接して東洋に立つをもって、一朝想像しがたき困難に遭遇する場合にのぞみたは、ひとえに海軍の力によるの外なし。これらの事をよく考えて慎思熟慮し、決して目下の政治問題等に関することなく、かたき覚悟をもって、余事をなげうち、一意専心、海軍の修業にはげみ、将来国家のため努力せられんことこそ、老生の君等に切望してやまざるところなり……」(『伯爵山本権兵衛伝』上)という情理兼ねそなわる、ねんごろなことばであったという。 山本はその真意を悟り、 今日から他を顧みず、「一意海軍の修業にはげみます」 と誓ったが、左近充の方は、 「あくまでも先生と生死を共にします」 ガンとしてきかないのだ。 「それならば、山本を京都まで送った上で、また鹿児島に帰ってきたらよかろう」 と西郷いった。 京都まできて、あすは山本が東京にたつというときになって、二人の間に激論がはじまった。佐近充はカンカンに怒り、 「いったん生死を共にすべしと誓っておきながら、たとえ西郷先生にいわれたからにもせよ、簡単に考えを変えて友を裏切るとは卑怯千万!」 といって、信玄袋に入れていた短刀をとりだして、山本をさそうとした。ところが、その短刀がなかった。そこで左近充は気合が抜けててしまった。山本はその機を逸せず、静かに事の理非を説いてきかせ、左近充もようやく紊得した。翌日、二人は打ちつれて出発し、無事に兵学寮にもどったのである。 山本はその年十月に卒業、海軍少尉補。筑波艦乗り組みを命ぜられたが、左近充の方はその前に考えを変えて、鹿児島にもどっていた。 明治十年二月、私学校生徒一万数千人が旧騎兵場に集められ、歩兵五個大隊、騎兵二個小隊に編成されたとき、左近充はその中にいた。このころ山本少尉補は、艦務研究のためドイツ軍艦ビネタ号にのりこみ、シンガポールにいた。彼と同行した河原要一の「日誌」によれば、左近充が隊ごに加わったその日、「晴、午後一時三十分、山本、横尾(道昱)、中山(訥)、早崎(七郎)の諸氏と共に上陸、帝王の洗水場にいた。各自身体を清む。この日は当地の正月元旦なり、市中大いに賑う」とある。 熊本城が包囲された三月二十二日、ビネタ号はクリスマス島の付近にあり、八十歳になったドイツ皇帝ウイルヘルムの誕生祝いが艦上で行われていた。西郷軍はジリジリ後退し、わずか三百人で城山にこもったのが九月一日である。ビネタ号は南米沿岸を航行中で、山本は四日にリオジャネイロに上陸した。 征討総督有栖川宮熾仁親王有栖川宮熾仁親王、参軍山県有朋(陸軍卿)に率いられた政府軍八個旅団が、十重二十重に城山をかこみ、総攻撃の火ブタを切ったのが二十四日。二十三歳の慶應義塾生で、アルバイトで報知新聞の従軍記者となっていた犬養毅(のち首相)が、「……天既に明戦全く止む。諸軍喧呼していう、われ西郷を獲たり、われ西郷を獲たり、と。しかして西郷の首ははたして誰が手におつるを知らざるなり。午前九時、偉身便ふく(大きく腹の出た私ふく)に一屍を獲て来たり、これを検すればはたして西郷なり。ついでにその首級を獲たり。首は屍のかたわらに埋め、うすく頭髪をあらわす。よりてこれを掘り出し、ついに桐野等の屍を併せて常光明寺に集め、両参軍以下諸将これを検し、同所に埋む。実に明治十年九月二十四日午前十一時也……」と書いたこのときまでに、左近充隼太も討死していた。 ちょうどこのころ、山本をのせたビジネタ号はサルバドル港を抜錨し、一路大西洋を北上していた。山本が祖国の戦雲を思い、旧友のことを考えていたかどうかは、記録の上では明らかでない。 ※参考1:明治七年十一月一日、山本権兵衛、日高壮之丞ら十七人は、海軍兵学寮を二期生として卒業し、海軍少尉補となった。 ※参考2:左近允姓:左近允尚正(Sakonju Naomasa)生誕1890年(明治23年)6月6日鹿児島県死没1948年(昭和23年)1月21日(57歳没)香港スタンレー監獄 日本の海軍軍人。海兵40期卒業。最終階級は海軍中将。鹿児島県出身。 左近允の二人の息子も兵学校を出て太平洋戦争に従軍し、長男の正章(68期)は昭和19年10月、駆逐艦島風で戦死、次男の尚敏(72期)は生き残り、戦後は海上自衛隊に入って海将となった。 2019.07.23 |
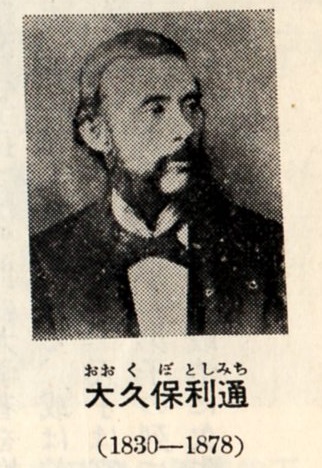
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.94~98 大久保 利通 渋沢栄一と犬猿の仲 明治政府が渋沢栄一というタレントに目をつけたのは明治二年のことであった。このとき渋沢は三十歳で、前年にパリからもどり、二年一月に日本最初の株式会社「商法会所」を静岡の紺屋町に創立し、めざましい業績をあげていたのである。「殖産興業・富国強兵」をスローガンとする政府にとっては、よだれの出るような才能にちがいなかった。 出京を命じたのが二年十月、「租税正」に任じたのが十一月。彼を説得した大蔵大輔(次官)大隈重信は、「商法会所」の業績を評価して上でスカウト―したはずであるが、「後に知られたが、当時渋沢を推挙した人は、大蔵卿伊達 宗城と郷 純造であったという」(土屋高雄『渋沢栄一伝』)。 ところで筆者は、このほかにも渋沢を推挙した人物があったように思う。「築地梁山泊」の仲間の一人、中井弘がそれであったろうと、証拠もなしに考えている。 すでにのべたように、中井は薩摩藩を脱藩し、江戸で安藤対馬守襲撃計画などに加わったりして大いに志士活動をしていたが、そのころ、武藏国(埼玉)榛沢郡血洗島、すなわち渋沢の故郷の隣村手許をたずねたことがある。そこには儒学者尾高惇忠(藍香と号す)がいた。栄一の従兄であり、かつ学問の師匠である。この惇忠の弟に長七郎という剣道の達人がおり、早くから江戸に出ていて、ときおり友人をつれて帰省し、時勢を談じた。その友人の一人として、中井弘がいたのである。当時、栄一は十七、八歳。十四歳のころには藍商売で一人前になっていたほど俊才で、ことに十七歳のとき代官の侮辱をうけて発奮し、封建制度の政治社会組織にたいする不満と懐疑を中心に真剣に思索しはじめていたから、これら志士たちの議論に加わり、おのずと中井ともことばをかわすことがあり、中井も、若僧ながらできるやつだ、と感じたことであろう。 中井は、女性を多く愛したが、同時に後輩も多く庇護した人物だ。司法省法学校を放校された原敬を拾って報知新聞に入れたのも中井である。しかも就職の世話をしてやっただけでなく「中井は原敬の学問の師」「原敬が報知新聞紙上に載せた論文は、中井の感化によるところが多いように察せられる」と前田 蓮山も書いている。原の家は南部藩の家老で、戊辰の役で官軍にひどい目にあい、薩長にたいする反感は根強いものがあったのに、薩長出身の中井には、そういう旧怨を捨て、そこまで傾倒させる人間的魅力があったのである。そういう「体温」の持ち主が、かって遊学したことのある土地の俊秀栄一のことを忘れさり、あるいは冷淡であったはずはなく、維新後その動静のことを聞きだして、築地梁山泊をたずねたとき、盟友大隈に推挙したこともあったのではないか――以上は単なる推測にとどまるが、あってしかるべき光景であり、それを実証する文献を筆者はさがし求めているのである。 それはそれとして、政府の役人となった渋沢は、大隈、大久保、井上などの数人とも知りあうこととなった。そして、大久保とはけんかし、大隈とはしたしくなることはなく、井上とはもっとも親密となる。その成り行きには理屈をこえたところがあり、つまりは人生の不思議さを思わせるのである。 渋沢は、政治家としての大久保を高く評価している。『論語』に「君子は器ならず」(為政28)とある。「立派な人間は、決して単なる専門家ではいけないものだ」ということらしい。渋沢は「いやしくも人間である以上は、これをその技能に従って用いさえすれば、必ずその用をなすものであるが、箸には箸、筆には筆と、それぞれの器に従って用があるのと同じように、凡人にはただそれぞれ得意の一技、一能があるのみで、万般に行きわたった所のないものである。しかし非凡な達識の人となると一技一能に秀れた器らしい所がなくなってしまい、将に将たる奥底の知れぬ大きな所のあるものである」「私は(大久保)の日常を見る毎に、器ならずとは必ずや公の如き人をいうものであろうと、感激の情を禁じ得なかった>(『実験論語』)とのべている。最大級の賛辞ともいえるであろう。しかるに、「大久保公は、私を嫌いで、私はひどく公に嫌われたものであるが、私もまた大久保公をいつでもイヤな人だと思っておった」。「好ききらい」が原因で反発したようである。 参考:デジタル版「実験論語処世談」(黒崎) そういう気持が低迷しているところに四年八月、予算問題で正面衝突することになった。陸海軍の歳費を一千五十万円と定め、大久保が意見を求めたとき同席していた谷鉄臣、安場保和は何もいわず、渋沢ひとりが反対したのである。 「総じて財政は《入るをはかって出を為す》を原則となすべきです。まだ歳入も精確にわかっていないときに、兵事はいかに国家の大事だといっても、これがため一千五十万円の支出を怱卒の間に決するのはもっての外、本末転倒の甚しきものではありませんか」 すると大久保は「怫然と色を帯びた」。冷徹をもって聞えたこのひとが顔を赤くした、というから、その立腹のほども察しられる。 「それなら渋沢は陸海軍の方はどうでもかまわぬという意見か?」 「ちがいます。いかに私が軍事に通ぜぬとは申しながら、兵備の国家に必要であるぐらいのことは心得ております。しかしながら大蔵省で歳入の統計ができあがらぬ前に、巨額な支出の方ばかりを決定されるのは、危険この上もなきご処置であります」 そういう議論がつづいたが、渋沢のいうには、「総じて薩州人には一種妙なクセがあって、何か相談でもせられたときに、すぐそれに可否の意見をのべるとこれを悦ばず、熟考した上にお答えするとでも申していったん引きさがり、翌日にでもなってから意見をのべると、これを容れるというような傾きがある。薩州人であったから、さすがの大久保公にもやはりこの癖があった」、要するに、意見表明のテクニックのまずさ、大久保の癖のために正面衝突したのだということらしい。 しかし大久保にしてみれば、不平不満の士族軍と農民一揆が焦眉の急、第一義の問題だという判断に立ち、陸海軍歳費額を決めたのに、そういう危機意識をもたぬ若僧が、いかにも小りこうそうに、ソロバンの帳じりだけの理屈をこねまわして反対したため、色をなして怒ったのかもしれない。すなわち、そのノンキさ、危機意識の欠如許せぬと思ったためで、渋沢のいう薩州人一般の癖から<小癪なやつ」と思ったのではなかったかもしれない。 そのへんのニュアンスが大切なところであろうが、ともかく渋沢は、こんなわけのわからぬ長官の下では仕事をしてもはじまらぬ、やめよう、と考え、井上に慰留せられてとどまった。その後、大久保・渋沢の相互理解、握手の機会はついに訪れなかった。十一年五月、現ホテルニューオータニの側の紀尾井坂(清水谷)で、大久保がテロにやらたからであった。 2019.05.21写す。小島直記著『人材水脈』近代化の主役と裏方は「維新から現代まで日本の近代化に努めてきた四十七人の男たちの人生に、人間の生き方の根源をさぐる」と著者は書いている。
我が国、欧米各国とすでに結びたる条約は、もとより平均を得ざる者にして、その条中はほとんど独立国の体裁を失する者少からず。……英仏のごときに至っては我が国内政いまだ斉整を得ずして、彼が従民を保護するに足らざるをもって口実となし、現に陸上に兵営を構え、兵卒を屯し、ほとんど我が国を見ることおのが属地のごとし。ああこれ外は外国に対し、内は邦家に対し恥ずべきの甚しきにあらずや。かつ、それ条約改定の期すでに近きにあり。在朝の大臣よろしく焦思熟慮し、その束縛を解き独立国の体裁を全うするの方略を立てざるべけんや。
(征韓論反対の意見書)
この日(8月10日)鹿児島藩士に生まれる。明治維新の推進者の一人。新政府の中心となり、新国家の基礎をきづいたが暗殺された。:明治11年(1878年)5月14日、馬車で皇居へ向かう途中、紀尾井坂(東京都千代田区紀尾井町)にて暗殺された(紀尾井坂の変)。享年49〈数え年〉、満47歳没。 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)より ※関連:大久保利通 ※図書:海音寺 潮五郎著『西郷と大久保』(新潮文庫) 2010.08.10 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.99~103 郷 純造 "幕末太閤記" コツコツと財築く 明治四年の廃藩置県のあと、政府がもっとも手を焼いたのは諸藩の旧債処理で、このため五年二月、大蔵省内に負債取調掛をおくこととなった。そのとき主任としてこの問題に専念したのが大蔵省丞(しょうじょう)郷 純造である。 郷は四十八歳になっていた。大隈や井上など、三十歳そこそこで大蔵省の首脳になっていたにくらべればいかにも出世がおそい感があるが、二十歳のとき給金三両の草履とりをふりだしに、藩閥の背景もなくこの地位まではい上り、さらには大蔵次官、男爵となるその生涯は、「幕末太閤記」ともいうべき苦闘によって築かれたものであった。 渋沢栄一が代官に侮辱され、武士になって見返してやると発奮したのは十七歳だが、美濃国(岐阜)の豪農のせがれであった純造が同様の決意で江戸出奔を企てたのも十七歳である。このときは追っ手のために引きもどされ、家の許しを得て江戸に出たのが二十歳である。はじめ大垣城主戸田采女正の用人正木某の若党(草履とり)となり、二十一歳のとき旗本松平某の中小姓(給金年四両、月白米一斗五升、銭五百匁)、二十六歳のとき芝増上寺の寺侍(給金年四両、他に余得年六両)、二十三、四歳のとき町奉行加役牧志守の中小姓(給金年四両、他に余禄あり)と転々としたが、なかなかウダツが上らない。念願は「笠松の郡代」だが、そのためには幕府の直臣となる必要があり、その直臣となるには与力か同心の株を買うのが早道である。 しかるに与力株は千両、同心株が三、四百両でとても手が出ないから、養子になればその十分の一ぐらいで買えるだろうと考え、実家から終身の分け前として二十両、これに自分のヘソクリ五両を加え、二十五両の持参金で「家の良否を問ふに暇あらず」(『郷純造履歴日記』)、駒込の同心今村某の養女へ婿養子に行き、その女に不都合があったので離縁してあらためて火事場見廻り寄合席蒔田某の家老内田角右衛門の娘を妻にした。これが正妻「ゐ祢」であるが、このひとに子供がなく、数人の女性に八男二女が生まれた。 純造はこのあとも芽が出ないで、二十八歳のとき小納戸役神田某の用人、三十一歳のとき日付役堀織部正の給人、三十六歳のとき堀伊豆守(堀織部正の父)の用人、三十七歳のとき大阪奉行鳥居越前守家老、三十九歳のとき大阪奉行松平勘太郎家老というふうに陪臣(またげらい)という日の当らぬ仕事を転々としたのである。ただこの間に、必死になって金を蓄(た)めていた。給料は大したことはなかったから、そこに別途の工夫があったであろう。その息子誠之助の語るところによれば明治維新の直前、知りあいの検校(けんぎょう:盲人の最上級の官名)に利殖法を相談した。盲人は幕府の保護政策で高利貸を許されている。その検校も、 「私におまかせなさい。利殖してあげましょう」 といった。そこで純造は、千両ほどのあり金をあずけたというのである。 ところが間もなく、明治維新のドサクサで検校の居所がわからなくなった。粒粒辛苦の虎の子をあずけた純造としては、あきらめにもあきらめきれない気持ちであったろう。 だが、人生四十の坂を越してから、このひとはツイてきたようであった。維新のドサクサも、このひとにとっては運命好転の契機となったのである。 慶應三年、四十三歳になってもまだ幕臣の株の売り物がなく、千葉の成田山に参詣して三七二十一日の断食を行ったほどであったが、翌四年(明治元年)正月、ようやく「撤兵」にとり立てられた。これは一日おきに鉄砲をもって江戸城の門衛をつとめる役目である。そして二月に御作事方勘定役、三月に小十人格工兵左図役並勤方、「裏金の陣笠」をかぶって練兵のさし図をする身となった。六月には工兵左図役頭取(四百俵)、「幕府中比類なき立身」をした。その幕府は瓦解したが、新政府から「会計局組頭」の辞令が出たのが同年八月である。会計局は会計事務局、会計官となり、二年七月に大蔵省と変わって、純造も大蔵少丞となり、やがて大蔵卿大久保利通のもとで藩債担当の主任となったわけである。 そしてちょうどうこのころ路上でバッタリーと検校にめぐり会った。検校は目が見えないので、純造の方から声をかけると、 「郷さん、よいところでお目にかかりました。おあずかりした金が大分ふえましてね」 といって、検校は一万円近い金を返したのである。 このころ三井の番頭三野村左衛門(三井財閥の中興の祖)が純造の家に出入りしていた。二人の間に一万円の話が出て、床下にかくしておくこともできずこまっていると純造がいうと、三野村がその保管を引き受け、相当な利まわりでふやしてくれた。このあと、純造はさかんに土地に投資した。二番町九百坪の土地は坪六銭二厘、計五十六円であった。純造が官を辞したのは明治二十一年、このとき財産は十六万円になっていたが、そのほとんどが土地の値上がりによるものだったという。 せがれの誠之助がその財産の一部をわけてもらったのは二十五年、二十八歳のときである。住居にする家のほか、地所、株券、五、六軒の貸家など総計二万六千円、月に三百円ぐらいの収入になるもので「当時としては小さい生活をたててゆくには差支えなかったのであるが、我輩とすれば、貰ったものを身につける考えがなかった」(『男爵郷誠之助自伝』)。誠之助は、 「これを勝手にに使うがよろしいですか」 と父にたずねた。 「よろしい」 と純造は答えた。そこで「この財産を滅茶苦茶にする本当の道楽がこれから始まった」。その道楽には一つの方針があった。吉原をふりだしに、その土地でもっともアバズレの芸者をよび、遊びというものを徹底的に鍛えてもらった。それから、柳橋、新橋、日本橋、赤坂と順番に遊んでまわる。遊びの金は掛にはしないで、赤い皮の財布に現ナマを入れておいて、その場ではらった。当時は、お茶屋も一流、芸者も一流どころを五、六人よんで遊んでも十五、六円という時代である。 誠之助の家には、女中二人、書生一人、車夫一人がいたが、家があるというのは名ばかりであった。 「先月は幾日家に寝たか?」 と女中にきくと、 「ずいぶんよく帰られまして、三晩でございました」 と答える始末。しかも家に帰って寝た日にしても、芸者を同伴していた。 そういうわけで、コースを順々にまわって、二年目ぐらいに赤坂までたどりついたとき、おやじの金はなくなっていた。 ※:郷 純造:美濃国黒野(現在の岐阜市黒野)の豪農の三男として生まれる。弘化元年(1845年)江戸に出て大垣藩用人に武家奉公した後に旗本など奉公先を転々とするが、長崎奉行牧義制の納戸役として嘉永5年(1853年)のオランダ使節来訪問題に対応し、続いて箱館奉行堀利煕の用人としてその樺太・蝦夷地巡回に随行するなど対外問題に遭遇、更にその経験を大坂町奉行鳥居忠善に買われて貿易問題を担当して同家の家老として抜擢された。鳥羽・伏見の戦い直前に撒兵隊に属する御家人の株を買って幕臣となり、程なく差図役(士官)に登用され、最終的には撒兵隊差図役頭取、旗本となる。江戸開城前後、同隊の新政府に対する徹底抗戦路線には従わずに江戸開城後は新政府軍に従った。明治維新後は新政府に入り大蔵官僚として活躍する。特に渋沢栄一や前島密、杉浦愛蔵ら旧幕臣の登用を大隈重信伊藤博文らに薦めた功績は特筆すべきである。だが、それが原因で幕臣嫌いの大久保利通から憎まれていた(明治3年10月25日の大久保から岩倉具視あての書簡には郷を「断然免職か転勤にならす」と名指しで明記されているほどである)。そのため、大久保が大蔵卿に就任して政権の中枢を担った時代には重要ポストから外されて干されることになった。大久保の没後、大隈や伊藤が政権の中枢に立つようになると漸く再評価されて大蔵大輔(後に初代大蔵次官と改称)を務めたが、実務官僚の地位に留まった背景には大久保政権下の不遇時代が尾を引いたからと言われている。退官後は貴族院議員となった。 2019.07.26 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.104~108 郷 誠之助 道楽から一転、会社再建の名人に 仲間奉公をふりだしい、薩長土肥の出身者で要職を独占していた明治政府において大蔵次官までになったのであるから、郷純造が頭のいいヤリ手であったことはいうまでもないが、とくに精力絶倫といわれた。十三歳のとき、肥桶一荷をかついでほめられたことがある。普通、二十歳ぐらいでないとかつげないものであった。また、四十代になっても芽が出ないので、成田不動に二十一日間の断食祈願をしたあと、三日後には江戸に帰り、しかもみやげに芋を一荷かつでいった。常人ならば満願となって宿へ下がると、最初は重湯、それからお粥、つぎにご飯を食べて、しだいに元気づくには一週間か十日はかかるものであった。 多数の女性を愛し、八男二女を生ませたが、最終の子は七十歳のときに生れ、「すなわち終り初物の意を表し朔雄となづけたり」とある。このバイタリティーは子供たちにうけつがれ、さまざまなデフォルメをうけて表現されたが、跡とりとなった誠之助の場合、不羈(ふき)奔放の行動となってあらわれた。 小学生時代の楽しみといえば、屋根の引き窓にのぼり、女中たちが働いている台所へ小便をすることだった。というのであるから、栴檀(せんだん)は双葉(ふたば)より芳しかったわけだ。十三歳のとき父の乾分(こぶん)である宮城県大書記官の家にあずけられたが、肩上げのついた着物をきて、上級生の悪太郎にくっついて紅灯の巷(ちまた)をさまよう。これではいかぬと中学の寄宿舎に入れられると、毎晩ぬけだして遊郭に通い一升酒をたいらげて「あんたというひとは……」と、アバズレ女郎のどぎもをうばった。 十五歳で東京に帰り、十六歳のとき無銭旅行に出かけた。手を焼いた父親からアメリカにやられそうで、「アメリカに行ったのでは人間がますます軽薄になるばかりである。俺も日本人だ。日本人は日本固有の方法で修養しなければならぬ。それには日本全国を広く行脚して、その土地土地の志士とか、偉い人物に面会し、議論を戦わすのが一番よろし」と考えたからである。 辞書などを売って旅費二十円を工面したが、これは川崎の遊郭で使いはたし、一面識もない静岡県知事に借金に行った。玄関で「郷誠」と書いた名刺を出すと、「忙しいから会えない」という。そこで、「郷純造男誠之助」と書き直すと、慇懃(いんぎん)な態度で会ってくれた。旅の目的などをしゃべった。県知事は<ちょっとお待ちくださいといって奥に引っこもり、やがて紙に包んだものをさしだした。五円札が二枚はいっていた。 しかし、県知事の注進で純造は烈火のように怒り、勘当状をわたした。「汝不幸不仁にして余の訓戒に悖戻(はいれい)し……」ととても丁寧な字で書いてあったという。 勘当されて京都に行き、同志社にはいった。そのうち薬の行商に加わり、若狭の小浜まで行った。「本家は江州安土町、その又薬の効能は、腹痛、頭痛、胸つかえ……」と宣伝文句をとなえ、軒なみに押し売りしていく商法だったが、誠之助は新法をあみだし、裁判所、中学校に押しかけた。中学校では授業中の教室にはいりこんで、教師をつかまえて薬の効能を説くだけでなく、「あなた方のような一般人より一段知識の進んでいる人から、まずこの有用なる薬を試して普及してくれなくてはこまる」と文句をつけて、学生に買わせたところに、そのあつかましさとユニークな才能があらわれていたといえよう。 十九歳のとき、未来を誓った恋人が自殺し、ショックをうけた。二十歳のときから二十七歳のときまでドイツ留学。「ドイツでは我輩も道楽もしたが、初めの三年間は真面目に、真剣に、ミッシリ勉強をした」という述懐は語るに落ちる。ちょうど森鴎外も留学中でその「独逸日記」には「郷誠之助と相見る。誠之助はハルレにありて経済学を修む。……快活の少年にて、好みて撞球戯をなす」と、プレイボーイぶりが記されている。仲間には、井上哲次郎(のち文学博士)、和田継四郎(八幡製鉄所長官)、松方巌(正義長男、十五銀行頭取)、田村恰与造(たむら いよぞう:参謀本部次長)、都築馨六(つづき けいろく:井上馨の女婿、枢密院書記官長)、青山胤道(あおやま たねみち:医科大学長)、佐藤三吉(同東京帝国大学医科大付属医院長)など将来の大物たちがいる。 帰国旅費は三回送らせ、三度とも遊びに使ってしまったため、フランス船で帰国したときは、「ドミノ(西洋賭博)で小遣銭を稼ぎながら帰ってきた」。 帰国して農商務省嘱託(無給)となり、それをやめてから数年間、前回のべた「本当の道楽」で父からもらった金をきれいに使ってしまうのである。父も心痛したであろうが、親類の連中も心配して、何とか「正業」につかせたいと考えた。しかし、「もともと気位の高い奴だから、サラリーマンなどでは承知もせず、できもしないだろう」というので、いきなり社長のポストにつけてやったのである。父は草履とり、せがれは社長が人生のスタートだったことになる。ただ「社長」とはいってもボロ会社の典型で、資本金二十万円、払い込み四万五千円、七年間に社長が六人も変ったという日本運輸会社の社長であった。 誠之助は、職についたのであるから借金の跡始末をしようと考え、抵当にはいっていた麹町六番地の住宅を売りにだした。これを四千円で勝ったのが横浜税関長有島武郎、有島生馬、里見弴の父親である。 さて、借金を片づけた誠之助は、三年間一歩もお茶屋に出入りしなかった。そして繰り越し欠そん四万円の業績を立て直して、八分配当にまでこぎつけた。今まで道楽者あつかいして信用しなかった世間も、いささか認めはじめてきた。「ボロ会社」再建の名人という評判が立つて、日本メリヤス、日本鉛管製造、入山採炭、王子製紙、日本火災保険、日本醤油、帝国商業銀行、東京製絨など、つぎつぎと問題会社がもちこまれてきた。このうち、最も成功したのは、三十六歳のとき社長になった入山採炭である。反対派は、「東京へ刺客を送る」といつておどしにかかったが、そこは単なるお坊ちゃんではない、逆に自分から鉱山に出かけて、ただ一人ブラブラ山もとを歩きまわった。そうなると、だれも手をだせなかった。 在職十七年で、資本金はばい額、配当は無配から一割となった。社長をやめると退職金に三十万円もらったが、半分の十五万円は従業員に分配し、腹心の鉱務所長に二万円、その他記念品をつくって関係先にくばるなどして、ご自身は二万円しかうけとらなかった。二代目はケチだ、とか、若いときの道楽者はシブチンになる、とかいわれるが、彼はその通説を見事にくつがえしたのである。そういう「男」になったせがれに満足しつつ、純造は八十五歳で永眠した。 2019.07.28 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)(昭和五十八年八月十日発行) P.109~113 小栗 忠順 政治の暴力性に泣く 幕府崩壊前後のドサクサに、ツイていたのが郷純造とすれば、ツイていなかった筆頭は小栗 忠順(ただまさ)ではなかったか。 郷は草履とりからスタートしたが、小栗は二千五百石取りの旗本の家に生まれ、その妻は播州林田藩主建部内匠頭の次女路子であった。徳川幕府体制の崩壊が、それまで日のあたらなかった下っ端に成り上がるチャンスとなり、わが世の春を謳歌していたパワーエリートをその座からけおとしてしまった、といえばそれまでのことのようであるが、小栗の運命には、こういう図式だけでは盛ることのできない人間の悲劇、政治の暴力性が刻まれている。 小栗が、この妻の里となる建部家にはじめて客となったのは十四、五歳のときというが、すでにその挙動は人びとの感嘆するところであった。なだ少年ではあるがすでにたばこをくゆらし、たばこぼんをはげしくたたきながら「なるほど」「なるほど」と藩主と応答した。人びとはその高慢におどろきながらも、言語明晰、音吐朗々、堂々たる対応ぶりに感心して、将来はどいう人物になられるであろうか、とうわさした。 正しいと信ずることを直言し、上正を容赦しない剛直の性格は、多くの敵をつくり多くの味方をつくった。彼の識見と能力を評価したのは大老井伊直弼で、万延元年、安政条約批准書交換のため使節を派遣したとき、目付として使節三人の中に加えたのである。このとき小栗は三十四歳で、これから幕府崩壊までの八年間、外国奉行、勘定奉行、歩兵奉行、江戸町奉行、軍艦奉行などの要職にあった。 こういう要職を歴任した人びとは他にもいる。小栗がこの中において一異彩といえたのは、第一に風流を好まず酒と女に縁がなかったこと、第二に歌舞音曲を好まず、第三に詩文の閑文字を好まなかったことである。勝海舟は明治になってから「(小栗は)眼識局小にして、あまり学問のなかった人>と評したが、これには疑問がある。米国では多くの書物を買いもとめ、帰国後その研究に打ちこんでいた。ふ換紙幣の使用に対する反対意見をのべた「上書」の原文を例示して、小栗のおい蜷川新は「何人といえども、公正の念をもってこれを読むならば、野蛮な攘夷論者の横行していた時代に、すでに欧米の経済および財政の学に通じ、これを十分に消化し、何ら直訳的の跡もなく、事理明白に論述しうる政治家のあったことに、驚異の念を禁じえぬであろう」(『維新正観』)といっているが、なるほど「上書」を読めば、これは決して身びきのドグマではなく、勝海舟の方言的批評よりははるかに客観性があると思われるのである。 しかし、彼の悲劇は、剛直真摯(しんし)の性格、幕府体制への忠誠心、時勢に先行する識見の三つがないまぜになり「旗幟鮮明」を態度に打ち出したときに胚胎(はいたい)した。彼は、長州征伐のオピニオン・リーダーであった。さらに慶應四年正月、江戸城最後の評定においては主戦論をとり、朝令暮改、迷いに迷う将軍慶喜の袖をとらえて、 「われに反逆のなを付せられる理由はありません。非はすべて彼らにあります。何故にすみやかに、正義の一戦を決定いたされませんか」 とせまった。慶喜は顔面蒼白、その袖をふりきって奥に逃げ去った。 こうして、最後の会議は和戦ふ決定のまま終了。小栗は、もはやこれまでと思い、江戸を引きはらう決心をしたのである。このとき、小栗の引き立てによって三井組の番頭となっていた三野村利左衛門は、千両箱をもってきて渡米をすすめたが、彼はこれをことわった。そして、長持八棹に洋書や外国の機械などをつめ、装飾用として玄関に備えつけていた青銅砲一門を引いて、その知行所である上州権田村(群馬県倉淵村)に引き揚げていった。このとき、その荷物を見て、数十万両の幕府の官金をおさめたものであろう、とうわさしたものがある。 三月四日、一団の無頼漢が権田村を襲った。小栗は少人数の家来を指揮してこれを撃退したが、折から近くにきていた官軍――東山道総督岩倉具定(いわくら ともさだ)、参謀板倉退助、同伊地正治らは、暴徒を煽動して、 「小栗には、暴徒七千余人を撃退できるほどの兵備がある。大砲もある」 と吹聴させ、「朝廷反逆の企図あり」と断定する口実とし、「小栗追捕令」を発したのであった。 これを知らない小栗は、新しい住宅を建てようと思い、毎日馬にのって工事を監督し、また五段歩の畑を開墾させたが、官軍の色めがねでこれを見ると「陣屋等厳重に相構え、これに加うるに砲台を築き……」ということになる。 官軍の命令で、高崎、安中、小幡三藩の兵八百が小栗の宿した東善寺を囲んだ。小栗は反逆の意思がないことを弁じ、青銅砲一門、小銃二十一丁を引きわたし、さらに翌日、二十一歳の養嗣子忠道に家来三めいをつけて官軍出張所に出頭させ、自分は東善寺を出て農家にうっつたが、な主は官軍の命令だとして、村を立ちのかぬ場合は村民一同に難儀がかかると、といった。小栗は官軍の意図を見ぬき、母堂および妊娠中の妻道子を越後に落ちのびさせた。 四月五日、小栗捕縛。 六日早朝、烏川河原で斬首。その首は青竹につきさされ、路傍にさらされた。小栗の享年四十二歳。嗣子忠道も斬殺。 母堂と夫人は、野に伏し、山にかくれるという辛苦をなめて新潟にたどりつき、さらに会津まで逃げて、夫人は六月十四日に女子国子を産んだ。しかし会津も安住の地とはならず、落城ののち、母子は東京に送られ、深川の三野村利左衛門の邸に引きとられた。 三野村は旧主の恩義にこたえ、よく母子の面倒を見たようである。やがて未亡人道子が病死すると、遺児国子大隈重信邸に引きとられた。大隈夫人は旧旗本三枝氏の出で、小栗家とは親戚だった縁による。大隈夫妻は国子のために、矢野文雄の弟貞夫を夫に選び、小栗のみょう跡をつがせた。 小栗を斬ったのは丹波篠山の剣客原保太郎(当時二十二歳)で、その後岩倉に従って外遊、滋賀県知事時代に大津事件に遭遇し、その後貴族議員、赤十字社常議院となって八十九年の生涯を日の当る場所で過ごした。小栗のおい蜷川新が、その真相を知ったのは大正八年、斬首の五十一年後である。蜷川は原に会って、そのときの状況をはじめて知ることができた。 「何故に小栗を斬殺したのですか?」 という問いに原は答えた。 「板垣参謀から、厳重に処分せよと命ぜられ、その命令に従って斬ったのです。……長州征伐の張本人であり、またフランスから軍艦と資金を得て、長州藩を討滅しようと企てたことが、斬殺の理由でありました」 2019.07.28 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.114~118 蜷川 新 反体制精神を貫き維新をえぐる 小栗 忠順夫人道子の妹、すなわち播州林田藩主建部内匠頭の三女はつは、旗本蜷川 親賢にとついだ。 蜷川家は五千石の大身である。神田川小川町に上屋敷があり、敷地千七百坪、馬場五百坪、建坪七百六十坪で、三十畳の広間をはじめ部屋数は五十九もあった。小石川には下屋敷があり、敷地五千坪、ここに中二階の家屋があった。 維新の変動を迎えたとき、親賢は三十六歳、はつは三十一歳。小栗家に長女が生まれたのと軌を一にして蜷川家にも長女あかが生まれた。 将軍慶喜が退隠、徳川宗家を五歳の田安 亀之助(徳川 家達:いえさと)がつぎ、駿河、遠江、陸奥の一部を合わせた七十万石の大みょうとなった。亀之助が百人ほどの家来に守られて東京(西暦一八六八年七月十七日改称)を出発し、駿府(静岡)についたのが八月十五日である。 江戸占領軍が旧幕臣の屋敷没収命令を出したのは七月十六日である。このとき蜷川家の上屋敷は没収され、さらに十月下屋敷も没収されることとなった。武士としての親賢には、二つの道しかなかった。「帰順」して<朝臣>となるか、駿河に「無禄移住」するかである。親族の大みょう、高級旗本の中には「朝臣」となって没収を免れるものが多かったが、親賢は「旗本としての意地に生きることを決意した」(坂井誠一『遍歴の武家』)。 駿府移住を決意して家財道具を売ったところ、八千両になったというが、これは大したことである。騎兵頭の益田孝は、「帰商」を決意して小石川の家を売ろうとしたが一文にもならず、ようやくへっついの銅壺が三両二分に売れて、それをもって横浜へ行った、と語っている(『自叙益田孝翁伝』)。こういうドサㇰサで、二束三文にたたかれやすい情勢下に古道具で八千両にもなったということは、いかに蜷川家が裕福であったか、道具類が上等のものであったかを物語るようである。 蜷川家が裕福になった一つの理由は、側用取次の職にあったことらしい。大みょうたちが将軍のご機嫌伺をするには、この側用取次を通じなければならなかった。そこで大みょうたちは、定期的に進物をとどけた。目録には「御太刀一腰」とか「御馬一匹」とか書かれ、内容は黄金であったという。この「役得」によって蜷川家の財産はふくれたのであった。 親賢が使用人をつれて総勢二十人、東京を出発したのは明治元年十一月七日である。無禄移住者は総数三万余といわれるがそのほとんどは三千石以下の旗本、御家人、徒士であり、駿河藩の役人になった者をのぞくと、三千石以上の旗本は、蜷川と阿部邦之助(三千石)だけであった。 静岡で二女かつが生まれ、明治六年一月に初めて男の子新がうまれたが、誕生五日前目に親賢は熱病で急死した。未亡人はつは、あか、かつ、新の三児をつれて上京、神田五軒町の建部家に寄留した。すでに小川町の上屋敷はこわされて小学校が建っていたし、下屋敷は大学のしょく物園となっていた。旧幕臣の子女で、芸者、茶くみ女などになったものも多かったし、市ヶ谷見附の土手では首くくりが絶えなかった。こういう暗い雰囲気の中に、新は成長していった。少年の日、隣の一狂人が欅の大木の切り口を棒でたたきながら、 「天子の畜生! 日本政府の畜生!」 と叫ぶのを見て異様な感銘をうけた。 静岡の財産管理者から毎月二十円ほど送金してきたが、明治二十年突然打ちきられた。未亡人は十五歳の新たちと六畳、三畳二間しかない借家にうつった。新は苦学しながら第一高等中学校、帝国大学のコースを進んだが、同時に独特の反体制=反骨の精神も育っていった。一高時代、親友渡辺千冬(のち浜口内閣法相)、五来欣造と「真面目」という回覧小冊子をつくり、新は「華族論」を書いたが、その中には「余ㇵクロームウエルヲ愛シ、又足利尊氏ヲ愛ス……」という一節がある。それを評して渡辺千冬は「豈(あに)計ランヤ、幕下ふ平ノ士ハ、岳南(新の雅号)其ノ人ノ如キふ平児ヲ生マンㇳハ。……岳南ニススム、君ノ一生ヲ通ジテ之ノ主意ヲ忘ルルナカレ。注目シテ我ㇵ君ノ為スㇳコロヲ見ル」と書いた。まことに新の人生は、此の基本的姿勢で貫かれたのである。 大学生となった新は、内務大臣西郷従道に「国有土地下戻申請書」を提出し、没収された小石川下屋敷の返還を求めたが却下されたので、今度は内務大臣を相手に行政訴訟を起こし、これは八年目に棄却された。すでに韓国政府財政顧問となっていた新は、この判決をふ満とし、「全然事実ㇳ法理ㇳニ背反スルモノ……形式ハ裁判宣告ナリㇳ雖モ、実質ハ政略ニ基ㇰ行政処分」という批判文を知友に送った。 新は外交官試験をうけたことがある。試験官は石井菊次郎(のち大隈内閣外相)でフランス文を読まされた。新がスラスラと読むと、石井はその意味をたずねる。 「わかりません」 「何故か?」 「単語が二つわかりません。それで意味がとれないのです」 「教えてやろう」 「試験場に出てきて、知らない文字を教えられては私のふめい誉です」 石井は怒っていった。 「それならば、もうよろしい」 不合格であったが、いかにも旗本の子孫らしい気骨のある行動>と坂井誠一はほめている(前掲書)。 外交官にならなかった新は、国際法学者となり、法学博士となった。大正以降は、徳富蘇峰に望まれて同志社大学教授となり、国際法・外交史を教えるかたわら、国際赤十字連盟の仕事に貢献した。 昭和五年以降、駒沢大学教授以外の公職を退いて大磯の吉田元首相邸隣に閑居し、著述に専念し、敗戦を迎えた。そして沈黙を守ること七年、七十九歳のとき神田共立講堂で「国防の声と憲法蹂躙」という講演を終わったあと、猛然と著述活動をはじめた。わずか五年間に『愛国者への道』『天皇』『維新正観』等、十数冊出したのであるから、その仕事ぶりは壮者をしのぐというよりも何か異常な狂熱を感じさせる。無論、仕事の量でそうであるとともに、その内容のはげしさが目をみはらさせるのである。 ことに『維新正観』は、反国定教科書的立場で維新の醜悪さをあばき、「彼等は薩長藩閥政府を作ることによって、慶喜が自ら進んで放棄した権力を、天皇のなにかくれて詐取したにすぎない。彼等の眼中には天皇もなく、国もなく、人民もなかった」と書いている。頼山陽は、上杉謙信の心情を「遺恨十年」とうたったが、蜷川新の場合は「遺恨八十年」の感じがする。どうやら「明治百年」の背後には、「遺恨百年」があるようだ。 2019.07.30 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.119~123 小室 三吉 買われたその愛社精神 松平春嶽は、幕府の政事総裁、明治政府初代民部卿などをつとめたが、その政治活動の基盤は、横井 小楠のようなすぐれた学者を招いて賓師とし、原理原則を教えてもらうと同時に、各地にバラまいた多数の情報係に、さまざまの出来事を報告させることにあったようである。 情報は、ごく薄手の紙に「一ミリの空白をもむだにせず、ごく細字で隙間なく書きこまれて」(小池 藤吾郎編『幕末覚書』)あったというが、その一つとして、京三条大橋より南一町ほどの河原に、三つの木像の首がさらされていることが報告されたのは文久三年二月、小栗忠順が梟首(きゅうしゅ)される五年前のことであった。 木像は、等持院におさめてあった足利尊氏、同義詮のものである。人間の生首ではないがほかならぬ足利三代の首となると、単なるいたずら、いやがらせをこえた深刻な意味をもっていた。小池 藤吾郎によれば「足利三代の木像は、実に将軍家を代表する。これは徳川将軍家にとっても、たまらない一種のふ𠮷の前兆にみえたであろう。連想は徳川 家康、秀忠、家光三代のそれに及ぶ。足利家の冒涜であるとともに、徳川将軍家の抹殺……」という意味がある。この意味から、幕府は木像梟首を重大視し、京都守護職松平 容保(まつだいら かたもり)の家来たちは嫌疑者十四めいを逮捕し、うち五めいは無罪で釈放した。逮捕された中に、烏丸三条下ル、小室 雄太郎手代十蔵(四十歳)がおり、やがてその主人の小室 信夫(しのぶ:二十六歳)も検挙されて、阿波藩につながれ、在獄五年、慶應四年正月に釈放された。 彼の実家は丹後国(京都府)の豪農兼縮緬(ちりめん)生糸問屋であり、信夫は京都支店の監督をしているうち、尊皇攘夷運動に加わったのである。 信夫は、明治新政府になって岩鼻県知事をしたあと、民権議院設立建白書の署めい者の一人となったが、「家業にして振るわざれば富国の基礎立たず」という考えから実業界に進出し、大阪築港、小倉製糸、奥羽鉄道、六九銀行、北海道製麻会社、京都鉄道会社に関係した。また、明治十六年、三菱に対抗するため、三井系で設立された共同運輸会社では、創立委員をへて理事となった。三井物産社長益田孝と親しくなったのはそのためであろう。やがて信夫のせがれ三吉は、英国留学のあと三井物産に入社し、上海支店長上田安三郎の下に配属された。 上田寿四朗氏(安三郎四男)からお借りした益田孝と上田安三郎の往復書簡を見てみると、明治十八年以降の分に小室三吉のな前が出てくる。上田支店長は小室を非常に信任したようである。 ちょうどこのころ、益田の弟英作も物産にいたようで、上田はその上海支店配属を希望したらしく、「令弟英作氏を当地に御派出下されたく御所望申上げ候ところ御許容云々」と感謝しているが、社長の弟よりも小室の方を高く評価したことは、十八年末、本社に提出した「社員昇等ならびに増額願」を見れば明らかである。上田の下には九めいの部下がいたようで、そのうち手代二等月給二十五円の福原栄太郎がトップで、これを「手代一等銀貨四二十円」にしたい、と上田は書いている。「手代三等十五円」というのが小室三吉と益田英作の二人であったが、小室を「手代二等銀貨三十円」に、益田を「手代二等銀貨二十五円」にというのが上田案である。五円の格差をつけたわけである。 この「格差」、ことに社長の弟を低くしたことについては、社長自身に釈明の要がある、と上田支店長は考えたようで、十九年二月、益田個人への親書において、二人の人物論がのべられている。 「……小室三吉と益田英作とは、益田の方古参にして事務も充分出来候ことは承知まかりあり候へども、当方ではさしあたり小室の方、当方の商業に馴れ、別してこのたび香港に派出後、本人の動作をとくと注目いたし候ところ、諸事取扱方いたって深実にして、労をおしまず勉強にして人に功をゆずり、事の細大となく会社の得失を思考して要点に着目し、つねに人にまじはるに温和にして礼譲あつく、なかんづく身の品行は一点の申し条もこれなく、その会社のためにつくすの精神は勿論じつに感心まかりあり候。この人この姿にて末ながく会社に従事するものなれば、まことに当社にとりて大なる幸福にこれあり。かかる人物はなるべく重く登用して本人には倊々その童心を(?)「せしめ、一つは他の標準とも致し候方しかるべく存じ奉候。英作氏、小室に劣るにあらざれども、不幸にして当地にくることおそく、いまだこれまで充分智才を示すの機会を得られざりしことに候間、必ず成すことあるは存じながらも、私としては小室の方を一歩進めざるを得ず勘考申し候。……」 まことに条理をつくしためい文という気がする。上田はこのとき三十二歳でもとより経営学などの学問はなかった。しかし、見知らぬ異国で一軒一軒「三池炭」を売りこんでいくという血のにじむ体験が、人間をどこでどう評価すべきか、を学ばせたようである。勤務評定をどうすべきか、上田は「知識」ではなくて「生活体験」としてわかっていたようである。その上田にこれほどの評価されたのであるから、小室三吉ももって瞑すべし、ということになろうが、反面、社長の血族関係よりも個人的能力を優先させた支店長、それを容認した社長がいてこそ、会社は本当に伸びたのであろう。戦前における「三井物産」発展のかげにはいろいろの原因が数えられるであろうが、この「昇等増額願」一件の人事政策こそ、その重要なキメ手ではなかったろうか。 さて、益田孝は、弟に格差をつけた上田を、その年「元締役」に抜擢した。これは<平重役>ということらしく、それまでは馬越横浜支店長、拝司長崎支店長の二めいだけで、上田といっしょに松岡譲(函館支店長)、宮本新左衛門とが元締役になったらしい。 明治二十五年四月、上田は「三井物産会計委員」(役員)に任ぜられ、本社の「専務委員外国部受持」となり、後任支店長に小室が昇格した。 小室がとくに信任して身辺から離さなかった部下が山本条太郎である。山本は、前にのべたいきさつで頼朝丸に左遷されていたが、明治二十一年三月、上海支店勤務と、小室が支店長になったときは二十六歳であった。山本が商法上英文をしたため小室に提出すると、ときどき筆を加えて訂正された。山本のは頼朝丸での独学、小室はロンドン仕込みでそこには格段の差がある。山本はこの訂正をうけたときはそのままにせず、必ず別紙に写しとって大切に保存した。傲岸不遜(ごうがんふそん)といわれた山本にも、このような謙虚さ細心さがあったが、それは小室の人間的魅力があったらこそ、とも思われる。 2019.07.30 |
 小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.124~128
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.124~128
馬越 恭平 かつての部下を会社再建に登用 三井物産横浜支店長であつた馬越恭平は、その前に大阪の宿屋の主人だったことがあり、商売にかけては社内第一という自信をもっていた。当時さかんであったドル相場にも手を出し、大いにもうけたつもりで、会社主任の石光真澄をよびだし、利益計算をたずねてみた。すると石光は、利益どころか、かなりの搊だ、という。馬越は真っ赤になって怒り、そんなバカな計算があるか、としかりつけた。 石光は帳簿をもってきてくわしく説明したが、馬越はなつ得せず、そばにあった筆で黒々と帳面に線を引いた。 「こんな帳面があてになるか。おれの勘定ではたしかに利益があるはずだ」 とどなった。すると石光は姿勢を正し、 「支店長、計算は決してまちがいのない組織になっておりますから、まちがいはあなたの胸算用でありましょう。しかもその上、あなたは帳簿面に墨を引かれたが、商店の会計帳簿なるものは神聖にして侵すべからざるもの、いかなる地位の人でも、これを毀損し、これを無視することはできません。あなたがしいてそのムリを押し通そうとするのなら、あたくしにも相当な覚悟があります」 と馬越にせまった。三等手代、月給八円の吹けばとぶような存在とはいえ、必殺の気はくがこもり、そのことばには一分のスキもない。さすが自信家の馬越にもこれには参って、沈黙することしばし、やがて、 「ああ、おれがわるかった。どうか勘弁してくれ」 とあやまったが、石光は承知しない。 「あたくしに対する申しわけはそれですみましょうが、この帳面を汚した以上、店に対して謝罪してもらわねばならぬ。それはどうしますか」 とつめよった。馬越は、棒をのんだように硬直し、無言のまま帳簿をもって神棚の前にいって供え、パンパンと柏手を打ち、頭を畳にすりつけること三回、ようやく許してもらったのである。 傲岸の支店長を理で屈ぷくさせた石光は、熊本の産、父真民は細川藩の産物頭頭取をつとめた清廉剛直の士、生家のあった本山村には横井(小楠の家)、喜悦(孝子の家)、古荘(幹郎大将の家)、金森(通倫の家)等々、多くの人材を輩出させた家がならんでいた。 真澄はこの家の長男で、従兄の浮田和民(法博、早大教授)、下村孝太郎(工博、大阪瓦斯初代社長)などと熊本洋学校に通っていたが、明治九年廃校となったので上京し、やがて三井物産横浜支店にはいったものである。 明治十五年、次弟真清が上京すると、真澄は双子木綿の着物に角帯、前だれかけというスタイルで出迎えた。弟は、その姿に軽蔑の念を感じた。 真清は叔父野田 豁通(のち男爵、貴族議員)の家に身をよせたのち、柴 五郎(のち陸軍大将)のもとにあずけられた。柴は、野田が初代青森県知事時代、旧会津藩士の子弟二めいを県庁の給仕に採用したときの一人で、当時近衛師団砲兵連隊付中尉であり陸軍幼年学校を志望している真清のためには都合がよかろうというわけであった。「遊びから完絶された私には、兄真澄が訪ねてくるのが唯一の楽しみだった」(『城下の人』)と真澄は回想している。 真澄は月に一回、勘定のため高崎へ出張する。そのときは前夜に上京して、翌早朝、万世橋の馬車立場から乗合馬車で出発、二日ほど滞在して帰京するが、強行軍でへとへとに疲れていた。にもかかわらず真澄は弟をつれ出し牛肉屋などで夕食をたのしんだ。弟の小遣いは月一円で、それも真澄がやっていた。「八円の月給のうちから一円あたえることはずいぶん苦痛であったろうが、私は一向にそんなことに頓着なく、予算を超過しては臨時要求することがしばしばであっいた。兄は嫌な顔もしないで、そのつど三十銭、五十銭と追加してくれた」(前掲書)。支店長をトッちめる剛毅の反面に、このやさしさをもつのが真澄であった。というよりも、そのやさしさのゆに、自分の人生を犠牲にした面があるとさえいえる。 父が死に、母もまた重態になったのが明治十七年、真清が幼年学校にはいったつぎの年である。母は、長男の結婚を見とどけなければ死んだ夫に顔を合わせられない、といいだし、孝心深い真澄は、恩師元田 永孚の紹介で河野某とあわただしく挙式したが、この新婚生活は一月で破れた。母は熊本に帰るといいだし、真澄は三井物産を退社して同行することとなった。熊本では、母の希望で旧藩士戸田家の娘と結婚したが、今度は十日目に花嫁が行方ふ明となった。約束した男があったのである。 真澄は母の看護に全力を打ちこみ、ようやくもち直すと、当時では珍しい人力車を買って、朝夕、母をのせ、自分で引っぱって散歩した。これを毎日見ていた喜悦孝子(日本女子商業創立者)は、<ああ私は親への尽し方が足りないと深く自ら省みたのでした。それ以来村には親孝行な人が出来ました>と語っている。 親孝行もほどほどにせい、と親戚のものはいい、母を説得した。真澄は三度目の妻をもらって上京し、三井物産横浜支店に復職したが、妻をコレラで失い、物産は益田社長と経理問題で衝突して退職した。このあと、いくつも会社をつくったが、すべて失敗した。しかし母には一切を秘密にしていて、三井時代と変わらなく生活費をわたすところに血のにじむ苦心をしたが、母はそれを知らず、一向にパッとしないふ甲斐なさを責めることが多かった、「兄は私の手を握ってあるときは嘆き、あるときは自嘲し、私には耐えられないことが多くなった」(前掲書)。 このとき、救いの手をのばしたのが馬越 恭平である。彼は明治二十四年、破産直前の日本麦酒醸造会社の再建をまかされた(物産は二十九年五十三歳で退社)。このとき、支配人に、かつての剛直の部下を起用しようと考えたのである。彼は真澄のがん固さにほれ込んでいた。これからの事業は、信用と資本と組織だが、一番大切なものは信用だと考える馬越は、真澄の正直と誠意を再建のカギとしたのである。彼は真澄の母にも会って、 「良いご子息をおもちです。人は勉強によって術を得ることはできます。生まれながらにそなわった誠意というものは、数万貫の鉱石の中から掘り当てた宝石のように貴いものです」 と賞め、よろこばせた。 真澄は会社構内の小さな社宅に住みこみ、昼夜をおかず働いた。暇があれば構内の古釘などをあつめビール箱をつくった。業績は立ち直ったが、わずか三年目に、心身をすりへらした真澄は急逝したのである。しかし馬越は彼の功績を忘れず、その遺族に対する援助、命日の礼拝、正月の来訪を、大正、昭和と四十数年間、その死にいたるまでやめなかった。 2019.05.24 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中央文庫)昭和五十八年八月十日 P.129~133 より。 石原真清 軍人やめて諜報活動 年代職業などの区別をこえて、旅をする人の記録は心にしみるものがあるが、この数年間に読んだもののなかでもっとも心に残ったものは『菅江真澄遊覧記』(東洋文庫)と、石原真清の手記による『城下の人』『曠野の花』『望郷の歌』『誰のために』(いずれも竜星閣)であった。つまりその記録を残した菅江真澄(本めいは白井秀雄)と石原真清の、旅にその大半を消費した生涯の哀れさに強く胸をうたれた、ということである。
これにくらべれば、石原真清の旅の原因は明白であった。三井物産横浜支店員の兄真澄に迎えられて東京の土を踏んだ真清は、明治十六年に陸軍幼年学校にはいった。五十一めいの生徒は二班にわけられ、真清は第一班にはいったが、第二班の取締生徒(三年生)橘周太(のち軍神橘中佐とうたわれた人物)を敬慕し、そのいうことなら何でもそむくことがなかった、というところにその人柄を示すものがある。橘もその真情に打たれ、二十二年に士官学校を卒業した真清が近衛歩兵第二連隊付きになったとき、卒業祝いとして伝家の宝刀一文字を贈った。 やがて三弟真臣(のち中将)も士官学校にはいり、連隊づとめの真清とともに、日曜祭日の休みには兄真澄の社宅を訪ねた。真澄は馬越恭平にたのまれて恵比寿麦酒会社の再建に打ちこんでいた。そこで弟たちも軍ぷくを仕事着にかえて一日中工場の古クギ拾いや箱造りをしたという。真清は兄に人力車をプレゼントした。一台二十五円、少尉の俸給は二十九円五十銭。「私には少々骨が折れた。兄は涙を流さんばかりに悦んで、毎日この車に乗って活躍していた」(『城下の人』)。 兄を訪ねない日は橘を訪ねた。彼は紺がすりの着物の前をキチンと合わせて机に向かい、寸暇をおしんで兵の教育指導要綱を起草中であった。「……兵汗を拭わざれば拭うべからず。兵休まざれば休むべからず。兵食わざれば食うべからず。兵と難苦を同じうし、労逸を等しうする時は、兵も死を致すものものなり。信用は求むるものに非ず。得るものなり……」。そういう文章に感動する真清は、やがて職業軍人としての栄進とは関係のないところで、国のためにつくそうと考えるようになる。 日清戦争では台湾に出征した。新橋駅まで送りにきた真澄は、真清が宇品から輸送船にのる前日、急性肺炎で死亡した。悲しみを胸に秘めて転戦し、やがて凱旋して功五級金鵄勲章勲六等瑞宝章を賜った。だが彼の心は、三国干渉でその野心を露骨にしたロシア帝国にひかれ、ロシア研究の必要を感じ、ロシア語を学びはじめた。三十歳で妻を迎えてもその決心はかわらず、参謀本部田村怡与造大佐の了解のもとに、休職願とロシア留学願(私費)を出し、三十二年六月、許可がおりた。このときをもって、真清の軍人生活は事実上終わったのである。 最初の留学地はブラゴペシチェンスク。菊地正三という仮名の真清は、在留シナ人三千めいが、子供にいたるまで殺されたアムール川の濁流に葬られる惨事に直面したあと、ハルピン潜行の命をうける。いのちがけのその旅で彼のいのちを救ったのは日本女――馬賊の妾などになっている薄倖の娼婦たちであった。真清は予備役となり、写真館を開いて諜報活動を行う道を選ぶ。<国につくす道に現役と予備役のちがいはない。軍人としての栄誉を捨てて国家のため生涯を捧げてくれ>と伊地知少将にいわれたとき、 「銃声こそ聞えませぬが私にとって満州は激しい戦場であります」 とかれは答えた。しかし、そのための旅がいかに大きな犠牲をしい、しかも報いられることのないものであったかは、晩年においてはじめて悟るのである。 三十七年早暁、ロシア憲兵にたたき起され、日露開戦による国外退去を命ぜられて、無一文で日本にもどったものの、すぐに招集されてまた満州にわたった。 凱旋後、また満州に行ったのは参謀本部の田中義一大佐(のち大将、首相)にたのまれたが、四十年八月、無一文で帰国せねばならなかった。ロシアに勝って国際的地位も向上し、官界も軍部も自信をもって近代国家への組織化に急であったが、それは反面、軍の官僚化となり、原住民への威圧と変っており、真清の心は痛んだ。 真清は今度も日本におちつくことはできなかった。叔父野田豁通(男爵)を中心につくられた会社の仕事に、半ば強制的に引きこまれたためだ。しかしこれも失敗して帰国した彼は、四十二年から世田谷村の三等郵便局長としての静穏な生活にはいり、ようやく妻子との日常生活に人間としてのしあわせを味わうことができた。だがその喜びもつかの間、またもや大陸行きの仕事が彼を引きずりだした。満蒙貿易公司の満州商品陳列館経営が表面のめい目、実は英国の利権侵略に対抗するため、陸軍が立てたプランで、その仕事について間もなく、すでに少将となっていた同期の生高公通(都督府参謀長)から、黒竜州アレキセ゚―フスク付近の諜報勤務命令をうけとった。「シベリアの冬は暮れやすく、人の生涯は移ろいやすい。青年将校の軍ぷくをぬいでブラゴペシチェンスクに初めて留学した日から二十年……この貴重な歳月の二十年をいつしか過して私は五十歳の身を久しぶりにこの地に運んだ」(『誰のために』)と彼は書いている。そしてソビエト革命下の動乱にまきこまれ、いのちがけの体験にもとづく献策も司令官大井中将に一蹴され、君は一体だれのために働いとるんだ、ロシアのためか、と罵倒された。 帰国したあと、郵便局を失い、愛妻の死、借金の山に押しひしがれ、失意のうちに七十六年の生涯をとじるときは、おのれの過去を嫌悪していたという。私心なく奉公した彼には何の報償もなく、くだらぬ男たちが勲章と爵位で胸をそらしたのが、帝国日本の一面でもあった。上記四冊の本はその手記をもとに一人むすこの真人が編んだものだが、「一国の歴史は、一民族の歴史は英雄と賢者と聖人によって作られたかのように教えられたが、野心と打算と怯懦と誤解と無知と情性によって作られたことはなかったか」と、血を吐く思いの疑問が書き留められている。 ※プロフィル:石光 真清(眞清)(いしみつ まきよ、慶応4年8月30日(1868年10月15日) - 昭和17年(1942年)5月15日)は、日本陸軍の軍人(最終階級陸軍少佐)、諜報活動家。明治から大正にかけてシベリア、満州での諜報活動に従事した。 明治元年(1868年)熊本に生れる。少年時代を神風連の乱や西南戦争などの動乱の中に過ごし、陸軍幼年学校に入る。陸軍中尉で日清戦争に参加し台湾に遠征、ロシア研究の必要を痛感して帰国、明治32年(1899年)特別任務を帯びてシベリアに渡る。 日露戦争後は東京世田谷の三等郵便局長を務めたりしたが、大正6年(1917年)ロシア革命の後、再びシベリアに渡り諜報活動に従事する。 帰国後は、夫人の死や負債等、失意の日を送り、昭和17年(1942年)76歳で没した。没後に石光真人が編み完成させたのが手記(遺稿)四部作『城下の人』『曠野の花』『望郷の歌』『誰のために』である。この四部作は、毎日出版文化賞を受賞し、また伝記作家の小島直記など、多の識者が自伝のめい作と評価している。 ※参考:森銑三著作集 続編 第5巻 森銑三/著 中央公論社 出版年月 1993年6月 に掲載されている。 |
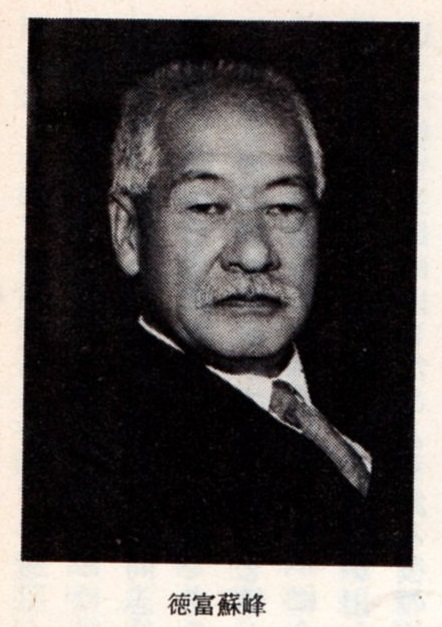
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.134~138 徳富 蘇峰 福地 桜痴を慕い記者志す 昭和四十二年夏に出た『京都二十景』という本は旅情を大いにそそる。ことに空気のうまさ、町をとりまく山なみの稜線の目を洗うようなあざやかさ、舗装した道の下をながれる溝のせせらぎが耳につくほどの静けさ、鷹ヶ峰、下六丁峠、苔寺のほとり、鞍馬街道、今熊野の泉涌寺、嵯峨野の上の菖蒲谷池、山科の疎水べりなど、「恋を語る散歩道」という形容詞をつけられたあたりは、一人でもいいから歩いてみたい衝動を感じる。 今日においてもこういう自然環境なのであるから、約九十年前、同志社入学を思い立った徳富猪一郎が訪れたころはどんなによかったかと思われるが、『蘇峰自伝』には、その印象をつたえる文章は一行もなく、明治十三年十八歳のときつくった「京都」とい詩は、「春帰春去遂如何。五歳星霜容易過。恥汝東三十六峰。屏顔依旧翠烟多」というもので、明治青年の一タイプらしく立身出世を思う気持が強く出ている反面、詩的情熱という面は淡いように感じられる。 それはそれとして、徳富が東山三十六峰を眺めて感慨にひたるまでには、いくたの迂路(うろ)をたどっている。郷里水俣を出たのは明治三年、八歳の秋で、彼をつれていったのは横井小楠未亡人、すなわち母の妹津世子(つせこ)であった。 そして熊本時代がはじまる。いくつかの塾を転々として熊本洋学校にはいったのが十歳のときで、このときは成績が上がらず、年齢不足の名目で退校させられ、八年夏、再入校した。九年一月、小楠の忘れ形見時雄、金森 通倫(みちとも)、海老な 喜三郎(弾正)、浮田 和民など有志三十五めいによる「花岡山事件」がおきた。彼らは熊本の西南にある花岡山にのぼり、円坐して「奉教主意書」を朗読し、神に祈り、誓約署めいしたが、その中に徳富のな前もある。ただ彼は、「予の真意は深くキリスト教を研究して、それを信じたのではなかった。もとよりキリスト教のために一生を捧ぐるという了見は露ほどもなかった」(『自伝』)と述懐している。 学校のキリスト教化は大問題となり、彼らは父兄たちに猛烈な圧迫をうけた。徳富も自宅によびもどされ聖書と讃美歌を焼かれ、父一敬にきびしく折檻(せつかん)されたあと、上京して勉強しなおすことになったのである。 一方熊本洋学校は閉鎖され、学生の一部は外人教師の紹介で、前年十一月に開設されたばかりの、京都の同志社英学校にはいった。彼らは「熊本バンド」といわれ、その学力とまじめな素行を創立者新島 㐮に高く評価されたが、彼らも新島に建白書を出し、酒、タバコはもとより、買い食いしない、料理屋へ行かないなどの塾則案を示し、採用された。 東京で神田一ッ橋の東京英語学校に入った徳富は二月ほどで絶望し、京都に金森通倫を文通したあと、親戚の反対を押しきって同志社入学を決行した。「予は学校は書物を読むところというよりも、むしろ師について学ぶ処であるという考えをもっていたから、その場所を東京において見出さず、京都において見出さんと欲したのである」。 しかし、同志社には絶望した。第一に食事に閉口した。麦飯がきらいで、親戚にとまって麦飯が出ると一日ぐらいは絶食し、麦飯が出ないと「今度は麦飯これなく、ご安心下され候」という手紙を父母に出したこともある彼の前に、麦の中に牛肉の塊を入れて煮たものがほとんど毎日出された。肉は引き出して細かく切り、菜っ葉とともにスープにし、麦は茶わんにもって食べるのであるが、「麦飯ともつかず、ただザラザラに煮たものをすすりこむことは、予にとって少なからざる苦役であった」。 その上、学費がなくなった。東京をたったときもってきた三十円は次第になくなったが、無断転校をしたため、郷里にいってやるわけにはゆかない。「絶望の倹約」で、着物も一度きたらそれが切れてなわのようになるまで替えない。しかし、とくに必要ないかぎりは帯もとかずに起臥(きが)し、ふろにもほとんどはいらないため、学生たちは彼のそばに近づくのをいやがるようになった。旅の途中に彼とあった従兄は「猪一郎さんはまるで乞食のような風をしている」という報告書を送ったほどだ。 徳富の心を苦しめたのは貧乏ではなく、「何事もアメリカ、アメリカといい、日本の事を全く忘れているような」学校内の空気であった。明治十年、新島の説教のあと、外国の飢饉(ききん)にたいする救助金募集があったとき、たまりかねた徳富は声をふるわせて立ちあがり、「今わが国には戦争があり、私の郷里熊本には、これがために非常なふ幸に陥っているものがある。それらにたいして救助することをせず、縁もゆかりもない他方の人の不幸を救うのは、前後緩急をあやまったことで、いかに結構でも私一人として賛成できない。故に私は寄付をことわる。しかしもし西南の役においてふ幸になったものを救うならば、自分だけのことはするつもりです」と叫んだ。 宗教書を読むことよりも、彼は新聞雑誌をむさぼり読んだ。自分で買う余力はなかったが、同志社には、東京のものでは『東京日日新聞』、『報知新聞』『朝野新聞』が、大阪のものでは、『大阪日報』がきていた。福地 桜痴、犬飼 毅、成島 柳北など、ジャーナリズムの花形の存在も、「花形」として心にきざまれたが、とくに福地の人間像は、徳富の人生に大きな影響をのこしたようである。福地はこのとき三十七歳、各社とも社長級の大物を動員したにもかかわらず、報知の矢野竜渓、朝野の成島柳北とともに京都にとどまって南下しなかったのに、東京日日新聞社長たる福地は、自ら特派員となって現地にのりこみ、「戦報採録」で好評嘖々(さくさく)、紙数を激増させた。そのころ、道楽者として聞えた彼は「池の端の御前」としてぜいたくなくらしをしていたが、従軍にあたっては、家族に後事を託し、愛妓にも手当をして出発したといわれる。そういう裏面をしらぬ福富は福地を敬慕し、ことに木戸孝允の要望に京都御所に伺候し、戦況報告をした一事は、「一布衣(ほい:無位無官)の身をもって謁見仰せつけられ……此事の如きは予の頭脳に少なからざる刺激をあたえたように覚えている」(『自伝』)と彼自身も文章にしている。 同年五月二十六日、内閣顧問木戸 孝允が京都で病死した。享年四十五歳。福地は戦地から電報で原稿を送り、五月二十八日から六月四日まで「木戸小伝」として連載された。「公ノ病ニ在ル、一眼覚ル毎ニ則チ曰ク、某ニ遇ヘリ、曰ク、某来レリㇳ。(中略)一日奄然ㇳシテ睡ニ就キ、将ニ逝カンㇳスル者ノ如ク、而シテマタニㇵカニ大呼シテ曰ク、"西郷モー大抵ニセンカ"。コレヨリ二日ヲ経テ薨ズルㇳ云フ」というこの連載を、徳富は「もっとも愛読した」。そして福音を説く説教師ではなく、一管の筆に慷慨(こうがい)の志を述べる新聞記者になろうという志が、まさにこの京都の時代に確立したのである。 2019.06.29 |
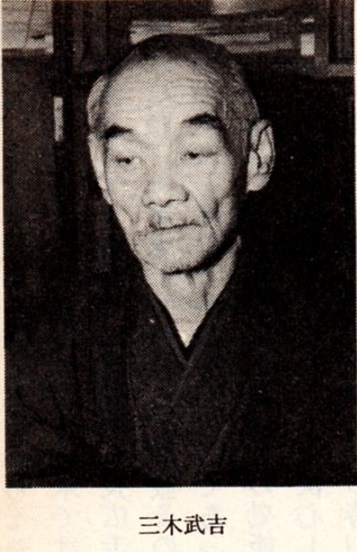
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.139~143 三木 武吉 山県家門前で毎晩演説ぶつ 京都同志社にはいりながら、キリスト教の信仰にはいらなかった徳富蘇峰も、創立者新島襄の人格に魅了され、終生師と仰いだ。新島は明治二十三年四十八歳の若さで世を去った。このとき二十八歳であった蘇峰には、昭和三十二年に永眠するまで、なお六十七年の人生があったわけだが、遺言によって京都若王寺三頭の新島の墓石のかたわらに自分の分骨の墓を建てさせたほどであるから、その敬慕の念がいかに深かったかを思わせるのである。ひとり蘇峰だけではなく、新島の死後もその遺風を慕う青年は全国から集まったというが、その中にうどん食い逃げ事件で高松中学から退校処分をうけた十七歳の三木武吉がいた。 退校させられて郷里を出る前に、武吉は易者に見てもらうと、後年有めいになった三白眼を注視した易者は、 「この目をもっているいる者は天下をねらうものだと古来いい伝えられている。豊臣秀吉も由比正雪もこの双瞳だ。楚の項羽もこれだったと物の本に書いてある。お前は出世するぞ」 と激励した。このあと、同志社中学部の編入試験をうけるまで大阪の親戚のうちにあずけられた。武吉は勉強にあきると市内を歩きまわり、道頓堀の芝居や見世物小屋では、絵看板だけ見て中にはいらなかった。腹がへると、すうどんを食った。 「二銭だったナ。そのときの念願は、一杯五銭のしっぽくを腹いっぱい食うことだった。出世したら、これを食ってやろうと思ったことだ」とは彼の述懐である。 二年の編入試験をうけ、合格して入学してみると、五年生に永井柳太郎という暴れん坊の旗頭がいる。眉目秀麗の長身、剣道は免許皆伝と呼号し、とりすましているところが三木にはカチンときた。ある日、永井は級友・下級生たちにとりかこまれているとき、 「僕はようやく無我の境に達することができた」と自慢しはじめた。いきなりきりつけられても、間髪をいれず身をかわせる。ぼんやりしているようでじつはしからず、八方に構えがある。「これが無我の境地というものだ」、といい気になっていると、 「それは無我の境地とはいえない。有我の境というものだ」と水をさしたものがいる。二年生の三木だ。永井と三木はさっそく口論をはじめたが、そのうち三木は脳貧血でよろめいた。医者にみてもらうと、ひどい胃弱症にかかっているので、長期間の療養が必要だ、という。口論がきっかけで仲よしとなった永井も、からだをつくり直して再起を期すべきだ、という。三木もついに涙をのんで休学帰国を決意した。彼の同志社時代はこうしてわずか数ヵ月でおわる。 翌年六月、胃弱を直して三木は東京に向った。有めいな政客星亨の法律事務所で書生にやとわれることになっていたのでる。ところが明日から事務所に住みこむという日、星は東京市会議事堂で伊庭想太郎に斬殺され、このため武吉の運命もまた大きな余波をうけることとなった。※明治三十四年(一九〇一年)六月二日午三3時過ぎ斬殺された。 彼は神田の駄菓子屋の二階三畳を一月一円の部屋代で借り、昼は大成中学に通い、夜は製本屋で働いた。五時間働けば十銭になる。一ぜんめし屋は一食四銭であったから、一日二食はどうにか食えるという計算であった。すると父の知人である郷士出身実業家中野武英(なかの ぶえい:東京商業会議所会頭)が早稲田にある東京専門学校の学監高田早苗に紹介状を書いてくれ、その縁故で早稲田の学生となることができた。喜んだ郷里の父は、毎月八円の郵便為替を送ってくれるようになり、武吉はようやく愁眉(しゅうび)を開いた。灰色の苦学生とも別れて、人なみに青春を味わえるようになった彼は、まず野球に関心をもった。当時は学習院、一高が野球界の王座についていた。 「学習院や一高が、国の費用で勉強しているくせに、一段偉いような顔をしているのはけしからん。野球でも、やつらの鼻をたたきおるんだ」 と、武吉は五歳年長の学友橋戸信(はしど しん/まこと:文献により一定していない:頑鉄)をたきつけて野球部をつくらせた。橋戸は選手生活をへて野球評論家として世に知られる存在となるが、三木の方は、「彼の将棋におけると同じように、腕前よりはヤジの方がすぐれていた。舌戦というところだ。だから自然ヤジの方にまわることになり、応援団の方に力を入れることになったんだ」と永井は語っている。後年のヤジ将軍は、まず早稲田の森の応援からそのキャリアをはじめたことになる。 だが、単なるヤジで満足できる三木ではなかった。アメリカきっての雄弁家といわれるブライアンが来日して大講堂で二時間余も長広舌をふるったことがある。ぎっしりと場内を満たした七百の学生は、セキとして声なく、静寂そのもので聞き入ったが武吉もその一人であった。はっきりわかったことばは十か二十くらいであったが、なんとなく論述の趣旨はのみこめた。彼は、語学の境界をこえて意思を伝える雄弁の効能に打たれ、自分も魂のはいった弁舌、ことば以上に魂のこもった弁舌のけいこをしようと決心した。 川をへだてた目白には、山県有朋の椿山荘があった。夕食をすませて夜になると、武吉は椿山荘まで散歩に出かけ、豪勢な大みょう門の前にたつと、藩閥政治の非をたたく演説をはじめる。請願巡査が出てきてとがめると、 「天下の公道で演説するのがなぜいかんのだ」と逆ネジをくらわせた。議論となると、巡査は法律学生がニガ手だ。だが、腕ずくでも止めさせることはできたであろうに、それをしなかったのは、武吉の演説が面白く、内心では(その通り!)と拍手していたためかもしれない。追っぱろうとして苦心しているふりはするが、本気でとめようとはしないのである。三木は、表門からだけでは効果がうすいとさとると、横手にまわり、さらに裏口にまわってガナリ立てた。山県は三十二年九月に立憲政友会総裁伊藤博文に内閣をゆずって以来、表面に出ていないが、長閥、陸軍を背景とし、宮中、府中に隠然たる勢力をもつ公爵である。その山県と対決する意気ごみであるから、三木としても政治、政策について真剣に勉強し、それを十分にたたきこんで原稿なしでしゃべりまくった。ある夜、寺内正毅(陸軍大将、のち首相)が訪問していてこの演説をきき、「うむ、狂人か。面白いぞ。狂人でもなかなかスジの通ったことをいうわい」と感心したらしい。しかし毎晩やられる山県の方はカンカンに怒りだし、岡部半蔵伝来の槍術で一刺しとばかり長押(なげし)の長槍に手をかけたこともあったという。 権威にいどむ青春の狂熱とはいえ、山県邸にほえ立てる三木青年の姿は、ヘルメットにふくめん、角材をもち、徒党を組まなければ交渉の場にも出られないような、現代の一部学生よりよっぽど男らしいというべきでないか。 2019.08.05 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.144~148 原 敬 "ひとやま"あてて宰相となる 雅号というものがある。もともと文人、学者、画家などが、実めいのほかになのるものらしいが、そういう実質をはなれて、一般の人間もさかんにつけたものらしい。ひところ日本人には鼻ヒゲが流行した。人間の実質いかんよりもまず外形を整えて、そこに一種の意味をもたせようとするポーズともいえるようで、よくいえば東洋的ダンディズム、率直にいえばスタイリストのアクセサリーということになろう。その人物を判断する一つの手がかりがある。 原敬、犬養毅、尾崎行雄とならべて書けば、日本憲政史上の花形スターを選んだということになるが、これらの人物がすべて雅号にからむ逸話を残しているのは興味がある。 犬養と尾崎が雅号をつけたのは、慶應義塾在学中のことらしい。犬養は「木堂」、尾崎は「琴泉」であった。二人は別々のグループに属していて、まず尾崎が、波多野承五郎、加藤敬之助、桐原捨三などと協議社というグループをつくり、これを横目ににらんだ犬養は猶興社というものをつくった。そのライバル意識が相手方にたいする悪口となり、犬養はとくに尾崎の雅号にケチをつけ、女の画家かアンマみたいだ、と毒舌をたたいた。それは尾崎の耳にとどき、それを気にして尾崎は「学堂」という雅号に変えた。 両雄の間をとりもとうとしたのが波多野承五郎で、その仲介で二人が会ったとき、犬養が、今度は何という雅号だ、と尾崎にたずね、「学堂」だときくと吹きだしたのである。 「学堂とは君、シナではスクール、学校のことだぞ。また妙なものにしたもんだな」 「そういう君はどうなんだ?」と尾崎は反問した。 「おれは、木堂じゃ」。すると尾崎はせせら笑った。「木堂? それは材木小屋じゃないか」 犬養はムクれて、そのまま帰ってしまった。しかし、尾崎も犬養の毒舌が気になったのか「咢堂」と改めている。 のちに「憲政の神様」といわれた両人の初対面は、こうして「雅号」のくさし合いということで、けんかわかれとなってしまった。 「平民宰相」といわれた原敬の雅号は「一山」、これは俳句をつくりはじめてつけたものというが、その発想法は、犬養や尾崎とまるきりちがっている。「山」という字があるのでなんとなくものものしいけれども、要するにその語源は「一山百文」の「ひとやま」であり、安く買える見切り品、非高級品の意味がある。ただ、それは原敬自身の単なる自己卑下の気持でつけられたものでなかったところに、人生的、人物論的意味があった。 原敬は、明治維新における戊辰の役で、賊軍側とされた南部藩の出身である。このとき官軍側に立った薩・長・土・肥のいわゆる「薩閥人」には、自分たちに反抗した奧羽諸藩にたいする敵愾心があり、それはやがて侮蔑心とも変わった。そこで彼らは東北人を「一山百文」と呼んで、侮辱したのである。 原の「一山」は、その歴史的呼称の一山をとったのである。したがってそれは尾崎行雄が、琴をならっていて、その琴の音と泉の流れとを組みあわせて、いわば上品にあるいはキザに「琴泉」という雅語をつくった遊びの心とは別のものであった。おれは藩閥人に侮蔑されている東北人の一人だ、という自己意識が根本にあった。ウラを返せば、いつまでも下風には立たぬ、いずれお前たちを見返してやるぞ、という闘志の表明であり、卑下ではなくて自負のしるし、ともいえたのである。 だが、藩閥政府の秩序の下で、道は嶮しく、遠かった。まず生活の窮迫がある。家老であった彼の家も例外ではなく、十六歳で東京遊学するときは、二十余室あった屋敷のうち、母屋だけを残して売り払った金が学資にあてられた。しかしその金も半年でなくなった。そのとき、財産家に嫁いでいた義母から学資援助が申しこまれたが、彼は断った。伯母の金であるから、もらっても恥にはならぬと思うけれども、同年配の叔母の子に一生頭があがらなくのがイヤだっからで、「一山」らしい気骨と自尊心はこのとき示された。 このあと、麹町にあったカトリック神学校にはいったが、経典を静かに学ぶどころか、第二維新をおこなう方法などを議論して夜ふかしをしたというから、伝道師になる希望で、ダビデという洗礼めいをうけていたとしても、ダビデよりも「一山」が勝ったわけである。ここに一年半いて、新潟天主教会のフランス人宣教師ェプラルの学僕となった。これまた宣教師になるためではなく、フランス語を学ぶためであった。二年後、司法省法学校にはいり、予科三年生のとき賄征伐事件がおきて、秋月左都夫(のち大使)、福本誠(日南、大新聞記者)、加藤恒忠(のち公使)等が夜中に寄宿舎を追いだされた。 原は事件に関係なかったが、学友が夜中に寄宿舎を追いだされたことには義憤を感じ、学校当局にたいする争議の先頭に立って、 「われわれ生徒は学校の規律にふく従すべき義務をもつけれども、いかなる人によっても、良心の自由を束縛される理由はない。校長に心腹するかどうかは、われわれの自由であらねばならぬ」と痛論した。ただちに立って、これに賛成したのが国分高胤(青厓、漢詩人)である。彼は仙台藩であった。つづいて賛成の声を上げたのが陸実(羯南、政治評論家)である。彼は津軽藩出身であった。 ところが校長は薩摩藩出身であった。ここに期せずして、校長に対する生徒の「東北同盟」ができ上がったわけである。「東北同盟」は司法卿直訴を考え、何度か門前払いをくらわせながらもこれに屈せず、ついに面会をもとめて陳情書を手渡し、実情を説明した。司法卿大木喬任は佐賀藩の出身だが、寛厚の君子人で、穏便に処置せよと校長に訓示し、「処罰取り消し」となった。東北同盟は勝ったわけである。 ところが、校長はひそかに報復をねらっていた。事件のほとぼりも冷めかかったころ、春季大試験があり、そのあと、原、陸、国分、加藤、福本など、事件関係者十六人は、理由ふ明のまま、退学を命ぜられたのである。 原は、陸、国分、加藤らと京橋の安下宿にはいった。このとき原は二十四歳、陸、国分は二十三歳、加藤は二十一歳である。 彼らは将来の方針を相談し、官吏など、たのまれてもなってやらない、まず新聞記者、それから国会議員となり、それから天下をとるのだ、と誓い合った。「まず新聞記者」の口にあたって、月給八円の朝野新聞記者となったのは国分である。そして、理想達成を「一山あてる」といういいかたで形容すれば、一山あてて宰相となったのは「一山」の雅号の持ち主だけであった。 ※明治・大正の政治家。陸奥(むつ)盛岡藩家老の子。司法省法学校中退。改進党系の《郵便報知新聞》記者を経て官僚派の《大東日報》主筆となる。井上馨,陸奥宗光の知遇を得て外務省の次官まで進んだ。退官後,大阪毎日新聞社社長。1900年立憲政友会創立に参画。1902年以降代議士。1906年西園寺内閣の内務大臣,1914年政友会総裁。藩閥勢力を切りくずし,1918年米騒動で倒れた寺内内閣のあとを受けて最初の政党内閣を組閣。〈平民宰相〉といわれたが,政友会の絶対多数を背景に強硬施策を行い世論の非難をあびた。1921年東京駅頭で大塚駅員中岡艮一(こんいち)により暗殺。 2019.07.10 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.149~153 陸 羯南(1857∼1907) 健筆、青年の血わかす 靺羯とは、北狄の別種、朝鮮咸鏡道以北より黒竜江一帯にかけて住んでいたツングース族というが、シベリアから北の広い地域をばく然とさす意味もある。原敬とともに司法省法学校をおわれた陸実が、十五歳のとき弘前の古川他山塾で詩をつくり、その一節に「風濤、靺羯の南より来る」と書いたときの靺羯は、あとの方の意味だったらしい。そしてこのことは、「そのころから彼がシベリア方面の外国から来るあらしを忘れないという対外経営の志をもっていたことをそれとなしに語るものであったろう」(柳田泉『陸羯南』)。この詩は古川先生に激賞されたが、陸実が羯南を生涯の号とするるにいたったのは、恩師にほめられたうれしさ以上に、国際政局における危機感、対露政策という問題意識をもちつづけたからではなかったか。 ところで彼は、司法省法学校の前に宮城師範学校に在学しており、その学校も中途退学している。この方は、ある事件の処置について学校のやり方にふ満があり、卒業は目の前であったのに、自ら断固として学校をさったのである。師範学校は、当時(明治七年)士族子弟の生活安定策としては最善のものとされていたし、羯南自身、成績もわるくはなく、ことに詩文においては頭角をあらわし、竹内東仙という先生は師弟というよりも友人として遇したというから、居心地もわるくなかったはずだ。そこ卒業寸前で出てゆくのであるから、潔癖さ、功利的打算と縁のなかった五十一年の生涯は、すでに十八歳のその行動に象徴されていたともいえよう。 法学校時代でも、点取り虫にはならずに自分のやり方で勉強した。学校はフランス法学中心なのでフランス語をやるとともに、「学問は西洋が精緻でよいから、それに従うが、大局的見識を養うには、東洋、漢学(歴史諸子)でなければならぬ」という考え方をし、和漢の書物を手にとったが、一字一句にこだわらず、音や調がまちがっていてもそれにはかまわずに、非常なスピードで読破していった。 少年時代から生涯を通じて好きだったのは諸葛孔明であるが、法学校時代には王陽明の人柄が好きになり、その文章を愛読した。金があれば酒をのんだが、金のあるときは少ないので、もっぱら歩きまわることをたのしみとした。鎌倉、千葉、鴻の台、銚子などに出かけ、国分高胤(青厓)といっしょに関西旅行をして神戸までいったときは、警察署から召喚された。人相風采、敝衣破帽の様子で大久保利通暗殺者の一味と疑われたのである。 法学校の賄征伐では、原敬とともにそれに参加しておらず、その処置について校長を批判し、退学させられたのである。そのとき二十三歳で原、国分、加藤恒忠(拓川)とともに、新聞記者をへて代議士となり、一国の宰相たらんという誓いを立てたことは前回に述べた。その年帰郷して青森新聞の記者兼編集長となったのはその路線をいったものであるが、間もなくやめて北海道紋別の開拓使製糖所の事務員にやとわれたのは、志の挫折、というよりも家庭の事情であった。家庭は窮迫し父は老齢に達しているのに、青森新聞は月給が安くて面倒を見てやることができない。父母の難渋を放っておいて、経国済民を説くのはまちがっているという考え方だったらしい。 しかし、その北海道生活は九ヵ月にすぎなかった。官有物払い下げの問題にイヤ気がさしたのであろう。上京して、フランス文の翻訳で生活を立てはじめ、その訳文が認められて太政官文書局の御用掛になったのが二十五歳の暮である。 彼はここに足かけ五年つとめ、官制改革で内閣官報局となってからも足かけ四年つとめた。それだけつとめても高等官にはなれなかった下っぱの地位であったが、この下積みの期間が彼の人生に決定的な役割をはたした。立身出世を望むだけの男にとってはまことに味気ない数年間であったろうが、羯南の目的、努力の仕事は別のところにあった。彼はこの期間、組織的に本を読む、という一事に打ちこんだのである。ド・メートルの『主権言論』を訳出したのも、その組織的な勉強の一環をなすものであった。二十五から三十二歳までの、その地味な努力が、彼をして「日本の羯南」とよぶにふさわしい地位を約束したのである。単なる出世亡者が位階勲等の階段を上っていっても、本人が死ねば一切はゼロとなるが、羯南はその空虚なもののかわりに不朽の名声を獲得した。その原因がこの忍従の基礎工事なのである。 ところで今「日本の羯南」ということばを用いたが、これには二つの意味がある。一つは、日本的に有名となった言論人という意味であり、もう一つは『日本』社主兼主筆として日本的存在になった、という意味である。 官報局時代、羯南は次長高橋健三と親交を結んでいた。局長青木貞三がやめて東京米穀取引所頭取となったあと、次長の高橋の昇格を期待していたのに、曾禰荒助が局長になったので、羯南は浪人になり、筆で立つことをきめ、兜町で出ていた『東京商業電報』を高橋や谷干城の世話でまかされたので、これを『東京電報』と改め、社長兼記者としてスタートした。三十二歳の春のことである。 『東京電報』は刊行数ヵ月でゆきづまったが、谷干城、三浦梧楼、浅野長勲、福富孝季、千頭清臣、高橋健三の応援で、翌二十二年二月十一日に刊行したのが『日本』である。羯南は社主兼主筆、法学校の退校仲間福本日南、国分青厓がはいり、つづいて古島一雄がはいって編集長の役をはたし、三宅雪嶺が関係し、おくれて正岡子規、中村ふ折、長谷川如是閑なども入社する。 羯南は、「真弓にも征矢にもかへてとる筆のあとにや我は引返すべき>という歌をつくったことがある。原稿を書くのはシナ輸入の毛筆で、急ぐときは、できるはしから一枚ずつしょく字場へわたした。<それで印刷になってみると、堂々たる達意の文章で、笏を把って上に立つの概があった」と古島一雄は語っている。「新聞は政権を争ふ機関にあらず、私利を得る商品にもあらず、博愛の下に国民精神の回復を発揚する……」という彼の刊行の辞のとおり、『日本』は議論一点ばり、ニュースも政治教育方面のものを主とし、三面記事はこれをしりぞけた。 印刷用にはフランスからマリノニ式輪転機を入れ、写真をはじめてとり入れても部数五千部(最大二万部)、また黒田内閣に三回三十一日間、山県内閣に二回三十二日間、松方内閣(第一次)に二回九日間、伊藤内閣(第二次)に二十二回百三十一日間、松方内閣(第二次)の一回七回間の発行停止をくらうというふうで、経営は困難をきわめたが、雄健な文章、あふれる情熱は青年の血をわかし、神田の下宿屋では、この新聞をとるのを誇りとした。五十一歳の死は早すぎたとしても、しとげたことは「男子一生の仕事」とよぶにふさわしい。 2019.06.07記す。
|
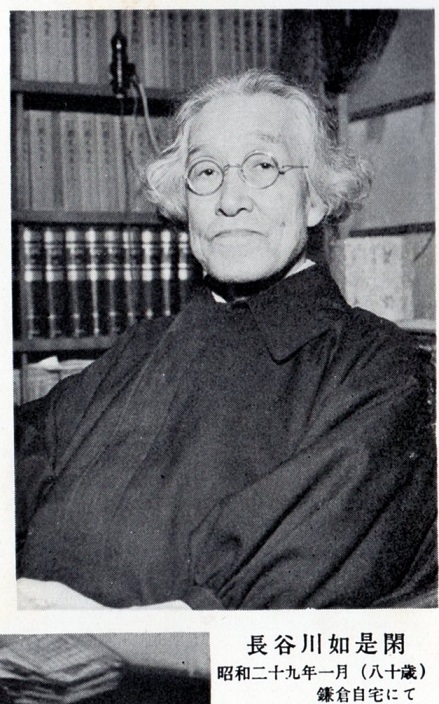
小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.154~158 長谷川如是閑(1875~1969) 記者時代に羯南の影響を受ける 「羯南の識見と文章は『羯南文録』によってその思想の根底をも窺うことができるが、僕の最も遺憾に思うことは、彼をして最も不得意なる経営のことまで引き受けて、その記者たる本分に専念せしめ得ざりし一事である。彼はみょう利に恬淡(てんたん)というよりも、みょう利を卑しむ孤高の国士である。それが社長であり、主筆であるために、彼の天分を十分に発揮することができなかった」と語ったのは古島一雄である。 羯南の文業については二つの見解があった。「僕は子供のとき、日本新聞を愛読したが、陸実という人は全集なんか読んでみると、どうも後世に残るようなものを書いたかどうか知らんと思うな。時事論文はあるけれども、これといってまとまつたものはないですね」と否定的だったは馬場恒吾である。(『三宅雪嶺博士と明治・大正・昭和を語る』日本評論社、昭和十一年十一月号)。 これにたいして、「私はそのころそういう種類の本を広く読んだのではないが、そのころまでの新聞記者や学者の本で、羯南のこの数冊(注、『近時政論考』『近時憲法考』『国際論』)に匹敵するほど学問的のものは、小野梓の『国憲汎論』の他には見た覚えはない。……全く独自の見地……その後の祖述学者のそれとはちがって、たしかに羯南自身のもの」と高い評価をしたのは長谷川如是閑であった(『ある心の自叙伝』)。 このほか彼は「青年の私は羯南のこの『憲法考』と『政論考』とを読んで、『日本』一派の立場に自分を置くようになったのであったが、もし羯南に自由主義にたいするそのような理解がなかったら、私はあこがれの『日本』であったにしろ、恐らくその一派におのれを投じることを躊躇したであろう」と書き、また「私がもしも『日本』にはいる前に、その羯南の『国際論』を読んでいたら、その論旨よりも、そのニュアンスが、私の当時の気分と合わないために、私は『日本』の同人たることを躊躇したであろう」とも書いている。 評価は二つにわかれたようであるが、これは前書を高しとし、後書を低しとするものとはいえないであろう。前書(『政論考』等)と後書(『国際論』)の執筆時点には、約三年のズレがあり、その思想的推移についてゆけなかった、ということであって、原理原則に忠実であろうとした若き如是閑の潔癖感と批判力を示すものであったとしても、羯南の本がつまらない、という意味ではないであろう。価値があると思えばこそ、それを相手としたはずであった。 さて、この如是閑こと長谷川万次郎が東京・深川木場の材木商の次男として生まれたのは明治八年であるから、羯南よりは十五歳下、古一念(古島)よりは十歳下、馬場とは同年だったことになる。病身で、三十歳までのいのちと医者にいわれたが、その如是閑ひとり今なお健在であるのだから、人間の寿命はわからぬものである。 万次郎の父は、論説を主とする「大新聞」をとり、「小新聞」はいかがわしい記事があるから、というのでとらせなかった。そこで子供の万次郎も、ほとんどふりがな新聞を読まず、反面、羯南、雪嶺などのな前には親しみをおぼえていた。 杉浦重剛の東京英語学校(のち日本中学)をへて、東京法学院(今の中央大学)にはいったが、弁護士を目標にしないで、新聞記者を目標に勉強した。学校は半日なので、半日は図書館――それもおもに上野図書館に通った。マルクスの〚資本論〛(英訳)も借りてみたが、歯が立たなった。 そのころ、浅草花屋敷まで経営していた父が事業に失敗した。万次郎は一時休学して、日給四十銭の海軍省雇員となったが、肋膜にかかって、これをやめ、しばらく療養したのち、二年の編入試験をうけて法学院にもどった。学生時代は、めい刺の肩書に「飲食の交際はお断申候」と刷りこんで友人にわたすほど、つきあいぎらいであった。 卒業しても、四年間ブラブラしていた。父は、弁護士の試験準備をしているものと思いこんでいたが、彼自身は「借家のありもせぬ床の間を背にして一日中父は端座し、その二階では、飯の種にもならぬことを考えながら、椅子にかけて一日中海を見ていた」(前掲書)と書いている。じつは歴史と古典に打ちこんでいたのである。日本の古典は博文館の普及版によったが、「直ちにボロボロになるので、二十銭の安本でも、新しく買う余裕もない生活だったので、私はその数十冊を、一々和装の表紙をつけて、自ら製本した。……それを見ると、いつも当時の貧苦と闘いながらの読書を思い出して、涙に目が曇る」という述懐は胸を打つ。 彼はのちに、「万葉集における自然主義」という論文を書き(『改造』八年一月号)、「進歩的な史学者も進歩的な国学者もまだこの領域ではどれほども活動するにいたっていない時期に、これだけ鋭い古代社会批判をこめた万葉集把握はほとんだ例がなく(津田左右吉はべつとして)、読者にきわめて強烈新鮮な刺激を与えた」(小田切秀雄『現代文芸評論集』(一)解説)といわれる業績の背後に、こういう努力が積み重ねられていたのであった。 就職運動は何もせず、友人はこれを評して、「君という男は、弓を引いたって、的をねらんじにゃねえ、いつまでもただ満を持するてやつで、引っぱったまま的が矢の先にくるのを、いつまでも待っているんだと」といわれた。 浪人二、三年目ごろ、匿めいで『日本』に投書した中間読物が縁となって古島一雄らに知られ、三十六年の秋、打ちあわせのために社をたずねると、「いよいよ君に社にきてもらうことになった」と古島にいわれた。 「それはどうも」といったものの、その帰途、あともどりしてことわろうかと迷い、そのままとなった。 入社翌年に、羯南は欧州漫遊から帰ってきた。「文章も文章だが、何よりも羯南の人をひきつけたのは、その人柄だった」」久しく別れていたおじさんか何かに出会ったような、なつかしさを感じて、それだけで『日本』の記者になった幸福をさえ感じ、あのときあともどりしないでよかったと、帰りがけにあらためて思った」。 明治三十九年、羯南は病気で倒れ、『日本』を伊藤欽亮に譲渡し、翌年九月、鎌倉で長逝した。 伊藤新社長は、時事新報編集局長のキャリアもあり、自信満々三宅雪嶺の文章にまで加筆したため、社員は承ふくせず、古島上在中に表題『日本』を勝手に変更するにおよんで連結辞職し、雪嶺の雑誌『日本人』にうつって『日本及び日本人』と改題した。如是閑が行をともにしたことは書くまでもない。 参考:『昭和文学全集・第三十七巻』長谷川如是閑集・大内兵衛集・笠新太郎集(角川書店版)昭和二十九年五月三十日 初版発行 「ある心の自叙傳」「日本新聞のころ」 の記事あり。 2019.06.10記す。 |
31 杉浦重剛 (1885~1924年)

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.159~163 明治三年、政府は各藩に命じて貢進生を選ばせ、学力品行ともに抜群の秀才三百人が大学南校に入学した。大学南校は明治二年にでき五年に第一番中学、六年に開成学校、七年に東京開成学校、十年に東京大学となるが、九年に学生たちが「有名三幅対」として、仲間の中からベストスリーを選んだことがある。 「算数家」としては仙石貢、増田礼作、木場貞長があがった。「書家」としては、河上謹一、高橋健三、内田三省が選ばれた。「遠足好き(ただし無銭)」は増田六一郎、仙石貢、杉浦重剛であり、「貧乏」には杉浦重剛、宮崎道正、磯野徳三郎のながあった。この他「入浴ぎらい」、「放屁家」、「慷慨家」、「漢学家」、「短」、「詩好き」、「近世史好き」、「植物好き」、「芝居ぎらい」等いくつもの部門があった中で、総合得点のトップに立ったのは杉浦重剛であり、河上謹一(のち住友理事)、仙石貢(のち満鉄総裁)がこれにつづいた。 杉浦は琵琶湖畔の膳所(ぜぜ)藩から選ばれた貢進生である。梅が好きで、長女に梅路(夭折)、二女に梅子というなをつけたほか、雅号を梅窓とした。この他、天台道士、破扇子、鬼哭子、礫川、無了居士、安政居士などの号も用いた。このうち天台道士がもっとも世に知られたが、謹一の息子河上弘一が<杉浦先生は少壮の頃より夙に高士の風があったので「杉浦はまるで天台の道士のようだ》と言った父の言葉をそのまま先生がうけいれて一生《天台道士》と号して通されました」(藤本尚則『国師杉浦重剛先生』序)というように、親友河上謹一の命名によるものであった。杉浦の郷里は比叡山に近く、ここは天台宗の開祖最澄・伝教大師が延暦寺を建て、その本拠としたので天台山の異称がある。杉浦は十六、七歳のころ、すでに山僧の風格をもっていたということであろう。 天台道士は、四年の廃藩置県で貢進生制度がなくなり、県費生となったが、これまた五年にやんだので、借金して学問をつづけ、給費制度ができたので、「貧窮願」を出して給費生となっていた。しかし、ふところは寂しくても学問はよくできて、「幅対」金メダルの投票数をあつめたこの年、海外留学生にも選ばれた。この制度は八年からで、第一回は小村寿太郎、鳩山和夫、斎藤修一郎、古市公威、長谷川芳之助、松井直吉、原口要、安東清人、菊地武夫、平井晴二郎、南部救吾の十一人、九年の第二回は杉浦重剛、穂積陳重、沖野忠雄、関屋清景、増田礼作、岡村輝彦、山口半六、桜井錠二、谷口直貞、向坂兌(さぎさか なおし)の十人で、それぞれ専門で一流人となり、歴史になをとどめたが、このうち杉浦の専門は化学であった。 はじめはロンドンにおり、ここは日本人がたくさんいるので、英語を学ぶには日本人のいないところをというわけで、マンチェスターのオーエンスカレッジに学んだ。このときの恩師ロスコ―博士の自叙伝には、「杉浦という男は非常に勝気な性質でつねに首席であったが、あるときの試験に二番に落ちたのを憤り、余のもとを去った」と書かれた(大町桂月、猪狩史山共著『杉浦重剛先生』)。 十三年二十六歳で帰国。このあとの職歴をたどると、同年東京大学理学部博物場掛取締、十四年文部省准奏任御用掛、十五年東京大学予備門(のち一高)長、十八年辞職、二十一年文部省参事官兼専門学務局次長、二十三年六月依願免官、同七月衆議院議員当選。洋行帰りの希少価値で、出世街道をまっしぐらというふうに見えるけれども、じつはこの前後から、天道道士らしい本領が発揮されるのである。 彼は議員たちの腐敗に我慢ができず、病気を理由に辞職した。このあと、松方内閣のとき文部次官をことわり、また芳川顕正文相時代、「称好塾」頭として、じつに多くの人材を育てたのである(これは後述)。その門弟の一人が古島一雄で、もっとも尊敬する四人として、三浦梧楼(観樹)、杉浦重剛(天台道士)、犬飼毅(木堂)、頭山満(立雲)をあげ、四人の寸評を求められて「直言断行は観樹也、立言断行は木堂也。聖言躬行は天台也。ふ言実行は立雲也」と書いた。この四人の間で、おたがいに深く尊敬しあったのは杉浦と頭山で、頭山は「杉浦のすることなら、なんでもヨカ」と無条件で賛成した。 「決して人の悪口をいわない人」天台道士には無数の逸話があるが、自分の貧乏をよそに、親友小村寿太郎を高利貸しから救った話は光っている。名外交官小村は、父の事業の失敗で巨額の負債に苦しんでいた。これを見かねた天台道士は、学友数人の連帯保証で救おうと思い、まず河上謹一をたずね、そのことわりをいった。河上はかねて連帯保証の危険を説いていたからである。河上は、「それは結構なことじゃ、僕も一口加入する」といい、長谷川芳之助、高橋健三、菊地武夫なども加わって、一人一月十円掛けで七口、数年かけつづけて小村の急を救った。やがて河上は杉浦に「君も貧乏の中からもう三年もつづけたのだから、あとはオレが引きうける」といい、結局、河上、菊地でかたをつけたのである。 杉浦はあまり丈夫でなく神経衰弱が持病で、二十五歳のとき一年間、四十五歳のとき四ヵ月間、四十八歳から五十五歳まで八年間病臥(びょうが)したことがある。この最後の八年間でほとんど世に忘れられ『万朝報』には「故杉浦先生云々」の記事が出た。一方、急迫の度も加わって文字通り柱は傾き、屋根は破れ、寝ていて青天井が見えた。彼は職人をよんで新聞紙を三、四枚張らせ、その上にコールタールを塗らせた。米屋は、米代がたまったので米をもってこなくなった。ある人は見かねて、すでに侯爵となっている小村寿太郎に助力を求められたら、とすすめると、 「小村はいやしくも国家の柱石をもって自らを任ずる男である。それにたいしてわが一家の私事をもって心配をかけてはならぬ。のみならず、かつて小村の貧窮時代、自分は彼を援助したことがあるから、その小村にたいして無心をいうのは、彼に当時の報償を求めるような観がする。断じていかん」 と承知しなかった。數多い知人、門弟で彼のことを思うものがなかったとき、頭山満から五百円がとどいた。「頭山氏天野氏を使いとして五百金を贈らる。我深く頭山氏の厚誼に感ず」と彼は日記に誌(しる)した。 病気は四十二年に全快。そして、ほとんど彼の存在を忘れていた性急にして薄情な世間が、あっとおどろくことが起きた。大正三年、東宮(皇太子)御学問所ができ、帝王学の根幹となるべき倫理ご進講の大役が彼に課せられたからである。一部では「博士でもないのに」と首を傾けるものもいたというが、笑止千万とはこのことであろう。
東京大学予備門長、日本中学校長、東宮御学問所御用掛を歴任した国粋論者で教育家の杉浦重剛(1855-1924)が側近に語った談話録。帯封から。 ※杉浦重剛氏は大正天皇が皇太子のとき、御進講の大任に当っている。大正天皇の皇孫:明仁天皇退任の日。写す。 ※参考図書:小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.89~95 第十三話 育英の名人 2019.04.30。 |
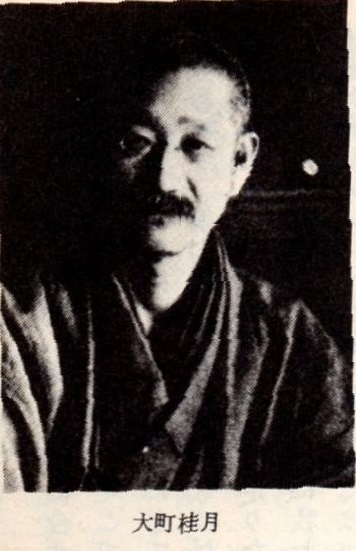
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.164~168 大町 桂月 酒客・中毒で筆動かぬ時も 飲酒喫煙のレコードを伝記で探ったことがある。タバコは『続さらりーまん外史』でのべたように、住友総理事中田錦吉の五歳からというのがいちばん早いようであったが、酒は西園寺公望ではなかったろうか。養育にあたった老女に相模というのがいて「男は酒をのまぬといけませぬ」といって五歳から食膳に酒をつけたので、子供のくせにちびりちびりとやったのである。 高橋是清も、はじめた年は不明だが、十三歳のころにはひとかどの酒客で、横浜の外国銀行のボーイになっていたが、馬丁やコックなどと朝夕のんでいた。さかなはねずみとりで捕えたねずみを、支配人のビフテキ焼きで焼いたものであった。慶應三年十四歳のときコロラード号で渡米したときは、旅費としてもらっていた二十ドルをウイスキーで使いはたし、同行の友人の分までのんでしまったので、サンフランシスコに着いたとき、引率者の富田鉄之助に「君はこの船で帰れッ」と大変な剣幕でしかられた。 第一回の総選挙で当選しながら「アルコール中毒の為、評決の数に加はり兼ね辞職仕候」という辞表を書いてやめてしまった中江兆民も、酒客列伝からおとすわけにはゆくまい。もっともアルコール中毒は一口実で、予算問題で政府側に寝返った板垣退助ら四十数名にたいする怒りが原因であった。 兆民には『三酔人経綸問答』という評論があって、主人公南海先生の酩酊ぶりを書いている。南海先生は生まれつき酒が好きだが、わずか一、二本のときは気持ちよく酔っぱらい、気分もふわりと、宇宙を飛びまわるようで、見るもの聞くもの楽しい。この世に憂いなどがあろうとは思えぬほどだ。さらに二、三本のむと、精神がにわかにたかぶる。思想がしきりにわきおこり、身は小部屋の中におりながら、眼は全世界を見通し、一瞬間に千年前にさかのぼり、千年後にまたがり、世界の進路を示し、社会の方針を教え、「自分こそ人類の社会生活の指導者である」と思うようになる。さらにもう二、三本のむと、耳は鳴り、目はくらみ、腕をふりまわし、足をふみならし、昂奮のはてはひっくり返って前後ふ覚となる。おそらくはご自身の体験にもとづく記述であったろう。 天台道士杉浦重剛の周辺には、とりわけ酒客がそろっていたようだ。その門下生からは巌谷小波、大町桂月、江見水蔭、近藤紅緑などの文人が出たが、桂月と水蔭に酒の上の逸話がある。桂月は高知のひとで、天台道士の稱好塾に学び、東京大学国文科を卒業したが酒を讃える詩として、「一杯陽気発し、二杯寒温を忘れ、三杯慮尽き、四杯世喧を絶し、五杯六杯多々益々弁じ、唯だ一身の乾坤に合するをお覚ゆ」というのをつくった。 五十歳のとき、アルコール中毒。そこで一年半ばかり酒を断ち、酒毒はなくなったが、筆が動かない。そこで「節酒」ということにして、非難攻撃の声があつまった。そのなかで天台道士はひとり非難せず、頼山陽の菅茶山のものだという瓢箪に酒をつめて贈った。桂月は感激し、容量をはかると、三合八勺、四合に足りない。そこで四合を酒豪に引っかけて、「しゅごうには好し成らずとも御情のこもるひさごに我は酔はなむ」という歌をつくった。 水蔭は岡山の人。十七歳で稱好塾にはいったが、あるとき吉原に遊びに行き、しこたま酒をのんで泥酔のあげく、町角で菰をかぶって寝こんでいるところを新聞社の写真班にうつされ、翌日新聞にのった。塾生一同は激怒し、体面を汚したから即時退塾処分にして下さい、と師に申し入れたが、このときの天台道士のことばがいい。<いやそれはならん。君たちはあの江見にくらべ品行方正、学業優等だからどこへ放り出しても何とかなる。しかし江見は、ここにおいてもあのようなふ始末なやつだ。いまここを出してしまえば、どんな悪党になるかもしれん。だから出すわけにはゆかん。もし君たちがふふくなら、君たちに出てもらうより外はない」。一同、この慈心に打たれ、返すことばもなかった。 天台道士には、「酒を詠ずるの詩」がある。「之れ無くして礼楽全うする能わず。笑ふを休めよ七賢と八仙とを。誰か道ふ禹王亡国を戒しむと。国家の命脈実に焉に存す>というものである。しかし本人はむしろ愛煙家であった。ところがある日から、タバコを口にしない。周囲が理由をきいても笑って答えない。しっこくたずねると、今にわかるとだけいった。禁煙一年におよぶと、今日からはのむ、と宣言した。 この禁煙のいきさつはあとでわかった。彼の親友に福富孝季がいる。この物語の第五話に岡倉天心の親友として登場した人物である。六尺余の巨漢で、ケンブリッジ留学時代、下宿屋の主人が<日本のジャイアント>とよんでいた。まだ三十代はじめなのに、満頭房々とした白髪。東京師範学校教授であったが、とりわけ酒が強い。いつからはじめたかはふ明だが、あるとき友人たちの前で、日本酒を七升、ビールを二十四本のみほしてみせたことがある。千頭清臣は、土佐藩の貢進生として天台道士とともに学び、のちその妹楠緒は杉浦夫人となった人だが「余は君(福富)の酒量を知れり。君嘗て一呼吸して一瓶のウイスキーを傾け尽したることあり」と書いている。 天台道士は、この福富の酒を心配したのであった。彼はかつて『講学雑法』というのを出して、穂積陳重(のち法学博士)とならんで「飲酒の利害」という論文をのせたこともある。化学者としてアルコールの害を説く知識をもっていたが、それをことばだけで説こうとはしなかった。親友に忠告して酒をやめさせるには、まず自分で好きなタバコをやめてから、と考えた。そして禁煙一年、ようやく忠告の資格ができたとして、いったのである。 「タバコをあれほど好きだった僕でも、やめようとすればこのようにキッパリとやめることができるのだ。君も将来国家のために尽くそうという精神があるならば、どうか酒をやめてくれよ>福富は親友を思うその誠実さに打たれて、あびるほどのんでいた酒をピタリとやめた。それからしばらくして、福富はのどを斬って自殺した。ときに三十三歳。天心は二首の弔詩を献じた。天台道士は、「あんなことになるなら酒をとめるではなかった」と涙を流した。 2019.08.10 |
33 岩波 茂雄 重剛に直談判し特別入学(1881~1946年)
|
長野県の長野中学は松本中学校の分校であったが小阪順造(のち枢密顧問官、日本発送電総裁)は本校に進まないで、東京の日本中学に転校した。同級生仲間で雑誌『日本及日本人』をとつて輪読していたので、三宅雪嶺、陸羯南、杉浦天台道士の文章に親しみ、とくに天台道士に感銘があったためである。そのとき、同県諏訪の人間で、丸坊主の眼のクリクリした岩波茂雄という少年がおなじ転入者の一人にいた。 岩波は諏訪実科中学に学んでいたが、明治三十一年十七歳の春杉浦重剛に「請願書」という一文を送ったのである。「謹呈ス我大日本ノ教育家/杉浦先生閣下/茲(ここ)ニ信陽ノ一寒生泣血傾首再拝シテ自己ノ境遇ヲ述ベ胸中ヲ吐露シテ敢テ閣下ニ誓願スル所アラントス/拙劣ノ文閣下ノ耳目ヲ瀆フニ止マルト雖モ伏シテ希クハ一読ノ栄ヲ賜ランコトヲ>という書きだしで、片親(父)を失った自分の境遇を述べ<童心無邪気ナル時ノ死別ハ悲シミヲ感ズルコト少シトスルモ漸ク父母ノ為ニ其身ヲ成長シ之ヨリハ少シク孝道ヲ致サントスル暁ニ際シ突然父君ニ後レ給フノ悲傷如何/嗚呼余ハ実ニコノ悲境ニ沈ミタル可憐児ナリ」と書く。 しかし、いたずらに哭泣くするよりも、奮励刻苦、身を立て名を挙ぐるにしかず、と発奮した。そして、「力ノ及ブ限リ学識ヲ磨励シ社会ニ出ヅル暁ニハ至誠一貫以テ現今腐敗セル社会ヲ改革シ国家ノ為ニ身骨ヲ捧ゲ大事業ヲナシ一ハ亡父ノ霊魂ヲ慰メ聊(いささ)カ孝道ノ終リヲ為サンㇳスル>志望を立てた。だが、その志望を果すには障害がある。<夫レ我家ハ母ト余ㇳニ妹アルノミ。故ニ余ハ家ヲ襲ヒテ母ヲ養フノ義務ヲ「ス。故ニ東都遊学ハ容易ニ母ノ許シヲ得ザリシ也>。<余ハ斯カル境遇ヲ脱出シテ都ニ遊学シ其目的ヲ達セントス>るが、学資がない。そこで<真正ノ大人物ノ家ニ請ヒテ身ヲ托シ己ノ管督ヲ請ヒ……今書生タラントスルニ付イテ其人ヲ求ムルコト急也。側カニ聞ク、閣下英邁卓識磊落奇偉超然トシテ脱俗シ大ニ教育ノ為ニ尽力セラルルㇳ……先生願ハクハ余ノ愚鈍ヲステ給ハズふ幸ナル可憐児ガ至誠ナル心ヲ哀ミ我ヲシテ書生タラシメヨ。先生許可セラルルヤ否ヤ。……先生豈ニ許サザルノ理アランヤ。至誠ノ発動スル所威尊ヲ冒涜シテ恐懼已ムナシ。撓首屈指命ノ下ルヲ待タンノミ。若シ忝ナクモ返書ヲ恵マレバ何ノ栄カ之ニ過ギシ。頓首百拝」。 これについて安べ能成は「≪……後レ給フノ悲傷如何≫という敬語の置き損ないの如きは、晩年の彼の会話にも往々あることで、如何にも岩波らしい」といい、また、「この文章は幼稚ではあるけれども、恐らく晩年の彼の宣言文章の如く、実にしつこい苦心彫琢の末になったものであろう」(『岩波茂雄伝』)ともいぅている。ともかく、生一本の情熱とまごころは行間にあふれており、杉浦も動かされて、書生におくことはできないが、とにかく上京せよという意味の返事を書いた。 そこで三月下旬、岩波は友人の「男子志を立てて郷関を出づ、学もし成らずんば死すとも還らず」の詩吟に送られながら、肌寒い湖畔の暁風をついて出発したのである。 四月四日、岩波は五年の編入試験を受けたが、英語のできがわるくてふ合格であった。彼は大いに憤慨し、「けしからん、けしからん」と連呼し、「おれがこれほど杉浦先生を慕ってきて入れないというなら、おれはもう死んでしまう。死ぬ死ぬ」とダダをこねた。 そして結局、杉浦校長に直談判したが、「不合格では仕方がない」という返事である。そこで岩波は、「自分はいなかから出てきて外の学校へはいろうという気は毛頭ありません。日本中学に入れてもらえなければ死ぬよりほかに道はありません。家にもおめおめと帰れません。何とか入れてください>と泣いて訴え、<入れていただかねば、ここを動きません」とまでいった。「それではおれが再試験をしよう」ということで、その結果、特例中の特例として入学を許されたのである。 日本中学は明治十八年にできた東京英語学校が二十七年にめい称と組織を改めたもので、杉浦は二十三年七月、三十六歳で衆議院議員に当選したおなじ月から、校長になっていた。どこの学校にも、退学、停学、説諭という三つの処罰法があるが、日本中学には停学がなかった。これは「悪いことをした学生でも改悛の見込みがあれば何度でも説諭するがよい。到底改悛の見込みがないとあれば、保証人をよんで引き取ってもらうがよい。しかし停学というのはいけないよ。元来なまけたいものを停学にすれば、本人はむしろよろこんで、親の目をかすめて遊び歩くだろう。それも決してよい所には遊びに行かない。停学のためにかえってますます本人を悪くするだけだ」という杉浦の考え方によるものであったが、しかし、生徒にはほとんど干渉しなかった。 小坂たちが入学して間もなく四年の組と五年の組とが大げんかをした。椅子がとび、机は倒れ、窓ガラスは破れる大騒ぎで、一番広い廊下で格闘していると、「ああ、校長さんがやってきた」と叫ぶものがあり、たちまち大風が静まったようになって、鼻血をふいたり、コブだらけの頭をなでたりしている生徒たちの前に半白のアゴひげを生やした、痩せた、目の光る和ふくの校長は上がってきたが、「オイ、こうやられると、頭の上にホコリが落ちてこまるから、やめてくれ」といったきりで悠々と降りていった。それきりで何のとがめもなく、「なるほど、こう行くべきだ」と小坂はしみじみ感じた(藤本尚則『国師杉浦重剛先生』序)。 ある冬三年生が教室で机をこわし炭俵を積み、床の上で火をたいたことがある。生徒取締はカンカンに怒って校長に訴え、即時退校処分に願います、といった。すると杉浦は、「君らは教室で火をたいたそうであるが、君らも子供ではない。もしあやまったらどんなことになるか、わかりきっているだろう。これからはそんなつまらないことをしてはならん。今度は許してやる」といった。生徒たちは感涙にむせんだ。そいう光景を壁の上の軸が見下ろしていた。それは杉浦の親友河上謹一が自ら揮毫して贈ったもので、「待人寛、持身厳」の六文字が墨痕淋漓と書かれてあった。 小坂が浜口内閣の拓務政務次官となったとき、事務次官は中学同級生小林欣一、そして外務次官吉田茂も一年半ほど在学したことのある同窓生であった。 *小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.169~173。 ~より ※参考図書:小島直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.89~95 第十三話 育英の名人 ※関連:岩波書店のマーク 2010.03.04 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.174~178 浜尾 新 謹直で人格第一主義 古島一雄がはじめて上京したとき、玄関番漢学僕として身をよせたのは小石川区金富町の浜尾新の家であった。明治十二年、浜尾は三十一歳で文部省権大書記官、古島は十五歳である。古島の祖父良平と浜尾とがもと但馬豊岡藩士であった縁による。古島の父玄三は備中松山藩士で竹田といったが、江戸桃井塾で武芸を学んだとき、古島良平の息子誠輔といっしょであった。そのあと武田玄三が武者修行の途中古島家を訪ねると誠輔は死んでおり、しばらく泊まっているうちに良平に懇望されて誠輔の妹八重の婿となった。 二人の間に生まれたのが一雄である。その父玄三はかつて浜尾と町の警護にあたったことがある。夏のことで、夜はかやをつるが、浜尾はその中にはいっても机に向って読書するばかりで、横になっているのをみたことがなかった。「警護に対する責任感からか、それとも読書趣味であったかしらぬが、何にしても感心な男だと思った」と玄三は一雄に話した。しかし古島は「子供の時分から、人を人と思わぬような性分で、教師や上級生などに対しても、特別に尊敬するような考えがありませんでした。従って浜尾先生に対しても、別段偉い人とも、恐ろしい人とも思わず、ただイイおじさんぐらいに思うておりました」(『浜尾先生を追悼する』)と語っている。 古島少年は、浜尾の気の長さに閉口した。手紙の使いにやられるとき、まず二階の書斎によばれる。浜尾は少年を待たせておいて、それから「藤田東湖流の文字を、螺旋(らせん)にしたような文字」で書きはじめるが、一字まちがうとすぐ引きさいて書き直す。巻き紙一間ほど書いていても一字まちがえばまた破って、最初から書き直す。そういうわけで、一本の手紙ができあがるまでに相当な時間がかかる。少年の方は神妙に待っているのがバカくさくなって、本箱から勝手に本を引きだして、読みながら待つことにした。書き搊じの反故(ほご)で紙くずかごがいっぱいになるという現象の背後に、一字一句いやしくもしない浜尾の謹直な気持ち、人柄を読みとり感銘をおぼえたのはずっと後年のことであった。 ちょうどこのころ、杉浦重剛が英国留学から帰ってきて、小石川伝通院境内の別院、貞照庵に寓居していた。ある日、先輩の浜尾を訪ねると、浜尾は少年をよびだして、「これは古島一雄という学生で、将来有望なものだから、君の引き立をたのむ」といって引きあわせた。少年は神田の共立学校にはいったが、学友をなぐって退校を命ぜられたのを手はじめに、行くさくざきの学校で問題を起して放校されていた。浜尾はこれに手こずって杉浦に指導をたのんだのである。 少年は毎日貞照庵を訪ねて、英語や数学を教えてもらった。杉浦は、教えを請えば何でも親切に教えてくれるが、しいて注入するような教育はいっさいやらない。そして特に歴史―古今東西の英雄豪傑の話をしてやった。天台道士は、大江広元を「偉い」といい、竹中半兵衛を「崇敬おかず」といった。ことに半兵衛を「楠公に劣らない人物」とほめ、「崇敬の対象となるのは、その寡欲である」といった。これは少年に大きな感銘をあたえ、その生涯を左右する。 ある日、浜尾は少年にたずねた。 「お前は、将来何になるつもりか?」 「そんなこと、考えたこともありません」 「それはいかん、人間というものは、ある目的を定め、志を立てて、それに向って進むことが大事だ」 それから同郷人の実例を一々あげて示し、「お前は一つ、鉄道の技師になってはどうか」といった。少年がびっくりしていると、浜尾はつづけた。「これから、日本でいちばん大事なことは鉄道だ。それには技師が必要だ。ところがその方面はまだだれもやっていないから、お前はぜひそれをやるがよい」。 天台道士の英傑談に酔っていた少年は、鉄道技師にされてたまるかと思った。そして、無断で浜尾家をとびだし、郷里に帰ってしまった。 豊岡の宝林塾という漢学塾にはいり、「僕の一生を通じて、このときほど真剣に勉強したことはない」というほど勉強し、一年目に塾頭の代講をやらされ、これを二年やって小学校の補助教員となり、再度の状況をねらっていると、天台道士から長文の手紙がとどき、「〽五月雨に しばし濁れる山の井の 底の心は 汲む人ぞ汲む」という短歌がそえられてあった。「わが輩は、ここに人生感激の第一歩を踏み出したのだ」と彼は語る。「おれをしってくれるのはこの先生だ。この先生の懐へとびこんでゆくより外はない」。上京費がないので、母親の入れ知恵で松江裁判所の下級吏員をしたあと、ようやく東京に出ることができた。このとき二十三歳である。「これから何をやるか」と天台道士はたずねた。「何をやろうという考えもありません。ただ、正式の学校をふまずにすぐ世の中に出たい」というと、「それでは新聞記者になるがいい。今、わが輩は雑誌をやっているから、しばらくその方を手伝って、それから新聞をやるんだ」といわれ雑誌『日本人』の記者に採用、さらに陸羯南の『東京電報』(まもなく『日本』と改む)に推薦された。『日本』記者として、古島は浜尾を訪ねたことがある。新聞に対する発行停止を、各社同盟して廃止しようと運動中のことで、浜尾がもっともがん固保存論者ときき、古島が自ら出かけたのである。 ところが、いかに口をすっぱくして説いてみても、浜尾はこれをきき入れない。そこで古島は腹を立てて、「先生こそ、日本における官僚の典型型だ!」ときめつけた。
東大安田講堂のそばにつくられた浜尾の銅像は、新宿フーテン族にペンキを塗られ首を落とされかかった。そして今、「学歴あって師縁なき輩」の、学業を放てきしたゲバ棒訓練を黙々と見守っている。 2019.08.02 |
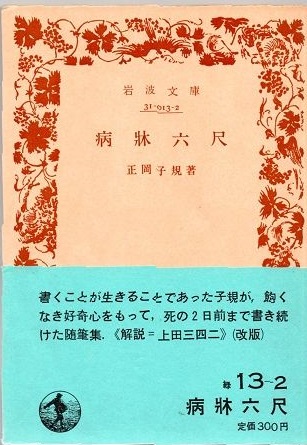
▼『病牀六尺』正岡 子規著 (岩波文庫) 1984年7月16日 第26刷改版発行 一
●病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余りにも広すぎるのである。僅かに手を延ばして畳に触れる事はあるが、布団の外へまで足を延ばして体をくつろぐ事も出来ない。甚だしい時は極端の苦痛に苦しめられて五分も一寸も体の動けない事がある。苦痛、煩悶、号泣、麻痺剤、僅かに一条の活路を死路の内に求めて少しの安楽を貪る果敢(はか)なさ、それでも生きて居ればいひたい事はいひたいもので、毎日見るのは新聞雑誌に限って居れど、それさへ読めないで苦しんで居る時も多いが、読めば腹の立つ事、癪にさわる事、たまには何となく嬉しくてために病苦を忘るるやうな事がないでもない。年が年中、しかも六年の間世間も知らずに寐て居た病人の感じはまずこんなものですと前置きして(以下略)P.7~
(五月五日)
二十一(P.43) ●余は今まで禅宗のいはゆる悟りといふ事を誤解して居た。悟りといふ事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思って居たのは間違ひで、悟りといふ事は如何なる場合でも平気で生きて居る事であった。 ●因に問ふ。狗子に仏性ありや。曰、苦。 また問ふ。祖師西来の意は漢字奈何(いかん)。曰、苦。
また問ふ。……………………………………。曰、苦。
(六月二日)
参考:「因に問ふ。狗子に仏性ありや。>は『無門関』の<趙州の狗子(くし)」からの引用である。
四十五 ●写生といふ事は、画を画くにも、記事文を書く上にも極めて必要なもので、この手段によらなくては画も記事文も全く出来ないといふてもよい位である。これは早くより西洋では、用ゐられて居つた手段であるが、しかし昔の写生はふ完全な写生であつたために、この頃は更に進歩して一層精密な手段を取るやうになつて居る。しかるに日本では昔から写生といふ事を甚だおろそかに見て居つたために、画の発達を妨げ、また文章も歌も総ての事が進歩しなかつたのである。それが習慣となつて今日でもまだ写生の味を知らない人が十中の八、九である。画の上にも詩歌の上にも、理想といふ事を称(とな)へる人が少くないが、それらは写生の味を知らない人であつて、写生といふことを非常に浅薄な事として排斥するのであるが、その実、理想の方がよほど浅薄であつて、とても写生の趣味の変化多きには及ばぬ事である。理想の作が必ず悪いといふわけではないが、普通に理想として顕(あらわ)れる作には、悪いのが多いといふのが事実である。理想といふ事は人間の考を表はすのであるから、その人間が非常な奇才でない以上は、到底類似と陳腐を免れぬやうになるのは必然である。固(もと)より子供に見せる時、無学なる人に見せる時、初心なる人に見せる時などには、理想といふ事がその人を感ぜしめる事がない事はないが、ほぼ学問あり見識ある以上の人に見せる時には非常なる偉人の変つた理想でなければ、到底その人を満足せしめる事は出来ないであろう。これは今日以後の如く教育の普及した時世には免れない事である。これに反して写生といふ事は、天然を写すのであるから、天然の趣味が変化して居るだけそれだけ、写生文写生画の趣味も変化し得るのである。写生の作を見ると、ちよつと浅薄のやうに見えても、深く味はへば味はふほど変化が多く趣味が深い。写生の弊害を言へば、勿論いろいろの弊害もあるであろうけれど、今日実際に当てはめて見ても、理想の弊害ほど甚だしくないやうに思ふ。理想といふやつは一呼吸に屋根の上に飛び上らうとしてかへつて池の中に落ち込むやうな事が多い。写生は平淡である代りに、さる仕搊ひはないのである。さうして平淡の中に至味を寓するにものに至つては、その妙実に言ふべからざるものがある。 (六月二十六日) 八十七 ●草花の一枝を枕元に置いて、それを正直に写生して居ると造化の秘密が段々分かって来るような気がする。 (八月七日) 参考:『この世 この人生』の著者:上田三四二さんが、書くことが生きることであった子規が、飽くなき好奇心をもって、死の2日まで書き続けた随筆集《解説=上田三四二》 その解説の最後の部分に、『病牀六尺』の最後の回の載った翌九月十八日、覚悟の子規は妹律らにたすけられて辛うじて筆を持ち、画板に貼った唐紙に辞世の句を書付けた。「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」。痰を切り、ひと息いれて、「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」。またひと休みして「をとゝひのへちまの水も取らざりき」。そこで、筆を投げた。穂先がシーツをわずかに汚した。そしてその日のうちに昏睡におちいった子規は、越えて十九日の午前一時に、息を引き取る。三十六歳。いまふうに数えて、三十五歳になる直前であった。 追加:子規の著作に『仰臥漫録』(岩波文庫)がある。子規が死の前年から明治34年9月から死の直前まで、俳句・水彩画等を交えて赤裸々に語った稀有な病牀日録。現世への野望と快楽の逞しい夢から失意失望の呻吟、絶叫、号泣に至る人間性情のあらゆる振幅を畳み込んだエッセイであり、命旦夕に迫る子規の心境が何の誇張も虚飾もなくうかがわれて、深い感動に誘われる。(表紙の文章)
参考1:小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中央文庫)昭和五十八年八月十日 P.179 より。 正岡子規 露伴の評で小説を断念し俳句に 伊予松山の正岡升は、明治十六年十七歳のとき上京し、第一高等中学校在学中二十三歳で喀血して<子規>と号した。子規はほととぎす、杜鵑、杜宇ともいう。蜀の国王であった望帝(杜宇)は、自分の徳が宰相に及ばないと思い、帝位を譲って他国に亡命した。のち帝は死し、その魂は化して子規となり、蜀に飛来して血を吐きながらなきつづけたという故事の因む。 翌年、文化大学にはいり、国文科を修めることとなったが、学業よりは俳句に打ち込んだ。たまたま幸田露伴の『風流仏』に感心した。自分もこのような作品を書きたいと思い、うるさい寄宿舎をでて本郷駒込の借家にうつり、小説『月の都』を書き上げて露伴を訪ねたのが二十六歳のときである。 露伴も同年の二十六歳で『風流仏』は二十三歳の作品であった。(子規、露伴の生まれた慶応三年には尾崎紅葉、石橋忍月、夏目漱石などの文人が生まれている)。子規は露伴に、「この小説の趣向は『風流仏』から盗んだところがある。それは『風流仏』を喜ぶからである。周囲の人のすすめにしたがって上梓しようと思うが、君の諒解を得ておきたい」とのべ、座に客があったので、二十分ぐらいで原稿をおいて帰った。 一日たって原稿が送り返され、ざっとした批評がついていた。子規はもっとくわしい批評をききたいと思って、かさねて訪問した。露伴はこの作品に「文章の骨は得ているが肉はいまだし」とか、「覇気強し」という評語をあたえたようである。この一作を世に問い、小説家として立とうとした子規の野望は挫け、小説は断念して俳句の道に専念することとなった。 陸羯南の親友加藤恒忠は子規の叔父にあたる。子規は在学中から新聞社にはいりたいと思い、叔父を通じて申しに入れていた。古島一雄が<加藤の親戚の者で、正岡という青年が入社したいというから、会ってくれ>と陸にいわれたのはそのためである。古島が合ってみると、紺がすりの着流しで、顔色蒼白の男である。「目下帝大にいるが、退学して入社したい」という。「あと一年で卒業するなら、入社はそれからでも遅くあるまい」とさとすと、「実は、もはや試験のための学問はイヤになった。ことに井上哲次郎の哲学の講義など、この上きかされてはたまらない。自分は元来病身だから、一日も早く所信を実行したいのだ。それは俳句の革新だ」と正岡青年はいった。古島は俳句のことは何も知らなかったが、試験のための学問がイヤになったという意気に共鳴して、ただちに入社を予約して、まず作品の寄稿を求めた。 そこで子規が書いたのが「かけはしの記」という俳句まじりの紀行文で、これが社中の認めるところとなり、九月に大学を退学した子規は、十二月に日本新聞社にはいった。入社して初めて書いたのが『獺祭書屋俳話』で、俳句界革新の暁鐘となった。ついで「岐蘇三十首」という漢詩をのせ、この方面では自信家ぞろいの社中を驚倒させた。 『日本』は、伊藤内閣の発行停止処分にそなえて『小日本』を出すこととし、その編集責任者に子規が抜擢された。推薦者は古島で、論説は古島が一時間ずつ出張して兼務するという条件になっていた。それから毎日一時間ずつ机をならべているとき、子規は古島に「俳句をやってみないか」とすすめた。 「タカが知れた十七のチョンノマ文学だ、一夜百句ぐらいワケはない」 と古島はうそぶいた。子規は「梅」という題を出し、翌日、百句をつくってみせると、子規は一笑した。 「これはまるで漢詩の翻訳じゃ。俳句には俳句の作法もあれば、材料もある。こんなものは俳句でも何でもない。まずは古人の俳句を詠むことだ」 子規は『古人五百題』という本と、かねて自ら分類していた材料の「種本」をくれた。それは、「大」の例句としては、「荒海や佐渡に横たふ天の川」(芭蕉)が、「美」の例句としては、「狩衣の袖の浦這う蛍哉」(蕪村)が、「奇の」例句としては「日の光今朝や鰯の頭より」(蕪村)が掲げてある。その他、「雅」としては、「時雨るるや黒木つむ家の窓明り」(野沢凡兆)、「繊」としては、「つかむ手の裏を這ふたる蛍哉」(蕪村?)、「比喩」としては、「しだり尾の長屋々々のあやめ哉」(嵐雪)、「即事」としては、「文もなく口上もなし粽(ちまき)五把」(嵐雪)などがあげてある。 作句の模範であると同時に、子規の鑑識による選句集として貴重な入門ガイドとなるはずであった。さらに子規は「古州」という俳号まで選んでやった。また「達磨さんこちら向かん花も候」という古州の句を紙上にのせたりして奨励したが、「無縁の衆は済度しがたく、こちらの方でサジを投げてしまった」古島は、晩年になって、「もしあのとき勉強しておいたら、老後の楽しみになったろうものをと、今になって後悔している」とひとに語ることになる。「古州」という子規直選のゆかりの号の代わりに「古一念」という別号が世に知られるゆえんでもある。 それはそれとして、古島は子規の絶倫の精力におどろいた。肺病だというのに連載小説を書き、材料の取捨、原稿の検閲、絵画の注文、募集俳句の選、艶種の雑報まで、自ら筆をとって朝から晩まで努力したのである。しかし、病いは次第に進み、二十九歳のとき従軍記者となって大連から帰る船中で喀血がやまず、翌年から歩行の自由を失い、病床につくこととなった。三十一歳のとき腰部疼痛がはげしくなり、重体に陥ったこともある。三十二歳のとき自ら墓碑銘を書いた。 「正岡常規又ノなハ処之助又ノなハ升又ノなハ子規又ノなハ獺祭書屋主人又ノなハ竹ノ里人伊予松山ニ生レ東京根岸ニ住ム父隼太松山藩御馬廻加番タㇼ卒す母大原氏ニ養ハル日本新聞社員タリ明治三十□年□月□日没ス享年三十□月給四十円」 というもので、空欄の個所はそれから四年目に埋まった。すなわち「明治三十五年九月十九日没ス享年三十六歳」となったのである。 森鴎外は「遺言には随分面白いものが有るもので、現に子規の自筆の墓誌抔(など)も愛敬が有って好い。樗牛の清見潟は最高だろう。我々なんぞとは趣味が違ふ。西洋の昔の人の中で、最も面白く感じたのは、第十三世紀に死んだ独逸詩人 Walther von der Vogelweide の遺言だ。それは西洋の風習どほり、地面と平らにひらたい石を置いて、其石に窪みを四つ彫り込ませて、それに麦と水とを入れさせて、鳥に飲ませたり食わせたりしてもらひたいといふのであつた」(『妄人妄語』)と書いた。 ※参考1:広辞苑によると、し-き【子規】ほととぎす。しき【子規】→まさおかしき(正岡子規)。なは常規となっている。 ※参考2:最近、司馬 遼太郎『坂の上の雲』でNHKで放映されて多くの人が視聴されたようです。子規は(1867~1902)、秋山真之は(1868~1919)である。 ★プロフィル:正岡 子規は、日本の俳人、歌人、国語学研究家。なは常規。幼めいは処之助で、のちに升と改めた。 俳句、短歌、新体詩、小説、評論、随筆など多方面に亘り創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治時代を代表する文学者の一人であった。死を迎えるまでの約7年間は結核を患っていた。 2009.10.27,2011.01.02追加。 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.184~188 安田善次郎(1,838~1,921) 趣味に生きた実業家 「文豪に似た字でおよそ関係のないものに富豪がある。露伴は自分は富豪でも何でもないがいくらかつきあった富豪はある」(『幸田露伴』下)と塩谷贊は書いている。それは、安田善次郎、大倉喜八郎、渋谷栄一の三人であったが、その「いくらかのつきあい」の跡は、各人によってちがいはあるとしても、露伴その人を語るとともに、またこれら高めいな実業家たちの人と4なりや生活態度を、別の角度から語っている。 安田善次郎については竜渓矢野文雄の伝記(大正十四年刊)があり、その趣味、余技などもくわしく書かれている。二十歳で越中富山から江戸に出て、両替屋に奉公しし、二十六歳のとき、五両の金をもとでに、日本橋小舟町の四辻に露店を出し、戸板の上にバラ銭をならべて両替店を開いたのが発端であった。幕末から明治初年の変動期をうまくのり切って、その基礎も定まった明治九年三十九歳のとき、偕楽会(かいらくかい)という富豪同好者のあつまりをつくったのを手はじめに、拙碁会、馬談会、和敬会(茶湯同好会)などをつくった。「亦此の外にも色々の会があったようであるが、上記に記する諸会の如く、永続しなかった。また常に出席もいなかった」(前掲書)と竜渓がそのなをあげなかったものに、「欣賞会」というのがある。文豪露伴と富豪安田との交友の場はここであった。われわれはその詳細を、塩谷贊の労作によってはじめて知ることができたのである。 この会は、明治四十年十月から四十四年一月まで、すなわち安田の七十歳から七十四、露伴の四十一歳から四十五歳におよぶ出来事である。本所横網町の安田邸で開かれた愛書家のあつまりで、はじめ珍書会といわれたが、露伴がたのまれて「欣賞会」と命めいした。「陶淵明の移居の詩に、≪奇文共に欣賞す≫の文字が存するのに拠ったと思われる」(塩谷本・中)。露伴は、「一体に名公富豪なるものは驕気を以て人を圧するところがあって、それにあてられるのもいやだし、大金持の前で畏っているより誰にも遠慮もない空の下で釣をして遊ぶほうが好き」な人だが書物を欣賞するこの会はよほど気に入ったようで、「欣賞会定」なるものも自ら書いた。「一、四五部づゞの書 一、都合よき夜を月に一会 一、まうけは茶まで至らず 一、みやげも花か団子ほどにて>という味のあるものである。初会は四十年十月五日夜、会する人は露伴、赤松磐田、林若樹(はやし わかき)、岡田紫男(むらお)、それに松廼舎(まつねや)すなわち安田である。「氏は晩年益々書を巧みにし画も上達し、狂歌も巧みとなり、その雅号を福々子と称し、堂号を勤倹堂とも称した。又松翁と称へた」(竜渓本)とあるが松廼舎があったわけである。 この第一回で、露伴は「ものわりのはしこ」という木版本のことを話した。「ものわり」は化学、「はしこ」じゃ「はしご」で、化学階梯の訓読、和学者の手になったものらしい。「酸素」を「すいね」、「窒素」を「むせびね」としたあたり絶妙ではありませんか、と露伴はいった。 第二回では、露伴は『黒韃事略(こくだつじりゃく)』『釣客伝』『何羨鏘(かせん)』などの珍書を携行して見せている。 第三回では、表紙の莚打(むしろうち)というつくり方の話をし、安田が「芝居の評判記以外にも評判記は五十種ぐらいあるそうですね」といったことをうけて、「その中でも魚の評判記が一番しゃれておもしろくできております。つぎには虫でございましょう……」と語っている。 第四回では、釣をはじめた動機をきかれて、「明治三十二年の春のころ、この時分好きだった鉄砲なりかけて末の弟につきあって、中川向うの奥戸で鮒つりをやった。そのときそばにいたじいさんが講釈をして釣竿を貸してくれまして、それは十二本のつぎのもので、それで釣るとぼくばりよく釣れる。どうも釣れるのは釣竿のせいだと思って、東京一といわれる釣竿製造師たちのことをきいたりした。こんなことから釣好きになりましたわけで……」と語っている。 第五回は休み、第六回では「喜三二は朋誠堂と同じ人であります」というような話をした。第七回には内田 魯庵(うちだ ろあん)もきた。このあと、露伴は京都大学行きの話でしばらく会を休み、第十一回は露伴の送別会をかねた。露伴は四十一年八月京都に向い、四十二年夏休みに東京に帰ったきり京都へはもどらなかった。そして欣賞会に出席したのが四十三年一月で、会はすでに第二十五回となっている。このとき、安田は出席していない。三月に第二十六回が開かれたが、露伴の出欠は上明である。これから約十ヵ月休みがあって、第二十七回が開かれたのは四十四年一月二十三のことであった、この間に、露伴は「妻とともに幸福にも訣別した」。彼が二十九歳のとき迎えた二十一歳の幾美子夫人は、名妓ぽん太に似た顔でなおいっそうの美人であった。顔ばかりでなく、心も美しく、暖かく、毅然として、文字どおり最良の伴侶であったことは『日本さらりーまん』で書いたことがある。 良妻にして賢母であったこの人が、三人の子供を残して三十七歳の若さで先立ったのである。露伴は棺前の読経の間、ほとんど泣き崩れるばかりに右手で顔を蔽っていたそうである。第二十七回はその喪中に開かれ、露伴は生花の本二冊を出品した。欣賞会がこれで終わってしまったのかどうかはふ明だが露伴が出席したのはこれが最後であった。「決して長いとはいえない会との因縁だったが、この記事からいくつかの伝記資料を得ることができる」と塩谷はいう。これは露伴の伝記資料のことなのだが、安田にとっても同様のことがいえるであろう。 安田は富豪であること以上に吝嗇家としての悪めいが高かった。筆写は若いころ安田講堂における入学式と卒業式で、彼のな前を冠した講堂に一種の抵抗感、違和感を抱いたことをおぼえている。それは深くその生涯を調べもせずに、安易に一部の世評をうけ入れいたからにほかならなかった。近来財界人の伝記を探るにあたって、安田のみならず、多くの悪評につつまれた人びと、あるいは、賛辞ばかりの人びとの中に、必ずしも世評とは一致しないものがあることに気づいている。安田の場合、皮肉なことに矢野の『安田善次郎伝』では格別の感銘、新発見はなく、欣賞会の逸話と、鶴見 祐輔の『後藤新平』第四巻でそれを感じた。露伴とともに書物を語り、また東京市長となった後藤が、大風呂敷といわれる大都市計画をつくったとき、これをだれより理解し、進んで協力したのは安田であった。「果してあなたが使う人となられるならば、私は集める人となってお手伝いができると信ずる。私はそいう意義のある仕事に向って家産を傾けることは決して厭(いと)わぬ」といえる人が、どうして卑しむべき、単なる吝嗇漢であったろうか。
八王子鉄道 これはいつかもお話したことがあると思いますが八王子と東京との鉄道をつくるときの話。それは後藤 新平さんの時代でありましたか。さあいよいよ鉄道をつくろうというときになると、その左右の村長町長がひっきりなしに陳情にやってくる。いずれも、私の村に停車場をつけてほしい、私の町につけて下さいというのだそうです。もしその陳情をいちいち聞いておりますと、ジグザグ鉄道ができる。そんなことをやっておったのでは、いつまでたつても、とうていできないことは明らかだ。そこでその時の鉄道の係の課長でありますか、部長でありますかその方が、たいへん頭のいい人であったと見えまして、「よろしい、あなた方、鉛筆と紙と定規を持ってきなさい」といって、地図の上の東京と八王子とに定規をあてて、まっすぐに鉛筆で線をひき、「さあ、このとおりにやるんだ」といってやったのが当時日本一真直ぐの東京恥王子線だったということです。町村長は、そのときは必ずしも満足しなかったでありましょうが、それがいちばん近い方法でありますから、その恩恵は長くその地方に及んだわけであります。 これは自明の理であります。しかるに人間というものは、なぜか、この大道を忘れてゆく。小さな利益、小さな便利というようなことに心が奪われて、あちらこちらにさまよっていく。つまり小径にさまようて、大道を忘れるのであります。それがいけない。それではいつまでも人間の目的地には達し得ないわけです。 参考2:鶴見 祐輔:政治家,著述家。岡山県出身。1910年東京帝大法科大学卒。初め官界に身を置いた。1928年衆議院議員となり,以後3回連続当選,1940年米内(よない) 光政内閣の内務政務次官,のち翼賛政治会顧問となる。この間,アメリカ,オーストラリアなどを歴訪し,海外の対日世論悪化防止に尽力。第2次大戦後は日本進歩党幹事長となり,公職追放後,1953年参議院議員に当選,第1次鳩山一郎内閣の厚生大臣となる。1959年政界引退。著書は《英雄待望論》など。後藤 新平の女婿。評論家鶴見 和子〔1918-2006〕・鶴見 俊輔姉弟の父。 2019.07.02 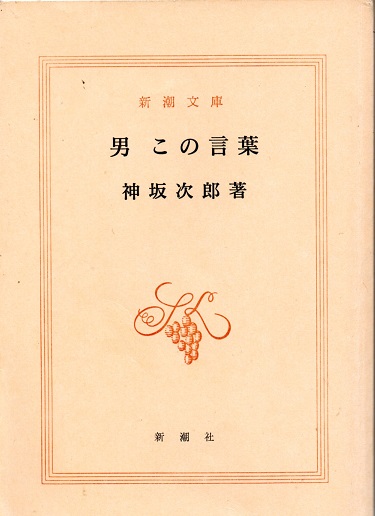
明治の金融王と称われた勤倹堂主人こと安田善次郎(初代)が越中富山から江戸に出てきたのは安政元年(一八五四)十七歳の時であった。 武士とはなばかりの、軽輩微禄の貧苦をきわめた家に育った善次郎は、幼い頃から商人にあこがれていた 「この世の中で」 と、おさない善次郎は思う。 「サムライより強いものは金じや」 こうして、商人として身を立てようと決心した善次郎は、三つのことを心に誓っている。 一、能力を頼まず独立で商人として身をたてること。 一、虚言をいわぬこと。 一、収入の八割をもって生活し、その他は貯蓄すること。 江戸での善次郎は、両替商に奉公し、銭両替に必要な知識を学んだ。こののち善次郎は、(玩具店に四年、海苔屋に三年奉公した後、日本橋の小舟町に一家を構えて、海苔と鰹節との小売を始めた。それは二十五歳のことだった) と、後年、善次郎と親交のあった陸軍軍医総監、子爵の石黒忠悳は『吾輩の見た安田と大倉』(『実業之世界』明治四十一年)のなかで語っている。 《その時、安田君は考えた。商売を繁盛させるには、近所の評判からよくしてかからねばならぬ。といって贈物をするには金がかかる。それではと毎朝、五時に起きるところを四時に起きて、両隣の店先を掃除して、水を撒いて置くことを続けた。それで(両隣の店では)一体誰が掃除してくれるのか、近頃引っ越してきた海苔屋さんだ、と評判が次第に高くなった。これらの親切な遣り方が、安田式ともいうべきもので、今日までそれを貫いている。その一方では元方(帳簿)の勘定を正確にして、品物を安く仕入れて客に売る。それでお客は芝あたりからも来るようになって、店は次第に繁盛した。これが現今資産数千万円と称せられる富豪安田の初めである》 が、一説では、このとき善次郎は店の方は一切妻の房子にまかせ、自分は大きな袋を肩に、毎朝《風呂屋を廻って風呂屋の穴銭(小銭)を大銭に両替して》歩いていたという。 ともあれ、機を見るに敏な善次郎は幕末、維新の混乱に乗じ明治新政府の極秘情報を掴んで太政官札を買占め、一日で三ばいもの利益を得るという濡れ手で粟の大儲けをしている。 その善次郎が次に目をつけたのは、廃藩によって禄高に応じて新政府から与えられた、一種の失業手当、秩禄公債である。公債の償還期限は十五年だが、生活苦に喘ぐ士族たちはそれを安く叩き売り、換金を急いでいた。善次郎はそれを手当りしだいに買い集め、公債を担保にして、借りた金は高利で貸し、利を稼ぎに稼いだ。 やがて二万円という大金をつかんだ善次郎は、これをスプリング・ボードとして明治七年(一八七四)、新政府の官金御用達ともいう司法省為替方にのしあがり、自己資金三万九千余円に加えて、自己の判断で無利子の官金を、三十万円の枠内で使える特権を得た。 余談になるが当時の四等巡査の月給六円、小学校長の古参で十五円。新政府高官のサラリーは、東京府知事が二百円、太政大臣の三条実美、右大臣の岩倉具視で八百円、内務卿の大久保利通は千円といった時代である。 こうして勢いに乗じた善次郎は、明治九年、第三国立銀行、十三年、安田銀行を設立。彼の勢力の下に集まったのは明治商業銀行、金城貯蓄銀行、百三十銀行、日本商業銀行、京都銀行。そのほか二十二銀行、十七銀行、肥後銀行、九十八銀行、高知銀行、根室銀行、信濃銀行、群馬銀行、山形銀行……と、続々と彼の傘下に加わり善次郎は金愉界の最高実力者として"富"への階段を駈けのぼっていく。 立志伝中の人となった後も善次郎は初心を忘れることなく、ある人から、「どうすれば、そんなに成功できるのでしょうか」と訊かれたとき、善次郎は、 「儂はただ、若い時から"勤倹貯蓄"を実行しただけ」 と応え、勤倹貯蓄などといえば、ただ倹約して貯金するだけのように思うであろうが、そうではない。 《勤倹とは勤勉にして節倹を守るの意にして換言すれば「業務を勉強し、冗費を節する」の謂なり、即ち勤は積極的の語にして進取を意味し、倹は消極的にして保守を意味す。故に両者相俟って始めて其効著るし、余は諸子に教えん、勤なると共に倹なれ、倹なると共に勤なれ。 夫れ易きを好み、難きを避くるは人の常情なり、勤倹は美徳なりと雖も、其の実行に至っては頗る至難の業に属す。茲に於てか意志の強固即ち克己心の養成を最も肝要とす。余は日常目撃する処に依り、意志薄弱の徒が常に失敗の悲況に陥るの例証を挙げ、克己心の必要する反証とせん》 そう言って善次郎は、『安田善次郎家訓』のなかで、彼が説く勤倹貯蓄談の実行の困難なことを語り、意志薄弱な者が失敗する例を一つひとつ揚げていく。 《第一、意志の弱き人は……》 なにごとにつけても気が移りやすく、衣服なども流行を追って外見ばかりを飾る。こうした表面だけの欲望にとらわれる人間は出費がかさみ、ついには先祖伝来の財産まで減らしてしまう、貯蓄などとんでもない話である。 《第二、意志の弱き人は》 深い思慮もなく友人知己の保証人などになって、自分から災難を求めることがある。一時の人情にかられて自分の利害を考えない人に、なんで勤倹貯蓄ができようか。 《第三、意志の弱き人は》 商売上の取引などをするにも、いつも人の後になって、いわゆるヒケをとる(負ける・おくれを取る)。こうした人は情実にこだわり、つねに搊失をまねくものだ。 《第四、意志の弱き人は》 困難な事や紛糾した事件などに直面すると、たちまち弱音を吐いたり、これを避けようとして、なにごとも成し遂げることができない。こんな人物は結局、発憤して事に当ろうとする覇気がないので、向上することなど出来る筈はない。 《第五、意志の弱き人は》 その行動がいつもふ規律で、精神が活発でない。こんなことで勤倹貯蓄ができる筈はない。《要するに勤倹貯蓄実行の骨髄は自己の情欲を抑制し、己に克つことに在り、斯くも勤倹貯蓄を遂行するは、人生の必要事項として、又成功の一手段なり》 善次郎はこの自家訓を実行するだけでなく、他人にもそれを奨励した。また毎年二季、従業員たちのボーナスを渡す時に、その袋の中に貯蓄を勧める善次郎の文章が入れてあった。その字句がまた懇切で、こうしてトップから勧められると、従業員たちもついボーナスを銀行預金してしまうということになる。で、 「安田銀行は賞与金に百万円支出しても、それはみな預金として入ってくることになるし、従業員のほうも自然に金が積みたてられて、後には皆々、その社長の好意を徳とした」と、市島謙吉の『春城代酔録』にいう。 神坂次郎著『男この言葉』(新潮文庫)P.55~59 2021.06.16記。
安田善次郎の「運命」 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)(昭和五十九年四月十五日発行)P.231~235 安田財閥の創始者安田善次郎は、大正四年七十八歳(数え)のとき「運命」について語った。(『実業之日本』二月一日所載)。 彼は、「この世にはやはり運というものは確かにある」と語っている。 「しかしその運の神は先方から自分の方へ来てくれるものか、または自分からその運をとりに行くものか、この二つの事の判断のしかたによって、人生の成功と失敗とがおのずからわかれる」 「運は⦅ハコブ⦆なりである。すなわち我身で我身を運んで行かなければ、運の神にあうことも運の神に愛せられることもない。運は確かにこの世に存在しているものとすれば、そこまで自分が行ってそれを取る。それがすなわち⦅運はハコブなり⦆である」 安田はこの処世訓を、自分の生涯に対比させ、その結論として、確信をもって語ったのであろうとおもわれる。
「江戸を去る百里の僻境に生まれ、陋巷の寒家に人と為り、寺小屋の外は、高等の教育を受くるの機会なく、赤手単身にて郷関を出でたるいち少年が、その一代に於て、二億円と称せらるる資産を積み得たるは、我が国数百年の財界を通じて、蓋し稀覯(きこう)の事に属す」 と書いている。 天保九年、越中国富山の町外れに生まれた。父は苦心して金を貯め、下士の株を買って茶坊主にとりたてられたが、内職をしなければ家族をたべさせられない。善次郎も七、八歳頃から花売りをして家計を助けた。十二歳以後は、天秤棒をにない、野菜の行商をして歩く。夜は『太閤記』の写本をつくり、これを売った。そのうち、売薬行商で全国を歩く若者たちから話をきき、広い天地で大いにもうけたいと志すにいたった。 江戸に行くつもりで家出。江戸についたものの、家につれもどされた。親を説得しその許しを得てまた江戸にもどり、両替店に奉公し、ようやく独立したのが二十六歳である。両替店ではあるが資本金はわずか五陵両。日本橋小舟町の四辻で、戸板の上に小銭をならべただけのあわれな露店である。 しかし、幕末から明治維新のドサクサに大いにもうけた。 「最初の目的は千両の身代になりたいとの希望で、出来るあぎりの勤倹を実行して二十八歳のとききその目的を達したから、このさいさらに第二次の希望をおこして、一ヵ年千両のくらしをするような身代になりたいと望んで、四十二、三歳の頃首尾よく目的どおりになった」 と彼は肩っている。 安田銀行の開業が明治十三年、四十二歳のときであった。貧家に生まれて日本の代表的富豪になるその一生は、棚からボタ餅の幸運を夢みてのんびり待っていたものでなく、まさに刻苦精励、我身で我身を運んで運をとりにいったものとというほかはない。 そのかぎりにおいて、安田の談話はいささかもウソをついていなかった。しかし、その「ハコビ」そのものが別の運を招くものだったことが恐ろしい。それは「ケチ」という悪名が世間にひろまったことによる。 それは矢野の『安田善次郎伝』が、「氏が一方にて世人から称賛せられる事柄か、一方にはまた暗に恨みを買う種子となっていたのは是非もない事である」 と書いたところである。 「ケチ」という悪名の原因は「寄付ぎらい」にある。しかし彼には無論、社会に対する富者の義務の意識はあったのであのである。ただその意識は、第一に「陰徳をもって本とすべし。慈善をもって名誉を望むべからず」という父の遺訓にしたがった。第二に、「人の寄付などをたよりにしているようなことで、なんのまとまった仕事ができるか、結局は人をあやまらせるh。自分の汗と血をもって事をなすという方針の上に立った仕事でなければモノにならない」という彼のことばが示すように、寄付を求める者の、自己責任なき他力本願主義を嫌悪していた。金を出すことを絶対いやがったのではなかったのである。 その証拠は、東京市長後藤新平が大東京市開発のため「八億円計画」をつくったときに示された。世間は大風呂敷と嘲笑したのに、安田は正しく評価した。そして、その計画はちいさすぎはしないかといったあと、 「私はこれまでいずれの慈善事業にも、郷里のことにも名前を現わして出金したことはありません。が慈善の根本から割出された事業ならば、微力をつくしてみたい心はもっております。(中略)私の心は神明の知り給う所とうぬぼれているのです。(中略)あなたが使う人となられるならば、私は集める人となってお手伝いができるよ自ら信ずるのであります。しかしあなたが他人の力に信頼せぬとおっしゃればおれまでであるが、私はそういう意義のある仕事に向って家産を傾けることを決していとわものである。死んでいくときは黄金の棺に入れるわけでも参りません」 といったのである「鶴見祐輔著『後藤新平』第四巻」。
この申し入れをして間もなく、大正十年九月二十八日朝、大磯の安田別荘に一人の面会強要者があらわれた。 男は、まず労働会館建設のための寄付金を申しこみ、ことわられると短刀を出して、安田の顔を二ヵ所刺し、さらに庭に逃げようとする背後からおどりかかって、咽喉にとどめをさした。男は、自分も咽喉を刺して自殺した。 男は朝日平吾三十二歳。ふところに斬奸状を書いたものをしのばせており、その冒頭には、「奸富安田善次郎巨富ヲ作(ナ)ストイへドモ富豪ノ責任ヲハタサズ、国家社会ヲ無視シ貪欲卑吝ニシテ民家ノ怨府(えんぷ)タルヤ久シ。予ソノ頑迷ヲ愍(あわれ)ミ仏心慈言ヲモツテ訓(おし)フルトイへドモ改悟セズ、ヨッテ天誅ヲ加へ世ノ警(いまし)メトナス」 とあった。朝日は寄付がことわられることをあらかじめ予測し、殺すつもりで会ったのだ。 安田善次郎八十四年の不屈の生涯が、そういう凶変で閉じられたことはいたましい。七十八歳で「運命」を論じた彼にも、六年後のそのことは予期できなかったところに人間の限界があるのだろう。 (昭和五十二年八月) 20203.06.05 記す。 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.189~193 大倉 喜八郎 功成り、風流の日送る 「鶴彦」という名前は、スマートな優男を連想させる。大倉 喜八郎晩年の雅号がその鶴彦で、写真を見ただけの印象では、ご本人よりもむしろ伜の喜七郎の方こそふさわしかったようにも思えるのだが、ともかくも喜八郎は鶴彦をなのり、喜寿記念として出した『喜寿狂歌集』は大倉鶴彦選となっている。功成り、なとげて、向島の別荘で悠々と過ごす風流三昧の日常は、実業家喜八郎でなく、風雅人鶴彦のものだったようである。その向かい側の家に幸田露伴が越してきたとき、おなじ向島の住人であった画家中村提雨、彫刻家木内半古(きうち‐はんこ)などから露伴のことをきいた鶴彦は、 「お会いしたいのでいつでも……」 とことづけをたのんだ。しかし露伴はすでにのべた理由で、名公富豪と会うよりは魚を釣る方を好む。いつも用にかこつけてことわっていたが、ある日、露伴ひとりを招きたいとのことで、行ってみた。明治三十八年というから、鶴彦六十九歳、露伴三十九歳のときである。 会って第一に感じたことは、鶴彦が礼儀正しく慇懃な態度で露伴のきらう「人を圧する驕気」はまるでなかった。当時ロシアにとらわれていた郡司成忠大尉(しげただ:幸田露伴の兄)に関して弟の露伴への慰問のことばにはじまったがそれは少しもいや味にきこえなかった。それから、人間にあっての「窮通の運」ということに話しが移った。 「私も人にはひどく言われたり、仕事はまずく手づまりになったりしたこともありますが、幸いに今日にいたり、せんだってもも店の者たちが私の像を銀で作って寿を祝ってくれましたが、なあに人はいのちさえありゃ……」と鶴彦はいう。「もし病気から発せられたのなら厭わしい気もしようが、主人はただ事実をいったにすぎないのであって、その≪なあに人は≫という段には、主人の手強い信条と剛邁な気象とを洩らしたのである」(塩谷 賛(しおたに さん):『幸田露伴』中)。 「それはまことにおめでたいことですが、銀のご自分の像にお向かいになったときどのようなお気持ちがなさいました?」と露伴がきくと、鶴彦は率直に「別に何の心持ちということもありはしません。銀はせんから世界にあったので、これから先も世界にあるので、ただかりにちょっと姿を結んで私になっているのだ、私だといえば私だが、私はかりそめの主人なのです。だから末末は私の知ったことではない。だがみんなの心持がこの像をこしらえてくれていると思うと……」とそこまでいってあとはなかったが、満足そうにのびやかなふうであった。 「さよう仰せあれば事業も財産もみんなそうでしょうが」 「そうでござんすとも」 間髪を入れないで主人は答えた。これはひょっとすると、華厳金獅子の話でもだれかにきいたことではないかと露伴は思って、 「まるで金獅子ですね」といってみた。鶴彦はそれを知らなかった。ということは、そういうまた聞きの話をもとに、したり顔のツケ焼き刃的悟りをいったのではなく、まったくの自家自談、体験からおのずと発したことばであるということだ。露伴はそれまでにきいていた世評の非を知った、というが、たしかに鶴彦ならぬ喜八郎にはいまわしい噂が散っていた。 大倉 喜八郎が姉からもらった二十両をふところに、ふるさとの越後国新発田から江戸に出たのは十八歳のときである。まず麻布飯倉の鰹節店に住みこみ、二十一歳のとき下谷に間口二間のささやかな乾物店を開いたが、幕末の情勢が緊迫するにおよんで、鉄砲店「大倉屋」を神田和泉橋に開いたのが二十九歳のときである。上野の彰義隊に拉致され、官軍に武器を納入したかどで詰問されたこともある。返答次第では一刀両断されるところであったが、商人は商売が生命、現金で品物を買ってくれるのがお客さまなのだから売るのは当然でしょう、と啖呵を切って釈放された。 維新後は貿易業に転換したが、日清戦争のとき、缶詰に石ころをつめて納入した、という評判が立った。また、日露戦争でも大倉の牛罐を食べた姫路師団の兵士が血を吐いたとか、軍靴が糊ではりつけたものだったため、旅順閉塞にいった兵士の靴が海水でぬれ、裏皮がはがれて甲板からすべり落ち、溺死した、といううわさが流れた。当時軍用糧食はすべて大倉組の独占するところであり、それによって莫大な利益を得たことへの反感から発したデマ宣伝だったらしく、露伴もそういううわさを鵜のみしていたのである。 初対面の印象は双方ともによかったようで、それから交際がはじまった。鶴彦は、露伴の家の庭先へ静かによって少し話を交していくこともあった。奉書に大きな字を書き、鶴彦と署名したのをとどけてよこすこともあった。文字はうまくないが、光悦流であった。四月八日は灌仏会(かんぶつえ)、おりから向島は花のさかりで、鶴彦のところでは感涙会という催しがある。この招待文で露伴に相談することもあった。露伴は行ったことはなかったが、やがて半月形の溜塗(ためぬり)に桜の花を朱で散らした重ね重箱に幕の内をつめて届けられた。『喜寿狂歌集』ができるときは序文をたのみ、また鶴彦の一字をとってつくった鶴友会の委嘱で戯曲『名和長年』を書き、これは戦前東京で十回、戦後東京と大阪でそれぞれ二回上演されるということもあった。鶴彦が入手した虫太平記二軸を見せて、意見をきくということもあった。 鶴彦が八十歳をすぎてから、愛妾に子供ができた。近所の百姓たちは、「いくら大倉さんでも、そいつは無理だろう。多分、小作がはいったのだろう」とうわさしていたが、生まれた赤ん坊は鶴彦そっくりの顔をしている。「やっぱり大倉さんは偉いもんだな」と彼らは感心した。 露伴は、鶴彦のこういうエピソードをこっけいに思いながらも、何でも大掛りにやることや無邪気なところを好ましく思っていたようだ。あるとき、袁世凱から送られたという珍しい酒をよばれ、うまいうまいといって大量にのんだ。そのあとで鶴彦が「この酒は、袁世凱が兵隊何百人をつけて雲南の奥から運ばせたものです」といったので、露伴は恐縮してしまった。 小林勇は、露伴が鶴彦のうわさをするのを何度もきいていたようである。赤石山を丸ごと買ってしまった話、シナに野心をもってみずからのりこみ、袁世凱に会った話。維新のころ、鉄砲を売りこむときの様子を露伴が話すと、大倉は英雄のようになった。ところが、あるときを境に、露伴は鶴彦を離れた。「自分の伝記を書いてもらいたいというようなことをちらといったのである」 (『蝸牛庵訪問記』)。 2019.07.26 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.194~198 伊庭 貞剛 栄達よりも心の平静 翁は、媼とともに、老人にたいする敬称だというが、この字をその雅号にとり入れた幽翁伊庭貞剛が八十歳、どん(金偏+屯)翁益田孝が九十二歳、松翁安田善次郎が朝日平吾の凶刃にかかったとき八十四歳というふうに、いずれも長寿であったのは不思議な符合であったというほかはない。そして三翁とも、それぞれの仕方でおのれの老年を享受し、後世の人間に無言の教訓をたれているかのとうでらる。 「年をとることは死ぬことよりもむずかしい」と書いたのはアミエルである。彼はこのとき三十九歳であったが、このことばにつづけて、<……一つの宝をひとまとめにして一度であきらめることは、その宝を毎日なしくずしに新しく犠牲にすることほどつらくはない、という理由によってである。わが身の衰えに耐え、わが身が小さく弱くなってゆくことを受け容れることは、死を物ともしないこと以上に苦く稀な徳である。悲劇的な夭折には栄光がある。つのりゆく衰には長い悲しみがあるばかりである。しかしもっとよく考えてみよう。すると、苦痛を耐え忍ぶ・宗教的な老年のほうが、若い時代の英雄的な激情よりも胸を打つものがあることがわかってくる。魂の成熟はいろいろな能力の輝きや力のゆたかさよりも価値がある。そしてわれわれの裡の永遠なるものは"時"の猛威によって加えられる損害のかずかずを利用するにちがいない。そう考えると慰められる」。 アミエルはこのあと二十一年生きて六十歳で死んだが、その最後の日々をみると「恐ろしい夜。引きつづき不眠にさいなまれて第十四夜を迎える……」「意気消沈。……肉体と精神とのものうさ。生きるというこは何と困難だろう。おお、私の疲れた心よ!」というように、その心境は必ずしも平穏でなく、東洋風の「悟り」というものとほど遠いような感じをうける。その印象自体、「年をとることは死ぬことよりもむずかしい」という彼のことばの真実性を裏書きするかのようであるが、この意味において、年のとり方、老年の迎え方に、もっとも見事な実例を残したのは幽翁伊庭貞剛だったように思われる。「出処進退」においても意識的に実行された人生の一大事であった。 大阪上等裁判所判事をやめて郷里に帰ろうとしたのが、明治十一年三十二歳のときである。世渡り、立身出世主義だけを考えれば、弊履のように捨て去るにはおしいステイタスであったろが、彼は暮夜ひそかに権門勢家に出入りしてその鼻息をうかがうような官界の腐敗堕落にたえられなかった。栄達よりも心の平静、満足を求めることが人生だと考えたのである。 その彼が、叔父広瀬宰平の説得で住友入りしたいきさつは『日本サラリーまん外史』でのべた。本店支配人となり、大阪紡績、大阪商船の取締後、大阪参事会員、大阪商工会議所議員、大阪株式および米穀取引所の役員などを兼ねたが、四十一歳のとき琵琶湖畔石山に隠居の地を求めた。現世的にはもっとも欲や執着の出るその立場と年齢において、彼はすでに晩年をみつめていた。それは無常観にとらわれた敗北主義のあらわれでなくて、いつでも辞表を書いて引退できる場所を確保した上での、戦闘の構えに他ならなかった。仕事への没入と同時に名利からの離脱が期せられていた。 死を決して別子銅山の争議現場にのりこんだのが四十八歳である。このときの彼のやり方を評して「不思議なる哉、氏が山を登ったり降りたりしている間に、人心はいつの間にか鎮静して、さしもの紛擾も漸次解けてしまった。こうして氏は遂に大難関を首尾よく切り抜けて、住友を泰山の安きに置いたのである。自分は伊庭氏の大処、即ちエライ処はここにあると信ずる。このような大事件に処して、目立ったことはなにもせず、ただ日々山を登ったり、謡曲をうなって日を暮しているというような飛び離れた芸当は、とても常人の考えもつかない業である。誠に今日のいわゆる敏腕家なるものをしてこれに当らしめよ。そのする事は大抵わかっている。あるいは規則を改正するとか、あるいは取締を加減するとか、とかく枝葉に走りたがるのは世間を通じて一般というても過言ではあるまい。このようなことをもって伊庭氏のやり口とくらべてみるとまるで段がちがう」と河上謹一(伊庭貞剛に破格の待遇をもって招聘された)は書いている。 この河上というひとも、住友理事を四十九歳でやめると須磨の別荘で悠々自適の生活を送り、加藤高明内閣のとき外務大臣就任の交渉を受けたがこれを断るというふうで、八十九歳で世を去るまで俗生への執着心をもたない点では段ちがいの偉材であったが、このひとが「長い間にいわゆる人格の人というのを唯一人見た。性来頑固で余り人に感心しない自分も、この人の人格には感心せざるを得ない」といった相手が幽翁であった。 幽翁は荘重達意の文章家であったが、新聞雑誌には一度も寄稿したことはなかった。それが五十八歳のとき、はじめて『実業之日本』に「少壮と老成」という感想文を発表した。かれはこの中で、老人の経験の貴重さをいうとともに「老人はとかく経験という刃物をふりまわして、少壮者をおどしつける。なんでもかんでも經驗に盲従させようとする。そして少壮者の意見を少しも採り上げないで、少し過失があるとすぐこれを押えつけて、老人自身が舞台に出る。少壮者の敢為果鋭の気力はこれがために挫かれるし、また青年の進路はこれがために塞がってしまう。……事業の進歩発展に最も害をするものは、青年の過失ではなくて、老人の跋扈である」と書いた。そして彼自身は、これから五月後に住友総理事のポストを四十四歳の鈴木馬左也(第三代住友総理事)にゆずり、十七年前から用意していた石山の別荘「活機園」に隠棲したのである。 彼はこの山荘で静かに老いていった。はじめは、日常の動静を語るに「悠々自適」のことばを用いていたが、七十八歳のときから「曠然自適」というようになった。「悠々」にはまだどこかにアカのぬけきらないところ、自力をたのんで得々然とした趣が残っている。「曠然」は、何ものにもとらわれぬ無礙自在の境である。大正十五年五月、八十歳のとき子女をあつめて遺言し、財産を分けてやった。そして十月「ああ、こんな悦びはない。この徹底したよろこびを皆の悦びとして笑ってお別れしたい」といい、家族順々の水をふくませてもらった。そのとき、幼い孫が二度ふくませようとすると、「お前はさっき、くれたではないか」といって微笑し、やがて大往生をとげた。筆者はこの間恩師から、「昨今は隠居入道ということがない。隠居即入墓と考えているようだ」という話をきき、伊庭貞剛のことを思いださずにいられなかった。 2019.07.24 |
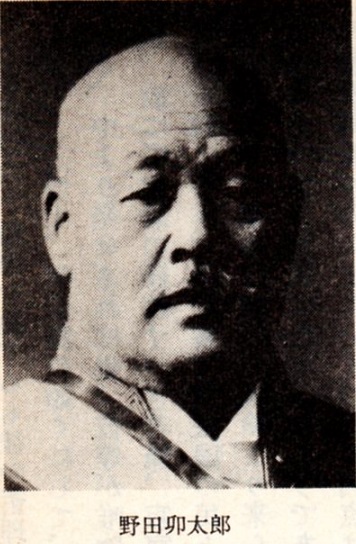
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.199~203 野田 卯太郎 益田孝にほれこまた大食漢 伝記が、ある人物の生涯を物語るものである以上、業績や奮闘談ばかりでなく、たとえば大食であったとか、便所が長かったとか、日常生活のディテールも書かれておいた方が人間味が出てよろしいように思うが、そういうものは意外に少ない。それだけに、別の人物の伝記や記録などでそういう事実が語られているのを見つけると、大変にたのしい。 益田孝はその伝記(『自叙益田孝翁伝』)の中で、二人の大食漢の話をしている。一人は松方正義、もう一人は野田卯太郎(大塊と号す。政友会副総裁、商工大臣)である。松方は、晩年でも常人の二人前は平気で食べたあと、そのあとでカルカシなどをむしゃむしゃやったし、金本位実施のときは、毎朝生タマゴを十五ずつ食って出たというのである。野田は益田に茶の接待を所望した。益田は承知して明晩五時と約束したが、その時刻になってもやってこない。五時半になってもあらわれない。約束して来ないのはけしからん、と憤慨していると一人でやってきた。どうしたのかというと、茶をご馳走になるので飯のご馳走になるのではないから、銀座で天プラを食ってきたのだという。話しているとまた一人やってきた。これは富士見軒で西洋料理を食ってきた。茶に招かれて、飯を食ってくるやつがあるものかというと、どうも知らないものだから食ってきたのだが、せっかく用意ができているのならご馳走になろう、といってむしゃむしゃと懐石料理を平らげた、というのである。天プラの方か西洋料理の方かははっきりしないが、二人のうちどちらかが野田であったことはまちがいない。 團琢磨にも野田についての回想があって「野田君と初めて知りあったのは、たしか明治十七年か八年、私がちょうど三池へ技師となっていっていたころで、そのころ野田君は郡会議員をしておった。きたない兵児帯をしめてワラジがけで郡内をまわり歩いていたものである。当時から肥満した大男で、体重三十貫もあって、梅ヶ谷から、政治家などにならないで角力とりになんなさいとすすめられたほどであるが、私のいた工場へよくきては、赤ん坊の頭ぐらいある大きなにぎり飯を十ぐらい竹皮包から出して、むしゃむしゃ食べていたが、その姿が今でも目に浮ぶようである。そして梅干しのはいったそのにぎり飯をほおばりながら天下国家を論じていたものです」と語っている。 このころ野田は三十二歳で、さらに四年たったとき、三池炭礦の払い下げをうけた益田に知られ、その庇護をうけて中央進出のチャンスをつかむのだが、野田を信用した原因も、食事に関係していた。炭礦の引きつぎで益田が石炭問屋に泊まっていると、そこに地元の有志家野田卯太郎、永江純一などが久留米ガスリにねずみ色になった白木綿の兵児帯でやってきて、炭礦の製作所(鉄工場)を売ってもらいたいと申し入れた。どうするのかときくと、われわれも何か仕事しなければならないから、農具でもつくろうと思う、と答える。それじゃ仕方がない、君方のために考えておることがあるから、まあ僕にまかせておきたまえ、といって帰らせた。そして益田は野田の身辺を調べさせたのである。 「野田なぞは自由党の壮士で、仲間が五、六人三池付近で家を一軒借りて同居しておったが、だんだん調べてみると、じつに感心なもので、品行方正で女気なぞはまったくない。世話をしている婆さんが、野田さん今日は何をこしらえようかなあ。ゆうべのタクアンは残っていないかい、残っているか、それならそれでええじゃないかというような調子で、じつに質素な生活をしておった。よし、この連中なら信用してよいと思って、君らのために考えておるのはじつは紡績だという話をした」と益田は語っている。 これは野田の人柄と同時に、益田自身の人の見方をも語っている。今日流の判断の仕方――何よりも先に「学歴」を調べるやり方でなくて、単刀直入、その食生活を見て信用したというやり方は、何となく山路愛山の考え方を思わせるものがある。愛山は「……博学畢竟拝むべき者なりや否や。もしもシェクスピアを読まずんば戯曲の消息を解すべからずとせば、シェクスピアは何を読んでかシェクスピアたりしや」、「たとひ深遠なる哲理を論ずるも彼の論理に非ずして書籍上の哲理ならば、何ぞ深く敬するに足らんや。……博士、学士雲の如くにして、其言聴くに足る者少なきは何ぞや。これ其学自得する所なく、中より発せざれば也。彼等が唯物論として之を説くのみ。未だ嘗て自ら之を身に体せざる也。故に唯物論の経験すべき苦痛、寂寥、失望を味わざる也。彼等が憲法を説くや亦唯憲法として之を説くのみ。未だ嘗て憲法国の民として之を論ぜざる也。故に其言人の同感を引くに足らざる也。彼等の議論は彼等の経験より来たらざる也」(『明治文学史』)とそのふ信感を書いている。益田にはその種の言説はなかったようであるが、発想法、人の見方の根本に、似たものがあった。 学歴を尊重することにいくつかの利点はあろう。しかし、それ以上の、人間的、本質的なものを見逃しはしないか、野田の場合、父は四町歩の地主の家に生まれたが、次男坊であったため、妻と三歳の卯太郎をつれて他家に養子にゆき、その翌年死亡した。未亡人は卯太郎とともに里に帰り、やがて子供を里の父にあずけ、亡父の夫の弟と再婚した。卯太郎は祖父に養われて成長し、早くも十代からは家業の豆腐屋を手伝い、天びん棒をかついで豆腐を売り歩いた。寺小屋にいっただけで学歴はなく、ただ猛烈な読書家で、暇を見ては本を読み、独学独習、ただ一人で開眼し、大志を抱いた。 明治十一年二十六歳で三池郡小区会議員に当選し、二十八歳で自由民権運動に加わり、三十一歳で村会議員、三十四歳で福岡県会議員に当選した。團と知りあったのは村会議員になった年、益田にしられたのは県会議員になった年であるが、無論、團も益田も、その議員の肩書で彼を信用したのではなかった。團は、野田の大牟田開発のビジョンに共鳴し、益田は生活態度を信用したのであった。「肩書」や学歴にとらわれなかったことが、野田のよさを見逃さない利点に化したようである。 益田がこの払い下げのとき、新しい就職先のきまっていた團を強引にもらいうけた話はすでに書いたが、それは團が当時としては非常な希少価値があったマサチュ―セッツ工科大学出身のバチュラー・オブ・サイエンスの学士号をもっていたからではなくて、三池炭礦開発のために上可欠の優秀な体験と実行力をもっていることを重視したのであった。学校を出たことと実力があることとは、一つのこととみえて、じつは別々のことである。益田という人は、そのことをはっきり見ていたようである。 2019.08.09 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.204~208 小泉 策太郎 『国民之友』読み開眼 小泉 策太郎が「三申」という雅号をもったのは十二、三のころだという。このころ俳句をはじめ、小学校の先生につけてもらったのである。この先生は元幕府につかえた漢学者で、幕府瓦解のあと天城山をこえて南伊豆に入り込んだ。そして子浦に安住し、小学校ができたたとき、その初代訓導になった。「三申」というのは、小泉少年の生まれた明治五年十一月三日午後四時というのが、申(さる)の年、申の日、申の刻にあたるところからつけたものだが、のち少年が政友会代議士となってからは、見ざる、聞かざる、言わざるの「三猿」の意にうけとられることもあった。政治家として、大いに見、大いに聞き、大いに言うくせに、あえて「三猿主義」を標榜するところが策士らしい、という見方による。 それはともかく、三申少年は大変な読書家であった。十三、四歳になると、為永春水や滝沢馬琴の作品を愛読した。小学校を出たとき、家が貧しいので進学できなかった。蘭学塾にはいろうにも、月十銭の謝礼を払う余裕がなかった。そこで子守をアルバイトにしながら、子供をおんぶしたまま塾の縁側の方から室内の講義の声に耳をかたむけるという工夫までした。東京に徒弟奉公にいったが一年でやめて帰校し、母校の先生となった。このとき生涯を決定する大事件がおきたのである。 二十五歳の徳富蘇峰が『国民之友』を創刊したのがこの年(明治二十年)二月である。これを読んで感激した静岡県庁の雇員山路愛山は蘇峰に手紙を出し、やがて蘇峰の庇護のもとに史論家としての人生コースが開けた話はのべた(六〇ページ)。小泉三申も、蘇峰に手紙こそ出さなかったが、大きな影響をうけた。のち岩波書店から『小泉三申全集』が出たように小泉三申は政治家という以上に史論家であり、文人であったが、その文書的開眼をしてくれたのが『国民之友』なのである。そして三申は手紙を書かず、個人的に恩顧をうけるということはなったのに、二人はふ思議な糸に結ばれる運命にあったのである。 三申は、二十二歳のとき村上浪六の居候となり、作家を志して、『新小説』の懸賞小説に一等入選したこともある。ところが百円はもらえるものと考えた原稿料が十円だったため、これでは生活できぬと断念して三十三歳のとき『自由新聞』記者となった。このとき同僚に幸徳秋水、堺枯川、斎藤緑雨らがおり、とくに秋水とは終生の交りを結んだ。三申はこの新聞に『慶安騒動記』を連載して史論家として注目され、これを改題した『由比正雪』以下、『加藤清正』、『明智光秀』、『織田信長』が『偉人史叢』シリーズとして公刊された。このうち、とくに『織田信長』の一巻は徳富蘇峰の注目するところであったが、三申本人はそのことを知らなかった。彼にとって生涯の目標は政治家になることであり、文章は余技にすぎなかった。財界進出に転換して、新聞記者から米相場、石材売りこみにかわったのが三十二歳、衆議院議員になったのが四十一歳のときである。そして五十歳のとき、逗子の老竜庵にはじめて蘇峰を訪ねた。『国民之友』以来三十五年、『織田信長』以来二十四年の歳月が流れていた。 蘇峰はにこにことして迎え、 「いやもう先生のことは、よく知っています。先生の『織田信長』を熟読、敬朊しています」 といった。三申はびっくりし、これをお世辞だとうけとった。(さすがに蘇峰先生は老熟大成の域に達していられる。人をそらさぬ、ほどのいいことをいわれるものかな)と感心したのである。ところが蘇峰はふいと起って、ぎっしり本のつまっている書架から、さがしもせずに一冊抜きだしてきた。 「この通りですよ」 と示されたのをみて、三申はおどろいた。偉人史叢の一冊『織田信長』で、しかもところどころに付箋して、何か細かく書きいれてある。蘇峰は、そのような熟読、評価の体験をふまえて三申を「先生」とよんだのである。この真面目さが「文人」蘇峰の真骨頂であったわけだが、どこまで三申がそのことを理解したかは疑問であった。 「蘇峰翁は僕を叱って、何故文章に精進せずして、ろくでもない政治家になったかといわれます」ということを三申は「痴遊に寄す」という文章の中に書いている。この蘇峰のことばに自分が何と答えたかは書いていないが、文章全体はおのずとその回答となっている。三申は伊藤痴遊(仁太郎)が講談師として有めいとなり、政治家として世にあらわれなかったことを、余技が本技をしのいだ例として遺憾の意を表している。三申において人生の「本技」とは「政治家」となることであり、その意味において「文人」としての生涯は、第二義的な、余技の世界への陥没に他ならず、蘇峰の忠言もその意味では「片腹いたい」ということだったかもしれないのである。 しかし蘇峰の真意は「政治家」と「文人」の相互比較において、後者を高しとする価値体系から、三申に文章への精進をアドバイスしたのではなかったであろう。政友会代議士としての三申は「政界の黒幕」、「策士」のなを喧伝されている。そういうマキャベリ的世界への没入は、経国済民を本旨とする「政治」の邪道であり、そこに三申の才能が消耗することを愛惜したのではなかったか。 三申は、昭和三年五十七歳のとき、田中義一首相と所見を異にして、政友会を脱党した。この二年後の総選挙のとき、非常な苦戦をしたが、このとき蘇峰は応援のため、沼津、三島の演説会場に姿を見せたのである。「私もくだらぬ顔ですまされない。潜行して楽屋まで礼に出たついでに、先生の演説をぬすみ聴きしたのだったが、先生は昔山田武甫(やまだ たけとし)――熊本の自由党の開山です――の選挙応援をした後、二十年来か三十年来か、政治演説に出たことがないが、小泉が負けそうだときいて、久しぶりに出て来たというので、天下独歩の快弁をふるわれ、自分が小泉を相知ったのは、古今稀れなる英雄に紹介された。その人はすなわち織田信長である。信長がわれわれを親しくさせたと説きはじめられたのが、おかしくもあり、こそばゆくもあった」と三申は語っている。 この選挙は、政治家三申にとって最後のものであった。「政界風雲の策源地」として注目された往年の華やかさは消えて、書画、仏像に親しみ、文筆を友とする日常と変わった。彼はとくに西園寺公望に近づき、『随筆西園寺公』などを書いたが、やがてその仕事は中断した。策士の接近を警戒する園公側近が、彼の訪問をよろこばなかったためで、「本技」が「余技」の成就を妨げた、ともいえそうである。 2019.07.30 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.209~213 深井 英五 牧師志し同志社へ、しかし 徳富蘇峰の民友社に、明治二十六年の末ごろから深井英五という二十三歳の青年が加わった。青年は「金蘭簿」という社員めい簿の指定項目のところに、「得意は無し、趣味は無し、主義は厭世、希望は寂滅」と書きこんだ。いかにもニヒルな感じであるが、深井自身は「少し茶目気分もまじったのであろうが、自棄に傾いた懊悩の心境があらわれている」と回想している(『回顧七十年』)。 彼は上野国高崎藩士の四男坊である。家系が苦しく、中学への進学をあきらめて小学校の「授業生」になっていた。これは小泉三申も郷里でなったことがある助教員のような仕事で、若干の月給がもらえたから本代ぐらいにはなった。そして十六歳のとき、米国人ブラウン夫人の奨学金をうけて同志社普通学校に入ることができた。 そのころ同志社には、普通学校と神学校があった。神学校はキリスト教の牧師を養成するところで、普通学校(五年)を卒業したものを収容する仕組みであった。すでに十四歳のとき洗礼をうけてていた英五は、この神学校をへて牧師になるつもりであった。「同志社教育は広汎にして深厚なる影響を私の一生にあたえた。もっとも重しとすべきは、新島襄先生の感化による人生観の育成である」(前掲書)と彼は書いているが、新島は淡々とした態度しか示さないので、自分にたいして格別関心がないのかとさえ思ったことがあ。ただ、新島は、とくに訓戒するというような態度はとらず、むしろ自分の体験を語るという形で静かに人生への心構えを説いたのであった。 それには、三つのポイントがあった。第一は自己の信念に立脚しなばならぬ、付和雷同やゴマかしてはいけないということ、第二は、単に自己生活のためではなく、世の中のためになるように心がけねばならないということ、第三は、何か仕事しなければならないということ、である。 「それが訓戒ではなく、先生の胸中を吐露されるがごとく聞えたので私は一層深く感動した。神を父とし、人間を同胞とする教理の応用として、私の実践的人生観の基礎ができた」。ところが、自分独自の思索を深めてゆくにしたがい、英五は教理にたいする疑惑をつぎつぎと感じた。たとえば処女受胎という奇蹟につまづいた。「しかしながら信仰は思想にあらずして、心の熱である。熱の源たる伝統の権威がなくなって、その教理を単なる思想として検討すれば、矛盾または不合理らしく見ゆる点にたいしてふ安が拡大される」。 ※関連:椎な麟三著『私の聖書物語』。 「宗教と理性を調和せんことを期したところの思索は逆の結果を生じ、私の数年間心にいだきたる念願は破壊した」。普通学校を卒業したとき、もはや牧師になる気持ちはなく、神学校入りはやめ、「真理および人生価値の標準について全然懐疑におちいってしまった」。それと同時に生計をどうするか、の問題でもあり、神経衰弱になるか、大脱線をするかもしれぬ境界に立っていた。それを見て、同志社の学友で、早くから新聞記者を志して『国民新聞』に入っていた平田久(ひさし)が徳富蘇峰に助力を乞うたのである。 蘇峰はこのとき三十一歳で、深井青年に哲学への執着があるのを見て、東大で心理学を講じていた元良勇次郎に庇護と指導をたのんでやった。深井は元良の学問に深い影響をうけたけれども生活費をかせぐ道は見出せなかった。そこで蘇峰は、外国新刊書の要領をパンフレットにし、毎月一冊ずつ民友社から出版して生活費をかせがせる方法を考えてやり、これが約一年つづき、そのあと『国民新聞』に入社しないか、とすすめたのである。それも、普通の記者ではなく、後方にあって政治、法律などの学問を研究するという仕事で「いわば捨扶持の読書生の如きもの……月給は少ないが、書物を多く買ってもらった」。深井は感激して蘇峰の好意をうけた。 蘇峰自身は、「君を予の理想的の新聞記者につくり上げようと思ったが、その方面では予はいささか予の考えがまちがいであることを悟った」(『蘇峰自伝』)と回想している。「君は小心に過ぐるというべきほど、堅実性に富んだ人であって、山気たる事とか、冒険的な事とかは好まない。頭脳は全く倫理的にできていて、自らまず酔うて、しかして後人を酔わしむるなどという手際は、望むべきでなかった」。ただ、その英語と調査能力が抜群であることを見ぬいた蘇峰は、七年後、大蔵大臣松方正義(薩摩藩士)、にその能力を推薦し、深井はその秘書官となって、別個の人生が開けるのである。 深井は、「一生懸命に努力したつもりだが、成績からいえば自分でも甚だふ満足であった。ただ私自身のために得るところはすこぶる多かった」という。 それは第一に、「世間表裏の臭いをかいだ」こと、第二に、「国家本位の現実主義」を心にうえつけたことである。蘇峰のスタッフであった七年間の、特に重要な事件として彼は三つをあげる。第一は、日清戦争のとき、大本営地広島で通信員となり、ついで従軍記者として関東州にわたったことである。このとき徳富のスタッフとして、参謀次長川上操六中将の庇護をうけ、その人間味に接したことは大きかった。それまでは蘇峰も川上に好意をもってなかった。ところが「一見旧のごとし」「会ってみて、日本の陸軍の脈はここにあり」と感じた。川上は、「徳富君に何一つ不足はないが、こまったものは例の平民主義……これさえ止めてもらえばまことに結構である」といった。しかし蘇峰は「彼(川上)は薩摩の生地にドイツのメッキをした男で、ついに平民主義の真諦はわからなかったが、しかしその考え方も、その態度も、彼は自らしらず覚えざるに平民的であった」と評している。 第二は、二十九年春から三十年夏にかけて蘇峰が欧米を巡遊したとき、その随行をしたことである。ロンドンでは、タイムズ紙の編集次長を数十年やって特異の経歴をつくったキャッパ―と蘇峰は「一見して意気投合」、深井も「共通の接遇」をうけた。ところがこれから十年後、日露戦争の外債募集で高橋是清がロンドンにきたとき、深井は高橋に随行し、キャッパ―を紹介して便宜をうけることになる。 第三は、英文雑誌『THE FAR EAST』を編集したことである。 松方の秘書官となり、徳富と深井の関係は一段落となったが、深井の心情においては依然として「門下生」の意識がつづき、それは終生変わらなかった。国民新聞社をやめるとき、蘇峰は「春鴻秋燕人力に非ず明月清風我に随いて長し」ということばを書いて贈ったが、深井は自分の心境を道破したものとして書斎に掲げた。昭和十四年、すでに日銀総裁、枢密顧問官の顕職をつとめた深井が、病気療養中に蘇峰にもらった手紙を整理装幀させると、十一巻二帖の大部数になったという。 昭和十二年に総裁職を辞任しました。
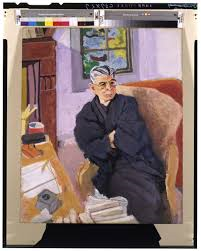
安井曽太郎の「深井英五氏像」 六月十一日まで、東京・京橋のブリジストン美術館で「生誕九十年記念 安井曽太郎展」が開いている。NHKテレビでは「日曜美術館」でこの内容を紹介し、日本経済新聞は五月二日の教養読書特集で、同画伯の「深井英五氏像」と、嘉門安雄の解説を掲げた。 この「深井英五氏像」は、昭和十二年に描かれたもので、肖像画の代表的傑作であるという。 なにが代表的傑作たらしめた要因であろうか。 「深井さんの普段の姿を描きたいと思って、その書斎での深井さんを絵にすることにした。深井さんの書斎は余り広くなく、そのうえ大き過ぎるくらいのテーブルが置かれてあり、床には沢山の書物が積み重ねてあって、やっと画架が置けるくらいであった……」 とは安井の述懐である。 「私はこの絵を見るごとに、やや斜めに構えて微動だにせず、じっと日銀総裁の深井さんをまともから見据えている安井曽太郎のきびしさを思う。だからこそ、このような素晴しい肖像が、人間像が描かれるのである。豊かに深く、さわやかに温かい絵である」 と嘉門は賞めている。たしかにそのとおりであろう。 ただこの画像をじっと見つめていると、おのずと別の感慨がわいてくる。 深井英五は、昭和十六年第十三代日銀総裁となった。その前には、パリ講和会議、ワシントン軍縮会議に、全権随員となった。ロンドン国際経済会議には、全権として列した。貴族議員、枢密顧問官にもなっている。 ところが安井は、そいうステイタスに何の関心を示さず、「普段の姿」を描こうと志向している。そして深井も、和服にくつろいで描かれている。その書斎が余り広くなく、床に沢山の書物を重ねてあるというのも好ましい。そこに、とりつくろわぬ素顔、日常生活が露呈されており、スノピズムの侵入する余地はない。そして、じっと見据えるきびしい画家の眼にこたえているのは、深井自身の、ウソのない人生である。 ※参考:スノビズム(snobbism)は俗物根性と訳される。 多くの場合「知識・教養をひけらかす見栄張りの気取り屋」「上位の者に取り入り、下の者を見下す嫌味な人物」「紳士気取りの俗物」といった意味で使われる。(黒崎記) 安井の眼と、これにこたえる深井の年輪。 その激突と均衡の上にこそ、豊かで、深く、さわやかな人間像が温かく形成されたのであろうとおもうが、腕を組み、室内の一点を凝視する深井の姿に、向学心に燃えていた青少年期の原型が感じられてならない。 深井は、上野国高崎において、百五十石取だった旧藩士の第五男として明治四年(一八七一年)に生れている。 父は、前代の遺臣として固く自ら持し、まつたく世間から退隠してくらした。寡言沈重、学問および立志の方向について希望をしめすことはほとんどなく、ただ体格の弱小を心配して護身のために少し武芸をならえ、と注意した。情操、行状などについて訓戒をあたえることは少なかった。ただ貧乏生活がせがれの心境に悪影響をおよぼすことを憂慮し、武士らしい気節を伝えるため、身をもって模範を示した。 高崎は連隊所在地で、そこに所属する将校の子供たちゃ、別の階級のように優遇され、「坊ちゃん」と呼ばれていた。 深井も別に深い理由もなく、周囲の風習にしたがっていると、父からきびしくとがめられた。 「坊ちゃんというのは、主筋に対してのみ使うべきことばである。我家貧なりといえども、卑屈の心になってはいけない」 と父は訓戒したのである。「これは私が六、七歳の頃のことで、その深き印象は一生を通じて種々の場合に私の意気を動かした」と語っている(『回顧七十年』)。 上級学校に進学できない深井に、そのチャンスをあたえたのは新島襄である。新島は、高崎の隣の安中出身で、元治元年(一八六四年)国禁を犯してアメリカにわたり、アムハースト大学のアンドヴィァ―神学校で学び、明治七年(一八七四年)帰国し、翌年京都に同志社を創立した。 その新島が群馬県に帰省したとき、奨学金を支給して同志社に入学させるべきものを物色し、深井がその選にあたったのである。 「同志社教育は広汎にして深厚なる影響を私に与えた。最も重しとすべきは、新島先生の感化による人生観の生成である」 と深井は語っている。また、「当時の同志社教育は、教師と生徒の気分に就いていえば、単なる授業ではなく、心と心との接触による切磋琢磨であった」 とものべている。 深井は、毎月奨学金を新島から手わたされるので、他の学生よりも多く接触した。彼はこれを幸いに、鼓吹激励をうけたいと期待した。が新島は、かねて評判のように熱烈の態度を示さなかった。 「温情は感受したが、談話は概して淡々たるものであった」 一生は長いから急がずにやれとか、健康をそこねないように注意しろ、というような話が多かった。庭の果物を、枝つきのまま手折ってくれたり、休暇の旅費をあたえたりしたこともある。 賄食(まかないしょく)に甲乙の区別ができたとき、深井は乙を選び、その月は先生からいただく学費をそれだけ減らしてもらいたいと申出る、それはまちがっている、健康には栄養が大切だと注意された。 「先生は特に私を訓戒するごとき態度をもってせず、むしろ自己修養の体験を語るように人生の心構えを説き示された」 深井はその印象を三つに要約している。 第一は、自己の信念に立脚しなけばならぬ、付和雷同やゴマかしてはいけないということ。 第二は、単に自己生活のために働くのではいけなく。世の中のためになるように心がけねばならぬ。世のためになるというのは、必ずしも大事業をなすのみに限らない。分に応じてそれぞれの途(みち)がある、といった。 第三は、何か仕事しなければならなければいけない。その趣旨は、仕事の種類をとわず、世の中との接触を必要とし、独善高踏をいましめることにあったらしい。 深井は、以上の三つをしばしばきかされた。それも訓戒ではなく、その胸のうちを吐露するようにきこえたので、深井はいっそう深く感動した。 「神を父とし、人間を同胞とする教理の応用として、私の実践的人生観の基礎ができたのである」 安井の「深井英五氏像」には、この人間的原型が、清潔で、明澄な強さとして、よくとらえられているようにおもう。 (昭和五十三年六月) 小島直記著『出世を急がぬ男たち』(新潮文庫)P.263~267より 2019.08.04 |
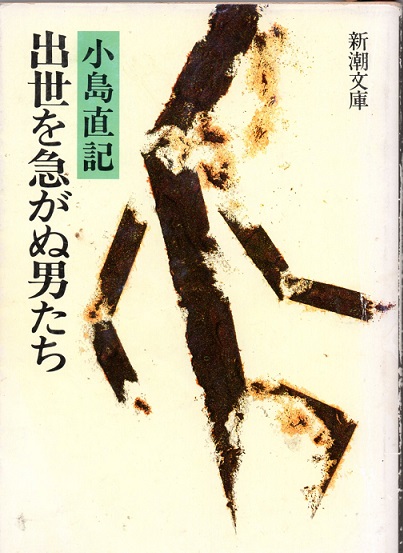
新鮮な高橋是清伝〚波瀾万丈〛 昭和五十三年秋から「東京新聞」(中日・北陸中日、北海道)に長野広生氏の『波乱万丈―高橋是清 その時代』の連載がはじまり、三六〇回で完結したあと、このほど単行本として出版された。その上・下二冊本を読み返しながら、改めて高橋是清のことを考えている。 周知のように、彼には〚高橋是清自伝〛がある。いわゆる自叙伝も数多いいが、その中からベスト・テンを選ぶとなると、福沢諭吉の『福翁自伝』や川上肇の〚自叙伝〛などとならんで、この高橋自伝が入るにちがいないと私は信じ、ひとにもそう語ってきた。ところが何分にも昭和十一年(千倉書房刊)の本なので、簡単に手に入れて読み、確認してもらうわけにゆかない。残念におもっていたところ、昭和五十一年に<中公文庫>として再刊されたので、恐らく多くの方がこの本のおもしろさを味わわれたにちがいないとおもう。 高橋自伝はそのように、おもしろさの点では太鼓判がおせるが、ただ一つ根本的なところに問題があった。それはこれが、明治三十八年暮まででおわっていることである。このとき高橋は五十二歳。昭和十一年二・二六事件の凶弾によって八十三年の生涯をおわるまで、なお三十一年におよぶ後半生がブランクとなっているのである。 しかもこの後半生こそ、七回におよぶ大蔵大臣就任と、第四代政友会総裁時代であって、政治家、財政家として歴史に残る仕事をした時期であった。つまり、人間の生涯をのべる自伝としては、本命といわねばならない。その本命のない伝記にすぎないともいえるのである。 その後、全生涯をのべた伝記が出なかったわけではない。たとえば昭和三十三年には、時事通信社から『三代宰相列伝』全十五巻が出て、その一冊として今村武雄著『高橋是清』も書かれている。 この今村本は、まことによくできた高橋伝である。ただ、このシリーズは、新書版で二四〇ページ前後という制約を課せられていた。いくつもの事業が割愛され、また記述も簡略化されざるを得ない条件下に、よくもこれまでまとめたと感嘆させられるものが今村本にはある。しかしそれだけに、紙数の制限なく、自由に書かせたらどんなに立派な高橋伝ができたであろうか、と嘆息させられるのだ。 その意味において、長野広生著『波乱万丈』は、B6版上下六五六ページ、今村本よりも大きな本であることが、まず無条件に高橋伝としてのメリットを与えている。しかしそれも相対的なものにすぎない。長野本もまた紙数が足りないのである。 大ざっぱにその理由をいえば、全部で六五六ページのうち、〚高橋自伝〛に相応する個所が上巻全体と、下巻二一五ページに書かれている。つまり、全体の八二・一パーセントが五十二までに費され、本命の部分が一七・五パーセントの分量しかないわけである。 この点、今村本は全二四一ページのうち、高橋自伝の分は七二ページ、全体の二九・六パーセントを使い、本命の部分に七割をあてており、構成の面からだけいえば、この方がよいといえるだろう。 ただ、あえて推測をのべれば、長野本は、当初から「本命の部分はわずかでよい」という考えのもとに書き進められたものではない気がする。新聞の連載であるから、大体の回数はあらかじめ決められいたであろうが、連載がはじまってしばらく読むうちに、これは相当の回数をあたえられているな、とおもわせるものがあった。叙述の仕方が丁寧で、筆者の眼がよくディテールまで行きとどいていた。したがって物語のテンポは大河の流れをおもわせるゆるやかさであり、腰の落ちついた立派な仕事ぶりだと感心させるものがあった。波瀾万丈の八十三年をこの調子でたどるには、たとえば司馬遼太郎〚胡蝶の夢〛(全五巻)の紙数であるいはふ足するかもしれないのである。 それを三六〇回でおわるのは、明らかに無理であり、惜しいことであった。一般的に「三六〇回」というのが新聞連載としては「適当な回数」ということかもしれない。しかし新聞社の幹部の中に、この連載を真剣に読み、その内容価値を理解される方がおられたならば、これはもっと多くの回数があたえられるべきであった。そうすれば、高橋是清伝の決定版ともいうべき見事な成果があげられたはずである。 外債募集のとき、のちの日銀総裁深井英五が随行した。深井は、文章の起草、代理応接、暗号電信などから微細の事務にいたるまで手当たり次第にとりさばいた。徹夜にちかいこともしばしばで、食卓で居眠りをするほどに疲れたこともあった。懇意になった英国人たちは、深井を「過労望郷の可憐児」とよんで同情してくれた。 深井は、ときどき自分の意見も主張した。ただ、高橋という人は反対意見を猛烈に撃退する人だから注意せよ、と出発前に注意されていたとおり、深井の異論は即座に反撃をうけたが、時をあらためて別の角度から進言すれば、前言を忘れたかのように冷静にきき、採るべきものは採った。それまで高橋は、人に紹介するのに深井をセクレタリーとよんでいたが、やがてアシスタントとよぶようになった。辞令の文言が変ったのでなく、高橋の深井評価が変ったのである。 ところが〚波瀾万丈〛では、深井随行の事実は無論記述してあるが、上の逸話はのせられていない。 ことわるまでもあるまいが、この逸話は、深井の手柄話ではあっても、じつは、高橋その人の、部下に対する態度を示すいい話である。〚波瀾万丈〛には、そのプロローグに、高橋が大蔵省の部下の名前を、ほとんどおぼえずに終わったのではないか、という話が出てくる。「この失念をただの性癖といっても、それだけでは片のつかない、底の深いものがあるように思える。失念の彼方に、いったいなにがあったのだろうか」と著者は書いている。このこととも関連が深く、要するに高橋という人間をよりよく示すための大事なといころで、オミットするには惜しいのである。 著者は無論、この逸話を熟知いたはずなのに、それを文字どおり「割愛」しなければならなかった。その理由は他でもなく、回数の制限である。指定回数の半ばをすぎてもまだ本命の部分に達しない焦慮が、そうさせたのであろう。私はそう信じ、同情にたえない。 だが一方で著者は、高橋自筆の未公開文書を一族に見せてもらっている。この点「日記も提出するから」ということで『松永安ヱ衛門伝』を引きうけたのに、ついに見せてもらえなかった私よりは、非常にめぐまれていたというべきで、うらやましくて仕方がない。(昭和五十五年三月) ★児島直記〚出世を急がぬ男たち〛(新潮文庫)昭和五十九年四月二十五日発行 P.46~50 より
高橋是清:生年:安政1.(1854.9.9) ~没年:昭和11.2.26(1936) |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.219~223 田中 義一 三申の影響で政界へ 結識とは「近付きになる、交際する」ことを意味するらしい。したがって、一人の人間にとって結識の相手は数多くあるともいえそうだが、たとえば小泉三申の場合、このことばを使っているのは、筆者の見たかぎりでは、二回きりのようである。一つは、幸徳(秋水)とは年齢感情での他共通点が多いものだから、自然親密になったのだろうが、これぞ私が江湖に結識した最初の一人である>(『暖窓漫談』、三申全集第四巻)で、もう一つは、「(明治四十五年春)私は初めて代議士となったが、その三、五年前から、軍人方面に結識する必要を感じ、海軍の八代(六郎)、秋山(真之)、陸軍の田中(義一)、宇都宮(太郎)、この人々に着目して交わりを通じ、毎月一回、赤坂の三河屋で宴集……」(『懐往時談』、全集に入らず)である。 小泉三申は、明治二十七年二十三歳のとき、自由党機関誌『自由新聞』の記者となった。社長の板垣退助は毎日出勤してきて社員を集めて『孫子』の講釈をする。ところが古参記者たちはききあきていて、よりつかない。結局、新米の三申と、もう一人の青年記者がきき役にまわった。 その色が黒く、背が低く、風采のあがらない男が幸徳伝次郎、かつては玄関番をしたことのある中江兆民から「秋水」という号をもらっていた。秋水は三申よりも一歳年長で話が合う。ともに文学青年で、つれ立って牛肉屋で飲み、烏丸の地獄屋で女遊びをした。月給はともに七円で、下宿代が六円、二人は収支のバランスをとるため、社の宿直を引きうけ、一晩一人前十六銭をかせぎ、また連載小説を引きうけて一回分二十五銭をかせいだ。 二人の『自由新聞』時代は一年ほどしかつづかなかったが、職場を異にしても親交はつづいた。やがて三申は『九州新聞』主筆として熊本に去り、秋水は『万朝報』につとめているうちに二人の思想的断層は深くなった。秋水が左傾化したのである。 明治三十六年、三十二歳の三申が『九州新聞』をやめて上京し、財界進出を意図して米相場などに手を出したとき、秋水は『万朝報』をやめて平民社を創立した。『週刊平民新聞』第一号には賛助執筆者の一人として三申のながあり、三十七年一月十日号の同紙に「病床噡語」(全集第四巻)を寄稿して「平民新聞を手にして覚えず落涙の滂沱たるを禁じ得なかった」と書いているが、同志的関係にはいたらず、むしろ背を向けて相反する立場に人生の座標をおいた。軍人と知り合う必要を感じたのもその路線における必然といえるかもしれない。上述した数めいのうち、もっとも深く結ばれたのが田中義一である。 明治四十五年の「三、五年前」とはばく然としているが、五年前の四十年とすれば、田中は四十四歳、五月に歩兵第三連隊長、十一月に歩兵大佐となった年である。三年前の四十二年にすれば、一月に陸軍省軍事課長となった年で、その翌年に、大逆事件で秋水が逮捕され、田中は思想の悪化に対する方策として在郷軍人の創立をなしとげ、陸軍少将、歩兵第二旅団長となったのである。 三申の「結識」は、この左と右の両巨頭に対するもので、しかもそれは表面上、矛盾なくつづけられた。「今春君の忠告に従って一切の世事を抛ち著述の生活に入ろうと決心したときは、今思えば既におそかった……」という秋水の三申宛書簡は、この時期における両者の関係を物語る。三申は秋水に『通俗日本戦国史』の執筆をすすめ、この仕事によって「主義者」から立ち直らせようとした。秋水もこの気持ちをうけて湯河原の宿にこもり、その仕事を進めた。ただ、どういう理由からか、小泉は約束の金をわたさず、秋水は中途で中止して『キリスト抹殺論』を書いた。そして湯河原駅でつかまり、翌年一月死刑になるのである。秋水は刑執行の三日前にも三申に手紙を書き、三申は『キリスト抹殺論』の出版許可の意向を警視総監からきいて秋水に知らせてやり、また、墓碑銘を書いてやり、遺品遺稿は彼のもとにとどけられた。 一方、三申は田中を政治と結びつけることに努力した。「四谷の拙宅で橋渡しをして、二人(注、原敬と田中)を逢わせたのが、やがて田中が原内閣の陸軍大臣となり、後年政友会の総裁となる機縁ともなった」』(『懐往時談』)あるひは「度々赤坂辺に席を設け、党内の要人と田中との接近を図った」(同)と三申も語っている。決定的な事件は高橋是清の後任として、田中を政友会総裁に引っぱりだしたことである。田中の正伝は、「一体誰が彼を引きずりだしたか? 政界に引入れた張本人は三浦観樹、久原房之助(くはら ふさのすけ)であり、さらにこれを政友会に引っぱり高橋総裁の後任にもってくる道筋をつけたのは横田千之助といわれ、小泉策太郎といわれる。ルートは一つではなかったろう」(『田中義一伝記』下巻)というが、横田は小泉の親友であり、田中引き出しの策源地が三申にあったことはまちがいない。これが大正十四年五月のことで、田中は六十三歳、三申は五十二歳であった。そして二年目に、田中は内閣総理大臣になり、外相を兼任する。三申の喜びも察しられるが、意外にもその翌年、両者は離反し、三申は政友会を去ったのである。 原因は久原房之助の入閣問題にあった。「しかるに同氏(注、久原)登用に関し閣内の一部及び与党政友会内に異論が起った……党内に閣僚候補多数存在するにもかかわらず政界の一年生、商売人上りの久原を登用するのは情実に流れすぎるというのであって……反対論者は小泉策太郎」、「小泉の機知、文章は当時政界第一であったろが、首相は久原氏の人物をより高く評価した」というのが『田中義一伝記』の記述である。はたしてそうであったか。かつて鮎川義介は『日本経済新聞』紙上で、首相になった田中が<いずれは久原を総理にするつもりだから」と語り、「まず外相に擬したが……逓相の椅子があてがわれてあって、外相は田中が兼摂した」「その後、田中の動きは……どうやら外相の椅子のすわり心地が気にいったらしい……それに気づかぬ久原ではない、ある日、久原は私に同行を求めて田中邸を訪ねた。三人鼎座して話しているうち、久原は……田中の食言を責め……言いわけをきこうとせず椅子を振り上げて肉薄した」(『私の履歴書』第二四巻)と回想している。 一国の宰相に、椅子をふりあげて肉薄するという狂態の原因が、田中の「食言」にあるのか、あるいは多年のスポンサーだった事実をふまえての脅迫であるのか、その真相はふ明だとしてもこういう関係の中に純粋の「人物評価」だけをもちこむのは無理である。一方、大逆事件はデッチ上げだといわれる、ということは、三申の結識と離反の中に、彼自身の人物のみならず、それぞれの時期におけるわが国の権力を解くてがかりがある、ということであろう。 2019.08.02 |
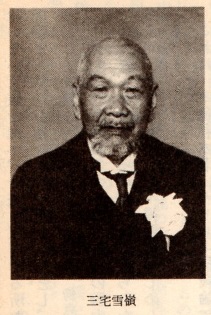
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.224~228 より 三宅 雪嶺 スゴ味のきいた筆誅 『日本』時代の雪嶺三宅雄二郎については、長谷川 如是閑や古島 一雄が語っている。如是閑の入社は、正岡子規の没した翌三十六年というから、このときの雪嶺は四十四歳、原稿は家で毛筆で書き、それを自分でもってきた。いつも角帯の着ながし、羽織をきないことが多く、頬ヒゲをのばし、髪は七分刈。急ぎ足で入ってきて、決して椅子につかず、つっ立って雑誌を読みながらゲラ刷を待っている。彼は校正も自分でやった。ときどきドモった口で、一言二言いって皆を笑わせた。 彼の「不ふ得要領」は評判であった。何をきいても、ことさらドモったように、ウウウというだけで、決してはっきり可否をいわないからである。それをみなは彼の文章の口調をまねて、「何何するも可、せざるも可」といっていた(如是閑『ある心の自叙伝』)。 半面、原稿については厳格をきわめ、一字一句精苦の結晶である。もともと遅筆の上に、想をこらし、句をねるのでときどき締切りに間にあわない。あるとき古島一雄は、他の原稿で間にあわせ、雪嶺のものはデスクにしまいこんでいた。雪嶺は、いくら待ってもゲラ刷が出ないので、しょく字室に催促にいき、そんな原稿はきていないといわれ、古島に原稿の返却をもとめた。 「明日にまわすから、このままにしてあずかっておく」 「いや、明日もってくるからぜひ返してくれ」 その翌日返された原稿には、さらに添削の跡があった。「この苦心惨憺を経ればこそ、あのめい文章ができるのだ。いわゆるめい工の苦心だ」と古島は感嘆している。 遺憾ながら、筆者にはその「名文章」がむずかしすぎる。雪嶺三十四歳の作『王陽明』に接したときは、鼻血が出るようなおもいをした。とくに縦横に引用された漢文には長大息した。そういうわけで、あまり多くの文章は読んでいないけれども、その一部分にふれた印象だけでも「スゴい」というおもいは誇張でなくて実感である。 かつて、板垣 退助洋行問題というのがあった。自由党結成(明治十五年)直後、出所上明(じつは三井)の旅費をもらって外遊し、党内の馬場辰猪などから猛反撃をうけた。とくにその動機について、たとえば阿部 真之助が戦後において<彼が党の分裂を代価に払ってまで、洋行を固執しなければならないわけは、いまでもわからない>(『近代政治家評伝』)と書いた事件である。 ところが雪嶺は、「各地方における自由党員の鎮圧はいよいよ厳を加へ、寸毫も仮借する所なし。……板垣は政治運動を継続するの困難を感ぜる際後藤より洋行を勧められ、渡りに船とし、旅費の出所の如き、深く問はず……文明の政治を探討せんことを希ふ」(『同時代史』第二巻、傍点引用者)と書いている。「渡りに船と」は、比喩というよりはむしろ心理描写である。板垣の胸中を見透して、そのおく底のものをグイとつかみだいしたような感じがする。その切れ味はこちらをドキとさせる。新聞社内のつきあいにおいて、「するも可、せざるも可」の不得要領をしめしていたのは、まさに対照的、対極的なスゴ味が出ている。 これは、幸徳 秋水著『キリスト抹殺論』に書いてやった序文には、もっとはっきり出ている。秋水は四十三年春、湯河原でこれを書き、六月逮捕、十二月公判終了、原稿完成、翌年一月死刑を執行された。「秋水に死刑の宣告の下つた翌日……序を執筆、内務省より掲載を禁ぜられる」(『同時代史』第六巻、三宅雪嶺年譜)。 大逆事件の首魁の本に序文を書いてやる、ということ自体が、すでに相当の覚悟を要する。雪嶺は五十二歳、思想的には秋水と反対で、同志的義務感に殉ずる必要もなかった。それをあえてした。そして、たとえばその一節に、「秋水は既に国家に在りてはふ忠、剰へ大不忠。家族に在りてふ孝、剰へ大不孝。不忠不孝のなに於て死を求めて死に就く。悪とせんか、愚とせんか、誠に適当なる形容詞なきに苦しむも、窮鼠と社鼠と孰か択ぶべしとする」(傍点引用者)という表現は、ズバリと「何か」を斬り捨てている。その「なにか」とは「窮鼠」「社鼠」の用語から、推測もむずかしくない。とくに「社鼠」とは、「やしろに巣くうねずみ」の意味から転じて、「主君の側にいる小人のたとえ」である。「窮鼠」が秋水ならば、「社鼠」は体制側のエリートたち、ぬくぬくと肥えふとる元勲や閣僚たちを諷するものである。そういう連中と秋水を対比した場合、人間の生き方としてどちらが「悪」か「愚」かわからない、といっているのである。まことに痛烈無比、腐敗した特権階級へのいのちがけの筆誅であったといえる。秋水は「先生の慈悲実に骨身にしみて嬉しく何となく暗涙が催された。僕はこの引導により十分の歓喜満足をもって成仏する」と高嶋米峰あての手紙に書いたのである。 大正十二年雪嶺六十四歳のとき、雑誌『我観』創刊(第一号は十月十五日)、十五年一月から同誌上に「同時代観」第一篇「万延元年」をのせ、以後二十年間つづけて「昭和二十年」におよんだ(のち『同時代史』と改めて六巻刊行)。この間に長男の上慮の事故死(六十九歳のとき)、長女(中野 正剛妻)の病死(七十五歳のとき)、妻竜子(花圃)の病死(八十四歳のとき)、女婿中野の自刃(同)のほか、空襲、病気もおそったが、その筆をうばうことはできなかった。そしてライフワークとよぶにふさわしいこの仕事を完成してもなお闘志満々、新たに長篇をはじめようとした。「構想は頭の中に去来して居り、両手で頬を押さえて日当たりの良い所にすわって想を練るのが普通であった」よ孫中野泰雄は書いている。 二十一年二十五日、約二時間、床の上に横臥したまま「文化創造への参照」の冒頭部分を口述し、「十四枚、(注、二百字)もうそんなになったのかと、うれしそうであった。しかし翌日二時ごろから容態一変、深い眠りに入ったままついに覚めなかった。文字どおり眠るような大往生」であった。如是閑は<このように雪嶺の生涯は郷里(注、金沢)の白山を象徴したと思われる雪嶺のなにふさわしい孤高の生涯であったが、彼の周囲からは古島一雄、内藤 湖南、田岡 嶺雲、国府 犀東らの人材が輩出した。かくいう筆者もその一人である。孤高ではあったが、数多い同志、友人後進を、そして愛読者を持った生涯はまた幸福であったといえないこともなかろう>と書いている。「いえないこともなかろう」どころか、これこそ文人の本懐ではないか、と筆者は考える。
谷沢永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.160~161 兵は拙速を尚ぶと云うが、兵のみでなはない。多くの事は拙速を貴んで居る。巧みでも遅くては必要がなくなって仕舞う。熟考の上でとか、篤と考えてとか云う事はせぬ方に慣れを作るが宜い 三宅 雪嶺『世の中』
参考:「兵は拙速なるを聞くも、未だ巧久なる賭ざるなり。」(読み下し)。 戦争には拙速――まずくともすばやくやる――というのはあるが、巧久――うまく長びく――という例はまだ無い。(口語訳) 『孫 子』(岩波文庫)金谷 治訳注 1984年6月20日 第24刷発行 P.28
「熟考と速断」と題するこの文章は、「考え過ごしては事は出来ぬ」との小見出しを掲げて、次の如く悠然と雪嶺調に説き始める。 ――「無鉄砲とか、盲滅法とか云う事は、皆な悪い事になって居る。後悔先に立たぬとも謂う。或は此類の事を板鼻主義となづける。板塀に鼻が閊えるまで先が分からぬのを意味するのである。向う見ずは実に危険至極である。が、危険として考え過ぎると、事が出来なくなる。熟考の上でとか、篤と考えてとか云う事を言うが、其割合に事が能く行くとも限らぬ」。つまり「熟考」は、要するにわが国で特に頻用される逃口上で、"当り障りなく"を第一に念じての拒絶である。個人間の場合だったら有無相通じて結構でもあろうが、この牢固たる習慣が公機関に持ち込まれると支障を来たす。 ――「役所の事務の運ばぬのは様々の事情もあるが、是等の事が与って居らぬとはせぬ。漢字にせぬと云うのではあるが、成る可く判断を避けようと云うに過ぎぬ」。出来れば難題を自分以外の者に押しつけ、判断の責任を慎重に免れようと企る。仮にある判断が正しくて効果を挙げても、役所の機構ではどのようにも顕彰されず、失敗のみが大きく取り上げられるのだから、誰もが石橋を叩いてそれども渡らぬ。 いずれにせよ「判断を延ばすのは悪い習慣である。速かに判断を下すと重味がないような懸念をする」。そのような「慎重の態度」よりも、事態を打破するための巧みな方法が別に控えている。 ――「無鉄砲だの盲滅法だのと云うのは悪い事になって居るが、時に依るとそれで勝つ事もある。あれの無鉄砲には適わぬ盲蛇に怖じぬで致し方がないとか言って、開けて通すような場合もある」。人間の長い一生にうちには、何回か「無鉄砲」で事を裁決せねばならず、その勘が働かなくては進歩も成功も望めぬであろう。
谷沢 永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.130~131 人は善くも言われ、悪くも言われるのがよい 三宅 雪嶺『世の中』 三宅 雪嶺の話術は淡々として平易であるが、実は人を鼓舞するところもっとも深い。読者の気宇を高めるというはなはだ難しい効能においては、近代のあらゆる著作家を見渡したところ、三宅雪嶺と幸田露伴をもって双璧と見做してよいであろう。 雪嶺は世の『毀誉褒貶』に思いを致し、「毀誉褒貶の巷に立ち、善くも言われ、悪くも言われるのは性格を鍛錬するに与かって居る」と断言する。 そして「評判は何でも宜い、俺は俺のなす所さえ為せば宜いと云うのは、其(その)評判が利害に関係せぬ限りに於てである。一旦、利害に関係すれば其恐るる事、虎よりも甚だしい」という調子で、雪嶺の真骨頂は温和の辛辣にある。 雪嶺の一大特色は人間の生涯を、有為転変の連続として見る視野の大きさである。――「人は善くも言われ、悪くも言われるのがよい。善くも言わるる事に慣れたものは少しばかり悪く言われて腹立て愚を現す事がある。悪く言われ続いた者は僻んで善い事を為なくなる」。 しかし「人の一生は種々の波瀾がある、己一身は同一種の人物であるが、世間との関係が様々に変ずる」。この<世間との関係>こそが褒貶問題の起源なのだ。 結局のところ人間は誰でも、「時として善く言われ時として悪く言われる」ものなので、悪く言われるのをわれるのを完全に防ぐ方法は見出し難い。 だが、「人の噂も七十五日、善く言われたとて当てにならず、悪く言われたとて当てにならぬ。が、煙の起るのはただでは起きぬ、当てにならぬ所に何事かある」。それは自分が無意識のうちに、煽いだ火種に基くに違いない。 恐らく人間は初め悪く言われて、当初は不可解であった理由を探り当てようと、努力するうちに成長するのであろう。同時にまたいかなる悪口にも退かず、毅然として動かぬ度胸も必要である。「評判ばかり心配するのも変なものである」と見る雪嶺は、「錬磨に錬磨する間に自然に兼合(かねあい)が出来る」のだと説く。に
プロフィル:(1860年~1945)哲学者・評論家。歌人三宅 花圃(みやけ かほ)の夫。石川県生。なは雄二郎。東大卒。志賀重昂(しが しげたか)らと政教社を結成し、雑誌「日本人」を創刊。国粋主義に基づく社会批判を行なう一方、哲学的な著述でもなをあらわし、「中央公論」等諸誌に多彩な論説を発表した。のち政教社を離れ、中野 正剛と「我観」を創刊した。文化勲章受章。回想録『同時代史』等著書多数。
※参考図書:小島 直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.182~187 第二十七話 いのちがけの筆誅 2010.03.02 |
|
小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.229~233 福沢 桃介 体験からの処世術を説く偽悪派 三宅雪嶺の書いた序文で異色とおもわれるのが、福沢桃介著『桃介式』に書いたものであった。 この本は、「予が処世観」、「羨むなかれ世のいわゆる成功者」、「金儲けは株にあり」、「憎まれていやがられて世を渡れ」、「どうすれば金持ちになれるか」、「出世の秘訣」の六篇からなっている。 第一篇は明治三十九年、桃介は三十九歳で、北海道炭礦鉄道会社の社員であった。第二篇は四十歳、一月に日清紡績を設立して専務取締役となり、三月に持株を処分、「いよいよ実業界に入る」(『福沢桃介翁伝』年譜)中間の二月のもの。第三篇は同年六月、第四篇は同年七月のもの。 第五篇は四十一歳、後輩松永安左エ門にかつがれて福博電気軌道会社発起人となり、また豊橋電気の取締役、高松電気軌道の発起人となった年のもの。第六篇は四十四歳、すでにな古屋電燈大株主の地位を拠点に中京財界に進出し、また日本瓦斯を創立して社長となったあと、四国水力電気社長、浜田電気社長、野田電気社長、唐津軌道取締役となった年のもの。翌年五月には千葉県から衆議院議院選挙に立候補して当選、政友会公認となるふうで、公私ともいよいよアブラののってきた時期の所産であり、考え方の反映であった。 ただその内容は、自ら桃介式と自負するほど天下独歩の創見ではないようにおもわれる。むしろそのユニークな味は、あくまでも自分の体験をふまえ、歯に衣をきせぬやり方でズバズバいうという表現法にあるようである。たとえば第一篇には「人に可愛がられる方法を教えてあげます」といって、「人に面と向っていろいろなことはいわなくても、カゲにおってあの人は善い人だ、まことに利口な人だ、というように、つねにほめていると、いつかその人にわかる。以心伝心、自然とそれが先方の人に通じて喜ばれる。ひっきょうするに、人をそしるということは、自分の無能を表明するものだから、よくよく慎まなければならぬ」とか、「金というものは、もってみるとそれほど楽しいものではないのです。ただ金をこしらえてみたい、金をこしらえてこういう家に住んでみたいとか、うまいものを食ってみたいとかいう、その道中が楽しみなのである」、「いまだ衣食の足らざる会社の社員などは、相互に送別会を催すとかなんとか、そんな交際や礼儀にお金を出すには及ばない……炭礦会社の寄生虫として桃介は、一銭一厘たりともそういうお金は使わない」と語っている。自ら「寄生虫」という一種の偽悪趣味がその味のようでもある。 第二篇では、世の中の金持ちは「偶然今日の結果を得たくせに、かしこぶってホラをふくので、先見の明とは真赤のウソだ」、「人を見たらたいがい泥棒だと思えばまちがいない」といっている。第三篇では、「三井、三菱が儲けるのに諸君が儲けられぬというはずはない。ただ彼は一万株を売り、諸君は一株を売るというだけの差である」、「若い人はどうしても金をためなければならぬ。人間は独立して生計ができてのちはじめて大胆に自己の意見をのべられる。どうかすれば免職され、翌日から飯が食えぬといううような、パン問題を争うている中は、おもいきって意見を述べられなければ、よい考えも出ぬ」といっている。 第四篇では、「憎まれていやがられて世を渡れという……これ世渡りの一秘訣」、「歴史を見るに、古来貨殖に成功した者は、多くは世の中をいやがられて渡りたる者にして、可愛がられる人は、下について働く側の人にして、頭立ちたる人になれるの例はあまり見受けざる処なり」、「妻子眷属、朋友知己の前に傲然としていばっていても、助けられたる人の前にピョコピョコ頭を下げざるにおいては、決して男子の快事にあらざるなり」、「天は人の助けざる者を助く」という。 第五篇では「私はケチが自慢」、「世間の人のごとく森村(市左衛門)さんが貿易に成功し外国の金を日本にもってきた点において尊敬しているのではない。あの人は片意地の強い人である。私の取る所はここだ」という。第六篇には、サラリーマンの処世法が書いてある。要約すると「味」がぬけるが、紙数の関係で要点を列挙すれば、(一)入社先の社風に従え。善かろうが悪かろうが、ただ盲従せよ。(二)上役の性質を知り、その人の気に入るように仕事をしていけ。上役は、敬い奉れば必ず喜ぶ。(三)月給で暮らせ。(四)表を絹にし、裏を木綿にする態度で生きよ。(五)勉強を見せかけよ。メクラ千人の世の中では、自分が正しければ、その正しいことを人に知らせる必要がある。(六)上役より先に帰るな。(七)利口らしく見せかけるともに正直らしく見せかけることも必要。(八)病気と失職にそなえ、貯蓄せよ。「上役は、世の中の呼吸をのみこんでいるから、なるべくタダのお世辞でゴマ化し、実質をあたえずして人を使おうとする。前途に希望をもたせておく。働くのはわるくないが、ただ正直に一生懸命に働けば、それで必ず立身出世すると思うと大まちがいである」という。 引用してゆけば、キリもないが要するにこういうふうで、その桃介的姿勢に興味をもったのか、雪嶺の序文も、「面白い」、「愉快である」ということばを使っている。雪嶺は「偽善めかぬ所がよい」と、そこに男らしさを見た。 けれども、ただベタぼめしないところが「雪嶺式」である。この本の出版元は実業之世界社で、野依秀市にたのまれてお義理で書いたぽうではあっても、そこに一本のスジを通し、いうべきことはいう、というところがいい。「桃介君をもって快男子とするは当らぬかもしれぬ。さほど愉快な男でもなかろう、が、言う所行う所すこぶる愉快」という表現にもそれがうかがえる。 ポイントは養子問題である。桃介は川越の提灯屋岩崎家の次男坊、在学中諭吉に見込まれ、二十歳で入籍、アメリカ留学をおえて二十二歳で諭吉次女ふさと結婚した。しかし福沢家には四人の息子がおり、「養子は諭吉相続の養子にあらず、諭吉の次女お房へ配偶して別居すること>と申しわたされていた。そういう限定をしてまで養子として何ほどかの便利を得来たったったであろうか、もし今後大いに手腕をのばし、一個の桃介となって社会に存在するようになれば、養子とならんだった方が、よかったように思われるかもしれぬ。尋常人では翁の眼鏡にかから、君が養子に選ばれのは人物を見ぬかれたのであって、祝すべきであるが、独立独行という点よりせば余計の事……福沢の家に養子になったとて何程の事がある」。 桃介が愛人川上貞奴との仲を公然化したのはこの前後である。「福沢」コムプレックスのせいかどうかは、よくわからない。 2019.08.07 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.239~243
八代 六郎 「真の序」知る老提督
小泉三申は「軍人方面に結識する必要を感じ、海軍の八代(六郎)、秋山(真之)、陸軍の田中(義一)、宇都宮(太郎)、この人々に着目して交わりを通じ」たが、この中もっとも親しくなったのは田中義一であった。第一旅団長時代の少将田中を政友会総裁原敬に結びつけ、やがて原内閣の陸相、政友会総裁、田中内閣成立の手引き役をつとめるのは三申である。しかし、どういう理由で田中と特に親密になり、他の人びととはそれほどでなかったかは、三申も語っておらず、推測はむずかしい。 ただ筆者がひそかに思うことは、たとえば田中の過去に、三申自身のものと共通する体験があったことである。田中は十三歳のとき小学校の<授業生>となり、十九歳で他家の玄関番をしながら『資治通鑑』三百五十数巻を読破し、これを抄写した唐紙は六十センチ以上に達したという。三申も授業生をし、教養の基礎、その身につけ方も田中に似ていた。「策士」三申が自ら軍人成長株に近づくのである以上、そこに功利的打算がなかったとはいえないであろうが、しかもなお彼等を結びつけたものは、相似た過去をもつ同志としてのなつかしさ、心のバイブレーションというものではなかったか。 ところで、三申とは浅かった八代 六郎にも「結識」に関する逸話が残っている。大正十二年――といえば、八代は六十三歳、すでに大隈内閣の海軍大臣、第二艦隊司令長官、佐世保市鎮守府司令長官をへて男爵を授けられ、七年海軍大将に昇進、軍事参議官として重きをなしていたときである。ある一夜、青年学者安岡正篤と自宅において酒をくみ交すうち、談たまたま陽明学の問題に及んで、意見が対立した。安岡正篤はこのとき二十六歳、金鶏園内に東洋思想研究所を設立し、後藤文夫、松本学、湯沢三千雄などエリート官僚の来訪も繁くなり、大川周明、永田秀次郎と拓殖大学東洋思想講座講師に招聘され、青年学徒の尊敬を一身に集めていたときである。すでに前年には『王陽明の研究』も刊行されていた。いかに相手が男爵海軍大将という大物であろうとも、学説、所信をまげるわけにはゆかない。堂々と真正面から、老提督の見解に反駁した。 席には酒が出されていた。両者ともに斗酒なお辞せずという酒豪である。酔うどころか、飲めば飲むほど頭がさえて議論いよいよ白熱、夕方五時ころにはじまって十二時になってもおわらない。そのとき八代夫人が姿を見せ、安岡青年に、 「あなた、もうお帰りください」 といった。すでに二人で五升平げており、夫人は老齢の夫の健康を案じたのである。帰ろうとすると、老提督は、 「逃げるか!」 と叱咜した。無論、逃避退散するのではない。一週間後に再会、その間熟慮反省して、まちがっていた方が弟子入りをし、相手を床の間を背にすわらせて奉ろう、という約束になった。 一週間後、八代大正は紋ぷくに改めて安岡家を訪ね、弟子入りをするといった。 「ご冗談でしょう」 「冗談じゃない」 老提督はあくまでも真剣で、それからは三十七歳も年下の安岡を「先生」と呼び、宴席においてもかならず下座につき、昭和五年に死ぬまで師の礼をとりつづけたのであった。「長幼序あり」というのが東洋道徳の基本である。しかし学問、真理の前には階級、職業、年齢など問題にしないことこそ本当の「序」――人間の生き方、結びつき方である。これが老提督の思想であり行動方式であったと思われるが、この壮快な一挿話は、おのずと昭和初年における将軍たちの思想、行動方式を連想させるのである。 昭和六年秋「十月事件」がおきた。中野雅夫著『橋本中佐の手記』によれば、「決行計画は一夜にして政府機能を撲滅し、之れに代るべき政府者に大命降下を奏請するにあり、之が為に各大臣、政党首領、某某実業家、元老、内相、宮相等を一時に殺戩(さつせん、殺しほろぼす)し、陸軍高級者は監禁乃至殺戩し、之に使用する兵力は歩兵二十三連隊、機関銃六十丁、毒瓦斯、爆弾、飛行機等なり……」という物騒なクーデター計画で、少壮軍人有志の桜会リーダー橋本欣五郎、長勇(ちょう いさむ)ら中堅将校が中心となり、大川周明ら民間人も加わり、在京部隊の青年将校も軍隊をひきいて参加することになっていた。 ところがその計画は世間に知れ、橋本日記も「遂に宮内次官陸軍省に来り此旨を告げ、制止を乞ひたるなり。……十月十六日(十七日?)夜八時頃陸軍省陸相官邸に於て三長官其他軍首脳部集り此事件に就いて会議す」と書いている。「其夜予は将来の兵器の分配場所偵察の為各料理屋を転転とし夜三時頃築地金竜に至る。長、田中あり、突然三時過大木憲兵少佐より後刻下士官を貴官等を逮捕に向はすべく伝ふ。……夜三時ころ憲兵曹長以下数めい来り憲兵隊へ連行を乞ふ」。 ところが、連行はされたものの、決して「犯人」あつかいでなかったことは、たとえば橋本らのシンパであった内田絹子の談話が物語る。「八時ごろ自動車が家の前で停ったので、そら来た、と思ったところ憲兵隊の小使いが長勇さんのめい刺をもってきて、クシとタオルと石けん、それに歯ブラシを三人分持ってこいということである。……(憲兵隊長)官舎前で自動車をおりて門をはいると憲兵が二人ピストルを持って隠れていた。部屋に入ってみると憲兵隊の奥さんとお嬢さんが橋本さんらに給仕をしている。……翌日分散した情報がはいった。数日して金竜亭の女将がきて、橋本さんから芸者を三人つれてこい、と連絡があった。ちょうど松タケをもらっていたので松タケ御飯をたき、芸者をつれて千葉稲毛の海気館にいった。橋本さんは立派な部屋で習字をしていた」(前掲書) そういう優遇だけにとどまらず、彼等首謀者は謹慎させられただけで、処分らしいことは行われなかった。彼等の背景に、社会腐敗、政党の堕落=政治の貧困があったにせよ、天皇の軍隊を私兵化し、首相以下を殺害しようと企てることは、国家の法秩序無視、軍規の紊乱であったにもかかわらず、陸軍首脳部の将官たちは、これほどまでの寛大さ、わけ知りぶりを示したのであった。「問題は事件そのものや処分にあるのではなく、政治的欠陥、腐敗、国民的困窮にあるのだから、この原因をとり除かない限り処分しようがしまいが起るべき事件は起こるものだ」と中野雅夫はいうが、しかしこの無法の容認が、同種事件続発の誘因をなしたことは否定できない。このような法秩序を無視してまでの後進への譲歩、媚態は、八代六郎の親和とは似て非なるもの、「万機公論」の提唱者横井小楠が横死して六十二年目に、「問答無用」のテロリズムを復活させたのであった。老将軍らのわけ知り顔、寛大さ、「理念なき親和」には歴史を後退させる力しかなかったのである。 2019.07.19 |
 長崎に旅されたお方は、「お蝶夫人」の旧邸と称するめい所に案内され、美しい港の眺望を楽しまれたであろう。「マダム・バタフライ」はアメリカの作家ジョン・ルーサ・ロングが明治三十年に書いた小説のヒロインで、これをイタリアの音楽家プッチーニが三十七年にオペラ化したため世界的に有めいとなり、長崎めい所の一つともなったわけであるが、もともと実在の人物ではない。ただ、ロングの姉が「ヒロインのモデルは長崎在住の実在の人物」と語ったことばから、グラバー夫人ツルであろうと、そのあたりの考証は大まかにして、グラバー旧邸イコールお蝶夫人の家ということになったようである。
長崎に旅されたお方は、「お蝶夫人」の旧邸と称するめい所に案内され、美しい港の眺望を楽しまれたであろう。「マダム・バタフライ」はアメリカの作家ジョン・ルーサ・ロングが明治三十年に書いた小説のヒロインで、これをイタリアの音楽家プッチーニが三十七年にオペラ化したため世界的に有めいとなり、長崎めい所の一つともなったわけであるが、もともと実在の人物ではない。ただ、ロングの姉が「ヒロインのモデルは長崎在住の実在の人物」と語ったことばから、グラバー夫人ツルであろうと、そのあたりの考証は大まかにして、グラバー旧邸イコールお蝶夫人の家ということになったようである。
 参考:城山三郎著『雄気堂々』(上):大隈重信との関係について、P.323~「若き神々たち」に書かれている。(黒崎記:2023.03.07)
参考:城山三郎著『雄気堂々』(上):大隈重信との関係について、P.323~「若き神々たち」に書かれている。(黒崎記:2023.03.07)
 菅江については、「天明の初年に二十八で、故郷の三河国を出てしまってから、出羽の角館で七十六歳を以て没するまで、四十八回の正月を雪国の中で、次々に迎えて居た人」(『雪国の春』)という柳田国男の叙述にもっともフィーリングがあるようだ。「どうして斯ういふ寂しくも又骨折な生涯の旅行が始まったか」はわからない。「真澄の目的は、いままで学んできた国学・本草の知識をもって、当時ほとんど知られることのなかった辺境の地、陸奥――北海道をふくめた東北地方――の風物をすべてにわたってたしかめてみたところにあるように思われる(内田武志『菅江真澄というひと』:黒崎確認:『菅江真澄遊覧記』(東洋文庫)P.16)という解説も、二十八歳から七十六歳まで郷里に帰らず、みちのくを歩きつづけた孤独な魂の秘密まではときあかしてくれない。
菅江については、「天明の初年に二十八で、故郷の三河国を出てしまってから、出羽の角館で七十六歳を以て没するまで、四十八回の正月を雪国の中で、次々に迎えて居た人」(『雪国の春』)という柳田国男の叙述にもっともフィーリングがあるようだ。「どうして斯ういふ寂しくも又骨折な生涯の旅行が始まったか」はわからない。「真澄の目的は、いままで学んできた国学・本草の知識をもって、当時ほとんど知られることのなかった辺境の地、陸奥――北海道をふくめた東北地方――の風物をすべてにわたってたしかめてみたところにあるように思われる(内田武志『菅江真澄というひと』:黒崎確認:『菅江真澄遊覧記』(東洋文庫)P.16)という解説も、二十八歳から七十六歳まで郷里に帰らず、みちのくを歩きつづけた孤独な魂の秘密まではときあかしてくれない。
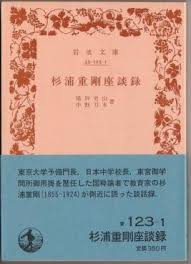 『杉浦重剛座談録』猪狩史山(いがり しざん)中野刀水(なかの とうすい)著(岩波文庫)1986年4月4日 第9刷発行
『杉浦重剛座談録』猪狩史山(いがり しざん)中野刀水(なかの とうすい)著(岩波文庫)1986年4月4日 第9刷発行
 明治四十四年、古島は四十七歳で代議士となり、浜尾のとこに挨拶にいった。浜尾は「代議士でやるならソレで突き通すがよい。人からおされたからなったというような気まぐれでもゆかぬ、どこまでもそれで押し通せ」ということを、礼の長談義で長々としゃべったあと、「何をやっても人格が第一」といった。この言葉に古島は感銘した。少年期において鉄道技師問題で反発し、青年期において政治の考え方に反発したとはいえ、浜尾はまた、古島にとってはかけがえのない貴重な恩師であった。浜尾が杉浦に紹介しなかったならば、古島のその後の人生はなかったのである。その意味において、古島という人は、学歴に縁がなく、師縁には恵まれていたというほかない。
明治四十四年、古島は四十七歳で代議士となり、浜尾のとこに挨拶にいった。浜尾は「代議士でやるならソレで突き通すがよい。人からおされたからなったというような気まぐれでもゆかぬ、どこまでもそれで押し通せ」ということを、礼の長談義で長々としゃべったあと、「何をやっても人格が第一」といった。この言葉に古島は感銘した。少年期において鉄道技師問題で反発し、青年期において政治の考え方に反発したとはいえ、浜尾はまた、古島にとってはかけがえのない貴重な恩師であった。浜尾が杉浦に紹介しなかったならば、古島のその後の人生はなかったのである。その意味において、古島という人は、学歴に縁がなく、師縁には恵まれていたというほかない。
 参考1:諸橋徹次『古典の叡智』(講談社学術文庫)P.64
参考1:諸橋徹次『古典の叡智』(講談社学術文庫)P.64